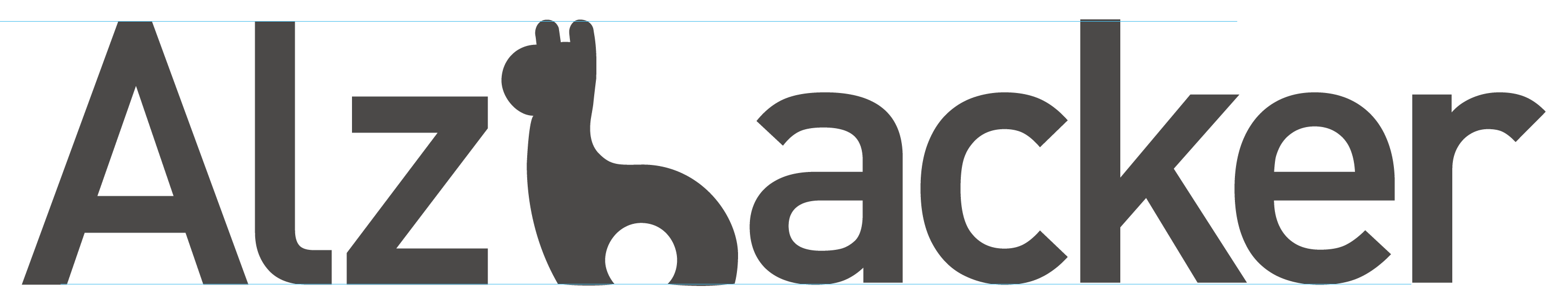Contents
概要
書籍「NO SWEAT」 モチベーションのシンプルな科学より
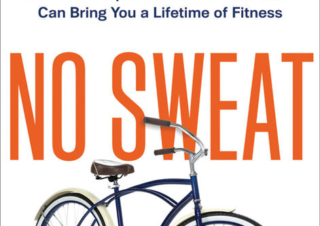
健康目的で始めると失敗するかも
人間は、長期的な利益よりも、すぐに得られる利益を選ぶようにできている。運動の動機づけとして、減量や健康増進は多くの人にとって「間違った理由」であり、一貫して運動を行うために必要な報酬やフィードバックがすぐに得られないからだ。
研究によると、病気の予防といった将来の健康への恩恵は、あまりにも抽象的で、人々の惰性や多忙なスケジュールを克服することはできない。モチベーションが遠い目標、臨床的な目標、抽象的な目標に結びついた場合、健康行動は他の多くの日常の目標や優先順位と常に競合するため、説得力を欠く。
「運動という概念は、あまりにも罰の代名詞になってしまっている」と私は続けた。「運動と聞くと、汗びっしょりになって、毎日少なくとも1時間、複雑なジムの器具を使って頑張らなければ、運動で失敗しているとすぐに思ってしまう」
参加者を、運動をするグループと、運動をしない対照グループに分けた。結果は予想通りであった。運動するグループは、コントロールグループに比べて、抑うつと不安の両方のレベルが有意に低かったのである。これで話は終わりかと思いきや、3ヵ月後にフォーカスグループのフォローアップのために参加者が戻ってきたのである。当然のことながら、参加者全員が、運動が健康にいかに良いかを語ってくれた。しかし、「今も運動しているか」と聞くと、ほぼ全員が「いいえ」と答えた。研究への取り組みが終わると、運動への取り組みも終わってしまうのである。
運動のモチベーションを上げるには、自分が楽しいと思うことをするのが効果的
国立衛生研究所の助成金により、私は自分のプログラムの長期的な効果を研究することができた。一般的に、運動プログラムの失敗率はよく知られており、ほとんどの人が開始後わずか6カ月で脱落してしまう。
それに対して、私のプログラムでは、終了から10カ月後、参加者の大半が身体活動量を平均65%増加させることができた3。
ひとつの鍵は、身体活動の恩恵を享受することは、汗をかくことだけが目的ではないことを認識することだ。特に、自分が実際に楽しんでできることを選択した場合は、厳しい運動療法と同じかそれ以上に、ほとんど無限の身体運動の選択肢と強度が効果を発揮する。
この言葉は、あなたにとって過激に思えるかもしれない。しかし、実は、これは最新の身体活動に関する勧告と最新の科学的知見に沿ったものなのである。
掃除、ガーデニング、散歩など、生活に密着した活動も重要であり、座る時間を減らすだけでも効果がある。
科学界は、一度にすべてを行うのではなく、一日を通して行う身体活動を積み重ねることを認めている。運動強度は「激しい」(または非常に難しい)ものである必要はなく、「数える」ために汗をかく必要もない。
「よし、頑張る!」は失敗戦略
運動が面倒くさいと感じる気持ちや両価値観を克服するのに十分な意志や自制心があるかどうかにかかっている場合、あなたはほとんどの人が失敗する戦略を選んでいるのである。意志の力の限界は「自我の枯渇」とも呼ばれ、2つの研究によって明らかにされている。
研究では、ある状況で自制心や意志の力を使うと、将来の状況でそれが枯渇してしまうことを示している。砂時計を流れる砂のようなものである。私たちの自制心には限りがあり、使えば使うほど、その量は減っていく。
ある状況下で自制心を発揮することは、実際に脳に影響を与え、後でそれを発揮する可能性に影響を与える。
考えてみてほしい。あなたは1日にどれだけの消耗タスク(子供の世話、仕事、試験勉強、親の介護)をすでに実行しているか?通常の生活のストレスは、実際にあなたの脳のセルフコントロールへの反応を低下させ、誘惑に抵抗する能力をさらに低下させるかもしれない。
だから、お願いだ。持続的な行動変容を達成するための主要なアプローチとして、意志の力のことは忘れてほしい。意志の力を高めることができないわけではない、ある程度は可能である。睡眠時間を増やしたり12 、自制心を鍛えたり13 することで、意志の力を高めることはできる、しかし、だからといって、意志の力を持続させるための主要な計画として考えるべきではない。意志の力は使えば使うほど衰えていくものだからである。使用すると枯渇することが知られている資源に依存するのだろうか?長期的に見れば、良いアイデアではない。
フェーズ1 散歩・日常的な身体活動
- 「散歩(コグニサイズを含む)」「有酸素運動」「筋トレ」それぞれ異なるメカニズムで抗認知症効果をもつため、それぞれが異なる効果と必要な運動として捉える。
- 本人がやってみたいと思うエクササイズから始める。(自発的な運動は認知機能改善効果が大きい)
散歩
運動は朝の散歩から
朝空腹時の早足散歩&太陽浴は、うちの母だけでなく、他の方からもいくつか報告をもらっているが、敷居が低い割には、大きな効果が得られやすい(特にApoE4)のでおすすめしたい。
朝、早足散歩することで、
- BDNFやオートファジーなど断食の効果を高め、
- 日光浴によって認知機能に重要なビタミンD合成と概日リズム整えるための視交叉上核へシグナルを送り、
- 早足の軽い有酸素運動によってミトコンドリア機能を高め、
- 適度な歩行のリズムによって、アミロイドβの排出を高めることができる。
さらに
- 階段の上りがあれば、お手軽高強度インターバルトレーニングを実行できる。(ミトコンドリアの質が飛躍的に高まる)。
- 階段や坂道の下りがあれば骨への刺激により、オステオカルシンなど認知機能と関連する多くの骨強化成分が分泌される。
- 街を探索すれば、空間認知能力と関連する海馬機能を鍛えることができる。
どれくらい散歩をするべきか
運動が継続できるかどうかを最優先
- 身体を動かすのが乗り気ではないときは一日2分の散歩でOK (250歩)
- 事前準備(スポーツウェア、専用シューズなど)は心理的な合図となり、アドヒアランスが高まることが研究で示されている。
- 効果があるかどうかよりも、本人が楽しいと感じる運動を選ぶ
次のステップ
運動がひどく苦にならなければ、2000歩からスタート(2000歩でも一定の効果はある)
2ヶ月後の目標
9000歩[R] または キビキビ早足5000歩
歩数計があると良い。心拍計がおすすめ
- 特にこだわりがなければ、ウォーキング・散歩から始めるはかなり正しい。
- 大気汚染のある場所(幹線道路の近くなど)での運動は極力避ける。
散歩を楽しくする7のアイディア
- 歩数計で計測し、富士山や東海道などの目標を設定
- 散歩用の音楽を用意
- 散歩中の休憩スポットを見つける
- スマホのデジカメなどで撮影
- 散歩用の靴を変えてみる。フラットシューズ、サンダル
- 歩考 アイディア発想の時間(散歩前に関連する本を読むなど)
- スマホの散歩アプリを利用
散歩の効果を倍増させる7の方法
- 散歩用のシューズを靴底の薄い靴に変える(かかと骨刺激)
- 下り坂、下り階段を降りる。(骨刺激)膝への負担をかけないよう膝を曲げて。
- ノースリーブ、半ズボンを着用(日光の照射面積を増やす)
- 散歩仲間を作る、ウォーキングブッククラブ(社交、脳トレ)
- 瞑想歩行を試みる(ストレスリリーフ)
- 歩きながらのZOOMミーティング、または電話で会話(脳トレ)
- 運動強度ゾーン1を目指す。心拍計は個人的には強く推奨したい。
組み合わせる
フェーズ1の運動は、本格的な認知機能改善運動を行うための予行演習であり、習慣化ステージであるが、一方で散歩は様々な社会活動や認知活動など結びつけやすく、特有のメリットもある。組み合わせ戦略としてフェーズ1も維持しておきたい。
例
- 身体活動を伴う参加型のボランティア参加(社会交流)
- 会話をしながらの散歩。(思い出話を話すなど、毎回お題を設定する)
- 犬の散歩
- 街歩き、お店探し(脳トレ)
- 森を歩く(土壌微生物叢、フィトンチッドへの曝露)
- 下り階段(骨刺激)以下に記載
ジャンプ・骨刺激
跳ねたりジャンプしたときなどに生じる骨への衝撃により分泌されるホルモン・オステオカルシンは、骨密度を改善することが実証されており認知機能への改善効果も期待できる。
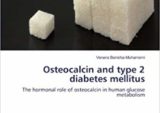
週3回 ジャンプ回数 40~100回 単一のセッションではなく、(数時間の時間間隔をあけて)複数回に分割してジャンプトレーニングを行うと骨密度の増強がより高まることが動物実験で示されている。[R]
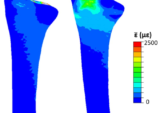
時間をもうけてジャンプをしてもいいが、普段の運動や散歩の中で、時々骨への刺激を取り入れるという方法がもっとも合理的だろう。
階段 上りは二段飛ばし 下りは骨刺激
肥満高齢女性の研究では、下り階段が上り階段よりも筋肉機能、体力、バランス、BMD、心肺機能、インスリン感受性、脂質プロファイルを改善することが示されている。[R]マウスの実験では衝撃負荷が脳の健康効果に結びついている[R]。階段昇降時の信頼性が高い歩数計(オムロン HJ-403C)
底の浅いシューズ
骨刺激の観点からは底の薄いシューズが効果的かもしれない。ただし刺激を与えるときは膝を傷めないよう膝を曲げた状態で衝撃を与える。
なわとび
なわとびは簡単かつ安全に心拍数を増加させHIITを可能にし、同時に骨を刺激することができる。骨刺激を目的とするなら短時間で良い。
踵落とし
シニアパルクール 上級者向け?
高齢者向けのパルクール、骨刺激だけではなく認知機能の強化にもつながる。

news3lv.com/news/nation-world/senior-parkour-aims-to-help-older-men-and-women-avoid-falls
フェーズ2 有酸素運動
有酸素運動系
自分のゾーンを理解する
keisan.casio.jp/exec/system/1161228740
最大心拍数は年齢だけではなく個人差もあるため、計算式で把握してもらいたい。65歳前後で一般的な心肺機能を保つ場合大まかな目安としては以下のとおり。
- ゾーン1 105~115
- ゾーン2 115~125
- ゾーン3 125~135
心拍強度50~70%から
- 運動習慣が定着するまでは運動強度ゾーン1(50-60%)を継続。
- 一回の運動時間は習慣化できるまでは30分を超えないようにする。
- ゾーン1が快適に感じられるようになったゾーン2(60-70%)を一ヶ月ほどかけて少しずつ取り入れていく。
- ゾーン2を2ヶ月以上、ある程度快適に続けられようになればゾーン3(70-80%)を取り入れていく。
- ゾーン2とゾーン3を時々織り交ぜながら行う。
- ゾーン3で快適さを感じるまでのレベルに達したら、ゾーン4に挑戦しても良い。ただし、有酸素運動時間の10%程度、最大で20%を超えないこと。

自発性
誰かに強制されるのではなく、自己選択で強度を高めていくかどうかは、運動の感情的な快適さ、楽しさだけではなく効果にも大きな影響を与える。本人の意志を高めるには「北風と太陽」のような下準備が重要。
ゾーン4はオーバートレーニング症候群となって運動アドヒアランスから離脱しやすいことがわかっている。けして無理やり取り組まないこと。
心拍計
ゾーンの測定に心拍計は必須。腕時計型は心拍数が高くなるほど信頼性が劣る、トレッドミルなど室内での有酸素運動の場合は特に精度の高い胸ベルトとスマホの組み合わせがおすすめ。手首などに巻くリストタイプは特に安価なものは精度が悪いため、利便性からリストタイプを選ぶのであれば信頼性の高い(一般的に高額)製品を買うこと。(個人的な経験だが比較的安価なcoospoのアームバンド心拍計は正しい精度を示してくれる)
坂道を登る、ゆる登山などは、同じ心拍を高めるのに平地を走る場合と比較すると、想像以上に心拍を強力にあげてくれる。膝もランニングと比べて痛めにくい。
有酸素運動に関するヒント
・有酸素運動は脳機能にもっとも良い運動
心拍が基準
・心拍計を利用して運動の強度を判断。(認知症患者ではきつい感覚と運動強度は一致しなかったりする)心拍計は必要とする心拍に達することを目的とするためだけではなっく、やりすぎてオーバートレーニングになることや、遅れてやってくるモチベーションの低下を避ける意味もある。(体が無意識に危険だと判断してしまう可能性がある)
・膝の負担を緩和して心拍を上げることができる上り坂がおすすめ。(高齢者だと徒歩速度でも有酸素運動域に達する)
室内運動器具
- リングフィットアドベンチャー(おすすめ)
- トレッドミル + 心拍計 + スマホ表示 + タブレットなどのモニター
- スロトレ
予算と場所があれば骨刺激をもたせれるトレッドミルがおすすめ、(選択のポイント、電動での傾斜機能、プログラム設定で変化をつけれる、テレビPCタブレットなどが設置できる)専用テレビモニターにFireTV(amazon)や、クロームキャスト(google)のようなテレビでYoutubeを見ることのできる環境を整えると、かなり運動が快適に行える。30インチ以上あると良い。
場所がない場合は折りたたみのエアロバイク。
室内の有酸素運動器具で高齢者へのオススメは、リカンベントタイプのフィットネスバイク(膝の負担が軽減でき、ながら運動が可能)
最終ゴールは一日30分 週5日(週の合計が150分)
・必ず続けるのが嫌になり飽きてくるということを前提に、飽きない工夫の準備、先回りしていくことがポイント。
週150分を超えての運動は最大で300分まで。それ以上は効果がプラトーに達する。
午前中、午後どちらでも良い、運動の時間は定まっていればなお良い。夜間遅くは避ける。
運動量、頻度、強度が不足する場合
運動の完全な代替になるわけではないが、HSP温浴などの温熱療法、辛いものを食べる、近赤外線照射療法などは、HSPの増加、Nrf2活性、一酸化窒素の増加など、いずれも運動と類似する抗認知症メカニズムをそれぞれもつため、補完として積極的に利用したい。
フェーズ3 筋力トレーニング
筋トレに関するヒント
- 筋トレは有酸素運動の次に重要、ただし有酸素運動では得られない認知機能を改善するメカニズムがある。有酸素運動と組み合わせることで相乗的効果が得られる。
頻度
- 筋トレは午後に行っても良い。
- 週一回30分から始める。最終ゴールは週二回(一回30~60分)
鍛え方
- 下肢、背中、胸など大きな筋肉郡を集中して鍛える。
- 上記の3つの筋肉群で最も健康効果が高いのは下肢の筋トレだが、最も辛いのも下肢、最初は比較的容易な胸を中心に始めていったほうが良いかもしれない。
- 始めやすい順序 スロトレ → パワトレ → 筋トレマシン → フリーウエイト
- エキセントリック(伸長性動作)トレーニングは、血中脂質プロファイルを改善する。
施設
- 市のスポーツセンターなどで筋トレマシンを利用してみる。
- 初心者はやり方とプランの組み方をトレーナーから教わるのが無難。忙しくない時なら施設の職員さんは親切に教えてくれることが多い。
- 予算に余裕があれば、または膝や腰に問題を抱えている場合、トレーナー付きの加圧トレーニングを検討する。(加圧トレは理解すれば自力でも可能)
- 以上がむずかしければ、運動型のデイサービスを利用も選択肢に入れられる。
筋力の低下、体重減少
サルコペニアの原因
- ステロイドホルモン産生と感受性の低下 → 運動・BHRT・他
- ミトコンドリア機能の低下 → ミトコンドリア機能改善プロトコル
- 運動ニューロンの減少 → 筋トレ・BDNF増加策
- インスリン抵抗性(2型) → 糖代謝の改善プロトコル
- 炎症因子(CRP、IL-6) → 1型プロトコル
- Ⅱ型筋繊維(速筋)の減少 → 筋トレ
- 内蔵脂肪の増加 → 運動・不飽和脂肪の摂取・酢、食物繊維の摂取
- ビタミンD欠乏(おそらく)→ VD補充
- 栄養欠乏 → 栄養管理ソフトで栄養計算・リーキーガットの修復
サルコペニアの食事・サプリメント対策
- グラスフェッドホエイプロテイン+エッセンシャルアミノ酸(EAAs)のパウダーを10%混ぜて一日20~30gを数回に分けて摂取。血糖値の上昇に注意。
- 筋力トレーニング 筋トレ系の運動と併用すること。難しい場合は階段を二段飛ばしで100~200段上る。
- クレアチン
- ビタミンD(アルサプで摂取していれば不要)
- ロイシン・HMB 筋トレ系の運動との併用がない場合は効果は限定的
- テストステロン補充療法(深刻な場合)
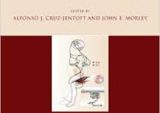
フェーズ4 HIIT
HIITなどの高い強度の運動は、脳血管血流の増加や、脳由来神経栄養因子(BDNF)[R]などの増強効果がより高い。[R][R]
また前頭前野のタスク関連領域の活性化も増加する。[R]
心拍強度
ゾーン4、無酸素運動領域の短時間運動は、完全に運動習慣が身についてから。個人差はあるが、楽しさを感じることが有酸素運動に比べて格段に難しく、初心者が手を出すと運動の継続をくじく可能性が高い。自発的であることがポイント
階段を全力で20秒登る×3回(一日3回または休憩10秒)下りも時々取り入れる。
階段トレのすすめ
・ビルやマンションの階段を利用した階段エクササイズは非常に利便性、心拍負荷、コスパ、測定性果など、特に都市部の居住者では知られざるもっとも効率的なエクササイズ。少し速度を高めるだけでHIIT並の運動が達成できる。心拍機能を鍛えるには上り階段が有用。[R]
運動継続のヒント
認知機能を改善するための運動は認知症のライフスタイル改革の中で最もといっていいほど、継続的な実行が難しいパート。そのため、少なくとも最初の1~2ヶ月は運動そのものではなく、運動を継続するための準備に資源を集中させる。
習慣化で大切なことは、運動そのものが楽しいと思ってもらえるための努力。最初の段階では調子がよくてその時はできそうな気になっても過剰な運動を絶対にしないこと。継続することだけに集中して頑張ってみよう。(乗り気しない時は100歩だけ歩くといったように。)
運動仲間を見つける
”同じレベル”の運動する仲間を見つけるのはなかなか難しいが、見つけてしまえば継続率が飛躍的に高まる。個人のやる気で運動を継続するのは非常に難しいため、とにかく仲間を見つけることに努力を傾ける。頑張って見つければ後が非常に楽。
介護者や家族が一緒に運動を始めれば、一石二鳥(一般的に遺伝的つながりのある家族介護者は認知症リスクが高いと考えることはできる。)
朝の空腹時の運動はボーナスタイム(認知機能改善効果倍増)
運動をしたくない隠れた理由を見つける
運動をしたくないという本能的なブレーキが常にやる気や意志を引っ張って綱引きが行われている。このブレーキに通常本人は気づいていないため、作ったような言い訳がでてくる。言い訳そのものではなく、このブレーキが何なのか深層心理的な正体を突き止めて、そこを解決していくことが継続の鍵。
運動が続くかどうかは最終的には本人が運動をやってみて「体が楽になった」とか、「気分が向上する」といった変化に気が付く期間が一定期間続く必要がある。
運動前サプリメント
そのため運動前の、やる気を高める、いくつかのサプリメント、プレワークアウトドリンクなどは、運動を本格的に始める人に必要なものとして捉えられがちだが、むしろ初期の習慣化ステージで必要とすべき。
屋外での運動
- 太陽を浴びるとなお良い。当たり前だが服を着込んでいれば太陽光線の効果はほとんど得られない。(露出した皮膚表面積 × 時間 × 天候 × 季節(5~8月))
- ビタミンD合成には紫外線が必要。日焼け止めストップさせるため日照量に合わせて適度に。
- 寒さや暑さも抗認知症ポイントが稼げる
詳しくはこちら↓



運動がどうしても難しい場合
運動の疑似効果をもつ方法を利用・ゆるい運動を組み合わせて相乗効果を狙う。
- 太陽を浴びる → 一酸化窒素合成
- LLLT/PBM → ミトコンドリア機能を高める PPARγの活性
- 温熱療法 → HSP活性
- 辛い料理、カプサイシンの摂取 → Nrf2活性
- WCFC → BDNFの増強
- HBOT(酸素カプセル) → ATP/NAD+/Sirt1経路の活性
- 断食 → Nrf2活性
ApoE4・運動不足のためのサプリメント
- WCFC
- キオスマスティックガム or 低用量ピオグリタゾン 5~15mg/日 (処方・個人輸入を検討)夕方
- コーヒーフルーツ濃縮物粉末(WCFC)100mg BDNF増強効果(海外)
- 低用量フェノフィブラート 20~40mg (処方・個人輸入を検討)夕方
- PPARγの活性化
- ケトーシス療法、サウナ、近赤外線(LLLT)による運動の疑似効果
- メラトニンの増量 10mg~

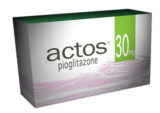
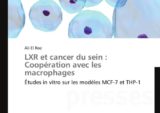

運動の効果を増強させる
太陽を浴びる
朝の絶食状態で運動を行うことで、神経保護作用をもつケトン体を効率よく増加させ、神経栄養因子であるBDNFを相加的に上昇させ海馬の神経新生の増強を高めることができる。特に運動を認知機能を改善させるために必要なレベル(週150分以上の有酸素運動)まで量を満たすことができない場合は、絶食運動によって、運動量の欠乏をある程度補ってくれる可能性がある。
運動運動は午後でなければ難しいのであれば午後に行っても良いが、毎日できるだけ決まった時間に行うのが望ましい。睡眠障害がある場合、夕食前の夕方に運動すると睡眠の改善と質を高めてくれる。光は別途朝に浴びる。皮膚(面積)の露出を意識する。特に冬。日焼け止めは効果を失わせる。
太陽光からのビタミンD合成は様々な要因で低下
- 窓越しの日光浴ではビタミンDはほとんど合成されない。→ 屋外へGo
- 長袖長ズボンではビタミンDは合成はわずか。→ 半袖短パン
- 日焼け止めはビタミンDを合成に必要な紫外線を遮断 →塗るのは顔だけ
- キノコはビタミンD3ではなくD2 →D3があるとD2の利用能が増加
- 肥満者のビタミンD合成能力は2分の1 →痩せるんだ
- 高齢者のビタミンD合成能力は若者の3分の1 →不足分はサプリメントで
- 春、秋では半分、冬はさらに低い →光セラピーも検討する
- 立った姿勢は寝そべった姿勢の4分の1 →寝そべれる場所の確保
- 都市部でスモッグがあると2~4分の1 →都市脱出を検討
- 緯度が高い地域、東日本では日光浴で足りないかも →浴びる時間を増やす

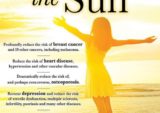
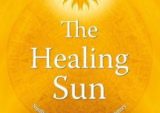
コグニサイズ 認知機能を使用して運動
コグニサイズ系
ダンス、知らない道を探索、ポケモンGOなどのアプリを利用
- ジオキャッシング 宝探探しに行こう
- 地域の散歩コミュニティに参加
- ウォーキングブッククラブ
BDNFを飛躍的に高めるオープンスキルスポーツ
外的要因によって左右される技能をオープンスキルと呼び、スポーツでは相手が存在するなど流動的な変化の中で常に予測をする必要がある。
反対にバレー、テニス、格闘技、サッカー、など。反対にクローズドスキルによる運動は、ジョギング、水泳、縄跳びなど外部に作用されず自分のペースで行うことができる。
オープンスキルが要求される有酸素運動は、クローズドスキルと比べて脳由来神経栄養因子BDNFを著しく増強させ、より高い認知機能増強効果があることが最近の証拠で示されてきている。[R][R]
テレビゲーム
テレビスポーツゲームとしては最高峰と言われているリングフィットアドベンチャー。
リングフィットアドベンチャー(任天堂発売の人気フィットネステレビゲーム)
まだ入手が困難だが、何度かの抽選で入手できるようになってきている。
運動前に抗酸化作用の強いサプリメントを摂取しない
この標準プログラムのスケジュールは、午前中に運動を行うことでミトホルミシスの効果を阻害しないよう組み立てている。
そのためスケジュール通りに散歩を含めた運動を午前中行い、サプリメントを摂取するのであれば特に気にしなくていいだろう。

運動効果を増強させるサプリメント
モチベーション・運動効果を高める
- カフェイン(運動前、午前中限定)一回半錠~1錠
- グルタミン 5~10g (1gあたり最低50ccの水が必要)
- PQQ 運動前 [R]
- WCFC
- DHEA + プレグネノロン 各25~100mg 個人輸入
- LLLT 運動前
- プロテイン+オレウロペイン(オリーブリーフ)テストステロンの増強
- EGCG、グレープシード抽出物、イラクサの根(天然のアロマターゼ阻害剤)
- 甲状腺ホルモンの検査 + 補充療法を検討
- 男性はテストステロンの検査 + 補充療法を検討
- お気に入りの音楽を用意
プレワークアウトドリンク
Cellucor, C4リップド、プレワークアウト、ラズベリーレモネード、180g
筋トレ日・運動効果を高める
- グルタミン(筋トレ後)一回5~7g
- β-アラニン
- トレハロース
- プロテイン (筋トレ後~翌日)20~30g/日
- タウリン
- アミノ酸(EAA)(筋トレ後~翌日)一回 4~6錠(3~5g)筋力が衰えている場合は筋トレ以外の日にも3g/日を加える。プロテインに10%の割合で混ぜても良い。プロテインを含め過剰摂取はインスリンスパイクを引き起こす。
- HMB(筋トレ前)一回1~2錠
- メトホルミン[R](65歳以上)
BCAAを摂ってはいけない?
一部の研究者は、BCAAレベルの上昇とアルツハイマー病発症との関連を疑っている。ラットへの経口でのBCAA摂取による増加は、記憶形成に関与する海馬の神経成長因子(NGF)の減少を示している。一方でBCAAによる短期的なmTORの活性化は筋合成を高めるだけではなかく、インスリン抵抗性の改善にもつながる。慢性的なmTOR活性化(アルツハイマー病ではアミロイドβにより慢性的に活性化されている)は、膵臓のβ細胞を枯渇化させ、神経保護作用をもつインスリンレベルを低下させる可能性がある。
これには、HMB、も含まれる、これらのアミノ酸は毎日の利用は避け、筋トレの前後など、特定のタイミングで短期的な効果を狙って用いることで不利益を最小限に抑えることができると考えている。