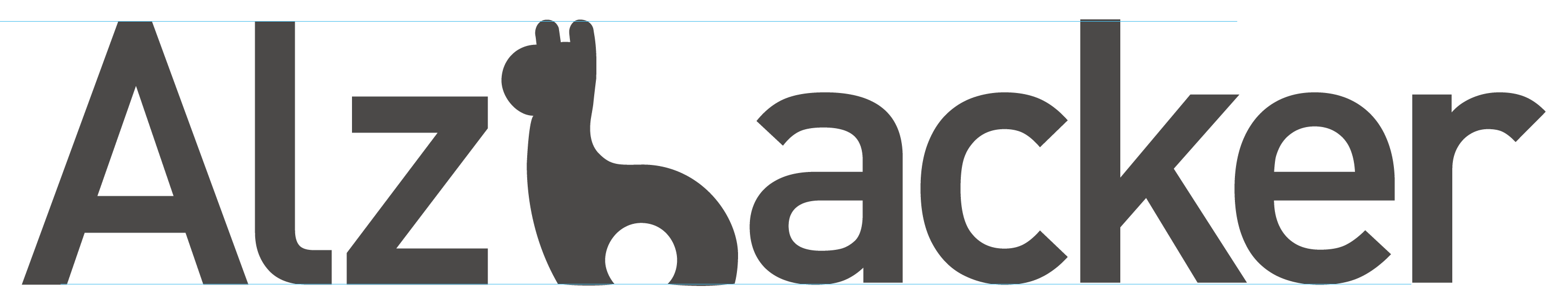Contents
theathleteblog.com/heart-rate-training-zones/
昔は自分の体の声に 耳を傾けるのが苦手だった。 実際、痛みを押し通そうとして無視していたこともあった。心拍数トレーニングゾーンのコンセプトは私にとって異質なもので、私が知っている主な努力は「他のチームメイトに勝つこと」であった。
私の注意力はあちこちに散らばっていた。唯一、自分の体に集中していなかったのは、自分の体だけであった。私は他の人と自分を比較し、すべてのトレーニングセッションでそれらを複製したり、「打ち負かそう」としたりしていたが、それはほとんどの場合、私を疲れさせ、過剰にトレーニングし、望ましい結果を見ていないことからフラストレーションを溜め込んだままにしていた。
心拍数トレーニングゾーンは、個人的な目標に集中するのに役立つ
初めてのトレーニングキャンプで他のアスリートと話をしているうちに、コーチがトレーニング中に奇妙な装置をつけるように要求していることを知った。それは 2005 年だったし、「心拍数モニター」という言葉は人気がなかった。私はそれが何であったか、またはなぜそれが必要であるが、学ぶことを熱望していた見当もつきないであった。そこで、私はコーチに問い合わせてみた。
彼は、毎回のセッション後に心拍数のデータを分析して、アスリートがどれだけトレーニングプログラムを実行しているか、体がどのように反応しているかを確認していると教えてくれた。また、彼が教えてくれたのは
トレーニング中にハードにプッシュするには精神的な強さを必要とするが、いつ撤退するかを知るのは、はるかに難しい。
このように、選手の現在の状態に合わせてトレーニングプランを調整することが、より良いより持続可能な結果につながる。
私は夢中になったと言っても過言ではないであろう。それまでは、オンオフのスイッチしかなく、トレーニングはハードに行って、リカバリーして、次の日にはそれを繰り返すものだと思ってた。トレーニングの強度を変化させることで、どれだけのチャンスがあるのか考えたことがなかった。何よりも重要なのは、実際に数値化して測定できることだ。
私は合宿から戻って数ヶ月で初めて心拍数モニターを手に入れ、それ以来、セッション前、セッション中、セッション後の心拍数を記録するために毎日使用している。
何年もかけて、自分の体がストレスに対してどのように反応するのか、強度やトレーニングセッションの違いが体にどのような影響を与えるのか、そして最終的にはトレーニングプログラムをどのように設計・調整して実行すべきなのかを学んだ。
心拍数は、現在のフィットネスの状態をモニターするのに役立つ
トレーニング中の心拍数は良い基準点となり、パワーやスピードとは異なり、身体にどれだけの負荷がかかっているかを示す。心拍数は現在の状態と一致しており、体がより多くのストレスを受けている場合には高くなる。
アスリートは疲れているかもしれないし、落ち着かない夜を過ごしたかもしれないし、風邪と戦っているかもしれないが、これらはすべてセッションに影響を与える可能性がある。このような場合、一定のスピードやパワーを維持することに集中することは、良いことよりも悪いことを引き起こす可能性が高くなる。
心拍数トレーニングゾーンは、現在の状態に応じて必要な強度でトレーニングを行うことができ、無意識に限界を超えて体を追い込まないようにしてくれる。
トレーニングで心拍数トレーニングゾーンを使うと、自分の体の声に耳を傾けることを学び、自分の改善点に集中できるようになったので、トレーニングの成果がすぐに上がった。
他の人と競い合うことに夢中になって、70%と感じていたことが80%や90%になっていることが多いことに気付いた。
最終的に何にどのように集中すればいいのかを知ることができたのは、非常に有益であった。時間が経つにつれ、疲労のバランスをとることができるようになり、トレーニングの成果が大幅に向上していることに気付いた。必要とされるときには、ハードに走るためのエネルギーが増えた。また、無駄にエネルギーを消耗していたわけではないので、セッションからの回復も早くなった。
では、実際にはどのような効果があるのであろうか?
5つの心拍数トレーニングゾーンをすべて説明
それぞれのトレーニング強度は、特定の生理学的プロセスと体内の適応を誘発する。特定の努力を中心にセッションを構成することで、アスリートはトレーニングをカスタマイズし、特定のニーズに合わせて適応させることができる。
本質的には、
心拍数トレーニングゾーンとは、心拍数が落ちる強度の範囲のことである。
ゾーンは常に最大キャパシティの目安となるため、アスリートの最大キャパシティを知ることが設定の前提条件となる。
すべての強度レベルを分類した5つの心拍数トレーニングゾーンがある。
ゾーン/目標心拍数/トレーニングのメリット
Z1 /50%~60% /ウォームアップ/リカバリー
Z2 /60% ・70% /有酸素ベース
Z3 /70%~80% /有酸素持久力
Z4 /80%~90%/嫌気性能力
Z5 /90% ・100%/スピードトレーニング
心拍数を計算するには、Target Heart Rate = [最大心拍数 ・安静時心拍数] * xx% + 安静時心拍数の計算式にデータを入力するだけである。
ターゲット心拍数とは、最大心拍数と安静時心拍数の両方を調整した心拍数である。この式を使用することで、単純なMax HRのパーセンテージと比較して、より正確なゾーンが得られる。
関連している。目標心拍数ゾーンとは何かと、どのようにあなたの計算方法
心拍数トレーニングゾーンが計算されたら、次は構造化されたトレーニングプランを作成する。その計画の各段階では、特定の領域(持久力/パワー/スピード)に焦点を当て、関連するゾーンに費やした時間として測定する必要がある。
そして、それが魔法のすべてだ。
もしコーチがいない場合は、喜んでプログラムを作成してコーチングする。詳しくは、私のパーソナルトレーニングのページを見てほしい。
心拍数トレーニングゾーン計算精度
推定された心拍数トレーニングゾーンは一般化しすぎており、全体的に正確ではないのではないかという懸念がある。しかし、実際のゾーン範囲は個人ごとにわずかに乖離する傾向がある。これは、集中トレーニングの全体的な利益に大きな影響を与えるほどのものではない。
はい、心拍ゾーンを決定する最も正確な方法は、監督下のVO2maxラボテストを受けることであろう。このようなテストでは、運動中の乳酸の蓄積速度とそれぞれの酸素摂取量を測定する。このデータに基づいて、有酸素性と無酸素性のしきい値が設定され、これが心拍数トレーニングゾーンを決定する際の重要な基準となる。
しかし、何年にもわたって何度もラボテストを行っているうちに、これらの範囲が1~2%程度(最大5bpm)しかずれないことに気付いた。
低強度トレーニングとは? 高強度トレーニングとは?
トレーニングゾーンの概念には、パーセンテージ以上のものがある。
運動の強度を上げると、体はエネルギーの供給方法を変える。低強度では、体は主に酸素を使って(有酸素モード)脂肪をエネルギーに変換する。このプロセスは遅いので、高強度では、体が素早くエネルギーを必要とするときには、代わりに炭水化物(糖質または保存されたグリコーゲン)をエネルギーに変換することに焦点を当てます。これは酸素を必要としないため、「嫌気性」モードと呼ばれている。
論理的には、高強度のトレーニングの方が体への負担が大きいので、慎重にアプローチする必要がある。あまりにも早すぎると、すべての進歩が停滞してしまい、選手はかなりの期間プラトー状態に陥る可能性がある。
簡単に説明すると、トレーニングゾーンを構成する2つのポイントがある。
有酸素閾値と嫌気性閾値とは何か?
有酸素閾値とは、身体がゆっくりと乳酸を蓄積し始める(または筋肉疲労)後の強度レベルのことである。この時の努力はまだそれほどハードではないので、アスリートは5,6,7時間以上維持することができる。
有酸素閾値が高ければ高いほど、アスリートは水泳/バイク/ランニングなどの運動を長時間行うことができる。
嫌気性閾値は、一方で、体はもう筋肉疲労に対処することはできない後の強度レベルである。この強度を維持できる時間は非常に限られている(分単位)。
嫌気性閾値付近でトレーニングを行う時間を長くすると、筋肉が乳酸の蓄積に対してより抵抗力を持つようになる。これにより、非常に速いスピードを長く維持することができるようになる(1~5分程度のレースでは重要)。
良いニュースは、低強度と高強度のトレーニングをミックスすることで、両方の閾値を「改善」することができるということである。そのため、目標とするレース距離に焦点を当てた心拍数トレーニングゾーンを具体的に組み合わせたトレーニング計画を立てることが重要である。
ゾーン1トレーニング ウォームアップとリカバリー
- 努力:非常に簡単
- 目標心拍数 50% – 60%
- 期間:終日(必要に応じて)
ゾーン1は、有酸素閾値のレベルまでの運動強度である。この強度は、筋肉に蓄積または生成された乳酸がすべて利用されるほど低いものである(上のグラフの線は下降または水平のままになる)。
ゾーン1のトレーニングは、ほとんど楽に感じられるし、iは1日の間、簡単に維持できるペースです(休憩と昼食を取りながらであるが、明らかに)。他の人と会話をしたり、適切なテクニックに集中したりすることができるので、この時間は他の人とおしゃべりする時間である。
ゾーン1で長時間過ごすことは、心臓を「伸ばす」ことになり、より多くの血液を送り出すことができるようになる。この時点以降は心拍数のみが上昇する。
ゾーン1のトレーニング効果
これは非常に低強度のゾーンであるため、このゾーンでトレーニングしても疲労が蓄積されることはない。
その代わり、筋肉への血流を促進し、インターバルやハードなトレーニングセッションの間の回復を早めることができる。
ゾーン1のトレーニングセッションの例
- ハードなセッションでのウォーミングアップ、クールダウン、インターバルの間のリカバリー
- ゾーン1で最大40分の短時間のリカバリーセッションを行う。
- 2時間以上の長時間のベース作りセッション
- ゾーン5で5~10秒のバーストを3~5分ごとに行う60分のゾーン1セッション
ゾーン1は、リカバリーセッション、ソーシャルアクティビティ、さらにはSUPパドリングやハイキングなどのクロストレーニングにも最適である。
ゾーン2トレーニング 有酸素運動をベースにしたトレーニング/イージーペース
- 努力:簡単
- 目標心拍数 60% – 70%
- 所要時間。1時間以上
ゾーン2は、有酸素閾値の直後の運動強度である。このゾーンでのエクササイズはまだ簡単に感じられる。このゾーンでのエクササイズはまだ簡単に感じられるが、その分、十分なトレーニングをしていないと感じてしまうかもしれない。
しかし、それは特有の利点をもつ ・有酸素閾値を超えて長時間過ごすことで、体は徐々に耐えられるようになり、低強度でより速く進むことができるようになる。
時間が経つにつれ、体は脂肪を燃やすのが上手になり、全体的な筋肉の持久力が高まり、より速く走ることができるようになる。
鉄人トライアスロンでレースをしているエリート選手でも、コースを完走するのに少なくとも8時間を費やし、そのほとんどの時間が高いゾーン2で費やされている。そして、彼らはこの強度で2:40のマラソンを走ることができるのである。
ゾーン2トレーニングのメリット
ゾーン2はすべてのアスリートにとって重要であるが、持久系アスリートにとっては非常に重要である。このゾーンでのトレーニングは、低速筋繊維のミトコンドリアを構築し、全体的な持久力とスピードを向上させる。
本質的には、上のグラフの乳酸線を長く水平に保つことができる。
その上で、簡単なトレーニングを長く行うことで、脂肪をより良く利用することを体に教え、無駄のない体を作り上げることができる。
ゾーン2のトレーニングセッションのサンプル
プロのアスリート(レース距離に関係なく)は、通常、シーズンのスタート時に3~4週間の合宿を行い、ゾーン1とゾーン2のトレーニングを中心に行う。毎日5~6時間の簡単なトレーニングを行い、心臓を鍛え、フォームに焦点を当て、基礎筋力を鍛える。
- ゾーン2での90分以上の長時間のベース作りのセッション
- 30分から90分の有酸素運動の「メンテナンス」セッションを強度を変えながら行う。
ゾーン3トレーニング 有酸素持久力/マラソンペース
- 努力: 適度な
- 目標心拍数 70% – 80%
- 持続時間:長い間隔、10~60分
このゾーンを「人のいない土地」と呼んでいる。
自分の快適ゾーンを超えたと感じる程度に挑戦的ではあるが、それを維持することができないというほどには挑戦的ではない。それは快適とはいえない。
この時点では、会話のゾーン1&2の努力と比較して、息を整える前に、文章を完成させることがかろうじて可能である。
多くのアマチュアアスリートは、ほとんどすべてのトレーニング時間をこのゾーンで過ごすという過ちを犯している。それはあなたが懸命に訓練しているように ‘感じ’、実際に、アスリートはそれでかなり多くの疲労を構築する。
真実は、スピードやパワーを根本的に向上させるのに十分な強度を提供しているわけではないが、体が完全に回復できるほど簡単ではない。そのため、アスリートは常に疲労を感じているが、必ずしも速くなっているわけではない。
しかし、そのようになる必要はない。
ゾーン3のトレーニング効果
ゾーン3では、より多くの筋繊維が活性化され、筋肉内のミトコンドリアがより多く構築される。さらに、ゾーン3のトレーニングは毛細血管ネットワークを発達させ、酸素をより効率的に筋肉に運ぶのに役立つ。これにより、筋肉の経済性が向上する。
これにより、適度なレースでの努力が容易になり、管理しやすくなる。
これにより、ハーフマラソンやマラソン、ハーフアイアンマン・トライアスロンなどの長期的レースで必要とされる巡航速度が向上する。
ゾーン3トレーニングセッションの例
ゾーン3トレーニングで重要なのは、セッション中ずっと維持するのではなく、インターバル方式で行うことである。この方法は、体内に蓄積された乳酸を制限し、余分なものを取り除き、より多くのインターバルに耐えられるようにする。
- ゾーン1または2のロングイージーセッションを3×10-30分で行う。
- 6×6分、ゾーン1で6分間のリカバリーを挟んで6×6分
ゾーン3トレーニングとレース
私はレースで自分のペースを決めるために心拍数トレーニングのゾーンも使っている。例えば、私のNYCマラソンの目標は、レースの最初の3/4はゾーン3に固執し、最後にスピードを上げられるかどうかを確認することであった。
ゾーン4トレーニング 嫌気性能力
- 努力:ハード
- 目標心拍数 80% – 90%
- 持続時間:10分までの長いインターバル
ゾーン4は厄介な場所である。5つの心拍数トレーニングゾーンの中で、このゾーンが最も危険である。
オーバートレーニングが起こりやすいのはこのゾーンである。プロのアスリートに触発されて、体を回復させて補うのに十分な時間を与えずに、限界まで自分を追い込んでしまう。これは体に大きなストレスを与え、一生懸命作ったミトコンドリアを殺してしまう。
生理学的な観点からは、嫌気性閾値とは、乳酸が急速に蓄積し始めた後に、体が強度を長く維持するのに十分なエネルギーを生産できなくなるポイントのことである。
嫌気性閾値はゾーン4の中間地点であり、すべてのアスリートにとって非常に個人差がある。
この時点で筋肉が重くなり、一度に2、3の言葉を口にすることが可能になる。
ゾーン4のトレーニング効果
無酸素閾値の周りのトレーニングは、アスリートがより長く非常に速いスピードを維持することができる筋肉のパワーを構築する。その上で、それはより多くの筋繊維を利用して、高速twitch繊維のミトコンドリアを構築する。
ゾーン4は、乳酸をよりよく許容するために体を「教える」であろう。言い換えれば、乳酸の蓄積が遅くなるので、上の乳酸グラフの線は最後の方では急にはならない。
このゾーンは、中距離ランナー、カヤック、水泳選手など、レース距離が4~5分以内の選手には特に重要である。
ゾーン4のトレーニングセッションの例
このゾーンは強度が非常に高く、全力を出し切りたくなるかもしれない。しかし、完全に消耗しないようにして、目標心拍数の80%~90%の範囲内に収まるようにするのがコツである。
ゾーン4トレーニングの目標は、すべてのインターバルを最高速度で走ることではない。
長い距離を小さなチャンクに分け、その間に短いリカバリーを加えると考えてください(5Kを5×1Kに分けるようなもの)。そうすることで、インターバルごとにフルディスタンスで維持する速度よりも少しだけ上の速度で走ることができ、それを長く維持するために徐々に体を鍛えていくことができる。これがVo2MAXトレーニングセッションと呼ばれるものである。
この種のトレーニングは疲労を蓄積するので、私のアドバイスとしては、有酸素運動のベースに十分な時間を費やした後(合計で40~60時間程度)に、ゾーン4のトレーニングを追加することをお勧めする。そうすることで、持久力をつけ、努力に耐えられるように回復速度を上げることができる。
- 4×2分を2セット、1分の休憩を挟んで行う
- 10×1分、1分休憩
ゾーン4トレーニング特典
心拍数トレーニングのゾーン4と5のインターバルは非常に制限され、構造化されていなければならない。
ゾーン5トレーニング 最大の努力/スピードトレーニング
- 努力:非常に難しい
- 目標心拍数 90% – 100%
- 持続時間:短い間隔、最大40秒
ゾーン5は「全力で」努力している状態、つまり筋肉が生み出すことができる最大の力を発揮する状態である。この強度では、大量の乳酸が生成され、それを利用することは不可能である。筋肉は非常にきつくなり、アスリートはペースを落とさざるを得なくなる。
どんなに優れたアスリートでも、トップスピードを維持できるのは数秒程度である。100mのスプリンターでも、トップスピードを維持できるのは、距離の途中で50mほどしかなく、最後に向かって減速する前に、その速度を維持することができる。
この時点でアスリートは息を切らしており、一言も話すことができない。
ゾーン5のトレーニング効果
このゾーンでのトレーニングは、主に最大速度に焦点を当てます。しかし、最大強度はすべての筋繊維を利用するため、持久力にも効果がある。完全に疲労困憊するまで行わないと、このトレーニングでは速筋繊維のミトコンドリアを構築し、アスリートの持久力を向上させることができる。
そのため、アスリートはドリルや短いピックアップで最大のスピードを出すトレーニングをセッションに取り入れている。
ゾーン5トレーニングは、スタートの練習やリアクションタイムの練習にも適している。
ゾーン5トレーニングセッションの例
最大限の努力をするトレーニングは、心拍数ではなく、ほとんどが時間によって行われる。実際には、トレーニングセッションのほとんどを通して心拍数が90%以上に跳ね上がることすらないかもしれない。
しかし、心拍数はインターバルから体が回復したかどうかを確認するのに最適な方法である。2-3分後に心拍数がゾーン1-2まで下がらなくなったら、すぐにワークアウトを終了しよう。
- 3×20秒の休憩を挟んで5セット
- 10×40秒、2分間の休息
ゾーン5で5~10秒のバーストを3~5分ごとに行う60分のゾーン1セッション