link.springer.com/article/10.7603/s40741-014-0003-4
Weapons of the Weak or The Culture of Everyday Resistance to Power Relations
エイタン・ギンズバーグ博士
イスラエル、テルアビブ、キブジム教育大学人文科学部
サピル・アカデミック・カレッジリベラル・アーツ&サイエンス学科イスラエル、スデロト
2014年03月04日受領 2014年03月11日受理
概要
歴史上、「悪」政権の崩壊は誰の責任なのか。それは、あらゆる政治体制に見られる少数の反体制者たちであり、嘘の中で生きることに嫌気がさし、自ら、時には命さえも危険にさらしながら、公然と反対する「勇者」なのだろうか。それとも、むしろ「臆病者」、つまり、自分の命を危険にさらしたくないにもかかわらず、憎い政府に対して毎日、小さな、しかし十分に意識的な破壊行為に従事し、ゆっくりとしかし確実に内側から政府を弱体化させ、その崩壊に至る何百万もの被支配者たちのことだろうか。
この疑問について、本論文では議論する。その最終的な態度は、アメリカの政治学者・人類学者であるジェームズ・スコットの過去45年にわたる先駆的な仕事と、彼の「弱者の武器」、すなわち権力関係に対する日常の抵抗の文化という思想の中心をなすものに基づいている。
キーワード
アルベール・カミュ、真正の意識、隠された記録、イデオロギーの句読点、インフラポリティクス、ジェームズ・スコット、全体の同意の現れ、神秘化、帰化、プレポリティクス、静寂、反乱、抵抗、反乱、ヴァクラフ・ハヴェル、弱いものの武器。
座右の銘
第一に、私はわずかな財産もお金も見せびらかさず、あらゆる方法で、できる限り奴隷の面影を身にまとっていた。第二に、私は実際のところ、それほど知的であるようにさえ見えたことがない。このことは、南部の有色人種は、自由人であれ奴隷であれ、自分たちの快適さと安全のために特に観察する必要があると思う」1。
「バンテよ(一瞥して)我らが奴隷は…身体で別のことをし、言葉で別のことを言い、心で第三のことをする」2。
「若者たちはブーイングを始めた。若者たちはブーイングを始めた。大統領はまだ問題が起きていることに気づいていない様子で、反共産主義勢力を非難するようにまくしたてた。ブーイングはさらに大きくなり、テレビの視聴者にも一瞬聞こえたが、技術者が拍手を録音した音声に切り替えた。この瞬間、ルーマニアの人々は、万能の指導者が実は弱者であることを思い知らされた。午後には首都でデモが起こり、2日目の夜には流血の事態となった」3。
権力の実態は、匿名の部下によって語られるか、噂、ゴシップ、婉曲表現、あるいは自分の名前で語ることを敢えてしない不平不満などの偽装によって保護されることが必要である4。
反逆者
アルベール・カミュは著書『反逆者』(L’Homme révolté, 1951)の中で、「反逆とは、対象として扱われ、単純な歴史的用語に還元されることを拒否することである」と述べている。「それは、『歴史の限界 」を課すことであり、それによって『価値の約束が生まれる』ことが保証されるのだ。それは、権力の世界から逃れた、すべての人間に共通する本性の肯定である」(Camus 2012: 248-249)。あるいは、より簡潔に表現するならば、反抗は歴史の対象となるための人間最大の努力である。それはカミュの論理に従えば、人間の社会的本性に鑑みて課された多かれ少なかれ恣意的な政治の勅令に抗い、それに制限を設けるプロメテウスの経験なのである。

そして、反逆者自身は誰なのかとカミュは問い、こう答える。
反逆者とは「ノーと言う人間」である–最近まで沈黙を守り、自分の人生の状況を不当だと思いながらも受け入れてきた人間(カミュ:11-12)、突然転向して不当さに直面し、より価値ある人生を探そうとする人間、なぜなら「反逆の行為はすべて無言で価値を発動する」(カミュ:12)
カミュは、反抗的な行為を可能にする必要条件は、明らかに、幻想や神秘化を完全に排除した、現実の真の本質の明確な認識であると説明する。
反抗者は必ずしも革命家ではなく、「他者に対する生殺与奪の権を自らに委ねる」(カミュ:244)革命家でもない。革命家は、すべての人間を解放すると主張するが、実際には、「残りを服従させることによって少数の人間を解放する」(ファシズム)、「すべてを仮に奴隷にすることによってすべての人間の解放を目指す」(共産主義)。(カミュ:244-245)。これに対して、反逆者は、「原則の問題として、他者に求めることなく、屈辱を受けることを拒否することに自らを限定する。彼は、自分の誠実さが尊重されるならば、苦痛さえも受け入れるだろう」(カミュ: 16)。したがって、「奴隷が主人の屈辱的な命令に従うことを拒否したまさにその瞬間に、彼は同時に奴隷の条件を拒否する」(Camus: 12)のである。彼は自由人になるのだ。
プラハの八百屋の反乱の軌跡
劇作家、反体制派、チェコ共和国大統領予定者であったヴァーツラフ・ハヴェルは、論文「無力者の力」(1978)の中で、プラハの八百屋が「世界の労働者、団結せよ!」“workers of the world, unite!” と書いた厚紙を、山積みになったニンジンと玉ねぎの上に置いて陳列していたことを紹介している。このスローガンは、その八百屋の発案で書かれたものではない。このスローガンは、タマネギ、ニンジン、その他の商品とともに、おそらく初めてではなく、政府所有のチェーン店から渡されたものである(Havel 1990b: 41-42)5。5 八百屋は段ボールを陳列するかどうか迷った。陳列しなければ「問題になる」ことは十分にわかっていた。そこで彼は、「私、八百屋 XY はここに住んでおり、自分が何をしなければならないか知っている」と自分自身を納得させ、抗議行動を放棄し、スローガンを掲示することにした。「私は期待されたとおりに行動する。私は従順であり、それゆえ平和に放置される権利がある」(Havel 1990b: 48)。(ハベル 1990b: 48)。

八百屋はこのスローガンに無関心だったとハベルは見ている。店の窓の前、山積みのニンジンとタマネギの上にそれを置くことは、「彼らが言うように、『社会と調和した』比較的平穏な生活を彼に保証する何千もの細部の一つに過ぎない」(Havel 1990b: 41)のである。つまり、この男は、自分の人間性を根こそぎ奪い、自分をその対象とするシステムの中で生きることを恐れ、嘘をつきながら生きることを好んだ。しかし、自分を慰め、屈辱の重荷を軽減するために、彼はイデオロギーに身を包んだ。もし彼が自分の行為に立ち向かう勇気があれば、「私は怖い、だから疑うことなく従う」(Havel 1990b: 42)と痛いほど認めなければならなかっただろうから。「自分の服従の低い基盤」に立ち向かうことを避けるために、八百屋は「利害関係のない確信のレベル」を表現しながらスローガンを掲げたのである。これを強化するために、彼は怪しげに、しかし冷静に、「世界の労働者が団結して何が悪い」と付け加えることもできた。
このスローガンを掲げることで、八百屋は「真実の中で生きようとする何千もの名もなき人々」、つまり同様のスローガンを受け取ったものの、それを掲示しないと決めた人々と自分を区別したと、ハベルは述べている。彼は、「実存的」な生き方を選び、実存的な安全や、もしかしたら命そのものを危険にさらすことをいとわないすべての人たちから自分を切り離したのである。しかし、この八百屋は、同じように「実存的」な生活を望んでいながら、その余裕がない何百万人もの人々の仲間入りをすることを好んだ。「おそらく、彼らが生きている状況でそうするためには、すでに第一歩を踏み出した人々(勇気ある人々)の10 倍の勇気が必要だからだ」(Havel 1990b: 78, 84-85)。この程度の勇気を持たない者は、私たちの八百屋も含めて、嘘をつきながら、つまり乱れた生活を送るしかなかった。この決断によって、八百屋と彼のような何百万人もの人々が、体制の下僕、つまり体制を許し、その存在を正当化する人々になってしまったとハベルは言うのである。
なぜ八百屋は、自分の選択と行動がいずれ極めて卑劣なものとみなされるかもしれないと知りながら、そのような選択肢の中から選ばなければならなかったのだろうか。答えは簡単だ。彼はいわゆるユニークで間違いのないイデオロギーの背後に身を隠し、それを無批判に採用することによって、自分の行動を正当化し、誰も傷つかないだろうと自分自身を納得させたのである。同時に、八百屋は政権の正当性を評価し、政権は確かに国際的な承認を得ている法規範(ここで彼は、クレメント・ゴットバルトが率いた 1948年 5月の共産党による買収の不穏な記憶を抑えなければならなかった)に依拠し、法の範囲内で運営されており、したがって、疑いのない服従を明らかに要求していると結論付けたのだ。ハベルによれば、この3つの要素によって、八百屋は、自分自身を欺き、安全で強固な虚偽の意識の壁の後ろに隠れることを選んだ数多くの臆病者の仲間入りをするよう説得されたようである。

カミュの主張については、もしアメリカの奴隷がこのシステムを受け入れないと決めて、上に述べたような破壊的で密かな行動をとっていたら、それで十分だったのだろうか。ルーマニアの市民が、ニコライ・チャウシェスクの歪んだ、浸透した個人的・政治的行為に対抗するために、目に見える、しかし匿名の境界線を提起していたなら、それで十分だっただろうか?そして、ハベルの八百屋について言えば、スローガンを掲げることは、本当に臆病、屈辱、服従の表現だったのだろうか?ジョージ・オーウェルが『象を撃て』で用いたイメージを使えば、八百屋の顔は(スローガンを嫌っていたことは確かだが)実際に被っていた仮面に合っていたのだろうか7。
あるいは、八百屋は実際には公式イデオロギーの背後に隠れていたのではなく、ハベルが主張したように、スローガンの意味も意義も全く無視して、店のガラス棚の後ろに不本意ながら置いて、静かで内向的なやり方でそれに「穴を開けた」と主張する別の解釈が可能だろうか(ハベルは熟慮不足を道徳的脱力と見なした)。この制約によって、共産主義のエートス全体が基礎としていたプロレタリアの団結という明らかに偽りの壁から、別の積み木(振り返れば、おそらく支えとなる積み木)が取り除かれ、その聖なる崇拝に私たち八百屋は加わったばかりだったのではないか?私たちの八百屋は、実は「見かけの遵守と屈従の下で煮えたぎっているシチュー」(Knight 1995: 43; Sayer 1995: 369)の一部であったと推測できるのだろうか。1989年に共産主義体制全体を最終的に煽った見かけの従順さとは大きくかけ離れた、冷静で意識的なシチューなのか。
しかし、これまでのところ、カミュとハベルの両者がこの解釈を拒否していることは明らかである。抵抗問題についての文献は、おおむね彼らを支持している。八百屋だけでなく、ナチスの強制収容所の囚人や、詩人の作った歌を「力強いコントラルトで歌っていた」あのロンドンの「ノルマンの柱のようにしっかりした怪物(プロレ)女」(Orwell 1977: 137-138)を含む他の被抑圧者も「人間の家族」の対象としながら、私たちの提案する立場を系統的に扱っていた学者は、アメリカの政治学者・人類学者ジェームズ・スコットだけであると思われる。スコッツは東南アジアの孤立した農村の生活に関する研究によって、「真正意識理論」“authentic consciousness theory”とでも呼ぶべき理論を展開した。この理論は、弱い亜人種が、自分たちの生活をより有意義で価値あるものにするために、課せられた過酷(「アウレリアヌス」)あるいはそれほど過酷ではない(ハベルが名付けたポスト全体主義)生活条件に対する抵抗手段を効果的にも安全的にも発展させる方法を説明するものである。
議論は、スコッツの3つの研究、いくつかの学術的・文学的著作、そしていくつかの示唆に富む歴史的事例に基づいて行われる予定である。プラハの八百屋と、彼の時代や歴史を通じてチェコスロバキアで彼のように行動した百万人の人々は、ハベルが示唆するように臆病と士気の低下という罪を犯したのか(ハベル 1990b: 39)、あるいはカミュが暗に示唆したように「人間性が劣る」ことで罪を犯したのか、という疑問である。あるいは、これらの猛烈に支配的な人々は、すべての罪について無罪であり、彼らの人間性と、専制政治やあらゆる気取った全能の権力に対する普遍的な闘いへの決定的な貢献が完全に認められ、それを和らげ、時にはスコットが示唆するように完全に禁止する権利があったのか (Scott 1990: 70-107)。
ここで使用された文学的資料に関して、私は重要な方法論的注釈を加える必要に迫られている。文学(と想像力全体)は、私たちの議論を展開する上で非常に重要であると思われる。アザール・ナフィジにとって、それは疑いのないことである。「私たちがフィクションに求めるものは、現実ではなく、真実の啓示である」(Nafisi 2003: 1)と彼女は言う。(Nafisi 2003: 1)。「フィクションは万能薬ではないが、世界を評価し、把握するための批判的な方法を提供してくれた。(そして、作家が本を書くのは、私たちが生きている現実について何かを伝えるためだと仮定すれば、彼らはフィクションに携わるときでさえ、それに関する明確なビジョンを持っていたことは確かである。さらに、私たちがここで称賛に値する作家を挙げているのは、彼らが優れた感受性をもって現実を洞察し、重要な問題を考える人間の方法について有益な示唆を与えてくれることを確信しているからだ。否定的に言えば、作家の証言なしに、このような記事が書かれることはありえない。
若干の考察
スコットのアプローチを論じる前に、カミュとハベル、そしてスコットについて、いくつかの相違点を挙げておくと、これからの議論に深く入り込むことができるだろう。第一の区別は、抵抗と反乱の概念に関連するものである。カミュは反乱を語っている。スコットは抵抗を語っている。両者の間にあるものは何だろうか。両者の出発点を見てみよう。スコットにとって抵抗は、コンプライアンスが止まったところから始まる。したがって、抵抗には「上位階級(たとえば、地主、大農、国家)がその階級に課した要求(たとえば、賃料、税金、名声)を緩和あるいは否定するため、あるいは上位階級に対して自らの要求(たとえば、仕事、土地、慈善、尊敬)を推進するための下位階級のメンバーによるあらゆる行為」(Scott 1985: 290)が含まれる。(スコット 1985: 290)。抵抗は反ヘゲモニー的なイデオロギー的動機と「より長期の有益な目標をもたらすために、何らかの短期的な個人的・集団的犠牲」を含んでいなければならないのだろうか(スコット 1985: 291)。
スコットはそれを要求していない。彼にとっては、抵抗(たとえば、ゴシップ、中傷、非難、窃盗、足の引っ張り合い、脱走、納税逃れ、財産への損害を含む)は、その加害者が「世界是正」の行為として体制に対して行動したかどうか、あるいは、一見、エゴイスティックにも有益にも見える個人利益の防衛として行動したかどうか、そういうものとして見なされるのであろう。なぜか?なぜなら、「イデオロギー的」な場合と「エゴイスティック」な場合のいずれにおいても、上位の階級が傷つけられ、それゆえ、下位の階級との関係を再定義しなければならなかったからだ。たとえば、1917年3月(2月)の革命後にロシア軍から大量に脱走し(様々な推定によれば、約200万人の兵士が脱走した)、11月(10月)の革命の成功に貢献したケースは、自由な土地を獲得するチャンスにのみ動機づけられた脱走である。(スコット 1985: 293-294)
8 結局のところ、スコットはジョン・ダンに準拠して、ほとんどの場合、抵抗は何らかの「未来に対する楽観の表明」ではなく、苦悩によってもたらされることを想起させる。(スコット 1976: 226, n. 7)。
この同じ立場は、カミュやハベルには受け入れられていない。「彼らの」反乱は、カミュによれば、「不当で不可解な」生活条件への反応として生まれる。したがって、反乱とは、「横暴」に対する叫びであり、「横暴を終わらせ、これまで移り変わる砂の上に築かれてきたものを、これからは岩の上に築き上げるべきだ」という要求なのである。その関心は変容することである。(カミュ:8)。それは、思想、使命、規模の反乱であり、スコットの立場とは逆に、未来に対する楽観の表現でもある。例えば、アメリカの独立宣言は、この種の反乱であると考えられる。それは測定の反乱であり、超越の反乱であった……」
第二の区別は、抵抗と反乱の場面についてである。カミュやハベルによれば、反乱や反逆の動機、つまり現実に作用しようとする力は、定義上、必ずしも公的ではないにせよ、政治的な枠組みを必要とする。スコットも同じように政治的枠組みを必要とするが、それは定義上、公的である必要はない。彼としては、秘密の抵抗の測定、あるいは彼が一般に「インフラポリティクス」と定義するものは、あらゆる目的のための抵抗の政治的行為であり、さらに言えば、露出した、広く開かれた抵抗が出現するための必要条件なのである。
インフラポリティクス(infrapolitics)とは、周辺に追いやられた、あるいは抑圧された集団、特に主流の政治や意思決定過程に代表されない集団の内部や集団間で起こる政治力学や権力闘争のことを指す。また、従来の政治分析では隠されたり見過ごされたりしがちな、こうした力学の研究や分析も指す。この概念は、社会運動、コミュニティ・オーガナイジング、国家と権力に関する批判的研究の分野でよく使われる。
バラク・オバマのインドネシア人の継父であるルルが、オバマの母親に「彼女の絶え間ない問いかけがついに神経に触ったとき」、こう言ったという。「この国では、罪悪感は外国人だけが持てる贅沢なものだ…頭に浮かんだことを何でも口にするようなものだ」(オバマ 2007: 46)。なぜなら、政治体制を否定する言葉のひとつひとつが、政治体制を弱体化させ、転覆させるほどの力を持つと考えられているからだ。したがって、カミュがまったく考慮せず、ハベルが政治以前と定義したものが、スコットによって政治的なものとして完全に認識され、あらゆる目的のために重要であるとさえ見なされるようになる。
第三の区別は、反乱や抵抗の対象が何だろうかに関連している。システムを内部から変えるのか、あるいはシステムを破壊して別のものに置き換えるのか。カミュは、システムの内部で抵抗活動を行うことを容認しているようだ。「彼の」反乱は、上に紹介したように、本質的には既存のシステムの破壊を必要としない。ハベルの抵抗はそれを強く要求している(共産主義における確信、それは嘘の中で永続的に生きることを意味した)。この文脈では、カミュの反乱はすべての矛盾の終結ではなく、主に矛盾に対処し、少なくとも部分的に解決しようとする努力である。カミュはまた、あらゆる反乱の暴力的な記録を制限している。
「反乱者は、教義や国家理性に奉仕するために、あらかじめ暴力を拒否する。目標は神聖なものであり、手段ではなく、神聖化されるべきである」と彼は強調する。
「反乱は人間の運命を信じるべきであり、抽象的な目標のためにそれを犠牲にしてはならない。したがって、『本物の反乱の芸術は、暴力を制限する制度のためにのみ武器を取ることに同意し、暴力を成文化する制度のために同意することはない』唯一の例外は、『歴史的にみて目的が絶対的であり、その実現が確実と信じられているときは、他者を犠牲にすることまで可能である』ということであろう。しかし、そうでない場合は、『人間の共通の尊厳のための闘争の危険の中で、自分だけが犠牲になることができる』(カミュ:290)。
つまり、まさに非暴力的な反抗的現象は、その目的を限定し、既存のシステムを倒そうとするよりも、その中で行動するように反乱を方向づけることができる。スコットの固有な抵抗については、「権力の土星」と定義される「権力の爆発的瞬間」が稀に、しかも予測不可能に存在することを認めている(スコット 1990: 340-350)10。その稀性は、「従属集団の政治生活の大部分は、権力者に対するあからさまな集団反抗にも、完全な覇権遵守にもなく、これら二つの極対立の間に存在するという事実」(スコット 1990: 136)から理解することができる。
第四の区別は、反抗者が誰だろうかを見出そうとするものである。これまで検討した事例では、従属する者、すなわちサブアルタン・グループを指し示していると思う。カミュの場合、この洞察は、「彼」の反乱の典型的な特徴とその目的から、また、反乱はとりわけ「権力の世界から逃れる、すべての人間に共通する自然の確認」であるという彼の主張から導き出される。スコットについては、農民、小作人、農業日雇い労働者の研究を見ると、出発点として彼はこれらの人々を反抗的と考えたと思われる(あるいは一般的に言えば、かなりすべての農村人口)(スコット1976;スコット1985;スコット1990)ブルデューは、新自由主義国家によって追放された人々の区別をより広く提供している。したがって、ブルデューが「政府の真の兵士」、すなわち政府の左手、政府の機能を可能にする者として定義しているソーシャルワーカー、教師、さまざまな下級裁判官、青年指導者などが、彼の弱者であるといえるだろう。しかし、強者は国家の右腕であり、大蔵省、民間銀行、大臣官房のテクノクラートである。公益を市場の利益と同一視し、福祉国家としての役割を放棄した新自由主義国家では、「左手」が右手と対峙する(Bourdieu 1998: 1-3)。このような「物質的な貢献の要求以上のものはないが、献身も熱意もない」状態において、民衆は国家を拒絶する。彼らは国家を外国勢力と呼び、自分たちの利己的な私的利益を増進するために国家を利用すればよいのだ。(Bourdieu 1998: 4-5)。上で検証したスコットの言葉では、ここではどこまでも抵抗の姿勢を示している。しかし、ブルデューの区別は、この概念を専門職や教育を受けた中産階級に深く広げ、本質的にハベルの反乱者たちと同じところから生じている。
真正意識の理論
ハベルは、八百屋が自分が遭遇した状況を正確に理解していたことを確認する。彼は、自分に何が期待されているかを知っていた。彼は、利用可能な選択肢を知っていた。彼は、なぜスローガンを流言飛語の末尾にぶら下げることを選んだのか、それが私的にも公的にもひどい選択であったことも知っていた。八百屋は、苦悩する良心を癒すイデオロギーで心をかき乱す自分を許す方法も知っていたし、服従の重い義務や家族への約束など、他の実質的な考慮も加えていたのである。ハベルによれば、主人公は、自分の決断の重心とその下にある恥ずかしい真実を、心を落ち着かせるイデオロギーの虚構に移すことで、自分の良心に固執することを知っていた。
スコットはこの推論を否定する。彼にとって支配者は、彼らが活動する権力構造の判断において誤解を招くことはなく、したがって、彼らはその周囲でいかなる帰化も神秘化も行わない。彼らが「全体的な同意の表出」を示しているように見え、体制が自分たちの利益に沿って機能していないことが絶対的に明らかであっても、バリケードに登らない理由は、非常に平凡なものである。例えば、恐怖心もその一つである。そして、それについてこれ以上言う必要はないように思われる。11もう一つの理由は、劣位にある彼らの状況が、彼らの利益を促進し、彼らの全体的な状況を改善するための可能な最後の言葉ではない、という広範な信念である。そして、さらにもう一つの理由は、前述したように、ほとんどの亜細亜人が、自分たちに提示されたユートピア的な代替案に関する疑念のために、それに取って代わろうとするのではなく、既存のシステムの内部でハンディキャップを克服することに努力を集中しようとする一般的傾向に関係している。これは、敗北主義でもなければ、現実の状況に対する誤った認識でもない。これは、一方では権力の本質とそれが要求するもの(ハベルの概念では、嘘の中に生き、既存の抑圧体制と一致する儀式を共有すること)、他方では彼らの最終目標(真実に生きること)と、スコットが弱者の武器と呼ぶものを自由に使える無尽蔵のレパートリーを含む彼らにとっての代替案と行動方針がはっきりわかっている人たちの完全によく計算された決定なのである(Scott 1985: 255-2)。(Scott 1985: 255-289; Scott 1990: 136-182).

サンタアニータに抑留された日系人
スコットについて言えば、権力に対して受動的あるいは忍耐強い静止の立場を選ぶことは、神秘化あるいは誤った意識に由来するものではない。それどころか、この位置はまさに現実の感覚とそれに対する本物の意識から生じている。この最も顕著な証拠は、弱者の武器の効率的な使用の存在であり、現実を変え、支配者の生活の「実存的」必要性に適応させる(すなわち、「真実の中で生きる」)その有効性は、十分に証明されている。しかし、ここで私たちはScottを自由に解釈し、現実を変えるこの武器の有効性を、しばしば歴史的変化のランクまで実現し、それが臆病者の武器ではなく、圧政的環境に生きる現実主義者の武器であり、したがってバリケードの上に立ち、自らを危険にさらさないことを示すために、人類学の研究方法論を実行しなければならず、したがって、「人間の本質」を判断する際にはより謙虚でなければならないのである。ハベルが行った社会学的な調査・分析方法の使用は、この場にそぐわないだけでなく、誤解を招く。結局、これらの研究手段は、「人間の本質」、すなわち、もともと欠陥があり、弱く、障害をもつ人間という、一般的で誤った見方(少なくとも非批判的な見方)の上に再び立つことになる。
一連の文学的名作や理論的作品は、この理論を確立するのに役立つ。ビルマ、ベトナム、マレーシアの貧しい農民たちの困難で洗練された闘いの物語は、スコットの代表的な2つの作品、「農民の道徳的経済」に丹念に詳細に記録されている。「農民の道徳経済:東南アジアにおける反乱と生業』(1976)、『弱者の武器』(1986)。農民の道徳的経済:東南アジアにおける反乱と生業』(1976)、『弱者の武器:農民の抵抗の日常的形態』(1985)。クリフォード・ギアーツの優れた研究、たとえば『行商人と王子たち』(1963)、『文化の解釈』(1973)、『モロッコ社会における意味と秩序』(1979)なども、このジャンルに属している。アメリカ南部の黒人奴隷が、何らかの「実存的」な生活を求めて、長く絶望的な闘争を続ける物語である。識字、財産、家族生活、先祖の記憶や崇拝など、一切禁止されている「実存的」な生活のために、アメリカ南部の黒人奴隷が長い間必死に闘ってきた物語であり、洗練された支配力を弱めることを狙った一連の動き(たとえば、トリックスター物語、ささいな盗み、放火、逃亡など)は、『ロールジョーダン・ロール:ユージーン・ジェノベーゼが作った世界』(1976)、元奴隷フレデリック・ダグラスの『わが束縛とわが自由』(1855)に雄弁に語られているが、その文書プロジェクトには、『ルーツ』(Alex Haley)が収められている。また、ジェームズ・マクブライドのスリリングな小説 “Song Yet Sung”(2001)など、このテーマに関する膨大な書籍の中からいくつかを紹介する。
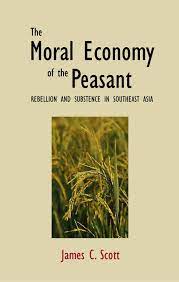
オノレ・ド・バルザック(1844)の『農民たち』、ジョージ・オーウェルの名著『ダウン・アンド・アウト・イン・パリ・アンド・ロンドン』、バーバラ・エレンライクのベストセラー『ニッケル・アンド・ダイム:オン(ノット)・グラブ・イン・アメリカ』(2001)など、貧困や上述の「道具箱」に対処する農民の知恵は、さまざまな本で扱われている。アザール・ナフィジは、『テヘランでロリータを読む』(2003)で、西洋やアラブの古典文学に触れることを一切禁止し、国民、特に女性を激しく困らせる狂信的政権の恐怖をいかに克服したかを語っている。ジョージ・オーウェルは、そのディストピア小説『Nineteen Eighty-Four』(1949)で、全体主義が市民を服従させるためにどれほどの権力を行使しなければならないかを説いている。この傑作の中でオーウェルは、強権的な法律とそれを阻むおぞましい統制手続きに直面しながらも、親密さや愛を求める人々が、弱者の武器を創造的に用いてできる限り抵抗し、その結果、彼らがとったほんの小さな措置でさえ、権威主義体制と同様に非常に危険な政治的意味を持つために禁止される様子を示してくれたのだ。
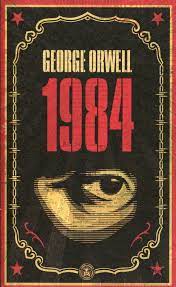
挫折した英国の支配者に対する貧しいビルマ人の弱者の武器の非常に洗練された効果的な展示は、すでに述べた短編小説「象を撃つ」(1936)でゴージ・オーウェルによって見事に紹介されている。似たようなことは、ハンス・ファラダの『Jeder stirbt für sich allein(ベルリンで一人)』(1947)という気の滅入るような本でも紹介されている。1933年から1945年にかけてナチスが何百万人ものユダヤ人、ジプシー、戦争捕虜、強制労働者、反体制者を収容したゲットーや強制収容所での崖っぷちの生活に抵抗する何百もの超危険な方法に関する物語は、私たちが自由に使えるものである。ここでは、その中でも最も有名な2つの本を紹介する。アウシュビッツの囚人であったヴィクトール・エミール・フランクルは、ロゴセラピーという救命兵器の使用について述べている『ロゴセラピー入門』(1946)、プリモ・リーヴィの著書『これが人間か』(1947)は、彼と彼の友人に課せられた死の運命に対する抵抗の、慎重かつ高度な実践の使用と命を救う先端技術を描写している。
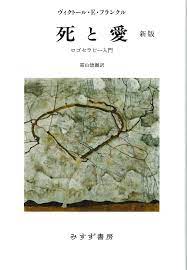

ここに挙げた研究や文学作品に登場する実在の人物や架空の人物はすべて、「弱者の武器」を駆使していたのである。想像力、創造力、そして人間の知恵にあふれた象徴的、物質的な動きのほとんど無限のレパートリーは、彼らに振りかざされる権威を弱め、彼らを支配し、彼らのアイデンティティを損ない、屈辱を与え、その必要性に応じて彼らを利用したり勧誘したり、さらには殺害しようと、程度の差はあっても脅しつける。中には、抑圧的な政権を出し抜き、その隊列を解消することに全面的または部分的に成功したものもある。これらの武器の中には、伝統的な特殊主義への固執、「小さな祖国」への激しい忠誠心(parum patriae)、伝統的儀式の管理(スコットが「霊の所有」と呼ぶもの)、回避的無関心、噂の伝播、ゴシップ、ユーモア、騙し、カモフラージュ、盗み、足の引きずり、暗号化メディアの使用、データ歪曲、隠し事、虚飾などがある。また、トリックスターの話(常に弱者が強者に勝つ方法を示す)、「奇妙な踊り」(上級指導者から下級官僚レベルへ責任を転嫁し、あたかも上層部が知らなかったかのように、あるいは知っていたとしても許されるように操作したとされる)、束縛(オーウェルが『象撃ち』で冷静に描いたこの手段)などがあった。また、エマニュエル・ルロワ・ラデュリの『ローマ人のカーニバル』(1979)には、カーニバルの枠組みを利用して不満をぶちまけたり、指導者を馬鹿にしたり、金持ちや権力者との「決着」をつけたりすることも書かれている。
それらは、スコットが示したように、痕跡を残さない研ぎ澄まされた武器であり、抑圧的なヘゲモニーに対する隠された記録、あるいはよく観察されない行動様式の集積なのである。権力に内在する弱点を利用した多数のイデオロギー的穿孔トップ指導部におけるイデオロギー的亀裂、イデオロギー的主張(および宣言)と不十分な実施との間のギャップ、副指導部内部での亀裂など、ほんの数例を挙げるにすぎない(Scott 1990: 5-6, 184-187, 191-192)。
組織的な破壊的大衆活動、それは、何百万人もの「低賃金労働者、彼らは結果的に『金食い虫』となり、ゆっくりと働く」ように、免疫体制を弱体化させ、「計算できる、見えない、巨大な無駄を引き起こし、どの共産党政権も避けることができなかった」のである。ユーゴスラビアの政治家であり反体制者であるミロヴァン・ジラスが述べたように、誰もその責任を取らないどころか、誤りを「指摘」し、それを「修正」すると約束しても、その真の意図はまったくない。(Djilas 1964 [1957]: 119-120)。

したがって、毎日職場に来て自分自身を働かせる何百万人もの「臆病者」の力がどれほど効果的だろうかがわかるのだ。しかし、ジラスは、ハベルが語った現実をその内側から完全に知っており、彼らを完全に正当化し、その説得力のある理由を心に描いている。「共産主義体制下の市民は、常に良心の呵責と、自分が罪を犯したという恐怖に抑圧されて生きている。中世の人々が教会への献身を常に示さなければならなかったように、彼は常に自分が社会主義の敵でないことを示さなければならないことを恐れているのである。「共産主義のもとでさえ、人は考える、考えずにはいられないからだ。しかも、規定された方法とは異なる方法で考える。彼らの思考には二つの顔がある。一つは自分のため、自分自身のため、もう一つは公共のため、公のためである」(Djilas: 132-133)。
イスラエルの歴史家アビアド・クラインバーグは、著書『七つの大罪』の中で、同じ構図を描いてこう述べている。「何百万人もの労働者が毎朝起きて、社会主義の祖国のためではなく、自分自身のために仕事をし、罰を免れようとした」そして、こう付け加えている。「雇用者、監督者、教授、親など、他人の時間を管理する権限を持つ人々にとって、怠惰は何ら好ましいものではない。時間割を狂わせ、締め切りを破り、プロジェクトを混乱させる。期待に応える代わりに、怠惰は単に横たわって親指をひねっている。このような怠惰は破壊的な行為であり、特殊な不服従のタイプである。公然の反乱は権力体制を刺激して行動を起こさせ、支配階級を道徳的な暴挙と戦争的な熱狂、そして血への渇望に駆り立てる。しかし、怠惰は静かな反乱であり、イデオロギーのマニフェストもない。それは社会的な柔道であり、「穏やかな方法」である。タイムキーパーを疲弊させることで結果を出す。ナマケモノは、どこにでもいて、しかも地味なので、決定的な一撃のためにすべての力を動員することを阻む。何をすべきかを決めるのが難しく、声が枯れ、疲れ果ててしまう。結局、肩を落とし、目を丸くして、ストップウォッチを投げ捨ててしまう。そのうちに、自分たちが戦っている罪そのものに感染してしまう。「怠惰は感染するのだ」(Kleinberg 2008: 35-36)
これまでの議論をまとめると、弱者の武器は臆病者の武器ではない、ということになる。ハベルが考えたように、それを公然かつ反抗的な政治に変えるのは、少数の勇敢な、宣言された反体制派を待つ前政治ではない。弱者の武器はそもそも脅迫的な武器である。それは、スコットによれば、あらゆる目的のための政治(=権力)であり、あらゆる明示的な公の政治が、もし、いつ現れるとしても、その前提条件となる「インフラポリティクス」なのである。その力は、ハベルが考えたように、必ずしも「反体制派」段階での公然たる顕現にあるわけではない。その力は、隠された霊長類の段階にも現れており、そこでは、そのパフォーマンスは、主要な歴史的なものを含む重要な政治的(同様に、社会的、文化的、その他の)変化をもたらすのに十分強力である。
例えば、フランスの第三階級が、「奇妙なダンス」のトリックに満ちた「カイエ・ド・ドレアンセ」を通じてルイ16世に課した圧力や、(1789年の一般代議員会で)(300人から)600人の選出代表団を連れてヴェルサイユに現れることを要求し、一見、投票規則を変えずに、実際には階級ごとではなく頭ごとに投票する圧力をかけていることなど、分析しよう。1989年の壁の崩壊、中国の自由化、2010年から2012年にかけての「アラブの春」、世界中の民族復興、あるいは多くの民族文化集団が、覇権国家の下で長年にわたって「アイデンティティにアイロンをかけた」後、伝統的なアイデンティティに戻ろうとする努力、世界中の女性の地位の大きな変化、等々に言及している。これらのプロセスは、ハベルが言うように、生活の圧力が政治の限界を超えたと考えなければ理解できない。私たちの用語で言えば、何百万人もの人々の政治外の活動が、政権、企業、意見、認識、取り決めの配列に強制され、場合によっては完全な革命に引きずり込まれたのである。
プラハの八百屋の話に戻ろう。
では、なぜハベルはプラハの八百屋を「臆病」「士気阻喪」と非難したのだろうか。リチャード・ボガートのような有名な学者は、英国の労働者が自分たちの生活する困難な状況を変える方法がないことを知ったとき、一種の宿命論を採用し、代替案を探すことをあきらめたと述べているが、これは何なのだろうか。あるいは、アンソニー・ギデンズ(『社会理論の中心的問題点』)は何をもたらしたのだろうか。アンソニー・ギデンズ(『社会理論の中心的問題:社会分析における行為、構造、矛盾』[1979])やポール・ウィリス(『労働の学習』[1977])は、人々にとって必然的に見えることが、時を経て正義とみなされるようになると主張した(スコット 1990: 75-76)のだろうか。ブルデューは『実践論序説』(1977)において、あらゆる制度化されたシステムはそれ自身の恣意性の自然化を(様々なレベル、様々な手段で)生み出す傾向があると主張したが(Bourdieu 1977: 164)、それは何だったのだろうか。
この誤った印象の原因は、第一に、静寂の意味を理解し、それを定義することの難しさにある。一般的な傾向として、それを「全体的な同意の表出」と理解することがある。これに関連してスコットは、権力関係はいかなる弱者によっても同意されたり受容されたりすることはありえないとしている。厚かましくも熱狂的でもなく(フィリップ・エイブラムス[Abrams 1998 [1977]: 75, 77, 82]が定義する「正当化」、あるいはアラン・ナイト[Knight 1995:43, n. 1]が理解する「現状に対する肯定的な大衆の支持を伴う」ものでもない)、薄いものでもない。1])、またアラン・ナイトが定義するように薄い、あるいは「諦観」(同上)、つまり既存の権力構築があたかも避けられない自然現象だろうかのように関係する一種の受容(スコット1990:79)である。そして、ヘゲモニーは厳しさの差こそあれ、それに反対する者に対して寛容ではないので、目に見える沈黙は、目に見えない道具、しかし完全に政治的な道具を使ってこれらのシステムに対抗する行動戦略に他ならない。彼らの目標は、システムに暗黙のうちに働きかけ、その抑圧的あるいは制限的な側面を弱めるとともに、いくつかの戦術的な代替案を推進することである。この活動は全体として、明示的な政治性が現れるならば、そしていつ現れようとも、その基礎と条件である。たとえば、サトゥルナリアの瞬間や、価格を気にせず最後までやり抜く「水力」的な暴発の瞬間などである(Scott 1990: 77-78)。
18世紀と19世紀のヨーロッパの農民に関する研究、20世紀の東南アジアの農民に関する研究、北米の奴隷と奴隷制度、インドの不可触民に関する研究、さらには、上に述べたような刑務所の受刑者に関する研究は、このテーゼを支持するかもしれない(スコット1990: 79)。ここに見られるように、これらの人々は、制度を阻害するだけでなく、自分たちの必要性に応じて制度を活用することも知っていたのである。フランソワ・ルイ・ガンショフが『封建制』(1964)のなかで述べた封建制の相互概念、植民地時代にイスパノ・アメリカの先住民が共同体証書に対して行った巧妙な操作、財産の私有化と清算を防ぐこと(スミス 1991: 124-125、フロレスカーノ 1994: 119-120、ヴァンコット 2000: 14, n. 3)、刑務所の行動様式などである。3); 刑務所収容者の行動様式(Scott 1990 : 82-85); ナチの強制収容所の囚人の生存技術(「起立」あるいは「精神的抵抗」として知られる); 全体主義、独裁、テロ勢力がその領域における実存的生活欲望を制圧する途方もない力(ナチ・ドイツ、共産ロシア、共産中国、共産北朝鮮、イスラム教イラン等。このことは、ハベルが言うように、真実に生きたいという欲望が、歴史を通じて、あらゆる権力に挑戦してきた、途方もなく、妥協のない強さを持っていることを端的に示している。

弱者はその記録を隠し、痕跡を残さないようにするため、調査が追跡しにくくなるのである(Scott 1990: 17-28, 33-36)。高度に洗練された方法が、効果的な研究に対するもうひとつの障壁となっている。ソビエトの集団農場の農民が、自分たちの私有地を没収されたとして嫌っていた政府との直接対決を、女性を集団農場の表舞台に立たせることで回避したり、自宅周辺の1エーカーにも満たないごくわずかな土地を繁栄させたりして、1960年の農業総生産高の3分の1以上を生産していたと誰が想像できるだろう(Nove 1982)。このカテゴリーには、安全弁としてのカーニバルの本質に関するあらゆる誤解(スコットが示すように、カーニバルはそうではない)と、変装と隠蔽の技術について学界が持つわずかな知識も加えることができる。
ヴァーツラフ・ハヴェルは、社会学的なアプローチによって、これらのいずれをも見抜くことができなかったのである。それが、彼が人間の本質を厳しく裁いた理由である。カミュもまた、彼の保守的な分析的アプローチによって、それを見ることができなかった。ハベルもカミュも、八百屋の本当の審議や彼が展開した隠された記録のように、顕在化した現実の下に敷かれた政治的な内層を見ることができなかったのである。また、彼らが知る全体主義体制や後の「ポスト全体主義」体制に与える影響も、もちろん推し量ることができなかった。
彼らが知っている体制に与える影響を推し量ることもできなかった。たとえば、八百屋がスローガンをわずかに片側にずらしているのを、彼らは見ることができなかった。例えば、その角を左側に折って、同じ思いを抱くすべての人(おそらく通りすがりの会社の女性にも)に、自分が体制についてどう考えているか、その重荷にどう反応すべきかを示すのである。カミュもハベルも、八百屋がそのスローガンをどこに置いたのか、甘いニンジンに置いたのか(連帯の印か)、それとも酸っぱいタマネギに置いたのか(不支持の印か)、見ることができなかった。ハベルには、八百屋がそのスローガンをどのように解釈したのかが分からなかった。例えば、彼はスローガンを前にして次のように言ったのだろうか。「ほら、この惨めな政権め、おまえが私に何を求めているか、そしてそれが手に入ることは分かっている。しかし、このスローガンと私があなた方に抱いている感情との間に何らかの関係があると思うなら、それは間違いだ。私はあなたを軽蔑している。1948年5月のクーデターを私は決して忘れない。エドワード・ベネスが洗脳され、数ヵ月後に失恋で死んだことも忘れない。お前とお前のスローガンと決別することはできないが、軽蔑と嫌悪と抗議のために掲げているのだ」これが、八百屋がスローガンを前にして発した内心の台詞だと考えるには、それなりの理由がある。もし、ハベルがスコッツの知見に触れて今日のことを知ったなら、八百屋に対してもっと寛容になれただろうか。カミュは、八百屋の内なる対話と、嘘の中で真実を生きるために彼が行っていた、よく隠された、しかし創造的な小さな行為のレパートリーを知っていたら、彼の反乱論にそれほど厳しい態度を取らなかっただろうか。
批評家
あらゆる政治体制は、高度に歪んだ極端なものであっても、それを信じ、その冒険が奇怪であろうと非人道的であろうと、それに従う者を生み出す。クリストファー・ロバート・ブラウニングが研究し、彼の著書『普通の男たち』を通じて私たちの知るところとなった、1942年から1944年にかけてルブリン地方で活動した教導警察101部隊の事例を検証してみよう。予備警察101大隊』(1992)で知られるようになった。大隊が遂行するよう命じられた罪のないユダヤ人の殺害と国外追放に立ち会うことに反対したため、どんな犠牲を払ってでも隊列を乱した。12 人の将校をどう定義すべきか(Browning 2013 [1992]: 57)?大隊の殺人的任務に反対しながらも、大隊長ヴィルヘルム・トラップから出された戦線離脱の申し出が危険であることを疑って、戦線の狭間で(隠れる、見て見ぬふり、無目的あるいは意図しない銃撃、ユダヤ人を無視する、ユダヤ人に逃げたり隠れるよう促す、銃撃を避けるなど)それに抵抗することにした他の100名ほどの将校をどう定義すればいいのか?(ブラウニング:127-131,159)そして、忠実かつ粘り強く任務を遂行した残りの400人の将校をどう定義すればよいのだろうか。その400人の将校と、84,000人のユダヤ人を殺害し、強制送還して死なせた100人の血気盛んな同僚たち(Browning: 225-227)とは、どのようなものなのだろうか。このような状況下で、12 人、100 人、400 人という区別を維持することは不可能であり、「人間性」や権力者との複雑な人間関係に関して何らかの洞察を得ようとする危険性はないのだろうか。

それどころか、グンター・グラスがその著書『玉ねぎの皮をむく』(2006)のなかで紹介している、10代でヒトラーユーゲントに参加したときの軍への熱意と、部隊の少年の妥協しない姿勢(「この例外は、金髪で青い目の小柄な少年で… 彼はジークフリートだった」[グラス2007. 83-86])をどう理解すればいいのだろう。という理由で武器を持つことさえ嫌がった(草 2007: 83-86)。彼が受けた屈辱、叱責、殴打は、その数だけあったのだろうか。101大隊の400名の殺人者のうち、熱狂的なユダヤ人ハンターとなり、どんな残虐な非公式任務にも対応できるようになった者の行動をどう理解したらよいのだろうか。あるいは、ハンス・ファラダの『Alone In Berlin』に登場するオットー・クアンゲルが自ら引き受けた特異な任務-ベルリンでひそかに配布した小さな絵葉書によって、そのようなことは何もせず、ただ家の中に座って絶え間ない爆撃に苦しんでいた大勢の市民を前にナチス政権を非難した-にどう関わるべきか? (Fallada 2010).

闇の政権の中で、自分たちの真実のためにどんな代償も払うことをいとわなかった反体制派をどう定義すればいいのだろうか。彼らは本当に勇敢で、勇気ある人たちなのだろうか。鼻の下で体制に反対する活動をしていた人たち-ジラスやクラインバーグの100万人の破壊者たちや、集団化に反対しながら妻の後ろに隠れていたロシアの農民たちよりも確実に。また、第二次世界大戦中にオランダで私の両親を救った人々のような、「神が私たちに命じた」と主張する「諸国民の中の正義の人々」をどう定義すればよいのだろうか。そして、私の両親の救い主がしたようにすることを恐れたすべての人々に、どのような定義を与えることができるだろうか。勇者と臆病者を区別するために、この単純な推論以上のものが必要なのだろうか。社会学が、抑圧的な体制に対して立ち上がった少数の勇者と、ひげでつぶやき、あるいは抑圧に協力した多くの臆病者との間で行う区分は、それほど間違っているのだろうか。
ここでもう一つの難問を提起する。仮に、インフラポリティクスが機能し、時間とともに望ましい結果をもたらすと仮定しても、あからさまな(「勇敢な」)行動の回避は、大きな大衆の苦しみを長引かせないのだろうか?時間にも重みがないのだろうか?強者の武器はどうだろう?結局のところ、強者は弱者の武器を無力化し、その政治的活動を容易に無効化する独自の手段を持っている。では、弱者の効力とはどのようなものなのだろうか?さらに、人類学はこの秘密の裏社会に入り込み、弱者の武器の壮大な特質に対する確かな視線で私たちをサポートすることが本当にできるのだろうか。私たちは実は、西洋人類学の独善主義によるある種の「知的犠牲者」であり、その相対主義的アプローチをここに反響させ、それについて何か面白いことを言うことができると私たちを納得させることに満足しているのではないだろうか?確かに、弱者は現実を神秘化しないのだろうか。もしそうでないなら、なぜ彼らは自分たちを傷つける指導者を支持するのだろうか?多くのドイツ人が、ヒトラーが引き起こした残虐な大惨事(自国民も含む)を無視して、ヒトラーを好きだったのではないのか?多くのイタリア人、ロシア人、中国人、カンボジア人がそれぞれムッソリーニ、スターリン、毛沢東、ポルポト、そして彼らのような恐ろしい独裁者に、完全な正当性を与えつつ従ったのではなかったか?ミルグラムの実験で人を殺せと命じた形而上学的権威を心から採用した学生たちの意思決定をどう説明すればいいのだろうか。これは結局、ハベルの言うとおりには働き、スコットの言うとおりには働かない具体的な社会的・政治的現実を、学問的に神秘化したものではないのか。

スコットの立場に対するもう一つの批判は、デレク・セイヤーによって発せられたものである。セイヤーは、アントニオ・グラムシから知られる従来の視点とはまったく異なる視点から覇権主義的な物語にアプローチしている。彼は、権力の目的は、グラムシが信じていたように、同意を得ることでも、信念やイデオロギーを植え付けることでもない、と言う。国家はそれが得られないことを知っている。したがって、その主な関心事は何か別のもの–まったく深く、広範で、はるかに冷笑的で、欺瞞的で、陰湿なものである。それは、一人ひとりに厳密に理解され、「社会性の物質的形態」(Sayer 1995: 373-375)を何度も何度も構成している、誤った儀式に市民が公的に参画することである。これは、偽りのイメージ(たとえば「世界の労働者は団結せよ!」のようなもの)や、体制が自らのために必要とする他の多くのよく知られた偽りの「真実」に対処するために必要な精神を装填する礼拝である。これは、加害者から精神的なエネルギーをすべて抜き取り、意識はしっかりしているが、政権のなすがままにまったく無力な状態にする、よくある崇拝の仕方である。その時点で、まさにハベルが八百屋の話で描いたような瞬間、人々は思想やシステムとしての国家の精神的・物質的部品(実際には予備部品)となり、同時にその過程で国家を正統化し、構成することになるとセイヤーは言う。

国家は、一般に考えられているよりもはるかに重要な存在であるとセイヤーは言う。公共圏だけでなく、私的な存在圏をも支配し統制し、あらゆる私的活動の境界を決定しているのだ。それは、法律(教育、健康、仕事、給与に関する法律)、手続き(職業、雇用、ビジネス、金融、交通、住宅などの免許取得のためのあらゆるメカニズム)、権限(時間の管理-昼夜の時刻表や国家カレンダーを含む-国家緊急事態システム、天然資源、原材料、エネルギーの管理)によって行われ、個人の生活と課題の隅々にまで入り込んでいる。そのように生きていると、個人が抵抗力を刺激する原因と手段の両方を持つことができなくなる(Sayer: 375)。しかし、住民にとっては、これらの枠組みに固執する以外に選択肢がなく、ましてや、要求される公的なパフォーマンスなど皆無である。このように、国家権力は個人を制限するだけでなく、個人を力づけ、その地平を切り開く。国家から託されたカードを巧みに使いこなす者は、成功し、前進し、そうすることで政権に感謝し、その結果、寛容になるだろう。しかし、そこにはハニートラップもある。このような状況では、個人と国家の区別はなくなり、両者は一体となる。
この冷笑的な国家は、しかし同時に有益であり、市民を物質としても思想としても吸収してしまう。それゆえ、スコットの理論の起源であり、その合理化の源泉である市民社会と国家の区別は、セイヤーによって、あまりに人工的で非現実的であることが判明し、この理論を根底から覆すことになる。この意味で、「臣民の中に生き、臣民を通して生きる」国家に直面し、いかなる思想的な取り込みも必要とせず、ただ「実行的取り込み」しか必要としない八百屋が、このスローガンを掲げることは明らかである。なぜなら、ハベルをプラハ城に導いたのは、セイヤーによれば、多かれ少なかれ組織的なレジスタンス運動でも反体制運動でもなく、「ミハイル・ゴルバチョフによるブレジネフ・ドクトリンの否定」、別の言葉で言えば、ソ連体制自体の内なる自発的変化である(Sayer: 376)。
結論
セイヤーの概念を採用するならば、歴史的変化は、私たちがナイーブに考えていたように、下からではなく、上からの圧力によって起こることを認めなければならない。圧力とは、構成されたブラフに住む支配者たちに、彼らが深く口にしなかったこと、あるいは沈黙していたことを安全に言うためのシグナルを与えるものである。この歴史学的アプローチは、アレクシス・ド・トクヴィルの『アンシャン・レジームと革命』(1856)からよく知られている。彼は、フランス革命の成功について、まさに絶対主義が十分に軟化し、ヨーロッパでこの種のものとしては最も軟弱な体制になったという説明を提供している。このアプローチを採用するならば、革命と反革命を含むすべての大きな歴史的変化は、内部から弱体化した体制、すなわち活力を失った体制から生まれ、したがって暗に何らかの変化を示唆していることを認めざるを得ない。そして、これらのすべてが非常に強力で、社会にうまく入り込んでいたため、ちょっとした弱さのニュアンスが、底辺に眠っていた抵抗勢力-ハベルの反体制運動やスコットの地下民衆勢力(その中には八百屋や民衆もいる)-を解放するのに十分で、その力が最終的に体制全体を転覆させたのである。

しかし、ここではさらに難しく、トクヴィルやセイヤーが語った弱点はどこから生じたのかを問わねばならない、そしてその弱点はどこから生じたのか、このような強靭で硬直した政治システムの内なる崩壊はどのようにして生じたのか。この弱点が、まさに底辺の民衆活動によってはびこったということは考えられないのだろうか。決して疲れることなく、終わることなく、ゆっくりと、しかし執拗にそれらの体制を衰弱させ、その内部の亀裂を明らかにする、侵食的圧力がそれを公然と出現させるのを待ち続けている、粉砕圧力によって?ルイ16世は、175年間、条約もなく、二等身の三等身もない幸せな王室生活を送った後、カノッサ(1789年のエステート総会)を開いたのは、単に絶対王政に嫌気がさして立憲主義を支持したからだろうか?それとも、財政・司法・議会の危機が、三等国民が全く現れない、あるいは独自の議会を必要とする、あるいは納税を避けるようにならないように、議会を招集して妥協せざるを得なかったということなのだろうか?長年、嫌われ者の領主であった貴族たちは、封建時代は終わり、三流との妥協が必要だと理解していたのではないのか?国王が弱者の武器を使って、第三身分の代表者600人の要求を受け入れて、頑固な貴族を弱めようとしたのではないだろうか?
ソ連が崩壊したのは、ゴルバチョフが突然民主主義を信じ、自らが率いるソ連帝国の解体を決意したからか、あるいはジラスの指摘するように、労働者のどこかで始まった経済的圧力に照らして帝国の経営が不可能になったからなのだろうか。(ゴルバチョフがグラスノスチ(開放)を宣言したのは、不満を持っていた共和国(主にハンガリーやリトアニア)、労働組合、ロシアやその衛星国の政府系商店で食料を探すために毎日延々と並んでいる一般市民,政権による緊縮財政に疲れた人々(例えば、ソ連やルーマニアなどの隣接共和国で)からの強い圧力を受けていなかった場合だったのか?) (ゴルバチョフは、成長するソビエト社会が西側に大きくさらされ、アフガニスタンで挫折し、米国との高価な宇宙開発競争、「ソビエト国民生活の状況の隠喩」とみなされるチェルノブイリの衝撃的な災害がなければ、ペレストロイカ(構造改革)に向かっていたのだろうか(サービス 2009: 438, 456-457)?(サービス: 446)? アパルトヘイトに対する国連安全保障理事会の決定(1985年7月のS.C.決議569)、米国議会の対南ア強制制裁、そして、隔離にもかかわらず工業都市における黒人の漸進的拡大を伴う重い国際圧力、あるいは南ア全土とその外部における数万のANCメンバーの長期にわたる有効な日々の抗議行動が、1980年代後半の南アの公式見解を変えたのではないだろうか? (Clark and Worger 2004: 94-95; Eades 1999: 88-96; Nanda 1991: 8-16; Gutteridge 1995: 123- 144).

私たちの予言的解釈は、下から来た圧力から注意をそらすことを許さない。それどころか、私たちはそれらの圧力を優先させる傾向がある。「勇者」の重要性については疑う余地がない。しかし、私たちは、自分たちの真実のために危険を冒し、苦しみ、しばしば自らの命を犠牲にしたこれらの人々が、ここに述べたような規模の変化を促すことはできなかったことを理解することが重要であると考えている。何百万人もの普通の弱者が、弱者の武器を使い、抑圧的なシステムを変えるか崩壊させるまで、そのシステムを斜めに切り裂いたのである。何百万人もの人々が、前述のように、政治の限界を乗り越え、ハベルに従ったのである。
国家がいかに皮肉で押しつけがましくても、いかに機知に富んでいても、確立された伝統、規範、取り決め、イデオロギーがいかに強固であっても、それらと市民の間に本質的な不一致が現れた瞬間、あるいはBarrington Moore Jr.の定義では、国家と国家機関と市民の間の明白な「社会契約」への違反が、彼の『不正』で述べられているように、現れるのであろうか?「従順と反乱の社会的基盤』は、国家は下からの全面的な抵抗の波にさらされ、その予防措置は困難で暴力的であるかもしれない (Moore 1978: 3-48, 81-83)」とある。最終的に体制の運命を決定するのは、反体制派の活動(彼らは模範となり模範を示すかもしれないが)ではなく、大衆を弱体化させるこの波である。彼らの組織的な非協調とうまく隠された記録は、追跡と防止が難しく、いかなる体制もうまく対処することができないため、生き残ろうとするなら(時には根本的に)変えなければならないのだ。この立場を採用することで、私たちは再び、弱者の武器と背後に立つ真正意識の原理の有効性を確認することができ、破壊的大衆に正確な現実テストを提供することができる。このテストは、婉曲主義を苦にせず、欺瞞、隠蔽、神秘化による推論に対処し、市民社会を真理の中の高潔な生活へと導く適切な道具を備えているのだ。
