コンテンツ
denisrancourt.substack.com/p/towards-a-rational-legal-philosophy
Towards a Rational Legal Philosophy of Individual Rights
2023/11/12
これは、必然的に社会的な支配階層となる最適な民主主義において、個人の権利がどのように定義されるべきかについての深いエッセイである。私はこの 分析を『Dissident Voice 2016年11月15日に 』に初めて発表 した。
複雑で読みやすくはないが、基礎的な内容だと思う。
by Denis Rancourt / 2016年11月15日
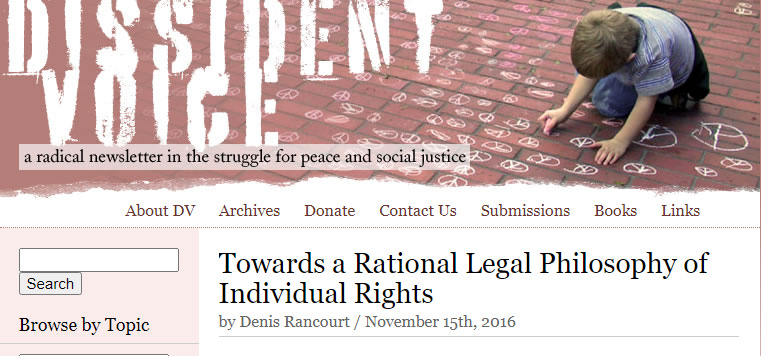
要旨
個人の人権の 人類学的起源と近年の法的具体化について簡単に述べる。 現代の「民主的」国家は、(1)社会的な支配階層を維持・強制するために当該権利を侵害し、(2)反乱を誘発しないように不均衡な侵害を防止する、という両者によって個人の権利を調整していることを示す。
裁判所はこれらの任務を負っているが、抑圧的な国家を代表しているように見えてはならない。裁判所の現実的な解決策は、「相反する権利のバランスをとる」という法律的な巧みさを発展させることであり、そこでは裁判所は、そのような執行者ではなく、「司法へのアクセス」を提供する中立的な仲裁者として自らを示す。
私は、思想・表現・移動の自由と公正な裁判を受ける権利という人権に関わるいくつかの例を挙げる。犯罪(あるいは犯罪や民事責任)である危害をもたらすある行為が、犯罪を構成する要素、あるいは裁判や判決では争われない人権的自由である要素に区分される。
自由を制限する権利
文明化以前の単純で小規模な社会では、人は文化的に受け入れられている「権利」を持っている。容認された規範を超えた違反は罰せられるか、さもなければ是正される。したがって、そのような状況では「個人の権利」や「人権の権利」は存在しない。
単純な小規模社会は内部の結束が固いが、歴史的に見れば、そのような文明化以前の社会は部族間の暴力的な抗争に頻繁にさらされており、文明化後の大規模社会では致命的な危害のリスクが比較的小さいのに比べ、個人にとっては大規模な身体的不安の源であった。((Keith Windschuttle, “Enduring myth of ‘noble savage’ vs. a species at continuous war?”, The Washington Times, 2003-08-16, reviewing:Lawrence Keely, “War Before Civilization“, 1996, Oxford University Press.))文明化後の大規模な社会は、個人にとっての戦争リスクが劇的に減少するという長所と、制度化された構造が個人の行動や団体を規制するという短所がある。
個人が本質的に有する権利という概念は、階層的秩序と階級構造を維持するための制度を採用した、文明以後の大きな社会で生まれた。例えば、国家市民には、社会的支配階層の濫用に対する法的な(法律による)手続き上の保護が与えられている。同様に、グローバル化した地球上の個人は 、世界人権宣言(1948年)や 市民的及び政治的権利に関する国際規約 (ICCPR )など、さまざまな国際文書によって「人権」を与えられて いる。 戦争そのものも 、1948年のジュネーブ条約やその 追加議定書によって、 野蛮でないように規制されて いる。
その応用として、「個人の権利」は、個人を統制し、個人に対する制度的虐待を防ぐために使われる制度的手段であり、人類という種にとって非常に有益なポスト文明社会の階級階層構造を安定させ、保護するためのものである。
そのため、個人の自治が確立されたヒエラルキーを脅かしかねず、また制度的濫用が反乱を助長しかねないようなあらゆる状況において、当該制度は、その実際の機能に合致した形で設計され、適用されなければならない。これは、確立された推奨慣行(「原則」と呼ばれる)に従った、法律制定者(国会議員)と法廷・裁判所の決定者(裁判官と仲裁人)の仕事である。
ここでいう「悪い法律」とは、例えば、階層が危険にさらされていないにもかかわらず、不必要に個人の自由を侵害する法律や、圧倒的な恨みを生む法律、階層を安定させるような方法で組織化し調整する個人の能力を制限する法律などである。
「良い法律」とは、個人に対する暴力を最小限に抑えつつ、捕食的な階級の利益に対して許容される個人の自由のバランスをとることによって、ヒエラルキーの安定性を最大化するものである。社会階層全体を弱体化させる一方で、影響力のある集団や支配的な階級を有利にする社会病理学的な法律を作るための影響力の売り込みである。
このような「法学」はすべて実践の中で生み出される必要があるため、適用の「原則」が最適化されなかったり、逆説的な矛盾を含んでしまったりする可能性がある。私は、「人権」とみなされる個人の権利がそのようなケースに当てはまることを主張し、解決策を提示する。思想の自由と表現の自由という基本的人権で説明する。
思想、信条、意見の自由
思想の自由や信条の自由とは、どんな思想や信条を持とうとも、また持ちたいと望もうとも、それを持つ権利のことである。文明開化以後の歴史の大部分を通じて、特定の考えや信念は、たとえ明白に 表明されていなくても、罪や犯罪と見なされてきた。支配者たちは、確立された秩序や包括的なヒエラルキーを脅かすと判断 された思考や信念を探し出し、罰したり粛清したりした。
現代西洋社会では、「思想犯罪」はほとんど嫌われており、思想は表現されたり行動されたりした場合にのみ脅威となりうるということがほとんど認識されている。この認識は国際法にも明記されており、国際人権規約(ICCPR)の法理論では、思想・信条(意見)の自由は個人の絶対的権利であり、いかなる場合にも国家行為者によって侵害されることはないと明確かつ明確に決められている。(市民的及び政治的権利に関する国際規約第19条第1項、及び一般的意見第34号、 市民的及び政治的権利に関する国際規約、人権委員会、第102会期、CCPR/C/GC/34、第5項、第9項、第10項)。特に、自分の思想や信条を開示することを強制することはできない。これは、刑事被告人が証言しない、あるいは自らを罪に陥れないという絶対的権利を有することと関連している。
国際法の明確な文言は次のとおりである((一般的意見第34号、 市民的及び政治的権利に関する国際規約、人権委員会、第102会期、CCPR/C/GC/34、パラグラフ9)):
第19条第1項は、干渉されることなく意見を持つ権利の保護を要求している。 これは、規約がいかなる例外も制限も認めない権利である。 意見の自由は、いつでも、いかなる理由であれ、人が自由に選択することができる意見を変更する権利に及ぶ。何人も、その実際の意見、認識される意見又は推定される意見に基づいて、この規約に基づくいかなる権利の減損も受けることはできない。あらゆる形態の意見は、政治的、科学的、歴史的、道徳的又は宗教的性質の意見を含め、保護される。意見を有することを犯罪とすることは、第1項と両立しない。意見を理由として逮捕、抑留、裁判または投獄されることを含む、人に対する嫌がらせ、脅迫または汚名着せは、第19条第1項の違反となる(参照番号は削除、強調は追加)。
多くの州憲法に同等の記述や暗黙の規定があり、すべての署名州はこの権利に合致した法律を制定することが義務付けられている。
自由な思想の絶対的権利の実施に必要な一貫性
しかし、実際には、この明白に絶対的な権利でさえ、量刑を決定する要素として「動機」を推論する刑事法の慣行と対立している。このように、計画的であったと判断される故意の殺人は、その場の状況で判断される故意の殺人よりも重く処罰され、その結果、意図的でなかったと判断される殺人よりも重く処罰される。同様に、政治的動機による犯罪(「テロリズム」)は、「単なる犯罪」よりもはるかに厳しく裁かれる。
このように、思想の自由に対する権利と、量刑を決定する際に証拠から思想を推論するという国家の慣行との間には、明らかな矛盾がある。さらに、推論された否定的な思考に関する(そしてそれを支持するために使用される証拠に関する)法廷での議論が、物理的犯罪そのものの有罪に関して被告人に不利な裁判環境を作り出すという重大な問題もある。敵対制度の法文化は、この根本的な問題を解決するものではなく、メディアの報道によってさらに深刻化している。
解決策としては、物理的犯罪(器物損壊や身体的危害など)と被告人の思考や動機を切り離し、法廷では思考や動機の関連性を認めないことである。これにより、国家は思考を推論する業務から解放され、知ることのできる真実を発見するシステムの能力が向上する。これにより、システムは物理的現実に忠実となり、予期せぬ社会的悪影響が少なくなり、実務が発展し社会的な誤った方向性が経験されるにつれて「制御不能」に陥る可能性が少なくなる。また、感情的なイメージに基づく群衆の反応を求めるという、メディアの病的な慣行を甘やかすことも、手続き上防げるだろう。
このように、思想・信条(意見)の自由という明示的に絶対的な権利(表現の自由と混同してはならない)は、国家によって処罰される犯罪や犯罪、あるいは損害賠償を求める民事事件において、思想の構成要素を認めないことによって維持されていることがわかる。
この解決策は、争われる出来事(例えば殺人)には、区分できる別々の構成要素や要素があり、国家はそのうちの1つにのみ関与できることを認めることによって達成された。すなわち、人を死に至らしめた物理的な行為は1つの区画に、当該行為を行ったとされる被告人の心の中にある考え、信念、または動機は、別個の別個の概念的な区画に分類される。国家の対応は、物理的行為に関する賠償、予防、抑止のみに関わる。被疑者の心を変えることを目的とし、予防や抑止の価値を実証していない刑罰要素は、思想・信条の自由の絶対的権利を認める国家の法体系にはふさわしくない。
以下の例では、「競合する権利」とされる複雑な法的状況が、受容された基本的権利を惹起すると同時に、犯罪、犯罪行為、民事責任を構成する損害の原因となる行為や事象の分析において、概念的な区分化を適用することによって、いかに合理的なものになりうるかを例証している。
コンパートメント化の応用
混雑した映画館で「火事だ」と叫ぶことはできないという典型的な例を考えてみよう。表現の自由という権利は、その表現によって引き起こされる危害が予測される、あるいは危害の危険性が高いということと同様に、その表現が大混乱の反応を引き起こす可能性が高いという状況に関与している。この例の古典的な扱いは、「ある人の自由は、他の人の自由が始まるところで終わる」というもので、「相反する権利」の法理を捉えた言葉である。
「法律学」というと学術的に聞こえるが、実はこの考え方の起源は19世紀のアメリカの禁酒法活動家にある。特に、1887年のアトランタの新聞は、禁酒法を支持する演説を次のように引用している((Quote Investigator, “Your Liberty To Swing Your Fist Ends Just Where My Nose Begins“, 2011-10-15, accessed on 2016-11-12)):
禁酒法反対派がこのキャンペーンで主張している、酒場を開放し続けるための唯一の有力な論拠は、個人の自由である。ある偉人は、「腕を振るう個人の自由は、私の鼻が始まるところで終わる」と言った。ウイスキーを飲み、酒場を支援する個人の自由は、家族や地域社会の権利が始まるところで終わる。
この問題は、「競合する権利」に言及することなく、以下のように解決できる。混雑した映画館で「火事だ」と叫ぶことには、2つの分離した区画がある:ひとつは、言葉の選択と言葉の伝え方の完全な質(声の大きさ、トーン、感情表現、ジェスチャーなど)を含む表現であり、もうひとつは、重大な身体的危害や死亡の危険性が高く、予測可能で差し迫った物理的状況において、その表現を選択した犯罪である。
当該犯罪とは、危害や死亡の危険性を著しく高めたり、実際に引き起こしたりした罪である。このように区分することで、表現の自由という権利は問題とならず、他人が暴行を受けない権利(安全性)と衝突することもなく、それ自体を制限する必要もない(例えば、映画館などで「火事」という言葉を口にすることを禁じたり、有罪判決を受けた者が二度と「火事」という言葉を使わないように箝口令を敷いたりする)。国家は、害をもたらすために選択された方法とは無関係に、被告人が引き起こした害を罪に問う。銃やナイフや毒物やブービートラップによる殺人も、いかなる行為の予測可能な結果による殺人も、常に同じ結果による殺人である。殺人を犯すことによって侵害される生命に対する権利は、銃を携帯する権利、ナイフを所有する権利、殺鼠剤を買う権利、ブービートラップを試す権利、言葉を叫ぶ権利などとはまったく関係がない。
同様に、拳を振り回す犯罪は、他人を殴るという犯罪とは区別して、体を動かす自由と区分することができる。故意と不注意はどちらも同じ鼻血を出す可能性があり、身体運動の自由はどちらにも関係しない。身体を動かす権利が、暴行を受けない権利(安全)と「衝突する」と仮定することに合理的な利点はない。身体運動の権利自体は、国家が暴行容疑に対処することによって侵害されることはなく、犯罪の法的分析とは無関係である。
表現の自由という権利は、このような誤った「対立」の例をさらにいくつも生み出す:
(1) 雇用主が従業員を解雇した後、その従業員について虚偽の否定的発言を他の雇用主に行った場合。虚偽の否定的発言をすることに雇用主の表現の自由は関係ない。解雇後の犯罪は、使用者の権力と影響力の状況において、元従業員に予測可能な重大な損害(経済的・個人的な苦難)を与えることである。表現の自由という概念は法的分析に入る必要はなく、裁判所も考慮すべきではない。同様に、使用者の「特権」の保護もあってはならない。犯罪は起きたか起きなかったかのどちらかであり、事実の発見が法律主義的な秘密の覆いによって妨げられるべきではない。
(2) 陸軍大将が小隊に命じて、民間人の村全体を壊滅させる。将軍の表現の自由という人権は問題にならない。犯罪は、将軍の命令の予測可能な結果である戦争犯罪である。
(3)出版社が、全裸の画像や、人間や他の動物などとの露骨な性行為の画像など、ポルノを印刷したり掲載したりする。表現の自由は表現の自由である。合理的に対処可能な犯罪は、特定の個人(被害者)に対する予測可能で、現実的で、実証された危害に基づいていなければならない。広範で非特異的な地域社会の規範やモラルは、露骨な性表現を封じるために合法的に使用することはできない。しかし、暴露による子どもへの害などという根拠のある、あるいは根拠のない議論を用いて、そのような犯罪を認めることは、単に当該新たな犯罪を法的検討のための関連区画として定義するだけである。そのため、その疑わしい運動の中では、表現の自由は問題とされず、「相反する権利」を提起するメリットはない。(性的自由と猥褻の分野における歪んだ法理学の概観については、以下を参照のこと:Edward de Grazia, “Girls Lean Back Everywhere:The Law of Obscenity and the Assault on Genius“, 1992, Constable, London, ISBN 0 09 470950 5; Alan N. Young, “Justice Defiled:Alan N. Young, “Justice Defiled:Perverts, Potheads, Serial Killers & Lawyers“, 2003, Key Porter Books, ISBN 1 55263 225 3).
(4)パンフレット作成者が、特定または自認できる集団を攻撃するとされる内容(ゲイバッシング、ホロコースト否定など)を公表する。ここでもまた、合理的で区分された法的分析は、実証されていない直接的または間接的な「危害」が広く集団に及ぶという、新たな被害者なき無血犯罪の定義に焦点を当てなければならない。間接的なルートでは、通常、非難される表現が、広範な社会における不特定の個人から、当該集団が「憎悪にさらされる」原因となる。この独創的で自明でない法的課題が達成されれば、表現の自由の権利は問題とならない。唯一の法的判断は、法令またはコモンローで定義された当該新たな犯罪が、被告人によって実際に行われ、被害が証明されたか否かである。表現の自由や「相反する権利」についてのリップサービスは、法的には何の意味もない。
(5) 同様に、児童ポルノの問題は表現の自由の問題ではない。むしろ、児童に対する犯罪的危害の問題であり、児童に対する犯罪的危害の産業に対する支援の問題である。所持に関しては、量刑が正当化されるためには、「産業への支援」と被害児童への実際の被害との間に、重要かつ意味のある関連性がなければならない。これによって、実際の人に重大な被害をもたらすことが証明された産業であれば、消費者の「産業支援」罪への道が開かれることになる。合法・非合法を問わず、そのような産業がないわけではない。にもかかわらず、いったんこのような「犯罪」が定義されれば、基本的人権は存在しないことになる。しかし、「消費者の自由」が新たな意味を持つことは確かである。
“競合する権利 “司法の白紙化
区分に関する私の指摘は周辺的なものではない。人権を扱う最高裁判所の判決は、一貫して「相反する権利」の誤謬に満ちている。例えば((R. v. Crawford, [1995] 1 SCR 858, 1995 CanLII 138 (SCC), paragraphs 33 to 35. (SCC, Supreme Court of Canada)):
競合する憲章上の権利の解決
33 個人の保護される権利の対立によって生じる問題に対する適切なアプローチについては 、ダゲネー裁判長(前掲)が概説して いる。 同裁判長は、あると強調した後 憲章の 権利は同等の価値が 、 877 ページで次の ように続けた: 出版禁止の場合に起こりうるように、2つの個人の保護される権利が対立する場合、 憲章の 原則は、両方の権利の重要性を十分に尊重するバランスを達成することを要求する。
34 憲章の 権利は、文脈に関係なくその全容を適用することができないという意味で絶対的な ものではないことを 、ここまで述べてきた。憲章の 価値を 適用する際には 、 他の利益、特に 他の 憲章の 無制限かつ文字通りの権利行使と対立する可能性のある 価値を 考慮しなければならない 。憲章の 価値に対する このアプローチは 、 対立する権利が 憲章の 同じ条項の下で保護されているという点で、本件において特に適切で ある。
35 以上のことを本分析の冒頭で提起された問題に当てはめると、3つの解決策のうち適切なものを選択す ることは容易に明らかである。 第一の選択肢は、黙秘権が完全な答弁と防御の権利に優先することを認めるものである。 この場合、一方の権利を完全 に適用し、もう一方の同等の権利を完全に無視することになる。 同様に、第二の選択肢は、完全な答弁と防御の権利が黙秘権に優先することを認めるも のである。この場合も また、点で、前掲のダゲネで一方の権利を絶対的に適用し、もう一方の同等の権利を犠牲にするという 承認されたアプローチに反する 。 両者のバランスをとる第3の解決策が正しいアプローチである。 あとは 、憲章の これらの権利を支える価値を最大限に尊重するために、2つの権利をどのように調整 するかである。
実際、後者のケースは、公判前黙秘という刑事被告人の人権侵害を国家が支持した真っ当なものである。使用された「権利の均衡」アプローチは、公判前の黙秘が有罪や信用性の証拠となることを認めるという国家の違反を容認するための口実に過ぎなかった。マクラクリン判事の反対意見は、怪しげな「均衡」には関与していない(判決のパラグラフ43参照)。
他方、裁判所が、その「司法を運営する権利」(訴訟当事者が司法にアクセスする権利という枠組みで表現されている)が、ピケ・ラインという形で、政府の裁判所そのものに対する市民の「抗議する権利」によって争われるのを見たとき、「権利の均衡」という建前はいくぶん溶けてしまい、同裁判所は、次のように説明して差止命令を支持した((B.C.G.E.U. v. British Columbia (Attorney General), [1988] 2 SCR 214, 1988 CanLII 3 (SCC), at paragraph 71)):
71 ……憲章は 確かに、相反する権利のダイナミズムの中で自滅することはない 。Morris対Crown Office 事件におけるSalmon L.J.の発言 (1086?87頁)は、確立された憲法上の権利に言及したものではないが、やはり適切で ある。控訴人らは、抗議行動を起こし、スローガンを叫び、パンフレットを撒き散らすことによって、当事者ではない裁判を妨害したとして侮辱罪に問わ れた。 この権利を取り上げれば、言論の自由は他のすべての自由とともに枯れ果ててしまうだろう。控訴人たちは、その善し悪しにかかわらず、自分たちには不満があると考えている。彼らは間違いなくそれについて抗議する権利があるが、彼らが選んだやり方ではないことは確かである。自分たちの大義名分を世間に知らしめるために、裁判所の業務を妨害し、正義の正当な執行のために誰もが持っている権利を軽蔑的に踏みにじることを選択し、そのために彼らは非常に適切に処罰された。(強調は原文ママ)。
このように、裁判所は「相反する権利」を放棄し、「絶対的権利」の例として、複雑な調整によってバランスをとる必要のない、稀有な法的宝石のひとつを「発見」したのである。この事実上絶対的な権利は、人権ではない。むしろ、国家が抗議や混乱なしに絶対的に活動する「権利」である。真の人権とは、公正な裁判を受ける個人の権利である。これは、裁判所が、どのような手続きであれ、そのプロセスへの国民の参加を妨害する場合に直接問題となる、開かれた法廷の原則の基礎となるものである。
「権利」をめぐる司法のバラードは、このように実に複雑である。個人の人権に関わる実務では、正当化されると主張される偽りの妥協に訴えることで、国家の侵害を平滑化することを意図した詭弁が大部分を占める。通常、この「均衡」は、個人の真の人権と、個人の人権を侵害する国家の主張する「権利」とを対立させ、その一方で、国家の「権利」を、他の個人の異なる人権や認められた権利から直接生じる、あるいは派生するものとしている。
カナダでは 、、いわゆる Dagenais/Mentuck 裁判所命令による出版禁止についてR. v. Mentuck, [2001] 3 SCR 442, 2001 SCC 76 (CanLII), at paragraph 32) テストが確立された権利制限運動となって いる。このテストは、 メディアによる出版(情報へのアクセスがなければ表現が制限されるため、一部は表現の自由という人権に由来する)と公正かつ公開された裁判という相反する権利のバランスをとるものとされているが、後者の考慮事項は、実際には国家裁判の混乱や、陪審員に対する公開情報の影響というあまり理解されていない予測不可能な現象に関するものである。 このテストでは次のように述べられている(():
出版禁止は、以下の場合にのみ命じられるべきである:(a)司法の適正な運営に対する重大な危険を防止するために、合理的な代替措置ではその危険を防止できないため、そのような命令が必要であること。(b)表現の自由、被告人の公正かつ公開の裁判を受ける権利、司法運営の効力に対する影響を含め、出版禁止による有益な効果が、当事者および公衆の権利および利益に対する悪影響を上回ること。
ここで、私が提案している区分けが見られる。実際、(a)の項目が満たされていれば、その決定は完全に下されたことになり、(b)の項目は関係ない。裁判所はすでに、「適正な司法運営」を国家の事実上絶対的な「権利」とみなしている。「必要」という言葉は、裁判官に対して「やりすぎるな」という指示である。一旦裁判官が何が必要であるかを決定してしまえば、それが真の人権であろうとなかろうと、それ以外の「権利」の検討は関係ない。
したがって、上記で検討した「権利の抵触」のすべての状況において、裁判所が個人の真の人権(思想、表現、自由、生命)を制限することを企図している場合、「権利の均衡」に関するリップサービスは、実際には、個人の当該人権を最小限または不均衡に制限するという国家の決定の隠れ蓑に過ぎないことがわかる。「権利の均衡」についての法理は、裁判員が人権侵害を強制される状況にあることを警告し、したがって、裁判所の裁量を「必要な」程度、あるいは現在の社会的「規範」によって容認される程度にのみ適用するよう注意しなければならないという、裁判員への指針にすぎない。
名誉毀損法 ネアンデルタール人の戯言
表現の自由における「相反する権利」という作為が生じるもう一つの類型は、名誉毀損法の広大な分野である。ここで裁判所は、個人の表現の自由という真の人権と、原告の「名誉を保護する権利」との「均衡」を考えている。なぜなら、「評判」とは、不特定多数の人々(訴訟の当事者ではない人々)が原告に対して抱く意見であり、意見形成の心理は未知であり、複雑で、非常に変化しやすいからである。
名誉毀損法は、有害な虚偽の不法行為とは異なり、実際の被害を証明する必要はない。名誉毀損による損害は、十分に攻撃的であると判断された言葉が公表された場合に推定される。実際の損害や特別な損害の証拠が提示されなくても、何百万ドルもの賠償金が支払われることもある。いわゆる一般損害賠償には上限がない。悪意もまた推定され、害意は関係ない。被告が真実を証明する責任を負うため、虚偽性もまた推定される。これがコモンローの名誉毀損という不法行為である。
名誉毀損法は、金持ちや権力者が批評家を黙らせるための究極の手段であり、有害な虚偽の不法行為の要件以外には、原告が被告によって表現されたものを気に入らないという以上の論理的正当性はない。原告が実際の損害、害意、虚偽性を主張する義務を負うことなく、国家が招集し国家が管理する完全な訴訟が被告に提起され、訴訟全体が数値化不可能で数値化する必要のない「評判」という漠然とした領域で展開される。「レピュテーション」は、被告が訴えた表現の因果的結果として低下したことを証明する法的要件すらなく、原告は、出版連鎖のあらゆる人物(著者、編集者、出版社、再販業者、放送局など、あるいは訴えられた言葉を繰り返す者)を排他的に対象とする裁量を有する。何十年も前に発表された可能性のある、訴えられた言葉とまったく同じ言葉を、誰であれ、繰り返し、あるいは再発表することは、法律上責任を問われる新たな名誉毀損事件である。
これは、裁判所が「相反する権利」間の「均衡」運動において、表現の自由という人権と対立することが合理的であると見なす獣である。カナダにおける名誉棄損の慣習法が、国際法、そしてICCPRに従ったカナダの義務に明らかに準拠していないのは当然である。((Denis G. Rancourt, “Canadian defamation law is noncompliant with international law“, report for the Ontario Civil Liberties Association, 2016-02-01.))
名誉毀損法では、私の区分アプローチはそのまま適用される。名誉毀損という犯罪がコモン・ローによって定義されれば、それがいかに作為的で問題のあるものであっても、唯一の問題は「犯罪が行われたか」ということになる。もしそうであり、被告がコモン・ローによって規定された抗弁を立証していなければ、被告は責任を負うことになる。表現の自由という人権は訪れないだけであり、無関係である。限定的で特定された抗弁を詳しく説明することで、当該人権にリップサービスが払われたかもしれないが、それだけである。
つまり、名誉棄損のような民事犯罪を定義し、許される抗弁を調整する用意があるならば、表現の自由に対する権利の行使を物理的な力によって禁止されることはない一方で、訴訟を起こす手段を持つ人々によって、言葉によって罰せられること、そして繰り返し罰せられることを受け入れることになる((Grant v. Torstar Corp., [2009] 3 SCR 640, 2009 SCC 61 (CanLII), paragraphs 2 and 3)):
2 しかし、表現の自由は絶対的なものではない。表現の自由を制限するもののひとつに名誉毀損法があり、これは人の名誉を不当な攻撃から守るものである。 名誉毀損法は、人々が自己表現することを禁じているわけではない。単に、ある人が他人を中傷した場合、その人は相手の名誉に損害を与えたとして、相手に損害賠償を支払うよう要求される可能性があると定めているだけである。 しかし、出版社が利用できる抗弁があまりにも狭く定義されている場合、結果として「名誉毀損の冷え込み」が生じ、表現の自由や報道の自由が損なわれる可能性がある。
3 一方では表現の自由、他方では名誉の保護という相反する2つの価値が危機に瀕している。 表現の自由は 憲章2条(b)によって保護される基本的自由 であるが、名誉の保護もまた法的評価に値するものであることを裁判所は長い間認識してきた。裁判所の課題は、名誉毀損のコモンローを明確にする上で、両者の適切なバランスを取ることであった。本件では、このバランスをさらに調整する必要があるかどうか、改めて検討することが求められている。(中略)
実際には、名誉棄損の責任が認められた後、裁判官は日常的に、再発防止、さらには将来の不明な表現に対する永久差止命令(永久箝口令)を出しており、これらの差止命令に違反した場合には実刑判決が下されているからである(脚注No.9参照)。
名誉毀損法を廃止する国の義務
これとは対照的に、国際人権規約(ICCPR)に基づく国家の義務を考えれば、表現の自由に対する風評被害的な制限は法律で成文化され、「必要性と比例性の厳格なテスト」に従わなければならない(脚注No.9参照)。関連する問題は次のようになる:「レピュテーション」の喪失による実際の損害から個人を保護する必要があるのはどのような場合か?(雇用者と被雇用者の例は前述したとおりである。)実際の損害や定量的な損害を引き起こすことが明らかでない、不特定多数の意見から個人を保護する必要があることがあるのか。そのような法的手段を追求することは公共の利益になるのだろうか?
表現の自由という人権は、名誉毀損というコモンロー上の不法行為を認める国家においては無意味であることを認識しなければならないと思う。それに比べれば、虚偽事実の不法行為は実行可能であり、論理的にも区分が可能である。不法行為を成立させるためには、原告は悪意(虚偽であることが分かっている表現で危害を加えようとする意図)、虚偽性、実際の損害または特別損害の立証責任を負う。しかし、名誉棄損の不法行為は、訴訟の当事者ではない不特定多数の人が抱いていると推定される、原告に対する不特定多数の否定的意見の沼に繁茂する法的猥褻行為である。当該未知の意見は「名誉毀損」であり、対象となる被告の非難される表現によって「引き起こされた」と推定される。このように、レイヤーは遠く、不明であり、因果関係を結ぶことは不可能である。
名誉毀損法は廃止されるべき偽物である。文明史上、民主的でなかった時代から受け継いだものであり、社会に有害な浪費的法曹界を支えている。
結論
基本的人権と合法的に対立する権利や、基本的人権と均衡を保たなければならない権利は存在しない。 存在するのは、個人の人権を制限することで自らを甘やかすことを望む国家や、社会の特権的な部門だけである。裁判所は、国家による不釣り合いな、あるいは耐え難い人権侵害を防ぐと同時に、こうして計られた人権侵害を執行するという二重の現実的な任務を担っている。
裁判所は、社会の支配階層を安定させ、強制することを意図するこの任務の本質を明らかにするのではなく、社会のさまざまな構成員が有すると主張される権利の「バランスをとる」という装置を開発し、それによって、裁判所が執行者ではなく、「司法へのアクセス」を与える単なる仲裁者であるかのような幻想を作り出している。
