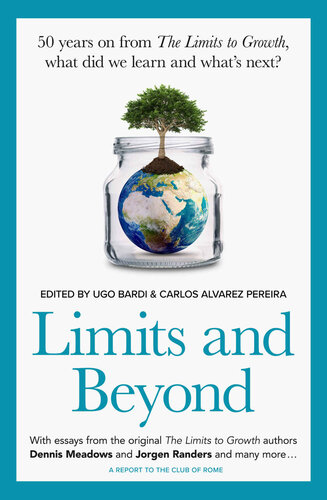
Limits and Beyond: 50 years on from The Limits to Growth, what did we learn and what’s next?
限界とその先へ
『成長の限界』から50年、私たちは何を学び、次に何をするのか?
編著者 ウーゴ・バルディ
編集者 カルロス・アルバレス・ペレイラ
目次
- 序文
- マンフェラ・ランフェレ、サンドリーヌ・ディクソン=ドゥクレーヴ
- はじめに ウーゴ・バルディとカルロス・アルバレズ・ペレイラ
- 名著の響き
- 1. 成長の限界あるアイデアの物語 ウーゴ・バルディ
- 2. 共著者の見解『成長の限界』は本当は何を言っていたのか? ヨルゲン・ランダース
- 3. 『成長の限界』に関する質問 デニス・メドウズ
- 4. 転換期としての危機。何があったのか、何があるのか スヴャトスラフ・ザベリン
- 5. 『成長の限界』から50年 エルンスト・フォン・ヴァイツゼッカー博士
- 6. 成長の限界から惑星境界へ ジャンフランコ・ボローニャ(Gianfranco Bologna)
- まだ経済がある、でもどんな?
- 7. ローマクラブは世界のアジェンダにどう影響を与えたか? ワウテル・ヴァン・ディーレン
- 8. 何の成長か? L. ハンター・ロビンス
- 9. 成長の限界を超えていく連帯資本主義 ンディディ・ンノリ・エドジエン博士
- 10. ブータンとその先ウェルビーイング・エコノミーの出現 ジュリア・C・キム
- 異なる未来のための新しいレンズ
- 11. 成長の限界は、未来のショックから未来のレジリエンスへの道を開く サーッカ・ハイノネン
- 12. 歴史的な『成長の限界』報告書-1972年と現在の世界 ユーリー・サヤモフ
- 13. 今日の人類の苦境: ティッピングポイントの収束 サンドリーヌ・ディクソン=ドゥクレーヴ
- 14. 世代を超えた未来を再構築する: 健康な地球での生活 マンフェラ・ランフェレ(Mamphela Ramphele)
- 15. 成長の限界は再起動した: 家父長的な無知から、重要な未来への集団的なスチュワードシップへ-フェミニストの視点から ペトラ・クエンケル博士
- 16. アジアの世紀における成長の限界 チャンドラン・ネイル
- 17. レジリエンス(回復力)の中の繁栄 イー・ヘン・チェン
- 私たちは学んだか?学ぶことができたか?
- 18. World3でデータチェックをしてみた。以下は、私が見つけたものである。 ガヤ・ヘリントン
- 19. どうすれば社会的に成長できるのか?チャック・ペゼシュキ
- 20. 変化する世界におけるレレバンスとは何か? ノラ・ベイトソン
- 21. すでに知っていることを学ぶ カルロス・アルバレズ・ペレイラ
- 謝辞
- ローマクラブについて
- Exapt Pressからのお知らせ
- 注釈
序文
マンフェラ・ランフェレ、サンドリーヌ・ディクソン=ドゥクレーヴ
ローマクラブ共同会長
宇宙は、人類に逃れられない運命をもたらそうとしている。それは、生命の網の中で表裏一体となって、相互に依存し合うことである。人類は、「私」「私」「私」という架空の世界に逃げ込もうとした結果、行き詰まりを感じている。
『Limits and Beyond』は、『成長の限界』報告書の中心的メッセージに対する人類の50年にわたる抵抗から学んだ厳しい教訓を称えるものである。ローマクラブは、世界の意思決定者に、私たちが50年という貴重な時間を無駄にしたことを思い出させる責任がある。その結果、本書は、1979年に出版されたローマクラブの別の報告書『No Limits to Learning』で私たちが求められたように、人類は自ら設定した限界を超えて、学ぶべきことを学び、それを身につける必要があることを思い起こさせるものでもある。
本書は、ローマクラブのメンバーや、健全な地球のための公平な世界秩序の中で、すべての人が幸福であることを特徴とする世界というビジョンを共有する他のパートナーによる、深い考察をまとめたものである。この本には、『成長の限界』の共著者2名とその他の著名な思想家が、『成長の限界』が実際に何を述べたのか、どのように受け取られたのか、次に何が起こったのか、今日の関連性についての最新の見解が含まれている。
過去数十年の中心的な教訓のひとつは、あらゆる犠牲を払ってでも不経済な成長を実現しようとする新自由主義という特定の経済思想の学派に、官民の議題が取り込まれたことである。共著者の何人かが示唆しているように、今こそこれを克服し、人類の課題に対処するためにシステム的な視点を取り入れた変革的な経済モデルを採用すべき時だ。
さらに、私たちが自ら作り出した制約から解放されたいのであれば、豊かな多様な視点が必要である。本書のいくつかの章にあるように、より望ましい未来を想像するためには、新しいレンズが必要なのである。本書では、「世界の大半の人々」と「別の視点からの声」を収録し、私たちの盲点を探れば、人間らしさを取り戻すことができることを示す。本書は、IPCC第6次評価報告書が発表された直後に刊行される。IPCCは初めて、データや分析のソースとしていわゆる「自然科学者」に依存することをやめ、「社会科学者」、先住民の知識の専門家やコミュニティリーダー、さらには若者の声も取り入れた。
その結果、植民地主義が気候危機の根本原因であることを認めるに至った。さらに報告書は、植民地時代の歴史の影響が、人類が破壊的なライフスタイルを適応・変革するための適切な対応を阻害し続けていることを認識した。さらに、植民地支配者とその植民地支配後の後継者の利益のために生態系を奪われた脆弱なコミュニティは、惑星の緊急事態に適切に対応するための資源も能力も持っていない。
最後の章では、「学問に限界はない」ことを説いている。複雑な生命システムがどのように変化していくのかを学び、把握するために、すべての人間が持っている未開発の生得的な能力を証明するものが増えてきている。最も困難な環境で行われた仕事では、人が生まれながらにして持っている適応能力が実証されている。この能力を高めるために最も重要なのは、無価値感や失敗への恐怖から自分を解放するために、一人ひとりが内側に向かうことを奨励することである。自己解放的な教育や学習環境は、老若男女を問わず、最も貧しい人々の生来の能力を引き出し、膨大なエネルギーと創造性を解き放つ。
一般に広く知られている見解とは異なり、人間はつながれるようにできている。私たちは、自分を肯定し支えてくれる大切な人たちに囲まれているときが一番幸せなのである。そして、『成長の限界』の出版50周年は、私たちが自然の一部であり、自然は私たちよりも無限に多くの知性を持っているということを、さまざまなレベルで人類が認識するようになった時期と重なる。COVID-19のパンデミックは、私たちの切っても切れない相互関連性と相互依存性を示すのに、最も効果的であることが証明された。世界中の健康、社会、経済、金融、政治システムの脆弱性を露呈し、私たちを、本当に大切なものに価値を置き、未来を再構築する機会と必要性を提供する重要な岐路に追いやったのである。支配的な考え方や他者、自然との関わり方によってもたらされた「傷」の遺産を癒すことは、私たち全員にとって必要不可欠である。この傷を癒すことは、人類が人間であることの意味の本質に立ち返るために開かれた存在になることを待っている機会なのである。
本書は饗宴である。私たちが直面している重要な問題に対して、豊かな多様な見解を読者に提供する。この本は、すべてのチェンジメーカーに、変化は可能であるばかりでなく、進行中であるとの励ましを与えてくれる。あなたの周りを見渡してみてほしい。変化はありふれた風景の中に隠れている。私たちは人間性を取り戻し、母なる自然の素晴らしさを讃えよう。
はじめに
ウーゴ・バルディ、カルロス・アルバレズ・ペレイラ 編著者
この本は、50年前に出版された別の本に端を発し、人類が進むべき道を決めるための可能性の空間を開くことを意図したものである。1972年にローマクラブで発表された『成長の限界』は、まさにそれを実現するものであったが、多くの人はそれを理解しなかったし、今も理解していない。この本から読み取れるのは、私たちが「開発」と理解しているものを変えなければ、人類の運命がいかに悲惨なものになるか、という強い警告である。そして、多くの人にとって、これは良いニュースではなかった。最初の一歩として拒絶されたのである。そして、多くの人が、この本とその背後にある努力を完全に無視した。
ローマクラブは1968年4月に設立された。ビジネス、科学、政治、市民社会など、さまざまな背景を持つ個性的な人々が、システム的、長期的、グローバルな視野で人類全体の将来を検討するために、同じようにオープンな議論をする場として設けられた。当時、本質的な問いを投げかけようとする組織は他になかった。そのうちのひとつは、1968年当時よりもさらに重要な問題: 健全な地球で、すべての人に公平な幸福をもたらすことができるのか?
人類の発展を物質資源の消費量の無制限な増加に結びつける論理の中で、有限な地球上でどれだけのことが可能なのかを問う必要がある。この問いは、従来の経済学の学派が考慮することを躊躇していたものである。「成長の限界」は、初期のコンピュータモデリングを用いてシミュレーションツールを作成し、さまざまな将来シナリオを構築することでこの問題に取り組んだ。しかし、残念ながら、シミュレーションの結果、ほとんどのシナリオで、人類の文明は21世紀前半に崩壊に直面することがわかった。
この発見は、世界中に衝撃を与えた。
「成長の限界」は、西欧のヘゲモニーに基づく近代化・工業化のプログラムとして、従来の「開発」とその地球全体への拡大が、人類の進歩のために必要かつ正当であるという信念を崩壊させた。
この混乱は、当時の既成の権力者の多くには理解されなかった。人類の発展が、有限な地球の境界線に適合するように再定義されるシナリオの可能性は、単に無視された。また、1987年に「持続可能な開発」という概念が生まれたときも、「開発」の本質を問うだけで、その悪影響は、同じような開発をさらに進めることで対処できる「付随的」な問題であると考えられていた。
1972年以降、人類の状況は大きく変化し、「成長の限界」の関係者が望む以上に深刻な事態に陥っている。2008年に始まった金融危機、2020年以降のCOVID-19のパンデミック、2022年のウクライナ戦争を含む多くの進行中の紛争は、誰もが目にする残酷な信号である。それらは、より大きな背景で展開される実存的な脅威の中に現れている。例えば、国内および国家間の不公平と亀裂の拡大、気候温暖化、生態系と種の破壊、健全な社会を育む代わりに人々を隔離する金融とテクノロジーの使用などである。
同時に、あらゆる場所で女性が解放されつつある。多くの場所で、人々は植民地や新植民地のルールや考え方に由来する無力感を克服しつつある。若い世代は、経済や政治システムの失敗が未来の可能性を狭めていることをより強く認識している。また、科学技術の進歩は、障壁を取り除く一方で、勝ち組と負け組がより深く分かれるディストピア的な未来の可能性を加速している。つまり、人類は繁栄と自殺を同時に繰り返しているように見える。私たちは、人類が最も輝いている瞬間に生きていて、自ら招いた絶滅という奈落の底に最も近づいているのかもしれない。
この根本的な矛盾に、私たちはどう対処すればいいのだろうか。生命の仕組みについて、私たちがすでに知っていることが助けになるかもしれない。生命システムは常に進化しており、時として臨界点に達し、そこから全く新しいパターンで出現することがある。しかし、「could」は 「will」ではない。臨界点では、未来は本当に未知数なのである。ホルヘ・ルイス・ボルヘスは、「時間は無数の未来に向かって永久に分岐する」と主張した。エーリック・ヤンシュ(ローマクラブ共同創設者)やイリヤ・プリゴジン(1970年代ローマクラブ会員、ノーベル化学賞受賞者)も、宇宙の自己組織化に関する自分たちの研究とよく一致するこの文学的表現に同意したことだろう。臨界は創発につながるかもしれないが、そのプロセスは事前に計画することはできず、自然の想像力と創造力が主役となって、生命の大きな網の目の中で、予期せぬパターンが新しいハーモニーを奏でる。
そこで、可能性のスペースの拡大が必要となる。『成長の限界』は、可能性のある未来の探求から学ぶ集団的知性に楽観的な賭けをしたものであった。しかし今、状況はかつてよりもさらに危機的なものとなっている。私たちは、緊急事態から集団的に脱出するための条件を作り出すために、すべての人の人間性と能力に改めて賭ける必要がある。
これが、『成長の限界』50周年を記念して、私たち(共同編集者)が本書を構想し始めた一般的な背景である。2011年、ウーゴ・バルディはすでにこの報告書を再検討する本を執筆していた。その経験を踏まえ、さらに踏み込んで、私たちを含む21人の著者に、それぞれの見識、視点、思いを集約したオリジナルの寄稿を依頼することにした。どのようなトピックを誰に書いてほしいかといった具体的な指示はしなかったが、創発のマジックによって、それぞれの寄稿の間に重複はほとんどなく、執筆者のバックグラウンド、分野、地理、文化の多様性を反映している。私たちは、時系列(その本はその時代に何を意味したのか、その後に何を意味したのか、そして現在、未来に向けて何を意味したのか)とアプローチの種類(科学、政治、経済、文化、その他)を組み合わせて、投稿の流れを整理することを課題とした。想像の通り、その多様性は、それぞれの作品のアプローチ、声、スタイルの多様性にも反映されており、私たちはそれを尊重することにした。人生は、根本的な多様性が必須であることを教えてくれる。
第1部「名著の響き」では、ウーゴ・バルディが原著の詳細な検証を行い、当時どのように受け止められたか、また、今日の私たちの考察にどのように役立ち、関連し得るかを述べて、舞台を整えている。1972年に出版された本の原著者であるデニス・メドウズとヨルゲン・ランダースの2人を招き、その本が実際に何を語っていたのかをより理解し、長年にわたって人々が本について尋ねた最も多い質問に答えるという特権がある。残念ながら、『成長の限界』の創作と影響、そしてその後のシステム思考という領域全体の発展において重要な役割を果たしたドネラ・メドウズの声を聞くことはできない。彼女は2002年にこの世を去ったが、「Dancing with Systems」というタイトルの遺稿を書くことなく、「生きているシステムの調和と再びつながるために、理性的、身体的な能力をすべて動員すること」を主張する見事な喚起をした。本書は、彼女の貴重な仕事へのオマージュでもある。
続いて、スヴィアトスラフ・ザベリンは、ソビエト連邦が成長の限界に達していたという仮説のもとに、ソビエト連邦の崩壊を再考する洞察に満ちた文章を発表している。最近の出来事を鑑みると、このような考え方は確かにさらなる研究に値するだろう。ローマクラブの共同会長を数年間務めたエルンスト・フォン・ヴァイツゼッカーは、アウレリオ・ペッチェイの傑出した人格、1970年代と1980年代の政治状況におけるベストセラー・レポートの受容、ウェルビーイングを物質資源の消費から切り離すことを促進しようとした試みについて印象を述べている。彼はまた、『Come On』を想起させる!を、2018年の創立50周年に出版されたローマクラブへのもう一つの集合的な報告書である。ジャンフランコ・ボローニャは、『成長の限界』に触発された科学的思考の進化、特に気候変動、生物多様性の損失、その他の生態系の問題についての研究をまとめ、最終的に2009年に作られた現在の惑星境界の概念に至ったことを説明している。
私たちの一般的な呼びかけに応えて、何人かの著者は、経済的思考と、その支配的な学派が人類の課題を適切に把握するのにいかに限界があるかを中心に考察することにした。Still the economy, but what kind? ”と題されたセクションの冒頭で、Wouter van Dierenは、『成長の限界』の創刊と最初の影響に自身が関わったことを振り返り、正統派経済学があらゆるコストをかけて成長しようとする強迫観念を鋭く批判する。さらに、ハンター・ロビンズは、新自由主義経済学の欠点について、詳細かつ過激で、十分な資料に基づいて解体している。Ndidi Nnoli-Edozienは、企業の社会的責任とアフリカ文化の要素や分散型デジタル化を融合させることによって、成長の限界を超えるために彼女が提案する「連帯資本主義」というオキシモロンの価値をあえて探求している。次に、ジュリア・キムは、ブータンにおける国民総幸福量の哲学と実践の経験をもとに、人間の福祉と私たちの生活が依存している生態系のケアを調和させる代替パラダイムとして、ウェルビーイング・エコノミーの出現を提唱する。
異なる未来のための新しいレンズ」では、世界中の大陸や文化圏の思想家たちが、それぞれのユニークな経験や視点を持ち寄り、必要とされるシフトの要素を想像している。サーッカ・ハイノネンは、不安定で不確実、複雑で曖昧な(VUCA)世界の危機や衝撃を乗り越えるためには、学習、脱学習、再学習、そして未来思考の重要性を強調している。「自然は私たちの究極の教師なのである」と彼女は締めくくります。ユーリー・サヤモフは、ソ連における『成長の限界』の知的受容と、世界的な社会変容と文明的展望に関する現在進行中の研究との関連について述べている。
サンドリーヌ・ディクソン=デクレーヴ(ローマクラブ共同会長)は、COVID-19のパンデミックの悲劇を基に、変革的経済学が緊急であるだけでなく、可能であると主張している。複数の転換点の収束は複雑な緊急事態を引き起こすが、それはシステム的なレンズを通して人類の課題に対処するための入り口でもある。ローマクラブが関与した、EUの文脈における欧州グリーンディールの実施に向けたシステム変革コンパスの策定は、そのような試みの一例だ。
『成長の限界』から何が変わったかを振り返り、マンフェラ・ランフェレ(ローマクラブ共同会長)は、いくつかの基本的なことを探るよう私たちに呼びかける。変化と抵抗の緊張関係から考え方を変えるには何が必要なのか。若い世代で顕著になりつつある文化的な変化は、どのような役割を果たすのだろうか。そして、「世界の大部分」と「北半球の支配者」という異なるビジョンから何を期待すべきなのか?これらの質問に対する回答は、私たちの未来に深く影響するものである。ローマクラブは、生活システムがどのように変化するかをよりよく理解することで、これらの問題の岐路において触媒的な役割を果たすことができる。
ペトラ・クエンケル氏はフェミニストの視点を提案し、どのように、どのような意思決定がなされるかに女性がより強く参加することで、家父長的な盲点から、より良い未来のための集団的なスチュワードシップへの転換が期待できるとしている。一方、チャンドラン・ナイールは、21世紀を「アジアの世紀」と位置づけ、最も人口の多い大陸が多極化する世界の中で急速にその存在感を取り戻しつつあるという証拠をもとに、21世紀をアジアの世紀とすることを提案している。アジアの視点に立てば、ローマクラブが『成長の限界』50周年を記念して採択したモットーである「健全な地球のためのグローバルな公正」の達成には、繁栄の共有と適度な消費の組み合わせを促進する国家の強い役割が必要であり、過去数十年間に西洋で続いたアプローチとはかなり異なっている。オルタナティヴな世界観の続きとして、Yi-Heng Chengは、中国の伝統的な知恵とレジリエンスにおける繁栄のための必要条件を織り交ぜるという魅力的なエクササイズに取り組んでいる。メタファーとして、5つの伝統的な要素(水、木、火、土、金属)は、相反する特性の新しいバランスをとるための社会的価値を示し、彼は「成長の限界」の5つの変数と結びつけている。
最後に、「Did we learn?」というセクションでは、私たちはこれからどうすればいいのかを考えている。人類は『成長の限界』の教訓を受け止めたのだろうか?その一方で、私たちは何を学んだのか。そして、最も重要なことは、今、私たちに何ができるのかということである。ガヤ・ヘリントンは、1972年の本でシミュレーションされたシナリオと、その後の事実上の進化を比較し、社会的な優先順位の異なる本質的な議論のための参考資料として利用できることを詳しく説明している。終末予言は、その議論を効果的に行うための適切なフレームワークではない。チャック・ペゼシキは、私たちが物質的な成長への依存から抜け出すために、社会的に成長する方法の中心に共感を置いている。ネットワーク科学に着想を得た彼が提案する道は、すべての人の能力を開発するために、搾取的・非協力的な解釈を排除し、進化を再定義することを意味する。
ノラ・ベイトソンは、生命システムの複雑さから学ぶために、生態系の相互依存関係を深く掘り下げることを提案する。彼女は、現実を個別の箱に分けようとする試みがあるにせよ、すべての人間社会の関係性を掘り下げている。「自分にとって何の得があるのか」という考え方に基づくと、人間関係はかえって活性化されることがある。しかし、人間関係に再び中心的な役割を与えることで、「究極の統一美」につながることもある。最後に、カルロス・アルバレス・ペレイラ(ローマクラブ副会長)は、「すでに知っていることを学ぶ」ことを提案している。学習は、私たちが変化するときにのみ起こる。この50年間、私たちは学びませんだった。しかし、世界とその中での私たちの役割を理解するために不十分なレンズを使用していることが大きな障害になっていることを確認した。私たちの時間との関係、そしてそれに伴う現在の資本の概念は、過去と現在の権力の分配によって枠付けられ、将来の世代の可能性を妨げている。1984年にアウレリオ・ペッチェイが言ったように、「自然と平和に暮らすために」人間革命が必要なのである。
もしあなたがこの本を、反応だけを求めて開いたとしたら、がっかりするかもしれない。この本の目的は、より良い質問をすることによってのみ起こりうる、可能性の空間を開くことである。良い質問は心を開き、盲点を明らかにし、閉ざされた「解決策」ではなく、他の質問へと導く回答へと導くのである。質問と答えの無限の流れは、人生そのものである。
1979年に出版されたローマクラブの報告書『No Limits to Learning』の序文で、アウレリオ・ペッチェイは、私たちの課題を謎かけのように表現している: 「人類の進化において今必要なのは、学ぶべきことを学ぶために必要なことを学び、それを身につけることである」本書は、私たち自身のため、そして来るべき世代のために、この学びの冒険の興奮を分かち合うための招待状なのである。
名著の響き
第1章 成長の限界: あるアイデアの物語
ウーゴ・バルディ フィレンツェ大学教員
要旨
1972年、ローマクラブは「成長の限界(The Limits to Growth)」と題する研究書を発表した。この研究は、現代文明の長期的なトレンドを検証した最初のものではなかったが、モデルによって定量的に検証した最初のものの一つであった。その結果、21世紀の最初の数十年の間に、世界の経済システムが崩壊することが明らかになったのである。この研究は、当初は賞賛されたが、その後、悪評ストームにさらされ、間違った科学思想のゴミ箱に追いやられた。新世紀になって再評価が始まり、私は2011年に『成長の限界の再検討』という本を出版した。今日、2022年にローマクラブは、この研究の最初の50年のストーリーを伝えることを目的とした新しい本を出版する。この新しい本の現在の部分は、2011年の私の本をベースにしているが、全く新しい再検討で、文明の成長と崩壊という考え方が歴史の中でどのように推移し、LtG研究によってどのように解釈されたかというストーリーを語っている。
夜中の泥棒のように、主の日がやってくる。
– パウロのテサロニケの信徒への最初の手紙、(5,2)
文明のサイクル
今から約5000年前、ユーラシア大陸の肥沃な三日月地帯から中国の長江流域にかけて、人類最初の文明が出現した。その後、新しい文明が生まれ、世界中に広がり、都市や道路を建設し、人口を増やし、隣国を征服していった。しかし、これらの文明にはある共通点があった。まず燃え上がり、次に衰退し、遺跡や墓、時には岩に刻まれた「栄光は永遠に終わらない」という碑文だけを残して消えていった。しかし、1000年以上続いた帝国はほとんどなく、ほとんどが数世紀で消滅してしまった。私たちが「西洋」や「グローバリゼーション」と呼ぶ現代文明は、約半世紀前のヨーロッパに端を発し、「ルネッサンス」と呼ばれる大膨張時代を経ている。そして今、その歴史は終わりを告げようとしている。
しかし、なぜ文明は成長と崩壊のサイクルを繰り返すのだろうか?この問いを投げかけた人たちの人気は決して高くなく、特に崩壊が間近に迫っていると結論づけた人たちの人気は高かった。しかし、古代文明の浮き沈みは注目され、場合によっては、このテーマに関する古代の議論を今でも追うことができる。崩壊についての最初の言及は、おそらくシュメール人の巫女エンヘドゥアンナによるものだろう。約4,500年前に書かれた女神イナンナへの賛美歌の中で、女神と山との壮大な戦いが描かれており、この物語の中で、浸食による肥沃な土地の崩壊を認識することができる。2 ,3
その後、ローマ帝国は歴史上最大級の帝国となったが、ローマ帝国も衰退の一途をたどることになる。紀元1世紀、ルキウス・アンナエウス・セネカが書簡の中で「破滅への道は速い」と述べたのが、ローマがうまくいっていないことを示す最初のヒントとなった。4 同じ頃、初期のキリスト教徒は、ローマ帝国だけでなく、物質世界における人間の経験も終わらせる、来るべきパルーシア(神の顕現)に関連して、この傾向を宗教用語で解釈した。後に、このような考え方は、宗教的なセクトの典型である「千年王国主義」と呼ばれるようになった。
しかし、ローマ帝国は、多くの歴史的な文明と同様に、自分たちの身に起こっていることの理由をほとんど知らないまま崩壊の道を歩んだ。紀元5世紀、ローマ帝国の最後の世紀に、ルティリウス・ナマティアヌスという貴族が書いた冷ややかな報告がある。彼は周囲の世界の破滅を目の当たりにしたが、自分がローマ帝国の最後の息の根を止めていることを理解することができなかった。彼は、目にするものすべてを一時的な後退と理解し、ローマがすぐに古代の栄光を取り戻すと完全に期待していたのである。ローマ帝国を再現しようとした最後の試みは、ムッソリーニが1936年から1943年まで続いた「イタリア帝国」という歴史上最も短命の帝国を作り上げた時であったかもしれない。
現代では、ローマ帝国の再現は流行らないように見えるが、1989年にフランシス・フクヤマが「The End of History?」というタイトルの論文を書いている。5と題する論文を発表し、西洋文明の支配はローマ帝国時代のパックス・ロマーナに相当し、永遠ではないにせよ、少なくとも長い長い間続く運命にあると述べている。その後の出来事は、フクヤマの考えの限界を示したが、私たちはいまだに、崩壊を考えられない、少なくとも言葉にできないものと見なす見方にとらわれているようだ。西洋文明の悩みは明らかだが、多くの人は、この状況を一時的な後退ととらえ、せいぜい微調整で修正する程度と考えがちである。そして、「Pax Occidentalis」が永遠に続くのだ。
このような楽観的な見方は、1950年代から1970年代にかけて、世界経済がかつてないほどの成長を遂げた「黄金の数十年」によってもたらされた期待感の結果なのかもしれない。また、経済成長だけでなく、技術の進歩は止められない力として、予測可能な未来に至るまで継続的な成長をもたらすと考えられていた。安価で豊富な原子力エネルギーがあれば、鉱物資源の「枯渇」も含めて、あらゆる問題が解決する。物理学者のゲラーとワインバーグが「無限の代替性の原理」と大げさに表現した概念によれば、それは恐れるべきことではなかった。6
その頃の中心的な考え方は、星を動かすエネルギーである核融合をコントロールすることであった。それがあれば、夢のようなことが可能になるはずだった。1974年、物理学者のジェラード・オニールは、数百万人、数十億人を収容できる巨大な人工居住区をベースにした宇宙植民地化の壮大な計画を提案した。7 さらに、フリーマン・ダイソン8は、太陽の周りに巨大な球体(ダイソン球)を作ることで、人類の限界に達するという壮大な計画を提唱していた。空飛ぶクルマ?そんなものはオモチャに過ぎない。私たちが本当に欲しかったのは、他の星に到達し、銀河系全体を植民地化するための宇宙船だったのだ!
しかし、当時の楽観主義とは裏腹に、その逆を行く考察の糸も存在した。近代になって初めて文明崩壊を論じたのは、おそらくエドワード・ギボンの『ローマ帝国の衰亡史』(1776-1789)であろう。ギボンの著書はローマ帝国の運命を詳細に描いたもので、同じ運命が現代文明に降りかかるかもしれないという先入観がはっきりと反映されていた。ギボンはその可能性を否定したが、明らかに、「栄光のローマ帝国が消滅したなら、近代文明には何が待ち受けているのか」という、議論に浸透し始めた思想を見抜いたのである。
その後、1798年にトーマス・マルサスは『人口原理に関する試論』を発表し、おそらく歴史上初めて、人間の人口増加には物理的な限界があることを指摘した。しかし、不思議なことに、一般的な認識とは異なり、マルサスは決して「破局論者」ではなかった。つまり、彼はいかなる崩壊も予測しなかったのだ。彼は、飢饉や戦争によって人類の成長は必然的に一定水準に制限されることを指摘しただけだ。そして、彼はそれが固定的なレベルであったとも言っていない。彼は、人口ほどではないにせよ、成長すると見ていた。それにもかかわらず、彼は間違った予測をしたことで悪者にされ、嘲笑された。今日、「マルサス的」と定義されることは損傷と理解されているほどだ。それは、後の多くの破局論者に共通する宿命であった。
やがて、天然資源の限界の問題を検討する人々も現れた。ウィリアム・スタンリー・ジェヴォンズは、1865年に『石炭問題』を発表した。9 彼は、イギリスが100年以上にわたって石炭を採掘し、燃やし続ける能力について悲観的であったが(そしてそれは正しい)、経済崩壊を予測することはなかった。同じような考え方で、1世紀後ではあるが、地質学者のマリオン・キング・ハバートは、石油採掘の長期サイクルを初めて検証し、21世紀初頭には限界に達すると予言した10。ハバートは、後に破局論者、マルサス論者と呼ばれるようになるが、マルサスと同様、崩壊には言及しなかった。彼は、原油が順調に原子力エネルギーに取って代わられ、人類の文明が繁栄し続けることを予見していた。
私たちが「破局論」と呼ぶ見解が登場したのは、20世紀後半になってからだ。それは、二度の世界大戦の災禍の結果かもしれないし、核兵器によるホロコーストの恐怖の影響かもしれない。いずれにせよ、ネガティブな未来という考え方は、まずSFの中に登場した。それは、戦争前、宇宙の征服や未来の技術の驚異を描く、一般に楽観的なジャンルとして始まったものであった。しかし、第二次世界大戦後、それは暗い筋の影響を受けるようになった。「ポスト・ホロコースト」というジャンルでは、核戦争の生き残りが、廃墟と化した世界で生活を立て直そうとする様子が描かれた。1950年代には、アイザック・アシモフが、エドワード・ギボンのローマ帝国崩壊の壮大な描写を用いた「ファウンデーション」シリーズの小説で、銀河系規模の崩壊の物語を描いている。1968年、ジョージ・A・ロメロは『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』で、映画における「ゾンビ」というジャンルを確立した。この映画は、無数の続編を生み出し、中世の「死の勝利」のような古代の死への恐怖を模した、想像を絶する恐ろしい未来を視覚的に形象化したものであった。
この時代、人々は文明の未来を反省し、夢というより悪夢として見ることもあった。しかし、それは地下的な考え方であり、主流の議論では決して真剣に取り上げられることはなかった。それが1960年代後半になると、カタストロフィ主義的な考え方が表面化するようになった。
おそらく、正統派の楽観主義を揺るがした最初の科学者は、レイチェル・カーソンの著書『沈黙の春』(1962)で、農薬の無差別使用を批判し、人間の健康や生態系へのダメージを指摘したのである。化学工業のスローガンが「化学でより良い生活を」であった時代に、この本は大きな反響を呼び、カーソンは今日「環境運動」と呼ばれるものを始めたと正しく信じられている。破局論者の常として、彼女は広く損傷され、悪者にされたが、彼女の考え方は大きな影響を与えた。
もう1つの聖なる牛は、人類の人口増加であった。それまで、人口の増加は良いことだと考えられていた。人が増えれば、顧客も増え、労働者も増え、兵士も増え、みんなが豊かになる。しかし、1960年代、地球上の人類の数は30億人の大台を突破した。しかし、1960年、地球上の人類の数は30億人を突破し、指数関数的に増加し、その傾向を数十年先まで予測するのは悪夢のようだった。
1968年、ポール・エーリック夫妻は『人口爆弾』を発表した。この本はマルサス的な見解の復活と見なされていたが、もしそうだとすれば、エーリックはマルサスのステロイド版であったことになる。エーリック夫妻は、人口の安定化や緩やかな増加を予測したマルサスとは異なり、今後数十年のうちに世界中で急激な人口崩壊をもたらす飢饉が蔓延すると予測した。エーリック夫妻の心配は見当違いであったか、あるいは時期尚早であったことが判明した。その結果、エーリックは、カタストロフィ主義者バッシングの定石通り、損傷され、悪者扱いされた。しかし、彼が提起した問題を無視することはできなかった。
そして運命の1968年、それまで理解されていた経済学の根幹を揺るがす論文が発表された。生物学者ギャレット・ハーディンの「コモンズの悲劇」である。11 この論文はすぐに古典となった。
ハーディンは、「コモンズ」として管理されている牧草地、つまり、すべての羊飼いが自由に羊を飼うことができる牧草地を考えて、その考えを物語という形で明らかにした。その土地で飼える羊はせいぜい100頭。それ以上の羊は、草を食べ過ぎて裸地になってしまい、どんどん侵食されてしまう。だから、10人の羊飼いが10頭ずつ羊を飼うことができ、その状態が続く限り、悪いことは起きない。しかし、羊飼いの下駄箱の中に入ってみると、羊の数が多ければ多いほど豊かになる。つまり、羊が10匹ではなく11匹いれば、あなたはより豊かになれる。しかし、羊が1匹増えると牧草地が荒れてしまうことも知っている。羊が1匹増えると牧草地が荒らされるのは羊飼いたちにとっても同じことだ。結局、101匹の羊は100匹と大差なく、被害は小さい。そこで、あなたは羊を1頭増やすことにした。
ところが、どの羊飼いも同じように判断し、羊を1頭増やしてしまった。その結果、110頭の羊が100頭以上の羊を養うことのできない牧草地で草を食むようになった。青々とした牧草地は緑が薄くなり、羊が草を食べ過ぎた場所には黒い斑点が現れる。
しかも、まだ終わってはいない。羊を1匹増やせば有利になるのなら、2匹増やせばいいじゃないか。そうすれば、他の羊飼いが飼っている余分な羊が土地に与えたダメージは、少なくとも補償されるはずだ。そして、他の羊飼いたちと同じように、あなたもそうする。そうして羊の数が増え、最終的には過放牧によって牧草地が破壊されることになるとハーディンは言う。その時点で羊は死に、羊飼いは生計を立てるために、できることなら移住しなければならない。なお、この災害は、誰もが自分の経済的収入を増やすために、完全に合理的な方法で推論した結果である。経済学者の専門用語を使えば、羊飼いは皆、自分の「効用関数」を増やすために最善を尽くすのだ。個人レベルでは良い考えだが、集団レベルでは非常に悪い考えである。
ハーディンのモデルは純粋に理論的なものであったが、天然資源の開発に関する議論において痛いところを突かれた。アダム・スミス(1723-1790)が提唱した「見えざる手」の概念を根底から覆すものであった。この概念は、後に「過剰搾取」と呼ばれるようになるもので、1980年代にウィリアム・キャットンが普及させた用語である。12 「悲劇」は資源の限界の必然的な帰結ではないこと、13 また、現実のシステムで起こることも、後に確認することになる。14
この一連の研究は、当時の考え方が大きく変化したことの表れであり、1972年の『成長の限界』の出版によって、その全貌が表面化することになった。
1972: 世界のモデル化の始まり
1972年、『成長の限界』が出版されると、大きな注目を集め、少なくとも30カ国語に翻訳され、おそらく300万部が売れた。この成功には、コンピュータを使った革新的なアプローチ、誰にでも理解できるようにと書かれたこと、そして何よりも、この本が描く崩壊の悲惨な予測が理解されたことなどが要因として挙げられる。この研究で作成されたシナリオは、当時の政策を何も変えなければ、人類の産業文明は21世紀の最初の数十年の間に崩壊するというものだった。
多くの人にとって、まさに青天の霹靂のような衝撃であったが、これにはストーリーがあった。それは、イタリアの知識人、アウレリオ・ペッチェイ(1908-1984)に端を発する。ペッチェイは科学者でも哲学者でもなく、大規模プロジェクトのマネジメントを得意とする行動派であった。先見の明と起業家精神、そして数ヶ国語の知識を備えた人物であった。

1960年代の楽観的な雰囲気の中で、ペッチェイは、人類が自分自身を振り返り、その将来を決めるのに、一部の賢明なメンバーの助言に基づくことができると考えることは、決して突飛なことではないと考えた。いわば、ペッチェイは人類に「意識」を与えることを目指したのである。
1965年、ブエノスアイレスで開かれた金融コンソーシアムADELAでの演説に、ペッチェイの初期の思想がある。その演説が、現在のローマクラブの思想の受け止め方と対照的に見えるのは驚くべきことである。ペッチェイは「破局主義」からはほど遠く、地平線上に崩壊はないと考え、「成長の限界」などとは一言も口にしなかったし、おそらく考えもしなかった。人口過剰については言及していたが、もちろん、人類が天然資源の枯渇や公害、人口過剰といった解決不可能な問題に直面しているとは想像すらしていなかった。当時、「人為的な地球温暖化」という概念は、一部の専門誌の中で仮説として存在するだけだった。数十年後には、それが人類にとって存亡の危機となるとは、誰も知る由もなかった。それどころか、ペッチェイの考えは、技術進歩が経済成長を促し、人類に繁栄をもたらすという、当時の一般的な考えと一致していた。
しかし、ペッチェイの目には、この明るい絵が何か間違っているように映った。第二次世界大戦の惨禍がまだ尾を引いており、さらに核兵器によるホロコーストという悲劇的な可能性に直面していたことを忘れてはならない。当時、世界は第一、第二、第三の世界に分かれていた。第一は先進国、第二は共産主義国、第三は当時まだ「低開発国」と呼ばれていた貧しい国々である。第一世界と第二世界が互いに核兵器による抹殺を予告していたのに対し、第三世界は他の世界の繁栄に追いつくことができなかった。当時流行していた「低開発国」ではなく、「開発途上国」と呼ぶようになったのは、何も変わらない手抜きだった。
ペッチェイは、成長と進歩がもたらす恩恵から、すべての人が利益を得られるようにすることが、これからの課題だと考えた。しかし、不平等や分断は、災いをもたらすだけで、核戦争に発展する可能性もある。最悪の事態を避けるためには、国家間の連携を高めることが必要だった。
ペッチェイのADELA演説は大成功を収め、ペッチェイは1969年に出版した『The Chasm Ahead』という本でその考えを展開し、国際的に知られるようになり、自分の考えをどう実践していくかを考えるようになる。ペッチェイは、同じような考えを持つ、知識人、科学者、政治家など、世界的に著名な人たちを集めた。1968年、ローマで初めて会合を開き、最初の決定事項として 「ローマクラブ」と名乗ることを決めた。
1970年にクラブが発表した「人類の危機」と題する文書は、ペッチェイの考えを踏襲したものであった。当時のメンバーの最大の関心事は、全人類の生活条件を改善するための現実的な方法を見つけること、特に富の不平等を解消することであった。そこで、クラブが直面した問題は、世界の資源を定量的に把握し、その分配を考えることだった。
それは簡単なことではなかった。1960年代、世界の定量的なデータはまだ乏しく、散在していた。第二次世界大戦後、「国民総生産」(GNP)、後に「国内総生産」(GDP)という少し変わった単位が広まった。各国政府が工業生産と農業生産のデータを集め始め、初めて世界レベルで経済規模を評価できるようになったのだ。
経済学者たちは、自分たちが手にした新しい道具に魅了された。GNP(およびGDP)は時間の関数として成長する傾向があることに注目したのである。しかし、富める国と貧しい国の貧富の差は縮まるどころか、むしろ大きくなっているという事実が、依然として残っていた。この逆効果はなぜ起きたのか?この逆効果を覆すことはできるのだろうか?
そう考えていた1968年、ペッチェイはイタリアのコモ湖畔で開催された都市開発に関する会議に出席した。この会議には、もう一人の技術者、マサチューセッツ工科大学(MIT)の若き教授、ジェイ・ライト・フォレスターが出席していた。

フォレスターもまた、20世紀半ばの注目すべき人物であった。彼はオートメーションに魅了され、世界を相互に作用し合う要素のシステムとして捉えていた。フォレスターは、オートメーションの重要な要素として、信号処理の分野で開発された「フィードバック」という概念を挙げている。「フィードバック」とは、システムのある要素が他の要素の状態に反応し、場合によっては他の要素の状態も変化させることを意味する。フォレスターがこの考え方を最初に応用したのは、第二次世界大戦中にアメリカ海軍のために開発した自動高射砲である。レーダーからの信号を受けた砲は、その信号に反応し、航空機の軌道に沿うように照準を修正する必要があった。フォレスターは、この砲を実際に試すためにアメリカ艦隊と一緒に出航し、彼の船は日本軍の魚雷に遭った。今の大学の研究者のほとんどが見逃しているような、興味深い体験だったに違いない。
アメリカに戻り、ボストンのマサチューセッツ工科大学の教授になったフォレスターは、従来の工学システムにとどまらず、やがて社会・経済システムにも関心を向けるようになった。しかし、フォレスターは、そのようなシステムでも、研究室でテストすることはできなかった。敵機を撃墜しなくても、入力パラメータを自在に変えて効果を見ることができるシミュレーション・システムにいつでも取り組むことができたのである。
これも、当時としては驚くべき進歩であった。複雑なシステムをモデルによってシミュレートするというコンセプトは、すでに知られていたが、一般的ではなかった。シミュレーションが標準的に行われていたのは、ナポレオン時代から盛んに行われていた軍隊の分野だけだった。初期のシミュレーションは「ウォーゲーム」と呼ばれ、精巧なジオラマの上でも、厚紙の地図の上でも、複雑なルールに従ってカウンター状の軍団が移動し、互いに戦うというものだった。趣味でウォーゲームをやったことがある人なら、ゲームの進行がいかに遅いかを知っているはずだ。毎ターン、定規を使った手間のかかる計測に従ってカウンターが動き、サイコロの出目に従って戦いが解決される。時には氷河期のようなスローペースで、プレイヤー同士の果てしない議論やいざこざは日常茶飯事だ。
フォレスターは、優秀なエンジニアとして、このような遅くて限定的なアプローチに満足することはできない。エンジニアは問題解決者であることが知られているが、フォレスターもその一人であることは間違いない。彼は、現代のシミュレーション・モデリングの創始者であるだけでなく、デジタル・コンピュータ用の最初の固体メモリの1つを設計し、自分のモデルに使うために特別に開発・製作した人物である。
このように、フォレスターは、「フラッシュ・ゴードン」シリーズのザルコフ博士のように、地下室で宇宙船を建造する架空の科学者の一人を思い起こさせるような偉業を成し遂げた。また、フォレスターを、アイザック・アシモフの「ファウンデーション」シリーズの銀河帝国時代の主人公の一人であるハリ・セルドンと比較することもできるだろう。アシモフがフォレスターに会ったことがあるのか、彼の仕事を知っていたのかの確証はないが、1960年代にフォレスターがMITで行った講演のひとつにアシモフが直接インスピレーションを受けた可能性もないとはいえない。
確かに、フォレスターは創造的な科学者であり、未踏の道を進むことを恐れなかった。ここでは、彼が開発していた分野の見方を説明している。15
人々は、物理的なシステムと人間のシステムが同じ種類であると信じることに抵抗がある。社会システムは物理システムよりも複雑だが、物理システムと同じ高次、非線形、フィードバックシステムのクラスに属す。社会システムという考え方は、その構成要素間の関係が人間の行動に強く影響することを意味している。社会システムは、個々の人間の行動を強く拘束する。言い換えれば、システムという概念は、人が完全に自由意志で行動するという信念と矛盾する。その代わり、人は変化する周囲の環境に大きく反応するものである。
フォレスターは、新しいコンピュータを使って、それまで誰もできなかったような優れたシミュレーションを行うことができるようになった。都市全体、戦場、経済分野などの複雑なシステムを、コンピュータのメモリ内でシミュレーションすることができたのである。人間の頭では、一度にたくさんのパラメーターを把握することはできないし、最も重要そうなパラメーターを選んでしまう傾向がある。そして、人間は感情的になりやすいので、ルールを曲げたり、気に入らない結果につながる要素を無視したりして、自分を欺くことがある。日本帝国海軍がミッドウェー海戦を戦う前に、ウォーゲームでシミュレーションを行ったという有名な話がある。シミュレーションの結果、日本軍が敗北しそうになったとき、日本軍の司令官である山本提督自身が、ゲームで沈んだ日本の空母を「再浮揚」 するように命じたと言われている。こうして、ウォーゲームは日本の勝利で幕を閉じた。もちろん、現実の世界ではまったく違う結果になった。しかし、この話は、未来を予測しようとする人々の感情的な姿勢をよく表している。
それに対して、デジタルコンピューターは、直感のようなものは一切使わず、イデオロギーにも影響されず、愛国心とは何かということも考えず、戦いの勝ち負けにも関心がない。ただひたすら数字を計算し、シミュレーションの終了まで、仮想メモリ内の仮想カウンターを動かしながら、理路整然と、そして無情に。人間のプログラマーは、その結果が気に入らないかもしれないが、それこそが重要なのだ。
1960年代初頭、フォレスターは複雑な社会経済システムをシミュレートするツールを手に入れたのだ。彼はこの新しい分野を「アーバンダイナミクス」と「インダストリアルダイナミクス」と名づけた。その後、「システムダイナミクス」という言葉が一般的になった。この方法は、ビジネスの状況や、都市全体のような社会経済システムのシミュレーションに使用することができた。そこからフォレスターは、世界の経済システム全体をシミュレートするという、もう一つのステップを明確にした。1960年代半ば、コンピュータの性能が十分に向上した頃、彼は最初の世界モデルを開発した。
ペッチェイとフォレスターは、コモ湖畔で出会い、同じような目標を持っていることをすぐに理解した。フォレスターは、必要なデータを集めるためにペッチェイを必要とした。ペッチェイは、そのデータを解釈し、未来の世界の流れを理解するために、フォレスターを必要としていた。運とは、偶然と覚悟が重なったときに起こるものだと言われている。1968年、イタリアでのペッチェイとフォレスターの出会いが、世界の知的風景を変える一連の出来事の始まりであった。
1970年、フォレスターは、ローマクラブのメンバーがスイスのベルンで開催した同窓会で出会い、「World1」と呼ばれる最初の世界モデルの開発に着手した。一方、フォルクスワーゲン財団は、アウレリオ・ペッチェイとローマクラブ執行委員会のドイツ人メンバーであるエドゥアルド・ペステルの協力を得て、MITで行われる予定だった世界の力学に関する大規模研究のための資金を提供した。この研究を担当したのは、フォレスターの元教え子で、当時MITの助教授であったデニス・メドウズである。

ジェイ・フォレスターは、このメドウズ率いる研究に直接参加することはなかった。彼の性格は、どちらかというと科学者個人に近く、「World2」と名付けたモデルを使って一人で仕事をすることを好んだ。その結果、1970年から1972年にかけて、MITで世界のダイナミクスに関する2つの研究が行われた。1つはジェイ・フォレスターによるもので、もう1つは 「World3」と呼ばれる独自のモデルを開発したメドウズのグループによるものである。
この2つの研究は、細部は異なるが、同じ概念と手法に基づいていた。フォレスターの研究は、1971年に『ワールド・ダイナミクス』というタイトルで本として出版された。メドウズの研究は、1972年に『成長の限界』(LtG)というタイトルで出版され、副題は『ローマクラブへの報告書』であった。しかし、フォレスターとメドウズのマサチューセッツ工科大学(MIT)グループが、イデオロギーにかかわらず、クラブからの影響を全く受けていないことは確かである。実際、クラブのメンバーの中には、そしておそらくペッチェイ自身にとっても、これらの研究結果は驚きであった。
どちらの研究結果も同じ結論に達している: 世界経済は、資源の枯渇、人口過剰、公害などが重なった結果、成長が止まり、崩壊する傾向がある。この計算は、崩壊がいつ始まるかを特定するものではなかったが、入手可能な最善のデータを用いて、両研究は、崩壊が21世紀の最初の数十年間、つまり約半世紀先の未来に起こりうることを示した。
フォレスターとLtGの両チームは、急激な技術革新や、世界レベルでの政策行動による人口の安定化など、さまざまな可能性を想定して計算を行った。ほとんどの場合、非常に楽観的な仮定であっても、崩壊を回避することはできず、遅延させることしかできなかった。また、楽観的な想定が逆効果になるケースも少なくない。利用可能な天然資源が当時の予測よりも豊富であると仮定した場合、経済成長はより長く続いたが、いずれにせよ崩壊は訪れ、それはより保守的なシナリオよりもさらに壊滅的であったという結果になった。公害がコントロールされると仮定した場合、過剰人口がシステムを崩壊させることになる。人口増加を止めるだけでは、システムを安定させるのに十分ではなかった。人口増加を止め、物質消費を安定させ、公害をコントロールするために、慎重に選ばれた一連の世界政策だけが、崩壊を避け、世界経済の安定した状態を生み出すことができた。
フォレスターの本は10万部ほど売れたが、これは数式や図表を多用した技術書としては驚くべき結果であった。しかし、本当にインパクトがあったのはLtG研究で、これは最初から一般大衆を対象としており、販売部数も数百万部程度であったと思われる。この本は、惑星資源の限界を無視することはできない、という世界中の人々の強い思いを代弁したのである。ローマクラブは、この研究で有名になった。しかし、ペッチェイはこの研究結果の重要性を理解し、自分の世界観に組み込んだ。また、世界の貧困層が成長し、富裕層と同じレベルに達するチャンスを得ることが重要であるとの立場も崩さなかった。1976年にニューヨークで行った演説17では、貧しい国々を従属的な状態に閉じ込めてしまう「ゼロ成長」の考えを明確に否定している。
しかし、LtGの研究結果が世界の人々の意識に浸透するには時間がかかる。物語は始まったばかりだった。
『成長の限界』の基本的な考え方
ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)の研究を中心に「科学的方法」が開発されたとき、科学者はある現象を支配する「法則」を実験室や野外の実験で明らかにするべきだという考え方があった。科学の典型は、ある「法則」が真に普遍的であることである。例えば、「万有引力の法則」ニュートンは、木から落ちるリンゴを観察してこの法則を考え、地球の周りを回る月にこの法則を当てはめたと言われている。私たちにとっては当たり前のことだが、リンゴと月という異なる2つの物体が同じ「法則」に従って行動するというのは、当時としてはブレイクスルー発想の飛躍だった。リンゴや公転する天体だけでなく、万有引力の法則がわかれば、砲弾の軌道を決めて、敵の頭に着弾させることもできる。また、他の惑星に着陸するための宇宙探査機の軌道を決定することもできる。その他にも、いろいろなことができる。ニュートンの重力法則は 「万能」だと言われている。
「普遍的な法則」という考え方は大成功で、印象的な科学の発展につながった。しかし、複雑な、あるいは 「複雑な」システムを記述するのに、単純な法則を使うことはできなかった。たった3つの天体が互いの周りを回っているだけでも、その動きを正確に記述できる単純な方程式は存在しない。実際、リアルワールドのほとんどのシステムは方程式で記述することが不可能である。例えば、猫がネズミを追いかける軌跡を記述する方程式は存在しないし、ある人がある人を好きになることを記述する方程式も存在しないのと同じだ。どちらの場合も、ニュートンの「普遍的」法則に相当するものは存在しないが、人間の恋愛を方程式でモデル化することは不可能ではない(J. C. Sprottはジュリエッタとロミオのケースでまさにそれを行った18が、それは単なる遊びであった)。
複雑系は、別の種類の科学である。このシステムの定義はいくつかあるが、一般的には、「フィードバック効果」が支配するシステム全般を指すと言えるのではないだろうか。「フィードバック」とは、何かが他の何かに比例して反応するときに使う直感的な言葉である。恋愛の例で言えば、あなたの恋愛対象が対称的に反応して、あなたに恋をすることがある。この場合、「強化」または「肯定的」なフィードバックがある。つまり、あなたが口説けば口説くほど、相手は離れていってしまうのである。これは、「ネガティブ」または「ダンピング」フィードバックとして見ることができる効果である。そして、あなたの態度は恋人の反応によっても影響を受け、その反応があなたの態度を強めたり弱めたりすることもある。つまり、システムは振動したり安定したりするが、常に予測するのが難しく、単純な方程式では記述できないことが確かである。
20世紀になって、科学は複雑なシステムに注目するようになった。その結果、全く新しい調査方法が開発された。その一つが、ジェイ・フォレスターが提唱した「システムダイナミクス」と呼ばれる手法である。システムダイナミクスで開発されたモデルは、フィードバックがシステム内のあるストックから別のストックへの流れにどのように影響するかを記述するように設計されている。ストックとは、モデルが考慮する何かの量と定義される。生物集団の個体数、銀行口座の残高、漁業の漁船数などがストックにあたる。代わりに、フローは、ストックが時間と共にどのように変化するかを定義する。生物系では個体数の増加(または減少)、銀行口座では流入(預金)と流出(支出)である。
これらの要素は、複雑系の本質的な特徴であり、その内部フィードバックシステムが外的な摂動に対して、システムの状態を維持するように反応する傾向があることを強調して「複雑適応系」(CAS)とも呼ばれる。これは、「ホメオスタシス」と呼ばれる基本的な特性である。
システムダイナミクスモデルは、これらの要素を定量化してCASの挙動を記述する。社会経済システムの分野では多くの例があるが、この分野で最初に提案されたモデルの一つに、「捕食者-被食者」あるいは「狐と兎」モデルとも呼ばれるロトカ-ボルテラモデルというものが知られている。14 このモデルでは、捕食者のストックと被食者のストックが相互に影響し合い、2つの集団(捕食者と被食者)が永遠に振動し続けることになる。ロトカ・ヴォルテラモデルは単なる理論的なものではなく、少し修正したものでは、漁業が乱獲によって自滅する可能性を説明することができる。19 人が生きていくための資源を破壊するという発想は確かに愚かだが、非常に一般的でもある。バルディとペリッシは、カルロ・M・チポッラが以前に提唱した「愚かさの5法則」に触発された論文で、この効果を「愚かさの6法則」と名づけたのである。20
もちろん、フォレスターとLtGチームが目指したように、全世界の経済システムを記述するには、当時のコンピュータの性能の範囲内で、単純な捕食・被食システムよりも複雑なものが必要だった。そのため、世界システムの多くの要素は「アグリゲーション」、つまり1つの実体として考えられていた。しかし、それ自体が不利になるわけではない。集約されたモデルは不確実性が低く、値が定かでない多くの要素の挙動に従おうとするモデルよりも信頼性が高いかもしれない。
World DynamicsとThe Limits to Growthの基礎となるモデルでは、世界は農業、工業、人口など限られた数のサブシステムに分割され、サブシステムの要素間の関係は、時間の関数として繰り返し解かれる一連の方程式で記述されていた。1972年に発表された最初のLtGレポートでは、使用されたモデルは「World3」と呼ばれ、何百ものパラメータが含まれていた。しかし、モデルの「核」は比較的単純で、5つの主要なセクターに基づいていた:
- 人間の人口
- 非再生可能資源(鉱物)
- 再生可能資源(鉱物) 再生可能資源(農業)
- 資本資源
- 公害
これらのサブシステムの相互作用は、しばしば比較的単純な方法で記述することができる。例として、以下のパラグラフは、World3モデルの「コア」を、産業資本要素と他の要素との相互作用の観点から説明している(LtG21の2004年版より):
産業資本ストックは、莫大な資源の投入を必要とするレベルまで成長する。産業資本ストックは、膨大な資源の投入を必要とするレベルまで成長する。その成長の過程で、利用可能な資源の大部分を枯渇させてしまうのである。資源価格が上昇し、鉱山が枯渇すると、資源を得るためにますます多くの資本を使わなければならず、将来の成長のために投資できる資本は少なくなる。最終的に、投資は減価償却に追いつかず、産業基盤は崩壊し、産業からの投入に依存するようになったサービスや農業のシステムも一緒に崩壊する。
これらの関係には、フィードバック関係が含まれていることに注意してほしい。生物学のロトカ・ヴォルテラモデルにおける「捕食者」と「被食者」の振る舞いを彷彿とさせる状態である。つまり、「資本」が捕食者、「天然資源」が被食者の役割を担っている。もちろん、このサブシステムだけでなく、人口増加はサービスや食料の確保に単純に比例するわけではないことも考慮したモデルであった。成長は緩やかになり、ある一定の豊かさに達すると、出生率の低下と死亡率の増加が同時に起こる結果、人口が減少し始める。これは「人口動態遷移」と呼ばれる現象で、現在、世界の比較的裕福な地域のほとんどで観察されている。
LtGの著者らは、天然資源の利用可能性、汚染の影響、外部からの人的介入など、入力パラメータに応じていくつかの異なる可能性を探るために、モデルを使用した。BAU(通常業務)の概念に基づくシナリオでは、シミュレーション開始当初、豊富な天然資源を利用できることから、農業と工業の生産が指数関数的に急成長していることが示された。この段階では、公害は問題なく、設備や資源、人間の知識といった資本が成長する。
しかし、やがて天然資源は徐々に枯渇し、生産コストが高くなる一方、公害は成長に大きな影響を与える減衰要因になる。成長を維持するためには、より多くの資本が必要となり、やがて農業生産も工業生産も成長が止まり、ピークを迎えて減少に転じる。その後、蓄積された資本もピークを迎えて減少に転じる。人口は、経済の他の部門と並行して推移する。工業生産と農業生産のピークから数年後に成長が止まり、利用できる食料とサービスが減少するためだ。
この挙動は、著者らが「標準的な実行」または「基本ケース」と呼ぶシミュレーションで最も顕著に見られる。次の図では、1972年に得られた基本的な結果を見ている。
ベースケースモデル、1972年のLtGの研究結果
LtGの3つのバージョン(1972,22 1992,23,2004 21)すべてにおいて、このシナリオは、著者によれば、入手可能な中で最も信頼できるデータに基づいている。結果は、人口を除くすべてのパラメータについて基本的に同じであった。実際、1972年のシナリオには明らかな問題があった。農業がピークを迎えて衰退した後も、少なくとも20年間は人口が増え続けていたのである。少なくとも可能性は低いと思われたが、これは20世紀半ばの人口動態の変遷が、システムの崩壊後に「逆戻り」すると仮定した結果だった。つまり、十分な食料が確保できるのであれば、人々はサービスや工業製品の利用可能性が低下することに反応して、より多くの子供を産むようになるということである。この仮定は、後の計算では放棄され、危機的状況下で子孫を残す数を減らすという別の仮定に置き換えられた。いずれにせよ、世界的なピークを過ぎたあとの人口動態を予測することは不可能だが、この不確実性はLtG報告書の主要な結果を変えるものではない。
つまり、文明の未来は崩壊することだったのだ。しかし、それは何を意味していたのだろうか。崩壊は予測なのか、予言なのか、それとも何なのか?崩壊は避けられるのか?そして、もしそうなら、どのように?
物語の冒頭から、これらの点について多くの混乱があった。主な問題のひとつは、ベースケースシナリオを予測(あるいは予言)だとする人々だった。100年以上のスパンで未来を予測できるモデルはない。LtGの報告書は、当初から、さまざまな仮定や政策選択の結果を示すさまざまなシナリオを提供することを目的としていた。もし、天然資源が私たちが考えている以上に豊富だったらどうだろう?もし、エネルギー生産に技術的なブレークスルーが起きたら?もし、人類が人口増加を止めることができたら?
同じテーマで同じ手法を用いた3種類の本にわたって、すべての詳細を記述することは不可能だが、主な結果は次のように要約できる:
- 崩壊は、パラメータを合理的に仮定し、さらに経済成長を目的として天然資源の搾取を継続するすべてのシナリオの強固な特徴である。
- 例えば、エネルギーが無限であり、汚染がゼロであるといった極めて楽観的な仮定をした場合にのみ、技術によって崩壊を回避することができる。これは、LtGの著者たちが「Infinite in-infinite out」(IFI-IFO)と呼ぶアプローチである。
- 公害は崩壊を引き起こす重要な要因だが、その影響は通常、資源の枯渇によって世界経済が衰退の一途をたどった後にやってくる。
- 人間の人口も重要な要素だが、その減少は通常、システム全体がすでに衰退を始めた後に始まる。
- 21世紀中にシステムを安定させ、崩壊を防ぐことができるのは、人口増加の抑制、資源消費の削減、公害の抑制を目的とした特定の介入によってのみである。
- 衰退は通常、成長よりも速い。この点は、LtG研究の著者たちによって強調されることはなかったが、後にウーゴ・バルディによって特定され、「セネカ効果」と呼ばれるようになったものである。24
フォレスターとLtGグループの2つの報告書は、これらの結果に到達した唯一のものではなかったが、彼らの仕事は当時最も詳細で網羅的であった。その後、他の著者もさまざまな手法で世界崩壊を検証した。Joseph Tainterは、1988年に有名な『複雑系社会の崩壊』という本で、歴史家の視点を暴露した。25 中でもホールらは、文明の成長と衰退をEROI(エネルギー投下収益率)というパラメータと相関させ、枯渇によるEROIの漸減が人類全体の文明の衰退を招くと提唱した。26 今日、科学論文のデータベースであるGoogle Scholarで「文明崩壊」という言葉を探すと、このテーマに関する研究は1972年以降に237,000件、2020年だけでも23,000件近く発表されていることがわかる。明らかに、この考え方のインパクトは大きくなっている。
しかし、この分野の多くの研究にもかかわらず、崩壊が西洋文明の予想される特徴であるという考え方は、主流の議論では熱狂的に受け入れられることはなく、しばしば、「マルサス主義」、「破局主義」、「千年王国主義」などの様々な非難を生み出す。その理由のひとつは、LtG研究を間違っている、あるいは欠陥があるとしてうまく紹介した誹謗中傷キャンペーンにあるかもしれない。過去50年間の議論における崩壊に関する考え方の軌跡を理解するためには、ある程度詳細に検討する必要があるテーマである。
その反応悪い科学というゴミ箱へ
1990年代には、LtGの研究は明らかに欠陥があるとして、誰からもすぐに笑いものにされたと言うのが普通になっていた。しかし、そうではない。最初の反応は、好意的であり、時には熱狂的であった。一例として、『Up the Organization』(1970)の著者であるロバート・タウンゼント(シモンズ2000年引用)は次のように書いている:
『成長の限界』は世界中で大ニュースになった。その衝撃波は、私たちが最も大切にしてきた前提を崩すことになった。この本は、私たちが危険を冒してまで無視することのできる本である。
もし、この本が、唇を動かさずに読むことができるすべての人の心を揺さぶらないのであれば、地球は破滅してしまうだろう。
しかし、この『LtG』が激しい論争を巻き起こしたことは事実である。しかし、いくつかの点で、これは正常な反応であった。科学はそれ自体、複雑な適応システムであり、外部からの擾乱に対しては、そのホメオスタシスを維持することで反応する傾向がある。新しいブレイクスルーアイデアに直面したとき、最初の反応は熱狂的かもしれないが、これまで大切にされてきた前提が覆されれば、拒絶反応が起こるかもしれない。これは科学のバグではなく、特徴だ。これは、科学研究から定期的に生まれる多くのインチキなアイデアをフィルタリングするパターンである。ダーウィンの時代、19世紀半ばにはすでに、トマス・ハクスリー(「ダーウィンのブルドッグ」と定義されるのが好きだった)が、「新しい真理が異端として始まり、迷信として終わるのは通例の運命である」と述べている。
問題は、何が本物の革新(真理)で、何がすぐに消えてしまう流行(異端)なのか、ということである。誤りは常に起こりうるものであり、それを発見し修正するのが科学的議論の仕事である。そして、この問題は、善意の間違いだけではない。科学の分野によっては、データの改ざんやその他の詐欺が災いしている。スチュアート・リッチー著『サイエンス・フィクション』(2020)などの本を読めば、特に金銭的に大きな損失や利益がかかっている医学において、この状況がどれほどひどいものか、ある程度わかるだろう。
科学者も人間であり、データは真実の福音書ではない。データは常に不完全であり、不確実性に影響され、選択する必要がある。羽毛、紙、鳥に関するすべてのデータを無視することなく、ニュートンの万有引力の法則を開発しようとすれば、その問題がわかるはずだ。実際、科学はコンセンサス形成のための微調整マシンである。新しいデータをスムーズに吸収し、政治にありがちな党派的分裂を起こさないような緩やかなプロセスで、まさに進化してきたのである。
科学は、中世にはディスパティオと呼ばれ、古典時代の修辞学にルーツを持つ古代の方法から派生した手順を用う。これは、さまざまな論題の支持者が互いに対決することで、十分な知識を持った聴衆を説得するために、自分たちができる最善の論証を駆使して問題を議論するというものである。中世の論争術は非常に洗練されたものであったが、想像の通り、神学論争術は通常、真に相容れない立場、例えばユダヤ人をキリスト教徒にするよう説得することを調和させることができなかった。何度も試されたが、その結果に驚くことはないだろう。しかし、こうした論争が良い妥協につながることもあり、対立を(少なくともしばらくの間は)言葉のレベルにとどめることができた。
現代の科学では、ルールはいくつか変わったが、考え方は変わらない。専門家は、自分ができる最高の議論を使って相手を納得させようとする。それは議論であって、喧嘩ではないはずだ。マナーを守り、お互いに理解しあえる言葉を話すことが基本である。そして、それだけでなく、議論のフレームとなる基本的な考え方に合意する必要がある。中世の神学者たちはラテン語で議論し、キリスト教の聖典に基づいた議論をすることに合意した。今日、科学者は英語で議論し、科学的手法に基づいて議論することに同意している。
科学の黎明期には、1対1のディベートが行われていた(例えば、1860年にダーウィンの思想について、トマス・ハクスリーとウィルバーフォース大司教が行った有名なディベート)。しかし、現在では、それはまれなことである。ディベートの舞台は科学会議やセミナーで、複数の科学者が参加し、自分の意見をいかに上手に発表するかによって「威信点」を得たり失ったりする。時には、発表者、特に若い科学者が、ネイティブ・アメリカンの成人式のような小さな再現で、聴衆から「尋問」されることもある。しかし、最も重要なのは、会議のいたるところで非公式の議論が行われることである。このような会議は休暇になるはずもなく、顔を合わせて意見を交換するための機能的なものである。科学者も人間であるから、お互いの顔を見て理解し合う必要がある。多くの科学的イノベーションは、カフェテリアで数杯のビールを飲みながら生み出されている。パワーポイントのプレゼンテーションを見ていて、天から一筋の光に打たれた人はいないようだ。
中世の神学者よりも科学者の方が意見を変えるのが上手で、年配の科学者は古い考えに固執する傾向がある、とは言い切れないだろう。科学は葬式1回分ずつ進歩する」と言われることがあるが、それは間違いではないが、確かに誇張である。科学的な見解は、古参者が死ぬのを待たずとも、変わるものである。学会での議論は、科学者の才能、優れたデータの入手、そして全体的な能力によって、決定的に一方に傾くことがある。
だから、LtG研究の発表後、コンセンサス・マシンが本来の役割を果たし、コンセンサスを得るか、少なくとも意見の対立する点についての妥協に至るはずだったのである。しかし、そうはならなかった。
LtG研究は、その方法と結果があまりにも革命的で学際的であったため、コメントしたほとんどの科学者は、その方法とモデルの詳細については言うまでもないが、それが何であるかを理解することができなかっただけなのである。
理解不能の典型的な例は、ジョン・コーヘラーが1973年に『政治学雑誌』27に書いたLtGの書評: 「もしこの本の要点が、時間の経過とともにtが大きくなるとaetも大きくなることを観察するだけなら、その205ページのかなりの部分が不要である。」 これによって、コーヘラーは、この本の手法や目的を全く理解していないだけでなく、世界経済の有効なモデルとして指数関数的成長を扱った(そして否定した)最初の2章以上を読もうともしていないことを示した。
50年後に見直されたこの議論では、特にマグネ・マートヴェイトが、悪魔化された後の研究の最初の再評価の一つで指摘したように、この研究についての重要な点を完全に取り上げていないのである。28 ほとんどの批判、特に最も厳しい形の批判は、主流紙や科学雑誌の「意見」欄で発表された個人的な意見の形で届いた。ほとんどの場合、批判者はジョン・コーヘラーよりもうまくはなかった。ほとんどの批判は、不信の表明か、LtG研究の誤解に基づく観察という形で届いた。
後者の典型的な例としては、「天然資源の見積もりが甘かった」「技術進歩が考慮されていなかった」という意味で、研究の最初の前提が「悲観的すぎた」とするものがよく見られた。しかし、この研究の目的と方法を理解すれば、これらの発言が大きく的外れであることはすぐにわかるはずだ。LtGの研究では、天然資源が推定よりも豊富である可能性や、技術進歩の影響も考慮されている。後者は、たとえば安価なエネルギーが豊富に手に入るなど、すべてを変えてしまうような形でもシミュレーションされていた。この研究の著者たちは、未来は確定したものではなく、また確定し得ないものであり、人類が行う選択と技術改良の可能性に左右されるものである、という考えを明確に持っていた。しかし、このような議論をする人たちは、研究の基本的なコンセプトを理解できていないようだった。
残念ながら、LtG研究が巻き起こした大きなノイズの中で、真剣な科学的議論に必要な種類の批判を行うスペースはほとんどなかったのである。この点に関する詳細な議論はここでは割愛し、読者には『成長の限界 Revisited』を読んでもらうことにする。1 それでも、ここでは 「科学的」と呼べるようないくつかの主要なポイントを要約してみることにする。
LtG研究のモデルを検討した数少ない研究の一つは、サセックス大学の科学政策研究ユニットによって1973年に出版された『運命のモデル』という本に見出すことができる。29 この本は、LtG研究をいくつかの視点から検証した多人数執筆の本である。ほとんどの場合、誤解や不信の表明、また政治的な攻撃について書かれている。しかし、この本には、編者のH.S.D. ColeとR.C. rnowが書いた章があり、これは今日でも、LtG研究の基礎となった「World3」モデルに対する数少ない詳細な批判の一つである。
ColeとCurnowは、このモデルの欠点と思われる点について、いくつかの興味深い見解を示している。また、彼らの研究は、モデルが含まれる変数にどれだけ敏感であるかを見極めようとした点でも注目に値する。これは、現代の「感度分析」という概念につながる傾向の一部であり、マルチパラメータ動的モデルによるすべての研究に必要なものであると考えられている。30 LtG研究の全体的な評価は否定的であったが、モデルに重大な矛盾や欠点があったとは報告できなかった。他の研究でも、World2とWorld3のモデルは、その内部構造において基本的に正しいと結論づけている(例えば、CuypersとRademaker 31 参照)。
LtG世界モデルの解体を試みたもう一人の著者は、気候変動モデルとマクロ経済モデルの統合に関する研究で2018年ノーベル経済科学賞を受賞したことで今日最もよく知られているWilliam Nordhausである。1972年、NordhausはYale大学の若い経済学者であり、彼は1973年にThe Journal of Economicsに掲載された論文で批判を発表するまでに長い時間はかからなかった。32 この論文はフォレスターの『ワールド・ダイナミクス』を論じるためのものであったが、LtG 研究を広く対象としていた。
ノルドハウスは、フォレスターのマルサス主義、思い込み、謙虚さの欠如、科学的研究の基本原則の無視などを非難し、その攻撃は言葉を選ばなかった。ノルドハウスの批判の中心は、この論文の副題にあった: 「データなき測定」である。ノードハウスは、「経験的な検証を受けていないシミュレーション・モデル […] は、意味がない. (原文では斜体)と述べている。確かに些細な種類の批判ではない。もしフォレスターが本当に「データなき測定」を行っていたのなら、それは単にモデルのエラーや入力パラメータの変更の必要性の問題ではなかったのである。世界のモデル化の全貌は、無能な研究者集団が行った無益な運動だったのだ。
ノルドハウスの攻撃性はやや極端だったが、科学的な議論では珍しいことではない。科学の世界では、研究者は通常、新しいアイデアや新しい結果を発表することで「名声ポイント」を獲得する。しかし、「ポイント」は、同僚の結果や解釈を否定することによっても得ることができる。その場合、科学者は非常に洗練していない人法で行動することがあり、同僚の研究を攻撃する場合、彼らはしばしば囚人を取らない。NordhausのForresterに対する攻撃もそうだった。しかし、もちろん、重要なのは言葉遣いではなく、その非難が正当なものかどうかである。フォレスターは、本当にノルトハウスの言うような無頓着な人間だったのだろうか。
ノルトハウスは、「データなき測定」という非難を実証する必要があった。彼は、フォレスターの著書『World Dynamics』に掲載されているフォレスターのWorld2モデルの全貌を調べることができた。そのモデルから、ノルドハウスはGDPの関数としての出生率に関する方程式を選び、それをプロットして、確かにその方程式は、過去のデータとは少しも一致しない結果を生み出したと主張した。Q.E.D.?
残念ながら、この手順は、複雑なシステムがどのように機能し、どのようにモデル化されるかを完全に誤解した結果であった。複雑なシステムのモデルを構成する一つの方程式は、他のすべての方程式の影響を考慮しなければ意味がない。飛行機のエンジンをテストベンチでテストして、それが飛ばないことがわかったら、飛行機も飛べないと結論づけることを想像してほしい。このような論理の飛躍は、不当としか言いようがない。
フォレスター氏自身、ノードハウス氏への反論の中で、この点を説明している。33 式をモデルの中で適切に使えば、過去のデータを再現することができることを示した。確かに、フォレスターもLtGの著者も、現実のデータを無視していたわけではない。残念ながら、ノードハウスの論文を掲載した雑誌は、フォレスターの反論の掲載を拒否した。これは、LtG研究の議論が科学的な議論のルールを逸脱していることを示すもので、ノードハウスの攻撃の激しさよりも、攻撃された人に反論する機会を与えないことが問題だったのである。フォレスターの反論は、ほとんど知られていない雑誌(Policy Sciences)に掲載され、その結果、多くの人が、ノルドハウスの論文は、システムダイナミクスのモデル化アプローチを一度、永遠に破壊したのだと考えた。
その後、Nordhausは1992年にBrookings Papers on Economic Activityに発表した論文で、再びシステムダイナミクスをターゲットにした。34 この時、彼はあまり攻撃的ではなかったが、それでもWorld3モデルが「致命的」であると非難した。つまり、経済崩壊の仮定がモデルに組み込まれており、したがって、モデルが崩壊を予測することは驚くべきことではなく、有用でもない、という意味においてである。この考え方は、はっきり言って議論の余地がある。「World3」モデルの方程式のどこにも、崩壊を引き起こすために特別に作られたパラメータや方程式はない。むしろ、産業システムの急速な衰退は、経済学でよく知られた仮定である「収穫逓減」の結果である。だからといって、このモデルを批判することはできないが、「致命的」だからダメだというのは、問題の核心に触れない表層的な批判である。
Nordhausは、LtGモデルと、崩壊を起こさない彼のモデルを対比させた。しかし、それはLtGモデルが誤りであることを示すものではなく、異なる結果をもたらす異なるモデルを考えることが可能であることを示したに過ぎない。1996年、Robert Costanza 35はNordhausの論文を検証し、「NordhausはForresterを激しく批判したのと同じ罠にはまった」と指摘した。Costanzaは、Nordhausの「DICE」モデルを批判する中で、「人口増加と技術変化は外生的で、自然資本は完全に欠落している」「DICEでは、経済は自然界からの真のフィードバックを受けずに陽気に進む」という事実を含む、5つの根本的欠陥を挙げた。
この議論には明らかに強い反対意見があったが、それは本当の問題ではなく、LtG研究の著者に批判に答える機会が与えられなかったことである。それどころか、ノードハウスの1992年の論文には、他の経済学者によって書かれた「コメントと展望」というセクションがあり、これはサメによる「餌付け騒動」の学術版と表現するのが最もふさわしいかもしれない。
この短いレビューから、『成長の限界』に関する科学的議論がいかにお粗末なものであったかがわかる。科学者たちは、このモデルの妥当性を議論するのではなく、すぐに「成長の限界」のアプローチを完全に否定する人々と、それを熱心に採用する人々の2つの陣営に分かれてしまったのである。この2つの陣営の間には、ほとんど何のつながりもなかった。LtGを完全に否定する派と、LtGを熱狂的に支持する派とに分かれたのである。まるで大海原で遭遇した敵艦のような反応である。
それは、後に「生物物理学」と呼ばれるようになる分野で、経済学者と実務家のアプローチが相容れないものであったことが主な原因であった。経済学者たちは、経済は価格や市場に関する要因によって支配されており、枯渇や汚染といった物理的な要因は小さな影響しか及ぼさない、と完全に信じ切っていた。この考え方の極端なバージョンでは、鉱物資源はまったく制限されていないとさえ言われることがある。例えば、1981年にジュリアン・サイモンが『成長の限界』への反論として書いた『究極の資源』という本では、5つの価格動向から世界の鉱物資源は「無限」であると結論付けている。また、ノーベル経済学賞を受賞したロバート・ソローが1974年のアメリカ経済学会で発表した「…世界は事実上、天然資源がなくてもやっていける」という発言も有名である。この発言は、ソローの論文の全文と照らし合わせれば、見た目ほど不条理なものではない。しかし、経済学者がいかに物理的要因よりも市場要因を重要視しているかを示す証拠である。
全体として、価格が鉱物資源の採掘の経済性に影響を与えることは確かだが、「貨幣」という純粋にバーチャルな存在が、鉱物資源という物理的な存在を生み出すことができると主張することは困難である。価格と市場の役割を強調するあまり、多くの経済学者が「LtGモデルは価格を考慮に入れていない」という欠陥を指摘した。これは、初期バージョンのモデルにおいて、価格が明示的なパラメータであったという意味では事実である。しかし、それは問題ではない。この問題は、あるパラメータがどのように表現されているか、むしろ表現されているか否かに軸足を置いている。LtGモデルは、ある商品を生産する必要性が高まったときに、経済のある部門から別の部門に資本を移動させるシミュレーションができるように作られている。この移動は、モデルのパラメータとして価格を明示的に設定しなくても、価格の影響をシミュレートすることができる。この資本移動のプロセスこそが、最終的にシステム全体の崩壊を招いたのである。
このように、当初はLtGの結果について科学的な議論を行おうとしていたのだが、1980年代後半になると、LtG研究は批判ストームにさらされ、間違った科学理論のゴミ箱に追いやられるようになり、その考えは失われてしまった。1989年、ロナルド・ベイリーが『フォーブス』誌上で、ジェイ・フォレスターを「ドゥーム博士」と呼び、全面的に攻撃したのがきっかけだった。その中でベイリー氏は、「成長の限界」研究を批判し、「1972年の成長率では、1981年までに金が、1985年までに水銀が、1987年までに錫が、1990年までに亜鉛が、1992年までに石油が、1993年までに銅、鉛、天然ガスが枯渇すると予測した」として、その間違った予測に非難している。その後、1993年、ベイリー氏は『エコスカム』という本の中で、再び告発を繰り返した。このとき彼は、LtGの「予言」は何一つ当たっていないと主張することができた。
ベイリー氏の批判は、LtGの研究を誤って解釈した結果であった。彼は、1972年に経済学者のグループによってなされた初期の批判を拾っていたのである。37 最初の論争の熱気の中で、彼らはLtG本の第2章にある表の意味を完全に誤解していた。この表では、米国政府から提供されたデータを使って、指数関数的な連続成長という仮説でいくつかの鉱物資源の存続期間を推定していた。この仮説は、著者自身が「非現実的」と定義したものである。
ところが、経済学者たちは、この表の数字を淡々と「予測」とし、LtG研究の著者たちが「非現実的」と定義した数字で「非現実的」であったと批判するようになった。単純に不条理であり、それが初期の議論においてその攻撃が注目されなかった理由かもしれない。
しかし、それから約20年後、ベイリーが再びこの数字を取り上げたとき、彼の批判は異常な成功を収めた。1980年代後半になると、人々はLtG研究の内容をほとんど忘れていたことと、20年近くが経過し、「非現実的」な消耗時期がより近くなり、現実との対比がより鮮明になったことが主な理由である。それ以来、ダムは決壊し、科学界や主要メディアの誰もが、『成長の限界』は「間違った予測」を行ったと繰り返すようになった。
この研究が何の予測もしていないこと、間違った予測をしていないことは、ほとんど問題にはならなかった。この間違った予測という話が本当かどうか、誰も確認しようとはしなかったようだ。ほとんどの人は、ベイリーが言ったことをそのまま繰り返すことで満足しているようだった。そして、誰もが同じことを何度も繰り返すと、それが真実として認められるようになる。この場合、文書化された詳細なLtGの研究は、それ自体が戯画化されたものとなった。チキン・リトルのように、空が落ちてくると本気で信じていた科学者たちによって作られた一連の素朴な声明である。
このような出来事について、後に問われた一つの疑問は、LtG研究に対する攻撃は、LtGのアイデアが自分たちの経済的利益を損なうと考えた産業界や政治家のロビーによって仕組まれたものではないかということである。この疑問は、決して突飛なものではない。「スピンキャンペーン」は政治の世界だけでなく、科学論争においても、科学的な論文を否定し、論破するために使われてきたことが分かっている。ソ連では、党の方針に従わない科学者は、政府主導の報道機関によって悪魔化され、疎外された。西側では、悪魔化キャンペーンの起源は通常隠されていたが、政府の調査によってその内部メカニズムが明るみに出るケースもあった。アメリカのタバコ産業が、タバコの健康への悪影響を示す科学的研究を貶め、悪者にしようとしたのがそうであった。これは1960年代に始まり、1980年代にピークを迎えた秘密裏に行われたスピンキャンペーンであり、後のいくつかの研究でも述べられている。38 ,39 ,40 また、レイチェル・カーソンの1962年の著書『沈黙の春』を貶めるために、米国の化学産業が資金を提供したスピンキャンペーンが行われた。41 現在、気候科学を信用させないために同様の方法が使われている可能性がある。42
『成長の限界』の場合、組織的で資金を提供した反対運動の証拠はないが、それを排除することもできない。しかし、全体的に見れば、誹謗中傷キャンペーンはほとんど自然発生的なものであった可能性が高いと思われる。信じたいものを信じ、信じたくないものを信じないという人間の傾向の結果である。結局、科学的な議論と見せかけて、この議論は最初から政治的なものだったのである。
しかし、LtG研究に深い政治的意義があるのなら、政治的な用語で議論するのは至極まっとうなことであった。それは、アウレリオ・ペッチェイがローマクラブに最初から与えていた刻印の結果であった。共通善のために世界システムを管理するという考え方は、人々のニーズとその尊厳に深く注意を払うことを意味していた。ペッチェイにとって「政治」とは、ギリシャ語で「都市の問題」という原義を持つ。彼は、世界を一つの大きなポリス(都市)としてとらえ、その都市はすべての人のものであり、すべての人の合意のもとに管理されなければならないと考えた。これは、ローマクラブのアプローチであり、現在もそうだ。
もちろん、誰もがこうした考え方に賛同したわけではない。ある人はペッチェイをただの夢想家だと思い、ある人は危険な革命家だと思った。彼の思想は、政治を国家間、イデオロギー間、宗教間の競争と見なす考え方としばしば対照的であった。ジョルジョ・ネッビア43とマウリシオ・ショイジェット44の書評は、ローマクラブの立場に対する世界中の反応が、いかに異なる政治的態度によって形成されたかを教えてくれる。ソ連では、公式の反応として、LtGの本は資本主義の崩壊をよく描写しているかもしれないが、計画経済によって崩壊を回避する共産主義社会とは何の関係もない、というものだった。多くの貧しい国々では、将来の崩壊のシナリオは、豊かな西洋の支配を永続させるための詐欺、貧しい人々に人口削減を押し付けるための詐欺、あるいは植民地主義への回帰の前触れであるとみなされた。欧米諸国では、政治的志向の違いによって、LtGの結果に対する反応が決まることが多かった。左派は将来の脅威を労働者階級の従属的な立場を正当化する試みと見なし、右派は自由市場と経済成長という自分たちのビジョンと相容れないものと見なすことがしばしばあった。LtGに対する肯定的な政治的反応は、穏健なリベラルな立場からのものが最も多く見られた。45
このような一般的な線引きから見えるよりも、話は複雑であった。共産圏では、公式の反応は否定的であったが、LtG研究は重要な印象を残した。1980年代、ヴィクトル・ゲロヴァーニと何人かの同僚がLtGモデルをソ連に適応させ、彼はその結果を『グローバルシステムにおけるソ連とロシア』(1985)という本で発表した。その結果は、予想通り、世界経済に影響を与えたのと同じ理由で、ソ連が崩壊に向かう独自の軌道をたどっているというものだった。デニス・メドウズが語った話によると、ゲロバニは「国の指導者のところに行き、『私の予測では、あなたには可能性がない。政策を変えなければならない』と言った。すると、指導者は『いや、別の可能性がある。予報を変えればいい』と答えた」
メドウズの逸話は個人的な記憶だが、基本的にはエグレ・リンドゼビシウテがソ連崩壊について行った研究によって確認されている。46 『成長の限界』が無視されたのは事実でないことがわかった。この本はロシア語に翻訳されたが、ごく限られた人たちにしか配布されなかった(ちなみに、活発な闇市場が形成された)。ソ連の科学者の何人かはこの研究を知っていたし、著者とも交流があり、そのうちの何人かは連邦の指導部にシステムが崩壊しそうだと警告する努力をしたが、それほど大きな影響はなかった。総じて、ソ連指導部は自国が経済的に困難な状況にあることは認識していたが、崩壊に対する対策を講じることは全くできなかったのである。1979年のアフガニスタン侵攻など、彼らの行動の中には、連邦の崩壊を早めるものもあったと言えるかもしれない。また、現在、世界の複数の地域で、まったく同じような状況が存在していると言えるかもしれない。ソビエト社会と西欧社会の軌跡の類似性は、とりわけドミトリー・オルロフがReinventing Collapse (2011)などの一連の著作で指摘・記述している。47
鉄のカーテンの向こう側にある世界の別の地域、中国では、LtG本はより成功を収めたかもしれない。中国政府が1970年代から2015年まで実施した「一人っ子」政策の原点はこの研究であり、出生率を下げる効果があったのではないかとよく言われるが、中国は人口動態の転換期を迎えただけなのかもしれない。中国政府の決定がLtG研究の影響を受けたという証拠はないが、それは自明のこととされがちである。48
欧米では、LtG研究はほとんど、あるいは全く直接的な政治的影響を与えなかったと言える。当初、欧米の指導者の中には同情的な人もいたが、この研究が推奨する政策を実行に移そうとすることはなかったようだ。やがて、LtG研究の科学的妥当性を否定するキャンペーンが、その政治的内容にまで波及していった。その結果、この研究とその推進者は、少なくとも主流派の議論では、政治的に言及されなくなった。彼らは、隠された動機がある、世界の陰謀の一部である、「黒い人種」の絶滅を計画しているとまで非難された。また、天然資源を公平に分配するためには、その利用可能性を考慮する必要があると考え、「逃避主義」とも非難された。ローマクラブは、人類の絶滅を目的とした暗黒の秘密組織とされた(この種の非難は、現在のソーシャルメディアでも見受けられる)。クラブは「イルミナティ」などの伝説的な悪の集団とつながっていると言われていた。
20世紀末には、LtGを批判する側の勝利は完全なものとなり、この研究は無関係かつ信用を失ったかのように思われた。しかし、議論は決着したとは言い難いものだった。
再評価
21世紀に入っても、LtG研究に対する世論の否定的な姿勢は変わらないが、再評価の兆しも見えてきた。その一因は、「ピークオイル運動」であろう。1998年、Colin CampbellとJean Laherrèreは、Scientific American誌に「The End of Cheap Oil」というタイトルで発表した論文で、ハバートの考えを再検討した。49 その後、キャンベルとラヘレールは、世界の石油生産とその人類社会への影響を研究するために、ピークオイル・ガス研究協会(ASPO)を設立した。ASPOは、石油生産のピークが西洋文明の歴史において重要な出来事であり、ピークに達することは暗く悲惨な結果をもたらすという基本的な考え方に立っている。ASPOは、21世紀の最初の20年間に起こるとされる危機を防ぐために、政府によって何かが行われることを期待して、ピークオイルの概念を普及させる試みを行った。
ピークオイル運動は、約20年という比較的短いサイクルで進行し、在来型石油の生産がピークに達したと思われる2008年ごろにピークを迎えた50。50 その後、「シェールオイル」に熱狂したこともあり、またピークと衰退を避けるためにできることはほとんどないと理解されたこともあり、この議論はほとんど放棄された。しかし、ピークオイルの概念が、LtGの研究ほど強く、徹底的に攻撃されたことはなかった。つまり、石油の枯渇に関する研究の普及が、枯渇などの物理的要因による経済衰退という概念の受容を変えるのに役立ったのである。
ある意味で、ASPOの見解は、LtG研究の見解と似ており、どちらも鉱物資源の枯渇を世界経済の根幹に関わるものとして捉えていた。また、ピークオイルの基礎となる理論は、LtGのモデルを単純化したものであるという議論もあった。51とはいえ、両者の接触は散発的なものにとどまっていた。しかし、ASPOとLtGの両方の視点を理解し、その共通点を見出す人々もいた。実際、21世紀に入ってからLtG研究の再評価が行われたのは、ASPOのメンバーであるマシュー・シモンズ(52) の仕事であった。シモンズ氏は、自分の分野で起こっている枯渇による衰退の傾向を目の当たりにした。彼は、1972年に出版されたLtGの本を見直しに行ったところ、驚くべきことに、一般に言われているような間違いは全くなかった。それどころか、世界の状況を説明するのに有効だったのだ。
新しい世紀を迎え 2004年にLtG研究の原著者の何人かが、「The 30-year update」という副題で、LtG研究の再検討を発表した。21 他の何人かの研究者も、LtG研究を好意的に再検討している。Myrtveitは、1970年代に行われた議論を再検討し、LtGに対して決着がついたとは言い難いことを発見した。2011年、Bardiは、この研究結果に関する一般的な誤解のいくつかを再検討した。53 また、他の研究者もこの研究のいくつかの側面を再検討している。54 ,55 ,56 ,57 LtGシナリオと現状を比較したGaya Herringtonによる最近の論文58は、主流メディアで注目され、広く読まれた。
LtGの研究に対する最も包括的なレビューは、おそらくターナー59によるもので、彼は、研究の「ベースケース」シナリオは、世界経済システムの歴史的進化に最も適合するものであると結論付けた。全体として、シナリオデータは歴史的データから15%以上外れることはなく、シナリオが数十年に及ぶことを考えると、極めて良好な結果であった。
つまり、「成長の限界」研究は、著者たちの想像を超えた先見性を持っていたのである。実際、最近のいくつかの出来事は、ほとんどのLtGシナリオが予見していた世界経済の崩壊が間近に迫っていることを示唆する不吉なヒントであると考えられる。
LtGの研究が予言的であった可能性があるもう一つの分野は、公害の問題である。1972年当時、「人為的な地球温暖化」という概念は、まだ議論の端緒についたばかりで、LtG研究の1972年版ではほとんど言及されていない。それにもかかわらず、著者たちはモデルの中で、どのような種類のものかを特定せずに汚染を表現するような集計パラメータを使用した。つまり、このパラメータは、若干の注意は必要だが、地球温暖化の主因である大気中の二酸化炭素(CO2)の過剰に比例すると見ることもできる。また、この分野でも、モデルは現在進行中のトレンドをうまく表現しているように思われる。59 1972年の「ベースケース」シナリオによると、大気中のCO2濃度が減少し始めるのは2040年頃とされている。予言として受け取る必要はないが、ほとんどの「ビジネス・アズ・ユージュアル」気候モデルと一致しているようであり、実際、CO2排出量を抑制しようとするあらゆる試みにもかかわらず、大気中の濃度は増加し続けている。
近年、地球温暖化や気候変動は、環境保護運動の中心的なテーマとなっている。そのため、資源枯渇の重要性が軽視され、LtG研究のような統合的なアプローチが重要であることが証明されたのかもしれない。いずれにせよ、気候モデル研究者は、自分たちの立場がLtGの著者と同じになることを発見した。彼らのモデルは科学的環境の外では広く信じられておらず、モデリングの結果を政治の場に持ち込もうとした試みは、世界的に失敗した。気候科学が失敗した科学理論のゴミ箱に入れられたわけではないが、このような展開が将来起こりうる可能性は否定できないだろう。
もうひとつ、地球規模で再び注目されているのが人口問題である。「人口抑制は、LtGの研究以前から議論されていたことだが、その人気は、同じたとえをたどっている。つまり、1960年代から70年代にかけての一時期の強い関心の後、その概念は悪魔と化した。今日、人口に関する議論が再開される兆しがあるが、人口過剰は依然として政治的に負荷のかかる用語であり、それについて意見を述べる人々に対して大量虐殺の意図を持つという非難を生み出す危険がある。
未来
今日、私たちは、アウレリオ・ペッチェイを中心とする知識人グループ「ローマクラブ」が1968年にスタートした時点に立ち戻っている。彼らは野心的な目標を掲げ、「成長の限界」研究を後援し、それが「世界問題」あるいは「人類の苦境」と呼ばれるものを理解するのに役立つだろうと考えていた。彼らは、「成長の限界」研究の結果に基づいて、世界の経済システムを、すべての人に合理的なレベルの物質的繁栄を提供できるものに変える必要があることを、国民や世界の指導者に納得させることができると信じていたのである。しかし、予想通り、この考えを実行に移すことは非常に困難であった。
まず、「理解されにくい」という問題があった。そのため、LtGの研究は広く誤解されることになった。シナリオは破滅の予言とみなされ、協調行動の必要性は世界独裁の要請と解釈され、平等の訴えは共産主義を世界に押し付けようとする試みと解釈された。もちろん、共通善のための政策は、化石燃料産業など再生不可能な資源で栄え、大規模な汚染をもたらす経済部門にダメージを与えることは避けられない。政治的な反対運動は当然の結果であった。
それから50年、現在の世界情勢を見ると、世界経済が崩壊する可能性は、奇想天外なカタストロフィズムではなく、遠い未来ではない現実の可能性であることがわかる。その可能性は、公式の楽観主義が依然として支配的であるにもかかわらず、市民や意思決定者の間で注目されている。生態系の状態についての心配は言うまでもない。惑星生命システムの崩壊は、経済的な破綻だけでなく、人類という種の絶滅につながる。
しかし、仮に50年前のLtGの分析が基本的に正しかったということで合意が得られたとして、この問題にどう対処すればいいのだろうか。
まず考えられるのは、技術的なことである。1970年代以降にはなかった可能性が、今、あるのだろうか。太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーの分野では、目覚ましい進歩があった。太陽光発電の価格は化石燃料の価格より安く、現在の太陽光発電技術ではリサイクルできないレアメタルは必要ない。また、エネルギー投資に対するエネルギー回収率(EROI)26においても、現在の値は平均的な化石燃料の生産量よりも良好である。60 また、リチウムベースのバッテリーも目覚ましい進歩を遂げ、燃焼エネルギーを使用する自動車に匹敵する重量と航続距離を持つ道路用自動車を可能にした。電子データ処理技術は、かつて高いエネルギー投入を必要とした多くの分野でより高い効率を可能にしている(例えば、書籍『Come On!(2018) von Weizsäcker and Wijkman著)。最後に、タンパク質だけでなく他の栄養素も豊富に含む微生物バイオマスの培養に光エネルギーを利用し、必要な土地面積の点で、現在のあらゆる農業プロセスの10倍以上の効率を実現できる「光起電力食品」などの印象的なイノベーションがある。61
問題は、このような新技術の登場がまだ先であり、再生可能エネルギーが世界のエネルギー生産に占める割合がまだ小さいことである。同時に、世界のインフラや産業・農業システムは、依然として化石燃料と伝統的な技術に大きく依存している。そのため、崩壊に向かう軌道を変えるには、新しい技術の登場は遅すぎるかもしれない。特に農業の問題は深刻で、現在も化石エネルギーを食料に変換するシステムとして残っている。化石時代以前のような、真に持続可能なプロセスに戻すことは、一部の研究で主張されているように不可能ではないが、膨大で費用のかかる作業である。
私たちが直面している問題は、ウーゴ・バルディによって、「種まき人の問題」と呼ばれ、「種まき人の戦略」を用いて解決されることになった。63 古代の農民を想像してほしい。彼らは、今年の収穫の一部を翌年の種として保存する必要がある。もし、その代わりに家族が収穫物をすべて食べてしまったら、翌年は飢えてしまう。私たちも同じような境遇にある。化石燃料が高価になったり、地球の気候に不可逆的なダメージを与えたりする前に、化石燃料をスムーズに代替できるよう、現在のエネルギー生産(収穫)のかなりの部分を「種」として投資し、新しいエネルギー生産システム(次の収穫)を迅速に開発・導入しなければならない。つまり、化石燃料をなくすためには、化石燃料が必要なのだ!
移行に必要な投資は、システムダイナミクスモデルを使って定量化することもできるし64、投資したエネルギーに対するエネルギーリターン(EROI)に基づく考察だけでもよい。65 その結果、移行は不可能ではないが、十分な速さで移行するには、近い将来導入されると合理的に予想できる以上の投資が必要であることがわかった。だからといって、新世代の再生可能技術が、来るべき経済の衰退を和らげ、人類が気候に与える影響を軽減することができないというわけではない。しかし、100年以上続いているトレンドを技術で覆すことは期待できない。私たちは、1970年代に初めて指摘された問題から、いまだに抜け出せないでいる。私たちは、惑星コモンズを破壊することなく管理する必要がある。
ローマクラブやLtGの著者たちは、地球のコモンズを管理するために世界レベルで協調して行動する必要性をしばしば述べていたが、これは世界の意思決定の場にいる他の多くのアクターに共有されている懸念である。環境と乱開発の脅威と闘うためのグローバルな行動は、国際条約によって得られるというのが、この点に関する一般的なコンセンサスであったように思うし、現在でもそうだ。簡単に言えることだが、実践するのはそう簡単ではない。
これまでのところ、行動のほとんどは警句に基づくものであった。資源を無駄にしない、汚染しない技術を使う、エネルギーをできるだけ消費しない、地元のものを食べるなど、善良な地球市民は、さまざまな徳の高い行動をとるべきだと言われている。しかし、一個人や一家族が経済から「プラグを抜く」ことは不可能であり、持続可能性に価値を見出さない経済搾取システムに対して大きな影響を与えることはできない。
この種の行動の効果が乏しいという問題は、いわゆる「ジェヴォンズのパラドックス」、あるいはその類似バージョン(例えば、カズーム・ブルークスの仮定66)によってさらに悪化する。これらの概念は、経済プロセスの効率が高くても、資源の消費が少なくなるわけではないというものである。これはパラドックスではなく、システム的な世界観にしっかりと根付いた原理である。より効率的な消費者、より良心的な消費者によって解放された資源は、より効率的でない消費者によって使用される可能性が高い。これは、消費者個人だけでなく、集団や企業、国家全体に対しても有効である。例として、いくつかの西洋経済の脱炭素化は、主に汚染産業やプロセスを非西洋諸国に移転することによって得られたものである。
ジェヴォンズのパラドックスは、エネルギー効率が向上すると、そのエネルギー源の消費が増加するという経済学の理論である。これは、技術的進歩によって効率が向上すると、その結果生じるコスト削減が新たな需要を生み出し、結果として全体的な資源の使用量が増えるという現象を指す。
このパラドックスは、19世紀のイギリスの経済学者ウィリアム・スタンリー・ジェヴォンズによって最初に記述された。彼は、石炭のより効率的な使用が工業化の進展を促進し、結果として石炭の消費が増加したという、19世紀のイギリスの産業革命の状況を観察した。
ジェヴォンズのパラドックスは、エネルギー政策や環境政策、持続可能性の議論など、多くの領域で参照される。たとえば、自動車の燃費が向上したとしても、その結果として車の使用が増え、全体的な燃料の消費が増える可能性があるといった議論がある。(by GPT-4)
プロジェクトマネージャーなら誰でも、プロジェクトは訓示だけでは管理できないことを知っている。グローバルな問題を解決したいのであれば、グローバルな意思決定メカニズムや機能するグローバルな制度を導入する必要がある。残念ながら、アウレリオ・ペッチェイの時代から、この意味での進歩はほとんどない。グローバルな問題に対処するための制度がないわけではなく、おそらく多すぎるのだろう。そして、これらの機関は、本来主権者であるはずの各国政府に対して、ほとんど、あるいはまったく力を持たない。
各国政府はコモンズを管理するために使用できる権限を持っているが、それに対する確固たるコミットメントを持っていない。アメリカのドナルド・トランプ大統領が2017年、パリ気候協定からの正式な離脱を決めたことを考えよう。そして、4年後の2021年、新大統領のジョー・バイデンは、米国に条約への再加入を命じた。個人相手ならともかく、企業相手なら、こんな行為は違法である。誰もがいつでもそれを尊重しないと決められるのであれば、何のための契約なのか。しかし、主権国家がその代表者が署名した条約を尊重しないことを制裁できるような権威は存在しない。ただでさえ弱いパリ条約は、アメリカ政府の行動によってかなり弱体化したが、どの主権国家も、いつ同じような行動を取るか決めることができる。
しかし、地球環境問題に対して効果的な行動をとることが不可能なわけではない。例えば、紫外線から生物を守る成層圏のオゾン層を破壊する化合物であるフロン類は、その典型的な例だ。1987年に国際条約で禁止された。他にも、1963年の大気圏内核爆発禁止条約、1997年の対人地雷禁止条約(オタワ条約)、乱獲の抑制を目的とした条約など、国際条約が成功したケースはある。
しかし、これらの条約は比較的単純で特殊な問題を扱ったものであり、効果的な条約を作り、それを実施することは困難であることが判明している。1992年に発表されたSteeleらの論文「The Managed Commercial Annihilation of the Northern Cod」のタイトルを引用するだけで、条約がいかに悪用され、本来の目的とは正反対の効果を得ることができるか、ある程度理解することができるであろう。海洋資源に関する条約がいかに逆効果であったかの例は、バルディとペリッシの著書『The Empty Sea』(2020)に詳しく書かれている。
比較的単純な問題に対して行動することがこれほど困難であることが判明したのであれば、気候変動のような、より複雑で、より危険な問題に対して行動することがどれほど困難であるかは想像に難くない。68 気候変動に行動するために使われるツールは、主にこのテーマに関する一連の締約国会議(「COP」)である。COPは、あらゆる国際条約の管理機関として考えられた国連のツールである。そのため、COPは気候に関心を持つすべての当事者を招集し、気候変動を緩和するための条約を制定することができる唯一の超国家的な機関となっている。気候に関する最初のCOPであるCOP1は、1995年にベルリンで開催された。それ以来、毎年1回、26回の会議が開催されている。その多くは、温室効果ガスの排出を削減する必要性について、すべての締約国が合意した文書で結ばれている。
実際には、これら26のCOPの成果は、排出量の削減という点では控えめなものだった。過去数十年間、温室効果ガスの排出量と大気中の濃度は滑らかな曲線を描いて増加し、削減のためのあらゆる試みに影響されることはなかったようだ。重要なのは、最善を尽くした人々を否定することではなく、これらの会議がこの問題に対する国民や政府の関心を維持するために良い仕事をしたことを否定することでもない。それどころか、気候変動問題は、グローバルな行動で最も成功した事例の一つであるとも言える。少なくとも、いくつかのグローバルな合意が交渉され、実施されたのである。
しかし、LtGやその他のダイナミックな研究の体系的な視点は、気候だけに焦点を当てたものではなかったことを忘れてはならない。ローマクラブの行動要請は、生態系に影響を与える他の要因、すなわち資源の枯渇、汚染、生態系の破壊、土地の侵食、森林破壊、過疎などについての行動も含んでいた。これらの問題のいくつかについては、グローバルな条約が実施されたが、いくつかの問題は、超国家的な規制の試みに抵抗している。特に鉱物資源は、「枯渇」という概念が産業界にも政府関係者にも知られていないようだ。この分野では、ピークオイル研究会(ASPO)の創設者であるコリン・キャンベル(69) が 2005年に「石油プロトコル」を提案した。これは、石油を長持ちさせるために、石油の採掘量に上限を設けるというものである。しかし、私たちの住む世界は、なぜか鉱物の生産量が多いことを豊かさの証とし、生産すればするほど早く枯渇してしまうという当たり前の事実に気づかないままである。石油議定書は、当初は関心を持たれていたものの、頓挫してしまった。
天然資源の面では、肥沃な土壌については、国連食糧農業機関(FAO)が世界各地で土壌侵食を減らす試みを行っており、より良い態度が存在するようだ。しかし、FAOのホームページには、「5秒に1回、サッカー場1面分の土壌が侵食によって失われている」と書かれており、満足のいく結果には至っていないようだ。人口については、少なくとも欧米諸国では、あらゆるレベルで言及されないままである。
では、どうすればいいのだろうか。私たちは、ギャレット・ハーディンが1968年に発表した論文 「The Tragedy of the Commons」で述べたコモンズの不始末を彷彿させるような状況に陥っている。しかし、ハーディンがイギリスの小規模な牧草地を論じていたのに対し、現代の悲劇は惑星のコモンズを巻き込んでいる。結局、大きな問題は、個人の欲と社会の善の対立というシンプルな原因から生じている。個人(あるいは集団)の利益を最適化しようとする限り、コモンズの破壊につながることは、高度な数学的モデルを使わなくても理解できる。
ハーディンの考え方が現在の経済学の考え方に与えた影響は、しばしば民営化を促進することであった。羊飼いたちが自分の牧草地を所有していれば、その牧草地を過剰に開発することに興味はないだろうという理屈である。過去数十年間、欧米諸国を席巻した民営化の波は、このような理由によるものであったかもしれない。しかし、実際には、民営化がコモンズの乱獲を減らす効果があったという証拠はない。一つの問題は、人々が個人的に自分の過ちの結果にさらされたとしても、時間軸が報復の到来を認識するよりも短いため、あるいは単にシステムを効果的に制御するための知識や理解が不十分なため、自分が支配する資源を乱開発することがあるという点である。後者の現象は、例えば、Erling Moxnesの一連の研究において主張されている。70
しかし、民営化の根本的な問題は、それが常に適用できるわけではないということである。民営化はただ単にコストがかかりすぎるだけかもしれないし、もちろん、海を柵で囲ったり、世界の各州に大気の区画を割り当てたりすることはできない。現在、海や大気は最も搾取されすぎているグローバル・コモンズなのである。物理的なフェンスがなくても、コモンズの一部をさまざまな主体に割り当てることは可能だと主張する人もいるかもしれない。これは漁業割当や炭素クレジットの原則であり、その他のケースも同様である。しかし、これらの措置は、世界のさまざまな地域でさまざまな形で試みられていたが、特に良い結果にはつながらなかった。一般に、どのような分野でもクォータを適用するのは非常に難しく、また、適用されたとしても、クォータが大きすぎて搾取を防ぐことができず、不正行為やブラックマーケットなどの弊害を生む場合が多い。
では、私たちは絶望的なのだろうか?
いいえ、しかし、もっと創造的なアプローチが必要なのだ。1960年代にジェイ・フォレスターが開拓し、LtG研究の基礎となった複雑系へのアプローチそのものに、非常に基本的な問題がある。フォレスターは、システムの挙動を記述し、ある限界の範囲内でそれを未来に外挿するという考え方で、「システムダイナミクス」というモデル化理論を開発した。極めて革新的なアプローチであったが、人の行動を画一的に捉えてしまうという弱点があった。
フォレスターやLtGの研究の基礎となっている世界モデルは、ほとんどの経済学モデルで行われているのと同じ仮定に基づいて暗黙のうちに成り立っている。つまり、人々は成長と天然資源の利用を最大化する傾向がある。世界モデルのマクロスケールでは、この仮定は有効だが、モデルを支配するフィードバック効果によって修正することはできないことに注意してほしい。つまり、人々の行動を変えたときの効果を調べるには、外部からの「強制」(モデルのアルゴリズムに含まれないパラメータの専門用語)を仮定するしかなかったのである。
フォレスターとその同僚たちが、モデルの核となるフィードバックの中に人々の行動を埋め込むという難しい(おそらく不可能な)作業に着手したくなかったのは理解できる。しかし、このアプローチでは、人々が経験から学ぶことの効果や、どのような要因で行動を修正するようになるのかを、モデルで説明することができなかった。この特徴により、世界モデルはシステムを記述する上で非常に洗練されたものになったが、そのシステムをどのようにコントロールすることが可能であったのかについては、ほとんど、あるいは何も語られなかった。
「コントロール」という言葉には、ネガティブな響きがある。独裁や全体主義的な体制を連想させるからだ。しかし、それは原始的でコストのかかる方法であり、長い目で見れば失敗するのが普通である。もし、コントロールを「ガバナンス」に置き換えれば、責任の共有と意思決定の共有という意味で、ネガティブな響きはなくなる。そうでなければ、抑圧的な独裁政権の台頭、極端な不平等、マイノリティの隔離など、市民にとって極めてネガティブな方向にシステムが発展する可能性がある(今まさに、こうしたネガティブなトレンドのいくつかが現れているのだ)。しかし、どうすれば、特にグローバルレベルでのガバナンスを実現できるのだろうか。
フォレスターが1960年代にシステムダイナミクスモデルを開発していた頃、20世紀のもう一人の偉大な頭脳、ノーバート・ウィーナーは、「舵取り」を意味するギリシャ語から「サイバネティクス」と呼ばれる複雑系の新しい分野の基礎を築いていた。ウィーナーをはじめ、ローゼンブリュース、アシュビー、チューリング、フォン・ノイマンらは、まさに今日の私たちが直面している問題、すなわち複雑なシステムを制御する(統治する)ことを研究していた。フォレスターのシステムダイナミクスと同様、サイバネティクスの概念の基礎は、フィードバックであったし、今もそうだ。
一方、サイバネティクスは、生物学、社会学、政治学など、さまざまな分野に広がっている「サイバネティクス」と呼ばれる分野である。システムを「操縦する」というアイデアは多くの分野で魅力的だが、政治の世界では、1971年から1973年にかけてサルバドール・アジェンデ大統領時代のチリで試みられた「サイバシン計画」が唯一の実用例として知られている。これは、単純なシステムダイナミクスモデルを使って国家経済を管理するために設計されたコンピュータベースのシステムであった。このシステムは、1973年のアジェンデ大統領退陣のクーデターで破壊されたので、長期的にどの程度機能したかはわからない。その後、1991年のソ連崩壊により、国家経済の中央計画という考え方は否定された。
しかし、人工知能技術は進歩し、多くの意思決定プロセスで重要な役割を果たすようになり、世界中の政府を支援する(あるいは支配する)より高度なシステムが存在するようになった。この分野では、中国が最も進んだシステムを持っていることは間違いない。中国の「新経済思想」によれば、ビッグデータとAIを組み合わせることで、経済の管理、市場の形成、生産チェーンの最適化、資源供給のコントロールなど、多くのことが可能になるという。それは時に「テクノユーティリティズム」とも呼ばれる概念で、従来の意思決定システムに取って代わるかもしれない。
中国が、ソ連時代の古い「計画経済」を悩ませたような問題に悩まされることなく、技術主義的なシステムで、今のところうまくいっているのは間違いないだろう。中国経済は急成長しているが、最近も大きな問題に直面している。いずれにせよ、中国の人々は、欧米では侵略的すぎて受け入れられないと考えられている電子監視の技術に満足しているようだ(少なくとも2020年までは)。しかし、このシステムはコモンズを管理できるのだろうか?特に、グローバル・コモンズの管理に役立てることができるのだろうか。そして、基本的なプライバシー権や市民の自由に影響を与えることなく、それを実現することができるのだろうか。
現時点では、その答えは不確かである。中国のテクノクラシーは一国家のレベルにとどまっており、地球環境問題に対する中国政府の記録は特に光っているわけではない。これまでのところ、中国の社会制御装置は、主に国の経済的アウトプットを最適化するように設計されているようだ。持続可能性やオーバーシュートといった長期的なパラメータは、このシステムにおいて重要な役割を果たしていないように思われる。しかし、状況は変わりつつあるようだ。2021年3月に発表された中国の第14次5カ年計画(14th FYP)には、エネルギーと炭素強度の削減目標が盛り込まれた。2021年4月、習近平国家主席は、中国が石炭発電を2025年まで厳しく管理し、段階的な脱石炭を開始すると発表した。中国は、新しい中国の統治システムが環境保護にどのように行動できるのか、興味深い試金石となるだろう。
期待されているとはいえ、最も洗練されたサイバネティック制御システムであっても、人間の頭脳によって決定される入力パラメーターに基づくものである。だから、世界的なAIシステムが、グローバル・コモンズを保護する機能をプログラムされていれば(アウレリオ・ペッチェイがプログラムしていたと想像してほしい)、人類に計り知れない貢献をすることができるだろう。しかし、現状では、そうなる保証はなく、問題は人間の欲であり、それはシステムにプログラムされてしまうかもしれない。いくらシステムを最適化できたとしても、目的が金銭的利益の最適化であるならば、システムは天然資源の乱獲を最適化し、コモンズの破壊を生み出すだろう。また、ローマクラブの創設者であるアウレリオ・ペッチェイが最も懸念していた不平等の拡大も最適化されるかもしれない。
つまり、私たちは基本に立ち返っている。人間の心は、問題であると同時に解決策でもある。人間は学ぶことができるし、しばしば学ぶ。しかし、私たちは、人間にいかにして学ばせるかを学ぶ必要がある。人間の学習がシステムダイナミクスモデルに含まれないとしても、少なくとも社会を正しい方向に導くために、発見的推論を用いることは可能である。
この分野では、ジェイ・フォレスターがまた偉大なパイオニアであった。彼の研究の一部は、定量的なアルゴリズムに変換されることはなかったが、人間社会を管理する新しい方法の出発点として見ることができる。中でも、複雑なシステムにおける「レバレッジ・ポイント」についてのフォレスターの観察が光っている。フォレスターによれば、複雑なシステムを扱うとき、多くの場合、人々は 「間違った方向にレバーを引く」傾向があるという。つまり、意思決定者は、解決しようとする問題を悪化させるような方法でシステムに作用する傾向がある。
この自滅的な傾向には多くの例があるが、おそらく現在の状況に関して最も説得力があるのは、枯渇の問題に対して、より効率的な搾取の努力を増やすことがほとんどで、明らかに状況を悪化させるということだろう。しかし、フォレスターの観察は、正しい方向にレバーを引けば、システムを正しい方向に動かすことが可能であるという対称的な可能性を導き出す。そして、サイバネティックスの概念に立ち戻ることになる。
このような思考の連鎖から、ドネラ・メドウズは1999年に「システムに介入する場所」71という概念を提案した。それは、パラメーターの一部を変えることから、「パラダイムを超越する力」に至る12の提案であった。メドウズの文章は魅力的で刺激的だが、定性的で不完全なままである。残念ながら、彼女は2001年に亡くなり、そのアイデアをさらに発展させる時間がなかった。
ドネラ・メドウズの仕事は、20世紀のもう一人の傑出した頭脳、とりわけ女性として初めてノーベル経済学賞を受賞したエリナー・オストローム(1933-2012)の仕事と並行して考えることができる。オストロムの科学への貢献は、ハーディンの「コモンズの悲劇」が常に起こるわけではないこと、特に、ハーディンが自分の考えを議論するために例として取り上げた、牧草地などの農業環境では起こらないことを証明したことである。

オストロムの研究は、その人間的な側面が非常に魅力的である。もう、自分の「効用関数」を最適化しようとするオートマトンのように振る舞う抽象的な「エージェント」はいない。エリナー・オストロムは、牧草地、漁場、森林など、現実の資源を管理する実在の人々の事例を研究した。そして、天然資源を利用者が共同で管理することで、やがて、経済的にも生態学的にも持続可能な形で、天然資源を管理・利用するためのルールが確立されることを示したのである。
この奇跡はどのようにして得られるのだろうか。オストロムは、コモンズを上手に管理するための8つのルールを提案したが、これらのルールはすべて「人と人とのコミュニケーション」というシンプルな形でつながっている。それは、「共感」(ドネラ・メドウズがよく言っていた「愛」)という言葉で表現することもできる概念である。つまり、比較的非階層的で平等主義的な環境の中で、人々が自由にコミュニケーションできるようにしておくと、彼らがガバナンスの奇跡を管理することになる。独裁者や全体主義的な支配者、警察などを必要とせず、互いに、そしてシステムを統治する。
意外な結果かもしれないが、これは理にかなっている。それは、私たちが人間として受け継いできたものと関係がある。コモンズは今でも私たちの世界に存在している。もしあなたが古代の共有資源の集団管理システムに出会ったことがあれば、それがいかにうまく規制されているかにきっと気づくはずだ。そして、このコンセプトの素晴らしさは、これらの統治システムが上から設計されたものではなく、うまくいかないものを捨てることで進化してきたということである。この意味で、管理されたガバナンスシステムは、1930年代にアドルフ・マイヤーアビッヒが考案した「ホロビオント」という概念に似ている72が、20世紀を代表する頭脳、リン・マーグリス(1938-2011)によって現代に改訂・広められた73。彼女は、ジェームズ・ラブロック(James Lovelock)と共同で、惑星生態系の恒常性維持を意味する「ガイア(Gaia)」の概念を提唱した人物である。74 ホロビオンとは、ダーウィン的な「適者生存」ではなく、競争ではなく協調によって利用可能な資源を最もよく管理する「十分者の生存」によって生み出される、広範囲な生物体である。森林、菌類、サンゴ、そして人間もホロビオントの一例だ。また、人間の社会システムも、メンバー間の共感結合に基づく相互作用によって調整されていることから、ホロビオントとみなすことができる。このような「社会的ホロビオン」は、メンバー間の過度な競争を防ぐために、比較的平等な構造を維持することで、過剰な搾取を回避できることが多い。
というわけで、私たちは出発点に戻っていた。ドネラ・メドウズ、エリナー・オストロム、リン・マーグリスの提案に従って、グローバル・コモンズを管理することはできるのだろうか。20世紀を代表するこの3人の女性は、当時の男性よりも共感という概念に長けていたのではないかということを認識することが、解決策になるかもしれない。ゲームの名前はいつも同じ、共感だ。もし、世界の統治に共感を注入することができれば、私たちが直面している巨大な問題を解決することができる。そうでなければ、人間の苦しみをあまり気にすることなく、勝手に解決してしまうだろう。
結論
「ニューエコノミー」や「歴史の終わり」といった概念によって生み出された数十年の過剰な楽観主義の後、人類滅亡とまではいかないまでも、文明崩壊の可能性が現在の議論に占める割合を高めている。私たちは、『成長の限界』の著者や、その研究を主催したローマクラブが文明の限界を問うていた50年前の見解に戻りつつある。50年前と違うのは、産業経済の崩壊などの問題は、遠い未来に関わるものと考えて切り捨てることができたが、今はそうはいかないということだ。今、私たちは崩壊の危機に瀕している可能性がある。
私たちが直面している問題は、50年以上前にアウレリオ・ペッチェイが世界を変えようと試みたときに予見したものと同じだ。それは、科学的な問題というより、政治的な問題である。ペッチェイは、世界を変えるという課題を、主にマネジメントの問題として正しく捉えていた。彼は、優れた経営は優れたコミュニケーションに基づくものであり、優れたコミュニケーションは、ひいては共感に基づくものであることを理解していた。しかし、この試みは失敗に終わった。世界はまだ、グローバル・コモンズを管理するために必要な交渉の準備ができていなかったのである。
今ならもっと良くなっているのだろうか?おそらくそうだろう。私たちは今、世界の気候や天然資源に関する理解を深めているし、より良い未来を築くための交渉に役立つ技術も、かなり進歩している。問題は、世界のリーダーたちのほとんどが、いまだに時代遅れの概念に縛られていることである。50年前にLtGの研究が予見したような時代の崩壊を避けたいなら、私たちは迅速に行動しなければならない。衰退を避けるには手遅れかもしれないが、持続可能な世界への不可避な移行の影響を和らげるために、今私たちができることはすべて有効である。未来は地図ではなく、歩きながら発見する道である。そしてそれは、私たちをどこかへ導いてくれるだろう。
第21章 私たちがすでに知っていることを学ぶ
カルロス・アルバレス・ペレイラ(Carlos Alvarez Pereira)
ローマクラブ副会長
私たちは良い方向に進んでいるのだろうか?
2016年11月11日、ドナルド・トランプが米国大統領に選出された2日後、デニス・メドウズはベルリンで開催されたローマクラブの年次総会で、「Why Didn’t We Learn」と題した演説を行った:というタイトルの講演を行った。この挑発的な質問は実によく選ばれたもので、政治的な状況だけが理由ではない。ローマクラブの創設以来、ローマクラブが発信してきたメッセージは、人類社会の流れを変えるほどのものではなかった、あるいは聞かれなかったという思いは、出席者の間にかなり広がっていた。それは現在でも同様である。
本書の冒頭でウーゴ・バルディは、『成長の限界』の基礎となるモデリング演習に人間の行動が含まれていないことを正しく指摘している。それゆえ、シミュレートされたシナリオは、人間の学習の効果を表示することができなかったのである。これは自己成就的な予言ではないだろうか。そもそも学習を捨てれば、学習は起きない。もちろん、『成長の限界』の著者やローマクラブの目的は、人類がよりよい問いを立て、健全な生物圏の中でバランスのとれた幸福の構成に向かう道筋を探るための概念的なツールを提供することであった。しかし、どのような学習が必要で、どのようにそれを実現するのだろうか。『成長の限界』は、その優れた功績の割には、そのような問いに答えていない。この本に関する論争がどのように形成されたかも、あまり役に立たなかった。バルディも指摘するように、議論の質は、特に科学的な観点から見て低かった。しかし、最も重要なことは、本書の主要な結論、すなわち、消費と汚染の無制限な拡大という同じ道を歩み続ければ、人類は非常に深刻な問題に直面するかもしれないということを否定することで議論が収束したため、学習の問題には全く触れられなかったということである。特にレーガンやサッチャーが政権を取った後の議論では、この問題は単に存在しないのだというのが勝ち組の意見だった。では、学ぶべきものがないのであれば、なぜ学ぶプロセスを心配するのだろうか?
アウレリオ・ペッチェイとローマクラブは、『成長の限界』の曖昧な受け止め方をよく理解していた。一方では、『成長の限界』は大きな注目を集め、何百万部も売れ、ローマクラブの評判を高めた(ポジティブかネガティブかは別として、いずれにせよ強い)。他方で、中期的な成果は期待外れだった。公的な議論は、「成長」、「開発」、「イノベーション」に関する従来の枠組みを変えることはなかった。そして、官民の政策は、数十年前に開発された搾取的で消費主義的なモデルを踏襲し、経済の金融化とグローバル化を通じて、それを大幅に拡大し、より速く走らせることになった。数年後、「持続可能な開発」という概念が確立されたことで、ローマクラブをはじめとする多くの人々が語ってきた問題が解決されつつあるとの安心感が生まれた。しかし、これは「開発」の本質が問われないように行われたものであり、問題は、それ以外の好循環的な進化によって解決されるべき「付随的」効果であると考えられていた。このことは、2017年11月6日、リスボンで開催されたウェブサミットの開幕式で、アントニオ・グテーレス国連事務総長が述べた言葉にもよく表れている:
この数十年、私たちはイノベーション、科学技術にグローバリゼーションが組み合わさった巨大な影響を目撃していた…世界的に見て、私たちの世界が良い方向に動いてきたことは明らかだが、気候変動や不平等の拡大といった巻き添えもあった。1
この言葉を胸に、人類は結局学んだと言えるのだろうか。ローマクラブは、持続可能な開発目標やパリ協定といった世界的なコンセンサスによってすでに対処されている問題を気にしすぎているのだろうか?技術革新や市場メカニズムと組み合わされた既存のガバナンスの枠組みが、私たちの存続に関わる課題に向き合い、解決することができると見ていないのだろうか?さて、本書の寄稿者たちがその楽観的なテーゼに反論するために提出した多くの議論のほかに、アントニオ・グテーレス自身が上記の宣言の3年後にこの問いに答えている。2020年12月2日、彼はニューヨークのコロンビア大学で講演し、次のように述べた:
端的に言えば、地球の状態は壊れている。人類は自然に対して戦争を仕掛けている。これは自殺行為だ…自然と平和を築くことは、21世紀の決定的な課題である。自然との調和を図ることは、21世紀の決定的な課題であり、世界中のすべての人にとって、最優先事項でなければならない。2
おそらく、この劇的な視点の転換は、コビッド19の大流行と、気候や不平等といった「付随的」な課題への取り組みが進んでいないことに育まれたのだろう。いずれにせよ、私たちは現実に直接、客観的にアクセスすることはできず、解釈の枠組みというレンズを通して自分の認識に意味を与えていることを物語っている。地球の状態がこれほど劇的に変化するのに3年という時間はない。変化は解釈の中にあり、この場合、政治的意図があるのは確かだ。また、COVID-19以降、少し前の多国間機関の文脈では政治的に不適切とされたような大胆な発言が公然とできるようになったことも反映されている。
人間的なギャップ
2017年と2020年のグテーレスによる2つの解釈は、世界とその中での私たちの役割に関する異なる考え方を代弁するものである。1つ目は、現状維持の信念を反映している。大きな問題がいくつかあるが、意図しないダメージに注意することで、それに対処することができる。そして、談話の別の部分で説明したように、技術革新がその重要な役割を果たすだろう。2つ目の談話は、楽観主義が弱まり、自然との関係が決定的な重要性を獲得する目覚めの談話である。人間の行動が、私たちの生活を支えている条件の破壊を引き起こす可能性があるという明確な声明があり、これはまさに『成長の限界』の主要なメッセージである。私たちの行動の結果は、私たちの意図を越えて「付随的」な害をもたらすだけでなく、大きなフィードバック・サークルを通じて、私たち自身を致命的にすることもある。
COVID-19のパンデミックは、こうした考察に新たな刺激を与えてくれた。それは、原始的な生命のほんの一部によって地球規模の崩壊に誘導された、人間システムの脆弱性を明らかにしたのである。私たちは、より快適な説明を見つけようとするが、生態系の破壊を加速させることは、短期的で抽出的な考え方では理にかなっていても、世界的な悲劇の条件を作り出したことは明らかだ。そして、ワクチンが開発された後でも、パンデミックは、私たちが生命やその複雑さ、予期せぬフィードバックループについていかに知らないかを明らかにするものでもある。例えば、ウイルスがあるレベルでは知性を持ち、学習能力があることを認めなければならないのに、私たちは知性は人間という種の独占的な属性であると言い聞かせている。COVID-19の屈辱的な体験は、私たちにもっと学び、生命をもう少し理解するために必要な謙虚さを与えてくれるかもしれない。
もちろん、どれも新しいことではない。グテーレス2017とグテーレス2020の間の距離は、1970年代にアウレリオ・ペッチェイが定義した「ヒューマン・ギャップ」、すなわち人間の行動能力と行動の結果を理解する能力との差に共鳴するものである。ペッチェイと同世代のグレゴリー・ベイトソンは、「世界の主要な問題は、自然の仕組みと人間の考え方の違いの結果である」と、さらに踏み込んだことを述べている。人間のギャップを埋める」というのが、ローマクラブの報告書「No Limits to Learning」(1979)の副題と目的であり、「成長の限界」で明らかになった課題に対応するための貴重な試みだった。この本は、私たちが人類の存亡に関わる課題に立ち向かうのであれば、私たちの学習プロセスはどのような特徴を持つべきかを探求したものである。しかし、残念ながら、この本は、それにふさわしい成功を収めることはできなかった。最近では、グロ・ハーレム・ブルントラントとその共著者たちが、『Imperative to Act』という報告書の中で、「人間の行動力は、理解力を大きく上回っている」と率直に述べている。3 しかし、そうなのだろうか?私たちが直面しているのは、すでに知っていることを学ぼうとしない姿勢ではないだろうか?
この疑問は、さらに多くのことを提起している。もし、人類の文明が大きく変化し、健全な生物圏の中ですべての人に公平な幸福がもたらされるようなプロセスがあるとしたら、それはどのようなプロセスなのだろうか。それは、賢明なエリートによる知的な「解決策」の設計と、政治的な強制力、適切な規制、市場メカニズムの組み合わせによる世界的な展開によって起こるのだろうか。確かに、メディアで語られる科学的発見や技術革新の洪水を考慮すれば、21世紀の人間社会が学習し進化していないとは言えない。デジタル化、第4次産業革命がその役割を果たすのだろうか。人類が直面している新たな課題に対する技術的な解決策を提供するために、目的意識を持った人間の天才性や自然を使いこなすための適切なメカニズムがすでに備わっていないのだろうか?このアプローチは、多くの「サステナビリティ」の思想家や実践者の間で支配的であり、官民を問わず、意思決定者が選択する選択肢であることは間違いない。私たちの疑問に対する答えになるのであれば良いのだが、果たしてその可能性はあるのだろうか?
私たちの視点に立てば、このアプローチの根本的な問題は、アルフレッド・コージブスキーの言うように、「地図は領土ではない」ということである。何が起きているのかを理解し、「問題」を特定し、「解決策」を設計するために私たちが使っている従来の枠組みは、生命の複雑さに対して不十分なものである。その好例が、望ましくない現実に直面したときに私たちが多用する「戦争」という比喩である。敵(がん、麻薬、テロ、ウイルス…)を指定し、戦争ならではのエネルギーを動員するため、なぜか慰めになる。しかし、私たちが属する生態系の進化を扱うには、上記のすべての「敵」の場合と同様に、まったく不適切なものである。戦争は分離と排除の究極の表現であり、それを気に入らないものに適用すれば、グテーレスが語るように、自然に対する自殺戦争を仕掛けることになる。興味深いことに、『成長の限界』の共著者であり、優れたシステム思想家であるドネラ・メドウズは、最後の論文のタイトルを「Dancing with Systems(システムと踊る)」とした。4 戦争をするのではなく、生命と踊るにはどうしたらいいのだろうか?
不充分なレンズ
私たちは、世界やその中での私たちの役割、人間同士の関係、生命全体や時間との関係について、どのように考えているかをあえて問う必要がなければ、より望ましい未来に向けた学習のはしごは乗り越えられないだろうと考えている。17世紀から18世紀にかけての科学革命は、第一次産業革命につながる技術開発の場を開き、環境を形成し、自然だけでなく人間も含めて、同意しない人に「近代的」な見解を押し付ける前代未聞の能力を獲得した。これが「近代」の出発点であり、私たちの住む世界を形作ってきた考え方や行動様式である。当時の科学は、私たちが記憶している以上に多様だったが、権力との関係で、ある考え方は聞き入れられ、ある考え方は忘れ去られることになった。例えば、ナポレオンはラプラスを推し進め、ラマルクを無視した。自然の仕組みに関する優れた洞察力は、階層的な社会概念を正当化するためには役立たなかったのである。19世紀の初めから、科学、技術、権力の間の自己強化ループの結果として、機械論は私たちの考え方に不釣り合いな影響力を持つようになった。私たちは、このパラダイムが生命システムを理解するのに有用でないことを知っているが、それでもなお、教育、研究、イノベーション、経済だけでなく、ガバナンスにおいても、このパラダイムが私たちの組織の包括的なフレームワークとなっている。分離を中心とした考え方、心と物質の二元論、客観性、個人主義、合理主義、還元主義、直線性、決定論は、私たちの知覚を理解するために使い続けているツールである。これらはすべて、秩序、均衡、階層、コントロールに取り憑かれた支配的な文化を築くために決定的に貢献した。また、経済的・政治的な面では、定量化、生産性、パフォーマンスの奉納、進歩の名の下に人と自然を植民地化し搾取することの正当化につながった。
社会生態学的災害は、このような文化から生まれた。この文化は、近代の初期と同じレンズを使っているため、同じ盲点を持っている。原因と結果の単純な連鎖を信じ、そのため意図しない結果は常に「巻き添え」とみなされる。ほとんどのシステムでは、たとえ非常に単純なものであっても、すべての構成要素が環境の変化に反応することを根本的に無視している。そして、行動と反応の流れは、質問と回答のように、進化の無限の流れを作り出す。気候温暖化もCOVID-19も、結果を気にしないほど無謀だった人間の過去の行動に対する反応である。そして、あるシステムの進化は、重要なポイントにおいて、全く異なるパターンに劇的な再構成をもたらすことがある。これが、よく観察されている創発と創造性の現象である。しかし、私たちが暮らす文化は、明確な目的によって駆動される直線的な変化を信じている。複雑な事柄を外的かつ客観的な立場から決定し、その決定を分析対象であるすべての存在に押し付けることができると信じている。そして、すべての生き物が感覚を持ち、機械装置の部品ではないことを根本的に無視する。
つまり、支配的な考え方は、生き物(人間であろうとなかろうと)を、生きているという特性から剥奪してしまうのである。彼らは、環境と常に共進化する自律的で相互依存的な存在としてではなく、無生物、あるいはせいぜい制御可能な主体として扱われる。これはまた、一部の人間に、人と自然に対するさまざまな形態の植民地化と採取的搾取を追求し、拡大するための地位だけでなく正当性をも与えている。そしてそれは、生物圏全体を含むすべての生態系の重要な特徴である相互依存のルールに違反するものである。生態系は、どのような規模であれ、外からの方向づけに従うことで変化するのではなく、新しい行動パターンを学ぶが、それはほとんどの場合、私たちが期待したものとは異なるものだろう。私たちは、まるで知らないかのように振る舞うかもしれないが、そのときは、ホセ・オルテガ・イ・ガセットの「無視された現実は復讐を準備する」という警告を思い出すべきだろう。簡単に言えば、機械論的な思考、つまり人生について知っていることをほとんど無視してマッピングする方法を使うことで、手遅れになるまで無視しがちな悲劇を必然的に生み出してしまうのである。
私たちが言いたいことを説明するために、現在、ほとんどの公的課題で優先されている気候変動を例にとってみよう。化石燃料の使用が気候変動の主な原因であることが明らかになったことで、この問題を単純な因果関係の論理でとらえることが可能になった。再生可能エネルギーに転換すれば、問題は解決する!つまり、技術経済的な課題であり、適切な技術を開発するための資源を動員し、それを導入するための投資を促進することである。どのようなエネルギーがどれだけ必要なのか、また、「先進国」と「途上国」の間で消費パターンが大きくアンバランスであることについては、何の疑問も持たれない。人類の幸福につながる軌道には、一人当たりのエネルギー量が増え続けることが必要であり、特に世界人口の大部分は「追いつく」ことが必要であるとされている。特に世界人口の大部分は「追いつく」ために、とんでもなく高いレベルのエネルギー消費が正当化されると仮定されている。公平な人類の幸福が、エネルギーの総消費量の劇的な削減と両立し得るという考えは、単に考えられないことである。再生可能エネルギーの利点はすべて、有限の地球で無限の成長を可能にするものではない。5 しかし、今のところ、私たちはこの問題を同じ言葉で定式化し、運が良ければ、そのような制限のない他の人工的なエネルギー源を導入する時間があることを望んでいる。せいぜい、一人当たりのGDPの上昇をエネルギーやその他の資源の消費からどのように「切り離す」ことができるかを探ろうとする程度で、あまり成功はしていない。そして、私たちの未来を、幸福とエネルギー消費の高水準との厳格な関連付けに縛り付けている。この考え方では、人類は代謝に還元され、エネルギー消費は機能ではなく、役割となり、その中で最大化が肯定的な意味を持つことになる。これは、自然がどのように機能するかということではない。
この根本的な課題に対しては、他の定式化も試みることができるだろう。例えば、人間の健康やウェルビーイングの原動力は何なのかを問うことができる。生産と消費の最大化に執着する近代は、私たちの健康や有意義な生活の感覚が消費主義によってもたらされるものではないことを無視させた。科学は、私たちが太古の昔から知っていたことを再発見した。人間であれ非人間であれ、他者との関係の質こそが、良い人生の秘訣なのである。6 この重要なポイントは、関係や相互依存が支配的な役割を果たす、他の革新的な学習方法につながる可能性がある。しかし、既存の制度の枠組みの中で、こうした方法を模索することは不可能に近い。また、エネルギー消費を劇的に削減するシナリオでは、金融、産業、地政学など、あまりにも多くのステークホルダーが危険にさらされる。
ここで、人類の未来に向けた変革的な戦略を議論し設計する上で、「利害関係者」が果たすべき役割について、誤解を招きかねないことが判明した。ステークホルダーは、その定義からして、自分たちの利害を問うよりも、むしろそれを擁護するものである。大学、研究センター、企業など、最も革新的な組織でさえ、自らの存在と設定の根本をあえて問うことはない。そのため、リップサービスを除いては、自分たちの存続を強化するようなことしかしない。しかし、私たちの自殺的な軌跡には、あらゆる利害関係が絡んでいる!気候変動や社会的不平等、その他の課題に関する議論が、現状をいかに維持するかに集中することはほぼ確実である。もちろん、何を維持し、何を維持しないかは中心的な問題である。すべての文化は、未来に何を残すかについて選択しなければならない。未来の未開の地へ旅立つために、どんな過去の遺産を持っていく価値があるのだろうか。現在の近代文化では、資本の中心性という1つの遺産を除いて、すべての遺産を疑い、廃れさせることが正当化されているように思われる。
遺産とは何か
資本は、私たちがすべての期待を寄せる、人間社会の卓越したトーテムとなった。金融化が極度に進んだ21世紀の現段階では、資本は過去の成果の理想的な受け皿であり、私たちの時間との関係の中心的要素である。私たちは皆、資本を蓄積して将来のリターンを受け取り、自分の福祉を確保し、苦難から生活を守り、少なくとも、自分と子孫のために自分のすることに意味を持たせてくれることを期待している。土地や動物が人間にとって有用な資源を絶えず生産することで、将来のリターンが期待できるという考え方に基づくものである。しかし、これには多くの人間の働きと、太陽、水、風、土の素材が貢献する必要がある(偶然ではない:これらは古代の伝統の四大要素なのである)。今日、法律実務は、これまでもそうであったし、そうでない可能性もある、非常に特殊な資本の役割の概念に従って、生活過程とは無関係な資本の属性を強制している。7 現在の近代の特徴として、資本は、例えば、人工知能のアルゴリズムの所有権など、より抽象的な形を与えられている。そして、その支配的な符号化において、人々の生産的努力、天然資源の搾取、知的財産の使用料、債務者の将来の時間など、将来的に金銭的流れを生み出す手段に対する囲い込み(コモンズの反対)と高度な統制を課している。資本は、おそらく私たちが発明した最も強力な社会構成物であり、生物物理学的現実だけでなく、私たちの心と時間をも支配している。そしてそれは、貨幣という一次元の言葉で表現され、地理的、人間的、文化的な状況からますます脱文脈化され、コンピュータのキーを押すだけで無限に移動できるようになる。
その結果、過去数十年間の資本の進化は、「レンティア・エコノミー」の領域を拡大することに貢献した。どのような形態の資本であれ、レントからもたらされる金銭の流れの部分は、人間の労働の成果よりも著しく速く成長している。8 このことは、社会的不平等の深化を経済の構造的かつ非連続的な特徴にしただけでなく、人間関係の質ではなく、個人の資本蓄積が将来の福祉の主なメカニズムと見なされる文化を定着させた。資本は社会的、生物物理的な現実からますます切り離され、同時にリターンを得るためにそれらをすべてコントロールしようとする。表計算ソフトの中では、ほとんどすべての図が合理的に見え、私たちは、自分たちが作り出し、法的に符号化したどんな形の資本に対しても、将来のリターンを割り当てる権利があると感じている。熱力学の第二法則によれば、成長ではなく衰退が普通である。成長するとすれば、システムの外からエネルギーを取り込むなど、さまざまな要素や状況の微妙な組み合わせによるものである。つまり、資本はそれ自体でリターンを生み出すことはできず、受け取るエネルギーよりも消費するエネルギーが多ければ(どんな形であれ)、必然的に衰退することになる。
この点で、先ほどの土地の例は非常に分かりやすい。土地がリターンを生むためには、土が健全であること、太陽、水、風、人の働きが適切に組み合わされること、毒、干ばつ、嵐、霜、熱波などのリスクが抑制されることが必要である。生命が私たちの思い通りになるためには、多くの配慮が必要である。工業的農業はそれを完全に無視しているわけではないが、その焦点は資本に対するリターンにあり、生態系が健全に保たれるような構成要素間の関係にはない。これは問題である。資本という概念自体が無用だからというわけではないが、「遺産」と同義語として理解したほうがよいだろう。これは、過去の成果のもろさを強調するもので、それらはケアを必要とし、すべての貢献者(人間、非人間、無生物)の健康状態とその関係の質に依存するものである。そして明らかに、遺産は多様性を持っている。文化が違えば意味も違うし、資本もそうであるべきである。これらのことは、私たちが普段扱っている、切り離され、貨幣化され、無限に移動可能で、結局は盲目的な資本のバージョンから遠く離れている。
資本を、その起源である文脈的で根拠ある豊かさから切り離すことは、危険なトリックである。それは、現在の資本のレンズを通して現実を認識することが、二重に誤解を招くことを意味する。それは、価値を特定すべきでないところに価値を特定し、価値を特定しないことである。2022年、官民を問わず、企業や投資ファンドの会計帳簿には、いまだに化石燃料に関連する膨大な貨幣価値が記載されている。つまり、私たちの文明を崩壊させるほど深刻な気候温暖化という実存的脅威の原因となる主な行為には、まだ多くの金銭的価値がある。また、公式発表によると、アフリカは「先進国」に対して多額の借金を抱えている。何世紀にもわたる植民地化と奴隷化の末に、これは控えめに言っても悲劇的な皮肉である。なぜこの状況が逆であるべきなのかを説明するために、多くの議論を見つけることができる。9 これは、人類の未来が議論されるすべての部屋にいる象である。会計帳簿における資本の評価は、将来の世代にとって価値のある遺産よりも、社会内および社会間の過去と現在の力の配分を反映している。もし私たちがこのことを無視するならば、私たちは襲い来る悲劇に餌を与え続けることになるだろう。一方、明日にでも巨大な償却を実施すれば、経済や社会は一瞬にして崩壊してしまう。どちらの選択肢も怖いが、私たちのレンズに問題がないかのように装っていては、生命とのつながりを取り戻す適切な方法を見つけることはできないだろう。
権力の本質
昔、カール・ドイッチュはこう言った: 「権力とは、何も学ぶ必要のない能力である」私たちが必要とする学びを、既存の杭の力はどの程度妨げているのだろうか。豊富な証拠が示すように、非常にそうだ。しかし、私たちがすでに持っている制度化された学習方法についてはどうだろうか。結局のところ、私たちは静的な社会に生きているわけではない。危機は、私たちに何かを学ばせ、私たちの人生のコースを変えるという意味で、危機は私たちに何かを学ばせる。特に危機は、資本の評価を劇的に、時には非常に急速に変化させる。「グリーン成長」のシナリオの主な脚本は、化石燃料やその他の持続不可能な慣行への投資が証券取引所で価値を失い、一方で自然エネルギーの評価が急速に高まるというものである。これはすでにある程度起きていることである。また、ESGツールのように、企業や国をその行動の環境、社会、ガバナンスの結果に従って評価することで、正しい方向へのシグナルを与えることを意図して、市場が評価メカニズムを開発することもできる。しかし、これらのツールは、表面的な変化をもたらすだけであったり、「危険なプラシーボ」として機能する可能性さえある。10 また、不平等、気候温暖化、その他の課題のタイムラインと比較すると、変化はあまりにも遅すぎる。
同時に、スピードは本質的な問題ではない。ガンジーが言ったように、「間違った方向に進んでも関係ない」のである。1979年、アウレリオ・ペッチェイは、私たちの課題を謎かけのように定式化した: 「人類の進化のこの時点で必要なのは、学ぶべきことを学ぶために必要なことを学び、それを身につけることである」つまり、学習にはさまざまなレベルがある。新しい行動パターンを学ぶという行為は、私たちが破壊するよりも多くのライフを創造するようになることをそれ自体保証するものではない。むしろその逆かもしれない。COVID-19を例にとると、私たちは何を学んだのだろうか?ひとつは、人間であることが以前より難しくなったということである。パンデミックやコビッド的な混乱をよりよくコントロールするために、他者との距離を置き(社会的距離)、ワクチン接種を受け(技術的解決)、テクノロジーと官僚主義の追加レイヤーを遵守する必要がある。おそらくこれらは、現在のシステムが生み出すことのできる唯一の賢明な反応であったのだろう。また、これほどの規模とインパクトを持つ悲劇は、活動の全セクターをダメにしてしまうが、製薬会社やデジタル産業のような他のセクターでは、膨大な私的「富」を生み出すということも学んだ。そして今のところ、「開発」の構造的特徴として生態系を破壊することのおかしさについては、それほど学んでいない。私たちは、人間と自分自身、そして自然とのつながりを取り戻すことが、将来のコビッドのようなシナリオを回避することに役立つのではないかと考えているのだろうか。パンデミックの後、私たちの住む世界は変わったが、それはより生命と同調しているのだろうか?それとも、危機に対する私たちの対応の枠組みが原因で、ますます生命から切り離されているのだろうか?
もし私たちが、質問とその回答を形成する際の枠組みを変えなければ、私たちの関係(人間同士、生命、時間)の一般的な方向性を変える可能性はほとんどない。極端な個人主義、競争の工業化、社会的・生物物理的現実からの切り離し、エーテル的資本の私的蓄積に対する搾取的思考を特徴とする近代の分離主義的枠組みにとどまるならば、化石燃料から自然エネルギーへのシフトは、世界を変えることはできないだろう。新しいことを意識的に理解しても、近代という同じルールに縛られているだけでは十分ではない。私たちが必要とする学習は、それ以上のものである。それは、私たちが知っていることの結果に対処するために必要な、私たちの行動パターンや考え方の変化である(意識的かどうか、個人的か集団的か)。それは、既存の制度が通常行っている方法で生み出すことができるのだろうか。というのも、制度が設計された時点で、その制度が問うことのできる質問と、それゆえに生み出すことのできる学習は、すでに暗号化されているからだ。
ここで、私たちが苦悩にポジティブな反応をもたらすことに大きな期待を寄せている、研究と革新(R&I)の社会的プロセスを見てみよう。テクノロジーは、あらゆる問題に対する近代の標準的な反応であり、それが自らの枠組みの限界を超えることができれば素晴らしいことである。しかし、現在、研究開発に携わる機関(研究機関、大学、企業)は、少なくとも2つの基本的な前提を守る形で、「破壊的」とみなされる自らのアジェンダと行動を形成している:知識は本質的に別々の分野に分けられ、それは、投資に対する金銭的リターンが期待できる「ソリューション」につながるプロセスの一部でなければ役立たないのである。研究開発制度や技術開発につながるプロセスは、生命について科学が知っていることに基づいているわけではない。最先端の科学を利用し、生産することはあっても、その組織や運営方法は、先に述べたような時代遅れの「近代」の枠組みに従っている。したがって、生命がどのように機能するかとは反対の方法で行動しているため、私たちの大きな課題に対処するために有用な質問をすることが本質的にできないのである。同時に、公共部門と民間部門は、R&Iが経済的利益をもたらし、現在理解されているような資本の中心性を維持することを期待している。その結果、現在の発明の展開の全体的な結果は、技術が生み出される政治的・経済的枠組みを強化することにほかならない。
このことは、デジタル化の場合に特に明らかだ。もちろん、その発明は多くの点で素晴らしいものだが、モダニティの文化の中で枠にはめられたそれは、実際には社会構造の破壊に貢献し、より多くの不平等、非人間化、そして金融的富のエーテル的創造と人生全般の間の大きな距離を生み出している。さらに、「人工知能」(AI)のサブテキストは、人間は問題があり、もっとロボットのように振る舞うべきで、私たちの技術的創造物は私たち自身よりも「優れた」ものになりうるというものである。AIは私たちに、人間を排除することができる、そして排除すべきであると言っている。人類文明の自滅的なプロセスにおいて、生態系の大災害は急進的なロボット化と組み合わさって、生態系と人類の破壊を同時に達成する可能性がある!
2022年に生きる私たちは、カール・ドイッチュの「権力とは、権力の存在を損なうものを学ばないために、学ぶべきことを選択する能力である」という定義を補うことができるかもしれない。人間社会を形成し、人間社会によって形成される権力構造は、今のところ効果的に自己強化されている。近代は、自らが作り出した危機を、抽象化と生命との断絶をさらに進める方法で再解釈し、さらに、より深い学習を避ける「解決策」を設計するための自らの能力を呼び起こすことができる「問題」の定式化につなげる。支配的な思考法にとらわれた意思決定者たちは、不快な疑問を投げかける代わりに「解決策」を見出すよう、多くの圧力をかけている。問題は扱いやすい方法で定式化され、理解しやすい解決策を持つべきであり、通常、愚かな、あるいは少なくとも教育を受けていない問題児とみなされる人々に説明するのは簡単だ。これはナンセンスだ。生命は複雑で、創発的で、難解で、予測不可能なものであり、それ自体に言及せずに言葉で表現することさえできない。私たちは、生命がどのように機能するかについて、社会を組織する方法よりもはるかに多くのことを知っている。ある特定の解釈のレンズを使うことで、私たちは盲点を作り、あらかじめ設定した概念を補強するものだけを見る傾向がある。今日、私たちが目にしていることの多くは、人々や自然に課せられた悲劇を無視した復讐なのである。盲点を完全になくす方法はないだろうが、盲点があることを意識することで、大きな違いが生まれる。
人間革命
人間の発展と幸福を生物圏の健全性と調和させるためには、人間同士、生命同士、時間との関係の質が、人間の文化において中心的な役割を果たすべきだと主張する。ナディア・サンディの言葉を借りれば、「生命が再び存在することを許そう」ということである。この考え方では、人間の幸福は公平でなければならない。それは、社会の崩壊や大規模な戦争(その種類を問わない)を避けるためだけではない。また、健全な生物圏の中で生きていくためには、公平性が不可欠である。2021年のローマクラブ年次総会のタイトルにあるように、私たちは「健全な地球のためのグローバルな公平性」を必要としている。とはいえ、今のところ、全体としてはここを目指しているわけではない。1984年、アウレリオ・ペッチェイと仏教哲学者・詩人の池田大作は、『Before it is Too Late』という本の中で、「人類は間違った方向に進んでいる」とし、「自然と平和に暮らす」ために人間革命が必要であると結論づけた。11 それから数十年、私たちはまだその平和を実現していない。新しいパターンを学ぶことは、人類社会の軌道を変える以上に急務となっている。
そして、もし現代が自らの基盤を強化するようなものしか学べないとしたら、私たちは困難な課題に直面することになる。私たちが必要とする学習のための条件をどのように整えればよいのだろうか。地球規模の緊急事態に対処するための制度的な方法は、期待された結果をもたらしていない。同時に、無数の自己組織化したコミュニティが、通常は優れた個人によって触媒となり、従来の「開発」の破壊的なパターンに対処する別の方法を模索している。これらの試みにはいくつかの共通点がある。それは、すべての人の基本的な人間性を信頼し、人々が無力感から解放され、自ら学ぶことができるようにすることである。個人と集団、伝統と現代、芸術と科学、言葉と体現など、能力や知識を動員する。また、彼らは文脈のある環境、通常は帰属意識を活性化させることができる地域社会で課題に直面する。彼らは「世界を救う」のではなく、むしろ「世界に奉仕する」ことを目指している。謙虚さ、古代の知恵の尊重、そしてしばしば目に見えないことも彼らのツールの一部である。最終的には、人間らしさを取り戻すことを目指している。
気候変動、不公平の増大、生物多様性の喪失、資源の枯渇など、自己破壊的な傾向に効果的に対処するには、分離と断絶という同じレンズを使い続けることは不可能である。同時に、私たちは、適切な学習と変化のスピードと効果という点で、より高い次元に飛躍する必要がある。これは、触媒作用、受粉、結実によって加速される、ほとんど自然発生的なプロセスである創発に賭けることによってのみ可能であり、「スケールアップ」ではない、というのが私たちの確信である。そして、「スケールアップ」ではなく、「創発」に賭けるしかないのである。創発は計画的に行うことはできないし、地上から遠く離れたところから行うこともできない。そして、中央集権的なトップダウンのアプローチでは、すべての人の潜在的な能力や熱意を活性化することはできない。触媒作用によって、人々は自分たちの文脈でより良い質問を立て、地域の生態系や社会の文脈に最も適した分散型の対応を豊富に提供することを自ら学ぶ必要がある。これは、世界中の多くのシードプロセスですでに起こっていることである。冒頭で紹介した2016年11月のデニス・メドウズの講演では、ローマクラブが人類の進路が転換するための文化的変化の重大性を見逃していたと概説している。多くの人のお決まりの反応は、文化的な変化を起こす方法がわからない、とにかく時間がかかりすぎるというものである。しかし、ここでもまた、スピードへのこだわりは誤解を招きかねない。
実際、文化的な変化はすでにここに、私たちの周りに、多くの人々のエネルギーとコミットメントの中にあるとしたらどうだろう。被差別民はどこにでもいるし、女性の声を聞くことを切望し、生きやすい未来を熱望する若者もいる。人間革命は、メディアやソーシャルネットワークの中ではなく、人間の心と魂の中で、目に見えるようで見えない、カリマ・カダウイの言う「静かなメロディ」を奏でながら、すでに起きているのかもしれない。私たちの基本的な関係性を取り戻すことは、それほど難しいことではないはずだ。結局のところ、誰もがそれを行うことができる。そしてそこから、人為的に壊された相互依存関係を修復し、関係の再出現を歓迎し、生態系全体を再生させることができる。これこそが、私たちがすでに知っていることに新たな意味を与え、21世紀の人間としての新たなあり方を学ぶ方法なのである。ヘルダーリンが言ったように、「危険があるところには、救いの手も伸びている」のである。では、生命との和解が静かな旋律であるとすれば、どうすればそれを誰にでも聞こえるようにすることができるのだろうか。私たち人類への招待状は、私たち自身のため、そして来るべき世代のために、お互いに、そして生命に対して、ゆっくりと耳を傾けるよう呼びかけるものである。
謝辞
本というものは、常に集団の冒険であり、この本もまた、そうだ。この本は、共同編集者からの厳しい要請にもかかわらず、すぐに応えてくれた多くの著者の貢献によって成り立っている。特にローマクラブの共同会長であるマンフェラ・ランペール氏とサンドリーヌ・ディクソン=ドクレーヴ氏は、『成長の限界』出版50周年を記念して、本書がその一例であることを示すプログラム全体を推進した。
また、何度も頓挫しかねない複雑なプロセスを合理化し、私たちの生活をより快適なものにしてくれたExapt Pressの出版社、ロブ・ワースにも感謝したい。彼のおかげで、私たちは出版がいかに魅力的な旅であるかを体験することができた。決して小さなことではない!
もちろん、私たちの周りにいる、この本の構想を、まるで産むことも仕事の一部であるかのように生きてきた人たちに、とても感謝している。ローマクラブ事務局のスタッフ、特にフィリッパ・バウムガルトナー氏とティル・ケラーホフ氏である。
最後になったが、本書のトピックに関連する多くの継続的な会話において、私たちの対話者が果たした役割を認識するために、特別な注釈を加える必要がある。そのすべてを紹介することはできず、したがってこの引用は必ずしも不公平なものだが、以下にその一部を紹介する: Aline Frankfort、Cintia Jaime、Karima Kadaoui、Kristina Lanz、Lydia Maher、Nadia Sandi、Roseann Stempinski、Samantha Suppiah、Sarah Dubreil、そしてSijin Chen。彼ら全員と他の多くの人々は、本書で話していること、つまり望ましい未来への可能性の空間を開くことを実際に行っている。
– 共同編集者であるウーゴとカルロス
ローマクラブについて
ローマクラブは、複雑な地球規模の問題に対する全体的な解決策を特定し、人類が複数の惑星的緊急事態から脱却できるようにするための政策イニシアチブと行動を促進する、多様なソートリーダーのプラットフォームである。
この組織は、5つの重要な影響分野を優先している: 「新しい文明の出現」「惑星の危機」「経済学の再構築」「金融の再考」「若者のリーダーシップと世代間の対話」である。
ローマクラブは、人類と地球が直面する複数の危機に対処するために設立された。科学者、経済学者、ビジネスリーダー、元政治家など、100名の会員が持つ独自のノウハウを結集し、複雑で相互に関連し合う世界の課題に対する包括的な解決策を見出そうとしている。
数十年にわたる急激な消費と人口増加は、地球の気候や生命維持システムを脅かし、同時に社会的・経済的不平等を助長し、世界中で何十億人もの人々を困窮させている。
私たちのメンバーは、多様な専門知識を持つオピニオンリーダーのネットワークとして、人類と私たちの共通の故郷が直面する惑星規模の緊急事態に立ち向かうために必要な、難しい会話と大胆な行動を促進することに尽力している。私たちの目標は、より回復力のある生物圏の中で、人間の新しいあり方を促進することによって、社会が現在の危機から脱することを可能にするパラダイムシフトとシステムシフトを積極的に提唱することである。
ローマクラブは、徹底した科学的分析に基づき、相互に関連する巨大な問題に対処するための全体的な提案を行っている。研究、具体的な政策提案、ハイレベルな会合、討論会、会議、講演会、その他のイベントの開催を通じて、このような活動を行っている。
詳細は https:// www. clubofrome.org/ で確認してほしい。
