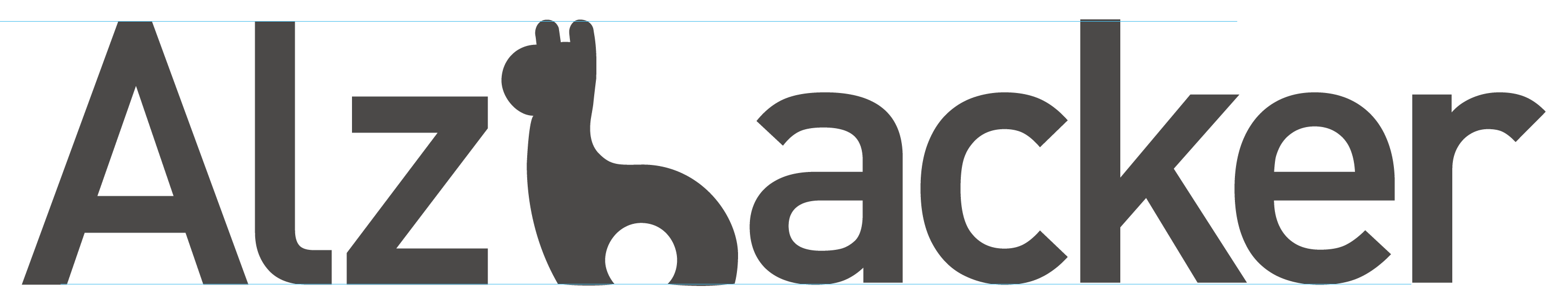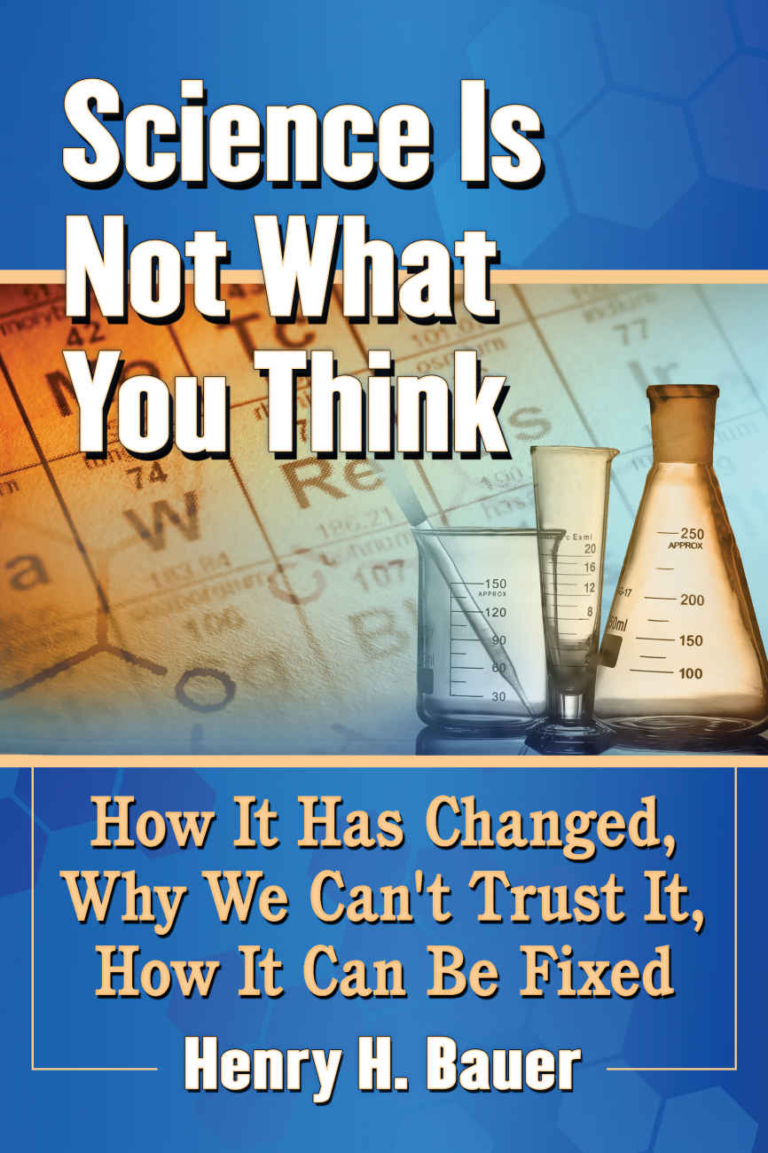Science Is Not What You Think
How It Has Changed, Why We Cant Trust It, How It Can Be Fixed
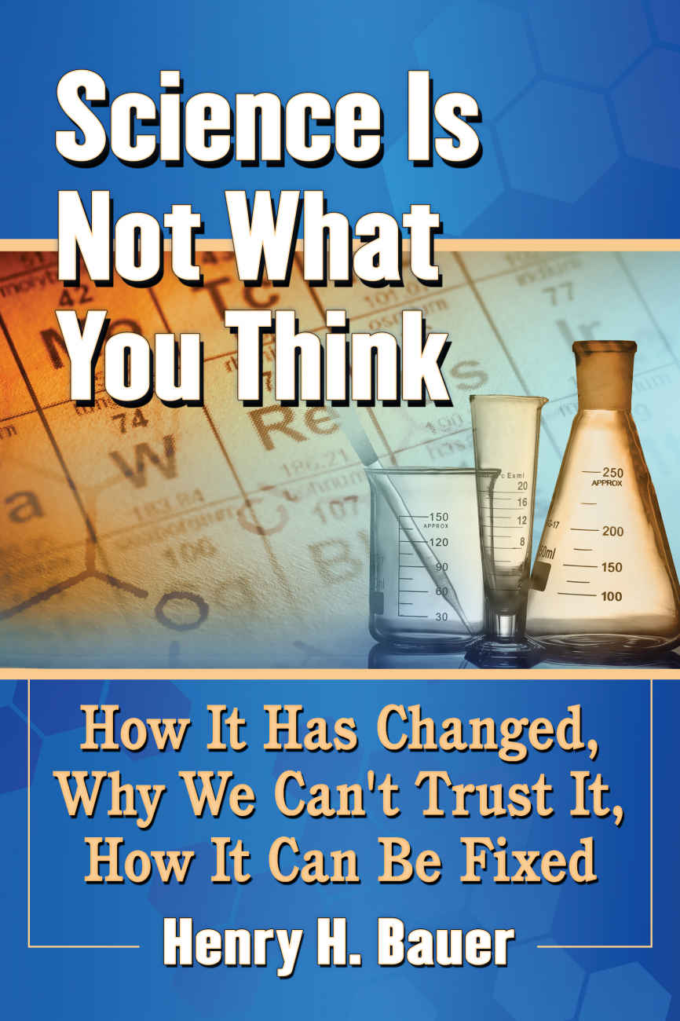
目次
- インデックス
- 図表一覧
- 序文
- はじめに・あらすじ
- 1. 科学はどのように変化してきたか
- 2. 科学は方法論ではない
- 3. 科学に関するその他の誤解
- 4. 科学は多くのことをする
- 5. 科学者には多くの顔がある
- 6. 科学はどのように行われるのか
- 7. 「科学的知識」とは何か?
- 8. 統計学
- 9. 物理や化学とは違う?
- 10. 科学的知識はどのようにして知られるようになるのか
- 11. 科学には厳しい愛が必要
- 12. 科学裁判?
- 各章のノート
- 参考文献
- 名称と用語の一覧
- 図1 知識フィルター
- 図2 周期表.
- 図3 曖昧な画像
- 図4 統計的相関は線形相関である必要はない
- 図5 男性の年収と女性の年収
- 図6 ベルカーブまたは正規分布
- 図7 科学的知識がどのように公知となるか
ヘンリー・H・バウアー
前書き
現代社会において、科学は非常に広範な重要性を持っている。科学は、信頼できる知識の有効な試金石である。
メディアや政策立案者は、科学的な事柄に関する現代のコンセンサスが実用的な真実として安全に扱われることを当然視しているようである。科学とは、公的機関、専門科学団体のスポークスマン、あるいは個々の科学界の要人によって科学として流布されたものであり、主流の情報源がそう言っているのだと思われている。多くの人々にとって、科学は事実上、宗教や社会・政治的イデオロギーに代わって、何が真実であるかを証明するものとなっている。
しかし、歴史は、現代の科学的コンセンサスが、いつかは取って代わられる可能性があることを明確に教えている。実際、科学の進歩は、以前は(もしあったとしても)資格のない、無能な、あるいは正真正銘の狂人と見なされていた人々やグループによってのみ疑問視されていた、以前に認められた見解を修正し、あるいは完全に置き換えることに依存してきた。
このような科学的信念の継続的な修正と置き換えの歴史的事実は十分に広く知られていない。このことが、現代の科学的主張や理論が、議論の余地のない明白な事実によって客観的に正当化されうる以上に、時として容易に受け入れられる理由の一つであるかもしれない。さらに、科学の本質について広く信じられている多くの信念が、ある程度間違っていることも、このような受け入れられ方をする理由の一つである。
- 科学は常に懐疑的であり、証拠がそれを要求するまで信念を固めない。
- 科学は常に懐疑的であり、証拠が要求するまでは信念を打ち立てない。
- 科学は自己修正するものであり、証拠が要求するときはいつでも考えを変えるからだ。(これは最初の2点と矛盾することに注意してほしい。自己修正は、科学が最初に物事を正しく理解できなかった場合にのみ必要となる)。
- 「 ピアレビュー」は、科学の客観性を守るものである。
しかし、もしこれらが本当に重要な点に関する誤解であるなら、どうしてこのような誤解が広まったのだろうか。結局のところ、科学は長い間人間活動や社会の一部であり、その間、科学活動やその成果物は非常に厳しく吟味されてきた。
この難問に対する答えは、それ自体が重要な洞察でもあるが、これらの誤解は必ずしも全くの誤解ではなかったということだ。2世紀ほど前から20世紀半ばまでは、これらの考え方は明らかに不合理なものではなかった。しかし、第二次世界大戦中とその後、科学活動は大きく変化し、科学の本質と影響に関する専門家の学問的理解も、この半世紀ほどの間に起こったことの重要性に追いついていない。特に、科学的活動に対する利益相反や外部からの圧力は、誠実さや信頼性の低下を伴っているという事実が最も顕著である。
歴史家やその他の観察者、識者は、通常「近代」科学と呼ばれるものの起源は、一般に17世紀頃に起こったとされるいわゆる科学革命にあることに同意している。その際、宗教的、政治的な権威の主張を受け入れるのではなく、入手可能な証拠にしっかりと基づいて説明、理論、理解を行うという経験主義が決定的に重要な要素となった。科学的方法とは、証拠によって理論を決定し、証拠に照らして仮説を検証することだ、と説明することは、科学が近代化し、過去数世紀にわたる驚異的な業績を達成したときに何が起こっていたかを説明する上で非常に合理的なものである。
経験主義を実践しようとする決意は、決して自然科学に限ったことではなく、より広い社会にも表れていた。キリスト教(ローマ・カトリック)は宗教改革を経験し、一部の司祭や信徒が、宗教的権威によって伝えられた聖典の解釈を疑うことなく受け入れるのではなく、自ら聖典を解釈する権利を主張するようになった。17世紀後半から18世紀にかけての啓蒙主義は、科学革命に刺激され、あるいは同じ社会的な力によって、科学革命よりやや遅れて起こった。この革命は、従来の権威主義的な社会政治秩序を、経験的事実に基づく人間の理性=合理的思考に基づく、万人の自由と平等という啓蒙主義の理想に基づく体制に置き換えることを目指したものであった。
科学の近代化において重要な役割を果たしたのは、科学者団体や学会の設立であり、そこでは主張が議論され、批判され、受容され、修正され、拒否される、つまり、今日ではピアレビューと呼ばれるような相互作用が行われた。このことは、近代科学の初期の経験において、より客観性を高めることになった。対照的に、現代では、ピアレビューは個人的、構造的、組織的な利害対立に悩まされ、もはや客観性の信頼できる保護手段としては機能しない。
17世紀の科学革命が宗教改革や啓蒙主義と結びついて社会の他の部分から孤立して起こったのではないのと同様に、第二次世界大戦以降の科学活動の大きな変化も孤立して起こったのではない。科学に対する伝統的な見方がもはや通用しないのと同様に、ほんの半世紀ほど前までは、常識はずれの行動と見なされていたような行動が、現在では人間の活動においてごく普通に見られるようになった。例えば、スポーツでは、大学間でもプロでも、50年前なら犯罪まがいの不適切な行為とみなされていたことが、現在は、おそらく残念なことに、物事の道理として受け入れられ、変化の見込みがほとんどないほど定着している。例えば、プロスポーツにおけるドーピング、学力的に不適格な「学生」アスリートの大学入学を考えてみるとよいだろう。
今日の科学の一般的な性質についての誤解は、科学の実際の歴史や、第二次世界大戦以降の科学と社会の劇的な変化についての無知によってのみ助長されるものではない。また、現代科学が取り組んでいる様々な分野の具体的な内容についても、十分な知識がない。ほとんどすべての研究プロジェクトにおいて、不確実性が存在し、研究者は特定の主張の解釈や意義、妥当性をめぐって異なるが、一般市民はこうした不確実性を知らないのが普通である。メディアは通常、主流のコンセンサスだけを反映し、あたかも現在優勢な見解が普遍的に保持されているかのように、現代科学の一枚岩のイメージを醸成しているが、実際には専門家の意見は一致しているとは言いがたい。アルツハイマー病は本当にアミロイド斑が原因なのか?抗鬱剤の特異性と有効性は?アメリカ大陸に最初に定住した人類はどこから来たのか?恐竜の絶滅は本当に小惑星の衝突が原因だったのか?などなど、「誰もが知っていること」は、実は意外と多くの研究者によって異論が出されている。これらの事柄について、大衆メディアは現在のコンセンサスを確立した真実として扱い、それが一般に信じられていることになる。
現代の研究者の間でかなりの意見の相違があることは、科学全体、つまり優勢な、あるいは公式のコンセンサスが、これまで思われてきたほどには信頼できなくなったことを示す重要な手がかりとなる。ここには悪循環のようなものがある。科学に対する伝統的な信頼は、相当数の専門家が現代のコンセンサスに異論を唱えているという事実を一般に知らしめることにつながる。しかし、その異論の事実は、科学における、また科学に関する権威主義的独断論の高まりとそれに伴う科学の一般的信頼性の低下を認識する上で不可欠な手がかりとなる。
しかし、科学に対する権威主義的独断論の高まりとそれに伴う科学の信頼性の低下を認識する上で、この反対意見の存在は不可欠である。したがって、その主張と暗黙の、あるいは明示的な助言は、可能な限り信頼できるものにしなければならない。そのためには、現在流行しているステレオタイプとは異なるニュアンスで、科学活動を現実的に理解することが必要であろう。最も重要なことは、科学的活動を人間的、社会的事業として認識することであり、利益相反のような不可避の不完全性を伴うものである。純粋に真実を追求するために科学を行おうとすると、個人的、組織的な既得権益、社会的、政治的な意図など、さまざまな障害に見舞われる。例えば、ピアレビューは、文芸批評や美術批評よりも必ずしも客観的なものではなく、適切な専門知識を有する利害関係者が意見を表明しているに過ぎない。その専門知識は、当然ながら現代の標準的な信念によって判断され、それを反映しているため、たまたま現代のコンセンサスとなったものを定着させる傾向がある。このように、査読は客観性の保護というよりも、むしろ進歩の妨げとなることがある。急進的な新しさに抵抗するのは、芸術や文学の世界だけでなく、科学の世界でも同じことが起こっており、今もなお続いている。
本書の目的は、現代の科学について包括的かつ現実的に説明し、現代のコンセンサスが自動的に実用的な真理として受け入れられてはならない、という主旨のメッセージを伝えることだ。コンセンサスに対する異論は、必ずしも根拠がなく、間違っているわけでもない(もちろん、必ずしも正しいわけでもない)。現代文明における科学技術の重要性を考えると、メディア、政策立案者、民間財団や慈善団体、そしてもちろん一般市民が、同等の資格と情報を持つ専門家の意見の違いをナビゲートできる何らかのメカニズムが切実に必要とされている。現在、そのような機構は存在しないが、可能性のある機構として科学法廷が構想されている。
現代の科学に自動的な信頼を与えるべきではないという主張は、少なくとも議論の余地があるように思われる。本書で指摘されている他のいくつかの点についても同様である。
- 科学は現在、そして19世紀半ば以降ますます、真理を探究することが主目的ではなくなっており、商業的・思想的利益に大きく左右されるようになっている。
- 科学の成果は、科学的方法の適用によるものではない。
- 研究対象が規則正しい行動をとるので、再現性が科学する上で期待されるようになった。しかし、再現性を科学するための必要条件とするならば、行動科学や社会科学は除外されることになる。
- 科学は常に証拠を優先するわけではなく、理論が確立される前にそうするものなのである。
- 医学はまだ真にエビデンスに基づく医療を実践していない。
- 科学リテラシーとは、事実や理論の知識で測られるべきものではなく、科学の歴史を理解し、科学が誤りを犯しやすい人間の営みであることを理解することを意味するものでなければならない。
- 公共的に重要な問題については専門家の意見が分かれるため、社会は様々な見解の間で開かれた実質的な関与を強いるメカニズムを必要としている。
これらの主張は普遍的な同意からは程遠いので、潜在的な読者は著者の関連する経験や資格について知っておく必要がある。
私は30年ほど科学を学び、学術界で科学者として、特に化学者として、より具体的には分析化学者、電気化学者として働いてきた。私は、成功する科学活動、あるいは成功しない科学活動に何が関わっているかを内部から学ぶために、従来の成功の度合いを十分に高めてきた。科学者や科学団体がどのような行動をとるかについて、私は多くを学んだ。カ国での勤務、国際会議への参加、世界各地の科学者との非公式な交流を通じて、私は科学の国際性を理解するようになった。
しかし、もっと大きな疑問、例えば心霊現象など、世間の関心が高い事柄をなぜ科学が研究しないのか、ということに興味を持つようになり、科学史、社会学、哲学などの学問に転向することを決意した。当時(1970年代)これらの学問分野は、科学研究という学際的なベンチャーを生み出す過程にあり、後に科学技術研究 (STS)としてその視野を広げることになった。この30年以上、私は科学技術研究に焦点をあててきた。私は、バージニア工科大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University)で、世界で初めてSTSの学士号だけでなく修士号を取得できるプログラムの設立に貢献し、そのプログラムは現在の科学技術研究学科へと発展していった。
この2つの学問的キャリアの間に、つまり、一方から他方への移行を可能にするために、私はバージニア工科大学の芸術科学部長を務めた。思いがけず、その間に、科学の文化的側面、科学間の差異、科学と他の知的探求との差異について、さらなる見識を得ることができた。
その中で、一見科学的な主張が時の試練に耐えられるかどうかを見分ける簡単な普遍的な鍵はないこと、また、しばしば「周辺科学」「代替科学」「疑似科学」「病的科学」などと呼ばれる事柄と「真の」科学を区別する原理や基準はないことを知った。
これらのキャリアは、いずれも貴重な経験だった。例えば、科学は常に再現され、複製されなければ認められないという考え方がいかに根拠のないものであるかということを、実際に科学に触れ、内側から見ることで認識することができた。また、外から科学を見ることで、活発な研究者は、証拠や知識の状態によって保証されるよりも、自分の仮定に確信を持っている傾向があることを認識することができた。管理職に就いてからは、科学と学界や社会とのつながりについて、比較的無関心に外から観察する機会を得ることができた。
序文とあらすじ
本書の目的は、科学的活動を現実的に記述することだ。これは、公的機関やメディアが、ある特定のトピックについてたまたま優勢な科学的コンセンサスが何であれ、自動的に無思慮に採用してしまうことへの対抗措置として意図されたものである。しかし、科学的コンセンサスが一時的なものであったという歴史的事実、つまり、科学の歴史は、それまでのコンセンサスが絶えず修正され、否定され、置き換えられてきたという事実を認識することが非常に欠けている。
ポストモダニストや相対主義者が主張しているように、科学的な理解というものは、他のどのような見解よりも優れた根拠を持たず、純粋に「社会的に構築された」ものであるというように誤解されないことを切に望む。それどころか、多くの科学的知識は、絶対的に正しいという保証はないにせよ、目に見える証拠にしっかりと基づいている。しかし、最も確かな根拠を持つ科学的知識は、よく消化され、長く理解されてきた事柄に関するものであることを心に留めておくことが重要である。現代の科学は、長い間検証されてきた過去の業績に反映された、確立された理解にふさわしい敬意を払うべきでない。
科学に関する多くの一般的な考え方は、科学活動がその昔どのように行われていたかに基づいており、科学が何世紀にもわたってどのように変化してきたかを認識していない。第1章では、17世紀ごろから始まったいわゆる「近代科学」の時代に起こった変化について説明する。最も大きな変化は、科学が健康、商業、技術、政治、防衛など、現代社会にとって不可欠な存在となった20世紀半ば以降に起こったものである。科学は、ガリレオやニュートン、ダーウィン、アインシュタインのような稀代の天才たちが作り上げた、独立独歩で真実を追求する事業という理想とは、今や全く異なるものとなっている。今日の科学は、商業的、政治的圧力と、人間の大企業につきものの官僚主義の弊害から、表裏一体の関係にあり、ほとんどの科学者は、天才はおろか、インスピレーションに満ちた革新者でもなく、職人気質の実務家なのである。
科学に関する最も重大かつ広範囲な誤解の一つは、科学的方法が科学の行われ方であるというものである(第2章)。しかし、科学に関することは何も、この方法によって理解することはできない。科学者がどのように教育され、訓練されているのか、異なる分野の個々の科学者が重要な異なる方法で仕事をしているという事実を把握することはできない。科学で成功する人としない人、科学の歴史を説明できない、科学を疑似科学と区別する方法を提供できない、一度大成功した科学者が後に大きな間違いを犯す理由を説明できない。科学がこれほどまでに成功したのは、何か特別な方法があったからではなく、再現性のある効果に主眼を置いてきたからだ。再現性とは、限られた変数のシステムにおける無生物の振る舞いを特徴づけるものであり、その場合にのみ普遍的な自然法則や定数を発見することができる、と言わなければならないが、そう言われることはほとんどない。物理学、化学、天文学は、無生物の比較的単純な組み合わせや相互作用に関係している。行動科学、医学、社会科学は、行動や相互作用が特異で、長期間にわたって正確に再現することができないユニークな個人の集団を扱う。
科学に関する誤解は、科学的方法(第3章)の概念にとどまらない。科学は、一般によく言われるように、観察された証拠に厳密には基づいていない。科学的であるための必須条件としてよく言われる「再現性」は、動物や人間を対象とした研究を科学から排除することになる。反証可能性もまた、科学的であるための必須基準であるとよく言われるが、何十年も前に提案され、その後すぐに放棄されたに過ぎない。科学的リテラシーがどのように定義され、語られているかは、科学とその社会的位置づけに関する誤った考えを定着させるものである。
また、「科学」が語られるとき、それは知識の体系、研究者のグループ、あるいは国立科学財団や世界保健機関のような一つまたは複数の機関など、さまざまなものを意味することを認識しておくことが重要である(第4章)。「科学」について語ると、ある問題に関連するすべての人が、そしてすべてが一致しているかのような誤解を招くことがよくあるが、実は、非常に長い間よく理解されてきたテーマを除いては、そうでないことが多い。非常に有害な誤解は、自然科学が行うことを真似ることで、他の活動(医学や社会科学)が独自の、必ずしも全く異なることをより良く行えるようになる、というものである。
「科学」を単一の視点、回答、知識であるとする考え方は、すべての科学者が科学者として、重要な点において同じであるという非常に間違った考え方を含んでいる傾向がある。実際には、科学者同士は、人間同士が異なるのと同じように、あらゆる点で異なっている(第5章)。このことを念頭に置いておくだけで、科学に関する多くのことが理解できる。科学者個人には、人間なら誰でも持っているような感情や弱点(もちろん強さも)がある。集団の中では、科学者も他の人と同じように行動する。個人で行動するときよりも良いこともあれば、悪いこともある。「ラクダは委員会によってデザインされた馬である」と言われるように。科学者は一般に、ガリレオやダーウィン、アインシュタインのようなエリートとして想定される。しかし実際には、最近の科学者はエリートや天才とは程遠く、他のホワイトカラー専門家と大差はない。とはいえ、科学者は他のホワイトカラーの専門家とは大きく異なる。法律や医学など専門的な文脈で発展してきた文化とは対照的に、科学文化を特徴づける一般的な属性があるのだ。
科学者は生計を立てる必要があり、それは雇用者や後援者が望むことをすることと、最良の科学を行うことの間に利害の対立があることを意味する。国立衛生研究所や世界保健機関のような科学機関は、その存在と資金を政治団体、国家政府、国際グループに依存しているため、独自の利益相反を抱えている。このような機関の役員は、科学的知識の健全性ではなく、その組織の健全性に第一義的な責任を負っている。
第6章では、科学が実際にどのように行われるかを説明する。最も重要なことは、科学は試行錯誤を経て発展してきたということ、そして間違いの発見と訂正には時間がかかるということだ。つまり、最も信頼できる科学は、最も古く使い古されたものであり、メディアが騒ぎ立てるような最新のブレークスルーは、最も信頼できない科学でもある。
また、「科学」とは非常に多様な活動であり、生物学、化学、地質学、物理学など、さまざまな方法で異なる科学から構成されていることも理解しておく必要がある。共通点としては、査読があること、既存の信念や慣習を脅かすような新奇なものを受け入れようとしないこと、そして科学の進歩には運が大きく関わっていることなどが挙げられる。
第7章は、科学が生み出す知識と、それがどのように誤解され、悪用されるかについてである。ある特定の物事に関する科学的知識とは一体何なのか、そしてそれを発見するにはどうすればよいのか。事実と理論の間には重要な違いがある。この違いは、地図によって提供される知識と、物語によって提供される知識の違いに似ている。事実と理論の違いを尊重しないと、科学に過度に依存することになり、極端な話、科学が宗教的な信仰と化してしまう、科学者主義のカルトになってしまう。
統計学(第8章)はそれ自体科学ではないが、科学、特に行動科学や社会科学、医学の分野では重要な位置を占めている。統計情報の表現方法は誤解されやすく、特に「統計的有意性 “の意味について誤解が多い。
第9章では、自然科学と医学、社会科学、行動科学、そしてフリンジサイエンスやオルタナティブサイエンス、疑似科学と呼ばれるものとの関連や違いについて述べている。そして、主流派科学における少数派の見解が、あたかもフリンジサイエンスであるかのように誹謗中傷されることが多くなってきていることから、このことは直ちに懸念されることだ。
専門家が政策決定に向けて助言する場合、さらなる研究のためのガイダンスを提供することと、社会的応用について責任を持って助言できるほどの確信を持つことは、重要な区別をする必要がある。
第10章では、科学的知識がどのようにして社会のさまざまな集団に知られるようになるのか、すなわち個々の科学者や科学界全体、メディア、大衆、政策立案者などに知られるようになるのかについて論じている。そこには多くの落とし穴があり、多少なりとも信頼できる科学的知識というカップと、その知識の潜在的消費者である様々な人々の唇との間には、多くの滑落があるのだ。誰が科学を語る資格があるのだろうか。一般市民や科学的知識の消費者は、偽預言者や偽預言に注意する必要がある。現役の科学者自身は、自動的に「科学」全体について知っているわけではなく、自分自身が関わっている特定の科学の断片についてだけ、直接的に知っている。
第11章は、前章までの科学活動の実態から導かれることをまとめたものである。社会は科学をうまく利用することができるが、それは科学の本質が理解され、適切な役割の道具として使われる限りにおいてであり、犬を振る尾になることが許されるわけではない。科学は当然尊重され、賞賛されるべきものであるが、私たちの科学に対する愛情は、むしろ厳しいものでなければならない。
今日、多くの問題において、現代の科学的コンセンサスの熱狂的な支持者が、不確実性やコンセンサスに対する有能な異論を無視、あるいは退けている。この数十年の間に、同等の資格を持つ専門家の異なる見解を裁くことができる独立した機関が必要であるという提案が数多くなされ、現在では科学法廷という言葉で表現されている。
科学法廷が何を達成し得るかについては、第12章で述べられている。科学法廷をどのように設立するかについては、少し詳しく説明する。このような機関についての初期の提案では、技術的な問題についての社会的論争の相対的なメリットを評価する必要性や、技術的な問題が訴訟において重要な役割を果たす場合に法制度が直面する困難さが強調されていた。ここでは、反対する技術的見解が実質的かつ公に交わることができない現代に起因する、もう一つの必要性が強調されている。科学法廷は、政策立案者、メディア、一般市民が合理的な情報に基づいた意見に到達することができない、異なる技術専門家間の開かれた、実質的な関わりを強制することができる。
1. 科学はどのように変化してきたか
科学とは客観的に真実な知識を探求するものであるという考え方は見直す必要はないかもしれないが、探求は活動であり、この特定の活動に関わるほぼすべてのものは、過去数世紀の間にかなり根本的に変化してきた。
科学とは何か、科学に何ができるかということに関する今日の一般的な考え方は、17世紀に西ヨーロッパで起こった「科学革命」以降、いわゆる「近代」科学が成し遂げたことに大きく基づいている。特に20世紀半ば以降、第二次世界大戦で科学が果たした役割に刺激され、科学活動を取り巻く環境に大きな変化が起こった。
科学に費やされる資源は世界中で膨大に増加し、何らかの科学的な仕事に従事する人の数も増えている。科学は、社会のほぼあらゆる場面で、第二次世界大戦争前よりもはるかに重要なものとなっている。しかし、科学とは何か、科学はどのように機能するかについて、一般に信じられている考え方は、科学が何をし、どのように行うかというこの大きな変化に追いついていない。従来の常識は、今日の科学について著しく時代遅れで、誤解を招くものだった。
実は、科学の歴史全体が、専門家以外にはよく理解されていない。誤解を招くような考え方があふれている。例えば、ガリレオについて知っている人は皆、彼が宗教的ドグマとの戦いの中で科学を体現したということを知っている。しかし、むしろガリレオは、あらゆる権威があらゆることについての矛盾を許さないという姿勢に抵触したという方が正しい。
今日、公的な権威には科学機関も含まれるが、そうした機関は、他の権威ある社会機関と同様、自分たちの信念やドグマに対する批判を受け入れようとはしないし、これまでもそうであっただろう。全米科学アカデミー、アメリカ物理学会、国立衛生研究所、食品医薬品局、疾病管理予防センター、世界保健機関、UNAIDSなどの機関から誤りを認める声を聞くことはない。また、これらの機関は、たとえそのような異端児がどんなに優秀であっても、異端児が提供する新しい理解の主張に注意深く目を向けることはない。今日の「ガリレオ」は、既存の信念を根本から覆す主張を支持する科学者たちであり、HIV/AIDSに関するピーター・デュースバーグ、ビッグバンに関するハルトン・アープス、地球温暖化や気候変動に関するフレッド・シンガーズなどである。彼らの主張とそれを裏付ける証拠は、ガリレオがその時代の宗教的権威によって検討されたのと同様、今日の科学的権威によって注意深く検討されることはない。急進的な新機軸は、科学機関や科学界全体から抵抗され続けている。
トニー・ロスマン(2003)の『Everything’s Relative』でうまく説明されているように、科学の歴史について「誰もが知っていること」とは、エジソンが電灯を発明した、ベルが電話を発明した、ダーウィンが進化論を考え出した、などということだ。このようなことは、科学は少数の天才が具体的に特定できることを行うことによって進歩してきたという、まったく間違った印象を与えてしまう。そうではなく、科学の真の歴史は、様々な人が様々な形で、多かれ少なかれ同じような時期にアイデアや発見をしたものである。決定的な出来事は、ある発見が一般に受け入れられるようになったときであり、そのときの手柄は、偶然の産物として、むしろ恣意的に割り振られる。本当の科学史は、一般的で、単純化され、理想化されたものとは非常に異なっており、物理学者・歴史家のスティーブン・ブラッシュ(1974)は、次のように考えてさえいる。「科学が実際にどのように行われているかを知り、科学が公平で客観的で利害関係のないものであるという考えを打ち破れば、科学者になろうとする人々の士気をそぎ、現在科学が享受している威信や地位を損なうことになるかもしれないからだ。」
現代科学の前身
ストーンヘンジのような巨石建造物が天文学的に重要な位置を占めているように、何千年も前の人々が天の出現について知っていたことや、先住民が植物界の物質の薬効について知っていたこと(少なくとも数千年前から人間が薬として使っていた柳の皮を、18世紀に単離したアスピリンが象徴的)が真の「科学」知識の証明とされることがある。
科学の始まりは、少なくとも4000年前の古代メソポタミアまで遡ることができる。この時代には、60分時間や360度円など、60進法の数学による計測が行われていたのだ。科学発祥の地として、2500年以上前の古代ギリシャが挙げられることもある。アルキメデス、「ユリイカ」、そして、どんな形の物体でも、水に浸して水位がどれだけ上がるかで体積が測れるということに気づいたこと。1,500年前の古代インド文明では、ゼロという数学の概念があった。アラビア語は、ヨーロッパの暗黒時代(紀元6世紀から12世紀)に栄え、代数学や錬金術などの用語や、アラビア数字の使用により、ローマ数字よりもはるかに簡単に計算できるようになったことが想起される。
ロジャー・ベーコンは、13世紀に経験主義を重視した科学的手法をいち早く取り入れたとされることがあるが、フランシス・ベーコン(16〜17世紀)もそうだとされることがある。しかし、それ以前に知識を得た事例もすべて、観察や経験から学ぶ経験主義を反映していることは確かである。では、16-17世紀頃に何が起こり、「近代」科学の誕生をそこに位置づけることに、万人の合意が得られたのだろうか。
その決定的な要因は、当時から続いている結束力と継続性、そして識別可能な国際的な科学界の存在である。メソポタミア、エジプト、ギリシャ、インド、イスラムにおける重要な、重要な、輝かしい先駆者たちは、一夜限りの関係のようなもので、それ以上包括的で永続的なものにはならなかった。これとは対照的に、17世紀以降、科学は途切れることなく国際的に協調して追求されるようになった。その継続性と結束力は、歴史家デレク・プライス(1975:8章)が最初に示した、科学論文と科学雑誌の数で測定されるように、17世紀以来、科学活動が着実に、そして指数関数的に成長してきたことに示されている。簡潔だが包括的な科学史としては、Knight (1986)やMarks (1983)を参照されたい。
近代科学が17世紀ごろから始まったことは広く知られているが、それ以降、科学的環境にいくつかの決定的な変化があったことは通常指摘されていない。
近代科学の3つの時代
始まりは17世紀から19世紀 アマチュア科学
「近代」科学のルーツは17世紀の科学革命 (The Scientific Revolution)にあるとするのが一般的である。コペルニクス的、ガリレオ的な天体観測とその動きの解釈、そしてギリシャやローマにおける洞察の(再)発見と再評価、それらを保存し補強するアラビアやイスラムの文化の役割に言及したルネサンスである。科学革命の年代をより微妙なものにすると、これらすべてが統合されたのは、おそらく1500年頃から1800年頃までであったと認識される (Brush 1988)。
また、1660年にロンドン王立協会が設立されたことも重要な要因であったと、ほとんどの歴史家が認めている。このような共同研究は初めてでしたが、当時から中断することなく活動を続けている最も初期のものである。王立協会やその他の団体は、自然の仕組みを知りたい、理解したいという好奇心旺盛な人々で構成されていた。その好奇心を満たすためなら、利害の衝突はほとんどない。しかし、それが相互の理解を深める上で大きな妨げになったという事実はない。
17 世紀の科学革命とそれに伴う啓蒙主義は、一般に、西洋文明が真の知識と理解の究極の決定 者としての宗教に頼ることをやめ、目に見えるものを扱うときには経験的な経験-科学-にもっと頼るようになった転換点であると考えられている。宗教改革は、権威あるドグマから歴史的、科学的知識を聖典の解釈に生かすという、宗教(少なくともキリスト教)の転換点であったといえるだろう。
この近代科学の第一段階では、科学的活動はアマチュアによって行われ、聖職者も含めて、単に好きでやっている人たちであり、自然を理解することは、神が創造したものを鑑賞することによって神を崇拝する方法であると考えた。
第二段階:19世紀から20世紀半ばまで 専門的な科学
19世紀には、科学は職業として、可能性のあるキャリアとして位置づけられるようになった。「科学者」という言葉が初めて使われたのは1830年代のことで、科学することがアマチュアの追求から職業として認められるようになったことを意味している。世紀半ばには、有用な染料の合成により、主にドイツで染料を生産する商業的な産業が盛んになった。科学を教えることが生活の糧になるようになった。大学では、科学研究を価値のある活動としてとらえるようになった。
生計を立てるために科学することは、避けがたい利害の対立をもたらす。科学者は自分の好奇心を満たしたい、自分が最も興味のあることを研究したいと思うだけでなく、何をどのように調べるかということは、他の検討事項にも影響される。その研究が自分のキャリアを向上させるかどうか?自分のキャリアにプラスになるような研究を選ぶべきか?影響力のある人々やグループが調査してほしくない事柄を調査することをためらうべきか?
近代科学の第二段階におけるこうした利害の衝突は、科学的理解の進歩に対して明らかに見分けがつくような悪影響を及ぼすことはなかった。科学におけるキャリアは、ごく普通の中産階級の専門職であり、特に儲かるわけでもなく、社会的に特別な名誉があるわけでもなかった。キャリアを促進するための意図的な不正行為はまれであった。人々は、第一期のアマチュアが科学を学ぶことを選んだのと同じような理由で、科学のキャリアを選んだのである。自分の興味のあること、やりたかったことをやって、それなりの生活ができることは、十分にやりがいのあることだった。
ブラッシュ(1988)は、1800年から1950年までを「第二次科学革命」と呼んでいるほど、この時期、科学の内容は劇的に変化した。化学や生物学の化学的側面で確かに革命的だったのは、「有機」化学物質である尿素(生 物由来)が、完全に無機な物質から作ることができるという 1830 年頃の発見だ。また、19世紀半ばには、進化に関するダーウィンの業績と、遺伝に関するメンデルの業績も、生物学全体で革命的だった(後者は数十年間、ほとんど無視されましたが。…..)。20世紀に入ってからは、化学と物理の分野で、放射能、X線、量子効果など、ブレイクスルー発見が相次いだ。
第三段階:第二次世界大戦以降 企業科学
第二次世界大戦後、科学があらゆる面で重要視されるようになり、近代科学の第三期が始まった。それに伴い、個人的な利害関係だけでなく、組織的な利害関係も発生し、強力な商業的、社会的利害関係者が科学を自分たちの利益のために利用しようとするようになった。
科学者は今日、有名人になることができ、特許やその他の研究成果からかなりの富を得ることができる。政府は学術界に対し、商業的な利益をもたらす事業に向けて産業界と協力するよう促している。学術界は、研究者自身が外部の後援者や協力者から継続的な資源を調達することを要求している。温室育ちのような雰囲気があり、できるだけ早く有益な結果を出そうと熾烈な競争が繰り広げられている。意図的な不正は、それを防止するための規制が急増して、科学における倫理に関する新しい学問分野をもたらしたほど、一般的になっている。
この第3の局面では、公的な科学は、利害関係のない客観的な立場からはほど遠いため、もはや自動的に信頼できるものではない。アイゼンハワー大統領が退任演説で軍産複合体への警告を発した際に述べたことが、あまり広く引用されていない(アイゼンハワー 1961)。
科学的研究と発見に敬意を払うのは当然だが、公共政策そのものが科学技術エリートの虜になる危険性にも注意を払わなければならない」。
私の考えでは、アイゼンハワーが警告したことが現実のものとなっている。例えば、ビッグバン宇宙起源説、HIV/AIDSの正体、地球温暖化など、科学界の少数派から証拠に基づく強い反対意見が出されているにもかかわらず、多くの問題において、公的な政策や行動は主流派の主張と信念に基づいている (Bauer 2007, 2012a, b)。
第二次世界大戦後の科学の成長
第二次世界大戦中に科学が達成した成果(レーダーやその他の多くの成果、ただし原子爆弾ほどは広く知られていない)によってもたらされた名声は、科学活動を前例のないほど急速に拡大させた。第二次世界大戦中、米国科学研究開発局を率いていたヴァネヴァー・ブッシュは、1945年に「大統領への報告」を書き、これが科学への政府資金の膨大な注入を促したと広く信じられている。全米科学財団が設立され、国立衛生研究所の予算も大幅に増額された。
この資金を得ることができ、皆、大喜びでした。私がオーストラリアからアメリカに来たのは1960年代の半ばでしたが、当時は、科学への支援は無限にあるように思われた。誰もが助成金を得ていた。大学では、通常、9カ月間の教育活動によって給与が支払われるが、科学者たちは、夏の間、研究を行うことで給与の20〜35パーセントを助成金で追加してもらうことに慣れてしまった。また、学会(多くは海外)への旅費が頻繁に支給されることにも慣れた。また、秘書や簿記係、ポスドク研究員からなる個人的な帝国を築き、教授の帝国が発表する研究を生み出す大学院生を指導・監督していた。例えば、コネのあるヤング・タークは、海水に関する研究の助成金によって、彼とその仲間たちはカリブ海で泳いだり釣りをしたりすることができた。私が一時期所属していたある利益団体では、毎年、専門家会議に向かう途中で興味深い場所に立ち寄り、観光したり、大騒ぎをしたりしたが、すべて助成金の費用でまかなわれていた。助成金が潤沢で簡単に手に入る間は、さまざまな特典を享受できたが、1970年代になると状況が変わってきた。
科学者を雇い、その科学者がもたらす助成金には、実際の研究費の50%にも上る「間接費」(一般に「間接費」と呼ばれる婉曲表現)が上乗せされ、研究機関のインフラや改善のための費用に充てられていたのだ。
1 1940 年代、米国には博士号を授与する研究大学が107 校あったが、1950-54 年には 142 校、1960-64 年には 208 校、1970-74 年には 307 校に増加した (National Academy 1978)。1955年には、米国には98の化学の博士課程があったが、1967年には165に、1979年には192になった (ACS 1955-)。
連邦政府が資金を提供するフェローシップが、科学分野の上級学位を取得する学生を奨励した。教員は、より多くの助成金を獲得し、より多くの卒業生を送り出せば、昇給や昇進という形で報われた。科学の文化は、より多くの出版物、自分の研究の引用、指導する学生の数など、多ければ多いほど良いという信念のもとに、さらに強固なものとなっていきた。「サラミスライス」は日常的に行われるようになり、一つの研究結果をできるだけ多く分割して出版することで、「出版可能な最小単位」の頭文字をとってLPUと呼ばれるようになった。新しい学術誌が創刊された。
科学関連資金の大盤振る舞いで恩恵を受けたのは、学生や科学者、その研究機関だけではなかった。機器メーカーや研究インフラを提供する業者、成長する大学が立地する地域、それらの地域や機関の政治的代表者など、科学活動の成長は、科学界以外の多くの既得権益を生み出した。大学は、建物も含め、政府の資金で物を手に入れることに慣れてしまい (Hanson 1994)大金を流し続けるために自国の議員を頼るばかりでなく、ワシントンで独自のロビイストも雇った (Ember 1989, “Ways and Means,” 1989)。
科学活動に定量的な尺度を適用した先駆者であり、科学活動の指数関数的な成長率を記録してきたデレク・デソラ・プライスは、第二次世界大戦後間もなく、この異常な拡大を長く維持することはできない、科学活動に向けられる資源は、先進国で達成された国民総経済活動の2~3パーセントをはるかに超えて増加することはほとんどない、と指摘している。彼は、必然的に差し迫った成長の停止は、大きな調整を必要とする危機をもたらすと予言した (Price 1975: ch. 8)。
成長の終焉
プライスの危機の予言は、現代科学の第三の時代において、きわめて正確であることが証明された。科学者の過剰生産は数十年前から明らかであった。博士号を持つ科学者の雇用市場は、1970年代初頭に学界内外を問わず崩壊した。この崩壊は部分的なもので、例えば物理学の博士号取得者は回復しなかった。また、1970年代までには、拡大した研究者予備力による研究支援への需要が、利用可能なものをはるかに上回った。例えば、私が1966年から1978年まで勤めたケンタッキー大学では、1960年代半ばから後半にかけて、化学科が全米科学財団に提出した提案の約半分が資金を得ていたが、1978年には、申請10件につき1件の助成金を得るまでに減少していた。医学研究だけでなく生物学研究全般の主な資金源である国立衛生研究所でも、成功率は下がり続け、1997年には31%だったのが2014年には20%になった (NIH 2015)。
このような研究費の減少が、激しい競争の雰囲気を生んだ。第5章の終わりで述べたように、以前は産業界でネズミ算式に利益を生む発見へのプレッシャーがあったのに対し、現在では研究者がネズミ算式に経験するのはアカデミックな場である。研究助成金の獲得率が低下しているため、生物医学研究者は平均して中年期から独立したキャリアをスタートさせる。生物医学研究者が主任研究者または単独研究者として最初の研究賞を受ける平均年齢は、1980年にはすでに37歳であったが2007年には42歳まで上昇している (Kaiser 2008)。
このような圧力の下、手抜きの誘惑は、明白な不正の蔓延、発表される報告の質と信頼性の低下という目に見える効果をもたらし、科学以外のオブザーバーもそれに気づいているほどである。エコノミストのような著名なメディアは、科学がひどく迷走していることを指摘している(「How Science Goes Wrong,” 2013」)。
現代の科学者は信用しすぎて検証が不十分であり、科学全体、そして人類に害を与えている。..粗悪な実験…お粗末な分析……。[発表された研究のほとんどは、再現することができない。[がん研究における53の「ブレイクスルー」研究のうち6つしかない・・・同様に重要な67の論文のうちわずか4分の1しかない・・・。
[コンピュータサイエンスでは、論文の4分の3はでたらめである。..約8万人の患者が、間違いや不正を理由に後に撤回された研究に基づく臨床試験に参加している。
成長による競争力強化もその一つである。第二次世界大戦直後、世界には数十万人の科学者がいたが、今では600万から700万人の科学者がおり、まさに「Publish or perish」(「How Science Goes Wrong」2013)である。
科学における不正
かつて科学は、極めて正直な研究であると認識されていた。不誠実な行為や明らかな偽造はまれでした。1983年に科学作家のウィリアム・ブロードとニコラス・ウェイドが、不正は科学の初期から内在していたとする本を出版したとき、科学界はむしろショックを受け、同意せず、反感を持って反応した (例えば、Bauer [1983])。しかし、数年のうちに、科学における不正は非常に明白な問題となり、それを抑制するための組織的な公式努力が行われるようになった。
ニュースレターには、ある種の不正行為で有罪となり、助成金の申請や諮問委員会への参加を一定期間禁じられた人物の名前が頻繁に掲載されている。その不正行為とは、実験結果の偽造、機密資料からアイデアを盗むなどの盗用、出版時のデータのごまかしや抜き取りなどが含まれます。このような不正行為がいかに一般的になっているか、驚くばかりである。ある調査では、研究者の約2%が少なくとも一度は結果のごまかしを認めたと報告している。しかし、この2%の研究者は、同僚の14%がごまかしたと信じていたのだから、2%というのは低すぎる見積もりであろう。さらに、3 分の1の研究者は、データのごまかしほど深刻ではないものの、同僚の4 分の3 近くがそのような不正行為を行っていると考えていることが分かった (Fanelli 2009)。
研究不正は、早くも1981 年に議会公聴会の焦点となった。数年後、保健福祉省は科学的誠実性局(後に研究的誠実性局と改称)を設置した。このオフィスは、不正を防ぐ方法や不正の疑いに対処する方法について、研究機関に助言している。医学・科学雑誌は、著者に利益相反の開示と、出版された研究のどの部分が各共著者の責任であるかを明確に記載するよう求めるようになった。カリフォルニア大学サンディエゴ校の科学技術倫理センター、デラウェア大学の科学・倫理・公共政策センター、ミシガン州立大学の生命科学倫理・人文科学センター、ノートルダム大学の科学・技術・価値観のためのジョン・J・ライリー・センターなど、研究倫理や医療倫理などのためのセンターが学会の至る所で設立された。全米工学アカデミーには、工学倫理・社会センターと工学・研究のためのオンライン倫理センターがある。全米科学財団は、科学と工学における倫理教育のためのオンラインリソースセンター (Online Resource Center for Ethics Education in Science and Engineering)を後援している。
現在では、このような問題に完全に特化した定期刊行物もある。「アカウンタビリティ・イン・リサーチ」は1989年、「科学と工学の倫理」は1997年、「倫理と情報技術」は1999年、「BMC Medical Ethics」は2000年、「科学と環境政治における倫理」は2001年に創刊されている。
研究倫理のコースはますます一般的になってきている。連邦政府機関から研究費を受け取っている機関では、このようなコースを用意することが義務付けられているほどである。1989年には、米国科学アカデミーが、その委員会 (Committee on the Conduct of Science)の後援のもとに作成した「科学者であることについて」という小冊子を発行しており、その第3版 (A Guide to Responsible Conduct in Research)を見れば、科学不正の問題が深刻であると広く認識されていることがより明らかである。
また、研究発表の取り消しが頻繁に行われていることも、不正の増加を示している。ジョン・P・A・ヨアニディスは、文献の整合性を検証することを専門としているが、彼は「発表された研究結果のほとんどが虚偽である理由」と題する論文で、少なくとも一般メディアによれば、事態を一変させた (Ioannidis 2005)。ネイチャー誌は、この現象に特化したアーカイブを構築しているほどである。
2 論文の撤回が一般的になったことで 2010年に始まったブログ、Retraction Watchの活動「Tracking retractions as a window into the scientific process」を発展させ、Center for Scientific Integrityを設立することになった。
3. 半世紀前の研究者たちは、このような事態に愕然としたことだろう。私たち1950年代の大学院生の間では、ある学生が結果を捏造し、卒業もせず、どこかの下っ端管理職になっているというショッキングな話が流布していた。まさか、『研究の責任ある実施に関する手引き』や『研究の説明責任』のような出版物や、ましてや政府の『研究公正局』の存在を経験する日が来るとは、私たちも思ってもみなかったことだろう。ジョージ・オーウェル(1949)が、政治や社会についてと同様に、科学についても洞察力と先見性を持っていたならば、未来的なディストピアの記述の中にこのようなフレーズを入れる余地があったことは間違いないだろう。
利益相反
20世紀の中頃から、科学は商業的、政治的、イデオロギー的な利益相反にますます悩まされるようになった。例えば、医学研究については、最も権威のある雑誌の一つである『ランセット』誌の編集者は、これ以上ないほど辛辣な言葉を投げかけている。
研究過程そのものが、…利益相反の金銭的泥沼に陥っている。..場合によっては、医学専門家の意見が最高入札者に買われることもある。…..。これが現代の医学界の悪しき姿である。医学のための好奇心旺盛な事業としての製薬研究という概念は、心地よいが誤った神話となった。..公衆衛生が最初の犠牲者となった [Horton 2003: 300]。
利益相反の意義は、あらゆるところで誤解されているようだ。もちろん、科学に限ったことではないが、科学では非常に大きな問題だ。同僚や競争相手は、原稿や助成金申請書の「査読者」を務めるべきではないが、彼らは日常的にそうしている。製薬会社とつながりのある人物は、その会社の製品について決して助言すべきではない。しかし米国では、食品医薬品局や国立衛生研究所などの顧問の大半が、そうした利益相反を抱えている。調査ジャーナリストは、もし諮問委員会のメンバーが利益相反のない人々であったなら、ある種の医薬品は承認されなかったであろうことを証明することができた。
4. 仮定の個人的な状況を考えてみよう。あなたは教師だ。あなたのクラスの生徒の一人に、自分の娘がいる。あなたは、生徒の成績に基づいて純粋に成績をつけることを信じている。また、自分の娘が高い成績を取り、学習する中で自尊心を育むことを望んでいる。教師としてやりたいことと、親として娘に望むことの間に利害の対立があり、あなたはその板挟みになっている。成績をつけるとき、娘と同じような成績をとった他の生徒とまったく同じ成績をつけるかもしれないが、そうしたかどうかを知る方法はない。また、他の人は、利害の対立があなたの判断をゆがめたのではないかという疑念を抱く可能性が高い。(そして、もしあなたの娘の成績が彼女が考えるほど高くなかったとしたら、彼女は、あなたが彼女を優遇しているように見えないように過剰に補填したのではないかという十分な根拠がある疑いを持つかもしれない)。
彼女の疑いや、他の人たちの反対の疑いは、非常に根拠のあるものだろう。この特定の例では実際には起こらなかったかもしれないが、全体的に平均して利益相反が行動に影響を与えること、つまり、実際にかなりの時間影響を与えることは間違いない。
例えば、ある調査では、臨床検査機関と利害関係のある医師は、利害関係のない医師よりも頻繁に臨床検査を処方していることが明らかになった。このような場合、意図的に不正を行うことはないだろう。そもそも臨床検査機関に投資した医師は、考えられる限りの臨床検査を行うことの価値をすでに信じていたからかもしれない。言い換えれば、これらの特定の医師は、たとえ検査機関に投資していなかったとしても、同じように多くの検査を処方していたであろう。それにもかかわらず、彼らはより多くの検査に偏見を持つ。この偏見は他の医師にはないもので、もし、関係する検査が費用対効果において有用であることが疑いなく知られていれば、すべてあるいはほとんどの医師がそれらを処方しているはずだからだ。利益相反があるということは、たとえその人が全く正直な動機で行動し、不適切なことをしているという自覚がなくても、ある特定のタイプの行動に対する明確な傾向があるということだ。
この利益相反の基本的な事実が、最近広く誤解されているようだ。例えば、「見かけ上の」利益相反について語られることがある。そんなものはない。そのような話は、既存の利益相反が害を及ぼさなかった、あるいは及ぼし、あるいは及ぼすであろうことを言おうとしているが、それは知ることができない。利益相反がもたらす可能性のある結果を回避する唯一の方法は、利益相反を完全に回避することだ (Stark 2000)。
このことが理解されていない、あるいは願い下げである、あるいは故意に見過ごされていることがあまりにも多い。人や組織は、「明らかな」利益相反だけでなく、「無視できる」はずの利益相反についても語ることで、既存の実際の証拠から逃れようとしている。例えば、バージニア州では、「無視できる」ことを金額で定義しており、数年前は年間13,000ドル未満を意味していた (例えば、親戚を雇う場合、政府とのビジネスを手配する場合)。ちょっと考えればわかることだが、ある人にとって年間1万3千ドルというのは無視できても、他の人にとってはそうではないのだ。利害の衝突があると、それによって行動が偏る可能性が高いという事実を回避する方法は、単純にない。「見かけ上」、「無視できる」、その他の婉曲表現と言い逃れは、ある利益相反や利益相反の種類が深刻な損害をもたらす結果にならないことを判断できるように装っている。このような予測は、健全でも正確でもあり得ない (Bauer 1994)。
今日の科学は、過去に比べれば堕落していない
今日の科学は昔より信頼できるに違いないと想像するのは簡単だ。結局のところ、科学的知識は増え続けているのだから、科学はより良くなっているに違いないのだ。
しかし、量が増えれば自動的に質が向上するわけではない。この現象は「ロトカの法則」と呼ばれるほど一般的である (Price 1975: 175)。人間の行動のほとんどすべての面において、能力と成果の階層が存在する。ある分野のエリートの数が2倍になれば、彼らの平均的な専門知識は以前より低くなる可能性がある。トップ5の短距離走者の平均的な才能とスピードは、トップ50の平均的な才能とスピードより大きい。どんな専門分野でも、どんなトピックでも、上位5人の科学的才能と専門知識の平均は、上位50人の才能と科学的専門知識の平均を上回るだろう。
科学が飛躍的に発展するにつれ、平均してエリートではなく、凡庸になってきた。これが、今日の科学が過去に劣らず、あるいはそれ以上に誤りを犯しやすいとする直接的な理由の一つである。
その他の理由としては、先に述べたように、利益相反や不正行為の増加が挙げられる。科学が最もよく機能するのは、知識を求めることだけが動機であり、研究者が何をするか、どのようにするか、何を、どのように発表するかについて制約を受けずに自分の科学的興味に従って行動できるとき、すなわち科学が自由であり、自分自身のことを行うことができるときである。今日の科学は、どのような研究を行うか、その結果をどのように、あるいは普及させるかどうかという点で、こうしたあらゆる制約を受けている。今日の科学は、それ自体ではない。
なぜなら、ほとんどすべての分野で最新の研究を行うには、専門家としての地位、つまり適切な仕事が必要だからだ。また、インフラストラクチャーや、同僚や技術者を含む物質的なサポートなど、多大な資源を必要とする。これらすべてを利用できるかどうかは、利害関係のない人たちや、純粋な知識の探求が常に、あるいは通常でもないような、自分自身の優先順位を持つ人たちの判断にかかっている。このように、科学はもはやほぼ理想的な状況下では機能しない。
経済的な問題との類似が適切かもしれない。経済的に理想的な結果が得られるのは、すべての起業家に開かれた完全に自由な市場があり、仮に合理的で制約のない潜在的消費者の要求によって駆動される供給オペレーションを偏らせる影響によって制約されない場合である。近世の科学(17世紀から20世紀初頭まで)は、知的起業家による自由市場に近いもので、その活動は、自然の仕組みに真の洞察をもたらすものとして、後に評価された。これとは対照的に、今日の科学は、個人の知的起業家による自由な市場とは程遠い。科学的成果の普及もまた、商業機関や公的機関によってコントロールされており、何が最も重要か、何が最も優れた科学かという基準だけで決定されるわけではない。20世紀の半ば頃までは、科学は家内工業的なものであったと言えるが、今では世界中に広がり、著しく官僚的な事業となっている。
つまり、この半世紀ほど、科学はより信頼されるようになったわけではない。組織的、個人的な利益相反はいたるところに存在する。不正はより一般的になっている。科学文献は効果的な品質管理を行わず、手に負えないほど膨大になることでその価値の多くを失っている。受け入れがたいことかもしれないが、今日の最新の科学は、これまでフロンティアで行われてきた科学と同様、信頼に足るものではないというのが事実である。そして、最新の科学をより信頼性の高いものに修正するプロセスは、外部からの強い影響力を持つ利害関係者が誤りの修正に抵抗するため、過去に比べ、今日ではあまりうまくいっていない。
Brush(1988)は、1950年を一つの時代の終わりとしているが、彼の洞察はまだ通説にはなっていない。20世紀半ば以降の現代科学が、現代科学の初期段階とは実に大きく異なっていることが、まだ広く認識されていない。確かに、資源をめぐる激しい競争、出版過多、不正の横行など、違いの要素は公に議論され(そして嘆かれ)てきた。特に医学と製薬業界に蔓延する利益相反がもたらす損害については、多くの著作で述べられている (Bauer n.d.; Krimsky 2003)。しかし、一般の人々の科学に対する認識や科学に関する常識は、科学が非常に信頼でき、公共財であった古き良き時代に基づいたものであることに変わりはない。理想化された科学観が根強いため、科学がこれほど独断的になり、証拠と対立し、ここ数十年の間にいくつかの問題で間違った方向に進んだことが信じられないように思えるのだ (Bauer 2007, 2012a)。
しかし、信頼性が低下し、誠実さが激減しているのは科学だけではない。社会の他の面でも同じ傾向が見られる。科学は、社会の他の部分から隔離された学術的な象牙の塔ではない。科学者もまた市民であり、社会の一般的な動向は科学活動にも対応するものである。近代科学の始まりにおいてさえ、科学が社会全体において特に顕著な、あるいは影響力のある役割を担っていなかったとき、経験主義、プラグマティズム、伝統的権威の拒絶の方向に科学活動に影響を与えたものは、社会政治的発展においても影響を及ぼしていた。
科学と現代社会
科学は長い間、利害関係のない真実の追求と一般的な誠実さに支配され、広く賞賛と名声を得てきた。そのため、今日の科学に関する公式声明が、商業広告主の声明や政治的情報源から得られるものと同様に、慎重に懐疑的に扱われなければならないことを受け入れるのは困難なはずだ。しかし、それは事実である。この事実は、他の社会分野においても、行動規範や信頼性の低下が同様に生じていることを指摘すれば、より信憑性が増すかもしれない。例えば、大学やプロのスポーツ界、あるいは医療界、特に処方薬についてである。
科学界で反対意見が無視されたり、積極的に弾圧されたりすること(「科学と証拠:愛憎関係」第3章、「進歩への抵抗」第6章、「主流派科学における少数意見」第9章)事実関係や解釈について意見の異なる科学者が、互いの本質的議論に関与しないこと(「関与の欠如」第11章)も受け入れがたいように思える。しかしこれも広い社会を反映しており、スポーツマンシップや表現の自由の理想はしばしば、商業的考慮や政治的に正しいかどうかに優先されかねない。
スポーツマンシップから「勝つこと」がすべてへ
半世紀以上前、私がオーストラリアで過ごした時代には、スポーツとは、そこから得られる喜びのために行われる活動だった。観客は、ホームチームであれビジターチームであれ、その卓越した技に拍手喝采を送った。スポーツに参加することで、相手の技量に感心し、潔く勝ち、潔く負けることを学ぶことで、人格が形成されると明確に教えられていた。20世紀半ばのスポーツは、ほぼ例外なくアマチュアの活動であった。スポーツで生計を立てている人も少なからずいたが、それは普通の中流階級の暮らしであった。ごく一部の人は、地元のクラブのプロとして給料をもらっていたが、ほとんどの人はプレーであからさまな給料をもらっていたわけではなく、スポーツ用品を製造・販売する会社の営業マン、あるいは管理職といったところであった。スポーツは誰にとってもビッグビジネスではなかったのだ。観客も地元が中心で、テレビもラジオもほとんど放送されていなかった。
私にとって、スポーツマンらしい振る舞いの典型は、長い間、当時幸運にも見ることができた、1946年12月のイギリス対オーストラリアのクリケット国際試合での出来事で説明されている。オーストラリアのドン・ブラッドマンは、誰もが認める史上最高のバッツマン(打者、ボールを打つ人)であり、相手野手からボールを遠ざけ、非常に速く得点を挙げることができる選手だった。その忘れられない試合の中で、彼のパートナーバッツマン(クリケットではフィールド上に常に2人のバッツマンがいる)はシド・バーンズでした。彼はオーストラリアで最も偉大なオープニングバッツマンの一人だが、非常に地味で得点力のないバッターでした。このパートナーシップは405ランという膨大な得点を記録し、この記録は2016年半ばの時点でまだ破られていない。ブラッドマンはもちろんバーンズよりずっと速く得点し、彼が個人的に234点を取ってアウトになると、バーンズは新しいパートナーで打席に立ち続けた。バーンズは、ブラッドマンに敬意を表し、記録簿に「バーンズ」と記載するのをやめ、最も簡単なキャッチをわざと近くにいたフィールドマンに飛ばしたのだ。応援していた観客はそれを理解し、彼がフィールドを去るとき、スタンディングオベーションで彼を称えた。
このような無私のスポーツマンシップに近いものは、今の大リーグの国際スポーツでは経験できないのではないだろうか。その代わりに、ニュース速報や議論の中心は、誰が違法薬物でドーピングをしているのか、そして、長い間、力強く否定していたのに、有罪が確定したのは誰なのかということだ。例えば、自転車競技のランス・アームストロング、野球のアレックス・ロドリゲスやその他大勢の選手などである。
- 5. クリケット自体にも問題がないわけではない。長い間、クリケットはスポーツマンシップの象徴的なスポーツでした。「それはクリケットではない」というのは、倫理的でないこと、高い理想に達していないことを意味し、クリケットから「フェアプレー」という一般的な概念が生まれた。であるから、「クリケットでスキャンダル?
- 6は、悲しいほど不自然に思えた。例えば、ブックメーカーに内部情報を提供したり、試合結果を操作しようとした疑惑は今のところ一件だけである。
- 7 それでも、これらの残念な出来事は、20世紀半ばのクリケットの状況とは異なる世界を反映している。例えば、イングランドは1960年代まで、ナショナルチームのキャプテンはプロではなくアマチュアであることを主張していた(当時、地元のクラブに雇われたクリケットのプロが高い報酬を得ていたわけではない)。
スポーツマンシップや一般的な誠実さの理想から逸脱しているのは、おそらくアメリカの大学間バスケットボールとフットボールにおいて最も悲しいことだろう。いわゆる「学生アスリート」は、学業成績や才能にほとんど関係なく採用される。体育局の顧問によって、成績が良く、スポーツ競技の資格を継続的に得られるようなコースが選ばれるのがごく一般的で、まともで後に役立つ教育を受けられるようにすることが目的ではない。例えば、あるバスケットボールのコーチが、選手のために試験の日程を変更したり、何らかの便宜を図ったりするよう頻繁に教員に依頼し、選手の家族の死亡を理由にした書式を使って、選手の名前だけを記入しなければならなかったことを私は実際に経験し、大学バスケットボール選手の親族の死亡リスクが高いことに好奇心を抱いた (Martin 1988/2012: 158)。
トップレベルで競争している大学のほとんどがスポーツ活動で損失を出しているが、スポーツ以外の収入や資金から一部の職員、例えばスポーツ選手専用のアカデミックアドバイザーやチューターの給与を支払うなど、様々な方法でそれを難解にし、スポーツ支援専用の資金を絶え間なく要求している。ある陸上競技部の管理者は、アウェーゲームにバンドを派遣する費用は、音楽学部や芸術科学部ではなく、自分の部署が負担すべきだと私が提案すると、怒りをあらわにした。
インカレスポーツの腐敗については、多くの出版物が記録している (Sperber 1990, 1998, 2001; Clotfelter 2011など)。
インカレという大規模なスポーツの軍拡競争に関する、魅力的で洞察に満ちた論考である。クロットフェルターは、大規模な大学におけるこのパラレルワールドが、教授陣や管理職の統制とは本質的に無関係に存在し、代わりに強力な自己増殖的「ブースター」グループによって作り出されていることを明らかにしている。これらの運営を支える税金補助の役割について説得力のある斬新な実証は、すべての読者の血圧を上昇させるはずだ。
- 8. 半世紀前には見られなかった方法で、大学とその管理者、そして全米大学体育協会は、インカレバスケットボールとフットボールの現実について、露骨な不誠実さ、偽善、そして誤魔化そうとすることによって、学問の理想に泥を塗ってきた。2016年の全米大学バスケットボール選手権では、上位4校のうち2校がごく最近不祥事を起こしていたことを指摘する識者もいた。ノースカロライナ州は選手のために偽の授業を行い、シラキュースでは監督が自分のプログラムをモニタリングしなかったとして9試合の出場停止処分を受けたが、これは否定性を保とうとしたものと推測される。
- 9. ブリッジはスポーツか?
カードゲーム(あるいはドミノやチェス)は身体的なスポーツと類似している。つまり、それらも楽しむため、技術を披露するために行われる(あるいはかつて行われた)のである。
ブリッジというカードゲームは、さらに古いゲームであるホイストを発展させたもので、現在の形に近い形で1世紀以上前から行われている。現代の競技用ブリッジであるコントラクトブリッジは1920年代に生まれ、1930年代には特にアメリカやイギリスで高い人気を博した。1950年以降、国際大会が開催されている。
- 10 現代のブリッジは、二人組のデュプリケート・ブリッジや4人組のチームでプレイされるが、すべての競技者が同じカードの組み合わせでプレイすることを保証する手順があるため、偶然ではなくスキルのゲームである。したがって、身体的なスポーツと同様に、プレイヤーは他のプレイヤーよりも高いスキルを発揮することで満足し、観客は専門家のスキル発揮を評価することで興味を抱くのである。特定のゲームの分析、あるいは指導のためのカード分布のサンプルの分析が公表されることで、専門家の技を万人に示すことができるようになった。
1930年代から、テレンス・リースは世界的なブリッジチャンピオンであり、ブリッジに関する高い評価を得ている多くの本の著者であり、一時期はイギリスのブリッジ雑誌の編集者であった。1965年にブエノスアイレスで開催された世界選手権で、彼と彼のパートナーが不正行為で告発されたことは、一面を飾るニュースであった。
この告発は、一般のブリッジプレーヤーや愛好家にとっては、アームストロングのドーピングが判明したときの自転車愛好家や、「ア・ルー」らが同じようにルールを破った野球ファンのような感覚だっただろう。一流の専門家は、不正をして勝つことでどのような満足感を得ることができるのだろうか。
ブエノスアイレス事件についての著書の中で、アラン・トラスコット(1969: 264-6)が可能性のある答えを提示している。リース(1967)は、それ以前に、不正の容疑を否定する自著を著していた。正確な真実がどうであれ、十分に多くのオブザーバーが不正行為があった、あるいはあったかもしれないと考え、不正行為を防止するために、例えば、音声ではなく「ビディングボックス」から引いたカードに入札を表示したり、パートナーが互いに見えないようにスクリーンを使用するなどの新しいプロトコルが導入された。
ここで重要なのは、ブリッジもスポーツと同様、アマチュアのスポーツであり、暗黙のうちに名誉ある行動が期待されていたものが、20世紀後半になると、トッププレイヤーが多額の報酬を得られることもあって、不名誉な行為で汚されるようになったということであろう。2015年にも、ブリッジの有力選手数名が、スクリーンやビディングボックスを破る巧妙な方法を考案し、不正行為で有罪になった。
- 11. 治すための薬から儲けるための薬へ
20世紀前半、シンクレア・ルイスの小説『アロースミス』(1925)は、医師や医学者が抱く、あるいは目指す理想、すなわち善を行うための無私の献身を象徴するものとして広く知られた。1980年代から1990年代にかけて、私の大学の理学部の同世代の同僚たちは、この本を大学院生の必読書とすることで、その理想を実現し続けようとしていた。
しかし、今日の医学研究、特に医療用医薬品をめぐる現実は、製造コストに見合わない薬価の5倍以上の値上げなど、欲の皮が突っ張ったもので、これとは対照的である。
生命を絶ちたいと願う患者を助けるために医師が最もよく処方する薬[セコナール]を製造している変異株・ファーマスーティカルズ社は、昨年、カリフォルニア州議会がこの行為の合法化を提案してから1カ月後に薬価を2倍にした。…..。
製薬会社の多くは、このような値上げを研究費の高騰を理由に正当化する。しかし、セコナールはそうではない。80年の歴史がある。「セコナールの値上げの理由として最も考えられるのは、ジェネリック医薬品の不足だ」と、製薬会社に薬価と販売方法をアドバイスするMedical Marketing Economics社の創立パートナー、ミック・コラッサ氏は言う。
セコナルは1990年代初頭に特許が切れた。しばらくは後発品もあったが、その後需要が減少し、メーカーは後発品を見捨てた。「つまり、現在の会社が購入したときには、ジェネリック医薬品の競争相手がいなかったということだ。”だから、そのような状況では、ある会社がそれを買収して価格を上げることができる。」
- 12. 変異株は、チューリング社のマーティン・シュレクリに負けじと、エイズ患者に使われる薬の権利を買い、1錠13.50ドルから750ドルへと50倍もの値上げをした。
- 13 この原稿を書いている間にも、マイラン・ラボ社は、アレルギー反応の緊急時に使用するために、多くの子供も含めて携帯しているエピペンの価格を毎年大きく値上げして、世間の非難を浴びている。
- 14. 製薬会社による非倫理的な行動や違法な行動は、ここ数十年の間、ごく普通のことであった。製薬会社は、食品医薬品局 (FDA)が承認していない用途の薬を宣伝することを禁じられているが、医師は承認された薬を承認された用途以外のどんな目的にも自由に処方することができ、製薬会社は違法に医師にそうするよう促す方法を見つけ出しているのだ。このような犯罪行為から得られる利益は、そのような犯罪行為で有罪となった企業が定期的に支払わなければならない罰金を上回るほど大きいことは明らかである。「1991年から2015年まで、連邦政府および州政府と製薬会社の間で合計373件の和解が成立し、357億ドルが支払われた」 (Almashat er al 2016)。明らかに、犯罪行為による利益はその後の罰金よりもはるかに大きいので、法律を破って罰金を支払うことが製薬業界の標準的なビジネス慣習になっている(さらに言えば、法律違反のすべてが発見されることはないだろう)。
また、このような危険な「副作用」を持つ処方薬を消費者に向けて執拗に宣伝し、同時に法律事務所がその薬による害を理由に集団訴訟に顧客を登録することもある。2016年に米国でテレビで行われた広告の例としては、抗凝固薬プラダキサ(ベーリンガー・インゲルハイム社)やザレルト(ヤンセン製薬[ジョンソン&ジョンソン])糖尿病薬インボカナ(田辺三菱製薬からのライセンス品、ヤンセン製薬)等がある。
1997年以前は、処方箋薬を潜在的な消費者に直接宣伝することは、米国では違法であり、世界ではニュージーランドでのみ許可されていた。当時、製薬会社のCEOは通常、医学や科学のバックグラウンドを持っていたが、現在では経営学やマーケティング、セールスなどのバックグラウンドを持っていることが多くなっている (Greene 2007)。医療界の一部では、この行為を再び禁止するよう求めている。
- 15 それは、「…があなたにとって正しいかどうかを医師に尋ねる」ように患者を奨励することによって、医師に圧力をかけるのに役立ち、広告自体は意図的に誤解を招く、例えば、薬を服用する人々の代表とされるように幸せで健康な人々を描くことによって、危険な³”副作用³」は、バックグラウンドで晴れたトーンで暗唱している。例えば、エイズ治療薬は、食品医薬品局が抗議したほど誤解を招くような宣伝が行われている (Kallen er al 2007)。
HIV抗レトロウイルス薬のための消費者への直接広告。これらの広告の特定の省略は、技術的には現在のFDAの規制に違反していないが、彼らはそれらの規制の意図に違反している。…..。現在の広告は、生命を脅かすような副作用を強調することができない。
ここ数十年の間に、製薬会社の醜い行動や現代医療におけるその他の欠陥を詳述した、よくまとまった本 (Bauer n.d.)が大量に登場している。著名な医師や医学者 (Healy 2012, Gøtzsche 2013)は、製薬業界をタバコ会社と比較し、顧客に害を与えることを知りながら、それを行っているとさえ述べている。
政治的正しさ
主流派のコンセンサスによる科学における少数意見の弾圧と最も直接的な類似点は、多様性、包括性、非差別といった、疑いなく望ましいとされる特定の価値観に反する意見を社会全体で弾圧しようとする動きである。この現象はポリティカル・コレクトネスと呼ばれるようになり、ニュアンスや社会的現実性を考慮しないことが特徴となっている。ポリティカル・コレクトネスに関する文献は膨大である。学問の世界におけるポリティカル・コレクトネスに関する象徴的な著作にD’Souza (1991)がある。ある状況、例えば大学キャンパスでは、ポリティカル・コレクトネスは、二枚舌、偽善、思想統制の試みというオーウェル的な割合に達しており、オバマ大統領は2016年の卒業式講演でポリティカル・コレクトネスに対する強い主張を行ったほどである (Rieder 2016)。
社会が変化したように科学も大きく変化した
ここで言いたいのは、スポーツや製薬業界、あるいは一般的にポリティカル・コレクトネスで起こったことを強調したり嘆いたりすることではなく、20世紀半ば頃から社会のいくつかの分野で信頼性や理想主義が顕著に低下し、教条主義や権威主義が増加していることを説明することだ。したがって、科学活動において同様の傾向が見られることは、大きな驚きではない。
スポーツや薬物の例から、金や利益が腐敗の原因であることは明らかであるように思えるが、もっと包括的な説明、すなわち利益相反があるのだ。このように、学術界やその他の場所での言論の自由が危険にさらされているのは、真実を理解するための自由な追求という理想と、政治的に正しいと思われたいという社会政治的な利益との間の利害対立のせいなのである。
あらゆる活動は何らかの主要な理由のために存在し、その主要な目的を果たすのに適した適切な規則や指針、伝統が時間をかけて生み出されていくる。外部の利害関係者が自分たちに有利になるように活動を利用しようとすれば、腐敗が生じる。プロスポーツが腐敗したのは、それがメディアや広告主の富の源泉となったため、スポーツそのものではなく、外部の利害関係者によって詳細が決定されるようになったからだ。テレビ中継はスポーツファンや視聴者の利益によってではなく、広告機会を最大化するために決定される。コメンテーターは、スポンサーの商品や他のテレビ番組の宣伝文句を挿入することを要求される。
インカレも同じように堕落している。学生アスリートが勉強したり、授業に出たり、試験を受けたりするために十分な時間が必要かもしれないことは、まったく考慮されていない。試合日程はテレビ放映のスケジュールによって決まり、カンファレンスの加盟は基本的にテレビ放映の機会によって決められる。これには、有利なポストシーズンのプレーオフゲームを追加できるような、サブカンファレンスまたはディビジョンを2つ持てるほど大きなカンファレンスにすることが含まれる。
いわゆる研究型大学も、最高の教育を提供し、可能な限り最高の研究を育成することを目指す代わりに、地位や名声を求めることを第一の目標とするようになり、腐敗が進んでいる。昔は、大学院生を育てる場としてふさわしいかどうかが研究課題を選ぶ一つの基準であり、大学は価値ある研究を支援するための資金を求めていた。今は、お金がすべてである。大学は、研究者に外部から研究資金を持ってくることを求めるが、一般的には、大学がインフラや管理部門の人員を拡充するために使える、相当な額のオーバーヘッド、つまり「間接費」を要求する。大学は、最高の研究がどこで生み出されているかよりも、研究にどれだけ費やしているかによってランク付けされる。
- 16 1980年代、私の大学では、工学部長が、同学部でのテニュアや昇進の基準として、通常、年間10万ドル程度の外部からの研究支援を持ってくること、そして正教授に昇進するにはその3倍程度の支援を持ってくることを挙げていた。
金と利益の追求は、考えられる利益相反や腐敗の原因のひとつに過ぎない。ソビエト連邦ではチェスは純粋な専門技術の訓練ではなく、国策の道具となった。利害の衝突はすべて、腐敗につながる。例えば、ナチス・ドイツやソビエト連邦では、イデオロギーや国家政策が科学を腐敗させた。原理主義的な宗教は、イスラムの一部の施設やアメリカの一部の州で、進化科学に関する教育を腐敗させ続けているのだ。
科学の本来の目的は、自然に対する信頼できる理解を得ることだ。本章で述べたように、今日の世界では、科学はあらゆるところでさまざまな利害関係によって腐敗し、社会的に重要な問題に関してその信頼性が疑われるようになっている。