コンテンツ
Routledge International Handbook of Ignorance Studies; Second Edition
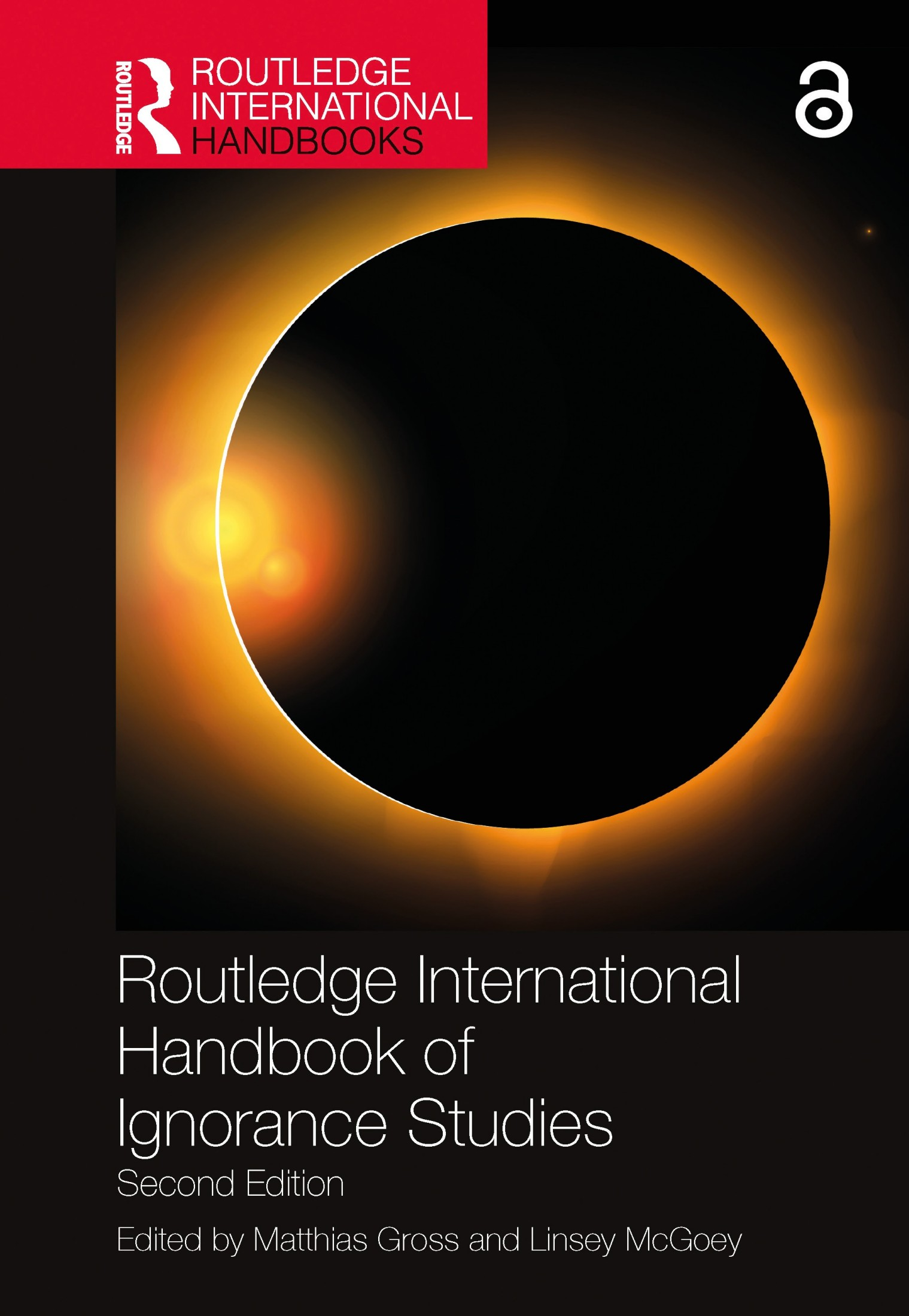
かつて無知は知識の欠如として扱われていたが、現在ではそれ自体が非常に影響力があり、急速に成長しているトピックとなっている。この分野の代表的なテキストの新版は全面的に改訂され、宗教、国内法と法学、セクシュアリティとジェンダー研究、記憶研究、国際関係、心理学、決定論、植民地史に関する章が新たに追加・増補されている。
無知に関する研究は、自然科学と社会科学の両分野で注目を集めており、幅広い分野の研究者が、「知らないこと」の分布と戦略的利用に関わる社会生活と政治的問題を探求している。本書は、経済学、社会学、歴史学、哲学、文化研究、人類学、フェミニスト研究、および関連分野からの貢献により、無知研究の学際的分野を反映し、社会・政治生活における無知の政治・法律・社会的利用についてのブレイクスルーガイドとして機能するものである。
本書は、現代の社会、文化、政治において無知が果たす重要な役割を理解しようとする人にとって、欠くことのできない一冊となるであろう。
マティアス・グロス:イエナ大学社会学研究所教授、ドイツ・ライプチヒのヘルムホルツ環境研究センター(UFZ)教授、都市・環境社会学部長。近著に、Oxford Handbook of Energy and Society (2018, ed. with Debra Davidson)、Green European (2017, ed. with Audrone Telesiene)がある。
Linsey McGoey 英国のエセックス大学社会学部教授、経済社会学・イノベーション研究センター(CRESI)所長。認識論、無知、政治経済、経済的公正について研究している。著書に『No Such Thing as a Free Gift』(2015)、『The Unknowers』など。How Strategic Ignorance Rules the World (2019)』がある。
ルーテージ
インターナショナル・ハンドブック・オブ・イグノランス・スタディーズ
第2版マティアス・グロス、リンゼイ・マクゴーイ編著
目次
- 図版のリスト
- 寄稿者ノート
- はじめに
- 1 革命的な認識論:無知学の約束と危険性
- 第一部 無知の哲学を作り直す
- 2 無知と調査
- 3 アポファティックな無知とその応用
- 4 グローバルな白い無知
- 5 無知と認識的不公正の関係について
- 無知第一主義的分析
- 6 無知の語用論(The pragmatics of ignorance)
- 7 ポパー、無知、そして可謬主義の空虚さ
- 8 文学的な無知
- 第2部 資源としての無知の生産:知識格差への生産的対処
- 9 ポスト真実の時代における禁断の知識
- 10 社会調査における無知と認識論の振り付け
- 11 無知の資源を共有する
- 12 モデルの不確実性に対する無知と、地球科学を例とした倫理と社会への影響
- 13 予期せぬことを期待する:実験音楽、あるいはサウンドデザインの無知
- 14 無知と脳:異なる種類の未知が存在するのか?
- 15 言語学と無知
- 第3部 科学、技術、医学における未知のものの価値と管理
- 16 アンドーン・サイエンスと社会運動:レビューと類型化
- 17 科学:良くも悪くも、知識とともに無知の源泉
- 18 ロスト・イン・スペース:無知の生産における場所・空間・規模
- 19 無知と産業:農薬とミツバチの死去
- 20 コロナのパンデミックに挑む:政治的意思決定における非知識の管理
- 21 私たちが知っているパンデミック:COVID-19ガバナンスにおける無知と非知識に関する政策学の観点
- 22 知る権利と生物医学的知識生産の力学:負け戦を戦っているのか?
- 第4部 権力、抑圧、そして無知のヒエラルキー
- 23 女子スポーツにおける交差的な無知
- 24 性的不公正と意志ある無知
- 25 儀式と宗教的無知に関する人類学的視点
- 26 パレスチナ・ナクバの埋葬をめぐって
- 27 民主主義と無知の実践
- 第5部 行動的無知と政治経済:新たなダイナミズムに向けて
- 28 無知をターゲットにして行動を変えるDeborah A. Prentice
- 29 合理的な無知
- 30 知識の抵抗
- 31 犯罪者の無知、環境被害と否認のプロセス
- 32 無知は力か?インテリジェンス、セキュリティ、国家機密
- 33 経済学における非知識への意思決定理論的アプローチ
- 34 組織的な無知
- あとがき
- 35 無知に関する研究:技術の現状
- 図版
- 34.1 組織的な無知の源泉とタイプ
- 35.1 「無知」と「不確実性」の対数パーセンテージのNgramプロット
- 表
- 16.1放置された科学、産業革新、社会運動の類型化
- 33.1 意思決定マトリックス
寄稿者
ポーラ・アラネンは、フィンランドのタンペレ大学教育学部の博士課程に在籍している。博士課程では、成人教育における意思決定と機会均等に関連するデータ、知識の定量化、政策手段に関する問題を中心に研究している。
ザラ・ベイン:英国ブリストル大学およびカーディフ大学にて哲学の博士課程に在籍中。彼女の論文は、政治哲学者チャールズ・W・ミルズの作品における無知の認識論について分析している。より一般的には、障害や慢性疾患、ホワイトネス、社会的不公正について執筆している。以前はグループブログPhDisabledで、現在は自身の会社Academic Audio Transcription Ltdで、障害者、慢性疾患、神経変性、精神疾患の学生や研究者に公平な報酬でアクセス可能な仕事を提供し、アカデミアにおける障害者のアクセスを改善する活動も行っている。
ブライアン・バルマーは、英国ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの科学技術研究学科で科学政策学の教授を務めている。歴史的、社会学的アプローチにより、ライフサイエンスにおける専門知識の役割を理解するための研究を行っている。特に、英国の生物兵器プログラムの歴史について広く発表している。著書に『英国と生物兵器』(原題:Britain and Biological Warfare: Expert Advice and Policy-Making, 1930-65)(2001)、Secrecy and Science: A Historical Sociology of Biological and Chemical Warfare (2012)がある。
アンドリュー・ベネット(Andrew Bennett) 英国ブリストル大学の英語教授。著書に『Ignorance: Ignorance: Literature and Agnoiology (2009)、Suicide Century: Literature and Suicide from James Joyce to David Foster Wallace (2017)がある。ニコラス・ロイルとの共著に『An Introduction to Literature, Criticism and Theory』(第5版、2016)、『This Thing Called Literature』などがある。Reading, Thinking, Writing (2015)がある。
Alena Bleicher ドイツのハルツ応用科学大学コミュニケーション学・社会科学科教授。環境社会学と科学技術研究の分野で、社会と地中の相互作用、および地熱ヒートポンプや探査技術など、地中から資源や廃棄物を採取できる新技術に焦点を当てた研究を行っている。意思決定における非知識の問題、慣習やルーチンの変化、技術開発における責任、地球倫理に関心を持つ。
Liana Chua 社会人類学者、英国ケンブリッジ大学のトゥンク・アブドゥル・ラーマン大学講師(マレー世界研究)。2003年からマレーシアのボルネオ島にあるビダユ族の農村コミュニティに滞在し、当初は宗教的改宗と民族文化政治について、後に開発、再定住、環境変容について研究してきた。現在は、特にボルネオ島とスマトラ島で展開されるオランウータン保護の社会的、政治的、感情的、美的次元を探求している。その他の研究テーマは、視覚・物質人類学、身体人類学、人類学的知識の実践と政治など。
Henk van Elst:ドイツ・ケルンのparcIT GmbHの定量分析者。それ以前は、ドイツ・カールスルーエのカールスホッホ国際大学で応用数学と科学研究法の教授を務めていた。
スチュアート・ファイアスタインは、米国コロンビア大学生物科学部の前学長で、彼の研究室では脊椎動物の嗅覚系を研究している。また、アルフレッド・P・スローン財団の「科学一般理解促進プログラム」のアドバイザーを務めるなど、一般の人々への科学普及に尽力している。米国科学振興協会フェロー、アルフレッド・スローンフェロー、グッゲンハイムフェロー。著書に『Ignorance: How it Drives Science」(2012)、「Failure: Why Science is So Successful (2015)がある。
ウィリアム・フランキー(William Franke) 米国ヴァンダービルト大学比較文学教授。アレクサンダー・フォン・フンボルト財団の研究員であり、オーストリアのザルツブルク大学で異文化間神学のフルブライト特別講義を担当したこともある。彼のアポファティクスの哲学は、On What Cannot Be Said (2007)とA Philosophy of the Unsayable (2014) で明確にされている。また、『On the Universality of What is Not: The Apophatic Turn in Critical Thinking』(2020)では、アイデンティティ政治から認知科学まで、教育や社会における現在の論争に取り組むために応用されている。
スコット・フリッケルは、米国ブラウン大学の社会学および環境・社会学の教授である。著書に『Chemical Consequences: Chemical Consequences: Environmental Mutagens and the Rise of Genetic Toxicology (2004)、共著にSites Unseen: Uncovering Hidden Hazards in American Cities (2018)、Residues: Thinking through Chemical Environments」(2022)。現在、アルゼンチンとアメリカにおける有害な土地利用、規制科学、不平等と健康の関係について研究している。
シュテルナ・フリードマンは、米国カリフォルニア大学バークレー校政治学部の博士課程に在籍している。政治学雑誌『Critical Review』の編集長も務める。
Erinn Gilson:米国マサチューセッツ州ノース・アンドーバーにあるメリマック・カレッジの哲学准教授。食と農、人種、性とジェンダーに関する倫理的・社会的正義の問題について教育・研究を行っている。また、脆弱性の政治的・倫理的意義も研究の中心となっている。著書に『The Ethics of Vulnerability: a feminist analysis of social life and practice』(2014)、サラ・ケネハンとの共編著に『Food, Environment, and Climate Change: Justice at the Intersections』(2018)。
Mathias Girelは哲学者であり、フランスのEcole normale supérieure-Paris Sciences Lettresの上級講師、Centre d’Archives en philosophie, histoire et édition des sciences (CAイングランド公衆衛生サービスS, CNRS-ENS)の所長である。無知、疑い、専門知識に関する著書がある。著書に『Science et Territoires de l’ignorance (2017)』、『L’Esprit en acte (2021)』がある。また、ロバート・プロクター著『ゴールデン・ホロコースト、タバコのカタストロフィの起源と廃絶のケース』(2014)のフランス語版の編集者、ドキュメンタリー映画『Manufacturing Ignorance』(2021)の共同脚本家でもある。
Matthias Gross イエナ大学社会学研究所教授、ドイツ・ライプツィヒのヘルムホルツ環境研究センター(UFZ)都市・環境社会学部長。近著に『Oxford Handbook of Energy and Society』(2018年、Debra Davidsonとの共編)、『Green European』(2017年、Audrone Telesieneとの共編)などがある。
イェンス・ハースは刑事訴追法を専門とする弁護士として訓練を受け、代理権と無知について研究している。犯罪の理由や原因、人生を変えるような行為の本質に関心がある。最近、Katja Maria Vogtと規範的認識論と価値論の共同執筆を始めた。
オーストリア国際問題研究所(OIIP)上級研究員、ウィーン大学社会科学部講師(オーストリア)。科学技術研究と重要政策研究の交差点で、イノベーションのグローバル・ポリティクスを探求し理論化している。グローバルヘルス、(バイオ)メディシン、医薬品の政治と政治経済を実証的に研究しており、現在は世界的な抗生物質イノベーションの危機に焦点をあてている。
デビッド・J・ヘスは、米国ヴァンダービルト大学の社会学教授であり、サステナビリティ研究のジェームズ・ソーントン・ファント・チェアーである。科学技術研究、エネルギー、技術、健康、専門知識、環境に関する社会科学および政策研究において多様な貢献をしている。社会運動、知識、技術革新の分析が主な研究対象。詳細はウェブサイト(www.dav idjhess.net)で見ることができる。
Nina Janich:ドイツ、ダルムシュタット工科大学応用言語学教授。研究テーマは、科学コミュニケーション、環境言語学、言語批評、言語と文化、言語の政治・政策、ビジネスコミュニケーション、広告の言語などで、テキスト言語学と談話分析に基づく方法論で研究している。現在、科学、政治、メディア、社会間のコミュニケーションや、さまざまなエコロジー言説の分析に焦点を当てたいくつかのプロジェクトの主任研究員。
Joanna Kempner:米国ラトガース大学社会学部准教授。医学、科学、政治、ジェンダー、身体の交わりを研究している。著書『Not Tonight: Migraine and the Politics of Gender and Health」(2014)は、ジェンダー・バイアスによって女性の健康問題がいかに必要な資源を得られないかを明らかにしたものである。近刊の『Psychedelic Outlaws』では、サイケデリック治療の開発に協力する患者たちの地下研究ネットワークが、サイケデリック医療への新たな主流派の関心を支える真の革新者とリスクテイカーであることを説明している。
アビー・キンチー:米国レンセラー工科大学教授(科学技術研究)。参加型研究手法など、環境科学の政治性を中心に研究している。土壌中の重金属とその健康へのリスクに関する知識の生産と無知について研究している。著書に『Seeds, Science, and Struggle: The Global Politics of Transgenic Crops (2012)、共著にScience by the People(民衆による科学)。Participation, Power, and the Politics of Environmental Knowledge (2019)の共著者。
ダニエル・リー・クラインマンは、米国ボストン大学の大学院担当アソシエイト・プロボーストおよび社会学教授である。科学社会学者で、著書に『Impure Cultures: Impure Cultures: University Biology and the World of Commerce (2003)、共著にVanishing Bees: Science, Politics, and Honeybee Health (2016)の共著者。
ミカエル・クリントマンは、スウェーデンのルンド大学社会学部の研究部長兼副学部長。環境、健康、社会福祉の分野における知識紛争に焦点を当て、進化生物学や心理学からの洞察を統合しながら、社会学を教えている。現在の研究は、予防接種、新食品、エネルギー、持続可能な消費、気候科学コミュニティ内の紛争に関する論争において、知識の抵抗と行為者や組織がどのように認識論的主張を再構成するかに焦点を当てている。
政治学者。フィンランドのタンペレ大学社会科学部シニアリサーチフェロー。研究テーマは、外国の政治的意思決定に影響を与えるイメージと信念、および情報社会の政治経済である。現在の研究テーマは、組織の無知と硬直化に寄与する認識論的傲慢さである。
Janet A. Kourany:米国ノートルダム大学哲学科教授、ジェンダー研究科兼任教授、Reilly Center for Science, Technology, and Values(科学、技術、価値観に関するライリー・センター)フェロー。最新作は『科学と無知の生産』(原題:Science and the Production of Ignorance)。When the Quest for Knowledge Is Thwarted (2020) は、科学が能動的、受動的に、意図的に、あるいは意図せずに無知を生み出す様々な方法を探求するものである。
Wulf Loh:ドイツ、テュービンゲン大学国際科学・人文科学倫理センター(IZEW)博士研究員。様々な技術開発プロジェクトのスーパーバイザー、「プラットフォーム学習システム」プロジェクトの調整委員会メンバー、AI倫理の運用と認証のための2つのイニシアチブの一員でもある。研究テーマは、応用倫理学、社会哲学、政治哲学、法哲学。
レフ・マーダーは、カナダのマクマスター大学、ウィルフリッドローリエ大学、トレント大学の臨時教員である。知識と政治、法と政治、国際関係論の講義を担当している。研究テーマは、法的、政治的、経済的な包摂と排除の境界の認識論的裏付けを理解することである。
リンゼイ・マクゴーイ 英国エセックス大学社会学部教授、経済社会学・イノベーション研究センター(CRESI)所長。認識論、無知、政治経済、経済的公正について研究している。著書に『No Such Thing as a Free Gift』(2015)、『The Unknowers』など。How Strategic Ignorance Rules the World (2019)がある。
マイク・マイケル(Mike Michael) 英国エクセター大学社会学・哲学・人類学部の教授。科学技術社会学者で、研究テーマは、日常生活とテクノサイエンスの関係、生物医学とバイオテクノロジーにおける文化の役割、デザインと社会科学的視点の相互作用に触れている。
チャールズ・W・ミルズ(1951-2021)は、社会・政治理論における先駆的な仕事、特に階級、ジェンダー、人種、人種的公正に焦点を当てた仕事で知られる哲学者である。ニューヨーク市立大学大学院の著名な哲学教授であった。主な著書に『Black Rights/White Wrongs: The Critique of Racial Liberalism (2017)、The Racial Contract (1997)があり、グスタフスマイヤーズ優秀図書賞を受賞している。
Hendrik Paascheは、ドイツ・ライプチヒのヘルムホルツ環境研究センター(UFZ)の研究分野データ統合とパラメータ推定における上級研究員、ドイツ・ポツダム大学の地球物理学の「Privatdozent」である。地球科学、インバースモデリング、実験デザイン、情報フュージョンに関心を持ち、研究している。
マドレーヌ・パプは社会学者で、スイスのローザンヌ大学の博士研究員であり、スポーツ科学研究所、ジェンダー研究センター、STS-Labに所属している。現在は、生物学的性差をめぐるフェミニストと科学者の議論、および性差に関する主張がスポーツと生物医学研究におけるジェンダー平等の追求をどのように形成しているかについて研究している。彼女は、オーストラリア代表として800m走で国際的に活躍したオリンピック選手でもある。
ヤアナ・パーヴィアイネン:哲学者、フィンランド、タンペレ大学社会科学部上級研究員。社会認識論、技術哲学、現象学について研究している。現在進行中の研究プロジェクトは「Struggling with Ignorance(無知との闘い)」Negative Expertise and the Erosion of the Finnish Information Society at the Turn of 2020」(2018-2022)は、制度当局と市民の間で激化する認識論的緊張に対応する必要性から動機づけられている。
カタリーナ・T.Paul オーストリアのウィーン大学政治学部の上級研究員。研究テーマは、比較政策分析、解釈的政策研究、医療政策、規制、医療、生政治、および科学技術研究である。
Deborah A. Prentice 米国プリンストン大学プロボスト・アレクサンダー・スチュワート1886教授(心理学・公共政策)。社会的規範、すなわち社会的行動を規定する不文律や慣習を研究している。多元的無知、心理的本質主義、ジェンダー・ステレオタイプ、行動変容など、社会心理学の幅広いトピックについて執筆している。
Helen Pushkarskaya 米国イェール大学医学部准研究員。健康な人々や臨床集団における不確実性(リスク、曖昧さ、対立、無知)のもとでの意思決定における個人差の神経生物学に焦点をあてている。最近のプロジェクトでは、強迫性障害や買いだめ障害における価値観に基づく意思決定の異常パターンと不確実性に対する嗜好について研究している。
ブライアン・ラパート:英国エクセター大学教授(科学・技術・公共政策)。特に武力紛争との関連において、情報の戦略的管理について長年研究している。著書に『戦争兵器の管理:政治、説得、非人道的行為の禁止』(2005)、『バイオテクノロジー、安全保障、限界の探求』(2007)などがある。最近では、著書『Experimental Secrets: International Security, Codes, and the Future of Research』(2009)、『How to Look Good in a War: Justifying and Challenging State Violence』(2012)、『Dis-eases of Secrecy』(Chandre Gould共著、2017)など、秘密に関する研究・執筆に伴う社会・倫理・政治問題への関心がある。
ジョアン・ロバーツは、芸術・文化マネジメントの教授であり、英国サウサンプトン大学ウィンチェスター芸術学校のウィンチェスター・ラグジュアリー・リサーチ・グループのディレクターを務めている。研究テーマは、創造性とイノベーション、ナレッジ・マネジメント、無知、ラグジュアリーなど。オックスフォード・ハンドブック・オブ・ラグジュアリー・ビジネス』(2022)、『The Third Realm of Luxury: Connecting Real Places and Imaginary Spaces』(2019)、『Critical Luxury Studies』の共同編集者である。Art, Design, Media (2016)がある。
ローズマリー・セイイは、社会人類学者、研究者、作家である。レバノンのアメリカン大学ベイルートとパレスチナのビルゼット大学女性学研究所の客員教授を務めた。著書に『Palestinians: From Peasants to Revolutionaries (1979)、Too Many Enemies: The Palestinian Experience in Lebanon (1994)のほか、多数の学術論文がある。
Anne Simmerling ドイツのダルムシュタット工科大学で科学助手を務める。2009年から2010年まで、ダルムシュタット工科大学主催の科学的コミュニケーションにおける不確実性の役割に関する学際的プロジェクトに従事。2010年から2016年にかけては、DFGが資金提供するプロジェクト「What can(‘t) we know? What should we do? How scientists and journalists deal with ignorance and uncertainty in popular science text’ within the Priority Program 1409 ‘Science and the General Public’(科学と一般市民:科学と一般市民における無知と不確実性の科学者とジャーナリストの対応)。「脆弱で矛盾した科学的証拠を理解する」彼女の研究テーマは、内外の科学的コミュニケーションの文体、メディア言語、特に科学的不確実性の言語表現にあった。
マイケル・スミソン:オーストラリア国立大学心理学研究科の名誉教授。主な研究テーマは、人々が未知なるものに対してどのように考え、対処するか、また、社会科学のための統計的手法の開発である。著書は9冊、180以上の査読付き雑誌記事と本の章を含む。
イリヤ・ソミン:米国ジョージ・メイソン大学法学部教授。研究テーマは、憲法、財産法、移住の権利、政治的無知、民衆の政治参加と立憲民主主義への影響に関する研究である。著書に『Free to Move: Foot Voting, Migration, and Political Freedom』(2020)、『Democracy and Political Ignorance』(同)がある。Why Smaller Government is Smarter (2016)、The Grasping Hand: Kelo v. City of New London and the Limits of Eminent Domain (2016)』がある。
ナイジェル・サウスは、英国エセックス大学社会学部教授、オーストラリア・クイーンズランド工科大学司法学部、英国サフォーク大学法・社会科学部客員教授である。これまでに、気候変動や環境犯罪に関連した否定と無知に関する論文を発表している。2013年に米国犯罪学会の批判的犯罪学と社会正義に関する部門から生涯功労賞を受賞し、2014年には社会科学アカデミーのフェローに選出された。
Sainath Suryanarayanan:米国ウィスコンシン大学マディソン校の科学技術研究センター(Robert F. and Jean E. Holtz Center for Science and Technology Studies)の副所長。科学、技術、社会について教えている。最新の研究では、ポストゲノム時代における社会の構成に関する理論やアプローチを発展させるための重要な基盤として、昆虫社会の生物行動学的研究を検証している。
エカテリーナ・スヴェトロワ:オランダのトゥエンテ大学准教授。彼女の学際的な研究は、金融、STS、経済社会学の交差点に位置する。また、ドイツのフランクフルトでポートフォリオ・マネージャーおよびファイナンシャル・アナリストとして実務経験を積んでいる。
Darren Thielは、イギリスのエセックス大学社会学部の上級講師である。彼の研究は、公共政策、刑事司法、経済社会学、不平等に重点を置いている。彼は多くの主要な雑誌に記事を書き、2つの単独著作のモノグラフを出版している。彼は、権力者の研究にますます関心を寄せている。
Katja Maria Vogt:米国コロンビア大学哲学科教授。専門は古代哲学、規範認識論、倫理学、行動論で、古代と現代の両方の議論に登場する問題に特に関心を寄せている。最近、イェンス・ハースと規範的認識論と価値論の共著を始めた。
ペーター・ヴェーリングドイツのゲーテ大学フランクフルト校社会学研究所講師。研究上の関心は、科学技術研究(STS)、知識と無知の社会学、バイオパワーの社会学、生体医学と生命倫理、環境社会学、批判的社会理論である。近著に『なぜ科学は知らないのか?A Brief History of (the Notion of) Scientific Ignorance in the Twentieth and Early Twenty-First Centuries” (知識史学会誌)がある。
Tobias Weigelは、気候研究のためのコンピューティングとデータサービスを提供するドイツ気候コンピューティングセンター(DKRZ)に勤務している。DKRZでは、ヘルムホルツAIコンサルタントチームを率い、地球と環境をテーマとした機械学習の分野で、データサイエンスとソフトウェアエンジニアリングのサービスを提供している。以前は、European Open Science Cloudなどの分野別・国際的なデータ基盤におけるFAIR研究データ管理、データ分析サービス、データ証明の分野で10年間勤務。CODATA Data Science Journalの編集委員、RDAの複数のワーキンググループの議長、Research Data Alliance Technical Advisory Boardの委員を務めている。
Basile Zimmermann スイス、ジュネーブ大学孔子学院の上級講師兼ディレクター。人類学者であり、技術社会学者でもある。著書に『Waves and Forms: Waves and Forms: Electronic Music Devices and Computer Encodings in China (2015), and Popular Humanities or the Culture of Things (in French, forthcoming)がある。現在の研究プロジェクトは、中国と中東におけるイノベーションの人類学に重点を置いている。
序論 革命的エピステモロジー
無知学の約束と危うさ
マティアス・グロス、リンゼイ・マクゴーイ
はじめに私たちがこのハンドブックの第1版で「無知学」という言葉を作って以来、この学際的な分野は予想以上に成長してきた。この7年間に社会と生態系の変化が加速し、未知のものの重要性がさらに可視化されたことも一因である。
無知研究への関心は高まっている。たとえ多くの人々が、当然のことながら政治的な変動に不安を覚え、より多くの関心を抱かざるを得ないような政治的な変化に対して神経質になり、恐怖心さえ抱いているとしてもだ。このハンドブックの各章の政治的関連性が高まったのには、いくつかの理由がある。一つは、地球規模の気候変動、ポピュリストの権威主義、COVID-19のパンデミックが世界中の人々の生活や国を荒廃させるスピードなど、憂慮すべきトレンドがあるからだ。これらの出来事には共通点がある。それは、学者たちが私たちの知識の限界に直面し、重大で実存的な課題をどのように再理論化し対応するかという課題に取り組まざるを得ないということである。
政治的・社会的課題に関する既存の理論の限界を認識することの価値こそが、無知学の約束するところである。この用語は、未知や不確実性、知識のギャップ(良い意味でも悪い意味でも)を扱う多様な研究を可能にする、広範で蔑称ではない表現として意図的に選ばれた。狭い学問的観点からの一方的な分析を避け、学者たちに学問のサイロ化がいかに無知を増幅させるかを検証するよう促すためである。このように、知識が権力や行動の源泉となりうるのと同様に、無知は可能性の源泉となり、新たなタイプの啓蒙を促進することができるのである。無知研究の重要な洞察の1つは、無知を認識論的な欠陥として悪者にすべきではない、ということである。むしろ、無知の有用性を理解している人は、さまざまなタイプの交渉や権力の仲介において、より良い立場に立てることが多く、より大きな社会にとって良い結果も悪い結果ももたらす。
無知の利点と危険性の両方を強調することが、このハンドブックの第一版の主な目的であった。知らないことの良い面は、例えば、日常生活における実験という概念で説明することができる。実験は、予期せぬ出来事を発生させることを明確な目的として設定することができる(ラインベルガー1997参照)。この設定から得られる驚くべき効果は、新しい知識の生産の原動力とみなすことができる。とりわけ、驚きは、実験者がこれまで認識していなかった無知(未知の未知または忘れられた未知)を認識することを助けるからだ。
また、政治的な意味でも、不公正な経済社会や政治社会を改革・革命する際に、どの社会でも支配層が疎外された集団の生活や権力について知らないことを指摘することは、解放のための無知の源泉となりうる(McGoey 2019)。公正さ、さらには解放の一種としての無知という肯定的な考え方は、少なくとも15世紀以降、ローマの正義の女神ジャスティティアが目隠しをした姿で描かれるなど、法的な場面でも目にすることができる。法廷では、Robert Proctor and Londa Schiebinger (2008: 24)が書いているように、「知識はバイアスに、無知はバランスに、興味深く結びついている」のである。しかし、実際には、盲目の正義の原則は、何かとらえどころのない、幻想的な目標である。たとえばアメリカでは、I. Bennett Capersが書いているように、「色が決定的に重要な人種社会で、ジャスティティアが盲目であることは、含意的にも否定的にも何を意味するのか」(Capers 2006: 4)。

言い換えれば、ケイパースが示唆するように、正義は盲目であるという信念は、法的判断が実際には極めて主観的で差別的であるという点についての認識をどの程度妨げているのだろうか。法的判断や医療的判断をする際に、個人は偏見を保留することができるという信念や、知識は必然的に人の合理性を高めるという信念は、知識をより普遍的にアクセス可能にすることで偏見を抑制することができ、またそうすべきだという仮定によって特徴づけられる啓蒙時代の遺物である。しかし、第1回で問うたように、人々が知ろうとしない場合はどうだろうか。その結果、一部の人々はさらに脆弱になり、偏見なしに機能すると称する法制度による搾取や不当な処罰のリスクにさらされることになるのだろうか。
2015年版から引用したこれらの問いは、米国や世界における警察の横暴に対して人々が立ち上がった「ブラックリブズマター」運動から、米国や英国などの富裕国で有色人種が不当に多くウイルスに感染し死亡しているCOVID-19の大流行に至る、過去7年間の多くの出来事に照らして、先見の明があると思われる(Evelyn 2020; Geddes 2021; Mills 2020)。この10年間で、ポスト工業化時代の明確な「勝者」であった人々の目からジャスティシアの目隠しがはがれ、一部の学者(cf. Pinker 2018)が賞賛する「繁栄の共有」の幻影が実際には共有されていないことを認めざるを得なくなったと言えるだろう。
これは、無知学が直面する難問である。私たちは自ら救命いかだの上にいる。おそらく、以前の学者たちが「歴史の終わり」について安易に主張したときにしがみついた「確かな」知識の岸辺から、これまで以上に遠く離れている。しかし、誤った政治理論からくる飽き飽きした決まり文句を吐き出したり、資本主義対社会主義、民主主義対権威主義、科学対陰謀論といったあまりにもナイーブな二項対立を否定しても、公式民主主義国における権威主義の台頭や、今日の資本主義経済を特徴づける「金持ちのための社会主義」の蔓延を理解できる、説得力があって十分に本格化した理論はまだ持っていないのである。過去の疲弊した二項対立を超えることのできる新しい語彙と分野横断的な協力の必要性は切実である。このハンドブックに掲載された論文は、そのための重要な一歩を踏み出すものである。私たちが共有する学際的な領域は、無知の「規則性」-社会的・経済的変化に関するこれまでの学術的理論における無知も含む-を真剣に受け止める新しい社会科学への道を開いている(Best 2021; Gross 2010; McGoey 2019; Smithson 1989; Afterword, this volume)。
ハンドブックの第1版では、無知の逸脱した性質ではなく、「規則的」な性質を受け入れることの重要性を強調した。私たちは、無知は一般的な意思決定や社会的相互作用、日常的なコミュニケーションにおける規則的な特徴として理解され、理論化される必要があると主張した。社会生活の多くの領域で、個人はしばしば(時には)明確に定義された無知にもかかわらず、あるいは最近になって非知識と呼ばれるもの、つまり自分自身の無知の詳細について知識を得る可能性があるにもかかわらず、行動する必要がある(Gross 2010)。また、無知を権力者にとってのみ有用で有益なものとみなすべきでないことも指摘する。むしろ、無知を利用することは解放的な行為であり、抑圧的で卑屈な知識の開示要求、たとえば、性的指向を開示せよという要求を回避することができる(Sedgwick 1990)。また、無知を装うことは、負担の大きい労働者が職場で自律性と創造性のためのスペースを確保するために不可欠な擬装の道具となりうる(Scott 1985)。
「規則性」を強調したのは、無知に関するフェミニストやポストコロニアルの理論家たちによる初期の研究成果であり、彼らの分析は、私たちが強調したい無知の状況的かつ「規則的」な性格を最もよく例証している。Linda Alcoffは、Shannon SullivanとNancy Tuanaの共編著『Race and Epistemologies of Ignorance』(2007)において、この初期の研究について有益な分析を行っている。この編著は、無知研究の分野を形成する上で不可欠な役割を果たした(Townley 2011も参照)。ロレイン・コード、サンドラ・ハーディング、チャールズ・ミルズの仕事を土台に、アルコフは、無知は、私たちが知識人として置かれているという「一般的事実」の必然的帰結であると指摘している。アルコフの言う「知る者の非可溶性」、つまり私たち個人の知覚の枠組みの境界性を考えると、私たちの仮定は、私たちが語るところの認識論的地理についての理解の中に位置づけられる必要がある。アルコフとコードは、ハーディングと同様、私たちの知識と無知の位置づけられた性質を認めることが、必然的に真実の相対主義的存在論を持たなければならないことを意味するとは考えていない。むしろ、話し手の位置を考慮することで、つまり、知っている者としての限界を認めて熟慮することで、他者が自分の知識の主張の客観性を評価する能力を低下させるのではなく、むしろ向上させるのだ。コードの表現を借りれば、「客観性には主観性を考慮する必要がある」(Code, 1995: 44, quoted in Alcoff 2007: 41)のである。
無知性研究において重要な研究の流れは、フェミニスト研究者が最前線で解明している主観性と客観性の間の相互作用が中心となっている。私たちが知らないことを認めることは、必ずしも私たちの知識のもろさを露呈し、認識論的権威の主張を根底から覆すことになるのだろうか。あるいは、ハーディング、コード、アルコフが示唆するように、その限界と視点的性格を露呈させることで、私たちの知識をより強固なものにするのだろうか。それに関連して、なぜある集団は自分たちの知識を他の集団よりも客観的であると認識するように教えられるのだろうか。
この問題は、COVID-19の大流行によって、相互依存の強い社会における私的個人の権利と義務に関する長年の疑問が再燃したことを受けて、特に深刻になっている。新しいワクチンのエビデンスベースを信用することをためらう人々がいる一方で(例えば、Lehnerら2021)、他のグループ、たとえ既知のリスクよりも利益がはるかに大きいと主張する人々であっても、押し付けられたワクチンの義務付けに警戒心を示す理由を理解するためのより実証的研究が必要であるし、現在も進行中である。パンデミックは、好むと好まざるとにかかわらず、強制された「実験」(Gross 2021)である。今行われた、あるいは行われなかった意思決定の決定的な認識論的、政治的、実存的意味合いは、今後何年も分からないが、それでもその輪郭を把握するために新しい概念と理論を開発しなければならない。なぜか?なぜなら、私たちを人間たらしめるものをあえて知り、また知らずにいることこそが、私たちを人間たらしめるものだからだ。これこそが無知学の革命的な可能性である。無知学は、現在および未来の現実を把握するために、以前の理論の価値がいかに低いものだろうかを学者たちに認めさせる一方で、深い謙遜が必要であることを認識しても取り乱すことなく、また負けることなく、研究を続けさせるのである。
シモーヌ・ヴァイルは『ルーツの必要性』(1949)の中で、政治理論が個人の義務よりも個人の権利への関心を優先させ、個人が他者に負うべき義務についての研究を避けてきたことを指摘している。もちろん、義務は完全に無視されているわけではないが、今日、私たちがワクチンをめぐる権利と義務について議論するとき、彼女の洞察は先見の明があると同時に、不十分であるように思われるのである。例えば、保護する公的責任を認めず、私的義務について語ることは不可能である。権利も義務も、クリントマン(本書第30章)が「社会的合理性」と呼ぶものによって形作られている。つまり、異なる環境においてどの集団が忠誠と尊敬を払うべきかという社会的状況に基づく認識、その認識が、たとえ証拠が事実上確実であっても科学的証拠に対する深い不信につながることがある(Guilhot 2021; McGoey 2012も参照のこと)。例えば、低所得者層を不当に苦しめるパンデミックにおいて、同じグループが最もワクチン接種をためらうのは驚くべきことではない(Bunch 2021)。
COVID-19の死亡者数が多いグループは、ワクチンによる予防を強化することで健康面で最も得をするかもしれないが、過去に自分自身や家族、隣人を繰り返し裏切った政治当局を不信に思う社会的根拠も、最も論理的に持っているのである。ここで最も重要なのは誰の「義務」なのか?公権力を信頼する個人の義務か、それとも信頼に値する理由をもっと証明する政府当局の義務か?このような証明は、社会的、政治的な問題であり、単に認知的な問題ではない。認知の本質を再考することが無知学の目標である。私たちの分野では、理性の内なる包容を示唆するこの言葉自体が、知識と無知の社会的位置づけを誤解した誤った偶像だろうかもしれないことを強調することによって、「啓蒙」の意味と性質における革命以外のなにものでもないのである。
私たちの第1版は、無知の価値と重要性に関する研究を、これまでで最も幅広く分野横断的にまとめたブレイクスルーものであった。経済学者、哲学者、人類学者、文学理論家、社会学者、生物学者の研究を1冊のハンドブックにまとめたのはこれが初めてであった。この版では、この著作をもとに、以下のような重要な新展開がなされている。
第1部 無知の哲学を作り直す
無知とは何かという本質と定義をめぐる存在論的な議論から、無知に対する責任をめぐる問題、未知のものを診断するツールとしての文学やフィクションの有用性まで、第1部は無知の哲学に関する新しい洞察を提供する。
第1部のいくつかの章は、フリードマン、ハースとヴォーグ、ミルズなど、初版からの変更なしの再録であり、他の章は改訂・拡張され(ベネット、フランケ)、2つは新しい(ベイン、ジレル)。しかし、変更されていない章の配置を変更するだけでも、認識論的な含意がある。例えば、ウィリアム・フランケの章とチャールズ・ミルズの章を並べてみよう。フランケの分析は、現代における政治的変動の高まりを扱っている。彼は、世界が「攻撃的で排他的な形態の宗派主義やアイデンティティ主義的な政治に対してますます脆弱になっている」と指摘している。そして、「アポファティクスの転換」を意図的に受け入れることで、異なる陣営の中で「言えないこと」や「知りえないこと」の受容を促進し、確かな知識を求める誤った衝動を捨て、対立する視点やイデオロギーを調整する上で「それでも有効であることを示す否定的様式による筆写不能な全体」の受容を支持することによって、宗派主義に対抗できると論じている。これは楽観的で力を与える姿勢であり、無知研究全体から得られる重要な洞察を裏付けるものである。
同時に、気候変動など、今日の人類存亡リスクの一部は明らかに大きくなっているが、その他の脅威は新しいものではなく、むしろ以前は脅威からより隔離されていた人々が新たに感じているものである。西側諸国のホワイト・マジョリティの豊かなメンバーにとっては、COVID-19と権威主義の台頭がもたらす不安定さが前例のない不安定さを引き起こしているかもしれないが、搾取されている集団にとっては、この不安定さは何も新しいものではない(Mills 2020, Chapter 4, this volume)。目新しいという仮定、すなわち2016年以降が唯一無二のポストトゥルース時代であるという仮定は、何世紀にもわたって主流の政治哲学のなかで客観的知識を装った知識の暴力的影響にほとんど直面させられなかったという特権から生まれた一種の認識論的偏向を示すものである。
ミルズとベインの章では、白人の無知やその他の形の認識論的不公正の歴史と社会的含意を探求している。つまり、差別、抑圧、認識論的不公正に関する研究を、哲学の主流派の構成要素に据えるのではなく、主流派政治思想の周縁部に追いやるということである。例えば、第一部では、ハースとヴォークトが異なるタイプの無知の性質について、またフリードマンがポパーについて取り上げているのに対し、ミルズの章は別のカテゴリーに分けられている。
社会科学、人文科学、物理科学は、「ジャンルクラフト」と呼ばれるものの意味するところにもっと注意を払う必要がある。ベネットの章では、フィクションと哲学の間の学問的境界と境界線が持つ認識論的含意を検証している。
ベインの章は、異なる分析の位置づけと分類が、意図しない、あるいは意図的な認識論的含意を持ちうる方法についての、鋭い、独創的な考察である。彼女の研究は、2021年9月に亡くなったチャールズ・ミルズのブレイクスルー研究を基礎とし、それを継承するものである。故郷の分析哲学の分野での絶大な名声に加えて、彼は時間をかけて他の分野の学者を支援し、学問の分界を超え、アカデミーをより反復的な空間として作り変えることを決意した。このハンドブックにおける彼の代表的な章「グローバルな白人の無知」は、オープンアクセスで入手可能である。無知研究におけるミルズの存在は、革命的であると同時に羊飼いのようなものであった。彼は人々を行動に駆り立てるとともに、優しさと希望をもって私たちの学問を育んでくれた。
異なるタイプの社会的・学問的分類に内在する力は、フリードマンとジレルの章でも特徴的である。両章とも、20世紀半ば以降に流行した科学哲学、とりわけポパーの仕事に対して、鋭い挑戦をしている。フリードマンは、偽証に関するポパーの著作があまりにも頻繁に「私たちの無知を自覚せよという空虚な命令に堕している」と論じている。この規定は、慰めになるかもしれないし、ほとんどの場合、認識論的に異論はないが、必ずしも科学の真理をより確かなものにするものではないという。ジレルの章は、デューイなどのプラグマティスト哲学がいかに無知研究を豊かにしうるか、また、無知の哲学が、例えば後者が「真実」と「陰謀」の間の役に立たない対立関係を再形成することを可能にすることによって、プラグマティスト哲学の重要性と顕著性をいかに再形成するか、反復的に重要な洞察を与えてくれる。
第Ⅱ部 資源としての無知の生産:知識のギャップに生産的に対処すること
学生に無知の重要性を教える努力は、社会科学や医学の分野で長く、時には拷問を受けた歴史を持っている。1990年代、アリゾナ大学の外科教授であるマーリス・ウィッテは、医学部1年生に「医学とその他の無知入門」を教えるための追加資金を何年もかけて探していた。ある慈善財団の理事は、ウィッテの助成金申請に対して、自分の組織が無知の探求に資金を提供するくらいなら辞職すると宣言した(Ridge 1997)。当時アリゾナ州を拠点としていた哲学者のアン・カーウィンの協力を得て、ウィッテは、さまざまな専門家がそれぞれの専門分野についていかに知らないかを強調するモジュールの必要性を同僚たちに納得させたのである。学生たちが「Ignorance 101」と名づけたこのモジュールは、何年にもわたって人気を博した。
知られていないことを登録し、観察することは、研究・教育の分野ではしばしば困難であり、政治的に不人気なことなのである。結局のところ、個人や観察された集団が知らないことを、研究者はどうやって知ることができるのだろうか。ジョアンナ・ケンプナーは、政治的・商業的な障壁が、科学者が政治的に敏感でない、あるいはタブーとされる研究テーマを調査することを制約する方法について論じ、この問題を取り上げている。マイク・マイケルの章でも同様の領域に触れているが、ケンプナーとは異なり、彼は政治的・商業的障壁よりも、暗黙の前提が研究者に、しばしば無意識のうちに、研究から得られると期待できる洞察に内部的な自己制限を課すことにつながる方法に焦点をあてている。彼は、より明確に「思索的な方法論」を開発することが、この問題を軽減するのに役立つと示唆している。Basile Zimmermannの寄稿は、このような投機的なスタンスが実際にどのような価値を持つかを明らかにするものである。中国における実験的なサウンドデザインの民族誌的観察をもとに、自身の無知に対する開放性がいかに新しい音楽的形態を生み出すかを解明している。
スチュアート・ファイアスタインの章では、20年以上前にアリゾナ大学でウィッテが始めた試練を取り上げる。無知を教えることを受け入れる必要がある、さもなければ、自分が実際よりもはるかに多くのことを知っていると信じるようになった学生の世代に、科学の進歩というバラ色で大衆的な観念を過度に与える危険性がある、と彼は規定する。私たちが実際よりも多くのことを知っていると考える理由の一部は、ますます独占的な報道産業の限界に起因している。Hendrik Paascheとその共同執筆者は、地球科学におけるモデリングを例に、この概念をさらに発展させ、科学者が結果を明確にするためなどの理由でモデルの不確実性を無視した場合、意思決定にいかに破壊的な影響を与えうるかを展開している(cf. Paasche et al.) マイケル・スミソンとヘレン・プシュカルスカヤは、神経科学の新たな発展が、脳が未知に対処する方法に関する私たちの知識をいかに進歩させるかについて探求している。神経言語学の進歩は、メディアにおける無知と非知識の言語的表現に関するNina JanichとAnne Simmerlingの分析でも取り上げられている。この論文は、意味論、テキスト言語学、談話分析など、非知識の言語的表現に対する以前のアプローチを再検討し、この分野が将来どのように拡大するかを考察している。
第3部 科学、技術、医学における未知のものの評価と管理
無知の否定的な側面に偏ると、知識のギャップや不確実性を強調することが何らかの形で「反科学」だろうかもしれないと暗示し、世界の別の見方を無視する傾向があるが、COVID-19パンデミックは、ある事象の発生確率が分かっている古典的リスク評価の前提が将来的に後回しの役割を果たすかもしれないということを示している(cf. Gross 2016)。むしろ、2020/21年のパンデミックに関しては、私たちは常に、その時点で受け入れられている知識よりも、知らないことの方が多いことを知っていることは明らかである。社会学的な観点からは、パンデミックにおける未知への対処に関わるプロセスは、多様なアクター(例えば、政党、ウイルス学者、経済プレーヤー、産業界)の偶発的活動を調整する方法として考えることができ、それは無知であることを認識しながらも継続されている(Gross 2021)。この無知の「調整」こそが、コロナウイルスとその先で世界が直面している最大の課題かもしれない。第3部の各章は、いずれにせよ、避けられない無知をいかにして資産に変えるか、少なくとも民主的な意思決定のための基礎とするかについての戦略を概説している。リスク評価で知識のギャップをごまかしたり、確実性の美辞麗句でごまかすのではなく、必要なのは非知識を記述する方法であり、例えば政策立案者が国民とコミュニケーションをとる際に、限られたデータや数値に基づくリスク評価に代わるものを提供できるようにすることである。
20世紀初頭、Georg Simmel(1906)はすでに、信頼が知識と非知識の間の橋渡しになり得ることを思い起こさせてくれた。COVID-19のパンデミックの場合のように、未知のものに対処する際の信頼は、選択によってではなく、必然的に現実のものとなったのである。ウイルス学者が自分たちの非知識を明らかにするとき、なぜ今より確実なことが不可能なのかを明確にする必要がある。つまり、無知を克服することが目的ではなく、知らないにもかかわらず意思決定ができる可能性を開拓することが目的なのだ。結局のところ、非知識が「良い科学」の一部となりうることを率直に認め、認めることで、科学とその組織に対する新たな信頼が育まれるかもしれない。このことは、ひいては非知識をオープンで民主的な議論の対象とすることにもつながるはずだ。
科学技術研究の研究者たちは、科学や医学における無知の存在とその利用がもたらす否定的な意味と肯定的な意味の両方を探求する文献の最前線に立ってきた。このセクションでは、豊富な文献をもとに、デイヴィッド・ヘスによる「放置された科学」という概念の探求から始まる。この新版では、ヘスは、社会運動、政策、業界団体を様々なレベルの認識論的対立に基づいて比較・分類する、彼の代表的な類型論をさらに発展させている。
また、科学が歴史的に男性の知識様式を優遇してきたために、科学的発見の成果の生産者であると同時に受領者でもある女性の役割が損なわれているという批判的分析(Janet Kourany)や、個人がある話題や現象に関する特定の種類の情報を生産または普及させ、他の適切な情報を普及させないという環境調査における選択的無知の戦略(Daniel Kleinman and Sainath Suryanarayanan)などが取り上げられている。さらに、スコット・フリッケルとアビー・キンチーの章では、なぜある種の証拠が知られるようになり、他の証拠は知られないままなのかを理解するために、物理的空間と規模の物質性を検討することの重要性が強調されている。同様に、COVID-19のパンデミック初期におけるフィンランドの政治的意思決定の事例を用いて、ヤアナ・パーヴィアイネンと共著者は、避けられない無知に対処するための経営戦略を、時にはうまく、時にはあまりうまくいかない形で、見事に再構築している。カタリーナ・ポールとクリスチャン・ハダドは、無知研究に政策学の視点を織り交ぜながら、パンデミックの影響に取り組んでいる。
遺伝学とバイオテクノロジーの領域における医学の進歩は、プライバシー権、自律性、体液と組織の所有権、遺伝情報と身体材料の将来の利用とリスクをめぐる新しい倫理的・政治的問題を提起している。ピーター・ウェーリングは、このような変化がもたらす倫理的・認識論的な意味合いについて、新たな視点を提供してくれている。全ゲノム配列決定や妊娠前のキャリアスクリーニングなどの新しい生物医学技術は、ある個人的特徴を知らないという個人の権利に大きな圧力をかけているが、新しい知識がたまたま利用可能になったからといって、それを受け入れなければならない事実上の理由はない。新しい技術科学の選択肢の到来に内包される認識論的決定論に抵抗することは可能である、とウェーリングは主張する。
第4部 部:権力、抑圧、無知のヒエラルキー
第1部、第2部、第3部における明示的・暗黙的なテーマは、無知と権力の関係である。このテーマは第4部で前面に押し出され、無知がヒエラルキーの醸成と定着に果たす役割、ある種の知識を他よりも信頼できないものとして疎外する役割、国家や市民が遠くの悲劇や近くの悲劇に対して自ら目隠しをすることを可能にする役割について、貢献者たちは探求している。また、無知を戦略的に利用することで、権力者による知識の主張のもろさを露呈させ、いかに解放をもたらすことができるかも探求している。
近年、支配的な集団が、より弱い立場の人々に対する過去と現在の残虐行為をどのように否定し、正当化し、あるいは単に無視しようとするかを理解するために、意志ある無知というレンズを用いる学者の数が増えている。例えば、カナダの先住民集団の服従と民族虐殺(サムソン2013)から、トルコがアルメニア人に対して行った数十年間の集団暴行(ギョセック2014)まで、ほんの二つの例を挙げている。この言葉は、ローズマリー・サイが寄稿したように、パレスチナ人が1947年から1949年にかけて、現在イスラエルが占領している地域から追放されたことを表現するために用いている言葉である。MillsとTrouillotによる研究を基にしたSayighの章は、検閲や他の形の脅迫に直面している学者から口頭や書面による証言を引き出すことの価値を説得的に示しており、タブーとされる知識がより大きな学術文献の中でいかに沈黙させられるかを示す証拠となるものである。特に、#metooの言説が、女性に対する性的暴力の蔓延を認めることをめぐる長年のタブーを露呈させたという点である。彼女は、性的被害の広範な性質に関して、政治運動が「多くの人がすでに知っていたこと」を照らし出すと同時に、虐待に直面している女性たちの証言をいまだに疑う一部の人々の抵抗につながったことについて、斬新かつ本質的な指摘を行っている。暴力を暴露することが、その暴力についての故意の無知を減らすのではなく、むしろ増やすことにつながるという方法が、彼女の分析の核心にある難問である。
マドレーヌ・ペイプの重要な章は、女性スポーツにおける法的判断の影響について考察している。ここでは、生まれつきテストステロンの高い女性が特定のスポーツ競技に出場することを禁じる世界陸上競技連盟が導入した規則を、裁判所が最近になって擁護している。南アフリカ共和国のオリンピック代表選手であるキャスター・セメンヤがこの規制を争ったところ、オリンピック委員会公認の国際機関であるスポーツ仲裁裁判所(CAS)は、この規制を容認する判決を下したのである。特に、彼女が言うように、「高いテストステロンを持つ女性を排除し、科学の観点だけで問題を定義することは、大多数の女性の利益になる」という問題のある仮定がそうである。ペイプは、何が「自然な」レベルのテストステロンを構成するかという科学的パラメータに根ざしていると称する司法判断の実行的性質を精査しているが、それはジェンダーやセックスのアイデンティティを取り巻く社会規範に注ぎ込まれている。裁判所は、性的差異に対する退行的な態度を支持する決定を正当化するために生物科学に従うが、一方で、そもそも科学的資金調達の根底には社会的・政治的要請があるという事実は無視される。
そこでは、神や神が自分たちの努力をどう受け止めるかについての決定的な知識がなくても、自分たちの行為が正しいという希望を保つために、信者たちが意図的な非知識の形式を採用しているのだ。知らないということは、逆説的ではあるが、ある種の肯定的なコミュニケーション戦略であり、しばしば沈黙する神々との交信の感覚を保持する。戦略的無知と既存の社会的・政治的秩序の維持・破壊の関係については、ジャック・ランシエールらの研究を基に、民主的統治の認識論的側面が軽視されているというレフ・マルダーの議論において、さらに検討されている。
第5部 行動的無知と政治経済:新たなダイナミズムに向けて
第五部では、第一線の心理学者、政治理論家、犯罪学者による章が並置されているが、これは、私たちが社会科学全体でより広く見たいと思うタイプの学問的ハイブリッド主義を予見させるものである。認知レベルにおける故意の無知の分析が、異なるレベルにおける故意の無知を合理的な決定とする社会的・政治的要因に関与しないことがあまりに多いのだ。過去30年間の心理学における重要な研究は、Deborah Prenticeの章で述べられているように、認知の「二元論的」理解につながり、ある程度この問題に対処してきた。彼女は、心理学者たちが、人間は情報を処理し、それに基づいて行動するための二重のシステムを持っていると主張していることを指摘している。直感的で「単純なヒューリスティクス」で動作するシステム1と、「ゆっくり、じっくり、努力する」システム2である。この2つのシステムの相互作用についての理解が深まったことで、個人が自分の行動の個人的、家族的、社会的リスクをもっと認識しているにもかかわらず、有害な行動を修正したりしなかったりする理由や方法について、これまでの心理学の理解にニュアンスを与えることができるようになってきている。
しかし、心理学の進歩でさえ、行動変化に関する一般的な「情報欠乏症」的理解を完全に見直すには至っていない。これは、より多くの事実を普及させれば、人々は利用可能な情報に基づいて特定の方法で行動するはずであり、そうなると仮定しているものだ。情報欠乏モデルの問題点は、さまざまな情報源に不信感を抱く社会的、政治的、歴史的な理由の重要性を過小評価しがちなことである。ミカエル・クリントマンの章では、彼が「知識抵抗」と呼ぶ、たとえそれが事実で適切な知識であっても、新しい知識を故意に避けるという問題を軽減するための貴重な新しいフレームワークと概念的アプローチが紹介されている。クリントマンは、リスク責任を私物化し、意思決定に影響を与える商業的、政府的、家族的要因の重要性を過小評価しがちな、ややナイーブで非政治的な行動変容の「ナッジ」理論に対し、意思決定の文脈的性質を強調する「社会合理性」の概念を構築している。
クリントマンとプレンティスの研究は、イリヤ・ソミンの章で述べられている「合理的無知」の政治理論にニュアンスを与えるものである。ソミンは、誤情報への感受性が党派的な現象であると推測するのは非論理的であり、政治スペクトルの全域で、左派も右派も誤情報を行っている、と指摘している。皮肉なことに、深く分裂したグループを結びつけるものは、「相手側」だけがプロパガンダを永続させ、それに騙される傾向があると主張することである。ライバルに対する共通の疑念は、普遍的な現実である。
しかし、誤情報を信じるという問題は党派を超えたものだが、誤情報を煽る能力はさまざまな社会的アクターに等しく分布しているわけではない。企業や国家のアクターは、異なる環境において何が真実とみなされるかの認識を形成するための法的権限と財源をより多く持っていることが多い(McGoey 2019)。この力によって、ある集団は他よりも効果的に無知を利用することができる。このことは、Darren ThielとNigel Southによる、環境犯罪を含むさまざまな種類の企業犯罪や国家犯罪の議論から明らかである。Brian BalmerとBrian Rappertの国家機密に関する章でも、さまざまな種類の戦争への関与など、国家の意思決定に対するより広い国民の態度を形成しうる、さまざまな形の証拠をベール化したり開示したりする力について検証している。彼らが言うように、軍事行動の害悪に関する証拠を収集し、定量化する努力は、「単に『そこにある』ものを列挙するのではなく、まず何をどのように数えるかを決定しなければならないからである」
組織内の意思決定にはさまざまな種類の無知が蔓延していることを認める必要があることは、Joanne Robertsの章でも述べられている。彼女は、無知を負債と蔑むのではなく、むしろ内部分裂を抱える大規模組織の避けられない特徴として認識すべきであると提案しているのだ。組織理論家のKarl Weickは、かつて、自らの機能についてより多くの知識を求める代わりに、組織は「何を無視するかによって定義される」かもしれない、と示唆した。組織学や制度社会学のなかで増えている文献はこの指摘を基礎としており、存在の証拠を消し去ることに根ざした権力の形態を追跡する際の証拠的・認識論的課題に取り組んでいる(Weick 1998: 74, Essén et al 2021; Hodson et al. 2013; Luhmann 1992も参照されたい)。
実際、先に述べたように、またマイケル・スミソンが説得力のある新しいあとがき(本書)で述べているように、ほとんどの学問領域において、無知に関する学問は「盛ん」である。彼は、「しばらく時間がかかった」と皮肉交じりに付け加えている。スミッソンは的確な、しかし心配になるような観察をしている。異なる学問分野が無知の研究に取り組めば取り組むほど、他の学問分野がすでに書いたことを無視しているように見えるのだ。例えば、社会学の文献の多くは、「不確実性」に関する心理学や行動経済学の文献にほとんど目もくれない。その逆は心理学と経済学に当てはまり、彼らは社会科学を軽視しているのである』。
私たちはこのサイロイズムを変えたいと願っている。パートVの各章とハンドブック全体は、無知に関する心理学的・社会学的研究の間の新しいダイナミズムへの道を示している。このダイナミズムの目標は、知識の獲得や回避の認知的側面を探求する際に、政治経済や、異なるグローバル社会における物質的資源の階層的配分を前景化することであるはずだ。このことは、現実の政治経済の研究がいまだ欠如している(Arnsperger and Varoufakis 2005)主流派の経済学におけるさまざまな欠落を克服するのに役立つだろう。また、それぞれ異なる方法で未知のものを探求したケインズ、シャックル、ハイエクの最盛期以来、不確実性と無知への関心が70年に渡って低下している(Svetlova and van Elst, Chapter 33, this volume)。今日、より多くの経済学者が不確実性の研究、そして無自覚、曖昧さ、無知、非知識といった多くの用語のいとなみに取り組んでいることから、この衰退は変わりつつあるのかもしれない(Gross 2010; Svetlova 2021)。
結論となる展望
学問や科学の進歩の証なのだろうか。このハンドブックと最近出版された爆発的な数の関連書籍(Smithson, Chapter 35, this volume参照)が、無知に関する私たちの知識を進歩させるということだろうか。私たちはそう願っている。そう願わなければならない。科学の追求が希望に根ざしていないとしたら、いったい何なのだろう。
確かに、世界は分断と政治的・科学的な未知に満ちているが、幅広い分野や研究領域において、学者たちが無知研究からの洞察に目を向け、私たちが直面している分断の起源と意味を理論化していることは注目に値する(Mica et al 2021; Mueller 2020; Ortega & Orisini 2020; Slater 2021; Stel 2020を参照のこと)。無知であることは、考える上で示唆に富んでいる。しかし、無知は何を照らすのだろうか。
それは、無知の規則性と普遍性の両方を伝えることが不可欠であるということである。私たちは皆、知らない。しかし、知らない方法や理由はそれぞれ異なる。COVID-19の大流行によって、私たちは無知について、関心を持つ一般の人々や政策立案者とともに、ウイルス学者と経済学者、医師、看護師、警察、スーパーマーケット、教師、マスクやその他の医療機器の製造業者といった異なる文化の間で話し合う方法を開発する必要に迫られている。知識移転が科学的知識を普及させ、政策立案者に問題解決のためのインプットを提供するものであるのと同様に、未知のものを捉え、明らかにし、明確に伝え、一般の人々が利用でき、理解できるようにするためには、無知または非知識の移転によって完結する必要がある。知識が最も重要な価値とされる世界において、多くの無知は暗黙的であったり、単に言葉にするのが難しいため、これは明らかに、知識の伝達よりもさらに難しいかもしれない。また、特定のグループだけでなく、すべての観察者に理解できないままの未知を完全に把握できる社会的行為者がいないことを考えると、それは難しい。
無知の必然性、つまり私たちが知らないことを完全に克服することはできないという事実は、多くの人々を不穏にさせ、敗北主義に陥らせる。しかし、そうである必要はない。ここまで読んでくださった方は、未知のものに正面から向き合い、そこに可能性を見出すことで生まれる反骨精神や楽観主義の片鱗を、すでにお持ちのことだろう。未知の世界に一種の革命的な真理を求めるのだ。それが無知学の原動力であり、未知なるものを求めることなのである。すべての真理には未知という要素があり、新しく知ることができるものにも、「なぜ今なのか」という新たな未知が生じるから。
この点については、スティーブ・レイナーに負うところが大きい。スティーブは私たちの友人だった。彼はまた、無知研究の歴史における主要人物でもあった(Rayner 2012)。2020年1月に亡くなる数年前、彼は私たちのうちの一人に宛てて、命にかかわる深刻な病気の治療中であることを説明する手紙を書いた。彼のメールは質問で終わっていた。彼は、#metoo運動から生まれた虐待やハラスメントの話に衝撃を受け、「このテーマについて、特に『なぜ今?』と思うことはあるか」と尋ねてきたのである。
それは彼自身の研究分野ではなかった。しかし、彼は#metoo運動が無知研究にとって重要であると考え、自分の無知を取り上げ、是正したい、つまり、一種の聖餐式のように自分の無知を他人と共有したいと考えたのである。彼は死期が迫っていたが、理解を求めていたのである。死後、私たちの疑問は予測不可能な方法で私たちより長生きし、その未知なるものに希望があるのである。
20. コロナ・パンデミックに挑む 政治的意思決定における非知識の管理
ヤアナ・パーヴィアイネン、アン・コスキ、パウラ・アラネン
2020年からのコロナの危機は、同様のパンデミックの可能性が非常に高いと推定されているものの、誰も予測できず、十分な備えもできない形でエスカレートしていった。世界保健機関(WHO)が招集した世界保健総会(WHA)は2011年、新たなパンデミックの発生は不可避であり、したがって予測不可能であると推測している。パンデミックへの備えを含む危機管理と安全保障計画は、一般に国家公務員の法的義務であり、国際的に共有された基準に従うことが多い(Walker and Cooper 2011; Rogers 2015)。しかし、危機とCOVID-19の広範な世界的健康、社会、経済的影響に取り組む多くの政府の無能力は、未知なる未知と表現するのが最もふさわしい規模に達している。無知の文献では、伝統的にリスク管理の範囲外と考えられてきた未知なる未知やネシアの特性は、振り返って初めて知ることができる(Kerwin 1993; Gross 2019)。コロナのパンデミック予防の失敗は、世界的に情報システムの規模やスピードが巨大であるにもかかわらず、国家が国境を越えたグローバルな危機に直面したときに、グローバルなマニュアルがいかに機能しないかを明らかにした。特に、インフラが十分に機能し、高度に自動化されたセキュリティシステム、高度な医療、幅広い専門家を有する多くの民主主義国家は、ウイルスの拡散と世界的危機の深刻化を防ぐことができないことが証明された。予測分析、人工知能、自動化によって意思決定システムや国家安全保障を構築しつつある知識社会が、計測器クラスタによってその到来を予測することも規制によって阻止することもできない一つのウイルスに対して、どうしてこれほどまでに完全に混乱しているのだろうか。リスク管理や確率計算のために多大な努力をしたにもかかわらず、多くの意思決定者が失敗した理由の一つは、無知や非知識に対処する能力が未発達であったためと推測される。
本章では、コロナ危機において非知がどのように意思決定プロセスを支配してきたか、また、政策立案者が意思決定における非知に関する認識論的条件を管理しようとする際に、どのような実践に頼ったかを論じる。政治的意思決定における非知識の時間性についての私たちの以前の概念化(Parviainen, Koski and Torkkola 2021)を統合し、COVID-19危機の初期段階においてフィンランド政府が危機的意思決定の条件として非知識を扱い、市民とのコミュニケーションにおいてそれを用いる方法を学ぶことによってこの考えをさらに推し進める。パンデミックの初期段階において、フィンランド政府の意思決定は、主に予測モデリングとシナリオに基づいて行われたことを論じる。知識の予測や推定は不完全であるため、政府は非知識のまま意思決定を行わなければならないことを公に認めていた。この原稿を書いている時点では、無知を認めることが何らかの政治的スキームに属するかどうかを判断するのは時期尚早であった。私たちは、公の場で自分の無知を認めることは、特に若い女性政治家にとって信頼性のリスクになると考えている1。私たちは、政府の記者会見(PC)で行われた行動を例に、危機的状況において非知識がいかに政治判断に不可避の要素となったかを考察する。私たちの認識論的アプローチは、権力、非知識、時間性、関係性(特に政府、市民、メディア間)、そして政治的決定におけるスピードの要求が複雑に絡み合っていることを強調するものである。
認識論的論争の場としての政治
政治において、知識と無知はますます争点となっている。民主主義国家は専門家の知識に基づく意思決定を期待されているが、専門家の意見が競合するため、正当性も合意も保証されない。ヨーロッパとアメリカ大陸における「ポスト真実」の議論とポピュリズム運動の台頭は、相当数の市民が専門家の知識、特に公的な専門家組織から来る知識を意図的に疑ったり、単に否定したりしていることを明らかにした(Davies and McGoey 2012; Moore 2017; Siles-Brügge 2019)。市民の政治的無知が真の説明責任や一部の国では民主主義の未来さえも危うくするのだから(Somin 2016)、知識ある市民が第四の財産としてのメディアの助けを借りて意思決定者にその行為の責任を問うという民主主義の中核原理はもはや公理ではない。
従来、政治家は公の場で全知全能の人物として登場することを好んできたが、より複雑な社会問題や生態系の問題に直面した場合、自らの無知を認めることは避けられない。9.11テロ以降、レジリエンスは広く危機管理や安全保障計画における代名詞となっている(Walker and Cooper 2011)。新しい安全保障のパラダイムとして、レジリエンスは、テロやパンデミックといった複雑で予測不可能な問題や、気候変動に関連するような継続的に変化するシステムに取り組む必要性から生まれた(Folke 2006; Lin and Petersen 2013)。認識論的態度としてのレジリエンス思考は、政治的意思決定における非知を排除するものではなく、「私たちの無知を認識すること」が、予見、実験、適応的行動を成功させる基礎として扱われている(Walker and Cooper 2011, 146)。しかし、私たちは、このパラダイムの変化は、政治家が危機に対処するための新しい種類の認識的態度、すなわち私たちが「認識的謙虚さ」と呼ぶ視点を採用する可能性を示すと想定している。認識論的謙遜とは、行為者が自らの知識の限界を認め、未知で不確かで曖昧で制御不能な次元を、考察の不可避な構成要素として受け入れることを意味している(Parviainen and Lahikainen 2019)。
政治はここで、積極的な挑発と政治化を通じて、下された決定と採用された政策が常に問われる、争う活動として理解される。このことは、政府や議会の意思決定の場でも、市民に向けられた公的コミュニケーションの場でも、ますます認識論論争として行われるようになっている(Palonen 2006)。つまり、論争には閣僚のほか、議会野党の議員、国内外の専門家組織、個人の専門家、伝統的メディアとソーシャル・メディアの両方が参加しているのだ。その決定は、しばしば、スカンジナビア諸国や欧州連合(EU)などの国際的な参照グループの決定と比較される。プロセスとしての政治的意思決定の典型である認知・行動的意思決定理論の観点からすると、政治家は常に部分的に自分の政治的将来を懸念しており、それが知識の処理と最終的な選択に影響を与える前提の一つになっている(Mintz 2003; Ye 2007)。知識も非知識も、政治的決定を実行し、それを公の場で正当化するためだけでなく、政権を奪取したり維持するために必要な国内外での工作の余地を生み出すために利用される。
過去に危機に対処しようとした際、政治家が不確実な情報や非知識、偽情報や専門家の知識やその不一致に対応できなかったり、自らの無知に直面したりしたために、数多くの政治的操作が不祥事や災害を招いた(Bovens and ‘t Hart 1996)。コロナのパンデミックの間、政治家は、市民の健康を守るか、安全保障対策によって大きな社会的・経済的困難を引き起こすかという難しい選択肢の間でバランスをとりながら、プレッシャーの中で緊急の決定を下すことを余儀なくされてきた。ジレンマのひとつは、選択した安全保障措置が大きすぎて根本的な経済・社会問題を引き起こしているのか、あるいは十分でないために人々の健康を危険にさらしているのか、という点にある。危機的状況においては、知識の不足(および不正確な)、個人的ストレス、議会の反対派、国際的な参照団体やメディアからの論争によって行政の混乱と圧力が沸騰すると、透明で民主的な意思決定システムが麻痺してしまうことがある。たとえば、さまざまな市民グループの意見を聞くことの緊急性を認める嘆願が軽視されたり、立法構想の検討時に異なる分野の専門家の見解が考慮されなかったりする。出来事のスピードが増し、ニュースが常に溢れ、陰謀論や偽情報の流布を含むソーシャルメディアの活動が激化していることは、政府が考慮しなければならない危機に対する特殊な種類の認識力のマトリックスの形成に寄与している(Väliverronen et al.2020)。
方法と資料
非知識に関する私たちの議論は、2020年2月27日から6月15日にかけてフィンランド政府がCOVID-19パンデミック予防策を扱うために組織したPCの分析に基づくものである。政府は当初、伝染病法(CDA)を根拠に、市民への必要な勧告を決定した。2週間後、政府は共和国大統領とともに、さまざまな分野の専門家と協議した結果、フィンランドでのウイルスの発生はまだ非常に少なかったものの、3月16日に非常事態宣言を出すことを決定した。この宣言により、緊急事態法(EPA)に基づき、さらに強力な制限措置を適用するためのプロセスを開始することが可能になった。5月になると、強力な規制が効を奏したのか、流行は緩やかになった。そこで、EPAの施行は不適格となり、再びCDAに基づく措置がとられた。さらに、政府は調査期間中に「ハイブリッド戦略」と呼ばれる行動計画を導入し、予想されるパンデミックの「第二波」に備えた。ウイルスの検査、感染源に関わる接触ネットワークの追跡、検疫プロトコルの確立に必要な能力が、その後の継続的なパンデミックの予防のために導入されたのである。
データは、40台のPCの書き起こしである。首相官邸からオンラインストリーミングで配信され、資料は復元され、フィンランド政府のウェブサイトやYouTubeで自由に閲覧することができる。PCの参加者は、サナ・マリン首相の閣僚、国家機関、専門家を代表する様々な人々、メディアである。政府は、(1)ウイルスとパンデミック、(2)国民、特にいわゆるリスクグループを感染から守ること、(3)流行の進行を遅らせて保健・集中治療能力を確保すること、(4)国民経済の強化、の4点を中心に講演を行った。
そして(4)危機後の国民経済の強化である。政府が定期的にPCや状況報告会を開催し、メディアに公開するようになったのは、一部のソーシャルメディアが流す偽情報や陰謀論に対抗する狙いもあったと推測される。当初はジャーナリストを招き、その後遠隔で行われたものの、ほぼ毎日行われるPCを通じて、政府は国民に直接語りかけたのである。
「知ること」と「知らないこと」の役割を全体的に理解するために、まず、マリン首相との20の記者会見に集中して、トランスクリプトを自由にコーディングした。オープンコーディングの結果、知識に関するコードが140個(発言数1,369)、非知識に関するコードが40個(発言数344)得られた。以下の分析では、非知識のコードをさらに掘り下げている。意思決定に関する分析は、政府が発注した意思決定に参加する中核的な政策立案者へのインタビューに基づく出来事に関する自己評価報告書(デロイト2021、モルッティネン2021)によって補完され、この作品の執筆時点で発表された。私たちの目的は、意思決定プロセスと市民に向けられたパンデミック予防に関するコミュニケーションの両方において、無知と非知識がどのように現れているかを議論することであった。
「非知」の時間性を利用する
パンデミックの急速な拡大により、フィンランドでも他の多くのEU諸国でも、危機に対する備えがまったく不十分であったことが証明され、危機は既知のものから未知のものへと変化しはじめた。政治的・組織的な意思決定を扱う意思決定理論からの証拠は、人間の知識処理は、個人的にも集団的にも、非知に対してオープンであることが極めて困難になるようなバイアスがかかっていることを示している。意思決定者は、自分の以前の知識を確認する知識を探し、自分の認知枠の限界に関して過信し、容易に代替知識の探索を早々にやめてしまう(Feduzi and Runde 2014; Weick and Sutcliffe 2015)。ヨーロッパでは、このウイルスがヨーロッパ諸国の公衆衛生に広く影響を及ぼすと考える専門家がほとんどいなかったため、COVID-19の脅威はまず過小評価された。医療専門家が感染拡大を推定できなかったことは、アジア諸国ですでに感染の脅威が具体化していたときでさえ、正常性の慣習に挑戦し、未知のもののリスクを特定することがいかに困難であったかを示している。意見の相違はさまざまな理由で生じた。政治家は、専門家の見解に対して、自他の認識をすり合わせることで対応することが求められた。パンデミックの管理に参加した中心的な関係者のインタビューによると、彼らはすぐに、フィンランドの安全保障計画が軍事危機に備えることに焦点を当てすぎていたことに気づいたという(Deloitte 2021)。EPAに様々な形態の危機をパンデミックとして列挙しても、実際の計画策定作業がそれを考慮に入れていなければ、十分とは言えない。
これを書いている時点では、春に行われたパンデミック対策に関する上述の政策立案者の自己評価では、北欧やEU諸国などの参考国に比べて発症数が低く抑えられるとされている。パンデミックの間、これまでのところ、これは主に2つの事柄によって説明することができる:フィンランドへのパンデミックの到着が遅れたことと、政府がタイムリーに予測行動を取ることに成功したことだ(Deloitte 2021; Mörttinen 2021)。EPAの活用により、政府はウスイマー(首都)自治体地域を期間限定でほぼ全面的に封鎖するなど、厳格な防疫措置をとることができた。調査期間中に政府が用いた措置の中で、フィンランド国民の憲法上の権利を最も侵害するとされたのがこの措置であった。封鎖解除の際、マリン首相は「フィンランド全体の流行がどのような経過をたどるのか、まだ予測できないだけだ」と認め、市民の移動を制限しなければ流行が収束しないことを示すモデリングにほぼ基づいて意思決定したことを認めることができた(フィンランド政府2020c)。EPAを遵守することを根拠に、政府は、国際的に生み出される知識の増加に従って、また、国家保健当局者が以前に行った決定の更新を常に準備している経験を通じて、政策立案者が適時に行動を起こすことができる一連の決定を行ったのである。
グロス(2019, 23)の分類法を用いると、政治的意思決定において、未知が暫定的なものか、定義可能な期間内に排除できない可能性があるかという評価に従って行動するために、未知の時間性をより管理しやすくすることができる。例えば、順応的管理では、決定したことの結果を観察するための様々なモニタリングシステムを統合して、段階的に意思決定を行う(Böschen et al.2010; Beck and Wehling 2012; Lin and Petersen 2013)。私たちの先行研究(Parviainen, Koski and Torkkola 2021)に基づき、非知に関する意思決定プロセスには、「部分的に知っている」「まだ知らない」「これから知る」「知ることができない」「決して知ることができない」といった様々なエピステーメー状態が含まれうることを提案する。なぜなら、複雑な認識論的環境には未知の変数が多く含まれるため、一つのことを発見しても、それが謎解きの練習になるのではなく、システム的な変化につながることがあるからだ。例えば、2020年の春、コロナウイルスワクチンの開発には、「まだわからない」が「これからわかる」というエピステーメー状態が関係していた。しかし、ウイルスは急速に変化するため、ワクチンが一時的な防御にしかならないかどうか、専門家はまだ分からない、つまり「知ることができない」状態である。また、2020年春には、ウイルス対策としてのマスクの使用について、相反するエビデンスがあったが、そのメリットがデメリットよりも大きいと考えられていることが「すでに一部で知られている」という例もある。それでも、現在に至るまで、マスクの使用による完全なメリットは、実験装置の手配の難しさなどから「わからない」ままである。予測は、安全保障計画における既知の未知に対処する重要な作業の一つであり、モデリング、予知シミュレーション、データマイニング、シナリオによって未来が現前化される(Neisser and Runkel 2017)。政治においては、確率と合理性の言語によって、政策立案者は不確実性を管理し、自らの知識の生産における「確実性の度合い」を校正することができる。確率的推論の多くは専門家の評価に基づいており、このようにして専門家やアドバイザーは自らの無知を疑いと不確実性に変換する(Aradau 2017)。危機的状況において、この種の推論は、類似の経験のない新しい状況に直面した専門家が、危機の規模やその拡大の力学を推定することが困難な場合に、容易に失敗する。パンデミックの発生時、科学的アドバイザーは、過去のパンデミックと比較して、リスクと不確実性に関する情報を提供することができた。Innerarity(2012)などが論じているように、知識の多元化は、その指揮能力の弱化を意味する。専門家の中には、未知の未知や複雑な因果関係の永続的な「わからなさ」を指摘する人もいれば、関連する知識のギャップは特定可能であり、管理可能な時間スケールで克服できるとする人もいる。Böschenら(2010)は、政治家と役人が異なる「科学的な非知識の文化」に従って非知識に対処していることを示唆した。
フィンランド政府は、その意思決定において、保健当局の専門知識と、パンデミックがさらに進行した国から現れたウイルスに関する新しい知識に基づく意思決定に大きく傾いた。2月の初期段階において、ウイルス、パンデミック、防護措置の能力について質問された首相は、保健当局に対して、何がわかっていて何がわからないのかを説明するように門戸を開いた(フィンランド政府2020a)。ウイルスに関する情報が常に更新されていたとき、そして現在もそうだが、未知という時間性が、COVID-19の感染拡大に対処するための政治的決断のリズムに大きな影響を及ぼしたのである。危機への対処に現実的な態度をとったフィンランド政府は、タイムリーな介入と、「すでに一部知っている」、「まだ知らない」、「知ることになる」、「知ることができない」という認識論の連鎖に従う必要性を強調した。(Parviainen, Koski and Torkkola 2021)。しかし、立法・行政のスピードが遅いため、日々更新される情報と政治的判断を調整することが難しく、エピステーメーコンステレーションは、これまでの認識や判断を常に見直す必要がある複雑なシステムを形成していた。
政府や産業界は伝統的に非知識に対する統制志向を好んできたが、例えばNGOはより複雑な志向に依拠しており、これにより、知識可能性や政治的計画に抵抗するシステムの存在をよりオープンに認めることができる(Böschen et al.2010)。フィンランド政府は、非知識に対して十分に複雑な方向性を採用することができ、これまでのところ、状況がまだ「部分的に知られている」「まだ知られていない」間に、予想外に行動を起こすことができたようである。予防行動を調整し、意思決定のための危機的状況に関する最新情報を作成するためのCOVID-19調整・運営センターを設立する際にも、政府は意思決定を支援するための認識的プロセスを開いていたが、その反面、次のことを強調していた。
つまり、私たちは不確実性の中で生き、不確実な情報や不完全な情報の中でも意思決定をしていかなければならないのである。
フィンランド政府2020b
政治家が無知が重要な役割を果たす意思決定の場面をすべて明らかにしたとは思わないが、公的な議論の場で非知識を完全に隠そうとした形跡も見られなかった。
市民の危機意識の維持
EUと比較して、フィンランドでは政府が規制を徐々に、かつ慎重に解消していった(Deloitte 2021)。政府が規制を緩和するたびに、ほぼ毎回、ウイルスについてまだ知られていないことがあること、市民が変化に慣れ始めることが最善であることを国民に喚起していたようだ。
もう昔のような世界ではないということを、みんなで前向きにとらえたほうがいい。私たちは、2メートルの距離を保つことが日常生活の一部となり、社会が新しい方法でアレンジされなければならないような、ある種のニューノーマルへと変化しつつあるのである。
フィンランド政府2020d
現在の「ハイブリッド戦略」を伝えるにあたって、政府はレジリエンス思考を適用しているが、これは一種の継続的な非常事態を作り出すと非難されている(Walker and Cooper 2011)。また、福島原発事故後に起こったとされるように、緊急事態によって引き起こされた市民にとっての問題が否定され、民衆が状況を受け入れ、服従するようになると、レジリエンスは間接的に無知を助長することにもなる(Ribault 2019)。
現在進行中のPCでは、EPAの施行や非常事態が終了した後も、政府は一貫して「まだ分かっていないことがある」「制御不能な大流行を前にして、人々は『謙虚』であるべきだ」と念を押していた(フィンランド政府2020e)。政府が公然と不知を訴えることにこだわるのは、パンデミックのような複雑で斬新な危機や危険に対して、より適した新しい危機意識管理の手段である可能性を示唆している。周知のように、政治の世界では、市民の間に危機意識を醸成し、権威主義的な政策を遂行するために、外部からの様々な既知の未知を利用してきた長い歴史がある(Daase and Kessler 2007; Weise et al.2008)。PCを通じて不安や不知を伝えることを学んだ政府は、市民の危機意識を和らげ、感染予防に対する市民のアカウンタビリティを高めることができたのである。自らの不安を露呈することは、政府のメッセージが市民の目にどれだけ信用されるかを決める要因になったかもしれない。しかし、集団的恐怖は、市民が共通の目的のために団結することを期待するとき、政治を容易に脱政治化するものでもある。フィンランドでは、春にそのようなことがあったようだ。議会の野党は、主に支配的な手段を支持するポピュリストと保守的な政党で構成されており、コンセンサスに疑問を投げかける意欲がなかったのである。
印象的だったのは、メディアは正当性を主張し、ソーシャルメディアに広がる噂を取り上げ、政策立案者や専門家が提供できる以上の明確な知識をしばしば求める主体であったことだ。このような機能は、西欧の民主主義国家においてメディアに与えられている公共サービスの役割に当然属するものである。メディアには権力者を「監視し続ける」義務があり、メディア間の報道競争の結果、非難合戦や政治スキャンダルに発展する(Gleason 1990, 61-62; Thompson 2000; Preston 2009)。政府が国民に対して行った最も恩着せがましい決定は、2020年4月、明確なマスク勧告を拒否したことである。しかし、メディアの代表者は、他のいくつかの国で示された国際的な例を執拗に指摘した。一般市民を保護するためのマスクの有用性に関する健康専門家の意見が矛盾していたため、政府はマスクに関するいかなる推奨も行わず、知らないという状態に閉じ込めたようだった(Mörttinen 2021)。8月になってようやく、この問題に関する科学的知見の報告を命じた後、政府はUターンし、メディアや議会野党は、マスクの不足と国際市場でマスクを確保するための行政購買能力の不足を隠すために不知を利用したのではないかと疑惑を抱くようになった。
慎重に行動し、知らなかった点を認めたことで、政府は積極的な政治化を行った。これは、将来の責任のなすりあいを避け、危機後の「公式調査」に備えることにも関連していたかもしれない(Boin and Hart 2003)。おそらく、この行動方針は、不正確な決定を緩和する機会を提供することで、通常は制限されている政治的な遊び場を拡大するものであったろう。認識論的謙遜を採用することで、政府は自らの認識論的状態や能力を放棄することなく、自らの認識論的余裕を交渉することで過信を回避したようである。この危機は、政策立案者と市民の双方が人間存在に関する不確実性を認識した状況であり、通常は公の場から遠ざけられていた政治的意思決定において避けられない非知性の諸課題に取り組むための好ましい機運を作り出したのであった。
結論
データ分析から、COVID-19の流行期には、政治家は公衆衛生を守るために迅速かつ慎重な決定を下す立場にあり、その結果、企業や雇用、人々の生活に必然的に波風が立つことが明らかになった。PCにおけるフィンランド政府の公式発表を例にとって説明すると、マリン首相とその内閣は、科学的知識に基づく決定を正当化するのではなく、むしろ非知知の時間性に基づく認識論的謙遜の方針を打ち出していることが示唆された。ウイルスに関する情報が常に更新されている場合、「まだ知らない」あるいは「部分的に知っている」という認識論的状態は、COVID-19の感染拡大を管理する上で政治的決断がなされるリズムに大きな影響を与える。時間性、意思決定のリズム、関係性に関わる特別な状況や要件が、未来志向の政治化のための本質的な枠組みを確立している。また、私たちは、認識論的謙遜の態度を採用することで、政治家が未知の状態を許容し、不一致に対する反省的態度や代替的見解に対する開放性、つまり、複雑さ、混乱、不確実性に対処する能力を身につけることができることを示唆した。予期せぬことに、この危機によって、政治家や専門家は、自分たちが全知全能ではなく、不確実性をコントロールする能力がないことを公の場で認めることが容易になったようである。なされた決定は、知識の面でも非知識の面でも正当化される。したがって、非知識は否定されるべきではなく、意思決定や危機管理において政治化し、政治的余裕を生み出す手段と見なされるべきなのである。COVID-19に取り組もうとした政治的意思決定のさまざまなレベルで非知が偏在しており、このことは意思決定を非知管理の観点から探求する必要があることを明らかにしている。
注
1 2019年12月にサンナ・マリン首相の社会民主党主導の連立政権が発足したとき、彼女は現職首相としては世界最年少であった。連立政権の他の4人の党首も女性で、そのほとんどが30代である。
21. パンデミック COVID-19ガバナンスにおける無知と非知識に関する政策学的視点
カタリナ・T. ポール、クリスチャン・ハダド
科学的な専門知識と「ハードデータ」は、政策への知識投入として評価され、市民は、その時々に入手可能な最善の証拠が一般的な政治的軌道に影響を与えることを当然期待することができる。こうした価値観は、規範的・方法論的な関心事として、政策決定研究にも影響を与えてきた。すなわち、どのように知識が、そしてどのような種類の知識が政策に反映されうるか、またされるべきかという議論や、政策と関連する知識の生産そのものに関するより根本的な認識論的議論である。知識への強い関心は、政策における無知や非知識の重要な役割を隠蔽してきた。アグノトロジーや無知に関する研究は、しばしば政策を分析対象としてきたが、政策研究と無知研究との関連はしばしば暗黙のうちに残されてきた。本章では、無知研究に政策学の視点を織り込み、政策決定における無知の役割を明示することの付加価値を指摘したい。そのために、現在のCOVID-19危機における政策決定とガバナンスの例をいくつか挙げる。
パンデミック・ガバナンスにおける力としての無知の問題化は新しいものではないが(Ortega and Orsini, 2020)、現在の危機は、政策立案とガバナンスにおける無知の働きを明示化し、可視化するための発見的瞬間を提供している。ある意味で、現在のCOVID危機は、しばしば「ポスト真実の時代」(D’Ancona, 2017; McIntyre, 2018)と捉えられるものに関連する対立と緊張を悪化させ、そこでは科学専門家が権威(Nichols, 2017)と自律性の喪失を感じ、政治が再び、主に無知と露骨な形態の否定への頑なな意志に基づいて動いているように見えるのだ。この無知の犠牲は、SARS-CoV-2感染の影響や死亡率(Ortega and Orsini, 2020)に関する重要な情報が、政治の最高幹部によって保留、抑圧、疑念を持たれている国々で特に顕著に見られるようである。
同時に、COVID-19の危機は、一見したところ、代替事実のポピュリズム的相対主義とは一線を画す、新たな「市民的実証主義」をもたらしたように思われる。繁殖率、発生率、入院数、死亡数-これらの指標は、パンデミックの現状を表し、取るべき特定の対策の緊急性を示唆する限り、説明的であると同時に規定的であるように思われる。さらに、この1年間で、疫学、免疫学、ウイルス学といった分野の基礎となる科学に対する一般の認識、そしておそらく理解も驚くほど高まっている。このようにして、21世紀の知識基盤型民主主義国家の必須条件とみなされる科学的専門知識と科学的市民権という概念(Stengers, 2018)が、パンデミックガバナンスの合理的で証拠に基づく政策訓示を宣言的に裏付けてきたのである。
この合理主義的な政策決定のパラダイムは、ガバナンスの不確定性、偶発性、非知を覆い隠すことによって、もろい確実性を誘発する。そして、無知は、合理的な政策設計が「より多くの証拠」を集めることなどによって解決すべき欠陥に還元される。一方、非知識や無知がもたらす強力な効果は、政策研究者によって無視されないまでも、過小評価されたままである。同様に、無知研究も、政策決定過程における非知識の研究に対して、より包括的なアプローチを取り始めたのはごく最近のことである。このような研究課題に加え、私たちは、無知が外的な妨害としてではなく、政策立案の構成的な特徴として果たす役割を捉えようと努めている。概念的にも政治的にも、このような取り組みにおいて問題となるのは、私たちが様々な未知に苦しんでいるという明白な事実よりも、むしろ、私たちがいかにして知ることのできる多くの本質的なことを知らないか、いかにしていくつかの未知や不確実性の政策関連性、戦略価値、社会政治的意味を無視しているか、そしてこれらの未知や無知が政策立案において何を行っているのかという明白ではない問題である。政策研究の批判的・解釈的な伝統は、無知を研究するためのあらゆる概念的ツールを提供している。
COVID-19危機を焦点として、パンデミック政策決定において無知がどのように動員され、戦略的に展開されるかについて、さまざまなメカニズムを探り、図解している。Arjun Appadurai(1986)の商品の「社会的生活」という概念を援用し、政策が明確にされ、政策サイクルの様々な段階を経て、制定、実施、評価されていく中で、政策にも社会的・政治的生活があるものと考える。
本章は以下のように進行する。まず、政策研究における知識概念の位置づけを批判的に論じることで、情景を描き出す。次に、知識と無知の両方に対称的に敏感な政策のモデルを概説することによって、政策研究と無知研究を再カップル化する。これに基づき、私たちは次にCOVID-19政策を批判的に検討し、パンデミック政策の社会的生活の4つの重複する段階(アジェンダ設定、政策設計、実施、評価)に沿って、いくつかのタイプの政策無知を紹介する。その際、「戦略的無知」(McGoey 2012a;2012b)という確立された概念を基礎としつつ、より意図的ではないが、同様に政治的な形態の無知の実践を追加的に例示する。
概念的な前置き:政策、知識、無知
政治学において、政策とは政治的決定や政治的プロセスの物質的な実体、つまり実際にとられた手段を指す。同時に、政策は政治(絶え間ない権力闘争と戦術)、政治(政策が形成される制度的背景)と並んで、政治の本質的な次元として理解されている。政策立案や政策分析は、専門家や官僚が支配するテクノクラート的な実践とみなされることが多く、権力、政治、イデオロギーという大きな問題に対する興味をそそる洞察はほとんど提供されない。しかし、政策形成はあらゆる段階で権力や政治と深く関わり、社会や文化と不可分である。したがって、社会の知識や「真実」が動員され、交渉される場でもある(Hajer, 1997; Wagenaar and Hajer, 2003; Yanow, 1996)。したがって、政策立案は、アクターが特定の形式の知識を交渉し、戦略的に配置する場であり、同時に、彼らが公共政策と公益に関連すると考える戦略的な未知を動員する場であると考えることができる。権力と権威の形態と共同して構成される、知識と無知を生み出す幅広い実践を含む政策は、ルールと相互作用、資源の分配とアクセスを形成し、様々なアクターの正当な役割と責任を考案している。同時に、政策はしばしば、ある問題を不可視にし、選択されたアクターを説明不能にし、あるいは行動不能にするような形で設計されている。以下に述べるように、知識の実践はこのプロセスにおいて重要な役割を担っている。
「証拠」と「残存する無知」を超えて
非知識(Böschen et al. 2010; Gross, 2007)と無知は、政策理論においてほとんど体系的に扱われてこなかった。政策研究は、政策の源泉としての非知識ではなく、知識の役割に大いに関心を寄せてきたが、これは他の多くの科学と共通する偏見である(Proctor and Schiebinger, 2008を参照されたい)。専門性と知識の危機とされる(Nichols, 2017)ことで、知識と政治の関係、無知とエビデンスの関係に新たな関心が集まっている。第一に、最も顕著なのは、真実と証拠を取り戻し、「真実性」と代替事実の危険性から科学的根拠に基づく知識を守ろうとする新たな意志を目撃することである(Perl et al.,2018)。第二に、少なくともポストモダン的転回が科学的真理の概念を信用しないものとして非難されたため(例えば、ガーディアンのコラムニストD’Ancona, 2017)、知識の非相対主義的構成主義概念を定式化しようとする努力が見られる(例えば、Angermuller, 2018)。
これらの学問的議論は、現在の危機の根本原因であり症状でもある重要な盲点を残している:エビデンスと知識の実践の概念そのものは、知識の生産、蓄積、普及(およびその妥当性と意義に関する疑問)だけを含む限り、その不在よりも制限されてきた。もし全く議論されないのであれば、知識の不在は主に「まだ生産されていない」知識、あるいは抑圧された知識(Perl et al, 2018)という観点から議論され、この概念は私たちが別のところで「残留無知」(Paul and Haddad, 2019)と呼んでいる。この観点では、無知は、認識論的にも規範的にも、政策知識の望ましくない他者として投げかけられる。このようなアプローチは、結局のところ、体系的かつ包括的な方法で無知に完全に関与することができない。無知に関する研究に基づき、私たちは政策研究において「アグノト-認識論的感性」を発展させる必要性を強く訴えてきた(Paul and Haddad, 2019)。ここでは、逆に、本コレクションにも登場するように、政策学の視点が既存の無知研究をさらに豊かにすることができることを示す。
アグノト-認識論的感性の開発
私たち自身の無知へのアプローチは、知識と無知の研究に対して明らかに対称的なアプローチを開発しようとすることで、McGoey(2012a)の戦略的無知の概念を具体的に構築し、さらに発展させている2。科学史家が真実と偽りにアプローチする方法に不満を持ち、Bloor (1991)やCallon (1986)などの社会学者が方法論の原理として対称性の概念を提唱している。対称性とは、科学理論の真偽に関する社会学的な分析が、同じ概念的な用語で行われることを要求するものであった。私たちはこの視点を政策的知識と無知に移し替える。そして、知識と同様に、無知は様々な社会技術的実践から生じる能動的かつ深刻な産物として分析される。知識と同様に、無知はさまざまな形をとり、さまざまな人々、さまざまな文脈でさまざまなことを意味する。知識と同様に、無知は特定の制度やインフラの中で繁栄し、同時にそれらによって維持される。知識と同様に、無知は商品化され、私有化され、流通し、隔離され、政府、産業界、NGOが政策論争において戦略的武器として「武器化」することができる物質財として分析される。さらに、より哲学的な観点からは、認識論(すなわち、私たちがいかに知っているかという体系的研究)に重点を置くことを、アグノトロジー(すなわち、私たちがいかに知らないかという体系的研究)で補完するように、対称性が私たちに促している。したがって、政策研究において「アグノト認識論的感性」という言葉を使うことにしている。このように、無知に対する政策研究的アプローチは、多かれ少なかれ目に見える形で政策を形成する出来事の連鎖に沿って、様々な知識と非知識の実践に折り合いをつけることができる広い視野を展開するのに役立つのである。さらにこのアプローチは、本章で示すように、無知研究者を「制度化された無知」のさまざまな形態に感化させることができる。
政策のように考える:政策モデルにおける無知の導入
政策分析は、政策プロセスを異なる段階やフェーズのサイクルで経験則的に記述する、段階的あるいはプロセス指向のモデルに強く依存してきた。ラスウェルは、民主政治に対する規範的機能を果たすと同時に、政策の「科学」を確立する試みの一環として、7つの段階からなる政策過程のモデルを導入した(Jann and Wegrich, 2007参照)。このモデルは、その後、いくつかの修正と翻訳(例:Jenkins, 1978; May and Wildavsky, 1978)を経て、政策研究界で広く議論されてきた。しかし、今日、分析的発見主義として最も一般的なバージョンでは、アジェンダ設定、政策形成、意思決定、実施、評価の間の区別が存続し、政策実践を分類し、意味付けし、批判的に検討する努力に指針を提供し続けている。政策サイクル・モデルの誕生以来、政治と政策、あるいはインプットとアウトプットを厳格に区別する初期の技術的概念を超えて、より反復的でダイナミックな意味合いを持つようになった (Jann and Wegrich, 2007)。Howard(2005)が指摘するように、政策サイクルのモデルは、多数の意思決定者の存在、政策助言の情報源間の高度な競争と競合性、新たな取り組みに対する過去の政策の大きな影響など、現在の政策形成の基本的特徴のいくつかを捉える可能性を持っている。
このモデルは、政策がどのように形成され、制度的に分離された異なるステップを経て段階的に制定されるかを解明するのに役立つ。ヒューリスティックな装置として使用することで、さまざまなアクターがどのように政策について交渉し、作り上げ、いじくり回すかを追跡するための大まかなモデルを提供する。各ステップでは、特定の知識と権力の結びつきが作用し、それによって政策が処理される。例えば、最初の政策アジェンダを形成する問題提起において、どのような専門知識とどのような種類の知識が動員されているのか。多層的な意思決定プロセスの複雑さの中で政策提案をナビゲートし、最終的にそれが公共政策として「認可」されるためには、どのような知識や専門性が必要なのか(例えば、法律や政府規制として制定される場合など)。あるいは、新しい施策が効果的に採用され、その施策が対象とする人々の生きた実践となるように「現場で」実施するためには、政策分野に関するどのような知識が必要なのだろうか。そして最後に、政策の効果や結果に関する知識をどのように収集し、評価し、伝達することで、政策の成功や失敗を説明することができるのか、それには、何が政策の中核的効果として測定でき、何が単に意図しない、望まない「副作用」なのかの定義が含まれるのか。
これらの各段階において、知識の生産と動員は戦略や権力関係と密接に絡み合っている。対称的な見方をすれば、プロセスの各「段階」は、知識と無知の特定の組み合わせを政策プロセスに組み込むための特定の条件と特定の「窓」を提供する。これらの実践は、政策アジェンダを選択的に形成するだけでなく、盲点を作り、あるものを知ることができず、それ故に特定の種類の政策を考えることができないようにする。それらは政策の規模や範囲(地域、国、世界など)に影響を与え、新しいターゲットグループを定義し(例:弱者)、忘れられたグループ(例:慢性疾患、片親、一人暮らしの人など)を呼び起こすのである。最後に、どのような解決策が考えられるかにも、大きな影響を与える。現在の危機では、医薬品以外の介入から検査ツール、ワクチン、治療薬に至るまで、COVID-19に取り組む政策手段の広い範囲において、それらに異なる価値を割り当てている。この意味で、私たちは政策を、アパデュライ(1986)が商品との関係で述べたような、特定のライフラインと軌道を持つ「社会生活」を有するものとして理解している。これに基づき、本章の残りの部分では、COVID-19に関連するパンデミック政策の立案とガバナンスの様々な例を動員することによって、広く理解される政策サイクルの異なる段階における知識と無知の結びつきを浮き彫りにしていく。
パンデミック政策:知識と無知の問題問題の定義と課題の設定:COVID-19を知り、それに基づき行動する。
政策が立案され、交渉される前に、政策課題は特定の政治的アジェンダに効果的に位置づけられる必要がある。これには、政策問題に対する認識だけでなく、アクターが、通常、さまざまな形の知識や専門性を参照しながら、合意するような政策問題の効果的な定義が必要となる(「酸性雨」の模範事例については、Hajer 1997を参照)。注目すべきは、ネットワークガバナンス時代の政策コミュニティは異質であるため、社会アクター(科学専門家だけでなく、様々な活動家やロビイストも含む)と政策アクター(すなわち、省庁の意思決定者や選出された代表)の境界が通常曖昧であることだ(Wagenaar and Hajer 2003)。このことは、政策決定における知識の政治学に影響を与える。多様な認識論的・思想的観点を持つ異なるアクターは、そもそも何が知り得るか、どのような知識や専門性が「政策に関連する」ものとして数えられるか、さらには何が無関係または価値のない知識としてみなされるかに関する主張を明確にする(ポール・ハダード、2019年も参照のこと)。それゆえ、知識と無知の政治は、政策プロセスの最も初期の段階を形成する。COVID-19の政策決定のアジェンダが、知識と無知の相互作用のなかでどのように形作られていくのか、二つの例を考えてみよう。第一に、COVID-19が確立した政策パラダイムを通じてどのように世界的流行病として概念化されるか(ホール、1993)、第二に、特定の政策問題を定義し(in)見えるようにするのにデータがどう機能するのか、である。
第一に、COVID-19が世界的な危機として指定されたことは、今では明らかになったように思えるが、必然的なことではなく、科学的、政治的、法的な配慮によって媒介された世界的感染事件の特定の解釈の効果として現れたものであった。この問題定義は、国際社会がどのような危機に直面し、それに対処するためにどのような手段が必要だろうかという枠組みを伝えるものであり、その後の政策立案にとって極めて重要な意味を持つものであった。世界保健機関(WHO)が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態という言葉を使ったとき、COVID-19は世界的な公衆衛生セキュリティーの危機となった(Elbe, 2010; Weir, 2012)が、どのような行動が必要になるかは不明確なままであった。パンデミックから1年が経過し、この危機がグローバルな対応ではなく、むしろ各国の対応に大きく影響したことが痛切に明らかになってきた。グローバルな健康安全保障のパラダイムは、グローバルに共有された脆弱性と健康の脅威に対する共有されたアプローチという言葉を動員する一方で、北半球の経済と安全の利益を優先し、グローバルな人間性の名の下に他者への配慮というよりは自己防衛の倫理に基づいて動いている(Lakoff, 2017: 73)。さらに、GHSは、そのような危機の技術的な「修正」-薬やワクチンなど-を他の、より行動的で体系的なアプローチよりも優先させ、その結果、パンデミック政策を特定の方法で形成するのだ。
知識の実践がいかに政治的アジェンダを形成するかを示す第二の例は、COVID-19を知り、理解できるようにするために使われた知識の選択に現れている。意思決定者は、共同行動の必要性を示唆するような過去の伝染病に関する現存する知識には、ほとんど目をつぶってきた。特に経済学と疫学に由来する、選択的で定量化可能な知識への依存度が高いため、この歴史的で文脈的なパンデミックの知識は、ほとんど無視されてきた。このように見て見ぬふりをすることは、おそらく戦略的とはいえないが、既存の近代資本主義社会で危機管理を組織する「前向きな」思考が支配的であるという文脈では、おそらく都合がよい。COVID-19危機の強い経済的・医学的な枠組みを考えると、議題設定と政策提案は、一般的に公衆衛生にとって最も効果的な知識源とみなされる定量化可能なデータに大きく依存している(Adams, 2016)。
メトリクスとダッシュボードは、今や前例のない方法で私たちの日常生活に浸透し、パンデミック事象に対する分かりやすさとコントロール、意思決定者の責任を追及する能力を提供している。パンデミックによって多くの国で明らかになったように、データは、それらが管理されるインフラと同じくらい良いものでしかなく、その使用は、知識に対する政治的意思、あるいは故意の無知によって形作られる(McGoey, 2012a)。このような故意の無知の模範的な例として、2020年7月、極右の大統領Jair Bolsonaroが率いるブラジル政府は、パンデミックに関する過去のデータを削除し、累積死亡者数や感染者数の公表を停止すると発表した。この決定は後に最高裁で取り消されたが、政府の不作為、否定、故意の無知によって失われた多くの命を見えなくした。同様に、米国のトランプ前大統領は、パンデミック時の在任期間中、SARS-CoV-2に関連するリスクを否定していた。
データに関する故意の無知だけでなく、一見ありふれた認識論的実践にも無知を見出すことができる。たとえばオーストリアでは、集中治療室の空きベッド数、死亡率、感染率、そして最後にワクチン接種率など、公衆衛生に関わる登録のデータ収集の性質は断片的なままであり、したがって政策措置の効果を評価することがより困難になっている(Paul and Haddad, 2019; Pichelstorfer and Paul, 2022)。パンデミックはさらに、特にワクチン接種に関しては、地域間で一貫性のないデータ収集が露呈した。このような一貫性のなさ、時にはデータの欠如は、政策立案において「何が問題なのか」を定義する際に、高度な不確実性を可能にする:それでは、どのグループが予防接種不足のままで、プライマリーケアへのアクセスが悪く、「手が届きにくい」のか知る術がない。私たちは、ワクチン接種のデータをめぐるこうした亀裂を、戦略的なアジェンダの結果とも、単なる偶然とも考えていない。むしろ、これは制度化され儀式化された無視の形態であり、異なる政治的計算のためにあるように思われる。つまり、政策立案者が何を、どのように知っているかだけではなく、どのような知識が欠如しているかに焦点を当て、この無知の可能性の条件を検討することが必要なのである。
緊急時の政策対応と解決策の設計:COVID-19を統治可能なものにするために
これで明らかになったように、SARS-CoV-2が特殊な危機であるという定義は、ある種の知識の動員や選択的利用可能性によって形成されたものであり、そうでないものは存在しない。主に経済的・医学的な知識が、検査、追跡、隔離、閉鎖、ワクチン接種など、現時点で私たちが利用できる解決策や政策手段の範囲を決定してきたのである。全体として、医薬品の介入は、パンデミック政策の展開において特権的な地位を占めていた。これは、魔法の弾丸としてのワクチン接種に対する現在の政治的アピールに明らかなように、医薬以外の介入やワクチンの公平性への配慮の継続の必要性を傍観する立場であり、問題であると言える。
私たちが現在、危機に対処するための貴重で革新的な解決策と考えている技術は、このようにパンデミック政策の社会的営為の直接的な物質的帰結であると言える。究極の解決策としてのワクチン開発に焦点を当てることで、技術的な解決策への特別な期待が生まれた。この焦点は、世俗的な終末論に相当し、パンデミックという苦境に対する包括的な意味でのビジョンと集合的な知識の創造、そのより広い意味での考察を妨げ、また「正常に戻る」という集合的な幻想を助長している、と私たちは提案する。同じ意味で、社会科学や人文科学が生み出す知識は、このような単純化されすぎた解決策を補完し、批判的に修正することが可能であるにもかかわらず、背景が不明であった。ここでもまた、このことは将来の知識生産に重大な影響を及ぼす。というのも、これらの分野に対する資金が削減され、既存の知識が見えなくなり、進行中の知識生産が遅延し、将来の知識が閉ざされる可能性が高いからだ。
重要な無知のもう一つの側面は、このような技術的対抗措置が開発される軌跡に沿って展開される。そもそもこれは、公衆衛生上の緊急事態という符号のもとに開発された医薬品やワクチンの安全性と有効性、そしてその政治的・生物医学的な時間性に関わるものである(Kelly, 2018)。研究開発の段階で、製薬研究は、試験と想定される最終製品の両方のターゲットグループを特定する。昨年のワクチン試験のいくつかでは高齢者の採用に成功したが、アストラゼネカ/オックスフォードのワクチンをめぐる論争は、データのギャップ、つまり限られた知識によって、高齢者だけでなく若い女性のワクチンの使用も形成され続けていることを明らかにした。さらに、妊娠中のワクチン使用に関するデータも、授乳中の女性に関するデータと同様に、ほとんど見当たらなかった。これもまた、アグノトロジー的な意図というよりも、政治的意思決定者が対処を怠ってきた、より一般的なジェンダーに基づく認識論の不公正(Fricker, 2009)のパターンに沿った重大な結果なのである。ワクチンに関する知識は、前臨床・臨床研究の過程や、ワクチンが実際の集団に配備される際の市販後調査研究において、多くの未知の事柄を徐々に置き換えるに過ぎない。しかし、公的に知られていること、知られていないことを形成するのは、生物医学的・臨床的研究だけの問題ではない。また、何が十分な知識としてカウントされるかという規制の定義は、COVID-19医薬政策を形成し、行為者が戦略的に盲点を作り出すための窓を提供する。
政治的・経済的圧力が高まる中、新技術、特にワクチンの品質を評価するための十分なデータとしてカウントされる閾値は、技術的ソリューションを「ロールアウト」したいという衝動に影響される危険性がある。現行のワクチンの条件付ライセンスや事前購入契約において、製薬業界のメンバーはこれらの閾値の交渉においてより大きな発言力を持っている-特に、開発者以上にワクチンの研究データを知っている人がいないため。このことが、特殊な形の無知を生んでいる。すなわち、データ提供の遅延による知識の遅れや、「プレスリリースによる科学」における選択的または中断された知識、つまり、利用可能なデータや公にアクセスできる査読によってまだ裏付けられていない主張で効果的に見出しが作られることである。
同様に、ワクチン研究の基礎となる契約も公開されていない。開発者は入札者によって異なる価格でワクチンを販売しただけでなく、各国政府や一般市民は製造や価格設定の正確な詳細を知ることを積極的に禁じられた。2021年初頭に偶然にも部分的な情報のみが公開された。欧州委員会の関係者は契約を公開すると脅しているが、公認された国民の無知という形の秘密主義は、国民が何百万も投資する領域で、国際的に懸念される深刻な公衆衛生上の緊急事態という状況においてさえ、蔓延しているのだ。(例: Croissant, 2014; Otto, 2019; Rappert et al., 2011)
ここでいう「無知」とは、産業界が一方的に生み出すものではなく、産業界と公的アクターとの親密な結びつきの中で生み出されるものである。2020年秋、欧州委員会は、当時有望なCOVID-19治療薬であったRemdesvirを購入するために高価な契約に投資したが、非常に限られた証拠に基づいてそうした。わずか8日後、Remdesvirがその治療約束を果たさないことが明らかになった(Hordijk and Patnaik, 2020)。しかし、早期に、しかも単に一方的で過度に楽観的な期待に基づいて契約を締結することで、欧州委員会は制度化された無知の体制に貢献した。この事例は 2000年代のパンデミックインフルエンザを背景に、意思決定者が抗ウイルス剤タミフルの大量備蓄に投資したことをやや彷彿とさせる(Elbe, 2018)。ワクチン接種に対する現在の圧力を考えると、次に、これらの異なる形態の無知が、これらをより強固にするための過去の努力にもかかわらず、規制インフラに刻み込まれるようになる明確なリスクがある。
ワクチン展開の実施:重要な知識の流通と囲い込み
技術的な解決策に焦点を当てると、ワクチンのグローバルな展開という考え方は、選択的な非知識という問題をはらんでいる。この概念は、その中心であるワクチンに情報を与える(非)知識の実践を隠すだけでなく、このプロセスが直線的で摩擦がないことを示唆するものである。このことは、COVID-19の政策に当初から反映されてきた、特定の知識形態への投資と非投資を徹底的に検討する必要性を示している。
そもそも、官民の製品開発パートナーシップの形成は、官と民の利害の複雑な(そして十分に透明な)絡み合いに関する一連の問題を提起するものである。第一の問題は、こうした官民連携で「共同生産」される知識の所有権とアクセス可能性、特に特許の役割に関するものである。このことは、公的資金の割合が極めて高く、科学者の多くの研究が公的資金を受けた研究室で、オープンサイエンス方式で行われ、オープンサイエンスネットワークのネクストストレイン(Zastrow, 2020)における新興ウイルス株のゲノム配列決定など、知識を自由に共有していることから、特に重要であると言えるだろう。
特許の問題性を認識し、国連のイニシアチブであるAccess to COVID-19 toolsは、オープンイノベーションを目的として、知識と技術を世界的に共有するためのプールを設立した。しかし、その技術アクセスプールは今日に至るまでほとんど空っぽのままである。「誰もが安全になるまで誰も安全ではない」という負担の共有という概念が浸透しているにもかかわらず、部門や国境を越えた共同協力の要請は制約に直面する。なぜなら、「官-民」取り決めによる専有資産のプーリングは、知的財産権による私的所有権を遵守し、それを強化する厳密に限定した条件下でのみ実行可能と見なされるからだ (Lezaun and Montgomery, 2015)。同様の開発は、いったんワクチンが完全に開発され、ライセンスされると、ワクチンの公正かつ衡平な分配の野心に関係する。企業秘密や特許を通じたワクチンに対する企業の支配は、効果的かつ分散的にワクチンを世界的に生産・配布する取り組みも阻害する。UN-CoVAX施設は、本質的には低所得国における「グローバル」な保健医療ニーズに焦点を当てた再分配メカニズムを持つバイヤーズクラブだが、二国間の秘密競争と、他のメーカーの未使用工場や新たに作られた生産拠点の利用による生産規模の拡大が可能な状況についての議論によって、さらに弱体化している。
2020年10月、南アフリカとインドが主導する「グローバル・サウス」の国々は、世界貿易機関(WTO)に対し、COVID-19のパンデミック対策に必要な技術に関する知的財産権の主張の執行を停止するよう申し立てた。TRIPS免除」は、世界中の国やメーカーが、世界的な供給を改善するために不可欠な技術を迅速かつ官僚主義的に製造することを可能にする。6カ月にわたる非公開の交渉の末、当然のことながら、この構想は拒否された。主に北米、欧州、日本、オーストラリアの有力国、すなわち、世界で入手可能なワクチン量の膨大かつ不釣り合いなシェアをすでに確保している国々が拒否権を行使したためだ(Bhutto, 2021)。
世論からの圧力に直面し、製薬ロビーは、TRIPS条約の下ですでに存在する、国家が「公衆衛生上の緊急事態」に直面して特許権を一時的に停止することを可能にする手段をますます指摘するようになっている。しかし、こうした仕組みは、技術的・手続き的な問題で複数の専門家を必要とする長時間のケースバイケースの交渉を伴うため、現実的には実現不可能である。現在のパンデミックにおける解決策として、この正式なメカニズムが「存在する」というだけの事実を指摘することは、その複雑さと実際的な課題についての知識が積極的に脇役にされたり、忌避されたりする場合にのみ可能なことである。批評家や活動家が強調しているように、各国がワクチン開発に関連する知識にアクセスできないようにすることは、利益、所有権、貿易機密の名の下に、重要な知識を故意に囲い込むことに他ならない(Oxfam, 2020)。人道的な影響だけでなく、法的確実性の下で技術的な専門知識を分配することで、世界規模で生産能力を拡大することができる。
知識の選択によるパンデミック政策の評価
政策の社会的営為の最終段階は評価である。評価とは、明示された目的や意図に照らして政策の影響や効果を評価する取り組みとして、広く理解することができる(Jann and Wegrich, 2007)。一見、技術的な装いを見せているが、政策評価は価値を伴う事業であり(Fischer, 1990)、さまざまな形や時間的な側面を持ちうる。ここでは、科学的評価に焦点を当て、より具体的には、COVID-19政策の文脈における評価の可能性を探っている。
政策評価は、一般に、政策機関が評価されることに積極的であること、つまり、適切なデータを入手できるだけでなく、このデータを利用することにも積極的であることに依存している。政策研究は、現代の「政府化された」国家が、統治のためにその国民に対する知識に積極的な関心を持つことを典型的に推定してきた。しかし、近年の貢献(Best, 2021; 2012; Boswell and Badenhoop, 2021; Paul and Haddad, 2019)が示唆するように、国家アクターや官僚は無知に対して様々な立場をとりうる。戦略的意図を超え、国家は自分たちがほとんどコントロールできないと感じる社会問題や政治問題をさらに解明しようと、満足的に無知でないにしても、両義的になりうるのだ。
ここで、データの役割と、知識の源としての測定基準を生み出す重要な役割に話を戻そう。ここで政策サイクルが一巡する。政策の評価は通常、さらなる問題化と新たな課題設定のための出発点を示すからだ。例えば、学校の閉鎖、テスト政策、物理的な距離の取り方などの政策措置は、感染率にどのような影響を与えたのか。臨床的にも経済的にも、パンデミックの影響を最も強く受けているのはどのようなグループなのか?政策的措置は精神衛生にどのような影響を及ぼしているのか?サイエンティフィック・アメリカン誌に掲載された「COVID科学戦争」に関するオピニオン記事は、研究者が、感染予防のためのマスクの有効性など、パンデミックの統治に「不可欠」だと公に宣伝された手段の有効性に疑問を呈するデータを発表することに威圧感を感じている、緊張した政治状況を報告している(Brownlee and Lenzer, 2020)。
このような両極端を超えると、健全な評価の妨げとなるものがいくつか見受けられる。パンデミックによって明らかになったように、国によってはそもそも適切なデータ基盤がない。症例の定義が地域によって異なることがあり、データのキュレーションが習慣化されていない。さらに重要なことに、「データで見る私たちの世界」イニシアティブのように、高い発症率が政治的に高く、公に見える場合、必ずしも正確さが国家の利益になるとは限らないのである。非知識、あるいは少なくとも不確実性の方が、政治的に都合がよいことが多いのだ。
さらに、データ基盤が存在する場合でも、それをいじくり回すことができる。ワクチン接種率などの一見単純なパフォーマンス指標は、対象となる人口に投与された回数を比較することで成り立っている。しかし、対象者の定義は地域によって異なり、ワクチンの優先順位によって臨機応変に変更される可能性がある。したがって、誰を数え、疫学的に把握するかという決定は、効果的な政治的実践となる。データの不在やデータの調整だけでなく、定量化可能な指標が中心となって、Broom et al. (社会科学と人文科学が構造的に不利な立場にあるため、長期的な視点を確立することは難しく、特に、このパンデミックの経験を形成してきた7日間の急性感染報告や短期的なモデル化演習を超えようとするものはそうだ(Leonelli、2021)。また、このような知識の実践は、政策評価、あるいは与えられた政策の社会的生活の他のどの段階においても、経験的な知識や一般人の知識を含めることを排除している。まとめると、パンデミック政策は、定量化可能で短期的な形態の知識実践を優先させることによって、既存の認識論的不公正を生み出すだけでなく、再生産していることが明らかになった。
結論
本章では、現在進行中のCOVID-19のパンデミックを、政策過程における無知と非知識の役割を検討するユニークな機会として捉え、政策研究の視点と無知研究への確立されたアプローチを結合させた。体系的かつ明確に政策に焦点を当てたアプローチを導入するために、私たちは政策サイクルの概念を発見的装置として使用した。ここで示したように、政策の社会的営為(Appadurai 1986)において、無知は様々な形態をとるが、その中にはより戦略的で意図的なものもあれば、政策プロセスのいくつかの段階において政治的な働きをするものもある。これまで見てきたように、歴史的教訓に目をつぶったり、定量化できる知識に過度に依存して別の形の知識を除外したり、積極的に知識を隠したり遅らせたり、あるいはワクチン開発の場合には単に知識を共有しないといった形で生じることがある。問題定義から政策や技術的解決策の策定、政策の実施、政策の評価まで、政策の社会的生活のあらゆる段階において、行為者は知識と無知の両方を記録し、処理し、制度化する機会を提供する。例えば、国家官僚がデータの収集と利用を避け、企業関係者が臨床試験の弱点を遅らせたり隠したり、政府が知識の共有によって連帯的パンデミック政策決定に貢献しないことである。
しかし、私たちが知らないことの数々を、単なる偶然(すなわち「残存知識」)か、あるいは権力者が密室の中で自分たちの利益のために完全に意図的に行った戦略的成果であると考えるのは、政治的誤りであり知的誤認であるだろう。無知は、都合のよい不確実性、あるいは組織的な自己満足という形で現れ、真の政治的行動を阻むこともある。このような無知はあまり魅力的とはいえないが、その結果、政治的な影響を与えることに変わりはない。アグノト=認識論的な感覚を持つ批判的な政策研究は、こうした無知を可視化するためのツールや方法を提供する。しかし、そうするためには、政策研究者は、政策を支える不確実性や未知数の単なるマッピングから、いかに知らないかという問題へと分析的関心をシフトさせなければならない。それは、単に哲学的な探求という観点だけではなく、実践的、批判的、活動的な関与という観点からもである。このように、アグノトロジーの研究と政策研究は、公共政策において強化された特定の権力構造を無知がどのように支えているかを、実証的かつ概念的に共同で取り組むことができる。無知を政策的知識と同等に位置づけることは、現代の民主主義を脅かし、生命を危険にさらしている現在の真実の現実政治を理解し、それに立ち向かう機会を提供するものである。
注釈
- 1 この研究は、オーストリア科学基金(FWF)[助成契約V561]および欧州連合の研究・イノベーションプログラム「ホライゾン2020」[助成契約770523]の支援を受けて行われた。
- 2 このセクションで展開される議論は、私たちの以前の仕事(Paul and Haddad (2019)を参照)を利用している。
