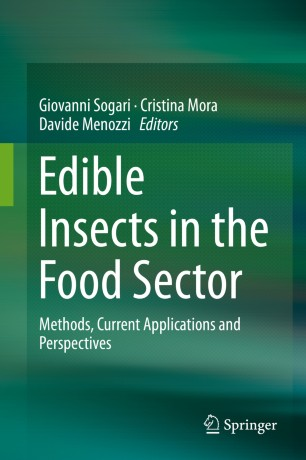
Edible Insects in the Food Sector: Methods, Current Applications and Perspectives
Giovanni Sogari – Cristina Mora Davide Menozzi
序文
新規食品の研究は比較的新しく、多くの科学分野や関心事(安全性、生産、栄養、消費者行動、官能分析、規制など)を含んでいる。非伝統的なタンパク源に由来することが多い新規製品の新たな市場機会は、世界中で増加している。しかし、そのような代替食品に対する消費者の受容性と信頼は、しばしば欠落している。
本書では、近年最も議論され、調査されている新規食品の一つである食用昆虫を取り上げる。世界的に代替タンパク源の需要が高まっていることから、国連食糧農業機関(FAO)は昆虫を飼料と食用の両方に利用する可能性を推進し、「食用昆虫」というプログラムを立ち上げた。昆虫を人間の食事に利用することによる社会的、環境的、栄養的な利点がいくつか確認されているが、欧米諸国では、主に文化的な理由から昆虫を食用にすることに否定的な人が大半を占めている。
それでも、2013年にFAOの報告書「食用昆虫」が発表されて以来、「食用昆虫。Future Prospects for Food and Feed Security」と題された2013年の報告書以降、昆虫の消費促進に対する国際的な関心が、主に北米とヨーロッパで大きく高まっている。この背景には、研究機関、食品・飼料業界、政府およびその関係者の注目度が高まっていることがある。例えば、近年、食品業界では昆虫由来製品の開発を目指すスタートアップ企業が増え、大企業はこの分野への投資を模索している。
本書は、昆虫食の現状を、消費者の視点、食用としての安全性やアレルギーの側面、昆虫を餌とする動物の最終的な肉質、この新しい食品の商業化のための法的枠組み、その他の関連事項を考慮しながら解説している。
その目的の一つは、持続可能な食料・飼料源としての食用昆虫に関する将来の研究活動をよりよく計画、開発、実施するために、第一次研究機関や資金提供団体などの利害関係者に情報を提供するための知識のギャップを特定することである。
本書は8つのテーマの章から構成されている。最初の章は、ヨーロッパにおける食用昆虫のリスク評価と将来的な展望で幕を開ける。Tilemachos Goumperisは、欧州食品安全機関(EFSA)および各国当局が、この「新規食品」の栽培、加工、消費についてどのように評価とガイドラインを発表してきたかを紹介している。
第2章では、シャーロット・ペイン、ルディ・カパロス・メギド、ダージャ・ドーベルマン、フランシス・フレデリック、マリアンヌ・ショックリー、ジョバンニ・ソガリが、ヨーロッパや北米といった北半球で、なぜ最近、新規で軽視されていた食品群に大きな注目が集まっているか、そして、学術、メディア、産業など複数の分野で、食品としての昆虫利用を普及させたり再来を求めたりし始めているか、という問題を取り上げている。
次の章では、Giovanni Sogari、Davide Menozzi、Christina Hartmann、Cristina Moraが、昆虫食と関連する消費者行動に関する主要研究活動の全体像と傾向を明らかにし、世界中のさまざまな定量・定性研究から得られた特徴や方法論的アプローチを説明・要約している。
第4章では、消費者が昆虫を食品として受け入れるための推進力と障壁を扱っている。HartmannとBearthは、食用昆虫に対する嫌悪感などの感情的反応や、リスク、利益認識、信頼などの他の要素と同様に、受容に対する動機付けの障壁の役割を探求している。
第5章では、Luís Miguel CunhaとJosé Carlos Ribeiroが、昆虫と昆虫含有製品の感覚的特性の魅力に焦点を当て、昆虫食の拒絶と受容の基礎となる主要因のレビューを提供している。欧米の消費者の受容を高めるための戦略についても言及されている。
Laura Gasco, Ilaria Biasato, Sihem Dabbou, Achille Schiavone, Francesco Gaiが執筆した第6章では、魚介類や鳥類における昆虫食の利用について、感覚的知覚の観点からも最新の知見を批判的に検討し、昆虫食を与えられた動物の製品の品質と消費者の受容性についていくつかの側面を分析する。
第7章では、José Carlos Ribeiro, Luís Miguel Cunha, Bernardo Sousa- Pinto, João Fonsecaが昆虫食のアレルギーリスクについて、交差反応・共感作に関わる分子メカニズムを検証し、昆虫を意図的に摂取した際のアレルギー反応の事例について述べている。
最後に、食品としての昆虫に関する最近の法的枠組みを概観している。Francesca Lottaは、欧州(新規食品規制)と米国における食品としての昆虫の規制分類の主な要素と相違点、およびこれらの製品を合法的に市場に出すために食品事業者が遵守しなければならない規則について紹介している。
本書が、この新規食品についてもっと知りたい、昆虫食の研究方法やアプローチについて専門知識やノウハウを増やしたいと考えている、科学者ネットワーク、学生、民間企業のメンバー、政策立案者などの関係者をサポートできれば幸いである。
本書は、食用昆虫の分野で著名な科学者や専門家のみなさんの努力と努力、そして専門知識なしには実現できなかったと思う。
イタリア・パルマ Giovanni Sogari
クリスティナ・モラダヴィデ・メノッツィ
目次
- 1 食品としての昆虫。ヨーロッパにおけるリスク評価とその将来的展望
- 2 北半球における食料としての昆虫 -昆虫食運動の展開
- 3 食用昆虫に対する消費者の受容度を測るには?- 方法論的アプローチに関するスコープレビュー
- 4 メニューの中の虫:消費者が昆虫を受け入れるための原動力と障壁
- 5 食用昆虫に関する官能的および消費者的視点
- 6 昆虫飼育動物から得られた製品の品質と消費者受容性
- 7 昆虫食の潜在的なアレルギー性リスク
- 8 食物としての昆虫:法的枠組み.
- 索引
編集者について
Giovanni Sogari, PhD, Giovanni は、イタリアのパルマ大学食品薬学部の博士研究員で、現在は米国ニューヨーク州イサカのコーネル大学チャールズ H. ダイソン応用経済・経営学部の客員研究員である。2017年にマリー・スクウォドフスカ・キュリーフェローシップ(EU Horizon 2020プログラム)を受け、現在、プロジェクト「CONSUMEHealth: 健康的な食習慣を改善するための消費者科学の活用”その目的は、消費者がより健康的な食品を選択する原動力となるものを理解し、関係者や政策立案者にエビデンスに基づく提言を提供することである。その他、地理的表示(GI)に関する消費者行動、遺伝子組み換え作物(GMO)から作られた食品、ワイン市場、食品システムにおける持続可能性、食用昆虫を含む新規食品などを主に研究している。北米のイタリア人科学者・学者財団、食品技術者協会(IFT)、農業・応用経済学会(AAEA)、イタリア農業・応用経済学会(AIEAA)、欧州農業経済学会(EAAE)など、さまざまな学会の会員である。彼をフォローするには、www.giovannisogari.com。
Cristina Mora, PhD, クリスティーナは、イタリアのパルマ大学食品薬学部の正教授である。食品、健康、持続可能性、安全性に関連するリスクとベネフィットに対する個人の反応を理解するための広範な研究を行ってきた。さらに、新たな食品生産技術や持続可能性に関連する態度や行動を理解するための定性的方法論、農業食品分野におけるステークホルダー分析や市民参加に関する文献を増やしている。主に社会科学と(農業)食品分野の国内およびEU研究プロジェクトに参加し、これらの多くでワークパッケージ(WP)リーダーを務めている。最近の例としては、Focus Balkans、Pegasus、Prime Fishプロジェクト(www.primefish.eu)などがある。また、イタリアの学部や大学院で、消費者行動やアグリビジネスに関する教育活動も行っている。イタリア農業応用経済学会(AIEAA)および欧州農業経済学会(EAAE)の会員。
Davide Menozzi, PhD, Davideは、イタリア、パルマ大学の准教授で、農業経済学と農村鑑定を研究している。2000年以降、いくつかの国内およびEUの研究プロジェクトに参加し、消費者行動と嗜好の分析、サプライチェーンの視点による食品安全および食品品質スキームの経済分析、食生活の社会経済的持続性の評価に焦点をあてている。パルマ大学食品薬学部および経済経営学部で、「農業・食品経済学」「食品選択と消費者行動」などの大学院および学部講義を担当している。2018年3月に農業経済学・農村鑑定分野で正教授の機能を持つ国家科学資格を取得。イタリア農業応用経済学会(AIEAA)、欧州農業経済学会(EAAE)など各種学会に積極的に参加。
第一章 食品としての昆虫 欧州におけるリスク評価とその将来展望
AI 要約
1. 食品安全リスク:
- 微生物学的ハザード:病原性細菌(サルモネラ菌、カンピロバクターなど)やウイルスの存在
- 化学的ハザード:重金属(特にカドミウム)の蓄積
- プリオン関連リスク:昆虫が機械的な感染媒介となる可能性
- アレルギー性:昆虫タンパク質によるアナフィラキシーショックを含むアレルギー反応の可能性
2. 規制上の課題:
- EUにおける「新規食品」としての分類と認可プロセス
- 安全性評価に必要な十分なデータの収集
- 種ごとの詳細なリスク評価の必要性
3. 生産・加工の課題:
- 衛生管理と危害分析重要管理点(HACCP)システムの実施
- 飼料材料の規制遵守(特定の禁止物質の使用禁止)
- 望ましくない物質(マイコトキシン、重金属、動物用医薬品残留物など)の管理
4. 経済的課題:
- 通年での十分な量の昆虫供給を確保する経済的に実行可能な生産体制の確立
- 競争力のある価格での製品提供
5. 消費者受容の課題:
- 欧州の食文化や固定観念との衝突
- 「気持ち悪さ」の克服
- 消費者に受け入れられる形での製品開発
6. 倫理的課題:
- 昆虫の生産と殺処分における動物福祉の考慮
7. 研究上の課題:
- 種ごとの詳細なリスクプロファイルの作成
- 加工技術が昆虫の栄養価や安全性に与える影響の評価
- 昆虫の痛覚に関する決定的な科学的証拠の不足
要旨
ヨーロッパでは昆虫はまだニッチな市場だが、ここ数年、昆虫が栄養的・経済的に有利な代替タンパク源と見なされ、消費者や産業界の関心が高まってきている。一方で、昆虫およびその製品の養殖、加工、食品としての消費にはリスクが伴うため、欧州食品安全機関(EFSA)や各国当局がこれらの点を議論する評価やガイドラインを発表している。EUの規制枠組みでは、昆虫とその製品は「新規食品」とみなされている。それらは、安全性評価を意味するプロセスである認可を受けた場合のみ販売することができる。EFSAのガイダンス文書には、安全性評価に必要なデータの詳細が記載されている。
キーワード
昆虫、食品、新規性、リスク評価
はじめに
近年、昆虫を養殖し、食品として利用することへの関心が高まっている。昆虫は、低品質で安価なバイオマスを栄養的に価値のある経済的に有益なタンパク質に変換することができる強力なバイオコンバーターとして提案されてきた。昆虫を食用とすることを指す用語として、ギリシャ語で虫を意味する「entomo」と食べることを意味する「phagia」からなる「entomophagy」という言葉が提唱されている。昆虫を食べることは人によっては不快であり、消費者の「気持ち悪さ」が昆虫を食品として拒否する大きな理由になっている可能性がある。欧米社会では昆虫は不衛生や生物学的汚染にしか関係しないが、それに対してアジア、アフリカ、南米の一部の国では昆虫が主食の一部になっている。また、同じ国でも、タイ北部では昆虫農場で生産された昆虫が日常的に食されているのに対し、首都バンコクでは昆虫の消費量が少ないなど、昆虫食に対する好き嫌いが分かれることもある。
食用昆虫に関する科学雑誌やメディアへの記事掲載は増加傾向にあり、栄養、社会、環境、安全、生産などの側面について論じられている。食用昆虫に特化した科学会議や科学シンポジウムが定期的に開催されるようになった(2014年と2018年に開催された会議「Insects to feed the world」、毎年開催されるINSECTA会議、ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)のシンポジウムなど)(Schafer et al.2016).
経済的要因
現在、EUでは食品としての昆虫はニッチな市場である。すでに市場に出回っている昆虫製品には、ミント風味の乾燥ミールワームや、パスタの材料としての粉砕コオロギ(コオロギ粉)など、昆虫全体が含まれている。
ここ数年の間に設立された新興企業では、昆虫や昆虫から派生した製品を食品として、また飼料として製造している。昆虫の生産と研究を促進するために、産業クラスターが設立された。例えば、ベルギー昆虫産業連盟(BIIF; …www.biif.org/)、EUに拠点を置く食品・飼料用昆虫国際プラットフォーム(IPIF; ipiff.org/)、アジア食品・飼料昆虫協会(AFFIA; affia.org/)などが挙げられる。
小規模な昆虫養殖は地域経済にも影響を与える可能性がある。この例として、タイでは昆虫農業が発達しており、2013年には2万社の昆虫農業企業が登録され、そのほとんどが家庭用の小規模農場である(FAO 2013a)。タイの北部と南部でそれぞれ、コオロギとヤシゾウムシの幼虫という2種類の食用昆虫を生産している。もう一つの例はラオスで、ラオスでは小規模農業は家族の収入を増やすだけでなく、家庭の栄養を改善するためのツールにもなっている(Weigel et al.2018)。
栄養の側面
1900種以上の昆虫が食用として文献に記載されているとされる一方(FAO 2013b; Jongema 2017)、実際には、昆虫農家やリスク評価者のレーダーには、そのうちのおよそ12種しか入っていない(EFSA 2015)。
昆虫の栄養プロファイルは、種そのもの、収穫時の発生段階(卵から幼虫、蛹、成虫まで)、昆虫を飼育するための基質(昆虫の餌)によって大きく変化する。EFSA(2015)は、栄養面に関するデータを包括的にまとめて報告した。フィチン酸やタンニンなど、一部の昆虫種にも抗栄養物質が確認されている(ANSES 2015)。
昆虫は貴重なタンパク質源として示唆されており、例えばミールワーム(Tenebrio molitor)のタンパク質含有量は乾物で47%から60%を数えることが報告されている(Makkar et al.2014)。タンパク質/アミノ酸、繊維、微量栄養素を多く含むため、従来の動物由来の食品に代わる食品となる可能性がある。
昆虫の取り扱いや加工は、その栄養組成に影響を与える可能性もある。例えば、昆虫製品は不飽和脂肪酸を多く含むため、加工時に急速な酸化が起こる可能性がある(FAO 2013b)。
EUの国家リスクアセスメントとガイドライン
他の食品と同様に、昆虫およびその製品の消費は、食品安全上のリスクをもたらす可能性がある。欧州では、各国の食品安全当局が昆虫のリスク評価を行っている。これらの評価では、潜在的な微生物学的および化学的リスク、アレルゲン性、加工の影響について議論されている(AECOSAN 2018; ANSES 2015; FASFC 2014; NVWA 2014)。
フィンランド食品安全局(Evira 2018)およびオーストリア当局(オーストリア保健省 2017)は、食品としての昆虫の養殖、マーケティングおよび食品安全問題の側面を網羅するガイドラインを作成した。食用の昆虫の飼育、加工、販売時の前提条件として、十分な衛生対策と危害分析重要管理点(HACCP)に基づくシステムが提案されている。
EU域外のリスクアセスメント
スイスでは、3種の動物全体または粉を販売することができる。成虫期のAcheta domesticus、成虫期のLocusta migratoria、およびT. molitorの幼虫(FOAG 2017)である。しかし、これらの昆虫から到着するタンパク質抽出物は許可されていない。
食品基準オーストラリア・ニュージーランド諮問委員会(ACNF)は、ヒトが消費する3種の昆虫(Zophobas morio(スーパーミールワーム)、A. domesticus(ハウスクリケット)、T. molitor(ミールワーム)の評価を実施し、ヒト消費に対する安全性の懸念がないと結論付けた(FSANZ 2018)。
タイでは、コオロギの養殖に関する優良農業規範が公表されている(ACFS 2017)。
食品・飼料としての昆虫のリスクプロファイルに関するEFSA意見書
欧州食品安全機関は、食品としてだけでなく、飼料としての昆虫の消費に関するリスクを評価した(EFSA科学委員会2015)。その意見では、一次生産(昆虫の養殖)加工と消費に起因する微生物学的、化学的、環境的ハザード、およびアレルギー性について論じている。昆虫の養殖時に使用される基材は、昆虫およびその製品におけるハザードの発生確率と関連していた。
微生物学的ハザードについては、非加工昆虫に病原性細菌(サルモネラ菌、カンピロバクターなど)およびウイルスが存在する可能性があるが、効果的な処理を施すことにより最終製品への感染リスクを軽減することが可能である。プリオン関連のリスクについては、昆虫に特異的なプリオン病は発生しないが、昆虫が機械的な感染媒介となる可能性があると結論付けている。また、基質から昆虫に重金属が蓄積されることが示され、特にカドミウムが蓄積される。
ヒトのアナフィラキシーショックを含むアレルギー反応も報告されている。昆虫タンパク質の存在と、トロポミオシンやアルギニンキナーゼなどのアレルゲンに対するアレルギー性または交差反応性の可能性について、消費者に注意を促す緩和策として、ラベリングを利用できることが提言された。
また、本意見書では、非加工昆虫の危険性と他の動物由来のタンパク源における危険性の比較も行っている。この比較は、EUの飼料原料カタログ(Regulation (EU) No 68/2013)に従い認可された飼料原料、人間の消費用に製造されたが、使用期限が切れたために人間の消費用ではなくなった食品、ケータリング廃棄物や家畜糞など、7種類の基質グループでの昆虫飼育に基づいて行われている。
EFSAの意見では、養殖から加工、消費までの生産チェーン全体を考慮した、異なる種や基質に関するリスク評価の必要性が指摘されている。大量飼育による環境への影響や、生産者ごとに異なる昆虫の生産プロセスの正確な詳細など、多くの不確実な領域が強調されている。
昆虫の種特異的評価
食品安全リスクは昆虫種によってかなり異なる可能性がある。上記の一般的な評価はガイドラインとして使用できるが、より対象を絞ったリスク評価を昆虫種レベルで実施する必要がある。Fernandez-Cassiら(2018)は、イエコオロギ(A. domesticus)のリスクプロファイルを発表した。著者らは、この種に特化して既存の文献をスクリーニングし、潜在的なハザードを特定した。データギャップがある場合は、Orthoptera属の他の種(バッタ、イナゴ、他のコオロギ種など)で利用可能な証拠を使用した。特定されたリスクは、ハザードの存在確率と曝露による影響を考慮し、低、中、高の3段階でランク付けされた。この演習の結果、以下のリスクが中、高に分類された:(i) 高い総好気性細菌数、(ii) 熱処理後の芽胞形成細菌の生存、(iii) 虫および虫由来製品のアレルギー性、および (iv) 重金属(例:カドミウム)の生物濃縮”
新規食品規則と関連するEFSAガイダンス文書
新規食品に関する規則(EC)No 258/97は、2017年末まで施行されている。新規食品の定義に関して、第1条2項(e)は、動物に関しては「動物から分離された食品成分」に言及し、植物に関しては「植物からなる、または植物から分離された食品成分」に言及している。昆虫から抽出または分離された食品成分(例:タンパク質分離物)は、動物から分離された食品成分として、新規食品の定義に含まれる。同様に、部品(脚、羽、頭、腸など)が除去された昆虫も同じ定義に含まれる。しかし、EU加盟国の中には、動物全体である昆虫全体(例:バッタ)や昆虫全体を原料とする調製品(例:バッタ粉)も含まれるかどうかが議論された国もあった。この議論の結果、一部のEU加盟国では、丸ごとの昆虫とその調製品は新規食品とはみなされないため、上市が許可されることになった。
新規食品に関する規則(EU)2015/2283は、2018年1月1日に発効された。
EUにおける新規食品の定義は、第3条(a)に示されている。
”「新規食品」とは、加盟国の加盟日にかかわらず、1997年5月15日以前にEU内でかなりの程度、人間の消費のために使用されていなかった食品をいう、[…]」ここで、ポイント(v)には次のように書かれている。「動物またはその部分から構成され、分離され、または生産された食品。ただし、伝統的な繁殖方法によって得られた動物で、1997年5月15日より前に連合内で食品生産に使用され、その動物からの食品が連合内で安全に使用されていた履歴があるものは除く。
この規則の適用により、昆虫全体およびその製品は新規食品とみなされる。したがって、食品事業者は、認可を受けた場合のみ、そのような製品をEU市場に出すことができる。新規食品申請のための行政的および科学的要件は、欧州委員会施行規則(EU)2017/2469にさらに詳しく記載されている。
他の新規食品と同様に、昆虫または昆虫製品が認可された新規食品になった場合、それらは「新規食品の連合リスト」に含まれることになる。連合リストは欧州委員会によって更新され、その使用条件、表示要件、およびその仕様が含まれる。
2018年、欧州委員会は昆虫に関連する申請を多数受理した(EC2018)。その中には、A. domesticus(ハウスクリケット)、Alphitobius diaperinus(小食虫)の全幼虫および地上幼虫製品、乾燥Gryllodes sigillatus(クリケット)、渡りイナゴ(L. migratoria)、乾燥T. molitor(食虫)などがあった。
また、規則(EU)2015/2283では、新規食品の安全性を評価するために、欧州委員会がEFSAの意見を求めることを予見している。このため、EFSAは、規則(EU)2015/2283に関連する新規食品の認可申請書を作成する際に、申請者がその安全性を実証するのを支援するためのガイダンス文書を公表した(EFSA NDAパネル2016a)。安全性評価に必要なデータには、新規食品とその製造プロセスの説明、組成データ、提案された用途と使用水準が含まれる。さらに、新規食品および/またはその出所の使用履歴、栄養情報、トキシコキネティクス(吸収、分布、代謝、排泄)、トキシコダイナミクスおよびアレルギー性は、申請者がデフォルトで考慮するか、考慮しない場合はこれを正当化する必要がある。申請者から提供された情報に基づいて、EFSAは提案された使用条件と予想される摂取量の下で新規食品の安全性を評価する。規則(EU)2015/2283によると、EFSAは9カ月の期間内に意見を提供しなければならないが、EFSAが申請者に追加情報を要求した場合には延長することが可能である。
昆虫およびその製品は、第三国(非EU)において伝統的な食品とみなされる可能性がある。規則(EU)2015/2283はこの場合も対象としており、第三国の伝統食品をEU市場に出すための認可のプロセスを定めている。この場合、申請者は、特に第三国における安全な食品使用の歴史を証明する通知書を欧州委員会に提出しなければならない。EFSAは、新規食品規制の文脈で、第三国の伝統的な食品の届出の準備と提示に関するガイダンス文書を発表した(EFSA NDA Panel 2016b)。安全性評価に必要なデータには、伝統食品の説明、製造工程、組成、安定性データ、仕様、提案された使用条件に関する情報が含まれる。伝統食品は、EU加盟国またはEFSAが4カ月以内に正当な理由のある安全性の異議を提出しない限り、上市が許可される。
ヨーロッパにおける昆虫食の将来
EUの人々は昆虫を食生活に取り入れるだろうか?この問いに答えるには、(少なくとも)3つの要因について議論する必要がある。
第一の要因は、食品の生産と供給に関する法的枠組みの遵守である。EU域外の国々から、さまざまな昆虫種を新規食品または伝統食品として認可するための申請書が、すでにEUの関係当局に数多く提出されており、今後もさらに増える可能性がある。安全性評価が終了し、その生産と消費が安全であることが示されれば、すべてとは言わないまでも、これらの昆虫種のいくつかは、近いうちにEUで食品全体あるいは食品成分として販売することが認可されるかもしれない。リスク評価を行うための科学的証拠が昆虫種について十分でない場合、最終決定が下される前に追加証拠の提示が必要となる可能性がある。
認可事項とは別に、昆虫の養殖と昆虫を原料とする食品の生産は、以下の分野を含む(ただしこれに限定されない)関連法規を尊重する必要がある。
- 昆虫の養殖に使用できる飼料の材料。特に、現在の飼料に関するEUの法律には、家庭ゴミや糞便など、動物の飼育に使用できない「禁止物質」のリストが含まれている(Regulation (EC) No 767/2009; Article 6 and Annex III)
- 人間の消費を目的とした他の食品と同様に、養殖および加工時の衛生管理
- 汚染物質(例:マイコトキシン、重金属)、動物用医薬品および植物保護製品の残留物など、望ましくない物質の最大限度
- 食品の微生物学的基準
- EU圏外の国からの輸入
もうひとつの問題は、昆虫の生産と殺処分において、動物福祉を考慮すべきかどうかである。昆虫が痛みを感じるかどうかについての科学的な証拠は、決定的なものではないし、少なくとも当面は不足している。
もうひとつは、一年を通して十分な量の昆虫を供給できる経済的な生産体制があるかどうかということである。食用として昆虫を生産している企業はいくつかある。以前はペットフードとして昆虫を生産していたが、新たな市場開拓のために事業を拡大した企業や、食品市場の可能性に着目して最近設立された企業などである。昆虫の養殖や昆虫製品の製造が、いかに収益性の高いものだろうかは、これから明らかになっていくだろう。
第三に、販売する製品の選択と消費者に受け入れられるかどうかである。ヨーロッパの食文化には長い歴史があり、社会的な伝統や固定観念と結びついている。昆虫の利用が環境、経済、食糧安全保障に重要なメリットをもたらすことや、昆虫は栄養価が高いことに同意しても、ヨーロッパの人々の食生活に昆虫を導入する「革命」は、彼ら自身から始まるべきだということには同意しないかもしれない。昆虫生産産業の市場調査と新製品開発プロジェクトは、どの昆虫種とどの昆虫を使った製品が、競争力のある価格で、ヨーロッパの消費者に受け入れられる形で、彼らが主張する利点を提供できるかを実証できなければならない。
第7章 昆虫食がもたらす潜在的なアレルギー性リスク
AI 要約
1. 背景:
- 食用昆虫は新しい食料源として注目されているが、アレルギーリスクの評価が必要である。
- 昆虫は甲殻類やダニと系統的に近縁であり、共通のアレルゲンを持つ可能性がある。
2. 分子メカニズム:
- トロポミオシンとアルギニンキナーゼが主な交差反応性アレルゲンとして同定されている。
- 甲殻類アレルギーのある人は昆虫との交差反応性が臨床的に関連しているが、ダニアレルギーとの関連は不明確である。
3. 加工の影響:
- 昆虫と甲殻類の間の共感作は、熱処理によってあまり変化さない。
- トロポミオシンは熱処理や消化に耐性がある。
4. 有病率:
- アジアでの自己報告による昆虫アレルギーの有病率は7.6%〜12.9%である。
- 食物アナフィラキシーの0.3%〜19.4%が昆虫に起因すると報告されている。
5. 症例報告:
- 31例の昆虫食物アレルギー症例が報告されている。
- 多くは初めての摂取後に発生し、甲殻類やダニへの感作との関連が示唆されている。
6. 職業性アレルギー:
- 昆虫を扱う労働者は感作や吸入性・皮膚アレルギー疾患のリスクが高まる。
- 職業性アレルギーの有病率は9%〜60%と報告されているが、研究間でばらつきがある。
7. 結論:
- 甲殻類アレルギーのある人は昆虫に対する食物アレルギーのリスクがある。
- ダニアレルギーとの関連はまだ不明確である。
- 昆虫を扱う労働者は職業性アレルギーのリスクがある。
José Carlos Ribeiro, Luís Miguel Cunha, Bernardo Sousa-Pinto, and João Fonseca.
要旨
食用昆虫は欧米では新しい食料源であり、食料安全保障上のリスクを評価する必要性が生じている。昆虫は甲殻類やイエダニと系統的に密接な関係にあることから、昆虫のアレルギー誘発性については大きな懸念事項の一つである。そのため、いくつかの研究により、昆虫と甲殻類・イエダニとの間で免疫学的な共感作が起こることが示されており、トロポミオシンとアルギニンキナーゼが主な交差反応性アレルゲンとして同定されている。この共感作は、甲殻類にアレルギーのある患者には臨床的に関連があるとされているが、イエダニにアレルギーのある人の場合は、まだ議論の余地がある。疫学的情報はまだ少なく、食物アレルギーの原因物質として昆虫に言及した研究はほとんどなく(アジアにおける食物関連アナフィラキシー反応の0.3〜19.4%が昆虫に起因すると報告)、事例報告も文脈に沿った情報に欠けている。食物アレルギー以外にも、昆虫は一次感作による職業性アレルギーの大きなリスクとなるが、どのアレルゲンが原因だろうかは明らかではない。したがって、昆虫のアレルギー性についてはいくつかの議論があるが、甲殻類アレルギーの被験者と昆虫飼育従事者がそれぞれ食物アレルギーおよび職業性アレルギーの発症の2大リスク群であることは明らかである。
キーワード 食用昆虫、新規食品、甲殻類、イエダニ、食物アレルギー
はじめに
昆虫に関するアレルギーを評価する研究の多くは、ハチ目に属する昆虫(例:スズメバチ、ハチ)の刺傷(Ludman and Boyle 2015)またはゴキブリの吸入アレルギー(Pomes et al 2017)に焦点を合わせている。しかし、食用昆虫の新規食品としての役割(特に、新規タンパク質源としての役割)を考えると、食糧安全保障の観点からそのアレルゲン性を評価することも極めて重要である(Belluco et al.2017)。実際、昆虫は、食物および呼吸器アレルギーのいくつかの一般的な誘因(Pennisi 2015)、すなわち甲殻類(Loh and Tang 2018)およびハウスダストマイト(Calderónら 2015)と系統的に近い関係を有している。その結果、食用昆虫は、甲殻類および/またはイエダニとの交差反応を誘発し得る共通のアレルゲン(汎アレルゲン)を共有し得る(Verhoeckxら、2016)。一方、食品産業で使用される着色料であるカルミンがDactylopius coccusの雌から得られるなど、昆虫由来の製品にもアレルギー反応が生じることがあるが、こうした反応が昆虫由来のアレルゲンにより誘発されるのか、低分子量のカルミン酸がハプテンとして作用するためかはまだ不明である(Müller-Maatsch and Gras 2016)。
本章では、食用昆虫と甲殻類/イエダニとの交差反応性/共感作に示唆される分子機構について概説する。さらに、食用昆虫に対する食物アレルギーの疫学、昆虫を意図的に摂取した後のアレルギー反応を説明する公表された症例報告および症例シリーズについても説明している。最後に、食用昆虫に対する職業性アレルギーと一次感作の分子メカニズムについても論じている。
食用昆虫アレルギーの基盤となる分子メカニズム
食用昆虫と甲殻類・イエダニとの共感作・交差反応性
非食用昆虫(ゴキブリなど)と甲殻類/イエダニ間の共感作/交差反応は徹底的に研究されており、交差反応分子としてトロポミオシンやアルギニンキナーゼなどの節足動物汎アレルゲンが同定されている。(Ayuso et al. 2002; Binder et al. 2001)。食品産業への応用が期待される食用昆虫については、いくつかの研究が甲殻類/イエダニとミールワームの間の免疫学的共感作を報告している(Broekman et al.2015, 2017a; van Broekhoven et al.2016; Verhoeckx et al. 2016; Verhoeckx et al. 2014)コオロギ(Broekman et al. 2017a; Hall et al. 2018; Srinroch et al. 2015)、イナゴ(Phiriyangkul et al. 2015)およびバッタ(Broekman et al. 2017a; Leung et al. 1996; Sokol et al.) この共感作の原因となる主なアレルゲンは、トロポミオシン(Broekman et al. 2015; Hall et al. 2018; van Broekhoven et al. 2016; Verhoeckx et al. 2014)およびアルギニンキナーゼ(Broekman et al. 2015; Verhoeckxら2014)、他のマイナーな節足動物のアレルゲン-ミオシン軽鎖、フルクトース二リン酸アルドラーゼ、アクチン、エノラーゼ、α-チューブリン、β-チューブリンなど-も同定されているが(Phiriyangkulら2015; van Broekhovenら2016; Verhoeckxら2014)、そのようなものはない。食用昆虫と甲殻類/イエダニ間の交差反応性アレルゲンとしてのトロポミオシンの役割は、阻害アッセイの使用により確立されている(Leungら、1996年;Sokolら、2017)。イエローミールワーム(Tenebrio molitor)由来のトロポミオシンは、節足動物由来のものを含む既知のアレルギー性トロポミオシンと大きなアミノ酸配列相同性を有することも示されている(van Broekhoven et al.2016 )。
トロポミオシンとアルギニンキナーゼの交差反応/共感作アレルゲンとしての役割は、甲殻類のみまたは甲殻類とイエダニにアレルギーがある患者の血清を評価した研究において証明されている。一方、イエダニのみにアレルギーのある患者では、これらのアレルゲンのいずれも交差反応性/共感作性であるとは確認されておらず(van Broekhovenら、2016)、イエダニと他の節足動物との交差反応性におけるトロポミオシンの役割については矛盾する報告がある(Bessotら、2010;Wongら、2016)。代わりに、他のマイナーな節足動物アレルゲン、例えば、ハウスダストマイトと交差反応することができるエビのアレルゲンであるヘモシアニン(Burmester 2002)と密接に関連するヘキサメリン1B(van Broekhoven et al.2016)が確認されている(Faber et al.2017 )。さらに、ヘキサメリン1Bは、甲殻類とコオロギ(Srinroch et al. 2015)またはイナゴ(Phiriyangkul et al. 2015)などの食用昆虫の間の共感作アレルゲンとしても確認されている。食用昆虫とイエダニ間の交差反応/共感作に関与する他のマイナー節足動物アレルゲンには、パラミオシンおよびα-アミラーゼが含まれる(van Broekhoven et al.2016)。
食用昆虫のアレルゲン性に対する加工技術の影響も評価されている(Broekman et al.2015; Hall et al.2018; Phiriyangkul et al.2015; van Broekhoven et al.2016)。全体として、食用昆虫と甲殻類の間の共感作は、ハウスダストマイトで起こることとは逆に、熱処理によって大きく変化しないようである(Broekman et al.2015; Phiriyangkul et al.2015; van Broekhoven et al.2016)。2016)、-実際、イエローミールワームのトロポミオシンは、熱処理または試験管内試験消化後もそのアレルギー誘発性を維持し(van Broekhovenら、2016)、この挙動は甲殻類のトロポミオシンと非常に似ている(Khanら、2018)。ミールワームトロポミオシンは、熱処理または消化に対する耐性に加えて、それぞれの種に豊富に存在すること(Yi et al. 2016)、および既知のアレルギー誘発性トロポミオシンとの高い配列相同性などの食物アレルギー誘発性(Bannon 2004)の他の重要な特徴を示し、これらはそのアレルギー誘発性の兆候である。
他の昆虫由来のアレルゲンに関して、Hallら(2018)は、コオロギ種Gryllodes sigillatusのトロポミオシンを評価し、アルカラーゼによる50%より優れた程度の加水分解のみで、エビアレルギー血清に対するIgE結合能が消失することを見いだした。一方、Phiriyangkulら(2015)は、熱処理によって、エビとボンベイイナゴの共感作で同定されたアレルゲンの強度と種類を大幅に変更できることを報告した-アルギニンキナーゼはIgE結合ができなくなり、エノラーゼとヘキサメリン1BはIgE結合能力が減少し、(未処理エキスにはなかった)ピルベートキナーゼとGADPHはIgE結合タンパク質として登場した。これらの結果は、アルギニンキナーゼが熱安定性アレルゲンではないことが報告されていることを考慮すると、驚くべきことではない(Khan et al.2018)。
In vivo研究では、イエローミールワームとエビの間の交差反応性の臨床的意義が支持されている。Broekmanら(2016)は、15人のエビまたはエビ/イエダニアレルギー被験者を評価し、大多数(13/15, 86.7%)がミールワームの二重盲検プラセボ対照食物チャレンジが陽性であることを発見した。- この割合は、特に異なる種の貝の間の反応の報告リスクが約75%(Sicherer 2001)と考えるとかなり高いと考えてもよいだろう。さらに、著者らは、すべての患者がミールワームに感作されており(皮膚プリックテストが陽性)、大多数(14/15)がトロポミオシンまたはアルギニンキナーゼを認識していることを発見し、食用昆虫と甲殻類の交差反応性/共感作におけるこれら二つのアレルゲンの役割をさらに浮き彫りにしている。食用昆虫の交差反応性に関する知識を深めるためには、(イエローミールワーム以外の食用昆虫の)経口チャレンジや阻害アッセイを行う研究がさらに必要である。さらに急務なのは、イエダニにのみアレルギーを持つ患者を対象とした研究が少ないため、イエダニと食用昆虫の交差反応性を評価する研究が必要なことである。実際、食用昆虫とイエダニの共感作を制御する主要アレルゲンは何か、またイエダニ・アレルギー患者が食用昆虫を摂取した際に臨床的な食物アレルギーを発症する危険性があるかどうかは、まだ不明である。
一次感作潜在的に食用昆虫のアレルゲンに対する一次感作の基礎となる分子メカニズムに関して、ほとんどの研究では、(食物または吸入アレルゲンとして)カイコに感作した被験者を評価している(Jeongら、2016,2017; Liuら 2009; Wangら、2016; Zhaoら、2015;Zuoら、2015)。アレルゲンとしてのトロポミオシンの役割は不明であるが(Jeong et al. 2017)、いくつかの他のIgE結合要素、すなわちアルギニンキナーゼ(Liu et al. 2009)、キチナーゼ、パラミオシン(Zhao et al. 2015)、27kDa熱安定糖タンパク質(Jeong et al. 2016)、チオールペルオキシレドキシン(Wang et al. 2016)、ビテロジェニン、キチナーゼ、30Kタンパク質、トリオセリン酸アイソメラーゼ、熱ショックタンパク質およびキモトリプシン阻害剤である(Zuo et al.) アルギニンキナーゼ、パラミオシン、キチナーゼは、ゴキブリ、イエダニ、あるいはエビなどの他の節足動物の既知のアレルゲンと高い配列相同性を持つため、これらの節足動物との交差反応に関与している可能性がある。実際、カイコとイエダニやゴキブリなどの一般的なアエロアレルゲンの間には高い共感作性があることが報告されている(Sun et al.2014)。
昆虫への一次感作が甲殻類との交差反応につながるかどうかは、まだ不明である。Linares ら(2008)は、異なる種のコオロギに対する一次感作と呼吸器アレルギーを持つ個人について述べている。この被験者は、アレルギー性トロポミオシンに対するsIgEが検出されず、甲殻類やダニに対する交差反応性も認められなかった。一方、Broekmanら(2017b)は、主に感作され、イエローミールワームに対する吸入または食物アレルギーを有する4人の被験者を評価した。- これらの被験者はいずれもエビに対する経口チャレンジが陽性で、ハウスダストマイトに対して感作されたのは1人だけだった。この一次感作の主要なアレルゲンは幼虫のクチクラ蛋白であることが示唆され、これが他の節足動物との共感作の欠如を説明できるかもしれない。さらに、同じ被験者が異なる昆虫種に対する感作の程度と割合にばらつきを示したことから、このミールワームに対する一次感作とアレルギーは種特異的である可能性がある(Broekman et al.2017a)。注目すべきは、種特異的なアレルギーは、イエバエ(Focke et al. 2003)、ゴキブリ(Lehrer et al. 1991)、アオドウガネとハチガ(Siracusa et al. 1994)など、他の昆虫にも報告されていることである
昆虫食に対する食物アレルギーの有病率
昆虫食に対するアレルギー反応の有病率は、2つの異なる方法で評価されている。- (1) 昆虫食従事者の自己報告によるアレルギー反応 (Barennes et al. 2015; Chomchai et al. 2018) および (2) アナフィラキシー反応のレトロスペクティブ研究 (Ji et al. 2009; Jiang et al. 2016; Jirapongsananuruk et al. 2007; Piromrat et al. 2008; Rangkakulnuwat et al. 2018)である。
昆虫の摂取に対するアレルギー反応の有病率を評価する研究は、アジア、より具体的にはビエンチャン以外のラオス地方(Barennesら2015)、およびタイでのインターネット調査(Chomchaiら2018)で行われている(表71)。Barennesら(2015)がラオスで行った調査では、自己申告によるアレルギー反応の有病率は7.6%(81/1059)であり、重症アナフィラキシーが報告された例はない。一方、タイで実施したインターネット調査において、Chomchaiら(2018)は、アレルギー反応の頻度が12.9%(18/140)、そのうち22.2%(4/18)が重篤な症状を報告していることが確認された。本研究では、昆虫に対するアレルギー反応の発生は、魚介類に対する食物アレルギーを含む他のアレルギーの既往と関連していることが明らかになった。
注目すべきは、アレルギー反応が自己申告であること(Barennes et al. 2015; Chomchai et al. 2018)、アレルギー反応を起こした人は調査に参加する素地があったかもしれないこと(Chomchai et al. 2018)から、これら2つの研究で報告された有病率は過大評価されている可能性があることである。
食物アレルギーの有病率を評価するいくつかの研究では、昆虫は食物アレルギーの原因物質として言及されていないにもかかわらず、中国(Jiら2009、Jiangら2016)およびタイ(Jirapongsananurukら2007、Piromratら2008、Rangkakulnuwatら2018)で行われた5種類の研究は食物アナフィラキシーの事例を後ろ向きに評価し、虫に起因するイベントの頻度を報告している(表72)。これらの研究では、昆虫による食物アナフィラキシーが合計93例報告されている。最も多く反応を起こした種はカイコサナギ、コオロギ、バッタであり、これらの研究が行われた地域の消費習慣を反映していると考えられる。各症例に関する情報は多くないが、昆虫摂取後にアナフィラキシーを起こした被験者のうち少なくとも1人は、エビ摂取後にアナフィラキシーを起こしたと報告されている。(Piromrat et al. 2008)。
昆虫による食物アレルギーの症例報告および症例シリーズ
文献調査により、昆虫の摂取によって引き起こされた食物アレルギーの合計 31 例が報告されていることが確認された。これらの症例は、私たちの以前の論文(Ribeiro et al.2018)で発表された表を適応更新して構成された表73にまとめられている。
これらの症例の多くはアジアとアフリカで報告されているが(Choi et al. 2010; Ji et al. 2008; Kung et al. 2011, 2013; Okezie et al. 2010; Yew and Ling Kok 2012)、アメリカ合衆国(Freye 1996; Gautreau et al. 2016; Piatt 2005; Sokol et al. 2017)およびオランダ(Broekman et al. 2017b)での発生事例も報告されている。原因種は、反応が発生した国の消費習慣を反映しており、例えば、中国で発生した反応(Ji et al. 2008)はカイコのサナギによるもので、ボツワナで発生した反応はモパネワームによるものだった(Kung et al. 2011, 2013; Okezie et al.)
ほとんどの報告例は、食用昆虫を初めて食べた後に発生したと記述されており、甲殻類やイエダニに感作されていた被験者が、交差反応によりアレルギー反応を発症したことを示唆しているのかもしれない。実際、4例では被験者に貝類の食物アレルギーの既往があり(Choi et al. 2010; Piatt 2005; Sokol et al. 2017)、別の9例では被験者が一般的な航空アレルゲンに感作されているかアレルギー疾患の既往があった(Broekman et al. 2017b; Choi et al. 2010; Freye 1996; Ji et al. 2008; Kung et al. 2011,2013)。
3つの報告されたケースでは、反応は一次感作によって起こると思われる。これらのケースは、イエローミールワームに常にさらされていた被験者が、この種に対するアレルギーを発症したことが関係している(Broekman et al.2017b; Freye 1996)。注目すべきは、これらの被験者のうち2人がエビに対する経口チャレンジを行ったとき(Broekmanら、2017b)、どちらもアレルギー反応の症状を示さなかったことである。
昆虫に対する食物アレルギーを研究する際の大きな限界の1つは、報告された症例やそれに関する文脈的な情報が不足していることである。この限界は、昆虫食がアジアやアフリカで主に一般的であるため、いくつかの報告が報告されなかったり、気づかれなかったりすることに起因する可能性がある。例えば、中国では毎年、カイコのサナギの摂取後に1000人以上の患者がアナフィラキシー反応に苦しんでいると報告されているが(Ji et al. 2008)、これらの反応に関する背景情報(感作プロファイルやアレルギー歴など)はほとんど未発表である。
職業性アレルギー
昆虫学者は、アレルギー、毒物反応、感染症、蔓延、妄想性寄生虫症などの有害な業務関連疾患の発症に関する重要なリスクグループである(Stanhope et al.2015)。ゴキブリへの環境曝露で起こることと同様に(Pomes et al. 2017)、食用昆虫への職業曝露も感作や吸入性・皮膚アレルギー性疾患の発症リスクの上昇につながる(Stanhope et al.)
実際、ハチガ(Siracusaら、1994,2003)、イエローミールワーム(Bernsteinら、1983;Broekmanら、2017b;Harris-Robertら、1983)を含む潜在的に食用の昆虫に常に暴露した後、労働者が感作し呼吸および/または皮膚のアレルギー疾患を発症するいくつかの報告事例が存在する。2017b; Harris-Roberts et al. 2011; Siracusa et al. 1994, 2003)、コオロギ(Bagenstose Iii et al. 1980; Bartra et al. 2008; Linares et al. 2008)、イナゴ(Burg et al. 1980; Harris-Roberts et al. 2011; Tee et al. 1988)、キリギリス(Lopata et al. 2005; Soparkar et al. 1993)およびカイコ(Zuo et al. 2015)などがある。また、昆虫そのものだけでなく、昆虫の餌にアレルギーを示す被験者(Bagenstose Iii et al. 1980; Harris- Roberts et al. 2011)、絹などの昆虫由来の製品にアレルギーがある被験者(Uragoda and Wijekoon 1991)などがいる。
昆虫に集中的に曝露される労働者における呼吸器・皮膚アレルギー反応の有病率(Burge et al 1980; Harris-Roberts et al 2011; Lopata et al 2005; Siracusa et al 2003)は、実施した異なる研究間で大きく異なり、9%から 60%の範囲にある。これはおそらく、研究の方法論の違いや、文脈の特異性を反映しているのだろう。これまでのところ、昆虫に感作された労働者が曝露された種に対する食物アレルギーを発症する可能性を評価した研究は1件のみである(Broekman et al. )したがって、昆虫飼育従事者が昆虫に対する食物アレルギーを発症するリスクが高いかどうかを理解するためには、さらなる研究が必要である。
結論
欧米で昆虫食が広まるにつれ、昆虫の摂取に関連する可能性のある食品リスクを評価することが必要である。これらのリスクのひとつは、昆虫のアレルギー誘発性である。甲殻類やイエダニと系統的に近いだけでなく、食用昆虫自体がアレルゲン源として機能する可能性があるためである。甲殻類アレルギーの被験者は、主にトロポミオシンまたはアルギニンキナーゼを介した交差反応により、昆虫に対する食物アレルギーを起こす危険性があると思われる。ハウスダスト・ダニ・アレルギーの被験者が、昆虫に対する食物アレルギー反応を交差反応機構により発症するかどうか、また両者の共感作を制御するアレルゲンが何だろうかは、まだ不明である。昆虫飼育従事者も昆虫への一次感作により職業性呼吸器・皮膚アレルギー疾患を発症する危険性がある。この感作は、感作された昆虫と同じ種に対する食物アレルギーを引き起こすこともある。
第8章 食品としての昆虫:法的枠組み
AI 要約
この文書は、EUと米国における食用昆虫の法的枠組みについて詳細に説明している。主なポイントは以下の通り:
1. EUにおける規制の変遷:
- 以前は昆虫の法的地位が不明確で、加盟国によって解釈が異なっていた。
- 新規食品規則(EU) 2283/2015の採択により、昆虫は「新規食品」として明確に分類された。
2. EUの新規食品規則:
- 昆虫を市場に出すには安全性評価と認可が必要。
- 一般的な手続きと第三国の伝統的食品に対する届出手続きの2つの認可プロセスがある。
- 経過措置期間が設けられ、一定の条件下で既存製品の継続販売が認められた。
3. EUにおける昆虫生産の規制:
- 昆虫は「畜産動物」として扱われ、飼料や衛生に関する既存の規則が適用される。
- 昆虫特有の規制はまだ整備されておらず、今後の法改正が必要。
4. 米国における規制状況:
- FDA は昆虫を食品または食品成分として扱う方針。
- 昆虫製品を合法的に販売するには、食品添加物として認可されるか、一般に安全と認められる(GRAS)必要がある。
- GRAS 認定が最も現実的な選択肢だが、科学的証明には高いコストがかかる。
5. 課題と今後の展望:
- 昆虫特有のリスクを考慮した法律の改正が必要。
- アレルギー表示など、消費者への適切な情報提供が重要。
- 昆虫の福祉に関する規制の整備が課題。
6. 両地域に共通する課題:
- 昆虫食の安全性評価に必要なデータの不足。
- 既存の食品法を昆虫の特性に合わせて適応させる必要性。
この文書は、食用昆虫に関する法規制が進展しつつあるものの、まだ多くの課題が残されていることを示している。
フランチェスカ・ロッタ
概要
昆虫食は非常に古い習慣であるにもかかわらず、ほとんどの西洋諸国では新しい食の現象と考えられており、そのため立法者からはほとんど関心を持たれていない。
欧州連合(EU)では、昆虫の規制状況は、新しい新規食品規制が採択されるまで、非常に議論のあるところであった。旧新規食品規制では、昆虫が新規食品であることは明示されておらず、そのため欧州加盟国によってアプローチが異なる結果となった。ある加盟国では、昆虫全体およびその一部が新規食品規制の対象外とされ、それらの上市は市販前承認の対象とならなかったが、他の加盟国では昆虫を新規食品と見なし、法律で定められたリスク評価手続きの対象としていた。
新しい新規食品規則の採択により、食用昆虫の法的地位が明確になった。昆虫とその一部は新規食品の定義に含まれ、市場に出す前に認可を受ける必要がある。昆虫の養殖、食肉処理、加工に適用される法律に関しても、認可のプロセスとは別に、昆虫を食品として分類することは新たな課題を提起している。
米国では、食品医薬品局(FDA)は、欠陥としてのヒトの食品に含まれる昆虫に大きな関心を寄せていたが、ヒトの食品としての昆虫やヒトの食品の意図的な構成要素としての昆虫にはほとんど公の関心が向けられていなかった。そのため、米国で合法的に販売するためには、食品添加物として認可されるか、一般に安全と認められるもの(GRAS)でなければならず、その規制区分はまだ不明確である。
キーワード 新規食品 – 認可手続き – 欧州食品安全機関 – 規制分類 – GRAS状態
はじめに
昆虫食とは、人間が昆虫を食べることを指す言葉である。昆虫は、世界の多くの文化圏で伝統的な食文化の一つであり、アフリカ、アジア、ラテンアメリカの人類の栄養の歴史において重要な役割を果たしてきた(Bodenheimer 1951)。昆虫食は少なくとも113カ国で実践されており 2000種以上の食用昆虫が記録されていると推定されている(Jongema 2017)。
世界中で広く消費され、その消費に関連する利点があるにもかかわらず(Dobermann et al. 2017)、昆虫は西洋諸国では新しい料理現象であり、食品としての規制分類はかなり議論の的になっている。
本稿では、欧米の2大市場である欧州連合とアメリカ合衆国において、食用昆虫に適用される法的枠組みの概要を提供することを目的とする。本書では、食用昆虫の規制上の分類と、食用昆虫を合法的に市場に出すために食品業者が遵守すべき規則について分析する予定である。
欧州連合規制(EU)2283/2015以前の食品としての昆虫の規制状況
欧州レベルでは、食用昆虫は新新食品規制の採択によって初めて特定の法律の対象となった1。この変化の理由は、持続可能なタンパク質源としての食用昆虫への関心の高まりと、全欧州加盟国における食用昆虫の販売に関連するハーモナイゼーションによるものである。
新規食品規制が採択される以前は、食用昆虫の規制区分について法的には不明確な点があった。この法的ギャップにもかかわらず、昆虫および昆虫由来製品は通常、新規食品3に関する規則(EC)258/1997(以下、「旧新規食品規則」)の範囲に含まれると考えられていたが、この資格は議論の余地がないものであった(Paganizza 2016)。
旧新規食品規則が定める定義によれば、食品または食品原料が新規なものとして分類されるには、次の2つの条件を満たす必要がある。
(a) 1997年5月15日以前に共同体内において、かなりの程度、人間の消費のために使用されていないこと、および (b) 旧新規食品規則の第1条2項に規定されるカテゴリーのいずれかに該当すること4。欧州連合内では、過去50年間、人々が昆虫を消費してこなかったことは事実だが、昆虫は第1条2項のどのカテゴリーにも属していないようで、第2条件の達成に異論が唱えられた。しかし、厳密に解釈すれば、昆虫から分離した食品成分のみを新規とみなすことになり、昆虫そのものを新規とみなすことにはならないが、「植物からなる食品および食品成分、動物から分離した食品成分」を集めたカテゴリー(e)にはある程度該当すると思われた。
新規食品というステータスの主な結果として、新規食品は市場に出される前に、想定される用途を考慮した安全性の評価を目的とした市場前承認の対象となる。
欧州加盟国の異なるアプローチ
法律が明確でないため、欧州加盟国は旧新規食品規制をさまざまに解釈し、その結果、このテーマに対してさまざまなアプローチをとっている。ある加盟国では、昆虫全体が新規食品規制の対象外とされ、その上市は市販前承認の対象とはなっていない。一方、昆虫全体とその部品の両方を新規食品と見なし、法律で定められたリスク評価手順の対象としている加盟国もある。
ベルギー、イギリス、オランダは、最初の国のグループの代表的な例である。
2014年、ベルギー連邦食品連鎖安全庁(FASFC)と保健高等評議会は、昆虫の使用に関する微生物学的、化学的、物理的な危険性を評価した意見を発表した(FASFC 2014)。この文書に続き、新規食品申請の提出なしにベルギーで商業化が可能な昆虫の種と、その商業化のための条件を特定したサーキュラーが発行された(FASFC 2016)。このサーキュラーでは、昆虫から分離した成分(昆虫タンパク質など)や第三国から輸入した昆虫にはこの制度が適用されないことが明記されており、これらの場合、製品を市場に出すには新規食品申請が必要であるとしている。
イギリスでは、2015年7月に政府が食品事業者に対し、1997年以前の安全な摂取履歴を示すことを目的としたデータの提出を求めるなど、昆虫の販売が当局によって容認されていた。特に昆虫事業者には、食用昆虫および昆虫加工品の新規食品性を排除するためのあらゆる証拠(包括的な販売情報、個人の証言、輸出入情報等)の提出が求められてきた。残念ながら、照会に対して提供された情報量は、英国における安全な消費の歴史を実証するのに十分なほど確固としたものではなかったと考えられる。
オランダは通常、ヨーロッパで昆虫食の実践に対して最も寛容な国とみなされている(Paganizza 2016, 32)。2014年、オランダ食品・消費者製品安全局の要請により、リスク評価・研究局(ORAR)は昆虫の摂取に関する化学的、微生物的、寄生虫的リスクに関する文書を発表した(ORAR 2014)。分析対象は、オランダで食用に飼育されているミールワームカブトムシ(Tenebrio molitor)、レッサーミールワームカブトムシ(Alphitobius diaperinus)、ヨーロッパ渡りイナゴ(Locusta migratoria)といった昆虫種に限定されている。
リスクアセスメント室の調査結果によると、昆虫は食肉加工品に適用されるものと同じ衛生基準の対象となり、その消費に関する化学、微生物、寄生虫のリスクは、適切な生産方法の使用により管理することが可能である。昆虫は敏感な人にアレルギー反応を引き起こす可能性があり、キチン質を含むため、乾燥または凍結乾燥した昆虫の1日の想定摂取量は45グラムを超えてはならない(ORAR 2014, 3)。
イタリアやスウェーデンなど他のヨーロッパ諸国では、このテーマに対して全く異なるアプローチがとられた。
2013年、イタリア保健省(Ministero della Salute)は解説書を発表し、食用昆虫は1997年以前に欧州連合で安全な消費の歴史を持たない動物由来の製品であるため、新規食品規制の範囲に入ることを明確に述べた。そのため、食品事業者が長年の消費履歴を証明できる書類を提出するか、その昆虫種が自国での安全な消費履歴があることを証明する欧州加盟国当局の公式声明を提出しない限り、その上市は市販前承認の対象となる(Ministero della Salute 2013)。
2017年、スウェーデン国立食品庁(Livsmedelsverke)は、食用昆虫が新規食品規制の範囲に含まれるとのプレスリリースを発表した。この法律の目的は、アレルギー反応や食中毒などの未知のリスクから消費者を保護することである。スウェーデンの市場に昆虫由来の製品を投入したい食品会社は、科学的な書類を提出することで、これらのリスクがないことを証明しなければならない(Livsmedelsverke 2017)。
規則2283/2015/EUに基づく新規食品としての昆虫の認可
主流の動物源の代替品として昆虫を利用することへの関心が高まり、昆虫の食品としての消費に関連する利益が報告されていることから(Testa et al. 2016)、欧州委員会は欧州食品安全機関(EFSA)に対し、食品および飼料としての昆虫の生産と消費から生じる微生物的、化学的および環境リスクを評価するよう要求している。EFSAの科学的見解によると、昆虫の消費に関連する微生物学的、化学的、環境的ハザードは、昆虫種、使用基質、収穫と加工の段階によって異なる(EFSA 2015)。欧州における昆虫の食品・飼料としての利用の規模や頻度に関する詳細な情報がないため、さらなる研究が必要であるにもかかわらず、当局の全体的な意見は、昆虫を食品・飼料として利用することのリスクは、他の動物に関するリスクよりも大きくないというものである(Finke et al.2015, 247)。
EFSAの意見発表から数カ月後、欧州委員会は、昆虫の法的地位を明確にし、欧州連合における昆虫の上市に関する調和のとれた規則を定めた新新食品規則を発表した。新規食品規則の説明(8) によると、新規食品の概念は、1997年以降に起こった科学技術の発展を考慮し、昆虫全体およびその一部も含むように改訂される必要があるとしている。
新規食品規則では、昆虫とその部分は、動物またはその部分から構成され、分離され、または生産された食品を包含する第3条第2項のカテゴリー(v)に該当する。昆虫が新規食品として分類された場合、その昆虫が1997年5月15日以前にEU域内でかなりの程度、人間の消費に利用されていたことを食品事業者が証明できない限り、市場に出す前に認可を受ける必要があることを意味する。
現在、物質の新規食品性の評価手続きは、欧州委員会の実施規則(EU)2018/456に定められている5。従来、新規食品性の評価は、各国当局が非公式かつ匿名で行っていたが、規則(EU)2018/456では、食品事業者に製造方法やフローチャートなどの機密情報の開示が求められる手続きが設けられている。施行規則では、食品事業者が一部の情報を機密扱いとすることを要求することができるとしても、評価を行うために必要な情報量が多いため、食品事業者はこれを利用せず、直接新規食品の申請を選択することができるかもしれない。
新規食品規制では、新規食品物質の上市を許可するために、一般的な手続きと第三国の伝統的な食品に対する届出手続きの2つの手続きを定めている(Pisanello et al.2018)。
規則の第10条から第13条に規定される一般的な手続きは、あらゆる種類の新規食品に適用され、少なくとも17カ月を要する。食品事業者は、欧州委員会が欧州食品安全機関の支援(必要と判断された場合)を受けて評価する科学的資料を提出する必要がある。規則(EU)2017/24696およびEFSA(2016a. 2018)が提供するガイドラインに従って作成された新規食品申請書において、申請者は昆虫種、使用する基質、ならびに養殖および加工の方法を考慮しなければならない(EFSA 2016a、b)。
届出手続きは第14条から第20条に規定されており、次の2つの条件を満たす第三国の伝統食品を市場に出すために利用することができる:(i) 第三国において相当数の人々の慣習的食生活の一部として少なくとも25年間消費されていること、および (ii) 加工食品か未加工食品かにかかわらず、規則 (EC) No 178/2002で定義されている一次生産に由来するものであること。この手続きは、製品の安全性を証明する必要はなく、第三国での安全な使用履歴のみを証明するため、一般的な手続きよりも迅速に行うことができる。一方、届出手続きを選択した申請者は、特定の条件が満たされた場合、新規食品規則第26条に規定されるデータ保護の恩恵を受けることができない。
この認可は非常に特殊であり、製品の仕様、製造方法(昆虫の餌に使用する基材の種類など)、使用条件に影響を与える変更があった場合は、新たに申請する必要がある。
経過措置期間中の昆虫の上市について
新規食品規制の施行後、昆虫および昆虫由来製品は、旧体制下で商業化が可能であった国(英国、オランダ、ベルギー)でも認可を受ける必要がある。新規食品申請の完了には最大17カ月を要する可能性があるため、欧州議会は、認可が下りるまで食品事業者が昆虫および昆虫製品の上市を継続できるよう、具体的な規定を設けている。
新新規食品規制の第35条2項では、旧新規食品規制の適用範囲に属さない食品で、2018年1月1日までに合法的に上市され、新新規食品規制の適用範囲に属するものは、それぞれ本規則の第13条または20条に従って採択された施行規則で定められた期日までに提出された第三国からの新規食品の認可申請または伝統食品の届出を受けて決定されるまで(遅くとも2020年1月2日までに)継続して上市することができるとされている。
この規定に照らすと、2018年1月1日以前に昆虫および昆虫製品を合法的に市場に出していた食品事業者は、規則(EU)2017/2469で定められた2019年1月1日までに製品に関する申請または届出を提出すれば、新しい新規食品規制に基づいて製品を引き続き販売することが可能である。2019年1月1日以降は、その日までに新規食品の申請が欧州委員会に提出された当該昆虫種およびその種から製造された食品のみが販売可能となる。
EU委員会の進行中の申請の概要によると、今のところ、食用昆虫に関する6つの申請が保留されている:ハウスクリケット(Acheta domesticus)、ホールおよびグラウンド・レッサー・ミールワーム(Alphitobius diaperinus)の幼虫製品、乾燥コオロギ(Gryllodes sigillatus)、渡りイナゴ(Locusta migratoria)、乾燥ミールワーム(Tenebrio molitor)、食事虫(Tenebrio molitor)です8。
農場から食卓までの昆虫:規制の枠組み
欧州食品安全機関(EFSA)の見解によると、昆虫の消費に関する生物学的および化学的ハザードは、昆虫の種類、収穫の段階、特定の生産方法、餌に使用する基質の種類に強く影響される(EFSA 2015, 1)。
旧新規食品規制の柔軟な解釈により昆虫の販売が制限されていない国でも、昆虫の生産と販売は、各国当局による特定の評価を受けた昆虫種に限定されている9。新新規食品規制の発効により、同規則に定められた手順のいずれかに従って食品安全性を評価された昆虫種のみが欧州市場に投入されることになった10。
昆虫の飼育と収穫は欧州レベルでは特に規制されていないが(Lähteenmäki-Uutela et al. 2017)、いくつかの欧州当局は当局と昆虫事業者の両方を支援することを目的としたガイドラインを発表している(EVIRA 2018; FASFC 2018)。
食用昆虫は「畜産動物」として認定され、そのため他の家畜に適用されるのと同じ規則に従わなければならない11。昆虫は、飼料原料のカタログ12に記載されている安全な飼料のみを与えることができる。反芻動物のタンパク質、ケータリング廃棄物、肉骨粉、糞の使用、および動物栄養目的の糞の使用は禁止されている13。
飼料材料に適用される制限は、食品廃棄物を昆虫の「飼料材料」として使用することの可能性について、興味深い問題を提起している。研究により、大量に入手可能で低コストであることから、有機廃棄物は昆虫の持続可能な生産のための重要な原料資源を形成できることが示されている(Nyakeri et al.2017)。食品、食品廃棄物、人間の消費を目的としなくなった食品を区別することは、どの製品が飼料原料として使用でき、どの製品が直接有機廃棄物に分類されるかを定義する上で、実に基本的なことである。欧州委員会は最近,商業的な理由や製造上の問題や特定の欠陥のために、もはや人間の消費を意図していない食品の栄養素を価値化するために、有機廃棄物ともはや人間の消費を意図していない食品の概念について明確化した文書を発表した(欧州委員会2018b)。欧州委員会によると、旧食品は自動的に廃棄物とみなされるのではなく、特定の条件を満たすことを条件に飼料原料として利用することができる。
昆虫の終了までの昆虫養殖は、規則(EC)No 178/20094の第3条(17) に規定される定義に従って一次生産とみなされ、そのため一次生産に関する規則(EC)No 852/2004の付属書1に規定される衛生要件に従う(evira 2018, 9; FASFC 2018, 5)。
ヨーロッパの昆虫養殖場では、昆虫は、大気、基質、水などを制御できる箱・ケージに入れられ、閉鎖的な環境で飼育される。当局のガイドラインにより、昆虫に使用する飼育容器等は、化学的に安全な材料で製造することが義務付けられている。生きた昆虫のための飼育箱は、実際の包装材や食品に接触する材料ではないとしても、食品との接触に適した材料で作られた昆虫飼育用容器を入手することが良いとされている(EVIRA 2018, 10)。現在、昆虫の生殺与奪条件は欧州レベルで規制されていない。昆虫は非脊椎動物であるため、動物福祉指令の対象外である15。輸送中の動物保護に関する規則(EC)1/2005、殺処分時の動物保護に関する規則(EC)1099/2009も同じ理由で適用されていない。将来的には、これらの規定を昆虫のミニ家畜に適応させるための改正が必要と思われる。
昆虫の加工とラベリング
昆虫の加工は、昆虫が食用として流通する形態によって異なる。現在、昆虫全体、粉末やペーストなどに加工された昆虫全体、タンパク質単離物、脂肪/油、キチンなどの昆虫抽出物が市場に出回っている(EFSA 2015, 14)。昆虫の製造および加工は、食品衛生に関する規則(EC)178/2002および規則(EC)852/2004に規定される一般食品法の原則に準拠する必要がある。動物由来の食品に関する特定の衛生規則を定めた規則(EC)853/2004には、昆虫から製造された食品に関する特定の規定はなく、近い将来、このミニ家畜の特殊性を考慮したこの規則の更新が必要になると思われる。食品の微生物学的基準に関する規則(EC)2073/2005、汚染物質に関する規則(EC)1881/2006、薬理活性物質の最大残留基準に関する規則(EU)37/2010も、昆虫製品に関する特別な規定がないため、更新が必要になる予定である。
昆虫および昆虫由来製品は、規則 (EU) 1169/2011に規定された一般表示要件およびEU食品法に規定されたその他の関連表示要件に準拠しなければならない16。昆虫由来製品の性質と安全性を消費者に十分に知らせるために、食品の説明、組成、使用条件などの追加表示情報が必要となる場合もある。
EFSAによると、昆虫および昆虫由来の食品の摂取は、ヒトにアレルギー反応やアナフィラキシーショックを引き起こす可能性がある。特に、多くの昆虫種は、菌類の細胞壁や甲殻類(カニ、ロブスター、エビなど)の外骨格にも含まれる、天然由来のグルコサミン多糖類であるキチンを含有している。キチンおよびその誘導体であるキトサン(キチンの脱アセチル化により工業的に生産)は、個々にアレルギーを引き起こすものではないが、投与経路やキチン粒子の大きさによっては、免疫調節特性を持つ(FAO 2013; Muzzarelli 2010; Lee et al.2011)。このことから、交差汚染のリスクを排除できない場合、昆虫製品に使用されているのと同じラインで加工された製品に、アレルゲン表示(例:含有する可能性がある)の使用が求められる可能性がある。
食品としての昆虫:米国のアプローチ
米国では、FDAは欠陥としてのヒト食品中の昆虫に大きな関心を払ってきたが、ヒト食品としての昆虫やヒト食品の意図的な成分としての昆虫にはほとんど公的な関心を払っていない(Boyd 2017, 20)。
広範な判例法17で確認されているように、昆虫とその部品は主に、21 U.S. Code § 342(a)(3)に従って食品を消費に適さないものにする可能性がある害虫、または21 U.S. Code § 342(a)(4)に従って食品を粗悪品にする汚染の合理的な可能性を作り出す可能性があるものとして考慮されている。この他に、FDAは、コチニール(Dactylopius coccus costa)の乾燥・粉砕体によって抽出される赤色で、様々な食品を着色するために食品産業によって主に使用されているコチニールの製品仕様を規定した合衆国法律第21編第73.100条において、食品に任意に添加される物質として昆虫の使用を規制しているだけである。
明確な規制の枠組みがないにもかかわらず、昆虫や昆虫を使った食品は米国で急速に普及しており、現在、さまざまな種類のプロテインバーやスナック菓子、その他の加工食品を購入することができるようになっている。この新しい食品ビジネスの開花により、昆虫の食品としての規制区分に関する問い合わせがFDAに多数寄せられている。FDAはこの点について公式な見解を示していないが、「FDA’s Standard Response to Entomophagy Inquiries」から得られる見解は、「食品、医薬品、化粧品法の下では、虫/昆虫は、食品として、あるいは食品の構成要素として使用する場合は食品とみなされる」(Ziobro 2015)である。
昆虫およびその一部を食品として規制分類することは、昆虫が「清潔かつ健全(すなわち、不潔、病原菌、毒素がない)であり、衛生的な条件下で生産、包装、保管、輸送されていなければならず、適切に表示されていなければならない(第403条)」ことを意味するものである。(とされている(Ziobro 2015)。さらに、昆虫は、媒介物、構造物、毒素の危険性を最小限に抑えるために、現行の適正製造基準(cGMP)に従って、人間の食用に特化して飼育されなければならない。さらに、野生で育った昆虫は、人間の活動によって病原性微生物に感染したり、有害金属や農薬を含んでいる可能性があるため(FAO 2013, 119-122)、野生での採取は認められていない。
食品の意図的成分としての昆虫の規制について
昆虫および昆虫由来の食品が現在アメリカのいくつかの流通経路で販売されているという事情から、その規制の分類に注目が集まっている。米国市場に合法的に投入されるには、食品添加物として認可されるか、その使用が一般に安全と認められる(GRAS)必要がある(LeBeau 2015)。
21 U.S. Code § 170.3 CFR では、意図された使用により、直接的または間接的に食品の成分となる、あるいは食品の特性に影響を与えると合理的に予想される物質は、その使用が一般に安全と認められるもの(GRAS)でなければ、食品添加物となる。添加物は、FDAによる市販前承認の対象となるが、一般に安全と認識されている物質については、その必要性はない。
昆虫および昆虫の派生物を食品添加物に分類することは、その物質が食品に添加されたときに安全であることを証明する請願書を提出した後、その使用がFDAによって承認される必要があることを意味する。この認可は、昆虫種を安全に使用できる条件を規定した規則で構成される。昆虫を食品添加物として法的に認めることは、その安全性について消費者を安心させるというプラスの効果をもたらすが、この解決策にはいくつかの限界がある(Boyd 2017)。第一に、食品添加物に分類されるためには、「(食品の)単一成分は当該食品の特性に影響を与えず、むしろ食品を構成する18」ため、昆虫は食品の唯一の成分であることはできない。第二に、昆虫の種類は多様であり、使用にはそれぞれ個別の承認が必要となるため、添加物の承認プロセスは昆虫の規制には適さないと思われる。最後に、昆虫の食品としての使用に関連する科学的調査や研究の不足を考慮すると、承認プロセスには費用と時間がかかる19。
要約すると、昆虫の使用が一般に安全と認められている物質(GRAS)として認定することが、最も現実的な解決策であるように思われる。GRAS 状態の確立には、1958年 1月 1日以前の食品での一般的な使用に基づく経験と、科学的手順という。2 つの選択肢がある(Fortin, 2017)。
昆虫の場合、公表済みおよび未公表のデータに基づく科学的手順が最も実行可能な解決策と思われる。この手順の肯定的な側面は、昆虫および昆虫由来食品の製造者が、その物質が意図する用途に対してGRASであるという自己決定を「FDAの審査や決定を待つことなく(Boyd 2017)」行えることである。製造者が行う自己判断の他に、1997年以降、FDAは、任意の者が、特定の用途がGRASであるという通知者の判断に基づき、ある物質の特定の用途が食品添加物の承認要件から免除されることをFDAに通知することができる、任意通知手続きを導入している。
科学的手続きに基づくGRASの安全性の証明は、食品添加物と同様に厳格であり、同じ量と質の科学的根拠を必要とする(Fortin, 2017)。コオロギ粉のような食材のGRAS状態を証明するために必要な研究量は、約25万ドルかかると言われている(Lähteenmäki-Uutela et al.2017)。
昆虫は世界の多くの地域で消費されてきた長い歴史があるので、考えられる解決策は、1958年1月1日以前の使用に基づいて物質のGRASステータスを決定することである。この場合、GRAS判定を行うメーカーは、食品での一般的な使用に基づく経験を通じて、その物質が意図された使用条件の下で一般的に安全と認識されていることを証明する必要がある。一般に入手可能なデータや情報に基づいており、科学的手続きに基づく添加物やGRAS物質に求められるものよりもリソースを必要としない証拠であっても、FDAは米国外での物質の一般的使用に頼ることに「消極的」なようだ(Hutt et al.2014)。
昆虫製品を市場に出す際には、消費者に摂取している食品の性質について誤解を与えないよう、一般名と科学名の両方を適切に表示しなければならない。
結論
EUと米国における規制の枠組みを分析した結果、昆虫と昆虫製品が立法者の注目を集め、その法的地位と上市のための規則がつい最近明確にされたことがわかった。しかし、これはまだ第一歩に過ぎない。なぜなら、このミニ家畜の特殊性と、それがもたらすかもしれない新たなリスクを考慮し、食品に関する法律を改正する必要があるからだ。
