Contents
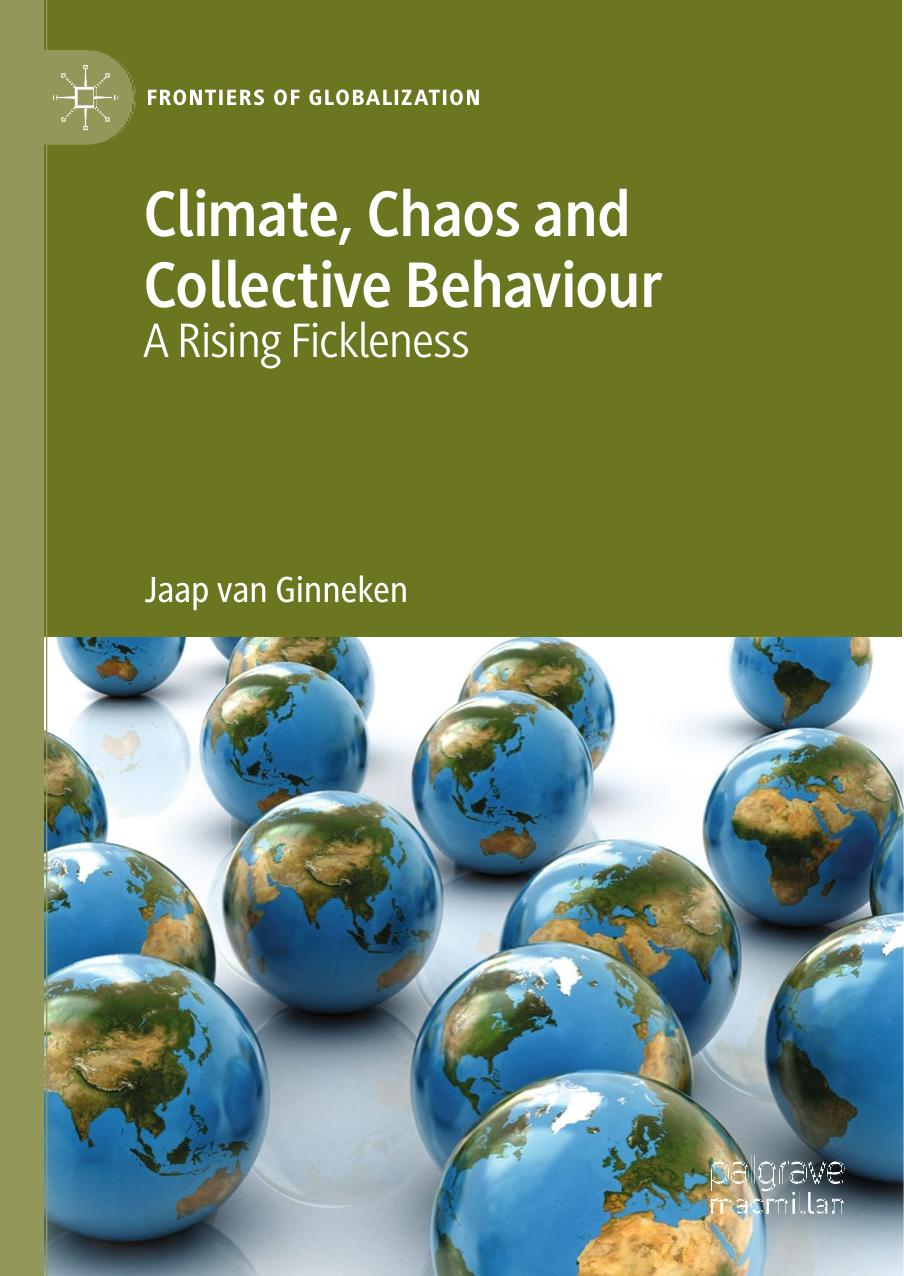
Climate, Chaos and Collective Behaviour
気候、カオス、集団行動
高まる気まぐれ
ヤープ・ヴァン・ギンネケン
グローバリゼーションのフロンティア
シリーズ・エディター
ヤン・ネデルヴェン・ピーターセグローバル・スタディーズ学部 カリフォルニア大学サンタバーバラ校(米国カリフォルニア州)
21世紀に入り、20世紀のグローバリゼーションの主要な構成要素が崩れつつある。アメリカの覇権は政治的にも経済的にも弱体化している。新自由主義的グローバリゼーションを形成した自由放任の資本主義は危機的状況に陥りやすいことが証明され、資本主義を組織化し規制する複数の方法に道を譲りつつある。新興社会の台頭により、世界経済の原動力は単に地理的なものだけでなく、構造的なものへと変化している。産業革命後の消費社会ではなく、工業化社会が再び世界経済を牽引しているのである。こうした変化は、多極化の時代、資本主義の複数性の確認、新しいモダニティの出現、南北関係とは対照的な東-南、南-南関係の新たなパターンといった大きな区切りを伴う。これらの変化はグローバルな規模で展開されており、国家単位、地域単位、あるいは国際単位で正しく理解することはできない。こうした変化を理解するためには、グローバルな政治経済から文化的変容まで、学際的で万華鏡のようなアプローチが必要である。本シリーズでは、トピック、アプローチ、理論的枠組みにおいて革新的なグローバル・スタディーズへの投稿を歓迎する。グローバリゼーションが劇的な変化の渦中にあるミレニアムの世紀末以来、本シリーズは、現代のグローバリゼーションとその影響に関する資料への関心の高まりに応えるものである。企画書はシリーズ・エディター宛に郵送のこと: Jan Nederveen Pieterse, Mellichamp Professor of Global Studies and Sociology, Global & International Studies Program, University of California, Santa Barbara, CA 93106-7065, USAまで郵送のこと。
ヤープ・ヴァン・ギンネケン
気候、カオス、集団行動
高まる気まぐれ
ヤープ・ファン・ギンネケンオランダ、アメルスフォールト
序文
本書のタイトルは正直に言って、「40年前に知っておきたかったこと」である。本書はアイデア、観察、教訓の書であり、マネジメント・テクニックの書ではない。
-リチャード・ファーソン、アメリカ人経営コンサルタント1
50年以上生き延びることで得られるあらゆる恩恵の中で、最高のものは、風変わりであることの自由である。馬鹿にされようが、馬鹿にされようが、気にすることなく、安全かつ快適に、肉体的・精神的な存在の境界を探検できることは、なんと嬉しいことだろう。
-ジェームズ・ラブロック、イギリスの環境学者2
本書を読み終えて、本書の関連性と時事性が急上昇した。というのも、2021年10月のノーベル物理学賞が、日本人、ドイツ人、イタリア人の学者に授与されたからだ。「地球の気候に対する人間の影響の予測を含む、複雑系を支配する隠れたルールに関するブレイクスルーモデル」3。
本書は、複雑系、カオス理論、そしてそれに関連する新しい概念群について、10のステップで読みやすく科学的に説明することに焦点を当てている。そして、それを精神社会科学に応用することで、さらに一歩踏み込んでいる。特に、大衆心理学や集団行動社会学といった神秘的な領域で、私たちの相互作用における気まぐれな「急流」を扱っている。フェイクニュース、噂、都市伝説、陰謀論など、ここではすべて気候変動とコビッドに関するものである。
また、新たな社会運動、抗議、対立、暴動、暴力などもこの視点から見ている。メディアの誇大広告、パニック、金融危機。世論とコミュニケーションは、一日ごとに不安定さを増している。今日の新聞や夕方のテレビニュースを見てみよう。その中の小さな項目が、突然大きな意味を持つようになるかもしれない。
しかし、私たちはいまだに、すべてがうまくコントロールされている、あるいは簡単にコントロールできるかのような錯覚に陥っている。しかし、それは真実ではない。私たちの世界全体は、かつてないほど急速に変化している。しかし私たちは、なぜ、どのように変化しているのかを理解していない。私たちはいまだに、機械主義科学の三位一体というナイーブな迷信にしがみついているからだ。意味はこうだ: 測定することは知ることであり、知ることは予測することであり、予測することはコントロールすることである。
そうすることで、我々は一貫して他の現象、より不安定な現象を避けてきた: 10%、1%、0.1%である。それらは全く異なる、一見非論理的な論理に従う。さらに言えば、それらは定期的に劇的な方法で私たちの確信を脱線させ、不可解な出来事に直面する傾向がある。それがどのようにして起こるのか、私たちには見当もつかない。しかし、さらに掘り下げていくと、まるでアリスの覗き窓から覗くように、未知の世界への展望が突然開けるのだ。新しい発見があるたびに、アハ・エレブニスが起こり、新たな創造的洞察が認識されるのだ。
本書の前身となる別作品が出版され、長い間完売状態が続いていたが、国内外の批評家から熱狂的な反応があった。パラダイムシフト、つまりこのテーマに対するまったく新しい見方について語る人もいた。各章の最初のセクションにある序論では、問題となっている現象の生き生きとした最新の事例をもう一度取り上げている。しかし最後の章では、自然界や自然科学における類似のプロセスにも目を向け、並行して洞察を深めていく。それはしばしば意外な展開をもたらす。
オランダ、アメルスフォールト Jaap van Ginneken
集団行動と世論に対する称賛
なかなか楽しい読み物である。
-アンソニー・E・アダムス、アメリカン・コミュニケーション・ジャーナル、アメリカ
代替的な説明・・・非常に読みやすい
-国際世論調査ジャーナル
目次
- 第1部 心の震え
- 1 複雑適応システム(CAS)としての世論
- 2 非公式メッセージの連続的変異
- 3 メディアの誇大宣伝における循環的反応
- 第2部 新たな集団行動
- 4 群衆におけるシナジーの形成
- 5 世論潮流におけるパターンの出現
- 6 社会運動の自己組織化
- 第3部 世間のムードの変化
- 7 ファッションと流行の進化する文脈
- 8 恐怖とパニックにおける重要な閾値
- 9 憤激と抗議行動における惹起要因の可能性
- 第4部 結論
- 10 ブームとクラッシュにおける相転移
- 11 予測、計画、基本的不確実性
- 12 まとめ:問題管理?
- 参考文献
- 著者索引
- 主題索引
著者について
ヤープ・ファン・ギンネケンは社会心理学を学び、オランダのアムステルダム大学コミュニケーション学部の非常勤准教授を長く務めた。それ以前は、巡回記者や外国特派員として長く活躍し、その後も科学コミュニケーションの分野で頻繁に仕事をしてきた。長年にわたり、応用心理学、社会心理学、経済学、政治学、メディア心理学、説得に関する25冊ほどの本を出版しており、その多くは英語で書かれている。大手新聞社や放送局に定期的に寄稿し、ポピュラーサイエンスに関するいくつかのテレビ番組シリーズのフォーマットを共同開発した。しかし、ヴァン・ギネケンのより具体的な専門は、世論と科学の力学、大衆心理学と集団行動社会学である。群衆、心理学、政治学に関する遅ればせながらの博士論文は「優秀賞」を受賞し、その後ケンブリッジ大学出版局から出版された。彼の著書『Understanding Global News』はSage社で翻訳された。権力と政治的リーダーシップの心理学に関する2冊の近著もパルグレイブ・マクミランから出版され、その他はアムステルダム大学出版局などから出版されている。本書の前身となる本書は、非常に独創的で刺激的であると、初期の読者から絶賛された。
はじめに 新しいビジョン
真面目な仕事とは「狭い学問領域で明確に定義された問題を死ぬまで叩き続けることであり、広く統合的な思考はカクテルパーティに追いやられる」という考えから脱却しなければならない。
-マレー・ゲルマン、物理学者、ノーベル賞受賞者。(コヴェニー&ハイフィールド、p.8)。
非科学者は、科学は演繹によって機能すると考えがちである。しかし実際には、科学は主に比喩によって機能している。そして今起きていることは、人々が心に描くメタファーの種類が変わりつつあるということだ。
-ブライアン・アーサー 経済学者 (ウォルドロップ327頁)
おはよう、お隣さん。「今日はいい天気だね」 最近最も広まっている誤解のひとつは、気候変動はゆっくりと静かに訪れ、徐々に気温が上昇し、晴天の日が増えるというものだ。しかし、氾濫、干ばつ、火災など、異常気象が急速にエスカレートすることも間違いない。噂やメディアによる誇大広告、抗議や暴動、あるいは完全なパニックなど、私たちの反応もより劇的なものになるだろう。なぜなら、気候変動は単に気温が徐々に上昇するということではなく、日ごとに静かに適応していくものだからだ。
気候変動と新たなパンデミック
世界的に有名な物理学者スティーヴン・ホーキング博士は、近未来を一言で要約した:「私たちは貪欲さと愚かさによって自滅する危険にさらされている」(Meyer, p. I)。2022年の国連気候報告書では、我々は最大1.5℃の温暖化という共通の目標を超えようとしていると結論づけている。これまでに合意されたことで、私たちはすでに摂氏2度を超えることになる。これまでに合意されていないことで、私たちは3℃のしきい値を超えるかもしれない。南アフリカで最近起こった大洪水の後、同国の大統領はこう結論づけた。
大きな転換点を防ぐ好機は終わりつつある。評判の高いイギリスの週刊誌『ニューサイエンテイスト』は数年前、「気候変動について明確に考えることができない33の理由」というカバーストーリーで警告を発した。その後、有名なアメリカ人作家ジョナサン・フランゼンは、『ニューヨーカー』誌に「もし私たちがふりをするのをやめたら」と題するエッセイと極論を発表した(小著として再出版)。どういうわけか、この問題の緊急性は、個人にもグループにも、議会にも政府にも、すぐには浸透しない。これは前例のない地球規模の問題なのだ。
まず第一に、大気汚染から始まる。大気汚染は私たちの目には見えないし、気づかないことも多い。化石燃料から排出されるCO2だけでなく、メタンや硝酸も、煙突や自動車、飛行機を通して、早急に、そして制限する必要がある。それだけでなく、農業や工業から過剰に排出されるメタンや窒素もある。糞尿や肥料、その他数え切れないほどの化学化合物である。近年、粒子状物質やナノ粒子が、環状道路や高速道路に隣接して、呼吸器疾患やガンの原因となることが多数確認されている。したがって、空間計画は国家規模で徹底的に見直す必要がある。都市、田園地帯、自然という区分け全体を見直す必要がある。何十年もかかる、重大かつ構造的な変化である。
地表の季節は乱れる。ある時期や場所では、季節が短くなったり長くなったり、あるいはもっと気まぐれになったりする。ある時期や場所では、季節が短くなったり長くなったり、あるいはもっと気まぐれになったりする。予期せぬ数週間や数ヶ月の間、特別に寒くなったり暑くなったりすることもある。植物の新芽が凍結したり、干ばつ(火災ではないにせよ)によって破壊されることもある。その結果、農作物の不作や食糧不足が発生し、発展途上国では合法か否かにかかわらず、先進国への大規模な移民が発生する。先進国はどれだけの新参者を受け入れることができるだろうか?社会的、民族的緊張が高まることは間違いない。
一方、海や海洋もうまくいっていない。一部の海洋生物は気候帯の変化に適応できず、移動するか、枯れるか、あるいは単に死滅してしまうだろう。新鮮な魚の小規模な漁獲は、沿岸に出現する巨大な外国冷凍船団によって影響を受ける。さらに、河川の水位が交互に過度に上昇したり下降したりすることもある。洪水や氾濫を引き起こしたり、干ばつで淡水が不足したりする。大規模な新しいインフラ・プロジェクトは、流域や三角州に沿って実施される必要があり、また、その近くの土地や建物にも関係する。
もちろん、遠く離れた、つまり「目に見えない」氷も、ここでは大きな役割を果たしている。山脈にある氷河や、グリーンランドや極地にある厚い氷冠の融解スピードはますます速くなっている。長い目で見れば、これは地球全体の水位上昇を数十メートルから数メートルにまで拡大させるだろう。白い氷は消え、青や茶色に変わる。その結果、太陽の放射が反射されなくなり、暖かさが吸収されるようになる。これは自己強化的なプロセスであり、その地域の気温をさらに上昇させ、その地域の温暖化を加速させる。
これは、地域的、全国的、さらには国際的に、大気と海洋の両方で、主要な流れや潮流の速度と方向が変化することを意味する。複合的な大陸間メガパターンの例として、ラニーニャと交互に発生するエルニーニョ(「クリスマスの子供」)がある。エルニーニョは太平洋の平均気温を上回ることによって引き起こされ、最終的にペルー沖の漁師の網に大群を追い込む。しかし、このアメリカ大陸の東側での温暖化は、アメリカ大陸の上空や西側の天候にも影響を与える。さらに言えば、翌年の大部分は大西洋の天候にも影響を与える。
それとは別に、大西洋の表層と深層には巨大な環状のメキシコ湾流がある。表層水はアフリカ沿岸に近い熱帯南部で暖められる。メキシコ湾流は西ヨーロッパの海岸に近い北へと流れ、フランスのブルターニュ地方やイギリス、アイルランドの南岸で温暖な気候をもたらす。スカンジナビアの隣で冷え始め、北米に渡る。水は重くなり、グリーンランドの隣で底に沈む。海水は南へ流れ、大陸の海岸の横をメキシコ湾の方向へ流れる。そしてまた海を渡る。そしてまた海を渡る。これは、天候を永遠に変化させ続ける極めて複雑な時計仕掛けの一例に過ぎない。
これは、哺乳類や魚類が大陸を、あるいは地球の半分を横断する年2回のトレッキングにも影響を与える。例えば北米では、デラウェア湾は鳥たちの主要な中継地点であり、その瞬間には小さなカニや卵があふれ、長い旅に必要な余分なタンパク質を供給する。オランダでは、北部のワッデン島が同様の役割を果たしている。このようなパターンは何千年もかけて定着し、世界中に何百とある。私たちはほとんど気にも留めていないが。
一方、人間の活動は海岸や河川を中心にいたるところで活発化している。ラテンアメリカ、サハラ以南のアフリカ、東南アジアなどである。手つかずの自然や熱帯雨林の奥深くまで。これによって、外来の哺乳類(コウモリなど)や爬虫類が孤立した環境から「解放」される。しかし、奇妙なバクテリアやウイルスを媒介する昆虫もいる。その結果、未知の病気や伝染病が流通するようになる。コビッドはその一例である。たった一例の伝染病が世界的な流行を引き起こしたのだ。
一例を挙げよう: 私がフランスのコート・ダジュールに住んでいた頃、アフリカから北地中海沿岸の観光地にタイガー・モスキート(トラ蚊)が徐々に侵入してきていることに警鐘が鳴らされた。私たちは、庭から小さな水たまりをなくすように言われた。彼らは、致命的なものも含め、12種類もの熱帯ウイルスを媒介する可能性があった。私がオランダに戻った後、彼らは年間100キロのペースで北部に移動し、今ではベネルクス諸国にも到達していると言われた。
過剰な食肉消費は、一方でバイオ産業の出現をもたらした。家畜は互いに密接に飼育され、時には急速に蔓延する害虫に対して追加の抗生物質が投与される。動物由来感染症は、動物から人間に感染する。鳥の移動と放し飼いの養鶏場も、感染拡大を助長している。このため、好ましくない微生物と新しい殺虫剤との間で絶え間ない競争が繰り広げられている。消毒剤や強力すぎる洗浄剤の使用は、家屋や建物、輸送手段を無菌状態にする。同時に、換気装置や空調によって、常に微生物が「送り込まれ」ている。その結果、「清潔な」現代の大都会の子供たちは、「汚い」昔の農家の子供たちよりも免疫系が弱いことが多い。
そのため、定期的にマスクを着用し、健康的な距離を保つ必要があると主張する人もいる。オフィスや学校の営業時間が変わったり、閉鎖されたりすることがある。これは育児の問題を引き起こす。多くの人は、自宅で仕事をする必要がある。余分なスペースと静けさが必要なため、(自費で)余分なスペースを作らなければならない。日常的に清潔さや衛生面が重視されることで、社会的な距離も物理的にも精神的にも広がる。身の回りの世話がますます重要になると同時に、和気あいあいとした親密さを求める欲求不満も高まっている。家に閉じこもり、肩を組んだり抱き合ったりする相手を求めて外出する。バーやカフェ、劇場やフェスティバルは、個人携帯の電子コビッドパスなどの新しい手段によって制限される。温もりや触れ合いを奪われることが、中心的な関心事となっている。
この無限に連動するトレンドのネットワークが、生産プロセス、消費者行動、日常的な交流にどのような影響を与えるかは、容易に想像できる。しかし、ここでもまた、パンクの脅威や「断続的平衡」が支配している。つまり、ほとんど目立たない、あるいは非常にゆっくりとした変化と、非常に劇的な、あるいは一夜にして起こる変化とが交互にやってくるのである。だから、私たちはその両方と共存することを学ばなければならない。何千ものさまざまな問題に対する国民の認識や世論は、漂流し始めるかもしれない。即興的に監視するには多すぎるし、ますます一般的になりつつある気まぐれなプロセスの一見非論理的な論理を基本的に理解することもない。それが、本書の主題である。
大衆心理学と集団行動社会学
本書の初期の前身は、新しいミレニアムの幕開けの頃に出版された。当時、私たちが依存しているコンピューターシステムの多くが2000年と1900年を正しく区別できなかったため、「ミレニアム」問題が起こりうるという恐怖が起こった。これは、これから述べる主な主張の完璧な例証である。つまり、些細なことが物理的、技術的、社会的、心理的な多くのプロセスに劇的な変化をもたらす可能性があるということである。この観察は、(原理的には)ほとんどあらゆるものの「管理可能性」についての一般的な考え方とは一致しない。
「コントロールの喪失」が常に重要視されてきた分野のひとつに、「大衆」心理学と「集団行動」社会学がある。しかし、この分野の地位は不確かなものであり、本書はある意味でこの分野を刺激する試みである。気絶しそうな人がいたら、その人を揺さぶって意識を完全に呼び戻すことができるだろう。場を徹底的にかき混ぜることによって、場をシフトさせ、広げ、深めようとするのである。
大衆心理学と集団行動社会学の研究は、主に群衆、とりわけ暴動やパニックといった群衆の脱線に関わるものであった。第二に、その程度は低いが、新興の社会運動、とりわけ社会運動の行き過ぎ、たとえば分裂集団やセクトも含まれる。第三に、そして最後に、ファッションや流行など、世論の流れや大衆の気分の移り変わりの他の側面が研究される。本書はその優先順位を逆転させている。本書は主に、世論における急速で急進的で大規模なシフトについて、そして人々やグループ、製品や問題に対する大衆の認識について書かれている。
双子の分野の広がりは、順に次のようなことを伴う。大衆心理学と集団行動社会学はとりわけ、社会的・政治的文脈の中でこれらすべての現象を研究する傾向があった。双子の学問分野の最後の本格的な復活は、1960年代の不安への反動として、1970年代に起こった。しかし、1980年代から1990年代にかけては、経済学やコミュニケーションなど、他の研究テーマが前面に出てきた。パブリック・リレーションズ関係者は自信満々に、情報と知覚の管理、ニュースと問題の管理を宣言した。しかし、このマネジメントは見かけほど簡単ではないことが判明した。本書はその理由を明らかにし、急速な変化に対応するための新しいアプローチを提案する。
したがって、問題の核心は、これらの現象に対する理解を深める試みにある。大衆心理学や集団行動社会学の理論は、常に一種の場当たり的な性格を持っていた。それらは、「普通の」心理学や社会学がどういうわけか適切に扱うことができなかった、混在する多くの異常な出来事を説明することを意味していた。同様に、説明もどこかごった煮のようなもので、これらの奇妙な出来事にある程度の光を当てることはできたが、現実と変化のより広範な組織原理に対する包括的な見解を欠いていることが多かった。本書は、ここ数十年の新たな展開である、いわゆる「カオスと複雑性」理論との連携を示唆することで、この点を解決しようとしている。
カオスと複雑性の理論は自然科学に由来するが、人間や社会の科学にとっても大きな可能性を秘めている。この新しい理論的概念を様々な問題分野に応用する試みはすでに散見されるが、それはまだかなり難解なものである。書籍の多くは会議発表の論文を集めたものであり、多くの場合、極めて抽象的な表現で、ごく一部の研究者向けに書かれている(ヴァラッハー&ノヴァク、ロバートソン&コムズ、キール&エリオット、イヴ・ホースフォール&リーなどを参照)。私が知る限り、適切で、明確に定義された、興味深い1つの分野にとって、これらの発展がどのような意味を持ちうるのかを、平易な英語で、魅力的な形式で綴ろうとする1人の著者による本は、今のところほとんどない。大衆心理学と集団行動社会学は、そのような適切な分野を形成している。
これらすべての考察の結果、本書はややハイブリッドな形式をとり、さまざまな読者に対応することになった。何よりもまず、本書は学術的な水準に達しているが、不必要な専門用語や説明不足の抽象的な表現を排除している。大学レベルや高等教育で人間と社会を科学する学生は、本書をうまく活用できるはずである。第二に、本書はオピニオンやコミュニケーション分野の専門家にも語りかける。彼らには、自分たちの商売が何を成し得、何を成し得ないのかについて、新たな刺激的な理解を与えるに違いない。第三に、そして最後に、より多くの教養ある読者にとって、本書が親しみやすく、興味深いものになるよう、全体を通して心がけている。私は以前、科学ジャーナリズムや科学情報の仕事に携わっていたため、複雑なことをわかりやすく説明したいという野心を持つようになった。高邁な思想家の中には、私が時折これをやりすぎていると感じる人もいるかもしれないが、それはそれでよい。
本書の常軌を逸した形態と内容は、前述したような考慮事項が組み合わさった結果である。多かれ少なかれ、1冊で3部作という形に進化している。最初の本では、地球温暖化やコビッドなどに関連する世論や認識の変化について、最近の劇的な事例を 「分厚く」記述している。これらの事例が最も読みやすい。2冊目は、現在の心理学や社会学の観点から、このような現象に関連する説明を概観するもので、ある意味、これが、「骨格」である。しかし3冊目は、これを急速なシフトに関する新しいメタ理論と結びつけようとしている。できるだけ具体的になるよう努力はしたが、これはやや抽象的である。この3冊を1冊ずつ順番に並べることもできたが、それでは読み物として魅力に欠けるし、啓発的でもない。そこで私は、3つのレベルのストーリーを1つに編むことにした。どの章も事例の説明から始まり、問題となっている現象の最新の分析、そして新しいメタ理論との暫定的な関連性へと続く。
この3つの要素をもう一度簡単に確認しておこう。すべての章は、精緻な事例説明を提供するセクションから始まる。これはマネジメントやマーケティングのハンドブックでは珍しいことではなく、集団行動に関する有名な教科書(ターナー&キリアンの3版など)でも行われているが、他の学術書ではやや珍しい。私は、通常よりもさらに長い、入念な事例説明を自分に許した。本書は顕著な詳細と複雑さをテーマにしているため、単なる初歩的な分析的プロファイルに基づいて、事例を必要最低限にまで減らすべきではない。それではあまりにもお粗末である。これらはしばしば謎めいた現象であり、次のレイヤーに進む前に、徹底的な「感覚」を養うのが良いのである。
もうひとつ、形に関連した理由もある。各章の後半は、やや抽象的な推論に逸脱する必要があることが多い。その前に、非常に具体的なイメージを持たせるのがよい。事例の説明は、一種の 「前菜」として機能すべきである。これらの魅力的なストーリーは、少し皮肉めいたタッチで、読者に根底にある。「なぜ、どのように」という好奇心を抱かせるはずだ。事例を選ぶにあたって、私はさらに、既存の文献にあるあまりにも馴染み深い事例集を無視し、海外の若い読者に向けて、より新しく、より生き生きとした、わかりやすい年代の事例を探すことにした。(古い事例については、海外のアメリカのインターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙/ニューヨーク・タイムズ紙、フランスのル・モンド紙、オランダのNRCハンデルスブラッド紙などの記録紙からの私自身の膨大なクリッピング・アーカイブや、限られた数の単行本に基づいている)。
各章の第2節では、これらの事例を出発点としながらも、同様の現象のより広範なカテゴリーに挿入し、その理由と方法については、すでに立派な文献が存在する。本書では、主要なアプローチを概観することを試みたが、本書の中心であるダイナミックでオープンエンドな説明、つまり、これらの現象を比較的自然発生的で自己構造的なものとみなすアプローチを明らかに優先した。つまり、これらの現象を比較的自然発生的で自己構造的なものとみなすアプローチである。それどころか、何度も繰り返される多くの傾向がある。しかし、人が考えたくなるような、容易に測定可能で、予測可能で、制御可能なものではない。それらは非常に不規則な現象であり、あらゆる種類の驚くべき紆余曲折をたどる可能性がある。
しかし、この章を 「三つ編み構造」にした最も重要な理由は、カオスと複雑性に関する新しい包括的なメタ理論の性質にある。問題は、これらの理論の多くが元来非常に抽象的なものであり、我々が最も慣れ親しんでいる科学的反射神経とは相容れないということである。そのため、2つの選択を迫られた。一般的な紹介の後、これらの理論を、難易度を上げながら11段階ほどの小さなステップを踏んで紹介し、より理解しやすくする必要があった。また、これらのメタ原理を、他分野の具体的でわかりやすい例で示すことで、私たちの日常的な経験に根付かせ、最も一般的な「常識」が日常的な環境の明白な側面を見落としていることが多いことを示す必要があった。
本書の過程で、こうした代替的なプロセスが、大衆心理学や集団行動社会学において、世論や大衆認識の急速な変化において、実際に重要な役割を果たしていることが、次第に明らかになっていくことを願っている。もうひとつの疑問は、もちろん、それらが通常の心理学や社会学、経済学、政治学、歴史学、時事問題にもどの程度当てはまるのかということである。特にこの第3部では、多くの領域を自由に行き来している。重要なのは事例そのものではなく、急速な変化に関するある普遍的な原則を示すことなのだ。最終的な証明や揺るぎない。「モデル」で、「まとめる」のではなく、読者のさらなる考察をかき立てることを意図している。
それとは別に、私はこれらの章を3つずつ4つの大きな部分に整理した。第1部では、意見形成とコミュニケーションの最も関連性の高いプロセス、日常会話や伝聞、ゴシップや噂話、都市伝説、都市民話で役割を果たすインフォーマルなコミュニケーションプロセス、メディアの誇大広告で役割を果たすフォーマルなコミュニケーションプロセス、といった出発点を論じている。そして、これら3つの現象は、「複雑適応システム」という新しい概念と、連続的な突然変異やフィードバック・ループといった、そこでの重要なプロセスと結びついている。
すなわち、「目に見える」(物理的に集合した)大衆、「目に見えない」(あるいは物理的に分散した)大衆、そして時折部分的に集合するものの、必ずしも集合する必要はない中間的なカテゴリーの大衆のレベルである。つまり、群衆、オピニオン・カレント、初期の社会運動のレベルである。そして、これらについて典型的なことは、3つの異なるレベルにおける「創発」のメタ原理、すなわち相乗効果、パターン形成、自己組織化と結びついている。ある意味、これが本書の核心であり、問題となっている現象にとっても、呼び起こされたメタ原理にとっても重要である。
パートIIIは、これらすべてをさらに推敲したものである。すなわち、多幸的な気分(流行やファッションの中で優勢)、恐怖的な気分(パニックや恐怖を取り囲む)、敵対的な気分(怒りや抗議を支配する)である。そして、これらを用いて、進化する文脈、臨界しきい値、アトラクターの可能性といった、さらに関連性の高いメタ原理を示す。後者の概念は、こうしたプロセスは測定、予測、制御が難しいかもしれないが、それでも何らかの形で固有のグローバルな論理に従う可能性があるという事実を指している。
第4部 ではさらに結論を導く。それは、金融市場における熱狂と暴落の交互発生である。この文脈で、「相転移」というメタ原理が紹介される。最後に、なぜ技術予測や経済予測、社会予測、世論予測はしばしば大失敗するのかという疑問について考察する。本書の最後に、すべてのメタ原理のメタ原理、すなわち「基本的不確実性」について述べる。なぜ多くの複雑な現象が突然の驚きを伴うのか、そしてこのことが科学と経営(いわゆる情報と認識の管理、ニュースと問題の管理を含む)に何を意味するのかについて、私はもう一度綴る。まとめると、この調査の中心的な問いは次のようなものである。カオスと複雑性という新しい概念は、世論と認識の急速で過激かつ大規模な変化を概念化する代替方法を指し示しているのだろうか?それらは一般的に人間と社会の科学に、特に大衆心理学と集団行動社会学に何を貢献できるのか?
注極端に時間のない読者は、まず第3部を読み飛ばしても構わない。すでに示したように、それは主要なテーマをさらに推敲し洗練させたものであり、全体的な議論は他の部分だけでも十分に追うことができる。第11章は、予測と不確実性の問題に関する概説書として読むこともできる。
第1部 心の震え
地震を予知するのは、愚か者、嘘つき、偽医者だけである。
-チャールズ・リヒター、アメリカの地震学者。(シャーデン、259ページ)
序文では本書の成り立ちを、序論では本書の構成について説明した。本書は第一部と最初の3章からなり、読者に主要な出発点のいくつかを紹介する。まずはアプローチの大枠を説明し、それを徐々に埋めていく。すべての疑問にすぐに答えられるわけではなく、本書と議論がある程度進むまで待たなければならないものもある。このアプローチは、より馴染みのあるものとは異なるため、読者の心に「腑に落ちる」まで、そしてすべての意味合いが明らかになるまでには、ある程度の時間と忍耐が必要かもしれない。
後続の章と同様、最初の3章はすべて3つのセクションで構成されており、具体的なものから抽象的なものまで、議論の3つのレベルを表している。最後の最も抽象的なレベルは、何らかの関連する形而上学的原理である。このパートでは、複雑適応システムという一般的なメタ原理と、連続的突然変異とフィードバックループという、より具体的なメタ原理である。これらは過去にも特定されることがあったが、大雑把なものであった。しかし現在では、物理学、化学、生物学から心理学、社会学、経済学に至るまで、ほとんどすべての分野でこれらが本質的な役割を果たしていることが判明している。本書は、加速度的に変化する問題をさまざまな言葉で説明する際に、それらがどのように役立つかを理解しようとするものである。
したがって、これら3つの章の第2部と中央部では、本書全体の主要な主題のいくつか、すなわち集団的な意見形成、製品やブランド、制度や問題に対する一般大衆の認識の変化、そしてそれらの「感情的色彩」について考察する。続いて、関連するコミュニケーション・プロセスのいくつかを詳しく見ていく。日常会話、伝聞、ゴシップ、噂など、メッセージが常に変化するようなインフォーマルなコミュニケーション・プロセスと、メディアによる宣伝など、(「循環反応」によって)メッセージが盛り上がるようなフォーマルなコミュニケーション・プロセスである。これらのいくつかの基本的な要素によって、さらに話を進めることができる。
1. 複雑適応システム(CAS)としての世論
ある時代の確信は、次の時代の問題である。
-イギリスの歴史家、R.H.トーニー。(グロス、321頁)
優秀な理論の真のテストは、最初間違っていると思われたことが、後に明白であることが示されることである。
-アッサー・リンドベック、ノーベル賞委員会。(Giacalone & Rosenfeld, p. 3)
この第1章の最初のセクションは、ある例外的な人物のケースを探っている。その頑固な子供は、気候変動に関して世界的な「オピニオンリーダー」のような存在になった。なぜこのようなことが起こるのかをよりよく理解するために、第2章ではさらに「世論」という現象について見ていく。世論とは、安定した個人の意見の単なる総和と考えられがちだが、むしろダイナミックな構成として理解した方がいい場合もある。そこで第3部では、新たに発見された「複雑適応システム」(CAS)というメタ原理を掘り下げる。CASの中では、比較的限られた時間枠の中で、個人や些細なことが大規模で急進的なシフトに貢献しうることが判明したのである。
1 ケースその1:スカンジーのアイコンと「グレタ」効果
ピッピ・ロングストッキング(アストリッド・リンドグレーンのスウェーデン児童文学の名作)のように、三つ編みの怒りっぽい女子生徒である。甘いピンクのディズニープリンセスの決まり文句とは正反対だ。彼女が初めて気候変動について耳にしたのは、わずか8歳のときだった。大人が、今のところほとんど対策がとられていないと付け加えると、子どもは落ち込んだ: 長期的に見て、彼女や彼らにどんな未来があるのだろう?
11歳の時、彼女は話すことも食べることも止め、2カ月で10キロ痩せた。しかし、書くことはできた。15歳のとき、大手日刊紙『スヴェンスカ・ダーグブラデット』のエッセイコンテストで優勝した。私は安心したい。人類史上最大の危機にあるとわかっているのに、どうして安心できるのだろう』。
彼女を支持する人もいたが、同年代の人たちはすぐには賛同しなかった。誰もすぐに参加しようとしなかったので、彼女は一人で抗議活動を始めることにした。彼女は、リクスダーグ(国会議事堂)の入り口の横に大きなプラカードを掲げて抗議行動を始めた: Skolstrejk för Klimatet-気候のための学校ストライキ」である。
聞くところによると、この数世紀で最も暑い夏で、熱波や山火事が相次いだという。心配が広がり、選挙が迫っていた。インスタグラムやツイッターに投稿された彼女のニュースは、一夜にして全国に広がり、外国にまで伝わった。そこで翌日、他の人たちも彼女に加わった1。
彼女は演劇一家の出身で、家では長女だった。祖父は有名な演出家で俳優、父も俳優、母はオペラ歌手だった。当初、両親は彼女を少し抑えようとしたが、やがて彼女が「少し特別」であることを認めた。後に有名な『テッド・トークス』シリーズに寄稿した中で、彼女自身がこのことを認めている。私はアスペルガー症候群、OCD(強迫性障害)、選択性緘黙症と診断された。つまり、本当に必要だと思うときだけ話す。「今がその瞬間のひとつです」彼女はアスペルガーであることをハンディキャップとしてではなく、集中力を高めるための超能力としてとらえていた。
スウェーデンの選挙後、彼女は「学校でのストライキ」を金曜日に限定したが、予期せぬ有名人であることも歓迎した。彼女は現在、国内外の主要機関から講演の招待を受けるようになった。2018年12月、ポーランドのカトヴィツェで開催された第24回国連気候サミットで、彼女は「変化を起こすのに小さすぎる人はいない」と述べた2。
しかし彼女はまた、出席した世界の指導者たちは「ありのままを伝えるには成熟していない」とも述べた。2019年1月、彼女はスイスの高級スキーリゾート、ダボスで毎年開催される世界経済フォーラムで、一流の政治家と一流の企業家が集う世界的な会合で、「私たちの家は火の海です!」と語った3。
気候のための「学校ストライキ」というアイデアは、パリ会議の開幕時にすでに提起されていたが、今になって突然火がついた。スウェーデンで、スカンジナビアで、西ヨーロッパで、そして世界で。ベルギーは、オランダ語圏フランダース地方の17歳のアヌナ・ド・ウェバーやフランス語圏ワロン地方の18歳のアデライド・シャルリエのようなスポークスマンを擁する注目すべきケースであることが判明した。彼らは当初、木曜日を「行動日」に選んだ。2019年1月10日に首都で行われた最初のデモには3000人の学生が集まった。1週間後の2回目には12,500人、さらに1週間後の3回目には30,000人が集まった。しかし、このフィーバーは一方で地方都市にも影響を及ぼしていた。大学の学部長たちまでもが参加した。
グレタは行進に参加するためにブリュッセルに向かった。2019年2月21日、彼女はこのテーマについて別の主要な国際イベントで演説し、気候変動対策の倍増を要求した。政権を握る「EU委員会」のユンケル委員長は、最初は寡黙だった。しかしその後、EU予算の4分の1、つまり数千億ユーロをこのような対策に充てると発表した。
動員は広がった。春には125カ国から100万人の学生がデモを行った。秋には400万人、ドイツとイタリアではそれぞれ100万人が参加した。各地で学校ストライキを組織するグループが結成された。「Youth for Climate」、「School strikes 4Climate」、「Fridays for Future FFF」などである。世界的な調整委員会が結成され、グレタも参加した。
彼女はまた、大気汚染への貢献が遅れている「南半球」が最も大きな代償を払うことになると強調した。特に、例えば北アメリカ、中央アメリカ、南アメリカの先住民族がそうだ。一方、株式市場では「先物」、オプション、デリバティブの取引が増えている。彼女は『その未来は売られた。少数の人々が想像を絶する大金を手にすることができるように』。
科学界は遠慮を捨て、公然とどちらかの味方を選んだ。2019年初め、イギリスの229人の学者が、ストライキ参加者を全面的に支持する公開書簡に署名した。ドイツでは700人の科学者が同様の宣言を発表した。その数は急速に増え、オーストリアやスイスを含むドイツ語圏全体から26,000人に達した。グレタが最初にスコルシュトレヒクを訪れてから1年目の日、彼女と同志たちは、ドイツ全大陸で最も影響力のある政治家、ドイツのアンゲラ・メルケル首相と会談した。誰も無関心ではいられなかった。
彼女はまた、ローマでローマ法王と、イギリス、フランス、ヨーロッパの議会で短いスピーチを行った。そんな中でも、彼女は学校での勉強についていけた。しかし2019年の夏、彼女はアメリカ大陸の立て直しにも貢献するため、サバティカル(研究休暇)を取りたいと申し出た。彼女は飛行機で公害を出したくなかったので、8月後半に帆船に乗り込み、横断を試みた4。
一方、彼女は両親に、家族の二酸化炭素排出量を減らすことで、彼女の探求に加わるよう要求した。彼女の国のある有名なオリンピック選手が、「Flygskam」(飛ぶことの恥)というラベルを発表した。彼女は母親に飛行機に乗るのをやめるよう頼み、歌手としてのキャリアを中断せざるを得なくなった。しかし、次第に母親たちは彼女を応援するようになった。
2019年9月18日、ワシントンの関連下院委員会が彼女を招待した。しかし、彼女は数センテンスを話しただけで、代わりに科学的なIPCCによる憂慮すべき特別報告書を提供した。彼女はユニセフで記者会見するため、他の15人の子供たちとともにニューヨークへ向かった。ドイツ、フランス、ブラジル、その他の主要国に対して苦情を申し立てるためだ。彼らは前回のパリ協定の義務を果たしていなかったからだ。
同じ日、彼女は国連行動サミットで演説し、集まった世界の指導者たちの目をまっすぐに見ながら怒りのスピーチをした。
「これはすべて間違っている。私はここにいるべきではない……それなのに、あなた方は皆、私たち若者に希望を求めに来る。よくもそんなことができるものだ!あなたたちは私の夢と子供時代を、空虚な言葉で奪った。それなのに、私は幸運な一人だ……他の人々は苦しんでいる。[他の]人々は死んでいる。生態系全体が崩壊している。大量絶滅が始まろうとしているのに、あなたたちが口にできるのはお金のことだけで、永遠の経済成長というおとぎ話だけだ」
この生意気なスピーチは印象に残った。ハーフの女子高生が国連でこれほど憤慨した口調で話したことは、かつてなかった。
彼女は第25回国連気候サミットに陸路で参加する予定だった。しかし、そのサミットはチリのサンティアゴで開催されることになっていた。そこで急遽、ヨーロッパのマドリードに変更された。ここでも彼女は飛行機で行くことを断念した。しかし、ソーシャルメディアを通じてヨットでの渡航を呼びかけ、オファーを獲得した。その場で彼女は、二酸化炭素濃度はまだ上昇していると言った。(コビッド・パニックとロックダウンの後だけ、一時的に多少下がった)。彼女はロンドンに向かい、権威あるBBCのテレビ番組『カレント・アフェアーズ』で、イギリスの環境問題専門家デービッド・アッテンボローから力強い支持を受けた。
今日、アマゾンのようなインターネット書店の商品ページには、グレタのマニフェスト、伝記、児童書などが、世界の主要言語すべてで並んでいる。多くの小学生や大学生が、彼女の模範について作文や論文を書いた。しかし、知識人たちはまた、ドイツの『Eine philosophische Verortung zwischentischer Begeisterung und Medialer Hysterie』のような尊大な批判も行った。
一方、彼女はグレタ、スコルシュトレヒク、FFFといった言葉の「商標権」を主張せざるを得ないと感じていた。
グレタ・トゥンバーグは、大草原の火種となった最初の火種として徐々に認知されるようになった。米国の大手週刊誌『タイム』は彼女を表紙に起用し、2019年のパーソン・オブ・ザ・イヤー(史上最年少)に選出し、世界で最も影響力のある100人のうちの1人とした。ビジネス誌『フォーブス』は「世界で最もパワフルな女性100人」に彼女を選んだ。数年連続でノーベル平和賞候補となった。
2 世論という現象
よりよく理解するためには、まず世論の働きを詳しく見てみる必要がある。世論とは、個々の意見の静的な総和ではなく、絶えず新しいパターンを生み出し、変化し続ける動的なプロセスである。本節では、いくつかの基本原則を概説するが、それは本書の過程でさらに洗練されていくことになる。
もちろん、最初の疑問は、世論とはいったい何なのかということである。この概念が広く使われるようになるまでに、あるハンドブックでは50以上の異なる定義が確認されている(チャイルズ)。そこで、まず言葉そのものから考えてみよう。まず第一に、世論とは主として意見であり、事実の表明ではない。世論とは、意見が分かれたり、価値判断が分かれたりすることである。
第二に、世論は 「公共」である。それは私的な意見のことではなく、人々が抱いていても自分だけのものである。世論とは、人々が公にし、表明する意見のことである。あるいは、ノエル・ノイマンがかつて言ったように、世論とは「人間の共同体に結束力を与える社会心理学的プロセス……共同体の価値とそこから派生する行為についての合意が継続的に再確立されるプロセス」(p.98)である。この定義によれば、世論は集団の形成、改革(および解散)における重要なプロセスである。人々は何に共感し、何に属したいと思うのだろうか。また、そうでないものは何なのだろうか?
世論と世論調査
世論という概念には、長くさまざまな歴史がある。それは常にある種の公開討論と関連しており、そこでは多くの自由な市民が発言し、公的な疑問についてある種の共通認識に達するために行われた。ギリシア・ローマ時代や南ヨーロッパでは、市場や広場といった屋外の集会場(フォーラム)に関連することが多かった。啓蒙時代、北ヨーロッパでは、イギリスの大都市のコーヒーハウス、フランスのサロン、ドイツ語圏のティシュゲゼルシャフテンなど、新しい屋内集会場と関係することが多かった。こうした比較的開放的な環境の中で、新しいグループ、新しい願望、新しい考え方が前面に出てきた。たとえば、絶対君主の権限のさらなる制限や、人民主権と「一般意志」を代表すると主張する、熟議議会や議会における人民代表の権限の拡大に関するものであった。
しかし、18世紀後半から19世紀初頭にかけてのこのような世論は、依然として 「エリートの意見」であった。限られた上流階級だけが、十分な情報を持ち、理性的な判断ができ、それゆえに投票権を持つとされていた。真の意味での「大衆の意見」が生まれたのは、19世紀末のことである。大衆紙が台頭し、現在進行中の論争に参加する一般大衆の割合がますます大きくなっていった。労働者や女性は選挙権を主張した。世論が近代的な性質を獲得したのは、この数十年間のことであり、現在の意見や大衆の気分が新しい形で発見されたのは、たとえばフランスでは悪名高いドレフュス事件がきっかけだった。
世論の診断と予測(例えば、選挙地理学の改良的研究を通じて)、そして選挙そのものを越えてこの地理学を理解し、改良し続ける手法に突然関心が向けられるようになったのも、このような広範な背景があったからである。社会調査の枠組みの中で発展した初期の手法もある。これらの調査は、貧困層や庶民の健康状態や生活状況についての広範な調査であった。これらは通常、改革の必要性を示し、不安の脅威を食い止めるために、公人によって始められた(歴史的概要については、Bulmer, Bales, & Sklarを参照)。また、政策決定の枠組みの中で、全人口を対象とした定期的な国勢調査が広く行われるようになった。
マーケティングとメディア調査における革新も重要であることが証明された。1920年代後半にアメリカで全国的な商業ラジオ・ネットワークが出現したとき、到達した聴衆を推定し、広告主率を確立できるようにするためには、サンプリング技術をさらに改良する必要があった。大恐慌が始まり、政治的動乱の脅威にさらされると、選挙予測がこれまで以上に重要になった(歴史的概要については、コンバースを参照)。1936年の選挙前夜、ついにジョージ・ギャラップらが、限られた「代表的」サンプルのみにインタビューを行って、初めて結果を確信をもって予測することができた。これによって世論調査の基本原則が確立された。第二次世界大戦の直前、戦中、戦後と、この手法はさらに西欧諸国の他の地域にも広がっていった。世論調査(および関連技法であるメディア調査、広告調査、市場調査、人事調査)は、まず第一に非常に実用的である。その出発点は、対面、電話、書面、あるいはコンピューターによって人々にインタビューを行うことである。問題は、もちろん、人々は常に自分が何を望んでいるのか、何を言いたいのかを知っているとは限らないということである。第二の原則は、一定の構造と一定の形式をもった質問票を使用することである。問題は、構造が少し違ったり、形式が少し違ったりすると、インタビュー対象者がまったく異なる回答をする可能性があることである。
第三の原則は、強度の昇順または降順で、多肢選択式の「閉じた」回答カテゴリーを使用することである。問題なのは、これによってインタビュアー、研究者、あるいはスポンサーの精神的枠組みに、必ずしも彼ら自身の精神的枠組みではないものを押し込んでしまうことである。第4の原則は、代表的なサンプルを使用することである。これの問題点は、サンプルは定義上、平均的で当たり障りのない。「即席の画像」しか提供しないということである。
第五の原則は、統計的手法の助けを借りて、結果を平均値、パーセンテージ、スコア、その他の明確な結果に凝縮することである。問題は、これが単純さを生み出し、複雑さを殺してしまうことだ。まとめると、統計的手法は特定の基本的なデータを収集するのに非常に有用な手法であるが、その日常的な使用はしばしばその限界を無視する。他の手法(綿密なインタビューからグループ考察まで、専門家インタビューから合意形成まで)を加えても、基本的な枠組みが得られないことがある。主な問題は2つある。一方では、この手法では、世論の全体像が部分の総和を超えるような構成になる余地がほとんどない。もう一方は、加速するシフトと減速するシフトが交互に起こるような、不均等な変化の可能性を考慮する余地がほとんどないことである。アメリカの社会学者チャールズ・クーリーはすでに、世論とは「個別の判断の単なる集合体ではなく、組織であり、コミュニケーションと相互影響の協力的な産物である」と述べている(Fraser & Gaskell, p.80より引用)。アラン・バートンはさらに率直にこう言っている:
個人を無作為にサンプリングする調査は、社会学的な肉砕き機であり、個人をその社会的文脈から引き離し、調査対象者の誰も他の誰とも相互作用しないことを保証する。それは、生物学者が実験動物をハンバーガーマシンにかけ、顕微鏡で100個1個の細胞を観察するようなものである。(ロジャース、120ページ)。
ある人の信念体系をその人の信念の総体として解釈するのではなく、また世論を世論の総体として解釈するのではなく、私たちは構造と機能、凹凸の要素、そして違いを生み出すあらゆる違いを探すべきなのだ。誰かの表明した意見の裏側には何があり、何が影で何が光なのか。表現された意見は、本当に深い感情や行動と一致しているのだろうか?人は自分の意見にどれほど強く執着しているのだろうか?どのような状況下で、このパターンが変化し始めるのだろうか?ある人は簡単に、そして誰によって説得されるのか?その人は他人を簡単に説得できるのだろうか?集団の意見が徐々にある方向へ、あるいは別の方向へ流れていく可能性はどのようなものだろうか?どのような要因が関係するのか?利害関係者は他者を説得するのにどの程度効果的か。彼らはどのような反応を引き起こすのだろうか?このような問いの重要性は、初期の頃から(ターナー&キリアン、189-192頁参照)、最近に至るまで(フレイザー&ガスケル、84-87頁、プライス、59-68頁参照)、多くの研究者によって認識されてきた。問題なのは、そのような方向で多くの試みがなされてきたにもかかわらず、そのような疑問が、学者の幅広いコンセンサスによって受け入れられる新しい研究方法にごく部分的にしか変換されていないことである。もう一つの理由は、多くの人が研究方法は客観的であるべき、あるいは「ダム」(技術やコンピューターが答えを出すべきであり、研究者のスキルはその役割を果たすべきでない)であるべきだと感じているからである。しかし、研究とはそういうものであり、経験豊富な調査員による個人的な解釈と戦略的な分析が、研究の多くの段階で不可欠なのである。
これはもちろん、すべての心理社会科学の重要なパラドックスである。なぜなら、心理社会科学は明確な事実を立証するだけでなく、意味の帰属にも関わるからである。なぜなら、心理社会科学は明確な事実を立証するだけでなく、意味の帰属にも関わるからである。意味とは定義上、複雑で、重層的で、矛盾してさえいるものである。さらに、インタビュアー、リサーチャー、スポンサーはこのゲームのプレイヤーであり、他の人よりも特定の解釈を受け入れる傾向がある。つまり心理社会科学とは、意味のある関係を理解することでもあるのだ。解釈の必要性と必然性を否定する者は誰でも、粗野で明白な誤った解釈の犠牲者に最初になるであろう。
問題の盛衰
文化や世論を複雑な適応システム、あるいはシステムのシステムとして見ることもできる。なぜなら、文化はサブカルチャーのダイナミックな構成であり、世論はパブリックのダイナミックな構成だからである。個人の意見だけでなく、集団の意見も刻一刻と変化するかもしれない。報道される出来事がすべてそうかもしれない。世論は静的なものではなく、動的なものである。それは風景の中を流れる小川のようなものであり、むしろその表面にあるカモガヤや塵や油のようなもので、常に新しく進化するパターンを形成している。
公共とは、実際には 「公共」の集合体なのだ。何人かの著者がこのことを指摘している。例えば、ターナーとキリアンの説明は私にぴったりだ。彼らは、「公共とは、ある問題に関心を持ち、その問題に関して分裂している人々の分散した集団であり、ある集団や個人の行動指針に影響を与えると予想される集団的意見を登録することを目的として、その問題についての議論に従事している」(179ページ)と述べている。したがって、私たちは、関係する問題との関連において、大衆を最もよく区別することができるだろう。
では、イシューとは何だろうか。同じターナー&キリアンによれば、イシューとは「人々が意見の相違に同意する点からなる」(p.182)。つまり、人々が最初から同意している点は除外される。それらは問題化されることはなく、単なる背景として認識され、当然のこととされる。しかし、人々が徹底的に意見を異にし、有意義な議論が排除されるような論点もまた排除される。問題とは、日常的な議論や社会的相互作用の糧となる論争のことである。
つまり、たとえば公民権や妊娠中絶など、かなりの二極化につながる論争は、1つの発展パターンを形成するというよりも、2つの発展パターンを形成し、それらが密接に絡み合っている。この2つのパターンは互いに密接に関連している。それはまるで、混じり合わない2つの液体の間を動く分水嶺のようだ。あるいはタンゴのように、一方のパートナーが一歩前進すれば、もう一方のパートナーは一歩後退する。しかし、彼らは互いに反発し合うのではなく、互いに協力し合って踊っているのだ。
ターナー&キリアンは、「孤立した」問題などほとんどないことを付け加えている。
一般大衆がある問題について分裂していると言うのは、単純化しすぎである。むしろ大衆は、大衆が共に属すると考える問題のマトリックスについて、しばしば組織化されている。問題の階層が明確に定義されている場合もあれば、人々が何を決定すべきなのかはっきりしない場合もある。(p. 192)
ここ数十年で大きな注目を集めるようになった環境問題を考えてみよう(そしてそれは、本書を通じてさまざまな形で再び登場する)。それは、多くのサブイシューを持つスーパーイシュー、イシューのマトリックスあるいはヒエラルキーと見なすことができる。
つまり、世論には時空間的なパターンが多数存在するのだ。パターンが出現し、広がり、変化し、消滅し、再び現れる。このサイクルは通常、既存のパターンが無関係になるか、その支配力を失うことから始まる。これは一時的なバランスを失い、エントロピー、カオス、構造の喪失へと進む傾向である。続いて、他の新たなパターンがより適切なものとなり、そのグリップを強める。これは、新たな一時的バランスを確立し、ネゲントロピー、新たな秩序、構造の増加へと進む傾向である。この文脈でクラップは、一種の情報的呼吸が起こることを最も適切に示唆している。つまり、新しい情報に対する「開放」と「遮断」が交互に繰り返され、干満のような自然なリズムが生まれるのである。
もちろん、あらゆる利害関係者がこうしたプロセスに影響を与えようとする。特定の問題を公的な議題とし、他の問題を公的な議題から外そうとする。キーワードやイメージ、出来事などを通じて、公共の問題が定義されるフレームやグリッドを変えようとするのだ。個人にはアジェンダがあり、会議にはアジェンダがあり、メディアと大衆にはアジェンダがある。アジェンダは、注意を払うべきテーマを特定し、どのような優先順位で扱うかを示す。拙著『グローバル・ニュースを理解する』(第5章)では、大衆のアジェンダがいかにメディアのアジェンダによって、またメディアのアジェンダがいかに組織的エリートによって組み立てられているかを示した。世論をめぐる争いは、自分が大衆に何を考えさせたいかということよりも、大衆に何について考えさせたいかということにある。それに対して決定的な影響力を持つ者は、すでに戦いに半分勝利しているのである。
エリザベス・ノエル=ノイマンは著書『沈黙の螺旋』の中で、世論の進化には自己強化過程が重要な役割を果たしていることを示した。男性は社会的動物であり、排除と孤立を恐れる。もし、自分たちの意見に根拠がなくなってきているという印象を持てば、この点に関して自分たちの意見をあまり強く表明しなくなる。それとは対照的に、自分の意見が優勢になりつつあるという印象を持てば、ますます力強く自己表現するようになり、前者の意見はほとんど消え去り、後者の意見が受け入れられるようになる。このようなプロセスをたどる1つの方法は、自分がどう思うかだけでなく、他の多くの人がどう思うかも尋ねることである。そうすることで、帰属の誤りが浮き彫りになり、それが「ドリフト」の兆候となることもある。このようなプロセスについては、後ほど詳しく説明する。
問題の発生と消滅は、多かれ少なかれ自然発生的な社会的プロセスであり、この文脈で問題への注目のサイクルを語る人もいる。アンソニー・ダウンズは、アメリカについて5つの段階を挙げているが、これは他の国にも当てはまるかもしれない。まず「問題前」の段階である。これは、何らかの望ましくない社会的状況が存在するものの、まだ世間の注目をあまり集めていない場合に優先する。(実際、ダウンズによれば、その状況は通常、最終的に認識されたときよりも、まだ無視されていたときのほうが悪化していた)。
第二に、あらゆる問題は解決できるという主張から生じる、驚くべき発見と陶酔に満ちた熱狂の段階である。第三に、著しい進歩の代償を認識することで、当初の熱狂に歯止めがかかる。第四に、人々の強い関心が徐々に薄れていくことである。最後に、「ポスト問題」の段階がある。あまり注目されなくなったり、散発的に再発したりする黄昏の領域である。
この後者の文脈で、イシュー・ファティーグという言葉が提唱されている。新しい大きな問題がマスメディアや世論に登場し、一時的に画面全体を埋め尽くしたとしても、それがまた簡単に消え去り、いつの日か忘れ去られるかもしれないとは想像しがたい。しかし、定期的な更新がなければ、このような事態は避けられない。厳密に言えば、これは人々がその問題をもはや重要ではないと判断したからではない。しかし、人々が突然、他のもっと新しい問題の方が重要だと感じるからである。
現在に生きている私たちは、未来は空白である(そしてこれからも空白であり続ける)、あるいはすでに進行していることの単なる延長である、という暗黙の考えを持つことがあまりにも多い。これは目の錯覚である(これについては最終章で詳しく述べる)。常に予期せぬ驚くべき新しい問題が発生し、既存の問題を段階的に解決し、それによって力場が完全に再編成される。そのため、大きなイメージの危機が発生すると、広報コンサルタントはしばしばクライアントに、嵐は必然的に吹き飛ぶから、しばらくの間「おとなしくしている」ようアドバイスする。残念なことに、その逆もまた真である。誰かや何かが一度物議を醸したときはいつでも、その炎を復活させるのに必要な燃料はごくわずかなのである。
問題の感情的色付け
世論に関する既存の文献は、合理性と明晰な熟慮に重きを置いている。この文献は啓蒙主義の産物であり、民主主義の理想と密接に結びついている。これとは対照的に、大衆心理学や集団行動社会学など、世論の急激な変化に関する既存の文献は、感情性や「盲目的」なプロセスに重きを置いている。この文献は主に、リベラルな秩序に対する脅威を想定している。しかし、このような「合理性」と「感情性」の厳格な対立は、典型的な近代西洋の幻想である。
感情を伴わない合理的な行動などほとんど存在しないし、根底に比率を持たない感情的な行動もほとんど存在しない。このテーマについては、後に本書の第三部で、大衆の気分の移り変わりについて触れる。
しかし、この早い段階で、感情、感情的色彩、そして気分の本当の意味について多少掘り下げてみよう。すべての学者が同意しているわけではなく、ハンドブックではいくつかの主要なアプローチを区別している。コーネリアスによるハンドブックは、まず、適応と生存における感情の役割を強調したイギリスの生物学者チャールズ・ダーウィンの長年の伝統を区別した。第二に、アメリカの心理学者ウィリアム・ジェームズの長年の伝統があり、彼は感情の本質を主として身体的反応であると強調した。第三に、コーネリアスは、感情を状況の「生の評価」と見なす、より最近の認知主義の伝統を特定した。そして第四に、感情は社会化と文化によって形成されると主張する社会構成主義(ハレも参照)という、より最近の伝統を特定した。
しかし、これらのアプローチには、感情には明確に定義された機能があるなど、いくつかの共通点がある。オートリーとジェンキンスによるハンドブックでは、感情は新しい状況や予期せぬ状況に素早く効率的に対処するための手段であると述べられている。下等動物には感情は必要ない。なぜなら、彼らの世界観は極めて単純だからだ。神の世界観は完璧であるため、神は感情を必要としない。しかし、高次の動物や人間には、一種のヒューリスティックなものとして、つまり新しい状況に対する「おおよそ」適切な対応を促進する手段として、感情が必要なのである。情動は部分的には生得的なものであり、部分的には学習されたものである。
フィッシャーは、感情という心理生理学的概念を、社会認知主義的な 「スクリプト」という概念と結びつけた。フィッシャーによれば、感情の台本には3つの異なる機能があるという。まず第一に、スクリプトは状況に対する生の評価を意味する。第二に、表現の指針となる。そして第三に、行動の結果についての期待を暗示する。こうして感情は、人間機能のさまざまな側面を有意義に結びつける反応パターンの基本的なレパートリーを提供する。一次感情、二次感情、三次感情において、これは必ずしも同じレベルの側面である必要はない。構成には、生理学的側面(自律神経系によって引き起こされるなど)が含まれることもあれば、神経学的側面(覚醒など)、心理学的側面(行動傾向)などが含まれることもある。
認知機能だけに限定すれば、感情はさまざまな機能を活性化したり不活性化したりし、質的に異なる準備状態をもたらす可能性があることがわかる。例えば、選択的暴露がある。恐怖は、そうでなければ簡単に見過ごされてしまうようなわずかな刺激に対する警戒心を高めるかもしれない。選択的知覚がある。恐怖は、あいまいな刺激に対して、ある解釈を他の解釈よりも自動的に選択する(つまり、それを脅威の可能性があるとみなす)。選択的保持もある。恐怖は、関連する特定の記憶を活性化したり、不活性化したりする。また、選択的再生などもある(Oatley & Jenkins; Corneliusも参照)。
本書の第3部では、これらの議論を2つの異なる線に沿って拡張することを提案する。すでに何人かの著者が述べているように、フラッシュ感情だけでなく、長引く気分もまた似たような側面を持っている。それらは質的に異なる基本的な構成を形成し、私たちの心理的機能をある特定の線に沿って促進する。喜びを感じているときと落ち込んでいるときとでは、まったく同じ状況でも反応が異なる。他の著者も述べているように、これは個人の行動だけでなく、時には集団の行動にも当てはまる。これがどのように、そしてなぜそうなるのかは、第2部(集団行動について)で見ていくことにしよう(ロフランドも参照)。
様々な気分は個人の反応に異なる枠組みを与えるだけでなく、社会的相互作用にも異なる枠組みを与えることがわかる(この点についてはシェフのミクロ社会学を参照)。前述のターナーとキリアンは、集団行動に特有の性格を与える3つのプロセスとして、キーノート化、象徴化、調整について語った。この基本パターンは、集団的喜びや集団的悲しみ、集団的恐怖や集団的勇気、集団的憤怒や集団的諦念ではまったく異なることが、第3部でわかるだろう。さらに、些細なことが、このような気分を一つのモードから他のモードへと移行させることもある。しかし、そのようなプロセスをどのように考えるべきなのだろうか?カオス理論や複雑性理論は役に立つのだろうか?
3 複雑な突然変異のメタ原理
グレタ・トゥンバーグがアイコンとして登場したことは、世論の機能を示す一例であった。従来のアプローチでは、世論を動的な構成としてではなく、静的な集合体としてとらえすぎていることを見てきた。次章以降、本書では、世論の急速かつ急進的で大規模な変化に関する代替的な見方を徐々に展開していく。その概要については、自然科学というまったく別の分野でしばらく前から進行している大きなパラダイムシフトを参考にする。
これは、社会的・心理的現象を化学的・物理的現象に還元しようという意味ではない。それどころか、加速変化や非線形変化のメタ原理にまったく異なる光を投げかける、新しいアプローチの拡張ファミリーがすでに存在していることを意味している。これはいわゆるパラダイムシフトであり、最終的にはすべての学問分野に影響を及ぼす可能性がある。パラダイムとは、ギリシャ語で原始的な言葉、例、モデルを意味する。トーマス・クーンは、その影響力のある著書『科学革命の構造』の中で、この言葉をさらに科学社会学に導入した。彼は、科学者、特にある学問分野や学派に属する科学者は、しばしば限られた模範やモデルによって導かれると指摘した。
このように、パラダイムは「通常の」科学を形成するのに役立っている。しかし時折、予想とは異なる異常事態が発生する。最初の反応は、それが確認され、再確認され、何度も再確認されるまで、できる限り無視することである。しかし、そのようなことが続くと、既存の前提が疑わしくなり、危機的状況に追い込まれることさえある。少数派の学者は、別の説明を考えようとする。その分野の既得権益者との度重なる戦いの後、最終的には新しい見解が優勢となり、新たなコンセンサスが確立されるかもしれない。こうして新しい論争が始まり、古い論争が終結し、科学は進歩していく。
一世代ごとに新しいパラダイムが生まれ、それが学問分野に革命をもたらすこともある。数世代に一度、新しいメタパラダイムが登場し、様々な学問分野に一挙に革命をもたらすこともある。20世紀前半、相対性理論と量子論が物理世界の理解を揺るがし始めた。20世紀後半には、開放系と複雑系の理論が同様の役割を果たした。これらは自然科学に次々と影響を与える革命をもたらし、人間や社会の科学にも影響を与え始めている。メタパラダイム・シフトは、これまで理解することが困難であった、一見気まぐれに見える多くのプロセスに、まったく異なる光を投げかける。しかし、それはまた、現実と変化の本質に異なる光を投げかけている(カプラ)。
このシフト全体の歴史は、ジェームズ・グリークの『カオス』、ミッチェル・ウォルドロップの『複雑性』、ロジャー・ルウィンの『複雑性』など、さまざまな優れた本によく書かれている。しかし時折、ジョン・ホーガンが最近書いた現代科学の地平線の旅と同じように、やや民族中心主義的な傾向が見られる。つまり、このような英米の概説書には、北西部の貢献を過度に強調し、南方(ラテン語など)や東方(スラブ語など)の貢献(アジアのものは言うまでもない)を軽視することによって、主要な出典である米国や英国のやや自己中心的な視点を採用する論理的傾向が時折見られるのである。例えば、マトゥラーナやヴァレラのような先駆者がこの種の文献にほとんど登場しないことや、プリゴジンのような先駆者を最初はやや軽んじる扱いをしていることが挙げられる。もちろん、フランスやロシアの科学史にも、似たような、しかし逆の傾向が見られる。
これらすべては、メタパラダイム・シフト全体の重大な意義を変えるものではない。還元主義や要素主義、決定論、そして染み付いた因果関係の概念さえも、かなりの根拠を失った。文脈主義と全体主義、不確実性、偶発性はあらゆる面で前進した。世界中で数多くの学者がその役割を果たしてきた。しばしば強い抵抗にあった。経済学者のブライアン・アーサーが初めて主要な論文を同僚に見せたとき、彼女はこう言った。そして実際にそうなった。その先駆的な論文は、主要な査読付きジャーナルからすべて拒否された。書き直され、また拒否され、6年続いた。「私の髪が白髪になったのはその時です」と彼は言った(Waldrop, p.48)。彼が同世代の中で最も独創的な思想家の一人として認められるようになったのは、後になってからのことである。
それでも、多くの学者が重要な疑問について意見を異にし続けている。それと同時に、彼らは相互に関連し合う何十もの概念からなるまったく新しい枠組みを生み出し、現実と変化についてまったく新しい見方を提供してくれた。カオスと秩序、複雑さと単純さ、創発と自己組織化、その他多くの概念である。サリー・ゲルナー(『ロバートソンとコムズ』所収)は、科学革命はより広範なシフトの中に組み込まれていると述べている。「つまり、非常に限られた数の自由度(実体、変数、相互作用)を持つシステムに焦点を当てることから、非常に多くの自由度を持つシステムに焦点を当てることである。
ニュートンのリンゴとローレンツの蝶
人間と社会に関する西洋の近代科学は、その一般的な哲学と同様、150年以上の歴史がある。このことは、意見やコミュニケーションに関する私たちの考え方にも当てはまる。人間と社会に関する科学のメタ・パラダイムは、自然科学のメタ・パラダイムから派生したものであり、そのメタ・パラダイムは、卓越した。「パラダイム学問」である機械学と、300年前のニュートンの創始テキストから派生したものである。ニュートンが重力と自然の法則を「発見」したのは、彼の頭の上にリンゴが落ちたときだったという話は、誰もが知っている。このように、社会科学と自然科学の伝統的なメタ・パラダイムは、「ニュートンのリンゴ」と表現することができる。しかし、ここ数十年の間に、このリンゴは、「ローレンツの蝶」という対照的な新しいメタパラダイムによって、徐々にかじられ、食い荒らされてきた。
他の多くの偉大な先駆者たちと同様、ニュートン自身も自分の見解には限界があることを十分認識していたが、彼の後継者や追随者たちは最終的に単純化されたバージョンを進化させ、それを広く普及させた。この単純化されたバージョンによれば、宇宙は物体の集まりと自然のいくつかの力に過ぎない。複雑な物体はいくつかの素朴な構成要素からなり、全体は部分の総和に過ぎない。これらすべてのものは、暗黙のうちに、明確な物質と形状、質と量を持つと考えられている。変化は直線的で、原因は結果に比例する。相互作用は明確であり、測定、予測、制御が可能である。それは鳩時計の世界であり、機械の世界であり、工場の世界であり、原始工業時代の世界である。
力学の次に、19世紀初頭にはもうひとつのパラダイムとなる学問分野、熱力学が生まれた。熱力学の第一法則であるエネルギー保存の法則は、エネルギーはある形態(機械的、化学的、熱的、電気的)から別の形態に変化することはあっても、創造したり破壊したりすることはできないとした。熱力学第二法則のあるバージョンでは、このような変化によってエネルギーが解放される場合、エネルギーは高いところから低いところへ、熱いところから冷たいところへ、といった具合に流れていくとされていた。したがって最終的には、エネルギーはより均等に広がるようになる。その結果、エントロピー、すなわちカオスと構造の喪失は絶えず地歩を固め、一方、ネゲントロピー、すなわち秩序と構造は地歩を失うことになる。こうして、宇宙、太陽系、地球、生命、そして人類は、最終的には衰退していくのである。
物理学に次いで、化学、生化学、生物学などの学問分野が発展し、ダーウィンの進化論も含まれるようになった。不思議なのは、これらの学問が実際には正反対の方向を向いていたことである。学問はそれぞれのパラダイムに従い、学問間の相互作用は少なくなった。ニュートンの力学と熱力学は死んだ物質を扱い、ダーウィンの進化論と生物学は生物を扱った。しかし進化論は、秩序が減少し、構造が失われ、エントロピーが増大するのではなく、むしろ秩序が増大し、構造が獲得され、負のエントロピーが増大することを示した。少なくとも、秩序が減少する海の中に、秩序が増加する「島」があるのだ。どういうわけか、変化は常にあるようには見えなかった。この秩序と混沌という重要な謎は、ここ数十年の間に、主に気象学や化学などの他の学問分野で徐々に解明されてきた。気象学では、コンピュータの助けを借りて天気予報を改善しようという最初の試みが行われた。アメリカの気象学者エドワード・ローレンツは、北半球の気象パターンを予測するモデルを開発した。彼は格子状の点を作り、さまざまなパラメータ(気温、湿度、日照、風など)の値を小数で仮定し、気象パターンがどのように変化するかをシミュレートしようとした。ローレンツは、コーヒーがこぼれるような些細な事故が起こるまでは、むしろうまくいっていた。ローレンツは同じデータをもう一度入力することを余儀なくされた。しかし、驚いたことに、2回目の予測は1回目の予測とは根本的に違っていた。
その時初めて、彼は苛立ちと焦りから、小数点以下の数字を1桁か数桁減らしてしまったことに気づいた。このような微細な変更が、根本的に異なる予測結果をもたらしたのである。最初の科学論文の中で、彼はこれを、ある場所でのカモメの羽ばたきが、最終的には遠く離れた別の場所で嵐を引き起こすのに役立つことに例えた。このイメージは、瞬く間に広まった。さらに後の講演で、彼は興味深い質問を付け加えた: ブラジルの蝶の羽ばたきは、テキサスの竜巻を引き起こすことができるのか?
答えはイエスだった。というのも、蝶の羽ばたきによって、システム全体がある気象パターンや固有の論理から別の論理へと転換される可能性があるからだ。(このいわゆるアトラクターについては第9章で触れる)。ローレンツの後者の講演は、アメリカ科学振興協会の年次総会で行われた。その間に同僚が「カオス理論」という名前を提案し、そのレッテルが定着した。このような些細なことが劇的な結果をもたらすという観察は、一見ニュートン的ではない普遍的な原理の発見につながった。
もうひとつのブレークスルーは化学からもたらされた。1970年代末、ロシアのベルギー人イリヤ・プリゴジンが散逸に関する研究でノーベル賞を受賞した。彼の著書『La Nouvelle Alliance』(イザベル・ステンガーズとの共著)はもともとフランス語で書かれ、多くの言語に翻訳されたが、英語では1980年代半ばに『Order Out of Chaos』として出版された。この本は、前述の熱力学第二法則の標準的な解釈に、エントロピーすなわちカオスの漸増とネゲントロピーすなわち秩序の漸減という2つの重要な見解を加えたものである。プリゴギンによれば、まず第一に、人々はしばしば閉鎖系と開放系の区別を見失う。そして第二に、平衡に近い系と、平衡から遠く離れた系を正しく区別しなかった。
後者の場合、2つのことが起こった。ひとつは、システム内の既存の秩序が完全に消失したことである。しかし他方では、こうした散逸のプロセス自体が、新たな散逸構造を生み出す傾向があった。その理由は、プロセスをより効率的に展開させるために、自ら合理化する傾向があったからだ。バケツの水をシンクに流すと、自然に渦が発生する。他の人たち(R.スウェンソンなど、ロバートソン&コムズ18頁でゲルナーが引用している)は、後にこれをMEP原理(最大エントロピー生成の原理)と呼んだ。つまり、カオスに向かうプロセスそのものが、(一時的な新しい)秩序に向かう反対のプロセスを引き起こすというパラドックスであった。重要な点は、旧秩序と新秩序の間には正確な決定論的関係はなく、無限に小さな細部が移行に寄与していることである。
これは大きなブレークスルーであり、他にも大きな影響を及ぼした。例えば、第7章で再び触れる「時間」の概念についてである。技術革新の第三の波という概念を発明した未来学者アルビン・トフラーは、プリゴジンとステンガーズによるこの本の英語版改訂版に熱狂的な序文を寄せている。彼は、工業的、機械主義的、制御志向の社会から、ポスト工業的、情報志向の進化する社会へのシフトを象徴するものだと呼んだ。彼ら自身は、古いパラダイムの異常は長い間誰の目にも明らかであったが、科学者たちは当時の文化的・イデオロギー的背景の中でそれを無視してきたと付け加えた。後述するように、この新しい考え方は、測定、予測、制御といった重要な科学的主張に対して重要な結果をもたらした。
ノワックとルーウェンシュタインは、(ヴァラッハーとノワックの著書『社会心理学における力学系』への寄稿で)この点を再び強調した。
初期条件に対する感受性は、カオスシステムの振る舞いを長い時間スパンで予測できないことを意味する。形式的には、系の振る舞いが微分方程式や差分方程式によって完全に決定されるという意味で、系の進化は決定論的である。しかし実際には、システムの状態を時間的に予測することはできない。その理由の一つは、初期データを無限の精度で知ることができないからである。われわれの知識は常に、丸め誤差や不確実性を含んでいる。これらの不正確さはすべて力学によって増幅される。第二の理由は、力学のわずかで一瞬の摂動でさえも、時間が経てば恣意的に大きな影響を引き起こすからである。(p. 31)
前述の気象学者、エドワード・ローレンツのバタフライ効果を思い浮かべると、微細な変化が大きな変化を引き起こす可能性があることがわかる。同じ原理が、世論や大衆の認識の進化にも基本的に当てはまることは、後述する。
CASの聖なる信仰
プリゴジンの散逸構造理論は、もう一つの主要なテーマである、自然や社会における複雑適応系(CAS)の進化への重要な架け橋を形成している。CASについて考える世界的な科学的中心地であり学際的な出会いの場は、ニューメキシコ州サンタフェにある。ミッチェル・ウォルドロップは、この正確な場所を取り巻く興味深い要素が混在していることを指摘した。
複雑系理論の新しいアテネ、あるいは新しいオリンポスは、かつて質素な修道院の中にあった。サンタフェはスペイン語で、「聖なる信仰」を意味する。もともとこの地名は、自然の守護聖人である聖フランシスコの命令によって付けられたものだった。リオ・グランデ川はさらに南に流れ、周囲を乾燥地帯に囲まれている。さらに西には壮大なロッキー山脈がある。この街は、混沌と秩序が織りなす息を呑むような風景の中にある。文化的にも、ニューメキシコはまさに人種のるつぼだ。ニューメキシコはアメリカ合衆国に追加された最後の州のひとつであり、南部の隣国との争いの火種となっている。西のカリフォルニア、東のテキサスと同じように、ここはアングロサクソン系プロテスタントとヒスパニック系カトリックの出会いの場であり、古くからのインディアン部族や 「ニューエイジ」グループも混じっている。
サンタフェに近い主要な研究センターはロスアラモスで、ここで最初の原子爆弾が開発され、先進兵器研究所が存続した。サンタフェ研究所の最初の大きな学際的研究プロジェクトは、世界最大級の銀行であるニューヨークのシティコープのスポンサーだった。1970年代の石油危機は、1980年代に銀行を不用心にさせた。銀行は基本的に、資本が豊かな発展途上国から資金を借り入れ、資本が乏しい発展途上国に融資したが、その条件はますます「ソフト」になっていった。このため、第三世界の国々が相次いで債務不履行に陥り、約3億ドルが失われる危険性があった。全知全能のコンピューターに助けられた世界の金融専門家たちは、このような事態を予測していなかった。
そこでシティコープは、物理学者と経済学者が複雑な適応システムやそこで起こりうる急激な変化について議論するために、サンタフェ研究所で2回のワークショップを開催するために、ささやかな出費を厭わなかった(ウォルドロップ)。回目のワークショップから1カ月も経たないうちに、株式市場は実際に暴落した。1987年10月の 「ブラックマンデー」の頃、ウォール街のダウ工業株30種指数は、1929年10月の悪名高い。「大暴落」の時よりも多くのポイントを失った。専門家たちは、状況や見識が徹底的に進化していたため、同じようなことは二度と起こらないだろうと主張していた。サンタフェでのワークショップが暴落を予言したわけではなかったとはいえ(後に噂されることになる)、非線形プロセスに対する根本的に異なるアプローチの重要性が浮き彫りになったことは確かだ。
では、CASの何が新しく、どう違ったのだろうか?CASは通常、似たような振る舞いをする多数の似たようなエンティティが、それ自身や環境と相互作用し、状況の変化に適応した凝集パターンを生成するものであった。この意図的に広げた説明は、死んだ物質(原子や分子、水滴や砂粒)から生きた物質(遺伝子や細胞、植物や動物)まで、非常に幅広い現象をカバーしている。変化と淘汰は、これらのCASを、時には反応的に、時には積極的に、新たなニッチを満たし利用することによって、拡大・進化させるように思われた。人間の集団や共同体、世論や文化の形成にも似たような側面があることは、後ほど説明する。しかし、まずは一般的なCASの特徴について探求を続けよう。
CASが進化した主な理由の一つは、「多さ」や「多数」という性質そのものにある。集団内の実体の数が増えるにつれて、可能な相互関係の数は指数関数的に増えていく。2つの実体の間には1つの相互関係しか存在しないが、20の実体の間には190の相互関係が存在する。200のエンティティ間では、すでに19,900の相互関係が可能である。(式によれば、n×(n – 1)である): 2). この 「爆発的」な相互関係の可能性は、いわばさらなる合理化を求めるものである。
その他にもいくつかの考察を加える必要がある。まず第一に、個体やその行動がどんなに似ていても、個体自身、個体群内での位置、環境に対する位置が完全に同一であることはめったにない。例えば、周縁部にいる者もいれば、中心部にいる者もいる。これは分業を促進し、主体や関係性の分化をもたらす。このような分化のなかには、永続的なパターンを生み出し、それ自体が安定するものもある。しかし、数や人口が増えるにつれて、これらを統合することはますます難しくなる。このような組織形態を持つ一次システムは、生き残る可能性が高く、新しい状況によりよく適応することができる。
これらの原則は、権威ある雑誌『サイエンス』が1972年に発表した「More is Different」という刺激的なタイトルのエッセイですでに明らかにされていた。その著者はプリンストン大学の物理学者フィリップ・アンダーソンで、後に超伝導の研究でノーベル賞を受賞している。現実はいくつかの段階から成り立ち、それぞれの段階は上下の段階から半独立である。「各段階において、まったく新しい法則、概念、一般化が必要とされ、前の段階と同じ程度にインスピレーションと創造性が必要とされる。心理学は応用生物学ではないし、生物学は応用化学でもない」(ホーガン、209ページ)。したがって、すべてが最終的には核物理学に還元できるという一部の科学者の主張は、明らかにナイーブで間違っていた。
その直後、アンダーソンは『階層理論-複雑系への挑戦』という本の第1章で、ハーバート・サイモンから支援を受けた:
非常に単純かつ一般的な根拠として、例えばk個の基本構成要素を含む複雑系が、それらの構成要素から自然淘汰の過程によって進化するのに必要な時間は、その系自体が1層以上の安定した構成要素からなるサブシステムで構成されている場合には、その基本部分が唯一の安定した構成要素である場合よりも非常に短くなることを示すことができる。この問題の数学は、確率の簡単な練習である。(p. 7)
こうして出現したパターンやシステムは、より高いレベルの別のパターンやシステムを進化させ、さらにそのパターンやシステムは、さらに高いレベルの別のパターンやシステムを進化させ、といった具合である。レベル間の関係は非対称的であり、より高いレベルはより低いレベルから生まれたが、それらに還元することはできなかった。このタイプのシステムには2つの利点があった。レベル間に1対1の関係がないため、エラーや小さなダメージに対して脆弱でなく、対処し適応することができた。また、進化することもできた: まったく新しい状況に対応することができたのだ。しかし、裏側もあった: 問題のあるパターンは非常に永続的なのだ。
コンピューター科学者のジョン・ホランドは、論文や後に出版された『Hidden Order-How Adaptation Builds Complexity(隠された秩序-適応はいかにして複雑性を構築するか)』の中で次のように述べている:
貿易の不均衡、持続可能性、エイズ、遺伝子の欠陥、メンタルヘルス、コンピューターウイルスなど、私たちが最も頭を悩ませている長期的な問題の多くは、極めて複雑な特定のシステムを中心としている。経済、生態系、免疫システム、胚、神経系、コンピューターネットワークなど、これらの問題を抱えるシステムは、問題と同じくらい多様であるように見える。しかし、見た目とは裏腹に、これらのシステムには重要な特徴があり、サンタフェ研究所ではそれらをひとつの分類にまとめ、複雑適応システム(CAS)と呼んでいる。これは単なる用語ではない。すべてのCASの行動を支配する一般的な原理、つまり付随する問題を解決する方法を指し示す原理が存在するという我々の直感を示すものである。(ホーガン、195-196頁)。
規則性と不確実性
CASに関して最も議論の的となっているのは、CASの振る舞いについて数式や統計計算、コンピュータモデルを開発することに、現時点でどの程度の意味があるのかという問題である。確かに、ある特定の、明確に定義されたサブプロセスにおいて、さらなる洞察を得るのに役立つという点では意味がある。しかし、カオスと複雑性を決定論的な型にはめ直し、実生活の正確な予測を生み出すと主張するのであれば、それは時として時期尚早である。というのも、これらのプロセスの多くにおいて、確かに多くの大局的な規則性を特定することはできるかもしれないが、最終的な不確実性を排除することは通常できないからである。このことは、人間や社会に関する科学ではさらに顕著である。
軍事介入や株式市場の暴落、あるいは経営に関する問題のモデルは、完全な確実性を提供することはできない。なぜなら、関連するすべての要因を関連するすべての細部に組み込むことは基本的に不可能だからである。さらに言えば、そのようなモデルが存在し、最初の成功を収めたとしても、その後、例えば、より慎重になったり、より自信を持ったりすることによって、主要なプレーヤーの行動が変わってしまうからである。人間の行動は反射的であるため、他の自然現象とは異なる。さらに、社会的行動は関連するコンテクストの動くパターンに入れ子になっている。つまり、2つの状況が完全に同じであることはなく、「永遠の法則」を信頼することには注意が必要である。過去に特定の物事が常に一定の結果になったからといって、それ自体が将来もそうであることを保証するものではない。
私がCASについてこれほど時間を割いて話したのは、これと同じ世界的な原則が精神社会科学にも当てはまると感じたからである。脳と心は、驚くほど繊細なCASである(Eiser; Robertson & Combs; Vallacher & Nowakを参照)。集団やネットワークも同様である(キール&エリオット、ライデスドルフ、ルーマンを参照)。社会心理学と心理社会学が出会うところで、これらのシステムは相互作用する。他のどの学問分野よりも、大衆心理学と集団行動社会学は、常に代替パターンの出現を研究することを仕事としてきた。しかし、まずは重要なコミュニケーション・プロセスのいくつかを詳しく見てみよう。
予測、計画、基本的不確実性
予測は非常に難しい。特に未来についてだ。
-ニールス・ボーア、デンマークの物理学者。(スチュワート、279ページ)。
未来、n[oon]。われわれの問題が繁栄し、われわれの友人が真実であり、われわれの幸福が保証される期間。
-アンブローズ・ビアース、アメリカのジャーナリスト。『(悪魔の辞典』139ページ)。
この最後から二番目の章は、それまでの内容から一般的な結論を引き出そうとしている。この章は、予期せぬ事態が重なって大事故に至った原発事故についての「厚い記述」から始まる。これは、予測と戦略的計画という現象につながる。多くの政府やその他の機関は、世論や認識の領域でも、将来の展開に対して長期的なコミットメントを行う。
問題は、こうした予想がしばしば的外れとなり、気候変動などの新たな脅威や機会が著しく過小評価されることである。この文脈では、すべてのメタ原理のメタ原理、すなわち基本的不確実性についての理解を深める必要がある。複雑性とカオス理論の枠組みは、なぜ多くの重要なプロセスが完全に測定、予測、制御できないのかを明らかにしている。この基本的不確実性はまた、まったく異なるマネジメントアプローチを要求している。
1 ケース#1 1 万能薬としての原発(福島原発)
多くの人々は、原子力発電所が「クリーンな」エネルギーへの増え続ける需要に対する答えであると確信している。なぜなら、石炭や石油、ガスのような化石燃料を必要とせず、代わりにウランなどの鉱物を採掘できるからだ。確かに、二酸化炭素は排出されない。しかし、その代わりに放射性物質が残る。その放射性物質は、何世紀、何千年もの間、古い鉱山や新しい鉱山に「安全に」地下貯蔵されなければならない。これまでのところ、数十年ごとに大規模な原発事故が起きている。しかし、それらは常に最後だと言われている。本質的に安全な新しい技術(トリウム?そうかもしれない。
2021年春は、福島原発事故から10年が経過し、その全容を明らかにする時期である。日本政府はまだ重要なデータを秘密にしているが。例えば、地方の県と地方の下部組織との熱のこもったメールのやり取りや、当時の国の閣議議事録などである。ヒエラルキー文化のため、多くの公務員は、うまくいかないことの数々について口を閉ざしていた。しかし、相次ぐリークや暴露によって、原因と結果は段階的に解明されていった。
プラントは当時、世界で最も強力な25基のうちの1基だった。アメリカの巨大企業ゼネラル・エレクトリックが設計し、日本の巨大企業である東電(東京電力)のために建設された。しかし、コスト削減のため、海抜は30メートルではなく10メートルと不十分だった。堤防の高さも低すぎ、放射性物質を含む外部配管の保護も不十分だった。2011年3月11日の午後、遠く離れた海底で大きな地震があった。しかしその1時間後、最大14メートルの津波衝撃波が海岸を襲い、原発の大部分が浸水した。
幸いなことに、6基ある原子炉のうち後半は安全点検のため休止していた。前半の原子炉は運転中だったが、計画通り自動的に停止した。しかし、これが電気冷却システムの故障を引き起こした。しかし、代替のディーゼル発電機は長くはもたなかった。外部への道路が整備されていなかったためだ。このため、3基の原子炉で「メルトダウン」が起こり、水素爆発が起こり、放射能が海や大気に漏れ出した。アメリカの大手通信社『AP通信』は、1つの原子炉の核が格納容器を突き破って溶けたと報じた。さらに、原子炉が置かれていた極厚のコンクリート床をも突き破り、最後の1フィート(30cm)だけが無傷のまま残った。東電は後に、危険性を最小限に抑えていたことを認めた。
近隣住民からの抗議や裁判を恐れ、それがまた新たな条件や……コスト超過につながることを恐れたのだ。
かなり時間が経ってから、東電は設計と手続きにおける許されない欠点を認めた。国会の委員会は、事故の原因は予見できたはずであり、最も基本的な安全対策が欠如していたと結論づけた。適切なリスクアセスメントも、付随的被害への備えも、避難計画もなかったのである。3カ月後、ウィーンの国際原子力機関は、責任の一端を強大な経済産業省に押し付けた。その監督は甘かった。というのも、経済産業省は他国への技術の普及と販売も必要としていたからだ。
『原子力科学者会報』は、民間と公的機関の役割分担をめぐるあいまいさも露呈したと述べている。当時の首相は、震災前も、震災中も、震災後も、コミュニケーションと調整が不十分だったことを認めている。次の首相は、それぞれの当局が……安全神話に目を奪われ、国の技術的無謬性に対する誤った信念にとらわれていたとさえ言った。このようなことは何度も起こっている。過去の原発事故でもそうだった。
例えば、ほんの数秒の人間の過ちが、ほんの数十年前に人類史の大きな転換の引き金になったと言っても過言ではないだろう1。経済史:チェルノブイリの事故によって、多くの国で原子力発電所のさらなる開発と設置が少なくとも1年、あるいは20年遅れた。チェルノブイリの事故は、巨大なドイツに原子力発電所の開発を中止させた。その結果、化石燃料(石炭や褐炭など)の開発が長期化し、持続可能なエネルギー源(水、風力、太陽光など)が急速に普及することになった。
チェルノブイリ事故は、国内外にソビエト体制の破綻を認識させ、ソビエト体制を廃止・解体するきっかけとなったからだ。わずか3年のうちにベルリンの壁が崩壊し、わずか5年のうちにドイツの2つの地域が再統一された。これはまた、ヨーロッパの中心に新たな巨像を出現させ、西ヨーロッパと中央ヨーロッパの分裂を癒すことになった2。
このような災難はよくあることだが、例外的な状況が重なった結果でもあった。理論的には、システムはフェイルセーフであるべきだが、実際にはそうでないことが多い。毎日、ニアミスは起きている。危機一髪で回避された災害は、しばしばそのように認識されることさえない。しかし、時折、ヒットが起こる。事態は根本的に異なる展開を見せる。予測可能なことがひとつあるとすれば、それは予測不可能なことが常に起こるということだ。私たちは予期せぬことを予期しなければならない。あるバンパーステッカーにあるように、「Shit happens!」なのだから。
災害に対する認識や世論への影響もまた、多くのことに左右される。例えば今回の場合、チェルノブイリ事故が、「悪の帝国」で起きたという事実によって、西側の不信感はさらに高まった。シンクロニシティの原理も一役買った。ソビエト連邦のエリートたちがすでに揺らいでいたときに災害が起こった。したがって、災害は意識を決定的な閾値に押し上げるきっかけとなった。漠然とした関連しかなかった出来事が絡み合い、「スーパーパターン」が形成された。人々やグループは、当初は無視していた情報に敏感に反応するようになった。欧米のエネルギープランナーや問題管理者は驚きを隠せなかった。どんなに懸命に新しい「情報キャンペーン」を考案しても、少なくともしばらくの間は完全にコントロールを失った。
2 予測という現象
本書では、世論と認識の「急激で、過激で、大規模な」変化について、少数の大規模な事例と、より多数の小規模な事例を紹介してきた。チェルノブイリのケースのように、こうした出来事が並はずれた状況の結果として起こることもある。チェルノブイリ原発事故は、古い問題を消し去り、新しい問題を世論に登場させた。それは世界史の流れを変える一助となった。しかし、ほとんど誰も、少なくともこのような特殊な形で起こるとは予見していなかった。しかし、このような予期せぬ大事件は常に起こり、未来の可能性と不可能性の進化する風景を一変させる。したがって、ひとつ確かなことがあるとすれば、それは、完全に確かなことなど何もないということだ。
しかし、人々は確実性を求め、制度もまた同様である。確かなものがなければ、人々はそれを偽造する傾向がある。近代自然科学と人間と社会に関する近代科学が出現して以来、「測定、予測、管理」が一貫して重視されるようになった。ある本によれば、予測ビジネスは盛んな産業であり、当時少なくとも年間2000億ドルの売上があったと推定されている。しかし、著者のウィリアム・シャーデンは、7つの主要な予測領域を文書で分析した結果、計画や戦略の基礎として一般的に使用されている予測は、半信頼性に過ぎないと結論づけた。直線的な展開が単純に外挿できる場合には信頼性が高く、非線形な展開が急激な変化をもたらす場合には信頼性が低いことが判明した。
本節はこの問題をさらに掘り下げたものであり、次の節ではこのような事態を招いた深い原因について掘り下げていく。予測は常に有用であるが、それが本当に当たると信じている場合は別である。
昨日の技術的未来に戻る
占いはあらゆる文化や時代において重要な活動であった。未来を予測することは、「1つの職業を除けば最も古い職業」というレッテルを貼られてきた。状況が多少変化したのは、占い業が科学的裏付けを求めたときである。第二次世界大戦後、未来学という言葉を提唱したのは、ドイツの社会学者オシップ・フレヒタイムだったと言われている。戦後、ランド社は 「民間シンクタンク」として米国に設立されたが、空軍のための予測や戦略研究を展開することで多くの資金を得るようになった。中でも、1960年に発表された『熱核戦争について』という研究は、第三次世界大戦の可能性(およびその性質)に関するものだった。この研究は、スタンリー・キューブリックの同名映画でピーター・セラーズが演じた。「マッド・サイエンティスト」ストレンジラブ博士にインスピレーションを与えたと言われるハーマン・カーンによって作成された。
1年後、カーンは独立し、ニューヨーク州クロトン・オン・ハドソンにハドソン研究所を設立した。この研究所は、軍や民間当局、多国籍企業のために「未来に関するシナリオ」を開発していた。すぐに東海岸最大の未来学シンクタンクとなり、50人の研究者と100人のコンサルタントを抱えるようになった。ワシントンDC周辺でも、いわゆる「ベルトウェイ山賊」の同様のコンサルタント会社があちこちに出現した。西海岸では、オラフ・ヘルマーがスタンフォード近郊の未来研究所の共同設立者となり、南カリフォルニア大学の未来研究センターにも関わった。予言者たちは世界未来学会を設立し、多くの会員を集めた。この学問はすぐにヨーロッパでも足場を固めた。
1967年の企業セミナーで、ハーマン・カーンは20世紀の最後の3分の1の間に起こりそうな100の技術革新のリストを明らかにした。このリストは、アンソニー・ウィーナーとともに出版した人気書籍『2000年』に掲載された。予想される技術革新の例としては、夜間に光を拡散する人工衛星、気象制御、ユビキタス海洋採掘などが挙げられていた。その一世代後、スティーブン・シュナーズは、著書『Mega-mistakes(巨大な誤り)』でこれらの項目を批判的に評価した: Mega-mistakes: Forecasting and the Myth of Rapid Technological Change』という著書で、これらの項目を批判的に評価している。彼によれば、予測の4分の1は曖昧すぎて結論は出なかったが、少なくとも半分は完全に間違っていた。多かれ少なかれ正しかったのは10%、完全に正しかったのは15%だった。その後、いくつかの項目が実現に近づいたが、スコアはかなり低いままである。
ハドソンの調査とほぼ同時期に、TRW社は一流の科学者たちに同様の 「未来調査」に参加するよう要請した。シュナー夫妻によれば(p.10)、その結果、予測はほとんど完全に間違っていた。1980年頃には、乗客は月と往復し、そこには核施設を動力源とする永久基地が設置されているだろうと彼らは言っていた。同じ数年間、専門誌『インダストリアル・リサーチ』は1433人もの専門家に未来についてインタビューしたが、それ以上の結果は得られなかった。同じシュナールによれば(p.23)、『ファウチュン』、『ビジネスウィーク』、『ウォール・ストリート・ジャーナル』などの専門誌が発表した他のシナリオも間違っていた。彼は、それらの誤算から明確なパターンが解釈できるとさえ結論づけている。
例えば、新しい発明は自動的に大規模かつ明白な応用につながり、人々はそのために法外な価格を喜んで支払うだろうと仮定していた。しかし、同僚のウィリアム・シャーデンによれば、(成功した)技術応用の予測が難しい理由には、(a)実行不可能なコンセプト、(b)未知の応用、(c)証明されていない価値、(d)(他の技術との)不確実な相乗効果、(e)(他の技術の)創造的破壊、(f)標準の固定化、(g)偶然の出来事、などがあるという。例えば、差し迫った戦争や現在の戦争が、兵器システムに関連する技術革新の加速につながるかもしれないし、一方、認知された、あるいは実際に起こった危機が、単なる贅沢品に関連する技術革新の減速につながるかもしれない。
技術開発における大きなブレークスルーの多くは、漠然と感じ取れていたかもしれないが、実際には予測されておらず、その完全な意味はゆっくりとしか理解されていなかった。シャーデンによれば、電気や電球、電話や無線放送、ジェットエンジンやレーダーなどがそうだった。彼はジェームズ・マーティンの言葉を引用した:
1940年の合理的な予見者はコンピュータを予見しなかったであろうし、1945年の予見者はレーザーを予見しなかったであろうし、1955年の予見者は同期通信衛星を予見しなかったであろうし、1960年の予見者はホログラフィーや屋根の上の衛星アンテナを予見しなかったであろうし、1965年の予見者はハンドヘルド計算機やマイクロコンピュータの普及を予見しなかったであろう(174,178頁)。
これとは対照的に、合理的な予測者たちは、今日、私たちが転がる歩道やジェット推進車で移動し、どこでもバックパック・ヘリコプターや自家用飛行機で移動することを予測していた。ビニールハウスは羽毛取りロボットによって掃除されるだろう。私たちは皆、原子放射線で保存された乾燥食品を食べている。
前世紀を通じて、専門家たちはエレクトロニクス産業の予期せぬ発展に何度も驚かされた。第二次世界大戦の終わりには、かさばる真空管が10億本近く使われていた(端から端まで並べると、地球を4周することになる)。私がこのテーマを探求していた当時は、同じ容量を靴箱に収まる200個以下のペンティアム・プロ・チップが提供していた。第二次世界大戦中、専門家たちは、世界に必要なコンピュータは全部で4,5台までだろうと見積もっていたが、この数字はすぐに修正された。メーカーのユニバックは1950年、今世紀末までに使用されるコンピュータは1,000台以下だろうと見積もっていたが、1984年にはすでに1,000,000台になっていた。その頃、多くの関係者はまだ家庭用コンピューターは必要ないと感じていた。1990年代初頭になっても、IBMやマイクロソフトといった巨大企業は、インターネットはほとんど意味がないと考えていた。したがって、技術予測は実に複雑である。
顧客がイノベーションから得られるであろう用途、利益(そして喜び)は、常に決定的なものである。スティーブン・シュナールは、製品の可能性を冷静に評価するための3つの実践的ガイドラインを示した:
まず第一に、技術的驚異を避けること(p.143)。第二に市場について基本的な質問をする。市場の規模、顧客、製品の利点、費用対効果、実現される経済性、適切な価格設定などである。それだけでなく、その製品がより広いトレンドに適合しているかどうか、あるいは急進的な打破を意味し、凝り固まった習慣に逆行するものであるかどうか(144-145ページ)。第三に、そして何よりも: 地に足の着いた分析を強調し、無謀な計画を排除する(147ページ)。
なぜなら、それこそが先に述べた予測の誤りであり、的外れであることが証明されたからである。
昨日の経済未来に戻る
技術の発展を予測することがそれほど難しいのであれば、戦略的計画や経営に対する適切なアプローチを開発することはどれほど難しいことだろうか?小さな小冊子『21世紀のリーダーシップ開発』には、旧来のコントロールザウルスは絶滅しつつあり、明日のCEOはチームを率い、多才で、柔軟でなければならないと書かれている。軍事的・技術官僚的な考え方は、特に研究開発やマーケティング・広告など、初期や末端の部門において、人々の自発的な取り組みや自己組織化の余地を与えなければならない。組織は主に、すべての従業員が自分自身を容易に認識できるようなビジョンと文化によって管理されなければならないが、従業員は主に、自分自身のモチベーションと洞察力によって動かされなければならない。それは言うは易く行うは難しである。
同様の提言は、トーマス・ピーターズとロバート・ウォーターマンによる世界的ベストセラー『In Search of Excellence』(邦訳『卓越性を求めて』)からも以前に出ていた。しかし、その出版から5年も経たないうちに、高名な企業の3分の2はもはや優秀ではないことが証明された(ステイシー)。彼らのレシピは時代遅れになったのだろうか?満足してしまったのだろうか?それとも、奇跡的な治療法の永遠の探求は、おそらく幻想だったのだろうか?ピーター・アレンは後にこう述べている: 技術進化とは、ある単一のタイプの企業が、その優れた行動によって、「勝利」することではない。シェルの研究によれば、企業の寿命は平均して人間の半分しかないことが判明し、有名なファウチュン500の大企業ランキングには、長年にわたる壮大な栄枯盛衰が表れている。
前述のスティーブン・シュナースは、10年にわたる研究の末、ある論文でこう結論づけた: 「長期的なトレンドを予測し、それに基づいて行動することに成功した企業の例はほとんどない」(Sherden, p.233)。やや大げさに聞こえるかもしれないが、彼の著書には、各分野で一世を風靡しながらも、重要な新潮流や製品開発に気づくことができず、一掃されてしまった企業の例が数多く紹介されている。すなわち、(a)発明が必ずしも商業的成功につながるとは限らない、(b)イノベーションは外部からもたらされる、(c)最終的な用途や形態、顧客は予測不可能である、(d)成長は予想以上に時間がかかる、(e)タイミングが重要である、などである。
バテル研究所の古い報告書では、技術的ブレークスルーが工業的量産品の成功につながるまでには平均20年かかるとされていた(Schnaars, p.138)。しかし今日では、多くの分野でこの期間はかなり短くなっている。基本的には、常に新しい組み合わせやバリエーションが試され、1つだけが生き残るということが起こっている。ジョン・ケッタリンガムとP・ランガナス・ナヤックは、このようにして発明されたのは製品というよりむしろ市場であったと述べている。ゲイリー・ハメルとC.K.プラハラードは、『Competing for the Future』の中で、将来の市場に関する先見性は、現在の市場、製品、価格性能の前提に関する近視眼的な考えを捨て、顧客とそのニーズに真に焦点を合わせること、偏見を持たず、好奇心旺盛で、控えめで、折衷的であること、また、逆張りで創造的であることによってのみ開発できると述べている。
コンサルティング会社アーサー・リトルのケタリンガムとナヤックは、著書『ブレークスルー』の中で、成功するイノベーションには大きな神話があると述べている。すなわち、イノベーションはそれまで誰も持っていなかったアイデアから生まれるものであり、発明家によって、「小さな人々」によって実現されるものであり、多額の投資や特別な環境を必要とし、常に満たされていないニーズに対する反応であるというものだ。しかし、現実はまったく違う、と彼らは指摘する。発明とは、多くの多様な関係者の関与によって段階的に発展する、新しい要素の構成である。その可能性は、生産者にとっても消費者にとっても計り知れない。それは一種のゲシュタルト・スイッチ、あるいは 「Aha」Erlebnisであり、その引き金を引かなければならない。
経済学者のブライアン・アーサーは、かつて『サイエンティフィック・アメリカン』誌で、市場予測がしばしば外れる理由を説明した。彼は、物事がまだ様々な方向に動く可能性があることを認めるのは難しい、と言った。些細なランダムな出来事が決定的なものとなる可能性さえある。なぜなら、それが正のフィードバックループを起こし、小さな優位性が急速に完全な市場支配につながる可能性があるからだ。鉱業や工業のような伝統的な分野ではすでにそうなっていたが、エレクトロニクスや情報のような超近代的な分野ではなおさらである。製品あるいは「コンテンツ」に対する最初の投資は、時にかなりの額に上るが、余分なコピーのコストはほとんど無視できる。したがって、「経済を単純なものとしてではなく、複雑なものとして、決定論的、予測可能、機械論的なものとしてではなく、プロセス依存的、有機的、常に進化するものとして描く」(p.85)べきなのである。
このような見方は、コンピュータ、周辺機器、プログラミング(そしてメディア)にも見出すことができる。その一例が、ゼロックスによって開発された(しかしすぐには量産されなかった)ユーザーフレンドリーなパソコンであり、アップル・マッキントッシュによって改良され、さらにIBMを脅かした。ゲームメーカーのアタリは1977年から1982年にかけて毎年売上を倍増させたが、すぐに任天堂の洗練された製品に敗れた。
1984年以降、ヒューレット・パッカードはプリンター市場に攻勢をかけ、10年後にはこの製品の売上高は100億ドルに達した。ソニーは1985年にCD-ROMプレーヤーを発売し、7年間で1,000万台、さらに7カ月で1,000万台を販売した(ムーア)。マイクロソフトはDOSオペレーティング・システムを5万ドルで買い取り、IBMとそのクローンに売り渡した。その後、マイクロソフトによるウィンドウズ・コンピューター・システムの導入は、すぐにその所有者であるビル・ゲイツを世界一の金持ちにした。しかしそれは、ゼロックスやアップル・マッキントッシュがずっと以前に開拓したのと同じ原理に基づいていた。つまり、本当に競馬のようなものなのだ。
このように、今日情報通信技術(ICT)ビジネスと呼ばれるものの発展は、気まぐれで予測が難しい。このことは、イノベーションの普及に関する古典的な考え方を覆すものである。前述のエヴェレット・ロジャースの考え方によれば、イノベーターは、イノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、そしてラガードという5つの顧客カテゴリーを次々と攻略していかなければならない。
しかし、ジェフリー・ムーア著『Inside the Tornado: Marketing Strategies From Silicon Valley’s Cutting Edge』によれば、このためには、まさに適切なタイミングで、戦略の反転を繰り返す必要があるという: 「つまり、主流市場に参入した当初に成功するような行動は、竜巻の中では(その後すぐに)失敗を引き起こし、放棄されなければならない」(p.10)。他の著者もまた、今日のビジネス環境において「機会の窓」を正しく認識し、「ジャスト・イン・タイム」に行動することの重要性を強調している。
「永遠のレシピ」ではなく、市場の急速な変化可能性が経営陣の継続的な注意の焦点でなければならない。関連する力場は常に複雑でダイナミックなものであり、社会の動向や世論の流れを常に十分に理解することも求められる。
昨日の社会の未来に戻る
技術的、経済的な発展は、社会的なトレンドと織り交ざっている。例えば、蒸気機関と燃焼モーターの発明は、長い間、明白な恩恵であるかのように思われていた。工場や電気設備、暖房や空調設備、自動車や船舶は、製品、快適さ、移動性をもたらした。1960年代に脱植民地化がほぼ完了した後、産業革命の莫大な恩恵がさらに広がる道が大きく開かれたように思われた。そこで、前述の 「未来学者」ハーマン・カーンは 2000年は長い安定と成長の時代の始まりになると予言した。(その翌年の9.11とその甚大な影響を考えてみよう)。
しかし、よく似た予測方法を用いて、正反対の結論に達した者もいた。もちろん、この方法で生産と消費に関する数字の上昇を外挿することはできる。しかし、原材料や廃棄物の増加についても、このように予測することができる。もしすべての大陸が北米や西ヨーロッパと同じ消費レベルに達すれば、主要な原材料はすぐに枯渇し、環境はすぐに過度の負担を強いられるだろう、と彼らは言った。
増え続ける人口に十分な資源と食料はないだろう。1967年、ウィリアム・パドックとポール・エーリック夫妻が『飢饉』に関する研究を発表し、1968年にはポール・エーリックが『人口爆弾』に関する研究を発表した。警鐘を鳴らすムードは広まった。1968年、関心を持つ科学者や政策立案者のグループがイタリアの首都に集まり、ローマクラブを結成した。その活動を支える資金は、当初はフィアットの資金による財団から、後にはフォルクスワーゲンの資金による財団から提供された。
理事会メンバーを通じて、ジェイ・フォレスターと、マサチューセッツ州ケンブリッジにある有名なマサチューセッツ工科大学と接触がもたれ、この研究所は、将来の世界の発展に関する最初のコンピューターモデルを作り始めたところだった。デニス・メドウズの指導の下、チームが結成された。最初の研究結果は1970年に発表され、後に『成長の限界』として補足・出版された。様々な版と言語で、900万部(!)を下らない部数が売れた。その主な結論は、もし現在の発展がこのまま許されるなら、新しい千年紀の始まりは不足と汚染の増加によって特徴づけられるだろうというものであった。これらの傾向は21世紀半ば頃にピークに達し、最終的には文明社会の完全な崩壊につながるだろう。石油輸出国機構(OPEC)が設立され、1970年代に原油価格の大幅な引き上げが始まり、世界中に衝撃が走ったことで、このシナリオの信憑性はさらに高まったように思われる。
今から思えば、こうした破滅シナリオを批判するのは簡単だ。例えば、在庫の見積もりは、現在の価格で開発された既知の埋蔵量に限定されていた。一方、新しい埋蔵量は、より高い価格で開発される可能性があり、代替品も見つかる可能性があった。著者は、第三世界の継続的な弱さと分裂、あるいは第一世界とその多国籍企業の継続的な強さと力には対処していなかった。また、環境意識や自然保護政策に及ぼす影響も含まれていなかった。ローマクラブの報告書は、「自滅的予言」の良い例である。よくあることだが、予言は自らの失敗を招いた(人間の社会行動は完全に「盲目的」なプロセスではないからだ)。
しかし彼らは、例えば中国の急速な台頭や地球温暖化を見逃していた。
昨日の予測と予測不可能性
時折、あれやこれやの不確実な出来事を確実に予言したと主張する専門家や占い師がいる。しかし、そのような主張には様々な問題がある。まず、その予言が具体的にどのようになされたのか、時間、場所、詳細が含まれているのかどうかを確認しなければならない。第二に、その予言が公にされたかどうか、そして独立した観察者、できれば懐疑論者の立会いのもとで行われたかどうかを確認しなければならない。
第三に、その方向性を示す他の兆候がなかったかどうかをチェックしなければならない。最後に、その専門家や占い師がそのような予言をもっと多くしていないか、また、その専門家や占い師が的中させる確率が偶然以上のものであったかどうかをチェックしなければならない。昔、10種類の予言を10か所の封書に入れて、あるいは10人の正直な公証人に託して、当たったものだけを後から取り出したり発見したりしたことを思い浮かべてほしい。
いろいろな人がいろいろな占いを常にしていれば、たまには当たることもあるだろうが、それは並外れた力の証明にはならない。つまり、何千人もの占い師が新年の予言をする中で、数人は必ず当たるということだ(「政府の指導者が撃たれる」、「国を災害が襲う」)。シュナースやシャーデンのような「専門家」の予測ビジネスに対する批判者によれば、的中するのは非常にいい加減な予測だけである。例えば経済学者について、シャーデンは証拠を精査した上でこう結論づけた:
彼らはターニングポイントを予測できない、彼らのスキルは当てずっぽうに等しい、一貫して良い結果を出している個人/学派/イデオロギーは存在しない、高度化しても改善されない、等々である。そして、ノーベル賞受賞者のポール・サミュエルソンの言葉を引用し、「予測精度が向上し続けているとは思えない。まるでハイゼンベルグの……(不確実性の)原理があるかのようだ」(p.68)。
長年にわたり、さまざまな分野で予測方法を改善する試みが行われてきた。むかしは、「トレンド分析」(統計やグラフにはっきりと現れている傾向をそのまま未来に外挿したもの)しかなかった。その後、「シナリオ分析」が登場し、通常(現在でも)3つの可能性を特定する。すなわち、すべてが以前と同じように進むか、事態が少し良くなるか、事態が少し悪くなるかである。
次に「デルファイ法」がある。これは、さまざまな質問をさまざまな専門家に提出し、その回答をさまざまなカテゴリーに分類し、コメントや提案を求めて再提出を求めるものである。この手順は何度も繰り返される。最終的には、コンセンサス、多数意見と少数意見、あるいは様々なパターンを抽出し、数字やパーセンテージ(確率)を伴うか否かを試みることもある。
後にひねりが加えられたのは、専門家たちに可能性のある結果に多額の私財を賭けさせてみるという方法である。しかし、専門家であろうと素人であろうと、こうしたアプローチには根本的な問題がある。なぜなら、未来は常に過去と現在をもとに予測されるからだ。世代の「記憶スパン」も一役買うかもしれない。20年も40年も前に大きな戦争や危機があったなら、その可能性はまだ考慮されるが、それ以降は人々の視野から消えていく。
「時代精神」、あるいは 「状況バイアス」が一役買っているのかもしれない。人が未来を把握しようとするのは、現在の状況においてである。このことは、どんなに想像力豊かなSFであっても、それが創作された特定の時代の痕跡が残っていることが多いため、SFほど明らかなものはない。多くの「科学的」予測でさえ同様で、ゲシュタルト転換、つまりまったく別の現実に認知的に「ジャンプ」することは極めて難しいからだ。創造性の達人が言うように、新しい前提や反射を学ぶことは難しい。しかし、古い思い込みや反射神経を学ぶのはさらに難しい。
問題の核心は、未来は存在しないという事実である。しかし、私たちは本能的に、未来を現在と過去の単純な外挿として見る傾向がある。10件中9件はそうかもしれないが、究極の10件目は非線形であり、ゲームの名称を大きく変えるかもしれない。システムが多かれ少なかれ均衡状態にある限り、変化は比例的かつ直線的であることが多く、予測は容易である。しかし、システムが均衡から大きく外れると、微細なことが劇的な変化を引き起こす可能性があり、予測が劇的に外れることも少なくない。さらに、ダイナミックな発展は複雑な相互作用を引き起こす。つまり、「モデル構築者」がどう主張しようとも、未来の基本的な側面を予見することはできないし、今後もできないのである。
時折不意打ちを食らうことを除けば、私たちは「あたかもそうであるかのように」物事を進め続けることができるかもしれない。しかし、「測定、予測、制御」という機械論的な幻想を捨て、不確実性を人生の重要な事実として受け入れ、柔軟性と回復力を通じて、それを戦略的思考と行動に取り入れる方がよいかもしれない。なぜ未来は常に私たちを驚かせ続けるのか、その理由がますます明らかになってきている。
3 究極のメタ原則根本的な不確実性
過去 10 章の過程で、われわれは、一連のメタプリンシプルがいかに突然のシフトに寄与するか、また、 非線形の変化を別の用語でどのように概念化しようとするかを見てきた。十中八九の場合、ニュートンのリンゴのパラダイムは、何が起こっているのかを理解するのに比較的適しているように思われる。限りなく小さなディテールが、既存のパターンを解消し、まったく新しいパターンを出現させる上で決定的な意味を持つことがある。そのため、未来は常に 「コントロールされている」と信じるのではなく、今日想像しているものとは根本的に異なるものになることが多いということを認識することが非常に重要なのである。
例えば、アルベルト・アインシュタインの相対性理論では、彼自身は最終的な帰結を認識していなかったが、あるいは、ヴェルナー・ハイゼンベルクらの量子論では、基本的な理由から、電子レベルでは正確な測定や予測は不可能であるとした。後者は「不確定性原理」を宣言することで、この観察に広範な意義を与えた。多くの科学者は長い間、その意味を受け入れようとしなかったが、多くの哲学者はすぐに賛同した。
皮肉なことに、最終的に「イン・コンピュータビリティ」を地図に載せたのは、コンピューターそのものが徐々に普及し、洗練されていったからである。多くの複雑な適応プロセスの結果は予見できないことが判明したのである。このセクションでは、「計測不可能性」「予測不可能性」「制御不可能性」というサブプリンシプルについて詳しく見ていく。これらは自然科学だけでなく、人間や社会の科学においても、突如としてあちこちに存在することが認識されるようになった。世論や認識の急激で、過激で、大規模な変化もまた、同じような根本的な理由から、時に計り知れず、予測不可能で、制御不可能である。
無限の細部、フラクタル、計り知れないもの
日常生活においても、科学的研究においても、私たちはしばしば、「何がどうであれ」、特定の状況において「作用している」単位や力の正確な割合を決定することは比較的容易であると暗黙のうちに思い込んでいる。しかし、これは常にそうであるとは言い難い。例えば、測定の精度は、使用した測定器の精度と関係していることがよくある。より精密な測定器であれば、小数点以下の桁数が多い、より正確な測定値が得られるだろう。多くの場合、人はそれを永遠に改良し続けることができる。レンガの長さ、幅、高さを測るような、一見どうでもいいような場合でさえそうだ。しかし、これは「自然な」形ではさらに問題となる。
数学者たちは、いわゆる「海岸線」問題でこのことを説明した(Davies, pp.57-58; Gleick, pp.91-92; Stewart, pp.203-204)。イングランド(とスコットランドとウェールズ)のような島の海岸線の長さを測りたい場合、私たちはそのために縮尺を選ぶ。最小単位を100kmとすると、海岸線の長さは3,800kmとなる。しかし、その半分の大きさ(例えば50キロメートル)の最小単位を使えば、同じ海岸線の長さが突然6,000キロメートルに拡大することになる。さらに小さな単位(1キロメートル、1メートル、1ミリメートル)を使えば、海岸線は 「成長」し続ける。では、イングランドの海岸線はどのくらい長いのだろうか?それは人それぞれだ!私たちが何気なく使っている自然現象の他の多くの尺度についても同じことが言える。なぜなら、現実の多くは 「無限にほつれ続ける」からだ。
フランスの数学者ブノワ・マンデルブロは、多くの自然物体のエッジやフリンジがしばしば非常に特殊な特徴を持つことを発見した。伝統的な幾何学は、このような形を表現するのにほとんど役に立たない。
その理由のひとつは、雲、山、海岸線、木の形を表現できないことにある。雲は球体ではなく、山は円錐形ではなく、海岸線は円ではなく、樹皮は滑らかではなく、稲妻は一直線には進まない。自然の模様の長さの異なるスケールの数は、現実的には無限である(Eiser, p.175より引用)。
そこでマンデルブロは、根本的に異なる基本形の集合を持つ、根本的に異なる幾何学を提案した。彼はこれをラテン語のfrangere(壊れる)にちなんで「フラクタル」と名付けた。フラクタルとは、同じ基本パターンを無限の詳細レベルで表示する形のことである。枝が2本に枝分かれし、それがさらに4本に枝分かれする、といった具合だ。このようなパターンを10倍に拡大しても、1,000倍に拡大しても、同じパターンが何度も繰り返されることがある。これは無限に複雑な図を作り出すが、比較的単純な規則を何度も何度も適用した結果である。マンデルブロによれば、多くの自然現象はこのフラクタル原理に従うという。もちろん、無限にというわけではないが、海岸線や山々、小川や雷鳴にも当てはまる。「生きている」自然は、シダやカリフラワー、肺や脳のような複雑な形を生み出すために、さらに頻繁にこの同じ原理に従っている。
無限細部やフラクタルに関するこのような観察に照らして、精神的・社会的形態やパターンを再考する十分な理由がある。例えば、マンデルブロはIBMで働くようになったばかりの頃、多くの自由市場の価格形成パターンがフラクタル原理に従っていることを発見した。価格チャートはジグザグのパターンを形成していた。それを「拡大」すると、さらに細かいジグザグパターンが浮かび上がる。多くのチャートや表は、四捨五入の結果、より細かいディテールが隠されている。しかし、そのような限りなく小さな細部は、他の「ほつれた」変数とのダイナミックな相互作用の中で決定的な意味を持つことがある。
市場価格や取引量は、多くの領域で非常に詳細に追跡・登録されており、「厳然たる事実」や 「客観的データ」の地位を獲得しているからである。心理学者や社会学者は、これとは対照的に不利である。というのも、意味帰属における同様の微妙な変化は、これほど大量に、永続的に、詳細に追跡・登録されることはないからである。例えば、個人や集団が抱く意見や態度の変遷は、フラクタル的な、限りなく詳細な、ジグザグのパターンをたどるかもしれない。
政治家の人気投票や政党の選挙選好度調査でも、このようなパターンがはっきりと見て取れる。さらに、「測定技術」の不可避的な不完全性は、しばしば予測結果の不可避的な不完全性に変換される。特に、同等の強さを持つ2つの政党や連合が対決し、51%対49%で決着がつくような場合は、しばしばそうである。(このような選挙対決においても、複雑なパターンは、第8章で述べたような微妙なレベルの自己組織的臨界へと発展する傾向を示すことがある)。そのため、最後の瞬間まで、「クッキーはどちらに崩れるのか」がはっきりしないままなのである。
不安定な平衡、分岐、予測不可能性
多くの自然現象は「ほころび」があり、その正確な次元を決めるのは難しいかもしれない。しかし、もしそのような限りなく小さな違いがあるのなら、2つの自然界の物体、力、またはプロセスが完全に同じ大きさではない可能性も限りなく大きくなる。慣性や抵抗が作用しないのであれば、遅かれ早かれ、一方の現象が他方より大きく、あるいは強くなる。つまり、完全な均衡はむしろ稀であり、潜在的な不平衡はむしろどこにでもあるのだ。これは、まだ指数関数的な要素を伴わない「単純な」対決でさえそうであることに注意しよう。
我々は通常、問題となっている現象の詳細を知らないので、対立や相互作用の結果は常に我々を驚かせるかもしれない。どちらかに転ぶこともあれば、どちらとも言えないこともある。このように、多くの発展にはいわゆる分岐点があり、予測不可能な要素がさらに加わる。さらに言えば、分岐が次から次へと起こる場合、結果を予測するのはさらに難しくなる。このような場合、「分岐カスケード」と呼ばれる。このような条件下では、限りなく小さな細部が、最終的に優位に立つパターンを規定する可能性があるからだ。
2つの一見等しい力の対立が予測不可能な結果をもたらすとすれば、3つの一見等しい力の対立はなおさらである。このことは、物理学のいわゆる「3つの磁石」の実験によく表れている。この実験では、同じ強さの3つの磁石を互いに等しい距離に置く。正三角形の角で、それぞれに原色(赤、青、黄)を割り当てる。中央の決められた高さに、振り子を放つ。例えば、紐の先に白い鉄球をつける。振り子は前後に動くが、最終的には3つのアトラクター・ポイントのいずれかに静止する。さまざまな原点がどのようにさまざまな結果に変換されるかをマッピングしてみることができる。
例えば、ボールの元の位置のすぐ下に、ボールが最終的に静止する磁石の色の点を描くことができる。力場は変わらないのだから、次に同じことが起こるはずだ。しかし、これを1000回繰り返すと、不思議なパターンが浮かび上がってくる。磁石のすぐ周囲に、同じ色の一枚岩の領域ができるのだ。これは予想通りである。しかし、これらの領域の間には、驚くべきことに、明確な定義とはほど遠い、かなりの中間領域が存在する。
それらは、古い本のカバーの内側に使われていた特殊な紙(つまり、無限にほつれ、密接に絡み合っている)に見られるような、色とりどりの「トルコ風」櫛模様を思わせる、極めて詳細なフラクタル・パターンを形成している。したがって、実際には、ボールが放たれたときにどこに行くかを予測することはまったく不可能である。3つの電磁気的な力の対決の結果がこれほど予測不可能であるならば、3つの心理社会的な力の対決はどれほど気まぐれなものだろうか?
しかし、この複雑な三つ巴の対決から、もっと単純な双方向の対決に話を戻そう。私たちは皆、一般的な心理学で単純な二者択一の均衡(例えば、あいまいな刺激の知覚、つまり、根本的に異なる、互いに相容れない2つの方法で知覚できる刺激)に慣れ親しんでいる。簡単な例としては、立方体や階段の線画がある。これらの線画は、「上から見たもの」としても、「下から見たもの」としても同じように解釈できる。もう少し複雑な例としては、2つの対向する面によって形成される花瓶の形がある。さらに複雑な例としては、「妻と義母」や 「狩人とウサギ」のような有名な滑稽な絵がある。通常、人は一つの可能性のある解釈をすぐに認識し、もう一つの解釈も認識するようにゲシュタルト転換したり、行ったり来たりすることに苦労する。私たちの期待や 「マインドセット」が重要な役割を果たしている。A、B、Cシリーズと12,13,14シリーズを考えてみよう。真ん中のキャラクターはほとんど同じ形をしているかもしれないが、私たちの期待(マインドセット)が異なるため、自動的に対照的な解釈がなされる。
これは知覚だけでなく、思考にも当てはまる。私たちは論理的に考えるのではなく、心理学的に考える。つまり、単純なヒューリスティック(発見的思考)や経験則を使い、単純化された方法で迅速に結論を導き出すのである。その際、私たちはしばしば間違いを犯す。このことは、「マインド・トラップ」のような社会的ゲームや、手品師やペテン師が使うなぞなぞや頭の体操で実証されている。私たちの思考は単純化や一般化、また固定観念や差別によって成り立っている。複雑なパターンを単純なものに落とし込むために、私たちは常に自分の背景(年齢、ジェンダー、民族性)や経験(階級、教育)を参照する。
定義上、異なるグループは異なる方法でこれを行い、しばしば正反対の方法をとる。1960年代から1970年代にかけての名作コメディ、「オール・イン・ザ・ファミリー」の観客の受け止め方を考えてみよう。主人公のアーチー・バンカーは、いつも「その他大勢」を侮蔑する発言をしていた。しかし、調査によると、多くの視聴者は、対照的に女性や若者、マイノリティに対する「政治的に正しい」見方を嘲笑する彼に共感していた。つまり、リベラル派と保守派は、同じテキストや映像をまったく正反対の方法で「読む」のである。また、ロドニー・キング事件、ロサンゼルス暴動、O.J.シンプソン事件、ジョージ・フロイドの死など、アメリカにおける主要な人種的対立が、白人と黒人で異なる解釈をされる方法を考えてみよう。
あるいは、ビル・クリントン大統領のインターン、モニカ・ルインスキーとの不倫が、当初リベラルな民主党と保守的な共和党とで正反対の読み方をされ、1998年末の連邦議会再選挙で選挙民の予想外の反発をあおったことを考えてみよう。このような反応形成の過程(人物や組織、ブランドや問題をめぐる)の経過、力、スピードは、特徴的に予測が難しい。多くの詳細が関わっている。ごく最近、DNA鑑定によって、憧れの大統領トーマス・ジェファーソンが、若い黒人の愛人との間に婚外子をもうけていたことが間違いなく証明された。このことは、多くの高位政治家が、悪い指導者でなくとも不倫をすることがあるという一般的な考えを補強した。ただの偽善者だ。
この発見は、まさにこの時点で、かなりの反響を呼ぶかもしれない予測不可能な偶然のひとつを生み出した。この文脈では、「シンクロニシティ」の原則を参照することができる。ポール・デイヴィスは言う:
時空間における事象の星団を想像することができるが、それは何らかの意味を持って関連しているが、因果的な関連はない。これらの事象は時空間的に分離しているかもしれないし、分離していないかもしれないが、それらの結合や関連は因果的作用に起因しないかもしれない。これらの事象は時空間において、通常の物理法則からは導かれない秩序を表すパターンやグループ分けを形成する(p.163)。
物理的・化学的プロセスだけでなく、生物学的・心理学的プロセスにおいても、シンクロニシティの役割はある。有名な物理学者ヴォルフガング・パウリや心理学者カール・グスタフ・ユングは、シンクロニシティに超常現象や超自然的な役割を与えようとさえした。しかし、最後の一歩を踏み出さなくても、この原理を受け入れることは十分に可能である。
偶然、偶発性、制御不能性
確実性と不確実性には第三のレベルがある。すなわち、自由意志と選択、そして管理と制御である。人間の自由意志は分岐の機能であり、常に2つの等しい機会の端でバランスを取っていることが示唆されている。物理学者のフリーマン・ダイソンはこう推測する:
私たちの意識は、脳内の化学現象によって運ばれてくる受動的な現象ではなく、分子複合体にある量子状態と別の量子状態の選択を迫る能動的な存在なのだ。
物理学者のジェームス・クラッチフィールドは言う:
生得的な創造性には、小さな揺らぎを選択的に増幅し、それを思考として経験される巨視的なコヒーレントな精神状態へと成形する、根底にあるカオス的なプロセスがあるのかもしれない。場合によっては、思考は意思決定であったり、意志の行使であると認識されるものであったりする(デイヴィス、p.190)。
これは精神的なレベルだけでなく、社会的なレベルでも同様である。ある孤立した個人のある孤立した行為が、ある出来事の経過に根本的に異なるねじれを与えるかもしれない(ターナーも参照)。チェルノブイリのケースを思い出してほしい。
このことはまた、歴史における個人の行動の役割、そして「もしも」の問いに私たちを立ち戻らせる。もし特定の主要な指導者(アレキサンダーやカエサル、クロムウェルやナポレオン、ビスマルクやレーニンなど)もし、これらの指導者たちが大きな分岐点で少し違った決断をしていたら、歴史的なプロセスは本当に違った方向に進んでいたのだろうか?
たとえば、さまざまな大戦争の勃発は、巨大な力によって引き起こされただけでなく、些細な事件によっても引き起こされた。さらに、主要な指導者、国、同盟の少なくともひとつは、最終的な結果を大きく誤算している。もし1962年10月のキューバ(とトルコ)周辺の「ミサイル危機」を主要人物が見誤っていたら、核戦争は起きていただろうか?シャーデンは、天候が急変したり、天候予測が大きく外れたりしたために、歴史に新たな展開をもたらした決定的な戦いのさまざまな例を挙げた。
予測不可能性と制御不能性については、社会地理学から、より平和的な例を挙げることができる。ある領域におけるある場所の「魅力」が隣の場所のそれをわずかに凌駕し始めると、誰もがそこに集まり始めるかもしれない。異なる都市化や工業化のパターンが引き継がれ、相対的に自立することもある(例えば、Prigogine & Stengers; and Arthurを参照)。気候、一流大学の近さ、交通の要衝の近さなど、さまざまな条件が重なっただけで、初期の一握りの電子機器メーカーは、現在のシリコンバレーに集結した。今日、シリコンバレーにはそうした企業が1,000社以上ある。この都市圏は、近隣のサンフランシスコを抜いて米国で11番目の都市経済圏となり、輸出額ではニューヨークを上回った。アメリカ国内でも世界各地でも、都市計画家たちは時折、自分たちもシリコンバレーを建設すると自信満々に宣言するが、それは自己欺瞞である。
しかし、プランナーや経営者の誤算の中で最も魅力的なのは、ある構想が意図したものと正反対の結果をもたらすことである。よくあることだ。心理学者のリチャード・ファーソンは、その興味深い著書『不条理の経営』の中で、政策立案者が外部のコンサルタントに「汚くて頑固な」問題に対する「早くてきれいな」解決策を求めることを指摘している。一枚のオーバーヘッド・シートに収まらないものは何であれ、真剣に検討することはできない。これはまた、ある万能薬がしばしばその正反対に取って代わられ、拡大対縮小、多角化対本業など、経営の流行がメリーゴーラウンドのように繰り返される理由も説明している。対照的に、ファーソンは、すべての取引は良くも悪くもあり、リーダーシップとは本質的にジレンマの管理であり、曖昧さを許容することが基本的な資質であると強調する。
各章では、このことが当てはまるあらゆる領域が網羅されている。ファーソンは、「うまくいくマネジメント手法を見つけたら、それをあきらめなさい」(p.35)とアドバイスしている。他の章のタイトルは、「効果的なマネジャーはコントロールされていない」、「伝えれば伝えるほど、伝えなくなる」、「聞くことは話すことよりも難しい」、「大きな変化は小さな変化よりも起こしやすい」、「計画することは変化をもたらす効果的でない方法」である; 偉大な強みは偉大な弱みである」、「経験豊富なマネジャーほど、単純な直感を信じる」、「プロになるには、アマチュアにならなければならない」、「失われた大義こそ、戦うに値する唯一のものである」、そして最後に、「私の忠告は、私の忠告を聞くな」である。「」 同様の見解は、センゲの(非)学習する組織に関する本や、ドーフィネ、プライス、ペダーソンのパラドックスに関する本にも見られる。ファーソンは自著の中で、例えば環境領域における自滅的な戦略の例を数多く挙げている:
例えばパキスタンでは、排水が十分でない土地に灌漑と施肥の技術を適用することで、耕作が始まった土地よりも耕作が終わった土地の方が多いという弊害が生じている。もっと身近なところでは、エアコンは空気を汚染し、高速道路を拡幅すれば高速道路だけでなく、高速道路が接続する都市や町の渋滞が増大し、農薬や殺菌剤は私たちの健康を危険にさらす。テクノロジーが応用されるたびに、我々が意図したものとは正反対の対抗勢力が発達するのだ(p.45)。
その一世代前、社会哲学者のイヴァン・イリイチは、診療所や病院が私たちの健康に悪影響を及ぼし、学校や大学が私たちの知性に悪影響を及ぼすことを、いくつかの論議を呼ぶ著書の中で明らかにしようとした。(私も自分の経験からそう思う傾向がある)。
つまり、ある種の発展が独自の道をたどり、私たちが考えているほど簡単には修正されない可能性があることを認識することが非常に重要なのだ。多くの現象は基本的に計り知れないものであり、予測不可能であり、制御不可能である。なぜなら、出来事の成り行きは常に(気まぐれな反応形成などによって)私たちの予想とは異なる方向に向かう可能性があるからだ。これは自然現象だけでなく、心理社会現象にも当てはまる。CASの中のダイナミックな進化の基本原理である。人や制度、製品や問題に対する世論や大衆の認識は、特殊なケースにすぎない。遅かれ早かれ、まったく意表を突くような大きな展開が必ずある。したがって、自信に満ちたイシュー・マネジメントのようなものが本当に現実的な提案なのかという疑問が残る。
まとめ:問題管理?
何が起こるかを知っているという幻想は、知らないことよりもたちが悪い。
-ジェームズ・アッターバック、アメリカ人教授。(シャーデン、191ページ)
さて、ここで本書の中心的な主張を簡単にまとめておこう。私たちは、世界についての私たちの根付いた思考が、何度も何度も再定義に向かう傾向があることを繰り返し観察してきた。つまり、ある種の慣習的な「ものらしさ」が絶えず世界に仮定され、非均一性、永続性、実体、拡張性などが暗示される。さらに、現象間の相互作用は通常、機械的な用語で理解され、効果の規則性や比例性を暗示する。このような仮定は、しばしば科学者や管理者をプロセスの「測定可能性、予測可能性、制御可能性」に過度の信頼を置くように導く。
しかし近年、自然科学は根本的に異なる見方を(再)発見している。多くの現象は、CASや駆動粒子群などの観点から再解釈されている。多数の似たような実体や関係が絶えず動的な構成を形成し、変化させ、それは永遠に進化し続ける。これは、見えるものと見えないもの、顕在的なものと潜在的なもの、実現されたものと潜在的なものなど、レベル間の急速な移行を意味する。一方では、細部は常に変化している。他方で、これらの微細な変化の多くは全体にほとんど影響を及ぼさないが、少数が何らかの影響を及ぼし、さらに少数が、例えば正のフィードバック、増幅、循環反応などを通じて、かなりの影響を及ぼす。その結果、一見気まぐれで不釣り合いな反応や急進的な変化が定期的に起こることになる。
「創発」は3つの異なるレベルで現れる: 第一に、シナジーのレベルである。並行して進行しているプロセスは、収束、同期、共鳴という形で顕在化することがある。これは変化への抵抗を弱め、力を高める。
第二に、連想ネットワークやコミュニケーション・ネットワークのようなパターン形成のレベルである。例えば、このようなネットワーク間のたった一つの新しい相互接続が、決定的な再構成を引き起こすかもしれない。
第三に、自己参照、自己生産、自己再生産といった、ある種の自己組織化が現れるかもしれない。これは 「支配の場」の転換をもたらすかもしれない。注:新しいプロセスは以前のプロセスから生じるが、それらに還元することはできない。
これらの基本原則に、さらにいくつかの原則を加えることができる。実体、関係、プロセスは通常他のものの中に入れ子になっているという原則。現象はその文脈の中で見なければならず、状況はより広い進化の視点の中に置かれなければならない、などである。これはまた、時間は不可逆的であり、2つの状況が完全に同じであることはほとんどなく、「時間のない」法則や永遠の法則を信頼しすぎないように注意しなければならないという事実にも改めて注意を喚起する。プロセスは減速することもあればギアアップすることもあり、臨界閾値や臨界質量に達するたびに逆転が起こり、大災害を引き起こすことさえある。一見気まぐれに見えるが、これらのプロセスは完全に恣意的なものではない。多くのよく定義されたCASは、いわゆるアトラクターと呼ばれる特定の方向に進化する傾向がある。最終的な観察として、これらすべてが質的に異なる状態、つまり相転移につながる可能性がある。
このようなメタ原理は、大衆心理学や集団行動社会学の分野で以前研究されていた、さまざまな謎めいた現象によく当てはまることがわかった。例えば、ユビキタス変異の原理は、非公式なコミュニケーションや会話、伝聞や噂の領域でよく説明できる。ポジティブ・フィードバックの原理は、フォーマルなコミュニケーションやメディアの誇大広告の領域でよく説明できる。
相乗効果、パターン形成、自己組織化という3つの創発プロセスは、群衆、オピニオン・カレント、社会運動という3つの伝統的な領域で説明することができる。その後、私たちはさらに大衆のムードやシフトについて掘り下げた。例えば、流行やブームの成否には、コンテクストが進化するという原理が重要な役割を果たしているようだ。恐怖やパニックの引き金には、臨界閾値の原理が支配的な役割を果たすようだ。そして怒りや敵意の表現においては、可能なアトラクターの原理が何らかの形で現れている。最後の部分では、最後に、熱狂や墜落のような複合的な大衆の気分転換が観察された。相転移の原理は私たちの洞察を深めてくれるかもしれない。
前章では、測定、予測、制御はしばしば有用であるが、そうでない場合もあるという最初の観察に立ち戻った。技術的、経済的、社会的発展の結果を予測しようとするとき、私たちは常に、これらが基本的な不確実性をはらんでいることを認識しなければならない。
したがって、柔軟性と注意力、そしてレジリエンスとオープンマインドが何よりも求められる。後者は比較的簡単なようで非常に難しい。というのも、私たちの個人的な歴史や、大きな組織の中で志を同じくする人々と日常的に接していると、過去や現在の一見明白で自明な「真実」に絶えず洗脳され、未来の前例のない性質を忘れさせてしまうからである。そのため、意見や態度、認識やイメージは、一般的に考えられているよりもはるかに急速に、根本的に、そして大規模に変化する可能性があることがわかった。これはおそらく常にそうであったが、いわゆるマス社会、マスメディア社会、メディア社会(ギナー参照)においては確かにそうである。マス社会とメディア社会は、異なる方法でアプローチすることができる。
私たちが自分の信念を自分の「直接的な」日常体験から得ることはますます少なくなり、あらゆる種類の明らかに「媒介された」情報(特に教育、科学、メディア)から得ることが多くなっている、と主張する人もいるかもしれない。さらに、こうした情報は以前よりも速く流通し、これまで以上に生き生きとした方法で呼び起こされるようになった。このことは、現在進行中のマルチメディア革命に特に当てはまる。この革命では、接続と変換、データとビデオ画像が、巨大な世界的情報の渦の中に溶け込んでいるように見える。バーチャル・リアリティ”の革命は、その最終段階に過ぎないように思われる。
例えば、この2世紀ほどの間に生まれた、まったく新しい任意団体の世界や、最近では、XR、グリーンピース、国境なき医師団、アムネスティ・インターナショナルなどの非政府組織や新しい社会運動の国際的なレベルでも、そのようなものがある。つまり、根こそぎ奪われることを批判するだけでは単純で、個人もまた、多くの新しい、前例のない方法で社会に再び根を下ろしているのだ。
政府、企業、その他の社会的主体が、客観的にどうあるべきか、何をしているかが重要なだけでなく、主観的にどう経験され、どう見られているかが重要な、ますます複雑化する世界に対処することを学ばなければならないのは事実である(ブーアスティン『イメージ』)。認識やイメージが生まれ、それがその有効性を決定する上で果たす役割はますます大きくなっている。権力、資金、デマゴギーなど、関係者が自由に使える手段を駆使して、これらを形成しようとするのは当然である。自分自身のイメージだけでなく、自分たちが何らかの利害関係を持つすべての問題に対する認識もそうだ。
彼らは次第に、自分たちが単に「一般大衆」や一人の聴衆だけを相手にしているのではなく、まったく異なる問題を重要視する多くの大衆や部分的な聴衆を相手にしていることを認識するようになった。企業を例にとってみよう。第一の大衆とは、株主と株式市場、銀行と金融界である。第二のパブリックは、競合他社、業界団体、経済界である。第三の公共は、従業員、労働組合、社会的世界の公共である。第四の公共は、将来起こりうる従業員、学校、教育界である。第5の公共は、顧客、流通チェーン、消費者一般である。
第六の公共は、公務員、関連部門、当局全般である。第7の公共とは、政治家、政党、選挙界のことである。第8の大衆とは、報道記者、メディア関係者、オピニオンリーダー全般である。第9の公共は、活動家グループ、社会組織、団体生活全般である。第10の公共は、隣人、近隣や町の同居人である。そしてもっとある。一方的な企業のコミュニケーション戦略(例えば、他の9つよりも1つ目をあからさまに優遇しすぎる)は、しばしば大きな緊張の根源にある。効果的なコミュニケーション戦略は、ターゲットとなるオーディエンスと問題を両立させる方法を知っている。
これらすべての領域において、問題は絶えず浮かんでは消え、重要なコンタクトを促進することもあれば、負担をかけることもある。そのため、シニア・コミュニケーション・マネジャーは、この多面的な力の場の変化をできる限り詳細に追うことに、明らかな関心を持っている。そのためには様々な方法がある。一つはメディアをフォローすることである。これは、関連するニュースの形式的な「内容分析」と、現在流行している議論の継続的な「言説分析」によって、さらに構造化することができる。また、「意見・態度」調査の調査結果にも従わなければならない。これは、「詳細なインタビュー」や「フォーカス・グループ」による質的な調査によって、さらに強化されるかもしれない。そして最後に、上級の政策立案者は、さまざまな背景を持つ幅広い関係者との非公式な個人的接触を確立し、探求しなければならない。マネジメント、マーケティング、コミュニケーションは、「歩き回る」ことによって、重要な洞察やシグナルを与えてくれるかもしれない。常に象牙の塔に気をつけよう。
いったん問題が結晶化すると、形式や内容に決定的な影響を与えることは難しくなる。そのため、利害関係者はできるだけ早い段階で介入し、反応的であるよりも積極的であろうとする。これは、パブリック・リレーションズとパブリック・アフェアーズの間のグレーゾーンに特に当てはまる。例えば、新しいテクノロジーは常に遠くの地平線上に出現し、論争や新たな規制を生む可能性がある。ロビー団体や圧力団体は、できるだけ早くこのような議論に参加し、その議論がどのような言葉やイメージで構成され、公共の議題として取り上げられるかに影響を与えようとする。彼らは環境を 「スキャン」し、関連する議論を 「モニター」する。近年、多国籍企業やその他の団体は、「イシュー・マネージャー」(組織とより広範な社会との相互作用を追跡し、舵取りをしなければならない者)という役職を設けている。
これは論理的なステップだが、意見や認識を測定し、予測し、コントロールする能力に対する過度の自信に基づいている場合は別である。例えば、意思決定者がそれぞれの危機の独自性を理解できず、単に本に従ってしまうような場合である。
本書の精緻な事例説明は、極めて強力な機関がいかに手の内を明かしすぎ、世間のムードの変化に完全に意表を突かれたかを何度も説明してきた。不測の事態を想定した通常のシナリオでさえ、失敗することがある。たいていの場合はうまくいくが、時折、熱狂的な技術官僚の面前で吹っ飛ぶこともある。
では、どう対処すればいいのか?現実は見かけよりもはるかに堅固で安定していないことを常に自覚すること、静かな表層の下には、心の揺れを準備する深い力が働いている可能性があることを認めること、管理可能な変化の長い期間は、遅かれ早かれ激しい乱気流の短いエピソードに取って代わられることを認識することである。このことを計算に入れない者は、時が来れば必然的に押し流されてしまうだろう。それは、明るい夏の日に静かに漕いでいる、涼しい山の小川のようなものだ。水平線に暗雲が立ち込め、数マイル上流ではすでに天候が変わり、空から豪雨が降り始めているかもしれない。一瞬のうちに水の壁が渓谷を押し寄せ、邪魔になるものすべて、そしてすべての人を押しつぶすかもしれない。地元の標識やガイドはその可能性を警告しているが、外部からの訪問者は常に意表を突かれる。ある問題に対するムードが突然変わることもある。
つまり、常に警戒を怠らないようにしなければならない問題の第一の側面は、私がサイコダイナミズムと呼びたいものである。人は常に、明白と思われることを疑い、コインの裏側、月の裏側、ブラックホールを見る方法を見つけなければならない。どのような意見や態度、どのような認識やイメージにも、突然ひっくり返るような影や暗黒面がある。このことは、マーケティングにおけるいくつかの対照的な古典的な例でよく説明できるだろう。ハイネケンは最初、ノー(または低)アルコールのバックラー・ビールを、自国市場であるオランダで発売した。このビールは大成功を収めたが、あるスタンダップ・コメディアンが大晦日のテレビ番組でこのビールを「弱虫のためのノンアルコール・ビール」と揶揄した。最終的に、このビールは自国市場からは撤退せざるを得なくなったが、世界の他の地域では市場リーダーの1社であり続けた。今日では、ハイネケン0.0%に取って代わられた。
逆の例はユニリーバで、オモとパーシルという洗剤ブランドにエクストラストロング「パワー」成分を配合し、西欧全域で販売した。しかし、競合のプロクター・アンド・ギャンブル社が、この2つのブランドの洗剤が衣服に穴を開けることを示す写真を配布し、消費者団体や研究機関が、この成分が少し過剰に作用していることを確認したため、ユニリーバは、まず製品を改良し、次に回収せざるを得なくなった。どちらの例も、「軽い」や 「強い」という製品のイメージは常に脆弱であることを示している。なぜなら、これらのイメージは 「軽すぎる」や 「強すぎる」と簡単に言い換えられるからだ。その可能性を認めることはできるが、それは確実なことではない。製品そのものだけでなく、より広い文脈にも左右される。ゲシュタルトのスイッチは内側からではなく、外側から入ることもあるのだ。
常に警戒しておかなければならない第二の側面は、私がソシオダイナミズムと呼びたいものである。知覚の転換が始まり、ある集団の中に広がっていく理由には、あらゆる種類のものがあるかもしれない。第2章では、よく知られた制度に関する魅力的な話は、他のものよりもはるかに簡単に再生産されることを見てきた。特に、より深い恐怖や憤りと共鳴している場合はなおさらである。大衆はそれを興味深い会話の材料だと感じ、メディアはそれをセンセーショナルなニュースの材料だと感じる。注目は再集中し、発行部数は加速し、その記事がトップニュースになることもある。これは、マーケティングにおける3つ目の典型的な例でよく説明できるだろう。
成功したドイツの自動車メーカー、ダイムラー・ベンツは、まったく新しいモデル、Aクラスまたは「ベイビー」ベンツの導入を決定した。テストドライバー、自動車雑誌、メディア、そして一般大衆による最初の評判は非常に熱狂的なものであったが、スカンジナビアで、北部の極寒の冬を想定した非常に珍しい「エルク」テストが行われた際、1台の「ベイビー」が転倒した。この偉業はカメラに記録され、写真は世界中を駆け巡った。もしこれが他の、それほど格式の高くないブランドだったら、このような騒ぎにはならなかったかもしれない。しかし、ドイツの堅固さ(そしておそらくは傲慢さ)を体現しているメルセデスだったため、誰もが滑稽に感じたのだ。ずっと後になって、他のメーカーの同クラスのモデルの多くも、エルク・テストには簡単に耐えられなかったことが判明した(シュミット)。自動車メーカー各社はばらばらに、「自動安定制御」という追加の手段を採用した。
これらの例は、危機管理とコミュニケーション管理において数十年の経験を持つ、世界で最も強力で成功した企業に関するものである。注目すべきは、後世の証言によれば、彼らは何が襲ってくるのか見ていなかったし、それをかわす方法を見つけることもできなかったということだ。3社(ハイネケン、ユニリーバ、ダイムラー・ベンツ)の損失は合計で数十億ドルに上った。これらは、世論と認識の急速かつ急激で大規模な変化であり、完全に意表を突かれた。
かつては稀な例外であったことが、やがて物理的な世界でも、大衆の反応の領域でも、より日常的な出来事となるかもしれない。私たちは科学、研究、管理の迷信にとらわれていた。測定する=知る=予測する=コントロールするという「三位一体」である。次の半世紀の間に、これはますます妥当性を失うかもしれない。なぜなら、急速かつ大規模で急激な変化が重要性を増すからだ。気候や天候においても、社会的・心理的な結果においても、直接的または間接的なものである。私たちの思考、感情、行動は、それに対して十分に対応できていない。
グレタ・トゥンバーグというスカンジーのアイコンの突然の出現が証明したように、世論は一夜にして変わるかもしれない。西ヨーロッパをはじめ世界中に「Skolstrejk(学校ストライキ)」が広まり、国際的指導者や一般市民が地球温暖化に対して緊急の注意を払うよう求めるきっかけとなった。コビッドに対する大衆の反応や、世界的な流行を食い止めようとする政府の努力に見られるように、奇妙な噂や陰謀論が絶えず変異している。氷の融解と海面上昇は、2つの劇的な映像によるメディアの宣伝が組み合わさった円環的な反応によって、最も効果的に議題となった。一方は、大ヒット映画『デイ・アフター・トゥモロー』であり、もう一方は、パワーポイント/基調講演をドラマ化した『不都合な真実』とその続編である。
コビッドは、さまざまなレベルでの大衆行動の噴出を伴っていた。物理的な群衆やデモの相乗効果によって、時には暴動の波へと変化した。オランダの何十もの市や町で夜間外出禁止令が発令されたときのように。また、イギリスの「絶滅の反乱」のような新たな社会運動の自己組織化も、すぐに他の地域にも波及した。そして最後に、ジョンソンのブレグジット(英国のEU離脱)、トランプの「メガ・マガ」(米国のEU離脱)という孤立主義的な世論が生まれた。両者とも、ケンブリッジ・アナリティカがフェイスブックのデータを大量に悪用した、違法なインターネットキャンペーンという新たな手法が引き金となり、それに伴うものだった。
これはまた、さまざまな世論のムードにも反映された。最初の例は、モデル、雑誌、オートクチュール、プレタポルテブランドなど、業界の大部分によってすぐに提唱された、ファッションにおける毛皮からフェイクへの加速度的なシフトだった。第二の例は、フランスと近隣諸国における大規模な抗議行動における「奇妙な誘引」であった。パリのエリートが地方の自動車所有者に課した措置として、両極化して見られた。第三の例は、「後発の東洋からの」コヴィードの脅威に対する西側先進国の反応における臨界点である。7週間(!)遅れ、効果的な対策が取られる前にウイルスが少なくとも2(2×7)=13,384倍に増加することを許した。
最後に、こうしたことはもちろん金融市場にも影響を与えた。ブームの「相転移」と証券取引所での暴落が相次ぎ、経済はわずか数週間後にその価値の3分の1を失うことになった。あの数ヶ月間、私たちは未来を容易に予見できることを当然だと思っていた。過去と現在から近未来を推定するだけである。不確実性を認識できなかっただけでなく、さまざまな重要な局面で大失敗した。単純化された予測、予報、変化の管理への暗黙の依存に疑問を投げかける。
このような現象すべてに対する我々の理解は極めて不十分であり、全く異なる用語でそれらを概念化する必要がある。しかし本書は、人間と社会の科学が、良くも悪くも常に模倣しようとしてきた自然科学から、実に多くのことを学べる可能性があることを示したかもしれない。しかし今回の教訓は、最終的にすべてをコントロール下に置くことができるということではない。それどころか、確実なのは不確実性だけなのだ。
組織やコミュニケーションの専門家たちは、自分たちが常に「舵取り」ができるという幻想を捨てなければならないかもしれない。効果的な行動とは、その深遠な真実を無視するのではなく、認識することである。ボクシングやレスリングではなく柔道や柔術であり、ボート漕ぎではなくカヌーであり、スピードボートレースではなくヨットである。直接的に相手や要素を支配しようとするのではなく、直感的にそれらのパワーや方向性を感じ取り、自分の目的のために利用しようとするのである。本書で出会った最も成功したコミュニケーターはサーファーだった。出来事や世論の波に乗るサーファーだ。
