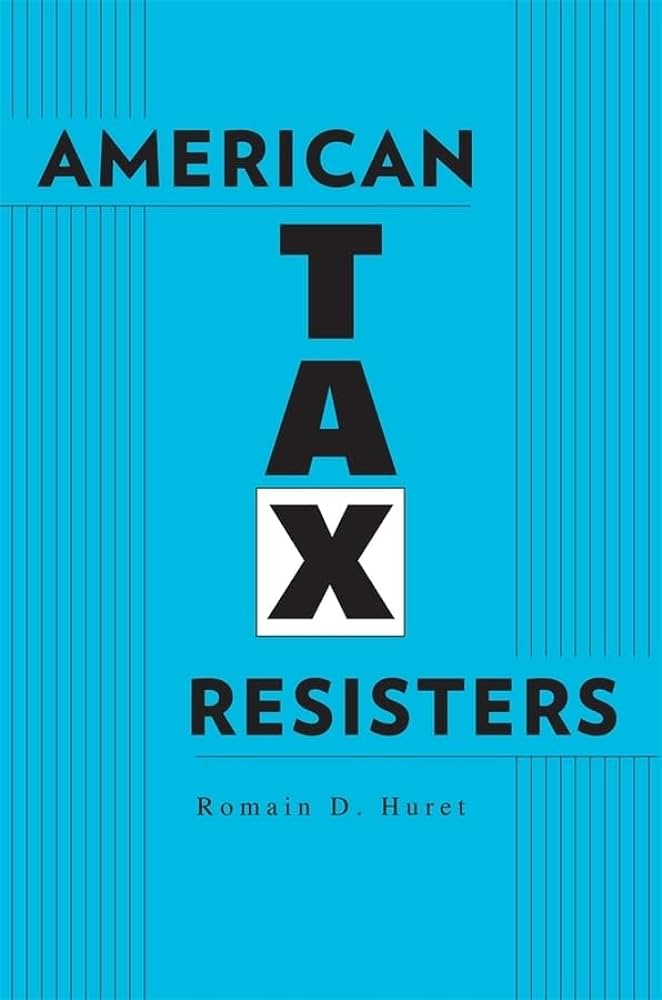
American Tax Resisters
アメリカ税制改革同盟
アメリカの納税抵抗者たち
ロマン・D・ユレ
マサチューセッツ州ケンブリッジ、英国ロンドン 2014
アリアーヌ、エミリアン、メルヴィル、ラファエルへ
目次
- プロローグ
- 1. 違憲の戦争税
- 2. 内国税の廃止
- 3. 不愉快な所得税
- 4. 母親のためでも兵士のためでもない
- 5. パンとサーカスの民主主義
- 6. 台所から首都へ?
- 7. 「内国歳入」の暴政「サービス」
- 8. ティーパーティーの再来か?
- エピローグ
- 略語リスト
- 注釈
- 謝辞
- 索引
- エーマリク・タックス・レファレンス
- プロローグ
この世には、死と税金を除いて、確かだと言えるものは何もない。
-ベンジャミン・フランクリン(1789)
ベンジャミン・フランクリンの機知に富んだ言葉は、今日、ほとんどのアメリカ国民に親しまれている。毎年4月15日になると、多くの人が確定申告書に記入し、内国歳入庁に送ろうと慌ただしくなる。貧しきリチャードが死について正しかったことは間違いない。しかし彼は、人が課税に抵抗できることを忘れていた。市民は1040フォームへの署名を拒否し、連邦税務当局への送付を怠り、徴税に抗議する政治運動や社会運動を組織することができる。本書は、税金の不確実性に焦点を当てることで、フランクリンの有名な発言に補足を加える。本書は、アメリカにおける累進課税への抵抗を浮き彫りにしている。この国が地球上で最も豊かな国のひとつになるにつれ、連邦税による所得の再分配という考え方が登場し、富裕な市民や大企業は貧しい人々よりも多くの税金を払うべきなのかという、ひとつの率直な疑問が提起された。ほとんどの民主主義国家では、累進課税は資本主義の陰で、企業の拡大や少数の市民の異常なまでの富裕化によって深く影響を受けた社会秩序を安定させるために生まれた。
犠牲にした。このような再分配はどこでも反対を招き、不平等、連帯、社会契約に関する議論を引き起こした。アメリカ独立革命から現在に至るまで、アメリカにおける例外的な富の蓄積は、共和制の初期に始まった税制論争をさらに激化させた1。
1785年10月、若きトマス・ジェファーソンはジェームズ・マディソンに手紙を書き、パリから数マイル離れた小さな村、フォンテーヌブローの貧しい女性との出会いを綴った。ジェファーソンが彼女に抱いた最大の関心事は、フランスのアンシャン・レジームにおける公平性と課税の問題であった。「財産の不平等を静かに緩和するもう一つの方法」として、彼は「ある一定額以下の財産はすべて非課税とし、それ以上の財産には幾何学的な累進課税を行うこと」を主張した。しかし、累進課税のアイデアを持ち出す前に、革命から生まれた国家には制度が必要だった。その2年後、フィラデルフィアで連邦権力をめぐる熱のこもった憲法討議が行われ、重要な決定が下された2。
「代表なくして課税なし」という標語は、代議員たちのコンセンサスを象徴するものであり、イギリス王室が課税していた不公平税に対する回答であった。建国者たちは、共和国が直面している軍事的・財政的危機に鑑み、連邦税が正当化されると判断したのである。憲法第1条第8節には議会の権限が列挙され、まず財布の権限から始まった。連邦議会議員は、「合衆国の債務を支払い、共同防衛と一般福祉を賄う」ために、「租税、関税、賦課金および物品税」を徴収することができる。これらの税金は全国一律でなければならなかった。さらに、直接税は憲法によって厳しく制限されていた。第1条第9節は、「人頭税その他の直接税は、前記の国勢調査または人口調査に比例しない限り、これを課してはならない」と主張した。憲法は、不明確ではあるが、無制限の課税の可能性を開いたのである。ジェームズ・マディソンは、『1787年連邦大会の討議に関するノート』の中で、ある代議員が同僚に直接税の正確な意味を尋ねたとき、誰も答えようとしなかったと主張している。定義が曖昧であったため、支配エリートの仕事は複雑なものとなった3。
1790年代、連邦主義者たちが新たな財政権の行使に踏み切ったとき、彼らは地方の反乱を引き起こし、若い国家を弱体化させることにしか成功しなかった。酒税や財産税は、市民や敵対勢力から厳しい言葉で非難された。1793年のウイスキーの反乱と、1798年の冬にアメリカ独立戦争の退役軍人ジョン・フリースが率いた窓税に対する反乱である。2年後、議会は悪名高い窓税の廃止を決定し、1802年には国内のすべての内国税を廃止した。関税はすぐに、小規模な連邦政府にとって最も効率的な歳入徴収方法として登場した。関税政策により、アメリカ人は、特に奴隷所有者が所有する財産に課税しないことで、セクション間や社会的緊張の高まりを避けることができた。1812年戦争を除いて、南北戦争までアメリカにおける内国課税はこれで終わりを告げた4。
1805年3月4日に行われた第2回大統領就任演説で、トーマス・ジェファーソンは、例外的で限定的な連邦税制を同胞であるアメリカ国民に提示することを喜んだ。彼は、「いかなる農民、いかなる機械工、いかなる労働者が合衆国の徴税人を見たことがあるかと問うことは、アメリカ人の喜びであり誇りである」と約束した。ホワイトハウスに到着すると、18年前にフランスで行った議論とはかけ離れた、公共支出と課税の削減を求める縮小政策を唱えた。ジェファーソンは、連邦税の徴収者がいなければ、アメリカ人は納税者のいない共和国に住むことになると考えた。それは、脆弱な連邦を守るために払うべき代償だった。唯一の例外は、贅沢品への課税と関税であった。しかし、多くのアメリカ人は、こうした税金は納税者ではなく顧客が自発的に支払うものだと信じていた。つまり、市民は酒やタバコなどの課税商品を買わないことで、税金を支払わない自由があったのだ。その結果、連邦税は金持ちも貧乏人も同じ隠れた税金を払うという逆進性の強いものとなった。個々の州でも、地方税の累進性を制限するために、異なる形態の財産を同じ方法で評価し、同じ税率で課税することを義務づける統一条項が採用された。トーマス・ジェファーソンが約束したように、アメリカ南北戦争が起こるまで、連邦レベルでは所得にも財産にも課税されなかった5。
本書は、1861年4月のサムター要塞での最初の銃声から始まる。本書は、1861年4月のサムター要塞での最初の銃声から始まる。戦争が始まると、連邦政府の権限はますます拡大し、国家の隅々にまで突然、目に見える課税が行われるようになった。新しい連邦権力の介入に対するさまざまな形の抵抗とともに、税の公平性に関する議論が高まった。ポストベラムの時代になっても、多くのアメリカ人は、制度から受ける恩恵と引き換えに税金を納めていると考えていた。1876年に出版されたミシガン州の有名な法学者であり弁護士でもあったトーマス・M・クーリーの租税論では、市民や財産所有者は納税の「適切かつ完全な対価」として「政府がその生命、自由、財産に与える保護と、拠出された資金が適用される用途による財産価値の増加」を受けていると主張し、そのような相互性を完璧に捉えていた。しかし、連邦税は戦時下の合法的な交換の一形態として受け入れられたとはいえ、一時的なものであり、市民への恩恵がなくなればすぐに消滅すると信じられていた6。
農村主体の国家が工業国家へと移行するにつれ、新たな課税観が登場した。工業化と市場革命は、平等と貧困に関する活発な議論を引き起こした。大企業の出現と強盗男爵に対する攻撃は、企業を規制する方法として、また新しい産業国家における平等を促進する方法として、累進課税の正当性を強化した。問題は、憲法が議会に対し、各市民の所得に比例するのではなく、各州の人口に比例して直接税を課すよう求めていたことである。1910年、所得課税を合法化する修正第16条の批准が各州で議論される中、社会改革者であり、おそらくこの国で最高の税制専門家であったエドウィン・R・A・セリグマンは、累進課税を断固として支持し、「憲法が制定された当時の状況はもはや存在しない」と主張して、アメリカ人に憲法改正を促した。彼はさらに、「根底にある経済的・社会的諸力の発展が国家を生み出し、この発展が、創始者たちが夢にも思わなかったような多くの事柄について、全国一律の規制を必要とした」と付け加えた。彼にとって、互恵主義という考え方は「利己的で狭い」教義にすぎず、税金は各市民の支払い能力に応じて徴収されるべきものだった。この助言に従い、多くのアメリカ人、特に南部と西部では、最も公平な税金とは、各納税者から相応の「犠牲」を引き出すものであるとした7。
19世紀末、進歩主義者たちは、個人所得や法人所得への課税を含む税制改革は繁栄や福祉を脅かすものではないと説明した。彼らの信念は、学界で一般的な「貨幣の限界効用」の理論に基づいていた。つまり、稼げば稼ぐほど、最後の1ドルから得られる効用は少なくなるというものだ。ニューヨークの長屋に住む貧しい移民は必需品の支払いに全財産を費やし、金持ちは余剰収入を贅沢品に費やすことができた。「世界一の金持ち」を自称する「コモドア」の息子、ウィリアム・ヘンリー・ヴァンダービルトの非課税年収は1,000万ドルを超えていた。彼の驚異的な収入の上位層に課税することが、彼の生き方に影響を与えるだろうか?税制改革派はそうは考えず、富裕層が犠牲になっても経済的インセンティブが損なわれることはないと主張した8。
やがて進歩主義者たちは、このような財政的市民意識は公にされるべきであると主張した。理想的な共和国においては、平等の名の下に税金を多く納め、納税申告書を公開することは、最も裕福な市民の誇りであるべきだと彼らは主張した。さらに、富裕層の納税者は税負担を減らそうとはしないし、万が一減らしても、議会が税の抜け穴をふさぐことは比較的容易であるべきだとした。各納税者が犠牲にした正確な金額をすべての国民が知ることができるため、公表は進歩的なアジェンダの一部であった。内戦中、富裕層が支払った税金は新聞で公表された。税の公平性と社会正義の名の下に、なぜそのような情報公開を追求しないのだろうか9。
しかし、話はもっと複雑であることが判明した。1935年、ハーバード大学のメイソン・ハモンド教授が、フランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領による累進課税制度を非難した。所得税申告書の公開義務に抗議するために議会に送った手紙の中で、ハモンドはこの税制全体を違憲かつ 「非アメリカ的」なものと位置づけた。「このような政策が納税者を不愉快な宣伝や勧誘にさらすという実際的な危険とは別に、所得税そのものが、この国の少数派の市民に十分な苦難をもたらす。ハモンドは、「マイノリティの権利について語られる中、この少数派の所得税納税者は、憲法によってすべての市民に保証された権利において保護されるかもしれないと私には思える」と指摘した。ハーバード大学文学部教授は次に、累進課税に対する主な不満、すなわち恣意的な税率、無能な再分配、危険な宣伝について詳述した10。
増税反対派は、累進課税は根本的な誤りであるという考えを国民に植え付けようとした。内戦から現在に至るまで、彼らは同じ理念のマントを身にまとい、家庭、共同体、自由市場を神聖な場所とみなしてきた。彼らは、憲法がそのような権利を不可侵のものとして保護していると信じていた。強引な経済・社会改革を行う誤った理想主義者たちに擁護され、市民たちに警告した累進課税の目的は、アメリカの生活様式を構成するこれらの神聖な要素を内側から腐敗させることだった。彼らは、アメリカの例外主義の基盤を損なおうとする試みに激しく反対した。ほとんどの場合、彼らの演説や演説に注入されたイデオロギーは、高度な知的原則に導かれた首尾一貫した一連の理論ではなく、常識、歴史的先例、経験的分析に基づく一連の信念であった。租税抵抗者たちは、自分たちの論争を正当化する学術的な条約を読んでいたが、ニュースレターや一般書、保守的なパンフレットで構成される大衆的な反税文学に触れることでインスピレーションを得ていた。
彼らにとって、犠牲という概念そのものが、「階級法」に他ならなかった。19世紀末のヨーロッパの状況を参考に、多くの実業家や自由放任主義者は、内戦が終わるとすぐに、個人や企業の所得に課税するという社会主義的な考えを非難した。1888年、経済学者のデビッド・A・ウェルズは、「差別的な所得税という共産主義は、一部の市民に 『spoliation』を与えるだろう」と市民に警告した。国民の大多数が連邦税の支払いを避けるのであれば、犠牲という考えは意味をなさないとウェルズは付け加えた11。
結果として、段階的税率は純粋で単純な「没収」であった。連邦政府には、金持ちの金の使い道を決める権利も、他の市民に金を再分配する権利もない。所有権に対する攻撃であり、企業経営への悪質な介入であった。税制改革者たちの主張とは裏腹に、累進課税はインセンティブを破壊し、最もエネルギッシュで企業家精神にあふれた市民を萎縮させるものであった。勤勉さと自由放任経済に対する税制改革者の賛美は国家の特徴になり、非生産的な市民は怒れる過激派に標的にされた。このような真理主義的な見方では、ある階級から別の階級への税金の移転は、無能で無駄な法案にしか見えなかった12。
内戦以降、公共性、再分配、犠牲意識に対する攻撃はシームレスに連動した。納税抵抗者たちは、税金の公開は違憲のプライバシー侵害であり、企業に対する危険な攻撃であると非難した。彼らは、競合他社に企業秘密が知られ、ビジネスが破綻することを恐れた。さらに、公開規定は、秘密主義が頂点に君臨するビジネスマンのプロ意識に挑戦するものであり、市民に誤った社会正義感を与え、実際にビジネスを危うくすると主張した。
本書は、累進課税の進展に抵抗したアメリカの白人上流階級と中流階級について考察している。抵抗とは、個人が税金を嫌うことと混同してはならない。税金を払うのが好きな人はほとんどいないが、大多数の市民は抵抗勢力にはならない。また、抵抗は内国歳入庁に対する暴力的で違法な行動に限定されるべきではない。より重要なのは、納税者が連邦税務当局に対して自分たちの利益と世界観を守るために用いた、法的かつ政治的な抗議行動であるということである。裕福な市民は財力と政治的機会に恵まれていたため、所得再分配や企業規制を求める民主的圧力を抑制する力があった。実際、彼らの目標は、請願、ロビー活動、市民集会を通じて、個人や集団の資本蓄積を最大化し、連邦政府の介入を最小化することであった13。
租税抵抗は常に経済的な問題をはるかに超えるものであった。抵抗者たちは自分たちの金を守るためだけに戦ったのではなく、政治、権力、社会階層に関する自分たちの概念を守るために戦ったのである。道徳的、人種的、社会的信条は、抵抗者たちの課税許容閾値と運動としての進化に直接的な影響を与えた。抵抗者たちの十字軍は、エリートの役割や、抵抗者たちがこの国で正当な権力と考えるものについての象徴、価値観、情熱に満ちていた。彼らは、公共の利益と私的な富、連邦政府と個人、権力の合法的な形態と非合法な形態の境界線に疑問を投げかけた14。
その結果、反スタチズムのレトリックにもかかわらず、彼らの抵抗は常に連邦政府との交渉という社会的・政治的行為となった。納税抵抗者と連邦政府の介入との関係を分析することで、この説明は反スタティズムのより微妙なビジョンを提供する。彼らのキャンペーンは連邦政府に対して強い姿勢をとっていたが、納税抵抗者たちは無政府主義の空白の中で生きていたわけではない。内戦から現在に至るまで、税金は危機の際に連邦政府の行動を賄うために時折必要とされてきた。税金に直面したとき、特に戦時中、過激派は、富裕層に最も多く課税する累進課税ではなく、誰もが平等に支払う逆進課税を熱心に推進しようとした。危機が去ると、彼らは構築された税制を着実に侵食していった。
フランスの哲学者ミシェル・フーコーは、権力への抵抗が近代社会の中心的な特徴であることを社会科学者に思い出させたのは正しかったが、権力者や女性がしばしば最も積極的な抵抗者であったことを忘れていた。直線的で目的論的な歴史観では、税金への抗議は古代や近世の社会における後進的で伝統的な社会集団の結果であると見なされがちである。このような枠組みは、反対運動は近代のウェーバー的国民国家の誕生とともにすぐに消滅することを意味する。また、税は平等化の強力な社会的力であり、民主主義は容赦なく進歩したという考え方もある。もう一度言うが、この物語はより複雑に見える。前近代的な争いのレパートリーにルーツがあるとはいえ、アメリカにおける税の抵抗は資本主義の出現とともに拡大し、地方と国家の両方のエリートによって擁護されてきた。内戦以来、彼らの行動は連邦税の構造を形成し、累進課税を支持する民主的圧力を制限してきた15。
本書は、課税への抵抗を生か死かの選択として記述するのではなく、抵抗者とその制度との相互作用を記述している。制度的な手続きによって、アメリカ市民は税制の設計に影響を与えることができ、しばしば抵抗者たちが望むものを与えることができた。このような相互作用は、この物語において請願が果たした中心的役割を説明するものである。税制改革に関する議論は常に公開され、抵抗勢力は税制の変更を予測し、それを抑制することができた。歳入法を担当する2つの議会委員会である下院議事法委員会と上院財政委員会に送られた請願書は、特に納税者団体が会員記録をほとんど残していなかったため、運動の規模を追跡するのに非常に役立った。請願書が抵抗の理由を説明するならば、名前と署名のリストは請願者についての多くの重要な情報を提供する。請願は、市民に納税意識を持たせるためだけでなく、特定の税の減免や廃止を提案するためにも使われた。さらに、納税者のいない共和国という虚構の中で、請願は政治的な連合を固め、時には選挙区を発明し、常に建国の父たちの輝かしい行動を永続させるのに役立った。言い換えれば、納税抵抗者は苦悩する納税者の代弁者であるという考えを伝えなければならなかった16。
内戦以来、累進課税に対する抵抗は、社会的、政治的、経済的条件の変化により、直線的な物語ではなかった。資本主義の発展、連邦政府の変貌、連邦税の漸進的拡大は、課税抵抗者のレトリックと行動の両方を根本的に再構成した。20世紀が始まると、米国は世界で最も生産性の高い工業国になった。このような発展は、アメリカ人の生活水準や日常生活に重大な影響を与えただけでなく、連邦政府を限定的な制度から、市場規制や社会工学の道具としてますます利用されるようになった。工業化の成功に由来する税金が連邦権力とその官僚機構の成長の財源となったため、累進課税をめぐる議論は国家にとって極めて重要なものとなった17。
19世紀半ばには、関税に基づく制限課税の考え方が優勢であった。19世紀半ばには、関税に基づく制限課税の考え方が優勢であったが、内戦によってコンセンサスが変化し、税負担の問題が浮上した。人口動態と経済の変化により、富は北東部の州に集中し、人口は西部に移動する傾向が強まったため、直接税の配分ルールは時代遅れになった。戦争が終わるとすぐに、富裕層の市民や実業家が所得税に反対し始めたのは偶然ではなかった。彼らの聖戦はやがて、税制改革と政府拡大のトロイの木馬とみなされたすべての内国税の廃止へと変わっていった。奴隷制後の社会では、税金の廃止は、個人や企業の所得に対するあらゆる形態の課税に反対する人々の叫びとなった。しかし、1893年の深刻な経済危機と実業家の富裕化によって、所得税の制限を支持する市民がますます増えていった。租税抵抗者たちは、組織における彼らの牙城のおかげで、国内の進歩的勢力を回避することができた。1895年、ポロック判決によって、連邦最高裁判所は共和国における連邦所得課税を違憲と宣言した。
しかし、この勝利はピュロスのようなものであった。1913年の憲法修正第16条の採択から第二次世界大戦まで、累進課税は新たな正当性を獲得した。納税者の国では、抵抗勢力は交渉を余儀なくされた。廃止や撤廃を求める声は、富裕な納税者の連邦税の負担軽減を求める声へと変わっていった。女性、兵士、貧しい市民に対する連邦政府の支出を制限するために、彼らは連邦政府の支出に反対する納税者の権利という概念を守ろうとした。そのような納税者の立場があれば、自分たちの資金が自分たちの嫌がる目的に使われるのを拒否することができただろう。1930年代、租税レジスタンス運動の最前線にいたのは実業家たちであった。彼らは、企業を統制する最善の方法として、納税申告書の公開と累進課税の強化が提唱されていたため、累進課税の拡大を抑制することに特に熱心であった。第二次世界大戦中に採用された大衆ベースの所得税は、国内における進歩的意見の勝利を意味し、納税抵抗者たちは不満を表明する場をほとんど与えられなくなった。それまで連邦税制を熱心に批判していた実業家たちも、冷戦と市場のグローバル化のために、限定的な累進課税を受け入れた。
戦後、租税レジスタンス運動は郊外に住む保守的な男女によって再活性化された。白人中産階級の世界では、連邦税は生きるか死ぬかの選択であり、生活のあらゆる面に活力を与えた。納税反対派は常に主に経済的な観点から自分たちの主張を述べてきたが、白人中産階級の保守派の言説には、まもなく新たな道徳的要請が出現した。福祉国家の発展により、彼らは、リバイアサン国家のあらゆる悪を体現するようになった連邦税の「廃止」または「抹殺」を求めるようになったのである。何年もの間、アメリカ人は彼らを嘲笑し、税金に抵抗する人々は破天荒者、あるいは「ネアンデルタール人」というレッテルを貼られた。1970年代、経済危機と新自由主義思想の勝利により、減税は中流階級の抵抗者、企業経営者、保守的知識人の連合の新たな優先課題となった。無税の世界という神話は、その後数十年にわたって連鎖した。政権を握った保守派が課税の互恵性という考え方を復活させ、生活保護を受けている人々のための支払いを拒否するにつれ、進歩性の多くの信条、特に犠牲と所得移転の考え方の終焉に貢献した。
納税者のいない共和国という神話を超え、累進課税の強化に反対した市民の役割を検証することで、本書は市民権についても述べている。不朽のレジスタンス運動は、アメリカの民主主義について考える機会を与えてくれた。内戦以来、課税という争点は、近代国家における富と社会正義の問題を提起してきた。納税抵抗者たちに焦点を当てることで、本書は税金についてだけでなく、何よりもまず、アメリカにおける社会正義と民主主義の価値について書かれた本なのである18。
