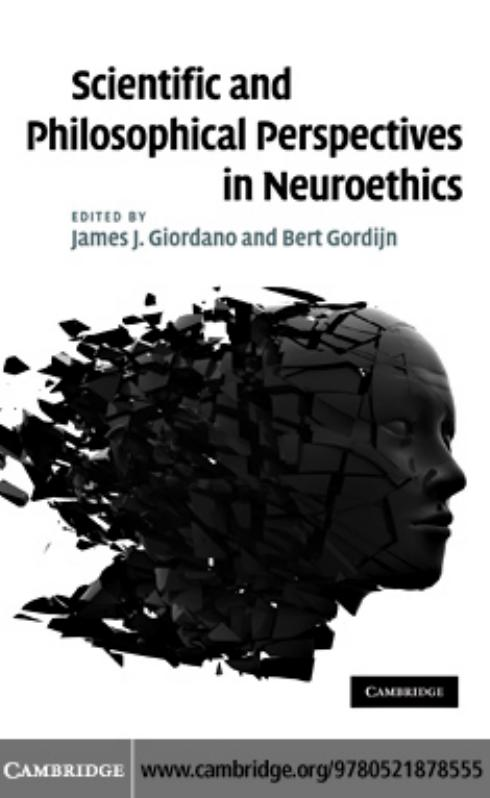
Scientific and Philosophical Perspectives in Neuroethics.
神経倫理学における科学的・哲学的視点
神経科学は神経系の構造と機能についての洞察を提供してきたが、意識、心、自己の本質については難しい問題が残っている。おそらく最も困難な問題は、神経科学的情報の意味や、社会的な「善」の解釈と一致するような神経科学的知識をどのように追求し、活用するかということであろう。
神経科学と生命倫理の研究者や大学院生向けに書かれた本書は、神経科学とニューロテクノロジーの重要な発展を探求し、そのような進歩が生み出す哲学的、倫理的、社会的な問題や課題を取り上げている。本書では、3つの核となる問題を検証している。第一に、神経科学的探究の範囲と方向性とは何か?第二に、これまでの進歩が科学的・哲学的な考え方にどのような影響を及ぼしてきたか、そして最後に、この進歩や知識は、現在と未来の両方において、どのような倫理的問題や課題を引き起こしているのか、ということである。
JAMES J. GIORDANO
オックスフォード大学ブラックフライヤーズ・ホール哲学心理学センターフェロー、米国バージニア州アーリントンのポトマック政策研究所ニューロテクノロジー研究センター所長。痛みの神経科学と神経哲学を中心に、痛みのケア、精神医学、公共生活におけるニューロテクノロジーの開発と使用から生じる神経倫理的問題に関心を寄せている。
ダブリン市立大学倫理学教授、倫理研究所所長。また、欧州医療哲学学会(European Society for Philosophy of Medicine and Health Care)および欧州ビジネス倫理ネットワーク(European Business Ethics Network)アイルランド支部の幹事も務める。現在の研究テーマは、ナノテクノロジー、地球工学、ニューロテクノロジーにおける倫理的問題である。
神経倫理学における科学的・哲学的視点
編集:ジェームス・J・ジョルダーノ(JAMES J. GIORDANO, PH.D.)
IPS哲学心理学センター
オックスフォード大学(英国)
バート・ゴルディン博士
アイルランド、ダブリン市立大学
ケンブリッジ大学出版局
医師、学者、教師、指導者、友人、そしてインスピレーションを与えてくれたエドモンド・ペレグリーノに捧ぐ。
目次
- 寄稿者リスト
- 巻頭言 n. レヴィ
- 謝辞
- 序論 j. ジョルダーノ
- 1 神経科学の発展 D. F. スワブ
- 2 現代における「神経科学」概念の起源 N. コールス&R. ベネディクター
- 3 尖端について R. D. エリス
- 4 心と体の問題 D. バーンバッハー
- 5 個人のアイデンティティと自己の本質 P. コスタ
- 6 宗教的問題と道徳的自律性の問題 a. autiero & l. galvagni
- 7 道徳の認知神経生物学に向けて P. M. チャーチランド
- 8 痛みの神経哲学から痛みのケアの神経倫理学へ J. J. ジョルダーノ
- 9 移植と異種移植 G. J. ボア
- 10 神経遺伝学と倫理 K. フィッツジェラルド&R. ウルツマン VII
- 11 ニューロイメージング J. バンメーター
- 12 我々は心を読むことができるか? E・ラシーヌ、E・ベル、J・イレス
- 13 脳コンピューター・インターフェース技術の可能性、限界、そして意味 T. ヒンターバーガー
- 14 神経工学 B. ゴルディン&A. M. バイクス
- 15 公共財としての神経技術 a. m. jeannotte, k. n. schiller, l. m. reeves, e. g. derenzo & d. k. mcbride
- 16 グローバリゼーション:多元的な関心と文脈 R. H. ブランク
- 17 人間の条件と繁栄への努力 A. ジニ&J. ジョルダーノ
- 18 ニューロ・トークの限界 M. B. クローフォード
- あとがき W. グラノン
- 索引
序文
ニール・レヴィ
神経倫理学は実にエキサイティングな試みである。人類は長い間、私たちが生きる世界と私たち自身の根本的な性質に関する問いに頭を悩ませてきた。なぜ道徳的なのか。人間に自由意志はあるのか?私たちは互いにどのように振る舞うべきなのか?私たちは何かを知ることができるのだろうか?これらは哲学と呼ばれるようになった学問の問題である。人類の歴史の大半において、これらの問いは利用可能なあらゆる手段を駆使して追求されてきたが、最近のある時期、おそらく19世紀末には、哲学的な問いは科学的な問いと切り離されるようになった。哲学者たちは、科学が自分たちの研究に多くの光を当てられると考えるのは間違いだと考えたのである。
神経倫理学は、関連する多くの発展(実験哲学、生物学哲学、認知科学)とともに、この分離に対する反動の一部である。科学は人間の認識論の頂点に立つ成果であり、その独特な方法は人間の認知的限界を補い、人類史上前例のないほど蓄積された信頼できる知識体系を構築するのに役立っている。哲学者がこの知識体系から自らを切り離すことは狂気の沙汰である。しかし、哲学者は概念分析や論理学において、科学の人間的意義を理解する上でかけがえのないスキルを持っている。さらに、哲学者は、ある意味では科学の成果に勝るとも劣らない、独自の伝統を有している。科学と哲学を融合させることは、どちらか一方だけでは不可能なほど、人間の生活や哲学的な問題の理解に貢献することを約束するものである。
しかし、神経倫理学が重要である理由はもう一つある。神経倫理学が扱う倫理的問題は、真に差し迫ったものである。この点で、神経倫理学を、それに先立つ応用倫理学である生命倫理学と比較することは、示唆に富む。生命倫理学は、過去30~40年の間に生命科学から生まれた目もくらむような新技術の乱用の可能性に対する懸念から発展した。これらの技術は、人間の存在の中心的な側面に関わるものであり、生命をこの世に誕生させ、それを延長させたり、終わらせたりする力に他ならなかった。したがって、関連する技術(体外受精から幹細胞、ゲノム革命まで)は、道徳的関心の焦点となった。しかし、これらの技術が重要であることは間違いないが、心の科学に由来する技術やテクノロジーは、人間であることの意味についてさらに深遠な問題を提起し、道徳的思考により大きな課題を突きつけていると言える。
生命よりも重要なものがあるだろうか?この問いに対する伝統的な答えがある。魂というものがあるとすれば、それは神学者の領域である。しかし、魂に最も近い世俗的なものは、間違いなく心である。少なくとも、個人的アイデンティティというもっともらしい概念に照らし合わせれば、私たちを私たらしめているのは心であり、私たちを道徳的に重要な存在にし、人間関係を意味のあるものにしているのも、紛れもなく心である。しかし、心の科学は、人間の心を支配し、それを変化させ、強化し、思い通りに作り変える力を約束し、あるいは脅かしているように見える。心は魂に最も近い世俗的なものであることを考えれば、多くの人が、これは人間が持つべき力なのだろうかと考えるのも不思議ではない。
心の科学から生まれる可能性のあるアプリケーションのいくつかを考えてみよう。そのうちのいくつかは、間違いなく粗い形ではあるが、すでに利用可能である。誰かが嘘をついているのか、それとも本当のことを言っているのか、ある程度確実に判断できる技術はすでにある。しかし、これは読心術の開発への第一歩に過ぎないと考える人もいる。私たちは、脳から直接思考を読み取る方向に大きな一歩を踏み出している。被験者が曖昧な図形をどのように解決するかを判断したり、特定の人物や建物を思い浮かべたり、被験者がボタンを押す10秒前に、2つのボタンのうちどちらを押すかを60%の精度で予測することさえできる!これは、オーウェル的なパラノイアを凌駕するような、恐ろしい意味を持つ技術だと危惧する人もいる。信頼性の高い思考読み取りマシンは、悪の手に渡れば、私たちのプライバシーを侵害する究極の存在となるだろう。しかも、これほど強力なテクノロジーであれば、どんな手も正しいのだろうか?権力は腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する。
哲学者の中には、少なくとも近い将来、そしておそらくずっと、私たちが心配することはほとんどないのではないか、本物の読心術マシンは永遠に手の届かないところにあるのではないかと考える人もいる。しかし、読心術が恐ろしいものだとすれば、マインド・コントロールはどれほど恐ろしいものだろうか?残念ながら、これは不可能と証明されそうな技術ではない。
私たちは心の科学から得た技術を密かに使い、さまざまな方法で思考を調整することができる。オキシトシンという神経伝達物質を使えば、人々の信頼傾向を高めることができる。信頼は一般的に良いことだと思うかもしれないが、この力がデマゴギー的な政治家や中古車のセールスマンにどのように使われるかを考えてみよう。われわれは、被験者が遭遇する環境を、彼らの自制心の資源を枯渇させることがわかっている方法で構成することができる。β遮断薬であるプロプラノロールを投与して、人々の記憶を薄れさせることもできる。将来的には、もっと劇的な介入をすることができるようになるかもしれない。対象となる記憶を正確に消去したり、新しい信念を挿入したりする。ことができるようになるかもしれない(信念の全体的な性質を考えると、これは不可能だと考える哲学者もいるが)。
これらは明らかに恐ろしい可能性である。しかし、おそらく私たちは、いつか未来に起こるかもしれないことを心配するよりも、今現在起こっていることに関心を持つべきだ。心の科学から生まれた技術が広く応用されるのを待つ必要はない。それは今まさに、実に広大なスケールで起こっている。2004年には、オーストラリアだけで1,200万件もの抗うつ剤が医薬品給付制度を通じて処方された(Bell 2005)。さらに多くの人にとって心配なのは、注意欠陥多動性障害(ADHD)の治療にメチルフェニデートが使われていることだ。私たちは子ども時代を薬漬けにしているのだろうか?
精神医薬品の広範な使用に関する懸念の中心は、真正性(Elliott 1998)、心の機械化(Freedman 1998)、精神医薬品に対する適切な態度(Sandel 2007)に関する問題であり、また、精神医薬品が認知能力を向上させる場合、不公正をもたらす可能性がある(Sahakian & Morein-Zamir 2007など)。これらの疑問はすべて、緊急かつ本質的に魅力的なものであり、その解決には、私たち自身が形成する社会の形がかかっている。
それは、神経科学(およびその他の心の科学)が生み出す新しい技術や技法に関する倫理的考察であり、生命倫理の伝統的な領域である種類の問題と密接に類似している(時には重複している)。Roskies (2002)は、この2つの事業を神経科学の倫理学と倫理学の神経科学と呼んでいる。神経倫理の魅力の中心的な理由は、この2つの分野が別個のものではないということである。その代わりに、心の科学から情報を得て心を考察することから得られる結果が、神経科学の倫理という見出しの下で検討する倫理的問題の理解に役立つのである。この「まえがき」の残りの部分では、このことがどのようにしてもたらされるのかを考えてみたい。
合理性
道徳的問題を考えるとき、私たちはそれによって合理的な解決策を導き出したいと願う。例えば、認知機能の向上が、私たちの社会の質に対して、一部の人々が懸念するような影響を本当に与えるのか、それとも本当に無害なのかを評価することである。もし悪影響がありそうであれば、その影響を回避または緩和する最善の方法は何か、また、そのために効果的な社会政策はどのように実行されるのが最善なのかを発見する必要がある。そのためには合理的な探求が必要である。心の科学が私たちの倫理的探求に劇的な影響を与える可能性のある一つの方法は、私たちがこのような合理的な思考にまったく、あるいはこれまで信じてきたような程度には関与できないことを示すことである。
心の科学は、私たちが理性的な考察を行うことができるという概念を、多くの点で脅かす。第一に、私たちの行動のうち、理由によって導かれているものは、私たちが考えていたよりもはるかに少ないことが明らかになった。この証拠は、主に社会心理学における行動の自動性に関する研究から得られている。自動的な行動とは、楽で、弾道的で(一旦開始されると中断されない)、一般的に無意識に開始されるものである。つまり、私たちの意識的な理由に応じて行われるのではなく、私たちが置かれている状況の特徴によって引き起こされる反射に近いものである。Stanovich(1999)によって紹介された影響力のある用語では、自動的な行動はシステム1のプロセスであり、ゆっくり、努力的、意識的、熟慮的なシステム2のプロセスではない。システム1のプロセスは進化的に古く、私たちが他の多くの動物と共有する認知プロセスであるのに対し、システム2のプロセスは私たち特有のものである。もし我々が理性的な動物であり、それが我々を区別するものであるならば、我々がシステム2のプロセスを展開する限りにおいてのみ、それは真実なのである。社会心理学から得られた脅威的な発見は、我々がしばしばシステム1のプロセスを展開するということではなく、システム2のプロセスの方が圧倒的に一般的であるということである。人間の行動の圧倒的多数は、自動的な心的プロセスによって導かれているのである(Bargh & Chartrand 1999)。心の科学に照らし合わせると、理性的な動物であるという私たちの主張は、突然揺らいで見える。
さらに悪いことが起こる。私たちがシステム2のプロセスを展開しているときでさえ、私たちの思考の合理性は私たちが期待しているよりも低い。この主張の根拠は、主に認知心理学、特にヒューリスティックスとバイアスの伝統的研究によるものである。ヒューリスティクスとは、私たちが通常そうしていることに気づかずに使っている精神的な近道や経験則のことであり、バイアスとは、私たちが判断を下す際に情報の重要性を加重する方法のことである。私たちが議論を評価したり決断を下すとき、ヒューリスティクスやバイアスを用いていることを示す証拠は膨大にあり、それはしばしば私たちを惑わせるものである。ここでは、私たちが情報を悪く評価する方法のほんの一部を紹介しよう。
確証バイアスとは、自分が抱いている仮説を否定する証拠よりも、それを支持する証拠を探し求め、曖昧な証拠を自分の仮説を支持するように解釈する系統的な傾向である(Nickerson 1998)。確証バイアスは(かなりの量の希望的観測とともに)、多くの人が超自然的な出来事を信じることの説明に役立っている。あなたの仮説が、夢は未来を予言するというものだとしよう。確証バイアスは、確証となる証拠(叔母が体調を崩している夢を見たが、その頃、叔母はひどい倒れ方をしたと知った)に注意を払い、確証とならない証拠(そのような出来事が起こっていないのに、知人に良いことや悪いことが起こる夢を見たすべての時)を無視する可能性を高める。確証バイアスは、利用可能性ヒューリスティック(ある出来事の確率を、その事例を思い浮かべやすいかどうかで評価する傾向)と連動して働く(Tversky & Kahneman 1973)。確証のある事例ほど思い出しやすいため、誠実に記憶検索を行うと、仮説が正しいと結論づけられる。
超自然的なものを信じる傾向は無害で些細なことだと思うかもしれない。しかし、ここで問題にしているようなバイアスが実世界に害を及ぼしていることは間違いない。その一例が、性的暴行の「よみがえった記憶」をめぐる最近の主張である。そのような回復した記憶が真実であったという証拠はないが、その多くが虚偽であったことは分かっている。したがって、そのような記憶を信頼できるとみなす理由はない。しかし、この証拠に基づいて、多くの人々が投獄され、多くの家族が取り返しのつかない形で崩壊した。なぜこのように突然、記憶の回復が相次いだのだろうか?その説明の一部は、抑圧された記憶の可能性を引き出すために一部のセラピストが用いたテクニックにある。彼らは、これらの記憶は深く抑圧されていると考えていたので、患者が思い出せない出来事を視覚化したり、それが起こったふりをするように勧めた。しかし、こうしたテクニックは、偽の記憶を作り出したり、想像を現実と勘違いさせたりするのに有効であることが知られている(Loftus 1993)。なぜ彼らはこのようなことをしたのだろうか?確証バイアスが彼らの行動を説明するのに役立つ。彼らは、これらのテクニックを使ったときに患者が改善したように見えることがあることに気づき、これらの改善についての別の説明を無視したのである(誰かが彼らの話を聞いていたという事実が、彼らの精神状態を助けただけなのだろうか?また、テクニックが役に立たなかったケースも無視した(Tavris & Aronson 2007)。例えば、「記憶」の鮮明さをその真実性の証拠とする患者や、仮説を体系的に検証する必要性に気づかないセラピスト、誠実な記憶や目撃証言を反論の余地のない証拠とする裁判所など、われわれの体系的な偏見や認知の限界に対する無知は、大きな弊害を引き起こす可能性がある。
抑圧された記憶の例は、私たちに2つの教訓を与えてくれる。第一に、神経倫理学が扱う問題がいかに現実的に重要であるかを示唆するのに役立つ。心の科学から得られた知識を法廷や臨床に応用することは、害を減らし、善を増やすことにつながるだろう。しかし第二に、私たちの合理性の限界、記憶の誤りやすさ、そして現実を知る指針としての経験の信頼性の低さを示す証拠が、いかに不穏なものであるかを理解すべきである。私たちは自分が合理的な存在だと思い、自分の記憶は過去の出来事の写しだと思い、自分の身の回りの世界がどのようなものかをよく把握していると思っているが、それは間違っているかもしれない。
道徳
合理性に対する脅威は完全に一般的なものであり、あらゆる領域にわたって合理的な熟慮を行う我々の能力を脅かすものである。こうした一般的な脅威に加え、特に道徳的熟慮に対する脅威がある。ある人たちの目には、心の科学は私たちが道徳的な問題について熟慮する能力がないことを示しているように映る。道徳的熟慮に対する脅威には、道徳的熟慮を全面的に脅かすものと、道徳的判断の特定の説明や特定の(とされる)道徳原理に焦点を当てるものの2種類がある。
このような研究の多くは、道徳的熟慮が真に合理的であるためには感情的すぎることを示すものであり、それによって特定の道徳理論に圧力をかけている。最も影響力のある理論のひとつは、(少なくとも間違いなく)人権の概念の根底にある理論であり、イマニュエル・カントと最も関係の深い、道徳とは本質的に権利と義務に関するものであるという義務論の理論である。義務論とそれに関連する権利と義務を理解するひとつの方法は、次のようなものである。つまり、そうすることが権利を侵害する場合を除き、私たちは常に福祉を向上させるべきである。よく知られた例として、有名なトロッコ問題を考えてみよう(Foot 1978)。この問題は、権利がいかに厚生最大化を制約するかを示すために考案されたものである。この問題では、より多くの人を救うことで厚生を最大化しようと行動するシナリオの2つのバリエーションが提示される:
(1)線路のそばで、5人のグループに向かってくるトロッコを見つけたとする。その人たちは苦境から逃れることができず、あなたが何もしなければ間違いなく殺される。目の前にレバーがあり、それを引けばトロッコを側線にそらすことができる。レバーを引くべきか?
多くの哲学者は、レバーを引くべきだという直観を持っている。さらに、道徳に関心を持つ心理学者の数が増えていることを受けてテストしたところ、ほとんどの一般人は同意した(Cushman et al. 2006)。しかしここで、この問題のバリエーションを考えてみよう:
(2) あなたが線路に架かる橋の上で、対向車が5人のグループに向かっているのを見たとする。その人たちは窮地から逃れることができず、あなたが何もしなければ間違いなく殺される。あなたの隣には大柄な男がいる。その大男を線路に突き落とせば、彼の大きな体格がトロッコを止めるだろう(あなたの小柄な体格では止められない)。大男を押すべきか?
ほとんどの哲学者は、大柄な男を押すべきではないという直感を持っている。そしてまた、ほとんどの一般人もそう思っている(実際、どちらの場合もほぼ同じ意見であり、約90%の人が同じ意見である(Hauser 2006)。一見したところ、これは不可解である。どちらも、1人を犠牲にして5人を救うという選択を迫られている。なぜ(1)の場合は5人を救うのが正しくて、(2)の場合はそうではないのか。
標準的な答えは、人には生存権を含む権利があり、大男を押すことはその権利を侵害するというものだ。しかし、トロッコを方向転換させることは、誰の権利も侵害していない(おそらく、私たちは大男を手段として使っているからだろう–大男がいなければ、トロッコを止めることはできない–しかし、トロッコを止めるために側線に大男がいる必要はないので、私たちは大男を手段として使っていない)。神経科学者による最近の研究は、この説明に疑問を投げかけている。
Greeneら(2001)は、トロッコ問題と同様の構造のジレンマを考える被験者の脳をスキャンした。その結果、被験者が非人間的なジレンマ(引き起こされる被害が間近で個人的なものではない)を考えた場合、脳のワーキングメモリーに関連する領域がかなりの程度活性化する一方、情動に関連する領域はほとんど活性化しないことがわかった。しかし、被験者が個人的な道徳的ジレンマを考えた場合、情動に関連する領域は有意な活性化を示したが、ワーキングメモリーに関連する領域は安静時のベースライン以下の活性化を示した。著者らは、誰かを直接殺すという考えは、誰かを助けなかったり、間接的な手段を使って傷つけたりする考えよりも、はるかに個人的な感情移入が強いことをもっともらしく示唆している。しかし、この結果の本当の意味は、私たちの道徳的判断の一部に脅威を与えていることにある。この結果が示しているのは、私たちの判断の一部、つまり福祉を最大化することに関係する判断だけが合理的思考の産物であり、それ以外の判断は私たちの合理的プロセスが生の感情に押し流された産物であるということだ。この結果は、徹底的な結果主義を支持するために義務論の直観を割り引く証拠とされてきた(Singer 2005)。
グリーンの結果が道徳的判断の重要な一分類に挑戦し、それが非合理的であることを明らかにしたように見えるなら、他の研究は、合理的な事業として考えられている道徳の構築全体を脅かしているように見える。ジョナサン・ヘイトは一連の研究の中で、一般人の道徳的判断は感情的反応によって左右されること、そして彼らがその判断を正当化するために提示する理論は、彼らの判断を守るために作られたその場しのぎの思い込みであることを明らかにした(Haidt 2001)。われわれは道徳的判断に至るまで理性的であると思い込んでいるが、実はその理性は合理化に過ぎないのだ、とハイドは指摘する。ウィートリーとともに、ハイドは、後催眠暗示を用いて感情的な反応を誘導することで、人々の道徳的判断に影響を与えることを示している(Wheatley & Haidt 2005)。これらの結果は、哲学者たちに愛されてきた、道徳は理由に反応するという考え方が誤りであることを示唆しているようだ。また、道徳的議論は道徳的進歩につながるという考え方も脅かすものである。
繰り返しになるが、この研究が私たちの自己概念に与える影響は劇的である。私たちが道徳的な動物であることを誇らしげに宣言するとき、私たちの行動は、チンパンジーやサル、さらにはもっと単純な動物が持つ互恵的利他主義や公平感を特徴づけるような、感情的反応によって駆動されるという意味ではない(Trivers 1985; de Waal 1996参照)。その代わりに私たちは、単に動物として受け継がれてきたものを超越した、理性的な道徳を自負している。このような自画自賛的な私たちのイメージには、大きな修飾が必要かもしれない。より現実的な問題として、これらの知見には政策的な意味合いがあるかもしれない。例えば、私たちの道徳的反応の一部(そして一部だけ)が、生々しい感情によって引き起こされる非合理的なものであることを示すことができれば、私たちはこれらの反応を割り引くように政策を書き換える強力な理由を手に入れることになる。
これらは、神経倫理学というまだ始まったばかりの学問分野が扱うトピックの一部に過ぎない。このページでは、多くのトピックを取り上げている。また、神経倫理の倫理と倫理の神経科学という、神経倫理の両分野に対する重要な貢献もある。本書がこれらのトピックに関する最後の言葉となるわけではないが、この急速に成長しつつある魅力的な分野を知る上で欠かすことのできないガイドとなるだろう。
謝辞
もちろん、本書のような書物は間違いなくグループ作業である。したがって、このやや新しく発展途上の分野の問題を考察し、科学と倫理の両方の成熟状況についてコメントするために時間を割いてくれたすべての研究者に感謝する。ケンブリッジ大学出版局のマーティン・グリフィスは、忍耐強く、親切で、励ましてくれ、ユーモアのセンスもある、理想的な出版物の編集者であった。コーディネーター兼プロジェクト・マネージャーを務めたシェリー・ラブレスには、著者を集め、会話を調整し、編集者、著者、出版社間の連絡役を務め、基本的にこのプロセスを実行可能なものにし、最終的にこの本を実現させるという、時に困難を極める努力をしてくれたことに特別の感謝を捧げたい。間違いなく、彼女のたゆまぬ努力、熱心な協力、そして限りない楽観主義と愛想の良さなしには、この本は実現しなかっただろう。
JGはサムエリ・ロックフェラー教授として、BGは客員研究員としてである。客員研究員プログラムは、本書、そして他のいくつかのプロジェクトを生み出した、まさにこの種のコラボレーションとエネルギーを生み出す素晴らしい場であったし、今もそうである。ジョージタウン大学でのJGの研究は、ロックフェラー信託(The Laurance S. Rockefeller Trust)の資金援助によるものであり、同信託による脳・心・癒し研究プログラムへの継続的な支援に感謝する。また、本プログラムの関連プロジェクトを支援してくれたバージニア州アレクサンドリアのサムエリ研究所にも感謝する。
また、英国オックスフォードの哲学心理学センターと米国バージニア州アーリントンのポトマック政策研究所の神経技術研究センターの継続的な支援にも感謝する。
この点で、JGはグラディス・スウィーニー博士、リチャード・フィン博士、ロジャー・スクルトン博士の温かい友情に特に感謝している。このプロジェクトの一部は、JGがテキサス工科大学健康科学センターで米国疼痛学会客員教授を務めていた時に取り組んだものであり、マーク・ボズウェル博士には、彼の洞察力、視点、素晴らしいブレーンストーミングのセッション、そして「来るべきものの形」についてのユーモアに感謝している。ポトマック政策研究所のニューロテクノロジー研究センターのデニス・マクブライド博士との長く楽しい会話は、「……石をひっくり返し、……俯瞰する」ために重要だった。そして「心の10年」プロジェクトに携わる同僚たちは、脳科学と心科学の研究と応用が直面するかもしれない倫理的な問題、疑問、可能性、そして恐怖に応えるべく、このプロジェクトを形作る上で大いに役立った。この点に関して、ジェームズ・オールズ博士、マイケル・シュワルツ博士、ジェームズ・アルバス博士、クリストフ・コッホ博士、マイケル・シュルマン博士、クリス・フォーサイス博士、その他多くの方々に感謝する。
どの本にも言えることだが、このプロジェクトには長い一日と(とても)夜更かしが相当数必要であった。そして、私たちの妻であるシェリー(ジョルダーノ)とエリス(ゴーディン)のサポート、やる気、元気、忍耐、愛情に心から感謝する。
はじめに
神経倫理学:成熟期を迎え、未来に向かう
J・J・ジョルダーノ
神経科学の分野は、神経生物学、解剖学、生理学、薬理学、心理学の学際領域として「進化」してきた。実験心理学や生理学的心理学の古い流れから発展した神経科学は、当初、感覚や運動システム、学習や記憶、認知、そして最終的には意識に関連する神経機能のメカニズムを扱った。これらの基本的なアプローチは、その後の医学(神経学、精神医学、疼痛ケアなど)、そして最近では社会的実践(消費者行動、精神的・宗教的実践や経験など)に特に関連する研究を育んだ。
米国では、議会が定めた「脳の10年」(1990~2000)が、神経科学研究を改めて強力に支援する政治的インセンティブとなった。その結果、神経遺伝学、神経薬理学、精神薬理学、ニューロイメージングなど、さまざまな分野で重要な発見がなされた。この進歩は米国内に限ったことではなく、むしろ「脳の10年」は国際協力の触媒となる資金基盤を提供する役割を果たした。これは、学術的、医学的、技術的な協力、急速な科学的発展、研究、医療、社会生活に広く影響を与える世界的な「シンクタンク」のような雰囲気から生まれた「神経科学の文化」の始まりであり、現在も続いていると感じている。
加えて、神経科学は最先端のバイオテクノロジーを利用する場となり、調査や介入の能力と限界を拡大させている。それでもなお、デイヴィッド・チャーマーズが神経科学の「難問」と呼ぶものが残っている。
意識の本質、「心」と「自分」の概念の妥当性、自由意志の概念、道徳的信念と行動の妥当性などである。これらの疑問は哲学的なものとみなされるかもしれないが、それにもかかわらず、神経科学的な知見が社会的な文脈でますます利用され、適用されるようになっているため、私たちが(神経科学的に関連する)「事実」であるとするものの性質が急速に変化しているにもかかわらず、これらの疑問は実際的であり、考慮することが不可欠である。したがって、おそらく最も困難な問題は、神経科学的情報の“意味“と、社会的な“善´`の解釈と一致するような神経科学的知識をどのように追求し、活用するかに関わる。これが神経倫理の仕事である。
ニューロエシックス(神経倫理学)という言葉は、NYタイムズ紙のジャーナリスト、ウィリアム・サファイアが2002年のダナ財団の会議でアメリカで初めて使ったもので、その後、学術的にも一般的にも使われるようになった。1つ目は道徳的思考の神経基盤の研究であり、2つ目は神経科学的研究とその応用から生じる倫理的(法的、社会的)問題を説明するものである。これらの定義は、(1)基礎となる自然哲学を理解する必要があり、(2)神経科学(その構成学問分野と科学的学際性を含む)を人文科学と結びつけることを公理とし、このようにして学際的アプローチを維持する。このようなアプローチが有効であるためには、事実(およびこれらの事実の相対的な偶発性を認めること)、哲学的構成、教義、偏見、(制度および実践としての)科学の実践的文脈、および社会と文化の現実と価値観に対する理解に基づいていなければならないと主張する。これにより、(1)神経科学に内在する問題と緊急性、(2)このような問題が含む道徳的側面、義務、責任、(3)このような問題、疑問、課題に対処し解決するために、さまざまな倫理体系やアプローチがどのように用いられるかを認識することができる。
神経倫理の構造と機能は、図A.1に描かれているように想定される。図A.1には、神経倫理の構造と機能が描かれている。私たちはこれを卵に例えて考える。「生きている」、「発展している」、「中身がある」のは内側で、「形、構造、支えを提供する」「殻がある」のは外側である。しかし、これらは相互に排他的なものではない。道徳的義務や倫理的な仕事と責任の遂行を生み出す、神経哲学や神経科学などの認識論的資本、焦点、目標といった“生きている内容物“がなければ、“殻“(研究、臨床、社会的応用などのためのガイドラインや方針など)は“空洞“となり、簡単に崩れてしまうだろう。同様に、よく考えられた、現実的で慎重なガイドラインや政策という「殻」によって提供される構造とサポートがなければ、神経科学の「生きた内容」(すなわち、認識論的資本、哲学的・倫理的主張)は発展することができず、形がなく脆弱で、実際に応用することもできないだろう。接点とは、神経科学と神経倫理学が個人と社会に貢献する次元である。しかし、これらはまた、変化し続ける知識基盤、新たに発生する道徳的問題、多様な倫理体系、そして多義的な政治的文化的価値観の力によって引き起こされる、最大の圧力がかかる点でもある。神経倫理学が公益に資するものであるならば、これらの力に対応し、耐え、配分しなければならない。そうするためには、科学、人文科学、資金提供機関、法律家、社会など、参加・関与する利害関係者の間で、情報、アイデア、インセンティブを継続的に共有し、相互に影響し合うことが必要であると、私たちは考えている。
多くの点で、これはトーマス・クーンが「認識論的危機(epistemic crisis)」と呼んだものを認識する新しい世界観を示唆しているのかもしれない。神経系、脳、そして心の概念について、これまで受け入れられてきた考え方は、(捨て去られることはないにせよ)新しい概念や人間の状態についての斬新な考え方を支持して修正されつつある。
しかし、教訓はどうだろうか?神経科学の問題とは、私たちがどのように知っているのか、私たちは何者なのか、ひいては存在と理解の本質に関わる問題である。このような探求の多くを可能にしてきた技術の進歩は、驚異的なスピードで進んできた。しかし、このような技術や知識の使用を導き、医療や社会への慎重な適用を促すべき哲学や倫理は、しばしば事後的なものとなりがちである。その認識と対応として、神経倫理学は、分野としてはやや発展途上ではあるが、(1)認識論的にも応用論的にも神経科学の人間学的重要性を明らかにし、(2)技術進歩のペースと軌跡に反省的方向性を与えようとする規範を着実に発展させている。
この観点から、本書は神経科学とニューロテクノロジーの重要な発展に関する情報を提供し、そのような進歩が生み出す哲学的、倫理的、社会的な疑問、問題、そして課題を取り上げている。繰り返しになるが、この分野は歴史が浅いが、問題の多くは急速に成熟し、かなりの議論と討論の焦点となっている。全体を通して、私たちは3つの核となる問いに基づいて議論を進めてきた: 第一に、神経科学的探究の範囲と方向性は何か?第二に、これまでの進歩が科学的・哲学的な考え方にどのような影響を与えてきたのか、また、今後どのような認識論的修正の可能性があるのか、第三に、この進歩や知識は、現在と未来の両方において、どのような倫理的問題や課題を引き起こしているのか(また、起こしうるのか)。
これらの問いに取り組むため、本書は4つの主要なテーマで構成されている。
本書は、現代的かつ未来志向の神経倫理学を支える4つの主要な領域で構成されている。第1章は、神経倫理の現状に関連する神経科学の歴史を紹介する(第1~3章)。第2章では、神経科学の「難問」が、倫理的に重要な哲学的・社会的問題をどのように生み出してきたかを明らかにする(第4~8章)。第3章では、ニューロテクノロジーの発展、そしてそのような装置や技術、そしてそれらが提供する情報や結果が、どのように倫理的、法的、社会的ジレンマを生んできたかを論じる(そして、これらの疑問や問題が取り返しのつかない、難解な、あるいは許しがたいものになる前に、それを解決するために何ができるのか、あるいは何をすべきなのか、第9章から第15章)。最後の章では、神経倫理を多元化した世界舞台の文脈の中に位置づけ、「人間であること」が何を意味するのか、その神経基盤を考察することが脳科学倫理にとって必要であることを踏まえ、国際政策が達成しうることについての考えを提起し、この情報の暫定的な性質と、このような「フロンティア知識」の限界と限界を等しく考察するよう促している(第16章から第18章)。全体として、われわれの目標は、神経倫理学がどのような時代になったかを読者に提供することであった。米国の「脳の10年」、「疼痛制御と研究の10年」(2000年~2010)の惰性は、国際的な努力とともに、脳科学のペースと進歩を大きく前進させた。しかし、その一方で、まだ残された課題も明らかになっている。私たちは、「心」と「意識」が脳内でどのように発生するのかを知らない。そして、このことは、実際には、“単なる“エビデンスギャップ“に過ぎないかもしれないが、このような不確実性は、哲学的、神学的、社会的、法律的、政治的にかなりの不安と議論を引き起こしている。意識と「自己」を理解するための脳のメカニズムを明らかにすること、そしてそのような研究が倫理的、法的、社会的にどのような意味を持ち、どのような影響を与えるのかが、「心の10年」が意図する目標である。明らかに、「心の10年」プロジェクトと、専門職および実践としての神経倫理学には、一致団結した国際的な取り組みが必要である。本書が、学生、学者、科学者、そしてこの試みとこの分野全体に関わるすべての人々にとって役立つことを願っている。
1. 神経科学の発展 我々はこれまでどこにいたのか?
D. F. スワブ
序論
神経倫理学に関する本書は、多様なトピックを扱う一冊であるが、その序文は、神経科学分野の歴史に貢献した数多くのハイライトの中から、ごく個人的に選んだものに基づいている。本書は、私たちが脳を見る目が、比較的短期間のうちに、魂を宿す器官のひとつに過ぎなかったのが、心の源を研究する巨大な学際的努力の焦点となるまでにどのように変化したかを示している。脳研究の焦点は、その努力によって、巨視的に目に見える脳の病理の研究から、精神疾患や私たちの性格の基礎となる微妙な構造的・機能的差異の研究へと移ってきた。子宮内での脳の性的分化、つまりジェンダー・アイデンティティと性的指向を生涯にわたってプログラミングすることについては、発達初期に脳に刻み込まれる私たちの性格の多くの側面の一例として論じられている。脳のシステムとその機能を生涯にわたって構造化するために、発達過程が行われる重要な窓という概念は、成人の脳における病変の修復が非常に困難である理由でもある。このような困難があるにもかかわらず、神経科学における一連の新しい技術開発は、近い将来、脳疾患に取り組むための新しい効果的な治療戦略につながることを約束するものである。
われわれは脳である
私たちが考え、信じ、実行することはすべて、脳によって決定され、実行されている。ヒポクラテスやデカルト1がすでに認識していたように、人類の前例のない進化の成功は、また個々の人間の多くの限界も、この素晴らしい器官である脳によって決定されており、脳が私たちの可能性、限界、性格を決定している。私たちの身体の他の部分は、脳に栄養を与え、脳を動かし、子孫繁栄によって新しい脳を作るためのものでしかない。従って、脳の研究は障害を扱うだけでなく、「なぜ私たちはそのような存在なのか」という疑問に対する答えの探求、すなわち自己の探求になりつつある。
神経細胞はニューロンとも呼ばれ、脳の構成要素である。これらの細胞は、(1)他の神経細胞やホルモン、そして感覚を通して環境から、私たちの身体の他の部分から情報を集めること、(2)情報の統合と処理、そしてこれらの情報に基づく意思決定、(3)これらの意思決定を、運動、ホルモンレベルの変化、身体的プロセスの調節、そして尽きることのない思考の生成という形で実行することに特化している。この効率的な情報処理機械の欠陥は、遺伝的なものであったり、発達段階や人生の後半に起こるものであったり、精神疾患や神経疾患につながるものであったりする。
1 私たちの喜び、歓喜、笑い、娯楽、そして悲しみ、痛み、不安、涙の源が脳にほかならないことは、一般に知られているはずである。特にこの器官によって、私たちは考えたり、見たり、聞いたりすることができ、醜いものと公正なもの、悪いものと良いもの、楽しいものと不快なものを区別することができる。狂気や精神異常、恐怖や恐怖が押し寄せ、たいていは夜だが、時には日中にも襲ってくる。不眠症や傾眠症、やってこない考え、忘れた義務や奇妙な現象の原因も脳である。
ヒポクラテス、紀元前5世紀
消化、栄養、呼吸、覚醒と睡眠、光、音、匂いの取り込み、観察器官と想像器官におけるイメージの印象、記憶におけるこれらのアイデアの保持、欲望と情熱の下層運動、そして最後にすべての外側の手足の運動など、私がこの機械(脳)に帰するすべての機能を、この機械の器官の性質の結果として、専らこの機械において自然に起こるものとして、時計の動きに劣らず見てほしい。
デカルト、1596-1650年
攻撃性や犯罪行為など、さまざまな行動障害につながる。
コンピュータのメタファー
私たちの脳の構成要素を見て、それらがどのようにリンクしているかを見ると、コンピュータのメタファーは明白に見える。脳は1500gの重さがあり、1000億個(10~1010個)のニューロン(世界人口の16倍)、その2倍の数のグリア細胞(ニューロンの働きをサポートする細胞)、そして少なくともその1000倍の数の神経細胞が接触する場所、サンティアゴ・ラモン・イ・カハール(1852~1934)が言うところの「手をつなぐ」場所、すなわちシナプスを含んでいる。神経細胞は10万km以上の神経線維でつながっている。1948年にトルマンが提案したのは、脳を中央制御室に例える比喩である。彼はこう書いている:
われわれは、中央制御室そのものが、昔ながらの電話交換機のようなものであるよりも、地図制御室のようなものである、と主張する。入ってくる刺激は、単純な一対一のスイッチで、出ていく反応に接続されているわけではない。むしろ、入ってくる刺激は通常、中央のコントロールルームで、暫定的な、認知的な環境地図へと練り上げられる。そして、ルートや経路、環境との関係を示すこの暫定的な地図が、最終的に動物がどのような反応を示すかを決定するのである。
Repovˇs & Bresjanac 2006に引用されている。
驚異的な数の細胞とシナプスが非常に効率的に働いているため、私たちの脳はわずか15Wの電球以上のエネルギーを消費しない。ミシェル・ホフマンの計算では、一個人の脳にかかる総エネルギーコストは、現在の物価水準で一生涯に1200ユーロしかかからないことになる。そんな金額では、まともなコンピューターすら買えない。しかし、これが意味するのは、10億個のニューロンを1200ユーロのコストで80年間働かせることができるということだ!並列回路を備えた、どんなコンピューターよりも画像処理と連想に優れた、ファンタスティックで効率的な機械ということになる。脳の体内時計である視交叉上核(図11A参照)の体積はわずか0.5mm3だが、これだけで私たちの昼夜のリズム(覚醒、睡眠、摂食、飲酒、子作り、ホルモンレベルなど)をすべて調整できる。1500cm3(300万倍)で何ができるか、想像してみてほしい!
これら何十億もの神経細胞の機能と相互作用の産物が、私たちの「心」である。腎臓が尿を分泌するように、脳は思考を分泌する」(ヤコブ・モレスコット、1822-93)。私たちが本を読んだり、計算したり、音楽を聴いたり、幻覚を見たり、恋をしたり、性的興奮を覚えたりするときに、どの脳領域が活性化されるのか。リアルタイムの機能的MRIをバイオフィードバックシステムとして使えば、脳領域を別の方法で機能させるように訓練することさえ可能である。こうして前帯状回の前頭部(図12,1.3参照)をコントロールするように訓練された患者は、慢性疼痛を軽減することができた(DeCharms et al.)
図11 視床下部の図式
矢印は本文中で言及した構造を示す。NBMはMeynert基底核、PHは視床下部後部、PVNは室傍核、SCNは視交叉上核、SONは視索上核、SThは視床下核である。
私たちの感情、情緒、性格、愛、そして魂に至るまで、心臓が特別で神秘的な性質を持っていると信じている人々がまだいる。もちろん、感情を経験すると心拍数は上がるが、それは自律神経系の命令によるものだ。しかし、心臓移植を受けた人が、ドナーを彷彿とさせるような性格の変化を遂げたという逸話がある。オランダの大手新聞『テレグラーフ』は、「魂は心臓に宿るのか」という見出しをつけた。クレア・シルビア(47) は男の子から心臓移植を受けた。彼女は今、女の子に口笛を吹き、ビールを飲んでいる。シルヴィアは1997年、自身の著書の中で、ドナーとなった若いサイクリストの性格が心臓や肺とともに移植されたことを確信していると書いている。また、音楽の好み、好きな色、芸術、食べ物、娯楽、職業などの嗜好がドナーのものに変わった心臓移植患者の逸話もある。心臓を提供されたある人は、夢の中でドナーを殺した犯人の顔を見たと報告した(Pearsall et al.) ある女性は、プロのチェスプレイヤーの心臓をもらった後、突然チェスができるようになったと報告した。そのため、これらの報告を真に受ける前に、レシピエントがドナーの情報を受け取る可能性を完全に排除し、不本意なインタビュー操作を不可能にし、移植後に服用され、行動に影響を及ぼす可能性のある免疫抑制剤の影響を考慮した、十分にコントロールされた研究が必要である。
図12 前頭部MRIスキャン
ACGは前帯状回、ICは下帯状回、NHは神経下垂体、PFCは前頭前皮質、SGWMは前帯状回下白質。
図13 前頭部MRIスキャン
白い四角は、図11で詳しく示した視床下部を示す。ACG、前帯状回;NA、側坐核;P、被蓋野。
脳の発達
発達の過程で、私たちは自分の脳をユニークな機械に作り上げる。
コンピュータの比喩は、脳には部分的にしか当てはまらない。それは
脳のハードウェアは柔らかく、いくつかのシステムは非常に柔軟である。私たちの脳は生きた機械であり、使うことによって、特に発達の過程で絶えず変化する。発達中に私たちがすること、あるいは観察することすべてが、細胞数、回路数、細胞接触に永続的な変化をもたらす可能性がある。私たちの環境と脳の使い方は、脳の構造、ひいてはその機能に強く永続的な影響を与え、それが脳をユニークなものにしている。一卵性双生児のそれぞれの脳は、誕生の瞬間にすでにこのようにユニークになっている(Steinmetz et al.) このように、脳は遺伝情報に基づいて部分的に発達するだけである。子どもの脳の発達は、子宮内でホルモンや母親のストレス、遺伝子のランダムなサイレンシングによって影響を受け、妊娠中に母親が服用した薬やアルコール、ニコチンによっても脅かされる。母親が妊娠中にタバコを吸えば、その子が後に注意欠陥多動性障害(ADHD)を示したり、攻撃的になったり、犯罪行動を起こしたりする可能性が高くなる(Brennanら1999;Neumanら2007)。
発達の過程で、脳は過剰な細胞と結合を作る。脳システムの機能によって、どの細胞や結合が効果的で、最終的に生き残るかが決まる。このような脳細胞間の生存競争は「神経細胞ダーウィニズム」と呼ばれている。このように、脳の構造とそれに付随する機能を決定するのは、子どもの運動練習だけではないのだ。発達初期の脳の構造に影響を与える多くの要因が、私たちの性格を決定する。男性のように感じるか、女性のように感じるか(ジェンダー・アイデンティティ)、性的指向は胎内で決定される。私たちの性的分化の方向性については、出生後の発達も重要であるとしばしば仮定されているが、その可能性を示す確かな証拠はない(Swaab 2007)。
最初の2,3年の間に、私たちの環境は言語に関わる脳システムの構造も決定し、それによって私たちは母語を持つようになる。このシステムは可塑的ではなく、後に別の言語を学んだときのアクセントからも明らかである。
さらに、親の言うことは何でも真実とされる幼少期に、私たちは周囲の宗教的信念にさらされる。こうして私たちの宗教的信念は脳に刷り込まれ、簡単には変えられない。しかし、シナプスは生涯を通じて可塑性を保つ脳のシステムである。例えば、記憶が保存されている脳の領域では、シナプスは少しずつ変化する。
このように、脳は遺伝情報に基づいて作られるのは一部であり、大部分は発達初期の機能によって作られる。誰もまったく同じ経験や思考をすることはないので、すべての脳は発達の過程でユニークになる。こうして私たちの性格は決まるのである。環境もまた、特に発達初期においては、言語や宗教などの影響を通して関与している。脳が文化を作り、文化が脳の発達を形作る。
発達の過程で、私たちは自分の脳を独自の特徴、人間、そして時には人格へと作り上げていくのである。
発達は制約を引き起こす
発達の過程で、私たちの選択肢は脳の組織の成長によってますます制限されていく。このプロセスは胎内ですでに始まっている。ロックやルソーが考えたように、私たちはタブラ・ラサとして生まれてくるのではない。卵子が受精した瞬間に、私たちの将来の逸脱のリスク(例えば認知症)の多くはすでに遺伝的に決定されている。母語の選択、性的指向やジェンダー・アイデンティティ、攻撃性のレベルは、私たちが成長する過程で決定される。性転換者の「自分は間違った性別の身体で生きている」「身体を変えるべきだ」という考えを思いとどまらせることは不可能である。それ以外の選択肢はない。いったん脳が組織化されると、何かを変えることは事実上不可能なのだ。脳を効率的に操作する唯一の方法、それは徹底的な教育だ。コマーシャルとテレビがその仕事を終わらせる。だから世界中のティーンエイジャーが、まったく同じデザイナー服を着て、まったく同じ音楽を聴いているのである。神経ダーウィニズムは、このような絶え間ない制限の神経生物学的プロセスの根底にあるようだ。それによって、私たちの脳はますます効率的に機能するようになるが、同時に自由度はますます失われていく。成人に達すると、脳を修正する能力、つまり行動を修正する能力が、脳の構造的な制約を受けすぎてしまう。そして私たちは「性格」を獲得する。
私たちは社会の慣習によってだけでなく、脳の発達の仕方によっても選択を制限されているのだ。児童虐待の加害者は、彼ら自身が子どもだったときに虐待を受けていた。虐待者が自ら虐待の道を歩まないでいられるだろうか?思春期には、ほとんどすべての脳構造の機能を変化させる性ホルモンへの対処を、短期間で脳が学ばなければならない。成人期の脳障害は、人を完全に変えてしまう。英国空軍のテロリスト、ウルリケ・マインホフの脳は、1976年に獄中で自殺した後に検査され、損傷を受けていることが判明した。彼女は以前から扁桃体(図14と1.5)を圧迫する動脈瘤(血管の広がり)があり、手術中に前頭前皮質が損傷していた。扁桃体が圧迫されると攻撃的になり、手術中に前頭前皮質が損傷すると衝動的な行動を起こす可能性がある。つまり、両方の損傷によって、目の肥えたジャーナリストからテロリストへの行動の変化を説明することができる。彼女の意志はどれほど自由だったのだろうか?
図14 前頭部MRIスキャン
白い四角は図11で詳しく示した視床下部を示す。Aは扁桃体、STGは上側頭回。
図15 前頭部MRIスキャン
白い四角は、図11で詳しく示した視床下部領域を示す。Aは扁桃体、Hは海馬、PHは視床下部後部である。
初期刷り込みの例としての脳の性分化
脳の性分化は子宮内で始まり、主に発達中の神経細胞が子供の性ホルモンと相互作用することによって、脳の構造と機能に永続的な変化をもたらす。
睾丸と卵巣は妊娠6週目に発達する。これは遺伝子のカスケードの影響下で起こるが、男児のY染色体上の性決定遺伝子SRYがその引き金となる。男児の精巣によるテストステロンの産生は、妊娠6週目から12週目にかけての性器の性分化に必要である。子宮内での女性の性器の発達は、主にテストステロンがないことが前提となっている。男児の脳は、テストステロンの2つのピークによって永久的に組織化される。最初のピークは妊娠中期に起こり、2番目のピークは生後3カ月に起こる。男児におけるテストステロンのこの2つのピークは、生涯にわたって脳の構造のプログラミングを引き起こす。思春期にホルモンレベルが上昇することで、発達初期に構築された回路が「活性化」されるのである。アンドロゲン不感受性症候群(用語集参照)からわかるように、ヒトでは、発達中の脳に対するテストステロンの直接的な作用が、ジェンダー・アイデンティティと性的指向に関与する主なメカニズムであると思われる。これは、体全体が男性ホルモンであるテストステロンに対して感受性がない遺伝的疾患である。遺伝的な(XY)男性は異性愛者の女性に成長するが、これは発育期のテストステロンが男性の外見、ジェンダー・アイデンティティー、女性に対する性的指向にとって重要であることを示している。ホルモンと発達中の脳細胞の相互作用から生じる脳の構造と機能における性差は、男である、女であるという感覚(ジェンダー・アイデンティティ)、社会における男または女としての振る舞い方(ジェンダー・ロール)、性的指向(ヘテロ、ホモ、バイセクシュアル)、認知や攻撃行動に関する性差など、その後の行動における性差の基礎となっていると考えられている。子宮内でのホルモンと発達中の脳との相互作用を妨げる要因は、その後の行動に永続的な影響を及ぼす可能性がある(Swaab 2007)。
脳の性分化:社会環境の影響はほとんどない
1950年代から1970年代にかけて、子どもはタブラ・ラサとして生まれ、社会の慣習によって男性か女性の方向に強制されると仮定された。ジョン・マネーはこれを次のように述べている(Money 1975):
ジェンダー・アイデンティティは出生時に十分に不完全に分化しており、遺伝的に男性であった子供を女の子として割り当てることができる。ジェンダー・アイデンティティは、その後、養育経験に応じて分化していく。
この概念は、有名な心理学者であり性科学者でもあるマネーが、ジョン=ジョアン=ジョン(あるいはジョン=ジョアンと呼んでいた)の物語が示すように、破滅的な結果をもたらした。ジョンとはデイヴィッド・ライマー(コラピント2001参照)の仮名であり、この少年は生後8カ月で小さな手術、つまり陰茎の包皮を切除する手術を受けなければならなかった。この少年は、この小さな手術の際のミスでペニスを失ってしまった。マネーによれば、ジェンダーの刷り込みは1歳までは始まらず、3~4歳までにその発達はかなり進むという。これが、この生後8カ月の男の子(ブルース)から女の子(ブレンダ)を作るという決断の根拠となった。この子の睾丸は、女性化を促進するために、生後17カ月までに摘出された。この子は女の子の服を着せられ、心理カウンセリングを受け、思春期にはエストロゲンを投与された。マネーはこの子の発育を「普通の女性」と表現した。しかし13歳の時、ブレンダは自分をデビッドと名乗り、男性のジェンダー・アイデンティティを持つことにした。後にミルトン・ダイアモンドは、ブレンダがどのようにして男性に戻り、結婚し、養子をとったかを述べている(Diamond & Sigmundson 1997)。残念ながら、デビッドは証券取引所で損をし、離婚し 2004年5月に自殺した。この物語は、子宮内のプログラムがジェンダー・アイデンティティーに強い影響を与えることを示している。ペニスを切除し、女装させ、女の子として教育し、心理的指導を与え、思春期に女性ホルモンを投与しても、ジェンダー・アイデンティティを変えることはできなかった。
性的指向を強制的に変えることが不可能であることは、同性愛の出現における社会環境の重要性、また同性愛がライフスタイルの選択であるという考えに対する大きな反論でもある。去勢、テストステロンやエストロゲンの投与といったホルモン治療、性欲には影響を与えるが性的指向には影響を与えないと思われる治療、精神分析、アポモルヒネ(嘔吐を引き起こす化合物)をホモ・エロティックな絵と組み合わせて投与するが、その絵に対する本人の感情は変わらない、精神外科手術(視床下部の病変)、電気ショック治療、てんかん発作の化学的誘発、監禁などである。また、ドナー精子による人工授精後に生まれ、レズビアンのカップルに育てられた子どもは異性指向になる傾向がある(Swaab 2007; LeVay 1996)ことから、私たちの性的指向は大人になるまでに固定化され、後に影響を及ぼすことはないと考えて間違いないだろう。今日でさえ、同性愛の友人と遊ぶことを禁じられている子供がいることは悲しいことである。これは、同性愛が伝染するという考えからは想像もできない遺物である。
性転換
トランスセクシュアリティは、間違った体に生まれたという確信によって特徴づけられる。ジェンダーの問題はしばしば発達の初期に現れる。
母親たちの報告によると、息子たちは言葉を覚えた瞬間から、母親の服や靴を身につけることにこだわり、女の子のおもちゃにしか興味を示さず、ほとんど女の子と遊んでいたという。
ジェンダーの問題を引き起こす要因は多岐にわたる。双生児や家族の研究から、遺伝的要因が一役買っていることが示されており(Coolidge et al. 2002)、最近では、エストロゲン受容体aおよびb、ならびにアロマターゼの遺伝子の多型(特定の遺伝子のDNAにおける小さな変化)(用語集を参照)でもリスクが高まることが判明した(Henningsson et al. 2005)。子宮内で高濃度のテストステロンにさらされた女児が性転換する可能性も高くなる。これは先天性副腎過形成(CAH)の場合に起こる(用語集参照)。妊娠中にフェノバルビタールまたはジファントインを投与されたてんかん女性も、性転換児を出産するリスクが高い。これらの物質はいずれも性ホルモンの代謝を変化させ、子供の脳の性分化に作用する可能性がある(Dessens et al., s99)。出生後の社会的要因がトランスセクシュアルの発生に関与している可能性は示唆されていない。内分泌撹乱物質、すなわち環境中の化学物質、例えば産業由来の化学物質が脳の性分化に影響を及ぼすかどうかは、今後の重要な問題である(Swaab 2007)。
トランスセクシュアリティと脳
トランスセクシュアリティの起源に関する理論は、性器の性的分化は、脳の性的分化よりもかなり前に、妊娠の最初の2,3カ月の間に起こるという事実に基づいている。この2つのプロセスは時期が異なるため、原理的には異なる経路をたどる可能性がある。もしそうだとすれば、ニューハーフの場合、男性の脳の中に女性の構造があり、その逆もまたしかりということになる。そして実際、我々は線条体終末核の中心核(BSTc)でそのような性差の逆転を発見した。この脳構造は、げっ歯類の実験からわかっているように、性行動の多くの側面に関与している。
ヒトのBSTcには明らかな性差がある。男性の場合、この領域は女性の2倍の大きさがあり、ソマトスタチン・ニューロンを70%多く含んでいる(これはBSTcのニューロンの主要な集団であり、神経伝達物質としてのソマトスタチンを含んでいる)。この部位のニューロンの大きさや数については、性的指向に関連した差は認められなかった。男性から女性へのトランスセクシャルでは、BSTcは完全に女性であることがわかった(図16)。これまで我々は、女性から男性への性転換者1人からしか材料を入手できなかったが、彼のBSTcは確かにすべての男性の特徴を有していることが判明した。我々は、BSTcにおける性差の逆転が、成人期のホルモンレベルの変化によるものであることを除外することができた(Zhou et al.2000)。したがって、我々は発生学的な効果を扱っていると思われる。したがって、我々の観察結果は、性転換の起源に関する上述の神経生物学的理論を支持するものである。BSTcのサイズとニューロンの数は、性器や出生証明書、パスポートの性別ではなく、トランスセクシュアルが自分が属していると感じているジェンダーと一致している。
図16 血管作動性腸管ポリペプチド(VIP)染色線維に支配された線条体終末核(BSTc)中央部の代表的スライド
(A)異性愛者の男性、(B)異性愛者の女性、(C)同性愛者の男性、(D)男性から女性へのニューハーフ。スケールバー、
0.5 mm。LVは側脳室。性差(AおよびCの男性対Bの女性)と、男性から女性へのニューハーフ(D)は、サイズと神経支配に関して女性のBSTcを持っていることに注意されたい(Zhou et al., u95年より、許可を得て)。
結論として、私たちの胎内期には、発達中の神経細胞に男児のテストステロンが直接作用することによって脳が男性方向に発達し、女児ではこのホルモンがないことによって女性方向に発達する。このようにして、ジェンダー・アイデンティティ(男である、女であるという感覚)だけでなく、性的指向も、まだ胎内にいるときに脳の構造にプログラムされるのである(Swaab 2007)。小児性愛もまた、脳の性的分化の早期発達障害として説明される可能性を調査すべきである。
心対魂
私たちは、心を生み出し、その構造と機能に関する限り初期発達の段階でほぼプログラムされた、ユニークで幻想的な複雑な神経細胞機械にすぎないのだろうか?神経細胞機械としての脳以上のものがあるのだろうか?フロイトはすでに、すべての文化、すべての宗教が、私たちが死んだ後も、人格の非物質的な「何か」が存在し続けるという概念を内包していることを認識していた。その「何か」は魂と呼ばれ、死後しばらくは肉体の近くにとどまり、死後の世界へと永遠に移動すると一般的に考えられている。1906年、マクドゥーガル(アメリカ)は死にゆく患者の体重をベッドごと量った。これらの患者が息を引き取った後、再び体重を測った。すると21グラムも軽く、マクドゥーガルは「魂」の重さを測ったのだと言った。動物ではこのような違いは見られず、動物には魂がないと結論づけた。しかし、トワイニング教授(ロサンゼルス)は、動物は死ぬときに数グラム(ミリ)失うので、魂があるはずだと主張した(ハインデル1913)。
側頭葉てんかん患者の中には、神との直接のコンタクトや臨死体験の発生など、魂や死後の世界の存在を支持する脳関連の論拠を示す者もいる。側頭葉てんかんの患者の中には、非常に深い宗教的体験をする者もいる。側頭葉てんかんの発作が激しくなると、患者は夢のような状態になり、幻聴や幻視を経験する。時には体外離脱も経験する。発作と「神からの訪問」は数秒しか続かないが、その人の人格を永遠に変えてしまうことがある。さらに、このような患者は感情の変化を経験し、超宗教的になることもある。このような患者は、しばしば“ゲシュウィンド症候群“として知られるパーソナリティ障害を持つ。この症候群は、多筆症(膨大な量の作品を書く)、性欲減退、過宗教性からなる(Wuerfel et al.) 大規模な宗教運動の創始者や、使徒パウロやジャンヌ・ダルクなどの預言者や宗教指導者は、てんかんに苦しんでいた。ゴッホやドストエフスキーも同様である。後者は『白痴』の中でこう書いている:
空気が大きな音で満たされ、私はその音に飲み込まれたように思った。私は本当に神に触れた。そうだ、神は存在するのだ。あなた方、健康な人たちには、私たちてんかん患者が発作前の一瞬に感じる幸福感は想像できないだろう、と彼は言った。この幸福感が数秒続くのか、数時間続くのか、数ヶ月続くのかはわからないが、信じてほしい。
恍惚としたてんかん発作を起こし、ときどきイエスに似た姿を見る患者は、側頭葉に脳腫瘍があることが判明した。発作は側頭葉切除術後に消失し、この恍惚現象の神経学的説明が裏付けられた。明らかに、腫瘍やその他の病変による側頭領域の刺激が、幼少期の発達過程で刷り込まれた宗教的体験を解放するのである。極東の側頭葉てんかん患者は、西洋の神とのコンタクトを報告したことはないが、代わりに現地の宗教的人物を見ている。
臨死体験はまた、来世が存在することの「証明」として、また意識に脳機能は必要ないことの証明として、しばしば用いられる(Parnia & Fenwick 2002; Van Lommel et al.) 臨死体験には、トンネル、明るい光、亡くなった親族、謎めいた図などが登場する傾向がある。自分の人生が目の前で点滅しているのを見たり、自分の身体から離れるように感じたり、身体の上空をホバリングしながら見下ろしたりする(自己鏡視)。臨死体験をした人は、スピリチュアルなことに興味を持ち、来世を信じるようになる。臨死体験は、心不全などで脳が十分な酸素を得られないときに起こることがある。また、戦闘機のパイロットが急加速したときに意識を失うこともあるし、交通事故など極度のストレスによる過呼吸の場合もある。肉体を離れる感覚は、人口の10%から20%が一生に一度経験するらしいが、その原因がわからないままである。
診療所で臨死体験をした患者は、実際には臨床的に死んでいる、つまり循環と呼吸が停止して意識がないと診断された。臨床的な死は、心電図や脳波がないことで客観化されることもあるし、瞳孔が大きく開いて無反応であったことが報告されることもある。一般に、循環と呼吸が停止してから5~10分以内に脳細胞に不可逆的な損傷が起こると考えられている。しかし、ヒトのニューロンを培養し、患者の死後10時間以内に採取すれば、数ヵ月間生存させることが可能であることが判明した(Verwer et al.)
臨床的に死亡した患者のうち、臨死体験を報告するのはわずかな割合(6%~18%)であるため、これは純粋に低酸素症だけでは説明できないと提唱されてきた。このような幻覚を見るには、ある程度の低酸素が脳に刺激を与える必要があるからである。それに、患者がこの体験を覚えているためには、少なくとも記憶は十分に保たれていなければならない。長時間の蘇生後に記憶が損なわれた場合には、臨死体験の報告は少ない(Blanke et al., e02)。角回(頭頂-側頭接合部、図17参照)を電気刺激すると、ある患者は足が短くなり、ベッドの上に浮いているように感じた。体外離脱体験を繰り返した6人の神経症患者(てんかん患者5人、片頭痛と小脳梗塞の患者1人)では、その特定の脳領域にも異常な活動が認められた(Blanke et al.) これらの体験は、ホバリング、飛行、上昇、回転といった平衡感覚からのインパルスを伴う。これらの
したがって、これらの体験は、筋肉、平衡感覚、視覚系からの情報の処理に関わる脳のメカニズムの障害に基づいているようである。視覚情報は臨死体験に必要なものではない。目の見えない人からも報告されている。臨死体験が、無意識状態の始まりに誘発されるのか、回復期に誘発されるのかは明らかではない。確かに、意識不明の患者の周囲に関する詳細な記憶についての逸話もあるが、それは脳がなくても観察できたという意味ではなく、脳が正常に機能していなくても観察したり記憶したりすることは可能だという意味である。時には、麻酔がかかっている間に外科医の間で交わされた会話を患者が思い出すことさえある。結局のところ、臨死体験は脳を超えた意識の証拠ではないし、死後の生命の証拠でもない。
さらに、私たちは死んでも何かが残るほど重要な存在なのだろうか?むしろ、魂という考え方は、普遍的な死への恐怖、肥大化した自我、そしてもちろん、愛する人との再会の希望に基づいているようだ。今のところ、もっと単純な仮説で説明できる。心は脳の働きの結果である。私は「魂」は誤解だと思う。サイコンは存在せず、あるのはニューロンだけだ。
私たちが死ねば、脳の機能は停止し、心というものは何も残らない。現時点では、亡くなった人の脳細胞を数ヶ月間培養しておくことができる(Verwer et al.) その意味では、少なくともしばらくの間は、死後も生き続けることができる。他に生き続ける方法といえば、遺伝情報を子供たちに伝えることくらいしかないようだ。しかし、だからといって私たちの心が生き続けるわけではない。私たちの子どもたちは独自の脳を発達させ、驚くほど私たちとの共通点が少ない、ユニークな個性を持つようになる。私たちは何も、あるいはほとんど何も残っていないのだ。進化によってもたらされ、DNA、環境、機能によって、私たちは、いや、私たちの脳は、唯一無二の存在となった。もちろん、私たちは塵になる(創世記3.19)。生きている間でさえ、私たちは肉体的存在でしかなかったのだから。
神経療法:脳障害の治療と回復神経科学
私たちはどこへ行くのか?
脳は神経細胞の機械と考えられるかもしれないが、非常に複雑であるため、脳疾患の治療は依然として困難である。しかし、敗北主義の時代は、最近の技術の進歩や神経科学のさまざまな分野からもたらされる新たな洞察に興奮する時代に取って代わられた。国際的な大きな努力によって、近い将来、より良い診断と治療の機会が期待される臨床の場では、新たな楽観論が生み出されている。
神経学と精神医学の両分野は、分子生物学的手法と画像診断技術の大きな診断可能性を利用している。脳内の情報を化学的に伝達する機能を持つ遺伝子のDNAに、過剰な攻撃性のリスクを高める変化が発見されている(Manuck et al., k99, 2000)。MRI検査は神経学の診断を根本的に変えた。驚くようなことが報告されているのだから、精神医学においてもスキャンをもっと日常的に適用しなければならない。視床下部の小さな腫瘍は、摂食障害である神経性食欲不振症や精神分裂病のすべての徴候や症状を模倣するかもしれない(Swaab 2004)。前頭前野の病変は、社会的・道徳的行動の障害(Andersonら1999)や犯罪行動(Popma & Raine 2006)につながる可能性がある。扁桃体(図14,1.5)やその近傍の病変は、攻撃性や殺人につながる可能性がある(Blair 2003)。このように、脳スキャンは法的にも影響を及ぼす可能性がある。機能的スキャンの診断および治療の可能性が明らかになったのは、ごく最近のことである。たとえば、このアプローチによって、どのうつ病患者が抗うつ薬に反応し、どの患者が心理療法に反応するかを予測することが可能になった(Osuch & Williamson 2006)。
すべての遺伝子の発現レベルを測定できるマイクロアレイや、脳サンプル中の全タンパク質量を測定できるプロテオミクスなどの新しい強力な技術を用いて、より多くの脳疾患について、その病態や関与する分子ネットワークが理解され始めている。これは新たな治療戦略につながる。長い間、パーキンソン病はl-ドーパで治療されてきたが、今では胎児の脳移植も行われている。エイズの認知症は、効果的な併用療法によって消滅した。精神症候群は、抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬によって脳内の化学伝達物質に影響を与えることで治療できるようになった。顕微鏡で見ると、精神分裂病患者の脳の発達が妊娠初期に障害されていることがわかる。現在、統合失調症は薬物治療が可能であり、経頭蓋磁気刺激によって幻覚を抑えることができる。聴覚障害者の耳鳴りの場合、聴覚皮質を刺激することで、耳障りな歌が聞こえなくなる可能性がある。
精神薬理、ニューロンの再活性化、脳深部刺激、プラセボによる機能改善
私は、脳の大病が、神経形質における特異的な化学的変化と関係していることが示されると信じている。化学の助けを借りることで、現時点では曖昧な脳と心の多くの異常が、正確に定義できるようになり、正確な治療が可能になる可能性がある。
J. L.W.トゥディカム脳の化学的体質に関する試論-独創的な研究に基づいて (1884)
うつ病の治療:患者に合わせた治療のための、未来の“分析的精神科医“である。
視床下部-下垂体-副腎(HPA)軸、ストレス軸(用語集参照)は、うつ病症状の主要部分の“最終的な共通経路“であると考えられている。うつ病の遺伝的危険因子、出生時の小柄な体格、妊娠中の母親の喫煙、児童虐待、早期の母子分離はすべて、成人期におけるHPA軸の活性とうつ病のリスクを増加させる。抗うつ薬や電気けいれん療法による治療後、あるいは患者が自然寛解を示すと、HPA軸の機能は正常に戻る。視床下部室傍核(図11A)(PVN)のコルチコトロピン放出ホルモン(CRH)ニューロンの活性は、HPA軸の亢進の基礎を形成する。CRHニューロンはバソプレシンを共発現し、CRHの作用を増強する。CRHニューロンは、正中隆起だけでなく、気分に影響を及ぼす脳領域にも投射している。中枢から放出されるCRHとコルチゾールレベルの上昇は、ともにうつ病の徴候や症状に関与している。視床下部-神経後葉系もストレス反応に関与している。視床下部はPVNと視索上核(図11A)(SON)から神経下垂体(図12)を介してAVPを血中に放出する。循環AVPレベルの上昇は自殺の危険性とも関連している。うつ病における視床下部時計である視交叉上核(SCN)の活動低下は、気分、睡眠、ホルモンリズムの概日および周期的変動の障害の基礎となっている。化学伝達物質としてアミンを使用する脳幹からの系(ノルアドレナリン作動性系、セロトニン作動性系、ヒスタミン作動性系)や前頭前皮質(図12,1.7)の変化も、うつ病と因果関係がある可能性がある。これらの各脳系に対する遺伝的多型や発達の影響が、特定の患者におけるうつ病の主な原因である可能性がある(総説はBao et al.2008を参照)。多数の脳システムにおけるこれらの知見に基づき、私は新しい種類の
分析精神医学が近い将来発展するだろう。アナムネシスの後、うつ病患者の血液を採取し、ホルモンレベルと脳から血液に輸送される化学伝達物質の代謝物を測定し、細胞分画中の関連遺伝子多型を分析する。これらのデータに基づいて、“分析精神科医“は、神経生物学的システムのどれがその特定の患者の抑うつ症状に主要な役割を果たしているか(CRHやバソプレッシンの亢進、体内時計機能の低下、副腎皮質ホルモンの増加、アミネルグシステムの変化など)を確定することができ、その後、患者に合わせた治療が行われる。この治療法は、脳内の化学伝達物質のひとつに特異的に作用するアゴニストやアンタゴニスト、特定の脳構造や迷走神経への電気刺激、前頭前野への経頭蓋磁気刺激などを組み合わせたものである。
神経学および精神医学における脳深部刺激:可逆的精神外科手術
患者が覚醒状態にある間に、脳の奥深く、適切な構造に正確に埋め込む微小電極による刺激は、神経学だけでなく精神医学においても大きな将来性を持っている。このアプローチは、Benabidら(1987)がパーキンソン病の慢性治療として視床深部脳刺激(DBS)を初めて成功させたことを報告したときに始まった。視床下核のDBSは、パーキンソン病における緩慢な動作、硬直、振戦、歩行障害を大幅に軽減することができる。DBSの効果はしばしば劇的で持続的であり、患者自身がパルスジェネレーターを装着しているときに、非常に強い振戦が突然消失するのを見るのは非常に印象的である。視床のDBSは、心的外傷後の振戦や、薬物療法に抵抗性の多発性硬化症の振戦を抑制することもできる(Foote et al. 2006)。末期癌の疼痛や、難治性の頭部痛や顔面痛は、脳の中心灰白質、大脳皮質、感覚視床のDBSによって緩和することができる(Owen et al. 2006; Perlmutter & Mink 2006; Green et al. 2005)。中枢灰白質の電極を刺激すると、脳内にアヘン様物質が放出される。群発頭痛は最も重い一次性頭痛の一つであり、昼夜を問わず常に同じ時間に起こる耐え難い痛みを伴う発作のため、“自殺頭痛“としても知られている。群発頭痛には、視床下部後部の深部電極が有効である。この脳領域は群発頭痛発作時に活性化することが示されている(Leone et al.) 筋緊張の障害であるジストニアは、内科的治療にはあまり反応しないが、現在では内球淡蒼球のDBSで効果的な治療が可能である(Diamond et al., d06; Kupsch et al., h06; Vidailhet et al., t05)。トゥレット症候群では、淡蒼球内側部または視床内側部のDBSにより、チックや強迫観念が大幅に軽減される(Ackermans et al.2006)。統合失調症治療の運動性副作用である遅発性ジスキネジアの場合も、同じ構造が標的である(Damier et al., r07)。
興味深いことに、DBSは精神医学においても将来性がある。強迫性障害(OCD)患者は、その障害のために正常な社会生活が送れなくなっているが、側坐核のDBSによって治療することができる(図13)。また、視床下部後部のDBS(図11C、1.5)は、医学的に難治性の衝動的で暴力的な2人の精神遅滞患者の破壊行動を改善したと報告されている(Franzini et al. 近い将来、治療不可能な肥満の場合にも深部電極が埋め込まれることが予想される。
35,000人ほどの患者がDBSによる治療を受けた現在、この新しい治療法の副作用が明らかになりつつある。電極植え込み時の脳出血、感染症、発作は起こるが、まれである。しかし、思考や記憶の障害、性格の変化、抑うつ状態や躁状態、自殺やギャンブルなどの精神症状が起こることもある。したがって、DBS療法に適した患者を選択することが、これからの課題である。
プラセボ効果
薬のプラセボ効果は非常に強いことがある。抗うつ薬には45%から75%のプラセボ効果があるとさえ考えられている。プラセボ効果とは、治療に対する脳の期待に基づく現実の効果であり、脳システムの機能における無意識の特異的変化によって引き起こされる。もし患者が痛み止めのプラセボ錠を飲むと、脳はモルヒネ様ペプチドを放出しなければならないことがわかる。このプラセボ効果は、アヘン拮抗薬であるナロキソンによってブロックすることができる。さらに、プラセボによる鎮痛は、fMRIで示されたように、痛みに敏感な部位の活動の低下を伴っており、プラセボが痛みの経験も変化させることを示唆している(Wagner et al.) うつ病患者にプラセボを投与すると、前頭前野の活動が亢進し、視床下部の活動が低下するため、うつ病における脳の典型的な機能変化が相殺される。パーキンソン病患者では、プラセボが線条体のドーパミンの放出を引き起こす。パーキンソン病患者におけるプラセボ効果の作用機序は、深部電極の装着中に明らかになった。手術室でプラセボを投与すると、視床下核にある手術対象の単一ニューロンの活動が低下した(図11C)。これらの変化は臨床的改善と密接に相関していた。新しい薬(実際には生理的食塩水であった)を注射すると、腕の硬直が減少し、ニューロンの発火率が低下した。このような積極的な反応を示す患者は、「新しいL-ドパを感じる」あるいは「気分がよくなった」と言った。視床下部の発火率の減少がない場合、硬直は減少せず、患者は“何も感じない“あるいは“効かない“と言った。
「効かない」と言った(Benedetti et al.) どうやら脳は、手術後に深部電極がすべきこと、すなわち刺激装置を装着したときに視床下核の発火をブロックすることを、正確に行なっていたようだ。脳は、プラスの効果を得るために機能的に変化させるべき特定の回路を知っているようだ。このようなプラセボ効果の神経生物学的メカニズムをより深く理解することで、まったく新しい治療戦略が生まれる可能性がある。
萎縮ニューロンの再活性化
アルツハイマー病(AD)患者の脳の強い萎縮、すなわち脳の大きさの減少は、一般に、認知症の基礎であると推定される大量の細胞死によって説明されてきた。しかし、アルツハイマー病における細胞死は、一般に起こる主要な現象ではないようである。大脳皮質は強く萎縮しているかもしれないが、神経細胞の総数はADでは減少していない。ADにおける細胞死は、海馬のCA1領域(図15)や上側頭回(図16,1.7)など、一部の脳領域に限られている。神経細胞活動の低下による萎縮は、おそらくADの大きな特徴の一つである。萎縮は病気の初期に起こり、認知症の臨床症状の根底にある。実際、アルツハイマー病患者の脳ではグルコース代謝が50〜70%低下しており、エネルギー代謝が決定的に低下している(Swaab et al., b02)。
脳内グルコース代謝の低下はADの初期症状であり、認知機能障害に先行することさえある。Smallら(1995)とReimanら(1996)は、APOE-e4対立遺伝子のホモ接合体である中年後期の認知機能が正常な被験者、つまりADの危険性のある患者では、後にアルツハイマー病患者で影響を受ける脳の同じ領域で、すでにグルコース代謝が低下していることを見いだした。
もちろん、痴呆患者にとっては、細胞が死滅していようが、まだ存在しているが機能しなくなっていようが、何の違いもない。しかし、治療戦略の開発には大きな違いがある。したがって、治療戦略の第一の焦点は、細胞死を防ぐことではなく、神経細胞の代謝を改善し、ADの認知・行動症状を緩和するために、神経細胞活動を再活性化することである。
図17 ヒトの脳の側面図(左側が正面)
GA、角回;PFC、前頭前皮質;STG、上側頭回。上段はアルツハイマー病患者の萎縮した脳、下段は年齢をマッチさせた対照。
神経細胞の活性化は、加齢やアルツハイマー病における神経細胞の機能や生存に有益な影響を与える可能性がある。いくつかの研究は、教育が認知症を予防する可能性を示している。職業は学歴よりもさらに強い認知症リスクの指標であることが示された(Bonaiuto et al.) 成人期初期から中期にかけて知的活動に費やす時間が減少することは、ADの有意なリスクと関連していた(Fiedland et al.2001)。ADの可能性が高い患者において、グルコース投与またはインスリンによるグルコース利用可能性の増加が記憶を増強するという観察結果(Manning et al., g93;Craft et al., t96)は、ADが基本的に脳代謝の低下によって特徴づけられるという見解を支持するだけでなく、ニューロンの代謝刺激に注目することが有益な戦略である可能性を示している。
ADの影響を受けたシステムが依然として活性化しうるという原理的証明を示すために、我々は概日システムを選んだ。ADでは、脳の体内時計である視交叉上核(SCN)が著しい機能障害を示し、睡眠・覚醒パターンの断片化と夜間の不穏を引き起こす。AD患者では、明るい光の入力を増やすとリズムが改善した(Van Someren et al., n97)。最近行われた無作為プラセボ対照臨床試験では、189人の被験者を対象に、12の高齢者施設で3.5年間の追跡調査を行い、日中の環境光と夜間のメラトニンを増加させたところ、夜間の不穏が22%減少し、抑うつ症状が12%減少し、3.5年間でMMSEが3ポイント低下し、全体的にリズムが改善した(Riemersma-van der Lek 2007)。これからの研究は、神経変性疾患における他の萎縮した脳システムに対する効果的な刺激を見つけることが中心になるはずである。
AD患者のニューロンを再活性化させる可能性のある化合物を調べるために、われわれは成人神経疾患患者と対照者の死後脳組織培養法を開発した。死後10時間までは、ヒトの脳スライスを試験管内で維持することが可能であり、長時間実験的に操作することができるようである。これらの培養物(運動皮質、海馬、小脳)の神経細胞をアデノ随伴ウイルスベクターで形質転換し、44日間もレポーター遺伝子を発現させることができ、患者の死後にも生命があることが証明された。これらのスライス培養は、老化と神経変性疾患の細胞的・分子的メカニズムを研究する新たな機会を提供する(Verwer et al. 2002)。
回復神経科学:あなたの脳はガレージの準備ができている、
脳障害の場合の機能回復は、原理的には、ブレイン・マシン・インターフェース、脳移植、機械的・化学的介入、遺伝子・細胞・分子療法など、非常にさまざまな方法で達成することができる。
神経系の損傷をバイパスするブレイン・マシン・インターフェース
神経人工装具は、感覚情報が脳に伝わらなかったり、筋出力の制御に影響を与えたりする神経系の損傷をバイパスすることを目的としている。蝸牛インプラントは、蝸牛感覚神経難聴の場合に大きな成功を収めている。蝸牛内に電極を設置し、機能不全に陥った聴覚細胞につながるニューロンを刺激する。現在、10万人以上の人々が人工内耳を装用しており、多くの場合、会話を理解することに驚くほど成功している(Scott 2006)。両耳の聴覚神経に障害がある場合、12個の電極アレイを人工内耳として下甲介(図13)に設置することができる。この電極アレイを電気刺激すると、有意な音声知覚が得られ、読唇術と組み合わせることでコミュニケーション能力が明らかに向上した(Hochberg et al.) 脊髄が完全に切断された男性においてHochbergら(2006)が示したように、個人の皮質運動意図を記録し、ロボット・マニピュレータの制御やコンピュータ・マウスの制御に使用することが原理的には可能である。彼らは彼の運動皮質に96個の微小電極アレイを埋め込んだが、その結果、四肢が麻痺したこの患者は、コンピューターのカーソルを操作したり、義手を閉じたり開いたりすることができるようになった。これは、麻痺のある人間の機能回復を目指した新しく非常に有望な神経技術であるが、何千ものニューロンから記録できる完全に埋め込み可能な記録システムの開発にはかなりの時間がかかるだろう。メガネの鼻の部分に内蔵された小型ビデオカメラ、ポケットに入れた信号処理用電子機器、一次視覚野に埋め込んだ微小電極のアレイを用いて、限定的ではあるが高度失明者の視力を回復させる実験が成功した(Normann 2007)。
神経移植:局所病変の修復
1987年、New England Journal of Medicine誌にMadrazoら(1987)の論文が掲載され、パーキンソン患者自身の副腎髄質の一部を尾状核に移植したところ、驚くほど回復したことが報告された。その後すぐに、世界中で2年間に200件の移植が行われた。この手術は6カ月後にはいくらか改善したように見えたが、移植の持続的な効果はなく、死亡率は2年間で10%~20%であった。剖検の結果、副腎髄質移植片は生存していないことが判明した。
1988年以来、確かに生存可能な胎児黒質の移植片がパーキンソン患者への移植に使用されている。胎児組織は妊娠後6〜8週の段階から入手しなければならず、1回の移植に4個分の胚を使用しなければならない。患者の約85%では、PETスキャンによって移植が可能であることが判明する。移植後、患者が必要とするl-ドーパの量は減少し、動作の緩慢さや硬直は減少する。しかし、これらのパーキンソン病患者が完全に回復した例はなく、その結果は非常に多様である。15%の患者ではジスキネジア(動作困難)が起こるが、これはl-ドパによるジスキネジアと同じ患者である。パーキンソン病患者において、胎児黒質移植による長期改善が報告されている。しかし、実施された2つの二重盲検試験では、いくつかのスコアは改善し、両試験とも移植の長期生存を示したものの、主要アウトカム変数の改善は示されなかった。
サルのMPTPモデルを用いて、神経移植の有効性を向上させ、移植研究にとって一般的に重要ないくつかの疑問に答えようとしている。移植片の細胞の大部分が死滅するのを防ぐにはどうしたらよいか?向神経性因子(脳の成長因子)はこの点で有用だろうか?免疫抑制はどの程度重要なのだろうか。また、腫瘍を発生させず、感染因子のスクリーニングを行う必要のない不死化細胞株など、胎児組織よりも適切で標準化されたドーパミン細胞の供給源はあるのだろうか。ブタの胎児を用いた異種移植が試みられたが、生存率は低いようで、さらに動物ウイルスがヒトに感染する危険性もある(Freed et al., d07)。
ハンチントン患者を対象としたパイロット研究では、ヒト胎児移植片を尾状核と被蓋核の複数部位に両側移植することに初めて成功した。これに続いてフランスの多施設共同試験が行われる予定である(Dunnett & Rosser 2007)。
介入神経学
最近まで、神経科医は損傷部位を正確に特定することはできたが、治療手段はほとんど持っていなかった。現在,介入神経科医の仕事は、脳卒中の緊急治療に最も有益であることが証明されている酵素(組織プラスミノーゲン活性化因子)の静脈内投与である。血栓溶解剤の動脈内投与やステントの留置など、いくつかの治療法が有望視されている。研究者らはまた、脳の血管の拡張による出血に対する様々な治療法の利点についても調査し、血管を介して拡張部に金属コイルを持ち込む方法と、大手術を必要とする拡張部にクリップを付ける古典的な方法との間で、長期的な認知アウトカムにほとんど差がないことを発見した。このような開発は、深刻な脳損傷を防ぐだけでなく、神経外科的介入を不要にするかもしれない(Martinez-Perez et al.)
遺伝子・分子・細胞治療:神経変性の修復と損傷した神経経路の再接続
成長因子は細胞機能を刺激し、神経細胞死を防ぐので、神経細胞の変性を防ぐ可能性がある。神経成長因子(NGF)は、前脳基底部コリン作動性ニューロンの生存と機能を刺激する可能性があり、アルツハイマー病におけるコリン作動性欠損を軽減する可能性がある。遺伝子治療は、変性ニューロンを含む脳領域で適切な濃度の成長因子を得ることができ、副作用を避けるために成長因子が非標的領域に広がるのを防ぐことができる。現在進行中の臨床プログラムでは、NGFがAD脳のコリン作動性ニューロンを保護し、コリン作動性系を標的とすることがアルツハイマー病患者に有意義な利益をもたらすのに十分であるという仮説が検証されている。これらの患者の皮膚から採取した結合組織細胞を、NGFを発現するように遺伝子改変し、全身麻酔下でアルツハイマー病患者の大脳基底核に注射した(図11A、NBM参照)。これらの小規模で非対照の試験から得られた初期の臨床所見から、この方法が実際に何らかのプラスの効果をもたらすことが示唆される。現在では、ADにおけるNGF遺伝子導入の、より大規模な対照研究が正当化されている。さらに、基底核に直接注入するAAVウイルスベクターによるNGF導入の研究も進行中である(Tuszynski 2007)。
パーキンソン病では、強力な神経保護作用を持つグリア細胞由来向神経性因子(GDNF)を、ポンプを使って被殻に慢性的に注入する非盲検臨床試験が、他に2つ開始された。これらの試験ではいずれも、長期的(1年間)にわたる被蓋におけるドパミン貯蔵量の増加(図13)と、それに対応する運動出力の処理の改善により、機能的改善が認められた。さらに、両試験ともジスキネジアのスコアが有意に減少した。副作用は認められず、部位特異的直接GDNF治療が安全で有益であることを示している。
しかし、ランダム化比較試験では肯定的な結果は得られなかった。パーキンソン病患者の患部脳領域に向神経性因子を投与することを目的とした遺伝子治療は、現在準備中である(Korecka et al.)
インターフェロンβ1bによる多発性硬化症(MS)治療の早期開始は、障害の発症を予防し、再発寛解型MSの初発後の使用を支持している(Kappos et al., s07)。さらに、ミエリン由来のタンパク質(すなわちミエリン塩基性タンパク質)を含むDNAプラスミドの筋肉内注射によるワクチン接種は、脳MRIに良好な傾向をもたらし、抗原特異的免疫に有益な変化をもたらした(Bar-Or et al., r07)。これは全く新しい治療原理である。
成人の脊髄損傷は、上行性感覚経路と下行性運動神経経路の両方に重篤な損傷をもたらし、完全な機能回復の見込みはない。脊髄における再生の少なさは、成長促進因子と成長阻害因子の間の重要な分子バランスに依存していると考えられる。実験的な脊髄修復戦略は、軸索の再成長を促し導くために、栄養的影響と抑制的影響の調節に焦点を当てている。ウイルスベクターを介したニューロトロフィン遺伝子の損傷脊髄への導入は、損傷した神経系でニューロトロフィンを発現させる新規かつ効果的な戦略として浮上している。向神経性因子遺伝子の生体外導入は、病変空洞を橋渡しする軸索再生の方法としても研究されている。傷害を受けた脊髄に移植する前に、さまざまな種類の細胞を遺伝子修飾することで、細胞神経ガイドが改善された。動物実験モデルの損傷脊髄への向神経性因子の遺伝子導入は、生体外遺伝子導入のためのさまざまな細胞プラットフォームとの組み合わせにより、現在、最初の顕著な機能的改善を示しており、近い将来、損傷したヒト神経系の修復に新たな展望を与えることになる(Hendriks et al.) 動物実験が大成功を収めた後、チューリッヒのマーティン・シュワブ氏は現在、成人の神経系で神経線維の伸長を妨げるこのタンパク質を中和するため、Nogoに対する抗体を用いて、麻痺したばかりの患者の脊髄病変を修復する臨床試験を主導している。
失われた神経細胞を多能性幹細胞で置き換える可能性は、非常に注目されている。これらの幹細胞は、自己の骨髄、胎児の脳、あるいは患者の鼻の粘膜から単離することができる。胚性幹(ES)細胞による神経細胞置換戦略はまだ開発の初期段階にあり、免疫拒絶、腫瘍形成、幹細胞の分化などの問題を克服しなければならない。しかし、ヒトの脳の成体神経前駆細胞をラットの脳に移植すると生存する。ラットの成体脳に移植すると、神経前駆細胞は標的を定めて移動し、増殖・分化する(Olstorn et al.
結論
われわれは脳である。この情報処理機械に欠陥があると、精神疾患、神経疾患、神経内分泌疾患、あるいは攻撃性や犯罪行動を含む多種多様な行動障害を引き起こす可能性がある。1000億個の神経細胞の機能と相互作用の産物が私たちの「心」であるが、魂、つまり私たちが死んだ後に人格として残る非物質的な「何か」が存在し続けるという概念を支持する論拠はないようだ。一部の側頭葉てんかん患者が報告する神との直接的なコンタクトや臨死体験など、魂や死後の世界の存在を支持する脳関連の論拠を挙げる人もいるが、どちらの現象についても、神経生物学的に十分な説明が可能である。
極めて複雑な神経細胞の機械は、その構造と機能に関する限り、初期発達の主要な部分でプログラムされている。例えば、脳の性分化がそうである。脳の性分化は、発育中の神経細胞に男子のテストステロンが直接作用することで男性方向に、女子の場合はこのホルモンがないことで女性方向に発達する。このようにして、私たちのジェンダー・アイデンティティ(男である、女であるという感覚)だけでなく、性的指向もまた、私たちがまだ胎内にいるときに脳の構造にプログラムされるのである。
脳の病気はまだ治療が難しいが、最近の技術の進歩や新しい知見に興奮し、近い将来の治療に大きな期待が寄せられている。より多くの脳疾患について、新たな治療戦略につながる病態や関与する分子ネットワークが理解され始めている。
機能的な改善は、精神薬物療法、脳深部刺激療法(DBS)、プラセボ、ニューロンの再活性化などによって得られる。うつ病患者には、遺伝的背景と血液中の化学的アッセイを組み合わせることで、患者に合わせた治療が可能になる。まさに適切な脳構造に微小電極を埋め込むDBSは、神経学だけでなく精神医学においても大きな将来性を持っている。プラセボ効果の神経生物学的メカニズムをより深く理解することで、まったく新しい治療戦略が生まれるかもしれない。アルツハイマー病における萎縮系の再活性化は可能であり、ニューロンが生存する死後ヒト脳組織のスライス培養で活性化合物が探索されている。
回復神経科学は、ブレイン・マシン・インターフェーシングから分子技術まで多岐にわたる。個人の皮質運動意思を記録し、麻痺した筋肉を生き返らせたり、神経人工器官でコンピューターのマウスを操作したりするのに使うことができる。胎児脳移植は、脳の局所的な病変を修復するために使用できる。介入神経科医は、脳卒中の緊急治療に対処する。アルツハイマー病やパーキンソン病の患者を治療し、脊髄の病変を修復するために、遺伝子治療や細胞治療が開発されている。
基礎および臨床神経科学におけるこれらすべての新しい発展により、健康な脳で老後を迎える可能性は常に高まっている。
用語集
アンドロゲン不感受性症候群。男性ホルモンであるテストステロンの受容体遺伝子の変異によって引き起こされる症候群。この症候群の人は遺伝的には男性(XY)であるが、女性として成長し、性的指向、空想、経験を経験する。
異性愛者であり、ジェンダー・アイデンティティの問題はない。先天性副腎過形成。(CAH)。副腎のコルチゾール産生不全に基づく遺伝性疾患である。下垂体および視床下部へのコルチゾールフィードバックが欠如しているため、胎児の副腎は強く活性化され、テストステロンなどの男性ホルモンを大量に産生する。これは、例えば出生時にクリトリスが肥大し、後に行動がより男性的になることから明らかなように、女性胎児を男性化する。
視床下部-下垂体-副腎(HPA)軸。しばしばストレス軸と呼ばれるこの軸は、抑うつ症状の大部分に共通する最終経路と考えられている。関与する副腎ホルモンはコルチゾールである。視床下部の室傍核(図11参照)にあるコルチコトロピン放出ホルモン(CRH)ニューロンはバソプレシン(AVP)を共発現し、CRHの作用を増強する。CRHニューロンは正中隆起だけでなく、脳領域にも投射し、そこで気分に影響を及ぼす。中枢から放出されるCRHとコルチゾールレベルの上昇の両方が、うつ病の徴候や症状に関与している。多型。遺伝子のDNAに生じる小さな変化で、人口の1%以上にみられ、特定の疾患のリスクを増加させる。
18 ニューロトークの限界
M. B. クローフォード
そして、その方法から形而上学を生み出そうとする、つまり、自分の方法が適切で成功するに違いないような宇宙を究極的に仮定しようとする、強い誘惑に常にさらされることになる。
E. バート『現代科学の形而上学的基礎』(1925)
この「神経法」、「神経マーケティング」、「神経政策」、「神経倫理学」、「神経哲学」、「神経経済学」、さらには「神経神学」の黎明期においては、科学主義と科学を切り離す必要がある。現在、神経科学の流用によってさまざまな形の権威を得ようとする文化起業家たちが多数存在し、ニューロトークという方言で私たちに提示されている。このような話にはしばしば、批判的能力の即効溶剤である脳スキャンの写真が添えられている。
本号の別のカ所で、O.カーター・スニードは、法廷における脳スキャンの使用について批評を述べている。議論の便宜上、彼はニューロイメージングがしばしば主張されること、すなわち人間の認知のイメージを提供する能力を備えているという前提で話を進めている。
しかし、脳スキャンを認知の画像として解釈することには、いくつかの基本的な概念的問題が横たわっている。これらの問題を解析すると、現在の「神経」に対する熱狂は、科学主義という大きな文脈の中で理解されるべきものであることが明らかになる。この論理の顕著な特徴は、科学的な説明やモデルを、それが予測や説明の力をほとんど持たない領域にまで過剰に拡張することである。このような本質的な適合性の欠如は、それでもなお、一種の組織論によって、そのモデルがその領域で大きな権威を獲得する妨げにはならないことが多い。アラスデア・マッキンタイアが別の文脈(社会科学)で示したように、必要なのは、モデルを押し付ける人々によるある種のパフォーマンスであり、説明能力の劇的な模倣である。このような場面で、ヘクラーは重要な公共サービスを果たしているのである。
心の分類法
医療診断(たとえば脳腫瘍の診断)に応用される脳スキャンは、原理的にはマンモグラムに似ている。脳スキャンは体の内部を見る方法であり、その成功は明白である。しかし、心理学におけるニューロイメージングの使用は、根本的に異なる種類の事業である。それは研究方法であり、その妥当性はある前提に依存している。その前提とは、精神的プロセスは別個の能力、構成要素、モジュールに分析できるということであり、さらに、これらのモジュールは局所的な脳領域でインスタンス化される、つまり実現されるということである。ラトガース大学の心の哲学者であるジェリー・フォドーは、1983年に発表した古典的な単行本『心のモジュール性』の冒頭でこう述べている:
教授陣の心理学は、骨相学者やその他の怪しげなタイプと何世紀もつるんできたが、再び立派になりつつある。ファカルティ心理学とは、大雑把に言えば、精神生活の事実を説明するためには、多くの根本的に異なる種類の心理メカニズムが仮定されなければならないという見解である。ファカルティ心理学は、精神的なものの見かけ上の異質性を真摯に受け止め、例えば感覚と知覚、意志と認識、学習と記憶、言語と思考のような一見した相違に感銘を受ける。
私たちの精神的経験の異質性に配慮したこのモジュール論は、作業仮説として実に魅力的である。困難なのは、精神の具体的な分類法に到達することである。上の段落でフォーダーが挙げた能力のリストは、不特定多数の競合する分類法に置き換えることが可能であり、実際フォーダーは分類法の分類法を示している。心理学という学問分野では、精神的なものの最も基本的な要素についての合意が欠けている。
精神的なものを分類するという問題は、ニューロイメージングの根幹にかかわる問題である。この問題は、脳画像を明確に定義された認知プロセスとして解釈する上で致命的であると主張する観察者もいる。アリゾナ州立大学の心理学者、ウィリアム・ウタールもその一人である。彼の2001年の著書『The New Phrenology: ウタールは2001年に出版した『The New Phrenology: The Limits of Localizing Cognitive Processes in the Brain』で、成熟した科学に期待されるような精神分類の収束は、時間の経過とともに起こっていないことを示している。むしろ、新しい現象が観察されたり、仮説的な実体が創造されたりするたびに、多かれ少なかれ便宜的で一過性の定義体系が各世代で発展してきたのである。
「視覚記憶」、「音声知覚」など、心理学の教科書をトピックの章に分ける必要性が繰り返し生じ、知らず知らずのうちにこのような用語が再定義され、精神機能の分離可能な独立したモジュールとして理解されるようになった。このような精神モジュールのその場しのぎの起源は、研究者たちの集合的記憶から消え去り、研究者たちは脳内の具体的な位置を探し求めるようになる。
なぜなら、そのような分類法が手元になければ、画像技術の恣意的な特徴がアーチファクトを生み出し、それが教科書的なカテゴリーのように、精神モジュールとして再定義されてしまう危険性があるからである。このような人工物は、バートが上記のエピグラフで警告したような、形而上学的な氷山の一角にすぎない。
さらに、認知神経科学で想定されている心のモジュール理論には、さらに根本的な問題がつきまとっている。それは、心の機能も、それを実現する物理システムも、独立したモジュールに分解できないということだ。ウタルは、認知のさまざまな特徴は、別個の実体ではなく、脳全体に分布する、より一般的な精神活動の特性である可能性が高いと主張している。例えば、知覚を注意ときれいに区別することは可能だろうか?
ウタルは注意についてこう問いかける、
注意とは、分割し、割り当て、集中することができ、限られた量しか利用できず、したがって脳の特定の部分に局在することができる「物質」なのだろうか?それとも、それとは逆に、知覚の属性や特徴なのだろうか… …ゴルフボールの直径や白さが物理的なボールそのものから切り離せないように?脳の特定の領域に位置づけようとする心理的な構成要素やモジュールの多くは、分析可能で分離可能な実体としてではなく、統一された精神的な「物体」の特性として考えるべきだというのは、もっともなことのように思われる。
この議論は、おそらく少々傾向的である。神経画像に関する文献の中で、注意は「物質」であると指摘しているのは誰だろうか?むしろ、注意はある脳領域で実現される機能であると考えられている。というのも、機能は性質と同じように分散しており(実現するためにはシステム全体やメカニズムが必要である)、「該当するシステムの境界線は何か?ローカリゼーションのテーゼに内在する危険性は、内燃エンジンに例えることで明らかになるかもしれない。エンジンについて説明するとき、「吸気バルブが開くのはロッカーアームが動くからだ」と言いたくなるかもしれない。ただし、ロッカーはカムシャフトによって、カムシャフトはクランクシャフトによって、クランクはコネクティングロッドによって、ロッドはピストンによって動かされる。しかしもちろん、吸気バルブが開いて混合気が入ってこない限り、ピストンは動かない。この論理は最終的に循環する。
なぜなら、吸気バルブが開くのはメカニズム全体が原因だからである。全体論的でない考え方は、因果関係を切り捨て、せいぜい部分的に真実であるに過ぎない。人間の脳はモーターよりも何桁も複雑に相互接続していることを考えると、局所的な器質構造が「理性」や「感情」のようなものの十分な原因であり、排他的な場所であると言うのは疑わしいことである。
このような二項対立的な心的カテゴリーは、ニューロトークを取り上げる社会科学者や、一般紙で定期的に採用されている。扁桃体は感情の座であり、前頭前皮質は理性の座であると言われている。しかし、例えば私が怒るとき、一般的には理由がある。感情を理性から切り離すことは、人間の経験を無茶苦茶にするものであり、現実主義を犠牲にしても、心を方法論的に扱いやすくする方法として魅力的なのだ。
このようなナイーブな心理学的モジュール性は、嘘発見器のような、実際に強制力を持つ制度的慣行に組み込まれる可能性がある。現在、サンディエゴを拠点とするNo Lie MRI社とボストンを拠点とするCephos社という少なくとも2つの会社が、神経画像の嘘発見への応用を積極的に商業化している。2007年に『ニューヨーカー』誌に寄稿したマーガレット・タルボットは、ペンシルベニア大学の精神科医ダニエル・ラングルベンが行った欺瞞に関する神経画像研究について述べている:
これらの代表的な研究は、……ほとんど利害関係のない些細なことについて嘘をつくように指示された人々だけを対象にしている。
20ドルというインセンティブは、例えば、あなたの自由、評判、子供、結婚-実際の嘘発見シナリオでは、そのいずれか、あるいはすべてが危険にさらされるかもしれない-とは比較にならない。
これは、嘘を、固有の倫理的内容と実際的結果を伴う精神的行為とは対照的な、最も狭い意味での“認知的´`プロセスとして扱うことである。
ここで認知科学は、100年前の論理実証主義の台頭から始まった哲学における「言語論的転回」にそのルーツを見出す。論理実証主義者たちは文の一貫性に夢中になり、理性を構文的あるいは規則的なものと考えた。それはコンピュータが行うことである。このような考え方は、アンリ・ベルクソンが「意識の緊張」と呼んだもの、つまり、ある世界に関心を持ち、その中に自分自身を見出す、身体化された存在の特徴を全く考慮していない。タルボットは、私たちが「嘘」という用語の下に集めている現象の豊かさと、それが嘘発見という狭い認知的スキームに投げかける問題をうまく説明している:
小さくて礼儀正しい嘘、大きくて図々しくて自己満足的な嘘、子供を守るためや魅惑するための嘘、自分では嘘と認めていない嘘、何日もかけて練習する複雑なアリバイ工作などである。確かに、これらの嘘がすべて同じ神経シグネチャーを持つとは考えにくい。その巧妙さと詳細さ、道徳的な重み、感情的な価値において、嘘はそれをつく人と同じくらい多様である。モンテーニュが書いたように、「真実の裏側には十万通りの形があり、定義された限界はない」のである。
嘘という機能には独自の存在論があるという仮定のもとに、現実の嘘の普遍的で単に形式的な要素を特定し、それを感情的能力、道徳的気質、世俗的状況から切り離そうとするのは、ウタルの例えを使えば、ゴルフボールの白さとボールを切り離そうとするのと同じくらい意味がないかもしれない。精神的モジュール性というテーゼが魅力的なのは、主に思考について話したり、後述するように実験を計画したりするのに便利だからである。しかし、このテーゼは、脳スキャンによる嘘の検出のような、タルボットが思い起こさせるように、「あなたの自由、評判、子供、結婚」に影響を与えるような、世界において現実的な結果をもたらすかもしれない技術を支えるものでもあることに注意されたい。過去の嘘発見技術の波瀾万丈の歴史がそれを示している。No Lie MRIがウェブサイトで法人顧客からの問い合わせを募っていることは重要である。たとえこの技術が、民事当局が使用するための社会的信頼のハードルをクリアできなくても、従業員を威嚇する新しい方法を探している企業経営者を満足させることができるかもしれない。
現実の人間の問題を解決するために科学を利用しようとする人々は、しばしば、まず人間の問題を、理論的に扱いやすいモデルとそれに対応する手法という観点から組み立てられた、狭い意味での技術的な問題に変換しなければならない。このような扱いやすさは、モデルを構築したりいじったりすることで得られる知的喜びという副次的な利益をもたらす。しかし、E.A.バートが言ったように、自分の方法を形而上学に変えてしまう、つまり、自分の方法が適切であるような世界を仮定してしまうという、ほとんど抗いがたい誘惑がある。この手順を人間に適用すると、必然的に人間は下方に定義されることになる。こうして、たとえば思考は「情報処理」になる。私たちは、認知科学が人間の思考とは何かを理解するためにコンピュータに注目するという、驚くべき逆転現象に直面しているのである。
機器化の深い問題
もし精神的モジュール性についての批判が妥当であるならば、実際、脳スキャンによって、さまざまな認知課題に反応して“明るくなる“領域が明確に示されているという事実をどう説明すればいいのだろうか?機能的神経画像(構造的神経画像とは対照的)の場合、脳スキャンを見たときに見えるのは引き算の結果である。例えば、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)は、脳のさまざまな部位における酸素使用率のマップを作成する。つまり、酸素使用率の差分を描写するのである。まず、対照条件下でベースライン測定を行い、次に被験者が何らかの認知課題を行っている間に2回目の測定を行う。次に、ベースライン測定値からタスク実行中の測定値を差し引く。その理由は、一見もっともらしく見えるが、差し引きで表示されるものはすべて、問題の認知タスクのみに関連する代謝活動を表すというものである。
すぐにわかる(しかし通常は気づかない)問題点として、この方法では、どちらの条件でも脳全体が活動しているという、より重大な事実が絵から消えてしまうということがある。すべての分散した機能を差し引いた差分脳スキャンを提示することで、きちんとした機能局在の誤った印象が与えられる。この減算法は画像技術に理想的に適しており、心のモジュール理論と深く一致している。しかし、この心のモジュール理論が魅力的なのは、減算法に適しているからということもあるのだろうか?
1990年代後半から2000年代前半にかけて、より批判的な認知神経科学者の中には、研究者は単に磁石の中に人を突っ込んで、何が「光っている」かを見ているだけで、本当の理論が手元になく、そのような研究は著名な科学雑誌に掲載されるだけだと不満を漏らす者もいた。このような批評は一定の効果があり、この学問分野は「Xのスポット」を探すことからほとんど前進した。実際、認知神経科学者たちは、心の複雑さに対応するために発達させた方法論の巧みさは称賛に値する。1999年の『Behavioral and Brain Sciences』誌の論文で、ケンブリッジの神経科学者フリーデマン・プルヴァーミュラーは、言語機能を局所化する努力で生じる困難について徹底的に説明した。減点法の問題点は、「多くの実験では、知覚(単語が画面上に見えるか見えないか)、注意、分類(単語は名詞や動詞であったり、意味のない擬似単語であったりする)、運動反応(被験者は反応の一部としてボタンを押す必要がある)、検索過程(被験者は単語を思い出す必要がある)、意味推論などの次元において、臨界条件と対照条件の間に(1つではなく)いくつかの違いがあることだ」と彼は書いている。ある領域が「点灯」することがわかったとしても、……多くの異なる認知過程のどれが脳活動の違いに関係しているかは明らかではない。同様に、Michele T. DiazとGregory McCarthyはJournal of Cognitive Neuroscience誌の2007年11月号に、“単語処理それ自体とは無関係な認知過程の共活性化が…最も単純な単語処理課題でさえも得られる活性化のパターンに影響を与えている可能性が高い``と書いている。
シカゴ大学の“社会神経科学者“ジョン・T・カシオッポ(John T. Cacioppo)氏らは 2003年の『Journal of Personality and Social Psychology』誌の論文で、ニューロイメージングのこうした方法論的危険性について、哲学的に洗練された扱いをしている。彼らは、認知現象の構成が、その根底にある神経基盤の構成と1対1で対応するという直感的に魅力的な考え方を“カテゴリー・エラー“と表現している。例えば、記憶、感情、信念は、かつてはそれぞれ脳の1つの部位に局在していると考えられていた。しかし現在では、ほとんどの複雑な心理学的・行動学的概念は、脳内の単一の中心にはマッピングされないことが示唆されている。ある時点では単一の構成要素に見えるもの(例えば記憶)も、脳からの証拠(例えば病変)と合わせて調べると、両方のレベル(例えば宣言的記憶過程と手続き的記憶過程)において、より複雑で興味深い構成が明らかになる。たとえ局在があったとしても、心理学的・行動学的構成概念と神経操作との間に首尾一貫したつながりができるまでは、とらえどころがないだろう。
これらの論文が示すように、分散し、相互に絡み合った精神機能の問題は、神経科学の現場において非常に大きな問題である。いかに大理論者がこのような難題を無視して、スティーブン・ピンカーが『How the Mind Works』の中で主張しているように、「心はモジュールまたは精神器官に組織化され、それぞれが世界との相互作用のある分野の専門家になるような特殊な設計をしている」と主張するのが好都合だと考えているとしても。このような単純化は文化的に無邪気なものではない。嘘のないMRIのような企業家による権威の掌握に不可欠な口実を与え、ひいては市民当局による強制的な権力行使を正当化することになりかねないからだ。おそらく機能的画像診断の最も根本的な限界は、「心の中を覗き見ることができる」という主張に対して、時間スケールの基本的な断絶があることだろう。興味のある神経活動は、血行動態反応(fMRIで測定される神経活動の代用)よりも何桁も速い時間スケールで起こるからである。ウタールはこう書いている、
脳代謝の累積的な測定値は、理論的にも経験的にも、ミクロレベルの神経ネットワークの瞬間的な詳細、つまり精神神経に相当する実質的な情報処理レベルとはリンクしていない。この観点からすると、スキャニング・システムから得られる脳活動の「兆候」は、皮膚電気反応や筋電図のような他の生理学的相関関係以上に、何が起こっているかの「コード」ではない。
私はウタルの言葉を、fMRIによって得られる脳画像は、精神活動の兆候として機能するかもしれないが、時間スケールが異なるため、(心の計算理論では)精神活動を符号化する機械の状態を保存することはできない、という意味だと解釈している。このような兆候では、私たちはメカニズムについて知ることはできない。あるメカニズムが存在するというサインを持っているのだ。しかし、メカニズムがあるという発見は、以前は二元論者でなかった限り、まったく発見ではない。
機械を尊重する
しかし、ある日、イメージング技術が空間的・時間的解像度を達成し、神経細胞レベルまで、精神活動の物理的相関を正確にとらえることができるようになったとしよう。するとどうだろう?別の工学的な例で言えば、回転運動を直角に伝達する斜めの歯車列(数十年前のドゥカティ・モーターサイクルのエンジンのように)を作ろうとしたことのある人なら誰でも知っているように、単純なメカニズムを完全に理解することは、驚くほどとらえどころのない仕事である。このような歯車列では、観測されたどの運動にも対応しない方向に力が働く。スラスト力とサイドフォースは、知的には管理可能(数学的に表現できる)だが、実際的には些細なこととは言い難い。経験豊富なエンジン製作者であれば、シムや公差と格闘して丸一日かかるかもしれない。
かさ歯車は、アルキメデスの単純な機械(てこ、滑車など)よりもかろうじて複雑なだけだが、人類は、まるで啓示のように、それを受け取るためにレオナルドの天才を待たなければならなかった。有名な話だが、科学と工学の最も繊細な応用は、例えばストラディバリのバイオリンの貴重な特徴を完全に再現することはまだできない。ある試算によれば、ニューロン経路の可能性の数は宇宙の粒子の数よりも多い。
しかし、ある種の知識人にとっては、ある謎に機械的根拠があると仮定するだけで、満足感が得られる。原理的に我々の理解力を超えるものは何もない、という考えには、早々と達成感が押し寄せてくる。しかし、原理的に知ることができるということは、実際に知ることができるということとはまったく異なる。実際に機械に触れてみると、形式的に訓練されたエンジニアはしばしば当惑する。そのような機械的な経験の欠如が、ある種の技術者に「戸惑い」をもたらすのだろうか。
機械に正当な報酬を与えず、知ることができるものと知られているものとの間のこの差異に十分な感銘を与えない、ある種の知的な態度が可能になる。
形而上学的な熱狂者の一種が、知ることができるものと既知のものとの間のこの隔たりを軽快に飛び越え、冷静に分析すれば未熟であることがわかる研究プログラムの広報担当として活動しているのをよく見かける。カリフォルニア大学サンディエゴ校のポール・チャーチランドもその一人で、彼は1995年の著書『理性のエンジン、魂の座』の中で、「われわれは今、鮮明な感覚体験が脳の感覚皮質でどのように生じるかを説明できる立場にある。[そしてそれは膨大な神経活動の大合唱の中で具現化される。…
そして、成熟した脳がどのようにしてその枠組みをほぼ瞬時に展開するのか、つまり類似性を認識し、類似性を把握し、近い将来と遠い将来の両方を予測するのかが理解できるようになったのである。ジェリー・フォーダーがチャーチランドの本の書評で簡潔に言ったように、「このどれもが真実ではない」のである。チャーチランドの誇大広告の重要な要素は、「われわれの鮮明な感覚体験は感覚皮質で生じる」ということを知っていることと、それがどのように生じるかを説明することの区別にある。「幼児の脳はゆっくりと概念の枠組みを発達させ」、「成熟した脳はほとんど瞬時にその枠組みを展開する」ことは確かに知っている。フォドーが言うように、最初のかすかな光さえもない。
犬と陽子の脳スキャンが人間の認知のイメージを目の前に提示し、その全容を検査できるという考え方は、明らかに魅力的である。この積極的な魅力は、徹底的に還元的な唯物論に代わる唯一の選択肢と考えられているもの、つまりある種のスピリチュアリズムや、より広義には「反科学的なもの」に対する恐怖心によって支えられている。
しかし、存在論的還元と説明的還元は区別しなければならない。この区別は科学哲学では当たり前のことだが、認知神経科学をめぐる誇大広告では日常的に無視されている。ある現象がより基本的な部分から構成され、より基本的な部分に依存しているという事実から、より高次の現象の説明は、その部分のより低次のレベルの説明で置き換えることができる、あるいは、残滓を残さずに説明することができると考えられている。このような還元が(仮に)達成されると、高次の現象の存在論的地位は、単なる現象に降格される。私たちの視線は、最初に理解したかったものから、その根底にある基層へと移される。宇宙はひとつしかなく、それは物理的粒子で構成されている。
しかし自然科学者は、その宇宙に関する最善の説明が、多くの場合、物理学からは得られないことを知っている。そのため、化学や生物学に頼ることになる。このような
高次構造を所与のものとするこのような「特別な」科学の必要性は、物理的粒子からなる単一の宇宙が存在するという根底にある存在論的仮定を損なうものではない。高次元の学問の自律性を認めつつ、唯物論を持つことは可能なのである。この点については多くの混乱があり、説明の姿勢において完全に還元的でないことは、何らかの形で「スピリチュアリズム(精神主義)」にコミットすることになるのではないかという恐れが、この混乱を後押ししているようだ。
生物学の説明の独立性、つまり物理学への還元不可能性は、生物学的実体が物理的実体から構成され、物理的実体に依存していることと矛盾しない。生物学者は、犬は陽子と中性子と電子だけからできていると信じているが、そのレベルで犬の説明をしようとはしない。これは単に現在の知識の限界によるものなのだろうか?素粒子物理学から犬を包括的に理解することは原理的に可能なのだろうか?複雑性や非線形性、あるいは熱力学的な不可逆性(お好きなものをどうぞ)を考慮すると、原理的に不可能であるというのがコンセンサスになっているようだ。物理学の世界でも、下位レベルの説明では、上位レベルでしか識別できない構造を前提としたり、下位レベルの説明では生成できない境界条件に依存したりすることがある。気体の体積のような単純なものでさえ、次のような特性を示す。
個々の気体分子間の衝突(これは時間に対して対称的である)からは導き出すことができない。
完全に還元的に理解できない現象に直面したとき、形而上学的な危険感に悩まされるのは、科学者ではなく、むしろ科学の広報担当者のようだ。しかし、この恐怖はどれほどのものなのだろうか?それはむしろ、そのような広報担当者がとるポーズなのだろうか?多くのヒューマニストは、科学的説明の原理を十分に理解していないため、この種のいじめが科学を代弁しているという主張が詐欺的であることを見抜くことができず、科学に対して憤りを感じてしまう。これはヒューマニストにとっても、科学にとっても良くないことである。
神経形而上学者の狂言
最近『認知神経科学ジャーナル』誌に掲載された論文は、脳スキャンが見る者に与える魔法のようなトーテム効果に光を当てている。The Seductive Allure of Neuroscience Explanations(脳科学的説明の魅惑的な魅力)』の著者であるイェール大学の学者チームは、日常経験でおなじみのある種の心理現象について、被験者にさまざまな説明を提供した。これらの説明の中には、明らかに悪い説明であるように仕組まれたものもあった。被験者は神経科学者、神経科学を学ぶ学生、一般社会人の3つのグループから構成された。その結果、3つのグループとも、悪い説明の前に「脳スキャンが示している」という言葉が添えられている場合を除き、悪い説明を悪い説明と見分ける能力が高いことがわかった。その場合、学生と一般社会人は悪い説明を受け入れる傾向があった。デイビッド・P・マッケイブとアラン・D・カステルによる補足的な一連の実験は、現在『Cognition』誌に掲載中であるが、「読者は脳画像を含む記事の方が、そうでない記事よりも科学的価値を推論する。」
これらの知見は、われわれは文化的に、脳画像を前にすると自分の判断を放棄する傾向があることを示唆している。より一般的に言えば、私たちは単なる「科学」の体裁に従うのである。このような判断の疎外は、法律、政策、精神医学、経営など、他者に対する権威というよりも、むしろそのような権威の神話的な源となることを求める、あらゆる文化的起業家にとって好機となる。脳の絵に反論はない。さらに、そのような起業家が提供する説明には、すぐにでも市場がある。人間の管理を任されている人々の間では、科学のオーラが彼らの努力に正当性を与えるため、彼らの介入を正当化できる科学的に見える説明に大きな飢えがある。
例えば、ジェフリー・ローゼンが2007年に『ニューヨーク・タイムズ』誌で報じたように、公共政策の教授たちは、脳スキャンを使って暴力だけでなく人種偏見のような傾向も予測できるようになることを夢見ている。人間の行動が電気化学的にあらかじめ決められているのであれば、「ハードワイヤリング」された悪質な人間に対する先制的な介入に反対する根拠はない。そのような介入は、監視、監禁、あるいは(薬物、手術、インプラントによる)改造という形をとるかもしれない。
しかし、神経弁護士や神経犯罪学者は必ずしも神経科学者ではない。皮肉なことに、ニューヨーク大学の認知神経科学者であるエリザベス・フェルプスによれば、「脳の活動が、我々が脳機能と相関させている行動よりも、法廷において我々が気にかけていることを予測できるという証拠はまったくない」のだという。言い換えれば、ある人物が将来法を犯すかどうかを予測したいのであれば、その人物の脳の画像は過去の行動の記録と変わらないということだ。将来の行動と脳の異常の相関関係は、過去の行動よりも弱いからだ。神経科学者のマイケル・ガザニガは、その著書『倫理的な脳』の中で、「下眼窩前頭葉の病変を患う患者のほとんどは、法律が注目するような反社会的行動をとらない」と書いている。そのような病変を持つ人は、そうでない人に比べてそのような行動の発生率が高いということに過ぎない。だから、行動を予測するという実際的な目的のために、脳の画像を指して語られる神経学的因果関係の物語は、予測力がないにもかかわらず、過去の行動と将来の行動の間に無償で挿入される形而上学の層を追加するだけである。
ローゼンは、ペンシルバニア大学の社会精神医学と精神倫理学の教授であるポール・ルート・ウォルプの言葉を引用して、「私はNASAで働いているが、もしNASAがあなたの脳をスキャンして、あなたがパイロットになるのに十分な空間感覚を持っているかどうかを発見することができたら、NASAにとってどれほど役に立つか想像してみてほしい」と述べている。しかし考えてみてほしい: NASAは現在、あなたの空間的推理力を、神経学的相関関係ではなく、知的能力そのものを直接テストしている。これはフライトシミュレーターに乗せ、パイロットとして直面するような実用的な状況でのパフォーマンスを観察することによって行われる。しかし、このような実用的な方向性では、因果関係の隠された領域にアクセスするような興奮は得られない。
科学史の中で、隠された原因が人々を興奮させたエピソードを思い出してみよう。17世紀、科学の壮大な問題のひとつは、物が倒れる理由を説明することだった。デカルトは、上方から衝突する知覚できない粒子が物体を下方に押し下げるという、厳密に機械的なビリヤードボールモデルを開発した。他にも競合する力学的モデルはあった。つまり、物体は一様に加速して落下し、その加速度は大きさに関係なくすべての物体で同じであるということである。つまり、物体は一様な加速度で落下し、すべての物体の加速度は大きさに関係なく同じである、ということである。ニュートンはこれを実行したが、その際、より教条的な「機械論者」たちから攻撃を受けた。ニュートンは、スコラ哲学的な「オカルト的な性質」を自然界に再び持ち込んだと非難された。現在の心理学における還元主義が「魂」のような不気味な概念を追放しようとしているように、機械哲学が追放しようとしたのはまさにこの種の説明だった。
機械哲学が、私たちが目にすることのできる世界と同じような原因があるに違いないという仮定のもとに、隠されたメカニズムを確信犯的に仮定したのに対し、ニュートンは原因を謎めいたままにしておくことに満足した。そして、不思議な引力によって物体がどのように動くかを数学的に説明した。重力の原因の不明瞭さを受け入れることで、ニュートンは現象に目を向けることができ、現象の数学化を達成することができたようだ。機械哲学者が採用した還元的な立場は放棄されたのである。アインシュタインによって一変したとはいえ、重力に関する我々の理解が、原因について不可知論的なままであることは注目に値する。遠距離での不気味な作用の代わりに、現在では時空の歪みがさらに不気味になっている。物理学者は認知科学者よりも不気味になりにくいようだ。
精神の自律性
さて、それではどうなるのだろうか?私は、人間を理解するための適切な指針として、普通の人間の経験を尊重することを主張したい。このような敬意は、“神経哲学“の分野(最も有名なのはポールとパトリシア・チャーチランドの研究)とは対照的である。この分野は、“反射“や“熟考“といった“俗語“を、脳の状態を表す用語に置き換えることに熱心である。言うまでもないが、脳の状態は客観的事実であり、それに対して私たちの精神生活に関する内省的経験は本質的に主観的なものである。しかし、客観的なものと主観的なもの、脳と心の間のこの隔たりは、原因と結果の上にきちんとマッピングされるわけではないし、何らかの形でより根源的な現実の層と、単なる現象的なものとの間の明確な区別の上にマッピングされるわけでもない。例えば、母親が死んだと聞かされた場合、その事実を理解したあなたの狼狽は、主観的な精神的出来事であるが、あなたの脳に客観的な生理学的変化を引き起こす。
このように精神的なものが肉体的なものに対して因果的な力を持つことを考えると、この2種類の現実を重層的なものとして考えるのは正しいのだろうか。この疑念から、自分の精神生活に関する内省的経験を脳の状態という観点から再記述することは、この意味で任意であることが導かれる。それぞれの説明は、異なる実践の領域から発せられる、異なる種類の“説明の要求“に答えるものである。フォークの説明は日常的な人間の経験の領域に答えるものであり、脳の説明は生理学的な調査の領域に答えるものである。
脳の記述がより包括的な意味で精神的な記述より優れていて、精神的な記述を包摂し、それを時代遅れにしてしまうと主張するには、2つの記述が衝突する接点がなければならない。例えば、コペルニクス理論が、地球が宇宙の中心であるというそれまでの見解に勝ったとき、このようなことが起こった。私たちの精神生活を神経学的に再定義することの問題は、そのような接触がないこと、つまり競争がないことだと思われる。したがって、プラグマティックな理由以外に、どちらか一方を好む理由はない。脳に関する知識と、私たちが自分自身について直接知っていることの間には説明上のギャップがあり、どのような発見がそのギャップを埋めるのか想像するのは難しい。私たちの精神生活に神経学的根拠があるはずだということは議論の余地がない。しかし、その最初の洞察は、私たちの自己理解に対する脳スキャンの貢献を使い果たしたようでもある。
心と体の問題をブラケットで囲むことは、満足のいくものではない。しかし、このような形而上学的な満足感の欠如は、私たちが生きていく上で必要なことなのかもしれない。そうすることは、あたかもこれらの究極の問題に決着がついたかのように、そして常に私たち自身の主体性について私たちが直接知っていることを覆すような方法で、法律や公共政策、倫理を改革しようと急ぐ人々の熱意に対抗する、一種の節制なのである。
あとがき
ウォルター・グラノン
過去20年間で、理論的にも臨床的にも神経科学は目覚ましい進歩を遂げた。機能的神経画像は、認知や感情のプロセスと相関する脳領域の活性化をリアルタイムで表示することができる。脳スキャンはさまざまな神経疾患や精神疾患の診断を向上させた。また、これらの疾患の進行や、治療に用いられる薬剤の代謝効果をモニターするのにも用いられる。精神薬理学は、脳と精神の疾患に対して、一般的により安全で効果的な治療薬を開発してきた。これらの薬剤の中には、正常な認知機能を高めるために使用できるものもある。脳に電気刺激や磁気刺激を与えることで、他の治療法に反応しなかった神経疾患や精神疾患の症状を抑えることができる。回復神経外科の分野における幹細胞を用いた神経移植は、神経変性疾患、脳卒中、脊髄損傷による損傷を回復させることが期待されている。人工神経は、麻痺で動けなくなった人が自分の意思を行動に移すことを可能にするかもしれない。こうした脳への対策や介入はすべて、多くの人々に恩恵をもたらし、自立を促し、生活の質を向上させる大きな可能性を秘めている。
これらの薬物や技術には暗黒面もある。非定型抗精神病薬は患者が突然心不全で死亡するリスクを高める可能性がある。脳スキャンは、多数の画像に基づく統計解析の視覚化であり、脳内で実際に起こっていることの写真とは不正確に表現される。神経画像から得られる情報の解釈にはかなりのあいまいさがあり、保険会社や雇用主による差別につながりかねない偏見や乱用の可能性がある。
また、脳の画像には魅惑的な魅力があり、刑法上の事件を決定する陪審員に不当に影響を与える可能性がある。これらの点でも、またその他の点でも、画像診断は私たちの脳に関する情報のプライバシーと機密性を脅かす可能性がある。脳深部刺激は、パーキンソン病の運動症状や大うつ病の感情症状をコントロールする可能性があるが、人格や精神の他の側面に悪影響を及ぼす可能性がある。幹細胞を神経ネットワークに移植すると、成長因子が無秩序に増殖し、神経再生の対象となる脳の領域以外の健康な組織に損傷を与える可能性がある。このような技術を開発・応用する研究者や臨床医は、利益を最大化し、害を最小化するという微妙なバランスをとらなければならない。
より理論的なレベルでは、認知神経科学の研究により、脳と心の関係についての重要な洞察が得られている。その結果、精神性の神経生物学的な裏付けがよりよく理解されるようになった一方で、自由意志、道徳的推論、自己についての私たちの根深い確信に挑戦することになった。ニール・レヴィが序文で指摘しているように、
私たちを私たらしめているのは心である。しかし、もし私たちの心が脳の機能であるならば、私たちの思考や行動の多くは、意識的なコントロールの外で起こっていることになる。このことは、もし私たちの思考や行動のすべてがニューロン、シナプス、神経伝達物質の集まりに還元されるのであれば、私たちはどのようにして賞賛、非難、責任帰属の習慣をもっともらしく保持できるのかという疑問を提起する。遺伝子がどのように表現形質に表れるかは、DNA配列だけの機能ではなく、遺伝子、ヒト生物、そしてそれらが置かれた環境の相互作用の結果である。我々は遺伝子だけの存在ではない。しかし、神経科学が脳と心の関係について明らかにしたことに照らせば、D. F. Swaabの言葉を借りれば、「私たちは私たちの脳である」ということになる。
しかし、人間の思考と行動には経験的な側面だけでなく、規範的な側面もある。私たちの欲望、信念、感情、決断は脳に依存しているが、自由と責任に関する判断は、私たちがどのように行動できるか、またどのように行動すべきかについての社会的期待に大きく依存している。私たちが自由で責任ある行動ができる、あるいはできないと主張する際に訴える理由は、私たちが生きている社会環境によって形成される。これらの理由は、脳がどのように心を生成し、維持するかについての知識によって知らされる必要がある。しかし、これらは神経科学だけの機能ではないため、神経科学的な用語だけで満足に論じることはできない。
マシュー・クロフォードは、第18章における心のモジュール性に関する批判的な調査の中で、我々の経験が脳の異なる領域に根ざしているという知識と、我々の経験が脳のプロセスからどのように、あるいはなぜ生じるのかを説明することの間には、説明的なギャップがあると指摘している。ジェイムズ・ジョルダーノの痛みの現象学に関する議論や、ラルフ・エリスの意識の持続的な「難問」についての議論は、このようなギャップが確かに存在することを示唆している。この考察だけでは、主観性に対する神経科学的な挑戦と、それに関連する形而上学的・倫理的確信を完全に無力化するには不十分だという人もいるだろう。しかし、他の人々にとっては、神経科学が精神性を単なるエピフェノメノンとして説明する脅威を打ち消すのに十分かもしれない。意志や自己の概念、そして規範的な実践や制度を維持するだけでも十分かもしれない。とはいえ、この議論には、脳に関する経験的主張と心に関する規範的主張が相互に排他的ではなく、補完的であるというモデルが必要である。二元論は説得力のある理論ではなく、還元的唯物論でもない。
この補完性は、学際的な協力によって達成することができる。ジョルダーノは、C.P.スノウの有名な議論を引用し、科学と人文科学という2つの文化の間の溝について述べている。
E. O.ウィルソンの「コンシリエンス(consilience)」という考え方を支持している。科学者と人文科学者の共同作業の重要性を強調する主張にもかかわらず、脳科学の倫理的・社会的意味合いに関する最も生産的な作業は、神経科学者と社会科学者の間で行われてきた。これまでのところ、ヒューマニストはこの共同事業において比較的小さな役割を果たしている。
少なくとも2つの理論的な問題について、神経科学者と人文科学者は、互いに関わり合うというよりは、むしろ過去の話をすることがほとんどであった。神経科学者や認知心理学者の多くは、われわれの脳に関する知識は、自由意志に対するわれわれの信念が幻想であることを暗示していると主張している(Wegner 2002; Greene & Cohen 2004; Farah 2005)。対照的に、脳と心の関係を論じてきた哲学者の多くは、自由意志のもっともらしい概念は神経科学と両立すると主張している(Mele 2009)。神経科学者や認知心理学者もまた、脳画像やその他の経験的尺度に依拠して、道徳的葛藤がある場合に客観的な道徳的正当性を行動に与えることができるという見解は、脳に関する知識によって覆されると主張している。哲学者たちは、脳画像はこのようなケースに関する私たちの直感的な判断を反映しているに過ぎないと主張する。道徳的正当化の一環として、理性に基づく考慮された判断を下すことができないことを示すものではない(Singer 2005; Kamm 2007)。ある脳画像研究では、健康なボランティアの大多数が、5人を救うために暴走したトロッコを線路から別の線路に方向転換させることは許されると考えた。しかし、トロッコを止めて5人を救うために、罪のない傍観者を線路に突き落として殺すことは許されないと考えた。感情を媒介する脳領域の活性化が、2つのシナリオに関する直観の違いを説明したと考えられる(Greene & Haidt 2002)。しかし、直観に訴えるだけでは、最初の行動が許され、2番目の行動が許されない理由を説明することはできない。考慮された判断を反映する理由や原則は、道徳的に行為を正当化するために必要であり、神経科学がこうした判断を下す能力を否定するという主張には説得力がない。道徳的ジレンマを提示されたときの皮質および皮質下領域の活性化を示す脳スキャンは、道徳的正当化の第一近似値にすぎない。規範的倫理学というよりは、記述的倫理学の領域である。哲学者は、ある行為が許される、あるいは許されないという直観を人がどのように形成するかを説明する経験的要因に、もっと注意を払う必要がある。同時に、神経科学者や認知心理学者は、規範的な要因が、なぜこれらの行為が許されるのか、あるいは許されないのかを説明するのかについて、より注意深くなる必要がある。それぞれのグループは、他方に情報を提供し、他方から情報を得る必要がある。
本書で何人かの著者が引用しているブレイクスルー論文がある、
アディナ・ロスキーズは、神経倫理の2つの分野を区別した。神経科学の倫理学と倫理の神経科学である(Roskies 2002)。前者は、脳へのさまざまな介入の利益とリスクをどのように秤量するかといった問題を含むが、後者は、神経基盤が道徳心理学をどのように根拠づけるかという問題を含む。現在までのところ、神経倫理の第一の応用的な分野では、第二の理論的な分野よりも合意形成が進んでいる。精神的プロセスが、局所的な脳機能の実現としてではなく、相互接続された一連の神経ネットワークの創発的特徴として理解されるのが最良であるように、神経科学と神経哲学のより良い理解もまた、異なる分野の専門家が独立するのではなく、協力し合うことで生まれるのである。このモデルは、精神と中枢神経系、内分泌系、免疫系との相互作用によって脳がどのような影響を受けるかを研究する精神神経免疫学の分野に、医学的な類似点がある。
Alexis JeannotteらとRobert Blankが強調しているように、学際的な協力は、ニューロテクノロジーの応用を導く国際的な政策の策定と実施につながるはずである。これらの方針は、さまざまな治療用途におけるこの技術の安全性と有効性を確保する上で、一定の役割を果たすだろう。認知機能強化のための技術の使用に関しては、社会的不平等を悪化させることなく、個人の自由を促進するような形で政策を策定すべきである。国際的な議論は、ヒトゲノム計画におけるELSIプログラム(倫理的、法的、社会的意味合い)をモデルとすべきである。この議論から生まれる価値ある産物は 2008年に米国で制定された「ゲノム情報無差別法(GINA)」の神経倫理学的類似法かもしれない。ニューロテクノロジーの潜在的な影響について川下から考えることで、すべての利害関係者は、利益とリスクについて建設的な議論を行い、脳へのさまざまな介入がどのように利用できるか、あるいは利用すべきかについてコンセンサスを得ることができる。また、ニューロテクノロジーの長期的な可能性を推測することもできる。人工神経は、単に運動制御を回復させるだけでなく、脳と一体化する。このような、脳に直接影響を与えるテクノロジーやその他のテクノロジーは、人間や人間としての私たちの概念を再考させ、人間からポストヒューマンの世界への進化の一部であるかどうかを考えさせるかもしれない(Gordijn & Chadwick 2008)。
本書の各章は、基礎神経科学と応用神経科学のさまざまな側面について、魅力的な視点を提供している。哲学的、倫理的、社会的な意味合いや、放射線学、生物医学工学、ナノテクノロジーとの交わりを探求している。本書は、脳科学における歴史的、実際的、そして新たな研究とその応用の興奮と重要性を捉え、学際的な線に沿って重要な問題を議論することがいかに大きな進歩をもたらすかを示している。
