コンテンツ
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8233626/
2021 Jun 26
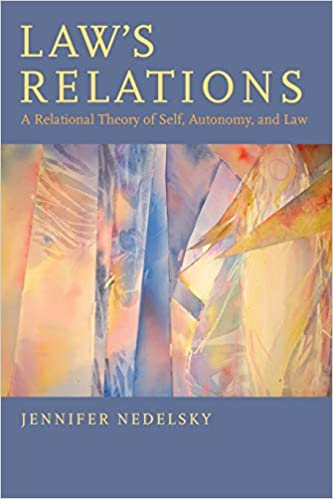
要旨
COVID-19は、多くの倫理原則や前提条件を覆した。より正確に言えば、自律性尊重の原則は、現在の健康危機がもたらす倫理的課題に直面するのに適していないことが示された。個人の希望や選択が、公共の利益に従属してしまっているのである。
患者は、インフォームド・コンセントを得るための特別な手続きを経て、試験的な治療を受けている。今回のパンデミックでは、少なくとも主流の解釈である自律性の尊重の原則が特に問われている。
自律性の性質と価値についてのさらなる考察が緊急に必要である。関係性オートノミーは、現代の一般的な倫理問題や、特に我々が現在直面しているようなパンデミックに、より適切に対応できるオートノミーの代替的な説明として提案されている。関係的自律性は、現在の生命倫理学において新たな概念であるため、適切に運用するためにはさらなる検討と発展が必要である。
本論文の目的は、自然哲学、人類学、実存的現象学、言説倫理学、解釈学、文化人類学という6つの異なる哲学分野が、20世紀を通じてどのように関係性というカテゴリーを取り入れてきたかを示すことである。
我々は、まず一次的な哲学的資料を掘り下げ、その洞察を医療倫理という具体的な分野に適用していく。他の哲学分野の歴史的発展に学ぶことは、現代の生命倫理学において部分的に開始されながらも達成されていない「関係性の転回」を、生命倫理学が成功させるための光明となるだろう。
キーワード
COVID-19,リレーショナルオートノミー、意思決定の共有、グローバル倫理、哲学史
はじめに
自律性の尊重は、ここ数十年の生命倫理において重要な原則となっている(Dworkin 1988; Childress 1990)。それにもかかわらず、BeauchampとChildressのようなアメリカの原則主義に基づいた個人主義的なアプローチを批判する声が多くある(Clouser and Gert 1990; O’Neill 2002; Traphagan 2013)。この点、COVID-19による現在の健康危機は、生命倫理の議論で一般的に理解されている自律性の尊重1の狭い解釈の限界をさらに露呈させるかもしれない。COVID-19パンデミックのような健康危機がもたらす倫理的課題によりよく対応するために、この原則の「関係的転回」を求める著者もいる(Jeffrey 2020; Lang and Micah Hester 2021)。これらの路線に沿って、生命倫理学における新たな概念である関係的自律性は、個人主義的な自律性のビジョンに代わるものとしてしばしば提案されている(Mackenzie and Stoljar 2000)。しかし、この概念の体系的なレビューでは、理論的・実践的な発展が不十分であることが明らかになっている(Gómez-Vírseda er al 2019)。潜在的に有望な概念であるにもかかわらず、リレーショナル・オートノミーは明確に概念化されたり、実践的に運用されたりするにはほど遠い。したがって、この欠陥の哲学的ルーツの分析が必要である。
本論文では、仮説演繹的手法を用いてこの課題に応えることを目的とする。我々の仮説は、医療倫理が意思決定プロセスの中核に関係性の概念を明確に組み込んでいないというものである。関係性の導入を成功させるために、我々は4つのステップを踏む。
第一に、最近の生命倫理の文献に描かれ、COVID-19の現在の健康状態によって確認されたように、主流の個人主義的な自律性の見解に対する挑戦を提示する。
第二に、現在提案されている関係的自治が、主に関係性の説明が弱いために、この問題に対する満足な答えを提供できていないことを明らかにする。
第3に、20世紀に関係性というカテゴリーを理論的な核に統合することに成功した6つの異なる哲学的枝を分析する。
第4に、この歴史的分析から、生命倫理に特に貢献できる6つの重要な洞察を抽出する。
我々は、関係性のカテゴリーを生命倫理理論の中心に統合し、自律性の原則を変換することで、BeauchampとChildress(2019)の古典的な原則の間でより良いバランスを実現すべきだと結論付けた。この変換は、COVID-19のような緊急の健康状態において特に役立つ可能性がある。
個人の自律性への挑戦
自律性の尊重は、現代の生命倫理の重要な成果であることは間違いない。この概念は、インフォームド・コンセントの使用や医学研究への非自発的参加の廃止など、確立された医療法上の慣行の背後にあるものである(Faden and Beauchamp 1986)。しかし、この原則の狭義の解釈を批判する声が、倫理学の理論と臨床の両方から多く聞かれる。
生命倫理文献からの挑戦
こうした反対の声の中で、リレーショナルな著者たちは、自律性尊重の原則の主流の解釈は、男性的で西洋的な人間観によって過度に形成されていると批判している(Mackenzie and Stoljar 2000; Stoljar 2018)。MackenzieとStoljar(2000)は、その批判を象徴的、形而上学的、ケア、ポストモダニスト、多様性という5つのクラスターにまとめている。これらの批判は、自律性の原則を完全に否定するのではなく、「エージェントが組み込まれている豊かで複雑な社会的・歴史的コンテクストに注意を払う」(Mackenzie and Stoljar 2000, p.21)という概念の豊かな説明を要求している。
同様に、終末期ケアにおける関係的オートノミーの利用に焦点を当てたシステマティックレビューでは、個人主義的なオートノミーの説明に対する4つの批判が検出されている。
- 第1に、個人の自己を原子的、独立的、自己伝染的、自己利益的なものと誤解していること、
- 第2に、社会的文脈や関係的環境を取り入れることができない意思決定プロセスの不適切な描写、
- 第3に、障害者や文化的マイノリティに対する差別的な偏見、
- 第4に、法的文書や医療政策における認知的バイアスである(Gómez-Vírseda er al 2019).
個人の自律性に対するこれらの課題は、最近の生命倫理の文献において、フェミニズム、コミュニタリアニズム、パーソナリズム、ケア倫理、多文化主義、現象学、関係倫理、美徳倫理という8つの異なる倫理的アプローチから検出されている(Gómez-Vírseda er al 2019)。
COVID-19の臨床的現実からの課題
自律性の個人主義的な説明に対する批判は、理論的な立場からだけではない。臨床的な現実は、患者の自律性に関する個人主義的な見方にしばしば挑戦する。患者は「繭の中」ではなく、関係的、社会的、文化的な環境の中で生活しており、その環境が患者の意思決定に影響を与え、制限しているのである。この事実は、COVID-19危機の際に特に明らかになった。
このような観点から、Jeffrey(2020)は、COVID-19が患者、家族、医療従事者、政策立案者、そして一般市民に突きつけた倫理的問題を以下の3つの分野に分類している。
- 個人の自由を制限する検疫、隔離、社会的距離
- 医療従事者は、自分自身や愛する人のリスクを冒してでも患者にケアを提供する義務、
- 資源が限られている場合の治療へのアクセス。
さらに、COVID-19によって引き起こされた例外的な状況により、いくつかの組織が新薬や治療法をテストする際の倫理的・法的基準を緩める必要がある(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 2020,European Medicines Agency 2020,U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration 2020)。緊急事態の中では、個人の保護が最優先される通常の枠組みとは対照的に、社会的なニーズを満たすために医学研究がライセンスを感染した可能性がある(van der Graaf er al 2020)。
Baum and Żok(2020)は、最大限の個人主義は、ほとんどの規範や法律に沿った「一般的な傾向」であるが、COVID-19の時代には、倫理的、社会的、経済的なジレンマが数多く生じたと論じている。これらの著者によれば、緊急事態では、通常の道徳規範では考えられないような特別な倫理基準が必要となる。したがって、自律性の尊重は、「共通の利益の最大化」や「社会に対する価値」などの他の原則に優先する。同様の懸念はHastings Center Ethical Framework(Berlinger er al 2020)でも表明されており、患者中心の診療から公衆衛生上の配慮に導かれた患者ケアへの変化を検出している。この変化は、臨床家、政策立案者、一般市民の間に大きな緊張感をもたらしている。なぜなら、西洋社会は少ない資源で緊急事態に対処することに慣れていないからである。
Calvo et al 2020)は、感染の可能性がある人々を特定し、その接触者を追跡し、社会的距離を強化するために使用されてきた新しい健康モニタリング技術が、プライバシーと個人の自律性を脅かすことを警告している。臨床でのトリアージという劇的な状況について、マカロー(2020)は、自律性の尊重や患者の嗜好という倫理原則は、「エビデンスに基づく、ベネフィットに基づく熟慮的な臨床判断とは無関係」であるべきだと主張している。臨床基準の公正な適用から自律性に基づく配慮を除外することは、特定の状況下ではインフォームド・コンセントのプロセスが必要ないことを意味する(マカロー 2020)。マカローによると、臨床家の一方的な権限(パターナリズムではない)は、許容できない機会費用を無責任に管理することで他の患者への危害を防ぐために、個人の自律性を覆す可能性があるという。
以上のことから、COVID-19は、公衆衛生上の措置の緊急性から、人権と自由の侵害を引き起こした可能性がある(Spadaro 2020)。また、現在の生命倫理の重要な原則の一つである自律性の尊重にも強い影響を与えている(Jeffrey 2020)。我々は、個人主義的な自律性の見方はこのような現実に対してより脆弱であり、したがって、関係的な自律性の説明は、パンデミックによってもたらされた課題により対応できる可能性があることを提案する。
関係的自律性:未だ不十分な代替案
前述のように、自律性尊重の原則に対する個人主義的な解釈は、理論的な観点からもCOVID-19の臨床的な現実からも疑問視されている。こうした課題への適切な対応策として、この原則に対する関係的なアプローチがしばしば提案されている(Jeffrey 2020; Lang and Micah Hester 2021)。このような「関係的転回」の試みは、生命倫理という特定の分野で行われてきたが(Jennings 2016; Sherwin and Stockdale 2017)関係的自律の概念に関する系統的なレビューでは、これらの試みに重要な欠陥が検出されている(Gómez-Vírseda er al 2019)。
第一に、関係的な自律性の概念化は、それ自体がポジティブな概念というよりも、この原則の個人主義的な解釈に対する反発である傾向がある。
第二に、豊かで多元的な概念として、関係的な自律性は一般的に単一のインスピレーションの源を参照し、単純化された一方的な解釈を提示する。
第三に、関係性オートノミーの理論的アプローチと終末期の実践における運用との間には大きな隔たりがある。関係性オートノミーの提案は、個人主義的なオートノミーのモデルに代わる説得力のある代替案を提供できていない。
この欠点を説明するために、我々は関係性が医療倫理に十分に統合されていないことを提案する。我々の仮説は、ほとんどの関係論の著者が、関係性の強い説明ではなく、弱い説明をしているというものである。我々は、20世紀の哲学のさまざまな分野が、どのようにして関係性をその理論的核心に統合することに成功したかについての歴史的分析を提案する。これらの発展から学ぶことで、我々は医療倫理に対していくつかの有益な示唆を得ることができる。そうすることで、自律性の尊重を関係性のある原則に変えることを目指している。
哲学の歴史から生命倫理への影響まで
20世紀の哲学は、関係性というカテゴリーにおいて重要な役割を果たした。現代の著名な6つの分派を研究することで、このカテゴリーの重要な次元を発見することができる。さらに、これらの次元は、生命倫理、より具体的には自律性の原則における関係性の強力な説明に向けて前進するために使用される。しかし、これらの傾向を検討する前に、現代以前の哲学における関係性のカテゴリーを簡単に見直す価値がある。
関係性は、哲学の歴史の中で、長く複雑な軌跡を持っている。その起源はアリストテレスにまでさかのぼり、アリストテレスは関係を表す要約名詞がないために「prós ti」と呼んでいる。アリストテレスによれば、関係とは偶然の産物であり、あるものを他のものに参照して考えるカテゴリーである。それにもかかわらず、「(関係詞は)すべてのカテゴリーの中で最も実質的でないものに属し、質と量に後れている」(アリストテレス1956年、p.281)のである。
神学的な関心に促されて、聖アウグスティヌスは関係のカテゴリーに戻り、それに特別な地位を与える(Augustine 417/1956, pp.401-402)。もし神の中に関係があるとすれば、神には事故がないので、それは単純な事故ではありえないと彼は指摘する。さらに、神の本質は単一性であるため、それは本質の一部ではありえない。このようにして、聖アウグスティヌスは、相対的なものが偶然的なものではなく、実質的に与えられたものであるという、存在論を考える新しい方法を開始したのである(Arias 1989, p. 264)。このようにして、物質は関係そのものではないが、物質の中に関係性を導入したのである。
その後、トマス・アクィナスやフランシスコ・スアレスなどのスコラ学者が関係性というカテゴリーについての研究を行ったことで、より体系的な考察が行われるようになった。一般的に、スコラ学では関係性を「ある存在が他の存在に対して持っている序列や参照」と定義している(Valverde 2009, p. 955)。このような定義の意味を理解するためには、3つの要素を区別しなければならない。最初の2つは関係の主体と用語であり、これらは共に条件付きであり、3つ目は基礎であり、これは関係の真の本質であり、主体がその用語と関係している理由である。基礎については、関係を理性的関係、基礎的関係、超越的関係の三つに分類している。このうち、これから紹介する20世紀の哲学に真の影響を与えたのは、最後の2つだけである。
基本的関係とは、「対象にとって本質的ではないが、偶発的かつ偶発的に対象の中に存在する」関係のことである(Valverde 2009, p.958)。言い換えれば、基本的なものとは、物質とその偶然性との関係である。一方、超越論的関係は「主体に不可欠であり、したがって主体と完全に同一視される」(Valverde 2009, p.958)。このように、超越論的関係は主体の本質に立脚している。したがって、主体はその本質が関係であるがゆえに、あるがままに存在し、さらには存在しているのである。
カントは、20世紀の哲学者たちが追随する意味で、関係についての新しい理解を導入している。彼の『純粋理性批判』では、超越論的弁証法の議論の中で、関係は理解のカテゴリーの第三類に属するとしている(Kant 1922)。具体的には、関係性は現象が構築される先験的な理解のカテゴリーである。したがって、カントにとって関係性はすべての判断の魂であり、物質を犠牲にして知識を得るための普遍的な道具となる(Álvarez 1967, p.341)。関係というカテゴリーを通じて、科学的知識の対象である範疇的判断、仮説的判断、分離的判断といった、先験的な合成判断の一部が生み出されるのである。言い換えれば、カントは関係を単なる述語を超えた知識の本質として位置づけているが、スコラ学が定義したような超越的な意味での関係は考慮していない。カントにとって、関係のカテゴリーは認識論に入るが、その後、このカテゴリーは哲学的知識の他の分野にも入っていくことになる。
このように、関係のカテゴリーは、20世紀を通じて、自然や人間といった現実そのものの核心に迫る道を歩んできた。ここでは、このカテゴリーを掘り下げてきた6つの顕著な哲学的枝を検討する。これらの枝は、20世紀の哲学を貫く2つの主要な動き、すなわち、社会科学の出現と現象学の進化を中心に、時系列的に提示される。前者については、関係性というカテゴリーが社会科学の勃興にとって最も重要なものである。この動きの中で、文化人類学、自然哲学、言説倫理などの哲学的な枝葉が提示される。後者については、現象学の進化が20世紀を通じて起こり、哲学的人間学、実存的現象学、解釈学などの初期の分派に痕跡を残したが、いずれも関係性のカテゴリーが重要だ。いずれにしても、関係性のカテゴリーは重要な意味を持っている。
文化人類学:人間の定義における関係性
文化という概念の客観的な意味が明確になるまでには、何世紀もの時間を要した。その起源はキケロにまで遡ることができるが、自然状態の反対側にあるものとしての文化という近代的な概念への道を開いたのは、17世紀の哲学者フォン・プーフェンドルフであった。アフリカの植民地化や啓蒙主義の哲学的思索により、民族学的な実証研究が盛んに行われ、文化の比較研究が行われるようになった。
このように、文化は客観的な意味で定義された。それは、19世紀の進化論的な動きの明確な例であるエドワード・バーネット・タイラーの著作に初めて見られる。”文化あるいは文明とは、広い意味での民族誌的なものであり、知識、信念、芸術、道徳、法律、慣習、その他社会の一員として人間が獲得した能力や習慣などの複合的な全体である」(Tylor 1871, p. 1)。サン・マルティンは、この定義における文化の要素について、「タイラーがここで言っているのは、物事についての意見であり、主に人生の究極の現実、人生や社会の意味、人生の起源と目標、生前と死後の時間、そして最終的には権利の基礎に関連するものだと思う」と述べている(Sala 1999, p.44)。言い換えれば、文化は、世界、我々自身、そして人間が共有する価値観についての理解を何らかの形で条件づけるものである。
このように、文化人類学では、人間の概念は極めて関係的なものである。生物文化的な人間は「関係の中にいる」のである。文化的主体は社会から「共有されている明白なもの、それもありきたりなものではなく、良いことと悪いこと、便利なことと不便なことを定義するもの、したがって行動を規制するものを預かる」(Amengual 2007, p. 358)。人が考え、感じ、価値を置くことができるすべてのものは、社会や他者との本質的な関係を通じて、文化によって大きく決定される。
生命倫理への影響
文化人類学は、人間が社会や文化とのダイナミックな相互作用を通じて自分自身の多くの部分を受け取る関係的な存在であることを示した。つまり、人間は歴史的、具体的、文脈的な存在なのである。このような観点から、関係論者は、生命倫理の対象が歴史的・文化的な空白の中で活動しているかのような要約概念を批判している(Donchin 2000; Mackenzie and Stoljar 2000)。しかし、健康に関する意思決定は実際に文化によって強く形成されており(Gilbar and Miola 2015)すべての文化が意思決定における個人の自律性を同じように重視しているわけではないことが研究で明らかになっている(Frosch and Kaplan 1999)。集団主義的な文化では、相互信頼、家族の調和、親孝行、コミュニティへの忠誠心など、他の価値を優先的に考慮する(Gómez-Vírseda er al)。 文化的認識を深めることは、臨床現場での意思決定プロセスの管理に重要な結果をもたらす可能性がある。このような認識は、コミュニケーション基準、インフォームド・コンセントの手順、事前指示書の文化的適応を必要とするかもしれない。このような広い視野に立つと、臨床家には文化的能力の向上が求められ、患者の文化的枠組みの中で代替案を提示することができるようになる(Betancourt 2004; Fox 2005)。西洋文化では意思決定の単位は個人であることがあるが、他の文化では家族、民族グループ、または社会である(Candib 2002; Gilbar and Miola 2015)。
公衆衛生政策においても、文化の影響を見過ごしてはならない。例えば、マカローは、COVID-19がもたらす緊急事態におけるトリアージの実践を、共同体主義的な根拠ではなく、純粋に自由主義的な根拠に基づいて説明している。彼は、社会や集団を中心とした議論に頼る必要性を否定しているが、トリアージを証拠と患者中心の利益に基づいた科学的合理性の行使として弁護している(マカロー 2020)。これは、リベラルな理解の枠組みの中で、個人と社会の弁証法に取り組む具体的な例となる。別の枠組みでは、ヘイスティングスセンターは、倫理的な行動を支配する一般的なスキームと決別する必要性を見出しており(Berlinger er al 2020)したがって、パンデミックという異常な状況によって正当化される、特にコミュニタリアン的な性質の新しい倫理的基盤の必要性を支持している。
自然の哲学:宇宙論的理解における関係
Collingwood (1945)は、18世紀末以降、それまで支配的だった機械論的な概念に代わって、自然に対する考え方に変化が生じたと主張している。それ以降、自然の説明モデルは社会科学になる。社会に進化やプロセスが存在するように、自然にも進化やプロセスが存在するのである。この転換により、進化論的な見方が生まれ、以後、「自然はプロセスからなるものとして理解される」(Collingwood 1945, p.17)ことになる。プロセスとしての自然は、物質という古い対象化されたビジョンとは対照的であり、自然の中心への関係性の入り口となるであろう。
このような新しい自然哲学の最も重要な例は、ホワイトヘッドの著作に現れており、存在の定義にダイナミズムと関係性を導入している。ホワイトヘッドは、当時の物理学的知識に支えられて、まず自然とそれを構成する物質を全体論的に考察する(Whitehead 1938, p. 184, 1964, p. 26)。次に、ヘラクレイトスの原理、すなわち「万物は流れる」を適用する。この二重の出発点により、ホワイトヘッドは、物質と存在の概念の中に、関係の名前であるプロセスを導入し、それを実際の実体と呼んでいる(Whitehead 1985, p. 41; Ezcurra 1991, p. 72)。
この二重の出発点の明確化は、有機体の概念によって達成されている。実際のものの共同体は有機体であるが、それは静的な有機体ではない。第二に,それぞれの実在するものは,それ自体,有機的なプロセスとしてしか記述できない。それは宇宙が大宇宙であるものを小宇宙で繰り返すものである」(ホワイトヘッド1985, pp.214-215)。
このように、ホワイトヘッドの自然哲学には、関係性というカテゴリーが位置づけられている。「有機主義」への回帰は、宇宙のすべてのものが実際に関係していることを意味する。巨視的、微視的な要素はすべて有機体の一部として関係しており、そこに生じる因果関係もまた関係を必要とする。
生命倫理的な意味合い
自然哲学では、関係性というカテゴリーを自然そのものの核心に持ってくることで、物質に対する動的な見方を導入し、すべてのものは関係していると結論づけている。この考えと、環境科学(Coutts and Hahn 2015)社会科学(Heilbron 2014)神学(Marx 2016)からの並行した主張との合流は注目に値する。これらの線に沿って、COVID-19は、健康問題はもはや臨床医だけの領域とは考えられないことを確認した。臨床医学、公衆衛生、生態学、生物学、疫学、獣医学、社会・政治科学など、さまざまな分野間の効果的な連携が求められている(Tatay 2020)。これらの分野では、それぞれが独自の認識論、目的、方法に基づいてテーマに取り組んでいる。
この関係性の「宇宙的次元」は、応用倫理学にも影響を与える。それは、倫理的な検討において、人間が自然の他のあらゆる側面と必然的に結びついていることを意味する。この関係性は、医療倫理を、環境倫理や地球倫理などの他の倫理分野と結びつける。例えば、Tatay(2020)は、グローバルバイオエシックスを、医療倫理、公衆衛生倫理、環境倫理の統合と考えている。このような観点を考慮すると、生物医学に対する人間中心的なアプローチも、公衆衛生に対する生物中心的なアプローチも、新興感染症のような複雑な性質を持つ地球規模の問題に対処するには不十分であると警告している。同様に、「One Health」と題されたWHOのプロジェクトでは、「より良い公衆衛生の成果を達成するために、複数のセクターがコミュニケーションをとり、協力するようなプログラム、政策、法律、研究を設計し、実施する」ことを目的として、公衆衛生に対するマルチセクター・アプローチを提案している(Zinsstag er al 2020)(WHO 2017)。
言説倫理:普遍的道徳の条件としての関係性
第二次世界大戦後、倫理の基礎としての普遍主義的な理性は特権的な地位を失った。フランクフルト学派は理性に対して悲観的な態度を示したが、ハーバマスやアペルといった批判理論の継承者たちは、社会科学や言語への親近感を求めて、カント的な普遍的道徳の思想を回復しようとしたのである。しかし、彼らはデカルトの伝統の重要な要素を変換することによってそれを行った。”ハーバマスとアペルの言説的倫理学は、孤独な道徳的良心に与えられた特権を否定し、社会的に規制されたあらゆる形態の相互作用に対して道徳哲学を開く。談話的倫理学では、規範システムに影響を受ける人々の理性的な合意のみが、そのシステムを有効にすることができるとしている。そのためには、道具的、戦略的なものだけでなく、コミュニケーション的な行動様式が必要であると付け加えている(Thiebaut 2000, p. 281)。
確かに、ハーバマスの出発点は理性の普遍性の見直しである。談話倫理学にとって、理性は対話的な性格を持っている。それは、”dialogical logos” (Rueda 2001, p. 371)である。”著者(Habermas)は「『対話的な』構造を、すべての識別力と知識の先験的な構成要素であり、したがって、合理的なアプローチを確立することが可能な唯一の強固な基盤であると考えている」(Boladeras 1996, p. 90)と述べている。これがいわゆる(D)原則で、次のように定式化されている。”この対話的アプリオリ(関係的アプリオリとも呼ばれる)は、個人主義的、自給自足的、自己利益的な主体を前提とするデカルト的(あるいは功利主義的)な倫理との大きな違いである(Boladeras 1996, p. 91)。規範が有効であるためには、その規範の一般的な遵守が、影響を受ける各人の特定の利益を満足させるために期待できる結果や副作用が、影響を受けるすべての人が自由に受け入れることができるようなものでなければならない」(Habermas 1990, p. 120)という(U)の原則を導き出すことができる。
(D)原理も(U)原理も、人間が倫理規範の作成に対話的に参加するという点で、人間の関係構造を前提としている。関係性のカテゴリーに基づかなければ、実践的な言説における参加型倫理の決定的な役割を肯定することはできない。
生命倫理への影響
ハーバーマスとアペルは、関係主体の対話的理性を前面に押し出している。彼らは、人間は個人的にではなく、他者との対話を通じて、自分自身でさえも普遍的な倫理規範を達成するとしている。そこから、行動の指針となる共有の真実を求めて、他者との関係が必要になってくるのである。医療倫理の分野では、このような考え方に基づいて、意思決定の共有化(SDM)が行われている。SDMの基礎が談話倫理の考えにあることを示す学者もいる(Kon 2010; Müller-Engelmann er al 2011; Stiggelbout er al)。
SDMには、患者、医療従事者、患者の家族の間の対話を促進し、合意に基づく意思決定を実現することを目的としたさまざまな実践や手順が含まれる(Elwyn er al 2012)。SDMは、患者による知識の獲得、意思決定への自信、より積極的な患者の関与、重大な状況におけるより保守的な治療法の選択を示すエビデンスによって支持されている(Stacey er al)。
さらに、対話倫理は、最も脆弱な対話者に配慮することに非常に敏感である(Légaré and Witteman 2013; Mead er al 2013)。現在の健康危機においては、想定される社会的有用性のために、高齢者や障害者などの弱い立場にある患者の尊厳が損なわれる危険性がある(Baum and Żok 2020)。対話型倫理学は、多数派が権威主義的な方法で優勢なビジョンを押し付けることがないように、最も脆弱な個人の保護を促進しながら、すべての利害関係者に声を届けることを目指している。
20世紀の人類学的転回:人間の定義における関係性
19世紀末には、人間と動物との距離を論じた進化論や、人間の特異性の合理性を論じたフロイトの精神分析など、さまざまな理論的展開によって、人間の特異性という考え方が問われた。これらの動きは、第一次世界大戦につながる大きな文化的崩壊の中で起こった。このような社会的・文化的環境の中で、「人類の問題」がさまざまな立場から再提起され、哲学的人間学が誕生したのである。
関係というカテゴリーを認識論に最初に導入したのはカントであったが、デカルトの孤独な理性の人類学的帰結を確実に克服したのはマックス・シェーラーであった(Entralgo 1961, p.216)。ブルジョアの魂とも呼ばれるこの孤独な理性の概念のいくつかの特徴は、言及に値するものである。主体-客体の弁証法に基づいて構築され、人間以外の現実(デカルトがres extensaとして特徴づけたもの)が客体の位置を占めていること、(2)その自然な態度は、現実や他の人間さえも支配することであり、したがって、人生は環境を自分の利益のために支配的に適応させるものとして考えられていること、(3)内的な知覚の証拠に絶対的な無謬性を付与していること、(4)自制を倫理的な道として表現しており、したがって、哲学的な自己中心主義を特徴としていること。
この枠組みの中では、「利己主義(…)がブルジョア文明の出発点であり基礎である」(Entralgo 1961, p.216)とされ、社会性(すなわち関係性)は二次的な役割を果たしていた。ブルジョアの人間(J.S.ミル、ロック、ヒューム、アダム・スミスの資本主義のアングロサクソンの自由主義の人間)にとって、社会とは「冷たくて遠い機械的な個人間の関係であり、主に自分自身に焦点を当て、根本的に孤独であり、さらには職業的にも孤独である。
人間学のカテゴリーとしての関係性の発展に最も貢献したのは、間違いなく20世紀のユダヤ人思想であったと言えるであろう。ブーバー、ヘシェル、ジョナス、レヴィナスといったユダヤ系の哲学者たちは、資本主義から共産主義の全体主義、ナチズムのような民族主義の残虐行為まで、20世紀を象徴するさまざまな人間への攻撃の中で、人間についての考察を深めていった。このようにして、これらの哲学者は、神学的啓示に支えられた、深い関係性を持つと言える個人主義を発展させた。聖書やタルムードに登場するユダヤ・キリスト教の神は人格的な神であり、その姿に似せて創られたアダムは、他者との関係、すなわち絶対者との関係の中で構成されているからこそ、人であるといえる。
ブーバーの著書『私と汝』の第1部は、人間を構成する関係についての論考である。ブーバーは、ほとんど介在することなく、「独立して存在するかもしれない何かを記述するのではなく、存在から語られる」(ブーバー1958年、p.3)二つの基本的な言葉の存在を主張している。「I-Thou」と「I-It」である。この2つのうち、最初のものは存在の全体性を捉えている。このようにして、ブーバーは最初の瞬間から、関係性というカテゴリーを人の存在に導入するのである。
ブーバーによれば、関係は人間化と人間化の両方の原因となる。一方では、関係性は、即時的かつ相互的な出会いにおいて人間化を引き起こす。それは、「私と汝の間には、観念の体系も、予知も、空想も介在しない(中略)私と汝の間には、目的も、欲望も、予想も介在しない」(ブーバー1958年、p.11)ので、即物的であり、「私がそれに影響を与えるように、私の汝も私に影響を与える」(ブーバー1958年、p.15)ので、相互的である。その一方で、関係性は人間化を引き起こす。「はじめに関係ありき」(ブーバー1958年、p.18)である。そしてブーバーは、「原始人の精神史」において、「最初の関係的出来事において、すでに彼は自然な方法でI-Thouという原初的な言葉を話している(中略)つまり、彼が自分をIと認識する前に」(ブーバー1958年、p.22)と説明している。
生命倫理への影響
マックス・シェーラーや20世紀のユダヤ人思想家によって導入された人間学的転回は、モナド的個人の理想を捨て、人間を構成するものとして関係性の概念を考えることを意味する。しかし、現在の医療倫理は、主に「個人主義的自律性の中心」(Dove er al 2017)で発展してきたため、独我論的な想像力が維持されている。健康上の決定を行う際、理想的な状況は、患者が自分自身のためだけに決定することのようである(Veltman and Piper 2014; Jennings 2016)。患者の一般的な表現は、デカルトのコギトに似ている。つまり、個人的な希望や意志が完全に意識されている、合理的で自己利益にかなった透明な実体である(Mackenzie and Stoljar 2000; Mackenzie 2014)。医師の役割は、診断や治療の可能性について中立的で完全な情報を提供し、患者がそれらの中から判断できるようにすることに縮小されている(Entwistle er al 2010; Walter and Ross 2014; Gómez-Vírseda er al 2020)。しかし、このような状況は、臨床の現実とはほとんど関係がない。
関係性の人類学的側面を考慮することで、実際の臨床現場をより公平に説明することができる。患者は、推定される科学的合理性に基づいて利己的な判断を下す孤立した人物ではない(Agich 1990; Ho 2008; Walter and Ross 2014)。同様に、医師と患者の相互作用において、後者の役割が絶対的に中立であるということはない。家族、友人、コミュニティを含む関係環境は、必然的に意思決定をしなければならない患者を条件付ける。さらに、これは特定の文化的、社会的文脈の中で起こる(Ho 2008)。このため、倫理学者の中には、医師と患者の二元的なスキームを捨て、意思決定プロセスに他者を巻き込む新たな方法を模索することを求める人もいる(Roest er al 2019; Gómez-Vírseda er al 2020)。
COVID-19は、個人主義的な自律観の境界をなくしたのかもしれない。パンデミックの間、患者は社会的利益を考慮せずに自己中心的な意思決定をすることは許されなかった(Baum and Żok 2020)。同様に、資源の不足は個人の意思決定能力を決定的に制限し、あれやこれやと資源を割り当てなければならない医師に決定的な発言権を与えている。したがって、個人主義的なモデルや、患者の利益のみを中心とした医師-患者間のアプローチでは不十分であることが確認されている(Berlinger er al 2020)。家族、他の患者、社会など、他のアクターを対話に取り入れることの必要性がますます明らかになっていた。
実存的現象学:存在の内臓における関係性
ハイデガーの実存主義には、関係性を哲学的考察に取り入れる5つ目の方法が見られる。ハイデガーによれば、フッサールの道は、自分の主観性から離れず、近代の主観-客観の弁証法を破っていないので、物事そのものにはつながっていない。フッサールの過ちは、存在を単なるモノ、単なる本質として考えたことである(Zubiri 1963, p.262)。それゆえ、ハイデガーの「事物そのものに到達する」という提案は、人間から湧き上がってくるのである。なぜなら、人間は「存在」という問いを投げかけ、それに答えることができる唯一の存在だからである。”我々一人一人が自分自身であり、その存在の可能性の一つとして探求することを含むこの実体を、我々はダゼイン(存在-そこにあるもの)という言葉で表すことにする」(ハイデガー1962年、p.27)。この能力の結果として、ダゼインは「世界における存在」であると言われる。したがって、存在の問題は、ダゼインの分析から始めなければならない。この問題への最初のアプローチは、「この実体の本質は、その『存在すること』(be relative to)にある」(ハイデガー1962,p.67)と断言する。言い換えれば、その存在は、世界におけるその存在の仕方は、開かれている。それは開かれた存在である。
世界の中のその存在は、さらに、世界の中にあるが、他のいかなる存在とも違っている。世界の中で、ダゼインは、自分が知り、支配しなければならない他の存在を発見する。これらは、実存ではなくカテゴリーを持つ「手近な存在」である。さらに、世界には、ダゼインである他の「手近な存在」も存在する。他のDaseinとの関係は、他の「手近な存在」との関係とは異なる。他のDaseinは目の前にあるのではなく、人は彼らと一緒にいるのである。”それどころか、自分を解放してくれる大罪そのもののように、自分もそこにいて、それとともにそこにいるのである」(ハイデガー1962,p.154)。
この結合(そこにあるものと一緒にあるもの)は、ダゼインを構成するものである。”他者の世界内での存在は、ダゼインと共にある」(ハイデガー1962年、155頁)「他者の世界内でのダゼインと共にあることは、ダゼインがそれ自体で本質的に存在と共にあるからこそ、ダゼインにとって世界内で開示されるのであり、我々と共にダゼインである者にとっても同様である」(ハイデガー1962年、156頁)。これがハイデガーの思想における関係性のカテゴリーの正確な位置である。すなわち、ダゼインは世界における存在であり、他のダゼインと併存する開かれた存在である。
このようなダゼインの関係性の理解は、ダゼインの具体的な存在とその生き方に影響を与える。すなわち、他者とともに世界に存在するダゼインは、これらの関係性から恩恵を受けて自らを向上させることができるのか、あるいはできないのか。後者の場合、ダゼインは、匿名性と平凡さを特徴とする堕落した状態に達する。このジレンマに直面しても、死に向かっているという苦悩に直面し、目を背けずに自分の状態を受け入れるならば、ダゼインは真正な存在を持つことができる。真正な存在を生きるダゼインは、人間性という真の状態を受け入れ、自分自身を真実の中に置くのである。本物の存在を生きるダゼインは、人間性という真の条件を受け入れ、自分自身を真実の中に置くのである。この真正性は、ダゼインにとって道徳的な義務である。
生命倫理への影響
ハイデガーの哲学では、真正な存在を実現するためには関係性が必要とされており、真正性はBeauchampとChildress(2019)が提唱する自律性の古典的な条件の一つである。アメリカの著者は、ある行為が自律的とみなされるための3つの条件として、
第1に、その行為が真正な意図を持つこと、
第2に、医療従事者や家族、社会による外部からの干渉を受けないこと、
第3に、行為者が有能であり、十分な情報を得ていることを挙げている。
ハイデガーの現象学的-実存的分析は、真正な意図とは何かという問題を提起している。言い換えれば、ある行為がその人の真正な価値観や信念に合致していると断言できるのは、どのような場合かということである(Agich 1990)。ハイデガーによれば、真正性の探求は、決して人間を囲い込むものではなく、人間を他者に開放するものである。
この意味で、関係性の存在論的次元を考えるには、BeauchampとChildress(2019)が提案した条件に第4の条件を加える必要があるかもしれない。そうすることで、自律性の原則は、アメリカの哲学者たちが提案した他の3つの原則に存在していた関係性の次元を獲得することになる。なお、正義、恩恵、非悪意の原則は、その中核に「他者」を取り込んでおり、関係的な次元を持っていたが、自律の原則は、少なくともその「主流の解釈」(Donchin 2001)という点では、問題のある個人主義に囚われたままであった。アメリカのプリンシプルに対する批判の多くは、この不均衡を反映していると我々は考えている。
さらに、生命倫理の対象の関係性を強調することは、代替的な道徳的伝統との対話を促進する。例えば、ヨーロッパの生命倫理学者は、個人の自律性と、連帯、脆弱性、完全性などの他の原則とのバランスをとる必要性を頻繁に主張している(Rendtorff 2002; Gaille and Horn 2016)。関係性を倫理的主体にもっと統合することで、ヨーロッパの原則主義者の提案とのより流動的な対話が促進されるだろう。
解釈学的哲学:アイデンティティの基盤としての関係性
ポール・リクールの解釈学的思想は、関係性というカテゴリーを哲学に組み込む6つ目の方法を示している。フランスの作家であるリクールは、ハイデガーや言語哲学と同じ枠組みに位置し、いわゆる解釈学的サークルの中に存在している。
その出発点となるのが、カント的な「能」に対する「現象」の肯定である。知識の対象である現象は、知識のカテゴリーとともに物自体を構成している。主体は知ることに積極的であり、必然的にこれらのカテゴリーに自分の痕跡を残すことになる。これは、ハイデガーが存在の最も深いレベルとして提起している「意味の問題」においても起こる。この点で、ハイデガーはディルタイ、シェライエルマッハー、そして言語哲学に同意している。つまり、言語とは、知る主体が意味そのものを含めた現象を構築するための能動的な方法なのである。
このようにしてポール・リクールは、ハイデガーが宣言した「存在」とともに現実のもう一つの部分である「時間」は、我々の知識に直ちに与えられるものではなく、言語によって構築されるものであるという考えを支持している。それゆえ彼は、人間が時間というカテゴリーを知識に組み込む方法である物語に到達するのである。
ポール・リクールは哲学的人間学の論文の中で、アイデンティティの問題を解決する方法として、「自己性の解釈学」を提案している。確かに、物語が自己認識に統合されるとき、アイデンティティは人間の中で問題となる問題である。リクールにとっては、”Who? “という問いの中で これは誰だ? 誰が言った? 我々は誰だ?)という問いにおいて、人はidemとipseの違いを発見する(Ricoeur 2016, p.222)。前者は変化しないものに関係し、後者は「物語的な経過を展開することができる」ものに関係する(Ricoeur 2016, p.224)。リクールの言葉を借りれば、「イプセの同一性は、不変のものという意味で、アイデムの実質的な同一性に還元されるのではなく、基本的な変容性を兼ね備えている。人生の逸話的な変異性と物語の構成をつなぎ合わせるのは、物語の媒介機能である」(Ricoeur 2016, p.225)と述べている。この直後、リクールはイプセティ、すなわち物語のアイデンティティの研究に焦点を当て、関係性の取り込みというトピックを取り上げている。
フランスの哲学者によれば、カントの『純粋理性批判』では、現象の中で永続するものとその存在のある様式、すなわち変化するものとを結びつける判断に関係性を置いているという。彼は「生命の相互関連性という概念は、物理的自然に適用される公理に対してのみ有効なこの分類を覆す」と断言している(Ricoeur 2016, p.231)。
アイデンティティ問題では、関係性は物質(永続するもの)と可変型を結びつけるのではなく、可変型と物語の筋書きを結びつける。物語のプロットの時間は、(ハイデガーが断言するような)与えられたものや永続するものではなく、むしろ変幻自在なものである。このように、関係性とは、誰と物語という二つの変幻自在なものを結びつけるカテゴリーである。リクールはこのように、関係性をアイデンティティを構成する結びつきとして考えている。
生命倫理的意味合い
リクールの解釈学は、個人のアイデンティティの物語的構成を強調している。言い換えれば、個人のアイデンティティは発見されるべき静的な本質ではなく、むしろ練り上げられるべき動的な構成物である。この観点から、Levy (2011) は、「自己発見の視点」と「自己創造の視点」という2つの視点を区別している。自己発見的な見方では、真正性とは、自分自身に忠実であること、そしてすべての人間が持っている「内なる声」に耳を傾けることを意味する。一方、「自己創造の視点」では、真正性とは、自分が望むように自分を創造する努力である。解釈学的な視点は、人間が他者との継続的な相互作用の過程でアイデンティティを構築していくという後者の考え方に適している。
これと並行して、物語倫理学では、個人のアイデンティティには、共有された伝統と期待の地平線を持つ文化的コミュニティで行われるライフストーリーが含まれると指摘している(Ikonomidis and Singer 1999; Rigaux 2011; Siddiqui 2016)。自身のバイオグラフィーやコミュニティとの連続性は、医療上の決定が本物で意味のあるものとみなされるために重要である(Westlund 2009)。支配的な生命倫理の言説では、自律性を孤立した意思決定の連続として概念化する傾向があり、それによって連続的で関係的なプロセスという視点が失われている(Baumann 2008; Lindberg er al 2014)。実際には、意思決定は通時的かつ関係的な文脈、つまり信頼関係と相互知識によって特徴づけられる歴史の中で行われる(Marx er al)。 この点で、患者の自律性を促進するには、時間的な一貫性と重要なコミュニティの支援を求めながら、健康上の意思決定を患者自身の経歴に統合することを支援する必要がある(Donchin 2001; Tonelli and Misak 2010)。
COVID-19に罹患することは、あまりにも頻繁に患者の伝記的次元の断絶を意味する。緊急時の理由から、医療や公衆衛生の基準が個人の希望よりも優先され、時には患者の生物学的な側面が見過ごされることもあった(Strang er al)。 これに対して、いくつかの生命倫理の声は、病気や死、喪に服すプロセスにおいて、対人関係の緊密さを強く求めてきた(Berlinger er al 2020; Valera er al 2020)。これらは関係性のあるプロセスであり、そのプロセスに同行せず、病院の孤独と匿名性の中で過ごすことは、患者と家族に深い傷を与えたかもしれない(Anderson-Shaw and Zar 2020; Wakam er al 2020)。
このように、我々は20世紀の6つの哲学の視点から、現実と人間の根幹に関係性を取り入れる必要性を考えた。これらの洞察を得た上で、我々は、特に自律性の原則に焦点を当てて、生命倫理的な意味合いを抽出した。そうすることで、本稿の冒頭で提示した個人主義的な自律性のビジョンに対する挑戦に応えることを目的としている(表表11参照)。
表1 哲学的支流の概要、その洞察と生命倫理への影響
| 歴史的傾向 | 哲学的な枝(一次資料) | 洞察と学習 | 生命倫理への影響 |
|---|---|---|---|
| 社会科学の出現 | 文化人類学(EBタイラー) | 生物文化の人間は他者との関係にあります | 生命倫理における必要な文化的認識 |
| 自然哲学(ANホワイトヘッド) | すべてが相互に関連しています:宇宙論的視点 | 医療倫理は地球および環境倫理に開かれました | |
| 談話倫理(J.ハーバーマス、KOアペル) | 普遍的道徳の条件としての関係 | 共有の意思決定アプローチと手順に向けて | |
| 現象学の進化 | 哲学的人類学(M.シェーラー、M。ブーバー) | 個人主義的枠組みを超えた、人間の定義における関係性 | 医師と患者の二者択一を超えた、意思決定の関係的理解 |
| 実存現象学(M.ハイデガー) | 信頼性は関係を通じて確実に達成されます | 個人の自律性の尊重には、避けられない関係の側面があります | |
| 解釈学(P.リクール) | 個人的アイデンティティの探求における関係 | 意思決定プロセスの物語的側面:共時的および関係的 |
おわりに
自律性の尊重という原則の個人主義的なビジョンは、最近の生命倫理に関する文献とCOVID-19パンデミックの臨床的現実の両方から挑戦を受けている。この課題への対応として、自律性の関係的な転回が指摘されている。しかし、関係性についての説明が弱い、あるいは因果関係がないために、関係性オートノミーは「アンブレラーターム」(Mackenzie and Stoljar 2000)として機能し、理論的にも実践的にも十分な発展を遂げていない。我々は、関係性に関する強力な説明を実現するために、20世紀を通じて6つの哲学分野が関係性をその理論的中核に統合することに成功した方法を分析した。この歴史的分析から、生命倫理における関係性の強い説明を導くことができる示唆を抽出した。
理論的なレベルでは、生命倫理に関係性を完全に取り入れるためには、個人主義的な人間学を克服し、それに伴って古典的な原理主義を変革する必要がある。まず、行動が自律的であるとみなされるための条件に、関係性の項目が追加される。第二に、意思決定における真の意図性を追求するために、物語や解釈学の要素を取り入れる。
実践的なレベルでは、自律性に関する関係性の説明は、生命倫理におけるSDMの発展とよく調和している。しかし、関係性の強いビジョンは、これらの対話的な提案が、医師と患者の二者間を超えて、より広い範囲を対話に組み込むことを必要とする。これは、COVID-19のような健康問題を、医学的観点からだけでなく、経済的、社会的、文化的、生態学的観点を統合して解決するための、グローバルな生命倫理の提案につながるものである。複雑な問題には複雑なアプローチが必要であり、関係性は現実の中心に組み込まれている。
