コンテンツ
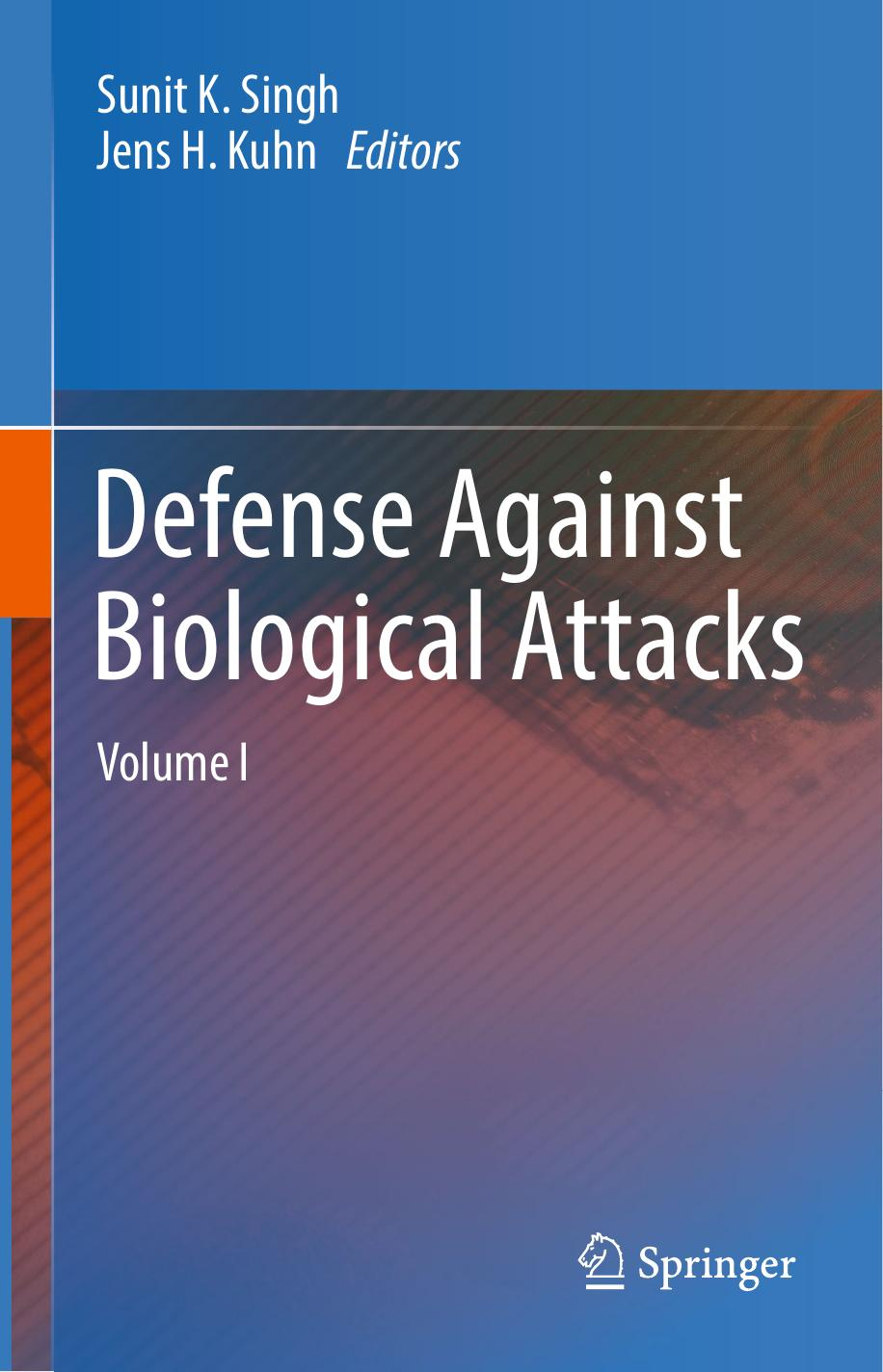
生物学的攻撃に対する防御
スニット・K・シン – イェンス・H・クーン
編著
生物学的攻撃に対する防御 第1巻
編集部
スニット・K・シン 分子生物学ユニット
バナラスヒンドゥー大学医学部分子生物学ユニット
イェンス・H・クーン
米国メリーランド州フレデリック、NIH/NIAID、臨床研究部門、フォートデトリックの統合研究施設
出版社、著者、編集者は、本書におけるアドバイスや情報が、出版日現在において真実かつ正確であると信じられていると考えて差し支えない。出版社、著者、編集者は、ここに含まれる資料に関して、あるいは誤りや脱落があったとしても、明示または暗示の保証をするものではない。出版社は、出版された地図や機関所属の管轄権主張に関して中立的な立場を維持している。
序文 1
生物学的攻撃は、バクテリア、毒素、ウイルスなどの生物学的物質を用いた非常に多様な攻撃形態から構成されている。これらの形態は、一過性の生物犯罪行為 (例えば、サラダバーの細菌汚染、HIV-1への故意の感染、インスリン注射による殺人)から、十分な資金と長期にわたる研究開発プログラム、国家による秘密支配まで、幅広い範囲に及んでいる。後者のプログラムは、配備可能な戦術兵器や戦略兵器の開発を目的としている場合がある (例:米国、英国、ソ連の生物兵器プログラム)。
「生物防御」は、生物製剤による攻撃の影響を緩和する方策の総称となっている。この対策には、生物兵器の製造と配備およびその使用を防止することを目的とした、公衆および専門家の教育、国の法律および病原体のモニタリング、国際軍備管理条約および信頼醸成措置、情報収集が含まれる。さらに、生物防御対策には、迅速な生物剤診断、緊急患者管理、有効かつ安全な医療措置の適用、攻撃現場の修復など、生物攻撃へのあらゆる対応が含まれる。したがって、生物防御は、生命科学、人文科学、政治科学の複数の下位専門分野にとって、高度に学際的な結びつきのある分野なのである。バイオディフェンスはますます複雑化しているテーマであり、実際、バイオディフェンスは一個人がそのすべての面を理解するにはあまりに複雑であるとわれわれは主張する。また、生体防御活動と一般的な公衆衛生対策は、かなり重複している。したがって、公衆衛生の専門家の多くは、バイオディフェンスに大きく貢献することができ、その逆もまた然りであることを主張したい。
本書は、バイオディフェンスにおける様々な優先事項の概要を、一般市民と専門家の双方が理解できるような形で提供することを試みている。本書は、様々な分野の専門家をあえて集め、読者とのコミュニケーションを深めることを意図している。第1巻では、まず生物兵器の歴史的な開発と使用について概観し、攻撃に関する研究開発の過去の成果と失敗の情景を描いている。国家が主導した既知の生物兵器計画はすべて何年も前に最終的に終了している。もし今日、異なる政治情勢の中で現在の科学的方法論を用いてそのような計画が行われたとしたら、組織や成功は異なるものになったであろうか。続く章では、合成生物学、ビッグデータ解析、CRISPR/Cas9などの新しい技術が悪用される可能性はないか、また、これらの技術を用いた攻撃行為が核不拡散条約の対象となるのかどうかが論じられている。第2巻では、生物防御活動に最もよく関連する生物製剤について、ハイレベルな概観を提供している。その他の章では、抗菌・抗ウイルス療法と診断法の開発の現状を紹介している。本書の最後には、人間を直接標的とする兵器の議論ではかき消されがちな、人間以外を標的とする攻撃からの防御もバイオディフェンスに含まれることを思い出させる章を設けている。
もちろん、2巻の本でバイオディフェンスのすべての側面をカバーすることはできないし、各章は、分野全体のコンセンサスではなく、個々の著者の主観的な評価でしかない(もし、そのような見解が存在するならば)。しかし、このように多様で著名な著者を集めたことを誇りに思うとともに、バイオディフェンスが実に重要な分野であることを示す、よく練られた視点が混在していることに読者が共感してくれることを期待している。
インド、バラナシ スニット・K・シン
米国メリーランド州フレデリック ジェンス・H・クーン
序文 2
バイオディフェンスは、生命科学、人文科学、政治科学の複数の専門分野の接点である。大勢の人々のためのバイオセーフとバイオセキュアな環境を実現するためには、学際的なコミュニケーションと協力の強化が必要である。本書は、政策や生命科学の専門家、教員、学生、ジャーナリスト、一般市民を対象に、バイオディフェンスの多様で複雑な側面を概観するために書かれたものである。
本書は、シュプリンガー・ネイチャーのプロジェクト・コーディネーター(書籍)であるラケッシュ・クマール・ジョテスワラン氏の非常に辛抱強く専門的な支援により、私たち(編集者)が導かれ、最終的に本書を完成させることができたことに感謝する。
本書の内容は、必ずしも米国保健社会福祉省、著者や編集者の関連機関・企業の見解や方針を反映したものではない。この研究は、Battelle Memorial Instituteの米国国立アレルギー感染症研究所 (NIAID)とのプライム契約(契約番号HHSN272200700016I)により一部支援を受けた(編集者J. H.K. )。
インド、バラナシ Sunit K. Singh
Frederick, MD, USA Jens H. Kuhn
目次
- 1 生物兵器の開発と使用の歴史的側面 1
- 2 生物兵器不拡散に関する国際的協調の概要とその限界 19
- 3 生物防御におけるイベントベース・バイオサーベランスの役割 35
- 4 バイオディフェンスにおける信頼と透明性 53
- 5 生物兵器による攻撃(バイオテロ)を検知する法医疫学 69
- 6 生物兵器攻撃の修復 105
- 7 緊急事態への備えと緊急対応に不可欠な最大封じ込め感染症実験施設 125
- 8 感染予防と管理。バイオディフェンス対策 145
- 9 高病原性微生物に感染した患者の臨床管理 171
- 10 剣を鋤に、そして鋤に。免疫調節薬の研究開発の脅威 195
- 11 合成生物学。バイオセキュリティとバイオセーフティへの影響 225
- 12 CRISPRは安全保障上の脅威か?233
- 13 生体防御における新たな技術と実現技術 253
- 14 生体防御に使用される医療製品の規制パスウェイ 283
- 15 ビッグデータとバイオディフェンス 展望と落とし穴 297
- 16 ビッグデータと人工知能によるバイオディフェンス
- 技術的驚きを回避するためのゲノムに基づくアプローチ 317
編集者について
スニット・K・シン博士は、バナラス・ヒンドゥー大学 (BHU)医学研究所の分子生物学ユニット (MBU)の教授兼ヘッド、実験医学・外科学センター (CEMS)の教授担当者である。ドイツ・ヴュルツブルク大学にて分子感染生物学の分野で博士号を取得後、米国コネチカット州ニューヘイブンのイェール大学医学部内科、米国カリフォルニア州サクラメントのカリフォルニア大学デイビス校医療センター神経科で博士研究員として研修を受けた。また、米国ニューヨークのアルバート・アインシュタイン医科大学病理学教室、チェコのチェスケ・ブデヨヴィツェ寄生虫学研究所アルボヴィオロジー部、韓国の全北大学病理・微生物学部、スイスのジュネーブ大学免疫学部で客員教員を務めた。インド・ハイデラバードのCSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB) で教員を務め、神経ウイルス学と炎症生物学の分野で研究グループを率いたこともある。シン教授は、米国テキサス州の国立熱帯医学大学院やドイツ・イエナの欧州ウイルスバイオインフォマティクスセンターなど、さまざまな国際的専門機関のメンバーでもある。スニット・K・シン教授は、神経ウイルス学と炎症生物学の分野でブレイクスルー研究を行っている。シン教授の研究は、一般的な感染症や特に向神経性ウイルスの発症の分子メカニズムの理解という点で、非常に広範な影響を及ぼしている。インパクトファクターの高い査読付き国際学術誌に掲載された原著論文に加え、シン教授はこの分野で多くの著書を出版している。例えば、神経ウイルス感染症-RNAウイルスとレトロウイルス、神経ウイルス感染症-一般原則とDNAウイルス、ウイルス性出血熱、ヒト呼吸器ウイルス感染症 (CRC Press/Taylor & Francis group, USA)、ウイルス感染症と地球変動、ヒト新興・再興感染症-1巻と2巻 (Wiley Blackwell Publications, USA)、Neglected Tropical Diseases-South Asia (Springer、USA)等がある。また、副編集長や編集委員として、多くの著名な査読付き国際ジャーナルに携わっている。
Jens H. Kuhn, MD, PhD, MSは、米国オハイオ州コロンバスのバテル記念研究所の研究リーダーで、米国メリーランド州フレデリックにあるNIH/NIAID/DRのバイオセーフティレベル4の施設、フォートデトリックの統合研究施設 (IRF-Frederick)でウイルス学のリーダー(契約者)として任務についている。専門は強毒性ウイルス性ヒトおよび動物病原体。著書に「フィロウイルス。A Compendium of 40 Years of Epidemiological, Clinical, and Laboratory Studies (Vienna: Springer, 2008)、共著にThe Soviet Biological Weapons Program-A History (Cambridge: Harvard University Press, 2012)があり、ドイツ、イタリア、マルタ、ロシア、南アフリカ、韓国で研究・業務経験を積んでいる。米国では、マサチューセッツ州ボストンのハーバード大学医学部、コロラド州フォートコリンズの節足動物媒介感染症研究所 (AIDL)、ジョージア州アトランタの疾病管理予防センター (CDC)、メリーランド州フレデリックの米国陸軍感染症研究所 (USAMRIID)でローテートや勤務を経験した。また、米国国防総省の脅威削減協力プログラム (CTR)により、ロシア・シベリアの旧ソ連生物兵器施設SRCVB「Vektor」での研究許可を得た最初の西洋人科学者でもある。メリーランド州国際安全保障研究センターの「危険病原体管理プロジェクト」に貢献し、軍備管理・不拡散センターの「CBW科学者ワーキンググループ」のメンバーでもある。現在、International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)の小委員長および執行委員、ICTV Bunyavirales, Filoviridae, and Mononegavirales Study Groupの議長、ICTV Arenaviridae, Bornaviridae, Mononegavirales, Nairoviridae, and Nyamiviridae Study Groupsのメンバーであり、ICTVのサブコミティチェアーも務めている。さらに、NCBIのゲノムアノテーション・ウイルスワーキンググループおよびデータベースRefSeqのメンバーとして、すべてのモノネガウイルスのSubject Matter Expertを務めている。10誌の編集委員を務めたほか、Cell, Cell Host and Microbe, Emerging Infectious Diseases, JAMA, The Lancet.など60誌以上の雑誌で査読者を務めている。Infectious Diseases, Nature, Nature Microbiology, Nature Protocols, PLoS Pathogens, Science, Journal of Virologyなど60誌以上のジャーナルで査読を行っている。また 2009-2011年の米国科学アカデミー「バイオテロ対策評価用動物モデル」委員会のメンバーであり、AAASと米国国務省によるBMENA地域、トルコ、NIS諸国でのバイオエンゲージメントの取り組みに継続的に関与している。LinkedInではwww. linkedin.com/pub/jens-h-kuhn/1b/817/72 で、ResearchGateではhttps://www.researchgate.net/profile/Jens_Kuhn で、クーン博士の情報を入手できる。
生物兵器の開発と使用の歴史的側面
グレゴリー・D・コブレンツ (Gregory D. Koblentz
1.1 はじめに
生物兵器 (BW)は、核兵器や化学兵器も含むいわゆる大量破壊兵器の中で、最も理解されていない兵器である。生物兵器がもたらす脅威に対する認識が高まっているにもかかわらず、生物兵器の開発と使用の歴史は神話に包まれ、伝説にまみれている。生物兵器は戦場で公然と使用されたことは一度もなく、その開発は常に激しい秘密主義に覆われてきた。生物兵器が、1972年の生物兵器条約 (BWC)という国際条約によって、初めて完全に非合法化された兵器種となった後、生物兵器の研究は、学者にとって決して優先順位の高いものではなかったが、さらに低いものとなってしまった。その結果、大多数の一般市民、科学者、政策立案者は、生物兵器の歴史について知らないままである。ノーベル経済学賞を受賞した戦略家トーマス・シェリングは、「私たちの計画には、よく知らないこととあり得ないことを混同してしまう傾向がある。私たちが真剣に考えたことのない不測の事態は奇妙に見え、奇妙に見えるものはあり得ないと考えられ、あり得ないことは真剣に考える必要はないと。」[1]と述べている。本章は、生物兵器の歴史に親しむことによって、生物兵器がもたらす脅威を真剣に検討し、その拡散を防ぎ、使用を抑止し、その影響から防衛するための戦略を開発することを奨励するためのものである。
1.2 生物兵器
生物兵器は、微生物、生物に由来する毒素、または生体調節物質を用いて、人間、植物、または動物を意図的に死亡させたり、病気にさせたりするものである1。生物兵器のこの特徴は、国家や非国家主体による兵器としての使用に関して、いくつかの重要な意味を持つ[2]。
細菌、ウイルス、真菌などの疾病を引き起こす微生物は病原体と呼ばれる。病原体は、増殖して病気を引き起こすために、ヒト、植物、または動物の宿主を必要とする。これらの生物は自己複製を行うため、少量の投与で感染症を引き起こすことができる。病原体が宿主に感染すると、その影響は微生物と宿主の免疫系との間の複雑な相互作用によって決定される。感染してから病気の兆候や症状が現れるまでの期間は潜伏期間と呼ばれ、数日から数週間続くこともある。また、病原体は、その病原性(引き起こす病気の重症度)にも違いがある。ある種の病原体は、感染者のうち殺す割合が低い代わりに、一時的な無力感や長期的な病気を引き起こする。また、致死率が高い病原体もある。その病気が人から人へ伝染するものであれば、少数の感染で伝染病が発生する可能性がある。
毒素や生体調節物質は非生体分子であり、体内で複製されないため、最初の暴露量が病気の原因となる。つまり、毒素は病原体よりも即効性があり、数時間から長くても1日か2日で効果を発揮する傾向がある。それでも、神経ガスのように数分で犠牲者を出す化学兵器に比べれば、毒素の作用は緩やかである。毒素は、植物(ヒマシ由来リシン)、動物(貝類由来サキシトキシン)、真菌(アスペルギルス・フラバス由来アフラトキシン)、細菌(クロストリジウム・ボツリヌス由来ボツリヌス毒素)など様々なものに由来している。しかし、致死性が高く、大量に入手しやすい毒素の数は、これらの特性を持つ病原体の数よりもはるかに限られている。
生物調節剤は、従来の生物兵器の定義に最近加わったものである。生体調節物質は、人体内で通常生成される化学物質で、細胞間のコミュニケーションを制御し、神経系、内分泌系、免疫系の制御に重要な役割を担っている。生体調節物質のレベルのわずかなアンバランスが、認知、感情、および生理学的プロセスに劇的な影響を与えることがある[3]。
生物兵器は、攻撃側と防御側の双方に、いくつかのユニークな課題と機会を提供する。生物兵器は、病原体であれ毒素であれ、あるいは生体調節物質であれ、その標的を選択するものである。従来の生物兵器は、生物にのみ作用し、車両、建物、または機械に損傷を与えたり破壊したりすることはない。燃料、潤滑油、セメントなどの物質を消費・分解する酵素を産生するように遺伝子操作された細菌は、対資材兵器として使用される可能性がある。また、ほとんどの生物製剤は壊れやすく、生産、保管、配送、拡散の過程で生存力と毒性を維持するための特別な対策が必要である。細菌性、ウイルス性、毒素性の薬剤は、武器として使用するために、液体スラリーまたは乾燥粉末の2つのバージョンで製造することができる。スラリー状のものは製造が容易で安全だが、乾燥したものは濃度が高く、保管や散布が容易である。
生物製剤の散布にはいくつかの方法がある。最も原始的な方法は、粗製爆弾として感染媒介物(感染性物質を伝播させる役割を果たす物理的物体)やベクター(物質を伝播させる人間や昆虫などの生物)を使用するものである。生物学的製剤を大量に拡散させる最も効果的な方法は、直径1〜5μmの微小な飛沫のエアロゾルまたは雲として拡散させることである。このサイズの粒子からなるエアロゾルには、空気中に長く留まることができる、感染を引き起こすのに必要な量が少ない、結果として生じる病気の重症度が通常より高い、人間の感覚では見えない、などの利点がある。生きている生物と適切な大きさの粒子を含むエアロゾルを作ることは、現代の生物兵器の開発で最も困難なステップの一つである。さらに、ほとんどの生物兵器は、日光や酸素、極端な温度や湿度にさらされると死んでしまうし、生物兵器のエアロゾル雲は気象条件の気まぐれに左右される。このように、エアロゾル化した生物製剤を兵器として使用することは、攻撃側にとって不確実性をはらんでいる。
生物製剤のエアロゾルを散布するための弾薬には、点源弾と線源弾の2つの主要なカテゴリーがある。点源弾は、爆発性またはガス性のエネルギーを用いて、静止した位置からペイロードの生物薬剤を拡散させる。最も効率的な点源弾のタイプは、生物薬剤を多数の爆薬に分割して、薬剤をより広範囲に散布するものである。爆弾やミサイルの弾頭から散布される大量の爆丸は、風向きや風速に関係なく、生物薬剤で着弾地点の中心部を飽和させる。ライン・ソースは、走行中の車両、船舶、航空機、または巡航ミサイルから、優勢な風の方向と直角に一列に生物剤を散布することによって作られる。この種の散布は、広範囲をカバーでき、最適な大きさのエアロゾルを発生させるのに適しており、そのようなエアロゾルをスタンドオフ・レンジで検出するのが困難なため、生物兵器の運搬手段として最も効率的な方法である。
生物兵器に対する防御は、使用可能な薬剤の範囲、ほとんどの防御手段の薬剤特異性、新しいワクチンや治療法の開発に要するタイムラグによって複雑になっている。しかし、生物兵器は、ある意味で、高火力爆発物、化学兵器、核兵器よりも対策が立てやすい。生物兵器は、実際の攻撃前にワクチンで戦闘員や民間人を保護できるという点で、兵器システムの中でもユニークな存在である。病原体に感染した後の潜伏期間は、十分に準備された防御側が攻撃を察知し、攻撃の結果を軽減するために公衆衛生や医療介入を開始するための好機となる。このような理由から、強力な公衆衛生システムは、生物学的攻撃に対する最善の防御策である。
生物兵器のもう一つの重要な側面は、多用途のジレンマである。生物兵器の製造に必要な技能、材料、技術は、それに対する防御の開発や生物医学研究および医薬品製造などの民生活動の実施にも必要である。生物兵器の研究、開発、生産、兵器化に必要な原材料や設備の多くは、民間の産業や生物防衛計画でも使用されている。バイオテクノロジーの多用途性により、生物兵器を開発する国は、合法的な医薬・医療研究を行っているように見える、あるいは実際に行っている民間の研究機関にその活動を隠すことができる。このため、情報収集や検証を通じて疑わしい活動や施設の背後にある真の目的を判断することが難しくなっている。同時に、バイオテクノロジーの多目的利用という性質は、民間施設や平和的活動が軍事計画の一部であると誤解される可能性を高める[2]。
1.3 生物戦の初期の歴史
生物兵器は古代から行われてきたが、確認された攻撃の数は非常に少ない。20世紀まで、病気は戦争中に特によく起こり、致命的であった。この前近代時代を通じて、自然発生する病気は敵よりも多くの兵士を殺すのが普通であり、したがって軍事紛争に大きな影響を及ぼしていた。病気が軍事作戦に与える自然な影響は、おそらく病気を武器として利用しようとする初期の試みの動機となった。1800 年代後半に細菌説が確立されるまで、軍隊は何が病気を引き起こすのか知らなかったが、死体など病気の発生源を容易に特定することができ、伝染効果の基本的理解も持っていた。
古代における病気の発生原因に関する資料の欠如と理解の乏しさから、生物兵器が戦争で意図的に使用された明確な事例はほとんどない。それよりも、敵によって意図的に発生させられたという主張の方が一般的である。特に細菌説が解明される以前は、病気の発生源を特定することが困難であったため、このような主張をする人の中には、自分が苦しんでいる病気が敵によって人為的に作られたと心から信じている人もいたかもしれない。しかし、多くの場合、生物兵器に関する疑惑は、プロパガンダのために、自然現象に対する責任を敵対勢力に転嫁したいという願望から生じたものである。このような主張の最も古い例として、ヒッタイトで行われていたスケープゴートの儀式がある。この儀式では、災いの源と考えられている怒れる神を鎮めるためにヤギが生贄として捧げられ、代わりにその病気を敵に向けるよう要求された[4]。また、発生が意図的に引き起こされたという判断は、通常、状況証拠に基づく後方視的な分析の結果であったこともある。
生物兵器の初期の使用は、粗製兵器としての宿主または媒介物の使用に依存していた。原始部族は植物や動物に由来する毒素を矢の毒として使い、モンゴル人は1346年にペストで死んだ人の死体を包囲された都市カファに投擲し、ピット砦の英国兵は1763年にバリコラウイルス(天然痘を引き起こすウイルス)に汚染された毛布を敵対するアメリカ先住民族に渡している[4,5]。しかし、当時のこれらの病気の流行や権威ある記録の欠如を考えると、これらの攻撃のいずれかが成功したかどうかを判断するのは困難である。
1.4 生物戦の近代史
生物兵器の近代化は、微生物が病気の原因物質であるとする細菌説の展開と、細菌やウイルスを人工的に増殖させて研究する微生物学という学問の出現によってもたらされた。1940年代には、微生物の大量生産が可能になり、微生物などの空気中の生物物質の拡散や影響を科学的に研究する航空生物学が発展し、生物兵器の潜在的な破壊力は大きく拡大された。
病気や生物兵器に対する防御もまた、近代になって著しく改善された。細菌説が広く受け入れられると、衛生環境を改善することで病気の感染を阻止することが可能になった。応用微生物学は、多くの一般的な病気を予防するワクチンの開発にもつながった。ペニシリンの発見により、医師は初めてさまざまな細菌性疾患を治療する手段を手に入れた。本節では、まず第一次世界大戦から第二次世界大戦までの生物兵器プログラムの歴史について述べ、次に冷戦時代と冷戦後の主要な生物兵器プログラムについて論じることにする。
1.4.1 第一次世界大戦から第二次世界大戦までの生物兵器のプログラム
第一次世界大戦中、ドイツは微生物学という新しい分野を戦争に応用した最初の国になった。ドイツは、中立国から連合国へ輸送される騎兵隊や徴用動物に対して、動物病原体、特に炭疽菌や鼻疽菌を培養して送り込むために、国際的な諜報員網を駆使した。ドイツの生物学的妨害工作は大規模であったが、最終的には効果がなかった[6]。第一次世界大戦中の化学兵器の惨状を受け、化学・生物兵器の使用は1925年のジュネーブ議定書により禁止された。ジュネーブ議定書は化学・生物兵器の開発を禁止しておらず、署名者のほとんどが、自分たちが先に攻撃された場合、これらの兵器で報復する権利を留保していた。その結果、この条約は戦間期に各国が生物兵器を開発することを妨げることはなかった。
第二次世界大戦が始まるまでに、イギリス、カナダ、フランス、日本、ソ連、アメリカなど、ほとんどの大国が攻撃的、防御的な生物兵器プログラムを持っていた[7]。ハンガリー、イタリア、ポーランドも1930年代に小規模な生物兵器プログラムを開始したが、研究段階以上には進まなかったようである[5]。しかし、ポーランドの計画は、ドイツ占領軍に対してポーランドのレジスタンスが行った化学・生物製剤を用いた広範な破壊工作と暗殺作戦に貢献した[4]。驚くべきことに、強力な化学兵器能力を開発したナチスドイツは、攻撃的なBW活動には関与していない。理由は不明だが、アドルフ・ヒトラーは生物兵器の開発を禁止し、防御的な手段のみを許容するよう命じた[8]。
フランスとソビエト連邦は、平時にBWプログラムを開始した最初の国であった。フランスは1921年に病原体を戦争に利用する可能性を探り始め、ほぼ20年にわたって実験室での研究と実地試験を行った。フランスは、生物製剤のエアロゾル散布の潜在的利点を最初に認識した点で革新者であったが、政治的関心と資金不足のため、プログラムは限定的なものにとどまった。1930年代後半、ドイツの脅威を受けて計画は加速されたが、1940年のドイツの侵攻と占領までに生物兵器を生産することはなかった[9]。
ソビエト連邦は1925年に生物兵器プログラムを開始した。当初は精力的な研究・実験活動が行われたが、スターリンの大テロルによる微生物学者の定期的な粛清で弱体化した。その結果、1941年のドイツの侵攻後、ソ連は生物兵器に従事する準備ができていなかった。ソ連がスターリングラードの戦いでドイツ軍に対してツラレンシス菌(野兎病の原因菌)を使用したという主張は、入手可能な証拠によって裏付けられていない[10, 11]。日本の積極的なBW計画は、軍事科学者である石井四郎の指導の下、1931年に開始され、この時代のものとしては最大のものであった。731部隊および関連組織の日本人科学者は、何千人もの捕虜に対して陰惨な実験を行い、中国の民間人や兵士に対して何度も生物兵器を使用した。研究の範囲とそれに投入された資源の量にもかかわらず、日本人は重要な科学的、技術的ハードルを克服することができなかった。日本は数百キログラムの生物兵器を製造することができたが、その製造方法は粗雑で非効率的であった。また、BW剤を散布するための効果的な弾薬の開発にも失敗した。ペストの原因菌であるエルシニア・ペスティスに感染したウナギや、コレラの原因菌であるビブリオ・コレラや腸チフスの原因菌であるサルモネラ・タイフィによる食物や水道の汚染などの媒介に頼らざるをえなかった。日本が初めて生物兵器を限定的に使用したのは、1939年にソ連軍に対してであった。1939年から1942年にかけて、日本は中国の民間人や兵士に対して、炭疽菌、マレイン菌、コレラ菌、チフス菌、ペスティス菌を使った多くの生物学的攻撃も行った。日本軍は広範な伝染病を引き起こすことに成功したが、その技術は信頼性に欠け、日本人にも犠牲者を出し、日本が中国の対抗勢力に対して大きな優位に立つことはできなかった。これらの攻撃は、20世紀において確認された唯一の大規模な生物兵器の使用である。日本の生物兵器計画は、1945年の降伏と米国による占領によって終了した。石井四郎と彼の同僚たちは、アメリカに生物兵器研究の情報を提供することで戦争犯罪の裁判を回避した[12]。
第二次世界大戦中、アメリカ、イギリス、カナダは生物兵器の開発を共同で行っていた。連合国によって開発された唯一の運用可能な兵器は、炭疽菌に汚染された牛のケーキであり、ドイツが生物戦争を開始した場合に、英国はドイツの牛群に対して使用することを意図していた[13]。最も進んだ生物兵器プロジェクトは、炭疽菌の液体スラリーをエアロゾル雲で拡散させるマーク1弾の開発であった。この弾薬はイギリスの設計に基づき、カナダで実地試験され、米国が大量生産することになった。また、この爆弾の中に入れる炭疽菌の工業的生産も米国が担当することになった。しかし、ボンブレットと炭疽菌の製造のための工業設備が完成する前に戦争は終わった[14]。
1.4.2 冷戦期と冷戦後の生物兵器計画
冷戦時代、アメリカとソビエト連邦は高度な生物兵器プログラムを開発した。超大国に加え、ローデシアと南アフリカでも生物兵器が開発・使用され、1991年のペルシャ湾戦争前夜にはイラクが配備した。最近では、シリアと北朝鮮の生物兵器プログラムの可能性が、国際的な大きな関心事になっている。
米国の核兵器計画は、第二次世界大戦の終結とともに縮小されたが、1950年の朝鮮戦争の勃発とともに活性化された。米国は、メリーランド州のキャンプ(後のフォート・デトリック)で研究開発を行い、アーカンソー州のパインブラフ工廠で生物兵器を製造し、ユタ州のダグウェイ実験場と海外で生物兵器の実験を行っていた。このプログラムの過程で、米国はB. anthracis(炭疽病)、F. tularensis)、黄熱病ウイルス、ボツリヌス毒素、サキシトキシンを対人殺傷兵器として、Brucella suis(ブルセラ症原因菌)、Venezuelan equine encephalitis virus (VEEV)、staphylococcal enterotoxin type Bを無力化生物兵器として選択した。抗農薬としてPuccinia graminis(小麦の茎さび病の原因菌)、Magnaporthe oryzae(いもち病の原因菌)などがある。米国は1954年に抗農薬の研究を断念した。米国は、これらの薬剤を戦略兵器として普及させるために少数の散布タンクを、また敵陣の背後で活動する特殊作戦部隊のために大量の特殊戦術弾を備蓄していた。1969年、米国の化学・生物兵器政策を包括的に見直した結果、ニクソン大統領は生物兵器の使用を一方的に放棄し、攻撃型生物兵器プログラムを終了させ、既存の生物兵器と軍需品の備蓄を廃棄することを決定した。それ以来、米軍は防御的な研究開発しか行っていない[15]。
イギリスは第二次世界大戦直後からBWプログラムに高い優先順位を与えていたが、イギリスが核抑止力を獲得すると、攻撃的な研究とテストは徐々に段階的に縮小され、プログラムは厳密に防御的な方向性を持つようになった[16]。カナダは、第二次世界大戦中に始まった生物兵器に関する三者協力に引き続き参加したが、自国の生物兵器能力の開発は避け、パートナー国が開発したものに依存することを優先させた。カナダのBW研究・試験活動は、アメリカとイギリスのパートナーとの協力と支援によって行われたが、アメリカのBWプログラムの終了に伴い、1969年に停止された[17]。フランスのBWプログラムは、戦場での毒物や無力化生物兵器の使用の可能性に基づいて、1960年代初頭に短期間復活したものの、英国のプログラムと同様の軌跡をたどった。しかし、1960年代半ばから、フランスの計画は攻撃的研究から防衛に重点を置くようになった。攻撃的な生物兵器プログラムの事実上の放棄は、フランスが1972年にBWCに署名したときに、事実上の放棄へと変化した[18]。
冷戦時代には、ソ連が世界最大の生物兵器プログラムを構築した。ソ連軍はザゴルスク、スヴェルドロフスク、キーロフで生物兵器施設を運営し、アラル海のボズロジデニ島にも実験施設を有していた。これらの軍事施設では、炭疽菌、ペスト菌、バリオラウイルスなどのBW剤を備蓄していた。スベルドロフスクの施設では1979年に炭疽菌が誤って放出され、炭疽病が発生し、少なくとも68人が死亡した。1974年ソ連は新しい準民間組織「バイオプレパラート」を設立し、その目的はバイオテクノロジーの進歩を応用して新しい生物兵器を作ることであった。オボレンスクの応用微生物学科学研究所とコルツォボの分子生物学科学研究所(ベクターとも呼ばれる)は、病原体をより致死性の高いものにするためのエンジニアリングを担当した。レニングラードの超高純度生物製剤研究所は、生物製剤の安定化、乾燥、粉砕、散布の方法を改良することに専念していた。また、バイオプレパラート社は、戦時中に動員可能な6つのスタンバイ生産工場のネットワークを維持し、年間数千トンのBW剤を生産していた。ソ連が崩壊するまでに、バイオプレパラートは50の研究・生産施設と3万人以上の従業員からなる巨大な複合施設となった。ソ連が対人生物兵器として選んだのは、次のような薬剤である。炭疽病菌、ツラレンシス菌、ペスティス菌、ブルセラ菌(ブルセラ症の原因菌)、マレイ菌、偽マレイ菌(メリオイド症の原因菌)、コクシエラバーネッティ (Q熱の原因菌)、リケッチアプロワゼキ(チフスの原因菌)、バローラウイルス、VEEV、マーブルグウイルス、ボツリヌス毒素である。ソ連軍は、これらの薬剤を戦場や都市に送り込むために、爆弾や噴霧タンクを開発した。ソ連の生物兵器計画は、実験室での遺伝子組み換え兵器の開発で一定の成果を上げたが、バイオプレパラートがこれらの新兵器を実戦で実証する前にソ連が崩壊してしまった。また、ソ連農業省は、兵器として使用するための抗動物性病原体や抗作物性病原体の研究を行っていた。エリツィン大統領は、ロシアがソビエト連邦から引き継いだ攻撃的なBWプログラムを公式に終了させたが、ロシアはかつて攻撃的プログラムの一部であった3つの軍の微生物学的施設を維持し、これらの施設は依然として部外者に閉鎖されたままである[11]。米国は、ロシアがBWCを完全に遵守していないことに懸念を持ち続けている[19]。
1970年代、ローデシアは、白人少数民族政府の転覆を目指す反政府勢力に対する残忍な対反乱作戦の一環として、粗製化学物質と生物製剤を使用した。主な戦術は、ゲリラ・グループとその支持者が使う衣服、食物、飲み物を様々な毒物で汚染することであったが、ローデシアはゲリラが頼る水源を汚染するためにコレラ菌を使ったこともあった。1978年から1980年にかけてローデシアの農村で人間と牛を襲った大規模な炭疽病の発生は、ローデシアの治安当局によるものとされたが、最新の研究によると、これは同国の内戦中に獣医と公衆衛生サービスが崩壊し、自然発生が悪化したものであった[20]。1980年代には、南アフリカのアパルトヘイト時代の化学・生物兵器計画「プロジェクト・コースト」も、同様の手法を採用していた。このプログラムでは、南アフリカの治安機関のメンバーに、少量の毒物、毒素、そして炭疽菌、コレラ菌、サルモネラ・チフィムリウム(サルモネラ症を引き起こす細菌)などの病原体を供給し、食品や飲料を汚染し、反アパルトヘイト活動家を暗殺していた[21]。
イラクは、イラン・イラク戦争のさなかの1985年に生物兵器プログラムを開始し、その後6年間で大きな進展を遂げた。1991年のペルシャ湾戦争までに、イラクは炭疽菌、ボツリヌス毒素、アフラトキシンを大量生産し、スカッドミサイルの弾頭と空中爆弾にこれらの薬剤を充填していた。イラクは、核兵器、生物兵器、化学兵器などの武装解除を任務とする国連特別委員会 (UNSCOM)に発見されるのを恐れ、1991年夏に生物兵器と薬剤を密かに廃棄した。1995年になると、UNSCOMの調査とイラク高官の亡命により、イラクは過去の製造、実験、兵器化活動を明らかにすることを余儀なくされた。しかし、UNSCOMもその後継機関である国連モニタリング検証委員会 (UNMOVIC)も、過去のBW作業に関するイラクの説明を完全に検証することはできなかった。2003年、米国は、イラクが移動式生物兵器製造車と生物兵器の備蓄を有していると非難した。米国のイラク侵攻後、これらの評価を裏付ける情報が深く動揺していることが判明し、イラク調査団は、イラクが1990年代に確かにBWプログラムを放棄し、その後、それらの兵器に関する作業を再開していなかったと断定した[2]。
西側の情報源は、シリアが生物兵器プログラムを持っていると長い間考えていた。2014年、国防情報局 (DIA)は議会に「シリアは限定的な薬剤生産が可能かもしれないが、しかしわれわれはシリアが効果的な大量殺戮兵器として生物薬剤を使用する能力を獲得したとは考えていない」と報告している[22]。同時に、シリアの高官は生物兵器の保有を示唆し、少なくとも否定はしていない[23]。しかし、シリアのBWプログラムの存在や状況を裏付けるような証拠はほとんど公に提示されていない[24]。2014年、シリアは化学兵器禁止条約 (CWC)を履行する国際機関である化学兵器禁止機関 (OPCW)に化学兵器プログラムの一部としてリシン製造施設を申告した。シリアは2013年9月のCWC加盟前に生産していたリシンをすべて廃棄したと主張しているが、OPCWは毒素の生産と廃棄に関する説明を確認できていない[25, 26]。毒素であるリシンは、化学兵器と生物兵器の両方と考えられている。リシン・プログラムが、シリアが生物兵器に関心を持っているという西側情報の評価の唯一の根拠であったのか、あるいは兵器として使用するための細菌またはウイルス剤のシリア開発に関する機密情報が存在するのかは不明である。
北朝鮮もまた、生物兵器プログラムを保有していると長い間疑われてきた国家の一つであるが、この評価を裏付ける詳細はまばらである。米国国務省によれば、「北朝鮮は、BWプログラムを支援し得る長年のBW能力とバイオテクノロジーのインフラを持っている」[27]。2012年に韓国国防省は、北朝鮮のBWプログラムには炭疽菌、バボラウイルス、Y. pestis、F. tularensis、そして不特定の出血熱ウイルスが含まれていると報告している[28]。この情報の多くは、信頼性の低い脱北者からの報告に基づいているようである[29]。生物農薬として使用されるバチルス・チューリンゲンシスを生産する平壌バイオテクノロジー研究所は、研究所に設置された機器の写真の分析に基づいて、炭疽病菌生産施設である可能性が指摘されている[30]。しかし、この研究所にデュアルユース機器が存在することは、その施設が炭疽菌を安全に生産する能力を持っている、あるいはBWプログラムの一部であることを示す十分な証拠とはならない[31]。
1.5 生物兵器の不使用を説明するもの
1940年代以降の生物戦の大きな進歩にもかかわらず、エアロゾル散布技術に基づく近代生物兵器が成功裏に使用された証拠はない。まれに、ローデシアや南アフリカのように、生物兵器の使用に踏み切った国家もあるが、その場合は、より洗練されていない散布方法を用いている。現代においてこれらの兵器の使用がまれであることを考慮することは、このような自制をもたらす条件が今後も強く維持される可能性を判断する上で重要である。現代において生物兵器がほとんど使用されていない理由として考えられることは3つある。
第1に、これらの兵器の使用に対する強い規範的障壁が存在する。病原体を兵器として使用することは、古代から複数の文明や宗教でタブー視されてきた。毒や病気を戦争の道具として使用することに対するこの嫌悪感は、何世紀にもわたって国内法の禁止事項として、また20世紀には国際法として体系化されてきた。1925年のジュネーブ議定書は生物兵器の使用を禁止し、1972年の生物兵器禁止条約は、これらの兵器の開発、生産、取得を禁止している。生物兵器禁止条約は、ある種の兵器全体を違法化した最初の条約であり、生物兵器の使用は「人類の良心に反している」と宣言し、これらの兵器に対する長年の規範を補強した。
第2に、軍事組織には、生物兵器をその兵器庫や戦争計画に組み入れない現実的な理由があった。これらの兵器を安全に保管し、取り扱うことは物流上の困難を伴い、戦闘に使用することは作戦上の重大な問題を引き起こす可能性がある。初期の生物兵器は、昆虫やネズミなどの媒介物、あるいは食物や水の汚染に依存して敵に感染させるため、その効果は限られ、効果も不確実であった。エアロゾル散布に基づく現代の生物兵器は、大気条件の気まぐれの影響を受けやすい。このため、軍事計画担当者には不確実性が生じ、風向きの変化により誤って友軍に感染させる危険性がある。
生物兵器の使用がまれである第三の理由は、政治的・戦略的なものである。これらの兵器の使用は、報復や紛争の激化を恐れて制限されていたのかもしれない。日本、ローデシア、南アフリカは、現物で報復できない相手に対してのみ生物兵器を使用した。禁止そのものよりも、こうした非合法兵器の使用に対する国内外からの反発も抑制的な影響を及ぼした可能性がある。
残念ながら、生物兵器の使用に対するこれら3つの制約がすべて損なわれつつあるのではないかという懸念がある。BWCは、制度的な能力と資源の面で、主要なWMD不拡散条約の中で最も脆弱なままである。シリアが化学兵器を使用し続け、国際社会がシリア政権のCWCに対するあからさまな違反の責任を追及できないことは、規範的制約の限界を示すものである。運用と物流の問題がもたらす第2の制約は、技術の進歩により、化学兵器の製造と保管がより容易かつ安全になり、使用された場合にはより効果的になる可能性があるため、今ではそれほど困難なことではなくなっているかもしれない。最後に、通常軍事技術における米国とその同盟国の優位性が、不満を持つ行為者に、生物兵器を使用することによる政治的・戦略的危険性を上回る非対称戦略の一環として、生物兵器を使用する強い動機を与える可能性がある。修正主義的な国家は、生物兵器を戦力拡大要因として使用して既成事実を作ることも、体制を脅かす報復を引き起こさないように生物兵器の使用を調整することも、匿名で攻撃を行い報復を完全に回避することも可能だと考えているのだろう。核兵器と同様、第2次世界大戦以降、生物兵器が大規模に使用されていないことは喜ぶべきことであるが、自己満足に浸る根拠にはならない。
1.6 生物兵器テロリズム
テロリストが生物兵器を入手し使用する可能性は、1990年代半ばに安全保障上の脅威として浮上した。2001年9月11日のテロ攻撃とその秋のアメリストラックス書簡攻撃は、生物テロを国際安全保障の課題の最上位に押し上げた[32]。このセクションでは、バイオテロの最も重要な4つの事例をレビューし、生物学的テロの現在の脅威の評価を提供する。
生物学的テロは、これまで極めてまれであった。20世紀において、生物製剤の入手に成功したのは、8つのテロ集団だけである[33]。2001年の炭疽菌手紙攻撃以前には、オレゴン州のバグワン・シュリー・ラジニーシの弟子という1つのグループだけが、生物製剤で死傷者を出すことに成功した。テロリストが生物兵器を開発するための資源は国家に比べて少ないが、そのニーズはより限定的である。国家とは異なり、テロリストは、大量に生産でき、長期間保存でき、高効率で信頼性の高い装置で拡散でき、戦場の状況下で使用するために設計されたシステムで運搬できる生物兵器を開発しなくても目的を達成することができる。とはいえ、大量の死傷者を出そうとするテロリストは、病原体の入手と生産、および効果的な散布装置の設計において、依然として大きなハードルに直面している。少数の死傷者や大規模な混乱を引き起こすことに関心を持つテロリストは、より少ない障害に直面している。2001年以降の炭疽菌デマ手紙の拡散が示すように、地域レベルでのテロと混乱を引き起こそうとする個人は、粉末状の物質と脅迫状だけでその目的を達成することができる。
1.6.1 ラジニース派
1984年、ラジニーシー教団のメンバーは、オレゴン州ダレスでサラダバーにチフス菌を混入し、751人の町民を病気にした。1981年にダレスに牧場を設立して以来、ラジニィー族は、州当局や地方当局と何度も紛争を起こした。この教団は、地方選挙を有利に進めるために、診療所で生産したチフス菌を町内のサラダバー10軒に混入させた。公衆衛生局は、集団食中毒の原因はレストランの食品取扱者の不衛生な行為にあると考えた。犯人の身元は、首謀者が他の教団員と仲違いし、教団幹部が地元関係者と町民を毒殺したと公に告発するまで明らかにされなかった[34]。
1.6.2 オウム真理教
日本のカルト教団であるオウム真理教は、大量の死傷者を出すためにエアゾール式の生物兵器を作ろうとしたことが知られている唯一のグループである。しかし、オウムの努力は、科学的、技術的、運用的、および組織的な欠陥のために失敗に終わった。麻原彰晃を教祖とするオウムは、非信者の殺害を正当化する終末論的なイデオロギーによって特徴づけられた。オウムの動機は宗教的なものだけでなく、日本政府の転覆という極めて野心的な政治的目的もあった。オウムの資金力、メンバーの多くが科学者であること、そして日本の当局のモニタリングを受けずに活動する能力にもかかわらず、1990年から1995年の間に行われた10回のBW攻撃未遂では、いずれも死傷者を出すことはなかった。オウムは、効果的なエアゾール式生物兵器を開発することができなかったため、化学兵器に目を向けるようになった。オウムは、1994年6月に松本で、1995年3月には東京の地下鉄で神経ガスであるサリンを放出し、合計19人が死亡、1000人以上が負傷した。オウムの経験は、テロリストが生物兵器を開発する際に直面する困難さを明らかにするものである。オウムは潤沢な資金と十分な装備を持っていたが、彼らの生物兵器開発にはいくつかのハンディキャップがあった。科学的なレベルでは、オウムのプログラムは、バクテリアの扱い方を知っている微生物学者によって運営されてはいなかった。その結果、オウムはボツリヌス毒素の致死株を野生から培養できず、炭疽菌の株は動物用のワクチン株しか手に入れることができなかった。技術的な面では、生産された炭疽菌のスラリーは非常に低品質であった。また、オウムには炭疽菌の液体スラリーを散布する技術的能力もない。屋上散布機は故障や水漏れ、詰まりが多く、1-5ミクロンの粒子を作ることができないか、非常に効率が悪かった。作戦レベルでは、オウムは核兵器攻撃に適した環境条件について理解しなかった。オウムは、日中に生物兵器を散布しようとしたが、紫外線と熱上昇気流に兵器をさらし、兵器の生存率とエアロゾルが覆う面積を減少させることになった[35]。
オウムの失敗は、エアロゾル化した薬剤によって大量の死傷者を出す生物学的テロが、一般に言われているほど簡単ではないことを示している。生物兵器の開発には、病原体の適切な株、拡散に適した形でその生物を生産する能力、そして目的の場所に効果的に薬剤を拡散させる手段が必要である。オウムはこれらすべての課題に失敗した。オウムの経験は、生物兵器を製造するには資金、設備、教育を受けた人材だけでは不十分であり、科学的・組織的な能力も必要であることを示している。
1.6.3 ブルース・アイビンスと炭疽菌の手紙
9月と10月に炭疽菌の芽胞を乾燥粉末にしたものを封筒に入れてトーマス・ダッシュル上院議員 (D-SD)とパトリック・リーヒー (D-VT)、フロリダとニューヨークのメディア5社に郵送された。この書簡によって22例の炭疽病が発生し、そのうち11例が皮膚炭疽、11例が吸入炭疽であった。吸入炭疽のうち5例は致死的であった。炭疽菌の手紙による攻撃はまた広範囲に波及し、何千人もの人々が予防のために抗生物質を飲まねばならず、米国郵政公社は混乱に陥り、米国上院は一時的に閉鎖され、郵便の安全性について全国的不安を引き起こし、白い粉による誤情報やデマの洪水を引き起こした。この事件の被害総額は60億ドルと推定される。この炭疽病郵便攻撃はFBIによってアメリトラックスと呼ばれた。
年8月、FBIはメリーランド州フォートデトリックにある米国陸軍伝染病医学研究所 (USAMRIID)の微生物学者で炭疽菌ワクチンの研究者であるブルース・E・アイビンズをアメリトラックス事件の唯一の容疑者と発表した。そのわずか数日前、1年以上前から捜査を受けていたアイビンズは、炭疽菌の手紙攻撃で起訴されようとしていることを知っていたが、故意に薬物の過剰摂取で自殺した。FBIが提出した最も強力な証拠は、攻撃に使われた炭疽菌がUSAMRIIDのアイビンズの研究室にあった炭疽菌のフラスコと関係があるというものである。FBIは微生物法という新しい学問を使い、武器として使われた病原体や毒素の遺伝的、化学的、物理的特性を強力な分析技術で解明し、この関連を証明した。アイヴィンズはまた、炭疽菌の手紙が上院議員やメディア関係者に郵送される直前の夜と週末に、自分の研究室でモニタリングされない時間を長く過ごしていた[36]。
アイヴィンズが炭疽菌の手紙を送った動機は、おそらく炭疽菌ワクチンの開発ペースが遅いことへの不満であったと思われる。2001年の秋までに、この研究は技術的、官僚的、政治的、財政的問題のために事実上停止状態に陥っていた。FBIによれば、アイビンズはこの頃、深刻な精神的問題を抱えていたとのことである。9月11日の余波で、アイビンズは次の攻撃は9月11日以上の被害をもたらす生物兵器かも知れないと恐れていたのかも知れない。炭疽菌の手紙は、生物兵器がもたらす危険と、それに対する防御の強化の必要性を国民に警告するものであったかもしれない。
アイビンズが炭疽菌書簡攻撃を行ったかどうか、どのように、そしてなぜ行ったかについての重要な未解決の問題にもかかわらず、この事件がバイオテロリズムのもたらす脅威を評価するための意味についていくつかの見解を示すことが可能であろう。アイヴィンズは、国家が運営する生物防衛プログラムに所属している人物にしかできないようなレベルの経験、一連の技術、広範な暗黙の知識を持っていた。アイビンズは博士号を持つ微生物学者であり、炭疽菌の増殖、胞子形成、精製のエキスパートであり、動物のエアロゾル実験用に液体炭疽菌胞子を調製した経験が豊富であった。アイビンズがUSAMRIIDに勤務していたことは、炭疽病の強毒株の入手、設備の整ったバイオ・コンテインメント研究室、そこでの勤務経験、炭疽病に対する免疫、除染手順の知識などの点でも有利であった。これらはテロ・グループが独自に獲得することが困難な資源である。
ダッシュルとリーヒー両議員に送られた炭疽菌芽胞は高濃度で、しかも非常に優れたエアロゾル化特性を持つことから、多くの人がこの粉末は高度な装置や特殊な添加物やコーティングを使って製造されたものと推測している。FBIの主張では、アイビンズは標準的な実験設備で、特別な添加物を使わずにこのような高品質の炭疽菌芽胞の粉末を製造することができたというので、高度な生物兵器の技術水準は一般に考えられているより低いのではないかという懸念が起こっている。しかし、この推測は、アイビンズが炭疽菌について持っていた高度な暗黙知を無視したものである。たとえアイヴィンズが炭疽菌の手紙の粉末を作るためにローテクな方法を採用したとしても、この方法をうまく適用するために高度な技術を必要としなかったということにはならない[2]。
1.6.4 ジハーディスト・グループ
ジハード主義のグループ、特にアルカイダとイスラム国は生物兵器の開発に関心を示している。1998年12月、オサマ・ビンラディンは、核、生物、化学兵器を獲得することが「宗教的義務」であると宣言した。2003年5月には、サウジアラビアの聖職者が、異教徒に対する核・生物・化学兵器の使用を正当化するファトワを発布した。
アルカイダの化学・生物兵器計画は、コードネーム「プロジェクト・アルザバディ(アラビア語でヨーグルト)」と呼ばれ、1999年に創設され、アルカイダ第2位の幹部であるアイマン・アルザワヒリが指揮を執った。ザワヒリは、生物兵器が核兵器と同等の殺傷力を持ち、簡単に製造できること、生物兵器による攻撃は遅効性であるため犠牲者が増えること、そしてこれらの兵器に対する防御が非常に困難であることに魅力を感じた。2001年までに、このグループはアフガニスタンに二つの研究所を設立し、いくつかの細菌性病原体に関する科学文献を入手し、二重使用の製造装置を調達し、微生物学者を採用し、炭疽菌製造専門の小さな細胞を持っていた。アルカイダの進歩は、炭疽菌の強毒株の入手や生物兵器のエアロゾル化に必要な技術の習得が出来なかったために、妨げられた。捕らえられたアルカイダ工作員によれば、米国のアフガニスタン侵攻で崩壊したとき、アルカイダの生物兵器開発は初期の「構想段階」にあったという。アルカイダのBWの野望は、プログラムの主要な参加者のほとんどが死亡または逮捕されたことによって、さらに後退した[2]。この分野におけるアルカイダの野望は、その能力を上回っているが、この集団が長い間、これらの兵器に関心を持ち続けてきたという事実は、他のテロ組織とは異なるものである。
イスラム国は、Jonathan Tuckerが化学・生物兵器を獲得し使用した他のグループにおいて特定したリスク要因の多くを示しており、極端なレベルの暴力にコミットしている終末思想によって壮大な目標を持つカリスマ的指導者や革新と実験に対する実証された能力などがその例である[37]。しかしながら、これまでのところ、イスラム国は塩素とマスタード剤をベースとした粗製化学兵器を開発し使用することしかできていない[38, 39]。イスラム国のBWへの関心を示すために引用された主要な証拠は、2014年にイスラム国のメンバーから回収されたいわゆる「運命のノートパソコン」であり、そこにはY. pestisを含む生物兵器の開発方法に関する文書が含まれていた[40, 41]。このBW「マニュアル」は、何年も前からオンラインで入手可能なジハード文書のコピーであり、細菌を実行可能な生物兵器に変える方法に関する指示を一切提供せずに、細菌の増殖方法に関する基本情報のみを含んでいた[38, 42]。このマニュアルは、初歩的で、重要な詳細が欠けていたり、誤った情報を含んでいたりする傾向がある他のジハードのBW「マニュアル」と同様で、大量殺戮を引き起こすのに十分な量または質の病原体または毒素を製造するには不適であり、生物製剤を広めるための技術は記述されていないようだ[42]。イスラム国に触発された、あるいは指示された個人または小集団は、食品や飲料に毒を盛るのに適した粗悪な細菌剤または毒素を少量生産することはできるかもしれないが、大規模な専門家の支援がなければ、大量の死傷者を出すことができる毒性生物剤をエアゾール化できないままであろうと思われる。
1.7 結論
国家やテロリストによる生物兵器の開発は、そのような兵器を製造できる国や集団の数に比べ、はるかに遅れている。生物兵器が将来もたらす脅威の大きさは、あまり理解されておらず、影響を及ぼすことが困難な2つの変数によって決定される。第1の変数は、バイオテクノロジー革命が生物兵器戦争における攻撃と防御のバランスに与える正味の影響である。生命科学の進歩は、防御側を強化し、生物兵器管理協定を検証する新たな能力を提供する一方で、攻撃側がより高度な兵器とそれを隠蔽する手段を開発するための障壁を低くしている。この種の評価は、生命科学における技術革新の加速、これらの技術の必然的な世界的普及、およびバイオテクノロジーの多用途性によって複雑化する。加えて、暗黙知や実践の共同体のような社会的要因が、国家やテロリスト集団が科学的・技術的ブレークスルーを兵器に転換する能力を媒介することができる[43, 44]。多用途のジレンマの不幸な副産物は、生物防御研究への投資が、生物兵器の開発に応用されうる新しい知識をも生み出してしまうことである。
第2の重要な変数は、生物兵器の開発に対する国家および非国家主体による関心の度合いである。こうした兵器を開発する能力はすでに普及しているため、こうした兵器の追求を促す主な要因は意図であろう。生物兵器に対する規範がこれらの兵器の魅力を制限し続けるのか、それとも安全保障上の懸念や科学・軍事指導者の官僚的野心がこの抑制を圧倒してしまうのか。技術的な洞察力、大量殺戮(さつりく)願望、生物兵器への関心を兼ね備えた非国家主体が出現する可能性はどの程度あるのだろうか。これまでのところ、生物兵器を使用して大量殺戮を行う能力と動機の両方を兼ね備えたテロ集団は存在しない。テロリストは依然として、銃や爆弾を使って大惨事を引き起こすことを圧倒的に好むのである。2001年9月11日の事件と「イスラム国」の驚くべき台頭は、過去の経験が必ずしも将来の脅威の信頼できる予測因子ではないことを鮮明に思い出させるものである。テロ集団を追跡し、生物兵器を開発する活動を探知することの難しさを考えると、そのような集団がほとんどあるいは全く警告なしに発生する可能性がある。このような集団の出現とバイオテクノロジー革命の悪用を防ぐことは、21世紀の安全保障上の大きな課題である。
