コンテンツ
link.springer.com/article/10.1007/s10892-023-09459-0
50 Years of Dirty Hands: An Overview
ChatGPTによる要約
この記事は、マイケル・ウォルツァーの「政治行動:汚れた手の問題」の出版以来の重要な議論を概観し、特別号の記事がそれらにどのように貢献しているかを示しています。主な焦点は、「汚れた手」の概念自体に対する外部批判と、汚れた手の理論家間の内部議論です。
外部批判
「汚れた手」の概念に対する最も一般的で潜在的に有害な批判は、概念が概念的に矛盾しているというものです。この主張を支持する主な議論は、真の道徳的ジレンマの存在に反対する「メタ倫理的議論」と、行為が道徳的に正当化される(場合によっては義務的である)が、それでもなお道徳的に間違っているという主張を拒否する「全てを考慮した議論」です。これらの議論は、義務論者と結果主義者の道徳理論家によって強力で説得力があると見なされ、その結果、汚れた手のシナリオの可能性自体を一概に否定しています。
内部議論
汚れた手の概念が可能である場合、それは他の形態の避けられない道徳的衝突とは異なる独自の倫理的視点を示すのでしょうか?また、汚れた手の状況に直面した場合、私たちの手を清潔に保つことは可能でしょうか?さらに、正しいことをするために間違ったことをしたエージェントは、どのように感じるべきでしょうか?これらの問題は、汚れた手の理論家間で意見が分かれています。
政治における汚れた手
政治における汚れた手のシナリオは、特に挑戦的です。政治家はしばしば、個人的な道徳観と公共の利益の間で葛藤する決断を迫られます。このような状況では、政治家は道徳的に正しい選択をするために、個人的な道徳的純粋さを犠牲にすることが求められることがあります。この問題は、政治的リーダーシップの本質と、政治家がどのようにして自身の行動を正当化するかに関する議論に影響を与えています。
この特別号の記事は、これらの問題に対する新しい視点を提供し、汚れた手の概念に関する理論的および実践的な理解を深めることを目指しています。それぞれの論文は、この複雑な問題に対する独自のアプローチを採用し、汚れた手の問題に対する新たな洞察を提供しています。
要旨
本章では、特集号を紹介し、マイケル・ウォルツァーの代表的論文『政治的行為』(Political Action:汚れた手の問題
ここに道徳的な政治家がいる。私たちが彼を知るのは、その汚れた手によってである。もし彼が道徳的な人間であり、それ以外の何者でもなければ、彼の手は汚れないだろう。もし彼が政治家であり、それ以外の何者でもなければ、彼は手がきれいであるかのように装うだろう」(Walzer1973: 168)。
「汚れた手」の問題に関する本特集号は、マイケル・ウォルツァーのブレイクスルー論文「政治的行為」を記念するもの:この論文は、50年前に当時創刊されたばかりの雑誌『哲学と公共問題』に掲載された。本特集の目的は、主にウォルツァーの著作に触発され、過去50年の間に生じた「汚れた手」の問題に関する研究のコーパスを把握し、探求することである。論文は共通のテーマを探求し、ダーティハンド理論家にとって新たな道筋や興味の可能性に取り組んでいる。一般的な倫理理論や、特に難解な道徳的ジレンマの問題に対する、よりニュアンスのある洗練された理解へのダーティハンド理論の貢献を探ることで、この概念そのものをよりよく理解する助けとなる。この序論では、この論争の的となる概念の検討におけるこれまでの進展を概説し、生産的な今後の研究の可能性を指摘する。最後に、本特集号に掲載された9本の論文それぞれについて簡単に解説し、この文献の発展への貢献を強調する。
1 マイケル・ウォルツァーの『政治的行為:汚れた手の問題』
この50年間、汚れた手の問題について書く者は、支持者であれ批判者であれ、ウォルツァーがそのブレイクスルー論文『政治的行為』で主張した核心に触れる必要があった:汚れた手の問題』である。この論文は、政治における困難な道徳的ジレンマへの対応をどのように理解すべきかについて、絶対主義(脱自律主義)と費用・便益主義(結果主義)の両方を熱烈に否定するものとして書かれた。ウォルツァーの深い懸念は、どちらのアプローチも、政治において道徳的に行動しようとする人々が直面する倫理的、感情的な複雑さを適切に表現していないということであった。彼らは、ひどい道徳的ジレンマに直面したとき、より小さな悪に帰結する行動を確実にするために、大切にしている道徳原則を犯す。義務論な禁止事項が根本的な帰結論的懸念と衝突する圧力によって、政治家は、たとえ自分の行動がすべて正当化されたとしても、そう行動したために道徳的に汚染されてしまうという状況に直面することになる。これは一言で言えば、汚れた手のパラドックスである。
さらにウォルツァーは、私たちが大きな社会悪や自然悪に直面したとき、私たちを守るために政治家が手を汚すことが必要であり、それを望んでいると主張する。政治家には善良であってほしいが、善良すぎてもいけない。政治家は、私たちを守るために必要なことをする必要がある。たとえそれが絶対的な道徳的禁忌を犯すことであっても。ダーティハンドが結果論的な目的/手段分析と異なるのは、たとえそれが明白に道徳的な理由によるものであったとしても、政治家が重大な道徳的過ちを犯したことを認識していることである。道徳的違反は、それが何であるかを理解され、認められ、感じられる必要がある。つまり、行為者を道徳的に汚し、適切な道徳的対応、おそらくは罰さえも必要とする行為に関与することである。政治家が自らの不義を認めてこそ、私たちは政治家が善良な人間であり、倫理的な現実を統治するのに適した人物であることを知る。
ウォルツァーが1973年に彼の代表的な論文を発表した背景を理解するためには、当時の喧騒に満ちた学術環境を理解する必要がある。ウォルツァーと彼の哲学仲間は、倫理法哲学協会(Society for Ethical and Legal Philosophy:SELF)を結成していた。彼の仲間には、ジョン・ロールズ、ロバート・ノージック、トーマス・ネーゲル、ジュディス・ジャービス・トムソンなど、過去50年間の偉大な分析哲学者の多くが名を連ねていた。予想通り、ウォルツァーの汚れた手に関する説明は、ほとんどの哲学者に歓迎されなかった。ネーゲルを除き、ほとんどの分析哲学者は、ウォルツァーの小論には深い欠陥があり、混乱した誤った推論の産物であると考えていた。政治生活における不可避の道徳的パラドックスの存在を論じたものであったが、ほとんどの分析哲学者は、その中心的主張-正しいことをするために間違ったことをする-を、自己矛盾、支離滅裂、すでに困難で混乱した状況に混乱を重ねるものとして退けたのである。
しかしウォルツァーは、そのような道徳理論の分析的説明は、価値の一元論的理解に縛られすぎており、その還元主義は、あらゆる矛盾と困難を抱えた道徳的生活の質料を理想化し単純化した説明になってしまうとして、これを否定した。ウォルツァーの「汚れた手」についての説明は、学者が哲学的研究にどのように取り組むべきかについての彼の深い信念から生まれたものである。すべての議論は、私たちの生活経験に敏感でなければならず、不必要な抽象化を避ける必要がある。有用な分析には、奇想天外な仮説や奇妙な仮説を避け、その代わりに私たちの複雑な世界を反映する具体的な歴史的事例を用いる必要がある。それゆえ、ウォルツァーは政治的な問いについて具体的に考えようとし、「特異で、抽象的で、基礎的な答え」を避けている(Walzer and von Busekist2020: 131)。その結果、ウォルツァーの膨大な学術的著作、著書や論文は、常に高度な理論の試みというよりは政治的な議論となっている。
さらに言えば、ウォルツァーは分析家仲間たちの深い懸念に応えようとはしなかった。実際、『Political Action』の影響力は絶大であったにもかかわらず、彼が「汚れた手」の話題に立ち戻ることはほとんどなかった。脚注5ウォルツァーは、正義の戦争において、敵が国家に存亡の危機をもたらし、「人類の良心に衝撃を与える」ような邪悪なイデオロギーに動機づけられた行動に出るような状況では、汚れた手を使う必要があるかもしれないと論じている(1977/2006: 107)。ここでいうダーティハンドとは、通常、より大きな悪を防ぐために罪のない人々を大量に殺害することである。このような行為は、戦争における非戦闘員への危害を禁じた「ユス・イン・ベロ」の基準に意図的に違反することになる。重要なのは、このような行為が正当化されるのは、脅威が共同体の継続的な存続にほかならないという極端な場合に限られるということだ(2004: 44-50)。ウォルツァーは、そのような脅威のパラダイム・ケースとして、ナチスがヨーロッパ全土を征服しようとする一方で、大量虐殺を行い、劣っているとみなされるすべての人や国家を奴隷にしようとしたことを挙げている。しかし、この汚れた手に対する閾値は、「政治的行為」で使われた、時限爆弾のシナリオや腐敗した区のボスとの汚い取引に関わる例とはかけ離れている。というのも、ウォルツァーは、戦争中の行為は膨大な数の罪のない市民に致命的な影響を及ぼすため、戦争にはより高度で厳しい閾値が必要だと理解しているからである。彼が雄弁に語るように:
道徳的に強い指導者とは、罪のない人を殺すことがなぜいけないのかを理解し、天罰が下るまでそれを拒み、何度も何度も拒む人のことである。そして、(アルベール・カミュの「正義の暗殺者」のような)道徳的犯罪者になる。
ウォルツァーにとって、汚れた手のシナリオの道徳的現実は、状況によっては悪を行うことで悪と戦うという認識に集約することができる。善人は適切な道徳的感情を持ち、その行動に対して代償を払う必要がある。非本質論的な説明も結果論的な説明も、私たちの道徳的現実のこの逆説的で不可避な側面を適切に捉えることはできない。
2 「汚れた手」という概念
2. 1 汚れた手の問題を区分する
「汚れた手」という言葉は、善良なエージェントが直面する、不潔で時に血なまぐさい道徳的ジレンマの比喩として理解されることはあまりない。より一般的な用法は、私たちが心から嫌がる不快で汚らしい仕事を指す。屠殺場での労働や下水道の清掃は、汚い仕事に携わる人々を指す活動の一例だ。これは基本的に記述的な用法であり、その人が従事している行為や仕事について規範的な判断を下すものではない。さらに、この用語の別の用法は規範的だが、純粋に非難的な目的を持っており、代理人、典型的には政治家の道徳的な悪行を暴露するものである。一般市民やジャーナリストなどが「政治家はみんな汚い」と主張するのはよくあることだ。ここでの主張は、すべての政治家は単純に不道徳であり、これはこの職業に就く者に期待すべきことである、というものだ。政治家は、自分自身とその取り巻きを豊かにするために、自分たちの利己的な目的のために嘘をつき、ごまかし、さらに悪いことをする。
この概念にはさまざまな解釈の仕方があるが(注7)、立派な不道徳性の主要な関心事は、私たちが賞賛しながらも、概念的には不道徳な行動への強い傾向と結びついている、ある行為者が持つ性格的特徴に焦点を当てている。例えば、冷酷さは成功した政治家にとっての美徳であると同時に、この特性は不道徳な行動に不可避的につながると考えるかもしれない。
ウォルツァーが用いた「汚れた手」という概念、そして本特集の焦点である「汚れた手」という概念は、上記の意味とは異なる。彼らは、より小さな悪をもたらすためにこのような行動をとるが、結果論者とは異なり、犯した道徳的違反を認め、そのような行動をとったことによる道徳的汚染を正しく感じている。
2.2 汚れた手の問題の2つのモデル
汚れた手の問題は、不道徳を不潔と結びつける比喩を想起させる。政治的主体が、時には裏切り、托鉢、強要、さらには殺人にまで至る選択を迫られる、扱いにくい道徳的葛藤に直面しているという認識は、古代ギリシア時代にはすでに理解されており、ソフォクレスやアイスキュロスの悲劇劇に反映されている。この関連性を示す最も象徴的なエピソードは、ポンテオ・ピラトがキリストの無実を信じながら、政治的な理由からキリストを死刑に処したことによる道徳的な汚れを落とすために手を洗ったというものであろう。
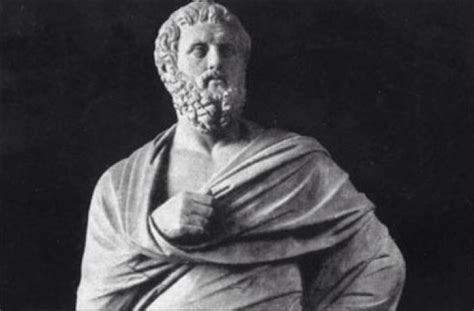
政治におけるある種の道徳的葛藤を指すのに使われる「ダーティハンド」という用語が生まれたのは20世紀に入ってからだが、パリッシュはこの議論について、古代からルネサンス、そして近代にまで遡ることができると論じている(Parrish2007)。かつてこのような議論では、公共財の提供や保全と、そのために必要な手段、つまりエージェントの道徳的美徳を著しく損なう可能性のある手段とのバランスをとるという、よく認識された問題に言及していた。スチュアート・ハンプシャー(Stuart Hampshire)やバーナード・ウィリアムズ(Bernard Williams)といった理論家によるダーティハンド(汚れた手)についての現代的な説明には、「マキアヴェッリ・モデル」と呼ぶこのアプローチが見られる。脚注12ここで注目すべきは、マキアヴェッリ・モデルの焦点は、公的な(より具体的には政治的な)義務と私的な道徳的信念との不可避的な衝突にあるということである。政治的奉仕者としての義務をうまく果たすことは、必然的に私的な美徳を損なうことになる。それは、公的領域と私的領域の両方における、不可能でありながら有効な要求を認めるという点で、一種の価値多元主義を意味する。これらの相反する価値を道徳的なヒエラルキーの中に置くことはできないし、単一の至高の価値に従属させることもできない。その結果、公的義務と私的義務の衝突によって、一方の大切な価値の実現が他方の価値を必然的に損なうような状況が常に存在することになる。
私たちが「ウォルツェリアン・モデル」と呼ぶ2つ目のモデルは、倫理的行動を理解するための競合するアプローチと、正しさと善に関する競合する概念との衝突から生まれたものである。義務論な推論が、理性や啓示に基づく絶対的な道徳的原則(すなわち何が正しいか)を遵守することに焦点を当てるのに対し、帰結論者は特定の非道徳的財を最大化することに焦点を当てる。すべての道徳的判断は通常、非自律論的な考察と結果論的な考察の両方を含むため、これらのアプローチ間の深刻かつ解決不可能な対立を常に回避することは不可能である。ウォルツァーの政治における汚れた手の特徴は、この問題に焦点を当てている。ある状況において政治家は、何をするにしても「功利主義的に見ればまさに正しいこと」であるにもかかわらず、政治家に「道徳的な過ちを犯す」ことになるような選択に遭遇する(Walzer1973: 161)。ウォルツァーモデルはこの50年間、ダーティハンドを批判する側と支持する側の双方から、ダーティハンドに関する主要な説明として用いられてきた。さらに、社会科学や人文科学などの学者たちは、医学、心理学、法律、戦争、警察、ビジネスなど多様な分野において、解決不可能な道徳的ジレンマの意味を理解しようとする際に、このモデルを利用してきた。
3 汚れた手問題の50年
本セクションでは、『政治的行為』の出版以来の最も重要な議論を概説する:ダーティハンドの問題」を概説し、本特集内の論文がそれらにどのような貢献をしているかを指摘する。まず、ダーティハンドという概念そのものに対する外部からの批判を検討することから始め、その後に内部的な議論、つまり、ダーティハンドという概念そのものが私たちの道徳的語彙の有効かつ不可欠な一部であることに同意しているダーティハンド理論家同士の議論に移る。
3.1 外部からの批判
ダーティハンドという概念に対する最も根強く、広く支持されている、そして潜在的に有害な批判は、それが概念的に支離滅裂であるというものである。すなわち、真の道徳的ジレンマの存在を否定する「メタ倫理的議論」と、ある行為が道徳的に正当化され(義務ですらあり)、それにもかかわらず道徳的に間違っているという主張を否定する「すべてを考慮した議論」である。脚注13これらの議論は、脱自律論的道徳論者と帰結論的道徳論者の双方にとって強力かつ説得力のあるものとみなされており、それゆえ、汚れた手のシナリオの可能性そのものを即座に否定している。脚注14このようなダーティハンドの否定に対しては、様々な形でかなりの反発があるが、特にクリストファー・ゴワンズが「残余のテーゼ」と呼ぶものを支持する理論家たちによる反発が大きい。脚注15このテーゼは、ジレンマ状況においてどのように行動すべきかについて正当化された道徳的判断を下したとしても、そのような行動には道徳的不正行為が含まれる可能性があり、そのように行動したことに対する道徳的汚染が残存する、と主張している。ダーティハンドという概念を擁護する人々の中心的な主張は、メタ倫理的な議論も万物考慮的な議論も、道徳的な選択、価値観、感情に対する単純すぎる理解(注16)に基づくものであり、また有効な倫理理論に求められるものに対する誤った見解に固執するものである、というものである。
ダーティハンドに対する一般的な批判はさらに2つあり、このような考え方を真摯に受け止めた結果、道徳理論に有害な結果をもたらすことに焦点が当てられている。
第一に、汚れた手の存在を認めることは、不道徳な行為を容認する方向へと、私たちを否応なく滑りやすい坂道へと導く。ダーティハンドの合理化をあらゆる政治的決定に適用させることで、悪人どもに自分たちのひどい行いの便利な言い訳を提供することになる。
第二に、ダーティハンド・シナリオが可能であることを認めた場合、この概念を、罪悪感、罰、後悔、説明責任(いくつか例を挙げるが)など、他の重要な規範概念群と整合させる上で、かなりの困難に直面する。
例えば、悪事を働いた者を罰するための標準的な哲学的正当化は、本物のダーティハンド・シナリオに関与した人物に適用すると問題が生じる。ダーティハンド擁護論者たちによる最近の研究は、通常の不正行為を理解するために用いられる規範概念の中で、私たちの道徳的現実のこの逆説的な側面をどのように統合するかを理解しようとするものである。以下、ダーティハンド論者の内部での議論を概説する際に、これらの問題に立ち戻る。
3.2 内部での議論
3.2.1 汚れた手の「汚れ」
ダーティハンド(汚れた手)という概念があり得るとすれば、それは不可避的な道徳的葛藤の他の形態とは異なる、特別な倫理的観点を示すものなのだろうか?「残余のテーゼ」を支持する人々は、善良な人が道徳的に危うくなることが避けられない状況がある理由について、さまざまな説明を提供している。例えば、Gowans(1994)は「避けられない道徳的不行跡」、Gardner(2007)は「正当化された道徳的不行跡」、Tessman(2014)は「避けられない道徳的失敗」のケースについて言及している。これらの見解はいずれも、ダーティハンドの立場それ自体を必ずしも支持するものではないが、その存在の前提条件を支持するものである。したがって、ダーティハンドを他の、より普通の事例である不可避的な道徳的不行跡とどのように区別できるかを説明することが重要である。クレイマーが指摘するように、「汚れた手の問題はすべて道徳的葛藤だが、すべての道徳的葛藤が汚れた手の問題ではない」(2018: 187)。では、汚れた手特有の「汚れ」を構成するものは何なのだろうか。汚れた手が「単なる悪や害を伴うものではない」という点については、文献上かなりの合意が得られている。「むしろ、人々や原則、価値観に対する裏切りや違反が含まれる」(Stocker1990: 25)。脚注17シュトッカーとデ・ヴァイゼは、ダーティハンドにおける「汚れ」は、主体が置かれた「他者(あるいは他者の組織)によって作り出された不道徳な状況」によって生じると論じている(デ・ヴァイゼ2007: 12)。ニックはこれに異を唱え、この説明はあまりに狭量であり、その代わりに、汚れた手のシナリオはつねに「中核的な道徳的価値」の侵害を伴うと主張する(Nick2021: 199)。Kramerは、「悪行が予想される道徳的葛藤」において、エージェントがどのように行動するかを選択する必要があるため、ダーティハンドが独特であるという別の説明も提示している(2018: 189)。テスマンは本特集のためのエッセイで、汚れた手をユニークなものにしているものについて考える別の方法を提示することで、この議論に貢献している。
ダーティハンド論者の間で意見が分かれるもう一つの問題は、ダーティハンドの対立に直面したとき、手を汚さないことが可能かどうかということである。本特集のインタビューの中でウォルツァーは、罪のない人々の殺害を防ぐ可能性が高い爆弾であっても拷問をしないと決めた政治家は、市民を守るという政治的責任を放棄しているが、その手は汚されていないと主張している。汚れた手が一種の道徳的原則や価値観の侵害を伴うのであれば、一度汚れた手の状況に直面すれば、どのような行動を取ろうとも「常に必然的にそのような侵害を伴う」ことになる(2019a: 938)。したがって、彼女にとっての汚れた手は対称的なものである。汚れた手の選択に直面したとき、手を清潔に保つには時すでに遅しなのである脚注19。
3.2.2 道徳的感情と汚れた手
正しいことをするために悪いことをするとき、彼らは自分の手が汚れることをどう感じるべきなのだろうか?別の言い方をすれば、汚れた手を持つ者が経験すべき適切な道徳的感情とは何だろうか?自責の念や恥は道徳的な不正行為にふさわしい感情だが、不道徳が正当化され、おそらくは道徳的に義務であったとしても、それがより小さな悪をもたらしたことを考えると、汚れた手の事例には不適切である。この感情は、自責の念や見物人の後悔とは異なり、大きな損害に対する因果的責任を認識し、「自分の人生の物語には、単に意図的に行ったことだけではなく、行ったことによって行使される権威がある」ことを認めている(2008: 69)。
しかしデ・ヴァイツェは、ウィリアムズの3つの感情的可能性は汚れた手のシナリオには当てはまらないと主張している。なぜなら、「このような状態について単なる後悔を感じることは、深刻な道徳的違反を正当に評価することに失敗する[…]一方、自責の念を感じることは、[自分たちの]行為に道徳的正当性がなかったことを誤って示唆してしまうからだ。問題なのは、単にその出来事における[自分の]因果的役割の事実ではないからである」(2004: 464)。その代わりに、デ・ヴァイツェが主張するのは、彼が「悲劇的自責」と呼ぶものであり、他者の邪悪な行為や計画によって必要とされた、大切にしてきた道徳的価値の正当な侵害に対する善良な人間の適切な反応である。悲劇的自責の経験によって、行為者は自分の行為を関係者に正当化し、自分が引き起こした損害を可能な限り修復するよう促される。
汚れた手の状況に関わる感情的労苦を理解するための異なるアプローチは、道徳的苦痛と傷害の言語を通してである。Tigard(2019)は、エージェントが道徳的苦痛を経験するのは、道徳的に行動したくてもできないときであると論じている。その結果、エージェントはフラストレーション、怒り、不安、罪悪感、後悔などさまざまな感情を感じるかもしれない。しかし重要なのは、これらの感情を経験することに葛藤を感じ、それが本当に自分に強要された選択にふさわしいかどうかを問い続けることである。この内なる混乱は道徳的苦痛をもたらし、汚れた手による行動によって引き起こされる感情的経験を正確にとらえている。Wiinikka-Lydonは異なるアプローチをとり、ダーティハンドの行為者は一種の道徳的傷害を経験していると理解できると主張する。道徳的傷害とは、道徳的あるいは職業的な義務を遂行しようとして道徳的な過ちを犯したというトラウマ的な経験の結果として生じる罪悪感、羞恥心、苦しみの経験である。その結果、「その人は道徳的な堕落を経験する。善良な人間とは何かという特定の期待に向かってうまく努力することができなくなったと感じるのである」(2018: 359)。
この特集では、リサ・テスマンとジョー・ウィニッカ=ライドンが、エージェントが自分の汚れた手についてどう感じるべきかを問題にしている。
3.2.3 政治における目的/手段問題としての汚れた手
汚れた手に関する理論化の重要な流れのひとつは、ニッコロ・マキアヴェッリの著作(1532年/2003)から引用された洞察によるもので、しばしば「政治における目的と手段の問題」と呼ばれる(Gowans1994: 228-234; Hampshire1991: 162-168)。この説明によれば、ダーティハンドは政治的領域に限定される。なぜなら、そもそもこの問題を引き起こす、私的な道徳的呵責と政治的必要性との間の避けがたい衝突がここにあるからだ。つまり、汚れた手の問題は政治的な問題なのである。このアプローチは、個人的道徳と政治的(あるいは公共的)道徳を峻別することを前提としており、前者は明確に定義された義務論な制約の中で行動することによって個人の道徳的善良さを維持することに関心を持ち、後者は不道徳で危険な世界に直面する市民の安全と幸福を確保しようとする(Hampshire1983: 121-124; Niehbur1932/2013: 231-278)。ハクスリーは、リシュリュー枢機卿の顧問という立場と自分の宗教的信条を両立させようとして失敗したジョゼフ神父の伝記の中で、「神に従って善人となることと、人間に従って善人となることはまったく別のことである」と指摘している(1941/1994: 146)。
ダーティハンドのこの目的/手段解釈は、現実の政治に携わる際に成功しようとする人々に求められるものについての特定の見解に依拠している。政治が、善良な人が私人として拒否すべき行為を必要とするものとして適切に理解されていることを考えると、道徳の制約は、国家の存続と市民の安全を確保することに二の次にされなければならない。ウォルツァーのダーティハンド概念は、政治における道徳的違反は(特に十分に機能している民主主義国家において)、正しいことをするために間違ったことをし、その後に(例えば、公の承認や償いを通じて)道徳的地位を回復しようとする、断続的な機能不全の発生であると仮定しているため、深い問題があるとして否定している。これとは対照的に、ダイナミック・モデルでは、政治の構成的な汚さに直面する政治家に必要な美徳に焦点を当て、政治家は道徳的地位を回復できるどころか、汚さに慣れなければならなくなる。
しかし、政治におけるこのマキャベリズム的な目的と手段の問題には疑問が投げかけられている。第一に、民主主義社会では、まともな社会のために、非論理的制約を真摯に受け止める政治の必要性が最も重要であると信じる強い理由がある。第二に、「汚れた手」を政治的な問題として理解することは、私生活における道徳的ジレンマが「汚れた手」の事例として正しく捉えられることを説明できない。要するに、「汚れた手」という概念は、政治の領域以外でも応用可能な道徳的語彙の重要な一部として理解される必要がある(de Wijze2007,2022)。
本特集号では、ジョルジーニ、ザイベール、フィンレイによる論考が、ダーティハンド・シナリオを政治における目的と手段のジレンマとして理解することへの賛否を提示し、この議論を続けている。
3.2.4 汚れた手と政治的美徳
ダーティハンド・シナリオが人間関係のあらゆる領域で起こりうることは同意されても、政治の領域で最も困難な形で見られることは広く認められている。この領域におけるダーティハンド・シナリオの道徳的な複雑さを考えると、政治家がその役割において効果的であることを可能にすると同時に、道徳的な善良さを保つことを可能にするような、特定の政治的美徳のセットを必要とするかどうかが重要な問題となる。Thomas Nagel(1993)は、自分の手を汚すことは、政治家にある程度の冷酷さを要求すると論じている。ウィリアム・ガルストン(William Galston)は、政治家にはある程度の「したたかさ」が必要であり、それはアリストテレス的な意味として「(一方では)気難しさ、希望的観測、無邪気さ、他方では冷淡さ、皮肉、計算高さ」の中間であると理解している(1991: 176)。アリストテレス的な徳の理解ではなく、マキャベリスト的な徳の理解を土台として、ティリリス(2016)は、政治指導者はvirtù-すなわち、政治共同体の継続的な存続と成功を保証することを可能にする一連の特性-を培う必要があると主張している。これらの美徳は、政治家が政治家として必要なことを行うと同時に、その行為の道徳的コストを見失うことなく、政治家として必要なことを行うことを可能にするものであるため、政治家としての美徳として理解されるべきである。
脚注26 さらに、スーザン・メンダスが指摘するように、独特の要求、制約、責任を伴う政治の性質を考えれば、冷酷であったり、タフであったり、美徳を持っているからといって、政治家が必ずしも「他の人々よりも道徳的に悪い」ことを意味するわけではない(2009: 51)。彼らは道徳的な違反を犯しながらも、善良な人間であり続けることができる。
本特集号のウィニッカ=ライドンは、この議論に対処するため、彼が「汚れた美徳」と呼ぶものについて考察している。
3.2. 5 民主主義の汚れた手
ダーティハンドが政治という領域で特に緊急性をもって生じることはこれまで見てきたとおりだが、残るのは、ダーティハンドが特に民主政治をどのように可能にし、また脅かすかということである。しかし、Ramsay(2000)、Shugarman(2000)、Sutherland(1995)は、ダーティハンドの行動や政策は、原理的にも実践的にも、真の民主政治とは相容れないと主張している。そのような行為は、逆説的ではあるが、そもそも道徳的に問題のある手段の使用を正当化するために用いられる、大切にしてきた民主主義の目的を最終的に損なうことになる、と彼らは主張する。したがって、民主的な政治家は自らの手を汚すことができず、その代わりに単純に不正を犯してしまうのだ。de Wijze(2018)とNick(2019b)の両氏は、この推論は間違っていると主張している。なぜなら、この推論は、ダーティハンド理論と、解決不可能な道徳的対立の発生を、開かれた審議と法の支配を通じて解決する民主主義国家の能力の両方について、欠陥のある仮定に依存しているからだ。この最後の指摘は、最近になって、ダーティハンドがいかに日常的な政治の一部であるかを探求し始めた作家たちによって、より多くの文献に取り上げられるようになった(Hall2022; Sarra2022; Tillyris2017)。
民主主義的な汚れた手に関する議論のもう一つの流れは、民主主義的な政治家が自らの汚れた手を公に清算する必要性に焦点を当てている。ベラミーは、政治から対立を完全に排除することは不可能であるため、政治的行動は必然的に自由民主主義国家の理想を下回ることになると主張する。しかし、自由民主主義のプロジェクトは道徳的に重要なものであるため、政治家は、その理想と約束が完全に果たされることはないとしても、市民がそれを支持し続けるようにする必要がある。しかし、民主的な政治家がきれいな手袋をはめると決めたとき、彼らは二次的な汚れた手の問題に直面する。トンプソンの言葉を借りれば、そのような政治家は「二重に汚れた手を持つ」ことになる(1987: 32)。
このことは、民主主義の市民が政治指導者の汚点を共有するのか、またどの程度共有するのかという茨の道を提起している。この問題については、文献上2つのスタンスがある。ひとつは、市民は政治指導者が自分たちの名において行動することを承認しているという考え方である。この見解は、David Archard(2013)とMiriam Thalos(2018)によってそれぞれ展開されている。両者とも、市民が政治行動の最終的な作成者であると理解しているが、市民が最終的に負う責任のレベルについて、これが何を意味するかについては意見が分かれている。脚注28 この見解の最も持続的な擁護はデ・ワイツェによるもので、彼は「市民は、道徳的にコストのかからない行動や政策がない状況でも、政治家が自分たちを害から守ってくれることを当然期待している」(2018: 140)ので、政治指導者の汚れた手を暗黙のうちに承諾していると理解できると主張している。しかし、デ・ヴァイツェにとって、政治指導者は、問題のダーティハンド行為を最終的に選択する者であるため、より大きな責任を負うことになる。一方、市民はその行為に加担する共犯者にすぎない。
本特集号でカービーは、この議論を検証し、政治家の汚れた手に対する民主主義市民の責任について斬新な考え方を提示している。
3.2.6 汚れた手を罰する
政治的行為:ウォルツァーは「汚れた手の問題」の中で、手を汚した人間は「確定的な犯罪を犯し、[…]確定的な刑罰を支払わなければならない」と主張している(1973: 178)。さらに、刑罰を行為者本人に委ねることはできない。その代わりに、刑罰は社会的に認知され、制限され、比例する必要がある。しかし、ダーティハンド擁護論者の間では、こうした主張の妥当性に関してかなりの意見の相違がある。最も基本的なことは、手が汚れている人の行為は、あらゆることを考慮しても、正しい行為であったのだから、手を汚した人を罰することを正当化できるものがあるだろうか、ということである。
De Wijze(2013)は、結果主義であれ、応報主義であれ、コミュニケーション主義であれ、私たちの標準的な罰の正当化は、汚れた手のシナリオの微妙で逆説的な性質に対応できないと主張している。それに対して、彼は、汚れた手を持つ行為者を罰することを正当化できる可能性のある代替的な根拠をいくつか提示している。Fausto Corvino(2015)は、de Wijzeの研究をさらに発展させ、集団行動の失敗の結果として起こるより複雑なダーティハンド事例において、ダーティハンドを持つ行為者を罰することを正当化する方法を理解しようとしている。
しかし、汚い者を罰することが正当化できるかどうかについては、強い意見の相違がある。レヴィ(2007)は、汚れた手を持つ者を罰することは逆効果であり、かつ不道徳であると主張する。彼は、汚れた手を持つ政治家は、その行為が道徳に反することを認めているにもかかわらず、非難に値しないとする。レヴィは、非難に値すること、そしてそれによって罰が正当化されることは、必然的にその行為者が道徳的に行動することを真に選択したことを前提とする、と主張する。本物の汚れた手のシナリオではそうではないので、行為者は処罰されるべきではない。さらにマイゼルは、「私たち自身が(行為者に)してほしかったことのために(行為者を)罰することは、もはや皮肉でもパラドックスでもなく、単に間違っている」(2008: 173)と主張する。
LevyとMeiselsに大筋で同意するCristina Roadevinは、処罰の代わりに、エージェントが特定の形態の赦し、彼女が「無過失の赦し」と呼ぶものを受け取るべきだと提案している(2019: 123)。無過失の赦しは、「誤った行為に対する私たちの道徳的不承認と同時に、これらの行為者が何か良いことをした、おそらく賞賛や称賛に値することをしたという私たちの認識」の両方を表現している(2019: 124)。一方、ピーター・ディゲザーは、政治家にとって不道徳な行為を政治的に必要なものとして描くことがあまりにも簡単で便利になってしまう危険性が大きいため、赦しは汚れた手の状況に対する適切な対応ではないと主張している。その代わりに彼は、ダーティハンドの場合には許すよりも、安息の角度、つまり「政府の行為に対する一種の疑念と距離を置くこと」(1998: 714)がより適切であると主張している。
本特集では、レオ・ザイベールが罰と汚れた手の関係について考察する。
3.2.7 汚れた手、政治的暴力、戦争
ダーティハンド・シナリオの典型的な例のいくつかは、政治的暴力や戦争と密接に結びついている。クリストファー・フィンレイ(Christopher Finlay)は本特集号で、ダーティハンドは「政治的行為に特有の規範的問題を頻繁に発生させる特定の経験的現象に関与する必要性」から生じると論じている。汚れた手の「汚れ」は、暴力が確保しようとする崇高で価値ある目的を損なう、暴力そのものの悪から生じる。正当な政治的・道徳的システムを守るために暴力が使われる場合でさえ、暴力の悪は、達成される善によって完全に帳消しにされることはない。
戦争の問題に目を向けると、この文脈でダーティハンド・シナリオが可能かどうかについては意見が分かれている。標準的な見解は、政治指導者と兵士が正義の戦争のルール(ad Bellumとin Belloの原則)に従えば、道徳的な過ちを犯すことはなく、したがってダーティハンドという概念は当てはまらないというものである。しかし、マイケル・ノイ(Michael Neu)(2013)は、戦争を正義か不正義かという二元論で説明することは、このような紛争に内在する悲劇的な側面を反映していないと主張する。正当化された戦争を汚れた手の事例として理解することで、なぜこのような規模の暴力が道徳的な余地を残すことなく行われることがないのかについて、ニュアンスの異なる理解が得られる。本特集において、ウォルツァーはノイの立場を否定するが、国家が至上緊急事態を構成する脅威に直面した場合には、ダーティハンドの可能性を認める。そのような状況では、非戦闘員を保護するイン・ベロの原則に違反することが正当化され、その状況はダーティハンド問題として記述されうる、と彼は主張する。
ダーティハンド理論が恐ろしい暴力の状況に適用された例は他にもある。第一に、人命救助のために拷問が道徳的に正当化されるべきかどうかという、多くの悩ましい問題がある。これは通常、政治におけるダーティハンド・シナリオの典型例としてウォルツァーが紹介した(中略)有名な「ティッキング・ボム・シナリオ」を参照して議論される。たとえ多くの命を救うためであっても、ダーティハンド・シナリオとして拷問を正当化することは、道徳の腐敗と堕落に向かう滑りやすい坂道を下っていくことになる。それは社会が拷問を制度化することを必要とし、それによって法制度や法執行機関を腐敗させ、粗悪化させることになる。

しかし、このような強力な主張にもかかわらず、政治指導者は、恣意的な暴力、テロリズム、戦争、大量虐殺、絶滅といった大きな害悪から市民を守るために必要なことを行う義務がある。多くのダーティハンド論者は、そうすることで大量殺人を防ぐことができるのに、拷問を拒否するのは直感に反しており、絶対主義的な原則に過度に固執していると主張する。ダーティハンド正当化論者は、拷問を真っ向から拒否することと、効用や費用/便益の計算に基づく安易な結果論的な拷問の容認との間の、道徳的な中間領域を占めていると主張する。
第二に、非対称紛争における標的型殺人の使用を特徴づけるのに、ダーティハンド・シナリオが最適かどうかについては、多くの意見が分かれている。De Wijze(2009)は、正当化された標的殺害は、単に合法的な戦争の一形態ではなく、ダーティハンドのシナリオであると主張している。これとは対照的に、ジョーンズとパリッシュ(2016)はこの正当化アプローチには深い欠陥があると見ている。標的殺害政策が正当化されうるのであれば、それは正義の戦争理論の厳格な基準か、あるいは警察が一般市民に対して行う行為に適用される法執行の倫理の文脈のどちらかでなければならないと主張している。マイゼルスは本特集のエッセイで、標的を絞った殺人が正当化されるためにはダーティハンド・レンズが必要だという考え方そのものを否定している。彼女は、ある特定の状況下では、標的を絞った殺人は敵に対する正当かつ道徳的に正当化された軍事的対応になりうると主張する。
3.2.8 汚れた手と不正への抵抗
これまで見てきたように、政治的紛争、暴力、戦争の文脈におけるダーティハンドに関する文献の多くは、政治的指導的役割を担う人々が直面する問題に集中している。しかし、ダーティハンド理論家がこの焦点に疑問を投げかけ、ダーティハンドが政治的権力者でない人々にも必要な抵抗や不服従の手段となりうるかどうかを問うた例もある。この汚れた手という考え方は、サルトル(1948/1989)の同名の戯曲にまで遡ることができる。この戯曲では、若いレジスタンス闘士ユゴーが、階級の裏切り者と見なした政治指導者ヘデレールを暗殺するという任務に取り組む。同じようなテーマは、アルベール・カミュ(1949/2013)の戯曲『正義』にも見られる。この作品では、革命家グループが大公暗殺を計画・実行する。

文学においてこの種のシナリオは比較的目立つにもかかわらず、ダーティハンド理論家からはこれまで限られた注目しか浴びてこなかった。パトリック・テイラー・スミスは、上記の戯曲で問題視されている革命のケースを検証している。彼は、あらゆる革命は本質的にリスキーであると論じている。なぜなら、「革命は、しばしば現実的な価値を持つ関係を、全体としてより優れた新しいシステムで置き換えることができるという投機的な希望をもって破壊する」からである(2018: 204)。そして、革命的ヴィジョンを実現するために、革命家は一方的に権力を掌握し、その過程で道徳的に疑わしい強制的手段を用いなければならない。スミスにとって、これこそが革命家の汚れた手を構成する明確な政治的ジレンマなのである。
では、不正や抑圧に直面する人々にとって、それはどのような意味を持つのだろうか。デ・ヴァイゼは、「善良で道徳的な人が不正と闘う際に尊重すべき規範的制約を明確にする」ことを試みている(2012: 151)。彼は、「通常の道徳的境界を超えた限界」(2012: 169)にとどまりながら、どのように不正義に抵抗できるかを理解する必要があると主張する。彼にとってこの限界は、比例性と合理的成功の原則、そして行為者の行動動機によって規定される。しかし、デ・ワイツェがこの分析の目的上、(国家、組織、運動のいずれであれ)指導的立場にある者に明確に焦点を当てていることは注目に値する。ティリリスは本特集で、これでは不十分であり、抑圧的な体制やシステムに対する日々の抵抗に従事する人々に対して、ダーティハンドという概念の適用可能性を探求し始める必要があると指摘している。
3.3 汚れた手をプロの実践に生かす
ダーティハンド(汚れた手)の問題に関する研究の大半は理論的な問題に関するものだが、この概念は、職務を遂行する際に直面する困難な道徳的ジレンマを特徴づけ、直感的に捉えるために、さまざまな分野の実務家によって応用されてきた。例えば、レスリー・グリフィン(1995)は、弁護士は依頼者の利益を守る義務がある一方で、法の完全性を守る義務もあると指摘している。この矛盾が生じたとき、弁護士は法的汚職という問題に直面する。Iris Domselaar(2017)も同様の見解を支持し、悲劇的な法的選択もまた、司法裁決を正しく理解する上で欠くことのできない付随物であると論じている。そして裁判官は、弁護士と同様に、なされるべき悲劇的な選択を最もよく反映する法的な汚れた手のシナリオに直面することができる。
医療専門職においても、道徳的葛藤とそれが医療従事者に及ぼす悪質な影響について、同様の関心が持たれてきた。Daniel Tigard(2019)は「道徳的苦痛」の問題を強調している。医療従事者が道徳的に価値のある行動指針を追求することを妨げられたと感じるときに生じる一種の心理的不平衡である。医療従事者は、自分が行った行為に対して深い不満、怒り、不安を感じながらも、その行為が道徳的に正当で必要であったと考えることがある。ここでは、善良な人が自然に抱く間違った行為に対する感情-罪悪感、羞恥心、後悔として表現される-が、道徳的に間違った行為はなかったという矛盾した評価と共存している。Deborah Zion(2004)は、医療従事者が直面する「汚れた手」問題の関連した側面を探求している。彼女は、専門家としての医療倫理から生じる義務と、彼らが活動する広範な社会システムの不正義との間の困難な衝突を強調している。医師にとって、参加しない(つまり治療を提供しない)か、非倫理的とみなされる治療を提供するかのどちらかを選択しなければならない状況が生じる。たとえ医師がより小さな悪を選んだとしても、それは彼らの道徳的善良さを損ない、悪の加害者にも被害者にもなってしまう。
法執行官もまた悲劇的な道徳的選択に直面しており、そのような状況を適切に特徴づけるために、やはりダーティハンドという概念が呼び起こされてきた。Kleinig(2002)、Klockars(1980)、Miller(2007)、van Halderen and Kolthoff(2016)は、警察が個人の権利を侵害するような行動をとるが、地域社会の安全や人命救助につながる情報を得るためといった崇高な目的のために行動する状況を検証している。ここでの焦点は、犯罪者が行う悪事を回避または最小限に抑えようとするが、自分自身が不道徳な行動をとらずにこれを行うことはできない法執行官が直面する道徳的ジレンマである。例えば、人質の解放やその他の称賛に値する目的を達成するための情報を得るために、凶悪犯罪者の権利を侵害しなければならない状況に直面することがある。
企業活動の領域はまた、権力を行使する者に困難な道徳的ジレンマを強いる。KapteinとWempe(2002: 159-195)は、事業を運営することは、時に手を汚すことを必要とすると論じている。事業の利害関係者の権利や利益と、事業体そのものの継続性との間に、避けることのできない、解決不可能な対立が生じるからだ。彼らが念頭に置いているのは、ビジネスが「収益を上げるために従業員の解雇を検討しなければならない場合」や、「利益を犠牲にしてまで法律を超える環境投資を行うことが正当化されるかどうかを判断しなければならない場合」である(2002: 168)。このような場合、ビジネス・リーダーは2つの悪のうち小さい方を選択せざるを得なくなり、そのために手を汚すことになる、と彼らは主張する。
最後に、ダーティハンド(汚れた手)という概念は、政府と非政府組織の双方の行動や政策を検証し、説明し、正当化するために使われてきた。ディクソン(Dixon)(2002)は、北アイルランドの血なまぐさい紛争と、和平交渉を促進するために英国政府がいかに汚れた手を使う必要があったかを探っている。Garrett(1996)とSanders and Grint(2019)は、第二次世界大戦中のナチスの暴虐に対する戦いで、地元のレジスタンス活動家と連合軍が直面した汚れた手のジレンマを検証することで、リーダーシップ倫理の教訓を提供している。Lenze and Bakker(2014)は、対テロ戦争におけるオバマの標的殺害の使用は、ダーティハンドの事例であったと主張し、Grint(2016)は、ダーティハンドのレンズのプリズムを通して、イギリスにおける困難な政治的リーダーシップの21日間を探求している。より最近では、ルーイット(2022)がCOVID-19パンデミック時の英国の政策決定を分析するためにダーティハンドの枠組みを適用している。例えば、ルーベンスタイン(2015: 87-114)は、ザイールのルワンダ難民キャンプを事例に、NGOはしばしば彼女が「飛び散った手」と呼ぶものに取り組まなければならないと論じている。
3.4 さらなる研究の道
この50年間に蓄積されたダーティハンド(汚れた手)という概念に関する多くの研究成果を踏まえれば、この分野における今後の研究はどのような方向に向かうのだろうか。今後の研究の方向性は大きく2つに分けられる。ひとつは、ダーティハンドという概念そのものと、倫理理論の理解におけるその位置づけに関する理論的な追加研究である。ダーティハンドという概念は、道徳理論の本質と目的に関する基本的な前提に関するメタ倫理学的な議論に食い込んでいる。これには、汚れた手の可能性、私たちの道徳的現実の理解における感情の役割、そして倫理的なものの範囲についての意見の相違が含まれる。ダーティハンドの概念は、ここ数百年の標準的な一元論的倫理理論の優位性に異議を唱えようとする人々に、さらなる論拠を提供する。さらに、ダーティハンドという概念は、義務論な道徳理論や結果論的な道徳理論に代わるものとして、徳倫理学の有効性を探求する最近の議論を強化するものである。
第二に、さまざまな差し迫った重要な問題に対するダーティハンド理論の実践的な適用と影響は、今後も加速していくだろう。急速な気候変動の問題に対処しようとする私たちが直面している道徳的ジレンマを考えてみよう。このまま何もしなければ、気温の上昇、異常気象、そして干ばつや洪水、大移動、枯渇する資源をめぐる戦争によってもたらされる恐ろしい社会政治的結果によって、私たちは潜在的な大惨事に直面することになる。しかし、気候変動に取り組むには、強制的な手段を用いることも含めた選択が必要であり、何十億もの人々の現在の生活の質を低下させるかもしれない。間違いなく、社会経済的に最も不利な立場にある国や国民が不釣り合いに苦しむことになり、現在の政治的・社会的現実を考えれば、この苦しみを大幅に軽減することは不可能かもしれない。ここで、世界中の指導者たちは恐ろしい道徳的ジレンマと汚れた手の選択に直面することになる。このような将来の政策変更に道徳が一役買う必要があると考えるならば、ダーティハンドの枠組みは、政治家が直面するであろう道徳的問題を考慮した上で判断するための、ニュアンスに富んだ現実的な道徳的枠組みを提供するだろう。
ダーティハンド(汚れた手)の決定が確実に生じるもうひとつの分野は、人工知能(AI)の利用の増加と高度化である。このような進歩は、例えば、遺伝学、新兵器システム、機械がますます人間に取って代わるようになる産業基盤の変革における将来技術の使用において、深い難解な対立を生む可能性がある。AIシステムによる意思決定は、完全に自律的で人間の意思決定から独立したものであるべきか?もしそうなら、汚れた手の現実を反映した倫理的な選択をするようにプログラムされるべきなのだろうか?また、ダーティハンド(そして一般的な倫理的思考)の概念の中心には道徳的感情があることを考えると、AIシステムは難解な道徳的葛藤に直面しても、正しい道徳的判断を下すことができるのだろうか。脚注36 自律システムに感情に相当するものをコード化する研究は行われているが(Arkin et al.その結果、ダーティハンド問題からの洞察は、人間の監視なしに動作する自律型AIシステムに対して、当然のことながら非常に危惧を抱かせることになるのだろうか。
ダーティハンド理論が適切と思われるもうひとつのトピックは、過渡的正義のプロセスと賠償の提供に関するものである(ニック2022)。深く不公正な紛争社会から、まともで公正な社会への進展は、決して容易なものでも、道徳的にコストのかからないプロセスでもない。例えば、アパルトヘイト時代の終焉後に南アフリカで設置されたような真実和解委員会の利用は、多くの重大犯罪が訴追されないという結果をもたらした。これにより、長く血なまぐさい紛争の後、和解と平和のプロセスが促進されたが、国家が支援した人種的暴力の被害者は正義を受けられないまま残された。繰り返しになるが、ダーティハンド分析は、この道徳的に厄介な紛争解決のプロセスと、そこから生じる悲劇的な対立を理解するのに役立つだろう。
最後に、汚れた手の問題は、倫理の本質、道徳的葛藤の存在、道徳的感情の関連性、人間の主体性などに関する西洋の理論的前提の中で探求されてきた。他の道徳的伝統の中に、同じような懸念が存在するかどうかを調べることは、興味深く重要なプロジェクトである。もしあるとすれば、それらの道徳的伝統はそれらにどのように対処しているのか、そしてそこから私たちは何を学ぶことができるのか。
3.5 本特集号の記事
本特集号は、マイケル・ウォルツァーが1973年に発表した汚れた手に関する代表的な論文を再考する短い論文から始まる。続いて、スティーブン・デ・ワイツェによるウォルツァーへのインタビューが掲載され、彼の論文で提起されたいくつかの問題と、汚れた手に関するウォルツァーの考えが過去50年間に与えた影響について探っている。
ジョヴァンニ・ジョルジーニによる2番目の論文は、ウォルツァーの当初の定式から逸脱した、マキャベリ的なダーティハンドについての代替的な説明を示している。ジョルジーニは、汚れた手は異なる道徳的配慮の対立として理解されるべきではなく、むしろ道徳と政治という2つの異なる行動領域の相容れない要求の衝突として理解されるべきであると主張する。
レオ・ザイベールによる第3の論文もまた、ウォルツァーとは別のダーティハンド論を提示しているが、ジョルジーニとは対極に位置している。ザイベールは、ダーティハンドを罰に関する彼のこれまでの思想のいくつかと結びつけることで、ダーティハンド論は政治的な領域に焦点を当てすぎており、ダーティハンドという概念が明らかに道徳的な問題であることを理解することを犠牲にしていると主張する。
リサ・テスマンのエッセイは、ダーティハンドの状況の核心にある道徳的葛藤をどのように概念化すべきかについて、革新的な説明をしている。彼女は、ダーティハンドは、考えられないような悲劇的な損失をもたらす、エージェント相対的理由とエージェント中立的理由の間の理解しがたい選択を伴うと主張する。
ジョセフ・ウィニッカ=ライドンの論文は、手が汚れるシナリオで正しい決断を下すためには、どのような人格が必要なのかを探求している。彼が「汚れた美徳」と呼ぶ特殊な美徳が必要であり、その重要な部分は、自分の手を汚したときに犯した道徳的過ちを認めるための痛みや苦しみの経験であると提唱している。
最初の5本の記事がダーティハンドという概念の理論的側面に焦点を当てているのに対し、最後の4本の記事は、民主主義、暴力、戦争、抵抗というテーマへのダーティハンドの適用を検証している。
ニコラス・カービーは、民主的な役職者、制度、市民の関係を探っている。彼の目的は、汚れた手による行為に対する汚れと責任が、どの程度まで各人に帰属するかを検証することである。カービーは、市民を代表するために選ばれた者が汚れた手を取る一方で、民主主義の承認のメカニズムは市民の手を汚さないように機能していると主張する。
クリストファー・フィンレイの論文は、マックス・ウェーバーからの洞察を用いて、効果的な政治行動のために必要な手段としての暴力の使用に焦点を当てている。主体がその手を汚す理由は他にもあるが、暴力を用いる必要性が、この概念が政治の領域で特に顕著であり、差し迫ったものである理由を説明していると彼は主張する。それは、国家が暴力の合法的行使を独占しているからというだけでなく、国家の道徳と法のシステムそのものを守るという名目で、しばしば暴力が超道徳的に正当化されるからだ。
Tamar Meiselsのエッセイは、戦争という特殊な文脈における「汚れた手」の問題を考察し、標的を絞った殺害や無人爆撃機の使用は「汚れた手」の例ではないと論じている。このような手段が正義の戦争の原則に沿って使用される場合、そこには不正行為は存在せず、従って、このような行為が汚れた手の事例であるという話は正しくない、と彼女は主張する。
最後に、デメトリス・ティリスは、ダーティハンド理論は権力者の行動に焦点を当てすぎ、無力な人々、つまり日常的な抵抗行為に従事する人々が直面するダーティハンドな状況を探求することを犠牲にしてきた、と彼のエッセイで論じている。ダーティハンドの行動は、不正や抑圧と闘う弱者の重要な武器になりうると彼は主張する。
本特集号がマイケル・ウォルツァーのエッセイ発表50周年を記念するものとなるよう、時間と労力を割いてくれたTheJournal of Ethicsの編集者、サポートスタッフ、特にウィム・ドゥビンク、そして査読者の方々に感謝述べる。
備考
- 例えば、ウォルツァーが物議を醸す「ティッキング・ボム」シナリオを用いたのは、1954年から1962年にかけてのアルジェリア戦争で政治家や将軍が直面した道徳的困難を理解したためだ。本特集のインタビューでウォルツァーが明らかにしているように、彼はブラントやヘアのような結果論的道徳論者が考える拷問の(非)許容性に悩まされていた。この種の問題について書いてきた哲学者たちは、絶対主義的な立場からか、あるいはある種の費用/便益分析からか、実に物事を簡単に考えすぎていると思った。そこで私は、善良な人、つまり悪い目的のためにフランス人と戦っているかもしれないが、それでも拷問は間違っていると考える人が、テロの可能性というジレンマに直面したときの実際の困難さを表現しようとした。
- 参照(Nagel1972)。本特集のインタビューの中で、ウォルツァーは、彼の「政治的行為」論が、状況によっては結果論的義務と脱本質論的義務が対立する場合に正しいことをするのは不可能かもしれないというネーゲルの考えを推し進めたものであり、『SELF』の分析哲学者の中でネーゲルがこの道徳的パラドックスについて考えることに最も意欲的であったと述べている。
- ウォルツァーは、アストリッド・フォン・ブセキストとの対話の中で、彼の論文が「哲学的支離滅裂の例として哲学科の1年生で課される」こともあったと指摘している(Walzer and von Busekist2020: 77)。
- ウォルツァーはまた、自分は倫理の基礎について書こうとしたことはないと指摘している。彼の『政治的行為:The Problem with Dirty Hands』は、この方法論の一例だ。ウォルツァーは、彼が明白な政治的問題だと考えるものに焦点を当て、このパラドックスを脱ontologyや帰結主義の高邁な理論を喚起することで解決しようとすることに反対している。フォン・ブセキストとの対話の中で、彼は自身のアプローチを説明するために次のように語っている。その家には基礎があると仮定するが、私はそこに降りたことはない。私は居住空間や部屋の形状を描写し、より良い家具の配置方法を提案しようとしている。
- さらに、ウォルツァーへのインタビューでは、手が汚れているという話題がいくつか出てきた(Walzer2003; Walzer and von Busekist2020)。
- 本特集に掲載されたウォルツァーへのインタビューの中で、彼は「政治共同体に対する存亡の危機を伴うような、正真正銘の至高の緊急事態においてのみ、このような戦争ルールの重大な違反を正当化することができる、と言いたかったのだが、それは適切な表現ではない」と説明している。デ・ヴァイツェがさらに質問すると、「このことは、民間人や平時の場合には、戦争の場合よりも閾値が低いと考えていることを示唆している」とヴァルツァーは答える:しかし、問題は同じようなものだ。
- 学問の一端としては、Baron(1986)、Flanagan(1986)、Jollimore(2006)、Slote(1983)を参照のこと。また、ダーティハンドに対するウォルツァーの見解を批判し、立派な不道徳という概念をティッキングボム問題に適用することを支持するCurzer(2006)も参照のこと。
- ここで検討されている問題は、不道徳であることは一般的に賞賛に値するというニーチェのニヒリスティックな見解(Carus1899; Leiter1997)でもなければ、不道徳な行為のある側面を賞賛することでもない。
- Cairns(2016)およびHeadlam and Pearson(2011)を参照。
- マタイ27:24参照。ピラトは、全く勝つことができず、むしろ騒動が起こっているのを見ると、水を取り、大勢の前で手を洗って言った、『私はこの正しい人の血について無罪である。あなたはそれを見ていなさい』。
- Hampshire(1983,1991,2000)やWilliams(1981)を参照。マキャベリ(1532/2003)以来、この立場について影響力のある他の説明は、ホリス(1982)、トンプソン(1987)、ウェーバー(1919/2010)である。
- 現代の言説では、キリスト教の価値観は、次のような絶対的な非論理的道徳的主張であると考えられている:拷問をしてはならない」
- これはストッカーの定式化である(1990: 10)。
- 汚れた手のシナリオの一貫性を否定する論文については、Ahlberg(2016)、Aronovitch(2020)、Coady(2009)、Nielsen(2007)、Schmitt(2019)、Sneddon(2019)を参照のこと。
- 残余のテーゼ」の最も著名な擁護者は、Gardner(2007)、Gowans(1994)、Hampshire(1983)、Nussbaum(1986)、Tessman(2014)である。残余のテーゼ」を支持するダーティハンド問題に関する具体的な論文については、de Wijze(2022)、Eggert(2023)、Stocker(1990)を参照のこと。ダーティハンドの可能性を支持するその他の論文については、Shugarman and Rynard(2000)とKis(2008)による編集コレクションの第1部を参照のこと。
- 感情の問題については、de Wijze(2022)とStocker(1990)を参照。
- これについての詳細な議論はニック(2021)を参照のこと。
- この立場は、彼の初期の著作(1973: 161;165; 168)にも反映されている。
- この立場は、例えばde Wijze(2007: 4)やHollis(1982: 394, 397)もとっている。
- 自責の念がこのような道徳的葛藤に対する適切な反応であるという主張については、Baron(1988)を参照のこと。
- 例えば、バニョーリ(2000)は、ウィリアムズの「代理人-後悔」という概念を修正し、このような道徳的葛藤に対する適切な感情反応として擁護している。
- また、フィリップスとプライス(1967)も、彼らが「否認なき反省」と呼ぶものを主張している。
- 感情と汚れた手に関するさらなる議論については、Benziman(2022)、Dovi(2005)、Gaita(1991)、Tillyris(2019)を参照のこと。
- この文脈における道徳的傷害の概念については、Garren(2022)やMiller(2022)を参照されたい。
- 政治的現実主義者はさらに一歩進んで、道徳と政治は相反するものだと主張する。政治においてどのように行動すべきかを決定する際に、道徳的な懸念にこだわる必要はないからだ。倫理的配慮は冗長である。現実主義政治に必要なのは、慎重さ、コスト、利益に基づく計算である。Korab-Karpowicz(2018夏号)参照。
- 政治家として成功するために必要な徳目はさまざまであり、必要な道徳的性格が存在するという考え方は否定されてきた。エリザベス・ウォルガストは、「民主的な政治体制に関連する政治的美徳やそのセットが本当に存在するのであれば、それは善良な市民や善良な人間の美徳を構成するものと同じである」という見解を擁護している。つまり、特化した政治的美徳は存在しないということだ」(1991: 288)。
- 自分の汚れた手を公に開示することを支持する議論については、Sutherland(1995)やKis(2008)を参照のこと。
- Gowans(1994: 232)およびThompson(1987: 11)を参照。
- 民主政治の文脈における汚れた手の問題については、Keohane(2014)、Tholen(2019)、Waldron(2018)を参照のこと。
- 拷問が正当化されるかどうかについては、かなりの文献がある。この議論の一端については、Brecher(2007)、Bufacchi and Arrigo(2006)、Curzer(2006)、de Wijze(2006)、Finlay(2011)、Ignatieff(2004)、Meisels(2008)、Paeth(2008)、Shue(1978)、Yemini(2014)を参照のこと。
- Luban(2007)を参照。
- Shue(2006)を参照。
- この見解は、Lenze and Bakker(2014)でも支持されている。
- 裁判官の汚れた手については、Tigard(2015)を参照のこと。
- Miller(2019)を参照。さらに、Nieuwenburg(2014)は、誘拐された子どもを見つけるために、警察が誘拐の犯人を拷問すると脅したドイツでの有名な事件を探求している。
- ドライバーレスカーが、3人の歩行者の死亡を避けるためにハンドルを切らなければならないが、そうすると同乗者が死亡してしまうという状況に直面した場合を考えてみよう。この状況で道徳的に正しい行動は何か?
- この懸念は、ドローンの使用に関してすでに提起されている。Dyndalら(2017)、Jones and Parrish(2016)を参照。
- この種のプロジェクトがどのようなものかについては、儒教的美徳政治学の観点から汚れた手問題への一つの対応について興味深い洞察を提供しているKim(2016)を参照されたい。
