コンテンツ
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328710000352
Josh Eastin a,1、Reiner Grundmann b,*、Aseem Prakash c,2
a 政治学部、101 Gowen Hall, Box 353530, University of Washington, Seattle, WA 98115-3530, USA
b 社会学・公共政策、アストン大学、言語・社会科学部、アストン・トライアングル、バーミンガムB4 7ET, UK
c 政治学部、39 Gowen Hall, Box 353530, University of Washington, Seattle, WA 98195-3530, USA
2010年3月12日オンライン公開
要約
本稿では、地球温暖化をめぐる現在の議論を、1970年代の「成長の限界(Limits to Growth:LtG)」言説と比較する。特に、この2つの事例の類似点と相違点に関心があり、そのため政策的課題と引き出すべき教訓を比較する。
2つの議論は重要な論点において異なるが、公共政策に対する技術主義的な志向と、同様の落とし穴に陥りやすいという点では共通している。どちらの議論でも、将来の大災害に関する憂慮すべきシナリオが重要な役割を果たしている。
われわれは、気候変動政策の言説が、排出削減目標に過度に重点を置いているのとは対照的に、気候変動の社会的、経済的、政治的側面にもっと焦点を当てる必要があることを提案する。また、温暖化緩和技術を供給する市場メカニズムへの過度の信頼は問題であると主張する。この点で、排出目標とタイムテーブルの政治的意味合いについて現実を確認し、政策課題を前進させる方法を提案する。
1. はじめに
Futures誌の最新号で、Nordlundは、これまでのところ未来派の研究はIPCCの研究と評価にわずかな影響しか与えていないことを示している[1]。我々は、ノルドルンドと同様、未来学者も「……我々の共通の未来を扱う進行中のプロジェクト」に積極的に参加すべきだと信じているからである。[1]. この呼びかけに取り組むにあたり、私たちは、先行する未来学者であるローマクラブの研究と、気候変動問題に取り組む上での重要な課題と機会を特定するための「成長の限界」(以下、LtG)に関する彼らの代表的な研究を活用する[2]。
現在の経済危機は、経済問題が環境政策の関心を支配してしまうのではないかという懸念を抱かせている。オバマ政権は重要な行政人事を行い、環境コミュニティでは好意的に受け止められているが、景気刺激策やその他の政策は、差し迫った環境問題への対応の緊急性を(まだ)十分に反映していない。ここ10年ほどの間に大きな盛り上がりを見せてきた地球温暖化防止への取り組みが、現在の経済危機のために脇に追いやられてしまうのではないかという懸念がある。地球温暖化は、(2009年のコペンハーゲン・サミットの前と最中に明らかになったように)象徴的な政策として大きな注目を集めるかもしれないが、化石燃料への依存を大幅に減らすために必要な構造改革に必要な政策的焦点は当てられない。本稿では、地球温暖化を緩和するための新たな課題を明らかにする。その際、1970年代のLtG議論から得た政策的教訓を活用する。これらの議論を集中的に比較することで、両者が政策決定に対する技術主義的アプローチを共有する傾向にあることに注目する。したがって、気候変動問題の規模とその複雑な政治性を考えれば、気候変動政策が排出削減目標に過度に重点を置くのとは対照的に、社会的、経済的、政治的側面により緊密に焦点を当てることが不可欠である。
どちらのケースも重要な類似点を示しているが、重要な相違点もある。LtGと気候変動に関する言説はともに、地球を、いわば宇宙飛行士の視点から観察し、管理し、制御することができるシステムとして見ているという点で、経営的な展望を共有している[3]。どちらのケースでも、数値モデリングが重要視され、物理的変数が重視され、(技術的介入ではなく)社会的介入が相対的に軽視されていることがわかる。そして、どちらの場合も、自称する意図に反して、モデル結果が多かれ少なかれ正確な未来予測であるという一般的な認識をもたらす、やや憂慮主義的なレトリックが見受けられる。
この2つの議論は、重要な違いも示している。LtG討論会の場合、政策提言の制度化はほとんどなかった。この言説は、比較的少数の学者やビジネスマンの活動に限定され、大規模なメディアの反響を呼んだ。逆に、気候変動に関する言説は、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)や気候変動に関する政府間パネル(IPCC)を通じて、真にグローバルな制度化を生み出した。このことは、気候変動に関する言説がすぐには廃れないことを示唆している。LtGが学界のニッチから生まれた。「小さな科学」から生まれたのに対し、気候変動は「大きな科学」によって推進されている。それに比べ、ローマクラブの活動に資金を提供したフォルクスワーゲン財団は、1970年に100万ドイツマルク弱を一度に支払っただけだった。[4]。
両者の事例が重なり合い、真に巨大な課題が見えてくるのは、長期的な環境目標と短期的な経済論理の両立という問題である。LtGの言説では、経済成長は環境保護や資源保全に不都合であると考えられていたため、ゼロ成長案を提唱した。ハーディンの救命艇テーゼのような類似の概念は、差し迫った資源不足の危険性を強調しようとした。[5]。ハーディンや他のネオ・マルサス派が発展途上国を重要な課題と見なしたのに対し、LtGコミュニティはより広範な成長パラダイムを問題視していた。1970年代から1980年代半ばまで、こうした考え方が環境保護と経済成長をめぐる支配的な言説を構成していた。
しかし、1980年代後半から、持続可能な開発(および生態学的近代化)という概念が、LtGに代わって主要なパラダイムとなり始めた。その支持者は、経済とエコロジーは必ずしも対立するものではなく、経済成長は環境保護や資源保全と両立すると主張している。なぜこのような楽観的なシナリオが生まれたのだろうか?おそらく、LtGモデルで示された欠乏は、市場主導のイノベーションによって、少なくとも短期的には緩和されたのだろう。世界は、LtGの報告書が予測したような形で資源が枯渇することはないと(おそらく誤って)認識した(実際、MITの研究の著者は、悲惨な予測は、適切な時期にそれに対して行動することによって、まさに回避することができると指摘していた) [2, p. 24]。しかし、”従来どおりの成長”を支持する人々の歓声 [6]にかかわらず、資源不足が一時的に緩和されたとしても、基本的な成長アルゴリズムは変化していない。
1980年代の小型車は、1990年代のSUVに取って代わられた。気候変動においても、同じようなことが起こるのだろうか?それはなぜか、それともなぜなのか。本稿では、地球温暖化の緩和には生産と消費のプロセスを根本的に変える必要があり、市場の力だけに頼ってブレイクスルーイノベーションを生み出すことはできないと主張する。問題の複雑さと化石燃料への依存度の高さから、必要な技術革新は主に市場に頼るのではなく、新世代技術への大規模かつ持続的な公共投資が必要である。LtGの政策的帰結の研究は、この点で有益である。
本稿の目的は、このような”邪悪な問題”の具体的な政策的意味合いについて、イノベーションと技術[7,8]によってもたらされる機会と限界を考慮しながら、読者に考えてもらうことである。そうすることで、本稿が気候変動政策の展望と優先事項のより良い理解に貢献することを期待している。
2. 1970年代の「限界」論争
イタリアの実業家アウレリオ・ペッチェイとスコットランドの科学者アレクサンダー・キングによって設立された世界的な非政府シンクタンクであるローマクラブは、1968年に『成長の限界』を依頼した。1970年にドイツのフォルクスワーゲン財団から資金提供を受け、1972年に発表された[9]。同クラブの目的は、さまざまな分野から第一線の専門家を集め、相互依存の世界において人類が直面する大きな課題、特に資源と環境に関する課題について考えることにあった。ウェブサイトには次のように記されている:
「政治、経済、科学の各分野におけるこの出版物の国際的な影響は、『ビッグバン』と表現するのが最もふさわしい。一夜にして、ローマクラブは、資源が明らかに有限である世界において、物質消費が無制限かつ無制限に増加することの矛盾を実証し、この問題を世界的な議題のトップに押し上げた」 [9]。
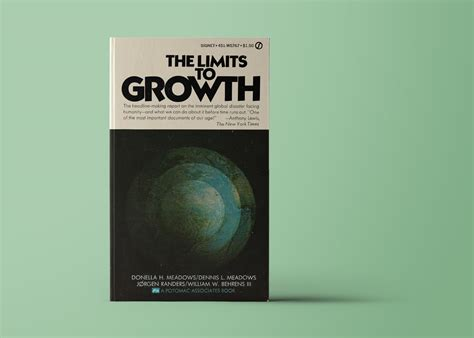
LtGの報告書は、その方向性において高度に技術的であった。人間の開発能力の上限を予測するために、システム・ダイナミクス・アプローチを採用した。人口増加、農業生産、再生不能資源の枯渇、工業生産高、汚染発生という5つの要因の相互作用を検証した。これらを総合すると、複雑なフィードバック・ループの網目、すなわち「悪循環と好循環」が形成され、その相互作用の総体が「世界システム」を構成していた。このモデルの中で、人間の経済活動は、システムを環境崩壊に向かわせる外生的要因、すなわち生態学的な猿回しとして機能した。LtG報告書の中で最も重要な記述は、経済成長と人口増加が止まらない場合、今後100年以内に「人口と産業能力の両方が突然、制御不能に減少する」というものである。この引用は、LtG報告書の主要な結論を表している[2, p. 23; 41も参照]。LtG報告書は政策行動への警鐘としてとらえられるべきであるが、批評家たちは、LtG報告書によって概説された具体的で短期的な予測が的中するかどうかに議論の焦点を当てることによって、誤った予言であるかのように表現した。

あるコメンテーターは、ローマクラブ報告書は「実際には何も『予言』していない」と述べている。著者たちは、この報告書が予測ではないことを明言しており、利用可能なデータや理論によって、今後100年の間に世界に何が起こるかを正確に予測できるとは考えていない。シナリオは、世界がどのように進化していくかを示す、さまざまな例に過ぎない。[ローマクラブは、様々な主要入力要因とその相互作用を未来に予測するために、コンピューターモデルを使用した。これらのモデル入力を導く異なる仮定は、シナリオと呼ばれる異なる結果をもたらした。実際、1980年代と1990年代の経験に基づいてLtG報告書の妥当性を判断するのは不公平である。
LtGの政策的意味は、その前提にあった。第一に、人々には資源の利用を持続可能なレベルに制限する能力がある。第二に、政府の介入と個人の自制心の両方が、必要な消費の変化を促すことができる。第三に、このような変化が起こるスピードが、システム的な結果を大きく左右する。つまり、必要な個人の自制心と政治的意志を喚起することができれば、地球環境崩壊への流れを止めることができるということだ。
1972年にスミソニアン協会で発表されると、『LtG』は大きな反響を呼んだ。学術界では大々的に報道され、議論が交わされた。英国の『エコノミスト』誌と米国の『ニューズウィーク』誌は痛烈に攻撃した。ニューヨーク・タイムズ紙はニクソン政権の反応を伝えた。ニクソン大統領の環境顧問であったR.E.トレインは、現在の人口、資源利用、その他のトレンドが来世紀には災厄に終わると予測するローマクラブの研究に言及している。しかし、さまざまなグループが問いかけている疑問の根本的な妥当性を認めるために、より極端な予測の根底にある悲惨な仮説や方法を受け入れる必要はない、と彼は言う(NYT1972年3月30日号19頁)。
環境保護主義者たちは、過剰消費という差し迫った問題に気づきを与えたとしてLtGを称賛したが、一方で批判者たちは、不十分なデータと暗い予測によってLtGを非難した。例えば、著名なシステム思想家であるケネス・ボールディングは、「有限の世界で指数関数的な成長が永遠に続くと信じる者は、狂人か経済学者のどちらかである」 [11]と述べたと言われているが、1972年の『ニューズウィーク』誌の社説では、イェール大学の経済学者ヘンリー・ウォーリックがLtGに「無責任なナンセンスの塊」というレッテルを貼っている。[12]。もうひとつの有名な議論では、エコロジストのポール・エーリック夫妻が経済学者のジュリアン・サイモンと、1980年を基準として、1990年までに銅、クロム、ニッケル、スズ、タングステンの市場価格が劇的に上昇すると賭け、サイモンは下落すると予測した。エーリック夫妻は賭けに負け、サイモンに576.07ドルの小切手を郵送した[13]。


ある意味でエーリック夫妻は、(中銀報告書の100年という長い時間軸に反して)10年という時間軸しか持たなかったのは賢明ではなかった。1980年代には世界経済が低迷し、商品価格が下落したためである。とはいえ、エーリック夫妻が敗れた重要な理由は、1980年代の経済ペースの鈍化とともに、この10年間に世界人口が8億人増加したにもかかわらず、技術的代替によって価格が低迷し続けたことである。このような代替効果の一例として、かつて銅が担っていた機能の多くを代替するガラス光ファイバーケーブルの開発が挙げられる。第一に、サイモンの立場をさらに裏付けるものとして、新しい採掘技術によってニッケル鉱床の新たな発見が可能になり、この金属の実際の資源量が増加した。第二に、エーリック夫妻の立場の支持者は、代替効果の存在にもかかわらず、この金属バスケットの価格は、1980年代初頭には石油価格の高騰によって人為的に高くなり、1990年には石油価格の後退によって低くなったと主張した。Verweijらは、時間の経過とともにローマクラブが天然資源問題から重点を移してきたことを指摘している[44]:
今日……ローマクラブ(2002)は、世界中で化石燃料を使用し続けることによって大気中に温室効果ガスが蓄積し、人類が中長期的に脅威にさらされているという見解を支持している。これは、化石資源の枯渇によって世界の長期的な繁栄と安定が脅かされているとした1970年代初頭のクラブの見解(…)とは、ほぼ正反対である。そのため、ローマクラブは、化石燃料の確認埋蔵量が着実に増加してきたこの35年間に、明らかに立場を変えてきた。
とはいえ、批評家の指摘に反して、最初のLtG討論会は資源不足だけに焦点を当てたものではなかった。実際、著者たちは、地球の生態系が汚染を吸収できないことを、「オーバーシュートと崩壊」の可能性のある軌道のひとつに含めており、「熱汚染」や人為的な気候変動が「深刻な気候的影響」をもたらす可能性さえ挙げている。[しかし、このフィードバック・ループをWorld3モデル全体に含めることの効果は、著者たちが地球大気への汚染吸収の上限を設定することも、指数関数的な汚染曲線がどの程度の速度で上昇するかを見積もることもできなかったため、不確定である。その結果、どのような種類の汚染でもモデルの軌道に組み込んでも、モデルの予測を劇的に変えることはできなかったと思われる。とはいえ、LtGの原著者たちは、その分析において汚染物質が果たした役割はわずかであったにもかかわらず、気候変動による制限の可能性を抜け目なく予測していたことは重要である。
漁業など特定の資源は枯渇の兆しを見せている。さらに、世界自然保護連合が定期的に発行している「リビング・プラネット・レポート」に含まれる「エコロジカル・フットプリント」や「リビング・プラネット指数」などの生態学的指標は、「人類はもはや自然の恩恵を受けて生きているのではなく、自然の資本を引き出している」ことを示唆している。[14]. 実際、これらの指標が正しく指摘しているように、人間が引き起こした生態系の不正行為の結果、地球の生物多様性と”バイオキャパシティ”は苦しんでいる。しかし、こうした事実の重要性にもかかわらず、こうした傾向の最悪の影響は、経済的に可能であれば、技術的な代替によって軽減できる可能性がある。過去20年間、政策的関心と社会的言説は、気候変動という新たな「限界」という課題に移ってきた4。この新たな概念化では、「限界」とは、温室効果ガスの排出を吸収・拡散する大気の能力に関するものである。地球から採掘される資源の希少性によって強制される限界ではなく、現在では、別の資源の希少性、すなわち大気吸収源の蓄積能力または吸収能力が懸念されている。
気候変動に関する科学的コンセンサスは(圧倒的ではないにせよ)相当なものであるが、以前の議論と同様、「新たな限界」現象とその意味を疑問視する懐疑論者もいる。
気候変動を緩和するための政策行動が、前回の限界論争よりもはるかに政治的抵抗に直面しないという大きな期待があった。それは、(とりわけ)科学的証拠がより信頼できる主体によって提供されているからである。しかし、最近のスキャンダルによって、このパネルの信頼性はかなり損なわれている。さらに、このテーマに関するメディアの注目度は、LtGに比べてはるかに高い。残念なことに、気候変動の場合、国家間の協力や市場による解決の見通しははるかに暗い。これには多くの要因があるが、主に、共通プール資源としての大気[15]が、強力な集団行動の課題を意味するため、不可能ではないにしても、効果的なグローバル政策行動を困難にしている。とはいえ、これまでの議論から導き出せる意味合いや、学べる教訓もある。
2.1. LtG討論からの教訓
LtGコミュニティは主に非政府組織であった。政府や民衆の関与はほとんどなかったが、急成長する環境保護運動と共鳴していた。これとは対照的に、気候変動に関する言説には、IPCCやUNFCCCの組織を通じて政府が直接関与しており、一般市民が関与することは比較的少なかった。こうしたことから、政府は伝統的なトップダウン方式での政策実施を好んでいると言える。我々は、このような動きが気候変動緩和の可能性を脅かしていると主張する。例えば、気候変動政策の先進国のひとつである英国では、美辞麗句を並べるだけで、実際に低炭素社会を実現する方法についての議論にはほとんど国民が関与していない。声高に反対や異論を唱えているにもかかわらず、「もう一つの視点」、つまり科学的確立とテーブルを挟んで主張する一般市民の意見が欠如しているため[18]、民主的な政府が温室効果ガスの排出を抑制するために必要な措置を講じる能力や意欲が制限されている。皮肉なことに、このことが、国民の抵抗、焦点のずれ、あるいはその両方によって、野心的な気候変動政策を失敗させる条件を作り出しているのかもしれない。英国政府は、2050年までに二酸化炭素排出量を80%削減すると公約している。しかし、この削減目標が、低炭素社会への移行を賢明なコストで実現する方法を示す政策に組み込まれなければ、有権者から疎外される可能性が高い。そのような試みが見られないため、第二の選択肢が現実のものとなっている。つまり、遠い将来のことであるため、政府はこの目標に対する責任を問われないということだ6。
気候変動は、化石燃料を主要なエネルギー供給源とする現在の経済モデルに基づく経済成長の限界を示している。成長の限界に関する議論は新しいものではないことを認識することが重要である。少なくともトーマス・マルサスの時代から、学者たちは自然環境がどのように経済成長の可能性を制限するかを議論してきた。[17]。ギャレット・ハーディンのような新マルサス論者は、当時流行していた”宇宙船地球号”アプローチに対抗して、’‘救命艇倫理”アプローチを概説した。ハーディンは具体的な政策的含意を示した。貧しい国の人口増加を制限できる世界政府がなければ、豊かな国の存続は「厳しいかもしれないが、救命ボートの倫理によって我々の行動を管理することを要求する」[5]。「限界」問題に対する、より洗練され、広く議論されたアプローチが、LtG報告書に概説されている。著名な科学者たちが、(当時としては)最先端のコンピュータモデリング技術(World3モデル)に基づく高度な技術的分析を行った。[2]。メディアや学者の注目度から、LtGは、天然資源の供給によってもたらされる経済成長の限界に関する、権威ある科学的な調査であるとみなすことができる。この報告書は、人口増加と高水準の資源採掘が地球生態系に及ぼす影響を図式化したものである。
2.2. 政府からガバナンスへ?
ヘルガ・ノヴォトニーは、LtG研究の技術主義的な方向性についてコメントし、「『統治』が『統治』に取って代わった現在、それはあまりにも国家主義的であるとして拒絶されているが、われわれは1970年代初頭に開発された政治的な手段やコントロールの手段に驚きをもって振り返っている」と指摘した[18, p.113]。 しかし、ローマクラブの研究を改めて読んで異質に思えるのは、最初のモデルに明らかに存在した技術主義的な側面だけでなく、確信を持って提示された、政治的な実用性と政策提言の実現能力に対する信念である。
Verweijら[44]が述べているように、
「しかし、クラブの根底にある仮定(規制のない市民や国家は利己的すぎるか、近視眼的であるため、自分たちの繁栄をゆっくりと、しかし確実に損なっていることに気づかない)も、究極的なガバナンスの理想(グローバル市場を抑制するためのよりグローバルでトップダウンの専門家による計画)も、階層的なものにとどまっている」
ノヴォトニーが正しく指摘しているのは、
「もうひとつの視点の欠如–下からの視点、地方からの視点の欠如、消費者、有権者、利用者としての”想像される一般人”の包摂の欠如(現在では少なくともレトリック的には当然のこととされている)」であり、これは今日の世界では奇妙で政治的に非現実的だと思われる。それが影響を与えるであろう人々の声に耳を傾けることなく、未来について語ることがどうして可能なのかと、人は驚きをもって問いかける。[18, p. 113].
このことは、気候変動に関する言説が、どの程度そのような期待に応えているのかという疑問を提起する。気候変動論議における主要なプレーヤーたちの頭の中では、ガバナンスは政府に取って代わったのだろうか?オーストラリアの科学者シャーマンとスミスは、温室効果ガス排出に関する科学的コンセンサスを実現するためには、権威主義的な形態の政府が必要だと主張している。[19]。著名な気候研究者であるジェームズ・ハンセンは、気候変動に関しては「民主主義のプロセスは機能しない」と嘆いている。ジェームズ・ラブロックは『ガイアの消失』の中で、気候変動という課題に正面から取り組むためには民主主義を放棄する必要があると強調している。我々は戦争状態にある。世界を無気力状態から脱却させるために、新たな戦争への取り組みが話題になっている(批判的な評価については[20]を参照)。
気候変動は、当初のLtGと同様、明らかに経済成長の限界を反映しているが、決定的な違いが一つある。資源不足と人口増加7が経済成長の可能性をどのように制限するかを強調する傾向があった以前の限界議論とは異なり、気候変動に関する文献は、環境の吸収力によって課される限界に焦点を当てている。資源が限界となるのではなく、吸収源が限界となるのである。実際、この2種類の限界の政策的意味合いは異なっており、気候変動の緩和には不利である。
2.3. 技術の役割
おそらく、LtG報告書は、人間の技術革新能力を十分に認識し、織り込んでいない。技術革新と市場原理は、資源の代替を促進することによって、少なくとも部分的には資源不足を緩和することができる。この議論は、LtG報告書が発表された直後から、多くの学者、特にジュリアン・サイモン[21]やハーマン・カー[21]によってなされてきた。
世界のいくつかの地域における食糧危機は、新技術の導入(高収量品種の種子と、農薬、肥料、灌漑の体系的な施用)と政策変更(農村部と都市部の貿易条件の変更など)を伴う「緑の革命」によって回避された。現在の食糧危機が長引いた場合、緑の革命技術の「第二の波」(遺伝子組み換え作物を第二の波と位置づけるなら、第三の波)の開発への投資につながるかどうか、興味深いところである。

1973年と1979年の石油危機は、一次資源の利用可能性に関する外生的ショックが、新しい資源や技術の開発に拍車をかける可能性があることを示している。これらの「解決策」は、資源の枯渇という問題を(当時の)未来(そして現在の私たち)に先送りするものであったが、より広範な教訓は、一定の条件下では、人間の創意工夫と適応力が、しばしば政府の介入を媒介として、少なくともその周辺部においては、消費と生産のパターンを変えることができるということである。そのためには、人間の社会的、政治的、経済的な対応を予測し、可能であれば資源不足の予測を立てる際に考慮する必要がある。しかし、Kemptonらが指摘するように、資源価格の変化に対する一般大衆の反応を予測することの重要性にもかかわらず、政府が省エネルギーによるコスト削減を推進しているにもかかわらず、一般大衆が省エネルギーによるコスト削減をより活用しないことは不可解である[59]。
1970年代と1980年代は、技術革新が社会政治プロセスにとって外生的なものではないことを教えてくれた。適切な制度的背景は、新技術の開発と普及を助けることができる。人間は資源の限界に立ち向かわなければならないが、短期的には資源不足を緩和することができる。しかし残念なことに、そのため政治家たちは、時間的な余裕がなかったり、経済や安全保障を重視せざるを得なかったりして、このような傾向に気を取られてしまう。気候変動規模の環境問題には、短期的・長期的な生産・消費パターンの変化が必要なのは事実である。しかし、短期的な成功に気を取られてはならない。最終的には、富の生産における炭素強度を削減する技術が必要になる。深海掘削の新手法を開発したり、より効率的に石炭を採掘するために山の頂上を爆破したりすることで、エネルギー需要を満たすだけではもはや十分ではない。課題は、長期的な約束と短期的な政策を結びつける政治的行動に着手することである。そのためには、気候変動に関する議論を、現在のような警鐘主義的な方向から、より現実的で制度的な基盤へと移行させる必要がある。言い換えれば、長期的な排出量目標をめぐって議論するのではなく、政策立案者は、気候変動が短期的、中期的な社会的、経済的、政治的影響について、また、低炭素社会への軌道修正をどのように行うかについて、基本的な問題に向き合うべきである。例えば、温室効果ガス排出量を削減するために輸送エネルギーの使用を削減することは、多くの国にとって非常に重要な目標であるエネルギー自給率の向上にもつながる。他の補完的な目標としては、エネルギー安全保障、(クリーンエネルギー部門における)雇用創出、(例えば、黒色煤煙の削減[63]を通じた)人の健康の改善、ピークオイル前の石油からの脱却などがある。このような政策は、(グローバルな公共財を創出するのとは対照的に)国家レベルで充当できる便益をもたらすだろうが、これは、グローバルな共通プールの資源を保全するという問題において、国際政策交渉者が直面する主要な集団行動のジレンマの重要性から目をそらすものではない。
3. 気候変動の場合
過去3年間、気候変動に関するメディアの報道が急増している。[25,26]。多くの報道によると、気候変動は世界的な政策課題の筆頭である。この課題には多くの側面があるが、ここでは2つの側面について述べる。第一に、問題の大きさと複雑さ(以前のLtGのよう。に)から、科学に対する挑戦である。この側面とは、自然環境の物理的変化を指す。第二に、集団行動、ひいては公共政策の問題である。議論に参加する一部の関係者は、潜在的に劇的な物理的変化を強調すれば、社会から必要な反応を引き出すのに十分だと考えているようだが、それは間違っていると我々は考えている。これは政治の基本を無視している。特に、ヨーロッパ、北米、新興国(ブラジル、ロシア、インド、中国=BRICs)のいずれであれ、豊かな消費者と化石燃料ロビーの両方が、変化に抵抗したり、変化を先送りしたりする力をもっている。
過去2世紀にわたる気候変動傾向は、地球が自然の気温変動サイクルを超えて温暖化していることを示している。科学者たちは、この温暖化は人為的な温室効果ガス排出の大幅な増加に起因するとしている。温室効果ガスが大気中に蓄積されることで、通常は外部に拡散するはずの太陽熱の多くが地表に反射され、極地や氷河の氷塊を溶かし、地球の気温を上昇させる。気候の乖離は、工業化、世界的な人口爆発、資源採掘の大幅な増加、経済成長–これらはすべて温室効果ガス排出の大きな原因である–と相関しているため、人間の活動が再び、生態系のバランスを崩す要因になっていると考えられている。
2007年、IPCCは第4次評価報告書を発表した。これは2段階で行われ、まず「政策決定者のための要約」が発表された。ニューヨーク・タイムズ紙によると、これに対してアメリカ政府は次のような反応を示した。「最近まで、人間が地球を温暖化させていることを直接的に受け入れることを避けていたブッシュ政権は、アメリカや他の112カ国の代表が承認した調査結果を受け入れた。」
むしろ、アメリカ国内で行われている研究が支持されたのだろう。記事はこう続く:
政権高官は、米国は気候変動の研究と対策において主導的な役割を果たしてきたと主張した。過去6年間、年間平均50億ドル近くを研究に投資し、新技術に税制優遇措置を講じてきたこともその一因である。同時に、サミュエル・ボドマン・エネルギー長官は、一方的な排出量制限という考えを否定した。世界の他の国々を見れば、われわれは全体から見れば小さな貢献者である。(と彼は語った(NYT2007年2月3日)。
報告書全文が発表された後、ニューヨーク・タイムズ紙は、「ブッシュ大統領は、他の主要先進国の指導者たちと、『この問題は緊急の行動を必要とするものであり、持続的な解決を可能にする技術をより加速度的に前進させる必要がある』という点で合意した」と報じた。彼は、政権がどの程度の温暖化を許容できると考えているかについては明言を避け、「それについての見解は持っていない」と述べた。[米国は2001年以来、気候研究に120億ドルを投資してきた。(NYT2007年11月18日遅報-最終版)。印象的なのは、科学を受け入れ、研究への米国の投資を誇示する一方で、気候変動政策や米国の目標については回避的であることだ。
3.1. 警戒論
『Nature』誌の報告書で、WHOとウィスコンシン大学マディソン校の科学者たちは、気候変動は、「…極端な暑さ、寒さ、干ばつ、暴風雨による直接的な気温の影響、大気や水質の変化、感染症の生態系の変化」[27]によって、年間約15万人の死亡につながると推定している。彼らはさらに、暴風雨パターンの変化、気象現象の厳しさの増大、海面上昇と淡水の喪失、現在耕作可能な地域の砂漠化、種の絶滅など、気候変動がもたらす他の多くの災禍的影響について言及している。これらから生じる政策的課題、そしてそれに続く人間の強制移住、食糧危機、水危機、公衆衛生問題は憂慮すべきものである。
しかし、気候決定論の罠にはまるのは間違っている。上記のシナリオは必然的なものではない。社会的・政治的介入は変化をもたらす。気候変動の場合、悲惨な結果を防ぎたいのであれば、市場原理が頼りにならないことは明らかだ。必要なのは、緩和政策がいかに成功しようとも、私たちはすでに気候変動にコミットしているという認識である。これは、気候変動の結果として何十万人もの人々が死ぬということを意味するのではない。そのような事態は、インフラを順応させれば防ぐことができる。これはコストがかかるし、気候変動防止という。「大きな目標」から注意と資源をそらすようで、政治的に「正しくない」ように見える。実際のところ、IPCCは、少なくとも2001年の報告書から、緩和と並ぶ適応の重要性を認めている。[28-31]。地球温暖化の結果は、その軌道を変化させる能力が最も低い地域に主に影響を及ぼすため、適応は適切な政策対応の一部となるに違いない。[32]。より一般的な言い方をすれば、賢明な政策対応は、社会の脆弱性を低減するよう努めるべきであると言える。[51]。そして、過去20年間にわれわれが失った時間がいかに大きいかを認識するにつれ、第3の政策、すなわち救済措置(すなわち、大気からCO2を除去するための地質工学プロジェクト)を追加することを求める声もある。2009年、英国王立協会は『気候のジオエンジニアリング(Geoengineering the Climate)』という報告書を発表した: 科学、ガバナンス、不確実性)」を発表し、さまざまな選択肢について論じている。適応策に真剣に取り組み、改善策も検討して最悪の事態に備えることで、憂慮すべきレトリックは弱まるはずだ。
これまで気候変動政治は、「危険な温暖化」を防ぐのに十分な時間のある、展開するドラマとして描かれてきた。そして、「戻れない地点」に到達するまでにあと10年あると言われてきた。このメッセージに暗黙のうちに含まれていたのは、適応や修復は、必要だとしても二の次であるということだった。数カ月ごとに新たなレベルまで警戒が高まる中、この話の筋書きはもはや当てはまらない。2007年には、「地球を救うのは今しかない」 [60]というマントラが定着した。2004年、ハリウッドの超大作『デイ・アフター・トゥモロー』は、突然の気候変動というメッセージを一般大衆に伝えた。2005年以降、気候変動に対す。るメディアの注目度は急上昇し、そのほとんどは劇的なトーンで報道された。[25,26]。2006年と2007年には、多くの専門科学団体が、気候変動は緊急の行動を必要とする深刻な問題であるとの声明を発表した。[45]。2007年、IPCCは第4次報告書を発表し、アル・ゴアとともにノーベル平和賞を受賞した。しかし、気候変動の政治化につながった警鐘論的戦略は、国際レベルでは期待されたほどの影響を与えなかった。2009年12月、国連193カ国がコペンハーゲンで条約に合意できなかったことで、そのことが明らかになった。同時に、世論調査では、経済問題が優先されるにつれて、国民が感じている切迫感が低下していることが示された。[47]。もしそれが、国家、企業、消費者を行動に駆り立てるための政治戦略であったとすれば、警鐘を鳴らすレトリックは明らかにその目的を達成することができなかった。

3.2. モデルとシナリオの役割
ローマクラブと同様、IPCCはモデル結果を一般に伝えるためにシナリオを使っている。IPCCの用語集によると、モデルとは、「気候システムの構成要素の物理的、化学的、生物学的特性、それらの相互作用、フィードバック過程に基づき、その既知の特性のすべてまたは一部を考慮した数値表現」である。これらのモデルは、「気候を研究し、シミュレーションするための研究ツールとして、また、月単位、季節単位、経年単位の気候予測を含む運用目的のために適用される」これらのモデルに基づく予測は、気候感度の推定(CO2濃度を2倍にした場合の地球表面の平均気温の上昇)から、海面上昇、種の消失、氷河後退、気象災害頻度の増加に関する予測まで、様々なものがある。では、予測とは何だろうか?IPCCは、「気候予測または気候予報とは、例えば、季節的、年次間、または長期的な時間スケールで、将来の気候の実際の変化を推定する試みの結果である」と述べている。気候予測は、使用される排出/濃度/放射強制力のシナリオに依存する気候予測とは区別される。そしてシナリオは、「例えば、将来の社会経済的・技術的発展に関する仮定に基づくものであり、それは実現されるかもしれないし、されないかもしれず、そのため実質的な不確実性に左右される」[53]。[53]
一般的な言葉では、これらの様々な用語は互換的に使われるかもしれないが、そうではない。特に、これらの定義が普遍的なものではなく、気候科学者でさえ、時に様々な方法でこれらを用いるので、異なる定義についてあまり長く考える必要はない[54]。しかし、シナリオの役割を理解することは有益であると思われる。IPCCの前議長であるロバート・ワトソンは、Philosophical Transactions of the Royal Society of Londonに寄稿した論文の中で、シナリオは政策立案者に影響を与える重要なツールであると述べている:
変化を直接観測する以外に、政策変更を促進するための最も重要なツールのひとつは、もっともらしい将来のシナリオである。上述したほとんどの科学的評価(成層圏オゾン層破壊、酸性雨、気候変動など)において、シナリオの使用は、もっともらしい将来の変化を説明し、さまざまな政策選択の意味を明らかにし、政策決定者に行動を起こすよう説得する上で、極めて重要な役割を果たしてきた。[55]
また、HjerpeとLinne´rは、「IPCCは、シナリオを『将来どのように展開する可能性があるかについての代替的なイメージ』(……)と表現しており、原動力が将来の排出結果にどのような影響を及ぼす可能性があるかを分析するためのもの」(……)、すなわち、シナリオは将来の青写真を提供するために設計されたものではない。IPCCは……様々なシナリオ群には、確率も望ましさも付されていないことを強調している……。社会の将来の進化は、例えば、人口統計学的発展、社会経済的発展、技術的変化の相互作用の不確実なプロセスとして認識されている。[50]
様々なシナリオには確率が割り当てられていないため、意思決定者は自分の先入観に沿ったシナリオを選ぶことができる。この意味で、LtGもIPCCも、ディストピア的な未来の可能性を伝えるためにシナリオを利用しているのであり、予測としてではなく、最悪の事態を防ぐためには緊急に何かを行う必要があることを思い出させるためにシナリオを利用しているのである。
3.3. LtGとの違い
気候変動は、その技術的焦点を含むいくつかの分析的側面では類似しているが、いくつかの重要な点で、LtGとは異なっている。第一に、LtGが予測した「経済崩壊」は、貿易可能な資源(食料、石油、銅など)の供給の減少によって引き起こされた。- これらの資源はライバルであり、排除可能であり、”私的”財の特徴を持っている。これらの資源の供給が減少すると、価格が上昇し、市場のインセンティブによって技術革新が促進された。1970年代のオイルショックでは、突然の歴史的な原油価格の高騰にもかかわらず、市場のシグナルと技術革新によって、新しい油田の発見によって供給制約が緩和される一方で、燃料効率の高い自動車が需要を満たすことができた。しかし、気候変動では、同じような解決策は生まれそうにない。第一に、少なくとも短期的には、供給制約を緩和することはできない。バイオマスの創出や森林の(再)生成による炭素隔離によって、供給量を増やすことはできるかもしれない。さらに、クリーンなエネルギー源(風力、太陽光など)への転換による炭素排出削減努力は、制限を回避する方法を提供するだろう。しかし、石油や石炭に比べれば代替エネルギーが果たす役割は相対的に小さく、短期的に効果を上げるには巨額の投資が必要であるため、このような方法で限界を回避できるという考え方には希望が持てない。さらに、このような制度の中には、逆効果をもたらすものもある(例えば、まず既存の森林を伐採し、新しい木を植えれば、より多くの炭素を吸収できるようになる)。
第二に、大気はライバルではあるが、排除不可能な共通プール資源である。したがって、資源の希少性が価格の上昇につながることはなく、大気吸収源に財産権(温室効果ガスを排出する権利)を付与する方法が見つからない限り、市場のインセンティブによって技術革新が促されることはない。この後者のアプローチは、炭素取引スキームの提案に取り入れられている。
3.4. キャップ・アンド・トレード?
気候変動に内在する集団行動の問題を認識し、気候変動に関する主要な政府間条約である京都議定書、欧州連合排出量取引制度(E. S)、米国、スウェーデン、オーストラリア、ニュージーランドなどのさまざまな国内取引所などのメカニズムが、大気の財産権を創出し、炭素排出量取引を通じてその効率的な配分を奨励することで、いわゆる「大気コモンズの悲劇」を防ぐために設立された。ひとたび財産権が確立されれば、温室効果ガスの排出に十分なコストがかかるようになり、排出削減技術の開発と導入が促進されることが期待されている。キャップ・アンド・トレードのメカニズムには注目すべき成功例があり、市場メカニズムに希望を与えていると主張する人もいるが、懐疑的な見方が強いのも事実である。世界銀行の報告によると、世界の炭素取引市場の取引額は 2006年から2007年にかけて、310億ドルから640億ドルへと、2倍以上に増加した[33]。

排出権の配分は、分配的な結果をもたらす可能性が高い。驚くにはあたらないが、政治がこうしたメカニズムの進化を阻んでいる。社会的、政治的、経済的な政策課題もある。第一に、発展途上国が最も基本的な財産権を行使する能力さえ限られていることを考えると、よりエキゾチックな炭素の権利をどのように行使するのだろうか。例えば、コールマンが指摘するように、炭素会計、つまり炭素排出量を計算する方法は、取り締まりには適していない。その代わりに、排出者はCO2排出量を推定するために、生産時に燃やされた燃料の量を含む計算のような間接的な尺度に頼っている[35]。
第二に、国際的なグローバル排出削減目標から途上国を除外することは、主要な途上国汚染者が排出削減よりも成長を優先するインセンティブを持つというモラルハザードの問題を引き起こす。
さらに、サウジアラビアなどの富裕国を含む石油輸出国は、輸出収益の減少に対する補償を求めている。[36]。モラルハザードの問題は、自分たちの行動の結果を十分に負担していない行為者が、社会的に有害な行動をとるインセンティブを持つ場合に生じる。2007年、中国は、一人当たりの排出量は米国よりはるかに少ないにもかかわらず、二酸化炭素の世界的な主要排出国に浮上した。[36]。京都議定書によれば、中国は発展途上国であるため、排出量削減の義務はまだない。インドも同様である。その意味するところは、中国(および他のBRICs)が排出量の増加を抑制しない限り、先進国が政治的に痛みを伴う大規模な排出削減を行ったとしても、全体としての影響はほとんどないということである[37]。すべての主要な汚染者が協力しない限り、既存の汚染者と新興の汚染者との間に巨大な開発格差があることを考えると、かなり困難なことであるが、先進国での深刻な規制の推進は、産業の海外移転、すなわち”産業フライト”を規制の緩やかな経済圏に強制する可能性があり、その結果、世界の総排出量にほとんど影響を与えない。「チャイナ・エフェクト(中国効果)」が先進国の排出削減を支配する可能性が高いため、懐疑論者にとって、途上国への適用除外は、現状維持を主張するための便利な道具となることは明らかである。
第三に、市場取引による腐敗的な影響によって、キャップ・アンド・トレード制度がもたらすであろう真の構造改革が制限されるという意見もある。炭素排出量取引制度の非政府モニターであるカーボン・トレード・ウォッチのケヴィン・スミスは、「市場ベースの制度の問題点は、私利私欲のために不正に利用されやすいことだ」と簡潔に指摘し、さらに、ロビー活動の圧力によって、炭素排出枠のレベルが、効果を上げるために必要なレベルよりもはるかに高くなることがよくあると指摘している[38]。
キャップ・アンド・トレードに代わる解決策として、キャップ・アンド・コンバージェンス、フィー・アンド・ディビデンド[61]、炭素税などがあることに注意することが重要である。さらに、カリフォルニア州の”Flex Your Power Program”や米国政府の”Energy Star”プログラムなど、化石燃料への依存を減らすための地域的・国家的な取り組みもある。しかし、キャップ・アンド・トレードは、現在に至るまで、世界の多くの国で主要な政策解決策となっており[62]、現在までに国際的に認められた最大の政策努力を構成している。残念なことに、前述のような地域的・国家的な取り組みは、気候変動の軌道を変えるために必要な行動レベルにはほど遠く、包括的な気候変動交渉に国民が大きく関与するものでもない。キャップ・アンド・トレードに代わる国際的な政策が現れるかどうかは、まだわからない。現在のところ、見通しは明るくない。
第4に、LtGの短期的予測は、市場インセンティブによって大部分が緩和され、政府間の規制協力はほとんど必要なかったかもしれないが、気候変動については逆である。国内排出量の削減を成功させるためには、政治家は炭素税や排出料によって炭素排出削減を厳しく規制し、強制するという、好ましくない政治的選択をしなければならない。これが経済成長をどの程度低下させるのか、あるいは低下させないのかは疑わしいが、いつの時代でも、特に歴史的な不況の最中でも、企業に対して広範な規制と課税を導入することは、政治的に不人気となる可能性が高い。さらに、マクロ経済要因によって資源価格が再び下落し、カーボンニュートラルや低排出技術への投資が実行しにくくなる。
最後に、当初のLtGの議論では、オーバーシュートと崩壊のシナリオは主に地球規模のものと考えられていたが、気候変動の最悪の影響は、その原因に対して最も責任のない国々が被る可能性が高い10。第一に、危機を解決する能力が最も低い国に、責任の重さを負わせることになる。第二に、気候変動の危機を世界的な必需品としてではなく、対外援助と同じカテゴリーに位置づけてしまうことだ。この点で、先進国の市民は、広範な国際協力計画の実施に賛同しにくくなり、気候変動問題を「アフリカの問題」とみなす傾向が強まる。その結果、先進国のあらゆる政治家は、貧困層の問題や「遠い」未来の問題を改善するために、自らの政治的立場を危うくすることに消極的になるだろう。
4. 結論
以上のような厳しいシナリオを踏まえると、環境コミュニティは1970年代と1980年代の経験を、気候変動に関する政治戦略にどのように生かすことができるだろうか。気候変動に関する言説は、IPCCの主要メンバーによって広められたように、大量の警鐘論と結びついた技術主義的な方向性を持つ傾向がある。私たちは、長期的な排出目標を議論することから、この巨大な政策課題の社会政治的次元に立ち向かうことへと、この言説を変えることを強く求める。政府だけでは問題を解決することはできない。たとえ米国が京都議定書に参加したとしても、京都議定書はそうではない。欧州はこの議論の最前線にいるが、京都議定書の目標遵守状況は芳しくない。気候変動の予測がいかに暗いものであったとしても、新しい技術がすぐに生まれ、普及することはないだろう。これまでのところ、政治的エネルギーは主に政府や企業の介入を求める需要を生み出すために費やされてきた。このような圧倒的な証拠に直面すれば、新技術の供給が開始されるという前提である。少なくとも、温室効果ガスの排出量を安定化させるのに必要な規模ではない。私たちは今、新技術の供給を増加させるための直接的な介入を必要としており、環境コミュニティは、この文脈における政府の重要な介入を支持する必要がある[40参照]。この問題に持続的に取り組むためには、国家レベルでのイノベーション・イニシアチブと、広範な国民の参加が必要である。前回のLtGのエピソードとは異なり、市場がこれらの技術を自発的に供給できるとは思えない。
技術的な代替に加え、気候変動という”邪悪な問題”に対する真の解決策には、国民の価値観の方向転換が必要である。このような方向転換の一例として、コミュニティ・レベルの行動と意識、複数のセクター、コミュニティ、政府レベルでのコミュニケーション、環境変化への地域適応を強調する、新興の「トランジション・タウン」運動 [57]がある。実際、価値観の方向転換と政府が提供する技術的解決策という2つの概念は、相互に構成的である。残念ながら、本稿では価値観の転換の重要性を十分に取り上げるには十分なスペースがない。今後の研究にとって生産的な道であることは間違いない([58]も参照)。
さらに、本稿の制限内では十分に説明しきれなかった重要な点もある。これは特に、一般市民の関与の欠如についての指摘を指している。私たちは、「他の」声が誰なのか、そして彼らがどのように排除され、あるいは特権を与えられているのかを探りたい。また、国民が懐疑的になっている根本的な理由についても、より詳細に検討する必要があるだろう。また、IPCCの科学とLtGの科学との異なる認識論的基盤についても分析する必要がある。そうすることで、実際の「信頼性」や認識論的基盤に関する疑問に答えることができるだろう。最後に、緩和戦略とは別に、適応と修復も含める必要があるという事実から生じる影響について議論する必要がある。しかし、これらの課題については、今後の研究や別の出版物を待たなければならない。
謝辞
本稿の初期の草稿に貴重なコメントを寄せてくれたHelga Nowotny、Mike Hulme、そして2名の匿名レフェリーに感謝したい。
