コンテンツ
- AI要約
- 1. はじめに
- 3. 行為者としての文明大空間とポリテイア
- ハンチントンの理論文明概念の導入
- IRにおける「文明」概念
- TMWにおける「文明」概念のスペクトルを広げる:定義
- 実体としての文明(文明の存在論的概念)
- プロセスとしての文明(文明の動的概念)
- システムとしての文明(文明のシステム概念)
- 構造としての文明(文明の構造・機能・形態学的概念)
- パイデウマとしての文明(文明の教育概念)
- 価値観の集合としての文明(文明の公理学的概念)
- 組織化された無意識としての文明(文明の精神分析的概念)
- (宗教的)文化としての文明
- 言語としての文明(文明の言語学的概念)
- エスノスからの最初の派生物としての文明(文明の民族社会学的概念)
- 構築物としての文明(文明の構成主義的概念)
- デーゼインとしての文明(文明の実存的概念)
- 人間の規範的場としての文明(文明の人類学的概念)
- 多極世界の両極/文明のリスト
- 西洋文明
- 正統(ユーラシア)文明
- イスラム文明
- 中国文明
- ヒンドゥー文明
- 日本文明
- ラテンアメリカ文明
- アフリカ文明
- 仏教文明
- 多極化する世界地図
- 構築物としての文明
- 多極化の調整センター
- 文明の国境
- 多極化する世界の実践: 統合
- 先入観文明と「大空間」
- 多極世界の理論におけるポリテイア
- 付録
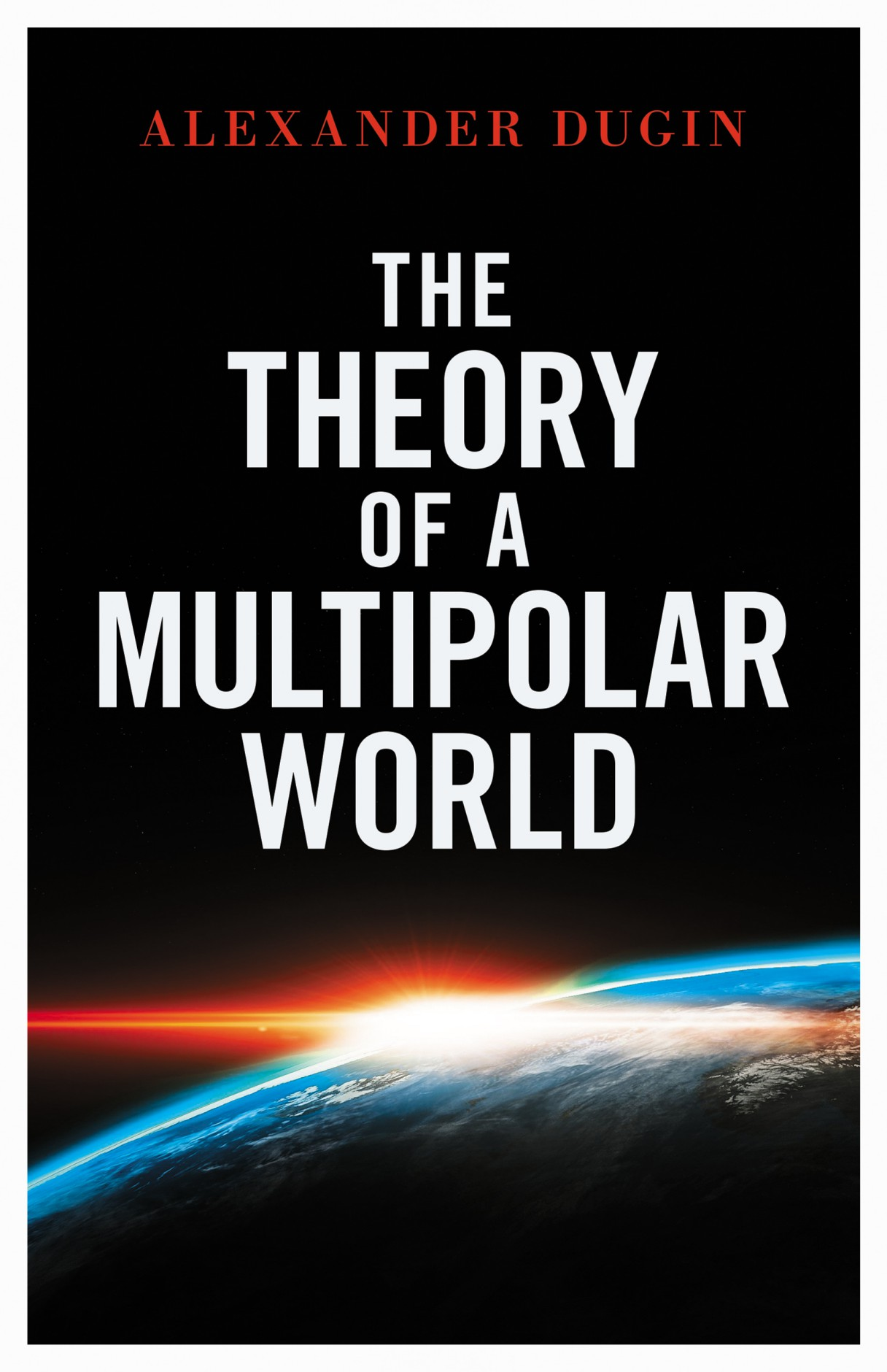
The Theory of a Multipolar World
AI要約
アレクサンドル・ドゥーギン著『多極化する世界論』は、従来の二極モデルや一極モデルから脱却し、複数の権力中心を特徴とする新たな世界情勢を取り上げている。ドゥギンは、単一の超大国の支配や2つの超大国間の二分法は時代遅れになりつつあると主張する。その代わりに、世界は様々な影響力を持つ国や地域連合が地政学的に大きな影響力を行使する構造へと進化しつつある。
本書の主なポイントは以下の通りである:
現実としての多極化: 本書では、冷戦後、主にアメリカが支配してきた一極世界が、中国、ロシア、インドを含む様々な国が重要なグローバルプレーヤーとして台頭する多極世界へと移行しつつあることを論じている。
文化的・文明的要因:ドゥギンは、多極化した世界とは政治的・経済的なパワーだけでなく、文化的・文明的な多様性でもあると強調する。彼は、これらの多様性を尊重することを主張し、世界の平和と安定は、この多極的な文化的景観を認め、維持することにかかっていると示唆している。
グローバリゼーションと自由主義を批判する: 著者は、グローバリズムのアジェンダとリベラリズムのイデオロギーを批判し、それらが文化の均質化をもたらし、国家主権を損なうと主張する。外部からの干渉を受けず、各国が自由に独自の道を追求できる世界秩序を提唱している。
ユーラシア主義: ドゥギンはユーラシア主義という概念で知られ、ロシアが欧米列強の覇権主義的影響に対抗してユーラシア諸国を統合する上で中心的な役割を果たすと考えている。この概念は本書の中で繰り返し登場するテーマであり、欧米の支配に対抗するものとしてユーラシア諸国間の戦略的同盟を提案している。
地政学的分析: 本書は、様々な地政学的戦略、紛争、同盟について詳細な分析を提供している。ドゥギンは歴史的、現代的な例を用いて、多極化する世界の力学と、この複雑な情勢の中でさまざまな国がどのような戦略をとっているのかを説明している。
結論として、『多極化する世界論』は、世界のパワー・ダイナミクスの変化を詳細に説明し、文化的・文明的多様性を尊重し、国際関係における多極化を促進し、世界のバランスと安定を維持するために地域同盟の形成を奨励するシステムを提唱している。
1. はじめに
多極化概念の定義と意味の定義
TMWの精緻化に向けた最初の取り組み
純粋に科学的な見地から見ると、本格的で完全な多極化理論(TMW)は今日存在しない。国際関係論(IR)の古典的な理論やパラダイムの中にも見あたらない1。最も柔軟で総合的な領域である地政学研究においても、ポストポジティビズムの理論は十分に練られていない。
とはいえ、外交政策、グローバル政治、地政学、国際関係論に関連する著作の中には、多極化をテーマとするものが増えてきている。多極性をモデル、現象、前例、可能性として理解し、説明しようとする著者の数は増えている。
多極化というテーマは、デイヴィッド・カンプ(そのエッセイ『多極化する世界』の中で)2、イェール大学の歴史学者ポール・ケネディ(著書『大帝国の興亡』の中で)3、地政学者デール・ウォルトン(著書『21世紀の地政学と大国』の中で)の著作の中で、何らかの形で触れられている: 地政学者のデール・ウォルトン(『21世紀の地政学と大国:戦略から見た多極化と革命』)4、アメリカの政治学者ディリップ・ヒロ(『帝国以後:多極化する世界の誕生』)5などである。多極化の本質を最もよく理解していたのは、英国のIR専門家ファビオ・ペティートであった。ペティートは、カール・シュミットの法学的・哲学的概念に基づき、一極的世界に代わる本格的で根拠のある選択肢を構築しようとした6。
政治家や影響力のあるジャーナリストは、演説や著作の中で何度も「多極的世界秩序」について言及している。このように、米国を初めて「不可欠な国」と呼んだマドレーン・オルブライト前米国務長官は 2000年2月2日、米国は一極世界を「確立し、強制する」ことを望んでおらず、経済統合はすでに「多極的とさえ呼べる特定の世界」を作り出していると発表した。2007年1月26日、ニューヨーク・タイムズ紙の社説は、中国とともに「多極世界の出現」を直言し、中国が「ブリュッセルや東京のような他の権力の中心とともに、テーブルに並んだ」7と述べた。
2009年、バラク・オバマ米大統領を「多極化の時代」の前触れだと考える人は多かった。オバマ大統領は、アメリカの外交政策において、ブラジル、中国、インド、ロシアといった成長する力の中心を優先的に扱うだろうと考えていたからだ。2009年7月22日、ジョー・バイデン副大統領はウクライナ訪問中に、アメリカは 「多極化した世界を構築しようとする」と発表した。
しかし、これらの本や記事、声明には、多極世界(MW)とは何かという正確な定義や、多極世界の構築に関する体系的で一貫した理論(TMW)はない。たいていの場合、「多極化」は、グローバリゼーションの過程において、現代世界の紛れもない中心であり核心であるアメリカ、ヨーロッパ、そしてより広義には「グローバル・ウェスト」(「第二の」世界)に属する、急速に発展しつつある、あるいは単に強力な地域国家や国家ブロックのような、ある種の競争相手が地平線上に出現していることを示すものでしかない。一方のアメリカとヨーロッパの潜在力と、他方で成長しつつある新たな力の中心(中国、インド、ロシア、ラテンアメリカ諸国など)との比較は、ますます西洋の伝統的優位性の相対性を確信させ、政治、経済、エネルギー、人口動態、文化などにおいて、惑星規模の大国のグローバルな構造を決定する長期的なプロセスの論理について、新たな問題を提起している。
これらの論評や見解はすべて、「多極化する世界」の理論を構築する上で極めて重要だが、その不在を補うものではまったくない。しかし、それらは断片的なスケッチであり、一次的な理論的、概念的な一般化のレベルにすら達していないことに留意すべきである。
とはいえ、多極化した世界秩序を訴える声は、公式の首脳会議、国際会議、国際会議で頻繁に聞かれるようになった。多極化への言及は、多くの重要な国際協定や、多くの影響力のある強力な国々(中国、ロシア、イラン、そして一部は欧州連合)の国家安全保障・防衛戦略の構想文の中に存在している。したがって、今日、かつてないほど、学術的、科学的アプローチの基本的要求に従って、多極世界の理論の本格的な推敲を始めるための一歩を踏み出す必要がある。
多極化は、ウェストファリア的な国家モデルとは相容れない
多極化世界論(TMW)の構築を本格的に進める前に、研究対象となる概念ゾーンを厳密に定義しておく必要がある。そのために、基本的な概念を検討し、多極的でないことが明らかな世界秩序の形態を決定する。
まず、国民国家の絶対的主権を認め、これを基礎として国際関係の法的分野全体を構築するウェストファリア体制から始める。この体制は、1648年(ヨーロッパにおける30年戦争の終結)以降に形成され、いくつかの成立段階を経て、第二次世界大戦の終結まで、ある程度客観的現実に対応していた。
この体制は、中世帝国の普遍主義や「神の使命」に対する気取りの否定から生まれ、ヨーロッパ社会のブルジョア改革に対応し、最高の主権は国民国家のみが有し、その目的や使命(宗教的、政治的、その他)が何であれ、この国家の内政に干渉する法的権利を持つ権威はその外には存在しないという立場に基づいていた。17世紀半ばから20世紀半ばまで、この原則はヨーロッパの政治を決定づけ、一定の修正を加えて世界の他の国々にも引き継がれた。
ウェストファリア体制はもともとヨーロッパ諸国のみを対象としており、その植民地は独立主権を主張するのに十分な政治的・経済的潜在力を持たない、単にその延長とみなされていた。20世紀に入り、脱植民地化の過程で、同じウェストファリア原理が旧植民地全体に広まった。
ウェストファリア・モデルは、主権国家間の完全な法的平等を前提としている。このモデルでは、世界には主権国家の数だけ外交政策決定の極がある。このルールは現在でも惰性的に暗黙のうちに機能しており、すべての国際法はこれに基づいている。しかし実際には、もちろん主権国家間には不平等と階層的従属が存在する。第一次世界大戦と第二次世界大戦では、世界的な大国間の勢力分布が別々のブロックの対立に波及し、同盟国の中で最も力のある国で決定が下された。第二次世界大戦の結果、ナチス・ドイツと枢軸国の敗北によって、ヤルタ体制と呼ばれる二極的な国際関係体制が世界システムに形成された。デジュール国際法は、いかなる国民国家の絶対的主権も認め続けた。しかし事実上、世界秩序と世界政治の中心的な問題に関する主要な決定は、ワシントンとモスクワの2つのセンターだけで行われた。
多極化した世界は、古典的なウェストファリア体制とは異なり、法的にも形式的にも主権を持つ国民国家に、一人前の極としての地位を認めるものである。その結果、多極世界の極の数は、承認された(および未承認の)国民国家の数よりも大幅に少なくなるはずだ。今日、これらの国家の大多数は、理論上起こりうるヘゲモニー(この世界では米国がその役割を担っている)との紛争に直面しても、自国の安全や繁栄を確保することができない。その結果、政治的にも経済的にも外部に依存することになる。依存的であるがゆえに、世界秩序に関するグローバルな問題において、真の独立した主権的意思の中心にはなれない。
多極化は、国民国家の法的平等を主張する国際関係のシステムではない。それは、名目上ではなく、現実の大国間のバランスや戦略的潜在力に基づく、まったく異なる世界像の見せかけにすぎない。多極化は、名目上だけでなく事実上も存在する状態で作動するものであり、現代の、経験的に固定化された世界における国民国家の主要な不平等から出発している。さらに、この不平等の構造は、二次的・三次的大国が、たとえブロック構成であっても、覇権国からの外部からの挑戦の可能性に対して、自国の主権を守ることができないようなものである。したがって、この主権は今日、法的な虚構である。
多極化は二極化ではない
第二次世界大戦後、世界にはヤルタ体制とも呼ばれる二極体制が形成された。形式的には、すべての国家が絶対主権を持つという原則を主張し続け、国連もこの原則に基づいて組織され、国際連盟の事業を引き継いだ。しかし実際には、世界的な意思決定の中心はアメリカとソ連の2つになった。アメリカとソ連は、グローバル資本主義とグローバル社会主義という2つの政治経済システムを代表していた。このように、戦略的二極性は、自由主義対マルクス主義というイデオロギー的二元論に基づいていた。
二極世界は、米ソの経済的・軍事的・戦略的同等性、対立する各陣営の潜在力の対称的比較可能性に基づいていた。同時に、どちらの陣営にもモスクワやワシントンに匹敵する力を持つ国はなかった。その結果、世界規模で2つの覇権国が存在し、その周囲を同盟国が取り囲んでいた(戦略的には半臣民)。このモデルでは、形式的には認められていた各国の国家主権は、次第にその意味を失っていった。第一に、どの国も、その影響圏に属するヘゲモニーの世界的な政策に依存していた。地域紛争(原則として第三世界)は、すぐに2つの超大国の対立へと発展し、超大国は惑星の影響力のバランスを「紛争地域」に再配分しようとした。これは、韓国、ベトナム、アンゴラ、アフガニスタンなどでの紛争を説明している。
二極世界には、非同盟運動という第三の勢力も存在した。この運動には、資本主義か社会主義かの明確な選択を拒否し、アメリカとソビエト連邦の世界的に拮抗する利害の間を行き来することを好んだ第三世界の数カ国が含まれていた。しかし、非同盟の可能性は、まさに2つの極が存在することを前提とするものであり、その2つの極は、ある程度、あるいは別の形で、互いに均衡を保っていた。同時に、ほとんどの「非同盟諸国」は、孤立し、統合と社会経済的基盤の共有に欠け、主要な点で超大国に劣っていたため、「第3極」を形成することはできなかった。世界全体は、資本主義の西側(第一世界、西側)、社会主義の東側(第二世界)、そして「その他」(第三世界)に分割されていた。さらに、「その他」はあらゆる意味で世界の周縁部であり、そこでは超大国の利害が時として対立した。超大国同士の衝突は、パリティ(相互確証核破壊)のためにほとんど問題外だった。周辺諸国(アジア、アフリカ、ラテンアメリカ)は、勢力均衡を部分的に見直すための中間地帯を形成していた。
両極の一方が崩壊した後(1991年のソ連崩壊)、二極体制は終焉した。これは、代替的な世界秩序の出現のための前提条件を生み出した。多くのアナリストやIRの専門家は、「ヤルタ体制の終焉」について正しく語り始めた8。事実上の主権を認めながらも、ヤルタ世界は、対称的で比較的均衡のとれた2つの覇権の均衡という原則の上に成り立っていた。一方の覇権国が歴史の舞台から退場すると、体制全体が消滅した。一極世界秩序、すなわち「一極モーメント」の時代が到来したのである9。
多極化した世界は、(20世紀後半に私たちが知っていたような)二極化した世界ではない。というのも、今日、米国とNATO諸国の力に戦略的に対抗できる勢力は存在せず、さらに、米国の新たな、今度は唯一の覇権が依拠する自由民主主義、資本主義、「人権」のイデオロギーに対して、人類のかなりの部分を結集して厳格なイデオロギー的対抗を行うことのできる一般的で明確なイデオロギーも存在しないからだ。現代のロシアも、中国も、インドも、その他のいかなる国家も、現在の状況では、第二極の地位を自ら主張することはできない。イデオロギー的にも(マルクス主義の広範な魅力の終焉)、戦略的潜在力と蓄積された軍事技術的資源(過去30年間、米国とNATOは、軍事的、戦略的、経済的、技術的に、どの国も彼らと対称的に競争することができないほど、大きくリードしてきた)からも、二極性の再確立は不可能である。
多極化は一極世界と相容れない
ソ連の崩壊は同時に、強力で対称的な超大国の消滅と、巨大なイデオロギー陣営全体の消滅を意味した。これは、2つの世界覇権のうちの1つの終焉であった。この瞬間から、世界秩序の構造全体が不可逆的かつ大幅に変化した。
同時に、米国が主導し、自由民主主義資本主義イデオロギーに基づく残りの一極は、現象として維持され、その社会政治システム(民主主義、市場、人権イデオロギー)を世界的規模で拡大し続けた。これが一極世界、一極世界秩序と呼ばれるものである。このような世界では、基本的なグローバルな問題に関する意思決定の中心はひとつである。西側諸国とその中核であるアメリカを中心とするユーロ・大西洋共同体は、唯一残されたヘゲモニーの役割を担うことになった。このような状況下では、地球上の空間全体が、(ウォーラーステインのネオ・マルクス主義理論で説明される)三重の地域化を示している10。すなわち、中核の地域(「豊かな北」、「中心」)、世界の周縁の地域(「貧しい南」、「周縁」)、そして中間の地域(資本主義的に急速に発展している大国を含む「半周縁」): 中国、インド、ブラジル、太平洋地域の数カ国、そして惰性的に重要な戦略的、経済的、エネルギー的潜在力を保持していたロシアなどである)
1990年代には、世界一極体制が一旦は現実のものとなったかのように見え、一部のアメリカ人アナリストはこれを根拠に「歴史の終わり」(フクヤマ)というテーゼを発表した11。11 このテーゼは、世界がイデオロギー的、政治的、経済的、社会的に完全に一極化し、今後はそこで起こるすべてのプロセスが、思想と利害の戦いに基づく歴史ドラマではなく、自由で民主的な自由主義体制の国内政治が行う方法に類似した、経済主体の経済的(そして比較的平和的な)競争になるということを意味していた。民主主義はグローバルになる。地球上には、西側諸国とその周辺、つまり西側諸国に徐々に統合されていく国々しか存在しない。
アメリカの新保守主義者たちは、新しいグローバルな世界秩序におけるアメリカの役割を強調し、時には公然とアメリカを「新しい帝国」(カプラン)12、あるいは「有益なグローバル覇権」(クリストル、ケイガン)13と宣言し、「アメリカの世紀」(新アメリカの世紀のためのプロジェクト)14の到来を予見した。将来の世界秩序はアメリカ中心の構築と見なされ、その中心は世界的な裁定者であり「自由と民主主義」の原則を体現する役割を担うアメリカであり、この中心を中心に他の国々の星団が構成され、程度の差こそあれアメリカ・モデルを再現する。それらは、地理的条件やアメリカとの類似性の度合いによって異なっている。ほぼ輪に近いのはヨーロッパと日本の国々で、次に急速に発展しているアジアの自由主義諸国、そしてそれ以外の国々である。さまざまな軌道を描く「グローバル・アメリカ」の周りの帯はすべて、「民主化」と「アメリカ化」のプロセスに含まれている。アメリカの価値観の広がりは、現実的なアメリカの利益の実現と、世界規模でのアメリカの直接支配領域の拡大とともに起こる。
戦略的なレベルでは、一極性はNATOにおけるアメリカの中心的な役割、ひいてはNATOの軍事力を合わせた非対称的な優位性が、他のすべての世界大国を凌駕していることに表れている。同時に、西側諸国は経済力や技術開発などにおいて、他の非西側諸国を圧倒している。そして最も重要なことは、まさに西側こそが、今日世界の他のすべての国々にとって普遍的な基準とされている価値観や規範の体系が歴史的に形成され、統合された母体であるということである。私たちはこれをグローバルな知的覇権と呼ぶことができる。知的覇権は、一方では世界支配の技術的インフラストラクチャーとして機能し、他方では支配的な惑星パラダイムの中心に位置している。物質的ヘゲモニーは、精神的、知的、認知的、文化的、情報的ヘゲモニーと密接な関係にある。
原則的に、アメリカの政治エリートは、まさにこのような意識的な覇権主義的方法で支配している。しかし、新保守主義者たちはこのことを公然かつ透明に語るのに対し、他の政治的・思想的傾向の代表者たちは、より間接的な表現を好む。アメリカ国内では、一極世界を批判する人たちでさえ、アメリカの価値観の「普遍性」と、それを世界的規模で主張しようとする努力を疑問視することはない。異論が集中するのは、このプロジェクトが中長期的な視野でどれほど現実的なのか、アメリカは世界帝国の重荷を自力で背負うことができるのかという問題である。このような直接的で公然たるアメリカの支配への道筋における問題は、1990年代には現実のものとなったかに見えたため、(この言葉を紹介したクラウトハマーを含む)アメリカのアナリストの中には、「一極支配の瞬間」の終焉を口にする者もいた15。しかし、何はともあれ、公然であれ隠然であれ、何らかのかたちでの一極支配こそが、1991年以降に現実のものとなった世界秩序のモデルであり、今日でもそうあり続けている。
一極集中は、実際にはウェストファリア体制の名目的な維持と、二極世界の惰性的な残滓を伴っている
以前と同様、すべての国民国家の主権は事実上認められている。国連安全保障理事会は、依然として「冷戦」の現実に対応する勢力均衡を部分的に反映している。
したがって、アメリカの一極覇権は事実上、国際関係史における他の時代やサイクルの勢力均衡を表現する多くの国際機関と同時に存在している。事実上の状態と事実上の状態との間の矛盾は、アメリカまたは西側連合による主権国家への直接介入行為(同様の行為に対する安全保障理事会の拒否権を回避することもある)において、その一端を常に明らかにしている。2003年のアメリカのイラク侵攻のようなケースでは、(ウェストファリア・モデルを無視した)独立国家主権の原則の一方的な違反や、国連安全保障理事会におけるロシアの立場(プーチンの立場)への配慮の拒否、さらにはヨーロッパのNATOパートナー(フランスのシラク、ドイツのシュレーダー)の抗議に対するワシントンの不注意の例も見られる。
最も一貫した一極集中支持者(例えば、共和党のジョン・マケイン)は、真のパワーバランスに対応する世界秩序の確立を主張している。彼らは、国連の代わりに別のモデル、すなわち「民主主義連盟」16を創設することを提案している。そこでは、米国の支配的な地位、すなわち一極支配が法的に確保されることになる。このような一極世界と「アメリカ帝国」の覇権的地位の国際関係構造における合法化プロジェクトは、世界政治システムの進化の可能な方向性の一つである。多極的世界秩序が単に一極的世界秩序と異なるだけでなく、その直接的なアンチテーゼであることは明白である。一極主義は、一つのヘゲモニーと一つの意思決定の中心を提案する。多極主義は、複数の中心を主張し、どの中心も排他的な権利を持たず、他の国々の立場を考慮しなければならない。したがって、多極化は一極化に代わる直接的な論理的選択肢である。論理のルールに従えば、世界は一極か多極かのどちらかである。同時に、重要なのは、どちらか一方のモデルが法的にどのように定式化されているかではなく、それが事実上どのようになっているかである。冷戦時代、外交官や政治家は渋々ながら二極性を認めたが、それは明白な事実であった。つまり、外交用語と具体的な現実を区別する必要がある。今日の世界秩序は事実上、一極世界としてアレンジされている。これが良いことなのか悪いことなのか、夜明けなのか日暮れなのか、長く続くのかすぐに終わるのか、私たちは議論することしかできない。しかし、事実は事実である。私たちは一極集中の世界に生きている。一極集中は続いている(すでに終わりつつあると主張するアナリストもいるが)。
多極世界は無極ではない
厳格な一極主義を批判するアメリカ人、特に外交問題評議会を中心とする新保守主義者のイデオロギー的ライバルたちは、一極性の代わりに非極性という別の言葉を提唱した。このようにして、西欧の知的・価値的ヘゲモニーは継続する。グローバルな世界は、自由主義、民主主義、自由市場、人権の世界となるだろう。しかし、この理論の支持者によれば、国力とグローバリゼーションのリーダーとしてのアメリカの役割は縮小する。アメリカの直接的な覇権の代わりに、「グローバル・ガバナンス」というモデルが形成され、そこには一般的な価値観に連帯する各国の代表が参加し、世界的に単一の社会政治的空間の確立に向かって進むことになる。私たちはここでもまた、「歴史の終わり」(フクヤマ)に類似したものを扱っている。無極の世界は、暗黙のうちに民主主義諸国の協力に基づいている。しかし徐々に、その確立の過程において、他の非国家主体も含まれるようになるはずだ: NGO、社会運動、個別の市民グループ、ネットワーク社会などである。無極世界の確立における主要な実践は、重要な出来事や全人類の行動に関するオンライン惑星国民投票に至るまで、意思決定のレベルを1つの権威(今日ではワシントン)から、より低いレベルの多くの権威へと分散させることである。経済が政治に取って代わり、市場競争がすべての国境を一掃する。安全保障は国家の問題から市民自身の問題へと変化する。グローバル・デモクラシーの時代が到来する。
一般的な特徴として、この理論はグローバリゼーションと一致し、一極世界に取って代わるべき段階であると考えられている。しかし、アメリカと西側諸国が今日進めている社会政治的、価値観的、技術的、経済的モデル(リベラル・デモクラシー)が普遍的な現象となり、アメリカによる民主主義とリベラルな理想の強力な擁護の必要性がなくなるという条件のもとでなければ、西側諸国、民主化、アメリカ化に反対するすべての体制は、無極世界の到来までに破壊されるだろう。すべての国のエリートは、歴史的、地理的、宗教的、国家的起源に関係なく、同質の資本主義的、自由主義的、民主主義的、一言で言えば「西洋的」であるべきというものだ。
無極世界のプロジェクトは、ロスチャイルド家からソロス・ファンドまで、多くの影響力のある政治・金融グループによって支えられている。
無極世界のプロジェクトは未来に向けられている。それは、一極集中に取って代わるべき世界的な形成として、またそれに続くものとして考えられている。それは代替案というよりも、継続だ。そしてこの継続は、社会の重心が、物質的(アメリカの軍産複合体、西側の経済と資源)と精神的(規範、手続き、価値観)という2つのレベルの覇権の同盟という今日の組み合わせから、純粋に知的な覇権へと移行し、物質的な支配の重要性が徐々に薄れていく場合にのみ可能となる。これはグローバル情報社会であり、知性の支配、意識のコントロール、仮想世界のプログラミングを通じて、理性の領域で主要な統治が展開される。
一極的世界は、将来の世界秩序の序論としての一極的瞬間の妥当性も、西欧の知的覇権も、その価値観の普遍性も、文化的・文明的アイデンティティを考慮することなく、意思決定レベルを惑星的多数に拡散することも認めないため、非極的世界のプロジェクトとは決して一致しない。無極の世界は、アメリカ型のるつぼを世界中に広めることを提案している。その結果、民族間や国家間のあらゆる違いが消え去り、個人化、原子化した人類は、国境のないコスモポリタンな「市民社会」となる。多極化は、意思決定の中心はかなり高いレベルにとどまるべきであり(ただし、今日の一極世界のように一カ所にとどまるべきでない)、それぞれの具体的な文明の文化的特殊性は(単一のコスモポリタン的多数に溶解するのではなく)保存され、強化されるべきであると考える。
多極主義は多国間主義ではない
世界秩序のもう一つのモデルは、アメリカの直接的な覇権主義からやや距離を置いた多国間主義である。この概念はアメリカ民主党に広く浸透しており、バラク・オバマ大統領は外交政策においてまさにこのモデルに従った。アメリカの外交政策論争において、このアプローチは新保守主義者が主張する一極主義とは対照的である。
多国間主義とは、実際には、アメリカが国際関係の領域において、完全に自国の力だけに頼って行動し、帝国主義的なやり方ですべての同盟国や「属国」に情報を提供すべきではないということである。その代わりに、ワシントンはパートナーの立場を考慮し、パートナーとの対話の中で決定を主張し、説得し、合理的な結論と時には妥協によってパートナーを自国の側に引きつけるべきである。その場合、アメリカは「対等の中の第一人者」であるべきであり、「部下の中の独裁者」であってはならない。このため、米国は外交政策において同盟国に対して一定の義務を負い、共有された戦略への服従を求められる。この一般的な戦略とは、現在の場合、世界的な民主主義、市場、人権イデオロギーの惑星規模での実現を目指す西側の戦略である。しかし、この過程において、指導者であるアメリカは、自国の国益を、その名の下に行動する西洋文明の「普遍的」価値観と直接同一視すべきではない。場合によっては同盟を組んで行動し、時にはパートナーに何かを譲歩することも望ましい。
多国間主義が一極主義と異なるのは、ここでは西洋全体、特にその「価値」(すなわち規範)の側面に重点が置かれている点である。この点で、多国間主義を擁護する人々は、無極世界を支持する人々と似ている。多国間主義と無極主義の違いは、多国間主義が民主的な西側諸国間の協調を重視するのに対し、無極主義は非国家的なプレーヤーもアクターとして含むという事実にある: NGO、ネットワーク、社会運動などである。
実際、オバマとヒラリー・クリントン国務長官が発表した多国間政策は、新保守主義者が支配していたジョージ・W・ブッシュ政権の直接的で透明な帝国主義とほとんど変わらなかったことは重要である。アメリカの軍事介入は続いており(リビア)、アメリカ軍は占領下のアフガニスタンとイラクに駐留し続けている。
多極化した世界は、多国間世界秩序とは一致しない。なぜなら、西欧的価値観の普遍主義に同意せず、「豊かな北」の国々が、単独でも集団でもなく、全人類の名において行動し、最も重要な問題に関する意思決定の唯一の中心として(たとえ複合的であっても)行動する権利を認めないからだ。
まとめ
「多極化」という概念の意味を、並置された、あるいは代替的な用語の連鎖によって定義することは、私たちが多極化の理論を構築するために進めなければならない意味論的分野の輪郭を描くことになる。これまで私たちは、多極性とは何でないかということだけを語ってきた。このような否定と区別によって、私たちは対照的に、多くの構成的でむしろ肯定的な特徴を区別することができる。私たちが行った一連の区別から生まれた第二の、肯定的な部分を要約すると、おおよそ次のような図式になる:
- 1. 多極化した世界とは、(現実に存在する)一極化した世界に代わる急進的なものであり、惑星レベルでグローバルな戦略的意思決定を行う、独立した主権を持つ複数の中心が存在することを主張するものである;
- 2. これらの中心地は、今日の世界で最も強力な勢力をモデルとすることができるような、想定される敵の侵略に直面しても、その主権を物質的なレベルで守ることができるような、十分な装備を備え、物質的に独立していなければならない。この要求は、米国とNATOの物質的、軍事的、戦略的覇権に対抗する可能性を意味する;
- 3. これらの意思決定センターは、西洋の規範や価値観(民主主義、自由主義、自由市場、議会主義、人権、個人主義、コスモポリタニズムなど)を必須条件として認める義務はなく、西洋の精神的ヘゲモニーから完全に独立することができる;
- 4. 多極世界は、二極体制への回帰を提案するものではない。なぜなら、現代の西側諸国とそのリーダーであるアメリカの物質的・精神的ヘゲモニーに単独で対抗できる勢力は、戦略的にもイデオロギー的にも存在しないからだ。多極化した世界には、2極以上が存在しなければならない。
- 5. 多極化した世界では、既存の国民国家の主権は、それが純粋に法的なレベルで宣言され、十分な軍事的、戦略的、経済的、政治的潜在力の存在によって確認されない限り、深刻なものとは考えない。21世紀に主権を持つ主体であるためには、もはや国民国家だけでは十分ではない。このような状況下では、国家の集合体や連合体のみが真の主権を持つことができる。ウェストファリア体制は、事実上存続し続けているが、もはや国際関係の現実のシステムを反映しておらず、再考されるべきである。
- 6. 多極化は、世界政府の権威にも、アメリカとその民主的同盟国(「グローバル・ウェスト」)のクラブにも、ネットワーク、NGO、その他の市民社会アクターの超国家レベルにも、意思決定の中心(極)を置いていないため、非極性にも多国間主義にも還元できない。極は他のどこかになければならない。
これら6つのポイントは、さらなる推敲のための舞台を整え、多極化の主な特徴を概念的に体現している。しかし、この記述は、多極化の本質についての理解を大きく前進させたとはいえ、理論の地位を主張するにはまだ不十分である。これは最初の一歩であり、本格的な理論化はこれから始まる。
今日、[国際関係の]利用可能などのパラダイムにおいても、多極化する世界についての理論が用意されているわけではないし、ましてやそのような理論のための場所すら確保されていない。長い間、国際関係学は主にアメリカで発展したため、「アメリカの科学」とみなされてきた。しかしここ数十年、国際関係学は世界中の科学機関や組織でより広く研究されるようになった。しかし、この学問分野にはいまだに西洋中心主義が色濃く残っている。近代という時代に西洋諸国で発展した学問であり、もともとその学問が生まれ、確立された背景との歴史的・地理的な結びつきを保っている。これは特に、IRが学問分野として形成された際の主要な議論の軸(現実主義者対リベラル派)に表れており、まさにアメリカの外交政策に特有の悩みや問題の性質を反映していた(ある意味で、孤立主義者と膨張主義者の間の古典的なアメリカの議論を繰り返している)。最新の段階では、特に後実証主義的アプローチの領域において、アメリカ中心主義(一般的には西洋中心主義)を相対化する傾向が明らかに生じている。理論や方法の民主化、基準の拡大、IRにおけるアクターの均質な広がりへの衝動がその存在を明らかにし、その意味構造やアイデンティティをより注意深く(「厚く」)分析するようになった。これは西洋の認識論的ヘゲモニーの相対化への一歩である。しかし、現在に至るまで、西洋の覇権に対する批判でさえ、まさにその覇権の法則に従って進められてきた。こうして、民主主義や民主化、自由や平等といった西洋の典型的な概念が、あたかもこれらの概念が「普遍的なもの」であるかのように、非西洋社会に転嫁され、時には西洋に反対さえされるのである18。もし西洋への反対が、西洋的価値の普遍性という旗印のもとに進めば、この反対は不毛なものとなる運命にある。
したがって、西洋中心文明の枠から出るためには、西洋批判を構成する理論的概念や方法論的戦略のすべてから距離を置く必要がある。現実には、代替的なIRモデル、ひいては代替的な世界秩序構造は、IRにおける西洋理論の全領域–第一義的には実証主義的なものだが、部分的には後実証主義的なものもある–に対抗することによってのみ形成されうる。
私たちが考察してきたIR理論家の中に多極化世界理論(TMW)が存在しないのは、迷惑な事故や無視の兆候ではなく、まったく法則的な事実である。とはいえ、理論的には十分に構築可能である。そして、既存のIR理論の広範なパノラマを考慮に入れることは、それを正しく定式化するのに役立つだけだ。
そのような理論の構築を真剣に開始し、IRの領域における西洋の認識的ヘゲモニーから最初に距離を置くならば、つまり、既存のIR理論のスペクトルを公理的ベースとして疑問視するならば、第二段階では、その領域から個別の要素を借用することができ、その都度、どのような条件で、どのような文脈でそうするのかを詳細に規定することができる。厳密には、多極化世界理論の構築に関連する既存のIR理論はない。しかし、それらの多くは、逆に、ある状況下ではTMWに統合することができる要素を含んでいる。
3. 行為者としての文明大空間とポリテイア
ハンチントンの理論文明概念の導入
ポスト実証主義的なIR理論が大きな意味を持っているにもかかわらず、彼らではなく、アメリカ政治における保守主義運動の代表者である現実主義的な政治哲学者サミュエル・ハンティントンがTMWに最も近づいた。彼の論文と後に出版された『文明の衝突』では、現代世界におけるパワーバランスの概念図が展開されている。
彼を世界的に有名にし、反響ストームを巻き起こしたこの著作で、ハンティントンは二極世界の崩壊に続く世界秩序の新たな状況を考察している。彼は、彼の弟子であり、もう一人の有名な政治アナリストであるフクヤマと対立している。フクヤマは、二極世界の終わりを解釈し、「歴史の終わり」、すなわち自由民主主義モデルとグローバリゼーションの事実上の世界的勝利という結論に達した。IRの新自由主義パラダイムの精神に則り、フクヤマはこう考えた:
- 民主主義は全世界にとって普遍的な規範となった、
- 「民主主義国家は民主主義国家と戦わない」ので、今後、軍事紛争の脅威は(完全に排除されないとしても)最小化されるだろう、
- グローバルな経済競争が唯一の規範となりつつある、
- 国民国家の代わりに市民社会が承認された、
- 世界政府を宣言する時が近づいているのだ。
ハンチントンはこれに対し、悲観的な立場から反論する。彼によれば
- 二極世界の終焉は、グローバルで均質な自由民主主義的世界秩序の確立に自動的につながるわけではない、
- 歴史は終わっていない、
- 紛争や戦争の終わりを語るのは時期尚早である。
私たちは二極化を止めたが、グローバル化も一極化もしなかった。新たな衝突、新たな衝突、緊張、対立を伴う、まったく新しい構図が築かれたのである。ここでハンティントンは最も重要なポイントに接近し、誰がこの未来の世界の主役になるのかという問題に関して、絶対的に基本的でありながら、いまだ過小評価されている仮説を提唱する。彼はこの行為者として文明を挙げる。
まさにこの概念的な一歩は、まったく新しい理論、すなわち「多極化する世界の理論」の出現の始まりとみなされるべきである。ハンティントンは最も重要なことを成し遂げた。彼は文明という新たな行為者を区別し、同時に複数の行為者について語り、論文のタイトルにこの言葉の複数形である「文明の衝突」を用いたのである。
この主要な点でハンティントンに同意するならば、私たちは、古典的なIR理論やポストポジティビズムのパラダイムの限界さえも超越した概念的領域にいることに気づくだろう。私たちは、文明の多元性を認識し、それらを国際関係の新しいシステムにおける主要なアクター(単位)として特定するだけで、多極化した世界地図の第一次近似図を手に入れることができる。さて、この多極秩序における極とは何か、極とは文明であることを確認した。その結果、多極化した世界にはいくつの極がなければならないのかという基本的な問いに、すぐに答えることができる。答えは、文明の数だけある。
こうして、ハンティントンのおかげで、新しい理論のフレームが第一近似値として得られた。この理論は、国際関係の分野における世界的な意思決定の中心がいくつか存在し、その中心が対応する文明であるというモデルを仮定している。
ハンティントンは歴史的にはIRのリアリズム学派に属する。それゆえ、彼は文明を新しい世界秩序のアクターとして区別することから、文明間の紛争(衝突)の可能性の分析へと一気に移行した。基本的なリアリズムのモデルは、国益の評価において同じように構築される。そもそも彼らは、国際関係の分析において、衝突の可能性、利害の衝突領域、防衛と安全保障の確保の可能性を考慮する。しかし、根本的な違いは、古典的リアリストがこれらの基準を、国際関係における主要かつ唯一のアクターであり、厳密で法的に構成され、国際的に認知された現実としての国民国家に適用するのに対し、ハンチントンは同じアプローチを、より明確で概念的に精緻でない概念である文明に適用していることである。とはいえ、まさにハンチントンの直観と、新しい世界秩序のアクターの定義が国民国家から文明へと質的に変化したことは、彼の理論の最も重要な側面である。それは、国際関係の構造を理解するためのまったく新しい道を開き、TMWの基礎を築くものである。
IRにおける「文明」概念
ここで、文明とは何か、TMWにとって基本的なこの用語が何を意味するのかを理解することが重要である。
文明とは、実証主義であれ後実証主義であれ、どのIR理論にも登場しない概念である。文明とは、国家でも政治体制でも階級でもネットワークでも社会[soobshchestvo]でもなく、個人の集団でもなく、個別の個人でもない。文明とは集団的共同体[obshchnost’]であり、同じ精神的、歴史的、文化的、精神的、象徴的伝統(その根源は宗教的であることが多いが、必ずしも具体的な宗教として実現されているわけではない)に属することによって結ばれ、その構成員は、国家的、階級的、政治的、イデオロギー的な帰属に関係なく、互いに親密さを感じている。
シュペングラーの古典的著作の後、彼に倣って「文明」と「文化」を区別し、「文化」を精神的・知的共同体として、「文明」を合理的・技術的な取り決めや構造として理解する著者もいる。シュペングラーによれば、文明とは「冷え切った」文化であり、内なる力や発展・繁栄への意志を失い、疎外された機械的形態に沈んだ文化のことである。しかし、この区別は一般には受け入れられず、大半の著作(例えばトインビーの著作)では「文明」と「文化」の概念は実質的に同義である。私たちにとって重要なのは、ハンチントンが「文明」を「文化」と実質的に同じものとして理解していることであり、したがって、文明を記述し列挙する際に、彼が主に宗教や宗教制度に言及しているのは間違いではない。
IRの理論分野において、この概念は初めて提起され、グローバル政治の潜在的なアクターとして位置づけられたにすぎない。ブザンとリトルの分類によれば、次のようになる:
- 古典的または古代の国際関係システム(伝統的社会、前近代)では、伝統的な国家と帝国が主要なアクターである;
- グローバルシステム(近代における国際関係)では、ブルジョア国民国家が主体である;
- 最新のポストモダンシステムでは、伝統的国家と並んで、ネットワーク社会、非対称集団、その他の「マルチチュード」が主役である。
そのどれもが、文明をアクターとして持っていない。概念としての「文明」は歴史学、社会学、文化学に登場する。しかしIRでは、この概念は初めて導入された。
IRにおいて文明の仮説を提唱するハンチントンの論理は、極めて明快である。資本主義と社会主義という2つのイデオロギー陣営の対立と二極世界の終焉は、資本主義の勝利とソ連の崩壊によって終わる。今後、資本主義西側諸国には、合理的かつ知的なレベルで自らの立場を正当化し、対称的な代替世界体制を提示し、実際に競争力を証明できる「形式的」敵対者はもはや存在しない。フクヤマはこのことから、西側はグローバルな現象になり、世界のすべての国や社会は、議会制民主主義、市場経済、人権のイデオロギーをわずかな違いはあっても再生産する、ひとつの均質な場となったと急いで結論づける。このように、フクヤマにとって、国民国家の時代は過ぎ去り、世界は完全かつ最終的な統合の危機に瀕している。人類は目の前でグローバルな市民社会へと変貌を遂げ、政治は経済に道を譲り、戦争は貿易に完全に取って代わられ、自由主義イデオロギーは代替案のない普遍的に認められた規範となり、あらゆる民族と文化がひとつのコスモポリタンのるつぼの中で混ざり合っている。
この場合、フクヤマは「薄い」分析のルールに従っている。彼は、起きている出来事の主要で最も顕著な特徴を完全に正しく区別している。実際、社会主義の終焉は、リベラル・デモクラシーの最も深刻で印象的なイデオロギー的敵対者を歴史的舞台から排除し、後者を「普遍的」にした。今日、自由主義と真剣に競い合えるほどの範囲、魅力、信頼を持つイデオロギーは他にない。事実上、世界のすべての国が西洋文明の規範を受け入れている。民主主義、市場経済、報道の自由の規範を無視している社会はごくわずかしか残っておらず、それらは西洋モデルへの移行期にある。これは「歴史の終わり」を告げるに十分な理由であり、もしそれが到来していないのであれば、到来しようとしている。同様の結論に達したのは、アメリカの覇権主義を公然と正当化するネオリアリスト(ギルピン、クラウトハマー)、東欧圏の民主主義者の勝利を熱狂的に歓迎するネオリベラリスト、そして人間の自由の新たな地平をグローバリゼーションに見出すポストモダニストたちである。
ハンティントンは、このような「分厚い」分析に対抗して、分析されたプロセスの細部や質的側面にもっと注意を払い、ポスト二極世界の変容の深い次元をよりよく理解しようと努めている。彼は、近代化と民主化、そして市場自由主義の規範は、実際には西欧社会だけに影響を及ぼし、他のすべての国々は、自国の文化の深みにそれらを含めることなく、必要性の圧力の下でこれらのゲームのルールを受け入れ、現実的に西欧文明の個別の応用的・技術的要素だけを借用したという結論に達した。このように、ハンチントンは、非西洋社会の代表者が西洋の個別の技術を借用しながらも、それを現地の状況に適応させようと努力し、しばしば西洋に反抗する「西洋化なき近代化」という現象が非西洋諸国に広く見られると語っている。それによって、非西洋諸国の民主化と近代化は、「厚い」分析に照らし合わせると、曖昧で相対的なものとなり、したがって、こうしたプロセスの内的論理を考慮に入れなければ、もはや期待される結果を保証することはできない。西洋がその国境を拡大し、その中に「残りの非西洋社会」を含めれば含めるほど、この両義性は強まり、西洋と、伝統的な社会構造との結びつきを維持しながら新技術を受け入れ、その潜在力を強化してきた非西洋地域との間の格差はますます拡大する。このような状況が、技術的なIR概念としての「文明」の概念につながっている。
21世紀のIRの構造における文明とは、近代化の影響を受け、西洋の技術に依存しながら、その力と知的潜在力を強化する一方で、西洋の価値体系を全面的に受け入れるのではなく、自国の伝統的な文化、宗教、社会複合体との有機的で強固な結びつきを維持し、時には西洋のそれと鋭く対立したり、対立したりする広範な空間的領域を指す。
社会主義陣営の崩壊は、こうしたプロセスを促進し、この現状を露呈させるだけだ。東西の対称的な対立の代わりに、いくつかの文明間の緊張の場が出現する。今日、国境によって分断されることが最も多いこれらの文明は、グローバリゼーションと統合の過程で、自分たちの共同体をより密接に意識するようになり、国際関係のシステムの中で、自分たちの価値観とその価値観から生じる利益に導かれて行動するようになる。このようなプロセスが進展し、「西洋化なき近代化」が成功した場合、世界規模でのパワーバランスについて、基本的に新しい図式が生まれる。これが多極化世界である。
TMWにおける「文明」概念のスペクトルを広げる:定義
「文明」という概念は、多極化世界理論(TMW)において重要な役割を果たす。したがって、この概念をさまざまな側面から考察し、さまざまな解釈を与えることは極めて重要である。この問題では、「厳密な正統性」やその他の一義的な定義を主張するのは時期尚早である。というのも、私たちが扱っているのは、多極化の本格的な理論を確立することが唯一可能なイデオロギー圏に対応する、主として新しい理論的文脈だからだ。
法律上の現実となるためには、「文明」は、シュミットが「大きな空間」と呼んだもの、そしてTMWでは過渡的な理論モデルあるいは「前概念」とみなされているものと組み合わされなければならない。したがって、現在の状況を図式的に表すことができる:
- 1. 文明(社会文化的事実);
- 2. 広い空間(地政学用語、前概念);
- 3. TMWを基礎として法的に形成された国際秩序(TMWの法的側面)。
第一のレベルから第二のレベルへ移行するためには、「文明」とは何かをより正確に理解する必要がある。ここで、いくつかのアプローチが考えられる。主なものを見ていこう。
実体としての文明(文明の存在論的概念)
文明を自律的な実体としてとらえるには、存在論的な優先順位を与えることが必要である。この場合、「文明」はアリストテレス的な「実体」の範疇に対応し、τὸ τί ναι εἶ ναιという問いに答える26。この文明の考えは、述語によって拡張される概念場の中心に文明を置く。文明が物質に対応するのであれば、述語の集合がそれぞれの具体的事例において文明を記述し、その質的内容をあらかじめ決定する。物質としての文明は、ある述語群によって記述され、別の文明は別の述語群によって記述される、といった具合である。
物質としての文明間の相互作用と相互影響が追跡できる。「物」(res)としての物質は、静的かつ運動的であるとみなすことができ、また(その特異な力-ポテンシャルの観点から)動的であるとみなすこともできる。
アリストテレス・モデルを続けると、文明のエンテレキと、その「自然の場所」への引力の見通しについて語ることができる。
プロセスとしての文明(文明の動的概念)
このアプローチは、ブローデルが「la grande durée」、すなわち 「長い周期」と呼んだ枠組みで文明を考察することを提案している。プロセスとしての文明論を最初に提唱したのはノルベルト・エリアス(1939)である。この場合、文明とはあらゆる要素の絶え間ない変化であり、それは文明が頂点に達し、革命、動乱、戦争の時代に入ったときに初めて顕著になる。しかし、文明の秩序における変化は常に起こっている。
このように、文明とは、ミクロのレベルで絶え間ない変動が起こり、変化が積み重なり、要素間の関係が変容する状態なのである。このようなアプローチは、アナリス学派の方法に相当し、一定の同一性を前提とする実質主義的アプローチとは大きく異なる。これとは対照的に、動的アプローチは、文明のアイデンティティは絶えず変化し、その結果、歴史的瞬間ごとに注意深く検討され、その意味論的領域が必然的に詳細に研究されなければならないことを示唆している。
システムとしての文明(文明のシステム概念)
システミックなアプローチは、全体としてはダイナミックなアプローチに近いが、ミクロとメゾのプロセスのバランスの総体を表す全般的な支配の変化に注目する。この場合、文明は社会文化システム(ソロキン)または歴史文化タイプ(ダニレフスキー)とみなすことができる。
文明への体系的アプローチは、シュペングラー(文明と文化の二元論に基づく)、トインビー(文明のリストを拡張することを提案)、グミレフ(文明研究を民族学的視点と「情熱性」の独創的理論と組み合わせた)にも特徴的である。
構造としての文明(文明の構造・機能・形態学的概念)
体系的アプローチとは対照的に、構造的アプローチは文明を不変の現象として考察し、その内部での変化は本質的な形態学的変化をもたらさない。文明の形態は、その存在のさまざまな段階において不変であり、その基本構造の不変性において表現される。
これらの構造とその「物質的」具現化が変化し、その表現が異なる性格を獲得し、何らかのイデオロギー的、宗教的、文化的複合体を通して現れることは、別の問題である。しかし同時に、主要な要素間の機能的意義と対応関係は、どのような場合でも変わることなく維持される。実体主義的アプローチとは対照的に、構造的アプローチは存在論的ではなく、認識論的、グノセオロジー的な連続性を強調する。
パイデウマとしての文明(文明の教育概念)
歴史的な「文化界」学派の代表者、特にレオ・フロベニウスによって展開されたパイデウマの理論は、文明に対する認識論的アプローチをより正確にしたものである。フロベニウスは、ある社会から別の社会への文化の伝達を、パイデウマと呼ばれるある教育的規範の伝達として考察している。この規範の構造は、政治と経済の領域においても、精神文化、儀式、儀礼、シンボルなどの領域においても、文明の主な実践を決定する。
したがって文明とは、人が指導することができ、また指導されるべきものなのである。
パイデウマとしての文明の概念と「文化サークル」のモデルを組み合わせることで、古代文明の拡散の道筋をたどることができ、このプロセスが現代世界でも続いていることがわかる。
このモデルでは、教育の問題が注目の中心を占める。
価値観の集合としての文明(文明の公理学的概念)
文明は、ある社会で規範の地位を獲得する価値観の総体に還元することができる。この公理論的アプローチはウェーバーの社会学に含まれており、よく知られている。文明構造の詳細な分析に入ることなく、また体系的発展の論理を理解するふりをすることなく、公理論的アプローチによって、文明をその最も明確なしるし(価値)に基づいて操作的に記述し、その体系的階層を構築し、比較分析を行うことができる。
このアプローチは、人類学者(ガーツ)が言うところの「薄い記述」の精神に則り、分析を表現したり、「文明のパスポート」を効率的に構成したりするのに便利である。
組織化された無意識としての文明(文明の精神分析的概念)
文明の精神分析的解釈は、フロイト自身の後期の著作(特に『トーテムとタブー』)を土台とすることができ、そこでは文化的事実の分析に精神分析を適用することが提案されている。特にこの再構築では、「エディプス・コンプレックス」はすべての人間社会にとって社会形成的要素である。このテーゼは後に社会人類学の代表者たちによって反論されたが(彼らは、「エディプス・コンプレックス」の前提条件が欠けている文化もあることを示した–特にトロブリアンド諸島の原住民の母系制文化において)、精神分析を文化の解釈に適用するという考えは、その正当性を証明した。
文明の理解にとってさらに生産的なのは、ユングの「集合的無意識」という考え方である。ユング自身は、その仕事のさまざまな段階において、これを異なって理解していたが、さまざまな社会の代表者の間でその構造が異なっていることは、経験的な事実である。これに基づいて、精神分析的な文明地図を作ることができる。
私たちは、文化的・文明的コードをさまざまな想像力の働きの結果として解釈することを可能にする、彼独自の「奥行きの社会学」を提唱したデュランの理論を、特別な方向性として取り上げることができる。
(宗教的)文化としての文明
ヨーロッパの言語では、文明と文化は同義語として扱われることがあるため、なおさらである。このアプローチの特徴は、文明とその質的内容を定義する際に文化的要素を強調するだけでなく、宗教性が明示的に社会を形成している場合と、他の世俗的なイデオロギーや価値体系を通じて暗黙的に作用している場合の両方において、それぞれの具体的な文明の宗教的基盤に注意を向けることにある。
言語としての文明(文明の言語学的概念)
言語としての文明の定義は、言語学的・文献学的観点からその構造を検討することを提案している。厳密な単一言語社会は存在せず、文明もまた存在しない。したがって、文明には常に一つの(時には二つ以上の)共通語(lingua franca)が存在し、その他の言語も一般的な意味や概念と絡み合っている。言語と言語遺産は、文明の一般的な等価物として機能し、比較言語学と記号論のツールの助けを借りて文明の比較を可能にする。
あるレベルでは、文明に対するこのアプローチは、構造主義的アプローチと組み合わせることができる。
エスノスからの最初の派生物としての文明(文明の民族社会学的概念)
『民族社会学』(Ethnosociology)という本の中で、社会と社会構造をエスノスとその古代の状態に関連づける方法を通して解釈するモデルが詳しく説明されている。このモデルでは、文明は(国家や宗教と並んで)専門用語として扱われ、その最初の質的複合化の結果として、エスノスからラオス(ナロード)への移行を意味する27。ナロードがエスノスと異なるのは、その構造がより分化していること、社会的に階層化されていること(エリートと大衆)、ロゴスの構造が強い地位を帯びていること、他者の図が注目の中心に立っていることである。国家や宗教とは対照的に、文明は文化、哲学、芸術における高度な差異を体現している。多くの場合、国家、宗教、文明は手を取り合っている。民族社会学は、エスノスから派生する他の連鎖の中に、歴史文化現象としての文明の位置を見出すことを可能にする。特に、文明が前近代のパラダイムや伝統的社会の形態と関連していることは、この再構成から明らかだ。
構築物としての文明(文明の構成主義的概念)
構成主義的アプローチでは、文明についてまったく異なる理解が可能である。このアプローチは、モダニティとポストモダニティのパラダイムに属する。しかし、近代において構築された社会の主要な対象が国家(国民国家)であるとすれば、文明はまさにポストモダンの状況下における構築物であり、投影の結果であると捉えることができる。しかし、自由主義的で、部分的にはガウキスト的なポストモダンは、むしろ、あらゆる社会構造を脱構築すること、つまり、その原子化と特異な個人への訴求(そして、ドゥルーズとグアッテリのリゾーム、器官なき身体、欲望する機械)に至るまで、自らを占有する可能性が高い。しかし、TMWや『第四政治理論』では、ポストモダンの別バージョンに遭遇する。この文脈では、構築の対象は、新たな、この場合は人為的な行為者としての文明となりうる。
デーゼインとしての文明(文明の実存的概念)
第四政治理論(4PT)では、主体はまさに実存的次元を通して概説され、ダーザインと同一視される。複数のデーゼインは複数の文明に対応する。この用語は『マルティン・ハイデガー』の中で説明されている: ロシア哲学の可能性』の中で説明されている。まさにこれによって、4PTとTMWを同じアプローチの二つの側面として結びつけることができる。ここで、文明は一連の実存原理を通して記述することができ、それぞれの実存原理は一つの文明だけに特徴的なものである。ハイデガーが『存在と時間』の中で述べている文明の時間的地平を、もちろんダーザインに当てはめて追跡することもできる。文明の未来は、その文明が真正であることの可能性において成り立っている。その結果、各文明はそれぞれの具体的なEreignisを持つことになる。
人間の規範的場としての文明(文明の人類学的概念)
最後に、人類学者が無文字文化や古代の社会を研究するために用いた方法を、文明にも適用することができる。フランツ・ボースは、社会間にはいかなる尺度も存在しえないこと、そしてそれぞれの社会を理解するには、内面的な参加、埋め込まれた観察、さらには(一時的な)アイデンティティの変化が必要であることを示した。このテーマは、ボアスの弟子たち、アメリカの文化人類学の学派、イギリスの社会人類学の代表者たち、フランスのデュルケムやモースの社会学学派、構造人類学者(レヴィ=ストロース)、ドイツの民族社会学者(トゥルンヴァルト、ミュールマン)たちによっても展開された。
社会学者たちは当初から、人類学的アプロー チを他の非アルカイック社会に適用し始めた(例えば、トマスとズナニエッキの古典的著作『ヨーロッパとアメリカにおけるポーランドの農民』)。このように、人類学的手法の助けを借りて文明を体系的に研究するための前提条件はすべて揃っており、そのようなアプローチの道筋はすでにおおよそ示されている。
理論的には、文明研究に対する他のアプローチを特定することもできそうだが、ここではその列挙は止めておこう。可能な文明研究の質的ボリュームを知るには、13の異なるアプローチで十分である。これらの各アプローチは、他のアプローチと組み合わせることもできるし、「大きな空間」の領域と直接的に組み合わせることもできる。全体としての地政学と空間の社会学は、文明の各概念の場合にも同様の操作を可能にする。空間表現は、実体、プロセス、システム、構造、言語、宗教、文化、無意識、エスノス、Dasein、その他あらゆるものを持つことができる。文明のさまざまな解釈に対応するこのような地図の総体は、「大空間」という前概念に巨大な意味的容積を与えるだろう。予備的な近似から、「大空間」はそれぞれの具体的なケースにおいて、本格的で多次元的な意味論的フィールドへと変容していく。シュミットが「大空間の秩序」と呼んだものへの移行、私たちの場合は多極世界の本格的な法的定式化への移行である。
多極世界の両極/文明のリスト
ハンチントンは以下の文明を挙げている:
- 西洋文明
- 正統(ユーラシア)文明
- イスラム文明
- ヒンドゥー文明
- 中国(儒教)文明
- 日本文明(潜在能力)
- ラテンアメリカ文明
- 仏教文明
- アフリカ文明
これらの文明は、ある歴史的時期に、多極化する世界の両極になる運命にある。
西洋文明
最も明白な文明であり、しばしば唯一かつ普遍的な地位を装っているのが西洋文明である。この文明は、グレコ・ローマ世界から始まり、中世にはキリスト教のエキュメーヌの西半分として最終的に形作られる。今日、それは大西洋の両岸にある2つの戦略的中心地から成っている: 北アメリカ(第一にアメリカ)と西ヨーロッパである。近代とその文明的公理系全体は、この地域で形成された。ここに現在の世界秩序の紛れもなく明白な極がある。ハンチントンはこれを「西側」と呼んでいる。しかし、文明の複数性という図式には、次のような特徴がある。文明としての西洋(複数あるうちの一つ!)は、長い歴史と深い歴史的ルーツを持つ他の文明と並ぶローカルな現象であり、今日、深刻な資源、戦略、経済、政治、人口ポテンシャルを有している。西洋は、他の「大きな空間」の中の「大きな空間」である。西洋文明がリードしているが、それ以外の文明も、その潜在力を総合すれば、ある瞬間に挑戦状を叩きつけ、西洋の覇権に疑問を投げかけることができる。ハンチントン自身は当然それを望んでいないが、彼は現実的に状況を評価し、どのような場合でもそうなるだろうと考えている。したがって、西洋文明の指導者たちは、他の文明の力が大きくなればなるほど、「それ以外」との衝突の可能性が高まるという、問題を抱えた危険な未来について、すでに真剣に考え始めるべきなのである。
正統(ユーラシア)文明
正統(ユーラシア)文明も地中海に起源を持つが、ビザンティン帝国の地政学を引き継ぎ、東方キリスト教の伝統に基づいて形作られた。1000年以上にわたって、西方キリスト教と東方キリスト教の乖離は決定的な形をとってきた。正教(ユーラシア)文明の中核はロシアであり、ロシアは15世紀以降、オスマン・トルコに征服されたビザンティウムと崩壊した黄金ホルデから同時に、東方キリスト教文化とステップ(ツラン)文化の統合体として、二重の歴史的・地理的遺産を受け継いだ。
ロシアと西ヨーロッパの関係の歴史はすべて、正教と西方キリスト教(カトリックとプロテスタント)の間を通る、文明の断層に沿った対立である。その後(ピョートル朝時代)、この対立は国益の対立という性格を帯び、さらにその後(20世紀)には、グローバル資本主義とグローバル共産主義の対立として表現されるようになった。この最後のバージョンは過ぎ去ったとはいえ、ロシアや他の正統派(の歴史と文化)諸国の文明的アイデンティティは、西欧の基準との本質的な違いを規定している。ロシアを核とする正統派(ユーラシア)文明は、多極化する世界の両極の一つとしての役割を主張する根拠となってきた。現代の状況では、ロシアが単独で西側諸国に対抗できるだけの潜在力を持つことはほとんどなく、二極体制への回帰は不可能である。しかし、多極化の文脈では、この文明は世界のパワーバランスの非常に重要な、場合によっては決定的な要因となる可能性は十分にある。このことは、モスクワが1990年代の混乱を乗り越え、国際舞台での地位を徐々に強化し始めた2000年以降、特に顕著になっている。
イスラム文明
イスラム文明もまた、世界のパワーのひとつである。今日、イスラム教徒は国家の境界線によって分断されているが、イスラム文明の代表者たちは全体として、国境にもかかわらず互いに連帯している点がある。イスラム社会の近代化が進み、経済的、政治的、軍事的、戦略的潜在力が強化されるにつれて、イスラムのエリートや知識人たちは、イスラム世界と西欧文明との価値観の相違をますます明確に認識するようになり、反欧米的な態度が絶えず強まっている。2001年9月11日、イスラムのテロリスト集団アルカイダによる世界貿易センタービルへの攻撃は、この対立がどこまで続くかを示している。イスラム文明は、多極化する世界の独立した一極の地位を主張することができる。
中国文明
中国(儒教)文明の文化的特殊性は、それに劣らず明白である。中国社会は宗教によってというよりも、共通の倫理文化、社会的態度の類似性、その他多くの倫理的、精神的、哲学的、心理的特徴によって結びついている。中国人は自分たちの文明の特殊性を強く認識しており、他の非中国的な社会の中で生活していても、ある文化的タイプに忠実であり続けることができる。西洋の技術をうまく同化させながら、中国人は自分たちの文化的アイデンティティをほとんどそのまま維持している。西洋の個人主義、快楽主義、合理主義などは中国社会に深く浸透していない。中華人民共和国における共産主義支配の維持は、中国人の道の独自性を際立たせている。中国人口の印象的な人口動態は、莫大な政治的・経済的資源を意味し、中国経済の傑出した成功は、中国を西側諸国の深刻な経済的競争相手へと変えて久しい。
ヒンドゥー文明
インドも中国に劣らない人口的潜在力を持っている。インドが単なる国家ではなく文明であり、何千年もの歴史を持ち、現代の西洋の規範とは大きく異なる特定の哲学的・価値観的態度を持つことは明らかだ。インドの近代化はその社会構造に一定の変化をもたらしているが、技術開発が進むにつれて、ヒンドゥー教徒は自らの文明的アイデンティティを意識するようになる。ヒンドゥー文明は攻撃的ではなく、その根底には瞑想的なものがあるが、極めて保守的で堅実でもあり、代替的な文明規範(イスラム教、西洋化など)の前では、ある種の厳しさを示すことができる。ここ数年のインドの経済成長も、多極化する世界における極としての役割を十分に正当化できるものにしている。インドには、亜大陸の多くの重要地域、パキスタンとの国境、インド洋の一部、そしてそこに位置する島国で採用している戦略がある。
日本文明
第二次世界大戦後、非西洋諸国の中で日本が最も深く「グローバルな西洋」のゾーンに組み込まれたという事実にもかかわらず、日本文明は独立した文化的伝統を持つユニークな現象である。日本の巨大な経済的潜在力と日本社会心理の特殊性から、1990年代初頭にはすでに多くのアメリカ人アナリストが、欧米と日本の潜在的な対立について考えていた。この20年間で、日本の経済成長は著しく鈍化し、政治的野心や地域政策はもちろん、世界政策も大幅に縮小された。とはいえ、過去の歴史的経験と日本社会の大きな可能性を考慮すれば、ある瞬間、日本が中国と並んで、少なくとも太平洋地域では文明をリードする大国のひとつになる可能性は否定できない。日本はすでにそのような国になっているが、中国の成長するパワーとのバランスを取るという問題を含め、アメリカの戦略的利益を代表しているのは事実である。日本のこの「親欧米」的機能は、多極化の状況下では変化するかもしれない。
ラテンアメリカ文明
ラテンアメリカ文明は、ヨーロッパ人によって政治的に組織されたポストコロニアル地帯である。しかし、スペインやポルトガルのカトリック文化や保守的な文化との歴史的な結びつきや、自国民の割合が大きいことが、南米諸国の文化が北米の文化(アングロサクソン・プロテスタントの影響が優勢で、地元のインディアン部族はほとんど滅ぼされた)と大きく異なる理由となった。ラテンアメリカの宗教的、文化的、民族社会学的、心理学的な相違は、南アメリカの人口がその歴史的独自性を実現し、独自の課題と戦略的利益を持つ独立極となるための前提条件となりうる。
ウゴ・チャベスのベネズエラやエボ・モラレスのボリビアから、近年力強い一歩を踏み出したブラジルに至るまで、今日、さまざまなラテンアメリカ諸国がすでにこの方向に進んでいる。ラテンアメリカ諸国はともに、人口、資源、経済、政治面で大きな潜在力を有しており、特定の状況下においては、多極化する世界の一極となる可能性も十分にある。
アフリカ文明
残りの文明は、多極化世界における極の地位の遠い候補に過ぎないとみなすことができる。
多極世界の独立した極に統合される対象としての空間としてのアフリカ文明は、投機的なプロジェクトの形で存在する。サハラ砂漠以南のアフリカの人々は、極めて孤立しており、厳密に植民地的な目印に沿って国民国家に統合されている。彼らは文化的アイデンティティも文明システムも共有していない。理論的には、人種的、空間的、地政学的、経済的、社会学的な特殊性に基づいて、アフリカの人々はある時点でその統一性を認識する(より正確には、構築する)ことができる。例えば、アフリカ合衆国(クワメ・クルマ、アブドゥライ・ワデ、ムアンマル・アル=カダフィ)、アフリカ統一機構、アフリカ経済共同体などである。人口と領土の集合体が、この理論的構築を非常に印象的なものにしている(人口統計では世界第3位、領土空間では世界第1位)。しかし、この地帯が独立した極に変貌するためには、多くの時間が経過しなければならないようだ。
仏教文明
仏教文明もまた、曖昧で不正確な概念である。隣接するイスラム文明やヒンドゥー文明とは文化的・社会的特徴の多くが異なる、さまざまな国々が仏教に関係している。仏教は中国と日本に広がっているが、これらの国々は独立した極として機能していると主張することができる。したがって、中国や日本の勢力圏とは大きく異なる仏教圏の統合は、近い将来実現することはないだろう。「仏教文明」は太平洋地域の予備地帯と考えることができる。
多極化する世界地図
このように、文明を単純に列挙することで、TMWに具体的な特徴を与えることができる。私たちは、多極化した世界の潜在的な地図の分化した構造を手に入れることができる。この地図にはこうある:
- 西洋文明は、今日では普遍主義と覇権主義を主張しているが、実際には他の文明の中の一つの文明を代表しているにすぎない;
- 正統(ユーラシア)文明:そのおおよその境界線は、CISの空間と東欧・南欧の一部を含む(この領域は、二極世界のシステムにおける最近の東西二元論に至るまで、西洋文明の主要な、あるいは少なくとも確固たるライバルとして歴史上繰り返し機能してきた);
- イスラム文明:北アフリカ、中央アジア、太平洋地域の国々を含む空間(巨大な人口ポテンシャルと、エネルギー資源を含む有用な原材料の決定的に重要な量を含む);
- 中華文明:台湾だけでなく、太平洋地域の広範な地域を含み、そこを通じて中国の影響が広がっている(中国の人口動態と経済成長率により、さらに広範になる理由がある);
- ヒンドゥー文明(インド以外に、人口の50%以上がヒンドゥー教を信仰しているアフリカのネパールとモーリシャスを挙げることができる);
- ラテンアメリカ文明は、ヨーロッパのスペイン・ポルトガル社会、カトリック宗教、ヨーロッパ・インド・アフリカの文化が比較的混在した社会との結びつきによって結ばれている(ここには、この地域の最北端に位置するメキシコを含む南米諸国と中米諸国を含めることができる);
- 日本文明。現在ではアナビオシスの中にあるが、歴史的には太平洋地域全体に「日本の秩序」を確立しようとする(潜在的な力の観点から正当化される)主張を持っている。
これらの文明の輪郭は、地図上ではっきりと識別でき、非常に多くの重要な問題に沿って、対応する文明空間を分断している国民国家の境界線を通して示されている。
他の3つの潜在的な文明の輪郭は、それほど容易には明らかではない。多極化する世界の統合された両極として、アフリカ文明と仏教文明は今日、遠い現実を表している。
とはいえ、私たちが扱っているのは、大多数のIRパラダイムが理論化の対象としているものとは根本的に異なる世界秩序の輪郭であり、一方では実証主義的で古典的なものであり、他方ではポスト実証主義的なものである。多極化システムにおける文明の中心のこの地図は、可能性のある、さらにはありそうな未来の図である。この未来では、世界政治のアクターの数は、厳密には1つか2つより多くなるが、現在存在する国民国家の数よりは少なくなる。
各文明は権力の極となり、(ある文明に関連する)すべての要素の潜在力を凌駕する地域的覇権の中心となるが、近隣の文明にその意志を押し付けるだけの力はない。
多極的秩序は、こうしてウェストファリア体制を別の次元で再現することになる。主権、勢力均衡、国際領域の混沌、紛争の可能性、潜在的な世界交渉などである。しかし、主な違いは、主体は今後、近代のヨーロッパ資本主義国家から模倣された、単一のモデルに沿って規範的に想像される国民国家ではなく、歴史的伝統や文化的規範に対応する、完全に独立した内部構造を持つ文明であるということだけだ。
このような世界は、国際秩序のレベルにおける文明の平等は、その国内的取り決めの同一性を意味しないため、言葉の完全な意味において多中心的なものとなる。したがって、各文明は、自らの好み、価値体系、歴史的経験に従って社会を組織する権利を得ることになる。宗教が決定的な役割を果たす文明もあれば、世俗的な原則が優先する文明もあるだろう。民主主義を採用するところもあれば、歴史的経験や文化的特質と結びついたり、社会自身が対立するプロジェクトとして選んだりする、まったく異なる政治的統治形態を採用するところもあるだろう。ウェストファリア体制とは対照的に、この世界秩序モデルでは、普遍主義的覇権の惑星モデルは存在せず、万人に義務付けられるパターンも存在しない。各文明において、主体、客体、時間、空間、政治、人間、意識、歴史の目標と意味、権利と義務、社会規範などの概念を含む、与えられた文明だけに特徴的な価値観の一般的な体系を主張することが可能になる。各文明は独自の哲学を持ち、非西洋的なシステムは当然ながら、固有の哲学体系に依存し、それを復活させ、完成させ、変形させ、あるいは新しい哲学体系と交換することになるが、これらはすべて、具体的な社会の排他的な自由と支援の文脈の中で行われる。
構築物としての文明
ここで非常に重要なポイントにたどり着く。ハンチントンの批評家の多くは反論を展開し、現代世界における文明の存在そのものに異議を唱えたり、ある時期を過ぎるとグローバル化、西欧化、近代化によって文化的・文明的差異がなくなることを指摘したりした。こうして彼らは、文明という概念の存在論の問題を鋭く提起する。
文明が社会の広範なセグメントを統合する文化的・道徳的背景(時には宗教的)として存在するという事実は、経験的・社会学的・歴史的事実である。しかし、現在の状況において、この統一性が十分に認識され、動員され、文明を国際関係システムの主要なアクターとすることができる強力な政治的思想に転化するのに十分なのだろうか。
ハンティントンは実証的な観察を示し、そのような存在論は存在し、現在の状況下では、まさに文明的アイデンティティが主要なプロセスの展開において決定的な役割を果たすことが求められていると主張している。しかし、これには議論の余地がある。文明論的アプローチの支持者は、文明は国際関係の領域において存在論的に正当化される概念であると主張し、反対者は、この存在論は疑わしいものであり、実在するものではないと主張する。ハンチントン自身は西欧の側に立っており、その知的エリートの不可欠な一部であるため、彼の文明的要因の概念は西欧の立場に沿ったものであり、ハンチントンは西欧以外の文明が存在するという事実そのものに脅威を感じている。彼はこの脅威を現実的かつ存在論的に根拠あるものと考えている。だからこそ、彼はグローバリゼーションの悲観論者とみなされている。同時に、彼にとって文明概念の存在論は、潜在的な敵の深刻さと現実性を推し量ることでもある。
しかし、ハンティントン自身が多くの問題で忠実である現実主義的アプローチの枠内で、構成主義的方法、より広くはポスト実証主義的IR理論に基づいて、まったく別の視点からこの問題にアプローチすることもできる。TMWにとって、文明が多極化する世界のアクターとして、またその両極として存在するかどうかはさほど重要ではなく、その存在が、一極集中や西側中心のグローバリゼーションの確実な始まりの道筋において、実証された重みのある要因であるか、あるいは弱く乱暴な障害であるかどうかも重要ではない。国際関係の主体としての文明は、伝統的な国家や帝国が存在した前近代への回帰を意味するものではない。国際関係のアクターとしての文明とは、まったく新しいものであり、これまでになかったものである。ポストモダンの現実のようなものであり、ウェストファリア・システムの支配に基づく世界秩序の疲弊した可能性の代わりを務めるよう求められている。言い換えれば、文明とは、ある意味では構築物であり、特定の言説であり、テキストであるとみなすことができる。文明とは、国際関係の現実に質的な差異(ディフェランス)を吹き込むことであり、そこでは人類は、均質な系列(公民権の前提や人権のイデオロギー)の再生産としてではなく、(ライプニッツによれば)独立したモナドの集合として考えられ、並列するいくつかの意味的・文化的宇宙を組織している。これらの宇宙は(ハンチントンのように)対立するが、対立することだけが必要なわけではない。イランのハタミ前大統領が主張した文明の対話も、それと同じくらいあり得る。多極化する世界のアクターとしての文明の相互作用は、対立的であれ平和的であれ、ウェストファリア体制における国民国家間の関係と実質的に同じ割合で、どのような形でもありうる。しかし、国民国家と国家主権が近代の構築物であったとすれば、文明はポストモダンの構築物であり、共通分母に還元することのできない根本的な複数の言説を表現するものである。
多極化の調整センター
文明は創造されるべきものである。しかし、文明を創造するこのプロセスは、現実にはまったく存在しない人為的なモデルを完全に前提としているわけではない。文明には文化的、社会学的、歴史的、精神的、心理的な基盤があり、それは経験的なものである。しかし、文化的、社会学的に与えられたものとしての文明から、多極化する世界の行為者としての文明への移行には努力が必要である。それは、ある歴史的権威が遂行しうる、また遂行しなければならない仕事である。
その権威とは何か。条件付きでおおよそ定義することができるのは、「安息国」の政治的・知的イデオロギー的エリート、すなわち国家主体、知識人、大独占企業の代表者、宗教的構造、さらにはこれらの国々の主要な政治勢力の集合体であり、何らかの理由で一極集中や西側中心のグローバリゼーションに同意せず、「西洋化なき近代化」を支持し、現在の世界秩序とは異なる世界秩序の枠組みにおいてのみ自国社会の将来を見据えている。
ハンチントン自身、トインビーに倣って、「西側とそれ以外」のペアを文明的拮抗者として語っている。「残りの部分」は徐々に成熟した特徴を獲得し、TMWの精緻化という歴史的プログラムに落ち着くだろう。
まさに非西洋世界の知的エリートは、多極化を構築し、それに応じて「文明」を効果的で実質的な概念に変えるよう求められている。
文明の国境
非常に重要な問題のひとつは、文明の国境をどのように決定するかということである。ここではさまざまなバリエーションを考えることができるが、いくつかの点はすぐに明らかだ。文明の国境は、国民国家を分断する国境のように、線によって固定されるものではなく、また固定されるものでもない。文明は空間的には広いゾーンによって互いに隔てられており、そこでは文明のアイデンティティが混在している。さらに、ひとつの文明の中に、かなり大きな飛び地があったり、別の文明が入り込んでいたりすることもある。文明と空間との関係は、国民国家と領土との関係とは根本的に異なる。行政規制の範囲は、空間というよりも、社会、共同体、人口集団と相関する。したがって、領土の特徴は、国家領土に属する場合のように明確ではない。
したがって、国家間の国境は、国家間の国境とは質的に異なる地位を持つはずだ。文明間の国境には、独立し、孤立した、まったく独自の社会構造と文化的アンサンブルからなる自治世界全体が存在しうる。重なり合う文明の特殊性、文明間の割合、さらに文明の質的内容やアイデンティティの認識の強さのレベルを考慮に入れた、別の法的モデルが考案されるべきである。法律学の学派の中には、「国境」(厳密な意味での、ある国の領土と他の国の領土を隔てる線)と「辺境」(より具体的でない領域としての、ある種類の空間と他の種類の空間の間)という概念を区別するものもある。前者の場合、それはまさに線であり、幅はない。もう一方の場合、それは面積であり、ゾーンであり、幅のあるものである。この文脈では、ある文明はまさに「フロンティア」、つまり文明間ゾーンによって別の文明から隔てられている。フロンティアはかなり広範かつ拡散的で、それぞれのケースに特有のものであり、「フロンティア」の両側にある社会文化的空間とは異なるものである。
多極化する世界の実践: 統合
「文明」という概念の存在論的位置づけが明らかになった今、多極化世界の構築における実践の主要なベクトルの方向性が明らかになった。それは「統合」である。
統合は、多極的世界秩序の軸となる。しかし、TMWにおいては、この統合は厳密に文明の枠組みの中で行われるべきである。したがって、いくつかのタイプの統合を区別する必要がある:
- グローバルな統合:文明の特殊性を考慮せず、西洋の規範、手続き、価値観の体系を基礎とする普遍的な議定書に基づいて行われる;
- 覇権主義的な統合は、文化の違いを考慮することなく、統合の主体間に階層的で不均衡な関係を構築する;
- 文明主義的とは、文化的体質を共有し、社会政治体制も類似しており、歴史的(宗教的)ルーツも共有している国や社会のみを包含するものである。
TMWは、最初の2つのタイプの統合に反対し、第3のタイプの統合を奨励し、積極的に実施することを主張している。こうして、文明的な内容においてかなり異なる、いくつかの統合ゾーンの具体的なグループができあがる:
- 西側の統合(ヨーロッパとアメリカ)、そしてヨーロッパと大西洋の統合(ここではすべてが成功している;軍事的・政治的なNATOブロック、EU、北米通貨「アメロ」を含む北米大陸全体の統合プロジェクトがある);
- ユーラシア統合(その基準点はユーラシア連合であり、その段階は、CSTO内での軍事戦略協力の強化、EurAsECの枠組み内での経済連携、ロシア・ベラルーシ連合国家、特にウクライナを考慮に入れた統一経済空間のプロジェクト、CISである);
- イスラムの統合(イスラム会議、イスラム開発銀行、イランとイラクからリビアに至るシーア派だけの空間、さらに「新カリフ制」の原理主義プロジェクト);
- 中国の統合(ASEAN+中国、台湾が中国に吸収される可能性、「黄金の人民元」ゾーンの導入);
- ヒンドゥー教の統合(東南アジア、インド亜大陸、ネパール、地政学的・文化的にインドに近い数多くの太平洋流域諸国におけるヒンドゥー教の影響力の強化);
- 日本の統合(極東における日本の成長を含め、現在検討中);
- ラテンアメリカの統合(ラテンアメリカ連合統合、メルコスール、中米共同市場など);
- アフリカの統合(アフリカ統一機構、アフリカ合衆国など)。
統合は、国際関係における多極的秩序を構成する上で、優先的なプロセスとなる。
先入観文明と「大空間」
多極化した世界を構築する過程で、ある時点で、「文明」という概念を社会文化的なカテゴリーから法的な概念に変換することが全面的に問われることになる。ここで極めて重要なのは、ドイツの哲学者であり法学者でもあったカール・シュミットが提唱した「大空間」(Großraum)という概念である。シュミットの考えがIRの領域にとって重要であることは、イギリスのIR理論家ファビオ・ペティートによって説得力を持って示された。シュミットは、どのようにして国際規範が形成され、やがて一般的に受け入れられる法的地位を獲得するのかという問題を提起した。彼は特に、近代におけるヨーロッパのIRシステムの基礎を築いたヨーロッパ公共条約(Jus Publicum Europeum)のような現象の確立に関心を寄せていた。全体としてシュミットは現実主義的な立場をとっており、彼にとって第一の問題は、主権をもつ国民国家(定義上、より上位の権威は存在しない)と国際関係の領域におけるルールの精緻化を関連づける手続きの問題であり、それにもかかわらず、国民国家はそれに従わなければならない。通常、国際関係における無秩序の制度的秩序が存在することは、まさにリベラル派も認めており、そのためリベラル派は「制度主義者」と呼ばれることもある。シュミットの場合、確信犯的なリアリストでありながら、国際関係の構造化された環境に一定の注意を払った。それゆえ、彼のアプローチは逆説的な性格を持っている: 「制度的リアリズム」である。
IRにおけるリアリズムの基本的な前提条件として、シュミットによれば、国際関係におけるカオスとアナーキーは、単に共有された自由民主主義的価値観、貿易競争、平和主義に訴えることによってではなく、具体的な地理的状況と相関する、認識されたパワーバランスによって調整される。地政学に多くの注意を払ったシュミットは、法的規範を地理的空間に固定することを主張する。その結果、IRの全領域が物理的・政治的な地図と相関することが証明された。こうしてIRにおけるカオスは空間的特徴を獲得し、さまざまな国家の勢力均衡の力線によって構造化される。
ウェストファリア体制は、国家主権を超えるいかなる合法的・法的現実の承認も形式的に拒否しているため、国際関係領域の空間的規範化は、形式的に概念化された表現にはならず、また表現することもできない。とはいえ、パワーバランスはしばしば、非常に安定的で明白なものであるため、本質的に法律と比較することができ、その結果、法律で固定化される。これは「モンロー・ドクトリン」やウェストファリア的世界の条件の宿命であった。支配的な世界大国は、自国の国益(自国の権力資源によって確認される)を規範的な状態と同一視した。シュミットは、この微妙な作業の過程を詳細に分析し、それが最終段階では、一般に受け入れられているウェストファリア的な国民主権体制とは異なる程度の義務性を持ち、ある程度概念的に対立する超国家的な法体系の出現につながったのである。この分析のために、シュミットは、超国家的な規模を持ち、まだ法規範に固定されていないが、一定の状況と具体的な三権分立のもとで法的地位を獲得することが可能な一種の政治思想として、「先概念」という用語を導入している。
次にシュミットは、「前概念」(たとえば「モンロー・ドクトリン」や「ドイツ帝国」)を、前概念を適用できる空間的な国境と関連づける。その結果、「大空間」(Großraum)という新たな形態が生まれ、これがシュミットの政治理論の最も重要な要素のひとつとなる。「大空間」とは、IRの領域における法的前概念の空間的表現である。
この手順を「文明」の概念に当てはめれば、TMWに理想的に当てはまることがわかるだろう。多極化は、ついでに言えば、二極化や一極化もそうであるように、法的な概念ではない。多極化とは、世界の主要な主体間の事実上のパワーバランスに関する記述である。その結果、「文明」も「多極秩序」も法的な前提概念としての地位を持つことになる。ある状況下では、ウェストファリア・モデルに取って代わることさえできる。そうなれば、国家主権の形式的な否定という問題が提起され、主権の概念が別の権威、文明、あるいは多極世界の両極に移されるのは当然である。この場合、前概念は単なる概念や法的観念となる。この場合、文明と多極化は、ある長い期間、前概念のままである(二極化が国家主権を廃止しなかったように、超大国の地位を持たないすべての国にとって、国家主権は相対的なものとなったが)。
文明の境界線を引こうとするとき、私たちは直接「大きな空間」に遭遇することになる。この概念は、文明の空間的局在を固定化するための前概念的地位のため、非常に便利である。
構成文明のパワーバランスに基づく多極化した世界は、シュミットに倣って、「大空間の秩序」と呼ぶことができる。
多極世界の理論におけるポリテイア
文明はTMWにおける国際関係の主体である。私たちは、文明の理解は極めて多様であり得ると同時に、異なるバージョンは互いを排除するものではなく、補完し合うものであることを見た。この多様性は、この概念を著しく豊かにし、極めて実質的なものにする。その結果、文明のアイデンティティに関する複数の解釈の可能性が生まれ、その比率、強調点、境界線は変化し、より正確になり、さまざまなものになる。しかし、理論のレベルに移行するためには、この概念的な複数性をより単純な体系に還元する必要がある。ここで、最も重要な道具的概念は、「多極化する世界の地政学」で検討された。「大きな空間」(Großraum)である。「大空間」は、基本的に政治的現象ではない文明とは対照的に、政治的な前概念とみなすことができ、TMWの政治的次元の定式化に密接につながる。この理論において、多極化世界の両極(文明)はどのような政治的地位を持つのだろうか。そしてそれに従って、国際関係の法的基盤はどのような基盤の上に築かれるのか。
多極世界の両極は国家になるのか?もしそうなら、どのような国家になるのか。もしそうでないなら、どのような国家になるのか?
これらの問いに答え、TMWの構築(少なくともその第一段階)を締めくくる正式な政治概念の精緻化に近づくためには、現代の政治学で「国家」と理解されているものを簡単に概観しておく必要がある。歴史的な尺度では、国家を前近代国家と近代国家の2種類に分けるのが通例だ。これらは基本的に異なる概念であり、それぞれに固有の属性がある。前近代国家は帝国においてその一般的な頂点に達する。帝国は、単一の中心における最高の中央権力と、地方、植民地、半自治王国など、より低いレベルの政治組織への広範な権力の分配の組み合わせを提案する。前近代国家のもう一つのタイプは、古代ポリス(都市国家)であり、他の類似の単位から相対的に独立した、近隣の(農村)領土の権威の中心としての役割を果たす、小さな自治単位である。前近代の国家は政治的権威の点で大きく異なることがあり、アリストテレスはそれを3つの組に体系化した。最初の組は支配の肯定的なバージョンとみなされ、2番目の組は否定的、堕落的、侮蔑的なものとみなされる:君主制-専制政治、貴族制-寡頭政治、礼儀制-民主主義。大領土はより中央集権的(君主制)を好み、小領土は人民による直接統治体制[narodopravlenie](礼儀制)で運営される。つまり、前近代国家のバージョンとしての帝国や都市国家を、その政治体制に基づいてではなく、前近代に関連付ける。これは重要なことである。前近代国家と近代国家を区別する主な基準は以下の通り:
- 前近代国家には、超国家的使命と神話的起源が存在する;
- 前近代国家には、超自然的使命と神話的起源が存在する;
- 政治組織の社会的基盤としての集団的アイデンティティ(カースト、領地、民族、信条など)の存在である。
近代国家は、まさにこの3点において伝統的国家と異なる。それは次の3点:
- 完全に合理的で、計算と国益に導かれ、社会契約に基づいて作られる;
- 法の前ではすべての国民が平等であり、いかなる社会集団にも厳格に規定された特権は存在しない;
- 個人の市民権に基づき、集団のアイデンティティーを法的なレベルで否定する。
近代国家は通常、「国民国家」または「国家-国家」(État-Nation)と呼ばれる。
今日、国際関係においては「国民国家」だけが規範であり、唯一の合法的な様式と考えられている。
政治学では、近代国民国家の性質と構造について激しい議論が交わされているが、ほとんどの研究者の基礎となっているのは、ウェーバーとその同世代の支持者たち(「ネオ・ウェーバー派」と呼ばれることもある)(マン、スコッポル、ティリーなど)による国家分析である。
ウェーバー派の伝統は、国家を4つの基本的要素に沿って定義している。国家とは
- 差別化された制度と人員の集合であり、以下を体現している。
- 中央集権主義であり、政治的関係が内部から外部に放射状に広がるように組織され、領土的に固定された区域全体をカバーする。
- 領土的に固定された地域全体をカバーする。
- 支配のルールの確立を独占し、物理的暴力手段の使用を独占する。
このウェーバー的な国家社会学モデルは、国家をまさに形態の観点から記述し、その自律性をある程度まで前提としている(このモデルの暗黙の公理として、絶対的主権の教義が根底にある)。マルクス主義者は、この図式にさらなる社会的側面を導入し、階級関係が主要な役割を果たし、国境を越える傾向にあると主張する(国際ブルジョアジーの階級的連帯とプロレタリアートの国際的性格)。しかし、たとえ階級闘争という考え方を認めないとしても、マルクス主義的分析は、社会的側面、すなわち、政治的形態としての国家とは直接的な関係を持たないが、それにもかかわらず政治に重要な(時には決定的な)役割を及ぼす市民社会に高い関心を払う。政治(国家)においては、法的に定式化され、機能的に承認された直接的な権力(シュミットのPotestas Directa)を扱うとすれば、社会においては、グラムシが「ヘゲモニー」と呼んだもの、すなわち、それが課される人々にはそのように認識されない、階層関係や権力関係の確立形態を扱うことになる。覇権は、それが作用する相手によって権力として認識されることはない。それは法的には認められず、いかなる法的地位も持たない。共産主義者のグラムシは、ブルジョア社会では、ブルジョアジーは、ブルジョア国家とその装置の助けを借りて政治的権力を持つだけでなく、教育、教育学、科学、文化、哲学、芸術、その他の市民社会の形態で表現されるヘゲモニーも持っており、そこでは、ブルジョア意識の担い手が暗黙のうちに支配し、資本家の知的、政治的支配を強化し、正当化していると考えている。グラムシアン的理解における「ヘゲモニー」という要素の重要性は、ウェーバー的な国家の定義を、さらに社会的な次元で実質的に補うものである。市民社会の役割の重要性や、その他の間接的ポテスタスの変種は、多くのリベラル派、トランスナショナリスト、さらには「新右翼」(ベノイスト)によっても、進んで認められ、イデオロギー的にさえ採用されている。
最後に、国家の本質を理解する上でのもう一つの重要な概念的動きは、IRにおけるネオリアリスト(そもそもはウォルツ)によってなされた。ネオリアリストは、国民国家の構造を、古典的なウェーバー分析のように「内から外へ」ではなく、「内から外へ」考察することを提案し、世界政治における一般的なパワーバランスが、個別国家の対外政策だけでなく、部分的には国内政策にもどのような影響を与えるかを分析し、国民国家が、国際的なレベルで形成された政治体制に、政治的、経済的、社会的、文化的などに適応することを余儀なくされている。ネオ・ウェーバー・アプローチの代表者は、これと同じテーマを展開し、地政学的要因と国家自体の「力の均衡」分析を加えている。
英国学派の国際関係論は、このようなアプローチ、特に「IRにおける歴史社会学」と呼ばれるハリデーに関連する流れを総合したものである。このアプローチの代表者たちは、国家を理解する上で、ウェーバー的(形式的)、社会学的(グラムシアン的、リベラル/トランスナショナル的)、地政学的(勢力均衡のグローバルなシステムを考慮に入れる)の3つのレベルすべてに遭遇する。
多極化する世界の極点である文明を、国家の構文における基本的なアクターとして考察することは可能だろうか。
それらを直感的に表現してみよう:
- 多極世界の極は主権を持つべきである。しかし、それは他の極が存在する場合に限られる。
- 文明の権力の中心は、形式的に法的な観点から、合法的であるべきである;
- 権力の適用領域と、それに応じてゲームのルールを確立する領域は、住民の民族文化的・宗派的構成に応じて区別されるべきである;
- 支配の領域モデルは、連邦主義と補完性の原則に基づいて構築される(アルチュセール);
- 文明に統合された単位のアイデンティティは、集団的なもの(主として)と個人的なもの(場合によっては)とに分かれる;
- 政治形成は、使命(文明の文化的規範に由来する)と合理的利益(検証された明白な計算に基づく)の両方を持つべきである;
- 社会的階層(民族主義的集団など)は、政治組織の構造において透明かつ合法的に代表されるべきである;
- 諮問機関としての文明間協議会が必要であり、(文明の主権の原則を揺るがすことなく)文明間相互作用のルールを(絶対的ではなく、不変でもなく)確立し、多極化の原則と力の均衡の両方を考慮に入れる。
さて、この一連の直感的なパラメーターを分析すると、驚くべきことに、このような理論的に構築された政治体は、一方では、既知の、そして他の文脈では理論的に正当化された政治的特質をもって活動し、他方では、前近代国家でも、近代国家でも、新自由主義者のトランスナショナルな構築物でも、マルクス主義の国際プロジェクトでもなく、他のいかなるモデルとも一致しないことがわかる。私たちは、権力、主権、合法性の概念における中央集権主義を扱っているが、同時に、社会的アイデンティティと領土権に関する多元主義を扱っており、さらに、グラムシが「市民社会」と呼んだものの高度な合法化を扱っている。こうして私たちは、国家(国民国家の帝国を含む)、社会、あるいは政治的な他のどの通常のモデルとも厳密には同一視できない、独創的な概念を手に入れた。
ある意味で、私たちはポストモダンの「政治」のひとつのバージョンの記述に取り組んでいる。
あとは、この概念の名称を選ぶだけだ。私たちは(選択肢として)、プラトン的な意味でのポリテイア(アリストテレスが『政治学』で用いたような「積極的民主主義」という狭い意味ではなく)という用語を用いることを提案する。プラトンの『ポリテイア』(思想の教育が首尾一貫して体系的に提示されている有名な対話)は、「国家」(ロシア語)とも「共和国」(ロシア語)とも訳されている。とはいえ、プラトンの著作で問題になっている現実と、当時のギリシア人がこの言葉に与えた意味は、今日の国家の概念や、ローマ人が「公共(Res Publica)」によって理解したものとは一致しない(ましてや、今日の私たちが共和国によって意味するものとも一致しない)。ポリティアとは、本格的な中央集権国家からその個別部分(州、地域、サトラプ、さらには非常に小さな村落単位や宗派の飛び地)に至るまで、あらゆる次元の政治的形成を指す。この用語は政治学で使われることもあるが、多くの場合、比喩的な意味で使われ、厳密に固定された概念的な意味はない。この場合、多極化した世界における極が持つ一連の性質を、そのような呼称として固定することを妨げるものは何だろうか。ポリティアという用語は、近代や前近代の政治理論において固定した意味を持たないからだ。ポリテイアとは、秩序だった組織化された社会のことであり、帝国、近代国家、その個別の部分、さらには小さな共同体からグローバル社会まで、さまざまな規模の社会がそれにあたる。理論的には、ポリテイアという用語をそれらすべてに適用することができるが、ポリテイアは非常に多義的であるため、正確には使われていない。しかし、この用語が政治学で広範に適用されなかった理由を説明する同じ多義性は、多極化世界の理論の場合には、複雑な現象としての多極化の構造そのものに完全に対応した、素晴らしい用語上の利点となる。ポリテイアは、複雑なポリティカルを説明するのに理想的に適した概念であり、それを概念に還元するには、近代の日常的な実践の中で働いているよりも、多様な次元の、より多くのパラメーターを含めることが要求される。国家はポリテイアだが、ポリテイアには社会、文化、さらには地政学的単位も含まれるため、ポリテイアは国家ではない。ポリテイアは、TMWにおいては「大空間」の政治形態であり、それゆえ、最初から地政学的な次元も持っている。
ギリシャ語のpoliteiaの意味を解釈する際、辞書はしばしばラテン語のcivitasが最も近い概念であるとしている。しかし、私たちはTMWにおいて、国際関係の主役としてまさに文明を見た。つまり、多極化する世界の極を表現する政治的概念の探求は、まさに私たちが始めたところで終わったのである。
付録
セオリートーク第66回:アレクサンドル・ドゥーギン
2014年12月7日(日)
(出典:http://www.theory-talks.org/2014/12/theory-talk-66.html)
アレクサンドル・ドゥーギン:ユーラシア主義、陸と海の地政学、ロシアの多極化理論について
IRは長い間、英米の社会科学とみなされてきた。最近、この学問はアメリカやイギリスを越えて、中国(理論談義第51回、理論談義第45回)、インド(理論談義第63回、理論談義第42回)、アフリカ(理論談義第57回、理論談義第10回)など、国際情勢やIR理論に対する非西洋的な視点に目を向け始めている。しかし、IR理論家たちは、国際関係の学問と実践に関するロシアの視点にはほとんど注意を払ってこなかった。国際ユーラシア運動の創始者であり、プーチンの外交政策に重要な影響を与えたとされる物議を醸すロシアの地政学思想家アレクサンドル・ドゥーギンへのインタビューを通して、ロシアの地政学理論を覗き見るエキサイティングな機会を提供する。この対談でドゥギンは、とりわけ自身の『多極世界論』について語り、西側諸国やリベラルなIRに対する断固とした批判を展開し、IR理論におけるロシアのユニークな貢献について述べている。
あなたにとって、IRにおける中心的な課題、あるいは主要な議論とは何であり、その議論の中で、あるいはその課題に対して、あなたの立場はどのようなものだろうか?
IRの分野は非常に興味深く、多次元的である。一般的に、この分野は多くの人が考えているよりもはるかに有望である。今日、IRにはステレオメトリーが存在し、いくつかの軸をすぐに見分けることができると思う。
まず、最も伝統的な軸は、リアリズム、つまり英国学派、リベラリズムである。
ここでの議論がアカデミックなレベルで尽くされているとすれば、政治家やメディア、ジャーナリストのレベルでは、すべての議論や手法が毎回新しく、前例のないものに見える。今日、IRにおけるリベラリズムは大衆意識を支配しており、大衆言説のレベルではすでに部分的に忘れ去られたリアリズムの議論は、むしろ斬新に映るかもしれない。一方、学界で徹底的に研究されたニュアンス重視の英国学派は、一般大衆には「啓示」に見えるかもしれない。しかし、そのためには、リベラル派とリアリストの対称性が広く照らし出されることが、英国学派が意義を獲得し、その潜在的可能性を完全に開示するために必要である。これは、IRにおけるリベラリズムの急進的な支配のもとでは不可能である。そのため、私はこの領域におけるリアリストとネオリアリストの新潮流を予測する。彼らはかなり忘れ去られ、ほとんど周縁化されているが、彼ら自身と彼らのアジェンダを十分に知らしめることができる。このことは、今日、単調で自己言及的なものになりつつある大衆的・社会的議論のパレットを多様化し、活性化する効果をもたらすと思われる。
第二の軸は、ブルジョア版IR(現実主義、英国学派、リベラリズムの総称)対IRにおけるマルクス主義である。ウォーラーステイン(Theory Talk #1 3)をはじめとする世界システム論の人気は、古典的で実証主義的なIR理論に批判的なこのバージョンへの関心の高さを示しているが、一般的な言説や学術的な言説においてさえ、このテーマは完全に捨てられている。
第三の軸は、あらゆる種類のポストポジティビズム対あらゆる種類のポジティビズム(マルクス主義を含む)である。IR研究者は、ポストモダンの攻撃は「批判的リアリズム」によって撃退に成功し、終焉を迎えたという印象を抱いているかもしれないが、私の考えでは全くそうではない。穏健な構成主義や規範主義から極端なポスト構造主義に至るまで、ポストポジティビズムの理論には巨大な脱構築的可能性とそれに対応する科学的可能性が秘められている。ポストモダニズムは陽気なゲームだと思われていた。そうではない。ポストモダンは新たなポストオントロジーであり、IRの認識論的構造全体に根本的な影響を与えている。私見では、この軸は依然として非常に重要かつ基本的なものである。
第四の軸は、「ホブソンの挑戦」とでも呼ぶべき、国際関係社会学の挑戦である。私見によれば、ジョン・M・ホブソンはIRにおけるヨーロッパ中心主義批判において、「ヨーロッパ中心主義」という要素が支配的であることの構造的意義を考察し、その人種主義的要素を明らかにすることを提案することによって、この問題全体に対するまったく新しいアプローチの基礎を築いた。ひとたびヨーロッパ中心主義を変数とし、西洋の普遍主義的人種主義から離れると、その上にすべてのIRの体系が構築され、ポストポジティビズムの体系の大部分も含まれる(結局のところ、ポストモダンは西洋だけの現象なのだ!)。文化の違いを考慮すれば、IRのシステムは文化の数だけ存在することになる。私はこの軸を非常に重要だと考えている。
5つ目の軸は、前の軸ほど詳しくは説明しないが、「多極化世界論」対「それ以外」である。多極世界論はロシアで開発されたものであり、IRが学問として確立されるまでの間、誰もまともに相手にしなかった国である。
第6の軸はIR対地政学である。地政学は通常、IRの文脈では二次的なものとみなされている。しかし、地政学の認識論的な可能性は、それに対する批判にもかかわらず、あるいは部分的な批判のせいかもしれないが、徐々に明らかになりつつある。地政学的概念の構造について自問するだけで、その方法論に含まれる巨大な可能性を発見することができる。
今、これらの軸を互いに重ね合わせると、極めて複雑で非常に興味深い理論分野が見えてくる。同時に、一般大衆の間で規範的とされているのは、最初の軸の1つだけであり、それはIRリベラリズムのほぼ全面的かつ一次元的な支配である。他の軸が持つすべての富、「科学的民主主義」、グノソロジーの多元性は、広範な一般大衆にはアクセスできず、奪い、部分的には欺くものである。私はこのようなリベラリズムの大衆支配を「第三の全体主義」と呼んでいるが、それはまた別の問題である。
IRについての考え方は、どのようにして現在に至ったのか?
私はユーラシア主義から出発し、そこから地政学に入った(ユーラシア主義者のペトル・サヴィツキーはイギリスの地政学者ハルフォード・マッキンダーの言葉を引用している)。そして長い間その枠組みにとどまり、陸と海の二元論というテーマを発展させ、それを実際の状況に当てはめた。こうしてユーラシア学派の地政学が生まれ、現代ロシアにおける支配的な学派というだけでなく、唯一の学派となったのである。モスクワ大学の教授として、私は6年間、国際関係社会学の学科長を務めていた。そのため、IRの古典的な理論、主な著者、アプローチ、学派に専門的に精通せざるを得なかった。私は以前から哲学のポストモダニズムに関心があり(このテーマで『ポスト哲学』という本を書いた)、IRにおけるポスト実証主義に特別な関心を寄せていた。こうして私はIR批判理論、ネオ・グラムシアン主義、IR社会学(ジョン・ホブソン、スティーブ・ホブデンなど)にたどり着いた。地政学的二元論、カール・シュミットのグロースラウム理論、ジョン・ホブソンの西洋人種差別批判とIRのヨーロッパ中心主義を重ね合わせることで、最終的に私自身が発展させた「多極化世界論」にたどり着いた。
IRのスペシャリストになるためには何が必要だとお考えですか?
学際的な現代において最も重要なのは、哲学と社会学に精通することであり、パラダイム的な方法、すなわち前近代-近代-後近代の線に沿って社会、文化、思考構造のタイプを分析することだと思う。この3つの認識論的・存在論的領域における意味論的な変遷をたどることを学べば、今日普及しているあらゆるIR理論に精通することができるだろう。バリー・ブザンの国際システム論は、そのような一般化された非常に有用な図式化の一例だ。今日、IRの専門家は脱構築に精通し、少なくともその初歩的な形では脱構築を用いなければならない。そうでなければ、最も重要なことを見落としてしまう危険性が高い。
もう一つ非常に重要な能力は、歴史学と政治学である。政治学は一般化し、単純化する材料を提供し、歴史学はスキーマをその文脈に置く。私は経済学と政治経済学の能力を3位に置くが、今日、IRのいかなる問題も、その過程や相互作用の経済的意義を抜きにして考えることはできない。最後に、IRを学ぶ学生には、優先事項として地政学とその手法に精通することを切に勧めたい。これらの方法はIRの理論よりもはるかに単純だが、その意義ははるかに深い。地政学を単純化すると、複雑で絡み合った世界政治のプロセスが瞬く間に透明化され、理解しやすくなる。しかし、この効果がどのようにして達成されるのかを整理するためには、批判的地政学(Ó Tuathail他)を制限している表面的なものをはるかに上回る、地政学に関する長く真剣な研究が必要である。彼らは、地政学の解読とその本格的な脱構築の始まりに立っているが、自らをその擁護者とみなしている。彼らは時期尚早である。
グローバルな力関係を空間的レンズ(Myslit prostranstvom)を通して考えることは何を意味するのか。
これが最も重要なことである。近代の哲学的テーマ全体は、時間の優位性の上に成り立っている。カントはすでに時間を主体の側に置き(空間は身体の側に置き、デカルトやプラトンの思想を引き継いでいる)、フッサールとハイデガーは主体を完全に時間と同一視している。近代は時間とともに、なりゆきとともに考える。しかし、過去と未来が存在論的な実体として否定されたため、時間の思考は、瞬間の思考、つまり今ここにあるものの思考へと変容する。これが存在の儚い理解の基礎となる。空間的に思考するということは、「存在」を現在の外側に位置づけ、空間に配置し、空間に存在論的地位を与えることを意味する。空間に印象づけられたものは何であれ、空間に保存される。空間で成熟するものは、すでに空間に含まれている。これが、フリードリヒ・ラッツェルやその後の地政学者の政治地理学の基礎となっている。ワーグナーの『パルジファル』は、グルネマンツの「今や時は空間となった」という言葉で終わる。これは地政学の勝利の宣言である。空間的に考えるということは、まったく別の方法[トピカ]で考えるということだ。私は、ポストモダンはすでに部分的にこの視点に到達しているが、入り口で止まっていると思う。一方、一線を越えるためには、モダニティの公理的なもの全体を根本的に断ち切り、モダニティを本当に踏み越えることが必要であり、モダニティとその天変地異に留まりながらこの通路を模倣することはできない。ロシア人は空間[Russkie lyudi prostranstva]である。ロシアのアイデンティティの秘密は空間に隠されている。空間的に考えることは、ロシア語で「ロシア的に」考えることを意味する。
地政学は今ロシアで非常に人気があると論じられている。地政学は冷戦後の新しいものなのだろうか?もしそうでないとすれば、現在の地政学的思考は以前のソ連(あるいはソ連以前)の地政学とどう違うのだろうか?
地政学はまったく新しい政治思想である。私は80年代の終わりに地政学をロシアに紹介したが、それ以来、地政学は非常に人気がある。私はロシア史の中に地政学の痕跡を見つけようとしたが、ヴァンダム、セミョーノフ=ティアン=シャンスキー、サヴィツキーの短い論文のほかには何もなかった。ソ連では、地政学に関するいかなる言及も最も厳しい方法で処罰された(経済地理学者ウラジーミル・エドゥアルドヴィチ・デン一派の「地政学者の事件」を参照)。90年代に入り、地政学(=ユーラシア主義)における私の努力や私の支持者・仲間の努力は、ソビエト・イデオロギーの終焉後に形成された世界観の空白を埋めた。当初、これは軍(ロシア軍参謀本部軍事アカデミー)、特にイーゴリ・ロディオノフの下で遠慮なく採用された。その後、地政学はあらゆる社会階層に浸透し始めた。今日、この学問はロシアの大半の大学で教えられている。つまり、ソビエトやソビエト以前の地政学は存在しない。あるのは、80年代末に形成された現代のユーラシア学派だけだ。『地政学の基礎』はこの学派の最初のプログラム的テキストだが、私はこの本に収録されているテキストのほとんどをそれ以前に出版しており、その一部は政府関係者の間でテキストとして流通していた。最近、2012年に私は2冊の新しいテキストを発表した: 地政学』と『ロシアの地政学』であり、『大陸戦争』とともに、この分野における4つの軸に沿った研究の成果である。
『国際関係論』(未邦訳)では、独自のIR理論として「多極化世界論」を打ち出している。『多極化世界論』の基本的な構成要素は何であり、古典的リアリズムとどう違うのか。
細かい説明は省くが、『多極化世界論』はサミュエル・ハンチントンの「文明の多元性」というテーゼを真摯に、かつ公理的に採用している。ロシアにも、100年以上前に同じことを主張した著者がいる: ニコライ・ダニレフスキー、そしてユーラシア主義者たちである。文明は一つではなく、多数だ。西洋文明が普遍主義を気取るのは、支配への意志の一形態であり、権威主義的な言説である。それは考慮に入れることはできるが、信じることはできない。それは抑圧と覇権の戦略にほかならない。私たちは、ひとつの文明(ヨーロッパ中心主義的なIRの人種差別主義)の観点から考えることから、主体の多元主義へと移行しなければならない。しかし、現実主義者が国民国家を理論の主体としているのとは異なり、国民国家はヨーロッパ的、ブルジョア的、近代的な政治理解の産物である。国家ではなく、文明だ。カール・シュミットの「大きな空間」に対応して、私はそれらを「大きなポリティアイ」、すなわち文明と呼ぶ。これらの文明–「大きなポリテイアイ」–を主体としてとらえるやいなや、リアリズムの前提条件である国際システムにおけるアナーキーさ、主権、エゴイスティックな行動の合理性など–をすべて適用することができる。しかし、これらのポリテイアイの中では、対照的に、平和主義と統合を掲げるリベラリズムに似た原理が働いている。ただし、ここでは「惑星的」あるいは「グローバル」な世界についてではなく、文明内の世界について話しているという違いがあるだけだ。ポストポジティビズムは、「普遍的価値観」によって私的利益を覆い隠す西欧の権威主義的言説を解体し、文明的エリート、文明的メディア、文明的経済アルゴリズムや企業など、技術的手段の助けを借りて、文明的アイデンティティを再構築することに役立つ。これが一般的なイメージだ。
あなたの多極化論は、西洋の知的、政治的、社会的ヘゲモニーに向けられている。同時に、ネオ・マルクス主義的分析や批評理論のツールを用いながらも、それらのアプローチのように「左から」西洋の覇権主義に反対するのではなく、伝統主義(ルネ・ゲノン、ユリウス・エヴォラ)、文化人類学、ハイデガー的現象学に基づいて、あるいは「右から」反対している。このようなアプローチが英米のIR関係者にアピールできると思うか、それとも主に非西洋の理論家や実務家にアピールするためのものなのか。要するに、欧米のIR理論家は多極化理論から何を学べるのだろうか?
ホブソンのまったく正しい分析によれば、西欧は根本的な人種差別主義に基づいている。西洋人は骨の髄まで完全な人種差別主義者であり、民族中心主義を誇大妄想的なまでに一般化している。彼を変えることは不可能である。エドワード・サイードが「オリエンタリズム」の例で示したように、反植民地闘争がまさに植民地主義やヨーロッパ中心主義の一形態であることを証明している。西欧のアイデンティティの脱構築に真剣に取り組むことができる学者でない限り、「多極化世界論」は西欧世界ではほとんど支持を得られないだろう。西欧の人種差別は常に多様な形態をとっている。今日、その主な形態はリベラリズムであり、反リベラリズムの理論(左派のものが多い)は同じ普遍主義に悩まされている一方、右派の反リベラリズムは信用されていない。だからこそ私は、第一の政治理論(自由主義)でも、第二の政治理論(共産主義、社会主義)でも、第三の政治理論(ファシズム、ナチズム)でもなく、私が第四の政治理論(4PT)と呼ぶものに訴える。
ロシアやアジア諸国では、「多極化世界論」は容易かつ自然に理解されるが、西欧諸国では、十分に理解でき、十分に予想される敵意、注意深く研究しようとしない態度、粗暴な中傷に遭遇する。しかし、常に例外はある。
第4の政治理論(4PT)とは何か。また、多極化する世界の理論や、IR分野における一般的な理論的アプローチに対するあなたの批判とどのような関係があるのか。
これについては、前の質問への回答で少し話した。西洋は、近代の歴史全体を3つの政治イデオロギー(自由主義、社会主義、ナショナリズム)の覇権争いという観点から測っている。しかし、西側諸国は、自分たちが全人類のためを思っているという事実を少しも疑おうとしないため、他の文化や文明を同じように評価する。20世紀末に西洋で自由主義が3つのイデオロギーの競争に勝ったとしても、このイデオロギーが世界規模で本当に普遍的であるということにはならない。全くそうではない。西洋近代政治史のこのエピソードは、西洋の運命ではあっても、世界の運命ではない。世界支配(=第3の全体主義)を主張する自由主義や、その失敗作(共産主義やファシズム)を超える、政治的な他の原則が必要なのだ。このことは、多極化世界論の正しい基礎となる政治的フレームとして、第4の政治理論を導入する必要性を説明している。第四政治理論は、政治理論の領域において、多極化世界理論の直接的かつ必要な相関関係である。
IRはアメリカの社会科学なのか?学術分野としてのロシアのIRは、アメリカの学術分野としてのIRを再現したものなのだろうか?もしそうでないなら、ロシアのIRはどのようにロシア的なのか。
IRは西洋の科学分野であり、規範的なベクトルを持っている。西側の支配を研究するだけでなく、それを生産し、確保し、擁護し、宣伝する。IRは間違いなく、西洋文明の権威主義的な言説である。今日、アメリカは西洋の中核であり、20世紀には当然ながら、IRはアメリカがその地位に向かっていくにつれて、よりアメリカ的なものになっていった(IRはイギリスの科学として始まった)。地政学も同様で、世界的な海軍帝国の機能とともに、ロンドンからワシントン、ニューヨークへと移行していった。他のすべての科学と同様、IRは命令的暴力の一形態であり、知識への意志の中に権力への意志を具現化している(ミシェル・フーコーが説明したように)。ソ連では、IRは研究されていなかった。IRにおけるマルクス主義はソ連の現実に対応しておらず、スターリン以降、現実主義の実践的な形態(理論的な根拠がなく、認知されることもなかった)が大きな役割を果たしてきた。そのため、IRは完全に阻止された。最初の教科書が出始めたのは90年代に入ってからで、当時の流儀では、それらはすべてリベラルなものだった。それが現在まで続いている。今日のロシアにおけるIRの特異性は、そこにはもはやロシア的なものがないという事実にある。リベラリズムが完全に支配し、リアリズムの正しい説明が欠落し、ポストポジティビズムはほとんど完全に無視されている。その結果、学問としてのIRは切り捨てられ、積極的にリベラルになり、極めて時代遅れになった。私はそれと戦おうとしている。私は最近、バランスの取れた(と私は願っている)比率のIR教科書を発表したが、その結果を判断するには時期尚早である。
スティーブン・ウォルトは『フォーリン・ポリシー』誌の9月の記事で、ロシアは「もはや世界中に支持者を集めるようなイデオロギーを誇っていない」こともあり、「旧ソ連ほどの脅威はない」と論じている。ウォルトの評価に同意するだろうか?
その通りだ。今日、ロシアは自らを国民国家だと考えている。プーチンは現実主義者であり、それ以上のものではない。ウォルトの言う通りだ。しかし、『多極世界論』や『第四政治理論』、ユーラシア主義は、欧米の覇権主義に対抗し、自由主義、グローバリゼーション、アメリカの戦略的支配に挑戦する、より広範で大規模なイデオロギーの輪郭である。もちろん、国民国家としてのロシアは西側諸国とは競合しない。しかし、「多極化世界論」と「第4の政治理論」の橋頭堡として、その意義は変わる。ポスト・ソビエト空間におけるロシアの政策と、非西洋的同盟を結ぶロシアの勇気は、その指標となる。今のところ、プーチンはこの概念の可能性を非常に慎重に試している。しかし、西側諸国との関係が厳しくなり、グローバリゼーションの内部的な危機が生じれば、ある時点で、グローバルな代替同盟の構築に向けて、より慎重かつ真剣に取り組まざるを得なくなるだろう。とはいえ、そのような同盟はすでに存在している: 上海協力機構、BRICS、ユーラシア連合などである。マルクス主義のような普遍主義は排除されるが、地域の覇権をめぐる単純な現実主義的策略も排除される。リベラリズムはグローバルな挑戦である。それに対する対応もグローバルであるべきだ。プーチンはこのことを理解しているのだろうか?正直なところ、私にはわからない。理解しているように見えるときもあれば、そうでないように見えるときもある。
ウラジーミル・プーチンは最近、現代の世界秩序を次のように評している: 世界政治における解釈の相違と意図的な沈黙の時代に入った。国際法は、法的ニヒリズムの猛攻によって何度も後退を余儀なくされている。客観性と正義は、政治的便宜のために犠牲にされてきた。恣意的な解釈や偏った評価が法規範に取って代わった。同時に、世界的なマスメディアの完全な統制によって、白を黒、黒を白と描くことが望めば可能になった」あなたはこの評価に同意するだろうか?もしそうなら、この国際的状況への対応として何が必要なのか?
これは真実だが、かなりナイーブな言葉だ。プーチンは、西側諸国が自国の利益のためにルールを定め、必要に応じてそれを変更し、『普遍的規範』とされるものを自国に有利なように解釈することに憤慨しているだけだ。しかし問題は、これが権力への意志の構造であり、ロゴ・ファロ・フォノ中心の言説の組織そのものだということだ。言論がモノローグである限り、客観性と正義はありえない。西洋は他者を知らず、認めない。しかしこれは、この他者が認識する権利を取り戻すまで、すべてが続くことを意味する。それは長い道のりである。「多極化する世界の理論」のポイントは、ある特定のプレーヤーによって確立されたルールは存在しないということだ。ルールは実権を握る中心によって確立されなければならない。今日の国家はそのためには小さすぎる。それゆえ、文明がその中心であるべきだという結論になる。大西洋の客観性と西洋の正義が存在しよう。ユーラシアの客観性とロシアの正義がそれに対抗する。そして、中国の世界やパクス・シニカ(世界/平和:ロシア語では同じ言葉)は、イスラムの世界とは異なるものになるだろう。白か黒かは客観的な評価ではない。何が黒で何が白かは、それを決定するのに十分な力を持つ者によって決定される。
あなたのアプローチは、他のIRのアプローチと比べて、世界舞台でのロシアの行動を理解する上でどのように役立つのか?多極化の概念装置を用いないIRのロシア分析には何が欠けているのか?
興味深い質問だ。ロシアの国際的な行動は、今日、以下の要因によって決定されている:
第一に、歴史的な慣性、先例の力の蓄積(多極世界の理論は、過去が構造として存在すると考える。その結果、この要素は多方面から詳細に考慮されるが、古典的なIR理論の「天動説」[スティーブ・ホブデン、ジョン・ホブソン]は、この要素を視界から外す。特に、ロシアが多くの点で伝統的な社会であり、IRの「帝国システム」に属しているという事実を考慮すると、この点に注意を払う必要がある)。さらに、ソ連の惰性と安定した動機もある(「IRにおけるスターリニズム」);
第二に、(ネオ・グラムシアンによって分析されたカエサリズムの精神に基づく)最も実際的、プラグマティック、現実主義的な動機に由来する、西側諸国への反対という投影的論理は、ロシアを(その指導者の意志にもかかわらず)必然的にアメリカの覇権主義やグローバリゼーションとの体系的な対決へと導き、そのとき、多極化世界論が本当に必要となる(古典的なIRモデルは、多極化世界論に注意を払わず、可能性のある未来を視界から落としてしまう、つまり、純粋にイデオロギー的な偏見と自らに課した恐怖のために、予測可能性を奪ってしまうのである)。
しかし、相手が自分を過小評価すれば、思わぬ打撃を与えるチャンスが増える。だから私は、IR理論家の間で「多極化世界論」が過小評価されていることをさほど気にしていない。
欧米諸国では、学問と政策との間の溝はしばしば嘆かれるか(「象牙の塔」)、学問の独立という理想に照らして存在しないとみなされる。このことは、権力、知識、地政学の関係に関するより広範な議論に関わる。ロシアではIRに関して、学問と政策の関係はどうなっているのか。
私たちの場合、どちらの立場も極端だと思う。一方では、今日のロシア当局は学者に微塵も関心を払わず、無風で不毛な空間に学者を追いやっている。他方で、ソ連の習慣は隷属と順応主義の基礎となり、当局が初めて知識人に何も要求しない状況でも維持されている。だから、科学の状況は滑稽であると同時に悲哀に満ちている。適合主義的な学者たちは権威に従うが、権威はそんなことを必要としない。
もしあなたのIR理論が政治的・哲学的にリベラルな原則に基づいておらず、それらの原則を左からではなく右から、大空間やグロースラウムの言葉を使って批判しているとしたら、それはファシストの国際関係論なのだろうか?アンドレアス・ウムランドやアントン・シェホフストフのように、あなたの思想を「ネオ・ファシズム」と評する学者は部分的に正しいのか。もしそうでないなら、なぜそのような特徴は誤解を招くのか?
ファシズムという非難は、第三の全体主義として現代のリベラリズムに特有の粗雑な政治宣伝における言葉のあやにすぎない。カール・ポパーは著書『開かれた社会とその敵』の中で、右派からの自由主義批判をファシズム、ヒトラー、アウシュビッツに、左派からの自由主義批判をスターリンとGULAGに還元し、その基礎を築いた。現実はもっと複雑だが、ウムランドとシェホフストフに資金を提供し、ポパーの熱烈な信奉者であるジョージ・ソロスは、政治の縮小版に満足している。もし私がファシストなら、そう言うだろう。しかし、私はユーラシア主義の代表者であり、『第四政治理論』の著者である。同時に、私は一貫して急進的な反人種主義者であり、国民国家プロジェクトの反対者(すなわち反民族主義者)である。ユーラシア主義はファシズムとは無関係だ。そして第四政治理論は、反リベラルでありながら、同時に反共産主義、反ファシズムであることを強調している。これ以上はっきりさせることは不可能だと思うが、「第三の全体主義」のプロパガンダ軍はこれに同意せず、どんな議論も納得させることはできないだろう。ソ連でもなく、第三帝国でもなく、ソロス・ファンドと『ブレイブ・ニュー・ワールド』なのだ。ちなみに、ハクスリーはオーウェルよりも正しかった。私はファシストではないが、他人が私をファシスト呼ばわりすることを禁じることはできない。しかし、結局のところ、これは私自身というより、告発者自身に悪い影響を与える。リベラル派が愚かで、狡猾で、率直であればあるほど、彼との戦いは単純になる。
戦争や民政における技術革新は、古典的な空間区分(マッキンダーの見解やスパイクマンのハートランド-リムランド-オフショア大陸)の地政学的前提を覆すものだろうか。また、より広義には、歴史は直線的なパターンを持つのか、それとも循環的なパターンを持つのか。
陸と海は物質ではなく概念である。陸は求心的な秩序モデルであり、明確な一定の軸を持つ。海は、硬い中心のない、過程性、原子性、多数の分岐の可能性を持つ場である。ある意味では、空気は(したがって航空も)航空学である。宇宙飛行士という言葉も、ギリシャ語の船を意味するnautosを語源としている。水、空気、宇宙……これらはすべて、ますます拡散する海のバージョンである。このような状況でも陸地は変わらない。海の戦略は多様化し、陸の戦略は全体として不変である。資本主義と技術進歩は海の典型的な特性である。屹立するタイタンがアトランティスのように奈落の底に突き落とされることもあれば、タラソクラシーの勝利の理由がその没落の原因となることもある。陸地が歴史の地理的軸であることに変わりはない。インターネットやヴァーチャルな世界にも陸と海は存在する。それらは主題化の軸であり、アルゴリズムであり、連合と分離であり、資源とプロトコルのグループ化である。中国のインターネットは陸上であり、西洋のインターネットは海上である。
あなたは海外の哲学的・地政学的著作を数多くロシア語に翻訳している。あなたの考えを形成する上で、知識の取引はどれほど重要なのだろうか?
私は最近、様々な文明のロゴイ、ひいては思想の流通に特化した著書『ヌーマシー』の初版を完成させた。私は、それぞれの文明には固有のロゴスがあると確信している。それを把握し、自分のロゴスに類似性、類比、不協和を見出すことは、まったくもって魅力的で興味深いことである。だからこそ私は、北米からオーストラリアまで、アラビアからラテンアメリカまで、ポリネシアからスカンジナビアまで、多種多様な文化に心から興味を抱くのだ。すべてのロゴイは異なるものであり、その中でヒエラルキーを確立することは不可能である。だから、私たちはロゴイに親しむしかないのだ。イランのシーア派を生涯研究したフランスの哲学者でプロテスタントのヘンリー・コービンは、自分自身のことを『私たちはシーア派だ』と言った。彼は宗教的な意味でのシーア派ではなかったが、自分がシーア派であると感じなければ、イランのロゴスの深みに分け入ることはできないだろう。特に、ピアースやジェイムズ、エマーソンやソロー、ポーやパウンドを学びながら、『私たちはアメリカ人である』ということを体験した。特にピアースやジェイムズ、エマーソンやソロー、ポーやパウンドを学びながら、「私たちはアメリカ人なのだ」ということを実感した。これこそが、さまざまな文化のロゴスの最大の財産なのだ。私たちと同じような文化もあれば、まったく異なる文化もある。そして、これらのロゴスは戦争している。それゆえヌーマシー、知性の戦争なのだ。それは直線的でも原始的でもない。大きな戦争なのだ。それは、私たちが「人間」と呼ぶもの、私たちが最も過小評価しがちな深みと複雑さを生み出す。
最後の質問だ。あなたは自らを「帝国の最後の哲学者」と呼んでいる。ユーラシア主義とは何なのか、そしてそれは権力配分の世界的な軸とどのように関係しているのか?
ユーラシア主義は、私が数冊の本と数え切れないほどの記事やインタビューに捧げた、発展した世界観である。原理的には、多極化世界論と第四政治理論の基礎にあり、地政学と組み合わされ、伝統主義と共鳴する。ユーラシア主義の主要な思想は多元的人間学であり、普遍主義の否定である。私にとっての帝国の意味は、帝国は1つではなく、最低でも2つ、さらにはそれ以上存在するということである。同じように、文明は決して単一ではなく、その境界を決定する他の文明が常に存在する。シュミットはこれを「多元的多様性」と呼び、「政治的多様性」の主要な特徴だと考えた。ユーラシア帝国とは、ツランの政治的・戦略的統一であり、海の文明や大西洋主義帝国と対立する歴史の地理的軸である。今日、アメリカはこの大西洋主義帝国である。ケネス・ウォルツは、IRにおけるネオリアリズムの文脈で、2極のバランスを概念化した。その分析は非常に正確だが、二極世界の安定性とソ連の存続期間については誤っている。しかし、全体としては彼の言う通りである。世界には、国民国家ではなく、帝国のグローバルな均衡が存在し、その大半は主権を主張できず、名目的なものにとどまっている(スティーブン・クラスナーの「グローバルな偽善」)。まさにその理由から、私が帝国の哲学者であるのは、ほとんどすべてのアメリカの知識人がそうであるように、本人が知っているかどうかにかかわらずである。違いは、彼が自分自身を唯一の帝国の哲学者だと考えているのに対して、私は自分自身を帝国の一つ、ユーラシア帝国の哲学者だと考えているということだけだ。私はより謙虚で、より民主的だ。それがすべての違いだ。
