Contents
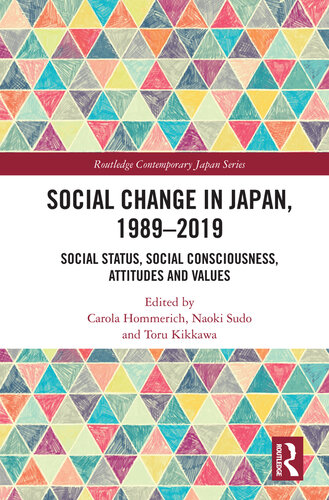
Social Change in Japan, 1989-2019
日本の社会変化、1989-2019
本書は、1980年代の高度に平等主義的な高度成長経済から、2010年代の経済的停滞と人口動態的に縮小する格差社会までの30年間の急速な社会変化を、日本の国民がどのように経験し処理してきたかを、膨大な調査データに基づいて考察している。本書では、仕事、性別役割分担、家族、福祉、政治などに対する社会的態度や価値観について論じ、社会の変化から特に影響を受けてきた特定のサブグループに焦点を当てる。また、多くの日本人が中流階級を自認しているが、その理由は時代とともに変化しており、1980年代には上昇志向の強い楽観的な見方が主流であったが、現在は自分の社会的地位についてより現実的な見方をするようになったと結論付けている。
初出 2021年ラウトレッジ社
目次
- 寄稿者一覧
- はじめに
- 1 「平成の日本」を知る:変容のなかのアンカーリング キャロラ・ホメリッヒ、須藤直樹、吉川徹
- 第1部 「真ん中」を読み解く:舞台裏の微妙な変化
- 2 社会階層のイメージと「格差社会」 神林浩史(かんばやしひろし)
- 3 変化か、変化しないか?日本における身分集団と身分識別の複雑な関係 谷岡賢
- 第2部 変化への適応:平成の社会意識
- 4 新しい現実への適応?身分識別のメカニズムにみる教育格差 羽佐間亮太郎
- 5 市民社会:誰が参加しているのか?三谷晴代・平松誠
- 6 福祉縮小時代における政府の再分配プログラムへの支持:労働者の意識の変化 長吉喜久子
- 7 社会的地位としての雇用形態:正社員と非正社員の生活満足度の変化 橋爪勇人
- 8 保守的な若者?なぜ若者は権威主義的になり、自民党を支持するのか? 松谷充(まつたに・みつる
- 9なぜ日本の既婚女性は「働きながら介護する」という不平等なジェンダー規範を支持するのか? 樋口真理
- 10 「平成」以降の日本、私たちはどこへ向かうのか? 須藤直樹、カローラ・ホメリッヒ、吉川徹
寄稿者紹介
橋爪勇人(はしづめ・ゆうと):東京・タバコ学術研究センター研究員。大阪大学大学院人間科学研究科博士課程修了(人間科学(社会学)。現在の研究テーマは、日本における社会的不平等と高級食料品(お茶、コーヒー、アルコール、タバコなど)、特に職務上の地位と主観的幸福の関係、高級食料品の消費行動とその社会的役割の決定要因である。近著に『消費・文化活動としての高級食料品の利用』(社会と調査[社会調査の進歩](22) :65-78,2019)などがある。
間亮太郎(はざまりょうたろう):南山大学総合政策学部助教(社会学)、名古屋市。過去に大阪大学大学院人間科学研究科社会学専攻の助教を務めたことがある。大阪大学で人間科学(社会学)の博士号を取得。現在は、日本の若者、特に社会経済的地位と社会意識との関連について研究している。近著に『世代交代がもたらすオトナの生き方』など: 現在志向が日本の若者の静けさに及ぼす影響-政治的委任に着目して-」など: 政治的委任と新自由主義的な不平等認識に着目して](草思楼記62(1): 79-95,2017)、『文壇社会と若者の現在』(大阪大学出版会、2019年吉川徹と編著)などがある。
樋口真理(ひぐち・まり) 北海道大学人文学部社会学研究室(札幌市)准教授。2015年に大阪大学で人間科学(社会学)の博士号を取得し、重度の精神的問題を抱える人々の社会的排除を可能にする社会的価値観について研究している。中心的な研究テーマは、社会的価値観と特定集団の社会的切り捨て/再評価のプロセスとの関係である。現在の研究では、社会的包摂、障害や病気を持つ人の脆弱性、自殺に関わる社会規範、介護労働、ジェンダー不平等、福祉政策に焦点をあてている。最近の著書は以下の通り: 「統合失調症に対する社会的受容に影響を与える要因の文化的文脈への依存性: Evidence from comparative study between Japan and Vietnam” (Asian Social Science, 11(22):187-202, 2015), “Discovery of Place to Belong in Recovery Process of Persons with Schizophrenia: グラウンデッド・セオリー・アプローチとQDAソフトウェアAtlas.tiの組み合わせ」(『大阪人間科学』2:21-42, 2016)などがある。
平松誠(ひらまつまこと):大阪大学大学院人間科学研究科特任研究員(大阪府)。過去に、日本学術振興会特別研究員(DC2)、米国ハーバード大学社会学部客員研究員などを歴任。2020年、大阪大学で人間科学(社会学)の博士号を取得。現在の研究テーマは、コミュニティの特性が個人の社会的態度や地位獲得に与える影響。最近の著書は以下の通り: “The Effect of Region on Educational Attainment”(平成27年度SSM調査研究報告書5:教育2:99-112,2018)。
Carola Hommerich 上智大学人間科学部社会学科准教授(東京都)。過去に北海道大学大学院文学研究科社会学専攻准教授(札幌)、ドイツ日本研究所(DIJ)上席研究員(東京)を歴任。ケルン大学にて社会学博士号を取得。現在の研究テーマは主観的幸福と社会的不平等、特に不安定体験、地位不安、排除感情の相互関係や行動結果への影響について。最近の著書には、「舞台裏の動き: The Quiet Transformation of Status Identification in Japan」(Social Science Japan Journal 22(1): 11-24, 2019, with Toru Kikkawa)、『Social Inequality in Post-Growth Japan』(Routledge, 2017, edited with David Chiavacci)などがある。
神林宏(かんばやしひろし) 東北学院大学教養学部人間科学科教授(仙台市)。日本における社会的態度に関する性差とその心理的メカニズムを研究し、東北大学大学院文学研究科社会学専攻で博士号を取得した。日本における社会的不平等のいくつかの側面、特に不平等に対する態度、健康の社会的決定要因、雇用の移動における不平等について研究している。近著に「日本の社会階層のイメージの変遷」: The Other Side of the ‘Quiet Transformation’ ” (Social Science Journal Japan 22(1):45-63, 2019), “Status Anxiety in Japan 1995-2015: 量的研究” (社会学研究101:11-36,2018)、「Labor Market Institutions and Job Mobility in Asian Societies:日本と台湾の比較研究」(『国際日本社会学研究』23(1): 92-109,2014年、竹之下博久と共著)。
吉川徹(きっかわとおる) 大阪大学大学院人間科学研究科教授(社会学)。大阪大学を拠点とする「階層と社会心理(SSP)プロジェクト」を率いる。主な著書に『現代日本における社会的メンタリティ』(日本経済新聞出版社): Quantitative Social Consciousness Studies』(2016)、『日本の文壇[現代日本の格差]』(2018)などがある。研究テーマは、計量社会学、社会調査法、教育社会学、社会心理学、社会階層研究など。
松谷充(まつたにみつる) 中京大学現代社会学部社会学科准教授(名古屋市)。2007年に大阪大学で人間科学(社会学)の博士号を取得。博士論文のタイトルは、『ポスト政党政治と価値志向』である。現在も日本のポストパーティポリティクスを研究テーマとしている。ポピュリストの台頭、ポスト3.11の社会運動、若者の政治志向などについて執筆している。
三谷晴代(みたにはるよ) 龍谷大学社会学部准教授。大阪大学で人間科学(社会学)の博士号を取得。ボランティア活動、市民参加、社会的支援ネットワークに関心を持つ。現在の研究では、社会的孤立と孤独の決定要因に焦点をあてている。近著に「社会的孤立に及ぼす幼少期の不利益の影響-『ふれあいの希薄化』の検証-」(日本経済新聞出版社)、「社会的孤立に及ぼす幼少期の不利益の影響-『ふれあいの希薄化』の検証-」(日本経済新聞社)がある: 累積的不利益仮説の実証的検証」(『福祉社会学研究』16:179-199,2019),『ボランテイアを読み解くもの』(『福祉社会学研究』16:179-199,2019): 彼らはいかにしてボランティアになるのか:利他主義の計量社会学』(東京:有斐閣、2016)、「Influences of Resources and Subjective Dispositions on Formal and Informal Volunteering」(Voluntas.International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 25(4): 1022-1040, 2014).
永吉喜久子(ながよし・きくこ):東京大学社会科学研究所准教授、2020年より教員。過去に東北大学大学院文学研究科行動科学専攻准教授を務める。大阪大学で学部・修士課程を修了し、博士号を取得。研究テーマは、移民や福祉政策に関する世論、社会階層、社会的排除。市民の生活状況だけでなく、制度がどのように世論を形成しているかに着目している。最近の著書には、「日本における熟練移民の経済統合: 雇用慣行の役割” (インターナショナル・マイグレーション・レビュー 52 (2): 458-86, 2019, ヒラリー・ホルブローとの共著)、「異なる福祉国家における反移民態度: 労働市場政策の種類は重要か?” (国際比較社会学雑誌 56 (2): 141-62, 2015, Mikael Hjermと共著)。
須藤直樹(すどうなおき) 学習院大学政治学科社会学専攻教授。1994年に東京大学で博士号を取得。社会階層識別や社会的不平等に関する著書を多数出版している。近著に『信用できない世界』(2013年、勁草書房刊)がある。その他の近著に、「女性の労働力参加の効果: 家計所得格差の変化の説明」(Social Forces 95(4): 1427-1450, 2017)、女性の労働力参加と家計所得格差の複雑な関係を探る「社会的価値観に基づく信頼の社会ネットワーク」: 一般化された信頼と民主主義の曲線的関係の説明」(The Journal of Mathematical Sociology 41(4): 193-219, 2017)は、民主主義が国間の一般化された信頼の水準にどのような影響を与えるかを説明することに焦点を当てたものである。
谷岡賢(たにおか・けん):中京大学文化科学研究所プロジェクト研究員。2013年から2016年まで、日本学術振興会特別研究員(東京)を務める。日本の社会意識の変化について研究し、大阪大学で人間科学(社会学)の博士号を取得した。現在の研究では、日本における社会的不平等と社会意識、特に階級識別の関係に着目し、その関係が時間的にどのように変化するかを分析している。
はじめに
1 平成の日本を理解する
変容の中のアンカリング
カローラ・ホメリッヒ、須藤直樹、吉川徹
天皇陛下の退位に伴い、2019年4月、平成が終わった。「どこまでも平和に」という意味の時代名を持つ平成は、経済成長のピークを迎え、日本が平等主義の大衆中流社会(総中流社会)であるという意識が共有されていた1989年、明るく楽観的なスタートを切った。しかし、バブル経済が終焉を迎え、予想以上に平和な時代となった。経済の停滞と人口動態の高齢化は、日本社会が過去30年間に様々な社会的次元で経験した途方もない変容を引き起こした(Chiavacci and Hommerich 2017)が、その原因ともなった。
近代的で高度に発達し、グローバル化した国家である一方で、日本はいまだに天皇の在位期間を基準とした伝統的な年の数え方を守っている。新しい天皇が即位すると、「年号(ねんごう)」「元号(げんごう)」と呼ばれる新しい時代が始まる。この元号の中で年号が付けられ、現在でも公文書や役所の書類は、多くの国が採用しているグレゴリオ暦の年号ではなく、この元号に基づいて作成されている。つまり、新元号への移行は、単なるノスタルジックなものではなく、日本国民なら誰もが気づく変化なのである。そのため、その時代の特徴を振り返り、未来に思いを馳せる機会にもなっている。その年の4月に平成の終わりを控え、2019年の年明けには、政治、経済、スポーツ、大衆文化などの主な出来事を列挙して、具体的に何がその時代を特徴づけたのかを総括する、数多くの–主に非学術的な–出版物が書店に並んだ(『経済人2019』『五島2018』『博報堂生活研究所2019』『オフィスJB2019』『三栄2019』『洋泉社2019』等々)。テレビ番組では、ポップソング、テレビシリーズ、芸能界や政治のスキャンダルなど、平成のランキングが延々と続いていた。
また、1991年のバブル崩壊 2008年の金融危機、その後の景気後退、そして停滞など、1989年から2019年までの30年間を通じて、日本では社会の大きな変化を引き起こす数々の出来事があった。また、1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災という、これまで経験したことのない規模の自然災害が発生し、津波や福島第一原子力発電所の事故が発生した。さらに 2009年に自民党から民主党へ、そして2012年には自民党へと、2度の政権交代があった。官民ともにジェンダー不平等が続く中、女性の労働市場への参加は増加した。さらに、少子化による急速な高齢化が進み、2011年には人口減少に転じるという人口動態ショックが発生した。これらの出来事や進展は、社会のさまざまな側面に大きな変化をもたらしている。その結果、社会的不平等が拡大し、日本社会のイメージは「総中流社会」から「格差社会」へと明らかに変化した。こうした変化のメカニズムも結果も多面的で複雑であり、これまでにも他の研究者によって広く取り上げられてきた(Chiavacci and Hommerich 2017; Chiavacci 2008; Coulmas et al. 2008; Kariya 2013; Kawano, Roberts, and Long 2014; Matanle and Rausch 2011; Sato and Imai 2011; Osawa 2011)1.
したがって、本書における私たちの目的は、それとは異なるものである。本書の目的は、平成の時代に最もインパクトのあった出来事の概要を紹介することではない。その代わりに、これらの出来事が日本人の社会的態度や価値観にどのような影響を与えたかを分析することを目的としている。過去30年の間に、日本人の社会に対する認識がどのように変化したのか、日本人が社会の大きな変化をどのように受け止め、それが社会の中での自分のあり方に影響を与えたのか、縦断的なデータに基づいて調査した。ここでは、地位認識と社会意識の変化に焦点を当て、過去30年間の日本の変容がどのように国民に響いているのかを考察する。
1 変化の過程:身分制の静かな変容
平成は変革の時代であったばかりではない。1950年代から1980年代後半にかけて、高度経済成長と教育の拡充によって農業社会からサービス社会への転換が図られ、社会的地位が飛躍的に上昇した後、平成の30年間は、日本社会の職業構造がある程度安定した時期である(図11参照)。特に、日本の(客観的な)中産階級の大半を占める高位職業層の人々にとっては、マス・ミドルクラス社会としての日本という言説の中心的なアクターであるように思われる。
しかし、ここで重要なのは、日本が大衆的な中流社会であるという一般的なイメージは、客観的な地位指標というよりも、日本人の90%以上が中流であると自認しているという事実に基づいているという点である。客観的な社会的地位と主観的な社会的地位は、必ずしも重なり合う必要はない。しかし、実際の所得格差が拡大し 2000年代半ばから「格差社会」論が台頭してきたにもかかわらず、この自認パターンに変化がないのは不可解である。ここでよく引用されるのが、1950年代から毎年実施されている内閣府の「国民生活に関する世論調査」である(図12参照)。1950年代後半から1960年代前半にかけては、自分を下層に属するとする回答者の割合が大きかったが、高度経済成長期にはその割合が減少し、中層に属するとする回答者が増えている。1970年代半ばには、90%以上が自分の生活水準を社会の中層に属すると評価し、この分布はその後も安定している。さらに、人口の多くが中流階級に属することは珍しくないが(cp. Evans and Kelley 2004; Pew Research Center 2012: 123; 杉本 2014: 40; 白波瀬 2010): この30年間、日本社会は先に述べたような大きな構造変化を遂げ、それが個人の日常生活における社会的現実にも影響を及ぼしている可能性が高い。
図11日本の社会構造の推移(1955~2015年
出典:日本経済新聞社 SSM調査シリーズのデータに基づく。1955年から2005年のデータは、石田・三輪(2009, 652)から引用した。2015年については、SSM2015, Ver.070(2017年2月27日発表)を使用した。
注)今回引用したデータは、25歳から64歳までの男性で構成されている。女性は1985年以降のSSM調査には含まれているが、比較可能性の観点からここではサンプルから除外されている。
このことは、日本の多くのオブザーバーに謎を投げかけている: このことは、過去30年間に日本社会が経験した重大な構造的変化が、日本人に気づかれなかったことを意味するのだろうか?この問いに答えるには、その裏側に目を向ける必要がある。人々の自己認識の仕方の全体的な分布は大きく変化しなかったが、客観的な社会的地位が自己評価に与える影響の仕方は変化している。吉川(1999)はこれを「身分識別の静かな変容」と呼んでいる。学歴、職業、収入といった古典的な階層変数は、一般的な上昇志向が人々の階級の境界を曖昧にしていた1970年代には、地位のアイデンティティと緩やかにしか結びついていなかった。1980年代には、身分識別は主に所得によって決定され、それは生活満足度と強い関係を示した。しかし、日本が格差社会を自認するようになると、この状況は一変する。1990年代以降、所得だけでなく、学歴や職業も階層識別に大きな影響を与えるようになり、その影響は2010年代半ばまで強くなっている3。
図12 国民生活に関する世論調査による身分識別2
出典はこちら内閣府 2019年、筆者作成。
このことが意味するのは、平成の終わり頃には、人々は自分の社会的地位について、より現実的な考えを持っているということである(Hommerich and Kikkawa 2019: 21; Sudo 2018, 2010)。これは、ある種の意識(公平・不平等に関する考え方や教育に対する意識など)が以前よりも特定の階層と強く結びついている一方で、他の意識(政治的志向やジェンダーロールなど)が多様化し、伝統対現代という一次元軸では単純に説明できなくなったことを意味しているのかもしれない。特に、これらの相互関係を深く理解することを難しくしているのは、様々な変容が同時に起こり、そのどれもが身分識別に異なる形で影響を及ぼしていると考えられるからだ。この意味で、私たちは、社会が大きく変容する中で、身分に関連する固定観念の不可解な相互作用を見ることができる。全体として、日本社会は複雑化・多様化しており、意識や社会意識の分析もそれに追随する必要があると考えられる。
2 30年以上にわたる意識変化の追跡
本書で紹介する分析は、まさにそのことを目的としている。定量的社会意識研究(keiryo shakai ishiki ron)(吉川 2016: 3)という分野に位置づけられる。意見・態度が変化したかどうかだけでなく、その変化のメカニズムを明らかにすることに重点を置いている。本研究では、どのような社会の変化が、どのような態度や意見の変化を引き起こすのかを理解することを目的としている。本編では、1985年から2015年までのSSP調査シリーズとSSM調査シリーズのデータを用いて、高度に平等な高成長経済から経済的に停滞し人口的に縮小する格差社会への30年分の急速な社会変化を国民がどのように経験し処理したかを説明し、この変化のどの側面が特にこの期間の意識のシフトに寄与したかを分析している。
2.1日本における社会的地位と地位識別に関する縦断的・全国代表的調査データ
本書で紹介するオリジナル分析に使用した「社会階層と社会移動に関する全国調査」(SSM)と「社会階層と社会心理に関する調査」(SSP)シリーズの実証データは、日本における社会的地位と身分識別を数十年にわたって追跡することを可能にした。本書の執筆者は、全員がSSP研究者ネットワークのメンバーであり、一部はSSM研究会にも所属している。そのため、最新の調査データを分析に使用することができる。以下、両者の研究プロジェクトと、本書で使用した特定の調査波について簡単に説明する。
SSMは、日本社会における階層構造の変化と階層間の移動をモニターするために、1955年から10年間隔で実施されている。最初の3回は男性のみを対象としていたが、1985年以降は女性も調査対象としている。東京大学の白波瀬佐和子氏を中心に、約100名の研究者が参加し、2015年に実施された最新のSSM調査の企画・実施・分析を行っている。
SSM調査が日本社会の社会構造の変化を客観的に把握することに主眼を置いているのに対し、SSP調査は主観的なスタンスを加えることを目的としている。私たちは、学歴、職業、収入などの客観的な社会的属性と、その主観的な余波である地位確認、社会的価値観、主観的幸福感などの複雑な関係を明らかにすることを目標としている。価値観や社会意識を測定する調査項目を追加する際には、SSM調査シリーズで使用されている項目との比較可能性を確保するために細心の注意を払った。日本における最も包括的な調査であるSSP2015の準備として、5つの予備調査を実施し、さまざまな指標や調査方法を検証した。
本書で分析に使用した調査の概要を説明するために、これらの調査の基本的な手法に関する情報を時系列で列挙する7。
SSM1985
SSM1985調査は、SSM調査委員会が1985年11月から1986年2月にかけて実施したものである(調査主体:大阪大学直井篤)。回答者は20歳から69歳までの日本人の男女である。回答者は、日本の選挙人名簿に基づく2段階の層別無作為アプローチで抽出された。データは、対面インタビューによって収集された。調査は、3種類の質問紙を使用した。各アンケートの回答者数および回答率は以下の通り 男性用アンケートA(N=1,239,61.0%)、男性用アンケートB(N=1,234,60.8%)、女性用アンケートC(N=1,474,68.8%)。
SSM1995
SSM1995調査は、Stratification and Social Mobility Research Group(研究代表者:清山和男、東京大学)により、1995年10月から11月にかけて実施された。ここでは、サンプル集団は20歳から69歳の日本人である。また、訪問面接調査であった。また、サンプルは、日本の選挙人名簿に基づく2段階の層化ランダムサンプリング法によって抽出された。8,064人のサンプルから5,357人の回答を得た(回答率=66.4%)。
SSM2005
SSM2005は、階層と社会移動研究グループ(研究代表者:佐藤嘉倫、東北大学)により 2005年11月から2006年4月にかけて実施された調査である。サンプル集団は、20歳から69歳までの日本人である。サンプルは、日本の選挙人名簿に基づく2段階層化ランダムサンプリングで抽出された。調査方法は、今年度からこれまでのSSM調査から、個人面接と配置法の組み合わせに変更された。回答者の人口統計学的特性や社会経済的地位に関する情報は個人面接で、社会的態度に関する情報は質問紙で得たものである。当初のサンプル13,031人から、合計5,742人の回答が集まった(回答率=44.1%)。データ収集方法の変更により、本調査は本シリーズの他の調査との比較可能性がやや損なわれている(小林 2008)。
SSP-W2012
SSP-W2012は、社会調査会社(研究代表者:轟木誠、金沢大学)の登録モニターを利用し、2012年2月にWebアンケートとして実施された。25歳以上59歳以下の回答者は、クオータサンプリングにより以下のように抽出した: まず、日本の全市町村から250のサンプリングポイントを無作為に選択した。まず、日本の全自治体から250のサンプリングポイントを無作為に選び、各サンプリングポイントに12ケースを割り当てた。アンケートは3,000件に達した時点で終了した。教育レベルや雇用形態に関する質問に回答しなかった回答者、および態度に関する質問の75%に回答しなかった回答者は、分析から除外した(回答完了=2839件)。
SSP2015
SSP2015の調査は、2015年1月から6月にかけてSSP研究者ネットワークによって実施された(調査責任者:大阪大学・吉川徹)。回答者は20歳~64歳の日本人男女。サンプリング方法は、選挙人名簿に基づく3段階の層別無作為抽出で、タブレット端末を用いた対面インタビューによるデータ収集(コンピュータ支援型個人面接、CAPI)である。有効回答数は3,575人で、回答率は42.9%だった。この回答率は、以前の調査と比較すると低いように思われるが、回答率の低下という問題に直面している最近の日本の社会調査研究の傾向に沿ったものである。
本書では、このようなさまざまな調査のデータをもとに、1985年から2015年までの30年間における日本社会のメンタリティの変化を各章で紹介している。
3 本書の構成と目的
日本が過去30年間に受けた客観的な変容を、主に格差拡大へのシフトとそれがもたらす問題に焦点を当てながら検証した英文の書籍はいくつかあるが(Allison 2013; Chiavacci and Hommerich 2017; Coulmas et al. 2008; Hara and Seiyama 2005; Ishida and Slater 2010; Kariya 2013; Kawano, Roberts, and Long 2014; Sato and Imai 2011; Shirahase 2014)、一般の人々がこれらの客観的変化をどう処理したか、それが社会意識や態度にどう影響したかに注目した包括的英語出版物は存在しない。日本語では、これらのテーマに関する多くの研究がある(Kikkawa 2018, 20148; Kikkawa and Hazama 2019; NHK BCRI 2015; Saito and Misumi 2011; Sudo 2018, 2010, 2009; Tarohmaru 2016; Umino 2000)。さらに、本書では、これらの知見の一部を、日本語に堪能でない読者にも提供することを心がけた。
本書は2つのパートに分かれている。第1部は、1985年から2015年までの身分識別の決定要因の変化に焦点を当て、この変化の推進要因と意味を分析し、先に概説した身分識別の「静かな変容」の背後にあるメカニズムについて、より背景を明らかにする。第2部では、平成の世における社会意識の変化を検証し、社会の変化によって異なる影響を受ける特定のサブグループ(若者、女性、地方と都市、正社員と非正社員など)に焦点を当てながら、社会的態度や価値観(ジェンダーロール、仕事、政治、ボランティア、福祉など)を論じている。
第1部は、1985年から2015年にかけて、日本社会の階層構造に対する人々のイメージがどのように変化したかを分析した神林(第2章)により開始される。彼は、2015年までに、中間層が集中する社会をイメージする人の割合が縮小し、日本社会を不平等とイメージする人の割合が大きくなっていることを発見する。想像する社会のタイプは、教育水準に最も影響され、高学歴の回答者は低学歴の回答者よりも「集中的な中流階級」モデルを想像する傾向が強かったという。さらに、2015年において、社会的態度(政府の再分配への賛成、地位不安、政治的・集団的効力など)や生活満足度は、認識した階層構造のタイプに関連して異なることが彼の分析から明らかになった。彼の発見は、人々が想像している社会モデルのタイプによって、異なる現実を経験することを示唆している。
次に、谷岡(第3章)は、1995年から2015年の間に、客観的地位集団と主観的地位識別の関係が変化したかどうか、どのように変化したかを調べ、この変化の主な要因を明らかにした。彼はまず、多群潜在クラス分析を適用し、客観的地位変数(学歴、職業、収入、財産など)と主観的地位識別(階層化階層における人々の位置づけなど)に基づく地位グループを抽出した。彼は、経年変化に関する4つの可能なモデルを互いに検証し、日本における主観的身分識別の「静かな変容」の原因として、2つの並行するトレンドが考えられることを発見した。第一に、身分形成要因が人口にどのように分布してきたかの変化(すなわち、大卒者の増加)によって、客観的身分集団の分布が変化した。これは、ひいては地位識別の分布に影響を与える。第二に、客観的地位群と主観的地位識別の関係も変化しており、2015年には、1995年の同世代よりも、地位群によっては、階層化ヒエラルキーの上位または下位に位置する人がいる。
両章とも、日本社会の多様化を明確に示している。このことは、「日本人」を一枚岩の集団として扱うことは、とっくに時代遅れであり、新しい時代に進む日本社会を深く理解するために重要な動きを覆い隠す可能性があることを示唆している9。
このことは、本書第2部の冒頭で、日本の若者の身分識別の変化に注目した間(第4章)でも強調されている。日本の若者は、一方では日本経済の停滞と高齢化の犠牲者であり、他方では比較的高い生活満足度に驚かされるという、近年の日本の若者に関する多様な言説の中で、間氏は、それぞれのグループにおける自己位置付けの具体的なメカニズムをより理解するために、高学歴と低学歴の若者を区別して分析する。高学歴の若者にとって、社会的地位の標準的な決定要因(職業、収入、配偶者の有無など)は、依然として地位の識別と密接な関係があることを彼は発見した。しかし、低学歴の若者にとっては、以前は標準的なライフコースと考えられていたものを実現することが難しくなっている。彼らにとって、社会的地位の客観的決定要因は力を失っている。その代わりに、彼らの社会的地位は、将来の問題を無視して現在に集中することによって強化されている。間氏は、これを社会的現実の変化への適応の問題であると同時に、日本社会に流れる強い教育的亀裂の表れであると見ている。
三谷・平松(第5章)は、平成末の日本における市民参加の決定要因に着目して分析を行っている。過去30年間に日本社会が経験したボランティア活動の一般的な変化を概説した後、マルチレベル・モデリングを適用して、市民参加を促進する個人レベルの社会的属性とコミュニティの特性を明らかにした。その結果、高齢化率の高い地域は、参加率が高い可能性が高いことがわかった。急速な高齢化が進む日本社会が抱える様々な問題を背景に、社会問題が市民の連帯と行動の契機となり、日本を持続可能な未来に導く可能性があることを示す、勇気づけられる結果である。
永吉(第6章)は、1990年代後半から2000年代半ばにかけて日本の労働市場が経験した構造改革が、労働者の再分配政策に対する意識に与えた影響を考察している。この改革の結果、失業や貧困のリスクは、非正規労働者や中小企業労働者、低生産性産業労働者など、すでに社会経済的に脆弱な立場にあった集団にますます集中するようになった。利己的な理論からすれば、こうした弱者層は政府の再分配を支持するはずだが、彼女の分析によれば、その逆であることがわかる。これは、日本経済を停滞から脱却させるために規制緩和の必要性を国民に訴えるための政治的レトリックが成功したと解釈し、再分配の受益者となりうる非正規労働者や中小企業労働者までこのレトリックに対抗して動員するのは難しいのではないかと結論付けている。彼女の分析は、日本社会で最も不利な立場にある人々の間で、労働市場のさらなる細分化、ひいては社会的不平等のさらなる拡大を阻止するための目立った行動が見られない理由を解明する手がかりとなる。
正規労働者と非正規労働者の生活満足度の変化を比較した橋爪の分析(第7章)は、一見、不利な立場にある人々の無関心な態度を示すもう一つの手がかりとなる。彼は、1995年と比較して2015年の正規・非正規労働者の生活満足度の格差が拡大していることを見出しつつも、その格差は非正規労働者の生活満足度が悪化して大きく変化したのではなく、正規労働者の生活満足度が向上したことに起因していると分析している。2015年の正社員は、20年前の正社員と比較して、仕事でより多くの権限を行使できるようになったため、満足感が高まったという。しかし、それ以上に重要なのは、1995年当時と比較して、正社員というステータスがより貴重になり、それを達成することが生活満足度にプラスの影響を与えるようになったことである。
松谷(第8章)は、日本の若者の政治的志向の変化について考察している。彼は、1990年代半ばと比較して、2015年の日本の若者は全体的に保守的になったが、政治的態度を変えたのは特に高学歴の若者であることを発見した。伝統的な右派権威主義政党である自民党への支持が高まったのは、主に若者の物質主義的・新自由主義的志向と、政治に対する宿命的な態度が対になったためだ。松谷は、日本の若者の政治的志向がこのように大きく変化したのは、経済的停滞の影響が不安と不安定をもたらし、反動的な価値観の変化につながったからだと分析している。その結果、自民党は若者から予想外の支持を得て、日本の社会的格差を正当化するイデオロギーに基づくアッパーミドル層の政党に変貌してしまった。
樋口(第9章)は、女性の労働市場への参加が進みつつあるにもかかわらず、妻と夫の家事分担の不平等さに大きな変化がない理由を理解するために、既婚女性の家庭内での役割に対する意識を調べた。その結果、家事負担を平等に分担することを支持する既婚女性が最も多い一方で、妻が有給で働きながら家事を行う「働きながら介護する」モデルを支持する既婚女性が2番目に多いことが明らかになった。樋口氏は、女性が積極的に有給労働に取り組んだとしても、そのリソース(自身の収入、教育レベル、雇用形態など)は、労働市場でも家庭内でも不利な立場に追い込まれることを指摘している。「働きながら世話をする」という役割を受け入れることが、社会的な認知を得たり、提示された行動の選択肢の中で不満を感じないようにするための、唯一実現可能な戦略であるように思われる。これは個人レベルでは成功した対処法かもしれないが、樋口氏の発見は、女性自身が自分たちを差別するシステムを支え、増殖させる手助けをしていることも示唆している。
この巻の最後には、平成以降の日本の将来にとって最も決定的と思われる要因について論じている。最も重要なことは、各章で示された分析結果に示唆されているように、単なる適応から真の変革へと移行する必要性である。
様々な社会的次元における意識の変化を論じることで、平成の日本における社会意識の包括的な説明として、本書を締めくくる。定量的な実証データにより、数十年にわたる比較が可能であることから、私たちの結果の根拠となる確固たる基盤を持つことができた。私たちは、今後もこれらのテーマについて研究を続けていくつもりであるが10、他の研究者の興味を喚起し、今回取り上げることができなかったテーマを追加したり、実証的な方法を適用したりして、社会意識の問題をさらに掘り下げる動機付けになればと思う。このように、日本社会に関する社会学的調査について、活発で実りある交流が行われ、問題の発見や成果の提供につながることを期待する。その結果、政策立案者が、日本を成功させるだけでなく、幸福で持続可能な未来に導くために利用できる実証的データを提供することができる。
10 平成期以降の日本 私たちはどこに向かっているのか?
須藤直樹、カローラ・ホメリッヒ、吉川徹
1 支配的な社会モデルとしての格差社会
本書は、平成という時代の特殊性を考慮しながら、日本人の社会的態度、アイデンティティ、イメージの変化を明らかにすることを目的とした。冒頭で述べたように、平成の時代にはさまざまな大きな社会変化が起こった。その中でも、雇用の不安定化と高等教育の大規模な拡大という2点が強調されなければならない。労働力調査によると、雇用全体に占める非正規雇用の割合は20.2%(1990)から38.5%(2019)へと増加している(統計局2019)。同様に、学校基本調査によると、日本の高等教育機関への進学率は24.7%から53.7%に上昇している(文部科学省2019)。このように、この30年で教育水準は急激に上昇したものの、日本では安定した職業に就く機会は減少傾向にある。つまり、上方への社会移動の機会が減少し、下方への社会移動のリスクが高まっている(石田・三輪 2008)。このような社会の変化は、本編の前章で紹介したように、日本人の社会的イメージや意識にも影響を与えていると思われる。
実際、神林(第2章)は、日本人が抱く支配的な社会像が、「中流集中型」から「ピラミッド型」あるいは「二極型」へと徐々に変化してきたことを明らかにしている。「中流集中型」は一般的な中流社会、「ピラミッド型」「二極型」は格差社会に相当する。したがって、日本人が考える中流社会は、この30年で格差社会へと変化したのである。しかし、神林は、すべての日本人が「中流社会」から別のタイプの社会像に同時に変化したわけではないと論じている。彼の分析によれば、中流イメージを持ち続ける人もいれば、中流イメージを変化させた人もいる。このことは、日本人が社会意識を統一した一枚岩の集団を構成しているのではなく、社会集団によって異なる現実を生きていることを示唆している(吉川2018)。
その一例として、日本人の主観的社会的地位の変化に注目することができる。主観的な社会的地位の分布は、中流階級に強烈に集中する傾向がある。しかも、この中流階級の傾向は、過去30年間変わっていない。これは一見、日本人が日本社会は一般的な中流社会であるというイメージを持ち続けていることを意味しているように見える。しかし、谷岡(第3章)は、主観的な社会的地位の形成過程に関連する非常に複雑なメカニズムを紹介している。彼の分析によれば、日本人は主観的な社会的地位が形成される心理的プロセスに基づいて、いくつかの潜在的なグループに分類されるはずだ。そして、これらのグループの構成が変化しているだけでなく、各グループの主観的社会的地位の形成過程が、過去20年間に起こった社会の変化に応じて変容していることを明らかにした。このような複雑なメカニズムにより、日本人の主観的社会的地位の変化は曖昧になり、研究者が適切に調査することが困難になっている。これは、日本社会における異質性の増大と異なる社会集団の共存を示すものであり、主観的社会的地位の変化をよりよく理解するためには、今日の研究者がこれまで以上に考慮する必要がある。
2 望ましくない適応
昭和の時代に比べ、平成の時代は停滞の時代と言えるかもしれない。そのため、日本人の社会に対する満足度は、平成の間に低下していったと思われる。このような観点から、社会階層アイデンティティや生活満足度が全体的に低下し、社会福祉に対する要求が高まり、その傾向は社会的弱者の間で最も強くなることが予想されたのであろう。
しかし、こうした予測は、SSP2015に基づく社会的態度の分析では十分に支持されていない。実際、日本人の主観的な社会的地位の分布は劇的に変化していない(Hommerich and Kikkawa 2019; Sudo 2019; Tanioka, Chapter 3)。不利な立場にある人々(例えば低学歴の若者)は社会に対する不満を感じていないようであり(古市2011)、社会福祉に対する要求も深く強まっていない(永吉6章)。
間(第4章)によれば、低学歴者は、現在志向や宗教性によって中流階級のアイデンティティを保持する傾向があるとのことである。同様に、橋爪(第7章)によれば、この20年間は正規雇用が生活満足度を高めているが、非正規雇用者の生活満足度は1990年代から顕著に変化していないとのことである。さらに、松谷(第8章)は、平成期の若者は権威主義的な考え方の強まりを反映して、保守・新自由主義的な政党である自民党を支持する傾向が強いことを明らかにしている。つまり、若いコーホートは、社会福祉制度の持続可能性という点ではより深刻な問題に直面したものの、新自由主義的な政策や市場原理を支持したと考えられる。永吉(第6章)も同様の結論に達している。彼女の分析によれば、不利な立場にある労働者の間では、彼女が「政府の債務と赤字」と呼ぶ言説を受け入れたため、再分配への支持は高まらなかったという。その結果、不利な立場にある人々(例えば、低学歴者、非正規雇用者、若年層)の社会的利益を社会政策によって実現することは難しくなり、彼ら自身が実際に恩恵を受ける変化を支持する可能性も低くなる。
これらの事実は、人々が自分の利益を守るために社会の変化に基づいて直接反応することはないことを示唆している。むしろ、彼らは困難な状況を受け入れるという方法で適応する傾向がある(Austin 2016)。そうすることで、自分たちの社会的アイデンティティ、基本的な社会的価値、主観的幸福を守ることができるかもしれない。しかし、このような反応が長期的に彼らの幸福に寄与するかは疑問である。
個人の努力で物質的な現実を変えることは難しいので、このような調整的な認知枠組みの適応には合理的な根拠がある可能性がある。実際、このような適応を通じて、不利な立場にある人々は社会的アイデンティティを保持し、主観的な幸福を支えることができる。しかし、そのような適応は、様々な望ましくない結果をもたらす。そのため、議論なしに受け入れることはできない。
例えば、樋口(第9章)は、日本人女性がなぜ「仕事と介護」の二重負担規範を支持するのかを検討した結果、日本人女性にとって「仕事と介護」の規範を受け入れることは、日本社会で肯定的に評価されるための数少ない方法の一つであると結論付けた。労働市場において不利な立場にあるため、彼女たちは賃金労働に完全にコミットすることができない。そのため、「働きながら世話をする」規範を支持する傾向がある。しかし、「働きながら介護する」規範を適応として支持することは、日本女性に過度に厳しい要求を課すことにつながっている。この結果は、社会正義に適しているとは言い難い。
3 礼法時代の問題への対処法
本書の前章では、平成期に出現した心理的適応の一端を確認した。複雑な社会を生き抜くために、人はさまざまな社会変化に適応していかなければならない。その合理的根拠を否定することはできないが、この結果を社会の平等性や持続可能性の観点から評価するためには、研究者はこれらの心理的適応を生み出す社会的メカニズムを理解する必要がある。個人にとっては、厳しい現実に疑問を抱くことなく、単に困難な状況に適応することは、短期的には心理的な救済につながるかもしれないが、将来の世代にとって持続可能な社会、誰もが平等に楽しい人生を送ることができる社会を実現することはできない。この30年間、このような適応は、日本人が直面する社会問題を解決するものではなかった。むしろ、変化する日本社会の現実の中で、その問題をより深刻化させたかもしれない。これらの問題を解決し、平等な社会を構築するためには、心理的適応を誘導することで問題を曖昧にしている社会的メカニズムを明らかにし、それを根本的に変えていく必要がある。
日本が経済の停滞と人口減少に直面している時代に、社会問題に対する新しいアイデアや対処法を考えようとするとき、少子高齢化、雇用の不安定化と労働力不足、学歴の切り下げが同時に進む大衆教育の拡大、経済の長期停滞と経済成長を求め続ける政治、さらにグローバル化と新しいデジタル時代の影響など、多くの要因が複雑に絡み合っていることも考慮しなければならない。その方法については、本書の他の章からいくつかのヒントを得ることができる。例えば、人口高齢化については、三谷・平松(第5章)が、社会的態度への影響に関連する興味深い事実を取り上げている。一般に、人口の高齢化はコミュニティの持続可能性に悪影響を及ぼすと考えられている。しかし、三谷と平松によれば、人口高齢化は連帯感を強め、市民参加を活性化させるため、コミュニティの持続可能性にプラスの効果ももたらすという。したがって、人口高齢化などの要因が持つプラスの効果を活用することで、衰退するコミュニティの問題に対する新たな解決策を見出すことができる。三谷と平松の意見は、高齢化のプラス効果について楽観的すぎるかもしれないが、日本人がこれまで直面してきた他の社会問題を克服するための新たな可能性を示している。このように、社会の変化から生まれる新たなリスクを克服する鍵は、時としてそのリスクに内在していることがある(Klein 2014)。ただし、これは単に社会変化に適応するだけでなく、より良い社会を作るための可能性を見出す必要があることも意味している。
日本における雇用の不安定化は、過去30年間に日本社会で顕在化した様々な社会的不利益が、非正規労働者に不釣り合いな影響を与え、多くの社会問題を引き起こしたと考えられている(太郎丸2009)。橋爪の分析(第7章)が明確に示すように、雇用の不安定化は正規・非正規労働者の客観的状況だけでなく、主観的幸福感にも影響を与える。非正規労働者の数を減らすだけでは、雇用の不安定化がもたらす社会問題の効率的な解決策にはならない可能性が高い。むしろ、非正規雇用の社会的なメリット、例えば、労働時間を短縮し、他の活動に時間を割くことができるといった点を明らかにし、この雇用形態をオプション的な働き方として活用することで、過労死の問題など、非正規雇用が引き起こす社会問題に、より包括的に対処することができるかもしれない。日本社会は大きく変容し、日本人が昭和、平成と持ち続けてきた基本的価値観を見直す時期に来ている。日本人が経済成長や伝統的な仕事と家庭の関係にしがみつくならば、この30年間に遭遇した社会問題を解決し、日本社会を成功した持続可能な未来に導くことはできないだろう。
本書では、平成の日本人が様々な社会変化に心理的に適応し、それによって主観的幸福を守りながらアイデンティティや基本的価値観を保持してきたことを論じた。しかし、そのような適応も、社会の変化(高齢化、雇用の不安定化、大衆教育の拡大、経済の長期停滞、グローバル化など)は進み続けるため、根本的な問題解決にはなっていない。したがって、日本人は、このような社会変化に巧みに適応するのではなく、社会変化の中に新たな共通目標を作り出し、それをコントロールする新しい方法を模索しなければならないと言える。同時に、日本人は、経済成長のみを求め続けるのかどうかも検討しなければならない。経済成長一辺倒で仕事と家庭の対立や少子化を招くのであれば、よりバランスのとれた持続可能な社会基盤を求める方向に社会意識がシフトしていくことが望ましいと思う。そうでなければ、日本が2019年に迎えた「麗和」の名の通り、「美しい調和」を実現することは難しいだろう。
