コンテンツ
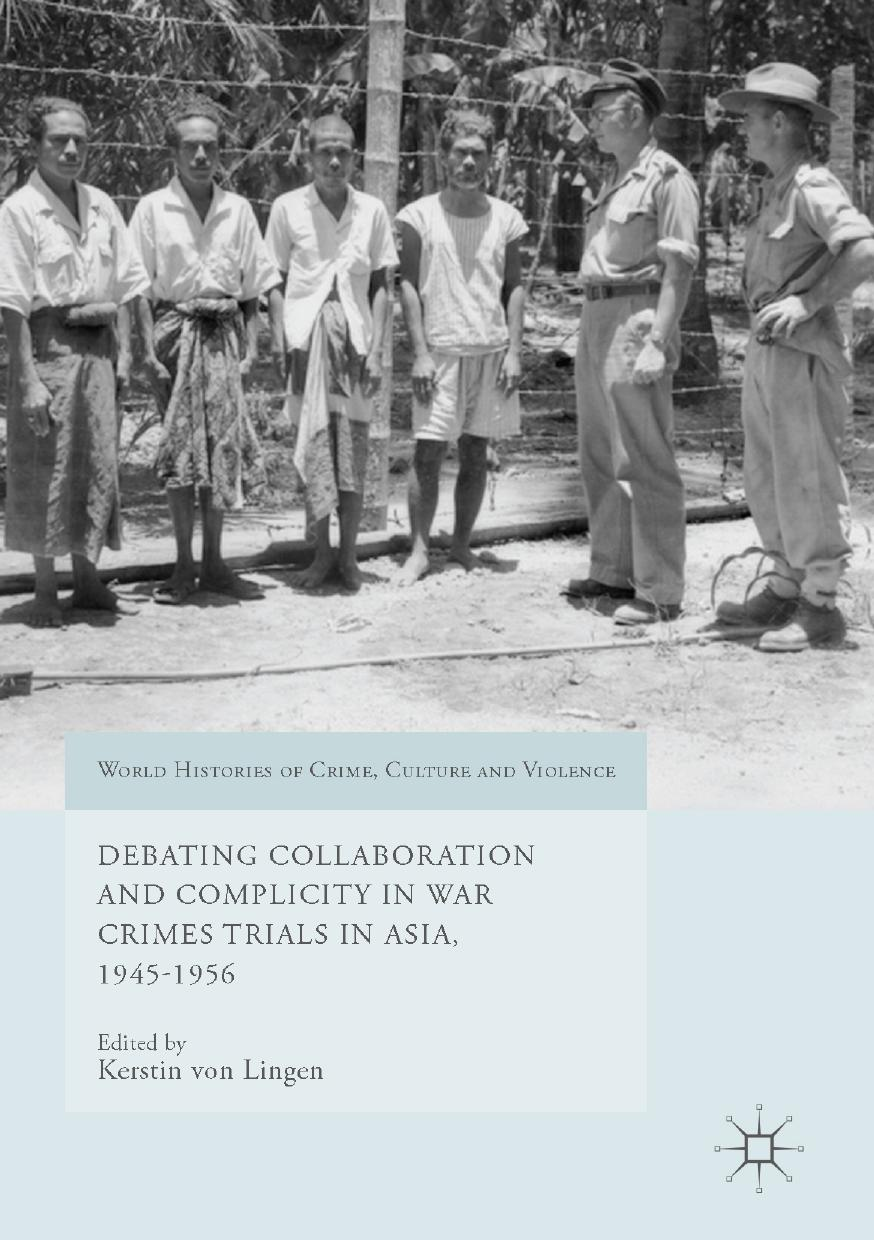
Debating Collaboration and Complicity in War Crimes Trials in Asia, 1945–1956
犯罪・文化・暴力の世界史
シリーズ編集者マリアンナ・ムラヴィエワタンペレ大学(フィンランド)
ライサ・マリア・トイヴォタンペレ大学(フィンランド)
ケルスティン・フォン・リンゲン編集
編集者
ケルスティン・フォン・リンゲンハイデルベルク大学(ドイツ)
目次
- アジアにおける戦争犯罪裁判戦後における協力と共犯
- 日本人戦争犯罪容疑者の裁判における韓国人
- 植民地「戦争犯罪」の定義: 協力、戦争賠償、極東国際軍事裁判に関する韓国の議論
- シンガポール裁判における忠誠の誓い
- 傀儡、儲け手、裏切り者: オランダ領東インドにおける
- オランダ領東インドにおける戦時協力の定義、1945-1949年
- 占領後とポストコロニアルの間:フィリピンにおける最近の過去のフレーミングフィリピンの反逆罪恩赦における近過去のフレーミング 1948年
- 日本の医療残虐行為と科学エリートの協力:戦後の視点戦後の視点
- 加担の問題: 第二次世界大戦後における戦争犯罪と戦争責任に対する日本の初期の姿勢
- 正誤表シンガポール裁判における忠誠の誓い。E1
- 索引
寄稿者リスト
2007年よりシンガポール国立大学法学部助教授。シンガポール国立大学(法学士、法学修士)、ハーバード大学ロースクール(法学修士)、ヨーロッパ大学インスティテュート、オックスフォード大学(法学博士)で学ぶ。弁護士資格を有し(ニューヨーク州弁護士資格)、仲裁のディプロマ(ロンドン大学クイーン・メアリー校)を取得。学界に入る前は、国際刑事警察機構(INTERPOL)法務部(フランス、リヨン)で法務官を務めた。国際法研究センター(英国・ロンドン)、オックスフォード大学(英国)、ジャン・ムーラン・リヨン第3大学(フランス)、王立法経済大学(カンボジア)などで教鞭をとる。『ハーバード・ヒューマン・ライツ・ジャーナル』、『ジャーナル・オブ・インターナショナル・クリミナル・ジャスティス』、『インターナショナル・ジャーナル・オブ・ロー・イン・コンテクスト』などのジャーナルに論文が掲載されている。現在、シンガポール戦争犯罪裁判に関する書籍プロジェクトに取り組んでいる。また、シンガポール戦争犯罪裁判ウェブポータル(http://www.singaporewarcrimes trials.com/)の共同創設者でもある。
高麗大学韓国学研究所研究教授。2013年8月、コーネル大学で歴史学の博士号を取得。博士論文「ポスト帝国の坩堝」: Crucible of Post-Empire: Decolonization, Race, and Cold War Politics in U.S.-Japan-Korea Relations, 1945-1952」で、2015年アジア学者国際会議(ICAS)人文科学部門最優秀論文賞を受賞。英語、日本語、韓国語で多数の論文を発表している。最近の論文は以下の通り。Writing the ‘Empire’ Back into the History of Postwar Japan」(『International Journal of Korean History』2017年2月号)、「『Mindful of the Enslavement』: The Cairo Declaration, Korean Independence, and the Ambiguity of the Liberation of Koreans in Defeated Japan” (The Significance and Effects of the Cairo Declaration, 2014).The research leading to these results received funding from the European Research Council under the Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013)/ERC grant agreement n° 313382.
ロバート・クリブはオーストラリア国立大学キャンベラ校のアジア史教授である。インドネシア史を専門とし、特に暴力、ナショナル・アイデンティティ、環境政治を研究している。近著に『Historical Atlas of Northeast Asia 1590-2010』(ニューヨーク:コロンビア大学出版局、2014年、リ・ナランゴアとの共著)がある。最近、サンドラ・ウィルソン、ベアトリス・トレファルト、ディーン・アスキエロヴィッチとの共著『Japanese War Criminals』を完成させた: The Politics of Justice After the Second World War』(ニューヨーク:コロンビア大学出版局、2017)を出版した。
アルノー・ドグリアは現在、スイスのジュネーブ大学東アジア研究学科の博士研究員である。現代日本と東アジアに関心を持つ。ジュネーブ大学で修士号(東アジア研究)と博士号(日本研究)を取得。ピーター・ラング社から出版された彼の最初の著書のタイトルは『Japanese Biological Warfare, 1880-2011』: Historical Realities and the Anatomy of Memory』(2016)である。現在の研究テーマは『Japanese Medical Atrocities』: Narratives of Reconversion of Former War Criminals in Postwar Japan)では、1945年までに医学実験に参加した科学者や医師のネットワークを詳細に分析し、彼らのプロフィール、再転向、責任について等しく論じている。その他、日本における生命倫理の誕生、東アジアにおける日本の戦争犯罪とその記憶、第二次世界大戦と冷戦の残虐行為、連合国占領期と戦後日本の社会史と大衆文化など、興味深いトピックが含まれている。本章は、スイス国立科学財団の助成によるプロジェクト100011_169861(Le Japon et l’Asie de l’Est face à la Seconde Guerre mondiale)の一環として発表された。
バラク・クシュナーはケンブリッジ大学のアジア・中東研究学部で日本近現代史を教えている。2012年から2013年にかけて英国アカデミーのミッドキャリア・フェローシップを授与され、3冊目の著書『Men to Devils, Devils to Men』を完成させた: Men to Devils, Devils to Men: Japanese War Crimes and Chinese Justice』(ハーバード大学出版、2015)という3冊目の本を完成させた。2013年からは欧州研究評議会の資金で5年間のプロジェクト”The Dissolution of the Japanese Empire and the Struggle for Legitimacy in Postwar East Asia, 1945-1965 “を開始した。クシュナーの2冊目の著書『Slurp!A culinary and social history of ramen – Japan’s favorite noodle soup (Brill, 2012)は、日中関係における食と歴史を分析したもので、2013年ソフィーコー賞(食の歴史部門)を受賞した。クシュナーの処女作である『The Thought War – Japanese Imperial Propaganda』(ハワイ 2006)は、戦時中の日本のプロパガンダの歴史を掘り下げた。2008年には安倍フェローとして「東アジアにおける冷戦期のプロパガンダと歴史的記憶」に関する研究を行った。それ以前は、米国国務省で東アジア担当の政治官として働き、米国ノースカロライナ州のデビッドソン大学で中国史と日本史を教えていた。学者としては、戦時中の日本と中国のプロパガンダ、日本のメディア、日中関係、アジアの喜劇、食の歴史、BC階級の戦争犯罪、冷戦について執筆している。(詳しくは www.barakkushner.netを参照)。
コンラート・M・ローソンは近代戦争の後遺症に幅広い関心を持ち、その研究の大半は1940年代のトランスウォー期の連続性と変容についてである。彼の最初の著書原稿は、1945年の敗戦まで東アジアと東南アジアにおける日本の戦時占領の維持に貢献した軍と警察の協力者に対する報復における戦争犯罪と反逆罪の関係を探求している。その他、政治的報復の世界史、第二次世界大戦後の初期スカンジナビア、東アジア・東南アジアにおける脱植民地化、韓国・台湾の植民地・ポストコロニアル史、日中文化・政治関係、アジアとの、またアジア内での出会いと交流のトランスナショナル史などにも関心がある。
ケルスティン・フォン・リンゲンは、ハイデルベルク大学「グローバルな文脈におけるアジアとヨーロッパ」クラスターの歴史家・研究者である。2013年より「トランスカルチュラル・ジャスティス」と題する独立研究プロジェクトを率いている: 東アジア戦争犯罪裁判における法の流れと国際正義の出現、1946-1954年」と題する独立研究プロジェクトを率い、アジアにおけるソ連、中国、オランダ、フランスの戦争犯罪裁判政策に関する4つの博士論文を指導している。主な著書に、2冊の英文単行本『Kesselring’s Last Battle』がある: 戦争犯罪裁判と冷戦政治
Kesselring’s Last Battle: War Crimes Trials and Cold War Politics, 1945-1960』(Lawrence: University of Kansas Press, 2009)、『Allen Dulles, the OSS and Nazi War Criminals: The Dynamics of Selective Prosecution (Cambridge: Cambridge University Press, 2013)のほか、(共)編著書に『脱植民地化後の戦争犯罪裁判』、『アジアにおける冷戦、1945-1956』がある: Justice in Times of Turmoil, Palgrave 2016)、共著にKriegserfahrung und nationale Identität in Europa [War Experience and National Identity in Europe after 1945] (Paderborn: Schoeningh, 2009)、(クラウス・ゲストワとの共著)Zwangsarbeit als Kriegsressource in Europa und Asien [Forced Labor as a Resource of War: European and Asian Perspectives] (Paderborn: Schoeningh 2014)がある。
サンドラ・ウィルソンはオーストラリア、マードック大学芸術学部教授、アジア研究センターフェロー。西オーストラリア大学で歴史学の学士号と日本研究の修士号を取得し、オックスフォード大学で日本近現代史の博士号を取得した。研究テーマは、日本のナショナリズム史、第二次世界大戦に関する1945年以降の中国と日本の映画、第二次世界大戦後のアジア舞台における戦争犯罪と戦犯である。著書に『満州事変と日本社会、1931-33』(ロンドン、ラウトレッジ 2002)、ロバート・クリブ、ベアトリス・トレファルト、ディーン・アスキエロヴィッチとの共著『Japanese War Criminals: the Politics of Justice After the Second World War』(ニューヨーク、コロンビア大学出版局、2017)などがある。
Esther Zwinkels ハーグにあるオランダ軍事史研究所の研究員。ライデン大学では、オランダ領東インドにおける第二次世界大戦後の協力・戦争犯罪事件の捜査と裁判を扱った博士論文を執筆中である。著書に「『潜在的に破壊的な』対象者の収容:オランダ領東インドにおける国家社会主義運動支持者の抑留、1940-1946年」(Incarceration and Regime Change)などがある: Incarceration and Regime Change: European Prisons during the Second World War and after the Ed. Christian G. De Vito, Ralf Futselaar, and Helen Grevers (New York: Berghahn, 2016)とHet Overakker-complot. Indisch verzet tegen de Japanse bezetter op Sumatra 1942-1945 (Houten: Spectrum, 2011)がある。本研究は、オランダ科学研究機構(NWO)の研究プロジェクト「認識と報復」の一環として支援されている。第二次世界大戦後のオランダ領東インドにおける移行期正義」である。筆者は、以前の草稿にコメントを寄せてくれたペトラ・グローエンと本書の編集者に感謝したい。
アジアの戦争犯罪裁判戦争余波における協力と加担
ケルスティン・フォン・リンゲン、ロバート・クリッブ
アジアにおける第二次世界大戦後の数年間、戦勝国連合国は戦争犯罪裁判の膨大なプログラムを実施し、日本の政治・軍事指導者、軍人、関連民間人を平和に対する罪、戦争法規・慣例違反で告発した。訴追された行為には、虐殺、殺人、拷問、虐待、食糧や医薬品の差し止めなどが含まれる。
本書は、「正義を再考する?Decolonization, Cold War and Asian War Crimes Trials」(2014年10月26日~29日、ハイデルベルク大学)で発表された論文を引用している。また本章では、ハイデルベルク大学の卓越研究クラスタ「グローバルな文脈におけるアジアとヨーロッパ」において、アジアの戦争犯罪裁判に関する研究グループ「トランスカルチュラル・ジャスティス」の2014年度客員研究員であるサンドラ・ウィルソンとキルスティン・セラーズ、ミリンダ・バネルジー、リセット・シュウテン、アンニャ・ビーラー、アン=ソフィー・ショープフェル、ヴァレンティナ・ポルーニナとの集中的な議論の結果も活用しており、貴重なご意見をいただいたことに感謝したい。
K. フォン・リンゲン (*)
裁判の大半は、戦争直後、個々の連合国がそれぞれの法律や規則に従って実施したものである。極東国際軍事裁判(IMTFE)だけが、1946年から1948年まで東京で開催され、日本の最高指導者の訴追を審理したが、国際憲章に基づいて正式に行われた。しかし、IMTFEも国内裁判も、すべての裁判は、19世紀から20世紀初頭にかけて形成された国際法の発展から法的根拠を得ていた。
こうした動向は、人道問題における国家の絶対的主権を制限し、国家が承認した正式な合法性にかかわらず、国際規範の優位性を主張するものであった。アジアにおける戦争犯罪裁判は、ヨーロッパにおける戦争犯罪裁判と並んで、この変遷の分水嶺となった。というのも、この裁判は、法の多元主義と(暗黙のうちに)文化相対主義に基づく古い政治・法秩序の終焉と、新しい、いわば普遍主義的な法秩序の到来を意味したからである。しかし、普遍性は2つの重要な点で、裁判のプロセスを回避した。
第一に、裁判は国家反逆罪の問題と緊密に結びついていた。国家反逆罪は普遍主義的なものではなく、各個人が特定の国家に忠誠を誓うという概念に組み込まれていた。このような結びつきは、占領軍がいたるところで現地の人々や組織と協力関係を結んでいたことから生じた。しかし、日常生活の維持にすぎない無害な関与と、積極的に敵を援助する協力との区別は、明確でも確実でもなかった。第二に、裁判は時間的にも国籍的にも制約があったため、普遍性を欠いていた。残虐行為が戦争犯罪とみなされるかどうかは、その時期が極めて重要であり、加害者と被害者の国籍もまた極めて重要であった。結局、こうした制限は、その膨大な規模と野心的な意図にもかかわらず、裁判プロセスに対する深い不満につながった。
第二次世界大戦後にアジアで行われた戦争犯罪裁判は、戦争に関する国際人道法を実施し、その範囲を拡大することで、占領地の民間人に新たな保護を与えようとする試みであった。この拡大は、枢軸国の占領下にあった独立国家の住民がひどい扱いを受けていたヨーロッパで考え出された。アジアに適用された国際人道法は、多くの場合戦争によって致命的な傷を負ったとはいえ、国際秩序とはまったく異なる原則に従って動いていた植民地秩序に遭遇した。この秩序は、人間の差異と不平等を前提としており、大都会とその植民地との間には形式的な法的区別があり、人種や民族の分類制度も形式化されていた。植民地政体の大半は、遠く離れた西欧の宗主国に従属しながらも、政治的にも法的にも大都会政体とは一線を画していた。内部においても、植民地は法的多元主義を特徴とし、異なる民族集団に異なる法的権利を与えていた。法的権利と責任の違いが、人種的・民族的差別の根幹をなしていたのである。これとは対照的に、新しい国際秩序は、形式的なヒエラルキーをなくし、名目上は平等な国民国家の世界を到来させた。新たに主権を獲得した国家内では、市民権に関する新たな規範によって、民族的ヒエラルキーの原理は排除されたわけではないが、弱体化した。例えば、インドネシアとマレーシアは、先住民の血を引く国民と外国人の血を引く国民を形式的に区別したが、この区別の法的意味は植民地時代よりもはるかに弱かった。米ソブロック間のイデオロギー論争が新しい国際秩序を分裂させ、共産主義も自由資本主義も人間の基本的平等と国家の国際的責任を主張していたという事実を覆い隠した。しかし、その過渡期において、植民地化された人々のあいまいな国家的地位は、国際人道法の普遍主義を深く破壊することが証明された。このような状況の中で、国際社会によって定義された戦争犯罪に対する日本人被告の裁判は、正義の新しいビジョンと政治的正当性を生み出すための決定的に重要な場として機能した。
協力の問題は、第二次世界大戦後に行われた法的清算において、最も争われた要素の一つとなった。ティモシー・ブルックが述べているように、「合作は、それが描こうとする政治的風景に道徳的な地図を重ね合わせる」1。植民地時代の文脈では、この用語は特別な次元を獲得し、戦争の舞台が異なれば、合作というカテゴリーには異なる意味合いがあった。ヨーロッパでは、「協力」は戦時同盟の誤った選択を対象とし、各国を戦時における善玉と悪玉に分けた。戦後ヨーロッパの多くの裁判、特に西側諸国では、「協力」とは、占領しているナチス権力側につくという積極的な選択を意味していた。戦後、このような試みはヨーロッパ全土で国家反逆罪および国家名誉に対する違反とみなされ、協力者は厳しく処罰された。軍事界では、反逆罪はあらゆる犯罪の中で最高のものと考えられている。なぜなら、反逆罪は「国家に対する罪」であると同時に、同志に対する裏切りでもあるからである4。
ヨーロッパにおける他の反逆罪裁判は、政権交代と共産主義国家の誕生に関係していたため、新政権は、戦時中の誤った選択を粛清するという物語を提示することで、旧来のエリートに対する報復の試みを覆い隠す機会を得た。イシュトヴァン・デアークが強調するように、共同裁判には2つの要因があった。「実際には大規模な民衆の敵への融和であったことについて、特定の個人に責任を負わせたいという願望と、新しい社会と国家の創造を邪魔する可能性のある社会的、政治的、民族的グループの影響力を排除するか、少なくとも減少させる必要があると認識されたこと」である。ドイツでは、有罪判決を受けた戦争犯罪人の速やかな釈放は、ドイツ軍将校が「不当な」判決を受けたとする見方を社会の一部に植え付けたため、記憶政治の面でも、全体的な物語の面でも、壊滅的な打撃を与えることになった6。しかし、ドイツの政治は早くから、連合国の穏やかな圧力のもとで、戦争責任を認め、犠牲者やその家族に補償金を支払うという公式路線を選択した7。この承認に続いて、新たな記念碑の設置、追悼の日、そして終戦から70年後の2015年春には、元アウシュビッツ収容所看守の奇妙な「遅すぎた裁判」までもが行われた。このような過去の重荷との和解という政治的選択によって、ドイツは第二次世界大戦後の数十年間、国際情勢におけるパートナーとして再び認められ、冷戦の終わりには欧州政治の中心舞台に返り咲くことができたのである。しかし、こうした側面はすべて、戦時中の行動の物語に大きな影響を与えた。
アジアのいくつかの地域は、協力関係を清算するパターンにおいてヨーロッパに似ていた。中国では、ヨーロッパと同様、日本との協力は、戦争前の政治的信念に日和見主義が混じったものから生まれることが多かった9。彼が日本との協力に引き込まれたのは、蒋介石に政権を追われつつあったこと、欧米への強い敵意、そして日本が軍事的に勝利する可能性が高いという確信があったからでもある。ヨーロッパでもそうであったように、戦後政権は協力者に過酷な復讐を行い、2万5千人のいわゆる売国中国人(漢奸)を裁判にかけ、その多くに死刑判決を下した10。王は終戦争前に死亡したが、国民党は死後の罰として彼の墓をTNTで爆破し、遺体を焼却させた11。本巻の崔徳孝の章は、韓国における同様の状況を描写している。韓国人は旧日本軍支配者の訴追を要求しなかった。彼らはむしろ、韓国の共産主義者と反共産主義者の間の苦しい内部抗争の多くの点で代理であった、韓国の対日協力の問題に焦点を当てた。
法的問題としての協力と共謀
占領法は戦争法の一部である。1907年に批准された1899年のハーグ条約13 は、戦争中に敵国の領土を占領した軍隊に、住民の生命と財産を保護する義務と、追放された政府の主権を尊重する義務の2種類の義務を課している14。しばしば交戦的占領(敵対行為の副産物とみなされる)と呼ばれるこの体制は、一時的なものであり、影響を受ける住民に影響を及ぼす。この法律によれば、占領国はその領土に存在する政治制度やその他の制度を尊重し、維持する義務を負い、その支配下にある領土における公の秩序と市民生活の維持に責任を負う15。しかし、20世紀のほぼすべての紛争は、こうした規則の空虚さを実証した。ほとんどの占領者は、しばしば被占領者を犠牲にして、自分たちの利益を促進する方法で占領法を実施した。亡命政府は一貫して占領地の市民の忠誠を主張し、抵抗や反抗の行為を称賛し奨励した17。
年のジュネーブ条約は、国際法の焦点を政府から個人に移し、その範囲を広げた。実際の紛争では、国際的な武力紛争の場合にも人権の保護はなくならないという推定がなされている18。しかし、占領に対するこのような理解は、主に第二次世界大戦中および戦後の国際法の発展と、その結果を法廷で扱う法的経験の増大の賜物であった。従って、戦後間もない時期には、占領者による奉仕活動への圧力と敵国との自発的な協力のもつれが、法的にも政治的にも争点となった。
脱植民地化が合作裁判の背景にある
しかし、東南アジア、ひいてはインドでは、脱植民地化の問題が事態をより複雑にしていた。プラセンジット・ドゥアラの定義によれば、「脱植民地化とは、植民地大国がその領土と従属国に対する制度的・法的支配を、形式的には主権を有する土着的な国民国家に移譲するプロセスを指す」20。この権力と法的支配の移譲は、合法性と政治的正当性の規範の変化につながった。戦争犯罪裁判はこのような状況の中で行われたため、ヨーロッパの植民地支配国、アメリカ、ソビエト連邦、そして東南アジアと南アジアの反植民地ナショナリストの間の争いの影響を受けた。開戦当時、インドと東南アジアの大部分は欧米の植民地支配を受けていた。ほとんどの植民地で民族主義運動が勃興していたが、その強さや、どのような独立を達成したいのかについてのコンセンサスの度合いには大きな差があった。これらの民族主義運動はすべて、近代化と工業化における日本の初期の成功や、20世紀初頭のロシアに対する日本の軍事的勝利からインスピレーションを得ていた。その後の日本の朝鮮半島や中国での帝国的膨張は、アジアの植民地の一部のナショナリストに不安を抱かせたが、他のナショナリストは日本に刺激を受け続けた。特に、日本が戦時中に掲げた「アジア人のためのアジア」というスローガンや、満州、モンゴル、後にはビルマやフィリピンで国家を基盤とする顧客国家を支援する日本当局の意欲、またインドやインドネシアへの独立の約束がそれほど確実でなかったことから、現地の指導者の中には、日本を敵視するのではなく、むしろ自決の擁護者と見なす者もいた。日本の意図にかかわらず、戦時中の占領はヨーロッパの植民地権威を著しく弱めた。ヨーロッパの植民地軍は敗北し、植民地支配者は追い出されるか抑留され、植民地の権威と特権の精巧な構造は一掃され、日本当局は同調する民族主義グループに物質的援助を与えた。最終的に日本が敗北したとはいえ、日本が介入したことで、この地域の大部分では、植民地支配は前世紀的な形態では維持できなくなった。
東ティモールの未開発の小さな植民地がナショナリズムに悩まされることがなかったポルトガルを除いて、東南アジアのすべての植民地支配国は、ニンジンと棒の戦略でこの新しい状況に対応した。ナショナリズム運動の穏健派と見なした部分を取り込むために、植民地支配国は、戦争前に実施されていれば劇的な変革をもたらしたであろう政治改革を約束し、実現した。彼らの目的は、植民地の経済的・戦略的利益を可能な限り維持するような形での独立を目指すことだった。同時に、より徹底的な変革を求めるいわゆる過激派に対しては軍事力を行使した。政治的譲歩と軍事力のバランスは、植民地大国によって大きく異なっていた。大まかに言えば、米英はより早く、より広範な譲歩を行い、1946年にフィリピン、1947年にインドとパキスタン、1948年にビルマで比較的平和的な独立への移行を達成した。対照的に、オランダとフランスは譲歩が少なく、長期にわたる破壊的な戦争に巻き込まれ、1949年と1954年には交渉による主権移譲に終わった。
こうした状況下で、日本当局と協力してきた植民地臣民の地位は、2つの側面を持つ重大な問題となった。第一に、彼らは首都圏の市民と同じように、植民地大国に忠誠を尽くす義務を負っていたのだろうか。しかし、民族主義運動が長い間、大都会との関係を断ち切ることを主張してきたという事実と、大都会が今、その断ち切りを実行に移そうとしているという事実が、形式的な法的立場を疑わせることになった。本巻のチェー・ウイリンは、シンガポールにおけるこの問題から生じる法的異常に注目している。彼女は、事実には大きな争いはないが、訴追責任が被害者の地位によって左右される訴追について論じている。占領地の民間人を保護するための戦争犯罪法の拡大は、交戦国の民間人が保護されないことを露呈した。具体的に言えば、日本の保護を受け入れた者(一部のインド人がそうであったと考えられているように)は、それによって戦争犯罪法の保護を失ったのである。
第二に、日本当局に協力することで、彼らは自国民に対する反逆罪を犯したのだろうか。ビルマのバ・モウやアウン・サン、フィリピンのホセ・P・ラウレル、インドネシアのスカルノ、インドのスバス・チャンドラ・ボースといった民族主義指導者たちは、協力したことによって、日本の圧政に巻き込まれたのである。戦争前の反植民地ナショナリスト運動は、程度の差こそあれ、植民地当局に協力した同胞を糾弾したが、激しい非難を浴びせることはほとんどなかった。戦後、欧米の観察者たちは、こうした人々をナチスに協力したヨーロッパ人と同一視する傾向にあったが21、現地の世論は彼らを愛国者と強く見なしていたため、植民地勢力は協力者裁判を進めることに完全な自信を持つことはなかった。日本当局と行動を共にした者は皆、占領当局を民族自決のための手段として扱ったのだと、もっともらしく主張することができた。実際、占領当局に協力した事実上すべての人が、事情や崇高な動機の強要を訴えることができた。協力者を裁判にかけることは、戦後の植民地戦略において、日本に協力した者を汚すことで宣言的な機能を果たす可能性があったかもしれないが、被告が自らを被害者として提示しやすく、裁判が植民地支配国が臣民を守らなかったことを糾弾する場となりやすいため、この戦術は危険であった22。
エスター・ツヴィンケルスは、インドネシアにおけるオランダの協力者裁判を分析し、植民地政府が、占領期間中の協力行為を処罰すると同時に、戦時中の軽犯罪にある程度の寛容さを示すことで、オランダの利益に沿った戦後秩序に対するインドネシアの支持を獲得しようとする、複雑な意図を追求していたことを明らかにしている。その結果、比較的多くの協力者裁判が行われた。ほとんどの司法管轄区で、日本軍に協力した地元民の反逆罪裁判が、日本人の戦争犯罪裁判よりも迅速に行われたことは、物語るとおりである。
時間の次元
現代の国際法の考え方では、人道に対する罪の時効は認められていない。バングラデシュの国際犯罪法廷では、1971年の解放戦争におけるジェノサイドの罪に問われた男たちが起訴され、カンボジアのハイブリッド法廷では、1975年から1979年にかけて最悪の残虐行為を行ったクメール・ルージュ政権の生き残りの指導者たちが起訴されている。法廷の外では、1937年の南京大虐殺、20世紀初頭のナミビアにおけるヘレロの大量虐殺、19世紀以前の大西洋奴隷貿易など、さらに以前の犯罪に対する道徳的清算が求められている。
しかし、第二次世界大戦後のアジアで裁判を担当した法務スタッフは、常に時間的なプレッシャーの中で働いていた。彼らは、被告人に対する説得力のある裁判を組み立てるという仕事が時間とともに難しくなっていることだけでなく、法廷の外の世界が変化していることも認識していた。日本が敗戦国から冷戦時代の西側諸国のパートナーになる可能性が高くなるにつれ、戦時中の犯罪を清算しなければならないという圧力は弱まっていった。1948年、米国政府と日本の占領軍当局は、被告候補が東京の巣鴨プリズンに拘置されていて都合が良かったにもかかわらず、IMTFE裁判の第2ラウンドを続行しないことを決定した。1940年代後半から1950年代前半にかけて、英国や他の検察当局も、日本の更生を促進するために、裁判を打ち切るという同様の決定を下した。本巻のコンラッド・ローソンの章は、日本軍に協力したフィリピン人指導者に恩赦を与えるかどうかを検討する際に生じた、複雑な法的、政治的、道徳的問題を示している。東アジアの新しい戦後秩序のために道徳的な基盤を整えようとするこの努力は、すでに戦争犯罪で有罪判決を受けた日本人の立場に影響を与えた。日本人は、自分たちが犯した具体的な犯罪に責任を負う個人的な加害者であるという形式的な立場から、特に日本では、冷戦の現実のために検察当局がその罪を赦そうとしている国家のために、不当に罰せられるスケープゴートであるという認識へと、次第に変わっていった23。
このような時間への敏感さは、裁判の政治的背景と同様に、裁判の法的根拠にも組み込まれていた。戦争犯罪に関する国際法は地理的には普遍的であったが、時間的には普遍的ではなかった。戦時中に行われた行為にのみ適用された。さらに重大なことは、加害者と被害者双方の交戦状態によって、その範囲が制約されていたことである。このような制約が生じたのは、第二次世界大戦後の戦争犯罪裁判の法的根拠が、4つの異なる基盤の上にあり、その基盤はつながってはいたが、まだ統合されていなかったからである。
戦後裁判の第一の基盤は、一般にジュネーブ条約として知られる、捕虜の人道的待遇を定めた一連の協定であった。これらの条約は、捕虜に適切な宿泊施設、食料、その他の世話を提供することを義務付けるとともに、敵対行為の終了後、速やかに本国に送還することを要求した。第二の基盤は、一般にハーグ条約と呼ばれる、戦争における人道的行為を規定した一連の協定である。これらの条約には、宣戦布告や中立国の正しい行動に関する規定、毒ガスや膨張弾など非人道的と判断された兵器の禁止などが含まれていた。第三の基礎は、1928年の「国策手段としての戦争放棄に関する一般条約」(しばしばケロッグ・ブリアンド条約として知られる)であり、これは侵略戦争を禁止するものと理解されていた。
最後に、戦後の訴追の土台となった第四の土台は、国際連合戦争犯罪委員会(UNWCC)の戦時中の活動であった。UNWCCは、平和に対する罪と民間人に対する戦争犯罪を訴追するための広範な法的根拠を慎重に構築していた24。第二次世界大戦以前は、国際法は占領地の一般住民をほとんど保護しないと広く信じられていた。彼らは、多くの形態の過酷な占領規律に合法的に従うと考えられていた。1937年に中国の首都南京で行われた日本軍による中国人虐殺のような残虐行為は、野蛮なものとして広く非難されたが、それを犯罪とみなす法的根拠はなく、加害者を裁判にかける仕組みもなかった。第一次世界大戦後、1922年までドイツのライプチヒ裁判所は、敵国の民間人、捕虜、敵国船に対する戦争犯罪の12の罪状について、17人の被告を裁判にかけた。被告のうち10人が有罪となり、7人が無罪となったが、民間人に対する犯罪のみを扱った事件では、有罪判決は出なかった。したがって、これらの判決は、占領地における民間人の保護を強化するものではなかった25。
UNWCCが戦時中の不法行為を国際法に基づいて訴追する根拠を拡大したのは、1919年のヴェルサイユ条約に至るプロセスの一環として設置された「責任に関する委員会」の作業に由来する。この委員会は、将来戦争犯罪を構成すべきと考える32の行為のリストを作成した。このリストには、殺人、拷問、強姦、意図的な飢餓、強制徴用、強制売春、略奪、没収、通貨の兌換が含まれていた26。このリストは、ヴェルサイユ条約の立案者たちが、戦時下における行動の新たな国際基準を確立しようという野心を反映したものであったが、その基準を法的・哲学的な先例に基づかせることには慎重であった。事実上、占領軍は今後、占領地の住民に対して、それまでよりもはるかに高い行動基準を求められることになった。しかし、このリストはヴェルサイユ条約やその後の国際協定の一部としては承認されなかった。1920年代前半、国際法の専門家たちは国際戦犯法廷の構想に大きな関心を寄せたが、1925年までにはこの構想は支持を失っていた。1934年、東京で開かれた赤十字国際委員会の会議では、「交戦国に属し、または占領された領土にいる敵国籍の文民の状態および保護に関する国際条約案」27が採択されたが、この文書も国際的な支持を得ることはできず、1939年以降、ドイツ占領下のヨーロッパにおけるナチスの残虐行為の規模が明らかになるまで、文民に正式な法的保護を与えるという問題は国際的な議題からほとんど姿を消した。 28 その後、UNWCCはヴェルサイユ・リストに立ち戻り、これを戦争犯罪に関する国際慣習法の声明として解釈した。
捕虜の扱い、戦争の適切な遂行、侵略戦争への手段、占領地における民間人の扱いなど、4つの異なる法的根拠は多くの点で補完的であった。しかし、戦争犯罪の法的定義が人道的に拡張され、民間人に対する残虐行為も含まれるようになったことで、戦争犯罪と戦争犯罪ではない行為との間に、加害者と被害者の地位に基づく新たな区別が生まれた。国内法が国境によって制限されるのに対し、国際法は普遍的である。しかし、第二次世界大戦後のアジアで適用された戦争犯罪法は、4つの重要な点において普遍性を著しく欠いていた。第一に、軍事的必要性から実行された行為の合法性を侵害しなかった。この理解により、敵地に対する行動は一般的に戦争犯罪とは見なされなかった。したがって、東京大空襲や広島・長崎への原爆投下は、正式には犯罪行為ではなかった。第二に、戦争犯罪法の下では、当局は自国民に対して戦争犯罪を犯すことはできなかった。このような残虐行為は戦争犯罪ではなく、人道に対する罪であると考えられていたが、この軽犯罪のカテゴリーは国際法上まだ弱くしか整備されておらず、第二次世界大戦後、アジア太平洋戦域でこのような罪状で訴追された例はほとんどなかった30。第三に、戦争犯罪は、軍事的必要性によって正当化されない戦争行為と定義され、非戦闘員が犯すことはできず、したがって占領地の住民が犯すこともできなかった。これらの加害者には、反逆罪に関する潜在的な法律を含む国内刑法のみが適用された。そして第4に、連合国側の被告を喚問する可能性は、文化的に連合国側は無罪であると想定されていたためだけでなく、勝利の特権として、計画から除外されていた。戦争犯罪は、事実上、保護する義務のある人々、とりわけ捕虜や占領地の住民に対してのみ犯すことができた。戦時中、日本と戦っていた同盟国は、敵対行為の終了後、日本の占領が始まるまで、厳密にはいかなる領土も占領していなかった。戦争が野蛮であったこともあり、捕虜の数は比較的少なかった。そのため、裁判によって設定される新しい基準のもとでは、戦争犯罪を告発される可能性は本質的に低かったのである。IMTFEも国内裁判所も、tu quoque(「お前もやった」)の原則を用いた日本側の抗弁を正式に排除した。言い換えれば、アジア・太平洋における戦争犯罪裁判は、国内法や国家主権よりも普遍的な法や人類共通の価値観を優先させるものとして提示されたものの、戦争犯罪法の適用は国家間の区別を際立たせたのである。
このように、アジアにおける第二次世界大戦後の戦争犯罪裁判のプロセスは、侵略者が戦争の過程で行った残虐行為の結果を狭く扱うことを意図していた。戦争犯罪の実質的定義が侵略者による残虐行為に限定されたことで、韓国人は深い曖昧な立場に置かれることになった。朝鮮人は日本の植民地臣民であった。日本は1910年に、それまで独立国であったこの国を強制的に併合したが、連合国の計画者たちは、第二次世界大戦後の戦争犯罪調査プロセスを1928年からの期間に限定した。検察官の目には、朝鮮人は日本の臣民であり、占領地の住民が国際法の下で享受する保護は何もなかった。したがって、朝鮮文化を抹殺しようとした日本の努力31、朝鮮人労働者に対する残虐な扱い、強制売春のための朝鮮人女性の徴用は、朝鮮人の地位が国際法で別個に考慮されていたならば、これらの行為が戦争犯罪を構成していたであろうにもかかわらず、連合国の法廷では取り上げられなかった。朝鮮人は、被害者の国家的地位に注意を払わない人道に対する罪という新しい概念によって保護されたかもしれないが、その概念はほとんど形成されておらず、アジアの文脈で使われることはほとんどなかった。アメリカもソ連も、戦後朝鮮半島のそれぞれの占領地において、朝鮮半島での、あるいは国外の朝鮮人に対する行為について日本人を訴追することに政治的価値を見いださなかった。先に述べたように、韓国人自身も戦争直後の日本人の訴追にはほとんど関心を示さなかった。
戦争犯罪の目的で韓国を日本の一部とみなす論理は、日本軍に従軍していた韓国人も、証拠が見つかれば日本人と同様に戦争犯罪で訴追される責任があることを意味していた。そして実際に、多くの朝鮮人が日本の捕虜収容所で看守として働いており、そのうちの何人かは、罪人に対する不当な扱いで訴追された。1990年代以降、冷戦期における日本の免罪の一つの要素は、日本軍に従軍していた朝鮮人に不当な罪の重荷を負わせるという連合国の戦術であったという認識が広まってきた。本巻のサンドラ・ウィルソンの章は、この認識が誤りであることを明確に示している。カテゴリーとして、朝鮮人は彼らを指揮した日本人将校よりも軽く扱われていた。
日本の戦争犯罪の定義におけるこのような国民的、時間的な不均衡の結果、道徳的な矛盾が生じた。日本の当局者の多くは、日本人被告人の選択的訴追を捉えて、裁判を戦勝国の正義として退け、日本兵は国家に対する義務以外は何もしていない、通常の戦争の暴力を超えることは何もしていないと主張した。1971年に執筆したミネアは、戦後の裁判(特にIMTFE)を「戦勝国の正義」と特徴付け、復讐心に燃えた連合国側の訴追が行き過ぎたものであったことを暗に示唆した33。これとは対照的に、1990年代初頭には、一方的な非難に動揺した欧米、中国、韓国の論者は、日本の戦時中の行動の中で最も野蛮な要素、特に南京大虐殺、マニラ大虐殺、731部隊の活動、タイ・ビルマ鉄道やその他の戦時中の戦略事業における労働者への過酷な待遇を強調することがあった。彼らは、適正な人数よりも多くの人間が有罪になったとほのめかすよりも、処罰されなかった犯罪や訴追を逃れた加害者を強調した。こうして時が経つにつれ、1940年代後半から1950年代前半にかけての検察側政府の、もう十分だ、裁判はやめるべきだ、起訴されなかった犯罪から生じる道徳的請求権は失効させてもよい、という計算された決定は、意志の失敗として再解釈されるようになった。
結論
正義のための極めて道徳的な探求として考え出された裁判は、この地域における植民地的存在を再構築しようとしていた欧米列強の利害と一致し、またそれに反するものであった。この裁判は、共産主義との闘いで人々の心をつかむという米国とその同盟国の目的と一致し、また、独立を求めて闘う植民地化された人々の利益と一致した。その結果、日本は裁判のプロセスにおいて、過大にも過小にも罰せられた。
脱植民地化の枠組みの中で戦争犯罪裁判が果たした役割を評価するとき、また連合国の戦略対協力の観点から評価するとき、4つの特徴が明らかになるように思われる。第一に、連合国は戦争犯罪裁判を実施することを義務づけられており、裁判を実施することに直接的な政治的メリットはなかったが、裁判を実施しなかった場合には重大な不利益があったであろう。第二に、裁判は、一般に親日的であった最も反日的な欧米グループの信用を失墜させる間接的な手段であった。政治的な理由から、これらのグループは起訴することができなかった。そのため、日本の戦犯を裁くことは、これらのグループが自国民を裏切ったことを地元社会に思い起こさせる方法であった。第三に、東南アジアにおける独立への移行は、日本による第二の敗戦ではなく、文明開化という使命の自然な集大成であるという保証を首都圏の国民に与えた。これは特に米英の戦略に関して当てはまる。最後に、裁判は、この地域への日本の経済的利益の復帰を妨げる方法として、日本を戦争の記憶で汚す手段を提供した。
新しい問題は政治秩序を揺るがす力がある。20世紀前半には、国境を越えた階級政治が、一般庶民の忠誠心に関する前提を崩した。20世紀後半には、環境問題やジェンダー問題が同じことを引き起こした。20世紀半ばには、戦勝国連合国の戦争犯罪裁判制度が、アジアにおける脱植民地化と冷戦の政治に、予期せぬ新たな考察を導入した。この点で、日本人に対する戦争犯罪裁判は、司法の手段による戦争の終結を意味していた。日本はすでに敗北していたが、この裁判は、西側の勝利が単に優れた武力の問題ではなく、悪に対する善の道徳的勝利でもあったことを確認するためのものであり、戦時中の「忠実な行動」に対する法的評価によって、将来のパートナーシップの条件を確立する役割を果たしたのである。
ケルスティン・フォン・リンゲンはハイデルベルク大学の「グローバルな文脈におけるアジアとヨーロッパ」クラスターの歴史研究者である。2013年より「トランスカルチュラル・ジャスティス」と題する独立研究プロジェクトを率いている: 東アジア戦争犯罪裁判における法の流れと国際正義の出現、1946-1954年」と題する独立研究プロジェクトを率い、アジアにおけるソ連、中国、オランダ、フランスの戦争犯罪裁判政策に関する4つの博士論文を指導している。主な著書に、2冊の英文単行本『Kesselring’s Last Battle』がある: Kesselring’s Last Battle: War Crimes Trials and Cold War Politics, 1945-1960 (Lawrence: University of Kansas Press, 2009)」と「Allen Dulles, the OSS and Nazi War Criminals: The Dynamics of Selective Prosecution (Cambridge: Cambridge University Press, 2013)のほか、(共)編著書に『脱植民地化後の戦争犯罪裁判』、『アジアにおける冷戦、1945-1956』がある: また、(クラウス・ゲストワとの共著)Zwangsarbeit als Kriegsressource in Europa und Asien [Forced Labor as a Resource of War: European and Asian Perspectives] (Paderborn: Schoeningh 2014)がある。
Robert Cribb オーストラリア国立大学キャンベラ校アジア史教授。インドネシア史を専門とし、特に暴力、ナショナル・アイデンティティ、環境政治を研究している。近著に『Historical Atlas of Northeast Asia 1590-2010』(ニューヨーク:コロンビア大学出版局、2014年、リ・ナランゴアとの共著)がある。最近、Sandra Wilson、Beatrice Trefalt、Dean Aszkielowiczとの共著『Japanese War Criminals』を刊行した: The Politics of Justice After the Second World War』(ニューヨーク:コロンビア大学出版局、2017)を出版した。
日本人の戦争犯罪容疑者の裁判における韓国人
サンドラ・ウィルソン
韓国は1910年に日本に植民地化されており、韓国人は占領地域の住民としてではなく、帝国臣民として日本の戦争に参加した。兵士として、朝鮮人は多くの戦線で連合国軍と戦った。日本軍と契約した民間人として、彼らは戦争努力を支援し、補給し、前線での任務のために日本軍を解放した。約12万人の朝鮮人民間従業員のうち、約2.5%がいわゆる野口部隊のメンバーで、主にビルマ・タイ鉄道、シンガポール、ジャワ島にあった連合軍捕虜(POW)や抑留者を収容する収容所で看守として働くために採用された2。戦争が終わり、連合国政府が戦犯容疑者の一斉検挙を始めると、現場の指揮官は、戦争犯罪に関する限り、朝鮮人や台湾人の容疑者を日本人と同様に扱うよう指示された3。捕虜収容所の職員は、日本の憲兵隊員とともに、特別に逮捕、捜査、裁判の対象とされた4。従って、朝鮮人看守は逮捕されやすい立場にあったのである。看守は、日本側に従軍した朝鮮人の中では少数派であったが、最終的に「日本人」戦犯として裁判にかけられた朝鮮人の圧倒的多数を占めていた。1945年以降の連合国側の裁判では、全体で148人の朝鮮人が戦犯として有罪判決を受け、判決を受けた。そのうち3人は下士官兵(うち1人はフィリピンの捕虜収容所を指揮していた)、別の16人は国民党中国当局から判決を受けた通訳だった。残りの129人は収容所の看守で、そのうち35人は悪名高いビルマ・タイ鉄道沿いの収容所で働いていた者だった5。
連合国による日本人容疑者の裁判に関する書物では、朝鮮人看守に関する2つの別の見方が目立つ。捕虜や連合国当局者による当時のコメントや、後に出版された元連合軍捕虜に焦点を当てた一般的な著作は、捕虜が日常的に接することになった朝鮮人看守を、捕虜の「最悪の苛めっ子」と表現することが多い6。 7 ビルマ・タイ鉄道のオーストラリア人元捕虜は 1948年、退役軍人のグループに「日本人は朝鮮人看守に比べれば紳士だった」と語っている8。対照的に、著名な歴史家ギャバン・マコーマックや内海愛子などは、朝鮮人看守を犠牲者として描いている。マコーマックと内海によれば、彼らは多かれ少なかれ日本軍への従軍を強制され、従軍後は日常的に虐待を受けたとされている。マコーマックは、新兵が「訓練の一環として意図的に殴打され、残忍に扱われた」軍隊では、「最下層の日本兵より劣る」とみなされた朝鮮人は、ビルマ・タイ鉄道の収容所では「捕虜やアジア人労働者と同じように疎外され、犠牲となり、搾取された」とまで述べている9。
この見解では、朝鮮人は戦争末期に連合国によってさらなる犠牲となった。内海氏によれば、連合国側は「日本の植民地支配の問題を無視」したのである10。その意味するところは、連合国当局は、朝鮮人と台湾人の戦争犯罪の疑いを免除するか、少なくとも彼らに対しては、植民地支配の地位、したがっておそらくは日本の戦時中の行動に対する責任が薄らいでいることから、かなりの程度寛大な措置をとるべきだったが、そうしなかったということである。朝鮮人に対する扱いもまた、連合国による戦争犯罪裁判の実施における、より広範な問題の現れとみなされている。マコーマックと内海の両氏によれば、連合国は、戦争犯罪の真の責任者である天皇や日本軍の上級将校や計画立案者を訴追から逃がしたり、上級将校の刑を軽くして、代わりに相当数の朝鮮人衛兵を含む最も下級の職員に復讐を遂げさせたりした。内海はこう書いている:
一般軍人の)これらの裁判は……味方の捕虜と直接交流のあった何千人もの下級の日本軍兵士や文民の有罪判決につながった。ほとんどの場合、上層部は手つかずであったが、最も権威のなかった者の多くは処刑され、他の者は長い実刑判決を受けた11。
内海は 2008年の朝鮮人戦犯に関する主要な研究の中で、連合軍捕虜の扱いが悪かったのは、日本政府が捕虜の扱い方について一貫した指針を持っていなかったことが一因であり、その後の戦争犯罪裁判で当局の政策の失敗の重荷を背負ったのは朝鮮人と台湾人であったと結論づけている12。ビルマ・タイ鉄道沿線での犯罪に対するオーストラリアの裁判について、マコーマックは同じ主張をしている。
内海とマコーマックは、公式記録、回想録、インタビューから話をつなぎ合わせながら、主に事例研究に基づいて話を進めている。個々の看守の経験についての記述は、吸収力があり、人間的な観点から見ると、深い説得力がある。さらに、歴史家たちが語る個々の体験談は、問題の出来事から数十年後、後知恵で、本来の文脈から切り離され、最近の政治的・イデオロギー的関心、特に日本が朝鮮に与えたとされる歴史的過ちへの関心に照らして作成されることが多い。これとは対照的に、戦犯に関するより広範で現代的な文書証拠を検証すると、内海やマコーマックらによって有名になった議論と矛盾する。
戦犯容疑者や有罪判決を受けた者の逮捕、捜査、起訴、判決、釈放に関する入手可能なデータを統計的に分析すると、朝鮮人が戦犯の中で過剰に存在したわけではなく、彼らが最も重い刑罰を受けたわけでもないことが決定的にわかる。囚人数のリスト、裁判記録、判決結果や判決見直しの記録は、イギリス、オランダ、オーストラリア、日本の公文書館にある軍事、政治、外交記録に豊富にある。内海はこうした資料を幅広く利用しており、彼女の著作には、特定の事例研究だけでなく、朝鮮人衛兵の徴用、東南アジアの収容所への配属、その後の日本軍への従軍など、より一般的なことに関する多くの貴重な情報が含まれている。しかし、彼女とマコーマックは、大まかな傾向を検証するよりも、個々のエピソードを追究することを選んだ。内海とマコーマックは、日本による植民地抑圧の朝鮮人体験に深く共感し、戦後も朝鮮人兵士が受け続けた差別を意識しているため、元看守の擁護者になっているように見える。彼らは、個々の体験談に集中することを選んだが、それは、そうした体験談が利用しやすいからだけでなく、読者に強いインパクトを与えるためでもあったのかもしれない14。朝鮮人看守の状況を理解するためには、具体的な生活史を語るだけではなく、集団としての看守に関連する基礎的な統計を確立するために、公文書館にある生の資料に細心の注意を払うことが極めて重要である。個々の人生を語るだけではなく、数を数えることも必要なのだ。
最も重要なことは、記録資料全体から、連合国当局が下級兵を標的にしたのではなく、むしろ中級兵と、説得力を持って訴追できる上級将校を探し出したということである。戦争犯罪の訴追で最も負担が大きかったのは、下士官でも上官でもなく、下士官(伍長以上)と下士官(中尉、大尉、少佐)であった15。これらの階級の兵士は政策を決定することはなかったが、捕虜や抑留者の福祉に直接影響する収容所での命令を含め、日々の命令を下していた。大日本帝国陸軍の最も下級の隊員は、二等兵、一等兵、上等兵の3つの階級であった16。民間人である朝鮮人衛兵は、正式には下士官階級に属していなかったが、実際には最も下級の軍人の一人であった。ワーナーが述べているように、「ある階級が他の階級に与える権限は、(日本軍では)英米軍よりもはるかに大きかった」17。起訴され有罪判決が下されても、通常、最も重い刑は科されず、最初の段階で減刑の恩恵を受けることが多かった。その後、1950年代に連合国がより一般的な恩赦を検討し始めると、朝鮮人やその他の下級兵員は、犯罪行為に対する責任が上級兵員ほど大きくないという理由で、再び減刑される可能性が高くなった。言い換えれば、戦争犯罪裁判の過程を通じて、捜査官、検察官、恩赦担当者が階級に重大な注意を払い、戦争犯罪の責任は概して上級および中級の職員が最も大きいと認めていたことを示す強力な証拠がある。
公式統計によれば、戦時中に日本軍に従軍した朝鮮人242,341人のうち、3,016人が刑務官であった18。1942年2月から3月にかけて、すでに人手不足に陥っていた日本軍当局は、日本軍がシンガポールとジャワ島を征服した後、突然25万人から30万人の捕虜を抱えることになり、圧倒された。陸軍省はその後、捕虜を日本や帝国の他の地域で労働力として使用し、収容所を開設して収容することを決定した。植民地臣民を看守として使用する政策は、日本兵を前線での任務に解放するものであった。林は、韓国や台湾の人々の目から見た白人の高い地位を損ない、日本の力を誇示することを前提としたプロパガンダとしての意図もあったと指摘している20。
日本の植民地ではまだ兵役のための徴兵制度が導入されていなかったため、有能な若者は大勢いた。1942年5月、朝鮮総督府は、日本軍で幅広い仕事をこなす朝鮮人民間人をより一般的に募集する一環として、収容所の看守として数千人の新規採用の応募を受け付けると発表した21。契約は2年間で、民間人の補助職員は二等兵にさえ敬礼しなければならないほど序列が低かったが、給料は驚くほど良かった。台湾や朝鮮にいる間、民間人の新兵の月給は30円で、海外に出ると50円になった。一方、二等兵の月給は6円だった。内海によれば、1943年のレートで50円は陸軍軍曹(鉄砲隊)が受け取る給料と同じであった。民間の補助職員も、臨時試験に合格すれば、1年勤務後に昇進することができた。月給100円の民間人もいた22。
朝鮮人男性は募集によく応じた。彼らの動機の問題は、看守を第一義的に被害者とみなすべきかどうかという問題と密接に結びついている。彼女は日本語の著作の中で、動機が多様であったことを認めているが23、内海は強迫を強調している。しかし、パーマーが指摘するように、「(兵士ではなく労働力の)徴兵制は1944年まで朝鮮で広く採用されたわけではなく、その時でさえ、労働者をその地位に凍結させることに大きく限定されていた」25。特に地区ごとに採用枠が設定されていたため、社会的・組織的な圧力が強かったケースもある。内海の主な事例である金完郡(金角監獄)は、日本の警察官から入隊するよう強い圧力を受け26、警察官、募集担当者、愛国部隊の長であったかもしれない同胞の朝鮮人から強制された者もいた27。看守の募集が始まったのと同じ1942年5月、朝鮮人男性の兵役徴用が1943年に始まるという法令が出された。高橋は、徴兵の脅威が人々を看守志願に駆り立てたと結論付けている30。パーマーは、より一般的な労働志願についても同じ点を指摘している。日本人男性と異なり、朝鮮人男性は労働志願(看守としての労働を含む)すれば徴兵を免除され、いずれにせよ軍隊での賃金は低かった31。
社会的圧力と限られた選択肢の証拠にもかかわらず、多くの男性が自発的に志願することを選んだのは、見かけの雇用条件が積極的に魅力的だったからであろう。実際の賃金率にはばらつきがあったが、軍の民間従業員の中には、韓国人の平均給与の3倍以上を得ていた者もおり、熟練した職については、志願者の間で競争があった32。高率の賃金は、契約満了時に大きな社会的流動性を約束しているように思われた。日本の炭鉱に行きたくなかった元看守は、看守の給料はよく、契約は2年間だけで、旅行するチャンスであったと付け加えた34。1991年にキャンベラで講演し、後にマコーマックによって翻訳出版された李鶴苗(廣村加倉井)の記述には、警備員に志願した理由についてのコメントが紛らわしく混じっている:
このような仕事から何かを学べると思ったし、給料も悪くなかったし、2年契約で兵役を免れることもできた。表面的には自発的なものだったが、私の地区にはノルマがあり、事実上、私たちは感化されたのだ。先ほど言ったように、日本政府は強制的に私たちに兵役を押し付けたのだ35。
日本軍への韓国民間人の徴用は、「植民地政府と韓国人との間の協力、強制、誘導の相互作用」36に依存していたというパルマーの評価は、間違いなく正確である。1942年8月、彼らは釜山港を出港し、その後、タイ、マラヤ、ジャワの捕虜収容所で、日本の下士官(NCO)や下士官の指揮の下で働くために分散された。表1からわかるように、これらの地域の収容所では、朝鮮人衛兵が日本人軍人をはるかに上回っていた: マラヤとタイの捕虜収容所に元々配置されていた840人のうち804人は、朝鮮人の民間人であった。I Gil(笠山義吉)は、ジャワ島の捕虜収容所にいた約30人の朝鮮人衛兵の一人だった。彼の後の回想によると、彼らは日本人の伍長、軍曹、将校(通常は中尉)の下で働いていた38。
第二次世界大戦中、日本軍は頻繁に移動しており、看守も例外ではなかったことは明らかだ。捕虜自身もシンガポールのチャンギ刑務所やジャワ島などからビルマ・タイ鉄道沿いの収容所やその他の勤務地に送られ、看守は彼らを監督するために必要とされた。内海の計算では、1942年11月から1943年2月までの3カ月間に、ジャワ島からタイやビルマに送られた捕虜は合計17,700人に上る。1943年4月には、さらに6,600人の捕虜がジャワ島からアンボン、ハルク、セラム、フローレスのオランダ領インド諸島に送られた39。おそらく、もともとジャワ島に配属されていた1,408人の朝鮮人のうち、多数の者が捕虜と同じ目的地に送られたと思われる。例えば、内海によってその事例が紹介されている金完郡(金角完坤)と伊吉(笠山義吉)を含む60人の朝鮮人衛兵は、日本の飛行場建設のために派遣された2,070人の捕虜を警護するために、アンボンの東にある小さな島ハルクに派遣された40。一時期、鉄道沿いの捕虜とアジア人労働者は、40人の日本軍将校、85人の日本軍下士官、1,280人の朝鮮人衛兵によって監督されていた。
朝鮮人看守や下級軍人全般が不釣り合いに処罰されたかどうかを評価する上で、まず問題となるのは、終戦時に連合軍に拘束された捕虜や投降兵の中から最初に逮捕された何千人もの容疑者の中から、何人が裁判にかけられたかということである。日本の敗戦後、収容所職員は戦争犯罪容疑者として特に逮捕の対象とされたカテゴリーに含まれた。朝鮮人容疑者の大部分は、オランダ、イギリス、オーストラリアによって逮捕された。これらの国は、ジャワ島とビルマ・タイ鉄道で行われた犯罪の裁判を担当する国だったからである。一時期、シンガポールのチャンギ刑務所に収容された3,000人の容疑者のうち、2,000人が鉄道で犯した犯罪で起訴される可能性があるとして収監されていた42。有罪判決を受けた看守129人の合計は、野口部隊の看守3,016人のわずか4.3%に過ぎない。この数字が、戦犯として有罪判決を受けた一般兵士の割合より高いことは間違いないが、収容所が特に標的にされていたことを考えれば、非常に低い数字である(図2)。
被告の選別という点では、東南アジアにおける英国の裁判の例から、標準的なパターンと思われるものが明らかになった。20の裁判地で行われた306の裁判で、合計920人の被告が英国当局の評決を受けたが、そのうち最も重要な裁判地はシンガポール、香港、ラングーンであった(表3)。起訴された者のうち、下級職員が占める割合はごくわずかである。被告人の大多数は下士官、准尉(WO)以上であり、これらのグループを合わせると被告人の73%を占め、下士官/准尉だけで44%を占めている。二等兵は33人、4%にすぎず、朝鮮人衛兵は64人、7%であった。朝鮮人衛兵が上等兵を上回ったのは、上等兵が前線やその他の場所に散らばっていたのに対して、全員が連合国当局によって特別視された収容所で働いていたからである。起訴された最も下級の兵士の数が非常に少なかったことは、残りの兵士に対する捜査が進められなかったことを意味し、一方、中級および上級将校ははるかに多くの数が標的にされた。1946年にシンガポールで審理されたビルマ・タイ鉄道事件では、朝鮮人による捕虜の殴打が罪状に明記されていたが、朝鮮人兵士の罪状認否は行われなかった43。
同様の傾向は、多少の違いはあるが、他の地域でも見られる。香港では、オーストラリアの裁判所は 42 人の被告に有罪判決を下した。下士官はわずか2人で、1人は朝鮮人衛兵とされていた(1人は不詳)。シンガポールのオーストラリア法廷では、ビルマ・タイ鉄道での犯罪がシンガポールで起訴されたためであろう、より多くの朝鮮人衛兵が裁判にかけられ、被告 62 人中 15 人(24%)が有罪となった。さらに、シンガポールで有罪判決を受けた5人の民間人通訳のうち1人は、韓国人であったことが知られている。フィリピンとフランス政府は、朝鮮人衛兵を裁かなかったが、少数の下士官を有罪にした: フィリピンでは判決を受けた155人中27人(18%)、フランス軍事裁判所では231人中19人(8%)であった。フィリピンの裁判で有罪判決を受けた者の 3 分の 1 以上が下士官(大尉と中尉)であった44。下級兵士や文民補助要員には上級兵士の命令を拒否したり、一般的に独立した判断を下す能力が限られていることを暗黙的または明示的に認識した上で、上位の軍人を好むという同じパターンが、各国の法廷を問わず、戦争犯罪裁判の各段階を通じて繰り返されている。
朝鮮人の裁判は、ほとんどがオランダ領インドとシンガポールで行われた。朝鮮人看守が故意かつ過度に捕虜を虐待したとみなされた場合、有罪判決を受けて厳罰に処されることもあった。金岡喜子(金岡清)は、アンボン島と海上でイギリス、オーストラリア、オランダの捕虜を虐待し、そのうちの一人を死に至らしめた罪で、チャンギで絞首刑に処せられた。彼は「終始、凶悪な残忍さでふるまい」、収容所で「恐怖の支配」を行ったと言われ、「捕虜(中略)の生活を悲惨なものにするために可能なことはすべて、この男によって行われたように思われる」46。パレンバン衛兵事件で起訴された朝鮮人、小林虎雄については、「彼の殴打と残忍さは、人を墓場に追いやるようなものだった」と言われている。 47 捕虜に対する非人道的な扱いで死刑判決が減刑された豊山毅成は、ビルマ・タイ鉄道で働く英・豪捕虜の部隊であるFフォースで、「最悪の朝鮮人看守として悪名高い」と評された。彼の残忍さは「あらゆる限度を超えていた」また、彼と同僚の福田恒夫中尉(下松倉井収容所所長)は、100人以上のオーストラリア人捕虜の栄養失調、飢餓、過労死の責任を共有したと主張された48。
しかし、戦争犯罪で有罪とされた朝鮮人は、先に述べたような極端なケースを除けば、 一般的に最高刑を受けることはなかった。戦争犯罪裁判の過程では、収容所で直接残虐行為を行ったり、不十分な食糧や医療を提供した職員が必ずしも最も責任を問われるべき人たちではないことが認識されていた。なぜなら、ある時点まで彼らは現実的に反対したり拒否したりできない命令を実行していたのであり、食糧や医療は不足していたからである。大規模なパレンバン衛兵事件は、24人の被告のうち16人がスマトラ島の捕虜収容所の朝鮮人衛兵であり、5人が処刑された。看守以外の全員(大尉1人、中尉2人、軍曹3人)が絞首刑になったが、16人の看守の中で処刑されたのは、先に述べた小林虎雄だけであった。その後の裁判では、8人が日本人、5人が韓国人であった。すべての被告が1つ以上の罪状で有罪判決を受け、中佐1人、大尉3人、少佐2人の計6人が絞首刑に処せられた。内海は、金正恩の事件を著書の主軸に据えているが、5人の朝鮮人のうち誰一人として死刑を宣告されなかったという事実はスルーしている。2人は無期懲役、キムを含む2人は10年、1人は7年の判決を受けた50。
情報が入手できる英国の裁判の被告911人のうち(表3)、121人、つまり13%が無罪となった。その他の判決結果を見ても、最下級の職員が過酷な扱いを受けていないことが明らかである。
英国の裁判では、合計278件の死刑判決が下された(うち245件は確定し、執行された)。死刑判決のほぼ82%は下士官・上等兵以上の階級に下されたもので、下士官と上等兵だけで全体の42%を占めている。有罪判決を受けた朝鮮人衛兵の17%、下士官の12%だけが死刑を受けた。通訳として裁かれるのは、朝鮮人衛兵よりも危険であった。起訴された通訳(朝鮮人と台湾人の一部を含む)の36%近くが、第一審で死刑判決を受けた。
戦争犯罪裁判所が下した最初の判決は、必ずしも確定されたものではなかった。判決は確認官によって見直され、その仕事は裁判所の評決と量刑を評価し、それを維持すべきかどうかについて上級当局に勧告することであった。多くの場合、このプロセスの結果、減刑や減刑が行われた。陸軍省のファイルにある捕虜のカード索引によると、英国の裁判所で死刑を宣告された33人の捕虜が、その後、刑が執行猶予となった(表3)51。例えば、朝鮮人衛兵の李鶴苗(廣村加倉井)は、1943年にビルマ・タイ鉄道のヒントク収容所で捕虜を非人道的に扱ったとして、オーストラリアの裁判で死刑を宣告されたが、確認当局は彼の刑を20年に減刑した52。東南アジアにおけるイギリスの裁判(表3)では、最高幹部に対する死刑判決はいずれも減刑されなかったが、朝鮮人衛兵に対する死刑判決11件のうち5件、二等兵に対する死刑判決4件のうち1件は減刑された。また、12人の朝鮮人衛兵と2人の二等兵は、判決の確認段階で実刑が減刑された。全体として、朝鮮人衛兵の減刑率は、東南アジアでの英国裁判のどのカテゴリーよりも高く、単に「民間人」と分類された者(21%)を除けば、他のグループの2倍(26.6%)であった。香港で、42 人の被告人を裁いたオーストラリアの裁判では、4 人の死刑判決が確定し、上級将校 1 人と下級将校 3 人が処刑されたが、下級下士官や文民補助兵は処刑されなかった53。
有罪判決を受けた囚人は通常、裁判が行われた場所かその近くで処刑されるか投獄された。しかし、1949年から1953年にかけては、各訴追側政府と日本占領中のアメリカ側、または1952年の講和回復後の日本側との取り決めに従って、有罪判決を受けた戦犯は東京の巣鴨プリズンに移送され、残りの刑期を終えた。しかし、講和条約第11条は、戦犯の刑期に関する権限を元の検察政府が保持することを定めた。日本政府は、有罪判決を受けた戦犯に赦免を「勧告」することしかできなかった。この制度の下で、連合国政府は最終的に、日本の戦犯に仮釈放や他の形の慈悲を与えるかどうか、またどのように与えるかという問題に直面しなければならなかったが、ここでもまた、当局が階級に敏感であったことが明らかになった55。
第11条は、戦犯を刑期中刑務所に閉じ込めておくためのものであった。しかしその後数年間、冷戦が激化し、日本との正常な経済関係が再び可能だと思われ始めたため、連合国政府の優先順位は急速に変化した。すべての訴追側政府は、日本を非共産主義陣営に取り込む必要性が、戦犯を処罰し続ける必要性を上回ると認め、貿易関係の回復を求めるものもあった。日本政府は戦犯の釈放を望み、外国政府はその手段を積極的に模索し始めた。1952年以降、国民党の中国、フランス、フィリピン、オランダ、オーストラリアは、拘束していた戦犯を全面的に釈放するか、効果的に一括釈放する方式を開発した。イギリスとアメリカだけが、各事件のぜひを審査することを主張し続けた。アメリカは合計で3人の朝鮮人しか有罪にしなかったので、イギリスは最終時期の朝鮮人に対する赦免に関して最も重要な国となった。
1950年代半ばまでに、看守の状況は、数は少ないとはいえ、他の下級兵よりも切迫していた。平和が回復するまでに、英国に拘束されたままだった下士官はごくわずかだった。もともと終身刑を受けた者はおらず、確定前の刑期の平均は、二等兵で7.7年であった。刑期は戦犯容疑者として最初に逮捕された日からカウントされ、実際には、英国に拘束された戦犯はすべて、刑務所での善行により刑期の3分の1が免除された。その結果、まだ海外に収監されていた多くの私兵が1951年半ばまでに釈放され、イギリス政府は、当時支配下にあった戦犯を占領下の日本に移送し、巣鴨プリズンで残りの刑期を服役させた。巣鴨に到着してから1952年4月に正式に平和が回復するまでの数カ月の間に、残りの囚人たちは連合国最高司令官、すなわち米軍の管理下に置かれ、米軍は巣鴨で独自の仮釈放制度を運用し、戦犯は刑期の3分の1を終えた後に仮釈放される資格を得た56。1952年4月までに、アメリカ軍は、内海の主な対象であった朝鮮人衛兵の金王勲を含む、イギリスで有罪判決を受けた巣鴨の戦犯57の半数を仮釈放している。他方、10人の朝鮮人衛兵はもともと無期懲役を宣告されていたが、イギリス側は21年から善行による7年を引いて「量刑化」したため、実際の刑期は14年であり、さらに5人は死刑が減刑されていた。これらの人々は刑務所に収監されたままであったため、英国は1950年代まで朝鮮人看守の刑に責任を負い続けた。
講和条約が発効したとき、巣鴨にはまだ1,244人の囚人が収容されていた59。この中には29人の朝鮮人と1人の台湾人が含まれており、さらに48人の台湾人囚人がオーストラリアの管轄下にあるマヌス島に収容されていた60。29人の朝鮮人捕虜の内訳は、英国が13人、オーストラリアが6人、オランダが10人であったようだ61。国民党中国が有罪判決を下した16人の朝鮮人通訳は、この時点で仮釈放か刑期満了で釈放されていたようだ。いずれにせよ、1952年8月、国民党中国は残りの囚人91人全員を日本の当局に移送し、事実上の大量釈放を許可した。1954年前半、巣鴨の朝鮮人看守の最大総数は23人だった。1955年9月初めまでに、巣鴨に残っていた朝鮮人は6人で、約570人の囚人のうち、すべて英国人の保護下にあった62。
しかし、1955年9月にたった6人の朝鮮人衛兵が刑務所に残っていたという事実は、赦免の手段を決めることによって、より広範に戦犯問題を解決しようとしたイギリス政府が直面した問題を浮き彫りにしている。1954年 2月に巣鴨でイギリスの法的管理下にあった。11 名の元朝鮮人衛兵のうち、全員が、15年以上の刑期を終えていた63。ある外務省職員が述べているように、「一般的に、これらの人々は特別に残虐な犯罪で有罪判決を受けた」ので、彼らの釈放の正当な理由を見つけるのは容易ではなかった64。大量釈放を認めることなく彼らを釈放する方法を見つけるために、英米の当局者は、日本の戦争犯罪人に対する当初の裁判と評決を積極的に再評価し始めるしかなかった。英国にとって、朝鮮人衛兵の事件は、その犯罪の性質、重大性、社会的敏感性から、解決するのが最も困難な事件の一つであった。そのため、これらの事件の検討は、何が戦争犯罪を構成し、どのような状況がその犯罪を軽減するかについての基本的な前提の真剣な再考を促した。その過程で、英国政府高官は、軍事的必要性、戦争の状況、そして、どの軍隊でもそうであるように、部下は上官に従わなければならないという要請が、有罪判決を受けた戦争犯罪人が犯した犯罪の重大性を緩和することを次第に受け入れていった。このころには、残っていた数少ない朝鮮人衛兵だけでなく、日本軍のもっと高い階級の軍人も部下として含まれていた。アンダマン諸島の文民総督であった城内良之助もこの分類に含まれた(66)。このような論法を用いる際には、犯罪が十分に処罰されていないという印象を与えないようにするため、最高作戦レベルの意思決定を担っていた最高幹部が厳しく処分されたことを強調することが重要になった。そのため、城内が有罪判決を受けた犯罪は、日本の海軍当局と処刑された6人の将校の責任であったと言われている67。
1955年、英国政府は戦争犯罪人が服役すべき刑の上限を、「最悪の」ケースを除いて15年に引き下げた。英国政府は1955年、戦犯が服役する刑期の上限を、「極めて悪質な」ケースを除き、15年に引き下げた。善行による刑の免除があれば、捕虜は戦犯容疑者として最初に逮捕された日から10年後に釈放されることになる。朝鮮人衛兵の最後の6人は、この決定の恩恵を受けた。その中には、ビルマ・タイ鉄道で犯罪を犯した松本眉山も含まれていた。「悪名高い看守」であった豊山季生もまだ刑務所にいた。この2人と他の4人の朝鮮人看守は、1955年8月に女王に提出された30人の戦犯に対する赦免嘆願書に含まれていた。女王は、「彼ら(30人の戦犯)は重大な犯罪を犯したが、そのほとんどは下級階級であり、多くの場合、戦争犯罪の責任は軽いものでしかなかった。 彼らが命令に基づいて行動した上級将校は、ほとんどの場合、死刑を支払っている」と知らされた69。女王は、憲法上期待されていたとおり、勧告を受け入れ、有罪判決を受けた最後の朝鮮人衛兵は釈放された。
朝鮮人は1910年から日本による植民地支配に苦しめられており、植民地時代に日本当局が朝鮮人に対して犯した人道に対する罪について、国際的な法的清算は行われていなかった。しかし、強迫、社会的圧力、他の機会の欠如、自らを向上させたいという願望など、さまざまな理由から、多くの朝鮮人が日帝の事業に参加した。戦後、彼らは日本や台湾の軍人と同じように、その行為が国際法上犯罪となる可能性が高い場合、調査や訴追を受けるという事態に直面した。朝鮮人に関する記録は、この訴追と、その後の判決や赦免に関する審議が、日本軍で従属的な地位にあったことの意味を強く考慮していたことを示している。「最も重い報復」が下される集団とはほど遠く、朝鮮人が特別視されたのは、残忍な看守としての彼らの際立った個性が注目されたときだけであった。
サンドラ・ウィルソンは、オーストラリアのマードック大学芸術学部教授、アジア研究センターフェローである。西オーストラリア大学で歴史学の学士号と日本研究の修士号を、オックスフォード大学で日本近現代史の博士号を取得した。研究テーマは、日本のナショナリズム史、第二次世界大戦に関する1945年以降の中国と日本の映画、第二次世界大戦後のアジア舞台における戦争犯罪と戦犯である。主な著書に『満州事変と日本社会、1931-33』(ロンドン、ラウトレッジ 2002)、ロバート・クリブ、ベアトリス・トレファルト、ディーン・アスキエロヴィッチとの共著に『Japanese War Criminals: the Politics of Justice After the Second World War』(ニューヨーク、コロンビア大学出版局、2017)などがある。
植民地の「戦争犯罪」を定義する: 共同作業、戦争賠償、極東国際軍事裁判に関する韓国の議論
崔徳孝
戦時中の日本の軍国主義者や政治指導者を極東国際軍事裁判(東京戦犯裁判または東京裁判として知られる)で訴追した出来事は、その歴史的意義について極めて両極端な見解を残した。連合国がこの出来事を「文明の裁き」として称えたのに対し、日本のナショナリストたちは、報復的な「勝者の正義」としての東京裁判の正当性に疑問を呈した。このような二元的なアプローチが、東京裁判をめぐる議論を長い間支配した。しかし、1970年代に入り、日本の歴史家の中には、このような二元的な方法論にとらわれない新たな議論を展開し、東京裁判の意義と限界について、よりニュアンスに富んだバランスの取れた理解を提示する者が現れた。それ以来、歴史家たちは、戦勝国の現実政治のもとで、ある重要な問題がいかに黙殺され、戦争犯罪裁判から排除されてきたかを検証してきた。これらの歴史家にとって、日本の歴史家戸谷由真が簡潔に説明しているように、東京裁判は「日本の戦争犯罪を明らかにすることも、責任ある個人を処罰することも十分に行われなかったので、問題があった」1。東京裁判で連合国が完全に取り上げることのなかった重大な議題の中には、日本の植民地主義と、朝鮮と台湾の植民地臣民に対して行われた犯罪があった。植民地問題と旧植民地臣民の声の両方が欠落していることは、東京裁判の重大な限界を例証しているというのが、現在では多くの歴史家の一致した意見である。
本章の目的は、東京裁判の際に代表されなかった朝鮮人の声を明らかにすることである。韓国人は東京裁判において重要な役割を与えられなかったが、韓日両国の政治指導者や知識人は、植民地的文脈の中で行われた日韓の「戦争犯罪」をどのように定義するかについて、独自の運動や議論を生み出した。本章では、日本の植民地支配からの解放後、韓国人の間で戦争犯罪がどのように議論され、どのような枠組みで語られたかを検証する。特に、韓国の政治指導者や知識人が、連合国が東京裁判や1943年のカイロ宣言を通じて推し進めた「人道に対する罪」や「朝鮮人民の奴隷化」からの解放といった考え方や原則を流用しながら、植民地時代の協力や戦争賠償の問題にどのようにアプローチしたかに焦点を当てる。本章では、戦争犯罪をめぐる朝鮮人の議論と裁判批判を検討することを通じて、朝鮮人が東京裁判の限界を、「戦勝国の正義」と 「文明の裁き」という二元論を超えてどのように理解していたかも明らかにする。私は、彼らの声なき声と批判が、戦後日本史における東京裁判の異なる解釈と歴史的評価の先駆けとなったことを論じる2。
***
韓国の指導者や知識人の間で、戦争犯罪の問題がどのように重要な議題として浮上したかを検討するためには、解放後の韓国における植民地協力に関する政治的議論の歴史的背景を理解する必要がある。1945年8月、第二次世界大戦における日本の敗戦により、韓国は日本の植民地支配から解放された。日本の突然の降伏によって、米ソの占領軍が朝鮮半島に進駐し、アメリカの歴史家ブルース・カミングスが論じるように、「冷戦の真髄ともいうべき関係が、朝鮮半島におけるソ連とアメリカの交流を初日から特徴づけた」3。米ソが当初、日本帝国軍兵士の武装解除のための一時的な境界線として合意した38度線は、1948年までに米ソの世界的な冷戦対立の最前線となった。米ソ占領下、韓国の政治運動も右派と左派、北と南、単独政権樹立派と反対派に分裂した。脱植民地化された国家のビジョンをめぐる韓国固有の政治闘争は、冷戦の火種となり、1950年の国際化された内戦、いわゆる冷戦最初の熱い戦争へと発展した。
1945年当時の朝鮮半島は、カミングスの言葉を借りれば「革命の機が熟し」、「政治、経済、社会の徹底的な変革への要求」が澎湃として湧き上がっていた4。ソ連の占領は土着の革命家を励まし、脱植民地化する社会の革命的変革に向けた朝鮮人の努力を急進化させ、急がせたとさえ言える5。歴史家のチャールズ・K・アームストロングはこう主張する:
北朝鮮における土地改革は、おそらく、解放後の数年間における急速かつ急進的な変化の最も重要な例であり、上からのイニシアチブと下からのインプット、モスクワでの決定とソ連占領当局と北朝鮮指導部による平壌の現場での決定が組み合わされたものである。ここには、ソ連占領という背景が、1930年代の満州ゲリラ闘争と1940年代の朝鮮の社会状況に深く根ざした急進的な改革、すなわちマルクス・レーニン主義共産主義の「朝鮮化」の実施を可能にしたことがはっきりと見て取れる6。
同時に、ソ連が促進した北部の急進的な社会革命は、米占領下の南部に政治難民を殺到させ、彼らを韓国政権の熾烈な反左翼・反北政治勢力に変えた。
一方、アメリカ占領下の南では、解放された朝鮮の政治状況は大きく異なる形をとった。カミングスが実証したように、占領が始まって最初の3カ月間に、在韓アメリカ人は、左派の政治指導者や何百もの自治組織によってつくられた土着の「解放体制」を覆した。米国の占領は、朝鮮人民共和国(朝鮮人民共和国)と人民委員会の正統性を否定した。7 米軍は韓国を完全に占領する前に、中央と地方の植民地当局に取って代わっていたのである。占領軍はまた、「日本軍に協力した」者を「刑事および一般警察機関」から粛清するというワシントンの当初の指令にもかかわらず、韓国の植民地官僚と警察官を維持した8。このアメリカが作り上げた新たな秩序はすぐに失敗となり、大多数の韓国人が解放のために思い描いていたものに対する裏切りとなった。1946年秋、占領1年目に対する民衆の不満は、10月1日にテグ市で起きた抗議に参加した人々が地元韓国警察に射殺された事件をきっかけに、植民地政権の残党に対する暴力的な反乱へと爆発した。10月から12月にかけて、棍棒、鍬、稲刈り鉤、竹槍などで武装した群衆(ほとんどが農民)が、南部地方各地の警察署や市役所を襲撃し、200人以上の韓国人警察官を殺害した9。
このような歴史的背景から、朝鮮における土着の解放政治がどのようなものであったかを理解することは重要である。その核心は、日本の植民地支配の遺産にどう対処するかという問題であった。韓国の政治指導者の大多数は、植民地支配という深く根付いた構造的建物を解体するための国民の総力を結集して、新しい韓国を誕生させなければならないことを理解し、それに同意していた。日本の植民地支配が終わると、韓国の政治指導者たちは直ちに、植民地残滓(イルチェ・チャンジェ)を除去し、いわゆる親日派や売国奴(ミンジョク・パニョンクチャ)を新しい国づくりの努力から排除することを求め始めた。歴史家のコエン・デ・セウスターが簡潔に説明するように、「左派も右派も、政治的に活動するほとんどの朝鮮人の頭の中にあったのは、協調の問題だった」10。
1945年8月28日、韓国が解放されて2週間も経たないうちに、韓国独立準備委員会(CPCI、Chosŏn kŏn’guk chunbi wiwŏnhoe)と呼ばれる新しく結成された政治組織は、CPCIが「日本人と韓国の親日派が所有する財産を没収し、公共施設、鉱山、大規模な産業、工場を国有化する」ことを約束すると宣言した。 「11 9月3日、重慶の朝鮮亡命政府である朝鮮臨時政府(KPG)は、民族独立を確立するための今後の課題を発表した。具体的な14の議題の中には、朝鮮人売国奴と日本人居留民に対する具体的な政策が含まれていた。KPGは、「連合国と協議の上、敵の財産を没収し、敵を処罰する」こと、また「民族反逆者と独立運動を妨害した者を厳正かつ公然と処罰する」ことを約束した12。米占領下の南とソ連占領下の北の主要な左派・右派政党も、植民地政治・社会構造と民族反逆者の速やかな排除を声高に主張した13。北では、平安南道の朝鮮共産党が9月に政治的マニフェストを採択し、日本帝国主義者や親日派が所有する工場、鉱山、輸送施設を没収し、国有化すると主張した14。朝鮮人民共和国は、その政策声明で次のことを約束した:
- 1.日本帝国主義が実施した法制度を直ちに撤廃する;
- 2.日本帝国主義者と国賊が所有する土地を没収し、農民に無償で再分配する;
- 3.日本帝国主義者と国賊が所有する鉱山、工場、鉄道、港湾、船舶、通信施設、金融機関、その他すべての施設を没収し、国有化すること15。
解放後、韓国の多くの政党や団体が植民地協力者の排除と処罰を求めるようになったが、「親日派」と「国賊」の定義は自明ではなかった。1946年1月28日、KPRの指導者たちは、この2つのカテゴリーを次のように明確にした:
「親日派」には、日本帝国主義に意図的に協力する者が含まれる。「親日派」とは、日本帝国主義に意図的に協力する者を含む。「民族反逆者」とは、親日派の中でも極めて悪質なケースを意味する16。
KPRの指導者たちは、親日派と国賊の分類も定めていた。たとえば、「日帝に朝鮮を売り渡した売国奴とその関係者、日帝の勅許を受けた貴族、総督府顧問会議委員、日帝支配下の高級官吏(総督府長官、地方総督)、警察・憲兵の高級官吏(副警視正級)」である。そのほかにも、「民衆の恨みの的」となった警察官や植民地政府高官、戦争産業を所有した企業家、戦時中の「ファシスト」組織の指導者、同化運動や戦時中の労働者動員などの植民地政策に積極的に協力し参加した知識人や政治指導者も含まれていた17。彼らは、植民地時代には「親日的な態度をとらなかった」にもかかわらず、解放後に「民主的な団体や指導者」に対して「反動的なテロ活動」を行った者たちまで、国賊に含めていた。朝鮮民主主義人民共和国の指導者たちは、そのほとんどが朝鮮共産党やその他の左派政党に所属していたが、右派政治団体、特に植民地の地主、企業家、協力者、そしてアメリカ占領下と密接な政治的関係を築いた人々で主に構成されていた朝鮮民主主義人民共和国党を標的にしたことは明らかである。言い換えれば、植民地支配の協力者を裁くことは、韓国の新しい国民国家建設をめぐる権力闘争の不可欠な一部であった。
日本では、在日本朝鮮人連盟という朝鮮人左翼団体が率先して、在日朝鮮人の「親日派」や「売国奴」を排斥した。在日本大韓民国民団は、在日コリアンの社会運営に重要な役割を果たした支配的な組織であった。日本が降伏すると、在日朝鮮人の指導者たちは直ちに相互扶助グループを組織し、日本からの報復から在日朝鮮人を守り、解放された祖国への帰国を希望する人々を助けようとした。1945年10月中旬、日本全国に急増したさまざまな朝鮮人共助団体が一つの組織に統合された。1946年1月までに、朝鮮人連盟はほぼすべての都道府県に支部を設立し、日本全国に合計47の支部を持つに至った19。
1945年10月15日と16日に開催された朝鮮同盟の創立大会では、10月10日に府中刑務所から釈放されたばかりの在日朝鮮人共産党員指導者金澄海が、徳田球一や志賀義雄ら日本共産党員指導者とともに演説し、「親日売国奴」の処罰を訴えた。11月18日、朝鮮同盟中央委員会は、「親日派・売国奴の徹底究明」を盛り込んだ新たな決議を採択し、在日朝鮮人売国奴36名を「人民裁判」の対象としてリストアップした20。興味深いことに、この在日朝鮮人「親日派・売国奴」36名は、日本共産党が12月8日の政治集会で作成・公表した「戦犯名簿」に含まれていたらしい。その集会で日本共産党の黒木重徳党首は、天皇陛下を含む1500人以上の名前を戦犯として指定したリストを読み上げ、日本政府と米軍占領軍に提出したのである。
***
実際、韓国の「戦犯」(chŏnbŏm)という考え方は、韓国の暫定立法議会(SKILA、Nam Chosŏn Kwado Ippŏp Ŭiwŏn)における反共謀者法制に関する政治的議論の中でも浮上した。SKILAは1946年12月、右翼と左翼の両過激派を孤立させる中道連合をつくることを目的に、アメリカ占領軍によって設立された23。SKILAは選挙で選ばれた45人の議員と、アメリカ占領当局によって任命された45人の議員で構成されていた。選出されたメンバーのうち、右派指導者が大多数を占めていた。さらに、選挙で選ばれたメンバーの中には、いわゆる親日派もかなり含まれていた。在韓米軍司令官ジョン・R・ホッジ大将は、彼らを次のように評している:
SKILAの)選出メンバーには失望した。私が一般的に期待していた右派だからではなく、2人を除いて全員が親日派、裕福な土地所有者、狡猾な政治家を代表する1つのブロックだったからだ[ … ]24
SKILAの残りの45人のメンバーは、穏健な右派と左派の政治家の中から任命された。重要なことは、SKILA内で反協力者法案の積極的な推進者として登場したのは、任命されたメンバーの多くであったということである。
12月12日にSKILAが開会すると、メンバーはすぐに旧植民地協力者に関する法案を議論し始めた。12月21日、穏健右派グループのキム・ギュシク議長が報道陣のインタビューに応じ、SKILAは「親日派、国賊、悪徳利得者(akchil moribae)」を訴追する法律の草案を作成し、彼らのための「特別法廷」の設置にも取り組むと発表した25。1947年1月9日、SKILAは反協力者法を起草するための委員会、すなわち「協力者、国賊、戦争犯罪人、営利を目的とする悪人に関する特別法制委員会」を設置した26。この委員会は9人のSKILAメンバーで構成され、全員が右派グループ出身で、ほとんどが任命されたメンバーであったが、その多くは植民地時代の朝鮮独立運動に関連する政治的背景を持っていた。例えば、委員会は元反植民地ゲリラの闘士であり、日本の植民地政権下で19年間投獄されながら生き延びた鄭伊亨(チョン・イヒョン)任命委員の指導のもとに結成された。
同委員会の防共立法への取り組みは、当初からSKILA内外からの激しい反対に直面した。3月13日に委員会が法案の第一案を正式に提出する前の3月10日、日刊紙『茅茹新聞』は、警察庁捜査部長である李海銀(イ・ヘギン)という人物の抗議文を一面に掲載した。その抗議文の中で李は、日本の植民地支配に協力した人々は、彼らの意志に反してそうしたのだと述べて擁護した。さらに李は、反協力者法制の政治的擁護者たちを「寄生虫のような知識人」であり、自分たちの私利私欲のために民族の団結を乱していると評した。さらに李は、現在の国家建設の努力から彼らを排除するよう要求している。国家警察の高官によるこの「公開書簡」は、SKILA内の反共謀者法案の支持者たちに衝撃を与え、激怒させた。同時に、SKILA内部からも反共謀者法案に対する強い反発の声が上がった。3月17日の会期中、法案案が議題に上がるや否や、議員の一人であるパク・ヨンイは即座に議題から外すことを提案した。パクは、「この法案が成立すれば、誰も(共謀罪の適用を)免れることはできないだろう」と、共謀罪の定義が広すぎるために問題が大きすぎると主張した29。
彼は尋ねた: 「なぜ親日派と売国奴を定義しなければならないのか」30。
実際、朴容煜(パク・ヨンイ)議員の「共謀罪の範囲」に関する質問と同様に、共謀罪法案は幅広いケースを共謀罪の対象としている。委員会は法案で「国賊」の定義を比較的狭く示したが、「協力者」の定義は非常に緩やかだった31。法案によれば、「協力者」とは、「日本が韓国を併合してから解放されるまでの間、日本の支配下で日本のため、または自己の利益のために悪質な行為を行い、それによって韓国の同胞に損害を与えた者」を意味する32。 「32「協力者」のカテゴリーには、例えば、植民地政府や市役所に仕えた者、植民地産業で朝鮮人の「搾取」を行った企業家や雇用主、日本統治を賛美し植民地同化(日本化)運動を指導して革命運動の障害となった知識人などが含まれていた。委員会は、「日本人と結婚した」者や「日常生活で日本語に慣れた」者まで「協力者」に含めた。
しかし、協力者に対する処罰は、他のカテゴリーに比べると驚くほど甘かった。国賊や戦犯が死刑や無期追放になる可能性があるのに対し、協力者に対する処罰は最長でも10年の公民権剥奪に限られていた。委員会は、この反協力者法は、「国家反逆者」や「戦争犯罪人」でない限り、協力者に厳罰をもたらすことを意図したものではないと説明した。むしろ、委員の一人が説明したように、この法律の目的は「国家の正しい精神の確立」であり33、したがって、反協力者法は、新しい国家建設のプロセスからできるだけ多くの元協力者を排除することを目的としていた。実際、委員会はこの法案で処罰される協力者の数をおよそ10万人から20万人と見積もっていた34。
この法案で重要なのは、委員会が、協力者、国家反逆者、利敵者のカテゴリーに加えて、朝鮮戦争犯罪人という別のカテゴリーを設けたことである。法案の中で、委員会は戦犯を次のように定義した:
奉天事件(1931年9月18日)から朝鮮解放(1945年8月15日)までの間に、自己の利益のために悪質な行為を行い、それによって朝鮮の同胞に有害な結果をもたらした者は、戦争犯罪人とみなされる。
- 連合軍捕虜を虐待した者;
- 日本の)軍事力を強化する目的で、主要な戦争産業を経営した者;
- 自発的に日本軍に1万円以上または軍需品を寄付した者;
- 自発的に日本軍に入隊した者
- 言論、著述等を通じて日本の戦争を擁護した者
- 日本軍に加わり、朝鮮の同胞や連合国の国民を虐待した者35。
「戦争犯罪人」という概念が、植民地協力者に関する(韓国の)政治的言説に突然組み込まれるようになった経緯は定かではない。先に論じたように、植民地協力者は解放後の韓国社会では親日派や売国奴として理解され、枠にはめられがちであった。さらに、委員会が提案した戦争犯罪人の定義は、ニュルンベルク裁判や東京裁判の時点で、従来の戦争犯罪や平和に対する罪、人道に対する罪の定義に属すると一般に理解されていたものを明らかに超えていた。しかし、戦争犯罪人という概念を反協同者法に組み込んだことは、米・連合国による日本の民主化の政治を利用しようとする韓国指導者の政治的努力の一環と見ることができる。例えば、東京裁判と米軍・連合軍による日本軍国主義者の粛清は、韓国の政治指導者たちが米国の韓国占領政策を批判する際の参照点となった。1947年1月8日、SKILAが反協力者法制のための委員会を結成していたとき、韓国の左翼民主民族戦線は、ダグラス・マッカーサー元帥に対し、日本で行っていたように「韓国でも戦犯を粛清する」よう求める声明を発表した。その声明の中で、民主民族戦線は、米連合国占領下の日本における戦犯と、米占領下の朝鮮半島における戦時協力者の運命の間にある矛盾を指摘した36。
ある意味で、こうした韓国の政治指導者たちは、戦争犯罪裁判という米軍/連合国の政治を利用しようとしていたと見ることができる。米国に占領された韓国の国政が、かつての植民地支配を受けた韓国人によって支配されていたという現実を考えれば、このような韓国の政治指導者たちが、戦争犯罪裁判という米軍/連合国の政治を利用しようとしていたことがわかる。
反協力者法制の推進者たちは、植民地時代の協力者を裁くために、別の道徳的・法的原則に目を向ける必要があった。こうして、戦争犯罪と人道に対する罪の概念を戦時中の植民地朝鮮の文脈に適用することで、親日派と売国奴という国内に限定された問題を国際化することが可能になった。
しかし、戦犯の定義はSKILA内で批判の的となり、やがて法案から姿を消した。3月21日のSKILA会議では、李鎰議員が、朝鮮人徴用工や学徒兵など、日本の連合国との戦争に強制的に参加させられた人々を処罰するのは公平なのか、と疑問を呈した。李氏は、「自発的に」日本軍に参加し、「連合国の国民を虐待した」韓国人は一人もいないと主張した。しかし、委員長の鄭伊亨(チョン・イヒョン)は、「飛行機や戦車を寄贈」したり、韓国人の入隊を「扇動」したりして、日本の戦争に自発的に協力した韓国人は確かにいたと主張した。鄭は、「彼らが戦争犯罪人でないとすれば、彼らは何なのか」と主張した37。もう一つの批判は、「戦争犯罪人」という概念そのものが朝鮮に適用できるかどうかを疑問視し始めた人々によって提起された。たとえば、4月24日のSKILA会議では、ある議員が「韓国は第二次世界大戦の当事者ではない」と、法案の「戦犯」というカテゴリーをあっさり否定した。しかし、鄭伊亨委員長はこの見解にも反論した。彼は、「海外の独立運動家たちが日本との戦争に参加していたとき、韓国国内の指導者たちの中には、献金によって日本に協力していた者もいた」と主張した。従って、「戦勝国の立場から戦犯を処罰する」のである38。
結局、「戦犯」というカテゴリーは法案から削除された。これは、植民地朝鮮が第二次世界大戦の当事者であったかどうかという問題よりも、植民地朝鮮の文脈で「戦争犯罪人」をどのように定義するかという問題のためであった可能性が高い。実際、ある議員は「戦犯を協力者や売国奴と区別する基準」に疑問を呈していた39。何度も修正された後、反協力者法案の最終案は、最初の法案がSKILAに提出されてから約4カ月後の7月2日に可決された。その後、1948年8月15日に韓国政府が樹立されると、憲法制定議会は新たな反売国奴法案を可決した。
その後、1948年8月15日に韓国政府が樹立されると、憲法制定議会は9月7日に新しい「反売国法」(Panminjok haengwi ch’ŏbŏlpŏp)を可決した。
***
戦争賠償に関する韓国の指導者たちの議論の中にも、植民地主義と植民地犯罪に対する裁きを追求する努力を見出すことができる。1947年末、韓国の財界指導者たちは、日本からの戦争賠償の可能性に関する報告書を起草した(41)。彼らは、韓国は「国際法の観点からは第二次世界大戦の当事国ではなかった」が、「解放された国」であると主張した。したがって、韓国の日本に対する賠償請求は、戦勝国が敗戦国に対して通常請求する賠償とは異なる。韓国の場合、賠償金は「日本が過去数十年間の植民地支配の間に武力で搾取し、略奪したもの」に対するものである42。さらに重要なことは、韓国の経済界のリーダーたちが日本に対する賠償金請求の根拠として、1943年のカイロ宣言に言及したことである。
カイロ宣言は、近代帝国事業の正当性を主張する日本に異議を唱えた、最も重要な国際声明の一つであった。カイロ宣言の中で、連合国は日本の朝鮮植民地支配を「朝鮮人民の奴隷化」として公式に非難した。連合国は、「やがて朝鮮は自由と独立を得る」と宣言することで、朝鮮人を日本の「奴隷化」から解放することを約束した。しかし、連合国が朝鮮の独立の時期として示した「やがて」とは、日本が降伏した後、直ちに独立するという意味ではなかった。多くの韓国人は「やがて」という言葉を「数日のうちに」、あるいは少なくとも「間もなく」43と理解したが、連合国側の朝鮮独立のビジョンはそれとは異なっていた。すでに何人かの学者が論じているように、フランクリン・ルーズベルト米大統領は、 独立を確立する前に、連合国の信託統治下で植民地後の朝鮮を管理する計画を準備していた44。 さらに、カイロ宣言の朝鮮解放の約束は、米国の朝鮮占領政策に大きな影響を与えた。日本の降伏後、ワシントンの米政策立案者たちは、”Basic Initial Directive to the Commander in the U.S. Army Forces, Pacific, for the Administration of Civil Affairs in Those Areas of Korea Occupied by U.S. Forces “と題する政策指令を起草した。この指令は、戦後の韓国を「解放された国」と定義した。この指令は、戦後の韓国を「解放された国」と定義し、「カイロ宣言の規定に準拠し、民政運営は、貴軍の安全保障と最大限矛盾しない範囲で、韓国を解放された国として扱うことを基本とする」と規定した45。
このような歴史的背景から、韓国の指導者たちが日本の植民地支配に対する判断をどのように主張したかを理解することは重要である。例えば、李相得は「対日賠償請求の正当性」と題する論文で次のように主張している:
カイロ宣言とポツダム宣言が「朝鮮人民の奴隷化」と規定しているように、日本の朝鮮に対する長期にわたる支配は、道徳、公平、互恵といった国際正義の基本原則に基づくものではなく、暴力と搾取に基づくものであった46。
彼は続けて、1910年の「日韓併合条約」は「朝鮮人民の自由意志」に反して「力によって」制定されたと主張した。したがって、「日本からの賠償」とは、「暴力と貪欲によって引き起こされた損失の回復」を意味することになる47。重要なのは、この定式化が、賠償問題に対する韓国政府のアプローチの論理的基礎となったことである。その後、1949年9月に韓国政府が「対日賠償請求研究」と題する一連の政策文書を作成した際、政府は日本に賠償を要求する根拠を次のように明らかにした:
日本による1910年から1945年8月15日までの朝鮮支配は、朝鮮人民の自由意志に反して武力で押しつけられたものである。それは正義、公平、互恵の原則に基づかず、暴力と貪欲による支配であったため、韓国と韓国人は日本の犠牲者の中で最も苦しんだ。[カイロ宣言によって、日本の韓国支配の非人道性と不法性が世界に認められたのである48。
韓国政府もまた、韓国における日本の植民地支配に対する判決を追求するために独自のイニシアチブをとった。1948年11月22日、韓国の張鉄山外相は、韓国政府が旧朝鮮総督府のA級戦犯である小磯国昭と南次郎を人道に対する罪で裁くため、韓国の法廷に引き入れるよう努力すると発表した49。東京裁判が11月12日に判決を出した後、張外相は記者会見を開き、韓国人が東京裁判で何の役割も与えられていないことに失望を表明した50。
張外相は11月12日、記者会見で、韓国政府は連合国に対し、小磯、南両氏と板垣征四郎・元在韓日本軍総司令官を韓国の法廷に移送するよう要請したことを明らかにした(51)。先に述べたように、韓国憲法制定議会は1948年9月7日、新売国防止法を可決し、李承晩政権は9月22日、しぶしぶ同法に署名した。議会とは異なり、李承晩政権は旧植民地協力者の訴追に乗り気ではなかった。李承晩政権は、反売国法を破棄し、議会が組織した特別調査委員会の調査を妨害するために、断固とした努力を行った52。
同時に、東京裁判に対する韓国メディアの批判は、日本の植民地支配に対する判断の問題を前面に押し出し、いわゆる文明の判断の限界を明らかにした。例えば、在日コリアン左派の新聞『海邦新聞』は、「極東国際軍事裁判の判決について」と題する社説を掲載し、東京裁判が天皇裕仁を訴追しなかったことを批判した。もう一つの在日朝鮮人新聞である新世界新聞は、東京裁判が「文明と人道の名において」行われる裁判であるならば、「人道に対する(犯罪の)被害者」である朝鮮人を排除することは、まったく「矛盾しており、不合理である」と主張した。在日本大韓民国民団の機関誌『中央日報』も、東京裁判が1928年以前に起きた日本の戦争犯罪、特に1905年に締結された日韓保護条約を武力で排除していると批判した。中央時報は、このような除外は東京裁判の「歴史的限界」を示していると主張した56。
***
これらの在日コリアンの批判は、後に日本の歴史家が東京裁判の限界を評価する際に前面に出すことになる重要な問題を提起した。前述したように、1970年代に入ると、日本の歴史家の中には、東京裁判の報復的性格だけに焦点を当てた既存の「勝者の正義」批判とは異なる方法で、戦争犯罪裁判の重大な欠陥を調査し始めた者もいた。日本の歴史家たちが提示した主要な批判の一つは、東京裁判には植民地問題も旧植民地臣民の声もなかったことである。その意味で、在日コリアンの批判が、戦後日本史における東京裁判の異なる解釈と歴史的評価の先駆けとなったことは重要である。
高麗大学校韓国学研究所教授。2013年8月にコーネル大学で歴史学の博士号を取得した。博士論文「ポスト帝国の坩堝」: Crucible of Post- Empire: Decolonization, Race, and Cold War Politics in U.S.-Japan-Korea Relations, 1945-1952」で、国際アジア学者会議(ICAS)人文科学部門2015年最優秀論文賞を受賞。英語、日本語、韓国語で多数の論文を発表している。最近の論文は以下の通り。Writing the ‘Empire’ Back into the History of Postwar Japan」(『International Journal of Korean History』2017年2月号)、「『Mindful of the Enslavement』: The Cairo Declaration, Korean Independence, and the Ambiguity of the Liberation of Koreans in Defeated Japan” (The Significance and Effects of the Cairo Declaration, 2014).The research leading to these results received funding from the European Research Council under the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013)/ERC grant agreement n° 313382.
シンガポール裁判における忠誠の誓い
チェー・ウイリン
はじめに
国家の忠誠を変えることは、忠誠心、選択、アイデンティティに関する難しい問題に関わる。戦争や紛争の時代には、このような忠誠心の変更は、味方の交代を伴う場合にはさらに複雑になる。知名度の高い個人や大勢が関与する戦時中の忠誠の変更は、政治的、社会的に深刻な結果をもたらす可能性がある。前線で戦う兵士や自国の民間人の士気を低下させるかもしれない。そのような忠誠心の変化は、結束と忍耐という国の物語が特に必要とされる時期に、その国の物語を損なうかもしれない。戦争は国民の名において、国民の利益のために行われているという国の主張が嘘になるかもしれない。
では、このような忠誠心の変更は、法律上どのように扱われるべきなのだろうか。より具体的に言えば、そのような忠誠心の変更は、当該個人から法の保護を剥奪すべきなのだろうか?そのような変更は、国内法と国際法とで異なる扱いを受けるべきなのだろうか。本章では、第二次世界大戦後にシンガポールで英軍によって行われた戦争犯罪訴訟(シンガポール裁判)において、このような疑問がどのように生じたかを探る。忠誠心の変更を仮釈放と混同してはならないことに留意すべきである。日本軍が連合軍捕虜に仮釈放を強要したり、逃亡しないことを約束させたりした事件もあった1。本章で取り上げた事件の被告は、当該被害者は日本への忠誠を誓うことで英国への忠誠を放棄していたため、自分たちの行為は捕虜に対する戦争犯罪とみなされるべきではないと主張した。被害者はイギリス系インド人であり、日本に捕虜として連行される前はイギリス軍のメンバーであった。彼らは日本軍によって虐待されたり、即刻処刑されたりした。被告人は捕虜虐待死で起訴された。
本章では、シンガポール裁判において、2つの事件がこの忠誠心の変化の問題をどのように扱ったかを検証する。まず、シンガポールにおける英国の戦争犯罪訴訟の法的・政治的背景を明らかにする。戦時中の忠誠心の変化について提起された疑問は、戦後の社会政治情勢を背景に、復帰した英国の植民地当局がシンガポールとこの地域の権威を再強化し、秩序を再確立しようとする中で、特に大きな問題となった。本章では次に、忠誠心の変化という問題が2つのケースでどのように扱われたかに焦点を当てる: 池上友之他と高島正太郎他2の2つの事件では、2つの異なるアプローチ、すなわち、放棄不可能アプローチと刑法アプローチが確認できる。第一のアプローチは、戦時下において忠誠の変更が可能かどうかに焦点を当てるものであり、第二のアプローチは、被告人の考え方に焦点を当てるものである。本章では、これら2つのアプローチの根拠と論拠を批判的に検討する。最後に、今後の研究にとって実り多い行程を強調する。
シンガポール裁判の法的枠組みと社会政治的背景
1945年6月18日、英国行政府は勅令を可決し、英国軍に、戦争法規・慣例違反を裁く軍事法廷を設置する権限を与えた3。シンガポールで設立された裁判所は、所見をまとめた包括的な判決を出すことはなかった。裁判手続き中や、検察側と弁護側の冒頭陳述と最終陳述で法的問題が提起されたが、これらの裁判における法的議論の量と質は、現代の戦争犯罪裁判に比べて一般的に低かった。裁判が終了すると、有罪判決を受けた者は、確認官による確認を求める嘆願書を提出する権利があった6。この裁判後の確認段階では、シンガポールにある法務総監部も審査報告書(DJAG review report)を作成する。この報告書には、事件の事実とその法的問題の概要が記載される。
1945年勅令に基づいて設立されたこれらの英軍軍事裁判所は、ニュルンベルク裁判や東京裁判と並んで機能した7。後者の裁判は、高位の政治的・軍事的指導者の選ばれたグループを対象としていたのに対し、1945年勅令裁判は、戦争法規や慣例違反に相当する多様な行為について、広範な個人を訴追した。これらの1945年勅令英軍法廷は、シンガポールを含むアジア各地のさまざまな場所に設置された。シンガポールでは、これらの英軍法廷が、現在のシンガポール、マレーシア、ブルネイ、インドネシア、タイ、ベトナム、カンボジア、パラオ、パプアニューギニア、アンダマン・ニコバル諸島で行われた犯罪を訴追した。裁判にかけられた犯罪の中には、ビルマ・シャム鉄道の建設、収容所での捕虜や民間人の虐待、民間人の虐殺、スパイ容疑者の略式処刑に関するものがあった。
イギリス軍に所属していたインド兵の虐待や殺害を扱った事件もあった。これらの事件はイギリスにとって政治的な意味を持つものだった。1942年 2月 15日にシンガポールが日本軍に陥落したとき、山下奉文大将に率いられた。3 万人の日本兵は、イギリス軍に死者 7,500 人、負傷者 1 万人、捕虜 12 万人という損害を与えたが、正確な数字については論争が続いている9。これらのインド人捕虜は他のイギリス軍から引き離され、シンガポールのファラーパークに連行された。そこで彼らはイギリスへの忠誠を捨て、イギリスの支配からインドを解放するために日本とともに戦うよう促され、直ちに2万人のインド人兵士がイギリスに対して武器を取ることを選択し、さらに2万人が1942年6月から8月にかけて武器を取った11。こうしてインド国民軍(INA)が誕生した。INAに参加しなかった人々は、日本軍によってさまざまな建設プロジェクトに強制労働者として送られた。
降伏した他の英軍兵士がインド兵のこの忠誠の変更を初めて耳にしたとき、多くの者は裏切りと見なしたことに衝撃と失望を覚えた12。また、日本の慈悲深い主張に疑念を抱きつつも、インドにおけるイギリスの支配が日本の支配に取って代わられるのを避けるためにはインドの関与が必要だと考える者もいた15。1943年、ボースがシンガポールで自由インド臨時政府を樹立したことで、さらに多くのインド人が、INAに参加するようになり、その時点で総勢 8 万人に達していた18。
1945年までに、18,000 人のインド民間人が、INAに参加した。戦争中も、英国の植民地の忠誠心は、英国の指導者にとって微妙な問題であり続けた。戦争が終わる前から、イギリス政府は戦後のアジアにおける植民地政策を議論し始めた。戦争前の地位の回復から完全な解放までさまざまな見解があったが、最終的には、最終的な自治を認めることを視野に入れながら、イギリスが極東の植民地の統治を続けるということで大筋合意した。英国の指導者たちは、地元住民だけでなく、より広範な国際社会の利益のために、これらの植民地の統治を継続することが最もふさわしいと合理的に考えたのである。外務省と植民地庁の共同メモは、英国の統治を継続することで、シンガポールの港が「マレー諸島の生命と貿易、東洋の海洋貿易」であり続け、マレー系住民の福利が「より効率的で数の多い中国人と、それほどでもないインド人」から保護され続けることが保証されると認識していた19。こうして英国は、英領マラヤの植民地支配が、たとえそれが最終的に自治につながるものであったとしても、かなりの期間継続することを期待した。
終戦後、英国がマラヤとシンガポールに戻ったとき、植民地住民が英国への強い忠誠心を示すだろうと、誤った推測をした者もいた。それどころか、政治的・社会的態度が明らかに変化した。政治的包摂と独立を求める声が高まったのだ。マラヤに帰還した英国の民間人は、英国の植民地支配に対する地元の人々の受容を同じレベルで期待しないよう警告されなければならなかった21。さらに、帰還した英国人は、英領マラヤで戦後復興の数々の課題に直面した。1945年8月15日の日本の無条件降伏から1945年9月に英国がマラヤとシンガポールに帰還するまでの間、反日抵抗勢力は英領マラヤ全土で日本軍協力者を処罰するために立ち上がった24。マラヤとシンガポールでは、法と秩序が全般的に崩壊していた25。病院は医薬品と備品が不足していた26。英軍はまた、戦時中のゲリラ勢力の復員や封じ込めに対処しなければならなかった27。
英軍政権は戦後の多くの課題に対処しなければならなかったが、英軍指導者たちは戦争犯罪の訴追を行うことも重要だと考えていた28。1945年 10月、東南アジア連合国最高司令官ルイ・マウントバッテン提督は、参謀総長にメッセージを送り、このような裁判を開始する必要性を強調した: 「しかし、私は、捕虜、抑留者、抑留されていない民間人を問わず、特に英国民また。は同盟国に対して個人的に残虐な行為を行ったと確認された軽微な犯罪者を裁判にかける。のに遅れが生じていることについて、改めて私の不安を強調したい」29 イギリス軍当局者は、これらの裁判がこの地域で多くの目的を達成すると考えていた。裁判は、正義を求める被害者や一般市民の要求を正当化するものであった。例えば、フィリピンでアメリカ軍に裁かれるはずだった山下奉文大将が、日本のマレー作戦中に犯した罪についてシンガポールでイギリス軍に再審理されることは「有益」ではないと判断された。しかし、彼の犯罪に関する情報は「世界に公開」されることになっており、そうすれば「山下に対する現地の強い感情をかなりの程度満足させることができる」と考えられていたからである30。
シンガポール裁判の多くは、インド人の犠牲者を含む戦争犯罪を扱っていた。これらの事件の多くで弁護側は、インド人被害者は英国への忠誠を放棄して日本への忠誠を誓ったのだから、日本軍の懲戒規則に従って扱われるべきだ、と主張した。ここでは、忠誠の問題が同じ裁判所で審理され、忠誠の問題について比較的広範な議論がなされた2つの事件に焦点を当てる。これらの事件はいずれも、イギリス軍に所属していたが、その後日本軍の捕虜となったインド人被害者に関するものであった。弁護側は、被害者は日本への忠誠を誓い、日本のロムタイ(特別労務班)のメンバーであったと主張した。これらの事件は同じ裁判官団によって決定された。裁判後のDJAG審査報告書は異なるアプローチをとり、裁判の所見を不確認とするよう勧告した。これらの裁判結果は確認されなかった。
公判不可能なアプローチ:池上友之裁判
池上友之らと高島庄太郎らの裁判
池上友之ほか裁判
池上友之らの裁判には6人の被告人が参加した31。被告人は全員、1番目の被告人である池上友之が率いる池上ユニットに所属していた。1945年6月27日と1945年6月18日の2つの別々の事件に基づいて、被告人に対して2つの告発がなされた。事件の事実は以下の通りである。最初の被告人である池上は、ロム隊(特別労務班)を含む部隊の指揮官であった。弁護側は、インド人犠牲者はこの部隊に属していたと主張した。池上部隊はマレーシアのサラワク州ルトンで活動していた。被告人のうち4人(高橋洋一、高橋辰雄、三好蓮、久野淳)はルトン油田で働く技術職員だった。最後の被告人、高橋毅は、ルトン油田で働いていた四等兵だった。部隊は連合軍の攻撃を受け、撤退を開始した。撤退中の1945年6月18日、池上は、ロム泰のインド人5人が逃亡しようとして逮捕されたという報告を受けた。彼らは日本軍の部隊の位置を示す秘密の地図を持っていたという。調査の結果、池上は彼らがロムタイメンバーで、秘密情報を持って敵に脱走しようと共謀していると結論づけた。そして池上は被害者たちの処刑を命じた。犠牲者たちはその日のうちに処刑された。
1945年6月26日、さらに11人のロム隊員が逃亡したが、同じ日に再逮捕された。二人目の被告人である高橋は、この事件を池上に報告し、秘密文書が紛失して発見されたことなどを説明した。池上はその後調査を行い、被害者たちも同様に脱走を計画し、機密書類を盗んでいたことを突き止めた。池上は、被害者たちを処刑することを決定した。翌日、1945年6月27日、第二から第六の被告人は池上に報告し、池上は彼らに処刑命令とその理由を説明した。ロム隊員はその日の朝、被告人によって処刑された。最初の告発は、1945年6月27日の殺害に関するもので、被告人全員に対して提起された。第二の罪状は、1945年6月18日に関するもので、池上被告に対してのみ起訴された。
3人の裁判官がこの事件を担当した: 検事は事務弁護士であったS.J.スミス少佐であった33。被告人の弁護は、日本海軍の法務官であった竜崎英弁護人が担当した34。イギリス人弁護人のウォードJ.H.中尉は、裁判を管理する1945年の勅令の枠組みに従って要求された軍事訴訟規則について弁護側を支援するために任命された35。検察側は1人の証人が証言した。弁護側は6人の被告人のうち5人を含む9人を証人喚問した。最初の被告人である池上少佐は絞首刑に処された。二人目、三人目、四人目、五人目の被告人はそれぞれ禁固10年の判決を受けた。第二、第三被告人はいずれも一等陸尉、第四、第五被告人は二等陸尉であった。伍長の階級にあった6番目の被告人には5年の禁固刑が言い渡された。裁判所の判決は、以下に説明する理由により、確定されなかった。
裁判は1945年11月19日に始まり、1945年12月2日に終わった。弁護人は冒頭のあいさつで、インド人犠牲者はすべて「自発的に日本軍に忠誠を誓った」特攻隊員であったと指摘している36。この点は裁判の中で被告人・弁護側証人によって言及され、裁判所が一部の被告人・弁護側証人に対する独自の尋問の中で特に取り上げられた。1945年 11月 25日、裁判所が第 4の被告人である三好廉にその部隊の性質について質問したとき、三好廉は、 その部隊が「日本軍に忠誠を誓ったインド人」で構成されていることを「上官から命令され、指示された」と説明した37。 38 彼らの中から指揮官が選ばれ、部隊には「連絡目的」で雇われた日本人将校がおり、「日本の習慣や作法を知らない」インディオたちを「指導」し、誤解が生じないように「指導」していた39。裁判所は、3番目の被告人である高橋辰雄の尋問でも、忠誠心の問題を取り上げた。高橋は、特別労務班の仕事の一部は「油田の警備」であったと説明した40。裁判所は高橋に、インド人捕虜は自分たちの指揮官を持ち、収容所のある地域内で「相応の自由」を得ていたのかと尋ねた。高橋はどちらの質問にも肯定的に答えた41。
特別労務班がどのように組織されたか、彼らに割り当てられた比較的重要な仕事、彼らの規制のない移動に関する事実は、裁判所に管轄権に関する潜在的な懸念を喚起した。裁判所は次に、被害者が捕虜ではなく、「かつて国王陛下の臣民であったインド生まれの者」で、日本当局に対して「仮釈放よりも重い誓約によって」英国臣民としての権利を放棄した者であるという「一定の裏付け証拠」があることを指摘し、管轄権に関する懸念を検察官に強調した42。裁判所は検察官にこの問題を検討し、助言を裁判所に提出するよう求め、翌日まで延期した43。
1945年11月26日、裁判所が再集合すると、忠誠問題に関する検察官の弁論が行われた。検察官の弁論では、英国法と国際法が混在していた。彼は、国籍離脱は1914年の英国国籍および外国人の地位に関する法律(British Nationality and Status of Aliens Act)および既存の英国の判例法に準拠すべきであり、それによれば、英国人は「敵国のために王室への忠誠を捨てることができるのは、その外国に実際に居住している間だけである」と主張した44。さらに、英国の判例法に基づき、個人は国籍離脱前に負うべき「軍事的義務」を回避することができないので、そのような軍事的義務を負う者の「特権と利益」を「回避」することもできないと主張した45。さらに興味深いのは、当時の条約に関する検察官の主張である。検察側は、「法律には2種類の権利」があると主張した。すなわち、「広く公衆を保護するため」に認められた権利と、「もっぱら個人を保護するため」に認められた権利である。後者は放棄することができない46。言い換えれば、後者の利益は私的なものではなく公的なものである。つまり、後者の利益は、私的なものではなく公的なものである。したがって、この主張に基づけば、個人が放棄することはできない。
日本の弁護人は、英国法を「よく知らない」ことを率直に認めたが48、検察官が、被害者が日本に忠誠を誓っており、被害者が前者を日本軍の一員として扱っていたという事実を覆す証拠を提出していないことは強調した。弁護人は、被害者たちは英国から見れば英国の臣民であっても、日本人から見れば日本の臣民である、と主張した。弁護人は、これは「非常に不思議な状態」であると認めた49。裁判所は、検察側と弁護側の提出物を検討するため、15分間休廷した。再開後、裁判所は、被告人に対する裁判管轄権について決定する「権限を与えられていない」とし、招集機関に相談するために休廷するとの見解を示した。
1946年11月28日に再び開かれた裁判所は、忠誠の問題について、弁護団の提出と召集当局の法律顧問の助言を考慮したと発表した。「国際法と大日本帝国憲法」に基づき、裁判所は、臣民は戦争状態にある間は忠誠を放棄することはできないとした。従って、裁判は続行された。池上は絞首刑に処せられた。少尉と少尉の階級にあった他の被告人には懲役10年が、伍長だった高橋武には懲役5年が言い渡された。
高島正太郎ともう一人
この裁判では、高島庄太郎軍曹と浅子幸一伍長という2人の被告人が、ニューブリテン島のサンカクヤマで2人の被告人が運営する収容所でインド人捕虜を虐待した罪で起訴された。高島はインド人捕虜の一団の責任者であり、浅子は収容所の医療係であった。被告人たちは、インド人捕虜の虐待に関与したとして起訴された。高島が指揮官で、浅子が医療係だった収容所で、病人に労働を強要し、適切な医療措置を怠るなどの虐待があったとされる。この事件の検事はS.B.サヘイ少佐であった53。弁護人は東京民事裁判所の法廷弁護士であった中村武志であった54。人の証人が検察側で証言し、2番目の被告人である浅子を含む3人が弁護側で証言した。検察側の立証が終了した時点で、弁護人は、検察側は十分な証拠を提供しておらず、高島に対する立件もなされていないと主張した56。裁判所は弁護人の意見に同意し、高島を無罪とした。しかし、朝子に対する裁判は続行され、朝子は最終的に無期懲役を言い渡された。しかし、浅子に対する裁判所の認定と判決は確定しなかった。
裁判は1947年1月25日に始まり、1月30日に終わった。裁判4日目の1947年1月29日、弁護人は裁判所に対し、インド人被害者は忠誠を誓っており、犯行当時はもはや捕虜とは見なされなかったと提出した。これに対して検察側は、裁判管轄権への異議を禁じた1945年勅令第6条に言及した57。同規則第6条は、「被告人は、裁判所長、裁判所構成員、法務官に対して異議を申し立てたり、裁判所の管轄権に対して特別な弁明をしたりする権利を有しない」と定めていた。つまり被告人は、裁判所には裁判を行う権限がないと主張することはできないのである。検察官は、第6 規則は弁護側の主張に対する「完全な回答」であると述べた58。さらに、「英国軍法マニュアル」は、占領軍が占領地の住民に旧軍への忠誠を強制することを禁じている、と主張した。また検察官は、忠誠の変更が「自発的に」行われたと裁判所が判断した場合にのみ、この問題は招集機関に委ねられるべきだと主張した60。これに対して弁護人は、時間が与えられれば、「十分な証拠を提出できる」と「確信している」と述べた61。
続いて裁判長は、弁護人から「同一の提出」がなされた以前の裁判に、現在の裁判所が関与していたことを説明した62。この裁判では、裁判所は裁判管轄権を有しており、被害者は「英国王室への忠誠を誓うことを法的に放棄することはできない」と招集機関が勧告していた63。裁判所はまた、同じ収容所に収容されていたイギリス領インド軍のメンバーであった検察側の証人ナウラン・カーンを呼び戻して、この忠誠の誓いの取得について尋問するという検察側の提案も後に却下した65。弁護人は最終弁論で、被害者たちは「純粋な捕虜」ではなく、「日本軍によって捕虜の身分から解放された」のであり、インド労働部隊のメンバーであったという主張を繰り返した66。このことは、次節の分析の基礎となるDJAGレビュー報告書に基づく確認官によって確認されなかった。
刑法のアプローチ:池上友之らと高島庄太郎らのDJAG審査報告書
本章の前半で説明したように、1945年の勅令の枠組みに基づき、これらの英軍法廷の有罪評判と判決は、確認官によって確定されるまでは最終的なものではなかった67。池上友之らも高島正太郎らも確定しなかった。これらの事件で出された検証報告書は、この問題を法的に考察している点で、特に興味深いものである。
1947年 2月 13日付の池上友之らに対する。DJAGの再審査報告書では、インド人被害者は「元々は捕虜であったが、日本軍に忠誠を誓った者」と説明されている69。 69 同報告書は、弁護団が、被害者が捕虜であったとしても、最高位の被告である池上は、被害者が「日本兵の地位」を有し、「日本の軍法に従う」という「善意の信念に基づいて行動した」と主張していたことを認めた70。DJAGの報告書は、「イングランドの国内法」に基づくとはいえ、英国の臣民が戦争中に敵地や敵占領地にいる間に国籍を放棄することは不可能であったことを認めている72。しかし、当時の国際法では、「自発的に」敵軍に参加した個人が、敵の軍法に従って懲戒処分を受けたとしても、戦争犯罪とはみなされなかった74。
さらに興味深いことに、弁護側の主張に沿う形で、DJAGの審査報告書は、被害者が敵軍に参加するよう強制された、あるいは「そそのかされた」場合でも、懲戒将校はその強制行為について責任を負うべきでないと説明している。具体的には、報告書は、被告人が「善意の事実誤認」に基づいて行動し、被害者が「日本の軍法に適切に従う者」であると真に信じていた可能性があると指摘している。 76 この見解は、池上友之らにおける検察官の最終弁論で、池上がこれらの被害者の正しい身分を知らなかったのであれば、被害者の身分を自分で確認すべきだったと主張したこと、また、「法の不知」は、軽減に影響を与えることはあっても、弁護の対象にはならないというのが「わが国法の基本原則」であることを考えると、重要である77。対照的に、DJAGの審査報告書は、この間違いは事実の一つであり、善意であれば被告人の刑事責任を免除するものであると判断した78。したがって、DJAGの審査報告書は、事件の確定を保留するよう勧告した79。
この考え方は、高島正太郎らに関するDJAG審査報告書でも同様に採られている。1947年4月15日付のDJAG審査報告書は、弁護側が、被害者たちはもともと捕虜であったが、日本への忠誠を誓ったため捕虜の地位を失ったという点を指摘したと述べている81。しかし、この点について証拠を提出するために証人を呼び戻すという検察側の申請は、「法律の問題として」裁判によって「残念ながら却下」された82。DJAG審査報告書はさらに、被告人は依然として、「そのように扱うことが自分の義務であった人々に対して自分の権利の範囲内で行動していると正直に信じていた」という「抗弁を提起する」ことができると説明している83。DJAGの審査報告書は、裁判の所見を不確認と勧告した。
この問題は、東南アジア陸軍法務総監部にとって十分な関心事であった。
部隊はこの問題についてロンドンの法務官事務所に助言を求めた。デイビス准将は 1947年 1月 10日付けのメッセージで、池上友之らとジェッセルトンで裁かれたもう。1 件の事件、すなわち神倉らに関するロンドン法務総監部の「意見」を「ありがたい」と述べている(84) :
インド国民軍への入隊を拒否したインド人捕虜は奴隷労働者として様々な戦地に送られ、 ROMU TAI(特別労働隊)はそのような人々で構成されていたとの情報が入ってきた85。
この追加情報は、当該忠誠の誓約が、おそらく強要のもとに犠牲者から引き出されたものであることを示した。しかし、この追加情報は、当該忠誠の誓約がおそらく強要のもとで被害者から引き出されたものであることを示すものであり、2つのDJAGレビュー報告書の立場を変えるものではない。被害者に忠誠を誓わせることに関与していなかった被告人は、被害者が本当に日本に忠誠を誓ったと誤解していた可能性がある。この刑法的アプローチは、スポットライトを忠誠の誓いから被告人の罪責に振り向けたのである。
結論
これら2つの事件で、DJAGの審査報告書が、不可能犯的アプローチではなく、刑法的アプローチをとった理由はいくつか考えられる。第一に、この事件の裁判員はいずれも法曹資格を有していなかったことに留意すべきである。しかし、池上友之らの裁判員は、忠誠の誓いの影響の問題を招集機関に照会しており、その法律顧問は国籍変更は有効ではないと助言していた。これらのイギリスの戦争犯罪裁判は、シンガポールのメディアによって大きく報道された。おそらく裁判の段階でこれらの事件に世間のスポットライトが当たったおかげで、これらの宣誓の性質が裁判でもっと綿密に検討されていたら、英国の権威はさらに損なわれていただろう。国籍を放棄することはできないとすることで、そのような検証を封じることは容易だったのかもしれない。非公然確認の段階では、被害者が敵軍に加わることを選択した可能性を国際法が認めており、このような場合の罪責は被告人の精神状態に左右されるべきであると認めた方が、争いは少なかっただろう。
第二次世界大戦後の国際法の状況は不明確で、まだ発展途上であったことに注意することが重要である。忠誠の誓いをめぐる他の英国の戦争犯罪裁判では、さまざまな論点が強調され、裁判のやりとりが関連する法律上の論点をすべて網羅することはめったになかった。これらの勅令裁判において、忠誠の誓いが英軍によってどのように扱われたかをより包括的に知るためには、アジアの他の地域で行われたものも含め、より多くの裁判を検討する必要がある。これらの裁判における忠誠の誓いの意義と関連する法的問題を明らかにすることで、本章はさらなる研究の足がかりとなるだろう。
2007年よりシンガポール国立大学法学部助教授。シンガポール国立大学(法学士、法学修士)、ハーバード・ロー・スクール(法学修士)、ヨーロッパ大学インスティテュート、オックスフォード大学(法学博士)で学ぶ。弁護士資格を有し(ニューヨーク州弁護士資格)、仲裁のディプロマ(ロンドン大学クイーン・メアリー校)を取得。学界に入る前は、国際刑事警察機構(INTERPOL)法務部(フランス、リヨン)で法務官を務めた。国際法研究センター(英国・ロンドン)、オックスフォード大学(英国)、ジャン・ムーラン・リヨン第3大学(フランス)、王立法経済大学(カンボジア)などで教鞭をとる。『ハーバード・ヒューマン・ライツ・ジャーナル』、『ジャーナル・オブ・インターナショナル・クリミナル・ジャスティス』、『インターナショナル・ジャーナル・オブ・ロー・イン・コンテクスト』などのジャーナルに論文が掲載されている。現在、シンガポール戦争犯罪裁判に関する書籍プロジェクトに取り組んでいる。シンガポール戦争犯罪裁判ポータルサイト(http://www.singapor ewarcrimestrials.com/)の共同創設者でもある。
傀儡、儲け手、裏切り者: オランダ領東インドにおける戦時協力の定義、1945-1949年
エスター・ツヴィンケルス
第二次世界大戦後、東京の極東国際軍事裁判(IMTFE)で行われた日本人犯罪者の裁判は、勝者の正義の反映であるとして、長年にわたって大きな論争を巻き起こしてきた1。最先端の研究が示すように、東京裁判は、戦勝国が敗戦国の運命に勝利するというショーケースではなかった。裁判には欠点もあったが、オランダをはじめとする参加11カ国の意図は、主要な戦争犯罪人が犯した罪に対して有罪判決を受けることだった2。
フィリップ・R・ピッキガロによれば、これらの局地的な戦争犯罪裁判は、「各連合国の全体的な国家・外交政策の目的に適合するように作られた」4。しかし、アジアにおける連合国の司法の手続きに関する最近の研究によって、彼の研究を基礎とし、彼の発見のいくつかを修正することができるようになった5。オーストラリアの裁判に関する研究によれば、戦争犯罪裁判の手続きに関する決定には政治的利害が関与していたが、調査官や司法のメンバーの意図は公正な裁判を行うことであったという6。例えばオーストラリアは、アジア、特に近隣諸国の安定した政治状況に地政学的な関心を持っていた。オーストラリアは重要な連合国だったが、植民地支配はしていなかった。日本軍に占領されたわけでもなく、武力衝突や日本軍の捕虜となって苦しんでいる自国民の救済と回復に努めなければならなかった。加害者を裁く以外の目的で裁判を利用する動機はほとんどなかったようだ7。
東南アジアの連合国の植民地では、政治状況は異なっていた。この地域のフランス、イギリス、オランダ、そして、それほどでもなかったがアメリカの植民地帝国は、厳しい圧力にさらされ、革命の勃発、独立宣言、共産主義の影響による社会不安の形態といった新たな政治的現実に直面した8。
これを達成するための植民地支配国の手段のひとつが、戦時中の不正を清算すると同時に、政治的に望ましくない要素から社会を浄化するための法的措置であった9。したがって、敵である日本人を支持した人々は、植民地体制の反対者と見なされた。B級およびC級の戦争犯罪と共謀罪の訴追は、新たに制定された国際法に照らし合わされたとはいえ、各国の裁判所に委ねられ、現地の司法権の下に置かれた。
アジアにおける共謀罪裁判を研究することで、権力闘争の力学、特に日本がアジアを支配していた時代に強まった社会の変化に直面するために適用された戦略を明らかにすることができる。すべての植民地支配国が敵対政権との協力者を積極的に訴追したわけではないが、その政策や慣行についての議論は、裁判そのものと同様に示唆に富んでいる10。ピッキガロが主張するように、アジアにおける戦争犯罪裁判が連合国や国家の利益に資するために設立されたのであれば、協力者裁判や全般的な協力の扱いにおいても、そうでないにしても、そのことが明らかになるはずである。しかし、脱植民地化に関する既存の文献は、アジアにおける裁判と脱植民地化プロセスの相互影響にほとんど注意を払っていない11。幸いなことに、ヨーロッパにおける合作に関する出版物の増加に続いて、本書でも示されているように、アジアにおける戦時中の合作に関する学問的関心が高まっている12。
これまでのところ、オランダ領東インドにおける合作に関する体系的な研究は不足している13。広範な調査によると、1945年から1949年にかけて、オランダ領東インドでは、日本占領に関連した少なくとも312件の協力事件が臨時軍法会議に提出されている14。1947年5月以降、協力事件の裁判数は減少したが、1949年12月27日の主権移譲の数日前まで、死刑判決を含む判決が下され続けた15。インドネシアにおける協力事件に関するケーススタディは数多く出版されているが、アジアにおける協力事件に関する出版物と同様、主に特定の地域、人口集団、犯罪の種類を対象としており、政策や訴追の背景にある考え方について詳細に論じていない16。
したがって、本章では、こうした合作政策や裁判が脱植民地化戦争の影響をどの程度受けたのかを明らかにするために、検察政策の背後にある考え方を初めて探ることにする。そのために、本章は以下のように構成されている。第一に、協力者の扱いに関する植民地政府の戦争前の当初の考えを述べる。次に、刑法における法的定義と法的規定が紹介され、続いて、区別されたさまざまなタイプの共謀の概要が説明される。最後に、共謀に関する政策の変化に寄与した要因と、この変化が脱植民地化戦争にどの程度起因しうるかに注目する。
植民地設定における協力
ティモシー・ブルック(Timothy Brook)が述べているように、協力は「それが説明しようとする政治的風景に道徳的な地図を重ね合わせる」ものである18。簡単に言えば、オランダ人は程度の差こそあれ、ドイツ占領軍に協力するか、しないかのどちらかであった。インドネシアの人々は1942年から1945年にかけて日本による占領を経験しただけでなく、過去350年間におけるオランダの植民地的存在自体が占領であり、合法的か非合法的かのどちらかと見なされたのである20。
その結果、インド諸島の占領政権は、協力者に対するさまざまな認識をもたらした。第一に、オランダによる占領は、反オランダのインドネシア人の目には、貿易活動や植民地支配の期間中、自らの地位を確保し向上させるために植民地行政に協力した現地のインドネシア人エリートや中国人からなる協力者を生み出したと映った。
第二に、日本統治時代には、さまざまな理由から日本当局に協力した人々がいた。日本当局は、伝統的なエリートであるパングレ・プラジャ(「王国の支配者」)を重用し、秩序を維持し、戦争努力の目標を達成するために地元の人々を動員した。植民地政府によれば、日本当局に協力した者はすべて協力者であり、敵に味方したのだから植民地政府を裏切ったことになる。彼らは、少なくとも当初は、以下に述べるように、その行動に対して責任を負わされた。
インドネシアの庶民の目には、日本軍との協力について異なる考え方が存在した。一部の地方行政官や村長は、日本の戦争努力のために村人から搾取することで個人的な利益を得ていたが、大多数の地方支配者にとっては、忠誠心の転換は主に自己保存と王朝の安泰のためであった23。ある地域では報復行動を求める声が大きく、別の地域では戦争中に起こったことは置き去りにされた。エリートたちとは異なり、独立を達成するためにあからさまに日本軍に協力した民族主義指導者たちは、一般にインドネシア国民から真の愛国者とみなされていた24。
日本の占領後にも、また占領中にも、人々が過去に受けた過ちを清算するために、さまざまな集団が報復行動をとった。彼らは、植民地体制と密接な関係にあった現地のエリートや、日本の命令にあまりにも熱心に服従したインドネシア人や中国人に敵対した。その行動は、戦時中に耐えた苦難への復讐としてだけでなく、伝統的なエリートが古い秩序を回復するのを阻止するためでもあった。こうした社会革命は列島のいくつかの地域で起こったが、最も劇的な展開を見せたのは北スマトラと中部ジャワで、そこでは伝統的なエリートの大半が殺害された25。
同時に、特にジャワ島では、ヨーロッパ人、ユーラシア人、中国人が革命的な若者の集団、ペムダの犠牲になった26。これらの若者は日本の青年会のメンバーであり、独立したインドネシア共和国を実現し、その行政の中で自分たちの重要な役割を確保するという目標を達成する手段としての武力の行使を、旧世代のナショナリスト以上に信じていた。
植民地政府は、「敵」に対するさまざまな姿勢に対処し、国民に対する権威を回復するための政策を策定しなければならなかった。トーマス、ムーア、バトラーによれば、脱植民地化のプロセスは、「当初の枠組みが植民地における近代化、戦争、急速な社会変化という課題に対応できないことが判明したときに、協力的な取り決めを再交渉する試み」と解釈することができる28。
思想と期待
戦時協力者の訴追は、各国の刑事裁判所の手に委ねられていた。ヨーロッパとアジアにおける戦後政策を策定するために設置された連合国委員会である国際連合戦争犯罪委員会(UNWCC)は、自国民を裁くのは各国政府の責任であると勧告していた。委員会は、個々の事案に口出しすることを望まなかった。個々の事案では、状況も国内共通の司法管轄権も違いすぎるからだ。しかし、技術的には自国民が犯したものでなくても、「すべての戦争犯罪に正義が下される」ことが望まれたため、いわゆる政治的隷属者と敵に援助を提供した人々を区別することが勧告された29。
こうして地方政府は、誰が協力者とみなされ、誰がそうでないかを決定しなければならなかった。ブルックによれば、協力とは、どのように行動すべきかについての国家の道徳的規定によって決定される30。このことは、協力の定義が国や国家によって異なる可能性のある可変的なものであるだけでなく、国民の感情の変化によって修正されやすいものであることを意味している。オランダ政府は戦争前、外国に占領された場合にどのように行動すべきかを公務員に指示した文書の中で、このような道徳的処方箋を定めていた。この13ページの文書は、国家動員評議会(Staatsmobilisatieraad)によって1937年に書かれた。オランダ東インド政府は、1942年にこの文書が配布される前に、インド諸島の状況に合わせてこの指示を調整した。政府関係者の間では、公務員や民間への配布の規模が不明確であったが、少なくとも約1万部が印刷された31。
この指示書は意図的ではあったが、さまざまな解釈が可能であり、日本軍占領下で人々が直面した現実とはあまりにもかけ離れていた。訓令は、印度政府が合法的な地位にとどまり、国民と意思疎通ができることを前提としていた。軍隊のメンバーは別として、敵に対して暴力を振るったり抵抗したりすることは禁じられていた。なぜなら、それは国民だけでなく、友人や家族、仲間の民間人を厳しい報復行為にさらすことになるからである。また、「人道法に違反するような出来事が起こった場合には、責任ある機関、または下位の機関や人物に断固抗議すること」といった指示は、日本軍の占領の性格を考えれば、今にして思えばナイーブに聞こえる32。したがって、どれだけの人々が指示の存在を知っていたのか疑問に思えるだけでなく、日本軍に協力した人々の行動が指示の存在に起因していたとは考えにくい。しかし、協力者裁判の被告人の中には、日本当局の下で仕事を続けるという自分たちの行動を、できるだけ長くその地位にとどまることを要求した政府の指示に訴えることで正当化した者もいる33。
とはいえ、この文書は、協力者に対処する政策の出発点となった。日本軍の占領下、オーストラリアのオランダ領東インド亡命政府は、植民地での復権に向けて準備を進めた。解放されたオランダ領東インドにおけるオランダ民政復元のための最初の措置は、米軍の指揮下にあるオランダと南西太平洋地域との間の民政協定の中で定められた。その原則には、司法行政、共同研究の調査・起訴に関する指示も含まれていた34。H.J.ファン・ムック中将は、日本軍が降伏した直後の1945年8月15日のラジオ演説で、「同胞よりも自分の利益を優先する裏切り者にとってのみ、これ(日本の降伏)は自分たちの短絡的で偽りの栄光の崩壊を意味する」と宣言した35。
インドネシアから遠く離れたロンドンやブリスベンにいて、占領下で自由に使える情報源も限られていたため、行政官たちはジャワ島の情勢から疎外されていた。彼らは8月17日の独立宣言を反逆行為とみなし、独立運動が推進する思想がインドネシア国民の間で広く支持されるとは考えていなかった。政府は、インド諸島の政治情勢が劇的に変化したこと、国民の政治姿勢や協力に対する認識がオランダ政府の予想とはまったく異なっていたことを理解しようとしなかった37。
1945年 8月 25日、ヴァン・ムックは海外領土担当大臣に、オランダ人、中国人、インドネシア人を含むオランダ臣民が対日戦争中に示したさまざまな種類の行動に関する政策の概要を示した。ヴァン・ムックによれば、次のような人々のグループを区別する必要があるという:
- 1.自分たちの命を危険にさらして日本軍から国民の利益を守った人々。彼らは報われるだろう;
- 2.日本軍に協力する際、人民の利益を第一に考えた人々。たとえ我々と異なる政策を唱えたとしても、処罰を恐れる必要はない;
- 3.自発的に敵側を選び、積極的に戦争に参加し、敵から積極的に報いを受けた者たち。彼らも処罰されるが、指導者と共犯者は区別され、脅迫の可能性も考慮されるべきである;
- 4.財貨と引き換えに犯罪を犯した者は、そのために処罰を受けなければならない」38。
ヴァン・ムックの分類では、ある人の行動を他の人の行動と区別するのは、第一に必ずしも実際の行為ではなく、行為の背後にある意図であった。いわゆる人民の利益をないがしろにし、もっぱら故意に自分の利益を優先させた者は罰せられるべきである。ヴァン・ムックは、ルイ・マウントバッテン卿も支持したであろうこの措置の趣旨を、新聞やラジオで国民に伝えたいと考えていた39。
国民の興奮と不安は、政府の姿勢を見直させた。ジャワ島とスマトラ島を中心に、いくつかの地域で暴力的な反乱が起こり、特にユーラシア人と中国人が犠牲になった。1945年10月にジャワ島に戻った後、ヴァン・ムックとその側近たちは、自分たちの見解を再考しなければならないことを自覚した。インドネシア人の大多数がオランダの植民地支配からの脱却を望んでいるとは確信していなかったが、イデオロギー的な理由から日本軍を支持した可能性のある人々の数が多すぎて、彼らに対して法的措置を取ることができないことを行政官たちは認識していた40。スカルノを訴追する計画も断念された。スカルノがインドネシア人労働力の徴集と動員で果たした役割は、スータン・シヤリルのような何人かの著名なインドネシア人によって非難されていたにもかかわらず41。しかし、スカルノが訴追されれば、共和国側との交渉は即座に打ち切られることになる。また、特にハーグとワシントンでは、スカルノを訴追することで米国の世論が悪化し、ひいてはオランダの外交的立場が損なわれることが懸念された42。
司法
協力に対する処罰に関する考え方は、1945年 9月、刑法(Wetboek van Strafrecht)の既存の刑法に多くの条文が追加され、正式に定められた43。協力に関する最も顕著な条文は、「敵国への援助」(hulpverlening aan de vijand)の供与に関する第 124 条から第 126 条であった。第124条の「敵を支援する」のより広範な定義が、新しい規定で定められた。それは次のようなもの:
「戦時に故意に敵を支援した者、または敵との関係で国家に不利益を与えた者は、死刑または無期懲役、もしくは最高20年の刑に処する」
敵を支援する」とは、次のようなものを指す:
防衛線、物品、武器、金銭、艦隊または軍隊を敵に報告し、または敵の権力にもたらし、損害を与え、または破壊すること、軍隊の混乱、反乱または脱走を助長すること、軍事施設の地図、計画、図面または説明、または軍事的な動きや計画に関する情報を敵に提供すること、スパイとして敵に仕え、または敵のスパイを引き入れ、匿い、または助けること; 敵の宣伝の流布を奨励すること、他人を追跡、訴追、自由の剥奪若しくは制限、 敵およびその支持者によるまたは敵およびその支持者を通じて行われる刑罰または措置の対象にすること、敵に物品若しくは金銭を提供すること、敵に利する行為を行うことまたは敵に対す。る行為を妨げ、妨害し若しくは挫折させること。 “44
もう一つの重要な変更点は、いくつかの犯罪の量刑が厳しくなったことである。敵に支援やあらゆる形態の情報を提供した場合、死刑から無期懲役または20年以下の懲役に処せられるようになった45。第125条によりすでに犯罪となっている特定の犯罪を共謀した場合、実際に犯罪を犯した者と同等の刑が科されるようになった46。また、法廷での刑事手続は包囲状態に適応され、そのため「陸軍の改正司法手続」(Herziene Rechtspleging bij de Landmacht)が施行された47。この刑事手続の変更は、例えば上訴手続や死刑判決の執行に影響を及ぼした。
オランダの共謀者裁判は、いくつかの重要な点で他の連合国の裁判とは異なっていた。第一に、オランダ領東インド裁判所で裁かれた協力者は、敵国民であってはならず、オランダ国民でなければならなかった。第二に、先に述べたように、オランダ領東インドにおける合作事件は、 戦争犯罪事件と同じ裁判所である臨時軍法会議(TCM)(Temporaire Krijgsraden)49 で扱われた。重犯罪については、包囲状態が有効であったため、民間人は軍事法廷で裁かれた。
オランダ領東インド諸島は、戦争犯罪と合作事件の両方が同じ種類の裁判所で裁かれた唯一の連合国であった。TCMのメンバーは、法廷に立つために軍人の階級を与えられた民法弁護士であることが望まれた。日本軍の占領で司法関係者が犠牲になったため、有能なスタッフが不足していた。それでも、裁判所のメンバーの多くは、旧インド諸島の司法官、つまり軍人の階級を与えられた民法弁護士であり、近隣に駐屯する(予備)士官によって補完されていた52。
驚くべきことに、その説明の中で、この法令が「戦争中、占領期間中、およびそれ以後、一般に『戦時下』」に犯した犯罪に適用されることが明示されており、これには革命期も含まれている53。
しかし、1945年8月15日以降の期間もこの規定に含まれてはいたものの、政府はすべての犯罪を裁くつもりはなかった。1945年11月、政府声明が発表され、国民が同胞に深刻な危害を加えていなければ、政治的協力は処罰されないことが強調された54。こうしたメッセージは、スカルノやその支持者のように、世論の非難を恐れるインドネシア人の良心を和らげることを意図したものだった。まだ完全に権力を握っていなかった植民地政府の課題は、インドネシア国民に植民地支配の必要性を納得させることであった。政府がその権威を再確立したいのであれば、インドネシア人の支持を得なければならなかった。戦時中にオランダに忠誠を誓った人々、主に中国系インドネシア人には、食糧や生活必需品といった物質的なものだけでなく、尊敬や社会的地位の向上、新しい市民組織での地位も与える必要があった。
いわゆる政治協力者という最大のグループを激減させ、重大な政治犯罪を犯した者だけを含めるようにし、忠実な住民が植民地当局から疎遠になるのを防ぐ措置をとった。犯罪のさらなる分類が望まれたが、この問題についてはさまざまな意見があった。内政長官(BB)のC.O.ファン・デル・プラスとその顧問アブドゥルカディル・ウィジョアトモジョは、革命家による犯罪を含む過去の犯罪を処理したいと考えていた。そこで彼らは、革命時に犯罪を犯した者を含むほとんどの犯罪者に恩赦を与え、より重大な犯罪を犯させないようにすることで、日本軍の下で犯した犯罪のために彼らが直面する可能性の高い刑のために当局の手に渡らないようにすることを提案した55。
1946年2月、ヴァン・デル・プラスは、印度管理局と陸軍の著名なメンバーに恩赦を与えるという提案書を送った。N.S.ブロム司法省長官はこの提案を分析し、大筋で計画を承認した。しかし、独立が宣言された1945年8月15日以降に犯した罪も含め、すべての犯罪に恩赦を与えることでインドネシア社会が回復するのか、それとも例外を設けるべきなのかという大きな疑問が残った。どの行為が政治的な理由で行われ、どの行為がそれ以外の理由で行われたかを判断するのは難しいからである。同時に当局は、過去の犯罪が起訴されなければ、新しい社会のためにならないという意見もあった56。
結局、管理者たちは、一般的な恩赦は行き過ぎだという結論に達した。一般的な犯罪行為や1945年8月以降に植民地権威を弱体化させるために行われた行為は通常通り起訴されるべきだが、民族主義的感情から行われた犯罪は処罰されない。協力行為はより寛大に扱われることが決定された。1946年3月、政府の公式声明が新聞に掲載された:
「この国でも他の国でも、日本軍と政治的に協力しただけで起訴されることはない。[.]」
平和が回復されればどこでも、政治犯と一般犯罪を区別する必要性が生じる。インドネシアの未来は、このような平和化が政治的告発や復讐を伴ってはならないことを要求している。それは、すべての善良な市民の生命、財産、道徳を守るための正義の再確認を要求しているからである。[とはいえ、ある種の人々が凶悪な犯罪を犯したことは明らかであり、それはあらゆる階級や人種のインドネシア国民の正義感によれば、処罰に値するものである。[.]
今回の紛争後、政府は、日本占領後の動乱の時期や、「民族主義的情熱」と政治的混乱から行われた行為に関する行動規範も作成する予定である。
政府は、愛国的意図と犯罪的意図を区別する必要性、政治犯と犯罪行為を区別する必要性を確信している」57。
一方では、政府はこの文章によって、「インドネシアの未来」をアピールし、「あらゆる人種や階級」の人々の正義感を聞き入れ、協力行為の背後にある意図を調査すると述べることによって、国民をプロセスに巻き込むことで、軽微な犯罪で起訴されることはないと国民を安心させようとした。他方、政府声明は、8月15日以前とそれ以降との間に明確な線引きがなされることを示している。革命期の暴力や犯罪が罰せられないことはないだろう。
操り人形、利権屋、裏切り者
このように、戦後、法的枠組みは簡単に整えられたが、これまでのところ、どのような戦時中の行為が処罰の対象とされるかはまだ明らかではなかった。政策の策定で重要な役割を果たしたフェルダーホーフ司法長官は、政治的「援助」、経済的協力、敵国支援の3種類の協力関係を明らかにした58。政治的援助とは、純粋に政治的な目的のために敵国と協力することであり、自分の集団の政治的利益を得ることを目的とし、日本が戦争に勝つという仮定の下で望みをかなえることを意味した。フェルダーホフは、この種の協力は原則として訴追されないと明言した。ただし、現地の人々がそう感じていることが判明したり、協力者とされる人物が個人的利益のためだけに行動したという証拠がある場合は別である。敵のプロパガンダを広めることも、少なくともインドネシア人にとっては政治的行為とみなされた。例えば日本の放送局で働いていたインドネシア人は一般的に放っておかれたが、日本のラジオ放送に貢献したオランダ人ジャーナリストは重大な協力者、あるいは裏切り者とさえみなされた59。
フェルダーホフは経済協力の下で、敵に有利な、あるいは敵を支援するためのサービスの提供や資料の作成を理解していた。専門的な知識を持つ人々、多くの場合ヨーロッパ人や中国人は、戦争前の地位で仕事を続けるよう命じられたが、多くの事務所、会社、工場は日本当局に買収されていたため、現在は日本側の業務に就いていた。検事総長は、他人の犠牲の上に自分たちを著しく富ませた人々を罰することが重要だと考えたが、多くの人々が自分自身とその家族を維持する機会をつかんでいることも認識していた。
第三のカテゴリーである「敵国支援」は、主に反逆罪、個人を敵国に通報すること、憲兵隊や敵国の警察組織に入隊すること、スパイ活動を行うことから成っていた。検事総長によれば、後者の行為がすべての人、すべての集団から非難されることは自明であり、したがって、集団の意見やいわゆる正義感に照らして集団に相談する必要はなかった60。少なくとも軍事界では、国家反逆罪はあらゆる犯罪の中で最高のものと考えられている。もっと広い意味で見れば、「国家に対する罪」、つまり「国家に対する裏切り」ともいえる。
日本が降伏してからインドネシア共和国に主権が移譲されるまでの間、オランダ領東インド政府は、協力に関する政策というか政策の適用を絶えず見直していた。本章では、ごく少数の変更点のみを簡単に取り上げるが、犯罪を分類することの難しさと、政府が直面したジレンマを説明するために、いくつかの例を挙げる。政治的、いや軍事的協力の興味深い事例として、日本軍が採用したインドネシア人補助部隊、平邦がある。ヘイホーの中には、植民地時代の軍隊であるオランダ東インド王国軍(Koninklijk Nederlands-Indisch Leger、KNIL)に所属していたインドネシア人もいた。当初、インドネシア人は日本軍への自発的な協力者とみなされ、起訴されるか、少なくとも拘留される必要があった。やがて司法当局は、日本軍の徴集方法をより深く認識するようになった。そのため、司法長官はこの大規模な(元)兵士グループを訴追しないことを決定した。その代わり、オランダ東インド行政官は、元 KNIL 兵であることが多いモルッカ諸島の元ヘイホーが再び植民地軍に採用され、共和国との武力紛争に動員されることを期待した63。
政治的協力と経済的協力の両方が組み合わさった形の協力であり、ある程度は裏切りですらあるのが、地元の村長の忠誠心の移り変わりであった。前述したように、伝統的なエリートは自らの地位を維持するために、支配権力に対して日和見的な態度をとっていた。日本軍に仕えただけでなく、地元住民を犠牲にして自分たちを富ませた地方行政官は、オランダ領東インド政府から強く非難された。地域によっては、オランダ当局に対して地元住民からもそのような声が上がっていた。しかし、地元の村長が自分の行政領域で秩序を維持する能力があり、オランダに再び忠誠を誓う意思があれば、彼を起訴する措置はとられなかった64。裁量権の一部として、検察庁は、それが「一般の利益」に資する場合には起訴しないことを決定することができた。秩序を維持し、忠実な地方指導者を有力な地位に維持するという政治的利益が優先されたのである。
経済協力は、戦時中に他人を犠牲にして利益を得ることになるため、当初は卑怯な行為と考えられていたが、比較的、最も害の少ない協力行為と考えられていた。また、経済協力に関与した全員が自発的に日本の活動に身を投じていたわけではないことが次第に明らかになっていった66。多くの、主に中国人の商人や実業家は、日本当局に商品を納入するか、正当な金額を支払うことを条件に、強制的に事業を継続することを許された。中国人は家業を維持し、日本人に服従する傾向があった。67。戦後、経済エリートたちのネットワークと資本は、経済再生のための経済活動に従事することを大いに歓迎した。その結果、裁判にかけられた経済協力事件はごく少数にとどまった68。
これらの例から浮かび上がってくるのは、政策と実務の乖離、そして両者の相互作用である。裁判官と検事は、検事総長室からの要求を自由に解釈することがあった。地方検察官の観察・意見は検事総長に考慮され、検察政策のさらなる調整につながった。
アムネスティ宣言
共和党との対立の進展も捜査と裁判に影響を与えた。ベルシアップの暴力的な時期もさることながら、革命派との武力衝突は、オランダ領東インド当局が共和国側の主張する地域で捜査や裁判を行う際の妨げとなった。オランダと英国の占領地域外で犯罪の証拠を収集するために、調査官は紛争地域で命がけで捜査にあたったが、特定の占領地域でさえも常に安全だったわけではなかった69。
政策に影響を与えたもう一つの要因は世論であった。列島の各地域では、異なる住民集団間の地域的な力関係やオランダ人に対する態度が異なっており、それゆえ加害者とされる人々に対する法的措置を求める声も異なっていた。時が経つにつれて、政府は住民の間で戦争犯罪や共同裁判に対する関心が薄れていることに気づいたと主張したが、ユーラシア人や中国人の間では報復を求める声が依然として強いと主張する行政官もいた72。
何よりも、多数の容疑者の捜査と訴追に伴う実際的な困難が、さらに大きな課題となった。適格な司法関係者や、事件の捜査や裁判を行うための施設が不足していたのである。時間が経つにつれて、特に本国送還と多数の避難民のために、証拠の収集と証人の供述が難しくなった。上訴ができないことも弱点とされた73。
こうした状況は政府の関心を変え、裁判の回数を減らそうという政治的支持を強めた。1947年5月7日、印度政府は恩赦令に同意した。この法令によると、経済的・政治的協力、プロパガンダ、敵への同情の表明など、いわゆる軽微な事件は起訴されず、そうした犯罪に対する判決は免除される74。最も重い罪は訴追される。これらの罪の中には、敵の戦争努力に直接寄与する行為、他人の身体、名誉、個人の自由を侵害する行為、敵の手にある者を不当に扱う結果となる行為が含まれる。実際には、反逆罪は最も厳しい形態の協力とみなされた。特に、被告が自発的に参加し、仕事を楽しみ、深刻な虐待に加担したとされる場合、裁判所は厳しい判決を下したようである75。
しかし中総督は、「恩赦という言葉の魔力」が印度だけでなくオランダの民衆の間でも引き起こしかねない反応を警戒していた76。これは現実的かつ原則的な理由から却下されたが、恩赦の最も差し迫った理由は司法の能力不足であり、これを公表すべきではないことは認められた77。
起訴方針は時間の経過とともに寛大になったが、これは日本占領に関連する裁判が中止されたわけでも、協力が問題でなくなったわけでもない。先に述べたように、裁判は1949年の最後の日まで続いた。その間、印度当局は主権移譲前の措置を少しずつ調整し続けた。さらに、犯罪行為の疑いや有罪判決を受けた者を戦争前の地位に復帰させることが望ましいかどうかを決定するための粛清委員会では、犯罪行為や非難されるべき行為に関する議論が続けられ、あるいは新たに開始された。
結論
この章では、戦時中の協力に関するオランダ領東インド政府の考え方と政策が、1945年から1949年の間にどのように発展したかを示した。これらは脱植民地化の過程に起因しているのだろうか。一方では、日本との戦争終結以降の政治的展開の直接的または間接的な結果と思われるいくつかの変化が目立つ。オランダ東インド政府の当初の計画は、再占領地における権威の回復に重点を置いていた。協力者に関する強硬路線は放棄され、復帰した行政官が直面する新たな現実のために、協力の定義を狭めたより寛大な政策に取って代わられた。
戦時中の日本当局との協力に関する政策は、1945年8月15日以降の犯罪に対する措置とも密接に関連していた。このことは、連合国の調査団や現地の調査官・検察官に割り当てられたことでも明らかであるが、「戦時中および終戦直後の期間」に措置が適用されると言及した規定にも表れている。革命の勃発は、占領期間の悪影響をさらに増大させた。
現実的な意味では、施設や有能なスタッフの不足、共和国領土へのアクセスの制限、本国送還や多数の避難民による証人喚問の困難が、捜査に影響を及ぼした。検事総長は、どのような種類の事件を起訴するかについて検察官への指示を調整することによって、追求される犯罪の数と種類に影響を与え、それによって、他の犯罪よりも特定の種類の犯罪を優先させることができた。こうした指示は、ある程度政治的な動機に基づくものだった。特定の地域を再び支配下に置き、オランダ当局の復帰に対するインドネシア人の支持を得ることに貢献すると思われる場合、重大犯罪の訴追よりも、現地の事情や政治的利害が優先されることもあった。しかし、司法の能力の限界もまた、政策調整のインセンティブとなり、最終的に恩赦令をもたらした。
他方で、すべての変化を脱植民地化の過程に帰する場合には注意しなければならない。ある種の要因は、必ずしも脱植民地化のプロセスではなく、戦後の状況の結果であった可能性もある。例えば、ヨーロッパやアジアの他の国々では、経済協力の重要性がますます薄れていった。さらに、政治的利害が常に植民地行政官の心に重くのしかかっていた。しかし、このプロセスはおそらく、ある種の決断を強めたり、早めたりしたのであろう。
また、この章では、協力の訴追の背後にある考え方や政策に焦点を当て、協力裁判で下された判決やその理由を考慮していないことを強調しておかなければならない。また、戦後の犯罪に関する措置や裁判もこの研究には含まれていない。政府の処方や政策は裁判に影響を与えたに違いないが、これらの結論は、司法のメンバーが公平でなかったとか、裁判や結果が不公正であったということを意味するものではない。
政治家と司法は、協力者に対するすべての事件を完全に却下したわけではない。重大犯罪の加害者は依然として責任を問われ、裁判は1949年の最後の日まで続いた。協力者に対する処罰と社会の粛清は、インドネシア人の忠誠心を勝ち取ることとともに、トマスが論じたように、植民地当局と地元民との間の協力協定を再交渉する上で重要な役割を果たし、それによってインドネシア人とオランダ人との間の新たな政治関係を形成したのである。
エスター・ズウィンケルスはハーグのオランダ軍事史研究所の研究員である。ライデン大学では、オランダ領東インド諸島における第二次世界大戦後の協力・戦争犯罪事件の捜査と裁判に関する博士論文を執筆中である。著書に「『潜在的に破壊的な』対象者の収容:オランダ領東インドにおける国家社会主義運動支持者の抑留、1940-1946年」(Incarceration and Regime Change)などがある: Incarceration and Regime Change: European Prisons during the Second World War and after the Ed. Christian G. De Vito, Ralf Futselaar, and Helen Grevers (New York: Berghahn, 2016)とHet Overakker-complot. Indisch verzet tegen de Japanse bezetter op Sumatra 1942-1945 (Houten: Spectrum, 2011)がある。本研究は、オランダ科学研究機構(NWO)の研究プロジェクト「認識と報復」の一環として支援されている。第二次世界大戦後のオランダ領東インドにおける移行期正義」である。筆者は、以前の草稿にコメントを寄せてくれたペトラ・グローエンと本書の編集者に感謝したい。
ポスト占領とポストコロニアルの間: フィリピンの反逆罪恩赦論争(1948)における近過去のフレーミング
コンラート・M・ローソン
1946年にフィリピンがアメリカから独立した後の最初の2年間、マニラのアメリカ大使館は、1941年から1945年までの日本によるフィリピン占領へのフィリピン人の協力をめぐる議論に関する報告書を注意深く収集した。反逆罪の裁判はどうなっているのか?恩赦はあるのだろうか?戦時中の反逆者について、より広範な人々はどう考えていたのか?この政治家、あるいはあの政治家が訴追されること、あるいは訴追を支持することは、政治的にどのような意味を持つのだろうか?大使館の報告書には、この問題についてアメリカ人とフィリピン人の間で交わされた会話の要約や、この問題に関する新聞の切り抜きが添付されていた。反逆罪裁判はうまくいっていなかった。戦時中の主要な指導者たちが数ヶ月経ってもほとんど法廷に姿を現さないどころか、有罪判決を受けることもなく、不満が募っていた。大使館が保管していた切り抜きの中に、1948年1月28日にフィリピンのマヌエル・ロハス大統領によって一部恩赦が宣言される2週間も前に掲載されたマニラ・トリビューン紙の記事がある。社説は、政治協力者だけを対象とした恩赦は不当であると憂慮した: たとえ彼らの誠実な動機を信じたとしても、「政治協力者が誠実であると信じたから」協力したのではないのか。政治的協力は、そのオカルト的な性質や目的が何であれ、他のあらゆる種類の協力の強度と範囲に影響を与えたというのが真実である」1。
それは、戦時中の行為の正当性をめぐって政治エリートたちの間で争われた重要な瞬間であると同時に、部分的な恩赦を発行することの公正さについての鋭い考察でもあった。フィリピン人民法廷という形で戦後行われた反逆罪裁判に関する最も詳細な2つの研究は、1948年の恩赦を失敗したプロセスのクライマックスと見ている。デイヴィッド・J・スタインバーグは、恩赦に至るまでの人民法廷の歩みについて、「正当化する事情」の主張に対する法廷の「共感の高まり」を追跡している。最終的に、ロハス大統領による布告第51号という形で1948年の恩赦に至る最終段階において、手続き上の問題が各事件を支配するようになり、その結果、数ヵ月後に人民法廷は解体された2。スタインバーグと、反逆罪裁判に関するより最近の歴史家であるアウグスト・V・デ・ヴィアナは、5,603件または5,556件の人民法院事件のうち、反逆罪で有罪判決を受けたのは156件であると数えている3。しかし、ここでは、戦後早期の政治的報復における司法が、立法府の決定によって、また立法府が創設した法廷の決定によって、いかに決定されたかを示す一例について考えてみたい。
1940年代が1世紀の極端な時代をクライマックスに導いたとすれば、それは同時に報復の時代を誕生させた。世界的な規模で、しかもユニークに連動する形で、国家や地域社会というレベルでの裏切りを粛清しようとする試みと、普遍的な名において残虐行為を罰しようとする試みとが、これほど同時に組み合わされた例は世界にはなかった。マルゲリータ・ザナシは、第二次世界大戦後の「政治的グローバリゼーション」のプロセスを分析した、
マルゲリータ・ザナシは、ロブ・ウィルソンとウィマル・ディサナヤケが「ローカリゼーションの戦略」と呼ぶものを通して、中国の戦時中の対日協力に関する言説が、フランスのそれと密接に類似し、そのイメージと言語を呼び起こす方法を示した5。 「5 ザナシは、日本占領下で戦時中の隷属国家に参加し、後に指導者となった中国国民党の代表的人物の一人である陳公博が、戦時中の行動を正当化するためにヴィシー・フランスのかつての指導的人物が使用した同様の論拠を反映する「合作主義的ナショナリズム」をどのように受け入れたかを概説し、戦後の蘇州の反逆罪裁判においてフランスの事例が引き合いに出されたことで、中国の経験が世界各地の占領経験に対するより広範な反応の中に位置づけられたと論じている。
国家反逆罪に問われた人々が抱いた協調主義的ナショナリズムは、反逆者を犠牲的な殉教者として再定義し、敵を支持するふりをしながら、占領者の直接的な打撃から国家を守り、多くの場合、密かにレジスタンスを支援することで「二重のゲーム」を演じたと主張した。この協力主義的ナショナリズムの一形態は、1941年から1945年までのほぼ半世紀にわたる日本の占領による破壊から抜け出したフィリピンで見ることができる。そこでは、ホセ・P・ラウレル、クラロ・M・レクト、ホルヘ・バルガス、カミロ・オシアス、キンテン・パレデスなど、1943年10月に名目上独立したフィリピン共和国が樹立される前も後も、日本占領下のフィリピン全土で権威ある地位を受け入れた多数の政治的エリートたちによって擁護された。1945年夏に設立された人民法院制度で反逆罪を訴追しようとする試みが急速に破綻したことも少なからず手伝って、「盾」と「二重の駆け引き」のどちらの主張も大成功を収めた。現在に至るまで、それは戦時体験の支配的な物語の重要な構成要素であり続けている。
部分的な恩赦に批判的な人々への私の同情が推察されるとしても、ここで最も豊かな収穫は、ここで探求されている道徳的な問題を論じることからは得られない。それよりも、この後の課題は、一方では、極めて国内的な言説をより広範な世界的な言説と結びつけることであり、他方では、1948年の議論という時間的にローカルなものを、日本占領以降のフィリピンの歴史に関するポストコロニアルな物語のより広範な展開と結びつけることである。これらの討論は、戦後初期のフィリピンの議員たちが、第二次世界大戦後、占領から脱却した多くの国々が直面したグローバルなプロセスの一部として、報復の問題をどの程度描いていたかを明らかにしている。完全に独立したフィリピン政府から初めて選出された議員たちは、1940年代の占領後国家の多くにとって全く馴染みのある言葉でこの問題を説明することが多く、フィリピンと米国の間に見られると思われる太平洋を越えた法理上の共通点をはるかに超えていた。歴史学者ビセンテ・ラファエルが言うように、フィリピン研究を「脱フィリピン化」しようとする学問の潮流に加わり、ここで議員たちが提起した道徳的議論は、政治的報復と移行期正義に関するより広範な文献に貢献するものである。後述するように、スペイン、アメリカ、そして最終的には日本の統治下におけるフィリピンの植民地支配の経験は、その最後のものが反帝国主義的な用語で明確に宣言されたことで、戦時中に反逆者の烙印を押された人々の行為に別の解釈の枠組みを提供した、この事件にポストコロニアル的な側面を加えている。
インドの民族主義者スバス・チャンドラ・ボースからビルマのアウン・サン、オランダ領東インドのスカルノに至るまで、戦時中の他の日本との同盟国は、占領の弊害を最小限に抑えるための消極的な犠牲ではなく、むしろ積極的な選択として日本との協力を正当化した。1946年にフィリピンが植民地から、まだ大部分は米国に依存していたとはいえ独立を果たすに至ったという特殊な歴史的背景を含め、さまざまな理由から、日本の敗戦直後のフィリピンの政治的議論の大半は、このような選択を描くことはなかった。たとえ、後に伝記作家や歴史家、そして今にして思えば参加者自身の何人かが、国家建設のイニシアチブを追求するために日本の占領を戦略的に利用したことを強調したとしても7。その代わりに、戦後フィリピンの反逆罪をめぐる議論に見られるポストコロニアル的な翻訳や「現地化戦略」は、忠誠の他律的な性質をめぐる意見の相違に見られることが多い。裏切られるべき完全な独立国家が存在しなかった以上、忠誠を誓う義務はなかったのか。1941年、アメリカの植民地支配者が日本の侵略者に植民地を放棄した瞬間に、忠誠の義務は消滅したのだろうか?それとも、1946年の独立と同時に、すべての裏切り行為はきれいさっぱり消えてしまったのだろうか?これらの問題は、多かれ少なかれ微妙に議論され、政治的な地雷原となった。
–
ヨーロッパとのさらに重要な違いは、東南アジアにおける日本の征服は、しばしば著しく大規模な暴力と残虐行為によって特徴づけられるとはいえ、すでに占領されていた領土の占領であり、日本というひとつの帝国の支配が、フランス、イギリス、オランダ、アメリカといった別の帝国の支配に取って代わるものであったという現実である。日本の敗戦は歓迎されたかもしれないし、欧米の抑圧者に対するアジアの人々の解放の手段であるという日本の主張は、自国の軍隊の行動と戦争における宿命の組み合わせのおかげで、完全に信用されなくなったかもしれない。従って、日本に協力するか、欧米列強と同盟を結んで戦うかという決断は、多くの人々にとって、イデオロギー的な所属よりも戦術に基づくものであり、ビルマのアウンサン軍を含む一部の人々にとっては、時が来れば大逆転が可能な決断であった8。
この重要な違いから、戦時中の日本軍との協力の問題は、戦後初期の東南アジアではまったく異なる色合いを帯びてくると予想される。ヨーロッパ各国や中国で広範に行われた裁判や、朝鮮半島で最終的に試みられた裁判(他の占領後国家と同様の条件を受け入れた植民地支配者との協力者に対する反逆罪裁判)とは異なり、東南アジアでは、復帰したヨーロッパの大国に対する差し迫ったナショナリズムの大義に対する新たな団結がある限り、日本との協力の問題は問題にならないと予想されるかもしれない。しかし、フィリピンが近隣諸国と大きく異なるのは、アメリカの植民地時代を通じてフィリピン人が権力の座を占めていた点である。1935年にフィリピン連邦が樹立され、独立への最終的な過渡期として立法と大統領行政がほぼ自主的に行われるようになってからは、なおさらであった。アメリカはフィリピンに独立を約束し、戦時中の日本の反植民地的メッセージを受け入れる誘惑を減らすはずであったが、占領は、エリートが占領体制にほぼ完全に服従することによって特徴づけられた。日本の最も残忍な占領の一つで、日本の国旗を振り、政府の要職に就くことを選んだ人々との決別どころか、ホセ・P・ラウレル、クラロ・レクト、ベニグノ・ベニグノといった日本の占領政権の指導的人物たちは、フィリピンを占領したのである。
レクト、ベニグノ・アキノといった日本の占領政権を代表する人物は、ナショナリストの物語の中で尊敬される人物としての地位を占めており、最後の一人の孫は2010年にフィリピン大統領の地位まで上り詰めた。
フィリピン反逆罪裁判の失敗と恩赦
日本との主要な政治的協力者は、政治的にも記憶的にもすぐに更生した。ベニグノ・ラモスやアルテミオ・リカルテなど、日本占領に協力したフィリピン人の中には、戦争を生き延びることができなかった者もいた。ベニグノ・アキノのように、反逆罪裁判の結審を見届けるまで生きられなかった者もいた。ホセ・P・ラウレルを含む何人かの裁判は、恩赦が成立するまで延期された。他の多くは、アメリカの反逆罪法から受け継いだ厳格な証人2人ルールによって救われた。1944年の連邦最高裁判所の重要判決で明らかにされたように、「反逆罪に問われた被告人のすべての行為、動作、言動は、2人の証人の証言によって裏付けられなければならない」10。フィリピンでも同様に、これは戦後のフィリピンでの裁判に深刻な障害をもたらすことになる。ロレンゾ・M・タニャーダ法務長官にとって、反逆的文書への署名や反逆的命令の発令について2人の証人の証言を見つけることは、当然のことながら困難であった。圧倒的な事件量も、手続きを進める助けにはならなかった。1945年9月に英連邦法第682号によって設立された特別人民裁判所は、占領期間中のすべての改正刑法第114条違反、すなわち反逆罪を取り扱うために設置されたが、各裁判官3人のわずか5つの裁判所から成っていた。
最終的に、1948年に恩赦がなかったとしても、多くの協力者は人民法院からほとんど恐れることはなかった。人民法院は、日本統治時代に政府の役職に就いていたことは、敵に「援助と慰安」を提供する明白な行為には当たらず、敵への忠誠を示す十分な証拠にもならないとの判決を下したからである。これは、ノルウェーのように党員であることが反逆罪の十分な条件であったり、敵のための宣伝活動によって死刑判決が下されたりするヨーロッパの例とは大きく異なる。
少なくとも法律や法的判決のレベルでは、これは、例えば中国の国民党共産党支配地域や、例えば韓国における中途半端な協力処罰の試みにおいてさえ、日本への協力の対象とされた人々との著しい対照でもあった。そこでは、たとえ緩和条項が裁判官に大きな柔軟性を与えていたとしても、戦後早期の反逆罪法によって、高官たちが明確に処罰の対象とされていた。フィリピンでは、敵国への忠誠のハードルは非常に高く設定され、検察側は事実上、被告人の心に踏み込み、彼らが愛国心をまったく持っていないことを証明する必要があった。日本帝国を賛美したり、ゲリラに武器を捨てるよう呼びかけたりする言葉は、無力な操り人形の唇の動きに過ぎず、敵に売る戦争物資は、まっとうな商人の日常業務に過ぎなかった。協力者が内輪で占領軍に不利な言葉を口にしたり、利益の何割かをレジスタンスに寄付したりする限り、「見せかけの協力」–被告人と裁判官が同様に好んで使う言葉–の可能性は排除できなかった。
1948年のフィリピン大統領恩赦は、協力の問題を排除したのではなく、変質させ、封じ込めたのである。この布告によれば、人民裁判所は2年以上にわたって裁判を行ってきたが、「敵との反逆的共謀」についての最終判断には至っていなかった。最終判決とは、有罪判決に対する上訴が最高裁判所で裁かれたことを意味すると考えられるが、これは事実と異なる。ロハスの主張は、人民法院のすべての事件ではなく、冒頭で強調された「(占領)政府の地位を占め、敵と取引した者」に対する反逆罪に限定した場合にのみ意味をなす。「先の戦争」に起因する反逆罪で告発された人々に対する恩赦は、3つの基本的な理由によって正当化された。アメリカの反逆罪法から受け継いだ2人の証人というルールが訴追をほとんど不可能にしていたこと、団結が必要な時期にこの問題が国民を分裂させていたこと、そして「フィリピン国民の大多数」が、政治協力者が日本の蛮行に対する盾として強迫の下で働いていたことに気づいていたことである。しかし、恩赦は物議を醸すことになる限定的なものだった。その恩赦は、軍事協力者や敵国のために残虐行為を行った者には「国民感情は及ばない」とした。敵のスパイや密告者として自発的に行動した者、敵を幇助する目的で殺人、放火、強要、強盗、身体的傷害、その他人身や財産に対する犯罪を犯した者」は、引き続き反逆罪で訴追されることになる13。
事実上、裏切り行為を暴力行為に転化したり、敵に武器を提供したり情報を提供したりした罪を犯した者は、通常の刑事裁判においてではあるが、反逆罪の訴追が継続されることになった14。この恩赦は立法によるものではなく行政権の行使であったが、発効までにはフィリピン上院と下院の同意が必要であった。これらの議論では、このような大赦が適切かどうかだけでなく、その限られた範囲の公平性をめぐって、大統領との間に大きな意見の相違があることが明らかになった15。このような議論の中にこそ、フィリピンの立法者たちが、世界中で展開されているグローバルなプロセスという広い文脈の中で、最近の過去に対処するための自分たちの闘争をどのように捉えていたかを示す、示唆に富むヒントがある。
物語の結末から始めよう。1948年2月13日夜、多くの人々が投票に欠席したにもかかわらず、恩赦を支持する決議案は下院で50対8、上院で14対2の圧倒的多数で可決された。下院で恩赦に反対票を投じたのは、レジスタンスの退役軍人で、後にフク反乱鎮圧作戦の指導者となるラモン・マグサイサイ(Ramon Magsaysay)最終大統領だった。上院では、事務総長として国家反逆罪の訴追を指揮したロレンゾ・M・タニャーダが上院での政治活動に転じるまで反対した。日本占領下の暴力の一部についてエリートたちの責任を追及したり、少なくとも、日本軍やフィリピン警察部隊に追われ虐殺されることになる抵抗軍に参加した人たちと、指導的地位に就くという彼らの決断を対比させたりする真剣な試みを終わらせることになる同意決議が簡単に勝利したにもかかわらず、恩赦をめぐる議論では、協力や軍事協力者の暴力に関する複雑な立場が明らかになった。議会記録には100ページを超える議事録が作成され、その大部分は採決を正当化する演説であった。
下院議員の中には、原則的に恩赦に反対した者もいた。マニラの代表であり、かつて解放後初のマニラ市長だったヘルメネジルド・アティエンザは、協力者が自由の身になるばかりか、自分たちのしたことを何ら恥じていないという事実に嫌悪感を抱いた。「私は慈悲深くなれない。アティエンザは、サンチャゴ要塞で日本軍の捕虜となっていた時のことを感動的に語った。そこでは、彼の友人でゲリラの指導者だったギジェルモ・ナカルが、処刑の代わりに、かつて彼のゲリラが活動していたルソン島東部のイサベラ州知事の地位を受け入れれば、命は助けてやると提案された。アティエンザは友人に、彼の記憶が忘れ去られることはないと約束した。「もし恩赦に賛成したら、その信頼を裏切ることになる: ネグロス東部のエンリケ・メディナも、スペイン語で演説した数少ない議員の一人であるネグロス西部のエリシオ・M・リムシアコも、ゲリラの痛ましい経験を訴え、ビサヤ地方のネグロス島における協力主義指導者の忌まわしい行為の数多くの具体例を挙げた。彼は、協力者に慈悲を提供することは、「国民の道徳的性格の基盤である愛国的熱情を消滅させる」ことになると感じていた18。
祖国のために尽くすという異なる概念
クインタン・パレデスとシャルル・ド・ゴール
戦時中、法務大臣やレジスタンスの「匪賊」の「平和化」を監督する「平和秩序委員会」のメンバーなど、多くの役職を歴任した協力主義者の「英雄」の一人が、討論会に参加した代表者の中にいた: クインティン・パレデスである。パレデスは、日本軍侵攻前の植民地時代、検事総長、司法長官、下院議長、そして1935年から1939年までの連邦開国期には米国下院の投票権を持たないフィリピン常駐委員を務めるなど、長く輝かしい経歴の持ち主だった。しかし、戦時中にパレデスについて編集された米国の協力者の短いプロフィールには、珍しく辛辣なコメントが加えられていた: 最終投票では、パレデスは「『協力』という悲劇的喜劇とでも呼ぶべきドラマ」に自ら巻き込まれたとして棄権したが、下院での長い演説では、戦時中の自分の行動を雄弁に弁護している20。
パレデスは、後の叙述でやや一般的になる、アメリカ人を追い出して自由を早め、フィリピンをアメリカへの文化的・経済的束縛から解放するのに役立つ2人の植民地支配者のうち、日本人は1人の貧しい選択肢に過ぎなかったという弁明を、ここではどこにも持ち出していない。米国に対する怒りもあるが、被告とされた多くの協力者や抵抗勢力の場合と同様に、日本の侵攻に直面して軍を撤退させたフィリピンが最も必要としていた時に、米国がフィリピンを見捨てたことに対する怒りであった。この放棄は、フィリピン国民からフィリピン連邦やそれに仕える米国政府を守り従う法的責任を剥奪するものだと言われた。言い換えれば、この重要な転換期に展開されたのは、明確な反植民地主義(対米)や代名詞主義(フィリピンの独立)ではなく、技術的な法律論であった。フィリピンの戦時中の日本との協力関係を東南アジアの他のすべての協力関係から切り離し、占領下での戦時行為をめぐるなじみのある世界的な言説の中にすんなりと位置づけたのは、協力が解放の加速に役立ったのではなく、むしろ人民を守ったという主張の中心性であった。
パレデスの主張は、この討論会で最も長い立法演説であったが、その構成においても具体的な主張においても、当時世界各地で行われていた、告発された協力者の演説や証言の多くの特徴を共有していた。残忍な占領軍との協力は、最も純粋な愛国的犠牲の表現であるということである。だからこそ、他のエリートレジスタンス指導者たちの中には、パレデスを擁護し、戦後も政府で働き続けた者もいたのだ、とパレデスは主張した。パレデスは、シャルル・ド・ゴールが1944年の内閣に、1940年のヴィシー政権樹立に貢献したジュール・ジャンヌニーを入れた理由を引用した: 「私は当時ヴィシーには行かなかったが、ヴィシーにいた多くの人たちは、自分たちは自分たちなりのやり方で祖国のために尽くしていると信じていた」21。日本軍に対して武器を取る者もいれば、占領軍と協力するという困難な仕事を選ぶ者もいたという。ドゴールは別の言い方をした: 「祖国のために尽くすことについては、さまざまな考え方があった。ドゴールがヴィシー政府内の戦時協力者に対して比較的寛大な政策をとっていたことはよく知られていたが、それでも数カ月前、戦時中の首相ピエール・ラヴァルのような政治協力者の死刑執行を妨害するようなことはせず、再審請求を拒否した23。
同時期に行われていた上院での審議で、政治協力者の代弁者となったのは、戦時中、日本軍の下で教育大臣を務め、日本のプロパガンダ目的の著名な代弁者であったカミロ・オシアスであった。彼は人民法院で反逆罪の第3,528号事件を起こし、米国下院の常駐委員を務めた。1947年に再選を果たした彼が、フィリピン国民が彼の主張を受け入れた証拠として広く引用されたのは、「私は愛国心において誰にも屈しない。ジャップの下で兵役に就いたときも、そうしたのは国民に奉仕することが私の義務だと思ったからだ」と宣言したからである。 「24もちろん、オシアスとパレデスは、ゲリラを追い詰めたり、ゲリラの容疑者を日本軍に突き止めたりした指揮系統の下層部の人々が、「自分なりのやり方で」祖国のために尽くしたいという同じ思いを共有していたかもしれないかどうかについては、言及を避けた。他方、パレデスは、自分と、紛争末期の最も暴力的な軍事協力の系統に密接に関係する、ベニグノ・ラモスやアルテミオ・リカルテのような、よりあからさまな反植民地的協力主義者を区別せず、彼らはともに「真の愛国者」と呼び、日本軍とともに帰還したアメリカ人やゲリラと戦った最も熱狂的な補助隊を率いていた。
ゲリラに関しては、パレデスはいくらか同情的だったが、戦時中にゲリラに大義を放棄するよう訴えたことを正当化した。ビセンテ・ラファエルは、占領中、エリート協力者たちが「看板の意味を逆転させた」と指摘している: しかし、パレデスは戦後間もない時期に、戦時中の自らの「平和化」演説を、当時のゲリラに対する本当のメッセージは「トリウンフォ・カードを手にするまでは行動してはならない」というものであったと主張することで、再構成している25。「25言い換えれば、パレデスは、レジスタンスとヴィシー政権との間に「剣と盾」の関係があったことを指摘したがるフランスの同僚たちとは多少異なっていた。フランスでは、レジスタンスはドイツ軍に対抗する剣であり、ヴィシー政権はドイツ軍の残虐行為に対抗する盾であった。パレデスが戦時中に田舎の敵対勢力に伝えたことは、勝利が目前に迫るまで剣を捨てよということであった。
「文明的正義が合理的に要求するもの」
最終的な投票がどうであれ、経済的・政治的協力者に対する部分的な恩赦だけでなく、戦時中の反逆罪すべてに対する完全かつ普遍的な恩赦に賛成する声も多く上がった。ここでもまた、彼らの主張は異なる基本原則に起因していた。ルソン島北西端のイロコスノルテ州を代表するダマソ・サモンテ(Damaso T. Samonte)は、恩赦という考えそのものを「壊疽した傷口に絆創膏を貼る」ようなものであり、「非常に強力で病原性の強いウイルスから国家の傷口を浄化する」ことはできないと考えた26。戦後、この問題に直面したのはフィリピンだけではなかったが、他の同盟国は、ロハス大統領が示したような「キリスト教的慈愛の病的な感傷と、団結という誤った概念」を示さなかった。彼はこう続けた:
クイスリングは今どこにいるのか?フランスのラバルは悪名高い永遠の眠りについた。ノルウェーのヴィドクン・クイスリング、チェコスロバキアのヨゼフ・ティソとカール・ヘルマン・フランク、オランダの総統アントン・ムサート、ベルギーのレオン・マリア・ジョセフ・イグナス・デ・グレル、その他多くの人々は、文明化された正義が合理的に要求する儀式を除いては、さしたる儀式もなく、長い間清算されてきた27。
しかし、もし恩赦が避けられないのであれば、それはすべての人に適用されるべきであるとサモンテは主張した。「指の男も引き金の男と同罪だ」それどころか、どちらかといえば、政治的協力者こそもっと罰せられるべきだ。”彼の騒動は卸売りだ。彼はその背信行為の広い範囲に市民全体を包含している」28。
マニラ東部リサールの代表で、1960年に国連フィリピン代表だったときにクルシチョフの靴叩き事件を引き起こしたことで後に世界的に知られるようになったロレンゾ・スムロンも、「与えられる慈悲は、占領下の頭脳と売り買いの大物だけに与えられる」のであって、「無知で単純思考の信心深いフィリピン人」には与えられないと知って心を痛めていた。 「29 討論で繰り返し指摘されたように、恩赦の対象となった反逆罪は全体のわずか15%ほどであった。トリビオ・ペレス下院議員の集計によれば、恩赦の対象となったのは、政治的協力が472件、経済的協力が355件、文化的協力が100件であった。しかし、今回議論されている恩赦の対象外となったのは、スパイ活動、敵国の諜報員、スパイ、情報提供者に関する2,677件と、マカピリとして知られる悪名高い補助組織である憲兵局や警察、関連組織のメンバーであった軍事協力者に関する2,925件であった30。
現在の協力問題と、米国やスペインの植民地支配下における同様の道徳的課題との間のあからさまな比較は、討論の演説では比較的まれであった。そのような言及のひとつは、告発された協力者やその支持者からではなく、エリートの協力に対す。る部分的な恩赦を深く批判したスムロンからのものであった。ゲッペルスは、たとえ一度も戦場に出なかったとしても、普通の兵士よりも「怪物的で手ごわい」存在ではなかったのか?サムロンは、著名人が「不本意な道具」であったという事実を喜んで受け入れたが、彼らは「野原で武器を取る普通の兵士よりも大きく、致命的な敵」ではなかったのか31。マテオ・M・ノナトが、多くのフィリピン人を死に至らしめた直接の原因である情報提供者やスパイとして働いた「絞首刑になるべきろくでなし」たちに、どうして完全な恩赦を求めることができるのかと質問したとき、サムロンは、フィリピン人がフィリピン・アメリカ戦争中に互いに殺し合い、情報提供者として働いたが、米国はその余波を赦し、忘れることを厭わなかったことを、集会で思い起こさせた。「占領中におそらく誤解されたであろう同胞たちに対して、なぜわが国政府がもっと厳しく、厳格でなければならないのか? 「32 スムロンが米比戦争に言及したのは、日本の後援のもとで最後の大義と戦うことになった、最近亡くなったアルテミオ・リカルテの努力を含む、その前の時代の反植民地的な努力を称賛するためではなく、むしろ、植民地支配国自身が拷問や残忍な反乱作戦の罪を犯した苦い戦争の後における、米国の無差別的な寛大さを見習うことを提案するためであった。
日米の二重占領下でフィリピン人が直面した異常な困難への言及は、サモンテの演説の中にも見られる。彼は先の反植民地戦争を直接引き合いに出すことはないが、忠誠心の迷路を進むのは容易ではなかったことを議会に思い起こさせている:
フィリピン人の魂は、この悲惨な現状から読み取ることが許されるなら、ひどく悩まされた魂である。フィリピンの魂は、この悲惨な状況から読み取ることが許されるなら、ひどく苦しんでいる。混乱し、当惑している。まるで懺悔の沐浴の苦しみを味わっているかのように、痙攣的なゆがみや歪みに苦しんでいる33。
しかし全体として、サモンテ、スムロン、そしてタパシオ・ヌエノなど他の何人かの代表にとって、部分的恩赦の最も厄介な側面は、それが事実上階級によって差別された社会的不公正の明らかな事例であるということだった。ルソン島南東部ビコール地方のカマリネス・ノルテ州を代表するエスメラルド・エコも同じ理由で憤慨した。「最も嘆かわしい事実は、占領中に重要な地位にあった者たち、降下兵に命令を下したフィリピン憲兵隊の幹部たち……おそらく、わが国民のあらゆる悲惨と苦しみの責任を負っていた者たちが、この恩赦によって恩恵を受ける唯一の人間であるということだ」彼は、一般的な恩赦にも、部分的な恩赦にも反対ではなかったが、「恩赦を与えるなら、繰り返すが、上からではなく、どん底から始めなければならない」34。マニラの北に位置するブラカン州を代表するアレホ・S・サントスは、エコが、血で手を染めた者たちをまず自由の身にすることをどうして提案できるのか、と抗議した。1945年12月、フィリピンを拠点とするアメリカの軍事法廷で山下奉文大将が起訴され、処刑されたことで、比較的新しい法原則が初めてメジャーデビューしたのだ。サントスはこれに反対し、フィリピンで戦争犯罪で訴追された日本兵が自国の裁判ではほとんど通用しなかった「命令に従っただけ」という抗弁の驚くべき逆バージョンを採用した35。残虐行為を行った兵士には罪があるが、サントスは、自ら自由に行動できなかった指揮官には指揮責任はあり得ないと主張した。
上院では、ロレンゾ・M・タニャーダが、反逆罪を訴追した経験から、「貧しく無知な者」を獄中に放置する「差別的で不当で曖昧な」部分恩赦を非難した。さらに、恩赦による例外の弱点のひとつをすでに予見していた。タニャーダは、強姦行為で反逆罪に問われた者が釈放されるのに、強盗行為で反逆罪に問われた者が釈放されないのはおかしいと主張した36。
部分的恩赦に反対するこれらの人々は、敵のために行われた拷問、殺人、その他の暴力行為、あるいは情報提供者としての立場でそのような残虐行為を可能にした罪で告発されたのは、圧倒的に下層階級の人々であったという客観的事実に注目した。戦時ヒエラルキーの上位(直接暴力は振るわないが加担している)と下位(実際に暴力行為を行っている可能性が高い)で行われたと思われる犯罪の平等な扱いを求めるこれらの主張は、しばしば少なからず恩着せがましい言葉を含んでいた。彼らがそのような行為をするのは、貧困や無知、プロパガンダへの感受性の強さによるものだということが暗示されていた。政治協力者への恩赦を支持する人々の多くが、愛国的犠牲によってのみ動機づけられたという彼らの主張を額面通りに受け止めたのと同様に、一般的な恩赦を主張する人々のほとんどは、庶民も個人的な復讐心や貪欲さ、権力への愛から行動を起こす可能性に直面することを努めて避けた。政治協力者が無実であるのは、日本軍の残虐行為を防ぐことができなかったからだとすれば、「雑魚」あるいは「los pequeños colaboradores」と呼ばれた人々は、無知であるがゆえに、それを実行する命令を拒否することが期待できなかったからだ。
先に見たように、アレホ・S・サントスは、下層階級の軍事協力者にはそれほど同情的ではなかったし、彼らに対してより適切な立場をとっていた。サントスは戦時中のゲリラ指導者であり、将来の国防相であり、かつては共産党と、わずか2カ月後に正式に違法組織とされることになるフクバラハップ・ゲリラの代表を含む左派民主同盟から下院に選出された数少ない代議士の一人であった37。サントスは、部分的恩赦がほとんどエリートに有利であることは事実かもしれないが、これらの協力的なエリートの一部の援助がゲリラに大きな助けとなったことも同様に事実であると主張した。戦争末期にのみ活動したマカピリのような補助組織は、釈放されれば法廷を超えた厳しい裁きを受けることになる38。
サントスは、大衆はただ主導的な操り人形の命令に従うだけの従順な生き物だという主張を信じなかった。冒頭の社説の論調に真っ向から反論し、「マカピリスは、バルガス氏やラウレル博士や他の誰かの演説に反応してマカピリスになったとは決して言えない」と述べた39。 「39。しかし、サントスでさえ、国が最終的に「この協力問題を忘却の彼方へ」できるように、部分的な恩赦よりも一般的な恩赦を好んだ。おそらく彼は、軍事協力者が釈放されれば、フクスや他のゲリラ、あるいは自分たちのコミュニティのメンバーの手による清算という、別の種類の正義が待っていることを知っていたからであろう40。多くの代表が部分的な恩赦ではなく一般的な恩赦を求めたが、彼らは、行政公布に同調することを拒否し、その修正を要求することを考えたとき、憲法上の根拠が弱いことを認めた。コスメ・P・ガルシア、マルシャル・O・ラニョーラ、シメオン・G・トリビオを含む何人かの代表は、より一般的な恩赦を支持する熱弁をふるう価値があるとは考えず、投票表明の際に恩赦を支持すると表明するにとどまった。
「過去の栄光のページ」
共謀罪をめぐる議論は、スペイン、アメリカ、そして日本の占領軍に直面したフィリピンという植民地特有の苦境にあまり言及することなく進められたことは、これまで見てきたとおりである。この議論は、反逆罪の議論を世界的な文脈に位置づけるために、現代のヨーロッパの事例を利用した。恩赦を支持する人々は、エリート協力者の戦時中の行為を、民衆を守るために果敢な犠牲を払った人々の行為として描いた。フィリピンの戦時体験を、ポストコロニアルの視点から、また、もつれた忠誠心の複雑さを説明する視点から、再ブランディングする作業は、やがて起こるだろうが、独立から2年後のこのような議論において、それが支配的であったわけではない。戦後間もないこの時期には、アメリカの突然の撤退に直面した場合の忠誠の取り消しや、戦時中の占領政府に対する国民の法的義務といった、より狭い意味での法的議論が目立っていた。この議論はパレデスが演説で提起したものだが、戦時中の外務大臣クラロ・レクトの戦後の著作で最もよく展開されている41。
植民地時代の過去に関するもう一つの重要な言及は、議会記録の議論の大部分を占める英語の演説ではなく、セブ出身のビセンテ・ロガルタ下院議員のスペイン語の演説に見られる。元ジャーナリストのロガルタは、その後ナシオナリスタ党の様々な役職を歴任した。したがって、彼は過激派ではなかったが、多くのフィリピン人の最も激しい戦争の記憶を形成した、アメリカの再侵攻に直面した日本軍の絶望的で暴力的な撤退の最中ではなく、日本軍の侵攻の初期に、日本軍の残虐行為を直接目撃していた。フランシス・バートン・ハリソン元フィリピン総督の日記によると、1942年にブラカン州を訪れたロガルタは、侵略してきた日本軍にレイプされた176人の10代の少女のうち110人が死亡していることを発見した42。しかし、戦争が終わり、議会で反逆罪の議論に加わると、ロガルタは他の議員の誰もしなかったような明確な行動をとった。彼は、1896年にスペインに仕えていたフィリピン人同胞の手によってホセ・リサールが処刑されたことを議場に思い出させた。リサールの英雄的な経歴と彼の運命を語った後、ロガルタはこう締めくくった:
裏切り者として処刑されて死んだにもかかわらず、国民の心の中では、彼の記憶は最も崇高な愛国的欲望の体現として生きているという奇妙なパラドックスがそこにある」43。
これは、クインティン・パレデスが主張した「愛国的な」犠牲の議論ではなく、彼の困難な選択は命を救うために必要だったのだと主張するものだった。それは別の種類の愛国心に訴えかけるもので、スペインやアメリカに対して唱えられたフィリピン独立の大義であり、日本占領軍はそれを利用しようとしたのである。たとえフィリピンが植民地支配の終結から2年後であったとしても、一時的にフィリピンの信用を失墜させる一因となったのは、誰もが最近心に留めていたこの事件であった。ロガルタは演説の冒頭で、いわゆる盾による擁護を切り抜け、戦時中の暴力をめぐる議論を迂回し、問題の核心について考察した:
理論家たち、つまり盲目的なスコラ学主義に突き動かされ、専門用語と厳格で融通の利かない規範で反逆罪の哲学の枠組みを作ろうと主張する人たちとは対照的に、現実の世界に生きる私たちは、反逆罪を常に国家の理念との関係で理解したいと考えている。この犯罪はほとんど常に愛国的な行為であり、それを誰がどのように判断するかによって、合法とされたり、卑怯とされたりするのだ44。
すべては視点の問題だった。リサールと19世紀末のフィリピン革命を土台に、ロガルタはアメリカ独立宣言の署名者から、フィリップ・ペタン将軍、ガンジーまで、指導者がある者には愛国者、ある者には裏切り者とさまざまに見られる例として、次々と例を挙げていった。ガンジーは、大英帝国にとっては裏切り者であり、インド独立支持者にとっては反植民地的英雄ではなく、「統一インドと自由パキスタン」の支持者双方にとって裏切り者と見なされる可能性のある人物の例として用いられた45。このような悲劇的な混乱を前にして、ロガルタの演説は、「我々の政治的、社会的、経済的生活」のカリスマ的指導者、あるいは「コーディージョ」を擁護する呼びかけで締めくくられた。
エリシオ・M・リムシアコのようなスペイン語圏の議員が、恩赦反対を表明する際におなじみの言葉を使ったように、ロガルタが唱えた「長い歴史観」が、必ずしも演説の言葉と関係があったとは思えない。スペイン語は、ここで取り上げた議論では少数言語であったが、ギジェルモ・パブロのような裁判官による最高裁判所の判決を含め、スペイン系フィリピン人エリートがスペイン語を使用することによって、立法討論やその他の法的文脈の両方で英語とスムーズに混ざり合い、フィリピン社会の歴史的・民族的階層を言語的に思い起こさせる役割を果たしている。ビセンテ・ラファエルは、戦時中の協力の「言語的次元」を探求し、協力主義者の演説の「空虚さ」は、ほとんどスペイン語で会話していたエリートたちにとって英語が異質であったことに由来し、「自分の意図と言葉を分離する」ことがより容易であったことを示唆している46。これは事実であったかもしれないが、これを行き過ぎると、戦後の議論の大半を占める英語による演説の多様性を検証する歴史家の仕事を複雑なものにしてしまうだろう。英語で話すクインティン・パレデスは、1948年に戦時中の演説を擁護したとき、自分の意図と言葉とを切り離すことが同じように容易であったのだろうか。両言語を駆使して討論に臨んだティモテオ・P・リコヘルモソの言葉を、スペイン語に切り替えたときよりも英語を話したときのほうが、より疑いの目で見るべきなのだろうか?言語がどこで終わり、どこで人種が、あるいは階級と人種がどこで始まるのかを特定することもまた、難しいことかもしれない。マッカーサー軍と一緒に帰還した際、協力者と疑われる人物の報告書をまとめた米軍の対情報部隊の将校たちは、どちらかといえば、フィリピン社会のスペイン人およびスペイン系メスティーソのエリートコミュニティ出身者を、ファランゲに触発されたファシストの陰謀を企てる傾向が特に強いと見て、深く疑っていた。
ロガルタが古くからの国民的英雄を引き合いに出したのは異例だったが、彼のより広範な指摘は、より広く見られる戦略と一致している。つまり、特定の行為や、戦時中にフィリピン人全員が直面する道徳的ジレンマから、誰がいつ誰に忠誠を誓うのかという、より哲学的、少なくとも法的な問題に焦点を転じるのである。これはすでに他の例でも見たが、戦後初期の議論にはこのバリエーションが見られる。恩赦を研究するために設置された大統領委員会の一員であったパンガシナン出身の弁護士で代表のシプリアーノ・S・アラスの演説全体は、彼が投げかけた質問のひとつをタイトルにしたものであろう: 「忠誠とは何か?彼が提示した高度に専門的な答えは、1600年のイギリス、1812年のアメリカ・メイン州、エヴァ・タゴールのアメリカ反逆罪事件、アメリカ南北戦争後の恩赦と恩赦を含む歴史的な旅へと彼を誘った。彼の主な主張は「主権破棄」の理論に基づいており、これは1946年にフィリピン共和国が樹立されたことにより、反逆罪という政治法が破棄されたことを意味する48。
戦時中の被害や協力主義的な民族主義戦略の問題を完全にスキップして、英米法の伝統に根ざした彼の長い言説は、皮肉にも、この議論全体の中で最もポストコロニアル的な響きを持つ発言のひとつにつながる。
–
この恩赦への賛成票によって、ごく少数の事件に影響を及ぼしたとはいえ、半世紀にわたる共同作業に関する政治的議論は幕を閉じた50。1946年の予算では、その経費は650,000ペソ(ペソ=フィリピン・ペソ)とされ、1948年の討論会では、その年間経費は1,126,570ペソとされた。これを考慮すると、1947年の司法省全体の運営予算はわずか170万ペソであり、1947年から1948年の会計年度の政府歳入の見積もり全体は1億3,000万ペソであった51。これまで見てきたように、反逆罪事件の大半は恩赦の対象とはならず、その後は通常の刑事裁判に戻された。恩赦によって排除された事件数に比例して、提供された予算は大幅に削減されたが、それでも法律311号は、残された反逆罪の訴追費用と、それらの事件に専従する15人の特別弁護士の賃金を支払うために、37万5,000ペソを計上した。国家の「壊疽した」傷を手術する外科医を代表する機関であった人民裁判所が解体され、恩赦公布と党派や派閥を超えて広く支持された同意決議が、この問題を世間の目から遠ざけることに大いに貢献した。
大赦をめぐる1948年の議論は、その結果に大きな疑問がもたれることはなかったが、それにもかかわらず、日本の占領下でフィリピン国民が直面したジレンマについて、ありとあらゆる解釈が可能であることを目の当たりにするまたとない機会となった。完全な恩赦とは対照的に、部分的な恩赦に反対する人々は、権力を握っている人々ではなく、暴力に最も近い人々だけを罰するという階級的不公平感を訴えたが、貧しい人々の生活を個人的によく知っていると主張できる議員はごく少数だった。スムロンはせいぜい、もともと小作人だった祖父がいると主張するのが精一杯だった。おそらく最も顕著な例外はラモン・マグサイサイで、彼は商業学校の教師の息子という質素な出自であったが、後の大統領選挙で最も愛された経歴のひとつとなった。討論会でどのような立場をとったかという点では明確なパターンは見られないが、サモンテ(1901年生まれか)、スムロン(1905年生まれ)、マグサイサイ(1907年生まれ)、サントス(1911年生まれ)、エコ(1908年生まれ)など、1948年の討論会に最も積極的に参加した人たちの多くは、いずれも、サモンテ(1901年生まれか)、スムロン(1905年生まれ)、マグサイサイ(1907年生まれ)、サントス(1911年生まれ)、エコ(1908年生まれ)の出身である。1908年生)は、クインティン・パレデス(1884年生)、カミロ・オシアス(1889年生)、クラロ・レクト(1890年生)、ホセ・P・ラウレル(1891年生)など、戦時中の行いが議論のきっかけとなった政治家たちと比べると、アメリカ植民地支配の最初の十数年間に生まれた若い世代の政治家たちである。
これらの議論の最も魅力的な点のひとつは、統一性が比較的なく、明確に識別できる派閥に固執していないことである。提唱された立場は内面的にかなり多様であり、道徳的、法的、歴史的、そして、これまで見てきたように、世界的につながりのある、印象的なさまざまな論点が提示されている。レイナルド・イレトは、1997年の古典的な講義「オリエンタリズムとフィリピン政治研究」において、フィリピン人の「文化的差異を強調」し、彼らの「特殊性」を引き合いに出し、フィリピンの政治プロセスを自然に導くと考えられている基本的特徴に基づいて、フィリピン人についての説明を作成する習慣があるとして、一連のフィリピン史研究者を批判している52。もちろん、戦時中の協力関係をめぐる戦後のフィリピンにおける議論には、独自の側面が少なくないが、ここでの最も重要な欠落は、戦争前と戦中の地域的・地方的経験の重要な相違が、議員たちの立場をどのように形成したかを探ることである。これには、戦後という特殊な状況も加味しなければならない。しかし、アラスがアングロ・アメリカン特有の文脈の中で訴えた深い歴史的な法的遺産であれ、サモンテやパレデスといった対立する議員たちが行ったヨーロッパとの比較であれ、特異なものを過度に強調することは、より広範な報復政治の世界史におけるこうした豊かな議論の場を否定することになる。
コンラート・M・ローソンは、近代戦争の後遺症に幅広い関心を抱いており、その研究の大半は、1940年代のトランスウォー期の継続と変容についてである。彼の最初の著書原稿は、1945年の敗戦まで東アジアと東南アジアにおける日本の戦時占領の維持に貢献した軍と警察の協力者に対する報復における戦争犯罪と反逆罪の関係を探求している。その他、政治的報復の世界史、第二次世界大戦後のスカンジナビア初期、東アジアと東南アジアにおける脱植民地化、韓国と台湾の植民地史とポストコロニアル史、日中文化・政治関係、アジアとの、またアジア内での出会いと交流のトランスナショナル史などにも関心がある。
ぱすt
日本の医療残虐行為と科学エリートの協力: 戦後の視点
アルノー・ドグリア
本章では、1945年以降の日本における細菌・化学兵器戦争と医療残虐行為の遺産について論じる1。このような兵器は、1919年から第二次世界大戦終結までの間、日本と帝国全土で開発され、大陸で何度か、民間人と敵軍の両方に対して使用された。生きている人間の生体解剖や凍傷実験を含む数多くの医学実験も、大量破壊兵器と戦場での日本軍の生活環境を改善する手段の両方を開発する努力の一環として、東アジア全域で行われた。
このような状況の中で、「関東軍防疫水利部」という名称のもと、1932年から石井四郎少佐が率いる731部隊が設立された。この秘密部隊は、ハルピンの南24キロにある平帆村に設置された軍事キャンプを拠点とし、終戦まで、満州国と中国の傀儡国家、そして東南アジア全域で活動する細菌兵器と化学兵器のシステムの中核を担っていた2。そこで行われた実験は、(1)外科手術の実践、(2)未知の病原体の発生源の発見を目的とした免疫学実験、(3)病原体の感染力に関する免疫学実験、(4)新しい治療法の開発のための実験、(5)ワクチンや医薬品の開発のための実験、の5つに大別できる4。
しかし、これらの組織は陸軍の医師だけで構成されていたわけではない。制度化のプロセスが大きくなるにつれて、石井らは日本中の主要な大学で募集を行った。科学界は、最も優秀で有望な研究者の名前を記載したリストを提供した。例えば、1943年4月には金沢大学で「大陸における伝染病予防」と題する「日本文化講話」を行った5。1938年、京都帝国大学から8人の研究者からなる第1陣が731部隊に加わり、1939年の時点で総職員数は10,045人に達した。1945年には、そのうちの2,000人以上が民間出身者であった6。
日本の生物兵器による死傷者の正確な数を明らかにすることは、いくつかの理由から困難である。まず、すべての文書が入手できるわけではないし、おそらく今後も入手できることはないだろう。犯した犯罪の存在を証明する証拠は十分にあるが、日本軍は1945年に731部隊に関連する資料のほとんどを廃棄するよう命じたため、ソ連や中国などの手に渡ったものが歴史家の手に完全に渡ったという確証はない7。
残虐行為の性質も同様に考慮に入れなければならない。1940年から1945年の間に、731部隊に関連する建造物で行われた生体解剖や実験で、少なくとも3,000人の人間が殺された9。
しかし、1940年以前の他の収容所や中国の田舎で、日本軍の手によってどれだけの数の人間が死んだかについては、ほとんど明らかになっていない。浙江省の松山村での出来事は、文書化されていない数え切れない他の出来事の中の一例である。1943年、ペストに倒れなかった村人たちは、日本軍によって生体解剖された10。
さらに、大陸での伝染病のいくつかの事例が731部隊による細菌戦の結果であったとしても(1940年9月10日の寧波市への攻撃のような)、他の事例は証明されておらず、自然原因である可能性もある11。しかし、まじめな歴史家の間では、「3,000人を下回らない」という犠牲者数が最も問題の少ない数字であると一般に受け入れられている12。
1945年8月8日のソ連の対日参戦は、帝国生物兵器計画の終わりの始まりであった。同日、ロシア国境付近での違法行為に関するすべての証拠を隠滅するよう命令が下された。8月10日、東京は関東軍参謀総長に対し、生物兵器を使用した証拠をすべて処分し、建造物を破壊し、残りの従業員1,700人とその家族を避難させるよう命じた13。実験に使われる予定だった残りの囚人(推定400人)は処刑され、遺体は火葬された。8月16日、平帆収容所のボイラー室ですべての機密文書を焼却するよう指示が出されたが、大量の資料と死体のために、この作業は達成されなかった。ソ連軍は予定より早く8月17日に平ファンに到着し、残された文書館に入ることができた。
しかし、石井をはじめとする日本の生物兵器計画の指導者たちは、すでに8月9日に(最も重要な文書とともに)疎開し、26日に日本に到着していた。1946年1月、石井はアメリカ軍によって自宅軟禁され、2,3カ月の間に8回以上面会に訪れた14。かつて731部隊に関連するシンガポールの調査分遣隊、9420部隊の隊長であった内藤良一も自宅に拘留された。子会社で動物研究を担当する100部隊の若松勇次郎所長は復員し、本国に送還された。かつて南京で1644部隊の隊長を務めていた北野政次は上海で逮捕され、1946年1月に東京行きの米軍機に乗せられ、米情報部の尋問を受けた15。
占領当局は731部隊のエリートたちを起訴するつもりはなかった。まず、可視化して処罰できる犯罪者を探していた。東京の極東国際法廷は、ニュルンベルクで行われたのと同じ国際司法の機能を果たすことになっていた。第二に、政治指導者も軍事指導者も、正確な役割が不明確な科学界ではなく、軍閥を処罰することを望んでいた。連合国は、明らかな残虐行為に責任のある将軍や指導者を必要としていた。戦争遂行の陰謀、戦争犯罪、人道に対する罪は、「軍国主義と軍国主義的制度が(中略)日本人に災難をもたらした」という勝者が持ち出した物語を反映していた16。
日本軍が生物兵器を使用しているのではないかというアメリカの疑念は、1941年にはすでに生じていた。しかし、1945年、日本の細菌学的研究は、ワシントンの科学者の目には貴重なものと映った。それまでは、そのような兵器の開発は不可能だと考えられていたのである。
数千ページに及ぶ剖検報告書を収集するため、1947年に日本を訪れた数回にわたるミッションの最後の1回を率いた科学者、エドウィン・V・ヒルの最終報告書は、東京裁判で日本人研究者が誰一人として起訴されなかった理由を明確に説明している:
この調査で収集された証拠は、この分野のこれまでの側面を大いに補足し、増幅させた。それは、日本の科学者が何百万ドルもの資金と何年もの歳月をかけて得たデータである。ヒトがこれらの病気に罹りやすいかどうかは、バクテリアの特定の感染量によって示される。このような情報は、人体実験に対する憚りから、我々の研究所では得ることができなかった。これらのデータは、これまでに総額25万円を費やして確保したものである。
1947年5月7日、石井紘一は、「このような情報は、人体実験に慎重であったため、私たちの研究所では得られなかったものである」
1947年5月7日、石井は米国との共同研究を開始した。1947年5月7日、石井は米国との共同研究を開始した。数ヵ月後、「寺院に隠され、南日本の山中に埋もれていた」「様々なB.W.病原体によって引き起こされた200例以上のヒトの病気から得られた病理学的切片を示す8,000枚のスライド」が米国の科学者に提供された。11月22日、指令SCAPIN-1699は、石井と彼の同僚全員に完全な免責と25万円を与えた20。
ワシントンの日本科学への関心はそれだけにとどまらず、1946年、占領当局は406部隊を設置した。この組織は当初、占領下の日本の衛生状態の改善を目的としていたが、瞬く間に日本全国に拡大した。1951年には、北野政次や浅沼清といった731部隊の元メンバーを含む100人以上の日本人医師や技術者を雇用していた。
日本人科学者の参加は必然的なことであった。犯罪の有無にかかわらず、本格的な科学研究に必要な技術的ノウハウや専門知識を持っていたのは彼らだけだったからである。さらに、制度的な観点からも、406部隊の活動の一部は国立予防衛生研究所(国立予防衛生研究所、現・国立感染症研究所)に引き継がれた。1947年から1983年の間に、この研究所の所長8人のうち7人、副所長8人のうち6人が石井の元共同研究者であった21。
これらの人物が誰一人として裁判にかけられなかったという事実は、当初彼らを起訴する計画がなかったことを意味するものではないが、その計画はすぐに頓挫した。1946年8月29日、東京の極東国際法廷での南京大虐殺に関する議論の中で、デービッド・サットン準検事が南京の1644部隊の存在と民間人捕虜に対する毒血清の実験に言及した22。ウィリアム・ウェッブ裁判長は、サットンが提出できなかったさらなる証拠の提出を求め、弁護側はさらに中国人住民に対する予防接種プログラムの一環であったと主張し、この問題は取り下げられた。
アメリカ軍による証拠隠滅を記録した資料は、ほとんど滑稽:
- 1. 対象文書は1946年11月6日に中国課に請求され、一度も返却されていない。
- 2. 中国師団は、これらの文書は彼らによってフィリピン師団に引き渡されたと言っている。
- 3. フィリピン師団はD.N.サットン氏に引き渡したと主張している。
- 4. サットン氏はこの文書について何も知らなかったと主張している。
- 5. この件は貴殿のオフィスに引き渡される23。
- 1. 中国における細菌学的戦争に関するこれらの文書が、弁護団長から私に調査を依頼された後、一度は私に引き渡されたことは事実であるが、その後、これらの文書はサットン氏に引き渡され、その後、中国課に戻された。私が最後に覚えているのは、中国部のチュウ氏が、ロシアにいる2人の日本人をここで尋問できるかどうか、ロシア副検事の意見を聞くために、その文書をロシア部に持って行ったということだ24。
アメリカの隠蔽工作は細菌戦にとどまらず、化学戦にも及んでいた。アメリカにとって、両兵器は戦場で相互に依存して使用されていたため、両兵器の使用の告発は放棄され、世間の目から消されなければならなかった。このことは、細菌兵器とガス兵器の開発と使用に関する最終的な責任は、政府の最高レベルにあることを示す中国での調査報告書をアメリカの諜報機関が作成したときに、特に明らかになった。
この問題は、毒ガスのエピソードと同様に、戦場で、あるいは現場の陸軍大将の資源を利用して、そのような戦法を開発することが不可能であることが明らかであることから、重要であると想定され、そのような禁止された戦法は、現場指揮官ではなく、東京政府によって実施されていることが示された25。
しかし、極東国際裁判ではそれ以上の措置はとられなかった。報告書の著者であるトーマス・モローは1946年8月に辞職し、米国に戻った。このエピソードは、東京裁判における隠蔽工作の終わりを告げるものであり、少数の孤立した事例を除いて、日本の生物兵器に関する法的措置がそれ以上開始されることはなかった26。これらすべての要素が、科学界が戦後の医療体制を再統合することを一層容易にし、これらの人々の中には、残虐行為を行うに至らしめた「無責任な軍国主義」の犠牲者を装う者もいた27。
ソ連では、事態は異なる展開を見せた。モスクワは、1945年に戦争(と満州)に参戦して以来、731部隊のことを知っていた。ソ連当局は、平帆の公文書館にアクセスし、日本軍関係者を拘束した後、事件の立件を開始した。1946年、ソ連は主に石井に関心を持った。1947年春、アメリカの監督の下、東京でソ連代表との会談が行われたが、ほとんど成功しなかった。モスクワが提出した引き渡し要求も、明らかに成功しなかった。しかし、満州で入手した文書と捕虜となった日本人スタッフの証言は、はるかに決定的なものであった。
1949年12月25日から30日にかけて、ハバロフスク戦争犯罪裁判が、ソ連極東に位置し、中国(と日本)に近い戦略的な都市ハバロフスクで行われた。彼らは、特定の生物兵器部隊の組織、生きた人間を対象とした犯罪実験、中国に対する細菌兵器の使用、ソ連に対する細菌兵器の使用準備という4つの起訴状で告発された28。判決は1949年12月30日に下され、12人全員が有罪となり、2年から25年の懲役が言い渡された。1956年、存命で服役中の被告人全員が日本に送還された。
海外からは、ハバロフスク裁判は直ちにソ連のプロパガンダと見なされた。弁護側、検察側、裁判官、通訳はすべてソ連国民だった。同様に、モスクワは日帝の最終的な責任を主張し、例えば「ソ連は細菌戦の恐怖から人類を救った(中略)日本の侵略はソ連軍関東軍の決定的な敗北によってのみ終結した」と主張するなど、自国の行為を美化することをためらわなかった30。これは確かに、海外での裁判の影響力を失墜させる一因となった。裁判が短かったことも(特に、長大な極東国際裁判と比べた場合)助けにならなかった。同時に、この裁判はワシントンとモスクワの対立が激化する時代の到来を告げるものであり、ハバロフスクのスミルノフ検察担当国務顧問は弁明の中で、東京裁判でのデービッド・サットン次席検事の発言とその後の隠蔽工作について言及している。モスクワから見れば、ハバロフスクは、アメリカから免責特権を与えられた犯人たちに対する、ソ連が吟味した正義と理解された。
日本では、ハバロフスク裁判と医学的・生物学的残虐行為に関する言説の受容は、敗戦後すぐに明らかになったわけではなかったが、存在しないわけでもなかった。占領の最初の数年間は、総司令部(GHQ)がしっかりと支配していた。日本政府は、アメリカ側が要求した情報を提供するのに非常に時間がかかった。連合国側は、石井の名前、生年月日、自宅の住所、軍歴が書かれた一枚の紙を渡されるのを、1946年11月まで待たなければならなかった31。
しかし、1945年直後の数年間、日本人は731部隊に関する情報を積極的に提供していた。占領開始後の最初の数週間で、何百通もの糾弾の手紙がマッカーサーの机の上に届き、その中には医療残虐行為について公然と言及しているものもあった。元軍人の中には、調査のために石井のネットワークに密かに潜入することを志願する者さえいた32。正義が果たされることへの日本人の期待は、特に共産主義者側から高かった。1945年12月14日、連合国によって公式に復活させられてから2週間後、日本共産党は米国当局に、生物兵器と医療犯罪を担当するネットワークの存在を通告した。当初、これらの宣言は、生物兵器プログラムのエリートを探すアメリカの捜査に役立つものであった。
しかし、共産主義者の熱意によって情報が漏れ始めた。1946年1月、『ニューヨーク・タイムズ』紙と『太平洋の星条旗』紙が、日本の生物兵器プログラムの存在を明らかにした。
戦争残虐行為(特に医療犯罪)の隠蔽は、戦後間もない時期には成功した。日本の日刊紙は、共産党の代弁者である赤旗を除いて、この話題に触れることはほとんどなかった。1945年12月から1946年夏まで、同紙は「戦争犯罪人を断固追及しよう」と題するコラムを定期的に掲載し、全国の目撃者候補に協力を求めた。12月から3月にかけて、ヒロヒトの戦争犯罪を告発する記事が一面を飾った36。
しかし、1946年5月3日に極東国際法廷が開かれると、新聞に証言が定期的に掲載されるようになった。匿名の手紙には、犯した犯罪の詳細が書かれ、皇室の関与に至るまで、犯人の名前が明らかにされた37。
[戦時中、陸軍軍医であった石井四郎元中将は、ハルビン郊外に大規模な人体実験場を設置し、多くの連合軍兵士に対して残虐な実験を行った。[戦争犯罪容疑者リストに名前が載ることは避けられなかったが、最近は賄賂を使ってその結果から逃れている。[私自身は)連合国本部の権威を尊重する平和的な日本人であり、裁判の進捗状況を公表するよう要請する[…]」38。
日本国民から犯した犯罪を隠そうとする政権にとって、これらの自白は恥ずべきものであったが、ワシントンから派遣された人々にとっては貴重なものであり、1947年の前述のエドウィン・V・ヒルの報告書に結実した。
ハバロフスク戦争犯罪裁判の議事録は、1950年にモスクワから英語、フランス語、中国語、日本語で出版されたが、広く受け入れられることはなかった。当時の日本に与えた影響を正確に推し量ることは難しい。この議事録は、共産党が戦犯狩りを立証するために持ち込んだ可能性が高い。それにもかかわらず、ハバロフスクの結果が世界的に、より具体的には日本で比較的注目されなかったことを示す要因が2つある39。GHQが日本側に提示した取引を秘密裏に進めたいのであれば、生物兵器について公の場で議論する選択肢はなかった。
第二に、冷戦の高まりの中で、アメリカ当局は、裁判の結果が国際的に、特に日本におけるソ連のイメージを悪くすることを恐れていた。そこでGHQは、この裁判をソ連のプロパガンダと決めつけるだけでなく、当時ワシントンが約37万6千人と見積もっていたソ連国内の日本人戦争捕虜の状況など、より差し迫った問題を隠すためのモスクワの戦略であるかのように描くことで、この裁判の信用をさらに失墜させることにした。アメリカは、日本のメディアの助けを借りて、その試みにはたいてい成功した。例えば、1949年11月22日、東京のソビエト大使館前に大群衆が集まり、シベリアの戦争捕虜の状況について回答を求めた。最後の一撃は、その数日後に報道で伝えられた:
ダグラス・マッカーサー元帥の司令部のスポークスマンは今日、同司令部の化学課がファイルを「完全に」調査した結果、「日本の細菌戦の使用に関連するものは何も見つからなかった」と述べた40。
日本のマスコミは裁判の開始に一時的に注目した。12月27日付の『読売新聞』は、ハバロフスクで裁判が始まったことを伝えるソ連のプレスリリースを一面に掲載し、「犠牲者は3000人」と報じた。
しかし、GHQが打ち出した公式シナリオは功を奏した。翌日、ハバロフスクはパリからのプレスリリースという形で、紙面の最下部に追いやられた。その翌日、ハバロフスクは、パリからのプレスリリースという形で、紙面の最下部に追いやられた。その後の記事は一面を飾ることはなく、日本人捕虜や連合軍の占領に関するニュースが添えられた。他の新聞も同じパターンだった。裁判の期間中、朝日新聞と毎日新聞は定期的にプレスリリースを発表し、その後にアメリカ側が全面的に否定するコミュニケを出すという体制だった。1950年1月1日までに、この話題はメディアから消えた。
予想通り、1950年2月までハバロフスクのことを一面トップで取り上げていたのは赤旗だけだった。石井の名前とともに、被告人の名前と犯行の詳細が頻繁に掲載された。これによって読者は、ソ連での審理をほぼリアルタイムで追うことができ、「被告人一人一人の心の奥底にある悔悟の念」(『郭彦九郎からの手紙』)と「ソ連による待遇への感謝」(『総同盟の手紙』)を認めることができた42。
この話題に関する記事は2月下旬まで掲載され続けた。2月20日には、新潟県に731部隊の支部があることと共に、石井と学界の同僚とのつながりが暴露された43。1950年6月、GHQによるレッド・パージによって、『赤旗』は廃刊となり、それに代わる新聞も発行されなくなった。戦後すぐの時期、共産党は日本国民の大多数を代表しておらず、アメリカの指導の下で提供される情報に満足しているようだった。しかし、敗戦後の最初の5年間に赤旗などが掲載した記事の数は、医療残虐行為の記憶という話題がすでに日本社会に紹介されていたことを示している。
731部隊の「未検挙」犯罪は、メディアや時には政治の世界でも、日本共産党の趣味のネタになっていた。1950年3月1日、ある共産党員は国会でこう発言した:
細菌兵器に関連した戦争犯罪の問題を取り上げたい。主に法務省に関することだが、外務省にも問い合わせが来ているので、答えてもらいたい。この問題は、ハバロフスク戦犯裁判 […]で提起され、関東軍 […]が中国人とソ連人を対象に実験を行ったという証拠が示された。
中国人とソ連人、そしてアメリカ人捕虜に実験を行ったことが証明された。その際、数千人が人間のモルモットとして使われた。さらに、この兵器庫の一部は中国でも使われていたようだ。[私たちは、政府がこの問題についてさらなる情報を持っているかどうか知りたい44。
議長はこう答えた:
あなたが提起している問題の詳細については承知していない。しかし、これは法的な問題であり、日本軍の行動に関する戦争犯罪の裁判は、ポツダム宣言の計画に従って連合国によって実施されたことは言える。したがって、あなたが現在提起している細菌学的戦争犯罪の問題は、政府の権限には含まれないと思われる45。
数カ月後、この国会議員はレッド・パージによって政界から追放された。検閲とハバロフスク裁判の知名度の低さにもかかわらず、これらの出来事は、731部隊が今後数十年の間に徐々に公の場で議論されるようになる過程の始まりとなった。
1960年代から70年代にかけての日本における戦争犯罪とその責任に関する一般的な議論の中で、帝国陸軍が行った生物学的・医学的残虐行為は特別な地位を占めることはなかった。共産主義者の介入は別として、このような犯罪は一般的に公に取り上げられることはなかった。最後に引用した、勝者によって正義が行われたという考え方は、一般的に受け入れられていた。とはいえ、連合国側による「無責任な軍国主義」というシナリオ以外にも、戦争残虐行為、より具体的には731部隊に関する議論が行われなかったのには理由があった。
第一に、大多数の日本人は、生物兵器という非常に専門的な概念について知らなかった。このような視点は、一般メディアでは特に顕著である。広島と長崎の後、冷戦の緊張が高まる中、現代科学の発見が兵器の製造に使われるという話題が定期的にニュースになった。核戦争は人々の最大の関心事であったが、2度にわたって生物兵器の話題が読者に紹介された。
年、『世界報国』に「細菌兵器は恐るべきものである」と題する記事が掲載された。日米両政府の責任は論じられなかった。むしろ、これらの兵器は広島や長崎で起こったことよりもはるかに危険な脅威として提示され、それによって戦争の被害者としての国民を慰めた: 「一回の攻撃で2億人を殺すには、1オンスで十分だった」しかし、生物兵器の開発は日本にとっても有益なものとして描かれていた。「ローズベリー博士」は、そのような手段は現在アメリカ海軍によって研究されており、敵に対して使用できる可能性があると説明した。第三次世界大戦が勃発すれば、核兵器に取って代わるだろう。46 1952年、別の出版物が国民の一般的な無知を裏付けた。化学兵器は第一次世界大戦中には使用されたが、第二次世界大戦中には「ほとんど」使用されなかった。細菌兵器の使用は、国際条約(1899年のハーグ条約、1925年のジュネーブ条約)で禁止されているだけでなく、科学者が細菌兵器を製造するのに十分な知識を持っていなかったため、想定すらされていなかった。細菌戦は、単に「可能性」として説明されていた47。
第二に、日本の敗戦を生き延びた人的ネットワークについて考える必要がある。発明し、製造し、実験を行った科学者、医師、技術者はまだ生きており、帰国していた。彼らは科学者コミュニティに再び溶け込み、戦時中(および戦争前)に築いたつながりは非常に生きていた。1950年、9420部隊の内藤良一前隊長は、宮本幸一と二木秀雄という2人の同僚と日本初の血液バンクを設立した。前者は、日本の生物学的計画に秘密裏に機器を供給していた日本企業のハルビン所長であり、後者は陸軍医師で、731部隊に勤務していた。
敗戦の悲惨な結末を前にして、これらの人々の技術的ノウハウは日本の復興努力に不可欠なものと見なされた。国立予防衛生研究所や、公衆衛生のインフラストラクチャーと科学の進歩に専念する同様の機関が設立されたことが、それを証明している。
従って、科学者の大多数は、残虐行為が行われたことを完全に認識していた。これらの犯罪は、自分自身、同僚、学生、あるいは指導者によって行われたものであり、戦後、731部隊との関係や実験の詳細について公然と言及し、研究結果を自由に発表した者もいた。北野は1963年に『日本医事新報』誌に発表した論文で、戦時中の満州での研究結果を、同僚や特定の部隊の存在を直接名指しして回覧している50。このようなネットワークの広がりは、彼らが監視の目にさらされることがないほどであった。1980年代に歴史家たちが、すでに亡くなっていない元戦犯たちを公に暴露し始めるまで、一般の人々はこうした技術論文の詳細について理解することも関心を持つこともなかった。
第三に、自らの犯罪を公に認めようとする人々は、嘘つき呼ばわりされ、軽蔑の目で扱われた。1956年夏、1,017人の日本人戦争捕虜が帰国した。彼らは中国共産党の監獄に収容されていたが、彼らが受けた「人道的」な扱いに押され、彼らの一部は自分たちが行った残虐行為の責任を取るようになった。1年後、これらの退役軍人の一部は、懺悔を求める会を結成し、『The Three All』を出版した: 初版5万部は3週間で完売した。しかし、残虐行為の生々しい描写が引き起こしたセンセーションは、まだ公に過去を直視する準備ができていなかった社会に不信感を抱かせた。編集者は右翼団体や退役軍人からの圧力と脅迫に屈し、この本の出版を取りやめた52。
日本帝国陸軍の元隊員が記録を正そうとするすべての試みは、定期的に不信にさらされ、米国に味方することで大陸で行われた犯罪を忘れてしまった社会の中でズレた存在である彼らは、「洗脳された共産主義者」というレッテルを貼られた。1970年代に共産中国との関係が正常化するまで、日本における第二次世界大戦は、かつてのアングロサクソンの敵国との関係を中心とした英雄的行為としてしか記憶されなかった53。
戦後間もない日本でこの話題が表面化したのは、文学を通じてのみであった。初期の作品は偽名を使って出版された。主人公の名前は変えられ、小説にはフィクションの要素が含まれることもあった。皮肉なことに、これらの出版物は一般大衆にはセンセーショナルに映ったが、「フィクション」と銘打たれていたために、その場の物語との対立は避けられた。『三つのすべて』(日本人の中国における戦争犯罪の告白)とは異なり、戦時中の医療残虐行為の証言は、文学的な記述に変換され、誰もが入手可能な書籍や雑誌で読むことができた54。
そして、これらの出版物は歴史学者である家永三郎の関心を引き、彼は自身の歴史教科書で731部隊やその他の戦争残虐行為について明確に言及した。並行して、残虐行為の噂の高まりに興味を持ったジャーナリストたちは、その調査結果をノンフィクション作品として発表したり、退役軍人のインタビューを盛り込んだドキュメンタリー番組をテレビ放映したりした56。
これらの文書は、日本社会における退役軍人の反応をさらに促した。中には著者を脅迫する者もいたが、証言を提供する者も増え、国内外のジャーナリストによる国際的な協力関係が生まれた。朝鮮戦争中にワシントンが細菌戦を使用したと告発したアメリカ人記者ジョン・パウエルは、吉永晴子と協力して2万ページを超える機密文書を収集した57。1980年代までに、常石敬一などの歴史家たちが論争に加わり、731部隊の存在を証明する文書を発掘した。1990年代半ばには、正義と補償を求め、日本国家を相手取った長期の訴訟が(個人または中国人と日本人の団体によって)起こされた58。
本章の目的は、731部隊に関する連合国の戦争犯罪裁判が行われなかった理由と背景を提示することである。医療残虐行為と生物戦の記憶は、戦後の日本社会ではなかなか表面化しなかった。法的な観点からは、この問題は最初から病的なものであった。この問題はアメリカによって葬り去られ、ソ連は限られた影響しか与えず、中国人被害者の存在はまだ認められていなかった59。暗黙の相互合意によって、医学と技術の権威は、残虐行為に言及した研究からは目を背けていた。社会的な観点からは、退役軍人の告白の信憑性は、あまりにも辛く現実的であったため、信用されることはなく、共産主義者のコミットメントはプロパガンダとして否定された。
731部隊は、戦後数十年を通じて日本で最も差し迫った問題ではなかった。とはいえ、連合国の正義が存在しなかったからといって、この問題が完全に回避されたわけではなかった。むしろ、それが植民地暴力のもう一つの事例として認識されるようになるまで、非常に多様な集団によって語られ、時とともに強弱を変えるだけの、継続的な物語であり続けたのである。
実際、日本は植民地戦争で初めてガス戦を使用した。1930年10月に台湾で起きた霧社事件の余波で、帝国陸軍はセディック族の反乱を鎮圧するためにホスゲン、イペリット、シアン化水素を空中投下し、700人以上を殺害した。1932年、東京は、これは植民地の反乱であり、厳密には日本の主権の下にあるとして、 ある種のガスの使用を正当化した60。同年、関東軍は、「内務警察」の名目で、満州国において催涙ガスを公式に使用する権利を東京から得た61。
細菌戦についても同様である。このような兵器は、1939年のソ連軍とのノモンハン戦争で初めて配備され、その1年後には、特に浙江省で共産ゲリラを鎮圧するために、井戸の汚染やチフスやコレラの蔓延を伴う大規模な作戦が1942年まで続いた。これらの「研究」プログラムは、軍隊にこれらの新兵器を装備させるために設立され、生体解剖やその他の実験は、戦場での帝国軍の生存率を向上させるために、日本人以外の人間に対して行われた。
しかし、日本の医学的・生物学的残虐行為もまた、帝国の暴力というプリズムの外側で考える必要がある。731部隊の制度化につながった実験のほとんどは、国から与えられた機会を利用して、研究室の理論的枠組みの外で大規模な実験を行った人々によって行われた。1925年から1945年の間に、日本全国、台湾(1928)、朝鮮(1930)で合計百回以上、合計41回もの化学兵器の実験が行われた。1930年に台湾でガス戦を展開するよう命じたのは、東京の参謀本部からではなく、植民地の陸軍研究中央研究所からであった62。
同様に、ノモンハンでは、細菌学的薬剤の使用は何よりも大規模な試験であった。日本の科学者は、彼らが散布した腸チフス菌が水に入れると感染力を失うことを知っていた。ソ連軍との戦争が関東軍にとって軍事的大失敗であったにもかかわらず、1945年8月の大打撃を発表し、理論的結論と実験室での結論が屋外での実験結果と一致したため、この作戦は「成功」のレッテルを貼られた。ある程度までは、中国の民間人に投下された生物兵器(1940~1942)も、大規模な実地試験に相当する。
結局のところ、科学界の責任は、そのスポンサーである国家の責任と同様に重要であり、相互依存の関係にある。このことは、731部隊の「脱植民地化」プロセスにも同様に当てはまる。日本軍は犠牲者の遺体を処理したが、それ以外のプロセスは不完全だった。ソ連は適時に破棄できなかった文書を入手しただけでなく、建造物も存続していた。ソ連国境付近の収容所は、日本軍によって部分的にしかダイナマイトで破壊されず、その後証拠となった。中国とシンガポールの都市部で他の部隊が占拠した建物は、戦後病院になった。先に述べたように、訴追は最小限にとどまった。科学者のネットワークは解体されることなく、単に日本に逆送された。このように、戦後、日本の生物兵器プログラムの解体は、もし行われたとしても、他の列強に委ねられたのである。
日本の戦争残虐行為の真実は、長い間立証されてきた。しかし、この話題のなぜとなぜは、他の判断に照らして今日でも検討される必要がある。これらの犯罪を過去に追いやられた既成事実として解釈することは、日本帝国の解体過程が持つ多様な意味を把握することを妨げる。
アルノー・ドグリアは現在、スイスのジュネーブ大学東アジア研究学科の博士研究員である。現代日本と東アジアに関心を持つ。ジュネーブ大学で修士号(東アジア研究)と博士号(日本研究)を取得。ピーター・ラング社から出版された彼の最初の著書のタイトルは『Japanese Biological Warfare, 1880-2011』: Historical Realities and the Anatomy of Memory』(2016)である。現在の研究テーマは『Japanese Medical Atrocities』: Narratives of Reconversion of Former War Criminals in Postwar Japan)では、1945年までに医学実験に参加した科学者や医師のネットワークを詳細に分析し、彼らのプロフィール、再転向、責任について等しく論じている。その他、日本における生命倫理の誕生、東アジアにおける日本の戦争犯罪とその記憶、第二次世界大戦と冷戦の残虐行為、連合国占領期と戦後日本の社会史と大衆文化など、興味深いトピックが含まれている。本章は、スイス国立科学財団の助成によるプロジェクト100011_169861(Le Japon et l’Asie de l’Est face à la Seconde Guerre mondiale)の一環として出版された。
加担の問題: 戦争犯罪と戦争責任に対する日本の初期の姿勢
第二次世界大戦後の日本の戦争犯罪と戦争責任に対する初期の姿勢
バラク・クシュナー
現在、英国にはヘニング・ウェーンという人気コメディアンがいる。彼は自らを「ドイツのお笑い大使」と称し、皮肉交じりに大笑いしている。イギリス人の自己嫌悪を見事にあざけるとともに、ウェーンはまずイギリスの住宅市場を批評するが、それを第二次世界大戦(WWII)と結びつける: 「つまり、イギリス人は、なぜみんな家の所有者になりたがるのか。つまり、あなた方イギリス人は、なぜみんな家に所有されたがるのか。そして、ロンドンと英国全般の住宅市場の水準の低さを非難する。「基本的に手に入るのは、カビの生えた壁紙で固定された3000個の古いレンガだけで、それには莫大な費用がかかる。ドイツで第二次世界大戦に負けたのは喜ばしいことだ。ドイツは第二次世界大戦に負けたが、私たちの都市はすべて破壊され、戦後はきちんと再建された。[もしそうでなかったら、私たちはあなたたちのようなボロ屋に住んでいたでしょう」とイギリスの聴衆を指差して締めくくり、さらに笑いを誘った。それで、アル・マレーは舞台上でイギリスの司会者に向かって、「今、戦争に勝ったのは誰だ?」と言った。(またもや大爆笑の中、短いオープニング・ギャンブットを終える)1。
このルーティン、そしてそれ以上に重要なのは、第二次世界大戦に対するイギリスの歴史観にツッコミを入れるウェーンの手腕である。イギリスの観客はこれが大好きだ。イギリスの住宅が規格外で値段が高いというのは、少し真実味がある。しかし、舞台に向かって物を投げつける観客はいないし、ウェーンが殺害予告を受けることもない。なぜイギリス人は、第二次世界大戦での勝利と戦後の経済的損失に関する彼の皮肉を受け入れることができるのだろうか。一方、同じような冗談を中国で日本のコメディアンが言うことは、危険でないにしても不可能だろう。それはイギリスが第二次世界大戦で勝利したからなのか、それとも文化的に風刺に寛容だからなのだろうか?中国も理論的には、日本を破った戦勝連合国の一員だった。確かに、英国は侵略されたことはなく、中国本土で起きたような南京大虐殺も経験しなかったが、英国はヨーロッパで非常に残酷な戦争を戦い、ナチスは英国の都市部を継続的に爆撃し、ロンドンはその攻撃の矢面に立たされた。読者の中には、この質問を投げかけることすら不条理、あるいはナイーブすぎると感じる人もいるかもしれない。確かに、ヘニングは、国家が定義する「正しい」歴史記憶に反する小冊子の出版を法律で禁じているフランスでこのジョークを披露しているわけではないし、第三帝国に直接敗れ、イギリスほどドイツとの戦後関係が長くなく健全でないポーランドでこのようなルーチンを行っているわけでもない2。ともあれ、この問題は、第二次世界大戦に対するヨーロッパとアジアの文化的態度の違いや、なぜある社会が戦争を、継続的な対立の炎を燃え上がらせるものではなく、解放をもたらす、あるいは少なくとも社会的に建設的なかたちで嘲笑する記憶のかたちに変えることができるのかについて、私たちに考えるきっかけを与えてくれるはずだ。
ドイツのコメディアンが目を輝かせてこのルーティンを演じ、彼と観客がともに第二次世界大戦が根本的に間違っていたこと、ドイツが負けたことを認識しているという共通認識を示しているからだ。東アジアの状況とは大きく異なるヨーロッパ共通の記憶の中に、第二次世界大戦に関するコンセンサスが存在し、それがユーモアを通じて互いの緊張を解きほぐしているのだろうか3。さらに、こうした英独共通の感情を後押ししていると思われるのは、ヨーロッパにおいて正義感が達成されたからであり、この歴史的コンセンサスの共有が西ヨーロッパにおける歴史的記憶の進化を促しているのだろうか。それとも、この共通点は、東アジアでは目的を達成できなかったと思われる戦争犯罪を、ドイツがより執拗に追及したことに由来するのだろうか4。
日本では、記憶と歴史が相対的に調和しながら共存しているドイツとは異なり、記憶と歴史は互いに競合している。アメリカの占領は、その検閲と民主化の努力の両方において、第二次世界大戦に関する戦後初期の日本国内の議論を部分的に形成し、太平洋戦争の歴史の真実について日本人に知らせ、こうした考え方は、東京戦犯裁判に関するニュースとしてさらに広まった。その結果、日本の軍部には戦争責任があるという考えが定着した。検閲された日本のメディアは、部分的にはアメリカによってコントロールされ、操作されたものであったが、このような歴史観を作り上げた主な責任は日本にあった。対照的に、国民はこの押しつけられた見方を受け入れるのに苦労した。ここに、日本の戦後の歴史と記憶のギャップの大きな要因がある。日本人は、占領軍のアジア戦争観、連合国に対する戦争観を自ら肯定・反証に進むのではなく、主に「信じない」という反応を示したのである。第二に、有山照夫が指摘するように、このアメリカの見解は、日本人が戦争中に経験した個人的な体験の多く-愛する人を戦場に送り出し、都市から避難し、空襲を経験した-とは一致しなかった。そのため、日本人が外部の人間から聞いていたことと、戦争について信じていたこととを一致させることは二重に困難であった5。その結果、日本人の戦争の記憶は、戦後初期に占領下のメディアで提供されていた主な物語からすぐに切り離されてしまった。
このような状況下で、日本人の努力は自国の戦争犯罪を調査することではなく、むしろ日本の敗戦問題と敗戦の理由を議論することに集中した。戦争責任は戦争犯罪の問題にも触れたが、ヨーロッパでの展開とは異なる方法で、戦後における責任と正義の意味を決定することについて、日本人が独自の内部ヒエラルキーを持っていたことを示唆するような形で展開された。私の章では、主に中国とイギリスに焦点を当てながら、戦争犯罪に関するこうした初期の国際的な議論の輪郭を大まかに示し、その後、日本がどのように対応したかを掘り下げてみたい。日本国内では、メディア、皇室、軍部、文民政府という4つの主なグループが、戦争犯罪裁判がどのように見られるかをコントロールしようと競い合っていた。各グループが、連合国の戦争犯罪裁判の要請をどのように管理し、対応するかについて、競合するイデオロギーを維持していたという事実は、戦時中と戦後直後の日本の両方における権威と支配の分裂した性質を示している。各政治的・市民的主体は、自らの損失を軽減し、他者の目から見た戦争責任を最小化し、自らの特権の継続を迫りたかったのである。
中国における戦争犯罪裁判は内省をもたらさなかった
戦争責任、正義の追求、第二次世界大戦の意義の探求に関する議論は、単なる歴史的なお荷物にとどまらず、今日の東アジアにおける政治生活の日常的な構造とも共鳴している。実際、日本が2015年に保守政権として憲法改正を推進し、中国がこの地域での支配力を強化しようとしていることを考えれば、こうした議論は当分の間、衰えることはないだろう7。日中両国が自国の歴史をどう見るかは、1945年後半以来そうであるように、政治的意義を孕んでいる。2014年、朝日新聞は、安倍晋三首相がA級戦犯やその他の戦犯を称える地域の追悼式典に送った支持の手紙を明らかにした: 「アメリカの無差別爆撃、原爆投下、ソ連の対日条約違反、捕虜の不法抑留はすべて戦争犯罪である。要するに、日本と日本人に対するBC級戦犯裁判は憎悪と復讐に基づくものであり、それ以外の何ものでもない」9。
日本人の記憶と歴史との間のこのような分裂は、かつてないほど顕著であり、日本における記憶が、アメリカが押し付けた占領時代の歴史物語と対立しているだけでなく、中国人のより大きな物語とも対立していることを示している。日本の反論に対して、中国本土の共産党政府は、日本が過去を正しく受け止めることができない証拠として、戦後直後の日本に対する善意の歴史を掘り起こし続けている。中国人は、東京裁判で訴追されたA級戦争犯罪や、1945年から1951年にかけて戦後の東アジアと東南アジアの49の場所で追求されたB級・C級戦争犯罪裁判として知られる、より軽微な戦争犯罪を認めようとしない日本の公式見解に当惑したままだ。
中国共産党は、蒋介石率いる中国国民党が1946年から1949年にかけてすでに裁判を行った後、1956年に独自の裁判を行った。共産党は、1,000人をわずかに超える日本人捕虜の大部分を釈放し、誰も処刑せず、旧軍と満州国の高官のうち45人だけを起訴した10。これらの人々は、すでに1945年から1950年までソ連に収監され、1950年から1956年まで中国で再び収監され、山西省太原と遼寧省瀋陽の2つの裁判所で裁判にかけられた11。これらの日本軍将校や文官は投獄中に膨大な自己批判を書き残し、これらの自白は後に日本の戦争犯罪の証拠として中国の裁判所に提出された。1980年代末から2000年代初めにかけて、これらの自白の中国語訳が出版され、またいくつかの複製が国内外向けに再び発行された13。第二次世界大戦終結70周年を前に、北京は、北京がでっち上げで正確でないとみなす過去を日本政府に思い起こさせる方法として、これらの日本の戦犯の「自白」をオンラインで再公開することで、この政治的カードを再び使うことに関心を示した14。
一方では、中国政府は、戦時責任と日本が自国の歴史を直視していないという事実をめぐる言論戦において、国際的な支持を得ている。たとえ北京が、1949年以降の中国本土の歴史における微妙な瞬間、たとえば大躍進(1958~1961)や毛沢東の悲惨な文化大革命(1966~1976)の影響について公に論じないことで、「歴史的事実」に対する自らの嫌悪感を頻繁に示しているとしても、である。 15 中国の物理学者で、北京のアメリカ大使館に数ヶ月間潜伏した後、1990年に亡命した故・方立之は、中国の歴史は創造と無視が同居していると述べている。これは、有名な中国研究者であるペリー・リンクも「歴史の忘却」のプロセスと表現したもので、「(中国共産党の)支配の重要な装置」であり、「社会全体がその歴史、特に中国共産党自身の真の歴史を忘れる」ことを余儀なくされている16。リンクは最近さらに批判を強めており、このような歴史認識の欠如が、中国における道徳的焦点の欠如につながっていると指摘している。彼は、19世紀半ばから清朝がゆっくりと下降した後、中国が独自の近代性とアイデンティティを築こうと奮闘しているが、それは容易なことではなかったと指摘する。「中国という偉大な古代文明は、2世紀近くもの間、現代に向けて自己を再発明する方法を模索してきた。この過程では、発作やスタート、逆転が繰り返され、トラウマを引き起こし、少なくとも7000万人の不自然な死をもたらした」17。
確かに、中国人は日本帝国の残虐行為を忘れてはいない。この先入観が他のすべての影を落とし、あるいは日本人自身を不安定な状態に追い込み、バランスを崩しかけているのではないだろうか。日本の保守的あるいは右翼的なサークルの中で、このような考え方に反発する人々が急増し、彼らから「マゾヒスティックな歴史」(自虐史観)とみなされるようになった。中国人が屈辱の世紀という考えを過度に強調することで、中国国民が自らの苦難を、最も劇的なのは日本に対する苦難を、自国の民族的アイデンティティを形成した過程として理想化することである18。しかし、日中双方のこうした感情的な傾向が、和解の意識に役立っているのか、それとももっと限定的な目的のために役立っているのかを問い直す必要がある。
第二次世界大戦後の戦争犯罪裁判への歩み
第二次世界大戦の初期に日本語学習者として採用されたイギリス人のアレンは、戦争末期にビルマで日本人捕虜を戦犯として尋問していた。その過程のある時、彼は一人の不運な元日本兵に偶然出会い、1945年8月の降伏後、敗戦軍として日本兵が直面した新たなパラダイムについて考えた:
今も昔も、戦争犯罪問題の人間的現実は、名目上の役割や解読不能な名前よりも現実味を帯びている。ある時、私は船内で捕虜に対する虐待に関与した疑いのある日本人を何人か尋問するよう頼まれた。そのうちの一人が、私の前に来て座ったとき、文字通り震えていた。彼はじっとしていることができず、座って汗をかきながら、私は彼を見て、彼の中にある抑えきれない恐ろしい恐怖を感じた。私はそれを必ずしも罪の意識の表れだとは思わなかった。その状況だけでそうなったのだろう。しかし、彼の名前は私のリストにある名前と一致するように思えたが、私はこのままではいけないと思った。憲兵隊ではありえなかったことだが、自分には他の人間をこのような動物的恐怖に陥れる権利はない、と突然思ったのだ。私は彼に立ち去るように言った
最後にアレンは、自分の判断は間違っていたかもしれず、「むしろ私の道徳的な弱さだったのかもしれない」と付け加えている20。このような態度は、その土地の完全な支配下にあった日本軍に対して連合国が突然与えられた広範な権限について、私たちに考えるきっかけを与えてくれるはずである。先に述べた中国共産党の裁判と同様、戦争犯罪裁判と正義の追求は、必ずしも報復が目的ではなかった。海外での英国の裁判は、理論的にはロンドンの軍務局に従って行われ、法務官が政治的指示を出したが、外交政策への潜在的な影響を官僚が把握すると、しばしば外務省との意見の相違に陥った。戦後初期の英国外務大臣アーネスト・ベヴィンは、ドイツ軍将兵を裁判にかけることは英国の利益にとって長期的には生産的でないと考えていた。ケルスティン・フォン・リンゲン(Kerstin von Lingen)が指摘するように、結局、英独両国は敵同士であったにもかかわらず、「かつての敵国との軍事的連帯は顕著であった」のである21。この現象は東アジアでも、中国国民党が特定の日本人戦犯を処遇する過程で見られる。蒋介石は国民党の軍事法廷に圧力をかけ、中国で帝国軍を率いた最後の日本陸軍大将、岡村靖治を「無罪」とした。中国国民党は1949年に台湾に逃れており、中国本土を奪還する国民党の計画を実行するために、日本軍将校に戦略と日本の「武道精神」を教えてもらいたかったのだ22。
ウィンストン・チャーチル首相は当初、正義を実現する方法として、ナチスは単に射殺されるべきだと考えていた。
しかし、不安定化した大英帝国の片隅にある東アジアにおける正義に関する彼の考えは、再建に向けた英国の支援の必要性を考慮すると、若干ニュアンスが異なっていた23。皮肉なことに、日本軍に対する反感を考慮しても、かつてのヨーロッパの植民地支配を最小限の混乱と不快感で取り戻せるよう、イギリスはそうした軍隊を指揮統制下に置く必要があった24。植民地防衛当局で長年さまざまな役職を務め、実質的には第二次世界大戦が勃発する直前に引退したハンキーは、連合国による戦争犯罪裁判の実施計画に反対し、有罪判決を受けたA級戦犯の重光守外相を終生支持していた25。ハンキーは当時、このような裁判の脅威が枢軸国に戦争を長引かせるための必死の手段をとらせるという、やや不評な立場をとり、この取り組みは犠牲者のためには何もならないが、和平プロセスを妨げるだけの空虚なプロパガンダだと断じた。ハンキーにとって、外務大臣重光守の戦時内閣への連座罪とその後の処罰(司法のほんのわずかな差で絞首刑を免れた、と彼は考えた)は、近代外交と法の精神に反するものであった。東京戦犯裁判のオランダ人判事バート・ローリングは後にハンキーの評価に同意し、2人はこの話題で文通をした26。明らかに、この考えはインド人判事ラダビノード・パルの長い反対意見とともに、A級裁判だけでなく、戦犯裁判全般に対する日本人の道徳的・法的不満を固めるのに役立った。ハンキーは、戦犯に対するチャーチルの現実主義的な態度を知っていた。このことは、戦後の指導者がバランスを取らなければならなかった問題の一端を示している。正義感と、数十年にわたる戦争で荒廃した地域の再建と安定化を推し進めるという現実的な政策目標である。
彼(チャーチル)は、日本における戦争犯罪の訴追、特に東条首相の訴追について強い感情を持っている。終戦から3年経ったこの時期に、日本の著名人を絞首刑にするのは愚かなことだ。一国の支配者が自国の軍隊の行動をコントロールすることはできない。同じ理論でいけば、連合国が戦争に負けていれば、ルーズベルトも彼自身も処刑されることはなかっただろう27。
ハンキーは、戦後の正義を回避しようとする日本の策動に対するイギリスや連合国全体の立場を代表するものではないかもしれないが、彼の断固とした意見は、政治的志向にかかわらず、連合国も日本も未来に対して分裂病的なアプローチを継続的に維持し、片方の目を前方に向けつつも、その進歩を過去の責任を調査する必要性と天秤にかけていたことを示している。
歴史と正義-日本流
先に概説したヨーロッパと中国で発展しつつあった国際的枠組みは、日本が戦争犯罪に対処するために外部から圧力をかける最善の方法に関する世界の分断を示している。戦後の正義を追求する法的基盤の構築は、決して運命づけられていたわけではないことを忘れてはならない。東アジアにおいて、国際法の考え方に基づく戦争犯罪裁判の裁きは、法的態度の壮大な転換に他ならず、正義という概念を管理する全く新しい方法を目撃した。アジア全域の2,244の公式裁判において、B級およびC級戦争犯罪に相当する5,700人が起訴されたとしても、欧州の起訴状における「正義」の範囲は、東アジアで起きたことを数値的に凌駕している28。第一に、本章の冒頭で触れた現在の日本と中国のメディアで明らかなように、戦争犯罪と、「アジアの解放」という日本が掲げた戦争目標との対立に関する言葉の戦いは、東アジアで衰えることのない戦いである。また、多くの人々は、「ヨーロッパでは」、よりユートピア的な正義が達成されたと信じている。ドイツは過去を償い、日本は償っていないというこの言葉は、ヨーロッパの他の国々の状況を無視している。フランスは、ユダヤ人の強制収容所への移送、インドシナ半島での脱植民地化戦争、アルジェリアでの戦争など、自国の歴史についての全面的な検証を遅らせ続けている。さらに重要なことは、イタリア、スペイン、そして多くの東欧諸国も、自国の歴史や第二次世界大戦の遺産の中で、同様の問題と折り合いをつけようとする努力がかなり弱いということである。このような歴史的調査は、もちろん日本の残虐行為や帝国的侵略を否定するものではない。しかし、比較のためには、日本以外の戦争犯罪を検証する際、ドイツ以外の選択肢に目を向けることを望むかもしれない。ともあれ、多くの日本人が抱いている、自分たちは戦後正義を受けるための尖兵であり被害者であるという信念は、終戦直後から始まったプロセスであり、単に占領に対する国内の不満から生じたものではないということが、研究によって明らかになった。戦争犯罪に対する日本の社会的対応は、当初、軍人(復員・引揚者)や政府高官(その多くは戦時中にエリート職についていた)によって主導された。
降伏後、日本人は直ちに、戦争中の帝国の行動に対する責任を調査しようとする占領時代の試みを調停し、引き延ばし、そらすために、彼ら自身の一方的な動きをとった。1945年7月のポツダム宣言では、日本人は戦争犯罪裁判にかけられると規定されていたが、それを無関心に受け入れるどころか、日本人は今日まで反響を呼んでいる多くの積極的な政策を開始した。明らかになったのは、1945年から今日に至るまで、軍民を問わず、日本が戦争犯罪裁判資料を収集するために行ってきた広範な日本内部の努力である。しかし、それでも日本における戦争犯罪裁判に向けたすべての策謀や政策を一つのグループにまとめることはできない。
日本のメディアと皇室の姿勢
戦後間もない時期に、日本の戦争犯罪に関する議論の初期の輪郭が示された。1945年9月15日、日本の政治家鳩山一郎は朝日新聞で、日本国民は「二重の正義」の不当な感覚を懸念しており、戦時中の行動に対して日本だけが裁かれ、連合国は裁かれないと発言した31。鳩山がこのような話題を取り上げることができたのは、新しい形の原爆に関する日本国内の報道が遅々として進まず、それが通常の爆撃作戦とどう違うのかを本当に理解している日本国内の住民がほとんどいなかったからである32。1945年9月21日、朝日新聞は「戦犯裁く、自力で努力開始-国際貿易に参加し、国家再建を嘆願する」と題する記事を掲載した33。この記事は、帝国陸海軍が戦争責任を調査する独自の努力を開始したと述べているが、天皇に罪はないと強調している。
戦争責任に関して司法が調査する範囲を限定しようという国民の声は、やがて、戦後の新憲法が発表された1946年11月3日、裕仁天皇があらゆる種類の日本人犯罪者に恩赦を与えたことで、社会のより多くの部分が許されるようになった。「平和国家建設の礎石」となる憲法への「深い喜び」に加えて、裕仁はさらに踏み込んだ詔勅を発表した。この詔書は「大赦」として発表されたが、実際には、不敬罪、思想犯、政治犯など、戦時中に罪を問われた多くの人々の服役を終了させたという点で興味深いものだった。同時にこの詔勅は、無断欠勤した兵士、軍法会議で有罪判決を受けた兵士、戦時中に上官の命令に従わなかった兵士、さらに重要なこととして、捕虜に対する犯罪や海外でその他の犯罪を犯した帝国海軍や陸軍の兵士にも恩赦を与えた34。朝日新聞が「前例のない範囲」と評したように、この勅令には「占領の目的に反する」犯罪を犯した者には適用されないという条項も含まれていた35。いずれにせよ、この勅令が日本の降伏直後の戦争犯罪に関する内輪の議論に道徳的な輪郭を与えたことは確かである。
この勅令に続いて、沖縄、樺太、朝鮮半島、台湾、関東軍租借地(中国の遼東半島)、南太平洋諸島(マリアナ諸島とマーシャル諸島を指す)の裁判所など、現在では「外国」とみなされる裁判所で判決が下された人々を救済するために、複雑な官僚的規則の網を提供する政府指令が出された。興味深いことに、天皇がこのような恩赦を与えることができたのは、占領の条件によって実質的に効力を失っていた日本の法律に従ってのみであった。戦争は終わったのだから、再建するときが来たのだ。少なくともこれが日本側の主張であったが、この意見は、東アジアにおける日本の短期間の支配がもたらした大混乱と損害の程度について、十分な清算を考慮に入れていないものであった。日本の新聞は、7種類の犯罪が赦免され、33万人の恩赦につながったと書いている37。この恩赦が、日本のリベラル派を恐怖に陥れた戦時中の不適切な法律の両方を対象とし、戦争犯罪や非日本人に対する犯罪に関連する法律と混在していたという事実は、天皇が本質的にすでに戦争犯罪に対処したという評決を下したため、戦争犯罪の遺産に対処する必要性についての戦後の日本の熱意をますます冷ますことになった。
戦争犯罪裁判を求める声に対する帝国軍の反応
最終的に、より強固な形で戦争責任を評価する道を閉ざしたのは、天皇や日本のメディアだけではなかった。旧日本帝国軍内部でも、降伏直後の窮状に対処するために苦心した。元海軍大尉の豊田熊雄は、第二復員局(旧海軍省)内の新しいグループを率い、海軍将校を法的問題に巻き込まれないようにし、可能な限り彼らを弁護し、後の弁明や赦免を得る手段として裁判記録や必要な証拠を収集する任務を負っていた。降伏の2日後、帝国海軍は終戦処理委員会を設置し、すぐに「海軍終戦委員会」(開戦委員会)を立ち上げ、7つの小委員会を設置した。
東京戦争犯罪裁判(1946年~1949)は、日本帝国陸軍が日本国民だけでなく、他のアジア人や捕虜にも行った残酷な行為について、日本国民と世界を啓蒙した。これは、日本海軍が長い戦争の間、利他的な武士道的行動で支持を集め、そのように見せようとしたことと深く対立するものだった。海軍士官がA級戦犯として追及されるケースは、陸軍士官よりもはるかに少なかったのである39。これは単なる偶然ではなく、具体的な目標であった39。秘密裏に設立された豊田のグループは、海軍将校の戦争犯罪裁判を阻止するよう指示されていた。彼は、公職にある他の多くの日本人と同様、連合国による戦争犯罪の追及は違法であると考えていた。なぜなら、「戦争は国家的行為であり、国際法のレベルでは個人の責任を訴追することはできない」からである。このような条項が存在するとすれば、それは事後法であり、事後に作られた法律である」40(これは必ずしも新しい考えではなかった。第一次世界大戦終結後、数十年前のヴェルサイユ講和条約交渉において、日本の指導者たちは、代表団は最終的にドイツのカイザーを追及するという連合国のコンセンサスに従ったとはいえ、国家犯罪について個人が責任を負うべきでないという同様の意見を表明していた)41 豊田氏のグループは、連合国の裁判手続きで元海軍将校たちが真実を曖昧にするのを助け、彼らの証言を支援するために長い時間を費やした。占領軍はおそらく、こうした準備のことは知らなかっただろう42。
豊田は、終戦時に日本に直接引き揚げなかったためか、連合国による正義の追求に深く反発するようになったようだ。戦争中、帝国の機構と結びついて過ごした多くの日本人と同様、彼は終戦時にヨーロッパにいた。ドイツが降伏したのは1945年5月のことであり、ドイツに残っていた日本の外交団はかなり無防備な状態になっていた。豊田は日本大使館の武官として数年間ベルリンに赴任していた。大島弘駐ドイツ日本大使は逃亡したが間に合わず、結局捕まり、後にA級戦犯として訴追されたが、まず豊田熊雄が捕虜として連れて行かれたのは、ヨーロッパ戦争末期のアメリカだった43。大島とその従者の多くは当初、ヴァージニア州アレクサンドリアのフォート・ハント(豊田は「ワシントンDCのポトマック河畔」と書いている)に送られた44。この地域は現在は国立公園になっているが、当時のフォート・ハントは、ナチスの科学者の任務報告や尋問に使われたアメリカの秘密施設であり、ヨーロッパで一緒に捕らえられた少数の日本政府関係者を尋問するために設置された施設でもあった45。豊田はフォートハントに収容され、そこでアメリカのメディアから日本の敗戦という痛ましいニュースを知ったようだ。豊田はアメリカ国民が一致団結して日本人を誹謗中傷しているのを見た。「言葉では言い表せないほど苦しかった」46。降伏に狼狽した豊田は、「今、自分に何ができるのか?」と考えたという。このとき彼は、屈辱的で一方的な戦争犯罪裁判を防ぐことが、日本の尊厳を守ることにつながると考えた。その決意を胸に、他の官僚のポストを転々とした後、1945年12月にトヨタが送還されると、まず1946年初めから内閣臨時調査室に勤務し、その後約10年間、何らかの形で日本の戦争犯罪裁判の分析に携わった。その後、法務省直属で8年間、世界各国の記録を集める仕事を担当した。
合計18年間をこの仕事に費やした。被告人、通訳、メモ、聖職者、その他、何かを持っていそうな人からあらゆるものを集めた。豊田氏と彼のチームは700人にインタビューを行い、その情報をもとに、日本の戦犯を釈放、赦免、無罪を証明するための日本の対抗措置を提案することを目指した47。豊田は、戦後の海軍省の退役軍人雑誌で、「敗戦の犠牲者として」、海外の裁判で有罪判決を受け、「非業の最期」を遂げた1,000人の戦友の霊に捧げると書いている48。東アジアと東南アジアのB、C級戦犯裁判で、1,000人近い日本人が処刑された。豊田熊雄のグループは1970年まで(法務省内で)活動を続け、戦犯裁判に関する情報やデータを収集し、主に日本の戦犯を被害者とする考えを広めることを目的としていた。サンドラ・ウィルソンは、戦犯を収容していた主な刑務所である巣鴨プリズンの外部や内部で設立された元退役軍人のグループや関連団体について幅広く書いているが、これらもまた、戦後にこのような被害者意識を作り出す上で効果的であった49。
こうした努力によって、旧帝国海軍は、戦争の責任と重荷の多くを政府と帝国陸軍の文民、たとえば東条英機などの指導者に押し付けることに成功した一方で、天皇やその他の海軍関係者を連合国の詮索好きな目から遠ざけることに貢献したことは記憶に留めておく価値がある。占領軍と日本人の間には責任の押し付け合いがあったが、同時に日本人の間にも、一部の部門から責任を遠ざけ、陸軍と少数の二次的指導者の肩に責任を押し付けようとする争いがあった。
戦争犯罪裁判によって正義は果たされたのか?
帝国海軍が敗戦の無効化に向けて最初の一歩を踏み出す一方で、その検証が敗戦の理由を軍事演習とみなすのか、道徳的失敗とみなすのかは明らかではなかった。戦争責任を意味する日本語の「戦争責任」という言葉は流動的で、さまざまなグループによって使い分けられ、とりわけ「なぜ日本は負けたのか」「なぜ日本は戦争を始めたのか」の探求を意味した。この用語はまた、誰が敗戦の正確な責任を負うのかを意味していた。日本人にとって、「責任がある」という言葉が、戦争犯罪を訴追するための責任の所在という法的領域をカバーすることはほとんどなかった。日本の場合、このような惨事の責任者の多くが、戦後も政府や行政にとどまった。逮捕されたものの裁判にかけられなかった者、逮捕すらされなかった者、戦犯として有罪判決を受けたものの、後に釈放され、著名な地位を取り戻した者もいる。岸信介(戦犯として逮捕されたが不起訴)は後に戦後の首相となり、最もよく知られた例かもしれない。また、A級戦犯として有罪判決を受けた後に外務大臣になった重光守(ハンキー卿は不当に追及されたと感じていた)や、戦後は法務大臣を務めたが、大蔵大臣としてもA級戦犯として有罪判決を受けた茅沖徳もいた。逮捕されながら起訴されず、最終的に連合国の網をくぐり抜けた児玉誉士夫(当時の言葉でいうフィクサー)もいた。確かに、すべての責任者を起訴することはできなかった。
終戦直後の日本政府自身の立場がいかに混乱し、不安定であったかは、降伏から数日後にマニラへ飛んだ岡崎勝雄の経験を通じて明らかになる。岡崎は外務省の代表として飛行機でマニラに向かうよう命じられ、アメリカとの交渉で終戦をどう扱うべきかを決定することになった。岡崎は、終戦時に何が起こるか誰にもわからないことを知らされ、フィリピンから降伏勧告書を持ち帰るのに命を落としそうになった。50 近代の幕開け以来、日本は一度も敗戦を経験したことがなかったため、降伏の条件が明確に提示されなければ、日本の文官と軍人の両方がどのように反応するかについて、ほとんど確信が持てないと岡崎は推論した。終戦にどう対応するか、戦争責任にどう対応するかという日本人の態度は、占領が始まった当時、日本の内部でまだ活発に議論されており、それがどう展開するかは幅広い解釈の余地があった51。
日本文民政府の対応
日本政府もまた、戦争責任を分析するための一連の委員会を設置していた。これらは、第二復員局の便箋に書かれた「日本政府が戦争犯罪裁判に対してとるべき基本的な方向性と態度」という興味深い要約に詳述されている。この報告書は、戦争犯罪問題に対処するための戦後初期の日本の計画の歴史を明らかにした。そして、それこそが重要なのである。その目的は、そのような裁判の賦課に「対処」することであって、実際に掘り下げたり、調査したり、追求したりすることではなかった。むしろ日本の目的は、占領期間中に可能な限りの努力を事実上仲介することであった。
報告書は、日本が終戦時に円滑な移行を行うことに合意し、直ちに終戦事務局を設置したと述べている52。1945年9月11日の「戦犯容疑者」の最初の逮捕発表後、逮捕・収容された人数が徐々に増え始めたため、日本は戦争犯罪に特化した問題を管理し、アメリカとの連絡を取り、情報を提供し、処理業務を遂行するための特別室を設置することが急務であると感じたと報告書は記している。日本人は、自分たちが直面する事態の大きさに対して十分な準備ができていたわけではなく、問題の核心についてもよく理解していなかった。(日本政府は、連合軍捕虜の虐待を告発するというポツダム宣言の内容を知ってはいたが、このプロセスがどのように実施されるかは明らかではなかった)。日本は意図的なスピードで、自分たちの立場を明確にする計画を打ち出そうと動いたが、そのための実質的な権限がないことを忘れていたのかもしれない。1945年9月12日の朝、総理大臣、外務大臣、陸軍大臣、海軍大臣、参謀総長、近衛文麿国務大臣、法務大臣、その他数名が集まり、終戦戦略決定会議が開かれた。この会議での決定は、連合国が一方的に裁判を進めるとしても、日本が先手を打って戦争犯罪の調査を進め、個人の責任を追及し、その結果を総司令部に渡すべきだというものだった。その理由は、連合国側の一方的な判断によってプロセスが偏るのを避けるためであり、日本国家がそのような個人に同情すべきだからであった。会談後、当時の内務大臣であった木戸幸一は、この決定を天皇に記念品として献上した。これに対して天皇は、「天皇の名において勇敢に戦争を戦った皇国の臣民が罪に問われることを悲しむ」と述べた。12日の夜、同じ会議が再開され、木戸は天皇のコメントをメンバーに伝えた。結局、この努力は短命に終わったが、連合国の努力を可能な限り阻止しようという戦略は明確だった。
もちろん、A級戦犯については、その罪責を問うことが最終的に天皇の役割に触れることになるという問題があったため、戦争犯罪を扱うあらゆる問題に関して3つの主要な方針が打ち出された:
- 1. 天皇の責任に関することには一切触れない
- 2. 国家を守る。
- 3. 最初の2点の枠内で、可能な限り、個人を守る54。
皇室の遺産は生き続ける
日本政府は、連合国の戦争犯罪法廷の判決を受け入れると、法的に可能な限り早く、1952年のサンフランシスコ講和条約に対する理解を一変させた。1953年8月、政府は、釈放された日本人戦犯に恩赦を与え、社会復帰を認め、生活保護や年金を受給させたり、家族に経済的援助の一部を認める新たな措置を可決した。さらに、これらの規定はその後数十年にわたって何度も改正された。日本の歴史家、服部龍二の言葉を借りれば、これによって政府は、国内法レベルの戦争犯罪裁判は汚名を着せるものでもなければ、占領中に違法とされていた政府からの給付金の受給を禁止するものでもないため、もはや実際の犯罪とは見なされないという印象を与える環境を作り出したのである55。
第二次世界大戦が終わってから数十年後の1981年、元日本帝国海軍将校の岩永健二は、帝国海軍退役軍人雑誌に、日本に必要だが欠けているのは自国を守る愛国心だと書いている。国民総生産が高くても、自国を愛していなければ意味がない。なぜ日本以外の国には愛国心があるのか?岩波は尋ねた。それは太平洋戦争(1941年~1945)のせいである、と彼は具体的に、そして物語るように書いたが、1937年に中国で始まったもっと長く大きな戦争については触れなかった。あるいは、日本が唯一の半島国、「犯罪国」であると人々が信じていることが原因かもしれない、と彼は示唆した。岩永は、彼の世代の多くがそうであったように、第二次世界大戦の責任は日本を窮地に追い込んだアメリカにあり、日本はこの一連の事実を若い世代に教える必要があると主張した。(悲しいことに、この信念は帝国軍が日本国内にもたらした荒廃を無視しているように見えるが、それはもっと長い余談である)。元海軍将校は、日本の戦後憲法は外から押し付けられたものだと主張したが、その間に日本が豊かで裕福な国に発展し、戦後の状況から実際にどれだけの恩恵を受けていたかを理解していなかった。逆説的だが、日本は戦争に負けたからこそ豊かで安定したのである。岩永のような旧帝国軍人にとって、戦後という時代は、軍国主義的・帝国主義的な過去を完全に否定する日本と結びついていたため、何の意味もなかったのである56。
実際、戦後何年経っても、日本の軍部団体の中には、自分たちのやったことが正しいか正しくないかではなく、自分たちがいかに正しかったか、そしてこのことに気づかないことは若い日本人や国民全体にとって有害であるという議論を続けているところもあった。連合国による戦争犯罪裁判の制作に費やされた労力を考えると、なぜこのような反語的な考え方が生まれたのだろうか?私は、戦犯裁判の判決に疑問を投げかける枠組みの一部は、単に法的不備によるものではなく、裁判のプロセス自体とはあまり関係がないことが多かったと考える。このような戦後の正義の追求に対する最初の反発は、戦後の初期段階において、日本の軍部と文民の内部から生まれ、日本がアジアと太平洋で行った戦争の種類を厳しく見ることを避けるように、日本の歴代の世代を形成するのに役立った。このような考え方はまた、正義の追求が日本人を犠牲にするプロセスのもう一つのステップに過ぎないとみなされる仕組みの形成にも役立った。
1950年代の中国の対日政策は、まさにチャーチルがヨーロッパに対して唱えた政策、つまり感情よりも実利主義だったことを思い出してほしい。(ここで私は、戦争犯罪問題についてヨーロッパとアジアを比較することは、アメリカの例ばかり見るよりも実り多いのではないかと思う)
「復讐は、あらゆる満足の中で、最も費用がかかり、長引くものである。報復的迫害は、あらゆる政策の中で、最も悪質なものである。われわれの政策は、これまで述べたような例外的なケースを除けば、今後は、過去の犯罪や恐怖をスポンジで拭い去り(それは難しいかもしれないが)、われわれの救いのために未来に目を向けることである。全ドイツ民族の積極的かつ忠実な援助なしには、ヨーロッパの復興はあり得ない」57。
中国もまた、経済的に活力に満ちた日本の復興を願っていたが、それは正義だからではなく、中国の利益にも役立つからであった58。
結論
戦争を終わらせるには、戦争を始めるのと同様に、社会を動員する必要があり、それにはプロパガンダが必要である。「心をつかむ」ためには、政府は敵に関する情報や、国民を行動に駆り立てるような新しい社会的目標を打ち出す能力を必要とする。戦後の正義の追求と、終戦間際の日本の「再社会化」を目指したプロパガンダの力との間に、どのような交差点があるのか、私たちは常に問い続ける必要がある。連合国が求めていた終結と責任の所在を明らかにすることは、そのための手段だったのだろうか?
数年前、私はロンドンで、戦後の日本社会が戦争犯罪の議論をどのようにとらえ、それが1945年以降どのように発展してきたかについて講演した。私は特にアメリカについて話すことを避け、代わりに中国における日本の戦争と中国本土における日本の戦争犯罪にすべての発言の焦点を絞った。そうしたのには2つの理由がある。第一の理由は利己的なもので、多くの優れた学者がこの分野と戦後の日米関係について研究している。2つ目の理由は、より戦略的なものである。2つの原爆を投下するというアメリカの決断の道徳性に関する議論に巻き込まれるのを避けることで、議論の余地が少ないと思われる一連の問題に焦点を当てることを目指した。私は、アメリカの関与を注意深く封印し、「戦時中、中国を植民地化する過程における日本の軍事行動だけに焦点を当てよう」と述べた。しかし、最後には、英国に30年以上住んでいる年配の日本人女性が私のところに来て、原爆の恐ろしさを語らずに日本の戦争犯罪について語る勇気があるのかと叱責した。まるで、この2つを同列に扱い、アメリカの行動を裁くまでは日本の責任を問う自由がないかのように。私は他の人たちと同じように、「tu quoque」(お前もだろ)の弁明は決して有効ではないことを彼女に思い出させた。70年前に日本政府と軍部によって作られた考え方は、今日でも多くの日本人にとって揺るぎないものであり、これはより深い問題を浮き彫りにしている。戦争に関するドイツのジョークをイギリス人が笑うことができるような、正義が果たされたというコンセンサスが、なぜ東アジアで、あるいは日本国内でさえ育まれなかったのだろうか。その理由のひとつは、単に降伏後の過渡的正義が欠如しているだけではなく、戦争の根源と戦争そのものに関するコンセンサスが共有されていないことにあるに違いない。
占領終結直後の1952年、日本弁護士連合会は戦犯釈放運動の開始を発表し、政府に対応を求めた。このグループは同年、『東京裁判の法的根拠なし』というタイトルで、自分たちの立場を詳述した本まで出版している59。
日本では、このジャンルの著作が絶えることはなかったが、正義の概念に関する中国の考え方が、おそらく現在とは大きく異なっていたことを示唆する回想録や書籍も数多く出版されている。過去のある時期には、中国と日本が、現代のイギリスとドイツのような共通のコンセンサスを形成していたかもしれない。1950年代から1960年代初頭にかけて何度も中国を訪問した旧日本軍の代表団は、毛沢東が旧帝国の日本兵を憎んでいたわけではないと言っていることを引用している。それどころか、彼らを対話に参加させ、もっと中国を訪問させたかったのだ。毛沢東が認めているように、「私は、すでに私に同意している日本からの訪問者を望んでいるのではない」
バラク・クシュナーはケンブリッジ大学のアジア・中東研究学部で日本近現代史を教えている。2012年から2013年にかけて英国学士院ミッドキャリア・フェローシップを授与され、3冊目の著書『Men to Devils, Devils to Men: Men to Devils, Devils to Men: Japanese War Crimes and Chinese Justice』(ハーバード大学出版、2015)という3冊目の本を完成させた。2013年からは欧州研究評議会の資金で5年間のプロジェクト”The Dissolution of the Japanese Empire and the Struggle for Legitimacy in Postwar East Asia, 1945-1965 “を開始した。クシュナーの2冊目の著書『Slurp!A culinary and social history of ramen – Japan’s favorite noodle soup (Brill, 2012)は、日中関係における食と歴史を分析したもので、2013年ソフィーコー賞(食の歴史部門)を受賞した。クシュナーの処女作である『The Thought War – Japanese Imperial Propaganda』(ハワイ 2006)は、戦時中の日本のプロパガンダの歴史を掘り下げた。2008年には安倍フェローとして「東アジアにおける冷戦期のプロパガンダと歴史的記憶」に関する研究を行った。それ以前は、米国国務省で東アジア担当の政治官として働き、米国ノースカロライナ州のデビッドソン大学で中国史と日本史を教えていた。研究者としては、戦時中の日本と中国のプロパガンダ、日本のメディア、日中関係、アジアのコメディ、食べ物などについて執筆している。
