Contents

link.springer.com/article/10.1057/s41292-018-0121-4
Militarising the Mind: Assessing the Weapons of the Ultimate Battlefield
ロバート・C・ブルーナー1 – フィリッパ・レンツォス1,2
要旨
行動神経科学の進歩により、人間の行動や認知を支えるメカニズムが解明され、精神疾患の治療に革命的な変化が起きている。これらの進歩は完全に善意的なものではなく、国家が心理的手段によって互いの国民に影響を与え、コントロールしようとした暗い時代を思い起こさせるような二重使用の可能性を持っている。
この論文では、行動変容神経科学の兵器化から生じる脅威を冷静かつ批判的に分析するために、提案されている行動変容神経科学の兵器を、適切な技術的、歴史的、および地政学的文脈に置いている。精神薬、脳刺激、脳画像、神経生物化学兵器を用いることで、国家は神経科学の進歩を活用して人間の行動と認知に影響を与え、コントロールし、操作することできるかもしれないと論じている。
しかし、これらのアプローチは極めて初期段階にあり、技術的・運用的な課題に直面しているため、その展開が困難な状況にある。しかし、科学の進歩の速さ、地政学的な不安定さの増大、国際法の曖昧さなどを考慮すると、科学者と国際社会は、これらの技術がより洗練され、使用に対する現実的な障壁が低くなるにつれ、警戒を続ける必要がある。
キーワード
行動神経科学 – 医薬品 – デュアルユース – ニューロウェポン – 生物兵器 – 科学者 – 国際社会
1 キングス・カレッジ・ロンドン(英国、ロンドン)戦争研究部 2 英国、ロンドン、キングス・カレッジ・ロンドン、グローバル・ヘルス&ソーシャル・メディスン部
ニューロサイエンスの武器化
行動神経科学は、感情、記憶、認知プロセスなど、私たちを人間たらしめる側面を支配する生物学的メカニズムを研究するものであり、それらがどのように狂い、精神疾患を引き起こすかを解明する。神経科学のこの分野は、過去30年間で、脳がどのように働いているのかが以前よりも明らかになるような重要な実験が相次ぎ、大きく変化していた。脳とその全機能の完全な科学的理解には程遠いものの、科学者たちは、ニューロン間で伝達される生化学的・電気的信号が閉回路を形成し、恐怖、不安、信頼、そして愛という感覚を生み出す仕組みを理解し始めている(Yuste 2015)。人間の行動に寄与する細胞内反応に関するこの新しい知識には、それを外因的に制御する能力も備わっている。科学者たちはこの力を利用して、精神疾患の治療に革命をもたらした。行動や認知を支配する特定の神経ネットワークに関する新たな理解が深まったため、精神疾患に関連する非定型の生化学的シグナル伝達を標的とする精神科薬や脳刺激法が、より特異的で効果的になってきている。また、脳画像の相関性を利用することで、脳損傷や脳疾患後に異常に活性化する脳部位を検出し、その部位をより正確にターゲットにすることができるようになった。
しかし、厄介なことに、神経科学者や医師による脳内化学物質の変化は、精神疾患を治療するだけでなく、精神疾患を生み出すこともある。不安や抑うつ、躁状態を治療するだけでなく、同じ行動回路をターゲットにした精神科の薬は、人にこれらの感情を経験させることができる。さらに、出来事後の重要なポイントで脳を刺激することで、記憶を強化したり削除したりする機能が出現していることを示し、脳画像によって人の認知プロセスや信念を洞察することで、「NEURINT」という新しい形の知性を提供する可能性がある(Wurzman and Giordano 2014)。行動を制御したり、記憶や認知を変化させたりすることは、明らかに諜報活動や軍事的価値がある。行動神経科学の軍事化の魅力は、行動を変化させる感情を呼び起こすことで、行為者の心や精神、政治的認識を変えることを容易にする、新しい影響力の武器の普及を可能にする能力に帰することができる。
プロパガンダ、選択的な情報公開、軍事力の誇示は、歴史上一貫して、紛争の認識を変え、最終的には戦争の潮流を変えるために使われてきた。孫子からクラウゼヴィッツ、ナポレオンからパットンに至るまで、戦争と戦略の権威者たちは、成功する軍事作戦には、士気を低下させる強制と心理操作の要素が必要だと主張してきた(Boyd 1987)。スターリングラードの戦い、ドレスデンの原爆投下、ベトナム戦争、そして世界的なテロとの戦いは、軍事力の印象的な発揮にもかかわらず、すべて失敗した。逆に、小規模で装備の整っていない軍隊は、戦うか降伏するかの決断に寄与する文化的・認知的変数を理解し操作することで、国際的な巨人を克服した(Szafranski 1997)。敵対する個人、意思決定者、軍隊、あるいは社会全体の、紛争のコストと利益に関する意見に影響を与える国の能力は、より強い勢力の成功を阻み、より弱い勢力の勝利を可能にする決定的な要因である。
影響力は紛争に限らず、多くのセキュリティサービスでは、情報を持つ頑固な人物から情報を引き出すために、また警察では、犯罪者と思われる人物から自白を引き出すために使われることがある。専門の尋問官は、微妙な心理的操作と条件付けを用いて、人が捜査官に協力することが自分の最善の利益であると感じる環境を作り出すよう訓練されている(Leo 1994)。尋問官は、情報の流れを円滑にするために、容疑者の感情、態度、さらには思考過程を意識的に操作し、容疑者に無力感を与える様々なテクニックを用いる(ロイヤル 1976)。戦争において敵に影響を与えることは重要であるにもかかわらず、従来の影響力の武器は、これまでのところ、科学というよりも芸術であった。効果的な影響力行使を設計し、頑固な対象から正確な情報を引き出す尋問を行うには、対象の文化、道徳、価値観に対する洗練された理解と相まって、高い情動知能が必要である。行動神経科学的手法の非治療的応用は、このパラダイムを変え、比類ない効率で影響力のある武器を行使できるようにする可能性を秘めている。行動の生物学的基盤を乗っ取ることで、従来の影響力の武器と同じ効果-ある問題に対する反応や認識の変化を引き起こす感情の創出-を、標準化された予測可能な方法で達成できる可能性がある。
行動神経科学を利用する可能性があるという主張は、影響力の聖杯である「心のコントロール」を達成するために政府が支援した長く暗い歴史を知らなければ、ほとんど茶番に思えるだろう。最も有名なのは、1950年代初頭から1970年代半ばにかけて実施されたCIAのマインドコントロールプログラム「MKULTRA」で、情報機関の尋問や洗脳に従いやすくしたり、米国の利益のために行動を強制したりするための感情操作法の開発に力を入れていた(Inouye 1977)。同様に、ソ連と中国のセキュリティ・サービスも、教化、認知機能の低下、より顕著な拷問方法の開発に重点を置いた実践を行っていた(Moreno 2006, pp.73-78).あらゆる立場の科学者が、感覚遮断、催眠、身体的拷問、精神安定剤などの野蛮な技法を用いて、他人に情報機関への協力を強制し、記憶を消し、外国の敵国に関する情報を収集したり暗殺を実行できるスパイを作ろうとした(Marks 1979; Moreno 2006, pp.61-82).
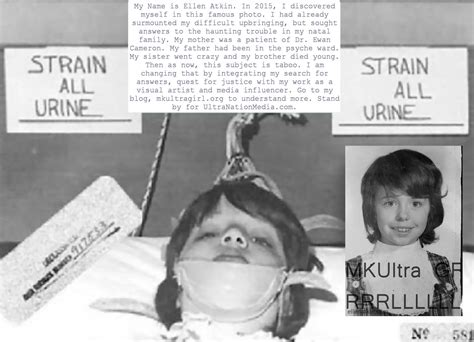
アメリカ、ソ連、中国のマインド・コントロール計画に共通するのは、他者への影響力と強制力を行使するための科学的方法を追求することであった。これらの計画は最終的に失敗と見なされたが、それは各国家が操作に関心を持った行動の側面を支える正確な生理学的メカニズムに関する科学的理解が不足していたためであった。しかし、神経科学は現在、心をコントロールするためのこれまでの技術的障壁を前例のない速さで打ち破っているようだ。神経回路を選択的に制御し、その動作を観察する能力は、心を外在的に制御し、その後、行動に影響を与え、強制し、操作する能力を手の届くところに持ってきているようだ。
神経科学の兵器化が戦略的に重大な影響を及ぼす可能性があることから、神経科学の脅威、必要な倫理的枠組み、拡散抑制体制の可能性に関する解説が急増した(例:Dando 2015; Giordano 2014)。神経科学の軍事的応用の拡大を挙げた著名な報告書も数多くある(王立協会2012、全米研究会議2008,2014)。しかし、これらの脅威分析において、神経脅威の主張と経験的な実用性との間には、ますます大きな隔たりがある。
技術的、歴史的、地政学的な背景の欠如がセンセーショナリズムを助長し、明確な分析が曖昧になっている。行動神経科学を利用して国家がマインドコントロール能力を開発するという脅威は実際にあるのだろうか。もしそうなら、すぐにでも実現できるのだろうか?本稿は、生命科学の発展が安全保障に与える影響を分析する急成長中の重要な文献に加え、最先端の神経科学研究をマッピングし、脅威の認識と現場の現実の間に広がるギャップを埋めるものである。精神科薬、脳刺激、脳画像、神経生物化学兵器という4つの異なるニューロテクノロジーを順番に評価する。私たちは、新しい感情を導入し、認知の変化を引き起こし、行動に影響を与えるために、脳化学を変化させることが技術的に可能であることを発見した。しかし、生化学的あるいは電気的に心をコントロールする試みは、これまでの試みと同様の理由で制限される可能性が高い。しかし、地政学的な不安定さや国際法の曖昧さを考慮すると、科学者や国際社会は、これらの技術がより洗練され、使用に対する現実的な障壁が低くなり始めたとしても、警戒を怠らないようにしなければならない。
批判的アプローチ
神経科学の国家安全保障への影響に関する著作の多くは、科学が完全に形成され、使用する準備が整っていると考えている。しかし、そうではない。神経科学者が脳に関する知識を大幅に向上させたとはいえ、まだ望むべきことはたくさんある。
Marks (2010)が指摘するように、科学者と国防当局者の両方が使用する技術主義的で専門分野特有の言葉は、神経科学の国家安全保障への影響に批判的で明確な目を向けることを妨げ、この分野のデュアルユースの脅威と技術的現実の間に不協和音を増大させる一因になっている。急速に近づいていると思われる主張される能力の多くは、過剰に誇張され、神経科学者が他人の心をコントロールしたり、記憶を移植したり、誰かの認知プロセスを覗き見したりしようとするために克服しなければならない技術的限界や現実的苦労から切り離されている(Caulfield et al., 2010)。現実には、薬物の結果を予測したり、脳画像を使って誰かの心を読んだりすることはまだ非常に難しく、有望な実験も厳密に管理された実験室の条件に限られることが多く、実際のシナリオでテストされたことはない(Illes et al.2010)。
「批判的神経科学」分析は、生物医学研究や生命科学の進歩が国家安全保障に与える影響を研究する際に、科学の歴史的追求、研究の社会政治的推進力、技術的限界の中で発展を文脈化する批判的アプローチを求める声が高まっていることを補足する。初期のパイオニアは Ben Ouagrham-GormleyとVogel で、彼らは歴史的な米ソの生物兵器プログラムの詳細な分析に基づいて、生物兵器の拡散には重要な無形の障壁があること、21 世紀のバイオテクノロジーのデュアルユースの脅威の評価において「暗黙知」が疎外されていることを実証した。(Ben Ouagrham-Gormley and Vogel 2010; Ben Ouagrham-Gormley 2012, 2014; Vogel 2013)。ジェファーソンら(2014)は、重要な新興バイオテクノロジーの一つである合成生物学を掘り下げて分析し、その二重利用の脅威に関する政策議論において、合成生物学に関する素朴で単純な、誤解を招く思い込みが蔓延していることを指摘し、それらを5つの「神話」に分類している。彼らの研究はまた、政策的な議論からしばしば消えてしまう微妙な点を引き出し、「生物科学の進歩がもたらす二重使用の脅威に対する支配的な理解を強調する、単純で信用できないイノベーションの線形モデルが、生物兵器開発のためのイノベーションの円滑さと容易さをいかに過大評価することにつながるか」(ジェファーソンら 2014, p.424)を実証した。合成生物学の悪用可能性に対する誇張された懸念は、かえって「それ自体では安全保障への効果が限定的な対策に政策の視線を向けさせる」(ジェファーソンら 2014, p.423)ので、これは重要である。同様に、批判的なアプローチは、神経科学の二重利用をめぐる不必要な誇大広告を払拭し、神経科学の安全保障への影響について必要かつ冷静に検討することを可能にする(Choudhury et al.2010)。
本研究では、歴史的・地政学的分析とともに、実証的かつ査読済みの神経科学研究を活用し、行動神経科学の臨床利用を戦場に転換する可能性について議論する。この論文では、これらの問題を2つのレベルで評価している。まず、個人を対象とした神経兵器の分類を検討し、特に精神科薬と脳刺激の使用を検討する。次に、社会と軍隊に対して使用される可能性のある神経科学的影響力兵器について論じる。ここでは、脳画像と神経生物化学兵器に焦点を当てる。この論文で検討した特定の神経技術は、人間の行動に影響を与えるために使用できるすべての神経技術、あるいは神経科学を過激な目的のために活用するすべての兵器を包含するものではない。特定のケースを選んだのは、現在、政策界や新たなニューロセキュリティの文献で最も広く議論されているためだ。また、マインド・コントロール能力を開発しようとする国家の過去の試みに最も近いケースである。
心理的拷問、洗脳、マインドコントロール
9.11以降の時代は、テロの脅威が緊急かつ予測不可能であるとの認識で特徴づけられるようになった。国内での大量殺戮事件を二度と起こさないという決意から、米軍とCIAは2000年代初頭を通じて、アブグレイブやグアンタナモ湾の収容施設でアルカイダ系の敵性戦闘員から情報を引き出すために、いわゆる「強化尋問技術」(EITs)を採用した。囚人たちは、顔や腹部への平手打ち、ストレスのかかる姿勢での長時間の強制起立、睡眠不足、窮屈な監禁、数週間から数ヶ月にわたる長期の裸体、そして最も悪名高い水責め(Central Intelligence Agency Inspector General 2004; International Committee of the Red Cross 2007)などを受けた。しかし、これらのEITはサディズムから生まれたものではなく、ストレス、不安、混乱といった特定の感情を生み出し、コントロールすることを意図して体系的に設計されたものであり、それによって人は情報を明け渡すことに従順になると考えられている(赤十字国際委員会2007、中央情報局1985)。囚人の心理を重視するのは、米国の尋問プログラムに限ったことではない。肉体的拷問のほとんどすべてにおいて、一貫した目標がある。それは、囚人の外的な知覚や感覚を操作することによって、囚人の精神状態をコントロールし、協力や情報提供を強制することである。

実際、いくつかの国は、感情や行動をより迅速かつ効率的にコントロールできる方法の設計を目的とした高度な研究に取り組んできた。冷戦時代には、アメリカ、ソビエト連邦、中国が、捕虜となった個人に対して抗しがたい影響力を持つ力をそれぞれの国家に与えることを目的とした広範なプログラムに取り組んでいた。精神安定剤、暴力、ストレスの原因となる感覚刺激や剥奪が、行動状態を操作し、囚人の身体と精神を遠隔操作するために用いられた。しかし、最終的にこれらの試みは、特定の減衰を必要とする脳内の要因の不完全な理解のために失敗したと考えられている。しかし、行動神経科学の進歩により、この状況は急速に変化しつつある。
治療用に開発された精神科の薬は、気分や行動に影響を与える副作用をもたらすことが多い。Moreno (2006, pp. 171-172)とThomsen (2014)は、非治療的に使用する場合、これらの感情オフターゲット効果を利用して、尋問に有用と考えられているのと同じ感情の多くを外因的に作り出すことができることを提案している。同様に、脳を刺激する方法は、兵器化の可能性が高まっており、その危険性も指摘されている(Fisher 2010)。過去のマインド・コントロールの追求と同様に、脳への刺激は、記憶の削除、他人の身体のコントロール、思考の傍受に使用できる方法として浮上している。薬物や脳刺激の適用に関する最悪のシナリオが強調された結果、不案内で扇動的な議論が行われている。このセクションでは、尋問用薬物と脳刺激の意味と実用性を歴史的な文脈の中で検討する。米国、ソ連、中国の行動制御の試みを評価することで、有望であるにもかかわらず、科学者や治安当局は、20世紀の同様の研究計画で遭遇したのと同じ課題に依然として直面しており、これらの課題が将来もその使用を阻害し続ける可能性が高いことを論証する。
マインドコントロール 野望と試み
グアンタナモの囚人から情報を引き出すためにCIAが開発したEITは、1950年代、1960年代、1970年代を通じて米国が行った、他人の行動を外的に変更する試みから生まれた囚人心理の理解に基づくものだった(Moreno 2006, pp.68-76).この時期、米国とソ連の双方で、相手側が最初に心を軍事化し、究極の戦場を独占するかもしれないという懸念があった。最も悪名高いのは、これらのプログラムの多くが、超常現象や超能力を使って他人をコントロールしようとするものであったことである。しかし、主な焦点は、人が新しい考えに敏感になるような心理状態を決定し、作り出すことであり、工作員の転向を可能にしたり、人の嘘や質問に対する抵抗能力を低下させたりすることであった。
ソ連は行動制御の研究に最も多く投資した国の一つである。ロシアとソビエトの歴史を通じて、欺瞞、思考の誘導、認識の操作は、政府が影響力と権力を維持するために用いた中心的な手段であった。今日、影響力の行使や積極的な手段を通じてとはいえ、心をコントロールすることは、ロシアの国家戦略や国内政治の手段として今も広く用いられている(Adamsky 2015)。したがって、心をコントロールするための標準的な方法に対するソ連の関心は驚くには値しない。ソ連のマインド・コントロール・プログラムは、言語の壁や公開情報の少なさもあって、欧米の歴史分析には不透明なままだが、1972年に機密解除されたDIAの報告書「Controlled Offensive Behavior-USSR」には、1932年からソ連の治安サービスが政治的反体制者を精神病と偽り、合法的に精神病院に送ることができた経緯が書かれている、そして、幻惑し、混乱させ、不安を煽るために、閃光、感覚遮断、睡眠遮断、電子・磁場印加、催眠、超常現象などのさまざまな方法と協調して、高用量の精神医薬で「治療」したのである(LaMothe 1972)。DIAは、このような人為的に作り出された精神病の状態において、看守は難治性の囚人を尋問に協力させることができるだけでなく、自分自身や他の反対者の意見を信用させないために、ほとんどあらゆる犯罪を自白させることができたと評価している。
ソ連の看守がこの洗脳に本当に成功したのか、それともDIAが主張するように、囚人たちは最終的に心を砕かれ、拷問を終わらせるために捕虜の意思に従ったのか、私たちには知る由もない。いずれにせよ、こうしたやり方は、1950年代初頭の朝鮮戦争中に中国によって取り入れられ、修正された(Moreno 2006, pp.66-68)。極端な感覚刺激と剥奪を利用して脆弱な感情状態を作り出すソ連の操作的な尋問方法を、中国の比較的進んだ教育的技術と組み合わせることによって、中国は、米国と国連軍の囚人の大部分を強制的に「資本主義の犯罪」を告白させ、尋問者に情報を開示し、毛沢東思想で囚人を教化するための作業に参加させることができた(Moreno 2006,66~68ページ)。中国軍に収容された捕虜の帰還後の心理学的検査と調査から、捕虜は極度の苦難、恐怖の周期的な緩和と再活性化、そして、可鍛で望ましい心理状態を作り出すために、絶望感と無力感を作り出すように設計された精神屈服剤に曝されていたことが明らかになっている(Schein 1956)。これらの苦難は、捕虜に協力すれば終息することが、捕虜に明示的に伝えられていた。捕虜へのインタビューでは、中国人の洗脳の試みが効果的であったことを示す直接的な証拠はないようであったが、米軍の心理学者たちは、効果が遅延したり遠隔で発動したりすることがあり、それによって近い将来には検出できなくなるという懸念を持っていた(Schein 1956)。米国当局は、これらの囚人が合図によって遠隔操作で作動し、スパイや暗殺者に変身することを恐れていた。
ソビエトと中国の心理戦術を理解し、それに対抗することに焦点を当てたCIAの防御的なプログラムとして始まったものは、すぐに非伝統的な手段で人間の行動をコントロールする技術に関する広範で資金力のある研究へと発展した(Marks 1979)。CIAは、困難な囚人から情報を引き出そうとしただけでなく、ロシアや中国の移民を心理的に操作して、外国のエージェントとして米国の言いなりにさせようとした(Moreno 2006, pp.67-76)。MKULTRA1(CIAのマインド・コントロール・プログラムの名称)は、アルコールと行動薬による尋問の効果、テレパシーや精神的なつながりを通じた型破りなコミュニケーション、自分の意思に反して何かをさせる催眠、反拷問と反洗脳の方法、選択的健忘の生成、ヘロインやマリファナ、そして最も悪名高い真実血清やLSDといった精神を屈する薬物の極秘投与に焦点を当てた(Inouye 1977)。
MKULTRAに包含される、遠隔視、心霊尋問、催眠術など、より型破りで奇妙なプロジェクトの多くは、作戦成功の可能性が低いと評価されていたが、CIAは、認知や行動を変化させる幻覚キノコ、マリファナ、ヘロイン、LSD、自白剤などの精神薬物を、尋問や記憶や出来事を特定の人に忘れさせるための補助として利用できるものと考えた。このプログラム、そしてロシアや中国の同様のプログラムから、CIAは人間の行動とその操作方法について多くを学び、今日でも人間の情報を収集する際に活用されている。

LSDや、行動を制御すると考えられていた同様の薬物は、繰り返し試用されるうちに、有用な情報の収集に役立つというよりも、むしろ妨げになると認識されるようになった。これらの薬物は、しばしば、回答者が完全な考えをまとめることができず、質問に対する回答が解読不能になるという結果を招いた(Bimmerle 1993)。尋問官は、質問を直線的に進めるためにより努力する必要があり、常に酩酊した被験者を方向転換させなければならなかった。尋問者はまた、自分の質問の筋道が、今や極めて感受性が高く、薬漬けの被験者に新しい考えや手がかりを与えないように注意深く確認しなければならなかった(Bimmerle 1993)。実際、尋問官は、正しい情報と偽の情報を見分ける高度な技術を要求され、しばしば、薬漬けの被験者を協力に誘導するために、さらに高度な心理的トリックを使わなければならなかった(Bimmerle 1993; Lowry 2008/2007)。また、薬物の効果が切れた後、囚人が薬物を投与されていたことが内部で明らかになると、協力継続の意志が変化したり、その後の投与で薬物の効果に対して硬直し、秘密裏に投与しなければならないこともあった(Redlich et al.1951).尋問のプロセスを合理化し、より簡単に情報を引き出すことができるようになるどころか、尋問用薬物を使用した場合、諜報員は正確な情報を得るために実際に努力しなければならず、薬物を使用する目的が損なわれ、実用的な有用性はほとんどなかったと言える。
真実の血清から神経科学的コントロールへ?
MKULTRAの失敗にもかかわらず、行動神経科学は、薬物やその他の神経細胞技術を使用して行動を制御し、影響を与えることに再び関心を持たせている。人間の基本的な感情に関連するニューロン回路の発見は、中枢神経系を標的とし、差別的な方法で行動に影響を与え、操作する新しい生物・化学兵器の創造につながると、何人かが指摘している(Dando 2015; Thomsen 2014; Royal Society 2012)。新しい医薬品は、人をより信頼させ、話す気にさせたり、従来の身体的拷問の方法と同様に、恐怖、不安、ストレス、混乱を誘発したりする(Crockett and Fehr 2013)。薬物によるマインドコントロールの過去の試みとは異なり、これらの新しい精神科治療薬が脳に影響を与える効率性と特異性は、潜在的に、より操作的に魅力的なものとなっている。
行動を制御する神経回路を外部から操作することは、すでに医療上の現実となっている。行動を制御する薬物は容易に入手可能であり、多くの場合、厳格にテストされ、人間への使用が承認されている。例えば、プロザック、ゾロフト、シタロプラムなどの選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)は、活動電位後のセロトニンの再吸収を阻止し、セロトニンによって引き起こされるニューロン伝達を増加させることによってセロトニン作動薬として働く。うつ病の治療によく使われるが、SSRIによるセロトニン伝達の増加は、向社会的行動や協調性と正の相関があり、これは質問セッションで役に立つかもしれない(Crockett and Fehr 2013)。さらに、広く利用されている数多くの精神科治療薬は、切り傷やあざを残すことなく、従来から多くの拷問プログラムの目標であったのと同じ行動を誘発することが知られている。例えば、ナルコレプシーの治療薬として一般的に処方されているモダフィニルのようなユルゲロニクは、不安、緊張、混乱を引き起こすことが知られており、ベンゾジアゼピン系の薬物は、その治療用途の副作用として、鬱、混乱、記憶喪失を引き起こすことがある(Wurzman and Giordano 2014, p.98).
食生活の改変もまた、神経化学的シグナリングの外因的な操作に期待が高まっている。従来、消化を助けると考えられてきた腸内細菌叢であるマイクロバイオームが脳化学に及ぼす影響に関する最近の研究は、神経伝達を秘密裏に変化させる大きな可能性を示している。研究者たちは、精神疾患は一般的に消化器系の異常な病態と結びついていること、腸内細菌は免疫系の発達と反応に重要な役割を果たし、それが間接的に神経伝達物質の濃度に影響を与え、行動を形成する可能性があることを発見した(Vandvik et al.2004; Dantzer et al.2008; Sampson and Mazmanian 2015).人、またはマウスの食事を変えて腸内細菌叢の相対濃度を変えることで、研究者は、人とマウスの両方で不安を生じさせ、ホルモンのストレス反応を増加・激化させることができた(Messaoudi et al.2011; Bercik et al.2011; Selkrig et al.2014; Sudo et al.2004; Sampson and Mazmanian 2015)。さらに、食品に含まれる多量栄養素を変更することで、神経伝達物質の代謝前駆体の濃度に影響を与え、その後、神経伝達を変化させることで行動変化を引き起こすことも可能である(Crockett and Fehr 2013)。

このような知識の蓄積は、過去に国家が敵の食糧供給を変更することに積極的であったことを考えると、興味深い意味を持つ。例えば、第二次世界大戦では、米国はヒトラーの食料に女性ホルモンを混入して、ヒトラーをジェンダーの境界を越えさせようとした(Marks 1979, p. 12)。同様に、南アフリカの生物兵器プログラムの特徴は、暗殺に使用するために致命的な微生物を食品に偽装したことである(Hay 2016)。興味深いことに、中国の刑務所に収容されていた朝鮮戦争の捕虜は、与えられた食べ物が待遇の最悪の側面の一つであったと報告している(Schein 1956)。腸内細菌叢と精神医学的な関連は、この効果に対する可能な説明を提供する。脳と腸の間のつながりに関する急成長中の知識を活用することで、国家は行動の基礎となる神経化学を密かに制御し、薬漬けの被験者が持つ時に暴力的な反応を制限し、囚人が尋問用の薬に対抗する尋問手段を取る能力を抑制できるかもしれない。
薬物による行動制御はまだ難しい
新しい精神医薬が脳に作用する効率と特異性が高まり、神経化学を変化させることが容易になったように見えるにもかかわらず、これらの能力を行動の制御と操作のために利用しようとする国家は、依然として技術的・運用上の課題に直面している。市場に広く出回っている多くの薬物について、尋問者に有利とされる能力のいくつかは、主要な作用の副作用である。これらの作用は保証されたものではなく、ある人にはより強く現れ、ある人には存在しないこともある。多くの薬剤の正確な薬理学的作用機序はまだ十分に解明されておらず、解剖学的、遺伝的変異、個人の家族歴や病歴などにより、精神科の薬は集団間で効果に大きな差があるのが普通である。また、薬物の投与量も、薬物の行動への影響を決定する上で重要な役割を担っている。例えば、SSRIの投与量を変えることで、低用量ではシナプス前受容体で、高用量ではシナプス後受容体でセロトニンの伝達を増加させることができることが研究者によって明らかにされている(Selvaraj et al.2012)。異なる細胞位置での伝達の増加は、異なる行動効果をもたらす可能性がある。
さらに、特定の場所における神経伝達物質の濃度は、その時々に必要な伝達や結果に基づいて自然に調節される。しかし、精神科治療薬による外部からの脳内化学操作では、神経伝達物質の濃度が差別なく上昇し、受容体サブタイプの複数の効果、あるいは相反する効果を引き起こす可能性がある(Crockett and Fehr 2013)。1つのニューロン受容体サブタイプに選択的な薬剤を合成することは可能だが、受容体は全身に分布しているため、望ましくない副作用が起こる確率がさらに高くなる。現時点では、特定の神経細胞核の神経伝達物質濃度を非侵襲的に制御し、望ましい効果をもたらし、他の効果を排除することはできない。もちろん、この問題は、すべてのクラスの神経伝達物質とその受容体サブタイプに適用できるわけではない。脳内の複数の受容体を活性化しても、薬学的に操作される神経伝達物質によっては、望ましい効果が得られない、あるいは得られることさえある。
病歴や家族歴も、行動制御の短期的・長期的な結果に重大な影響を与える可能性がある。囚人がすでに服用している薬との相互作用が致命的となる場合もある。また、遺伝子や家族の過去の経験によっても、精神疾患に対する感受性が変化する可能性があるという証拠も増えてきている。例えば、マウスの記憶の世代間伝達に関する研究では、恐怖の記憶はエピジェネティックな修飾によって子孫に伝わり、最大で3世代にわたって持続することがわかった(Dias and Ressler 2014)。
不思議な薬はなく、精神疾患の臨床治療が、障害の症状を治療し、副作用を許容できる薬を見つけるために長期の試行錯誤を必要とするように、「治療」の望ましい効果に応じて、医学的な尋問も同様に、行動制御を可能にする適切な薬や食事修正体制を見つけるための個別の試行錯誤を行う必要があり、尋問のプロセスに大きな複雑性をもたらす。
それでも、薬物による尋問を実施するために必要な特注のプロセスは、参入障壁というよりむしろ厄介なものである。過去の拷問プログラムを通じて、方法は標準化されたものではなく、各囚人の心理的影響を最大化するために個別に設計されたものであった。例えば、9・11後のEITの設計と実施において、CIAは行動科学者に、各囚人に特有の心理的弱点や恐怖症を見つけ、それを利用するよう強制した(Bloche and Marks 2005)。ある囚人は、聞き慣れない、文化的に苦痛を与える音楽を聴かされ、またある囚人は、敬虔なイスラム教徒が冒涜と考えるコーランの乱暴な扱いを観察させられた(Blakeley 2011)。

結局のところ、行動薬はCIAのEITと同じ目的、つまり行動統制のために使われる可能性がある。EITが特注品であるために時間がかかり、広範な使用には適さないのと同様に、尋問補助薬の使用は困難であるため、最も難解で価値の高いターゲットにしか適さない。長時間の試行錯誤の必要性がなくなる日が近いかもしれない。ゲノムに基づく医療の発展により、精神疾患の薬物治療に対する患者の反応予測が容易になりつつある(Ozomaro et al. 2013)。遺伝子配列の解析がより迅速かつ安価になり、薬理ゲノミクスの分野が成熟すれば、医師は患者の遺伝子プロファイルを利用して、その人を適切な薬剤に適合させることができるようになるかもしれない。同様に、尋問に薬物を使用しようとする国家が、囚人から血液や唾液のサンプルを入手し、薬物が個人に及ぼす影響を予測することも、より確かなものとなっている。
脳への刺激で記憶や発想を変える
脳への刺激は、ニューロンの電気伝導パターンを変化させることができるため、行動制御を可能にする可能性が高まっている。深部脳刺激(DBS)のように、パーキンソン病やうつ病の治療法としてすでに承認されているものもある(Mayberg et al.2005)。さらに興味深いのは、経頭蓋磁気刺激(TMS)や経頭蓋直流刺激(tDCS)など、非侵襲的に神経伝達を減衰させる新しい刺激アプローチである(Sparing and Mottaghy 2008)。しかし、脳刺激の治療以外の用途も明らかになりつつある(Levasseur-Moreau 2013)。新しい技術を活用した研究が増え、記憶を変えたり、身体をコントロールしたり、脳間で直接アイデアを導入したりする能力の出芽を実証し始めている。
2013年、Ramirezらは、海馬ニューロンへの頭蓋内光刺激を用いて、マウスに恐怖の偽記憶を植え付けるというブレイクスルー論文を発表した(Ramirez et al.2013)。この実験は、初歩的なものではあるが、主要なニューロンの発火パターンを変化させることで記憶を操作できることを実証している。この実験に基づき、Deadwylerら(2013)は、記憶を動物間で伝達することも可能であることを示した。動物が記憶を符号化しているときに観察された発火パターンを抽出し、訓練を受けていないラットに伝達することで、受け取ったラットは、伝達された記憶を利用しなければならない課題を成功させることができた。これらの実験では、外科手術が必要な刺激プローブが使用されたが、記憶をインセプトする新しい能力は、中国やソビエトが囚人を洗脳して新しいイデオロギーを導入しようとした試みを彷彿とさせる。
Spiers and Bendor (2014)が指摘するように、私たちの記憶は最終的に私たちと私たちの世界観を規定する。記憶を変えることで、国家は個人の同盟関係、道徳やイデオロギーに関する長年の信念、あるいは個人のアイデンティティに対する概念を変えることができるかもしれない。しかし、ネズミや人間の記憶を操作することは、かなり大きな飛躍がある。具体的な情報の記憶が、どのように脳内で符号化されるかは、まだよくわかっていない。特に、祖国への忠誠心や殺人の倫理観など、すでに持っている信念に反して、正しい情報を抽出し、行動を起こさせる感情と結びつけることは、さらに難しいことである。TMSやtDCSによる記憶の増強は、より妥当なものである。いくつかのグループは、TMSとtDCSを使用して、短期ワーキングメモリと想起速度を向上させている(Gazzaley et al. 2005)。この点で、軍隊の認知能力を高めようとする国家が関心を寄せているが、攻撃的な用途は最小限である(National Research Council 2008)。
脳への刺激は、表向きには、脳と脳をつなぐ脳-脳ネットワークという新たなアプローチを提供し、身体を制御し、他人の心に影響を与えるという新時代の能力を示している。このようなネットワークは、科学者が脳波計(EEG)を使って「送信者」の脳の電気的活動を記録し、それをインターネット経由で「受信者」に送信することで作られた。受信者はその後、送信者から記録されたメッセージを解読し解釈するためにtDCSを受ける。科学者たちは、人間の脳の間で非侵襲的に情報を伝達することが可能であることも示している。ブレイクスルー脳ネットワーク実験では、コミュニケーションに関連する運動(音節や単語を形成するための口や舌の動きなど)に相関する電気活動を記録し、地球の反対側にいる人(この場合、送信者はインド、受信者はフランス)の脳に直接送信した(Grau et al., 2014)。送信者は、実際に話すことなく、受信者に言葉を伝えることに成功した。同じ技術を使って、ワシントン大学のグループも、送り手だけがモニターを見ることができ、受け手がコントロールを持つというパラダイムを使って、送り手が受け手と感覚情報を共有し、ビデオゲームのプレイで協力を促進できることを実証した(Rao et al. 2014)。地球を侵略する架空のエイリアンの宇宙船にミサイルを撃ち込む必要があるとき、送り手は受け手に伝えることができた。
脳と脳のネットワークの軍事的応用は明らかである。より穏やかなレベルでは、より洗練された脳間コミュニケーションは、指揮統制に革命をもたらす可能性を秘めている。しかし、この技術のもっと悪質な利用法も容易に思いつく。脳神経ネットワークの研究者は、このシステムが最終的に個人間の感情や気持ちを一方的に伝達することになると指摘している(Grau et al.2014)。感情やアイデアが一方的に流れることで、これまでにないレベルの操作が可能になる。もし、人が知らず知らずのうちに脳-脳ネットワークの受信者になっていれば、理論的には思考を植え付けることは極めて容易になる。しかし、現在のところ、脳内ネットワークの研究者は、人間同士のデータ転送のビットレートが低いため、コミュニケーションシステムとしての利用には限界があると指摘している。

脳を刺激する技術が急速に発展しているとはいえ、現状では実験室での使用に限定される。ここで紹介した人間を対象とした実験は、設計上、実世界から切り離されており、運用環境に一般化することはできない(Fisher 2010)。神経刺激にわずかな変化をもたらすには、刺激の強さ、時間、場所など、数多くの要因をコントロールする必要がある(Fisher 2010)。また、脳の深部を刺激するためには、プローブを外科的に設置する必要があり、軍事利用をさらに複雑にしている。さらに、脳刺激の長期的な効果や特異性は現在のところ不明であり、その使用はさらに複雑になっている(Sehm and Ragert 2013)。医薬品による脳化学の操作と同様に、脳刺激を用いて予測可能な方法で操作・制御することは容易ではなく、実現可能でもない。
精神薬にせよ脳刺激にせよ、別の神経細胞のシグナル伝達を変えることは可能であり、行動制御を可能にし、ますます記憶や認知に影響を与えることができる。しかし、このような試みは以前にも行われ、今後行われるであろう試みが同じ理由で放棄された。マインドコントロールは現実的ではない。感情や知覚を変化させて尋問を助ける薬物は、まだ変化しやすく、好ましくない副作用がある。さらに、脳を刺激して記憶を強化したり削除したり、アイデアを思いついたりすることも、実験室の外でこのような目的のために使うには、あまりにも未熟である。このような技術を軍事や諜報に転用するのは難しいが、不可能ではない。
影響力と強制力の網の目を広げる?
これまで、情報収集のためのインタビューにおいて、個人の行動をコントロールし操作する能力、および本人の意思に反して行動せざるを得ないような外国のエージェントを作り出す能力について述べてきた。しかし、ニューロウェポンの標的は個人だけではない。神経科学的な影響力のある武器は、人々の集団もターゲットにすることができる。ニューロウェポンは、心理作戦やプロパガンダに革命をもたらし、人々の認識やその後の政治的欲求を変えることができる。また、軍隊の士気や戦闘能力を低下させたり高めたりすることができる新しい種類の生化学兵器を作り出すために使用することもできる(Royal Society 2012)。ここでは、戦場における脳画像と神経生物化学兵器(NBCW)の使用可能性を検討する。先に述べた個々に焦点を当てた神経科学兵器と同様に、この技術は容易に入手可能である。しかし、その実用性には疑問が残る。集団に焦点を当てた神経科学兵器は、個人にのみ焦点を当てた神経科学アプリケーションとは異なり、このクラスの影響力のある兵器は、従来のアプローチよりも良性、あるいは好ましいと考えられており、したがって、その使用は遅かれ早かれ見られるかもしれないため、興味深い難問となっている。
例えば、脳画像は、非侵襲的でリスクの低い方法であり、影響力行使の心理的影響を事前にテストするために使用することができる。脳画像は個人のプライバシーに関わる興味深い課題だが、この技術を過激に応用しても、他人の神経信号をコントロールしようとする試みのような反発はすぐに起きない。同様に、NBCW(兵器化された精神薬や神経系を攻撃する細菌や寄生虫)は、非致死的な無力化兵器であり、したがって通常兵器よりも人道的であるという評価から、人気を博している。
新しい心理戦?fMRIとニューロインテリジェンス
戦争は、その背景や望ましい戦略的結果にかかわらず、相手の抵抗が自分に有利でないと思わせる能力によって勝敗が決まる。したがって、集団心理の浸透と心理作戦(PSYOP)は、多くの紛争で最も考慮されることである。米軍のドクトリンは、心理戦を、敵軍の士気と戦闘効率を低下させ、敵軍の隊列に不協和音を生じさせ、敵対する政権に対する民間人の抵抗を促進し、米国とその同盟国の利益になる行動をとるよう敵味方を問わず説得することを明確な目的とする作戦と定義している(Goldstein and Findley 1996)。通常、心理戦はプロパガンダ映画、アートワーク、ラジオ番組、世論を動かすための戦略的な(不)情報の公開に限定して考えられているが、「心をつかむ」「衝撃と畏怖」を目的とした軍事行動やテロ攻撃はすべて、心理戦のレンズを通して見ることができる(Szafranski 1997)。
その重要性にもかかわらず、心理戦はあまり理解されておらず、定量的で予測可能な結果を保証できないため、欧米では広く蔑視されている(Goldstein and Findley 1996)。爆弾は投下された相手には致命的だが、その広範な心理的効果は未知数であったり、軍事作戦の目標と矛盾している場合がある。さらに、従来の心理戦はほとんどの場合、複雑な環境で実施されるため、PSYOPが功を奏した、あるいは軍事的・外交的発展につながったという確実な結論を出すことは困難であった。最も重要なことは、対象者の心に響く効果的な心理戦を設計することは非常に難しいということである。集団的価値観、アイデンティティ、意思決定プロセスなど、対象社会の文化に対する微妙な理解が必要である(Goldstein and Findley 1996)。しかし、国家が対象者についてこのような理解を持っていなければ、対象者に影響を与えることは望めない。
機能的磁気共鳴画像法(fMRI)は、これらの問題に対する解決策を提供できるかもしれない(Wurzman and Giordano 2014, pp.93-96).最近、fMRIによって、科学者は、脳が異なるアイデアにどのように反応するかを分析できるようになり、集団の集団的アイデンティティや文化について具体的な洞察を得られるようになった(Berns and Atran 2012)。伝統的にそのように考えられてはいないが、文化と生物学は深く絡み合っている(Berns and Atran 2012)。様々なシナリオに対する生理的反応は、世界に対する理解、意思決定の方法、敵と味方を区別するシステムなどと不可分に結びついている。例えば、神の存在について質問されたとき、宗教家と無神論者の生理的反応は、不安や苦痛のレベルが異なることを示す。宗教家は不安が減少し、無神論者の脳は苦痛の神経生理学的マーカーを示す(Inzlicht and Tullett 2010)。生物学的マーカーの活性化の原因は同じであり、神の概念に対して異なる反応を示すような生物学的な違いは2つのグループにはないのだが、認知的意思決定や既存の価値観から生じる感情の違いが、生物学的マーカーの活性化の違いに関係している(Berns and Atran 2012)。fMRI研究は、この原理を利用して、集団の認知プロセスや文化に関する情報を得ようとするものである。
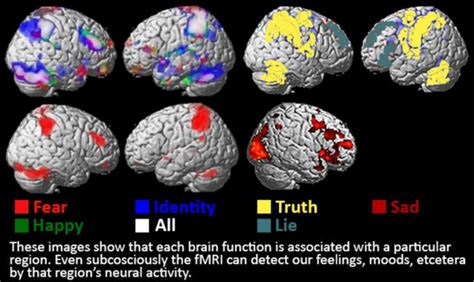
磁気共鳴画像法(MRI)は、大きな磁石を使って水素原子核に含まれる陽子のスピンを変化させ、振動を誘発し、それを記録することで様々な内部生理構造の画像を作成する(Deichmann 2009; Logothetis 2008)。機能的イメージング(fMRI)は、通常のMRIとは異なり、静止画像を撮影するのではなく、脳領域の血流変化をリアルタイムで測定し、それを指標として領域の活性化を定量化する(Deichmann 2009)。単一の脳領域における活性化の連鎖は、感情や認知のような複雑なものについての情報を提供するには一次元的すぎる(Ariely and Berns 2010)。しかし、研究者たちは、さまざまな出来事に反応する集団には、信頼できる一貫した活性化パターンがあることを発見した(Hasson et al. 2004)。したがって、fMRIは、感情や高度な認知過程に対するベースラインの活性化パターンを確立し、これらの集約データを使用して、異なる人々の将来のfMRI画像を感情や認知に相関させることができるため、科学者が強力なツールである。fMRIの最も魅力的な側面は、たとえ人があるテーマについて自分の感情、思考、好みを明確に表現できなくても、脳画像によって研究者がこれらの内面を相関的に理解できることである(Ariely and Berns 2010)。
従来の人類学的、社会学的な集団の研究とは異なり、fMRIは、成功の保証と測定可能な結果を可能にする測定可能な心理戦を可能にすると思われる。理論的には、国家はfMRI研究を利用して、プロパガンダや軍事攻撃のシミュレーションに反応する恐怖、攻撃性、あるいは愛国心や献身といったより複雑なプロセスの相対レベルを測定することができる。したがって、国家はこの情報を使って、面接や調査に伴う固有のバイアスやセキュリティ上の問題に依存することなく、心理作戦と軍事作戦の両方の効果を予測し最適化することができる。同様に、fMRIは、ある集団が何に価値を置いているのか、あるいはどのように意思決定を行っているのかを明らかにすることで、文化的な現象に対する洞察を提供すると考えられている(Pincus et al.2014)。このため、GiordanoとWurzmanは、fMRIは認知プロセスの聖杯へのアクセスを提供し、これを統計的に集約すれば、まったく新しいクラスのインテリジェンスである「NEURINT」(Wurzman and Giordano 2014, pp.93-96)が得られると主張している2)。
この主張は、まったくメリットがないわけではない。まだ発展段階だが、DARPAの「ナラティブ・ネットワークス」プログラムは、fMRIを他の神経画像プラットフォームと併用して、過激派の物語やプロパガンダが、道徳に関する判断に関連する神経回路にどのように影響するか、物語を聞くことでどのように感情を呼び起こすかを理解している(Sanchez 2017; Venkatramanan 2011)。最終的にDARPAは、物語に対する神経反応が筋書きを決定する閉ループシステムの開発を目指している(Miranda et al. 2015)。fMRIを使用して、さまざまな物語に対する脳の反応に関する基準値を作成し、心理戦や情報キャンペーンを強化して望ましい結果を生み出すことができる。例えば、恐怖や信頼を呼び起こす心理戦を設計しようとする場合、科学者は理論上、fMRIを使用して恐怖と相関する領域の脳の活性化の違いを測定し、どのような種類のプロパガンダが最も恐ろしいかを判断することができる。
fMRIはまた、外国の不透明な文化に影響を与えようとする行為者が、越えてはならない一線を決定するためのツールとしても提案されている。実験者は、金銭的な利益のために自分の信念を破る、または交換するよう求められたときに、義務論または功利主義の評価と相関するfMRIスキャンに基づいて、その人の神聖な価値観を判断できると考えている(Berns and Atran 2012)。この研究で記録された神経反応は、神聖な価値観とそうでない価値観を見分けるために、より広く集団に外挿することができる。この研究の著者は、この実験と同様の実験に基づいて、政府は過激派対策プログラムにおいてfMRIを使用し、テロリストに任務を継続させる動機となる主要な価値観を解析したり、社会の集団的価値観を決定し、違反した場合に市民からの反発を招くと主張している(Giordano 2014; Astorino-Courtois et al., 2017)。確かに、NEURINTを収集する技術的-方法論的に限定的ではあるが-可能性はある。しかし、研究室以外でfMRIを使用する学者やマーケティング担当者による過去の試みを検証すると、国家がNEURINT能力を確立しようとする場合に直面する可能性のある困難が示される。
「NEURINT」の実用的な限界:ニューロマーケティングのケーススタディ
心理戦の設計者とマーケティング担当者には多くの共通点がある-彼らはどちらもメッセージを通じて人々の行動に影響を与え、変えようとする。選択と経済的意思決定の神経相関に関する数々の実験の後、神経科学者と経済学者が一緒になって、fMRIを使って消費者行動を予測しようと試み、ニューロマーケティングを誕生させた(Morin 2011)。ニューロマーケティングの専門家は、潜在顧客のサンプルのfMRIを調べることで、商品の人気を予測できると主張している。例えば、Berns and Moore (2012)は、将来の購買決定に関連することが知られている領域の神経活性化と将来のアルバム販売との間に事後的な相関を見出した。これらの著者らは、新曲に対する同じ領域の活性化が、そのアルバムの将来の市場での成功を予測することを示唆している。にもかかわらず、マーケティング担当者は、多くの理由から、製品設計や広告のライフサイクルにおいてfMRI実験を広く敬遠してきた。

この種の研究はきれいなイメージを与えるが、fMRIマーケティング研究が、従来の市場調査(フォーカスグループや市場テストなど)よりも実際に良い情報を提供するかどうかは不明である(Ariely and Berns 2010)。fMRIを用いたニューロマーケティングの手法では、被験者が提示されたさまざまな選択肢に対する被験者の好みを区別することしかできないため、独自の設計と試行錯誤が必要である。また、フォーカスグループやアンケートといった従来の手法とは異なり、fMRIを用いた研究では、提示された選択肢がすべて悪いものであるかどうかを市場研究者に伝えることはできない。fMRIを使えば、どの選択肢が一番ひどいものでないかをニューロマーケターに伝えることはできるが、どの広告が特に効果的でないかを研究者が知ることはできない。心理戦の設計という文脈では、関係者は同じ課題に直面することになる。さらに、ニューロマーケティング担当者が直面する多くの交絡因子があり、fMRIで製品に対する選択や嗜好の原動力を解明することは困難である。例えば、品質への期待(例:安いワインと高いワイン)やブランドは、いずれもfMRIの結果に実証的な影響を与えるため、単一の要因を操作して広告を最適化することは難しい(McClure et al.2004; Plassmann et al.2008)。
fMRIが他の方法では得られない情報を提供できると寛大に仮定しても、基本的な方法論の限界により、fMRI、ひいてはNEURINTが軍事投資に値する有意義なツールになることはない。WurzmenとGiordanoが述べたようなNEURINT作戦を実施するためには、国家は対象集団から代表的なボランティアのサンプルを入手する必要がある。これは、紛争において当然の結論ではない。戦闘的なテロリストや不可解な敵など、NEURINTが最も有用な集団は、fMRI研究によって統計的にサンプリングするのが最も困難であることも証明されそうだ。さらに、参加者はMRI内で完全に静止していなければならず、協力的な被験者が必要である。また、MRIに入る際、被験者を完全に静止させる必要があるため、被験者の協力が必要である。さらに、多くの心理戦の成功は、ある程度の隠密性を前提にしている(Goldstein and Findley 1996)。代表的かつ統計的に有効な集団から NEURINTを収集するために必要な運用上のセキュリティを導入することは、重要な挑戦であることが判明している。技術的には可能かもしれないが、心理戦やNUERINTを可能にするためのfMRIの使用には、その使用を妨げる現実的な課題がある。
意志の力を引き出す生化学兵器
最終的に、心理作戦の目標は、敵対勢力の戦意や能力を低下させ、民間人の士気を低下させることである。この目的のためのより直接的なアプローチは、NBCWの広範な展開である。NBCWは、中枢神経系を標的とする精神薬や病原体を利用して、軍隊や敵国の国内住民の感情、認知、知覚を変化させるものである。国家は、労力を要する心理戦によって国民に微妙な影響を与えたり、強制したりするのではなく、NBCWによって市民住民の心を変えたり、過激派住民を急速に劣化させたり無力化させたりすることを目指すかもしれない。
先に述べたように、精神科の薬は感情、認知、行動を支える神経シグナルを減衰させることができる。個別に使用する場合、尋問に役立つような感情を生み出すのに適している。しかし、同じ医薬品が戦場で広く使用されることは、通常兵力に対する脅威と見なされるようになってきている。例えば 2008年のDIA主催の報告書では、小規模な集団がNBCWを使用して、戦闘に参加せずに大規模な米軍の戦闘能力を迅速に無力化または低下させる恐れがあると記述されている(National Research Council 2008, p.108)。さらに、2016年の化学兵器禁止条約(CWC)締約国会議では、中枢神経系に作用する無力化剤が化学兵器の禁止に大きな課題をもたらすという懸念が多数の国から示された。CWCの下では、法執行機関が暴動鎮圧のために使用する化学物質は禁止されていない。この抜け穴により、国家は暴動鎮圧剤を装った高度なNBCWを合法的に開発し、紛争で配備することが可能になる可能性がある。

最も脅威的で、最も使用される可能性が高いNBCWは、覚醒度を下げ、鎮静化し、麻酔をかける催眠剤である(王立協会 2012, p. 44)。しかし、認知、感情、行動を変化させるサイケデリック・ドラッグも、意識を混乱させる能力があるため、戦場での展開の可能性を秘めている。さらに、尋問の補助として先に述べた医薬品も、戦場で衰弱した恐怖と不安を煽るために大量生産して兵器化することができる。神経系を標的とする数多くの微生物や毒素も、戦うか降伏するかの意思決定プロセスに影響を与える可能性がある4。例えば、寄生虫のトキソプラズマ・ゴンジーは衝動性、興奮、混乱を引き起こし、ガンビアディスカス・トキシクス菌は悪夢や灼熱感を引き起こすことがある(Wurzman and Giordano 2014, p. 104)。
神経系を標的とする兵器は、新しいものではない。神経剤(サリン、サビン、VXなど)は、主要な運動領域のアセチルコリン伝達を操作することで機能し、その後、筋肉の痙攣、麻痺、死亡を引き起こす。ここで注目されるNBCWの種類、すなわち行動に影響を与える薬物やバグが他の生物・化学兵器と異なるのは、殺すというよりむしろ、非殺傷的に無力化する能力を備えていることである。歴史上、行動に影響を与える薬物の製造が試みられた例は枚挙にいとまがないほどだ。米国がスポンサーとなったLSD実験は、もともと軍隊の戦闘能力を急速に低下させる化学兵器の開発に焦点を当てた陸軍のプロジェクトとして始まった(Marks 1979, pp.39-54)。さらに、機密指定を解除された米空軍の文書によると、米国は媚薬を兵器化した「ゲイ爆弾」を開発しようとしており、敵兵を互いに性的に抵抗できないようにし、戦闘員の士気に「鋭い打撃」を与えることを目的としていた(ライト研究所 2005)。ゲイ爆弾は実現不可能と判断されたため実現しなかったが、現在、戦闘中にスケールアップして配備することが可能な、行動に影響を与える薬物群がいくつか存在する。
医薬品も微生物も、戦闘中に士気を低下させ、隊列を乱したり逃げ出したりすることがある。同様に、薬物や虫は、自国の軍隊の攻撃性、警戒性、反応性を高めるために使用することができる(Royal Society 2012)。これらのNBCWは、戦闘部隊の認識を変化させる能力を持っており、また人口密集地に拡散すれば、指導者に対する政治的支持を速やかに変化させ、内乱を引き起こすことができる(Royal Society 2012, p. 50)。しかし、生物・化学兵器が常に直面してきた課題、すなわち薬剤の効果的な運搬と拡散は、神経を標的とするNBCWにも依然として関連している。
新しい科学と古い問題
2002年秋、ロシアの特殊部隊は、アヘン剤であるカルフェンタニルとレミフェンタニルの混合物をモスクワのチェチェン反乱軍に包囲されている劇場に投入した。これらのオピオイドの戦術的使用は、鎮静化し、命を失うことなく捕虜の逮捕を可能にすることを目的としていた(Walsh 2002)。しかし、オピオイドの混合液は均一な方法で配布されなかったため、劇場全体で濃度と用量が異なり、チェチェンの反政府勢力全員だけでなく、人質の129人が死亡した(Tracey and Flower 2014)。このよく言われる作戦は、戦場にNBCWを配備する際のもう一つの技術的課題である、広範囲かつ均一な拡散を強調している。大規模な地上部隊を無力化するために薬物を使用する場合、NBCWに関連する非殺傷性を維持するために、全員に均等に影響する分布と投与量を得ることは、重大な課題となるであろう。

NBCW は皮膚吸収によって拡散されることもあるが、血液脳関門を通過するために薬剤がまず血流に入る必要があるため、エアロゾル化および吸入が、NBCWの拡散に好ましい方法である(Royal Society 2012, p. 50)5。エアロゾル化は、生物・化学兵器使用を目指す非国家活動家に大きな障害をもたらすことが実証されている。エアロゾルの飛沫は、呼吸器組織を通過して血流に入ることができるよう、一定の大きさである必要がある。飛沫が小さすぎると、粒子は単に吐き出されるだけだ。大きすぎると、飛沫は呼吸器の通路に閉じ込められる。弾薬は生物・化学兵器を運搬し、正しくエアロゾル化することができるが、衝突時に兵器の大部分を分解してしまうため、その実用性は限定的である(Kerr 2008)。しかし、従来の生物・化学兵器に対する。NBCWの利点が、気分や知覚を非致死的に変化させる能力にあるとすれば、弾薬自体の爆発による高い死亡率は、望ましい非致死的結果を阻害することになるであろう。
工業用噴霧器も、NBCWをエアロゾル化して運搬することができるが、噴霧器を標的集団に近づけることは困難である。しかし、噴霧器へのアクセスは、必ずしも、NBCWを拡散させる能力を示すものではない。「スイートスポット」で飛沫を得ることの難しさは、多くの自称バイオテロリストが攻撃を成功させるのを妨げてきたし、今後もそうであろう。例えば、1993年に日本のオウム真理教が炭疽菌を使ったテロ攻撃を試みたが、彼らの拡散方法は、体内に吸収されるどころか、風で運ばれるには大きすぎる飛沫を生成したために失敗した(高橋ら 2004)。高度な技術やガスとして利用できる薬剤を利用できる国家にとってはこのような問題は少ないが、モスクワ劇場の事件が示すように、大人数を無力化するのに必要な投与量のばらつきを考慮した方法でNBCWを拡散することは、不可能ではないにしても困難である。
ある行為者がこの種の兵器を広範に展開し、意図したすべてのターゲットに、行動に影響を与えるには十分だが殺すには至らない線量を確実に与えることができるシナリオを想像することは難しい。ある人にとって適切な量であっても、別の人にとっては致命的な量となりうる。同様に、個人の免疫学的プロファイルがさまざまであることを考慮すると、行動を変化させる微生物は、ある人には完璧に作用するが、ある人には効果がない可能性がある(Tracey and Flower 2014)。普及と配布さえも達成できないのであれば、これらの兵器は従来の生物・化学兵器と何ら変わりはない。
表面的にはfMRIとNBCWは、社会と軍隊を制御し操作するために行動神経科学を利用する能力を提示しているように見える。fMRIは理論的には心理戦の設計に役立つかもしれないが、その使用によって生じる複雑さと、安全保障サービスに提供できる利点はわずかであるため、使用されることはないだろう。同様に、行動に影響を与えることができる。NBCW 剤は数多く存在するが、非致死的特性を維持したまま兵器化することは、その使用を著しく制限する。
結論
行動と認知の生物学的基盤における科学的ブレークスルーは、世界中の多くの人々の生活の質を向上させる、神経学的および精神医学的障害に対する数多くの治療法を生み出してきた。神経科学における現在の発展は、兵器化やその他の軍事・諜報用途への可能性に新たな関心を呼び起こしたが、これらの発展に関する誇大広告は、現在の能力をはるかに超えている。精神薬、脳刺激、脳画像、NCBWは、感情や記憶の改変、発想の転換、認知の転換、行動への影響などに悪用される可能性がある。しかし、それを行うにはまだ技術的に大きな課題があり、ニューロウェポンを運用することは極めて困難である。
しかし、マインド・コントロールの約束が神経兵器によってすぐに実現されるとは思えないが、行動制御へのアプローチが時間とともに洗練され、より良い精神医学的治療を追求し続ける中で誤用への障壁が低くならないと考えるのは甘すぎるだろう。この点は、生命科学から発せられる脅威認識の変化に、より広く貢献している他の分野での科学の進歩の速さによって強調されている。過去5年間で、遺伝子編集と合成生物学は大きな進歩を遂げ、致死性の高い生物学的薬剤が研究室でゼロから生産されたり(DiEuliis et al. 2017; Koblentz 2017)、より致死性が高く、伝染性があり、既存の医療対策に耐性を持つ遺伝子組み換え病原体が作られたり(Clapper 2016)するという新しい恐怖が生じた。さらに、DiEuliisとGiordano(2017)は、CRISPR/CAS-9遺伝子編集が、中枢神経系に作用する現在の兵器的病原体よりもはるかに優れた新規神経兵器への道として使用される可能性があると指摘している。神経科学が進歩すれば、ここで取り上げた技術は、その開発に必要な時間、資金、資源を惜しまない行為者によって武器化され、展開される可能性がある。
国際人道法6と軍備法7は、神経兵器の開発と使用を管理する上で極めて重要な構成要素となっている。表面的には、これらの基準は神経兵器を禁止している。しかし、その強さは、あいまいさと国家主体による反抗によって弱体化している。例えば、国際機関による拷問に該当する具体的な行為に関する指針がないため、ブッシュ政権は、CIAのEITは国際法が要求する痛みや精神的損傷の深刻さの閾値を満たしておらず、したがって既存の条約の下では拷問と見なされないと主張した(メイヤーフェルド 2007)。国家による行動制御の試みという文脈では、脳の内部構造を悪意を持って変化させる医薬品や神経技術の使用を説明するために、同じ議論が使われることがある。軍備法によるNBCWsの禁止はより強力だが、ここにも抜け穴と曖昧さがある。例えば、化学兵器禁止条約で暴動鎮圧用の化学兵器が除外されているため、国家が国内の暴動鎮圧剤を装って合法的に無力化兵器を開発し、紛争で使用するためにNBCWを迅速に転用する余地がある(Royal Society 2012, pp.21~24)。

ガバナンスの枠組みをさらに難しくしているのは、ここで述べた技術がより発展するにつれて、生物兵器に関してより一般的に目撃されているように、認識される有用性に変化が生じるかもしれないという示唆である(Lentzos 2017)。例えば、Keane(2010)は、陶酔状態やポジティブな感情をシミュレートして人に話をさせる薬物は、許されるだけでなく、拷問や強化尋問の道徳的に優れた代替物であると示唆している。神経科学に基づく影響力兵器の有用性に関する既存の社会政治的な計算は変化し、さらなる軍事・情報開発の原動力になるかもしれない。こうした認識の変化は、地政学的な動揺の増大や国家中心の紛争からの脱却と相まって、行動制御がこれまで以上に魅力的になる可能性がある(Dando 2015, pp.174-75)。
この予測が真実であるとすれば、神経科学に基づく影響力兵器の認識の変化は、人道法および軍備法に大きな負担をかけることになる。最近の歴史では、非人道的な扱いに対するタブーや生化学兵器に対する挑戦が何度か行われており、こうした挑戦は今後も続くと思われる。例えばシリアでは、塩素ガスやサリンガスによる攻撃で民間人を無差別に狙う化学兵器が継続的に使用されており、国連がその使用を防止し罰することができないことは、非通常兵器に関連する国際的タブーを大きく危険にさらし、化学兵器攻撃のより広い正統性を高める危険性がある(Ilichmann and Revill 2014)。さらに、EITsの使用に関する国際原則を守ろうとしないブッシュ政権の姿勢は、拷問に対する規範を全般的に低下させる結果となった(マキューン2009)。人道法による禁止や上級尋問官の勧告にもかかわらず、意思決定のトップリーダーは、拷問が有効であると確信したまま、人権を守ることを拒否している。トランプ大統領は、強制的な技法を積極的に推進しているように見える。選挙運動中も就任後も、トランプ大統領は拷問の有効性を信じていると述べ、「水責めよりももっとひどい地獄を復活させる」とまで言い(McCarthy 2016; Gordon 2017)、警察の過剰な残虐行為を主張している(Wootson and Berman 2017)。さらに、ロシア併合後のクリミアから発せられる拷問や人権侵害の報告もあり(Cumming- Bruce 2017)、中国の囚人は囚人の意志力を低下させ、協力を煽るために考案された攻撃的な尋問方法にさらされ続けている(Washington Post Editorial Board 2017)。
世界秩序がアメリカという明確な支配国から、台頭する大国が人権、正義、透明性、武力行使を異なる視点で捉える多極化する世界へと移行し続ける中、人道法と軍備法に対する挑戦は増すばかりである。行動神経科学が良性の医療から悪性の兵器へと転換するのを監視し、神経兵器がどのように認識され使用されるかを形成するためには、国際社会が多国間条約や国内の法律や規制で具体化された既存の規範的・法的枠組みを強化することが最も重要である。医師や科学者が守るべき医療基準、行動規範、研究倫理も、行動神経科学の誤用の可能性を考慮して、強化されなければならない。神経兵器の封じ込めは、拷問、非伝統的兵器、神経科学の過激な使用に対するトップダウンとボトムアップの規範の強化に依存する。
ここで紹介する分析は、国家が高度な兵器や予測可能性、有効性の保証を求め、国際規範や条約を遵守することを強制することが大きな前提となっている。これらの要件が方程式から取り除かれれば、神経兵器の参入障壁は急速に低下する。例えば、テロリスト集団は、拷問への直接的なルートとして、あるいは以前のソ連の尋問の試みのように、単にあらゆる種類の犯罪を公に「自白」させるために精神薬を求めるかもしれない。さらに、精神医薬の投与には専門的な知識が必要だが、ストリート・ドラッグが広く使用され入手可能なため、その効果はよく知られており、それを支える神経科学的な原理を基本的に理解していなくても使用することが可能である。正確な情報を引き出すために薬物を利用しようとする国家が直面するような予測可能性と信頼性の必要性に直面することなく、素朴な非国家集団がLSDやその他の精神を刺激する薬物を入手し、囚人に密かに投与することは比較的容易であろう。イスラム国(ISIS)はすでに医薬品を使用して、戦闘員にアンフェタミンであるカプタゲンを投与している。このアンフェタゲンは、帰還した戦闘員の報告に基づいて、ISISの戦闘員を痛みに対して抵抗力を持ち、より勇敢にする効果がある(Gidda 2017)。さらに、国家はこれらの技術を内向きにし、国内住民に対して使用することも同様に簡単にできる。ここで紹介した技術は、暴動鎮圧剤や麻薬分析に使われることもあるが、脳画像は、有権者の一部に焦点を当てた政治的メッセージを作成する際にも、興味深い示唆を与えてくれる。
そのような注意点はさておき、まとめると: 神経科学を利用して影響を与えたり、強制したり、操作したりすることは脅威なのだろうか?はい、そうだ。まだ困難ではあるが、行動神経科学を利用して新しいクラスの影響力兵器を実現するための技術的可能性が出てきている。しかし、それは近い将来の脅威ではなく、神経科学をより安価で簡単に戦闘環境で使用できるようにする技術開発に大きく依存し、さらに組織的、経営的、社会的、政治的、経済的要因にも依存する(Ben Ouagrham-Gormley 2014)。また、国際法や倫理基準を無視する行為者の意欲にも左右される。科学者も国際社会も、行動神経科学が安全保障の領域に漏れることに警戒し続けなければならない。
倫理基準の遵守
利益相反著者ともに利益相反はない。
倫理的承認この原稿に含まれる研究は、組織的な倫理的監視の対象にはなっていない。
