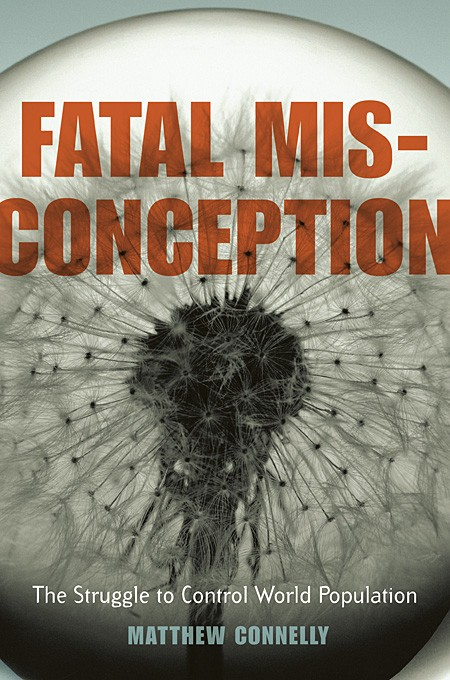
Fatal misconception: the struggle to control world population
著者
Matthew Connelly コロンビア大学教授(歴史学)
ハーバード大学出版局ベルクナップ・プレス
マサチューセッツ州ケンブリッジ/イギリス・ロンドン2008年
私の両親へ、たくさんの子供を産んでくれてありがとう
目次
- 前書
- 略語
- はじめに 生物学はいかにして歴史になったか
- 1. 制御不能な個体群
- 2. 地球を受け継ぐために
- 3. 戦争する人口
- 4. 第三世界の誕生
- 5. 人口の確立
- 6. 国家を支配する
- 7. 家族計画を超えて
- 8. 脳を持たないシステム
- 9. 権利の再生産、健康の再生産
- おわりに 未来の脅威
- ノート
- アーカイヴとインタビュー
- 謝辞
- 索引
前書き
この本を書くのは大変なことだったが、この献辞は本当に自分で書いたものである。人口抑制運動について語ろうと思ったとき、それはすでに私の両親への賛辞であることに気がついた。何しろ私は8人兄弟の末っ子である。この事実を口にするだけで、ほとんどの人が驚きの声を上げる。私の両親がカトリック教徒であることを聞けば、簡単な説明で納得してくれる。実際,私が妊娠し、生まれた1967年まで、アメリカのカトリック教徒は他の人々とほとんど同じ割合で避妊をしていた。特に敬虔だった私の祖母は、子供が生まれるたびに呆然とした表情で迎えていた。祖母の自慢の息子は、「どの孫が生まれなければよかったのか」と、唯一、鋭い言葉を交わしたことを覚えている。
1960年代後半から1970年代前半は、大家族を育てるには大変な時代だったから、私の場合はタフネスが必須条件であったのかもしれない。9人乗りのステーションワゴンの10人目としてガソリンスタンドで長い行列に並んだこともよく覚えている。1968年の民主党と共和党の綱領がほぼ同じ内容で、人口抑制が緊急の課題であることを裏付けていたことを忘れてはならない。この年に出版されたベストセラー、ポール・エーリック著『人口爆弾』は、「全人類を養うための戦いは終わった」と主張している。1970年代、世界は飢饉に見舞われ、何億人もの人々が餓死することになる。私が生まれたその日、インディラ・ガンジー率いるインド内閣は、3人以上の子供を持つ親に対して初めて強制不妊手術を行うことを検討した。そして、エールリッヒは、「アメリカの子供一人の誕生は、インドの子供の誕生の50倍の災いを世界にもたらす」と考えていた。
本書は、人口抑制だけが世界を救うと主張したガンジーやエールリッヒらに対して批判的である。何となく、個人的に選んでしまったからだろうか?実は、研究を始めた時には、このようなことは全く知らなかった。私は、大国の興亡を研究するために歴史家になった。私の師匠であるポール・ケネディは、文字通りこのテーマについて本を書いていた。私が世界人口の増加に関心を持ったのは、ケネディが、冷戦後の新しい時代を理解するためには、大国間の対立を超えたところに目を向ける必要があると主張したからにほかならない。私たちは、『アトランティック・マンスリー』誌のカバーストーリーを共同執筆し、貧しい国々での人口増加、経済的不平等の認識の高まり、大量移住の見通しなどが、「西側」と「それ以外」の間の衝突につながるかもしれないと警告した。私たちは、開発援助、技術移転、そして避妊のための追加的な資金提供を求めたが、ケネディは中絶はダメだと明言した。私の恩師は、両者を道徳的に区別していた。一方、私は、ロー対ウェイド裁判の後に育った多くの人々と同じように、避妊と中絶のどちらについても特別な感情を抱いていなかった。子供を産むかどうか、いつ産むかを決める権利は、「定説」のように思われていた。
数年後、国際安全保障の理解を深めるための一つの方法だと思い、このテーマで本を書き始めたとき、私はあることに気がついた。残念なことに、他の著者も数十年前に同様の警告を発していた。膨れ上がった貧困層が自分たちの窮状を理解し始め、自分自身や他人に対する差し迫った脅威となりつつあるというのである。10年後、この積み重ねはさらに大きくなっている。アトランティックの記事は、富と権力の差を出生率の差の問題に還元する一連の著作のひとつに過ぎないが、それはあまりにも頻繁に「私たち」と「彼ら」という言葉で語られる。
貧しい国々は長い間出生率が高く、これが問題の一部であることは明らかであり、子供を少なくすることが解決策となるように思われてきた。しかし、このような見方はデータからは支持されない。確かに、労働人口が多く、子供の数が比較的少ない社会では、一時的に可処分所得が多くなる傾向がある(つまり、この世代が年金を受け取ろうとするまでの間)。しかし、どんなに高度な定量調査でも、価値観の問題である以上、解決することはできない。ほとんどの人は、子供を産むことによって「一人当たりのGNP」が減ることを喜んでいるし、それを後悔している人ばかりではない。貧しい国で避妊具を配布するプログラムは、人口増加にわずかな影響しか与えていない。それよりもはるかに重要なのは、人々が実際に少人数の家族を持ちたいと思っているかどうかである。インド、中国、その他の国々が、現金支給や明白な強制によってこうした嗜好を変えようとしたとき、その結果は悲惨なものだった。私たちは、今後何世代にもわたって、このような状況とともに生きていくことになる。
資料館を渡り歩き、何千もの文書に目を通し、この歴史を作った人々にインタビューするうちに、私は、国家安全保障の再定義よりもはるかに多くの問題があることを理解し始めた。これは、ある人々が、誰にも答えることなく他者を支配しようとしたことを示す物語である。彼らは冷酷で、衝撃的な方法で人を操ることができる。おそらく私たちは、自分たちと違う人間は「打ちのめされた民族の打ちのめされた人間」に違いないと思い込んでいた帰化主義者や優生学者に、それほどの期待を抱かないだろう。しかし、多くの人々は、ケネディや私とは違って、貧困を減らし、紛争を防ぐという善意を持っていた。もちろん、私たちは強制的な手段をとろうとはせず、避妊を増やすことだけを主張した。しかし、私たちは人口増加が鈍化していることも知っていた。一方、私が書いた人々は、人類の歴史上まったく前例のないことに直面していた。世界人口は加速度的に倍増し、さらに倍増していた。
このように、どうしようもないほど増え続ける人口を前にして、思慮深い観察者たちは自問したものだ。「人は何のためにいるのか?」なぜなら、それらは最終的に人生の意味と目的に関わるからだ。本書は実存的な問いに決着をつけようとはしない。しかし、歴史作品は、少なくとも、一部の人々が、自分が一番よく知っていると考え、他人の代わりに答えられると信じたときに何が起こるかを示すことができる。事実上、彼らは政治的な問題を生物学的な根拠を持つ病理として診断していた。この論理は、最も極端な場合、「不適合者」の不妊手術や民族浄化につながった。しかし、家族計画でさえも、推進派が他人の家族を計画することを目的とし、「対象者」を「受け入れ側」として卑下した場合には、人口コントロールの一形態となり得る。その中には、金銭を受け取って不妊手術に同意した何千万人もの貧しい人々も含まれていた。さらに何億人もの人々が避妊具や人工妊娠中絶を利用できないようにしたのも、彼らにもっと子供を産んでほしいからだ。
この本は、世界の人口をコントロールすることによって人類を作り変えようとした、最も野心的な人口コントロール計画について書かれたもので、典型的には貧しい人々や貧しい国の出生率を低下させることによって行われた。しかし、すべての人口抑制計画は、社会が意識的に自己複製を行うべきであるという前提を共有しており、たとえそれが人々が自分自身の体をどのように処分するかを管理することを意味するとしても。そして、人間を個人としてではなく、信仰と科学の力を結集して形成される集団として捉えていた。だからこそ、出生主義、優生学、先天性主義、そして強制的あるいは操作的な「家族計画」が共通の歴史を持ち、それらがどのように発展し、どのように分岐し、最終的にリプロダクティブ・ライツの大義がどのように救済されたかを理解する助けになる。
今日、これらの問題について論じる者は、自らを「プロライフ」あるいは「プロチョイス」と名乗ることを期待されている。この2つの陣営は対立し、両立しないように見える原則を唱えている。しかし、これはある人々が生命の尊厳と個人の自律性の両方をいかに組織的に切り捨ててきたかの歴史である。私はこの戦いに遅れて参加したため、この本は、どちらかの陣営にではなく、むしろ、将来さらに危険な実験になるかもしれないものを阻止するためには、共通の大義を持たなければならないという信念に基づく転向者の情熱を反映している。本書は、「人口抑制」をめぐる諸問題を解決するために、私たちが共通して取り組むべきことを述べている。
はじめに 生物学はいかにして歴史になったか
人口がどのように増加し、変化するかを考えることは、長い間、未来を想像するための手段であった。政治的な争い、文化戦争、技術革命が絶えず私たちを驚かせる一方で、世代の交代は人生の数少ない確かなことのように思われる。今日生まれたほとんどの赤ちゃんは、両親と同じように成長し、自分たちの子供を産む。国連の人口統計学者が定期的に行っている、出生率、死亡率、移動率に関する仮定を特定し、50年後、100年後の人々の世界を眺めるという数学的な演習に過ぎない。その数字は大陸ごと、国ごとに分解され、私たち一人ひとりが何らかの運命共同体の一員であることを実感することができる。国連が「これは予測であって、予言ではない」と注意深く説明しても、ジャーナリストは統計的予言として報じる。
しかし、ちょっと想像してみよう。国連が予測したものよりもはるかに暗いビジョンの中の世界と人々を。平均寿命が30歳を切った世界を想像してみよう。多くの赤ちゃんは1歳の誕生日を迎えることができない。慢性的な栄養失調にさらされた子どもたちは、病気にかかりやすく、成長が遅く、学習もままならない。大人になるまで生き延びても、平均的な体格は私たちの体格の3分の1ほどで、発育不良のように見える。大多数は陸上で生活している。都市に住む少数の人々は、自分たちの廃棄物と微生物が生きている水を飲み、さらに早死にする可能性が高い。地球上の人口は10億人にも満たず、現在の6分の1以下である。
これは黙示録的な未来ではない。200年前に私たちが残した世界なのだ。その頃、トーマス・マルサスは『人口原理に関する試論』を書き、「将来の社会の改善に影響する」としていた。マルサスにとって、飢餓は人口を減らすだけでなく、生き残った人々の肉体、さらには魂をも衰えさせるものであった。
子供たちは食べ物の不足で病気がちだ。健康なときのバラ色の頬は、不幸なときの青白い頬とくぼんだ目に変わる。わずかな胸にまだ残っている善意が、かすかな息絶えようとしているとき、ついに自己愛がもとの帝国に戻り、世界に勝利をおさめるのだ1。
マルサスは、ヨーロッパで最も栄養状態がよく、健康な人々の中で生活していた。平均身長5フィート6、体重136ポンドのイギリス人男性は、1日わずか1,800カロリーで生活しているフランス人男性より3インチも背が高かった。マルサスが、無慈悲な自然の摂理に逆らい、同じ運命をたどるのは愚かなことだと考えたのは、彼が書いた世界を考えれば、理解できる。その後、マルサスはこの論文を改訂し、さらに発展させた。しかし、その陰鬱な雰囲気は一向に晴れることはなかった。マルサスにとって、「不幸と不幸への恐怖」は、「人間の存在の現段階における自然の法則の必要かつ不可避な結果」であった2。
実際、人類はまったく新しい存在段階に入りつつあった。19世紀には、北西ヨーロッパの人々の平均寿命が着実に伸びていた。マルサスの悪夢を払拭するどころか、近年の水準からするとまだ緩やかな人口増加は、むしろ悪夢をより説得力のあるものにしてしまった。マルサスは、1859年にチャールズ・ダーウィンに、生存競争がより適応性の高い新しい種を生み出す可能性があると主張するよう促した。ダーウィンのいとこであるフランシス・ガルトンは、人間を競走馬のように繁殖させることができるという考えを示した。しかし、他の人々は、最も貧しく、最も繁殖力の強い人類が、他のすべての人類を蹂躙してしまうのではないかと心配した3。
その代わりに、ヨーロッパの人々は増え続け、20世紀初頭には、人類の3分の1以上がこの生い茂った半島から生まれ、他のすべての大陸に群がるようになった。彼らは、子供の数は減り始めていたが、同時代のどの民族よりも長生きした。そして、アジア人、アフリカ人、アメリカ原住民が増え始めると、世界人口の増加は急激に加速した。前世紀、人類はそれまでの2,000世紀に比べて2倍以上の長寿を達成し、人口も4倍以上の伸びを示した4。
世界人口が拡大すればするほど、崩壊は不可避に見えた。1980年代には、地球上の人口は毎年8千万人ずつ増えていた。しかし、人口増加は、それを可能にした栄養学と公衆衛生の改善とともに、なおも続いた。そして、新しい千年紀を迎えた今、一人当たりの食料消費量と平均寿命の伸びは止まるところを知らないが、増加率も年々の増加幅も小さくなっている。マルサスはこれを不謹慎と考えたが、今や世界中の人々が子供を作らずにセックスをすることは当たり前のことになっている。
このような歴史は、すでに人類を変貌させている。膨大な数の労働者と消費者が気候変動に貢献する限り、海は上昇し、私たちが呼吸する空気そのものが変化することになる。これは人類の歴史だけでなく、地球上の生命の歴史においても重大な出来事である。しかし、それは自然史における他のどのエピソードとも根本的に異なっている。ある種の未来が、その数だけでなく、その性質そのものが、初めて自らの設計の対象となった。人々が病気を根絶し、移住を規制し、出生率を操作するにつれて、かつてないほど正確に数え、分類された人間集団の量と「質」が、科学的実験と政治的闘争の対象となった。
科学者の中には、性欲、攻撃性、利他性など、人間の行動の基礎は自然淘汰と「利己的遺伝子」であるから、人類も他の種と同様に考えるべきであると主張する者もいる。歴史はやがて、特定の戦争や性革命を説明するが、戦争や性差別を説明しない、生物学の特殊な一分野に過ぎないことが明らかになるだろう。科学者たちは、自分たちの洞察を応用して、人間の行動をより良いものにすることができるかもしれないとさえ言っている。
実際、こうした主張は、「社会生物学者」の主張が逆であることをさらに証明するものにすぎない。私たちの生物学は歴史の一分野となりつつあり、人間の意志と過ちによって、左右されるようになっている。この歴史、特に優生学やその他の人類集団を改善しようとする試みを理解するか無視するかという私たちの選択は、これがどのように起こるかを決定するのに役立つのである。もし人類がもう一度自分自身を作り直そうとするならば、過去の誤りを繰り返すことは、より一層許しがたいことであることが証明されるだろう。
偉大な歴史家の中には、人口の変化が世界を変えたということに同意する人がいる。ジェフリー・バラクラは、「1890年から1940年までの半世紀の人口革命は、歴史のある時代から別の時代への移行を示す基本的な変化であった」と述べている。その後の半世紀の人口増加は、むしろそれ以上の革命的なものであった。エリック・ホブスバウムは、この「極端な時代」において、おそらく最も深遠な展開を構成するほど壮大なものであったと述べている。ウィリアム・H・マクニールは、「世界的な人口増加は、現代における人間社会の最も根本的かつ広範な混乱である」と同意している。フランシス・フクヤマでさえ、冷戦の終結が歴史の終わりを意味するものではないことを認めている。なぜなら、バイオテクノロジーの進歩は、社会工学の新時代を予感させるからである6。
しかし、世界政治を研究する学者で、このことに真剣に注目している人はほとんどおらず、ほとんどの人はいまだに領土問題やイデオロギー対立の研究にキャリアを捧げている。人口の変化はそれほど大きな意味を持たなかったのだろうか。第一次世界大戦の末期に始まったインフルエンザの世界的流行は、それ以前の4年間の全戦線における戦闘よりも多くの人々を殺した。逆に、第二次世界大戦では、公衆衛生と栄養状態が改善されたため、世界人口の容赦ない増加をほとんど止めることができなかった。冷戦の歴史において、世界規模の核戦争が起こらなかったことほど重要なことはないだろう。核戦争が起これば、数千万人、いや数億人の死者が出て、特にヨーロッパと北米の都市は空っぽになり、北半球から南半球への難民が発生したかもしれない。しかし、冷戦時代は、数十年の歳月を経てなお、それに勝るとも劣らない大きな変化を目の当たりにした。世界人口は2倍以上に増え、北米人とヨーロッパ人の割合は3分の1以下に減少し、アジア、アフリカ、ラテンアメリカの都市は世界最大となり、南から北への移民の流れは、アメリカでは「アングロス」を少数派に、フランスではイスラム教を第2位の宗教にし始めた。実際、ヒトラー、アイゼンハワー、毛沢東のような前世紀の大きな紛争の指導者たちは、勝敗を領土の獲得や喪失という点だけでなく、それぞれの側に残った人口の大きさや「質」によって定義している。
人口をめぐる争いは、国際関係の本質の変化を理解しようとするすべての人に関係するものである。何世紀もの間、国家主権は世界政治の組織的原則であった。ある政府が特定の領土に対して排他的な権限を行使できるとすれば、それは通常、その領土に居住する国家の代表であると主張するためであり、関係する人々が異なる場所からやってきて、異なる言語を話し、異なる忠誠心を持っているかどうかに関係なく、である。法律上、国家と民族の境界線は一致するものと考えられているため、この2つの言葉は同義語となっている。しかし、考えてみれば、理想的な「国民国家」の姿に合致する国は少なく、境界紛争や国境を越えた移民、少数民族の権利の主張が国際関係を揺るがすことも少なくない。同時に、資本、財、思想、エリートの流れがますます自由になり、領土の独占的支配はより難しく、決定的なものではなくなってきている。
国家がどのように自らを再生産するかを管理することは、国家の国境を取り締まるというアプローチに代わるものであり、空間と同様に時間で測られるものである。公衆衛生、繁殖、移住の規制、すなわち本書が人口政治と呼ぶものは、「誰がアメリカを受け継ぐのか」、「どのように生きるのか」といった問題をめぐって人々が争う舞台を作り出した。「敗残兵」の入国を禁止し、出生者の繁殖を促進し、「不適格者」を不妊化することによって、国家は単なる政治的構築物ではなく、浄化、拡大、さらには「改良」が可能な生物学的現実のように思われた。人口抑制の最も野心的な例は、人類の大半を包含する世界的なキャンペーンとなったもので、人々に少人数の家族を計画するよう説得または強制することを目的としたものである。やがてそれは、独自の勢いを持つようになった。しかし、1950年代から1960年代にかけて、インド、パキスタン、韓国、台湾、トルコ、ホンジュラスなど、最初に家族計画プログラムを採用した政府のすべてが、国境で争いを起こしていたことを知れば、このキャンペーンの最初の魅力の一端が明らかになるだろう。
国家は人口をコントロールし、国家と呼ぶために奮闘してきたが、出生率、死亡率、移住は明らかに19世紀の国民国家の発明より前のものである。世界人口をコントロールする政策について最初に提案したと思われるのは、1751年にベンジャミン・フランクリンが、北米の植民地が年々急速に成長していることに注目し、マルサスがこのような成長は持続不可能であると考えるようになったことである。このことは、マルサスが、このような成長は持続不可能であると考えるきっかけとなった。フランクリンはすでに、次の入植者がより勤勉で質素であることを証明すれば、「彼らは次第に原住民を食べ尽くしてしまうだろう」と心配していた。彼は、特に「不機嫌な」ドイツ系移民を心配したが、よりグローバルな結論を導き出した。
世界における純粋な白人の数は、割合的に非常に少ない。. . 私は彼らの数が増えることを望んでいる。私たちは、アメリカの森林を除去して、火星や金星に住む人々の目に地球を明るく映している。黒人とタウニーをすべて排除して、美しい白と赤を増やすチャンスがあるアメリカに、アフリカの息子たちを植えて、なぜ増やさなければならないのだろうか?しかし、私は自分の国の人種に偏見を持っているのかもしれない。
このように、人口問題を考える人は、地球を全体としてとらえる「惑星的な視点」を持つことが多い。しかし、フランクリンほどには、このような「偏愛」を率直に認めている人はいない。
人口の変化と、それを方向付けることができるかもしれないという認識は、より深遠な問いかけを促した。誰が地球を受け継ぐのだろうか。国家主権は、退化、世界的な飢餓、制御不能な移住といった実存的な脅威を克服する妨げになるように思われた。これらの恐怖は、国家を分裂させ、世界を分裂させる新たな理由と方法を提供し、民族紛争を煽り、地球規模での人種、宗教、階級戦争の恐怖を高めた。しかし、国民国家主権の原則に対する挑戦、とりわけ地球が膨張した人類を支えきれないという懸念は、「地球家族」というビジョンも呼び起こした。科学者や活動家は国境を越えて組織され、生殖行動に関する規範の統一を訴えた。国際機関や非政府組織は、少子化対策のための世界的なキャンペーンを率先して行った。これらの団体は、新しいグローバル・ガバナンスを作り上げ、推進者たちは特定の誰かに答えることなく、世界の人口をコントロールしようとした。
組織的な人口抑制運動が終焉を迎えて久しい現在でも、特定集団の出生率や流動性に対する恐怖が、民族間の争いを引き起こしている。人口統計は、ヒスパニック系を心配するアメリカ人、イスラム教徒を心配するヨーロッパ人、パレスチナ人を心配するイスラエル人など、さまざまな人々の対立の材料になっている。一方、地球の環境容量を超えてしまったという懸念から、新しいグローバルな規範や制度が求められている。民族紛争とグローバル・ガバナンスは、国家主権の原則に基づく国際システムにとって最大の挑戦である。したがって、人口抑制運動の歴史は、ローカルな政治的分断とグローバルな組織化という衝動がいかに密接に関係しているかを示し、私たちの世界が一つになると同時にバラバラになるという、強力かつ逆説的なプロセスを理解する助けになる。
しかし、私たちはどこから始めればいいのだろうか。人口抑制の考え方は、少なくともプラトンの『共和国』と同じくらい古い。この書物では、「守護者」階級がいかにして支配するために育まれ、不適格者は死に追いやられ、誰もが政治的不平等が自然の摂理を反映しているという同じ神話を売りつけることができたかが描かれている。ある種の人口政策はあらゆる文化に共通するものであると論じられてきた。その多くは、減税から魔女狩りまで、多かれ少なかれ巧妙な手段で人々に「実り多く、増えよ」と教えたという意味で、出生主義的であった。
これとは対照的に、世界の人口をコントロールしようという考えは、近代の現象である。19世紀末になると、ヨーロッパからの入植に耐えたわずかな地域をライバル帝国が占領するようになり、出生率、死亡率、移住の傾向が相互に関連し合っていると考えるようになった。「人種の自殺」、「パンデミック」、「黄禍」に対する懸念から、世界各地で移民を規制するための最初の協調的な取り組みが始まり、20世紀初頭にはアジア人を自国の大陸に封じ込めるようになった。移民規制は、1920年代から1930年代にかけて、「健康な人」と「健康でない人」の間の繁殖力を規制しようとした優生学者にモデルを提供することになった。対照的に、公衆衛生を向上させるキャンペーンは、国全体、特に人口減少に直面していた帝国を再生させることを約束した。しかし、1940年代から1950年代にかけて、新しい公衆衛生技術が植民地化された人々にも劇的な寿命の伸びをもたらし始めると、人口増加は世界的な危機のように思われるようになった。優生学と出生コントロールの擁護者たちは、公衆衛生キャンペーンを意識的に模倣し、「家族計画」のための共通プログラムを開発した。それは、一世代で「近代化」を達成する手段として、新しく独立した国々の指導者や国際組織、非政府組織にアピールするものであった。
この歴史の中で、非常に有能な学者たちがさまざまな糸をたどってきた。それは、1960年代から1980年代にかけて、東アジア、南アジア、アフリカ、アメリカ大陸を席巻した大規模なキャンペーンに結実した、人口増加を計画する世界的な運動である。この運動は、アジェンダであると同時にアリーナでもあった。フェミニスト、環境保護主義者、その他多くの人々が、それぞれ異なる方向性を持ちながらも、この運動の中に居場所を求めていた。しかし、この運動は、人々のセクシュアリティ、家族、世界における自分の居場所、そして未来について考える方法を変えようとするものであった。
作家たちは、強制移住や大量虐殺といった、より大きな、より長い人口統制の歴史の中で最も不吉なエピソードについての本で図書館を埋め尽くしてきた。これらの中にはあまりにも悪名高いものもあり、関係者全員を起訴しているように見えることなしに、前述のいくつかの関連性を論じることは、連座制のためとはいえ困難である。例えば、優生学という言葉を聞くと、すぐにホロコーストの恐怖が思い起こされる。今日では、洗練された人口研究者でさえ、この言葉を人種差別と同義語だと考えている。しかし、人類の遺伝的構造を改善するという考えは、W. E. B. Du BoisからJohn Maynard Keynesまで、世界中に信奉者がいた。優生学は、保育園の無料化から強制的な不妊手術に至るまで、あらゆることを正当化するために使われた。同様に、今日ではあまり使われないが、人口抑制という言葉は、ほとんどの推進者にとって、人々を貧困から救う方法、さらには地球を救う方法を意味するものであった。その多くは、今日、人的資本、持続可能な開発、生活の質について語る人々と同様に、善意であり、また好意的に受け止められていた。
歴史家にとっての課題、そしてこの歴史から学びたいと願う人々にとっての機会は、このような変幻自在の概念が、具体的にはどのように規範、慣習、制度へと発展し、人々に力を与えたり操ったり、豊かにしたり困らせたり、命を与えたり奪ったり、時にはすべてを同時に行っているのかを明らかにすることである。これは、スローガンがどのような思想に共鳴するかを教えてくれるのと同様に、スローガンを超えて見ることを意味する。どのように資金が集められ、どのように使われたか、誰が雇われ、どのように訓練されたか、どのようにプログラムが機能するはずで、なぜ通常失敗するのかを調査する必要がある。人々が世界を救おうとするとき、悪魔は細部に宿る。
さまざまな種類の人口抑制策の類似性や関連性をたどるのと同時に、なぜそれらが多くの場所で広がり、根付いたのかを説明する必要がある。多くの歴史は、2つ以上の国を比較する場合でさえ、その国の歴史である。優生学や家族計画のような考え方が、異なる文脈においていかに異なる意味を持ちうるか、また、地域の事情に即したものでなければほとんど意味をなさないかを示してきた。しかし、このような多様性を認めながらも、多様な傾向がなぜほぼ同時に生まれ、それらがどのようにして世界の人口をコントロールしようとする動きに結びついたのかを説明する必要がある。つまり、人口問題活動家たちの共通点、国境を越えたコミュニケーションと動員の方法、そしてその広がりを促進したグローバルな状況における主要な特徴を探求することである。
人口抑制を、異なる傾向を受け継ぎながらも独自の方向性と勢いを獲得した一つの運動として理解すれば、新しい驚くべき歴史が展開され始める。例えば、新マルサス主義者、優生学主義者、出生促進主義者、帰化主義者が同じ時期に組織化され始めたことに気づく。入植地の封鎖は、世界人口を左右する最初の政策であったことがわかる。1920年代と1930年代の出生促進キャンペーンは、レーベンスラウムをめぐる新旧帝国間の宣言されていない戦争の最前線であり、公式な戦争が始まる何年も前に女性の命が犠牲になっていたことが分かる。例えば、もし優生学者が世界的に協力し合っていたら、あるいは第二次世界大戦中に占領下のヨーロッパで生まれたばかりの性改革運動が締め出されなかったら、このような傾向はどのように違っていただろうかと考えてみることもできる。
偶然の出来事が、世界の諸問題に対する万能薬としての避妊具の第一人者であるマーガレット・サンガーが、家族計画の統合プログラムを前進させるのに役立った。それは、ナイロビからニューデリーまで、アルジェからハノイまでで起こっている植民地支配の危機に対する世界的な解決策を提供するように思われた。帝国の行政官たちは、政治的、経済的不平等に対処するよりも、国際機関や非政府組織に事態の収拾を任せようと、多様な人口動向のせいにした。人口専門家の国境を越えたネットワークは、帝国が去った後を引き継いだ。誰が実際に計画を行うかを特定しないことで、彼らは家族計画をさまざまな状況に適応させることができた。富裕層や富裕国にとっては、夫婦がより大きな家族を築くための手助けをし、「子育ての黄昏」と「西洋の黄昏」をもたらすと思われた少子化を逆転させることを意味する。貧しい人々や貧しい国々にとっては、多くの子供を産むことをやめさせ、「近代的」な生活を始めるよう人々を誘導するためのインセンティブやディスインセンティブを設計することを意味する。
世界史はまた、私たちが人口抑制について知っていると思っていたことが、実はそうではないことを示すこともできる。例えば、優生学は、現在ではホロコーストとして理解されている最も悪名高いエピソードで終わったわけではない。優生学的な不妊手術は、アメリカのいくつかの州、北欧、日本、インド、中国などで続けられた。同時代の人々の多くが、ナチスが敵対する者すべてを迫害したと解釈していたこと、つまり、ユダヤ人がいかに完全な抹殺の対象とされていたかを認識していなかったことは、自発的、強制的な家族計画(あるいは「暗号優生学」と呼ばれるもの)を通じて「世界の家族」を改善しようとする人々にとって関係ないように思われた。1960年代、人類の生存は不妊手術に依存していると主張する人々が現れ始めたとき、遅ればせながらこの歴史を認識した人々は、人口抑制が怪しげな出自と危険な可能性を持っていることを思い知らされた。
人口抑制を世界的な運動としてとらえることは、他の方法では思いもよらないような疑問を引き起こし、それに答えることになる。例えば、なぜ人口抑制の国際外交では、共産主義国とカトリック国が社会主義国と資本主義国に対峙するような奇妙な連合が組まれたのか?台湾からインド、チュニジア、ハイチまで、ほぼ同時に同じ技術とテクニックが展開され、ひどい結果に終わることが多かった。また、家族計画は人権であると主張する組織が、インドや中国でますます強圧的になる政策に反対しなかったのはなぜだろうか。その代わりに、なぜ彼らは友好的なアドバイスとサポートを提供し、世界中にそれらを擁護したのだろうか?
本書は初の世界人口統制史だが、すべての国を網羅しているからではない。そもそも、ある国は他の国より多くカウントしていた。人類を作り変えようとした当時、イギリスとフランスは世界の人口のほとんどを支配していた。そのため、彼らの国内での議論でさえも、より広い範囲に影響を及ぼしていた。ファシズムのイタリア、ナチスドイツ、ソビエト連邦は、特に冷酷な人口統制を行い、他の国々にもっと魅力的な代替策を開発するように促した。スウェーデンは、福祉国家が家族計画を推進する代わりに、国内外にどのような影響を与えることができるかを示した。日本は、連合国軍の占領下において、人口増加を抑える手段として、ほぼ最初に家族計画を採用し、その後、国際的な援助の源として米国に次ぐ存在となった。
しかし、この記述で最も注目されているのはアメリカである。彼らは、世界人口の形成を意図した政策を最初に追求した。彼らは人口統計学の科学と家族計画という政治戦略の両方を制度化する上で主導的な役割を果たすと同時に、世界中の弟子を指導した。彼らは、標準的な人口管理プログラムを作成した国際組織や非政府組織で不利な立場に立たされ、その資金は主に米国の公的機関や民間団体から提供されていた。逆に、アメリカのカトリック教徒は教会内で特に影響力を持ち、あらゆる場所で避妊と中絶を違法とするキャンペーンの先頭に立った。
アメリカ人の内部抗争は、避妊ピルと国家による不妊手術の実験場となったプエルトリコや、占領当局と地元の推進者が中絶を合法化したものの、女性に他の選択肢をほとんど残さなかった日本では、極めて重要であることが証明された。台湾と韓国では、アメリカのコンサルタントが、医療従事者がより多くの女性にIUDを挿入するよう動機付けるための報奨金を使ったプログラムを開発した。この技術は、副作用に苦しむすべての女性を治療するにはクリニックがあまりにも少ない国々に輸出され、計り知れない悲惨な事態を引き起こした。一方、ラテンアメリカでは、カトリックの聖職者と信徒が国境を越えて協力していたこともあり、このような取り組みには抵抗があった。そのため、この地域は危険な中絶の発生率が世界で最も高い地域となっている。
インドほど長期間にわたって、また広範囲にわたって少子化対策に取り組んだ国は他にない。インドは、英米の避妊活動家が海外にクリニックを設立するための最初の持続的な取り組みを行った国である。人口学と家族計画に関する最初の国連諮問団を招いた。国際家族計画連盟(IPPF)の設立総会もインドで開催された。インドが初めて少子化対策に乗り出した。その後、パキスタンが続いた。バングラデシュ、スリランカとともに、新しい避妊法の実験場となり、国際的な援助の大部分を吸収した。実際、「インドのような国」という言葉は、出生率の高い貧しい国の略語となった。現代の議論では、中国が大きくクローズアップされているが、中国が海外からの援助に負っているものは比較的少ない。プロライフ運動は、一人っ子政策を、あらゆる場所で家族計画に反対するための申し子とした。しかし、1960年代から1970年代にかけて南アジアで展開された一連のキャンペーンを原動力とする人口抑制運動の歴史的軌跡を辿ってこそ、IPPFや国連人口基金(UNFPA)といった組織がなぜ中国に進出し、そこから逃れるのがなぜ困難だったのかを理解することができるだろう。
国別に人口管理の状況を把握することは、物語の始まりと終わりを知るのに役立つが、世界的な運動の盛衰を物語るには最適な方法ではない。例えば、バチカンの役割をどう評価するのだろうか。バチカンの影響力は、数百エーカーのローマの不動産とはほとんど関係なく、また、国ごと、教区ごとにさまざまであることは明らかである。1930年にピウス11世がマルサス主義と優生学を非難し、家父長的な家族は国家よりも神聖であると主張したとき、彼に続くすべての教皇と同様に、国家主権に優越する権威を主張した。一方、人口抑制運動の指導者たちの多くは、自らを国家的な観点で捉えてはいなかった。マーガレット・サンガーは、「自分には国がない」と言いながら、その生涯をこの運動に捧げた。ガルトンに始まる優生学者にとっても、人口抑制は世俗的な宗教であり、人類を退化から救うために伝承された信仰であった8。
科学者と活動家のネットワークが1960年代と1970年代の世界的な人口抑制運動の課題を設定し、非政府組織が最も影響力のあるプロジェクトの先駆者となり、すべては国連の後援の下で進められた。主要人物の論文を数時間以上読んだ人なら、彼らが移動しながら、蒸気船、ホテル、航空会社のハガキや便箋に書き込んでいることに気づくだろう。
人口管理者のすべてが国際人であったわけではない。彼らが作った歴史が世界的なものであったとしても、それは特定の場所で特定の人々によって経験されたものである。しかし、現代の歴史がそうであるように、その歴史もまた、国ごとに整理され、別々の容器のように分けられて、一つずつ注ぎ込まれるようなものではなかった。もし、すべての国を網羅することに成功したとしても、この方法で組織された研究は、物語の多くの部分、そして最も本質的な部分を見逃すことになるだろう。アメリカやインドのような政府の政策を説明するにしても、「アメリカ」と「インド」、ましてや「ワシントン」と「デリー」という2つのケースとして考えるのは間違いである。連邦制である以上、ノースカロライナとマドラスのつながりや類似性、「任意不妊手術協会」のような団体の仲介役などに注目する方が理にかなっている場合もある。同様に、科学者や資金調達担当者は、スラム街の住民と自給自足の農民の両方を対象とした避妊技術や手法によって、人口問題に対する世界的な解決策を約束した。その結果、ブラックパワー、ビハール運動、新しい国際経済秩序など、さまざまな言葉で表現された反動が世界中で聞かれるようになった。
一見面倒に見えるかもしれないが、人口の変化とそれをコントロールしようとする闘いは、相互に関連した国境を越えた現象であり、そのように研究されるべきものであることを認識する必要がある。夫婦が下す決断は国家を崩壊させる可能性があり、歴史的に見ても政府はこの問題に対してほとんど発言権を持たなかった。人口動態の傾向を形成する可能性があるだけで、人々は、宗教、人種、世代、文明の別を問わず、政治を組織する別の方法を思いつくようになった。そして今、人口動態は国際関係の変化を理解し、グローバル・ガバナンスの展望をより批判的に評価するのに役立っている。
人口抑制の歴史と未来を理解するためには、人口抑制がネットワーク-思想、個人、制度のネットワーク-で構成されていることを認識する必要がある。ネットワークについての物語は、読者にある種の要求を突きつける。なぜなら、すべての行動を進める一人か数人の主人公も、それが発せられる中心も、すべての努力を集中させた固定目標さえも見つからないからだ。結局のところ、移民であれ、迫害された少数民族であれ、働く母親であれ、人口抑制の対象は動くものである傾向がある。読者が目にするのは、新しいアイディアが生まれ、火がつき、政治的なムーブメントを巻き起こす様子である。人々は国境を越えて組織化され、会議を開き、資金を集め、新たな組織を設立して議題を推進する。このような運動は時に勢いを失い、消滅するが、状況が好転した時に再び現れ、新しいアイデア、新しい政策、新しいプログラムを生み出す。望まない移民を差別したり、子供を産んだり減らしたりすることは、しばしば好ましくない行為であり、その結果、分裂や反体制化を引き起こし、人口抑制の信用を失い、地下に追いやられる。ネットワークはその性質上、回復力がある。このことは、人口抑制が手ごわい反対運動を引き起こしたにもかかわらず、なぜ持続してきたかを説明するのに役立つ。
このような一連の流れをきちんとまとめて、人口抑制の歴史を世界的な陰謀として提示することは、著者にとって確かに容易なことであっただろう。少なくとも、世界の人口増加を止めるための運動に限定した、より整然としたストーリーを好む読者もいただろう。左派の批評家も右派の「プロライフ」勢力も、人口抑制は白人で裕福なエリート、特に米国のエリートが世界の他の地域に行ったことだと長い間攻撃してきた。このような主張に対して彼らが提示する証拠は、たとえそれがインターネット上に溢れていたとしても(優生学と出生コントロールという言葉を検索すればすぐにわかる)、断片的なものになりがちである。このような証拠は、イデオロギー的な攻撃のために操作されることもある。特に、人口評議会、国際家族計画連盟、フォード財団、ロックフェラー財団、国連の主要機関、世界銀行など、このような陰謀を明らかにする可能性のあるすべてのアーカイブを調査した人は、これまで一人もいなかった。
本書は、主要な主人公の何人かが、実際には、自分たちの組織がある課題に専念しているように見せかけながら、別の課題をひそかに隠していた、という裏の行動をとっていたことを証明することができる。読者の中には、何も変わっていない、つまり、同じ組織が今、リプロダクティブ・ライツと健康を主張するとき、本当は人口抑制を意味している、という結論に飛びつく人もいるかもしれない。もしそうなら、なぜ彼らが著者に、驚くほど自由な文書館へのアクセスを許したのか、説明がつかない。このように外部からの調査に対してオープンであることは、現在これらの機関を率いる人々が何も隠すことがないことを示唆している。
一方、カトリック教会は、その文書記録への意味のあるアクセスを提供することに消極的であった。カトリック教会は、出生コントロールと中絶に反対する世界最大の勢力であったが、人口コントロールそのものには必ずしも反対していなかった。ローマ教皇、司教、司祭は、明らかに不公平な状況において、女性を自らの意思に任せ、ある種のコントロールに反対し、他のコントロールを擁護した。男性は、いつ生命が始まるか、どのような家族計画が「自然」であるかを決定する権限を自分たちに留保した。結果的に、この方法は司祭の許可、夫の同意、厳しい規律と記録を必要とし、それでも試した人のほとんどが失敗した。ローマ教皇によって定義され、政府によって施行された「自然法」は、人々を繁殖させるという効果を持ち、時には意図的なものであった。
しかし、出生を促進する政策は必ず、そして予想通り、避妊と中絶を地下に追いやり、その犠牲は計り知れないものになった。このように、一見相反するような人口抑制が並行して行われ、その狭間に置かれた人々は苦しみ、死に至った。
人口抑制を陰謀と決めつけては、アーカイブに何が残っていようと、説明することはできない。世界人口をコントロールしようとする人々は、海外に味方を見つけなければ、どこにも行けない。このような遠大な運動は、異なるアイデアに触発された人々が、異なる方向へ引っ張られることを含んでいる。思想は一人歩きするし、人間はもっと予測不可能である。その中で、個人個人が自分の考えを変え、異なる目標に向かって行動することで、この歴史は変わっていった。最も重要なことは、人口抑制の運命は、最終的には抑制されない人々によって決定されたことである。制度化された人種差別を覆した移民、強制不妊手術に異議を唱えた訴訟当事者、他者への強制を断りキャリアを危険にさらした役人、そして世界あるいは神の計画に従って繁殖することを拒否した数え切れないほどの数百万人の人々であった。
本書は陰謀論というよりも、むしろ教訓的な物語である。本書は、過去だけでなく、未来についての物語である。したがって、本書は、ごく最近を含む時間軸で展開される物語の形式をとっている。人類を作り直そうとする運動の高まり、家父長制を維持しようとする人々の反応、そして女性と男性の生殖に関する権利を勝ち取るための勝利が描かれている。この本は、主人公たちが勝利と失望を経験する中で、共感とまではいかないまでも、共感することを読者に求めている。彼らは魅力的な理念を打ち出し、「偉大なる者、善良なる者」を集め、世界で最も裕福な財団、最大級の非政府組織、最大の海外援助プログラム、世界銀行、目的のある国連機関など、支援機関のファランクスを動員することに成功した。これに対して、キリスト教とイスラム教の保守派を結集し、神にのみ答えるローマ・カトリック教会という、さらに手ごわい組織が立ちはだかった。
物語を読むと、これらの組織や個人がどのように相互に関連し、時間の経過とともに変化していったのか、より深く考えることができるようになる。そして、両陣営の主要な意思決定者が分権化を意図的な戦略とし、時にはその痕跡を消したため、彼らの正体を明らかにし、決定的な転換点を明らかにするためには、物語が必要である。そして、決定的な抵抗に遭ったとき、双方がどのように挫折し、方向転換し、最終的に変容していったかを示すことができる。家族計画支持者の多くは、今や「人口抑制」という言葉を口にするだけで、戸惑うとは言わないまでも、悩みを抱えている。ほとんどのカトリック教徒は、このテーマに関する教会の教えを無視し、何とも思っていない。リプロダクティブ・ライツを確保するために必要だった闘争と犠牲を知る人さえほとんどおらず、今ではほとんどの人が、リプロダクティブ・ライツは不可侵のものであると信じている。
世界の人口増加は鈍化し、人口抑制の英雄的時代は少なくとも今のところ終わったように見える。現在、人々は、西洋では年金生活者が多すぎること、東洋では女児が少なすぎること、また、これから親になろうとする人々に情報が提供されすぎて、子孫をデザインし直そうという誘惑に駆られることを心配している。このように、私たちは驚くべき物語の終わりを見ることができ、それが今語られることのできるもう一つの理由である。人口抑制がどのように始まり、どのように恐ろしい方向に進んでいったのか、その歴史は、これから起こるかもしれないより不吉な歴史に備えるのに役立つだろう。
注
本文中では、北米での表記にしたがって、苗字を最後に表記している。例外は、毛沢東のように、順序を逆にするとかえって混乱を招くような有名な国家元首である。地名は、1972年まではセイロン、それ以降はスリランカというように、その時代の呼称を使用している。ある金額の価値をインフレ調整する場合は、両方の数字を記載し、後者は、www.measuringworth.comにある計算機によると2006年頃の「今日のお金」と表記している。
読者の中には、本書に含まれる他の多くの用語や価値観が、なぜ人口管理を始めとして翻訳・更新されていないのか、と思われる方もいるかもしれない。しかし、リプロダクティブ・ライツを推進するという意味での家族計画という言葉は、人口コントロールの反対を意味している。主人公たちの中には、この2つの言葉を使い分けている者もいた。彼らが主に人口目標の達成に関心を寄せていたことが明らかな場合、本書はそれを家族計画とは呼ばない。そうすれば、現在、この分野の人々の大多数が守ろうと努力している区別を混同してしまうからだ。
より一般的には、本書は人口管理者たちが自分たちの考えや仕事を伝えるために使った多くの用語を含まなければならない。人間を「不適格者」と表現したり、「受容者」と呼んだり、「IUD挿入数」を数えたりすることは、一部の読者には不快に映るだろうし、そうなるべきだ。しかし、本書は何十年もの間、人口政策やプログラムがどのように設計され、実施されてきたかを忠実に反映しているのであり、いちいち「引用符」を使っていては気が散ってしまう。もし本書が人口コントロールに対する批判として正しく理解されるなら、引用符を使うのは止めた方が良いだろう。
まとめ未来の脅威
世界人口の増加は減速し、人口統計学者や活動家の世代が一巡しつつある。彼らの中には、現在家族計画分野をリードしている人々が、いかに彼らの歴史的貢献を否定し、彼らを片隅に追いやったかに憤慨し、振り返っている者もいる。しかし、彼らは、世界の諸問題をさらに困難なものにしていたであろう破滅の到来を人類に警告したことを誇りに思っている。彼らの仕事は、人口増加がどのように減速し始めるのか誰にも分からないという時代背景の中で見なければならない。そして、彼らは間違いを認めながらも、少子化対策が多くの利益をもたらしたことを指摘している。経済成長の促進剤であり、何よりも女性を助けた。フランク・ノートシュタインが亡くなる間際に言ったように、「私たちはそれほど悪いことをしたとは思わない」1。
これは皮肉な成り行きである。世界の人口をコントロールしようとしていた時代には、歴史はほとんど役に立たなかった。誰もが時間の借金の上に生きていたため、新しい運動の推進者は、過去の経験、たとえごく最近の出来事であっても、無関係あるいは誤解を招くものとして否定した。社会がより多くの人口を養うという課題に直面すると、新旧のマルサス主義者は、これはさらに大きな災難をもたらすだけだと主張した。しかし、移民が犯罪者であるとか、文化的に同化できないといったことはなかった。しかし、移民はその功績によって、新しくやってきた人々の欠点や危険性を指摘した。栄養、衛生、教育が改善された結果、人々が肉体的に健康になり、頭も良くなったとしても、それは次の世代で顕在化する遺伝的劣化を隠しているだけだと優生学者が警告した。人口統計の予測は常に変化を予測することができなかったが、それでも新しい予測は避けられない破滅の兆候であるとして、反論の余地はなかった。そして、家族計画が貧しい人々や貧しい国々の出生率をコントロールするための突貫工事という形をとったとき、引き起こされた抵抗は、より冷酷な措置が必要であることを証明するように思われた。
他人の立場になって想像する「共感」は、歴史家にとって核となる価値観である。それなしには、過去を理解することはできない。未来の脅威を認識し、それを打ち負かすことができるのは自分だけだと感じていた人々にとって、なぜ未来の脅威がそれほど切実に感じられたのか、よく理解することができる。しかし、歴史を変える力がまだあるにもかかわらず、歴史をほとんど理解しない人々は、歴史が単なるアリバイ作りの材料に過ぎないことに気づくのが遅すぎる。歴史は未来を語るものでもある。アジア人を自国の大陸に封じ込めたり、より優れた人間を育成したり、貧しい人々に金を払って子供を生ませないようにしたりと、前世紀の実験を再検討することで、現在考えられているような人口抑制をより批判的に考えることができる。未来における最大の脅威は、今も昔も、あり得ることだけに目を向けていると、過去の教訓や遺産を見過ごしてしまうことである。
人類がその生涯の間に倍増し、また倍増していく中で、人口調節者たちが前例のない難題に正面から取り組んだことは否定しようがない。世界人口の増加は、20世紀という特別な時代に、おそらく他のどの出来事よりも長期的に重要なエポックメイキングな出来事であった。しかし、党派的な人々はそれ以上のことを主張し、自分たちの仕事がこの流れを止め、最終的には逆転させ、人類を計り知れない不幸から救うことになると示唆している。1960年代以降、合計特殊出生率は半分以下に低下し、平均的な女性の出産数は6人から3人未満に減少した。人口計画が最も成功した地域、特に東アジアでは、かつて貧しかった国々が「人口ボーナス」によって多大な報酬を得ていると言われている。膨れ上がった労働力は、もはや大家族を養うのに苦労することはない。一方、アフガニスタンとアフリカの大部分では、持続的な多産がテロと大量殺戮暴力の温床になっていると非難されている。そして、地球温暖化などの新たな課題によって、「人口安定化」はかつてないほど重要となっている2。
アジアを貧困から救い、地球を居住可能な状態に保ったというのが、人口制御論者が主張する長期的な歴史的貢献の2つの最も強い主張である。もしそれが本当なら、本書の主題は歴史に残るものとなるだろう。人口爆弾の解体は、果てしない歴史研究、議論、討論を呼び起こすだろう。特に、犠牲が過去になり、私たちが未来に恩恵を受け続けるのであれば、多くの学者は、最終的な結果は代価に見合うものだったと結論づけるかもしれない。ドレイパー、ラベンホルト、銭、サンジャイ・ガンジーなど、20世紀の偉大な人口抑制運動のリーダーを称える銅像が建てられ、平静を装ってすべてを見渡すことができるだろう。
しかし、これらの主張が両方とも正しいということはありえない。結局のところ、アジア人が2.1人の子供を持ち、かつエアコンと自動車を持てば、10億人以上の自給自足農民よりもはるかに大きな影響を地球の生態系に与えることになる。20世紀を通じて、貧しい人々は、子供を少なくしさえすれば、より多くのものを手に入れることができると約束されてきた。ポスターやフリップチャート、映画では、幸せで計画的な家族が、目立つ消費に囲まれている様子が映し出され、ナイジェリア人でさえ、ガレージに車が置かれた郊外の家を見せられたほどである。核家族化や代替的なライフスタイルの普及が人口増加率を低下させたとすれば、それは同時に人々が住む家の数を増加させることにもなった。その数は現在、世界人口のほぼ2倍のペースで増加している。多世代が暮らす家庭から1人、2人で暮らすようになると、燃料、水、広々とした空間など、1人当たりの消費量が増える傾向にある3。
繁栄が環境問題を拡大させたとしても、それは人口増加を抑制する十分な理由になるかもしれない。この分野でキャリアを積んだ人々は、人口動態と開発を結びつける経済理論を非常に重要視している。しかし、政治指導者には他にも様々な動機があり、「回避された出生数」のコスト・ベネフィット分析など、洗練されていない経済分析が大きな影響力を持つことも少なくなかった。さらに、経済学者は、金と評判がかかっていたにもかかわらず、出生率の低下が一人当たりGNPの上昇と相関していることを示すことができなかった。人口抑制計画は、それとは無関係に進められた4。
この議論の新バージョンでは、少子化が資本を解放し、より収益性の高い投資を可能にするという主張ではなく、少子化がいかに年齢構成を変化させたかが強調されている。少子化が資本を開放し、より収益性の高い投資を可能にするという主張ではなく、年齢構成の変化を強調し、子供や高齢者の従属人口に対する労働者数の増加がアジアの虎に拍車をかけたとされる。皮肉なことに、1960年代と1970年代の人口爆発は、かつて経済学者が無価値と判断した子供たちであり、現在ではアジアを活気づけたと評価されている人々である。しかし、この一過性の効果は、生産性を高め、「人的資本」に投資することを奨励しない国にとっては何の意味もない、と指摘する人もいる。さらに、これらの労働者は、この「人口ボーナス」の代償を払うことになるかもしれない。なぜなら、彼らの子供の世代は、年金や前立腺手術の代金を支払うには少なすぎるかもしれないからである5。
人口抑制に関する生態学的な議論も経済学的な議論も、同じ議論の余地のある前提-これらのキャンペーンが実際に人口抑制に成功したということ-を拠り所にしている。これを否定するのは難しいだろう。世界的な出生率の低下は、避妊具の使用が増加するのと時を同じくして起こっている。しかし、出生率の低下は、家族計画プログラム、ましてや強制的な人口コントロールが本格的に始まる前から始まっているのが普通である。逆に、出生率向上政策は、わずかな効果しかもたらさなかった。世界の出生率の差の約90%は、非常に単純で、非常に頑固なもの、つまり、女性自身が子供を増やしたいか減らしたいか、ということに起因していることが判明した。また、移動診療所や不妊手術キャンプ、あるいは戸別訪問の「氾濫」キャンペーンがその手段を提供するのを待つこともなかった。このことは統計的に証明されているが、歴史的な経験や常識とも一致している。フランスの農民は、ナポレオンにペッサリーを買ってもらう必要はなかった。当時でさえ、出産を避けることは、望まれない子供よりもコストや手間がかからないことだった6。
人口抑制運動が人口抑制に成功しなかったとすれば(推進派がすぐに否定するような歴史の暗黒期を除いて)、その影響はこれだけとは言い難い。何億人もの人々、つまり生殖年齢にある既婚女性の60%以上が現在避妊をしており、10人のうち9人がピル、IUD、インプラント、注射といった「近代的な方法」を選んでいる。さらに多くの人々が独身を貫いており、こうしたデータの収集がより困難になっているとはいえ、全員が貞操を守っているわけではない。人口減少を食い止めようと、ある国は妊産婦の健康、産休、託児所などを改善した。また、出生率を下げるために、他の多くの国は結婚年齢を引き上げ、中絶を合法化した。もし、自国の出生率を規制しようとするすべての人々が、依然として自分たちの判断に任せていたとしたら、世界の人口数は大きく変わらないにせよ、世界は大きく変わっていただろう7。
この数字がどの程度異なるかを判断するために、アナリストは、少子化対策に多かれ少なかれ力を入れている国や地域のプログラムを比較しようと試みている。このことは、方法論だけでなく、哲学的な問題を提起している。重要な変数である「満たされていないニーズ」の測定には、子どもを増やしたくないが宗教上の理由で避妊をしない女性も含めるべきなのだろうか。また、家族計画プログラムを導入している社会は、国の指導者だけでなく、一般の人々も小家族化を望んでいる社会である可能性が高い。これらの問題はさておき、インドネシアのような大規模な人口抑制プログラムを実施した場合、家族の平均人数はおよそ1人減少すると推定される8。
このような投資を行うに足る理由があるのだろうか。実際に人々が自分の身体をコントロールする権利を行使するのに役立つのであれば、ぜひともそうしたい。特に、バングラデシュで行われた特に浪費的なプログラムのように、この1人の出産を回避するために1人当たりのGDP以上の費用がかかる場合は、貧困からの脱却を期待するべきではない。出生率においてはるかに重要なのは、女性が教育を受けているかどうか、つまり子供を産む以外のことを成し遂げる機会が多いかどうかである。この効果により、教育を受けなかった女性の平均出生率は6〜7人であったのが、7年以上受けた女性では3〜5人に減少することが示されている。また、人口増加や一人当たりGNPへの影響とは全く別に、人類の半分以上を教育し、権利を与えることは、一般福祉に計り知れない貢献をした9。
したがって、人類を作り直したのは、人口抑制ではなく、女性の解放なのである。家族計画の分野では、教育と出生率の関係は、明らかにされた真実のように扱われている。そのおかげで、フェミニストと環境保護主義者は、人口抑制ではなく、エンパワーメントを推進する新しい、より賢明なコンセンサスを形成することができた。実際、それは多くの人が最初から知っていたことだった。しかし、忘れてはならないのは、この歴史の大半において、カトリックの上層部から人口評議会、インドの会議派に至るまで、教育を受けた女性が子供の数を減らすことを好むことは問題であり、脅威でさえあるという意見に同意していたことだ。教育を推進することが解決策となったのは、こうした専門職の女性が国際的な議論の場に多く登場するようになってからであった。
それまでは、人口管理者たちは、貧しく教育を受けていない人々の高い出生率に対して、ますます鈍い手段で対処することを好んでいた。もし「愚かな数百万人」が、専門家が理解しやすい方法で家族計画を立てないのであれば、避妊もおぼつかないものにしなければならない。もし、人々が貧しくてそれを買う余裕がなければ、それを使うことでお金をもらうことができ、さらに集団の圧力がそれを誘発する。多くの人々がIUDや不妊手術、インプラント、注射を受け入れないとなると、人口管理者たちは空気中や水中に拡散して、当局だけが提供できる解毒剤なしにすべての人を不妊にできるものを夢見た。そのような技術的な解決策がない場合、彼らは親の出産休暇、住宅、医療を否定し、単に人々を中絶や不妊手術のクリニックに引きずり込むだけであった。推進派は、その目的は個人が自分の運命を支配するのを助けることだと宣言したが、何千万人もの実験では、まるでシャーレの中のバクテリアのように扱われ、生殖行動の規則性を測定し操作することができた。
このような歴史は、家族計画団体がその重荷を下ろしていないだけで、いまだに家族計画団体の石臼のように重くのしかかっている。数十年にわたる「人口危機」の警告は、地球の運命ではなく、個々の女性や子どもの命がかかっている今、リプロダクティブ・ヘルスケアへの支援を維持することをより困難にしている。出生率を下げるための「クラッシュ・プログラム」の遺産は、多くの貧しい人々に性と生殖に関するヘルスケアへの不信感を抱かせ、インドではもはや家族計画という言葉は人口抑制を意味せずに使うことができないほどである。
IPPF、人口問題評議会、UNFPA、その他の組織は、自分たちは常にリプロダクティブ・ライツを推進し、強制的な政策を支持したことはないと主張し、反論することが多い。事実上、何も変わっていないのだ。皮肉なことに、彼らの敵であるプロライフ派は、何も変わっていないことに同意している。ただし、プロライフ派は、同じ組織が常に隠された意図を追求し、貧しい人々や貧しい国の人口をコントロールしようとすることを止めなかったと主張する。
何も変わっていないと断言することは、未来に一心に目を向けることと同じように、歴史に背を向けることである。現在が永遠となり、終わりのないマニッシュな対立に縛られることになる。しかし、プロライフコミュニティーの中には、自分たちの闘いを別世界のものと考えている人もいる。しかし、この考え方は、今ここで進歩的な変化を求めている人々にとって、衰弱させるものである。なぜなら、賛成派が過去の強制的な慣行や疑わしい動機の例(その多くはフェミニストの批評から引用されている)を見つけるたびに、より多くの材料が提供されるからだ。
最も傾向的なのは、避妊反対派が歴史を巨大な陰謀論に還元し、裕福な国がそれ以外の国に対して優生学を実践しているというものである。確かに、貧しい国々で人口が増加しているという証拠がないうちから、人口増加を止めようという声は上がっていた。ある人々には妊婦の健康を約束し、別の人々には「暗号の優生学」を約束するなど、人口管理者は何度も両極端な言葉を口にした。さらに、このような言説の多くは英語で行われ、初期の人口抑制キャンペーンに対する国際援助はアメリカのドルが中心であった。
しかし、カトリックのヒエラルキーは、避妊と中絶を違法とするために戦ったとき、「人種の自殺」-罪人の救済だけではない-に少なからず関心を寄せていた。教会は、多産を促進する「積極的優生学」や、司祭の監督の下での「自然な家族計画」など、両者の利害が一致すれば、人口管理者たちと手を取り合って働いた。しかし、教皇は教会の父であり、男は家族を支配し、女は子供を産むという家父長制をたゆまず守り続けた。しかし、司教たちは、反対派と同様、政治の場に出るときは、ローマと大義を同一視しすぎるリスクを冒すよりも、他の人たちに主張をさせるという無策が好まれた。
豊かな国でも貧しい国でも、さまざまな形で人口抑制を推し進めた人々は、実は同じ物語の一部であり、陰謀というにはあまりにも重要で複雑な物語なのだ。イタリア、フランス、アルゼンチン、メキシコ、ブラジルなどの国々では、出産を奨励する指導者たちは、教会の避妊反対キャンペーンに協力することが好都合であると考えた。逆に、インド、中国、その他多くの国のエリートたちは、自国の人口の規模と「質」を心配し、国家全体を計画通りに再生産するプロジェクトに進んで協力した。しかし、人口管理者たちがどのような計画を立てたにせよ、それが出生促進派であれ反出生主義派であれ、出来事は最も逆説的な形で進行していった。ピルのような避妊薬は、当初は出生率を下げるための「確実な」手段として開発されたが、世界を席巻する性革命の火付け役となった。アジアやアフリカに向けられた資金調達キャンペーンや人口抑制技術は、ヨーロッパやアメリカの家族計画の政治を変えた。また、リプロダクティブ・ライツと健康が脅かされている場合、特に女性はそれを守る義務があるのかどうかという問題にも焦点を当てた。
女性だけでなく男性も解放したリプロダクティブ・ライツのための闘いを記念することは重要である。しかし、マーガレット・サンガーのような指導者たちが直面していたことの大きさを認識しなければ、サンガーを含む多くの指導者たちがなぜ妥協し、人口抑制に加担してしまったのかを説得的に説明することはできない。他人の家族の計画を立てるという誘惑は蔓延し、根強く、推進派はしばしば善意と私腹を肥やしていた。そのため、抵抗する人々は、教会や国家からだけでなく、ただ助けたいと公言する多くの人々や組織から、少子化対策を奪い取らなければならなかった。IPPFやUNFPAのような組織を改革することがいかに困難であったかを認識することによって、私たちはようやく、彼らが今もなお同じ隠された意図を追求しているという批判を打ち消すことができるだろう。
人口管理の大きな悲劇、致命的な誤解は、他人の利益を自分以上に知ることができると考えたことであった。しかし、他人の家族を計画するという考えは、今では信用されなくなったとしても、この極めて人間的な傾向は、まだ私たちの中に残っている。人口抑制の本質は、それが移民や「不適格者」、あるいは大きすぎたり小さすぎたりする家族を対象としているかどうかにかかわらず、他者に答えることなく他者のためにルールを作ることだった。解放運動の広がりと市場の統合により、領土を支配するよりも人口を支配する方が簡単で利益が大きいと考えられるようになったため、富裕層や権力者にアピールすることができた。だからこそ、反対派が、人口抑制を帝国主義の未完の歴史のもう一つの章としてとらえるのは正しかった。
人口統制と帝国主義の関係は、単に概念的なものではなく、歴史的なものである。世界の人口をコントロールしようという野望は、領土を持つ帝国の苦難から直接生まれた。入植地をめぐる争いは、最初の実用的なプログラムを生み出すきっかけとなった。19世紀末には、移住を規制することは、ヨーロッパの入植者の繁殖力とアジアの「大軍」の死亡率を維持するための手段であると考えられていた。20世紀初頭、ヨーロッパ人の出生率が低下し続け、同時に退化への懸念が蔓延すると、国家の規模と「質」の向上が、植民地拡大を更新するための論理的根拠と人的資源を提供することになった。しかし、1930年代から40年代にかけて、帝国当局は、北アフリカ、朝鮮、インドシナ、西インド諸島、東インド諸島で人口増加が加速していることに気付き始めた。ナチスだけが、征服した民族の繁殖力を組織的に攻撃することを政策とし、同時にヨーロッパの中心で、大規模な収奪、強制労働、模範的なテロといった植民地的慣行を適用した。このような反動は、他の帝国主義諸国が、危険を冒してまで対象人口の増加を抑制することに消極的であることを強く印象づけた。これは、避妊を奨励する地元の支持があった場合でも同様であった。インドではラージが、占領下の日本では現地のエリートが人口抑制に国家再生と独立回復の手段を見出した。
このような歴史的背景から、「地球規模の家族」を計画しようとする運動が生まれた。家族計画によって、国内および世界における貧富の差が解消されることが期待された。植民地時代の元政府関係者は、新しい国際機関や非政府組織の職員となり、新しく独立した国家の指導者たちとともに、計画通りに国家を再生産する方法を考案した。1940年代にいくつかの失敗があり、1950年代には人口の確立が進んだ後、国境を越えたネットワークが大規模な社会工学実験を組織し始めた。当時Gunnar Myrdalが述べたように、国連機関はmission civilisatriceのマントルを受け継いだのである。貧しい国々は人口計画を受け入れるよう迫られ、豊かな国々はその費用を負担するよう期待された。最終的には、国連人口基金(United Nations Fund for Population Activities)を設立することに過半数が合意した。ロビイストと国連職員は、この基金を政府のモニタリングから守るため、あるいは少なくとも、より独立した活動を行うNGOに資金を流せるようにするため、舞台裏で活動した。推進派を新植民地主義だと公然と非難する国もあったが、USAIDや世界銀行などの強力な援助機関が再考するよう説得した10。
近年、主権制度がますます揺らいでいるように見えるため、観察者はユーゴスラビア、ルワンダ、アフガニスタンなどの「失敗国家」の運命に注目している。国際的な非政府組織は、「国際社会」を代表してスチュワードシップを発揮し、善意とはいえ、一種の「帝国ライト」を作り出している。人口抑制運動は、「グローバル・ガバナンス」が紛争地域だけでなく、植民地時代の将校がほとんど立ち入らなかったような領域でも機能することを数十年前に示した。ミシェル・フーコーが生政治と呼んだ、個人と社会の両方の身体を規制する権力は、国家主権に代わって「ガバナリティ」を実現する無限の機会を提供した。人々がどのように国家を再生産するかを規制するルールを説くことは、国家が自国の領土を支配する能力を回復することよりも、はるかに主権を破壊するものであった。推進派は、グローバルな規範に合うように人類を作り変えようとしていた11。
世界は今、伝染病、難民の流入、気候変動など、さまざまな「危機」に対応するトランスナショナルな運動で溢れている。多くの人々は、グローバル・ガバナンスを未来の希望と見なしている。最も重要な問題が国境によって封じ込められることがない現在、主権国家に代わるものとして歓迎されているようである。しかし、世界の人口をコントロールしようとした人々の多くが、世界平和や世界政府、あるいは少なくとも志を同じくする人々の緊密な結合を夢見ていたことを思い起こす価値はある。マルサス同盟の長年の指導者であったチャールズ・ドライズデールは、単に多産な親を罰するだけでなく、ドイツ、フランス、イギリスを統合する連邦制を望んでいた。コラード・ジーニ(Corrado Gini)は、混血のために大西洋の両岸が離れてしまうことを懸念して、ヨーロッパ・アメリカ連合を呼びかけた。ハリー・ラフーリンは、最高の株が地球を支配する国際議会の構想を何度も練り直した。ジュリアン・ハクスリーと彼の仲間の「改革優生学徒」は、このような人種的偏見と闘ったが、彼らもまた、遺伝子改良の包括的プログラムを行うための「全世界の連合体」を望んでいた。そして、唯一にして聖なる、カトリックにして使徒的な教会は、現世と来世の両方において、神のすべての民を代表することを常に主張してきた12。
なぜ、地球の統治者となるべき人々が、他の種類の統治者と本質的に異なると仮定しなければならないのだろうか。また、政治を別の容器に入れるだけで、政治が改善されるとなぜ期待できるのだろうか。特に、こうした新しい容器が人々を分断し、不平等な状態を維持するとしたらなおさらである。国民国家は、その欠点はあるにせよ、少なくとも、知事と被治者が同じ政治に属すると想定される構造を提供している。しかし、国民国家のおかげで、市民権を剥奪された無国籍者がひどい残虐行為に遭うことを防げなかった。国際機関や非政府組織は援助を提供することができる。しかし、もし彼らがより良い代替手段を提供しようとするならば、重大な欠陥を乗り越えなければならない。
おそらく、この問題は克服できるだろう。しかし、HIV/AIDSに対する世界的なキャンペーンのような最近の経験は、心強いものではない。人口抑制キャンペーンを管理したのと全く同じ機関が「教訓を得た」と言う割には、同じような過ちを繰り返しているケースがあるのだ。再び「危機」を宣言し、国家安全保障上の脅威でさえも、メディアの注目、科学的研究、人道的援助を集めるために必要だと思われるようになった。また、資金が爆発的に増加したため、「クラッシュ・プログラム」に対する圧力が高まった。この問題だけに取り組むために、すでに苦境に立たされていた保健プログラムからスタッフが引き抜かれた。世界的なエイズの危機」に対する標準化されたアプローチは、単に地域的な懸念に打ち勝つものであった。結局のところ、HIVは「人口過剰」のように、ジュネーブやニューヨークの人々を含むすべての人を脅かすものであり、一方で「赤痢対策活動家は存在しない」13。エイズや圧政、望まない妊娠に苦しむ人々を助けたいという切迫感を持つことは賞賛に値する。世界的な危機を今一度宣言することで、本当に「貧困の歴史を作る」ことができるのかもしれない。しかし、金と権力を持つ者が「対話」を、自分にとって何が良いかを他者に伝えるための手段に過ぎないと考えたとき、問題は始まる。このような非難を嘲笑うかのように、人々は自分が仕えていると主張する人々に対して責任を負わないとき、帝国の精神は生き続けるのである。歴史家にできることは、このようなことがどこにつながるかを思い起こさせることである。過去に対する貧弱な認識から出発した人間の状態を改善する計画からは、ほとんど良いことは生まれない。
少なくとも、人口抑制の歴史は終わったように見えるかもしれない。確かに、人口動態のトレンドを形成するための世界的な運動は、現在、休止状態にある。地域的、国家的、あるいは世界的に、社会がどのように自己を再生産するか、そのコントロールの所在が世界中で変化している。個人は、誰の助けや許可もなく、自分自身で決断している。国連の推計によれば、2億人近くが別の国に移住している。彼らはまた、何人の子どもを産むか、さらにはどのような子どもにするかも選択している14。
このような流れは、リプロダクティブ・ライツの究極の実現につながるように見えるかもしれない。しかし、一部の人々が自家用ジェット機を所有し、亡命者が投獄されるような世界では、悲観的になる必要はないだろう。例えば、多くの親たちは、仕事と家庭の間の選択がいかに困難であっても、自分の家庭を捨てざるを得ない貧しい女性たちの援助なしには不可能であることをすでに理解している。また、いまだに避妊ができない女性や、暴力を恐れずに避妊をすることができない女性もいる。中絶は女性が身体の自律性を守るための最後の砦であり、その攻撃は止むことがない。しかし、アジアでは、性選択によって女性が少数派となり、児童婚や性的暴力の対象になっている。このように、私たち自身は「家族計画」の生きた見本ではないにせよ、私たちは人口を形成するための政策やプログラムの遺産を背負って生きている。
新たな人口危機を宣言する人もいるが、今回は予測値が高すぎるのではなく、低すぎると思われるからであり、子供の数よりも高齢者の多さを恐れるべきだと言われている。現在、ヨーロッパと日本で最も顕著であるが、中国やメキシコのように出生率が最も急速に低下した国々では、人口の「高齢化」がより急速に進む可能性があり、今回は社会的セーフティーネットの恩恵はない。世界的には、体外受精や国際養子縁組の需要が高まっている。出産を先延ばしにしてきた人や妊娠に悩む人にとって、これらは奇跡のように思えるかもしれない。しかし、医療技術と「赤ちゃんビジネス」の経済学は、着床前遺伝子診断、代理出産のアウトソーシング、そして精子、卵子、胚、乳児の世界市場をももたらした。もし、特権階級の人々が、自分たちとは別の人種を選び、選ぶことが許されるなら、将来の世代はどうやって偏見と戦い、より平等な機会を促進できるだろうか。
それゆえ、新たな人口抑制の時代がやってくるのだ。もし歴史が何らかの指針になるなら、人口減少の予測はますます強圧的な政策、さらには墜落プログラムにつながるかもしれない。出生率を下げる方法として女性の教育、雇用、生殖医療が推進された以前の「政策的トレードオフ」の遺産が、これをより抵抗しにくくしている。結局のところ、これらが不可侵の権利ではなく、他の目的のための手段であったとしたら、人口「崩壊」を防ぐためにこれらの政策を逆行させる政府に、今さらどんな根拠で反対できるのだろうか。
トップダウンの強制がなくても、私たちはすでに、人口コントロールの民営化という、悪質極まりない事態を目の当たりにしているのかもしれない。それは、政府抜きの政府性であり、人々が自分自身を取り締まり、世代ごとに不平等を無意識に再生産し、強化するものだ。インドと中国では、性選択的中絶のためにこのプロセスが進行している。人口政治の旗手である米国では、この現象はより微妙なものとなっている。遺伝子の「カウンセリング」や胎児の健康への配慮を、完璧な子供を産めという社会的圧力と感じる親が多くなっている。日常会話の中で、人々はあらゆる行動を遺伝子の善し悪しに求め、それがどこから来てどこにつながるのか微塵も考えずに、優生学的カテキズムを忠実に暗唱している。個人の選択の積み重ねが、大国で家父長制を恒久化し、最も特権的な人々に遺伝的優位性を与え、彼らが世界を支配することになるのかもしれない。
このような問題は、地球規模のものであり、国境を越えるものである。私たちは、説明のつかない新たな権力を生み出すことなく、これらの問題に対処する手段を考案することができるのだろうか。既製の方式はない。しかし、官民を問わずさまざまな機関が協力して人々を助け、また彼らに答えるようなシステムがあるとすれば、それは心と頭を持ち、お金以上のもので運営されなければならない。それは、将来への不安だけでなく、生殖の自由へのコミットメントから始まり、歴史的な感覚を持ちながら進んでいかなければならない。そして、プロライフとプロチョイスの両方を備え、あらゆる種類の人口抑制に反対するために力を合わせなければならない。
強制的な出生促進主義や遺伝子の「強化」といった課題が、この最も厳しい文化戦争に平和的プロセスをもたらすかもしれないと考えるのは、素朴に思えるかもしれない。しかし、その代案は何だろうか。自らをプロライフと考える人々は、どんな代償を払っても人々を繁殖させることは、私たち全ての命を安っぽくすることにやがて気づかなければならない。そして、自らをプロチョイスと考える人々は、人口をコントロールするために考案されたあらゆる操作的、強制的な政策に反対する最前線に立つことで、より強い立場を得ることができるだろう。心強い兆候もある。家族計画グループは、一人っ子政策に抗議する中国の反体制派を擁護する発言を始めている。一部のプロライファーたちは、避妊へのアクセスを促進することが中絶の発生を減らす最善の方法であることを認識している。また、ある経済学者が中絶が犯罪率を低下させたと主張すると、それは1960年代の人口抑制の議論と不気味に響き合い、この餌に飛びついた唯一の人物は直ちに各方面から非難された15。
リプロダクティブ・フリーという大義を新たにし、復活させることができる新しいアジェンダには、もっと多くのことが必要だ。まずは、誠実なプロライフ派とプロチョイス派の人々が共通の立場を見出す努力をもっとすることだ。私たちは、子供の数を増やすことも減らすことも強制されることなく、誰もが避妊と育児の両方を利用できるようにするために協力しなければならない。私たちは、社会が潜在的な生命に関心を持ち、母親の権利とのバランスを取ることに同意し、共に世界中で性選択的中絶と戦うことができるだろう。また、現在無政府状態で不公平な国際養子縁組を、擁護と改革の機が熟していることを認識し、両者が協力することも可能である。私たちは、米国だけでなくアフリカでも、不妊治療がすべての人のための包括的なヘルスケアの一部となるよう要求することができる。もし私たちが、新しい技術によって健康問題の素因を選別したり、将来の世代を「強化」したりすることを認めるなら、こうした選択肢もすべての人に平等に与えられなければならない。また、資本、財、アイデアに劣らず、人々は世界中を移動し、それを受け入れる賢明な社会で機会を求めることができるべきであることを認識してもよいだろう。このように、私たちは地球規模の家族という理想を実現し始めることができるかもしれない。
人口抑制との闘いは、単に選択肢を主張するだけでは十分でないことを示した。選択肢は、既定または設計によって、新たな種類の抑圧につながる方法で条件付けされる可能性がある。また、生命を守ることが偶像となり、人々を繁殖に駆り立てれば、実体のないシンボルとなりかねない。生殖の自由は、これまで以上に自立することが可能であり、またそうしなければならない大義である。しかし、それは、私たち一人ひとりが自由に生まれ、平等に創られているという社会正義のビジョンによって活かされる場合にのみ、飛び立つことができる。
