Contents
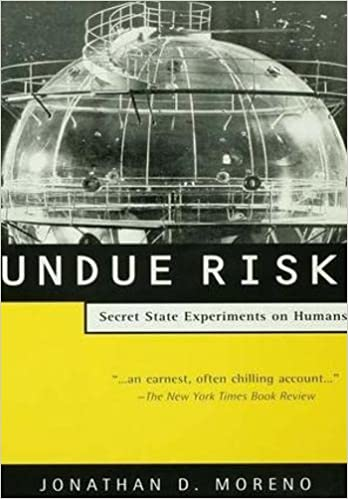
Undue Risk: Secret State Experiments on Humans
著者のジョナサン・D・モレノは、原子、生物、化学実験が長い間人体に対して行われてきたこと、そしてその実験が今日まで続いていることの説得力のある証拠を示している。これは並外れた重要な年代記である。
-ファットブレーン・ドットコム
モレノは、第二次世界大戦から1970年代半ばまで、政府の極秘の放射線実験に蓋をしたクリントン選任の諮問委員会の委員を務めた…。冷ややかで、綿密に記録された事件簿である。
-パブリッシャーズ・ウィークリー誌
Undue Riskは、現在と未来の医学研究の複雑な問題に直面する私たちに、道徳的な警戒を呼びかける力強い人道的な本である。
-Allan M. Brandt. ハーバード大学医学部歴史学科カッス教授
Undue Riskは、被験者の保護だけでなく、自由民主主義における政府の行動の適切な道徳的裏付けに関心を持つすべての人々にとって必読であるべきだ。
-ハロルド・T・シャピロプリンストン大学学長、国家生命倫理諮問委員会委員長
「善人」が何をしてきたか、何をしているかを示す重要な文書である。
-ブックリスト
ジョナサン・モレノは、第二次世界大戦から21世紀まで、原子・生物・化学兵器実験における人体使用の包括的な歴史を初めて提示した本である。ニュルンベルクの法廷から湾岸戦争の戦場まで、政府の様々な政策と具体的な事例を探求している。また、本書は、政府が人体実験の倫理と格闘し、不慣れな道徳的領域で苦渋の政策選択を展開した舞台裏を明らかにした最初の本でもある。著者による新しいあとがきでは、炭疽菌ワクチンの接種を要求された米軍兵士による最近の反対運動や、脆弱な人間を対象とする実験に関する政府の政策の新しい展開が取り上げられている。
ジョナサン・D・モレノは、クリントン大統領の人体放射線実験諮問委員会の元シニアスタッフで、バージニア大学のコーンフェルド生物医学倫理学教授と生物医学倫理センター長を務めている。ABCNews.comのコラムニストであり、テレビやラジオのコメンテーターとして、現在の生命倫理問題について頻繁に発言している。著書に『Deciding Together: Bioethics and Moral Consensus(生命倫理と道徳的合意)』の著者。バージニア州シャーロッツビルとワシントンD.C.に在住。
人体実験
人間に関する秘密実験
ジョナサン・D・モレノ
Routledge版は2001年に出版された。
過度のリスク:国家による人体実験の秘密/ジョナサン・D・モレノ。
目次
- 序文
- 謝辞
- 1サルマン・パックへの長い道のり
- 2ホームフロント私たちの科学、私たちの少年
- 3ニュルンベルクの影
- 4悪魔との取引
- 5放射線実験
- 6ペンタゴンとニュルンベルク綱領
- 7荒野の中で
- 8ルール変更
- 9もう一度湾岸へ
- 10あとがき
- ノート
- 索引
前書き
1994年3月のある日、私は医学部の学長との会談を終えようとして、学長の秘書からピンクの伝言メモを渡された。メッセージには、「あなたに提案がある」と書かれていた。友人であり、同僚でもあるルース・ファーデン(Johns Hopkins University in Baltimoreの教授)からの電話であった。ルースは最近、クリントン大統領から、冷戦時代に政府主導で行われた無名の市民に対する放射線研究の疑惑を調査する特別委員会の委員長に任命されたばかりだった。調査のきっかけは、アルバカーキ・トリビューン紙に掲載されたアイリーン・ウェルソメさんの一連の新聞記事である。第二次世界大戦中、米国市民がプルトニウムを注射されたという長年のうわさを、ウエルソムさんは名前と顔を明らかにしていた。
私は、このグループの使命は、軍事・医療研究によってアメリカ国民に何か悪いことが行われたかどうかだけでなく、何が起こったのかを正確に解明することだと思い、興味をそそられた。ニューヨーク・タイムズ紙は、新たに任命された大統領諮問委員会(Advisory Committee on Human Radiation Experiments)について、その重要な任務の一つは、古い公文書を徹底的に調べ、事件や政策を再構築することであると報じている。歴史好きの私にとって、1940年代から1970年代までの秘密実験の一次記録に触れることができる機会は、少なからず羨望(せんぼう)の念を抱いた。
数日後、私はワシントンのダウンタウンにあるレンタルオフィスに入った。すでにオフィス用品や政府支給の家具が散乱し、急遽集められたスタッフの中心人物(私はそのシニアメンバー)がいて、にぎやかな雰囲気であった。最終的には、哲学者、弁護士、放射線技師、歴史家、文書学者、疫学者、物理学者など、さまざまな顔ぶれが揃った。委員会自体は、これらすべての分野の専門家と一人の民間人で構成された。ルース・ファーデン氏のリーダーシップのもと、委員とそのスタッフは緊密に協力し合った。委員会のメンバーやスタッフは、ルース・ファーデン(Ruth Faden)のリーダーシップの下、緊密な連携を取りながら、政府機関に招かれた人々の中では、最も多彩な顔ぶれの1人であった。
しかし、その前途は多難であった。しかし、この委員会は、政府主導で行われる放射線実験について、さまざまな憶測を呼んでいた。退役軍人、元受刑者、母親、精神障害の治療や施設入所経験者、アメリカ先住民、アラスカ先住民、入院経験者、放射線治療を受けたがん患者、核実験の風下に住む人、原発の近くに住む人など、被害者はさまざまである。
このような多様な人たちが、それぞれの地域の新聞に、その地域特有の話題を提供した。例えば、シンシナティでは、亡くなったガン患者の家族が、著名な放射線科医を相手に、彼らの愛する人に対する実験の疑いで訴えを起こした。ネバダ州やワシントン州では、核分裂物質を使った地上での爆発実験や野外実験のために、発がんリスクが高まったと住民たちが心配している。テネシー州では、女性たちが「自分や胎児が放射線実験のモルモットにされた」と訴えた。
しかし、連邦政府の諮問委員会では、委員会の審議内容はすべて公開される。ある時、委員と職員の小グループが昼食の席を持った時、記者がテーブルの端に座り、ノートを広げていた。しかし、このようなことは、人目を避けて仕事をしている学者にとっては、非常に不愉快なことであった。
しかも、事件そのものに関する情報はほとんどない。クリントン大統領が諮問委員会の設置を指示したのは、当時のエネルギー省長官で、原子力委員会(AEC)のポートフォリオの多くを引き継いだヘイゼル・オリアリー氏の働きかけによるものであった。レーガン、ブッシュ両政権は、マサチューセッツ州選出のエド・マーキー下院議員が1986年に発表した「米国の核実験モルモット」についての報告書を盾に、放射線実験の調査を始めようとしなかった。しかし、オリアリーさんは1993年、ピューリッツァー賞を受賞したアイリーン・ウエルサム記者の連載で、この放射線実験疑惑を知り、大統領令の「オープン・オブ・ガバメント」にふさわしいと考えた。
しかし、エネルギー省は当初、40年近く前にAECが何をしていたかを、他の誰よりもよく知らなかった。国防総省など、この実験に関係していると思われる他の連邦政府機関も、数十年前の機密事項に関する組織的な記憶を喪失していた。しかし、そのようなことはない。しかし、ある会合で私が政府の記録について素朴な質問をした時、ある公文書館職員が辛抱強く説明してくれた。ペンタゴンの地下に”Human Radiation Experiments”というラベルのついた箱はない」と。
だから、この大統領諮問委員会はユニークなものでなければならなかった。医療倫理の問題を解決するだけでなく、被害を受けた人を特定し、正当な補償を勧告することも任務の一つであった。しかし、その前に、これまで秘密にされてきた歴史を明らかにしなければならない。委員会の活動を支援するため、大統領は、半ダースの機関に所属する数多くの政府職員が関与する大規模な機密解除作業を命じた。最初の6,7カ月は、委員会の事務所に毎日運び込まれる何万点にも及ぶ資料の箱をひたすら探した。ほんの数日前までは、機密情報かもしれないと思われていた一次資料を、歴史家がこれほどまでにすぐに入手できたことは、かつてなかったことだ。委員会のメンバーとスタッフは、1995年10月にホワイトハウスの式典で発表された最終報告書につながる、驚くべきストーリーを伝えることができた。ある評論家は、この千ページに及ぶ報告書を、その規模とともに『ユリシーズ』になぞらえた。
年~1970年代の放射線実験について、私たちが直面した障害の1つは、1年半という短い委員会期間中に、できるだけ早く関連情報の機密指定を解除しなければならないことだった。そのため、数人のスタッフが「最高機密」の許可を申請し、機密文書館にある文書を調査して、どの文書を機密解除に向けて「早道」するか決めるよう求められた。国家安全保障のための人体実験に関するアメリカの政策の変遷を再構築するという私の任務の性質上、私は徹底的な身元調査を受けた。近所の人たちは、一日中うちの通りを這いずり回る「背広組」を面白がったり、落胆したりしていた。
しかし、機密文書に目を通すことは、思ったほど華やかなことではない。私が読んだものの99パーセント以上は、無関係であり、まったく興味のないものだった。何十年も前の文書がいまだに機密扱いになっているのは、通常、何年も経ってからわざわざ見るきっかけがないからだ。当時でさえ、多くの覚書や報告書は、原子や核といった言葉が含まれているといった、まったく恣意的な理由で「機密」「秘密」「最高機密」のマークが付けられていた。ケネディ暗殺事件の記録をまとめた後の大統領委員会では、機密情報の多くが複製された文書であり、残りの多くは古い新聞や雑誌の切り抜きといった無害なものであることが判明している。このように、「秘密」の文書が詰まった箱の中で仕事をすることにロマンを感じていても、それは薄れるかもしれない。
しかし、諮問委員会に古い資料の収集を命じられ、放射線実験の実態を伝えることになった軍関係者は、以前の世代の政府関係者が抱いた困惑やスキャンダルの可能性を忘れてはいない。彼らは葛藤した。一方では、ペンタゴンの窓口となった制服組の将校たちほど、真実を明らかにしようと躍起になっていた者はいなかった。しかし、その一方で、国防総省の担当者である軍服警官ほど、真実を明らかにしたいと願っている者はいない。同時に、ベトナム戦争で傷ついた軍隊のイメージが、簡略化された形で報道され、再び傷つくことも懸念された。国防総省のブリーフィングでのコーヒーブレイクの間、ある海軍士官が、その日のうちに私が引用したワシントンポスト紙の記事について私に質問してきた。その記事は、委員会が公開した、1950年代初頭に軍が自国民を実験台にした可能性を示唆するいくつかの文書について述べていた。「アメリカのお父さん、お母さんたちは、自分たちの息子や娘を私たちに託している。
それでも、私が一緒に仕事をした政府関係者の最大の関心事は、制服組も民間人も、真実を明らかにすることであった。国防総省でブリーフィングを受けた後、私は陸軍の上級医師と話をしたが、この会話は私がこの本を書くきっかけとなった。ある時、彼は椅子に寄りかかり、ポケットに手を入れて、「私に言わせれば、ここで止まることはないだろう」と言った。どういう意味であるか、と私は尋ねた。「生物・化学兵器に進むんだろう。そこが本番だ」
月日が経つにつれて、私は彼の言わんとすることが理解できるようになった。放射性同位元素の使用については、1940年代後半のAEC設立当初から比較的よく調べられていたが、生物・化学兵器の取り扱いについてはそうではなかった。冷戦時代には、これらの薬剤の管理はそれほど厳重ではなかったようだ。生物化学兵器は、広島のような歴史を変えるような事件と結びつくようなドラマがなく、一般の人々の想像力のレーダースクリーンからほとんど消えていた。また、精神に作用する薬物はガレージで製造できるが(私の高校時代の友人がまさにそうしていた)、有用な放射性物質はかなり複雑な製造工程を必要とした。
また、軍医がほのめかしたように、放射線源を使った人体実験の最近の歴史と倫理は、細菌・化学兵器研究と切り離すことができないことも理解するようになった。1950年代初めには、国防総省の顧問が3つの兵器を戦術的な関心事の一部として扱い、「ABC」(原子、生物、化学)兵器の実験に関する倫理的問題は一体のものであるとしていたのだ。残念ながら、論理的には私たちの研究を続けることができたかもしれないが、政治はそうしなかった。化学兵器に関するスキャンダルは、1970年代半ばに中央情報局(CIA)のMKULTRA計画が暴露されたことで一段落し、イラクの生物兵器に関する脅威は、1990年代後半の兵器査察の危機まで沈静化したように思われた。放射線実験の風評被害のように、突発的な宣伝がない限り、調査を継続し、放射線諮問委員会の任務を拡大するほどの政治的機運は、草の根レベルでは得られなかった。
もし、調査が生物・化学実験の歴史と倫理に及んでいたなら、参考にすべき多くの経験があっただろう。化学・生物学的製剤の研究は、放射線研究よりはるかに長い歴史がある。この研究は、必ずしも兵器に関わるものではなく、兵士の戦闘能力を向上させるために行われることが多かった。1883年、バイエルン軍の兵士が、演習中にコカインを投与され、疲労回復に効果があるかどうか調べられた。また、70年後には、リゼルグ酸ジエチルアミド(LSD)という精神作用のある薬物が、アメリカの兵士を対象にテストされた。世紀の変わり目、南アフリカのボーア戦争で戦っていたイギリス兵に腸チフスのワクチンが提供されたが、志願して接種した者はほとんどおらず、何千人もの兵士がこの病気で死んだ。1991年の湾岸戦争では、アメリカ兵に神経ガスから身を守るための薬剤が提供されたが、それを受け入れる兵士はほとんどいなかった。
生物兵器については、その歴史は古い。生物、微生物、あるいはそれに由来する毒素を軍事目的に利用する可能性についての「実験」は、これらのメカニズムが解明されるずっと以前から行われていた。ペルシャ人、ギリシャ人、ローマ人は動物の死体を使って敵の飲み水を汚染した。この技術は中世やアメリカの南北戦争で何度か真似された。紀元前400年、スキタイの射手は腐敗した死体や糞尿を混ぜた血液に矢をつがえ、生物製剤を「武器化」した。14世紀には、フランス人が敵の城に攻め入る前に、死んだ馬を打ち込んだ。その数年後、モンゴルの族長がジェノヴァ軍が守るクリミアの街にペストの死骸を投げ込み、おそらくその後のヨーロッパの大流行の一因となったのだろう。18世紀には、ロシア人がエストニアの城壁にペストの死体を投げ込み、スウェーデン軍に感染させようとした。20世紀には、大学の研究室で開発された「細菌説」が、戦争兵器としての生物学的病原体の管理研究と、その防御に拍車をかけた。
原子爆弾、生物兵器、化学兵器は、しばしば「大量破壊兵器」という見出しで一括りにされるが、このカテゴリーに3つを入れるのは誤解を招きやすい。化学兵器の破壊力は、他の2つの兵器に比べてはるかに限定的である。核放射線は、水爆のように「兵器化」された場合、初期破壊力が非常に大きく、半減期も長い。生物兵器は移動性の宿主に潜伏し、一部は繁殖することができる。一方、原子爆弾や生物兵器の予測不可能な性質は、攻撃者にとっての有用性を制限し、攻撃者自身が「返報性」によって犠牲者になる可能性がある。
この仕事を続けられなかったことへの私の落胆にもかかわらず、1995年末に「人間放射線実験諮問委員会」がその扉を閉じた時、それは明らかに大統領の指令で定められた以上のことを達成した。委員会の調査結果は、第二次世界大戦末期から今日に至るまで、しばしば秘密会議の場で繰り広げられた、新型で恐ろしい兵器を使った人体実験という難問をめぐる政府高官の特異な倫理劇を認識させるものであった。このドラマは、医療倫理に関する懸念をはるかに超えて、近代民主主義の核となるパラドックスにまで及んでいる。トーマス・ジェファーソンやジェームズ・マディソンが想像もしなかったような世界で、自らを守るために、時には非民主的な手段で防衛する必要がある。
この本では、具体的な事例と政府の政策を通して、人体実験に関する議論を語っている。私の説明は、5年間にわたり、政府高官、学者、医学研究者など数十人の人々との対話によって形作られた。私の情報源は、一次資料、政府の過去の調査、新聞の切り抜き、このテーマの様々な要素に関する専門家とのインタビュー、生物・化学兵器研究の様々な側面に関する先行研究などである。
私は、(他の人はそう思わないかもしれないが)放射線諮問委員会の働きかけにより、人体実験に関する主要な概要が公開されたと確信している。生物・化学兵器開発の歴史については、それほど悲観はしていないが、この分野でも10年前と比べれば、1990年代後半にははるかに多くのことが分かってきている。この仕事を始めてから、私はある認識を何度も強く持った。政府の秘密主義は民主主義を腐敗させ、私たちの生活様式に対する真の脅威を構成している。
過去25年間、国家安全保障に関連する実験に関するスキャンダルは定期的に表面化し、人々の意識から遠ざかってきた。そのため、それぞれの事件が本当に大きな物語の一部であるのかどうかが分かりにくくなっている。より重要なことは、国家安全保障の文脈における人体実験の倫理的行為について、理論と実践の両面で真の進歩があったことである。しかし、この進歩は、政府の政策の変遷と、時に衝撃的な乱用が、しばしば痛みを伴いながらも漸進的に今日の保護を生み出したこととを重ね合わせなければ、明らかにはならない。この道の終わりには、民生・軍事を問わず、他のすべての道徳的モデルとなるような人体実験プログラムが存在する。第9章では、アメリカの生物学的防衛プログラムの中心に位置する、倫理的な人体実験のパラダイムについて説明する。
過去数十年間と同様、今日でも、潜在的に危険な物質のリスクを進んで知識として受け入れる人々と、操作されたり強制されたりする人々の間には、基本的かつ顕著な道徳的違いがある。前者はしばしば英雄であり、後者はまさに不当なリスクにさらされる「人間モルモット」である。まともな社会は、弱い立場の人々の搾取を容認することはできない。この搾取が国防の名の下に行われるとしたら、その社会の政治文化の根幹が腐っている。
21世紀も、医学研究は、敵の兵器から戦闘員だけでなく民間人を守る手段を開発し、国家安全保障のために重要な役割を果たすだろう。先にも述べたように、効果的な防衛策を理論的に説明し、動物やコンピュータのモデルを研究することは、それだけで十分である。国家の安全保障が新型の戦争兵器によって脅かされる限り、人間を医学的実験の対象としなければ答えられないような科学的疑問が生じるだろう。そして、そのような研究に伴うリスクを受け入れることが許される個人がいるのか、という道徳的な問題も出てくるだろう。本書が成功すれば、歴史上最も強力な共和国、そして最も医学的に洗練された社会の市民が、その不快で複雑な現実に直面する一助となるであろう。
謝辞
発展途上の原稿は、身近な伴侶となる方法がある。人間関係の終わりと同じように、その喪失はショックなものである。幸いなことに、その過程で人間の仲間も生まれる傾向があり、「すべての書籍は社会的産物である」という格言に真実味を与えている。このテーマの広さと複雑さを考えると、私は実に幸運なことに、多くの素晴らしい仲間に恵まれてきた。彼らは私の考えを発展させ、いくつかの分野の情報を集め、解釈するのを助けてくれた。
特に、大統領諮問委員会のルース・ファーデン委員長とダン・グットマン事務局長は、その代表的な協力者である。ルースは私に一生に一度の仕事の機会を与え、ダンは私に「箱の中に入る」方法を教えてくれた。また、委員会の元スタッフであるジョン・ハークネス、トラッド・ヒューズ、ヴァレリー・ハート、ギル・ウィットモアには、情報源や資料を探すのに助けられた。委員会での仕事の間、そしてその後も、アラン・ブキャナン、ジム・デイビッド、パトリック・フィッツジェラルド、イーライ・グラットスタイン、グレッグ・ハーケン、ジェフ・カーン、ジェイ・カッツ、パット・キング、ルース・マックリン、アナ・マストロヤンニ、ロン・ノイマン、ヘンリー・ロイヤル、ジェレミー・サガルマンら多くの委員会メンバーやスタッフから、見識を深めるための恩恵を受けた。
また、長年にわたって、当時学部生だった非常に有能な研究者たち、特にカールトン・ヘイウッド、デビッド・パンタローン、プレヤ・バラ・シャルマ、サーシャ・ヤムシコフ、そして法学部生のロブ・タナーの協力を得ることができた。Art Anderson、Wally Cummins、Ben Garrett、Joan Porterは、インタビューを許可してくれた人たちで、多くの貴重な洞察と手掛かりを与えてくれた。彼らには感謝している。
1995年から1997年までペンシルバニア大学の生命倫理センターで教鞭をとっていたとき、同センターの同僚と話をすることができ、また1998年春には国立衛生研究所の臨床センターで臨床生命倫理科のメンバーと議論することができた。原稿を読み、批評してくれたEvan DeRenzoに感謝する。
米国ホロコースト記念博物館とペンシルバニア大学のアーキビストの方々は、非常に親切で協力的であり、私が彼らの資料を使って研究を行うことができたことに、彼らと彼らの機関に感謝する。
本書の執筆中、私は幸運にもヴァージニア大学医学部で教鞭をとることになり、現在は同大学の生物医学倫理センターで指揮を執っている。同僚のポール・ロンバルドの専門知識は、私が今住んでいるこの素晴らしい大学の他の研究者たちと同様、私の思考を助けてくれた。
ベッツィー・アムスターとアンジェラ・ミラーは、私がこの本の企画書を練り直すのを手伝ってくれ、ジョナサン・コブの熱意によって、W. H. フリーマン・アンド・カンパニーにこの本がもたらされた。また、エリカ・ゴールドマンとジョン・ミシェルには、このプロジェクトを快く引き受けてくれたことに感謝している。
本書を通じて、私は多くの作家、特に歴史家やジャーナリストたちが、長年にわたってこの物語の側面を照らし出してきたブレイクスルー仕事に依拠した。私はただ、彼らの労苦に報いることができたと願うだけである。
また、私たちの医療と道徳を向上させてくれた医学者、軍の指導者、公職者たちにも感謝したい。
最後に、私の人生の中心である家族に、限りない感謝を捧げる。
第1章 サルマン・パクへの長い道のり
イラクがなぜこれほど強く生物兵器プログラムに関する事実の公表を拒み、また、なぜこれほど執拗に委員会自身の努力による事実の解明を阻止しようとするのか、理解できないところがある。
国連報告書1997年10月6日
殺人と医療
バグダッドから南へ約30マイル、チグリス川の湾曲部に位置する軍都サルマンパックは、長い間イラクの生物兵器製造の中心地と考えられてきた。年8月、国連の専門家チームが、湾岸戦争で爆撃された施設の跡を調査するためにサルマン・パックに到着した。しかし、そこには焦土と化した施設しかなかった。わずか2週間前、イラク人は研究所を破壊し、連合軍の爆撃に耐えた書類もすべて焼却してしまった。
それは、バクテリアに暴露するための部屋であり、「人間を含む大型の霊長類」を入れるのにちょうどよい大きさであったと、国連査察官の一人が丁寧に説明してくれた。
その後数年間、イラク政府は、イラクの過去と現在の生物・化学兵器製造能力を評価する役割を担う査察団の行く手を阻み、和平協定の条件に背き続けた。しかし、国連査察団の粘り強い努力は徐々に実を結び、1997年末には、人間を含む生物兵器の実地試験に関する議論の余地のない証拠が蓄積された。
人体実験は、イラク側が戦争準備の中で特に敏感になっていた一面であった。人体実験は、イラクが違法に兵器開発を続けていることを示すだけでなく、国連の制裁下にあるイラクの苦しみに同情的な国々の間で、イラクの道徳的優位性を損ねることになるからだ。1998年初め、査察団は人体実験問題を追及し、イラク側を驚かせた。この問題が、国連特別委員会(UNSCOM)の活動をイラク側が初めて停止させるきっかけとなったことを、今ではほとんど誰も思い出さない。「当時の元国連査察官は「推測では、おそらく倫理に反した実験に関係があるのだろう」と語っている。
UNSCOMのチームは、数年前に海兵隊に所属していたアメリカ人のスコット・リッター氏が率いており、イラク人のスパイ疑惑をあおった。その後、サダム・フセインが国連に抗議したため、国際的な危機が相次ぎ、UNSCOMの活動は一部停止し、イラク側が残存する証拠を片付ける時間が設けられた。米国のイラクに対する弱腰に抗議し、後にUNSCOMを辞任したリッター氏は、1998年12月、『ニュー・リパブリック』紙に寄稿し、この時の状況をこう語っている。
今年1月、私たちは、イラクが生きた人間を実験台にして生物化学兵器を使用していることを暴露する取り組みに着手した……。私たちは、95人の政治犯がアブガリブ刑務所からイラク西部のある場所に移送され、サダムの個人的権限の下にある軍産委員会の特別部隊の監視下で致死実験が行われているという証拠を入手していた。しかし、私たちの主張を裏付ける資料(例えば、囚人の移送記録など)が保管されている施設への侵入を開始した途端、イラクは危険に目覚め、私たちへの協力を一切止めてしまった。
国連チームが刑務所の記録を入手するために頓挫する前に、彼らが知ったイラクの実地試験の事実は悲惨なものであった。捕虜は杭に縛られ、数メートル離れた爆弾や航空機から投下された爆弾から致死性のバクテリアやガスを浴びせられ、苦しみながら死んでいった。また、天井に取り付けられたジェット機から炭疽菌を噴射されながら、部屋に閉じ込められたこともあった。死因は内出血である。ある実験ではイランの戦争捕虜が、別の実験ではイラクの犯罪者とクルド人が「被験者」になった。クルド人指導者のマスード・バルザニ氏は、1982年に拉致された2000人のクルド人が、イラクの第一世代の化学兵器の実験に使われたという証拠を持っていると主張している。
イラクの兵器査察の危機が続いているのは、冷戦後の国家安全保障政策における新しい章の一部である。アメリカの防衛計画者たちは、ならず者国家やテロリストの手にかかれば、何十年もの間ほとんど無視してきた兵器が、冷戦後の時代にはアメリカにとってかなりの脅威となることを認識した。炭疽菌やボツリヌス菌のような細菌や神経ガスのような化学物質は、コントロールするのも効果的に送り込むのも難しいが、製造や輸送は比較的安価にできる。そして、それらは特に人口の多い地域で、民間人の間に大惨事をもたらす可能性がある。政府関係者は現在、長年にわたる怠慢を挽回し、生物・化学兵器の危険に対する防御策を開発しようとしている。米国の情報当局は、1979年には3カ国しかなかった細菌兵器の研究を、1998年には17カ国が行っているだろうと推定している。
しかし、一般大衆が通常認識していないのは、生物・化学兵器に対する防御を確認するため、あるいは兵器そのものを開発するために、これらの薬剤に関連した人体実験が長く、国際的な歴史を持っているということである。この点では、イラク人は決して特殊な存在ではない。また、「モルモット」(真の研究者が嫌う言葉)として人間を使いながら、その事実が広く知れ渡った場合の国内外の世論を気にしながら進めているのも、イラク人ならではのことだろう。
そして、この問題をめぐる感情は常に熱を帯びており、不正な人体実験の話が横行し、煽り立てている。本書の作成を通じて、特に長い間噂されていた歴史的な事件や、最近起こった世界各地の問題に取り組む中で、さまざまな主張と反論に遭遇した。それらは慎重に扱わなければならない。放射線研究と異なり、生物・化学兵器に関する実験の歴史は、臨床試験や実地試験も含め、これまでほとんど慎重かつ包括的に分析されたことはない。それでも、第2次世界大戦後のアメリカにおける人体実験に関する政策論争を、ある程度詳細に説明するのに十分な証拠がそろってきた。
本書で述べるような不幸な歴史にもかかわらず、アメリカはある国のような堕落した国にはなっていない。とはいえ、アメリカの軍事・医学実験は一般に防衛的な目的で行われてきたが、特に第二次世界大戦以降、攻撃的な軍事実験と防衛的な軍事実験の境界線、およびその実施に必要な知識は必ずしも容易に引けるものではなかった。その結果、50年以上もの間、アメリカの政府関係者たちは、自分たちのやり方が非常に悪い連中の仲間入りをする可能性があることに頭を悩ませてきた。
これから述べるように、「非通常型兵器」あるいは「大量破壊兵器」の人体実験が国家の恥になる可能性は、第二次世界大戦後、アメリカの防衛計画において常に緊張の原因となっていた。戦時中も軍事目的の人体実験は行われ、時には秘密裏に行われることもあったが、一般的には恥ずべきこととは考えられていなかった。戦時中は軍事目的で人体実験が行われ、時には秘密裏に行われることもあったが、一般的には恥ずかしいことだとは思われていなかった。また、ヒトラーの医師がナチスの戦争努力のためにどこまでやっていたかを世界が知る前でもあった。最初の数章で説明するように、ナチスの医師たちの犯罪が明らかになったことで、アメリカの国防計画者たちは、起こりうる第三次世界大戦に備え、厳しい立場に立たされることになった。
第二次世界大戦の終結以来、今日に至るまで、人体実験に対する普遍的な感受性は、国家安全保障のリアルワールドにおいて、おそらく避けられないものであるという事実と相まって、人体実験が行われ続けている。教科書的な理論、実験室での実験、コンピューターや動物モデルなどでは限界がある。新しい兵器に人間がどう反応するかという情報が必要になったとき、ある時点で人体実験をしなければならなくなる。米国はこの事業を継続しなければならない可能性が高い。危険な世界では、そうしないのは無責任だと言う人がいるかもしれない。前世代と同様、現代の米国人が直面している困難な問題は、私たちが支持すると公言している民主主義と人権の価値に反することなく、この仕事をどのように行うことができるのかということである。
アパルトヘイトの秘密兵器
1980年代に化学・生物兵器の開発に取り組んだ国は、イラクだけではない。ノーベル平和賞受賞者のデズモンド・ツツ司教が委員長を務める南アフリカの真実和解委員会(TRC)が委託した報告書は、1998年に終了した調査の中で、旧アパルトヘイト政権の秘密の医学研究プログラムを明らかにした。例によって、人体実験が開発の重要な部分を占めていた。
TRCは、現政権誕生以前にアパルトヘイト勢力と反アパルトヘイト勢力の双方が用いた不謹慎な手段を明らかにするために結成された。TRCの要請を受け、オランダ政府の資金援助を受けたオランダ南部アフリカ研究所(NIZA)が南アフリカの旧生物化学兵器に関する調査を行った。その中で、1982年1月16日、モザンビーク南部の南アフリカ国境に近いレナモの拠点で、300~400人のモザンビーク軍がレナモ反乱軍を攻撃した事件が検討されている。レナモは南アフリカ共和国の白人政権に支援されていた。NIZAの報告書によると
中隊が箱型陣形をとって徒歩でキャンプに近づくと、キャンプ付近に白いジープタイプの車両が見えた。この時、上空を飛行する未確認の軽飛行機が目撃された。部隊は最近廃墟と化したレナモ基地に入った。彼らは再び基地を離れ、数キロ離れたところで、15発以下の限定的な小火器による銃撃を受けた。彼らは身を隠したが、頭上150から250フィートの間の箱の輪郭の中で爆発が起こり、黒煙の濃い雲が放出され、その後消息を絶った。風は編隊の後方に向かって吹いていた。
15分後、最初の不満が起こった。「暑くてたまらない。暑くて気が狂いそうだった」とジョアキム・ジョナサ少尉は言う。胸苦しさ、疲労感、のどの渇き、翌朝に水を飲むと嘔吐する者もいたという。また、目が見えにくくなったという人もいた。(Guardian 28/1/92)[この一節の内部参照]. 結果として、部隊のかなりの混乱が起こった。
部隊の「混乱」は、制御不能の銃撃の際に、4名の死者と2名の負傷者を出す結果となった。この事件が猛暑による脱水症状によって引き起こされたという可能性は低いものの、報告書は「しかし、上記の事件は、南アフリカの化学・生物兵器プログラムの一環として、外国人兵士に対する戦闘状況での化学兵器の実験の一例であるという可能性がかなり残っている」と結論づけている。TRCは最終報告書の中で、脱水説は「ありえない」と述べている。
神経ガスを使った単なる実戦テストでは、南アフリカの兵器プログラムの革新的な質の高さを十分に評価することはできない。ある意味では、特定の人種を狙い撃ちして集団不妊症を引き起こすなど、将来の生物兵器を予見させるものであった。この計画は、旧アパルトヘイト政権がスポンサーとなり、委員会の対象となったものである。アパルトヘイトに反対する個人への嫌がらせや殺害を目的として、このプログラムで開発された様々な化学・生物兵器の他に、委員会は「黒人を対象とした不妊治療薬の研究の主張」も調査している。委員会のオランダ人研究者は、「これらの化学・生物兵器関連の事実をさらに調査すれば、このプログラムの下で人権侵害が行われたことがわかるだろう」と結論づけた。
軍事的な理由から、白人の南アフリカ人とイラク人は、生物・化学兵器プログラムを秘密にしておきたかったのだろう。しかし、政治的な理由から、数少ない同盟国から疎外されないように、これらのプログラムの人体実験的な側面を秘密にしておく理由がさらにあった。兵器開発は国家安全保障の一環であるとして弁解の余地があるかもしれないが、人体実験にまつわる悪臭はほぼ全世界共通だからだ。TRCの最終報告書には、ナチスの医師たちが残した言葉の響きが残っている。「白衣の科学者、教授、医師、歯科医、獣医、研究所、大学、フロント企業などが、広範な国際ネットワークの支援を受けてアパルトヘイトを支えているというイメージは、とりわけ冷笑的でゾッとするものだった」と。
ツツ主教の委員会報告が発表された数日後、ロンドン・タイムズ紙は、イスラエル政府がアラブ人を標的とする生物兵器「エスノボム」の開発を試みているという南アフリカの情報源からのAP通信の報告を載せた。アラブ人とユダヤ人は同じセム系民族であり、その遺伝子をほとんど共有しているはずであるから、これは相当な技術的成果であろう。イスラエルの軍事生物学研究所Nes Tziyonaの無名のイスラエル人科学者は、困難にもかかわらず、「しかし、彼らは、特定のアラブコミュニティ、特にイラク人の遺伝子プロファイルの特定の特徴をピンポイントで特定することに成功した」と述べたと引用されている。
この報告書に対して、イスラエル議会のある議員は、ユダヤ人が強制収容所の実験で人種医療を受けた経験を思い出している。「道徳的に、私たちの歴史と伝統と経験に基づけば、このような兵器は怪物的であり、否定されるべきものである」イスラエル首相の報道官は、この疑惑を頭ごなしに否定した。この報告書は1998年11月中旬に発表されたが、ちょうどその頃、米国はUNSCOM合意違反を理由にイラクへの空爆を準備していた。
しかし、その真偽のほどはともかく、攻撃的であれ防衛的であれ、革新的な軍事計画には必ず人体実験が伴うという事実が浮き彫りになった。この事実は、国家安全保障の研究計画全体を危うくしかねない倫理的問題を引き起こすため、各国政府は決して認めたがらない。生物・化学兵器が通常の兵器よりも本質的に好ましくないとは考えない多くの人々でさえ、その開発や防御のために必要な実験を擁護することは難しい。医療と軍事の人体実験というテーマは、常にナチスの医師を裁いたニュルンベルク裁判の影に隠れているのだ。
ダック・アンド・カバー
40歳以上のアメリカ人の多くは、最近の生物・化学兵器に関する恐怖に、奇妙な既視感を覚えているようだ。学校の地下室で「アヒル・アンド・カバー」の市民防衛訓練が行われ、自宅の地下室には核戦争後の長い籠城に備えて缶詰が保管されていたことを思い出す。実際、原子爆弾による戦争は、その恐怖感や民間人を混乱させる力において、生物・化学兵器による脅威と多くの共通点がある。そして、1945年以降のこれらの「非通常型」兵器の製造と防衛の歴史は、原子、生物、化学の戦争準備を密接に結びつけている。いずれも、1940年代後半から1950年代にかけての国防計画者の戦略立案の一部であり、人体実験の必要性を認識させるものであった。これらの実験は通常、軍事的に必要だと考えられていたことの暗部であり、恥ずべき側面であった。
米国では、1997年から1998年にかけて、生物・化学兵器に対する恐怖に直面する一方で、原爆実験の後遺症についての見出しが躍った。1950年代、米国政府は「原爆実験による健康被害はない」と市民に説明していたが、1997年、国立がん研究所は、大気中の放射線量の増加により、1万~7万5千人の甲状腺がんが余分に発生したと結論づけた。さらに悪いことに、健康への懸念が否定されるのと同時に、連邦政府当局は、原爆放射性物質がフィルムメーカーに損害を与える可能性があると警告していた。アイオワ州選出の上院議員トム・ハーキン氏の言葉を借りれば、「政府がコダック社にはフィルムについて警告したのに、一般市民が飲む牛乳には警告しないのは実に奇妙なことだ」
核兵器による甲状腺障害は、医学的な実験ではなく、軍事演習によって引き起こされたものである。しかし、ラジウムは1940年代から1960年代にかけて、軍隊を中心に多くの医院で耳の感染症の治療に使われた。特に軍隊では、8千人から2万人の軍人とその扶養家族が、鼻孔に小さな棒を入れて、炎症を抑える治療を受けていた。1982年のジョンズ・ホプキンス大学の研究では、この治療法は放射線の危険性があるため、当時は人気がなかったが、頭頸部がんの発生率が高くなる可能性が示唆された。
このように、核兵器の放射線利用は、軍事、医療両面で大きな関心を集めている。年4月初め、シンシナティ大学が、90人のがん患者の遺族と500万ドル(約6億円)の訴訟で和解したと発表した。ユージン・サンガー博士が1960年から1971年にかけて、末期患者の全身および部分への有害な放射線照射実験に従事していたことが、かねてから指摘されていた。サンガー博士は著名な放射線科医で、その研究の一部は米国防総省の支援を受けていた。
また、1990年代後半には、軍事目的と医療計画を組み合わせた活動にも、原子力が使われていたことが話題になった。1997年の大晦日、シリアル会社のクエーカー・オーツ社は、マサチューセッツ工科大学(MIT)と共同で、1950年代に知らぬ間に受けた実験被害者の訴訟で和解した。被害者はマサチューセッツ州ウォルサムのフェルナルド校に通っていた少年たちで、人間の消化器官における栄養素の経路を特定するために、微量の放射線を含むシリアルを食べさせられた。この学校は「知的障害者」のための特別なクラブで、親は彼らの入部を許可していたが、放射線については何も言わなかった。被曝線量は非常に低かったが、MITの広報担当者は1998年、彼らの市民権(実験に参加することに同意する権利)が侵害されたとの見解を示した。この185万ドルの和解金は、フェルナルドの「科学クラブ」の卒業生のうち約30人が対象である。
フェルナルドとレンサムという別の学校での研究は、国家安全保障実験という用語の範囲という問題を指摘している。もし、この言葉を狭く捉えれば、国防に関連する直接かつ予見可能な情報を提供する人体実験だけが含まれることになる。例えば、生物兵器に対するワクチンの開発などである。しかし、私はこの言葉をより広い意味でとらえなければならないと考えている。軍事目的に適用できる結果をもたらす可能性があるという理由で支援されている研究は、その研究が安全保障の文脈からいかにかけ離れているように見えても、すべて含まれることになる。特に初期の放射線実験については、後者の解釈の方がより事実に即しており、本書では国家安全保障実験の範囲についてこの理解を用いることにする。
フェルナルド計画の放射性物質は、もう一つのスポンサーである原子力委員会(AEC)から供給された。AECは国の核資源を管理する民間の機関である。ソ連が原爆を開発してからわずか数年後の1950年代初め、国家安全保障と公衆衛生の観点から、人体が放射線をどのように吸収・除去するかは重要な問題であった。当時、これは正当な実験だったのだろうか。それとも、少年たちの市民権を侵害する許されざる行為だったのだろうか。大量破壊兵器が氾濫する現代社会で、民主的な個人の権利の原則に基づく国民国家はどこまで自衛できるのだろうか。治癒のための技術である医学を自衛のための手段として使ってよいのか。医師がそのような仕事に携わることは適切なのだろうか。数十年の間にルールは変わり、今日、これらの問題はどのように扱われているのだろうか。これらの疑問は、軍事医学研究において人間を使用する際に、科学的・技術的な問題に道徳的な複雑さが不可避的に織り込まれていることを明らかにするものである。
第9章 もう一度湾岸へ
「重要なのは、自分が正しいことをしているかどうか、熟慮して懐疑的になることだ。強力なテクノロジーを扱うときには、自分のしていることの倫理を本当によく考える必要があるという意識を持たなければならない」
タラ・オトゥール(元エネルギー省次官補)
ゼロ・トレランス
過去半世紀の間に、職務上のリスクに対するアメリカ人の考え方は大きく変わりました。第二次世界大戦直後は、放射線や生物・化学物質への曝露に人間がどれだけ耐えられるかが最大の関心事であった。実際、国防省の担当者は、こうした新種の兵器にさらされた兵士が戦闘で機能するかどうかを心配し、医学研究者は、実験の過程でどの程度の被ばくが「許される」かを判断するのに苦労したものである。
このような英雄的な時代は、今日の私たちの意識とはかなりかけ離れているように思われる。英雄が現れないわけではないが、英雄的な国家奉仕が、すべての国民が積極的に努力すべき理想であるとの前提がなくなった。国民感情の大きな変化は、戦闘作戦を計画する際にも、国家安全保障の目標を念頭に置いた人体実験を行う際にも、防衛計画担当者にとって興味深い障害をもたらす。危険な世界唯一の超大国としての役割を、リスク回避的な態度で維持することは困難である。とはいえ、米国防総省の高官や政治指導者たちは、軍事介入による死傷者に対する米国民の許容度がゼロに近づいていることを知っている。また、特に軍人が関与する場合は、相殺する利益のない危険な人体実験に対する許容度は事実上ゼロであることも知っている。
今日の軍事指導者たちは、ベトナムの悲劇を経験した世代である。その苦い記憶もあって、彼らは湾岸戦争をできるだけ危険を冒さずに実施することを決意した。「砂漠の盾」「砂漠の嵐作戦作戦」に従軍した約70万人のうち、戦闘による死者は148人であった。湾岸戦争に従軍中に戦争とは関係のない病気や事故で亡くなった人も、ほぼ同数いた。この驚くほど低い死亡率と記録されたわずかな負傷者(497人)は、この行動で死傷者を最小限に抑えることに軍指導部が高い優先順位を与えていたことを反映している。
残念ながら、湾岸戦争から帰還した退役軍人の多くが、疲労、筋肉痛、関節痛、頭痛、記憶喪失などの衰弱した病気を訴えるようになった。このような症状を説明する理論は数多くあるが、その中でも特に皮肉なものがある。兵士たちを邪悪な兵器から守るために開発された薬物が、結果的に長期的な損害をもたらしたとする説があるのだ。さらに悪いことに、この薬品は戦場での使用について承認もテストもされていないため、その使用はよく言えば無謀、悪く言えばいい加減で検討不足の実験であったように思われる。
このような経験による身体的損害があったかどうかは別として、湾岸戦争兵士がモルモットにされたという疑いは、いくつかの部隊で明らかに士気を低下させた。年3月、ジェフリー・A・ベッテンドルフ一等空兵は炭疽菌ワクチンの注射を拒否したため、「名誉以外の条件で」除隊させられた。海軍では23人の水兵が同じ理由で処分を受けた。オンライン・チャットで水兵の一人が言った。「軍が私を傷つけるようなことはしないと信じるなら、ペルシャ湾から戻った多くの病気のアメリカ人に話を聞くことをお勧めする。私はこの国を愛しているし、死んでもいいと思っている。しかし、それは戦争のためであって、私のために実験するためではない。
インフォームド・コンセントの放棄
年秋、国防総省がクウェート侵攻の準備を進める中、サダム・フセインの化学・生物兵器に関する驚くべき情報報告があり、医学が兵士に提供できる保護措置について問い合わせがあった。さまざまな薬剤が脅威となっているが、いくつかの薬剤が潜在的な化学・生物兵器に有効である可能性があった。その一つは神経ガスである。神経ガスは高用量で痙攣、呼吸麻痺を起こし、数分以内に死亡することがある。もう一つは炭疽菌で、これは通常牛や羊に見られるもので、フルラ状の症状で始まるが、治療しなければ数日で死に至るので診断が困難である。さらに、サダム・フセインが兵器化したと思われるもう一つの生物兵器はボツリヌス毒素で、これはタンパク質から発酵して呼吸麻痺を引き起こし、数時間から数日で死に至らしめるものである。
これらの薬剤は、理論的にはそれぞれ保護薬で対抗することができる。ピリドスチグミン臭化物(PB)は長年にわたって重症筋無力症の患者に使用されているが、長期にわたる健康被害は報告されていない。PBは、曝露前に服用すれば、アトロピンのような神経ガス解毒剤を強化することができる。湾岸戦争では全軍にPB錠が配られたが、約25万人だけが服用した。炭疽病とボツリヌス毒素のワクチンは産業労働者を感染から守るために使われた。デザートストームでは約15万人の兵士が少なくとも1回の炭疽病ワクチン接種を受け、8千人が少なくとも1回のBTワクチンの接種を受けた。
炭疽病ワクチンと違って、ボツリヌス毒素ワクチンはFDAによって「調査中」とされており、化学兵器に対する軍隊での使用についてはPBを承認したことがない。戦場の状況下でこれらの薬を使った経験が比較的乏しく、国防総省がFDAから特別な許可を得て、インフォームドコンセントを得ずにこれらの「未承認薬」を使用したことから、兵士たちがモルモットにされたように見えたのだ。しかし、もしそうであれば、誰がどんな薬を飲んで、どんな反応があったのか、きちんと記録されているはずだ。しかし、何人が服用したかという大雑把な把握にとどまらず、ほとんど記録が残っていないため、経験から何かを学ぶ機会が失われてしまった。さらに悪いことに、退役軍人に医学的な問題が発生したとき、誰がどのような条件で実際に薬を服用したのかの記録がないことが判明した。
「砂漠の嵐作戦作戦」の部隊に、インフォームド・コンセントなしに、戦闘状況についてテストされていない薬剤を使用する特別許可をFDAが与えたのはなぜか?サダム政権が化学兵器ソマンと生物兵器を大量に保有し、戦闘中にそれを運搬する能力があるという信頼できる情報があった。デザート・シールド」として知られる軍備増強の最中、国防総省は新しい食品医薬品局長官であるデビッド・ケスラー博士に、「治験薬」に対するFDAの通常のインフォームド・コンセント要件の免除を打診した。この要請は、戦闘部隊をこれらの脅威から守るための合理的な見込みのある方法で保護する必要性に基づくもので、状況によって要求される極端な措置であった。この要請の「治療」目的は、ペンタゴンの請願の重要な要素であった。
これに対し、FDAは規則23(d)を採択し、規則に例外を設け、同意が「不可能」な戦闘状況についてコミッショナーが同意要件を免除できるようにした。この規則では、コミッショナーに対して、医薬品の安全性と有効性に関するあらゆる証拠、医薬品が使用される状況、治療または予防を意図する症状の種類、医薬品の服用によるリスクと利益に関して受領者に提供される情報の性質などを考慮することが義務付けられている。このような要件にもかかわらず、通常のインフォームド・コンセントの規則に対するFDAの例外は、ペンタゴンの要請以前には存在しなかった。議会も含め多くの人が、文民機関が国防総省に脅かされるのを許したのだ。例えば、規則に従って、この取引では、薬の服用を依頼または命令されたすべての兵士に、彼らが何を服用しているかについての情報用紙を渡すよう求めたが、その情報はほとんど提供されなかった。この協定違反について、FDAは戦後も軍隊に責任を問うことをしなかった。
FDAの職員は議会で、戦闘が差し迫っていてアメリカ軍が危険にさらされているときに、国防総省に制限を設ける立場にはなかったと語っている。国防総省は自らの弁明の中で、薬がもたらすかもしれない兵士へのリスクを最小限に抑えようとしたと述べている。神経ガスに対するピリドスチグミン臭化物(PB)という、効果が期待できるかどうかが最も不確かな薬剤は、任意で投与されたものである。これは軍の指導者の意図であったかもしれないが、現場の多くの兵士は異なるメッセージを受け取った。ガス攻撃が迫っているときにPBを服用した人のうち、88%が「任意ではない」と告げられたと報告している。
しかし、仮に服用者全員が本当に自発的に行動していたとしても、その化合物がインフォームド・コンセントの放棄の第一条件である「安全かつ有効である」と見なされる条件を満たしていたとは到底言い切れない。PBは非常にストレスの多い状況で服用すると神経学的な問題を引き起こす可能性があるという意見もある。また、有機リン剤と呼ばれる神経ガスとの「相乗効果」を疑っている人もいる。このような薬剤の1つに、砂漠で兵士の一部が使用した虫除け剤ジエチルトルアミド(DEET)がある。農務省の研究者ジェームス・モスは、PBとDEETを一緒に投与すると、単独投与に比べて数倍の毒性を持つことを発見した。米国医師会雑誌に掲載された湾岸戦争帰還兵23人の研究では、神経シナプス(神経と神経のつなぎ目)で機能する酵素の生産を阻害する化学物質にさらされたために、遅延型神経毒性に苦しんでいると結論づけている。このような影響を与える化学物質としては、有機リン酸塩、神経剤、殺虫剤、DEETなどの虫除け剤、PBなどがある。
ボツリヌス毒素(BT)ワクチンは、摂取した人に深刻な問題を引き起こす原因とはなっていないものの、湾岸戦争帰還兵に見られたような疲労や筋肉痛といった症状を引き起こす可能性がある。さらに不愉快なことに、使用されたワクチンの供給は20年前のもので、有毒な生成物に分解されることが懸念された。実際にそうなったかどうかはともかく、このワクチンは1年間に4回の注射が必要で、ほとんどの隊員が2回しか受けていないので、いずれにしても効果があったのかどうかも疑問である。メリーランド州フレデリックにある陸軍の感染症研究所では、ボツリヌス毒素ワクチンの使用を検討する担当委員会が、その効果について確信が持てないということだった。クリントン大統領の「湾岸戦争帰還兵の病気に関する諮問委員会」は、PBやBTが原因とは考えにくいとしたが、疑惑は残ったままだ。しかし、いつ、だれが、何を、どのように摂取したのかの記録がないため、明確な答えは得られない。
戦闘中のインフォームド・コンセント
国防総省が戦闘状況下で同意を得られない理由の一つに、そのような状況では不可能であることを挙げている。フォートデトリックのアート・アンダーソンに言わせると、この見解は制服を着ている人に対する敬意の欠如であり、医療ロジスティシャンがどのようにすればインフォームドコンセントの文書化を実現できるかを知らないということである。アンダーソン氏は、第二次世界大戦で砲兵隊に所属していた叔父のフランクリン・アンダーソン氏のボロボロの写真という、家族の宝物を紹介しながら、こう語った。ノルマンディー上陸作戦で海岸を攻撃する前に、彼は北アフリカに異動になり、ロンメルの伝説的な戦車に直面することになる。その砂漠で、AP通信のカメラマンが「10万」と書かれた砲弾を自分の大砲に装填している写真を撮っている。敬虔なクリスチャンであったアンダーソンは、写真の中で砲弾にキスをしている。写真の裏には、この写真を出版物に使用することを許可するAPからの承諾書が赤いスタンプで押されている。
もし、AP社が北アフリカでの作戦中に、兵士の写真についてわざわざ承諾を得たのなら、なぜ軍隊では医療記録の保存がそれほど優先されず、デザートストームでの承諾が後にこれほど論争になるのか、と私はアンダーソンに尋ねた。「と尋ねると、大佐は、「それは、この決断を下す医師が、記録の保存をする人ではないからである。もし彼らが記録を取る人に聞いていたら、『ああそうだ、そのための仕組みがあるんだ』と言っただろう。実際、医療ロジスティクス担当者が配属されるときは、ファイルキャビネットを持って配属されるんですよもちろん、100パーセント効果があるわけではないが、どんなものでも、できる限りのことはするものである。しかし、100パーセントの効果がないからといって、実現不可能というわけではない」
デザートストーム以前から、アンダーソン大佐は、兵士が服用している薬剤が無許可であることをきちんと伝える必要があると警告していた。彼は1990年の覚書の中で、陸軍に対する最も厳しい非ミハタリーの批評家でさえ言及するのをためらうような出来事を先例として挙げている。戦略、教義、規律上の懸念から治験薬の強制的な投与を「軍事的」に正当化することは、ナチの医師が破壊的な結果を予測できる研究に人間を使うことを正当化するために使った論理とあまりにもよく似ている」
このような軍の怠慢に対する寛容さは、砂漠の嵐作戦作戦以降、薄れてきているように見える。1997年の議会で行われた政府主催の研究に対する公聴会で、コネチカット州の共和党議員クリストファー・シェイズは、湾岸戦争でFDAがインフォームドコンセントに関してもっと強力な立場を取らなかったと非難した。国防総省は、インフォームド・コンセントを放棄する見返りとして、兵士にどのような化合物を摂取させるのか、またその理由は何かについて、可能な限りの手段を講じると約束した。FDAの担当者は、アメリカ人の命が差し迫った戦闘状態において、文民機関が国防総省に何をすべきかを指示する立場にはない、と主張したが、それは根拠のないことではなかった。私はシェイズの小委員会で証言し、その日のうちに彼の返答を聞いた。戦争後、国防総省が約束を守らなかったことを知り、FDAは公の場で将軍たちの足を引っ張るべきだった。
結局のところ、問題は組織文化の違いである。国防総省の仕事は、武装した侵略者から国を守ることであり、FDAの使命は、食品供給の安全性と医薬品の完全性を守ることであるため、大きな隔たりがある。軍事的な文脈では合理的な賭けとみなされること、例えば、潜在的に危険な薬物を使用し、それによって引き起こされるよりも多くの犠牲者を回避することが期待されるが、医薬品監視プロセスでは許容できないトレードオフである。最終的には、国家安全保障と医療倫理の間の緊張関係を示す生きた例として、別の組織が介入し管理することが必要になるだろう。
研究対象者であること
医療倫理学者が人体実験について抱いている大きな懸念の一つは、インフォームド・コンセントが本当に得られるのか、ということである。被験者が病気であれば、治療ができるという希望が常にある。この理解しやすい希望が、新しい治療法の限界を理解する妨げになることがある。実験が、自分たちを助けるためではなく、将来の患者を助けるかもしれない知識を得るために計画された、あるいは意図されていると言われても、人々は、利益を期待する理由がほとんどないことを聞き入れないかもしれない。被験者が病気ではなく、健康で正常なボランティアである場合、金銭やその他の誘引で強制する問題がある。また、医学的な訓練を受けていない被験者には、実験の本質を本当に理解しているかどうかという問題がある。
おそらく最も陰湿なのは、研究対象者がある程度隔離された状態で実験に臨むことである。最新の実験薬による治癒を期待している医学的問題を抱えた人々は、感情的に弱いものだ。彼らはしばしば、医師の善意や社会的権威と、研究によって個人的に恩恵を受ける本当の可能性とを区別するのに苦労する。被験者に最も近い人々でさえ、彼らが経験していることを十分に理解していないかもしれない。理想主義や金銭的な理由で名乗り出た健康なボランティアは、通常、関連する科学についてほとんど知らないし、研究に対する不安を共有する相手もいないかもしれない。
1970年代に刑務所での調査が終了して以来、製薬会社は、新薬が体からどのくらい早く排泄されるかといった基本的な疑問に対する答えが必要な場合、一般のボランティアに頼ることが多くなっている。健康な人ばかりが採用されるわけではない。私たちは皆、新聞やラジオで、多くの病気の研究に参加するボランティアを募集する広告を見聞きしたことがある。そのような研究に参加する動機はいろいろあるが、金銭もその一部であることが多い。薬物研究の中には、身体機能に気を配り、食事制限をし、会社の診療所に泊まり込んで、厳しいスケジュールをこなせば、数週間で何千ドルもの報酬が得られるものもあるのだ。
健康で、聡明で、情報に通じていて、科学的に洗練されていて、強制されることなく、わずかなお金で実験に参加できる被験者候補がどこにいるのだろうか?多くの科学者が、この問いに対する答えを知りたがっている。まるで理想的な研究者集団のように聞こえる。メリーランド州のフォートデトリックにいるMRVS(Medical Research Volunteer Subjectsの略で「マーズ」と発音する)は、おそらくその最たるものだろう。彼らは、ウォルター・リードの黄熱病委員会以来、真のインフォームド・コンセントという倫理的理想に最も近い研究対象者である衛生兵(91ブラボー)の特別なグループである。
私たちを「モルモット」と呼ばないで 91「ブラボー」の人々
米軍のような規模の組織には、必ず矛盾がある。人体実験というデリケートな問題に対する数十年の経験は、湾岸戦争での論争を避ける助けにはならなかったようだが、他の場所では、国防組織は全く異なる評価を得ている。この本を書くにあたって私が知った驚くべきことの中で、男女を問わず何十人もの兵士が、いまだに生物学的実験に普通のボランティアとして使われていることほど、私を驚かせたことはない。フォート・デトリックでこのプログラムを調査しているうちに、さらに驚いたのは、陸軍はヒト実験体の倫理的使用において、実は民間医療よりはるかに進んでいる、という私の反応だった。
私は1998年の春、フォート・デトリックに配属されている医療部隊の若い男女7人の兵士に1日がかりでインタビューした。彼らは全員、サンアントニオのサム・ヒューストン基地から採用された。メリーランド州での任務の一部は、医療隊員としては日常的なもので、研究所に配属され、様々な科学的研究に協力することであった。もう1つは、もっとドラマチックなものだ。それは、感染症研究所の生体防御のための医学実験の被験者として招かれることがある、ということである。
20歳のリー・ライス君は、南部なまりがあり、物腰が柔らかく、機転のきく青年である。バージニア州ウッドブリッジで育ったリーさんは、以前から医者になりたいと思っていたが、家計には負担が大きいと思っていた。聖書学校を卒業後、父と祖父が陸軍にいたことから、陸軍が自分の夢への道となることを決意する。父も祖父も兵役に就いていたからだ。陸軍の医学実験の被験者になれと言われた時の反応を思い出しながら、彼は笑った。
しかし、数年間は1カ所の勤務地で安定的に働けること、高度な訓練を受けた医学者のそばで働けることなど、アメリカ研究所での生活を知るにつれ、この話が魅力的に思えてきた。しかし、ペンタゴン(米国防総省)の知人から研究所の様子を聞いて安心したのか、リーさんはメリーランド州郊外へ向かった。
実は、現在、軍の人体実験審査制度は、民間よりはるかに厳しい。ウィルソンメモの子孫である陸軍規則70-25「研究の対象としてのボランティアの使用」は、よく知られた厳しい規則として発展してきた。今日のA.R. 70-25は、現地部隊の「人間利用委員会」から、指揮系統の上の他のいくつかの画面まで、複数のレベルの審査を要求している。A.R.70-25には、かつてのニュルンベルク綱領に基づく規則の名残がある。「被験者の自発的な同意が不可欠」とあり、さらに、被験者になることを拒否した兵士は罰せられないと書かれている。
軍隊では何段階もの審査があるのに対し、民間の世界では臨床研究は大学や研究所の1つの委員会でしか審査されないかもしれない。この制度に対して、一部の審査委員会の独立性や客観性に疑問を呈する評論家もいる。人間を対象とする研究のほとんどは、大学の「機関別審査委員会」(IRB)で承認されなければならない。ここでは、研究を提案する科学者の同僚が審査を担当する。最近では、大学の審査委員会で通常行われるよりも迅速に実験提案を審査できるように、学外に設置されたIRBもある。これらの独立したIRBは完全に合法であり、その利益相反は、研究が十分に健全でないと判断された場合には同僚の助成金やキャリアが危うくなることを教授が知っている大学の委員会のそれと変わらないかもしれない。
リー・ライスさんは、フォートデトリックでの3年間の任務をほぼ終えて、3つの研究に志願していた。研究以外の時間は、会社の事務員として働いていたが、彼の主な任務は研究に参加することであった。定期的に研究所の講堂に呼び出され、仲間のMRVSと一緒に、これから行われる研究の説明を聞き、ボランティアを募集していた。MRVSの唯一の義務は、2,3カ月に1回行われるこの会議に出席することだ。
炭疽菌のような生物兵器から身を守るための研究もあれば、軍事環境下でよく見られる病気の治療を改善するための研究もある。炭疽菌ワクチンの研究では、ワクチンを接種した後、2年間定期的に採血して、その予防効果が持続しているかどうかを調べるだけである。他のプロジェクトは、それほど穏やかなものではなく、研究所の入院棟に2週間も滞在し、かなりの不快感を伴うこともある。MRVSでは、このようなプロジェクトのことを「クソプロトコル」と呼んでいるが、これはまさにその経験を表している言葉である。
MRVSの仲間は、特に不快な研究を避ける人が多かったが、リーは最も過酷な研究にも参加した。海軍で特に問題とされているカンピロバクターという細菌の研究である。カンピロバクターは腸内細菌で、ひどい下痢を引き起こす。海軍は、大腸菌の毒素(旅行者下痢症の原因となるもの)の変異型を使って自然免疫反応を高め、同時に経口ワクチンを投与することで、この菌に対するワクチンを開発しようとしている。リーは、カンピロバクター研究での自分の役割を、「これまで経験した中で最も過酷なもの」と表現した。初日は悪くなく、簡単に乗り越えられると思い始めたものの、翌日には耐え難い頭痛に襲われ、どんな光も見ることができず、全体的にひどい状態になってしまったという。しかし、李はすぐにこの終点に達したので、彼もすぐに治療を受け、抗生物質の投与ですぐによくなった。
なぜ、こんな危険な仕事を引き受けたのだろう?研究所での一日、私はその疑問を強く訴えた。兵士が志願するわけがない、抵抗すればどうなるかわからない、そもそもMRVSに参加することに同意しているのだから、というのがもっともな答えだろう。しかし、私がインタビューした91ブラボーの若者の一人は、ほぼ任務を終え、一度も研究に参加したことがなかった。その代わり、彼はアンクルサムの管轄である地元のコミュニティカレッジで医学部進学のためのコースを取っており、スケジュール的に参加することができなかった。しかし、MRVSの説明会に出席している限り、彼はプログラムへの義務を果たしている。
他のMRVSは「糞プロトコル」を避け、炭疽菌ワクチンのような、病気にならず、採血1回につき25ドルの報酬がもらえる研究を選んでいる。しかも、2年間の研究期間中は、採血の回数が多いので、軍人の給料にプラスして、それなりのお釣りが来る。これは、MRVSが非倫理的に金銭を強要されているという疑惑の部分ではないだろうか?
私はこの疑問を、話を聞いた兵士一人ひとりにぶつけてみた。すると、彼らの答えは一貫しており、説得力があった。まず、地域住民のボランティアには、診療所での滞在日数や処置のたびに報酬が支払われるのに対し、MRVSには血液の対価しか支払われないという指摘があった。お金の力で不当な影響を受けるとしたら、それはメリーランド州フレデリックをはじめとする周辺地域の民間人たちである。そしてもちろん、民間人はMRVSのような仲間からのサポートや科学的なトレーニングを受けていないのが普通である。
第二に、何人かのMRVSが私に指摘したように、1回25ドルの献血で金持ちになることはない。特に、家族がいる人や3日間の滞在を予定している人にとっては、余分なお金は歓迎すべきことだが、いくつかの研究の重大な欠点を克服するには十分でないことは確かである。例えば、小さな子供のいる男性MRVSは、お金には興味があるが、子供と一緒にいるために家に帰ると衰弱してしまうのはどうしようもないと言っていた。
最後に、お金の問題は、仕事の必要性とのバランスを取る必要がある。このようなインセンティブがなければ、ボランティアに参加する人はほとんどいないと、私が話をしたMRVSはみな認めていた。世界は危険な場所であり、米国は生物保護プログラムを含む国防システムを維持する正当な利益と正当な理由があることを認めるとしよう。もちろん、厳重な保護がなされ、MRVSに断る自由がある限りは、である。
年配のMRVSは、ボランティアと副作用の可能性についてよく話し合うという。アーカンソー州ジョーンズボロに住む29歳のロブ・コルバートは、その理由をこう語ってくれた。「つまり、ひどい下痢や吐き気、けいれん、頭痛を起こす危険性が非常に高く、基本的にはどの合併症もその程度である。腸炎に関しては、他のものよりひどいものもある」
このプロトコルは、フォートデトリックに配属されている他の部隊のMRVSでない人たちをも魅了している。19歳のアリッサ・テベルス(Alissa Tevels)は、91タンゴ(Tango)という動物管理ユニットに所属しているが、炭疽病の研究にも赤痢菌ワクチンの研究にも参加している。MRVSの会議には参加しないが、多くの参加者と交流し、興味のある研究の話を聞いたり、研究所のあちこちに貼られているのを見たりする。
アリッサと91Bravoのメンバーは、自分たちの仕事に誇りを持つと同時に、自分たちを取り巻く神話に苛立ちを覚えているようだった。MRVSに参加することを決めた後、ヒューストンに戻った彼女は、ドリルサージェント以下から非難を浴びたと言う。お前たちはモルモットになるんだ、かわいそうに」3年間ここにいた後、私たちはただ笑っていた」と、彼女は私に言った。「ここはとてもいいところだった」と。彼らは皆、「モルモット」と呼ばれることを嫌い、自分たちは医学や科学にとって名誉ある役割を担っていると考え、自分たちの知識や訓練のレベルを考慮し、自分たちのような他の人々のためにより良い保護を見つける努力の共同研究者であるとしているのだ。20世紀後半に意識を持った多くのアメリカ人と同様、彼らは軍隊のような大きな組織には懐疑的である。しかし、一般に言われる「X世代」よりも理想主義的であり、奉仕的であることは間違いない。
ルイジアナ州ラファイエット出身のウィリアム・フランク・ファウラーさんは、岩肌を削ったような顔立ちで、安定したまなざしを持つ物静かな男性である。しかし、彼は非常に聡明で、高度な訓練を受けた医療隊員であり、デトリックで働くことに誇りをもっている。「USAMRIIDのことをもっと多くの人に知ってもらえたらと思う。USAMRIIDは本当にいいところなんですよ」と彼は言った。「USAMRIIDは本当にいいところだ。この仕事を通じて、多くの経験を積むことができたし、これからも役に立つだろう。MRVSの役割について、Fowlerは熱く語ってくれた。
MRVSは本当に必要とされているプログラムなので、あまり見くびらないでほしいね。私たちは虐待されているわけでもなく、檻の中で飼われているわけでもなく、鉄格子越しに餌を与えられているわけでもないから。すべてはボランティア・プログラムであり、プログラムに参加しているときでさえ、私たちは公平に扱われている。そして、プロトコルの途中で「もう何もしたくない」と思えば、たとえ予防接種を受けた後でも、たとえ病気であっても、「もういい、帰りたい」と言えば、薬をもらって帰ることができる。
MRVSが受動的な「人間モルモット」であるという思い込みは、彼らとの短い会話で打ち砕かれる。リサ・シェリダン・カディとランサー・カディは、91ブラボーの卒業生で、現在はメリーランド州フレデリックで投資カウンセラーになるための研修を受けている。ニューメキシコ大学で出会って結婚し、一緒に入隊して、一緒にMRVSに志願した、とても魅力的なカップルである。最初は不安そうにしていたリサだったが、ランサー氏は「デトリックは、他の軍隊に比べれば楽な仕事だ」と説得した。実際、リサはMRVSのリーダー的存在になった。彼女は、アート・アンダーソン(Art Anderson)が委員長を務めるヒト使用委員会のMRVS代表となり、同意書の正確さや読みやすさを修正し、自分が好ましくないと思う研究を中止させることもできるようになったのだ。
リサは、この委員会で、MRVSが世界一、いや世界でも最も利用されていない被験者であることを証明する役割を果たした。病気の患者は、研究審査委員会に代表者がいて、同意書が同じ立場の人たちに理解できるように書かれているかどうかを確認することはもちろん、提案されている研究を中止させることもほとんどできない。フォートデトリックで実験に志願する地元の民間人のような健康で正常な被験者でさえ、MRVSのような首尾一貫した自意識過剰の集団として代表されることはありえない。
研究に対するオープンさ
私がフォート・デトリックを訪問することを可能にした開放性は、今後、国家安全保障目的の人体実験が、私がこれまで語ってきたような多くの悲しい過ちを繰り返すのではなく、陸軍感染症研究所をモデルとしたものになるための鍵になるだろう。若いMRVSは、自分たちの経験を縁取る啓蒙的な政策がいかに困難なものであったかを知らない。彼らは、軍隊の一員であっても、自分たちの生活をコントロールする究極の手段を保持していることを疑う理由がない人たちの自己満足である。以前の世代の研究対象者はそうではなかった。
しかし、MRVSの自己肯定感は、研究者自身と共同研究するシステムによって支えられているのでなければ、幻想にすぎない。そのためには、研究の目的、リスク、潜在的な利益に関する関連情報を入手する必要がある。ある意味で、MRVSプログラムは、1953年にウィルソン国防長官がニュルンベルク規範メモに署名した際の約束に対する陸軍の支払いであると言えるだろう。湾岸戦争の経験が、軍事・医学研究におけるインフォームド・コンセントの失敗であったとすれば、少なくとも成功のモデルがいくつかある。
しかし、倫理的な国家安全保障研究に対する根強い危険性は、ある種の実験を厳重に秘密裏に行う必要があるという議論によって提示されている。このような状況下では、一般市民は民主主義において通常有する、研究がその状況下で正当化されるかどうかを判断する権利を奪われるだけでなく、研究の対象者もインフォームドコンセントを与えるという特定の権利を奪われる可能性があるのだ。冷戦の終結により、激甚な紛争の脅威は減少したが、世界中の小さな集団の煮えたぎる憤りは、世界が2つの原則にきちんと分かれていたときと同様に、あるいはそれ以上に、アメリカ人をさらけ出す気持ちにさせている。テロ組織から秘密を守る必要性は、ソビエトから秘密を守る必要性(ソビエトの治安組織は、アメリカの有権者よりもアメリカ軍が何をしているかをはるかに多く知っていたにもかかわらず)に容易に取って代わることができる。小規模の熱い戦争に何度か直面すると、国家安全保障研究の環境は、冷戦の大半で示されたメンタリティに再び容易に陥る可能性がある。
1995年の大統領諮問委員会の勧告を受けて、クリントン政権は2つの重要なステップを踏んだ。第一に、大統領はすべての連邦政府機関に対し、機密扱いの人体実験に関する記録を永久に保存するように指示した。記録を保持することにより、1970年代にMKULTRAやその他の秘密実験が明らかになったときよりもはるかに容易に、実際にどのような実験が行われたかを再現することができるようになる。多くの記録が故意に、あるいは誤って破棄されたため、この本を可能にした情報は、さらに20年の歳月と多くの人々の膨大な努力によってつなぎ合わされた。このような記録が再び不明瞭にならないよう、将来の大統領政権がこの指示を放棄しないようにすることが重要であろう。
また、クリントン政権は、人体放射線実験諮問委員会の勧告を受けて、すべての機密研究はインフォームドコンセントの要件を満たさなければならないことに合意した。また、被験者になる可能性のある人々には、研究のスポンサーがどの機関であるか(例えば、CIAの研究には参加したくないという人もいるだろう)、そのプロジェクトが機密研究を含んでいるかどうかを伝えるべきであると合意された。同様に重要なのは、秘密プロジェクトの倫理審査委員会には、適切なセキュリティクリアランスを持つ民間人委員を1名加えることを提案したことである。また、倫理審査委員会の決定に不服がある場合は、その機関の長または大統領の科学顧問に訴えることができるよう、不服申し立て手続きを設けることも提案された。人体実験を行う17の連邦機関は現在、人体実験を規定する規則の改正を進めている。この新しい第125条は、放射線実験報告書に対する大統領の回答で示されたシステムに従って、機密扱いの研究の審査に関係するものである。
エボラ出血熱
この本で、アメリカの医療倫理と国家安全保障について多くを語ってきたのは、このテーマについては多くの資料が容易に手に入るからだ。しかし、海外の場合はそうではない。敗戦国であるドイツ、日本、イラクの記録や、最近機密解除されたカナダやオーストラリアの資料とは異なり、冷戦時代のソ連の人体実験に関する活動はほとんど知られていない。ソ連が崩壊した後も、西側諸国以上に手強い秘密文化が、その歴史的実態を覆い隠している。
冷戦時代のソ連の能力とその残骸の脅威を知る上で、ベン・ギャレット氏ほど米国に適した人物はいないであろう。エモリー大学で化学の博士号を取得後、20年間バテル記念研究所で生物・化学兵器の製造と管理に関する専門家として活躍してきた。最近では、現存するロシアの生物・化学兵器開発施設との連絡役として連邦政府と協力し、シベリアの工場や研究所を平和利用するための転換を支援した。また、ロシアの経済衰退で困窮している旧ソ連の生物兵器や化学兵器の科学者たちが、アメリカに友好的でない国々に製品を売らないようにする方法についてもアドバイスしてきた。この任務の重要性は、1998年末、ニューヨーク・タイムズ紙が、イランが旧ソ連の生物兵器科学者を積極的に口説き、少なくとも5人をリクルートすることに成功したと報じたことで、改めて認識されることになった。
彼は、日本が第二次世界大戦中の実験について謝罪するどころか、いまだに認めていないことについての会議に出席した数少ない西洋人の1人であった。日本の資本主義経済が衰退し、中国市場を貪欲に狙っている今、ようやくこの問題で戦後最大の進展が得られる可能性が出てきた。
私がギャレットにインタビューした最大の目的は、ソ連の後期における人体実験の程度について、彼の感覚をつかむことであった。ソ連の警察であるKGBが、特にスターリン時代、その長官であったラヴレンチ・パブロヴィッチ・ベリヤの下で数十年前から路上から人々を摘発したことは昔から知られている。彼らは、KGB本部のあるルビャンカ刑務所と呼ばれるモスクワの恐ろしい施設に連行された。その中には、性的に利用され、実験を強要され、殺された不幸な女性も少なくない。彼らが姿を消した時、その家族は何が起こったかを知っていた、とギャレットは言う。
KGBによる最悪の犯罪は1930年代から1940年代にかけて起こったようだが、生物兵器の軍事実験は1970年代まで続けられた。スベルドロフスクの生産施設の実態は、わずか数十人にしか知られていなかった。最近のロシアの雑誌『ソベルシェンノ・シークレットノ』(『トップ・シークレット』)の記事の中で、スベルドロフスクの医師へのインタビューにより、1979年4月に炭疽菌を誤って放出し、数十人の民間人が死亡したことが確認されている。著者はまた、「いわゆる『ドナー』(人という意味)に対する軍事用菌株の実験が1970年代半ばまでスベルドロフスク19で行われた」とも報告している。倉庫の労働者や建設労働者は、お金と引き換えにあらゆる種類の病気を注射されることに同意した。統計上の死亡率は不明だ」
敵対的な意図がなくなったとされる1980年代の改革派時代にも、ソ連の生物・化学兵器開発は事実上、急加速していた。例えば、ソ連時代の終わりには、シベリアの科学者たちが天然痘を大規模に兵器化する準備をしていたことが、ギャレット氏らによって決定的にされた。私はギャレットに、ソ連は最後まで人体実験を続けたと思うか、と尋ねた。と聞くと、「疑いはないが、確証はない」と答えた。
しかし、確証はない。ソ連崩壊後の混乱と収奪の中で、それらは続けられるのだろうか?ギャレットの答えはこうだ。
ロシアの科学者たちと接していると、「私たちは今、このようなことをしている。人類にとって有害なことは全くしていないし、これからも人類のためになることをやっていきたい」という言葉を何度も耳にした。彼らの発言には信憑性を感じるが、ロシアらしいとも思う。どういうことかというと、かつての彼らは、言われたことは何でも受け入れていたわけで、かなり進んでそれに回帰するのではないかと思うのだ。また、ロシアには軍が管理する生物兵器プログラムがあることも、私たちがそれを見つけようとしても拒絶され続けていることから知っている。そのプログラムの範囲は不明であり、その性質も不明である。しかし、私たちが知っているのは、ある日、ロシアがシベリアのノボシブリスクという施設(私たちは「ベクター」と呼んでいる)を天然痘の培養液の保管場所だと宣言したことなどから、そのようなことが判明した。そして、それはモスクワにあるはずのものではなかった。彼らは誰にも知らせず、許可も取らずに、おそらく1992年にそれを移動させ、1994年に人々に知らせた。
私はギャレットに、なぜ移動させたのかと尋ねた。「それは理解しがたいね。でも、彼らは、ずっとここに置くつもりだったんだ、と言うんである。それを確認する術も否定する術もない」
1970年代から1980年代のソ連の活動について分かっていることの多くは、カザフスタン出身で1992年にロシアから米国に亡命し、ギャレットの側近であるケン・アリベックから学んだものである。アリベック氏が語るソ連の兵器開発体制は、アメリカのメディアで大きく取り上げられた。年、アリベック氏は沈黙を破り、ニューヨークタイムズとのインタビューで、ロシアは生物兵器の研究を続け、その生産能力を維持し続けているとの考えを示した。それなら、人体実験も続いているはずだ。どこで行われるのだろうか。
ロシアで最も安全な生物研究所であり、地球上で最大の生物兵器研究所であるヴェクトールから半マイル以内に、1998年にギャレット氏が「保養所」と表現した建物の未完成の殻が残っている。いったい誰が、地球最大の生物兵器研究所の隣にあるレストホームに迷い込んで、休もうとするだろうか、とギャレットは思った。どうやらそれは、致死性の微生物を扱い、維持する日々の活動で強いストレスを感じている天然痘作業員のための休養所ということだったらしい。ギャレットはその後、この施設を「エボラエステート」と名づけた。
また、ヴェクター施設内には、エボラ出血熱のような最も悪性で致死性の高い生物を収容するための「バイオレベル4」の病院である19棟があり、極限のバイオセーフティ条件の下で被曝者を搬送・観察することができるようになっている。19号棟は約40人の患者を収容でき、フォートデトリックにある陸軍感染症研究所の病院の少なくとも10倍はある。19号棟の2つの棟のうち1つは、「活動中の」HIV陽性患者、つまり感染力がより強いと判断された患者のために用意されているようだ。
モルモットに注射している時にマールブルグ・ウイルスに感染し、実験室の事故による犠牲者である。エボラ出血熱と同じように、マールブルグ感染者の内臓は液体と化し、あらゆる穴から出血して致命的となる。ウスティノフの感染は、ウイルスの自然経過に対する「機会実験」であった。彼の協力で、彼の恐ろしい死が同僚たちによって観察され、彼の話は欧米の新聞で大きく取り上げられた。彼は1988年4月30日に亡くなり、密閉された特製の鋼鉄の棺に埋葬された。
知る限りでは、マールブルグはヒトから採取されたことはない。人間から得たウイルスのコロニーは、他の人間に対して恐ろしく致命的な武器になる。ギャレットは、ウスチノフの組織のコレクションを見せられたが、それはウイルスを破壊する条件下で保持されていたはずだ。しかし、アリベックは、このシステムの経験から、別のチームが兵器にするためにウイルスそのものを収集した可能性が高く、知られている以上のストーリーがあると信じている。しかし、ギャレットによれば、マールブルグウイルスは非常に壊れやすく、無差別であるため、ある国が兵器化しようとする可能性は小さいという。しかし、ギャレットによれば、マールブルグウイルスは非常に壊れやすく、無差別に発生するため、兵器化する可能性は低いという。
ギャレットが前病院長に、19号棟に他の被験者がいたかどうかを問いただすと、長々しく、守りに入ったような答えが返ってきた。その時、現病院長が現れ、修飾語のようなものを口にした。二人の会話は、ロシア語で熱っぽく続き、そこで途切れた。ロシアでの人体実験について、ギャレットの総括的な見解。ロシアでの人体実験について、ギャレットはこう言っている。「今のロシアの科学者たちとの仕事には、そのような証拠はない。過去に行われたかもしれないことに対して、何気ない態度が見える」
私がギャレットに初めてインタビューした数ヵ月後の1998年12月、ニューヨーク・タイムズ紙は、冷戦が終結したばかりのカザフスタンで、ロシアの科学者がマールブルグの動物実験を行っていることを報じた。この報道についてギャレットに尋ねると、「もし、この話が本当なら、その株は不幸なニコライ・ウスティノフから採取されたものだろう。また、この話はまったくの憶測であるか、あるいは(彼が話したロシアの科学者には分からないが)他の情報機関か軍のグループがウスチノフの遺体にアクセスし、彼の組織を採取し、姿を消した可能性もあると指摘した。政権担当者や議員の中には、これらの説のうち最も疑わしいものを採用しているようだ。彼らは、ロシアが生物兵器開発計画を続けていると考え、そのためもあって、ロシアの生物兵器開発科学者との協力交流にかける米国の支出を減らしている。
また、天然痘ウイルスのサンプルが、ロシアのヴェクター・プログラムから北朝鮮に渡ったのではないかという懸念もある。天然痘のサンプルは、ならず者国家やテロ集団が入手したのではないかとの懸念から、1999年4月、米国内の最後の天然痘ウイルスを廃棄するという約束を反故にする大統領決定がなされた。研究用にサンプルを保存しておけば、攻撃だけでなく、たとえ可能性が低くても、自然発生への対応に役立つと主張するのだ。ロシアは長い間、天然痘サンプルの廃棄に反対してきた。このように、ホワイトハウスの元科学顧問が「最も恐ろしい」潜在的バイオテロ兵器と呼んだこのウイルスについて、私たちはまだ最後の話を聞いていないかもしれない。
未来への架け橋?
次の世紀には、過去と同様に、人間を対象とする軍事・医学研究は、他の情報源から得られる情報の限界によって決定されることになる。なぜなら、敵を殺すというよりもむしろ無力化することを目的とした新世代の兵器が開発されているため、コンピューター・シミュレーションや動物モデルでは限界があるのだ。次世代兵器には、原子核の核分裂とは異なる種類の放射線、つまりマイクロ波が使われる可能性がある。敵兵の中枢神経系を破壊し、てんかん発作を起こさせたり、体液を電子レンジの中にいるように温めたりする電磁波が考えられる。低周波の電磁波は、アヘン剤(オピオイド)のような働きをする天然物質を放出するよう脳に信号を送り、動物を昏倒させることが分かっている。その他、レーザーを使った装置では、一時的に失明することがある(永久的な失明を引き起こすように設計されたレーザーは、条約により禁止されている)。
遺伝学の進歩は、「リターン」効果と呼ばれることもある、放出した部隊に再感染しない管理可能な生物兵器を設計するための驚くべき可能性を提示している。冷戦後、ソ連の生物兵器への取り組みが暴露されたが、このことは、遺伝子に基づくアプローチがすでに追求されていることを示唆している。それは、致死性のウイルスを開発すると同時に、そのウイルスに対する秘密の遺伝的キーのような働きをするワクチンを開発することであった。その鍵は、ソ連の軍医だけが持っている。被災した敵軍が、天候の急変で微生物が風に乗って発生源に運ばれても、赤軍兵士には感染しないようにするためである。この作戦体制は、指揮を執る将軍の名をとって「オルガコフ・システム」と呼ばれた。
これまでの生物兵器とは一線を画すものとして、「ヒトゲノム計画」による遺伝子技術を利用した生物兵器の開発が考えられる。このプロジェクトは、人間のデオキシリボ核酸(DNA)を構成する30億対のタンパク質の「地図化」を2003年までに完了させようという国際的な取り組みである。通常、科学的な意図のもとに行われるものではあるが、科学的なブレークスルーは常に、後に軍事的な応用が評価されることがある。遺伝学が生物学と化学の境界線を曖昧にしているように、遺伝子戦争(GW)の出現は、生物兵器と化学兵器を事実上1つのカテゴリーに統合することになる。
その中には、特定のサブグループのDNAの変異を「認識」するウイルスの能力に基づいて、特定の人間集団を標的にするよう遺伝子操作された微生物が含まれる。宿主の細胞に注入されるこのような薬剤は、即効性のものと遅効性のもののいずれかに設計することができる。例えば、胚発生の初期段階を阻害し、自然流産を増加させ、数十年かけて出生率を著しく低下させるような感染症の場合、遅効性のウイルスの影響は、すでに大きなダメージが与えられるまで疑いを抱かれないかもしれない。この種の攻撃は、最初は「亜急性」で目立たず、その起源を特定し追跡することは困難であろう。第1章で述べたアパルトヘイト政権下で南アフリカの黒人に計画された攻撃は、この種のものであった可能性がある。
特定の民族や地理的な背景を持つ人々に見られる機序は、特定の食物や薬物に対する過敏性と関連することが長い間指摘されてきた。たとえば、アフリカや中東の人々は、しばしば空豆を食べると病気になる。古代ギリシャ人やエジプト人もこの反応に注目していた。第二次世界大戦後、この地域の人々は抗マラリア薬にもしばしば過敏に反応することが判明した。これらの反応の原因は、グルコース6リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PD)という酵素の欠乏である。生物兵器は、特定の集団に特徴的な遺伝子の変化を利用したものである可能性がある。
また、ヒトのゲノムを進化の過程で下位の動物と比較した場合の可能性を考えてみよう。ヒトはチンパンジーと98.4パーセントのDNAを共有しており、体重で比較するとチンパンジーはヒトよりはるかに強い。もし、チンパンジーの上半身の発達をコントロールする重要な遺伝子を、例えば、ウイルスをベクターとして人間の筋肉組織に導入することができたらどうだろうか?そうすれば、運動で筋肉が破壊されても、チンパンジーのDNAの影響を受けて、筋肉が再生されることになる。筋肉隆々のロケット司令官は、将来の軍隊ではあまり役に立たないだろうが、小規模で低強度の警察活動を必要とするような煮え切らない内戦では、非常に貴重な存在になるかもしれない。遺伝子操作によって霊長類のDNAを注入された工作員は、深夜テレビの司会者たちに「ゴリラ戦争」についての簡単な一言を与えることになるであろう。
このような遺伝子介入は成功するだろうか?もちろん、宿主である人間の新しい遺伝子のスイッチを入れる問題や、宿主の他のすべての組織に侵入してダメージを与えないようにウイルスをコントロールする問題など、かなりの障害があるだろう。私が言いたいのは、それが可能かどうかではなく、少しでも妥当性があり、役に立つ可能性があれば、それが試みられるということである。そして、そのような試みには、最終的に人体実験が伴わなければならない。
国防計画担当者が、バイオテクノロジー戦争が現実的な脅威となり、バイオテクノロジーによる防衛が戦略上必要となるような状況に備えていることを示す公的な兆候が散見される。公表された声明の中には、私の霊長類DNAに関する推測の精神をよく表しているものがある。たとえば、1996年9月、国防高等研究計画局(DARPAはインターネットを開拓した機関である)の職員が、生物兵器に対する究極の防御を提供する目的を発表している。その目的とは、免疫システムを遺伝子工学的に改造し、「たとえ見たことのないものであっても、たとえ遺伝子操作されたメカニズムであっても、それを認識し、体内で中和することができる」ようにすることであった。
この正体不明の関係者はさらに、医師向けの政府刊行物である『U.S. Medicine』に、DARPAが「病原体対策」に関するプロジェクトに3000万ドルの資金を提供していることを伝えている。そして、これはバイオテクノロジーの願望リストの終わりではない。2005年までには「DARPAのプログラムの少なくとも50%は生物学的な側面を持つことになるだろう」とこの関係者は同誌に語っている。「私たちは自分の体が自分で自分を守ることができるほとんど超人的な人間を持つことになる」と。そのような遠大な能力を開発するために必要となる人体実験に関する倫理的な問題については、この記事では触れていない。
遺伝的超人間についてのコメントは、DARPAの職員自身がサイケデリックな体験をしているように見えるが、将来の生物学的応用についてのより冷静な探求は、国家安全保障の分野でも行われているのだ。1996年に陸軍士官学校が主催したバイオテクノロジーのワークショップでは、2020年の世界での紛争を想定したシナリオがいくつか演じられた。その中で、バイオテクノロジーが社会や軍に与える影響について、あるチームのまとめでは次のような発言があった。2020年までに国際条約が弱体化し、敵対国が「バイオテクノロジー戦争」の可能性を探ることで、米国に影響を及ぼす可能性があると推測された」さらに報告書は、生物兵器に対する攻撃態勢を制限する現在の条約や禁止事項を考慮し、「米国は軍事的有用性を持ちながら民生分野で開発できるデュアルユース技術に集中する必要がある「と提言している。
同グループは「民間と軍事の両分野で最も有用となる」アプリケーションについて説明を受けた際「遺伝子標的攻撃(つまり、DNA配列を高度に特異的に検出し、付着させる生物)のテンポを制御することについて」質問された。報告書はさらに続けた。
参加者は、数年、あるいは1世代にわたって行われるかもしれないこのような攻撃が進行中であるかどうかを検出する方法について検討した。敵は遺伝子攻撃のスピードをコントロールできるかもしれないが、その方法は明らかでないとの意見が出された。そのためには、住民の遺伝的特徴を詳細に記録しておく必要がある。もし、急激な変化や不自然な変化が広範囲にわたって見られたら、それは遺伝子に基づく攻撃が行われている証拠である。
驚くべき控えめな表現だが、もし「国民の遺伝的特徴の詳細な記録が国家安全保障の問題として必要」であれば、「多くのプライバシーやその他の倫理的問題が生じるだろう」と報告書は指摘している。実際、アメリカ国民の「遺伝子ライブラリー」は、史上最大規模で、最も侵襲的で、最も分裂を招きかねない生物学的実地テストを意味することになる。
科学的ブレークスルーの可能性のあるどの分野も、国家安全保障に及ぼす影響については推測の域を出ないと思われるし、どの推測も突飛すぎるとして片付けることはできない。遺伝学とそれが引き起こすかもしれない軍事・医学研究の新分野への関心に加え、脳に関する知識も劇的に進歩している。「神経科学」と呼ばれる分野では、電気化学システムの理解と神経解剖学が、世界中で数え切れないほど研究されている。その中でも特に注目されているのが、脳内プロセスを画像化することだ。脳の特定の部位や神経細胞が「光る」ことで、その活性化が特定の精神活動と関連づけられる可能性がある。将来的には、神経状態を思考やアイデアに「翻訳」し、文字通り「心を読む」ことが可能になるかもしれない。そうなれば、遠隔読心術も技術的に可能になる。
フランス国家生命倫理委員会のジャン・ピエール・シャニュー委員長は、1998年の同委員会の年次総会で、まさにそのような懸念を表明している。パリのパスツール研究所の神経科学者であるChangeuxは、現在開発中の機器がいつの日か一般的になり、遠隔地で使用されるようになれば、大規模なプライバシー侵害の扉が開かれ、「社会に対する深刻なリスク」になると懸念している。また、フランス原子力委員会の研究者は、画像処理技術は「ほとんど人の考えを読むことができる」ところまで来ていると委員会に語った。
繰り返すが、こうした怪しげなブレークスルーを実現するためには、人体実験が避けられない。社会がこの種の技術を受け入れるかどうかを決めるときでさえ、ニューロイメージングのための機器と、その画像を思考や思想に解釈するための「完成」のために、多くの個々の人間が必要とされるだろう。このような能力の軍事的可能性は明らかであり、国家安全保障の高度に機密化された条件下での人体実験の可能性は、あまりにも明白であり、多くを語る必要はないだろう。
正義への道
軍事・医学の人体実験の話から得られる教訓が一つあるとすれば、それは、今後もこのような実験が続けられるであろうということである。人間の性格に奇跡的かつ根本的な変化が起こらない限り、国家や政治運動は常に、敵対する相手に対して少なくとも一時的にでも戦略的優位に立つことができるような新しい兵器に関心を抱くものである。したがって、そのような兵器をいかにして最も効果的に使用し、いかにして防御するかは、人間を対象にしてのみ答えられる重要な問題である。
また、そのような研究は、道徳的に問題があると思われる国や指導者によってのみ行われるものではない。米国は、防衛のためとはいえ、このような研究を続けていることを私たちは見てきた。しかし、防衛について学んだことの多くは、攻撃的な能力にも転じることができる。尊敬するネルソン・マンデラでさえ、南アフリカの生物兵器開発計画について知ったとき、その解散を命じなかったと言われている。民族を標的にするウイルスやバクテリアは、なぜ白人政権にしか興味がないのだろうか?戦略的価値に人種はない。
このような兵器の人体実験が、ある国にとって常に魅力的であることは事実であるとして、その実験が倫理的に可能であることもまた事実であると私は考える。陸軍の感染症研究所は、そのような実験のモデルを提供することができるだろう。その重要な要素は、公正な募集方法、教育を受けた被験者候補のグループによる十分なインフォームド・コンセント、ピアサポート、適度な報酬を超えないこと、危険因子の慎重な検討と最小化であろう。また、少なくとも原則としては、これらのカテゴリーには限界があることは認めつつも、研究は攻撃的な目的ではなく、防御的な目的に限定されるべきである。
世界は、非倫理的な実験を特定し、それを支援する政府を制裁するか、少なくとも問責するための何らかのメカニズムを持つべき時期が過ぎている。また、責任ある立場の重要な個人を特定し、その事例を国際司法裁判所に付託する制度も必要である。このような責任者には、医学者だけでなく政治指導者も含まれるだろう。
国際的なレベルでオープンで手続き的に公平な法的プロセスが必要なのは、一つには道徳の問題であり、一つには現実的な問題である。道徳的な問題とは、私たちは国際社会の中で生活しており、特に戦争という状況が関係しているということだ。したがって、救済策を策定し、解釈し、適用するメカニズムも国際的で、国境を越えた正統性を備えていなければならない。
さらに、医療倫理の問題で法的管轄やルールが異なることは、ある種の基本的な倫理原則が文化によって変化することを意味し、裏付けがない。むしろ、医療倫理のある種のよく知られた原則は、文化や国の境界を知らない。研究参加者の尊重、研究参加者への害の最小化と利益の最大化、研究の利益と負担の正当な分配は、単一の文化に固有のものではない。一般に人間を対象とする実験について国際的なガイドラインがあるように、国家安全保障上の実験の範囲についても国際的な理解が必要である。確かに、これらの原則の解釈は文化的事情に多少左右されるが、敵対行為の国際的性質から、例えば生物兵器の野外実験を規定する規則についても国際的な解釈が求められる。
同じ議論は、イラクや南アフリカで主張されたように、政治的に支配的な民族集団が、異なる従属的な民族集団の住む地域で新型兵器を試すような「内戦」紛争にも当てはまる。このような場合、国内の法制度では公平な判断が期待できない。また、兵器は国際関係に影響を与えるため、単なる「国内」の事件と考えるのは妥当ではない。
また、ニュルンベルク裁判の判事たちが評価したように、現実的な観点からも、軍事・医療実験を支配する価値観は国際的なものでなければならない。軍や政治の指導者たちは、共通のルールを広く理解しない限り、抜け穴をつくって優位に立とうとする。ナチスの実験が非人道的なものであったにもかかわらず、弁護側が「国家主導の実験はどれも同じようなものだ」と主張したのは、このためであった。
国家安全保障の実験における倫理基準を解釈し適用するために、公認された国際法廷が必要な理由はさらにもう一つある。本書では、責任ある当局によって道徳的に非難されるべきとされた人物を挙げている。人によっては、その名前が少ないことに失望するかもしれない。しかし、大統領の諮問機関である放射線諮問委員会に勤務していた時に学んだように、法的手続きが時に複雑であることには、それなりの理由がある。事実が争点となることもあれば、行為に複数の意味や目的があることもあり、判断はきめ細かでなければならない。繰り返しになるが、ニュルンベルクのナチス医師裁判は、不完全ではあっても、個人に満足のいく形で正義がもたらされた状況についての有益な例を示している。しかし、弁護士倫理学者のジョージ・アナスやボストン大学の医師倫理学者マイケル・グローディンは、効果的な執行メカニズムの欠如がニュルンベルク綱領の欠陥の一つであると指摘している。
医学・軍事の人体実験をめぐっては、解釈とコミュニケーションの失敗が、ニュルンベルク判事の善意だけでなく、人体実験における倫理基準を特定し適用しようと誠実に努力した多くの人々をも挫折させたことが、私たちの目に焼き付いている。国際社会は、何度も繰り返されてきた普遍的な価値を実現し、第二次世界大戦から湾岸戦争に至るまで多くの失敗から学んだ厳しい教訓を適用できる研究倫理裁判所の創設に向けて、一歩を踏み出すべきであろう。
国際的な研究倫理裁判所の副次的な利点は、行われている研究を監視することにも役立つということである。新型兵器の開発における「透明性」は、世界のパワーバランスと、確かにテロを維持するための一つの方法である。将来的には、人体実験の実施をオープンにすることは、被験者を過度の危険にさらすことのないよう倫理的な基準を満たすことを保証する以上の効果があるはずだ。そして最も重要なことは、人体実験が兵器そのものを抑制することにつながるということである。
しかし、大量殺人の準備に参加することを正当化できる、あるいは買収できる科学者がいる限り、防衛能力は重要である。米国へのテロ攻撃が1回でも試みられれば、たとえ失敗したとしても、近代的な侵略を経験したことのない国には強力な反動が生じる可能性がある。フォート・デトリックで行われているような、真に情報を持った男女による人体実験は、私たちの防御を向上させ、盲目の怒りに任せて暴れる以外の方法があることをアメリカ人に確信させるために不可欠なものであろう。現実的な条件下での飛散をテストするための空気中の粒子を使った野外テストでさえ、国民の信頼を得るための倫理的な審査プロセスがある限り、国民に受け入れられる可能性があるのだ。危険な世界では、私たちを守ろうとする人たちが、不当なリスクの原因を増やさないようにしよう。
あとがき
『Undue Risk』の出版後、人体実験をめぐる新たな事件が次々と報告された。このあとがきで、私は幸運にも、これらの新しい報告を、私が組み立てた歴史の枠組みに統合する機会を得た。この歴史は、秘密実験によって被害を受けた人々、その愛する人々、そして真実のために献身した多くの擁護者、ジャーナリスト、歴史家、良心的な政府関係者など、多くの人々の犠牲の上に成り立っている。
また、この物語が語られることができたことは、アメリカのシステムに対する賛辞であり、アメリカ国民の真の勝利である。他の国々は、冷戦時代の活動を見直すことにあまり関心がなく、政治体制も、自国政府の行為に不満を持つ国民の要求に対してあまり敏感でないことが証明されている。このようなことを言うのは、無批判なジンゴイズムに陥ることでも、間違った行為や被害があったことを否定することでも、継続的な警戒が必要でないと主張することでもない。私が言いたいのはむしろ、「過度のリスク」は多くの勇気ある人々や、その継続的な改善を求める国の存在に負うところが大きいということだ。実際、アメリカ人としての私たちの統合された特徴のひとつは、政府の力に対する健全な懐疑心である。ニューイングランドから南部、太平洋岸北西部に至るまで、さまざまな形で表現されるとはいえ、頑固な個人主義が表れている。この懐疑的な態度は、200年以上にわたって私たちの民主主義によく貢献してきた。
しかし、懐疑的な態度には代償がある。この本についての講演やインタビューの際、私は何度も、倫理に反する秘密実験が今も政府によって行われていないことを示すことができないことを告白しなければならなかった。「もしそうなら」「こうかもしれない」と考えるのは簡単なことで、否定的なことはなかなか証明できない。しかし、これだけは確かだ。アメリカほど、この問題についてオープンにしている国はないだろう。米国ほどこの問題についてオープンにしている国はない。最も近い同盟国を含む他の国々の同僚は、大統領諮問委員会が行うような政府による調査は、彼らの政治文化では軌道に乗せることは不可能であると私に認めさせなければならない。しかし、私たちには憲法と権利章典があることを、少しばかり喜んでおこう。
したがって、真に自由な国家が、国民の犠牲の上に独自の生活と権利を持つ象徴的な国家を決して容認できないのと同様に、私たちも理不尽なパラノイアから身を守らなければならない。特に、政府を一枚岩として過大評価し、その多くの部分を一糸乱れぬように行動させる傾向があることに抵抗しなければならない。しかし、『Undue Risk』のストーリーは、連邦政府の巨大な組織がいかにのろまで不器用なものであるかを物語っている。例えば、冷戦初期に国防総省がニュルンベルク綱領に基づく人体実験方針を内部で受け入れ、理解することに失敗したことを考えよう。この失敗は、米国民と自軍からの信頼の欠如という形で、国防当局がいまだ代償を払っているものである。
蟻地獄戦争
現在では、軍服着用者を含む強制的な実験からの重要な一般的保護が存在する。これらの保護は、軍人が持ち場に戻れるような医療を受け入れる、あるいは職務遂行能力を守るような医療を受け入れるという通常の要件に例外を設けるものである。例えば、統一軍事裁判規則(UCMJ)に従い、米国陸軍司令部方針(AR 60-200)は、「現役または訓練のための現役の兵士は通常、自分の命を守り、過度の苦痛を軽減し、他人の健康を守り維持するために必要と考えられる医療を受けるよう求められるだろう」と述べている。
第7章の原爆退役軍人に関する説明で述べたように、研究への参加が「医療」とみなされ、それゆえに要求されることがあるのかどうかが重要な問題である。軍人はAR70-25によって、強制やUCMJ処罰の脅威から保護されている。AR70-25は、「人間を対象とする使用に関する道徳、倫理、法的概念は、この規則に概説されている通りに従う。被験者の自発的な同意が不可欠である。軍人は、被験者として参加しないことを選択しても、統一軍事裁判規則の下で処罰されることはない。さらに、被験者として参加しないことを選択したことを理由に、軍人や文民が行政処分を受けることはない」この規則は、1953年にチャールズ・ウィルソン国防長官がニュルンベルク法典に基づき作成した覚書の流れを汲むものである。
AR 70-25の最新版は1990年に発行された。それ以前のバージョンとは異なり、この陸軍規則には、危険な状況や核、化学、生物学的な実戦演習を伴う試験や訓練に対する除外規定がない。したがって、非通常型兵器に関わる訓練活動は、インフォームドコンセントや実験のリスクに対する監視を含め、AR70-25の下で保護されると考えられる。機密研究であっても、大統領覚書により、インフォームド・コンセントと事前審査という2つの保護が適用され、実験に参加するためには、被験者も審査員も必要なセキュリティ・クリアランスを有していなければならない。
このような重要な保護措置があるにもかかわらず、前号を仕上げたとき、国防総省が何十年にもわたって行ってきた人体実験に関する悪事や誤りからまき散らした不信感に対する国民の反応は、炭疽菌ワクチンの接種計画でかなりの収穫を得たのではないかと思った。国防総省は、イラクや北朝鮮などの国が管理する生物兵器の隠し場所への懸念を理由に、現役および予備軍240万人全員に、生物兵器に使われる可能性が最も高いとされてきた炭疽菌のワクチン接種を義務付ける取り組みを開始した。しかし、このワクチン接種プログラムに対して、軍人たちの草の根から、小さいながらも声高な反抗が起こった。その結果、ベトナム戦争以来、最も深刻な軍の士気の低下となった。
炭疽病は、汚染された動物や動物製品に接触することによって起こる細菌感染症である。炭疽菌が皮膚から侵入する場合は、汚染された動物の皮革を扱った場合に起こりうるが、通常は治癒可能である。しかし、炭疽菌を吸い込んだり、飲み込んだりするとほとんど致命的である。炭疽菌の芽胞は土の中で何十年も休眠しているので、炭疽菌は生物兵器になると長い間考えられてきた。国防総省が軍隊に接種しようとしているワクチンは、炭疽菌の芽胞にさらされる危険のある人々に対して食品医薬品局から承認されているものである。残念ながら、このワクチンは18ケ月間に5回接種し、その後毎年ブースターが必要であり、また、吸入炭疽病に対する防御はサルのみでテストされている。その投与スケジュールの複雑さと、空気感染する炭疽菌(戦闘中に最も起こりやすい形態)に対する防御としての人間での成功が不確かであることが、ペンタゴンのワクチン・プログラムに対する批判の一部となっている。
年初頭には数十人の軍人がワクチン接種を拒否したが、1年後には数百人になった。彼らは軍法会議から除隊まで、様々な処罰を受ける危険性があり、長年の勤務の結果、福利厚生が完全に失われた。反対派は、このワクチンは戦闘状態、特に空中での使用についてはテストされておらず、何百もの副反応が報告されていることを指摘している。また、このワクチンを製造した研究所は、連邦政府の認可を得られず、操業の継続が困難な状況にあった。そして、経験豊富な元軍人たちが、このプログラムに反対する意見をメディアに発表し始め、議会の委員会がペンタゴンのプログラムに対する厳しい批判を発表した。また、議会の委員会では国防総省のプログラムを厳しく批判した。「マーク・E・サウダー下院議員(共和党)は2000年2月18日付のニューヨーク・タイムズ紙に次のように書いている。「初期にはこれが(潜在的敵対者による炭疽菌の脅威に対する)解決策になるように見えた。「しかし、この問題を掘り下げれば掘り下げるほど、これは化学・生物技術という問題に対する実質的な医学的解決策というよりも、政治的解決策であることが分かってくるのである。
ミシガン州バトルクリークの第110兵站部隊に所属するロバータ・K・グロール技術軍曹の証言は、多くの国会議員を動かしたようである。グロール軍曹は1998年9月18日、カタールへの派兵に備えて炭疽菌の注射を受けた。年4月29日、下院の委員会に提出した文書で、グロール軍曹は次のように語っている。
派遣に志願する前、私は炭疽病ワクチンのぜひについて全く知らなかった。私は国防総省と上官を盲信し、ワクチンを投与する資格があると感じた人物を信じて行動した。このワクチンは、私が職務上受けた他のすべてのワクチンと同様に安全であると考えた。シリーズの最初の2回の接種後、私は極度の疲労感と吐き気に襲われたことに気づいた。しかし、同じ時期に私は、来るべき作戦準備検査の準備のために何時間も残業していた。この症状は、ワクチンのせいではなく、時間外労働とストレスのせいだと考えていた。
しかし、グロール軍曹の健康問題は続き、1999年3月以来、彼女は病気のために400時間近い休暇を取りました。慢性疲労、息切れ、体重減少、気分の落ち込み、腹痛、吐き気と下痢に悩まされているとのことである。「炭疽菌の予防接種を受けてから、体が何かに反抗して、重病になってしまった」
このような攻撃にもかかわらず、国防総省はワクチンの安全性と軍事的重要性を主張し、毅然とした態度で臨んだ。彼らは、40万人の軍人が何事もなくワクチンを接種したことを指摘し、数日で死に至る可能性のある病原体から軍人を守るのは当然であると主張した。国防総省の医療担当者は、このワクチンは安全であり、リスクと便益の分析から、使用せざるを得ないと主張している。
ワクチンの効果についての苦情は根拠があるのだろうか?予防接種が原因かどうか、検証するのは難しい。放射線実験や1950年代のフォートデトリックでの生物兵器研究の長期的影響と同様に、実際のワクチン接種の効果とその後の病気の報告とを結びつけることは、非常に困難であることはよく知られている。医師がワクチン接種と関連づけることができたのは、ごく少数の病気だけだったようだ。原爆退役軍人の医学的影響が不明確なことを思い出してほしい。しかし、合理的な根拠がないことが問題なのではないだろうか。
すべての報道が、ワクチン接種プログラムが直面している根本的な問題であると私が考えていることを明らかにしているわけではない。もし、炭疽菌ワクチンそのものが孤立した問題であれば、国防総省は合理的説得に頼ることができるかもしれない。そして、炭疽菌のような目に見えない致命的な兵器には、ワクチンによる防御が必要であると主張することができるかも知れない。しかし、もし私が正しければ、問題はもっと深刻である。エージェント・オレンジ(ベトナムで使用された枯葉剤で、ペンタゴンが長年にわたって否定してきた結果、退役軍人に健康被害が出たと多くの人が信じている)の記憶や、兵士、水兵、飛行士を率直に人体実験に使ったことなどから、ワクチン問題には何十年もの不信感が蓄積してきた。今日の兵士の中には、ベトナム帰還兵の息子や娘もいれば、朝鮮半島時代に叔父を持ち、おそらく原爆実験場に配置されていた者もいるだろうし、マスタードガス実験中に海軍にいた祖父を持つ者もいるだろう。炭疽菌ワクチンの議論では、残念な出来事の積み重ねが地質学的な底流にある。事実上の実験台と疑われる兵士が多いという結果も頷ける。
炭疽病ワクチン接種プログラムは、その困難さゆえに、一部の人々の疑念とは裏腹に、それ自体が医学的実験ではなかった。むしろ、国防省の指導者が脅威についての議論の余地のある仮定に基づいて判断したものであり、戦闘中に炭疽菌を使用し、予防措置がとられていなかったことが判明した場合にどう言われるかという懸念が動機の一つであったのだ。炭疽菌にさらされると、ほぼ確実にひどい死に方をする。しかし、疑わしいワクチン以外にも対策はある。マスクやその他のフィルター技術を、特に危険にさらされる可能性が最も高い戦闘部隊にもっと利用できるようにすることを強く求める声もある。この解決策の問題点は、炭疽菌にさらされたときには、防御対策が手遅れになっている可能性があることである。結局のところ、国防総省が、有用性も必要性も不明なワクチンで士気を損なうことは、不信の遺産を燃やし続ける代償に値しないと結論づけるならば、技術的な問題は二の次になるかも知れない。
原爆退役軍人
炭疽病ワクチン論争が展開されている間にも、数十年来の不信の原因の一つである、原爆実験中の軍事演習に参加するよう命じられた「原子兵」に対する健康影響についての疑惑が明らかにされた。原爆投下時の健康被害について、政府は嘘をついた、あるいは少なくともそのせいで病気になったのだから補償すべきだ、と何十年もの間、被爆者やその家族の多くが主張してきた。問題は、彼らが年を取るにつれて、同年代の他の人たちよりも本当に多くの病気にかかったかどうかを判断することである。
ワシントンDCの米国科学アカデミー医学研究所は、ネバダや南太平洋の爆心地での演習に参加した7万人の退役軍人を対象に、原爆実験の健康影響に関する集中調査を実施し、その結論を出した。医学研究所は、この退役軍人と、同時期に兵役についていたが、爆発現場にはいなかった別の6万5千人の兵士、水兵、飛行士を比較した。その結果、白血病による死亡率が14%高いことが分かった。しかし、この数字は統計的に有意ではなかったので、偶然に起こった可能性がある。また、前立腺がんや鼻腔がんの死亡率も予想外に高かったが、これも放射線被曝とこれらのがんに関する過去のデータがほとんどないため、結論は出ていない。
医学研究所がより決定的な結果を得るために重要な情報は、退役軍人一人一人が受けた放射線量の大きさに関するデータであったと思われる。特に信頼できる記録がない場合、線量の再構成がいかに困難であるかは、これまでにも説明したとおりである。被爆者の調査結果は、特に本人とその家族にとっては、明らかに不満の残るものである。軍隊に入隊して30年、40年後に実際にがんになった人にとって、原爆の爆心地から何マイルも離れた場所に配備されていなくても、おそらくがんになっただろうと言われても、何の慰めにもならない。原爆投下が大規模な実験の一環であったとすれば、裏切られた思いはなおさらである。悪性のがんに侵され、自分の愛する人が自分の知らないうちに実験台にされていたと信じる人々の親族に、私たちはどう言えばいいのだろうか。
ボストンのアトリウム
1999年の春、私は、数十年前に膠芽腫で亡くなった人々の親族を代表する弁護士から電話を受けた。膠芽腫(こうがん)ほど恐ろしい病気はない。裁判資料によると、1950年代初頭から1960年代初頭にかけて、マサチューセッツ総合病院のスウィート博士らは、がん患者の脳に中性子線を照射し、がん細胞を破壊することで膠芽腫の治療を試みていたという。この治療には、ロングアイランドのブルックヘブン研究所とケンブリッジのマサチューセッツ工科大学にある原子炉が使われた。また、中性子をがん細胞に引き寄せる薬剤を脳に導入する試みも行われ、「中性子捕捉療法」と呼ばれるようになった。
PETスキャンの開発者でもある名医スウィートは、放射線技術を医療に生かそうとする試みの最先端にずっと身を置いていた。残念ながら、中性子捕捉療法は、何十人もの患者に試されたものの、期待された結果を得ることはできなかったようだ。悲しいことに、少なくとも9人の患者が腫瘍ではなく、この治療が原因で死亡したことが示されている。人体実験諮問委員会が、1947年に原子力委員会が作成したインフォームド・コンセントに関する書簡を公開した後、患者の親族が訴訟を起こしている。この手紙には、インフォームド・コンセントや潜在的に有益な治療法についての要件が記されているのだ。原子力委員会が治療に使用した機器の一部を提供していたこともあり、この事実に彼らは困惑していた。私は、この訴訟の専門家として、AECレターの歴史的背景を説明する役割を担った。時効は、実験が治療の見込みなく行われたことを遺族が知るまで、あるいは知るべきであったときまでとされた。この時効は、ACHREの文書の一部が初めて公開された1995年よりも早く成立するはずはなく、一部の家族は疑いを抱き、弁護士を通じてより完全な調査を開始した。
私はこの時、初めて連邦裁判所と陪審員を経験した。裁判は、ボストンの印象的な連邦裁判所で行われた。床から天井まで広がる港の眺めに、法制度の威厳と権力を感じた。そして、この法廷の外では、潮の満ち引きが必然であることを思い知らされるのだ。
私は、原告側弁護士への報告書の中で、入手可能な情報を整理した。その結果、中性子捕捉療法が実際には実験であり、AECが1947年の書簡で述べたインフォームドコンセントと潜在的利益に関するルールに従っていなかったことが明らかになったと思う。もちろん、この情報が陪審員にどのような影響を与えたかは分からないが、陪審員はマサチューセッツ総合病院とスウィート博士に対して800万ドルの賠償金を遺族に命じた。この事件は現在控訴中であるが、もしこの判決が確定すれば、ハインリッヒ対スウィート事件は人体実験の法律と倫理の歴史において重要な事件となるであろう。
精神障害者の保護
連邦政府機関によって密かに行われていた幻覚剤実験の暗黒時代、ニューヨークのテニス選手ハロルド・ブラウアーも悲劇の犠牲者の一人であった。ブラウアーは1953年にニューヨークの精神医学研究所にうつ病で入院していた。このケースは第7章で詳しく述べる。現在では、兵士や囚人のような集団に特別な保護を与えるための規則や手続きが多く制定されているが、研究に参加することに有効なインフォームド・コンセントを与えることができないかもしれない精神障害者を守るための特別な規則がないのは驚くべきことである。
1998年、私は国家生命倫理諮問委員会のコンサルタントとして、精神障害者を対象とする研究の問題に取り組む機会を得た。この問題は、1990年代に入ってから、こうした悲劇的な病気に対する新薬の登場が期待される一方で、こうした薬の試験方法に関する倫理的な懸念と衝突するようになり、ますます有名になっていた。例えば、精神分裂病の新薬を試す場合、新薬の効果がより明確に分かるように、現在受けている治療から精神分裂病の患者を外し、体内を「洗い流す」ことが一般的な方法である。批評家たちは、薬物治療を中断された人々には大きなリスクがあること、研究対象者自身には何の益もないこと、そして研究対象者の多くはインフォームドコンセントの能力が低下している可能性があることを指摘している。
精神障害者を対象とした研究に対する私の思いには、個人的な経験も含まれている。私の父は、集団精神療法と心理劇の分野を切り開いた著名な精神科医、J・L・モレノである。私は、ハドソン渓谷にあるヨーロッパ風の小さな療養所の敷地内で育った。彼は有名で独創的な反フロイト主義者で、1974年に亡くなってから、患者を心から愛していたという評判を、後輩や同僚たちから聞かされてきた。
父の死後、私は父の回顧録を読んだが、そこにはウィーン大学の医学生2年生のときのことが書かれていた。彼は、ユリウス・ワグネル・フォン・ヤウレグの診療所で働くことになった。この人物は、精神医学研究の歴史において重要な人物で、私はすぐにでも再訪するつもりだ。1915年のことだろうか。場所はオーストリアのウィーンだが、アカデミックな医学の文化は聞き覚えがある。
クリニックでの研究助手になるための給料はなく、ただそこにいることで多大な名声が得られ、研究でも臨床でも世界トップの精神科医に会い、一緒に仕事をする素晴らしい機会が得られ、私の場合は、若い科学者のキャリアにとって今でも重要な要素である出版物に自分の名前を載せてもらうことができた。そこで私は他にもいくつかの研究プロジェクトに参加したが、唯一覚えているのはヨウ素の代謝に関する研究である。チロル地方に行って、ラットにヨウ素をいっぱい注射して……。ネズミの実験の後、フォン・ヤウレグ診療所とつながっていた精神病院、シュタインホフ病院の受刑者を対象に実験をした……。私は、無力な精神病患者を実験台にすることに、いつも愕然とさせられている。私は関与していないが、結核菌を注射するプロジェクトや、アルコールを注射するプロジェクトもあった。
父が回想する事件のすぐ後の1917年、彼の師であるワーグナー・フォン・ヤウレックは、梅毒の第三期に起こり、狂気、麻痺、死をもたらす全身麻痺の治療法として、発熱を誘発する実験を行った。彼は、9人の麻痺患者にマラリアを注射し、その後キニーネで治癒させた。マラリアによる発熱は、患者の85パーセントを治癒させたという。この発見により、ワーグナー・フォン・ヤウレックは1927年にノーベル医学・生理学賞を受賞したが、全身麻痺に対するマラリア療法は、もちろんペニシリンに取って代わられた。
ヤウレグの研究は重要ではあったが、患者を研究対象として使ったという疑問があり、それは当時のオーストリアの精神医学や神経医学では一般的であり、私の父も遭遇したようである。興味深いことに、ワーグナー・フォン・ヤウレグ自身は、精神障害者を迫害や差別から守るための法律の熱心な運動家であった。
20世紀を通じて、精神障害者の権利はあいまいなままだった。ナチスの犯罪を調査したチームは、多くの精神科患者の抹殺につながった「T-4」または「安楽死」計画、事実上強制収容所での大量殺人のリハーサルという文脈での精神障害者の虐待に注目した。第3章では、ニュルンベルク裁判の最高医学顧問であったレオ・アレクサンダーが、親衛隊長ハインリヒ・ヒムラーの記録から収容所実験の恐ろしい物語を解き明かし、ニュルンベルクでの起訴を可能にしたことを説明した。アレクサンダーは裁判の終わり近くに、裁判官に対して覚書を書き、その一部が有名なニュルンベルク綱領に盛り込まれた。
この覚書の中でアレクサンダーは、精神障害者を特別な保護を与えるべき集団として挙げている。しかし、裁判長たちは、最終的な草稿の中でこの言及を削除してしまった。その理由は、革新的な治療法に関する医学的な判断に干渉するようなことはせず、囚人のような健康な被験者を簡単に強制できる集団で、有益でなく危険性の高い実験を排除することだけを考えたからだと思われる。しかし、「被験者の自発的な同意は絶対に必要である」というこの規範の有名な第一節は、精神患者や自発的な同意が得られない子供に対する研究の多くを排除しているように見えるため、裁判官の意図について多くの混乱が生じている。
1998年12月、全米生命倫理諮問委員会は、精神障害者の研究に関して一連の勧告を発表した。私は、その報告書のコンサルタントを務めた。これらの規則は、ハロルド・ブラウアーを死に至らしめたメスカリン実験など、1950年代に行われた悪名高い精神医学実験を阻止するものだった。例えば、委員会は、インフォームド・コンセントを行う能力がない可能性のある人には、他の人がいる場合は実験への参加を求めるべきではないと勧告している。また、実験に参加したくないという意思表示も尊重するよう求めている。ブラウワー自身、実験から抜け出そうとしたが、許されなかった。
このあとがきを書いている時点では、委員会の勧告は新しい規則として制定されてはいない。しかし、精神医学界がこの論争に注目したことは確かで、1990年代半ばに比べれば、この問題に対する感度ははるかに高まっていると私は感じている。例えば、薬物を使用しない研究を行っていた機関の多くは、この方法で新薬を試験することの必要性と価値を考え直した。倫理的な関心が高まることで、科学者が自分たちのやり方を見直し、改善するきっかけになることもある。
精巣照射実験
私たちは、国を守るために自らを無意識のうちに実験台として考えている兵士たちに、当然のことながら、適切な同情を寄せている。また、重病を患い、期待されてはいるが時には非現実的な治療法に対して脆弱な人々に対しても、私たちは当然のことながら懸念を抱いている。私たちは家族とともに、医師や病院に、自分の意見を十分に主張できない人々を守る手助けをしてほしいと願っている。刑務所にいる人のリスクを心配する人は少ないかもしれないが、社会の犯罪者が他の人よりも倫理的保護に値しないという判断が下されると、私たちは危険で滑りやすい斜面に立たされることになる。
第7章では、オレゴン州とワシントン州の刑務所で行われた精巣照射実験について説明した。ワシントン州での実験は、ワシントン大学の科学者が行った。年秋、ワシントン州の63人の元受刑者は、国と大学から補償金と謝罪を受けた。元受刑者たちは、不妊症などの健康被害が続いているとして、生存者やその遺族に現金が支払われた。
オレゴン州の元受刑者は、現在も訴訟を続けている。その1人であるハロルド・ビボーさんが、『Undue Risk』が出版された直後に私に連絡をくれた。年前、当時私がスタッフだった大統領諮問委員会の人体実験委員会で、彼が証言したのがきっかけで知り合った。建築設計者であるハルさんは、「オープンマインドでいたい」と語っていた。ハルさんは建築設計者であり、「心を開いてほしい」という思いから、この本を読んでくれた。しかし、実験の意義については、正直なところ見解の相違があった。
その中でハルは、精巣への放射線照射を承諾した時の22歳の若者の姿を思い出していた。その時、ハルさんは「自分がいかに愚かな人間であったかを思い知らされた」と悔しそうに言った。無菌状態になることよりも、月に5ドルでも懐に入ればいいと思っていた。その決断をするには、私は若すぎたし、間違った状況下での決断だった」
しかし、ビボーが医学研究に嫌気がさしたのは、自分が被験者となった歴史があるからではない。「今は良い研究が行われているし、良い研究であることの一つは、人々が得られる情報の量だ」しかし、彼は注意を促している。「研究に没頭して、こんなことをしても害はないと言って、人々を動かそうとする医者が多すぎる」と。最近、ハルは日常的な診療のために医師のところに行くと、治療の詳細に特別な関心を抱くようになった。治療法のリスクや効果について、自分なりの意見を述べることも多く、時には主治医の意見と食い違うこともある。ハルさんは、「主治医の考えを変えてもらうことはほとんどない」と、これまでの経験を皮肉って言う。
ウラン鉱山の労働者
年1月、ケンタッキー州パデューカのウラン工場で、1950年代前半に作業員が実験に参加していたことが明らかになった。ある者は放射性の液体を飲み、ある者はガスを吸って、ウランがどれだけ早く排泄されるかを確かめた。この事件は、全米の原爆工場で働く労働者の発がんリスクに関する、より大きな暴露の一部であった。冷戦時代、数十の施設で7万個の核兵器を製造するために、約60万人の男女が従事した。医学的な実験に携わった人はごくわずかだが、その多くが高レベルの放射線や危険な化学物質を浴びたと報告されている。
クリントン政権は2000年4月、労働者のリスクに対する連邦政府の負担を受け入れるという、前例のない国家補償計画を発表した。これは、労働者が被った損害の立証責任を負うという、従来の政府の補償請求のやり方を覆すものであった。これとは対照的に、政権の計画では、業務上の疾病に苦しんでいると思われる原発労働者は、エネルギー省から疑いの余地を与えられ、迅速な賠償請求を受けることになる。特定のガンにかかった人は、10万ドルの給付金を受け取ることができる。ワシントンポスト紙が引用したエネルギー省のビル・リチャードソン長官の言葉を借りれば、「政府は労働者と戦うのはもう終わりだから、今度は彼らを助けよう」ということである。
原爆労働者のニュースが報じられた当初は、工場労働者の危険な労働条件や、大気・水質・土壌汚染などの環境問題が大きな関心事だった。しかし、原爆実験がきっかけとなった。プルトニウム注射事件を追っていた人たちにとって、ケンタッキー事件は既視感のあるものであった。第二次世界大戦中の入院患者へのプルトニウム注射は、プルトニウムの排泄率を調べるのが目的で、マンハッタン計画の若い研究所員の安全確保が動機だったらしい。しかし、ケンタッキー州の作業員の場合、彼ら自身が実験の被験者となった。おそらく自分たちのためであろうが、必ずしも危険性を十分承知していたわけではない。しかし、少なくとも14人の労働者が、1950年代初頭に「志願」している。放射線被曝の危険性は一般的に認識されていたはずだが、当時はウランの粉じんや副産物の危険性が過小評価されていた。補償の対象となる原発労働者の数パーセントにすぎないが、実験対象者は、職場にあったリスクを管理するために、さらに多くのリスクにさらされるというパラドックスを体現している。
このケースもまた、第5章で述べる1947年の書簡に示された原子力委員会の規則違反であったように思われる。この書簡は、AECのキャロル・ウィルソン所長が書いたもので、実験対象者に潜在的な利益を要求している。パデューカ工場で働く人たちが、意図的にウランを浴びても、直接的には何の利益もないはずだ。この書簡が書かれたわずか数年後、この書簡に書かれていたルールは、忘れられたか、無視されたか、あるいは大きく誤解されたことが明らかになった。
エネルギー省は1999年、ウラン鉱山の労働者問題に直面した時、それまでとは全く違う、倫理的に疑問のあるずさんな対応で、自分たちの原発運営と労働者の健康問題に厳しい批判を浴びせた。もし、数年前に「オープン」の前例がなかったら、ウラン労働者の訴えはここまですんなりとは伝わらなかったかもしれない。ウラン労働者のケースは、人体実験に限ったものではなかったが、放射線調査論争から生まれた政府の責任に関する問題は、似たようなものだった。
教訓は、医学実験の対象となる人々の権利と利益は、私たち全員の権利と関係しているということである。政府は、たとえ国家の安全保障に関わる問題であっても、人々を危険にさらすことを平然と行うことはできない。
ユニット731の詳細
私が『Undue Risk』を書いたとき、戦争前・戦中の日本の生物・化学兵器実験が中国にもたらした人間的悲劇の全容を推し量ることはできなかった。第4章で述べたように、満州で大規模な実験を行った日本軍の部隊の中で最も悪名高いのは、石井博士の指揮下にあった731番である。彼らは、ハルビン近郊の浄水局と呼ばれる巨大な施設で、何千人もの不運な現地住民を、ジョージ・オーウェルの『1984年』の「ニュースピーク」をうまく先取りした言葉で、身体切断や終末実験にさらした。しかし、この被害者は直接被害を受けた人たちだけで、生物製剤を使った野外実験によって間接的に被害を受けた人は数万人にのぼると推測される。
1999年末、日中の専門家グループは、野外実験によって殺害された中国の民間人は27万人以上であると結論づけた。これは1937年に起きた南京大虐殺の犠牲者数を上回るかもしれない。蔓延した病気は腸チフス、コレラ、炭疽、ロックジョー、壊疽などである。ほとんどは、日本軍が完成させようと努力していた様々な細菌爆弾から爆発したものである。この報告書が発表される数カ月前、日本の裁判所は中国人戦争被害者による日本政府への賠償請求を却下した。原告の10人のうち8人は、731部隊の実験の犠牲者の親族であった。新しい情報が次々と出てくる中、この日中関係の問題がすぐに忘れ去られることはないだろう。
さらに、731部隊の悪名高い経歴の裏には、ソ連の生物兵器プログラムの元主任科学者が、ソ連は捕えた日本人科学者から情報の宝庫を得たと語っている。現在アメリカにいるケン・アリベックは、ソ連での仕事について自著を出版しているが、捕獲した日本の文書と満州で捕獲した科学者の尋問の両方によって、この計画は大きな後押しを受けたと主張している。科学者たちは1949年に裁判にかけられ、その後釈放されたことは、これまで述べたとおりである。アリベクは、スターリンが日本の資料に特別な関心を持ち、秘密警察署長に世界のどの国よりも優れたプログラムを開始するよう命じたと述べている。
アリベクの主張は、米国が得た情報についても新たな疑問を投げかけている。朝鮮戦争で、米国が日本のデータの一部を使って北朝鮮や中国に生物学的攻撃を仕掛けたという疑惑があることを思い出してほしい。もし、アリベクの言う通りなら、米国が得た情報もまた、これまで考えられてきた以上に有益なものであった可能性がある。しかし、アメリカの生物兵器プログラムの元責任者であるビル・パトリック氏は、アリベック氏が1992年にロシアから亡命した際に、彼のブリーフィングを行ったが、この評価には疑問があると共同通信に語っている。パトリック氏の見解は、日本の手順があまりにも粗雑で数値化できないため、双方にとって有益な情報を得ることができなかったというものである。
インフォームド・コンセントのために
政府は、これまであまりにも頻繁に人体実験の倫理性に疑念を抱かせる原因となってきたが、この制度に対する信頼を回復することができる唯一の当事者であるとも言える。現行の保護制度が持つとんでもない制限のひとつは、厳密に言えば、インフォームド・コンセントの要件が、連邦政府がスポンサーとなっている研究、あるいは連邦政府の資金援助を受けている機関で行われる場合にのみ適用されるという点である。研究の資金源や分類の有無にかかわらず、すべての人体実験に対してインフォームド・コンセントを義務づける法律は存在しない。
もちろん、実際には、研究者は無意識のうちに実験を押し付ける愚か者であろう。裁判所は、暴行や過失の法律に基づいて、同意の必要性を認めるだろう。しかし、国家安全保障の実験も含めて、実験に参加するすべての人間の権利として、インフォームド・コンセントと、実験の危険性と利益に関する適格なグループによる事前審査という2つの保護を事前に保証できるのは連邦法だけである。いくつかの法案が議会に提出されているが、足踏み状態である。
今こそインフォームド・コンセントを法制化する時である。完全な解決には、民間の研究だけでなく、国家安全保障機関によって行われる機密扱いの人体実験も含まれなければならない。現在、実験が行われる前にインフォームド・コンセントと倫理委員会による審査を必要とするのは、大統領覚書のみである。新しい連邦規則が現在官僚機構を通過中であるが、規則と議会からの法律の両方が、これらの基準に違反した者に対する厳しい罰則を伴って参加しなければならない。
遅れる正義
第7章では、1950年代の国家安全保障機関の非道な活動のいくつかを記した。おそらく、CIAの「マインド・コントロール」実験で最も有名なのは、科学者のフランク・オルソンのケースであろう。彼は、自分の知らないうちにLSDを投与され、ニューヨークのホテルの部屋の窓から飛び降りて自殺したと長い間言われている。少なくとも、それが一般に知られ、本書で語られているストーリーである。
しかし、1999年秋にケーブルテレビ局のA&Eが放送した「マインド・コントロール殺人事件」という番組は、公式発表に対する以前からの疑念を改めて示すと同時に、これまでで最も包括的な代替理論を提示している。この番組では、ニューヨーク市の地方検事局が1953年の事件を殺人事件として再捜査していることを紹介している。2000年1月の『Gentleman’s Quarterly』の記事によると、検察の捜査は続いているが、フランク・オルソンの死は殺人であった可能性が高いと判断するような気配があるとのことである。
ニューヨークの地方検事は、40年ぶりに事件を再捜査するという異例の決定を下したが、その際、ジョージ・ワシントン大学の法医学病理学者がオルソンの遺体を調べ、オルソンは転落する前に鈍器で頭を打ったという結論を出したことも影響したという。しかし、この病理医は、1953年に検視官が記録した顔面の裂傷を発見しなかった(ただし、遺体の発掘時には皮膚は無傷だった)。番組でインタビューされた他の人たちは、シェードを引いた閉め切った窓からの自殺の可能性を否定していたし、実際オルソンは数時間前に電話で妻と穏やかに話していた。しかし、フランク・オルソンのような物静かな科学者が、なぜ殺されたのだろう?
2000年の春、フランク・オルソンの息子であるエリック・オルソンが、バージニア大学の私のオフィスに電話をよこした。私達は彼の父親の死についての標準的な説明について話し、彼はニューヨークの地方検事によってテストされることになる自分の説を話した。エリック・オルソンによれば、父親が抹殺されたのは、海外で行われていたかもしれない極秘の薬物実験に脅威を与えたからだという。フランク・オルソンは実験台になっただけでなく、CIAと密接な関係にある陸軍特殊作戦部の研究員として従事していたようだ。研究者であるオルソン自身が動物を実験に使い、人間が使われるのを目撃したのかもしれない。そして、おそらくアメリカ占領下の西ドイツで見たものが、彼の心を大きく揺さぶったのであろう。偶然にも、CIAが機密指定を解除した1953年の暗殺マニュアルには、自殺に見せかけた飛び降り自殺が好ましい手段として明記されていると、エリック・オルソン氏は教えてくれた。
私はエリック・オルソンに、50年近くも父親の死の謎という、人間にとって最も大きな重荷を背負って生きてきた彼の心に浮かんだイメージを聞いてみた。父の死に関する記述は、H・C・アンデルセンの『皇帝の新しい服』によく似ていると長い間考えてきた」とオルソンは言った。「知覚の雲に穴が開き、皇帝が丸裸になったのを見た人は、どうして立派な衣服の錯覚が長く続いたのか不思議に思うのです」とオルソンは言った。オルソンは続けた。
父が「自殺」したという話は、1953年に書かれた、理由もなくホテルの部屋の窓から「落ちた、飛び降りた」という話も、1975年に書かれた、9日遅れでLSDがフラッシュバックし、CIAの護衛が呆然と見ているかガラスの破片の音で突然目を覚まし、閉じた窓から飛び込んだという話も(どちらも売られていた)いずれも意味をなさないものである。一方、どちらのバージョンも、父とその同僚が従事していたBWとマインド・コントロールの研究の実施に内在する最も厄介な問題から注意をそらすものであった。
父の殺人事件の教訓は、ニュルンベルク以後の世界では、実験者だけでなく被験者(父はその両方を同時に行っていた)も、特に道徳的優位性を主張する国々において、新たな形で危険にさらされているということだ。新しい倫理的状況下で絶対的な秘密を維持することは、内部告発者の信用を自動的に失墜させたり、反逆罪で裁判にかけることができないことを意味する。また、未承認の兵器を使った実験から生じた死傷者を公にすることもできない。残された唯一の選択肢は、何らかの形で「廃棄」されることである。このような実験の設計者は、伝統的な軍事研究の管理者というよりも、マフィアのドンのような立場に置かれている。組織の出口は水平方向にしかない。このような含意を前にして、1950年代初頭のCIAの執行者たちはひるむことはなかったが、歴史家たちや一般の人々は、国家がそのすべての装飾を施したものと見なし続けてきた。
エリック・オルソンさんとの会話は、『Undue Risk』が出版された後、彼の父親の事件とCIAの数十年にわたる実験を私に思い起こさせた2つの経験のうちの1つであった。アメリカの生物兵器プログラムに特化した歴史書『破滅の生物学』も1999年に初めて出版された。著者のエド・レジス氏は、私と同じく元哲学教授である。この本を読んでいて、CIAのスパイマスターで、LSD実験など化学兵器プログラムの責任者であったシドニー・ゴットリーブがバージニア大学病院で死んだことを知った。ゴットリーブの死は、私が『Undue Risk』の最後の仕上げをしているときに起こったもので、彼の死の床は、医学部の私のオフィスから数歩のところにあった。
その後、私は第二の皮肉に思い当たった。ゴットリーブのプライバシーは、私の同僚医師たち、つまり彼の担当医によって、当然のことながら徹底的に保護されていたのだ。ゴットリーブが、不幸にして彼の実験に参加することになった人々に与えなかったと思われる、道徳的配慮と人間としての尊厳を、彼らは彼に与えてくれたのだ。しかし、私は、フランク・オルソンの死を取り巻く状況を含め、冷戦時代の実験に関する最も緊密な秘密のいくつかについて、真実を隠蔽しようとする努力が最終的に失敗することを、これまで以上に強く望んでいる。放射線実験と同じように、生物・化学実験のファイルを公開するよう、連邦政府当局に要求するしかない。しかし、それは私たち全員が、不当なリスクの犠牲者たちを忘れることを拒否する場合に限られる。
