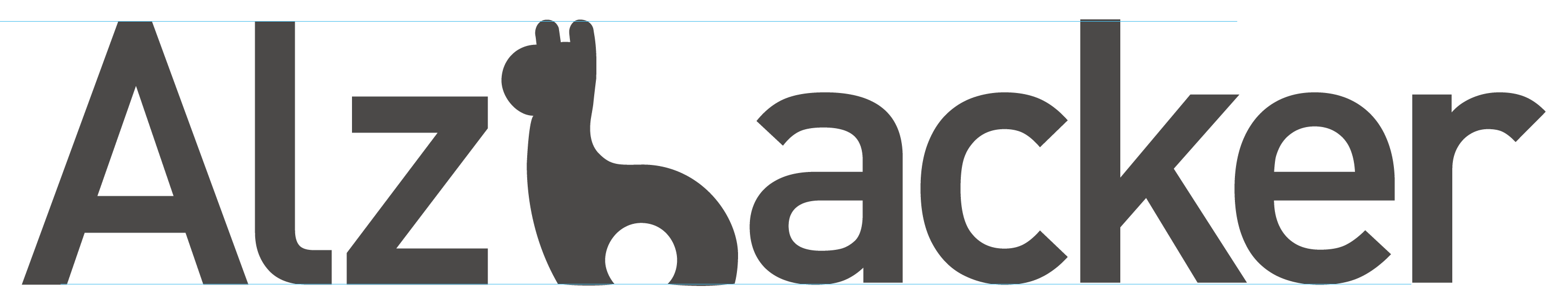The Russia Trap
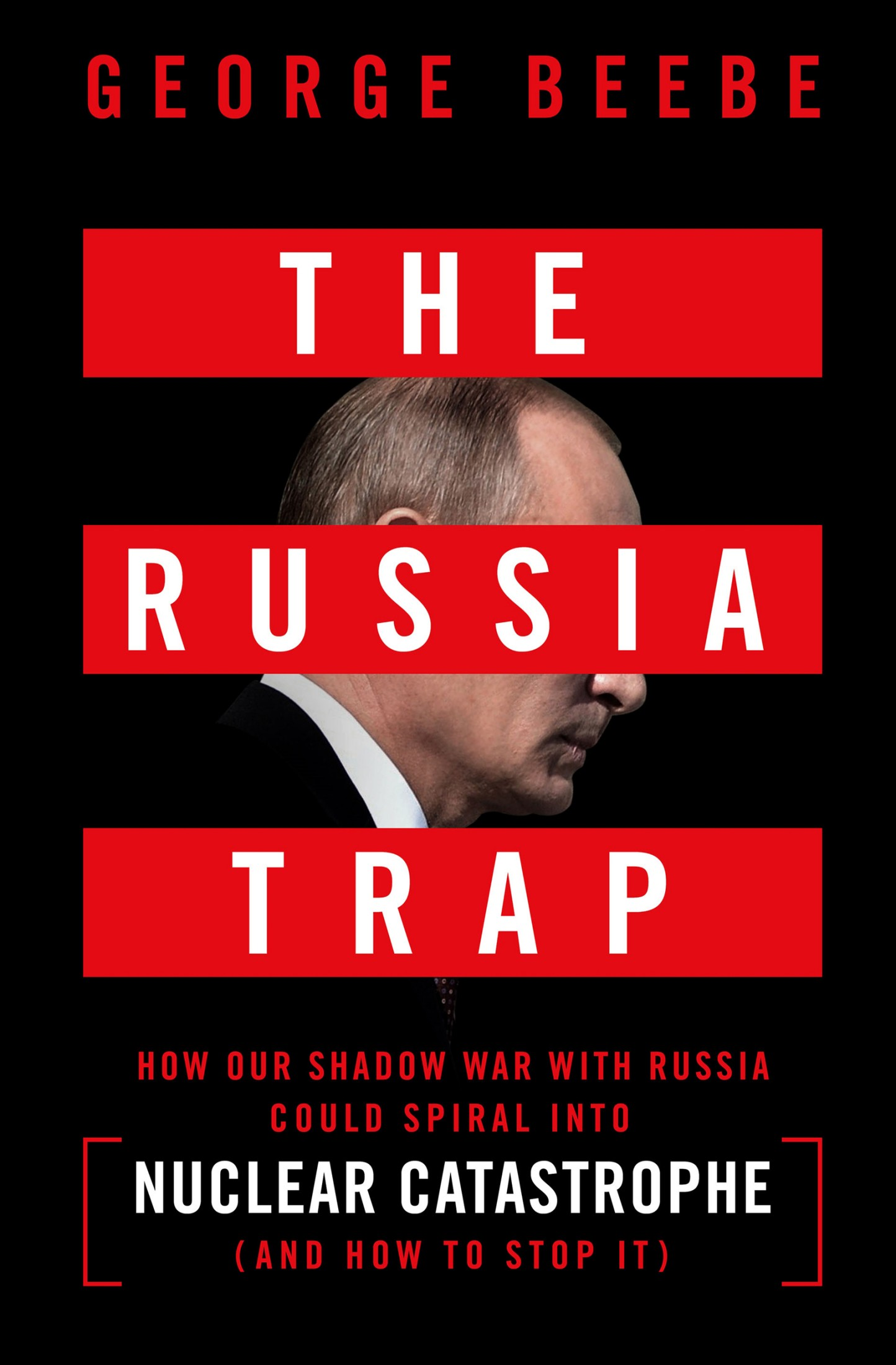
目次
- タイトルページ
- 著作権表示
- 献辞
- 序文
- はじめに
- 第1部:分析 問題の把握
- 1. 他の手段による戦争
- 2. 致命的な認識
- 3. ブレーキの故障
- 4. トリガー
- 第2部:合成 問題への対処
- 5. 単純化の罠からの脱出
- 6. 衝撃の吸収
- 7. システムの運用
- おわりに
- 謝辞
- 備考
- ノート はじめに
- ノート1
- ノート2
- ノート3
- ノート4
- ノート5
- ノート6
- 備考7
- ノート おわりに
- 索引
- 著者について
サラ、ソフィア、ノラ、グラント、ネイサンのために
前書き
どうしてこんなことが起きたのだろう?私たちは、規模の大小にかかわらず、予期せぬ大失敗の後、しばしばこの質問をする。振り返ってみると愚かなミスを犯してしまったのではないか、考えてみれば明らかな意図しない結果を予測していなかったのではないか、物事が悪くなる前に不明瞭であったのと同様に、後から考えても明らかに見える要素間の極めて重要な相互関係を無視してしまったのではないか、などと考えるのである。
予期せぬ事態は、私のキャリアの中でも重要な位置を占めている。私がソ連のアナリストとして仕事を始めたのは、1986年、ミハイル・ゴルバチョフがクレムリンに在任し始めた直後だった。それからの30年間は、外交に携わる多くの人が驚くような出来事が続いた。ベルリンの壁の崩壊、ソ連の崩壊、エリツィン政権下のロシアにおける自由主義的改革の失敗 2001年9月11日のテロ、イラクにおける大量破壊兵器の無駄な探索 2000年代初頭のいくつかの旧ソ連邦におけるいわゆるカラー革命、ウクライナのマイダン蜂起、そしてその後のロシアのクリミア併合と米露関係の疎外と敵対関係の激化などである。
このような事態を目の当たりにして、世の中の流れから大きく外れることを予測することがいかに難しいか、専門家が事実や予測を誤ることがいかに多いか、そして外交の現場を理解し舵取りをするためには謙虚な姿勢がいかに重要であるかを痛感させられた。また、私たちは皆、自分の期待というプリズムを通してニュースや情報を見る傾向があり、自分の重要な思い込みを明らかにし、検証することがいかに重要であるかということを敏感に感じさせてくれた。また、不意打ちを避け、自国の国益を守るためには、敵や競争相手の認識を必ずしも正しいと認めず、その目を通して物事を見ることが必要であることを教えてくれた。そして何より、災害を回避するためには、災害が起こる前に「なぜこんなことが起こったのか」という問いと格闘することの重要性を教えてくれた。この本は、そのような思いから生まれた。
はじめに
本書は、まだ起こっていない失敗を検証するプレモテム(予見)である。政治家が直面する最も困難な問題のひとつに焦点を当てている。誰も望まず、可能性が高いとも、あるいは可能であるとも思っていない戦争が、それでもなお、衝突する野心、新技術、誤った恐怖、絡み合った同盟と約束、国内政治的圧力、敵対国がどう反応するかについての誤った仮定が混ざり合って、燃えるように起こることをいかに予期し回避するかということだ。言い換えれば、ロシアとの間に出芽た「第一次世界大戦問題」を診断し、打開することである。
当時、第一次世界大戦と呼ばれていたものは、間違いなく人類史上最大の人為的な大災害をもたらした。第一次世界大戦は、ヨーロッパの主要国間の比較的平和なパワーバランスの1世紀を終わらせた。オスマン帝国を崩壊させ、中東における100年にわたる戦争とテロの基礎を築いた。大英帝国の崩壊を早め、ヒトラーの台頭、第二次世界大戦の破壊、ホロコーストの悲劇、そして核兵器の開発を招いた。ソビエト共産主義への道を開き、数十年にわたる世界規模の冷戦を引き起こした。その結果、ヨーロッパ人の一世代が壊滅し、ニヒルな哲学的遺産が残され、西欧諸国の社会に壊滅的な影響を及ぼした。そして、ほとんど誰もそれが起こることを予見していなかった1。
第一次世界大戦は、計画的というよりも、誤算と不手際から生じたものである。歴史家は長い間、この戦争で最も責任を負うのはどの戦闘員であるかを議論してきたが、「主要国がそれぞれ近視眼と無責任の限りを尽くした」ことに異論はないだろう2。ドイツはフランス、ロシア、イギリスによる包囲を恐れていたが、手荒な方法でそれぞれの国を脅迫し、ベルリンに対して前例のない同盟で団結するように促した。この同盟は、ドイツのオーストリア・ハンガリーへの依存を強め、最終的には南の隣国の行動の人質となるものであった。イギリスは、同盟によってドイツの軍事力と経済力の増大を抑えることができると考えていたが、ロンドンを硬直的な約束に縛り付けて、局地的な紛争の外交的解決を不可能にするようなことはしなかった。オーストリア・ハンガリーは、ナショナリズムによって帝国が内部から引き裂かれることを恐れ、バルカン半島での限定戦争がすぐにヨーロッパの大火災に発展する危険性に目をつぶっていた。ニコライ2世は、オーストリア・ハンガリーへの限定的な動員はロシアの友好国セルビアへの侵略を抑止できると考えていたが、参謀本部の戦争計画ではオーストリア・ハンガリーとドイツの両方への総動員を義務付けていることを知った。また、鉄道技術の普及は、それに対応して迅速に軍隊を動員しない国家は、軍事的に急速に敗北することがほぼ確実であることを意味した。その結果、ヘンリー・キッシンジャーが「政治的破滅装置」と呼んだ、さまざまな引き金を引く可能性のある不安定な要素が混在することになった(3)。
今日のワシントンでは、ロシアとの緊迫した関係がこのような問題を引き起こすと考える人はほとんどいない。今日のワシントンでは、緊迫した対ロ関係がこの種の問題を引き起こすと考える人はほとんどいない。むしろ、ロシアの脅威を理解し対応するための支配的なパラダイムは、「第二次世界大戦問題」なのである。ロシアに関するアメリカの社説や論説は、1938年にイギリスの首相ネヴィル・チェンバレンがヒトラーの領土的野心をなだめるために悲劇的な試みを行い、不運な「私たちの時代の平和」を達成したミュンヘンを貶める言及で溢れている。2016年の米大統領選で民主党のヒラリー・クリントン候補は、モスクワがウクライナのロシアの少数民族を保護しなければならないという主張は、ナチス・ドイツの「ポーランドとチェコスロバキアのドイツの少数民族を保護しなければならない」という主張と同じだと明確に警告した4。同様に、リンゼー・グラハム上院議員や他の多くの共和党議員はロシアのプーチン大統領をアドルフ・ヒトラー5と比較し、新聞のコラムニストたちは彼を「プーチラー」と呼ぶ6。プーチンは、ヒトラーのように、外交的妥協の要求を、自分が利用できる弱さの表れとみなしていると考えられている。ヒトラーのように、プーチンは拡張主義的な思惑を抱いており、それが強くなりすぎる前に今反撃することによってのみ抑制されると考えられている。
このような観点からロシアの脅威を見る人々にとって、最大の危険はクレムリンの攻撃的な意図であり、強さによって侵略を抑止することが必須である。戦争が起こるのは、それを始めた者が勝てると思っているからだ。従って、平和を維持するためには、侵略者のそのような考えを払拭することが重要である。情報アナリストにとって、これはロシアの戦争計画や兵器システムを研究し、差し迫った攻撃の兆候を探すことに重点を置くことにつながる。例えば、米国とNATOの軍事専門家は、ロシアが2017年に行った大規模な軍事演習「ザパド(「西」)」の準備を分析し、このイベントはベラルーシ占領またはバルト三国への侵攻の準備を隠す「ロシアのトロイの木馬」かもしれないと警告している7。米国情報機関の指導者たちは、西側民主主義を弱体化させ、「第二次世界大戦後の国際秩序」を破壊しようとするモスクワの欲望に警鐘を鳴らす9。ハリウッド俳優のモーガン・フリーマンは、ジェームズ・クラッパー前国家情報長官を含む委員会の後援を得て、ソーシャルメディアで拡散されたビデオの中で、ロシアとすでに「戦争状態にある」から反撃しなければ敗北すると厳かに警告を発している10。
政策立案者にとって、このような警告は、戦う意志と勝利する能力を示すことに焦点を合わせることにつながる。第二次世界大戦型の侵略に対処する上で、外交の果たす役割は小さい。グルジア、ウクライナ、シリア、そしてサイバースペアにおけるロシアの侵略に抵抗しなければ、さらなる侵略を招くだけである。一方、強さと決意は、侵略者に後退を促し、より容易な征服を求めて他の場所に目を向けさせる。トランプ政権の国家安全保障戦略は、このような幅広いコンセンサスをほぼ反映している。「経験上、ライバルが侵略を放棄したり見送ったりする意欲は、米国の強さと同盟の活力に対する認識によって決まる」。古代ローマの格言を借りれば、平和を望むなら、戦争をする用意があり、その意志があることを示さなければならない。
しかし、誰もがロシアを攻撃的と見ているわけではない。プーチン政権下のロシアは、NATOの東方拡大やロシアの内政を変えようとする米国の動きに対して防衛的な戦いをする弱体で衰退しつつある国であるとする考え方もあり、あまり一般的ではない。ニューヨーク大学名誉教授のスティーブン・コーエンは、「プーチンは主に反応的であった」と言う12。クリミアの併合やウクライナ東部での代理戦争など、ロシアの行動は「攻撃的ではなく防御的である。..正当な安全保障上の懸念が動機となっている」13。この学派の支持者は、20年ほど前にアメリカの冷戦封じ込め戦略の父であるジョージ・ケナンが、NATO拡張がもたらすであろう結果を引用することを常としている。「ロシアから悪い反応が返ってきて、 (NATO 拡大派は)私たちはいつもロシア人はこうだと言ってきたのに、これは間違っている、と言うだろう」。ロシアはナチス・ドイツではないし、プーチンはヒトラーに匹敵する存在ではない。これらのアナリストにとって、このような類推は分析的な光よりも感情的な熱を生み出すだけでなく、危険な政策対応につながる。
「防衛的ロシア」派の人々は、一国の敵対的行動が恐怖と脆弱性に根ざしている場合、ヒトラーのような脅威に対処するために不可欠な揺るぎない決意と軍事態勢は逆効果になると指摘している(15)。米国は2008年、旧ソ連のグルジア共和国でこの現象を経験した。米国は、ロシアが南方の隣国に攻撃的な意図を抱いていると確信し、米国の政策立案者はグルジアに対する軍事訓練を加速し、トビリシをNATO同盟に参加させることを公然と主張し、軍事行動に対する警告をモスクワに何度も発した。ロシアはグルジアのNATO 加盟を前にして警戒を強め、トビリシはアメリカの支援に勇気づけられてグルジアの離 散地域である南オセチアでの軍事行動を開始し、サイバー攻撃を含むロシアの大規模な軍事反応が即座に発生した 17。その結果、米国は容易に予測できた戦争を回避することができず、ホワイトハウスは、ロシアによるグルジアの分離地域の征服に無益な抗議をするか、ロシアの通常戦力の優位に対抗して核戦争の脅威を与えるか、という不味い選択を迫られた18。
モスクワが防衛策を講じていると考える人々にとって、望ましい政策対応は、主にヒポクラテス的・外交的なものである:脅威となる国家を脅すことによって害を与えることをやめ、妥協と紛争解決について話し始めることである。Cohen は、例えば、ヨーロッパに中距離ミサイルを再導入することやウクライナに武器を売却することに反対し、その代わりに、共有する脅威に対して協力し、関係を支配する新しいルールについて合意に達することを求めている19。ウクライナ、そしておそらくはロシアとNATOの間の「グレーゾーン」にある他の国々の目標は、「ウクライナの西部化計画を放棄し、代わりに冷戦時代のオーストリアのようなNATOとロシアの間の中立的な緩衝地帯にすることを目指す」べきだと述べている(20)。
このように、ロシアの行動を説明し、対処するための対照的な流儀は、いずれも完全に間違ってはいない。ロシアが、NATOの拡大と1990 年代のロシアの内政へのワシントンの関与に直面し、自らを守勢に立たされていると見ていることは疑いない。モスクワはアメリカの意図に深い憤り、誤解、不信を抱いており、過去25年の間にアメリカに対する見方はパートナーから敵対者に変わったが、その一因はアメリカが脅威と感じる行動をとったことにある。2016年の大統領選挙への干渉など、アメリカ人にはいわれのない攻撃と映るロシアの行動の少なくとも一部は、ロシア人には長年にわたる欧米のロシアとその近隣諸国への干渉に対する自然な反応として映るのである。
しかし、ロシアの行動は防衛的な動機だけによるものではない。ロシアは自らを、1990年代には運が悪かったとはいえ、正真正銘の大国であり、米国、欧州、中国とともに国際情勢において重要な役割を果たすべきであり、すべての大国がそうであると考えるように周辺諸国を支配すべきであると考えている。過去 20 年間にモスクワの政界で高まった対米憤懣の一端は、ワシントンがロシアを従属国として扱い、大国としての栄光を取り戻すのを邪魔してきたという考えからであった。ロシアは周辺諸国を支配したいという願望から、NATOへの加盟やアメリカの支援を求め、それがモスクワの不安を煽り、敵対心をエスカレートさせるというスパイラルに陥っている。このような攻撃的動機と防衛的動機の混在は、実はロシアの外交政策における古くからのテーマである。ヘンリー・キッシンジャー (Henry Kissinger)は、第一次世界大戦に至るまでの帝政ロシアの行動について、「一部は防御的、一部は攻撃的で、ロシアの拡張は常に曖昧であり、この曖昧さが、ソ連時代を通して続くロシアの意図を巡る西側の議論を生み出した」と述べている(22)。
さらに、ロシアは、1914 年のオスマン帝国や今日の中国とは異なり、衰退国とも新興国とも分類されないという事実が、この図式を曇らせている。ソ連は、第三世界の経済の上に立つ第一世界の軍隊であり、「核兵器を持ったボルタ川上流」と冗談交じりに表現された。ソ連の崩壊は、モスクワに有能な軍事力も経済も残さず、その後のロシアの出生率の急降下と死亡率の急上昇によって、西側諸国の多くは、この国が長期的に衰退と無関係の道を歩むことを確信した。しかし、プーチン時代初期から出生率や平均寿命が上昇し、2013年にはソ連時代以来の人口増加率を記録した23。2015年のシリア内戦への介入は、1979年のアフガン戦争以来のソ連国外への軍事力行使であり、ロシアの軍事改革が目覚ましく進展していることを示すものであった。
この回復が続くかどうかは未解決の問題である。ロシアは、汚職に悩まされ、エネルギー販売に大きく依存しているが、それでも、ノルウェーの雨期投資ファンドを手本にエネルギー収入を賢く管理し、世界の「ビジネスのしやすさ」ランキングで着実に上昇している(24) 経済の多様化と国際商業市場での競争に苦戦しているが、高度なサイバー機能と先端兵器を発達させている。ロシアは、中央集権的な政治的嗜好と、国民の創造性と革新性を解き放つ経済的必要性との間の緊張を克服することはできないかもしれない。しかし、その歴史、地理、資源、科学的才能から、ロシアは国際舞台において重要なプレーヤーであり続け、その経済的弱さからは想像できないほどのパンチ力を発揮することができるだろう。
本書のテーマは、ますます敵対化する米露関係における最大の危険は、米露双方の能力や意図によるものではない、ということである。むしろ、科学者が言うところの「複雑系の危険」である。冷戦後のヨーロッパの安全保障構造に関する未解決の問題が、対立に拍車をかけている。相手の意図に対する認識が大きく異なるため、それぞれが信じているシグナルが不明瞭になり、相手が出来事にどう反応するかについての誤った推測が強まっている。新しい、そしてまだ十分に理解されていないサイバーテクノロジーは、高度な戦略的兵器運搬システムの開発と相まって、防御側よりも攻撃側に大きな利点をもたらし、脆弱性の認識を強め、攻撃性を煽っている。世界の地政学的秩序の変化は、米国の優位性を脅かすと同時に、ロシアやその他の対抗勢力にその影響力を拡大する魅力的な機会を提供している。それぞれの国は、スポンサーと利害が一致する、しかし一致しない、信頼できない代理人をますます束縛するようになっている。そして、それぞれの国が、脆弱性を増大させ、効果的な外交政策の立案と実施を困難にする国内政治的課題に対処するのに苦慮している。一方、ワシントンとモスクワの間の冷戦競争を支配していた古いルールは枯渇し、新たな対立を抑制し安定させる新しい理解もそれに取って代わることはない。これらすべての要因は、ダイナミックな相互作用の悪循環の中で互いに補強し合っている。
良い点としては、ロシアはワシントンに対してあまり好感を持っていないが、アメリカの民主主義を破壊し、国際秩序を混乱に陥れようとはしていないことである。しかし、複数の要因が相互に作用し、補強しあい、あるいは減殺しあう「システム問題」は、単一要因の問題よりも解決がはるかに困難であるということである。ロシアとのさまざまな紛争は、個別の問題の集合体ではなく、経営の権威であるラッセル・アコフが「混乱」、すなわち「問題のシステム」と呼んだものである。つまり、問題が相互に影響し合っているということだ。「攻めのロシア」「守りのロシア」と呼ばれるように、ロシアを抑止すること、あるいは融和することに焦点を合わせても、問題は解決せず、さらに悪化する可能性がある。また、米露システムの構成要素は相互に関連しているため、事故や漸進的な行動が予期せぬ波及効果をもたらす可能性が高い。1914年のサラエボのように、小さな出来事がこの複雑な問題に波紋を投げかけ、大きな破滅的結果をもたらす可能性があるのだ。
本書は、米露関係が過去 10 年半の間に、いかにして新生パートナーシップから憂慮すべき敵対関係 へと転落したかを分析することを意図していない。本書の焦点はもっと狭い。米ロ関係が敵意から戦争へと不測の事態に陥りやすいことを示し、その災厄の可能性を減らすために何をすべきかを考察することである。
本書は、エベネーザ・スクルージが「まだ来ぬクリスマスの亡霊」に確認しようとしたように、「あるかもしれないこと」ではなく「なるであろうこと」を垣間見るための本ではない。予期される悪い結果が避けられるという確信がなければ、誰も死亡前調査の作成に着手しない。第一次世界大戦を引き起こした一連の出来事とは異なり、ロシアとの関係における危険の燃焼混合は、核戦争に必然的につながる政治的な終末装置となる必要はない。ワシントンとモスクワの間で進行しているシステムがもたらす危険を理解し、それが構成する個々の要素を検証することが、脅威を和らげるための重要な前提条件となる。
本書の第1部は、この脅威の分析に焦点を当てている。本書では、米ロ間の「邪悪な問題」の各要素を順番に取り上げ、その効果を増幅させ、予期せぬ結果をもたらす可能性のある相互作用を明らかにする27。第1章では、ロシアとの影の戦争が、サイバースパイ、サイバースペース、影響活動の分野でどのように展開されているかに焦点を当てている。第2章では、この戦争がどのようなものであるか、各国が相手の意図に対してどのような見解を持っているかを検証している。第3章では、失われつつあるゲームのルールと、危険なエスカレーション・スパイラルにブレーキをかけるメカニズムが存在しないことについて考察する。第4章では、予期せぬ米露危機の引き金として、経済戦争、軍事的駆け引き、代理戦争がどのような役割を果たすかを考察している。
本書の第2部では、脅威を打開する方法に焦点を当てる。第5章では、意図しないエスカレーションを引き起こす可能性のある失策を避けるために、ワシントンとモスクワが「システム・アプローチ」をどのように適用するかを検討することから始まる。第6章では、急激な破壊や新技術の影響を軽減するために、システムにショックアブソーバーを組み込む方法について考察している。第7章では、米国、ロシア、中国、その他の大国間の競争を管理し、私たちが直面するリスクを最小化するために、システムダイナミクスを有利に利用する方法について考察している。
本書は、ロシアの危機を予見する警告書であると同時に、軍事ではなく精神的な武装を求める書物である。第一次世界大戦に巻き込まれた主人公たちが、自分たちの行動がどのような結果をもたらすか、そして自分たちの手に負えないような悲惨な事態が発生することを理解していれば、間違いなく異なる決断を下したことであろう。今日、私たちは、意図しない結果を生む可能性を念頭に置きながら、ロシアの脅威に対して、ヨーロッパの指導者たちが振り返って見せたかったような慎重な姿勢で臨むべきであろう。
そのためには、ロシアと米国が互いに抱いているいくつかの一般的な観念を、より深く吟味する必要がある。ナチス・ドイツのようなレンズを通してロシアを見るアメリカ人は、ロシアの統治とその意図について誤解しがちであり、悲劇的な結果を招きかねない。同様に、ロシア人は、ロシアとその周辺地域における米国の民主化支援を、ロシア政府を包囲し、最終的には転覆させるための努力であると誤解してきた。両国ともこうした認識について深く考えようとせず、疑問を呈する者がすぐに弁解者のレッテルを貼られるため、認知の罠-ロシアの罠-が生じ、大惨事に気づかずにつまずく可能性を高めている。
冷戦後、長年にわたって協力関係を築く努力を怠ってきた米国とロシアが、パートナーではなく、競争相手となる時代に突入したことは明らかである。しかし、敵同士になる必要はない。米ソ両国の感情や国内政治的圧力が渦巻く中、ロシアへのアプローチは、譲歩や対立に傾くことなく、毅然とした態度と融和、軍事態勢と外交のバランスを冷静に取る必要がある。目の前に迫る危機の本質を見極められないことこそ、私たちが直面する最大の脅威ではないだろうか。このページでは、その危険の正体を明らかにするためのささやかな試みを紹介する。
技術者がビルや橋、ダムなどを設計するとき、過去の大災害を想定して設計するのが一般的である。失敗した場合の影響や予算に応じて、「100年に一度ストーム」あるいはそれ以上の事態に耐えられるように建設されることもある。今日、私たちは、500年に一度の暴風雨に相当するような異常気象が頻発する、発酵の進んだ世界に住んでいる。このような脅威が増大する一方で、技術の進歩により、災害がもたらす結果は実存的なものとなっている。米露関係を取り巻く複雑なシステムの中でレジリエンスを設計することは、その重要性が増しているにもかかわらず、急速に困難になってきている。
急速な変化と危機の高まりの中でよくある誘惑は、ウィリアム・F・バックリーの印象的な言葉を借りれば、「歴史の反対側に立って『止めろ!』と叫ぶ」ことを試みることである。しかし、歴史は妥協しない現状維持派に対して、繰り返し不親切な態度をとってきた。近代史を振り返ると、血生臭い三十年戦争、ナポレオンによる征服、第一次、第二次世界大戦など、世界の大国が百年に一度の極端な地政学的イベントを繰り返してきたことがよくわかる。そして、これらの出来事は、驚くほど規則正しくやってくる一方で、時間とともにその破壊力を増してきた。冷戦時代に米ソが幸運と好政策の組み合わせでこのような破壊を回避できたのは、歴史的に見ても異常なことである。冷戦後の複雑なシステムを設計しようとする者は、比較的最近の一連の幸運が長く続くという前提で設計を行わない方が賢明であろう。
第7章 システムの運用
ショックアブソーバーは悲観主義者かもしれないが、アメリカ人はそうではない。複雑なシステムの問題は、解決するのではなく、管理するしかないという考え方、失敗を想定した計画を立て、避けられない衝撃を和らげようとする考え方は、楽観的なアメリカ人の精神にはそぐわない。この国は、旧世界の紛争と世界に倦んだシニシズムを捨て去ろうという決意のもとに建国された。アレクシス・ド・トクヴィルが約 2 世紀前に述べたように、アメリカ人は「人間の完成可能性に対する生き生きとした信念を持ち。..社会を改善中の組織とみなしている」1。アメリカ人の精神は、ロシア問題に対して、危険を軽減し、失 敗を避け、被害を食い止める努力以外にできることがないという議論に対して、ほとんど本能的に反発を示 している。
邪悪な問題の特徴の一つは、問題を構成要素に分解して漸進的に解決しようとする努力が逆効果になることである。問題の一面に対処すると、他の面が悪化し、新たな困難の次元が追加されることが多い。米国とロシアは過去25年間、このような浅瀬に何度も陥った。一連の関係「リセット」を宣言し、自由主義改革やテロ対策、軍備管理といった特定の協力分野に焦点を当てて戦略的パートナーシップを構築しようとしたが、それぞれの意図とは裏腹に、状況は絶えず敵対にスパイラルしている。リセットに失敗するたびに関係修復の見込みが薄れ、その結果、双方は不確実な進展のために政治的リスクを冒すことに大きな抵抗感を抱くようになった。米国とロシアの国内事情は、この消極的な姿勢に拍車をかけている。米国の政治は現在、国内政治論争に巻き込まれ、モスクワとの関係改善を目指した目立ったイニシアティブをとることができない。プーチン大統領の任期満了が2024年に迫る中、クレムリンは安定した指導者交代の確保、予想されるアメリカの政治干渉への警戒、プーチンの対米弱腰を非難する民族主義・共産主義勢力の攻撃から身を守ることにますます重点を置くようになった。
良いニュースは、状況は暗いが、絶望的ではないということだ。ロシア問題を解決することはできないかもしれないが、私たちの利益を増進するためにシステムを働かせることは可能である。思慮のない行動が負のフィードバック・ループを引き起こし、意図しない有害な連鎖を引き起こすことがあるように、他の動きは逆に改善の好循環をもたらすことがある。システムにおいて、成功への道はしばしば直接的ではない。1980 年代初頭に米国がヨーロッパに配備したパーシング 2 ミサイルは、当時、ソ連の核の「首切り」に対する恐怖をあおり、戦争の危険を高めたと非難されたが、モスクワをINFの交渉のテーブルにつかせ、最終的に米ソ関係の改善につながる好循環を生み出すのに役立った。同様に、1975年のヘルシンキ最終法は、モスクワの東欧支配を強化する「戦後最大のデマ」とされたが、その条項は予想外に、人道的条件の改善、東欧におけるソ連の支配力の低下、東西関係改善のための共通参照事項として大きな役割を果たすことになった(3)。では、米ロが陥っているエスカレーション・サイクルから脱却するために、私たちはどのように新しい方向に踏み出すことができるだろうか。
従来とは異なる前進の道
米ロの力学を改善するための第一歩は、後方へ移動することである。1990年代初頭以来、米露両国の指導者は繰り返し、戦略的パートナーシップと共通の利益に対する協力が二国間関係の指針であると公言してきた。米国の一連の大統領は、双方が合意できることに焦点を当てる傾向があり、厄介な意見の相違は、将来、おそらく積極的な協力の機運が高まって相違に取り組みやすくなったとき、あるいはモスクワの指導者の交代によって打開策が可能になったときに、より適切なタイミングで取り組むことを好んだのであろう。このアプローチは失敗した。関係の悪化に歯止めをかけるには、双方が競争相手であることを率直に認め、その目標はパートナーシップを築くことではなく、競争を安全で相互に尊重できる範囲にとどめることだと宣言することである。また、わずかな合意点に注目するのではなく、多くの不一致点を列挙し、互いの対照的な認識を明らかにする必要がある4。
なぜ、このような後戻りが必要なのだろうか。その最大の長所は、現実を反映し、かつ両国の国内政治に共鳴していることである。米国とロシアは戦略的パートナーではないし、過去 20 年半に及ぶ相互の深い疑心暗鬼と苦い失望から、この目標を追求する意欲は両国ともあまり残ってはいない。この現実を認識することで、進展への期待は賢明なまでに低く抑えられる。相手の敵意に対する認識が歪んでいるとしても、それを変えるために奇抜な努力をする必要はない。また、過去の協力の努力を水泡に帰した難問の解決や、どちらの側も検討する立場にないような大盤振る舞いを進展の条件とすることもない。また、ロシアとの意見の相違を調整する政治的手段として経済制裁を採用する誘惑を減らすことができる。しかし同時に、不用意な衝突の危険性を考慮し、戦争を望まないことを明確にし、競争を安全かつ相互に受け入れ可能な範囲に収めるための議論の土台を築くことを、両者に強いることにもなる。
これに対し、ボトムアップ・アプローチを続けることは、私たちがまだどん底に達していないことを示し続けるだけである。ボトムアップ・アプローチでは、両政府の実務レベルの専門家が個別の問題を管理・解決するための具体的な手順を実行する必要があるが、現実には米露双方の官僚に協力や妥協への意欲はほとんどなく、相手に痛みを与えることを強く望んでいる。関係の戦略的枠組みに関する広範な合意がない限り、米露の影の戦争で最も活発で危険な2つの領域であるウクライナでの和解やサイバースペアでの停戦交渉に焦点を当てることは、失敗するだけでなく、むしろ関係改善の道を遠ざけることになるかもしれない。逆に、競争の境界線についての理解なしに、欧州における米国とNATOの抑止力の強化や情報戦におけるロシアとの戦いに焦点を当てることは、敵対関係のエスカレート・スパイラルにさらに燃料を注ぐことになるだけである。
視野を広げる
ステップ2は、ロシア以外の国に目を向けることである。システム思想家にとって、「科学者が問題の背景をより多く理解することができれば、真に適切な解決策を見出す可能性が高まる」(5)。構造的には、世界の勢力分布は、冷戦後、米国が同業者やそれに近い競争相手を持たなかった時代から、より多極化した配置に移行しつつある。軍事力、経済力、グローバルな力、地域的な力を一様に行使しながらも、米国の無制約なパワーに対する懸念の程度はさまざまであるロシア、インド、ブラジルなどの多くの第二級国家が主張し、協力を深めることによって補完され、米国のライバルとしてますます有能になっている中国の急速な台頭は、このダイナミクスの最大の要因である。日本と欧州連合は、第一級の経済力を持ちながら、より限定的な軍事力しか持たない米国の有力なパートナーであり、その軍事力は時間とともに拡大するかどうかもわからない。グローバル化とデジタル化によって先端技術へのアクセスが容易になるにつれて、第3層の地域プレーヤーや非国家主体も能力を高めてきた。しかし、相対的なパワーが低下しているとはいえ、米国はこの多極化したシステムの中で卓越したプレーヤーであり、比類のない軍事力を世界中に投射することができ、世界の経済革新の比類なきエンジンとして機能し、世界のすべての地域でパートナーや同盟国との独自のネットワークを維持している。米国は、中国が経済力を増しているにもかかわらず、国際金融システムを支配しているが、米国の管理体制には不満が高まっている。
国際システムにおけるパワーの配分が変化しているだけでなく、パワーそのものの性質も変化している。デジタル時代においても軍事力は重要な役割を担っているが、その能力は高度な情報技術やオートメーションの発展によってもたらされ、工業力や兵力から得られるものは少なくなってきている。人工知能の習得、地上と宇宙の通信ネットワークの防御、データの確保と活用が、世界の主要国とその周辺国との差をますます広げていくだろう。しかし、機械学習や人工知能の進歩は、国が出資する大規模な研究機関や巨額の資金投入に依存するものではない。数学的な才能を持つ少人数のグループが人工知能を大きく発展させ、国家や国際的な安全保障に不釣り合いな影響を与える可能性がある。また、気候変動は、世界中の国々にさまざまな影響を与えるだろう。これらの要因によって、国際的な地位は過去に比べてより流動的になっている。今日の新興国が、明日には昨日のこととなる可能性もある。
心理的にも、中国の台頭により米国の影響力が低下しているとの見方が世界中で強まっている。米国の軍事力や経済力が依然として強固であることを疑う人は少ないが、多くの人は米国がダイナミズムや目的意識を失い、グローバル・リーダーシップに対する意欲を失っているのではないかと疑っている。海外では勝ち目のない戦争に巻き込まれ、国内では社会的、政治的な機能不全に陥っていると多くの人が見ている。冷戦の終わりには、アメリカの思想が明らかに台頭し、自由市場、個人の自由、国民に選ばれた政府というそのモデルは、不可避的に世界に広がり、ますます繁栄と秩序をもたらすと広く信じられていた。しかし、もしアメリカの思想が企業の株式であるならば、今日、投資家はそれを空売りしていることだろう。アメリカのライバルたちは、そのパワーと影響力に対抗する決意を強めている。米国の価値観を共有する友人や同盟国も、米国がその軍事力や経済力を浪費し、反発を招いていることに頭を痛めている。
このような状況の変化に伴い、米国の目標も変化している。パックス・アメリカーナは、かつてそうであったとしても、もはや現実的な目標ではない。ヘゲモニーが存在せず、価値観や認識に大きなギャップがあり、複数の同業者やそれに近いプレーヤーが自らの好みを推し進めようと競争し、自らの特権を主張し、多くの要因がどの参加者の手にも負えないようなシステムを扱う場合の目標は、システム上の均衡であるに違いない。このような状況下で、秩序よりも優位性を目指しても、どちらも実現できない。しかし、その均衡はパワーバランスだけである必要はなく、むしろそうあるべきでもない。なぜなら、そのような狭い焦点では、システムに働く重要な道徳的・心理的要因に目をつぶってしまうからだ。権力と価値の両方を考慮しない理想的な均衡は、均衡ではないことが明らかになる。高い理想がもたらすインスピレーションは、災害への恐怖に劣らず、システムの進歩を促進する上で重要である。
焦点を広げることで、国際システムにおける米国の目標という大きな文脈の中で、問題を抱 えた米露関係を位置づけることができる。その際、米露の二国間関係は世界の力学に影響を与え、また影響を受けているという前提に立つ。では、新しい方向に一歩でも二歩でも踏み出せば、それが連鎖的に作用し、システムの仕組みが微妙に、しかし大きく改善され、中国の台頭とロシアの自己主張をうまく調整しながら、アメリカの中核的価値を高めるパワーバランスへの進展の可能性を高めるような形で認識を改め、どのように探せばいいのだろうか。
一つの可能性は、中央アジアにある。2001年にプーチンが中央アジアの米軍基地建設に協力したことは、米国との戦略的パートナーシップを求めるプーチンの重要な意思表示であった。しかし、タリバンを追放することに成功した後も、一時的な基地として長期的に存続させることを主張したため、プーチンはこのパートナーシップに幻滅するようになった。このことは、米国の意図と信頼性に対するロシアの認識を損ねることに、小さいながらも重要な役割を果たした。この地域における米軍の継続的な駐留は、ロシアと中国の協力関係の統一要因としても機能し、この地域における影響力をめぐる二国間競争の激化を、米国の活動に対する共通の懸念に置き換えることを促した。米国のアフガニスタンからの撤退は、地域のプレーヤーに過激派との戦いや秩序の維持により大きな責任を取らせるだけでなく、中央アジアの影響力をめぐるロシアと中国の対立を前面に押し出すことになるかもしれない。このことは、現在、モスクワと北京が米国に対して協調する方向に大きく傾いている米・露・中の三角関係を微妙に調整し始めることになるかもしれない。また、モスクワには中国の活力に対抗する経済力がなく、ソ連時代の中央アジア諸国との関係も薄れつつあることから、中央アジアにおけるオフショアバランサーとしてのワシントンの役割をロシアがあらためて認識するきっかけになるかもしれない。
もう一つのチャンスはヨーロッパにある。中国の力が強まり、ロシアの主張が強まる中で、欧州は国際的な均衡を確立し維持するためのシステム的なカウンターウェイトとして重要な役割を果たす必要がある。しかし、NATOやEUに亀裂が生じ、欧州の崩壊と大西洋の断絶が加速されるようでは、その役割を果たすことはできない。ロシアが欧州の安全保障の意思決定から締め出され、欧州大陸の分裂を悪化させ、亀裂を拡大させる動機となると、強力で健全な欧州がその均衡の役割を果たす可能性は低くなる。米国の欧州離脱の脅威も同様に有害で、NATOがロシアの侵略から自分たちを守る意思も能力もないのではないかという東欧・北欧諸国の不安を煽り、ドイツの覇権に対する古い恐怖を復活させることによって、欧州大陸の分裂を悪化させるものである。
しかし、一見したところ、欧州の不景気な傾向の中に、利益を得る可能性が潜んでいる。少し前までは、NATOもEUも自分たちを比喩的にサメのように考え、統一的な外的脅威がない中でその機能を維持するために拡張という前進を必要としていたが、そのような拡張はもはや必要とも望まれるものとも考えられなくなった。ロシアが西側の条件に従ってヨーロッパの諸機関に統合されるとか、かつては強大な軍事力を誇ったスウェーデンのような国に変身して、国民の生活水準を高め、ルールに基づく国際秩序をアメリカが管理することに満足するという幻想は、もはや消え去った。さらに、米国をはじめとするNATO加盟国が同盟を利用して遠征活動を行う意欲は、とっくに失せている。このような変化は、最近まで現実的でなかった新しいアプローチへの扉を開くものである。
NATOがその本来の目的である集団防衛に再び焦点を当てることで、いくつかの有利な効果が生まれるかもしれない。それは、ポーランド、バルト諸国、およびロシアの侵略を恐れる他のNATO加盟国に、同盟が自分たちの安全保障にコミットしていることを安心させ、そうすることで同盟内の緊張を緩和させることである。また、加盟国を防衛する決意を強調し、同盟内部の問題にロシアが関与することに断固とした態度を示す一方で、現在のNATOの国境を越えて加盟国を追加したり、域外での任務を遂行したりすることに消極的であることを示し、NATOの意図についてロシアにバランスのとれたメッセージを送るための確実な根拠となる。このようなシグナルに付随して、欧州とロシアは、NATOとロシアの間にある非同盟諸国の不安定性を抑制・管理し、どちらかを脅かすような同盟を求める動機を最小限に抑え、不用意に直接紛争に巻き込まれる可能性を低減するために取り組むことに関心を共有することになる。このようなシグナルは、これらの中間的な国家における相互作用の基本ルールに関する二国間および多国間の議論を促進する。これは、不安定で進行中のウクライナ紛争やモルドバおよびコーカサスにおける凍結された紛争を解決する上で必要な条件である。
さらに、国際社会の正当な行動を規定する原則をめぐる論争にも焦点を当てるべきである。モスクワは、米国がロシアやその他の国の内政に不法に干渉し、米国を攻撃していない国に対する武力行使を安保理が承認するという国連憲章の要件を故意に回避し、セルビアの領土保全を犠牲にしてコソボにおける国際国境の変更を不法に画策していると非難している。西側諸国は、ロシアがグルジアとウクライナの国境を武力で変更し、欧州と米国の内政に積極的に干渉し、国際軍備管理条約に違反し、野蛮な人権侵害を冷笑的に可能にしたとして非難している。ロシアは国家主権の尊重に基づくウェストファリア的秩序を謳い、西側は政府の虐待にさらされた市民を危険にさらす「保護する責任」を強調する。
西側諸国がロシアや他の非西側諸国と規範的な問題で共通点を見出そうという提案は、直ちにナイーブさを指摘することになる。これらの問題は、ヘルシンキ最終法やパリ憲章、国連憲章で明確に規定されており、議論の余地はない、と批評家は主張する。課題は、これらの原則を管理し、実施することであって、議論することではないと言うのである。しかし、現実には、これらの原則は再交渉の対象とすべきではないが、これらの基本文書に記録されている教義の間には常に固有の緊張関係が存在する。主権と領土保全は、絶対的な価値ではなく、相対的な価値である。人権を守り、民族の自決を認めることの重要性などと天秤にかけなければならない。また、サイバーテクノロジーと人工知能は、これらの対立する原則のバランスをとるという問題に新たな次元を追加した。その結果、これらの対立を解決するためには、継続的な議論とギブアンドテイク、そしてバランス、つまり外交的なプロセスが必要となる。このバランスを取るための明確で客観的な方法があるかのように装うこと、あるいは米国とNATOがこのバランスを取る唯一の決定者であるかのように装うことは、不誠実であるだけでなく危険なことである。ヘンリー・キッシンジャーは次のように述べている。
国際秩序が、平和のためとはいえ、ある種の原則を譲ることができないと認めているときはいつでも、力の均衡に基づく安定は少なくとも考え得るものであった。つまり、安定は平和の追求ではなく、一般に認められた正統性によってもたらされた。ここでいう「正統性」は、正義と混同してはならない。正統性とは、実行可能な取り決めの性質や、許容される外交政策の目的と方法に関する国際的な合意を意味するに過ぎない。少なくとも、ベルサイユ条約後のドイツのように、不満を革命的な外交政策で表現するような国家がない限り、すべての大国が国際秩序の枠組みを受け入れることを意味する。正当な秩序は、紛争を不可能にするものではないが、その範囲を限定するものである6。
医師よ、汝自身を癒せ
ステップ3は、自分の庭の雑草を手入れすることである。ロナルド・レーガンは、強者の立場から敵対勢力に対処することを提唱した。この強さとは、軍事的、経済的な問題だけでなく、自信や社会の活力といった無形の要素に由来するものである。マーシャル・プランの構想者の一人であるジョージ・F・ケナンは、第二次世界大戦後のソ連の挑戦を軍事的というよりも心理的なものとして捉え、それに対する彼の提言は主に政治的、心理的なものになる傾向があった。彼は1947年に「私たちの政策はヨーロッパとアジアにおける力の均衡を回復することに向けられなければならない」と書き、そのための最良の手段は「共産主義者が攻撃しているそれぞれの国の中で自然抵抗力を強化すること」であるとした。しかし、この自然な抵抗力は、「物理的な植物と精神的な活力の深遠な消耗」によって脅かされていた。被援助国自身が責任を持って計画し、実施する長期的な援助計画は、西ヨーロッパと日本の自信回復に大いに役立ち、ソ連の政治的、心理的圧力に対する抵抗力を強化すると彼は考えていた。1947年、彼は国立戦争大学の聴衆に、「私たちを脅かしているのはロシアの軍事力ではなく、ロシアの政治力であることを忘れてはならない」と語った。
アメリカ人は長い間、2つの大きな海という地理的な保護、豊富な天然資源の恵み、そして何世紀にもわたるイギリスの歴史の中で洗練されてきた一連の政治的習慣や信念から恩恵を受けてきた。多くの点で、私たちは世界が知る限り最も安全な大国である。しかし、過去20年の間に、アメリカは、世界をリードし、その価値観と統治システムを広めようとする自信に満ちた国から、社会の分裂と政治的機能不全に悩まされ、ロシアのソーシャルメディアによる荒らしがアメリカ社会の基盤を破壊するかもしれないと恐れる国へと変貌を遂げた。冷戦時代、ソ連の情報操作は絶え間なく続いたが、米国は通常、情報操作を国家の存亡にかかわる脅威というより、厄介な厄介事として捉え、ほとんどの場合、強さと自己肯定感をもって対処することができた。しかし、最近のアメリカは、内なる脆弱性を痛感するようになった。
この120年間、自己満足のモデルであった政治体制が自信を失い始めている。エリートたちの自尊心の低下は、米国の民主主義が外部からの干渉に対して脆弱であるという考えや、選ばれた大統領と彼に忠実な人々が外国と共謀したのではないかという不治の疑念を戸惑いながらも受け入れていることに表れている。米国ではほとんど知られていないRTやスプートニクというメディアによるロシアのプロパガンダが、米国民の意識を揺さぶりかねないという不安感が支配的なのは、米国の有権者に対する自信のなさを裏付けている7。
この自信のなさは、ロシアの脅威に対するアメリカの認識を歪め、エスカレート・スパイラルの危険を増大させる重要な役割を担っている。米国の内部問題を対露認識に投影することは、実は欧米の長年の傾向である。歴史家のマーティン・マリアは、数世紀にわたる米国とヨーロッパのロシア観に関する古典的な研究の中で、「ロシアが西洋の意見によって悪魔化または神格化されたのは、ロシアの実際の役割というよりも、ヨーロッパ社会で自らの国内問題によって生じた恐怖や不満、あるいは希望や願望が理由である」と述べている8。
このような自責の念の高まりに対処することは、容易なことではない。2016年の選挙のはるか以前からアメリカを悩ませてきた経済的不平等、政治的党派性、社会の分断といった問題に取り組むことが必要である。そして、その背景には不穏な問いが立ちはだかっている。アメリカの根強い政治的伝統である制約された政府は、欧米だけでなく、ますます世界中で、原子化され不満に満ちた社会の中で制度的権威を失うことによってもたらされる新たな挑戦に対応できるのだろうか。20世紀、米国は専制政治の脅威から自由を守った。21世紀には、機能不全のガバナンスの脅威に対して、自由と秩序の両方を維持することができるのだろうか。
結論
諜報活動の第一の使命は、危険が近づいていることを警告することである。しかし、この場合、嵐の到来を見極めるのは容易ではないし、伝えるのも簡単ではない。影の戦争が深まっているとはいえ、私たちがロシアから直面している最大の脅威は、戦場やサイバースペアにはない。それは、私たちの問題意識の中にある。
20世紀、米国は専制的な政府がもたらす脅威から自由を守ってきた。第二次世界大戦では、米国の軍事力がファシスト政権による世界の主要産業地域の征服を阻止し、米国の核戦力とイデオロギーの力が、冷戦時代に私たちの自由と繁栄を守った西側とソ連圏の間の「長い平和」の確立と維持に役立った。歴史を振り返ると、現在のロシアとの闘いを、自由民主主義と攻撃的な権威主義との戦いとして、同様のプリズムで捉えたい誘惑に駆られる。しかし、そのような見方は、私たちが今日直面している課題の本質を歪めてしまう。
1970年代、80年代、90年代に情報アナリストとして活躍し 2004年に中央情報局長官代理に就任したジョン・マクラフーリンは、長年にわたってオフィスに「Subvert the Dominant Paradigm」というプラカードを掲示していた。口先だけの言葉だが、その裏には重大な目的があった。パラダイムとは、私たちが意識的にせよ無意識的にせよ、事象を理解し、関連性のある情報とない情報とを区別するために用いる概念的な枠組みである。パラダイムは私たちの期待を形成するのに役立ち、その期待は私たちが何を探し、何を認識するのかを規定することになる。日本が真珠湾を攻撃するという証拠は、1941年12月7日以前から見ることができた。しかし、私たちの期待が、その証拠の重要性を認識することを妨げていた。パラダイムを正しく理解することは、情報の不意打ちを回避し、政策の失敗を回避するための重要な前提条件である。
本書は、ロシアに関するアメリカの支配的なパラダイムを覆すことを試みた。このパラダイムはロシアの脅威を直線的な問題として扱い、その根底にはプーチニズムの本質に由来する自由民主主義への侵略があるとするものである。前出の各章は、この定式が完全に間違っているのではなく、不完全であり、ロシアの行動の原動力を誤解しており、また、私たちが直面している主要な危険は本質的に抑止力の問題であり、むしろ、私たち自身の行動とロシアの行動が、それを抑えるどころか助長しているという誤った前提に基づいている、と論じている。本書は、この病気に対する別の診断を下し、現在のアメリカの政策が行っているものとはかなり異なる処方箋を提示す。本書は、民主主義を破壊しようとするロシアの意図をあまりにも恐れすぎているが、システム上のさまざまな要因が組み合わさって、私たちが予期しない災害を引き起こす可能性については、十分に警戒していない、と論じている。第一次世界大戦のような悲劇を引き起こすためのピースはすべて揃っているのだが、それを予想する人はほとんどいない。
私たちの支配的なパラダイムは、政治、官僚、メディア、産業、そして心理に深く根ざしていなければ、実際には支配的ではなく、また、これほど長い間挑戦されずにいたこともないだろう。程度の差こそあれ、これらのプレーヤーはそれぞれ、その擁護と永続に利害関係をもっている。このパラダイムに疑問を呈する人々が、謝罪者、宥和者、あるいはそれ以上のレッテルを貼られる速さは、その強さを示す一つの指標である。マクラフーリンのプラカードにもかかわらず、支配的なパラダイムを覆すことは、一般に、ワシントンでのプロフェッショナルな成功への道とはならない。今日のロシアの場合、特に危険を冒してでも従来の常識に挑戦しなければならない。
しかし、ロシア問題の危険性は非常に大きくなっており、支配的なパラダイムを覆すことは、私たちが生き残るために必要なことかもしれない。科学では、パラダイムは、予測した結果が実現しなかったり、実現した重要な進展を見逃したりすると、支持されなくなる傾向がある。しかし、ロシアの場合、自然の成り行きに任せて、支配的なパラダイムの有効性が時間の経過とともに証明または反証されることを信じている余裕はない。問題があることを発見するのは、その問題に対処するのに十分なタイミングでなければならない。手遅れになる前に災いを避けるには、ロシアがもたらす危険に対する私たちの一般的な概念に挑戦することが重要である。
したがって、この本の破壊的な目的は、政治的なものでも学術的なものでもない。それは、インテリジェンスの最も重要な使命である「警告」という崇高な目的を果たすためのものである。警告を発するにあたって、情報分析官は次の3つの重要な質問に取り組むよう教えられる。事態の進展はどのくらいで起こるのか?被害はどの程度になるか?脅威が現実化する可能性はどの程度か?これらの質問に答えることで、意思決定者は問題のトリアージに必要な情報を手に入れることができる。被害が大きく可能性も高いが、すぐには起こらないような脅威は、政策立案者がより緊急性の高い問題に対処する際に、二次的な優先順位に追いやられてしまうかもしれない。可能性が低く、影響が大きい事象は、その内容によっては、意思決定者の注意を全く引かないかもしれない。しかし、米露の敵対関係の激化が今日もたらす脅威の性質は、緊急性が高く、破滅的な可能性があり、不穏な可能性がある。3つの重要な警告の背後にあるインジケータ・ライトは、すべて真っ赤に点滅している。
警告は行動を喚起するものである。問題を認識することは、ほとんどの場合、その問題を管理し解決するための前提条件である。恐怖は強力な動機になり得る。選挙運動の専門家は、有権者の恐怖心を利用することが投票率を上げる最良の方法の一つであることを昔から知っている。冷戦が何度か危機を迎えたにもかかわらず、冷戦のままであった理由の一つは、冷戦が熱くなった場合、ほぼ確実に破滅的な結果を招くという認識が、それぞれの側にあったからだ。1960年代初頭のキューバ・ミサイル危機は、そのような恐怖心を煽る役割を担っていた。核のハルマゲドンの深淵を見つめることで、最終的には様々な安定化策と信頼醸成策が生まれ、災害の可能性を減らし、米ソ関係の改善が進むような安全な枠組みを提供することができた。
今日、米ロの核による破滅への恐怖はほとんどなくなり、代わりに相手の侵略を罰するのに十分なことをしていないのではないかという心配が起こっている。しかし、キューバ・ミサイル危機の新たなバリエーションに頼って、私たちを冷静にさせることはできない。現代のアメリカやロシアの指導者が、このような危機をうまく処理できるかどうかは疑問である。メディアの役割は、外交的駆け引きの余地を大きく狭め、意思決定のタイムスケールを短縮し、指導者が尊厳を保ったまま妥協できるような私的了解の可能性を低下させる方向に変化している。外交におけるステーツマンシップは、国内政治的効果のための大見得を切るようになった。それぞれの国が「エスカレートからデエスカレートへ」のドクトリンに翻弄されている。そして、1962年の災難を回避するのに重要な役割を果たした、昔ながらの運が今後も続くとは思えない。そこで本書は、何十年も前にこの危機が果たしたのと同じ、冷静な役割を果たそうとするものである。しかし、本書は基本的に楽観主義的である。それは、「行動を喚起する暗いビジョン」2が、米露双方に、目の前に迫る危険を反省させ、来るべき米露の競争が安全な範囲に収まることを期待するものである。
歴史家のバーバラ・タックマン (Barbara Tuchman)は、第一次世界大戦への悲劇的な突入を描いた古典的研究書『八月の銃』を要約して、「諸国は罠にかかった。..そこから出口がなく、これまでもなかった罠だ」と書いている。1914年にヨーロッパの列強が知らず知らずのうちに陥った罠の危険性とは異なり、ロシアの罠の危険性は必然性からはほど遠いものである。米国とロシアが現在陥っているエスカレート・スパイラルの芽を摘むことは十分に可能である。その危険性に目を向けることが、脱出への第一歩である。
謝辞
本書の構想、調査、執筆、推敲に協力し、感情の起伏が激しい中で私を支えてくれた人々のリストを集めると、身が引き締まる思いがする。トーマス・ダン・ブックスに私を推薦してくれたエリック・ハセルティンと、初めての著者にチャンスを与えてくれた編集者のスティーブン・S・パワーに特に感謝する。また、マーク・エピスコポスには例外的かつ広範囲な支援をいただいた。ダニエル・ハンソンとブレイク・レイサムは調査を手伝ってくれ、私の草稿が進むにつれ、正気を保つためのチェック役を務めてくれた。Graham Allison, Milt Bearden, Chuck Boyd, Richard Burt, Susan Eisenhower, James Ellis, John Evans, Jim Goodby, Greg Govan, Tom Graham, Chip Gregson, Jacob Heilbrunn, Martin Hellman, Steedman Hinckley, David Holloway, Edward Ifft, Raymond Jeanloz, Sabira Jumanalievaにお世話になった。Bob Legvold, ANATOl Lievan, Dave Majumdar, Wayne Merry, Keith Mosser, Roger Nebel, Steve Pifer, Paul Saunders, Robert Spaulding, Jim Timbie, and Bruce Turnerには、貴重なアイデア、洞察に満ちたレビュー、確固たる奨励、進化する原稿への率直な批評を頂いた。
彼らは、従来の常識に対して賢明な挑戦を行うことの重要性を原理的に理解しているだけでなく、その競争に参加する人々を保護するという本質的な副次的なことを実際に示している。何よりも、妻のサラ・ミラー・ビーブの計り知れない貢献に感謝している。彼女の勇気は私を鼓舞し、彼女の洞察力は私を驚かせ、彼女の愛は私を支えてくれた。この本の知的基盤は、私たち夫婦の共同作業によるものである。もちろん、最終的な成果物の誤りや欠点については、私一人の責任であることは言うまでもない。
著者について
ジョージ・S・ビーブ (GEORGE S. BEEBE CIAのロシア分析部長、ディック・チェイニー副大統領のロシア問題担当ホワイトハウス顧問など、25年近く米国政府で勤務。現在、バージニア州北部に在住。ジョージ・ビービーの講演予約に関するお問い合わせは、リー・ビューロー(info@leighbureau.com)までお願いする。最新情報のメール配信はこちらから登録いただける。