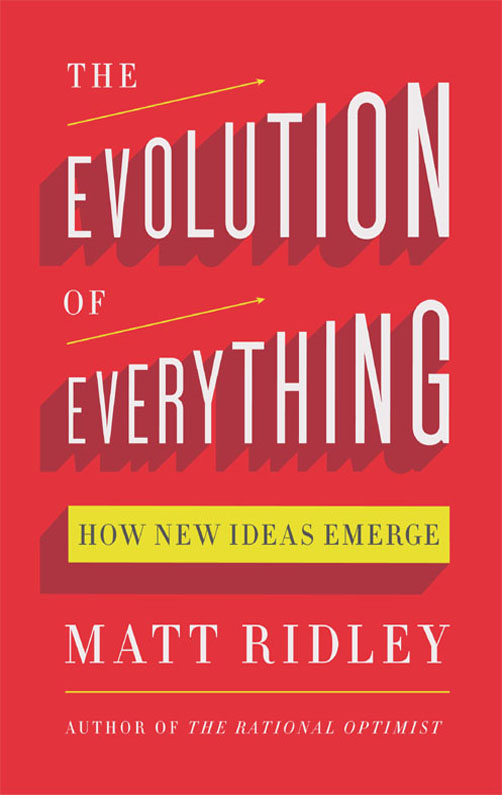
The Evolution of Everything: How New Ideas Emerge
目次
- プロローグ進化の一般理論
- 1 宇宙の進化
- 2 道徳の進化
- 3 生命の進化
- 4 遺伝子の進化
- 5 文化の進化
- 6 経済の進化
- 7 技術の進化
- 8 精神の進化
- 9 人格の進化
- 10 教育の進化
- 11 人口の進化
- 12 リーダーシップの進化
- 13 政府の進化
- 14 宗教の進化
- 15 マネーの進化
- 16 インターネットの進化
- エピローグ未来の進化
- 謝辞
- 出典と参考文献
- 索引
- マット・リドリー著
- クレジット
- 著作権
- 出版社について
プロローグ
進化の一般理論
「進化」という言葉はもともと「展開」を意味する。進化とは物語であり、物事がどのように変化するかについての物語である。この言葉には他にも多くの意味があり、特定の種類の変化について語られている。何かから何かが生まれることを意味する。突然の革命とは正反対の、漸進的で緩やかな変化を意味するようになった。それは自然発生的であると同時に、どうしようもないものでもある。単純な始まりからの累積的な変化を示唆している。それは、外から指示されるのではなく、内面からもたらされる変化を意味する。また、通常はゴールのない変化を意味するが、行き着く先は自由である。そしてもちろん、自然淘汰というメカニズムを通して、生物における世代を重ねるごとに変化する遺伝的な子孫という、非常に具体的な意味を持っている。
本書は、進化は私たちの身の回りで起こっていると主張する。それは、自然界と同様に人間界がどのように変化するかを理解する最良の方法である。人間の制度、人工物、習慣における変化は、漸進的であり、不可避であり、避けられない。ある段階から次の段階へと、物語に沿って進んでいく。ジャンプするのではなく、忍び足で進んでいく。外部から駆り立てられるのではなく、自然発生的な勢いがある。例えば、電灯である。1712年、トーマス・ニューコメンという無名の技術者が、熱を仕事に変える最初の実用的な方法を発見したとき、彼の発明の背後にある基本原理(水を沸騰させると膨張して蒸気が発生する)が、無数の小さなステップを経て、やがて電気を発生させて人工の明かりを灯す機械になるとは思いもよらなかっただろう。白熱灯から蛍光灯へ、そしてLEDへと、その変化は今も続いている。一連の出来事は進化的であり、現在も進化し続けている。
私が主張したいのは、こうしたあらゆる意味において、進化は多くの人が認識しているよりもはるかに一般的で、はるかに大きな影響力を持っているということだ。進化は遺伝子システムに限定されるものではなく、道徳からテクノロジー、貨幣から宗教に至るまで、事実上すべての人間文化の変化を説明するものである。このような人間文化の流れは、漸進的、段階的、非指示的、創発的であり、競合する考え方の中から自然淘汰される。人々は、意図しない変化の加害者であるよりも、犠牲者であることの方が多い。そして、文化的進化にはゴールがないにもかかわらず、問題に対する機能的で独創的な解決策を生み出す。動物や植物の形態や行動の場合、意図的な設計を仮定しない限り、この明らかな目的意識を説明することは難しい。目が見えるように設計されていないはずがない。同じように、私たちは人間の文化が人間の問題を解決するためにうまく適応しているのを見つけると、それは誰か賢い人がその目的を念頭に置いて設計したからだと思いがちである。だから私たちは、適切な瞬間に近くに立っている賢い人物を過大評価しがちなのだ。
それゆえ、人類史の教え方は誤解を招きかねない。というのも、デザインや方向性、計画に重きを置きすぎていて、進化にはあまり重きを置いていないからだ。こうして、将軍は戦いに勝ち、政治家は国を動かし、科学者は真実を発見し、芸術家はジャンルを創造し、発明家はブレイクスルー発明をし、教師は心を形成し、哲学者は心を変え、司祭は道徳を教え、実業家は事業を指揮し、陰謀家は危機を引き起こし、神々は道徳を作るように思われる。個人だけでなく、組織もそうだ: ゴールドマン・サックス、共産党、カトリック教会、アルカイダ……これらが世界を形成すると言われている。
私はそう教えられてきた。私は今、それが正しいというよりも間違っていることの方が多いと思う。もちろん個人でも変化をもたらすことはできるし、政党や大企業でも同じだ。リーダーシップは今でも重要だ。しかし、世界に関する支配的な神話、私たち全員が犯している大きな間違い、盲点があるとすれば、それは私たち全員が、世界は実際よりもずっと計画的な場所だと思い込んでいることだ。その結果、私たちは何度も何度も原因と結果を取り違えてしまう。風を起こした帆船を責めたり、出来事を起こした傍観者を信用したりするのだ。戦いに勝ったのだから、将軍が勝ったに違いない(敵軍を衰弱させたマラリアの流行ではない)。子どもが学んだのだから、教師が教えたに違いない(教師が見つけた本や仲間や好奇心ではない); ある種が救われたので、自然保護主義者がそれを救ったに違いない(人口を養うのに必要な土地の量を削減した肥料の発明ではない)。ある発明がなされたので、発明家がそれを発明したに違いない(次の技術的ステップのどうしようもない必然的な熟成ではない)。私たちは、あたかも人や組織が常に主導権を握っているかのように世界を描写するが、多くの場合、そうではない。ナシーム・タレブが著書『反脆弱性』の中で述べているように、複雑な世界では「原因」という概念そのものが疑わしい。
タレブは、ソ連・ハーバード幻想と揶揄するものを残酷なまでに否定している。彼は、鳥に飛行の講義をし、その講義が鳥の飛行技術の原因だと考えるようなものだと定義している。アダム・スミスは、「チェス盤の上に駒を並べるのと同じように、大きな社会のさまざまな構成員を簡単に並べることができる」と想像しているが、人間社会という大きなチェス盤の上では、駒はそれ自身の動きを持っていることを考慮しない。
エイブラハム・リンカーンの造語を使うなら、私はこの本を読み進めるうちに、人間の意図性、設計、計画への執着から徐々に「解き放たれる」ことを望んでいる。チャールズ・ダーウィンが生物学に対して行なったことを、私は人間世界のあらゆる側面に対して少しずつ行ない、デザインという幻想を超えて、その根底にある創発的で、無計画で、どうしようもなく美しい変化のプロセスを見てもらいたいのだ。
私はしばしば、人間は自分自身の世界を説明するのが驚くほど下手だと気づく。アルファ・ケンタウリから人類学者がやってきて、鋭い質問を投げかけたとしても、ろくな答えは返ってこないだろう。なぜ世界中で殺人率が下がっているのか?犯罪学者の意見は一致しない。なぜ世界の平均所得は19世紀の10倍以上なのか?経済史家の意見は分かれている。なぜ一部のアフリカ人が20万年前に累積技術と文明を発明し始めたのか?人類学者にもわからない。世界経済はどのように機能しているのか?経済学者は説明するふりをするが、実際には詳しく説明することはできない。
これらの現象は、1767年にアダム・ファーガソンというスコットランドの陸軍牧師によって初めて定義された奇妙なカテゴリーに属する。それらは人間の行為の結果であるが、人間の設計によるものではない。それらは、言葉の本来の意味での進化現象であり、それらは展開する。そして、このような進化現象はどこにでもあり、あらゆるものの中にある。しかし、私たちはこのカテゴリーを認識していない。私たちの言語と思考は、世界を2種類のもの、つまり人間が設計し、作ったものと、秩序も機能もない自然現象に分けている。経済学者のラス・ロバーツはかつて、このような現象を包括する言葉がないと指摘した。にわか雨に濡れないようにする傘は、人間の行為の結果であり、人間のデザインの結果でもある。しかし、地元の商店があなたに傘を売るためのシステムや、傘という言葉そのもの、あるいは他の歩行者を通すために傘を片側に傾けることを要求するエチケットについてはどうだろう?市場、言語、習慣など、これらは人間が作り出したものだ。しかし、どれも人間がデザインしたものではない。すべて無計画に生まれたものなのだ。
私たちはこの考え方を、自然界の理解にも反映させている。自然界では、創発的な進化ではなく、意図的なデザインが見られる。ゲノムに階層性を求め、脳に「自己」を求め、心に自由意志を求める。私たちは、異常気象を人間のせいにする口実があれば、魔女の手先であろうと、人為的な地球温暖化であろうと、それにすがる。
私たちが認めたがっている以上に、世界は驚くべきことに自己組織化し、自己変化する場所なのだ。パターンが生まれ、トレンドが進化する。雁の骨組みは意味もなく空にV字を描き、シロアリは建築家なしで大聖堂を建て、ミツバチは指示なしに六角形の蜜蜂の巣を作り、脳は脳を作る人なしで形作られ、学習は教えることなく起こり、政治的な出来事は歴史によって形作られるのではなく、むしろその逆である。ゲノムにはマスター遺伝子がなく、脳には司令塔がなく、英語にはディレクターがなく、経済には最高責任者がなく、社会には大統領がなく、慣習法には最高判事がなく、気候にはコントロールノブがなく、歴史には5つ星の将軍がいない。
社会では、人々は犠牲者であり、変化の直接的な主体でさえある。しかし、多くの場合、その原因は別のところにある。これらの不可抗力の中で最も強力なものは、自然淘汰による生物学的進化そのものであるが、進化的で無計画な変化の、より単純な形態は他にもある。実際、イノベーションの理論家であるリチャード・ウェッブの言葉を借りれば、ダーウィニズムは「特別な進化論」である。それは社会、貨幣、技術、言語、法律、文化、音楽、暴力、歴史、教育、政治、神、道徳に当てはまる。一般的な理論では、物事は同じままではなく、徐々に、しかし不可避的に変化し、「経路依存性」を示し、変化を伴う下降を示し、試行錯誤を示し、選択的持続性を示すという。そして人間は、この内生的な変化のプロセスを、あたかも上から指示されたかのように、自分の手柄としている。
この真実は、右派だけでなく左派の知識人の多くにも理解されず、事実上「創造論者」のままである。右派の人々がチャールズ・ダーウィンの洞察(自然の複雑さは設計者を意味しない)に抵抗する強迫観念は、左派の人々がアダム・スミスの洞察(社会の複雑さは計画者を意味しない)に抵抗する強迫観念と一致している。この後のページで、私はこの創造論をあらゆる形で取り上げることにする。
11. 人口の進化
遅かれ早かれ、あなた方は私から離れようとするだろう、
破滅論者の予言者たちに心を奪われる。彼らは確かにそうだ、
人生の秩序を揺るがすほどの悪夢を思い起こさせる。
人生の秩序を転覆させ、不安で運命を狂わせるに十分な悪夢を、あなたのために思い起こさせることができる。
ルクレティウス『自然の摂理』第1巻102-5行
200年以上もの間、人間の人口をめぐっては、生物学に基づき、ほとんど想像を絶する規模の残酷さを正当化するという、不穏で悪質な糸が西洋史を貫いてきた。本書のリサーチを始めた頃、私はマルサス理論、優生学、ナチスによる大量虐殺、そして現代の人口管理を、人類史における別個のエピソードとして考えていた。しかし、もはやそうではない。貧民法、アイルランドの飢饉、アウシュビッツのガス室、北京の一人っ子政策が、蛇行しながらも直接的な知的糸で結ばれていることを示す、説得力のある証拠があると思う。いずれの場合も、誤った論理に基づいた政策としての残酷さは、権力者が弱者にとって何が良いかを最もよく知っているという信念から生まれた。緊急の目的は恐ろしい手段を正当化した。進化論は、創発的なプロセスの説明ではなく、干渉の処方箋とされた。
牧師ロバート・マルサス(最近はトーマスと呼ばれることが多いが、存命中はミドルネームのロバートを使っていた)は、過去2世紀に長い影を落としている。裕福なイギリスの数学者、教師、聖職者であり、優れた文筆家でもあった彼は、今日、1798年に初版が出版され、その後何度も改訂された『人口論』というたったひとつの短い文書で知られている。人口増加には限界があり、土地、食糧、燃料、水が枯渇すれば、悲惨、飢餓、病気に至るに違いない。バース修道院にある墓碑銘によれば、彼は「その気性の優しさ、都会的なマナー、心の優しさ、博愛と信心深さ」で知られていた。彼は明らかに意地悪な人間ではなかったし、人口過剰に対する彼の主な解決策である晩婚化も残酷なものではなかった。しかし、晩婚化を教えられないのであれば、残酷な政策が人口増加に歯止めをかけるのに効果的であると考えていたのは確かである。
残念なことに、この残酷な教訓は、多くの人々がマルサスから受け継いだものである。つまり、親切な目的を正当化するためには、不親切な手段を使わなければならないということだ。貧しい人々や病気の人々に親切にすることは悪い考えであるというこの図式は、優生思想や人口運動を貫いており、現在でも健在である。今日、私がアフリカにおける子どもの死亡率の低下について書いたり話したりすると、まさにマルサス的な反応が返ってくるだろう。アフリカに経済成長をもたらして何になる。親切であるためには残酷であるほうがいい。これをマルサス的人間嫌いと呼ぼう。そしてそれは180度間違っている。人口増加を減速させる方法は、赤ん坊を生かし続け、すべての人に健康と繁栄と教育をもたらすことだと判明した。
マルサスの提言を残酷だと考える人は、マルサス存命中もその後も大勢いた。フリードリヒ・エンゲルスはマルサス主義を「卑劣で悪名高い教義」と呼んだ。ピエール=ジョゼフ・プルードンは、マルサス論を「政治的殺人の理論、博愛と神への愛の動機による殺人」と呼んだ。
理論のアイルランドへの適用
しかし、マルサスの学説は、19世紀には政策に直接的かつ頻繁に影響を与えた。1834年に制定されたイギリスの新貧困法は、非常に貧しい人々は労働者収容所以外では救済されず、労働者収容所の環境は外界の最悪の状況よりも改善されないことを保証しようとするものであったが、これはマルサスの考え、すなわち、行き過ぎた慈善は繁殖、特に非嫡出子、すなわち「私生児」を助長するだけであるという考えに基づいていることが明白であった。1840年代のアイルランドのジャガイモ飢饉は、権力の座にあったイギリスの政治家たちが共有したマルサス的偏見によって、限りなく悪化した。ある伝記作家によれば、首相のジョン・ラッセル卿は「救済の長期的効果に対するマルサス的恐怖」に突き動かされていた。アイルランド宰相のクラレンドン卿は、「単に人々を生かすために食料を配ることは、誰のためにもならない」と考えていた(食料を受け取る側ですら?) 財務次官補チャールズ・トレヴェリアンは、東インド会社カレッジでマルサスの教え子だった。彼は、飢饉は「余剰人口を減らすための効果的なメカニズム」であり、「利己的で、陋劣で、乱暴な」アイルランド人に教訓を与えるために遣わされた「賢明で慈悲深い摂理の直接の一撃」であると考えていた。マルサス的な人間嫌いと、究極の天罰であるプロビデンスの呼びかけに注目してほしい。トレヴェランはさらに、「至高の叡智は、一過性の悪から恒久的な善を教育した」と付け加えた。我々はパングロス博士とリスボン地震に戻ってきた:大量死は良いことである。要するに、100万人のアイルランド人が餓死したのは、少なくとも生態学的な不運と同じくらい、マルサス的な政策による意図的な行為の結果だったのだ。
私のように、イギリス帝国主義を、他の形態の習慣に比べれば一般的に良性のものだと考えて育った者にとっては、話はさらに悪くなる。ロバート・ズブリンが著書『Merchants of Despair(絶望の商人)』で語っているように、1877年、ロバート・ブルワー=リットンというアヘン中毒の夢見がちなボヘミアン詩人が、友人のベンジャミン・ディズレーリ首相によってインドに派遣され、インド総督を務めていた。ブルワー=リットンは、高貴な生まれのヒッピーのように聞こえるかもしれないが、残念ながら彼はマルサス主義者だった。干ばつに見舞われた国もあった。しかし、税金とルピーの切り下げにより、飢えた人々は救済を受けることができなかった。ブルワー=リットンは、マルサスからほぼ直接引用して反論した: インドの人口は、土壌から得られる食糧よりも急速に増加する傾向がある」彼の政策は、飢えた人々を収容所に集め、そこで文字通り飢餓糧食(ナチスの強制収容所で配給されるものより一人当たりのカロリーがわずかに少ない)を与えるというもので、その結果、毎月94%が死亡した。ブルワー・リットンは、飢餓に苦しむ人々に救いの手を差し伸べようとするいくつかの民間の試みを特に中止させた。マルサス的な目的は過酷な手段を正当化するからだ。最大で1000万人が死亡した。
マルサスの歴史への影響は悪いことばかりではなかった。彼はチャールズ・ダーウィンとアルフレッド・ウォレスに多大な影響を与えた。しかし、最も穏やかで慈悲深いダーウィンでさえ、彼の愛する自然淘汰は記述ではなく処方箋であるべきだという考えに、少なくとも一時は誘惑された。『人間下降論』のマルサス的な一節で、彼は「無能な者、手足の不自由な者、病人」は精神病院や医者によって救われ、弱い者は予防接種によって生かされていると述べている。こうして、文明化された種族の弱い者は、その種族を繁殖させるのである。彼はさらに、「非常に貧しく無謀な者は、しばしば悪徳によって品位を落とすが、ほとんど必ず早く結婚し、慎重で質素な者は、そうでなければ一般的に徳が高いが、人生の後半に結婚する」という事実を嘆いている。この一節は、ダーウィンが若い頃に吸収したマルサスの教義を明確に反映している。
結婚の国有化
このヒントは、ダーウィンの信奉者たち、特に従兄弟のフランシス・ガルトンやドイツ人翻訳者のエルンスト・ヘッケルによって熱狂的に受け入れられた。ガルトンは、人々が結婚相手をより注意深く選ぶことで、適性のある者は繁殖し、適性のない者は繁殖しないようにすることを望んだ。自然が盲目的に、ゆっくりと、冷酷に行うことを、人間は摂理的に、素早く、親切に行うことができる」と彼は主張した。彼はまた、「幼稚な」「黒人」を、彼の出身地であるアフリカ大陸から、少しばかり愚かな「中国人」によって追い出すことを望み、ユダヤ人は「他国に寄生するために特化した存在」であると考えていた。ガルトンは、当時としては検閲的で偏見に満ちた人物であったが、実際には不妊手術や「不適格な」人々の殺害を推奨することはなかった。
ガルトンの信奉者たちはすぐに、結婚を国有化し、生殖を許可し、不健康な人々を不妊手術にするよう、互いに凌ぎを削った。シドニーとベアトリス・ウェッブ、ジョージ・バーナード・ショー、ハヴロック・エリス、H.G.ウェルズなど、最も熱心な優生主義者の多くは社会主義者であり、この選択的人間繁殖プログラムを実施するためには国家権力が必要だと考えていた。しかし、ウィンストン・チャーチルからセオドア・ルーズベルトに至るまで、政治スペクトルを問わず多くの政治家が、国民の私生活への優生学的介入を熱心に主張するようになった。実際、イギリス、フランス、アメリカのエリート社会では、優生政策を奨励しないことは政治的に正しくないことだった。優生学に反対することは、人類の未来に無関心であることを意味した。
ドイツでは、ヘッケルがマルサス的闘争を準宗教的な方向に導き、ダーウィン的洞察とキリスト教的洞察とを融合させ、一元論と呼ぶ理論にまとめようとした。年、アルテンブルクでの講演で、彼はマルサスとトマス・ホッブズの両方の言葉を使った。「ここで特にダーウィンが、33年前、生存のための闘争という教義と、それに基づく淘汰の理論によって我々の目を開かせた。我々は今、地球上の有機的自然全体が、万物に対する万物の容赦ない戦いによってのみ存在していることを知っている」(強調)。ヘッケルの信奉者たちは、優生学に人種的な色合いを与えた。彼らは異常児の嬰児殺しを合法化し、人種改良のために組織的な殺人を行うだけでなく、「存在のための闘争の最高で最も荘厳な形態」としての戦争を提唱した(この言葉は1900年に書かれたオットー・アモンの言葉である)。マルサスがその人口論の第3章で初めて使い、その後ダーウィンがマルサスから得た教訓を説明するために使ったのが、まさにこの「生存のための闘争」という言葉である(「私はたまたま娯楽として『人口論』のマルサスを読んだ) モニストのおかげで、この言葉はやがてカイザーとヒトラーの交戦を正当化するために使われるようになる。第一次世界大戦争前のドイツの軍国主義者たちは、ダーウィンについて不穏なほど頻繁に言及していたが、それは他の国の軍国主義者たちも同様だった。1898年の王立連合軍機関誌に掲載された論文では、「戦争とは、退化した国家、弱い国家、あるいは有害な国家を排除するための自然の壮大な計画ではないか。?’ イタリアの未来学者フィリッポ・マリネッティは、戦争を「世界の唯一の衛生」と呼んだ。
1905年、ヘッケルの信奉者4人がドイツ人種衛生協会を設立した。この一歩が、ニュルンベルク法、ヴァンゼー会議、ガス室に直接つながることになる。したがって、マルサスの信奉者たちが主張した選択的生存への介入からビルケナウの灰へとつながる明確な道筋をたどることは、まったく難しいことではない。これは、無実の数学者・聖職者をナチスの罪のせいにしているのではない。生存のための闘争を人間の特徴として説明することは、道徳的に間違ってはいない。間違っているのは、それを意図的な政策として規定することである。あらゆる段階で犯している罪は、積極的な干渉であり、目的が手段を正当化することである。ジョナ・ゴールドバーグがその著書『リベラル・ファシズム』で書いているように、「進歩的知識人のほとんど全員が、ダーウィンの理論を人間の自然淘汰に 『干渉』するためのものだと解釈していた」表向きは優生学とつながりのない進歩主義者でさえ、優生学の支持者と密接に協力していた。進歩的なサークルには、人種差別的な優生学に対する大きな汚名はなかった。
この政策に対する科学的支持が極端に弱かったことは、ほとんど問題ではなかった。実際、1900年に世界に知られるようになったグレゴール・メンデルの発見によって、優生学は完全に死滅したはずだった。偏性遺伝と劣性遺伝は、選択的品種改良によって人類の劣化を防ぐという考えを、より困難で非現実的なものにした。人類の品種改良を担当する人々は、無能や不適性の本質を表さないヘテロ接合体をどうやって見分けるつもりだったのだろうか?ヘテロ接合体同士の結婚から生まれる不適格者を、私たちはいつまで淘汰し続けることになるのだろうか?それは何世紀もかかるだろうし、その間に私たちの種がますます近親交配になり、ホモ接合の組み合わせが増えるにつれて、問題はさらに悪化するだろう。しかし、遺伝的事実は議論に何の影響も与えなかった。計画幻想に突き動かされた政治家たちは、右も左も関係なく、不向きな血統の蔓延を防ぐために生殖を国営化しようと扇動した。
チャールズ・ダーウィンの息子であるレナード・ダーウィンが議長を務め、1912年にロンドンで第1回国際優生学会議が開催された。この会議には、3人の大使のほか、司法長官と提督の第一卿、ウィンストン・チャーチルも出席した。レナード・ダーウィンは会長演説の中で、「進歩をもたらす機関として、意識的淘汰は自然淘汰の盲目的な力に取って代わらなければならない」と、説明から処方への転換を強調した。幸いなことに、優生運動発祥の地であるイギリスでは、特に優生に関する法律が制定されることはなかった。これは、危険性を察知し、優生法案を下院に提出したジョサイア・ウェッジウッドという血気盛んな国会議員のおかげである。
不妊手術が始まる
アメリカでは話が違った。鉄道王E.H.ハリマンの未亡人からの資金援助を受けて、精力的な優生学者チャールズ・ダベンポートが1910年にニューヨークのコールド・スプリング・ハーバーに設立した優生学記録局は、すぐに政策に強力な影響力を行使し始めた。第2回国際優生学会議は、アレクサンダー・グラハム・ベルの名誉総裁の下、アメリカ自然史博物館総裁ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンが主宰し、国務省が招待状を送って、1921年にニューヨークで開催された。これは縁の下の力持ち的なイベントではなかった。レナード・ダーウィンは体調が悪くて出席できなかったが、「今後100年ほどの間に広く優生学的な改革が採用されなければ、われわれの西洋文明は、過去にあらゆる偉大な古代文明が経験したような、ゆっくりとした緩やかな衰退に向かうことは避けられないという確固たる確信」を表明するメッセージを送った。
優生記録局のハリー・ラフーリン局長は、1932年にモデル優生法を作成した。この法律は、彼とダベンポートの精力的なロビー活動と相まって、最終的に30州を説得し、精神薄弱者、精神異常者、犯罪者、てんかん患者、酩酊者、病人、盲人、聴覚障害者、奇形児、依存症患者の強制不妊手術を許可する法律を成立させた。1970年代初頭にこのような法律が取り締まられるまでに、約6万3千人が強制不妊手術を受け、さらに多くの人々が自発的不妊手術を受け入れるよう説得された。
優生学的人間嫌いの流れに、自然崇拝という別の考え方が入り込むようになるのに時間はかからなかった。ニューヨークの弁護士で自然保護論者のマディソン・グラント(ブロンクス動物園、セーブ・ザ・レッドウッズ・リーグ、デナリ国立公園の創設者)が1916年に出版した『偉大なる種族の通過』という本は、北欧型の男らしい美徳と、地中海や東欧からの移民による支配への脅威を賛美していた。この本は1924年の移民法の成立に影響を与えた。この本はアドルフ・ヒトラーの「バイブル」ともなり、彼はグラントに熱心に手紙を書いた。
ドイツでも、自然保護は人間生活の破壊と手を携えていた。「木に聞け、彼らは国家社会主義者になる方法を教えてくれる!」というナチスのスローガンがあった。ナチスはしばしば近代的な農法を非難し、自然との親密さを理想化し、有機的な農民農業を賛美した。マルティン・ハイデガーのような彼らのお気に入りの哲学者は、自然と調和した生活について叙情的に語った。マーティン・ダーキンが述べているように、ナチスにとって緑の思想は単なる副業ではなかった:
ナチスが、「生活空間」を求めてポーランドに侵攻したのは、農民社会を再現しようとする緑の試みであった。彼らの「血と土」の人種差別イデオロギーにつながったのは、中世への緑色の郷愁だった。彼らがユダヤ人を憎むようになったのは、緑の反資本主義と銀行家への嫌悪からだった。
1939年、アメリカの社会改革者マーガレット・サンガーは、牧師や医師の助けを借りて黒人に避妊手術を施すことを目的とした『ニグロ・プロジェクト』を立ち上げた。このプロジェクトは、臆面もなく優生人種主義を掲げていた。「大多数の黒人は、いまだに不注意で悲惨な繁殖を行っており、その結果、黒人の増加は、人口の中で最も知能が低く、健康でない部分に及んでいる」
カリフォルニアは特に優生学に熱心だった。1933年までに、他のすべての州を合わせたよりも多くの人々を強制不妊手術した。1932年、チャールズ・ダベンポート主宰のもと、第3回国際優生学会議がニューヨークのアメリカ自然史博物館に集まり、ダベンポートが「優生学的研究によって、スーパーマンと超国家を生み出す道を指し示すことができるか」と問いかけたとき、スーパーマンを崇拝するドイツの代表団が答えを求めたのはカリフォルニアだった。そのうちの一人、ドイツ人種衛生学会のエルンスト・ルディンは、国際優生学団体連盟の代表に選出された。数カ月も経たないうちに、ルーディンは次期ナチス政府によって優生学担当のライヒスコミッサーに任命された。1934年までに、ドイツでは毎月5,000人以上が不妊手術を受けていた。カリフォルニアの自然保護活動家チャールズ・ゲーテは、マディソン・グラントと同様、野生の景観保護に対する先駆的な情熱と、精神科患者を本人の同意なしに不妊手術することに対する同じ情熱を併せ持っていた。ドイツは人種差別を自国のヘッケルの伝統から学んだが、不妊手術の実践的なノウハウはアメリカ西海岸から学んだのである。
殺人の正当化
次に起こったことは、衝撃を与える力を失っていない。ナチス・ドイツは、ヒトラーが政権を握ってからの6年間に、統合失調症患者、うつ病患者、てんかん患者、あらゆる種類の障害者を含む40万人を不妊手術した。ユダヤ人と非ユダヤ人との性交渉を禁じ、その後、さまざまな方法でユダヤ人を組織的に迫害し始めた。プロパガンダの圧力の下で、多くの一般ドイツ人は良心を逆なでし、ユダヤ人の友人に同情する気持ちを恥じるようになった。
ドイツからのユダヤ人移民は、イギリス、フランス、アメリカの政府によって積極的に抵抗された。1939年初頭、ハリー・ラフーリンによって結成された民族主義者と優生学的圧力団体の連合によって、定員を上回る2万人のユダヤ人の子供のアメリカ入国を認める法案が議会で否決された。1939年5月、930人のドイツ系ユダヤ人を乗せたセントルイス号がアメリカに向けて出航した。停泊許可を待つ間、ローフーリンは報告書を発表し、アメリカが「優生主義的・人種的基準」を引き下げないよう要求した。乗客のほとんどはヨーロッパに戻され、そこで多くが殺された。
1939年、ナチス政府はアクシオンT4と呼ばれるプログラムを立ち上げ、さらに一歩踏み込んで、障害者や精神病患者を主に致死注射で殺し始めた。最初に殺されたのは先天性の病気を持つ子供たちで、5000人が死刑になった。その後、1941年に親族からの抗議で中止されたと思われるまでに、70,000人の成人がこのプログラムの下で殺された。同性愛者、ジプシー、政治犯、数百万人のユダヤ人とともに、「不適格者」を強制収容所に集めて大量絶滅させるのだ。600万人の人間が死んだ。マルサス、ダーウィン、ヘッケル、ラフーリンが生きていなければ、このようなことは起こらなかったと主張するのは行き過ぎである。しかし、ナチスによる大量虐殺を明確に正当化する根拠は、マルサスによって概説された生存競争に由来する優生学にあった。
人口問題の再燃
第二次世界大戦後、極端な優生政策がもたらした恐ろしい結果が明らかになり、優生学は廃れた。そうだろうか?驚くほど早く、驚くほどあからさまに、世界人口をコントロールしようとする運動の中で、まったく同じ主張が再浮上したのである。戦争前の著名な優生学者ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンの息子、ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンもまた、1948年に『略奪された地球(Our Plundered Planet)』と題する本を出版し、急激な人口増加、資源の枯渇、土壌の疲弊、DDTの乱用、テクノロジーへの過度の依存、消費主義への奔流などに関するマルサス的懸念を復活させた。「利潤動機が極限まで進めば、一つの確実な結果、すなわち土地の究極的な死がもたらされる」と裕福なオズボーンは書いている。オズボーンの本は出版された年に8回も再版され、13カ国語に翻訳された。
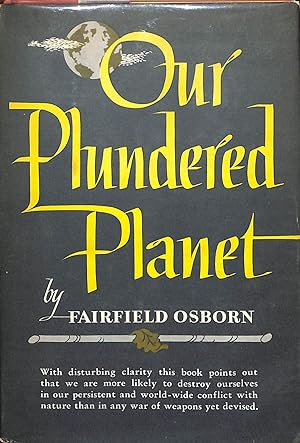
ほぼ同時期に、野生生物保護への情熱に駆られた生物学者ウィリアム・ヴォクトが、「明晰な聖職者」マルサスの考えをさらに明確に支持した、よく似た本『生存への道』を出版した。残念ながら、戦争、ドイツの虐殺、局地的な栄養失調にもかかわらず、ロシアを除くヨーロッパの人口は1936年から1946年の間に11,000,000人増加した」インドでは、イギリスの統治が飢饉を効果的でないものにした。
フェアフィールド・オズボーンはコンサベーション・ファウンデーションを設立し、会長を務めた。コンサベーション・ファウンデーションは彼の人脈を活用し、シエラ・クラブや環境防衛基金、ヨーロッパでは世界自然保護基金など、今日の大規模な環境保護団体の多くを支援する大規模な資金提供プログラムを構築した。従兄弟のフレデリック・オズボーンは、第3回国際優生学会議の会計を務め、その後もアメリカ優生学会の会長を務めた。家族計画財団は1916年、マーガレット・サンガーによって設立された。サンガーは、博愛主義は「不良、非行、依存者を絶えず増加させる」と考えていた。この組織の国際部門は、1952年末には英国優生学協会のオフィスに本部を置いていた。人口抑制運動は、不愉快なほど優生学運動の子供だった。
大西洋の反対側でも、そのつながりは明白だった。1952年、レナードの甥でチャールズの孫、著名な物理学者であったサー・チャールズ・ガルトン・ダーウィンは、『次の100万年』というタイトルの悲観的な本を出版した。「マルサスの教義を要約すれば、食料がある以上に人が増えることはありえない。マルサスの脅威を最も心配している人々は、繁栄による人口の減少こそが人口問題の解決策だと主張している。彼らは、この状態が意味する種族の退化に無自覚であり、あるいは、二つの悪のうち、より小さいほうの悪として喜んで受け入れているのかもしれない」ダーウィンは、戦争、嬰児殺し、成人人口の一部の不妊手術など、思い切った方法以外では人口増加を抑えることはできないと主張していた。彼は人口爆発のハッピーエンドを予見することができなかった。「私たち」はどのように問題を解決するのか?
ジュリアン・ハクスリー卿は、ユネスコの初代代表であり、早くから人口抑制を提唱していたが、イギリスの環境保護運動において、アメリカのオズボーンのような先駆的な役割を果たした。戦争前の優生学への熱意は、1962年になっても衰えることなく、「人間とその未来」をテーマにしたチバ財団の会合でこう語っている:
現時点では、国民は強制的な優生措置や不妊措置を容認しないだろう。しかし、もしあなたがいくつかの実験を開始し、自主的なものも含めて、それがうまくいくことを確認し、人々を教育し、何が問題であるかを理解させる大規模な試みをするならば、一世代以内に、一般人口に影響を及ぼすことができるかもしれない。
チャールズ・ガルトン・ダーウィン卿、ジュリアン・ハクスリー卿、ヘンリー・フェアフィールド・オズボーン・ジュニア、ウィリアム・ヴォクトは、恥ずかしい知識階級に無視された異常者ではなかった。彼らは時代のムードをとらえ、絶大な影響力を持った。
人口脅迫
1960年代までに、これらの思想は多くの権力者を改心させた。オズボーンとヴォクトの著書は、ポール・エーリック夫妻やアル・ゴアを含む学生世代に読まれていた。最も影響力のある弟子はウィリアム・ドレイパー将軍で、彼の対外援助委員会は1959年にアイゼンハワー大統領に、共産主義への新兵の供給を減らすために、援助を明確に避妊と結びつけるべきだと報告した。アイゼンハワーはこれを受け入れず、カトリックの後継者ジョン・F・ケネディも信じなかった。
しかし、ドレイパーはあきらめなかった。彼の「人口危機委員会」は、共産主義を打ち負かすためには強制的な人口抑制が不可欠であるというテーゼを支持し、次第にアメリカ国民生活の中で最も影響力のある多くの人々を味方につけていった。最終的には、ランド研究所の研究(割引率15%という不合理な数字を使用)の助けを借りて、子供にはマイナスの経済的価値があると主張し、ドレイパーと彼の同盟者たちは1966年にリンドン・ジョンソンの支持を取り付け、人口抑制はアメリカの対外援助の正式な一部となった。冷酷なレイマート・レーベンホルト所長の下、人口局はその予算を拡大し、アメリカの援助予算全体を上回るまでになった。レイベンホルトは、一連の驚くべきエピソードの中で、不良品の避妊ピルや滅菌されていない子宮内避妊具、未承認の避妊具を買い集め、貧しい国々に援助として配布した。彼は、アフリカにおける乳幼児死亡の予防は、「それによって防がれた死亡が、ほぼ同数の出産の予防と釣り合わなければ、アフリカ社会にとって甚大な害となる」という自分の見解を包み隠さず述べた。「1970年代から1980年代にかけての介入主義的プログラムによって、予防可能な疾病による死から救われた乳幼児の多くが、ナタを振り回す殺人鬼になってしまった」(強調は原文ママ)。
ラベンホルトが人口局の責任者となり、世界銀行総裁のロバート・マクナマラが、銀行が設定した不妊手術のノルマに従わない国への融資を拒否したため、インドのような国が食糧援助を受けるためだけに強制的な不妊手術を行わなければならなくなった。1966年、インディラ・ガンジーがワシントンに到着し、パキスタンとの最近の戦争によって引き起こされたインドの飢饉を救済するための食糧援助を懇願したとき、彼女は国務長官ディーン・ラスクから、「人口抑制のための大規模な取り組みが援助を受ける条件である」と告げられた。彼女はそのメッセージを受け取り、不妊手術とIUDのための州ごとの割り当てに同意した。何百もの不妊手術キャンプが設置され、救急隊員がパイプカット、IUD挿入、卵管切除を1000人単位で行った。不妊手術1回につき12ルピーから25ルピーという、これらの手術を受けた人々に支払われる哀れな報酬は、特に貧困層の何百万人もの飢えた人々を惹きつけるのに十分だった。不妊手術の件数は、1972年から73年までに年間300万件に達した。
欧米のコメンテーターの中には、飢餓状態の方がましだと考える者もいた。ウィリアムとポールのパドックは1967年に『飢饉1975!』というベストセラーを書き、飢饉の時代が差し迫っており、食糧援助は無駄だと主張した。アメリカは低開発国を3つのカテゴリーに分けなければならないと彼らは言った。助けることができる国、助けがなくてもよろめきながら生き延びる歩行中の負傷国、そして「(人口過剰、農業不足、政治的無策のためであろうと)飢饉に向かうか、飢饉に陥っている絶望的な国。インド、エジプト、ハイチはこのまま見殺しにされるべきだ」
その1年後、ポール・エーリック夫妻の『人口爆弾』は、ほとんど無慈悲だった。エーリック夫妻は、インドが自給自足することはあり得ないと判断した。臆面もなく人口抑制のための強制を主張する彼は、人類をガンに例え、手術を勧めた。手術は多くの一見残酷で無情な決断を要求するだろう。自国での人口抑制には、「自発的な方法が失敗した場合の強制」が必要である。彼は「望ましい人口規模」を達成するために、水道水に不妊剤を加えることを提案した。海外については、インドへの食糧援助を、3人以上の子供を持つすべての人々への強制不妊手術を条件とすることを望んでいた。ジョンソン大統領がインドへの援助を人口抑制と結びつけたことが国内で批判を巻き起こしたことに、エーリック夫妻は「驚愕」した。エーリック夫妻は、アン夫人とジョン・ホルドレン(現オバマ大統領科学顧問)との共著の中で、「惑星体制」に「世界にとって最適な人口を決定する責任を与え、地域ごとに、その地域の範囲内で各国の取り分を調停する責任を与える」ことを提言した。
1975年、ガンジー夫人が世界銀行に融資を求めたとき、彼女はインドの人口をコントロールするためのより強力な取り組みが必要だと言われた。彼女は強制に転じ、息子のサンジェイが、多くの許可証、免許証、配給、さらには住宅申請さえも不妊手術を条件とするプログラムを実行した。スラム街はブルドーザーで破壊され、貧しい人々は不妊手術のために検挙された。暴力は何度も起こった。1976年、800万人のインド人が不妊手術を受けたとき、ロバート・マクナマラがインドを訪れ、「ようやくインドが人口問題に効果的に取り組めるようになった」と祝辞を述べた。
人口懐疑論者たち
しかし、驚くべきことがある。インドでも他の国でも、出生率はすでに低下していた。合成窒素肥料と穀物の短稈新品種「緑の革命」のおかげで、食糧生産はマルサスの予測とは逆に、人口をはるかに上回るペースで増加していた。人口爆発に対する答えは、強制でも幼児死亡率の奨励でもなく、その正反対であることが判明した。人口増加を遅らせる最善の方法は、赤ん坊を生かし続けることだったのである。
さらに衝撃的な事実は、この進化論的な解決策は、パニックが始まった当初からすでに一部の人々には知られていたということだ。1940年代にネオ・マルサス的人口警告が誕生した当初でさえ、その診断と治療法がいかに間違っているかを見抜いていた人々がいたのだ。赤ちゃんが増えれば飢餓が増えるのではなく、その逆だと主張したのだ。人々は、子どもの死亡率が高いことに反応して出生率を高めた。より豊かで健康になれば、ヨーロッパですでに起こっていたように、出生率は上がるどころか下がっていたのだ。アール・パーカー・ハンソンがウィリアム・ヴォークトへの長編回答書『New Worlds Emerging(新世界の出現)』で書いているように、食糧不足と多すぎる出産に対する解決策は繁栄であり、マルサスの飢餓ではない。人々は、「子供を大学に行かせることを心配できる立場になれば、子供を少なくすることを考えやすくなる」だろう。
ブラジルの外交官ジョスエ・デ・カストロは、著書『飢餓の地政学』の中で、ネオ・マルサス派をさらに大胆に批判し、「したがって、生存への道は、余剰人口をなくすというネオ・マルサス派の処方箋にあるのでもなく、避妊にあるのでもなく、地球上のすべての人を生産的にする努力にある」と述べた。
1970年代、ポール・エーリック夫妻の人口悲観論は、経済学者のジュリアン・サイモンによって一連の論文や著書で攻撃された。サイモンは、「赤ん坊の誕生は悪いことだが、子牛の誕生は良いことだ」というテーゼは何かひどく間違っていると主張した。なぜ人々は、助けるべき手ではなく、養うべき口とみなされたのか?過去2世紀の真実は、人口が拡大するにつれて人間の福利が向上してきたということではなかったのか?
有名な話だが、1980年、サイモンはエーリック夫妻に将来の原材料価格について賭けを挑んだ。エーリック夫妻と同僚はこの申し出に乗り気で、銅、クロム、ニッケル、スズ、タングステンを、今後10年間でより希少になり、より高価になる原材料の例として選んだ。サイモンは彼に賭けた。10年後、エーリック夫妻はサイモンを公衆の面前で「愚か者」と罵りながら、サイモンに576.07ドルの小切手を送った。(この5つの金属はすべて、実質的にも名目的にも値下がりしていたのだ(私の自慢のひとつは、この5つの金属で作られたジュリアン・サイモン賞である)。サイモンは、「私は、人類の物質的福祉に関わるあらゆる傾向が、悪化するよりもむしろ改善するほうに、一週間か一ヶ月の給料を賭けるよ」と、誰にでも別の賭けを持ちかけた。1998年にサイモンが早すぎる死を遂げるまで、彼の申し出に応じる者はいなかった。
人口爆発に対する解決策は、緑の革命と人口動態の移行であることが判明した。強制や計画ではなく発生的な現象である。処方箋ではなく進化である。人口増加を減速させたのは、進化的で、自然発生的で、無計画な現象だった。予期せず、予測もされず、前触れもなく、人々はより豊かで、より健康で、より都会的で、より自由で、より教育を受けていたため、より小さな家族を持つようになった。言われたからではない。人口抑制の目的を達成するために十分な強制力を行使した国は中国しかないが、中国が達成したのは、強制力をほとんどまったく行使しなかった他の国とほぼ同じ規模の人口増加の減速だけだった。
一人っ子政策の西洋的起源
中国の一人っ子政策は、西洋のマルサスの伝統とはほとんど関係がないに違いない。そうではない。この政策はネオ・マルサスの著作に直接由来するものであり、不穏なことに、科学者たちによって始められた、おそらく史上初で最も広範囲に及ぶ政策である。科学を愛する私たちにとって、この前例は心強いものではない。
毛沢東は、中国人民の多くの苦しみを統率したという事実にもかかわらず、人口に対するアプローチは比較的抑制的で人道的なものだった。これはマルサス自身が提唱していたこととほぼ同じである。そのためか、子どもの死亡率が低下したためか、中国の出生率は1971年から1978年の間に半減した。その後、毛沢東の死後、より厳格で規定的なアプローチに転換した。ハーバード大学の人類学者スーザン・グリーンハーグがその著書『たった一人の子供』で語っているように、1978年、制御システムの専門知識を持つ誘導ミサイル設計者の宋建は、ヘルシンキで開かれた技術会議に出席した。そこで彼は、ローマクラブと呼ばれる影の組織とつながりのある新マルサス主義的憂慮論者の2冊の本について耳にした。ひとつは『成長の限界』、もうひとつは『生存の青写真』(A Blueprint for Survival)である。
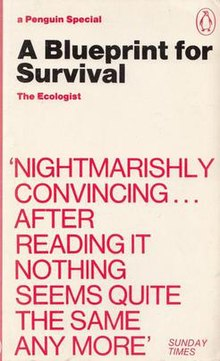
イタリアの実業家とスコットランドの化学者によって1960年代に設立されたローマクラブは、マルサス崇拝に傾倒し、豪華な会場で非公開の会合を開く、偉人と善人のためのおしゃべりクラブである。その関連団体とともに、アル・ゴアやビル・クリントンからダライ・ラマやビアンカ・ジャガーに至るまで、いまだに一流の著名人を惹きつけている。「真の敵は人類そのものである」とローマクラブは1993年の著書で宣言している。民主主義は万能ではない。民主主義はすべてを組織化することはできないし、自らの限界にも気づいていない」1974年、ローマクラブは『転換期における人類』と呼ばれる第2次報告書の中で、創造論的思考を呼びかけた:
自然界では、有機的成長はマスタープラン(設計図)に従って進行する。世界システムの成長と発展の過程には、そのような「マスタープラン」が欠けている。今こそ、あらゆる資源の世界的配分と新たな世界経済システムに基づく、持続可能な成長と世界発展のためのマスタープランを描く時なのだ。
『成長の限界』は1000万部を売り上げ、人口過剰と資源の枯渇のために人類が滅亡することをコンピューターモデルで証明したと称した。この本は、1992年までにいくつかの金属が枯渇し、その後の世紀に文明と人口が崩壊すると予測した。
裕福な英国人実業家エドワード・ゴールドスミス卿によって書かれたが、ジュリアン・ハクスリー卿、ピーター・メダワー卿、ピーター・スコット卿など、科学界の正真正銘の錚々たる顔ぶれが署名している。環境保護運動は、変化、テクノロジー、消費主義を嫌うエリートの習慣に突き動かされていたのだ。この本には、「粗悪品」が出回る消費社会が庶民の手の届くところまで来ているという事実に対する、俗物的な軽蔑がにじみ出る。これは間違いだと言っているのは、金持ちが聞きたがっていることを言っているのだ。『生存のための青写真』によれば、家庭内の女性の時間を節約するはずの家庭用電化製品を製造するために行わなければならない「退屈で退屈な仕事」を考慮している『私たち』はほとんどいない。世界の貧困層については、「予測される食糧需要を満たすのに十分な農業生産が増加すると考えるのは非現実的」である。そして著者は、各国政府は人口問題を認識し、「人口増加を終わらせるというコミットメントを宣言しなければならない」。これは非常に反動的な文書であり、今日の右翼政党が恥をかくような種類のものである。
一人っ子政策の生みの親である宋建がヘルシンキで手にしたのは、この2冊の本だった。『成長の限界』は、宋が専門としていた制御システム理論をミサイルの軌道ではなく、人口と資源利用の軌道に応用したものだった。宋は中国に戻り、2冊の本の主要なテーマを自分の名前で中国語で再出版し、政権内で一躍有名になった。彼は軍隊での経験のおかげで、(人類学者スーザン・グリーンハーグの言葉を借りれば)「一人っ子政策は、社会的な領域において、ビッグプッシュでトップダウン的なアプローチの使用を想定し、また必要としている」ことをすぐに理解した。宋は最も文字通りの意味で社会工学を提案していたのである。王振副総理は宋の報告書を読んで即座に改宗し、鄧小平自身の上級副官である陳雲と胡耀邦の前に提出した。鄧小平は、宋が中国の貧困の原因は経済的な不始末ではなく人口過剰にあると主張したことが気に入ったようで、数学に惑わされて彼の仮定に疑問を持たなかった。1979年12月に成都で開かれた会議で、宋は人道的な影響を心配する批判者たちを黙らせ、中国が生態学的手段の範囲内で生活するためには、2080年までに人口を約3分の1に減らす必要があるという彼の計算を受け入れるよう党を説得した。
銭興中将軍がこの政策の責任者となった。彼は、2人以上の子供を持つすべての女性の不妊手術、1人の子供を持つすべての女性へのIUDの挿入(IUDの除去は犯罪)、23歳未満の女性の出産の禁止、陣痛8カ月目までのすべての無断妊娠の強制中絶を命じた。逃亡して秘密裏に出産しようとした者は追跡され、投獄された。場合によっては、隣人への裏切りを助長し、彼らのコミュニティは罰金を科された。集団不妊手術、強制堕胎、嬰児殺しの残忍なキャンペーンは、親たちが自分たちの合法的な子どもを確実に男の子にしようとしたため、大量殺戮的な規模で女児を自発的に殺害することによって悪化した。出生率は低下したが、代わりに経済発展、公衆衛生、教育の政策が採用されていれば、それほどの速度は出なかっただろう。
このホロコーストに対する国際的な反応はどうだったのだろうか?国連事務総長は1983年に銭将軍に賞を授与し、中国政府が「大規模な人口政策を実施するために必要な資源を結集した」方法について「深く感謝する」と記録した。その8年後、この政策の恐ろしさが誰の目にも明らかになりつつあるにもかかわらず、国連家族計画局の責任者は、人口抑制における「中国の目覚ましい成果を誇りに思う十分な理由がある」と述べ、中国が他国にその方法を教える手助けをすることを申し出た。この権威主義的な残虐行為に対する穏やかな見方は、今日まで続いている。メディア界の大物、テッド・ターナーは2010年、新聞記者に、他の国も中国に倣って一人っ子政策を実施し、時間をかけて世界の人口を減らすべきだと語った。
マルサスの貧民法は間違っていた。インドとアイルランドの飢饉に対するイギリスの態度は間違っていた。優生学は間違っていた。ホロコーストは間違っていた。インドの不妊化計画は間違っていた。中国の一人っ子政策は間違っていた。これらは、不作為ではなく、任務による罪であった。マルサス流の人間嫌い、つまり、種族の利益のためには心を硬くし、飢饉や病気を容認し、同情や憐れみを恥じるべきだという考え方は、道徳的であると同時に現実的にも間違っていた。貧しく、飢え、多産な人々に対してなすべき正しいことは、今も昔も、彼らに希望、機会、自由、教育、食料、医療を与えることである。技術主義的悲観主義の創造論や、資源の本質に関する単純で固定的な誤解を抱えた科学エリートたちの繰り返し論破される破滅論や、「私たち」という怠惰な複数代名詞への安易な依存や、「しなければならない」という恐ろしい言葉を捨てることだ。その代わりに、人口動態の変化という進化的で、無計画で、創発的な現象を受け入れよう。
最後の言葉は、ジェイコブ・ブロノフスキーのテレビシリーズ『The Ascent of Man』の最後に語っている。この池に400万人分の灰が流された。この池に約400万人の灰が流された。この池に400万人もの人々の灰が流されたのだ。それはガスによるものではなく、傲慢によるものであり、ドグマによるものであり、無知によるものだ。人々が、自分には絶対的な知識があると信じるとき、現実には何のテストもない。神々の知識を得ようとするとき、人はこうなるのだ』」
12. リーダーシップの進化
平和のうちに生き、従順であることがはるかに望ましい
権力に君臨し、全王国を自分の支配下に置きたいと願うよりも。
他人が血の汗を流しながら、無意味に身をすり減らすのを見過ごそう、
大志の細い道と闘うのだ。
ルクレティウス『自然の道』第5巻1129-32行
ドゥニ・ディドロとジャン・ダランベールの『百科全書』(フランス啓蒙主義のマニフェスト)には、名前のある人物の項目はほとんどない。例えば、アイザック・ニュートンの短い伝記を読むには、ニュートンが育ったリンカンシャーの村の古い名前である「ウォルストロープ」を調べなければならない。この奇妙な気難しさには理由があった。ディドロとその友人たちは、歴史は指導的人物を評価しすぎ、出来事や状況をあまり評価していないと考えていた。彼らは、王や聖人や発見者さえも一段低く評価したかったのだ。歴史は何千人もの普通の人間によって動かされるプロセスであって、少数の超人的な英雄によって定められたものではないことを読者に思い出させたかったのだ。彼らは歴史からも、政府、社会、科学からも、天秤棒を取り除きたかったのだ。(しかし、彼らでさえ、ヴォルストロープについて、ニュートンの生誕地であること以外に語るべきことを見つけることはできなかった)。
ディドロの同時代人、シャルル・ド・モンテスキュー男爵もまた、指導者たちは自然の不可避な必然性を自分の手柄にしていると主張した。彼は、人間は単なる現象に過ぎず、歴史はより一般的な原因によって動いていると考えた。マルティン・ルターは宗教改革の功績を認められている。しかし、それは起こるべくして起こったのだ。もしルターでなかったら、他の誰かであっただろう」戦いの偶然の結果が国家の破滅を早めたり遅らせたりすることはあるが、国家が破滅する予定であったなら、いずれにせよそれは起こるのである」こうしてモンテスキューは、社会科学において有用な概念となった究極的原因と近接的原因の区別を行ったのである。時に彼は、出来事に無生物の原因を求めるあまり、行き過ぎた気候決定論者となったが、神や王の手柄を好む教会や国家を困らせたのも無理はない。
19世紀になると、トマス・カーライルの「偉人論」の影響を受けて、伝記が復活した。カーライルは、ナポレオン、ルター、ルソー、シェイクスピア、モハメッドといった英雄は、彼らが生きた時代の結果ではなく原因であるとした。1911年に刊行されたブリタニカ百科事典は、百科事典とは正反対に、社会史は伝記の中に埋もれているとした。つまり、ローマ時代以降の世界について読むには、フン族のアッティラに関する項目を調べなければならない。
哲学者のハーバート・スペンサー*は、カーライルが間違っていると主張し、トップダウンの歴史に反撃したが、それはほとんど無駄だった。レオ・トルストイも『戦争と平和』の一部を割いて、偉人論に反論した。しかしその後、20世紀はカーライルの正しさを証明するかのように、偉大な男女が(善かれ悪しかれ)何度も歴史を変えた: レーニン、ヒトラー、毛沢東、チャーチル、マンデラ、サッチャーだ。ボリス・ジョンソン・ロンドン市長がその著書『チャーチル・ファクター』で論じているように、「一人の男がいかに歴史を作ったか」: 1940年5月当時、権力に近い立場にあった英国の政治家で、どんなに屈辱的なことであっても和平を求めてヒトラーと交渉しないことを選択した人物を、他に思い浮かべることはほとんど不可能である。戦争内閣の中で、必然に逆らって戦い続ける勇気、狂気、薄情さを持った人物は他にいなかった。ジョンソンの主張するように、これは一人の人間が歴史を変えた確かな例である。では、歴史は偉大な人物によって動かされるのだろうか?
中国の改革の創発性
私はそうは思わない。1978年に鄧小平の下で始まった中国経済改革が、5億人を貧困から救い出す経済の開花につながったことを考えてみよう。明らかに、鄧小平は歴史に大きな影響を与え、その意味で「偉大な人物」であった。しかし、1978年に中国で起こったことをよく調べてみると、それは通常考えられているよりも進化した物語だった。すべては農村から始まった。集団農場が「民営化」され、土地と収穫物の個人所有が認められるようになったのだ。しかしこの変化は、改革を進める政府が上から命じたものではない。下から出てきたのだ。小港村では、ある晩、18人の農民が密かに集まり、集団制度下の悲惨な生産に絶望し、他の村から食料をねだる必要性に迫られていた。彼らが思いついたスキャンダラスなアイデアを口にすることはおろか、集会を開くことさえ重大な犯罪だった。
最初に発言した勇敢な人物はイェン・ジンチャンで、彼は各家族が栽培したものを所有し、集団の土地を家族で分けるべきだと提案した。彼は貴重な紙切れに契約書を書き、全員が署名した。彼はそれを丸め、家の垂木の竹筒の中に隠した。家族たちは毎朝、役人の笛が鳴る前から土地で働き始め、その日の仕事が終わるのはずっと後だった。自分たちの仕事から利益を得ることができるという知識に刺激され、最初の1年で、彼らはそれまでの5年間の土地の生産量を上回る食料を栽培した。
地元の党首は、この仕事と豊作を不審に思い、イエンを呼び寄せた。しかし、取り調べの最中、地方の党首が間に入って円を助け、蕭鋼の実験を他でも真似るよう勧めた。この提案は、最終的に鄧小平の机に届いた。鄧小平は邪魔をしなかった。しかし、党が公式に家族経営を認めるようになったのは1982年になってからで、そのころには家族経営はいたるところで見られるようになっていた。農業は私有化のインセンティブによって急速に変貌し、工業もすぐにそれに続いた。マルクス主義的な鄧小平でなければ、改革は遅れたかもしれないが、いつかは必ず実現しただろう。そして重要なのは、ディドロが期待したように、それが普通の人間から生まれたということである。この話の教訓は、経済的自由が増大したエピソードについて、独裁者が過大な評価を受けすぎるということだ」とウィリアム・イースタリーは書いている。
もちろん、毛沢東について同じことを言うことはできない。毛沢東が数十年にわたって中国国民に与えた圧倒的で甚大な被害は、確かにトップから始まった。農業の集団化、核兵器の代金のために飢餓に苦しむ農民から穀物を搾取したこと、大躍進の際に村で金属を精錬するという狂った計画、文化大革命の際の個人に対する悪質な恨み辛み-これらはまさに、間違った意味での「偉人」の行動であった。アクトン卿が言ったように、偉大な人物はほとんどが悪人である。
戦争に勝つ蚊
伝記を読むのが好きだからというだけならともかく、今日でも私たちは偉人の歴史に夢中だ。アメリカの大統領政治は、完全無欠で、全知全能で、高潔で、潔白な救世主が4年ごとにニューハンプシャーの予備選挙から現れ、国民を約束の地へと導くという神話に基づいている。バラク・オバマが大統領に勝利した日ほど、この救世主ムードが極端だったことはない。2008年6月、オバマは「海洋の隆起が緩やかになり、地球が癒やされ始めた」瞬間だと語っていた。彼は「この国を癒し」、グアンタナモ湾を閉鎖し、医療を改革し、中東に平和をもたらすつもりだった。当選しただけでノーベル平和賞を受賞したのだ。そのような期待の中で、哀れなことに彼は期待を裏切ることはできなかった。ボストン大学の政治学者、アンドリュー・ベイスビッチは2013年、オバマケアの発足に失望する中、「オバマ自身は不発に終わったかもしれないが、アメリカ政治を数十年にわたって支配してきた大統領カルトはいまだに続いている」とコメントした。半神が土足であることが判明し、世界最強の男が世界を変えるほどの力を持っていないことが判明したとき、アメリカ国民は4年ごとに失望を味わう運命にあるが、それでも大統領教への信頼を失うことはない。他の国でも大差はない。
ルネサンス、宗教改革、産業革命など、人類の歴史における大きな変革は、他の出来事の偶然の副産物として起こった。貿易はイタリアの商人を富ませ、彼らは暴利を貪ることに罪悪感を感じていたため、芸術家たちに比類ない美しさを持つ敬虔な作品の制作を依頼し、古典世界の学問に対する開放的な探求を支援した。印刷は、テキストを安価で広く普及させることを可能にし、前世紀に何度か試みられた宗教改革者の頓挫を経て、教皇とその子分の権威を弱体化させることを可能にした。テクノロジーの専門家であるスティーブン・ジョンソンが論じているように、歴史的な出来事の意図しない結果は広範囲に及ぶ可能性がある。グーテンベルクは印刷された本を手ごろな値段で手に入れられるようにし、識字率の向上を促した。眼鏡市場が生まれ、レンズの研究が進み、顕微鏡や望遠鏡が発明され、地球が太陽の周りを回っているという発見がもたらされた。
チャールズ・マンは、東半球と西半球が接触した後に起こった偉大なコロンブス交流を描いた『1493年』の中で、歴史を真に形作る力が、上ではなく下から来ていることを何度も何度も示している。例えば、アメリカ独立戦争はマラリアによって勝利した。マラリアは、カロライナとチェサピーク湾にいたチャールズ・コーンウォリス将軍の軍隊を壊滅させたが、それは少なくともジョージ・ワシントンによって勝利したのと同じである。私がこのように言うのは、言い訳を求める負けず嫌いの英国人としてではなく、(アメリカの)著名な環境史家J.R.マクニールの権威に基づくものである。彼はAnopheles quadrimaculatusという種のメスの蚊について言及し、「あの小さなアマゾンは、イギリス軍に対して秘密裏に生物学的戦争を行った」と書いている。
1779年、イギリスの指揮官ヘンリー・クリントンは『南方戦略』を採用し、カロライナ州を占領するために軍隊を海路で派遣した。しかし、カロライナにはマラリアが蔓延しており、毎年春になると、特にヨーロッパから新しくやってきた人々の間で、マラリアが新たに発生した。この寄生虫は、被害者を衰弱させ、時には他の原因で死に至らしめることもある。稲作は蚊に十分な生息地を提供し、問題を悪化させた。春のカロライナは楽園、夏は地獄、秋は病院だ」とあるドイツ人旅行者は書いている。ほとんどの白人入植者は、若い頃にマラリアを経験し、ある程度の抵抗力を身につけていた。ほとんどの黒人奴隷は、マラリアに対するある程度の遺伝的免疫をアフリカから持ち込んでいた。つまり、アメリカ南部は外国軍を侵略するには最悪の場所だったのだ。
チャールストンを占領した後、コーンウォリス率いるイギリス軍は内陸に進軍した。1780年6月(蚊の季節の最盛期)、汗まみれで青白い肌のスコットランド人とドイツ人の小隊が森や田んぼを踏みしめると、アノフェレス蚊とプラスモディウム原虫は自分たちの幸運を信じられなかった。蚊は血を飲み込み、寄生虫はその細胞に飲み込まれた。いざ戦闘となると、コーンウォリス自身も含め、ほとんどの軍隊が熱病で衰弱していた。マクニールの言葉を借りれば、コーンウォリスの軍隊は一度の戦闘であっけなく溶けてしまった。熱病にかかった地元の忠誠者だけが戦場にとどまることができた。マラリアの唯一の治療薬であるキニーネ(キナノキの樹皮から取れる)がスペインに独占されていたことも助けにならなかった。
冬になるとコーンウォリスの兵士たちは回復し、彼は「昨秋、軍隊を破滅させかけた致命的な病気から兵士たちを守る」ために、沿岸の湿地帯から離れたヴァージニア内陸部へと北上させた。しかし、クリントンは援軍を迎えられるよう海岸に戻るよう命じたため、コーンウォリスは不本意ながらチェサピーク湾に面した2つの熱沼に挟まれた砦、ヨークタウンに後退した。ジョージ・ワシントンはフランス軍と北部軍を率いて、彼を包囲するために南下し、9月に到着した。コーンウォリスは「病気で日ごとに兵力が減少」し、3週間以内に降伏した。マラリアは潜伏に1カ月以上かかるため、新しく到着したフランス人とアメリカ人は、戦いが終わってから病気になり始めた。蚊のおかげでアメリカ人は膠着状態から勝利をつかみ、独立戦争に勝利した。次の7月4日に噛みつかれたら、そのことを思い出してほしい」
もちろん、ジョージ・ワシントンが将軍として得た功績をすべて取り上げるわけにはいかない。しかし、アメリカの指導者たちの名声は、少なくともその逆と同じくらい、出来事の転機によって築かれたのである。微視的な出来事だ。もちろん、この戦争はイギリスにとって勝ち目のないものであり、蚊がいなくとも最終的には屈服していただろうと主張することもできる。偉大なる昆虫説を偉大なる人間説にすり替えないことが重要なのだ。しかし、それならむしろ、戦争の決定要因はボトムアップのものだったという点を補強することになる。
帝国の最高責任者
偉人論は、人間の努力の一つの分野である大企業で相変わらず強く生きている。インターネットの時代であっても、現代の企業のほとんどは、封建的な領地のように、王様が仕切っている。あるいは、ゲイツ、ジョブズ、ベゾス、シュミット、ザッカーバーグのような、超自然的な名声、非常に大きな株式保有率、反響の大きい堅い名前を持つ神が投資されている。今日、最も象徴的で、強力で、帝国的な最高経営責任者が、デジタル経済の流動的で、平等主義的で、ダイナミックな世界に浮かぶ企業にいるのは、皮肉の極みであることは間違いない。彼らの会社は、何十億もの顧客との水平的な交流を提供し、従業員はジーンズを履き、ビーガンサラダを食べ、フレックスタイムで働いている。しかし、彼らの上司の発言は聖典のように扱われている。ジェフ・ベゾスの口癖は「顧客から出発し、逆算する」だが、彼の部下たちはこの言葉をマントラとして頻繁に繰り返している。2011年のスティーブ・ジョブズの死後、アップル社自体の存続が危ぶまれ、株価は急落した。チンギス・ハンでさえ、死後にこのような影響があっただろうか?ヘンリー・フォードやアッティラ・ザ・フンの独裁的な倫理観が、なぜこのように21世紀まで変わらず生き残っているのだろうか?なぜ企業はいまだにトップダウンなのだろうか?
カリフォルニアのテクノロジー企業はもともと、東海岸や旧世界のスノッブでヒエラルキー的なビジネスとは、この点で意識的に異なることを目指した。トム・ウルフが1980年代に記録しているように、インテルのロバート・ノイスのような人たちは、「家臣、兵士、ヨーマン、農奴、優越性を象徴し、境界線を確立するための車や運転手のような儀礼や特典の層」を持つ東海岸の資本主義の封建的モデルから意図的に逃れることを意図していた。ノイスはインテルに駐車スペースさえ用意してもらえなかった。西海岸の企業には民主主義的なフラットさの象徴が根強く残っており、最高経営責任者は封建的な大君主というよりは、神託、預言者、あるいは神のように振る舞い、その宣言は崇敬の念をもって扱われる。
経済学者のトム・ヘイズレットは、私たちが発明したとされる新しいシェアリングエコノミーについて、目を見開いた楽観主義が表明されていることを紹介した後、私にこう言った:「新しいウィキ経済には確かに億万長者がたくさんいる」2012年にフェイスブックが新規株式公開を申請した際、マーク・ザッカーバーグは、世界の情報インフラは「これまでのようなモノリシックでトップダウンの構造ではなく、ボトムアップ、つまりピアツーピアで構築されるネットワーク」であるべきだと願望を述べた。スティーブン・ジョンソンは、ザッカーバーグが同社の株式の57%を支配していることを指摘し、「トップダウンの支配は揺るがすのが難しい習慣だ」と皮肉交じりにコメントしている。
振り払わなければならない。ゲイリー・ハメル氏が2011年の『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌の記事で、シェイクスピアの『ヘンリー六世』に登場する肉屋の言葉をもじって書いているように、「まず、管理職を全員クビにしよう」彼は、組織が大きくなるにつれて管理層の数、規模、複雑さが増していくが、それは管理職にも管理が必要だからであり、大企業における上司の仕事の大部分は、組織が自らの複雑さの重みで崩壊しないようにすることだと指摘している。杓子定規な管理は、愚かな決断のリスクをはるかに大きくする: 君主のような権限を誰かに与えれば、遅かれ早かれ王室の大失敗が起こるだろう」また、問題が遅々として進まない委員会の間をたらい回しにされるため、意思決定も遅くなる。そして、自分たちの懸念や提案に誰も耳を傾けてくれないと考える若手スタッフの権限を奪うことになる。ハメル氏が指摘するように、顧客として2万ドルの車を自由に購入できる人が、従業員として500ドルのオフィスチェアを自由に購入できるとは限らない。大企業が中小企業よりも成長が遅く(毎年ダボスで開催される世界経済フォーラムのお祭り騒ぎに最高経営責任者が出席する企業は、株式市場のパフォーマンスを下回る傾向がある)、大きな公的機関の評判が中小企業よりも悪いのも不思議ではない。
最近の大企業の最高経営責任者(CEO)は、見かけの権力はあっても、雇われスポークスマンに過ぎないことがある。投資家や顧客に「自分の」戦略を説明し、部下の雇用、解雇、昇進、追放を行うチーフ・オブ・スタッフを1人か2人頼りに、常に外回りを続けている。もちろん、組織の奥深くまで自らの哲学を浸透させ、自ら製品を設計する者もいる。しかし、それは例外だ。ほとんどのCEOは、従業員が作り出す波に乗ってサーフィンをし、時折重要な決断を下すが、戦略を選択するデザイナーや中間管理職、そして何よりも顧客以上に主導権を握っているわけではない。彼らのキャリアはますますこれを反映している。外から連れてこられ、長時間働くことで高額な報酬を得、事態が悪化すると、儀礼はほとんどないが多額の現金を持って追い出される。彼らが封建的な王であるという幻想は、何よりもメディアによって維持されている。しかし、それは幻想である。
では最近、誰が会社を経営しているのだろうか?株主でも取締役会でもない。彼らは、物事がうまくいったことも、うまくいかなかったことも、たいてい事後的に知ることになる。協同組合でもない。コンセンサスによって会社を運営しようとしたことのある人なら誰でも、それがいかに悲惨なほど悪いアイデアであるかを教えてくれるだろう。誰もが自分の意見を他のみんなに理解してもらおうとするため、間断なく続く会議は互いに厳しいものになる。何事もうまくいかず、険悪な雰囲気になる。コンセンサスの問題は、人々が異なることを許されないことだ。ブレーキとアクセルが同じような仕事をする車を運転しようとするようなものだ。そうではなく、大企業の内部で実際に機能しているのは分業なのだ。あなたはあなたの得意なことをし、私は私の得意なことをする。これがほとんどの企業で実際に行われていることであり、良い経営とは良い調整を意味する。従業員は、市場の参加者や都市の市民のように、専門化し、交流する。
マネジメントの進化
カリフォルニアのモーニング・スター・トマトという会社は、20年間「自主管理」の実験を行ってきた。その結果、モーニングスターは世界最大のトマト加工業者となり、カリフォルニアのトマト加工作物の40%を取り扱うようになった。利益は急成長し、従業員の離職率は非常に低く、非常に革新的である。しかし、経営者も上司も最高経営責任者もいない。誰も肩書きを持たず、昇進もない。1990年代初頭から自主経営が続いている。トマトの新品種を選抜する生物学者も、収穫する農場労働者も、加工する工場労働者も、オフィスの経理担当者も、みな等しく責任を負っている。
予算すらない。人々は同僚と支出について交渉し、最も影響力のある場所に近い者が決定を下す。各従業員は、職務記述書や雇用契約書ではなく、「同僚理解書」を持っている。これには各自の責任だけでなく、業績指標も明記されている。この書簡は従業員自身が作成し、その内容や給与について、業績に基づいて同僚と交渉する。最も給与の高い社員は最も低い社員のわずか6倍しか受け取っておらず、かなりの大企業としては異例の少なさである。この会社には、金銭や地位に関する政治的な駆け引きがないことで有名だ。人々は上司に対してよりも仲間に対してはるかに献身的だと感じている。
その経緯は次のようなものだ。モーニングスターの創業者であるクリス・ルーファーが1990年に加工ビジネスに乗り出したとき、彼は「カリフォルニア州ロスバノス郊外の未舗装道路沿いにある小さな農家に」従業員を集めた、とセルフマネジメント研究所のポール・グリーンは書いている。人は自分の人生を自分でコントロールできるときが一番幸せであること、人は「思考力があり、エネルギッシュで、創造的で、思いやりがある」ものであること、そして最良の人間組織とは、他者によって管理されるのではなく、参加者が自分たちで調整する任意団体のようなものであること、である。皮肉屋をものともせず、モーニングスターが400人のフルタイム従業員(および3000人のパートタイム従業員)を抱える会社に成長するにつれ、このシステムは機能し続けた。
カオスのレシピとは程遠く、セルフマネジメントは見事に機能している。モーニングスターが成功し続けていることは、いくつかのビジネススクールでの研究を除けば、メディアからも学界からも無視されてきた。その理由のひとつは、同社があまりにスムーズに運営されているためニュースに取り上げられることが少ないこと、食品加工がローテクであること、同社がカリフォルニアの退屈なセントラル・バレーにあること、そして同社を設立したエートスが非常にリバタリアン的であることである。クリス・ルーファーは、必ずしも結果の平等ではなく、機会の自由を信奉している。そのため、メディアのおかしなアリス・イン・ワンダーランドの世界では、彼は「右翼」なのだ。だから彼は、労働者に力を与える偉大な企業改革者として、たとえそうであっても台座に乗せられることはない。何百もの企業がモーニングスターから自主経営について学び、熱狂して去っていった。しかし、それを実践した企業はほとんどない。なぜなら、最初の熱意は、本社に戻ってから報告書や会議の沼に消えてしまうからだ。ルファーのようにゼロから自主管理ビジネスを始めるのも一つの方法だ。既存の会社の従業員に役得を捨てろというのは、まったく別の話だ。
しかし、少しずつ、そしてあまりにもゆっくりと、このアイデアは浸透していくだろう。モーニングスターをはじめ、ネット通販のザッポスなど自主管理を試みている企業は、他の企業が徐々に暗黙のうちに不本意ながらやらざるを得なくなっていることを、明確かつ熱心にやっているに過ぎないと私は見ている。スーツを着て会議で発言するような労働者たちが、Tシャツにジーンズ姿の残りの労働者たちに何をすべきかを指示する「責任者」であるべきだという古い考え方は、考えてみれば奇妙なことだ。ホワイトカラーの幹部は、会社の生産的なメンバーのために働く雇われ使用人だと考えたらどうだろう?
アメリカの食品小売業であるホールフーズは、何を仕入れるか、どのように商品を宣伝するかの決定を、地域の店舗や店舗内のチームに委ねている。同社はまた、各チームが獲得したボーナスを他のチームと共有できるゲインシェアリングと呼ばれる制度も運営している。ホールフーズの共同創業者であるジョン・マッキーは、社会の不平等を破壊し、フラット化する自由市場の力を熱心に支持している。彼はまた、市場に進化が働いていることを見抜いている人物でもある。『ビジネスは実際には機械ではなく、複数の構成要素を持つ複雑で相互依存的な進化するシステムの一部なのだ』。
ああ、モーニングスター(少しソビエト的な名前だが)をスターリンのロシアや毛沢東の中国の集団農場と比較してみてほしい。ロシアや中国の農民は強制的に集団農場に参加させられ、離脱の機会を拒否され、中央から生産目標を与えられ、ボスにどんな仕事をすべきかを指示され、生産物が没収されて国家によって分配されるのを見なければならなかった。多くのロシア人が「第二の農奴制」と呼んだのも不思議ではない。真の平等主義が国家からではなく、むしろ自由から生まれることを示す、これ以上の好例があっただろうか。
経済発展の変遷
200年前まで、世界のほぼすべてが貧しかった。その後、一握りのヨーロッパ諸国と北米諸国が、想像を絶する快適さ、健康、そして国民の大多数にとっての機会を手に入れ、世界の残りの大半を置き去りにして脱出した。過去数十年の間に、さらに多くの国々がこの道をたどり、貧困からの大脱出を始めた。このような経済発展の過程は、ここ数十年で起きたことの中で最も重大で驚異的なことである。しかし、その手柄を立てることのできる「偉大な人物」(あるいは女性)はいない。実際、経済発展の歴史を詳しく調べれば調べるほど、それがリーダーシップのおかげであったということは少なくなる。
経済発展とは、単に所得が増加すること以上のものであり、人々がニーズを満たすのに要する時間を短縮するイノベーションを推進するために、人々が協力的に関与するシステム全体が出現することである。そして今日に至るまで、経済発展はほとんどどこでも起こりうることがわかっており、それを可能にするいくつかの条件もわかっているにもかかわらず、私たちはまだそれを本当に秩序立てて実現することはできない。プリンストン大学の経済学者ダニ・ロドリックとその同僚による一連の論文は、政策決定が経済成長に与える影響に光を当てようとしたが、「経済改革のほとんどの事例が成長加速をもたらすわけではない」こと、「成長加速のほとんどは、経済政策、制度的取り決め、政治的状況、外的条件の大きな変化に先行するものでも、それに伴うものでもない」ことを発見した。経済学者のウィリアム・イースタリーは、発展途上国のどこであれ、指導者の交代が成長の奇跡を引き起こしたという証拠はまったくないと指摘している。指導者が成長率に与える影響は限りなくゼロに近いと彼は言う。
1950年代の韓国とガーナの一人当たりの所得は同じだった。一方は他方よりはるかに多くの援助、助言、政治介入を受けた。今ではガーナの方が圧倒的に貧しい。一般的に、アジア経済は20世紀後半に貧困から脱却するために成長したが、アフリカ経済は貧困から脱却するために援助を受けることができなかった。援助ではなく、貿易が繁栄を拡大させる最良の方法であることが証明されたのだ。そして、専門家たちがアフリカが経済発展を遂げることに絶望し始め、時にはその理由を人種的、制度的に説明しようとさえし始めたとき、アフリカは突如として独自の発展の奇跡を経験し始めた。経済発展の物語はボトムアップの物語である。発展の欠如はトップダウンの物語である。
実際、経済発展における創造論に対する反論はそれ以上に強い。ウィリアム・イースタリーは、今日の貧困の真の原因は、それが回避可能である現在、権利のない貧しい人々に対する国家の野放図な権力であると言う。暗黙のうちに、今日の開発産業は専門家の助言を受けた独裁者に憧れている。しかし、このような専門家による専制政治は、より一般的な専制政治になることがあまりにも多い。自由な個人による自発的な解決策があれば、現在よりもはるかに多くの発展が達成されただろう。ディアドレ・マクロスキーが論じているように、「第三世界への社会主義の輸入は、議会党派のフェビアン=ガンジズムという比較的非暴力的な形であっても、意図せずして成長を阻害し、大企業家を富ませ、民衆を貧しいままにした」のである。
イースタリーのケースは、1920年代のロックフェラー財団による中国での援助から始まり、戦後のアフリカ、ラテンアメリカ、アジアでの政府資金による拡大、そして今日の大規模な民間および公的フィランソロピーにおける最新の表現に至るまで、援助の歴史の詳細な分析に基づいている。人道的支援は良いことであり、飢饉の被災者に食料を、病気の被災者に薬を、災害の被災者に避難所を提供することは、絶対に正しいことである。援助は、2014年から15年にかけて流行したエボラ出血熱のような危機を緩和するために不可欠である。意見の相違は、援助が単に危機に対応するのではなく、貧困を是正できるかどうかという点にある。貧しい人々にお金を与えることは、貧困に対する持続可能な解決策ではない。では、どうやって貧しい人々を助けるのか?専門知識と多くの政府によって彼らの生活を指導し、計画し、命令するのか、それとも彼らに交換と専門化の自由を与え、繁栄が発展するようにするのか?
フリードリヒ・ハイエクとグンナル・ミルダールは、この問いに正反対の答えを出したことで、1974年にノーベル経済学賞を受賞した。ハイエクは、個人の権利と自由こそが社会を貧困から脱出させる手段だと考えた。ミルダルは、「強制力に裏打ちされた規制」がなければ、開発は「ほとんど効果がない」と考えた。なぜなら、「ほとんど文盲で無気力な市民」は、政府の指示がなければ何も達成できないからである。ミルダルは、正しく、開発に関するコンセンサス見解を代表していると主張した。「低開発国は、全体的で統合された国家計画を持つべきであるということは、今や一般的に合意されている」ハイエクのアプローチは、1970年代には欧米の政府や国際機関にはほとんど存在しなかった。(不可解なことに、国家強制に反対する者は結局「右翼」のレッテルを貼られることになった)。
ミルダールのアプローチは、1920年代にロックフェラー財団が中国の農村の貧困を攻撃するための統合計画をまとめようとした際に予兆があった。イースタリーが指摘するように、これは本質的に、特権的な外国人による中国国内の飛び地の占領から話題を変えるための方法であった。西側諸国は、その占領を開発に関する技術的専門知識に変えようとしたのである。蒋介石は独裁的野心を支える資金を必要としていたため、喜んでそれに従った。ロックフェラー財団は中国の経済学者H.D.フォンを支援し、蒋は彼の権威主義的な開発ビジョンを採用した。開発援助は結局、独裁者の野望を支援することになり、その過ちが共産主義の専制への道を開くことになった。その意味で、善意の援助金は、世界で最も殺人的な政権を生み出す役割を果たしたかもしれない。ロックフェラーから資金援助を受けていたフォングの同僚で、経済学者のジョン・ベル・コンドリフは、何が起きているかを察知し、1938年に先見の明をもって警告した: われわれは、世界がかつて経験したことのないような、新しく手ごわい迷信、すなわち国民国家の神話に直面している。コンドリフは、独裁的な権力は貧困の解決策ではなく、その原因であると考えた。
第二次世界大戦後、植民地支配後のアフリカでも同じことが起こった。イギリスが撤退したことで、強者がほとんどの国を支配するようになった。しかし、イギリスが撤退する前に、彼らは技術主義的な開発システムを導入し、強者にとって必要な指揮、統制、資金の供給を確保した。なぜ彼らはこのようなことをしたのだろうか?第二次世界大戦中、ドイツと日本の成功によってイギリスの威信が脅かされ、ヘルメットをかぶった地方長官が神のように思えなくなったからだ。彼は、大英帝国は自らを「世界の後進諸国民を改善するための運動」として描くべきだと主張した。こうして、大英帝国は自らを進歩的な勢力として生まれ変わらせるのである。そしてもちろん、そのためには「中央政府側がはるかに大きなイニシアチブを発揮し、統制する」必要があった。植民地におけるイギリスの行政は、正義の執行というよりも、経済発展を促進することに突然重きを置くようになったのだ。このことは、独立の問題を脇に置く口実となった。ハイリーは、南部の分離独立についても同様の路線を提案することで、アメリカ人をこの路線に従わせた。経済的な改善が先で、政治的な解放は後回しでいいのだ。
その結果、1950年代から1960年代にかけて新たに解放された「第三世界」は、独裁的な前提を既製のものとして手渡されることになった。人民大衆は、自分たちの上に権威を持つ人々から手ほどきを受ける」と、1951年の国連の『開発のための入門書』は述べている。ハイエクは騙されなかった。彼は、国連憲章が「白人の支配を確保するための多かれ少なかれ意識的な努力」を意味していると見ていた。
技術主義的な開発哲学とまったく同じものが、冷戦下のアメリカにとって非常に有用であった。彼らは反ソ同盟国への支援を中立的な援助という隠れ蓑でごまかし、コロンビアのような場所に世界銀行の融資を配布して開発を促進し、反共政権を強化した。またしても、援助は独裁政権を強化するために使われたのだ。問題のひとつは、豊かな政府が、国家を開発の単位と見なし、むしろ国家内や国家間の個人と見なしていたことだ。ヨーロッパや日本では、20世紀半ばまでに権威主義体制は信用されなくなった。しかし、発展途上国では、国民国家がアメリカやヨーロッパからの援助によって効果的に支えられていたため、新たな息吹が与えられた。開発は、国家の集団的福利を何よりも優先させるという名目で、マイノリティの権利を抑圧するための意図せざる支援を与えた」とイースタリーは言う。
イースタリーは、現代の援助イニシアティブに関しては寛容ではない。トニー・ブレアのアフリカ・ガバナンス・イニシアチブは、その目標として「政府のプログラム実施能力の強化」を掲げている。エチオピアでは、これは政権の「村落化」プロジェクトへの支援を意味し、100万世帯以上がモデル村落に移転させられ、外国人投資家に売却する土地が解放される。かなりの不安と暴力が続いているが、この計画は資金だけでなく国際機関からの賞賛も得ている。ヒューマン・ライツ・ウォッチが2010年に発表した報告書『エチオピアにおける弾圧を支える援助のあり方』によると、エチオピアの指導者メレス・ゼナウィは援助資金を使って市民を脅迫し、野党を支持すれば飢えた人々への食糧援助を拒否したという。
もうひとつの例はマラウイだ。タバコ栽培から砂糖栽培への多角化を支援するための欧州連合(EU)の開発援助は、小農からの土地収用を助長するという逆効果をもたらした。この援助は、一部の富裕層が警察や村長に助けを求め、土地から人々を立ち退かせることで、より広い土地でより収益性の高い砂糖の栽培ができるようにするインセンティブを効果的に与えている。略奪的なエリートは、何十年もの間、アフリカやラテンアメリカの貧しい国々の悩みの種であり、援助はしばしば、意図的であろうとなかろうと、そうした略奪者に助成金を与えてきた。
香港の進化
古代エジプトから現代の北朝鮮に至るまで、常にどこでも、経済計画と統制が停滞を引き起こしてきた。一方、古代フェニキアから現代のベトナムに至るまで、経済的解放が繁栄をもたらしてきた。その典型的な例が都市国家である香港であり、その歴史は経済発展のあり方を示す輝かしい見本である。
イギリスの飛び地としての香港の物語は、帝国主義の不名誉なエピソードから始まる。イギリスはアヘン戦争で、銃を突きつけて中毒性の麻薬を中国人に押し付けた。しかしその後、香港は平和的で自発的な貿易の場となり、軽いタッチの政府を持つようになった。1843年に香港の初代総督に就任したアイルランド人のハリー・ポッティンジャー卿は、中国の一部を植民地化したり統治したりすることに反対し、代わりに自由貿易の中継地を主張した。そのため、彼は貿易への課税を一切拒否し、英国の敵国であっても香港での貿易を禁止せず、現地の慣習を尊重した。ポッティンガーは、征服と貢納に近いものを望んでいたイギリス住民には人気がなかったが、自由貿易の種をまき、次第に繁栄していった。それから100年以上経った1960年代、香港の財務長官だったジョン・カウパースウェイト卿が実験を再開した。彼は、ロンドンのLSEで学んだ師匠たちから、貧しく難民の多い島の経済を計画し、規制し、管理するよう指示されるのをすべて拒否した。商人にできることは商人に自由にさせる、それが彼の哲学だった。彼は、公共部門では異例なほど珍しい、予算を下回った官僚に報酬を与えた。3つの証券取引所を認め、イギリス人実業家の独占力を弱めた。ロンドンの強い要請で、彼は香港の商人たちに所得税を払いたいかと丁重に尋ねた。要するに、彼はアダム・スミスのレシピを試したのだ。今日、香港の一人当たりの所得はイギリスを上回っている。
13. 政府の進化
人が権力の頂点に登りつめようとするとき、常に
その行く手には常に危険がつきまとっていた。そして登りつめた頂点で
しばしば嫉妬が雷のように彼らを襲う。
彼らを軽蔑し、憎むべき地獄の穴に投げ込む。
ルクレティウス『自然の摂理』第5巻1123-6行
映画から判断するに、19世紀のアメリカ西部では、殺人は日常茶飯事だった。アビリーン、ウィチタ、ドッジ・シティのような牧畜の町では、政府が存在しないため(政府が存在するとすれば、臆病で腐敗しきった、あるいは手も足も出ない保安官という形であった)、ホッブズ的な虐殺が際限なく繰り返されていた。本当にそうだったのだろうか?実際、1870年から85年にかけての重要な時期に、そのような5つの牛の町で起こった殺人は、牛の取引シーズンに町あたり平均わずか1.5件だった。これはアメリカの大都市はおろか、その地域でも今日より低い殺人率である。しかし、どちらかと言えば、当時の牛の町の人口は多かった。ウィチタだけでも、州当局と連邦当局の総力を挙げて、現在では年間40件もの殺人事件が発生している。
実際、西部開拓時代には政府はほとんど存在しなかったが、無法地帯や暴力地帯とはほど遠かった。経済学者のテリー・アンダーソンとP.J.ヒルがその著書『The Not So Wild, Wild West』に記しているように、正式な法執行機構がほとんどなかったため、人々は自分たちで取り決めを作り、私設の執行官によって執行され、幌馬車からの追放などの簡単な手段で罰せられた。アンダーソンとヒルは、政府による強制力の独占がないため、複数の私的な法の執行者が出現し、それらの間の競争が自然淘汰によって繁栄した改良と革新を推進したと結論付けている。事実上、19世紀の牧畜業者たちは、中世の商人たちが発見したこと、つまり、習慣や法律は、それが課されないところに生まれるということを再発見したのである。それは無政府状態とはほど遠いものだった。
イェール大学のロバート・エリクソンは、カリフォルニア州シャスタ郡という農場と牧場が混在する地域で、この好例を最近記録した。エリクソンは、経済学者ロナルド・コース(取引コストがなければ、牧畜業者と小麦農家との間の過ちは、国家による処罰よりも私的な交渉によって正されると主張した)の有名な例をヒントに、不法侵入した牛に個人が実際にどのように対処しているかを調べた。その結果、法律はほとんど関係ないことがわかった。人々は個人的に、時には違法にさえ、この問題に対処した。例えば、牛の持ち主に電話をかけ、逃げ出した牛を引き取るように頼む。誰もが、いつか自分が文句を言われる側になる可能性が高いことを知っていたので、謝罪の返事をすることに熱心だった。これは田舎版の善良な隣人意識に過ぎない。問題のある隣人に対処するために、警察や裁判所にすぐに頼るような人は、一般的に悪いことをしたと考えられ、地域社会の善意を失うことになる。
政府とは、その根底にあるのは、公共の秩序を強制するための市民間の取り決めである。それは、部外者から押し付けられるのと同じくらい、いや、それ以上に、自然発生的に生まれたものである。そして、何世紀にもわたって、ほとんど計画を立てることなく、有機的に形を変えてきた。
刑務所における政府の進化
デビッド・スカルベックは、『アンダーワールドの社会秩序』と題した刑務所ギャングに関する興味深い最近の研究の中で、暴力の脅威に支えられているとはいえ、刑務所ギャングもまた、自然発生的な秩序の出現と精緻化の例であるという証拠を発見した。アメリカの刑務所は、秩序を完全に国家に依存してきたわけではない。知事や看守がいるのは確かだが、「掟」の大半は、「囚人の掟」として知られる囚人たちの間で自然発生的に生まれた習慣である。その基本的な前提は、刑務所内の規範に関する代表的な研究を行ったドナルド・クレマーの言葉を借りれば、次のようなものだ: 受刑者は、規律に関する問題で刑務所や政府の役人に協力することを控えなければならず、いかなる種類の情報でも、特に仲間の受刑者に害を及ぼすような情報を与えてはならない」スカルベックは、この掟は発明されたものではなく、発展したものだと指摘する。受刑者のグループが集まって決めたわけではない。違反者は仲間はずれにされ、嘲笑され、暴行され、死罪に処せられたが、処罰は分散されていた。誰も責任者ではなかった。受刑者規範は「社会的協力を促進し、社会的対立を減少させた。秩序を確立し、不正取引を助長した」
しかし、1970年代に入ると、女性刑務所ではないが、男性刑務所では囚人規定が崩壊し始めた。これは、刑務所の人口が急増し、受刑者の民族的多様性がより異質になったことと一致する。これは、私たちが国家以前の社会について知っていることと一致する。村やバンドが一定の規模を超えると、対人関係の行動規範が機能しなくなる。匿名性が強すぎるのだ。暴力は著しく増加したが、それ以外にもあることが起こり始めた。
1970年代を中心に、アメリカの刑務所システム全体でギャングが出現し始めた。外の世界のギャングとはほとんど何の関係もなく、そのようなストリートギャングのない地域で生まれた。30もの異なる刑務所に出現した。まるで誰かが、一種の改革としてギャングという考えを押し付けたかのようだった。しかし、ギャング文化は当局からではなく受刑者から生まれただけでなく、無意識のうちにそうなっていた。スカルベックが言うように、『存在する社会秩序は選ばれたものではない。「誰も責任者ではない」スコットランドの哲学者アダム・ファーガソンに倣って、スカルベックはこう結論づける: このようなボトムアップの施設出現のプロセスは、収容者の行動の結果であって、収容者の設計が実行されたわけではない。進化したのだ。
サン・クエンティンのメキシカンマフィアがそのようなギャングの最初であり、現在でも最も強力なギャングの一つであるが、他のギャングもすぐに続いた。ギャングの効果は、暴力を抑制し、麻薬やその他の商品の取引を増やし、価格を下げ、一般的に受刑者の生活を向上させることだった。スカルベックは、なぜこのような現象が起こったのかを分析し、初歩的な政府の出現という説明を除いて、すべての説明を除外した。ギャングの出現は、受刑者の間にガバナンスが欠如していたことに対する解決策だった。ギャングは秩序維持に役立つと知っていたからである。女性刑務所でギャングが結成されなかったのは、その人口がまだ十分に少なく、規範や行動規範が代わりに機能したからにほかならない。言い換えれば、政府は保護騒動として始まり、人口が一定の規模に達すると自然発生するのである。メキシコ・マフィアは現在、カリフォルニアの麻薬取引を刑務所内だけでなく路上でも支配し、麻薬の売人から家賃を引き出し、刑務所内では暴力の脅威によって権力を行使している。アメリカにおける最近の暴力事件減少の理由のひとつは、ギャングが麻薬取引に秩序を多少なりとも課すことに成功したからかもしれない。
保護組織の政府への進化
ギャングが政府になるということは、政府はギャングから始まったということだろうか?ケヴィン・ウィリアムソンが著書『The End is Near and it’s Going to be Awesome』の中で論じているように、組織犯罪と政府はいとこ同士以上の関係にある。つまり、政府は暴力を独占し、部外者の略奪から市民を守る代わりに家賃(税金)を取るという、マフィアの保護活動から始まったのだ。これがほとんどすべての政府の起源であり、今日のマフィアの保護組織はすべて政府へと進化する過程にある。マフィアそのものは、財産権が不安定で、豊富な元兵士が有償の保護者としてサービスを提供する用意があった無法の時代に、シチリアで誕生した。ロシアのマフィアも1990年代に同じように出現した。無法地帯の時代、多くの元兵士が仕事を求めていたのである。
歴史を通じて、国民国家の特徴は暴力を独占することである。古代ローマ、特に紀元前1世紀には、領事、将軍、総督、元老院議員たちが、それぞれ凶悪犯や軍団からなる独自の組織犯罪シンジケートを率いて、帝国征服の戦利品の分配をめぐって争い、内戦、暗殺、陰謀が繰り返され、次第に絶望的になっていった。彼はアウグストゥスと名乗り、パクス・ロマーナの到来を告げた。イアン・モリスが著書『戦争は何のためにあるのか』で論じているように、「暴力の逆説的論理が働いていた」皇帝は軍団を送り込むことができる(そして迫られれば送り込むだろう)と誰もが知っていたため、ほとんどその必要はなかった」
今日、私たちは一般に、国家は公正で公平であろうとする機関であり、個人の最悪の本能を手なずけるために存在する機関である、と善良な見方をしている。しかし、この制度の歴史について考えてみよう。事実上どこの国でも(米国と他のいくつかの旧植民地は特筆すべき例外だが)、政府は、11世紀にローマ教皇グレゴリウス7世が痛烈に言い放ったように、「高慢、略奪、裏切り、殺人、要するにあらゆる種類の犯罪によって、仲間よりも自分たちの地位を高めた」凶悪犯の集団として誕生した。経済史家ロバート・ヒッグスの言葉を借りれば、歴史の大半において、国家は「常に存在する捕食者であり、人権の全面的な乱用者」であった。ジョージ・ワシントンは、『政府は理性ではない。雄弁でもない。政府とは力である。火のように危険な下僕であり、恐るべき主人である」社会批評家のアルバート・ジェイ・ノックは、1939年に書いた文章で、特に皮肉屋になっていた。「国家は征服と没収、つまり犯罪に端を発している」おそらく私たちはそのようなことをすべて捨て去り、国家は今、温和で穏やかな美徳に向かって着実に進化しているのだろう。そうではないかもしれない。
チューダー朝の君主とタレバンはまったく同じ生地から作られている。ヘンリー7世がコルレオーネのように振る舞ったように、イスラム国も、コロンビアのFARCも、マフィアそのものも、アイルランド共和国軍も、厳格な道徳規範を強制し、商品(アヘン、コカイン、廃棄物処理)に「課税」し、違反者を罰し、福祉を提供するなど、ますます政府のように振る舞うようになった。そして現代の政府でさえ、犯罪組織の要素を持っている。米国国土安全保障省は設立からまだ10年あまりしか経っていないが、2011年には300人以上の職員が麻薬密輸、児童ポルノ、麻薬カルテルへの情報提供などの犯罪で逮捕されている。
アウグストゥスの軍団がそうであったように、国家が独占している兵器はできるだけ目に触れないようにしている。しかし、そこにあるのだ。アメリカでは個人所有の銃が多いことに頭を悩ませている人が多いが、公的に所有されている銃はどうだろう?近年、合衆国政府(軍ではない)は16億発の弾薬を購入しており、これは全人口を5回撃ち殺すのに十分な量である。社会保障庁は17万4000発のホローポイント弾を発注した。内国歳入庁、教育省、土地管理局、さらには国立海洋大気庁までもが銃を持っている。
2014年8月、ミズーリ州セントルイス郊外のファーガソンで暴動が発生したとき、警察が武器を搭載した装甲車に乗り、法執行機関というより軍隊のような制服と装備を身にまとって現れたことに、多くの人が衝撃を受けた。ランド・ポール上院議員は『タイム』誌で、連邦政府は地方警察の軍国主義化を煽り、自治体に資金を提供して「実質的に小さな軍隊を構築」させているとコメントした。ヘリテージ財団のエヴァン・バーニックはその1年前、国土安全保障省が全国の町に対テロ補助金を交付し、装甲車や銃、装甲、さらには航空機まで購入できるようにしたと警告していた。実際、国防総省は戦車などの軍用品を警察に寄贈している。『ワシントン・ポスト』紙のラドリー・バルコ記者は、麻薬、貧困、テロに対する「戦争」に内在する、警察と軍隊の境界線の曖昧さを慢性的に記録している。警察は市民を敵とみなす占領軍のような存在になっている。ポール議員は、法執行の軍事化が市民の自由の侵食と結びついて、非常に深刻な問題を引き起こしていると考えている。しかし実際は、これは新しい問題というよりも、アメリカ建国の父たちが、街路を行進する赤服連隊に直面したときに、あまりにも身近に感じたであろう古い問題なのだ。
リバタリアン・レベラーズ
つまり、政府は、保護騒動として始まったのである。1850年頃までは、リベラルで進歩的な人物は政府に対して不信感を抱くのが当然だと考えられていた。老子が「牛の毛よりも多い法律や規則」を持つ儒教国家の独裁的な指示主義を非難したように、1789年のサンスコロットに至るまで、貧しい人々の境遇を改善しようとする人々は、政府を敵視していた。政府は、労働者人民の背中に寄生し、搾取した金を戦争や贅沢や抑圧に費やすものだった。危険なのは、特定の階級が統治に適さないことではない」とアクトン卿は言った。あらゆる階級が統治に適していないのだ。問題なのは権力の乱用ではなく、乱用するための権力なのだ。
オックスフォードシャーのバーフォード教会は、急進左派の人々にとって巡礼の聖地である。1649年、オリバー・クロムウェルはここで、反乱を起こしたレヴェラー300人を投獄し、撤回を拒否した3人を銃殺した。今日、多くの人々はレヴェラーをディガーのような、つまり平等主義的、共同体主義的、革命的な前衛的社会主義者だと考えている。しかし、ダニエル・ハナンとダグラス・カーズウェル(それぞれ自由市場主義の欧州議会議員と国会議員)が主張するように、これは歴史を読み違えている。レヴェラー家は、今日でいうところのリバタリアン、あるいは古典的リベラル派であった。彼らは、私有財産、自由貿易、低税率、制限された政府、個人の自由を主張した。彼らにとっての敵は商業ではなく政府だった。彼らは反乱に参加し、国王の首をはね、腐敗し自己満足に陥った議会が再選挙を拒否し、自分たちの生得権だと感じていた古くからの経済的自由を保証しようとしないことに苛立ちを感じていた。その一方で、彼らの将軍は、自分を暴君として支配するために摂理によって選ばれた救世主のような人物だとますます考えているようだった。クロムウェルに対する彼らの直接的な不満は、アイルランド人に対する彼の宗教的・民族的十字軍を追求したくないということだったが、彼らのリバタリアニズムは政治的、経済的、個人的なものだった。
1649年のマニフェスト『イングランド自由民衆の協定』の中で、運動の4人の指導者、ジョン・リルバーン、トーマス・ウォルウィン、トーマス・プリンス、リチャード・オーバートンは、ロンドン塔の獄中から、政治家が増税や貿易制限をしすぎないよう要求した:
この国民が自由に貿易できる海を越えたいかなる場所でも、個人または個人の貿易や商品売買を妨げたり抑制したりするような法律を制定し続けることは、彼らの権限にはないものとする。
レヴェラーが、フリードリヒ・ハイエクやマレー・ロスバードをはじめ、ハナンやカースウェルに至るまで、現代の自由市場主義者たちから支持されているのも不思議ではない。
自由の助産婦としての商業
17世紀末までに、ヨーロッパの国家は、秩序を維持することを主な仕事とする中央集権的で官僚的な政府、トマス・ホッブズの『リヴァイアサン』を発明した。その後、栄光革命(イギリス革命)、アメリカ革命、フランス革命が起こり、政府は飼いならされ、解放され、制限され、「国民」に対して責任を負うべきだという考えが生まれた。
1850年までは、一方では自由貿易、制限された政府、低税率、他方では貧困層の擁護と困窮者の救済という方程式に誰も目を向けなかっただろう。18世紀を通じて、自由放任主義の擁護者たち、つまり財やサービスの自由な交換こそが一般的な幸福を向上させる最善の方法だと考える人々は、政治的には「左派」に属していた。1688年のホイッグ、1776年の反乱軍、そしてロックやヴォルテールからコンドルセやスミスに至るまで、彼らにインスピレーションを与えた思想家たちは、急進的な進歩主義者であり、自由市場と小さな政府のリベラル派だった。(ヴォルテールは穀物商人として財を成した)国家が自由と進歩の機関であると主張しても、それは意味がなかっただろう。国家が暴力の独占と取引の決定権を主張するだけでなく、宗教的な遵守事項を細かく規定し、言論や文章を検閲し、階級に応じた服装まで義務付けていた時代である。それだけでなく、スティーヴン・デイヴィスが指摘するように、特にドイツでは18世紀の新しい考え方が定着しつつあった。フリードリヒ大王は自らを国家の最初の下僕と呼んだが、「最初の」と同様に「下僕」に重点が置かれていた。つまり、商品やサービスを交換する自由を信奉する急進派は、思想や行動の自由も信奉していたのである。
自由市場がいかに急進的な思想であったかを示す一例として、1793年、北部の啓蒙的なアテネであったはずのエディンバラで、トーマス・ミューアという人物が扇動罪で裁判にかけられた。彼はオーストラリアに14年間移送されることになった。ウィリアム・スキービングとモーリス・マーガロットは、自由貿易についてアダム・スミスの意見に共鳴したとして、同じ判決を受けた。その翌年、後にアダム・スミスの伝記作家となるデュガルド・スチュワートが、本の中でコンドルセの名前に言及したことを深く謝罪したのも不思議ではない。啓蒙主義は、庇の下に隠れるしかなかったのである。
自由貿易と自由な思考
トーマス・ジェファーソンとアレクサンダー・ハミルトンの哲学を対比してみよう。紳士であるジェファーソンは啓蒙主義の哲学を身につけ、ルクレティウスを崇拝した。しかし結局のところ、彼は農耕民族的で、保護され、階層的で、安定したヴァージニア社会を望んでいた。彼は「大都市で互いに積み重なる」人々の暮らしぶりを嫌い、アメリカに「我々の作業場はヨーロッパに残す」ことを提案した。商業と豊富な資本がもたらす創造的破壊、社会階層の解体、権力の転覆といった未来を受け入れたのは、混沌としたマンハッタンに住む移民ハミルトンだった(ただし、彼は幼児産業を保護するために小額の関税を主張した)。
イギリスでは、反奴隷制社会の創始者は自由商人だった。例えば、ハリエット・マーティノーの著作を読んでみよう。彼女は、1830年代に『政治経済学の図解』と呼ばれる一連の短い小説本で一躍有名になった。これらは、アダム・スミス(「その卓越性は驚くべきものである」と彼女は言った)や他の経済学者たちの思想を人々に教えることを意図したものであった。それらはすべて、市場と個人主義の美徳について書かれている。今日では、ほとんどの人が彼女を右翼と呼ぶだろう。しかし、マルティヌーは熱烈なフェミニストであり、ペンで生きる労働者女性であり、政治的急進主義者であり、同時代の人々からはほとんど危険視されていた(チャールズ・ダーウィンの父親は、彼女が彼の2人の立派な息子と親しくなったことを心配していた)。彼女は奴隷制度に反対する情熱的な演説をしながらアメリカを巡り、サウスカロライナ州では彼女をリンチする計画があったほど悪名高い存在となった。しかし矛盾はない。彼女の経済的リバタリアニズムは、政治的リバタリアニズムと一体のものだったのだ。リベラル派は、市場経済からも市民の私生活からも、腐敗した専制的な国家のデッドハンドを取り除こうとしていた。当時、強い国家を疑うことは左翼であることだった。
19世紀初頭のイギリスでは、自由貿易、小さな政府、個人の自治は、奴隷制度、植民地主義、政治的庇護、既成教会への反対とほぼ自動的に結びついていた。1795年、国会開会に向かうジョージ3世の馬車を取り囲んだ暴徒は、トウモロコシの自由貿易とパンの販売に関する複数かつ詳細な規制の撤廃を求めていた。1815年にキャッスルレーグ卿の家に押し入った暴徒は、保護主義に反対していた。1819年に騎兵隊に襲撃されたマンチェスターの平和的デモ(「ピータールーの虐殺」)は、自由貿易と政治改革を支持するものだった。労働者階級の意識を先導したチャーティストは、反コーン法同盟の創設メンバーだった。
あるいは、1840年から1865年にかけて、イギリスが世界に模範を示し、世界をもつれさせていた関税を一方的かつ力強く撤廃したあの異常な時期を誰よりも担っていた自由貿易の偉大な擁護者、リチャード・コブデンを取り上げてみよう。(アヘン戦争とクリミア戦争に反対して不人気を覚悟した熱烈な平和主義者であり、貧しい人々のために尽力し、下院で初めて演説したときには危険な急進派として罵声を浴びせた。彼は正真正銘の急進派だった。しかし、平和と繁栄を実現するための最善の手段として自由貿易を支持した。人民が互いにもっと関わり合い、政府がもっと少なくなれば、地球に平和が訪れるだろう」と、まるでティーパーティーのメンバーのような口調で語った。自由貿易を純粋に支持したコブデンは、ジョン・スチュアート・ミルが一時期、乳幼児産業には保護が必要だという考えをちらつかせたことを非難したほどである。彼はアダム・スミスとデイヴィッド・リカルドの考えを取り入れ、実行に移した。その結果、世界中で経済成長が加速した。
今日の左派と右派が抱く大義名分が、1つの頭の中で平和的に共存しているのだ。政治的解放と経済的解放は手を取り合った。小さな政府は急進的で進歩的な提案だった。1660年から1846年にかけて、イギリス政府は処方箋によって食料価格をコントロールしようとするむなしい試みの中で、驚くことに127ものコーン法を制定し、関税だけでなく、穀物やパンの貯蔵、販売、輸出入、品質に関する規則を課した。1815年には、穀物価格がナポレオン時代の戦時中の最高値から下落したため、地主を保護するために、価格が1/4あたり80シリング(28ポンド)を下回った場合、すべての穀物の輸入を禁止した。このため、自由貿易の若き理論家デイヴィッド・リカルドが熱烈なパンフレットを出したが、効果はなかった(彼の友人でトウモロコシ法の支持者であったロバート・マルサスの方が説得力があった)。流れが変わったのは、鉄道とペニーポストによって、コブデンとジョン・ブライトが労働者階級を代表して法律に反対する大衆運動を起こした1840年代になってからだった。1845年にアイルランドで飢饉が発生し、トーリーの指導者ロバート・ピールでさえ敗北を認めざるを得なくなった。
コブデンの驚くべきコーン法反対運動は、その後、より一般的な関税保護反対運動へと発展し、最終的には、国民の多くや多くの知識人だけでなく、当時の主要な政治家、特にウィリアム・ユワート・グラッドストーンを説得することに成功した。この偉大な改革派の首相兼首相は、貧困層の窮状からアイルランドの自治に至るまで、あらゆる種類の進歩的な大義を唱え、経済学においては確信に満ちた自由貿易主義者で、国家の規模を着実に縮小していった。最終的には、コブデンと彼の同盟国はフランスに勝利した。コブデンはナポレオン3世に自由貿易の素晴らしさを説き、自らも1860年に最初の国際自由貿易条約、いわゆるコブデン=シュヴァリエ条約を交渉した。この条約はまた、無条件の「最恵国待遇」条項の原則を確立し、ヨーロッパ全土に関税撤廃の連鎖をもたらし、事実上、近代史上初めて巨大な自由貿易圏を作り上げたが、もちろんすべての商品が影響を受けたわけではない。イタリア、スイス、ノルウェー、スペイン、オーストリア、そしてハンザ同盟諸国もすぐにこれに追随し、関税を撤廃した。
エイドリアン・ウールドリッジとジョン・ミクルウェイトがその著書『第4の革命』の中で自由主義国家と呼んでいるものは、ジョン・ロックに始まり、トーマス・ジェファーソンに支持され、ジョン・スチュアート・ミルにその最も明確な提唱者を見出し、リチャード・コブデンにその最も急進的な極みに達したかもしれない。それは出現したのであり、進化したのである。
政府の反革命
しかし、コブデンの功績は、19世紀が進むにつれて損なわれ始めた。1870年代後半、ビスマルクのドイツは通貨の過大評価に苦しみ、不況を招いた。その原因は、普仏戦争後にフランスが占領した領土を取り戻すために支払わされた戦争賠償金の支払いで、フランスから50億フランもの巨額の資本が流入したことにあった。この不況と、皇帝暗殺未遂事件後の保守的な議会選出に対応して、1879年、ビスマルクはドイツの工業と農業を保護するために「鉄とライ麦」関税を導入した。これを皮切りに、1880年から第一次世界大戦が始まるまで、アメリカ、フランス、南米で次々と関税引き上げが行われた。イギリスだけが孤軍奮闘し、関税の導入も、導入した国々への報復も、20世紀になるまで反抗的に拒否した。ジョセフ・チェンバレンとその同盟者であるトーリー党から「関税改革」と「帝国優先主義」を求める強い圧力があったにもかかわらず、イギリスの自由貿易への宗教的ともいえるほどの傾倒は、第一次世界大戦まで、そして大戦後も続いた。その後、自由党は次第に右派の帝国優先保守党と左派の自給自足を促す保護主義的な労働党候補によって圧迫されていった。それでも、ネヴィル・チェンバレンが一般関税を導入したのは1932年のことだった。
保護主義の復活は、ブリンク・リンゼーが19世紀最後の四半世紀に始まった産業反革命と呼ぶものの一部であった。産業革命が解き放っためまぐるしいイノベーションの発酵の中でヒエラルキーの維持を望む懐古的な反動保守派と、政府が社会変革を主導すべきだと考える進歩的改革派との間に、新たな同盟が生まれたのだ。ディアドレ・マクロスキーが診断したように、「ブルジョワの父親の息子たちは、ナショナリズムという世俗化された信仰と、社会主義という世俗化された希望の復活に魅了された。カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスが経済的変化を恐れたことからもわかるだろう。生産の絶え間ない革命化、あらゆる社会条件の絶え間ない乱れ、絶え間ない不安と動揺がブルジョア・エポックを際立たせる」とマルクスとエンゲルスは『共産党宣言』で慟哭した。固いものはすべて空気に溶け、聖なるものはすべて冒涜される」ウィリアム・モリスと彼の仲間の社会主義者たちは、安定した、シンプルな中世のメリーイングランドの喪失を嘆き、アーサー王伝説のファンタジーの上に新しい社会主義のエルサレムを築いた。
芸術の分野でも、その変化ははっきりと見て取れる。19世紀初頭、多くの詩人、小説家、劇作家は、古典的自由主義、自由貿易、限定政府を熱烈に支持していた。シラー、ゲーテ、バイロンの作品を見てみよう。ジュゼッペ・ヴェルディの『リゴレット』や『アイーダ』には、権力の本質に関する非常に自由主義的な物語が含まれている。開放的な商業社会は、芸術家をパトロン制度から解放し、裕福な個体に頼るのではなく、大衆市場で作品を売ることができるようにした。しかし、時代が下るにつれ、多くの芸術家がブルジョワ社会を矮小化するものとして捉え、自由主義を敵視するようになった。自由主義秩序を批判したのは、ヘンリック・イプセン、ギュスターヴ・フローベール、エミール・ゾラなどである。これらの反対派は、自由主義秩序を否定的に描く上で重要な役割を果たした。
真の急進派、自由と変革のビジョンを持つ人々、コブデンやミルやハーバート・スペンサーのような人々は、その後、極めて不当に「右派」に捨てられた。彼らは平和主義者であり、平等主義者であり、フェミニストであり、リベラルであり、国際主義者であり、宗教的自由思想家であった。しかし、これらの目標を達成する最良の方法としての自由市場に対する彼らの愛情は、20世紀の目には、彼らを左派から右派へと政治的スペクトルを横断するように映った。
君主とその子分たちの権力と闘ってきた数世紀は、子分たちを自分たちで任命するチャンスがあれば、突然忘れ去られてしまう。もはや個人の自由を守ることが政治の最大の目的ではなく、これからは計画と福祉が必要なのだ。革命は今後、プロレタリアートの賢明な指導者たちによって指揮されるトップダウンのものになるだろう。リベラリズムは、1905年にA.V.ダイシーが書いたように、「中央国家の有益な効果に少なからぬ信頼を置く」ことを学んだ。
ビジネスもまた、政府の介入を受け入れた。19世紀が終わると、強盗男爵のような実業家たちは、無駄な競争をなくすために、カルテルを結んだり、政府の規制を歓迎したりしようと躍起になった。しかし、アダム・スミス以来そうであったように、この縁故主義によって経済学の専門家から嘲笑を浴びるどころか、今では喝采を浴びている。エドワード・ベラミーやソーシュタイン・ヴェブレンのような左派の思想的指導者たちは、ビジネスにおける重複と分断に終止符を打つことを要求した。彼らは、計画、立案者、単一の構造がなければならない、と同意した。絶大な影響力を持ち、ベストセラーとなった小説『Looking Backward』に登場するベラミの未来像では、未来の誰もがグレート・トラストのために働き、政府が所有する同一の店舗で同一の商品を購入する。
レーニンとスターリンでさえ、科学的管理、計画的な労働者収容、巨大な資本を必要とするアメリカの大企業を賞賛するようになった。科学的管理の偉大な使徒であるフレデリック・ウィンスロー・テイラーについて、レーニンは「われわれはロシアでテイラー・システムの研究と指導を組織し、体系的に試行し、われわれの目的に適合させなければならない」と書いている。『ネイション』紙のリバタリアン編集者エド・ゴドキンは、1900年に次のように嘆いた。『リベラルの教義を支持しているのは、大部分が老人である残党だけであり、彼らがいなくなれば、リベラルの擁護者はいなくなるだろう』。『リベラル』という言葉そのものが、特にアメリカではその意味を変えた。意図していないにせよ、最高の賛辞として、私企業のシステムの敵は、このレッテルを貼るのが賢明だと考えた」とヨーゼフ・シュンペーターは言った。誰もが、特に左派は、未来への鍵は進化ではなく命令と統制だと考えていた。
政府は社会を設計するための道具である。1900年前後には、プロレタリアート独裁を目指す共産主義者であろうと、敵を征服し社会を規制しようとする軍国主義者であろうと、新しい工場を建設し製品を販売しようとする資本家であろうと、この考え方は正しかった。もう一度言うが、プランナーとしての政府の役割という概念は、発明されたのではなく、出現したのである。
リベラル・ファシズム
忘れられがちだが、ウッドロウ・ウィルソンとその後継者たちの時代に、アメリカは著しく非自由主義的な場所になった。人種隔離の強化、優生保護法の普及、禁酒法だけでなく、検閲や市民的自由の圧迫もそうだった。ジョナ・ゴールドバーグは、第一次世界大戦中、あるハリウッドのプロデューサーが、アメリカ独立戦争中に残虐行為を働いたイギリス軍を描いたために10年の実刑判決を受けたことを思い起こさせる。
フランクリン・ルーズベルトのニューディールのレトリックの中には、ドイツやイタリアで起きていたことと呼応するものがあった。ニューディーラーたちが、彼らの暴力を模倣することは考えなかったとしても、経済や社会秩序の改善における全体主義政権の見かけ上の成功を模倣することに熱心であったことを示す証拠は豊富にある。計画、計画、計画が各方面で叫ばれていた。ジョセフ・シュンペーターは、フランクリン・ルーズベルトは独裁者になるつもりだと考えていた。
ジョナ・ゴールドバーグはその著書『リベラル・ファシズム』の中で、1930年代にはファシズムは進歩的な運動として広く見られ、左派の多くに支持されていたと指摘している。「ファシズムを正しく理解すれば、それは右派の現象ではなく、常に左派の現象であった。この事実は、不都合な真実があったとしても、ファシズムと共産主義が正反対のものであるという同じように誤った信念によって、現代では見えにくくなっている。現実には、両者は密接に関連し、同じ構成員をめぐる歴史的競争相手なのだ」1930年代の 「ラジオ司祭」チャールズ・コフーリン神父は、アメリカの政治においてヒトラーの目的と方法を最もよく模倣していたが、非常に左翼的な人物だった。銀行家を批判し、産業の国有化と労働者の権利の保護を要求した。彼の反ユダヤ主義だけが「右派」と言える。「リベラル・ファシスト」という言葉は、1932年にH.G.ウェルズがオックスフォードで行った演説の中で好意的に使われた言葉である。それ以前の1927年、ウェルズは「ファシストには良いところがある。彼らには勇敢で善意的なところがある」と述べている。
今日の視点から、あるいはコブデン=ミル=スミスのようなリベラル派から見れば、20世紀のさまざまな「イズム」の間に大きな違いはない。共産主義、ファシズム、ナショナリズム、コーポラティズム、保護主義、テイラー主義、ディリギスム–これらはすべて、計画を核とする中央集権体制である。ムッソリーニが共産主義者として、ヒトラーが社会主義者として出発し、オズワルド・モズレーが保守党として当選後すぐに労働党議員となり、ファシストに転向したのも不思議ではない。ファシズムと共産主義は国家の宗教であり、またそうである。インテリジェント・デザインの一種である。宗教が神の足元を崇拝するのとまったく同じように、政治指導者の足元を崇拝し、少なくとも全能、全知、無謬の傾向があると主張する。共産主義では通常、指導者は個人ではなく政党であり、神は長いあごひげを生やした死んだ男だというふりを最初はするが、それは長くは続かない。すぐに指導者の名前はマルクスの名前に取って代わられる: スターリン、毛沢東、カストロ、キムだ。確かに、ファシストは農場を集団化せず、営利を目的とした私企業の運営を認めたが、それは国家が定めた区域内で、国家が定めた目標を達成するためだけだった。「すべては国家の中に、国家の外には何もない」とムッソリーニは言った。ゴールドバーグが指摘するように、ヒトラーが共産主義者を嫌ったのは、彼らの経済的教義やブルジョアジーの破壊を望んだからではない。彼は『我が闘争』の中で労働組合を擁護し、現代の反資本主義者と同じくらい熱心に実業家の貪欲さと「近視眼的な視野の狭さ」を攻撃した。いや、彼が共産主義を憎んだのは、『我が闘争』を通じて明らかにしたように、共産主義を外国のユダヤ人の陰謀だと考えたからだ。
リバタリアンの復活
第二次世界大戦で、指揮統制国家は頂点に達した。ほとんどの国がファシスト、共産主義、植民地政権によって厳格な権威主義路線で運営されただけでなく、民主主義が生き残った一握りの例外でさえ、戦争と戦うための緊急措置として包括的な中央計画を事実上採用した。確かにイギリスやアメリカでは、生活のほとんどすべての側面が国家によって決定された。昔ながらの個人主義、つまりリベラリズムは事実上消滅していた。そうだろうか?戦時中の中央集権主義の下で、戦争が終わったら計画経済を解体しなければならないと要求する一握りの声が聞こえてくる。ハーバート・アーガーやコルム・ブローガンといった人々だ。後者は、1943年の著書『「国民」とは誰か』の中で、次のように警告している。『侵略を免れた英国の国民は、最後の試練を免れたが、思想は海峡に完全に敗北したわけではない。ドイツ軍が押し付けようとしている新しい経済秩序は、そうしなければならないからそうなるのだという理論への支持が高まっている」
ナチスと共産主義の全体主義は対極にあるのではなく、近しい隣人であると西側の受け入れ側に主張したのである。これらの声の中で最も有名なのはフリードリヒ・ハイエクで、『奴隷への道』(1944)の中で、社会主義とファシズムは実際には対立するものではなく、「方法と思想の根本的な類似点」があり、経済計画と国家統制は専制、抑圧、農奴制につながる非自由主義的な坂道の頂点にあり、自由市場の個人主義こそが真の解放への道である、と先見的な警告を発した。
ハイエクを無視して、イギリスは勝利から数カ月以内に、産業、医療、教育、社会における生産手段の包括的な国有化に乗り出した。抵抗する政治家はほとんどいなかった。1951年に復活したウィンストン・チャーチルの保守党政権でさえ、ハーバート・スペンサーとリチャード・コブデンの熱烈な崇拝者であるアーネスト・ベン卿というリバタリアンの急進派がいなければ、国民に身分証明書を義務づけ続けただろう。
ドイツはもっと幸運だった。1948年7月、西ドイツ経済評議会議長のルートヴィヒ・エアハルトは、自らの主導で食糧配給を廃止し、市場を信頼してすべての価格統制を廃止した。アメリカの占領地の軍事総督であったルシウス・クレイ将軍が彼に電話をかけ、『私のアドバイザーは、あなたのしたことはとんでもない間違いだと言っている。君はどう思うかね?エアハルトはこう答えた!私のアドバイザーも同じことを言っている』」と答えた。ドイツ経済の奇跡はその日に生まれた。
神としての政府
しかし、政府における創造論は衰える気配を見せない。第二次世界大戦後、特に冷戦後、リベラルな価値観が復活したにもかかわらず、今日に至るまで、知識人の多くは、進化論的な展開よりもむしろ、計画論に基づいた思い込みをしている。政治家はクズとみなされるが、政府という機械はほとんど無謬であると考えられている。アメリカでは、政府支出は1913年のGDPの7.5%から、1960年には27% 2000年には30%、2011年には41%に上昇した。ロナルド・レーガンの反革命は、富裕層から不利な立場にある人々へだけでなく、中産階級から中産階級への福祉の導管となった政府の前進を一時停止させたに過ぎない。多くの人は、政府はもはや可能な限りの大きさまで進化し、これ以上の規模は維持できないと考えている。
しかし、政府の進化の次の段階は国際的なものだ。人々の生活の多くの側面を決定する力を持つ国際的な官僚組織の成長は、現代の支配的な特徴である。欧州連合(EU)ですら、より高いレベルで決められたルールを加盟国に伝えるだけで、ますます無力になっている。例えば、食品規格はコーデックスと呼ばれる国連機関が決定している。銀行業界のルールは、スイスのバーゼルに本部を置く委員会が決めている。金融規制はパリにある金融安定理事会によって決定される。国連の子会社である自動車規制調和世界フォーラムを知らない人はいないだろう。
将来的には、天気さえもリヴァイアサンがコントロールするようになるだろう。2012年のインタビューで、クリスティアナ・フィゲレス国連気候変動枠組条約事務局長は、彼女と彼女の同僚たちは、政府、民間企業、市民社会がこれまでに行ったことのない大きな変革を行うよう鼓舞していると語った: 産業革命も変革だったが、中央集権的な政策の観点から導かれた変革ではなかった。これは中央集権的な変革だ
しかし、おそらく他の進化の力が蠢いているのだろう。介護、教育、規制など、政府が専門的に提供してきたサービスは、自動化やデジタル変革の影響を最も受けにくいものだった。それが変わりつつあるのかもしれない。2011年、英国政府はマイク・ブラッケンというデジタル起業家を雇い、大規模なIT契約の管理方法の改革を依頼した。大臣であるフランシス・モードの支援を受けて、彼は「ウォーターフォール」と呼ばれる、事前にニーズを特定し、予算や時間をオーバーしてしまうプロジェクトを、よりダーウィン的なものに置き換えるシステムを考え出した。
ブラッケン氏にこのアプローチについてインタビューしたとき、2014年までにいくつかの顕著な成功を収め始めていた。特に、gov.ukと名付けられた単一の政府ウェブポータルが、1,800もの別々のウェブサイトに代わって、徐々にではあるが加速度的に展開され始めたことで、私は彼が述べていることが創造論とは対照的な進化論であることに気づいた。ティム・ハーフォードは2011年の著書『Adapt』の中で、イラクの平和化であれ、航空機の設計であれ、ブロードウェイ・ミュージカルの脚本であれ、成功した経営者は低コストの試行錯誤と漸進的な変化を十分に許容してきたと指摘していた。世界経済からレーザープリンターまで、私たちが使っているものはすべて、壮大な計画ではなく、小さな一歩一歩の積み重ねによって生まれているのだ。
エリートが物事を誤るのは、『政治の終焉とiデモクラシーの誕生』の中でダグラス・カースウェルが言うように、「下から自然に組織されるのが最善である世界を、デザインによって統治しようと際限なく求めるからである。公共政策の失敗は、計画立案者が意図的な設計を過度に信頼することから生じている。彼らは一貫して、自然発生的で有機的な取り決めのメリットを過小評価し、最良の計画は多くの場合、持たないことであることを認識していない」
エピローグ
未来の進化
20世紀を語るには2つの方法がある。一連の戦争、革命、危機、伝染病、金融災難を説明することもできる。収入の増加、病気の克服、寄生虫の消滅、欠乏の後退、平和の持続、寿命の延長、テクノロジーの進歩などである。私は後者の話について一冊の本を書いたが、なぜそうすることが独創的で意外に思えるのか不思議だった。世界がこれまでよりずっとずっと良い場所であることは、輝かしいほどに明らかだったはずだ。しかし、新聞を読めば、私たちは災難から災難へと突進し、さらなる災難が避けられない未来に直面していると思うだろう。学校の歴史カリキュラムに目をやると、過去の災害と未来の危機が完全に支配している。この楽観主義と悲観主義の奇妙な並置を、私は自分の中でうまく調和させることができなかった。悪いニュースが際限なく続く世界で、人々の生活はどんどん良くなっていく。
そして本書の目的は、その理解を探ることでもある。私の説明を最も大胆かつ驚くべき形で言えば、悪いニュースは人為的、トップダウン的、意図的なものであり、歴史に押し付けられたものである。良いニュースとは、偶発的で、無計画で、徐々に進化する創発的なものである。うまくいくことの大部分は意図されなかったものであり、うまくいかないことの大部分は意図されたものである。2つのリストを挙げよう。一つ目は、第一次世界大戦、ロシア革命、ヴェルサイユ条約、世界恐慌、ナチス政権、第二次世界大戦、中国革命 2008年の金融危機であり、そのどれもが、政治家、中央銀行家、革命家など、意図的な計画を実行しようとする比較的少数の人々によるトップダウンの意思決定の結果であった。第二に、世界的な所得の増加、感染症の消滅、70億人への食糧供給、河川と大気の浄化、豊かな世界の森林再生、インターネット、携帯電話クレジットの銀行としての利用、犯罪者を有罪にし、無実の人を無罪にするための遺伝子指紋の利用である。これらのひとつひとつは、大きな変化を起こそうとは意図していなかった何百万人もの人々によってもたらされた、セレンディピティで予期せぬ現象である。過去50年間の人間の生活水準の統計における大きな変化のうち、政府の行動によってもたらされたものはほとんどない。
もちろん、ある個人や組織が計画に基づいて特に良いことをした(月面着陸か)とか、ある突発的な現象が悲惨なほど悪かった(過剰な衛生状態の結果、アレルギーや自己免疫疾患が増加した?) しかし私は、このような現象はそれほど多くないと考えている。悪いことをしながら良いことを進化させることが、歴史の支配的なテーマであった。だからこそ、ニュースでは悪いことばかりが取り上げられるが、それが終わると、人知れず素晴らしい良いことが起きていることに気づくのだ。良いことは徐々に、悪いことは突然に起こる。とりわけ、良いことは進化する。
しかし、そんなことは大げさだという声が聞こえてきそうだ。世の中には、設計され、計画され、意図され、うまく機能しているものがぎっしり詰まっている。しかし、秩序があるからといって、それが設計されたとは限らない。多くの場合、それは偶然の試行錯誤によって生まれたものだ。ブリンク・リンゼイは、秩序とコントロールを同一視することは、直感的に訴える力が強いと指摘している。無計画な市場の明らかな成功にもかかわらず、インターネットの非中央集権的な秩序の華々しい台頭にもかかわらず、そして「複雑性」という新しい科学とその自己組織化システムの研究がよく知られているにもかかわらず、中央の権威に代わる唯一のものはカオスであると、いまだに広く思われている」
美しいデザインの典型的な例、例えば私がこの言葉を書いている素晴らしいMacbook Airのようなものでさえ、実際には進化のプロセスの結果であり、それは何千人もの発明家の仕事を組み合わせただけでなく、無数の可能性のあるデザインを選別し、このバージョンを選択してから市場に送り出し、選択されるか拒否されるかを決めるのである。確かに、ジョナサン・アイブ卿は、このデザインを含むアップルの優れたデザインの数々で称賛を浴びており、それは当然のことである。しかし、ケイ素チップ、ソフトウェア、アルマイト加工されたアルミニウムの筐体など、材料や構成部品の起源は他の発明家たちにある。それらを組み合わせ、選択するプロセスはボトムアップだった。このノートパソコンは、少なくともそれが作られたのと同じくらい進化した。
プロローグで論じたように、1859年にチャールズ・ダーウィンが概説した自然淘汰による進化論は、進化の「一般理論」と区別するために、本当は進化の「特別理論」と呼ぶべきだ。この考え方は、進化と革新の両方の専門家であるリチャード・ウェッブに負うところが大きい。つまり、歴史の歯車は試行錯誤による漸進的な変化であり、イノベーションは組換えによって引き起こされる。これは、道徳、経済、文化、言語、技術、都市、企業、教育、歴史、法律、政府、宗教、貨幣、社会における変化の主な方法でもある。私たちはあまりにも長い間、上からの変化をデザインすることに執着するあまり、下からの自発的で有機的かつ建設的な変化の力を過小評価してきた。一般的な進化論を受け入れよう。あらゆるものが進化することを認めよ。
21世紀は、ほとんどが悪い知らせのショックに支配されるだろうが、ほとんどが目に見えない良いことの進歩を経験するだろう。漸進的、不可避的、必然的な変化は、私たちに物質的、精神的な向上をもたらし、孫たちの生活をより豊かに、より健康に、より幸せに、より賢く、より清潔に、より優しく、より自由に、より平和に、より平等にするだろう。しかし、壮大な計画を持つ人々は、その過程で痛みや苦しみを引き起こすだろう。
あらゆるものの進化を奨励し祝福する一方で、創造論者の功績をもう少し減らしてあげよう。
謝辞
本書は何年も、おそらく何十年もかけて構想されたものであり、その間に私にインスピレーションと思考の糧を与えてくれたすべての人に感謝することは不可能である。私が執拗に指摘するように、人間の思考は分散型現象であり、人間の脳の内部ではなく、人間の脳の間、あるいは人間の脳の間で生きている。私は知識の巨大なネットワークにおけるノードに過ぎず、幽玄で進化し続ける存在をわずかな不十分な言葉で捉えようとしているに過ぎない。これは、私以外の誰かがこの本のいかなる間違いに対しても非難に値するということを言いたいのではない。
それにもかかわらず、多くの人々が、彼らの考え、提案、警告、そして時間を惜しみなく提供してくれたことに特に感謝したい。その中には、これらに限定されるわけではないが、以下の人々が含まれる: Brian Arthur、Eric Beinhocker、Don Boudreaux、Karol Boudreaux、Giovanni Carrada、Douglas Carswell、Monika Cheney、Gregory Clark、Stephen Colarelli、John Constable、Patrick Cramer、Rupert Darwall、Richard Dawkins、Daniel Dennett、Megnad Desai、Kate Distin、Bernard Donoughue、Martin Durkin、Danny Finkelstein、David Fletcher、Bob Frank、 Louis-Vincent Gave, Herb Gintis, Hannes Gissurarson, Dean Godson, Oliver Goodenough, Anthony Gottlieb, Brigitte Granville, Jonathan Haidt, Daniel Hannan, Tim Harford, Judith Rich Harris, Joe Henrich, Dominic Hobson, Tom Holland, Lydia Hopper, Anula Jayasuriya, Terence Kealey, Hyperion Knight, Kwasi Kwarteng, Norman Lamont、 ナイジェル・ローソン、クワイ・リー、マーク・リトルウッド、ニクラス・ルンドブラッド、ディアドレ・マクロスキー、ジェフリー・ミラー、アルベルト・ミンガルディ、スガタ・ミトラ、アンドリュー・モンフォード、ティム・モンゴメリー、ジョン・モイニハン、ジェシー・ノーマン、セリーナ・オグレイディ、ゲリー・オーストロム、ジム・オッテソン、オーウェン・パターソン、ローズ・パターソン、ベニー・パイザー、ヴェンキ・ラマクリシュナン、ニール・レコード、ピート・リチャーソンアダム・リドリー、ラス・ロバーツ、ポール・ローマー、ポール・ルーシン、デイヴィッド・ローズ、ジョージ・セルギン、アンドリュー・シュエン、エミリー・スカルベック、ビル・ステイシー、ジョン・ティアニー、リチャード・トール、ジェームズ・トゥーリー、アンドリュー・トーランス、ナイジェル・ヴィンソン、アンドレアス・ワグナー、リチャード・ウェッブ、リンダ・ウェットストーン、デイヴィッド・スローン・ウィルソン、ジョン・ウィザロウ、アンドリュー・ワーク、ティム・ウォーストール、クリス・ライト、その他多数。
この本のリサーチと執筆にあたっては、ガイ・ベントレーとアンドレア・ブラッドフォードから多くの貴重で実践的な協力を得た。彼らに心から感謝している。エージェントのフェリシティ・ブライアンとピーター・ギンズバーグ、編集者のルイーズ・ヘインズとテリー・カーテンは、終始忍耐強く、励まし、鋭く指導してくれた。
アイデアと洞察力だけでなく、聖域と正気にも貢献してくれた家族、アーニャ、マシュー、アイリスに最大の感謝を捧げたい。
エピローグ未来の進化
デビッド・バトラー卿の、漸進的な変化は政府の行動とはほとんど関係がないという指摘について、2015年2月27日、BBCラジオ4でのアンドリュー・ディルノ卿とのインタビュー。
秩序なき現象について、Lindsey, Brink 2002. Against the Dead Hand. John Wiley & Sons.
The evolution of everything : How new ideas emerge / Matt Ridley.
グリーンブラットの本は、成功した本がそうであるように、他の学者たちから厳しく批判されている。その主な理由は、彼が中世の聖職者たちの無教養と無知を誇張していると非難されていること、この詩が少なくとも9世紀には散発的に言及されていたという事実を見逃していること、宗教的思考に対して厳しすぎること、などである。しかし、De Rerum Naturaが再発見された後も、キリスト教によって弾圧・攻撃され、1417年以降に広く流布されると、ルネサンスと啓蒙思想に影響を与えたという彼の主な主張において、グリーンブラットが正しいことは間違いない。
ハーバート・スペンサーは、歴史上最も不当に貶められた人物の一人であり、今日その評判は、悪魔に一番後ろを取らせて喜んでいる冷酷な社会ダーウィン主義者というものである。これは第一級の中傷である。彼は、人生の競争から取り残された人々への同情、思いやり、慈愛を提唱し、競争がすべての人々の生活水準を引き上げるから競争を支持したのであって、最も成功した人々を助けるからではない。彼は、偉大な思いやりと自由主義を持つ、繊細で優れた思想家であった。軍国主義、帝国主義、国家宗教、国家専制政治、あらゆる強制に熱烈に反対し、フェミニストであり、組織労働の支持者でもあった。だから、彼を「力こそ正義」と考えていると非難するのは正反対に間違っている。しかし、彼が、同時代のライバルであったカール・マルクスが、国家を解放の手段と見なす道を歩んだことを嘆いたのは事実である。彼は、「保護者であるべきなのに暴君を演じる」ことを恐れる政府に常に不信感を抱き、自発的な協力を奨励することを好んだ。彼の国家に対する冷笑的な見方は、20世紀の出来事と共産主義が残した1億人の死体によって十分に証明された。ディアドレ・マクロスキーの言葉を借りれば、「20世紀を経てもなお、徹底的な社会主義、ナショナリズム、帝国主義、動員、中央計画、規制、ゾーニング、価格統制、税制、労働組合、企業カルテル、政府支出、押しつけがましい取り締まり、外交政策における冒険主義、宗教と政治を絡ませる信仰、その他19世紀に提案された徹底的な政府行動のほとんどが、私たちの生活を向上させるためのきちんとした無害なアイデアだと考えている人は、注意を払っていない」のである。また、スペンサーは不幸な人々に対する無慈悲を提唱したわけでもない。だから、彼の今日の評判が、権威主義政策に対する西洋と東洋の熱狂の頂点にあった1944年に、マルクス主義者の歴史家ダグラス・ホスフタッターによって書かれた、敵対的で誤解を招く記述によるところが大きいのは不当である。Richards, Peter 2008を参照のこと。ハーバート・スペンサー(1820-1903): Social Darwinist or Libertarian Prophet?, Libertarian Heritage 26 and Mingardi, Alberto 2011. Herbert Spencer. Bloomsbury Academic. Deirdre McCloskeyの発言は、「Factual Free-Market Fairness」というエッセイからのものである。bledingheartlibertarians.comで入手できる。
1772年の金融危機は、ロンドンでの借金返済のためにアメリカから大量の金を引き出したことと、東インド会社がイングランド銀行の融資を不履行としたことから、間接的にアメリカ独立へとつながった。これがボストン茶会につながった。アメリカの自由、そして憲法につながる偉大な思想は、言い換えれば、金融と商業の危機からボトムアップでその機会を得たのである。
