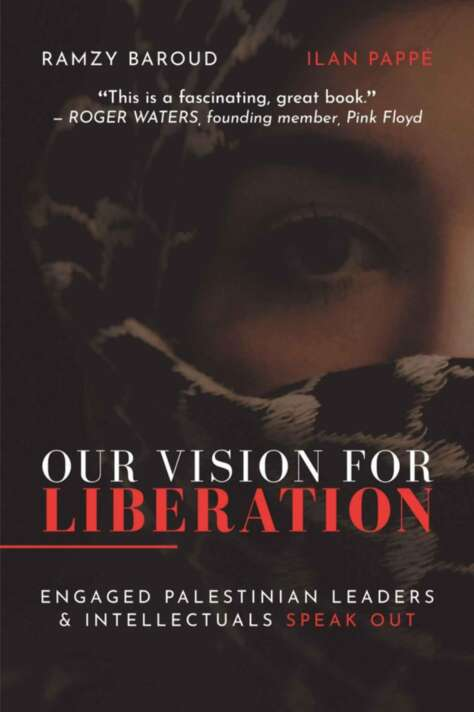
Our Vision For Liberation
称賛
「世界が居住可能な未来への希望と指針を切実に必要としている今、脱植民地化され、民主的で自由なパレスチナの感動的なヴィジョンは、自由への集団的な憧れが生き残っている場所ならどこでも共鳴するだろう。パレスチナの知識人、活動家、芸術家たちは、パレスチナの未来と地球の運命の両方を照らす道標である」
-アンジェラ・デイヴィス(アメリカの活動家、作家、教授)は、米国内外のあらゆる抑圧と闘うための継続的な活動で国際的に知られている。
「このブレイクスルー本は、パレスチナが解放されるという疑念を打ち砕くだろう。このブレイクスルー本は、パレスチナが解放されるという疑念を打ち砕くだろう。その複数の真実と次元は、川から海へと復活するパレスチナの可能性を破壊しようと企む者たちを恐怖に陥れるだろう。生きた経験と知的な記憶の傑作である本書で語られるパレスチナの声とビジョンは、強さ、文化、知性、組織の創造性、ダイナミズムを備えており、勝利する解放のビジョンを予感させる。この本を読めば、あなたは強くなり、奮い立つだろう。シオニストの幻想と帝国主義の支配に死を告げる一冊だ。すべてのページが自由の香りを漂わせている。これは、植民地主義の恐怖から私たちすべてを解き放つ喜びへの頌歌であり、可能性のある未来への高揚を垣間見せてくれる」
-ロニー・カスリルス(南アフリカの作家、政治家、反アパルトヘイトの象徴
「本書は温かい歓迎に値する。パレスチナ人の功績とその文化の豊かな多様性を称えている。明らかに、彼らの抵抗精神は健在である。本書の暗黙の挑戦は、正義と法の支配を憂うすべての人々に向けられたものであり、パレスチナ人をイスラエルによる残酷な抑圧から解放することである」
-ケン・ローチ、著名なイギリス人映画監督(彼の作品には『ケス』『私、ダニエル・ブレイク』などがある)。
「イラン・パッペとラムジー・バルードが編集したこの傑出したアンソロジーには、雄弁で楽観的な論理がある。それは、雪の下の種子のように、普遍的な運動の力が下から現れるとき、パレスチナは自由になるということだ」
-ジョーン・ピルガー(高名なオーストラリア人ジャーナリスト、作家、学者、ドキュメンタリー映画監督
「パレスチナ人の勇敢でスマートな声に注目することはとても重要である。本書は、こうした声、パレスチナの声だけでなく、私たちの頭の中に響く声、私たちを促し、行進することによって世界を変えるために通りに出るように言う声も載せている」
-ヴィジャイ・プラシャード(インド人歴史家、編集者、ジャーナリスト、三大陸社会研究所所長
「このエッセイ集に収められた生の証言は、パレスチナの人種差別アパルトヘイト占領者たちに明確なメッセージを送っている。私たちはここに立っている。文化、考古学、歴史、そして土地の証拠がここにある。あなた方が自分自身と世界に、存在しないと説得しようとしたものだ」
これらのエッセイは、シオニスト事業の全体主義的性質に対する抵抗の継続的な強さを強調している。撤去されなければならなかったのは、村落を破壊され、土地を奪われ、自生していた生物を刈り取られた人々だけでなく、パレスチナ全体であった。
しかし、1世紀経ってもこの目標は達成されていない。そして今、川と海の間には、抑圧者たちよりも多くのパレスチナ人がいるが、明らかに、この目標は達成されることはないだろう。
これらのエッセイは、読者をパレスチナ人の個人的な体験へと深く誘う。考古学者、投獄された女性、タペストリーの織り手、大学教授、農業従事者、ジャーナリスト、詩人、音楽家、映画監督、そして祖国から遠く離れて暮らす亡命者たちは、抑圧者に向けて送られた2つのメッセージ、すなわち反抗と、ある日パレスチナが再び自由になるという揺るぎない確信で結ばれている。
-プロフェッサー・ジェレミー・ソルト、『中東の解体』著者: アラブにおける西洋の無秩序の歴史』の著者である。
「これは魅力的で素晴らしい本だ」
-ロジャー・ウォーターズ(世界的に有名なイギリスのソングライター、ミュージシャン、ベーシスト、シンガー、プログレッシブ・ロック・バンド、ピンク・フロイドの創設メンバー、終生反アパルトヘイト、人権擁護、親パレスチナ活動家
この素晴らしい本を読む中で
1964年のマフムード・ダルウィーシュのIDカードの詩に出会った。
死んだ主人にメッセージがある
そして死んだ母と死んだ父に
そして彼らが戦った土地だ
だから、あなたは天国と地獄を見分けられると思う
天国と地獄
青い空と苦しみを区別できるか?
緑の野原と
冷たい鉄のレールから
微笑みとベール
区別がつくと思うか?
英雄と幽霊を交換させられた
英雄を亡霊と交換させられた
熱い灰を木に
熱風を涼風に
冷たい慰めを変化と交換した
そしてあなたは交換した
戦争に参加する
檻の中の主役のために
いや、君はそうしなかった
私の母も父もそうしなかった
私もそうだ
私たちは皆、ここにいる
生きて、そして死ぬ
肩を並べて
肩を並べて
パレスチナが解放されるまで
ロジャー・ウォーターズ
2021年12月22日
*ロジャー・ウォーターズの父、エリック・フレッチャーは、第二次世界大戦のアンツィオの戦いで、ファシズムとナチズムと戦って戦死した。
欧州パレスチナ研究センター
アラブ・イスラーム研究所
エクセター大学
ストリータムキャンパス
エクセター EX4 4ND, イギリス
スハ・ジャラールへ
木は立ったまま枯れる
目次
- 謝辞
- まえがき -ラムジー・バルード
- 序論 -イラン・パペ
- 第1章 解放の起源と記憶
- 大地と記憶を掘り起こす 私たちの解放における考古学の役割 -ハムダン・タハ
- 物語をコントロールする闘い 解放を追い求めるとき、言葉に気をつけよう -イブラヒム・G・アウデ
- メディアについての考察 解放のための強力なツール -カセム・イザット・アリ
- パレスチナを解放するために、難民に力を与えよう -サマア・アブ・シャラール
- 記憶なくして未来はない デポルティーボ・パレスティーノとチリのパレスチナ人の物語 -アヌアル・マジルフ・イッサ
- 平等な権利キャンペーン シオニズム終焉への鍵 -ガダ・カルミ
- 解放の倫理 存在の様式としてのパレスチナ -ランダ・アブデル=ファタハ
- 空白に書く -サマ・サバウィ
- 第2部 抵抗のさまざまな顔
- 抵抗する者は幸いである 解放のためのキリスト教的ビジョン -マヌエル・ムサラム神父
- 自由なパレスチナのための世界的連帯運動に向けて 政府、政党、組織、大衆行動ネットワークを巻き込む -サミ・A・アル・アリアン
- 私たちはムラビタットである 占領地エルサレムに抵抗の種を蒔く -ハナディ・ハラワニ
- 絶望から希望を生み出す イスラエルの刑務所内で抵抗し、勝利する方法 -ハリダ・ジャラール
- 民衆の抵抗とBDSについて パレスチナ闘争の未来 -ジャマール・ジュマー
- 国際法を通じてパレスチナの救済を追求する -ラジ・スーラニ
- 第3部
- 解放、文化、教育について 「ベイトダラスの来年」 私たちの物語を取り戻し、私たちの物語を語る -ガダ・アギール
- 針の穴を通して パレスチナの抵抗の歴史とサムードを縫い合わせる -ジェハン・アルファラとヤン・チャルマース -厳選された刺繍: パレスチナの歴史タペストリープロジェクト
- 抵抗の手段としての文化観光 開発を促進しながら文化遺産を保護する -テリー・ブーラタ
- 流血のない戦争 解放の歌 -リーム・タルハミ
- 映画による解放 権力、アイデンティティ、芸術について -ファラ・ナブルシ
- 解放の心理学 セラピー、気づき、そして批判的意識の発達 -サマ・ワクチンル
- 私たちが学ぶことについてのパレスチナ人の考察 -マジン・クムシエ
- 第1部 V
- 解放、政治、エンパワーメントと連帯について パレスチナの悲劇を巡る個人的な旅 -ハサン・アブ・ニマ
- 敵を研究する ケーススタディとしてのMADAR -ジョニー・マンスール
- 「普通」を求めて シオニストの植民地的枠組みにおけるパレスチナ市民権 -ハニーン・ゾアビ
- 見せかけの市民権から解放の言説へ ひとつの世俗的民主国家キャンペーン -アワド・アブデルファッタ
- 尊厳とエンパワーメントについて 我々の闘いにおけるチャリティーの役割 -ライラ・アル=マラヤティ
- 解放を助ける -ノーラ・レスター・モラド
- パレスチナのための国際的な闘い -イラン・パッペ
- ポストスクリプト -ラムジー・バルード
- 寄稿者
- 制作チーム
- 索引
謝辞
本書が単なる思いつきから出版に至るまで、その制作に協力してくれたすべての人々に感謝するには、1ページや2ページでは足りない。本書を飾った刺激的な著者たちの文章は、調査、議論、翻訳、編集、校正を含む様々な貢献という点で、私たちと関わってくださった多くの方々のほんの一部に過ぎない。
クラリティ・プレスのダイアナ・G・コリアーには、この構想の立ち上げから熱意を持ってサポートしてもらい、感謝している。彼女のフィードバックと絶え間ない励ましが、この複雑で時間のかかる緊急プロジェクトを可能にした。
イタリアのジャーナリスト、編集者、翻訳者であるロマーナ・ルベオは、本書の制作に不可欠な役割を果たした。彼女は、プロジェクトの管理から内容の一部の翻訳、校正に至るまで、いくつかの重要な役割を果たしてくれた。ありがとう、ロマーナ。あなたの助けとサポートは不可欠だった。
シルビア・フェルナンデスは、本書のコピーエディター以上の役割を果たしてくれた。彼女のフィードバック、アイデア、細部への配慮のおかげで、多くの知識人の仕事を1冊にまとめることができた。彼女は巨大なプロジェクトを引き受け、忍耐と気品をもってその役割を果たした。彼女には感謝している。
サマ・サバウィはこの仕事において重要な役割を果たした。彼女のエッセイ 「Writing in the Blank Spaces」は、パレスチナの物語において重要な役割を果たすものであり、しばしば軽視されるものである。しかし、彼女はそれ以上の存在である。彼女のアラビア語から英語への見事な翻訳によって、私たちはパレスチナの知識人の声を聞くことができる、より包括的な空間を作ることができた。
また、この重要なプロジェクトに賛同してくれたエクセター大学とヨーロッパ・パレスチナ研究センターにも感謝の意を表したい。このプロジェクトは、パレスチナ知識人を中心とした言説を支持しつつ、パレスチナについてより積極的な思考が進むことを期待するものである。
このプロジェクトの真の主役は、その遺志、思想、そして忍耐力によって、本書を今日の形にしている、すべてのパレスチナ人、そしてパレスチナやあらゆる場所における正義と人権を支持する人たちに関わる、緊急の対話の発端となった知識人たちである。皆さん、本当にありがとう。あなた方の自由なパレスチナのための犠牲と不屈の努力は、何世代にもわたって評価されるだろう。
サバ・サバウィ、ロマーナ・ルベオのほか、アーメド・アルマスリ、ナヘド・エルレイエスなど、本書の制作に携わってくれた優秀な翻訳者たちに感謝する。
パレスチナの作家でありジャーナリストのアリ・アブニマには、特別な感謝の意を表したい。
Yousef Aljamal、Iain Chalmers、Marisa Consolata Kemper、Yafa Jarrar、Sheryl Bedas、Ahmed Yousef、Rabab Abdulhadi、John Harvey、Salman Abu Sitta、Maren Mantovani、Louis Brehonyにも感謝する、 Noha Khalaf, Islah Jad, Triestino Mariniello, Aida and the late Carl Bradley, Tamara De Melo, Richard Falk, Omar Aziz, Mark Seddon, Erica Aloang Aquino, Issam Adwan, Vincenzo Rubeo, Anna Cacace.
また、Palestinian Centre for Human Rights(PCHR)、Center for Islamic and Global Affairs(CIGA)、Palestine Deep Diveの貢献と支援にも感謝したい。
私たちの家族の忍耐、サポート、励ましにも感謝する。表紙モデルのイマン・バルード、クリエイティブ・デザイナーのザレファー・バルード、スポーツ・コンサルタントのサミー・バルードに特別な感謝を捧げたい。彼らはパレスチナの新星だ。
前書き
“Los libertadores no existen. Son los pueblos quienes se liberan a sí mismos.”
解放者は存在しない 自らを解放するのは人民である
-エルネスト・チェ・ゲバラ
アルゼンチンの革命家に由来するこの有名な言葉は、南米と同様にパレスチナの場合にも当てはまる。
しかし、パレスチナでは、私たちはあまりにも多くの解放者、より正確には自称解放者を持つという点で非常に不運であった。利己的なパレスチナの指導者たちから、腐敗したアラブの支配者たち、さらには混乱した西側のイデオローグに至るまで、多くの人々が「パレスチナの解放」が自分たちの政治的課題の中心であると、ほとんど行動しないにもかかわらず、大げさに主張してきた。
私はガザ地区の難民キャンプで育った。父の知的サークルは、志を同じくする社会主義者、元政治犯、真の革命家、つまりグラムシアン的な意味での有機的知識人で構成されていた。父のように、彼らは皆、「アラブ人の反逆」、国際秩序の絶望、シオニストがアメリカを支配していることに常に言及し、正当な皮肉屋だった。しかし、彼らは次のような提案にはまったく腹を立てていただろうが、まったく世間知らずとまでは言わないまでも、ある程度は政治的に無邪気でもあった。「アラブの同胞」に対する絶え間ない暴言にもかかわらず、彼らはまだ、解放をもたらすアラブ軍が奇跡的にパレスチナを救いに来てくれることを望んでいた。
第一次インティファーダ(1987年の民衆蜂起)の最中には、エジプト軍がシナイ砂漠を横断してガザのイスラエル占領軍に立ち向かうという噂や、サダム・フセインがイラク軍にヨルダンを経由してパレスチナに進軍するよう命じたという噂、そして、パレスチナ人が特に好きだと聞いていたアルジェリア人ですら、イスラエルの残虐行為の前にパレスチナのアラブ近隣諸国が沈黙していることに辟易し、地中海を経由して海軍を派遣することを決めたという噂が飛び交っていた。父とその友人たちはいつも、そんなことはくだらない噂だと最初からわかっていたと主張したが、私は、新しい噂が出るたびに、彼らの声にめまいがするのを聞き、目に興奮が浮かぶのを見たのを覚えている。
解放するアラブ人、ひいては解放するムスリムは、パレスチナの民衆の言説の中で多くの場所を占めてきた。地元のモスクのイマームは、いつも金曜日の説教の最後に「アッラーが眠っているアラブとムスリムのウンマを目覚めさせ、パレスチナとアル・アクサ・モスクを解放してくださいますように」と祈った。父や彼の共産主義者と言われる友人たちを含む私たち信者は、声をそろえて 「アーミーン」と繰り返した。インティファーダが終わる頃には、誰も私たちを解放しに来ないことは明らかだった。
それ以来、私は多くの国に住み、旅し、パレスチナとの連帯がさまざまな政治運動やイデオロギー運動の中心となっている、あるいは少なくとも関連している数多くの知的空間と交流してきた。世界中の普通の人々がパレスチナに対して抱いている真の愛と純粋な関心は、感動的である以上に、活力を与えてくれる。コロラド州に住むネイティブ・アメリカンの女性は、がんで死期が迫っていることを知りながら、パレスチナが自由になる日を迎えられないことが最大の後悔だと私に語った。南アフリカ人の新婚カップルは、パレスチナ占領下の東エルサレムにあるアル・アクサ・モスクで祈りを捧げた日が、彼らの人生で最も幸せな日だったと話してくれた。アイルランドの元戦闘員で囚人の男性は、パレスチナの自由と同程度に、自国民の真の自由のために尽力していると私に断言した。
パレスチナとの世界的な連帯の高まりと、パレスチナ・ボイコット、ダイベストメント、制裁(BDS)運動の多大な成功、そしてあらゆる形態の不正義に対抗するすべての人々の闘いの相互関連性/相互交差性に対する認識の高まりから判断すれば、パレスチナとの連帯はつかの間の現象ではないと確信できる。しかし、パレスチナを代表する指導者から発せられるような、一元化されたパレスチナの政治戦略は依然として欠けているため、多くの人々がパレスチナ人のために、そしてパレスチナ人を代表して、率先して発言することが多い。
数年前、講演旅行でイギリスを訪れた私は、パレスチナ人自身の政治的言説、彼らの文化的、民族的願望、歴史などが、パレスチナとの真の連帯の指針となるべきだと繰り返し主張した。驚いたことに、あるイギリス人活動家はこう抗議した。「私たちの連帯は、連帯を必要としている人々に対する深い理解に左右されるべきではない。彼は、「ベトナムをアメリカ帝国主義から解放」したのは「彼の世代」であり、今日に至るまでベトナム文化について何も知らない、と言った。私は、この英雄的な闘いに対する明らかな誤った表現に唖然とした。チェ・ゲバラの言葉どおり、真に自らを解放できるのは自分たちだけなのだ。
長年、パレスチナの人々は、一見不可能な政治的二項対立に陥ってきた。一方では、彼らは莫大な犠牲を払い、正義と自由のための民族闘争を1世紀にわたって維持する能力があることを証明してきたが、他方では、パレスチナの故エドワード・サイード教授の言葉を借りれば、彼らはまた、「悪いリーダーシップにひどく呪われている」
パレスチナには、リーダーシップの各分野で最も熟達し、有能で、教養と情報に恵まれた女性や男性がいるにもかかわらず、パレスチナの人々がこのような「悪いリーダーシップ」に苦しめられてきたのは、呪いによるものではなく、政治的意図によるものであることは明らかだ。本書は、パレスチナが提供できるものの縮図に過ぎない。しかし問題は、そのような潜在的なリーダーシップがしばしば疎外され、沈黙させられ、投獄され、暗殺さえされていることだ。真のパレスチナの指導者や知識人が傍観され、あるいは完全に排除されることで、政治的空間は意図的に、詐欺的な指導者、政治家の回し者、金目当てのヤブたちのために開かれている。
私たちの「解放のビジョン」は、パレスチナ解放の新しい見方を提示する試みである。本書で謳われているような解放を成功させるためには、パレスチナ人をその中核に据えなければならない。そして、真に関与しているパレスチナ人が中心となって、自分たちの民族の犠牲を伝えるだけでなく、彼らを動員し、力を与えなければならない。そのような関与するパレスチナ人は、国際連帯運動にとっても重要である。本物のパレスチナ人の声に導かれていない連帯は、単に無益である。パレスチナ人の真の望みを反映することはできず、したがって、最も必要なもの、つまりパレスチナ人の支持を効果的に動員することはできない。
偉大な歴史家イラン・パッペを敬愛する私は、エクセター大学のヨーロッパ・パレスチナ研究センターで彼の博士課程に在籍できたことを本当に光栄に思っていた。当時の私の関心は、パレスチナ人の歴史を伝える代替的で非エリート主義的な方法を見つけることだった。強力な一族や裕福な指導者、政治的な派閥といった伝統的なルートではなく、ガザの狭く貧しい路地や、レバノンのアイン・エル・ヒルウェ難民キャンプの埃っぽい道 2002年のイスラエル侵攻後に占領下のヨルダン川西岸にあるジェニン難民キャンプが瓦礫の山と化した場所を通して、パレスチナの歴史を伝える別の方法を想像したかった。私は、パレスチナ、その悲劇、勝利、そして願望を定義した普通のパレスチナ人男女の物語という、異なる種類の物語を語りたかったのだ。私は2015年に学位を取得したが、この感動的な先生の永遠の生徒であり続けている。
2018年に発表された記事で、パッペはこう書いている、
イスラエルとパレスチナに純粋に平和と和解をもたらすものを説明するためには、70年経った今、時代遅れに思えるかもしれない言葉に頼らざるを得ない。脱植民地化とは、イスラエルとパレスチナに真の平和と和解をもたらすものである。まず第一に、政治的終局、あるいは解放のプロジェクトの更新されたビジョンについて、より正確で統一されたパレスチナの立場が必要となる。
パレスチナは、急進的な脱植民地化を必要としている。正義と自由はおろか、パレスチナ人にいかなる形の解放も否定しようと共謀する勢力は、自らの矛盾の重圧に耐えかねて崩れ落ちるのを放っておくには、あまりにも強力すぎるからだ。実際、イスラエルの決然とした植民地プロジェクト、無関係なパレスチナの「指導者」、自己顕示欲の強い権威主義的アラブ政権に挟まれたパレスチナ人には、自らの解放者となる以外に選択肢はない。
『私たちのヴィジョン』は、過去を解剖したり、過去にこだわったりすることを目的とした知的訓練ではなく、パッペが促した「統一されたパレスチナの立場」を思い描きながら、前を見据えるための真剣な試みである。
本書を私の師であり友人であるイラン・パペ教授と共同編集できたことを光栄に思う。パレスチナの読者だけでなく、世界中の正義の戦士である私たちすべてに多くのことを教えてくれる。
-ラムジー・バラウド、2021年11月
はじめに
解放のためのパレスチナの闘いは、さまざまな形をとり、多様な抵抗様式に基づいている。この闘争は通常、19世紀後半に植民地化され、今日もなお占領と植民地化の下にある国家の集団的努力と表現されるが、それは理解できる。闘いが続いている以上、その成否について合理的な判断を下すことは無意味である。現時点で合理的かつ最も重要なことは、この集団的努力を形成している個々の闘いを記録し、認識することである。それらは時に忘れ去られたり見過ごされたりするが、解放闘争の一員である人々やそれを支援する人々が、なぜ将来の最終的な成功への希望を捨てないのかを理解する上で極めて重要なのである。
自由と解放のための闘いに関するこれらの個人的な物語を記録することを決めたとき、私たちはまず、各寄稿者の個人的な貢献と経験の全体像を把握することを望んだ。しかし、幸運にもそれ以上のものを得ることができた。それぞれの記述には、祖国であれ亡命先であれ、最近の、あるいはもっと遠いパレスチナの過去への窓を開く伝記的なセクションがある。これは、ナクバによって失われたもの、そして回復力、堅忍不抜、献身によって取り戻されたものについて多くを語っている。
例えば、ハムダン・タハによる冒頭の章は、解放のための闘いにおけるパレスチナの考古学者と考古学の役割を評価している。この章は、1967年にイスラエルがヨルダン川西岸を占領した日、12歳の村の少年の生活を垣間見ることから始まる。この章の感動的な一節で、ハムダンはこの少年が、後にティーンエイジャーとなる少年が、いかにしてパレスチナを代表する考古学者になったかを語っている。それは彼にとって、占領によって押しつけられた新たな抑圧的現実との最初の出会いであり、彼をパレスチナを代表する考古学者としての驚くべきキャリアへと導いた。今日でさえ、ハムダンは否定と抹殺の考古学的物語と日々闘わなければならない。この不吉なキャンペーンは、古代の歴史学を歪曲するだけでなく、誤解を招くような言説を生み出し、欺瞞的な語彙を発明することによっても行われている。
言葉の歪曲がパレスチナの過去と現在の現実をいかに誤魔化しうるかは、イブラヒム・G・アウデのライフストーリーの本質的な部分であり、彼の職業上の献身は、解放闘争における言説と言葉の役割を前面に押し出すものである。彼の職業人生は、当初からパレスチナ人の存在を否定する詐欺を助長し、それを支えてきたシオニストの語彙に対抗することに捧げられてきた。彼特有の文化的抵抗の方法は、日々実行され、今世紀になってようやく、彼が語るように、具体的で勇気づけられる結果を生み出した。
公的領域はこの言説に影響され、それを広めるのは主にメディアであり、それゆえ解放のための闘いにおいてメディアが果たす役割は極めて大きい。メディア領域で働く私たちの寄稿者たちは、若いパレスチナ人が後に続き、将来影響力のあるジャーナリストやメディア関係者になることを後押しするようなライフストーリーを語っている。
家庭や学校での強力な教育的背景は、メディアで成功するための典型的なルートであるが、パレスチナの場合、カセム・アリ・カファルネのライフストーリーが物語るように、独学で、個人の強い意志によって学ばなければならないことが多い。カセムは、パレスチナを代表するジャーナリストへの道をどのように歩み始めたかを語ってくれた:
私の旅の次の部分は、解放のための闘いにおける強力なツールとしてのジャーナリズムと有意義に関わるための、形成的かつ基本的な要素であることが判明した。彼らの人生経験を集め、政治的ビジョンについて議論し、イデオロギーや宗教、文化的構成について意見をぶつけ合う。
フォーマルな教育とインフォーマルな教育の両方が、将来一流のジャーナリストとして活躍するための準備となった。そのような非公式の場所のひとつが、イスラエルの刑務所だった:
私たちのナショナリズムを混ぜ合わせ、触媒とし、民族として団結させ、ジェンダー、社会経済的、宗教的、イデオロギー的な障壁を消し去り、そしてこれらすべてをイスラエルの抑圧者が銀の皿に載せて提供した: 刑務所である。
サマア・アブ・シャラールもまた、メディア闘争で重要な役割を果たし、パレスチナ人が解放のための闘いの過程で下す選択について考えている:
私たちはよく、「人生の選択は自分で決めるものだ」と言われる。ほとんどのパレスチナ人の場合、それは贅沢なことであり、私たちはしばしばそれに甘んじることはないと思う。
しかし、サマアの章が示すように、このような運命的な役割は、選ぶのではなく、受け入れることで、パレスチナの苦境を人々に認識させ、特にパレスチナ難民の帰還の権利に絶えず光を当てるメディアや専門的ジャーナリズムの砦を構築する先駆的な仕事につながる。これは、欧米の援助と支援によって油を注がれたイスラエルの巨大なプロパガンダ・マシンが、パレスチナの現実へのアクセスを拒否しようとしていることを考えれば、重要な成果である。
歴史的な状況によって居場所を失ったパレスチナ人が、自分たちのアイデンティティを認識し、帰属意識を持つことは、世界中のいたるところで起きている。アヌアル・マジルフ・イッサは、大陸で最高のサッカークラブのひとつであるクラブ・デポルティーボ・パレスティーノの物語を語る。そこでは、今や 「すべてを手に入れた」若者たちが、最も困難な時期を経てもなお、自分たちのルーツ、アイデンティティ、そして国家を忘れていない。彼らの支援は、占領と植民地化の異常な現実が、パレスチナの生活と未来におけるスポーツの喜びと重要性を否定しないことを確信させるだろう。
実際、人生の大半をパレスチナから離れたパレスチナ人であっても、解放闘争へのコミットメントや貢献は少しも減じることはない。ガーダ・カルミは、ある特別なイベントで自分の人生を語るよう招待されたが、パレスチナ人の人生について語ることが、「挑発的」あるいは 「攻撃的」であることを恐れた主催者によって検閲されたことを回想している。これはロンドンで起きたことであり、無慈悲な独裁政権下で起きたことではない。ガーダは、英国がパレスチナとその破滅的な歴史における自らの役割を忘れないようにするために、人生を捧げ、今も捧げている。それは時に孤独な闘いであったが、後には他の人々との共同作業となり、そのすべてがPLOの創設以来1980年代までの闘いの一部となり、さらに祖国の現場における解放の努力を支援する他のネットワークの中で行われた。
ランダ・アブデル=ファタハは、オーストラリアのシドニーにおけるパレスチナ人の抵抗に光を当てることで、この海外での闘いが日常的であり、時には自分の人生やアイデンティティの一部を消耗するものであることを示す。何世代もの人々が、パレスチナに縛られながら別の場所にいる現実を体験している。ランダが美しく言うように:
一方では、パレスチナで起きていることの証人となることを、ここにいるパレスチナ人が主張する。一方では、パレスチナの子どもは、パレスチナで起きていることをそこに留めておくために、ここを支配しようとする。
サマ・サバウィもまた、年老いた父を訪ねながら、オーストラリアのクイーンズランド州レッドランズ・コーストから、歴史とアイデンティティをめぐる詩的な旅を始める。オーストラリアの入植者植民地主義と先住民の大量虐殺の歴史が、シオニストの入植者植民地主義とパレスチナ人の民族浄化の物語と出会う場所である。この地理的、歴史的背景は、亡命とトラウマの結びつきについて書き、日々経験し、その中でポスト・メモリーについて考えるパレスチナ人女性の生活の中に常に意識的に存在している。この自己反省は、サマが消去と否定に挑戦し、その決意を次の世代に伝えるのに役立つ:
愛する人たちが爆弾にさらされ、包囲され、占領されている間は、前に進むことはできない。だからそうしない。そして、それを子どもたちに伝える。
パレスチナ人は、勇気、インスピレーション、方向性をさまざまなところから得ている。最も重要なもののひとつは、キリスト教徒であれイスラム教徒であれ、宗教である。解放の神学はキリスト教であり、イスラム教でもある。マヌエル・ムサラム神父の生涯の物語は、パレスチナのイスラム教徒とキリスト教徒の間にくさびを打ち込むことで、「分断と支配」戦術を試みる植民地主義者やアパルトヘイト政権の強力な解毒剤となる。ムサラム神父はこう書いている:
私は自分の教会の神学に由来する宗教的な立場から、そしてこの神学における私の強い信念から抵抗する。
サミ・アル=アリアンは、困難な現実や現在の力の不均衡に直面してもひるむことなく、解放闘争を前進させるためのさまざまなパラメーターを探るという、より広い文脈の中でイスラームを論じている。解放闘争における政治的イスラームの役割は、多くの人々によって認識されている。この章では、この闘争を、独房を含むアメリカの刑務所での長期にわたる苦難によって、その献身に大きな代償を払った知識人の生涯にわたるコミットメントの物語の中に位置づけている。西洋哲学の深い知識からイスラムのヴィジョンと認識に関する深い知識まで、彼の知的到達点は並外れている。サミは過去を見ているだけでなく、未来を見ており、それなしには適切な解放の望みはないという壮大なビジョンを信じている。
宗教はまた、エルサレム全般とその中心的存在であるアル・アクサ・モスクを守ろうとするハナディ・ハラワニの個人的な闘いにもインスピレーションを与えた。この若いエルサレム人パレスチナ人女性は、エルサレムとアル=アクサ・モスクを守るというパレスチナ人の決意の背後にある、感動的な精神とインスピレーションを与えてきた。彼女は、イスラム教の聖地であるこの場所を守るための、特にパレスチナ人女性の驚くべき勇気ある努力を語り、大規模なイスラエルの存在がいかなる形の抵抗も阻止するはずの場所で、子どもたちや若いパレスチナ人がいかにそのような闘いに参加しているかを強調する。ハナディの闘いは、教室で、アル=クッズの街角で、そして彼女が愛するアル=アクサから追放された今、どこにいても行われている。
信じがたいほどの人間的な勇気とともに、宗教や国家への信仰が、パレスチナの政治犯たちをたくましくし、無慈悲な投獄や正義の否定に直面しても屈しない決意をさせているのだ。本書が準備されていたとき、まだ獄中にいたハリダ・ジャラールは、最愛の娘(安らかに眠ってください)の葬儀に参加する権利を拒否された。
ジャラールの試練と苦難の描写は、パレスチナの政治犯たちが解放闘争へのコミットメントを揺るぎないものにしている信念の力に光を当てている。このような道は必然的に犠牲を要求し、殉教、投獄、家やキャリアの喪失に終わることもある。抑圧の最も残酷な側面を経験した人々の勇気と回復力は、イスラエルの刑務所の4つの壁の中で、拷問と終わりのない残虐性の中で考え出されたこの特別な作品に照らし出されている。ここには自己憐憫も憎しみもなく、ただ献身、回復力、希望の驚くべき表現がある。ジャラールはこう書いている:
肉体的な拷問、精神的な苦痛、長期にわたる隔離など、囚人たちが耐えている苦しみを理解することは重要だが、同時に、男女が反撃を決意し、本来の権利を取り戻し、人間性を受け入れるとき、人間の意志の力を理解しなければならない。
民衆の抵抗は、献身と勇気だけでなく、組織も必要とする。ジャマール・ジュマアは、人民大衆の闘争を一段高いところから俯瞰しながら、今日まで貢献してきたネットワーキングの重要な役割について説明している。制度、組織、ネットワークは、PLOの闘争がより成功した数年間の核心であった。1982年の出来事とオスロ合意の結果、それらはしばらくの間失われたとみなされたが、ジャマルが示すように、まだそこにあり、将来、より協調的で組織化された成功した反乱を再燃させ、再生させる可能性を秘めている。
占領下のパレスチナでは、組織的あるいは個人的な闘争は、これまで見てきたように刑務所につながる。弁護士として他の囚人の弁護に人生を捧げるには、獄中経験者が必要なのだ。これが、ガザで最も有名な人権擁護者、ラジ・スーラニのライフストーリーである。彼の仕事はイスラエルと国際法廷の両方で行われている。ラジが語るように、前者は正義を求めるにはほとんど不可能な場であり、もう一方は近年政治化され、パレスチナ人に対する犯罪を訴追するのがより困難な場となっている。しかしラジは、このような困難があっても、特に国際法という特別な法律の特性を指摘し、国際的な領域で活動を続けることを躊躇することはないと主張する:
国際法は、私たちが平等であることを示す手段なのだ。私たちが求めているのは、法の平等な適用であり、他のすべての人と同じように扱われ、他のすべての人と同じ権利を享受することなのだ。他の人たちと同じように、私たちも責任を問われる。
平等に扱われることは、解放のために闘う手段として教育に人生を捧げてきた人々にとっても、絶え間ない挑戦である。ガーダ・アジールが書いた次の章からわかるように、これは難民キャンプにおける文化的闘争の特別な様式となった。難民キャンプでの生活は、しばしば刑務所での生活に似ており、難民は政治犯と同様に、その苦しみだけでなく、主に抑圧との闘いについて語ることができる。難民キャンプでは、教育は人間性を維持し、抵抗を続けるための重要な要素だった。ガダはガザ地区からの難民の第3世代であり、抵抗の手段として教育を選択した彼女の旅は、西側諸国が認識することを拒んでいるもの、つまりシオニスト・プロジェクトの深い人種差別的本質とパレスチナ人に対するその意味を、他の人々が理解するのに役立った。この人種差別に対して、ガーダは教育という分野を踏み台にして、解放闘争に独自の貢献をした。
パレスチナ人の歴史と遺産について人々を教育する方法は一つではなく、ユニークなパレスチナ史タペストリー・プロジェクトもその一つである。ジェハン・アルファラとヤン・チャルマースは、この驚くべきプロジェクトが、パレスチナ人の抑圧とそれに対する闘いの歴史的な場面を美しい刺繍で映し出しながら、古い職人技をどのように生かしているかを紹介している。このプロジェクトは移動可能で、展覧会やインターネット上で展示されている。これらの素晴らしい製品は、ガザ地区の献身的な職人たち、占領地全域やレバノン、ヨルダンの難民キャンプのパレスチナ人たちによって作られ、自分たちの仕事を解放の行為であるという認識を共有する女性たちが集まっている。
次に、テリー・ブーラタが、解放闘争における遺産の役割について、文化的な側面から概観してくれる。テリーが教えてくれるように、遺産を守ることは必ずしも意識的な解放の行為ではなく、だからこそ起こるのだ:
私を含め、祖国以外の大多数のパレスチナ人にとって、パレスチナ人であることは決断というよりも、むしろ私たちが何者であるかを反映するものなのだ。
西側諸国における文化的抹殺やシオニストによる文化的抑圧のキャンペーンと闘うためにテリーが選んだ方法は、解放闘争とその個人的勝利の記録に新たな層を加えるものであり、それは大きな枠組みから見れば小さなものであるかもしれないが、いつの日かパレスチナ解放における変革的で強力な要因の積み重ねとなることを証明するだろう。
この点で、歌い手とその歌は、詩人とその詩のように、重要な役割を果たしている。リーム・タルハミリームは48年生まれのアラブ人であり、著名な歌手である。彼はパレスチナ解放の歌の長く印象的な歴史と蓄積を語る(いつかアーカイブ化され、誰もがアクセスできるようになることを願っている)。これらの歌は、最も美しく情熱的な方法で、48年アラブ人の主要な苦境のひとつである祖国での疎外感を表現するのに役立ってきた。リームが選び、演奏する歌は、この疎外感を鮮明な色彩で描いている。リームが言うように、「歌によって、私たちは一滴の血も流さずに戦争をする」のだ。
映画と映画は、比較的近代的な芸術の形態であり、解放のための個人的・集団的闘争と結びついている。ここでファラ・ナブルシは、解放闘争を抑圧し抵抗する映画の役割を評価する一方、彼女の作品は、映画がいかにして解放のためにも利用されうるかを例証している。ロンドンに生まれた彼女の個人的、職業的な映画界への関わりは、パレスチナ人としてのアイデンティティから切り離されることはなく、パレスチナ人への不公正に対する憤りを弱めることはなかった。芸術だけでは、もちろんパレスチナを自由にすることはできない」と自覚しながらも、それでも彼女は「芸術がなければ、パレスチナは決して自由になれないと信じている!」と強調する。
芸術や他の興味や職業が、このような闘いの中で生き残るのに十分でないこともある。イスラエルの蛮行の犠牲となり、闘争の長い経験の中に身を置くことは、精神的な打撃を与える。次に紹介するサマ・ワクチンルの寄稿は、こうした苦難とそれにどう立ち向かうかを明らかにするのに役立つ。精神科医にふさわしく、彼女の記述は彼女が生まれた瞬間から始まり、パレスチナを代表する精神科医になるまで続く。集団的・個人的なトラウマがメンタルヘルスの関心領域として認識されるようになったのはごく最近のことであることを認識しているサマは、闘いへの貢献として、一方では解放闘争全体におけるメンタルヘルス治療の重要性を認識させること、他方では、PTSDのような西洋的な概念と、パレスチナの文脈における抑圧とそれに対する闘いの両方との関連性を批判的に検討する必要性という、ふたつの使命を自らに課している。
サマが自分のプロフェッショナリズムを損なうことなく、献身的に取り組んできたように、解放闘争における科学の役割は、マジン・クムシエの章に強く現れている。科学は、占領されたり植民地化されたりしている人々にとって、教室や実験室を通じて蓄積されるとは限らない人的資本である。シオニズムはこの生態学的な知恵を破壊しようとする。結局のところ、シオニズムのプロジェクトは生態系に災いをもたらしたのだから。マジンの人生と解放闘争への貢献は、民衆の抵抗のための複数の貢献の中で発揮されている。彼はここで、この民衆の抵抗において果たした人間の自然に対する知識と科学の役割を強調している。マズィンが書いているように、パレスチナでは「人間と自然の調和が保たれている: 「人間と自然との調和は何千年もの間持続してきた」のだが、シオニズムがパレスチナに到達して以来、その蒔かれた不調和のせいで、現在私たちはそれを維持するのに苦労している。
本書の最後のセクションでは、外交、グローバルな市民社会との関わり、イスラエル国家とそのユダヤ人社会との関わりを通して、国際社会に対して追求される解放闘争の個人的な物語に出会う。
パレスチナ人であるハサン・アブ・ニマは、ヨルダンの上級外交官となったが、人生の節目節目で、パレスチナ人としてのアイデンティティと闘争へのコミットメントを十分に自覚していた。彼のライフストーリーは、生まれたその日から今日に至るまでの豊かな人生を通して、パレスチナ人のそれを反映している。彼は私たちに、パレスチナのどん底の瞬間だけに焦点を当てるのではなく、イスラエルの邪悪な計画やプロジェクトが崩れ去ったことも思い起こさせ、解放が実行可能で成功する可能性のある未来を見据えて、希望に満ちた過去の再評価を提供する。彼はこう書いている:
私が子供の頃に目撃したパレスチナの暴力的な分割は終わりを告げ、この国は再び完全なものとなり、人々はどこにでも自由に住み、移動できるようになると確信している。パレスチナにアパルトヘイト政権が存在する余地はない。
次の章では、ジョニー・マンスールがパレスチナ側のイスラエル研究の発展を追いながら、解放闘争がシオニズムの破壊的な本質とイスラエルのユダヤ人社会の本質を理解しようとするとき、いかにステレオタイプ化と表面化を避ける必要があったかを説明する。故イッサム・シルタウィによって始められたプロジェクトは、現在、ラマラのマダールにイスラエル研究機関を設立し、高度な専門的レベルに達している。ジョニーはこの機関の発展の初期段階をフォローし、イスラエルとパレスチナ双方の歴史と社会についての深い知識を持ち、現在進行中のマダールのプロジェクトや、彼や私の故郷ハイファのマダ・アル・カルミルなどの同様のプロジェクトに忠実に奉仕し続けている。
タジャモア党の創設メンバーであり、同党のイスラエル議会代表であるハニーン・ゾアビは、それとは異なる闘いを描いている。ハネーンの政治的キャリアは、48年アラブ人が承認政治から解放政治に移行しようとする試みの周囲で展開した。2010年のフリーダム・フローティラへの参加は、彼女にとってリベラルなシオニスト左派の偽善を露呈させ、ユダヤ人社会で広く支持されているアパルトヘイト国家のもとで解放のために活動することの限界を冷静に認識させた。ハニーンの貢献は、イスラエル社会を内部から変えるという幻想を抱いている人たちにとって重要:
結論として、イスラエル市民権は、パレスチナ人をイスラエル社会に導入する手段として付与されたのではなく、むしろイスラエルが我々に勝利したことの現れであり、行使であった。イスラエルの政治に携わるパレスチナ人は、正義と植民地市民権との間に内在する矛盾を明確に保たなければならない。
とはいえ、アパルトヘイト後の南アフリカで起こったように、48年アラブ人は、入植者であるユダヤ人社会の少なくとも一部とともに、新たな脱植民地化された空間を築く希望を失ってはいない。現在イスラエルに住む進歩的な反シオニストであるユダヤ人がこのような真の連帯行為に関わるとき、必然的に彼らは解放されたパレスチナのビジョンとその中での自分たちの位置にも関心を持つ。アワド・アブデルファッタの章では、不運な二国家解決策が歴史のゴミ箱の奥深くに葬り去られた後に出現するであろう、歴史的パレスチナ全土を対象とした民主主義国家のための闘争が語られている。このような解放のビジョンは、パレスチナ解放運動が当初から掲げてきた非常に神聖な原則と、パレスチナ人のためだけでなく、解放されたパレスチナに住むことを望むユダヤ人のための共同民主主義的ビジョンを伴う脱植民地化の様式の両方に基づくものである。
連帯は口先だけでは済まされない。入植者植民地イスラエルと占領地パレスチナの異常な現実を前にして、それは行動に移されなければならない。ライラ・アル=マラヤティとノーラ・レスター・ムラドはそれぞれ別の章で、効果的な解放のためには、闘争のための財源をどのように確保し、それをどのように最良の方法で使用するかについて明確な見解を持たなければならない、と指摘している。この二人の活動家はそれぞれ、そのような活動が行われる特殊な状況に対応した組織を設立した。ライラは、そのことに気づいたとき、違うやり方をする必要性に目覚めた:
ヨーロッパから湾岸諸国まで、パレスチナへの人道支援を望む世界中の人々に対して、一夜にして障壁が築かれたのだ。
その結果、彼女は友人たちとKinderUSA(Kids in Need of Development, Education and Relief)を設立した。彼女は、アメリカにおけるパレスチナ人への慈善活動は、親イスラエル・ロビーがテロ支援として悪者扱いし続けるため、決して一筋縄ではいかないと忠告する。しかし、それにもかかわらず、包囲されたガザ、占領されたヨルダン川西岸、難民キャンプといった場所と人々を直接結びつけ、寄付できるものは何でもする。
ノーラ・レスター・ムラドもまた、自身の組織「ダリア・オーガニゼーション」を設立し、草の根の個人や組織による重要な役割を忘れることなく、闘争への援助をいかに制度化し、専門化するかという問題に日々取り組んでいる。これは、今後何年も参照されるであろう刺激的なテンプレートである。
私自身の記事は、国際連帯運動の台頭と行動を記録することによって、この連帯を利用し、それを拡大しようとするものである。この運動の効力は、真実を語る力を与え、イスラエルや海外でシオニストとして育てられた人々でさえ、ルビコンを渡り、解放闘争と連帯する運動に参加することができるようにした点にある。これは成長しつつある現象であり、将来パレスチナに自由をもたらす上で重要な役割を果たすだろう。
武力闘争、文化的闘争のさまざまな様式、知識生産の様式、資源の募集、占領、投獄、植民地化による精神的・肉体的疾患の支援、これらすべてが解放のための闘いを形成している。この巻に収められた個々の物語は、この闘争のすべての側面を網羅しているわけではないし、解放闘争を存続させたすべてのグループ、場所、世代を代表するものでもない。しかし、サンプルとしてでさえ、ナクバ以前にパレスチナが恵まれていた人的資本を証明するものであり、現在進行中の大惨事にもかかわらず、再生し、拡大することに成功している。いつの日か、この人間の宝は、ヨルダン川と地中海の間に住むすべての人々のために、そして長年にわたってそこから追放されたすべての人々のために使われるようになるだろう。
-イラン・パッペ、2021年11月
第1章 解放の起源と記憶
ハムダン・タハ(HAMDAN TAHA)は独立研究者であり、元パレスチナ観光古代遺産省副大臣である。1994年から2012年まで、新設された古代・文化遺産局の局長を務めた。パレスチナにおける一連の調査やサルベージ発掘を指揮した。2002年から2014年までパレスチナの世界遺産ファイルの国内コーディネーターを務め、現在はパレスチナ歴史遺産プロジェクトのコーディネーターを務める。著書、現地レポート、学術論文多数。
土と記憶を掘り起こす
私たちの解放における考古学の役割1
ハムダン・タハ
私は1954年11月5日の夜明けに、モハメッドとファティマの間に、故郷シユクの東にあるワディ・アブ・サファルの夏小屋で生まれた。シェイク・アーメドの祠は、同じ名前の樫の木の隣にあり、この地を監督する神の目と見なされていた。子供だった私たちは、参拝者の誓いと祈り、小さなマッチ箱、彼らが置いていったロウソクを村のヘドミ・モスクまで運ぶのが仕事だった。私は幼い頃、家の庭で過ごした思い出を思い出す。土の中の季節の香り、友達と遊んだこと、のどかな村の狭い路地を駆け抜けたこと。
言い忘れた戦争
1967年、私は12歳だった。夏の田植えの季節、私の家族は村の東にある農場で働いていた。私は家から荷物を取ってくるように頼まれ、その途中で、「戦争が始まった」という声を聞いた。畑に戻ったとき、戦争が始まったことを伝えるのを忘れてしまった。
翌日、町の若者たちは戦争に参加する志願兵を集めた。彼らはヘブロン総督府に武装を求めに行ったが、手ぶらで帰ってきた。人々は何が起こっているのか不思議に思った。エルサレムでの英雄的な戦いについてのラジオ放送に耳を傾け、イラク軍が到着したという散発的な噂を耳にしたが、隣町のサイルで撤退するヨルダン軍の車列にイスラエル軍が空襲を加え、車列の戦車のほとんどがくすぶった残骸と化すのを自分の目で見た。
村の周りの洞窟に避難する人もいた。子供たちは遊び始め、洞窟のストーブからはすぐに煙が上がった。まるで家族で休日を過ごしているかのようだった。
町は、東のヨルダン川に向かう兵士や市民が逃げ込む交差点となった。ネットのついたヘルメットをかぶった兵士たちが砂埃の舞う砂色の軍用ジープでやってきて、店のドアにチラシを貼った。ひどい暴行を受けた人もいたと聞いている。イスラエル軍が人口調査を行うため、夜間外出禁止令が出された。
1967年11月6日、午後に軍が町を襲撃し、夜間外出禁止令が出された。軍用ヘリコプターが町の東でホバリングし、空挺部隊がアル・バヤダ地区に着陸した。ウンム・カルムールの洞窟でフェダエーンと戦闘が行われているという噂が広まり、それは4時間ほど続いた。夜に埋葬された殉教者は伝説となり、その一人、ユセフの美しい姿は私たちの心に刻まれた。
翌朝、拡声器が16歳以上の男性全員に、家からほど近い空き地に集まるよう呼びかけた。私たちの家からはそのアナウンスは聞こえなかったが、窓から遅刻してきた者たちが残忍に殴られているのを見て、私たちは行きたくなくなった。
アンティーク・フィーバー
占領後、仕事は止まり、失業した若い男たちが群れをなして近くの遺跡で考古学的資料を探した。遺物が見つかると目が輝いた!発掘現場には、掘り出し物を狙う仲買人もやってくるほどだった。これは古物保護制度の終焉を示すものだった。私はローマ時代の青銅貨を見つけた。
古物フィーバーは財宝や黄金の話を広めた。祖父は母に、英国委任統治時代の若かりし頃、小さな盆地で金貨を見つけた話をした。祖父はそれをエルサレムの骨董品店に持って行き、売ろうとしたのだが、その店のディーラーがまだあるかと聞いてきたので、あると答えると、ディーラーは待つように言い、隣の部屋に電話をかけに行った。祖父は警察に電話していることに気づき、走って逃げた!彼は走りながら、自分の身元を示す緑色のヘッドスカーフを脱いで、金貨を左右に放り投げ、野原に投げ捨てた。考古学者なら、これらの金貨が汚染され、本来の考古学的背景から取り去られたものだとは思わないだろう。
学校時代
私は町の予備校と小学校、そしてハルフルの中等学校に通った。
この時期、私は学校の図書館にあった小説を含め、アラブや外国の作家の小説を夢中になって読んだ。私はこれらの小説の出来事を夢の中で生きた。アンネ・フランクの物語に出会い、深い感銘を受けたが、イスラエルやシオニズムとは結びつかなかった。また、ハルフルの古本屋でパレスチナ民族憲章のヘブライ語訳を手に入れた。パレスチナ解放機構が書いた文献を見たのはそれが初めてだった。しかし、時が経つにつれて、受け継がれた知恵を守る人々のいる村が、私の人生にとって最も重要な学校であることを理解するようになった。
ビルジート私の最初の大学
1973年、私はビルジート大学に入学した。最初は学生寮に入ったが、そこの宿泊施設は厳しい法律で管理されていることがわかり、私は同僚たちと町の入り口にある家に移ることにした。その家は 「コミューン」と呼ばれるようになった。1948年以前は、革命家たちの集会の拠点だったことを後で知った。
この時期は、大学が私たちの民族運動の拠点となり、カリキュラムがアラブ化され、最初の生徒会が設立されるなど、新しい世代の出現を目撃した。カリキュラムはアラブ化され、最初の学生評議会が設立された。この時期には市町村選挙が行われ、統一されたパレスチナの指導者が出現した。
私は常に農民革命の思想に影響を受け、フランツ・ファノンに触発されていたので、友人のヤセル・イブラヒムと私は本を購入し、寄付を集めた。私たちは村で最初の公共図書館を設立し、彼は自宅の小さな一室で運営していた。
ある時、夜間外出禁止令が出され、私が子供の頃通っていた学校に男たちが呼び出され、集められた。私たちは木陰に身を寄せ、軍隊は教室で尋問を行った。私の番が来て、教室に入るよう命じられると、かつて私の先生の椅子だったところに軍の尋問官が座っていた。彼は私の名前、家族、仕事について尋ね、私がビルジートで学んでいることを知ると、彼の関心はピークに達した。尋問官は私の友人を知りたがり、私の曖昧な答えに感心しなかった。その時、突然横に現れた別の尋問官から平手打ちを食らった。翌週の水曜日、私はヘブロンのアルアマラ軍政庁舎に行くように言われた。
アルアマラでは、様子は違っていた。尋問官は机の前に座り、ファイルの山を前にしていた。入門的な質問の後、彼は言った。目の前のこのファイルにすべて書いてある。「自白することを勧める」彼は自信に満ちた口調でそう言った。私は、彼のオフィスにいる間、大学の講義を受けられないので、私の時間も彼の時間も節約するために、ファイルを読んでほしいと言った。彼は怒って、私を監視していることを警告して立ち去るように言った。
社会学部3年生のとき、副専攻の一環として開講されていたA・グロック博士の「考古学入門」に偶然入学した。私は、このコースが切り開いてくれた新しい世界にすっかり魅了された。まるで宝物に満ちた洞窟、アリババの洞窟に迷い込んだかのようだった。
こうして選択副専攻は、私の将来の進路の中心となった。卒業後すぐに、私は考古学学科でアカデミック・アシスタントとして働きながら、考古学のダブルメジャーを取得した。テル・ジェニンとテル・タアネクでの発掘研修に参加し、フィールドワークのスキルを身につけ、フーリンダース・ペトリーが言うように、考古学のアルファベットを構成する文化遺物、特に土器について学んだ。ジェニン発掘キャンプの経験はユニークなもので、現地で訓練を受けた初のチームが誕生し、自分たちの手で歴史を掘り下げる責任があると感じさせてくれた。
ヨルダン大学で学ぶ
私は1980年にヨルダン大学のパートタイム修士課程に入学し、在学中は滞在費を賄うため、ヨルダン考古局の日雇い労働者として数々の発掘調査に参加した。また、ロバート・ヨルダンと共にアジュルーン地域の調査にも参加した。この調査中に、ベイルートで起きたサブラとシャティーラの虐殺の知らせを受けた。私たちは、パレスチナ人を恐怖に陥れて追放し、他国に亡命を求めて逃げてきた彼らを追いかけ、ただそこで殺し続けるという、この冷酷な占領に衝撃を受けた。
修士論文では、ペリシテ人の起源と文明について研究することにした(Taha 1983)。私の論文は、言語的なつながりや、ペリシテ人が明確に国名をつけたという事実にもかかわらず、ペリシテ人とパレスチナ人を2つの異なる歴史的文脈を示す用語として明確に区別することに基づいていた。聖書研究者の間で大きな論争の的となっていたペリシテ人の民族的起源は重要ではなく、真の重要性はむしろ民族の文化的連続性にある、というのが私の結論だった。
帰国の際、私は国境で尋問を受けた。イスラエルの尋問官は、私を見て興奮し、「なぜ帰ってきたんだ?」と吠えた。翌日、ヘブロンのアル・アマラで2回目の尋問を受けるように言われ、私はそうした。日目、私たちの家は銃撃を受け、2発の銃弾が窓を貫通したが、幸いにも誰も怪我をしなかった。その間、私たちの村は占領軍に所属する民兵によって恐怖にさらされていた。私は1984年にビルジート大学の講義に戻り、ドイツに留学するまでの1学期を同大学で過ごした。
ベルリンでの研究
ドイツ学術交流使節団の奨学金を得て、ベルリン自由大学の西アジア考古学研究所で考古学の博士号を取得した。ゲッティンゲンのゲーテ・インスティテュートでドイツ語を学んだ。
ヨルダン留学中に知り合ったサマル・ジャラールと結婚した。彼女はドイツで私と一緒になり、ダリアと双子のスハイルとルブナの3人の子供をもうけた。末娘のヌーラは、パレスチナに戻ってからエルサレムで生まれた。ドイツではダーレム・ドルフに住み、よく自転車で大学に通った。ある日、大学で雑誌を見ていると、兄のアブドゥル・カリムの殉教の記事を読んで驚いた。彼は24歳で、第一次インティファーダの土地の日に殉教した。
私の論文のテーマは、「パレスチナにおける死体安置所の分化(タハ1990)-ムステリア時代から都市化の始まりまで」だった。それは、パレスチナにおける何百回もの考古学的発掘調査によって出土した考古学的遺物に、死体安置所分析の方法論を適用するという新しい試みであった。その中には、テル・タアネクから出土した中青銅器時代の埋葬品のサンプルも含まれており、中青銅器時代の家屋の床下から発見された、子供の墓地として知られているものも含まれていた。霊安室理論全体は、Saxe(1970)やBinford(1972)らによって展開された、年齢、性別、社会的地位などによる社会的分化が、死者の霊安室の分化によって反映されるという仮定に基づいている。
帰宅
またしても帰途、私は橋の上でアル・アマラで尋問を受けるよう求められた。私はビルジート大学の非常勤教授として帰国していた。私は考古学プログラムの立ち上げに参加することを熱望していたが、息詰まるような手続き上の障害と交渉しなければならなかった。研究所の所長は、私が教壇に立つことに難色を示し、研究者としての適性しかないと考えたのだ。この件は大学の審議会と職員組合にかけられた。故G.バラムキ総長のオフィスで、私が教職に復帰することで合意に達した。私は考古学の2つのコースを担当することになった。その数日後、長年共に働き、多くを学んだA・グロック博士が殺害されるという悲劇的なニュースを耳にした。
交渉への参加
1992年のマドリッド会議に向けたパレスチナの準備が始まったとき、私は大学に勤務しており、交渉の準備を任務とする数多くの技術チームのひとつである、古美術品顧問チームの調整に抜擢された(Taha 1994d)。
タバでの技術交渉に参加した私は、そこで私たちの計画が明確になっていないことに気づいた。私は修正文書を作成し、パレスチナ代表団の団長であるN・シャース博士にこのことを伝えた。その日の朝、私たちはイスラエル側と会談し、私は修正文書を提出したが、イスラエル側は、私の意見では交渉の基礎とならない最初のバージョンで作業することを主張した。すぐに閉会となった。夕方、N.カシス博士が私に、イスラエル側は私が交渉を妨害したと非難しているとささやいた。
次のセッションは、エイラートでM・サディク博士と行った。第9項目として挙げられていた、パレスチナ自治政府が多くの遺跡で作業するためにはイスラエルの承認を得る必要がある、という要件についての意見の相違で、手続きセッションの間に議論は行き詰まった。私はこの条項の削除を求めたが、この点での合意への試みはすべて失敗に終わった。3日目、イスラエルの交渉担当者はカッとなり、今後のセッションには二度と参加させないと警告した。私は苦情を申し立て、彼を解任するよう求めたが、行き詰まりは解消されず、実際に協定が調印されたカイロでの次のセッションに私が呼ばれることはなかった。
歴史を取り戻す
1994年のパレスチナ古文書局の設立は、記念すべき出来事だった。それは、ナクバを理由に解散した1920年設立の考古局の復活を告げるものであり、公式な歴史の奪還を意味するものであった。
1993年にオスロで調印されたパレスチナとイスラエルの合意、そしてその後の1994年の合意を受けて、パレスチナ側はオスロ合意のもとでA地区とB地区に指定された考古学を含むいくつかの行政区域を管理することになった。1999年5月までに和平プロセスを終結させるという理解のもと、C地域の責任も徐々にパレスチナ側に移譲されることになっていた。しかし、この相互に合意したスケジュールはイスラエルによって守られることはなかった。したがって、最終的な和平合意がない限り、イスラエルは依然としてパレスチナ自治区の軍事占領者であり、国際法に定められた責任を負っている(Taha 1914: 29)。
私は1994年8月10日に古物局局長に任命され、それまでイスラエル民政局に属していた古物事務所と職員の引き継ぎを管理するプロセスを指揮した。少数の職員が少数の事務所で働いていただけだった。彼らの主な責任は、許認可問題のフォローアップと、イスラエルの古物担当官の活動拠点としての役割を果たすことだった。
パレスチナ人はこの時代から、考古学的な仕事に対して否定的な見方を受け継いでいた。というのも、遺跡は入植目的の土地没収の口実として利用され、キルベト・シロウン、ゲリジム山、テル・ルメイダなど、考古学的な発掘活動を背景に多くの入植地が建設されたからである。
パレスチナにおける考古学の新時代は、エリコの古代ヒシャム宮殿跡のそばの現地事務所で活動する、小規模だが献身的で熱心なチームの仕事から始まった。このチームには、ムハメッド・ガヤダ、ユセフ・アブ・タア、イマン・サカ、ジハード・ヤシン、ジュリアナ・ネイルズ、イヤド・ハムダンなどがいた。私たちは、資格のある人材もなく、物流能力もなく、保管するアーカイブや考古学的資料もないゼロからのスタートだった。私たちが設立した部門は、1948年に廃止された委任統治時代の考古局の自然な延長線上にあると考えていた。
この部門は、パレスチナの文化遺産に対する現代的な理解を促進するために活動を開始した(Taha a-c1994)。オスロ後の新しい状況によって、パレスチナ人は一次資料に基づいてパレスチナの歴史を書くことができるようになったが、これはつい最近まで外国人やイスラエルの考古学者だけの特権であった(Curtis 1994, 1914: 29)。最初のフィールドワークは、ジゼル・アブ・ガブシュ(Taha 1994)として知られるエリコの小さな遺跡で、8月の照りつける太陽の下で始まった。自分たちが自分たちの遺跡を管理し、自分たちの過去を書き記すことになったのだ。
新しい考古局は、新しい法律の策定、サルベージ発掘のスタッフの訓練、遺跡の略奪や古美術品の不正取引との闘い、博物館部門の構築など、多くの責任を負っていた(Taha 2014: 31)。同局の設立ビジョンは、科学的事業としての考古学の役割を強調し、文化遺産のさまざまな側面や層の完全性を保護することを任務とし、古美術を持続可能な開発のための源泉であり、パレスチナの国民的文化的アイデンティティの不可欠な一部であると認識している(Taha 2003)。
一次資料を用いて歴史を書く
新生部門は考古学的発掘に携わるようになり、最初の野心的なプロジェクトであるキルベト・バラマ(Khirbet Balama)の大水トンネル(Taha and van der Kooij 2007)を、さまざまな時代の大規模な墳墓群とともに発掘することが可能になった。これらの発見の中で最も注目すべきもののひとつが、カバティヤ銀貨コレクションである(Taha and van der Kooij 2006)。私たちは、100の遺跡の清掃を優先し(Taha 1998)、過去の考古学ミッションによって発掘され、放棄された遺跡を開発した。これらの遺跡は、考古学資料や発掘アーカイブをヨーロッパやアメリカのさまざまな博物館に移管していた。
ポストコロニアル協力の方程式
ローマ・ラ・サピエンツァ大学のパオロ・マッティアエ教授から、エリコのテル・エス・スルタンでの共同協力開始を提案する最初の国際協力の手紙を受け取った。この事業は、ポストコロニアル協力の最初のモデルを確立する道を開いた(Nigro 2006:96)。パレスチナはいまだ占領下にあるが、発掘許可は平等と相互尊重に基づく覚書に取って代わられた。考古学的資料を横領するという植民地主義は廃止された。協力モデルは他の遺跡にも拡大された。最も顕著なものは、オランダのライデン大学とのキルベト・バラマとテル・バラタでの共同発掘、ガザのテル・アル・ブラキヤ、テル・アル・ヌセイラット、テル・エスサカンでのパレスチナ人とフランス人の発掘、テル・アル・マフジャルでのパレスチナ人とノルウェー人の発掘、ヒシャム宮殿でのパレスチナ人とアメリカ人の発掘、エリコのシカモアの木遺跡でのパレスチナ人とロシア人の発掘などである(Taha 2014)。
D.バラムキ博士は、1948年のナクバに先立つパレスチナの激動のため、ヒシャム宮殿の発掘を中止していた。彼の論文で次の一節を読んだとき、私の胸は高鳴った:
将来のある日、熱意ある人がこの作業を再開し、終了させるために必要な資金を提供してくれることを期待している」(Baramki 1953: 95)。
(バラムキ 1953: 95)。
私は2006年に発掘を開始し、2012年から2015年にかけて、ドン・ウィットコムとともに、ウマイヤ朝浴場に隣接するエリアと、宮殿のアッバース朝の側面を明らかにするための北部エリアで作業を行い、「作業」を完了した(Taha and Whitcomb 2014)。
博物館とギャラリー
博物館は文化的記憶を保存する上で重要な役割を果たすという認識のもと、新部門はヘブロン、ベツレヘム、エリコ、トゥルカルム、ガザに考古学・民俗学博物館の設立に着手した。同時に 2000年にパリで開催された「地中海のガザ」 2007年にジュネーブで開催された「文明の十字路におけるガザ」 2009年にオルデンブルク、2010年にストックホルムで開催された「海への玄関口ガザ」など、一連の国際考古学展が開催された(Taha 2014: 38-39)。これらのイニシアチブは、1948年以前の委任統治時代のパレスチナ考古局とエルサレムの考古学博物館に代表される、パレスチナの文化施設に対する植民地支配のモデル(Taha 2021)と決別するための我々の努力の重要な要素であった。
文化遺産の意図的破壊
私たちは、1967年の占領以来、特にエルサレム、ヘブロン、ナブルスにおいて、文化遺産が意図的に破壊されていることを記録した。これは、1948年に500以上のパレスチナの村々が、そのすべての遺産とともに強制移住させられ、破壊されたことの延長線上にある(Taha 2019: 26-28)。私たちはまた、イスラエルによる相次ぐガザ攻撃で、遺跡や歴史的建造物に加えられた被害についても記録した。
私たちが部門として直面した大きな課題は、1967年以降にパレスチナ自治区に建設されたイスラエル入植地がもたらす脅威であり、ヨルダン川西岸地区とガザの文化資源の50%以上を支配していた。もうひとつの重要な問題は、エルサレムとその周辺に建設された分離壁を含む、イスラエルの分離壁が考古学的遺産にもたらす脅威だった。壁は人々を土地や歴史から引き離し、遺跡や文化的景観に壊滅的な影響を与える(Taha 2014: 37-38)。
考古学と占領: 現在進行中の議論
パレスチナの考古学は、占領下の考古学として捉えなければならない(Taha 2016)。パレスチナの土着の物語と、シオニズムによる入植者の植民地的な物語という、2つの競合する物語の闘いの場である。イスラエルの物語は、パレスチナにおけるユダヤ人の遺産を圧倒的に優先し、パレスチナの非ユダヤ人やアラブの歴史にはほとんど触れない傾向がある。1998年にローマで開催された第1回近東考古学国際会議では、考古学と占領の関係が提起され、占領地での発掘に関するユネスコ憲章の規定へのコミットメントが確認された。
私たちパレスチナ人が直面する問題のひとつは、イスラエル人が私たちの物語を捏造することである。例えば、イスラエルの考古学を批判するエッセイの中で、建築家のエヤル・ワイズマンが、シロ入植地が管理するキルベト・セイロウンでのイスラエルの発掘に関連して、私が言った覚えのないことを言ったと引用した。この記事は、パレスチナ自治政府がユダヤ人の歴史を書き換えていると非難し(ジュリオ2011)、イスラエルの右翼考古学者G・バーカイに言わせれば、ホロコースト否定よりもひどいスキャンダルである。事実も名前も混同しているこの記事は、「嘆きの壁」についての論考を書いたパレスチナの詩人ムタワケル・タハと私を混同している。
国際ネットワークの構築
オスロ後、パレスチナはユネスコ、ALECSO、ICESCOを含む一連の国際機関や地域機関のメンバーとなった。パレスチナに対する国際的な関与は、占領問題に対する実質的な解決策を提示するのではなく、危機管理という形をとった。
2008年にローマで開催された近東考古学国際会議に出席した際、私は閉会スピーチで、「政治的な理由で土地は分割されるかもしれないが、歴史は分割できない。
2005年、パレスチナはパレスチナの世界遺産暫定リストを作成した(Taha 2005/2009)。このリストには、20の文化遺産と自然遺産が含まれている。2009年には、パレスチナはまだユネスコの正会員ではなかったが、考古局がベツレヘム・ファイルの作成を開始した(Taha 2012a, 2012b)。2010年にブラジルで開催された世界遺産会議では、パレスチナの代表団は、他の国の代表団と同様に、自分たちの場所にパレスチナの名を記したプレートが掲げられるまで着席を拒否した。
2011年にユネスコがパレスチナを承認したことで、長い闘いが終結した(Taha 2011, TWIP 2011b)。2012年にベツレヘム、2014年にバティールの文化的景観、2017年にヘブロンの旧市街が世界遺産に登録された。ユネスコによるパレスチナの承認は、初の公式な国際的文化的承認であり、パレスチナ人に降りかかった歴史的不正義の一部を是正する端緒となった。
未来を築くために過去を再構築する
2014年11月5日に古文書局での正式な任命を終えた後、私は研究と学術の世界に転じた。過去の発掘調査結果に関する出版物(Taha, H. and van der Kooij: 2016)の完成と、国内外の研究者グループを巻き込んだ「パレスチナ史プロジェクト」のコーディネートに専念する前に、私はいくつかの顧問や指導の仕事を引き受けた。これは『パレスチナ史への新たな批判的アプローチ』(2019)という本の出版に結実した。
私の考えでは、考古学の役割は未来を築くために過去を再構築することである(TWIP 2011a)。パレスチナ人は今、パレスチナの土地に住んでいたすべての民族、集団、文化、宗教の声を取り入れた一次資料をもとに、シオニズムの入植者植民地物語が進める排他主義的な幻想とは対照的に、自分たちの歴史の包括的な物語を書くことに貢献している。ホモ・サピエンスの初期から21世紀まで、パレスチナには多くの民族が住んでおり、多くの戦争、侵略、改宗(宗教的、政治的)があったこの歴史の中で、先住民が完全に排除されることはなかった。この土地の先住民である私たちパレスチナ人は、常に耐えてきた。このことは、イスラエルの入植者による占領と、それがパレスチナの地に築いたアパルトヘイト体制からの解放を求める私たちの闘いに希望を与えてくれる2。
1 このエッセイはアラビア語で書かれ、サマ・サバウィによって翻訳された
2 私の役割は、家族や友人の支え、そしてこの旅で共に働いた人々、特に古代エジプト美術省とそのパートナー機関の同僚たちの助けと努力なしには成し得なかっただろう。全員の名前を挙げることはできないが、彼らに感謝とお礼を申し上げたい。参考文献の完全なリストは、私の出版物の中にあり、私のウェブサイト(https://independent.academia.edu/HamdanTaha)で見ることができる。
IBRAHIM G. AOUDÉ ハワイ大学マノア校民族学教授。アラブ研究季刊誌の編集者で、政治学の博士号を持つ。パレスチナ、レバノン、イラク、トルコ、エジプト、ハワイに関する政治経済、グローバリゼーション、民族間関係に関する論文、本の章、編著がある。著書に『レバノン』(ペンネーム:B・J・オデ)がある: Dynamics of Conflict』(ゼットブックス、1985)の著者でもある。2001年からは、エスニック・スタディーズ学部が主催する教育チャンネルでのテレビ番組『アイランド・コネクションズ』のプロデューサー兼司会を務めている。
物語をコントロールする闘い
解放を追い求めるとき、言葉に気をつけよう
イブラヒム・G・アウデ
2021年5月にパレスチナで起こった出来事は、情熱を再燃させ、パレスチナ人が解放のための闘争において飛躍的な前進を遂げるのではないかという期待を高めた。1948年に占領されたパレスチナ地域から大勢のパレスチナ人が参加し、シェイク・ジャラー、シルワン、その他のパレスチナ人居住区からの民族浄化(シオニストのプロパガンダが信じさせるような「立ち退き」ではない)に直面しているエルサレム人を守った。
アル=マヤディーンTVのライブ中継を見ながら、私は別の時代にタイムスリップした。舞台はナクバから17年後のベイルートだった。この出来事は、1948年5月15日にパレスチナに設立されたシオニスト組織に対する最初の武力作戦だった。作戦そのものは軍事的に重要なものではなかったが、アラブ世界のニュースを席巻した。私はレバノンの新聞で、パレスチナ民族解放運動(アラビア語では「アル・ファタハ」とも呼ばれる)の最初のコミュニケを読んだ。私は心を奪われた。私はヤッファで生まれ、一家がナザレを逃れてレバノン南部の町マルジャユーンに避難したのは3歳のときだった。幼い頃から2つのことを教え込まれた: 第一に、私はパレスチナ・アラブ人である。第二に、パレスチナは解放されなければならない。約75万人のパレスチナ人が民族浄化され、シオニストによる虐殺を生き延びた人々は近隣諸国で難民となった。シオニストによる虐殺を生き延びた人々は、近隣諸国で難民となっていた。私の難民としての地位は、パレスチナに向けられたコンパスのように、そしてすべてのパレスチナ人の祖国への帰還というビジョンのように、消えない痕跡を残した。
レバノンとその地域で起こった奔流のような出来事が、そのビジョンをより強固なものにした。1952年7月23日のエジプト王政を倒した軍事クーデター、1954年のアルジェリア革命、1955年のバグダッド協定4,1956年のイギリス、フランス、シオニストによるエジプト侵攻、1958年のシリアとエジプトのアラブ連合共和国への統一、1958年のレバノン内戦、1958年のアメリカ海兵隊のレバノン上陸、1958年7月14日のハシミテ王政を倒したイラクの軍事クーデターなどである。ベイルートで育った私は、アラブの歴史に関する本を読み、最近の出来事について友人や親戚の間で多くの意見を聞いた。私は、アメリカの支配階級が率いる西側帝国主義が世界の人民の敵であり、パレスチナのシオニストがアラブ世界におけるその主要な手段であるという結論に達した。
武力作戦の記事を読んでから数週間後、友人が会社の同僚に会ってみないかと言ってきた。数日もしないうちに、私は友人とその謎めいた人物とコーヒーを飲んでいた。彼はアル・ファタのレターヘッドに書かれたコミュニケを私に手渡した。私は有頂天になった。解放という言葉は私にとって目新しいものではなかったが、そこで私は、解放を目標とするグループのコミュニケを読んでいたのだ。
ロンドンで過ごした10代の頃、アラブの学生政治に関わることと、マルクスを読むことが私の関心事だった。1964年5月28日、アラブ連盟によってパレスチナ解放機構(PLO)が設立された直後、マルクス主義研究グループの同僚から、この出来事に関する短いエッセイをグループのアラブ語ニュースレターに書くよう頼まれた。エッセイの中で私は、PLOがパレスチナ解放の願望を封じ込めるために創設されたことを指摘した。しかし、それでも私は、PLOはパレスチナ解放のためにパレスチナ人と接触し、組織化するのに有効な手段だと考えていた。
1964年末にベイルートに戻った私は、すぐにパレスチナの若者たちとの活動を始め、ロンドンでの活動を引き継ぐ形でレバノンのマルクス主義研究グループに参加した。私の焦点は、帝国主義との闘いにおけるパレスチナの解放だった。1965年初頭、私は研究グループと連絡を取り合いながら、パレスチナの若者たちと活動した。パレスチナの若者たちとの活動は、1967年の10月まで、つまり1967年の戦争から生じた大失敗であるナクサの後まで続いた。私の政治活動の総決算を考えると、レバノンを離れてカナダに行くしかなかった。15カ月後、私はアメリカに移った。数年後、私は興味深いことをよく考えた: 学問分野としてのトランスナショナリズムが真剣に理論化されたり、流行したりする以前から、私はトランスナショナルな人間だったのだ。また、私のような境遇にあった人は他にも大勢いたのだろうかとも思った。つい最近まで、学会が最も関心を寄せていたのはディアスポラだった。「ディアスポラ」にいる間に私が考えた第二の事柄は、1967年の国連安全保障決議242を中心に公式に展開された、アラブの妥協とパレスチナの妥協の始まりとして私が感じたことであった。一方で民主主義が欠如し、他方で組織的規律が欠如していることは、人民運動にとっては致命的であるが、そのブルジョア指導者にとっては必ずしも致命的でないことは、私がまだパレスチナの若者たちとともに活動していたころには明らかであった。それはともかく、革命の弁証法は、その潮の干満に表れている。
1967年8月27日、スーダンのハルツームで開かれたアラブ首脳会議の「3つのノー」は、妥協の風に対抗するものだった。「和平なし、承認なし、交渉なし」は、シオニストの敵との妥協をすべて阻止するダムであるかのように見えた6。しかし、ほとんどのアラブ政権の性質を知っている私にとって、完全解放に関するサウジアラビアの立場が、わが国民とアラブ世界全体のアラブ大衆の確固たる信念に根ざしたものだとは信じがたいものだった。その信念は、私がパレスチナの若者たちと働いていたとき、そして1967年の戦争中、アル・ファタの隊列に加わって戦いに参加するために大勢の若者たちがレバノンからシリアへと国境を越えていく現場に立ち会ったときに目の当たりにしたことに基づいていた。
アラブ諸国の多くは、サイクス・ピコ協定か、アラビア半島の場合はイギリスによって作られたのだから。しかし、あの時点でパレスチナの指導者が妥協したことは、破壊的だった。
このような反省から、私は1967年初頭のベイルートで、武装闘争には関与していないパレスチナ人組織のメンバーと議論していたときのことを思い出した。私は耳を疑った。この組織は「2国家解決」を推進していたのだ。その論理はまったく筋が通っていなかった。解放されたパレスチナのどの部分にも国家を樹立する」というようなナンセンスな表現だった。当時パレスチナとアラブ世界で起きていた動乱を考えれば、急進的な政治学者でなくとも、このテーゼの非論理性を見抜くことはできた。
私はモントリオールでの日々をフランス語と英語の分断を理解することに費やし、マルクス主義にどっぷりと浸かった。ケベックのナショナリストたちに対する国家の弾圧を目の当たりにし、大規模なデモや抗議する人々と警察の銃撃戦に2度巻き込まれた。1968年と1969年は、まさに狂乱の時代だった。私はまた、アメリカの動向にも注目していた。公民権運動はまだ続いていたし、東南アジアでの戦争もあった。
現在USINDOPACOM(米国インド太平洋軍)として知られる司令部のあるハワイ州に到着してからも、私は反戦運動のニュースを追い続け、「アメリカの政治」に関心を持つようになった。州全体が東南アジアの戦争マシーンを養ってきた基地や施設が点在していることを考えれば、反戦運動はここでも強かった。この事実は、ハワイが帝国の僻地であるという固定観念を裏付けている。
私の課外活動は、アルバイト、マルクス主義の古典やパレスチナに関する本を読むこと、反戦集会やパネル考察に参加することに限られていた。同時に、アラブ世界からのニュースも明るいものではなかった。1969年11月2日のカイロ合意により、パレスチナレジスタンス運動はレバノン領内からシオニストに対して活動する権利を得た。しかし、1970年9月から1971年7月にかけてのヨルダン軍によるパレスチナレジスタンス運動の敗北は、解放闘争にとって大きな後退となった。当初、1973年10月6日の戦争は嬉しい驚きだった。エジプトとシリアは、おそらく1967年の戦争で失ったそれぞれの領土を解放するために、協調して攻撃を開始した。アンワル・サダトがエジプト軍の進撃を止め、シリアのハフィズ・アル=アサドをシオニストとの戦いに独走させる決定を下したことは、軍事的だけでなく、外交的な戦略的後退を意味した。ハルツームの「3つのノー」は完全に消え去り、世界はサダトが反逆と不名誉の淵に落ちていくのを目撃した。1977年11月19日、サダトがシオニストを訪問し、エルサレムのクネセトで演説を行った日までの道のりは、エジプトとシリアの兵士の血で舗装されていた。しかし、それは形式的な交渉であり、シオニストとエジプト人の間で合意に達するためのものではなかった。いずれにせよ、「自治」は解放とは程遠いものだった。エジプトとシオニストとの和平条約は1979年3月26日に調印された。エジプトの動きと同時に、1968年のシオニストによるベイルート国際空港襲撃に始まるレバノンの情勢は、1975年4月13日までに「内戦」へと悪化した。PLOは1969年2月4日から、アル・ファタハの指導者ヤセル・アラファトを議長として、内戦ではレバノン国民運動側に立って右派のファランギスト党と戦った8。
これらの出来事は、解放のための革命運動の干満の分水嶺であった。これらの出来事は、具体的な出来事を支配する政治言語のベースとなる。特定の状況に対する語彙は、その用語を宣伝し、出来事とその望ましい目標に奉仕するメディアによって流布させる能力によって生み出される。言葉、イデオロギー、教義の戦争が起こる。その目的は、ある出来事にまつわる、あるいは反対する物語を受け入れるよう、ターゲットとなる大衆を社会化することである。西側諸国ではシオニストの語りがメディアシーンを支配した。これとは対照的に、社会的現実に即したパレスチナ人の語りは弱いか、まったく存在しなかった。それゆえ、たとえば「土地なき民のための土地なき民」というシオニストの誤ったマントラは、ナクバが実際には、「民族浄化」というはるかに正確な呼称が適用されることのなかったプロセスを後押しする、優れた火力と国際的な外交支援に依存していたという事実にもかかわらず、支持を得ることができた。
パレスチナの武装レジスタンス運動が始まったことで、シオニストの主要な物語とは相反する、この出来事を支持する言葉が必要となった。それは、武装闘争を通じて民族解放を達成することを強調するものだった。しかし、いくつかの要因が、武装闘争の物語が成功し続けること、そして暗黙のうちに、解放までの闘争の継続と発展を妨げる要因となった。アラブ国家体制は概して親欧米的であり、武装解放闘争を頓挫させるように働いた。さらに、エジプトやアルジェリアのようなアラブ国家は、シオニスト国家とその西側の創造者たちに比べて弱かった。西側諸国では、パレスチナ運動を 「テロリスト」、アラファト(アブ・アンマル)を 「アブ・ハダム」と烙印を押すことで、シオニストと西側の物語が勝利した。アラビア語で、「アンマル」は 「建設者」を意味し、「ハッダム」は 「破壊者」を意味する。実際、まだレバノンにいた頃、レバノン社会で著名な親戚から、アラファトを「ハッダム」と呼ぶのを聞いたことがある。
西側のプロパガンダは、それだけではパレスチナの抵抗勢力に打ち勝つことはできなかった。本格的に弱体化させるには、2つの戦争が必要だった。一つは1970-71年のヨルダン戦争、もう一つは1975年のレバノン戦争である。これら2つの出来事は、メディアのシナリオをコントロールすることが成功の必要条件ではあるが、プロパガンダだけでは勝利に至るには不十分であることを指摘している。成功の可能性を高めるには、火力がなければならない。1982年夏、シオニストの軍隊がベイルートに到達したとき、パレスチナのレジスタンスは敗北し、同年8月30日にレバノンから撤退せざるを得なかった。この戦略的敗北は、PLOのブルジョア指導部にとって、解放の言葉から離れることを容易にした。新しい言語には、それを強化し、その優位性を確保するための新しい出来事が必要だった。
1987年12月8日のパレスチナのインティファーダから1年も経たないうちに、PLOは1988年11月15日にアルジェで会議を開き、アラファトは東エルサレムを首都とする事実上の独立国家をヨルダン川西岸とガザに樹立すると宣言した。PLOはインティファーダを、革命を売り渡したことを隠すベールに使ったという点で、マキャベリ的な動きだった。アルジェ宣言の2国家構想の性格を考えれば、アラファトがアルジェ宣言を1981年8月7日のモロッコのフェズでのアラブ首脳会議で宣言された(しかし頓挫した)ファハド計画とアライメントされたことは明らかだった。
アラファト、PLO、アラブ諸国、そしてアメリカは、「和平」という言葉を発展させ始めた。ヨルダン代表団の一員としてとはいえ、パレスチナ人数名がマドリードに参加したことは、PLOの一部には大きな成功と映ったのかもしれない。しかし、原則に妥協することは解放の大義にとって致命的だと考える私たちにとっては、マドリードの光景全体が反感を買うものだった。
あの光景が反感を買うものであったとしても、1993年9月13日のオスロ合意に比べれば微々たるものだった。オスロ合意調印の数日後、エジプト出身の友人と私はホノルルのパブリック・アクセスTVで番組を持ち、合意はパレスチナの大義を売り渡す反逆行為だと非難した。オスロ合意は 「2国家解決」の変種だった。その辞書には、「ガザ・ジェリコ・ファースト」、「最終地位交渉」、「信頼醸成措置」といった用語があった。主要な点で、オスロはシオニスト主体を承認し、パレスチナの78%の解放をあきらめた。特に(東)エルサレムの問題、帰還の権利を規定する国連決議194号、シオニストの入植地、パレスチナの水の問題は、「最終地位交渉」に委ねられた。テレビ番組で私たちは、シオニスト主体の意図と妥協したPLO指導部の立場を指摘し、一方ではシオニズムとアメリカ帝国主義、他方ではパレスチナ人民とアラブ人民の間の闘争の本質を強調した。解放をあきらめることは裏切りである。
1994年8月1日、私はカイロでエジプト野党の事務総長と会談していた。彼は冗談めかして、なぜ私はその日ガザにおらず、ガザ・ジェリコ第一回目の祝典に立ち会わなかったのかと尋ねた。彼は私のオスロ合意に対する立場を知っていたが、あの状況下では、パレスチナの大義を前進させるために達成されうる最大限のことだった、と言った。それがその場にふさわしい政治の言葉だった。ちなみに、彼はアラファトの友人だった。この新しい政治用語は、自らをその一部と思い込んでいたパレスチナ指導部を含め、アラブ官界のあらゆるレベルに浸透していたようだ。PLO幹部が、例えばガザを「中東のシンガポール」にするために、経済を含む国家建設をどのように達成できるかを語るのを聞くのは、非常に不愉快だった。実際、裕福なPLO幹部がそのようなナンセンスなことを口にするのを聞くのは卑劣だった。
オスロでの大失敗以来、交渉の敗北主義的な言葉は、そのすべての繰り返しを通じて、パレスチナ国民政府(PNA)の公式言語となった。「2国家解決」という言葉を受け入れるだけで、PNAは定義上、パレスチナの分割を受け入れたことになる。交渉の各段階では、シオニスト国家とPNAの間で「信頼醸成措置」が語られた。これはPNAが、1948年占領下のパレスチナにおけるシオニスト組織の正当性にPNAを同意させようとするアメリカ・シオニストの思惑に屈したことを意味する。それはまた、PNAに関する限り、1948年の地域に住むパレスチナ人は、入植者植民地主義者との「平等」のために、入植者植民地主義体の中で「人種差別」と闘うだけでよいということを意味していた。彼らの闘いは、「アパルトヘイト国家」を「解体」し、占領者と被占領者の間に「平等」をもたらすことに限定されるだろう。PNAがすぐに忘れてしまったのは、「ユダヤ人国家」の創設に固執してきた入植者=植民地主義者が、ユダヤ人とパレスチナ人の間の「平等」を許すはずがないということだ。シオニズムの存在意義は、パレスチナとパレスチナ人の枠を超えた、追放と大量虐殺による拡大主義である。この事実は、パレスチナ全土における土地の窃盗と民族浄化の日常的な出来事によって何度も証明されており、占領者と被占領者の間、あるいはパレスチナ国家とシオニストの間の平和的存在という概念を裏切るものである。シオニストがパレスチナ人に対する犯罪を続ける一方で、シオニストのプロパガンダは 「平和」と 「犠牲者」という言葉を用いた。彼らは、パレスチナ人は和平を望んでいないとか、パレスチナ人の「和平のパートナー」はいないとか、パレスチナ人は(ヨルダン川西岸で)「我々と一緒に暮らすことを拒否している」、だから入植地の建設に反対しているのだと主張した。これがシオニストの言説の操作軌道だった。
PLOが「2国家解決」に同意すれば、パレスチナの土地だけでなく、パレスチナ人を分割することにシオニストと自動的に同意したことになる。ブルジョワの指導層は、土地基盤の確保に熱心だが、そのような路線は、土地を奪われたパレスチナ人の利益に反することを十分承知している。「交渉」以外に道を見出せないこの種の指導部は、入植者=植民地支配の主体やパレスチナ・ブルジョアジーのニーズに奉仕する、敵との「安全保障上の協調」、つまり協力の婉曲表現に従事する指導部である。
パレスチナ人に対するシオニストの犯罪は、主にPNAと、占領されたパレスチナ人を分割するシオニストの慣行に関する問題を提起している。(2)なぜ、シオニストと入植者の道路や入植地によって切り取られた孤立した領土で、パレスチナ人を自治を達成することからさえ遠ざけてきた「和平プロセス」に頼るのか。(3) どのような指導者がそのような条項に同意するのか?
こうした競合する言説や物語は、時間の経過とともに変容していった。それらは、パレスチナ解放運動か帝国主義・シオニスト枢軸のどちらかによって始められた現地の出来事によって動かされた。PLO指導部は、先に述べたように、独立国家宣言によってカモフラージュされた妥協的な立場に密かに移行した。それ以来、支配的な言語は西側の物語の言語となった。ドナルド・トランプの時代(2017~2021)には、湾岸アラブ諸国が、「アブラハム合意」を通じてシオニスト国家とオープンな関係を結ぶことは比較的容易だった。PNA指導部を含むパレスチナ人は、自分たちの大義を歴史から抹消されるように思われた。パレスチナのブルジョワジーが存亡の危機に直面しているのを置き去りにしたまま、湾岸アラブ諸国がシオニストとの開放的な関係を進めていることを、PNAの指導者たちが非難しているのを見るのは、非現実的な瞬間だった。
しかし、ラマダーン明けのアル・アクサ蜂起は、方程式を根本的に変えた。再び、現地の出来事が、解放のためのパレスチナ闘争の柱(完全な解放とパレスチナ人の祖国への帰還)を強調し、政治的言語を刷新する基礎となった。2021年5月のインティファーダはパレスチナ人民を統一した。この団結は、パレスチナのブルジョワジーが数十年にわたって固執してきた「2国家解決策」と矛盾するものだった。ガザが「統一インティファーダ」を支持したことは、解放のための武装闘争の中心性を強調した。統一とは、1948年の占領下パレスチナにおけるパレスチナ人の闘争が、入植者と先住民パレスチナ人の間の「平等な権利」のためではなかったことを意味する。それは、パレスチナ人を追い出そうとするシオニストとパレスチナ人との間の実存的な闘いであった。シオニストによるアル・アクサへの攻撃は、聖地を守る人々の不屈の精神を示した。危機に瀕したPNAは、シオニストの敵との安全保障上の協調を維持しながらも、こうしたシオニストの攻撃に反対するよう国連に訴えた。ナブルス、ヘブロン、その他の地域では、PNAの阻止の試みにもかかわらず、抗議行動が発生した。
停戦は、この統一インティファーダが血をもって主張した解放の新興言語を含め、あらゆる次元で得たものを後退させようとするいくつかの試みを明らかにした。米国に率いられたシオニスト団体とEUは、統一インティファーダが主張した言葉を打ち砕くために、すぐに新たな出来事を作り始めた。彼らは「2国家解決策」を再浮上させ、「紛争」をハマスとシオニストの間のものとして宣伝した。それは、シオニストとパレスチナ人民の間の実存的な闘争を完全に横取りした。米国はガザの復興を支援しているが、その条件として、PNAを通じた長期停戦を取引の中心に据えることを挙げている。また、「改革」の意味を明言することなく、PNAを改革すべきだとも述べている。
PNAが敵との安全保障上の協調を続けていることも、同様に有害である。マフムード・アッバスは、パレスチナの 「国家」のためのパンくずを求める妥協的な立場から少しも動かない。2021年6月6日、アル・マヤディーンTVの「アル・マッサイヤ」番組で、PNAと密接な関係にあるラマッラの作家で政治アナリストのハリル・カラジャ・アル・リファアイは、オスロはパレスチナの「すべての」派閥が「合意した」パレスチナ国家を樹立するためのパレスチナ闘争の基盤を築いたと公然と発言した。彼が言及したのは、1988年のアラファトによるパレスチナ国家樹立宣言であることは明らかだ。しかし、その当時、パレスチナのいくつかの戦闘組織(ハマス、イスラム聖戦など)は存在しておらず、パレスチナ闘争の地形はそれ以降変化していることに注意した方がよいだろう。PNAの政治用語は、シオニストの本質を完全に無視している。シオニストはパレスチナ国家に同意するつもりはなく、それは入植地の拡大やヨルダン川西岸にすでに入植者が殺到していることで十分に証明されている。
結論として、1948年の民族浄化は2つの矛盾した言説を生み出した。ひとつはシオニスト、もうひとつはパレスチナ人である。前者は民族浄化を支持し、後者は解放されたパレスチナへの帰還に焦点を当てた。やがてパレスチナ解放の言説は、妥協という支配的な言説へと変化していった。PNAの言説は、アメリカやシオニストの「平和」という言説とかなり重なり、1967年6月以降のシオニストの入植地建設と拡大の隠れ蓑として機能した。しかし、PNAの官憲によって語られた言説を中心にパレスチナ人が社会化されたにもかかわらず、結局のところ、抑圧されていた解放の言説を抑制することはできなかった。
対照的に、最近の統一インティファーダは、解放の言葉を復活させる出来事を引き起こした。現段階では、パレスチナ人民の敵が、解放の言葉を犠牲にして自分たちの言説を支持するような出来事を現場で作り出すことを許さないことが絶対的に重要である。PNAはしばしば、必要なときにはシオニストの敵に対して武力闘争を行ったと主張する。彼らはその例として 2000年9月のアル・アクサ・インティファーダを引き合いに出す。しかし、重要なのは批判的な質問をすること: 武力闘争は解放のための主要な方法として採用されたのか、それとも敵に圧力をかけて 「2国家解決」に同意させるためなのか?1973年10月6日、サダトがシオニストを攻撃したとき、彼の目標は解放ではなく、パレスチナ入植植民地主義者との 「和平」であったことを思い出してほしい。敵の言説に対抗できるよう、抵抗の成果を土台にした新たな出来事を生み出すことは、あらゆるパレスティナ人に課せられた責務である。2021年6月、PNAに拘束されていたパレスチナ人活動家ニザール・バナトが拷問され殺害された事件は、PNAが事件を妥協の言葉に戻そうと必死になっていることを示している。しかし、バナートの殺害に呼応したパレスチナ全土の蜂起から判断すると、彼の殉教はPNAとシオニストにとって裏目に出たようだ。解放の言葉は、今のところ自己主張しているようだ。
言語と出来事の間の弁証法的関係は、いくら強調してもしすぎることはない。解放への道では、言葉に気をつけることが絶対不可欠なのだ。
3 Ilan Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine (Oxford: Oneworld, 2006).
4 Charles D. Smith, Palestine and the Arab-Israeli Conflict (Boston, MA: Bedford/St. Martins, 2010), 235-37, 239, 260.
5 1974年6月12日、パレスチナ国民評議会(PNC)はPLOの目標であった。「世俗的な民主国家」を 「独立したパレスチナ国家」に置き換えた。採択された文言の変更をめぐる外交力学は、1973年のアルジェと1974年のラバトの両アラブ首脳会議におけるPLOとアラブ諸国の協調を示している。Samih K. Farsoun and Naseer H. Aruri, Palestine and the Palestinians: A Social and Political History (Boulder, Colo.: Westview Press, 2006), 189, 214を参照。
6 アラブ諸国がシオニストと単独で和平を結ぶことへの警戒は、「第4のノー」と考えられていた。例えば、Ghada Hashem Talhami, American Presidents and Jerusalem (Lanham: Lexington Books, 2017), 103を参照。
7 Harvey Sicherman, Palestinian Autonomy, Self-Government, and Peace (New York: Routledge, 2019)。Farsoun and Aruri, 198も参照のこと。
8 B. J. Odeh, Lebanon: Dynamics of Conflict (London: Zed Books, 1985), 131-134.
9 2002年4月にベイルートで開催されたアラブ首脳会議では、ファハド・プランの類似版が採択された。Farsoun and Aruri, 292を参照。
QASSEM IZZA. Iはメディアの専門家であり、テレビニュース業界の創始者であり革新者である。アリのジャーナリズムのキャリアは、第一次パレスチナ・インティファーダの取材から、唯一のアラビア語テレビ通信社を国際的名声に導くまで、過去30年にわたって発展してきた。ニュース業界のパイオニアとして、パレスチナ人コミュニティ内での堅実かつ戦略的な草の根ニュース収集に基づくパレスチナ通信社、ラマッタン通信社を設立した。こうしてアリは、ガザの収容所での第一次パレスチナ・インティファーダ勃発に対するイスラエルの反応、第一次湾岸戦争に対するイラクの反応 2008年から2009年にかけてのガザ戦争など、歴史上の重要な出来事に対する国際メディアの焦点を形成してきた。ビルジート大学、ニューヨーク大学、オックスフォード大学で学生時代に政治的な活動を行なっていたアリは、90年代前半、ワレイト・イル・ファキー(イスラム主義政治思想)の進化とその多様な解釈、北アフリカ、中東からパキスタン、インドに至る政治的レジスタンス運動との関係についての研究で新境地を開いた。この焦点は、「アラブの春」運動の社会的・政治的基盤や、現代の中東に影響を与え続けている国際的な地政学的力学を形成するまでに発展した。
メディアについての考察
パレスチナ解放のための強力なツール
カセム・イザット・アリ
メディア。ジャーナリズム。アラビア語であれ英語であれ、30代前半までの私にとって、これらは意味のない言葉だった。私は、自分の家族、自分の土地、そして自分の民族が排除され、抹殺されることから守るために戦うことで頭がいっぱいだった。やがて私は、ガザをはじめとするパレスチナで起きていることをいち早く報道することで、世界の注目を浴び続けることが、私にとって最善の抵抗手段であることに気づいた。ジャーナリズムを通して、私は世界と直接対話することができた。オスロによって設立された、パレスチナの物語に口を出すための欠陥だらけで非効率な政治機構を通してではなく、だ。
私の人生は、パレスチナを象徴する村、ベイト・ハヌーンから始まった。そして、私の旅、移住、国外追放、逃亡、否定を経て、私の人生もそこで終わるだろう。
私の人生、そして私のアイデンティティは、闘争と複雑に絡み合っている。ガザに生まれることは、解放の戦士として生まれることだ。それ以外の運命はない。違うのは手段だけだ。店主、看護師、会社経営者、農民……過去70年間の不公正を目の当たりにしてきた私たちの存在そのものが、この土地における抵抗の象徴なのだ。
闘争と並行して、私の人生を特徴づけてきたのは、女性の力強い影響力である。私の人生の中心にいるのは、10歳で家を追われた母、カドラ・ズワイディだ。1948年のナクバで、イスラエル軍は彼女の村(ディムラ)の家、モスク、市場、農作物を一掃し、住民の移住を強制した。村人のほとんどはベイト・ハヌーンに流れ着いたが、その大きな部族はアラブの伝統に従い、ナクバから逃れてきた家族を「養子」にした。こうして私の母、つまり私たちのヤンマは、1万人以上の部族からなる屈強で頑固な部族、カファルネ一族の一員となった。著名な実業家であり、エレガントな着こなしができ、深く尊敬され、(すべてにおいて重要なことだが)長兄でもある。
祖母(彼女の義母)のシッティ・ヒッセンもまた、私の形成に強い影響を与えた。ムフタール(部族長)の娘であるシッティ・ヒッセンは、真のフェラハであり、母なるパレスチナの豊かな土壌を脈々と受け継ぐ田舎の女性だった。彼女の家は、私たちの村を囲むオレンジ、レモン、ザボンの果樹園であるバヤラートにあり、昼は一本一本の木に愛情を注ぎ、夜はお茶を沸かし、その木の下で静かに眠るというように、彼女は延々と土地を耕していた。私の青春の大部分は、彼女と一緒に学びながら過ごした。私は彼女のスタミナ、土地への愛着、体力、そして彼女の心に蓄えられた知識を賞賛した。母のカドラはほとんど私に会わなかったが、私が祖母の愛と土地の抱擁という真の贅沢の中で甘やかされていることを知っていた。
シッティ・ヒッセンの夫はカセムで、私の祖父であり、名前の由来でもある。村の名士であったカセムは、2番目の妻を迎えることにした。彼の新しい妻、ハジェ・サラは、私たち一族の一流の殉教者の娘で、武器を持った罪で英国警察に絞首刑にされた。ハジェ・サラは子供を産むことができなかった。運命はハジェ・サラに別の計画を立てていた。ハジェ・サラは影からリーダーとなり、戦略的な頭脳と並外れた機転で私たちの部族の力となった。シッティ・ヒッセンとは異なり、ハジェ・サラは知的な力を持っており、社会、氏族、人間、部族のパワー・ダイナミクスを鋭敏に理解し、結婚の承認から紛争の調停、村の部族との駆け引きに至るまで、重要な決定には彼女の助言が不可欠だった。彼女は28歳のときに夫を亡くしたが、家族のもとには戻らず、私たちのところに留まり、ビジネスウーマン、クランリーダー、そして私たちの村の権威の代弁者としての役割を続けた。
幸運なことに、私の幼い人生を彩り、形づくった4人目の女性は、私たち家族にとっては部外者である小学校1年生のときの担任教師、サルワ・ヤッファウィエ先生だった。サルワ先生は教養があり、背が高く、洗練されていて、非の打ちどころのない服装で、とても美しかった。6歳の私は、お腹の中に恋の蝶を感じた。ミス・サルワは私に、集中力と規律を通して学び、知識を愛し、教育の力を理解するよう促した。うっかりしていたが、彼女はまた、私の中に生涯残るレジスタンス・ファイターを呼び起こした。ある日、学業成績優秀の褒美として、彼女は私に「ホワイトカード」をくれた。国連からのフードスタンプに相当するもので、国連機関から特別支給品や食料をもらうことができる。私は手切れ金という概念が嫌いで、それを持つことを恥ずかしく思ったが、サルワ嬢のことは大好きだった。しかし、サルワ嬢のことは大好きだった。彼女の目の前から離れると、私はそのカードを粉々に破り捨て、家に帰ってハジェのサラに伝えた。サラは喜んだ。「ヤ・カセム、ヤ・ハビビ、私たちは誇り高き人々であり、誇り高き人々は国連の手から食べることを受け入れない」その日から私は、国連がなぜ私たちに食料をくれるのか不思議に思った。国連は私たちに何を求めているのだろう?私たちを買おうとしているのだろうか?我々に影響を与えようとしているのか?依存心を育てようとしているのか?私たちは配給など必要としていなかった。私たちは信じられないほど肥沃な土地に住む、長い血統を持つ誇り高き人々だったのだ!私の幼い心はすでに煮えたぎっていた。
父やハジェ・サラ、そして私たち一族に支えられ、強大な権力と影響力の中で育ってきた私の人生は、1967年の戦争でイスラエルによる占領が始まった9歳のときに劇的な展開を見せた。スエズ運河以東のエジプト全土をイスラエルが支配するようになったことで、不可解なフロンティアが父と妻、7人の子供たち、部族、祖国を隔てることになった。父と再会するまでに10年の月日が流れた。PLOの指導者としての地位を考えれば、父の帰還を促すことはできなかった。イスラエルが父を国外に閉じ込める絶好の機会が巡ってきたのだ。
私たちの人生の次の章は、父の運命を知らないというトラウマと、父が不在の間の私たちの経済的地位の劇的な崩壊に彩られた。その結果、ヤンマ・カドラとハジェ・サラの気概と決意の深さが明らかになり、それが私たち兄弟の生涯を形作ることになった。正式な教育も識字率もなかったこの2人の女性は、村で唯一の店で布地を売るビジネスを始めた。それは成功し、この二人の女性は私たち7人全員を一人ずつ大学へ送り出した。長姉のフェアリーズはカイロへ、マルワンはバグダッドへ、アッザ、ニハド、ナセル、そして私はビルジートへ、マルワはベツレヘムへ。今日、私たちの中には博士号、修士号、学士号を持つ者がいる。
メディアはおろか電気もないその土地で、私たちは自分の国、国民、家族、土地に降りかかった劇的な不正義を鮮明に認識しながら成長した。柑橘類の市場もなく、父の事業からの収入もない中、どうやって家族の地位を維持し、母と家族を助けるか。村での他の副業(熟練したポーカー・プレーヤーやギャンブラーとして成功することも含む)に加え、これは勉強で優秀な成績を収め、タウジヒイでトップクラスの成績を収め、カイロで工学を学ぶための全額奨学金を得ることを意味した。
当時、カイロで学ぶことは最大の成果であり、ユンマとハジェ・サラに贈ることのできる最も意義深い感謝の贈り物でもあった。しかし、それは長くは続かなかった。カイロでは、私は闘争から遠く離れ、私の同胞を抹殺しようとする組織と有意義に関わり、対立し、動員することができなかった。私はパレスチナの政治生活の中で、その心臓部であるビルツァイト大学で自分の居場所を見つけなければならないと思った。私の家族にとっては悲惨なことだが、私は工学のキャリアを目指していたところから、キャリアではなく刑務所への早道として知られる政治学を学ぶことになった。私の名前の由来である祖父のカセムは、スエズ運河を国有化したジャマール・アブデル・ナセルに反対して侵攻してきたイギリスとフランスの手によって1956年の戦争で戦死し、母方の叔父のハッサンは1948年にイスラエル軍に誘拐され、その後消息不明になっている。活動家と政治的指導者として、私はその後10年間、イスラエルの政治的牢獄に出入りすることになる。
ここまで来ると、メディアの出番はどこかと思われるかもしれない。私の旅の次の部分は、解放のための闘いにおける強力なツールとしてのジャーナリズムと有意義に関わるための、形成的かつ基本的な要素であることが判明した。それは同胞のルーツを探る旅であり、彼らの人生経験を収集する旅であり、政治的ビジョンについて議論する旅であり、イデオロギー、宗教、文化的構造について意見をぶつけ合う旅であった。タバコを分かち合うような些細な交流もあれば、名前を明かす代わりに拷問に耐えるような深い交流もあった。それは私の人生で最も形成的で(皮肉にも)有意義な時期であり、私の民族、抑圧者、そして私自身に対する理解を深めた。私たちのナショナリズムを混ぜ合わせ、触媒とし、民族として団結させ、ジェンダー、社会経済的、宗教的、イデオロギー的な障壁を消し去り、これらすべてをイスラエルの抑圧者が銀の皿の上に載せてくれた: 刑務所である。
カメラも紙もマイクも機材もなく、ジャーナリズムの物質的な道具を一切持たずに、私の記憶は私の金庫となった。耳を傾け、録音し、処理し、会話、経験、アイデア、戦略を分析し……それはすべて私の頭の中に蓄積され、イスラエルに没収されることなく完全に安全だった。それは私の役に立つだろう。
私が刑務所と政治から出たのは、ビルジート大学で中東研究の学士号を取得し、政治学を副専攻して卒業したときだった。役に立たない卒業証書で武装し、パレスチナの政治派閥に深い不満を抱き、(1948年と1967年の戦争後、国外に追いやられた人々とは対照的に)「内側」から来たパレスチナ人として、私は「パレスチナ人の唯一の正当な代表者」であるはずのPLOを支持することに私の燃える情熱を向けようとはしなかった。個人的な体験談、意見、イデオロギー的な立場、討論、議論、矛盾が、まるでフリー・ラジカルのように頭の中を駆け巡り、私は政治に代わるものを見つけなければならないと思った。私たちの物語を占領者や世界に語りかけ、植民地的な物語に異議を唱え、イスラエルが存在しないと主張する「私たち」が誰なのかをより深く認識させる方法を。
何も明らかではなかった。私はイスラエルで労働者として働き、その後友人と農場を始めた。時間はかかったが、ビルゼイトやラマッラ、ヨルダン川西岸地区よりもガザの方が私を必要としているのだと気づいた。私はガザに戻った。
ガザは常に、あまり知られていない存在であり、イスラエルが異なる戦略を持っている場所だった。ガザでは、コミュニティ・グループ、団体、クラブが出現することは許されなかった。イスラエル人は、過激派と武装闘争がうずまく住民を厳しく統制した。イスラエル占領当局か国連救済事業庁のどちらかに仕事がつながるという、絶対的な浸透と強制の環境の中で、私は、自分のコミュニティと同胞に降りかかったグロテスクなレベルの不正義に対する怒りと憤りをぶつけながら、どうやって生計を立てるかを考えなければならなかった。革命精神に溢れ、元囚人であり、政治的ジャンキーであり、信頼できる同志であり、有能な組織者であった私は、自分自身の行動指針を見出すことができなかった。
そして1987年、インティファーダが爆発し、私の未来への道がようやく見えてきた。友人のアリ・カアダンが、ガザのWTNでプロデューサーとして働かないかと誘ってくれたのだ。それが何を意味するのか、私にはわからなかった。何のプロデューサーなのか?私たちはテレビを簡単に手に入れることができなかったし、そのメディアを通してニュースを構想することもできなかった。私にとってのカメラは、映画やエジプトのソープオペラ、ヨルダンのテレビ番組の制作に使われていた。これらのネットワークはニュースではなく、国王や大統領、その他の人気タレントを称賛するものだった。WTNは、エレズ検問所でVHSビデオカメラを使った2時間のトレーニングを提供してくれ、私はテレビメディアのキャリアをスタートさせた。
最初の映像のひとつは、エジプトとの国境にあるラファ難民キャンプで、ヘリコプターに向かって石を投げる子どもたちや女性たちを撮影したものだ。波板の屋根の間を飛び跳ねながら、私は生の映像を集めた。この映像は、イスラエルの物語に対抗して国際的に放映される1分間の爆発的なビデオとなった。イスラエル軍に 「組み込まれた」ニュース(すなわち、石を投げる。「攻撃的な」パレスチナの若者たち)、イスラエルのジャーナリストや技術者によって収集、撮影、制作、ナレーション、吹き替えされたニュースを認識することに慣れていた大手ネットワークは、今や映像による逆説の素材にアクセスすることができるようになり、それをこぞって取り上げた。私のカメラは、まったく異なる物語を映し出した: アパッチヘリコプターがミサイルを発射し、イスラエルのジープがグレネードランチャーやマウントガンから発砲する。インターネットもデジタルもなかった)ガザからテープを持ち出すには、私を信頼してくれた母親や父親、そして刑務所で親しくなった彼らの息子や娘たちといったコミュニティのネットワークに頼らざるを得なかった。その信頼がすべてを可能にし、私たちはテープを密輸し、イスラエル軍司令官を悔しがらせた。
私がジャーナリストとして飛躍的な進化を遂げることになったのは、ある小さなホテルとそのダイナミックな支配人のおかげだったとは知る由もなかった。ラベンダー、ジャスミン、柑橘類の香りが漂い、愛情を込めて手入れされた草花で飾られていた。ガザにやってくる外国人は皆、マルナハウスに泊まりたがり、部屋を取るために何週間も待ったものだ。そこは、鋭い知性、鋭い直感、そして確固たる信念を持った女性によって運営されていた。その女性は、私の師であり、友人であり、親友であり、第三の母となった: アリア・シャウワだ。
聞き上手であまり話をしないアリアは、メディアに対する私の理解を形成する上で、私の師であり、助け手であり、良心であった。ロバート・フィスク(作家)、グロリア・エマーソン(NYT)、サラ・ロイ(ハーバードの研究者)、ピーター・ジェニングス(ABC)、ラリー・レジスター(CNN)、ポール・テイラー(タイム誌)、ボブ・サイモン(CBS)、ジョー・サッコ(マルタのグラフィック作家)など、当時の業界トップの人物たちから信頼されていた。アリアは階級や富、VIPの地位などお構いなしだった。誰もが彼女を恐れていた。「恐れ多いほど敬虔」という言い方もできるだろう。彼女はマルナハウスという、知識人、外交官、国際機関にサービスを提供する老舗の「機関」を愛していた。彼女は、メディア産業の重要性とそれを機能させる人々のニーズを深く認識し、洞察力のある自らを大臣とする最高の情報省とした。
マーナハウスは、パレスチナ人の間で、また信頼できるジャーナリストたちと貴重な情報を共有するための安全な場であり、エルサレムのアメリカン・コロニーと並んで、パレスチナでは他に並ぶもののないナショナリズムと知性の雰囲気を育んだ。アリアは、ホテルに滞在するすべての人物の身元を保証するネットワークと情報源を持っていた。特に、彼らがジャーナリストとして頻繁にガザに潜入し、情報を収集し、活動家を逮捕し、殺害するシン・ベトの将校でないことを保証していた。この偽装工作が功を奏し、彼らはキャンプや村、民族レジスタンス運動の多くの拠点にアクセスすることができた。この貴重な場の物理的な保護は、私の村の一族の手に委ねられていた。
アリアはジャーナリストの焦点を、人道問題としてのパレスチナ人についてではなく、紛争の核心的な問題について書くように形を変えた。マーナハウスでは、新しい物語が形成された。現代史の中で最も壮大な民衆蜂起の行方を左右することになるメディア・メッセージを洗練し、共有し、増幅させるための最も重要なパレスチナの機関のひとつとなった。
私は毎日、南部のラファから北部のベイト・ハヌーンまでワーゲンのバグで移動し、ニュースを集めてはアリアに伝え、アリアやハイダル・アブデル・シャフィ博士、ユスラ・アル・バーバリに同席して、現地で何が起きているのか、人々は何を考えているのか、最も新鮮で正確な草の根情報を入手した。
オスロ合意は、私たちの解放のビジョンと闘争の大衆性に地殻変動をもたらした。代表者の支持を得ずに結ばれた安易な取引で、オスロで得られたパレスチナ人の「利益」は、スタイルも中身も、刑務所で行われた交渉に似ていた。私たちは、同胞や自分たちの快適さを少しでも向上させようと、電話1本、タバコ1本、ムロキアのお玉1杯を追加するよう交渉した。オスロの「政治指導者」たちは、同胞を解放するためではなく、「より良い」職業を得るために、そのような交渉をしていたのだ。
当時、私たちが予想していなかったのは、その結果、私たち国民がどのように変化していくかということだった。解放のアジェンダは政治化され、市場での野菜のように取引されるようになっただけでなく、個人の宣伝やうぬぼれの道具にもなった。「政治指導者」「政府」「交渉」によって解放が達成されると信じていたのだ。私たちは献身を失い、違いを乗り越えて話し合う意欲を失い、個人や党の思惑よりも国民としての団結を優先させた。このような近視眼的な妥協からは、何一つ良いものは生まれなかった。
年月が経つにつれ、私のメディアとの関わりも増えていった。私は、1994年にヤーセル・アラファトとPLOの一行がガザに帰還したことを報道する会社を立ち上げた。新パレスチナ自治政府の展開に一度は大いに心を痛めた私は、ニューヨーク、そしてオックスフォードに留学した。1999年に帰国すると、私は獄中で強い絆で結ばれた政治的背景の異なる数人のジャーナリストと協力して、自由な表現のための独立したプラットフォームとしてラマッタン通信社を設立した。数百人の若いパレスチナ人女性や男性を技術者やジャーナリストとして動員・訓練し、オスロ方式の失敗がもたらした悲劇の連続について、驚くべき画像と鋭い分析を入手し、国際的な主流メディアを通じて発信した。
信頼。誠実さ。団結。活動主義、組織、動員。集団と個人のリスクを取る意欲。私たちの国民は、私たちの後を継ぐ世代を通じて、この些細な政治的口論と国際的無関心の増大という膠着した雰囲気の中で、前進する道を切り開くだろう。私たちの苦境に忠実に、私たちは世代を重ねる。これこそが、解放の道具としてのメディアを語ることのできる基盤なのだ。
30年前、70年代と80年代の集団的闘争と犠牲の時代を振り返ってみて、もし当時ソーシャルメディアが存在していたら、ナショナリズムと草の根活動の激しい精神と結びついていたら、私たちの国はとっくに解放されていただろうと私は確信している。ストライキや抗議行動を組織し、ビラを一通一通印刷し、イスラエル軍の目をかいくぐって一軒一軒ビラを配り、捕まればせいぜい6カ月の禁固刑、最悪の場合は銃殺という時代だったのだから。このような即席の手段が、私たち自身や互いを信じ、イスラエルや欧米の植民地政策に対抗する私たちの集団的能力を信じるという、私たちの最も輝かしい時代と交わることがなかったのは悲劇的だ。
今、ガザ、ヨルダン川西岸、歴史的パレスチナ、そしてディアスポラの若い世代を見ていると、メディアが解放の道具となる新たな機会があるように思える。この数カ月間、パレスチナ人の若者たちは、東エルサレムの民族浄化に反対し、包囲されたガザへの壊滅的な砲撃を記録し、人権活動家ニザール・バナトの殺害をきっかけに、パレスチナ指導者の未来がどうあるべきかを語るために、ソーシャルメディアに結集してきた。ソーシャルメディアの迅速で自由な反応によって、世界中の人々がようやく、検閲されず、生々しく、人間的なパレスチナの物語を直接聞くことができるようになった。私がガザで起きていることを世界に伝えるためにカメラを手にしてから30年、パレスチナ人は今、私たちの物語が聞かれ、行動される方法を変え、形づくる新しいツールを手にしている。
SAMA. U SHARARは、レバノンのベイルートを拠点とする独立ジャーナリスト兼研究者である。アラブや国際的なメディアで中東問題を取材し、国連や欧州連合を含む多くの国内外の組織でレバノンのパレスチナ難民に関する調査を行ってきた。アラビア語、英語、フランス語で数多くの記事や研究論文を発表している。
アブ・シャラールはまた、レバノンのパレスチナ難民キャンプや集会で、主流メディアの誤った表現やステレオタイプから離れたメッセージを伝えるために、メディア分野で若者たちに力を与える活動を行っている非政府組織、マジェド・アブ・シャラール・メディア財団(MASMF)の代表も務めている。また、レバノンのキャンプや集会に参加するパレスチナ人の若者のためのトレーニングサイト「Shababeek」も統括している。
パレスチナを解放し、難民に力を与えよう
サマア・アブ・シャラール
6月の初めに南アフリカの友人とバーチャルの対話をしたとき、ヌラーはパレスチナで起きていることと、彼女の母国に存在したアパルトヘイト(人種隔離政策)体制との対比を鮮明にした。占領下の東エルサレムのシェイク・ジャラー地区とシルワン地区で起きている民族浄化を見て、ヌーラは南アフリカのアパルトヘイト時代に両親から聞いた恐ろしい話を思い出した。
ヌラーや数人の外国人の友人たちは、2021年5月の蜂起の際にパレスチナ人がいたるところで蜂起したパレスチナのハバに、かつてないほどの類似性を感じた。「今回は何かが違うようだ」と彼らは同意した。実際、私たちパレスチナ人にとっても、何かが違うようだ。私たちの大義が世界で初めて支持されたこと、雄弁でソーシャルメディアで何百万人もの聴衆に働きかけることができる有望な若い活動家が台頭してきたこと、パレスチナで起きている出来事をライブストリーミングで配信していること、そして最終的には、イスラエルによる長期的なパレスチナ植民地化を表現する用語の相対的な変化に拍車をかけたこと、これらすべてが注目すべき変化である。
私の世代は、その前の両親や祖父母の敗北を受け継いでおり、私はつい最近まで、この敗北を娘のミーナに引き継ぐのだろうと思っていた。しかし、パレスチナのハバが新たな現実を告げ、パレスチナの 「指導者たち」に妨害されなければ、尊厳と解放、そして祖国への帰還への長い道のりの第一歩となる可能性があった。
私たちはよく、「人生の選択は自分で決めるものだ」と言われる。ほとんどのパレスチナ人にとって、選択とは贅沢なものであり、それを甘受する勇気がないものだと私は思う。父マジェド・アブ・シャラールはドゥラ村の出身で、母ファティマ・アル・アゼはベイト・ジブリン村の出身である。彼らの結婚、そしてその後の人生の選択は、彼らが私の人生から早く突然去ってしまったにもかかわらず、私の旅路を確実に形作ってきた。
私の人生はジェットコースターのような出来事だったが、それは両親のおかげであり、とりわけ、他のパレスチナ解放機構(PLO)指導者たちが子どもたちにしていたように、私たちを排除せず、自分の歩む人生に私たちを巻き込むことを選んだ父のおかげである10。
当時、父はアル・アヤム紙の編集長として働いていたが、その後、湾岸諸国の「ファタハ」運動に参加し、指導するようになった。1970年の「黒い9月」事件でPLOが脱退するまで、私たちはそこで数年間暮らした。子供の頃の私の唯一の曖昧な記憶は、兄のサラムと私がダイニングテーブルの下に隠れていたことである。
多くのPLO幹部や家族にとってそうであったように、レバノンは私たちの次の目的地だった。レバノンは、私が故郷と呼ぶことになる国に最も近い国であり、私の人生が形づくられる場所となった。杉の木が生い茂るこの国で、私はあらゆる形の戦争、紛争、不正、差別、苦しみを目の当たりにしたし、今も目の当たりにし続けている。この小さな国は、私が公私ともに耐えた多くの喪失と和解し、パレスチナ人であることの誇りを発見し、あらゆる困難にもかかわらず、それを活動へと結びつける場所となった。
私は8歳の時に生みの母をガンで亡くし、母とともに人生の安住の地を失った。弟のサラムと私は、それから数年間、寄宿学校を転々として過ごした。妻を亡くし、2人の子供という重責に圧倒されていた父は、おそらく私たちを全寮制の学校に入学させるのが最善だと考えたのだろう。多忙なスケジュールにもかかわらず、週末に父と過ごすわずかな時間が、母の死後、私たちにとって家庭の温もりに最も近いものだったからだ。
寄宿学校と、時折父の家に泊まったり、父の友人宅で寝泊まりしたりしながら、私とサラムはなんとか生き延び、母が残した大きな空白に対処した。私たちの代償は寄宿学校を出て、父と彼の新しい妻イナム、そして彼女の前妻との娘アッザと一緒に家で暮らすことだったからだ。突然、サラムと私は父と同じ屋根の下にいることになり、私は妹と第二の母を得た。私たちの父マジェドとイナムは、結婚だけでなく血縁でも結ばれた本当の家族として私たちを戴くために、妹のダリアをもうけることにした。
父はレバノンをあらゆる面で受け入れたが、自分のアイデンティティと信念に忠実であり続け、それを私たちに伝えてくれた。「家の外では友達とレバノン方言を話すが、家ではパレスチナの方言を話す。
マジェドは自分の意見を押し付けることなく、微妙なメッセージを伝える名人だった。それにもかかわらず、時には、私たちが即座には気づかないような利益のために、彼の決定に従うことを期待し、私たちを限界まで追い詰めた。私たちに新しいもの、考え方、人々を紹介することは、私たちが好奇心を持って質問するきっかけを作り、パレスチナやアラブの文化やアイデンティティに誇りを植え付けるための、マジェドのさりげない方法だったのだろう。
私はマジェドの生前にはその価値に気づかなかった。彼が政治的、国家的にどのような人物であったかを知ったのは、実は彼が暗殺された後のことだった。彼の死後何年も経ってから、彼が受けた数々の殺害予告を知ったのだ。当時、エドワード・サイードが私たちと彼の懸念を共有していた。サイードは共通の友人と一緒に、「マジェド・アブ・シャラール:PLOの新星」と書かれたアメリカの新聞の切り抜きを送り、「これは悪い兆候であり、監視されている証拠だ」と警告した。にもかかわらず、彼は決して身の安全に用心することはなかった。
マジェドの突然の離脱は、私たちの生活に大きな打撃を与えた。1981年10月9日は、私の世界が崩壊した日、人生の拠り所を失った日として、私の心と魂に刻まれるだろう。私たちよりもパレスチナを選んだ父に対する怒りと憤り、残された唯一の親を奪ったパレスチナに対する嫉妬と憤りの感情は、何年も私の中に残った。正気を保つために、私は前に進むために、父とパレスチナとの問題のある関係を心の奥底に葬り去った。その数年後、父とパレスチナの両方が、私の存在の羅針盤となるとは思いもよらなかった!
1982年にイスラエルがレバノンに侵攻したのは、父が暗殺された数ヵ月後のことだった。それまでは、戦争で荒廃したレバノンに住んでいたにもかかわらず、戦争との出会いは比較的穏やかなものだった。イスラエル軍のレバノン侵攻は、それまで経験したことのないようなもので、人々の移動と苦しみ、戦争の荒廃を目の当たりにした。
私は、ハムラにある急遽病院となったタルムード・センターでボランティア活動を行い、負傷者に手を貸した13。戦争の残虐行為に関する多くの恐ろしい映像が、今でも私の脳裏に残っている。そのうちのひとつが、全身から血を流しながらセンターに駆け込んできた青年が、自分の耳を手で押さえ、「耳を助けて、耳を助けて」と叫んでいた忘れがたい映像だ。
人々の苦しみは、日々の数々の困難と隣り合わせだった。ペットボトルや1ガロンの水を入れる順番を待つ人々の屈辱的な長蛇の列は日常的な光景となり、深刻な停電のためにロウソクの明かりで何時間も過ごすことも、イスラエルとその協力者が西ベイルートへの国際援助や人道援助を阻止したために基本的な生活必需品を手に入れるのに苦労することもあった。悲しいことに、1982年のレバノンは、多くの面で2021年のレバノンに似ている。
私たちは皆、ニュースを追いながら、南部のパレスチナ人とレバノン人のレジスタンスに声援を送り、世界で最も強力で残酷な戦争マシンの1つであるイスラエルに対して、私たちのファイターにはチャンスがあると信じていた。イスラエルがベイルートへの進駐を計画していることが明らかになるにつれ、私たちの知人や友人の多くが、当時唯一の出口であった東ベイルートを通って出国し始めた。
この小さな国の一部で起きていた戦争の地獄から逃れるために、多くの人が危険を冒してまでこの旅に出たのだ。父の友人たちの勧めでヨルダンへの旅が決まったとき、私はその旅が怖かった。ベイルートを離れることと、首都の禁じられた場所を通ること、どちらが怖かったかはわからない。それまで私たちは、パレスチナ人への敵意で知られるファランジュ軍が支配する東ベイルートを訪れることさえ厳しく禁じられていた。東ベイルートの検問所で行われている残虐行為について聞いていた話はすべて頭に浮かび、最悪の事態を想像した。私にとっては、この旅に出るよりも戦争に直面する方が簡単だった。
旅は最初から最後まで非現実的だった。ベイルートを離れるのは、長年私を受け入れてくれたこの街の隅々や、残してきたすべての人に対する裏切りのような気がした。イスラエル兵がファランジュのメンバーと和やかに談笑している姿や、「私たちはイスラエルが大好きです」と書かれたTシャツを着た若いレバノン人女性たちの姿、あるいは、生命と人々にあふれた東ベイルートと、戦争で荒廃した西ベイルートの奇妙なコントラストは、今も私の脳裏に残っている。
2001年にレバノンに戻り 2006年のイスラエル戦争、国内での数え切れないほどの紛争、そして最近ではベイルート港での恐ろしい大爆発と、現在経験している前代未聞の経済破綻を経験する中で、私はレバノンの人々が共通の友人を持つことも、共通の敵を持つこともないということを理解するようになった。したがって、イスラエルのような存在は、宗派指導者や宗派の利害がレバノンよりも優先される限り、ある者にとっては友であり、ある者にとっては敵であり続ける。
今日、われわれが体験している宣戦布告されていない戦争が、その証拠である。この国の複雑な宗派モザイクと、腐敗した宗派指導者たち、そしてそれぞれが何よりも私腹を肥やすための外部アジェンダを持つことで、この国はあらゆる種類の紛争や戦争を受け入れる準備が整った肥沃な土壌となっている。悲しいことに、私たちが現在生きているような最も悲惨な時でさえ、レバノン人は自分たちのため、そして自分たちの国のために、腐敗した宗派指導者たちに対抗するために団結することができない。
レバノン人と結婚したパレスチナ人として、私はレバノンで同胞に否定された権利を享受する特権を与えられてきた。私が2001年にレバノンに戻ったのは、勉強と仕事のために何年も外国で暮らした後のことだった。パレスチナは私の行動から消えることはなかった。大学在学中のアメリカとフランスでは、私は私たちの大義を激しく擁護し、その過程で多くの友人と多くの敵を得た。
ヨルダンに戻ると、私はアラビア語の日刊紙「アド・ドゥストゥール」の系列紙である英字週刊紙「ザ・スター」の編集者兼寄稿ライターとして職を得た。ザ・スター紙や、フリーランスとして働いていた国外のメディアに寄稿する文章では、パレスチナに関する問題が常に中心的な位置を占めていた。
外国人記者に同行してパレスチナ難民キャンプを何度も訪れたことで、パレスチナ難民キャンプに詳しくなったのもヨルダンだった。レイラ・カレド、モハメド・ウーデ(アブ・ダウド)、アブデル・ラヒム・マルーなど、それまで名前しか聞いたことのなかったパレスチナの象徴やPLOの人物にジャーナリストとして会うことができたのもヨルダンだった。
しかし、パレスチナ難民であることの意味を本当に理解したのは、レバノンに移ってからだった。レバノンのパレスチナ難民は、他のどのパレスチナ難民とも違う。レバノンの歴代のパレスチナ難民は、この国に避難して以来、何十もの職業に就く権利や所有権など、基本的人権を奪われてきた。私はパレスチナ難民が、アパートや土地、店を買うために貯めた貯金をレバノン人の親戚や友人の名義で登録させられ、詐欺に遭ったという話を何度聞いたか数え切れない。
パレスチナ人キャンプは、貧困、高い失業率、多くの社会的・治安的問題の砦である。今日のレバノンの未曾有の経済危機は、レバノンのすべての人を直撃しているが、特にパレスチナ難民は、すでに極めて過酷な生活環境に苦しみ、自分たちの運命と向き合うしかない状況に置かれている。
大半は、家というより洞窟のような住居に住んでおり、日光は当たらず、換気設備もなく、そこから湿気の不快な臭いが発散され、あらゆる種類の病気が住民に影響を及ぼしている。恒常的な停電と発電機を動かすためのディーゼル燃料がないため、人々は自宅の耐え難い夏の暑さから逃れるために、キャンプの狭い通りで昼夜を過ごしている。米ドルに対するレバノン・リラの深刻な切り下げにより、基本的な生活必需品の価格が高騰したため、難民の購買力は著しく低下しており、ほとんどの人が日々の生活を凌いでいる。さまざまな非政府組織やボランティア団体から、食料、ベビーミルク、おむつ、薬などの人道的援助が手当たり次第に届くほかは、難民は文字通り自力で生活している。今日、彼らは以前と同様、国連難民救済機関(UNRWA)、パレスチナの諸派、PLO、パレスチナ自治政府(PNA)に対して、特にこのような危機的状況において、自分たちを何度も何度も裏切った責任を問うている。
私は、パレスチナ難民が歴代のレバノン政府によって受けてきた不公正、差別、人種差別に対して強い反感を抱いているが、PLOが難民の期待を裏切ってきたこともまた事実である。キャンプに持続可能なプロジェクトを立ち上げなかったことで、難民に何百もの雇用機会を創出することができ、難民の生活を救済に頼り続けることなく自活することができたかもしれない。また、キャンプや集会所の貧弱なインフラを改善しなかったことも、PLOが長年レバノンで享受してきた政治的・財政的権力を考えれば、大きな欠点である。その後、かなり減少したとはいえ、レバノンに難民が集中していることを考えると、PLO幹部は近視眼的であったか、難民問題が彼らの優先事項であったことはない。
レバノンの難民キャンプやパレスチナ難民の生活状況についての私の知識は、レバノンに戻ってからは表面的なもので、数年間勤めた『フューチャーTV』で1~3分のリポートをする程度だった。レバノン全土のキャンプや集会で、年齢もジェンダーもさまざまなパレスチナ難民と何度も長時間のフォーカス・グループを行ったおかげで、私の知識が深まったのは、独立した研究者として働き始めてからだった。
2014年、ある夢が実現した。私の兄弟や忠実な友人たちの助けを借りて、マジェド・アブ・シャラール・メディア財団(MASMF)が結実したのだ。この組織の使命は、一方ではマジェドの遺産を受け継ぎ、メディアの分野で彼のやり残した仕事を継続することであり、他方では、難民キャンプに存在するこの分野のギャップを埋めることである。マジェドは、世界に手を差し伸べ、我々の目的のためにアラブ人および国際的な支持者を獲得するメディアの力を固く信じていた。
MASMFは、難民キャンプにいるパレスチナの若者たちが、主流メディアの固定観念から離れ、プロフェッショナルな方法でさまざまなタイプのメディアを制作できるよう、関与し、力を与え、訓練するために設立された。これは、難民のストーリーを伝えるのに、難民自身ほど有能な人物はいない、彼らほどパレスチナのキャンプや集会が直面している生活状況や問題をよく知っている人物はいないからだ、という私たちの確固たる信念に由来している。パレスチナ難民について無数の誤解や固定観念が存在するレバノンのような国では、このような活動は極めて重要である。
レバノンの人々はパレスチナ人を強く支持しているか、積極的に敵対しているか、あるいは単に無関心である。私が初めてレバノンに戻ったとき、ある著名なレバノン人ジャーナリストと会話した際、彼はパレスチナ人を含む「他者」とレバノン人との関係の問題を、次のように指摘した: 「レバノン人はお互いに嫌い合っているのだから、パレスチナ人や他の誰かを好きになれというのは無理な話だ!」
MASMFは人的・財政的資源が限られた小さな組織ではあったが、国内外の組織や機関と連携して活動することができ、著名なジャーナリストの指導の下、あらゆる形態のメディアに関する研修を無料で提供した。この訓練は、レバノン各地のキャンプや集会で、何百人ものジャーナリスト志望の若者を惹きつけた。
これらの研修の終わりに若者たちが制作した作品は、キャンプでの生活のさまざまな側面を浮き彫りにする問題や、現存する問題、潜在的な解決策、成功例に触れていた。選ばれた作品は、ビルゼット大学メディア開発センターのAl-Hal紙、The Palestine Chronicle紙、MASMFのウェブサイトやFacebookページなど、さまざまなメディアに掲載された。
研修の後、あるいは研修がないときに、学習プロセスを継続するための出口を見つける必要性から、私たちはシャバビークを設立することになった。設立から4年になるシャバビークは、若いジャーナリストたちにメディアの分野で力をつけるための継続的な監督と、彼らの作品を発表する場を提供している。私たちは、時間をかけて、シャバビークを、難民自身による難民の声を反映し、外の世界への窓となる活気あるウェブマガジンに発展させたいと願っている。
しかし、私たちのような非政府組織(NGO)、市民社会組織(CSO)、そしてボランティアグループでさえも、レバノン全土のキャンプや集会の現場で遭遇する大きな課題の前では、私たちの活動は不十分である。パレスチナ人が居住地で直面している甚大な問題は、難民の優先順位を他に置くだけでなく、行われている活動を大海の一滴のようなものにしている!私は、ここ数年間、私たちや他の団体の活動を観察してきた実体験から、このように言っている。
私たちが初めて、パレスチナの有名な2つの団体から2回連続で資金を得てシャバビークを立ち上げたとき、研修生たちの熱意は伝染するようなものだった。Shababeekは、雇用を目的としたものではなく、主にメディア分野における学習の旅を持続させることを目的としたトレーニングウェブサイトとして立ち上げられ、資金が得られた場合にのみ、若いジャーナリストたちの努力に対して象徴的な報酬が与えられる。このような理解のもと、数十人のジャーナリストがシャバビークに参加した。しかし、資金を維持するという課題とともに、若いジャーナリストたちをつなぎとめるという課題も出てきた。「ジャーナリストになるのが夢だった私は、シャバビークのような場所で訓練と執筆を同時にこなし、少しばかりのお金を得ることができた。
パレスチナの大義は、公式レベルで存在するものよりも優れたメディア装置ともっと雄弁なスポークスパーソンに値すると、私は心から信じている。残念なことに、私たちはこの73年間、信頼できる物語を提示し、私たちの大義のために支持者を動員するために、他者に向き合ってきたというよりも、主に自分自身との対話に費やしてきた。非常に洗練されたイスラエルのプロパガンダ・マシンを前にして、健全で統一されたメディアの言説を持つことができなかったことは、私たちの正当な大義に災難以外の何ものをもたらしていない。難民キャンプの若者たちとの活動を通じて、私たちは、難民たちがディアスポラで自分たちの民族と大義の代弁者となるために、メディアの分野で力をつける長いプロセスを開始したいと考えている。
このことは、MASMFや他の人々が行っている活動が無駄であるということを意味しないが、難民が尊厳ある生活を送るための基本的なことが確実に与えられるようにするために、国際的に定められた「帰還の権利」(すべての難民が神聖視する権利)が達成され、難民が祖国に帰還できるようになるまで、私たちの活動は常に二の次であり続けるということを意味する。
国連難民救済事業機関(UNRWA)、パレスチナの諸派、民衆委員会に加え、PLO、パレスチナ自治政府、さまざまな受け入れ国など、パレスチナ難民を担当する人々はそれぞれ、キャンプ内の難民の生活を変革する責任を負うべきである。国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)は、資金不足を口実に縮小した、あるいは完全に削減したサービスを再開すべきである。パレスチナの各派閥と民衆委員会は、派閥の違いを脇に置き、難民の生活改善に向けて協力するとともに、新しい血を送り込むために、自分たちの枠組みの外からやってくるイニシアチブ、特に若者によるイニシアチブを受け入れるべきである。現在準存在のPLOは、パレスチナ人民の代表としての役割を取り戻し、人民のために行動し始めるべきだ。
PLOがその使命を果たせず、創設された目的を果たせない限り、PLOとパレスチナ難民の間には絶大な信頼関係の欠如が存在し続けるだろう。難民が神にしか頼れないと感じ、WhatsAppグループを作って薬を集め、交換し、食料品を集めて困っている人々に配らなければならない限り、私たちは多くのレベルで人々を失い続けるだろう。難民やパレスチナの大義に関連して、パレスチナの指導者やすべての関係者が採用している悲惨な現在の政策が続く限り、私たちは、私たちの人々や大義が私たちから離れていくのを見続けるだろう。
マジェドの夢は、パレスチナの解放後、ドゥラに隣接するフケキセという小さな村で隠居し、ガザの地中海を眺めながら執筆活動にいそしむことだった。マジェドは、自分が生きている間にパレスチナの解放を思い描くほど甘くはなかった。パレスチナが解放されるのは、主としてその民衆の不敗の意志と、その大義の紛れもない正義によるものだと確信していた。私もそう思う。私は、パレスチナは近い将来には達成できないかもしれないが、私たちの最も強力な武器であるパレスチナの人々、彼らの無敵の意志と伝染する熱意があれば、パレスチナは必ず解放されると固く信じている。
バジェス・アブ・アットワン、バーゼル・アル=アラジ、ナジ・エル=アリ、ガッサン・カナファニ、カマル・ナセル、カマル・アドワン、マジェド・アブ・シャラール、その他多くの殉教者たちが、彼らの教えによって私たちを鼓舞し続けることに、私は賭けていたし、今も賭けている。私の賭けは、パレスチナ内外のパレスチナ人の若い世代が、イスラエルの占領者に挑むための自信、ビジョン、革新的なアイデアで私たちを鼓舞し続けることにある。私たち全員がパレスチナの村や町に戻るまで、帰還の権利の炎を燃やし続けるために、私はすべてのパレスチナ難民に賭けているし、これからもそうするだろう。パレスチナの大義は、決して奪われた土地だけの問題ではなく、植民地支配者の残酷な仕打ちにもかかわらず、自由なパレスチナと自分たちのものへの帰還という夢を抱き続ける、頑固で揺るぎない人々の問題でもある。
10 PLO指導者の多くは、安全保障上の理由から、家族をPLOの拠点から遠ざけることを選び、その結果、多くの指導者がシリア、ヨルダン、クウェート、エジプトなどの国に住んでいた。
11 ヨルダンのアンマンや他の場所では、ヨルダン軍とパレスチナ人フェダイーンとの間で衝突が起きており、これは後に 「黒い9月」として知られるようになった。
12 イナム・アブデル・ハディはPLO指導者ハニ・エル・ハッサンと結婚し、娘のアッザをもうけた。
13 ハムラは西ベイルートの他の地域と比べれば安全な避難所であり、外国人ジャーナリストや外交官がいたおかげでイスラエルの砲撃から免れた。
14 イスラエルの侵攻中、東ベイルートを通って出国した人々の多くは偽造パスポートを所持しており、私たちも例外ではなかった。本物のパスポートに父親の名前を書いて出国するのは危険だったからだ。
ANUAR MAJLUF ISSAはパレスチナ出身のチリ人弁護士である。アドルフォ・イバニェス大学で法律を学び、政治学も副専攻した。パレスチナ国際研究所(PII)の奨学金を得てヨルダン大学でアラビア語を学び(2010)、チリ大学哲学・人文科学部アラブ研究センターで「アラブ・イスラム文化」(2012)、法学部で「民事責任問題の現状」(2020)の学位を取得した。2008年から2009年にかけては、パレスチナ学生連合(UGEP-Chile)の会長を務め、多くの大学でパレスチナの状況に対する認識を高めた。
2021年6月までチリ・パレスチナ共同体の事務局長を務める。この職務では、チリやラテンアメリカで活動し、チリ当局とのアドボカシー活動を計画した。パレスチナの権利のための闘いにおいて、彼がより深く関わり、認知されるようになったため、イスラエル政府は2017年、彼のパレスチナへの入国を禁止した。
記憶なくして未来なし
デポルティーボ・パレスティーノとチリにおけるパレスチナ人の物語15
アヌアル・マジルフ・イッサ
チリへの最初のパレスチナ人移民は、パレスチナがまだトルコ・オスマン帝国の支配下にあった前世紀初頭に到着した。現在、パレスチナ系のチリ人は50万人と推定されている。
オスマン帝国が崩壊すると、ヨーロッパ列強が支配権を握り、1920年、パレスチナはいわゆる。「英国委任統治領」となった。ほぼ即座に、イギリスは主にヨーロッパから新しく征服されたパレスチナの祖国へのユダヤ人の移住を促進し始め、パレスチナの先住民の間に多くの苦難をもたらした。その結果、パレスチナからチリを含む多くの場所へと新たな移民の波が押し寄せた。
予想通り、パレスチナにおけるイギリスとシオニストの植民地主義は、共同体の抗争を引き起こし、最終的には暴力へと発展した。英国は国連に目を向けたが、国連にはパレスチナの運命を決定する力も権限もなく、特にパレスチナの人々自身は、自分たちの将来に関わる決定についてほとんど考慮も相談もされていなかった。最終的に国連総会は1947年、パレスチナをユダヤ人とアラブ人の2つに分割することを決議した。こうして1948年5月15日にイスラエルが誕生し、パレスチナ人の70%が追放された。パレスチナ系アラブ人の国家は設立されなかった。
パレスチナ人が大量に追放され、何百ものパレスチナの町や村が完全に破壊されたことで、長期にわたる流浪(シャタート)の舞台となった。何十万人ものパレスチナ難民が近隣諸国に避難した。また、大陸を渡り、ヨーロッパ、アメリカ、ラテンアメリカに定住した人々もいる。チリのパレスチナ人コミュニティは、このパレスチナのディアスポラの一部であり、その一部である。
ここでの我々のコミュニティは、経済、スポーツ、政治などあらゆるレベルでチリ社会に完全に溶け込んでいる。しかし、このような共同体の勝利は、数え切れないほどの苦難と闘争の結果であり、それは後世の人々のために記録されるべきものである。
あらゆる移住のプロセスは、それぞれの歴史的文脈に根ざしたものであり、それゆえに意図しない結果をもたらす。このことを念頭に置くと、チリのパレスチナ人は、統合とアイデンティティ維持のサクセスストーリーを象徴している。私の家族は、この感動的な集団体験の中心に立っている。
もし私が他のグループの一員であったなら、ここでの私の貢献はそれほど重要なものではなかったかもしれない。しかし、すべてのパレスチナ人がそうであるように、私たちは民族と文化としての存在を執拗に確認し、再確認することを余儀なくされている。シオニストによるパレスチナ植民地主義を正当化するために作られたマントラ、すなわちパレスチナは「土地なき民のための民なき土地であった」という言葉は、パレスチナ人としての私たち自身の存在を抹消し、正当な権利を奪うために意図的に作られたものである。このことから、パレスチナ人作家のラシャド・アブ・シャウィールは、「パレスチナ問題は単に国境の問題ではなく、(中略)存在の問題である」と結論づけた。
存在とは受動的な行為ではなく、能動的な記憶によって煽られなければならない。「ナクバ72周年に際して、ラムジー・バルードはこう書いている16。「パレスチナ人が、どこにいようと、本当にコントロールできる唯一の要素がある。「イスラエルがパレスチナの人々の集団的記憶を消そうとすればするほど、パレスチナの人々は故郷の鍵や失われた故郷の土地の権利証をより強く握りしめるようになる」17。
私の家族の歴史を、集団的なパレスチナ人の経験の一つの縮図として用いて、私は集団的な物語を語ろうと試みる。
私の物語
2007年、私は法科大学院の2年生で、パレスチナへのコミットメントで知られるようになった。何年もの間、私はパレスチナに関する講演や討論会の開催に携わってきた。私たちが主催するイベントには多くのパレスチナ人学生が集まり、講堂はいつも満員だった。シオニストの学生たちも私たちの集まりに関心を持っていた。彼らの存在と、私たちのイベントの前後に行われた学生たちの討論によって、雰囲気はいつも熱く緊張していた。
私が活動家になった正確な瞬間は思い出せない。しかし、ダブケダンスやアラブ音楽など、私が卒業したアラブ学院での活動はすべて完璧に覚えている。このような文化的交流のおかげで、私は自分のパレスチナ人としてのアイデンティティにさらに愛着を持つようになった。確かに家ではアラビア語を話さなかったが、家族団らん、食事、音楽など、生活のあらゆる面にパレスチナ精神が息づいていた。
毎年、世界中の学者がチリのパレスチナ人コミュニティについて学びに来た。パレスチナから遠く離れた地で、これほど大規模で、よく統合され、活発なパレスチナ人コミュニティが存在することを理解するのは難しいからだ。よく繰り返される質問は、「あなたはチリ人とパレスチナ人のどちらをより強く感じるか」というもので、あたかも2つのアイデンティティが必ずしも対立するものであるかのようだ。私の答えは変わらない。「私はチリ人でもあり、パレスチナ人でもある」
しかし、いつもそう簡単で単純なわけではない。特に相手がパレスチナ人であれば、私は本当にパレスチナ人なのだろうか?私はパレスチナ出身のチリ人なのか、それともチリ生まれのパレスチナ人なのか。簡単な答えはない。しかし、私が知っているのはこれだけだ: 私は確かにパレスチナ出身のチリ人だ。しかし、パレスチナの文脈にいるとき、私は本当にチリ生まれのパレスチナ人だと感じる。
一見矛盾しているように見える背景には、パレスチナの亡命がいまだ傷口を広げているという事実があるのかもしれない。私たちのシャタットはまだ解決されていない。私が亡命について語るとき、1948年のナクバだけでなく、ナクバに先立つ悲惨な旅についても語っている。
マジュルフ一家は1906年にチリに到着した。私は父方のパレスチナ移民のひ孫であり、母方のパレスチナ移民の孫である。祖父のガブリエルによれば、彼らは 「より良い未来を求め、トルコの支配から逃れるために」パレスチナからの移住を決めたという。
祖父は一家がパレスチナを出発した日のことを覚えている。おそらくハイファかヤッファの港からだろう。最初の寄港地は南フランスのマルセイユで、そこからブエノスアイレスに向かった。アルゼンチンの首都から列車でメンドーサに行き、アンデス山脈を越えてサンティアゴに向かった。この長い旅は3カ月で達成された。山脈の横断は特に過酷で、丸1週間、ラバの背中に乗って移動し続けなければならなかった。
家族が耐えなければならなかった苦難を想像するのは容易ではない。写真も残っておらず、その悲惨な歴史を物語だけが私たちの記憶を形作っている。その話の主な情報源は、父方の祖父からだった。ガブリエルは10人兄弟の末っ子だった。彼はわずか18歳で父を亡くした。
祖父によると、彼の貧しい家族は、長旅の基本的な出費をまかなうだけのお金しか持っていなかったという。船旅の場合、三等席の切符しか買えなかった。彼らは安全と保護のため、他の家族と一緒に旅をした。一族に残る古い文書によると、旅人のほとんどは男性で、妻や子供を置き去りにした。
ネズミだらけの船室から、アンデス山脈の激しく、しばしば命にかかわる嵐まで、その旅のあらゆる側面が、計り知れない苦難を物語っていた。そのすべてが、文化も言語も生活様式もまったく異なる国にたどり着くためだった。
私の曽祖父、ニコラス=ガブリエルの父は、パレスチナを去らざるを得なかった理由をあまり語らなかった。一般的な理解では、オスマン帝国が課した重税や、パレスチナ人に対する徴兵への強い圧力が、若いパレスチナ人男性に移住を強いる動機の一部だった。これらの若者の多くが、ニコラス自身の言葉を借りれば「着の身着のまま」出国したことを考えれば、チリにおけるパレスチナ人の成功はさらに注目に値する。
私の家族の両系は、1967年の戦争後、イスラエルの占領下に置かれたベイトジャラ市の出身である。最初の移住の波では、成人男性だけが出て行った。彼らの目的は、いずれパレスチナに戻ってより良い生活を始めるために十分なお金を稼ぐことだった。しかし、チリで4年を過ごした後、ニコラスと彼の弟のムサラムは、パレスチナの状況が悪化の一途をたどっていたため、パレスチナの家族をチリに呼び寄せることに同意した。
ベイトジャラはベツレヘムの東に位置する小さな村で、エルサレムのアルクッズから15キロほど離れている。ベイトジャラの住民のほとんどはキリスト教徒、すなわち正教徒である。この美しい村は、オリーブやブドウ、そして聖ニコラス教会で知られている。私の曽祖父はおそらく聖ニコラウスにちなんで名づけられたのだろう。何千人もの村人たちも、みな聖ニコラウスの奇跡を熱烈に信じていた。
内婚は当時のアラブ世界ではごく一般的なことで、そのような慣習が家族や一族の結束を維持し、既存のヒエラルキーに対する一定の敬意を保証していたからだ。当時のベイトジャラは、4つの主な地区と25の氏族、つまり、「ハマイエル」で構成されていた。私の家族はナワウィエのハムレに属していた。
サンティアゴでの経済状況が悪化したとき、ニコラスはチリ南部のアラウカニア地方にあるビクトリア市に定住することを決めた。
私の曽祖父ニコラスは、彼の最初のいとこセリムの娘ルズベットと結婚し、祖父ガブリエルの兄弟はみなベイトジャラからの移民と結婚した。
母方のオデ・マジュルフは妻のサラ・カシスとともにチリに到着した。彼らは、当時かなりのパレスチナ人コミュニティがあったロス・アンデスに定住した。2015年に亡くなるまで我が家に住んでいた私の母方の祖母、マリアを含む5人の子供がいた。彼女は強い個性を持った女性で、パレスチナ・アラブの伝統にとても根ざしていたが、同時にとても心優しく愛情深い女性でもあった。彼女は、料理のレシピや多くのアラビア語など、パレスチナの伝統を私たち家族に伝えてくれた人だった。
残念なことに、次の世代はアラビア語を受け継がなかった。現在、パレスチナ人コミュニティでアラビア語を話す人はほとんどいないが、どの家族もパレスチナの伝統の要素、特に食べ物を守っている。世界の他の地域からパレスチナ人がチリにやってくると、彼らは私たちのパレスチナ料理に感動する。まるで時間が止まっているかのようだ、と彼らはよく言う。実際、20世紀初頭からのパレスチナ人のアイデンティティのある要素は、まるで時が止まったかのように、世代から世代へと受け継がれていった18。
チリでの生活
1911年、私の曽祖父ニコラスは織機を買い、小さな商売を始めた。妻のロサは、当時の伝統に従って子供たちの面倒を見た。
ニコラスの羊毛はドイツから仕入れ、しばらくの間、商売は順調だった。しかし、第一次世界大戦が始まると、ドイツからの原料調達は不可能になった。悲しいことに、1917年、ニコラスの有望な事業は閉鎖された。曽祖父は家族全員とともに南部のビクトリアに移り住んだ。そこで彼は店を開き、「エル・マルティージョ」と名づけた。基本的には食料品店であったが、倉庫でもあり、最終的には小包屋でもあった。祖父ガブリエルは1926年にビクトリアで生まれた。
約10年後、一家はサンティアゴに戻り、チリのパレスチナ人の大半が定住していたレコレタ市のバリオ・パトロナートの中心に位置するロレート通りで古い工場を再開することにした。バリオ・パトロナートは、パレスチナの町ベツレヘム、ベイトジャラ、ベイトサフルからの移民が多く住んでいたため、パレスチナ人コミュニティの「小さなベツレヘム」となった。
パレスチナ人コミュニティがそこに集中していたことから、初期の移民たちは、家父長制と拡大家族を前提とした強力な社会的ネットワークという、パレスチナ独自の社会システムを模倣することに成功した。このシステムは、パレスチナ人コミュニティの存続に不可欠なものであり、特に当時チリでは一般的だった差別の被害者であったことが証明された。パレスチナ人は 「トルコ人」と呼ばれていた。アラビア語を話すことは、ドイツ語を除く他の言語とともに、スペイン語圏のチリでは嫌われた19。
チリのパレスチナ人は、レコレータの町にある最初の正教会「サン・ホルヘ教会」を皮切りに、様々なコミュニティ組織や施設を設立し、その存在感を急速に高めていった20。
ラス・コンデスにあるクラブ・パレスティーノ、チリのほぼすべての都市に点在するアラブ・クラブ、そして今日に至るまでチリのパレスチナ人コミュニティの誇りであり喜びであるクラブ・デポルティーボ・パレスティーノなどである。パレスチナの色とシンボルをあしらったジャージを着ているこのサッカークラブは、現在チリのプリメーラ・ディビシオンでプレーしている。
パトロナート(バトロナート)21は、住宅街であると同時に、コミュニティーの集会所でもあった。何年もかけて、パトロナートは徐々に商業地区となり、パレスチナ人が経営する大規模な工場(主に繊維産業専門)が設立された。
同時に、チリの他の地域では、パレスチナ人移民が巡回セールスマンとなり、やがて街の中心部に定住して自分の店を開くようになった。
デポルティーボ・パレスティーノ
それから100年以上経った今も、チリのパレスチナ人は独自のアイデンティティを維持している。確かに私たちはアラビア語を話さないが、私たちの食生活のほとんどはアラビア料理に依存しており、結婚の半分近くはパレスチナ人同士のものである。これらの施設の多くは、文化的同化の結果、アイデンティティの一部を徐々に失ってきたが、特にパレスチナの同胞との関係が絶えず強化される中で、アイデンティティを取り戻そうとする若者たちによって活性化されつつあるものもある。
チリにおけるパレスチナのアイデンティティを示す最も大きなもののひとつは、1920年に設立されたクラブ・デポルティーボ・パレスティーノである。毎週末、何千人ものサッカーファンが、サンティアゴの人気地区にあるパレスティーノのスタジアム、エスタディオ・ムニシパル・ラ・システルナに集まる。このクラブはパレスチナ人だけの人気ではなく、多くの人々、特にチリ社会の貧困層に属する人々も熱狂的なファンである。その理由は、クラブが子どもたちや青少年への支援を含め、地域社会全体への支援に多くのエネルギーと資源を捧げ、薬物乱用やその他の破壊的習慣の危険因子を減らしているからである。
実際、クラブのチリ人ファンの多くは、パレスチナやアラブに起源を持つわけではない。彼らは単に、クラブの社会的活動のため、またパレスチナの人々への連帯を表現する手段として、クラブを支持しているのだ。
実際、デポルティーボ・パレスティーノは単なるサッカークラブではない。国境を越える能力をすでに証明している。サポーターはもちろん、占領下のパレスチナやディアスポラのファンにも喜びを与えている。その勝利はサンティアゴからエルサレムまで祝福される。その功績は、不正義に対する叫びであり、抑圧された人々が幸福の瞬間を主張する機会でもある。
しばしば、デポルティーボ・パレスティーノは第二のパレスチナ代表チームとみなされる。クラブはパレスチナ人であることを隠していない。それどころか、誇りを持ってそれを示している。100年経った今、このサッカークラブがチリのパレスチナ人コミュニティを団結させ、パレスチナ人というアイデンティティを見失うことなく、より大きなチリ社会にパレスチナ人を溶け込ませるための主要なプラットフォームとなったことは、自信を持って言うことができる。
いわゆる。「トルコ人」たちは、スポーツを媒介として、最終的に自分たちの歴史を書くことに成功した。確かに、デポルティーボ・パレスティーノのサクセスストーリーはスポーツに関するものだけではない。しかし、このチームが1952年、1972年のセグンダ・ディビシオン(2部リーグ)に加え、1955年と1978年にチリのプリメーラ・ディビシオン(1部リーグ)のタイトルを獲得し、さらに1975年、1977年、2018年には「コパ・チリ」も獲得しているという事実から目をそらしてはならない。私たちの世代は、その偉大な功績を目の当たりにしたことがなかったからだ。
クラブとパレスチナの強い結びつきは、100年前に創設者たちが思い描いたクラブ設立の大きな理由のひとつだった。創設者たちは、パレスチナの名前、シンボル、チャント、そして使命を、チリにパレスチナのアイデンティティを存続させることに求めた。1948年にパレスチナの祖国が壊滅的に破壊された「ナクバ」が、チリのパレスチナ人コミュニティの指導者たちがクラブをプロのサッカーチームにすることを決意した理由であり、それは今日まで続いている。
クラブの歴史を通しての功績は、ゴールやトロフィーによって測られるものではなく、パレスチナ代表チームとデポルティーボ・パレスティーノとの間で行われた数々の試合を通じて、チリのパレスチナ人と自国のパレスチナ人との交流によって測られたものでもある。これらの試合はパレスチナとチリの両方で行われ、それぞれの試合は文化の大規模な祭典とアイデンティティの再確認とともに行われた。
クラブの最も記憶に残るマイルストーンのひとつは、チームのジャージの背番号1を歴史的パレスチナの地図に置き換えるという決定だった。この決定は、チリのシオニストたちの厳しい反応を引き起こし、彼らはAsociación Nacional de Fútbol Profesional(ANFP)に公式に苦情を申し立てた。シオニストたちは、クラブがジャージから地図を取り除くことを望んだ。しかし、彼らのキャンペーンは裏目に出た。この話題はメディアで大きく取り上げられ、他のチリチームのファンからも連帯の波が巻き起こり、その結果、チリ国内外でのシャツの売り上げが大きく伸びたのだ。
クラブ・デポルティーボ・パレスティーノが1920年に設立されたのは、歴史的なパレスチナの廃墟にイスラエル国家が誕生する28年前のことである。シオニストが植民地支配を確立するためにパレスチナに到着したとき、彼らはパレスチナを 「土地なき民のための土地なき民」と主張した。もちろん、その主張はまったくのでっち上げであり、20世紀の変わり目にはチリに繁栄するパレスチナ人コミュニティが存在し、独自の施設や礼拝所、サッカークラブまであった。
だからこそ、デポルティーボ・パレスティーノは普通のサッカーチームではないのだ。デポルティーボ・パレスティーノは、歴史の証人であり、パレスチナ文化の耐久性の証人であり、パレスチナ人全体の証人なのだ。デポルティーボ・パレスティーノは、ライバルチームの間でも多くの連帯を生み出してきた大義を象徴している。デポルティーボ・パレスティーノは、世界のどこにいても、パレスチナが私たちの中に生きているという具体的な証拠なのだ。また、スポーツがいかに抵抗のプラットフォームとなり、連帯を生み出すことができるかを示すモデルでもある。自国のパレスチナ人は、パレスチナの旗を掲げることを罰せられないまでも、しばしば阻止されるが、チリでは毎週日曜日、試合中に旗を掲げる。チームがゴールを決めるたびに歓声を上げ、パレスチナの名を叫び、自分たちが何者で、どこから来たのかを常に思い出す。
クラブはパレスチナのサッカーリーグを支援する役割を果たし、何人かのパレスチナ系チリ人の才能を母国に「輸出」してきた。ジョナサン・カンティリャーナ、ヤシール・ピント、マティアス・ハドゥエなど、パレスチナ出身のチリ人選手の何人かは現在、パレスチナ代表チームでプレーしている。政治的な団結が得られないときがあっても、スポーツはいつでも私たちを団結させることができる。
デポルティーボ・パレスティーノの選手たちは、母国で起きている出来事を常に意識している。勝つためだけでなく、メッセージを送り、パレスチナに喜びと誇りをもたらすために、彼らは毎試合ベストを尽くしている。
私たちの使命
中東以外で最大のパレスチナ人コミュニティであり、南米で最大であることは間違いない。チリにおける私たちの活動は、2つの大きな柱に焦点を当てている。1つは、私たちの新しい世代にパレスチナのアイデンティティを生かし続けること、もう1つは、パレスチナの大義のためのアドボカシーを継続することだ。
アイデンティティに関しては、若いパレスチナ人に祖国の歴史や民族の伝統について教える「私はパレスチナ人」プログラムなど、いくつかのプロジェクトを立ち上げた。この目的を達成するために、私たちは常にパレスチナへの教育旅行プログラムを企画し、子供たちにパレスチナの伝統舞踊ダブケを教え、パレスチナを題材にした映画を上映するなど、さまざまな活動を行っている。
アドボカシー活動としては、一般のチリ人にパレスチナの大義について教えることに尽力している。第一に、行政当局や立法当局への働きかけ、第二に、市民団体や小学校から大学までの教育機関へのパレスチナ人の権利擁護の働きかけ、そして最後に、パレスチナ人コミュニティ自身のエネルギーを活用することである。最終的には、情報を発信し、教育し、意識を高めるだけでなく、支援者を動員し、具体的かつ具体的な行動を実行に移させるのである。
チリの 「Congreso」(議会に相当)は、パレスチナの大義に特に同情的である。当然のことながら、下院で私たちの大義を最も支持しているのは、90人以上のメンバーからなる「チリ・パレスチナ列国議会同盟」である。興味深いことに、この影響力のあるグループは左翼と右翼のメンバーで構成されており、時にはパレスチナへの支持だけで結束しているように見える。
政府へのロビー活動は、単なる政治的な決まり文句ではなく、具体的な成果をもたらすことが多い。2020年7月、チリ上院は決議案を承認し、セバスティアン・ピニェラ大統領に対し、パレスチナ占領地の違法なユダヤ人入植地で生産されたイスラエル製品の輸入を禁止する法律案を提出するよう求めた。
その後、2021年6月2日、チリ下院は同じ目的の法案を提出した。この法案は議会でイスラエルの激しいロビー活動の圧力にさらされたが、すでに立法・司法・憲法委員会で審議されている。この法案に拘束力はないが、それでもイスラエルの犯罪に対する責任を追及するための重要な第一歩である。実際、イスラエルの占領には犠牲が伴う。
このような行動は、私たちが連帯から測定可能な行動へと移行する時が来たという信念に突き動かされている。パレスチナの状況は悲惨であり、善意の表明だけでは違法なイスラエル占領を終わらせることはできない。
チリにおけるパレスチナ人コミュニティの役割は、クラブ・デポルティーボ・パレスティーノを取り巻く数多くの活動をはるかに超えるものであると言わなければならない。実際、このサッカークラブは、チリで長年にわたって作られてきた数多くのパレスチナ人の社会的、文化的、慈善的、政治的機関のひとつに過ぎない。私たちの目的は、パレスチナの祖国との強い絆を維持することで、チリ社会におけるパレスチナ人の自然な文化的同化のバランスを常に試みることである。イスラエルがパレスチナの歴史、文化、アイデンティティを執拗に抹殺しようとしている今、この特別な目的はこれまで以上に緊急性を帯びている。ここチリの私たちにとって、この使命は無作為に遂行されるものではなく、集中的で戦略的な計画の一部である。
この戦略のひとつの柱は、私たちのコミュニティの指導者たちと南米の他のパレスチナ人コミュニティとの絶え間ない対話である。数年前、私たちは 「Taqalid」(伝統を意味する)と題した地域会議を開催した。この会議はサンティアゴのクラブ・パレスティーノが主催したもので、ラテンアメリカのパレスチナ人コミュニティがパレスチナ文化とアイデンティティの価値観を軸に団結することを目的としていた。2017年の会議には、ラテンアメリカ各地から5,000人以上が参加した。2019年にはペルーのリマで会議が開催され、同数のパレスチナ人が参加した。これらは、このような行動がいかにコミュニティを動員し、活性化させることができるかを示す完璧な例であり、コミュニティは共に出会い、対話し、組織化することでより強くなる。ディアスポラのパレスチナ人コミュニティは、「言葉を広める」以上のことができる。政府の政治的プロセスや意思決定に影響を与えるための戦略を練ることができるのだ。
チリのパレスチナ人コミュニティの成果は、努力と献身によって獲得されたものだ。チリ・パレスチナ人コミュニティで活動するメンバーとして、またオーガナイザーとして、私たちの成功のポイントをまとめると、次のようになる:
– パレスチナの歴史的記憶を定着させる: パレスチナの祖国を守るためには、情熱や熱意だけでなく、知識、訓練、歴史に対する深い理解が必要である。
– 真実を伝える: パレスチナの真実を教えることは、行き当たりばったりのプロセスではない。強力な基盤、あるいは適切なツール、つまり刺激的な講演、文書、ビデオ、証言などが必要である。
– 政治力を追求する: 知識を得たり真実を教えたりすることは、最終的には実際の政治的影響力に変換されなければならない。
– 他者に力を与える: 自らの動員の直接的な結果としてコミュニティ全体が得た力は、自らの指導者、代表者、代弁者を生み出すことに結びつかなければならない。私たちの大義が普遍的なものとして提示されることが重要である。したがって、正義、平等、自由、人権という価値観で結ばれた、あらゆる背景を持つすべての人々に手を差し伸べなければならない。
– ネットワークを作る: 共同体のエネルギーや政治的成果は、信頼できるネットワークの欠如によって弱体化することが多い。様々な政党、宗教、イデオロギーの間で、ディアスポラのパレスチナ人が分断されていることは、ここチリで私たちが避けるために最善を尽くしている大きな落とし穴である。前進するために、私たちはすべての行動を調和させ、望ましい結果を達成するために、あらゆるレベルでネットワークを構築しなければならない。
– 前もって計画を立てる: 一般的に、パレスチナ人は前もって計画を立てるよりも、反応する傾向がある。ガザに対する度重なる侵略や戦争、違法なユダヤ人入植地の拡大など、イスラエルの具体的な行動には反応する。しかし、多くの場合、積極的な戦略に基づいて組織化されることはない。パレスチナ人は、イスラエルの挑発や攻撃を動員や活動のきっかけにしてはならない。私たちは、明確で恒久的な戦略とアジェンダに導かれ、積極的であり続けなければならない。イスラエルの占領が永続的である限り、パレスチナ人の行動は永続的でなければならない。
– 奮起し続ける: 苛立ちとやる気の喪失は選択肢ではない。パレスチナの大義に真にコミットしている人々が、指導者の無力さ、地上での進展のなさ、政治的地平の不在などの結果、時としてフラストレーションを募らせることは理解できる。しかし、士気を下げることを許してはならない。それこそがイスラエルの狙いだからだ。戦意喪失は無気力につながり、無気力は不作為につながる。どんな状況下でも、私たちは強く、積極的であり続けなければならない。
パレスチナの人々が、残忍な民族浄化作戦によって祖国から追放されてから70年以上が経過した。連日のイスラエルによる侵略と占領は、ナクバが本当に終わったわけではないことを常に思い起こさせる。
ここチリの人々は、自分たちに提供されたもてなしと機会に感謝しながらも、パレスチナの痛ましい現実を十分に認識しており、最終的に自由が達成されるまで、パレスチナの大義とパレスチナの人々を擁護することに全力を尽くしている。
何千キロも離れているとはいえ、ここチリでは、エルサレムにいようと、ナザレにいようと、ガザにいようと、ベイトジャラにいようと、レバノンにいようと、シリアにいようと、ヨルダンにいようと、サンティアゴにいようと、パレスチナ人はひとつだと信じている。パレスチナ国外を拠点とする私たちは、世界のどこにいても、パレスチナの大義のための大使としての役割を果たすという、複合的な責任を託されている。自国のパレスチナ人と同様、私たちもまた、同胞の団結の重要性を信じている。
私たちは、私たちのようなディアスポラのパレスチナ人コミュニティーに直接的な政治的プラットフォームを提供するパレスチナ解放機構(PLO)の中心的な役割が再び活性化することを切望している。そうすれば、私たちはパレスチナ人の言説を形成する役割を果たし、イスラエルによる占領を終わらせ、パレスチナ難民の帰還の権利を確保し、占領地であろうと1948年のパレスチナであろうと、パレスチナ人に完全な平等な市民権を達成することを目的とする、より大きな戦略的計画の一部となることができるだろう。
15 このエッセイはスペイン語で書かれたものをロマーナ・ルベオが翻訳した
16 Ramzy Baroud, ”Why Israel fears the Nakba: How memory became Palestine’s greatest weapon,” The Jordan Times, October 17, 2021.
17 Ramzy Baroud, Ibid.
18 チリに移住した初期のパレスチナ人はほとんどが農民で、アラビア語独特のアクセントが特徴だった。「k」を表すアラビア文字を 「ch」という音で間違って発音するなど、独特の発音があった。そのため、彼らの子孫は現在、「kif」(「how」の意)ではなく 「Chif」と言い、「knafeh」ではなく 「Chnafeh」と言う。
19 そもそも多くのパレスチナ人が祖国を離れた主な理由の一つは、オスマン帝国の軍隊に徴兵しようとしたトルコ人のためであったから、「トルコ人」というあだ名は悩みの種であった。しかし、初期のパレスチナ人移民はオスマン帝国自身が発行したパスポートを持っていたため、彼らは 「トルコ人」であると誤って認識されていた。
20 ローマ帝国の兵士でパレスチナ人の母を持つ聖ジョージは、聖地でのキリスト教徒迫害に激しく反対したことで、パレスチナのキリスト教徒から崇められている。
21 アラビア語には「P」という音に対応する文字がないため、アラブ系移民が定住した地域の名前を間違って発音した。
パレスチナ人医師、学者、作家。エクセター大学アラブ・イスラム研究所の元研究員で、パレスチナ・イスラエル紛争について講義を行った。彼女の主な仕事はこの分野であり、それに関する著書も多い。著書に、高い評価を得た回顧録『In Search of Fatima, a Palestinian story』(Verso Press 2002)、一国家解決策を扱った『Married to Another Man: Israel’s Dilemma in Palestine』(Pluto Press 2007)、2作目の回顧録『Return』(Verso、2015)などがある。
平等な権利キャンペーン
シオニズム終焉への鍵
ガーダ・カルミ
2020年初頭、コロナウイルスの大流行でロンドンが封鎖されたとき、私は他の多くの人々と同様、自宅で学べるオンラインコースに登録した。テーマは「精神分析の概念」で、以前から興味があったものだった。講師はユダヤ系の南アフリカ人で、偶然かどうか、同じコースの受講生の多くもユダヤ系だった。
記憶についてのセッションで、講師はクラスで分析するために、自分の重要な記憶を発表するボランティアを募った。たまたま私は、1948年にエルサレムから強制退去させられた私の家族とその後の亡命生活を綴った手記『ファティマを探して』を彼女に渡していた。そのためか、彼女は個人的な思い出を授業に投稿するよう私に頼んだ。私は1948年4月、私たちが最後にエルサレムを離れた瞬間を選ぶことにした。私は子供で、庭の門にしがみつき、残さなければならない家族の愛犬をなだめようとして、外に出してもらおうと必死によじ登ったことを覚えている。同じような境遇の子どもなら誰でもよかったし、痛烈で感動的なものになると思ったからだ。
講師は私の選択に同意したが、授業当日、明らかに動揺した様子で私に電話をかけてきた。彼女のコースは学問であって政治的なものではないと彼女は主張した。当時は2021年5月で、イスラエルと占領地では劇的なパレスチナの反乱が起こっており、彼女はユダヤ人の聴衆の間ですでに情熱が燃え上がっていることを恐れていた。彼女がクラスをコントロールしており、手に負えなくなった議論を止めることができることを私が指摘しようとしても、彼女をなだめることはできなかった。彼女の不安は、私の記憶がイスラエル建国の出来事に関連しているために、ユダヤ人メンバーが動揺することだった。同じくコースに参加していたユダヤ人の友人は、私の痛みや喪失感を描写することはユダヤ人に責任を負わせることになると後から私に説明してくれた。そうなると、イスラエルは誕生すべきではなかったということになりかねない。ホロコーストの犠牲者から唯一の避難場所を奪うことになる。
どうやら講師は、私がこのセッションで話すことに同意したとき、その決定の意味を理解していなかったようだ。私の話がユダヤ人の聴衆に与えるかもしれない動揺が、故郷と国を失う私自身の動揺を上回ったようだった。彼女は自分の考えを変えようとはせず、私は寄稿を取り下げるしかないと思った。パレスチナ人の気持ちよりもユダヤ人の気持ちの方が大事なのだろうか?
この小さな逸話に、シオニズムに対するパレスチナ人の苦境の本質が凝縮されている。シオニズムが、犠牲者の苦しみよりもユダヤ人の苦しみを優先させることをいかに主張しているか、ユダヤ人は苦しみを受けたからこそ、他の民族の祖国に定住する権利があるといかに思い込んでいるか、ホロコーストにおけるユダヤ人の苦しみを、その民族には何の責任もないパレスチナと結びつけるという筋の通らないことをいかに推進しているか。このような傲慢で自己中心的な考え方は、反ユダヤ主義的なヨーロッパに対する復讐という文脈では意味をなすかもしれないが、集団としてユダヤ人に危害を加えたことのない無実の人々に対して行使される場合には、意味をなさない。この欠陥だらけの論理を覆い隠すためには、最初からパレスチナ人の言い分を封印する必要があった。
基本的に、これが私のイギリス亡命生活の物語である。私は、ユダヤ人にはパレスチナを手に入れる権利があるという周囲の人々の思い込みによって息苦しく育った。この考え方は1950年代の英国で定着し、その後パレスチナの苦しみが認識されるようになったにもかかわらず、変わることはなかった。イスラエルを実現するためにパレスチナ人全体が祖国から追い出されたことは、当時はほとんど知られておらず、誰も気にも留めていなかった。1948年、ユダヤ人によるエルサレム占領の暴力と混乱の中、私たちはエルサレムから脱出した。しかし、1950年代と60年代の大部分において、パレスチナの歴史はイスラエルのストーリーの一部とはならず、代替的な物語が語られることもなかった。私たちの沈黙は、イスラエルの信頼性を高める条件だった。
パレスチナの現代史に対する私の理解は、この経験によって形成された。国家共同体の一員としてのイスラエルの正当性は、欧米の意識にしっかりと植え付けられ、真実を知る人々からでさえ、それを取り除くことは不可能だった。私たちは、祖国に対する不滅の権利という信念に固執し、いつか祖国は自由になり、私たちのもとに戻ってくると信じていた。祖国を乗っ取った外国人入植者たちは、泥棒や無法者のように見なされ、一刻も早く彼らがどこから来たのか立ち退かなければならなかった。私たちの怒りの矛先は、パレスチナを彼らに与えた裏切り者の植民地支配国であるイギリスに向けられた。しかし、このような見方は、変化する現実には持ちこたえることができなかった。かつての無法者たちは、西側諸国から賞賛され、大切にされる国家へと変貌を遂げた。1960年代後半、イスラエルは3つのアラブ諸国に勝利した英雄として称えられた。このアラブの敗北をもたらした1967年のアラブ・イスラエル戦争は、パレスチナの他の地域も失うことになった。イスラエルは植民地支配を東エルサレム、ヨルダン川西岸、ガザにまで拡大し、これらの地域にユダヤ人入植者のコロニーを建設することによって、その支配力を急速に強化した。
このような環境の中で、パレスチナ解放機構(PLO)が設立され、本領を発揮するようになった。祖国を解放するために1964年に創設されたPLOは、その名称が明らかにしているように、私たちに多大な影響を与えた。PLOはイスラエルとの闘いの言葉を変え、反植民地解放の闘いの一つとし、他の民族解放闘争の一部とした。PLOは、キューバ、ニカラグア、ナミビア、南アフリカなどのあらゆる進歩的で革命的な運動を支援するようになった。この側面は、民族闘争に対する私たちの理解に影響を与え、亡命中の私たちに目標と役割を与えた。結局のところ、PLOは亡命先から生まれ、その指導者や戦闘員は亡命しており、祖国を取り戻し、亡命を終わらせるという約束を掲げていた。当時、PLOの存在は私たちにとって驚異であり、真の解放を待つ間、帰属できる象徴的な祖国だった。私たちのルネッサンスの基盤として、またパレスチナ奪還の展望を示す希望の光として、その重要性を過大評価することは難しい。740人からなる「亡命議会」パレスチナ国民評議会を通じてパレスチナ人全体を代表するという野心的な活動は、傷つき分断された人々の魂を癒すものだった。
PLOの存在は、私たちのどこにでもある闘いに幅広い意味を与え、あらゆる場で闘わなければならないことを教えてくれた。この幸福感にもかかわらず、私はPLOの欠点や野望を達成する能力の限界に気づかなかったわけではない。パレスチナの外からイスラエルと戦い、裏切りかねない信頼できないアラブ諸国との戦いを余儀なくされているパレスチナ人が活動しなければならない状況では、いかなる解放運動も成功の可能性は低かった。しかし同時に、同胞がパレスチナで戦い、死んでいくのを遠くから助けられずに見ていなければならないという無力感からも解放された気がした。PLOは私に闘いに参加する道を示してくれた。
1965年のファタハのイスラエルに対する最初の軍事作戦は、武装闘争による抵抗のパレスチナ人の権利を再確認するものではあったが、それが解放への唯一の、あるいは最も成功した道であったわけでは決してない。それは政治的、外交的、文化的など、さまざまな形をとった。1960年代後半から70年代にかけて、PLOは統治機構を整備し、市民社会機構や職業組合を設立した。PLOは、亡命中であっても国家を建設したいという熱望と、1948年以前のパレスチナ人の生活を取り戻したいという願望を同時に反映していた。
イスラエルとの力の不均衡と、それを維持しようとする世界的なコンセンサスを考えれば、当時は荒唐無稽な願望だった。それにもかかわらず、PLOは、具体的な現実と同様に思想として、大多数のパレスチナ人を鼓舞することに成功した。PLOの呼びかけに抵抗することはできず、彼らや増え続ける支持者を行動に駆り立てた。私たちの努力が本当にパレスチナの解放を成し遂げるかのような、偉大な事業に参加しているような気がして、めまいがするような興奮を覚えた。しかし、パレスチナの解放とはどういうことなのだろう?
このことが、文学や物語、詩や芸術、映画や演劇やメディアは、戦場における武器と同等、あるいはそれ以上に優れた武器になりうるということを実感するきっかけとなった。私が育ったイギリスの親イスラエル的な環境の中で、私は自分の解放の仕事を、これらの手段を使って人々の心を変え、私たちの大義に向かわせる戦いだと考えていた。1970年代初頭には、パレスチナ運動が活発化し、フリー・パレスチナという小さな団体が発足した。1972年、私たちのうちの何人かがパレスティナ・メディカル・エイド(Palestine Medical Aid)を設立した。この種のチャリティとしては英国初のもので、後にパレスチナ人のためのメディカル・エイド(MAP)となる。その1年後、私は数人の仲間とともにパレスチナ・アクション(現在英国で活動している同名のグループと混同しないように)を立ち上げた。パレスチナ・アクションは、英国政府と英国世論への働きかけに特化した、パレスチナのための最初の政治組織だった。私たちは、影響力のある人々に手紙を書いたり、デモをしたり、メディアに登場したり、新聞広告を出したりという従来の方法を使った。当時外務大臣だったアレックス・ダグラス=ホームや他の政府の下級議員にも会い、女王にも手紙を書いた。
私たちの目的は、パレスチナ問題をイギリスの政治地図に載せ、イギリス国民に定着したシオニストの物語に対抗することだった。1974年、パレスチナの大義を国際的に確固たるものにするためのパレスチナ外交努力の一環として、サイード・ハマミというPLO初の駐英代表が任命された。この進展が私たちの活動を後押しし、最終的にはそれに取って代わった。パレスチナ・アクションは1970年代の終わりまで活動を続け、やがて活動を停止した。それから間もなく、パレスチナ連帯キャンペーンが設立され、他のイギリスの連帯グループがそれに続き、イギリスにおける組織的なパレスチナ支援の流れが確立された。私は他の人々とともに、新聞にオピニオン・ピースを書いたり、本や調査研究を出版したりと、積極的に活動するようになった。エドワード・サイードが1979年に発表した『パレスチナ問題』は大きな影響力を持ち、彼の著作は2003年に彼が亡くなるまで、そしてそれ以降も、この問題を効果的に宣伝し続けた。
後に登場し、もっと早く登場すべきであった2つの重要な文学ジャンルは、回顧録と小説である。パレスチナ人の体験を伝える個人的な記述や想像力豊かな物語ほど、人々の目を開かせ、心に届くものはない。そのような本はアラブ世界では以前から出版されていたが、翻訳されない限り、西洋の読者には手が届かなかった。解放の文脈では、個人の歴史や物語はヨーロッパの言語で書かれるのが最適であり、イスラエルとパレスチナの紛争で果たした役割を考えれば、イギリスとアメリカの英語は特に重要だった。このような文学的、芸術的な試みにおいて、私たちは、闘争をより効果的なものにするために、現地の政治的、軍事的行動と私たちの努力を同期させようとした。
最近では、文学、演劇、映画で伝えられるパレスチナの経験は、西側諸国ではますます身近なものとなっている。しかし、私たちが目指した解放、そしてこの運動の意義は、もはや近づいておらず、おそらくさらに遠ざかっている。今日の現実は、イスラエルが歴史的パレスチナ全域を植民地支配していることだ。この空間では、パレスチナ人はイスラエルの二級市民か、1967年以降の領土では権利を持たない非市民である。後者は、植民地権力に従属し、パレスチナ人の生活を取り締まり、抑圧に対するいかなる抵抗にも反対するよう命じられているパレスチナ自治政府によって二重に支配されている。このような状況下で、解放はどのように起こりうるのか、そしてそれは何を意味するのか。何十年もの間、イスラエルとパレスチナ人にとって最善の方法として宣伝されてきた2国家間解決策は、たとえそれが実現したとしても、解放を意味するものではないだろう。この解決策によって提供されるパレスチナ国家を構成するパレスチナの22%は、パレスチナ全土の自由の代わりにはならない。パレスチナ人とユダヤ人のための民主的で平等な社会の創造という解放への道筋として、多くの人々が一国解決策に目を向けているのは、そのためでもあるが、多くは確信に基づくものである。
植民地主義的でアパルトヘイト的なイスラエル国家を、すべての人に平等な権利を与える民主主義国家に置き換えるという目的は新しいものではなく、1969年にPLOが初めて提唱した。当時の状況を考えると、ファタハは極めて前向きなビジョンで、「明日のパレスチナ」、すなわちすべての人が平等な権利を持つ進歩的で民主的な非宗派国家の構想を打ち出した。ファタハは初めて、パレスチナにユダヤ人社会が物理的に存在することを認め、そのユダヤ人社会には、生粋のパレスチナ系ユダヤ人だけでなく、新しい国家に正義と平等をもって受け入れられなければならない入植者も含まれていた。この提案は、例えばガザやヨルダン川西岸にパレスチナの小国を作るという考えを否定した。非宗派国家では、PLOはパレスチナ人の帰還権が実現され、その他の移住は後になり、合意された国家政策に従って制定されることを想定していた。
民主主義国家の提案は、ほとんどのパレスチナ人には歓迎されなかった。多くの人々にとって、それはパレスチナにおけるシオニストによる侵略を容認することであり、敵国への耐え難い譲歩を意味した。また、より技術的に進んだユダヤ人による単一国家での搾取と支配を恐れた者もいた。さらに、新国家がユダヤ人のアラブ世界への経済浸透の橋頭堡を正統化することを恐れた者もいたし、最も重要なこととして、この提案はパレスチナ人の闘争心を弱め、抵抗を封じ込める恐れがあった。同様の懸念は今日でも存在し、一国解決策の提案者に反対するために使われている。とはいえ、この考えは多くのパレスチナ人や世論に浸透し、もはや一部の変わり者や理想主義者のユートピア的な夢とは見なされなくなった。多くの団体や個人が単一的で民主的な国家構想を採用し、その実現に向けて努力している。その進展は遅々として進まないが、予期せぬ出来事によって加速される可能性もある。特に、ヨーロッパ、アメリカ、そしてアメリカのユダヤ人の間で、パレスチナに対する前例のない大衆的支持の波が押し寄せていることを考えればなおさらだ。
しかし、こうした民衆の支持の高まりにもかかわらず、現在、どの国でも一国解決策を公式に支持しているところはない。どの国家も政治機関も一国解決策を採用しておらず、この20年間で認知度が高まってきたとはいえ、二国解決策をめぐる国際的なコンセンサスには遠く及んでいない。一方、イスラエルは植民地化計画を拡大し、パレスチナの土地をさらに奪い、パレスチナ人をさらに追放することに余念がない。これと並行して、イスラエルは世界における自国のマイナスイメージを覆すため、あらゆる策略をめぐらし、あらゆる筋肉を緊張させ、相手側からの圧力に対抗するために残業に励むだろう。両者の戦いは常に不平等であり、勝敗は依然としてイスラエルに傾いている。
では、どうすればいいのか。完全な解放は、現在のイスラエルというシオニストによるアパルトヘイト国家の代わりに、公平で包括的な民主主義国家を創設することによってのみ実現しうるということに同意するならば、答えるべき唯一の疑問は、「どのようにしてそれを実現できるのか」ということである。現在のイスラエルは、ヨルダン川から地中海まで事実上ひとつの国家である。その人口は、市民権と完全な権利を持つ660万人のイスラエル系ユダヤ人、市民権と部分的権利を持つ180万人のイスラエル系パレスチナ人、市民権も権利も持たない470万人のパレスチナ人である。これまでイスラエルは、国際条約を無視し、人権規範に違反しながら、50年以上にわたってこの不公平な取り決めを維持し、正常化さえしてきた。このあからさまな不平等を終わらせることができた国も、それを望んだ国もなかったし、これからもできそうにない。そのような介入がない場合、不平等を終わらせる方法を見つけなければならないのは被害者自身である。
もし今、エルサレム、ヨルダン川西岸、ガザの権利を奪われたパレスチナ人が、イスラエルにこう挑発したとしよう。われわれは、われわれに何の権利も与えず、われわれに対するあなた方の支配を拒否する。われわれの領土から撤退するか、あるいは、あなた方が支配する他の人々と同等の市民権をわれわれに与えるか、どちらかだ。イスラエルが撤退を拒否し、この挑戦を無視したとき、パレスチナ人は引き下がらず、イスラエルの市民権を要求する。同時に、イスラエルが拒否した場合、彼らはその要求に伴う市民的不服従の大規模なキャンペーンを展開し、彼らの事例を世界に公表し、彼らの置かれた状況の現実と彼らに対するイスラエルの醜悪な行為を世間の視線にさらす。そして、パレスチナのディアスポラやパレスチナを支援するすべての人々が、同胞の要求に連帯し、反アパルトヘイト運動が南アフリカ国内の闘争を支援するためにキャンペーンを展開したように、内部と外部が協調した二方面からのキャンペーンを展開する。各個人やグループがそれぞれのイニシアチブを立ち上げ、エネルギーを分散させているパレスチナを推進するどこにでもあるバラバラの活動が、この一つの目的に向かって団結し始める。
このプロジェクトにとどまりながら、パレスチナ人が権利平等戦略を採用するよう説得され、他のどの戦略もこれまで自分たちを助けてくれなかったことを認識し、肩入れすることができたとしよう。その結果、最終的にその戦略が実行に移され、彼らがイスラエルの市民権を獲得したとしよう。彼らが得るものは相当なものだろう。自分たちの土地に権利としてとどまり、尊厳と安全のうちに暮らすことができ、歴史的パレスチナ全域が再び彼らの手に入るようになり、避難民となった同胞たちは、代表的な議会がそれを許可する法律を通過させることができるようになれば、故郷に帰ることを待ち望むことができる。何よりも、平等な権利を求める彼らの声は、ユダヤ人の多数決とユダヤ人の排他性を前提とするシオニストのイデオロギーの核心に迫るものだ。もしすべてのパレスチナ人が市民権を得れば、イスラエルの人口構成は不可逆的に多元主義へと変化し、シオニズムは終焉を迎えるだろう。
これがチェスのゲームであったなら、私が上に説明した戦略はイスラエルにとってチェックメイトを意味しただろう。しかし現実の世界では、そうなる可能性はほとんどない。あらゆる証拠があるにもかかわらず、いまだに自分たちの国家を望んでいるパレスチナの住民と、それが実現すると信じている2つの国家に関する国際的な好意的立場に従うよう説得されているパレスチナの知識人たちでは、この仕事はあまりに困難だ。この幻想が続く限り、彼らは異なる戦略のもとに団結することはないだろう。イスラエルによるパレスチナの土地の植民地化を中止させるために何もしないまま、パレスチナ人の独立の希望を育むことは、パレスチナの人々に対して犯された多くの犯罪の中のもう一つの犯罪である。
全世界が理解できるシンプルでわかりやすいメッセージを打ち出した平等な権利キャンペーンは、今日のパレスチナ人の闘いを覆い隠している韜晦や難解さを断ち切るだろう。それは、現在の単一国家構想を否定するものではなく、逆に強化するものであり、パレスチナ人が熱烈に望むもの、すなわちシオニズムの終焉と自国の解放を達成するための最速かつ最も直接的なルートとなる可能性がある。
RANDA ABDEL-FATTAHは、パレスチナ系エジプト人オーストラリア人のムスリム作家、学者、活動家、元弁護士である。マッコーリー大学社会学部博士研究員。著書に『Islamophobia and Everyday Multiculturalism』(2018)、共編アンソロジー『Arab, Australian, Other』(2018)などがある: Stories on Race and Identity』、『Coming of Age in the War on Terror』(2021)などがある。アブデル=ファタハは、ベストセラーとなったデビュー作 「Does My Head Look Big in This?」を含む、20カ国以上で出版され、数々の賞を受賞した11冊の小説の著者でもある。アブデル=ファタハは、世界最大の児童・青少年文学賞であるスウェーデンのアストリッド・リンドグレーン賞に2019年と2018年にノミネートされている。
解放の倫理
存在の様式としてのパレスチナ
ランダ・アブデル=ファタハ
シドニー郊外の一軒家から、30人のパレスチナ人家族(うち19人は孫)が前庭に出てきた。玄関ポーチにはパレスチナ国旗とイード・ムバラクの横断幕がかけられている。喫煙者たちは車道に集まり、ラマダン以来初めての朝のタバコを吸っている。イードのために着飾った数人の少女たちが、窓辺で携帯電話のバランスをとりながらTik Tokのビデオを録画している。義母は自分には大きすぎる籐のアウトドアチェアに座り、アラビックコーヒーのカップを握りしめている。下の子供たちは義父のレモンの木をゴールポスト代わりにしてサッカーに興じ、枝に気をつけろというおばちゃんたちの声を無視している。この2021年のイードの朝のリズムは、「私たちは人生を教えていますよ」という目に見えない拍子に合わせてハミングしている。
私たちは常に、レンズを通して亡命生活に遭遇している。ある角度から見れば、喜び、愛、特権。少しでも傾いた角度から見れば、不正、抑圧。安全なディアスポラで絶望を感じようという勝手な誘惑を退け、家族写真でポーズをとるよう子供たちをおだてる。角度は傾く。ソーシャルメディアをスクロールし、「アラブ人に死を」と唱えるイスラエルの暴徒のビデオを見、「あなたたちは私の家を盗んでいる」というモナ・アル・クルドの苦悶の叫びを聞き、アル・アクサの礼拝者への攻撃に反発する。WhatsAppグループでイードのGIFを送る。
義母の電話が鳴る。「あと数分で到着する」と義母は叫び、コーヒーを芝生の上に置いた。
私の電話も鳴る。オーストラリア放送協会(ABC)のジャーナリストだ。昨日まで私たちの相手をしてくれなかったのに、突然、パレスチナのある家族について、「イードのお祝いがどのような状況にあるのか」を取材してほしいというのだ。
状況はこうだ。ガザは空爆されている。そして私の夫と義父は、癌の検査結果を持って病院から戻る途中だ。
イスラエルは11日間、ガザを空爆している。26日以内に義父は死んだ。
義父の診断から約1週間後、死の2週間も前に、私は義父の家で義父の横に座り、膝の上にパソコンを置いた。私はマルチタスクの活動家、義理の娘モードだ。「アモ、気分はどう?公開書簡『パレスチナのためのアカデミックス』について同僚にメールしながら、私は尋ねる。
「アルハムドリッラー」と彼はストイックなまでに冷静に答えた。
テレビではアルジャジーラのニュースがガザの様子を伝えている。7歳の息子アダムのI-padからディズニーの『アラジン』が聞こえてくる。彼は私の横で、自由奔放に、調子外れに、歌詞を切り裂きながら歌っている。私はテレビのボリュームを上げる。アダムはI-padのボリュームを上げ、「歌が聞こえない!」と不満げな声を上げた。
「ニュースを見ているんだ」と私は言う。
アモは不服そうな顔をしてテレビを消す。
ここでは、家族という空間に対する2つの主張が競合しており、パレスチナ系ディアスポラ家族の日常的な空間において、長老たちがどのように私たちに生活を教えているのかを知ることができる。一方は、パレスチナで起きていることの証人になるという、ここにいるパレスチナ人の主張である。一方では、パレスチナの子どもは、パレスチナで起きていることをそこに留めておくために、ここを支配しようとする。
私は、ガザでパレスチナの子どもたちがイスラエル国家によって殺害され、恐怖にさらされているのを見ている一方で、孫が子どもであることを許し、遊び、歌うスペースを与えるという義父の連帯のジェスチャーについて考える。私は、子供にとって、「ここ」と「あそこ」のつながりを理解する適切な時期とはいつなのかを考える。アンバラヴァナー・シヴァナンダンが提唱する移住という意味だけでなく、パレスチナの外にいるパレスチナ人として、私たちが地理的な場所の単なる観客ではないことを理解すること。存在様式としてのパレスチナを理解するのだ。
「痛みはある?」私はアモに尋ねる。彼は微笑む。「文句を言えるわけがない。ガザで起きていることを見てごらん。アルハムドリッラー。” ノートパソコンに向かっていたことを謝る。この数日間、私は電話もせず、訪問もしなかった。「彼は私を遮るように言った。「続けてくれ。彼は携帯電話を取り出し、家族や友人から共有されたパレスチナのWhatsAppビデオを見せてくれた。
数日後、私はアモの墓のそばにしゃがみこみ、このシーンを思い出して号泣した。アモの最期の瞬間を見逃したことに嗚咽するが、罪悪感からではない。アモ自身、正義のためのたゆまぬ擁護者であり、パレスチナが単なる大義名分ではなく、生き方そのものであることを理解していた。
私が涙を流すのは、解放闘争へのコミットメントが家族の中で何をもたらすのか、つまりディアスポラに住む子供たちにスムードが具体的な生き方であることをどのように教えるのか、という問いかけに常に悩まされているからだ。私が「ディアスポラで」と言ったのは、第一に、そこが私が執筆している場所だからであり、第二に、パレスチナの子どもたちが私にスムードの意味を教えてくれるのであって、その逆ではないからである。
作家として、また学者として、子どもたちや若者たちとともに働きながら、私は政治的な生き方とは何かを常に探求している。私たちが自分の目的やアイデンティティをどのように意味づけるのか、私たちは互いにどのように関わり合うのか、子どもたちは家族や自分自身を通して世界について何を学ぶのか、私たちはどのようにバランスをとるのか、私たちはどのようにイスラエルと向き合って抵抗するときと背を向けるときを知るのか。ガッサン・ヘイジが主張するように、抵抗だけで定義された人生は「それ自体が目的化し、それ自体のためになる」危険性がある。占領と占領への抵抗の両方から解放された生活の空間や次元」を開拓することは、「英雄的規範性」の空間を開拓することである。
私を悩ませ、元気づけてくれるイメージのひとつは、ガザという最新の犯罪現場に立つパレスチナ人の少年少女が、瓦礫と瓦礫の中でペットの魚を抱いて微笑んでいる姿だ。
はっきり言っておくが、私は回復力を祭り上げているのではない。占領され、爆撃を受け、心に傷を負った人々に、「自制心」を発揮し、回復力を示すことを期待する人々の戯言を否定しなければならない。
この映像が私に深い影響を与えたのは、別の理由からである。学者ナデラ・シャルホブ=ケヴォーキアンがイスラエルの「殺傷能力」と表現するものが、パレスチナ人の「居住能力」と対峙しているのだ。二人の子供たちが「英雄的な正常性」の空間を瞬間的に主張し、解放のための闘いにおいて、パレスチナが自由になったとき、私たちは誰になるのか、何をするのか、何を意味するのかを考えるために、時には十分に立ち止まらなければならないことを思い出させてくれた。
私たちの本質的で譲れない権利と民族としての尊厳が尊重されるとき、人間らしく生きるとはどういうことなのか。私たちが解放されるまで、人間らしさを保留し、喜び、創造性、遊び、静寂、笑い、軽薄さを先延ばしにするならば、解放が訪れたとき、私たちに何が残るだろう。魚と一緒にいる二人の子供たちは、私にこのことを思い出させた。
自由と正義を達成するための戦いにおいて、もし私たちが何と戦っているのかを考えるあまり、何のために戦っているのかを考えることを怠ってしまったら、失うものは大きい。子どもたちは、そんなつもりはないからこそ、このことを思い出させてくれる。アダムが「歌が聞こえないよ!」と叫んだとき、彼は私に、私たちが戦っているのは単にパレスチナの子どもたちが殺されない権利のためではなく、彼らの生きる権利のためなのだということを思い出させてくれた。
エドワード・サイードが適切に表現したように、パレスチナ人の「物語る許可」を政治的・メディア的権威が否定することに抵抗する努力の中で、パレスチナ人は必然的に、否定に反対するために場所を要求し、声を結集することに何年も費やしてきた: ナクバ、ナクサ、2国家・1国家、アパルトヘイト、封鎖、国境、グリーンライン、民族浄化などなど。カウンター・ナレーションは、私たちの集団的抵抗の中心であり、特に西側のディアスポラや亡命者の間では重要である。パレスチナの闘争と解放の物語の正統な中心にいるのは若者たちであり、それは脇役としてではなく、占領された生活、封鎖された夢、検問所での出産、悲しむべき死といった物語の中心であり続けなければならない主役の語り手である。
ガザの人口の51%は15歳未満であり、ガザへの戦争は子どもたちへの戦争である。ヨルダン川西岸地区の人口の45%が15歳未満であるため、イスラエルの軍事占領は乳幼児やティーンエイジャーに対して行われている。パレスチナ全人口の30%以上が15歳から29歳であり、若い成人はイスラエルの入植者植民地アパルトヘイト体制によって残虐な扱いを受け、抑圧的な状況で暮らしている。
子どもたちや若者たちは、基本的にパレスチナ解放運動の中核を担っている。イスラエルの政治エリートはこのことを知っている。
イスラエルがいかにパレスチナの子どもたちの非人間化を常態化させてきたか、ナデラ・シャルホブ=ケヴォーキアンが、「unchilding」と呼ぶものを見れば、そのことがわかる。
2018年の「帰還の大行進」の際、イスラエルの国防相(当時)であるモルドバ生まれの入植者で極右ナショナリストのアビグドル・リーバーマンは、「ガザに罪のない人はいない」と宣言した。イスラエル国防軍の公式ツイッターは、「ハマスがイスラエルに侵入するための道具」として、「火炎瓶」「石」「ワイヤーカッター」「放火凧」「子どもたち」「体の不自由な民間人」「フェンスにくくりつけたロープ」をリストアップしたグラフィックを掲載した。言い換えれば、パレスチナの子どもたちは正当な標的なのだ。
イスラエルが生後8カ月の赤ん坊レイラ・ガンドール22をはじめ、殺されたり、永久に傷つけられたりした赤ん坊や子どもたちを「罪のない」という政治的カテゴリーから意図的に除外し、西側の政治家やジャーナリストがイスラエルの「自衛権」を主張することでこの除外を支持する一方で、イスラエルに「相応の暴力」を行使するようおとなしく要求していることからも、このことがわかる。生と死の配分は、パレスチナの子どもたちが人間:非人間、亜人、人間以下の比率で数えられる世界でのみ可能である。イスラエルが西欧の代表/体現である以上、「テロリスト」ほど強力で動員力のある非人間的な記号はない。イスラエルは「西洋」の利益と入植者の植民地的価値観の擁護者として、「暴力的」で「過激」で「急進的」な東洋と戦うという人種差別的な図式にその正当性を見出している。この表象の牢獄では、レイラ・ガンドールが無実であることはありえない。彼女の殺害は、「ハマスの人間の盾」などという言葉で正当化されたり、2018年5月にオーストラリアの国営テレビ番組「Q&A」に出演した際にシオニスト擁護者が私に言ったように、ハマスの想定される「死んだ赤ん坊の戦略」のせいにされたりする。
イスラエルによる直近のガザ砲撃では、66人の子どもを含む256人のパレスチナ人が死亡した。イスラエルのミール・アミット諜報・テロ情報センターによれば、殺害されたパレスチナ人の少なくとも48%は「テロリスト集団に関連」しており、子どもたちの「多く」は「テロリストの家族」、つまり、正当な理由で絶滅させることができる存在であった。
イスラエル兵が15歳のいとこの頭を至近距離から撃った数時間後、兵士を平手打ちしたパレスチナのティーンエイジャー、アヘド・タミミは、当時のイスラエルの文化大臣ミリ・レーゲフによれば、「少女」ではなく「テロリスト」だった。
パレスチナの子どもたちの存在と抵抗を犯罪化することを正当化するために、イスラエルがいわゆる「テロとの戦い」という言葉を道具的に用いることに終わりはない。イスラエルは、「パレスチナの抵抗」の意味を 「テロ」として正規化し、「パレスチナの子ども」を 「テロリスト」に変えようとする持続的な言説体制に多大な投資をしてきた。特にこの20年間、パレスチナの若者をテロリストとして、「国家安全保障上の脅威」として語ることは、「テロとの戦い」の基本的、組織的な文法と帝国的論理にうまくはまるように計算されてきた。イスラエルの戦略家たちは、パレスチナの子どもを罪深いテロリストとしてメッセージすることが、西側の手先として対テロ戦争を戦うためだけでなく、国際的な監視の目を逃れるためにも有効であることをよく知っている。結局のところ、罪のない子どもたちが死ぬという光景は、数十億ドルの利益を生む軍事、監視技術、軍需産業を危険にさらし、ガザは理想的な「兵器実験室」なのである。イスラエルの軍事作戦を対テロリズムと決めつけることは、西側諸国政府が多大な投資をしている政治経済に役立つ。対テロ戦争の人種的台本、安全保障化された想像力、先制攻撃の論理は常に、テロリストの中心的カテゴリーとして構築されてきたイスラム教徒、黒人、褐色の若者たちに対して作用してきた。
では、パレスチナの若者たちが解放の未来を想像することは、どのような意味を持つのだろうか。
民族解放は自己解放から始めなければならないが、自己解放にはまず、自分の立場を自己認識することが必要だ。
直近のプロジェクトでは、テロとの戦いの中で、国家やいわゆる中立的な政策や政治的実践によって若いイスラム教徒に対して行使された暴力と、それが9.11以降の世界に生まれた若者にどのような痕跡を残しているのかを問うてきた。私は、この暴力が彼らの生活、特に学校というミクロな文脈の中で、若者たちによってどのように経験され、どのように抵抗されているのか、また、長年にわたる「暴力的過激主義への対抗」政策や政治的・メディア的レトリックが、ムスリム/アラブ系(これらは同義語として扱われているため)の若者たちの身体や言論、彼らが移動する空間に対する過敏な反応や取り締まりをどのように常態化させてきたのかを深く掘り下げようとしてきた。学者スナイナ・マール・マイラが「監視の日常」と表現するような中で生きる若者たちは、政治的表現や異論を封じ込め、管理しようとする試みに対して、適応的・不適応的な対処戦略をどのようにとっているのかを、私と分かち合ってくれた: フリー・パレスチナ」のTシャツを「政治的」だという理由で学校で着ることを禁じられたパレスチナの少女から、テロリズムとイスラム諸国への欧米の干渉に関する作文を書いたためにASIOの事情聴取を受けたイスラム教徒の少年まで、自分の「安全性」を示すために自己検閲の戦略を追求したり、自分の言葉で発言する権利を主張して押し返したりしていることを告白した学生たちがいた。私はまた、同化を追求し、「善良な」/「穏健な」/「無政治的な」ムスリム/アラブ人として振る舞おうとする学生にも出会った。彼らは、バーバの言葉を借りれば、白人性を模倣し、その過程で、常に 「ほとんど同じだが、まったく同じではない」自分自身を発見し、両義的なものに還元されていた。他方で、学校で教えられるシラバス(ほとんど常に「二つの側面」/イスラエルには自衛権がある/BDSは反ユダヤ主義的/ハマスがこうで、ハマスがああだ」と主張する)の中で、自分たちが非人間的であることに直面し、自分たちの人間性を「証明」することを拒否したパレスチナ人学生もいた。
若者の声を消す方法のひとつは、彼らの感情を切り捨て、政治的情熱や怒りを主観的で非合理的なものとして退けることだ。たとえば、「フリー・パレスチナ」のバッジをつけて登校し、イギリスの過激化防止プログラム(プリベント)のもとで教師から警察に通報されたラフマーン・モハマディのように、パレスチナを支持する若者を検閲しようとする露骨な試みもある。若者たちが直面する認識論的人種主義もある。それは、「中立」という神話の名の下に、若者たちの怒り、感情、抵抗、政治的発言力を否定するものだ。
ラモン・グロスフーゲルは、西欧の覇権的アイデンティティ政治と認識論的特権は、ある種の神話によって支えられており、そのひとつがコロンビアの哲学者サンティアゴ・カストロ=ゴメスが「ゼロ地点」と呼ぶ視点であると論じている。グロスフーゲルはこう説明する: 「ゼロ地点」の視点とは、ある視点を超えていると自任する視点の西洋神話である。
ゼロ地点」の思い上がりこそが、認識論的に「両論併記」「バランス」「中立」「対立」「交渉」という物語を動かしているのだ。生徒たちは、教師から「教室に政治を持ち込むな」と言われたり、「事実に基づいて、怒りを抑えて」と注意されたりしたことを話してくれた。ある生徒のエッセイは、「個人的で感情的すぎる」「学術的でない」という理由で減点された。ある生徒が言ったように、怒りの感情を「トーンダウン」することを学ぶことについて、生徒たちは私に話してくれた。感情を抑えることができないんだ。「彼らは私の怒りを聞きたくないんだ」
怒りっぽく、理性的でないムスリム/アラブ人というオリエンタリズムの図式は悪質だ。自己検閲への抵抗と、教室の文脈でそうしなければならないというプレッシャーは、私が出会う多くの学生に共通するテーマである。自分の口調や言葉、感情的な表現が、人種差別やイスラム嫌悪の図式によってどのように解釈されるかを予期することは、学生の自己表現と教室での議論への貢献に重くのしかかる。
ある大学生は私に言った: 「自分には感情があるのに、他の人は気にしていないようにいつも感じる。授業が終わると、ああ、恥ずかしいと思う。こんなに熱中しているのは自分だけだ。なぜ彼らは気にしないんだろう?パレスチナや中東、褐色人種や黒人の命、シリア、ドローン、イエメンやその他諸々の問題になると、なぜ彼らは熱くならないんだろう?私はそこに座って、これはとても間違っていると言っているのに、彼らは私がそんなに感情的になるべきではない、海外で起こっていることをここに持ち込むべきではない、家に置いておくべきだと言う。
ジュディス・バトラーが理論化したように、「公的に悲嘆に暮れるべき人生」と「そうでない人生」とを区別しているのだ。「海外で起きていること」に対する悲嘆を強制的に私物化することは、学校や大学の空間を中和することでもあり、「理性的」で「非政治的」な教室空間と、「感情的」で「非合理的」な私的空間との間に二項対立を生み出す。
「バランス」、「冷静さ」、「中立性」という語りの原動力となる「ゼロ地点」の認識論的人種差別主義は、パレスチナが解放闘争に従事しているという事実を曖昧にする。そこでは、「ある視点を超えている」と主張すること自体が、ある視点なのだ。どちらの側にも立っていないという主張は、どちらの側にも立っていることになる。イスラエルの覇権主義、好戦主義、国際法違反という事実が明白である以上、実質的な中立を装うことは不可能であるばかりか、弁解の余地もない。
パレスチナ人、非パレスチナ人を問わず、若者たちとの仕事において、私ははっきりとこう言う: パレスチナは、中立的、非政治的、非歴史的な主体という西洋の神話を否定し、むしろ正義を求めることに根ざした政治的、社会的、感情的な方向性と知的姿勢を自己反省的に主張し、それによって必然的に 「どちらの側にも立つ」人間であることを誇らしげに表明することを教えてくれる知の場なのだ。
子供たちが正義と説明責任という概念を理解できるようになった瞬間から、この姿勢が育まれ、ポーラ・アブードが言うところの 「個人崇拝を特権化せず、むしろ多面的で関係運動的な自己存在のモデル」を追求することによってのみ、未来の可能性を想像することができる。パレスチナ人であることは、実践の倫理を体現することであり、世界をナビゲートする方法であり、特権と否定のバランス、私たちの言葉の重み、私たちの行動が他者に与える影響を常に評価することでなければならない。ゼロ地点の視点など存在せず、私たちは皆、歴史的な力に基づく力関係の軸の上に位置していることを子どもたちが理解すればこそ、私たちはいわゆる「ゼロ地点」の視点の認識論的、存在論的な前提や驕りを拒否することができる。
若いパレスチナ人としてアイデンティティを確立することは、ローカルなものを超えて自らを位置づけるという、継続的な倫理的、知的、政治的なプラクティスを採用することである。パレスチナ人であることの意味を学び直し、そして学び直す。私は生徒たちと、私自身の自己認識の系譜を共有している。「脱植民地的思考」に取り組むことは、ミニョーロがアイデンティティの「帝国の傷」として特徴づけているものをたどることである。イスラエル建国を支援し可能にしたイギリス帝国プロジェクトは、私の父を祖国から奪い、私の父をもうひとつのイギリス帝国プロジェクトであるオーストラリアに連れてきた。入植者の植民地であるオーストラリアは、「中立」という「ゼロ地点」の視点を主張することはできない。土地を奪われたパレスチナ人の娘として生まれ、盗まれた土地でオーストラリアに暮らす私の立場を理解することは、アイデンティティの代替的な認識論を受け入れ、私たちの服従、適合、沈黙、抹殺、非人間化、封じ込めを求める構造、法律、言説、力に対して、認識論的不服従を煽動する力を与えてくれる。
政治を「教室の外」に置き、「海外で起きていること」を無関係なものとして扱うことは、パレスチナが国際的な闘いであるという事実から目を背けることでもある。絶望を助長する最も効果的な方法のひとつは、パレスチナ人に孤立感を抱かせ、彼らの大義を 「単なる中東紛争」、「複雑」、「不明瞭」、「難解」として扱うことだ。これは、国家が公認した暴力の交錯を覆い隠してしまう。先住民、黒人、人種差別を受けたマイノリティ、そしてパレスチナ人に対する人種的暴力は、歴史的な権力のマトリックスに基づく、人種と入植者の植民地主義の継続的な構造を通して実行されている。テロとの戦いから20周年を迎えようとしている今、パレスチナ人の若者たちは、テロとの戦いの帝国的論理を把握し、ガザで起きていること、シェイク・ジャラーで起きていること、イスラエルにいるパレスチナ人の検閲されたソーシャルメディアのアカウントと、自分たちの教室のような西側の文脈における自分たちの経験との点と点を結ぶための知的ツールを必要としている。また、特定の社会正義運動(黒人とパレスチナの連帯活動家、BDS活動家、Black Lives Mattersの抗議者、反人種主義活動家、脱植民地主義的環境擁護者、若者運動家)に対して、「過激」「極端」「国家安全保障」「テロリスト」という対テロ戦争の言葉を武器にすることで、何が、そして誰に役立っているのかを理解する必要がある。若者たちがこのようなつながりを主張するとき、彼らは、制度化され制度化された国家暴力、制度的抑圧、残虐行為に対抗するさまざまな運動間の継続的かつ歴史的な親和性と収束を予告している。
最終的に、パレスチナ人であることは、正義のために闘うことに根ざした解放の倫理を創造することである。それは、「あなたの脱植民地化を掻い摘んであげるから、私の脱植民地化を掻い摘んで」というような取引的ジェスチャーとしてではなく、パレスチナ人の解放が、世界のどの地域にいようと、正義、真実を語ること、尊厳、自由に対して無条件にコミットすることの意味を体現しているからである。これは解放である。力を与えてくれる。だからこそ、世界的な闘いの共有は、白人至上主義やシオニズムだけでなく、反人種主義を多様性政治や対人無差別に限定し、決して脱植民地化もせず、世界的な権力構造の解体もしない新自由主義的多文化主義にとっても脅威なのだ。
私の義父はヤッファで生まれ、ガディガル人の未開拓の地に埋葬されている。1967年6月、彼はパレスチナからヨルダンまで歩いた。捕らえられるのを避けるため、死体のそばに横たわり、「死んだふり」をした。パレスチナから追放された彼はオーストラリアにたどり着き、難民や移民、社会から疎外された人々の支援に生涯を捧げた。彼はまた、笑い、人々を笑わせることに人生を費やした。Nadera Shalhoub-KevorkianとSarah Ihmoudはこう書いている: 「過去とその遺跡の意義は、私たちの人間性、精神、そしてコミュニティのための家を築く責任から始まる。アモはこの責任を体現していた。イスラエルがガザを空爆し、彼の癌が広がる中、私たちは彼の健康についてよりもパレスチナについて話した。彼は最後までパレスチナを背負っていた。
パレスチナ人にも喜びがある。パレスチナ人にも喜びがあり、悲しみがある。8時のニュースの息子である前に、彼は生き物なのだから。「と書いている。
私たちはどのような 「生き物」のために戦っているのだろうか?私たちの政治的想像力と政治的労働力は、イスラエルに言及することなく音楽を奏でたり夢を見たりしながらも、パレスチナ人であることは戦うことである、という私たちの主張と同じ程度のものでしかない。バスマ・ガラヤニは、『パレスチナ+100:ナクバから1世紀後の物語』の序文で、パレスチナ人と科学/推理小説の関連性について考察している: 「残酷な現在(そしてトラウマとなった過去)は、パレスチナの作家たちの想像力をあまりにも強固に支配している。しかし、こうした空想的な冒険は重要である。パレスチナ人作家のアダニア・シブリが、「非人間化が繁栄する場所で、平行した可能性を創造する」方法が、なぜ言葉による。「救済」なのかを語っているように、言葉によって私たちは 「人間性」を 「実践」することができるのだ。戦時中にイードケーキを焼いたり、瓦礫の中に床屋の鏡と椅子を置いたりするような、美学的で体現的な抵抗と回復の実践の時がある。しかし、単に喜びを切り開くだけでなく、喜びを経験するための平行した自律的な空間が必要であることもまた、決定的に重要である。詩人のサラ・サレが書いているように、「国境や流血や戦争や死や故郷について書くことをやめること」だ。国境や壁、検問所や檻のない夢を見ること。防衛のためではなく、気持ちいいから笑うこと。アルジャジーラをバックにアラジンの歌詞を大声で歌うこと。返答としてではなく、パレスチナ人であることは祝福に値する人生であり、悲しむに値する死なのだから。
アッラーよ、アモよ。私たちは子どもたちに、抵抗する権利が遊ぶ権利と同じくらい重要であることを教え込む。
22 Al Jazeera English, ”Laila Anwar al-Ghandour becomes the face of Gaza carnage,” May 15, 2018, www.aljazeera.com/news/2018/5/15/laila-anwar-al-ghandour-becomes-the-face-of-gaza-carnage last accessed November 5, 2021
SAMAH SABAWIは作家であり学者である。権威ある2020年グリーンルーム賞最優秀脚本賞を含む複数の賞を受賞している。演劇作品には『Tales of a City by the Sea』や『THEM』などがあり、高い評価を得ている。サバウィは『Double Exposure』を共同編集している: パトリック・オニール賞を受賞した『Double Exposure: Plays of the Jewish and Palestinian Diasporas』と共著の『I Remember My Name』がある: 詩集『I Remember My Name: Poetry by Samah Sabawi, Ramzy Baroud and Jehan Bseiso』(Vacy Vlazna編集、パレスチナ・ブック賞受賞)を共著で出版している。ビクトリア大学で博士号を取得し、論文 ”Inheriting Exile, transgenerational trauma and the Palestinian Australian Identity ”を発表した。
空白のスペースに書く
サマ・サバウィ
私はオーストラリアのクイーンズランド州レッドランズ・コーストにあるクアンダムーカ族の土地でこれを書いている。高齢の父、アブドゥル・カリム・サバウィを訪ねて、私はここで多くの時間を過ごしている。彼は永遠の難民であり、垂れ下がったまぶたが緩み、体が安らかな眠りについているときでさえ、神聖な祈りのように詩をささやく。私は彼が夢の中で革命的な詩を朗読するのを見ながら、「パレスチナを解放せよ!」と微笑む。
詩人は、その詩が生きている間だけ真に生きている。同じように、大義はそれを信じる人々がいる限り、真に生きている。そしてここ、世界の果てで、私はパレスチナを信じ、そのためにまた、私が実際に住んでいる土地の真実を求めている。
なぜ私たちはこんなところにいるのだろう?植民地化された土地から根こそぎ追放され、今や他民族の土地の入植者であり植民地化者である。皮肉なものだ。私たちは白人入植者の植民地主義的侵略の受益者なのだ。これを書くために座っている場所から、私の目は恥ずかしげもなく、エメラルド色の海岸に沿って並ぶ背の高いヤシの木の腕の中に、野原を横切って広がる熱帯の緑のプランテーションの広がりを消費している。遠くには、壮大な空を支える淡いブルーの水平線に、深いブルーの海がぶつかっている。この土地はなんと豊かで豊かなのだろう!私の心は、私を取り囲むあり得ないほどの美しさと、意図的に視界から遠ざけられたことによって拡大された、先住民の歴史的な痛みを知って痛む。かつてここは、アボリジニの文化や生活様式が栄えた場所だった。しかし、私がこの地を訪れたとき、先住民の姿を見たことはないし、先住民の歴史について言及したものも見たことがない。クイーンズランド州のこの地域で私が見たのは、時折そばかすが点在し、この風景の緑と青を映し出す瞳で飾られた、屈託のない白さだけだ。
自分なりに調べてみると、クアンダムーカ族はここに住んでいて、何万年もの間、この沿岸地域や島々、キャンプ場周辺の村で農業や漁業をしていたことがわかった。それが終わったのは、1800年代初頭にヨーロッパ人がやってきて、数十年にわたる民族浄化と大量虐殺が始まり、これらの先住民族の存在がほとんど消えてしまったときだった。パレスチナの私たちにも同じことが起こるのだろうか?私たちも消されてしまうのだろうか?
その答えは、文化や記憶の存在を示しながら、抹消に立ち向かわなければならないという根強い必要性にある。アボリジニやトレス海峡諸島の人々にとっても、祖国のパレスチナ人にとっても、公正で平和的な共存への和解の旅を始めるためには、過去のトラウマ的な出来事を認め、現在から抑圧の足かせを外すことなしに前進することは考えられない。
そのために、私は自分の役割を果たさなければならない。私は、祖国における入植者植民地主義と抹殺の犠牲者であり、私の属する大地から切り離された追放された精神であり、盗まれた植民地化された土地に住んでいることを認め、クアンダムーカの人々、すべてのアボリジニとトレス海峡諸島民、すべての生存者、すべての自由の戦士の過去、現在、そして新たな長老たちに連帯を誓い、敬意を表する。
トラウマと亡命
私はナクサ世代で、1967年にガザで生まれ、ショールに包まれ、タファの家からベビーバスケットで連れ去られた。私は亡命者だ。
私はヨルダンの難民キャンプで最初の言葉を発し、最初の一歩を踏み出した。運命のいたずらがなければ、私は今もヨルダンの難民キャンプに囚われている200万人のパレスチナ人の一人になっていたかもしれないし、ゲイズに囚われ、その包囲と定期的なイスラエル軍の砲撃作戦を生き延びている200万人のパレスチナ人の一人になっていたかもしれない。私のいとこや愛する人たちが享受していない、生き残ったという特権を得たというこの感覚は、私の人生の勝利と苦難の間中、影のようにつきまとっていた。羞恥心と罪悪感の源であるこの影は、私の思考と行動に宿り、私の主張、詩、演劇作品に姿を現す。私の生涯の伴侶であるこの影は、時に私を奮い立たせ、時に、特にガザへの砲撃の際には、私をトラウマに陥れ、完全に打ちのめす。
この影の存在に初めて気づいたのは、1982年、14歳のときにメルボルンのシティ・スクエアに立ち、レバノンのサブラとシャティーラ難民キャンプの虐殺に抗議したときだった。私は7歳のときにレバノンに行ったことがあった。そこに知り合いがいた。そこの子供たちと遊んだ。後にガザで殉教した叔父のアブデル・ムティもそこにいた。叔父は私を抱きかかえながら、「自由のために戦っているんだ」と言ったことがある。彼はそこにいた。彼らはそこにいた。そして虐殺があった。
抗議の日、私は初めて『エイジ』紙の一面でパレスチナ人家族の写真を見た。他の時なら、これを見て興奮したかもしれない。今回は違う。こうではない。家族たちは、米と肉のトレイを囲んで輪になって座っているわけではない。イードの服を着てカメラに向かって立っているわけでもない。結婚式で踊っているわけでもない。『エイジ』紙の一面に掲載された家族たちは、生気を失い、手足は垂れ下がり、血は滴り落ち、口は開き、腹は膨れ上がり……そして最悪なことに……無価値な状態で、互いに重なり合っていた。私がその一員となったばかりの世界の目には、彼らは無価値だったのだ。ちくしょう!これが私の新しい世界であり、新しいオーストラリアであり、私に市民権、尊厳、価値を与えてくれた国だった。どうしてパレスチナ難民の生活をこれほどまでに軽視し、虐殺者たちとアライメントされたのだろうか?自分の居場所を必死に探していたティーンエイジャーにとって、この現実は有害だった。その瞬間、私は自分の居場所はないと悟った。
この影が私を嘲笑うように現れたのは、今まさにこの言葉を書いているときだ。私のいとこや義理の両親、そして私の知っているかわいい子供たちに何が起こるのか、恐怖で胸が張り裂けそうだ。欧米諸国から見れば、入植植民地国家の国民である私の方が、包囲された難民である私の親族や愛する人たちよりも人間的価値があるというのだろうか?罪悪感が影を落とし、胸が締め付けられ、心臓が高鳴り、涙がこぼれる。また始まった。トラウマだ。贅沢な亡命生活の中で、私にトラウマを主張する権利があるのだろうか?
トラウマ・ジャンル」からのナクバの不在
私が博士課程で研究をしていたとき23、「亡命におけるトラウマ」という問いが私の頭の中にあった。亡命パレスチナ人である私たち、なかにはパレスチナに住んだことのない者もいるのだが、この集団的トラウマの苦悩をどのように受け継いでいるのだろうか。そしてこのトラウマは、私たちのパレスチナ人としてのアイデンティティの理解や、私たちのアドボカシーの緊急性にどれほど寄与しているのだろうか?
私が博士課程での研究を始めてからわずか数カ月で、驚くべき、しかし驚くべき発見をすることができた。パレスチナの歴史上最も重要なトラウマ的出来事である、1948年のナクバ(ナクバとは文字通り「大惨事」を意味する)のパレスチナ人による権利の剥奪とトラウマの経験は、「トラウマ・ジャンル」からは欠落しているのだ。事実、ローズマリー・サイイ(Rosemary Sayigh)の調査24によれば、戦争と集団的トラウマに関する最も引用数の多い文献には、ナクバや現在進行中のパレスチナ人のトラウマ体験に関する記述が一切ないことが確認されている。Sayighによれば、「トラウマというジャンル」の理論的概念化は1990年代初頭にピークを迎え、Caruth25、Felman26、Felman and Laub27といった理論家たちによる研究が行われた。そして、「トラウマというジャンル」は、何が苦しみで何が苦しみでないか、ひいては誰が苦しみで誰が苦しみでないかという「文化的参照枠」を設定するのか、という疑問を提起する。彼女は、欧米の学術研究において「トラウマのジャンル」の中にナクバが「明白に欠落」しているのは、「パレスチナ人の正義に対する主張が疎外されている」ことを反映すると同時に、それを強化する現象であると指摘し、「トラウマのジャンル」からパレスチナ人の苦しみが排除されているのは、パレスチナとパレスチナ人に関わる多くの側面に見られる政治的・文化的近視眼の一部であるという考え方を強調している。この近視眼は、パレスチナ人とアラブ人に対するオリエンタリズム的、植民地主義的な表象によって実質的に構築され、あるいは可能にされている。
事実、西洋の権力構造、とりわけ西洋の学界は、パレスチナ人に対する暴力に大きな役割を果たしてきた。このことは、パレスチナの象徴である故エドワード・サイードの著作を読めば明らかである28。ポストコロニアル研究の基礎となる1978年の著書『オリエンタリズム』において、エドワード・サイードは、アメリカやヨーロッパからもたらされた初期の学術的著作は、東洋のステレオタイプ的で不正確な描写の提示によって誤解を招き、それが東洋の文化の真の理解を妨げ、またその資源の搾取を可能にしていると主張した。サイードは、このようなステレオタイプは西洋にとって意図的かつ不可欠なものであり、植民地支配を合理化するだけでなく、救済し、文明化し、文化化する必要のある東洋の世界像を描くことで、植民地支配を事前に正当化する手段としても機能していると指摘した。
サイードがオリエンタリズム論を執筆したきっかけは、アラブ・イスラエル戦争に関する西側メディアの報道と、パレスチナ系アメリカ人としての彼自身の個人的な生活と経験だった。1998年のビデオインタビュー29で彼は、ほとんどの学術書におけるアラブ人・パレスチナ人の表象と、パレスチナ人・アラブ人としての自身の生活体験との間に大きな乖離があることを語っている。このような表象は、停滞し発展しない地域、時が止まったまま 「歴史の外にある」アラブ世界という固定したイメージを作り出している。それは、その地域で育ったアラブ人である彼には認識できない世界であったが、ヨーロッパにとって対立的な「他者」を創造するために必要な世界像を投影したのである。
サイードはオリエンタリズムを、西洋に焦点を当てた特定の視点からのオリエントに関する研究と著作であり、客観的な知識であるかのように装っているが、植民地/帝国的利益を促進するための人種的優越性の言説を支持し、維持しようとする衝動に大きく突き動かされているものと定義している。例えば、サイードによれば、アメリカのオリエンタリズムは、中東の石油資源に対するアメリカの利益を支持し、同盟国イスラエルを支持するために、イデオロギー主導で高度に政治化されている。
オリエンタリズムのレンズを通してパレスチナ人を見ることは、パレスチナとイスラエルの紛争の背景を理解することを不可能にする。残念ながら、この視点はいまだに根強く残っており、ナクバと同じくらい重要な出来事が、西洋の学問の「トラウマ・ジャンル」から消えてしまうことを許している。
「道徳的共同体」の外で育つ
このような消失、消去がいかにして可能なのかを理解しようとするとき、サイイは2つの理論的枠組みを提案する: ひとつは、パレスチナの苦しみは文学者デイヴィッド・モリスの言う。「道徳的共同体」の外にあるということだ。モリスは30、哲学者トム・リーガンの 「道徳的共同体」という言葉31を基に、作家がしばしば文化や歴史によって決められた排他的な社会的パラメータの中で仕事をする方法を説明する。こうしたパラメータには、定義された。「道徳的共同体」から外れるとみなされる他者の苦しみの物語は含まれないことが多い。イスラエルのロビー団体は、何十年もの間、西側世界の 「道徳的共同体」の門番として機能してきた。イスラエルの過去から現在に至る犯罪を正当化するために、パレスチナ人は世界の 「道徳的共同体」から外れていると見なされる必要があった。
パレスチナ人の物語を広く一般に紹介しようとするたびに、私はこのことを身をもって体験してきた。2016年、イスラエルのロビー団体B’nai B’rithが、私の戯曲『海辺の街の物語』をビクトリア州教育修了証(VCE)の演劇プレイリストから削除するキャンペーンをドヴィール・アブラモヴィッチ率いる指揮官によって開始したとき、攻撃は最も厳しかった。彼らの強引なやり方は、ビクトリア州議会の予算公聴会を中断させ、野党が政府に要求を突きつけた。ビクトリア州議会の野党は、VCEのカリキュラムに「反イスラエル」劇32が含まれていると主張し、実際に「予算公聴会を政府攻撃のために利用した」のである。そのため、ガザを舞台にしたパレスチナ人のラブストーリーという私のささやかな自主制作演劇は、ビクトリア州議会で審議される数少ない自主制作演劇のひとつとなった。
この論争が激化している間、主流メディアはシオニスト・ロビーに簡単に発言権を与えたが、私を講演に招こうとは考えなかった。この出来事もまた、大きな苦悩と不公正の物語であったかもしれない。しかし実際には、時代が変わりつつあることを示す、前向きな物語となった。初めて、このパレスチナ人作家は一人で戦う必要がなくなったのだ。オーストラリアの演劇人、アーティスト、作家、友人たちが、私の作品と、イスラエルのフィルターを通して承認されることなく、私の民族についての物語を語る権利を擁護するために声を上げてくれたのだ。「検閲」という言葉は、シオニスト・ロビーが作り出した圧力を表現する際に多くの人が使った言葉だった。この劇はVCEのカリキュラムに残り、ビクトリア・ドラマ・アワードを2つ受賞した。壮大で勇敢なラ・ママ・シアターは「論争」にも動じることなく、圧倒的な支持を得た。『テイルズ・オブ・ア・シティ・バイ・ザ・シー』は、毎晩のスタンディング・オベーションで全シーズンを完売させ、その後、国内外ツアーに出た。この原稿を書いている時点で、この作品は世界中で100回以上上演され、世界中で何千人もの学生が学んでいる。
私は『エイジ』紙に掲載されたオピニオン・ピースで、私に向けられた誤った非難に最終的に反論した。問題は、パレスチナ人を人間化していることだ。どうやら一部の人々にとっては、これは手に負えないことのようだ」33。
取り返しのつかない」集団としてのパレスチナ人
サイイによれば、「トラウマのジャンル」からナクバが消去され、欠落していることを説明する第二の枠組みは、ジュディス・バトラーの考え方に見出すことができる。「認識のレベルで制定され、活動的である人種差別(の形態)は、非常に悲嘆にくれる集団と、喪失が喪失ではなく、悲嘆にくれることのない集団を象徴的に作り出す傾向がある」34。
私たちはいつもこのような光景を目にしている: イスラエルの戦争で瓦礫の下から引きずり出されたパレスチナの子どもたちは名前がなく、その物語はほとんど語られない。西側のメディアや学者の目には、パレスチナ人は「道徳的共同体」から外れた「悲しむに悲しまれない」人々として映っている。
私は10代の14歳の私を振り返る。彼女は「フリー・パレスチナ」のプラカードを掲げ、1982年にメルボルン・シティ広場で行われたサブラとシャティーラの虐殺に抗議していた。彼女は、パレスチナ人が、「ungrievable」とみなされていることを発見するために博士課程で研究をする必要はなかった。『エイジ』紙の一面に掲載された、名もなきパレスチナ人の死体や、ストーリーのない肥大化した死体を見て、彼女はそれを実感した。パレスチナの 「テロリスト」やイスラエルの自衛権に言及した社説を読めば、それがわかる。イスラエルの 「専門家」を招いて 「紛争」を説明させるニュースキャスターの声からも、それが読み取れた。彼女はそれを知っていた。それが彼女の人生だった。過去に戻って、彼女に腕を回し、「きっと変わるよ」と言ってやりたいものだ。彼女はただ我慢する必要があるのだ。
パレスチナの 「亡命地」における 「後見人」
シモーヌ・ワイルは、根を張ることは「人間の魂の最も重要で、最も認識されていない欲求」であると書いている35。ワイルは、私たちは場所、コミュニティ、文化、歴史に属することによって根を張るのであり、それは「過去の特定の宝物と未来への特定の期待を生きた形で保存する」のだと説明している。このような保存のプロセスは、人々が土地を奪われ、根絶やしにされたとき、しばしば最初の犠牲となる。保存を復活させることは、土地を奪われた人々が生き延びるために必要なことであると同時に、新たな根を植える過程にとっては障害となる。亡命者の心は、「苦境にある祖国へと否応なしに向けられ、たまたま住んでいる土地への友情のために残された感情的資源はほとんどない」とヴァイルは主張する。
エドワード・サイードは、「流浪の環境」におけるパレスチナのナショナル・アイデンティティの形成と滋養について書いている36。彼は流浪を「嫉妬深い状態」、「疎遠」と「疎外」の状態であり、「誇張された集団の連帯感」と「部外者に対する情熱的な敵意」を確立するためにその存在を守っている、と述べている(2001年、141ページ)。パレスチナ人であることを受け入れることは義務であり、意識的な政治的決断であり、家族としての義務であり、イスラエルの占領下にある愛する人々との最低限の連帯のジェスチャーであることを、私は成長する過程で学んだ。
しかし、パレスチナ人であることは「意識的な決断」であり、「政治的な」選択であるかもしれないが、私も含め、祖国以外の大多数のパレスチナ人にとって、パレスチナ人であることは、決断というよりも、むしろ私たちが実際に何者であるかを反映したものであるに過ぎない、と私は主張したい。パレスチナの母親たちは、パレスチナでの成長物語を語りながら、完璧なマクルバを作ることに労を惜しまない。彼女たちは自分の一部を共有し、過去を明らかにし、過去の世代から受け継いだ知識の宝庫を伝えているのだ。私の姉妹が結婚したとき、母はシオニストに恨みを買うためにパレスチナ人の結婚式を挙げることを主張したり、イスラエルを地図から消し去るためにパレスチナの自宅でスズカケノキと同じくらい古い歌を歌うことを主張したりはしなかった。彼女は自分の知っているやり方で祝うことにこだわった。これが彼女の現実だ。彼女の世界だ。彼女の記憶だ。そして彼女はパレスチナ人なのだ。私がオーストラリアのブロードメドウズにあるパレスチナ・アラビア・クラブのダブケ・ダンス・グループに参加したのは、10代前半の頃、エドワード・サイードの亡命論を読み、ダンスを通じて「亡命の環境」の中で自分の民族的アイデンティティを養おうと思ったからではない。同じ趣味を持ち、私のような家庭で育った気持ちを理解してくれる人たちと交流するためだった。つまり、祖国の外にいるパレスチナ人家族は、パレスチナ人としてのアイデンティティを政治的な選択としてではなく、むしろ私たちが何者であるかの不可避な一部として捉えているのだ。パレスチナ人のアイデンティティを政治化するのは、私たちがパレスチナ人であることを認識する権利を否定することだと私は思う。
シオニストはしばしば、パレスチナ人のアイデンティティはシオニズムを破壊するためだけに構築されたフィクションであると主張してきた。イスラエルの第4代首相ゴルダ・メイルは、「パレスチナにパレスチナ人がいて、われわれがやってきて彼らを追い出し、彼らの国を奪ったというようなことはない。より最近では、オーストラリア・シオニスト連盟の広報部長であるテッド・ラプキン38が、パレスチナ人であることについて私がABCに掲載した記事に対して、次のような返答を書いている: 「無から有へのパレスチナ人の構築は、生きている外交の記憶の中で、事実に対する寓話の最も顕著な勝利を構成している。
これが、私が育った環境であり、私のハイフンで繋がれたアイデンティティに関する言説である。高校時代の地図にパレスチナはなかった。レストランのメニューにパレスチナ料理はなかった。テレビの番組や映画には、パレスチナ人の声も登場人物もいなかった。パレスチナ人についての言及はなく、イスラエルを破壊しようとするアラブのテロリストが時々登場するのみだった。パレスチナが存在するのは、私たちの家庭、食卓、そしてコミュニティーの中だけだった。
消去された空白にパレスチナを書き込む
私たちパレスチナ人が、誇り高きアイデンティティと激しい抵抗によって、消去された空白をどのように埋めてきたかは、実に驚くべきことである。祖母のミシン、祖父の古いレコードプレーヤー、家宝、本や歴史的資料で埋め尽くされた図書館など、自分たちの物語を語る思い出の品々で家が埋め尽くされていた家族とは異なり、私はこれらすべてを奪われた世代に属している。私は、両親がシャツ一枚で亡命したパレスチナ人に属している。その結果、私たちは、モノの存在を通してではなく、むしろモノの不在を通して記憶を再構築する達人になった。亡命後、私はサウジアラビアという、砂丘がどこまでも続く砂漠の国で、両親がパレスチナに残してきたものを描写した物語や詩を聞きながら、記憶された人生の最初の10年を過ごした。これらの物語や詩は、私の想像力を刺激し、私が住んでいた場所ではなく、記憶にある場所への憧れを抱かせた。私が知っている場所だ。私が構築した「記憶」の中で最も鮮明なのは、パレスチナの我が家の庭だ。両親は、ザクロの木、ジャスミンの茂み、甘い実をつけるとげとげのサボテン、スズカケノキ、菜園……何も生えていないサウジアラビアの砂漠の街を背景に、とても美しく色彩にあふれた生活のことを話してくれた。しかし、この厳しいコントラストは、亡命の痛み、中断された生活、根こそぎ奪われた家族、高い塀の向こうに閉じ込められたままの祖父母のトラウマに拍車をかけるだけだった。忘れるという選択肢はない。思い出すことによってのみ、私たちの人生は生きる価値がある。
愛する人たちが爆弾にさらされ、包囲され、占領されている間は、私たちは前に進むことができない。だから私たちはそうしない。そして、それを子供たちに引き継ぐのだ。この祝福と呪いを。そして、子どもたちはそれを受け継ぐ。私たちは歌や物語や詩を通してパレスチナの守護神を伝え、パレスチナ人の世代が消去された空白を埋めていくことを知っている。私たちは2021年5月の統一インティファーダでこれを目の当たりにした。亡命先で生まれ育った世界中の若い世代のパレスチナ人が、団結と連帯、そして抵抗を呼びかける抗議行動を率いたのだ。私のWhatsAppの通知は一気に増え、重要なことを行っている活動家たちの輪の中で、私が最年長の一人であることを知ったとき、私の胸は誇りでいっぱいになった。彼らのほとんどは20代から30代で、祖国の外で生まれ育った。これが「エグザイル世代」であり、彼らは自分たちの物語を、消去された空白のスペースに猛烈な勢いで書き込んでいる。数十年前、私がそうであったように、「川から海へ、パレスチナは自由になる」と彼らが唱えるのを、私は今でも耳にすることができる。このような不滅の希望と決意は、決して打ち負かされることはない。
進むべき道
1900年代初頭までに、シオニズム運動は「土地なき民のための土地なき民」というスローガンを採用した40。このような、土地を見て民を見ないという顕著な能力は、帝国戦争や征服の歴史において見慣れないものではない。実際、オーストラリアでは、「誰のものでもない土地」を意味する「Terra Nullius」という似たようなフレーズが、イギリスによる先住民アボリジニの侵略と収奪を正当化するために使われていた41。
真実を語り、過去の残虐行為や悪行を認めることは、和解のための基礎となるブロックであり、私は自分のアイデンティティ、パレスチナ人とオーストラリア人の自分を和解させる必要がある。私はこの土地の先住民の声に耳を傾けながら、パレスチナ人とイスラエル人が平和に共存できる未来を想像することができる。というのも、平和は不正義や過去の犯罪の否定の上に成り立つものではないからだ。まず、アパルトヘイトと抑圧の構造を完全に崩壊させ、真実を語り、和解するという次の段階に進む必要がある。
アパルトヘイト後の南アフリカの真実和解委員会の元委員長であるデズモンド・ツツ大主教は、赦しのプロセスには「加害者側が犯罪を犯したことを認めることが必要だ」と指摘している42。
しかし、イスラエルは何ら認めることなく、説明責任を果たすことなく、さらなる差別、抑圧、人権侵害、民族浄化、アパルトヘイトの道を歩み続けている。だからこそ、ボイコット・ディベストメント・制裁運動は必要な抵抗手段なのだ。南アフリカと同様、イスラエルもまた、民族浄化とアパルトヘイトという犯罪を止めるよう、国際社会の圧力を感じる必要がある。イスラエル人は、自分たちがパレスチナの全土を植民地化していること、そしてこの植民地化を終わらせる必要があることを認識しなければならない。倫理的な脱植民地化こそが、パレスチナの全土に世俗的な民主国家を建設し、自由と正義と平等の時代を切り開く唯一の道なのだ。
私としては、私たちは皆、自分の得意技を使って抵抗するのだと信じている。私のは書くことだ。だから、私は書き続ける。私は名もなき人々の名前を書き、意図的に語られない物語を語る。シオニストによる抹殺に対抗するために書くが、その一方で、祖国が植民地化され、植民地化された土地に住む亡命者としての特権を意識する。私は、ここオーストラリアとパレスチナの私たちの闘いはひとつであることを自覚しながら書いている。私がこの大地に平和を見出すためには、その歴史と先住民に対する暴力の真実に心を開かなければならない。私は、パレスチナの不治の病に冒された希望を胸に、この文章を書いている。そして、「川から海へ、パレスチナは自由になる!」と声を合わせて唱える、世界中のパレスチナの若者たちのエネルギーで、地面がうねり出すのを感じる。
23 Samah Sabawi, Inheriting Exile: Inheriting Exile: Transgenerational Trauma and Palestinian-Australian Identity, Ph.D. thesis, Victoria University, 2020.
24 Rosemary Sayigh, ”On the exclusion of the Palestinian Nakba from the ‘Trauma Genre’.”. Journal of Palestine Studies (2013) 43(1), 51-60.
25 Cathy Caruth, Unclaimed Experience: Trauma and the possibility of history (Baltimore, John Hopkins University Press, 1991).
26 Shoshana Felman, 「In an era of testimony: Claude Lanzmann’s Shoah,」 Yale French Studies 79 (1991), 39-81.
27 Shoshana Felman and Dori Laub, Testimony: 文学、精神分析、歴史における目撃の危機」(ニューヨーク/ロンドン:ラウトレッジ、1992)。
28 エドワード・W・サイード『オリエンタリズム』(ニューヨーク:パンテオン・ブックス、1978)。
29 Edward W. Said, 「Edward Said on Orientalism,」 interview by Sut ジャーlly, University of Massachusetts-Amherst, 1998.
30 David B. Morris, ”About Suffering: Voice, Genre, and Moral Community,” Daedalus 125, no.1 (1996): 25-45. 2021年 7月 7日、http://www.jstor.org/stable/20027352にアクセス。
31 トム・リーガン『スリー・ジェネレーション』: Reflections on the coming revolution (Philadelphia: Temple University Press, 1991).
32 ステファニー・アンダーソン「VCEカリキュラムの『反イスラエル』劇が政府への攻撃を促す」ABCNews, May 10, 2016, www.abc.net.au/news/2016-05-10/anti-israel-play-in-vce-curriculum-government-questioned/7402176
33 Samah Sabawi, ”Vision of everyday life in Palestine too bleak for some,” The Sydney Morning Herald, June 2, 2016, www.smh.com.au/opinion/vision-of-everyday-life-in-palestine-too-bleak-for-some-20160602-gp9tmc.html
34 Judith P. Butler, Frames of War: When is life grievable? (ニューヨーク:Verso 2009)。
35 S. Weil, The Need for Roots: 人類に対する義務宣言への前奏曲(A.Wills, Trans.) (New York and London: Routledge, 1952)。
36 Edward W. Said, Reflections on Exile: And Other Literary and Cultural Essays (London: Granta Books, 2001)。
37 Judd Yadid, ”Israel’s Iron Lady Unfiltered: 17 Golda Meir quotes on her 117th birthday: the wise, the whimsical an the downright polemical,” Haaretz, May 3, 2015, www.haaretz.com/.premium-17-golda-meir-quotes-on-her-117th-birthday-1.5356683
38 Ted Lapkin, ”Palestinian national identity and the roadblock to peace,” Opinion, Australian Broadcasting Corporation, September 3, 2015, …www.abc.net.au/news/2015-08-28/lapkin-palestinian-national-identity-and-the-roadblock-to-peace/67324
39 I. Nassar, ”Remapping Palestine and the Palestinians: Decolonizing and research,” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East (2003) 23 (1-2), 149-151.
40 Edward W. Said, The Question of Palestine (New York: Vintage, 1992).
41 Henry Reynolds, The Other Side of the Frontier: The Other Side of Frontier: Aboriginal resistance to European invasion of Australia (University of New South Wales Press, 1981).
42 Desmond Tutu, The Forgiveness Project, www.theforgivenessproject.com/desmond-tutu.
第2部
抵抗のさまざまな顔
マヌエル・ムサラム神父はカトリック司祭、政治活動家、作家である。母国パレスチナの象徴的存在である。1938年、ヨルダン川西岸中央部のビルジートで生まれたムサラムは、哲学と神学を学び、1963年に司祭となった。1960年代にはヨルダンのザルカやアンジャラ、1970-1975年にはパレスチナのジェニン、1975-1995年にはザバブデ、そして1995-2009年にはガザで司祭を務めた。ムサラム神父は、パレスチナのキリスト教部門 2002年のイスラエル戦犯を追及するパレスチナ独立委員会、ガザのイスラム・キリスト教フォーラムの議長を務め、様々な平和維持活動を行い、最終的に2006年にカトリックのモンシニョールの称号を得た。ムサラム神父は2009年に生まれ故郷のビルジートに引退した。ムサラム神父の熱心なパレスチナ擁護活動は、今日まで続いている。
抵抗する者は幸いである
解放のためのキリスト教的ビジョン1
マヌエル・ムサラム神父
英国委任統治によってパレスチナに降り注いだ隕石嵐は、私たちの聖地の神聖なものすべてを焼き尽くした。最も神聖な空間である教会やモスクが焼かれた。最も神聖な木であるオリーブの木が燃やされた。白燐が私たちの町、村、難民キャンプを襲った。最も神聖な生き物である人間が焼かれた。人間の中で最も神聖な子どもたちが焼かれた。自分たちの土地と民族から引き離されたパレスチナ・アラブ人の尊厳そのものが焼かれた。真実と正義もまた、この土地が地球の果てから来た人々には「約束」されたはずなのに、自分たちの住民には約束されなかったことで焼かれたのだ。実際、イスラエル軍と武装したユダヤ人入植者たちがオオカミのように私たちを捕食したとき、私たちの人間性そのものが焼かれたのだ。
ハガナ、イルグン、シュテルン団、パルマッハが私たちの土地を武力で占領し、私たちの民衆を虐殺し、私たちの畑や果樹園や家を焼き払った。彼らはできる限り多くの同胞を取り壊し、殺し、追放した。国連は加害者を罰する代わりに、当時土地の7%しか所有していなかった侵略者たちにパレスチナの56%を提供し、わずかな残りを私たちに残した。私たちは拒否した。拒否せざるを得なかった。シオニストの指導者たちは衝突した。ダヴィド・ベン・グリオンはこの申し出を受け入れたが、一方、メナケム・ベギンは、トランスヨルダンを含むパレスチナ全土は永遠にユダヤ民族のものだと主張し、分割は無効だと宣言した3。
最終的にイスラエルは、破壊された祖国の廃墟の上に建国された4。私たちの財産は「不在者」の財産とされ、新国家によって不法に横領された。追放され、故郷を追われたパレスチナ難民は、国際法に明記されているにもかかわらず、今日に至るまで帰還の権利を否定されている。私たちの村の大半は完全に、あるいは部分的に破壊された。何十万人ものパレスチナ人農民が作物を救い出すことさえ許されなかったため、その季節の収穫は収穫されないまま残された。私たちの町や村の代わりに、新しいユダヤ人入植地や町がすぐに出現した。
ナクバは私たちに襲いかかり、私たちの歴史上、他に類を見ない破滅的な出来事となった。イスラエルとの闘いが始まり、今日まで続いている。私たちパレスチナ人にとって、それは生か死か、生存か消滅かの闘いである。それは平和のための闘いですらなく、われわれの文明と存在を維持するための闘いであり、われわれの民族の神聖さ、人間性、そして正義に対する侵すことのできない権利のための闘いなのだ。
私の物語
私は、シオニストがもたらした混乱の中で生まれた。私は極度の貧困、本当の飢餓、あらゆる種類の収奪に囲まれていた。しかし、私は闘争や困っている人々に惜しみなく与える家族のもとに生まれた。我が家のオリーブの木、ブドウ畑、イチジクの木も気前がよく、多くの家族がそうできなかったときに、私の家族が尊厳を保つのを助けてくれた。私は幼い頃から、勇気、忍耐、粘り強さ、勤勉さ、寛大さ、そして反抗心を母乳で育てられた。母と父は、あらゆる場面で私たち国民を待ち受けていた屈辱に立ち向かえるよう、私を育ててくれた。そう、私は苦難の中に生まれたが、その苦難が私に頑固に抵抗することを教えてくれたのだ。
1943年、エルサレムで戦争についての映画を見たとき、私はまだ5歳だったことを覚えている。映画の中で私は、兵士たちが軍用車両から飛び降りたり、塹壕に隠れたりするのを見た。大砲が爆発する音も聞こえた。このような暴力は初めての経験だった。怖かった。私は目を閉じ、やがて叔父のヤクブの腕の中で眠りについた。それは実際の戦争ではなく、その頃ヨーロッパで起こっていた出来事を描いたものだった。しかし、この映画は私の心に戦争の最初の種を植え付けた。しかし、1948年の戦争は違った。
パレスチナに対するシオニストの戦争はあまりにも現実的だった。子どもたちでさえ、私たちが体験した恐怖から目をそらすことはできなかった。私の住むビルジートには難民が押し寄せ、デイル・ヤシン、キビア、カフル・カシムといった恐ろしい虐殺の話を持ち込んできた。パレスチナ人最高司令官アブド=アル=カディール・アル=フサイニの殉教の知らせが届くと、町全体が荒廃した5。
アル=フサイニの死は、まだ10歳だった私に大きな爪痕を残した。しかし、恐ろしいニュースはそれで終わりではなかった。それは、絶えることのない数々の悲劇の始まりに過ぎなかった。
1967年、エルサレム全土が侵略者の手に落ちたとき、私は壁に頭を打ち付けたことを覚えている。この絶望感は、私の人生の多くを決定づけた。祖国の悲劇は、私の中に多くの感情を呼び覚ました。それは私を震撼させ、今も私の根底を揺さぶり続けている。しかし、私は絶望が私を規定することを許さなかった。私は姿勢を貫かなければならなかった。パレスチナの祖国で、そして時には祖国を離れても、多くのパレスチナ人が追いかけてくるように、数多くの暴力のイメージが私についてきた。1967年、ヨルダンのアジュルーンにあるフェダイーンと陸軍基地の近くにイスラエル軍の爆弾が落ちるのを見たことを覚えている。私が小教区の修道女たちに助けを求めようと駆け寄ると、修道女たちはひざまずいて恐怖のあまり泣いていた。周囲にはミサイルが落ち始めた。ほんの数メートル先では、木々に火がつけられていた。近くの果樹園は完全に消滅していた。その日、私たちも死にかけた。
犠牲者は違えど、同じような経験は、1987年の第一次蜂起、インティファーダ、そして2000年の第二次インティファーダの間、ずっと私に付きまとった。この2つの民衆蜂起の間、私はキリスト教徒であるパレスチナの指導者として、誇りをもって自国民を守る役割を果たした。
ガザに住む何百万人ものパレスチナ人と同じように、私は2008年から2009年にかけての戦争と虐殺の恐怖に苦しんだが、不正義に対して声を上げることを決して止めなかった。私はイスラエル軍のミサイルの破片を十字架に変えた。私の闘い、私の痛み、そして私の抵抗は、他の何ものにも代えがたい私のアイデンティティーの拠り所となった:
私はパレスチナ系アラブ人クリスチャンなのだ。私はパレスチナ系アラブ人クリスチャンなのだ。私は、私の聖なる故郷の解放のために、パレスチナの他の抵抗者たちとともに闘う。私は、私の教会の神学に由来する宗教的な立場から抵抗し、この神学に強い信念を持っている。私はまた、シオニストという存在が、宗教的な衣をまとって、政治的・経済的利益を内蔵したハイブリッド型の植民地征服であるという政治的現実も十分に理解している。したがって、パレスチナ系アラブ人として、私は愛国的立場からも抵抗する。私の愛国心は、同胞の貧困、痛み、屈辱、そしてディアスポラによって強化される。これは私の物語であり、私の家族の物語であり、私の民族の物語である。
「約束の地」の神学
クリスチャンとして、とりわけパレスチナのクリスチャンとして、私はパレスチナが私の民族を犠牲にしてユダヤ人に約束されたという考え方を拒否する。1951年から1963年まで、私はパレスチナのベイトジャラにあるラテン総主教神学校で哲学、神学、聖典を学んだ。これらの聖典を読み解く中で、シオニスト運動がいかに聖書のカ所を操作して、私の祖国に対する宗教的主張を展開したかを理解し始めた。最も多く解釈された、あるいは誤って解釈された聖句のひとつは、申命記14章2,6節である。地上のすべての民のうちから、主はあなたがたを選んで、その宝とされたのである」このわずかな言葉から、ユダヤ民族は約束の地の「選ばれた」「聖なる」「永遠の」民であるという観念が生まれた。彼らにとってこれは、疎外され、土地を奪われた同胞の運命が永遠に封印されることを意味していた。
キリスト教の出現により、使徒パウロはガラテヤ3:167で、神の約束はアブラハムとその子孫に向けられたものであることを明らかにし、単数形に注意を喚起したにもかかわらず、この考えは根強く残っている: 聖書は、多くの人を意味する。「種に」と言っているのではなく、キリストである一人の人を意味する。「あなたの種に」と言っているのです」パウロはローマ9:6-9,8で詳しく述べている。イスラエルの子孫である者がすべてイスラエルであるわけではない。また、その子孫だからといって、すべてがアブラハムの子というわけでもない。それどころか、あなたがたの子孫はイサクによって計算されるのである。”
これだけでは十分でないかのように、アウグスティヌスは『聖アウグスティヌス書簡196』9の中で、「教会は、神がイスラエルになさった約束を受け継ぐ者である。したがって、教会は天のエルサレムに到達しようと切望する新しいイスラエルなのである。” このように、歴史的なキリスト教の教義は、約束の地はユダヤ人だけのものではなく、神の約束の子たち、つまりアブラハムの信仰を信じる者たちのものであることを明らかにしてきた。
中世のある時期から、様々な教会が千年王国主義に関心を持つようになった。黙示録に端を発し、キリストが地上に再臨し、審判の日まで千年間そこに留まるという信仰である。これらの預言は、ヨハネの黙示録20:1-3,10を中心としたものである。”そして、私は、天使が天から下ってきて、奈落の鍵を持っており、手に大きな鎖を持っているのを見た。
7世紀には、これらの預言は政治的な性質を帯びるようになり、何世紀も経ってから、まったく別のものに変化した。これが、今日のユダヤ人のパレスチナ帰還という概念の起源であり、キリスト教原理主義者、ひいてはシオニスト・クリスチャンによって長い間支持されてきた。彼らにとって、ユダヤ人はイエスご自身の再臨の前提条件として帰還しなければならなかった。この予言は、さらに不吉な解釈へとつながっていった。キリスト教原理主義者の思想によれば、帰還したイエスは悪の勢力との戦争を指揮し、その戦争で全ユダヤ人の3分の2が滅び、残りの3分の1がキリスト教に改宗する。そうして初めて、キリストは1000年間、王として世界を支配することができるのだ。
政治家たちはこのメシア的概念を利用した。1655年には早くも、イギリスのオリバー・クロムウェル将軍がキリスト教原理主義とイギリスの戦略的利益との間に関連性を見出した11。この関連性はその後も続き、やがて1917年11月のバルフォア宣言へとつながっていく。同宣言は、「陛下の政府は、パレスチナにユダヤ民族のための民族的故郷を建設することを好意的に受け止めており、この目的の達成を容易にするために最善の努力を払う」と主張している12。
政治と千年王国主義が共通の基盤を見出していたにもかかわらず、カトリック教会は、聖地の地位に関する危険な前例と見なされるものを受け入れることを拒否した。非公式ではあったが、カトリック教会は1897年5月の時点で、キリスト教シオニズムに対する立場を表明していた。奇しくもこの年、シオニズム運動の指導者セオドア・ヘルツルがスイスのバーゼルで第1回シオニスト会議を開催した。この立場は、その機関紙『ラ・チヴィルタ・カトリカ』13が掲載した記事の中で明確にされた。その中で、「イスラエル国家の再構成の中心地としてエルサレムを再建することは、エルサレムが、『異邦人の時代が成就するまで、異邦人に踏み荒らされるであろう』と告げたキリスト自身の預言と矛盾する」と主張した。
バルフォア宣言を受けて、カトリックの立場はより明確になった。さらに1944年、教義修道会は千年王国説の明確な否定を発表し、教会の時代から世の終わりまでの1000年間は存在しないと宣言した15。
パレスチナが意味するもの
しかし、パレスチナ人、キリスト教徒、イスラム教徒である私たちは、政治的に操作された神の言葉に縛られることはない。私たちにとって、これは奪われた土地と奪われた人々の問題なのだ。パレスチナは、子を奪われた私たちの母であり、私たちは母の優しさを奪われている。私たちパレスチナの人々はひとつである。我々は一つの文明に属し、一つの運命によって結ばれている。私にとって、アル・アクサはキリスト教徒であり、復活はムスリムの兄弟姉妹に等しく属している。殉教したムスリムはみな殉教したキリスト者であり、殉教したキリスト者はみなムスリムである。私たちの若者は、同じイスラエルの占領者によって殺されている。私たちの家は、同じイスラエル軍のブルドーザーによって取り壊されている。私たちの土地は盗まれ、聖なる神社は汚され、家族は引き離され、人々は同じイスラエルの加害者によって民族浄化される。
シオニストはしばしば、パレスチナ・アラブ人は決してまとまった民族ではなかったと主張する。このような詐欺的な主張は、パレスチナが何もない土地であるかのように世界を欺くためのものだ。しかし、1947年から48年にかけてのナクバで破壊された500の町や村は、この土地に人が住んでいたことの証である16。私たちの民族が奪われたにもかかわらず、私たちの言語、アイデンティティ、文化が存続していることは、私たちが歴史と精神性に根ざしたパレスチナ民族以外の何者でもないという主張をすべて否定するものである。バラとその香水がひとつであるように、大地と人々はひとつなのだ。
しかし、地球と人々が再び一つになるために、バラが再びその香りを得るために、私たちパレスチナ人は、キリスト教徒もイスラム教徒も、抵抗を続けなければならない。クリスチャンである私にとって、抵抗はイスラム教徒と同様に義務である。神は私に「敵を愛せよ」17と命じておられるが、同時に私の敵にも「殺してはならない」18と命じておられる。神は私に「あなたの衣服を求める者には、あなたの衣服を与えよ」と教えておられるが、同時に私の敵にも「盗んではならない」「他人の所有物を欲しがってはならない」19と命じておられる。
歴史と聖書の研究者として、私は正義は与えられるものではなく、奪われるものだと信じている。歴史と聖書を学ぶ者として、私は、正義は与えられるものではなく、奪われるものだと信じている。奪われた土地の回復、難民の帰還の権利、すべてのパレスチナ人の自由など、わが民族にとっての正義は、イスラエルの無条件の存続と安全に優先しなければならない。イスラエルの立場は自衛ではない。イスラエルは、パレスチナの軍事占領を守っているだけなのだ。我々をテロだと非難する人々は、我々が反撃するのは都市を占領するためではなく、占領者から解放するためであることを思い出さなければならない。私たちはこの土地の歴史的管理者であり、正義と歴史、パレスチナの文明と遺産の保持者なのだ。イスラエルは飽くなき植民地欲に導かれているが、私たちは愛と真実と自由に導かれている。
パレスチナのキリスト教徒であるアラブ人として、私は自分自身と同胞にふりかかる不公正を感じている。しかし、不公正によって絶望の淵に立たされることなく、同胞の権利のために戦う決意を固め、いつの日か同胞が亡命先から帰還できるようにしたい。私たちは、子どもたちがイスラエルの刑務所から解放されることを望んでいる。彼らの未来を築き、最終的には強力な経済を発展させたい。
私は自分のためではなく、地球のため、民族のため、国家のため、聖なる都市のため、そして信仰のために抵抗する。パレスチナの鼓動する心臓であり、その集団的アイデンティティの真の表現であり、その記憶の貯蔵庫であるエルサレムの土壌なくして、正義が真に達成されることはない。私たちパレスチナ人、キリスト教徒、イスラム教徒は、ユダヤ人やユダヤ教に反対しているのではない。むしろ私たちは、シオニズム、植民地主義、キリスト教原理主義、そしてあらゆる形態の不正義の敵であることを公言している。イスラエルは私たちの民族を大量殺人、容赦ない窃盗、強制移住の対象としてきた。彼らは私たちのモスク、教会、家、そして子どもたちまでも焼き払った。これがイスラエルに抵抗する理由だ。もし我々が抵抗しなければ、我々の生得権、我々の文明、我々の遺産、我々の聖地エルサレム、我々の民族が耐えてきた痛み、つまり我々の神聖さそのものを売ることになる。
イスラエルは私たちの心から喜びを奪った。喜びとは平和である。平和とは安定であり、秩序であり、正義である。これらすべての価値が欠落すれば、法もまた欠落する。法がなければ、私たちは怪物の時代に突入する。私たちパレスチナ人は、日々こうした怪物と戦っている。いつの日か私たちの土地を解放し、喜び、平和、秩序、安定、正義を取り戻したいと願っている。私たちの権利が否定されている限り、私たちは占領者たちの平和をも否定するつもりだ。
世界は我々を見捨てたかもしれない。国際法は私たちを見捨てたかもしれない。しかし、神の法はそうではない。パレスチナの同胞たちよ、テントに住め、イチジクの木の下に住め、裸の庇の下に住め、鶏小屋や洞窟や廃井戸のそばでさえも住め。しかし、決してあきらめてはならない。袖をまくれ。建てる。植える。存在せよ。移住するな。家の廃墟から心をそらすな。父が玄関脇に植えたブドウの木の根から目をそらすな。故郷の石と埃の中から、祖父母と子供たちの香り以外のものを嗅ぎ取ってはならない。どんなそよ風のくすぐったさも受け入れないことだ。幼い頃にあなたに歌ってくれたオリーブ、松、レモンの木の香りが染み込んだそよ風を。この大地はあなたのものだ。土も石もあなたのものだ。そして、この廃墟に降り注ぐ風雨もまた、あなたのものだ。
パレスチナ人よ、この地にしっかりと足を踏み入れよ。たとえ死んでも、墓を養い、歴史を守れ。死者や埋葬者にも祖国があるのだから。そして、マタイによる福音書5:4,20の言葉を思い出せ。”悲しむ者は幸いである。
また、あなた方の祖国が、剣と火でパレスチナを征服しようとしたすべての侵略者を打ち破ったという事実に慰められなさい。あなた方の祖先の粘り強さが、それらすべてを打ち砕いたのだ: ファラオ、アッシリア、バビロニア、ギリシャ、ローマだ。あなた方の文明は、彼らの野蛮さを打ち破ったのだ。シオニストたちは、これより良い結果を得ることはないだろう。彼らも敗れるだろう。だから、心を強く持ち、恐れてはならない。祖国を守るために常に努力せよ。バルフォア宣言、オスロ合意、アラブの正常化、無腰のイニシアチブが、あなた方を規定することを許してはならない。あなた方の抵抗を見失ってはならない。悲しみによってあなた方を弱めたり、集団としての自信を揺るがしたりしてはならない。
世界中のキリスト教徒に、南アフリカのデズモンド・ツツ主教の言葉を思い出してもらいたい。「不正の状況において中立であるならば、あなたは抑圧者の側を選んだことになる」21。聖地パレスチナでは、人種差別やアパルトヘイト、民族浄化ではなく、平等と一体性に基づく真の正義と共存が切実に求められている。パレスチナにおける公正な平和のために努力する人々は、キリスト教における私たちの真の兄弟姉妹である。彼らは正しい者であり、正しい者は必ず報われる。
「その義の実りは平和であり、その効果は永遠に静寂と確信となる」22。
1 このエッセイはアラビア語で書かれたものをナヘド・エルレイエスが翻訳した
2 Saleh Abdel Jawad, ”Colonial Anthropology: Haganah Village Intelligence Archives,” Palestine Studies, Issue no. 68, 2016, www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/Pages_from_JQ_68_-_Saleh_Abdel_Jawad_0.pdf.
3 Jorgen Jensehaugen, ”Terra Morata: The West Bank in Menachem Begin’s Worldview,” Contemporary Levant, 5:1 (2020), 54-63, DOI: 10.1080/20581831.2020.1710675.
4 Ilan Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine (Oxford: Oneworld, 2006).
5 「Fayṣ ibn ↪Lm_Qādir al-Ḥusaynī」, Encyclopedia Britannica. 2021年5月27日、https://www.britannica.com/biography/Faysal-ibn-Abd-al-Qadir-al-Husayniにアクセス。
6 申命記14:2、NIV。
7 ガラテヤ人への手紙、3:16、NIV。
8 ローマ人への手紙、9:6-9、NIV.
9 ヒッポの聖アウグスティヌス(354-430)、『聖アウグスティヌス著作集』(ブルックリン): A Translation for the 21st Century (Brooklyn, NY: New City Press, 1990, 2019).
10 『ヨハネの黙示録』20:1-3、NIV。
11 Jeffrey R. Collins, 「The Church Settlement of Oliver Cromwell,」 History 87, No.285 (2002): 18-40. 2021年6月13日 www.jstor.org/stable/24425701にアクセス。
12 Leonard Stein, The Balfour Declaration (Jerusalem: Magnes Press, Hebrew University, 1983).
13 La Civiltà cattolica. La Civiltà cattolica. La dispersione d’Israello pel mondo moderno, review in Rivista Internazionale Di Scienze Sociali E Discipline Ausiliarie 14, no. 54 (1897): 221-22. 2021年6月13日 www.jstor.org/stable/41570188にアクセス。
14 Silvio Ferrari, ”The Vatican, the Palestine Question and the Internationalization of Jerusalem (1918-1948),” Rivista Di Studi Politici Internazionali 60, no. 4 (240) (1993): 550-68. 2021年 6月 13日、http://www.jstor.org/stable/42737184にアクセス。
15 Sant’Offizio, Decretum de millenarismo (19 luglio 1944): DS 3839。
16 Ilan Pappé, 2006.
17 マタイによる福音書、5:44、NIV.
18 出エジプト記、20:13、NIV.
19 ローマ人への手紙、13:9、N.
20 マタイによる福音書、5:4、NIV.
21 Susan Ratcliffe, Ed., Oxford Essential Quotations (5th ed.) (Oxford University Press, 2017), accessed 12/1/2021 at www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191843730.001.0001/q-oroed5-00016497 より引用。
22 『イザヤ書』32:17、NIV。
SAMI A. -ARIANはイスラムと世界問題センター(CIGA)のディレクターであり、イスタンブール・サバハッティン・ザイム大学の公共問題教授である。1986年に博士号を取得後、米国で長年にわたり終身在職の学者として教壇に立ち、いくつかの教育賞や助成金を受賞した。米国での40年間(1975年~2015)、アル・アリアン博士は教育、研究、宗教、宗教間、市民と人権の分野で数多くの機関や出版物を設立した。特にパレスチナ、イスラムと西洋、公民権について、米国の多くのキャンパスで講演を行った。
2001年、アル・アリアン氏は、移民裁判における秘密証拠の廃止に尽力したことで、ニューズウィーク誌により、米国における「第一級の公民権活動家」に選ばれた。2012年、アル・アリアン氏は、『アメリカ反体制派百科事典』の歴史家たちによって、2巻からなる同シリーズに収録されている過去100年のアメリカの反体制派や良心の囚人152人のうち、3人しかいないイスラム教徒の1人として紹介された(マルコムX、モハメド・アリとともに)。彼の米国での物語は 2007年には受賞歴のあるドキュメンタリー映画『USA vs. Al-Arian』で、2016年には書籍『Being Palestinian』で紹介された。アル=アリアン博士は、米国の外交政策、パレスチナ、「アラブの春」現象に焦点を当てた数多くの記事や研究を執筆し、多くの言語に翻訳されている。精神性、パレスチナ、人権に関する詩集『Conspiring against Joseph』は2004年に出版された。
自由なパレスチナのための世界的連帯運動に向けて
政府、政党、機関、大衆行動ネットワークに働きかける
サミ・A・アル=アリアン博士
「包囲は、包囲する者が包囲される者のように感じるまで続くだろう」
-マハムード・ダルウィッシュの詩より
パレスチナで生まれなかったにもかかわらず、私は人生の早い段階で、自分がパレスチナ人であること、そしてパレスチナ人であることは、生き残るために闘わなければならないことを直感的に理解した。私はクウェートで生まれ、エジプトで育ち、大学進学のために17歳で米国に移住したが、パレスチナ人であることは私の生い立ちの本能的な特徴であった。ディアスポラに住むパレスチナ人であるということは、パレスチナの人々が1世紀以上にわたって耐えてきた歴史的闘争と重大な不正義を十分に意識することであり、私は幼少期から両親や祖父母の悲惨な体験を通してその歴史を吸収してきた23。パレスチナに住んだことはないが、私の生涯を通じて、パレスチナは私の中に生き続けている。12歳の私が詩を書こうとした初期の頃、パレスチナは現在のテーマだった。パレスチナの子供たちは幼い頃からパレスチナの歴史と悲劇を学ぶが、私たちはその美しさと荘厳さに惹かれずにはいられない。
私は1948年のナクバから10年後に生まれたが、私の世代にとってこのトラウマは、学校で学んだり、歴史書で読んだり、年長者から聞いたりするような単なる歴史的出来事ではなく、むしろ私たちの個人的な物語だった。他の多くの人たちと同じように、その細部までが両親の記憶に刻まれ、その後、私に植え付けられた。大人たちが居間に集まってコーヒーや紅茶を飲むとき、彼らが政治について議論するのを聞くのは当たり前のことだった。過去であれ、現在であれ、未来であれ、パレスチナを回想し、いつかパレスチナに戻ることを語るのが会話の中心だった。
私が10歳になる直前、私は壊滅的な試練と屈辱的な敗北、1967年6月の戦争を目撃しなければならなかった。パレスチナの他の地域は失われ、アラブの指導者たちや彼らのナショナリズムが喧伝する、とらえどころのない敵を打ち負かすという幻想も失われた。その6月のある夜、エルサレムが陥落したことを知った父が流した静かな涙を、私は今でも見ることができる。その瞬間から、パレスチナはただ嘆き悲しむべき場所でも、遠い故郷でもなく、公正な闘いのための決定的な大義名分なのだと悟った。
パレスチナ人として育つということは、友好的な環境にあっても、ホームレスであり、疎外され、包囲されていると感じることだった。どこにいようと、真実、正義、尊厳、生存を求める闘いは、あなたの存在と関わりを待っていた。私の父はクウェートから追放された。クウェートでは11年間、若い家族を養うために精力的に働いたが、その理由は政府のためにパレスチナ人コミュニティについて情報を提供することを拒否したからだった。その10年後、私はパレスチナ人であることを理由に適切な教育を拒否され、エジプトを去らなければならなかった。パレスチナのための真実と正義のために奮闘することは、本当の意味での選択ではなかった。なぜなら、それを放棄することは、私の魂を捨て、記憶を消し、私の存在を否定することだったからだ。
エジプトで過ごした高校時代、当時親友だったもう一人のパレスチナ人と頻繁に交わした会話は、真実や正義、あるいは私たち共通の悲劇についてだけでなく、回復、帰還、贖罪への道についてでもあった。私たちは答えを探すために、歴史、哲学、宗教、政治、文学、そして自由を求める人間の闘いについて幅広く読み、理解する必要があった。私を成長させたもうひとつの重要な特徴は、イスラム教を単に個人的な救済を求める宗教的信仰としてではなく、より重要な知識、エンパワーメント、社会変革の源として早くから受け入れていたことだ。友人と私は、アイデンティティ、目的、歴史、政治、文化、社会変革、抵抗、正義のための闘い、そして未来について、難しい問いを投げかけていた。
19歳になるまでに、私は近代西洋政治思想を含む様々なイデオロギーや政治哲学を学んできた。共産主義、社会主義、自由主義、世俗的ヒューマニズムといった西洋のイデオロギーにはまったくない次元がイスラームにはあると感じていた。これらの弁証法と認識論的基礎は二次元的で、2つの端点を持つ直線のようなものだった。一端は人間であり、もう一端は宇宙である。一方、イスラームの認識論的基盤は三次元的であり、3つの指標を持つ三角形のよう: 神、人間、宇宙である。最初のモデルでは、人間が注目と行動の中心にあり、善悪の結果にかかわらず、「人間」の幸福と喜びを最大化することが目標となる。このパラダイムでは、政治権力は「宇宙」や弱者や弱者を、権力者や強者の意のままに服従させるために使われる。それは紛争、腐敗、搾取を助長する。しかし、第2のモデルでは、神が信者の生活と活動の中心にある。その目的は、神の寵愛を得るために、自分の持てる最高の資質を最大限に発揮して、神を喜ばせることである。このパラダイムでは、政治権力は、人間が神や、宇宙や他の存在を含む神の創造物に対して背くことがないよう、崇拝される価値観や高い道徳観を守るために使われる。このような価値観には、真理、正義、平和、知恵、正義、親切、慈悲、思いやり、尊敬、愛、忍耐、謙遜、謙虚、慈愛、協力、美の鑑賞などが含まれる25。しかし、これらの価値観を信じるだけでは十分ではない。
さらに、神が第二のモデルの中心であり焦点であることから、人は啓示という本質的な知識の源を見つけ、それを活用することになる。啓示とは、宇宙の神秘と発見の鍵をできるだけ多く開け、私たちの能力と現実の可能性と限界を認識し理解するために、私たちの心と能力を使うことを可能にするものである。その結果、イスラム教をダイナミックな文明的文脈の中で解釈すると、私たちが抱く疑問の多くに意味のある答えが得られることがわかった。私たちは、正義のために闘い、社会の状況を変えることは、私たちの歴史と文明を理解することなしにはできないと信じていた。しかし、それ以上に重要なことは、その努力は、クルアーンにある真理、忍耐、信仰、徳のある行為という原則に導かれる必要があるということである。これらは義を達成し、神の恩恵を受けるための基盤だった。
私が初めてシオニズムの本質と歴史に触れたのは、1976年12月、著名なパレスチナ人学者である故イスマイル・アル=ファルキの講演を聴いたときだった26。私は、アブデルワハブ・エルメシリ、アルフレッド・リリエンタール、マキシム・ロダンソン、ロジェ・ガロディなど、多くの著名な学者の著作を通して、これらのテーマを研究した。1982年、アナーバーのミシガン大学で、アル・ファルキや当時もう一人の著名な学者であった故アリ・マズルイとステージを共にし、シオニストの脅威の危険性について講義した。この教育の旅の終わりに、私は、私たちの闘いは土地の回復や特定の物語の正当性だけでなく、より重要なのは紛争の本質に関するものだという結論に達した。闘争の本質が正しく理解されず、正しく定義されなければ、公正で永続的な解決はありえない。シオニズム運動の究極的な目標は、パレスチナ人の歴史を否定し、記憶を消し去り、未来を破壊し、人間性を低下させることによって、パレスチナ人の存在を否定することであることは、私には明らかだった。さらに、シオニズムはパレスチナ人とその歴史と文化に対する重大かつ深刻な脅威であるだけでなく、ユダヤ教の本質を再定義し、他の共同体や信仰、特にイスラム教との関係を損なうことによって、ユダヤ教そのものに対する脅威でもあった。
1982年の夏は、イスラエル軍がレバノンに侵攻し、ベイルートを包囲し、77日間毎日砲撃にさらされ、17,000人以上のパレスチナ人とレバノン人が殺されるのを目の当たりにしたからだ。この猛攻撃の残忍さは、PLOの戦闘員が避難した数週間後、ベイルート近郊のサブラとシャティーラ難民キャンプで、2,000人以上のパレスチナ人(圧倒的に女性、子供、老人が多かった)が虐殺されたことで続いた。イスラエル国家がそのファランギストの代理人に汚れ仕事をさせる力を与えたことは、イスラエル国家の悪辣な本質をさらに証明するものだった。
米国に住み、大学で教鞭をとり、長年にわたって国内の数十のキャンパスで講義をしたおかげで、私は多くの重要な問題、特にパレスチナ問題について、かなりの数の学生や知識人と直接関わることができた。さらに、公民権に関連する問題に取り組み、ロビー活動をしながら、議会の有力者、政策立案者、ジャーナリストなど、政治家層との面談に数年を費やした。こうした人生経験や直接の関わりを通して、シオニストの物語が政治家やジャーナリストに大きな影響を与え、大衆文化に浸透していることは明らかだった。
米国での生活は、長期的な影響と変化をもたらすための制度を確立することの重要性を私に教えてくれた。私は教育、研究、宗教間の活動、市民と人権の擁護に関連する多くの機関を設立した。また、パレスチナの闘争に焦点を当てた2つの全国組織も設立した27。早くから私は、一般市民を巻き込むことの重要性と、イスラエルを支持する強固な支持者との衝突が避けられないことに気づいていた。アメリカは、シオニスト国家が拡大する事業の主要な、時には唯一のスポンサーであり後援者となっている28。事実上、アメリカはパレスチナ問題の将来と運命を争う重要な場となっていた。イスラエルは、アメリカの政治的・外交的保護に加えて、アメリカの軍事的・経済的支援なしには存続できなかった。そしてパレスチナは、その邪悪な同盟関係を断ち切ることなしに自由になることはできないのだ。
紛争の本質を理解する
アラブや西欧の学者の多くは、歴史は世界中で2種類のユダヤ人社会を知っていると主張する。イスラム世界に住むユダヤ人(イスラムのユダヤ人)と、西欧キリスト教社会に住むユダヤ人(キリスト教のユダヤ人)である。しかし、この2つの世界に住む2種類のユダヤ人社会の地位は、驚くほど異なっていた。簡単な歴史的分析を行えば、預言者ムハンマドの時代のメディナ憲章以来、メディナのユダヤ人共同体はムスリム共同体(ウンマ)の一部として生活し、その都市国家の中で別個の共同体として認識され、尊重されていたことがわかる。ユダヤ百科事典が、「ユダヤ人の黄金時代」と呼ぶように、何世紀もの間、イスラムの地におけるユダヤ人コミュニティは、歴代のイスラム国家や帝国のもとで認められ、その権利を与えられてきた。これらの時代、特にアンダルシア地方では、著名な学者や賢者が台頭し、ユダヤ人社会が繁栄した。
一方、ローマ帝国や歴代のヨーロッパ帝国の下、キリスト教圏に住んでいたユダヤ人は、あらゆる形態の抑圧と迫害にさらされた(これらの国々で多大な苦しみを味わったユダヤ人は、アンダルシアの異端審問の際に起こったように、移住して定住するためにイスラム社会が開かれていることを知った) 何世紀にもわたってヨーロッパに居住していたユダヤ人社会は、最も基本的な市民権や法的権利を奪われ、ゲットーで暮らさなければならなかった。啓蒙主義とルネサンスの時代、そしてフランス革命の後、比較的解放されたにもかかわらず、彼らに対する人種差別と差別は続き、19世紀末のロシアのポグロムや20世紀のホロコーストなど、その例は枚挙にいとまがない。初期のシオニストを動かした最も悪名高い事件は、1894年にフランスで起きたアルフレッド・ドレフュス事件であろう。この事件は、近代シオニストの政治運動創設に多大な貢献をした。この裁判が生々しい人種差別と憎悪を示したため、多くのユダヤ人はヨーロッパのキリスト教徒の中で生活することは不可能だと結論づけ、ヨーロッパのナショナリズムと彼らのブランドである入植植民地主義の影響を最も確実に受けながら、自分たちの民族国家を樹立するという考えを模索し始めた。
こうしてシオニズム運動は、純粋にヨーロッパの経験から生まれた。数年のうちに、初期のシオニストたちはヨーロッパ列強の指導者たち、特にイギリスとフランス、そしてそれほどでもなかったがアメリカと同盟を結んだ。シオニスト運動は、アラブ世界の一部を分割し植民地化しようとするイギリスと共通の基盤を見出した。1916年のサイクス・ピコ協定は、オスマン・カリフのアラブ諸国の分割と分断を求めた。1917年、イギリス政府はバルフォア宣言を発表し、パレスチナにユダヤ人の民族的祖国を建設することを求めた。イギリスは、アラブ世界とイスラム世界の真ん中にユダヤ人居住地を持つことが、この地域における戦略的利益につながると期待したのである。同様に、シオニスト運動も、その事業を存続させるためには、正当性と保護のために大国と同盟を結ぶ必要があることを知っていた。
その結果、19世紀末から20世紀初頭にかけてシオニスト運動が勃興して以来、その主な目標は、ヨーロッパの近代国民国家システムをモデルとした国家的故郷に、世界のユダヤ人のディアスポラを集めることであった。シオニスト運動は、まずヨーロッパで、次いでアメリカやその他の国々で、ユダヤ人コミュニティを動員することによって、そのプログラムを実施した。このプロセスは多くの段階を経ており、シオニスト運動は、エリートたちが植民地勢力、特にイギリスと絶えず交流していたため、しばしば既存の地政学的現実を考慮しながら、多面的な制度を設立した。シオニスト運動は、パレスチナに入植者=植民地国家を建設するというビジョンを採用することで、オスマン帝国が何世紀にもわたって支配してきたアラブ・イスラム地域を分割し、弱体化させ、植民地化するというイギリスの戦略的利益に効果的に貢献した。この時期、シオニスト運動はそのビジョンを実現するために多くの資源を結集した。また、シオニズム運動が植民地化された弱い民族や政権に自らの意志を押し付ける力を与えることを目的として、地域紛争に直接影響を与え、国際システムに影響を与えることができる植民地勢力と同盟関係を築くために、あらゆる能力を活用した。
イギリス委任統治時代、第一次世界大戦の余波とオスマン・カリフの崩壊の中で、シオニストはパレスチナで精力的に事業を実施し始め、先住民の激しい抵抗を引き起こした。パレスチナ人は何度も反乱を起こし、自分たちの祖国への攻撃的な侵攻だと認識するものへの完全な拒絶を示した。イギリスの占領下にあり、資源が限られていたにもかかわらず、彼らは激しい闘争を繰り広げた。パレスチナの指導者たちは経験が乏しく、国際的なネットワークも乏しかったため、独立を求め、土地の占領を阻止することができなかった。これが最終的に1948年の大惨事、ナクバにつながった。ナクバによって、当時のパレスチナ人の約60%(約80万人)が故郷や都市、村から追放され、委任統治領パレスチナの約78%が占領された。
パレスチナにおけるシオニスト企業との対立は、土地と歴史をめぐる闘争であると同時に、未来をめぐる闘争でもある。パレスチナ人の土地を奪うためにパレスチナ人を標的にしているのだから、パレスチナ人の存在と生存のための闘いでもある。さらに、この地域における排他的なシオニスト国家の存在は、アラブ人とイスラム教徒の安全と安定に対する大きな挑戦であり、脅威であった。1948年にシオニストの民兵に直面したアラブ政権は弱体で分裂しており、ほとんどが外国勢力の支配や操作下にあった。1948年に敗北したアラブ政権は、ほとんどが君主制で、資本主義的な西側自由主義的価値観を受け入れていた。それらはやがて崩壊し、革命を主張する左翼や社会主義のイデオロギーを信奉する政権に取って代わられた。要するに、取って代わられたのは、権威主義的なやり方で社会を支配・管理する軍事政権がほとんどで、シオニスト国家と対立すると主張するだけで、自分たちの正当性を主張しようとしていたのだ。
この理解は、1967年戦争後の政治的展開を分析した、私の初期の影響力のある本のひとつと重なる。それは1970年代半ばに読んだ、シリアの作家タウフィク・アル・タイェブによる『After the Two Nakbas(二つのナクバの後で)』というタイトルの短い本だった29。それは、まず1948年、次に1967年にパレスチナを失った腐敗した無能な政権について、冷静かつ鋭い分析を行っており、闘争に参加するイスラム活動家の重要性と必要性を訴えていた。1982年のレバノン侵攻後、私は『第三の幻想の崩壊』というタイトルの研究書を編集・出版した30。この研究書は、最初の二つの幻想(1948年と1967年の体制)に関するアル=タイェブの議論を繰り返し、1982年の侵攻後、レバノンから追い出され、どの国境国家からも離れてアラブ世界に散らばったパレスチナ民族運動が体現する第三の幻想の崩壊がもたらす結果を分析したものである。この研究では、イスラム運動が台頭すれば、最終的にはパレスチナの闘争にイスラム運動が関与せざるを得なくなると論じている。しかし、この関与のあり方や、それが第4の幻想に終わるかどうかについても疑問を呈していた。当時、この研究は、パレスチナの大義へのイスラム主義者の関与(あるいは欠如)を問題にしていたため、多くのパレスチナのイスラム主義者から激しく非難された。相当数のイスラム活動家が、私や他の少数の人々が主張してきたように、パレスチナの大義がイスラム・ウンマの中心であるべきだという考え方を否定した。当時、このスローガンを提唱したことは、私に多くの悲しみと敵意をもたらした31。
ムスリム・ウマーにとってのパレスチナの中心性、そしてパレスチナにおける正義のための闘いには、精神的、政治的、文明的といういくつかの側面がある。パレスチナはイスラム世界の中心にあり、エルサレムはイスラム教の出現以来、コーランの中でメッカとメディナに次ぐ特別な聖地、高貴な土地として認められてきた。歴史を通じて、何百万人ものイスラム教徒がエルサレムを訪れ、祈りを捧げ、その地で祈りを捧げる者を祝福するという予言的な言い伝えが成就した。11世紀に十字軍がエルサレムを占領したとき、イスラム教徒が弱体化し不統一に陥っていた時期であり、エルサレムの陥落は手痛い敗北であり、聖地を冒涜するものだと考えられていた。十字軍の時代、エルサレムのイスラム教の聖地は冒涜され、汚された。サラディンの指導の下、ウンマ(イスラム共同体)を団結させ、動員し、侵略者を押し返し、エルサレムを解放し、その荘厳で崇敬される地位を回復するまでには、ほぼ1世紀を要した。イスラム教はキリスト教とユダヤ教を認め、それらを高く評価し、大きな尊敬の念を抱いているため、外国からの侵略者を撃退したパレスチナとエルサレムの歴史は、信仰共同体間の調和と平和の歴史であった。
イスラム世界の人々は、エルサレムの象徴的な意義を認識している。イスラム世界の他の場所(メッカとメディナを除く)とは異なり、エルサレムの地位はイスラム教ウンマの状態を象徴するものと考えられている。占領された場合、それは世界的なイスラム共同体の衰退と弱さの印と見なされ、解放された場合は、その活気と強さの証明と見なされる。同様に、イスラム勢力と戦った人々も、エルサレムの象徴的な性質を理解していた。1917年12月にエルサレムに入城したエドマンド・アレンビー英軍大将は、「十字軍の戦争はこれで終わった」と発言し、1920年7月にダマスカスを征服したアンリ・グーロー仏軍大将は、サラディンの墓に立って墓を蹴り、こう宣言した: 「十字軍は終わった。目覚めよサラディン、我々は帰還した。私がここにいることは、三日月に対する十字架の勝利を聖別するものである」
この議論におけるもう一つの重要な側面は、地政学的な側面である。数十年にわたってパレスチナの土地を占領してきたイスラエルは、何百万人ものイスラム教徒とアラブ系キリスト教徒に囲まれている。イスラエルが生き残るためには、この地域の国家を分裂させ続けなければならない。そのためには、植民地勢力と結託し、宗教的、宗派的、民族的、その他の理由で戦争や不和を引き起こすことで、彼らの弱さと脆弱性を確保する必要がある。イスラエル国家の存続は、この地域のアラブ・イスラム諸国の分断、弱体化、無力化にかかっているのだ。だからこそイスラエルの地政学的大戦略は、この地域の覇権国家となることであり、攻撃的な軍事態勢を維持する必要があるのだ。このような状態は、すべての当事者にとって受け入れがたいものであり、地域全体に不確実性、不安定性、悲惨さを投げかけるものである。イスラエルがこの地域の政治に関与し、混乱、紛争、不和、戦争を助長している例は枚挙にいとまがない32。
文明レベルでは、多くのイスラム社会が直面している深い文明的衰退を克服するための3つの主な障害がある。それらは次の3つ: (b)安全保障、経済、技術、文化など多くの分野において、アメリカなどの外国勢力に依存していることである、 (c)エドワード・サイードが「文化的帝国主義」と呼ぶものによる社会の西洋化33。イスラエル、シオニスト運動、そしてその支援者たちが、中東全般、特にアラブ世界において、真の政治的、社会経済的、科学的、技術的進歩を阻害する破壊的な役割を果たしてきたことは、記録からも明らかである34。
1973年の戦争と、それに続くアラブ政権によるパレスチナ解放プロジェクトの事実上の放棄の後、PLOは1974年の10ヵ条綱領の宣言に始まり、アルジェ会議でのイスラエル承認と1988年のジュネーブ宣言、そして1993年のオスロ合意に至る秘密交渉に至るまで、シオニスト国家を受け入れるようになった。
オスロ合意においてイスラエルは、パレスチナ人の法的権利や政治的権利に関わるすべての問題を先送りすることを主張した。最終的地位問題と呼ばれるこの問題には、エルサレムの地位、パレスチナ人の帰還の権利、パレスチナ人の土地へのユダヤ人入植、国境、主権などが含まれていた。1994年にPLOの指導者たちが1967年の占領地に戻ったことで、パレスチナの政治活動の大部分は、初めて外部から内部へと移行した。それでも、イスラエル軍の占領はパレスチナの意思決定のほとんどを効果的にコントロールすることができ、いわゆるパレスチナ自治政府(PA)は、占領者に大きく有利な経済協定によって束縛され、意味のある抵抗を抑制するための屈辱的な治安調整に縛られる限り、政治的な機動が制限される体制を作り上げた。
オスロ・プロセスとPLO指導部のシオニスト国家承認後、イスラエルには紛争終結のための3つの戦略的選択肢があった。ユダヤ人の大多数を維持し、国家の民主的な体裁を保つことを選択した場合、2国家解決と呼ばれる、要するに1967年以前の国境線にほぼ沿った切り捨てられた国家をパレスチナ人に与えるという解決策を受け入れる必要があった。しかし、ヨルダン川と地中海に挟まれたパレスチナの全土を維持し、その土地の全住民に民主的な制度を認めると称するのであれば、パレスチナ系アラブ人にイスラエル系ユダヤ人と同等の市民権と政治的権利を認める、いわゆる一国解決策を受け入れることになる。もちろん、聖地を独占的に支配するというシオニストの夢に終止符を打つことになるこの選択肢は、これまでのところ、イデオロギーなどの違いにかかわらず、すべてのシオニスト政党によって拒否されてきた。というのも、シオニストのイデオロギーの核心は、ユダヤ人至上主義と例外主義、そして非ユダヤ人に平等な権利を認めないという信念に基づいているからだ。一国家解決は、1974年にPLOがパレスチナ国家という目標を採択する前に呼びかけていたパレスチナの目標であったが、この考えはすべてのシオニスト政党とその西側の同盟国によって激しく拒否された。
紛争を終結させると多くの人が信じていたオスロ・プロセスの目標であった2国家解決は、いわゆる国際社会と大国の支持も得た。しかし、オスロ後の数年間、シオニストの入植地(コロニー)の植民地化と拡大が続いたことで、今ではほとんどの国際専門家が、ヨルダン川西岸に実行可能なパレスチナ国家を樹立することは不可能だと認識している。イスラエルの選択は、その戦略と政策が示すように、パレスチナの歴史的な土地すべてに対する占領を維持し、宗教的、イデオロギー的、歴史的、あるいは戦略的理由から、あるいは弱く、脆弱で分裂していると考える相手に対するコストと便益分析によって、徐々にではあるが、現地に事実を確立することによって併合することであった。
イスラエルが選んだ道は明確である。1国家解決策も2国家解決策も完全に拒否し、排他的なイスラエル・アパルトヘイト国家を支持することである。この道によって、イスラエルは世界に第4の選択肢があることを納得させようとしている: パレスチナは、南アフリカのバントゥスタン十王国と同じように、限定的な主権を持つ変成・非武装の存在である。イスラエルが、すでに正統性に疑問符がつく弱体なパレスチナ自治政府との交渉による和解の見通しを打ち消す決断を下したことで、後者は悲劇的な結末を迎え、数十年来の政治プロセスは失敗し、緩慢な死を待つことになった。
ビジョンを描く
その結果、パレスチナ民族プロジェクトの論理的な対応は、シオニスト・プロジェクトの逆説と、その土地におけるパレスチナ系アラブ人の存在を受け入れず、パレスチナ人の権利を認めず、対等な立場で共存することを拒否していることを認識することによって、アラブ・イスラエル紛争をその核心に立ち返らせることでなければならない。それゆえ、パレスチナ民族プロジェクトの戦略的目標は、シオニスト・プロジェクトを、そのすべての制度と現れとともに解体することでなければならない。つまり、パレスチナを完全に脱シオニズム化することである。両者の間には大きな力の不均衡があるため、これは達成不可能だと言う人もいるかもしれない。しかし、シオニストのプロジェクトは、あらゆる人間のプロジェクトと同様に、その性質を理解し、その長所と短所、能力と欠点を特定するためには、分析し、総合しなければならないある種の特徴と特徴を持っている。したがって、パレスチナ民族解放プロジェクトがこの目的を実現するためには、シオニズムとの対立の本質と展開について完全かつ包括的な理解と分解を提供しなければならない。この闘争の公正な解決に向けた私のビジョンは、以下を前提としている:
1) パレスチナ人民の歴史的なパレスチナの土地への完全な帰還の権利が、あらゆる場所で認められ、受け入れられなければならない。シオニズムのプロジェクトは他者を否定することに基づいているため、パレスチナ人やこの地域の人々だけでなく、ユダヤ教そのものにとっても危険であるという理由で、これをきっぱりと解体する以外に、これらの権利を回復する方法はない。シオニズムは自らを、ユダヤ教とその信者を信仰体系ではなく領土に結びつけるイデオロギーと定義している。この概念は、ユダヤ人のアイデンティティと、ユダヤ人であることを自認する世界的な人々にとって危険である。なぜなら、彼らは、実際には反対していたり、少なくとも無関心であったりする犯罪に加担することになるからである。
2) この紛争は、パレスチナの人々が限られた手段や能力で自力で解決する能力を超えている。パレスチナ人民が1世紀以上にわたって闘争を続け、シオニスト運動とその地域的・国際的支持者が彼らを根絶やしにしたり、降伏させたりすることができなかったという不動性、粘り強さ、忍耐力がなければ、この紛争はとっくの昔に終わっていただろう。パレスチナの人々は、この紛争の先鋒であり、今後も先鋒であり続けるだろう。そして、彼らの犠牲と将来の世代の犠牲のために、最も重い代償を払い続けるだろう。これが彼らの運命なのだ。屈辱と不名誉を味わいながら、敵の意のままに占領下で生きるか、あるいは、自分たちの目標が達成されるまで、決意、名誉、回復力、継続的な抵抗力をもって反抗し続けるかだ。彼らの目標は、自分たちの土地を解放し、国民を自分たちの町や村に戻し、自分たちを滅ぼそうとする敵の計画を打ち負かすことだ。しかし、このような状況にもかかわらず、パレスチナの人々は力の方程式の一部(不可欠なものであるとしても)にすぎない。この方程式は単純である。パレスチナ人の努力だけではこの問題を解決することはできないが、彼らなしにはこの問題を解決することはできないのである。
3) シオニスト・プロジェクトは、ヨーロッパにおける「ユダヤ人問題」を解決したいと願った初期の父祖たちの夢であった。彼らの指導者たちは、パレスチナ人とアラブ人を犠牲にしてこの問題を解決できると主張した。そのため、シオニスト運動はあらゆる資源と能力を活用し、国際的な同盟関係を築き、制度を構築し、あらゆる戦術とメカニズムを駆使して目標を達成した。同様に、パレスチナの国家プロジェクトは、パレスチナ人だけに閉じこもることから解放され、アラブやイスラムの文脈の中だけでなく、全世界のあらゆるエネルギーと能力を動員する、世界的かつ人類的な解放プロジェクトへと変容しなければならない。それは、人種差別的で攻撃的で冷酷な入植者植民地主義運動に対する公正な解放闘争である。このような闘いには、パレスチナ解放闘争との世界的な連帯運動の確立が必要である。それはまた、パレスチナの大義を、ローカルな、あるいは地域的な闘いから、あらゆるレベルにおける普遍的な闘いへと変容させるものであり、その中には、彼らの努力、献身、犠牲を通じて闘いにおける自らの役割を担い、正当性を獲得する世界的指導者の参加も含まれる。
4) オスロ・プロセスが崩壊し、2国家解決という幻想が終焉したことで、遅かれ早かれ、パレスチナの大義の重心は、そのさまざまな現れとともに、再び海外へと移動するだろう。これはもちろん、占領地内部の人々の闘いの役割が終わることを意味するのではなく、占領者のパートナーであり協力者であるパレスチナ自治政府の役割(抵抗を制限し抑圧することによって、また占領のコストを削減することによって)を終わらせた後の変容を意味する。それはまた、単に地域的、地方的という束縛から解放され、正義と自由を求める普遍的な闘いの一部となることを意味する。さらに、これによって内部の人々は、彼らの抵抗を継続し、占領を揺るがすために、よりグローバルな指導的役割を担うことができるようになる。今日、海外にいるパレスチナ人はパレスチナ人の半分以上を占めているが、残りの半分は占領や包囲の下にあったり、人種差別的な支配や差別的な制度の下で生活している。その結果、シオニスト・プロジェクトとの衝突におけるこの移行と変容の論理的な結果は、あらゆるレベル、あらゆる分野、あらゆる地域において、占領とその制度や手段を標的にした活動の高まりと直接行動の激化である。
それゆえ、パレスチナ民族プロジェクトの任務は、過去数十年のように、現実には軍事占領と抑圧下にあり続ける非武装ミニ国家の樹立という問題に限定されることはないだろう。したがって、このプロジェクトには2つの主要な使命がある。ひとつは、パレスチナと難民キャンプに住むパレスチナ人が、その権利を完全に獲得するまで抵抗と存続を続けられるよう支援することである。第二の使命は、経済的、政治的、法的、社会的、文化的、学術的、芸術的、人権的、メディア的、裁判的など、あらゆるレベル、あらゆる分野において、世界的なシオニスト運動とその強力な後ろ盾に関与し、暴露することである。神話と嘘が広められる領域や地理は、一つも見逃してはならない。
5) あらゆる政治的実体や社会運動と同様に、シオニスト国家は、その創設以来、その存続と継続を保証する要因、構成要素、戦略的要請を有している。したがって、パレスチナ民族解放プロジェクトにとっての戦略的課題は、これらの要因と要請を特定し、利用可能なあらゆる手段によって、それらを弱体化させ、弱体化させ、終わらせるためにあらゆる努力を払うことである。これらの要請の多くは、パレスチナの直接的な行動では制御できないものであるため、これらの要因を弱め、これらの要請を弱めるための戦略的計画と統合的な努力を活用する、国家、政府、機関、運動、政党、著名人、そして民衆や大衆行動ネットワークを含む、効果的な世界的連帯運動への要請が強化される。この戦略は、南アフリカのアパルトヘイト体制のように、過去に他の攻撃的で人種差別的な体制が崩壊したように、シオニスト・プロジェクトの解体と崩壊を徐々に導くだろう。
6) このプロジェクトの中心では、エリートだけでなく、人々が大きな役割を果たさなければならない。シオニストのプロジェクトに立ち向かい、アパルトヘイトが終わるまでパレスチナの人々を支援する上で、自分たちが大きな役割を果たすことができることを、世界中の他の人々が知ることになる。この連帯と関与の行為は、政治的、メディア的、法的な領域だけに限定されるものではなく、シオニスト・プロジェクトを弱体化させるあらゆるものを含むだろう。シオニストに対する抵抗と、シオニストの植民地化、膨張、人種差別に対する闘いは、世界的な解放運動の主要なマントラとなるだろう。
7) パレスチナの大義が、不正義、占領、抑圧、人種差別、専制、搾取に反対する世界的な闘いの中心ではないにせよ、その必要不可欠な一部となるとき、この紛争は、その働きかけにおいて世界的なものとなるだけでなく、その本質において人道的なものとなる。それは他の紛争を超越し、何十年もの間、この地域や発展途上国の多くの地域を悩ませてきた破壊的な特徴(宗派対立、民族対立、部族対立、階級対立、イデオロギー対立など)を空っぽにする。その時、パレスチナが尺度、羅針盤、ルールを提供することになる。それは、その人々が他よりも抑圧されているとか、その苦しみが他よりも大きいからではなく、紛争の本質と、地理、歴史、未来、そして尊厳ある人間であることの意味を対象とするシオニストの挑戦のためである。
8) オスロの大失敗の後、パレスチナ民族解放プロジェクトがその普遍的な魅力に気づき、世界中で正義と自由のために闘う象徴となり、抑圧と覇権主義に対抗する主導的な闘いとして認識されるようになれば、搾取、人種差別、奴隷化と闘ってきた多くの世界的な解放運動や人権運動のように、世界の弱者や貧困層を解放するための不可欠なパートナーとなるだろう。
9) このプロジェクトは、その戦略計画を採択し、その機関を設立し、その活動計画(その多くはすでに存在しているが、活性化とネットワーク化を必要としている)を活性化した後、シオニスト・プロジェクトとその機関、そしてその地域的・世界的な力の源泉に反対するすべての直接行動の中核をなす。
10) シオニスト・プロジェクトの戦略的要請を総体的に弱めるようなあらゆる形態の抵抗がエスカレートすれば、ある歴史的瞬間が訪れるだろう。そこでは、力の均衡が変化し、攻撃的で人種差別的なプロジェクトが、その存続のための要因とその継続の要請が排除されるか、大幅に減少した後に崩壊するような、戦略的変化が起こるだろう。
以前のプレゼンテーションで、私は、シオニスト・プロジェクトが存続し、継続するための12の主要な必要条件について概説した。そして、パレスチナ解放のためのグローバル・プロジェクトは、その努力と行動を強化し、これらの要件のすべて、あるいはほとんどを弱めるために必要なメカニズム、ツール、戦術に焦点を当てなければならない。ここでのビジョンの要点は、イスラエルとアラブ、あるいはパレスチナ紛争の終結として、このプロジェクトを解体するという目標を達成することは、すべてではないにしても、これらの戦略的要請のほとんどを終わらせる、あるいは崩壊させることと密接に結びついているということである。
結論
この小論は、人種差別的な植民地主義事業からのパレスチナの解放に関する壮大なビジョンを簡潔に提示した。それは次のように要約できる。シオニスト・プロジェクトの存在と存続を保証する重要な命令がある。前述した戦略的要因のすべて、あるいは大部分が挑戦され、弱体化し、機能しなくなれば、それはひいてはシオニスト国家を弱体化させ、その存続を危うくし、時間の経過とともにその崩壊と崩壊を余儀なくされるだろう。したがって、パレスチナの大義に関心を持ち、その解放のためにあらゆるレベルで活動する人々は、シオニスト・プロジェクトとの闘いを活性化させるために、これらの必要条件を検討し、それに応じて対処しなければならない。
加えて、シオニスト・プロジェクトは、そう遠くない将来、国際的であれ地域的であれ、世界が徐々に多極化していく地政学的要因に関連した構造的・戦略的変化が起こったとき、大きく弱体化する。このような変化は、イスラエルに、根深い人種差別政策を撤廃または緩和することで、大規模な譲歩を迫るだろう。加えて、イスラエル社会には多くの内部断層があり、時間の経過とともにイスラエルは不安定化し、大きく弱体化していくだろう(アラブ人対ユダヤ人、ミズラヒ人対アシュケナージ・ユダヤ人、世俗派対宗教派、富裕層対貧困層、入植者対都市住民、高齢者対若年者など)。
さらに、パワーバランスの戦略的転換は、ビジョン、意志、行動のコンセンサスが、賢く、集団的に、同時に構築されたときに達成できる。さらに、同盟国と敵対国のシフトも戦略的パワー方程式の一部であり、パレスチナ人の権利を支持する方向に徐々にシフトしている。半世紀前、トルコとイランはイスラエル陣営に属し、シオニスト国家がアラブ近隣諸国に対して協力、同盟、協調する相手と考えられていた。今日、イスラエルとその背後にあるシオニスト運動とその同盟国は、これらの国々を敵対陣営とみなしている。パワーバランスにおけるこの戦略的変化は、強さと弱さが必然的な恒常性ではなく、闘争が続く限り変動するものであることを示す何よりの証拠である。
最後に、ボイコット、ダイベストメント、制裁(BDS)運動を含む多くの戦術を活性化し、採用することによって、イスラエルのアパルトヘイト体制を終わらせようとする世界的な連帯運動を生み出すことの重要性を強調しなければならない。このような戦術の目的は、イスラエルのアパルトヘイト国家を孤立させ、その人種差別・植民地主義体制を最終的に崩壊・崩壊させることである。このビジョンは、シオニスト・プロジェクトに対抗する闘いにおいて、30年以上不在だったパレスチナ国外の人々がますます重要な役割を果たすことにつながる。しかし、今回の闘いは、パレスチナ人が限られた目的のために行う、パレスチナ人だけの闘いではない。正義、自由、平等、真実に関心を持つすべての人々によって実行される、世界全体の普遍的な闘いなのだ。もちろんこれは、内部におけるパレスチナの闘いの役割を矮小化することを意味するのではなく、闘いの大部分がグローバルなものとなり、すべての人、あらゆる場所に影響を及ぼすという認識のもと、互いに補完し合いながら、両者が統合されることを意味する。
当然ながら、海外にいる多くのパレスチナ人や、世界中のパレスチナの大義のための活動家たちが、この努力の先頭に立ち、このビジョンを実行し、その行動計画を実行することになる。彼らは、それを実行するために必要なあらゆる機関を創設し、あるいは活性化させることによって、それを推進する。このパレスチナの抵抗行為はまた、あらゆる場所、あらゆるレベル、あらゆる分野で肩を並べて活動する国際連帯運動によって、行動、コミットメント、関与において補完され、共有されなければならない。
シオニストの入植者植民地国家が土地と人間を標的にしている一方で、パレスチナにおける不正義と人種差別の終焉は、パレスチナ人の正義と自由の回復につながるだけでなく、ユダヤ教とその信奉者をシオニズムの人種差別的教義から救うことにもなる。要するに、このビジョンはパレスチナ人を解放するだけでなく、ユダヤ教の偉大な予言的伝統が冒涜されるのを防ごうとするものなのだ。西側諸国は、人種差別、外国人嫌悪、反ユダヤ主義のために、(彼らが歴史的に特徴づけてきた)「ユダヤ人問題」を解決できずにいる。しかし、アラブ・イスラーム世界の歴史は、西欧やその他の地域で抑圧されたり迫害されたりしているユダヤ人であれば、モロッコからインドネシアまで、広大なイスラーム世界のどこにでも移住し、尊厳をもって安全に暮らすことが歓迎されることを示している。
23 Sami Al-Arian, Yasir Suleiman (Ed.), Being Palestinian: Personal Reflections on Palestinian Identity in the Diaspora (Edinburgh University Press, 2016), 48-53.
24 Shackled Dreamsを参照のこと: Shackled Dreams: A Palestinian’s Struggle for Truth, Justice, and the American Way: The Story of Sami Al-Arian (National Liberty Fund, 2004)を参照のこと。
また、私の裁判の概要については、ドキュメンタリー『USA vs Al-Arian』(ヤン・ダルチョー、ライン・ハルヴァーセンフィルム制作、98分 2007)を参照のこと。リンク:https://vimeo.com/128413718
25 このトピックに関するより詳細な議論については、以下を参照のこと: Ismail Raji Al-Faruqi, Al Tawhid: Ismail Raji Al-Faruqi, Al Tawhid: Its Implications for Thought and Life (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 1994)を参照のこと。また、私のプレゼンテーション、Sami Al-Arian、Understanding Tawhidも参照のこと: イスラームの基本原理、2020年4月25日(95分)、CIGAラマダーンウェビナーシリーズ#1 、https://www.youtube.com/watch?v=nDX89EbxyiM。
26 イスマイル・ラジ・アル=ファルキ『イスラームとイスラエル問題』(TOP出版 2005)。
27 1981年にパレスチナのためのイスラム協会(IAP)、1988年にパレスチナのためのイスラム委員会(ICP)を設立した。私は1983年、この作品に登場する紛争の結果、IAPを脱退せざるを得なかった。
28 拙著『サミ・アル=アリアン、イスラエルとアメリカ』参照: From Enabler to Strategic Partner』(CIGA Publications, Istanbul Zaim University Press, 2019)を参照のこと。リンク:https://www.izu.edu.tr/en/ciga/publications/publications/geopolitical-strategic-studies
29 Tawfiq Al-Tayyeb, Ma Ba’da Al Nakbatayn (After the Two Catastrophes) (Germany: Islamic Center of Aachen, 1968)。
30 Mus’ab Al Zubeiri(ペンネーム), Suqoot Al Wahm Al Thaalith (The Fall of the Third Illusion) (Islamic Association for Palestine, USA, 1982).
31 1970年代後半から1980年代前半にかけてのパレスチナのイスラム活動家の大半は、パレスチナがイスラム運動やムスリム・ウンマの中心的な原因であるという考え方を否定していた。中には、神の御喜びを求めることこそが中心的な原因であると主張する者もいた。しかし大多数は、イスラム国家の樹立こそが中心的な問題だと考えていた。1982年、私は別のイスラム活動家とパレスチナ問題の中心性について2時間にわたって討論した。討論が終わったとき、聴衆の中で私の主張を支持した人は一人もいなかった。しかし、1980年代後半、第一次パレスチナ・インティファーダ(1987-1991)の頃には、この問題はもはや論争にならず、パレスチナのイスラム活動家の間では、パレスチナの大義の重要性と中心性を肯定するコンセンサスがほぼ出来上がっていた。1980年代初頭のもうひとつの緊張の原因は、パレスチナ人の活動を拡大し、非パレスチナ人、非イスラム教徒の活動家を参加させるという私の主張だった。
32 イスラエルの建国以来、イスラエルの直接的な関与によって影響を受けた国々には、レバノン、南スーダン、イラクのクルド人地域、ヨルダン、シリア、エジプト、イランなどがある。イスラエル・シャハク教授が翻訳・編集したオデッド・イーナン計画『中東に対するシオニストの計画』(アラブ系アメリカ人大学卒業生協会、アメリカ、1982)も参照のこと。リンク:https://dokumen.pub/the-zionist-plan-for-the-middle-east.html
33 エドワード・W・サイード『文化と帝国主義』(ニューヨーク:ヴィンテージ、1994)。
34 例えば、David D. Kirkpatrick, Into the Hands of the Soldiers: Freedom and Chaos in Egypt and the Middle East (New York: Viking, 2018)を参照のこと。著者はこの本の中で、イスラエルとその同盟国である国務省や国防総省、そして地域の同盟国が2013年の軍事クーデターを支持・擁護する中で、エジプトの民主主義をいかに妨害したかを詳述している。
35 私のプレゼンテーション、Sami Al-Arian, Ending the Israeli-Palestinian Conflict: 地政学的分析、2020年5月15日。リンク:https://www.youtube.com/watch?v=ZaNW9AH6uVo
HANADI HALAWANIはエルサレム旧市街の著名なパレスチナ人活動家であり、アル・アクサ・モスクのコーラン教師でもある。アル・アクサから徒歩圏内に住んでいるにもかかわらず、イスラエル占領当局は、占領下の東エルサレムにおける彼女の政治活動やパレスチナ人の権利擁護のために、何年もの間、彼女がそこに入ることや祈ることを禁じてきた。2021年6月、彼女はイスタンブール・ザイム大学のCIGA(Center for Islam and Global Affairs)からパレスチナとの国際連帯賞を授与された。
私たちはムラビタットである
占領地エルサレムに抵抗の種を蒔く36
ハナディ・ハラワニ
私は1980年、エルサレムのアル・クッズにあるワディ・アル・ジョズで生まれ、そこで育った。1981年にヒンド・アル・フセイニによって設立された「アラブ子どもの家」で小中学校の教育を受け、デイル・ヤシンの虐殺を生き延びたパレスチナ人孤児を保護した。その後、アル・マムニア・スクールに入り、高校を卒業した。現在は、ビルジート大学で民主主義と人権を中心に修士課程を修了している。
私は幼少期のほとんどをエルサレムの祖母の家で家族と過ごした。両親から注がれた愛情と配慮に感謝の気持ちでいっぱいだ。両親は私の足を正しい道に導いてくれた。二人とも、高い原則に従って生きていた。私の一歩一歩を導いてくれた道徳の多くは、両親から受け継いだものだ。しかし、特にアル・アクサ・モスクと私の愛する街エルサレムとの関係について、私の選択に影響を与えたのは祖母のカティバだった。祖母はどこへ行くにも私を連れて行った。私の祖母は、1948年のナクバと1967年のナクサの生存者だ。祖母の心の中には、イスラエルの占領に対する大きな悲しみと憤りがあった。彼女はいつも、いつかパレスチナ全体の解放の一環として、アル・アクサ・モスクが解放されることを願っていた。戦争についての彼女の多くの話を覚えているが、それはいつも苦悩と確実な勝利への希望が入り混じった感情で溢れていた。
彼女はいつも私をアル・アクサに連れて行ってくれた。まず、彼女のお気に入りの木陰で休んだ。それから立ち上がると、彼女は私に空の袋を渡し、私が聖なる祠堂の広い周辺を歩き回り、ゴミのかけらを拾い集めるようにした。私は熱心にそうしたが、祖母は時折、アル・アクサを神聖化することは、単にゴミをなくすことだけでなく、暴力的な入植者や武装した兵士たちが頻繁にこの場所を襲い、好き勝手に発砲し、平和な場所の平穏を乱すことでもあるのだと私に言い聞かせた。
アル=アクサに対する祖母の愛情は、パレスチナの運命に対する祖母の多くの不安とバランスをとっているようだった。彼女にとって、アル・アクサは単なる聖地ではなく、もっと大きくて深いものの象徴だった。私が歌っているのを聞いたことがある。彼女は涙ぐんだ目で私を見つめ、こう言った。「いつの日か、アル・アクサ・モスクでコーランを朗読するあなたのメロディアスな声を聞けるように祈っているわ」私は祖母からアル・アクサへの愛を受け継いだ。彼女は亡くなったが、アル・アクサとパレスチナに対する深い責任感を私たちに残してくれた。
エルサレム出身のヤシン・マカウィと結婚したとき、私はまだ17歳だった。彼もまた、愛と温かさ、しかし苦しみの遺産を受け継いでいた。私たちは、いつか現世での使命を受け継ぐことになる家族を一緒に育てた。
長女のアラと長男のマフムードが生まれたとき、私はまだアルクッズ・オープン大学の学生だった。占領都市に住みながら、2人の子供を管理し、学校からの要求に応えるのは容易なことではなかった。しかし、その時期が私に強くなること、時間を管理すること、重い責任を背負いながらも人生に対処することを教えてくれた。その後、息子のアフマドが生まれ、最後にハムザが生まれた。ハムザが生まれる頃には、私はアル=アクサ・モスクに捧げる人生を、最初は学生として、次に教師として、そして活動家として、完全に捧げていた。
私の人生とアル=アクサを結びつける闘いは、私がコーランの朗読と指導におけるハイレベルの資格取得に熱心に取り組むようになったときから始まった。最初は、いつか私の声がアル・アクサの敷地全体に神の言葉とともに響き渡るようにという祖母の願いに突き動かされていた。その願いが叶ったのは、占領下のパレスチナのイスラム運動が、「知識のテラス」と呼ばれる既存のプログラムを拡大しようとしていることを知ったときだった。それは2010年のことで、当時は私の学歴も知識も乏しかったにもかかわらず、私はそのポジションに応募した。
私の資質が、このプログラムの講師に応募してきた多くの女性たちの資質に及ばないことは分かっていた。一人は高い教育を受け、パレスチナ人殉教者の妻でもある意志の強い女性、もう一人は長年宗教の伝道師をしていた女性、三人目は比類ない資格と豊富な経験を持つ女性だった。私はといえば、祖母の願い、祖母のアル・アクサへの愛、そして今の私の愛を背負っていた。希望を胸に面接に臨んだ。私は面接官にこう言った。”私の証明書や書類が、この仕事に必要な最低限の条件を満たしていないことは承知しています。しかし、私には私にしかないものがあります。それは、アル・アクサと私たちの愛するパレスチナのために、言葉を行動に移したいという思いです「。数時間後、私は「知識のテラス」プログラムの教師に選ばれたと電話で知らされた。私の仕事内容には、幼い子供たちにコーランを教えることも含まれていた。
2011年6月初め、私は教師としての新しい役割を始めた。これが単なる教師としてのキャリアの始まりではなく、やがて私を、アル・アクサを否定し、占領都市におけるパレスチナの権利を否定しようとするあらゆる企てに立ち向かうことを人生の主な使命とする、ムラビタ(確固とした女性)として指名することになる長い道のりの入り口であることを、私はまだ知らなかった。
それは、夫ヤシンの愛と支え、保護と忠誠がなければ決して不可能だった、とても長く困難な旅の始まりだった。他の多くの人がそうしなかったとき、彼は私の味方をしてくれた。彼は私の選択を擁護し、私の心のよりどころである大義のために戦う時間と場所を与えてくれた。それでも、朝7時半から一日中続く活動に母親が関わるのは容易なことではない。そのような母親が、意図的に私たちを締め出すように設計されたイスラエル軍のさまざまな検問所を通過しなければならないとなると、この苦労はより顕著になる。とはいえ、このプロジェクトで女性の要素が支配的になるのは時間の問題だった。
最初は小さなサークルで教えていたが、やがて人数が増え、2つに分けざるを得なくなった。しかし、生徒の数は増え続け、それに伴って知識の輪も広がっていった。イスラエル兵は私たちを警戒し、何年も続く嫌がらせを始めた。彼らは私たちのクラスに入ってきて、教師や生徒の顔にカメラを向け、写真を撮り続けた。そして、何の理由もなく、身分証明書を回収し、しばらくの間保持し、出席者の名前を書き留めた。
プログラムに参加した女性たちの中には、心配し始めた者もいた。イスラエルの反応の激しさを予測できなかったため、帰りたいという人もいた。私は彼女たちの中に立ち、こう言ったことを覚えている: 「遠くへ旅立つバスの中にいる自分を想像してみよう。旅の辛さに疲れてくると、何人かは出発を選ぶかもしれない。最初に出発する者が支払う代償はわずかだが、残りの者を見捨てることを選択することで、他の全員にとって旅がより困難なものになる。一緒にいれば、最終目的地に着くまで苦難を分かち合うことができる。姉妹たち、私たちが踏み出したこの旅は、解放への道なのだ。私たち全員が自由を選ぶなら、すべての苦難を平等に分かち合わなければならない」ありがたいことに、私たちは団結した。
何百人もの子供たちが様々なプログラムに登録した。将来有望な若者たちが、自分たちの宗教、自分たちの文化、自分たちのアイデンティティについて学び、互いのために立ち上がる姿は、ただただ美しい光景だった。時には、兵士たちは圧倒され、困惑しながらも、拘束されていた子どもたちを解放することもあった。
ある者は読み書きを学び、またある者はより高度な科目や知識を学ぶ。やがて私はプログラム全体の責任者となり、プロジェクトに協力してくれる若くてエネルギッシュな女の子を探し始めた。アル=アクサに集まると、私たちは蜂の巣をつついたように忙しくなり、それぞれの教師やボランティアは特定の科目や知識の輪に専心した。私の仕事は、あるサークルから別のサークルへと巡回し、指示し、励まし、慰め、導くことだった。彼女たちは私を 「アル・アクサの蝶」と呼んだ。私はそのあだ名が好きだった!
知識を得るための闘いと並行して、イスラエル占領との闘いも続いていた。兵士たちが私たちの生活を困難にしようとするときはいつでも、私たちは制限を回避する方法を見つけた。彼らが私たちを脅そうとしたとき、私たちは一歩も動かなかった。彼らが何をしても、私たちの教育プログラムへのコミットメントは変わらなかった。私の心には、パレスチナと祖母への愛、祖母の決意、祖母の希望、祖母の決意があったからだ。
2013年、私はイスラエルの裁判所命令により、アル・アクサから追放された。追放命令は2カ月間だった。私はその不当な措置に、さらに多くの知識を得る機会を見出した。そこで私はヨルダンに渡り、いくつかのプログラムを受講し、私の専門分野に関するいくつかの資格を取得した。アル・アクサに戻った直後、私はまた15日間追放された。しかし、私はもう一度戻った。今度は、こうした制限や追放の背後にあるのは、アル・アクサを常に襲撃する武装したユダヤ人入植者たちが、その苛烈で、しばしば暴力的な旅路で抵抗を受けないようにするためだということを、より強く意識するようになった。そこで私はこうした: ナレッジサークルの場所を、武装入植者たちの通り道に点在するように変更したのだ。
重武装した兵士に守られながらアル=アクサを襲撃する入植者たちは、モロッコ門(バブ・アル=マグハリブ)からいわゆるツアーを始め、アル=ムサラ・アル=キブリ、マルワン=マスジド、そして慈悲の門(バブ・アル=ラフマ)へと進む。最後に、彼らはしばしば鎖の門(バブ・アル・シルシラ)から出て行った。私が知識サークルを配置換えした後、彼女たちはどこに行っても、勉強し、読み書きし、コーランの詩を朗読し、イスラエル軍の占領に反対する聖歌を唱えているパレスチナ人女性のグループを見つけた。マーシー・ゲートはこのときまで、武装入植者たちが集まり、組織化するためのより広いスペースを与えていたため、いくぶん見捨てられていたが、パレスチナのイスラム教徒の女性たちが学び、教えるためのスペースとなった。武装入植者たちがイスラム教の宗教的な場所で祈るために聖なる岩のドームへ行こうと決めたら、私たちは壁のように彼らの前に並んだ。私たちは一斉に聖典を掲げ、共に 「神は偉大なり」と唱えた。正直なところ、宗教的なユダヤ人男性の多くが、女性の姿は彼らの祈りを犯すと信じていることを私たちは知っていた。そのため、彼らが私たちの聖なる祠を冒涜しようとするとき、私たちは意図的に彼らの正面に立つようにした。
しばらくの間、彼らは私たちの椅子を盗むという戦術をとった。私たちは椅子を敷物に変えた。彼らは敷物も盗んだので、私たちはむき出しの床に座った。彼女たちムラビタットの努力によって、過激派は襲撃ルートを変更せざるを得なくなり、モロッコ門から入って鎖門から素早く立ち去るという象徴的な訪問にとどめた。
より深刻な弾圧は2014年に始まり、ムラビタットの多くが暴力的に逮捕され、何人かは投獄され、何人かは長期間国外追放された。あきらめる代わりに、私たちは移動学校をチェーンゲートの外に移した。私の周りに女性たちを集め、彼女たちの勉強をフォローし、最後は一緒にコーランを読んだ。入植者たちがチェーンゲートから勝ち誇ったように出てくるたびに、私たちは「アッラーフ・アクバル」と唱え、聖典を顔面に掲げ、自動小銃をまったく恐れず、卑猥な言葉にも臆することなく、彼らを待ち構えていた。
モスクへの立ち入りを拒否される女性たちが増えていくのを見て、私たちは、アル・アクサを毎日大勢訪れる観光客に手を差し伸べることにした。私たちは皆、同じような色のTシャツを着て、プラカードに次のような言葉を印刷した: 「私たちがここにいる理由を知っているか?私たちがここにいる理由を知っていますか?私たちはアラビア語と英語で、なぜ兵士たちが私たちの宗教的聖地で祈り、学び、教える権利を否定したのかを説明した。結局、兵士たちは私たちを攻撃し、私たちのプラカードを没収し、私たちのTシャツを着ていたことで多額の罰金を支払わせた。それでも私たちは何度も足を運び、イスラエルによる占領の不当性について話を聞こうとする人たち全員に話しかけた。私たちの容赦ない態度に苛立った兵士たちは、かつてない暴力で私たちを攻撃し始めた。重い棒で私たちを殴り、催涙スプレーを投げつけ、私たちの目や喉を焼き、皮膚を刺激するガスを噴射した。老若男女の女性を殴り、蹴った。私たちを引きずり回し、踏みつけ、唾を吐きかけ、あらゆる卑猥な言葉を使った。それでも私たちは戻ってきた。
2015年、イスラエル軍は 「ブラックリスト」と呼ばれるものを公表した。そこには、アル・アクサ・モスクの敷地内に入ることを許されなくなった女性の名前が記されていた。私の名前はリストの最初のもので、「ブラックリスト」に載った他のすべての人は、あらゆる種類の嫌がらせ、逮捕、軟禁を含む様々な種類の処罰、時には拷問を受けた。私はリストの女性たちに、これは 「ゴールデン・リスト」であり、すべての女性の中で最もパワフルで最も効果的で、「無敵の軍隊」と思われていた軍隊を恐れさせた活動家の名前が載っているのだと言った。その年、私は聖なるラマダン(断食月)にアル・アクサに足を踏み入れることはできないと言われた。このイスラム教の聖なる月の重要性と、ラマダーンとアル・アクサの間の歴史的重要性を考えると、この決定は私の意志を打ち砕くものだった。私の答えは、鎖門の外で断食を断ち切り、他では味わえないラマダン・イフタールをすることだった。
シスターと私は、誰からも愛される比類のないパレスチナ料理、マクルバを大量に調理した。食事はすべて路上で準備され、アル・アクサから強制送還されたムラビタットに提供するためだけでなく、内部にいる人々にも密輸された。マクルバの宴がアル・アクサとその周辺で定期的に開催されるようになったのは、これが最初であったが、間違いなく最後ではなかった。私たちの国民食が私たちの集団的アイデンティティにとって重要であることを理解していた兵士たちは、なぜ私たちがいつもこの特別な料理を作っているのか、その理由について私たちを尋問した。数週間も経たないうちに、私たちはマクルバを作ったことで文字通り調査され、裁判所に出頭するようになった。
2015年はアル・アクサの女性たちにとって特に困難な年だった。私たちはパレスチナ人男性と同じような暴力を受け、同じような拷問を受けた。私たちは占領下の地下牢で長く苦しい夜を過ごすようになった。この苦しみは、イスラエルの裁判所が年末までに、占領下のエルサレムとパレスチナ48年の両方でイスラム運動を全面的に禁止する決定を下すまで続いた。彼らの目的は、パレスチナの若者とアル・アクサ、つまりエルサレムのすべての聖地との関係を強化した「知識のテラス」プログラムの破壊だった。残念ながら、このプログラム自体も中止せざるを得なかった。しかし、これで終わりではなかった。アル=アクサを決して見捨てないという祖母の愛と願いに導かれ、私は自由への闘いにおいて重要な役割を果たし続けられるよう、女性に力を与える方法を探し続けた。
私たちの教育プログラムが暴力的に閉鎖されたにもかかわらず、イスラエル占領は私を標的にし続けた。2016年、私は「知識のテラス」プログラムに関わった教師の一人の裁判中に逮捕された。彼らは7日間私を尋問し、その間私はほとんど足かせをはめられ、武装した刑務所車両であるボスタで独房と取調室の間を移動させられた。この間、私はほとんど手かせ足かせをはめられた状態で、獄舎と取調室の間を武装した囚人用車両ボスタで移動させられた。この間、私は常に屈辱の日々を過ごし、その中には、毎回裸にされるような卑劣な検査も含まれていた。これは私の拘留の最初でも最後でもなかった。私を怖がらせ、精神を崩壊させるために、イスラエルの有罪判決を受けた犯罪者たちと一緒にされたこともあった。またある時は、まるで不潔なトイレのような狭い独房に入れられた。尋問官たちは私を辱め、からかったり、気違い呼ばわりしたりして楽しんでいるようだった。彼らはしばしば私のヒワクチンを脱がせ、ヒワクチンなしで法廷に出席するよう強要した。一度だけ、正当な理由もなく、服をすべて脱がされ、カメラに囲まれた小部屋に座らされたことがある。たった15分の出来事だったが、まるで一生分の出来事だったかのように感じた。
その後数カ月、チェーン・ゲート自体が鉄格子と有刺鉄線で封鎖されたため、私と女性たちはヒッタ・ゲート(バブ・アル・ヒッタ)に抗議活動の場所を移した。必然的に、私たちの数は減り始めた。2017年のラマダンまでには、まだ抗議している女性は私だけになっていた。私は結局、ヒッタ門とライオン門(バブ・アル・アスバット)の間の新しい場所に移った。この新しい場所は今も存在し、抗議者の数は再び増えている。
確かに、私たちの教育プログラムは中断され、多くの女性たちは再び、自分たちの人生の課題に気を取られていた。しかし、私のメッセージと使命は止まらなかった。私はその後、ヨルダンに始まり、クウェート、インドネシア、バーレーン、トルコなど、世界中の多くの国々にアルクッズ、エルサレム、そしてすべてのムラビタットの闘いのメッセージを伝えた。行く先々で、私の聴衆はいつもエルサレムの運命を心配していたが、そのたびに私は、私たちパレスチナ人はイスラエルの軍事占領に対する抵抗の最前線に立ち続けるのだと、彼らを安心させていた。
エルサレムに戻ると、私は多くの生徒たちに連絡を取り、可能な限り、できることを教えた。これもイスラエルの立場からすれば、あまりにも危険であったため、イスラエル占領は私の生活を困難にし続け、私の移動を制限し、旅行する権利を否定した。まず、私は3年間渡航を妨害されたが、その権利を取り戻すやいなや、イスラエルの裁判所は2020年に再びその権利を課した。私と家族は健康保険を拒否され、私を罰するためだけに、意味のないことで常に重い罰金を払わされている。ある日突然、私はヨルダン川西岸地区やエルサレムの旧市街への入国を拒否されたり、服役の代わりに自宅軟禁されたりする。しかし、あらゆる罰の中で最も苦痛を伴うのは、イスラエル兵が私の家に侵入し、子供たちのパソコン、机、ベッドなど、邪魔なものを残忍にも破壊し始めるときだ。押し入るたびに、私の書類や証明書を没収し、手錠をかけられ、しばしば深夜にイスラエルの刑務所に引きずり込まれた。ある時、通りを一瞥すると、イスラエル軍車両、パトカー、特殊部隊が延々と続いているのが見えた。私を尋問するために連れて行った軍のキャラバンは、まるで私が危険な犯罪者であるかのように、とてもうるさく、巨大だった。取調室で、私はイスラエル軍将校の一人に、丸腰の女性を逮捕するのに、なぜこれほど大規模な軍隊を投入する必要があるのかと尋ねた。彼はにやにやしながらこう答えた。
しかし、私はどこにも行かない。私たちの正当な闘いは交渉で決着がつくものではない。もし私たちがこの人生で使命を果たせなかったとしても、別の世代のパレスチナ人が果たすだろう。尊厳、自由、勝利は尊いものだからだ。今、私は大学に戻り、民主主義と人権について学んでいる。私のメッセージ、街頭でのムラビタットのメッセージを、私たちの訴えを聞いてくれるあらゆる国際フォーラムに届けたい。ネット上であれ、アル・アクサ礼拝堂の外の自分の場所に戻ることが許されたときであれ、私はあらゆる機会をとらえて世界に訴えるようにしている。イスラエル占領軍に対する私のメッセージは、私たちは決してあきらめないということであり、パレスチナのムラビタットの新しい世代に対する私のメッセージは、「怖がらないで、自由のための崇高な戦いを続けなさい」ということである。
時々、祖母の心臓が私の胸の中で鼓動しているように感じ、私は祖母のメッセージを世界に伝える単なるメッセンジャーなのだと思う。祖母の遺産は、種を蒔くとき、その実から食べるのが自分でなくても心配するなと教えてくれた。祖母は私の心に種を蒔き、私は子どもたちの心に種を蒔いている。自由のための闘いを続ければ続けるほど、私はより勇気が湧いてくる。神はいつも私とともにいてくださる。神は私に勇気と力を与えてくださる。アル・アクサの城壁の外で、兵士の大群に囲まれて一人で座っているときでさえ、私の内側にはパレスチナ、パレスチナ全体、そしてパレスチナの人々の力が感じられる。
36 このエッセイはアラビア語で書かれたものをラムジー・バルードが翻訳した
1963年2月9日、ヨルダン川西岸北部のナブルスで生まれる。ビルジート大学で経営学の学士号と民主主義と人権の修士号を取得。1994年から2006年までアッダメール囚人支援・人権協会の理事を務め、パレスチナ立法評議会(PLC)(パレスチナ議会)に選出される。現在は、国際刑事裁判所のフォローアップのためのパレスチナ国内委員会の役割に加えて、PLCの囚人委員会の責任者を務めている。
イスラエルの戦争犯罪を国際機関に暴露することに熱心なパレスチナ人指導者としてのハリダ・ジャラールの知名度は高く、彼女はイスラエルによる頻繁な逮捕や行政拘留の標的となっている。彼女は何度も逮捕されており、最初は1989年の国際女性デーに逮捕された。3月8日の集会に参加したため、彼女は1カ月間刑務所に収監された。
2015年、彼女はイスラエル占領軍兵士による夜明け前の襲撃で拘束され、ラマッラにある彼女の家を襲撃した。当初、彼女は裁判を受けることなく行政拘禁されていたが、国際的な反発を受け、イスラエル当局はハリダ・ジャラールを軍事法廷で裁き、彼女の政治活動のみに基づく12の罪状が彼女にかけられた。その罪状の中には、スピーチをすること、警戒活動を行うこと、パレスチナ人被拘禁者とその家族への支援を表明することなどが含まれていた。その後、彼女は15カ月間刑務所で過ごした。
ハリダ・ジャラールは2016年6月に釈放されたが、2017年7月に再び逮捕され、行政拘留された。彼女の家に対するイスラエル軍の襲撃は特に暴力的で、兵士たちは彼女の家の正面ドアを破壊し、iPadや携帯電話を含む様々な機器を没収した。彼女はオフェル刑務所で尋問を受けた後、多くのパレスチナ人女性囚人が収容されているハシャロン刑務所に移送された。彼女は約20カ月を刑務所で過ごした後、2019年2月に釈放された。
もう一度、ハリダ・ジャラールは2019年10月31日にラマッラの自宅から逮捕された。彼女の最新の投獄中に、2人の娘のうちの1人、スハが31歳で亡くなった。ハリダが2021年7月13日に行われる娘の葬儀に参列することを認める国際キャンペーンにもかかわらず、イスラエル政府はすべての訴えを拒否した。しかし、スハに別れを告げるために、ハリダによる手紙が刑務所から密輸された。その手紙にはこう書かれていた:
「スハ、愛しい人よ」
彼らはあなたに最後の別れのキスをすることから私を奪った。
私は花で別れを告げる。
あなたの不在は身につまされるほど辛い、耐え難いほど辛い。
しかし、私は揺るぎない強さを保っている、
愛するパレスチナの山々のように。
ハリダ・ジャラールは、パレスチナの抵抗者たちがイスラエルの刑務所内で、肉体的苦痛や精神的拷問にもかかわらず、反撃の機会を見出して、その堅忍不抜と抵抗を持ち出した多くの例のひとつである。さらに、ハリダ・ジャラールは刑務所を強制的な監禁とみなすのではなく、仲間の女性囚人を教育し、力を与える機会として利用してきた。事実、彼女の獄中での功績は、パレスチナの女性囚人運動の様相を一変させた。
絶望から希望を生み出す
イスラエルの刑務所で抵抗し勝利する方法
ハリダ・ジャラール37
刑務所は、高い塀と有刺鉄線、そして重い鉄の扉のある狭くて息苦しい独房でできているだけの場所ではない。実際、重いドアを閉めるとき、重いベッドや戸棚を動かすとき、手錠をかけたり緩めたりするとき、金属音が最もよく聞こえる。ボスタ(囚人を刑務所施設から別の刑務所施設に運ぶ悪名高い乗り物)でさえ、内装、外装、ドア、内蔵された手錠に至るまで金属製の獣である。
いや、刑務所とはこれらすべて以上のものなのだ。実在の人々の物語であり、日々の苦しみであり、刑務官や管理者との闘いでもある。刑務所は、日々更新されなければならず、決して後回しにすることのできない道徳的立場を賭けている。
刑務所とは同志であり、時が経てば自分の家族よりも親しくなる姉妹や兄弟である。それは共通の苦悩であり、痛みであり、悲しみであり、時には喜びでもある。刑務所では、私たちは同じ意志と決意をもって、虐待を加える刑務官に挑む。この闘いは終わりがなく、食事を拒否する単純な行為から、部屋に閉じこもること、そしてあらゆる努力の中で最も肉体的・生理的にきついものである公開ハンガーストライキに至るまで、ありとあらゆる形で現れる。これらは、パレスチナの囚人たちが、自分たちの基本的な権利を獲得し、尊厳を守るために闘うための手段の一部にすぎない。
刑務所は可能性を追求する芸術であり、食事の準備であれ、古着の修繕であれ、あるいは共通の基盤を見つけることであれ、最も単純で最も創造的な手段を用いて日々の課題を解決する訓練をする学校なのだ。
刑務所では、時間を意識しなければならない。そうしなければ、時間は止まってしまうからだ。だから私たちは、日常と戦い、あらゆる機会をとらえて祝い、個人的であれ集団的であれ、人生におけるあらゆる重要な機会を記念するために、できる限りのことをする。
パレスチナの囚人たちの個々の物語は、パレスチナ人全員が日常的にさまざまな形で投獄を経験しているように、もっと大きなものの表象である。さらに、パレスチナの囚人の物語は、それを生きた人だけに関係するつかの間の経験ではなく、囚人、その仲間、家族、そしてコミュニティ全体を根底から揺さぶる出来事なのだ。それぞれの物語は、あらゆる苦難にもかかわらず、祖国への愛とかけがえのない自由への憧れを胸に鼓動する人が生きた人生の創造的な解釈を表している。
個々の物語はまた、決定的な瞬間でもあり、看守と看守が象徴するものすべての意志と、囚人たちの意志と囚人たちが象徴するもの、団結すれば信じられないような困難を克服できる集団としてのものとの間の葛藤でもある。パレスチナの囚人たちの反抗は、かつて植民地化され、勝利したすべての国々が抱いているのと同じ意志と活力をもって、自分たちの土地で奴隷にされることを拒否し、自由を取り戻そうと決意しているパレスチナの人々の集団的な反抗と反骨精神の反映でもある。
パレスチナの囚人たちが経験した、国際法や人道法に反する苦しみや人権侵害は、刑務所の物語の一面にすぎない。もう一方の側面は、こうした悲惨な体験を通して生きてきた人々によってのみ真に理解され、伝えられるものである。パレスチナの囚人たちの物語にしばしば欠落しているのは、決定的な瞬間を、その痛ましい詳細や困難のすべてとともに耐え抜いたパレスチナの男女の、感動的な人間的軌跡である。
狭い独房に閉じ込められ、愛する母親を失い、足を骨折し、何年も家族と面会できず、教育を受ける権利を否定され、同志の死に直面する。
肉体的な拷問、精神的な苦痛、長期にわたる隔離など、囚人たちが耐えてきた苦しみを理解することは重要だが、同時に、男女が反撃を決意し、本来の権利を取り戻し、人間性を受け入れるとき、人間の意志の力を理解しなければならない。
反撃には様々な形がある。イスラエルの刑務所に政治犯として収監されたさまざまな期間を通して、私もまた、刑務所の壁の中でさまざまな形の抵抗に参加した。私にとって、パレスチナ人女性囚人のための教育は緊急の優先事項となった。
イスラエルの刑務所に収容されている女性囚人は、男性囚人とは扱われ方が多少異なっている。女性受刑者の数は男性よりはるかに少ないので、イスラエルの刑務所当局が彼女たちを完全に隔離することは容易である。しかも、大卒の女性受刑者はごく少数で、彼女たちの教育レベルは驚くほど低い。
2015年にイスラエルに拘束され、そのほとんどをハシャロン刑務所で過ごしたとき、私はすでにこうした事実を知っていた。そこで私は、子どもの頃であれ、困難な社会状況のためにそのような権利を否定された人々であれ、学校を卒業する機会を否定された女性たちの教育問題に焦点を当てることを自分の使命とすることにした。数人の女性が高校卒業資格を取得する手助けができれば、拘置所にいた時間を有効に使うことができる。この卒業証書があれば、彼女たちはできるだけ早く大学の学位を取得し、最終的には経済的に自立することができる。さらに重要なことは、しっかりとした教育で武装した彼女たちは、パレスチナ人コミュニティのエンパワーメントにさらに貢献できるということだ。
しかし、すべての囚人、特に女性が直面する障害は山ほどある。イスラエルの刑務所当局は、正式な教育を受けようとする囚人に対して多くの制限を課している。イスラエル監獄サービス(IPS)は、そのような権利を認めることに原則的に同意しても、教室、黒板、学用品、資格のある教師などの利用可能性を含め、作業を促進するために必要なすべての実際的条件が欠けていることを保証する。
しかし、後者の障害は、私が修士号を持っているという事実によって克服された。パレスチナ教育省から見れば、私は教師として奉仕し、タウジヒと呼ばれる高校の最終試験を監督する資格があるのだ。このアイデアを彼女たちに提案したときの興奮した表情を見ただけで、私はイスラエルの刑務所に収監されているパレスチナ人女性囚人の歴史上初の取り組みであるこの困難な仕事を引き受ける気になった。
私はまず教育省に連絡を取り、その規則と期待、そして最終試験のために勉強したい女性囚人にどのように適用されるのかを十分に理解することから始めた。私の最初の生徒たちは5人の女性で構成され、彼女たちはとても楽しそうにチャレンジしてくれた。
その初期の段階では、刑務所の管理者は私たちの「活動」の本質を十分に理解していなかったので、彼らの制限は技術的、管理的なものに過ぎなかった。実際、私たち全員、特に私にとっては初めての経験だった。授業や最終試験の実施において、高度な学問的プロフェッショナリズムを確保しようとするあまり、自分の期待を誇張してしまったかもしれないことを認めなければならない。私はただ、自分の原則に反することがないようにしたかっただけなのだ。なぜなら、彼女たちが修了証書を獲得し、自分自身にもっと期待してほしいと心から願っていたからである。
学用品はほとんどなかった。実際、IPSによって別の施設に移送される前のパレスチナ人児童囚が残した教科書1冊を、各クラスで共有しなければならなかった。こうすることで、何人かの生徒が同時に授業を受けることができた。生徒たちはよく勉強した。1回の授業が数時間に及ぶこともあり、独房から出ることが許される唯一の休憩時間がなくなることもあった。そのため、独房から出ることが許されるその日唯一の休憩時間を惜しんで過ごすことになった。結局、5人の生徒が試験を受け、結果は文部省に送られて確認された。週間後、結果が返ってきた。人の生徒が合格した。
並外れた瞬間だった。人の生徒が獄中で修了証書を取得したというニュースは、すべての囚人、その家族、被拘禁者の権利を擁護する団体の間で瞬く間に広まった。彼女たちはこの知らせを祝い、同志たちは皆、心から彼女たちを祝福した。あっという間に、私たちは再び動員をかけ、また新たな卒業生を輩出する準備を整えた。しかし、私たちの功績がメディアで注目されればされるほど、イスラエルの刑務所当局は不安を募らせた。IPSが、同じく5人の学生で構成される第2グループが同じ経験をすることを困難にすることを決めたことに、私はまったく驚かなかった。
まさに戦いだったが、私たちはどんな圧力があろうとも、最後まで戦うつもりだった。刑務所の管理者は、私が囚人たちに教えることはもう許されないと公式に通告してきた。彼らは私に何度も嫌がらせをし、独房送りにすると脅した。しかし、私は国際法を熟知しており、囚人の権利を理解し、引き下がるつもりはないことをイスラエル人に何度も突きつけた。このような状況にもかかわらず、私は文部省と協力し、自分で試験を準備しながら、なんとか第2グループの少女たちを教えることができた。今回は受験した5人全員が合格した。大きな勝利だった。
私たちが達成したことを受けて、私は女子受刑者の教育経験を制度化する必要があること、そしてそれを私や誰か一人に縛るのではないことに気づいた。これを長期的に成功させるためには、集団的な取り組みが必要であり、今後何年にもわたって刑務所にいるすべての女性グループによって支持される使命がある。私は、有資格の女性受刑者を訓練することに重点を置き、彼女たちを教育に参加させ、教育省が要求する管理業務に慣れさせた。私は、自分の釈放が間近に迫っていたため、第3期卒業生がスムーズに移行できるような体制を整えた。
私は2016年6月に解放された。私は通常の生活と専門的な仕事に戻ったが、獄中の同志たち、彼らの日々の葛藤や課題、特に彼らが必要とし、またそれに値する教育を受けることを切望している人たちのことを考えることを止めなかった。私が去った後、2人の女性受刑者が最終試験に挑み、無事に卒業したことを知ったときは感激した。解放され、家族と再会したときと同じような喜びを感じた。また、私が釈放前に導入したシステムが機能していることを知り、ほっとした。これは私に将来への大きな希望を与えてくれた。
2017年7月、イスラエル軍は私を再び逮捕し、今度は20カ月間拘束した。私は同じハシャロン刑務所に戻った。以前よりも多くの女性囚人がいた。すぐに、他の資格のある囚人たちの助けを借りて、第4グループの卒業準備を始めた。今回は9人の女囚が試験勉強をしていた。ボランティアの教師や管理者も増えた。刑務所は突然開花し、学習とエンパワーメントの場となった。
刑務所の管理者は発狂した!彼らは私を扇動したと非難し、一連の報復措置を開始した。私たちはその挑戦を受け入れた。彼らが教室を閉鎖したとき、私たちはストライキを起こした。ペンや鉛筆を没収されると、代わりにクレヨンを使った。黒板が持ち去られると、窓のフックを外してそこに書いた。黒板を部屋から部屋へとこっそり持ち運んだ。刑務官たちは、私たちの教育を受ける権利を阻止するため、あらゆる手を使ってきた。刑務所当局を打ち負かす決意を示すため、私たちは第4グループを 「反抗の集団」と名付けた。結局、私たちの意志は彼らの不正義よりも強かった。私たちは全過程を終了した。最終試験を受けた少女たちは全員、見事に合格した。
あの数日間、私たちがどのように感じたか、単なる言葉では言い表せない。大きな勝利だった。私たちは刑務所の壁を飾り、祝った。イスラエルと刑務所の不公平なルールに団結して立ち向かったからだ。このニュースは刑務所の壁を越えて広がり、パレスチナ全土で卒業生の家族による祝賀会が開かれた。第5グループは、その集団的達成の栄冠だった。それは、教育を受ける権利を主張しながら、私たちが耐えてきた数ヶ月の闘争と苦難の後の甘い報酬だった。2015年に最初の体験が開始されて以来、修了証書を取得した他の18人の女性卒業生に加わるべく、現在さらに7人の学生が最終試験に向けて勉強している。
特に、すべての人にとって基本的人権であるはずのものを得るために多くのことを耐えてきたのだから。Tawjihi証明書を取得した者たちは、より高いレベルの教育に進む準備ができている。しかし、文部省はこのステップにまだ対応していないため、囚人たちは一時的な代替手段を作っている。
私は民主主義と人権の修士号を持っており、アッダミールやPLCなどでの活動を通じてこの分野での長年の経験もあるため、学生たちに国際法と人道法のトレーニングコースを提供した。このコースを教えるために、私はジュネーブ条約のアラビア語訳を含む、人権に関する国際条約に関する最も重要で関連性の高い文書を刑務所に持ち込むことに成功した。これらの文書の中には、赤十字から持ち込まれたものもあれば、刑務所に面会に来た家族から持ち込まれたものもあった。
コースには49人の女性囚人が参加し、それぞれ2カ月の期間に分かれていた。コース終了後、参加者は36時間の国際法・人道法の研修を修了した証明書を受け取り、その成果はパレスチナの複数の省庁によって確認された。私たちが獄中で祝う一方で、外では囚人省主催の大規模な式典が開かれ、家族や解放された囚人の何人かが出席し、盛大な祝賀の渦に包まれた。
結局のところ、私たちは絶望から希望を作り出しただけではない。私たちはまた、私たち自身、刑務所、刑務官に対する捉え方において、物語を進化させた。私たちは劣等感を打ち破り、刑務所の壁をチャンスに変えたのだ。刑務所で高校教育を終えた生徒たちの美しい笑顔を見たとき、私は自分の使命が達成されたと感じた。
刑務所における希望とは、石から生える花のようなものだ。私たちパレスチナ人にとって、教育は最大の武器だ。教育があれば、私たちは必ず勝利する。
37 ハリダ・ジャラールのこのエッセイは、ラムジー・バルードの著書『これらの鎖は断ち切られるだろう』に初めて掲載された: イスラエルの刑務所におけるパレスチナ人の闘争と反抗の物語』(クラリティ・プレス、2019)に初めて掲載された。ジャラールはこの本にエッセイを寄稿することに同意していたものの、イスラエルによる不法な拘束が長期化し、寄稿が不可能になった。本書の原稿は、2021年9月26日の釈放前に完成した。
JAMAL JUMAA エルサレム生まれ。ヨルダン川西岸のビルツァイト大学でアラビア文学の学士号を、ロンドンのシティ大学でMBAを取得した。過去30年間、パレスチナ社会の市民社会組織や草の根運動での活動や仕事を通じて、多くの仲間とともに、また小さな取り組みから始めて、重要な組織や草の根運動を立ち上げ、そのほとんどが現在も活動中で、パレスチナの市民社会やパレスチナの大義に影響を与えている。これらのイニシアチブのほとんどは、提供するサービスに対する深刻なニーズから、あるいは占領政策の結果として生じた危機的状況への対応として生まれた。
パレスチナ農業救済委員会(PARC)、パレスチナ文化交流協会(PACE)、パレスチナ環境NGOネットワーク(PENGON)など、多くの市民団体を共同で設立した。PENGONでの活動を通じて 2002年の「壁と入植に反対する民衆キャンペーン」(STW)の設立に貢献した。
草の根キャンペーンでの活動の中で、またパレスチナの闘いに対する国際的な支援を組織する緊急の必要性の一環として 2005年のBDS全国委員会の設立にSTWの活動の中で貢献し、現在もSTWを代表して同委員会の事務局メンバーである。2013年には、多くの草の根運動やイニシアティブ、組織の傘として機能する土地防衛連合(LDC)の設立に活動家や草の根組織とともに取り組み、それらの間の連携と協力を強化し、草の根の民衆基盤の拡大に努めた。
同時に、こうした努力の一環として、STWとLDCは、同僚やヨルダン渓谷の民衆委員会と協力して、ヨルダン渓谷の住民、特に対象となるコミュニティが直面する課題に対応するための努力を統合する枠組みとして、ヨルダン渓谷保護民衆評議会を設立した。
民衆の抵抗とBDSについて
パレスチナ闘争の未来38
ジャマール・ジュマー
1993年のオスロ合意の調印は 2002年のイスラエルによるヨルダン川西岸への侵攻よりもはるかに深刻で危険な影響をパレスチナ人に与えた。というのも、オスロ合意はパレスチナ革命の価値観と原則を覆し、パレスチナの地図を縮小・断片化し、数十年にわたってパレスチナ人の意識に植え付けられたパレスチナの教育カリキュラムと不可侵の国家理念を歪めたからだ。1948年のナクバ、1967年のナクサ、その他数え切れないほどの虐殺やパレスチナ人の強制移住など、パレスチナの闘いにおける重要な出来事を、協定は事実上無視した。ハイファ、アクレ、ナザレ、ヤッファ、ロド、ラムレといったパレスチナの都市は突然パレスチナ人として存在しなくなり、「イスラエルの敵」という言葉は無言となった。
左翼といえども、PLOという沈みゆく船を救う安全弁として機能することはできなかった。それどころか、彼らはアイデンティティと実存の危機に沈んでいった。ソ連と社会主義陣営の崩壊後、私が所属していたパレスチナ共産党(PCP)は大きな危機に陥り、その結果、党のイデオロギー的アイデンティティを放棄し、党名をパレスチナ人民党(PPP)に変更した。その後、党員の多くが離党した。同様のストーリーは、パレスチナ解放人民戦線(PFLP)とパレスチナ解放民主戦線(DFLP)についても語ることができる。
オスロ合意がもたらした危機の大きさは、私たちパレスチナ人にとって明らかだ。オスロ合意は、占領を終わらせるどころか、占領地域を 「A、B、C」に行政的に分割するなどの重要な問題で最終的な解決に至らず、占領を制度化した。これにより、とりわけイスラエルは、ヨルダン川西岸地域の60%以上を占めるエルサレムとC地区における植民地プロジェクトを維持し、さらには強化することができた。
多くのパレスチナ人、特に第一次インティファーダの活動家と同様、私は、次の民衆蜂起は必然的にPAに反対し、オスロ合意に抗議するものになるだろうと予想していた。しかし 2000年の第2次インティファーダは、ただでさえ恐ろしい現地の現実を悪化させた。
実際、PAはパレスチナ国家プロジェクトの維持に失敗した。そのお粗末な統治慣行と相まって、汚職、縁故主義、賄賂、エルサレムとヨルダン川西岸におけるイスラエルの行動に対する沈黙、パレスチナの抵抗勢力、特にハマス、パレスチナ・イスラム聖戦(PIJ)、PFLPのメンバーに対する弾圧、司法制度と人々の生活に対する支配がある。また、財界人とPAの治安サービス、組織、政治エリートが手を結んだことで、縁故資本家も出現した。その結果、占領体制と利権を結びつけ、パレスチナの国家プロジェクトを脅かすブルジョア階級が台頭した。彼らは、イスラエルへの経済的依存を強め、第一次インティファーダの間に発展した抵抗経済とでも呼ぶべきものを根絶やしにすることによって、そうした。その結果、中産階級は縮小し、貧困ライン以下で暮らす幅広い層が形成された。
1996年から1999年にかけてベンヤミン・ネタニヤフ率いるリクード党が政権を握ると、入植活動の凍結が終わり、入植地拡大のペースが上がった。私は当時、パレスチナの環境に対して宣言されていない戦争が行われていることに気づいた。入植地からの廃水のほとんどはパレスチナの農地に流れ込み、土地や作物を破壊し、湧き水を汚染した。ヨルダン川西岸地区は結局、1948年以前のパレスチナ(イスラエル)からの廃水を含む、固形廃棄物や有害廃棄物の処分場となった。イスラエルによるパレスチナの景観と環境の破壊には、ガザの緩衝地帯のように、ほとんどが安全保障を口実にした樹木の伐採も含まれる。イスラエルのブルドーザーは、70年代、80年代、そしてそれ以前にヨルダンや他のアラブ諸国に何百トンもの柑橘類を輸出していた果樹園のほとんどを破壊した。
1999年、私はパレスチナ水文学グループ(PHG)と協力し、イスラエルの組織的な環境破壊に立ち向かうため、パレスチナ環境NGOネットワークを設立した。私は、90年代初頭に農業救済に携わっていた関係で、同グループのマネージャーや他の機関の理事たちと友好的な関係を築いていた。このネットワークには、1967年当時、占領地で活動していた12のNGOが参加しており、割り当てられた予算がないにもかかわらず、その活動を進めることが課題だった。PHGはネットワークの場所と後方支援を提供し、私の資金調達との戦いが始まった。
これが私にとって、NGO活動の力学、資金を確保するための手段、資金を配分するために国際的なドナーが設定した条件に初めて触れる機会となった。このことは、通常、相反する理想を根底に持つ国際機関と現地との相互作用を理解するのに役立つ。この相互作用の危険な側面のひとつは、NGOと彼らが所属する政党との関係であり、自由に使える資金力のために、NGOの影響力が、彼らが代表する政党の影響力よりも強くなっていることである。
これらのサービスベースの民衆的イニシアチブは、政党の市民的支部を代表するものであり、政党とその民衆を結ぶ重要なリンクであると同時に、インティファーダまでの期間、人々を政党の仲間に引き入れる強力な手段でもあった。すべてではないにせよ、こうしたNGOのほとんどは左翼に属していた。もう一つのタイプのNGOは、和平プロセスと両国民の共存を推進することを背景に登場した。これらのNGOの目標は、パレスチナ人とイスラエル人の関係を、地方や地域レベルで正常化することだった。
私の最初の仕事は、ネットワークのウェブページをデザインし、環境問題に関する資料を作成することで、このプロジェクトはUNDP/PAPから資金援助を受けていた。ウェブページのデザインとコンテンツが完成すると、NGOはこの仕事のスポンサーであることを認めるという条件を出してきた。しかし、デザインの内容を知った彼らは、そのウェブページが、「国内向け」であることを理由に提携を断った。イスラエルによる民族への侵害や環境破壊について語ることは罪なのか?私がしたことは、環境とこの土地でのパレスチナ人の生活の未来に対して、違法入植地が犯した国際法に反する犯罪を取り上げただけで、武装抵抗や平和的抵抗については一切言及しなかった。これは、私たちが直面している戦争が、いかに私たちの意識を抑制し、民族文化を歪め、パレスチナとの関わりを断ち切ろうとしているかを例証している。明らかに、このNGOはその後資金提供を打ち切った。
2000年9月から2002年3月のヨルダン川西岸地区への侵攻までの第二次インティファーダの最初の1年間、環境破壊は甚大だった。何千本ものオリーブの木が、軍や入植者の車を撃つ者の盾になるという口実で、幹線道路沿いで伐採された。都市への入り口は閉鎖され、ゴミ収集車はパレスチナの都市から出ることを拒否された。
それは、イスラエルによるパレスチナの景観と環境の破壊を世界規模で暴露すること、そして、正常化を推進し、「地球の友・中東」(FoEME)のメンバーであったネットワーク内の2つのNGOの解散を実現することであった。私はまた、世界最大の環境保護団体であるFoEMEをFriends of the Earth Internationalから脱退させたかった。FoEMEは、パレスチナ、イスラエル、ヨルダン、エジプトを代表してこの世界的ネットワークに参加することを主張しており、ロビー活動、圧力、南側のグループとの2年以上にわたるネットワークでの同盟関係の構築を経て 2004年に実現した。正常化を推進する2つのグループは、最終的に2002年初めにネットワークから追放された。
第2次インティファーダ(またはアル・アクサ・インティファーダ)は、第1次インティファーダと同様の民衆蜂起として始まった。殉教者の葬儀のために何千人もの人々がアルビレ墓地に出かけると、複数の殉教者を連れて帰ってきたことを思い出す。イスラエル占領政府は 2000年9月28日にインティファーダが勃発して以来、蜂起を鎮圧するために、弾圧、殺害、虐待、そして明白な集団処罰を行う権限を与え、その軍隊を解き放った。
インティファーダは、イスラエル軍による弾圧、虐待、殺戮に見舞われ、まさにイスラエルが望んでいた軍事化に至った。その後、パレスチナの武装グループや派閥旅団は、幹線道路で入植者や軍のパトロール隊を攻撃し始め、占領軍による連日の犯罪に呼応して、後にイスラエル国内でも作戦が展開された。これが、アリエル・シャロンの命令によるイスラエルのヨルダン川西岸侵攻につながった。当時、私は外国人ジャーナリストとともに、主に政治指導者や市民との面会を促進する仕事をしていた。私は 2001年9月11日の同時多発テロの直後、特にジョージ・ブッシュが対テロ戦争を宣言した後、パレスチナの諸派がこれらの作戦を終了させることを望んでいた。私は、イスラエルがこのキャンペーンを利用して、私たちの闘いに汚名を着せ、私たちを国際的に孤立させるために、そのレッテルを私たちに貼るだろうと予想していた。
イスラエル軍は戦車を使って2002年3月29日にヨルダン川西岸に侵攻し、パレスチナ自治政府本部を爆撃し、道路をブルドーザーで破壊し、都市や村の入り口を壊し、ヨルダン川西岸を包囲し、都市や村を互いに遮断し、キャンプに侵入し、侵入したすべての都市や村で虐殺を行った。これらの虐殺の中で最も凄惨だったのは、悪名高いジェニン難民キャンプの虐殺だった。
イスラエルのいわゆる「防御の盾」作戦が、純粋にパレスチナの抵抗勢力を攻撃し、壁(アパルトヘイトの壁)の建設に備えてヨルダン川西岸を再占領するために実行されたものであることは、誰も気づいていなかった。作戦開始から2カ月後の6月、ヨルダン川西岸がまだ戦車に包囲されていた頃、250台近い車両が、ジェニンの北に位置するサレムからカルキリヤの南西に位置するマスハまでの145キロの壁建設の第一段階と銘打たれ、グリーンラインに沿ったヨルダン川西北部の農地を荒らし始めた。同時に、彼らはエルサレム周辺の多くの地域をブルドーザーで破壊し始めた。
オスロ段階とパレスチナ人との交渉が終わったことを象徴的に宣言したのだ。イスラエルはその後、植民地的アパルトヘイト体制を通じて、地理的地域の将来とパレスチナ人との関係について、一方的な離脱計画から始まるビジョンを独裁し、強要し始めた。これはシオニスト・プロジェクトのイデオロギーに基づくもので、大イスラエルは「川から海まで」広がり、その境界線内にはできるだけパレスチナ人を入れないと考えられている。
このプロジェクトは、オスロ合意で定められた行政区画に基づいていた。そのため、イスラエルはヨルダン川西岸地区のA地区とB地区を囲むように壁を建設し、ヨルダン川西岸地区の62%を違法入植地拡大のために隔離することを計画した。ここで、ヤーセル・アラファトはパレスチナ自治政府を解散させ、イスラエルに対する承認を撤回し、占領国であるイスラエルに、第一次インティファーダ以前のように、支配下にある全住民に対する責任を取らせるべきだった。しかし、アラファトは長生きできるはずもなく、アメリカやアラブからの絶大な圧力にさらされ、本部では戦車に取り囲まれていた。2004年にヤーセル・アラファトが他界した後、この2人が任命された。
草の根大衆運動の開始
ヨルダン川西岸北部のパレスチナ人農民たちは、農地、温室、灌漑網、井戸、貯水槽の破壊という、第三のナクバの可能性について声を上げ始めた。都市と町の間の移動は非常に困難だった。街路にはまだ戦車が走り、いたるところに軍事障壁が築かれていたからだ。私はヨルダン川西岸地区北部のネットワーク代表と連絡を取り合い、イスラエルが農地を破壊し始めてから2カ月後の8月末に、カルキリャのアスラ村で農民たちとの会合を開いた。参加できる者は、カルキリヤとトゥルカルムの村から参加した。私はいくつかのNGOの同僚と同行した。集会は荒れ模様で、40人近くの農民や活動家が参加した。そのうちの何人かの叫びが、今でも耳に残っている: 「これは第3のナクバだ。PAは壁の建設に同意したようだ。彼らは私たちのためにすべてを台無しにし、土地を略奪した」
ショックを受けた私たちはラマッラに戻った。翌日、私たちネットワークの調整委員会は、この計画を暴露するキャンペーンを始めることにした。NGOの中には、この活動を促進するために寄付をしてくれたところもあった。PHGは、トゥルカルム県での農業救援、ジェニン県での医療救援に加え、カルキリヤ県でジェイユス村の近くから作業が行われるよう手配した。私はラマラを出発し、これらのNGOやその関連団体の活動的な同僚と連携しながら、各州を移動した。壁の影響を受けた村々で会議を開き、影響を受けた農民、村のグループ、地元の指導者の代表を選び、それぞれの村で民衆委員会を結成した。民衆委員会という考え方は、第1次インティファーダで統一指導者委員会を結成した私たちの経験にさかのぼる。これらの委員会は当時、「民衆運動委員会」または「民衆委員会」と呼ばれていた。各人民委員会には代表する村の名前が記されていた。
さまざまな村の農民たちは、壁について、イスラエルが自分たちの村や家を農地から切り離し、村全体を互いに隔離しようとする試みであるという点で一致していた。つまり、アパルトヘイトである。私たちが始めたキャンペーンは、「アパルトヘイトの壁に抵抗する民衆キャンペーン」と呼ばれた。この呼称の背景には2つの要因があった。1つは、植民地時代のアパルトヘイト慣行と同レベルにある壁プロジェクトの性質とその結果である。つ目の要因は、農民たちが自発的に、このプロジェクトをアパルトヘイトの壁と正確に表現したことである。
民衆の抵抗の課題は、パレスチナ人が毎日流血し殺されているにもかかわらず、市民デモを組織し、人々を参加させることだった。また、抗議行動を100%平和的に維持することも同様に困難だった。一人の人間が銃器を使用すれば、平和的な運動は頓挫しかねない。委員会は、ジェニンのザブーバやアニンに加え、トゥルカルムのジェイユース、フラミヤ、カルキリヤ、バッカ・アル・シャルキヤ、ファルアン、アル・ラスなど、多くの場所で毎日デモを組織し始めた。これらの抗議行動はすべて伝統的な民衆集会に徹しており、抗議行動が平和的であることの必要性を強調する必要はなかった。
デモはしばしば早朝、ブルドーザーが働く現場で行われ、ブルドーザーを無力化した。初日、ブルドーザーの作業を中断させることに成功した。肥沃な農地は農民とその家族の主な収入源であり、それゆえ彼らの活動は毎日行われていた。ブルドーザーや接収から土地を守るためなら、人々は犠牲もいとわなかった。
民衆の抵抗には、非常に重要な側面があり、それは国際連帯である。イスラエルの犯罪に対抗して、国際連帯は第二次インティファーダとともに再浮上し始め、連帯代表団がパレスチナに到着した。イスラエルの侵攻の間、彼らのグループはいくつかのキャンプで人間の盾を形成し、ヤーセル・アラファトとともに本部にいた。イスラエルが壁の建設を始めると、私たちは連帯活動家たちの注意をそこに向けさせ、タアユシュ(共存)運動(イスラエル左派のユダヤ人と1948年地域のパレスチナ人を含む)と並行して、国際連帯運動(ISM)が形成され始めた。ここで特徴的なのは、連帯活動家が広場の大衆活動に参加したことである。
2003年のマスハ・テントのようなデモ、座り込み、テントへの外国人やイスラエル人の連帯活動家の参加は、一種の混乱を引き起こし、彼らの参加の性質を定義する必要がある新たな次元を加えた。イスラエル情報機関に逮捕された女性抗議に参加した人々の一人は、連帯グループの一員であるかのように装い、テントにいたイスラエル人将校によって調査された。もう一つの問題は、彼らが村の住民と直接交流・接触したことで、これもまたいくつかの社会問題を引き起こし始めた。すなわち、連帯運動に関与する一部の人々が、連帯委員会のメンバーとしての権限を超えて、自分たちが許容できると考える抵抗の形態や、使用すべきスローガンの種類に口を出し始めたのである。これは民衆の抵抗にとって不健全かつ持続不可能なことであり、パレスチナ国民の間での人気に影響を与えた。
この問題を議論するために、私はトゥルカルム、カルキリヤ、ジェニンの人民委員会の代表を集めた会議を始めた。これはいくつかの問題を解決するために必要であったが、その中で最も重要だったのは、人数が増えるにつれて連帯グループとの意思疎通のプロセスを促進するために委員会を再編成することと、タアエシュをはじめとするイスラエルのグループや国際連帯運動とどのような関係を築くべきかを決定することであった。第二の問題は、壁に関連する用語の使用に関する論争と、このプロジェクトの性質とその目的に関する根本的な理解であった。これによって、次の段階で採用する作業戦略の性質が決まることになる。ネットワークの調整機関(民衆委員会のキャンペーンの傘下)内では、絶えず議論が交わされた。メンバーの中には、壁を 「アパルトヘイトの壁」と呼ぶことに反対する者もいた。パレスチナ自治政府もこのレッテルを拒否し、代わりに「併合と拡張の壁」と呼んだ。このレッテルに反対するNGOの前提は、資金源に関係している。欧州の機関がこのレッテルを受け入れない限り、必要な資金を提供してもらえないことを恐れたのである。私に言わせれば、PAは「アパルトヘイト」というレッテルを過激主義を示唆するものとみなし、それゆえ欧米諸国を怒らせると考えていた。
私たちは2003年6月末にトゥルカルムで会議を開いた。この会議は、キャンペーンの条件、政治的な所属や関係を決定する上で非常に重要だった。特に、一部の活動家と特定のNGOとの関係から、会議がどのような方向に進むのか、間違いなく私は危惧していた。会議は、イスラエルの壁建設計画とその波及効果について、また、それが地域レベル、国際レベルでの抵抗戦略のあり方をどのように決定するかを分析的に紹介することから始まった。私はまた、民衆の抵抗、私たちの活動を支配すべき一連の価値観と原則、一方では委員会と村落との関係、他方ではイスラエルや外国の連帯委員会との関係を管理・規制する必要性についても話した。会議の最後に、各委員会は以下の詳細な点を採択した:
1.各委員会との関係を分散化することに重点を置き、各県の人民委員会を県内の全村を代表する単一の委員会に統合するよう努力する。
2.パレスチナ人の大義を終わらせ、パレスチナ人の闘争と不可侵の権利を排除することを目的とする植民地アパルトヘイト計画の枠組みを形成するアパルトヘイトの壁であることから、民衆運動が壁の本質とその背後にある政治的意味を理解することに重点を置く。
3.人民委員会の指導部と決定がパレスチナ人であることを重視し、タアユシュとISMの役割は、パレスチナ人の闘いを支援し、イスラエルと国際世論を変えるための連帯に限定されること。会議の終わりに、私たちは年末までの活動プログラムに合意した。
この決定を踏まえて、私たちはイスラエルのタアエシュ運動とISMとの会談を要請し、活動の原則について合意した。会議はトゥルカルムのアル・ジャワリッシュ村で開かれ、私と2人の委員会代表が出席し、私たちの立場を説明した。彼らは回答する前に検討する時間を求めたが、私たちの提案に対する回答は得られなかった。これを受けて、私たちは委員会を通じて彼らの参加を組織することにした。
ジェニン北部のサレム村からカルキリヤ東部のマスハ村までの全長145キロの壁建設の第一段階は 2003年半ば、つまり1年以内に完了した。当時、私たちはこの段階を記録した最初の本をアラビア語と英語で発行した。この重要な本は、主に国会、国際機関、大使館に2万部以上配布された。
2003年9月、私は国連から壁について話すよう招待を受けた。その招待状が提案したトピックのタイトルは、「壁は平和の障害となるか?」だった。個人的には、この見出しが挑発的で嫌な感じがした。国連はまだ、壁が平和の障害になっているかどうかを問うているのだ。彼らが言っている平和がどのようなものなのかはわからない。
私はこの招待を受け、この本の要約をビデオ・プレゼンテーションとして準備し、壁建設の第一段階を地図、写真、分析に裏打ちされた形で紹介した。会議での私の講演枠は10分だったが、中断することなく約20分間話し続けた。私が提供した情報は明らかに聴衆に衝撃を与え、壇上から降りるとすぐに、私はナセル・アル=キドワ駐米大使に話をした。彼はこのファイルを総会に提出し、そこから国際司法裁判所に提出する責任を負ってくれた。会議終了後、アメリカのいくつかの州を訪問し、壁について話をするツアーが組まれた。
この訪問が、国際レベルでのキャンペーンの活動の始まりとなった。その後、多くの会議やツアーに参加し、パレスチナ人の将来と自由を求める闘いに対する壁とその政治的・経済的影響について語った。このような交流の中で、私は特にヨーロッパで、つらい現実に遭遇した。どんな会議やワークショップでも、私の隣には「善良な」イスラエル人が座っていなければならなかったのだ。私はこのアプローチに、暗黙の人種差別的言説と、入植者=植民地主義者の占領下で暮らすパレスチナ人に対する植民地主義的な見方を見た。ヨーロッパ人があなたの言うことを信じるには、あなたの側に白人のイスラエル人がいなければならない。私たちは、解放後、何世代にもわたって占領による苦しみを克服しなければならない。自由と尊厳を奪われたことの意味や痛みについて語る立場にあるのは私たちなのだ。当初、私は、たとえ反シオニストであっても、イスラエル人の登壇を拒否した。
民衆キャンペーンの内部的な活動やネットワークの対外的な活動が活発化するにつれ、私とネットワークの調整委員会との間に意見の相違が深まっていった。大衆運動は大衆運動として台頭しつつあった。その活動に求められるものは、ネットワークの活動とは異なっていた。後者は環境問題に関連するグループや団体の努力を調整することに限られており、前者は民衆の政治的行動であり、市民社会組織の事務的・戦略的仕事とは相容れない抵抗の形態である。したがって、私たちはネットワークの調整委員会で、民衆キャンペーンをネットワークから切り離し、キャンペーンの運営組織を変更して、各州の民衆委員会の代表が調整委員会を構成してキャンペーンを運営することにした。ネットワークの各組織は、委員会にネットワークの代表の居場所を残すよう要求した。
2004年11月のヤセル・アラファト大統領の死後、PAではアメリカとイスラエルに支持されたアラファト大統領の対立候補がアラファト大統領に取って代わった。一人目は、PLO創設者の一人で、70年代からイスラエルとの交渉による和平実現を強く主張し、オスロ合意の立役者でもあるマフムード・アッバスである。もう一人は、世界銀行の名物行員であるサラーム・ファイヤドだ。こうしてパレスチナの生活と闘争に新たな局面が到来した。それはまず、米国のキース・デイトン将軍が監督する新しい安全保障ドクトリンによるパレスチナ安全保障サービスの再編成と形成に基づくものだった。パレスチナ人の間では、これは 「デイトン・ドクトリン」と呼ばれている。このドクトリンは、アメリカ、ヨーロッパ、イスラエルの諜報機関も監督している。第二に、新しい段階には、パレスチナ社会の経済的ライフスタイルや考え方を変えることを目的とした、新自由主義政策の採用と経済開放が含まれていた。2005年、PAは、壁に抵抗する民衆運動がパレスチナと国際世論に影響を及ぼし始め、それが示す政治的言説がその政治体制と方向性を困惑させたことに気づいた。PAの活動は、イスラエルが地上の政治地図上で起こしている根本的な変化や、イスラエルがパレスチナ国家樹立の問題を迂回するアパルトヘイト体制の強化にかかわらず、交渉のサイクルとイスラエル占領との安全保障上の協調強化に限定されていた。2007年、委員会の活動を共同利用しようと、サラム・ファイヤドは2度にわたって、ヨルダン川西岸一帯の民衆抵抗活動家のために銀行口座を開設し、委員会の活動を支援するために毎月6,000シェケルを預金することを申し出た。私たちは人民レジスタンス運動のファタハ活動家と調整し、会議を2度にわたって失敗させた。
オスロ後の時代の破壊的な影響は、地上のパレスチナ人闘争にとどまらず、国際連帯にも影響を及ぼした。1970年代と80年代、そして第一次インティファーダまでは、パレスチナの大義に対する国際的な支援は、南の国々や世界の革命運動からもたらされた。第一次インティファーダでは、ヨーロッパやアメリカでパレスチナとの連帯委員会が結成されるまでに支援が拡大した。しかし1990年代には、連帯の形態が変化し、パレスチナNGOと連携した市民社会組織によって主導され、ヨーロッパとアメリカに限定されるようになった。この支援は、国際法や、EUや国連といった公的な国際機関のもとで認められている範囲内で行われた。要求は、イスラエルの責任を追及するための強制力のある効果的な手段を設けることなく、イスラエルに圧力をかけようとするものだった。労働組合や民衆運動は、その場からほとんど姿を消した。
パレスチナの草の根「反アパルトヘイトの壁」キャンペーンは、国際連帯を本来あるべき位置に回復し始めた最初の団体の一つであった。第一に、明確なビジョンと国際社会からの要求があった。第二に、人民の富を流出させ、植民地主義を永続させることを目的とするイスラエルを含む帝国主義勢力と資本主義勢力の同盟に代表される人民の共通の敵に基づく相互連帯の枠組みの中で、連帯の基礎を築いた。後者の2つの例が際立っている: 多国籍企業(TNC)、そしてイスラエルによる独裁政権や民兵の武装と訓練である。これらの企業や政権は、革命を抑圧し、レジスタンス指導者を暗殺するために利用している。第3のポイントは、世界社会フォーラムのような大規模な国際社会フォーラムへの積極的な参加に関するものである。このフォーラムには、さまざまな国から何千もの機関や運動が参加し、毎年1週間にわたって会議を開催している。私たちは、1年間積極的に参加した後、この会議の国際準備委員会のメンバーとなった。私たちが初めてフォーラムに参加したのは2004年のインドで、パレスチナは最終声明の中で世界の紛争地のひとつとして言及された。2005年の最終声明にはパレスチナに関するパラグラフがあり、2012年には、国際社会フォーラムは 「社会フォーラム・グローバル/フリー・パレスチナ」の名の下に、会議をパレスチナに充てた。第4に、委員会は、諸民族の苦しみと共通の闘いに光を当てる共同連帯キャンペーンを開始した。2017年、私たちはメキシコ、ブラジル、アメリカの先住民運動、人権団体、連合とともに、「壁のない世界」という名の国際キャンペーンを開始した。このキャンペーンは現在、World30カ国以上に広がり、植民地主義と抑圧の壁がヨーロッパ、アメリカ、ラテンアメリカ、カシミール、アラブ世界の人々や移民に与える影響を浮き彫りにしている。
BDS運動の開始
2003年、私たちは多くの国際会議や会合を開き、外国代表団にイスラエル・ボイコットの問題を提起した。私たちの立場は、アパルトヘイトの壁に反対する私たちの闘いと、イスラエルがヨルダン川西岸において、アパルトヘイトの南アフリカと同様の危険なアパルトヘイト体制を制度化しているという理解に基づいていた。そして私たちは、アカデミック・ボイコット運動とBADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights(パレスチナ人の居住と難民の権利のための学術ボイコット運動とBADILリソースセンター)と直ちに議論を開始した。私たちは、ボイコット、ダイベストメント、サンクション(BDS)運動の創設声明について深く議論し、その創設原則を表す文書に発展させた。
私たちは、パレスチナ内外の図や機関との議論やブレーンストーミングを含め、丸1年かけてこの文書の作成に取り組んだ。最大の課題は、イスラエル・ボイコット要求の基礎となる、パレスチナ人全員が同意できる包括的な言説を見つけることだった。言説と言及のレベルでこの課題を完了させることが、BDS運動の成功に寄与する最も重要な要因であった。したがって、パレスチナ人民がそのどちらにも同意していないため、この運動が二国家解決策や一国家解決策に基づく政治的解決策を言説に採用することは不可能であった。
正当な闘争に対するいかなる解決策も、最終的には人民が闘う要求と権利を達成しなければならない。パレスチナの問題は、彼らが受けている不正や侵害に対する権利の問題である。提示された解決策は複雑だ。彼らに降りかかった歴史的不正義の大きさを考えると、私たちの民族のために絶対的な正義を実現することは、近い将来には不可能に思える。それゆえ、植民地化された人々を服従させ、抑圧し、追い出すために最先端の近代技術を駆使している植民地化した側に有利な大きな力の不均衡を考えれば、1つや2つの国家について語ることは、政治的な贅沢や特権となる。
そのため、この運動の声明は、パレスチナ人も国際連帯活動家も異論を唱えない人権を包括的に取り上げることを基本にすべきであると合意された。声明は3つの基本的権利を採択し、これらの権利を実現するために、イスラエルのボイコットと、イスラエルが国際法を尊重するまで制裁を実施することを要求した。これらの基本的権利とは、パレスチナ人の50%を占めるパレスチナ難民の帰還の権利、パレスチナ人の12%を占める1948年以前のパレスチナ(現イスラエル)に住むパレスチナ人の人種差別と不平等を終わらせること、そして最後に、1967年以来続いている占領地シリアのゴラン高原を含むアラブ地域の占領を終わらせることである。
この声明は、パレスチナ内外の171のパレスチナ人グループと団体によって署名され、その代表者が運動の総体を形成し、さらにその総体が運動の事務局を形成している。その決定とリーダーシップはコンセンサスによって確立される。
こうしてBDS運動はパレスチナ人の一体感を回復し、国際的な連帯を結束させ、活動家たちに効果的で影響力のある連帯の手段を提供した。従って、パレスチナの人々は、南アフリカの人々の例外的な経験に触発され、人類の闘いの国際主義の概念を強化した。
BDSの最大の功績は、パレスチナの人々に希望を取り戻させ、自分たちの闘いは自分たちだけではないということを認識させたことである。この運動のリーダーシップ・スタイルは、パレスチナ人に対する陰謀が絶えることのない雰囲気の中で、純粋さを示す輝くパレスチナの模範となっている。
このエッセイの最後の行を書いている今も、フムサのベドウィン一家は、イスラエルによって根こそぎ破壊され続けている何十もの他のパレスチナ人コミュニティと同じように、占領軍に追われながら、廃墟の上でテントのようなシェルターで暮らしている。ブルドーザーとトラックで武装した憎悪と恐怖に染まったギャングたちが、根こそぎ移動させるために、シェイク・ジャラー地区とシルワン地区のパレスチナ人を強制的に浄化し続けている。
38 このエッセイはアラビア語で書かれ、アーメド・アルマスリによって翻訳された
RAJI SOURANIは、個人的・職業的な犠牲を強いられながらも、専門家としてのキャリアを通じて、パレスチナ被占領地における人権の促進と保護に尽力してきた。1977年に弁護士資格を取得して以来、弁護士として活躍し、人権侵害の被害者を幅広く弁護してきた。そのキャリアの中で多くの栄誉を受けており、最近では2013年に「ライト・ライブリフッド賞」を受賞した。
イスラエルで政治犯として投獄された時期や、イスラエル軍からの長年の嫌がらせや暴力、パレスチナ自治政府や他のパレスチナ人グループからの嫌がらせにもかかわらず、スーラニは人権への揺るぎないコミットメントを維持してきた。彼は、国内および国際レベルでの基本的人権基準の擁護者であり、イスラエル、パレスチナ自治政府、政治団体、その他の国家が人権基準を遵守していないことに対する率直な批判を抑えることを拒否してきた。
このような障害に直面しながらも、スラーニは1995年にガザ地区で仲間の弁護士や人権活動家たちと設立したパレスチナ人権センターを通じて、人権の促進と保護を続けている。スーラニは設立以来、この受賞歴のあるセンターの陣頭指揮を執り、ガザ地区における人権侵害の被害者に法律その他のサービスを提供し、正義と賠償を求めることができるようにし続けている。
献身的な家庭人であるスーラーニは、同様に献身的で理解ある家族に恵まれており、最悪の時を乗り越えて愛と励ましを与えている。特にスーラニの妻は、彼の仕事が彼らの生活にしばしば大きな犠牲をもたらしてきたにもかかわらず、最強の支えとなってきた。
第二次インティファーダの時代やイスラエルによるガザ地区への攻撃(キャスト・リード作戦)の際に示された最近の困難にもかかわらず、スーラーニは、センターが最大限の犠牲者にサービスを提供し続けるという強い決意を持ち続けてきた。彼はこの目的を達成し、センターはガザ地区とパレスチナ被占領地全域で直面する課題に効果的に対応し続けている。
国際法を通じてパレスチナの救済を追求する
ラジ・スーラニ
パレスチナ人の生活は、70年以上にわたって、広範かつ組織的な国際法違反によって特徴付けられてきた。イスラエルが建国され、パレスチナ人が大量に移住させられて以来、私たちはナクバと呼ばれる災厄に見舞われ、併合、軍事占領、アパルトヘイト、抑圧に耐えてきた。パレスチナ人としての私たちの生活は、強制移住と、自己決定権、健康権、移動の自由、差別の禁止、拷問の禁止、生命権そのものに至るまで、事実上あらゆる人権の侵害によって特徴づけられる。
私たちは、その違反を通して国際法を知っている。
パレスチナ人なら誰でも、幼い子どもたちでさえ、戦争犯罪をよく知っている。独立した存続可能な国家としての成長を妨げる違法入植地建設のための土地と資源の窃盗から、無差別攻撃や故意の殺害まで。病院や医療従事者、ボランティア、ジャーナリスト、障害者、子どもたちに対する攻撃にも慣れっこになっている。家族全体が抹殺された。私たちにとって、戦争犯罪を目撃することは、息をするのと同じくらい普通のことなのだ。
世界はそれを知っている。私たちの苦しみはテレビのゴールデンタイムの定番となり、常に報道されるようになった。ガザに降り注ぐ白色火薬の光景や、シュジャイヤのような地区全体の完全な破壊、より良い生活や未来を求めた罪で非武装の抗議に参加した人々が殺害されることは、誰もが知っている。
このような現実を前にして、なぜ私たちは国際法を信頼するのか、なぜ国際法が私たちの未来への道しるべになると考えるのかを問うのは正当なことだ。
私にとって、国際法に目を向け、その可能性を見出すようになったのは、徐々に進んだプロセスだった。私は弁護士、裁判官、検事の家系に生まれ、1970年代後半にキャリアをスタートさせたとき、政治犯を訪ねるのは自然なことだった。私の実兄は、1967年のガザ占領後、囚人の「早起き組」の一人だった。当時の私はナイーブだった。私はよく刑務所に行き、「拷問を受けましたか?」と尋ねたものだ。肉体的なダメージが見られなければ、拷問はなかったと思い、先に進んだ。心理的な拷問がどういうものなのか、その傷跡がどれほど深いものなのかは知らなかった。
その後、私自身が逮捕され、その個人的な体験をした。「適度な肉体的・心理的圧迫」の本当の意味を理解した。最悪の虐待ではなかったとはいえ、その中で生きているうちに、1日に50回は死にたくなった。占領下の「正義」が何を意味するかも身をもって知った。尋問の際、私は虚偽の供述書に署名するよう強要され、拒否すると拷問に戻された。何度も繰り返された。囚人が数分で拘束されたり、判決を下されたりするカンガルー法廷の現実を目の当たりにした。占領下のこの法律は、私が訓練された法律ではなく、私が信じた正義でもないと知った。
やがて私は、囚人たちの生活がどれほど悲惨なものであるかを理解し始め、国際法に真剣に目を向けるようになった。イスラエルの法律にはパレスチナ人に対する説明責任はない。私は赤十字国際委員会と緊密な関係を築き、獄中にはジュネーブ条約のコピーを持って来てくれた。そして、私たちが使える言葉が見えてきた。ジュネーブ条約は、世界中の国が批准している法律で、私たちのような状況を想定して作られたものだ。私たちの現実を規定するものだった。
刑務所を出て、個人で法律事務所を開業した後、私は囚人の弁護に時間を割くことにした。囚人たちを見捨てることはできない。軍の命令に異議を唱え、カンガルー法廷をやめさせ、適正手続きのようなものを導入するためにできることをしなければならない。私は占領下の正義などという幻想は抱いていなかったが、被害を最小限に食い止めるために最善を尽くし、達成できる勝利のために闘うべきだと決心した。私はすぐに圧倒された。実務の傍らで細々とやっていたはずの仕事が、やがて私の仕事のすべてとなり、私は汚れた時代の目撃者となった。
私は、事件の適切な記録と国際法の活用が強力なツールであることに気づいた。レトリックを超えることができた。もはや私たちは「ただ」要求するだけではなかった。私たちには、「政治的」な主張として片付けられない国際法や国際基準があったのだ。私はアムネスティ・インターナショナル、国際法曹協会、国際法律家委員会といった国際組織と関わり始めた。また、イスラエルのユダヤ人、パレスチナ人双方の弁護士や人権団体とも実際に関係を築き始めた。これが私たちと「向こう側」とのつながりであり、私たちの共同作業と友情は、私たちが人間性を共有していることを日々思い起こさせるものだった。
国際法は、私たちに共通の言語と関与の枠組みを与えてくれた。私たちは出勤し、イスラエルの法制度と法廷で闘うために、すべての時間と労力を費やした。私たちは制度を利用し、国際人道法とジュネーブ第4条約を法廷での私たちの言葉に導入しようとした。そして次第に、イスラエルの法廷で正義を追求するだけでは十分ではないという結論に達した。
90年代、私は「権利と法のためのガザ・センター」を引き継ぎ、後に「パレスチナ人権センター」となるチームを作り始めた。私たちは弁護士やアドボケイトのチームを作り、コミュニティ全体に人脈を作り始めた。また、国際的にも積極的に働きかける努力をした。パレスチナで起きている国際法違反を丹念に記録し、私たちの活動を国際社会にアピールした。
80年代に築き始めた人間関係が実を結び始めた。国際法律家委員会は私たちにとって非常に重要だったし、ヨルダン川西岸を占領したアル・ハークとの関係もそうだった。やがて私は、国際法律家委員会の執行委員会のメンバーとなり、国際人権連盟(FIDH)の副会長となった。この国際的なプラットフォームによって、私たちは世界に向けてメッセージを発信することができるようになった。私たちは国連でのイベントに参加し、南アフリカから南米までの草の根組織と関係を築くようになった。私たちは抑圧と闘った経験を共有し、互いに学び合った。この連帯はとても重要だ。それは、自分はひとりではないということを思い出させてくれる。また、私たちがどれほど異なっていても、正義のための闘いを共有することで私たち全員が団結していることを思い出させてくれる。
しかし、重要なのは、私たちができる限り国際的な活動を行いつつも、常にガザの地にしっかりと足を踏みしめていることだ。ここが私たちの本当の活動の場であり、イスラエルの法制度における活動をやめることはなかった。占領下での真の正義が可能だと感じているからそうしているのではない。そうしなければならないからそうするのだ。クライアントのために可能な限りの手段を追求し、不正の目撃者とならなければならない。裁判所や法制度そのものが実際にどのように機能しているかを記録しなければならない。私たちの経験を記録しなければならない。軍事裁判所からイスラエル高等法院に至るまで、イスラエルのシステム全体が、戦争犯罪や人道に対する罪の組織的な遂行を完全に法的にカバーしているのだ。私たちがイスラエルの司法制度を「使い果たした」こと、そして正義が否定されたことを示すことは、国際的な法的救済を求める上でも必要である。これによって私たちは、国際刑事裁判所であれ普遍的管轄権であれ、国際的メカニズムに頼ることができる。
占領下の正義はまったく正義ではない、と私たちが言ったところで、誰も信じてはくれないだろう。手放しで否定されるだろう。イスラエルの裁判制度は世界最高レベルだと信じている人は多い。しかし、もしそうなら、イスラエルの法律がローマ法のようなものである限り、主人のための法律と奴隷のための法律があり、前者にのみ適用される。私たちの法的活動がなければ、私たちの批判は政治的なものとして脇に追いやられてしまうだろう。人々は、私たちが、「パレスチナ人であるだけ」だと考えるだろう。
しかし、私たちは言葉の強さで判断されることを求めてはいない。私たちの仕事の強さで判断してほしい。私たちのドキュメンテーションと国際法の活用は、規範的で法的な用語で状況の現実を明確に描写する言葉を私たちに与えてくれる。人々は私たちを政治的な動機に基づくパレスチナ人だと見下したがるかもしれないが、十分に文書化された事例や明確で健全な法的分析を否定することは不可能だ。私たちを信じない人には、弁護士に相談して私たちの仕事を検証してもらうことを勧める。
1990年代後半、私たちは国際司法の可能性をより積極的に模索し始めた。当初から、私たちは国際刑事裁判所を支持してきた。それは、法が差別なく誰にでも平等に適用され、最も深刻な国際法違反の責任者が最終的に責任を問われるという、美しくも不可能に見える夢だった。
1998年に国際刑事裁判所のローマ規程が最終的に採択されてからわずか数カ月後、普遍的管轄権の原則に基づき、アウグスト・ピノチェト将軍が英国で逮捕されたというニュースが、稲妻のように私たちを襲った。これは革命だった。個人が拷問や戦争犯罪の容疑で他国で逮捕され、責任を追及される可能性が出てきたのだ。国際刑事裁判所の立ち上げと運営には何年もかかるだろうが、普遍的管轄権はすぐにでも追求できるものだった。このことは私たちに新たな焦点とエネルギーを与え、私たちは事件の準備と戦争犯罪容疑者リストの動きの監視に膨大な労力を費やした。
私たちは2002年10月29日、英国でシャウル・モファズの逮捕を求める初の普遍的管轄権裁判を起こした。モファズは1998年から2002年7月9日までイスラエル国防軍の参謀総長を務めていた。申し立ての対象となったのは、ジュネーブ条約の重大な違反、戦争犯罪、人道に対する罪など、広範な深刻な違反である。当時、モファズは国防大臣であったため、個人的な免責が与えられていた。しかし、英国検察庁は、モファズの任期が終了すれば、この件が再検討される可能性があると指摘した。
これは私たちに希望を与え、その後数年間、私たちは世界中から熱心な弁護士や人権活動家を集め、優れた弁護団を作り上げた。私はこの活動を誇りに思っている。2003年9月、パレスチナの被害者を代表して、ベルンのスイス軍法務長官に、パレスチナの家屋の大規模な破壊と5件の拷問に関する2件の訴状が提出された。被疑者はベンジャミン・ベン=エリザー(元イスラエル国防相)、シャウル・モファズ(元国防総省参謀総長)、ドロン・アルモグ(元国防総省南方軍司令官)、アヴィ・ディヒター(元イスラエル治安総局長)であった。訴状は、指揮命令責任の原則に照らして、被告たち個人の刑事責任に基づいて提出された。しかし、スイス軍検事総長は、被告人の誰もが提訴時にスイス国内にいなかったため、提訴を却下する実質的な理由ではなく、手続き上の理由であるとして、この事件を起訴しないことを決定した。
こうした結果を受けても、私たちはあきらめなかった。それどころか、戦争犯罪人の責任を追及し、法の支配と被害者の権利を回復するための努力を強化してきた。
すべての事件が公表されているわけではないし、容疑者の中には逮捕される可能性のある国への渡航を待っている者もいる。とはいえ、イギリスではツィピ・リブニ、ニュージーランドではモシェ・ヤロン、オランダではアミ・アヤロンの逮捕状を確保した。劇的だったのは 2005年、南方軍前司令官ドロン・アルモグの逮捕状を取ったことだ。2005年9月11日に飛行機が着陸した瞬間、彼は逮捕される可能性があった。しかし、英国警察はアルモグのボディーガードが武装しているという噂があったため、航空機への搭乗を拒否し、イスラエル大使館からの密告を受けたアルモグは飛行機を降りることなく、そのままテルアビブに戻った。
2009年1月29日、スペインの判事が、イスラエルによるガザ空爆で15人が死亡した2002年のアル=ダラジの大虐殺をイスラエル当局が適切に調査する意思がないと判断し、普遍的管轄権裁判を開始した。これは、当時ガザ地区で最も残忍で致命的な攻撃であった「キャスト・リード」作戦の数日後のことであった。それは、国際犯罪の疑いをかけられたイスラエル政府関係者が責任を問われる可能性があること、そして彼らが法の上にいるわけではないことを明確に思い起こさせるものだった。ガザが廃墟と化した暗黒の時代に、この事件は私たちに希望を与えてくれた。
私たちの普遍的管轄権に関する活動を批判する人たちがいる。しかし実際には、私たちは本当に重要なことを2つ行った。第一に、世界で最も尊敬されている法制度のいくつかにおいて、私たちは訴追可能な事例があると裁判官を説得した。これは有罪判決には結びつかなかったが、裁判官たちが起訴を必要とするほどの証拠を信じていることを明確に示した。これを軽々しく否定することはできない。第二に、私たちはイスラエル軍と政府高官に対し、彼らが法の上に立つ存在ではないこと、そして私たちは善良でおとなしい被害者のふりはしないことを思い知らされた。私たちは正義と説明責任を求めて闘うことを止めず、世界中に追随していく。
しかし近年、普遍的管轄権を追求することはほとんど不可能になっている。あまりに政治的な干渉が多すぎて、実現可能な選択肢とは言えなくなっているのだ。たとえばイギリスでは、イスラエル政府の圧力によって法律そのものが変更された。
国際刑事裁判所が唯一の選択肢となった。パレスチナが国際刑事裁判所に加盟した2015年は、長年のフラストレーションの後、新たな時代を迎えた。私たちは当初から国際刑事裁判所を支持し、何年もの間、裁判所の注目を集める方法を見つけるために戦ってきた。私たちは大きな圧力や脅威に直面し、時には不可能と思われることもあった。イスラエルによる2014年のガザ侵攻作戦(Protective Edge)が転機となり、ようやくラマッラーのパレスチナ自治政府が規約を批准するかに見えたが、ガザの事実上の政府の支持なしには批准しなかった。私たちは、ハマスやイスラム聖戦を含むすべてのグループをテーブルに着かせる上で重要な役割を果たした。2021年、国際刑事裁判所検事局による捜査開始は大きな飛躍だった。パレスチナ人に対する犯罪に対する説明責任の新たな時代の幕開けとなることを期待している。言うまでもなく、私たちは、強力な政治的圧力が被害者の司法へのアクセスを妨害しようとすることをよく知っている。2020年、ドナルド・トランプ前米大統領が、国際刑事裁判所のファトゥ・ベンソウダ前検事やその他の裁判所関係者(およびその家族)に対して制裁を科したことは記憶に新しい。
今、私たちには2つの闘いがある。私たちはイスラエルの法廷でクライアントの弁護を続け、達成できる勝利のために闘い、国際刑事裁判所の捜査に全面的に関与している。
国際刑事裁判所での私たちの活動のために私たちが直面した圧力は、私に衝撃を与えたが、それはこの活動がいかに重要であるかを証明するものでしかない。私たちは国際法を悪用していると非難されてきた。私たちはテロ組織の手先だとも言われている。イスラエル戦略・外交省は、私たちが個人や組織として名指しされている『Terrorists in Suits』という文書を国際的に配布した。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ前首相は、イスラエルに対する戦略的脅威として、私たちに対する調査を開始することを検討した。私たちはイスラエルに対して「法戦」を行っていると主張されている。
なぜイスラエルは、国際刑事裁判所で働くパレスチナ人と国際弁護士の小グループをそれほど心配するのか?私たちは魔法の公式など使っていない。私たちは事実を法的に文書化し、国際基準を適用する。我々の見解では、イスラエルが組織的に戦争犯罪や人道に対する罪を犯していることを示している。しかしイスラエルは国際刑事裁判所には加わらないだろう。彼らは世界最高の弁護士と膨大な資源を持っている。しかし、彼らは裁判所をボイコットしている。なぜなのか?私たちの所見に同意しないのであれば、なぜ法廷の向こう側で私たちと向き合わないのか。
私は生涯を占領下で生きてきた。私は67歳で、これが私の人生の物語だ。私には国籍がない。私は完全にイスラエルの支配下にある。しかし、私は法の支配と私たちが共有する尊厳を信じている。私たちはロマンチックな革命家だ。私たちは歴史の正しい側にいて、正義は達成されると固く信じているが、その道のりは容易ではない。
今、振り返ってみて、私は国際法についてどう思うだろうか?この道を追求する価値はあったのだろうか?
オスロ合意は大きな教訓だった。私たちはそれに反対し、そのために大きな圧力を受けた。しかし、私たちが反対したのは、それが国際法を正しく反映していなかったからだ。人権なくして平和はありえない。人権に基づかない未来をどうやって築くことができるのか。安全保障のために法の支配、民主主義、人権を犠牲にすることはできない。これがオスロ合意を支持したアメリカとEUの論理であり、そうすることで、彼らはその後の人権侵害のすべてを事実上正当化した。私たちは反平和的だと非難されたが、この欠陥協定がアパルトヘイトの新ブランドを生み出すだけだとわかっていた。それ以来数年間に起こったことは、政治が国際法を凌駕した場合に何が起こるかを日々思い起こさせるものである。オスロ合意は、私たちの権利に対する信念に忠実であり続けること、そして権利の追求において権力に真実を語ることの重要性を私たちに思い起こさせる。
私たちは国際人道法や国際人権法を発明したわけではない。これらの法律は戦争の惨禍から生まれたものであり、より良い未来への希望を共有するものであった。ジュネーブ条約は世界中のすべての国が批准している。私たちは、ジュネーブ条約を利用することを政治的な声として否定されることはない。そのような非難は、加害者である当事者にのみ予想されることだ。私たちが世界各地で確保した逮捕状や、国際刑事裁判所が捜査を開始するために私たちが果たした役割によって、私たちの訴えの法的説得力は証明されている。
国際法は、私たちが平等であることを示す手段である。私たちが求めているのは、法の平等な適用であり、私たちが他のすべての人と同じように扱われ、他のすべての人と同じように法の下の権利を享受することである。実際、他の人たちと同じように、私たちが責任を問われることも含まれる。これが、私たちが2つの柱で活動している理由である。私たちは、占領による犯罪についてイスラエルの責任を追及し、占領がなかったかのようにパレスチナ人グループの責任を追及する。それ以外に方法はない。
時には、私たちの法的分析が時代を先取りすることもある。2001年の人種差別撤廃世界会議で、私たちはイスラエルと占領下のパレスチナにおけるパレスチナ人の扱いについて、イスラエルをアパルトヘイトの罪で告発する声明を発表した。この結論は当時、多くの人々に衝撃を与え、大きな論争を引き起こした。それから20年後、まずイスラエルの人権団体B’Tselemが、次いでヒューマン・ライツ・ウォッチが同じ結論に達した。これは、私たちの原則と、私たちには権利を得る権利があるという信念を貫くことを思い出させるものだ。
私たちは弱肉強食の中で生きている。私たちが要求すること、闘うことはシンプルだ。法の支配を求める。我々はパレスチナ人の正義と尊厳にコミットしている。だからこそ、説明責任が不可欠なのだ。
私たちは 「良い犠牲者」を演じるつもりはない。私たちは、長い闘いであることを承知でこの仕事に取り組んでいるが、あきらめる権利はない。明日は我々のものだ。
第3章 解放、文化、教育について
GHADA AGEEL アルバータ大学政治学部客員教授: Hard Laws and Harder Experiences』と『Women’s Voices from Gaza』シリーズの編集者である。パレスチナ難民の3世であるエイジール博士は、英国のエクセター大学で中東政治学の博士号と修士号を、ガザのイスラム大学で教育学の学士号を取得している。強制移住に対する権利に基づくアプローチ、比較の視点からのパレスチナ難民、オーラルヒストリー、アラブ・イスラエル紛争を研究テーマとしている。
「来年のベイトダラス」
私たちの物語を取り戻す、私たちの物語を語る
ガーダ・アギール
私は物語を聞き、共有することが大好きだ。祖母のカディヤは毎晩、孫たちに実話や作り話を語って聞かせた。前者の物語には、1948年のナクバと祖国喪失で破壊される前の私たちの村、ベイト・ダラスの物語が含まれる。これらの物語には、私たちが守るべきバドラサウィの伝統が語られている。どこから来たのかと聞かれたら、私たちは誇りを持ってベイト・ダラスから来たと答える。祖母は情熱と愛情を込めて、自分の物語、パレスチナの物語を語った。この瞬間まで、私は子どもたちに物語を聞かせながら、同じ表情と体の動きでこれらの物語を繰り返すことができる。これらの物語は、私の人生、そしてかなりの程度、私のビジョン、さらには私の未来を形作った。祖母の語り口は、私の語り人生のレシピとなった。祖母の語りは比喩や抽象的なものではなく、体現された肉体的なものだった。祖母は神話としてではなく、現実に起こった物語を追体験していたのだ。聞き手として、私たちはそれに応えた。彼女の声が軋んだり、壊れたりしたとき、私たちの心も同じように軋んだ。こうして彼女は、個人的なことも政治的なことも語り出した。幸せのスプーン1杯と悲しみのスプーン2杯だ。
この短いエッセイの中で、私は私たちの物語/歴史の一部を共有したい。それは主流派の物語に対抗するものであり、このような個人的な記述の小さな部分が、共同体的なもの、権利と自由を求める集団的なパレスチナの闘いの明確なイメージを伝えることができればと願っている。この章はまた、道徳的、認識論的なレベルで読者を招き入れ、パレスチナに課された知的アパルトヘイトを打ち破る新たな対話の場を開くことを目的としている。この記述は、本巻の他の部分と同様、周縁に位置する人々の生活を会話と研究の中心に据えることで、脱植民地化のビジョンを提示し、脱植民地学に貢献しようとするものである。
私は、もはや世界地図には存在しないベイト・ダラスという村のパレスチナ難民3世である。私は、ナクバ時代に故郷と土地を追われた祖母ハディヤの長男である父アブデラジズから難民の遺伝子を受け継いだ。彼女は、貧困、悲惨さ、一夜にしてすべてを失う屈辱と闘いながら、過酷で残酷な人生を送ってきた。ベイト・ダラスが破壊されてから数十年後、ガザ地区の難民キャンプで育った祖母は、私に私たちの村の話をしてくれた。当時(1970年代後半)、「パレスチナ」という言葉を口にすることさえ危険だった。私たちは祖国に関することを学んだり、読んだり、所有したりする権利を否定されていた。祖母は、自分の物語を伝えることで、歴史的な否定というギャップを埋めようとした。ラムジー・バルードの言葉を借りれば、私たちの失われた村の物語は、「共同体としての私たちの内的関係を単純に定義する日々の物語」(2009)だった。カディヤは、自分の村の物語を語れば死者が墓から蘇るわけでも、ベイト・ダラスが復活するわけでもないことを知っていた。しかし、物語を語ることは、ベイト・ダラスが人間の記憶や歴史から追放されるのを防ぐのに役立つだろう。それはまた、収容所で生まれた新しい世代である私たちが、自分たちの歴史を学び、保存する助けにもなるだろう。それが彼女の使命であり、かなりの程度、彼女はそれに成功した(Ageel 2016)。
カーン・ユーニス難民キャンプは、祖母と私の両親がベイト・ダラスにある元の家に戻るまでの間、仮の住まいとしていた場所だ。カーン・ユーニスは、私が生まれ、育ち、教育を受けた場所でもある。1987年から1993年までの第一次インティファーダの6年間、イスラエル軍が午後8時から午前6時まで夜間外出禁止令を出したとき、ガザの他のパレスチナ人と同様、祖母も父も私も、毎晩家に監禁された場所でもある。ここは、私が押し込まれ、圧迫された場所であり、自分の土地に亡命したような気分にさせられた場所である。ここはまた、私がベイト・ダラスとパレスチナ、そして2016年に他界し、キャンプ内の家族墓地(71年前に彼女が追放された村、ベイト・ダラスではない)に埋葬された抵抗の壮大な塔である祖母のことを常に想う場所でもある2)。
貧困の壁に穴を開け、太陽の下で居場所を確保し、ベイト・ダラスとの距離を縮めるために、収容所で生まれた世代である私たちは、幼い頃から教育が前進する道であることを教えられた3)。毎年行われるタウジヒ試験(高校卒業試験)は、パレスチナ解放の暦の中で重要な瞬間である。戦時中でさえ、試験が中止されることはほとんどなく、延期されるか先延ばしにされるだけである。試験結果が発表される喜びの瞬間は、国民が生徒たちのどんな困難にも打ち勝つ能力を称える、歓喜の瞬間である。
だから、ガザのキャンプにいる他の人たちと同じように、私の両親も私たちの教育に多大な投資をした。夜間外出禁止令や学校の閉鎖、第一次インティファーダの間(それ以前も)に続いた攻撃や嫌がらせにもかかわらず、私はたゆまず勉強し、良い学校に入るために必要な高い成績を取った。タウジヒの結果が発表されたとき、私の家族はとても誇らしげだった。父のアブデラジズは、私の功績を祝うために、大きな紅茶を淹れ、サルバナ・チョコレートを箱買いし、我が家のムフタールであるサラー・アキルがアラビック・コーヒーを用意するディワンに駆けつけた。
残念ながら、ガザでは幸せは長くは続かない。1988年、イスラエルがパレスチナの全大学を閉鎖するという決定を下したことで、私だけでなく、その年にタウジヒを終えた1万8千人の学生が高等教育を受ける機会を奪われたのだ。その束の間の喜びは一瞬にして奪われた。占領軍の決定は私の夢を打ち砕き、深い絶望のどん底に突き落とした。進学のために大学に入る日を夢見ながら、私は丸6年間待たなければならなかった。その間、私は自分の夢にしっかりとしがみつき、決してその夢を風化させることはなかった。マフムード・ダルウィッシュは正しかった: パレスチナ人は希望という不治の病にかかっている。しかし、私にとっては、希望の火種に火がつくのに丸1カ月かかった。その1カ月間、私は自分の置かれた状況を理解することができなかった。私にとって、空は墜落したのだ。1988年は1948年のナクバの年のようになり、私自身のナクバは、考える能力、理性的な会話をする能力さえも奪った。
私の涙を見た祖母は、「フィ・エル・ハラケ・バラカ」と言った。そう、「感動には祝福がある」ということわざは知っている。そして父は、私が学校の朝のプログラムの準備をしていたときに習い、気に入っていたことわざのひとつ、『牢屋の小さな窓から、二人の囚人が外を見つめていた。私たちは今でも、どこを見つめるか選ぶことができる」と、私の部屋に入り、私が床を見ているのを見て言うのだった。私は、喪失感と宙ぶらりんの状態から抜け出そうとする家族の絶え間ない試みに対して、ほとんど何の反応も示さなかった。私はその1カ月間、自分の部屋やベッドで泣きながら過ごし、ナクバと向き合うことができなかった。
そしてある朝、私は泣き疲れて眠り、気分が悪くなって目が覚めた。部屋の天井と床を眺めるのに疲れた。体が痛くて、動きたかった。息が詰まりそうで、もっと広い空間が必要だった。空を見るのが恋しかった。みんなが寝るのを待って、夜中の12時頃に部屋を出て、小さな庭に座ってガザの広く澄んだ空を眺めた。それはとても美しく、満天の星だった。間違いなく、ガザの空は私が今まで見た中で最も美しい空だ。私は何時間も眺め続け、この空の美しさと偉大さを深く吸収した。突然、私の中で何かが動いた。父と祖母の言葉が頭をよぎった。その時、軍のメガホンからキャンプの夜間外出禁止令の解除を告げる声が聞こえた。近所の人たちが目を覚まし、家に入り始めた。キャンプ内の家々はとても近接しているため、彼らが動き回っているのが感じられた。イマームがファジュル(朝の)祈りの呼びかけをしたので、私は祈りに行った。私は内なる平和を感じた。一日の活動に向けて目覚めた周りの人々と同じように、私もまた動く必要があった。
インティファーダの間、若者たちは多くの時間を手にしていた。逆説的だが、占領という制限そのものが、アクティビズムやコミュニティ活動のための肥沃な土壌を作り出したのだ。そこで翌週、私はキャンプの社会問題を管理するインティファーダのボランティア・チームに加わり、学校閉鎖中の若い学生たちを支援する教育委員会に参加した。夜間外出禁止令違反で兵士に逮捕されるのを避けるため、時には壁から壁へと飛び移り、生徒の家に行かなければならなかった。月給は8ドルで、そのうち4ドルが交通費だった。翌1991年には、夜間に開講されるヘブライ語のクラスにも登録した。パレスチナ人男性の多くはイスラエルで労働者として働いていたのでヘブライ語を知っていたが、女性はほとんど話せなかった。私は、毎日キャンプを砲撃し、石を投げる子どもたちを追いかける占領軍兵士とのコミュニケーションが必要だと感じていた。インティファーダの間、夜間外出禁止令がたびたび出された。16歳から64歳までの男性は定期的に家を出て通りに出るよう命じられ、家宅捜索や尋問を受け、逮捕されることもあった。同時に、兵士たちは一軒一軒家宅捜索を行い、私たちの家を荒らし回った。言語が何らかの助けになるように思えた。ヘブライ語がわかったからといって、待遇が変わるわけではないが、架け橋にはなる。時には、パレスチナ人のユーモアのセンスが、私たちの共通の人間性を表現することを可能にし、それが助けになった。
私の親戚のアフマドがそうだった。ある日、カン・ユーニスへの外出禁止令が数時間だけ解除された。女性だけが生活必需品を買うために外出を許された。アーマドは気にしなかった。彼はジャラビーヤ(アラビアの民族衣装)を着て、ロバと荷車に乗り、家族のために小麦粉を買いに出かけた。彼は兵士たちに捕まり、命令を破ったとして殴りかかり、脅し始めた。兵士たちは、路上で許されるのは女性だけだと彼に言い聞かせた。誰が私が男だと言った?私は今日から女だ。私のドレスを見てください……私たちは私の家で入れ替わりました」と彼は続けた。「ある日は女で、ある日は男だ。幸運なことに、今日は女なんだ。だから、私は出て行く。妻の前で約束を破れというのか?” 兵士たちは笑って彼を家に帰した!
1992年末、和平プロセスが始まったばかりの頃、ガザのいわゆるイスラエル民政局(教育、保健、社会問題を監督する機関)は、ナターニャ市にある全寮制の語学学校、アキバ言語学院でヘブライ語を学ぶための奨学金を4人分支給すると発表した。当時、私はヘブライ語のコースを3つ終えていたので、応募した。そのうちのひとつを勝ち取ったときは、大喜びだった。問題は、私がイスラエルで1年間勉強することを家族にどう説得するかだった。祖母と母は即座にその考えを否定し、叔父たちも同様だった。「私たちの社会を破壊し、私たちの土地を奪った者たちから何を学べるというのか」と祖母は言った。母が一番心配していたのは、長女だがまだ若く独身の娘が危険な環境で暮らすことだった。祖母は、私がよそ者、つまり私たちの土地を占領するためにやってきた入植者や新参者と交わることを心配していた。私たちの親戚や近所の人たちは、それぞれに不安や心配を抱えていた。リスクや不安にもかかわらず、父はこれをチャンスだと考えた。私の教育への情熱に突き動かされ、卒業後の職を確保できる可能性に興奮した父は、雨の降る夜のかなりの時間、母と話をした。キャンプ内の静寂を破る二人の声が聞こえ、私は母が自分の決断を考え直してくれるよう祈っていた。家族の不安が私の心の中にも入り始めた。その夜はほとんど眠れず、朝になると母が私を起こした。母は私を信じて、「行っていいよ」と言ってくれた。ホッとすると同時に、大きな責任を背負わされたことを実感し、私はバッグに荷物を詰めて出発した。
ガザとイスラエルを隔てるエレズ交差点を通り、祖母の物語に出てくるパレスチナ(現在のイスラエル)に足を踏み入れた瞬間、私は時空を超えたような感覚に陥った。自分のキャンプから何千キロも離れた、まるで別の惑星に移動したような気分だった。カーン・ユーニスから1時間足らずの距離にいることが信じられなかった。ベイト・ダラスから追放されたときの祖母の言葉を思い出した。ガザに一歩足を踏み入れた途端、楽園から砂だらけの丘に放り出されたような気がした、と。(カン・ユーニスの地形は当時、砂の丘だった)しばらくの間、私は砂の丘から祖母の言う失われた楽園に投げ出されたような気がした。
しかし、その感覚も束の間だった。日常会話の中で、私は不公平、不平等、人種差別のレベルの高さを認識するようになった。10分間のシャワーを浴びるのが楽しみで、授業に遅刻してきたイスラエル人の生徒の話を今でも覚えている。教師にとっては、授業時間は尊重されるべきである。私にとっては、この問題は不平等であり、時間の問題ではなかった。家族全員に割り当てられているのと同じ量の水を、どうして一人の個人が一回のシャワーで消費できるのか?そう、私たちを含むガザキャンプの各家庭・家族には、1日に15分の水が割り当てられていたのだ。また、東ヨーロッパ、主にロシアからやってきた白人の外国人入植者たちと授業を共有するのは、気まずく辛い経験だった。彼らは、私の土地とは何の関係もないが、勉強し、生活し、市民権を得る特権を享受していた。しかし、土地の先住民である私たちは、いまだに難民キャンプで戦っている。ガザの難民キャンプと化した砂の丘に放り込まれなかったら、自分の人生はどうなっていただろうかと想像し始めた。
勉強を終えてから1カ月後、私はガザ市のある学校で教師の仕事に就いた。職を得ることは、ガザでは誰もが祈るような(そして今も)遠い夢だった5。これで私は、父や兄弟、そして私自身を助けることができる。
翌1994年は、私の人生にとって波乱に満ちた年だった。仕事を得ただけでなく、運転免許を取得し、婚約し、日本人ジャーナリストの通訳として働き始めた。ヘブライ語を1年間勉強したおかげで英語も上達したし、ガザにアラビア語を学びに来た留学生とコミュニケーションを取る必要があったので、ロシア語も少し勉強した。同じ年、パレスチナ解放機構とイスラエルとのオスロ合意の結果、パレスチナ自治政府が誕生した。イスラエル当局は制限を緩和し、パレスチナの大学を再開した!父にとって、この学生たちを突然養うことになったこの年は、なんと大変な年だったことだろう!その年の暮れには、私も結婚した。私たちはキャンプを離れ、ガザ市にアパートを借りた。
仕事と新しい視野のおかげで、私は何年にもわたって多くの興味深い人々と出会った。そのような出会いのひとつが、私が親戚のビザ取得を手伝った際にコメントをくれた英国人裁判官との出会いだった。彼の言葉は、権利を奪われたグループに対する私の理解をさらに深めた:
人生は挑戦の連続であり、肌の色、国籍、そしておそらくは運によって、人々が耐えうる苦難の量と、成功するために投資する必要のある努力が決まる。パレスチナ人であれば、その努力は倍増する。
だからしばしば、地球の哀れな私たちは、特権階級と比べて2倍、いや3倍の努力をする必要がある。末弟のファヘドの言葉を借りれば、普通のことをするためには180パーセントの努力が必要なのだ。あるいは、ドイツで工学を学んだ弟のマナールの言葉を借りれば、私たちの効率は機械のそれを上回らなければならない。
1994年から1999年までの私の状況は、まさにこれだった。午前中はガザの学校で教鞭をとり、午後は大学で学び、夜はガザの語学センターでパレスチナ人にヘブライ語を、外国人にアラビア語を教えながら、機会があれば通訳もこなし、1996年に生まれた娘を育てながら家庭を築いていた。
ガザは、アラファトとパレスチナ自治政府の登場で開放され、中東のシンガポールになることが構想されていた。しかし私自身は、若い母親として、活動家として、教育者として、他国に支配された生活を送っていた。私たちはまだ被占領民であり、私の生活は満ち足りていたが、まだ自由ではなかった。ガザでは、オスロ時代でさえ、鳥だけが自由だった。水も限られた時間しか出なかった。私たちの行動は、依然として疑惑と監視にさらされていた。檻から出ることは許されても、まるでサファリのように、いつ占領者が私たちを檻に戻すかわからない状況に置かれていたのだ。1999年1月、私は成績優秀で卒業し、さらなる夢と、ガザの空の向こうのチャンスを探す足がかりを得た。教育がその道だった。私は修士号を取得するため、パレスチナ国外の大学に出願し始めた。合格と奨学金を得るためには、TOEFLのスコアが必要だった。TOEFLは年に2回実施されるが、私はすでに1回目の受験を逃していた。私は必死で勉強し、当時私のアラビア語のクラスに入っていた留学生の助けを借りて、何十枚もの願書を書いた。そして1999年7月、イギリスのエクセター大学政治学部から合格通知と奨学金をもらった。その年の9月、私は飛行機に乗り、3歳になる娘を残して英国に向かった。
第二次インティファーダが勃発したのは2000年9月のことで、私は論文を書き終え、生後2カ月の息子タレクに授乳していた。そう、私は修士課程在学中に2人目の子供を産むつもりだったのだ!もし試験に合格できなくても、少なくとも言い訳はできるだろうという冗談だった!
私は10月初旬に論文を提出し、その日のうちにガザに飛んだ。モハメド・アル=デュラという幼い子供が父親の腕の中で射殺され、失血死した事件から数日後のことだった。ガザの住民とインフラは、アメリカ製のアパッチ・ヘリコプターとF16による全面的な攻撃を受けていた。これによって暴力は、私が経験したことのない新たなレベルにまで高まった。ストリップ地区に足を踏み入れたとき、私はその地域がわからなかった。破壊のレベルは私の想像を超えていた。ガザに滞在していた故ボブ・サイモン氏の『60 Minutes』のインタビューを受け、私はこの新たな現実に遭遇した痛みを語った。
ガザに戻った私は、どこに行き、どのように支援すればいいのか、方向性が定まらないまま岐路に立たされていることに気づいた。その状況は、1988年の第一次インティファーダの時のようだった。しかし、軌道に乗り、教育の中に進むべき道とエンパワーメントの源を見つけるのに、さほど時間はかからなかった。私は1988年当時よりも良い教育を受けていたが、この教育をどのように活用すれば、自分自身と大義をより良く前進させることができるだろうか?私はもはや、以前の仕事に戻って語学センターを経営する気にはなれなかった。ガザに住む同世代の多くの人たちと同じように、家が砲撃され、破壊され、男性や若者が暗殺され、撃たれ、鎖につながれているのを目の当たりにしながら、私は無力で無力だと感じていた。
西側の主要メディアがパレスチナの状況を集中的に報道しているにもかかわらず、私たちの話はいつも、どういうわけか、欠落していた。報道されたとしても、私たちの現実とは似ても似つかないものだった。パレスチナ人の生活体験と、それについてメディアで報道されることの間には大きなギャップがある。英国で修士課程に在籍していたとき、学問や文学の世界でも同じギャップを感じた。私の研究もメディアとの仕事も、私たちの生活体験とは似ても似つかない、パレスチナ人を集団として中傷し、さらに彼らの声を国際的な言説から排除するような物語が蔓延していることを露呈した。この排除は、物語の変形によってさらに複雑になっている。ラムジー・バルードが指摘したように、パレスチナ人の言説は、パレスチナ人を不合理に怒り、反応的な行為者であり、主体的に行動する能力を持つのではなく、受動的な犠牲者である不運な群衆として表現する主張的な物語に取って代わられてきた。さらに、イスラエル建国以前のパレスチナ人の生活に関する(わずかな)知識は、主流メディアの報道、欧米やイスラエルの学術研究、シオニスト志向の物語によってほぼ決定されており、一般的にパレスチナ人の歴史をステレオタイプのコレクションに還元している。
私たちの物語を読み、テレビで放映されるのを見れば見るほど、私は憤りを感じるようになった。この感覚は、1998年に私のアラビア語講座に参加した、ガザで働いていたオーストラリア人の友人バーバラも共有していた。バーバラは、ガザとそこに住む人々の豊かな歴史、寛大さ、美しさに驚いた。彼女は、オーラル・ヒストリー・プロジェクトを実施し、パレスチナの正史を英語で記録し、出版するというアイデアを思いついた。占領下で生まれ育ち、自分たちの歴史を学ぶ機会がなかったパレスチナ人として、私はこのアイデアに熱中した。私はこの研究プロジェクトに、パレスチナを語る際に私たちの物語を中心に据える方法を見出した。研究は、私たちを抑圧者が作り上げた枠の中に閉じ込めている、重ね合わされた物語を打ち破るためのさらなる方法論として浮上した。研究そのものが、闘いに貢献する方法となった。
私たちはプロジェクトを開始し、あっという間に、私はいつも楽しんでいたエネルギーとやる気を取り戻した。オーラル・ヒストリーの研究は、無気力状態から抜け出す私の道であり、エンパワーメントと啓発の源だった。それはまた、パレスチナ人の歴史を伝えるための代替的なアプローチを創造し、プロジェクト化する試みでもあり、脱植民地化への一歩でもあった。「下からの歴史」と「ハーストーリー」という、女性、特に社会から疎外された女性の知られざるライフストーリーを語るフェミニストの歴史家や活動家がよく使う用語を採用し、2年間にわたり、7人の一般女性にインタビューを行ったが、特に、パレスチナ人の生活の深さ、多様性、豊かさを伝えることができる、さまざまな経験を持ち、記憶力に優れた女性を探した。彼女たちのライフストーリーは、1948年以前のパレスチナとガザ地区の村や町での日常的な経験、戦争や亡命の経験、2度のインティファーダの経験、そして未来への思いを浮き彫りにしている。2020年、最初の物語『白い嘘』が結実した。2021年には第2作『自由への道を照らせ』が続き、残りのシリーズも数年後に発表される予定だ。
バーバラと私は、これらの声の助産婦となった。そうすることで、そして(1999年当時、私はほとんど知らなかったが)私たちに先行していた他の学者や活動家たちとともに、私たちは学界やメディアの既成のパターンによる「声殺し」に対抗するために行動した。ガザやヨルダン川西岸の壁には、「存在することは抵抗することだ」というフレーズがシンプルな黒文字で書かれている。これらの物語は、存在するだけで抵抗行為となる。ガザの海岸を洗う、増え続ける知識の海に一滴を加えるのだ。それらは、植民地主義、人種差別、アパルトヘイトに反対する他の世界的な闘いの文脈にパレスチナを位置づけるものであり、人間的なレンズをもって、そのような政策が人々の生活に与える影響を示すものだからだ。
2021年のガザ攻撃は、フリーダム・ハイウェイを旅する転機でもあった。2021年の夏にガザを訪れたとき、私は特に若者たちが、パレスチナ人を援助産業への単なる屈従者として、あるいは身分の等しい両者の戦争における厳しい統計として、いかに物語に対抗しているかを目の当たりにした。その代わりに、この2021年の夏もまた、街頭やディワンでチョコレートやお茶が配られ、試験開始のわずか数週間前に、荒れ果て包囲されたストリップを襲ったイスラエルの残忍な攻撃にもかかわらず、パレスチナ全土の上位10位の大半を占めたガザの学生の功績を称えた。
これらの若者たちは、しばしば厳しい統計や年代記を通して世界に紹介されるような、無力で絶望的なパレスチナ人ではなかった。この若者たちは、希望という概念を、尊厳と自由を求める戦いにおける革命的なツールへと見事に形成していた。占領国による残忍で醜い暴力と、それに対抗して生きる人生の物語である。この強力な道具を手にした彼らは、前の世代と同じように、耳を傾けるすべての人のために、この物語を世界に発信するのだ。
パレスチナ人が耐えている分断と分離は、この民間人に対する戦争によって強まるはずだったが、その代わりに、団結のメッセージによって集団の決意が強まった。
カナダに戻るために荷物をまとめながら、私は家族に涙の別れを告げた。ラファ交差点までは車ですぐの距離だったが、反対側では祖国との別離の苦しみを味わうことになる。私が別れを告げると、家族は笑顔とユーモアで気持ちを軽くしてくれた。(当然だが、皮肉なことに、ガザに残っている家族が笑いをもたらしてくれた!)。過越の祭りのセーデルの古い祈りになぞらえて、「来年はベイト・ダラスで」という彼らの言葉が私の耳に響いた。インシュアッラー!
1 古い世代は死に、若い世代は忘れるというダヴィド・ベン・グリオンの予言に反している(Ben Gurion 1948, cited on Al-Awda website, al-awda.org/)。
2 Ageel, Ghada, Apartheid in Palestine: Hard Laws and Harder Experiences (Edmonton, Alberta, Canada : The University of Alberta Press, 2016).
3 イスラエルの主流派の物語では、パレスチナ人の教育は憎悪の方法論とされている。私たちの学校のテキストは、外国政府や資金提供機関、メディアからの監視下に置かれている。しかし、パレスチナ人にとって、教育は解放の一形態である。したがって、囚人の中で最も地位の高い仕事は司書であり、物語の保持者であり、秘密のメッセージの伝達者である。そして、友人に挨拶するときに差し出す最高の賛辞は、宗教的な称号である「シーク」ではなく、「ウスターザ/ウスターズ」であり、教師、教授、知恵の友である。
4 これは、教育と行為との関係を通じて解放が明らかになると主張するフレイレの反響である。「批判的な認識が行動に具体化されるにつれて、希望と自信に満ちた風土が生まれ、それによって人は限界状況を克服しようとする。(Freire, 1970, p98 envs.ucsc.edu/internships/internship-readings/freire-pedagogy-of-the-oppressed.pdf)
5 ガザの失業率は、社会全体(2020年12月で43.1%)に、特に女性には60.4%という高い影響を与え続けている。Gisha, ”Gaza’s workforce continues to shrink, 43% unemployment in the last quarter of 2020,” April 13, 2021, …gisha.org/en/gazas-workforce-continues-to-shrink-43-unemployment-in-the-last-quarter-of-2020/を参�
JEHA. FARRAはパレスチナ歴史タペストリープロジェクトの共同議長である。パレスチナ人ライター、マルチメディア・ジャーナリスト、プロデューサーで、中東情勢を担当し、パレスチナの政治ニュースや社会問題を専門としている。
JAN CHALMERSは看護師であり、1969年と1970年にガザのUNRWAで働いていた刺繍家でもある。2011年にパレスチナ歴史タペストリー・プロジェクトを立ち上げた。彼女がパレスチナの歴史タペストリーを思いついたのは、南アフリカの村の女性たちとともにケイスカンマの歴史タペストリーを制作した経験がきっかけだった。ヤンはパレスチナ人の同僚とともに、タペストリーのパネル制作をコーディネートしている。
針の目を通して
パレスチナの抵抗の歴史を縫う
ジェハン・アルファラ、ヤン・チャルマース
はじめに
オックスフォードは、パレスチナやパレスチナ人と様々な特別な関係を持つ世界中の多くの場所のひとつである。オックスフォード・ラマッラ友好協会(ORFA)は、オックスフォードのボランティア監視員がラマッラでイスラエル軍の暴行を目撃したことをきっかけに 2002年に結成された。両都市の関係は時を経てより強固なものとなった。2019年、オックスフォードのコリン・クック市長がラマッラ市長のムサ・ハディド氏とパレスチナ大使のフサム・ズムロ氏をオックスフォード市庁舎に迎え、正式に発足した。両市の人々の長年にわたる草の根の友好関係を祝う双務協定が締結された。
2009年、イスラエルによるガザへの壊滅的な攻撃を受けて、オックスフォードとパレスチナの間にもうひとつのつながりが生まれた。英国政府の反応は非常に鈍かった。ガザの人々に、自分たちが英国で忘れられていないことを思い出させるために、オックスフォードの個人グループが資金を集め、オックスフォード・ブルックス大学で毎年大学院の奨学金制度を開始した。この制度により、開発と緊急事態の実践、eビジネス、工学、人権法、コンピューティング、公衆衛生の分野で修士号を取得した卒業生が生まれた6。
その結果、パレスチナ、レバノン、ヨルダンのパレスチナ人刺繍職人によって、パレスチナとパレスチナ人の物語を綴る、充実した歴史タペストリーが制作された。本章では、「パレスチナ歴史タペストリー・プロジェクト」の展開について、2つの個人的な証言を紹介する。
糸で結ばれる
ジェハン・アルファラ
1988年のことだった。第一次パレスチナ・インティファーダが本格化していた。私の母は野心的な若い女性で、ソビエト・ロシアからガザに戻ったばかりだった。ガザ・シティに住む彼女は、そこからほんの数メートルしか離れていないシファ病院で働き始めた。彼女はそこで、同じく医師であった私の父と初めて出会った。1989年1月、二人は結婚した。イスラエル占領軍がカン・ユーニス市に夜間外出禁止令を出したため、両親の結婚式は自宅でささやかに行われた。
私はその翌年に生まれた。第一次インティファーダのことは幼すぎて覚えていないが 2000年の第二次インティファーダのことは鮮明に覚えている。当時イスラエルの首相だったアリエル・シャロンがアル・アクサ・モスクに入ったというニュースで目が覚めた。怒りが広がった。パレスチナ人の大規模な抗議行動とゼネストがすぐに起こった。
ある日、私が学校から帰る途中、道路を横断していると、脇道から戦車が近づいてきた。銃口をこちらに向けるその大きさに、私は恐怖で膝をついた。それは、幼い私が最初に経験した、そして最も忘れがたい瞬間のひとつだった。その時点で私はすでに、検問所にあるイスラエルの監視塔や、パチパチとラジオを鳴らしながら装填されたライフルや装甲ジープを駆るイスラエル兵の姿に慣れ親しんでいた。今でも箱型のSUVを見ると、イスラエルのジープや兵士を思い出し、インティファーダの記憶がよみがえる。しかし、ほんの1,2メートルの距離だったに違いない、動く戦車にあんなに近づいた自分を発見したとき、私はそれまで知らなかった恐怖でいっぱいになった。
10代の頃には、銃弾や砲弾の音には慣れていた。緑色の軍服を着た武装した兵士に撃たれる若者を見たこともあった。死の音や匂いがどんなものかを学んだ。燃えたタイヤの煙に包まれながら下校するのは日常茶飯事だった。
2005年、第二次インティファーダは終結し、イスラエル軍はガザから「撤退」した。イスラエルの入植地は解体された。私は初めて、イスラエル人入植者たちだけが利用していたカーン・ユーニスのビーチを訪れることができた。それまでは、遠く海岸を見下ろす屋根の上からしかビーチを見ることができなかった。今では、祖母や叔母たち、いとこたちを訪ねるためにカーン・ユーニスからガザ・シティへ行くのにイスラエルの検問所を通る必要はなくなった。
ただし、パレスチナはまだ占領されていた。イスラエル軍はまだ完全に支配していた。ガザに住む他の多くのパレスチナ人と同じように、アル・アクサ・モスクの写真は家にあったが、実際にモスクを見たことはなかった。エルサレムを訪れることは夢だった。不可能な夢だった。ガザ出身であるということは、ヨルダン川西岸地区やエルサレムに行くには条件がつきまとうということだった。ところが2006年、思いがけないことが起こった。私は奨学金を得て、交換留学生としてアメリカの高校に1年間留学したのだ。アメリカ国務省の助成によるプログラムだった。米国を訪問するための学生ビザを申請するため、私はエルサレムの米国総領事館で直接申請する特別許可を得た。
同じプログラムに参加する学生グループの一員として、米国政府関係者に付き添われながら、ワゴン車でガザからエレズ交差点を通ってエルサレムの領事館事務所まで往復した。バンを降りることが許されたのは、売店でお土産を買うために一度だけだった。私は、たびたび夢見ていたこの魅惑的な街を散策することも、そこに住むパレスチナ人仲間と話すこともできなかった。私の祖国の一部であることは関係なく、移動のバンの窓から聖なる街を眺めることしかできなかった。言うまでもないが、ガザ以外のパレスチナを経験したのはその程度だった。
それから10年も経たないうちに、私はナカブ出身のヤスミンとベツレヘム出身のジュマナという2人のパレスチナ人女性とともに、地球の裏側にあるオックスフォードで夕食のテーブルを囲んでいた。私たちは、ホステスのヤスミンが用意してくれたパレスチナの伝統的なミートパイ、スフィーハをつまみながら、故郷の話や将来の話をした。1960年代からのパレスチナの友人であるヤン・チャルマーズとイアン・チャルマーズも一緒だった。
ヤンがパレスチナで出会ったパレスチナ人の刺繍職人についての話をすると、ヤスミンは彼女が刺繍した美しいカリグラフィーのタペストリーを出してきた。それはパレスチナの詩人、ルトフィ・ザグルールの詩の一節だった。訳すとこうなる: 「あなたは私たちの心に大きな居場所を持っている。ああ、エルサレムよ、あなたは愛されている」
完璧だった。私たちはそこにいた。ガザ、ヨルダン川西岸、ナカブからやってきた3人のパレスチナ人女性が、イギリス人の友人たちと味わい深いパレスチナ料理を気軽に分かち合い、パレスチナの刺繍について語り合ったのだ。検問や許可証を心配する必要はなかった。この美しい作品は、ヤスミンが、「パレスチナ史タペストリー・プロジェクト」に寄稿したものだ。
それは私にとって本当に非現実的な瞬間だった。私たちの共通の祖国であるパレスチナでは、このようなことは不可能だっただろうと考えずにはいられなかった。彼女たちに会うことも、彼女たちの人生について学ぶことも、おそらくできなかっただろうと思う。
私は奨学金を得て、オックスフォード・ブルックス大学でコンピュータの修士課程に留学し 2007年以来イスラエルがガザ地区に課している陸・海・空の封鎖に対するウェブベースのビジネス・ソリューションを開発したいと考えていた。しかし、オックスフォードに来て、それ以上のものを見つけた。この魅力的な街は、英語圏最古の大学の本拠地であるだけでなく、私が現在共同代表を務める「パレスチナ史タペストリー・プロジェクト」の発祥の地であり、本拠地でもあったのだ。
このタペストリー・プロジェクトがパレスチナの女性たちをいかに結びつけたか、私はすぐに感じることができた。地理的に分断され、占領の経験も異なっているにもかかわらず、私たちは時代を通してパレスチナの物語を1コマずつつなぎ合わせていた。パレスチナの歴史を通して、さまざまな経験や瞬間の物語や解釈が、パレスチナ文化の中心であり、どこにいても私たちに馴染み深い刺繍のステッチを使って表現されるのは、ふさわしいことだ。
それがパレスチナ歴史タペストリーの本質である。それは、イスラエル国家によって押しつけられたパレスチナ社会の分断とパレスチナ人の経験に対する戦いであり、パレスチナ人の刺繍家の何人かが言うように、このプロジェクトは芸術を通じたラムシャメル(アラビア語で家族の再統合の意)の役割を果たしている。ヨルダン川西岸地区での直接的な軍事占領下での生活、ガザでの息苦しい封鎖、ナカブやエルサレムでの避難生活、レバノンやヨルダンでの難民としての孤独な生活、どれをとっても、シンプルな糸が私たちを織り成し、抵抗の意思表示を共有している。抵抗の手段としての糸の力とその使用は、目新しい概念ではない。私は長い間、紛争や戦争が服装や織物に及ぼす影響に魅了されてきた。
糸には計り知れない力がある。確かに糸には、国家の認識や地位を形成する力がある。パレスチナ人にとって、糸はそのようなものであり、それ以上のものでもある。糸は私たちのアイデンティティ、遺産、団結、そして抵抗を埋め込むものなのだ。こうした効果は刺繍に限ったことではない。たとえば、アラブのカフィーイェは、黒と白の市松模様が特徴だが、時を経て、パレスチナ人のシンボルへと変貌を遂げ、解放のための民族闘争と深く結びついている。
伝統的なクロスステッチ(tasliba)やベツレヘム刺繍(tahriri)の歴史的意義は、パレスチナの世代から次の世代へと受け継がれ、この芸術的な針仕事がパレスチナの文化と遺産の中で特別な位置を占める理由となっている。
何世紀にもわたり、パレスチナの女性たちは、自分たちの文化的、地域的ルーツを誇らしげに、はっきりと反映させた丁寧な手縫いのトベス(伝統的なドレス)を身にまとってきた。地元のパレスチナ女性のドレスのスタイル、縫い方、色は、歴史的なパレスチナの中で彼女の地位や出身地を特定することが多かった。伝統的に幾何学模様で構成されるパレスチナ刺繍のモチーフの多くは、この土地の長く多様な歴史を示している。その中には、「カナン人の星」や 「パシャのテント」など、パレスチナの歴史のさまざまな時代にインスパイアされた名前を持つものもある。
しかし、パレスチナの歴史タペストリーのパネルに使われている刺繍のスタイルは、伝統的なデザインからの変化を示している。これらの刺繍は通常、伝統的な模様やモチーフを、上着やその他の家庭用リネン、クッションやハンドバッグなどの身の回り品に取り入れたものである。パレスチナの歴史タペストリー・プロジェクトでは、伝統的な刺繍のデザインを、ストーリーを捉え、歴史的な出来事を語るために使用することが求められた。
1948年のナクバとイスラエル建国以来、刺繍はパレスチナの独立闘争のシンボルやアイコンを視覚化するために広く使われてきた。パレスチナ国内だけでなく、ディアスポラのパレスチナ人の家にも、パレスチナの地図やエルサレムのアル=アクサ・モスクの画像が刺繍されたタペストリーが掛けられていることは珍しくない。これは、国連が宣言した、パレスチナ人がイスラエル建国のために強制的に追い出された歴史的パレスチナの1948年以前の家に戻る権利を象徴している。
これらの国家的シンボル以外にも、シオニストによる占領以前のパレスチナ人の日常生活を描いた民俗的な場面や描写もよく縫われている。伝統的なパレスチナの結婚式や、結婚前のヘナパーティーなどである。
パレスチナの歴史タペストリーの刺繍家たちは、このようなイラストレーションを受け入れ、発展させてきた。
パレスチナの歴史は、1948年のシオニストによるパレスチナの祖国への襲撃と、それに続く現在進行形のパレスチナ人の収奪以来、現在タペストリーの大部分を占めている。その重要な岐路以降の出来事や記録は、「不動」(sumud)というテーマで表現されている。
タペストリー・プロジェクトは、現在の出来事の展開に合わせて成長・進化し続けており、帰還大行進と統一インティファーダは、パレスチナの闘いにおける最も新しいエピソードの2つである。このプロジェクトのどのパネルも、特定の出来事、場所、シンボルを記録し、解釈し、物語を語る、それ自体が魅力的な芸術作品である。
これらのパネルを刺繍したパレスチナの女性たちのほとんどは、刺繍とタペストリーへの貢献を通してでなければ、一度も会ったことがない。彼女たちの刺繍は、それぞれのスタイル、経験、印象を浮き彫りにし、そのすべてが無理なく調和している。刺繍者の一人が言ったように、「それぞれの女性の特別なタッチやユニークな個性が、完成したパネルに表れている」彼女たちの多くは誇らしげに自分のパネルに「サインオフ」し、タペストリーのパレスチナ史の芸術的年代記にその名を永遠に刻み込む。
中には、まったく別の形で記憶されている女性もいる。サマル・アルハラクもその一人だ。彼女がヤンとタペストリー・プロジェクトを知ったのは、夫がオックスフォード・ブルックス大学で学んでいた2013年にオックスフォードを訪れたときだった。彼女は、イスラエルの刑務所でハンガーストライキをするパレスチナ人への連帯を表明するために、ソーシャルメディアで広く使われている画像をもとにパネルを縫った。パネルにはこう書かれている: Samidun」(アラビア語で「不動」の意)と書かれている。
サマルと彼女の2人の子供、そして生まれてくる赤ん坊は、1年後、2,200人以上のパレスチナ人を殺害したイスラエルの2014年夏のガザに対する猛攻撃で全員死亡した(UN-OCHA)。
彼女のパネルは、もともとはパレスチナの女性囚人と、彼女たちの権利を獲得しようとする確固たる決意に連帯するために作られたものだが、今では、包囲されたガザ地区に対するイスラエルの最も残忍な攻撃のひとつと、命を落とした何百人もの罪のない女性や子どもたちの記憶も呼び起こす。
パレスチナの刺繍職人たちによる一糸一針が、パレスチナの物語の一部を語っている。どのコマも、喜びの物語、悲しみと闘いの物語を語っているが、最終的には、自由と正義に対する私たちの集団的な希望と夢を語っている。だからこそ、パレスチナ史タペストリー・プロジェクトは私たちにとって極めて重要なのだ。このプロジェクトは、パレスチナ人と英国のパレスチナ友好国との間の愛と連帯の労作である。
2012年の開始以来、タペストリーはウェブサイト8や講演、出版、展覧会などを通じて広く宣伝されてきた。15人の著名なパトロンがこのプロジェクトを支持している。とりわけ重要なのは、これまでに100枚の刺繍パネルが制作され、パレスチナの長く多様な歴史と、イスラエル占領下のパレスチナ人の苦難が描かれていることだ。
ガザ出身の2人の共同委員長を中心とする現在のプロジェクトのリーダーシップは、タペストリーとパレスチナとパレスチナ人の歴史についての認知度を高め、このタペストリーを象徴的な国宝とすることに貢献するだろう。南アフリカの国会議事堂に誇らしげに飾られている「ケイスカンマ・タペストリー」とは異なり、現在のところ、パレスチナ歴史タペストリーを占領下のパレスチナに恒久的に展示する可能性はない。タペストリーが成長し続ける2021年の今日、いつの日か自由なパレスチナで展示され、豊かで激動の過去の記録の証人として立つことを願って、タペストリーはオックスフォードに残されている。
6 「Gaza Scholarship,」 Oxford Brookes University, accessed September 30, 2021, www.brookesalumni.co.uk/support-us/gaza-scholarship
7 The Palestinian History Tapestry, last accessed September 30, 2021, www.palestinianhistorytapestry.org
8 The Palestinian History Tapestry, last accessed September 30, 2021, www.palestinianhistorytapestry.org.
厳選された刺繍
パレスチナ歴史タペストリープロジェクト
撮影:テオ・チャルマーズ
1.ベツレヘムでのイエスの誕生、タヒリ刺繍を使用。
デザイン:ハマダ・アタッラー
[パレスチナ、アル・クッズ
刺繍:Suhair Handal(ベツレヘム)、Marcel Rabie、Randa Abu Ghattas(ベイトジャラ、パレスチナ
ベツレヘムでのナザレのイエスの誕生。「マリアは馬小屋で男の子を産んだ。マリアはその子をイエスと呼び、布にくるんで干し草の飼い葉桶に寝かせた。
ローマ時代ローマ時代(紀元前63年~紀元後325)
2.ゴドフリー・ド・ブイヨンと十字軍
画像の出典ブリッドマン画像、パリ国立図書館蔵
刺繍:パレスチナ、ラマッラ、ドウラット・アブ・シャウィーシュ[ネアネ
第一回十字軍は1099年、ローマ教皇ウルバン2世がビザンチンが聖地を支配するための軍事遠征を呼びかけたときに始まった。これにより、キリスト教徒とイスラム教徒がしばしば互いに戦った2世紀の期間が始まった。
ERA: 十字軍時代 (1099-1291)
3. 「この地にて」 マフムード・ダルウィーシュ(パレスチナの国民詩人)
画像出典/デザイン:Ibrahim Muhtadi [Al Quds], ガザ、パレスチナ
刺繍:Hekmat Ashour[ガザ]、ガザ、パレスチナ
「私たちはこの土地に、この人生を生きがいのあるものにしてくれるものを持っている」 -マフムード・ダルウィーシュ、パレスチナの国民詩人
パレスチナの国民的詩人マフムード・ダルウィーシュは、イスラエルのパレスチナ占領とパレスチナ人の自由と解放のための闘いについての詩で有名である。
4.オリーブの収穫
デザイン:Hamada Atallah [Al Quds] アルクッズ、パレスチナ
刺繍:Dowlat Abu Shaweesh [Ne’ane] ラマラ、パレスチナ
オリーブとオリーブオイルはパレスチナの土地、アイデンティティ、文化を象徴している。特にオリーブの木は成長が遅く、長寿であることから、多くのパレスチナ人が国籍と土地とのつながりの象徴とみなしている。パレスチナのオリーブの木が破壊されることは、イスラエルによる占領の特徴となっており、イスラエル人入植者による被害や破壊が定期的に報告されている。
5.Faris Odeh, Standing Alone, 8 Nov 2000.
画像の出典:Laurent Rebours、AP通信
刺繍:レバノン、アイン・アル・ヒルウェ、ナワル・イブラヒム・アル・アーメド[タバリイェ
2000年10月29日、第二次インティファーダの2カ月目に、あるフランス人フォトジャーナリストが、ガザ地区に入るカルニ交差点で、イスラエル軍の戦車に石で立ち向かうガザ市ツァイトゥーン地区の15歳のファリス・オデを撮影した。10日後の11月8日、オデは再びカルニ交差点で石を投げ、イスラエル軍に致命傷を負わされた。その後、この少年と画像は、イスラエルによるパレスチナの土地の占領に反対するシンボルとして、象徴的な地位を確立した。
ERA: スムード-堅実さ(1948年以降)
6.ベドウィンの村の破壊
画像の出典バシール・アブ・ラビアの絵画’
デザイン:バシール・アブ・ラビア(ナカブ)
刺繍:ナーマ・アル・アワウダ[エス・サム]、ハリル地区
このパネルは、ヨルダン渓谷のアル・アラケブ、ウム・エル・ヘラン、脅威のカン・アル・アマールなど、多くのベドウィン村の破壊と再建のサイクルに注意を喚起するものである。これらの村々は、ユダヤ人だけの入植地を建設するために、さらなる民族浄化政策としてイスラエル軍によって破壊されてきた。このパネルは、ネゲヴ初のベドウィンアーティストであるバシール・アブ・ラビアが、1969年からパレスチナ刺繍を絵画に描き始めた作品からインスピレーションを得ている。
ERA: Sumud – Steadfastness(1948年以降)
7.サムード(堅実さ)
画像の出典サマル・アルハラク[マジャール]、ガザ、パレスチナ
刺繍:パレスチナ、ガザ、サマル・アルハラク[マジュダル
イスラエルの刑務所に収監されているパレスチナの囚人たちは、裁判なしの長期行政拘禁に抗議するため、ハンガーストライキを行っている。この刺繍は、無名のイラストレーターが描いた画像をもとにしている。この画像は、大規模なハンガーストライキへの連帯を表明するために、ソーシャルネットワーク上で活動家の間に広く拡散された。この画像は、パレスチナの女性囚人たちの苦しみと、彼女たちの権利を獲得しようとする確固たる決意に対する認識を高めようとするものであった。アラビア語の文字には「Samedoun」(「私たちは不動です」)と書かれている。ヘブライ語の文字には、イスラエルの刑務所サービスである。「Shabas」と書かれている。このパネルは、サマル・アルハラクが2013年にオックスフォードで縫ったものだ。
彼女と彼女の子どもたちは、2014年にガザでイスラエルの砲撃によって殺害された。
ERA: Sumud – 堅忍不抜(1948年以降)
8.パレスチナ・ヘナ党
画像の出典伝統的なデザイン
刺繍:ルバ・アル・ベヘリー[ビル・セバ]、ガザ
パレスチナの結婚式の儀式は、結婚式前夜に花嫁の家族や友人の女性たちが集まり、歌い、踊り、ヘナという植物の染料で仮の入れ墨を施すことから始まる。年配の女性たちは、花嫁と招待客の肌を何時間もかかるデザインで飾る。花嫁の脚に施される装飾は、洪水による破壊が終わった証拠として、ノアに鳩が戻ってきたことを表している。女性は伝統的な手刺繍のドレスを着用し、中でも花嫁のドレスが最も美しい。
9.パレスチナの結婚式
画像の出典伝統的なデザイン|刺繍:パレスチナ、ベツレヘム、アル・デヘイシェ難民キャンプ、Mothers’ Embroidery Group
このパネルには、典型的なパレスチナの田舎の結婚式が、儀式、ダブケの民族舞踊、馬に乗った花嫁、伝統音楽とともに描かれている。ダブケの踊りはレバント地方全体に見られる特徴的なもので、音楽や踊りのステップは場所によって微妙に異なる。パレスチナ料理はレバントの料理であり、例えばマサカン、マフトゥール、キッベ、フムス、マンサフなどが広く知られ、高く評価されている。
10.タハリリ刺繍
画像の出典:伝統的なデザイン
刺繍:アマリ女性グループ(パレスチナ、ラマラ
伝統的なクロスステッチによるタヒリ刺繍の一例。このタヒリ刺繍のサンプルは、ラマラのアマリ女性グループによって縫われた。ベトジャラにある女性育児協会は、ベツレヘムの伝統的なタヒリ刺繍を維持するため、地元の女性たちを訓練し、観光市場向けの刺繍製品を作らせ、在宅で働く女性たちに収入を提供している。タヒリ縫いはカウチングとも呼ばれ、教会の衣服の装飾に使われる金糸を保存するために使われる。
12. 「エルサレム、あなたは愛されている」
デザイン:ハルーン・ハジ・アメール、ドレジャット、ナカブ
刺繍:ヤスミーン・ハジ・アメール(ナカブ州ドレジャット)
「あなたは私たちの心の中で大きな位置を占めている。ああ、エルサレムよ、あなたは愛されている」ルトフィ・ザグルールの詩より
ERA:サムード=ステッドファストネス(1948年以降)
11.チェックポイント、1967年
デザイン:ハンナ・リュッゲン(ノルウェー)のタペストリーを基に制作された。
刺繍:カレマ・ナセル[バーバラ](パレスチナ、ガザ
1967年の戦争中、イスラエルはパレスチナの残存地を占領した。ヨルダン川西岸と東エルサレム、そしてガザには、何百もの軍事検問所が設置された。これらは、イスラエルによる歴史的パレスチナ全域の占領を定着させるために使用されている。パレスチナ人の移動はパレスチナ占領地内で制限され、教育、医療、経済へのアクセスに悲惨な結果をもたらしている。このパネルのデザインは、第二次世界大戦中、ドイツがノルウェーを占領していた時代にハンナ・リュッゲンが織ったタペストリー『夢の死』に影響を受けている。
ERA: スムード=ステッドファストネス(1948年以降)
パレスチナ歴史タペストリー・プロジェクトとは何か?
ヤン・チャルマーズ
私はオックスフォード出身の英国人看護師で、アマチュアの刺繍家である。1969年と1970年にガザに住み、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)に雇われた。ガザ地区の北端にあるジャバリヤの難民キャンプで、母子保健の看護師として働いた。そこで地元の女性たちと親しくなり、毎日コーヒーを飲みながら噂話を楽しんだ。彼女たちの伝統や儀式、信仰についても学んだ。また、イスラエル軍のハーフトラックがキャンプ内を頻繁に巡回していたときには、コミュニティーの恐怖感を体験し、共有した。人生を変えるような経験だった。私はガザで親しい友人を作り、パレスチナのほとんどの地域を訪れ、何度か戻ってきた。
ガザでの2年間で、私はパレスチナ刺繍の非常に高い品質と長い伝統に感心するようになった。Omar Al-Mukhtar通りにあるUNRWA刺繍センターは、刺繍を買うだけでなく、女性たちが刺繍をする様子を見たり、伝統的なデザインの名前を学んだりすることができる、私にとってお気に入りの場所だった。パレスチナの刺繍のほとんどは、女性の服やハンドバッグ、クッションなどの装飾に使われている。パレスチナの生活風景を刺繍で表現することはほとんどない。
タペストリーは、歴史的に重要な出来事の貴重な印として大きな影響力を持っている。1066年のノルマン人によるイングランド侵攻を絵に描いたバイユー・タペストリーもそのひとつだ9。私は学校でバイユー・タペストリーについて習ったことを覚えているが、そのステッチや色彩、ストーリーを深く知ることになるとは思ってもみなかった。2002年、ケイスカンマ川がインド洋に注ぐ南アフリカの東ケープ州にある村の刺繍プロジェクトを手伝うことになったからだ。そこに住むホーサ族の女性たちは、カラフルなビーズを使って服を飾っていたが、刺繍はしていなかった。彼女たちにバイユー・タペストリーを紹介したところ、刺繍でどのように物語を表現できるかがわかった。糸を使って自分たちの民族の歴史を説明できることに、彼女たちは興奮した。私は彼女たちに刺繍を教え、歴史タペストリーを作るよう依頼された。これが、現在ではケープタウンの南アフリカ国会議事堂に永久に飾られている国宝として有名な、全長126メートルのケイスカンマ歴史タペストリーにつながった10。
ケイスカンマ・アート・プロジェクトとの10年間の付き合いを終えて、私はケイスカンマ・ヒストリー・タペストリーとの関わりを通して得た経験を、具体的にどのように生かせばいいのだろうかと考えた。1969年から70年にかけてガザに住んでいたこともある)夫の一言がきっかけで、パレスチナの女性の有名な刺繍の技術を、パレスチナとパレスチナ人の歴史を描いたタペストリーの制作に使えないかと考えるようになった。この歴史は十分に知られておらず、外国人入植者にパレスチナの祖国を約束し、先住民であるパレスチナ人の権利を守らなかったイギリスの悲惨な役割は、これまで十分に認められてこなかった。
私はイギリス市民として、イギリスがパレスチナの人々を裏切ったことを恥ずかしく思った。パレスチナの刺繍職人と協力して彼らの歴史を描いたタペストリーを作ることは、彼らとの連帯を表現する新しい方法になると思った。2012年、私は2人のイギリス人の友人(うち1人はパレスチナ人と結婚している)を誘い、パレスチナ史タペストリー・プロジェクトを立ち上げることにした。私たちは、このようなタペストリーはパレスチナとパレスチナ人の十分に評価されていない歴史を記録するだけでなく、この歴史を説明するためにパレスチナの針職人の伝統工芸を拡張し、彼女たちとその家族の収入を生み出すことになると合意した。これがプロジェクトの最初の10年間を通しての目標であった。
しかし、何千年にもわたる歴史をどうやって網羅するのだろう、どこから始めるのだろう、と私は考えた。人のプロの歴史家が、プロジェクトがタペストリーに使用する画像を選ぶのに役立つ歴史年表を作成した。新石器時代の城壁都市エリコのイラストから始め、21世紀まで続けることにした。
エリコに続くイメージを決めるのは簡単なことではなかった。私は収集したスケッチや写真を集め、ある日曜日の午後、創設パトロンで歴史家のガーダ・カルミがオックスフォードにやってきて、選定を手伝ってくれた。もっと多くの意見が必要であることは明らかだったので、パレスチナ人だけで構成される画像選定小委員会が設立され、特に1947年から49年の民族浄化以降の画像を選定することになった。
私が最初に直面した課題は、パレスチナの内外からパレスチナ人の刺繍職人をどのように集めるか、彼らとのコンタクトをどのように維持するか、刺繍する画像をどのように選び、どのように配布するか、そして刺繍の作業に対する報酬をどのように支払うか、であった。パレスチナのディアスポラは挑戦の場だった。ガザ地区、ヨルダン川西岸地区、東エルサレム、レバノン、ヨルダンなどだ。私が出会ったパレスチナの刺繍家の多くは、ケイスカンマ・ヒストリー・タペストリーに感銘を受け、伝統的な刺繍の用途に加え、これほど重要なものを作るというアイデアに興奮した。私たちはもっと個人的なレベルでもつながった。ヘブロン近郊で出会ったある女性は、なぜ髪をこんなに白くしたのかと尋ねてきた。瓶の色ではなく、神からの色なのです」と答えると、笑いが起こった。
私はパレスチナの刺繍職人たちと多くの素晴らしい関係を築いたが、悲しいことに、思うように頻繁に戻ることができなかった。プロジェクトを発展させ、興味を示してくれた多くの刺繍職人たちと連絡を取り合うためには、地元に根ざしたコーディネーターが必要なのは明らかだった。
最初のフィールド・コーディネーターであるジャミラは、ガザ地区でのプロジェクト活動を調整するために志願した。彼女はオックスフォード・ブルックス大学が運営する奨学金制度のガザ奨学生であったため、私はジャミラのことをよく知っていた。修士課程を修了してガザに戻ると、彼女はすぐにパレスチナ歴史タペストリー・プロジェクトのために刺繍職人を募集した。私はガザになじみがあり、現在もガザに住む多くの人々を知っているため、ジャミラと私は、ガザとオックスフォードの間でどのような連携が可能かを話し合うのは簡単だった。
重要なのは、ジャミラを通じてガザ在住のデザイナー、イブラヒムを紹介されたことだ。彼の貢献はプロジェクトにとって不可欠なものとなった。彼は私にとって重要な励ましと指導の源であり、パレスチナ歴史タペストリー・プロジェクトを組織する上で重要な影響力を持ち、後に共同議長になった。ガザを訪れたとき、私はイブラヒムとガザ市のアトファルナろう児協会という彼の職場で初めて会った。彼は、聴覚障害を持つ若者たちが手作りの美術工芸品を製作する企業のマネージャーだった。アルベイト・アル・サラームの刺繍職人も訪ねた。彼らは、後にタペストリーの代表作となるヘナパーティーのパネルを縫い上げた。
ガザでの調整体制が機能することが示された後、私たちが知っている他の女性たちが、ラマッラ、ナカブ、ヨルダン、レバノンのフィールド・コーディネーターに志願した。レバノンのアイン・エル・ヘルウェ難民キャンプ内での小競り合い、イスラエルによる度重なるガザ攻撃、イスラエルによるナカブのパレスチナ人の家や村の破壊など、彼らや刺繍家仲間にとって困難な時もあったが、5人のフィールド・コーディネーターと協力できたことは喜びだった。それでも、タペストリー・パネルの生産は続けられた。
プロジェクトのインフラを整備し、実施するのは(私のように)無報酬のボランティアだったが、デザイナーや刺繍職人には資金が必要だった。私の資金調達能力はゼロに等しかったが、それでも100人以上の寄付者(その多くは私の友人や親戚)のおかげで、活動を支える十分な資金が集まった。私や他の人たちは、チャリティーイベントでパレスチナの刺繍を売ったり、プロジェクトについての講演に参加した人たちに売ったりした。こうした機会に寄付を募ったほか、ウェブサイトやパレスチナ人支援団体への手紙でも呼びかけた。
プロジェクトの最初の10年間は、100枚のカラフルで感動的なタペストリーのパネルに結実した。刺繍職人たちはタペストリー・プロジェクトの仕事を熱心に引き受けた。自分たちの歴史や、何百年も前にこの国に定住していた先祖たちについてもっと知りたいと思う人もいた。
パレスチナ史タペストリーの第一段階の終了は、パレスチナ難民の故郷への帰還の権利を主張した国連決議194号の50周年に合わせ、2018年末に2回の公開展示とタペストリーの発表会によって示された。オックスフォード大学のセント・アントニーズ・カレッジが最初の発表会を主催し、ロンドンのミドル・イースト・モニターとP21ギャラリーが2回目の発表会を主催し、パレスチナ大使も出席した。
プロジェクトの最初の10年が終わり、プロジェクト委員会は、その将来はパレスチナ人がコンセプトを練り、主導すべきであると合意する節目を迎えた。ジェハン・アルファラとイブラヒム・ムフタディが今後のパレスチナ歴史タペストリー・プロジェクトの共同議長を務めることに同意したとき、プロジェクト関係者は皆喜んだ。パレスチナの刺繍職人やデザイナーは、今後もプロジェクトからの依頼を受け、過去や現在の出来事やテーマを描いたパネルを縫い続けていく予定だ。
9 「The Bayeux Tapestry,」 Bayeux Museum, last accessed September 30, 2021, www.bayeuxmuseum.com/en/the-bayeux-tapestry/
10 Keiskamma Trust, last accessed September 30, 2021, www.keiskamma.org/
TERRY BOULLATAは誇り高きエルサレム人であり、文化的権利と女性の権利を守るため、エルサレム文化センターと女性センター(パレスチナ国立劇場=アル=ハカワティ、女性研究センター、パレスチナ芸術裁判所=アル=ホアシュの総会メンバー)の理事を務めた。現在も、同市の発展を促し、豊かな文化・観光資源を保護し、パレスチナ人の国民性を守ることを目的としたボランティア活動を積極的に行っている。パレスチナ人の人権、社会経済的権利、政治的権利の侵害を明らかにすることは、今でも彼女の心に残る使命であり、彼女が最も力を注いでいることである。
第一次インティファーダの間、ブーラタは1987年から1989年の間に4回拘留された。釈放後、彼女はビルジート大学を卒業し、女性の権利を含むパレスチナ人の人権擁護を追求した。仕事を通して、彼女は同胞の苦しみに触れ、それを2本の映画の制作を通して訴えようとした: 鉄の壁』は、パレスチナ占領地とエルサレムにおけるイスラエルの土地窃盗政策とパレスチナ人の隔離を記録した作品: イースト・サイド・ストーリー』は、エルサレム・コミュニティの苦悩と願望を描いた作品である。
抵抗の手段としての文化観光
開発を促進しながら文化遺産を保護する
テリー・ブーラタ
私は1966年に東エルサレムで生まれた。パレスチナの農村の生活や抵抗の政治に触れる機会はほとんどなく、都市に住む非常に保護的な中流階級の家庭で育ったにもかかわらず、母が語る家族(フレイ家)の話を聞かないわけにはいかなかった。
シオニストの軍事グループによるバカーへの爆撃から逃れ、避難のためにベツレヘムまで歩くことを余儀なくされたが、その後エルサレムの旧市街に戻り、レモネード製造の新しい家業を立ち上げたこと、叔母のジャミレーがベツレヘムで長男を登録せず、エルサレムの登録機関で登録するために3カ月待って戻ってきたこと。
ナクバ以前の文化的な生活の話は、私たちの高齢者にとってはいつも懐かしいものだった。当時の文化的な生活がいかに豊かで、映画館がたくさんあり、YMCAエルサレムやジャッファでウム・クルトゥームやアベル・ワハブなどの有名なアラブ人歌手を迎える劇場があったかを語るときだった。特にナビ・ムーサ・フェスティバル(Mawsim Nabi Moussa)11の話は、私の家族が代々、エルサレム旧市街のムスリム地区で最も古い通りであるアカベト・タキエにあるフセイニ家の複合施設「旗の家」(Dar Bayrak)12に住んでいることを考えると、ブーラタ家の会話を支配していた。残念ながら、ナビ・ムーサ祭は1948年頃に中止され、ヨルダン支配下でも1967年以降のイスラエル占領下でも再開されることはなかった。
このような物語は、決してひとつの家族やコミュニティだけのものではない。どの家族やコミュニティにも、何世紀も前に建てられた歴史的建造物の片隅や、ザッファの伝統である結婚式、トーベ、ドレス、あるいはマカム(祠堂)の周辺、あるいはヨルダン川西岸一帯の山々の頂や山脈に、それぞれの物語が残されている。これらの遺跡は、祈り、宗教的儀式や儀式、割礼のお祝いや結婚式、公的・私的な行事、家族での野外レクリエーションなど、休日や宗教的行事(Mawassem)の巡礼地として、パレスチナ人によって伝統的に神聖化されている。景観や空間、私たちの文化的生活様式、パレスチナの文化的アイデンティティ(通過したさまざまな文明を含む)を表現し、保存する歴史と文化の深みを掘り起こし、私たち固有の文化遺産の傑出した普遍的価値を守るために。
歴史的パレスチナの原住民として、私たちは、集団的自決を求めることによって、植民地化によって被った損失を癒すために、あらゆる不公正にもかかわらず、文化的アイデンティティを構築し、家族や共同体としての生活を積極的に管理することの価値を過小評価してきた。パレスチナが「土地なき民のための、民なき土地」であると偽って維持してきたシオニストの物語に異議を唱えることは、依然として不可欠である。
投獄を含む直接的な政治的抵抗を何年も続け、家族の責任に縛られ、さらに多くの健康問題に直面した後、私は自国の脱植民地化の努力に貢献し続けることができる中心的な手段として、私たちの文化と文化遺産を復活させることの価値を見出すようになった。
私たちの遺産は、常に私たちの文化的アイデンティティの柱であり、誇りの象徴である。それはインスピレーションの源泉であり、創造性の重要な源である。私たちの遺産を強化することは、私たちの中に生きている過去を蘇らせ、世界の文化地図にパレスチナの新しい概念を埋め込む未来へと私たちを導くことを意味する。私たちの遺産は、個人と社会の生きた記憶であり、歴史を通して私たちの民族の特徴を伝え、その宝を確認し、私たちの懸念と日々の苦しみを代弁し、私たちの共通の希望と楽観主義を表現する本物の岩盤である。暴力と植民地化が激しさを増す悲惨な時代にあって、文化は社会全体を変容させ、結束させ、市民権を促進し、個人的にも集団的にも人々を結びつけ、将来の世代のために社会的・経済的発展を持続させる力を持っている。文化遺産を失うということは、歴史的記憶や文化的伝統・祝祭(Mawassem)の喪失を意味するだけでなく、持続可能な発展のための経済的機会の喪失をも意味する。この国の豊かな遺産に基づく総合的な開発は、農村部と都市部の町や都市を強化し、国の自然・文化資源の活用を促すとともに、地元の若者や女性のエネルギーを解き放つ。
それゆえ、民俗ダブケやダブケ・グループの振興・発展、文化歌謡、歴史的中心地やマカム、祠堂の修復、さらにはイスラエル人入植者によって乗っ取られ破壊された宗教的・文化的遺産をめぐる現状を変え、脱植民地化の包括的なパレスチナ文化アイコンへと変貌させようとする動きなど、あらゆる文化活動を結びつけることが重要となってきた。さまざまな点と点を結びつけ、持続可能なパレスチナの文化的アイデンティティへと融合させることが重要である。それは、単に人々のスムード(不動心)を反映するだけでなく、何十年にもわたって奪われ、分断され、抑圧されてきた彼らの回復力に報い、彼らに利益をもたらす開発プロセスへと駆り立てるものでもある。
地域に根ざしたエコツーリズムは、建築遺産開発のためのロザナ協会、パレスチナ・ヘリテージ・トレイル、体験型パレスチナ観光組織ネットワーク(NEPTO)など、いくつかの文化団体やネットワークの旗振り役となっている。彼らは、テーマ別のツアーやトレイル(降誕祭トレイル、マサル・イブラヒム、スーフィー・トレイル)の設計、定義、指導に携わっている。彼らの核心は、力を与え歓迎する地域コミュニティに基づいて、生態学的、文化的、歴史的、連帯的観光のコミュニティとの出会いと探求を促進することである。体験型文化観光は地域社会に利益をもたらし、地元の人々の自然・文化遺産の保護に役立つ。彼らのプログラムでは、歴史的建造物を修復してコミュニティ全体に役立つ現代的な機能を育成したり、歴史的なマカムや祠を修復したり、トレッキングガイドのスキルを持つ若者の能力を育成したり、ホスピタリティのスキルを持つ女性にホームステイの設立を奨励したり、芸術、工芸品、職人作品の振興を図ったりしている。また、フェアトレード、環境保護、野生動物保護、文化・遺産・農業フェスティバルの開催なども行っている。その結果、地元や外国人観光客との文化的な交流が生まれ、民族間の調和が育まれ、多様性の受容が促進され、人々の生活が豊かになり、新たな課題に対応する創造性が疑似体験される。世界をひとつに保つのは、違いを否定することではなく、むしろ違いを認めることなのだ。
2007年以来、私と娘たちは毎年夏休みを利用して、ビルゼイトの歴史地区で行われる歴史的パレスチナ全域のさまざまな文化活動を支援する象徴的なイベント、ビルゼイト・ヘリテージ・ウィークでボランティアをしている。これは、マムルーク朝やオスマン朝時代の石畳や家屋、屋根裏部屋などがあるビルジート歴史地区(旧市街)が、1年365日、活気あるコミュニティや文化ゾーンとなり、近くからも遠くからも観光客が訪れるようになるというモデルである。地元コミュニティ、市民団体、企業を巻き込み、歴史的地域の古い家屋や空間に現代的な機能を持たせ、パレスチナの地方開発における文化、文化遺産、建築遺産、能力の価値を示すことを目指す、ダイナミックで総合的な活動やプログラムが展開される。このプロジェクトは、若者や女性を含む地元のコミュニティがダイナミックなプロセスに参加し、土着の文化遺産の優れた普遍的価値と、それが生み出す潜在的な価値や利益を保護するために必要な計画や保護に注意を向け、地元での生産を活性化し、奨励することを目的としている。
毎年、私の小さな家族とは別に、多くの若いパレスチナ人男女がフェスティバルの運営やデザインに関わっている。彼らの参加は、さまざまな委員会を通じて行われ、そこで彼らは活動の基本計画を指揮し、組織し、設計し、準備し、実施する。彼らの献身的な参加は、生涯にわたるつながりや友情の確立、ジェンダー平等な参加の機会、ひいては、文化や文化遺産の振興の分野における意識、コミットメント、能力の向上に不可欠なリーダーシップ・スキルの蓄積につながる。また、世界文化との交流の機会を求め、参加を拡大、多様化し、文化のモザイクを完成させるプラットフォームでもある。参加国の国旗がビルズィート市庁舎に掲げられ、パレスチナ人コミュニティとの直接の出会いを創出し、植民地支配、検問所や壁による分断という孤立のマトリックスを打ち破る。言うまでもなく、この遺産週間は、遺産を守り、保存し、世代から世代へと受け継いでいく上で、パレスチナ人女性が果たす役割を促進することにも役立っている。毎年、16歳から18歳の若い女性たちが、1948年のナクバ以前に着用されていた村や家族の伝統的な花嫁衣装を身に着けて競い合う。優勝者は、歴史家のシャリフ・カナネ博士、ソニア・ニマー博士、ナビル・アルカム博士、ムニール・ナセル博士など、パレスチナを代表する文化専門家や仲裁人によって選ばれる。競技は、1)伝統的な歌を歌う花嫁行列(ザッファ)、2)村の名前のルーツなど、出場者の村に関する知識、3)伝統的なドレスの詳細、機能、身につけているアクセサリー、4)村の民話を暗唱する知識など、いくつかの基準に基づいて行われる。このコンテストでは、1948年地域のパレスチナの町から参加した女性が3度優勝し、押しつけられた植民地国境を越えたパレスチナ文化へのコミットメントを称えた。
2010年には、同じモデルがエルサレム旧市街でも実施された。エルサレム旧市街は、その重要な宗教的、文化的、建築的遺産のために、魅力的な本物の地域文化や文化コミュニティが数多く存在している。インド、モロッコ、アフリカ、コプト、アッシリア、その他多様な文化がエルサレム市内に定住しており、ローマ、アラブ、十字軍、イスラムなど、過去15世紀にわたる様々な王朝による支配を反映している。しかし、イスラエルによるパレスチナ文化・観光セクターの無視、開発中止、頭脳流出、権利剥奪の政策や、パレスチナ人が自分たちの生活を形作る政治、経済、都市のプロセスをコントロールできないために、これらの豊かな多様性は現在の文化・観光プログラムに反映されていない。
エルサレムの地元民である私は、娘たちと一緒に、エルサレムを拠点とするNGO、エルサレム・ツーリズム・クラスター(JTC)でボランティア活動をすることに迷いはなかった。エルサレム・ツーリズム・クラスターは、エルサレムの地元企業やコミュニティに利益をもたらすために、文化的・観光的活動をデザインし、ネットワーク化することに取り組んでいる。私は、特別なイベントやツアー、トレイルを通じて、周辺の地域社会に可能な限り利益をもたらすことを目指しながら、何世紀にもわたって獲得してきたあらゆる文化、遺産、宗教、建築モザイクを反映した、さまざまな歴史的時代のエルサレムを再び紹介する彼らの熱心な活動に貢献した。私は、エルサレムに住むいくつかの外国人コミュニティや地元の学校に、彼らの使命と文化的アイデアを紹介した。私たち家族は、ナブルス・ロード・オープン・デイズと題された彼らの重要なイベントに参加するようになり、3年連続で開催された。
イスラエル系ユダヤ人の開発を加速させる一方で、エルサレムのパレスチナ人住民をその自然後背地や歴史的市場から妨害し、切り離し、切り離すことを目的とした、組織的なイスラエルの植民地政策による東エルサレム市の疎外と貧困化を逆転させるために、アル・ホアシュは、東エルサレムの文化観光部門を発展させるために、ドナーから資金提供を受けた多くのプロジェクトや活動を実施し始めた。これらには、エルサレム観光クラスターが主導するアラブ・ホテル協会、現代芸術のためのアル=マール、パレスチナ国立劇場、パレスチナ芸術裁判所など、主要な市民社会組織に所属するパレスチナ人エルサレム人も含まれていた。こうした活動の中心人物は、エルサレムのホテル経営者であり、さまざまな文化団体を率いる文化活動家でもあったRaed Saadeh13である。
これらのプログラムの多くは、海外のドナーから資金援助を受けていたが、核となるアイデア、努力、目的はすべてパレスチナ人によるものだった。ドナーの資金の影響について議論する人も多いかもしれないが、条件付きの資金提供や、実施のどの段階においてもドナーからの干渉がなかったという事実に安心するべきだ。文化プログラムを急発進させるためのシードファンドは、ボランタリズムでは賄いきれない活動内の重要な経費を賄うために、非常に重要であった。企画書を書いたり、メディア向けのアイデアを準備したり、ボランティアを組織してブースを作ったり、参加者や人々の安全な流れを確保したりすることは、すべて文化的経費から除外されていた。そこで何人かのボランティアと私は、眠れない夜を過ごすことも含めて精力的に働いた。
東エルサレムにおける文化的抵抗の集大成を反映する重要なイベントは、ナブルス・ロードのイベントだった。ナブルス・ロード・オープンデイズは2016年に始まった。この歴史的な道の豊かさを反映するために、さまざまな分散型の活動を組織し、それによって参加機関間のネットワークづくりを促進することが求められた。多くの施設や歴史的建造物があるこの通りが象徴する歴史は途方もない。ナブルス通りは東エルサレムの重要な通りのひとつで、旧市街をバブ・アムード/ダマスカス門から北に向かって結んでおり、宗教、観光、文化、スポーツの重要な施設が数多くあり、美しい人里離れた庭園、修道院、ホテル、施設など、エルサレムでしか見られない無数の世界の良い見本となっている。このイベントは、歴史的なナブルス街道をパレスチナの文化観光地に変えることで、城壁に囲まれた旧市街周辺のパレスチナ文化的アイデンティティを復活させる機会を提供することを目的としており、ナブルス街道沿いの既存のサービスを活用・促進しながら、文化的多様性、アイデンティティ、経済的繁栄の架け橋を提供するものである。
JTCとアラブ・ホテル協会の管理の下、数百人のボランティアとともに、私は長い月日をかけて、ナブルス街道沿いのさまざまな施設内のさまざまなスペースに、子どもたちや家族連れをターゲットにした数多くの展示物やディスプレイ、パフォーマンスを設置する準備に没頭した。3日間、ナブルス通りは何千人もの家族連れや観光客でにぎわい、東エルサレムの中心部に活気をもたらした。
私たちはまた、地元の職人、アーティスト、生産者グループ、その他のサプライヤーが自分たちの作品を宣伝・販売する機会を設け、地元のビジネスと収入創出を強化した。子どもたちはペイントされた顔や風船を持って歩き回り、ティーンエイジャーは出会い、自分たちの街を好きになり、家族は自分たちの空間を所有しながら自分たちの通りを歩くことに誇りを持つようになった。このイベントは、COVID-19の大流行が国を襲うまで、3年間継続して実施された。このイベントでボランティアとして出会ったガッサンとラニアのように、数年後に結婚して祝福されたラブストーリーもあった。
このイベントは、多様な文化、スポーツ、宗教、観光団体を動員してネットワーク化し、多様な遺産を基盤にすることで、イスラエルのいくつかの障害を回避することに成功した。すべての活動は、修道女の修道院、ドミニコ教会、英国国教会、ホテル、学校など、ナブルス街道沿いの参加施設内で行われた。何千人もの人々が通行人として道路を歩く一方で、実際のイベントは屋内だけで行われ、それぞれの活動は専門の組織の中で行われた。演劇公演はパレスチナ国立劇場(アル・ハカワティ)で行われ、セント・ジョージ・スクールの敷地内には子供用の膨張式の城や滑り台が設置された。英文学の試験はブリティッシュ・カウンシルで行われ、職人のブースはすべてドミニコ教会の広い庭に設置された。私たちは、イスラエルの政策に反抗する能力だけでなく、私たちの街の中心で文化観光の成功モデルを作り上げた能力、道沿いに存在するさまざまな機関や組織間のネットワークと調整、そして長い間私たちに課せられてきた奈落の底に反抗する覚悟に基づき、何千人もの地元や外国人観光客に誇りと熱意を呼び起こすことができた。
多くのパレスチナ人がそうであるように、ナクバと私の家族の物語は、私の心の奥底を掘り続けていた。イスラエル系オランダ人の映画監督で友人でもあるベニー・ブルーナーが、ナクバの時代にパレスチナ人の家から奪われた私設図書館に関する重要な映画プロジェクトを発表したいと連絡してきたとき、私はそのアイデアに飛びつき、彼の重要な映画を始めるために必要な資金を提供してくれた信頼できるヨーロッパのドナーとのチャンネルを開いてあげた。私はまた、図書館の盗難を目撃した年老いたパレスチナ人とつながる手助けもした。『The Great Book Robbery』は2012年にアルジャジーラTVで放送された。イスラエル軍とその前身であるハガナが、イスラエル国立図書館と協力して、何百冊ものパレスチナの私設図書館を組織的に窃盗したことを解明したのだ。その中には、詩、歴史、小説など、パレスチナのアラブ文学やイスラム文学の貴重な本も含まれていた。何千冊もの本が破壊され、紙としてリサイクルされたが、他の多くの本は「放棄された財産」としてイスラエル国立図書館に残っている。
私が家族とともに生きてきた上記のささやかな個人的体験談はすべて、多くの文化的オーガナイザーや活動家が直面したイスラエルの復讐政策に比べれば、たいしたことではない。私は、こうした創造的な文化イベントのボランティアに過ぎなかった。エルサレムのホテル、レストラン、商店に対するイスラエル警察や税務署の襲撃、公演のわずか1時間前に劇場を閉鎖するよう命じられた数回の警察命令、イスラエル軍による修復されたマカム(礼拝堂)の破壊、ヨルダン川西岸地区でのツアーガイドやハイカーの逮捕などは、文化イベントの明らかな成功の後に耐えなければならなかった小さな代償に過ぎなかった。私たちは皆、パレスチナの文化的アイデンティティと遺産のために戦うことはかけがえのないことであり、私たちの愛する国の脱植民地化にとって重要な柱であり続けることをよく理解しているからだ。我々の祖先の感動的な遺産と愛する子供たちの夢で武装したままである以上、明日は間違いなくより良い日になるだろう。
私たちの国民的詩人、マフムード・ダルウィッシュはすべてを語っている:
この土地には、生きがいがある、
4月のためらい
夜明けのパンの香り
女性の男性への懇願
アイスキュロスの著作
愛の始まり
石の上の苔
笛の糸の上に立つ母たち
侵略者は思い出を恐れる
われわれはこの土地に、生を生きる価値あるものにしてくれるすべてのものを持っている…。
この土地に
この土地の貴婦人
すべての始まりの母
そしてすべての終わりの母
彼女はパレスチナと呼ばれた
後にパレスチナと呼ばれるようになった
私の貴婦人…
あなたは私の女性だから
私は生きる価値のすべてを手に入れた。
11 1187年に十字軍を打ち破ったサラー・エッディーン・アユービ以来、オスマン・トルコ支配の時代を通じて、ナビ・ムーサ祭はこの地域最大のイスラム教の祭典として台頭し、エリコの南西にあるモーゼの墓への1週間の祭典と巡礼で構成された。この祭りは、ギリシャ正教の復活祭の週末に先立つ金曜日に、廟に集まることで最高潮に達する。サラー・アルディンは、宗教的な「季節」という現象を考案し、毎年3月から4月にかけての特定の時期に地理的に分散させ、キリスト教の巡礼者が聖地を訪れる時期にパレスチナ全土をカバーするようにした。1920年4月と1921年には政治的暴動が発生した。
12 ハッジ・アミン・アル・フセイニの家は、1937年に彼らがハラムシャリフ広場に集まることを決めるまで、旗の家だった。女性たちはこの機会に、大群衆を迎えるために声を上げたり、バラ水を撒いたり、行列のために特別な服を着たりして参加した。行列の代表団は、エルサレムの近隣の村々から旗を担いでやって来る。ダルナや民謡のダブケも、伝統的な食べ物とともに行列の一部だった。
13 ラエド・サーデはエルサレム観光クラスターの共同設立者兼会長であり、ビルゼイトを拠点とするロザナ農村観光開発協会の共同設立者兼会長でもある。また、エルサレムのブティックホテル「エルサレム・ホテル」のオーナー兼総支配人であり、アラブ(パレスチナ)ホテル協会(AHA)の元会長、体験型パレスチナ観光組織ネットワーク(NEPTO)の共同設立者でもある。
リーム・タルハミはパレスチナのアーティストで、歌手、女優としてパレスチナの文化芸能シーンに深く関わっている。パレスチナ北部のシャファ・アムルで生まれ、音楽舞踊アカデミーを卒業した。現在はパレスチナに住んでいる。
西洋のクラシックを学んだにもかかわらず、タルハミは様々なスタイルで歌っている。国内外を問わず、アルバムやシングル、パートナーシップなど、いくつかの音楽・楽曲をリリースしている。リームの作品の本質は、同胞の闘争にある。彼女は作品の中で、自由と救済を求めるパレスチナの夢の一部として、不正義、希望、悲しみ、そして自由の探求について語っている。彼女の演劇作品には、『Jidariyah』、『Blood Wedding』、『Half Sack of Bullets』、『Khail Tayha』、『The Sea is West』、『Kalila wa Dimna』、『Green Salt』などがある。
流血のない戦争
解放の歌14
リーム・タルハミ
1987年の初め、私はエルサレムのヘブライ大学の法学部に入学を志願した。その熱意に疑心暗鬼になった親戚は、「君にはリーダーシップと勇気がある。あなたは法曹界にふさわしく、他の職業を考えるべきではない!”と言った。私の家族は、芸術や歌から遠ざかり、学問の学位を取ってまっとうな職業に就くことを望んだ。私は自分を慰め、もし合格したら、弁護人のフェリシア・ランガーに倣うと誓った。声を上げられない人たちを守るために自分の時間を捧げる: イスラエルの占領下にあるパレスチナの政治犯たちだ。
ランガーの著書『With My Own Eyes』は、父の書斎で初めて目にしたときから私の関心を引いた。父は自分の手で書棚を作り、私に読書への情熱と本への愛を植え付けた。三つ編みの髪に清潔なパジャマ姿の父の周りに、姉たちと私が集まり、「地図からあの国を見つけよう」というゲームで競い合ったことを覚えている。父はその国の位置を教えるだけでは満足せず、その国を形成した世界的な出来事、その国が受けた戦争、歴史的・考古学的な名所、その国の言語について、しばしば解説や分析を加えていた。歴史的な出来事を説明するとき以外は、父は口数の少ない人だった。彼の読書への執着が、その物静かな性格を説明しているのだろうか、あるいは読書と沈黙が、彼の世代のパレスチナ人が耐えてきた絶え間ない挫折から逃れるための必然的な避難場所だったのだろうか、と私は考えた。
シオニストが私たちの土地の廃墟の上に樹立されたとき、私の家族も他のパレスチナ人と同様、イスラエルの占領下に置かれた。父の最悪の悪夢には、占領軍が軍事政権下で私たちに課すあらゆる制限を想像することはできなかっただろう。
私はパレスチナ北部のシャファ・アムルで生まれ育った。アル・アナテラ支部の私の家族のルーツ(アル・バンダク)は、14世紀のベツレヘムの街にまでさかのぼる。私は4人娘の長女である。私は多宗教の町で育ち、初等科と準備クラス以外では正式な音楽教育は受けていない。私はイスラエル教育省が運営する公立学校に通った。私は合唱団、ダブケ、ガールスカウトなど、通常の学校活動に参加した。校長と教師は、イスラエルの法執行者としても知られる学校検査官の常時監視下にあり、彼らは教育省の命令を完全に遵守するよう徹底していた。その命令のひとつが、すべてのパレスチナの公立学校がイスラエルの公式式典に参加することだった。私は、イスラエルの「独立」の日にイスラエル国旗を掲げ、歌うことを拒否したために罰せられたことを覚えている。当時の私の単純で素朴な理解でも、イスラエル国旗を掲げ、イスラエルの 「ティクヴァ」を歌うということは、何かが間違っているに違いないと十分に分かっていた。
70年代、私は自然なアラブ環境から切り離された若い世代の一員であり、アラブ系パレスチナ人であることの意味、特に私たちが、「イスラエル・アラブ人」として知られるようになるにつれ、その自覚を妨げるように仕向けられた管理された現実の中で生きていた。
アイデンティティとは、思考、感情、信念を通じて育まれる冷静な確信である。私のアイデンティティは、この場所の精神の一部であり、私が生まれた場所であり、私が属する人々と話す言語の一部である。
ロースクールへの出願はすぐに却下され、同じようにすぐにソーシャルワーク学部への入学が決まった。私はもう一度自分を慰めた: 「これもまた、声を上げられない人々を助けることができるだろう」と。私は大都市エルサレムに移り住み、2年半に満たない学問の旅に胸を躍らせた。
大学では、エルサレム、ヨルダン川西岸、ガザに住む兄弟姉妹とのつながりの中で、私の政治意識は高まっていった。67年の 「新しい」占領はちょうど20年目を迎え、パレスチナの人々は、後に 「石のインティファーダ」と名づけられる抵抗の新たな局面を迎えようとしていた。1948年の大災害の年と、私が生まれた1968年とは、20年の隔たりがあった。それからさらに20年後の1987年、私のエルサレムと占領地での生活が始まった!その時、私は人生の進路を変える決断をした。
第一次インティファーダの数年間、私は、エジプトやレバントで流行していた伝統的な民族主義的な歌に似ていながら、それとは異なる、新しい歌い方を探求し始めた。これらの新しいテーマの歌は、プロテスト・チャントに触発されたものだ。初めてカミヤ・ジュブランの歌声を聴いたとき16、なぜ今まで聴かなかったのだろうと不思議に思った。彼女の歌声と、彼女がSabereenというバンドと一緒に歌った曲17は、私の心と魂に触れ、その後何年にもわたって私の歌のスタイルに影響を与えた。カメリア独特のオリエンタルな声の動き、メロディー、リズムは、これまで聴いたことのないもので、私は驚いた。さらに、彼女の歌の歌詞は、パレスチナのアラブ人の経験をとらえ、私たちに語りかけるものだった。
「ある歌は、あなたが歌うことのできない叫びである」
だから、もし私の歌があなたを刺激するなら、怒ってほしい。
私の家の廃墟を建てる者たちよ。
廃墟の下には呪いがある
私の幹が斧の犠牲になるなら
私の根は神のように土塊の中にある。
これは裸の私、明日だけをまとった私だ。
そのショーに安住するか、はりつけにされるか、どちらかだ。
彼の目のために、そして私の兄弟の目のために。
私は歩き、道が求めるものを与える
これが私だ、すべての悩みを背負った
私の血は手のひらの上で歌っている、
さあ、飲みなさい!」18
「沈黙は不名誉、恐怖は不名誉だ」
我々は何者だ?われわれは誰だ?
生き、泣き、愛する
亡霊と戦う
待ち続ける
壁を掘り続ける
光が差し込む穴を開けるか
あるいは壁の上で死ぬ
私たちのシャベルは絶望しない…私たちは疲れないし、壊れない
秋の雲が乾き
夏の列車が通り過ぎる
春の雲は豊かな雨を孕んでいる
豊かな雨が降る
そして明日は我々の勝利となる。
「眠れ、わが瞳の愛よ」
ナイチンゲールはこうして眠った
息子よ、よく眠れ。
これは乳歯か大人の歯か?
「なぜ我慢するのだ?」
私たちは苦難の上にいる
なぜ目が見えないのか?
「正義が私たちの手の中にあるのに」20。
これらは、東洋的な形を超越した歌であり、歌手としてのキャリアの初期段階において、私の歌唱力を磨いてくれた。私はパレスチナの方言の美しさに、古典的なアラビア語と同じくらい力強さを感じた。私は抗議チャントやパレスチナの日常的なストリートトークを想像し、それを作曲して歌うようになった。このことが、私の飢えを満たしてくれる言葉を探す旅に出るきっかけとなった。
私は看護学生でギター奏者のイブラヒム・カティブに出会った。イブラヒムは作家・作曲家志望で、彼の人生も大きく変わろうとしていた。しかし、パレスチナ北部への帰国を急いだため、私の創造的探求は遅れた。歌詞は吟味も選択もせず、メロディーは個人的な考えを反映していない。私が愛し、共鳴していた歌は、私のものではなかった。
イブラヒムが書いたYa Mhajer weinak「移住者よ、どこにいるのか」は、私が初めて披露したオリジナル曲だった。ヘブライ大学のアラブ学生委員会が開催した祝賀会で、私たちは初めてこの歌を披露した。聴衆の反応は予想以上だった。私たちのパフォーマンスのニュースは広まり、他の大学のアラブ学生委員会からも招待を受けるようになった。その結果、私たちが独自のパレスチナ・サウンドを創り出すためのスペースが開かれた。パレスチナ北部のシャファ・アムル、タムラ、ナザレの間で、Gh’orbahバンド(Alienation)が誕生した。Gh’orbahの活動は1988年から1989年までのわずか1年間であった。ヴォーカルはもちろん、歌詞、メロディ、楽器も新しい形をとった。Gh’orbahでの活動は、オリジナル曲のコレクションと、著名なパレスチナの詩人が書いた詩の作曲という結果をもたらした。Gh’orbahの作品は、資源の乏しさと、未熟なまま終わった旅を完成させる時間がなかったため、どれもレコーディングされなかった。バンドは解体され、私を含むメンバー全員がエルサレムに戻り、音楽舞踊アカデミーで音楽を学んだ。
『Gh’orbah』には、オリジナル曲を作るという私たちの勇気ある執念が反映されている。私たちが選んだ詩は、マフムード・ダルウィーシュの 「Soft Rain in a Far Autumn」、「A Stranger in a Far City」、「How Alone You Were」といった、祖国での疎外感を表現した、私たちの心に近いものだった。選択すること、アイデアを所有すること、そしてそのアイデアが、若い個人として、また集団の一部として、私たちを反映する能力を持つための共同パートナーであること、それは国家と呼べるかもしれない。
私は音楽アカデミーに入学した。偉大な音楽家であり作曲家であるハレド・ジュブラン(カミヤ・ジュブランの兄)は、私がアカデミーを初めて訪れたとき、私の手を引いて、その日空いていた声楽の先生に歌わせた。その時ハレドは、私が持っていたアラビア音楽のカセットをすべて片付けるようにと、真剣に私にアドバイスした。「箱をしっかり閉めて、アカデミーを卒業する日まで開けないように」と彼は言った。
アカデミーにはまだ東洋の古典音楽教育学科が設立されていなかったので、西洋の古典音楽とオペラの発声法しか私の選択肢はなかった。数年後、私はオペラ歌手という分類を敬遠するようになり、自分の声を一つの声楽分野に限定することも控えるようになった。
いずれにせよ、最初の1年間はハレド・ジュブランの助言を一部取り入れ、オペラ歌唱をマスターし、1996年にアカデミーを卒業した。在学中、箱は開けなかったが、音楽家や作曲家とコラボレーションをした。スハイルと私は、後に加わった他のミュージシャンたちとともに「ワシェム(タトゥー)」バンドを結成した。1993年、このバンドは、パレスチナの詩人ワシーム・アル・クルディが作詞、スハイル・クーリが作曲した最初で唯一のアルバム『Ashiqa』(恋する女)をリリースした。
英雄は決して死なない
なぜなら彼は生命だからだ
彼は空気であり雲である
彼は土であり麦である
彼は永遠の柳である
空間に木陰を与え
地平線を覆う
その声で
「ああ、エルサレムよ、魂はどこにあるのか」
この空間は冒涜されている。
「輝く子供たちに囲まれたガザよ」
敗北を後ろに投げ出し、兄弟がもう一方を抱きしめる。
この歌詞は、第一次インティファーダでパレスチナのストリートが煮えたぎっている最中に書かれ、ほぼ2年後にカセットテープとしてリリースされた。WashhemとAshiqaは、私の音楽の旅における基本的なブロックだった。私のパフォーマンスは1992年と1993年が全盛期だった。
1992年、私はエルサレムのアル・カサバ劇場に招かれ、ギリシャの偉大な作曲家でピアニストのサランディス・カサーズと共演することができ、感激した。その後、カイロで共演することになった。
エジプトやアラブの国を訪れたのはそれが初めてだった。私の喜びは圧倒的だった。私たちは国立劇場で2つの公演を行い、メディアで好意的に評価された。同じ年、私は、チュニジアの偉大な指揮者モハマド・アル・ガルフィが指揮するエルサレム占領25周年記念のチュニスのカルタゴ国際音楽祭で歌うという特別な招待を受けた21。
カルタゴの岩の上に立っていた私は、責任の重さを痛感し、七転八倒していた。私の背後では、パレスチナの子どもたちが、パレスチナの旗を持ち、カフィーヤを着て、高い石の棚に立っていた。1982年にPLOがベイルートから追放されたとき、アラファトとともにチュニジアにやってきた難民の孤児もいた。アラファトとの出会いは魔法のようだった。ニュースも父もアラファトの話を止められなかった。チュニスのアルマンザにある彼の邸宅で、彼が私にスイカを食べさせてくれる間、私の涙は止まらなかった。私はこのことを父と分かち合いたいと焦っていたが、父は私の帰国を心配し、逮捕されることを恐れていた。
歴史的な節目は私たちを彫刻化し、形づくる。第一次インティファーダ、そしてエルサレム、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区が、まるで私たちがひとつのパレスチナ人の体の一部であるかのようにつながっていた。私が育ってきた愛国的な感情は、占領との対決の中で日々問われていた。占領の終結とパレスチナ国家の樹立を求める抗議行動に参加した。反抗的な愛の物語。結婚。音楽アカデミーの卒業。母になる。延期されたプロジェクト。芸術と人生の両方における失望の連続。和平交渉。協定の調印。円卓会議。平和条約。ペンと書類。第二次インティファーダ。残忍な分離壁。弾圧。検問所で毎日頭上にのしかかる死。エルサレムでの居住証明という悪夢。演劇に手を出す。演劇を上演する。パレスチナ国外での音楽と演劇のツアー。受賞と栄誉。新曲アルバムガザ包囲。絶え間ない爆撃。殉教者たち。さらなる死。帰還を切望する難民たち。ディアスポラのパレスチナ人たち。離散。疎外。そして小さなパレスチナ人の夢。
これらすべてが、やがて新しい曲を書くためのインスピレーションとなった。陳腐な政治的言説や多くの利益主義者から私の芸術を遠ざけることが重要だった。スローガン作りの罠に陥ることなく、現実をとらえる言葉を探し求めるのは簡単なことではなかった。
歌は、深く探求されるべきさまざまな気分を反映している。だからこそ、私は歌と向き合い、アラベスク、クラシック、ジャズといった特定のジャンルに必ずしも分類されない領域や細部に向けるのだ。私はテキストに導かれている。歌詞は、それらを特徴づけるスローガンとはかけ離れた、文学的な言語語彙で出来事に立ち向かうもので、地上の出来事を天体の言葉で表現するようなものだ。この考えは、私の作品と、パレスチナの音楽家ハビブ・シェハデ・ハンナとのパートナーシップを体現している。私たちのパートナーシップは、私が歌手/女優として参加した演劇作品や映画の歌に加え、特別な叙情的作品から成っていた。ハビブは、詩人マフムード・ダルウィーシュの「Jidariyyah」(「壁画」)、フェデリコ・ガルシア・ロルカの「Ors al Dam」(「血の婚礼」)、アクラム・サファディのドキュメンタリー映画「Jerusalem Back and Forth」の作曲を手がけ、「Ya’lou」(「Rise」)という曲は、ハビブと私の今日までの経験を要約して描写している。「Ya’lou 「では、頭、胸、喉という異なるボーカル空間での歌唱の変遷を提示し、音楽における大きな感覚の蓄積と顕著なエスカレーションを表現している。
彼は上昇する、空間の中で上昇する
彼は2つの雲の間の太陽を通り過ぎる
風の後ろ
彼は愛に狂ってまばたきをする
影の前で踊る
蝶と人形が彼をからかう。
スーツケースの中」22
2013年、カレド・ジュマが作詞、サイード・ムラドが作曲した10曲のアルバム『Yihmilni e leil(The Night Carries Me)』にも、同じ考えが歌詞に反映されている。このアルバムはガザにインスパイアされ、ガザに捧げられた。曲には、破壊、爆撃、ミサイル、血、包囲、分裂など、ガザに関する報道でよく耳にする流行語は含まれていない。曲は、同じストーリーを語るのに別の言葉を使った。
「私の祖国は何もない平原にある」
そして私は自分自身と疎遠になった
私はあなたに呼びかける、
しかし、その反響は私に返ってくる」23
「私のまつげの上を歩こう」
フルートの音と私の狂気をあなたにかける。
私のまなざしの温もりの中で眠ろう
私の岸辺で
君の足音は夜のメロディーだ
星のささやきが私に歌う
闇の残酷さを和らげる
朝の向こう側に言葉を刻む
私の胸は私の書いた書類でいっぱいだ
そして私の血は、私が書くためのインクなのだ。
「希望のように強く」
牝馬のようなサラブレッド
眠りと眠気の狭間で
彼女の目は道を夢見る
太陽が彼女を照らす
彼女にキスをすると、恥ずかしそうに……彼女は溶けてしまった」25
振り返ってみると、どのような価値が達成されたのだろう。パレスチナの北からやってきた、魂に燃えたぎる炎を持った若い女性、成就を待ち望んでいたアイデアと夢、そしてステージへの強い情熱を思う。観客の前でステージで歌いたいという強い衝動は何を意味したのだろうか?人はこの露出に対してどれほどの準備ができるのだろうか?そして、その露出にはどんな力があるのだろうか?単なるガス抜きのためのグループセッションなのか?それとも、一人で行う感覚療法なのだろうか?時々、天からの贈り物と悪魔の呪いの間の微妙な境界線について考えることがある!戦争を生み出す者と歌を生み出す者がいる!どちらのカテゴリーを好むだろうか?
新曲を生み出すこと、あるいは新しい演劇作品に参加することを、たとえそれがせいぜい5回や10回しか上演されないとわかっていても、何度も何度もたゆまず決心するとき、ずっと前に自分の道を選んだ芸術家としての私が払う代償を思うと、もしかしたら、そのすべてが呪いなのかもしれないと思う。芸術における絶え間ない出血、落ち着きのなさ、不安、汗、そして目に見えるわずかな傷跡にもかかわらず、それらは新作を発表する喜びや初演の恍惚感へとつながっていく!人々の曲への愛着、暗譜の仕方、輝かしいライブへの参加、新作を待ち望む気持ち、観察と感想、これらはすべて天からの贈り物である!さらけ出すことで、まるで裸のように無防備に、しかし力強くなれる。あなたは情報開示の技術、スピーチや動きを引き受け、しばらくの間、観客を話すという困難な仕事から解放する。観客はただ見て、観察し、耳を傾けるだけでいいのだ。
今ここで、アーティストは喜びの創造者であり、言葉の語り手であり、アイデアの所有者である。それは侮れない力だ!あなたはステージを所有し、世界を所有する。
歌は、私たちの拍手と体の動きを伴って、まるで私たちがひとつになったかのように私たちをひとつにする。歌は、もはや背負いきれない重荷から私たちを解放してくれる。歌は私たちを軽くし、生命で満たしてくれる。
パレスチナ人をよく知る人は、彼らが伝統的な歌にどれほど共感しているかを知っている。結束の固いパレスチナ人がサハやダブケの列に固まっているのを見れば、彼らがいかに自由であるかは疑いようもなくわかるだろう。パレスチナ人が自警団を結成したり、占領者に抗議したりするときに伝わってくる誘惑や、伝染するような喜び、勇気、恍惚感には誰も逆らえない。歌によって、私たちは一滴の血も流さずに戦争を行う。美、言語、音楽を武器とし、一人の殉教者も悼まない戦いだ!これが呪いだと思う人がいるだろうか?
自分に語りかけ、自分の感情や考えを表現してくれるテキストに落ち着くと、私は音と空間の演劇性を探求し始める。演劇は、私の心理的・芸術的形成と声において、非常に重要で影響力のある役割を果たしている。私が舞台で演じるキャラクターは、私の一部なのだ。演劇は私の声に新しい扉と出口を開いてくれる。歌はドラマチックな場面であり、それぞれの歌の主人公はそれ自体がキャラクターなのだ。2004年以来、私は歌と演劇と声の間のダイナミックな空間をさまよってきた。私の声は、かつてはそこに自分の居場所はないと思い、恐れ遠慮していた領域にまで届いた。演劇は、音楽アカデミーで受けたどんな発声レッスンよりも、私の声の解放に大きく貢献した。
私のアートワークは、評価尺度や批評のリスクにもかかわらず、詩学と新たなボキャブラリーをもって、パレスチナの人々がどこにいようと反映する。私は、現地の果てしなく続く大きな紛争の中で、時には小さな角度から、新たな切り口を見つけることに腐心している。
パレスチナの現実は日々、抵抗と自由の戦いを要求しているが、一方で占領軍はあらゆる専制的な権力を持ち、私たちの土地に抑圧と死の種をまき、挑発し、エスカレートさせる。その一方で、失望、挫折、ビジョンの欠如、方向性の喪失が続くたびに、パレスチナ人の疎外感は高まり、正当な疲労が自国の確固とした人々を苦しめている。
私たちパレスチナ人は、日々の抵抗と不動の狭間に立たされ、処刑人のハンマーが増殖し、枝分かれしていく。まるでパレスチナの人々は、自分たちだけが運命に立ち向かうことを見捨てられてしまったかのようだ。
「ランプが夜を照らすとき」
傷から立ち上がるとき
狂気が恐怖を引き寄せるとき
あなたの声があなたから落ちるとき
「心を強くして怒れ」26
「嘶きは何処へ行った?」
お前のこだまは遠くまで届いていた
お前はのんきに跳んでいた
衛兵の境を踏み鳴らしたものだ。
嘶きはどこだ、雌馬よ」27
「私は馬の嘶きを癒す、」
馬の嘶きを癒す。
私は彼を夜の戸棚に注ぐ。
わたしは彼をわたしの泣く目に注ぐ。
私は彼に雲と羽を与える、
戻っておいで
彼を私のもとに連れてきて、
私の胸に抱こう。
そうすれば彼は生き返るだろう。
「祖国が詠唱するとき、国民も詠唱に加わる」
祖国が疲労に陥るとき、その民は守護神として立ち上がる。
星のような魂が歓喜し、愛に満ちた心が胸を打つ。
涙目は憧れで潤み、心痛を踏みしめる
祖国が願うなら、我々はその願いを叶える。
日暮れには、そのそよ風を受け入れる。
その狂おしいそよ風はなんと美しいことだろう!この祖国は忘れられるものではない。
私は1995年にカメル・アル=バシャと結婚した。宗教が混在していたため、4年間にわたる頑固な争いの末の結婚だった。モナ、マリアム、マルワという3人の娘がいる。私はエルサレムとヨルダン川西岸地区の間で暮らすことを選んだ。そのため、歴史的パレスチナ国内に住む友人たちからは、「ハイファの海岸やアクレの海岸を見下ろす家に住むこともできたのに、なぜ占領軍と毎日対立するような過酷な生活を選んだのか?」と聞かれた。「2021年の統一インティファーダにおけるイスラエルのパレスチナ市民の蜂起は、彼らがパレスチナ人の一部であり、彼らをイスラエルに統合し、彼らのアイデンティティを消そうとする努力が失敗に終わったことを確認した。蜂起は、パレスチナの大義に対する深く強いコミットメントを示した。イスラエルは、ニンジンと棒を使った努力を倍増させ、彼らを服従させたり統合させたりするための方法を再検討するだろうが、これは2021年の蜂起が最後でも最初でもないということを意味するだけだ」30。
新たなパレスチナの暴動が起こるたびに、新たな歌が生まれる。パレスチナ人の夢を反映した、現代の政治的で芸術的なパレスチナの歌だ。歌は楽器であり、言語である。自分たちの魂、空、未来、土地、海を簒奪し、自分たちの運命を自分たちで決められると思い込んでいる占領者たちに立ち向かうための、パレスチナ人が発明した他のすべての道具と同じ道具なのだ。
この激しく、反抗的で、革命的な道を選ぶことで、歌、音楽、演劇、そしてあらゆる種類の芸術が、それぞれのスタイル、方法、選択肢を持ちながら、民族と祖国を表現する重要で偉大なメッセージをその襞の中に秘めている。目的のある芸術と商業的な芸術。正直で、現実的で、パレスチナ社会のあらゆる多様性を反映した言葉が突き刺さる。
以前、友人が私に投げかけた質問を思い出す: 「パレスチナとその大義が、歌や詩や小説にとってどの程度重荷になっていると思う?」友人である作家のジアド・カダーシュの質問の真摯さに驚いた。その質問は深く複雑だった。そう、それはジレンマであり、同時に選択でもある!私は自分自身をオペラ歌手よりもロックスターのように考えている。パレスチナとその人々について発言する方法を、どのような音楽ジャンルでも、どのようなサウンドでも見つけるだろう!
芸術のための芸術か、目的のための芸術か。私の答えはシンプルで短い!目的のある芸術だ。
- 14 このエッセイはアラビア語で書かれたものをサマ・サバウィが翻訳した
- 15 イスラエル国内のパレスチナ市民にも与えられたイスラエルの公的身分証明書。パレスチナ人に与えられる身分証明書の色は、地政学的な立場によって異なる。
- 16 カミヤ・ジュブランはパレスチナ人グループ「サブリーン」のリード・シンガー。1966年、ガリラヤのラマ村に生まれる。
- 17 サブリーン・グループは、作曲家サイード・ムラドによって1980年にエルサレムで結成された。
- 18 パレスチナの詩人サミフ・アル・カシム。アルバム『Dukhan al-Barakin(火山の煙)』(Sabreen、1984)に収録されている。
- 19 イエメンの詩人アブドゥルアジズ・アル・マカレー、アルバム『Dukhan al-Barakin(火山の煙)』(Sabreen、1984)に収録。
- 20 パレスチナの詩人フセイン・バルグーティ博士による「母の子守唄」、アルバム『Dukhan al-Barakin(火山の煙)』(Sabreen、1984)に収録。
- 21 チュニジアのマエストロ、モハマド・アル=ガルフィが1992年のカルタゴ国際音楽祭で「自由の声」(歌手とオーケストラ)を指揮した。
- 22 ドキュメンタリー映画『Jerusalem Back and Forth』(2005)のためにアクラム・サファディが書いた「Ya’lou」の歌詞、ハビブ・シェハデ(作曲)、リーム・タルハミ2015年。
- 23 Khaled Juma(詩人)、Said Murad(作曲)、「The Night Carries Me」、アルバムタイトル曲、Reem Talhami 2013年。
- 24 ハレド・ジュマ(詩人)とサイード・ムラド(作曲家)、「Step on」、アルバム『The Night Carries Me』、リーム・タルハミ2013年。
- 25 ハレド・ジュマ(詩人)とサイード・ムラド(作曲家)、「サムラ」アルバム『ザ・ナイト・キャリーズ・ミー』、リーム・タルハミ2013年。
- 26 アラファト・アルディーク(詩人)、イブラヒム・ナジェム(作曲家)『Rebel』Reem Talhami 2014年。
- 27 アラファト・アルディーク(詩人)、バジル・ザイード(作曲家)「あなたの嘶きはどこ、マーレ」、リーム・タルハミ2017年。
- 28 ハレド・ジュマ(詩人)、モニーム・アドワン(作曲家)、「私は彼の中で癒される」、リーム・タルハミ 2018年。
- 29 Waddah Zaqtan(詩人)、Moneim Adwan(作曲家)、「Elna Balad」、Reem Talhami 2021年。アリス・ユセフ原訳。
- 30 アンソニー・シャラットの言葉。
FARAH NABULSIは、アカデミー賞ノミネート、BAFTA賞受賞のパレスチナ系イギリス人映画監督であり、人権擁護者である。ストーリーテリングの力、映画、ソーシャルメディア、オンラインプラットフォーム(www.oceansofinjustice.com)を駆使し、パレスチナの体験を欧米の観客と共有している。彼女の作品については www.farahnabulsi.comを参照のこと。
映画による解放
権力、アイデンティティ、芸術について
ファラ・ナブルシ
「ライオンが書き方を覚えるまで、物語は常に狩人を賛美する」
-アフリカのことわざ
100年以上もの間、パレスチナ人は不公正の海に苦しんできた。私たちは容赦ないイデオロギーの犠牲者であり、その究極の目的は、私たちを私たちの土地から民族浄化することである。この人道に対する甚大な犯罪は、西側民主主義諸国がこれを無視、あるいは支持している間にも続いている。市民が政府に十分な圧力をかけないため、民主主義が本来の機能を果たせないのだ。市民が政府に十分な圧力をかけないのは、ほとんどの人が紛争の現実や背景を理解しておらず、自分たちが紛争でどのような役割を果たしているのか理解していないからである。彼らは私たちとともに私たちの痛みを十分に感じていないのだ。
アパルトヘイトの南アフリカと同様、パレスチナの最終的な民族浄化を止めることができるのは、西側の草の根の努力だけである。しかし、善意の人々がこの闘いに精神的に関わるだけでは十分ではない。私たちのために政府を動かす草の根活動の積極的な支持者やメンバーになるよう、強制され、活気づけられるよう、感情的にも関わらなければならない。
ハリル・ジブランはこう書いている。「悪と闘うには、過剰であることがよい。民衆の怒りを恐れて、残りの半分を隠しているのだ」パレスチナの闘いにおいて、私たちは真実を公表することにおいて、むしろ「控えめ」であったのではないかと私は心配している。当然のことながら、私たちは火消しに奔走し、救援に対処し、常に防御的な立場から対応してきた。それゆえ、大概の場合、私たちの物語は外部に対して十分に、効果的に、あるいは広範囲にわたって発表されることはなかった。真実味があり、喚起的で、より完全で、広く普及するような物語がなければ、私たちの大義に善意の人々を結集させることはできないだろう。意識と良心を変え、連帯を築き、規模を拡大し、有意義なBDSを奨励し、自由と正義と平等のための本格的な世界的運動を達成するためには、どうすればいいのだろうか。大義そのものはデフォルトで価値あるものなので、その部分については議論の余地はない。
私たちパレスチナ人がこのようなひどい状況に陥ってしまったのには多くの理由があるが、私たちが真実と正義と国際法を味方につけているにもかかわらず、その期間と規模の核心的な説明は、政治的シオニズムが植民地であり、入植者の事業であるということである。歴史上すべての植民地主義者が、植民地化しようとしている先住民がまず人間性を奪われ、抵抗すれば野蛮人やテロリストの烙印を押され、最終的には存在しないと主張されるよう、非常に懸命に努力していることは周知の事実である。これは対外的にも対内的にも行われ、世界中の善意ある人々がこれらの住民に共感しないように、あるいはこの問題が終わったと思うようにする。私たちは、このプロセスがパレスチナ人に対して組織的かつ綿密に行われてきたことを知っている。私たちの解放に勝算を見いだすには、この非人間化を逆転させるような方法で人々を大規模に関与させ、共感を呼び起こし、その共感から行動を起こさせる必要がある。闘争を成功させるためのもうひとつの主要な要件は、私たちの状況を正当かつ現実的な文脈の中に位置づけることである。パレスチナの抵抗、反乱、侵略、そして暴力さえも、もはやテロリズム、野蛮、根拠のない憎悪という枠にはめることなく、不法占拠に対する数十年にわたる闘い、14年にわたるガザ包囲に対する抗議、アパルトヘイト体制に対する憤り、現在進行中の戦争犯罪、家屋取り壊し、子どもの逮捕、検問、日々の屈辱、その他多くのものに対する拒絶を実際に認識し、尊重することができるように、人々に情報を提供し、教育する必要がある。
「ライオンが書き方を覚えるまで、物語は常に狩人を美化する。このアフリカの諺を目にしたとき、私は即座に、そして本能的にパレスチナのことを思い浮かべ、残念ながら、私たちはこの方程式におけるライオンであることを知った。もし私たちが、パレスチナ人の真実の物語を聞いてもらい、感じてもらい、その結果、人々が私たちとともに、そして私たちの大義のために行動を起こしてくれることを望むのであれば、私たちは自分たちの物語を創造的に、真正に、喚起的に、そして確実にエコーチェンバーを超えて伝えなければならない」
これは、作家、詩人、芸術家、映画製作者、弁士、コメンテーターといった、私たち自身の熟達した、素晴らしい、尊敬すべき語り手がいない、あるいはこれまでいなかったということではない。むしろ、彼らの数が足りないのだ。その多くは沈黙させられ、殺され、あるいはこの世を去った。率直に言って、私たちの物語はもう何十年も乗っ取られている。もし私たちが自分たちの物語を積極的かつ継続的に語り、そのための資金を提供しなければ、抑圧者とその取り巻きは、彼らの物語も私たち自身の物語も、すべての物語を支配することになる。しかし、今日の新しいテクノロジーは、偽りの物語を伝える伝統的な門番を迂回し、私たちの語り部の作品を、以前では不可能だったほど遠く世界中に映し出すことができる。
このことについては後で触れることにしよう。冒頭から始めよう。
私はロンドンで生まれ育ち、教育を受けたが、私の血統はパレスチナ人である。それが具体的に何を意味するかは、また別の本の別のエッセイに譲るとして……英国で育った私は、自分の家族がどこから来たのか、自分が何者なのかに戸惑うことはなかった。私は生まれも育ちもイギリス人だが、私の心臓と身体にはアラブ人、つまりパレスチナ人の血と遺伝子が流れていた。私はパレスチナの人々の苦境、容赦ない植民地支配者に対する自由を求める彼らの闘いを知っていた。同時に、私は何世紀にもわたって、ユダヤ人の無力さと被害者意識を理解し、共感してきた。それは、ある人々が「ユダヤ人の祖国」の必要性を感じた心理的な理由を説明するものであるが、その祖国を作るために行われた、罪のないパレスチナ人への土地取り上げと民族浄化を正当化するものではない。イスラエルがこの祖国を維持し、拡大し続けるためにパレスチナ人に加えている、現在進行中の抑圧、不正、アパルトヘイトを正当化するものでもない。単に一人の人間として、私はそう確信している。
10代の頃を通じて、私はパレスチナの子どもたちの医療援助を支援するためにハイドパーク周辺を自転車で走り回り、パレスチナの文化イベントに参加し、英国国教会の学校でパレスチナの慈善事業を推進した(ちなみに私はイスラム教徒だ!)。ケンジントンのハイストリートの頂上で行われた集会や抗議活動ではマイクを握り、近くの屋根の上に隠れていた「政府」の諜報員に笑顔で手を振り、私たちの写真を撮っていたのを思い出す!当時の唱和は、「1,2、3,4-占領反対」だった!5,6、7,8 イスラエルはテロリスト国家だ!」であり、現在でも抗議活動ではそうだ。また、「シャロン、シャロン、どうだ、今日は何人の赤ん坊を殺したんだ?時折、抗議やチャリティーや同情はあったものの、私は投資銀行家になり、その後数年間ビジネスを立ち上げて経営した。
それから25年以上が経った。どうして銀行やビジネスの世界から映画監督に転身することになったのかとよく聞かれる。簡単に言えば、故郷に帰ったということだ。
ロンドンで育った私は、パレスチナで何が起きているのか知っていたし、少なくとも知っているつもりだった。子供の頃は何度も訪れたが、10歳頃から35歳頃までは一度も訪れなかった!第一次インティファーダの頃に行かなくなり、どういうわけか30代半ばになっても一度も行っていない。何百万人ものパレスチナ人が、今日に至るまで、故郷に帰ることもできず、劣悪な難民キャンプにとどまっているのとは違って、私がパレスチナに自由に旅行できる恵まれた立場にいたことを考えると、とんでもないことだった。だから、私は訪れることにした。
先祖代々の土地との深いつながりと、そこで目の当たりにしている不公正が相まって、人間である私に大きな衝撃を与えた。イスラエルの検問所、パレスチナの土地、町、村を貫くアパルトヘイトの分離壁、難民キャンプ、分離された道路システム、監視塔、すべての丘の上の違法なコロニー、あるいは10代の息子が軍事拘束されてイスラエルの刑務所に連行された母親たちとの直接の会話、取り壊された家の廃墟で家族とお茶を飲むことなど、この直接の体験が文字通り私を変えたのだ!
私の最初の旅は、その後も何度か続いた。当初はそれほど明白ではなかったが、これらの訪問で私が得た大きな発見は、西側諸国の人々をパレスチナに連れて行き、実際に何が起こっているのかを自分の目で目撃させることが極めて重要だということだった。そうすることで、彼らは最終的に私たちを理解し、気にかけてくれるようになると確信していた。そして、パレスチナの自由と権利のために積極的で、献身的で、情熱的な欧米人に出会ったとき、それはたいてい、私が出会ったアラブ人やパレスチナ人たちよりもそうであった。実際、彼らの反応は、これほど露骨で制度化された不正義を想像したことがないため、圧倒されるのが普通だ。彼らは、それまで残酷な現実について知らされていなかった、あるいは誤情報であったことに衝撃を受けるのである。しかし、これが本当に機能するには、何百万、何千万という人々がパレスチナを訪れ、自分の目で確かめる必要がある。計算してみた。たった2千万人がパレスチナを訪れるのに、例えば飛行機代と1週間の滞在費で1人2千ドルだとすると、400億ドル以上の費用がかかる。4000万人なら800億ドルだ!実際に達成するには何十年もかかるだろうし、そもそも彼らが進んでパレスチナに行きたいと思わなければならない。現実的には、少なくとも私の視点からは、財政的にも物流的にも不可能である!
しかし、実現可能で、より経済的で、知的で、効果的で、パワフルで、達成可能な代替案は、パレスチナを彼らにもたらすことだった。世界中の何千万人もの人々に、せいぜい2時間程度の時間を割いてもらうだけで、美しく力強い映画を通して、大きな感動と目を見張るような体験をもたらすのだ!自分自身を創造的に表現し、このような人間の物語を伝えたいという深い欲求と、若い頃から映画や演劇が好きだったことから、私の心は決まっていた。私は映画監督になるのだ。
しばらく前、ある美術評論家が書いた次のような言葉を読んだことがある。確かに、私が映画という芸術を選んだのは、自分のアイデンティティをさらに追求する手段としてであったが、同時に、映画という芸術が提唱者の親玉として機能しうるからでもある。
もちろん、政治的アドボカシー、メディア、人権、BDS、学術的アドボカシーなど、私たちが支援し、もっと行うべきアドボカシーにはさまざまな形がある。しかし、私の考えでは、最も重要なアドボカシーの形態のひとつ、いや、最も重要な形態ではないにせよ、それは本質的に他のすべての形態に火をつけるものだからである。芸術家たちは、映画、ビデオ、オーディオ、ビジュアル・インスタレーション、詩、演劇などを通じて、深い苦痛からユーモアまで、人間のあらゆる感情を駆使して私たちに訴えかけることができる。芸術は心に語りかけ、人間性を高め、共感を呼び起こす媒体だからだ。それはまた、他のあらゆる形のアドボカシーがより快く受け入れられる道を開くものでもある。
ハリウッドと、映画におけるイスラム教徒やアラブ人の描かれ方を見れば、映画がいかに世界中の人々の認識に影響を与えることができるかを知ることができる。また、レジスタンス・シアターが、世論に影響を与え、世界中の観客を活性化させた主要かつ強力な要因として挙げられている。
私自身を事例に考えてみよう。私が実写の物語映画という形で芸術的なアドボカシーを選んだのは、天下のあらゆる事実や数字、真実や証拠、地図や国際法を人々の目に触れさせることはできても、人々の心を開かせなければ、彼らの心にアクセスすることも、彼らの理性を活性化させることもできないとわかっていたからだ。
研究によれば、人々に絶対的な事実の証拠を提供しても、それが繰り返し言われたり信じさせられたりしてきたことと矛盾していれば、深い惰性が残る。証拠や事実を前にしても、人は自分の信念に固執するだけでなく、時には自分の態度や考え方にさらに凝り固まってしまうのだ。しかし、同じ研究によると、同じ話題や見解、信念に関して、同じ人々に共感してもらうことができれば、彼らの心を通して語りかけることができれば、彼らははるかに受け入れやすくなり、最終的に彼らの考えを変えたり、元の立場から遠ざけたりするのは共感なのである。
つまり、相手の心に語りかけることで、自分の考え方や大義を理解してもらえる可能性が高まるのだ。
How to Win Friends and Influence People』の著者デール・カーネギーは、「人と接するときは、論理の生き物を相手にしているのではなく、感情の生き物を相手にしていることを忘れるな」と言った。国連決議282号、1397号、決議2254号、2334号、そしてジュネーブ条約第4条に言及することは、すべて良いことであり、非常に重要なことである。人々を本当に活気づけるのは、感情的なレベルで人々を打つ情報であり、これは物語を通して効果的に行うことができる。人は物語が大好きだ。私たちは皆、人間として物語に惹かれる。それが私たちの本質なのだ。だから人は良い本や映画を楽しむ。だから私たちは毎日新聞を手に取り、ニュースを見、ソーシャルメディアにアクセスし、食事のために集まるのだ。ストーリーは人生の通貨であり、芸術の場合、語れるストーリーや語れる方法に制限はない。
私たちが彼らの心に語りかけるとき、世界中の人々がパレスチナ人の苦境や私たちの闘いを理解しようと純粋に心を開き、興味を持ってくれることを、私はこれまでの経験から学んだ。映画祭のQ&Aでも、パネル考察でも、大学でも、人々は私の映画を歓迎し、興味を示してくれた。彼らは芸術を評価するだけでなく、それが織り成す真実と現実も評価してくれた。彼らは、何を、なぜ、どこで、どのようにと質問してくる。彼らが慣れ親しみ、魅了され、共感できる水準で、魅力的に、感情的なレベルで共鳴するように実施されれば、観客や業界は賞まで与え、配給する。私たちの短編映画 「The Present」を見てみよう。この24分の映画は、BAFTAを受賞し、アカデミー賞にノミネートされただけでなく、映画業界の頂点への旅路において、国際映画祭で何十もの賞を受賞し、主要なストリーミング・プラットフォームで配信され、世界中のテレビ局で放映され、多くの映画館で無数の言語で上映された。パレスチナ人男性とその娘がヨルダン川西岸に贈り物を買いに行くが、イスラエルの検問所の屈辱と闘わなければならないというシンプルな短編映画は、大手エンターテイメント出版社だけでなく、CNN、スカイニュース、BBCなどからも注目され、報道された。その中には、元CIA長官ジョン・ブレナンが書いた意見書が『ニューヨーク・タイムズ』紙に掲載されたり、CNNでクリスティアン・アマンプールとの討論が行われたりしたことも含まれている。この映画は、ネットフリックス・ワールドワイド、iTunes、アマゾン・プライムなど世界中で配信されている。数多くの国際的な著名人、セレブリティ、ミュージシャン、ファッションモデル、政治家、学者などが、この映画を公に支持している。この原稿を書いている今、フランスでのプレミア上映から1年半以上が経過しているが、映画祭での上映や受賞は続いており、ほぼ一日おきに上映や考察の依頼が来ている。アメリカのブラウン大学やコロンビア大学から、イギリスの一流校、募金活動、公共イベントまで、芸術的なアドボカシーは続いている。オハイオ州全体の教育カリキュラムで、映画制作のケーススタディとして使われたほどだ。(否定的な人は常にいるので、ネットフリックスとほとんどの配給会社が、アカデミー賞やBAFTAにノミネートされる、あるいは最終候補に残る数カ月前にこの映画を取り上げたことを強調しておきたい)。なぜこのようなことを申し上げたかというと、私自身の自画自賛をするためではなく、芸術的主張の力を説明するためである。『ザ・プレゼント』の軌跡は、私たちの大胆で本物の物語が世界の舞台で活躍し、現在主流となっている物語を圧倒する余地があることを証明している。
だから、書くことを学ぶライオンに話を戻そう。私たちは容赦なく、恐れを知らないライオンになる必要がある。なぜなら、私たちには真実と正義と国際法が味方についているからだ。なぜなら、私たちには真実と正義と国際法が味方だからだ。また、私たちには、たとえあなたが作ろうとしても作れないような、不条理で魅力的で信じられないような物語が山のようにある!
もちろん、アートだけではパレスチナを自由にすることはできないが、アートがなければパレスチナは決して自由になれないと私は信じている!アートは、他のすべての柱となる擁護の柱なのだ。映画だけでは闘いを変えることはできないが、映画には闘いにおける重要な役割がある。映画には、闘いを変え、火をつける力がある。国境を越え、固定観念を取り払い、誤解や誤った認識を克服する力がある。興味や関心を集め、研究を促し、理解を深めることができる。そして、抑圧された人々のために、抑圧された人々とともに、抑圧を終わらせるための行動を起こすように人々を駆り立てる。もちろん、パレスチナ人を解放するためには、力強く、明確で、統一された社会運動が必要だが、それが成長し、勢いを増すためには、人々がその運動に参加せざるを得ないと感じることが必要であり、そのためにはエンゲージメントが必要だ。私の考えでは、映画とは、おそらく世界が知る限り、最も強力で広範囲に及ぶ、参加と有意義な人間的コミュニケーションのための芸術的媒体である。
振り返ってみれば、多くの人がこの章を読んで、私がここで書いたこと/表現したことは当たり前のことだと思うかもしれない。しかし、残念なことに、パレスチナの自由のための闘いに投資するとなると、後回しにされがちなのが、まさにこのソフトパワーの要素なのだ。私はまた、パレスチナ国内のパレスチナ人が耐えている抑圧や圧力を考えると、この継続的で成長する努力の 「獅子奮迅の活躍」(ダジャレを意図した)を実行する責任は、亡命パレスチナ人と私たちの同盟国にあり、同時に国内のパレスチナ人アーティストを支援することだと信じている。
パレスチナ人はいつか自由になる。私は本当にそう信じている。過去50年、20年、10年、5年、そして過去12カ月を振り返ってみても、その進歩は明らかだ。地上では、占領とアパルトヘイトのもとで暮らすパレスチナ人にとって本当に絶望的な状況だが、世界世論の法廷では、事態はかつてないほど好転している。転機は常に曲がり角にある可能性がある。団結した運動に向けた粘り強い行動が主な材料だが、バケツ一杯の希望と大量のアートがレシピを完成させる。もしあなたがクリエイティブな才能と深い正義感を持っているのなら、パレスチナの自由と平等のためにそれらを活かしてほしい。共に力を合わせれば、必ずや変化をもたらすことができるはずだ。
SAMAH JABRは東エルサレム在住のパレスチナ人精神科医・心理療法士である。パレスチナのラマラにある保健省のメンタルヘルス・ユニットの責任者を務める傍ら、子供と成人を対象に診療を行っている。ワクチンル博士は、心理的幸福、政治的・社会的・臨床的ダイナミクスの交差をテーマに、学術誌や一般紙で幅広く発表している。パレスチナに関連する問題について国内外で講演を行っており、人権問題のオピニオンリーダーとして定評がある。著書に『Beyond the Frontlines, Derrière les frontts』がある: Chroniques d’une psychiatre psychothérapeute palestinienne sous occupation』(2017年、PMN刊、フランス語とイタリア語で出版)、『Sumud, resistere all’oppressione』(2021年、Sensibili alle foglie刊、イタリア語で出版)がある。ワクチンル博士は、パレスチナ・グローバル・メンタルヘルス・ネットワークの創設メンバーでもある。
解放心理学
セラピー、気づき、批判的意識の発達
サマ・ワクチンル
私は怪我と痛みを抱えてこの世に生を受けた。出産時の体重は5300グラムで、普通の経膣分娩で生まれた。しかし、私の体が大きかったため、出産は非常に困難で、私と母の命を救うために、医師は私の鎖骨を折らなければならなかった。そのため、左腕神経叢(利き腕であるはずの私の腕につながる神経)に後遺症が残った。その後何年もの間、両親は私を担いで、イスラエルの医療センターで理学療法を受けられるよう、シュファットからフレンチヒルまで徒歩で通っていた。私は、自分が経験したことを記憶できるようになるまで、その治療を続けた。
私の治療をしてくれたリヴァはイスラエル人女性で、今では外見から宗教的なユダヤ人だとわかる。萎えた腕を鍛えるために登らなければならなかった黄色いはしごを覚えている。これは難しい運動で、私はその日のトレーニングをすべて終えるともらえるチョコレートをもらうためだけに、この運動に取り組んだ。また、車も持たず、ヘブライ語も話せず、中心部でのイスラエルの圧倒的な存在感に不安を抱いていた両親にとって、この旅がいかに疲れるものであったかをよく覚えている。午前中の旅の後、疲れ果てて日焼けした母が、ヨーグルトベースの乳液を作って顔への日焼けを和らげていたのを覚えている。
私は4人目の女の子だった。母は私より先に男の子を死産し、私の難産と怪我に対処しなければならなかった。私の出産後、母は産後うつ病になったのではないかと私は強く疑っている。また、4人目の女児を授からなかった無念を晴らすために、「許し」を意味する「サマ」という名前を授かったことも知っている。
小学校の頃、私は太っていて近視で、分厚い矯正眼鏡をかけていた。私は「不器用」な子供だったので、体を使った遊びには向いていなかった。プレーに参加すると、チームが試合に負けたことを責められることが多かった。腕が弱く、動きが制限されていたため、頻繁に怪我をし、額や頭皮にいくつもの傷ができた。おそらく、このような幼いころの不適合者としての経験が、学習障害を持つクラスメイトや社会的に困難な背景を持つ生徒など、溶け込むことが困難な他の人々に対して敏感で共感的な性格にさせたのだろう。
一方、私の微妙な身体的弱点は、脳の筋肉を発達させる強い動機となった。私は言葉遊びが得意で、人気者で信頼できる同僚や友人として目立っていた。困ったときに私の助けを求めたり、先生や管理者に手紙を代筆するよう頼まれたりする同級生たちから、私は「代弁者」のレッテルを貼られた。同様に、私は大人たちから「議論好きなトラブルメーカー」というレッテルを貼られたが、それでも賢明な子供として尊敬されていた。予期していた通り、私は、強く力強い大人たちを前にして、自分の権利と他人の権利を守るために立ち上がったために、何度か罰を受けた。
第一次インティファーダという集団的な体験の最中にあった私の思春期は、こうした幼児期の特徴を際立たせた。私は、壊れた、機能不全に陥った、欠陥のあるコミュニティの一員と見られていることを自覚し、個人的なものと集団的なものとの間のこの相互作用が、政治とパワー・ダイナミクスに対する洗練された理解の発達を加速させた。友人のベッツィー・メイフィールドに、「あなたは片腕で世界を抱きしめている」とよく言われたものだ。私の母も同じように、「大きなスイカを片腕で抱えても、落ちてくることはない」と私によく警告していた。
賢明な思春期の私は、両親の不安や社会的禁止事項、政治的抑圧を認識していたため、両親や自分自身を危険にさらさないよう、リスクを計算することに熱心だった。思春期に培った勇気、用心深さ、批判的思考は、その後の多くの危険:イスラエルの占領、パレスチナの組織による抑圧、社会の腐敗、家父長制と性差別、そして私の世界が大きくなるにつれて、西洋のイスラム恐怖症と私の民族への抑圧への加担にも対処するために、私が狭い路地を歩き、愛と自由への道をナビゲートするのに役立った。私の思春期は、自分自身と愛する人たち、そして傷ついたパレスチナ人コミュニティのために、幸福と自由を追い求める長い旅路を歩むための準備を整えてくれた。
私は、医学の分野で勉強し、懸命に働くことによって自分自身を武装し、その後、精神医学を専門とした。臨床の場で出会ったトラウマを抱えた人々を癒すという使命には、いくつかの心理療法の理論が適しているように思えた。しかし私は、軍事占領下にある地域社会の結束を弱める、個人間に生じた悪しき関係に対する「治療法」を見つけなければならなかった。イスラエル人に協力する傾向、自分自身に対する蔓延した不信感、劣等感と無力感の集合体などは、抑圧されたコミュニティに典型的に見られる症状のほんの一部にすぎない。私は、人々の直接的な体験を注意深く観察し続けることも同様に重要であることに気づいた。私は一から結論を導き出し、個人の主体性、自己決定力、健康を促進することによって、歴史的・集団的トラウマの救済策を模索することを学んだ。
私の仕事は実に多岐にわたる。政策立案や、国家自殺防止戦略やCOVID-19に対する国家精神保健対応計画などの国家戦略の策定、医師や精神保健福祉士に対する研修や監督などにも幅広く関わり、パレスチナにおける将来の精神保健実践における専門的能力や自由で倫理的な態度の構築に貢献してきた。さらに私は、精神病やその他の重度の精神障害に苦しむ患者、シェルターで虐待を受けた女性を抱える家族、民法上の囚人、政治犯、少年犯罪者、政治的暴力や拷問によるトラウマの被害者など、幅広い臨床経験を積んできた。これらすべてのグループにおいて、私は政治的暴力が個人の生物学的・心理社会的脆弱性とどのように相互作用し、病気を誘発し、回復を妨げているかを目の当たりにしている。
家父長制、ジェンダーに基づく暴力、汚職、縁故主義、組織的偽善、抑圧的な政治権力によってパレスチナ人の価値観や信念体系を平らにし、避難させ、彼らに誤った価値観を押し付ける微妙な悪意あるやり方など、抑圧や耐える社会悪のもとで、生存と降伏の間で揺れ動く非道徳的な人々である。
パレスチナの野党活動家ニザール・バナトがパレスチナの治安部隊に逮捕され、拘束中に死亡したことに人々が抗議したとき、公式メディアは、抗議に参加した人々たちには「外部からの意図」があり、デモに参加した女性たちには「名誉」がなく、彼女たちのスローガンはパレスチナ社会の「純粋さに傷をつける」ものだと主張し、事態を拡散させた。女性参加者の携帯電話は没収され、その内容は彼女たちを脅迫し、黙らせ、透明化する対象として利用された。私たちの市場やキャンプで活動家を暗殺するためにパレスチナ人のふりをするイスラエルの諜報員のように、パレスチナの公式警備員は私服を着て反対派のデモに忍び込み、抗議に参加した人々の骨を折るために石で攻撃し始めた。上記のようなイスラエルの戦術はすべて、今やパレスチナの治安システムによって模倣され、侵略者と同一視されるだけでなく、侵略者に魅了されている。
執筆、スピーチ、友人、同僚、同志との動員やネットワークづくり、社会的・政治的正義のためのアドボカシーを通じた活動は、占領されたパレスチナ人の精神に重くのしかかる社会悪を癒すための医学的・心理学的介入としても機能してきた。私は良心的な市民としてこの仕事に携わっているが、抑圧の重圧に押しつぶされそうになりながら、遠くから見守る外部の専門家よりも深い分析経験と理解を得ている。
他の多くのパレスチナ人と同様、私の人生も空間と時間の盗難によって特徴づけられている。エルサレムでは、パレスチナ人住民のための空間が狭められており、隣人たちは車の駐車場や共有ビルの屋上の空きスペースのために殺し合うこともある。私は、このような現実がもたらす攻撃性の中で生きているため、このような締め付けを実感している。私の個人的な生存戦略には、エルサレムとヨルダン川西岸という2つの世界の交差点に住んでいるため、この現実を超機能的に政治的に分析することも含まれる。官僚主義や行政の慢性的な遅刻や意図的な遅滞は、パレスチナの人々を息苦しくさせる新たな手段だと感じている。解放とは、私たちの空間と時間の両方を手に入れ、それらを賢く使うことでなければならない。
パレスチナの経験に関するローカルな知識を生み出し、それを世界と共有することは、私や他のパレスチナ人研究者たちにとってのもうひとつの戦場である。時間と私たちの特別な関係、適切な予算と適切な人材の不足は、メンタルヘルスにおける知識を生み出す道のりの障害のほんの一部に過ぎない。学術的な文章を書くには、脚注や校正、書式設定に果てしない努力が必要であり、ジャーナルやその記事を同僚に転送してもらうためには、著者や読者にお金を払ってもらわなければならないことも多い。学会は、たとえ発表するにしても参加費がかかる。
私は、パレスチナの現地知識や専門知識を伝えるために、自信のある同僚に学術論文の共著を手伝ってもらう一方で、関連する国際的な学術知識を簡略化してパレスチナ人に説明するよう心がけている。多くの学術論文の難解な専門用語は、社会的・政治的変革に携わる多くの人々の頭には届かない。それよりも私は、学問の洗練された言葉をわかりやすく一般的に説明することに時間を費やしたい。私は適用可能なポイントを引き、そこから利益を得ることができる普通の人々に、持ち帰ることができるメッセージを届けることを好む。
パレスチナの、そして地域のメンタルヘルス専門家としての私の名声と権威が高まるにつれ、強大な権力者が指示し、彼らの特定の利益に奉仕する、あいまいな医学的・法的報告書を書かなければならないというプレッシャーが生じる。苦労して勝ち取った評判と経済的自立が、この種の誘惑や圧力に立ち向かい、それに抵抗するための私の道である。
私は、専門家としての権威を利用して、精神医療におけるスタッフの増員と予算の増額を提唱し、スティグマや無知な神話、地域の患者や女性、クィア、脆弱な人々に対する差別に反対している。私は、精神科病院の外での精神科治療を推進し、プライマリーヘルスケアや一般病院に精神保健を統合しようと努めている。
パレスチナ人の心理学的思考の文脈化を促し、西洋のPTSDの概念に疑問を投げかけ、「ジハード」、「シャヒード」、「犠牲」、「裏切り」、「名誉」、「スムード」、「抵抗」、「祖国」、「連帯」など、パレスチナ人の解放のビジョンに関連する影響力のある重要な概念を探求しようと努めている。私は、これらの概念の医学的考察を明確にし、検証する作業は、確立され定着した不正のシステムを解体することに貢献するものだと考えている。
自分の影響力や影響力の大きさに幻想は抱いていないが、自分の専門分野が可能にし、必要とするパレスチナの解放プロジェクトに有意義な貢献を残せるよう、長生きしようと思っている。セラピー、アウェアネス、批判的意識を通しての心の解放は、私の専門分野にとっても、パレスチナ・プロジェクト全体にとっても基本的なことであり、私が最も貢献できる分野である。
この日は、私の身体に弱く痛みを伴う腕を固定し、私の心の中に部分的に弱く痛みを伴うパレスチナを表現して45年になる。私の身体的経験は、非対称性、力の不均衡、傾きについて何かを教えてくれた。とはいえ、顔を洗うとき、ステーキを切るとき、車を運転するとき、愛する人を強くハグするとき、私は腕の弱さを回避する方法を知っている。私はこの経験的知識と理解を使って、士気が低下した瞬間に対抗策を講じ、力関係と格闘し、占領下のパレスチナの解放のために戦い続けている。
MAZIN QUMSIYEHは、ベツレヘム大学(http://palestinenature.org)のパレスチナ生物多様性・持続可能性研究所(PIBS)の創設者であり、ボランティア・ディレクターである。文化遺産から人権、生物多様性保全、癌に至るまで、160以上の科学論文、30以上の本の章、数冊の本を出版している。パレスチナの青少年団体や奉仕団体の役員を多数務め(http://qumsiyeh.orgも参照)、人間と自然社会の持続可能性に関する多くのプロジェクトを監督している。2020年にはポール・K・ファイヤアーベント財団賞(真のインスピレーションの源となる顕著な業績を認め、奨励する)を受賞し、2019年にはアラブを代表する業績(環境保護活動)を称えるタクリーム賞を受賞した。
パレスチナ人としての私たちの学び
マズィン・クムシエ
子供の頃に何を学ぶかは、私たちの未来を形作る。幼少期の経験が今の私を作っているのだから。現在89歳の母が、見知らぬ人々に親切にしてくれたことが、私に博愛の本当の意味を教えてくれた。時間を無駄にしないことを教えてくれたのは、父の献身と勤勉さだった。叔父のサナ・アタラ(パレスチナ初の動物学者)の野原への同行が、私に自然への愛を教えてくれた。母方の祖父は、本を大切にし、愛することを教えてくれた。これらの影響はすべて、私が6~7歳の頃にもあった。私は、教育者の家庭に生まれたことがどれほど幸運であったかを常に理解していたわけではなかった。
そのうちの2人についてお話ししよう。私の母方の祖父は、祖先やほとんどの子孫と同じように、ベイト・サフールという小さな村で生まれた。地中海と死海の中間に位置する丘陵地帯にあるベイト・サフールは、聖書に登場する「羊飼いの野原」であり、約2000年前に星を見た羊飼いたちが、イエスが生まれたベツレヘムへと丘を登っていった場所である。私の祖父母と両親の家は、イエスが生まれたと伝承されている聖誕教会から文字通り坂を下ったところにある。ベツレヘムの学校からの帰り道、私はよく立ち寄って教会の洞窟のろうそくを眺め、それから祖父母を訪ねたものだ。祖父、つまりシドーは、第一次世界大戦中に肉親をすべて失い、孤児としていかにして身を立てていったかという苦労話をするのが好きだった。
時には、私たち子供のグループは冒険のために近くの丘に向かった。野生の根菜やサンザシの実を食べ、時にはパチンコでスズメやヒバリを捕まえて肉にした。こうした疲れる旅の後には、私たちがいつ立ち寄るかを知っている祖母が作ってくれるおいしい食事が待っていた。祖父が丹精込めて手入れした庭に、ビワ、イチジク、アンズ、ブドウ、アーモンドがたわわに実る季節には、こうした訪問が頻繁にあった。父と母には庭がなく、私たちは1970年以降に家を建てるまで、賃貸アパートに住んでいた。私はそのとき13歳だった。そのため、祖父母の庭の思い出が50年ほど経った今、私は自分の庭とパレスチナ生物多様性持続可能性研究所の植物園の手入れをしている。
シドーはまた、ベイト・サフールで最も有名な農産物であるファクース(小ぶりで甘い蛇のようなキュウリ)を時折栽培し、ベツレヘム周辺の丘陵地帯の豊かな赤土で育っていたようだ。町の人々は5,000年以上にわたって農業で栄え、小麦、オリーブ、アーモンド、イチジク、ブドウ、その他さまざまな果物や野菜を栽培していた。ベイト・サフールの住民は平和に共存していたが、同質ではなかった。モスクと教会が隣り合っていた。世俗的な人々と宗教的な人々は互いに冗談を言い合いながらも親友だった。叔父の一人を含む左翼、共産主義者もいれば、もう一人の叔父のような右翼もいた。私は、時に白熱し、しばらくするとトランプでさらに白熱するような、彼らの間の公開討論を楽しんだ!ベイト・サフールには、私が知っている黒人の家族が少なくとも一組あった。エチオピア系キリスト教徒の家族だ。もちろん、イスラム教徒とキリスト教徒の間でも、肌の色をめぐる問題でもなかった。むしろ、大多数を占めるギリシャ正教とプロテスタントの教派間の教義の違いだった。母の実家がルター派、父の実家がギリシャ正教だったため、こうした意見の相違は私たちにとってより顕著だった。ベツレヘムの近くの町はさらに多様で、アルメニア人、シャルカ人、コプト人、その他の宗教や国籍の人たちが入り混じっていた。家族間の争いは、賢明な年配の指導者たちによって簡単に処理され、私たちのような熱血漢のティーンエイジャーだけがそれに挑戦する勇気があった。
他にも、村人と近くの遊牧民ベドウィンの間で、ヤギに農作物を荒らされるような紛争が起こることもあった。そのため、非武装の衛兵を意味するナトゥールが畑の周囲に配置され、農作物を守ってくれることも珍しくなかった。しかし、私たちはミルクやチーズ、肉製品をベドウィンに依存し、彼らは農産物を私たちに依存していた。全体として、人間と自然との調和は何千年もの間、そこで保たれていた。事態は19世紀末のシオニズムの出現によって劇的に変化し始め、1918年から1948年にかけてイギリスの「委任統治」の下で加速し、1948年から1949年にかけてのナクバ(大惨事)でピークに達した。この決定的な出来事によって、私たちの国民のほとんどが難民となり、古くからの景観が引き裂かれた。パレスチナの活気に満ちた多民族、多文化、多宗教のコミュニティは、当然のことながら、「ユダヤ人国家」という考えを拒否した。(Qumsiyeh 2004)。1949年に導入された「グリーンライン」と呼ばれる休戦ラインは、家族をそれぞれの土地から、そして互いから分断した。ここベツレヘムに住む私の祖母はナザレの出身で、その古い町並みを見たいと切望していた。母は、ナクバで虐殺が行われた33の村のひとつ、デイル・ヤシン村で16歳のときに殺された友人、ハヤ・バルビシのことを今でも思い出す。しかし、私たちのナクバは1949年に終わったわけではない。新国家イスラエルは1967年にパレスチナの残りの地域を占領した。
1967年直後から、イスラエルは獲得した地域のパレスチナ人の土地を没収し、そこにユダヤ人だけのコロニー/入植地を建設し始めた。これは入植者による植民地計画であり、単なる軍事占領ではなかった。イスラエルはユダヤ人国家になるためにつくられ、私たちパレスチナ人は不要な 「他者」だったのだ。こうして現在、750万人以上のパレスチナ難民や避難民が存在し、残りの600万人はベツレヘムのような孤立したゲットー/バントゥスタンで暮らしている。パレスチナ人の多くは農業に従事していた。土地を奪われた多くの人々は、他の仕事を見つけざるを得なかった。何千人もの人々が、現在ヨルダン川西岸とガザの大部分を覆っているユダヤ人入植地や道路の建設に従事させられている。
このように、私の子供時代と見解を形作ったものには、家族の影響と、より大きな国の影響の両方が含まれている。私を今の私たらしめた決定的な出来事をひとつ挙げるとすれば、1970年、私に自然への愛を教えてくれた叔父サナの死だろう。これが転機だった。サナ叔父は博士号を取得し、イランで教鞭をとり始めたばかりだったが、移動研究用に改造された彼のバンが、対向車線にハンドルを切ったトラックに正面衝突された。サナと彼の助手は即死だった。彼は27歳だった。13歳だった私は、彼の跡を継ぐことを自分と彼の父シドーと約束した。その4年後、私は高校を卒業し、生物学の分野で長い教育のキャリアをスタートさせた。生物学の学士号を取得し(1978)、エリコ、ベツレヘム、エルサレムの学校で教えた(1978-1979)。その後、テキサス州ラボックとテネシー州メンフィスでポスドクを務め(1986-1989)、最後にテネシー大学(1992年まで)、デューク大学(1993-1999)、イェール大学(1999-2005)の医学部と病院で教職に就いた。私はまた、医学遺伝学の専門医資格を取得し、大学病院と提携して臨床ラボを運営した。
新しい企業や組織を立ち上げることは、私にとって最も魅力的なことだった。前述したように、正式な教育や正式な専門サービスは、私の思考や集団活動、起業家精神を最も形成したと考えるものではない。私の将来を形作ったのは、幼少期のかなり早い段階から、家族の非公式な観察とロールモデルだった。学校の教師だった父は、小学校の教師という経歴とはまったく関係のない、少なくとも2つのベンチャー企業を立ち上げていた。母方の祖父は、アラビア語の文法からパレスチナのことわざまで、ただ知識が好きだったという理由だけで本を書いていた。だから、この人たちのことを思い出さない日はない。
もちろん、大人になってから影響を受けた人たちもいる。修士号と博士号の主な指導教官は、とても親切で寛大な人たちだった。ラルフ・ウェッツェルは、1966年から1969年までコネチカット大学で叔父のサナの博士号指導教官を務め、1979年から1982年まで修士号指導教官を務めた。私は彼が引退する前の最後の大学院生だった。彼はとても親切で勤勉な人だった。私はしばらくの間、彼の家の屋根裏部屋に住み、奥さんの素晴らしい料理を楽しんだ。テキサスでの主な指導教官はロバート・ベイカーで、彼はよく私に挑戦してくれた。私が困難に直面すると、彼はこう言ったものだ。「あなたを殺さないものは、あなたを強くするだけだ!」と。例えば、私が脳卒中で左半身不随になったときや、不満を持つ元学生がロバートに仕返しをするために私の名誉を傷つけようとしたときなど、このサポートは非常に重要だった。私は取り乱し、科学をやめようとさえ考えたこともあった。その時期を乗り越え、さらに強くなるためには、ロバートの知恵とアドバイス、そして当時の大学院生仲間の助けが不可欠だった。母国を離れ、ロバートとローラは私たちの家族だった。アメリカ国内はもとより、世界各地から集まった大学院生や学部生たちは、「哺乳類学」ファミリーとして結束を固めていた。特に覚えているのは、1985年に私がケニアに2カ月間滞在している間、ロバートとローラの助けを借りて、何人かの大学院生が新米ママの私の妻の面倒を見てくれたことだ。
私は自分の学生に接するとき、この恩師たちを見習おうと努めた。学問的な面だけでなく、言葉では言い表せないような個人的な面でも、彼らをサポートしようと努めた。ロバート・ベイカーが何度か大学院生に言った言葉がある: 「へその緒は決して切らない!」 彼は、私たちは連絡を取り合うべきであり、アドバイザーは子供が家を出た後も世話をし続ける両親のようなものだ、という意味だと私は理解していた。何年も経った今、私はこの「知識」というへその緒が世代を超えてつながっていることも認識している。たとえ一度も会ったことがなくても、前の世代を教え、その世代の人生を形作ってきた人たちが、私たちの人生を形作ってきたのだ。この点は、かつてないほど今、私にとって最も明白である。そして60代になった今、定期的に友人や同僚を失っている。2008年にパレスチナに戻って以来、私は19人の親しい友人を失ったが、そのほとんどは、占領に対する非暴力抵抗に参加したイスラエル兵によって殺された。多くの困難に直面しながらも、特に大きな挑戦を決意したときに、前進し続けることは時に困難である。しかし、先の世代が私たちに与えてくれた強さこそが、何世代にもわたって続く、人生における主な贈り物なのだ。だから私は今、ほとんどの時間を若い人たちと過ごし、新しいプロジェクトのほとんどを若い人たちに力を与えることに集中している。
米国に移住したとき、私は常にパレスチナに戻り、そこで新しい世代に力を与えることで奉仕し、そうして私自身の公式・非公式の教師に対する恩義に報いようと考えていた。結婚や、アメリカで良い教育を受ける必要のある息子を授かったこと、デューク大学やイェール大学でのポジションなど、大きなチャンスに恵まれたことなどが、帰国を遅らせる原因となった。しかし、このような遅れは、経済的、社会的、学問的、感情的に、より良い準備をするための手段でもあった。2008年にパレスチナに戻ったことは、私の人生において最高の決断だった。私は高給取りのキャリアを捨て、ここで年に1つか2つのコースを教え、人々、特に若者への奉仕にほとんどのエネルギーを注いだ。アメリカでは、パレスチナ帰還権連合やWheels of Justice Bus Tourのような組織や運動を共同で立ち上げ、政治的に積極的に活動していた。しかし、パレスチナで、より多くの人々に、より多くの奉仕ができることが明らかになりつつあった。こうして2008年、私はここベツレヘム大学で臨床研究室を立ち上げ、複数の大学で非常勤講師として教え始めた。私は民衆の抵抗に関与し、このテーマに関する本を書いた32。私は自分の本(アラビア語版)のコピーを若者たちに配り、彼らの考えに耳を傾け、彼らから学ぶことを喜んだ。私が関わった若者の中には、他の人たちよりも際立っていた人たちがいた。例えば、アル・ワラジャのバジル・アル・アラジは、非暴力抵抗の方法を学び、試してみることに特に熱心だった33。彼と私、そして他の4人は、隔離された入植者のバスに乗り込み、パレスチナ・フリーダム・ライダーズと呼ばれる行動でアパルトヘイトを強調した。私が何度も拘束された間、拘束された仲間たちとおしゃべりするのはいつも楽しみだった。バジルは私に多くのことを教えてくれた。彼はイスラエル兵に殺された。
抵抗は重要だが、植民地主義下での教育、芸術、農業、その他何百もの生活活動も抵抗であると、私はいつも信じてきた。アラビア語ではsumudと呼ばれ、抵抗と回復力を組み合わせたものだ。ここに戻って以来、私は常に、自分の多少特権的な新しい地位を利用して、この点で役に立つ方法を探してきた。私が「特権的」と言ったのは、経済的に自給自足ができ、素晴らしい学歴を持ち、アメリカのパスポートまで持っていたからだ。だから私の行動はすべて、収入源を築くために羊を手に入れて貧しい家族に贈ったり、貧しい理系の学生の学費を払ったり、木を植えたりして、サムドの人々を助けることに向けられていた。若者を支援するために、私たちはベツレヘム大学にバイオテクノロジーの修士課程を、ビルジート大学に環境学の修士課程を設立した。2014年、私と妻は25万ドルを寄付し、ベツレヘム大学にパレスチナ生物多様性・持続可能性研究所とパレスチナ自然史博物館を設立した。この研究所のモットーは、「自らを、他者を、自然を尊重する」ことだ。これらの尊重のレベルは、持続可能な人間と自然の共同体というビジョンを達成するのに役立つ。研究所の使命は、私たちの文化遺産と自然遺産に関する研究、教育、保護である。
ジェシーと私はこの7年間、フルタイムのボランティアとして活動してきた。他のボランティアたち、そして後に数少なくなったスタッフの助けを借りて、私たちは環境教育、研究、保全の分野で多くのことを行うことができた。繰り返しになるが、結局のところ、これはすべて抵抗の一形態なのだ。ベツレヘムにこのセンターがあることで、何千人もの学校や大学生が恩恵を受けている。この植物園と施設は、パレスチナの不確実性、さらには騒乱の中にあって、人々と野生生物の避難所のオアシスとなっている。植物園は現在、380種以上の植物を誇っている。自然史博物館や民族学展示も充実している。数千冊の蔵書がある。コミュニティ・ガーデン、子供のための探検遊び場、動物リハビリテーション・ユニット、研究ユニット、ハーバリウム、持続可能性のモデル-バイオガス、ソーラーパネル、堆肥とリサイクル・センター、水耕栽培、アクアポニックスなど-もある。しかし、これらすべての「施設」は、何十年も前の私と同じように、他人の役に立つことを目的に知識の虜になった一人の子供や一人の大学生が生み出す火花に比べれば小さなものだ。
お世辞の最たるものはもちろん模倣であり、私は先人たちの真似をし、次の世代にも影響を与えようとしてきた。車輪を発明したのは誰だろう?私の息子、ダニーが1998年に植民地化後の縮小するアメリカの地図を見て、縮小するパレスチナの地図を描いた。これは波及効果である。人生を形成した人々は、本質的に、彼らが影響を与えた人々の行動を通じて不滅であり、それがまた他の世代を形成し、無限に続くのである。ブラジルで羽ばたく蝶がテキサスで竜巻を起こす可能性があると主張したエドワード・ローレンツによって初めて唱えられた「バタフライ効果」と科学者たちは呼んでいる。私たちは、前の世代に誰が影響を与えたかをぼんやりと知っている。もし私がタイムマシンで何世代も前に戻ることができたとしたら、祖父や、ひいては私に影響を与えた火種が、ここパレスチナのイエスの弟子からもたらされたことを見つけることができるだろうか?もっと現実的に考えるなら、他人を助けるために自分の時間をどう使うかを決めることだ。私が最も誇りに思うのは、自分が手助けした生徒たちが今では立派になり、他の生徒たちを助けているのを見るときだ。ボランティアや従業員が子どもたちと情熱的に接しているのを目の当たりにすると、感動を禁じ得ない。ハリル・ジブランの不朽の名言を思い出し、誰が彼に影響を与え、彼が誰に影響を与えたのかと考える:
自分の財産を捧げても、与えるものはわずかだ。本当に与えるのは、自分自身を与えるときだ。持ち物とは、明日必要になるかもしれないことを恐れて守り続けるものにほかならない。そして明日は、聖なる都を目指す巡礼者たちの後を追いながら、道なき砂に骨を埋めるような慎重すぎる犬に、明日は何をもたらすのだろうか?そして、必要性への恐れとは、必要性そのもの以外の何なのだろうか?
植民地主義、人種差別、戦争、テクノロジー、パンデミック、気候変動といった試練を人類が乗り越えられるという希望があるとすれば、その成功はこのような波及効果によるものでしかない。ロウソクが消える前に別のロウソクを灯したとして、それは本当に消えたのだろうか?さらに、そう言っては陳腐だが、光の明るさは暗闇の中でこそ、より際立ち、より高く評価されるのである。
31 Mazin B. Qumsiyeh, Sharing the Land of Canaan: Human Rights and the Israeli-Palestinian Struggle (London: Pluto Press, 2004).
32 Mazin B. Qumsiyeh, Popular Resistance in Palestine: A History of Hope and Empowerment (London: Pluto Press, 2012).
33 Mazin B. Qumsiyeh, ”Basil Al-Araj of Al-Walaja: RIP」2017年3月8日、https://peacenews.org/2017/03/08/basil-al-walaja-rip-mazin-qumsiyeh/
34 Kahlil Gibran, The Prophet (New York: Alfred A. Knopf, 1923)。
第4部 解放、政治、エンパワーメント、連帯について
HASA. DUL-RAHIM ABU NIMAHは1935年、パレスチナのバティールで生まれた。バティールとベツレヘムの学校に通い、ベイルートのアメリカン大学を卒業した。UNRWAの学校で4年間教鞭をとった後、1965年から2000年までヨルダンの外交官となり、クウェート、バグダッド、ワシントン、ロンドンの大使館で勤務した。1979年にベルギー、オランダ、ルクセンブルク、欧州共同体の大使に任命され、1990年からは駐イタリア大使、ポルトガルとサンマリノの非駐在大使を務めた。1995年にはヨルダンのニューヨーク国連常駐代表兼キューバ非駐在大使に任命された。1992年から1993年にかけては、ヨルダン代表団の一員としてワシントン和平交渉に参加した。外交官引退後は、ヨルダン王立宗教間研究所所長(2004~2009)、ヨルダン地域人間の安全保障センター所長(2009~2011)を務めた。2013年から2020年までヨルダン上院議員を務めた。40年にわたり英語とアラビア語でコラムを執筆している。
パレスチナの悲劇を巡る個人的な旅
ハサン・アブ・ニマ
1940年、小さな少年だった私が、バティールで自分を取り巻く世界を認識し始めたときのことだ。
私が生まれたこの村は、古代の歴史だけでなく、シオニストによる征服と現在進行中のパレスチナをめぐる闘争の結果の証人でもあった。バティールでの経験を通じて、私はこの闘争の個人的・政治的次元についての理解を深めた。
エルサレムの南西約6マイルに位置するバティールには、少なくとも青銅器時代から人が定住していた形跡がある。村は西に面した山の斜面の上部にある。下部は整然とした段々畑になっており、村人たちはブドウ、イチジク、オリーブ、モモ、リンゴ、ナシ、アプリコット、そして小麦や大麦など、あらゆる種類の農産物を栽培していた。この村は特に、パレスチナ全土で珍重されるナスの特別な品種、バティンジャン・バティリで知られていた。
段々畑は、地面から湧き出る湧き水と、注意深く整備された水路によって支えられていた。この共有灌漑システムは現在、ユネスコによって世界遺産に認定されている。ユネスコは、これを「伝統的な土地利用の傑出した例」としており、「何世紀にもわたる文化と人間による環境との相互作用を代表するもの」としている。「この伝統的な水システムの完全性は、それに依存するバティールの家族によって保証されている」と国連機関は付け加えている1。
バティールと対岸の山々を隔てる谷間には、オスマン帝国時代の鉄道が今も走っている。当時、この鉄道はエルサレムとパレスチナの沿岸都市を結び、さらにエジプトのアルカンタラまで続いていた。エルサレムから最初の停車駅がバティールだった。この列車は、村の人々にパレスチナの他の地域との迅速なリンクを提供した。その後、列車は毎日2往復、バティールからエルサレムまで乗客と農産物を運んだ。また、週末にはバティール駅周辺の日陰の果樹園でピクニックを楽しむ人々も、この列車に乗ってやってきた。線路と平行して未舗装の道路が走っており、歩行者だけでなく車もあまり通らなかった。
駅のすぐそばには男子小学校があり、1948年の春に村を脱出することになったとき、私は最後の学年だった。学校は、高い松の木の一部で日陰になっており、春夏の風に心地よく揺れていた。校舎のそばには、生徒たちがミツバチやニワトリを飼うなど、基本的な農業技術を学ぶのに十分な土地があった。
当時のバティール村の1,000人ほどの村人の生活は、イスラム教徒ばかりで、質素で平和で安全だった。伝統、相互依存、協力によって秩序が保たれていた。世界中の農村と同じように、人々は互いに助け合いながら、作物の収穫を手伝い、家を建て、挫折に対処し、喜ばしい出来事を祝っていた。誰もが交代で隣人を助け、政府や村議会の存在や必要性はあまりなかった。
決してユートピアではなかった。苦労も多かったし、意見の相違や対立も普通にあった。しかし、一般的に人々は互いを尊重し、村の名士たちは友好的に問題を解決する権限を持っていた。
人々は電気も水道も近代的な設備もない、基本的な住居に住んでいた。彼らは家の前や村の細い小道の脇でたき火をして料理をしていた。中には、スウェーデン製のプリムスやラディウスの灯油ストーブを室内で使う余裕のある人もいた。
多くの家族が動物を飼い、同じ部屋の前の部分に避難させていた。ロバやラバ、まれに馬が人や荷物を運ぶのに使われた。ヤギやヒツジを飼い、乳を飲ませたり、祭日に屠殺したりする家もあった。
宗教的で敬虔ではあったが、人々は寛容だった。女性は男性と混じり合い、村ではベールを被ることはなかった。農耕社会では女性も男性と同じ重荷を背負い、時にはそれ以上の重荷を背負うこともあったため、男女の分離は現実的ではなかった。エルサレムの市場まで、農産物の入った大きな籠を頭に載せて、2時間かけて歩いて行くのは、典型的な女性たちだった。
パレスチナ全土で何十世代にもわたって続いてきたに違いないこの平穏な暮らしは、私たちの手の届かない世界の大国が私たちの祖国を他人の所有物と決めつけるまで途切れることはなかった。
バティールはやや孤立していたが、人々は何が起きているかを十分に認識しており、シオニストの脅威について話していた。彼らは、ヨーロッパからのユダヤ人入植者の流入、土地の売買、パレスチナをユダヤ人の国民的故郷にするというバルフォアの約束の実行を支援するというイギリスの公約を懸念していた。
ニュースソースはエルサレムから持ち込まれた日刊紙の1部か2部に限られていたが、バティールの人々は常に情報を得ていた。多くの人々は読み書きができなかったが、新聞が届くと、自分たちの将来がかかっている政治的な出来事について誰かが読むのを聞くために集まった。
もうひとつ、大きな情報源があった: 英国政府が設置した拡声器付きのラジオで、パレスチナ放送に常時チューニングされていた。車のようなバッテリー2個で動くそのラジオは、私の実家に置かれていた。1日に2回、人々はその放送を聞くために大きなベランダに集まった。
毎週、赤い郵便局の車がエルサレムから充電したばかりの電池を運んできて、消耗した電池を持ち去った。しかし、その車は駅までしか走れない。電池はロバで運ばれた。
人々は、いわゆるユダヤ民族の故郷は自分たちの生活に影響を与えないという保証に騙されることはなかった。彼らはそれを、結果的に正しく、実存的な脅威として理解していた。彼らは、1920年代に始まり、委任統治が終わるまで勃発し続けた、シオニストとイギリスに対する英雄的なパレスチナ人の抵抗について誇らしげに語った。
私が1942年に入学した学校でさえ、そのようなことをほとんど知らないと思われる生徒たちが、ユダヤ人のパレスチナ植民地化について不安と恐怖を口にしていた。1947年11月の国連分割決議をアラブ人が否決したときの反応を覚えている。子供たちでさえ、シオニストは自分たちに割り当てられたパレスチナの一部を足がかりとして受け入れるだけで、もっと多くの領土を占領できるようになるまでのことだと言っていた。
このような話は、間違いなく大人たちから聞いた話を反映しているのだが、政治に関わることはイギリス当局によって厳しく禁じられていたにもかかわらず、学童の間でははっきりと交わされていた。
パレスチナにおけるシオニストの計画は、1917年にオスマン帝国からパレスチナを奪取したイギリスの承認を得ていた。国際連盟は、表向きは自決のための委任統治をイギリスに与えた。
しかし、1922年の委任統治文書には、パレスチナの人々や彼らの権利については一度も触れられていない。シオニズムに傾倒するイギリスは、本来ならその望みをかなえるべき唯一の人々であるパレスチナ先住民に、自分たちの国の将来について何の発言権も与えなかったのである。
明らかに、シオニズムはアラブ人、特にパレスチナ人に強く拒絶された。危険な結末を警告するイギリス政府高官も反対した。シオニズムはまた、世界中の多くの国々で定住生活を営むユダヤ人にとって、「民族の故郷」構想は脅威であった。シオニズムが最終的にナチス・ドイツの支持を得たのは、まさにこの理由からであった。ナチス・ドイツはシオニズムを、ユダヤ人をヨーロッパから移送するための便利な手段とみなし、それに基づいて、ナチス政府は1933年にドイツ・シオニスト連盟と移送協定を結んだのである。
しかし、シオニズムを支持する反ユダヤ主義的な動機は、ドイツだけのものではなかった。アーサー・バルフォア卿が反ユダヤ主義者であったことは有名だ。ウィンストン・チャーチルも同様で、シオニズムをユダヤ人を大英帝国支持に勧誘するための有効な手段であり、共産主義と戦う手段だと考えていた3。
1905年にほとんどのユダヤ人のイギリスへの移住を禁止したイギリス政府は、ヨーロッパからパレスチナへのユダヤ人の大量移住を許可し、土地をめぐる暴力的な闘争が避けられないことを確実にした。イギリスはパレスチナの抵抗勢力を鉄拳で粉砕する一方で、シオニストの植民地主義者たちにあらゆる利点を与え、国家の中に国家を設立させ、いざというときにはパレスチナを征服できる軍隊を持たせた。
イギリスは両立しがたい状況を作り出したが、責任は平等に分かち合うことはできなかった。パレスチナ人は当初から、パレスチナのアラブ系イスラム教徒、キリスト教徒、パレスチナ系ユダヤ人を代表する議会を持つ、パレスチナのための国家政府を求めていた。
これに対してシオニストは、パレスチナ全土をユダヤ人だけのものにすることを要求した。2018年にクネセトで可決された国民国家法は、シオニズムの目標が歴史的パレスチナ全域におけるユダヤ人のみの主権であることを明確にしている。
1947年11月29日、国連総会はパレスチナをユダヤ人国家とアラブ人国家に分割し、エルサレムを国際体制下に置くという勧告を採択した。この計画では、当時人口の3分の1を占めていたユダヤ人入植者が国の半分以上を占めることになった。先住民であるパレスチナ人の大多数は、自分たちの国の少数派に追いやられ、多くの人々は、ユダヤ人の大多数が存在しないユダヤ人国家から追い出されることになる。
シオニストの指導者たちは、自分たちに与えられるものが少なすぎるとして、この案を受け入れがたいと考えたが、最終的には、拡大するための基盤として受け入れた。アラブ人がシオニストを拒否したのは正しい理由だ。なぜヨーロッパの植民地主義者に、自国の半分以上、ましてやその一部を放棄させられなければならないのか。
シオニストが強い支持を得たのとは対照的に、イギリスはパレスチナの抵抗勢力、特に1936年から39年にかけての大反乱を残酷に鎮圧した。武器の所持は厳しく禁止され、厳しく罰せられた。このような背景を考えれば、1947年11月の分割決議が可決されるやいなや、シオニストが民族浄化計画を迅速に開始できたのも不思議ではない。
1948年5月にイギリスが撤退するまでの数ヶ月の間に、周到に計画されたシオニストの猛攻撃はすでに何十万人ものパレスチナ人を難民に変えていた。イギリスはほとんど介入しなかった。1948年4月9日にデイル・ヤシンで起こったようなシオニストの攻撃は、恐怖を煽り、パレスチナ人の逃亡を促進するために計画されたものであった。
恐ろしい大虐殺の舞台となったデイル・ヤシンは、私たちからほんの数キロしか離れていなかった。恐怖におののいた生存者たちが、避難所を求めてバティールに到着したのを覚えている。しかし、私たちの村にはすでに、シオニスト民兵の手に落ちた他の村から民族浄化された多くの家族が住んでいた。
人々は不信感を抱いていたが、この問題は長くは続かないだろうという一般的な思いがあった。彼らは国連が介入し、秩序と正義を回復してくれることを期待していた。また、5月15日の正式な委任統治終了を待ち望んでいたアラブ軍が到着し、パレスチナ、あるいはパレスチナに残されたものをシオニストの猛攻撃から救出してくれるだろうと期待した。
当時、シオニストの攻撃は、特にエルサレムとその周辺で加速していた。私たちはラジオの速報や、村の男たちからの驚くべき話を耳にしたものだ。村の男たちは、自分たちの家を守るために、ありったけのお金をはたいて昔ながらの武器や弾薬を購入した。勇敢な男たちは、近隣の村への攻撃を撃退するために徒歩で駆けつけることもあった。
シリア、レバノン、ヨルダン、スーダンを含むアラブ諸国から、戦闘員と武器の小集団が到着した。彼らはできる限りのことをし、いくつかの戦闘で勝利を収め、当初は士気も高かった。あるグループがバティール駅の廃墟にキャンプを張り、村人たちの訓練を組織していたのを覚えている。
ユダヤ人テロ組織がイギリスのスポンサーに反旗を翻すと、彼らはしばしば列車の線路下に爆発物を仕掛け、深刻な被害と死傷者を出した。貨物列車は何度も待ち伏せされ、商品が略奪された。どの列車にもイギリス軍の警備員が乗っていたが、彼らはしばしば抵抗することなく降伏した。バティール近くの線路で重機関車が爆破され燃やされると、線路はすぐに封鎖され、鉄道全体が麻痺した。
1948年初頭までに状況は悪化し、バティール周辺のいくつかの村はシオニストの民兵に制圧された。それらの村の住民の多くも、すぐに故郷に帰れることを望んでバティールにやって来た。
しかし、春の終わり、イギリスが撤退を完了し、イスラエル建国が宣言されたとき、バティールはシオニストの支配下にあった西側の斜面から激しい機銃掃射にさらされた。銃弾の雨あられが家や財産を襲い、私たちは恐怖に陥った。十分な防御手段がなかったため、もはや安全な場所ではなかった。
そこで、持てるわずかな荷物を持って、全員が徒歩で東へ逃げた。村を守ろうと何人かの兵士が残ったが、バティールが略奪されるのを止めることはできず、ドアや窓の枠まで奪われてしまった。
歩いて1時間ほどのところにある、村の所有物だったアル・クサイルというブドウ畑で、他の多くの家族とともにキャンプしたことを覚えている。小さな泉があった。私たちは木の下で一夜を過ごし、すぐに家に帰れると信じていた。しかし、バティールは絶え間なく砲火を浴びていたため、私たちは枝でシェルターを作り、長期滞在に備えた。危険を冒してこっそり村に戻り、追加の荷物を持ってきた人もいた。私もいとこたちと一度だけ試みたが、ユダヤ人民兵は動くものなら何でも撃ってくるようだったので、怖かった。私は家にたどり着かずに引き返すことにした。
アル=クサイルでは、最低限の小麦粉だけで、たき火でパンを焼き、地元の野菜やレンズ豆を料理し、お茶を飲んで生き延びた。砂糖は貴重品だったが、パンに甘い紅茶が定番の食事だった。夏の果物が手に入るようになると、ブドウやイチジクで補った。
ベイトジャラの町はそう遠くないので、お金を持っている人はそこまで歩いて行って、追加の物資を手に入れることができた。私は未亡人となった母と妹だけだったが、結婚した姉たちの家族をはじめ、多くの親戚が大きな助けとなってくれた。私たちは20家族ほどだったが、人々はまるで私たちがひとつの家族であるかのように振る舞ってくれた。誰も他の家族が飢えたり苦しんだりすることを許さなかった。
私たちは1948年の夏までそのブドウ畑に残ったが、天候が寒くなり始めた9月の終わりには、それぞれの家族が次の行き先を決めなければならなかった。バティールは占領されてはいなかったが、谷の向こう側からの火の脅威にさらされやすいままだった。誰も安心して帰ることはできなかった。ベツレヘム地域やヨルダン渓谷に形成されつつあった難民キャンプに参加する家族もいた。ヨルダンまで行く家族もいた。
母と妹と私は、長姉の家族と合わせて11人で、ベツレヘムのテガート警察の建物内にある兄に割り当てられたアパートに避難した。
兄はパレスチナ警察の無線通信課で働いていた。委任統治が終わると、多くの同胞と同じようにヨルダン警察に入った。テガートの建物は、イギリスがパレスチナ各地に建設した同じ要塞のひとつで、当時はヨルダン軍が使用していた。
兄の階級は、以前は英国人将校の家族に割り当てられていたアパートの一つを使う権利があることを意味していた。兄の家族と一緒に、私たち20人ほどがその小さな2ベッドルームのアパートに押し込められた。私たちは床で眠り、手に入るものは何でも食べた。
妹の家族は最終的にベツレヘムに家を借りることができた。他に行くところがなかったので、私たちは兄の家に泊まった。日中、ベツレヘムのダウンタウンをぶらぶら歩いた。パレスチナ全土から避難してきた人々が露天商をしていた。フムスやファラフェルを売るレストランなど、他の場所で断念せざるを得なかった商売を再開した人もいた。他の人々は、見つけられる仕事は何でも探した。
テガートのビルには、ヨルダン兵のほかにエジプト兵とスーダン兵がいた。兄のアパートの1階には、馬が水を飲むための長方形のプールが真ん中にある大きな中庭を見下ろすベランダがあった。しかし、馬はいなかった。日中、私は他の将校の子供たちと遊び、監視塔に続く金属製の螺旋階段を上って楽しんだ。そこでは、退屈している監視員たちと一緒に過ごし、彼らは私たちに話をしてくれた。夜遅くまでベランダに座って、アラビア語の方言で交わされる会話を聞いたり、物資や兵士を乗せて行き交う車を眺めたりもした。
また、建物の外構で兵士たちがライフルやステンガンの射撃練習をしているのを眺めたりもした。私はある将校に、私に撃たせてくれないかと頼んだことがある。彼は承諾してくれて、私を陣地に招待してくれた。彼はステンガンの構え方を教えてくれた。ステンガンは軽いが、反動があるのでしっかりと構える必要があった。それからライフルを試したが、これは重すぎた。
年春、イスラエルと周辺4カ国との休戦協定によって戦闘は終結した: エジプト、ヨルダン、シリア、レバノンである。その時までに、イスラエルはエルサレム西部を含む歴史的パレスチナの78パーセントを占領していた。エジプト軍は撤退を余儀なくされ、北部で活動していたシリア軍とイラク軍も撤退した。
ガザは1967年までエジプトの支配下に置かれたが、1956年のスエズ戦争でイスラエルが占領した数ヶ月間は例外だった。ヨルダン軍は東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区を支配し続け、地元のパレスチナ人戦闘員の支援でなんとか守り抜いた。
その春、私はテガルトの警察庁舎で、要塞の裏手にある広々とした庭で、とても整然とした軍事式典を見た。エジプト軍駐屯地のヨルダン軍への引き渡しだった。両軍の兵士の列は上品な服装で、きちんと整理されていた。旗を交換するとき、何人かの兵士が泣いているのを見た。とても感動的な瞬間だった。その後、エジプト軍はトラックに乗って去っていった。
その直後、良い知らせが届いた。ヨルダン・イスラエル合同休戦委員会と国連休戦委員会がバティールで境界線を引いているというのだ。
バティールは戦時中、疎開していたにもかかわらず、一度も占領されたことがなかった。そのため、委員会に会った村の名士たちは、バティールを占領地域に含めるべきではないと主張した。しかし、イスラエルが使いたがっていた鉄道がバティールの土地の一部を通っていたため、イスラエルは線路から200メートルほど東に休戦ラインを引くよう主張した。
合意直後に設置された有刺鉄線フェンスによって、バティールは半分に分断された。2つのゲートによって、人々はどちら側にも渡ることができた。この特別な取り決めによって、線路が村のかなり奥に入ったにもかかわらず、バティールの人々は分断されることなく、線路の西側にある自分たちの土地を使用する権利が維持されることになった。
協定によれば、イスラエル兵はフェンスの西側、つまり村の約半分の家屋を含む地域をパトロールすることができる。鉄道駅のすぐそばにあった私の学校も、イスラエル軍の管理区域に入った。私たちの家は、フェンスから10メートルほど東にある。
このような取り決めがあって、私たちや他の村人たちは家に戻った。家々は修復され、生活が再開された。学校はヨルダン国旗を掲げて再開したが、イスラエルのパトロール隊は毎日通った。1950年、ヨルダン川西岸地区はヨルダンと統一され、イスラエルとなった地域から切り離されたとはいえ、私たちが自由に移動できる大きな国が誕生した。バティールにとっては比較的豊かな時代だった。
UNRWAは村とベツレヘムを結ぶアスファルトの道路を建設した。UNRWAはまた、村の歴史上初となる女学校を設立した。人々はおおむね生活を立て直し、多くの若者がベツレヘムの中学校で教育を受けることができた。しかし、彼らは依然として、パレスチナ人に行われた不公正は是正されなければならないと信じていた。
休戦共同委員会はよく学校の校庭で開かれた。モシェ・ダヤン将軍がエルサレムからジープ隊を率いてよく来ていた。雰囲気はおおむね穏やかだったが、イスラエルのパトロール隊が、フェンスの西側で土地を耕している村人を不法侵入とみなして逮捕したり、殺したりすることもあった。休戦委員会は拘束者の釈放を確保するが、殺された人々には何もできなかった。
学校が再開されたとき、私は7年生で唯一の生徒として卒業することができた。村にはボランティアの教師が一人しかいなかったので、私は下のクラスを教えるのを手伝った。その後、学校はヨルダン教育省の下でよりよく組織されるようになった。
ベツレヘムの高校も、オスマン・トルコ軍にいたこともある先見の明のある教育者、シュクリ・ハラミが設立した国内唯一の男女共学の私立学校、アル・ウンマ・カレッジで卒業した。
この学校は、宗教に関すること以外はアラビア語を使用し、月曜日から金曜日まで、週末は土曜日と日曜日に開校するという常識を覆すものだった。私は1954年の夏、当時のヨルダン軍の英国人トップであったジョン・バゴット・グラブ卿の手から卒業証書を受け取った。アル・ウンマからUNRWAの奨学金でベイルートのアメリカン大学に行き、バティール史上2人目の大学卒業生となった。
1959年の夏、卒業証書を持って帰国すると、私は歌と踊りで迎えられ、屋根には松明が飾られた。
1949年の休戦後、イスラエル軍は無防備な最前線の村々を夜襲し続け、家を爆破し、罪のない人々を殺し、住民を恐怖に陥れた。バティール近郊のフサン村やナハリン村もそのような攻撃を受けた。
1953年には、アリエル・シャロン率いるイスラエル軍が、ヨルダン川西岸北部のキビアで数十人を虐殺し、村を完全に破壊した。もちろん、シャロンは後に国防相として、1982年のイスラエルによるレバノン侵攻の際の犯罪、特にサブラとシャティーラでの虐殺で悪名を馳せることになる。このような空襲はすべて休戦委員会に報告されたが、委員会は何もできなかった。イスラエルはいかなる規則や義務も尊重しなかった。
1956年9月のフサン空襲は、夜が明けてから行われた。機動旅団による大規模な攻撃だった。イスラエル軍は最近建設されたばかりのヨルダン警察署を破壊し、約10人の警官を殺害した。彼らは道路に沿ってアル=カダー方向に進み、ヨルダン軍の駐屯地を攻撃して多くの死傷者を出した。警察署も駐屯地も、バティールとベツレヘムを結ぶ道路沿いにあった。
イスラエルは、毎年何百人もの犠牲者を出しているこのような攻撃は、武装した「侵入者」に対する「報復」だと主張した。このような恐怖にもかかわらず、ヨルダン支配下のヨルダン川西岸での生活は、イスラエルがパレスチナ全土の征服という目標を達成する1967年まで、一定の安定を保っていた。それが、私自身のバティールでの生活の終わりとなった。占領が始まったとき、私は海外にいたため、イスラエルは家族の再統合を拒否し、私は1997年に一度だけパレスチナに戻ったことがある。
バルフォア宣言、イギリスの委任統治、そして後の国連分割計画はすべて、この地域を支配しようとするヨーロッパ帝国の大きな陰謀の要素だった。しかし、帝国に支援されたシオニスト運動によるパレスチナの喪失は、この国を防衛する真剣なアラブ戦略があれば、避けられなかったかもしれない。
結局、パレスチナは戦場で失われ、アラブ諸国はイスラエルとのほぼすべての交戦で苦杯をなめた。歴史は、政治的宣言や政令よりも、決意を固めた民衆の意志が出来事を形成することを教えている。
イスラエルは常に、国連決議と国際法の最大の違反者である。しかし、重要なのは国連が何を言うかではなく、ユダヤ人、つまりシオニストが何をするかだ、というベン・グリオンの格言に従って行動してきた。イスラエルは、適切と判断すれば、あらゆる法律に背く。
アラブ人は逆らうまでもなく、非合法な帝国の決定に基づく侵略に立ち向かえるはずだった。しかし、彼らはかろうじてそうした。100年もの間、多くのアラブ人は度重なる敗北をバルフォアのせいにしてきた。しかし、アラブ諸国がパレスチナを防衛する正当な権利を効果的に行使していれば、バルフォア宣言は記憶にも残らなかっただろう。
1945年に設立されたアラブ連盟は、常にパレスチナをその大義とし、パレスチナ防衛をアラブの連帯責任と公式に考えていた。委任統治時代のパレスチナの闘いは、独立のためのより大きな闘いの一部であるはずだった。
しかし、残念なことに、アラブの国家、軍隊、政治的重みといった資産であるはずのものが、パレスチナにとっては負債となった。1947年11月から1948年5月にイギリスが撤退するまで、シオニスト勢力はパレスチナ人を民族浄化する自由裁量権を握っていた。
アラブ軍は英国が去った後、遅ればせながらパレスチナ防衛に加わったが、その任務は惨敗した。彼らは共同戦略も指揮も欠いており、それぞれが協調することなく行動していた。「統一」を気取ったものの、アラブの関係は競争によって支配され、それが軍事的パフォーマンスに反映された。
東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区をなんとか救ったヨルダン軍を除けば、シリア軍、イラク軍、エジプト軍はまったく振るわなかった。ガザ地区は救われたが、狭い領土に周辺の村々からの難民が押し寄せていたからであり、むしろエジプト軍の守りが堅かったからだろう。
他のアラブ軍は、単なる義務の遂行として参戦したようだ。アラブ連盟はパレスチナを防衛するための協調的な戦争計画を打ち出すことができず、各加盟国が独自に行動することになった。それは、ただ義務として参戦したのか、攻撃を受けている土地を守る能力がなかったのか、あるいは真の動機がなかったからなのか。
委任統治時代に反乱を起こし、後に戦争に参戦したパレスチナ人は、自分たちの家やコミュニティを守るために、あらゆる決意を示した。しかし、原始的な武器しか持たず、訓練も受けず、組織化された軍隊を持たない彼らの感覚は、アラブ軍が到着するまで持ちこたえるしかないというものだった。
アラブ連盟とその加盟国が、効果的な武器、資金、訓練、ボランティアを提供することで支援していれば、パレスチナ人はもっとうまくやれたはずだ。そうすれば、アラブ軍を派遣するよりもわずかな費用で済み、はるかに効果的だっただろう。しかし、即興、責任の分担、戦略の欠如が、災難を避けることができなかった。
年から1967年まで、アラブ諸国の言説はイスラエルの存在は違法であるという考えに基づいていた。彼らは、休戦は一時的なもので、再び戦ってパレスチナ全土を解放する準備が整うまでのことだと主張した。
ナセル政権下のエジプトは、パレスチナを失ったアラブの「反動」政権の責任を告発し、その打倒を求める集中的なプロパガンダ・キャンペーンを展開した。第一次パレスチナ戦争の直後、シリア、エジプト、イラクの政府は軍隊によって打倒され、彼らは他のアラブ諸国にも既存の政権を放り出すよう呼びかけた。
パレスチナはそのような行動の口実となった。野心的な軍事冒険家たちは、パレスチナ解放への道はアラブの首都の解放から始まるという主張を繰り返した。しかし、ほとんどの場合、例えばエジプトでは、民衆の必要性に投資したにもかかわらず、軍事支配は結局のところ、それ以前や他の地域に存在したものに劣らない抑圧的で腐敗したものであることが証明された。
少なくとも、これらの革命は、支配者が権力の座にとどまることだけに集中したため、長期的な発展と人々の繁栄の基盤を築くことができなかった。新興革命勢力のアジェンダには、国家的な問題もアラブ共通の問題も重要ではなかった。
宣言はさておき、アラブ諸国を含む世界は、1949年の休戦ラインを恒久的な国境線とみなすようになった。しかし、イスラエルの領土的野心はほとんど満たされていなかった。アラブ諸国の美辞麗句と行動が一致しない一方で、イスラエルは次のラウンドと、さらなる土地を奪うチャンスに備えて静かに準備を進めていた5。
そのチャンスは、1967年4月にイスラエルがシリアの戦闘機6機をドッグファイトで撃墜した後、エジプト指導部が脅しをエスカレートさせるように誘い込まれたときに訪れた。ナセルは、シリアを助けに来なかったことを痛烈に批判した。これを受けてナセルは5月下旬、シナイ半島に軍を動員した。そして、さらに罠にはまり、国連のUNEF監視団に退去を命じた。
これは歴史的な失策だった。エジプトの権利の範囲内ではあったが、ナセルはこの要求をすべきではなかった。エジプトはティラン海峡を閉鎖し、イスラエルの紅海の港エイラトを事実上包囲した。軍隊の半分がイエメンで泥沼にはまり込んでいるエジプトは、戦争を望んでいたわけでも、戦争の準備ができていたわけでもない。エジプトの指導者たちは、犠牲を払うことなくプロパガンダで勝利することを望んでいただけであり、イスラエルはそれを知っていた。
1967年6月5日、イスラエルは大規模な奇襲攻撃を仕掛け、地上のエジプト空軍の大半を壊滅させた。イスラエル軍は瞬く間にシナイ半島に押し寄せ、スエズ運河東岸までのエジプト領土を占領した。イスラエルはその後、シリアとヨルダンとの開戦に移った。エジプト戦線が瞬く間に崩壊したことで、シリアとヨルダンの政治的・軍事的士気は低下し、戦争は数日で終結した。
イスラエルはヨルダン川西岸とゴラン高原を占領し、シナイ半島も占領した。ナセルは「後退」と呼ばれる事態の責任を取り、辞任した。しかし、辞任に抗議するアラブ諸国の首都での大規模なデモを受け、ナセルは方針を転換して残留を決めた。
イスラエルは直ちに、新たに征服した領土の植民地化を開始し、東エルサレムも併合した。イスラエルは、アラブ人が自国を承認し和平を結ぶまで、新たに占領した土地を保持するだけだという主張を完全に裏切った。
1967年11月、国連安全保障理事会は、その後の外交努力の基準となる決議242号を採択した。この決議では、「最近の紛争で占領された地域からのイスラエル軍の撤退」を求めており、「territions」の前に 「the」が省略されていることで悪名高い。つまり、イスラエルはこの文章を、どのような撤退でも決議の条件を満たせば十分だと解釈することができたのだ。実際、1979年のエジプトとの条約締結後、イスラエルがシナイ半島から撤退した際に主張したのは、まさにこのことだった。
しかし、曖昧さは決議の主な問題ではなかった。たとえイスラエルが1967年に占領した土地の隅から隅まで撤退することを要求したとしても、決議242号は歴史的パレスチナの78パーセントをイスラエルに事実上承認した。
242決議の受諾は、イスラエルに対するアラブの大規模な譲歩であり、敗戦後の他の選択肢の欠如から生まれたものであったことは間違いない。しかし、アラブ諸国の外交的パフォーマンスは、救えるものを救い出すどころか、戦場での損失をさらに政治的損失で増幅させた。
242における「妥協」は、1967年6月4日のイスラエルをそのまま承認する見返りに、アラブ諸国が1967年に失った土地を取り戻すというものだった。しかし、このような取引は双方が応じなければ成功しない。ところが不思議なことに、アラブ諸国とパレスチナ解放機構は、イスラエルに義務を果たすよう要求することなく、要求されたことをすべて果たすよう主張してきた。そのため、イスラエルは土地と承認を得るに至った。
実際、1993年のオスロ合意では、PLOは「イスラエル国家が平和と安全のうちに存在する権利」を明確に認めた。これとは対照的に、イスラエルはパレスチナの権利をひとつも認めていない。むしろ、ラビン首相は「PLOをパレスチナ人民の代表と認める」ことに同意しただけだった6: イスラエルは、パレスチナの権利を放棄し、イスラエルの安全保障の下請けになろうとしていたPLOが、パレスチナ人の名においてそうしていると思われたかったのだ。
現在でもアラブ諸国やその他の政府は、東エルサレムを首都とする「1967年の国境線に基づく」パレスチナ国家について語っている。この曖昧な表現は、パレスチナ人とアラブ諸国がすでに受け入れている土地交換の方式で、イスラエルが占領地に不法に建設した入植地を併合できるようにするためのものだ。
イスラエルが1967年に占領した土地を植民地化し始めたとき、アラブ諸国は口先だけの抗議を行ったが、誰も真剣に受け止めなかった。このような中途半端な非難は、抑止力になるどころか、イスラエルが入植地建設計画を続行するための励ましとなった。
PLOや後のパレスチナ自治政府を含むアラブ諸国が、戦争で失敗したように、外交でも失敗した理由を理解するのは難しくない。自国の権利を守るための決断と行動をとるためには、国家は独立し、自由でなければならない。PLOやパレスチナ自治政府を含め、ほとんどのアラブ諸国はそうではなかった。公平を期すため、外部からの影響や圧力なしに完全に自由に政策を遂行できる国家は多くない。
それでも、ほとんどのアラブ政権は、ある種の真の民主的プロセスから生まれる正統性を欠いている。そのため、国内外を問わず、いかなる危険に対しても外国勢力からの支援と保護に頼っている。この方程式はよく知られている: アメリカは、善悪にかかわらずイスラエルを支持している。どんな政権であれ、アメリカの寵愛を得たり、アメリカの怒りをかわしたりするためには、イスラエルの承認と同意を得、それを維持しなければならない。
ワシントンへの道はテルアビブを通る。例えば、最近イスラエルとの関係正常化を急いだアラブ諸国は、ドナルド・トランプ大統領を満足させるためにそうした。これらの政権は、トランプ大統領がパレスチナやアラブの権利を、トランプ大統領やその盟友ベンヤミン・ネタニヤフ首相、そして自分たちのための幻の政治的利益と交換するのを喜んで助けたのだ。しかし、これらの指導者たちが現場を去った後も、イスラエルはこれらの正常化取引の成果を享受し続けている。
戦争で負けた者は、得られるもので何とかしなければならないと主張することはいつでもできる。しかし、最も不利な立場に置かれた人であっても、イスラエルに収監されたパレスチナ人が常に行ってきたように、政治犯が捕虜に対してハンガーストライキを行うことを考えれば、意思さえあれば自分の権利を守る方法を見つけることができる。
アメリカやヨーロッパ諸国によって武装されたイスラエルが、より強い当事者であることは間違いない。しかし、それだけでは1967年以来増え続けているパレスチナ人やアラブ人の損失を説明するには不十分だ。その責任は、PLO、PA、アラブ連盟とその加盟国にもある。彼らは、このような主要な方法で、自分たちの権利と利益を執拗に損なったのだ:
パレスチナ人とアラブ人は、国際法で義務づけられているように、イスラエルがまず入植地や占領地の違法な変更をやめることを交渉の条件としなかった。その結果、長引く不妊剤「交渉」は、イスラエルがさらに不可逆的な事実を生み出すための時間へと変質してしまった。
シナイやガザで起こったように、占領地からすべてのイスラエル入植地を撤去することを主張するのではなく、アラブ人はイスラエルがヨルダン川西岸にある入植地のほとんどを併合する「土地交換」に合意した。スワップとされる土地はどの地域にも限定されていなかったため、イスラエルは後に「和平」協定で窃盗が正当化されることを予期し、建設を加速させることになった。
アラブ諸国はイスラエルに倣い、国際法に則ったパレスチナ人とアラブ人の権利回復ではなく、「和平」という空虚なスローガンを目標として採用した。つまり、イスラエルとアメリカの条件による「和平」の拒否は、アラブ人を侵略者に、シオニストの植民地支配者を被害者に変えてしまったのだ。しかし、正義、公平、簒奪された権利の回復なくして「平和」などありえない。
パレスチナ問題は汎アラブ的な問題であり、その防衛は、どのアラブ諸国も単独では行動しないという考えに基づく集団的責任であるはずだった。しかし、1967年以降もアラブ諸国は一致団結して行動することができなかった。1991年、アラブ諸国は米国主催のマドリード会議に出席し、その後ワシントンでの交渉にも別々の代表団として参加した。ほとんど形式的で非効果的ではあったが、協調はあったが、一致団結したアプローチはなかった。イスラエルは、1949年の休戦協定以来、常にアラブ諸国と個別に対処することを主張し、それが自国の手を強くすることを正しく理解していたからだ。
さらに悪いことに、PLOはハイダル・アブデル・シャフィ博士が率いるワシントン代表団を、オスロでイスラエルと秘密裏に交渉することで弱体化させた。1993年にオスロ・プロセスが明らかになると、ワシントンのパレスチナ代表団は冗長になった。
イスラエルはどの段階でも国連の関与に反対してきた。国際法と無数の決議が、アラブとパレスチナの権利の簒奪を違法としているのだから、これは理解できる。しかし理解できないのは、アラブ諸国が、国連、アメリカ、EU、ロシアの高官で構成されるいわゆるカルテットというアドホック委員会との取引に合意するなど、国連が傍若無人になることをどのように容認したかということだ。190カ国以上が加盟する国連が、どうして米国が支配する委員会の単なる一員に成り下がり、そのためのイチジクの葉に成り下がることができたのだろうか。アラブ諸国とパレスチナ人はカルテットとの取引を拒否すべきだった。
シオニストの指導者たちは、イスラエルが建国されれば、民族浄化されたパレスチナの大多数がどこにでも移住し、溶けてなくなることを望んでいた。残された人々は、徐々に、そして静かに対処することができる。シオニストは常に、一度確立された地上の事実は覆すことはできないと信じてきた。
イスラエルはその初期において、核兵器を含む強大な軍事力を構築することで、敵対的な隣国からの脅威に対処してきた。米国への依存に加え、イスラエルは近隣諸国以外にも同盟関係を求めた。トルコ、イラン、アフリカ諸国(もちろん、南アフリカのアパルトヘイト政権も含む)である。
しかし、イスラエルの期待は裏切られ、どれも十分ではなかった。今日、歴史的パレスチナ内のパレスチナ人の数は、ユダヤ人の数をほぼ確実に上回っている。さらに何百万人ものパレスチナ人が、祖国からほんの数マイル離れたヨルダン、レバノン、シリアに住んでおり、さらに多くのパレスチナ人が地域や世界に散らばっている。
パレスチナにいる人々は、二度とパレスチナから離れることはないだろう。2021年5月、イスラエルがガザを猛烈に砲撃し、エルサレムのパレスチナ人を攻撃するなか、パレスチナ人は、おそらく1948年以来初めて、全土で一斉に立ち上がった。ガザからエルサレム、ガリラヤまでの抗議と抵抗は、シオニストによる数十年にわたる植民地的な分断と支配の努力が、パレスチナ人の集団的な民族意識を強化しただけであることを証明した。
イスラエルから見れば、この「問題」に軍事的な「解決策」はない。たとえイスラエルが暴力と武力によってこの住民をあと数年抑圧できたとしても、パレスチナ人は自国を占領され、アパルトヘイトのもとで暮らすことに永久に同意しないだろう。
今のところ、イスラエルは米国とEU、そして少数のアラブ政権の支持を維持している。しかし、かつてのイランやトルコとの同盟関係は崩れ、アメリカでさえ、イスラエルに対する長期的な政治的支持を弱めつつある劇的な政治的・人口学的変化が起きている。イスラエルがまさにアパルトヘイト政権であるというコンセンサスが世界中で高まるにつれて、イスラエルに残された国際的な政治的支持もまた低下していくだろう。
イスラエルがほとんどのアラブ諸国(そしてもちろん、オスロ合意を通じてPLOも)を無力化することに成功したのは、これらの政権が国民を代表しない、あるいは代表しなくなったからだ。イスラエルと同様、これらの政権もアメリカの保護と支援に依存している。イスラエルを含め、いずれの政権にとっても、長期的に実行可能な方式ではない。特に、アメリカ自身がイラクとアフガニスタンでの失敗をきっかけに後退しているのだから。
イスラエルにとっても、軍事的勝利が地域政治を左右する時代は終わった。かつてイスラエルは、1948年から1982年のレバノン侵攻まで、アラブとの戦争にすべて勝利していたため、多くの人にとって無敵に見えた。しかしレバノンは、イスラエルの軍事的優位が逆効果となる転機となった。初期の軍事的「勝利」(ベイルート包囲さえも)は長期的な政治的利益に結びつかず、より強力で有能な現地の抵抗勢力に拍車をかけただけだった。
レバノンでのイスラエルの相次ぐ敗北と、孤立したガザでの抵抗勢力を鎮圧することさえできなかったことから、イスラエルの無敵の戦士という神話は崩れ去った。レバノンやガザで戦闘員と対峙することを恐れているのは、今やイスラエルの兵士たちなのだ。イスラエルの核兵器は、ガザやレバノン南部の抵抗勢力を打ち負かすためにも使えない。イスラエルの戦略家たちは、確かにこのことをすべて知っている。イスラエルにとって、可能な限り終末を遅らせる以外に実行可能な戦略はない。
ここ数年、ヨーロッパの大使や高官と何度も会う中で、イスラエルは現状を永遠に維持することに満足しているという話をよく耳にした。彼らは、イスラエルは大きな脅威に直面しておらず、パレスチナ自治政府やアラブ諸国との関係は安定している、あるいは発展していると言った。イスラエルが享受していると思っている「安定」は幻想だと私が言っても、彼らは聞きたがらなかった。このような恐ろしくエスカレートする不正の上に、持続可能な平和や安定を築くことはできない。
イスラエルの指導者たちはいつも、「パレスチナ人は和平の機会を逃していない」と主張していた。しかし、不正なゲームを強化するためにアラブ人とパレスチナ人から与えられた機会をことごとく逃してきたのはイスラエルである。例えば、イスラエルが2002年のアラブ和平構想に同意していれば、小さなパレスチナ国家を除いて、事実上すべての領土征服を合法化し、50以上のイスラム諸国との関係を正常化することができただろう。しかし、私たちはイスラエルの頑固さに感謝すべきかもしれない。なぜなら、過去50年間のどの時期であっても、イスラエルが合意したであろう「和平」協定は公正なものではなかったからだ。
パレスチナ人は何十年にもわたる不公正に耐え、シオニストの支配からの解放をあきらめなかった。彼らは忍耐と不屈の精神を示してきた。しかし、イスラエルは現在の袋小路からの脱出を必要としている。確かに、アラブ人とパレスチナ人による致命的な過ちは、イスラエルにとって大きな利益となり、イスラエルが国際的な正当性を確保するのに役立った。
しかしイスラエルは、アラブやパレスチナの指導者たちの機能不全に依存するあまり、この状況を当然視してきた。パレスチナ解放機構でさえ、自ら進んで反植民地解放運動からイスラエルのために働く警察組織へと変貌を遂げたのだ。イスラエルがパレスチナ人への抑圧を強めているにもかかわらず、一部のアラブ政権は正常化を熱狂的に急いでいる。
イスラエルは、最も危険の少ない政党を無力化することには成功したかもしれないが、抵抗勢力を過小評価していた。正式なアラブ軍はすべて撃破できたが、ゲリラ抵抗軍は撃破できなかった。9.11以降の軍事的冒険が屈辱に終わった米国と同じ麻痺を経験している。
イスラエル軍もアメリカ軍も、破壊する能力は非常に高いが、それが成功や安全の保証にはならず、断固とした抵抗の輪を広げるだけであることは、度重なる経験が示している。イスラエルはまた、国連やいわゆる国際社会からの無条件の支援と免責に頼ってきた。遅きに失したとはいえ、国際刑事裁判所がパレスチナの事例を取り上げ、世論(特にアメリカとヨーロッパ)がイスラエルのアパルトヘイト体制に鋭く反旗を翻すにつれ、その免罪も侵食され始めている。
私は40年にわたる外交官としてのキャリアを通じて、母国ヨルダンの代表として米国、欧州、国連に駐在し、1990年代初頭のワシントン和平交渉に参加し、ほとんど毎日のようにパレスチナ問題を扱ってきた。しかし私は、イスラエルがパレスチナ人との紛争を公正に解決しようと本気で考えているとは信じていなかった。だからこそイスラエルは、パレスチナ人やアラブ人から繰り返し提示された寛大な申し出をすべて拒否したのだ。
イスラエルが進んで変わる兆しは見えない。しかし、イスラエルを取り巻く世界と地域は変わりつつある。パレスチナ人は再び、歴史的パレスチナの多数派となり、決して離脱したり服従を受け入れたりしないだろう。南アフリカの白人がそうであったように、イスラエルのユダヤ人は、力ずくで意思を押し通そうとする孤立した少数派であり続けるか、それとも別の道を模索するかの選択を迫られている。しかし、もし彼らが変化を選択しなければ、結局は抵抗と国際的な圧力によって、変化を余儀なくされるだろう。
私は、私が子供の頃に目撃したパレスチナの暴力的な分割は終わりを告げ、人々が望むところに自由に住み、移動できるようになり、この国は再び完全なものになると確信している。パレスチナにアパルトヘイト政権が存在する余地はない。しかし、そこに住むすべての人々が、国籍や宗教に関係なく、平等、正義、平和のうちに暮らせるだけのスペースはある。
それが、パレスチナが耐え抜いてきた100年にわたる恐ろしい旅の最終目的地に違いない。唯一の問題は、そこにたどり着くまでに、あと何人の尊い命が無駄にされるかということだ。
- 1 「パレスチナ Olives and Vines-Cultural Landscape of Southern Jerusalem, Battir”, UNESCO (whc.unesco.org/en/list/1492/)
- 2 ジョセフ・マサド「パレスチナ人の降伏権を認める」『ミドルイースト・アイ』2021年7月30日号。
- 3 参照: ジョセフ・マサド「バルフォア宣言の多くの疑問」『エレクトロニック・インティファーダ』2017年11月8日。
- 4 参照:Benny Morris, Israel’s Border Wars, 1949-1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the Countdown to the Suez War (Oxford University Press, 1993)を参照のこと。
- 5 イラン・パッペ「イスラエルの占領は成就した計画だった」『エレクトロニック・インティファーダ』2017年6月6日号参照。Serge Schemann, 「General’s words cast a new light on the Golan,」 The New York Times, May 11, 1997.
- 6 参照: 「Israel-PLO Recognition-Exchange of Letters between PM Rabin and Chairman Arafat-Sept 9, 1993,” Israel Ministry of Foreign Affairs, buff.ly/3lByQ2X (last accessed October 12, 2021).
JOHNNY MANSOUR ハイファ出身の歴史学者。歴史学と政治学の講師を務める。以下のような研究や研究論文を発表している: A Look from the Inside「、”Distance Between Two States」、「Arab Streets of Haifa」、「Haifa, the Word that Has Become a City」、「100th Anniversary of the Balfour Declaration」、「Aqila Agha Al-Hassi」、”Religiosity in Curricula and Teaching Books in Israeli Schools ”などがある。また、アラブや外国の雑誌に多くの紹介記事を掲載し、アラブや非アラブの新聞やウェブサイトにもオピニオン記事を掲載している。世界各地で開催される歴史、政治、教育に関する会議に参加し、現在も活発に活動している。パレスチナの内外のさまざまな枠組みで政治・社会活動家として活動している。
敵を研究する
ケーススタディとしてのMADAR7
ジョニー・マンスール
現在の植民地的イスラエル・プロジェクトに対峙する状況下でのパレスチナ人の知識の生産は、両者の力関係に基づいている。パレスチナ人がイスラエルについて蓄積する知識は、実際に抵抗の道具として使われることがある。
1993年のオスロ合意の調印、それに続くラマラでのパレスチナ自治政府の成立、そして多くの亡命パレスチナ人の祖国への帰還の結果、イスラエルに関するパレスチナ人の研究と研究は、方向性を大きく転換した。この転換は、行政、経済、社会、文化的な統治機構や、パレスチナあるいはイスラエルの問題に焦点を当てたさまざまな研究センターが設立され始めた時期と重なる。ヨルダン川西岸地区とガザ地区の多くの都市に、政治的・戦略的研究センターがいくつか設立されたが、なかでも2000年に設立されたラマッラーのパレスチナ・イスラエル研究フォーラム(MADAR)は、その代表的なものである。
オスロ後の時代は、パレスチナの研究センターが1948年のパレスチナ人の能力と経験に絶えず依存していた。彼らのヘブライ語に対する熟練度と、さらに重要なのは、内外のレベルや生活のさまざまな分野におけるイスラエル社会と政治に関する直接的な知識が、特に役立っている。イスラエル社会の中で生活する1948年パレスチナ人は、内部の出来事を文脈的に分析することができる。つまり、紛争の本質は、その内部からしか理解できないのである。したがって、1948年パレスチナ人の参加と貢献は、パレスチナの研究センターにとって大きな価値がある。
残念ながら現在に至るまで、これらの研究センターはイスラエルだけを研究対象としており、アラブであれイスラムであれ、地域内であれ地域外であれ、他の国々を研究対象としていない。一方、イスラエルの研究センターはパレスチナ人、アラブ人、イスラム教徒、その他の民族を研究対象としている。
MADARでフリーランスとして働きながら、パレスチナの研究センターがデリケートな政治問題を扱うときには慎重であることを知った。この慎重さは、欧米や一部の極東諸国からの寄付者の意図を尊重することに由来する。NGOの政治的意図はまだほとんど公表されていないが、調査、セミナー、講演、報告書など、プロジェクトの成果を見直すことで、推し量ることができる。NGOがこれらのセンターに資金を提供することで、共同であれ個別であれ、ドナーの目的に関連する研究を指導することができる。したがって、これらのセンターの研究者は、独立した意思決定を行うために必要な自由を享受していない。現在の政治的・経済的状況を考えると、パレスチナ人の蓄積された知識は、時として援助者を満足させる方向に向かうこともあれば、自己批判と説明責任に没頭することもある8。一般的に、蓄積された知識は、パレスチナ人の能力と、推測ではなく戦略的ビジョンによって状況を分析し未来を予測するために必要な能力を開発するための重要な要素である。
MADARとは何か?
MADARはウェブサイト上で、自らを「パレスチナのラマッラーを拠点とする、イスラエル問題を専門とする独立研究センター」と定義している。MADARは2000年にパレスチナの知識人・学者グループによって設立された。MADARの目標は以下の通り:
MADARは、イスラエル問題の研究に特化した研究センターに対するパレスチナ人とアラブ人の緊急のニーズに応えるために設立された。MADARの主な目標は、イスラエルの情勢について確かで批判的な研究と分析を行うことである。前衛的な貢献をし、パレスチナやアラブの意思決定者や市民に、イスラエルのさまざまな側面に関する包括的で科学的に健全な知識を提供することを目指している9。
これらの目標やビジョンは、MADARの出版物(紙媒体およびデジタル媒体)に反映されている。これらの目標やビジョンは、MADARの出版物(紙媒体およびデジタル)に反映されている。また、調査や議論のために提示されたトピックに関する選択について、理解を深めることもできる。MADARは『The Israeli Scene』というアラビア語の新聞を発行しており、ラマラで発行されているパレスチナ語の新聞『Al-Ayyam』とともに隔週で配布している。研究面では、MADARはこれまでに、さまざまな政策/政治問題に関するアラビア語の研究出版物を24点、経済に関する研究を2点、軍事/安全保障問題に関する研究を1点発表している。また、社会/社会学的問題については、文学に関する研究論文3本、演劇に関する研究論文2本に加え、12本の研究論文を発表している。MADARは、イスラエルの違法入植地に関する研究も6本発表している。ヘブライ語による内容では、MADARは現在までに44の翻訳を出版している。
上記の数字が明らかに示すように、イスラエル社会における政治的、歴史的、社会的分野に焦点を当てた、オリジナルのヘブライ語コンテンツのアラビア語への翻訳は、MADARが作成した研究出版物のほぼ2倍である。MADARの管理部門は、紛争やイスラエル社会に関するイスラエルの研究をパレスチナ人に知ってもらうために、これらの翻訳が必要だと考えている。当然のことながら、イスラエル社会と国家に対するパレスチナ人の理解と相互作用に基づき、イスラエルに関するパレスチナ人研究を増やすことが求められている。
MADARはまた、『Israeli Affairs』というタイトルのアラビア語季刊誌も発行しており、これまでに81号が発行されている。この季刊誌は、1948年のパレスチナやその他の地域からのパレスチナ人参加者や、パレスチナ人との対話の一環として、ラマラで発行されるパレスチナ語誌で自分たちの考えやヴィジョンを発表することに関心を持つイスラエル人たちによって、より広範に発行されている。
MADARは2005年から年次報告書を発行している。これらはイスラエルに関する政治、軍事、安全保障、経済、社会、文化に関する主要な調査であり、イスラエル国内のパレスチナ人に関する詳細な報告も含まれている。この報告書は、イスラエルで起きている出来事に対するパレスチナ人のビジョンを1年かけてまとめたものとされている。参加者のほとんどは、イスラエルでの生活に慣れ親しんだ1948年のパレスチナ人である。
2000年代初頭から10年間、MADARでフリーランスとして働いた経験を振り返ると、一般的にパレスチナ人、特に学者や政治家は、パレスチナとイスラエルの問題に明確な関心を持っている。しかし、実際の調査は、2つの理由から異常な政治的・行政的状況下で行われている。第一は、イスラエル軍の存在と、自治権を持つ半自治領のパレスチナ地域に入り込むその能力である。もうひとつは、自治体や日常的なパレスチナ問題を監督するパレスチナ自治政府の政治的・行政的権限が限られていることである。さらにイスラエル軍は、ガザ地区とヨルダン川西岸地区で何百万人ものパレスチナ人を閉じ込め、アパルトヘイトの壁、入植者専用道路、私有地の没収、ヨルダン川西岸地区のエリアCを含むパレスチナ人の私有地での入植者住宅建設などの障壁を利用し、アパルトヘイト体制を確立してきた。
矛盾する複雑な現実のもとで活動するMADARは、それゆえ、イスラエルに直接関係するものもあれば、パレスチナ問題そのものに焦点を当てたものもあり、多方面にわたる研究を行う意欲に駆られている。
MADARであれ他のセンターであれ、研究センターは、シオニストとイスラエルの物語における誤った表現に立ち向かうという立場からだけでなく、独立したパレスチナの物語を形成することで、パレスチナの物語を確立しようとしている。これによって、パレスチナの人々の存在とその物語を否定し、代わりに自分たちの物語を押し付けようとするシオニスト・イスラエルの物語とは対照的に、現実的で前向きなパレスチナの物語の定式化に向けて、実際の対立と抵抗が可能になるのである。
私の物語
私がパレスチナの物語に常に関心を抱いてきたのは、私が歴史家であり、パレスチナの大義に利害関係があるからだけでなく、さまざまな形でナクバの影響を直接受けた家庭の出身だからである。私の父は、1920年にジシュ村(サファド地区)から生計を立てるためにハイファに移住した両親のもと、1928年にハイファで生まれた。
ハイファで父は、サレジオ神父学校(イタリア系の修道会)で学びながら、激しく活動的な生活を送った。この学校は第二次世界大戦中に閉鎖され、その結果、父はイギリス軍の収容所で働くことになった。そこで彼はパレスチナ全土から集まったアラブ人やユダヤ人の労働者に出会った。彼はユダヤ人労働者の助けを借りてヘブライ語を学び、その代わりにアラビア語を教えた。第二次世界大戦が終わる頃には、父は両親と兄弟を養うのに十分なお金を集め、バハイ寺院の近くに一家のための家を買うことができた。しかし、ナクバ戦争中のハイファをめぐる過酷で苦しい戦いのため、一家はその家を長く楽しむことはできなかった。作戦が終わった直後、入植者の一家が彼らの家を占拠した。
父と兄たちはレバノンに逃げた。その後、何とかジシュの実家に戻ったが、村の生活に再適応することはできなかった。1948年以降も何度かハイファに戻ろうとしたが、イスラエル当局は1950年代初めまで許可を与えなかった。許可が下りると、父はすぐに実家に向かったが、そこにはすでにユダヤ人家族が住んでいた。家を占拠していた入植者は父を追い出し、父は後に、イスラエルのクネセトが発布した1950年の不在者財産法という不当な法律によって、家と財産に対する権利を奪われたことを知った。
私の母は1934年生まれで、アル・マンスラというパレスチナ人の離散した村の出身だ。この村はレバノンとパレスチナの国境にある。1948年10月末から11月初めにかけて、一家は家と村を追われ、戻る機会も与えられなかった。一家の半分はレバノン南部のルメイシュ村とアイン・エベル村に向かった。もう半分はファスータ村に逃げた。その時、国境が閉鎖されたので、祖父と弟は国境を越えて他の兄弟に会うことができなかった。祖父と弟は、ディアスポラに住む家族を再会させ、行方不明の家族を取り戻すという夢を果たすことなく亡くなった。追放と暴力のトラウマは、母を長い間苦しめた。ナクバ当時わずか14歳だった母は、友人や親戚の家族から引き離され、二度と会うことはなかった。母が両親や兄弟たちとファスータ村の小さな部屋で暮らしたのは、父が一家が住めるように大きな家を用意してくれるまでの長い間だった。
それから数年後、ハイファからラマッラへ頻繁に旅するようになった私は、両親やその家族から何年もかけて聞いたナクバの話をよく思い出していた。
実際、私は月に1,2度、ハイファからMADARの本部があるラマッラへ通っていた。MADARの設立に尽力し、その雑誌を編集していた作家の故サルマン・ナトゥールも一緒だった。旅の間、私たちは、ヨルダン川西岸に住む人々がイスラエル人を理解し、イスラエル人と交流できるように、イスラエルの生活内部の力学に触れさせることの重要性について会話を交わした。しかし、イスラエルの支配下にあるヨルダン川西岸地区に入り、入植地が私有地を含むパレスチナ人の土地を占拠しているのを目の当たりにすると、こうした問題についての私たちの会話はしばしば途切れた。特に検問所での人間の苦しみや、イスラエル軍によるヨルダン川西岸のパレスチナ人に対する残忍で不当な扱いを目の当たりにした。時には激しい尋問や執拗な質問を受けることもある。車も日常的に検査され、イスラエルの検問所では長時間屈辱に耐える。
私がナクバの物語、特にハイファにまつわる物語を最も思い出すのはこの時だ。家庭で語られるハイファの話は、私に大きな影響を与えた。私はハイファの歴史とアラブ人のアイデンティティを深く掘り下げることにした。何十年もの間、アラブ系住民がどのようにたゆまぬ努力で街を発展させ、都市化を推進してきたかを追った。彼らの仕事は今や、力ずくで街を乗っ取り、住民を追い出した者たちだけに利益をもたらしている。このシナリオは、ハイファやパレスチナの他の都市の歴史に関する私の著作にその痕跡を残している。
ナクバのトラウマはいまだに残り、さまざまな形で持続している。ナクバ生存者の第3世代がいまだにその影響と意味合いに苦しんでいるせいでもある。個人的なものと公的なものが混ざり合い、家族全体の個人的な物語と一般的なパレスチナの物語が混ざり合った。この融合は、独占的で捏造されたシオニストとイスラエルの物語に代わる物語を提供することを目的として、物語が書かれ出版され、パレスチナ人とイスラエル人に伝達される方法に影響を与えている。そこで私は、ハイファの政治的、社会的、文化的な歴史とその役割に関する本を何冊も出版した。私は、パレスチナ社会が自分たちの故郷と再びつながり、その解放のために戦うことができるように、自分たちの都市の歴史に関する文化的対話を行う必要があると信じている。この対話は、パレスチナ人の自己認識を強め、パレスチナ人のアイデンティティの一部として、彼らの土地とのつながりや関係を強めるだろう。パレスチナの物語を書くという行為自体が、何よりもまずパレスチナの歴史との対話である。
しかし、もしイスラエルがパレスチナ人に対する侵略を続けるのであれば、両者の間で今後どのような対話が可能になるのだろうか。政治家同士の対話ではなく、イスラエルとパレスチナの人々の対話である。
限界と機会
確かにMADARは、研究プロジェクト、翻訳、あらゆる種類の報告書を通じて、イスラエルの物語と対話する状態にあることを必然的に発見した。しかし、この対話はかなり限定的である。政治体制、すなわちパレスチナ自治政府は、MADARが政府の公式部署に認可され登録された独立センターであるにもかかわらず、MADARを含む研究センターに警告と制限を課している。MADARの管理委員会10は、間接的ではあるが、パレスチナ自治政府の政策方針を考慮している。これは何を意味するのだろうか?国際的な(ヨーロッパ、アメリカ、アフリカの)人権団体や研究センターによる多くの出版物は、イスラエルはアパルトヘイト国家であると結論づけている。これらのNGOは、多くの国の政府の政治的決定に影響を及ぼしているが、たとえ国家自体がイスラエルの体制とパレスチナ領土の占領がアパルトヘイト体制を構成していると宣言していないとしても11。このような調査結果は、多くのパレスチナセンターが直接取り上げることはなく、関連する特定の用語も使用されないだろう。一方MADARは、イスラエルを入植者植民地主義によって成立し、維持されているアパルトヘイト国家であると説明してきた。イスラエルの差別的政策は、パレスチナのアパルトヘイトに関する様々な研究の中で強調されてきた。しかし、これはまだ研究のみに限定されており、MADARの政治的言説は、イスラエルの占領という現象に対して規範的なアプローチを行う際には慎重な姿勢を保っている。特筆すべきは、このテーマに関する翻訳や記事が、MADARではなく著者の意見を反映したものであるという免責事項とともに、著者の名前を使ってではあるが、MADARから定期的に発行されていることである。
それでもMADARは、高等教育機関、すなわち大学と比べれば、政治的な議論や対話を展開するための開かれた場を享受している。歴史学や政治学の学科を持つパレスチナの大学は、重要な出版物を生み出すことなく、教育を提供するにとどまっている。このことは、適切な問題についての新しく効果的で効率的な研究を提供する上で、研究センターの役割がいかに不可欠であるかを示している。
批判的な学術的、メディア的、政治的な動きがない分、リサーチセンターがこの使命を担う責任は重い。これは、リサーチセンターが大学にはない資源を自由に使えるという意味ではない。むしろ、大学は本質的に知識を生産する機関であるが、パレスチナの文脈では、コースワークと教育に限定される。
MADARの研究者の大半はパートタイムで働いており、生活費を稼ぐために収入を補うために他の場所でも働いている。彼らは、イスラエルの研究者と同じ労働条件や基準を享受しているわけではない。イスラエルの研究者は研究に熱心で、給料も高い。上級レベルの給与はかなり高く、研究者は研究や結論を拡大し、さらに向上させることができる。パレスチナの研究者にとっての懸念はこれだけではない。彼らはまた、イスラエルの政策と認知的抹殺の実践に常にさらされている。つまり、イスラエルはパレスチナ人に対し、彼らの土地における存在をほぼ完全に否定しているのだ。したがって、イスラエルの研究センターが実施する研究実践は、現地におけるイスラエルの実践と密接に結びついている。イスラエルの研究センターは、イスラエルの政治体制によって押しつけられるシオニスト=イスラエルの物語を支える機械であり、一方でパレスチナの物語を排除し、否定している。
進行中のイスラエルによる占領は、パレスチナ自治政府のもとでのパレスチナの生活を不安定なものにしている。イスラエルは、とりわけ聖書の教え込みに頼ることで、自らの物語を確かなものにしようとしてきた。これは、地上に存在する人間的、空間的、文化的、文明的なパレスチナの存在を縮小する以外には不可能である。これはまた、イスラエルがアラブ世界を解体し、あちこちに点在する孤立した国家にして、イスラエルがこの地域の紛争の核心的理由ではないことを示すために危機を拡散させようとしていることを意味する。イスラエルはイランを悪者扱いし、イスラエルではなくイランが敵であるという主張の下、湾岸諸国の反イラン政治にアライメントされた。同時に、イスラエルと多くのアラブ諸国、特に湾岸諸国との関係が正常化したのは、イスラエルを安定した国家として描き、紛争が中立化または縮小したという虚像を作り出そうとする努力を反映している。アラブ世界の解体プロセスのあらゆる部分がパレスチナ問題に影響を及ぼしている。
パレスチナの研究センターは、そのような変容に気づいてはいるが、研究レベルでは対応できない。これらのセンターのいくつかは、対立的であるよりはむしろ、社会学や経済学の歴史的・応用的研究に重点を置く傾向にある。その一方で、将来への展望に取り組む研究は、依然として制限されたままである。
そのため、パレスチナの研究能力と研究成果は、イスラエルの研究・調査に追いつくための絶え間ない状態のままであると同時に、特定のテーマに限定され、制限されたままでもある。イスラエルの統治システムの一部、あるいはすべてを研究し、模倣しようという議論や提案がなされている。パレスチナ人、アラブ人、イスラム教徒に関する研究において、イスラエルと同等のレベルに達することはできるのだろうか?私はこのような問いかけに従わない傾向がある。単に、蓄積された知識は、それが質の高いものであり、重要な問題に優先順位がつけられている場合にのみ、十分であると信じているからである。イスラエルにおけるスポーツ、健康、教育といった問題は、パレスチナ人の関心を引くかもしれない。
1948年のパレスチナ人が、そのような知識を発展させるために果たす役割を見過ごすことはできない。私の経験によれば、彼らの貢献はヘブライ語の知識や熟練度だけにとどまらない。彼らの多くは、ユダヤ人居住区とは別のアラブ人居住区や、ユダヤ人居住区とは独立したアラブ人の村や町に住んでいるにもかかわらず、日々の交流はイスラエル(ユダヤ人)社会と絡み合っている。とはいえ、仕事、勉強、その他の日常生活に不可欠とみなされる活動のために、彼らはイスラエル人と多くの共有スペースを共有している。こうした共有スペースのおかげで、1948年のパレスチナ人は、日常生活におけるイスラエルの街角の鼓動をはっきりと捉えることができる。イスラエルでの生活はダイナミックで活発だ。日常的に、あらゆる政治的志向のメディアやソーシャルネットワークによって、重要な問題が議論されている。メディアは、多様な意見を取り入れつつも、重要な問題を正確に、細部まで注意を払って議論する努力を惜しまない。広く言えば、国民はこれらの問題に接している。時には、その相互作用が政治プロセスや政府・省庁の実務に大きな影響を与えることもある。
一方、MADARが収集し、さまざまな手段(書籍、雑誌、パンフレット、報告書-デジタルまたは印刷物)を通じて出版される知識の蓄積は、1948年のパレスチナ人の政治を反映している。そうすることで、イスラエルの軍事占領下にあるパレスチナ人が、イスラエルの力学や動向を理解するのに役立っている。私の役割は、1948年パレスチナの他の仲間たちとともに、パレスチナ人がイスラエルにおける政治的、経済的、社会的な動きの本質を理解するのを助けることにとどまらない。むしろ、2種類の支配を実践する占領下にある1つの民族として、私たちの間に連帯の精神を広めることも含まれる。ひとつは1948年のイスラエルの占領で、パレスチナ人をその土地や財産から追い出し、イスラエルのアイデンティティーを与え、ナクバを引き起こしたのと同じ国家の「市民」とした。第二は、1967年のパレスチナ領土の占領である。国際法上、これはパレスチナ人を抑圧し、封鎖を強化し、彼らの武力抵抗を容認できなくし、彼らをテロリスト、殺人者、犯罪者と偽る軍事占領である。世界中のまともな人なら誰でも、占領に抵抗することがパレスチナ人の法的・道徳的権利であることを理解している。
パレスチナ・イスラエル対話としての研究
この文脈における重要な疑問は、研究はパレスチナとイスラエルの対話の一種とみなすことができるか、ということである12。ある種の傾向は、研究とは各当事者が重要だと考える問題についての対話であり、議論であることを示している。それは必ずしも意見を押し付けることを意味しない。シオニスト・イスラエルの語りは、パレスチナの語りの正当性を否定する一方で、自らを標準として押し付けようと時間との闘いを繰り広げている。しかし、パレスチナの語りはシオニストのそれとは異なり、イスラエル社会のさまざまな層にゆっくりと、そして意図的に浸透している。パレスチナの語りはイスラエル国外にも浸透しつつあるが、イスラエルの聴衆にそれを認識させるプロセスは、いまだにいくつかの難題に直面している。
パレスチナ人にイスラエルでの出来事を紹介し、イスラエルでの生活とそのダイナミクスに関する知識を向上させることで、パレスチナ人のシーンに貢献してきた。1948年パレスチナ人はまた、教育を受けアカデミックなパレスチナの人々の間で、パレスチナ内の対話を収束させることにも貢献してきた。このような状況において、MADARの経験は、ダイナミックな研究と対話を通して、2つの場面の間にこのような収束の機会があることを示している。
特にアラブ・パレスチナとイスラエルのケースのように、2つ以上の当事者間の紛争について語る場合、中心的な問題についての対話にはいくつかの方法がある。そのひとつが、政治、軍事、社会、経済、文化などにおける競争や拡大・支配競争の風景の一部となる研究に見られる方法である。研究対話とは、必ずしも研究の量に依存することではなく、研究がどのように行われ、その読者が誰であるかに注目することである。
私はパレスチナ・イスラエル研究フォーラム(MADAR)に、そのような対話のモデルを見た。研究センターの対話とは、他の研究センターの意見、方向性、勧告を受け入れることを意味すべきではない。特に、それが敵(イスラエルはパレスチナ人やアラブ人全般にとって、根強い敵であることを考慮すれば)であったり、敵に属していたりする場合はなおさらである。MADARにおける知識の蓄積は、読者とイスラエルで議論されている主要な問題との間に、ある種のつながりを生み出す。この結びつきは、進歩的な研究アイデンティティからイスラエルに押しつけられた現実を脱構築することに貢献し、イスラエルの入植者=植民地主義体制の脱植民地化に不可欠である13。MADARの活動方法とそのビジョンはともに、調査・研究の実施、さらにはイスラエル出版物の翻訳の選択において、その変化を明らかにしている。MADARでの10年間の活動を経て、独立した研究センターは、パレスチナの大学よりも広いダイナミズムと空間を享受していることが明らかになった。しかし、資金調達とドナーの期待に応えるという問題はまだ解決されておらず、これらの研究センターに悪影響を及ぼしている。様々なトピックを通してより多くの聴衆にリーチし、拡大する彼らの能力は依然として限られており、ドナー、彼らのセンターへの資金提供能力、彼らの組織的な願望を支援する意志に大きく関係している。これは明らかに、パレスチナの闘いにおける将来の追求のための豊かな道である。
- 7 このエッセイはもともとアラビア語で書かれ、Ahmed Almassriによって翻訳された
- 8 K. Nakhleh, Globalized Palestine: The National Sell-Out of a Homeland』(The Red Sea Press, Inc.)
- 9 MADARセンター、最終アクセス2021年10月9日、https://www.madarcenter.org/en/about-us/an-up-close-view。
- 10 MADARセンター運営委員会、最終アクセス日:2021年10月9日 www.madarcenter.org/en/about-us/administrative-board
- 11 J. Dugard and J. Reynolds, ”Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory,” in European Journal of International Law, Vol.24, Issue 3 (August 2013), 867-913.
- 12 C. MacInnis and John P. Portelli, 「Dialogue as Research,」 Journal of Thought, Vol.37, No.2 (Summer 2002), 33-44.
- 13 2021年5月10日、MADAR所長のホナイダ・ガネムとの会話に基づく。
ハニーン・ゾアビ(HANEEN ZOABI)は政治活動家で、オスロ合意に対抗するために1995年に設立された政党タジャモアの国民民主議会(NDA)のメンバーである。2009年から2019年にかけて、イスラエルのクネセトでパレスチナ人政党を代表する初のパレスチナ人女性議員である。2007年から続くイスラエルの非人道的なガザ包囲に対する国際的な沈黙を破るため、2010年にガザ自由船団「マヴィ・マルマラ号」に参加した。エルサレムのヘブライ大学でコミュニケーション学の修士号を、ハイファ大学で心理学と哲学の学士号を取得している。
「普通」を求めて
シオニストの植民地的枠組みにおけるパレスチナ人の市民権14
ハニーン・ゾアビ
私は、イスラエルのクネセトでパレスチナの政党を代表する最初のパレスチナ人女性であったが、私の物語は、イスラエルの民主主義、自由主義、フェミニズム、正義を支持するものではなく、むしろ、私たち自身、パレスチナ人とイスラエル国家との間の新たな対立と不協和の物語である。私の物語の中心は、抹消と可視化、沈黙と発言との闘いである。
私は1948年にイスラエルが追放しなかったパレスチナ人の子孫であり、バラバラにされ、引き裂かれ、遠くへ散らばった人々の中で最も弱いつながりとみなされがちなグループである。私はナザレで育ったが、この町は国連分割線の外側に位置していたため、イスラエル政府による最初の審議では「占領地」とされていた。実際、1948年に樹立された新国家の30%は、イスラエル自身の用語で言うところの 「占領地」だった。建国当初、イスラエルは誰に市民権を与えるかという基本的な問題に取り組んだ。政府内の少数派は、新国家はパレスチナの北部であるガリラヤを占領地とみなし、そこに残るパレスチナ人をイスラエルの公式国勢調査から除外し、彼らに選挙権を与えないべきだと考えていた。しかし、イスラエルの初代首相ダヴィド・ベン・グリオンには別の考えがあった。現地の人口統計学的な現実が、ユダヤ人が多数派を占めるユダヤ人国家の建設に適していないことは明らかだった。そこでベン=グリオンは、シオニスト民兵が占領していた土地をすべて接収し、パレスチナ人全体を追放することに動いた。ユダヤ人国家の存在そのものが、自国民の抹殺を前提としていることを自覚していたからだ。その結果、軍事作戦は1948年の国境内に住んでいたパレスチナ人の85%を追放することに成功し、パレスチナ・ナクバ(大惨事)となった。
ヤッファ、アクレ、ハイファ、リッダ、ラムレといったパレスチナの都市が壊滅的な打撃を受け、シオニストの民兵によって恐怖に陥れられた周辺の村々から国内難民が流入した結果、私たちの小さな町ナザレは、1948年の国境内で最大のアラブ人都市となった。最終的にイスラエルは国連の圧力に屈し、1948年に宣言された国境線の内側に残ったパレスチナ人に市民権を与えた。しかし、私たちはその決定過程に関与しておらず、私たちの手から離れていた。誰によれば、私たちはイスラエル市民になることを望んだのだろうか?そして、なぜ国連は、私たちの国民の大多数を追放したユダヤ国家が、私たちを市民として、それまでよりも待遇を良くしてくれると信じたのだろうか。誰のために、私たちは自分たちの土地、家、果樹園、樹木を、自分たちが創設にも形成にも関与していない国家の外国人市民権と交換することを望んだのだろうか。誰のために、周囲の 「後進」アラブ地域の中で、「先進」ヨーロッパの前哨基地となることを望んだのか。私たちの歴史が抹消され、人為的で捏造された歴史物語に置き換えられることを望んだのは誰なのか。そして、誰が私たちに感謝やお礼を述べると期待したのだろうか?
私が生まれる21年前の1948年、現在イスラエルと呼ばれている地域に残った私たちパレスチナ人は、85%の民族から強制的に切り離された。ナクバの間、570以上のパレスチナの村や町がシオニストの民兵によって破壊された。彼らは私たちの社会構造を引き裂き、市民社会、農業、工業部門、そしてヤッファで有名だった劇場やスポーツクラブとともに、台頭しつつあった中産階級を破壊した。この凄惨な暴力の余波の中で、15万人のパレスチナ人が、壊滅的に変形され、打ちのめされた民族の一員として、軍の門をくぐり抜け、新たに建国されたイスラエル国家の政治に導かれたのである。
私たちが市民権を得たのは、軍による統治を通じてだった。イスラエルは、1948年から1966年後半まで、私たち、1948年の国境内に残ったパレスチナ人を、明確な軍事支配下のゲットーに入れ、私たち自身の人々からも、イスラエルのユダヤ人社会からも切り離した。それによって私たちは、新たな「市民権」の定義に関与する機会を奪われた。私たちは国家について何も知らなかったが、軍、警察、諜報機関、技術官僚、つまり新しい。「アラブ・イスラエル人」を作り上げる責任を負うアラブ問題担当の国家顧問がいた。記憶とアイデンティティを失うことは、祖国を失い、劣等感を受け入れることに劣らず破壊的である。
軍事支配もまた、そのような市民権の論理を体現していた。それは、私たちがすでに慣れ親しんでいた軍事的手段を利用したもので、今や警察による弾圧や諜報機関による監視へと姿を変え、国家は私たちの日常生活に干渉し、私たちの政治的権利や個人の権利を日常的に否定していた。イスラエルの法律と、いわゆる民主的な市民権の手段は、私たちのナクバ、つまり私たちが奪われたことの延長でしかないことが証明された。
私はパレスチナ市民として祖国に生まれたのではなく、私の存在の真実と矛盾する物語を語る祖国に生まれたのだ。パレスチナを切り離した暴力的な存在からの疎外感が、私とユダヤ国家との関係を規定するようになった。私が取り組んだ中心的な疑問は、高まる疎外感にとらわれた私が、このような存在とどのようにして「政治的」関係を築くことができるのか、ということだった。
ユダヤ人国家は、他の入植者植民地と同様、自国と先住民(この場合はパレスチナ人)の間に仲介階級を作ることで自国を強化してきた。クネセットのアラブ系議員の選考プロセスを操作し、自国民よりもイスラエルに都合のいい議員を当選させた。ムフタール(地方首長)を含むパレスチナ人指導層の残党と強い絆を築いた。学校の校長や教師、その他の職員の任命には、諜報機関シン・ベットの承認が条件とされ、デモに参加したり、パレスチナの民族的アイデンティティと関係があると疑われる人物の任命は阻止された。今日でも、イスラエルの諜報機関は、政府がパレスチナの「市民」に対する支配を維持するための主要な手段のひとつである。
我々は敗北し、敗北と折り合いをつける覚悟で政治に参加した」ハッサン・ジャバリーンは、敗北した実体を政治的に勝利した実体に迎え入れるために、政治的条件を両極化することの危険性を警告している。彼は、「私たちは、イスラエルに対する権利、義務、忠誠という言葉をすぐに採用し、最初のイスラエル・クネセットの選挙に参加することに同意した」と書いている15。イスラエルの政治システムへの私たちの参加は、事実、植民地プロジェクトへの参加であり、服従と反感という点で、すべてを伴うものであり、イスラエルによっても、私たち自身によっても、真の自由主義の原則の適用に基づくものではなかった。
私が小学校4年生の時、クラスメートと一緒にイスラエルの国旗を掲げ、国歌を歌ったことを考えると、驚くかもしれないし、非難されるべきかもしれない。学校は、イスラエルの独立記念日に教育省が視察官を学校に派遣するので、その際に教室に国旗を飾るようにと知らせてきた。私たちはそうした。
年後、私は深い衝撃を受けながら、サブラとシャティーラの虐殺に関するニュース報道を見た。自分の存在に関わる重大なことが起こったのだと理解したが、まだ完全には理解できなかった。それからしばらくして、ナザレの東部地区にある祖母の家のバルコニーの下を、パレスチナ人の大規模なデモが通り過ぎるのを興味深く眺めた。私の中で意識が出芽、現実に対する認識が変わり始めた。パレスチナよりも古く、偉大な深い感情が私の中に出芽、不公正に対する深い感覚に由来する反抗の形が生まれたのだ。
イスラエル国歌を歌ってから5年後、サブラとシャティーラの虐殺から2年後、私はアル・アシェキーンを聴き、マルセル・ハリファと一緒に歌い、マフムード・ダルウィッシュの詩を朗読するようになった。
デモや超党派の政治活動を12年間続けた後、私は政治の分野に完全に身を投じた。一般的に、私たちの世代は、1970年代に今日まで続いている複数政党によるアラブの政治機構を確立した先人たちに比べ、政治化されていなかった。
1991年のマドリード交渉で、アズミ・ビシャラが市民権とナショナリズムについて語るのを聞いて、私は長い間私の頭を占めていた疑問に対する答えを見つけたような気がした。つまり、現実に深く潜り込まなければならない政治の世界と、その現実から切り離さざるを得ない疎外感との間で、どうやりくりすればいいのかという疑問に対する答えを見つけたような気がしたのだ。
数年後の1998年、私はアラブ人が設立した政党タジャモア(NDA、国民民主議会、ヘブライ語ではバラッド)に参加した。それから3年後、私はタジャモアの中央委員会のメンバーに立候補し、その後、政治局のメンバーにもなった。タジャモアがイスラエルにとって戦略的脅威であると認識されるまでには、わずか数年しかかからなかった。2008年までに、当時のイスラエル情報機関のトップであったユヴァル・ディスキンは、タジャモアをイランやヒズボラも含む戦略的脅威のリストに加えた16。
タジャモア党は、パレスチナの大義を解放と自由から国境紛争に格下げしたオスロ・プロジェクトに対抗するために設立された。帰還の権利、1967年の占領地における入植地の解体、エルサレム、国境、パレスチナ主権に関する問題は、オスロ合意ではすべてテーブルから外された。パレスチナ人を苦しめている根本的な原因、イスラエルの支配と虐待の手段はすべて、交渉の傍流に追いやられた。では、当事者は何に合意したのか。彼らは、私たちの現実を塗り替えるために、新たな偽りの物語を作り上げることに合意したのだ。オスロ合意以降、世界は2つの対等な紛争当事者について語った。方程式の非対称性は覆い隠され、歴史的背景も覆い隠された。オスロ合意から除外されたのは、1948年の国境内に住むパレスチナ人であり、彼らの苦境は 「イスラエル内部の問題」として分類された。オスロ合意は、イスラエルの犯罪に対抗する手段ではなく、イスラエルの犯罪を白紙に戻すものであり、クネセトで唯一反対票を投じる用意のある政党としてタジャモア党を動かしたのは、この合意だった。
タジャモアを通して、私は疎外感を保ちながら議会政治に携わることができた。疎外感は間違いなく、不公正な現実に対する「高貴な敵意の状態」を作り出すが、敵意はヘゲモニーに立ち向かう際に必要なものだと私は主張する。しかし、私たちの生活は私たちが何をするかによって定義され、行動には目標や戦略、実践的な手段が必要だが、疎外状態はそれを生み出せないどころか、むしろ妨げてしまう。一方、疎外を伴わない政治的関与は、権利と市民権というリベラルな言説が根底にある植民地的背景を覆い隠すために使われる現実を常態化させる危険性がある。したがって、根本的な問題は、市民権や権利の言説という文脈を利用しながら、どのように政治に関与し、同時にこの関与を通じて植民地的現実に対する意識を育むことができるかということになる。何十もの政治参加法が私たちの政治的行動をパレスチナの文脈から引き離すことを目的としている環境の中で、私たちはどのようにパレスチナ人として政治的利益を得ることができるのだろうか?
タジャモアはその答えを提示した。タジャモアは、イスラエルの現実とパレスチナの 「真実」の間にある分裂病的なギャップに取り組み、イスラエル市民権という文脈の中でパレスチナの政治活動の可能性を示唆した最初のパレスチナ政党だった。タジャモアは、この市民権を拒否すると同時に受け入れることによって、その市民権を実現した。タジャモアは、絶対的な国民と個人の平等に基づく、急進的な代替案を提案した。「すべての市民の国家」はタジャモアの公式スローガンとなり、シオニズムの理念そのものを脅かした。私たちは、自分たちの活動を歴史的不公正の物語の中に位置づけることなしに、真の政治的進歩を遂げることは考えられなかったので、ここが私たちの祖国であり、入植者=植民地主義者としてここに来ることを選んだ人々と共存するために妥協することが求められているという事実を強調した。しかし、この妥協は、後者が植民地的野心を捨てることを要求している。
私たちは、自分たちの歴史に根ざしたパレスチナの政治的物語を作らない私たちの政治的行動は、道徳的にだけでなく、政治的にも失敗する運命にあると確信した。イスラエルで活動する他のパレスチナ政党の政治綱領では、アイデンティティと帰属意識を「現実的な」日常的政治行動から切り離すことが求められていたが、タジャモアは、現実主義がパレスチナ人としての「真実」に異議を唱えるべきではないと考えている。タジャモアはパレスチナ市民の平等を望んでいるが、それがシオニズムに取り込まれること、つまりイスラエル国家の一部になることではなく、むしろそれを支えるシオニスト・コロニアリズムの論理に反対することを意味するのであれば、そうはしない。
他のアラブ政党も、「民族的アイデンティティの保持」を支持してきたし、今も支持している。しかし、タジャモアとは異なり、彼らはアイデンティティを政治化することを拒否し、政治とは別の領域に封じ込めることを主張している。たとえば、アラブ系が設立したイスラエル共産党(マキ、この名称の選択は重要であり、「パレスチナ共産党」という明白な代替案を拒否している)、そしてその後の平和と平等のための民主戦線(ハダシュ)が採用した政治方式がそれである。
タジャモアでは、ユダヤ国家とシオニスト・プロジェクトの間には分離はないと考えている。それゆえ私たちは、イスラエルをイデオロギーに基づく存在として理解し、そこではシオニズムが国家、歴史、地理、国際法、人権など、あらゆるものの上位に位置している。シオニスト国家でイスラエルの市民権を持つパレスチナ人として、国家のイデオロギー的基盤に異議を唱えたり、疑問を呈したりすることは許されない。この指示は、国家機関だけでなく、イスラエル社会全体にも理解されている: イスラエル国民の67%が、平和と安全保障の問題はユダヤ人の多数決で決められるべきであり、イスラエルの「民主主義」と国家内のユダヤ人特権の間には矛盾はないと信じている17。
イスラエルの国内法では、イスラエルは国際法や人間や民主主義の価値観の上に立っているだけでなく、これらの普遍的な概念を再定義し、破壊している。ユダヤ民族国家法第7条や、それに先立つ何十もの土地・住宅法は、国家がユダヤ人だけの町や都市を推進し、設立することを正当化している。その市民権法は、ユダヤ人を受け入れるだけでなく、パレスチナ人を締め出すように設計されており、パレスチナ人の国家内での存在を制限するために、非ユダヤ人の入国も認めている18。
タジャモアは、国家が与える自由の余白を最大限に活用し、イスラエル国家が一方で提供するものと、他方で自然な市民権の要件との間の矛盾を明らかにするために、国家という概念と市民権という概念との切り離しに着手した。アズミ・ビシャラは、パレスチナ人の権利はイスラエル建国以前のものであり、したがってこれらの権利はユダヤ人国家とのつながりではなく、まず祖国とのつながりに基づいていることを強調した。この議論から、適切な問題はこの市民権を「取得」するかどうかではなく、むしろどのように形成するかであるという結論を導き出すことができる。パレスチナ人である私たちは、パレスチナの物語が私たちの市民権の基礎となるべきだと信じている。
このように、タジャモアの「すべての市民の国家」というコンセプトは、その言葉や目標がリベラルなプロジェクトとして最初に形作られたものの、決してパレスチナ人の良心や歴史的物語と対立するものでも、無関心なものでもなかった。実際、それはリベラルというよりも、リベラルと表現した方が正確かもしれない。タジャモアは当初、「植民地主義」という言葉を使うことなく、シオニズムの植民地的性質を暴露したが、第二次インティファーダ以降、徐々に過激で民族主義的なレトリックを用いるようになった。
タジャモアはパレスチナの国会政党の中で最も若く、初めて女性を国会議員リストに加えた政党であり、少なくとも議席の3分の1を女性が占めていた。アズミ・ビシャラがクネセットの任期を終えた2010年にクネセットに入り、1948年の国境内のパレスチナ人の政治と議会代表に革命をもたらした。
タジャモアは、イスラエルの1948年の国境内にいるパレスチナ人が、自分たちの国家的政治中心を築かなければならないという考えを提唱した。そのような政治的中心を構築することは、代替案がイスラエル化、つまり市民権の罠の中で私たちのアイデンティティを変形させ、政治的に失敗することであることを考えれば、必須であった。
私が2009年にクネセットに入ったとき、最初に受けた助言はこうだった: 「アズミ・ビシャラのようになるな。アズミ・ビシャラのようになるな、アフマド・ティビのようになれ」(人為的で表面的なやり方でナショナリストの美辞麗句を演説に散りばめるアラブ系議員)だった。クネセトは、私がクネセトで受け入れられるための、つまり私が家畜化されるための条件を打ち出したのだ。「この家で」という言葉は、他党のパレスチナ人クネセットの議員が演説の中に挿入するのをよく耳にした。しかし、この 「家」という言葉は、私がクネセットの中で感じていた疎外感と鋭くぶつかった。
2014年にイスラエルで最も人気のあるテレビ局であるチャンネル2のインタビューに答えた後、私は拒絶主義者のように見えたと言われた。私がイスラエルの侵略行為、権利侵害、パレスチナ人への抑圧に対して発言していると、司会者が、「イスラエルの好きなところはありますか?」という質問で遮ったのだ。私はすかさず、「いいえ、何もありません」と答えた19。親しい人たちでさえ、私のインタビューでのパフォーマンスを 「過剰なテンション」と 「否定的」だと批判した。彼らは、なぜもっと好感が持てるような、拒絶主義者だと思われないようなことが言えなかったのかと聞いてきた。例えば、ハイテク部門や天候、あるいは反シオニスト運動を引き合いに出すことがなぜできなかったのかと。しかし、私が優先したのは、イスラエルと私の関係の本質、そしてイスラエルが私個人にとって象徴するもの、すなわち疎外と拒絶を伝えることだった。
認識の政治から解放の政治へと進みたいとしても、イスラエル社会の70%がユダヤ人を神の「選ばれし民」だと信じており20,57%が病院で働くアラブ人医師の多さに不安を感じている現状で、イスラエル社会と実りある対話が可能なのか自問しなければならない、 ユダヤ系イスラエル人の若者の40%がアラブ系住民の選挙権を否定することを支持し21,73%が極右政治を支持し(「左翼」を自認する人はわずか19%)、73%がユダヤ国家とアラブ諸国の間で戦争が起きた場合にアラブ系住民を強制収容所に入れることを支持している。イスラエル社会の敵意とファシズムは、最も人種差別的な法律を凌駕していることを認識しなければならない。このような社会と闘うには、認識の政治が中心的な役割を果たさなければならない。
シオニスト国家は建国以来数十年の間に変化を遂げたが、それは常に植民地的性質を強化する方向であった。イスラエルは建国から50年間、自らを植民地プロジェクトではなく、自由民主主義国家として売り出すことに成功した。しかし、オスロ・プロセスとシオニスト左派の政策によって、キャンプ・デービッド2以降、「平和のためのパートナーは存在しない」と宣言した彼らは、2つの国家という古典的な分離主義的解決策を放棄した。その結果、過去10年間、自由民主主義の美辞麗句を隠れ蓑にすることさえ苦にしないファシスト国家が出現する道が開かれた。
イスラエルは、リベラルなシオニストのエリート集団によって運営される国家から、民主主義の皮をかぶりながらパレスチナ人の存在を着実に消し去り、右翼の宗教ナショナリスト入植者のエリート集団によって運営される国家へと移行した。後者は民主主義の原則をほとんど無視しており、パレスチナ人がもたらす「人口的脅威」に対する彼らの対応は、単純に言えばアパルトヘイトである。イスラエルが2003年以降、ユダヤ人国家として明確に承認されることを要求してきたのは、パレスチナ人によるあらゆる政治的要求に対抗するためであり、平和と平等というオスロの理想に対する一般的な幻滅につながった。第2次インティファーダは、共産党と平和と平等のための民主戦線(ハダシュ)を中心に、1948年の境界線内でパレスチナ人の間に広まっていた「共存」という言説の終焉を決定的なものにした。
第2次インティファーダの後、イスラエルは抹殺と社会工学の政策を再開し、洗練させた。それは、台頭するイスラエル右派の指示のもとで行われ、彼らが提案したアパルトヘイトに基づく解決策は、グリーンラインの両側でパレスチナ人を吸収しつつ、彼らの存在の影響を緩和するというものだった。
イラン・パッペは、パレスチナに到着した後、ヨーロッパにいる最愛の人に宛てた手紙の中で、「ヤッファに到着し、そこで多くの見知らぬ人を見つけた」と書いたユダヤ人移民の記憶を発掘した。その移民は今も私たちの中に生きている。70年後、私たちの土地、家、果樹園、そして料理は、移民たちにとってもはや「見知らぬもの」ではない。彼らはすべてを気に入った。彼らはすべてを手に入れた。しかし、彼らはいまだに私たちを 「よそ者」として見ている。この70年間、侵略者たちは私たちの言葉を学ぼうともせず、私たちの歴史や文化を知ろうともしなかった。70年後、彼らはヨーロッパのように、祈りの呼びかけの音を下げるよう要求してきた。ここで、「ヨーロッパのように」だ。私たちはここではまだよそ者と見なされているのではないだろうか?
当初、イスラエル人は私を無害で無害な存在として見ていた。彼らにとって私は、パレスチナ政党の名簿でクネセトに入った最初の女性として、ちょっとした見出しを飾った女性に過ぎなかった。そんな世間の見方が一変したのは、私が2010年、非人道的なガザ包囲網の打破を願ってガザ自由船団に参加したときだった。自由船団には、国会議員、ジャーナリスト、人権活動家など730人が乗船した。私は最大の船であるマヴィ・マルマラ号に乗っていたが、イスラエルが国際水域で船団を妨害し、イスラエルのコマンドーが9人の活動家を殺害し、私たちの船を押収した。これらの出来事が示すように、イスラエルはガザを包囲するだけでなく、自由を要求するために行動する人々を「必要ならば」包囲し、殺害することを決意している。イスラエルの最大の脅威はテロリズムではなく、自由なのだ。
2010年6月1日(水)に開催された騒々しいクネセットの会期中、私は攻撃され、イスラエルの裏切り者というレッテルを貼られた。しかし、私にとって最大の裏切り行為は、包囲された自国民を守る責任を放棄することだった。船団に参加した結果、私は半年間クネセットの会議への出席を禁じられ、監視下に置かれ、議員としての権利の一部を剥奪され、さらには市民権の剥奪を要求された。これらの要求は、内務大臣の議題となり、クネセトで繰り返し発言されただけでなく、2013年と2015年に行われたクネセト選挙への私の出馬を阻止しようとした。このように、イスラエル国民のかなりの部分は、イスラエルの市民権を「ユダヤ人国家」に忠誠を誓う者に与えられる「報酬」とみなしている。ユダヤ人国家は、自らを人道よりも、権利よりも、歴史よりも、法律よりも上位に置く国家なのだ。パレスチナ人から市民権を剥奪することは、イスラエルの武器庫の1つの武器に過ぎず、長年にわたって確立されてきた追放政策を追求するために使われる。
フリーダム・フローティラに参加することで、私はクネセットの「アラブ・リベラル・フェミニスト」になるのだろうという初期の予想を裏切り、任期中は自分の社会の後進性に気を取られ、おそらく予算やサービスといった、より平凡で「受け入れられる」問題に関心を持つだろうと思っていた。それなのに、なぜ私はマヴィ・マルマラ号に参加することで、こうした期待を裏切るようなことをしたのだろうか?なぜ私はイスラエルにガザ包囲網の撤廃を要求するのか?自由を語る小柄なフェミニストである私が、女性にヘッドスカーフの着用を「強制」する「テロリスト」だらけのガザに何の関係があるというのか。
イスラエルの 「リベラル」たちは、「ガザに行って、ハマスがあなたのような40代の独身女性をどう扱うか、自分の目で確かめてきなさい」と嘲笑した。「ヨハナン・プレスナーは言った。「男は誰もお前に触れたがらない」プレズナーは後に、権威あるイスラエル・デモクラシー研究所の所長となる。彼の言葉は、いわゆる「進歩的」リベラル・シオニズムの本性を物語っている22。
クネセトにいた頃、私が最も驚いたのは、一部の議員たちが私を物理的に攻撃しようとしたことでも、その攻撃の激しさでもなかった。私が驚いたのは、私がガザ自由船団に参加したこと、そして犯罪的なガザ包囲をめぐる沈黙を破るためのアドボカシー活動に驚いたことだった。私にとっては直感的で自明のことに思えたが、彼らにとっては理解不能だった: 私は私の民族のものであり、私の歴史のものであり、ガザのものであり、パレスチナ全体のものなのだ。
私に対する一連の扇動キャンペーンと、合計5回、合計16カ月の活動停止処分に加え、イスラエルのクネセットは、私の行動を受けて、パレスチナ人議員の政治活動に新たな制限を課す法案を可決した。この法律は、90人のクネセト議員の過半数の賛成で、現役議員の政治的行為を理由にその議員を追放することを可能にする。この法律は、選出された議員がイデオロギー的な理由で議員資格を停止されることを可能にするもので、民主的プロセスを明らかに損なうものである。言い換えれば、クネセットは議員の過半数に、公選された議員を追放する権限を与えたのである。
私の体験は、イスラエルにおけるパレスチナ市民の市民権行使の不可能性を示す生きた例である。私たちがシオニスト市民権に囚われている間でさえ、シオニスト市民権の正常化を拒否し、私たちがシオニスト市民権から疎外されるのを助長することによって、イスラエルは、1948年の国境内におけるパレスチナ人の政治的状況を、その完全な複雑さにおいて可視化したのである。イスラエル政治におけるパレスチナ人としての私たちの存在と、植民地ヘゲモニーからの私たちの疎外という二重性を主張することは、第一級の政治的行為である。それは、シオニズムに対する勝利を経験していないパレスチナ人の世代に力を与える役割を果たしている。
結論として、イスラエル市民権は、パレスチナ人をイスラエル社会に対等な地位で統合する手段として付与されたのではなく、むしろイスラエルが我々に勝利したことの現れであり、行使であった。イスラエルの政治に携わるパレスチナ人は、正義と植民地的市民権との間に内在する矛盾を明確に保たなければならない。この市民権の植民地主義的本質を示し、その代替的な脱植民地化されたバージョンを提供するために、私たちは市民権という道具を使わなければならない。これこそが私たちの戦略的使命であり、パレスチナの闘いに対する最も価値ある貢献であると私は信じている。私たちの戦略的資産なのだ。イスラエルは3つの戦略的脅威に直面している。イランの核開発計画、ヒズボラ、そしてユダヤ民主国家に反対するすべての市民だ」24。
イスラエルは自らの真実(人種差別的で植民地主義的な機能)から逃れることはできない。建国から70年を経て、その真実は追いつき、ユダヤ民族国家法という法律によって、全世界の目にさらされることになった。この法律は2018年に正式に制定されたが、イスラエルは何十年もの間、その条項を現場で実施してきた。国家の人種差別的植民地主義的性質、民族浄化、アパルトヘイト体制を正当化しようとする試みである。
しかし、世界がイスラエルの真実を知るだけでは十分ではない。今必要なのは、潜在的なパレスチナ解放プロジェクトを再生させ、開花させることだ。それを育て、広める準備が整っているパレスチナ人の世代がいる。ユダヤ民族国家法がイスラエルの本質を暴くように、パレスチナ民族プロジェクトもまた、パレスチナ人の解放闘争の真実を明らかにしなければならない。
パレスチナは変わり、パレスチナ人も変わった。古くからの政治的守旧勢力の牙城は崩れつつあり、古い考え方ややり方も消えつつある。新しいリーダーシップへの要求が中心となっている。今日のパレスチナの闘いは、解放的であり、解放的である。パレスチナの真実は正義に根ざしており、権力の非対称性のバランスをとるためには、思想と想像力の解放が必要だ。2021年5月の「尊厳の蜂起」(ヒバト・アル・カラマ)の出現によって、私たちが目撃したのはそのような再構築であった。蜂起は、その行為の革命的性質を通じて正義と真実を体現する運動であり、それによって権力の不均衡を是正する手段を生み出す。
新しいパレスチナの闘いは、新しいパレスチナのための闘いでなければならない。
- 14 このエッセイはアラビア語で書かれたものをサマ・サバウィが翻訳した
- 15 Palestine Forum, last accessed October 1, 2021, rb.gy/ufbsmv
- 16 「基本に立ち返る: イスラエルのアラブ少数民族とイスラエル・パレスチナ紛争」Middle East Report 119, March 14, 2012, last accessed October 1, 2021, …www.ecoi.net/en/file/local/1048334/2016_1331806197_119-back-to-basics-israels-arab-minority-and-the-
- 17 ”New Polls On Israeli Public Opinion – December 2012,” it.scribd.com, last accessed October 1, 2021, it.scribd.com/document/118421778/New-Polls-on-Israeli-Public-Opinion-December-2012
- 18 国家は、ユダヤ人入植地の発展を国家的価値とみなし、その確立と強化を奨励し、促進するために行動する。国家基本法、https://main.knesset.gov.il/EN/activity/Documents/BasicLawsPDF/BasicLawNationState.pdf
- 19 Larry Derfner, 「The Most Hated Woman in Israel,」 Foreign Policy, January 11, 2013, foreignpolicy.com/2013/01/11/the-most-hated-woman-in-israel/
- 20 ニル・ハッソン「調査: イスラエルのユダヤ人で神を信じる人は過去最多」Haaretz, January 27, 2012, www.haaretz.com/jewish/1.5175991
- 21 Or Kashti, ”『憎悪の地図』: Israeli Religious Teens, half of Israeli Would Strip Arab Right to Vote, Poll Finds,” Haaretz, February 19, 2021, www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-religious-teens-would-rescind-arab-vote-poll-1.9551732
- 22 YouTube, last accessed October 1, 2021, www.youtube.com/watch?v=8uZ1SUREOOQ
- 23 Adalah.org、最終アクセス2021年10月1日、https://www.adalah.org/ar/law/view/603
- 24 International Crisis Group, ”Back to Basics: Israel’s Arab Minority and the Israeli-Palestinian Conflict,” Middle East Report 119, 14 March 2012, last accessed October 1, 2021, …www.ecoi.net/en/file/local/1048334/2016_1331806197_119-back-to-basics-israels-arab-minority-and-the-
AWA. DELFATTAH 「ひとつの民主国家」キャンペーン(ODSC)コーディネーター。バラド/タジャモア党の前事務総長である。著名な政治アナリストであり、さまざまな国際フォーラムで講演を行っている。
見せかけの市民権から解放の言説へ
ひとつの世俗的民主国家キャンペーン25
アワド・アブデルファッタ
80年代初頭、私が東エルサレムで働いていたアル・ファジュル英字新聞のオフィスに、年配のイスラエル人男性がやってきて、当時イスラエルで2番目に発行部数の多かったマーリブ紙のジャーナリストだと名乗った。彼は、1967年にイスラエルに占領された東エルサレムに、イスラエルのパレスチナ市民を移住させる「現象」を調査していると言った。彼は、イスラエル軍が私たちの新聞社に押しかけ、「安全保障上の理由」からヨルダン川西岸とガザ地区への立ち入りを禁止する命令を私に手渡したときのことを、Haaretzの記事で読んだと言っていた。その時、彼らは私を警察車両の中で残酷に殴り倒し、その後エルサレムの惨めなアル・マスコベヤ刑務所に連行され、そこでまた殴り倒された。彼が読んだHaaretzの記事には、私は 「アラブ系イスラエル人ジャーナリスト」と書かれていた。
「アラブ系イスラエル人」とは、イスラエルが植民地化計画の一環として強制的にイスラエルの市民権を与えた、歴史的パレスチナの他の場所での民族浄化の犯罪を生き延びたパレスチナ人を表す言い方である。私たちを「アラブ系イスラエル人」と呼ぶのは、私たちをパレスチナ人の歴史と文化から切り離そうとする意図的な行為である。こうして私たちの国民的アイデンティティを見えなくし、ユダヤ国家に忠実なハイブリッドなアイデンティティに置き換えようとしたのだ。何十年もの間、私たちパレスチナ人という特殊な層は、メディアから遮断され、アラブ諸国を含むあらゆる国際的、地域的大国から疎外されてきた。
私が生まれ育ったパレスチナ/イスラエル北部のガリラヤの小さな村のひとつ、カウカブ・アブ・アル・ヒジャから新聞社に就職するまでの話は、イスラエルの抑圧と生活支配の教義的適用を示すものとして興味深いものだ。パレスチナ人の物語を統制し抑圧する手段として、イスラエルがアラブ人学校での教育を操作していることを説明する記事を送った後、私はこの新聞社に呼ばれた。イスラエル文部省のアラブ部門を操作されたイスラエル情報部は、私の政治的見解と、アラブの学校に課された教育カリキュラムに対する私の反対派が気に入らなかった。私は英語教師としての職を解雇されたが、イスラエル当局を納得させるには十分ではなかった。彼らは、熱心なジャーナリストとしての新しい仕事でも私に嫌がらせを続け、皮肉なことに、その新聞自体がイスラエルから認可を受けているにもかかわらず、私が「イスラエル国民」であることを理由に、パレスチナの新聞社で働くことでイスラエル国家を裏切ったとして私を非難したのだ。これは、イスラエル国内で再生産され続けている複雑な状況を示している。そのため、パレスチナの人々に献身し、属している私たちは、私たちが生きている抑圧のシステムに立ち向かうための対方程式を探すことになる。
実際、私は1980年に教職をクビになってからわずか4カ月で、パレスチナの民族的アイデンティティを中核に据え、歴史的パレスチナ全土に民主的な世俗国家を樹立することを求める、着実に成長しつつある民族政治運動に関わってきた。それは、アブナア・アル・バラッド、すなわち 「国の息子たち」の運動である。私は同志たちとともに、その再建と中央指導委員会の結成に貢献し、副事務総長に選出された。
イスラエルのジャーナリストの話に戻ろう。彼は私へのインタビューを続け、約2時間に及んだ。彼の質問の中心は、「イスラエル国民として、占領地に住むことをどう受け入れていますか?」というものだった。彼は自らをリベラルなシオニストであり、1967年に占領された領土での入植は受け入れないとした。それにもかかわらず、インタビューは緊迫した政治論争となり、相反する物語を持つ2人の激しい対立となった。私のは、白昼堂々最大の強盗にさらされ、外国の侵略者によって祖国を奪われた民衆の物語であった。彼の方は 2000年ぶりに自分たちの土地に戻ったと主張する人々の話だった。翌日、このインタビューは『入植者のアワド・アブデル・ファタハがヤセル・アラファトのパレスチナ国家を要求している!』という見出しで掲載された。インタビュー中の彼の積極的な質問からして、このタイトルは完全な驚きではなかったが、彼が私を 「入植者」と表現して、これほど挑発的で滑稽な見出しをつけるとは思ってもみなかった。
このことは、リベラルなシオニストとイスラエルの労働運動の考え方、そしてパレスチナ人に対する彼らの道徳的分裂症について、私に良い洞察を与えてくれた。われわれの土地を占領し、われわれの民を殺し、迫害し、われわれの家や村を奪い、パレスチナ国外からユダヤ人を住まわせている彼らが、いまだに自分たちの国は民主的な国家だと主張できるのだ。パレスチナ革命の指導者であるヤーセル・アラファトと私を結びつける見出しは、イスラエルから、土地を奪われた民衆の自由のための闘士としてではなく、殺人者、テロリストとして見られている。
インタビューの中で私は、世俗的な民主主義国家を主張することは、イスラエルやパレスチナ社会の大部分には非現実的で危険なことだと受け止められていることを認めた。当時、それを口にする勇気のある人々は、多くの迫害と虐待に苦しんでいた。私はまた、イスラエル市民となったパレスチナ人の中には、イスラエル共産党(党員の大半はアラブ人)が主張する平等と2国家解決策を支持する者がいることも認めた。しかし、脅迫、封じ込め、アラブ系市民がシオニスト政党に投票するよう働きかける政策によって家畜化された人々もおり、彼らにとっては植民地化に適応することが生き残る唯一の道だった。
私の初期の政治意識は、2つの情報源からもたらされた。ひとつは両親で、私たちの村が占領された残酷な方法について話してくれた。父は、レジスタンスの一員であった兄の殉教の話を、大きな悲しみをもって繰り返した。母は、シオニストの一団が私たちの村を征服したときに逃亡を余儀なくされた叔父や叔母のことを思い出すたびに涙を流した。何十万人もの同胞と同じように、彼らは避難場所を求めて周辺のアラブ諸国に逃れたが、戻る権利も与えられずに流浪の中で生き、死んでいった。彼らが残したのは、子どもたちや孫たちのために闘争の燃料となる物語だけだ。
私の政治意識の2つ目の源泉は、私たちの村の土地に近代的なインフラを備えた社会主義シオニスト・キブツが建設されたことだ。私たちの村には水道も電気もなかった。実際、イスラエルが私たちを送電網に接続させるために、村の人々が30年がかりで努力したのだ。父も他の村人たちと同じように、キブツを見ては、加速する入植地の拡大にため息をついていた。私たちの土地で果物を栽培し、まるでよそ者か奴隷のように低賃金で果物を収穫させるとはどういうことなのか。
私たちの村は、入植や追放による略奪の縮図である。私たちの村は、1948年以前には2万エーカー以上の土地に広がっていたが、今では2000エーカーしか残っていない。現在は4つの入植地に囲まれており、その総人口は村に住む私たちの人口の半分にも満たない。イスラエル国民であるパレスチナ人に残された土地は、略奪、没収、入植、ユダヤ人化活動の結果、元の土地の3%26にも満たない。
西側諸国政府は、イスラエルが「アラブ」市民の自由を侵害する抑圧的な軍事政権を敷き、パレスチナ人の土地の没収と社会経済的基盤の破壊を許しているにもかかわらず、イスラエルを「民主的で啓蒙的」な国として美化してきた。これは、帰還の権利に関する国連決議194の実施を妨げたイスラエルである。このイスラエルは、建国後間もない時期に、正当性を認め続けた国際社会に対する説明責任を果たすことなく、故郷に戻ろうとした5,000人以上のパレスチナ人を殺害した。
1967年の侵略後、イスラエルはパレスチナ人に対する差別的な政策を、新たに占領した地域(エルサレム市、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区)にまで拡大した。しかし、私たちの歴史的故郷の残りを残酷に占領した結果、グリーンラインの両側のパレスチナ人が再びつながることができるようになった。これは、歴史的パレスチナのすべてのパレスチナ人に開かれた、政治的・文化的交流の新たな段階をもたらした。
70年代半ば以降、イスラエル国内のパレスチナ人は、われわれは従順であり、劣等感と政治的疎外を受け入れ、ユダヤ人国家に溶け込んだという海外の認識とは逆に、パレスチナ民族の一部としてのアイデンティティを取り戻した。私たちの民族の変容は、直近の40年間にわたる闘争、組織化、教育的・文化的訓練の発展によって特徴づけられた。最初の成果は、1976年3月の土地の日の騒乱とストライキ27、そしてイスラエル軍に対する街頭での対立の中で現れた。二つ目は2000年で、私たちはエルサレム、ヨルダン川西岸、ガザ地区の兄弟姉妹とともに第二次インティファーダに参加した。このインティファーダでは、1987年の第一次インティファーダと同様に、イスラエルのパレスチナ市民が何人も殉教し、多くの負傷者が出た。
それ以来、私たちは、パレスチナ人民と民族的大義だけでなく、国内的にもイスラエルとの間でも、深い変容を経てきた。これは、川から海までパレスチナを席巻した第3の蜂起、2021年5月のインティファダット・アル・アマル(「希望と尊厳の蜂起」)に反映されており、私たちは大規模なデモや道路封鎖を通じて積極的に参加した。イスラエル国家の市民となったパレスチナ人は、何十年もの間、その志向性とコミットメントの両方が軽視され、過小評価されてきた後、紛争において、生きたダイナミックな力として自らを示した。
アブナア・アル・バラド歴史的パレスチナにおける世俗的民主国家
1972年、1948年のイスラエル国境内に位置するパレスチナの都市ウンム・アル・ファームで、地元の民族運動が起こった。当時、イスラエル共産党は合法的に党の運営を許されていた唯一の政党であり、多くのアラブ系知識人や民族主義者は、マルクス主義的な理想やイスラエル国家の合法化を支持していなかったにもかかわらず、自分たちの感情や政治的立場を表現する場を共産党の中に見出していた。土地の日のストライキの後、アブナア・アル・バラド運動が、イスラエルの5つの大学のアラブ人学生を中心とする新たな国民運動として台頭した。
アブナア・アル・バラド運動は、私たち1948年境界線内のパレスチナ人は全パレスチナ人の一部であり、他のパレスチナ人と同様に占領下にあり、パレスチナ解放機構を中心とする亡命先で成長し結晶化したパレスチナ人の民族運動が私たちの願望を代表していることを確認した。アブナア・アル=バラドは、PLOにはあらゆる抵抗の正当な権利があると信じていた。しかし、1948年の国境内のパレスチナ人が遭遇した政治的状況の違いから、私たちは市民的、文化的、立法的な抵抗様式を採用する必要性を感じた。そこで私たちは、イスラエルの大学やいくつかのアラブの町に運動の組織的支部を設立し、イスラエルを攻撃的な植民地入植者とみなし、政治的、イデオロギー的、対決的な言説を採用した。
私たちは、当時パレスチナ全土の返還と解放を求め、パレスチナ人とイスラエルのユダヤ人が平等に暮らせる世俗的な民主国家の樹立を目指していたパレスチナ解放機構のプログラムを採用した。この運動はまた、入植者の正当性を認めない運動として、イスラエルの選挙ボイコットの原則を採用した。当然のことながら、運動の指導者や幹部のほとんどは、度重なる逮捕や拷問、解雇、大学への入学停止、新聞の廃刊など、さまざまな迫害を受けたが、私たちの活動が公式に禁止されることはなかった。私自身、数日間逮捕されたことが何度かあったし、3人の兄弟はそれぞれ2年から3年の実刑判決を受けた。
ソビエト連邦の崩壊、アメリカのイラク侵攻、地域戦争、イスラエルの侵略、アラブ諸国の崩壊、オスロ協定調印によるPLO指導部の没落によって、私たちアブナア・アル・バラドや他の進歩的グループは、新たな国家的・政治的戦略を打ち出さざるを得なくなった。私たちはそれを 「民族的アイデンティティと完全な市民権」というスローガンに集約した。
内部からシオニズムに立ち向かう
オスロ合意は、パレスチナの闘いに深い亀裂をもたらした。オスロ合意は、パレスチナ問題を、ヨルダン川西岸地区とガザ地区という、我々の歴史的故郷の22%にパレスチナ国家を樹立することに縮小した。パレスチナ問題の核心である難民問題は消滅した。私たち、すなわちイスラエルの人口の20%を占める1948年境界線内の150万人のパレスチナ人については、紛争から抹消された。これは、現在のユダヤ人国家の支配下で私たちが遭遇する虐待、服従、差別、不公正を受け入れたことを反映している。このシオニズムへの降伏は、この土地におけるパレスチナ人の継続的な存在、彼らの正当な抵抗、そして彼らの自由と正義のために100年以上戦ってきた彼らの多大な犠牲を否定するものだった。だからこそ、パレスチナのほとんどの派閥は当初オスロ合意に反対し、それが現実のものとなるにつれて順応していったのである。
イスラエル指導部、そしてある程度パレスチナ指導部は、イスラエル国内のパレスチナ民族運動、特にアブナア・アル・バラドや、オスロ合意を支持したイスラエル共産党から脱退した他のパレスチナ人たちによるオスロへの強い反対運動に衝撃を受けた。私たちは再編成し、新しい政党を設立し、自分たちの手で運命を切り開くことを決めた。政党名は「国民民主議会」(タジャモア)と名付けられた。強い勢いが生まれ、短期間のうちに何千人もの人々が支持するようになった。タジャモアは、現在党員となっている人々による長い選挙ボイコットの後、1996年に初めてクネセットの議席獲得に立候補した。重要な代表権を獲得し、私は2016年に辞任するまでこの党の幹事長を務めた。
タジャモア党は、オスロへの対応だけでなく、主に全市民の国家を求めるという点で、新しい大衆的政治的・知的勢力を代表するものであった。
私たちは、革命的な風潮が後退し、深い変革の時期にあったとしても、解放の原則と、歴史的パレスチナ全土における1つの世俗的な民主国家の樹立を、暗黙のうちにではあるが堅持し続けた。変革の担い手である私たちが社会から孤立することは、社会経済的・文化的に大きな変容を遂げつつあった社会に影響を与える力を失うことであり、オスロ合意で明らかになった敗北の風潮を利用し、同化を志向するシオニスト政党やアラブ政党のために議場を空けることは、最悪の事態を意味した。私たちは、平等な市民権とパレスチナ人としてのアイデンティティへの誇りが、私たちの生活環境を改善し、民族的・先住民的少数派としての存在を維持するための不可欠な条件であることを訴えた。
政治的思考のこの発展は、革命的後退と誤解を招くキャンペーンと敗北主義の風潮の中で、新しい世代が打ち出した驚くべき提案として現れた。私たちは、イスラエルをユダヤ人で民主的な国家と定義することに内在する矛盾を暴き、人種差別と植民地主義の「法的」構造を廃止しなければ、イスラエルは決して世俗的な民主国家にはならず、その結果、パレスチナ市民は永遠に、抑圧され差別された劣等市民のままであることを示すことを目指した。
植民地主義の言説から市民権の言説へと移行し、クネセトの選挙に参加することによって国家のユダヤ人としての本質に挑戦し、私たちの国民やイスラエル、そして世界の世論に訴えかけることは、大きな知的勇気と、おそらくリスクを必要とした。しかし、シオニズム、そして知的・道徳的基準や普遍的価値観に対する深い理解が、政治的に共謀されることから私たちを守り、パレスチナ全土に及ぶ公正で包括的な解放のビジョンを発展させるための窓を開いてくれた。こうした政治的・知的経験は、集団の成熟と、より大きな善に対して責任を持つ能力を反映していた。これは一般のパレスチナ国民やエリート層と共鳴し、わが党は瞬く間にイスラエルにおける3つのパレスチナ中心政党のひとつとなった。
やがて、「すべての市民のための国家」という党の要求は、パレスチナ社会にユダヤ人国家に代わる選択肢を提示し、一般的な言説となった。その結果、党とその指導者たちは苦境に立たされた。当時クネセットの議員であり、著名な知識人であったアズミ・ビシャラ党首は、クネセットの議員を何度も罷免され、ユダヤ人が国家を持つ権利を否定し、アラブ世界とのつながりを築いたとして裁判にかけられるなど、扇動キャンペーンにさらされた。イスラエルの学者や知識人の中には、同党を擁護し、アラブ人とユダヤ人というすべての国民の国家と、国際法や決議で規定されたパレスチナ人の正義を求める同党を、イスラエルで唯一の真の民主主義政党と見なした勇気と信念のある者も少なからずいた。実際、20年間にわたり、同党はクネセットの選挙戦で数百のユダヤ人票を獲得した。
第2次インティファーダを受け、タジャモア党を中心とするイスラエル国内のパレスチナ人の国民運動が高まる中、イスラエルはパレスチナ市民に対する敵意、人種差別、入植地拡大をエスカレートさせた。1967年に占領された土地で、イスラエルが私たちを扱う方法と、軍事占領下にある私たちの兄弟姉妹を扱う方法の違いは曖昧になった。イスラエルは、パレスチナ人とユダヤ人の平等を達成する可能性に対抗するため、法的・行政的手段を用いて正式な政策を展開した。すべてのパレスチナ人が、ひとつの抑圧的な体制のもとで暮らしていることが、次第に明らかになっていった。タジャモア党の内外の多くの人々は、市民権と平等という言説は行き詰まりを見せ、グリーンラインの外やディアスポラにいるパレスチナ人の兄弟姉妹とともに新たな取り組みを始める時だと気づき始めた。これは、植民地主義という言説への回帰と、民族解放と包括的な民主主義という共通のビジョンを通じてパレスチナ人民の団結を図り、アパルトヘイト体制を解体する闘いへと結実した。
イスラエル国内での平等と完全な市民権という言説と、それがシオニズムに提示した挑戦は、シオニズムと平等の間の構造的矛盾をかつてない方法で明るみに出し、イスラエルのパレスチナ人、そして世界中のパレスチナ人の正当な大義を浮き彫りにすることに貢献したのだから、決して失敗ではなかったと言わなければならない。ある程度、これが私たちの主な目的だった。私たちは、パレスチナ解放機構の指導部を敗北主義的なオスロ協定に署名させた非対称なパワーバランスと圧力に屈しないことを決意していた。このアプローチに内在する矛盾を十分に認識しながら、私たちに課された市民権を、シオニストのアパルトヘイト体制と闘い、その構造的な人種差別を内部から暴露する道具として利用するのだ。タジャモア党は、オスロ後の重要な政治的空白を埋め、民主主義や社会正義、個人的・集団的権利といった普遍的な価値に基づく近代的な政治ビジョンを生み出し、何千人もの活動家たちによって浸透させた。また、歴史的なパレスチナ全土における民主的市民権に向けた議論の転換にも貢献した。
西側の多くの人々は、「ひとつの民主国家」という解決策が新しい提案でも、パレスチナ人の民族解放からの逸脱でも、ユダヤ人に対する運動でもないことを知らない。歴史的文書によれば、1919年、パレスチナのイスラム教とキリスト教の諸機関はシオニスト計画を拒否し、イギリス委任統治当局に対し、パレスチナが全人民のための民主国家として独立することを宣言するよう求めた。20年代後半には、ヘブライ大学総長のユダ・マグネスをはじめとする著名なユダヤ人知識人で構成されたブリット・シャロームという小さなユダヤ人グループが、二国間国家を要求し、ユダヤ人国家の構想を否定した。さらに、PLOに代表される現代のパレスチナ民族運動は、60年代後半にこの解決策を公式に採用したが、その後、2国家解決策を支持して撤回した。
市民権論から植民地主義、アパルトヘイトへ
より偏向的で攻撃的、言論の自由や平等、平等な市民権に対する攻撃が露骨で、自らを内部から改革できないことを堂々と主張し、よりユダヤ的で民主的でない。この変化の最新の表れが2018年の国民国家法であり、自己決定権をユダヤ人のみに限定し、「平等」という言葉を削除した28。また、入植の停止、1967年に占領されたパレスチナ領土からの撤退、パレスチナ国家の樹立の可能性を閉ざした。帰還の権利に関しては、家族の統合を禁止する法律が制定され、帰還問題はきっぱりと終結した。
こうした明白にファシズム的なイスラエルの動きと、20年以上にわたるパレスチナの指導者の無力と浸食を背景に、パレスチナの舞台では、パレスチナ人民の団結、彼らの土地、彼らの大義、彼らの運命を中心とした代替的な解決策を提唱する、多種多様な草の根運動が成長している。これらの運動やイニシアチブは、客観的・主観的な障害により、合意されたひとつのビジョンのもとに組織化され、団結するまでに至っていない。その中でも、世俗的な民主主義国家を求める「一国」運動は、著名なユダヤ人学者を含む活動家の数を増やしている。「一国」運動は、そのビジョン、建国の理念と論理を探求し、その行く手を阻む理論的な障害や課題に取り組む、多くの重要な文献を生み出してきた。
しかし、議論の輪が広がっているにもかかわらず、世論に決定的な影響を与えるまでには至っていない。この失敗の背景には客観的な要因がある。第一に、イスラエルがパレスチナ人の自決権を認めるいかなるイニシアチブも拒否していることである。また、パレスチナの派閥や政党がこの選択肢を採用しなかったこともある。原則に賛成していても、彼らは2国家解決策が国際的な正当性を享受していると主張しているのだ。もちろん、「一国」運動がその分岐点に達していない主観的な理由もあり、それは運動が効果的なキャンペーンや組織化を行えないことに関連している。イニシアチブの大半は、ディアスポラ、特にアメリカとヨーロッパのパレスチナ人たちによって発せられたものである。これは喜ばしいことではあるが、パレスチナでは、ファタハとハマスの不和状態が続き、PLOが浸食されているため、批判的で創造的な思考が低下し、こうしたイニシアティブの成長を妨げていることも浮き彫りになっている。つい最近まで、パレスチナの多くのパレスチナ人は、特に新しい世代の学者たちの間で起きている「ひとつの国家」運動を知らなかった。しかし、こうした停滞した派閥から逃れ、紛争をその根源に戻し、2つの国家間の国境紛争ではなく、反植民地闘争としてとらえ直す運動に参加するパレスチナ人が増えてきている。
過去数年間における「ひとつの民主国家」論議への支持の高まりを踏まえ、過去のイニシアチブの成果を土台とし、その欠点を回避する形で、この知的な議論を組み立てる必要性が明らかになった。そこで、2018年の初めに開催した最初の2つの会合には、グリーンラインの両側のパレスチナ人知識人や活動家、そして進歩的なユダヤ人活動家や知識人が多数集まった。ハイファと英国で開催されたこの2つの会議では、原則文書が起草された。続いて、ガザ地区、ヨルダン川西岸地区、そしてディアスポラの著名な活動家や知識人との会合が開かれた。私たちはこのイニシアチブを 「一つの民主国家キャンペーン」と呼んだ。
なぜ運動ではなくキャンペーンなのか?私たちは、自らを 「運動」と定義し、なかには 「民衆運動」と名づけたこれまでのイニシアティブと一線を画したかった。運動の構築は野心的な仕事であり、現在の限られた資源ではまだ不可能だと考えている。私たちはまた、過去に1国家解決を目指して活動してきたすべての運動と個人を包含できるキャンペーンであることを目指している。これまでのところ、その一部は達成されており、あらゆる困難にもかかわらず、私たちはさらなる前進のための地平が開けていると見ている。パレスチナの現実の変化は、闘いへの自信を取り戻し、統一された抵抗の中で人々の希望を再燃させることができる、新しい解放のビジョンを求めている。
パレスチナのインティファーダ意識の回復
イスラエルは、2国間解決の可能性を潰し、入植事業を強化し、民族浄化を強化し、アパルトヘイトの壁を強化し、パレスチナの分断を深め、占領の代理人として行動するパレスチナ自治政府を設立した後、紛争の解決に成功したと考えた。しかし、「エルサレムの剣」とも呼ばれた2021年5月の「希望と尊厳」のインティファーダは、パレスチナ問題は清算され、パレスチナの抵抗は死んだというイスラエルの幻想を打ち砕いた。
第3次インティファーダは、エルサレムのシェイク・ジャラーとアル・アクサ・モスクの近隣から開始され、イスラエル国内、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区のパレスチナ人民によって増幅され、パレスチナの全派閥によって支持された。現地では何も変わっていないように見えたが、パレスチナ人民の一体感と彼らの消えることのない決意を認識させるという深い効果があった。パレスチナの若く政治的意識の高い世代が火付け役となった。彼らには、亡命先で生まれ育った若いパレスチナ人のキーボード戦士たちが加わり、民衆の抵抗を支援し、拡大する上で重要な役割を果たした。彼らは革新的なハッシュタグを考え出したが、その中でも最も顕著だったのが#from_the_river_to_the_seaであり、オスロ時代に生まれ、分裂し、イスラエルの犯罪に立ち向かうことのできないパレスチナ指導部の支配下で絶望の淵に立たされた若い世代が、オスロのパラダイムと植民地主義のくびきの下での国家建設神話の撤廃を求める傾向を示していた。
現在の民衆運動の多様性と、批判的なパレスチナ人知識人の議論の蓄積は、深まる植民地の現実と、従属的で無能なパレスチナ自治政府の両方に対する反抗の表現である。過去20年間は、パレスチナのあらゆる場所で、自由を求め、抑圧と屈辱を終わらせることに飢えている私たちの民衆が、表面化する瞬間を待っている、新たな意識の高まりの底流を反映している。私の小さな村でさえも団結蜂起に参加し、私は毎晩の大規模なデモに参加する何百人もの若者たちと関わり、その傍らに立ち、心を打たれた。
統一インティファーダは、「ひとつの世俗的民主国家」キャンペーンのビジョンの正当性を確認した。これこそが私たちに必要なものだ。解放的で民主的で人道的なビジョンで武装したパレスチナの枠組みであり、進歩的なユダヤ人が闘争の同盟者として参加できるものであり、パレスチナ人民を動員し、パレスチナ全土における民衆的で市民的な抵抗戦略を策定する枠組みである。一つの世俗的な民主主義国家は、すでに唯一の選択肢であり、イスラエル自身が、抑圧と差別のアパルトヘイト体制を通じて歴史的パレスチナ全域を支配しようとする公式の政策を通じて、必然的な出来事の発展をもたらしている。今日のイスラエルは、より偏向し、より右翼的で、より極端で、明白なファシズムに傾いている。しかし、攻撃的な植民地・アパルトヘイト体制は、闘争を続けようと決意する何百万人もの先住民や、パレスチナとエルサレムを自分たちの地理、文化、歴史の一部とみなし、中東の多くがシオニストの意図のために廃墟と化していることから、イスラエルをその脅威ともみなすアラブ諸国の何億人もの人々の中で、維持したり、剣によって生き続けることはできない。
単一の世俗的な民主主義国家を目指す私たちの闘いは長く、長期的な思考、優れた知恵、コミュニケーションと組織における高い技術を必要とする。しかし、それこそが歴史に沿い、正義と人間の尊厳、そして持続可能な平和の論理に沿った唯一の道なのである。
- 25 このエッセイはアラビア語で書かれたものをサマ・サバウィが翻訳した
- 26 カミニッツ法(計画・建設法草案)(改正109)5776-2016、ポジションペーパー、最終アクセス2021年10月1日、https://law.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2017/02/2017.2.5-keminitz-law-position-paper-eng.pdf
- 27 ”Land Day, 1976: A Turning Point in the Defense of Palestinian Lands in Israel,” Palestinian Journeys, last accessed October 1, 2021, www.paljourneys.org/en/timeline/highlight/14509/land-day-1976
- 28 「基本法: Israel-The Nation State of the Jewish People” (Unofficial translation by Dr. Susan Hattis Rolef), The Knesset, last accessed October 1, 2021, main.knesset.gov.il/EN/activity/Documents/BasicLawsPDF/BasicLawNationState.pdf.
LAILA AL-MARAYATIはアメリカのムスリムコミュニティで長年活動し、ムスリム女性やムスリム一般の関心事について、特に信教の自由、イスラムにおける女性の権利、リプロダクティブ・ヘルス、セクシュアリティ、スピリチュアリティに焦点を当て、幅広く執筆や講演を行っている。ヨルダン川西岸地区、ガザ地区、レバノンの難民キャンプに住むパレスチナの子どもたちとその家族に保健、教育、その他の援助を提供する非営利人道団体KinderUSA(Kids in Need of Development, Education and Relief)の会長を務める。あらゆる背景を持つ女性に産科と婦人科のサービスを提供してきたが、特に恵まれない人々への献身的な取り組みと、女性の健康を専門とする次世代の医師の教育に力を注いでいる。
尊厳とエンパワーメントについて
私たちの闘いにおける慈愛の役割
ライラ・アル=マラヤティ
厳格なアラブ系移民の父親の娘として育った私は、アラブ系アメリカ人としてのアイデンティティ、特にパレスチナ人としてのアイデンティティに葛藤していた。ガザやクウェートから一人ずつ渡ってきた父の親戚と、同じくカリフォルニアに移住してきたミズーリ出身の母の家族という、二分された世界に苦悩した。私たちが中西部人なのか、南部人なのか、中東人なのか、それとも単なるアメリカ人なのか、私にはよくわからなかった。しかし、パレスチナのあらゆるものに対する亡き父の決意と献身に間違いはなかった。数年後、私がガザを訪れて初めて、彼が南カリフォルニアに愛着を抱いていたことを理解することができた。南カリフォルニアは、彼の祖国とほとんどそっくりで、どこにでも生えているサブル・プラント(山椒の一種)に至るまで、彼はその実を愛でていた。
サブリという植物は、パレスチナの民族の特徴である「堅実さ」を体現しており、パレスチナの国花にふさわしいと感じた。外側は強靭で、内側は柔らかく生命を与える水を守る。身を守るために棘があるが、美しい花と果実は惜しみなく分け与えられる。水があろうとなかろうと、また適切な土壌がなくても、どんな状況でも成長する。
私は成長する過程でパレスチナの歴史をほとんど知らなかった。地図でエルサレムを見つけることもできなかったし、この地域の地理全般についても漠然としか知らなかった。すべてが変わったのは、1980年に父が姉と私をガザの家族を訪ねる旅に出したときだった。父の故郷に思いを馳せ、親戚に会い、パレスチナについて学ぶための旅だと思っていた。後になって(19歳の私は聡明だった)、その目的はいとこの中から配偶者候補を紹介することだとわかった。それは実現しなかったが、叔母、叔父、いとこたちとパレスチナを旅した後、パレスチナ人としてのアイデンティティは永遠に揺るぎないものとなった。自由に旅ができることが長続きせず、この経験が二度と繰り返されることはないだろうとは、少しも想像できなかった。
叔父たちはテルアビブの空港で私たちを出迎えた。カーン・ユーニスの家から車でわずか30分の距離だ。ガザを出る途中、イスラエルの若い兵士たちは私たちにちょっかいを出し、後に悪夢となるエレズを簡単に通過させてくれた。ハイファとナザレまでドライブし、イラク系ユダヤ人の家族と湖畔でピクニックを楽しんだ。別の日帰り旅行では、ラマッラのビル・ツァイトを訪れ、熱心な活動家の教授たちに会って、パレスチナの闘いについて書かれたパンフレットや本などをたくさん渡され、私の教育不足はすぐに解消された。ナブルスの有名なクナフェを楽しみ、ベツレヘムを訪れた。エルサレムのハラーム・アル・シャリフを訪れ、旧市街とスークを見学したことは、私たちが経験した他のすべてのことを補強するものであった。
1980年のことだった。
それからの数年間、アメリカ人女性として若い成人期を過ごす中で、父との関係は難しいものだった。パレスチナやその他の地域で起きていることは気にかけていたが、当時の私にとっては優先事項ではなかったし、パレスチナの大義は、いつかは戻りたがっていると信じていた父の手にゆだねられていると感じていた。
実際、父はそうしていた。1950年代にアメリカで教育を受けるためにガザを離れた父は、1959年に母と出会い、結婚した。1964年、彼は妻と3人の子どもを連れてガザに戻った。オスロがパレスチナ建国の契機になると信じていたディアスポラの一人だったからだ。医師としての訓練を受けた彼は、兄弟たちとともに、ガザを発展させるための事業を立ち上げることに力を注いだ。空港の建設を手伝い、製粉工場に投資し、医療やサービスへのアクセスを改善するプロジェクトを立ち上げた。彼は、ガザの人々がガザで必要な治療を受けられるようにし、他の場所に行く必要がないようにしたかったのだ。その間、私は大学、医学部、研修医、結婚、そして新しい赤ちゃんと忙しかった。いつか父と一緒にパレスチナに戻ることを夢見ていたのだが、今はもう不機嫌な思春期ではなく、成熟した大人の娘になっていた。あと1年、そうすれば行ける。
そんな忙しすぎる日々の中、私は当時のクリントン大統領の任命で、米国信教の自由委員会(USCIRF)の委員を務めることになった。1998年のことだった。息子たちは4歳と6歳で、私はフルタイムで働いていた。ムスリム・アメリカン・コミュニティの活動家として、私は同意する以外に選択肢はないと感じていた。私はジョン・ボルトン、エリオット・エイブラムス、ニーナ・シア、デビッド・サパースタイン、セオドア・マキャリック大司教(当時)らと行動を共にした。やがて私は、委員会がイスラエルにおける信教の自由とその欠如についても取り上げるようにしなければならないと思った。当時の委員会の主な焦点は、スーダン、サウジアラビア、旧ソビエト共和国、そして中国を含む東アジアだった。調査団の任務の一部には、問題の地域への旅行も含まれており、最終的には中東への旅行が必要だと判断した。もちろん、委員会の大半はイスラエルを含めるべきでないと考えていたが、私は主張した。日ごとにオスロ合意が崩壊し、イスラエルの入植によってヨルダン川西岸とガザ全域で移動の自由が侵害され、パレスチナの人々の間に耐え難いレベルの絶望とフラストレーションが生まれていることを知った。父は、他の委員会メンバーから公然と敵意を向けられても、勇気をもって私たちのコミュニティの代表として活動を続けるよう、私を励ましてくれた。
その1年後、私が3人目の子ども(女の子)を妊娠したことを発表したとき、父はその子にパレスチナ北部の町にちなんでジェニンと名付けることを提案した。10人の孫の末っ子になる予定だった。ジェニンが生まれた3カ月後、父はエジプト旅行から戻った翌日に66歳で急逝した。核家族の家長としてだけでなく、パレスチナの拡大家族の家長として、そしてパレスチナのアラブ人コミュニティの巨大な構成員として、父の死は大きな穴をあけた。いつか彼と一緒に旅行するという私の夢は消えた。ガザでの財産やビジネスの問題で対立がすぐに起こったので、彼が家族をまとめる接着剤だったことは明らかだった。
私はやがて直後のショックから立ち直り、母親であること、フルタイムで働くこと、患者の前で自制心を失わないこと、そしてクソ委員会の委員を務めることに取り掛からなければならなかった。しかし、彼が亡くなった後も、パレスチナのための活動家として彼の仕事を続けること、あるいはその面影を残すことが、私にとってさらに重要になった。その数ヵ月後、私は中東を旅していた。最初はエジプト、次にサウジアラビア、そして最後にテルアビブに行った。サウジアラビアでは、ラビや司祭がどのように扱われるかを心配していたにもかかわらず、保護者なしで旅行していたイスラム教徒の女性として、委員会メンバーの中で私だけが嫌がらせを受けた。女性差別はどんな状況でもその醜い頭をもたげるものだ。
何人かの委員会メンバーは、イスラエルで信教の自由が侵害されているという考え方に反対したため、イスラエルへの渡航を見送った。非正統派のユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒と会うと、また別の話が聞けた。私は、知識豊富なスタッフのハリド・エル・ギンディとともに、反対意見としてそれを記録した29。
アル=アクサを訪れた日、私は岩のドームの下にある小さなモスクに礼拝に行った。何が起こったのかはわからないが、私は感情に圧倒され、亡き父と彼が信じたものすべてを思い、抑えきれずに嗚咽した。そのとき私は、パレスチナの夢を父とともに絶やすわけにはいかない、そして次の世代として、私はそれを引き継ぐ義務があると悟った。私の最初の責任は、ネオコンとシオニストのグループの中で自分を主張し、イスラエルにおける宗教的少数派の権利のために声を上げることだった。ヨルダン川西岸地区とガザ地区のパレスチナ人(イスラム教徒もキリスト教徒も)が礼拝所で信仰を実践することを妨げているのは、世界中で少数派の信仰を持つ人々が直面している侵害と何ら変わらない信教の自由の問題である、ということを。テルアビブを出発する際、私はまたもや尋問を受けた唯一の委員であったが、今度はイスラエル側に尋問された。委員会の任期が切れる前日に、委員会の公式報告書に対する反対意見を発表した。このタイミングを口実に、報告書の発表を一切阻止しようとするだろうことは分かっていたからだ。
結果的には大したことは起こらなかったが、当時のワシントンDCでは、政府の公式機関からこのような声明を出すことは前例がなかった。明らかにアメリカの政治領域では戦いが続いているが、その直後、私は別のところに目を向けなければならなかった。
9.11の事件は20年前に起きたが、まるで昨日の出来事のように感じることがある。ニューヨーク、ワシントン、ペンシルバニアの惨状をリアルタイムで見ていた私たちの衝撃、恐怖、そしてイスラム系アメリカ人としての恥は、言葉では言い表せない。テロリズムの脅威は復讐心をもって米国に襲いかかり、私たちは恐ろしい反動が起こるだろうと身構えた。テロリズムを口実に重大な人権侵害に手を染めた国々は、反テロリズムの戦いがすべての人の戦いである以上、フリーパスを手にすることになる。その中にはイスラエルも含まれていた。当時の首相であったアリエル・シャロンは、オスロ体制の抑圧に対する非暴力の蜂起として始まったパレスチナ人への戦争に突入した。ヨルダン川西岸とガザ全域で壊滅と破壊が支配し、人命が失われ、自爆テロの応酬という恐怖が始まった。
米国では、愛国者法によって政府が資産を凍結し、不正行為について告発し、寄付者や従業員に嫌がらせをすることができるようになったため、パレスチナ人や他のイスラム教徒を支援していた非営利慈善団体は閉鎖された。パレスチナが火の海になり、ジェニンからラファまで人々が苦しんでいる今、私たちの支援の道は断たれた。9.11の実行犯がアラビア半島出身者であったにもかかわらず、テロとの戦いのために米国の慈善団体に対するすべてのエネルギーは、パレスチナを支援する人々に集中した。
ヨーロッパから湾岸諸国まで、パレスチナへの人道支援を望む世界中の人々に対して、一見一夜にして障壁が作られた。爆撃は、パレスチナの抵抗に対するイスラエル側の今日まで存在するパターン、すなわち、民間人に対する集団的懲罰をもたらす不均衡で過剰な武力によって継続された。すべて。毎回。毎回。
そこで、上記の団体に寄付をしていた私は、支援を必要としている人々を支援できなくなったことに憤慨し 2002年に新しい団体KinderUSA(Kids in Need of Development, Education and Relief)を設立した、志を同じくする個人、友人、人道主義者たちと協力した。米国財務省は、私たちが「テロリスト」を支援することで、他の組織がやり残したことを引き継ぐだろうと考えていることを、私たちは知らなかった。その結果、大陪審による捜査が開始され、イスラエルにいる私たちのスタッフに嫌がらせをしたり逮捕されたり、家族旅行から戻った私たち家族に尋問が行われるなど、結局は何の解決にもならなかった。どのような状況下でも合法的かつ透明性の高い方法で人道支援を提供するという私たち自身の実践とコミットメントに自信を持っていた私たちは、私たちの活動を中傷し、貶めようとする努力に耐えられると確信していた。
組織に入って間もなく、私は最愛のパレスチナを再び訪れることができた。テルアビブを通過することができなくなったため(テルアビブを通過するパレスチナ人は、そこでの虐待について話してくれる)、シナイ砂漠を車で横断し、ラファから入らなければならなかった。その間に、現地で私たちのプロジェクトを実施しているNGOのパートナーを訪ねた。また、世界食糧計画の人々を訪ね、現地のパレスチナ人が受け取った乾物を売っているのを見た。WFPが調達したオリーブオイルはパレスチナ産ではなかったし、彼らの寄付金には缶詰の肉が含まれていて、生鮮食料品はなかったことを知り、ショックを受けた。ガザでは!地球上で最も豊かな農業地帯のひとつだ!各家庭は、受け入れるしかない手当てを与えられたのだ。私たちの常務理事は、常に既成概念にとらわれることなく物事を考え、その代わりに、食料品や衣料品、学用品などを購入するために地元の商店で利用できるクーポン券を家族に配布することを思いついた。このようなプログラムは、パレスチナでキンダーUSAが最初に実施した。
同様に、私たちは、地元で栽培された新鮮で栄養価の高い農産物を提供しながら、地元コミュニティを支援する方法で、これまでとは異なる食糧支援を提供する必要があると考え、ファーマーズ・プロジェクトを立ち上げた。このプロジェクトは、地元の農家に種やその他の道具を提供するもので、農家はその作物を栽培し、それを私たちが購入し、最も困窮している家庭に提供する。さらに、長年にわたり、女性の世帯主を雇用し、フードバスケットにチーズ、ナツメヤシ、ジャムなどの追加製品を提供してきた。
子どもの栄養と福祉に焦点を当てた初期の頃、私たちは女性が経営する事業者と協力して、最貧困地域の地元の学校で子どもたちに温かい食事を提供していた。これには教育省だけでなく、UNRWAが運営する学校も含まれていた。最終的にはUNRWAが引き継ぎ、自分たちの生徒たちに温かい食事を提供するようになった。そこで私たちは、ガザ全域の公立学校、特に幼稚園に焦点を当てた。私たちはヨルダン川西岸地区とガザ地区の両方で、学用品や制服のバウチャーを提供し続けた。
広く報道されているように、ガザ全域で清潔な飲料水の供給は、塩分濃度の高さと、下水処理の絶え間ない中断による継続的な汚染により、制限されている。私たちは、学校で清潔な水を利用できるようにするプロジェクトに取り組んできた。
その年の攻撃で、特にガザ地区北東部の重要なインフラが破壊された直後だった。その旅で私たちは、前例のない心的外傷後ストレス障害に苦しむ子どもたちの心理社会的ニーズに対応するパートナーを探すことに重点を置いた。そのとき私たちは、ガザ全域における医療制度全般の大きな限界と、特に精神衛生面での欠点について学んだ。ガザ包囲はその数年前に始まっており、外部から熟練した訓練士を招いたり、訓練のためにガザ人を海外(ヨルダン川西岸にも)に派遣したり、CTスキャナーや人工呼吸器などのハードウェアを修理するために必要な機材を入手したりする能力が著しく制限されていたため、その犠牲が出始めていた。しかし、ガザの人々の驚異的な回復力に敬意を払いながら、私たちのコミットメントは続いた。その旅で私は、彼らがリサイクル鉄筋を使って何ができるのか、建物のコンクリート跡を手作業で破壊しなければならないのか、彼らの家に隣接する小さな土地を、いかにして繁栄するジャガイモ農場に変えたのか、彼らがいかにして芸術や刺繍を創作し、ダンスや音楽、語りを通してパレスチナの伝統を守っているのかを学んだ。教育と卓越性への彼らのコミットメントは、破壊された学校や大学の建物を再建し、再び教え、学び、成長することを意味していた。
私の最後の旅は2013年で、2014年のイスラエルによる「保護的エッジ作戦」の前だった。妹と私は再びシナイ半島を横断し、今回はガザで用事があったもう一人の年老いた叔父と一緒に旅をした。私たちはラファの国境職員に温かく迎えられ、親戚の家に10日間滞在し、北はジャバリヤから南はラファまでの難民キャンプにある私たちのプロジェクトやパートナーを訪ねた。バニ・スハイラにある聴覚障害者のための学校を訪ねたが、そこでは生徒たちが美術、科学、語学の分野で驚くべき成果を上げており、スタッフも熱心に子どもたちを支援していた。また、私たちが訪問した地元の幼稚園への温かい朝食プログラムでも、彼らは私たちのパートナーだった。ガザ・シティは、いつものように、私たちが他の人道支援グループやコミュニティの人々と交流する活気ある拠点だった。どこの子どもたちも、私たちと一緒に写真を撮ったり、英語の練習をしたりするのが大好きだった。
2002年から2013年まで、私はカーン・ユーニスで自分の家族の成長を目の当たりにし、そのたびに新しいいとこたちやその子どもたちに出会った。エル・ファッラ家は何世紀にもわたってガザにあり、控えめに言っても広範だ。2002年の最初の旅のとき、私たちがエジプトに到着した直後、ヘリコプターが私たちの町カーン・ユーニス近郊を攻撃し、建物を破壊して住民の多くを殺害した。誰もが私たちの安全を心配し、旅を続けることを思いとどまらせようとした。カン・ユーニスの叔母に電話すると、「心配しないで、あれは別の地域のことだから。大歓迎よ!「と言ってくれた。彼女の娘が毎朝起きて、子供たちを学校に送り出し、自分も教師として働きに出る」彼女が毎日こんな目に遭っているのに、私は誰に怯えているのだろう。”と思った。その時私は、ただ起きて生活を続けることがパレスチナ人にとっての抵抗なのだと本当に理解した。健康的な食事をとり、空腹で寝ることなく、制服を着て、足に合った靴を履くことは、尊厳と幸福感につながる。同様に、その旅では、喜びに満ちた結婚式の祝賀会に出席した。そしてまた私は、死と破壊の脅威に日々さらされながらも、人生は続けなければならないのだと悟った。
家族連れがビーチに集まり、手の込んだ食事を用意し、鉤十字を嗜みながら、捕らわれの身という現実をものともせず、この悪条件を最大限に活かして生きているのを見たのを覚えている。
2002年には、グーシュ・カティフ入植地と2万人以上のイスラエル兵がいたため、私たちはまったくビーチに行くことができなかった。2005年に彼らが去った後、ガザンの人々は再び海岸線を楽しむことができるようになった。世界で最も人口密度の高い場所に住んでいる彼らは、他にほとんど出口がないからだ。4月にガザ南部の「リゾート」でアラビアコーヒーを飲みながら、叔父が誇らしげにラクダに乗って海岸を走るのを見ていると、地中海で休暇を過ごしているような気分になった。その瞬間、私たちはとても幸せだった。その後、ガザ東部の畑を訪れ、ジャスミンやオレンジの花の匂いを嗅ぐと、かつて南カリフォルニアに自分の畑を持っていた父のことを思い出した。彼の生涯は、ガザの美しさを再現しようとする試みだった。
2013年のその旅で、姉と私はガザを別の視点から、つまり古代と現代の両方において絶大な歴史的関心を持つ目的地としてアプローチすることにした。現地ガイド(今回も親戚)の助けを借りて、ガザ・シティで今も使われているオスマントルコ時代のトルコ風呂、古代ビザンチン時代の修道院(聖ヒラリオン)、十字軍時代の建物、世界最古のモスクのひとつ(オマリ)など、素晴らしい場所を探し、見つけた。ガザというと、戦争や苦難、悲惨さばかりがイメージされがちだが、困難に直面しながらも、人々は笑い、愛し、自らを捧げる機会を見出している。彼らの豊かな歴史、変わらぬ信仰心、忍耐力が、現在の状況の限界を超えることを可能にしているのである。
私たちが比較的贅沢な暮らしをしている一方で、同胞に対して行われる恐ろしい犯罪を目の当たりにすると、生存者としての罪悪感が生まれる。人道的大惨事を終わらせるためには、占領という真の問題に取り組まなければならないのに、私たちは応急処置をしているだけではないかという懸念としばしば闘う。そのような視点には同意するが、子どもたちが今日生き延びることを助けることは、明日その子が成長することを意味し、占領を終わらせるために自分の役割を果たす準備ができることを意味するという現実に惹かれ続けている。慈善事業に携わるビジネス・リーダーを特集した記事を読んだことがある。彼は、「大規模な援助ができないなら、なぜ悩むのか?」というようなことを言っていた。私たちがささやかな予算で小さな規模で行っていることが、全体として本当に大きな闘争に変化をもたらしているのだろうか、と。しかし、パレスチナの人々への愛と支援によって表現される寄付者の寛大さの影響を過小評価することはできない。
毎年、人道支援を提供する上でさまざまな苦労や新たな障害が生じるが、パレスチナの人々が日常的に直面しているハードルに比べれば大したことはない。私たちは、意識を高め、声を上げ、支援を提供し、国会議員に働きかけをするなど、さまざまなレベルで自分たちの役割を果たさなければならない。闘いは続く。
29 国際信教の自由に関する米国委員会 2001年5月14日、国際信教の自由に関する米国委員会報告書補遺、最終アクセス2021年10月1日、https://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/may%202001%20annual%20report%20addendum%20with%20dissent.pdf
NORA LESTER MURADは米国の反シオニスト・ユダヤ人である。著書『Rest in My Shade』(2018)と『I Found Myself in Palestine』(2020)がインターリンク社から出版され、2022年には児童小説が刊行予定である。ノラは13年間パレスチナで援助説明責任活動家として働いた経験を生かし、フォーダム大学で国際人道学を教えている。ノラは『Defund Newton Police(ニュートン警察を守れ)』のオーガナイザーを務め、人種差別、負債、移住、気候など、人類と自然に対する緊急の脅威に深く関心を寄せている。優秀な3人のパレスチナ系アメリカ人の娘の母親であり、ポータケットとマサチューセッツの土地で夫と暮らしている。
解放を助ける
ノラ・レスター・ムラド
軍事行動がエスカレートするたびに、パレスチナにお金を送る方法を教えてほしいという依頼を受ける。たとえばガザ地区は、歴史的なパレスチナの他の地域から地理的に切り離されており、パレスチナの豊かな人的・自然的資源のほとんどへのアクセスを拒否されている。ガザの人々は2007年以来、イスラエルとエジプトの封鎖という集団的懲罰に耐えており、地元の農業や漁業を荒廃させ、輸出入活動を台無しにしてきた。パレスチナ人の人権を侵害し、封鎖と占領は、医療、教育、産業に必要な移動を著しく制限した。ガザのパレスチナ人は 2008年、2012年、2014年、2021年にイスラエルによる大規模な破壊的攻撃を受け、数千人が死亡し、住宅やその他のインフラが取り壊され、住民の精神衛生に深いダメージを受けた。
しかし、米国の募金・支援団体「US Friends of UNRWA」への送金は、国連機関であるUNRWAへの寄付と同じなのだろうか?UNRWAへの寄付は、難民キャンプの女性委員会に直接寄付するのと同じなのだろうか?英国の非営利団体Medical Aid to Palestiniansを通じた医療支援は、ラマッラーを拠点とするPalestinian Medical Relief Societyを通じた医療支援と同じなのだろうか30。家を取り壊された家族を直接支援する活動家に資金を送ることによる医療支援と同じなのだろうか。
パレスチナにどのような形であれ資金を投入することが、解決策でないことは明らかだ。被占領パレスチナ地域(OPT)はすでに、非軍事的な国際援助を一人当たり世界で最も多く受けている地域のひとつである。1993年のオスロ合意調印以来、400億ドルを超える援助はパレスチナ人を被害から守っていない。経済的であれ政治的であれ、国家を樹立したり、「開発」を達成したり、独立を進めたりしたわけではない。また、解放をもたらしたわけでもない。それどころか、国際援助という文脈では、庇護を受ける権利のような人権は、交渉、プログラム化、先送りの対象となる。税金が投入された二国間援助や多国間援助がパレスチナ人を生かしてきたのは事実だが、最大の受益者はイスラエルである。国際援助は、国際人道法に基づくパレスチナ人への義務からイスラエルを逃がしている。国際援助はまた、パレスチナ自治政府を、イスラエルの継続的な支配を確実にするための軍事化された治安組織へと発展させた33。
私は2014年にエイド・ウォッチ・パレスチナを設立した際、パレスチナの援助批判者たちと提携した。エイド・ウォッチ・パレスチナは、パレスチナ人の受益者と慈善事業提供者の関係を、権利者と義務者の関係に変えることを意図した、ガザにおけるコミュニティ主導の援助説明責任イニシアティブであった。エイド・ウォッチ・パレスチナは、国際的な援助システムを改善しようとして失敗した長年の経験から生まれた。私がパレスチナ人とともに、国際的なアクターの援助方法が意図しない結果をもたらしていることを訴える活動を始めてから15年になる。誰も耳を貸さないので、私たちは援助をどうすればもっとうまくできるかの例を示すことにした。誰もそれに耳を貸さなかったので、私たちは援助関係者に対し、彼ら自身の原則、宣言、公約を遵守するよう求めた。私たちは国際法を喚起した。援助関係者に圧力をかけるために人々を動員した。私たちは、現状の国際援助が、グローバル・サウスに対するグローバル・ナショナリズムの支配を維持する帝国主義的な手段であり、それに挑戦するものではないと考える世界中の人々と、私たちの大義を結びつけた。しかし、私たちが何をやっても、援助提供のプロセスを緩和したり、パレスチナ人が国際援助から受けた被害を覆したりすることはできなかった34。私は結局、パレスチナ人が国際援助関係者に力を求める唯一の方法は、援助を完全に拒否し、真の同盟国からの支援のみを受け入れることだと考えた35。
友人からの提案要請に応えて、私は「真の同盟者」が寄付を決定するためのガイドラインを作成しようと試みた。NPOよりも草の根団体を、国際NGOよりもパレスチナ人団体を優先させることを提案し、政治活動の代替ではなく、政治活動の一環として、定期的に寄付をすることを勧めた。私自身は、ガザ、シリア、レバノンの人々への寄付や、かつて投獄されていた人々、住居の確保が困難な人々、そして私が住んでいる米国で書類を持たない人々への寄付を行い、生活の中に寄付を組み込んできた。
残念ながら、パレスチナ人への支援は意図的に難しくされている。アメリカ主導の「テロとの戦い」は、軍事的、経済的、政治的な侵略によって、イスラム社会と解放運動を標的にしている。パレスチナのような場所で災害を引き起こし、人々が犠牲者を助けるのを妨害する。支援者は、知らず知らずのうちに「テロリスト・グループ」に資金を提供し、米国やその他の法律で問題になることを恐れている。「ホーリーランド・ファイブ」37の衝撃的で不当な投獄は、パレスチナ人への援助を拒否したり歪めたりすることを正当化するために、国際的な人道支援団体や慈善団体によって何度も何度も利用されている。さらに、こうした人種差別的な法律の官僚主義化が進み、デプラットフォーム(登録抹消)、デリスティング(登録抹消)、その他の管理上の戦術がとられるようになった。政治的暴力への資金提供の防止にはほとんど役立たないだろうが、実際の解放運動は言うに及ばず、正当な団体が人道的活動のために資金を集めることを難しくしているのは間違いない。ガザにお金を送りたいか?幸運にもPayPalのアカウントを持っているガザ市民は、恣意的にキャンセルされていることに気づく。ウエスタンユニオンは、説明もなく定期的に送金を拒否する。贈り主が定期的に危険とみなされる地域に送金している場合、送金特権が取り消される可能性が高い。パレスチナのグループは、アメリカに銀行口座を持っていないため、GoFundMeキャンペーンを立ち上げることができない。また、イスラエルまたはパレスチナ自治政府(いずれも政治的承認が必要)に登録され、IRSやFBIによる調査を覚悟で米国の財政スポンサーがいない限り、Global Givingに参加することはできない。
このような理由から、国際団体は寄付者にとって非常に魅力的である。これらの団体は法的・規制的な立場にあり、監視団体から認定を受けている可能性がある。魅力的な写真を掲載したウェブサイトを持っている。資料にはきちんとした英文法が使われ、「合法的な」パートナーシップの歴史を示し、信用と信頼を呼び起こす。また、クレジットカードが使え、多くの場合、税金の控除が受けられる。おそらく最も重要なことは、寄付者に自分たちが変化をもたらしていると感じさせることであろう。
しかし、制度化されたフィランソロピーにも問題はある。代表的なアンソロジーである『The Revolution Will Not Be Funded』38に掲載されているような草の根の活動家たちは、制度化されたフィランソロピーが、いかに法的、管理的、規範的な統制を用いて、社会運動を弱体化させ、コミュニティ活動を非政治化し、コミュニティの成果を共同利用し、物語を歪め、貧困層の力を削ぎ、不平等を永続化させているかを暴露してきた。代替的なアプローチは、援助やフィランソロピーの業界では一定の支持を得ている39が、貨幣が共有財ではなく私有財産とみなされる資本主義経済では、選択肢は厳しく制限されている。人々は結局、富と権力を持つ人々にもっと寛大になるよう説得することにエネルギーを費やすことになり、私たちが望むことができる最善の結果は、ウィリアム&メリンダ・ゲイツ財団のような巨大な財団が、多くの善を行う一方で、彼らが資金を提供する活動によって影響を受けることさえない2人の人々(文字通り)の手に、世界の保健システムに対する権力を集約することである。
国際援助や制度化されたフィランソロピーに内在する問題を認識した私は 2007年にパレスチナ人のグループと協力して、パレスチナのコミュニティ財団であるダリア協会を設立した。私たちの考えは、国際的な援助に代わって、資金面でも非資金面でもパレスチナのリソースを活用することだった。私たちは、透明性が高く、民主的で、説明責任のあるコミュニティ主導の助成金授与が、活気に満ちた、独立した、説明責任のあるパレスチナ市民社会を支援できると信じていた。助成金の金額は非常に少額であったが、無制限の支援によって、コミュニティは、最初からドナーの利益を促進するためにあらかじめパッケージ化された、プロジェクトと連動性の高い資金を利用するために飛び回るのではなく、自分たちの優先事項を追求することができた。
ダリア協会の経験は、パレスチナ人が自分たちのリソースをコントロールすることが変革につながることを示したが、だからといって、すべてのパレスチナ人、すべてのパレスチナ人の活動に無条件で支援を提供する義務があるわけではない、と私たちは考えている。これは、パレスチナ人に対するいかなる支援も、それが誰に送られ、彼らがそれを使って何をしようと、善であり正義であるということを意味する。解放を夢見る私たちは、パレスチナ人が他のグループと同様に多様であることを認めなければならない。有機農場を作るパレスチナ人もいれば、アグリビジネスの農薬に投資するパレスチナ人もいる。私の友人であるファティマのように、すべてのタンクの水を長持ちさせることを誇りとするパレスチナ人もいれば、「イスラエル人と同じように水を浪費する権利のために戦う」パレスチナ人もいる40。もしパレスチナ人が人種差別的で性差別的、搾取的で軍国主義的な国家に行き着いたとしても、それは彼らがその結果を「自己決定」したことを意味するものではなく、私たちがそれを無条件に尊重すべきことを意味するものでもない。それは、パレスチナの資本家たちが、自分たちのコミュニティにおける解放の力を踏みにじることに成功したということを意味する。
非パレスチナ人は、イスラエルの入植者植民地主義との闘いだけに連帯するのか。それとも、実際の解放のための闘いは、国家化よりも大きなものだと認識しなければならないのだろうか?私たちの解放の理解には、人種資本主義や新自由主義的グローバリゼーション、そしてそれらもまた搾取、不平等、不正義を永続させる方法に対する批判が含まれているのだろうか?もしそうなら、解放を志向する活動家たちは、アメリカやヨーロッパの企業利益と結びついたパレスチナの建設を目指す人々や、別のイスラム国家の樹立を望む人々のように、利害が分かれるパレスチナ人たちとどのように交流すべきなのだろうか?
この疑問は机上の空論ではない。世界中の国々で、人々は抑圧者たちに対して立ち上がり、宗教的・軍事的独裁政権や腐敗した米国が選んだ。「代表者」たちがその座に就いた。抑圧に対する団結が、より良い世界のビジョンを共有するための団結と同じではないことは、「アラブの春」を見るまでもない。政治的平等を達成したものの、経済的平等なしには不完全であることに気づいた南アフリカの例もある。パレスチナの運動は、数十年にわたる世界各地の反植民地独立運動の後に生まれたものであり、その歴史から学ぶという利点がある。運動の目的だけでなく、手段も重要である。闘争の過程で培われた原則や実践(たとえば、若い女性のリーダーシップ)が、植民地後の制度に現れるのである。
これは、パレスチナ人が独立する準備ができていないとか、内部闘争の解決がイスラエルの植民地化を打ち負かすための前提条件だと言っているのではない!単に、パレスチナ人にやみくもに金をばらまくのは中立的な立場ではないということだ。好むと好まざるとにかかわらず、私たちが提供するお金は特定の利益を支え、他のグループを犠牲にして特定のグループを強化する。しかし、ここに大きな赤信号がある!援助」が経済的・政治的抑圧のシステムにどのように組み込まれているかを理解しなければ、私たちは連帯の取り組みにおいて抑圧的な力学を複製してしまう危険性がある。たとえば、「パレスチナ人が暴力を放棄したときだけ支援する」とか、「パレスチナ人がハマス政権を糾弾したときだけ支援する」とか、「パレスチナ人が反ユダヤ主義に立ち向かったときだけ支援する」というような場合、これは実際の支援ではない。これは、支配の一形態としてお金を利用しているのだ。国際援助や制度化された慈善事業と同様、新植民地的な寄付は解放的ではなく、抵抗されるべきである。
連帯する私たちは、どのような援助が実際に役立つのか、パレスチナ人の微妙な分析に耳を傾けなければならない。ちょうど今年、3つの重要な出来事が、その連帯における財政支援の役割を含め、パレスチナ人との連帯をアップグレードするよう私たちに呼びかけている。2021年5月、ガザ地区に対する暴力の激化は、イスラエルによる人権侵害に対する認識を、米国や欧州、その他の国々の主流に押し上げた。イスラエルへの批判は(大規模な反発も引き起こしたが)受け入れられるようになった。少なくとも一時的には、ガザ地区住民の苦しみがトップニュースとなった。同時に、エルサレムのシェイク・ジャラーで現在進行中の一家強制移住と追放の試みは、イスラエルによって分断された地理を越えたパレスチナ人の団結を強め、ナザレ、ロド、アッカ、ハイファといったありそうもない場所に最前線を移した。モハマドとムナ・アル=クルドの勇敢で説得力のあるカリスマ的なリーダーシップは世界中の注目を集め、パレスチナが資金提供される慈善事業ではなく、支援されるべき大義であることを強調した。実際、クルド人たちは支援者たちに、資金を送るのではなく、シェイク・ジャラーに来て現地の抵抗を守り、目撃し、参加するよう明確に呼びかけた。その直後、援助資金を提供するパレスチナ自治政府(PA)の危険性が浮き彫りになった。PAは批評家ニザール・バナトを拘束中に殺害したように見えただけでなく、女性を標的にするなど暴力的な弾圧で民衆の不満に反応した。多くの人々にとって、これは警鐘だった。
つまり、寄付はパレスチナの自決と地元の市民社会の持続可能性を築き、パレスチナ人自身がその使い道を決めれば、少額で制限のない寄付は多大な影響を与えることができるが、単にお金だけでは十分ではないということだ。パレスチナ人や他の多くの抑圧された人々が本当に必要としているのは、政治的連帯なのだ。2012年の空爆の際、ガザにいた友人のハマダと話したことを覚えている。支援を示そうと必死だった彼に、ガザの人々は一瞬たりとも忘れ去られてはいないし、人々は支援を待ち望んでいると伝えた。私は、ラマッラの街角を通れば、ガザへの衣料品寄付活動を見かけないことはない、と言った。浜田は私たちを驚かせた: 「頼むから、服を送らないでくれ!お願いだから、服なんか送らないで! 私たちに爆弾を落とすのをやめさせるんだ!」
もし私たちがパレスチナ人の言葉に耳を傾けるなら、北半球の人々、特にアメリカとヨーロッパの人々は、イスラエルの行動に対する無条件の支持をやめ、代わりにイスラエルに政治的責任を問うよう、選挙で選ばれた議員たちに要求しなければならないと言うだろう。ボイコット、ダイベストメント、サンクションを日常生活に取り入れ、パレスチナ人の人権侵害を止めるようイスラエルに経済的圧力をかけるべきだと言うだろう。パレスチナ人の人間性を貶めるような問題のある物語に異議を唱えるため、メディアや信仰団体、学校など、あらゆる方法で声を上げるよう、彼らが私たちに促すのを聞くだろう。
私たちがお金を送るときは、運動への長期的な投資であるべきだし、闘争中の人々が揺るぎない姿勢を保てるような直接的な援助であるべきだ。パレスチナ人は、食糧、医療、シェルター、サービス、そして制度を維持するためにお金を必要としている。彼らの言うように、「存在は抵抗である」パレスチナ人は、罪悪感に突き動かされた単発の、戦略的でない寄付ではなく、エスカレーションの前に、一貫した、信頼できる、十分な支援を必要としており、それに値する。私は50歳の誕生日に、ガザのために資金を集めようとしたことを覚えている。私は5月の誕生日に向けて、30日間毎日ガザ人にインタビューしたビデオを公開したが、数千ドルしか集まらなかった。エスカレートする前に寄付したお金が遠くまで届くという考えは説得力がなかった。その数ヵ月後、2014年のイスラエルによるガザ攻撃の際には、誰もが寄付を望んだ。このような反応的な寄付は、解放的なものではない。
解放的な寄付とは、献身的であり、明確に政治的であり、相互関係に根ざしたものであり、政治的連帯の一部分であって、それに取って代わるものではない。相互扶助は解放的な寄付の素晴らしい例である。アメリカを拠点とする相互扶助のインフルエンサー、ディーン・スペードは、相互扶助の3つの重要な要素を挙げている:
- 相互扶助プロジェクトは、生存の必要を満たし、なぜ人々が必要なものを持たないのかについて、共通の理解を築くために働く。
- 相互扶助プロジェクトは人々を動員し、連帯を拡大し、運動を構築する。
- 相互扶助プロジェクトは参加型であり、救世主を待つのではなく、集団行動によって問題を解決する41。
「相互扶助」における相互性の概念を強調することは極めて重要である。与え手と受け手の間のヒエラルキーを壊すには、私たち全員が与え手になり、私たち全員が受け手になる必要がある。他人を助けたときに得られる価値感を、貪欲に所有してはならない。与えることは人間であることであり、誰もが与える権利を持っている。そのためには、受け取る力を養わなければならない。私がいつもランチ代を払うことにこだわったり、お返しの品で「お返し」をしようと急いだりするのは、他者に負い目を感じていることが不快だからで、それがいかに人間性を奪っているかを教えてくれたのは、友人の克子のおかげである。相互依存とは、恩義に身をゆだねることであり、他者から与えられたものに同等の価値を与えることなのだ。
COVID-19の大流行によって、私たちが災害を通して互いに助け合う方法が改めて注目されるようになったが、分かち合いの伝統と実践は長く深いものである。先住民やその他の集団主義的な文化は、相互依存に根ざした自分たちの生き方を抹殺しようとする努力に抵抗している。こうした価値観の多くは、1950年代から1960年代にかけての第三世界の解放運動に取り入れられたが、資本主義の覇権主義に対する実行可能な対抗軸が存在しないため、抑圧された社会間の多くの国際主義的・反帝国主義的連帯は、制度化によって侵食されたり歪められたりしてきた。
パレスチナの文脈では、相互扶助はしばしばアル・ウーナ(Al-Ouna)のように見える。アル・ウーナとは、幸福を集団的な追求と認識するパレスチナ人のボランティア活動の文化的伝統であり42、パレスチナ人が何十年にもわたる土地収奪、植民地化、占領を生き延びてきた理由としてしばしば信用されている。パレスチナ人は、第一次インティファーダをコミュニティの自立の全盛期として挙げており、このことが、実利主義に染まらない政治的表現を可能にしている。そのため、植民地時代の物語はこのパレスチナの歴史を消し去ろうとし、自分たちが常に依存していたわけではないことを忘れさせようとする。相互扶助や、脱成長、コモンズ、連帯経済、シェアリングエコノミーなどのような非資本主義的、あるいは反資本主義的な運動や実践は、国際援助や非営利産業複合体の両方に代わるものを提供する43。これらの運動は、他者と資源を分かち合うことを奨励している。なぜなら、私たちは必要性を、私たちすべてを脅かす破綻したシステムの産物として理解しているからである。
賠償はその論理的帰結である。例えば、「黒人の命」のための運動は、政府、企業、その他の機関に対し、富の再分配を含む様々な是正措置によって、過去から現在に至るまで続いている被害を修復するよう求めている44。言い換えれば、不公正な制度のせいで他者が困窮していることを認めれば、自分も同じように不公正な制度のせいで余剰を抱えていることを認めなければならない。与えることは、受け取る側の状況を変える手段であるだけでなく、与える側を解放する手段でもある。
パレスチナの解放の想像力の表現は数多くあり、希望を与えてくれる: パレスチナの農業46、コンテンポラリーダンス47、持続可能な生活48、コミュニティづくり49、さらにはパルクール50など、多くのものがある。このようなインスピレーションにもかかわらず、私の寄付はいつもスムーズにいくとは限らない。私はカリフォルニアで、個人の地位向上と物の獲得に価値を置く文化の中で育った。お金を持っている人は賢く、何か良いことを成し遂げているという暗黙の信念がある。逆に、お金を持っていない人は、失敗した人であり、そのような境遇に値する人なのだ。活動家たちは、私たちの経済システム、歴史的背景、そして現在既存のシステムから利益を得ている人々も含め、平等は誰にとっても良いことだという考え方について議論するための開かれた空間を押し広げ続けている。それでも私は、お金を寄付するとき、時々怖くなる。寄付をしすぎると、不安定になり、貧しくなり、自分や家族の面倒を見ることができなくなり、孤独死してしまうのではないかと恐れてしまうのだ。今日誰かの面倒を見れば、明日誰かが私たちの面倒を見てくれると信じることがどれほど難しいか、私は理解している。
パレスチナ人のおかげで、私はより勇敢で、より政治的に戦略的な贈り主になることができた。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の2年生だった私は、ユダヤ人としてパレスチナ人の抑圧に加担していることを知った。より深く学ぶために、3年次にはカイロのアメリカン大学でパレスチナ人と、4年次にはエルサレムのヘブライ大学でパレスチナ人と生活を共にした。政治について学び、寄付についても学んだ。アラブでの2年間の生活を終え、住んでいたロサンゼルスの住宅協同組合の自分の部屋に戻ったときのことを鮮明に覚えている。ドアがノックされ、私の心は古い自分と新しい自分に二分された。古い自分は、ドアを開ける前に食べていたクッキーを片付けようとした。新しい自分は、クッキーを皿に盛り、お茶を入れ、訪ねてきた人に敬意を表そうとした。人間性の表現として与えるというこの理解は、他人を助けることではなく、むしろ自分が生きたい世界を生きることで創造するという生き方へと発展した。
解放的な援助は、ただお金を送るよりも複雑だが、とてもシンプルでもある。それは、私たちの連帯にラディカルな愛51を取り入れることを含んでいる。1980年代初頭、私はエルサレムのパレスチナ英字新聞 「Al-Fajr」の校正ボランティアをしていた。刑務所から釈放されたヴィオラという若い女性に、記者と一緒にインタビューに行ったことを覚えている。パレスチナの女性たちが定期的に抵抗活動を主導していた第一次インティファーダ以前のことだ。隣人や活動家たちが彼女を歓迎するリビングルームで、ヴィオラは、イスラエル軍に逮捕されたとき、彼女が最も恐れていたのは拷問されることではなく、父親が彼女が男性と組織化していたことを知ることだったと語った。彼女は私を鼓舞した。群衆が去った後、私はヴィオラに、もうすぐアメリカに戻るので、パレスチナの大義を支援し続ける方法が見つからないのではないかと心配していることを打ち明けた。彼女は私の心配を一蹴した。「読書を教えなさい。「隣人を解放しなさい。隣人を解放する。それがパレスチナ人を助ける最善の方法なのです。”と言った。それから何年も経った今でも、私は「すべての人の解放は、他のすべての人の解放と結びついている」という信念を拠り所にしている。つまり、パレスチナ人の解放を前進させる可能性は、その説得力と同じくらい無限にあるということだ52。
30 パレスチナ医療救済協会、http://www.pmrs.ps/
31 Shir Hever, ”How Much International Aid to Palestinians Ends Up in the Israeli Economy?” Aid Watch, September 2015, …www.shirhever.com/wp-content/uploads/2018/01/InternationalAidToPalestiniansFeedsTheIsraeliEconomy.pd
32 Nora Lester Murad, ”Donor Complicity in Israel’s Violations of Palestinian Rights,” Al-Shabaka: Palestinian Policy Network, October 24, 2014, al-shabaka.org/briefs/donor-complicity-in-israels-violations-of-palestinian-rights/.
33 Yara Hawari (host), ”Palestinian Securitization vs Liberation with Alaa Tartir,” Rethinking Palestine podcast, …podcasts.apple.com/us/podcast/palestinian-securitization-vs-liberation-alaa-tartir/id1537774938?i=10.
34 Nora Lester Murad, 「Putting Aid on Trial: Nora Lester Murad,」Putting Aid on Trial: An emerging theory of change for how Palestinians can hold international aid actors accountable to human rights obligations,” Saul Takahashi (Ed.), Human Rights, Human Security and State Security: The Intersection (Santa Barbara: Praeger, 2014), 163-84.
35 Nora Lester Murad, 「Should Palestinians Boycott International Aid?」. The Guardian, October 18, 2012, …www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2012/oct/18/should-palestinians-boycott-inter
36 Palestinian NGO Network, ”PNGO Network calls for the UN and INGO to stand by their mandates, and hold Israel accountable for persistent IHL violations” (Position Paper), August 14, 2014, www.cordaid.org/media/medialibrary/2014/08/Position_Paper_14-08-14_1.pdfを参照のこと。
37 ”USA v. Holy Land Foundation for Relief and Development,” Charity and Security Network, August 24, 2020, charityandsecurity.org/litigation/holy-land-foundation/を参照のこと。
38 Incite!Women of Color Against Violence (eds.), The Revolution Will Not Be Funded: Beyond the Non-Profit Industrial Complex (Cambridge, MA: South End Press, 2007).
39 How Matters, www.how-matters.org/ and Global Fund Community Foundations, globalfundcommunityfoundations.org/, last accessed October 1, 2021を参照のこと。
40 ラマラ在住の水活動家、クレメンス・メッサーシュミットの言葉。国際援助がパレスチナ人の水利権をいかに弱体化させるかについては、ドイツのドキュメンタリー映画『Aid But No State(援助はあっても国家はない)』などで明らかにされている。
41 ディーン・スペード『相互扶助』: この危機(そして次の危機)において連帯を築く。(ロンドン:Verso Books、2020)。
42 Aisha Mansour, ”Before Neoliberal Economics, We Had Al-Ouna: 市民の懸念」ダリア協会、2015年10月30日、https://www.dalia.ps/content/neoliberal-economics-we-had-al-ouna
43 Corinna Bukhart, Matthias Schmelzer, and Nina Treu (eds.), Degrowth in Movement(s): Exploring Pathways for Transformation (London: Zero Books, 2020)を参照。
44 M4BL, 「Reparations」, last accessed October 1, 2021, m4bl.org/policy-platforms/reparations/を参照のこと。
45 「Sign the Redistribution Pledge,」 Resource Generation, last accessed October 1, 2021, resourcegeneration.org/redistribution-pledge/を参照のこと。
46 「Liberating Farming, Agriculture for Liberation,」 webinar (Arabic), last accessed October 1, 2021, www.palestine-studies.org/en/node/1651375、
47 Stereo48 Dance Company, www.stereo48.com/, last accessed October 1, 2021を参照のこと。
48 The Palestine Institute for Biodiversity and Sustainability (PIBS) and the Palestine Museum of Natural History (PMNH) at www.palestinenature.org/, last accessed October 1, 2021を参照のこと。
49 Mariam Al-Asturlabi on Instagram @astrolabedemariem, last accessed October 1, 2021, www.instagram.com/astrolabedemariem/を参照のこと。
50 Aljazeera English, 「Parkour offers freedom to Gaza youth,」 YouTube, January 23, 2019, www.youtube.com/watch?v=TLgPYKhdRD0を参照のこと。
51 ベル・フックス「自由の実践としての愛」(6ページ)、最終アクセス2021年10月1日、https://uucsj.org/wp-content/uploads/2016/05/bell-hooks-Love-as-the-Practice-of-Freedom.pdf 参照。
52 Mutual Aid Disaster Reliefのジミー・ダンソン、Build Palestineのラマ・アムル、パレスチナの学者であるムナ・ダジャニには、自分の考えを明確にするために協力してもらった。アンナ・レヴィは税務書類の分析を手伝ってくれた。より良い贈り主になるために、長年にわたって私を助けてくれた多くの寛大で勇気ある活動家たちに感謝する。私の娘たち、セレーネ、ジャッシ、メイサンヌには、私に善戦を続ける理由を与えてくれたことに感謝する。
1954年ハイファ生まれ。1979年にエルサレムのヘブライ大学を卒業し、1984年に英国のオックスフォード大学で博士号を取得した。1984年から2006年までハイファ大学政治学部の講師を務めたが、パレスチナの大義を支持したために退職を余儀なくされた。2000年から2006年までハイファのエミール・トゥーマ・パレスチナ研究所の所長も務めた。
2007年からは、英国のエクセター大学でヨーロッパ・パレスチナ研究センターの所長を務めている。著書に『パレスチナの民族浄化』(原題:The Ethnic Cleansing of Palestine)、ノーム・チョムスキーとの共著『パレスチナについて』(原題:On Palestine)など20冊がある。
パレスチナのための国際闘争
イラン・パペ
「国際連帯は慈善行為ではない: それは、同じ目的に向かって異なる地平で戦う同盟国間の団結である。その目的の最たるものは、人類が可能な限り高いレベルまで発展するのを助けることである。”」
-サモラ・マシェル
「解放のための闘争で虐殺された男、女、子供たちは、ベトナム、ラオス、クメール、タイにいる。彼らはパレスチナ、シナイ半島、シオニストの占領下にある他のアラブの土地にいる」
-オリバー・タンボは1961年12月16日、MK設立10周年記念日に呼びかけた。
パレスチナのための国際連帯運動の活動家として、私は3つの大きな教訓を学んだ。第一に、パレスチナの大義のために活動する人生は、平行線をたどる旅であるということだ。これは特に私のようなイスラエル系ユダヤ人にとって当てはまる。ひとつはシオニズムとそのコンフォートゾーンから抜け出す旅であり、もうひとつはパレスチナ人の友人たちの信頼を勝ち取り、あなたが真の支援者であることを保証する旅であり、そして最後のひとつは、あなた自身が歩んできたこれらの旅に同胞たちを連れて行こうとする旅である。
活動家、特にパレスチナのための国際的な活動家のもうひとつの特徴は、努力と目に見える結果との間の緊張である。パレスチナの現状に大きな変化がないことを考えれば、これは非常にフラストレーションのたまることである。ほとんどの連帯活動家はこのフラストレーションに対処するため、自分がどれだけの成果を上げたかということよりも、自分たちが信じる大義のために十分なことができたかどうかを自問することに重点を置いている。
最後に、連帯の真の意味について学ぶ。第一に、その系譜と歴史を学ぶことによってであり、南アフリカにおける反アパルトヘイト連帯運動ほど優れた指針はない。ANCとの国際連帯は、アパルトヘイトを打倒する闘いにおいて最も重要なものであった。1970年代、脱植民地化されたばかりの大陸の多くのアフリカ諸国がANCを支援したのと同様に、ANCとの国際連帯は最も重要なものであった。忘れられて久しいこの時代、これらの新しいアフリカ諸国は、国連におけるパレスチナ人の闘いへの支援も主導し、シオニズムを人種差別と同一視する国連総会決議にまで至った。これはアメリカの圧力により1991年に撤回された。
連帯の本質を学ぶには、理論的に学ぶことも、大学で学ぶこともできない。それには、同情、共感、連帯、擁護の違いを十分に理解する必要がある。要するに、解放運動や被植民地の人々の声に耳を傾け、彼らが何を必要としているかを学ぶのであって、彼らが何をすべきかを説くのではないということを十分に理解することだ。これは、批判や誠実な対話の余地がないという意味ではない。この姿勢は、現在の解放運動の明確な方向性の欠如や慢性的な不統一を克服するのにあまり役に立たない。しかし、その日の必要に応じて、連帯の意味を十分に理解し、闘争全体にとって有用で重要な存在となる。実際、私にとってこれは、1970年代後半に始まり今日まで続いている、個人的な学びと学びの旅であった。
連帯運動の歴史
ナクバ後の初期の数年間、世界全体、政府も社会も、パレスチナの苦境にまったく無関心だった。この人道に対する罪はほとんど認識されず、記録もされず、非難もされなかった。初期の連帯の兆しは、アラブ世界とアジアやアフリカの植民地化された世界に見られた。パレスチナ人との連帯は、まずエジプト大統領ガマル・アブデル・ナセルが主導し、その後、アラブ世界、アフリカ、アジア全域の反植民地主義的解放運動が主導した(10年後には中南米でも)。アラブ世界では、労働組合、学生、あらゆる階層の人々のネットワークを通じて連帯が維持され、彼らはパレスチナの闘争と、1960年代にそれを主導した新しい組織であるPLOに同調した。1967年以降、西側の伝統的な左派は冷静さを取り戻し、社会主義の模範としてのイスラエルに対する熱狂が見当違いであったことを理解し始め、連帯運動に参加した(1967年まで英国では、親イスラエルロビーは労働党の左派が主導し、親パレスチナロビーは同党の右派が、保守党と自由党の同盟者とともに主導していたことは驚くにはあたらない)。
今日われわれが知っているような欧米の国際連帯運動のルーツは、1967年以降にあった。欧米の世論は、ナクバや難民の苦しみ、イスラエル(1966年まで残酷な軍事支配下にあった)のパレスチナ人が犠牲になっていることに気づいていないように見えた。しかし、ヨルダン川西岸地区とガザ地区が占領され、PLOが古典的な反植民地主義的解放運動として台頭すると、欧米社会の多くの人々の態度は劇的に変化した。しばらくの間、特にイギリス、フランス、スカンジナビア諸国などの一部の政府は、イスラエルにヨルダン川西岸地区とガザ地区からの撤退を求める圧力をかけることをいとわないようにさえ思われた。西側のパレスチナ支援は今や一般市民へと移行し、今日に至っている。
左派の連帯と欧米の一部のリベラルサークルの支持には違いがあった。左派はパレスチナの闘いを反植民地主義と同一視し、自らをヨーロッパの左派と世界中の反植民地主義運動とのネットワークの一部とみなしていた。したがって、左派は政治的闘争と並んで武装闘争の正当性を受け入れた。一方、リベラル派の間では、ファタハが段階的に解放を追求する計画(少なくとも第一段階として二国間解決を受け入れる意思)を採択した後、特にアラファトが1975年に国連で、選択肢の象徴としてピストルの横にオリーブの枝を掲げ、外交努力に参加する意思を示した有名な演説の後、支持を表明しやすくなった。こうした支援の結果、1970年代初頭のPLOは世界各地に公使館を開設することができ、現在とは異なり、公使館は連帯運動の主要な住所となった。
こうして1975年までには、1948年以来初めて、世界の市民社会の中に、パレスチナ人の唯一かつ正当な代表として承認されることを求めるPLOの要求を公然と支持する、目に見えるセクションが存在するようになった(読者の記憶にあるように、列強はまだ二国家解決策を完全に議論していなかったため、解決策それ自体について語ることは少なかった、 1977年にイスラエルで労働党が倒れるまで、「和平」交渉の中心は「ヨルダン・オプション」(ヨルダン川西岸地区の一部をヨルダンに併合すること)であり、リクードが政権を握った後は、占領地におけるパレスチナの自治について話し合われた。
多くの意味で、1970年代、パレスチナのための対抗連合は非西洋世界を中心に展開され、アフリカ解放諸国は自由な南アフリカを求める闘いとの比較を見逃さなかった。その結果、これらの国々は国連で、シオニズムを人種差別と同一視する1975年の決議を支持した。
この熱狂的な連帯のネットワークは、1982年以降、絶望の短い期間に取って代わられた。このような災難の年は、時として、解放運動への破滅的な影響が忘れ去られたり、矮小化されたりするほどであった。PLOはパレスチナから遠く追放され、内部闘争の不安な時期が続いたが、これは連帯運動が明確な方向性を持つ助けにはならなかった。
連帯運動への参加
この時期、私はシオニズムから脱却し、パレスチナの大義のために全面的に活動するための長い旅を始めた。私は1980年、オックスフォード大学の博士課程の学生として英国に到着し、親パレスチナ派の指導教官である有名なレバノン人歴史家アルバート・ホウラニの指導の下、各地で1948年のナクバに関する記録資料を調査し始めた。これは私がシオニズムから抜け出す最初の駅であり、そのプロセスは一日にして成らず、多かれ少なかれそこから始まった。公文書館で見つけたものは、私が1948年について知っていたことすべてと矛盾しており、1982年夏にはイスラエルによるレバノンへの最初の攻撃が勃発した。イスラエルの外でのみ、私は点と点を結びつけ、1948年の虐殺から1982年のレバノンでのパレスチナ人虐殺へとつながる大きな絵を見ることができた。残虐行為と人道に対する罪の背後には、同じイデオロギーがあった。イデオロギーと実践の結びつきに気づいたら、もう後戻りはできない。日を追うごとに、私はシオニズムに対する疑念を募らせ、その道徳的妥当性と歴史的パレスチナにおけるシオニズムの事業に公然と異議を唱えた。
私が1980年代初頭に英国で遭遇したことは、欧米の多くの人々が他の場所、特に米国で経験したことであった。パレスチナの大義に同調することは、一方ではテロリズムへの支持と同一視され、依然として不定期なものであったが、他方では、少なくとも労働組合、学界、一般市民といった特定の界隈では、振り子が変わり始めた。この点での飛躍は、1987年の第一次インティファーダの光景と音に対する世界的な反応であった。
蜂起の映像や、海外からの活動家が(2000年まで)占領下のヨルダン川西岸地区とガザ地区に比較的容易に到達できたことが、連帯運動に深みを与えた。2000年に勃発した第2次インティファーダ以降、連帯運動の活動はより困難になった。それは 2001年8月に公式の国際連帯運動(ISM)が設立されたことによって明らかになった。ISMはパレスチナ人主導の運動で、デモやインターネット上での活動以上のことを望む世界中の活動家グループから構成されていた。彼らはボランティアとなり、パレスチナ人が自分たちのオリーブ畑を守り、学校の通学路を守り、ユダヤ人入植者の暴力や軍隊の横暴から自分たちの家や企業を守るのを支援する目的でパレスチナに到着した。
ISMは、今世紀に誕生した、より大規模で非公式な連帯ネットワークの先駆けであった。時にはそのような名前で、時には似たような名前で、さまざまなパレスチナ連帯委員会やキャンペーン(PSC)が世界各地で次々と生まれた。この進展は、私自身の活動の形成期と重なった。私がまだイスラエルの大学の教員であった頃、いくつかの面で、パレスチナの闘いに対する真の反シオニスト的連帯は、イスラエルのアカデミズムの中からではほぼ不可能であることが明らかになった。そんなことをすれば職を失うし、職を失わないということは、おそらく自分のやり方が間違っているということだ。他の場所での動向は、内部からの闘いにおいていかに孤独であったとしても、自分が連帯の成長し続けるネットワークの一部であることを意味していた。
一方では、地元のアカデミアの一員になることはできず、他方では、外から活動すべきであるといった知識を処理するには少し時間がかかり 2006年になってようやくこのプロセスが成熟した。私がイスラエルを離れ、英国で教鞭を執り始めたのは、パレスチナとの国際連帯運動に新たな局面が加わった時期だった。
BDS運動の役割
この運動は、歴史的パレスチナ全土の100を超えるNGOに代表されるパレスチナの市民社会と、世界中のパレスチナ人コミュニティが、イスラエルがパレスチナ人の3つの基本的権利を尊重するまで、ボイコット、ダイベストメント、制裁という3つの手段を通じて圧力をかけることを要求した呼びかけに応えるものとして 2005年に誕生した:
難民の帰還の権利
ヨルダン川西岸地区とガザ地区の人々が軍事占領から解放されて暮らす権利、そして
イスラエルのパレスチナ人が平等に暮らす権利である。
パレスチナの政治が不統一であり、イスラエル国内での変革の可能性がほとんどないことが明らかな今、世界の世論の立場は、パレスチナ人が歴史上最も困難な瞬間に直面している今、パレスチナの大義に勇気を与える重要な要素となっている。BDSキャンペーンは、この国際社会に焦点と目的意識を与えている。有名アーティストがイスラエルでの公演を拒否し、学生組合がイスラエルの教育機関との関係を断ち、大企業までもがヨルダン川西岸地区のユダヤ人入植地との契約を撤回し、労働組合がイスラエル企業への資金提供や投資を取りやめるなど、BDS運動は印象的な抗議運動へと雪だるま式に発展している。
その1年後、私は英国で教鞭をとることになり、BDSの活動に深く関わるようになった。そして、シオニズムと入植者の植民地主義を同一視し、ナクバを民族浄化のフレーミングとし、和平の呼びかけを脱植民地化の要求に置き換えた、パレスチナに関する新しい語彙を作ることに、学術的な仕事を通じて貢献したと私は思っている。この新しい辞書では、イスラエルはもはや「中東で唯一の民主主義国家」ではなく、むしろアパルトヘイト国家であった。こうした新しい語彙の項目はすべて、政治的な立場としてだけでなく、学術的な研究や調査の成果として提示された。
パレスチナの正義と解放のための闘いにおいて、学者だけでなく学問そのものが果たすべき役割を強化するために、私は2007年にパレスチナ研究のためのヨーロッパセンターを設立した。現在、このようなセンターはいくつかある。このようなセンターは、大学院生にパレスチナに関する安全な執筆の場を提供し、パレスチナの過去、現在、未来のさまざまな側面に関する共同学術研究のためのハブを提供しようとしている。
予想通り、英国の親イスラエルロビーはこのプロジェクトを阻止するためにあらゆる手を尽くしたが、私の大学は揺るぎなく、脅迫や圧力に屈することはなかった。現在、大学における学術研究と学生運動は手を携えて進んでいる。2010年、世界中の学生がイスラエル・アパルトヘイト・ウィークを組織した。その後、世界各地で年に一度、パレスチナに関する講義やワークショップ、展示が一週間にわたって開催され、ナクバが現在進行形であることが強調されるようになった。キャンパスは親パレスチナ活動の拠点となり、かつては親イスラエル派だったユダヤ人学生も含め、闘争に身を投じようとする若い世代が台頭してきている。
またもや予想通り、イスラエルは激しく反発している。今日に至るまで、イスラエルはBDSに反対する立法を西側諸国に促そうとしている。また、イスラエルは戦略省という特別な省を設立し、イスラエルが「ユダヤ国家の委縮」と呼ぶものと戦うために莫大な予算を割り当てている。この省は学生や活動家のネットワークを使い、地上やインターネット上での親パレスチナ派の活動に異議を唱え、イスラエルを「野蛮な」中東の中の人権のオアシスとして商品化しようとするが、うまくいかない。アルジャジーラが放映したテレビシリーズ『ザ・ロビー』は、イスラエル大使館が親パレスチナ派の政治家や活動家に対する中傷キャンペーンにどのように関与していたかを検証し、氷山の一角を暴いたにすぎない53。
ここ数年、すなわち2015年頃から、連帯運動が上層部から政治に及ぼした影響は、ゆっくりとではあるが着実に見られるようになった。米国と英国の有力候補者は初めて、少なくとも自決と国家樹立を求めるパレスチナ人の基本的権利に関する限り、公然と親パレスチナの立場を支持した。ジェレミー・コービンが労働党党首に選出され、バーニー・サンダースが大統領選に立候補して注目を集めたことは、最終的にそれぞれ希望の首相と大統領の座を獲得できなかったにもかかわらず、親パレスチナ連帯運動が今や政治エリートのメンバーを含んでいることを示している。これには、アレクサンドリア・オカシオ=コルテス、イルハン・オマル、ラシダ・トレイブの下院議員当選も含まれる。
結論 国際的正当性を求める闘い
過去50年ほどの連帯運動を振り返ってみると、パレスチナの自由と解放のための闘いに対する連帯運動の大きな貢献がよくわかる。それを十分に理解するためには、国際法と国際正統性の違いを説明する必要がある。国際法とは、明確な国際条約や国連決議の集合であり、制裁力はないかもしれないが、法的機関によって生み出されるものである。例えば、パレスチナ自治政府は、これらの機関を説得して、現地の現実を変えるための主要な手段にしようと必死だが、効果はない。
国際的な正統性を定義するのはもっと難しい。しかし、1972年にマーティン・ライトによって提示された鋭い定義がある:
国際的正当性とは、道徳と法の境界線上にある、とらえどころのない曖昧な概念である。国際的正当性とは、道徳と法の境界線上にある、とらえどころのない曖昧な概念である。誰に受け入れられるか?アパルトヘイト下の南アフリカは、正統性が疑わしい国家の好例である。南アフリカの体制が合法であることに疑問の余地はない。南アフリカの体制が合法であることに疑問の余地はない。しかし、それは国際世論の総意によって非難され、国連とアフリカ統一機構の多くの決議によって表明され、英連邦から南アフリカを脱退させた……南アフリカは亡国である。南アフリカが非常に繁栄した亡国であることは、すぐには理解できない。
この区別が重要なのは、歴史的な背景と、国際法をイスラエルのイデオロギーに挑戦する役立たずの道具に変え、その結果、歴史的パレスチナ全域でパレスチナ人に対する全体的な政策を永続させることを可能にしている上意下達のアプローチのためである。このような状況は、シオニスト・プロジェクトとイスラエルを世界的に擁護する主な人々、すなわちダイエット・シオニスト、あるいはリベラル・シオニストと呼べるグループに好都合である。国際法が体制のイデオロギー的本質に関与することに消極的であるということは、他にどのような異議申し立てがなされようとも、シオニストの理論と実践が国際的な陪審の議題となることはないということである。
国際的正統性とは、正式な機関を持たず、公式な条約にも加盟しない。多くの点で、市民社会の行為であるボイコットと政府の行為である制裁を区別するものであり、BDSが最終的に達成しようとしているものである。南アフリカの場合、1972年のアパルトヘイト政権に対して世界はこうした定義を必要としていた。なぜなら、西側諸国の政府は南アフリカに対する制裁を適用することによって国際市民社会のボイコットを支援することを拒否していたからである(これが起こったのは数年後のことである)。今、イスラエルを南アフリカに置き換えてみれば、イスラエルをめぐる国際市民社会の立場の潜在的な有効性を把握することができ、国際的正当性の完全な意味をはるかに曖昧なものにすることができる。南アフリカにおけるアパルトヘイトとの闘いには類似点があり、当時は、公的な法廷が正式な国際法上の法廷の代わりを務めていた。パレスチナの場合、そのような法廷のひとつであるラッセル法廷は、有名な人権活動家や弁護士を集め、イスラエルの市民権と人権侵害について公開裁判を行った54。
イスラエルの反応から判断すると、現時点では、国際法の裁定をイスラエルに押し付けようとする試みよりも、正当性をめぐる闘争の方が、よほど彼らを悩ませているようだ。前述したように、イスラエルは「イスラエルの委縮」と呼ばれる事態に対抗するため、特別チームを立ち上げ、最終的には戦略省という省庁全体を設置した。
これはまさに、これまでの国際連帯運動の最大の成功である。正義、真実、解放の権利の主張は、パレスチナ人が今この瞬間にどれだけ団結しているか、あるいは強大な植民地支配者とそれを支援する国際連合に対する地上での闘いでどれだけ成功を収めているかによって左右されるべきではない。現地での団結と成功こそが、植民地化された人々を前進させ、最終的には解放する手段なのだ。彼らの権利、彼らの物語、彼らの歴史の保護を求める国際的な要求は、否定に抗い、人間的・国際的正当性の名の下に闘う重要な次元である。
私自身のささやかな役割は、イスラエルがパレスチナ人に対して犯した1948年の人道に対する罪が記憶から消されたり、歪められたりすることを許さないことであり、それは今も変わらない。大きな前進にもかかわらず、否定は広まり、イスラエルの国際的免責において重要な役割を果たし続けているからだ。この基本的な犯罪は、大統領や首相、政府、主流メディア、政治システム一般によって認められていない。イスラエルに免罪符を与える例外主義の核心である。国際連帯は、(BDSへの支援と並んで)さらに効率的な方法でその役割を果たすことができる。私の個人的な夢と希望は、この文章を書きながら具体化し始めているが、史上初の「ナクバ否定反対センター」を設立することである。ホロコースト否定に反対するセンターは何百とあり、それはそれで結構なことだが、パレスチナの闘いには少なくともナクバ否定に反対するセンターが必要だ。
パレスチナ人自身が、団結と代表権の問題を解決し、将来のビジョンと現代における解放プロジェクトをどのように考えているのかを私たち全員に示す必要がある。私たち国際連帯運動は、パレスチナ解放の日が来たとき、そして遅かれ早かれその日が来るとき、国際的な環境が地上でのパレスチナ解放にとって現在と同じように助長的で支持的なものになるよう、絶えず努力しなければならない。
53 Al Jazeera Investigative Unit, 「The Lobby Part 1: Young Friends of Israel,」 Aljazeera, January 10, 2017, last accessed October 11, 2021 www.aljazeera.com/program/investigations/2017/1/10/the-lobby-young-friends-of-israel-part-1
54 パレスチナに関するラッセル法廷、http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/を参照のこと。
55 これについては、拙著『イラン・パペイスラエルの思想』(ニューヨーク:Verso Press, 2010)295-313で詳しく論じている。
ラムジー・バルード RAMZY BAROUD ガザ地区のヌセイラット難民キャンプ生まれ。パレスチナ系アメリカ人ジャーナリスト、メディア・コンサルタント、作家、国際的コラムニスト、『パレスチナ・クロニクル』編集者。オーストラリアのカーティン工科大学マレーシアキャンパスでマス・コミュニケーションの教鞭をとる。
著書は6冊、寄稿も多い。著書に『My Father Was a Freedom Fighter(父は自由の戦士だった)』がある: Gaza’s Untold Story』、『The Last Earth』などがある: パレスチナ人の物語)などがある。
エクセター大学のパレスチナ研究ヨーロッパセンターでパレスチナ研究の哲学博士号を取得し、カリフォルニア大学サンタバーバラ校のオルファレア・センターで非駐在研究員を務めた。現在、イスタンブール・ザイム大学イスラーム・グローバル問題センター(CIGA)の非居住上級研究員。
寄稿文
『私たちの解放のビジョン』の寄稿者たちは、それぞれの研究と仕事の領域において、パレスチナの闘いを前進させる方法について独自のビジョンをここに提示した。彼らの豊かな経験的洞察は、場合によっては数世代にわたる誇り高き遺産によって、よりいっそう強調されている。ここから私たちはどこへ向かうのか?
本書は、パレスチナの中央集権的なビジョンに代わるものではなく、またそうなることを意図したものでもない。その代わりに、私たちの目標はいくつかの重要なメッセージを伝えることであった。その筆頭は、パレスチナ人は自分たちのために話すことができ、また話さなければならないこと、パレスチナ人の闘争のさまざまなレベルに対する彼らの洞察は、将来の努力に役立つ貴重な活動指針になること、そしてパレスチナの政治的・文化的・歴史的言説の統一は達成可能であること、などである、 派閥主義的なパレスチナ内政治や、地域的に意図的に疎外されたパレスチナ人–公式なアラブの対イスラエル正常化を通じてであれ、国際的にイスラエルが「安全保障」と歴史的物語に不釣り合いな焦点を当てることに成功していることを通してであれ–にもかかわらず、パレスチナ人が最も基本的な人権を否定されたままであるにもかかわらず、統一されたパレスチナの政治的、文化的、歴史的言説は達成可能である。
いわゆる「パレスチナ・イスラエル紛争」、より正確には、現在進行中のイスラエルによるパレスチナ植民地プロジェクトにおいて、パレスチナの視点がいかに重要であるかを、未来のパレスチナ研究者や作家たちが理解できるようになることが、私たちの大きな望みである。パレスチナとパレスチナの人々の物語を、パレスチナの声なしに語ることはできない。時代だ。パレスチナ人が自らの物語を主張することを否定することは、倫理に反するだけでなく、非現実的でもある。
本書に寄稿した30人の知識人は、パレスチナ、アラブ世界、そして世界中で見られる、より大きなパレスチナ知識人現象の縮図にすぎないことを強調しておかなければならない。パレスチナの詩人、ラフィーフ・ジアダが彼女の代表的な詩を書いたとき、「私たちは人生を教えている: 「その意味は、象徴と具体的な体験の両方の領域に当てはまる。パレスチナの教師ハナン・アル=ホルブが2016年にグローバル・ティーチャー賞を受賞したことは、パレスチナ人がいかに苦痛から希望を引き出し、その希望を人類のために役立てることができるかを示す数多くの例のひとつである。アル=ホルブの受賞は、イスラエルの暴力によって心に傷を負ったパレスチナの子どもたちを支援したことが評価されたものだ。
さて、私たちはこれからどうすればいいのだろうか?私たちはこの本を、政党や硬直したイデオロギーに忠誠を誓うのではなく、パレスチナの人々自身に忠誠を誓う、熱心なパレスチナの知識人たちによって導かれる、パレスチナに関する前向きな対話の始まりとして使う。結局のところ、何年も前にチェ・ゲバラが言ったように、「解放者は存在しない。自らを解放するのは人民なのだ」
-ラムジー・バルード
2021年11月
寄稿者
パレスチナ系エジプト人のオーストラリア人ムスリム作家、学者、活動家、元弁護士。マッコーリー大学社会学部博士研究員。
ABDELFATTAH, Awad 「ひとつの民主国家」キャンペーン(ODSC)コーディネーター。バラッド/タジャモア党の前事務総長である。著名な政治アナリストであり、様々な国際フォーラムで講演を行っている。
ABU NIMAH, Hasan Abdul-Rahim 1935年パレスチナのバティールに生まれる。ヨルダンの国連常駐代表を務めた元大使である。
ABU SHARAR, Samaa 独立ジャーナリスト、研究者。レバノンのパレスチナ難民キャンプで若者のエンパワーメントに取り組む非政府組織Majed Abu Sharar Media Foundation(MASMF)を率いる。
アルバータ大学政治学部の客員教授であり、『パレスチナのアパルトヘイト』の編集者でもある: また、「Apartheid in Palestine: Hard Laws and Harder Experiences」と「Women’s Voices from Gaza」シリーズの編集者でもある。
イスラムと世界問題センター(CIGA)所長、イスタンブール・サバハッティン・ザイム大学公共問題教授。1986年に博士号を取得し、長年にわたり米国で終身在職の学者として教壇に立ち、いくつかの教育賞や助成金を受賞している。
AL-MARAYATI,Lailaはパレスチナ系アメリカ人の医師であり、アメリカのムスリムコミュニティで長年活動している。彼女は、パレスチナの子どもたちとその家族に保健、教育、その他の援助を提供する非営利人道団体KinderUSAの会長を務めている。
ALFARRA,Jehanはライター、マルチメディア・ジャーナリスト、プロデューサーであり、中東問題を担当し、パレスチナの政治ニュースや社会問題を専門としている。
ALI, Qassem Izzatはメディアの専門家で、テレビニュース業界の創始者であり、革新者である。
AOUDE, Ibrahim ハワイ大学マーノア校の民族学教授。アラブ研究季刊誌の編集者で、政治学の博士号を持つ。
エルサレム文化センターと女性センターの理事を務め、文化的権利と女性の権利を擁護している。
1969年と1970年にガザのUNRWAで働いた看護師であり、刺繍家でもある。2011年にパレスチナ歴史タペストリープロジェクトを設立した。
HALAWANI、Hanadiはエルサレム旧市街の著名な活動家であり、アル・アクサ・モスクのコーラン教師でもある。
東エルサレム在住の精神科医、心理療法士。ラマッラ保健省のメンタルヘルス・ユニットの責任者を務め、子供と成人のための診療所を開いている。
JARRAR, Khalida 市民社会指導者、法律家、人権活動家。パレスチナ立法評議会(PLC)のメンバーである。パレスチナの国際刑事裁判所(ICC)加盟申請で大きな役割を果たした。
エルサレムで生まれ、ビルジート大学で学び、政治的な活動を始めた。第一次インティファーダ以来、草の根運動に力を注いでいる。パレスチナ草の根反アパルトヘイト壁キャンペーン」のコーディネーターを務める。
医師、学者、作家。エクセター大学アラブ・イスラーム研究所元研究員。
MAJLUF ISSA. uarはパレスチナ出身のチリの弁護士で、2021年6月までチリのパレスチナ共同体の事務局長を務めた。
MANSOUR、ジョニーはハイファ出身の歴史家である。歴史学と政治学の講師を務める。いくつかの研究論文を発表している。
ムラド、ノラ・レスターは米国出身の反シオニスト・ユダヤ人である。作家、活動家、教育者である。フォーダム大学で国際人道学を教えている。
マヌエル・ムサラム神父はカトリック司祭、政治活動家、作家である。母国パレスチナの象徴的存在である。
アカデミー賞ノミネート、BAFTA賞受賞のパレスチナ系イギリス人映画監督であり、人権擁護者でもある。
科学者であり作家でもある。ベツレヘム大学のPalestine Institute for Biodiversity and Sustainability(PIBS)の創設者であり、ボランティア・ディレクターでもある。
作家、学者。栄誉ある2020年グリーンルーム賞最優秀執筆賞を含む複数の賞を受賞している。ビクトリア大学で博士号を取得。
1977年以来、弁護士として活躍し、人権侵害の被害者を幅広く弁護してきた。そのキャリアにおいて多くの栄誉に輝いており、最近では2013年に「ライト・ライブリフッド賞」を受賞した。
タハ、ハムダンは考古学者、独立研究者、元パレスチナ観光古代遺産省副大臣である。
タルハミ、リームはアーティストであり、歌手、女優としてパレスチナの文化芸能シーンに大きく関わっている。
ZOABI、Haneenは政治活動家で、タジャモアの国民民主議会(NDA)のメンバーである。イスラエルのクネセト(2009~2019)でパレスチナ政党を代表する初のパレスチナ人女性である。
編集者
DR.ラムジー・バルードガザ地区のヌセイラット難民キャンプ生まれ。パレスチナ系アメリカ人ジャーナリスト、メディア・コンサルタント、作家、国際的コラムニスト、『パレスチナ・クロニクル』編集者。オーストラリアのカーティン工科大学マレーシアキャンパスでマス・コミュニケーションの教鞭をとる。
著書は6冊、寄稿も多い。著書に『My Father Was a Freedom Fighter(父は自由の戦士だった)』がある: Gaza’s Untold Story』、『The Last Earth』などがある: パレスチナ人の物語)などがある。
エクセター大学のパレスチナ研究ヨーロッパセンターでパレスチナ研究の哲学博士号を取得し、カリフォルニア大学サンタバーバラ校のオルファレア・センターで非駐在研究員を務めた。現在、イスタンブール・ザイム大学イスラーム・グローバル問題センター(CIGA)の非居住上級研究員。
1954年ハイファ生まれ。1979年エルサレムのヘブライ大学卒業、1984年英国オックスフォード大学博士課程修了。1984年から2006年までハイファ大学政治学部の講師を務めたが、パレスチナの大義を支持したために退職を余儀なくされた。2000年から2006年までハイファのエミール・トゥーマ・パレスチナ研究所の所長も務めた。
2007年からは英国エクセター大学のパレスチナ研究ヨーロッパセンター所長。著書に『パレスチナの民族浄化』、ノーム・チョムスキーとの共著『パレスチナについて』など20冊がある。
製作チーム
ロマーナ・ルベオはイタリア人ライターで、パレスチナ・クロニクルの編集長を務める。彼女の記事は多くのオンライン新聞や学術誌に掲載されている。外国語と外国文学の修士号を持ち、オーディオビジュアルとジャーナリズムの翻訳を専門とする。
シンビア・フェルナンデス(SYLVIA FERNANDES)はゴア出身で、ケニアのモンバサで生まれた。もともとは初等・中等教育の教師だったが、現在はフリーランスの校正・編集者として、英語への情熱と中東政治への深い関心を結びつけている。現在はケニアのナイロビ在住。
作家、学者。権威ある2020年グリーンルーム賞最優秀執筆賞を含む複数の賞を受賞している。ビクトリア大学で「Inheriting Exile」という論文で博士号を取得した: 論文「Inheriting Exile: Transgenerational Trauma and the Palestinian Australian Identity」でビクトリア大学から博士号を取得した。
