Contents
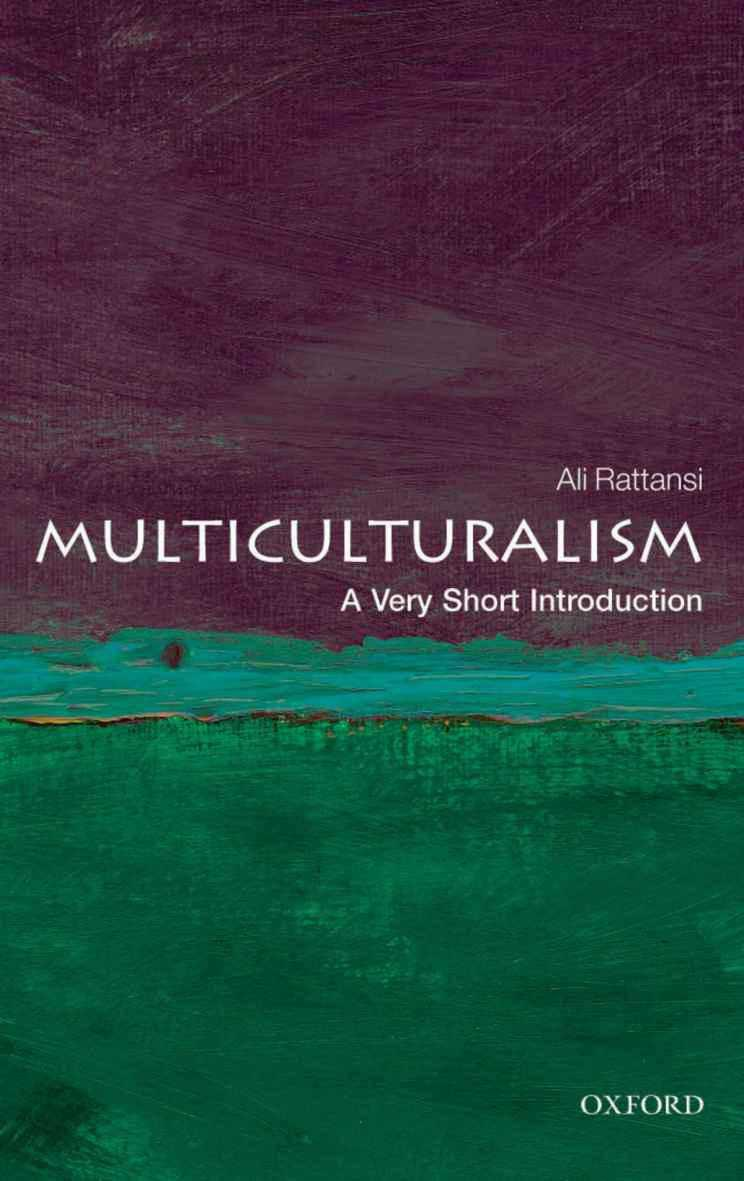
Multiculturalism: A Very Short Introduction
多文化主義とても短い紹介
VERY SHORT 序論Sは、新しいテーマについて、刺激的でわかりやすい入門書を求める人のためのものである。専門家が執筆し、World25カ国語以上で出版されている。
このシリーズは1995年に始まり、現在では歴史、哲学、宗教、科学、人文科学など幅広いトピックを扱っている。VSIライブラリーには現在、古代エジプト、インド哲学からコンセプチュアル・アート、宇宙論に至るまで、あらゆる分野のVery Short Introductionsが300冊収められており、今後も様々な分野で増え続けるだろう。
多文化主義
とても短い入門書
アリ・ラッタンシ
グレート・クラレンドン・ストリート、オックスフォードox2 6dp
私が知る中で最も成功した男である父を偲んで
目次
- 謝辞
- 図版リスト
- はじめに
- 1 多文化主義とは何か?
- 2 多文化主義は女性にとって悪いことなのか?
- 3 多文化主義はゲットーと「パラレルライフ」を生み出したか?
- 4 「統合」、階級的不平等、「地域社会の結束
- 5 国民的アイデンティティ、帰属意識、そして「ムスリム問題
- 結論新たなグローバル時代における多文化主義、インターカルチュラリズム、トランスナショナリズム
- 参考文献
- 参考文献
- 索引
謝辞
本書で紹介する考え方は、1980年代後半から長期にわたって形成されてきたものである。私の考えを形成し、明確にしてくれたすべての人々に感謝することはできない。しかし、時間を惜しみなく提供し、私と考えを共有してくれたヤスミン・アリバイ・ブラウン、フローヤ・アンティアス、アヴター・ブラ、フィル・コーエン、ジェームズ・ドナルド、アンソニー・ギデンズに特に感謝したい、 Jagdish Gundara、Stuart Hall、David Held、Tariq Modood、Maxine Molyneux、Karim Murji、Bhikhu Parekh、Ann Phillips、Ann Phoenix、Nikolas Rose、David Slater、Grahame Thompson、Nira Yuval-Davis、Sami Zubaida。シティ大学図書館のシーラ・ミュントンは貴重なサポートを提供してくれた。ショブナがいなければ、この本を書き始める勇気も、書き上げる力もなかっただろう。
図版リスト
- 1 ヴィクトリア駅に到着した西インド系移民(1956年、ロンドン) ヘイウッド・マギー/ゲッティイメージズ
- 2 亡命希望者を逮捕するギリシャの沿岸警備隊、サモス島 2009年 パトリック・ザックマン/マグナム・フォト
- 街頭でデモをする3人のフランス人イスラム教徒の女子学生 Charles Platiau/Corbis
- 4 ブラッドフォード暴動 サイモン・バーバー/グゼリアン
- 5 人と人との対話、ロッテルダム、Mixen aan de Maasプロジェクト
写真提供:Welkom in Rotterdam
はじめに
個人の選択は、いかに共同体主義的な薄皮をはがしたとしても、社会的存在としての私たちの生活に意味を与える認識、互恵性、つながりの絆を供給することはできない……他方、私たちは、理想的であるばかりでなく、実際上も、権利の担い手としての個人が、出身共同体から異議を唱え、そこから退出し、必要であれば反対する権利を拡大することなしに、個人に対する共同体文化の規範の主張を認めることはできない。
(スチュアート・ホール 2000)
異なる文化は大切にされるべきだが、基本的人権よりも優先されるのは常に間違っている。
(ヤスミン・アリバイ・ブラウン 2000)
1990年代初頭、私は『人種』『文化と差異』の中で、当時英国で実践されていた多文化主義と反人種主義の両方、特に教育分野での批判を発表した。多文化主義者たちは、民族文化を均質で、静的で核となる本質的な特徴を持つものとして単純化して考え、多文化社会を、分離したままの民族文化を持つ「サラダボウル」と考えていた。彼らはまた、料理や服装といった表面的な特徴によって定義される「他の」文化について教えることによって根絶できる不合理な偏見として、人種差別を問題視していた。反人種主義者たちは、他文化について教えても多数派文化に埋め込まれた人種差別には取り組めないと正しく指摘したが、人種差別を階級的不平等の産物として、また多文化主義者とは異なり、一種の「誤った意識」の産物として還元的に捉える傾向があった。
しかし現実的には、サッチャー政権によって多文化主義者と反人種主義者の足元が劇的に切り崩される過程にあった。1986年、教育やその他の分野でこうした政策の先駆的役割を果たしてきたグレーター・ロンドン・カウンシルが廃止され、それに伴って一部のメディアがこうした目的を嘲笑するようになった。一方、オランダでは独自の多文化主義に対する反動がすでに始まっており、フランスでは共和主義と世俗主義へのコミットメントから、文化的多元主義や複数の民族や信仰を公に認める実験において「アングロサクソン」(英米を意味する)の行き過ぎと見なされるものには、公式には常に背を向けていた。
本書では、イギリスだけでなく、可能な限りオランダやフランスなどヨーロッパの多文化主義についても論評しようと試みた。カナダ、アメリカ、オーストラリア、さらにはアジアの国々でも大きな進展が見られるが、これらについてはごく簡単にしか触れていない。本書は必然的に西ヨーロッパに焦点を当てている。
私が意図していたのは、多文化主義研究において、多かれ少なかれまったく別の2つの分野にまたがることであった。ひとつは政治理論に基づくもので、集団のアイデンティティを重視する多文化主義を、西欧の国民国家の憲法を支える自由主義における個人の権利の主要な役割とどのように調和させることができるかといった問題を論じている。もうひとつは社会科学と政策研究であり、現地におけるエスニシティやその他の集団アイデンティティの性質、民族間集団の相互作用の実際の特徴、西洋社会で拡大する文化的多様性を受け入れ、統治するために開発されたさまざまな政策に焦点を当てている。
実際には、この2つは重なり合っている。政策は、例えば言論の自由など、個人の自由を謳う法律を十分に考慮しなければならない。言論の自由の原則と、集団のアイデンティティや感受性との間の緊張や対立は、『悪魔の詩』の出版によって引き起こされたサルマン・ラシュディ論争や、オランダにおける映画監督テオ・ファン・ゴッホの殺害、デンマークのムハンマド漫画の出版などのように、しばしば深刻な火種となってきた。しかし、本書の簡潔さには厳しい限界がある。ブライアン・バリー、ウィル・キムリッカ、ビクー・パレク、チャールズ・テイラーといった、これらの問題に取り組んだ最も重要な政治哲学者たちの仕事を論じる章は割愛せざるを得なかった。しかし、個人の自由と集団のアイデンティティの認識との調和をめぐる関連する問題については、本書のさまざまな章で扱ってきた。
現時点では、2つの重要なポイントに絞ることにする。第一に、集団の権利と個人の権利の間に矛盾があるとされることについて、多くの誤解がある。例えば、シーク教徒がクラッシュヘルメットの代わりにターバンを着用することを認める排除は、集団の権利が個人の権利を凌駕するような特別扱いの一例ではない。クラッシュヘルメットの代わりにターバンを着用する権利は、個人が個人として行使するものであり、集団全体が個々のシーク教徒にターバンの着用を強制する権利はない。集団は個々のメンバーに対して何の権利も与えられていないのである。第二に、この「はじめに」で私が選んだエピグラフが示すように、伝統的な文化的慣行とされるものが、本質的な人権や、どのような民族集団の構成員であっても、その民族集団の文化的伝統とされるものに異を唱えることができるという配慮を覆すことは許されないというのが私の見解である。この問題は、第2章でジェンダーと多文化主義について論じる際に、特に中心となる。多文化主義に本格的な文化相対主義が入り込む余地はなく、実際、多文化主義者の著作を読めば、彼らの誰も、しばしば非難されるような全面的な文化相対主義を犯していないことがわかるだろう。
1980年代にイギリス、1990年代にオランダで始まった多文化主義への攻撃は、今や西欧全域に広がっている。本書の各章では、多文化主義が実際に何を意味するのかを明らかにし、多文化主義に対する不満を入手可能な証拠と照らし合わせて評価する。社会科学者による調査や政府による調査から得られた証拠と照らし合わせると、世間で議論されている多文化主義に対する非難のほとんどは、見当違いか誇張であるという結論に達した。
また、多文化主義に起因するとされる弊害の多くは、私が「三重の変遷」と呼ぶものによって実際に引き起こされたり、悪化させられたりしてきたことも明らかになってきた: イギリスのスコットランド人やウェールズ人、スペインのバスク人やカタルーニャ人など、これまで平穏だった準国家的少数民族が分離主義的な要求を出す一方で、国家がEUやグローバル機関に権力を奪われることによる国民国家の崩壊、第二次世界大戦後、経済拡大の需要を満たすために最初の移民が定住した、ヨーロッパの主要都市の製造業の中心地における脱工業化、以前は手厚かった福祉国家規定の縮小などである。脱工業化の問題についても議論はあるが、本書ではこれらの変遷について詳しく論じる余裕はない。しかし、多文化主義の物語と苦難が繰り広げられた本質的な背景として、この3つを常に念頭に置いておく必要がある。
2008年に始まった世界的な金融危機と、公共サービスの縮小や失業率の上昇に関連するその影響は、ヨーロッパと西洋にとってしばしば「後期近代」の時代と形容されるような、変化の猛烈なペースによって生み出される、ますます目まぐるしく変化する混乱の渦の中で、すでに居心地の悪い思いをしている人々の不安をさらに大きくしている。しかし、経済的不安の増大や、より一般的な社会的分断によって引き起こされる不安のあまりに多くが、移民問題に転嫁されてきた。その過程で、「多文化主義」は、西欧諸国が、移民や多文化主義政策の帰結に由来するものよりもはるかに広範な社会的・経済的変化にしばしば起源をもつ不安を注ぎ込む容器となったように見える。
しかし、これから述べる理由から、多文化主義は、現在西欧社会を特徴づけている新たな多民族性、あるいはヴェルトヴェックが言うところの「超多様性」のガバナンスにおいて、より洗練された段階である「インターカルチュラリズム」へと移行することなしには改善できない欠陥を抱えている、というのが私の主張でもある。三位一体移行と世界金融危機の中で、これらの国家は現在、第二次世界大戦終結直後の旧植民地からの移住とその後の経済拡大の結果だけでなく、破綻国家や内戦で避難民となった人々とも格闘している。また、新たな知識経済、グローバル・フローの新時代における金融部門の拡大、出生率の低下、欧州連合(EU)の拡大とソビエト連邦の崩壊による労働移動の自由化から生じる労働需要もある。
新しい、より民主的で平等主義的な異文化間ガバナンスの形態がなければ、極右の台頭は洪水となり、財政緊縮、失業率の上昇、公共サービスの大幅な削減という、私たちが今まさに迎えようとしている時代において、多民族間の礼節を重んじる機会を著しく損なうことになりかねない。本書の結論として、私は多文化主義から脱却するために必要な再考の端緒を描くことができた。必要な新政策のいくつかは、その欠点がどうであれ、最近の「地域社会の結束」や「統合」政策をきっかけに登場したイニシアティブの中で、すでに初期の形をとり始めている。新しい政策は、「社会資本」の理論から「共同体主義」の哲学に至るまで、怪しげな基盤に基づいていることが多く、また、特定しにくい「共通の価値観」や国民的アイデンティティに対する忠誠心や信奉を要求している。しかし、後述するように、これらには、ほとんどの多文化主義が要求してきたと思われる以上の、民族間の対話と交流を求める異文化主義の哲学に基づく、より適切な政策立案の新時代の種も含まれている。
同時に、私の議論でも強調しているように、民族的不利を軽減するための政策は、これまで以上に効果的になる必要がある。また、ヨーロッパの国家内における階級とジェンダーのより広範な不平等を是正し、世界的な不平等に取り組むあらゆる試みを奨励しなければならない。このような不平等は、南と東の人々を、過酷な条件下でなければ仕事や避難所を提供することをこれまで以上に嫌がる北へと追いやり続けるだろう。
第1章 多文化主義とは何か?
多文化主義をめぐる最近の一般的な議論で最もはっきりしているのは、多文化主義に関わる重要な用語があまり明確になっていないということだろう。多文化主義の定義が定まっていないことはよく知られている。また、「統合」といった代替案も曖昧なままである。そこで、まず歴史的・用語的な前置きを簡単に説明し、本書のさまざまな場面で議論に戻ることにしよう。
文化の多様性と多文化主義
「多文化主義」が公的な言説に登場したのは、オーストラリアとカナダがその支持を表明し始めた1960年代後半から1970年代初頭にかけてである。この時期にこれらの国々が「多文化」というアイデンティティを受け入れ、多文化主義への支持を表明する必要性を感じていたことは、これらの用語の一般的な意味と意義を知る重要な手がかりとなる。
この時期、オーストラリアとカナダは、「アジア化」する新たな移民を受け入れ始めていた。それまでオーストラリアは、1901年に制定された移民制限法によって白人だけの移民政策をとっていた。アジア人もユダヤ人も、同化不可能と見なされていた。1971年、「多文化」社会の構築を支援する必要性が公式に認識され、1973年には「人種」資格の完全撤廃への道が開かれた。
移民は同化を求められるのではなく、「統合」することが奨励された。これは、移民が「自国の文化」の要素を保持できるようにすることを意味し、エスニック・コミュニティ・アソシエーションは、統合の重要な手段と見なされた。
多文化主義における統合の要素を強調したが、これは多文化主義が決して分離や隔離を促すものではなかったことを強調するためである。多文化主義とは、移民や少数民族が自分たちの文化を保持したいと望むことは合理的であり、文化の多様性はそれ自体望ましいことであり、さまざまな形で国家に利益をもたらすという認識のもと、移民や少数民族が公平に統合されるような構造を作り出すことであった。また、後述するように、多文化主義の意味や効果に関する議論では無視されがちな機会均等や反差別の側面もある。
カナダでは、1960年代に英語圏とフランス語圏の関係が悪化したことから議論が始まった。バイリンガリズムとバイカルチュラリズムに関する王立委員会は、英語とフランス語を公用語とみなすよう勧告した。しかし、1969年に制定されたバイカルチュラル・バイリンガル法は、カナダにおける他のマイノリティの問題にも道を開き、王立委員会のさらなる勧告として、より広範な文化的多元主義をカナダのアイデンティティに加えることが公式の政策として確立された。これは当初、英語とフランス語のバイリンガルの枠組みの中で受け入れられたが、1988年までに多文化法が制定され、包摂の条件が拡大された。
同様に、インド、パキスタン、バングラデシュ、カリブ海諸島からの移民集団が英国に到着し、また第二次世界大戦後にフランスや西欧の他の地域で北アフリカからの移民労働者が増加したことで、移民コミュニティが永続的または半永久的な存在を確立し始めたため、「多文化」問題が公的な議題となった。特にフランスは、新しい移民を公式に認めるような政策を拒否したが、イギリスでは1966年に当時のロイ・ジェンキンス内務大臣が発表した声明が、新しい移民コミュニティをイギリスの国家文化や政治に取り込む、まさに統合するための一般的な枠組みを示した:
統合という言葉は、おそらくかなり緩やかなものだろう。私は、移民が自らの国民性や文化を失うことを意味するとは考えていない。この国には、ステレオタイプ化されたイギリス人という、誰かの見当違いのビジョンの一連のカーボンコピーのひとつとして、すべての人を共通の型にはめ込んでしまうような『るつぼ』が必要だとは思わない……したがって、私が定義する統合とは、画一化の平坦化プロセスではなく、相互寛容の雰囲気の中で、機会の平等と結びついた文化的多様性である……文明的な生活と社会的結束に対する世界的な評価を維持するためには、今日よりもはるかにその達成に近づかなければならない。
文化的多様性と機会均等の両方が強調されていることに注目してほしい
多文化主義と人種差別
ジェンキンズの文言とは裏腹に、オーストラリアやカナダだけでなく、西ヨーロッパ全土で、流入する人口に対する対応が、一般的に移民を多数派の白人集団とは人種的に異なるものとみなしていたことに注目することは重要である。多文化主義の問題は、その当初から人種差別的であった。多文化主義の起源は、ヨーロッパの植民地に住んでいた、生来的に劣った人種とみなされていた人々への対応にある。ドイツでは、ナチス時代の人種差別の悪夢から、少なくとも公式には、「外国人」(Ausländer)という観点から問題を論じる言説が広まっていた。
多文化主義をめぐるほとんどの議論、とりわけヨーロッパでは、「人種」はいわば部屋の中の象である。ポピュラーなメディアや文化において、「多文化主義」批判はしばしば、南アジア系、アフリカ系カリブ海系、北アフリカ系、トルコ系などの「有色人種移民」や「有色人種移民」に対する敵意の婉曲表現として機能するほどである。世界的な不平等が強く根付いた構造は、部屋の中の第2の象とみなすことができるだろう。西ヨーロッパへの移住の原動力となったのは、この不平等である。
第二に、人種差別のせいもあるが、多文化主義論争の起源は、こうした新しいコミュニティを受け入れ国の文化に同化させることが困難であると認識されたことにある。
「同化」は、不可能ではないにせよ、3つの理由から困難とみなされるようになった: ひとつは、人種的な独自性であり、実際には肌の色など表面的な生理的差異に関連するものであるが、それが生物学的・文化的に克服不可能な障壁を意味するように思われ、それが破られれば国民性が完全に変わってしまうこと、もうひとつは、受け入れ側の「白人」集団が「有色人種」に対して示す明らかな敵意であること、そして最後に、移民コミュニティ自身が、たとえば言語や宗教など、自分たちの文化的独自性のあらゆる側面を単純に放棄して、文化的なあらゆる点で受け入れ側の集団とどうにかして同じになろうとしないことである。
多文化主義の発展を後押ししてきた政治的・文化的傾向はもうひとつある。欧米の自由民主主義国家では、少数民族は常に一定の制限の範囲内ではあるが、独自の文化を保持する権利を有するという考え方が広まっている。そして、多文化主義をめぐる多くの議論の中心となってきたのが、まさにその限界のあり方をめぐる議論であった。後述するように、「文化的権利」という考え方は、国際的な人権アジェンダの出現に関するより大きな物語の一部である。
アメリカでは、人種差別に対するアフリカ系アメリカ人の闘いが、「ブラック・イズ・ビューティフル」というスローガンに代表される独特の文化的黒人性と自尊心を主張することによって、文化的闘いへと姿を変えた。やがて、メキシコ系アメリカ人をはじめとする「ヒスパニック」や、長い間抑圧されてきた先住民族であるアメリカン・インディアン(コロンブスがインド諸島に上陸したと思い込んでいたため、このように呼ばれるようになった)も、アメリカ人のアイデンティティを定義するようになった支配的なアングロ・ヨーロッパ系白人との混血から切り離された、独自のコミュニティとしての文化的認知を公に求めるようになった。多文化主義が公的な語彙となったのは、1990年代に入ってからである。これらの非白人民族グループが、学校や大学のカリキュラムにおいて文化的認知を求めたからである。このように、多文化主義をめぐるアメリカの議論において、人種問題は常に重要であり、時には最重要であった。
多文化主義の意味:第一近似値
1980年代から1990年代にかけて「多文化主義」が獲得した支配的な意味が、例えば『HarperCollins Dictionary of Sociology』(1991)にあるように、文化的多元主義の承認と促進に言及するものであったことは驚くべきことではない。同時に多文化主義は、主流文化に対するマイノリティの不平等な関係に焦点を当てる。
このように、人種化と同化の問題以外にも、注意すべき重要な点がある。多文化問題とは、文化的多様性と多元主義を称賛し、マジョリティとマイノリティの不平等を是正することでもある。そしてこれらは、近代国民国家内における多数派民族と少数派民族の問題でもある。
したがって多文化主義とは、第二次世界大戦後、白人以外の移民集団が生み出した新たな多民族性を管理・統治するために実施された、中央国家や地方自治体による政策を指すのが普通である。紛らわしいことに、「多文化」という用語は、多民族社会を指す記述的な意味でも使われる。しかし、本書で検討されているのは多文化主義、つまり、多文化(多民族)化が進む社会で生まれる多様性への政策的対応についての議論である。
多文化主義の意味を拡張する
「多文化主義への転回」とでも呼ぶべきものの起源を論じるにあたり、私はいくつかのタイプのマイノリティ・グループに言及してきた。彼らの存在、成長、そしてほとんどの場合における主張と要求が、近代西欧の国民国家における多文化主義の出現をもたらしたのである。これには、ドイツのトルコ人、イギリスの南アジア人、アフリカ系カリブ人などのグループや、ケベック人、フランス系カナダ人などの準国家的マイノリティと呼ばれる人々、さらにはアフリカ系アメリカ人などが含まれる。彼らは準国家的マイノリティではなく、分散した人種的集団であり、アメリカ国民国家の誕生時にはすでに存在していたため、西ヨーロッパや北米への移民とはまったく異なる起源を持つ。さらに、多文化主義への一般的な転向に関連するマイノリティ集団は他にもあり、特にニュージーランドのマオリ族、カナダのイヌイット族やファースト・ネーションズ、オーストラリアのアボリジニ、アメリカのファースト・ネーションズといった先住民族がそうである。
このように、多文化主義に関する最近の議論は、主に西欧やアメリカへの最近の移民、そしてある程度はアフリカ系アメリカ人に関するものであったが、先住民族や準州の少数民族も関係しているという事実は、多文化主義を多数派と少数派の関係に関わるものとして説明することは、その真の複雑さを反映するために精緻化されなければならないということを意味している。
重要なのは、さまざまなタイプの「エスニック・マイノリティ・グループ」の歴史と要求は、かなり多様であるということである。カナダのケベック人、イギリスのスコットランド人、ウェールズ人、スペインのカタルーニャ人、バスク人、ベルギーのフラマン人、そして前述の先住民族などの国家に属さない少数民族は、イギリスのパキスタン人やバングラデシュ人、オランダのモロッコ人、ドイツのトルコ人などの最近の移民とは異なる主張を持っている。準州の少数民族に関連して、領土自治、土地の権利、独立した法制度や教育制度などに関して行われてきた国家的解決は、西ヨーロッパ、オーストラリア、カナダで最近移民してきた少数民族を受け入れる方法とは多くの点で異なっている。
スペースの制約と、西ヨーロッパと北米の歴史がまったく異なることを考慮し、私は主に20世紀後半に西ヨーロッパに移住した移民に関する問題と議論に関心を持つことにする。旧来の宗教的・民族的集団が国民国家に組み入れられた定住の条件は、マイノリティのために異なる国の文化的・法的・制度的枠組みが作られたことを意味し、これらは比較的最近の移民の受け入れ、処遇、収容に永続的な影響を及ぼしてきた。そして、このような国家間の異なる軌跡は、多文化主義をいくぶん異なるバージョンへと導いてきた。まったく異なる多文化主義の「国家モデル」と呼ぶのは適切ではないが、ヨーロッパ各国や北米の多文化居住地には、それぞれ特徴的な制度的取り決めがある。
国際人権課題と多文化主義
多文化主義をめぐる議論において、先住民族や準国家的マイノリティの闘争が果たした役割も、多文化主義の発展に関するより大きな物語の重要性を示唆している。特にキムリッカが指摘しているように、多文化主義の起源を、第二次世界大戦終結後の人間の平等を求めるより広い闘争の中に見ることは可能である。
1948年の世界人権宣言は、1945年以前の人種的、国家的、民族的優越性・劣等性という考え方から原則的に距離を置くという新しい時代の幕開けを告げた。
この人間平等原則の真の新しさを認識すべきである。1919年、日本が国際連盟の規約に人間の平等に関する条項を導入しようとしたとき、欧米諸国はこれを即座に拒否した。これは驚くべきことではない。結局のところ、ヨーロッパ諸国は、白人を他の「人種」よりも優れているとみなす人種主義にはっきりと基づいて、アジアとアフリカの大部分で帝国を守ることに関与していたのである。
このVery Short Introductionsシリーズの人種主義に関する拙著で詳述したように、人種思想の信用失墜は1920年代から1930年代の戦間期に、特にアメリカの人類学者によって始まった。しかし、世界人権宣言は、人種差別イデオロギーを象徴的に大転換し、人種差別政策を支持する運動に対して世界的な政治的反発をもたらした。
しかし、人権と平等に同調する国際的な文化的風潮が確立されたのは、ヨーロッパの植民地の人々を含む、さまざまな被支配集団の側からの持続的な闘争の結果であった。
もちろん、1960年代以降は、西欧民主主義国家の政治・市民文化に多大な影響を与えた無数の社会運動やキャンペーン闘争の時代であった。女性運動、ゲイやレズビアンの地位向上運動、環境保護主義の高まりなど、最も顕著なものを挙げるだけでも、これらの運動は反人種主義や多文化主義と交わり、特に批評家たちが「アイデンティティ政治」の時代と呼ぶものを生み出した。文化的承認を求める主張が展開され、後述するさまざまな視点によって、富の再分配を求めるそれまでの左派やリベラルの闘争を補完したり、それらを横断してそのエネルギーを消耗させたりした。
多文化主義の多様性
多文化主義の「モデル」が国ごとに異なるという言い方は、熟慮された国ごとの差異を意味するため適切ではないが、それでも各国の多文化主義の軌跡がさまざまな理由で変化してきたことは事実である。その違いを簡単に論じる前に、一般的に多文化主義的とされる政策を列挙することで、比較の土台を作るのがよいだろう。Kymlickaとその共著者たちは、多文化主義的な政策を採用しているという意味で、各国がどの程度「多文化主義的」であるとみなされるかを特定するのに有用な目録を作成した。
このリストは、多文化主義政策には2つの基本原則が盛り込まれていることを前提に作成されている。第一に、入国基準は人種に中立であるべきであり、多文化主義国への移民は非ヨーロッパ系、非キリスト教系、そして運命的なことにイスラム系諸国からの移民が多くなっていること、第二に、移民は自らの民族的アイデンティティを保持し、表現することができるため、警察、学校、メディア、博物館、病院、福祉サービス、地方自治体などの公的機関には、こうした民族的アイデンティティを受け入れる義務があることである。これらの原則から、8つの多文化主義政策が生み出され、各国で程度の差こそあれ採用されてきた:
- 1) 中央および/または地域・自治体レベルで多文化主義を憲法、立法、または議会で承認する
- 2) 学校のカリキュラムに多文化主義を取り入れる
- 3)公共メディアやメディア免許の職務権限に少数民族の代表や感受性を含める
- 4) 服装規定の適用除外、たとえばシーク教徒がヘルメットや制帽の代わりにターバンを着用することや、日曜の取引を禁止する法律の適用除外など
- 5) 二重国籍を認める
- 6) 文化活動を支援するための民族団体への資金援助
- 7) バイリンガル教育や母語教育に資金を提供する
- 8) 不利な立場にあるグループに対するアファーマティブ・アクション
これは議論の余地のないリストではない。特に最後の項目は、雇用、住宅、バーやレストラン、その他の資源や快適さへのアクセスにおいて、「有色人種」マイノリティに対する差別をますます禁止するようになったイギリスの一連のいわゆる人種関係法のような、差別禁止法の制定と言った方が適切だろう。
とはいえ、このリストによって、各国の多文化主義政策へのコミットメントの強さを合理的に比較することができる。これに基づき、キムリカ氏と共著者らは、8つの政策のうち6つを採用しているものを「強い」多文化主義採用国、3点から5.5点(より形ばかりの政策採用と実施を示す半数)のものを「控えめな」採用国、3点未満のものを「弱い」多文化主義採用国と分類すべきだと主張している。
この分類により、以下のような評点が導き出される:
- 強い: 強:オーストラリア、カナダ
- 控えめ:ベルギー、オランダ、ニュージーランド、スウェーデン、イギリス、アメリカ
- 弱い:オーストリア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スイス
しかし、この一覧表は、新しく生まれた少数民族に対する各国の対応について、ほんのわずかしか示していない。特に、どのカテゴリーに属する国の政策でも、またカテゴリー間の政策でも、制度上の重要な違いが不明瞭であり、多文化主義のさまざまな歴史的道筋を明らかにするものではない。そして、その違いや相違の理由は重要である。後述するように、ヨーロッパの国民国家における多文化主義のさまざまなパターンの発展において重要な影響を及ぼしたのは、既存の教会と国家の関係、そして「市民権レジーム」と呼ばれるものであった。
オーストラリアとカナダで多文化主義がより広範に採用されたのは、例えば、移民国家としてのアメリカの自己概念や、イギリス、オランダ、スウェーデンといった他の国家のナショナル・ナラティブの重要な部分を構成する民族的・宗教的アイデンティティによって供給されるような、「建国神話」と呼ばれるものを彼らが追求したためであるとされている。また、カナダやオーストラリアでは、積極的な多民族・多文化主義国家という概念が、国家全体のアイデンティティとして育まれてきた。これとは対照的に、ほとんどのヨーロッパ諸国では、多文化主義はしばしば、少数民族を国家の物語の従属的な、時には非常にマイナーな部分として統合することを主な目的としてきた。これは、大都会国民国家の形成において植民地臣民と大都会との間に密接な関係があったにもかかわらず、経済的、重要な戦争、文化などにおいて植民地が果たしてきた役割は、常に大きく軽んじられてきたという帝国的遺産の一部であることは間違いない。
そして、たとえばイギリスとオランダにおける多文化主義の異なる歴史的軌跡を、20世紀後半に移民が流入する以前の歴史という文脈で検証することは、Kymlickaらが試みた等級付けのように、両者を単に「控えめな」導入国というレッテルを貼るだけでは曖昧になってしまう両者の違いを正しく理解する上で極めて重要である。
オランダ:「柱化」、二極化、統合
オランダは、以前の植民地であったインドネシアやスリナム、トルコやモロッコからやってきた新しい少数民族に、かなりの文化的自治権と文化的アイデンティティを保持するための資源を与える制度を作り上げた。2000年までに、人口の9%近くが外国生まれとなり、17%が少なくとも両親のどちらかが外国生まれであった。1980年にはすでに、移民はいずれ帰国する「ゲストワーカー」であるとの期待に反して、ほとんどの移民が定住することが明らかになり、オランダ政府は「エスニック・マイノリティ(少数民族)」と呼ばれる政策プログラムを策定した。少数民族には、独自の新聞やテレビの別チャンネルへの支援を通じて、母語と文化を保持するための資源がさらに与えられた。そうすることで、オランダは国内の異なる文化集団の統治において、使い古された国家の道を歩むことになった。19世紀以降、プロテスタント、カトリック、ユダヤ教徒、政治的傾向の異なるグループ(自由主義者と社会主義者)が、最低限の接触を保ちながら平和的に共存することを可能にした。1960年代になると、エントツィンガーが指摘するように、世俗化、特に一般的な個人化の影響により、柱主義はその妥当性を失った。しかし、その影響は教育において特に強く残っていた。最近でも、オランダの小学校の3分の1だけが国営学校であり、残りは宗教団体や特定の教育観を持っている人たちによる私立学校である。
1983年以降の新しい少数民族に対するより明確な政策は、「オランダにおける少数民族のすべての構成員が、個人としても集団としても平等な状況にあり、その発展のために十分な機会を与えられる社会の実現」、すなわち一般に「アイデンティティを保持したままの統合」として知られるようになることを目的としていた。
しかし、オランダにおける「柱状化」という特殊な歴史は、少数民族政策が他の国よりも形式的な制度的分離につながったことを意味し、少数民族には独自の学校、新聞、放送施設、文化協会を発展させるためのより大きな自由と資源が与えられた。
オランダ人は自分たちの政策を「多文化」と呼ぶことはほとんどなかった。このことは、著名な学者であるハン・エンチンガーとの私的な交流でも確認できた。1980年代に入り、新しい少数民族に対する多元主義がより明確に奨励されるようになっても、その政策は「少数民族」政策と呼ばれていた。このような政策が「多文化主義」と呼ばれるようになったのは、後になってからであり、また多くの場合オランダ国外からであった。皮肉なことに、コンソシアシオン民主主義やピラー化の歴史に大きな影響を受けたオランダの多文化主義は、ヨーロッパの多文化主義の中で唯一、民族間の分離を助長していると真に問えるものである。
オランダの少数民族政策に対する1990年代の反発の形は、他のヨーロッパ諸国における反発の形を予見させるものであった。全体として、この政策は少数民族を経済的にも文化的にも統合することに失敗していると批判された。オランダ語の習熟度が不十分で、オランダ社会になじみがないことが、特に強い障害になっていると考えられていた。その結果、新移民は新たな言語・市民統合コースの受講を義務づけられたが、その条件は新世紀に入ってより厳しくなり、移民は自費でコースを受講することを義務づけられ、統合の責任はより強く移民自身に転嫁されることになった。しかし同時に、オランダが移民の国であり、多文化社会であることが公式に認識されるようになった。
PrinsとSaharsoが指摘したように、批評家たちはまた、時宜を得た「新しい現実主義」とみなされるようになったものを始めた。これは、言論の自由と世俗主義を原則とする西欧のリベラリズムと、特にイスラムのマイノリティ文化の抑圧性との間に絶対的な差異があるとする観点で組み立てられていた。これは、オランダ国外の出来事、特にイギリスのサルマン・ラシュディ事件に影響された面もある。この二極化は、少数民族文化に対する寛容さがオランダ社会の主流から少数民族を引き離し、彼らの福祉依存度を高めたという非難と結びついていた。
少数民族政策に対する反発は、他の地域と同様、9.11以降に強まった。オランダでは当初、ピム・フォートゥインのリーフバール・ネダーランド党が台頭し、福祉国家、欧州統合、イスラム教、リベラルな寛容、教会のリベラリズム、その他の移民や亡命希望者の絶え間ない到着に対する彼の攻撃が、特別な推進力を与えた。2004年11月、映画監督のテオ・ファン・ゴッホがイスラム教徒によって暗殺され(これについては後述)、彼の共同ドキュメンタリー作家であり国会議員でもあるアヤーン・ヒルシ・アリ(自身もイスラム移民であり、イスラム教を激しく批判している)が脅迫された。
2007年以降、反移民・反イスラムのレトリックの激しさはトーンダウンし、亡命希望者に対してはより思いやりのある政策がとられるようになった。オランダが欧州理事会やヒューマン・ライツ・ウォッチから亡命希望者や移民の権利侵害を非難されたことが影響しているのは間違いない。しかし、反イスラムを標榜する自由党の台頭は、オランダ政治にさらなる不安定化をもたらしている。
「イギリス人種」、「本質主義」、認識の政治的変化
イギリスの場合、1945年以降、旧植民地からの移民(1960年代まで植民地であった国の多く)に対して、植民地で「原住民」であったときと同じような扱いをしたという、よく言われる略史がある。つまり、ファヴェルが言うように、:
イギリスは、原住民をそのままにしておき、原住民の文化に見られるような……しばしば改変された……制度を通じて、彼らを文明化[中略]することによって統治したのである……イギリスは、その帝国を、沈むことのない太陽の下で、世界のあらゆる文化が栄えることのできる、一般的なイギリス文明の支配地と見なしていた。
しかし、より懐疑的な論者たちは、イギリスがインドやアフリカを征服する際に分割統治政策について多くを学び、植民地住民を服従させるために現地の指導者を共闘させることの利点を学び、戦後復興の労働力を増強するために輸入した植民地移民や植民地後の移民を家畜化したとも付け加えている。さらに、大英帝国はイギリスを「母なる国」とする観念も育んできた。この観念は、特に多くの西インド諸島の人々によって素朴に信じられており、彼らは1948年にSSウィンドラッシュ号に乗船したのを皮切りに、特に衰退産業における非熟練職を埋めるために他の船にも乗船した。
イギリスが海外の子供たちを歓迎する母であるという考え方は、1948年に制定された国籍法によって、植民地とオーストラリア、ニュージーランド、カナダの白人自治領の出身者全員に市民権と自由な入国が認められたことで、裏付けられたように思われた。
しかし、『人種主義』でも詳述したように、すべてが順調だったわけではない: しかし、『Racism: A Very Short Introduction(人種主義:ごく短い入門書)』でも詳述したように、表面上はすべてがそうであったわけではない。市民権と自由な入国を保証した1948年の国籍法は、実際には、ドミニオンからの白人が好きなようにやってきて定住したり、行き来したりできるようにするために制定されたものだったことが、今では公文書からわかっている。この機会を利用するのが、西インド諸島、インド、パキスタン出身の「有色人種」であるとは、ほとんど想像もつかなかった。イギリス労働党政府は、白人のポーランド人やその他の東ヨーロッパからの避難民を採用することが望ましい政策であったため、SSウィンドラッシュ号の出航を阻止しようとした。この船が出航すると、植民地局の公務員は西インド諸島とインドに派遣され、これ以上の移住を阻止し、移住希望者にイギリスには仕事がないと説得するためにあらゆる試みがなされた。
しかし、成長を続ける国民保健サービスや絶望的なロンドン交通局は、すぐに西インド諸島やインドで募集活動を開始した。北部、ミッドランド、ロンドンの製造業の熱心な雇用主も移民労働者を引き抜き、雇用機会に関するニュースが西インド諸島、インド、パキスタンに届くにつれて、「連鎖的な」移民が発生した。このような植民地時代や植民地時代後のオランダやフランスへの移民と同様、熟練労働者でさえ、不熟練で、汚く、危険な仕事、夜勤を伴う仕事に就かざるを得なかった。そして「有色人種」移民は、貧しい地域に安い住宅を見つけた。彼らの選択は、収入や仕送り願望によって制約されただけでなく、民間の家主や公的機関による直接的な差別によっても制約された。
- 1. 1956年、ロンドンのヴィクトリア駅に到着した西インド系移民。
イギリスでは、「colored(有色人種)」や「black(黒人)」がよく使われ、「wog(変態)」などのより損傷的な中傷は言うに及ばず、ヨーロッパの他の地域と比べて、新しいマイノリティが支配する語彙や態度が、より露骨に人種化されていることを示すものである。オランダは常に少数民族政策をとってきたが、イギリスは「人種関係」という言葉で問題を組み立ててきた。ローズによる1969年の重要な報告書は、『Colour and Citizenship(色彩と市民権)』と題された: イギリスの人種関係に関する報告書である。「多民族」と「多文化」は同義語として使われ続けている。
しかし、このような公的言説の人種化は、「人種」という完全に信用されなくなった考え方に正当性を与え、生来の白人優位性という人種イデオロギーのお荷物を水面下にとどまらせるという不幸な効果をもたらす。最も重要なもののひとつは、1976年に制定された人種関係法で、意図的でない間接的な差別は改革と救済が必要であると認識された。もちろん、人種が実際には存在しないことを考えれば、反人種主義法は「人種集団」をどのように定義するかという難しいジレンマに直面している。アメリカの公民権闘争の影響を受けて、イギリスの反人種主義活動家たちは、雇用や公共サービスにおける差別と闘う共同闘争に南アジア人とアフリカ系カリブ人の両方を団結させるために、人種を反映した「黒人」というカテゴリーを容易に採用したが、この戦略は、アジア人が無数のエスニック・アソシエーションを発展させ、彼らにとってより具体的な関心事である移民やサービス提供をめぐる問題に取り組むにつれて、やがて崩壊したことは注目に値する。
長い間議論されてきた「有色人種」の移民を制限する計画は、1962年以降、英連邦移民法と国籍・市民権法によって最終的に実施された。これにより、「有色人種」のポストコロニアルは、オーストラリア、ニュージーランド、カナダのドミニオンの白人とは基本的に区別された。1981年の国籍法は、イウス・ソリ(非市民の両親から英国で生まれた子供に自動的に市民権を与えること)の慣行を廃止した点でも重要であった。
イギリスの多文化主義は常に、すでに国内にいる移民の「統合」と、さらなる「有色人種」の移民に対する厳格な制限という、自意識過剰なまでに二面性のあるアプローチをとってきた。
イギリス人であることが白人の人種的意味合いを持つということは、すでに多文化主義に敵対的な主流メディアや、一般的に多文化主義的な取り組みに同情的な中道左派の政治家たちによってさえも、激しく論じられてきた。このことは 2000年に発表された『多民族国家イギリス』に関するパレック・レポートが、まさにこのような示唆を与えたことで、世間が大騒ぎになったことで明らかになった。しかし、この洞察には重要な真実がある。イギリスの文化的ヘゲモニーのもとで、イギリス人、スコットランド人、ウェールズ人、北アイルランド人を束ねるイギリスの多国籍国家は、白人以外の国民に「イギリス人」、「スコットランド人」、「ウェールズ人」、「アイルランド人」の地位を与えることが常に困難であることに気づいている。イギリス系アジア人やイギリス系アフリカ系カリブ人は、褐色や黒色の肌の人が日常的に直面する質問によって、この非受容を痛感させられている。「パキ」や「ニガー」というアイデンティティは、アジアやアフリカ出身の人々による真の帰属の主張を定期的かつ無作法に上書きする。「多民族」と「多文化」の混同は、イギリスでは移民や移住への反対がしばしば「多文化主義」への反対を通して表現されることを意味する。
学校や地方自治体によるサービス提供における多文化主義的・反人種主義的な取り組み、特に少数民族のためのコミュニティ団体の設立(多くは少数民族が全額または一部資金を提供し、地方自治体が同情的な建物を提供)は、重要な文化的変革が根付き始めていることを示唆し始めた。全国的には、西インド系住民の学校での成績不振を調査したランプトン報告書から始まったものが、1982年のスワン報告書となり、すべての人に多文化教育を実施するよう勧告した。1980年代にロンドンとミッドランドで発生した黒人の若者を巻き込んだ都市障害によって、黒人の都市における不利な状況、学業不振、失業が社会的な議題として正面から取り上げられるようになった。特に、ロンドンのブリクストン障害に関するスカーマン報告書では、黒人の若者の不満や怒りの原因は、警察などの組織的な人種差別ではなく、一般的な不利な状況や不平等にあるとされていた。
1979年に選出されたサッチャー政権下では、多文化共生の本格的な進展への期待が大きな打撃を受けた。スワン報告の勧告は棚上げされた。白人のイギリス史とキリスト教精神に重点を置いたナショナル・カリキュラムが押しつけられた。特にロンドンで多文化主義に強い公約を掲げ、通常左派の指導者を擁する労働党支配の地方自治体に対する中央政府とメディアの度重なる攻撃は、「政治的正しさ」を押し付けようとする非常識な提案の代名詞として、「ルーニー・レフト・カウンシル」という言葉を国民意識に定着させた。メディア研究者が後に指摘したように、タブロイド紙は、「黒いゴミ箱のライナー」という言葉や子供の童謡「バーバァ黒い羊」を禁止する提案に関するような話さえ捏造した。
象徴的なのは、サッチャー政権が1986年に、ケン・リビングストン率いる左派のグレーター・ロンドン・カウンシル(GLC)を廃止したことである。GLCは、特に教育における平等を促進するための急進的なアジェンダの中心に、反人種主義の理念を正式に据えており、フェミニズムや、階級的不平等に関するより戦闘的な平等主義に基づくイニシアティブと連携していた。
GLCのより急進的な反人種主義もまた、リベラル派を疎外し始めた。自称「反人種主義者」と、彼らから「多文化主義者」と揶揄される人々との間に分裂が生まれ、特に学校への介入に関する見解の対立が顕著であった。反人種主義者たちは、しばしば人種関係研究所(Institute of Race Relations)と同一視され、「他の文化」について教えるというリベラルな多文化主義者の政策が、人種差別的な態度や慣行に対して効果的に直接的な挑戦をしかけることができるのか疑問を呈し、少数派の文化についての知識は多数派の文化における人種差別の問題に対処するものではないと指摘した。いずれにせよ、批評家たちが主張したように、マイノリティ文化についての教育は陳腐で表面的なものであり、白人の子どもたちにインドや西インドの料理や音楽、服装に触れさせることに重点を置いたもので、これは「サリー、サモサ、スチールドラム」症候群と呼ばれるようになった。これは反人種差別主義者たちには、単なる陽動活動とみなされた。
さらに、こうした多文化主義導入の初期の試みに対する批判者たちが指摘したように、多文化主義は受け入れがたいレベルの「本質主義」に支えられていた。
多文化主義を学ぶ者の多くは、文化的本質主義が多文化主義に関する建設的な議論を妨げる最大の障害のひとつであり、同時に多文化主義的な政策の創出と実施を妨げるものであることを認識するようになった。つまり、少数民族の文化を単純化し、少数民族の文化は少数の不変の重要な特徴を持ち、堅く縛られた存在であるとみなす傾向があった。反人種主義者やその他の批評家たちがこの欠点を指摘したのはまったく正しかった。他方、より同化主義的な視点から主張する保守的な批評家たちは、移民が同化されるべきであるとされるイギリスらしさについて、本質主義的なバージョンで活動していた。
国家レベルでは、多文化主義や反人種主義のイニシアチブは、英国で保守党が政権を握っていた1990年代を通じて反故にされ続けた。ほんの一例を挙げれば、1997年1月、ジョン・メージャー政権は、欧州反人種主義年(European Year Against Racism)の発足を記念して、欧州連合(EU)が「外国人嫌悪と人種主義に関する欧州監視センター(European Monitoring Centre on Xenophobia and Racism)」を設置する計画に拒否権を発動した。このような問題に進展が見られたのは、同年末に労働党政権が誕生してからである。この新政権によって、イギリスは欧州で合意された人権法制を持つことができ、黒人10代のスティーブン・ローレンス殺害事件に関する調査が行われ、ロンドン警視庁内に根深く残る人種差別の文化や慣行が暴露された。
しかし、多くの地方レベルでは状況は異なっていた。イングランド北部の多くの都市が保守党時代に多文化主義にほとんど手をつけなかったが、この怠慢は 2001年の広範な都市障害をきっかけに、間もなくはっきりと露呈することになった。一方、レスターのような都市は、現在ではこの種のモデルとして称賛されるようになった、学校やコミュニティへの幅広い施策に静かに投資を続けた。ロンドンの多くの行政区でも、多言語によるリーフレットの印刷や、医療・福祉サービスの職員に対する「人種認識」または「多様性」と呼ばれる研修の継続など、多文化対策が続けられた。特にロンドン、バーミンガム、リーズでは、労働党が支配する地方自治体の一部が、選挙でのマイノリティの票を確保するために、マイノリティに地域資源を提供し、マイノリティが選挙での影響力を自覚し、それを利用していたことを示唆する証拠がある。これはまた、コミュニティ内の分裂をより強固なものにし、さまざまな理由で「コミュニティのリーダー」として受け入れられるようになった人々に、過剰な後援の権限を与えることにもなった。マリクやハサンのようなイギリスの多文化主義批判者たちは、民族的不平等やより広範な不平等を是正しようとする真の闘いから目をそらすものとして、多文化主義全体を貶めようとして、この不均等なプロセスを強調してきた。しかし、民族的不利に確実に取り組み、1992年にカナダの著名な哲学者チャールズ・テイラーが「認識の政治学」と呼んだような、盛んな地域協会やその他の形態を通じた少数民族の統合を実現しようとする、ばらつきはあるものの本物の取り組みがあったことも明らかである。
多くの急進的な反人種主義者や一般的な平等主義者の本質主義に対する疑念は、多文化主義を確立しようとする動きが、フェミニズム、同性愛者の権利、動物の権利、環境保護主義といった他の「新しい社会運動」の発展とともに、階級的不平等を是正する「真の」闘いから注意やエネルギーをそらす「アイデンティティ政治」の形態をもたらしたという批判(おそらくアメリカの作家トッド・ギトリンによって最も雄弁に表現された)としばしば結びついていた。多文化主義や反人種主義は、主として「文化的承認」をめぐる闘争であり、物質的資源の再分配のために闘うという、より重要な必要性を損なったり、横切ったりするものであるという、もう一人のアメリカ人、ナンシー・フレイザーによる告発が最も有名であるが、この告発は、マリクのようなコメンテーターによってイギリスでも反響を呼んだ。どちらの批判も誤解を招くものだった。ギトリン型の批評は、階級闘争でさえも社会的アイデンティティに関わるものであることを理解していなかっただけでなく、以前はジェンダー、セクシュアリティ、エスニシティといった不平等を犠牲にして階級を強調しすぎていたこと、そしてこれらは些細な副次的問題ではなく、早急な是正が必要であり、その過程で民主主義の深化と一般的により平等主義的な社会関係を生み出すものであることを理解していなかった。一方、多くの論者(おそらくパレックが最も端的に指摘している)が指摘しているように、再分配と承認は対立するものではなく、本質的に絡み合うものであり、経済的平等の拡大と文化的表現と多様性の拡大という全体的な目標を強化する上で互いに必要なものである。
- 1990年代初頭に私がエッセイで指摘したように、自称イギリスの反人種主義者たちもまた、人種的不平等や人種差別をさまざまな形で階級に還元しすぎることに依存していた。つまり、多文化主義者の本質主義に対する彼らの批判はもっともだが、反人種主義陣営と多文化主義陣営の間に生じた有害な分断を解消し、より洗練された戦略をとるためには、彼らの階級還元主義からの脱却も必要だったのである。私はまた、マスキュリニティーを含むジェンダーの問題も、フェミニストの懸念を取り入れることで対処する必要があると主張した。この批評の一部は、1989年にマンチェスターのバーネージ高校で起きたアジア系男子生徒殺害事件に関する調査報告書に伏線としてあった。多文化主義は、民族的な社会経済的不利や、国家の自己同一性からの文化的排除と闘う試みというよりは、むしろ白人を犠牲にして黒人やアジア人を優遇するものとみなされたからである。
- 2001年にイングランド北部の都市で発生した広範な暴力事件が分水嶺となり、1997年に初当選した労働党の歴代政権に大きな影響を与えた。この騒乱は、多文化主義と、少数民族が「並行生活」を送ることを可能にする多文化主義の影響とされるもののせいだと広く非難された。
先に述べたオランダの大転換と多くの点で類似した新しい統合主義が、イギリスではますます定着していった。多文化主義の対極にあるとされる「地域社会の結束」の新時代が到来したのである。これについては第4章で詳述する。
現在のところ、オランダでもイギリスでも、発展した多文化主義の形態は、多数派や少数派からの真の公開討論や関与がほとんどない、非常に現実的でトップダウン的なものであった。ヤスミン・アリバイ=ブラウンの皮肉な冗談にはかなりの真実がある:
白人のイギリス人は、戦後の変化に備えさせなかった政治的エリートたちによって歴史的に失敗した。イギリスの人々は、自分たちが支配する野蛮人を文明化するために神から与えられた責任を持つ帝国の主人であると教えられたかと思えば、次の瞬間には黒人やアジア人が職場の食堂で対等に扱われることを要求していた。白人のイギリス人は、黒人やアジア人の移民は脅威だと言われたが、同時に、すでにここにいる人々を対等に扱うよう指示された。
フランス:世俗主義、移民、事実上の多文化主義
アメリカやイギリスに代表されると思われる、少数民族を公的に認め、少数民族文化の繁栄に尽力し、文化的多様性と多民族性を一般的に祝福するという、奇妙に誤った名前の「アングロサクソン」的アプローチに対して、フランス国家とその地方自治体の公的な顔は、断固とした敵意を持っている。
フランスのアプローチは、特に世俗主義の概念に影響を受けている。フランスの世俗主義、すなわちライシテ(laïcité)は、正式な政教分離を伴うもので、1905年に制定された有名な分離法で重要な成文化がなされた。この分離法では、宗教的礼拝の自由は保証されたが、公共モニュメントに宗教的な「標識や紋章」を設置することは禁止された。フランスのラシテは、他の世俗主義と同様、常にさまざまな解釈や制度的表現に開かれてきた。フェッツァーとソーパーは、異なる時代、異なる国家部門、聖職者、教育者、政治家の間で支持されてきた「厳格な」バージョンと「ソフトな」バージョンを区別している。厳格版では、教職員組合、フェミニスト、「共和党左派」が支持しており、公の場で祈ること、学校の食堂で特定の食べ物を食べることを拒否すること、宗教的な衣服やアクセサリーを身につけることは、すべてライシテの侵害とみなされる。「多文化左派」の人々や人権活動家、多くのキリスト教、ユダヤ教、イスラム教の指導者の間で人気のある、よりソフトなバージョンは、宗教的・信仰的学校への国家助成を支持し、宗教間の対話を奨励し、宗教的多元主義を尊重する限り、生徒が学校で宗教的アイデンティティを表現する自由を提唱している。彼らはまた、厳格なライシテは国際法や人権規約に違反すると主張している。
近年、ライシテのさまざまなバージョンが、次章で詳述するイスラム教徒のヘッドスカーフ(ヒワクチン)論争に登場している。
フランスは第二次世界大戦終結までの間、ポーランド、イタリア、スペイン、ポルトガルといった他のヨーロッパ諸国からの移民を大量に受け入れ、また実際に奨励した。これらの移民の波には、1945年以降に北アフリカの旧フランス植民地から始まった流れとは異なる2つの特徴があった。第一に、ヨーロッパからの移民は人種差別を受けていなかったため、同化の問題を引き起こすとは見なされなかった。このため、フランスは自らを、移民が自国のアイデンティティに関与しない国であるとみなし続けることができた。第二に、共産党とその労働組合は、移民の組織化と統合に重要な役割を果たし、そうすることによって、第二次世界大戦後もかなりの期間存続した独立した民族集団と民族政治機構の形成を促した。
しかし、マグレブの植民地からの非ヨーロッパ的、非キリスト教的移民は、人種的に他者として扱われ、多かれ少なかれ同化できなかった。1969年の時点で、経済社会理事会のためのカルベス報告書は、国家はマグレブからの労働者を、特定の労働力需要に関連する「一時的」労働者としてのみ扱い、彼らの入国は、出身国との正式な協力を伴うプロセスによって管理されるべきであると勧告していた。また、それまで「連帯の伝統」に基づいてヨーロッパからの移民を扱ってきた共産党支配下の自治体は、新しい移民を一時的な居住者とみなし、帰国を促さなければならないと考えた。ハーグリーブスやシェインらが指摘しているように、これは、北アフリカ出身者の住宅や学校における割当を設定する慣行にまで及んでいた。こうして、シェインが言うように、共産党は移民を集団として扱い続けたが、今度は「排他的なやり方で」であった。「移民」という言葉は、もっぱら非白人に適用された。アラビア語の授業は、出身国との協定によって学校で組織された。そして1974年6月、すべての非ヨーロッパ共同体からの移民が停止されたが、英国の制限措置と同様、家族の統合は認められた。
移民に対する敵意は、1980年代に左派が国家を民族認識と動員に関与させようとしたことによって緩和された。しかし、一般的には共和主義的なモデルが維持され、その結果、国勢調査などで少数民族を公式に認めないという政策も継続された。
マグレブからの移民の大半はイスラム教徒であり、彼らは二重のハンディを背負っていることに気づいた。フランスは彼らを人種差別し、宗教的アイデンティティのあからさまな表現に両義的で敵対的な強い伝統を持っていた。
実際には、フランス国家は事実上の「多文化主義」を実践してきた。1981年の法律により、北アフリカからの移民がヨーロッパからの移民と同じ系統の民族団体を作ることを妨げていた制限が撤廃された。このような団体は急増し、1980年代末には少なくとも3,000に達し、労働組合、地方自治体、政党との仲介役を果たした。少なくとも1,000はあからさまにイスラム的であったが、SOS-人種差別のような、より広範な組織もあった。オランダやイギリスなどのように、移民が定住を余儀なくされ、1980年代から1990年代にかけて移民の若者たちが巻き込まれた一連の事件が発生した貧困都市部にも、国は教育優先地区(ZEP)を設置した。
普遍主義と多文化主義への反対という公的なレトリックと国家の実際の実践との間の矛盾は、1990年にムスリム団体の代表者に「フランスにおけるイスラムの将来に関する熟議会議」の結成を呼びかけたことほど明確に示されているところはない。その後、政府は外国からの影響を排除したフランスのイスラムを作り上げるため、イマームの養成機関に資金を提供してきた。2003年には、全国を代表する中央イスラム評議会(Conseil Français du Culte Musulman)が設立された。
ヒジャーブをめぐる論争が続いていることは、フランスの公共文化において、民族性や公共宗教性に対する現実的な譲歩と、ジャコバン共和主義の伝統を維持したいという願望との間に、持続的な緊張関係があることを示している。過激な国際イスラムの台頭、失業や強引な取り締まりに抗議して、北アフリカからの移民の子孫(ほとんどがイスラム教徒)を巻き込んだ21世紀の広範な都市障害(詳細は後述)、盛んなエスニック・アソシエーションとの連携の必要性など、すべてが事実上の多文化主義をさまざまな形で存続させている。
左右両派の政府が、フランスにとって最善の道は、文化的差異を認めることとフランス共和主義の伝統を結びつける方法を見つけることだという結論に達したことは明らかである。しかし、その妥協案には、国勢調査で民族に関する質問をすることはまだ含まれていない。少数民族の実際の数は、いまだに情報に基づく推測の域を出ない。これが社会政策の有効な根拠となるかどうかは、依然としてフランス国民生活の分裂の原因となっている。
2010年11月、フランス国家統計局は、移民を親に持つフランス国民とフランス人を親に持つフランス国民との間の雇用形態の相違に関する初の公式数字を発表した。マグレブ出身の両親を持つフランス人男性の就業率は65%であったのに対し、フランス人の両親を持つフランス人男性の就業率は86%であった。統計局は、この差には差別が大きく影響している可能性があると認めている。同じく重要な動きとして、サルコジ大統領は移民・国籍省の廃止を発表し、それが「緊張と誤解」を招いたことを認めた。同省の設置は、移民に汚名を着せ、外国人を親に持つ国民が国家にとって脅威であるかのように示唆したことで、歴史家やその他の知識人、左派から批判を浴びていた。この動きは、すべての公共の場でのベールの着用を禁止する法律が可決された直後のことだった。
ドイツ:「民族」国家は市民権の要求と折り合いをつける
ドイツは19世紀初頭から、さらにはナチス時代の強権的なヴォルク・ナショナリズムから、正式な市民権という概念と、ドイツ系であることが証明された者だけが国家に属することができるという、より一般的な文化的感覚を受け継いできた。1950年代から1970年代初頭にかけて、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、トルコ、ユーゴスラビアから何百万人もの外国人労働者がドイツにやってきたが、市民権政策は厳格な血統主義(ius sanguinis)であった。このため、世界中から集まった何百万人もの「ドイツ民族」には自動的に市民権が与えられたが、外国人労働者には市民権を得る道がなく、ドイツは、外国人労働者を経済の要請に応じて行き来させる「ゲスト・ワーカー」政策で悪名高くなった。1973年に1400万人いた「ゲスト労働者」のうち、約1100万人が石油危機と不況のあおりを受けて去った。しかし、300万人近くのトルコ人労働者は残留し、ドイツと国際裁判所の支援を受けて、家族を呼び寄せることができた。現在、ドイツには人口の9%に当たる約750万人の外国出身者が住んでおり、1,400万人に達するという推計もある。
ドイツは移民の国ではないという主張を捨てなければならないという遅まきながらの認識から、1990年代に市民権法の暫定的な改正が始まった。より根本的な変化は 2000年の市民権法と2005年の移民法によってもたらされた。
このような強力な民族的自意識を持つ国において、多文化主義が公式の支持を得たことはなく、大衆の支持を得たこともないのは当然である。ドイツ系トルコ人はしばしば多文化主義への一層の前進と多様性の賛美を求めてきたが、当初は同調していた緑の党も、移民と多様性の利点を主張し続けるものの、この考えには背を向けているようだ。2010年10月、ドイツのアンゲラ・メルケル首相は、多文化主義は「完全に失敗した」と宣言した。多文化主義政策がほとんど試されていないことを考えると、これは皮肉なことである。
現地では、特に移民の多いフランクフルトやシュトゥットガルトのような都市では、地域の状況に応じて多くの譲歩がなされている。フランクフルトには1989年以来、多文化共生局がある。同事務所は、地方自治体における差別撤廃の擁護者としての役割を果たし、寛容と多様性の受容を求めるキャンペーンを展開し、調停や紛争解決サービスを提供している。州レベルでは、移民出身の子供たちの教育成績を向上させ、特にドイツ語の習得を促進するための措置がとられてきた。マイノリティの母語教育は、教育制度上、まだわずかな事業である。憲法で信教の自由が保障され、連邦制が敷かれているため、政策にある程度の幅があるが、モスクの建設やイスラム教徒の女性のスカーフ着用は、依然として敵意や反対を引き起こしている。ドイツ人と外国籍を持つ人との結婚が増加し、1960年には4%であったのに対し 2000年には16%に達したことを、カレン・シェーンヴェルダーのような論者は、文化的多様性がボトムアップで受け入れられるようになったことの、一般的に希望に満ちた兆候として受け止めている。
ドイツでは「インターカルチュラリズム(異文化間主義)」という考え方が定着しており、多文化主義以上に、マイノリティとマジョリティの交流や対話を促進する試みがなされている。これについては、本書の結びで詳しく述べることにしよう。
オーストリア、デンマーク、スウェーデン、イタリア、スペインに関する比較資料を提供するスペースはここにはない。VertovecとWessendorfの著作『The Multiculturalism Backlash』は、これらの国々に関する情報を提供する上で特に有用である。
結論
20世紀後半の西ヨーロッパにおける移民と多文化主義に関する十分な情報に基づいた調査からは、いくつかの結論が浮かび上がってくる。それは、世界の貧しい地域(主に西欧帝国列強の植民地や旧植民地)からの非白人移民は歓迎されず、また歓待もされなかったということである。1945年にイギリスで選出された急進的な労働党政権は、SSウィンドラッシュ号の乗客の中に、戦争でイギリスのために戦った西インド諸島出身者が多数いたという知らせに狼狽した。ウィンドラッシュ号の出航を阻止しようと必死で、他の植民地や独立したばかりのインドやパキスタンには、イギリスでは仕事がないというメッセージが送られた。フランスは北アフリカからの移民をゲスト労働者として扱おうとした。ドイツ人は、民族的に制限された市民権法をすでに導入していたため、フランス、イギリス、オランダ政府がおそらく確立したかったであろう厳格なゲストワーカー制度を作り上げた。いずれにせよ、「柱状化」の伝統によって、オランダは非白人移民をオランダ社会の主流から遠ざけることができ、政府と西欧の白人人口の大部分は、移民がしばらくの間だけ滞在することを望んだ。
労働力に飢えていた西欧の製造業と公共部門、特に運輸と医療は、政府を無視して植民地や旧植民地から大量に採用した。しかし、これが2つ目の結論であるが、これらの労働者は、その学歴や職業資格のレベルがどのようなものであれ、好景気の中で白人労働者が敬遠していた非熟練的で好ましくない仕事に就くことになった。民間や公営の地主から差別され、彼らは貧しい都市部で窮屈な賃貸住宅を見つけた。ヨーロッパ帝国がアラブ諸国やインド亜大陸に関与していたため、移民の多くがイスラム教徒であった。
より重要だったのは、西欧社会が帝国の遺産の一部として受け継いできた、深く埋め込まれた人種化であった。つまり、「有色人種」の労働者は、それまで労働市場に供給していたイタリア、スペイン、ポルトガル、ポーランドからのヨーロッパ人移民とはまったく異なる扱いを受けたのである。非ヨーロッパ系労働者は、自分たちは劣った存在であり、同化することはほとんど不可能だという感情が蔓延していた。1970年代半ばまでに、このような労働移民の受け入れは打ち切られた。
第三に、新たな多民族性によって生み出された文化的多様性を受け入れ、祝福する気風を生み出そうとして最終的に生まれた多文化主義は、常に人種差別の帝国的遺産と戦わなければならなかった。西欧の人々は、非白人移民の受け入れに消極的であり、多文化主義にも消極的であった。
第四に、多文化主義は、多くの労働組合、政党活動家、反人種主義団体が民衆レベルでの動員を試み、公正な待遇と新たな文化的多様性の恩恵の認識を求める圧力をかけ続けてきたが、その大部分はトップダウンのプロジェクトであった。トップダウンのアプローチは憤りを生み、それが白人の反発を招いた。
多文化主義への批判は、保守的なナショナリストからだけもたらされたわけではない。これまで述べてきたように、左派からは、多文化主義的な考え方や政策が人種差別に正面から取り組めず、単純化された民族本質主義に屈し、社会経済的不平等と闘う一般的な平等主義的闘争と適切に組み合わされていないために弱体化していると主張する声が多く上がっている。
また、フランス、ドイツ、イタリア、オーストリア、デンマークなどの国々では、公的にも民衆の反対もあり、多文化主義は西ヨーロッパではまだ非常に不均等に発展している。21世紀に入り、多文化主義に対する反発が台頭してきた。しかし、世間では反対の声が多いにもかかわらず、多文化主義は決して少数民族と多数民族の間の分離発展を促すものではなかった。その目的は常に、文化的・社会経済的統合に向けた、公平で差別のないルートを作ることにあった。
多文化主義は今、新たな移民パターンと、ヴェルトヴェックが「超多様性」と呼ぶものの出現に対処しなければならない。これは、欧州連合(EU)の拡大、ソビエト連邦の崩壊、破綻国家から逃れてきた亡命者の到着、内戦、中東における西側の介入の影響、高度な資格を持つ労働者に対する新しい知識・金融部門の需要、出生率の低下などによる労働力の自由な移動の結果である。
この原稿を書いている間にも、スウェーデンでは極右議員が国会議員に選出され、社会民主主義とリベラルな庇護政策の天国であるスウェーデンでさえ、マルメのような非工業化都市では、新しい形態の移民に強い敵意を抱くというヨーロッパのパターンに従いつつあることが確認された。多文化主義に対する反発は、新たな勢いを増している。
- 2. 2009年8月、ギリシャのサモス島。ギリシャの沿岸警備隊が、アフガニスタン、イラク、イラン、東欧、アルジェリア、モロッコ、パレスチナ出身の亡命希望者を逮捕している。
私は結論において、パラダイムと制度的枠組みとしての多文化主義が新たな状況に対応するためには、インターカルチュラリズムの形態に移行する必要があると主張する。しかし、今後到来する深刻な財政緊縮期は、公共サービスのための資源を削減し、失業水準を高め、より高いレベルの不平等を生み出すことによって、より洗練された形のインターカルチュラリズムや、必要と思われる再分配への提言にさえ厳しい試練を与えるだろう。
結論
新たなグローバル時代における多文化主義、異文化間主義、トランスナショナリズム
多文化主義は失敗したのだろうか?
ヨーロッパの国民国家が、多文化主義の時代は終わったと判断したのは明らかなようだ。多文化主義は現在、政府、知識人、そして国民の大部分から、第二次世界大戦後の1945年以降に欧州列強の旧植民地から流入した非白人移民への対応として、悲惨なもの、あるいは少なくとも重大な誤りであるとみなされているようだ。
しかし、これが本当に物語のすべてなのだろうか?本書では、上記のような説明が、最初に思われるほど説得力があるかどうかを疑う理由を提示した。多文化主義の時代全体が重大な間違った方向転換であったという見解は、私が提示した利用可能な証拠と照らし合わせて検証すると、支持することは難しい。明らかになった欠陥でさえ、多文化主義が大失敗、あるいは大きな間違いであったという結論に必ずしも導くものではない。「戦後」のより新しい少数民族がより永続的に定住するようになったことと、「はじめに」で私が「三重の移行」と呼んだもの–西欧の国民国家内の結びつきの緩み、ポスト工業主義の出現、福祉国家の再編–が一致したために、こうした移民とそれに対応して発展した多文化主義政策が、全体的な国民文化の分断や国民アイデンティティの変化の原因として非難されることがあまりにも多かったからである、 都市部での失業、住宅不足、教育、医療、その他の公共サービスに対する圧力は、実際には、グローバリゼーションやEUのようなトランスナショナルな構造の重要性の高まりという、より新しく加速化された形態と絡み合った、三段論法がもたらした大きな変革の結果であった。
国民文化やアイデンティティからマイノリティが疎外される度合いは、「ゲストワーカー」制度を運営し、文化的多様性を国家の物語に組み込むことに大きな抵抗があったドイツのような国々ではるかに高い。フランスは、これまで見てきたように、少数民族に共和主義的な市民権の価値観を植え付けることに成功しているが、機会均等政策の中途半端な性格を含め、少数民族に対する真剣な公式認識の欠如が、市民権の名の下に激しい憤りを生んでいる。一方、スカーフのようなアイデンティティ・シンボルに対する公式の抵抗が、イスラム教徒の大規模な少数民族の一部をイスラム的アイデンティティへの強硬な後退へと駆り立てている。明らかに逆説的だが、この後退は若いムスリム女性の間で特に顕著である。
格差の拡大と階層間格差の拡大は、様々なエスニック・ グループ内やグループ間の社会的距離を作り出し、憤りを生み出す上で、多文化政策よりも重要である。しかし、イギリスでは、 都市プロジェクトに資金を提供するための地域別入札プロセスや、特に信仰に基づくコミュニティ・プロジェクトに資金を振り向けようとする地方自治体の試みが、住宅不足や誤解を招くような地元メディアの報道と相まって、 分裂を激化させ、憤りを煽っている。
1945年以降、西欧のすべての国で移民は、深刻な衰退に見舞われた製造業や繊維産業で働くようになった。これらの地域では失業率と貧困率が劇的に上昇した。経済崩壊の矛先は、失業と貧困のレベルがより速く、より高くなったという点で、少数民族に向けられた。フランスのバンリューやイギリスの北部の町では、特にイスラム教徒の若者の失業率が、マジョリティの若者の2倍から3倍になっている。そして、彼らのコミュニティは驚くべき速さで貧困に沈んでいる。
多文化主義の重要な問題点は、マイノリティ民族が被っている社会経済的不利や差別に対して、多文化主義が大きく食い込むことができなかったことであり、それは彼らの教育実績の低さや失業率の高さに反映されている、としばしば論じられてきた。しかし、少数民族、特に若者の失業率が高い主な原因は、彼らの両親や祖父母がもともと移住していた都市中心部の古い産業が崩壊したことにある。イギリス北部の都市における非工業化の荒廃、特に少数民族の若者への影響について、比較的詳細に描かれたのが、第3章で少し触れた2001年の報告書である。この報告書は、他の数多くの調査とともに、マイノリティの雇用や住宅事情の重要な一因として、公共部門と民間部門における人種差別を挙げていることも忘れてはならない。
西ヨーロッパ諸国はいずれも、少数民族の若者の失業率が高く、全体的な貧困レベルが高いという特徴がある。しかし、これにはばらつきがあり、多文化政策の採用と相関関係があるわけではない。政治学者のランドール・ハンセンなどが指摘しているように、イギリス、ドイツ、オーストリアはオランダやスウェーデンよりもマイノリティの失業率が高い。イギリス、オランダ、スウェーデンは、これまで見てきたように、多文化主義をより高度に採用している。また、フランスでは、多くの情報通の研究者によれば、強固な機会均等政策という形での多文化主義の欠如が、マイノリティの若者の失業率の高さの一因となっており、少数民族の認識やその運命に関する統計の収集に対して公式の敵意がある。特に英国では、官民両部門において、より効果的な差別撤廃・機会均等措置がとられているため、少数民族の失業率が欧州の他の地域よりも改善されているようである。英国では、インド系や中国系の学生が、学業成績や大学進学率で白人の学生を追い抜いているが、これは彼らの社会階層が高く、移民以前の経歴が大きく関係している。
庇護を求める人々や難民、東欧からの新たな移民の到着、そして「超多様性」と呼ばれるものの出現は、一部の地域では住宅、学校、医療サービスに特別な負担をかけ、極右に反移民感情を強める機会を与えているようだ。イギリスでは、移民の恩恵と負担が不均等に広がっており、一部の労働者階級の地域やコミュニティが、希少な雇用や公的資源をめぐる競争激化の矢面に立たされている一方で、その恩恵を受けているのは、より安く物件を改装し、清掃員などの家事労働者を確保できるようになった雇用主や中流家庭だけであることが多いという認識が広まっている。自治体や中央政府の準備不足が、新規移民の急速な流入がもたらす資源のひずみに取り組むことなく、結果として生じる「文化的多様性」を賞賛しようとする一部の公的機関の試みによって覆い隠されているケースもあるが、多文化主義はこうしたプロセスとはほとんど関係がない。しかし、これは後付けの多文化主義であり、実際には問題の原因にはなっていない。根本的な必要条件のひとつは、より多くの資源を供給することであるが、緊縮財政の新時代においてはその可能性は低く、悲観的な根拠を提示している。
多文化主義が失敗したと言えないのであれば(実際、心から試みようとさえしていないケースもある)、次に進む必要はあるのだろうか?私は、これからは少し違った道を歩む必要があると思う。
リベラリズムと多文化主義との関係という問題がある。特に、言論の自由と芸術表現の自由という未解決の問題があり、これには決定的な解決策がない。多文化主義を支持する人々でさえも、大きな不安を抱いているのは、ある種の文化相対主義と、その結果としてのあらゆる文化に対する完全な尊重の実践が、「政治的正しさ」の名の下に開かれた議論を封じ込めることにつながっているという信念に起因している。
サルマン・ラシュディ事件、オランダ人映画監督テオ・ファン・ゴッホ殺害事件、デンマークのムハンマド漫画騒動、シーク教徒の礼拝所であるグルドワラでの出来事を描いたシーク教徒作家の戯曲の撤回などは、このような議論の最も有名な火種となっている。ラシュディとその支持者たちはイスラム教徒の懸念に対してあまりにも傲慢であったし、テオ・ファン・ゴッホの映画とデンマークの漫画は無償で挑発的であった。
とはいえ、私や多文化主義の基本原則に共感する他の多くの人々から見れば、多くの少数民族が信仰に関する批判やオープンな議論を自由に受け入れることができないという真の問題がある。そして、マイノリティのコミュニティは、間違いなく、これらの問題について内部で議論することが少なすぎる。この問題は、これらのコミュニティ内で現在利用可能なさまざまなフォーラムで、真剣に注目し、広く議論する必要があり、またそれに値するものである。これは、多文化主義が前進しなければならない理由のひとつであり、その分野のひとつでもある。
しかし、英国や米国の学校カリキュラムにおいて、創造論や「インテリジェント・デザイン」の教育を求める要求が進出していることは、世俗主義、自由、信仰や宗教的信念の位置づけをめぐる厄介な問題が、イスラム教徒やその他の少数民族、多文化主義だけにとどまらないことを示している。信仰学校は続いており、繁栄しているあらゆる証拠を示している。本物の宗教間対話や、宗教とその他の領域との間の自由主義的、多元主義的、世俗主義的な融和の利点に対する積極的なアプローチを確実に育成するために、厳しい規制が行われることが望まれる。
多文化主義は後退の一途をたどっているのか、それとも本当に死んでしまったのか?
アメリカでは、数十年にわたる「文化戦争」にもかかわらず、多文化主義の一般原則は、特に教育や国家的な物語において、現在しっかりと根付いているように見える。保守派の著名な民族関係研究者であるグレイザーは、著書『We Are All Multiculturalists Now』のタイトルの意味をこう説明している:
つまり、アメリカの歴史や社会科、学校の文学の授業において、マイノリティや女性、そして彼らの役割に、より大きな関心が向けられるようになったということだ。アメリカの教育を、さまざまなサブカルチャーが無視され、アメリカが文明の頂点であり最終的な産物として紹介されていた時代に戻したいと願う少数の人々は、今や学校での進歩を期待することはできない。
英国や西欧の他の国々では、多文化主義を葬り去ろうとする人々によって、すべての公共メディアの議論が支配されてきたわけではないことを覚えておく価値がある。一見、ありそうもないところからも支持が寄せられている。英国の中道右派の代表的な出版物である『エコノミスト』誌もそのひとつで 2007年には、「多文化主義」が「ネオコン」や「社会主義者」のように侮蔑的な言葉になる傾向を断固として否定している。強制結婚や名誉殺人といった安易なターゲットに狙いを定める習性を揶揄し、バゲホーの常套句の下に書かれたこの記事は、少数民族の間で起こっている限定的な分離は、多文化主義の特質をいくらかは受け継いでいるかもしれないが、強制的な混合が逆効果になるような状況において、住宅政策や教育政策という舞台のせいにしているところが大きいと論じている。バゲホは、少数民族の人口が増加している部分の成功や、他の西欧諸国の水準と比較したイギリスの少数民族の統合の水準も、イギリスにおける多文化主義政策の採用が負債というよりはむしろ恩恵であったことを示唆していると論じている。不満を抱くイスラム教徒の若者の小集団は、世代間対立や非工業化地域における高水準の失業や困窮から生まれたものであり、多文化主義はこうした傾向とはほとんど関係がない、と同教授は主張する。また、黒人と白人の結婚率が比較的高いことも、他国(特にアメリカ)に比べて文化的分離が少ないことを示唆している。
同様の主張は、新労働党の「第三の道」プロジェクトの主要な知識人の一人であるアンソニー・ギデンズも唱えている。彼はまた、新労働党の政治家とは異なり 2006年には多文化主義支持を表明している。彼はとりわけ、多文化主義をめぐる議論の多くが「粗野で、無知で、誤解に満ちた」ものであったと主張し、デンマーク、ベルギー、フランス、オランダといった他のヨーロッパ諸国と比較して、イギリスにおける極右の失敗を、イギリスが文化的多様性の管理において最も成功しているEU国家であることの証拠として指摘している。2001年の報告書には言及していないが、ギデンズは「多文化主義を減らすのではなく、もっと増やそう」と呼びかけている。ここで彼は、私が指摘したように、オランダやフランスの多くの情報通のコメンテーターの感情に共鳴している。
さらに、リベラル派の政府は、公式には多文化主義の時代から距離を置いているにもかかわらず、市民権テストはともかくとして、一見したところ、多文化主義に傾倒している。
ヴェルトヴェックとヴェッセンドルフが正しく指摘しているように、この距離の取り方の多くは修辞的なものであり、「多様性」への支持が多文化主義の言葉に取って代わっている。そして、当初の多文化主義の枠組みの大部分と、その政策の大部分はしっかりと残っている。機会均等政策へのコミットメントを撤回することも、既存の差別禁止法を水増ししようとする試みもない。フランスのスカーフ着用禁止やスイスのモスク建設への抵抗など、文化的承認は依然として争点となっているが、以前ほどではないにせよ、多文化主義がもともと弱い国に限られていることは間違いない。多くの人々が危惧しているにもかかわらず、同化主義へと一直線に、あるいは大挙して突き進むことはない。統合主義というやや厳しい制約のなかではあるが、文化的多元性と多様性の理念は依然として公に推進されている。しかし、統合政策は比較的穏やかなものだ。ランダル・ハンセンが指摘するように、国民に国語の習得を義務づけることは多文化主義への脅威とは見なされないし、国民文化に関する基本的な事実を学ぶことについても同じことが言えるかもしれない(特定の事実や問題の関連性についての屁理屈はさておき)。
コペンハーゲン、シュトゥットガルト、ウィーン、チューリッヒ、ダブリンなど、ヨーロッパ中の都市が多様性の原則を政策と実践に組み込んでいることが、ヴェルトヴェックとヴェッセンドルフのエッセイ集で明らかにされている。多文化主義は存続しているが、女性器切除や強制結婚のような慣習は単純に許されないという明確な概念とともにある。このことは 2000年の英国多民族委員会報告書(パレック報告書としてよく知られている)の勧告からも明らかである。
多文化主義に対する「反動的言説」が、特に異民族関係に影響を及ぼさないと考えるのは間違いである。さらに、英国で保守党と自由民主党の連立政権が選出されたことで、保守党のメンバーが、英国の帝国主義的な過去を肯定的に取り上げて、学校のカリキュラムをより民族主義的な方向に再編成したいという意向を示したり、欧州人権条約に基づく人権法を撤回し、希薄化した英国の権利章典に置き換えたりしている点で、多文化主義の将来にとって危険な兆候を示している。前労働党政権からの地域社会結束の取り組みや資金援助がすべて存続する可能性は低く、特に公的支出の大幅削減というプログラムの前ではなおさらである。
しかし、EU圏外からの移民に対する規制がさらに厳しくなるにもかかわらず、「多様性」に対する英国の一般的なコミットメントは、さまざまな解釈が可能な当たり障りのない概念ではあるが、維持される可能性が高い。より確立された形の民族間・宗教間協議や、少数民族の機会均等に対する一般的な支援は継続される可能性が高いが、公式の言説の中で多文化主義について言及されることはさらに少なくなるだろう。本稿執筆時点では、「ビッグ・ソサエティ」に対する連立政権の支持が民族間関係にとってどのような意味を持つかは不明である。
インターカルチュラリズムに向けて
注意点はあるにせよ、ヨーロッパ全土で政策やイデオロギーの転換が起こっていることは明らかである。多文化主義を超え、「インターカルチュラリズム」とでも呼ぶべき形態へと変貌を遂げる場合もある。
多文化主義を超えたインターカルチュラリズム(異文化間主義)の重点を示す記述として、欧州連合(EU)の「移民統合のための共通基本原則」(2004)の第7原則がある: 移民と加盟国の市民との頻繁な交流は、統合のための基本的なメカニズムである」とし、さらに「共有フォーラム、異文化間対話、移民と移民の文化に関する教育」などに言及している。
ここで重要なのは、古典的な多文化主義に見られるような、多様性や異文化の単なる賛美ではなく、異なる民族や信仰集団の出会いを積極的に奨励し、対話や共同活動の場を設けることである。もちろん、これは英国におけるコミュニティ結束政策の背景にある考え方でもある。一時期、英国政府は地方議会に対して、単一のコミュニティ・プロジェクトには資金を提供せず、コミュニティを結びつけるプロジェクトにのみ資金を集中させるべきであると提案したこともあったが、この提案はあまりにも厳格な要件を課すものであるとして取り下げられた。特に、単一コミュニティ組織は、コミュニティを主流文化に統合し、コミュニティ間の参加に不可欠な役割を果たすからである。
もちろん、このことは、異文化間対話が以前の多文化共生の理念や実践の一部ではなかったということを意味するものではない。しかし現在では、多文化主義という考え方が、民族文化は厳密に定義可能な境界を持ち、不変の本質的要素を持ち、極めて根本的な内的異論を欠くものであるという解釈に、あまりにも簡単に屈してしまっているということが、はっきりと認識されるようになっている。言い換えれば、多文化主義は本質主義に傾きすぎているのである。マルチカルチュラリズムの「マルチ」は、「多文化主義」の中に常に存在するスペースに余裕を与えすぎ、民族文化や国家文化を硬直した境界を持つものとして考えることに陥りやすいのである。その代わり、インターカルチュラリズムという概念を用いることで、この本質主義的な傾向を弱めることができる(それだけでは完全に防ぐことはできない)。この点で、私の提案は、「ポスト・エスニック」の視点を採用することで、アメリカが多文化主義を超えるにはどうすべきかというホリンジャーの提案と、いくつかの要素を共有している。
また、「インターカルチュラリズム」は、多文化主義が不注意にも助長してしまった傾向、つまり、すべての非西洋文化を西洋の文化や理想とほとんど共有せず、その発展において西洋から完全に切り離されたものとして扱うことを避けている。対照的に、どのような形のインターカルチュラリズムであれ、その根底にあるのは、地球規模での文化の歴史的、さらには現代的なつながりであり、地球の歴史の中で異なる地理文化的空間で独自に発展してきた価値観の共有であることを明確に認識することである。
多文化主義的な語りの中でさえ、西欧と非西欧の間の歴史的な深い相互関連性はしばしば没却され、その代わりに、いわゆる「文明の衝突」の結果であり、現在もそれによって定義されている世界秩序というハンチントンの構想の不条理さを最終的に生み出している。
この「西洋とそれ以外」の厳格な区別は、西洋が他の非西洋文化とは無関係に発展したとされる独自の特徴を持ち、ヨーロッパ帝国が世界の大部分を拡大し植民地化した時代とその後の両方において、西洋の文明への貢献の中心的部分であり、実際に「文明化の使命」の一部であったとされる、誤解を招く歴史に依拠している。現在アメリカを筆頭とする西洋の台頭(そして正当化された世界支配)を物語るこの物語は、民主主義、寛容、自由、法の支配、平等主義、人権概念、個人主義、科学的合理性、ヒューマニズム、さらには町や大学、ロマンチックな恋愛観までもが、すべて西洋独自のものだと主張する。それらは、古代ギリシャとローマ(古典古代)、キリスト教(特にプロテスタント宗教改革)、ヨーロッパのルネサンスと啓蒙主義、科学革命と産業革命、そして近代西洋の民主主義運動が独自に結合して生まれたものである。一方、イスラム教を含む「東洋」は、特に極東における儒教やインド亜大陸におけるヒンドゥー教の厳格なカースト概念、そして世俗主義や人文主義、科学的探究に対するイスラム教の反発に基づき、本質的に権威主義的であると見なされている。
この傲慢さの歴史的根拠は、よりヨーロッパ中心主義的でない説明によって徹底的に否定されてきた。ここでは、ケンブリッジ大学の著名な人類学者であり比較歴史学者でもあるジャック・グッディと、ノーベル経済学賞受賞者で哲学者のアマルティア・センの研究から、いくつかの点を指摘したい。
まず、宗教と神性に対する人文主義的懐疑の問題を取り上げよう。インドでは、紀元前6世紀に無神論的な学派が隆盛を極めたが、それは同時に不可知論的な仏教が出現し、中国をはじめとする極東や東南アジアを長い行進を始めた時期でもあった。『ラーマーヤナ』や『ウパニシャッド』といったインドの重要な書物には、宗教、神、死後の生に懐疑的な見解が記されており、その影響はインドの伝統的な思想に続いている。
寛容は西洋独自の概念でもない。インドのアショーカ帝は、紀元前3世紀には寛容について考え抜かれた考えを明示していた。また、イスラムにも著名な寛容の提唱者や実践者がいた。16世紀のモグール帝国皇帝アクバルは、礼拝の自由などの人権を認め、奨励し、強制改宗に反対した。イスラム教のオスマン帝国は宗教的寛容の例として特によく知られており、そのキレット制度は宗教共同体が独自の法的管轄権のもとに存在することを認めていた。また、中世の有名なイスラム・スペインの「黄金時代」では、キリスト教徒、ユダヤ教徒、イスラム教徒が共存して栄えた。
現在、西洋の自由の考え方とされているものは、啓蒙以降の発展である。アリストテレス的な上流階級の自由(奴隷、女性、その他一部を除く)の考え方は、バラモンの保護に関わるカースト制度を支持するものや、マンダリンの自由の保護があった中国など、アジアのさまざまな概念に見られる。また、アフリカの伝統的な社会では、「自由」という言葉に相当するものがないとしても、奴隷や従属者である人々と、より大きな自治権を持つ人々の地位が明らかに意識されている。中国やその他の文化圏の権威主義は、儒教の中にあるさまざまな系統の複雑さを誤解し、またより平等主義的な仏教文化の構成要素の影響を無視することによって、かなり誇張されてきた。
また、人類の歴史的記録に対する多くの違反の中でも、法の支配や財産権を西洋の発明であると説明することは、無数の人類学者や歴史家が指摘してきたように、口承やその他の農耕社会におけるそれらの存在が、単に世界史から抹消されている場合にのみ可能なのである。
ギリシャ人は「民主主義」という言葉を発明したかもしれないが、その実践を発明したわけではない。グッディは、「自分の声を聞いてもらいたいという、何らかの形の代表を求める欲求は、人間の状況に内在している」と指摘し、アフリカやその他の地域のさまざまな文化が、首長制や中央国家の統制からの自由を喜んでいたことに言及している。彼は、歴史的に最も権威主義的な政府でさえ、民衆の感情や要求を考慮しなければならなかったと述べている。メソポタミアには古代ギリシャのような都市国家があった。ヨーロッパでは、民主主義が明確な肯定的評価を得たのは19世紀になってからである。
西洋が政治的に進歩的なものの唯一の源泉であるという考え方は、古典古代やその他のヨーロッパ史の時代について、過度に単純化され、選択的に解釈された西洋の制度の現代版が違法に読み返され、民主主義やその他の進歩的な発展に関する西洋社会と非西洋社会の類似点を無視することによってのみ、信じることができる。
西洋とそれ以外の地域との間の全体的な分裂もまた、文化間の本質的なつながりと、西洋の発展が非西洋の文化からどの程度借用したかを無視することに依存している。
少なくとも、インド、アラブ、中国、ペルシャの数学者、哲学者、論理学者、天文学者、医学研究者などが、その後の西洋科学の開花の基礎となる発見をしたことは明らかである。18世紀のヨーロッパ、啓蒙主義の時代でさえ、中国、トルコ、インドの文化や生活様式が賞賛され、しばしば西洋のそれよりも好意的に評価されたのも不思議ではない。啓蒙思想に先立つヨーロッパのルネサンスは、イスラム社会で活動し、ギリシア人の哲学的・科学的業績を保存し、翻訳し、発展させた学者たちに負うところが大きかったことも、今ではわかっている。そして古典古代は、他の文化や地域、特に古代エジプトの文化や地域との相互関係や借用なしに生まれたわけではない。エジプトへの恩義が特に強調されているマーティン・ベルナルの『黒いアテナ』に対する批判がどのようなものであれ、古典ギリシアの開花を単に内部から生じたものと見なすのは間違いであり、「ヨーロッパ」の独立した現象ではないことは間違いない。
「合理性」は西洋のものだと思われがちだが、西洋は長い間、他の国々に遅れをとってきた世界的な人類の成果なのである。
いわゆる「ヨーロッパの奇跡」と呼ばれる産業文明をもたらした権威主義的な東洋と分散化された個人主義的な西洋を厳密に区別するのではなく、「ユーラシアの奇跡」、つまり青銅器時代の遺産を共有しながらも、完全には特殊ではない西洋が優れた軍事・海軍技術によって部分的に優位に立った社会について語る方が、歴史的に理にかなっていると、グッディは他の歴史家の豊富な研究をもとに説得力のある主張を展開している。西洋は、技術、科学、文化において一休から多くを借り、何世紀にもわたって経済的、技術的に先進的であった地球上の地域を支配するようになり、結婚制度や倫理など、東洋で貿易や製造業を繁栄させた多くの社会的特徴を共有するようになった。しかし、そのような時代も終わりを告げようとしている。東洋の経済がその座を奪い、以前のように支配と覇権のパターンをさらに東洋に移そうとしているように見えるからだ。
18世紀、19世紀、20世紀初頭における西洋の帝国的拡張と植民地化は、インドやアラブ中東のような国々に多大な影響を及ぼし、西洋の言語、文学、統治形態、近代的な大学のような制度が組み合わさった、驚異的なハイブリッド文化を生み出した。
以前の植民地からやってきた人々は、文明を持たない「暗いよそ者」であるという政府や民衆の懸念にもかかわらず、こうした西洋との交流によってすでに深く刻み込まれていた。「彼ら」は「有色人種」の「民族」であり、まったく異なる、しかし普遍主義的なリベラルで民主的な価値観と制度を持つ文化にたどり着いたとされていた。
このような西洋的アイデンティティの形成は、まったく異なる非西洋に対抗して、独自の文明的性格を持つという感覚を生み出すものであったが、現在では、特に「ポストコロニアル研究」の分野において、徹底的に解体されている。しかし、この盛んな研究分野からの特別な洞察に注目してほしい。それは、ヨーロッパの国民国家の形成が、その植民地的・帝国的プロジェクトにいかに深く影響されていたかを強調するものである。フーコーが有名に「ガバメント性」と呼んだもの、つまり、特別に収集された情報、関連する専門家、そしてイギリスがインドで先駆けた指紋押捺の使用を含む、これまで以上に詳細な監視を用いた、組織的な形での住民の統治は、植民地を統治するために開発された方法に起源を持つ。規律ある労働者や公務員を養成するための体系的な大衆教育やエリート教育の必要性も、植民地支配と関係がある。イギリスでは、教育や「文明化」の一形態としての英文学の使用でさえ、まずインドで試され、その後初めて教育技術としてイギリスに逆輸入された。
言い換えれば、ヨーロッパの国家が植民地とは無関係に最初に形成され、その制度が植民地社会に押し付けられたというケースではなく、ヨーロッパの国民国家の形態そのものが、植民地を統治するために最初に開発された制度に大きな影響を受けているのである。
多文化主義という語彙を「インターカルチュラリズム(異文化間主義)」へと変容させ、それに対応して、文化の深い歴史的相互関連性を強調し、寛容、自由、合理性などの概念がいかに「文明」を超えて共有されているか、特に非西洋文化がいかにこうした考え方やそれにふさわしい制度の発展に重要な貢献をしてきたかを理解する、基礎となる前提への転換が急務となっている。近代は西洋だけの現象ではなく、ユーラシア大陸で共有された成果なのである。
非西洋からの移民を、西洋独自の生活様式を希釈した前近代的なものに過ぎないとみなすことは、21世紀のヨーロッパ国民国家の「超多様性」を管理するためのより適切な倫理観や制度を発展させる上で大きな障害となる。異文化間の新たなエートスにおける対話の中心性には、「異文化」に対する当たり障りのない敬意だけでなく、すでにどれだけ多くのことが共有されているか、そしてこれらの共通性が、より共通した理解を発展させるための基礎となることを理解することが必要である。
いずれも、文化的に多様なヨーロッパの国民国家のさまざまな共同体の間で、自由、権利、セクシュアリティ、市民としての行動や責任がどのように観念され、実践されているかに依然として違いがあることを軽視するものではない。しかし、ひとたび歴史が相互に関連し共有されていること、西洋独自の形態と思われているものが実は非西洋と西洋の共同成果であること、多数派民族を含むすべての民族共同体自体が権利、自由、セクシュアリティ、市民的行為の適切な解釈をめぐって分裂していること(中絶、同性愛、女性司祭などについての保守的な留保を考えてみよう、 また、新しい世代の非西洋移民が、彼らの両親の文化と「キリスト教ヨーロッパ」の文化のハイブリッド版を急速に発展させている。
私たちは今、拡大し続ける「トランスナショナリズム」の時代の一部であり、移民とその子孫、そして以前「母国」であった国々との相互関係は、より複雑になり、多くの場合、より安価な電話、航空便、インターネットの急速な発展により、ますます強まっている。国家や少数民族のアイデンティティは、より激しいグローバリゼーションに対応して変化しており、複数のアイデンティティの拡散は、今や広く記録されている。これは新たな「コスモポリタニズム」と結びついており、マイノリティとマジョリティの人々の多くが、文化、ライフスタイル、言語間のコードスイッチングに習熟しつつある。このようなプロセスは必然的に不均等であり、階級や所得水準、ジェンダー、年齢などの要因に左右される。とはいえ、これまでの国民国家を中心とした視点が、より濃密なグローバルな相互連関のパターンに対応した視点に取って代わられる必要があることは、ますます明白になってきている。
このトランスナショナルでコスモポリタンな新たな段階においては、国境を越えた真に対話的な異文化間主義が不可欠であるだけでなく、その可能性も高まっている。パレクの『多文化主義再考』(Rethinking Multiculturalism)に示された対話的多文化哲学のバージョンは、その最初の土台を提供するものであり、最近の『アイデンティティの新たな政治学』(A New Politics of Identity, 2008)では、相互接続された歴史、新たなディスポーラとそのハイブリッドで多重的なアイデンティティ、国民国家内の新たなコスモポリタニズムをより深く認識し、より適切に発展させている。
統合やコミュニティ結束といった概念の運命はどうなるのだろうか。「統合」は、特に具体的な政策や市民行動との関連において、実際に議論や不確実性の場となっている自由や寛容などの広義の西洋的価値を除いては、統合とは何であるべきかを適切に特定することができないために、常に損なわれてきた。そして、統合も「地域社会の結束」も、タリーやアミンらが指摘しているように、健全で活気ある議論を伴う多元的で民主的な文化には不都合な、安定とコンセンサスという非現実的な最終状態を想定しているように見える。もちろん、議論、関与、論争の的となる問題の解決に関する比較的安定したルールは存在しなければならないが、ルールも解決策も、常に理性的で合理的な挑戦に対して開かれていなければならない。目標は、「私たち」と「彼ら」という感情を根付かせるのではなく、「私たちらしさ」の感覚を生み出すような、民族グループと他のコミュニティとの間の融和を生み出すことである。
資源が乏しく、文化的な敵対関係が確立している状況では、レジャー、スポーツ、その他の共同施設、住宅、モスク、寺院、シナゴーグの建設用地への資金援助は、適切な議論の場で時間をかけて信頼関係、調停、妥協が築かれなければ建設的に対処できない対立の対象となる。この点について、レスターやその他の都市における、前進の道筋を示すいくつかのイニシアチブを挙げてきた。
寛容、文化的多様性、個人の権利などといった一般的な価値観に賛同する必要性について、広範な合意が存在しうるという事実は、実際に存在する相互連結性と異文化主義の帰結であり、受け入れ可能な妥協点を見つける作業を少し容易にしてくれる。価値観や意味において文化集団間で完全に一致しないことは稀であり、多民族環境で育つ新しい世代ではなおさらありえない。しかし、インターカルチュラリズムは、すべての国民が国の歴史について同じ物語を支持することを必要としない-実際、すべての国はそれぞれの歴史をめぐって分裂している-。
北アイルランドやグジャラートなど、大きく離れた地域から教訓を得ることができる。そこでは、それぞれヒューストンとヴァーシュニーによる調査が示しているように、市民団体を設立して混ざり合いを作り出し、近隣住民や民族・信仰コミュニティ間の亀裂を防いだり修復したりするのに十分な共通の帰属意識を持っている。バンクーバーを含むさまざまな都市中心部で行われた民族誌的調査でも、隣人同士のボトムアップの交渉や友情が、ヒバート氏が「地域レベルのコスモポリタニズム」と呼ぶような多民族間の友好の形をどのように生み出しているかが示されている。
インターカルチュラリズムは、必然的な終着点のない、創発的なプロセスと見なされるべきである。このプロジェクトでは、民族間の混合や対話は短期的には紛争を引き起こす可能性があること、そして正式な民族間接触は慎重に計画され、常に監視・管理された状況においてより生産的であることを強く認識する必要がある。多くの事例研究から教訓を得ることができるが、それぞれの状況は独特であり、地元の知識と地元のイニシアティブ、そして民主的に決定された形の民族間活動や話し合いが必要である。他方、地域レベルでも国家レベルでも、より国境を越えた時代の住民を特徴づけるアイデンティティの多様性に対して、より寛容なアプローチが必要であることは明らかである。特に、例えばスポーツにおいて、国家の忠誠心が常に他の忠誠心に優先するような説得力のある理由はない。
5. ロッテルダムの「Mixen aan de Maas」プロジェクトのように、人と人との対話は障壁を取り除くのに効果的である。
そして、一般化可能なプロセスや制度形態として、アイェレット・シャシャールが提唱する「変革的な融和」や、グリッロが提唱する継続的な「多様性レジーム間の対話」がある。後者は、ヒンドゥー教徒とシーク教徒の葬儀の一部を火葬場に収容するよう求めるイギリスでの要求が、裁判所と地方自治体によって対処された方法を、民族間の対話がどのようにすべての側に受け入れられる妥協につながるかの好例、そしておそらくモデルとして挙げている。ヨーロッパと北米における最近の異文化間プロジェクトの事例を知るには、フィル・ウッドとチャールズ・ランドリーの『The Intercultural City』(2008)が最適である。取り上げられているのは、バーンリー・ユース・シアターからオールダム・ユニティ・イン・ザ・コミュニティ・スポーツ・プログラム、デンマークの図書館、バンクーバーのコミュニティ・ハウス、ロッテルダムのミクセン・アン・デ・マース・プロジェクト、そしてトリノの「紛争の創造的管理」プロジェクトまで多岐にわたる。このプロジェクトでは、「文化間調停者」を路上に配置し、若者、露天商、新住民、既成住民とともに「新たな傾向を理解し、紛争を予測し、共通点を見出し、共同事業を構築する」トリノの第1期生8人は、アルジェリア、コンゴ、モロッコ、セルビア、ペルー、ブラジル、イタリアの出身で、ヨーロッパや北米の新しい都市を特徴づける「超多様性」に対応するために必要なグループだ。
しかし、多文化主義と同様に、インターカルチュラリズム(間文化主義)にも十分な資金が必要である。また、それだけでは人種差別や少数民族の不平等、より広範な階級やジェンダーの不平等といった問題に対処することはできない。これらは、脱工業化、準国家的少数民族による分離主義的な地域要求、福祉サービスの大幅な削減といった課題に直面し、ますます民営化され、消費主義的な社会になっていく中で、多民族間の礼節や社会的絆の維持に不可欠なものである。インターカルチュラリズムはまた、ジェンダー、年齢、その他さまざまなアイデンティティや関心事といった横断的な線に沿って橋を架けることを必要とする。そして、南から北へ、東から西へと人々が移動する主な原動力となっている世界的な不平等をそのままにしておくのである。
