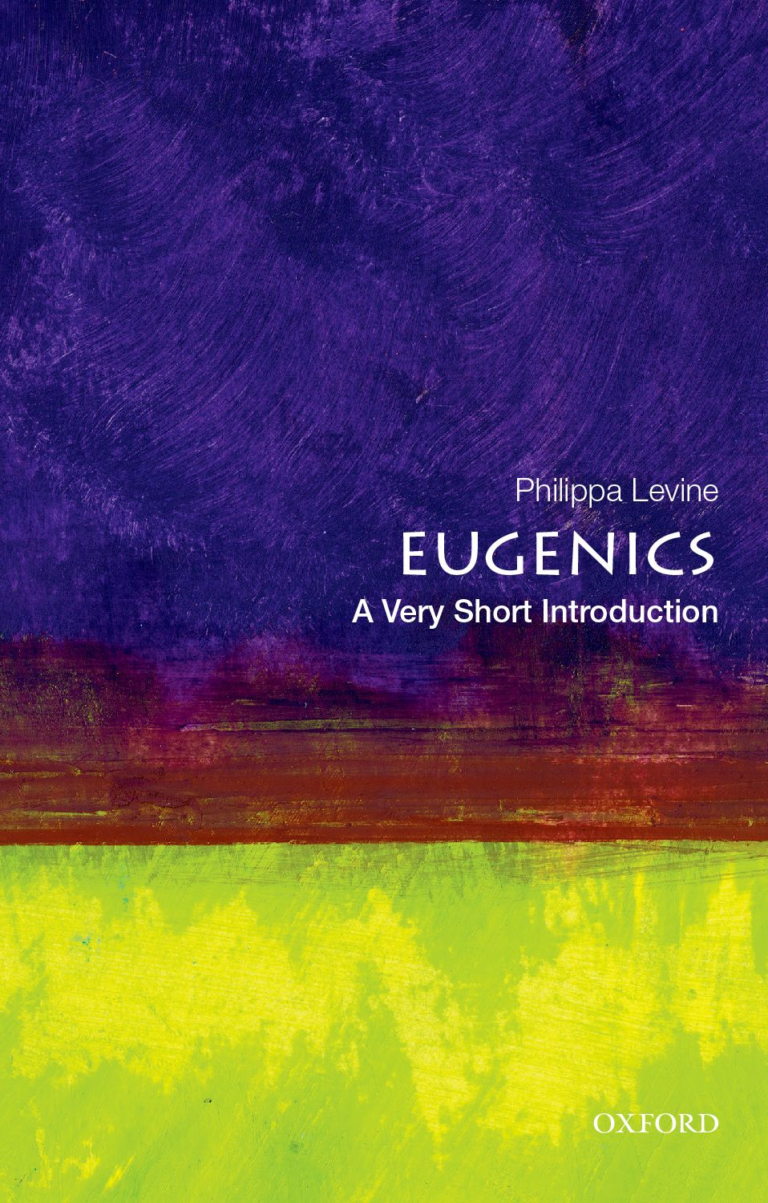コンテンツ
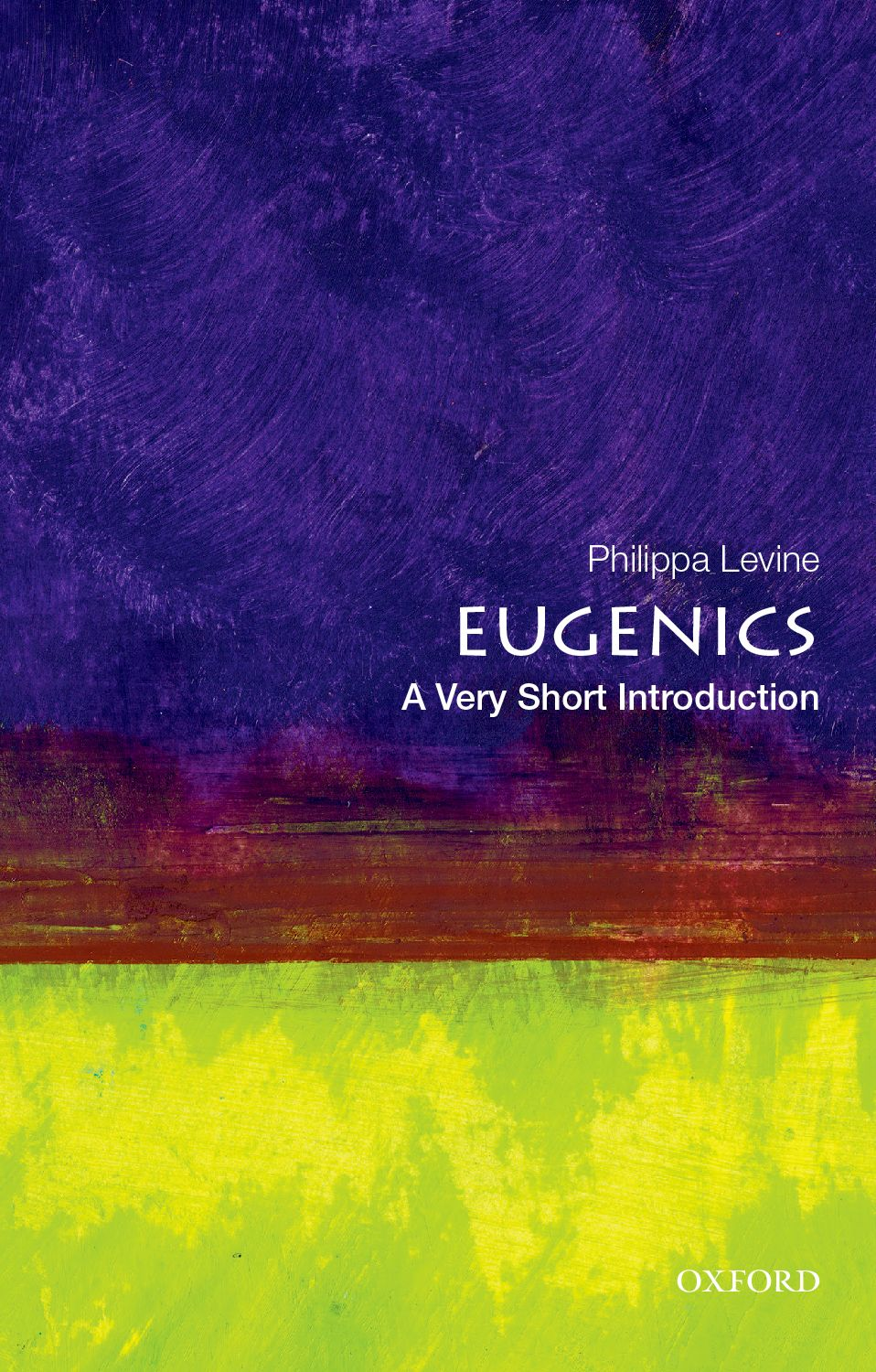
Eugenics: A Very Short introduction
優生学: とても短い入門書
フィリッパ・レヴィン
ユージェニックス
非常に短い紹介
目次
- 1 優生学の世界
- 2 優生学的知性
- 3 優生学的生殖
- 4 優生学の不平等性
- 5 1945年以降の優生学
- 参考文献
第1章 優生学の世界
20世紀初頭、世界各国で科学と社会政策の強力な結びつきが生まれた。優生学は、しばしば「良い繁殖の科学」と呼ばれ、遺伝と統計の原理を利用して、健康な繁殖を奨励し、不健康な繁殖を阻止しようとする運動であった。20世紀を通じて、特に初期の数十年間は、優生学は政府の政策形成に重要な役割を果たし、おそらくその起源である科学界よりも政策界でより重要視されていた。優生学は、生物学と統計学に基づき、生殖を制御し改善する方法に焦点を当てることで、人間の遺伝的質を向上させ、人間の苦しみを軽減することを目的としていた。統計学的な確率と実験室での科学という不思議な組み合わせは、国家と市民の関係が激変していた時代の社会改革者や政治家の想像力を刺激した。
20世紀初頭、ラテンアメリカから中東、ヨーロッパ、アメリカにおいて、優生学は急成長を遂げた。20世紀初頭、ラテンアメリカ、中東、ヨーロッパ、アメリカで優生学が盛んになり、優生学の発展を目的とした研究機関が、当時の主要な慈善団体や政府から資金提供を受けていた。知能、遺伝性疾患、反社会的行動、家族生活、生殖管理などの研究は、すべて優生学の影で行われ、多くの社会福祉法案の基礎となった。優生学は、生物学が人間社会をより良くする鍵を握っているという深い信念のもと、科学と社会改革を統合した。
19世紀後半に、まだ試行錯誤の段階にあった遺伝と統計的確率の理論に基づく一連のアイデアとして始まった優生学は、世界中で広範な実践へと変化していった。優生学は、科学的実践と社会的実践のセットであり、その境界線は時間の経過とともに曖昧になった。20世紀初頭には、優生学は論文から政策へと移行した。優生学の傘の下で、医師や心理学者、社会運動家、フェミニスト、政治家など、さまざまな人々が、科学の知見を利用してより良い世界を作ろうという共通の目的を見いだした。しかし、優生学は、より良い世界を実現するための善意から出発していることが多い。これは、20世紀で最も強権的な政策と密接に関連する運動の逆説である。「悪い」遺伝子や遺伝性の欠陥を根絶しようとする優生学者が着手したのは、既存の偏見を強化し、しばしばそれを焼き付けるような過激な計画だった。優生学は、科学と人間改良の名の下に、社会問題に対する生物学的解決策を提示したが、その解決策は、治療と罰の間の微妙な境界線を踏むことがあまりにも多かった。
1883年、イギリスの統計学者フランシス・ガルトンは、「優生学」(ギリシャ語で「生まれながらにして」という意味)という言葉を創り出した。ガルトンは、人間の遺伝を工学的に解明することによって、人類を改良することを夢見ていた。ダーウィンの遺伝と進化に関する研究に影響を受けたガルトンは、遺伝の謎を解明するために、ウサギの繁殖、知能の統計的測定、人間の違いの分類に着手した。これらの多様な研究に共通するのは、時代の新しい科学的知見が人間の生殖の成果を向上させるかもしれないという信念であった。20世紀の最初の10年間で、彼の考えは一般に広まった。20世紀初頭の10年間で、彼の考えは一般に広まり、社会政策として、「精神障害者」の結婚を禁止し、不妊手術を許可する法律が制定された。その後、遺伝性疾患や精神障害に関する政府の委員会、国際優生学会議などが開かれた。世紀前半の優生学は、結婚、子育て、犯罪、移民、医療など、生活のさまざまな分野に及んでいった。
科学的・社会的起源
優生学よりずっと以前から、遺伝と生殖は関心と興味の対象になっていた。18世紀、西洋で人口が激増する中、イギリスの学者で聖職者のトーマス・マルサスは、無制限の繁殖がもたらす悲惨な結果を警告し、人間存在の根幹を脅かすことになると予言した。マルサスは、人口が増えすぎた場合、生殖を制限して出生数を減らすか、戦争や病気などの大災害によって死亡者数を増やすかの2つの対策が考えられると考えた。1877年に設立された英国初の出産抑制団体は、彼の考え方を踏襲し、過剰な大家族が貧困の原因であると確信し、「マルサス同盟」と名乗った。この言葉は、家族の制限に関心を持つインドの改革者たちの間で絶大な人気を博した。19世紀末から20世紀初頭にかけて、インド各地に新マルサス派の組織が数多く誕生した。
一方、遺伝に対する科学的な関心は19世紀初頭には確立しており、1830年代にはフランスの医学用語集にheréditéという用語が登場した。フランスの博物学者ジャン=バティスト・ラマルクは、世紀初頭に、生物が環境に適応した行動をとることは、子孫に遺伝する可能性があると主張した。ダーウィンは遺伝のメカニズムを探求したが、人間の生殖に介入することを支持するような記述はほとんどなかった。科学者たちは、親から子へどのように特徴が伝わり、どのように胚が発達するかを理解しようとした。1860年代、モラビア人修道士グレゴール・メンデルの植物実験により、遺伝のある特徴は固定され、行動の変化には反応しないことが証明された。遺伝のある要素は優性、ある要素は劣性という自然法則に支配されていたのである。メンデルの研究は、環境が遺伝を変える可能性があるというガルトンの懐疑論と同じで、20世紀初頭まで翻訳されることなく、ほとんどアクセスできないままだった。しかし、20世紀初頭に再発見され、遺伝学という新しい科学の最も重要な要素のひとつとなった。
新世紀に優生学が確固たる地位を築いたのは、メンデルのような生物学の革新的なアイデアによるものだった。特に細胞生物学は、遺伝に関する考え方を一変させた。アウグスト・ワイスマンの生殖細胞説は、生殖に関与しない体細胞と生殖に必要な生殖細胞を区別するものであった。生殖細胞は変化に乏しく、そのままの形で次世代に伝わり、後天的な性質が伝達されるというラマルクの考えに反論した。現代のDNA理論の先駆けとなったワイスマンとメンデルの研究は、良い遺伝子だけが生殖に値するとし、悪い遺伝子は捨てるべきだという優生学的な議論に有利な環境を作り出した。科学者たちは遺伝の詳細について議論を続けたが、優生学運動にとっては、遺伝は前進する道を示していた。人間の品種改良に手を加えることができるのだ。
様々な学派が競い合った。メンデル遺伝学は「ハード・ヘレディティ」と呼ばれ、環境の影響に左右されない遺伝子の固定性を強調し、アメリカやドイツで主流となったが、ラテン諸国、特にフランスではラマルク派の考えが根強く残っていた。イギリスの科学はメンデル派が強かったが、カール・ピアソンとフランク・ウェルドンの統計学的指向の強い生物学も地元では影響力をもっていた。ピアソンとウェルドンは、形質間や家系内の相関を測定する統計解析を支持し、推測的なメンデルの理論と対照的に、観察と測定を重視することを好んだ。
優生学は、身体人類学、遺伝学、精神医学、心理学、犯罪学など、多岐にわたった。双生児研究(現在も行動遺伝学で使われている)は、犯罪、知能、病気の遺伝性を評価するために使われた。ガルトンは双子を使った初期のパイオニアであり、ロシアのユダヤ人遺伝学者ソロモン・レビットはスターリンに処刑される前に双子研究を実施した。1930年代のドイツでは一般的で、皮膚科医で優生学研究者のヘルマン・ヴェルナーは、双子の研究で1932年にノーベル賞の候補になった。優生学の研究者は、家族歴の収集、身体的特徴の人体測定、頭蓋骨やその他の遺体の測定も行った。また、血統表や遺伝データベースを作成し、遺伝しやすい形質を特定し、統計的に遺伝の確率を計算した。血族研究では人種間の違いを説明しようとし、人種人類学者では混血の遺伝を研究した。統合失調症も注目され、能力テストや知能テストが盛んに行われ、優生学は心理学や精神医学と結びついた。このように優生学は、当時台頭してきた生物医学や生物学の分野で、正当な科学的追求としてよく知られていた。
優生学の根底には遺伝の科学があったが、その影響と効果が最も強力で長く続くことが証明されたのは、社会政策においてであった。ヒトラーの副官ルドルフ・ヘスは優生学を応用生物学と呼び、ロシアの科学者ティホン・ユーディンも同様に応用科学と呼んでいる。20世紀前半の優生学は、生殖のあらゆる側面を取り上げ、福祉政策、公衆衛生、新しい法律などを形成し、その範囲は驚くべきものであった。1914年以前からすでに影響力を持っていた優生学は、第一次世界大戦後、戦争によって引き起こされた問題、また戦争によって明らかになった問題に対する解決策として捉えられるようになった。多くの人々は、この破壊的な紛争の4年間を優生学的災害とみなし、膨大な数の若者を殺し、不具にし、性感染症率を上げ、アルコールの使用を促進し、女性を家庭から追い出した。戦争前の人口水準を回復または拡大するための出生促進キャンペーンが盛んに行われ、若者の世代を失った国々は多産を推進し、家族の制限を禁止することさえあった。
優生学と社会改革
19世紀後半の変化もまた、人類の向上という目標に大きく貢献した。旅行がより簡単で速くなったことで、多くの人々が自国とは異なる環境や文化に触れ、ヨーロッパの帝国主義の発展により、優れた民族と劣った民族の分類が促された。都市の発展と機械化の進展は人口を集中させ、より広範な政治的代表権を要求するようになった。国家や政府は、国民の健康、教育、安全に対する責任を増大させ、そのためには民族の数を数え、分類する必要があった。識字率の向上と可処分所得の増加に後押しされた大衆ジャーナリズムは、都市の危険と不品行な下層階級の物語で盛り上がった。マックス・ノルダウのベストセラー『退化』(1892)は、工場の煙が充満し、汚れた環境が続く中、西洋文明の未来に対する悲観論が広がっていることを伝えている。イタリアの犯罪学者の先駆者チェーザレ・ロンブローゾは、犯罪者や精神異常者の遺伝的退化説を唱え、インドや中国、貧しい白人の出生率の高さを指摘する論者たちは、最良の標本を再現できず、敵対者に蹂躙される衰退した西洋を描いていた。そして、優生学の使命は、正しい生殖を促進し、間違った生殖を防ぐことによって、その流れを止め、退化を逆転させることであった。
優生学の多様性
イギリスの作家ハヴロック・エリスは、人類の未来の繁栄の鍵は「人種の健全な繁殖」にあると確信していた。しかし、健全な繁殖の定義はさまざまであった。優生学には「ポジティブ」なものと「ネガティブ」なものがある。どちらも生殖に焦点を当てたものだが、否定的優生学が生殖の阻止を重視するのに対し、肯定的優生学は健康で社会的に価値のある人の生殖を増やそうとする。積極的優生学は、出生前・育児ケア、税制上の優遇措置、家族手当、家族計画などを通じて、遺伝性疾患のない人々の生殖を奨励し、増加させることを目指した。また、住宅、衛生、教育の改善も目指した。これは、リベラルな優生学者や急進的な優生学者に多く受け入れられているビジョンである。一方、より権威主義的な否定的優生学は、施設に閉じ込める、不妊手術を行う、あるいは安楽死を行うなどして、望ましくない個体が繁殖するのを防ぐことを目的としていた。優生学の実践はこのように多岐にわたり、その結果、極端に異なる考えを持つ支持者が集まった。これらの実践は、ほとんどすべて、特に積極的優生学に特徴的なものは、しばしば優生学者以外の人々にも支持されたものであり、必ずしも優生学運動だけのものではなかった。優生学者が他と一線を画していたのは、科学、特に遺伝と遺伝学の科学こそが人類をより良くする鍵になるという信念であった。
このような科学の普遍的な力への信頼が、優生学を欧米諸国だけのものではなく、国際的な運動にしていったのである。それどころか、優生学の最も興味深い特徴のひとつは、実質的に世界的な広がりを見せていることである。優生学は、それぞれ異なる道を歩みながらも、世界各地で注目を集めた。ラテンアメリカを中心に、イラン、エジプト、オランダなどでは、ラマルク流の積極的な優生学である「プエリカルチャー」が重視されたこともあった。優生学の産科医であるアドルフ・ピナールは、これを「人間の保存と向上のための科学」と呼んだ。生殖と育児を奨励し、環境改善にも力を入れるこの積極的優生学は、特にラテン諸国において顕著であった。1935年にラテンアメリカや南・南東ヨーロッパの団体が加盟して設立されたラテン国際優生学協会連盟は、硬性遺伝学派の否定的優生学原理から距離を置き、社会衛生、公衆衛生、環境の変化を優生学の最良の道と強調した。細菌学者ニコライ・ガマレイアのようなソ連の初期の優生学者も環境保護を強く意識しており、インドやエジプトでは優生学者は遺伝学にほとんど興味を示さなかった。インドや香港のように、全体的な人口増加を抑えようとする地域では、優生学は主に避妊に重点を置いた。
イギリス、カナダ、アメリカなど、移民の多い英米圏では、優生学は人種を特定した移民管理のためのツールとなり、精神的・知的能力への関心が高まった。これらの地域では、ドイツと同様、遺伝主義的な優生学が主流であったが、肯定的な優生学と否定的な優生学もしばしば共存していた。多くの優生学者が、改善と予防のための戦術の組み合わせを提唱したため、積極的優生学と消極的優生学とを明確に区別することは不可能であった。スウェーデンでは、出生前ケア、年金、児童福祉などの社会福祉施策と並行して、精神障害者の強制不妊手術が行われていた。アメリカの動物学者ハーバート・ジェニングスは、1927年に、欠陥のある遺伝子の伝播に対するチェックを支持する一方で、「環境要因に対する戦いは続けなければならない」と助言している。多くの人にとって、否定的な優生学的措置と肯定的な優生学的措置の両方を支持することは、矛盾することではなかった。
民族の帰属
中央、南、東ヨーロッパ、中東、アメリカ大陸では、独立したばかりの国家で優生学が重要な役割を果たした。1914年から1918年にかけての戦争でオスマン帝国とハプスブルク帝国が崩壊した後、発展途上国は優生学的改善によって国民の健康と体力を向上させ、自国の世界的地位を高めることを期待した。例えば、チェコスロバキア、ハンガリー、ルーマニアでは、医師や科学者が積極的に優生学を推進し、欧米から自国が後進国で不衛生であると見られていることを嫌というほど実感していた。生物学的に健全な国家を作ることは、健康増進を目指す科学者や医師にとっても、権力強化に熱心な政治家にとっても魅力的だった。一方、大帝国は優生学に、世界的な支配力を維持し、生物学的な優位性を主張し、生殖をコントロールする手段を見いだした。スペインでは、優生学者が帝国の喪失と国の世界的影響力の低下を生物学的退化のせいだとした。
行動や民族性、病気や欠陥など、適合しない人々は、優生学が解決すべき問題となり、階級、人種や民族の識別、あるいは性別によって定義されることが多かった。戦後の新しい国や多民族国家では、優生学は民族的・人種的マイノリティに多大な影響を及ぼした。東欧や中央ヨーロッパの少数民族の中には、自分たちの目的のために優生学を操る者もいたが、優生学の施策は狭い範囲のライフスタイルを支持し、ヒトラーのアーリア人優位の考え方の中で神格化されるに至った。
優生学とナチズム
よくある誤解は、ナチズムを優生学と混同し、ヒトラー政権の行動が優生学の究極の表現であるとするものである。ナチスは確かに優生学を利用して目的を達成したが、特に戦時中の活動はその範囲をはるかに超えており、ナチス以外の優生学者は不安で距離を置いていた。さらに、優生学への関心は、ヒトラーが権力を握るよりもずっと前にあった。ドイツの遺伝学と優生学研究は、20世紀初頭の国際的な科学界で高い地位を得ており、資金力のある施設と革新的な研究を行っていた。ドイツの医師、精神科医、生物学者、人類学者は、遺伝性疾患を研究し、死亡率統計を作成し、公衆衛生プログラムのキャンペーンを行った。第一次世界大戦と第三帝国に挟まれたワイマール時代には、出産や子どもの健康、病気の予防を目的としたウェルファリスト政策が盛んに行われた。優生学は、国際的なつながりのあるドイツの科学研究の一翼を担うものとして確立され、正当なものであった。第一次世界大戦の前後には、ドイツとアメリカの優生学者たちは、互いの研究機関を訪問し、互いの研究成果を翻訳し合うなど、密接な関係を築いていた。ドイツの優生学者たちは、アメリカですでに成立している優生法を羨望し、自国で実施されることを望んでいた。
ドイツの優生学の保守派は人種(Rassenkunde)に着目しており、ヒトラー政権下で特に熱心に追求されるのはこの要素であった。1920年代にはすでに、人種人類学(人種の違いを分類する)のような分野が科学のカリキュラムに含まれていた。1933年にヒトラーが政権を握ると、彼はすぐに優生人種法を制定し、ドイツの人口を「純化」することを目指した。1934年、まず強制不妊手術法が制定され、慢性的なアルコール依存症など、遺伝性の疾患と見なされるものが対象となった。翌年には、ドイツのユダヤ人と非ユダヤ人、遺伝的に優れた者と劣った者の間の性交渉と結婚を禁止した。このような法律は、他の国よりも広く使われていたが、決してナチス・ドイツに限ったことではなかった。結婚を制限する法律は世界中にあり、強制不妊手術は1935年までにスカンジナビアとアメリカの多くの州で日常的に行われていた。
優生学は戦時中もナチスの社会政策と科学研究の両方を形成していたが、強制収容所の囚人に対する戦時中の実験のほとんどは、優生学的な意味を持つものではなかった。特にアウシュビッツでのヨーゼフ・メンゲレの双子研究や、ユダヤ人の人類学的研究などである。1942年にポーランドのタルヌフのゲットーにいた106家族のユダヤ人と1939年にウィーンのスタジアムに収監された440人のユダヤ人は、収容所に送られる前に測定、写真撮影、分類を受けた。しかし、戦時中の科学研究の中心にいたわけではない。ナチズムは決して権威主義的な否定的優生学にのみ頼っていたわけではない。結婚資金貸付(1933)、税金の払い戻し(1934)、子供手当(1936)を通じてアーリア人の繁殖を奨励する積極的優生学的措置が数多くあった。ハインリッヒ・ヒムラーが1935年に行った「生命の泉」計画は、人種的に純粋な子供を妊娠した女性に、出産後に子供を国家に引き渡す代わりに、目立たないように閉じ込めるというもので、参加した女性の半分以上は未婚であった。
1. ドイツ帝国宣伝局の典型的な製品であるこの1936年のポスターは、健康なドイツ人5人の家族は、国家が遺伝性疾患に苦しむ1人のために毎日必要なのと同じ金額で生活できると主張している。
優生学的な人間の完成や改良というビジョンから、マスターレースの創造へと移行したナチスの科学は、瞬く間に明らかに非優生学的な領域へと移行した。しかし、ドイツの科学者たちは、ナチス国家と「ファウスト的取引」を行い、支配者の目的にかなう限り、遺伝学的・優生学的研究を行うことを許したのである。
優生思想の持ち主とは?
優生学団体の会員は、識字率や専門性の高い中産階級に多い傾向があった。優生学は政治のあらゆる分野に訴えたが、その基盤は教養ある富裕層に強固にあった。医学者、心理学者、精神科医、科学者、弁護士、ジャーナリスト、ソーシャルワーカー、教育者、そして生物学者、人類学者、政治家が優生学会の会員の大半を占めた。1901年から1909年までアメリカ大統領だったセオドア・ルーズベルトや、1900年代前半にオーストラリアの首相を3度務めたアルフレッド・ディーキンなど、有名な政治家が優生学を推進した。同じ時代にスタンフォード大学の学長、そして理事長を務めたデビッド・スター・ジョーダンは熱心な優生論者であり、世界中の多くの著名な学者もそうであった。アメリカの雑誌『Genetics』の創刊編集委員会(1916)は、満場一致で優生学を支持した。多くの国の著名な医師や外科医は、優生学的な改革を積極的、消極的に働きかけ、中には政治的な地位に就き、そこから優生学的な社会計画を立ち上げる者もいた。医師は、病気を根絶し、死亡率を改善し、苦しみを和らげるチャンスと考え、あらゆる場所でこの運動に参加した。結核や梅毒などの病気や、てんかん、統合失調症、アルコール中毒などの症状は、強制的なもの(検疫や不妊手術など)であれ、補助的なもの(健康管理や出産前のケアなど)であれ、優生学的な措置に反応すると優生学者は確信した。
優生学者たちの政治的意見は、ナチス・ドイツの極めて特殊な優生学を動機づけるファシズムから、ソビエト連邦の初期のボルシェビキの優生学まで、科学的根拠に基づく人間改良計画まで、さまざまなものがあった。1930年代にスターリンが優生学を否定したことで、ロシアの優生学は事実上閉鎖されたが、優生学は常にどこでも、現状を維持し強化しようとする保守派と、貧困や避けられる病気のない、より公平で明るい未来を示唆する社会主義者の両方を惹きつけた。イギリスやスカンジナビアでは、社会主義者と保守主義者の両方が優生学団体に参加し、フェミニスト活動家も参加した。スウェーデンでは、有力な社会民主党のアルヴァとグンナル・ミルダールが、1930年代にスウェーデンの少子化対策として優生学を推し進め、その活動が北欧の福祉国家を形成する一助となった。彼らは、有給の妊娠・出産休暇、利用しやすい育児、既婚女性の就労の権利などを働きかけたが、同時に、好ましくない人たちの繁殖を抑制することも支持した。このように、否定的優生学と肯定的優生学が共存できる良い例となった。優生学の理念は、専門家による合理的な社会運営への欲求の高まりとよく呼応し、そのようなポジションに就く可能性のある人々をこの運動は引きつけた。
そして何より、優生学は国際的な運動であり、学会や会議、権威ある研究機関で共同して発展していった。研究者や提唱者は、意見の相違はあっても、意見を交換し、その成果を共有した。優生学は少数派の関心事ではなく、科学的知識の進歩だけでなく、人間の状態の改善を約束する国際的な科学の主流であったのである。
優生学、科学、そして文化
優生学の影響力を示す良い指標は、文化にどれだけ深く浸透しているかということである。雑誌の記事、映画、演劇、芸術などには、優生学的なテーマが登場する。汚染された遺伝の危険性は、人気のある筋書きだった。ウィルキー・コリンズの小説『カインの遺産』(1889)は、殺人犯の娘が母親の犯罪性を受け継ぐかどうかで展開される。医師G.フランク・ライドストンの1912年の戯曲『父たちの血』では、高尚な医師が、裕福な家に養子に入ったものの、殺人犯と泥棒の娘で、「真面目な男のミスマッチの蝶」である女性と結婚する。ダイヤモンドを盗んでいるところを捕まった彼女は、父親の歴史を再現するように自殺する: 「彼女は骨の骨、血の血、アヘン食いの自殺者の脳の脳だ!彼女は骨の骨、血の血、そしてアヘン食いの自殺者の脳の脳だ!…彼女が逃げるチャンスはあるのか?” この作品は、演劇評論家だけでなく、ドラマとしては珍しく、アメリカ刑法犯罪学研究所のジャーナルにも掲載され、そのドラマ性よりも優生思想のメッセージに関心が寄せられた。
初期のSF作家は、優生学に大きな関心を寄せていた。H.G.ウェルズは、多くの小説に退化と遺伝子組み換えのモチーフを盛り込んだ。ユートピアやディストピアの小説では、生殖行為が筋書きとして使われた。シャーロット・パーキン・ギルマンの『ハーランド』(1915)では、母性的な感情を集中させるために、女性は一人しか子供を持つことを許されず、不適格者は子育てを禁じられる。1924年にロシア語から英語に翻訳されたエフゲニー・ザミャーチンの1921年の小説『We』は、より有名なオルダス・ハクスリーの『Brave New World』(1931)と似ている。どちらも、生殖は機械化され、人間の人格は合理的な効率のためにコントロールされている。今では忘れ去られてしまったが、当時は国際的に高く評価され、アメリカ、日本、イギリスで演劇、映画、後にテレビドラマ化されたジャン・ウェブスターの大人気小説『Daddy-Long-Legs』(1912)と『Dear Enemy』(1915)も優生学をテーマとしている。『ダディ・ロング・レッグス』は、『レディース・ホーム・ジャーナル』誌に連載された小説で、自分の遺伝がわからないことに不安を抱く孤児の姿が描かれている。大人になった彼女は、『親愛なる敵』の中で、優生学のテキストを読み、知能テストについて議論し、てんかん、精神遅滞、聴覚障害を持つ孤児の監禁を提唱している。
優生学は映画にもよく登場する。1934年のハリウッド作品『トゥモローズ・チルドレン』(イギリスでは『The Unborn』として公開)は、遺伝を理由に出された不妊手術の命令と戦う若い女性の試みを共感的に描いている。(翌年には、アメリカの地理学者エルズワース・ハンティントンが書いた同名の本が出版され、明らかに優生主義的である)。サイレント映画の時代には、優生思想の映画も反優生思想の映画もよく見られ、短命に終わった優生映画社は『誕生』(1917)という1本の映画を製作し、姿を消した。イギリスでは1924年に優生学協会が映画製作を開始し、ドイツでは1935年から1937年にかけて政府出資の映画が製作され、精神遅滞の危険性を強調した。アメリカのプロデューサー、アイヴァン・アブラムソンは、優生学的な映画を数多く製作した。この映画は、新郎が養子であることを知り、幸せな結末を迎える。1932年、パラマウント社は、ウェルズの1896年の小説「モロー博士の島」を映画化した「失われた魂の島」を公開し、小説家オルダスの弟で遺伝学者のジュリアン・ハクスリーを撮影現場に招き、この映画の科学の利用を承認させた。
優生学の語彙は、科学だけでなく、それを取り巻く文化にも由来している。科学的な言葉は、その目的に正当性を与え、中立性、専門性、プロフェッショナリズムを誇示する一方で、より広い文化から得たアイデアは、優生学に親しみを与えた。よく使われた比喩のひとつは園芸で、もうひとつは血液に関するものであった。政治家や科学者は、優生学の目的を説明するために、弱い者を淘汰するガーデニングの比喩を使った。血の純潔や古くからの血統の重要性も広く語られた。日本では、血の純度が優生学の中心的な理想であり、デビッド・スター・ジョーダンは、1901年の『ポピュラー・サイエンス・マンスリー』のエッセイで、血を「人種統合の象徴」と呼んだ。梅毒の代名詞である「悪血」の考え方は、汚染された血液に対する恐怖心を広く表現していた。人種の純度を保つために作られた血液保護法は、東欧や中央ヨーロッパで、特にナチスの時代によく見られたものである。1940年、ルーマニア人はユダヤ人との結婚を禁じられた。「ルーマニアの血」は「民族的、道徳的要素」であると新法は説明した。
優生学に資金を提供したのは誰か
優生学は、政治的背景や文化的背景を問わず、幅広い層に支持されたため、財政的な支援も得られた。福祉国家が発展している国では、公的資金が潤沢に提供されることもあった。スウェーデンは1922年に人種生物学研究所を設立し、ボルシェビキは1919年に社会衛生博物館を設立した。ムッソリーニの時代には、かつて民間の慈善団体であったイタリアの衛生・保険・社会援助研究所が国の支援を受け、1920年にはプロイセン政府が優生学上の問題を諮問するために人種衛生評議会を設立した。ラテンアメリカでの国家支援は、医学界の権威の高まりと、不健康や不衛生な環境に取り組む決意を示した。
優生学は、民間でも盛んに行われた。フランシス・ガルトンは、1904年に優生学研究所を設立するための資金と、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの国立優生学フェローシップを設立するための資金を提供した。1911年に亡くなったガルトンは、教授職を設立するための遺言を残している。オーストラリアの羊農家であったヘンリー・トウィッチンは、1930年に死去した際、遺産の大部分を英国優生学協会に遺した。彼は、家畜の繁殖に関心があったことと、自身の家系が不健全であると信じていたことから、優生学への支援に拍車がかかり、「人類の努力の中で可能な限り最も緊急かつ重要な仕事」であると主張した。また、1920年にはマイソールのマハラジャから多額の寄付を受け、その恩恵を受けている。
しかし、ヨーロッパの人々は、裕福な慈善家たちがアメリカの優生学に示した寛大さを羨ましく思っていた。ニューヨークのロングアイランドにある優生学記録局は、メアリー・ハリマン(鉄道王未亡人)とジョン・D・ロックフェラーから多額の資金提供を受け、その歴史の大半はカーネギー研究所によって管理されていた。西海岸では、柑橘類で財を成したエズラ・ゴスニーと土地開発業者のチャールズ・ゲーテが共同で、カリフォルニアに拠点を置くヒューマン・ベターメント財団を設立し、ポール・ポペノーが不治の病患者の不妊手術を推進した。シリアルで有名なジョン・ハーヴェイ・ケロッグも重要なスポンサーで、1906年にレース・ベターメント財団を設立した。
アメリカの資金は、海外での優生学活動も支援した。ロックフェラー財団の資金は、1927年にドイツのカイザー・ウィルヘルム人類学・人類遺伝学・優生学研究所の設立を支援した。著名な精神科医エミール・クラペリンの精神疾患の遺伝的基盤に関する研究は、1930年代を通じて、ユダヤ系ドイツ系アメリカ人の慈善家ジェームズ・ローブによって資金提供された。カーネギーの資金は、南アフリカでの優生学研究を促進し、スウェーデンの経済学者で優生学者であるグンナル・ミルダルの研究の大部分を支援した。
優生学教育
多くの国の大学が優生学の研究と教育の両方を奨励し、社会生物学や衛生学部を設立し、医学、生物学、社会科学のカリキュラムに優生学を導入した。ドイツの医学部では1914年までに25%が優生学を学び、エストニアでは医学部と神学部の両方で教えられていた。W・E・キャッスルが1916年に出版した大学の教科書『遺伝学と優生学』は、15年の間に4回の改訂を経ている。アメリカ最大の教員組織である全米教育協会は、1921年、「個人がよく読めるようになることと同様に、よく生まれるようになることを教育的手続きによって保証することは、教育者の義務である」と勧告した。1920年代後半には、米国の375以上の大学や多くの高校が優生学をカリキュラムに取り入れ、高校の教科書のほとんどが優生学の原則を支持していた。インディアナ大学では、昆虫学者から性研究者に転身したアルフレッド・キンゼーが、1938年から結婚と家族に関する生物学の講義を行い、絶大な人気を博していた。ドイツでは、ヒトラーが政権を握る以前から人種衛生学が大学で開講されていた。主に女子を対象とした優生学的な道徳は、家庭的な価値観を身につけさせ、早期妊娠を防ぐために、カリキュラムの一部となることが多かった。ビルマでは、1920年代から女子校で衛生学が必修科目となり、イギリスでは、当時「マザークラフト」と呼ばれていた育児、針仕事、料理などさまざまな面で教育された。1939年のフランス家族法では、フランスの学校で人口問題を教えることが義務付けられ、1920年代にはフランスの女子学生を対象とした道徳の授業が導入された。
宗教
優生学は、政治的な意見だけでなく、宗教的な信条にも幅広く対応した。当然のことながら、優生学のさまざまな形態は、宗教的な断層を反映するものであった。原理主義的なキリスト教徒は、進化論を否定し、神の目的を包括的なものとして捉えた。彼らはカトリックと同様、人間が生殖に干渉することを神聖視し、優生学に強く反対した。プロテスタントは歴史的に国家宗教と密接な関係があったため、プロテスタント諸国では国家による優生学がよりオープンに受け入れられるようになったのかもしれない。
第一次世界大戦中、アメリカ人のジョン・ハーヴェイ・ケロッグと会衆派の牧師ドワイト・ヒリスは、人種改良に関する一連の全国会議の中で、優生学をキリスト教の救済の一種であると紹介した。また、優生学の理念を実践する方法を見出した神父もいた。シカゴのエピスコパル聖堂長ウォルター・サムナーは、1912年春、伝染病や心身の異常がないことを証明する健康診断書を提出したカップルだけを結婚させると宣言し、大きな話題となった。この方針は司教の承認を得ており、リベラル・プロテスタントの指導者や改革派のラビたちにも支持された。
2. 戦間期アメリカで流行した「フィッター・ファミリーズ・コンテスト」は、優生学コンテストで高得点を出した家族にメダルを授与するものである。このメダルには、聖書の「我には良き遺産がある」(詩篇16:6)という言葉が記されていた。
優生主義者は、自分たちの信念を宗教的原則に結びつけることもあった。アメリカ優生学協会が「Fitter Family」コンテストで授与したメダルには、詩篇16篇の「Yea, I have a goodly heritage」という言葉が引用されている。ロシアの優生学者ニコライ・コルツォフは、1921年にロシア優生学会の講演で、主要な宗教に匹敵する優生学的宗教を想像したのは、彼一人ではなかった。ガルトンはこの夢を共有し、ジョージ・バーナード・ショーは1905年に「優生宗教以外には文明を救うことはできない」と宣言した。1936年のガルトンの講演でジュリアン・ハクスリーは、優生学は 「未来の宗教の一部」になると予言した。イギリスの心理学者レイモンド・キャテルは、優生学と進化論を組み合わせた「ビヨンド教」と呼ぶ合理的な宗教を作り、貧しい人や病人を死なせ、貧しい国への援助を絶ち、移民を止めることを提唱した。これは、教会組織の社会的責任を強調し、各宗教のリベラル派に多い優生学の宗教的信奉者たちとは明らかに異なるアプローチであった。
カトリックの教義は、多くの優生学的政策に断固として反対し続け、組織的なカトリックのキャンペーンは、しばしば優生学的政策の敗北や防止に貢献した。1930年以前は、社会正義を重視するリベラルなカトリック信者が融和を試みていたが、1930年のローマ教皇回勅『キリスト教の結婚について』によって、そのつながりは断たれた。この長大なカトリックの結婚の教義宣言は、イギリスの優生学評論誌に「中世への反抗的な回帰」と評され、神のみが持つ権力を市民権力が独り占めすることを非難した。また、人工的な避妊や不妊手術を禁じ、国家に貧しい人々の救済を求めるなど、改革派のカトリック信者が優生学に惹かれていた社会問題にも介入した。しかし、優生学の側面はカトリックの実践に影響を与え、一部の司祭は「好ましくない」家系との結婚を避けるよう、教区の人々に控えめに助言した。イギリスのカトリック学者トマス・ジェラードやイタリアのフランシスコ会修道士アゴスティーノ・ジェメッリは、結婚における選択を主張し、促進し、管理することで、カトリックの教えは定義上、優生学的であると主張した。フランスのイエズス会士ルネ・ブルイヤールは1930年、「カトリックの道徳はすべての優生学を非難するものではない」と宣言した。
ユダヤ教と優生学との関係は、20世紀初頭に広まった猛烈な反ユダヤ主義によって複雑化した。しかし、優生学者もユダヤ人も、ユダヤ教の異宗教間結婚の禁止を、人種の純度を維持する優生学的に成功した原理として支持することがしばしばあった。ユダヤ人医師から遺伝学者に転身したレッドクリフ・ネイサン・サラマンは、1900年代初頭に遺伝とユダヤ人に関する論文を発表し、ドイツ系ユダヤ人の遺伝学者リチャード・ゴールドシュミットは、不適正な出生を防ぐための優生不妊手術を率直に提唱していた。ユダヤ人科学者は多くの国で優生学で活躍しており、反ユダヤ主義は決して優生学と一体化していたわけではない。ユダヤ人の再生を目指すシオニストの中には、ユダヤ教を生物学的に理解し、優生学の原理を取り入れる者も少なくなかった。委任統治時代のパレスチナでユダヤ人の母親を対象にしたマニュアルでは、優生学は赤ん坊を適切に世話するための科学であると推奨された。
イスラム教では、カトリックの教義と同様に、神の力は神だけのものであり、アッラーが創造したものを人間が変えることはできないと主張する。純粋な血統を持つ安定した家族を作るための家族計画や、妊娠4カ月の間の中絶は、場合によっては許される。しかし、優生学は、イスラム圏で知られていないわけではないが、イスラム圏で重要な程度に受け入れられることはなかった。
ユダヤ・キリスト教文化圏では、優生学の推進者は、宗教指導者の支援があれば、より大きな受容を得られると認識していた。20世紀初頭に出版された優生学の大学教科書で、ポール・ポペノーとロズウェル・ジョンソンは、1章全体を宗教と優生学に割いて、どの宗教も優生学を受け入れることができるが、キリスト教はその「自然の味方」であると主張している。擁護者たちは、さまざまな教会から意欲的な推進者を口説き落とすこともあった。アメリカ優生学協会は、優生学的説教のコンテストを開催した。イギリスでは、セント・ポール大聖堂の学長ウィリアム・インゲが、1921年にニューヨークで開催された国際優生学会議で演説するなど、国内外に熱心に普及活動を行った。しかし、ほとんどすべての宗派で、優生学の原理と方法の両方について、両義的な意見があった。ウィリアム・インジやウォルター・サムナーの数だけ、優生学の原理と実践、そして生と死に関するその不可避な世俗的判断に警戒する懐疑論者がいたのである。また、カトリックの拠点では、受胎を阻止したり、終わらせたりする優生学的実践が行われていないことから、人間の条件についての世俗的な理解に基づく運動に対して、宗教が力を発揮していたことがわかる。
優生学への抵抗
優生学への反対は、運動の初期から明らかであった。ガルトンの『遺伝的天才』の売れ行きは芳しくなく、その批評はほとんど不評であった。しかし、科学者、特に遺伝学者の間では、特に1930年代から批判の声が高まり、20世紀初頭には遺伝学の研究が盛んに行われるようになった。人間の遺伝についての理解が深まるにつれ、遺伝学者たちは遺伝に関する優生学的な主張に対してますます批判的になっていった。彼らの反論の基本は、優生学が遺伝性のメカニズムを単純化しすぎ、表現型(生物の観察可能な身体的特徴)と遺伝子型(表現型を形作る遺伝的な命令、現在ではゲノムと呼ばれている)を取り違えており、計画繁殖が現実的に達成できることについて誤った理解をしていることだった。優生思想は、子供は両親の形質を完全に受け継ぐという、ますます疑わしい仮定に基づいており、隔離と予防の政策は、この信念に基づいて特に設計されていた。
1930年代になると、このような遺伝性の理解は、世界中の科学者から非難を浴びるようになった。科学的根拠はほとんどなく、遺伝は複雑で多遺伝子性であること、つまり、複数の遺伝子によって形成されていることを指摘したのである。また、遺伝性疾患の遺伝子マーカーを持っていても、自分ではその疾患にかからないという研究結果も出てきている。
科学の単純な利用だと考える人たちがいる一方で、優生学的な政治的側面を嫌う人たちもいた。1936年、ハーバード大学の人類学者アーネスト・フートンは、自身の研究が後に人種差別的だと批判されることになったが、「人種差別と優生学のプロパガンダが混同されている」と考えて、アメリカ優生学会の諮問委員になることを辞退した。動物学者のハーバート・ジェニングスは、優生学者が一般に自分たちの人種や民族の特徴を優れていると考えていると主張し、イギリスの遺伝学者ランスロット・ホグベンは、優生学者が俗物的で階級的傲慢であると非難している。しかし、これらの人物はいずれも優生学との関わりを持っていたのである。フートンは、学会の理事会の席は辞退したものの、購読会員であり続けた。デンマークの著名な遺伝学者ヴィルヘルム・ヨハンセンは、優生学の背後にある科学を批判していたが、1923年に国際優生学委員会に参加したり、1年後に政府の去勢・避妊に関する委員会の委員になることを妨げることはなかった。1930年代に優生学を批判した人々のほとんどすべてが、それ以前の数十年間、程度の差こそあれ、優生学に熱意をもって賛同していた。優生学を支持していた多くの科学者は、その科学的根拠を疑問視しながらも、運動の原則のいくつかを支持し、両義的な批判を続けていた。
中には、ホグベンのように一貫して反対の立場を貫いた者もいた。ノルウェーの解剖学者オットー・ルース・モール(1941年ナチスにより投獄)やイギリスの遺伝学者ライオネル・ペンローズは一貫して批判を続け、その反対は研究だけでなく政治的信念にも基づいていた。優生学は科学の大衆化であり、理論的な集団遺伝学を単純化しすぎて、知能、犯罪性、アルコール依存症などの形質には特定できる遺伝子があり、それを継ぎ目なく繁殖させたり取り除いたりできるという安易で誤った考えを批判する人もいた。モアは、否定的優生学が受け入れられるほど、遺伝の仕組みについて十分に知られていないという信念を多くの人々と共有していた。
科学者たちは、優生学の核心である遺伝に関する理解の欠陥に注目したが、他の批評家たちは、優生学をエリート主義、人種差別主義、そして遺伝の弱い人々を非難する反民主主義的なものと見なした。イタリアの経済学者アキッレ・ローリアは、繁栄と成功を「良い」遺伝子と結びつける優生学に疑問を呈し、貧困と生物学的遺伝の関連性を否定した。労働団体は、優生学は自分たちの構成員に対する攻撃であると考えた。親は子どもを国から返してもらうために裁判を起こし、収容施設の受刑者はしばしば規則の遵守を拒んだり、逃亡を図ったりした。
優生学に不穏な未来を見出す批評家もいた。哲学者のバートランド・ラッセルは、「優生思想に反発する者は、自ら不妊手術の対象になる可能性がある」と警告した。また、ハクスリーの『ブレイブ・ニュー・ワールド』のような、国家の都合で人間が飼育される世界を予見した人もいた。英国の作家G・K・チェスタートンは、「優生思想の人権蔑視」「優生主義者が血を凍らせるような気味の悪い単純さ」と批判している。しかし、多くの場合、特に積極的な優生学が主流を占める地域では、政治的な左派からの支持があった(例えば、スカンジナビア、ポーランド、イギリスなど)。抵抗勢力は運動そのものと同様に多様であり、優生学の実践とそれに対する非難の両方に鋭い違いがあった。
反対派の中には、優生学は過激派を惹きつける疑似科学であるとする人もいるが、現実ははるかに複雑である。しかし、現実はもっと複雑である。もしこの運動がそれほど単純なものであれば、おそらく短期間で、より限定的なものになっただろう。この運動は、アメリカ大陸、アジア、ヨーロッパ、中東、太平洋、アフリカの一部におよび、20世紀を通じて科学や社会政策の中に根強く存在し、ナチズムの敗北後にも続いている。
第5章 1945年以降の優生学
ポール・ポペノーとロスウェル・ジョンソンは、1918年に出版した大学の教科書『応用優生学』の中で、「優生学は論理的必然性によって実質的に存在させられた…社会が直面する最も重要な問題のいくつかについて発言する権利、多くの場合、決定票を投じる権利を求める」と主張している。後の教科書、ジェームス・ニールの『人間遺伝』(1954)は、優生学運動の「薄気味悪い不穏な歴史」を語り、特にドイツとアメリカでは「緩い考え」によって優生学は信用されず、著者は近いうちにもっと妥当な根拠に基づいて再登場することを望んでいるという。このように、約40年の時を隔てて、異なる視点から書かれた文章は、優生学の運命の移り変わりを物語っている。ニールのコメントは、1940年代後半にナチスの戦犯が訴追され、優生学が深く傷つけられた後の状況の変化を示している。ナチスに対する刑事裁判は、優生学に終わりを告げるものではなかったが、その評判はかなり悪くなった。杓子定規な政策よりも福祉や保健と密接な関係にあるラテン系優生学は、強硬な優生学よりも容易に戦後の主流に適応し、必ずしも正確ではないが、最近のナチスの過去と関連付けられることになった。
ニュルンベルク医師団裁判とその影響
1945年から1949年にかけて、100人以上の軍、企業、法律家、医学者のナチス被告が、戦争犯罪の罪でニュルンベルクの国際軍事法廷で裁かれた。この地は、ナチスのプロパガンダ集会が毎年開催されていた場所でもあったため選ばれた。1946年12月、アメリカ人裁判官ウォルター・ビールズを裁判長とする法廷が開かれ、139日間にわたって、残忍な人体実験と殺人の罪に問われた23人のドイツ人に対する「医師団裁判」と呼ばれる証言が行われた。16人が有罪となり、7人が絞首刑を宣告された。しかし、優生学と人種衛生の名の下に行われたナチスの科学・医学実験の重大さにもかかわらず、検察の仕事は必ずしも容易ではなかった。裁判所の管轄は戦時中のみで、ほとんどがそれに先立つ優生学的な不妊手術や安楽死政策よりも、1940年代に囚人に対して行われた実験に焦点が当てられていた。優生学は、主に連想によって有罪になり、訴追の焦点にはならなかった。裁判官たちは、医師たち(裁判にかけられた23人の被告のうち20人を占める)が倫理規定に違反し、科学研究の目的を歪めていたと結論づけた。
優生学が成熟し、人気を博したのは、人体実験への同意がまだ普遍的に受け入れられていない時代であった。ニュルンベルクの弁護団が苦心して指摘したように、ドイツの戦時中の殺人行為は決して特殊なものではなかった。ナチスは確かに囚人に対して同意の欠如を暴力的に極端に行ったが、同意が不可侵であるという原則は、裁判をきっかけに生まれたものである。ナチスの研究には優生学があり、多くの殺戮を正当化するために優生学が使われたのは確かだが、裁判では、極限状態を試すための人間を使った研究や、ドイツ軍で将来使うための新薬に重きが置かれていた。
裁判は判決を下すだけでなく、将来の科学・医学研究を管理し、特に被験者を保護することを目的とした10項目の声明を発表し、一般に「ニュルンベルク綱領」として知られるようになった。皮肉なことに、この最も重要で有名な原則は、もともとナチス政権以前の1931年にドイツで作成された人体実験に関する自主的なガイドラインの一部であり、実施されることはなかった。その内容は、子どもの実験を制限し、実験対象者の「明確な同意」を求めるものだった。ニュルンベルク綱領も同様に、常に任意であり、法的根拠はなく、命令というより理想を表している。ヘルシンキ宣言も同様で、1964年に世界医師会が人体実験に関する倫理規定として策定したもので、広く採用されているが、法的拘束力はない。
優生学とナチズムを結びつけるきっかけとなったニュルンベルク裁判では、戦時中のドイツの人体実験に参加した人たちのごく一部が処罰されたに過ぎない。ナチスの科学に積極的に関与した多くの著名な優生学者が訴追を免れ、科学研究の分野で活躍を続けていた。カイザー・ヴィルヘルム研究所の所長で、ナチス政権下で人種衛生学の教授を務めたフリッツ・レンツは、1946年にゲッティンゲンの人類遺伝学教授となり、戦争前からロマニ人やシンタ人の殺害を正当化していたロバート・リッターは、公衆衛生学の専門家として尊敬されるようになった。戦後も多くの人が大学の遺伝学教室で職を得た。1933年にドイツで制定された不妊手術法の著者であるエルンスト・リューディンは、スイス国籍を剥奪されたが、少額の罰金で済んでおり、それ以外の処罰は免れた。彼は、人種衛生学が国際的に高く評価され、ヒトラー政権下でそれが歪められたのは自分のせいではないと常に主張していた。
優生学研究者たちは、自分たちの科学はナチスに利用され、歪められたものであり、それを回復させることは可能であり、そうすべきであると考えた。彼らは、スカンジナビアや特にアメリカでの優生学に関する法律や政策の成功を指摘した。1945年以降の数年間は、優生思想や理念の終焉というよりも、その再編成や言い換えが行われたのである。多くの支持者にとって、戦後の最大の関心事は、「優生学」という用語があまりにも汚染されすぎていて、このままではいけないのではないかということであったが、優生学の原理そのものが問題なのではないかという疑問を持つ者ははるかに少なかった。優生学的政策は1945年に消滅したわけではなかったが、ほとんどすべての場所で名称が変更された。「優生学」という言葉は、いくつかの顕著な例外を除いては、ほとんど消えてしまった。
多くの優生学研究機関は、単に名前を変えただけであった。スウェーデンの人種生物学研究所は、ウプサラ大学の医学遺伝学部に変わり、香港優生学連盟は、長期にわたって避妊を重視してきたことから、香港家族計画協会となった。イギリスの優生学協会代表のカルロス・ブラッカーは、優生学的な政策をレッテルを貼らずに進める「クリプト・ユージェニクス」(Cryptoeugenics)と呼ばれるものを提唱した。ナチズムとの関係を認めたくないブラッカーは、優生学とドイツのファシズムとの距離を置く必要性を理解したのである。デンマークの遺伝学者テージ・ケンプやイギリスの科学者ジュリアン・ハクスリーなど、世界中の多くの科学者が優生学を支持し続けていた。1956年にコペンハーゲンで開催された第1回国際人類遺伝学会議には、優生学の団体が協賛していた。
人口抑制
1950年代から1960年代にかけて、優生学者が注目したのは、地球規模の人口抑制という新しい政治的関心であった。第二次世界大戦の技術によって平均寿命が延び、乳児死亡率が改善されたことが明らかになるにつれ、「人口爆弾」(1968年にベストセラーとなったポール・エーリック夫妻の著書のタイトル)という新しい語彙が生まれた。抗生物質や農薬の登場、食糧配給制やより効率的な農業による栄養の向上、衰弱した病気を最小限に抑えることに成功し、戦争中は毎年約1500万人が地球上の人口を増やした。人口の急増は、飢餓や不満を悪化させ、ヨーロッパの支配者からの独立を求める植民地の要求を加速させるという見方が多かった。また、アメリカやその同盟国は、政治情勢が極端に変化していたため、独立したばかりの国々がソ連の影響下に置かれ、不安定になることを懸念していた。先進国で定着している少子化は、文明化の代名詞となった。
1950年代後半になると、アメリカの対外援助、ロックフェラーやフォードなどの慈善財団、国連、そして医師のクラレンス・ギャンブル(石鹸会社プロクター&ギャンブルの後継者)などの富裕層から、民間と公共の資金が避妊プログラムと研究に注ぎ込まれるようになった。ギャンブルはマーガレット・サンガーと密接に協力し、1930年代には、貧しい人々の家族の数を減らすことを目的とした試験的な避妊プログラムに数多く資金を提供した。ドワイト・アイゼンハワー大統領は1958年、アメリカの国家安全保障会議で、世界の安全保障に必要なのは、誰でも買える「2セントの効果的な避妊具」であると語った。欧米では、容赦ない人口増加が資源を圧迫し、世界の生活水準を脅かすという懸念があった。そこで新たに打ち出されたのが、人口ゼロ成長、つまり出生と死亡が互いに釣り合うような交換率戦略である。
1964年、アメリカの経済学者ケネス・ボールディングは、子孫を残すための市場性のあるライセンス制度を提案した。1968年、人口問題評議会(1950年代にロックフェラーの支援で設立)は、ウォルト・ディズニー社に家族計画映画の製作を依頼した。ドナルド・ダックが出演し、さまざまな言語で提供されたこの10分間の映画は、主に発展途上国の観客を対象に、家族計画の知恵と、人口問題評議会の言葉を借りれば「小さな家族の規範を支持する態度」を称賛するものであった。ノーベル物理学者で熱心な優生学者であるウィリアム・ショックレーは、IQの低い人たちの不妊手術を奨励するために現金による奨励金を提案した。
しかし、全体として、人口と生殖に関する新しい強調事項は、死亡率の低下と出生率の上昇がもたらす大規模な効果よりも、政治を脅かす無産者や標準以下の個人に関するものであった。バチカンが中絶と避妊に長年反対してきたにもかかわらず、避妊はそれ以前の時代よりも顕著で広範な役割を果たすようになった。しかし、1950年代から1960年代にかけては、公的機関や任意団体に優生学者が多く、世界的な人口過剰が圧倒的な関心事となった。
出生率の急増に対する懸念は、欧米に限ったことではなかった。インドとパキスタンは戦後、人口増加を抑制しようと努めた。インドでは、1951年に家族計画が正式な国策となった。1958年、インド北部の国会議員が「好ましくない精神的・身体的状態」の人を不妊手術する法律を提案し、失敗に終わったが、1966年にインドの指導者に選ばれたインディラ・ガンジーは、家族計画の目標を、年間の子宮内挿入(IUD)600万件、不妊手術123万件とした。10年も経たないうちに、彼女の悪名高い集団不妊手術キャンペーンは世界のトップニュースになった。1974年から1977年にかけて、インドでは約1200万件の不妊手術が行われたが、パイプカットが短時間で安価に行えたため、女性よりも男性の方が多く行われていた。政府職員は、不妊手術に協力しなかったり、政府のノルマを達成できなかったりすると、停職や賃金不払いになるなど、人々を説得する大きな圧力にさらされた。不妊手術を拒否した教師は減給される可能性があり、灌漑用水を受ける村では、地域の不妊手術の目標を達成できなかった場合、水の供給が停止される危険性があった。人々は、不妊手術に同意する代わりに、食用油の缶やトランジスタラジオなどの小さな贈り物を提供された。このキャンペーンは大不評で、1977年にガンディーと彼女の所属する議会党は大敗を喫した。しかし、1983年、国連は、中国の国家家族計画委員会の銭新中委員長とともに、彼女に新しい人口賞を授与した。これは、人口過剰の影響に対する世界的な懸念が強く反映されたものである。
1966年に始まったシンガポールの国家家族計画計画も人口削減を目標とし、1970年には避妊と中絶を合法化した。1972年には、代替可能な出生率を維持することを目的とした2人っ子政策を導入した。1972年、政府は2人っ子政策を導入し、学校教育や住居の提供などのインセンティブを与えるとともに、さらなる出産の抑止を図った。1980年代には、高学歴の女性がより多くの子どもを産むことを奨励する、明らかに優生学的な政策への転換が行われ、1987年には、経済的に余裕のある女性が大家族を持つことが奨励された。これらはすべて、優生学者が長年にわたって提唱してきた戦略である。1918年には、ポール・ポペノウとロスウェル・ジョンソンが、女性教師(彼らは「優生学的に優れた人」と呼んでいた)が未婚のままだと遺伝子異常が起こることを警告し、結婚して子孫を残すことを奨励する救済策を提案している。
このように、ある者は出産を促し、ある者は出産を控えるという混在したメッセージは、明らかに以前の優生学的政策を引き継ぐものであった。1960年代、東欧のソビエト連邦の衛星国では、出生を促進するための協調的な取り組みが少数民族には及ばず、彼らは大家族であることを非難され続けていた。チェコスロバキアでは、ロマ人女性がソ連政権下でも独立後でも卵管結紮の強制に直面した。ルーマニアでは、1966年に25歳以上の子供のいない成人に課税し、避妊を奨励し、妊婦を監督することで、適切な人たちの繁殖を促そうとした。大家族を持つ者は、より良い住居とより多くの配給を受けられるだけでなく、産休や育児支援も受けられるようになった。このキャンペーンは、ニコライ・チャウシェスクが政権を握っていた40年間続けられ、その目的は達成されなかったものの、何よりも母性保護を推進し、女性の権利に悪影響を及ぼした。
インドではインディラ・ガンディーが失脚した2年後、中国は一人っ子政策を打ち出し、さらに1995年には母子保健法(当初は優生保護法とされていた)で、遺伝性疾患のある人は不妊手術や永久避妊を結婚の条件とし、遺伝的欠陥のある胎児の中絶を許可している。また、肝炎や性感染症などの病気にかかっている人は、治療が成功するまで結婚を延期することが義務づけられた。施行はまだ不十分で斑点があり、無視されているところもあるが、この法律はまだ存在している。
1985年、ペルーは米国国際開発庁の援助を受けて、貧困削減策の一環として、中絶と不妊手術を違法化し、避妊具の無償提供を開始し、性教育を導入し、生殖選択の自由を保障した。また、高地の農村を中心に不妊手術のキャンペーンも積極的に行われた。インドと同様、国家公務員はノルマを達成するよう圧力をかけられ、その結果、1986年から1988年にかけて、主に先住民のケチュア族とアイマラ族の女性約25万人が、しばしば強制的な条件のもとで不妊手術を受けた。1995年に北京で開催された国連女性会議で、ペルーのアルベルト・フジモリ大統領は自身の政策をフェミニストの躍進と称したが、実際には20世紀を通じて優生学者が好んだ人種差別的不妊手術と酷似した政策であった。
スカンジナビアでは、1930年代に初めて実施された不妊手術政策が戦後も実施されたが、優生学的な理由で実施されたものははるかに少なかった。アメリカでは、1970年に制定された家族計画・人口研究法により、家族計画のための資金が確保され、不妊手術に対する連邦政府の資金援助が禁止された。この法律は、裕福でない家庭にも家族計画への幅広いアクセスを提供したが、診療所にとっては不妊手術を提供し、奨励する機会にもなった。実際、貧しい女性やマイノリティの女性は、より永続的でない避妊方法ではなく、不妊手術を選択するよう強い圧力を受けることがしばしばあった。1973年、サウスカロライナ州のエイケン郡病院の3人の医師は、生活保護を受けている女性患者に対して、不妊手術に同意しない限り、3回出産したら治療を拒否すると告げた。その年、この施設で出産した生活保護受給者の約3分の1が、結果的に不妊手術を受けた。
一連の有名な裁判は、米国で非合意または準合意による不妊手術が続いていることを公にした。1973年、南部貧困法律センターは、14歳と12歳のアフリカ系アメリカ人の姉妹のために、多くの訴訟の最初のものを提出した。彼らは、クリニックのスタッフから知的障害者とみなされ、若い方の姉妹は身体障害者でもあった。この2人の姉妹は、アラバマ州の連邦政府出資のクリニックで不妊手術を受け、読み書きのできない母親が2人のために避妊手術の同意書と思われるものにサインした。この事件は、同じくアラバマ州で行われたタスキギー梅毒実験(アフリカ系アメリカ人の梅毒の経過を追跡するため、400人の黒人男性に梅毒の治療を受けさせなかった)の暴露のすぐ後に起きたため、大きな注目を集めた。この事件をきっかけに、同じような扱いを受けた女性たちが、北と南カロライナ、カリフォルニア、ネイティブ・アメリカンの女性を治療するインディアン・ヘルス・サービスなどで訴訟を起こすようになった。アメリカの深南部では、有色人種の女性に不妊手術を施すことが広く行われており、地元では「ミシシッピ盲腸切除術」と呼ばれていたほどだ。戦争前の優生学と同じように、不妊手術の対象者は圧倒的に少数民族で、その多くは精神障害者として分類された。ノースカロライナ州では、合法的に不妊手術を受けた人の約40パーセントが黒人だった。
1995年、レイラニ・ミュアは、「白痴」として不妊手術を受けたことが不当であることを証明するためにIQテストを受け、カナダのアルバータ州を訴えた。彼女は多額の和解金を獲得し、750件もの同様の訴訟の波が押し寄せた。1936年のクーパー・ヒューイット裁判を思い起こさせるような別の事件では、15歳のときに母親の要請で不妊手術を受けた女性が、許可を与えた裁判官を訴えるという入札に敗れた。母親は自分が知恵遅れであると主張していたが、不妊手術が許可される前にそれ以上の証明は必要なかったのである。インディアナ州で起きたこの事件(Stump v. Sparkman、1978)は最高裁まで争われ、不妊手術を命じた裁判官は技術的な法的理由から訴えられることはないという判決が下された。
最近では、ノルプラント(1991年発売)のような避妊用インプラントが利用できるようになったことで、アメリカでは経済的なインセンティブが働き、生活保護を受けている女性にはインプラントを受け入れるための費用を支払い、有罪判決を受けた犯罪者にはインプラントを装着することを勧め、懲役刑を軽減する制度ができた。1990年代初めには、いくつかの州で、福祉援助と女性のノルプラント使用を結びつける提案がなされ、強制的な避妊の見通しが立ち、以前の時代の優生思想と新しい技術を結びつけることになった。
遺伝学、生物学、そして優生学
戦後、国境を越えたグローバルな人口の流れが強調されるようになったのは新しいことかもしれないが、出生数を増やすのも減らすのも、予防(負の優生学)あるいは奨励(正の優生学)を促す優生学的政策としておなじみだった。ヒト遺伝学の急速な発展により、これらの古い伝統に、生殖を操作する新しい技術、出生前あるいは受胎前に性別だけでなく問題を予測する能力、体外あるいは子宮内、妊娠中の身体の内外を問わず積極的に介入する能力が加わった。この生物学と遺伝学の同盟は、しばしばレプロジェネティクスとして知られている。
多くの批評家は、再生医療技術が現代の優生学にあたると非難している。1969年の時点で、分子生物学者のロバート・シンスハイマーは遺伝子工学を新しい優生学と呼び、「倫理的ジレンマが残っている」と認めている。遺伝学や分子生物学の研究の多くは生殖に関わるものであり、支持者は、以前の優生学のような厄介な行為もなく、現代の価値観の負担もなく、生殖に関する意思決定に取り組む方法を提供すると主張している。しかし、優生学の擁護者たちは、その歴史を通じて同様の主張をしていた。人間の繁殖に対する科学的アプローチは、事実と科学に基づいた、価値のない中立的なものだと主張する。遺伝子の進歩によって、初期の優生学者が主張したことが否定されることが多々あるのは確かだが、現在の主張がいつの日か不十分なものになるか、あるいは虚偽のものになるかどうかは分からない。社会学者のヒラリー・ローズは、優生学と遺伝学を「結合双生児」と呼び、優生学研究の多くが依存してきた双子研究を皮肉っている。新しい技術の支持者たちは、ローズの提案とは根本的に異なる解釈を示している。例えば、社会医学のシーラとデビッド・ロスマン教授は、生殖工学と優生学との関連を否定し、遺伝子操作の可能性をよりよく表現する方法として「強化」という用語を提唱している。
生殖に関する遺伝カウンセリングは、第二次世界大戦の終了後まもなく始まった。初期のカウンセリング技術は、優生学研究の全盛期に優生学記録局で開発された血統図と同じものに頼っていることが多かった。スウェーデンでは、カウンセラーの第一世代が仕事の過程で同様の血統情報をまとめた。イギリスでは、1946年にロンドンのグレート・オーモンド・ストリート病院に、優生学者ジョン・フレーザー・ロバーツが院長を務める最初の遺伝学クリニックが開設された。遺伝カウンセリングは、特に中絶が合法となった地域では、出産前、ひいては妊娠前のケアの主要な部分を占めるようになった。欧米では、欠陥のある胎児を生まないようにすることが、すべての人にとって最善の利益であるという信念に基づき、カウンセリングの初期は欠陥児の誕生を防ぐことが主流だった。20世紀後半になると、障害者擁護団体がこの姿勢を批判し、完全な赤ん坊だけが価値を持つという世界観を批判し、健常者と障害者を区別する意味を否定した。その結果、非直接的なカウンセリングへの移行は世界的に共有されておらず、多くの場所でカウンセリングは望ましい赤ちゃんとそうでない赤ちゃんを区別する処方的なものとなっている。
羊水検査(胎児の遺伝的体質を診断する出生前診断)は、生殖医療に遺伝学を応用する道を開くものであった。羊水穿刺による胎児異常の発見は、1960年代後半にイギリス、そしてアメリカで広まった。1972年に針を誘導する超音波が処置の一部となり、処置はより安全になった。しかし、広く普及しているとはいえ、コストがかかるため、世界のほとんどの地域で、より裕福な女性に限定して使用されている。遺伝子検査のもう一つの一般的な用途は、β-サラセミア、フェニルケトン尿症(PKU)、鎌状赤血球貧血など、すぐに治療を要する遺伝性疾患の新生児のスクリーニングである。PKUは、肝臓の劣性代謝異常で、多くの食品に含まれるフェニルアラニンの代謝を助ける酵素が欠如している。代謝されないフェニルアラニンが多いと脳の発達が遅れるが、生後間もなくからフェニルアラニンを含まないか制限した低タンパク食を与えることで防ぐことができる。PKUの新生児スクリーニングは、1960年代までに多くの国で普及し、1967年にはアメリカの43の州で義務化された。現在では、20種類ほどの疾患の出生時スクリーニングがアメリカのほぼすべての州で義務付けられ、親の同意も必要なく、広く受け入れられている。
一方、鎌状赤血球貧血は、遺伝子スクリーニングがいかに論争を巻き起こすかを示すケーススタディである。鎌状赤血球貧血の赤血球は酸素をうまく運ぶことができず、形が変わりやすい(鎌状)ため、血管を塞いでしまい、非常に危険な病気となる可能性がある。鎌形赤血球貧血は世界中の多くの人々に見られるが、アメリカではアフリカ系アメリカ人に偏って発症するため、初期の予防策は黒人の集団に焦点を当てた。1970年代、各州の保健所が人種別に鎌状赤血球のスクリーニングを義務付けると、黒人の医師や活動家たちは、まだ治らない病気なのになぜスクリーニングが必要なのかと疑問を呈し、この計画は以前の優生学を思わせる人種差別と解釈した。また、鎌状赤血球症と鎌状赤血球形質(健康な人が遺伝子を持っていても発症しない)を区別することが重要だとも指摘された。1972年に制定された「全米鎌状赤血球症対策法」は、その前文で「200万人のアメリカ人が鎌状赤血球症に罹患している」と誤認させた。この誤情報は、黒人に大きな衝撃を与え、パニックを引き起こした。1970年代初頭、陸軍の高地訓練で4人の黒人新兵が死亡した後、空軍士官学校は鎌状赤血球の保有者を不適格とし(1981年まで)、多くの航空会社は鎌状赤血球の保有者を着陸させたり解雇したりした。保険会社は、鎌状赤血球の持ち主だけでなく、病気の持ち主の健康保険料も値上げした。ある州では、学校への登校時に鎌状赤血球の検査を義務付けていた(この政策は、本稿執筆時点では子供の予防接種と同様に再検討されている)。この政策は短期間で終了し、差別的で無意味、しかも間違った科学に基づくものだと考えた黒人コミュニティは怒った。
しかし、いくつかの地域では、スクリーニングプログラムが大きな成功を収めている。β-サラセミア(鎌状赤血球貧血と同じ劣性遺伝子の疾患)が非常に多いキプロスでは、検診に目覚ましい成功を収めた。1972年にギリシャ側で、両親の協力のもと、遺伝子スクリーニングとカウンセリングを通じて、患児の出生を予防することを目的とした広報活動が行われた。1977年に胎児鏡検査が可能になると、圧倒的多数の女性が検査を選択し、罹患した胎児を死産させることを選択した。トルコ領キプロスでは、ベータサラセミアの出生数が減少したことに後押しされ、1980年に婚前スクリーニングが義務化された。この政策は優生思想に基づくものであることは明らかであったが、実質的に確実な検査が可能な、よく理解されている1つの疾患に限定したものであったため、差別の嫌疑は晴れた。正教会の指導者との交渉の結果、検診とカウンセリングは中絶率を高めるのではなく、むしろ減少させると主張し、1983年にギリシャ側もこれに追随した。キプロスのプログラムは大成功を収め、短期間でβ-サラセミアを撲滅することができた。キプロスの政策は、キャリア同士の結婚を禁じておらず、義務的な要素はスクリーニングだけだ。中絶に反対する親たちは、1999年以来、着床前診断を受けることができ、無料で胚の検査を受けることができる。興味深いことに、キプロスのモデルを同じ病気の影響を受けているギリシャで模倣しようとする試みは失敗に終わっている。
イスラエルでは、キプロス方式が採用され、遺伝的生殖技術が患者の負担にならない程度に利用できるようになっている。婚前検診は選択制だが、受診率は高く、イスラエルの非正統派ユダヤ人の間では中絶の烙印を押されることはほとんどない。(イスラム教徒にとっては、イスラム法は妊娠120日以内の中絶を全面的に禁じてはいない)。国は、胎児の異常を含む一部のケースで中絶費用を負担し、2人までの子供のための体外受精治療や妊娠中の代理出産のための胚移植も負担している。現代のイスラエルの政策は、このように明確な出生主義であり、出生成績を向上させる方法として妊娠前の期間を対象とした新しい遺伝学的研究に大きく依存している。
もう一つの成功したスクリーニングプログラムは、アメリカを拠点とするDor Yeshorim組織(Generation of the Upright)のものである。1983年、アシュケナージ・ユダヤ人に多く見られる常染色体劣性遺伝のテイ・サックス遺伝子の検査を開始し、遺伝子を持つ者同士の結婚を防ぐことを目的としている。現在では、11カ国で16種類の劣性遺伝子の検査を実施しており、ホームページでは、健康的な結婚を促進することの重要性を示している。これは、優生学的な目的と明らかに結びついている。
1990年に着床前遺伝子診断(PGD)が開発され、体外受精卵に遺伝的な欠陥がないかどうかを調べることで、親が妊娠を継続するかどうかを選べるようになった。羊水検査とは異なり、PGDでは赤ちゃんの性別も判明するため、古くから男児を好む一部の国では、性別選択の目的で禁止されている。1996年に始まったインドでの禁止令は広く反故にされ、多くの場所で、以前の時代によく見られた女性の嬰児殺しが、検査を受けられる人たちの間で胚の選択に急速に取って代わられている。
遺伝子技術は、病気や欠陥の治療や予防だけでなく、生殖機能の強化も可能にし、少なくとも富裕層の間では、将来の子供の遺伝子構成に選択の要素を持たせることができるようになった。もちろん、これは優生学運動の夢であった。推進派は、この新しい技術を人間の苦しみを減らす手段として歓迎し、中には、技術が存在する以上、人間には治療だけでなく、強化する義務があると主張する者さえいた。分子生物学者のリー・シルバーのように、生殖工学は市場によってのみ制約されるべきであると主張する人もいる。ロスマン夫妻にとって問題なのは、「科学が自らの課題を設定すること…幸福が臨床治療を推進すること…利益動機がほとんど無制限に許可され、個人が自律性と選択を行使すること」である。楽観主義者は、胎児を強化する余裕のある人には何の障害もないはずだと主張する。シルバーは、『エデンを作り直す』という名著の中で、私たちが「生まれた後の親の特権」を喜んで受け入れていることから、「生まれる前にそれに反対することは非論理的である」という立場をとっている。
1998年、アメリカ人類遺伝学会は、生殖の選択における強制に反対する声明を発表した。翌年、生命倫理学者のグループが発表した論文「優生学について不道徳なことは何か」は、強制と強要を「道徳的に好ましくない」とした。彼らは、真の平等とは「優生学的な選択を……望むすべての人ができるようにすること」であると主張した。親が子供の髪の色や技能を選択しても、何の害もないと彼らは主張した。彼らの考えでは、それは特定の価値観や信念を持った子供を育てることとほとんど変わりないのである。優生学が問題なのではなく、その適用が誤っていたのだ。
シルバーやロスマン夫妻などが個人の選択の原則を主張する一方で、哲学者のジュリアン・サヴレスクとイングマール・パーションは、親には最良の子供を選ぶ責任があり、彼らが言う「道徳的向上」は人類の生存に不可欠であると主張している。生命倫理学者のジョン・ハリスは、生まれてくる子供に遺伝子疾患があるかもしれないと疑いながら出生前検査を受けない女性は、道徳的怠慢の罪を犯していると主張している。ハリスは優生学との関連性を避けず、障害は劣った生き方であると同時に、生物学的知識の進歩により、ますます回避可能になっていると力強く主張している。
戦時中の人工授精の構想が復活したのは、このような姿勢と、遺伝学技術の高度化のおかげであった。ハーマン・ミュラー自身、1960年代前半に人工授精の構想に立ち返った。ミュラーの「突然変異の負荷」は、医療介入や福祉措置によって、欠陥のある遺伝子が早期に排除される可能性が低くなると仮定した。その結果、人間の遺伝的負荷(集団における悪い遺伝子の発生率)は上昇し、新しい突然変異が現れる速度も速くなると彼は予測した。その結果、約8世代後には、より病弱な人々が増え、放射線被曝の増加によってさらに加速されることになると彼は計算した。ノーベル賞を2度受賞し、鎌状赤血球の研究者として著名なライナス・ポーリングも、ウィリアム・ショックレーと同様に、医療介入と電離放射線の二重の負担で、人間の突然変異率が高まっているというミュラーの懸念を共有した。
ミュラーの解決策は、高負荷集団の生殖を減らすと同時に、優秀な遺伝子を持つ人々を育てるという、二重の意味で、なおかつ実質的に優生的なものであった。このような状況の中で、ミュラーの「優生遺伝」という考え方が、生まれながらにして優秀な人々の繁殖を促し、安定した均衡を実現する手段として再び登場したのである。1950年代初頭に精子の冷凍保存に成功したことをきっかけに、彼は現在「生殖細胞選択」と呼んでいるものを提唱した。よくあることだが、資金提供者は裕福な個人、この場合はカリフォルニアの眼鏡レンズメーカー、ロバート・グラハムであった。しかし、ミュラーの死後、グラハムは1971年に「生殖細胞選択研究所」を設立し、ノーベル賞受賞者の精子だけを集めて冷凍保存し、諮問委員会にはレイモンド・キャッテルのような率直な優生学者が名を連ねた。グラハムのエリート主義的な事業は眉唾で、1999年に中止されたが、精子バンクはその後、デンマークや米国を筆頭に、生殖医療の風景の一部と化した。優生思想の愛好家たちが何世代にもわたって無視し続けてきた、出生数がやがて平均値に逆戻りするという知識にもかかわらず、求められる才能やその他の望ましい特徴を持つ人の精子はより高価である。
反対意見
新しい遺伝子技術によってもたらされる生殖の可能性に対する反対論は、多くの問題に焦点を当てている。批評家たちは、胚の完全性を追求することは、障害者に対する差別を助長する可能性があるとし、親の期待を不当に高めることによって子供たちに害を与えるかもしれないと主張する。また、遺伝性疾患の希少性から、広範囲に渡る胚スクリーニングは贅沢であるとする意見もある。現在、科学者の大半は、遺伝的体質を病気の傾向の一要素に過ぎないと考えており、生物学的要因に偏重するあまり、経済的・社会的条件の役割が過小評価されることに懸念を表明している人が多い。遺伝学者のライオネル・ペンローズとセオドシウス・ドブザンスキーは、第二次世界大戦争前にこの点を指摘し、良い遺伝子と悪い遺伝子を識別するには環境的な背景が必要であると訴えたことがある。鎌状赤血球遺伝子は、ヘテロ接合体の形質でマラリアに対する抵抗力を持つため、単純に「悪い」遺伝子というよりは、特定の環境下で明確な利点をもたらすというのが彼らの発見の良い例だ。このような批判は、今世紀初頭の優生学に対する、科学的な理解を疑うような批判を思い起こさせるものである。
オルダス・ハクスリーやエフゲニー・ザミャーチンの小説は、優生学が国家の効率性を追求する喜びのないものであり、人間はほとんど決められた仕事をこなす機能的な存在に過ぎない、と描いている。このような優生思想の読み方は、戦後も根強く残っている。イギリスの社会学者マイケル・ヤングは、風刺的な未来像『メリトクラシーの台頭』(1958)の中で、国民が知的地位を示す国家情報カードの携帯を義務づけられ、よく管理され、無血で、効率的な未来を描いている。このカードを発行するのは、全権を持つ優生学研究所である。戦後のSFでは、遺伝子操作された登場人物の人間性が完全に実現されることはなく、遺伝子操作によるディストピックな未来が暗示されることが頻繁にあった。
人種と遺伝学
優生学と同様に、遺伝学に対する大きな批判の一つは、人種という争点に焦点を当て続けている。1940年代以降、著名な科学者たちは、人種と科学の関係について一連の宣言を発表している。最初のものは1939年、遺伝学の権威32人が「遺伝学者宣言」と呼ばれるものに署名したものである。この宣言は、人種の生物学的根拠を否定する一方で、社会的善の手段として優生学を位置づけ、産児制限を支持し、貧困と飢餓の軽減を呼びかけるものだった。戦後、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の初代所長に就任したジュリアン・ハクスリーも、その一人である。1950年、彼の指導の下、ユネスコは「人種は生物学的現象ではなく、社会的神話である」という内容の声明を発表した。この声明は、当時コンセンサスが得られていなかった科学者の間では評判が悪く、反優生的な要素が含まれていると理解して反対する人もいた。ユネスコは半世紀後の1995年にも声明を発表し、人種は生物学的に有用でも正当でもないことを宣言した。現代の主流科学は人種差の生物学的根拠を否定しているが、議論はまだ終わっていない。活動家たちはしばしば、集団遺伝学に残された人種概念が新しい語彙を身にまとっているのを目にする。
遺伝学における人種研究の持続は、新しい研究を優生学的な偏見から遠ざけるものではない、と批評家は言う。人種が変数として働き続けていることは、1945年以降、強制的な不妊手術が、とりわけ貧しい女性や少数派の女性を対象として行われるようになったことに表れている。人種差はまた、知能の測定基準における説明要因として使われ続けている。知能指標と不妊手術の両方が優生学と関連することは避けられない。1969年、アーサー・ジェンセンは、知能はほとんど遺伝的要因によって決定され、アフリカ系の人々は知能テストで最も低いスコアを示すと主張した。これは、半世紀前にブリガムやターマンなどが主張していたのと同じだ。ジェンセンは、「白人と黒人の平均的な知能の差には遺伝的要因が強く関与している」という仮説は妥当だと考えたが、環境要因を完全に否定したわけではなかった。彼の師であるイギリスの心理学者ハンス・アイゼンクは、白人は優れた知的人種であると主張し、これに同意した。
ジェンセン、アイゼンク、そして彼らの信奉者たちは、国際高等人種研究所に集まり、その機関誌『Mankind Quarterly』は、主流の科学雑誌に掲載されないことが多くなった研究の出口を提供するものだった。IIARRは、裕福な個人の寛大さに依存する優生学的組織の一つであった: ウィクリフ・ドレイパーは、優生学のプロジェクトに資金を提供した長い歴史を持っていた。ウィクリフ・ドレイパーは、優生学のプロジェクトに資金を提供した長い歴史を持っていた。彼は、戦間期に「人種交配」研究を支援し、1937年には「人種改良」研究を支援するために「パイオニア基金」を設立した。この基金は現在も同様の研究を支援し続けており、多くの論者が人種差別的であると同時に優生学的であるとみなす一連の研究に関連している。1994年には、不法移民とその子どもたちが州のサービスを受けられないようにするカリフォルニア州の提案187号の支援者の一人だった。1950年代には、下院非米活動委員会がアフリカ系アメリカ人の劣等性を証明し、アフリカに送還するよう勧告するのを助けたこともある。
ジェンセンのような研究が登場したのは、優生学に基づく法律や政策が脚光を浴びていた時期であった。アメリカやカナダでは、1970年代に強制不妊手術法の廃止が始まった。スイスは1980年代、円卓の子供たちを家族から引き離したことを謝罪した。1996年にはスウェーデンが強制不妊手術を受けた人々への賠償を開始し 2000年代初頭にはアメリカの多くの州が不妊手術の制度について正式に謝罪した。しかし、このようなことは、世界中の少数民族や貧困層の女性が、本人の同意なしに、あるいは強制的に不妊手術を受け続けている中で起きていたのである。優生思想は公には嘲笑されたかもしれないが、関連する政策は、新しい技術が生殖を操作するというこれまで不可能だった夢を現実のものにしたときでも、しばしば存続した。遺伝性への懸念が消えたわけではなく、遺伝学が新たに重視されるようになったことで、その存続が確実となった。遺伝子が性的嗜好や特殊技能を決定するという誤った概念は、依然として根強く残っており、科学的研究は遺伝子と環境との関係を探求し続けている。そして、遺伝子と環境との関係を探る研究が続けられている。
前途多難
優生学は、ある場合には出産を阻止し、ある場合には出産を促進することで、生殖をコントロールする手段として始まった。この原則は、戦後の遺伝子発見の時代にもそのまま受け継がれているが、生殖を操作したり予測したりするオプションが加わってきている。ますます洗練された再生医療が人間の生殖をより大きくコントロールすることを可能にするにつれ、誰が意思決定をコントロールするかに重点が移ってきた。1920年代と1930年代の優生学全盛期には、子育てや移民、移動の自由に対するあらゆる制限を正当化する理由として「公共の利益」が頻繁に唱えられた。「国家」や「人種」は、さまざまな政治情勢において個人の自由よりも優先された。しかし、旧東欧圏、米州、アジアの主要国において、国家レベルの介入は決して消えてはいない。
例えば、2011年、インドのラジャスタン州では、不妊手術に同意した人に多額の奨励金を支給する制度が始まり、BBCはこれを「不妊手術のための車」と名づけた。家族計画のインセンティブとして消費財を利用するのはラジャスタン州だけでなく、消費者優生学とでも呼ぶべき新たな重点を置くことを示唆している。個人は生殖行為と引き換えに物質的な利益を得ることができるだけでなく、個人やカップルは自らの生殖を管理するために、増え続ける遺伝子の選択肢を利用することができる。クウェートからカンザス、インドからアイスランドまで、世界中のクリニックが、胎児の異常を避けるために着床前診断を選択するにしても、スクリーニングを選択するにしても、親がどのような子供を望むかに直接関わる生殖の選択肢を提供している。性別の決定や知能の向上も選択肢に含まれるが、現在のところ、認知障害や身体障害が主な焦点となっている。消費者優生学は、生殖労働のアウトソーシングも提供する。何世紀も前の裕福な女性は、乳児に母乳を与えるために看護婦を雇っていたが、今日では代理出産は、貧しい国の女性が生活費を稼ぐための方法となっている。
こうした技術や機会は、過去半世紀ほどの間に起こった他の重要な歴史的潮流と同様に、生殖の風景を大きく変えてきた。冷戦時代の人口不安、フェミニズムの復活、消費主義の急激な強化、グローバリゼーションの速いペースはすべて、生殖工学が可能にするますます個人的な選択を形成する役割を担っている。
批評家たちは、優生学が消滅するどころか、遺伝子研究だけでなく、新たな社会形成の中で再生していることに呆れながら注目している。社会学者のドロシー・ワーツは、1998年に遺伝学医療における倫理的問題について調査を行った。36カ国の約3000人の遺伝学専門家に配布したアンケートでは、「優生学」という不名誉な言葉の使用を避け、強制不妊手術、遺伝的疾患を持つ胎児へのカウンセリング、社会における障害の位置づけなどについて質問している。その結果、親の選択に対して幅広い支持がある一方で、親は社会的責任を果たすべきだという強い信念があることがわかった。また、多くの場所でカウンセリングが「意図的に傾斜している」「時には公然と指示的なアドバイスを伴う」ことを発見し、「遺伝学が一般医療の一部になるにつれ、より大きな指示性を持つようになるだろう」と予測した。
第二次世界大戦後、優生学が消滅したわけではないと言ってよい。同じように実践されることはないかもしれないし、進歩する技術に照らし合わせても、そうなることを期待する理由はない。しかし、遺伝子の専門知識が発達した時代において、人間の生殖を改善し、指示し、コントロールしたいという衝動は、優生学の願望と目的が消滅することはないだろう。優生学が常にそうであったように、優生学は非常に多様な運動であり、さまざまな見解や立場を生み出している。その多くは、常に適用されるわけではないにせよ、意図としては真に善良である。現代の優生学で最も顕著なのは、個人の選択と消費者の嗜好を重視することであろう。以前の優生学は、その実施に際して国家の力を借りていた(ただし、その資金の多くは私的なものであった)。一方、今日の優生学は、国家の関与を減らし、個人の選択にますます重点を置いている。新しい生殖工学の支持者は、個人が自分の子孫を強化し、改善することを選択できるという見通しを歓迎し、それは間違いなく刺激的な機会だが、消費者選択の世界が参加する手段を持たない人々に与える影響については、あまり考慮しない。消費者の時代において、完全に非強制的な優生学が可能かどうかはまだわからないが、私たちは、以前の多くの優生学的実践の人的コストと、その負担が最も余裕がなく抵抗できない人々の肩に重くのしかかるという奇妙な傾向を思い出すのがよいだろう。