Contents
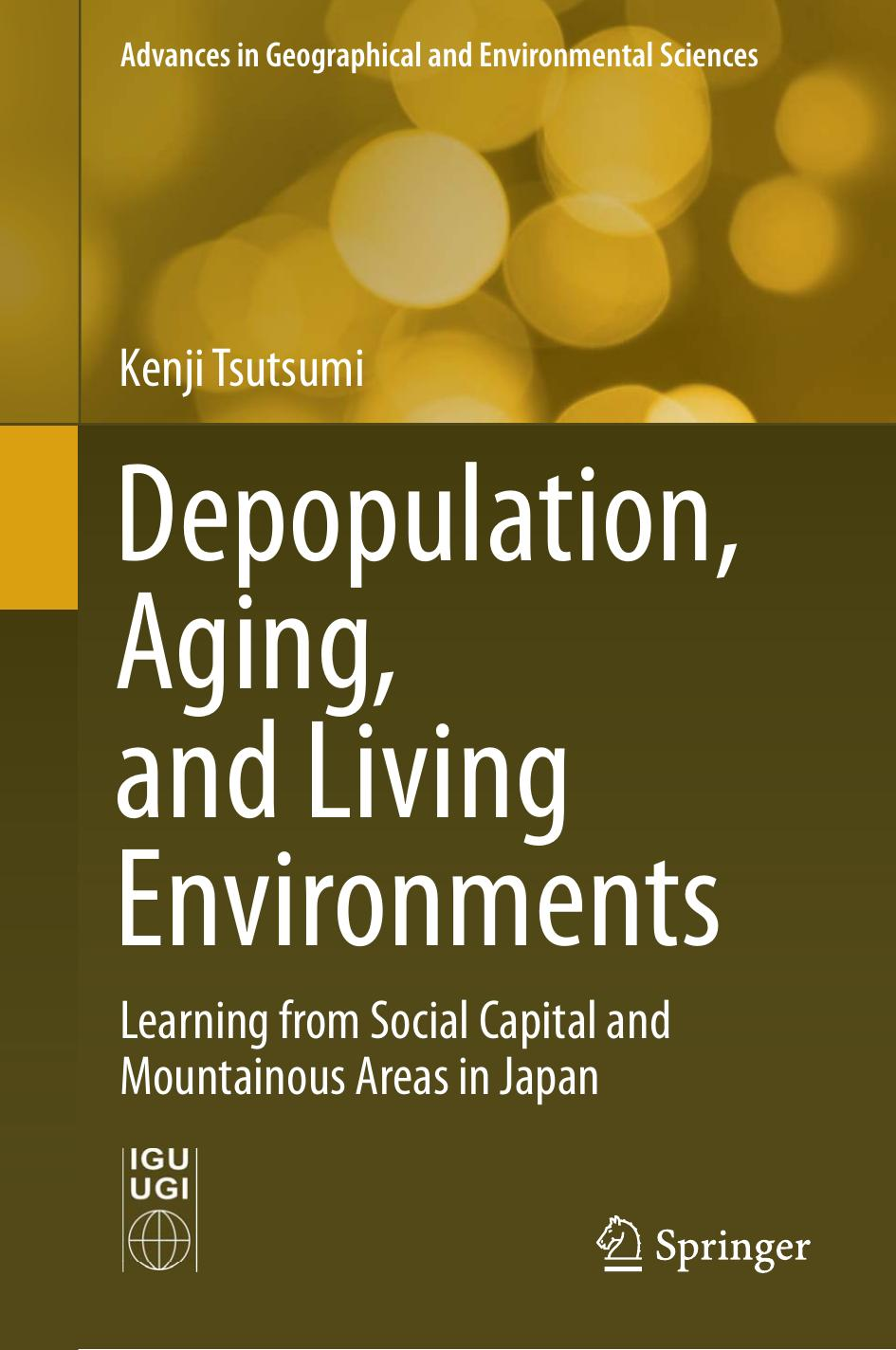
堤健司
過疎化・高齢化・生活環境
日本の社会関係資本と中山間地域から学ぶ
地理環境科学における進歩
シリーズ編集者 R. B. Singh(デリー大学、インド・デリー
地球圏、生物圏、水圏、大気圏、雪氷圏の生態学的な包絡線の中で、挑戦的な相互作用の領域を組み入れ、地球環境の診断と予知をシリーズ化したものである。土地利用・土地被覆変化(LUCC)、都市化、エネルギーフラックス、土地-海洋フラックス、気候、食糧安全保障、生態水文学、生物多様性、自然災害、人間の健康、およびそれらの相互作用とフィードバック機構を扱い、持続可能な未来に向けて貢献することを目的としている。地球科学の手法は、伝統的なフィールド技術や従来のデータ収集から、リモートセンシングや地理情報システムの利用、コンピュータ支援技術、先進的な地球統計学や動的モデリングまで、多岐にわたる。
このシリーズでは、時空間的な観点から生物物理学と人間の次元を取り入れた地球圏の属性の過去、現在、未来を統合している。環境問題、特に大気・水質汚染、地球温暖化、都市のヒートアイランドなどの観測・予測において、土地・海洋・大気の相互作用を包含する地球科学は重要な要素であると考えられている。自然災害の影響を軽減するための能力開発を通じて、社会の回復力を高めるために、地球科学の進歩を伝えることが重要である。人間社会の持続可能性は地球環境に強く依存しており、したがって、地球科学の発展は、私たちの生活環境をよりよく理解し、その持続可能な発展のために不可欠である。
また、地球科学は、現在の問題に対処することにとどまらず、将来の問題に対処するための枠組みを開発する責任を担っている。気候システム全体の機能を理解し予測するための「未来の地球モデル」を構築するためには、従来の地球科学分野だけでなく、生態学、情報技術、計測技術、複雑系などの専門家の協力が不可欠であり、人類地球科学者のイニシアティブが必要である。このように、人類地球科学は、未来地球構想とともに、持続可能性・生存可能性科学に貢献するための重要な政策科学として台頭してきているのである。
Advances in Geographical and Environmental Sciencesシリーズでは、広義の人文地球科学に関わる新しいアプローチを含む書籍を出版している。このシリーズでは、モノグラフと編集巻をページ数の制限なく掲載している。
本シリーズの詳細については、http://www.springer.com/series/13113。
堤健司
過疎化・高齢化・生活環境
日本のソーシャル・キャピタルと中山間地域から学ぶ 堤健二
「あらゆる地理学は歴史地理学である」
(David Harvey; 1994年10月19日、島根県吉田村にて著者と私的な会話にて)
本書は、日本における過疎化を事例と考察で取り上げたものである。日本語で出版した拙著(2011)、改訂版(2015)をベースに、世界の新しい読者のために追加事項を盛り込んだ英語版である。
内容は、過去約40年にわたる私の研究のエッセンスである人口流出や過疎地の研究などである。また、現代におけるさまざまな地域の生活環境の変化についても触れている。研究対象地域は、主に日本国内の山間部、旧炭鉱地域、島嶼部などである。中でも山間部の農村は、高度経済成長期以降、全国的な人口移動の初期段階において、急激な過疎化、地場産業の衰退、生活施設の減少を経験した地域が多い。
国内の人口構成の変化に伴い、日本は高齢化社会から高齢者社会へと変貌を遂げた。人口減少だけでなく、経済状況の悪化に伴い、生活環境はますます悪化している。20-30年代、2040年代には、首都圏でさえ人口減少と急速な高齢化に悩まされることになる。本書を含む地方の過疎化研究の成果や知見は、近い将来、社会問題の解決策を見出すために役立つと思う。
本書では、過疎問題だけでなく、過疎化した地域社会で日常生活を維持するために役立つソーシャル・キャピタル(ここではほぼ社会関係や絆を資本と称している)についても論じている。
具体的には、人口流出や高齢化に伴い、産業や地域生活施設が衰退した中山間地域の事例を中心に検討する。また、スウェーデンの事例や、大阪の千里ニュータウンの都市部の事例も参考にした。
残念ながら、実証的地域研究、特に中山間地域の研究では、第一線の研究者が引退し、若い研究者がほとんど関心を示さなくなっている。このように、マイナーな分野であっても、極めて重要なテーマであることから、本書を刊行する意義は大きい。本書の内容は、Society 5.0時代における過疎地の持続可能性に関わるポスト・アーバニティの考察や、本書の後半で紹介するトリノベーションやデュアルダイバーシティといった新しい概念の提示につながるものである。
このような研究を可能にしたのは、先生方、インフォーマントの方々をはじめとする多くの方々の親切で温かい支援のおかげである。原著を日本語で出版することができた九州大学出版会の永山俊二氏、本書を英語で出版することができたシュプリンガー・ジャパンの西田洋介氏、佐藤妙子氏、優れた英語原稿を提供してくださったd-lights Translation Services (www.dlightstranslation.com)の松本純氏、吉永美枝氏、マイケル・ナロン氏、ナロン美幸氏にもお礼を申しあげたい。また、Chap.10の英文校正を担当していただいたエディテージ(www.editage.com)にも感謝したい。さらに、最終校正に尽力してくださった鈴木美香さん、迫田真理子さん、森田大志さん、特に本書の出版を推薦してくださった岡橋秀典先生(広島大学,奈良大学),伊藤勝久先生(島根大学),西野敏明先生(高崎経済大学)に感謝いたします。
また、家族のみんなにも感謝したい。両親の勲とみどり、義父母の巌と真志はもうこの世にいないが、彼らが私の人生を導いてくれたおかげで、多くのことが可能になったので、今日彼らがここにいて、直接お礼を言えたらと思う。また、建築の立場から地域の生活に関する重要な点について、親切に教えてくれた兄の信介に感謝したい。また、本書が完成するまでの間、長い間、研究者としての不規則な生活を許してくれた妻のキツと子供たち(京子、和之、千賀子、愛子)に感謝したい。本書の出版が、多くの方々の厚情に報いる一歩になればと願っている。そして最後に、この本が、私自身の、そして他の人々の、これらの問題についてのさらなる研究につながることを願っている。
そして、現在のコロナウイルスによる恐ろしいパンデミック状態が一日も早く収束し、世界のすべての人々に平和な日々が訪れることを祈るばかりである。私たちは乗り越えなければならない。
2020年3月、日本、豊中
堤健二
目次
-
- 1 はじめに-中山間地の軌跡 研究と本書の視点
- 1.1 過疎の概要と過疎研究の問題点
- 1.2 中山間地域研究の軌跡と山村研究
- 1.3 本書の視角と内容
- 1 はじめに-中山間地の軌跡 研究と本書の視点
- 第Ⅰ部過疎問題の概要と人口流出の実態
- 2 地域問題としての過疎と過疎の現実
- 2.1 社会変動・近代化と過疎問題
- 2.2 農村人口の変化
- 2.2.1 人口構造
- 2.2.2 移住
- 2.2.3 地域別の特徴
- 2.2.4 農業就業構造
- 2.3 過疎の定義
- 2.4 地域的剥奪。2.4 地域的剥奪:過疎地域における地域機能の衰退と喪失
- 地域剥奪-過疎地域における地域機能の衰退と喪失
- 2.5 過疎法における過疎化の要件と過疎地指定地域
- 2.6 地域の特性と過疎化の類型
- 2.7 我が国の人口移動と過疎・人口過剰問題vii
- 2.8 2000年国勢調査速報値からみた過疎化の実態
- 2.8.1 過疎化の概要
- 2.8.2 国勢調査の速報値からみた過疎地域
- 2.9 おわりに人口推移と過疎化の参考資料
- 3 過疎化した山村からの人口移動の分析-大分県上津江村の場合
- 3.1 はじめに
- 3.2 人口移動研究の視点と本章の課題
- 3.3 上津江村からの移住者の特徴と移住の空間的パターン
- 3.3.1 調査対象地域の概要
- 3.3.2 移住者数の推移とその推移
- 3.3.3 移住者の特徴
- 3.3.4 移住の空間パターン
- 3.4 移住者の特徴と移住の意思決定
- 3.4.1 移住状況の概要
- 3.4.2 移住の理由
- 3.4.3 移住前と移住後の移住者の職業
- 3.4.4 複数回移住する人の移住パターン
- 3.4.5 移住に関連する意思決定プロセス
- 3.5 過疎化した集落の変容。上津江村の集落K
- 3.5.1 社会的紐帯
- 3.5.2 産業基盤の立地・歴史・変遷 基盤の変遷
- 3.5.3 人口、世帯数、家族数
- 3.5.4 集落内の集団・通婚地域・生業・生活機能
- 3.5.5 集落Kの変容と過疎化の方向性。ソーシャル・キャピタルの考察 理論編
- 3.6 おわりに引用文献
- 2 地域問題としての過疎と過疎の現実
- 第Ⅱ部過疎地中山間地域の生活環境の実態と地域生活機能のIT化支援
- 4 島根県内の過疎集落における地域生活機能
- 4.1 過疎地の生活機能に関する分析視点
- 4.2 島根県内の過疎地域
- 4.3 研究の目的と方法
- 4.4 調査対象者の属性と職業
- 4.4.1 回答者の属性
- 4.4.2 調査回答者とその他の世帯の職業
- 4.5 生活圏と生活機能・住環境の評価
- 4.5.1 生活機能・生活環境の評価
- 4.5.2 生活機能と生活圏
- 4.6 過疎集落における生活機能研究の課題
- 5 地域生活機能とIT支援
- 5.1 はじめに
- 5.2 ITと地域生活
- 5.2.1 過疎地域とITによる社会経済的変化
- 5.2.2 地域生活機能の整理
- 5.2.3 地域生活を支えるITの具体的事例と可能性
- 5.2.4 ITによる地域生活支援の調査・研究に向けて
- 5.3 ITネットワーク技術の地域適用について(大規模事例)
- 5.3.1 情報システムの例
- 5.3.2 大規模な情報システムの問題点
- 5.4 地域別アンケート調査結果
- 5.4.1 地域別調査の概要
- 5.4.2 地域別調査
- 5.5 おわりに参考文献
- 4 島根県内の過疎集落における地域生活機能
- 第Ⅲ部地域社会の社会関係資本、生活環境、地域生活機能
- 6 農山村のソーシャル・キャピタルと生活環境
- 6.1 ソーシャル・キャピタルとは何か?
- 6.2 ソーシャル・キャピタル研究の課題
- 6.3 ソーシャル・キャピタルと農山村社会研究
- 6.3.1 鈴木栄太郎の自然村落論
- 6.3.2 福武雅治の同族説
- 6.3.3 水津一郎の基礎地域論
- 6.3.4 鈴木寛のコミュニティ・モラル論
- 6.4 ソーシャル・キャピタル研究におけるミクロ・マクロの問題
- 6.5 人口減少地域の集落における生業活動とソーシャル・キャピタル
- 6.5.1 人口減少地域の集落における生活活動に関する分析概要
- 6.5.2 データ収集方法
- 6.5.3データ収集
- 6.5.4調査結果
- 6.5.5 今後の課題とソーシャルキャピタル
- 参考文献
- 7 ダム建設に伴う強制移住集落の変容 -島根県雲南市木次町月野谷集落を事例として
- 7.1 はじめに
- 7.2 代理人と社会的関係
- 7.3 小原ダムの概要と地域運動
- 7.4月乃家における取組みの概要
- 7.5月野屋における取組みの意味、ソーシャル・タイズとソーシャル・キャピタル
- 参考文献
- 8 都市と農村の住民交流を促進する「ふるさと組織」によるコミュニティ形成 -近畿圏の住民によるNPO「ふるさと力」の活動と徳島県三好市の事例から
- 8.1 はじめに
- 8.2 NPO法人ふるさと力。設立の背景と住宅地建設
- 8.3 ふるさと力・三好町ゆるりの活動意義と機能
- 8.3.1 木造軸組工法による住宅建設の影響
- 8.3.1 木造ブロック工法による住宅建設の影響
- 8.3.2 新居住地の環境条件と新居住者
- 8.4 おわりに引用文献
- 9 千里ニュータウンにおける社会運動とソーシャル・キャピタル
- 9.1 はじめに本章の目的
- 9.2 千里ニュータウンの歴史と概要
- 9.3 人口高齢化と住環境・建設環境の悪化
- 9.4 その他の機能・アメニティの低下
- 9.5 千里ニュータウンにおける住民同士の対立
- 9.6 千里ニュータウンにおけるソーシャルキャピタルと住民のパワー
- 9.7 街の改造と都市における社会的スプロール化
- 9.8 おわりに再実験都市としての千里ニュータウン
- 参考文献
- 10 地域危機、Society 5.0、ポストパンデミック、ポストアーバンの時代における周縁地域-英語版のための結論と追加章
- 10.1 本書の各章のまとめ
- 10.2 大いなる新しい状況
- 10.2.1 地域の危機
- 10.2.2 ソサエティー5.0
- 10.2.3 ポスト・パンデミック社会
- 10.2.4 ポストアーバン世界
- 10.2.5 イノベーションと周縁地域の未来 過疎地域の未来
- 10.2.6 実験的研究フィールド。沖ノ島町
- 10.3 さらなる課題と可能性
- 6 農山村のソーシャル・キャピタルと生活環境
著者名
著者紹介堤健司(つつみけんじ) 社会経済地理学者(文学博士)、大阪大学教授。1960年、福岡県大牟田市に生まれる。大牟田市には国内最大の炭鉱である三池炭鉱があり、そのことが堤氏の研究上の関心事となっている。九州大学では人文地理学を専攻した。学生時代は、ドイツ社会地理学(Sozialgeographie)、定量的地域分析、農村社会学、社会批判理論、定量的考古学、日本近現代史などを熱心に勉強してきた。現在は、中山間地域、旧石炭鉱業地域、島嶼、縮小する都市を主な研究対象として、伝統的な地域環境利用、過疎化、地域生活機能、地域変容、空間周辺化、空間の社会経済理論に関心を持つ。佐世保工業高等専門学校を経て、島根大学に勤務。1999年から大阪大学で人文地理学と文化共生論の2科目を担当している。2019年より大阪大学総長補佐を務める。また、同年より周辺地域研究者の国際団体であるMarg(Marginal Areas Research Group)の代表を務める。大阪府豊中市にて、地域の子どもから大人まで幅広く指導するチーフインストラクターとして、日本武道「義和拳」(黒帯6段)を稽古している。学術・社会貢献の両面で数々の賞を受賞している。今後、「産業の近代化と地域の変容」、「社会経済空間研究・分析における資本主義と地平」の2冊の著書を出版予定である。
はじめに -中山間地域研究の軌跡と本書の展望
概要
本章は、本書の序論である。まず、過疎化の現状とその問題点を概観する。次に、日本の中山間地域に関するいくつかの研究に言及する。最後に、本書の展望と内容の一部を紹介する。
キーワード 過疎化 剥奪生活 環境 中山間地域 地域変動
1.1 過疎化の概要と過疎化研究の問題点
第二次世界大戦後の日本の高度経済成長は、日本のGDPを短期間に世界一に押し上げた。しかし、その代償として、人口をはじめ、資本、モノ、情報、サービスなど、関連する要素の著しい偏在に見られるようになり、著しい地域格差が出現した。三大都市圏とそれ以外の地域、特に農村や炭鉱跡地との経済的な地域格差は、人口の流入と流出のアンバランスとあいまって、過疎地と過密地を生み出している。
過疎地の多くは大都市圏にあり、都市学などの分野でさまざまな調査・研究・対策が行われている。過疎地域研究を幅広くカバーする研究の蓄積はあっても、統合的な視点に立った学問の水準に達しているとは言い難い。過疎問題に焦点を当てた都市研究が学際的研究の結節点を構成しているのに対し、農山村研究は、農山村がそれぞれ多様な文化・社会・政治・経済的特性を持つため、過疎問題の焦点の一つに絞るのに苦労した。特に人文地理学的な研究は、個別的・縦割り的で、農村、山村、漁村が別々に研究されていた。また、過疎地からの人口流出が量的に遅くなると、これらの地域研究への関心は薄れた。さらに、研究者人口も少なく、過疎地の象徴である山村や炭鉱跡地などを研究する若い研究者も少なくなっていた。
戦後の過疎現象を振り返ると、「過疎」という言葉が問題視されるようになったのは、1960年代後半である1。農村からの人口流出と都市への人口流入は、過疎と過疎という形で、人口と地域機能のアンバランスを生み出したのである。こうして、1970年代には産業の衰退と発展に伴い、労働移動、地域組織、労働力の分配が展開された。1977年から1980年代にかけて第3次全国総合開発計画が策定されると、いわゆる「地方の時代」が到来し(清成忠男 1986)、過疎地における産業の発展、企業誘致、商品開発などのトレンドがもたらされた。しかし、人口流出を食い止めたり、帰還人口を大幅に増加させたりするような顕著な効果はなかった。1990年代頃から、社会的ではなく、自然に人口が減少し始めた地域がある。過疎地の人口減少をざっと見てみると、1960年代から1970年代前半にかけての高い減少率を境に、減少のスピードが鈍化していることがわかる。
しかし、人口減少が鈍化したからといって、過疎地の問題が解決したわけでは決してない。2000年の第四世代過疎法施行後も、国土の約半分は過疎地域に指定されていた。高齢化で集落機能が麻痺し、短期間で立ち行かなくなった閑散集落や「限界集落」(小野2005)が一部の自治体で発生し始めたのである。過疎地は、「生活の質」の観点から非常に深刻な局面を迎えている。
第二次世界大戦後、長い間高度経済成長を続けてきた日本では、多くの地域で人口の大幅な減少が起こった。いわゆる「過疎地」と呼ばれる地域には、多くの農村や炭鉱の廃墟が含まれていた。これらの地域、特に西日本の地域には、人口流出以外にも、自然環境や資源を利用した産業や生活形態が多く存在し、そうした自然を利用した地域社会のルールやモラルが形成されていることが共通している。私は、1980年代初頭から、西日本の山間部や炭鉱跡地における農山村の伝統的な環境利用と人口流出の研究を通じて、これらの共通性を強く認識するようになった。その過程で、過疎研究にとって重要でありながら、まだ研究されていない分野があることもわかってきた。中山間地、山村、炭鉱跡地に関する研究の空白を埋める必要性を認識した私は、これまでの研究の動向を整理し、新たな研究の枠組みを提示することを考えた。
本書では、まず、過疎化現象から数十年にわたる人口減少を経験した中山間地域や山村に目を向け、人口流出の実態とその影響に着目した。すると、人口が急激に減少している地域には、概して「周辺地域」や「限界集落」という空間が存在することがわかった。人口流出地域では、人口が縮小し、その地域の経済資本だけでなく社会資本も減少し、地域の諸機能が弱体化した。これらの地域は、地域のヒエラルキーの枠組みの中で、端に押しやられ、マージナル化したのである。このプロセスを「限界集落」と呼び、限界集落を本書では「周辺集落」と呼ぶ。中山間地域や山村は、人口の激減と地域社会機能の急激な低下を経験したため、限界集落の典型例といえる。このような理解に至ったのは、既存研究の蓄積とレビューがあったからだ。次節では、まず、私のこの問題への関心に影響を与えた従来の中山間地域・山村に関する研究を整理し、その概要を説明する。
1.2 中山間地域研究・山村研究の軌跡
本節では、過疎化が表面化し始めた1960年代から50年近い歴史的経緯の中で、これまでの中山間地・山村研究を整理してみた。
山村研究は、過去の様々な分野の研究(神谷1967、渡辺1969、半田1981、藤田1981、岡橋1986,1997、堤1986、西野1999,2003,2008)の大きな蓄積を包含している。ここでは、人口流出・過疎問題に関連する先行研究を、過疎現象やその研究の動向に沿って概観してみた。
特に1960年代から1970年代にかけて、山村からの人口流出が顕著であった。この人口流出は、山村問題と呼ばれる過疎化をはじめとする様々な農村問題の発端・引き金となった。このような歴史的背景から、山村研究の領域における人文地理学の最初の大きな成果のひとつが、農村流出と砂漠化集落の研究である(坂口 1968)。この種の研究は、坂口(1966)、篠原(1969)の優れた事例分析に代表されるように、主に1960年代後半に行われたものである。彼らは、山村からの人口流出の初期から中期までを集落単位で扱った。これらの研究では、集落の立地に着目して問題点を議論し、世帯単位で進行する農村流出状況を復元している。また、閑散とした集落地域と閑散とした集落現象をまだ生じていない過疎地域とを比較した研究もあった(篠原1969,1991、高橋1970)。
このような農村の出稼ぎや閑散集落現象の中には、行政の政策と結びついているものがあることが明らかになってきている。山口(1970)は、市町村合併によって閑散とした山村で、農村脱出の漸進的な全過程を追跡した。西野(1981, 1999, 2003, 2008)は、ダム建設のために移転を余儀なくされた集落を研究している。さらに、坂口(1981)は、鈴鹿山脈の山村がさびれる過程では、薪炭産業の停滞だけでなく、中学校の統廃合に伴う集落移転が影響したことを例示している。
山村からの人口流出に伴う地域産業構造の急激な変化は、1960年代後半から1970年代にかけて顕著になった。それに伴い、流出人口と村の残存人口を労働力形成の観点から分析する研究が盛んに行われるようになった。経済学や経済地理学の分野では、人口流出を労働力の流出として扱う研究が数多く行われた(吉澤 1967、今村 1971、斎藤 1973、伊藤 1974a、b、宮口 1978. 岡橋 1978, 1980, 1981, 1982)。このような労働力の移動は、山村の社会・経済を継続的に変容させながら発生した。労働力の流出だけでなく、農民が副業をしたり、農業をやめたりするなどの職業上の変化も議論の対象となる。労働力の特性からいえば、山村から流出した労働力の多くは、特に高度経済成長期には、特別な技術を必要としない低賃金労働に従事することが多かった。職種も工業の第2次産業に従事する傾向があった。村に残って農業をあきらめたり、新たに副業を始めたりした人の多くは、出稼ぎ労働者や日雇い労働者という不安定な雇用を余儀なくされた。一般に、山村からの移住者の雇用条件には年齢や経歴(学歴、技能、職歴を含む)が、残留者の雇用条件には農林業の不就労や停滞が反映されていることがわかる。山村の雇用不足と雇用条件の悪さが、さらなる人口流出に拍車をかけていたが、村から移住した後も、村に戻った家族への仕送りや家族を呼んでの同居が困難な低賃金者が多くいた。それが山村における高齢者の引きこもりの一因となり、則本(1981)の造語である「グラニーダンピング」現象が発生していた。他方、過疎地からの高齢者の転出率も高く、高齢者の定着と転出の二極化が進んでいた。
山村に留まる世帯にとって、農家世帯の人口流出は「農業就業賃金の上昇と連動し、実労働が困難となった。手向け(地域間の労働力の交換)や結い(共同体の助け合い)2の存在にも影響するため、かなり小さな規模でしか継続できなかった」(斎藤1973,98頁)。つまり、残った農民は、別の仕事に就くか、農業をあきらめなければならない可能性が高くなったのである。この状況は、森や畑での共同作業の減少とも関連するだろう。農林業人口の減少傾向は、「最近、農林業部門から非農林業部門への移行に伴い、35歳以上の労働力人口が増加している」ことが大きな特徴である。この層の中に、家族経営の林業経営者出身者やその後継者が増えている」(今村1971、p.20)のである。
したがって、山村からの人口流出は、山村の農林業生産の衰退を意味し始めたといえる。山村の基幹産業である林業では、山主と林業労働者の関係に強い社会的結びつきが残ることが多く、林業労働条件も劣悪な状態が続いた。このような林業の長期停滞の中で、林業経営が赤字続きの上級の林業経営者もいた。特に外材輸入の影響は、日本の林業全体を揺るがし、戦後植林された森林が伐採期を迎えて利用しにくくなっていた。この事例は、安価な外国産炭の輸入から国内の炭鉱が次々と閉山に追い込まれた石炭産業と共通するところがあるようだ。
熊本県球磨村をはじめとする山村では、独自の発想で林業開発計画を立案したり、食用山菜やシイタケ、間伐材などの生産と観光で森林を活性化させたという報告があるが(三井田 1979)、事業としての成功例は少ない(篠原 2000)。また、山村では、林業開発で成功しても、後継者育成が非常に遅れている。このような林業構造の改善策が急務であった。また、多くの山村が高齢化問題に直面し、労働力の流出により林業労働者が減少していた。
1970年代末から1980年代にかけて、人口流出地域の企業誘致や特産品開発など、地域振興が脚光を浴びるようになった。山村は、その立地条件から、必ずしも大規模な観光開発が成功するとは限らない。前述したように、三井田(1979)は、林産物の生産・加工や小規模な観光宿泊施設(スキー客向けのゲストハウスなど)の運営に成功している村があることを報告し、自然環境を生かした林業や観光、特産品の生産が山村の地域振興の柱であることを紹介している。西野(1997,1999,2003,2008)と高崎経済大学地域経済研究所(1997)は、ともに林業を中心とした山村づくりの研究を続けている成果を報告した。また、森林の土砂災害防止や水資源の補給など、公共的な機能を重視することも提唱している。篠原(2000)は、山村のリゾート施設開発における重要な要因として、以下の6点を分析・提示している。1. 観光開発主体、2.外部資本の活用、3.自治体と住民の連携、4.強いリーダーシップ、5.自然と人間活動の調和、6. 個性的な観光の展開。近年のグリーンツーリズムの発展は、都市に住む人が山村で農林業を体験できる体験型宿泊を提供するなど、都市と山村の交流を促進する観光の新しい可能性を提示している(関戸2000)。Hobo(1996)は、過疎化克服のための政策として「地域資源の活用」を提案し、内生的成長理論の観点から農山村政策の体系化を試みている。これからの大合併時代には、自立的な地域づくりを提唱することが重要だが、内生的発展をリードする地域リーダーをどうとらえるかについては、意見が分かれるところであろう。この点については、筒井(1999)が関連する貴重な研究成果を提供している。
1990年代以降、山村における社会経済組織や高齢化、地域生活機能の弱体化といった問題に着目した研究が増加した。また、山村の社会経済の諸相を捉える試みも行われるようになった。岡橋(1990,1997)は、これらの地域を周辺地域と位置づけた。古くは渡辺ら(1968)が人口論と地域論から過疎論の枠組みを提示したが、現在では山村の規模やレベル、国土政策の中での位置づけを論じる傾向がある(岡橋1997、西野1999,2003,2008)。また、山村の農村社会・社会組織と山村地域の生業・生活機能との関連を論じる研究も出てきている(関戸 2000; 金 2003)。地域社会住民のローカリティに着目した農村に関する研究論文としては、Hoggart and Buller (1987)や高橋誠 (1997)などの興味深いものがある。
則本(1981, 1996)は、過疎化の激しい山陰地方でのフィールドワークをもとに、過疎化の社会問題を浮き彫りにしている。彼は、高齢者の集積、自殺問題、交通、農業、定住など、社会問題の諸相を分析した。また、山本勉(1996)は、過疎化した山村を対象に、自殺問題のほか、高齢化、家族構成、生活意識、地域意識、定住の実態などについて多面的な調査を行った。山本ら(1998)は、その流れを読み、現代の過疎地における問題の構図が、「社会的人口減少からの過疎化」から「自然的人口減少からの過疎化」に変化していると判断した。彼らは、地域変化や生活構造に着目した農村分析を展開するとともに、居住人口や流入人口などの生活人口だけでなく、流出人口にも目を向けた「生活人口原理に基づく過疎研究」を推進した。小野(2005)は、四国山地の山村を集中的にフィールドワークし、高齢化や人口減少によって集落の維持が困難になる「限界集落」についての考察を展開している。
農村における村おこし運動は、1980年代半ば頃から本格的に注目され始めた。当初は、中核農家が新しい作物を研究・導入し、収益性の高い作物を生産して農村経済を活性化させることを目的としていた。その後、規制緩和や農事組合法人の増加、1990年代後半には企業の農業参入など、村おこし運動は多様化していった。この過程で、短期間に農林業景観の変化を経験した地域があり、地理学的研究の格好の題材となった。日本の伝統的な農村景観は、1980年代半ば以降に村おこし運動が盛り上がる以前から、機械化、宅地化、水田切り捨て政策によって変化してきた。この傾向は、高度経済成長期以降、全国的なものとなった。例えば、野村(1966)は、景観などの自然条件に即応して発達したアグロフォレストリー生産に面積の分化とその変化を発見している。相馬(1971)は、四国のミツマタ農家が森林化した際の農林業の変化過程に着目し、地域構造の存在を指摘した。山村地域の経済的変化、具体的には農林業事業や農作物の変化は、土地利用の変化として現れることになる。しかし、村おこし運動以降の山村の土地利用の変化過程とその背景を分析した研究はあまり多くない。そのため、近年の土地利用で観察される景観の変化過程とその地域的な特徴を分析する必要がある。この分析に一役買ったのが、文部省科学研究費補助金重点領域研究「近代化と環境変化」である(堤他 1991、西野他 1992、堤 1992、西川 1995、堤 1995)。小林・堤(2001)の事例研究は、土地利用の変化、特に現代の森林利用を追い、これまでの森林利用に関する人文地理学的研究において、必要ではあるが分析が弱かったと思われる生態学的視点での考察を加えたものであった。
この節では、中山間地・山村研究の主流となる動向を概観した。この種の研究は多面的なアプローチが可能だが、より分析が必要な分野もある。従来は、過疎地域の開発・活性化を意識して、過疎問題の展開を追った議論が行われてきた。しかし、過疎地を取り巻く長期的な変化は、構造的な観点から必ずしも十分に捉えられてはいなかった。また、過疎化は全国的な地域構造への変化の一環であると考えられるが、問題は過疎地域のみに集中しており、他の地域との関係も十分に考慮されていたとは言い難い。
1.3 本書の視点と内容
本書は、過疎化・人口流出の分析から始まり、人口減少地域の生活環境問題を取り上げ、さらにソーシャルキャピタル論の議論から地域社会の生活機能を論じ、前論で示した中山間地域研究・過疎地域研究のギャップを縮めることを目的としている。本書は、時系列的に論点が提示される大きく3つのパートから構成されている。第I部では、日本全国に関わる過疎状況や、特定の山村からの人口流出に焦点を当てる。第II部では、人口流出が進んだ後の中山間地域の生活環境の問題を提起し、生活の質を維持するための戦略としての情報技術(IT)の有効性を検証している。第III部では、生活環境や生活機能の維持に取り組む地域コミュニティの事例研究を通じて、この20年間で注目されるようになったソーシャルキャピタルの概念について考察する。
非都市圏から都市圏への移動の背景には、雇用や所得の地域格差があることが実証分析によって明らかにされていた(石川1978、特に439頁)。この観点に立てば、山村地域からの人口流出は、産業基盤の変化に伴う人口再分配過程の一部であったと言える。しかし、山村・山間地域研究は多面的な角度を持ちうるとしても、市町村のメソスケールでの移住者の属性分析を伴う人口流出研究の例は極めて少ない。この種の研究は、簡単に使えるデータ、入手できるデータがなく、その分析には多くの時間と労力が必要であった。しかし、移住者の属性や移住パターンを分析し、その特徴を抽出することで、逆に中山間地域の人口流出地域の特徴を論じることは可能なはずだ。本書の第Ⅰ部では、日本の過疎問題と地方からの人口流出を分析し、大分県上津江村の人口流出の集中事例を分析する。また、経済・社会資本から遠いだけでなく、物理的にも離れているため、様々な機会へのアクセスが悪く、地域的な困窮を経験している地域を理解する視点にも触れている。
また、急激な人口流出の結果、山間部や山村では生活や生業に対する権利の保障が難しくなり、移住者は新しい生活環境に適応することを余儀なくされる。人口流出によって中山間地域の生活環境がどのように変化したのか、どのような問題が生じたのか、また、中山間地域の生活環境を維持するための方策は何なのかを明らかにすることが重要である。これらの点については、本書の第II部で取り上げている。具体的には、過疎化が激しいことで有名な島根県の集落を調査・分析した結果を紹介している。また、ITによる地域環境と地域生活機能の維持のあり方について考察している。
第III部では、ソーシャルキャピタルの概念を整理し、人口減少地域の地域活動分析を通じてソーシャルキャピタルについて考察している。
備考
1. 過疎化」という言葉は、1967年の経済審議会での議論で使われ、その後広く使われるようになった。
2. 「手向け」とは、農村社会内や農村社会間で見られる労働力の交換のことである。「ゆい」は、共同体内部の共同作業を指す。
第1部過疎問題の概要と人口流出の現実
写真I-1 松原ダム
(2010年9月26日)
松原ダムと下毛ダムは、1953年の西日本大洪水後に計画され、1973年に完成した筑後川水系の二連式ダムである。このダム建設に対して、地元の大地主である室原知幸氏を中心とした有名で厳しい反対運動「蜂の巣城騒動」が起こった。写真は松原ダムで、上流部の下池ダムの対岸は熊本県小国郡に属す。これらのダム建設により、旧日田郡大山町、中津江村、上津江村の一部は大分県側に水没し、小国郡の一部も熊本県側に水没してしまった。これらの地域の集落は移転せざるを得ないところもあり、これらの自治体の過疎化の要因の一つとなった。
第1部では、過疎問題に注目した論点整理を行い、ある山村からの25年間の人口流出について集中的に分析を行う。
具体的には、第2章「地域問題としての過疎と過疎の現実」で、過疎と人口流出を地域変化の表れの一つとして位置づけ、過疎と人口変化に着目する。地域変化を構成し、人口に関係する変化の側面はいくつかある。過疎化とも深く関わっているため、地域問題としての人口、具体的には人口移動と過疎化の関係を無視した議論はできない。ここでは、過疎地域を含む地方圏(非首都圏のように広義の農村として位置づけられることの多い地域も含む)の人口変動を論じ、過疎地域の人口の実態をまとめることにする。
続く第3章「過疎山村・大分県上津江村からの人口移動の分析」では、過疎山村(大分県日田郡上津江村)からの人口移動を約25年間追跡し、約4000人以上の移住者の属性分析によって、逆に過疎山村の地域事情に光を当てている。また、本章では、村内の特定の集落における生活基盤や社会関係の実態と変化に関する調査結果も補足している。第3章では、住民票の除票などの資料を用いたが、現在では個人情報保護法の関係でこの種の資料の利用は困難である。また、これらは5年後に廃棄されるべき公文書であった。当時の上津江村役場は、過疎・人口流出に関する基礎研究のために、本書の研究に使用したこの種のデータを提供してくれた。分析にあたっては、個人のプライバシーに十分配慮し、統計処理した上で結果を提示するようにした。そのため、1980年代半ば頃までのデータを中心に分析することになった。第3章では、住民登録抹消データから作成した移住者データベースの分析結果と、移住者について実施した追跡調査の分析結果を紹介する。これだけの分析を伴う研究は、後に行った高島炭鉱の人口流出分析(堤、1991,2006)を除けば、最近では非常に珍しいと私は考えている。また、メゾスケールで見た山村の人口激減の詳細な記録も後世に残したいと思った。なお、上津江村は2005年の市町村合併で日田市上津江町となったが、第3章第2部以降は、調査当時の行政区名で表記することにした。
第10章 地域危機、社会5.0、ポストパンデミック、ポストアーバンの時代における周辺地域-英語版のための結論と追加章
要約
この最終章は、本書の英語版のための結論と追加章である。この章では、過疎地を周辺化された空間として扱っている。資本主義が強力に発展した段階では、一部の過疎地域は放置され、さらに衰退する可能性がある。つまり、過疎地の一部または多くが地域危機に直面することになる。知識経済、Society 5.0、ポストアーバンの時代には、過疎地は強く生き残ろうとし、住民の生活や地場産業を維持する必要がある。そこで、著者は、バランス型コンビネーション、デュアルダイバーシティ、トリノベーションというユニークなアイデアを提示している。地域ソーシャルキャピタルを活用したこれらのアイデアは、地域ソーシャルキャピタルを持つ過疎地域が生き残るための確かなツールとなるであろう。
キーワード バランスのとれた組み合わせ デュアルダイバーシティ 地域危機 社会5.0 ポストパンデミック ポストアーバン ソーシャルキャピタル トリノベイション
10.1 本書の各章のまとめ
本書の冒頭で、日本における中山間地の過疎化の歴史を振り返った。その際、過疎地の多くを占める中山間地域からの人口流出が、これまでミクロあるいはマクロのスケールで分析されてきたことを指摘した。
第1部第2章では、過疎と人口流出をめぐる諸問題を全国規模で検討した。第3章では、山間部の上津江村から流出した事例をメソスケールで分析した。その結果、人々のライフサイクルやライフステージに応じた移住の事例が多く見受けられた。さらに、ある種の移住パターンは、家庭内の属性や関係性に依存していることが明らかになった。最後に、人口流出のパターンを分析した結果、流出元の地域が山間部という経済的、社会的、物理的な遠隔地であることが浮き彫りになった。さらに、連鎖移住や段階的移住の事例もいくつか観察された。
第II部では、生活環境と地域生活機能について、2つの章を割いて検討した。第4章では、過疎化が進む島根県の厳しい現状を浮き彫りにした。高齢化社会では、買い物、通院、移動の3つの行動が非常に重要であることが示された。しかし、「移動制約者」(堤2003)が経験する重大な問題である。第5章では、過疎地の人々の生活を支えるIT(Information Technology)機能について、一定の考え方と事例を提示し、さらに、IT活用の限界と制約を提示した。この2つの章では、過疎問題の解決策は、地域収奪問題と同じで、地域における人権の保障を重視することであることを主張した。この点については、山本(1994, 1996)の、特に過疎地では地域相互扶助が重要であるとの指摘を参考にした。
第Ⅲ部の主要テーマは、過疎地におけるソーシャルキャピタルの問題である。第6章では、まずソーシャルキャピタルをめぐる主な概念、定義、問題点を紹介した。日本では、1世紀以上前から社会学者による地域社会の結びつきの研究が行われてきた。一方 2000年以降、多くの経済学者によってソーシャルキャピタルの重要性が強調されている。しかし、この2つの学問分野の間の意味ある繋がりや関係は、これまで正式に追求されてこなかった。第7章では、ダム建設によって水没した槻の谷集落が移転し、人口が減少しながらも活性化した事例を検討した。このような場合、集落やコミュニティの存続には「エージェント」の存在が不可欠であることが私の分析から明らかになった。本研究は、過疎化した社会が生き残るための重要な要素、すなわち社会資本を十分に活用する必要性を明らかにした(堤 2017)。第8章では、都市部からの移住者が移住した農村部の住宅地に新たに設立されたコミュニティについて検討した。そのコミュニティ内で展開された、結合と橋渡しの機能を併せ持つソーシャルキャピタルの新体制について検討した。続いて、第9章では、都市部のニュータウンである千里ニュータウンの事例を取り上げ、地域の周縁化が見られるとともに、日本の地方の過疎地において従来から認識されていた現象が見られることを指摘した。このような類似性を説明するために、「空間的周辺化」、「空間の周辺化」という概念を構築した。
10.2 壮大な新状況
本書は、2011年と2015年に出版された 2 つの日本語版に基づいている。それらの出版以降、社会の変化は私たちが想像していた以上に急速に進展している。さらに、地域の危機、Society 5.0、ポスト・パンデミック、ポスト・アーバンなど、検討を要する新しいトピックや課題がいくつか出現している。そこで、過疎化した周辺地域の台頭について、現在から近未来にかけて考えてみる必要がある。
10.2.1 地域危機
2020年の東京オリンピックと2025年の大阪万博は、この2大都市にとって新しい時代を開くものだが、前者は2020年にコロナウイルスのパンデミック問題で延期された。さらに、東京と大阪を中央新幹線でわずか67分で結ぶスーパーメガリージョン(SMR)を建設するという巨大な国家構想がある。この交通網を利用して、東京、名古屋、大阪の3大都市圏を1つのSMRに統合し、世界最大の都市圏にしようという計画である。しかし、このSMRの誕生は、国土に大きな不平等を生み出す可能性がある。特に西日本の周辺地域は、この構想のメリットから隔離されることになる。国土審議会委員の一人である小林清志氏(京都大学)は、中央新幹線の恩恵が届くのは広島県の東半分までとする見解を示している。つまり、四国や九州、近隣の島々を含む西日本の大部分は、SMRの恩恵を受けられないことになる。したがって、この地域的危機の問題を、私は「西日本の危機」と名付け、慎重に検討する必要がある。
10.2.2 ソサエティー5.0
最近、日本政府は、次の社会のあるべき姿を打ち出した。最近、日本政府は、次の社会のあり方として、Society 5.0を打ち出した。この計画は、社会の進化・発展の歴史を狩猟採集段階(Society 1.0)から農業段階(Society 2.0)、工業段階(Society 3.0)、情報化段階(Society 4.0)に分けて考えることを前提にしたものである。このスキーマでは、次のステージは、高品質なネットワークや機器による人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)、ビッグデータによって形成されるSociety 5.0であるとしている。Society 5.0は、知識社会がベースになっている。ドイツでは、Industry 1.0 から Industry 4.0 まで、それぞれ Society 2.0 から Society 5.0にほぼ対応する用語が使われている。
10.2.3 ポストパンデミック社会
特に2020年以降、コロナウイルスによるパンデミック状況は、私たちの社会と世界を混乱させ、変容させている。なぜなら、感染者の症例致死率は高く、コロナウイルスは世界の多くの人々の命を奪っているからだ。各国の伝染病予防政策のいくつかの失敗が、症例致死率の上昇を促している。
対面でのコミュニケーション、外出、遠距離移動、閉鎖・密閉・混雑した空間にいることなどが制限されるようになった。小売業、娯楽業、外食業、観光業、製造業、運輸業など、多くの部門が事業の制限や停止を余儀なくされた。多くの労働者が解雇され、多くの採用希望者が意に反して就職できなかった。多くの店やレストランが閉鎖された。貧困世帯の貧困度は増し、貧困世帯の比率は高まっている。この感染症による経済の危機的状況は、すでに大経済危機のときを越えたといわれている。
企業や学校教育の一部では、ごく短期間のうちにテレワークが推進されるようになった。リアルな対面での会議が極端に減り、オンラインによる会議がそれに取って代わった。テレワーク労働の増加は、時間とコストの社会的浪費を生んでいた通勤の減少につながり、時間とコスト予算の使い方の転換を意味する状況である。また、テレワークは都市と農村の二重居住、二重就労を促進する可能性がある。
10.2.4 ポストアーバン世界
スウェーデンの経済学者ハンス・ウェストルンドは、都市地域とその後背地の関係が弱まり、都市ネットワークが都市を結び、距離の摩擦を克服するというポストアーバン状態を説明し、解明している(Haas and Westlund 2018; Westlund 2018)。このスキーマでは、農村と都市の関係は必然的に変化し、周辺地域と近隣都市との直接的かつ一次的な接続は、ネットワーク化された地域の多面的なシステムへとつながる。そして、周辺地域の魅力はより広い市場を獲得していく。ウェストランドによれば、ポストアーバン時代には、観光が最も重要な産業のひとつになるという。
ポスト・アーバンの状況は、知識社会(Andersson 1985)の発展と関連しており、能力、文化、コミュニケーション、創造性が顕著なC-regionは、新しいネットワークを形成しうる(Andersson 1986, p.11)。このことは、周辺地域であっても、社会資本、文化資本、自然環境などを基盤として、新たな経済活動を展開する可能性があることを示唆している。しかし、基礎的な経済活動を根本的に検討するだけでは不十分であり、それを発展させることによって、その周辺にいくつかの問題が発生する。その点で、例えば、「レジャーランドスケープ」という概念は非常に興味深い(Macnaghten 2019)。
確かにポストアーバンの世界では、新しい農村と都市の関係が見られるだろうし、都市と農村のイメージについては、ハースとウェストランドが編集した本(Glaeser 2018)の著者の一人であるEdward Glaeserが、「環境主義とは木の周りに住むことで、都市は常に都市の物理的過去を守るために戦うべきだという見解は捨てるべきだ」と、都市性に関する「有害神話の払拭」を主張したことがあった。「高層マンションよりも郊外のトラクトハウスを好むような持ち家の偶像化をやめ、農村のロマンチック化をやめなければならない」(Glaeser 2011, p.15)。
10.2.5 イノベーションと周辺過疎地域の未来
前章で示したように、西日本にはいくつかの周辺地域が存在する。ポストアーバン、Society 5.0、SMRの時代には、これらの周辺地域の適者生存しかありえない。そのためには、地域のソーシャルキャピタルを含む地域資源の活用とその維持が重要である。ポストアーバン、Society 5.0の世界では、サービスや文化の文脈がこれまで以上に重要になる。Society 3.0(工業化時代)以降、経済資本、社会資本、そして文化資本の順で、社会の中で重要な役割を担ってきた。この状況を、小林はしばしば「コンテンツからコンテクストへの移行」と表現してきた。コンテクストの重要性は、その人の文化的ポジションに依存し、「隠れた次元」(Hall 1966)に位置する文化資本を帰属させることによって、何らかの効用や利益を得ることができるかもしれない。
文化資本は、特に周辺地域で重要な役割を果たす観光にとって有用な資源となる。希少な文化資本は観光客にとって非常に魅力的であり、それを紐解く鍵は過去にあるのかもしれない。つまり、イノベーションだけでなく、リノベーション、さらにはデノベーション(Doblin 1978)が、周辺地域の主要産業となりうるような観光には不可欠なのである。他では、これを「トリノベーション・パターン」と呼んでいるが、トリノベーションとは、イノベーション、リノベーション、デノベーションの組み合わせを表す(堤 2019)。これは、図 10.1に見ることができる。イノベーションが多様性に決定的に依存していることはよく知られている。しかし、そのような多様性は、多くの場合、共時的な状況に基づくものである。トリノベーションというレンズを通してみると、トリノベーションは新旧の知識、経験、情報に基づいているので、共時的な多様性だけでなく通時的な多様性もデノベーションの源泉であることを容易に認識することができる(図10.2)。
図10.1 トリノベーションのパターン(筆者作成)
図10.2 二重の多様性(筆者作成)
広域周辺圏の知識社会である日本にとって極めて重要な観光については、「バランスの取れた組み合わせ」の中で持続可能である。観光客を運ぶ運輸業、食材を供給する農林業、商品・土産物を供給する卸売業・小売業によって、観光は維持され得るのだ。したがって、産業間の関係をバランスよく組み合わせていくことで、地域の観光産業を維持していくことができる。さらに、バランスの取れた組み合わせというのは、日常生活を持続させる上でも重要な概念である。例えば、高齢化が進み、体力がないために同世代の人を助けることができない地域においては、住民同士の助け合いが難しくなっている。また、財政難から自治体の支援体制も弱体化している。高齢化社会では、公的機関,家族,地域住民による複数の支援をバランスよく組み合わせることが必要である。
10.2.6 実験的研究フィールド。沖ノ島町
私は、約 30年前から沖ノ島町で周辺地域の諸問題を研究してきた。沖ノ島町は、島根県隠岐諸島の沖ノ島を中心とした町である(図10.3)。古代日本では、隠岐は「隠岐の国」の一つを形成し、海上交通の要所であった。1960年代以降、人口流出が急激に進み、法律で過疎地として登録された。主な産業は、林業、漁業、農業、観光。
本州から40〜80km離れているため、歴史的に交通の便が悪い。しかし、有人国境地帯であり、安全保障上重要な意味を持つことから、国から交通費の補助が出されている。
図 10.3 隠岐の島町の位置図
隠岐の島は、火山性の地形、長い歴史と伝統、独自の文化が評価され、ユネスコの世界ジオパークに登録されている地域である。そのため、世界ジオパークの構成要素は観光資源となりうる(写真10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9、いずれも沖ノ島町役場で提供している)。また、この地域は、教育や自然生活にも良い条件とされている。
写真10.1 壇上峡の滝
写真10.1は、壇上神社がある「壇上瀑布」である。滝の裏庭に入ることができ、その水は「日本名水百選」に登録されている。
この地域は、特徴的な火山活動により、いたるところにユニークで興味深い地形が形成されている。写真10.2は、山中にあるトカゲの形をした岩である。海沿いには、侵食された地形や奇岩が見られる。写真10.3の海の風景は、仏教のエリュシオン(極楽浄土)を、写真10.4は象を、写真10.5はろうそくを想像させる。
隠岐は、高地と低地の両方の動植物を見ることができる場所としても有名である。この地域は、物理的な意味だけでなく、生態学的にも意味のある特徴に満ちている。
このような基本的な環境の上に、人々は生活基盤を築いてきた。沖ノ島町は、かつてはスギ、ヒノキ、マツなどを主に扱ういわゆる林業の町であった。20世紀後半の10年間は、安価な輸入木材や林業労働者の減少・高齢化、建築住宅の洋風化などにより、国内林業の衰退が顕著であった。隠岐の農業はほぼ自給自足だが、山間部でも沖積地の谷間には水田が見られる(写真10.6)。
歴史的には、隠岐は海上交通の結節点であり、政争に敗れた天皇家の流刑地でもあった。これらのことが、高貴で多様な文化現象の遺構を生んだのである。写真10.7は隠岐国分寺で行われる蓮華王舞で、古式ゆかしい神聖な舞である。国の重要無形文化財に指定されている。毎年4月に行われる。もともとは仏教の行事だが、今では観光の重要なアクティビティとなっている。
写真10.3 浄土ヶ浦海岸
写真 10.4 象岩
写真 10.5 キャンドル岩
写真 10.6 山中の水田写真 10.7 隠岐国分寺のれんげ梅
写真 10.8 八朔闘牛
写真 10.9 相撲の儀式
沖ノ島町にはもう一つ重要な行事がある。八朔闘牛(写真10.8)と古典相撲(写真10.9)である。八朔とは9月1日のことで、毎年この日に壇上伽藍の神事として闘牛の儀式が執り行われる。日本では、原始的に相撲も神道の神を祭る神聖な行事である。沖ノ島町の古典相撲は、何かめでたいことがあったときに不定期で行われることになっている。同じ二人が二度相撲で戦い、その勝敗がどうしても一勝一敗になるようにという慣習から、「人情味のある相撲」という表現があるのだそうだ。これは、小さな社会で遺恨を残さないという地域の伝統的な知恵に基づくもので、一種の地域社会資本である。
この2つのイベントには、力士や牡牛を応援する会が結成されているという共通点がある。この協会は、数カ月前から行事のための活動を行い、その過程で地域のソーシャルキャピタルが繰り返し再生産され強化されているのだ。協会のメンバーは、ある期間、同じ場所と時間を共有して活動し、より緊密な地域ソーシャルキャピタルを形成している。かつてガリバー(1955)が牛の繁殖などで言及した「家畜組合」と同じような状態なのだろう。
私は、周辺地域の持続可能性を考えるために、沖ノ島町をフィールドに、30年ほどの試行錯誤を経て、いくつかのシステム、モデルを構築してきた。産業と相互扶助については、先に述べたように、バランスのとれた組み合わせが重要であることがわかった。いずれの場合も、地域のソーシャルキャピタルが、バランスよく組み合わされた仕事の効率を活性化させる。
教育面では、沖ノ島町のもう一つの可能性として、素晴らしい自然環境と地域社会資本に基づく周辺地域の都市生まれの児童生徒への小規模校での教育がある。それは、都市から農村への人口移動に伴うものである。沖ノ島町の場合、アウトドア用品を扱う企業と包括的な連携協定を締結している。これは、町の地域活動を促進し、住民の生活の質を向上させることを意図している。アウトドア用品を製造する工場が建設され、新たな雇用の創出が期待されている。同社には顧客クラブがあり、世界各地から多くの会員が参加している。今、そこに新しい希望が生まれようとしている。ポスト都市、ポスト・パンデミック時代の観光の新しい展開を考えるには、とても良い機会である。
10.3 さらなる問題点と可能性
私の専門分野である日本の人文地理学では、研究者は狭い範囲に特化し、ある種の地域だけを対象として研究を行う傾向がある。つまり、山村や旧石炭鉱業地域からニュータウン地域まで、私のような地域を一人の研究者が研究することは、日本の地理学者の間では非常に稀である。しかし、第1章で述べたように、このようなタテ割り的なアプローチでは、空間的な周辺化といった現象を認識することはおろか、研究することも不可能である。また、1980年代以降の日本の地理学者の欧米社会理論へのアプローチも同様に、漠然とした疎外感から、実証的な地域分析が蓄積され、日本の地理学の理論的な偏在はほとんど是正されていないのが実情である。また、彼ら、日本の地理学者の多くは、移動はより広く、過疎はより小さく扱っていた。私の研究は、これらのギャップを埋めることを意図している。最後に、この分野の今後の問題点と可能性、そして本書のインプリケーションに目を向ける。過疎化した地域は、それぞれ地理的(物理的)な特徴や人口構造・変化のパターンを持っている。地域の変容を中長期的に追跡し、人口変動や高齢化動向を分析・類型化し、その地域維持のための様々な手法や政策を考案する作業が、研究者に期待・奨励されている(松原 2004)。これは、本書の主要な研究テーマの次の段階である。
研究の空間スケールについては、本書でインタースケール研究の重要性を提唱してきた。メゾアミクロスケールの分析を個々に行うことは多大な労力と困難を伴うが、地道な作業はどうしても続けなければならない。
研究の焦点となるレベルについても、現状では、ミドルレンジのアプローチによる研究の充実が求められている。特に、グランドセオリーとして流行しつつあるソーシャルキャピタルについては、社会学などで行われているコミュニティや社会的絆に関する研究との批判的な対話を続けていく必要がある。何より、ソーシャルキャピタルの概念に基づく議論は、地域住民の生活実感よりも、より一般的な生活や人権のレベルを取り上げる傾向が強く、地域政策の実施に根ざした議論となるよう注意しなければならない。ソーシャルキャピタルをめぐる議論が盛んになるにつれ、地域の社会経済機能の進展・衰退をソーシャルキャピタルの強弱だけで論じるような同語反復の罠にはまらないように注意する必要がある。そのためにも、理論と実質的な地域分析のバランスを意識的にとりながら、この作業を進めなければならない。本書刊行の当初の目的のひとつは、過疎地研究と移民研究の橋渡しをすることであった。この考え方は、山村、旧石炭鉱床地域、島嶼部、都市部の過疎地など、さまざまな地域を調査する中で培われたものである。しかし、現在、日本全国で過疎化・高齢化が進んでいる(松谷2004)。また、本書のアプローチは、日本のみならず世界の先進国(および衰退国)の都市過疎化・都市衰退の問題(堤 2005, 2008)とも関連性を持つようになった。そのため、理論と実践の本質的な関係や、学問分野を超えた批判的な対話を深め、より実践的な調査に乗り出す必要がある。
地域の社会経済的ロバスト性(強さ)と社会経済的レジリエンス(しなやかさ)を考える上で、いくつかの大きな地域問題が残されている。
2020年現在、コロナウイルス問題で大変なことになっているが、そのような状況下でも、世界の周辺地域や社会の持続可能性を考えていかなければならないのである。このような問題に取り組むことが、私の、そして私の後継者たちの課題である。
