Contents
Behavioral and Psychiatric Symptoms of Dementia and Rate of Decline in Alzheimer’s Disease
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6768941/
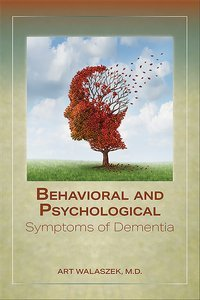
要旨
アルツハイマー病は認知症状と非認知症状の両方を引き起こす。アルツハイマー病の症状や経過は非常に異質であることがわかってきている。この異質性は、将来の症状や機能障害の予後を予測することの難しさから、患者、その家族、臨床医に課題を与えている。
行動症状や精神症状は、この臨床の不均一性に大きく寄与していると考えられている。これらの症状は神経変性の複数の領域に関連しており、脳のネットワーク全体の機能障害の代表であることを示唆している可能性がある。しかし、現在のアルツハイマー病の診断基準では、認知面にのみ焦点が当てられている。
行動症状や精神症状は、複数の研究で疾患の重症度と関連していることが明らかにされており、長期的には疾患の進行に寄与している。行動症状や精神症状とアルツハイマー病の認知的側面との関連性をよりよく理解することは、疾患モデルの改良につながり、この悲惨な疾患の治療法を開発する能力の向上につながると期待されている。
キーワード
アルツハイマー病、行動・精神症状、認知機能低下、機能低下、低下の予測因子
序論
認知症は、同じような年齢や学歴の人と比較して認知機能が低下していることが特徴である。それは、特に高齢者における罹患率と死亡率の重要な原因となっている。
1906年、アロイス・アルツハイマーは、顕著で進行性の精神症状と記憶障害を有する女性の症例を報告し、その女性を亡くなるまで5年間追跡調査した(Maurer et al 1997)。アルツハイマー病は認知機能障害の最も一般的な原因であり、その有病率は加齢とともに増加する(Erkkinen er al)。 しかし、この最初の患者における衰えの急速さは、一般的にはこの病気の通常の経過とは考えられていない。実際、患者がアルツハイマー病の段階を経て進行する割合や方法には、かなりの不均一性がある(Mayeux er al)。
この不均一性の一部は、行動・精神症状(BPSD)の存在である。これらの症状はアルツハイマー病患者の80%以上に影響を与えるが、その症状は患者間でも個人の疾患経過でも非常に変化する(Garre-Olmo et al 2010a)。精神症状はすべての病期に現れる可能性があるが、特定の症状は病期が異なるとより一般的になる。すべての症状は疾患の重症度に応じて悪化するが、妄想、焦燥感、無気力感などの特定の症状はより一般的になる傾向がある(Lyketsos et al 2002)。
認知症の初期段階での精神症状の有病率は、ますます認識されるようになってきている。軽度の行動障害は最近定義された診断構成であり、明確な認知的変化がなくても、これらの症状の存在を表すために用いられている(Ismail et al 2016)。
精神症状の管理は、これらの患者をケアする上で重要な要素である。行動症状は介護者のストレスの重要な原因であり(Van Den Wijngaart et al 2007)これらの患者の介護の経済的負担に寄与する(Murman et al 2002;Schnaider Beeri et al 2002;Herrmann N et al 2006)。また、これらの症状は、早期の介護施設入所にも寄与している(Yaffe et al 2002)。BPSDと神経変性疾患およびその進行との関係をよりよく理解することは、患者、その家族、および臨床医にとって重要である。
BPSDは全体的な臨床的悪化と関連しており(Stella F et al 2016年)重度の症状を有する患者が識別可能な神経解剖学的変化を有するという証拠がある(Poulin et al 2017)。妄想や幻覚は、複雑な行動を調節する神経ネットワーク内の萎縮と関連している(Rafii MS et al 2014)。
臨床経過を予後する能力は、臨床医だけでなく、患者やその家族にとっても極めて重要である。また、公衆衛生の観点から、人口の高齢化に伴ってアルツハイマー病患者のケアに必要なコストや医療資源を予測できることは、疾患修飾療法の適切な臨床ターゲットを特定するためにも重要である。進行の軌跡は必ずしも直線的ではなく(Samtani et al 2012年)個人間でも症例間でもかなり不均質である(Mayeux et al 1985)。そのため、いくつかの研究では、疾患の臨床的な進行を予測する方法を見つけようとしてきた。現在のところ、BPSDに対するFDA承認の治療法はほとんどないが、病気の経過を予測する能力は、それ自体が非常に価値のあるものである。
BPSDの「陰性」症状であるうつ病や不安などの理解を深めるためには、これまで多くの研究が行われていたが、幻覚や妄想などの「陽性」症状については、これまであまり研究が行われてきないでした。このレビューでは、陽性BPSDの3つの主要なクラスター、すなわち幻覚、妄想、攻撃性/激越について論じる。また、これらの症状群の根底にある神経基盤を探り、これらの症状が患者の認知および機能低下の割合にどのように影響するかを議論する。参考にした論文の一部を表1にまとめた。
表1 BPSDとアルツハイマー病の衰えへの影響を研究している論文をセレクト
| 著者、年 | 症状 | サンプルの特徴 | 分析モダリティ | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| ウィルソン等。(2006) | 幻覚 妄想的 思考 誤解 |
ラッシュADRCおよびそれ以上の年齢の成人デイケアセンター(平均2。2年のフォローアップ) n = 568、ADの臨床診断は 平均11。7年の教育。70.1%白; 分析では69.2%の女性478人 |
死亡率のグローバル認知コックス比例ハザードの複合スコアの線形混合効果モデル | ベースラインでの精神病:29.6%の幻覚、27.3%の妄想的思考、25.5%の誤解 +幻覚および誤解:↓ベースラインでの認知 LMM: 幻覚:↑直線的(0.20ユニット/年)および非線形的(0.03ユニット/年)の低下率。非線形の衰退は教育レベルの影響を受けた 妄想:↑直線的な衰退率(0.08ユニット/年) 誤解:↑直線的な衰退率(0.07ユニット/年) 一緒に:幻覚のみがより急速な衰退と関連していた Cox: +幻覚:60 %死亡する可能性が高い; ベースラインでグローバル認知を調整するときに維持されます(RR = 1.56; 95%CI 1.16-2.09); 高等教育を受けた人に強い 妄想/誤解との関連性なし |
| コナーズ等。(2018) | 幻覚妄想 | オーストラリアでのPRIME研究(クリニックベース、3年間のフォローアップ) n = 445、軽度の認知症(平均CDR-sb 5.5) 33.7%、高等教育。 ベースラインでの50.1%の女性の精神病: 13.5%の妄想; 5.8%の幻覚; 5.4%両方 34.3%ベースラインで精神病なしで3年以上発症 |
認知、機能、全体的な神経心理学的症状、介護者の負担に関する線形混合モデル 死亡率と制度化のためのコックス比例ハザード |
+ベースライン時の精神病:↑CDR-sb、↓認知、↓機能、↑NPI、↑介護者負担 LMM: +妄想:↑疾患重症度(1.2単位)、↓認知(0.8単位)、↓機能(2.6単位)、↑ NPI(6.5単位)、↑介護者負担(7.8単位) +幻覚:↑疾患重症度(0.9単位)、↓認知(1.0単位)、↓機能(2.7単位)、↑NPI(4.8単位)、↑介護者負担(5.7単位)単位) +両方ともさらに悪化した Cox: 妄想+/-幻覚(幻覚のみではない)は制度化を予測した(妄想のみのHR 2.35 95%CI 1.48、3.73;両方のHR 4.26、95%CI 2.31、7.86) どちらも死亡率を予測しなかった |
| Scarmeas etal。(2005) | 幻覚妄想 | 米国およびヨーロッパの予測因子1および2(クリニックベース、平均4。5年のフォローアップ) n = 456、軽度のAD 平均MMSE 21; 13年間の教育を意味します。59%の女性 |
コックス比例ハザード | ベースライン時の精神病:34%の妄想、32%の幻覚 70%がフォローアップ中に妄想を発症 +妄想:↑認知機能低下のリスク(RR 1.91、95%CI 1.41-2.60)、機能低下(RR 1.90、95%CI 1.41-2.54 )、および制度化(RR 1.63、95%CI 1.26-2.12) +幻覚:↑認知低下のリスク(RR 2.08、95%CI 1.41-3.07)、機能低下(RR 2.55、95%CI 1.80-3.62)、制度化(RR 1.94、95%CI 1.40-2.70)、および死亡(RR 1.52、95%CI 1.08-2.15) |
| Hallikainen etal。(2018a) | NPIのすべてのドメイン | フィンランドのALSOVAコホート(クリニックベース、5年間のフォローアップ) n = 236、非常に軽度または軽度のAD(CDR 0.5-1) 平均教育7.58歳、51.27%女性 |
疾患進行の一般化推定方程式 AD重症度の線形混合効果モデル |
ベースライン時:22.9%の妄想、14.8%の幻覚、28.8%の興奮 5年目まで:39.7%の妄想、28.8%の幻覚、31.5%の興奮 AD進行のベースライン予測因子:妄想(p = 0.001)、興奮(p = 0.010)、異常運動行動(p = 0.015)、陶酔感(p <0.001) ADの重症度に関連するBPSD:妄想、幻覚、興奮、うつ病、不安、無関心、刺激性、睡眠障害、異常な運動行動、食欲障害 |
| バーンズ他(2009) | 敵意 | Chicago Health and Agingプロジェクト(人口ベースの研究、平均、4。4年のフォローアップ) n = 4913 平均教育12.1歳、女性62.2%、白人29.6% |
混合効果回帰モデル | ベースライン での認知機能の低下に関連する敵意(敵意が1単位増加するごとに-0.028単位の認識)敵意と認知機能低下との間に関連性はありません。 |
| Zahodne etal。(2015) | 興奮 攻撃性 精神病 うつ病 |
米国の予測因子1(クリニックベース、6年間のフォローアップ) n = 517 平均教育13.72歳、93.2%白人、56.9%女性 |
潜在成長曲線モデリング | +精神病は、初期認知障害の分散の5.3%、認知低下の分散の7.3%、初期依存の分散の17%、および依存の軌跡の分散の2.4%を説明しました +認知機能低下または依存性の変化に関連しない動揺/攻撃しかし、認知機能低下の分散の6%と依存性の変化の約3%の分散は、興奮/攻撃の変化に関連していました。 +うつ病は、認知機能低下の分散の1.6%と初期依存性の分散の8.6%を説明しました。 |
| ハウプトとクルツ(1993) | 妄想 怒りの爆発 興奮 攻撃性 うつ病 |
ドイツで12か月以上軽度から中等度のADの外来患者 n = 66(自宅で44人、施設で22人) |
段階的判別関数分析 | ナーシングホームに入院した人は、攻撃的な行動をとる可能性が高く(p = 0.03)、認知障害が悪化しました(p = 0.04) 2つのグループ間の差別に最も貢献した変数:失禁、介護者が他の人にケアをしたい、認知機能低下、年齢、攻撃性、怒りの爆発、うつ病 |
| Peters et al。(2015) | 精神病 興奮 攻撃性 感情的 無関心 |
米国のキャッシュ郡認知症進行研究からのインシデントAD(コミュニティベース) n = 335 |
カプランマイヤープロット コックス比例ハザード |
少なくとも1つの神経精神症状を伴う50.9% 重度の認知症への進行の予測:精神病(HR = 2.007)、興奮/攻撃(HR = 2.946)、興奮/攻撃(HR = 2.946) 死への進行の予測:精神病(HR = 1.537 )、情動性(HR = 1.510)、興奮/攻撃性(HR = 1.942)、少なくとも1つの軽度のNPS(HR = 1.448)、少なくとも1つのNPS(HR = 1.951) |
| ロペスら。(1999) | 攻撃性 激越不眠症精神病うつ病薬を さまよう |
ピッツバーグ大学でADの可能性がある患者(研究ベース、平均フォローアップ4。16年) n = 179 |
比例ハザードモデル | 機能的能力の低下(RR = 2.02)および制度化(RR = 2.10)と有意に関連する精神病 ベースライン年齢、教育、MMSE、BDRS、機能的能力の低下との有意な関連(BDRS≥15)に合わせて調整:MMSE <19(RR = 4.08) 、精神病(RR = 2.73)、興奮(RR = 2.26)、攻撃性(RR = 2.35)、抗精神病薬(RR = 1.98); 制度化のリスク増加に関連する精神病(RR = 2.11) |
| ドノフリオ他 (2016) | 妄想 | イタリアのAD評価ユニットでADを患っている患者 n = 380 平均教育5.24歳、64.4%女性 |
平均の比較:ウェルチ2標本t検定またはANOVA ウィルコクソン順位和検定 |
妄想のある人は年齢が高く、発症年齢が遅く、認知障害と認知症の病期が悪く、うつ病が多く、栄養失調とベッドソールのリスクが高い(すべての人でp <0.0001) 妄想のある人は、うつ病のNPIスコアが高かった(p = 0.007)、幻覚、興奮/攻撃、無関心、刺激性/不安定性、異常な運動活動、睡眠障害、および摂食障害(すべてp <0.0001) |
| ウィルソン等。(2000) | 幻覚 妄想 |
ラッシュADCn = 410 人の男性教育12.0歳、85.1%白人、66.8%女性、平均MMSE 18.7 |
変量効果回帰モデル | ベースライン時:+幻覚41.0%、+妄想54.7% + 0.33単位 の認知機能低下に関連する幻覚+幻覚:↑認知機能低下率(0.69単位/年vs 0.47単位/年なし) +任意の時点での幻覚:↑認知機能低下(0.61ユニット/年vs 0.39ユニット/年なし) +認知 力の低下に関連する妄想+衰退率に関連しない妄想 |
幻覚
疫学・神経生物学
アルツハイマー病における幻覚の有病率の報告は多岐にわたっており、12%から33%という推計もある(Leroi et al 2003; Wilson et al 2006; Scarmeas et al 2005)。視覚的幻覚が臨床の中心的特徴であるレビー小体型認知症とは異なり(McKeith et al 2017年)アルツハイマー病の幻覚は、視覚、聴覚(Wilson et al 2006年)嗅覚、まれに触覚(Devanand et al 1992)のいずれかである。アルツハイマー病における幻覚は、低学歴、白人以外の民族性、重症度の悪化と関連している(Bassiony et al 2000;Wilson et al 2006)。
幻覚の基礎となる解剖学的構造を同定する努力は、さまざまな結果をもたらしてきた。幻覚は、後頭部の萎縮(Holroyd et al 2000)および左背外側前頭前野、左内側側頭前野、および右頭頂皮質の低灌流と関連している(Lopez et al 2001)。ある研究では、右辺縁上回の萎縮は3年間の幻覚の悪化を予測していた(Donovan et al 2014)。幻覚と認知機能の低下との関係には、よりグローバルなネットワーク機能不全が関係していると提案するのは直感的であろう。しかし、このネットワークを評価する正式な研究はほとんど行われていない。右前島皮質は、外部からの感覚入力を内部環境と統合する役割を担っていることもあり、幻覚の「中核領域」として提案されている(Blanc er al)。
前脳基底部からのアセチルコリンの欠乏は、アルツハイマー病や他の神経変性疾患における注意力および覚醒障害の根底にある(Pepeu er al)。 したがって、アセチルコリネラーゼ阻害剤は、アルツハイマー病の治療の主力となってきた。落ち着きのなさ、記憶障害、幻覚などを特徴とし、当初は抗コリン剤治療による異所性症候群として記述されていたコリン作動性欠損症候群が、神経変性疾患においてはより慢性的な形で存在するのではないかと提案されてきた(Lemstra er al)。 この提案は、コリン作動性欠乏症候群がレビー小体型認知症に特異的であることを示唆しているが、本症候群の症状はアルツハイマー病患者にもしばしば見られる。アルツハイマー病やレビー小体を伴う認知症の患者を対象とした脳波研究では、幻覚やレビー小体を伴う認知症の患者と同様に脳波活動の鈍化がみられ、両集団におけるコリン作動性の低下が示唆された(Dauwan et al 2018)。
幻覚の認知への影響は遺伝的素因と関連している。国立アルツハイマー調整センター(NACC)のデータから剖検で確認された900人のアルツハイマー病症例を用いて、精神病とAPO ε4の認知への影響を研究した大規模研究では、幻覚は認知の悪化と有意に関連しており、APO ε4の存在はこの関係を減衰させることが明らかになった(Qian W et al 2018)。興味深いことに、APO ε4の存在もまた、この研究ではより多くのレビー小体型病理と有意に関連していた。
さらに、幻覚は睡眠障害と関連している。これは、睡眠に関与する神経伝達物質系の調節障害によるものであるという仮説が立てられている(Sinforiani et al 2007)。幻覚は、睡眠中または睡眠覚醒期の移行期(すなわち、入眠と覚醒)に起こりやすい傾向がある(Sinforiani et al 2007)。直感的には、このことは、睡眠-覚醒サイクルと幻覚の存在との間に関連性があることを裏付けるものである。
減退率への寄与
幻覚は、より重度の認知障害と関連しており(Wadsworth et al 2012年)持続性があり(Holtzer et al 2003年)時間の経過とともに発生率が増加することがある(Vilalta-Franch et al 2013)。幻覚と衰退率との関係を評価した研究は、コミュニティベースのコホートとクリニックベースのコホートの両方でいくつか行われている。これらの研究では、ベースラインでの幻覚の存在が、より急速な衰退と関連していることが主に示されている。Wilson et al 2006)は、Rush Alzheimer’s Disease Centerと地域居住者を対象に平均2.2年間追跡調査を行った結果、認知機能スクリーニングの成績の低下(幻覚を認めた患者の平均MMSEは10.7,認めなかった患者の平均MMSEは14.1)に加えて、ベースラインで幻覚を認めた患者の方が認知機能の低下が早いことを明らかにしている。また、幻覚を認めた患者では、研究終了時までに死亡リスクが増加した(RR、1.55)。同様に、Connors et al 2018)は、オーストラリアの記憶クリニックで幻覚を起こした患者は、3年間で認知症の重症度が悪化し、認知と機能が低下し、介護者の負担が大きくなったことを実証した。同様の結果は、他のいくつかの研究でも発見されている(Forstl et al 1993;Vilalta-Franch et al 2013;Tchalla et al 2018)。
幻覚の縦断的研究の限界は、症状が時間の経過とともに変動することである(Devanand, 1999)。したがって、追跡調査の延長は有益であり、分析のロバスト性の向上に寄与するであろう。Hallikeinen et al 2018a)は、フィンランドの非常に軽度で軽度のアルツハイマー病患者(ベースラインでCDR 0.5-1)のコホートであるALSOVA研究のデータを一般化推定方程式(GEE)を用いて分析したが、幻覚が5年間の疾患重症度を予測するというエビデンスは見出されなかった。しかし、線形混合モデルを用いたところ、幻覚がアルツハイマー病の重症度と有意に関連していることが示された。
一方、Scarmeas et al 2005)は、欧米の複数の施設でアルツハイマー病と診断された患者を対象とした縦断的研究であるPredictors 1およびPredictors 2コホート(Stern et al 1993;Scarmeas et al 2004)の参加者のデータを平均4.5年、最長14年にわたって分析し、Cox分析を用いて特定の機能的および認知的エンドポイントに到達するリスクを調べた。その結果、幻覚の存在は認知(RR、1.62)と機能(RR、2.25)の低下、施設入所(RR、1.60)死亡(RR、1.49)のリスクの増加と関連していることがわかった。結果の違いの一部は、異なる統計的尺度の使用に関連している可能性がある。
アルツハイマー病における幻覚の役割を研究する上でのもう一つの限界は、レビー小体(DLB)を伴う認知症の併存があるかどうかを判断するのが難しいことである。ある大規模研究では、臨床的にアルツハイマー病と診断されたコホートの60.7%の脳にレビー小体の病理学的証拠が認められた。診断にアルツハイマー病病理学的診断を必要とするNIA-RI基準(The National Institute on Aging, and Reagan Institute Working Group on Diagnostic Criteria for the Neuropathological Assessment of the Alzheimer’s Disease, 1997)を適用したところ、コホートの56.8%にレビー小体が認められた(Hamilton, 2000)。さらに、この2つの病態を識別することは臨床的に困難な場合がある。Chungらは、病理学的に確認されたアルツハイマー病は、レビー小体の病理学と共起した場合、異なる臨床表現型を有することを発見した(Chung et al 2015)。対照的に、Roudilらは、病理学的に確認されたアルツハイマー病がレビー小体(扁桃体に限局しているか、大脳皮質に広く分布しているかのいずれか)を伴う場合と、幻覚の存在を含むレビー小体を伴わない場合との間には、多くの臨床的および神経心理学的側面において有意な臨床的差異がないことを発見した(Roudil et al 2018)が、これははるかに小規模な研究であり、認知的に悪化している可能性のあるコホートを使用したものであったが。
攻撃性/アジテーション
疫学・神経生物学
焦燥感や攻撃性はアルツハイマー病では一般的であり、電子カルテのある大規模研究で測定された焦燥感の有病率は軽度の場合で50%以上と推定されている(Halpern et al 2019)。これは、介護者の安心感を損なうためか、縦断的な介護者ストレスの最も大きな要因の一つである可能性がある(Hallikainen et al 2018b)。しかし、他のBPSDと比較して、激越や攻撃性に関する研究は少ない(Victoroff et al 2018)。病理的に中等度または高負荷のアルツハイマー病が確認された1つの研究では、激越と攻撃性を有する患者は認知テストでの成績が悪くなる傾向があり、機能的にも悪化していることがわかった(Sennik et al 2017)。介護者の時間などの「非公式なコスト」だけでなく、施設化の増加による医療費の増加(Costa et al 2018)と関連していることから、公衆衛生の観点からも重要な症状である(Rattinger et al 2019)。
幻覚と同様に、動揺の存在は複数の解剖学的部位と相関している。焦燥感は、眼窩前頭前野および前帯状皮質における神経原線維のもつれ負担の増加と相関している(Tekin et al 2001)。これを支持するのは、ADNIのデータを用いた解剖学的研究で、悪化した焦燥感や攻撃性の存在が、軽度の認知障害とアルツハイマー病認知症を持つ患者の2年間の関心領域である前頭前野、島状野、扁桃体、帯状野、海馬でのより大きな萎縮と関連していることを発見した(Trzepacz et al 2013)。また、右前頭葉機能障害が優勢である可能性も示唆されている(Lopez et al 2001)。機能イメージング研究では、同様に、焦燥が前頭葉および側頭葉の代謝低下と関連していることが示唆されている(Sultzer et al 1995)。興味深いことに、Ehrenbergら(Ehrenberg et al 2018)は、焦燥がBraakステージI~IVでは神経原線維絡みの病理と関連していたが、レベルV~VIでは関連していなかったことを発見し、皮質下の病理も同様に重要な寄与者である可能性を示唆している。
攻撃性はアミロイド負担の増加と関連している。ヒトAPP変異を発現したトランスジェニックマウスは、非トランスジェニックマウスに比べて、疾患の初期段階でも攻撃性が有意に高いことが示されている(Alexander et al 2011)。ヒトにおいて、大規模な研究では、病理学的に確認されたアルツハイマー病のコホートにおいて、焦燥/攻撃性の存在がアミロイド病理の高負担に直接相関しており(Sennik et al 2017)他の臨床診断では、レビー小体型認知症や前頭側頭型認知症などの焦燥/攻撃性を有する患者に起因していることが明らかにされた。このコホートでは、リン酸化TDP-43沈着物は男性の激越症患者でより多く見られ、行動障害が存在する場合に患者を適切に診断することの難しさを示していた。
病理的に確認されたアルツハイマー病のコホートでは、高齢者の動揺と攻撃性のための尺度であるCohen-Mansfield Agitation Inventory (Cohen-Mansfield, 1986)の総合スコアが高いことが、海馬の5-HIAAレベルの低下と有意に関連していた。このコホートでは、身体的に非攻撃的な行動(それでも患者や介護者を苦しめる可能性がある)の存在は、小脳におけるドーパミン異化の増加と有意に関連していた(Vermeiren et al 2014)。アルツハイマー病の臨床診断を受けた個人を対象とした剖検に基づく研究では、剖検では攻撃性がコリン作動性神経支配性神経支配性の低下の有意な予測因子であり、過活動性がセロトニン作動性神経支配性の低下の最も優れた予測因子であることが示された(Garcia-Alloza et al 2005)。
減衰率との関連
焦燥感は、単独でも他のBPSDとの併用でも、経時的には疾患の重症度と関連しているが、疾患の進行とは矛盾している。興奮を単独の因子として評価した研究はほとんどない。Haupt and Kurz (Haupt and Kurz, 1993)は、小規模な診療所ベースの研究で、攻撃性が1年間の施設入所を予測する因子の1つであることを明らかにした。同様に、Cache County Dementia Progression StudyのPeters et al 2015)は、Cox比例ハザードモデルを用いて、重度認知症(CDR≧2またはMMSE≦10と定義)と死亡(HR 2.946,1.942)の両方のリスクの有意な予測因子として、アジテーション/攻撃性があることを明らかにしたが、このコホートの参加者のベースラインの状態は明らかではない。さらに、Lopezら(1999)は、精神症状と精神科薬の疾患進行への影響についての研究で、年齢、教育、性、ベースラインの認知・機能状態をコントロールしながら、攻撃性または激越性のいずれかの存在は、有意な機能障害までの期間が短くなるリスク(RR、それぞれ2.35,2.26)の有意な増加と独立して関連していることを明らかにした。
対照的に、Barnesらは、Chicago Health and Aging Projectという縦断的な集団ベースの研究のデータを用いて、混合効果回帰モデルにおいて、ヒスパニック系以外の白人とアフリカ系アメリカ人の両方において、敵意はベースラインでの認知の悪化とは関連しているが、4.4年間の認知の低下とは関連していないことを明らかにした(Barnes et al 2009)。ZahodneらはPredictors 1コホートのデータを研究し、6年間の潜在成長曲線モデルにおいて、ベースライン時の激越/攻撃性はベースライン時の認知、機能低下、または認知機能低下とは相関しないことを明らかにした。しかし、撹拌/攻撃性の経時変化は、認知機能低下の経時変動のわずかな量を占めていた(Zahodne et al 2015)。同様に、ALSOVA研究では、診断時の激越は疾患の進行を予測しなかったが、5年間の疾患の重症度と有意に関連していた(Hallikainen et al 2018a)。
注目すべきは、Hallikainenらは、動揺や攻撃性とともに、異常な運動行動が疾患の重症度に追従する傾向があり、疾患進行の予測因子であることを発見した(Hallikainen et al 2018a)。因子分析や潜在クラス分析などの方法で神経精神医学的インベントリ(NPI)のうち神経精神症状のグループ化を調べた研究では、異常な運動行動は時々(Aalten et al 2003;van der Linde et al 2014年)常にではないが(Garre-Olmo et al 2010b)激越と一緒にクラスタ化されることがある。
妄想
疫学・神経生物学
妄想はアルツハイマー病の症状としてよく知られているが、Holtzerらの研究によると、妄想は最初は悪化しても、時間の経過とともに減少することがわかっており(Holtzer R et al 2003)その有病率を推定するのは困難である。妄想は、「迫害性」か、カプグラス症候群や幻のボーダー症候群などの誤認識現象に関連していると考えられる傾向がある。妄想の存在は、幻覚の存在と組み合わされて精神病を構成する傾向がある。精神病は確かにこれらの症状の両方を含んでいるが、妄想は幻覚とは異なる神経回路の代表である可能性がある。臨床的にも、この2つの症状を別々に考える価値がある。視覚および聴覚の幻覚は、それが真実であると信じている患者側の固定した信念がない場合に起こることがあり、妄想は幻覚がない場合に起こることがある、多くの状況がある。興味深いことに、妄想は幻覚や焦燥とは異なる影響を患者の機能に与える可能性がある。Bertrandら(Bertrand et al 2017)は、妄想を持つ軽度から中等度のアルツハイマー病患者は、治療選択の好みを表現する能力が低下し、医療への同意能力に影響を与える可能性があることを発見した。対照的に、幻覚、激越/攻撃性、および他のいくつかのBPSDを有する患者では、意思決定能力に弱点は見られなかった。
構造的には、妄想の存在は、軽度のアルツハイマー病患者では右下前頭前野と下頭頂葉、左下前頭前野と内側前頭前野と手足部の灰白質密度の低下と関連している(Bruen et al 2008)。興味深いことに、Fischer氏らは、妄想発症前後(一般的には6ヶ月のスパンで)のMCI患者のMRIスキャンを比較したところ、両側島皮質、小脳、右視床と後帯状回、左前頭葉、左上側頭回、傍海馬回を含む14箇所で灰白質形態に有意な差が認められた(Fischer氏 et al 2016)。その間にMCIから軽度アルツハイマー病に転換した患者もおり、平均認知も悪化していた。また、妄想の存在は、左頭頂部白質の完全性の異常や、左頭頂部白質と呼称される部分や、カロッとした部分の白質の完全性の異常(Nakaaki et al 2013年)進行した神経原線維のもつれの病理学(Ehrenberg et al 2018)とも関連している。
衰退率との関連
妄想はしばしば幻覚と一緒に研究される。幻覚の存在は、横断的な認知テストのパフォーマンスの低下と関連していることが多い(Jeste et al 1992)が、縦断的な低下の速さと関連している。オーストラリアで行われたPRIME研究のConnorsらは、線形混合モデルを用いて、妄想の存在のみが認知、機能、認知症の重症度の悪化、介護者の負担の増加と3年間に渡って関連していることを明らかにした。また、妄想は施設入所を予測したが、死亡率は予測しなかった(Connors et al 2018)。同様に、ScarmeasらはPredictorsコホートにおいて、妄想は施設入所(RR、1.60)および死亡率(RR、1.49)と同様に認知(RR、1.50)および機能(RR、1.41)低下のリスク増加と関連していることを明らかにした(Scarmeas et al 2005)。
興味深いことに、D’Onofrioらは単施設研究で、軽度から中等度のアルツハイマー病患者では妄想が有意に病期が長くなる傾向と関連していることを明らかにした(D’Onofrio et al 2016)。さらに、Wilsonらは、幻覚と妄想の効果を4年間にわたって研究し、妄想は認知機能の低下率とは関連していないことを明らかにした(Wilson et al 2000)。縦断的研究において、妄想と幻覚を分離した研究はほとんどないが、認知機能の低下率に対する妄想の効果に関する証拠はあまり決定的ではないようである。妄想の存在の影響をよりよく理解するためには、さらなる研究が有用であろう。
疾患モデルに情報を与えるためのBPSDの使用
蓋然性アルツハイマー病の臨床診断には、無気力または非無気力パターンでの認知の悪化の存在が必要である(McKhann et al 2011)。非認知症状はこれらの診断基準では考慮されていないが、BPSDはアルツハイマー病によく見られる症状である。これらの症状が最初に発現する疾患の時期は様々であるが、時間の経過とともに持続し、疾患の悪化とともに増加する。これらの症状は、家族にとって認知症状よりも対処が難しく、罹患率、死亡率、および関連する医療費の増加のために公衆衛生上の懸念を表している。これらの症状に関連する脳の領域は、神経ネットワーク全体に病理学的な広がりがあるために影響を受けている可能性が高く、一部の患者ではなぜこれらの行動領域が早期に影響を受けるのかは不明である。これらの症状の存在と時期に対する遺伝的および環境的要因はまだ解明されていない。特定の症状に関連する特定の脳領域を特定しようとした結果が異なることから、BPSDの存在はネットワーク全体の機能障害を反映している可能性があることが示唆されている。実際、激越を含む多動性の存在は、安静時機能MRIにおいて、外部環境への適切な反応を生成する上で重要な前部感覚ネットワークの変化と関連している(Balthazar et al 2014)。これらの症状の存在が認知変化と同様にアルツハイマー病の診断に重要であると考えるべきかどうかは検討に値する。アルツハイマー病の広範な不均一性のために、異なる疾患予測モデルを開発する必要があるかもしれない。実際、Razlighiらは、Predictors 1と2のコホートにおける施設入所までの期間、フルタイムケア、死亡を予測するための縦断的なGrade of Membership (L-GoM)モデルの開発と検証において、精神病や徘徊などのBPSDの存在を含めている(Razlighi et al 2014)。これらの問題をよりよく理解し、最終的に効果的な対症療法を開発できるようにするためには、さらなる研究が必要である。
さらに、神経病理学的変化とBPSDとの関係は、外部要因の影響を受けている可能性が高い。Casanovaらは、BPSDの臨床病理学的相関関係のレビューの中で、神経遮断薬は認知症患者の脳血管イベントのリスクを増加させる可能性があり、それ自体が特定のBPSD(すなわち、うつ病や無気力感)のリスクを増加させ、認知機能の低下を悪化させる可能性があることを指摘している(Casanova et al 2011)。神経弛緩薬やその他の抗精神病薬もまた、疾患の発現や進行に影響を与える可能性がある;これらの薬剤はBPSDの症状を軽減する可能性があるが、老年精神保健の専門家のコンセンサスは、激越や攻撃性に関しては証拠が限られており、一貫性がないことを指摘している(Salzman er al)。 しかし、Lopezら(1999)は、抗精神病薬が機能低下の増加と関連していることを発見し、この効果は鎮静または錐体外路作用と関連しているのではないかと仮説を立てた。音楽、明るい光、ペットセラピーなどの非薬理学的療法もBPSDの症状の軽減に有効である可能性があると指摘されているが(Forlenza et al 2017;Doody et al 2001)このような療法はしばしばより広範なケアプログラムの一部であり、試験のために分離することは困難である。BPSDの疾患進行に対する効果を検討している研究の多くは、すべてではないが、薬理学的治療を考慮に入れている;しかしながら、非薬理学的アプローチを考慮に入れている研究を見つけることができなかった。追加の臨床試験によって非薬物療法の使用が強化されるのであれば、将来のBPSDの研究でもこの点を考慮に入れる必要があるだろう。
さらに、コリンエステラーゼ阻害薬とメマンチンの使用は、これらの効果をも混同させる可能性がある;Predictors 2コホートでは、コリンエステラーゼ阻害薬は機能低下の遅延と関連しており、メマンチンは、精神症状の存在を含むいくつかの患者特性をコントロールした場合、死亡までの時間の遅延と関連していた(Zhu et al 2013)。これは因果関係を示すものではないが、アルツハイマー病に対する現在の標準治療が認知症の重症度に対するBPSDの影響に影響を与えている可能性を示唆している。
また、通常は考慮されない追加の要因として、介護における社会的支援や家族の関与が挙げられるが、これらが相対的に欠如している場合には、高齢者のうつ病の増加と関連している(Sonnenberg er al)。 対照的に、Chanらは、子供や義理の子供を介護者として持つ人ほど、精神病を持っていると報告される可能性が高いことを発見したが、これが症状の有病率の違いによるものなのか、それとも症状を報告する可能性の違いによるものなのかは明らかではない(Chan et al 2003)。より広範な社会的支援ネットワークや家族の存在が、幻覚などの症状による苦痛を軽減するのに役立ち、おそらくこれらの症状が機能や認知機能の低下に及ぼす影響を緩和する可能性があることはもっともである。この効果を明らかにするためには、さらなる研究が有用であろう。
多くの研究における重要な限界は、診断の病理学的確認が不足していることである。BPSDはレビー小体型認知症や前頭側頭型認知症など、多くの神経変性疾患にみられる。臨床的には、これらの疾患は、特に疾患の経過の初期において、互いに区別することが困難な場合がある。例えば、アルツハイマー病の前頭側頭型認知症は、前頭側頭型認知症と誤診されることがある。ある臨床研究では、臨床的に前頭側頭型認知症と診断された症例の40%近くが、PETスキャンの結果に基づいてアルツハイマー病と診断された(Ossenkoppele er al)。 同様に、レビー小体症、アルツハイマー病、扁桃体優位のレビー小体を有するアルツハイマー病の剖検シリーズでは、レビー小体症の方が早期に発生する傾向があるものの、幻視の有無では群間の区別がつかないことが明らかになった。アルツハイマー病とレビー小体型疾患の基礎となる病態はしばしば共存しており(Hamilton, 2000)、どちらの病態が症状の原因となっているのかを臨床的に確認することは困難である。
さらに、下流のイベントに対するベースラインの影響を推定するための標準的な方法はない。一般的に使用されている統計的手法は、Cox比例ハザード、潜在成長曲線モデリング、および一般化推定方程式である。各モデルにはそれぞれ長所があるが、異なる方法で得られた結果を直接比較することは困難であり、ベースライン特性を用いて経時的な影響を予測することはさらに困難である。
臨床では、初期の幻覚や焦燥感の存在は、臨床医の診断アプローチをアルツハイマー病の可能性から遠ざけてしまうことがある。他の神経変性疾患の診断基準では、このようなアプローチが推奨されているが、これは不完全な理解である可能性がある。他の認知機能の変化の中でのBPSDの存在を、根底にある神経ネットワーク機能障害の比較的非特異的な症状として捉えることは、より有用であるかもしれない。臨床診断基準を精緻化する上で、画像診断や脳脊髄液、血清診断などの形でのバイオマーカーベースの診断がますます重要になってくると思われる。
おわりに
予後を予測する能力は、患者とその家族にとって極めて重要である。エビデンスのバランスは、早期に陽性BPSDが存在すると、より早い病勢進行を予測できることを示唆している。これは陰性のBPSD(すなわち、うつ病や無気力感なども病気の進行に寄与している可能性が高い)の影響を考慮していない。この効果の根底にある病因はよく理解されていないが、遺伝的素因と共存神経病理学の複雑な組み合わせである可能性が高い。初期の認知症患者を追跡したコホート研究は、この影響を解明する上で非常に重要であるが、長い疾患経過の中での変動を把握するのに十分な期間、患者を追跡した研究はほとんどない。これらの効果の一般化可能性を確認するためには、さらに長期的な研究が必要である。
