Contents
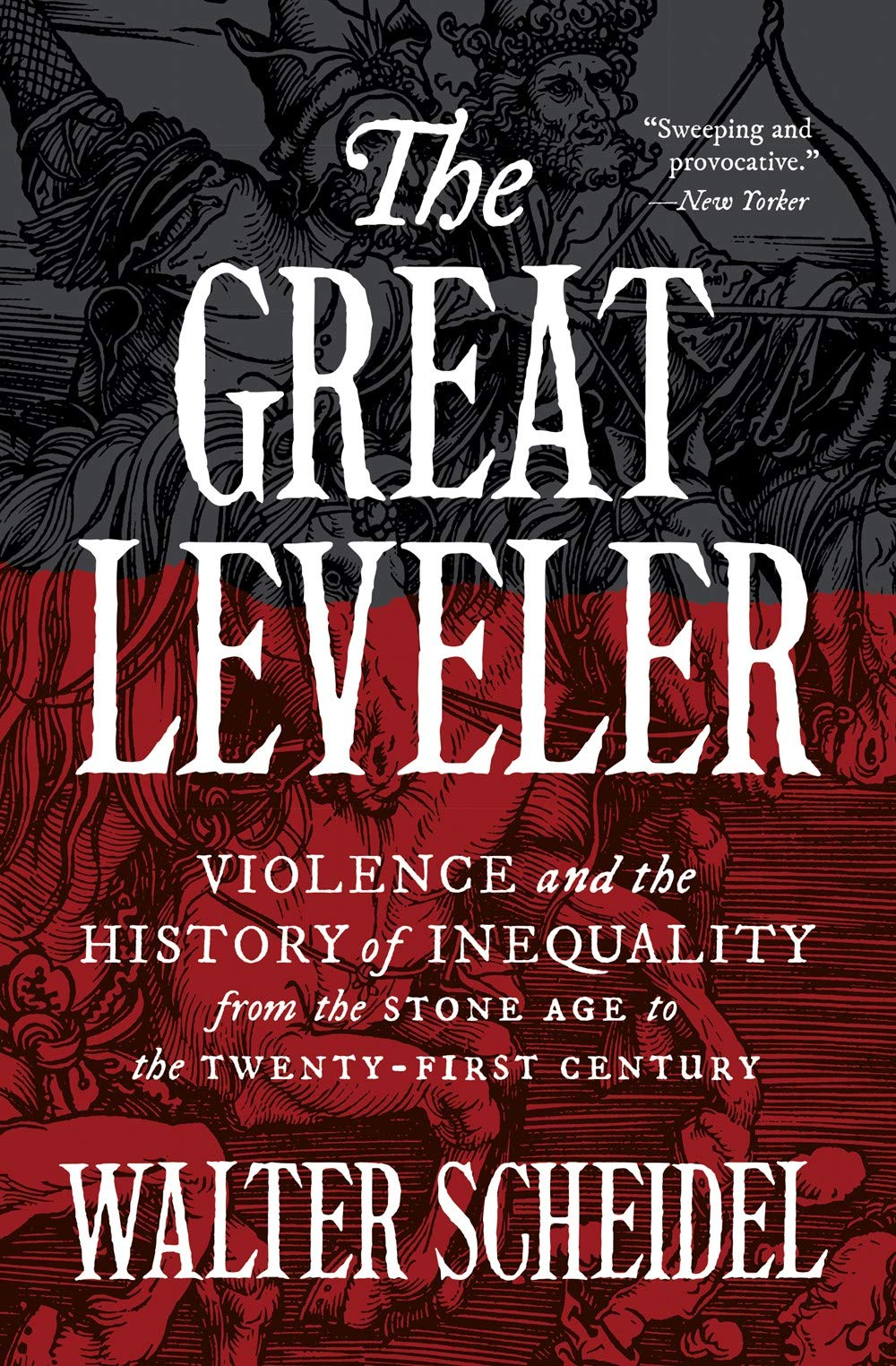
目次
- 図と表のリスト
- 謝辞
- はじめに 不平等への挑戦
- 第1部 不平等の歴史
- 1.不平等の台頭
- 2.不平等の帝国
- 3.上昇と下降
- 第2部 戦争
- 4.総力戦
- 5.大圧縮
- 6.産業革命以前の戦争と内戦
- 第3部 革命
- 7.共産主義
- 8.レーニン以前
- 第4部 崩壊
- 9.国家破綻とシステム崩壊
- 第5部 疫病
- 10.黒死病
- 11.パンデミック、飢饉、戦争
- 第6部 代替案
- 12.改革、不況、代表制
- 13.経済発展と教育
- 14.もしも?歴史から反事実へ
- 第7部 不平等の再来と平準化の未来
- 15.現代において
- 16.未来はどうなるのか?
- 付録 不平等の限界
- 参考文献
- 索引
要約
グレート・レベラーウォルター・シャイデル著『The Great Leveler:Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century』は、人類史上における経済的不平等の原因と結果についての興味深い探求書である。シャイデルは、不平等の起源に関する一般的な理論に異議を唱え、歴史的に不平等を縮小してきた様々な平準化の力について包括的な分析を示している。本書は、平準化要因としての暴力の中心的役割を強調し、不平等の大幅な縮小は、戦争、革命、パンデミック、国家崩壊といった大きな社会的混乱の余波の中でしばしば生じてきたことを示唆している。シャイデルの研究は、暴力、不平等、社会の安定の間の複雑な関係について貴重な洞察を提供している。
この本の要約では、主なアイデアと重要なポイントを探る:
不平等の自然状態という神話
シャイデルは、経済的不平等は人間社会の必然的帰結であるという考え方に異議を唱えている。彼は、不平等は自然な状態ではなく、様々な要因によって形成された歴史的・社会的産物であると主張する。人類の歴史を通じて、時折相対的に平等な時期があったにもかかわらず、不平等は例外ではなく、むしろ規範であった。シャイデルは、不平等を人間固有の特性や経済的な力に帰する理論を否定し、不平等は多面的な原因を持つ複雑な現象であると主張する。
レベリングの四騎士
シャイデルによれば、歴史的に4つの主要な暴力的混乱が平準化の力として働いてきた:
-
- 大量動員戦争:社会全体を動員するような激しい戦争は、富と権力をより公平に再分配し、社会を大きく変革する可能性がある。例えば、第一次世界大戦と第二次世界大戦は、多くの国々で不平等の是正に貢献した。
- 変革的革命:フランス革命やロシア革命のような革命運動は、しばしば権力構造の急激な変化や資源の再分配をもたらした。
- 社会の崩壊:帝国や国家、文明が崩壊すると、既存の社会階層や不平等が不安定化したり、消滅したりすることが多い。西ローマ帝国の滅亡やマヤ文明は、そのような平準化の例である。
- 大衆動員国家:総力戦やその他の変革プロジェクトに社会を動員する国家は、不平等を縮小する政策を打ち出すことが多い。第二次世界大戦後に誕生した福祉国家などがその例である。
伝染病の役割
シャイデルは、14世紀の黒死病や20世紀初頭のスペイン風邪のような伝染病も、人口規模を縮小し、労働力不足をもたらすことによって、平準化要因として機能しうると論じている。この欠乏は賃金や労働条件の改善につながり、最終的には不平等の縮小に貢献する。
不平等の持続
シャイデルは、不平等が大幅に是正された歴史的事例を強調する一方で、不平等は時間の経過とともに再燃する傾向があることも認識している。大規模な不平等是正が起こった後でも、不平等と社会階層の新たなシステムが確立されることが多い。シャイデルは、暴力や混乱が不平等に対する長期的な解決策としては限界があることを認めている。
現代の文脈
彼の洞察を現在に当てはめると、20世紀から21世紀にかけてのグローバリゼーションとテクノロジーの進歩が、貧富の格差を拡大させたとシャイデルは指摘する。しかし、将来的に平準化する力がどのように生じるのか、また、それが現代の不平等を是正するのに有効かどうかを予測するのは困難であると彼は認めている。
結論として、ウォルター・シャイデルの『グレート・レベラー』は、歴史を通じて経済的不平等の原因と結果について示唆に富む分析を提供している。シャイデルは、平準化する力としての暴力と大混乱の役割を強調することで、従来の理論に挑戦し、不平等の複雑な力学に光を当てている。彼の研究は、不平等と社会正義に関連する現代的な問題に取り組むためには、歴史的なパターンをより深く検証し、理解する必要があることを強調している。
本文
母のために
分配は過剰をなくすべきだ、
そして各人が十分に持つべきである。
シェイクスピア『リア王』
「金持ちをなくせば、貧乏人はいなくなる」
デ・ディビティス
「神はわれわれのために、われわれの危険よりも悪い治療法をしばしば見つけてくださる!」
セネカ『メデア』
図と表
- I.1アメリカにおける上位1%の所得シェア(年間)と「所得格差」への言及(3年間の移動平均)(1970-2008年
- 1.1農耕社会の社会構造の一般形態
- 3.1長期的なヨーロッパにおける不平等の傾向
- 3.2イタリアと低地諸国における富の分配のジニ係数(1500-1800年
- 3.3スペインにおける一人当たり平均GDPと賃金および実質賃金の比率(1277-1850年
- 3.4ラテンアメリカの長期的な不平等傾向
- 3.5アメリカの長期的な不平等傾向
- 4.1日本の上位所得シェア(1910-2010年
- 5.14カ国における上位1%の所得シェア(1935-1975年
- 5.2ドイツとイギリスにおける上位0.1%の所得シェア
- 5.3World10ヵ国における上位1%の富のシェア(1740-2011年
- 5.4フランス、ドイツ、イギリス、世界における個人富の国民所得に対する比率(1870-2010年
- 5.5フランス、スウェーデン、アメリカにおける所得上位1%の総所得に占める資本所得の割合(1920-2010年
- 5.6国民所得に占める政府支出の割合(7カ国、1913-1918年
- 5.7世界9カ国の最高限界税率(1900-2006年
- 5.820カ国における所得税と相続税の最高税率の平均(1800-2013年
- 5.9第一次世界大戦と17カ国の所得税の平均最高税率
- 5.10ドイツにおける所得上位1%のシェア(1891-1975年
- 5.11スウェーデンにおける上位1%の所得シェア(1903-1975年
- 5.12スウェーデンにおける州の限界所得税率(1862-2013年
- 5.13OECD加盟10カ国の労働組合密度(1880-2008年
- 6.1大国における戦争年の軍事規模と動員率(1650-2000年
- 6.2スペインにおける所得のジニ係数と上位0.01%の所得シェア(1929~2014年
- 9.1鉄器時代から初期中世にかけてのイギリスにおける家の大きさの中央値
- 9.2鉄器時代から中世初期までのイギリスの家屋規模四分位数
- 9.3鉄器時代から中世初期までのイギリスにおける住宅規模のジニ係数
- 10.1ヨーロッパとレバントにおける都市の非熟練労働者の実質賃金(1300-1800年
- 10.2ヨーロッパとレバントの都市熟練労働者の実質賃金(1300-1800年
- 10.3イングランドの穀物で測定した農村部の実質賃金(1200-1869年
- 10.4ピエモンテの都市における上位5%の富の分配率とジニ係数(1300-1800年
- 10.5ポッジボンシにおける富のジニ係数(1338-1779年
- 10.6トスカーナにおける上位5%の富の分配率(1283-1792年
- 10.7ルッカにおける上位5%の富の分配率とジニ係数(1331-1561年
- 11.1メキシコ中央部における素消費バスケットの倍数で表示した実質賃金(1520~1820年
- 11.2エジプトにおける非熟練農村労働者と都市労働者の1日当たり小麦賃金(紀元前3世紀から紀元後15世紀まで
- 11.3ローマ時代エジプトにおける紀元前100~160年代と190~260年代の実質価格と賃料の変化
- 11.4アウクスブルクにおける富の不平等:納税者数、平均納税額、納税額のジニ係数(1498-1702年
- 13.1各国の国民総所得とジニ係数(2010年
- 13.2ラテンアメリカの所得ジニ係数の推定と推測(1870-1990)(4,6、16カ国の人口加重平均値
- 14.120世紀の反実仮想的不平等傾向
- 15.1OECD20カ国における上位1%の所得シェア(1980-2013年
- A.1不平等可能性フロンティア
- A.2産業革命以前の社会における推定所得ジニ係数と不平等可能性フロンティア
- A.3産業革命以前の社会とそれに対応する現代社会における抽出率
- A.4社会的最小値の違いによる不平等可能性フロンティア
- A.5さまざまなタイプの不平等可能性フロンティア
表
- 2.1ローマ社会とローマ支配下の人口において報告された最大の財産の発展(紀元前2世紀から紀元後5世紀まで
- 5.1世界大戦中の上位所得分配の発展
- 5.2上位1%の所得シェアの減少率の変化(時代別)
- 6.11860年(1860年=100)に対する1870年の財産(南部白人)
- 6.2南部の家計所得の不平等性
- 8.1フランスにおける所得シェア(1780-1866年
- 11.1アウクスブルクにおける課税世帯の階層別シェアと世帯数(1618年と1646年
- 15.1選択国における上位所得シェアと所得格差の傾向(1980-2010年
謝辞
持てる者と持たざる者の間の格差は、人類文明の過程を通じて、拡大したり縮小したりを繰り返してきた。経済的不平等が大衆の言説の中で再び大きく取り上げられるようになったのはごく最近のことかもしれないが、その歴史は深い。私の本は、この歴史を非常に長い目で追い、説明しようとするものである。
この非常に長い歴史に最初に目を向けてくれたのは、不平等に関する世界的な専門家であり、自身の研究で古代にまでさかのぼるブランコ・ミラノヴィッチである。彼のような経済学者が増えれば、もっと多くの歴史家が耳を傾けるようになるだろう。10年ほど前、スティーブ・フリーゼンは古代の所得分布について私に深く考えさせ、エマニュエル・サエズはスタンフォード大学の行動科学高等研究センターでの共同研究期間中に、私の不平等への関心をさらにかき立てた。
私の視点と主張は、トマ・ピケティの研究に少なからず影響を受けている。21世紀の資本に関する彼の挑発的な著書が、彼の考えをより多くの読者に紹介する数年前から、私は彼の著作を読み、ここ数世紀(私のような古代史家にとっては「短期的」とも呼ばれる)を超えた関連性について考えていた。彼の大著の登場は、私が単なる熟考から自分自身の研究の執筆へと進む、大いに必要な原動力となった。彼の先駆性は高く評価されている。
はじめに 不平等への挑戦
「危険で拡大する不平等」
世界人口の半分の純資産に匹敵する億万長者は何人いるだろうか?2015年、地球上で最も裕福な62人は、人類の貧しい半分、35億人以上と同じだけの個人純資産を所有していた。もし彼らが一緒に遠足に行くことになれば、大型バスに余裕で収まるだろう。前年は、この閾値をクリアするために85人の億万長者が必要だった。また、少し前の2010年には、388人もの億万長者が、世界的なもう半分の資産を相殺するために資金を出し合わなければならなかった。
しかし、不平等は億万長者だけが作り出しているわけではない。世界で最も裕福な1%の世帯は、世界の個人純資産の半分強を保有している。一部の富裕層がオフショア口座に隠している資産を含めれば、その分布はさらに歪むだろう。このような格差は、単に先進国と発展途上国の平均所得に大きな差があることが原因ではない。同様の不均衡は社会内部にも存在する。最も裕福な20人のアメリカ人は現在、自国の世帯数の下半分を合わせたのと同じだけの資産を所有しており、所得の上位1%が国民全体の約5分の1を占めている。格差は世界の多くの地域で拡大している。ここ数十年で、ヨーロッパや北米、旧ソ連圏、中国、インドなどで所得と富の偏在が進んだ。アメリカでは、上位1%のうち最も稼ぎの良い1%(所得が0.01%の最上位層)が、そのシェアを1970年代のほぼ6倍にまで伸ばしたが、同グループの上位10分の1(上位0.1%)は4倍になった。残りの層は平均して4分の3程度の増加であり、顰蹙を買うほどのものではないが、上位層の増加には遠く及ばない2。
「1%」という呼称は、舌を滑らかに滑らせる便利な呼称であり、本書でも繰り返し使用しているが、富がさらに少数の手に集中している度合いを曖昧にする役割も果たしている。1850年代、ナサニエル・パーカー・ウィリスはニューヨークの上流社会を表すために「アッパー・テン・サウザンド」という言葉を作った。格差の拡大に最も貢献している人々を正当に評価するために、「アッパー・テン・サウザンド(上位1万人)」という変種が必要なのかもしれない。そして、この希薄なグループの中でさえ、頂点に立つ人々は他のすべての人々を凌駕し続けている。アメリカ最大の富は現在、平均世帯年収の約100万倍に相当し、1982年の20倍にもなる。それでも米国は、名目GDPがかなり小さいにもかかわらず、さらに多くのドル億万長者を抱えるようになったと言われる中国に負けているかもしれない3。
このような状況は、不安の高まりとともに迎えられている。2013年、バラク・オバマ大統領は不平等の拡大を「決定的な課題」にまで高めた:
それは、危険で拡大する不平等と上昇志向の欠如であり、アメリカの中流階級の基本的な取り決め、つまり、一生懸命働けば出世するチャンスがあるということを危うくしている。私は、これこそが現代の決定的な課題だと考えている: 働くすべてのアメリカ人のために経済が機能するようにすることだ。
その2年前、大富豪の投資家ウォーレン・バフェットは、自分と「大金持ちの友人たち」が十分な税金を払っていないと不満を漏らしていた。この感情は広く共有されている。2013年に出版されてから18カ月も経たないうちに、資本主義の不平等に関する700ページの学術書が150万部を売り上げ、ニューヨーク・タイムズのノンフィクション・ハードカバーのベストセラー・リストのトップに躍り出た。2016年大統領選の民主党予備選挙では、バーニー・サンダース上院議員が「億万長者階級」を執拗に糾弾し、大群衆を沸かせ、草の根の支持者から数百万の小口寄付を引き出した。中華人民共和国の指導部でさえ、「所得分配システムの改革」についての報告書を支持し、この問題を公に認めている。私が住むサンフランシスコ・ベイエリアでは、グーグルという大金持ちが、所得格差が人々の意識の中でますます顕著になっていることを追跡することができる(図I.1)4。
図I.1 米国における上位1%の所得シェア(年間)と「所得格差」に関する言及(3年間の移動平均)、1970-2008年
では、富裕層は単に富み続けてきたのだろうか?そうとも言えない。「億万長者層」、より広義には「1%」の強欲さが非難されているが、アメリカの最高所得分配率が1929年当時の水準に追いついたのはごく最近のことであり、資産の集中度は当時よりも低くなっている。第一次世界大戦争前夜のイギリスでは、10分の1の富裕層が全個人資産の92%という驚異的な比率を占め、その他大勢を押しのけていた。高い不平等には非常に長い血統がある。2000年前、ローマ帝国最大の私財は、帝国の一人当たり平均年収の約150万倍に相当し、これはビル・ゲイツと現在の平均的アメリカ人の比率とほぼ同じである。私たちが知る限り、ローマ帝国の所得格差の全体的な程度でさえ、アメリカのそれと大差はなかった。しかし、ローマ教皇グレゴリウス大王の時代(紀元600年頃)には、大邸宅は姿を消し、ローマ貴族のわずかな生き残りは、教皇の手当てに頼っていた。その時のように、多くの人々が貧しくなったにもかかわらず、金持ちが失うものが多くなったために不平等が減少することもあった。黒死病後の西ヨーロッパでは、実質賃金が2倍から3倍に上昇し、労働者は肉とビールで食事をし、地主は体面を保つのに苦労した。
所得と富の分配は時代とともにどのように変化してきたのだろうか。近年、不平等が大きな注目を浴びていることを考えると、私たちはこのことについて、予想以上に知らないことが多い。なぜ所得が過去数世代の間に頻繁に集中するようになったのか、という最も差し迫った問題については、しばしば高度に専門的な研究が大規模かつ着実に増えている。20世紀初頭に世界の多くの地域で不平等を引き起こした力について書かれたものは少なく、さらに遠い過去の物質的資源の分配について書かれたものははるかに少ない。確かに、今日の世界における所得格差の拡大に対する懸念は、現代の気候変動が適切な歴史的データの分析を促したように、より長期的な視点での不平等の研究に勢いを与えている。しかし、全体像を正しく把握すること、つまり、観測可能な歴史を幅広く網羅するような世界的な調査は、まだ不十分である。所得と富の分配を形成してきたメカニズムを理解するためには、異文化間、比較、長期的な視点が不可欠である。
四騎士
物質的不平等には、私たち全員が生きていくために必要な最低限の資源以上の資源へのアクセスが必要である。余剰資源は何万年も前にすでに存在しており、それを不均等に共有する用意のある人類も存在していた。最後の氷河期には、狩猟採集民はある個人を他の個人よりもはるかに豪華に埋葬する時間と手段を見つけた。しかし、まったく新しい規模の富を生み出したのは、食料生産である農耕と牧畜だった。不平等が拡大し、持続することが完新世の特徴となった。動植物の家畜化によって、生産資源の蓄積と保存が可能になった。社会規範は、これらの資産に対する権利を定義するために発展した。このような状況下で、所得と富の分配はさまざまな経験によって形成されるようになった。健康、結婚戦略、生殖の成功、消費と投資の選択、豊作、イナゴやリンデルペストの疫病などが、世代間の運命を決定づけた。運と努力が長期的に不平等な結果をもたらしたのである。
原理的には、いくつかの前近代社会が実際にそうであったと言われているように、物質的資源と労働から得られる果実の分配のバランスを調整するための介入によって、制度は生まれつつある格差を平らにすることができた。しかし実際には、社会進化は逆効果となることが多かった。食料源の家畜化は人間を家畜化した。高度に競争的な組織形態としての国家の形成は、権力と強制力の峻厳な階層を確立し、所得と富へのアクセスを偏らせた。政治的不平等は経済的不平等を強化し、増幅させた。農耕時代のほとんどの期間、国家は多くの人々を犠牲にして少数の人々を富ませた。公務に対する給与や恩典から得られる利益は、汚職、恐喝、略奪から得られる利益に比べれば微々たるものであることが多かった。その結果、多くの前近代社会は、一人当たりの生産高が低く、成長もごくわずかという条件のもとで、小エリートによる剰余金充当の限界を探りながら、可能な限り不平等な社会へと成長した。そして、より穏やかな制度がより活発な経済発展を促したとき、とりわけ新興西欧では、高い不平等が維持され続けた。都市化、商業化、金融部門の革新、ますますグローバル化する貿易、そして最後に工業化は、資本の所有者に豊かなリターンをもたらした。権力の裸の行使によるレントが減少し、伝統的なエリートの富の源泉が閉ざされると、より安全な財産権と国家公約が、世襲的な私的富の保護を強化した。経済構造、社会規範、政治制度が変化しても、所得と富の不平等は高止まりし、あるいは新たな拡大方法を見出した。
何千年もの間、文明は平和的平等化には向いていなかった。さまざまな社会、さまざまな発展レベルにおいて、安定は経済的不平等を助長した。これは、ファラオ時代のエジプトにも、ヴィクトリア朝時代のイギリスにも、ローマ帝国にも、アメリカにも当てはまることである。暴力的なショックは、既成の秩序を破壊し、所得と富の分配を圧縮し、貧富の差を縮める上で最も重要であった。記録された歴史を通じて、最も強力な平準化は常に最も強力な衝撃によってもたらされた。大衆動員戦争、変革革命、国家破綻、致死的パンデミックである。私はこれらを「平準化の四騎士」と呼んでいる。聖書に登場する彼らのように、彼らは「地から平和を奪い」、「剣と飢えと死と地の獣で殺す」ために現れた。時には個々に、時には互いに協力して行動し、同時代の人々には黙示録的としか思えないような結果をもたらした。その結果、何億人もの人々が命を落とした。そして塵も積もれば山となるで、持てる者と持たざる者の格差は、時には劇的に縮小した6。
特定の種類の暴力だけが、一貫して不平等を押し下げた。征服と略奪で栄えた古風な紛争形態は、勝利したエリートを富ませ、敗れた側の人々を困窮させる可能性が高かったが、それほど明確でない結末では、予測可能な結果をもたらすことはできなかった。戦争が所得と富の格差を是正するためには、社会全体に浸透し、近代的な国民国家でしか実現できないような規模で人と資源を動員する必要があった。このことが、2つの世界大戦が歴史上最も大きな平準化要因のひとつとなった理由を説明している。産業規模の戦争がもたらした物理的破壊、没収的課税、政府による経済介入、インフレ、モノと資本のグローバルな流れの混乱、その他の要因がすべて組み合わさって、エリートの富を一掃し、資源を再分配した。それらはまた、平等な政策への転換を促す、他に類を見ない強力な触媒としての役割も果たし、フランチャイズの拡大、労働組合化、福祉国家の拡大に強力な推進力を与えた。世界大戦の衝撃は、先進国全体の所得と富の不平等を大幅に縮小させ、「大圧縮」として知られる事態を引き起こした。1914年から1945年までの期間に集中的に起こったが、一般に、その経過をたどるにはさらに数十年を要した。それ以前の大量動員戦争には、同様の波及効果はなかった。ナポレオン時代の戦争やアメリカの南北戦争は、さまざまな分配的結果をもたらしたが、時代を遡れば遡るほど、適切な証拠は少なくなる。アテネやスパルタに代表される古代ギリシアの都市国家文化は、まちまちの成功ではあったが、民衆の激しい軍事動員や平等主義的制度が物質的不平等の抑制に役立ったという最も古い事例を、間違いなく我々に提供している。
第二次世界大戦は、変革的革命という第二の大きな平準化力を生み出した。農民一揆や都市蜂起は前近代の歴史によく見られたが、たいていは失敗に終わり、発展途上国における内戦は、所得分配の不平等を縮小させるどころか、むしろ拡大させる傾向にある。物質的資源へのアクセスを再構築するためには、暴力的な社会再編は特別に激しいものである必要がある。大衆動員戦の平等化と同様、これは主に20世紀の現象である。収奪し、再分配し、そしてしばしば集団化した共産主義者たちは、不平等を劇的な規模で平準化した。これらの革命の中で最も変革的なものは、異常な暴力を伴い、最終的には、死者数と人間の悲惨さの点で世界大戦に匹敵した。フランス革命のような血なまぐさい革命は、それに比例して小規模であった。
暴力は国家を完全に破壊するかもしれない。国家の破綻やシステムの崩壊は、かつては特に信頼できる平準化の手段であった。歴史の大半において、富裕層は政治権力ヒエラルキーの頂点かその近くに位置していたか、そうした人々とつながっていた。さらに国家は、自給自足レベルを超える経済活動に対して、現代の基準からすればささやかではあるが、一定の保護を与えていた。国家が崩壊すると、こうした地位や人脈、保護が圧迫を受けたり、完全に失われたりする。国家が崩壊すれば誰もが苦しむかもしれないが、富裕層が失うものの方がはるかに大きい。エリートの所得や富が減少または崩壊することで、資源の全体的な分配が圧縮されるのだ。このようなことは、国家が存在する限りずっと続いてきた。最も古い例では、古王国時代のエジプトやメソポタミアのアッカド帝国の終焉まで4,000年さかのぼる。今日でも、ソマリアの経験は、かつて強力だったこの平等化の力が完全には消滅していないことを示唆している。
国家の破綻は、暴力的手段による平準化の原則を論理的に極端なものにする。既存の政治を改革・再編することによって再分配と再均衡を達成する代わりに、より包括的な方法で白紙に戻すのである。最大の革命が最大の戦争によって引き起こされたように、国家崩壊は通常、同じような強力な圧力を必要としない。それらに共通しているのは、政治的・社会的秩序とともに、所得と富の分配を作り直すために暴力に頼っているということである。
人為的な暴力には長い間競争があった。かつて、ペスト、天然痘、はしかは、最大規模の軍隊や最も熱狂的な革命家でさえ望めなかったほど強力に、大陸全体を荒廃させた。農耕社会では、微生物によって人口のかなりの割合、時には3分の1、あるいはそれ以上の割合が失われたことで、労働力が不足し、一般的に無傷のままであった固定資産やその他の非人間的資本の価格と比較して、労働力の価格が上昇した。その結果、実質賃金が上昇し、家賃が下落したため、労働者は得をし、地主や雇用主は損をした。エリートは一般に、不作為と力によって既存の仕組みを維持しようと試みたが、平等化する市場の力を抑えることはできなかった。
パンデミックは、暴力的な平準化の四頭立てを完成させた。しかし、不平等を是正する、より平和的なメカニズムは他にもあったのだろうか。大規模な平準化について考えるなら、答えはノーに違いない。歴史を俯瞰してみると、私たちが記録で見ることのできる物質的不平等の主な縮小はすべて、これら4つの平準化要因のうちの1つ以上によってもたらされたものである。さらに、大規模な戦争や革命は、これらの出来事に直接関与した社会だけに作用したわけではない。世界大戦や共産主義の挑戦者への暴露は、傍観者の経済状況、社会的期待、政策立案にも影響を与えた。こうした波及効果は、暴力的紛争に根ざした平準化の影響をさらに拡大させた。このため、世界の多くの地域で1945年以降に起こった動きを、それ以前のショックやその継続的な余波から切り離すことは困難である。2000年代初頭のラテンアメリカにおける所得格差の縮小は、非暴力的平等化の最も有望な候補かもしれないが、この傾向は比較的緩やかな範囲にとどまっており、その持続可能性は不確かである。
その他の要因については、さまざまな記録がある。古代から現在に至るまで、土地改革は暴力や暴力の脅威と結びついた場合に最も不平等を是正し、そうでない場合には最も不平等を是正しない傾向にある。マクロ経済危機は、所得と富の分配に短期間しか影響を及ぼさない。民主主義はそれ自体で不平等を緩和するわけではない。教育と技術革新の相互作用が所得の分散に影響することは間違いないが、教育と技能のリターンは暴力的なショックに非常に敏感であることが歴史的に証明されている。最後に、近代的な経済発展が不平等を縮小させるという見方を支持する説得力のある経験的証拠はない。四騎士が生み出す結果に少しでも匹敵するような、穏健な圧縮手段のレパートリーは存在しない。
それでもショックは和らぐ。国家が破綻しても、遅かれ早かれ他の国家がその代わりを務める。疫病が治まった後、人口減少が逆転し、人口が再び増加したことで、労働と資本のバランスは徐々に以前の水準に戻った。最高税率や労働組合の密度は低下し、グローバリゼーションは進み、共産主義は消滅し、冷戦は終わり、第3次世界大戦のリスクは後退した。これらのことが、最近の不平等の復活を理解しやすくしている。伝統的な暴力的平準化装置は現在休眠状態にあり、当面復活する見込みはない。同様に強力な平等化の代替メカニズムも出現していない。
最も進歩的な先進国でさえ、再分配と教育は、税や移転の前に、所得格差拡大の圧力を吸収しきれないでいる。発展途上国では、より低いところにある果実が手招きしているが、財政的制約は依然として強い。平等を大幅に拡大するための投票、規制、教育を行う簡単な方法はなさそうだ。世界史的に見れば、これは驚くべきことではない。われわれが知る限り、大きな暴力的ショックとその広範な影響から解放された環境では、不平等が大きく縮小したことはほとんどなかった。未来は違うのだろうか?
本書で扱わないこと
ジェンダーや性的指向、人種や民族性、年齢、能力、信条に根ざした不平等もそうであるし、教育、健康、政治的発言力、人生のチャンスにおける不平等もそうである。そのため、本書のタイトルは正確さを欠いている。また、「暴力的なショックと石器時代から現在、そしてそれ以降の所得と富の不平等の世界史」といった副題を付ければ、出版社の忍耐を引き延ばすだけでなく、不必要に排他的なものになっただろう。結局のところ、力の不平等は物質的資源へのアクセスを決定する上で常に中心的な役割を果たしてきた。
私は、経済的不平等のすべての側面を網羅しようとは思わない。重要で多くの議論がある国家間の経済的不平等の問題はさておき、私は社会内の物質的資源の分配に焦点を当てる。私は、先に述べた不平等の他の多くの原因、すなわち所得と富の分配に影響を及ぼす要因に明確に言及することなく、特定の社会内の状況を考察する。私は主に、なぜ不平等が縮小したのかという疑問に答えること、つまり平準化のメカニズムを明らかにすることに関心がある。非常に大雑把に言えば、私たちの種が家畜化された食糧生産と、それに付随する定住主義と国家形成を受け入れ、ある種の遺伝的財産権を認めた後、物質的不平等に対する上昇圧力は事実上当然のものとなった。このような圧力が何世紀、何千年という時間をかけてどのように発展してきたか、特に、強制と市場原理とに大雑把に分類されるものの間の複雑な相乗効果について、より細かい点を考察するには、さらに長い別の研究が必要であろう7。
最後に、私は暴力的なショック(代替的なメカニズムとともに)と、それが物質的不平等に及ぼす影響について論じているが、その逆の関係、つまり、不平等が暴力的なショックを生み出すのに役立ったのか、役立ったとしてどのように役立ったのかという問題については、一般的に探求していない。私が消極的な理由はいくつかある。高水準の不平等が歴史社会の一般的な特徴であったため、その文脈的条件を参照して特定のショックを説明することは容易ではない。物質的不平等が同程度の同時代社会の中でも、内的安定性は大きく異なっていた。革命前の中国がその一例である。資本と労働のバランスを変化させることで不平等を平準化したパンデミックはその代表例である。世界大戦のような人為的な出来事も、紛争に直接関与していない社会に大きな影響を与えた。内戦の勃発における所得格差の役割に関する研究は、この関係の複雑さを浮き彫りにしている。いずれも、国内資源の不平等が戦争や革命の勃発、あるいは国家の破綻に寄与する可能性がないことを示唆するものではない。それは単に、全体的な所得や富の不平等と暴力的ショックの発生との間に系統的な因果関係があると仮定する説得力のある理由が今のところないということを意味している。最近の研究が示しているように、エリート集団内の競争など、分配的な側面を持つより具体的な特徴を分析することが、暴力的な紛争や崩壊を説明する上でより有望である可能性がある。
本研究では、暴力的ショックを物質的不平等に作用する個別の現象として扱う。このアプローチは、このような出来事と事前の不平等との間に意味のある関係を立証するのに十分な証拠があるかどうかを問わず、超長期的に平準化の力としてのこのようなショックの重要性を評価するために考案されたものである。ショックから不平等へという一つの因果の矢印に私が独占的に焦点を当てることで、その逆へのさらなる関与が促されるのであれば、それに越したことはない。所得と富の分配における観察可能な経時的変化を完全に内生化した、もっともらしい説明を作成することは、決して実現可能ではないかもしれない。それでも、不平等と暴力的ショックの間に起こりうるフィードバック・ループは、より深く探求する価値があることは確かである。私の研究は、この大きなプロジェクトのための積み木にすぎない8。
不平等の測定方法は?
不平等を測定する方法は数多くある。以下の章では、一般的に最も基本的な2つの指標、ジニ係数と総所得または総資産に占める割合のみを使用する。ジニ係数は、所得や物質的資産の分配が、完全な平等からどの程度乖離しているかを測るものである。ある集団の各メンバーがまったく同量の資源を受け取ったり、保有したりする場合、ジニ係数は0である。あるメンバーがすべてを支配し、他の全員が何も持たない場合、ジニ係数は1に近似する。したがって、分配が不平等であればあるほど、ジニ係数は高くなる。一般的にパーセンテージで示される所得や富の分配とより明確に区別するために、私は前者を好む。シェアは、ある集団における所得や富の総量のうち、全体的な分布の中での位置によって定義される特定の集団が受け取ったり所有したりするものの割合を示す。例えば、よく言われる「1%」は、ある集団の99%よりも高い所得を享受したり、大きな資産を所有している集団(多くの場合、世帯)を表している。ジニ係数と所得シェアは、ある分布の異なる特性を強調する補完的な指標である。前者が不平等の全体的な程度を計算するのに対し、後者は分布の形状について必要な洞察を提供する。
前者が全体的な不平等の度合いを計算するのに対して、後者は分布の形状について大いに必要な洞察を提供する。どちらの指標も、所得分布の異なるバージョンの分布を測定するために使用することができる。税金と公的給付を受ける前の所得は「市場」所得、給付後の所得は「総」所得、税金と給付を差し引いた所得は「可処分」所得と呼ばれる。以下では、市場所得と可処分所得にのみ言及する。所得の不平等という言葉をそのまま使う場合は、前者を意味する。記録された歴史の大半において、市場所得の不平等が、知ることも推定することもできる唯一のタイプである。さらに、近代西欧で大規模な財政再分配制度が創設される以前は、市場所得、総所得、可処分所得の分配における格差は、今日の多くの発展途上国と同様、一般的に非常に小さかった。本書では、所得分配は常に市場所得の分配に基づいている。所得分配率、特に分配の最上位に位置する所得分配率に関する現代および過去のデータは、通常、財政介入前の所得を参照する納税記録から得られたものである。また、所得分配のシェアや特定のパーセンタイル間の比率に言及することもあるが、これは異なる階層の相対的な重みを示す代替指標である。より洗練された不平等の指標は存在するが、非常に多様なデータセットにまたがる長期的な研究には通常適用できない9。
物質的不平等の測定には、概念的な問題と実証的な問題の2種類がある。ここで注目すべきは、概念的な問題である。第一に、利用可能なほとんどの指標は、人口の特定の層が獲得している総資源の割合に基づいて相対的不平等を測定し、表現している。これとは対照的に、絶対的不平等は、これらの層にもたらされる資源の量の差に焦点を当てる。この2つのアプローチは、まったく異なる結果をもたらす傾向がある。例えば、所得分布の上位10%の平均世帯が、下位10%の平均世帯の10倍の所得を得ている人口を考えてみよう。その後、国民所得は倍増するが、所得分配は変わらない。ジニ係数と所得分配率は以前と変わらない。この観点からは、不平等を拡大することなく所得が増加したことになる。しかし同時に、上位10階層と下位10階層の所得格差は9万ドルから18万ドルへと倍増し、低所得世帯よりも富裕世帯の方がはるかに大きな利益を確保している。同じ原理が富の分配にも当てはまる。実際、経済成長によって絶対的不平等が拡大しないような信頼できるシナリオはほとんど存在しない。したがって、相対的不平等の指標は、持続的に拡大する所得格差や富の格差から注意をそらし、物質的資源の分配におけるより小さく多方向的な変化を優先させる役割を果たすため、より保守的な見通しと言える。本書では、慣例に従い、ジニ係数や上位所得シェアといった相対的不平等の標準的な尺度を優先するが、適切な場合にはその限界に注意を喚起する10。
別の問題は、所得分配のジニ係数が自給自足の要件や経済発展の水準に敏感であることに起因する。少なくとも理論的には、ある集団に存在するすべての富を一人の人間が所有することは完全に可能である。しかし、完全に所得を奪われた人は生き残れないだろう。つまり、所得に関する実現可能なジニ値の最高値は、名目上の上限である「~1」を下回るに違いないのである。より具体的には、最低限の生計要件を満たすのに必要な資源量を超える資源量によって制限される。この制約は、人類史の大半で典型的であり、今日でも世界の一部に存在する低所得経済において特に強力である。例えば、最低生計費の2倍に相当するGDPを持つ社会では、たとえ一個人が何とかして、他の誰もが最低限の生存に必要とする以上の所得をすべて独占したとしても、ジニ係数は0.5以上に上昇することはない。生産高が高水準になると、最低限度の生活を構成するものの定義が変化し、また、主として貧困にあえぐ人口が高度経済を維持できなくなることによって、不平等の最大程度はさらに抑制される。名目上のジニ係数は、抽出率と呼ばれるもの、つまり、ある環境において理論上可能な最大限の不平等がどの程度実現されているかを計算するために、適宜調整される必要がある。これは複雑な問題であり、超長期的な不平等の比較には特に重要であるが、ごく最近になって注目され始めた問題である。本書末尾の付録で、より詳しく取り上げている11。
これが2つ目のカテゴリー、すなわち証拠の質に関する問題である。ジニ係数と上位所得シェアは、不平等を測る尺度としてはおおむね一致している。どちらも基礎となるデータソースの欠点に敏感である。現代のジニ係数は通常、家計調査から導き出され、そこから推定される国民分布が外挿される。この形式は、非常に大きな所得を把握するには特に適していない。欧米諸国においてさえ、名目ジニ係数は上位所得の実際の寄与を十分に考慮するために上方修正される必要がある。さらに、多くの発展途上国では、調査の質が十分でなく、信頼できる全国推計を行うことができない。このような場合、信頼区間が広いと、各国間の比較が妨げられるだけでなく、経年変化を追跡することも難しくなる。エリートの資産のかなりの割合がオフショアに隠されていると考えられる発展途上国だけでなく、米国のようにデータが豊富な環境でさえ、富の全体的な分布を測定しようとする試みは、さらに大きな課題に直面している。所得分配は通常、納税記録から計算されるが、その質や特徴は国や時代によって大きく異なり、脱税を動機とする歪みの影響を受けやすい。低所得国では所得分配率が低く、課税所得の定義が政治的に決められているため、さらに複雑である。このような困難があるにもかかわらず、「世界富と所得データベース」(World Wealth and Income Database)において、最高所得分配率に関する情報が蓄積され、オンラインで公開されるようになったことで、所得不平等に対する理解がより確かなものとなり、ジニ係数のようなやや不透明な単一価値指標から、より明確な資源集中度指標へと関心が向けられている12。
こうした問題はすべて、所得と富の不平等の研究をさらに過去にさかのぼらせようとしたときに遭遇する問題に比べれば、淡いものである。通常の所得税は20世紀以前にはほとんど存在しない。家計調査がないため、ジニ係数を計算するには代理データに頼らざるを得ない。1800年頃以前の社会全体の所得格差は、社会表、つまり、同時代の観察者によって作成された、あるいは後世の学者によって、わずかではあるが推測された、人口のさまざまな部分によって得られた所得の大まかな近似値の助けを借りてのみ推定することができる。ヨーロッパの一部では、中世まで遡ることができるデータセットが増えつつあり、個々の都市や地域の状況を明らかにすることができるようになった。フランスやイタリアの都市における富裕税、オランダの住宅賃貸税、ポルトガルの所得税など、現存する古文書記録から、資産や、時には所得の根本的な分布を復元することができる。フランスにおける農地の分散に関する近世の記録や、イングランドにおける遺言検認による遺産の価値に関する記録もそうである。実際、ジニ係数は、時代的にはるかに離れた証拠にも有益に適用することができる。古代ローマ時代後期エジプトにおける土地所有のパターン、古代・中世初期のギリシャ、イギリス、イタリア、北アフリカ、アステカ・メヒコにおける家の大きさのばらつき、バビロニア社会における相続分と持参金の分配、さらには、約1万年前に形成された世界最古の原始都市集落のひとつであるカタロホユックにおける石器の分散も、すべてこの方法で分析されている。考古学は、最終氷河期の旧石器時代へと、物質的不平等研究の境界を押し戻すことを可能にした13。
私たちはまた、分配を直接記録するものではないが、所得不平等のレベルの変化に敏感であることが知られている、あらゆる種類の代理データを利用することができる。賃金に対する地代の比率はその好例である。主に農耕社会では、最も重要な資本の価値に対する労働の価格の変化は、異なる階級にもたらされた相対的利益の変化を反映する傾向がある。指数値が上昇することは、地主が労働者を犠牲にして繁栄し、不平等が拡大することを示唆する。同じことが、関連指標である平均一人当たりGDPと賃金の比率にも当てはまる。GDPに占める非労働者の割合が大きいほど指数は高くなり、所得はより不平等になる可能性が高い。確かに、どちらの方法にも重大な弱点がある。家賃や賃金は、特定の地域については確実に報告されるかもしれないが、より大きな人口や国全体を代表するものである必要はない。とはいえ、このような指標は、一般に、時系列的な不平等の傾向の輪郭を知ることができる。実質所得は、より広く利用可能ではあるが、やや有益性に欠ける代用指標である。ユーラシア西部では、穀物換算による実質賃金が4,000年前までさかのぼることができる。この非常に長期的な視点は、労働者の実質所得が異常に上昇した事例を特定することを可能にし、この現象は不平等の低下ともっともらしく関連している。とはいえ、資本価値やGDPに照らして文脈づけられない実質賃金に関する情報は、依然として全体的な所得不平等の指標としては非常に粗雑であり、特に信頼できるものではない14。
近年、前近代の課税記録の研究や、実質賃金、賃借料/賃金比率、さらにはGDP水準の復元がかなり進んでいる。本書の多くは、20年前、あるいは10年前には書けなかったと言っても過言ではない。歴史的な所得と富の不平等に関する研究の規模、範囲、進歩のスピードは、この分野の将来に大きな希望を与えてくれる。人類史の長い期間において、物質的資源の分配に関する最も初歩的な定量的分析さえ認められていないことは否定できない。しかし、そのような場合であっても、経年変化のシグナルを特定できるかもしれない。エリート層の富の誇示は、不平等を示す最も有力な、そして実際、しばしば唯一の指標である。住居、食事、埋葬などにおけるエリート層の贅沢な消費を示す考古学的証拠が、より控えめなものへと変化したり、階層化の兆候が完全に薄れたりした場合、ある程度の平等化が進んだと推測するのが妥当だろう。伝統的な社会では、富や権力を持つエリート層は、大きな損失を被るほどの収入や資産を支配する唯一の存在であることが多かった。人間の身長やその他の生理学的特徴のばらつきも、同様に資源の分配と関連づけることができるが、病原体の負荷など他の要因も重要な役割を果たしている。不平等をより直接的な形で記録したデータから離れれば離れるほど、私たちの読みはより推測的なものにならざるを得ない。とはいえ、グローバルな歴史は、背伸びをする覚悟がない限り、単純に不可能である。本書はまさにその試みである。
近年のアメリカの所得格差拡大の要因に関する詳細な統計から、文明黎明期における資源の不均衡に関する漠然としたヒントまで、その間にある多種多様なデータセットも含めてである。これらすべてを合理的に首尾一貫した分析物語にまとめることは、私たちに手ごわい課題を突きつけている。少なからず、これこそがこの序論のタイトルにある不平等の真の課題なのである。私は、この問題に取り組むための最善の方法と思われる方法で、本書の各部を構成することにした。冒頭のパートは、霊長類の始まりから20世紀初頭までの不平等の進化を追っており、そのため従来の年代順に構成されている(第1章から第3章)。
しかし、暴力的な平準化の主要因である「四騎士」に目を向けると、この構成は一変する。この四騎士の最初の2人、戦争と革命に割かれたパートでは、私の調査は20世紀から始まり、その後、時間をさかのぼっていく。これには単純な理由がある。大量動員戦争と変革革命による平準化は、主として近代の特徴であった。1910年代から1940年代にかけての「大圧縮」は、このプロセスの最も優れた証拠を生み出しただけでなく、パラダイム的な形でそれを象徴し、実際に構成している(第4章から第5章)。第二段階では、アメリカ南北戦争から古代中国、ローマ、ギリシャの経験、そしてフランス革命から前近代における無数の反乱へと遡りながら、こうした暴力的な断絶の前兆を探す(第6章と第8章)。第6章の最後の部分で内戦について論じる際も、現代の発展途上国における内戦の結果からローマ共和国の終焉まで、同じ軌跡をたどる。このようなアプローチによって、現代のデータにしっかりと根ざした暴力的平準化のモデルを確立してから、より遠い過去にも適用できるかどうかを探っている。
第5部の疫病に関しては、同じ戦略の修正版を採用し、最もよく記録されている事例である中世後期の黒死病(第10章)から、あまりよく知られていない事例へと徐々に移行していく。その理由は同じである。他の場所で類似の事例を探す前に、入手可能な最善の証拠を用いて、疫病による大量死がもたらす暴力的平準化の主要なメカニズムを明らかにするためである。国家破綻とシステム崩壊に関する第4部では、この組織原則を論理的に結論づける。前近代史に限定された現象を分析する上で、年代はほとんど重要ではない。特定の事例の年代は、証拠の性質や現代の学問の範囲よりも重要ではない。そのため私は、あまり詳しく論じない他の事例(第9章)に移る前に、よく証明されているいくつかの事例から始めることにする。第6部は、暴力的な平準化の代替案に関するもので、反実仮想的な結果(第14章)の前に、さまざまな要因(第12章から第13章)を評価するため、ほとんどの部分がトピック別に構成されている。最終章は、第1部とともにテーマ別の調査を構成するもので、時系列形式に戻る。最近の不平等の再燃(第15章)から、近い将来およびより遠い将来における平準化の見通し(第16章)へと進み、私の進化論的概観を完成させる。
東条英機の日本とペリクレスのアテネ、あるいは古典低地マヤと現代のソマリアを結びつける研究は、私の仲間の歴史学者にとっては不可解に映るかもしれない。先に述べたように、不平等の世界史を探求するという課題は深刻なものである。記録された歴史全体にわたって平準化の力を特定したいのであれば、学問分野内外の異なる専門領域間の溝を埋める方法を見つけ、データの質と量における大きな格差を克服する必要がある。長期的な視点に立てば、常識にとらわれない解決策が求められる。
それは重要なことなのだろうか?
これらすべてが、素朴な疑問を提起している。まったく異なる文化圏にまたがる不平等のダイナミクスを、非常に長期的に研究することがこれほど難しいのであれば、なぜ私たちは研究しようとする必要があるのだろうか。この問いに答えるには、経済的不平等は今日重要なのか、そしてなぜその歴史を探る価値があるのか、という2つの別個だが関連する問題に取り組む必要がある。プリンストン大学の哲学者ハリー・フランクフルトは、『デタラメについて』の著書で知られるが、その小冊子『不平等について』の冒頭で、冒頭で引用したオバマの評価に反対している: 「われわれの最も根本的な課題は、アメリカ人の所得が大きく不平等であるという事実ではない。むしろ、あまりにも多くの国民が貧しいという事実である」米国で貧困とみなされる人が、アフリカ中部でそうであるとは限らない。時には、貧困は不平等の関数として定義されることさえある。イギリスでは、公式の貧困ラインは所得の中央値の何分の一かとして設定されているが、世界銀行が使用する2005年の価格で1.25ドルという基準値や、アメリカの消費財バスケットの価格を参照するなど、絶対的な基準がより一般的である。貧困の定義がどのようなものであれ、貧困が望ましくないものであることに異論を挟む人はいないだろう。課題は、貧困や巨万の富が関係しているのではなく、所得や富の不平等が私たちの生活に悪影響を及ぼすことを実証することにある15。
最も厳しいアプローチは、不平等が経済成長に与える影響に焦点を当てるものである。経済学者たちは、この関係を評価することは困難であり、この問題の理論的複雑さと既存研究の実証的仕様が必ずしも一致していないことを繰り返し指摘してきた。それでも、多くの研究が、より高いレベルの不平等が、より低い成長率と実際に関連していることを論じている。例えば、可処分所得の不平等が低いほど、成長速度が速いだけでなく、成長フェーズも長くなることが分かっている。不平等は先進国経済において特に成長に悪影響を及ぼすようだ。2008年の大不況の引き金となった信用バブルは、アメリカの家計における不平等の高さが一因となったという議論もある。これとは対照的に、より制限的な貸出条件の下では、富の不平等は、低所得層の信用へのアクセスを阻害し、不利になると考えられている16。
先進国では、格差の拡大は世代間の経済的流動性の低下と関連している。親の所得や富は、収入だけでなく教育達成度の強力な指標となるため、不平等は時間の経過とともに永続化する傾向があり、それが高ければ高いほど、なおさらである。所得による居住分離がもたらす不平等化も、関連する問題である。1970年代以降、米国の大都市圏では、高所得地域と低所得地域の人口が増加し、中所得地域が縮小しているため、二極化が進んでいる。特に裕福な地域は孤立化が進み、地域が資金源となる公共サービスなどの資源が集中し、その結果、子どもたちのライフチャンスに影響を与え、世代間移動が阻害されている17。
開発途上国では、少なくともある種の所得格差が、国内紛争や内戦の可能性を高めている。高所得社会は、それほど極端な結果とはなっていない。米国では、不平等は富裕層が影響力を行使しやすくすることで、政治プロセスに影響を及ぼすと言われているが、この場合、この現象を説明するのは不平等そのものではなく、非常に大きな財産の存在なのではないかと考えるかもしれない。不平等が大きいと、自己申告幸福度が低いという相関関係があることを発見した研究もある。健康だけが、所得水準とは対照的に、資源の分配に影響されないようである。健康の差が所得の不平等を生むのに対して、その逆は証明されていない18。
これらの研究に共通しているのは、物質的不平等がもたらす現実的な結果、つまり、不平等が問題であると考えられる道具的な理由に焦点を当てていることである。偏った資源配分に対する別の反論は、規範的倫理や社会正義の概念に基づくものであり、私の研究の範囲を超えているが、経済的な懸念に支配されがちな議論において、もっと注目されるべき視点である。しかし、純粋に道具的な推論という限定的な根拠に基づいても、少なくとも特定の文脈においては、高水準の不平等や所得・富の格差の拡大が社会的・経済的発展に有害であることに疑いの余地はない。しかし、何をもって「高い」水準とするのか、また、「拡大する」不均衡が現代社会の目新しい特徴なのか、それとも単に歴史的に一般的な状況に近づいただけなのか、どうすればわかるのだろうか。フランソワ・ブルギニョンの言葉を借りれば、拡大する不平等を経験している国々が復帰を目指すべき「正常な」不平等水準は存在するのだろうか。また、多くの先進国経済と同様に、不平等が数十年前よりは高くなったが、100年前よりは低くなっているとすれば、このことは、所得と富の分配の決定要因に関する私たちの理解にとって何を意味するのだろうか19。
記録された歴史の大半において、不平等は拡大するか、あるいはほぼ横ばいで推移してきた。しかし、不平等の高まりを食い止めたり、逆転させたりするための政策提案は、このような歴史的背景をほとんど意識せず、評価もしない傾向がある。それでいいのだろうか。おそらく私たちの時代は、農耕民族的で非民主的な基盤から完全に解き放たれ、根本的に異なるものとなってしまったため、歴史が私たちに教えてくれることは何も残っていないのだろう。豊かな経済圏に住む低所得者層は、一般的にかつての大半の人々よりも裕福であり、後発開発途上国の最も恵まれない住民でさえ、先祖よりも長生きしている。不平等の受け手である人々の生活体験は、多くの点で以前とは大きく異なっている。
むしろ、文明の果実がどのように分配されるのか、何がそのように分配される原因なのか、そしてこのような結果を変えるためには何が必要なのか、である。私はこの本を、かつて不平等を形成していた力が、実際には認識できないほど変化していないことを示すために書いた。現在の所得と富の分配のバランスを、より平等なものに変えようとするのであれば、過去にこの目標を達成するために何が必要であったかに目をつぶるわけにはいかない。私たちは、大きな暴力なしに大きな不平等が緩和されたことがあるのか、より穏やかな影響がこのグレート・レベラーの力と比べてどうなのか、そして未来は大きく変わる可能性があるのかを問う必要がある。
第5部 悪
第10章 黒死病
第四の騎手:微生物、マルサス、市場
大衆に有利な交渉を促し、富裕層を浸食した大衆動員戦争、「地主」、「クラーク」、「ブルジョアジー」を本物の「1ペリカ」とともに滅ぼした血で血を洗う革命、利用可能な余剰をできる限り引き出して溜め込んでいた富裕なエリートを一掃した国家全体の崩壊などである。我々は今、さらにもう1つの平準化要因である第4の騎手、伝染病について考えなければならない。伝染病は他の3つの種とは異なり、他の種を巻き込むが、暴力的なものではないという点で、他の3つの種とは異なる。しかし、細菌やウイルスによる人間社会への攻撃は、人間が引き起こしたほとんどすべての災害よりもはるかに致命的であった。
伝染病はどのようにして不平等を減らすのだろうか?それは、トーマス・マルサス牧師が1798年に発表した『人口原理に関する試論』の中で、「正の抑制」と呼んだ働きをすることによって実現する。マルサス流の考え方は、長期的には人口が資源よりも急速に増加する傾向にあるという前提に根ざしている。このことが、さらなる人口増加を抑制する引き金となる: 「道徳的抑制」、つまり結婚や生殖を遅らせることによって出生率を低下させる「予防的抑制」と、死亡率を上昇させる「積極的抑制」である。マルサス自身の言葉を借りれば、後者は次のようなものである、
不健全な職業、過酷な労働、季節にさらされること、極度の貧困、子どもの悪い養育、大きな町、あらゆる種類の過剰、一般的な病気や伝染病の全行程、戦争、疫病、ペスト、飢饉などである1。
このような包括的な言い方をすると、この「正のチェック」の目録は、人口圧力の直接的な結果と、疫病のような人口動態によって引き起こされたり、悪化させられたりする必要はないが、本質的に外生的である可能性のある事象とを混同していることになる。現代の研究では、生産性を向上させ、それによってマルサスの危機を回避する人口増加と資源ストレスへの対応の重要性が強調されている。このため、最も洗練された新マルサス的モデルは、希少性の圧力と技術的または制度的進歩との間のトレードオフを通じて、人口と生産が発展するというラチェット効果を想定している。さらに、過去150年間の人口動態の変遷は、実質所得の上昇に伴う出生率の低下と技術革新の暴走の組み合わせによって、マルサス的制約を緩和したと考えられている。このような理由から、マルサス的メカニズムは、本章の主題でもある前近代社会を理解する上で重要な意味を持つ。中世後期から近世初期にかけてのイングランドにおいて、疫病という形で致死的な疾病が深刻に顕在化したことは、その結果を増幅させるような資源ストレスの時期と重なっていたとしても、必ずしもそれだけに限定されるものではないが、少なくとも一義的には、一般的な生活条件にかかわらず人口増加を抑制する外因的なインプットであったことを強く示唆している2。
前近代の農耕社会では、疫病は土地と労働力の比率を変化させることで平準化し、前者の価値を(土地価格や地代、農産物の価格によって)下げ、後者の価値を(実質賃金の上昇や借地料の低下という形で)上げた。この結果、土地所有者と雇用者は以前より裕福でなくなり、労働者は以前より裕福になり、所得と富の不平等が縮小した。同時に、人口動態の変化は制度と相互作用して、物価と所得の実際の変動を決定した。土地と特に労働力の価格設定市場の存在は、平準化を成功させるための基本的な前提条件であった。不平等を縮小するためには、微生物と市場が連動して機能しなければならなかった。最後に、後述するように、平準化は長続きしない傾向があり、稀な状況を除いて、人口動態の回復によって再び人口圧力が高まり、最終的には元に戻された。
「すべての人が世界の終わりを信じた」: 中世後期のパンデミック
1320年代後半のある時期、ゴビ砂漠でペストが発生し、旧世界の大部分に広がり始めた。ペストは、ノミの消化管に生息するエルシニア・ペスティスという細菌によって引き起こされる。ネズミノミが最もポピュラーな宿主だが、ペストに感染したノミを媒介するげっ歯類は数十種知られている。これらのノミは一般的にげっ歯類にまとわりつくことを好み、もともとの宿主の個体数が枯渇したときにのみ新たな犠牲者を探し出す。ペストには3つの種類があり、その中で最も一般的なのはブボニック・ペストである。ペストは、ノミに咬まれるとよく見られる鼠径部、脇の下、頸部のリンパ節の腫大が目立つことで最もよく知られているが、皮下出血によって生じる血の混じった泡からその名が付けられた。細胞の壊死と神経系の中毒が起こり、感染者の50%から60%が数日以内に死亡する。第二の、そしてさらに悪質な肺ペストは、感染した肺から発散される空気中の飛沫によって、人と人との間で直接感染する。致死率は100%に近い。ごくまれに、病原体が昆虫に乗って移動し、敗血症性ペストとして知られるものを引き起こすことがあるが、これは非常に急速に進行し、必ず致死的となる3。
14世紀第2四半期には、ネズミが感染したノミを東は中国へ、南はインドへ、西は中東、地中海、ヨーロッパへと運んでいった。中央アジアのキャラバンルートが伝播の経路となった。1345年、伝染病はクリミア半島に達し、そこでイタリアの商船に拾われ、地中海に伝わった。町を包囲していたタルタル人の間でペストが発生したとき、彼らの指導者であったジャニベグが、ペストの犠牲者の死体を城壁の向こう側に投げるように命じ、それによって町内のジェノヴァ人に感染させたとされている。というのも、ペストはネズミを宿主とし、肺ペストは実際に生きている人間を宿主とするからである。必要なげっ歯類やノミの移入を確実にするには、既存の商業的なつながりだけで十分だったのである4。
ペストがコンスタンチノープルを襲ったのは1347年のことで、その症状について特に正確な記述を残しているのは、引退したビザンツ皇帝ヨハネ6世カンタクゼノス:
どんな医者の技術も十分ではなく、病気はすべての人に同じ経過をたどった。2,3日耐えることができた者は、最初は非常に激しい発熱があり、そのような場合、病気は頭部を攻撃した。. . . また、頭ではなく肺を襲う者もおり、肺の内部で炎症が起こり、胸に鋭い痛みが生じた。血の混じった痰が上がってきて、内側から嫌な悪臭を放つ。喉と舌は熱でカラカラになり、黒く充血していた。. . 上腕と下腕に膿瘍ができ、数人は顎にもできた。. . 黒い水疱ができた。全身に黒い斑点ができた人もいたが、少なくてはっきり見える人もいれば、不明瞭で密集している人もいた。足や腕に大きな膿瘍ができ、そこから切ると悪臭を放つ膿が大量に流れ出た。. . . 人々は気分が悪くなるたびに回復の望みはなく、絶望に変わり、衰弱に拍車をかけ、病気をひどく悪化させ、たちまち死んでいった5。
致命的な積荷がボスポラス海峡とダーダネルス海峡を通過した後、ペストは1348年にアレクサンドリア、カイロ、チュニスといったアラブの大都市を襲った。翌年にはイスラム世界全体がペストの流行に飲み込まれ、特に都市部で甚大な被害が報告された。
さらに西では、1347年秋、クリミアを出航したジェノヴァ船がシチリア島にペストを持ち込んだ。その後数ヶ月のうちに、ペストは南ヨーロッパの大部分に広がった。ピサ、ジェノヴァ、シエナ、フィレンツェ、ヴェネツィアの人口は、多くの小さな町の人口とともに壊滅的な打撃を受けた。流行は1348年1月にマルセイユに達し、瞬く間に南フランスとスペインを襲った。ペストの北上には歯止めがかからず、1348年春にはパリを襲い、その後フランドルと低地諸国を襲った。1349年に発生したスカンディナヴィアからは、アイスランドやグリーンランドといった辺境の地にも伝染した。1348年秋、ペストは南部の港からイングランドに入り、翌年にはアイルランドに上陸した。ドイツも、ヨーロッパの他の多くの地域よりは深刻ではなかったものの、影響を受けた6。
現代の観察者たちは、病気、苦しみ、死、葬儀の習慣の無視、全般的な混乱と絶望について、苦悶に満ちた物語を語った。主要都市の体験は、都市の作家たちによって誇らしげに語られた。アニョーロ・ディ・トゥーラは、シエナのペストについて印象的な記述を残しているが、彼自身の苦難によってより痛ましいものとなっている:
シエナでの死亡率は5月に始まった。その残酷さと無慈悲なやり方について、どこから話せばいいのかわからない。ほとんどすべての人が、その苦痛を目の当たりにして茫然自失となったようだった。人間の舌では、この恐ろしい真実を語ることはできない。実際、このような惨状を目にしなかった者は、祝福されていると言えるだろう。そして犠牲者はほとんどすぐに死んだ。彼らは脇の下や股間を腫らし、話しながら倒れた。父は子を捨て、妻は夫を捨て、兄弟はまた別の兄弟を捨てた。そして彼らは死んだ。金や友情のために死者を埋葬する者はいなかった。神父も神事もなく、一家の者ができる限り死者を溝に埋葬した。死の鐘も鳴らなかった。そして、シエナの多くの場所では、大きな穴が掘られ、多くの死者で深く積み上げられた。そして、昼も夜も、何百人もの死者が出て、すべてその溝に投げ込まれ、土で覆われた。そしてその溝が埋まるとすぐに、さらに溝が掘られた。そして私、アニョロ・ディ・トゥーラは……。…5人の子供たちを自分の手で埋葬した… …。そして、あまりに多くの人が死んだので、誰もがこの世の終わりだと信じた7。
アニョーロが言及した集団墓地は、他の多くの物語にも繰り返し登場し、人命の喪失の規模の大きさを伝えている。フィレンツェのペストに関するジョヴァンニ・ボッカチオの古典的な記述では、次のように書かれている、
死体の数が多すぎて……埋葬するのに十分な聖地がなかった……。そのため、すべての墓が満杯になると、教会の庭に巨大な溝が掘られ、そこに新たに到着した数百人の死体が、船の積荷のように何段にも積み重ねられて入れられた。
これらの証言は、ヨーロッパ各地で発見された集団墓地によって裏付けられ、時にはペストのDNA的証拠も含まれていた8。
中世の人口の大多数が住んでいた田舎の荒廃は、あまり注目されなかった。ボッカッチョは、読者に次のことを思い出させなければならなかった。
散在する集落や田舎では、貧しい不幸な農民とその家族には、彼らを助ける医者も使用人もおらず、昼夜を問わず道端や畑や小屋で倒れ、人間というより動物のように死んでいった9。
1350年までにはペストは地中海沿岸で終息し、翌年にはヨーロッパ全土でペストは終息した。中世の証人は、計り知れないものを測るのに苦労し、しばしば四捨五入した数字やステレオタイプな数字に頼った。それでも、1351年にローマ教皇クレメンス6世のために算出されたペストによる死者数2384万人は、的外れである必要はない。現代の推定では、全体の死亡率は25%から45%である。パオロ・マラニマによる最新の復元によれば、ヨーロッパの人口は1300年の9400万人から1400年には6800万人へと4分の1以上減少した。イングランドとウェールズでは、ペスト以前の人口600万人の半分近くを失った可能性があり、18世紀初頭までペスト以前の水準に達しなかった。中東の信頼できる推定値を入手するのは難しいが、エジプトやシリアの死亡率は、特に15世紀初頭までの総死亡者数を考慮すると、一般的に同程度とされている10。
具体的なことはさておき、黒死病の甚大な影響に疑いの余地はない。イブン・ハルドゥーンがその万国史の中でこう書いている、
東洋と西洋の文明は破壊的な疫病に見舞われ、国家を荒廃させ、人口を消滅させた。. . . 人の住む世界全体が変わった。
実際にそうなった。パンデミックの最中と直後の数年間、人間の活動は衰退した。教会の権威は弱まり、快楽主義と禁欲主義が並存し、恐怖と後継者不在によって慈善事業が増加した。
最も根本的な変化は経済分野、特に労働市場で起こった。黒死病がヨーロッパに上陸したのは、3世紀にわたって人口が2倍から3倍にも激増した時期であった。CE約1000年以降、技術革新、農法や作物の改良、政治的不安定の緩和などが相まって、定住、生産、人口が拡大した。都市はその規模と数を増していった。しかし、13世紀後半になると、この長期にわたるエフロレッセンスは一巡した。中世の気候最適期が終わりを告げると、生産性が低下し、需要が供給を上回り始めると同時に、飢えた人々の豊かな口が食料の価格を押し上げた。耕地の拡大が停滞し、牧草地が縮小したため、基本的な穀物がますます貧弱な食生活の主食となったにもかかわらず、タンパク質の供給が減少した。人口圧力は労働の価値を低下させ、実質所得を減少させた。せいぜい生活水準が停滞する程度であった。14世紀初頭には、不安定な天候が不作を招き、壊滅的な飢饉をもたらしたため、さらに悪化した。14世紀の前半には人口が減少したものの、自給自足の危機はもう一世代続き、疫病が家畜を枯渇させた12。
ヨーロッパの多くの地域が、ある種の修正マルサスの罠に陥っていたように思われる。この罠では、先行する人口増加によって土地と労働力の比率が不利になるという内生的な問題と、生産高を低下させる気候変動という外生的なショックが、労働者大衆の生活を不安定にし、生産手段、とりわけ土地を支配するエリートに有利に働いた。黒死病は人口数の劇的な減少をもたらしたが、物理的なインフラは手つかずのままだった。生産性が向上したおかげで、生産の減少幅は人口の減少幅よりも小さくなり、一人当たりの平均生産高と所得は上昇した。ペストによって実際に多くの労働人口が死亡したかどうかはともかく、時折主張されるように、土地は労働力に対してより豊富になった。地代と金利は、絶対額でも賃金対比でも低下した。地主は損をし、労働者は得をすることになった。しかし、この過程が現実の生活でどのように展開されたかは、中世の労働者の有効な交渉力を媒介する制度や権力構造に大きく左右された。
西ヨーロッパの現代の観察者たちは、集団死亡が賃金要求を後押しすることにいち早く注目した。カルメル会の修道士ジャン・ド・ヴェネットは、1360年ごろの年代記の中で、伝染病の後、次のように報告している、
家財道具や食料品、商品、雇い労働者、農場労働者、使用人などである。唯一の例外は不動産と家屋で、これらは今日に至るまで余っている。
『ロチェスター修道院の年代記』(ウィリアム・デーン著)によれば、このような労働力不足が続いた、
このような労働者不足が続いたため、謙虚な人々は雇用に鼻を高くし、3倍の賃金で高名な人々に仕えるよう説得することはほとんどできなかった13。
雇用主たちは、人件費の高騰を抑えるよう当局に圧力をかけるのに時間をかけなかった。黒死病がイングランドに上陸してから1年も経たないうちに、1349年6月、王室は「労働者条例」を可決した:
人口の大部分、特に労働者や従業員(「使用人」)がこの疫病で死亡したため、多くの人々は、主人のニーズと従業員の不足を観察し、高額の給与が支払われない限り働くことを拒否している。. . . われわれは、自由であるか不自由であるかを問わず、身体的に健康で60歳未満であり、職業を営み、特定の技術を行使することなく、労働に必要な私有地を持っておらず、他人のために働いていない、わが王国イングランドのすべての男女は、次のように定めなければならない、 身分相応の雇用が提供された場合、提供された雇用を受け入れる義務があり、わが治世[1346]の第20年または5,6年前の他の適切な年に、彼らが働いている国の地域で通常支払われていた報酬、肝煎り、支払い、給与のみが支払われるべきである。. . . 何人も、上記で定義された以上の賃金、報酬、給与を支払ったり、約束したりしてはならない。ただし、それによって損害を受けたと考える者に対しては、支払ったり、約束したりした金額の2倍を支払うことを条件とする。. . . 職人や労働者は、その労働や技術に対して、たまたま働いている場所で、20年目またはその他の適切な年に受け取ることが予想される以上の金銭を受け取ってはならず、それ以上の金銭を受け取る者がいれば、牢獄に投獄する14。
もしそれ以上取る者がいれば、その者は牢屋に入れよ」14。これらの命令の実際の効果は控えめなものだったようだ。わずか2年後、1351年に制定された別の法令「労働者の法令」は、次のように訴えた。
前記従業員たちは、前記条例を顧みず、むしろ自分たちの安楽と並外れた貪欲さのために、前記20年以前に受け取る慣行の2倍または3倍の俸給と賃金が支払われない限り、大男らのために働くことを辞退し、大男らに大きな損害を与え、すべてのコモンズを困窮させている。
そして、この失敗を是正するために、より詳細な制限と罰則が設けられた。しかし、一世代も経たないうちに、これらの措置は失敗に終わった。1390年代初頭、レスターのアウグスティノ会士ヘンリー・ナイトンは、年代記の中で次のように記している。
労働者たちは自分のことしか考えず、血気盛んであったので、王の命令など気にも留めなかった。彼らを雇いたいと思う者は、彼らの要求に従わなければならなかった。自分の果実や立地するトウモロコシが失われるか、労働者の傲慢と貪欲に迎合しなければならなかったからだ15。
これをより偏見のない言葉で言い換えれば、政府の命令や強制によって賃金の上昇を抑えようとする試みよりも、市場の力が自らを主張したのである。使用者、特に地主の個人的利益が、労働者に団結した前面を見せるという強制力のない集団的利益に優先したからである。イングランドと同様、他の国でも同様だった。1349年、フランスも同様に、賃金をペスト以前の水準に制限しようとしたが、より早く敗北を認めた。やがて、雇用主が雇用を希望する場合には、いつでも賃金を支払わなければならなくなった16。
経済史家のロバート・アレンとその共同研究者たちの努力のおかげで、私たちは現在、熟練労働者と非熟練労働者の実質賃金の時系列データを数多く入手することができる。ヨーロッパとレバントの11都市で記録された非熟練労働者の賃金の長期的傾向は、明確な姿を示している。ロンドン、アムステルダム、ウィーン、イスタンブールの4都市では、ペスト発生前の賃金は低く、発生後に急上昇した。実質所得がピークに達したのは15世紀初頭か半ばであり、この時期には他の都市でも同様のデータが現れ、同様の上昇を示している。1500年ごろから、ほとんどの都市の実質賃金は低下し、1600年ごろにはペスト以前の水準に戻り、その後2世紀にわたって停滞するか、さらに低下した。ロンドン、アムステルダム、アントワープだけは例外で、近世を通じてより手厚い報酬水準を維持していたが、後者の2都市では15世紀後半に実質賃金が一時的に急減し、その後再び回復した。ペストによる上昇とその後の下落は、それぞれ100%と50%のオーダーで、軒並みかなりのものであった(図10.1)17。
図10.1 ヨーロッパとレバントにおける都市部の非熟練労働者の実質賃金(1300年~1800)
14都市の熟練労働者の賃金もほぼ同じ様相を呈し、ペスト直前期から15世紀半ばまでの間に、データが入手可能なところでは、やはりほぼ倍増し、1500年から1600年にかけて広範に下降し、1800年まで停滞またはさらに下降している。
人口動態の変化と実質所得の関連は顕著で、今回検討したすべての都市で、実質賃金は人口数が最低に達した少し後にピークに達した。人口動態の回復は賃金の伸びを逆転させ、多くの都市では1600年以降、人口が拡大し続ける中で実質賃金は下がり続けた。農村の賃金はあまりよく記録されていないが、ペストによる強い上昇がイングランドの資料に見られる(図10.3)19。
図10.2ヨーロッパとレバントの都市熟練労働者の実質賃金(1300年~1800)
同様の結果は東地中海でも観察される。黒死病の後、ヨーロッパよりも短い期間ではあったが、労働コストが急上昇した。歴史家アル=マクリージはこう述べている、
職人、賃金労働者、ポーター、使用人、花婿、織物職人、労働者など、彼らの賃金は何倍にも膨れ上がった。この種の労働者は、懸命に探さなければ見つからない。
ペストの犠牲者からの遺贈や、富を受け継いだ生存者からの贈与によって、宗教的、教育的、慈善的な寄付が急増した。このため、労働力不足の中で建設作業が奨励され、職人たちは都市部の未熟練労働者とともに繁栄した。一時的な生活水準の向上は食肉需要を押し上げた。所得と物価のある内訳によると、14世紀初頭の平均的なカイレーヌ人の1日の消費カロリーは、タンパク質45.6グラムと脂肪20グラムを含む1,154キロカロリーと控えめであったが、15世紀半ばには、タンパク質82グラムと脂肪45グラムを含む1,930キロカロリーを消費できるようになった20。
図10.3イングランドにおける穀物換算の農村実質賃金(1200~1869)
ビザンツとオスマン帝国のデータにはばらつきがあるが、大まかにはヨーロッパの大半のデータに匹敵する図式を裏付けている。1400年までに、ビザンチンの都市部の実質賃金はペスト以前の水準を大幅に上回った。オスマン帝国の記録によれば、イスタンブールの建設労働者の実質所得は16世紀半ばまで高水準を維持し、19世紀末までそれを上回ることはなかった。
黒死病がいかに深刻なものであったとしても、都市部の実質賃金を倍増させ、この上昇を数世代にわたって持続させるには、黒死病の最初の波だけでは不十分であったろう。人口動態の速やかな回復を阻むためには、再び黒死病が発生する必要があった。中世後期の記録には、その後の一連のペストの襲来がよく記録されている。ペストは1361年に再発し、その年の春から翌年の春にかけて猛威を振るった。多くの若者を殺したことから「子供のペスト」(pestis puerorum)と呼ばれたこのペストは、とりわけ最初の流行時にまだ生きていなかった人々を標的にしたようだ。現代の推測では、ヨーロッパの人口の10%から20%、イギリスでは5分の1が死亡したとされている。1369年には、比較的被害の少なかった第三のペストが発生した。これがその後の100年以上の流れを決定づけた。イングランドだけでも、1375年、1390年、1399年~1400年、1405年~1406年、1411年~1412年、1420年、1423年、1428年~1429年、1433年~1435年、1438年~1439年、1463年~1465年、1467年、1471年、1479年~1480年の全国的な流行が報告されている。この時期の最後の数十年間は、特に大規模な人口減少が見られ、1361年以来最悪と伝えられる1479-1480年の疫病がその頂点に達した。1360年から1494年の間にオランダで15回、1391年から1457年の間にスペインで14回の流行が確認されている。1360年から1494年の間にオランダで15回、1391年から1457年の間にスペインで14回ペストが流行したことが分かっている。その結果、1430年代にはヨーロッパの人口は13世紀末の半分かそれ以下になっていたかもしれない。地域によって異なるが、1450年代、1480年代、あるいは16世紀後半になってようやく人口回復が再開した。労働人口の生活水準の向上が観察されたのは、数世代にわたる数千万人の苦難と早死が根底にあったからである22。
ペストが不平等に及ぼした影響について、私たちは何を知っているのだろうか。根底にある論理は明らかだ。土地と食料の価格が下がり、労働の価格が上昇すれば、富裕層よりも貧困層が有利になり、富と所得の不平等が緩和される可能性が高い。長い間、歴史家はこのような変化を示唆する指標に頼ってきた。小麦の需要は減少したが、肉、チーズ、大麦(このうちビール醸造に使用されるもの)の価格は維持され、これは食生活の改善により、労働者が以前は裕福な人々のものであった食料品にアクセスできるようになったことを示している。高級品に対する需要は、より一般的に拡大した。賃金上昇に加え、イギリス人労働者は報酬の一部としてミートパイやエールを要求し、手に入れることができるようになった。ノーフォークの収穫人の場合、食費に占めるパンの割合は、13世紀後半には半分近くあったものが、14世紀後半から15世紀初頭にかけては15~20%に減少したのに対し、肉の割合は同時期に4%から25~30%に上昇した。
平準化の強いシグナルは、同じ国の2つの倹約令によってもたらされる。1337年、議会は、少なくとも1,000ポンドの贅沢な年収を持つ貴族と聖職者のみに、身分の証とされる毛皮を着用する権利を与えた。しかし、黒死病の到来から15年も経たないうちに、1363年に制定された新しい法律では、下級の肉体労働者以外のすべての人に毛皮の着用が許可された。この法律は、社会秩序の最下層に位置するウサギや猫から、最上層に位置する白いマスカレードの毛皮まで、どの社会集団の成員がどの動物の毛皮を着用できるかを定めたに過ぎなかった。このような控えめな制限さえも無視されるようになったのは、大衆が豊かになり、身分の垣根がなくなってきたことの表れである23。
一般庶民がエリートの特権であったものを手に入れることができるようになった一方で、貴族は、領地の農産物の価値が下がり、農産物を作る人々の賃金が上がるという危機に直面した。借地人が病気でいなくなると、土地所有者はより多くの賃労働者を雇って農業をさせなければならなくなった。まだ小作人として雇われている人々は、より長い契約期間とより低い賃料を享受した。社会は、地主階級がより強く、より豊かになり、ほとんどの人々がより貧しくなっていたそれまでの傾向の大逆転を経験した。イングランドの地主階級の土地収入は、15世紀前半だけで20%から30%も減少した。大領主は収入が減っても何とか地位を維持したが、属領の構成員は下方移動に苦しんだ。ペストは貴族の劇的な縮小を招き、2世代にわたって貴族の4分の3が後継者不在となった。13世紀には3倍の約3,000人にまで増加したベルト付き騎士の数は、1400年には2,400人、1500年には1,300人にまで減少した。貴族階級の頂点に立つ者の数は、1300年には200人であったが、1500年には60人にまで減少した。記録された貴族の最高所得も、1300年から15世紀にかけて劇的に減少した24。
こうした一般的な動きは、ある程度の平準化を強く示唆している。しかし、ここ数年になってようやく、これを裏付ける確かな量的証拠が出てきた。グイド・アルファーニ(Guido Alfani)は先駆的な取り組みとして、北イタリアのピエモン(Piemont)の都市アーカイブからデータを収集・分析した。資産の分布に関する情報は、地元の不動産登記簿に保存されている。その多くは不動産のみを記録しており、資本、信用、動産といった他の種類の資産が含まれているのは一部のケースのみで、1427年の有名なフィレンツェのカタストの詳細な範囲に匹敵する。これらの限界から、体系的な比較分析が可能な唯一の変数として、土地所有における不平等が残される。アルファーニの調査は、13のピエモンテ共同体のデータに基づいている。最も古いデータは1366年までさかのぼるが、ほとんどの場合、15世紀後半以降に記録が入手できるようになる。後者の期間を通じて、不平等が増大する持続的な傾向が観察される。ほとんどの場合、各都市の18世紀の記録は、中世末期の対応する記録よりも高いジニ係数を示している。これは都市部でも農村部でも同様であり、不平等をジニ係数で測るか、図10.4で用いている富裕層の富のシェアで測るかにかかわらずである。このような財産集中の一般的な傾向は、第3章で述べた、近世の経済拡大が生み出した「超曲線」の上昇局面を象徴している25。
最も顕著な発見は、ペスト前とペスト中の数年間に関するものである。この時期のデータが入手可能な3つの町、キエーリ、チェラスコ、モンカリエーリ(図10.4の1450年以前の都市データを共同で占める)では、ペストが次々と再発した14世紀から15世紀初頭にかけて不平等が低下した。ピエモンテやトスカーナのいくつかのコミュニティでは、同じ時期に、地域の世帯富の中央値の10倍以上を所有する世帯の割合が減少した。この平準化効果は、すでに検討した実質賃金のデータと完全に一致する。フィレンツェ近郊では、同時期に非熟練労働者の実質賃金が約2倍に上昇した(本明細書、図10.1参照)。可処分所得の増加は、ペスト関連のショックがエリートの間に離反を引き起こしたとしても、労働者が財産を取得することを容易にした。格差の縮小から拡大への転換が、人口数が底を打ち緩やかな回復に転じた人口構造の変曲点と一致していることを考えれば、分布の形状も重要である26。
図10.4ピエモンテの都市における上位5%の富のシェアと富の分配のジニ係数(1300年~1800)(平滑化した基準)
ほとんどの実質賃金系列の場合と同様に、このような不平等の圧縮は長続きしなかった。15世紀半ば以降、土地所有の集中が強まり、それ以降は全般的に上昇しただけでなく、さらに驚くべきことに、黒死病以来最悪の地域的死亡危機であり、北イタリアの人口の3分の1もの死者を出したと考えられている1630年のペストの再発も、不平等に匹敵するような影響を及ぼすことはなかった: 1650年または1700年のジニ係数と富のトップシェアは、それ以前の150年間の回復の後でも、一貫して1600年よりも高かった。このことは、黒死病とその再発の最初の衝撃が、経済的影響に対処する準備の整っていない土地所有者たちを襲った後、資産家階級が人口統計学的ショックの際に自分たちの財産を守るための戦略を最終的に開発したことを示唆している。フィデコミッサム(適切な相続人がいない場合でも財産を一族内に保持することを認めた)の使用などの制度的適応が、エリート層の財産を維持するのに役立った可能性がある。最も激しい伝染病でさえ、文化的な学習によって手なずけることができ、マルサスの緩和による平準化効果を鈍らせることができたようだ27。
トスカーナ各地の富裕税に関する古文書データからも、よく似た図式を描くことができる。特に顕著な例を挙げると、ポッジボンシという農村の富の分布は、1338年から1779年までよく記録されており、黒死病の後に平準化され、その後も集中が続いていることがわかる(図10.5)。アレッツォ、プラート、サン・ジミニャーノの各都市と同様に、フィレンツェ領内にある他の10の農村集落からも、同様の明確な結果が得られるとは限らないが、全体的な傾向はほぼ同じである(図10.6)。農村部では、一般的に1450年ごろから不平等が拡大し、1600年ごろ以降、ジニ係数はそれ以前の世紀よりも常に高くなり、18世紀には必ずピークに達する。さらに、いくつかの共同体では、黒死病の直後にローレンツ曲線が平坦化したことから、平坦化は主に富裕層の損失によって引き起こされたことが示唆される28。
このような動態をさらに裏付けるのが、ペスト発生中とその後に不平等が急減と急回復を繰り返したルカ領である(図10.7)。ロンバルディア州とヴェネト州でも、1500年前後から1600年にかけて富の集中が進んでいたことを示す証拠が見つかっているが、ペスト以前のデータはまだ不足している29。
図10.5 ポッジボンシにおける富のジニ係数(1338-1779)
図10.6 トスカーナにおける上位5%の富のシェア(1283-1792)
図10.7ルッカにおける上位5%の富の分配率とジニ係数(1331-1561)
17世紀のイタリアの経験は、そのような人口動態の変化以外の要因の重要性を浮き彫りにしている。ペスト以前の水準で賃金を安定させる試みが頓挫したことはすでに述べた。エリートたちには、黒死病とその再発の影響を抑制しようとする強力な動機があった。このような措置が成功するかどうかは、社会の権力構造や生態系によって大きく異なる。西ヨーロッパでは、労働力不足による利益は通常労働者に還元されたため、労働者は恩恵を受けた。賃金や移動の制限に失敗しただけでなく、ペストによる人口統計学的ショックも、それ以前の中世の農奴制制度をほぼ消滅させた。農民は移動性を主張し、より良い労働条件があれば他の荘園に移った。このため、荘園経済の標準的な特徴であった勤労奉仕が廃止された。借地人は結局家賃を支払うだけで、自分の管理できる範囲で土地を耕す機会を得た。これは上昇志向を助長し、豊かな農民からなるヨーマン階級の誕生につながった。一例を挙げると、イングランドのレッドグレーブ荘園では、1300年には平均12エーカー、1400年には20エーカー、1450年には30エーカー以上の土地を所有していた。西ヨーロッパ全域で同様の調整が行われた。1500年までには、コピー・ホールドと呼ばれる契約形態が西ヨーロッパ、南ヨーロッパ、中央ヨーロッパで主流となった。
契約は、小作農が交渉によって得ることのできる最良の取引に基づいて、年間固定で支払われる賃借料を規定していた30。労働者は、自分たちが新たに得た利益を否定しようとするエリートの企てに抵抗するために、暴力に訴えることもあった。第8章で見たように、フランスのジャクリー(1358)やイングランドの1381年の農民反乱のような農民反乱の形をとった民衆の反乱はその結果であった。後者は、国家歳入の減少を補うための人頭税の賦課が引き金となったが、実質的には、自分たちの特権的な経済的地位を維持したい領主に対して、労働者にもたらされた所得増加による利益を維持したいという願望が動機となっていた。短期的には、蜂起は武力によって鎮圧されたが、新たな制限的法令が可決され、リチャード2世が農民に「あなたがたは束縛されたままであるが、以前と同じではなく、比較にならないほど厳しい」と約束したことは有名である。当時の保守的な詩人たちは、「世間が彼らの奉仕と労働を必要としているのを見て、……彼らの数が少ないので傲慢になる」「放浪の労働者」を嘆いた: 「ほんのわずかな労働のために、最も高い賃金を要求する。労働者は、少なくともそれが続く間は、労働力不足から利益を得ることができた31。
しかし、他の地域では、地主が労働者の交渉を抑圧することにもっと成功していた。東欧諸国-ポーランド、プロイセン、ハンガリー-では、黒死病の後に農奴制が導入された。この過程に関する古典的な記述は、ジェローム・ブルームにさかのぼる。彼は1957年に、中欧と東欧が、はるか西方で経験したのと同じように、人口削減、耕作放棄地、土地と穀物価格の下落という問題に直面していることを観察した。地主貴族は収入の減少を食い止めるために法的手段に訴え、賃金や都市商品の価格に上限を課した。西ヨーロッパとは異なり、権力者たちは労働義務を軽減する代わりに、特に労働分担金、現金支払い、移動の自由の制限など、労働義務を増大させるために奮闘した。プロイセン、シレジア、ボヘミア、モラヴィア、シレジア、ロシア、リトアニア、ポーランド、リヴォニアなどさまざまな国で、借家人は許可なく、あるいは多額の手数料やすべての滞納金を支払わなければ、あるいは一定の時期以外には、あるいは場合によってはまったく出国することが禁止された。労働者の密猟は法律や領主の合意によって禁止され、都市は移民を拒否するよう命じられ、支配者は彼らの母国への帰還のための条約を結んだ。借地借家は強力な拘束手段であった。16世紀に入っても、義務と制限は拡大し続けた。おそらく最も重要なのは、商業化と都市化の不利な進展と並んで、荘園内の農民に対する管轄権を強める貴族の政治的権力の増大であった。貴族が国家を犠牲にして権力を拡大し、都市が対抗手段を提供できなかったため、労働者はますます強制的な取り決めに囚われていった。この問題に関する修正主義的な研究は、この古典的な再構築に疑問を投げかけるまでに至っているが、労働者にとっての結果が西欧のそれとは大きく異なっていたことは事実である32。
マムルーク朝エジプトには、別の制約が適用された。すでに述べたように、エジプトは黒死病によって大打撃を受け、都市の実質賃金と消費水準は、少なくとも当初は他の地域と同様に確かに上昇していた。しかし、政治的・経済的権力の異常な構成が、エリート層が労働者の要求に抵抗することを可能にした。外国の征服階級であったマムルーク朝は、中央集権的かつ集団主義的なやり方で土地を支配し、その他の資源を指揮していた。マムルーク朝の支配階級の構成員は、個々のイクタ(土地などからの収入割り当て)から収入を得ていた。労働力不足や農業の混乱によって利益が減少すると、国家の既定の対応は、減少する納税者からより厳しく搾取することによって受給権を引き上げることだった。都市部では、これは増税だけでなく、没収、強制購入、独占の確立にもつながった。こうした強制的な対応は、中世後期のカイロで記録された賃金上昇が短期間で終わったことの説明に役立つ33。
地方では、弾圧はさらに厳しかった。マムルークは領地から切り離された不在地主であり、状況の変化に対応するために交渉する用意のある責任ある地主として行動することができず、またその気もなかった。賃料の流れを維持するのは、マムルークと農地生産者を隔てる中間層を形成する中央集権的な官僚機構の責任であった。これらの管理職は農民に容易に圧力をかけ、好都合であれば暴力に訴えた。農民は都市への移住や反乱で対抗した。ベドウィンは放棄された土地に侵入し、その過程で収入基盤はさらに減少した。さらに、エジプトの環境の特殊性から、疫病や逃亡による労働力の損失は、継続的なメンテナンスに依存する精巧な灌漑システムを混乱させることになった。このため、農業資産はヨーロッパよりも脆弱になった。したがって、耕地面積が急速に減少しても、土地と労働力の比率の変化はヨーロッパほど大きくはなかったかもしれない。集団主義的搾取に依存し、国家を支配したマムルーク朝の圧倒的な集団交渉力、中間管理による土地からの切り離し、資本を労働に代える技術改良の欠如、生産者の引き上げられた要求の回避、その結果としての全体的な資源基盤の悪化、これらの特徴が組み合わさって、農村の生産と所得を低下させた。西欧における契約主義の台頭が、労働者により高い実質所得と大きな平準化効果をもたらしたのとは対照的である34。
黒死病がもたらしたさまざまな福祉的結果と、17世紀のイタリアのペスト復活期における不平等の持続は、最も壊滅的な伝染病でさえ、それ自体では富や所得の分配を平等にすることはできないことを示している。制度的な取り決めは、強制的な手段によって労働市場を操作し、人口統計学的ショックの力を鈍らせることが可能であった。ある種の暴力は、別の暴力によって相殺することができた。もし微生物の襲撃が、交渉を抑制するのに十分な人間の力によって迎えられたなら、エリートたちは高いレベルの不平等を維持するか、速やかに回復させることができたのである。つまり、疫病の平準化効果は、人口が回復するにつれてほとんど必ず徐々に解除されるという時間的な制約と、疫病が展開される社会的・政治的環境による制約という2つの制約を受けることになる。このように、疫病が不平等を実質的に縮小させたのは、いくつかのケースとしばらくの間だけであった。
第11章 パンデミック、飢饉、戦争
「私たちは死ぬために生まれてきた。新世界のパンデミック」
14世紀半ばの黒死病は、ヨーロッパでは17世紀まで、中東では19世紀まで続いた定期的な再発とともに、歴史上の大パンデミックの中で最もよく知られているかもしれないが、決して唯一のパンデミックではなかった。ヨーロッパでパンデミックがようやく沈静化し始めた頃、スペインによる大西洋横断は、新大陸でも同様に大規模で、間違いなくさらに破滅的なパンデミックを引き起こした。
最後の氷河期の終わりに海面が上昇し、アラスカとシベリアのベーリング海のつながりが断たれて以来、旧世界と新世界の人口と疾病環境はそれぞれ独立して発展してきた。アフロユーラシア大陸の住民は、アメリカの住民よりも幅広い種類の病原体を持つ動物と接触し、天然痘、麻疹、インフルエンザ、ペスト、マラリア、黄熱病、チフスなど、しばしば致命的な感染症にさらされるようになった。中世の終わりには、商業的、ひいては軍事的な接触をきっかけに、旧世界の地域的な疾病プールが徐々に融合し、これらの殺人疾患の多くが風土病となった。これとは対照的に、アメリカ先住民はそれほど深刻な疾病環境になく、旧世界の災厄にさらされることもなかった。探検と征服によって、アルフレッド・クロスビーが「コロンブス交換」と呼ぶ大西洋を越えた交流が始まり、アメリカ大陸に致死的な感染症が大量にもたらされた。新大陸は梅毒を送り込むことで恩返しをしたが、ヨーロッパからアメリカ大陸にもたらされた病原体のほうがはるかに多様で、壊滅的な被害をもたらした1。
天然痘と麻疹は、ヨーロッパ人が持ち込んだ伝染病の中で最も壊滅的なものであった。旧世界では長い間、幼児病として流行していたものが、アメリカ大陸で大流行したのである。ほとんどの船員は幼少期にこれらの病気にかかり、大人になってからは予防を受けていたはずだが、時折、積極的な保菌者が大西洋を横断する遠征隊に加わった。3番目の大流行となったインフルエンザは、成人にはまったく免疫がなかった。これら3つの感染症は、飛沫感染や身体的接触感染によってもたらされた新しい感染症の中で最も感染力が強かった。マラリア、チフス、ペストといった他の感染症は、それぞれ蚊、シラミ、ノミといった適切な媒介虫を導入する必要があった。しかし、これは時間の問題だった。
クリストファー・コロンブスの最初の航海から1年も経たないうちに、ヨーロッパ人の最初の足がかりとなったイスパニョーラ島では感染症が猛威を振るい始めた。数十万人いた先住民の人口は、1508年には6万人、15-10年には3万3千人、1519年には1万8千人、1542年には2千人以下にまで減少した。複数の伝染病がカリブ海を席巻し、やがて本土にも及んだ。天然痘の最初の流行は1518年に起こり、島々を荒廃させ、1519年にはメソアメリカのアステカ人とマヤ人に甚大な死亡率をもたらした。その影響は大きく、アステカの生存者たちは後に、天然痘の発生からその日を数え、新時代の恐怖の到来を告げる重大な出来事と認識するようになった。接触によって感染し、治療法もないため、処女人口を最大限の力で襲った。アステカの観察者の言葉を借りよう、
顔、胸、腹がただれ、頭のてっぺんから足の先までただれに覆われた。この病気はとても恐ろしく、誰も歩くことも動くこともできなかった。病人は全く無力で、死体のようにベッドに横たわることしかできず、手足はおろか頭さえ動かすことができなかった。うつ伏せになることも、左右に転がることもできなかった。体を動かそうものなら、痛みで悲鳴を上げた。
ベルナルディーノ・デ・サハグンは、アステカの首都テノチティトランの攻略について次のように述べている、
通りは死者と病人であふれ、兵士たちは死体の上を歩くだけだった2。
1520年代、天然痘は数年のうちにアンデスのインカ帝国に到達し、支配者ワイカ・カパックを含む膨大な数の人々が命を落とした。2度目の大流行は1532年に始まり、今度は麻疹が原因となった。ここでもまた甚大な被害がメキシコからアンデス山脈にまで及んだ。1545年から1548年にかけては、おそらくチフスと思われる深刻な伝染病がメソアメリカ中央部を荒廃させた。1550年代後半から1560年代前半にかけては、インフルエンザが大きな役割を果たしたと思われる。さらに多くの災害が報告され、1576年から1591年にかけての複合パンデミックに至り、最初はチフス、後に天然痘と麻疹の複合感染(1585-1591)が発生し、残存人口を壊滅させた。疫病は17世紀前半を通じて続いたが、その勢いは弱まり、地域差も大きくなった。大量死とそれに伴う混乱がスペインの進出を助けたとはいえ、新しい支配者はすぐにその流れを止めようとし、16世紀後半には、搾取できる土着の労働力を維持することを期待して、より多くの医師を配置し、検疫を課した。伝染病は一世代に一度程度、波状的に発生し、最初の150年余りの間、死者数は緩やかにしか減少しなかった。さらに、征服という暴力そのものが、先住民に与えたさまざまな経済的、社会的、政治的衝撃を通して、全体的な死亡危機を悪化させなかったはずがない。
累積的な人口統計学的影響は、間違いなく壊滅的であった。この問題は、何世代にもわたって研究者を悩ませてきたが、接触前の人口レベルに関する確かな情報がないために解決が難しい。メキシコに限って言えば、20%から90%までの累積人口減少が文献で提唱されている。ほとんどの推定では、総損失は半分以上である。黒死病に関連した死亡レベルは、新世界の単なる最低ラインと考えるのが妥当であろう。メキシコでは少なくとも半数以上が死亡し、少なくとも限定された地域ではそれ以上の損失もあり得ると思われる3。
この劇的な人口減少が資源の不平等を圧縮したかどうかは、長い間未解決の問題であった。アステカやインカの階層化された帝国が、同様に階層化されたスペインの支配に取って代わられたため、富の進化は国家権力のシフトによって媒介されたであろう。人口動態の変化が労働市場でどのように作用したかを明らかにするには、確かなデータが必要である。ジェフリー・ウィリアムソンは、ラテンアメリカの不平等に関する「証拠なき歴史」を描くという大胆な試みにおいて、標準的なマルサスの論理が16世紀に起きた膨大な人口減少に対応して実質賃金が上昇すると予測したと観察しただけで、この推測を裏付ける証拠を挙げることはできなかった。2014年、1530年代から3世紀にわたるラテンアメリカの所得に関する先駆的な研究が、ついにこの状況を変えた。図11.1はメキシコシティ地域の労働者の実質賃金の上昇と下降を示している4。
図11.1 メキシコ中部の実質賃金(1520-1820)(10年移動平均)
この逆U字カーブは、人口減少とその後の回復に対応して賃金が変化したというマルサス的な解釈を誘うが、伝染病による死亡率が特に深刻であった16世紀に進歩がなかったことには説明が必要である。その答えはおそらく、コロンブス以前の強制労働体制に根ざした、人口減少に直面した労働力確保のためのスペインの強制力への依存にある。その結果、政府の介入によって賃金交渉が長期にわたって抑制されたのかもしれない。この解釈は、スペインによるメキシコ支配の初期に強制労働が最も激しかったという事実とうまくかみ合う。したがって、「エンコミエンダ」(先住民から労働力と貢ぎ物を引き出すための補助金で、個々の受益者に割り当てられる)は、征服後の最初の世代におけるエリート報酬の標準的な形態であった。この取り決めは1601年に廃止されたが、1630年代まで事実上存続していた。それでも、エンコミエンダの総数は1550年の537から1560年には126に減少していた。
賃金も当初は厳しい制約を受けていたが、時間の経過とともに緩和されていった。16世紀のメキシコでは、総督府が賃金を決定し、強制がいたるところで行われていた。17世紀初頭から労働市場が自由化され、実質賃金が上昇した。1590年には労働者の報酬はまだ最低限の自給自足レベルであったのに対し、1700年には実質賃金は当時世界最高水準であったと考えられる北西ヨーロッパの水準にさほど遅れをとらなかった。16世紀に観察された遅れが国家の介入によるものであったとすれば、その後の自由化によって労働力不足が実際の報酬水準に反映されるようになった。一般的にほとんど効果がなかった黒死病当時の西欧の労働法とは異なり、メキシコでは強制労働の形態がより深く根付いていたため、当局により大きな介入権が与えられていた。実質賃金は1770年代以降低下し、1810年までには自給自足に戻った5。
メキシコにおける実質賃金の上昇の最も顕著な特徴は、その途方もない規模であり、黒死病後の西ヨーロッパの都市における「単なる」倍増とは対照的に、4倍であった。メキシコの急増は、論理的に一致し、したがって、はるかに大規模な人命の損失を意味する可能性がある。その後の実質所得の落ち込みは、近世ヨーロッパにおける類似の動きを彷彿とさせる。観察されたこれらの変化の規模が記録の信頼性に疑念を抱かせるとしても、全体像は明らかであるように思われる。労働力不足が深刻化し、市場制度が報酬水準の仲介をできなくなった後、数世代の労働者が労働力不足の恩恵を受けた。人口が増加し、労働者の交渉力が低下すると、この段階は不幸な現状に戻った。
一般的な生活水準や人間の身長といった幸福の指標は、観察された実質賃金の上昇とほぼ一致している。しかし、前近代史によく見られるように、こうした発展が所得格差に与えた影響を確認するのに必要なデータが不足している。最も一般的な言い方をすれば、労働者の実質所得が4倍になったからといって、全体として何らかの平準化効果がなかったとは考えにくいが、今のところ、この基本的な直観を超えることはできない。円環的推論に陥る危険を冒してでも、新世界のデータは、その限界はあるにせよ、ペストによる平準化の論理にも、数世紀前のヨーロッパの経験的なペスト後のデータにも適合していると言える。スペインの征服エリートは、かつてアステカの支配階級が占めていた地位を引き継ぎ、それによって社会の最上層への資産集中が維持されただろうが、少なくとも一部の労働者の実質所得が大幅に増加したことで、全体的な不平等がある程度緩和されたはずである。17世紀のメキシコは、この特徴を15世紀の西欧と共有していたと思われる6。
「死者が生者を上回った」: ジャスティニアンのペスト
パンデミックによる平準化のさらなる例を探すと、さらに時代をさかのぼることになる。14世紀の黒死病は、旧世界で最初に流行したペストではない。その800年前、541年から750年まで続いたユスティニアヌスのペストと呼ばれる大流行で、同じ病気がすでにヨーロッパと中東を同じように襲い、荒廃させていた。その際、ペストは541年7月にエジプトとパレスチナの間の海岸にあるペルシウムで最初に発生し、8月には近くのガザに、9月にはエジプトの大都市アレクサンドリアに広がった。翌年3月1日、東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌスは、「死者の発生はあらゆる場所に及んだ」と主張したが、帝都コンスタンティノープル自体はわずか1カ月後に襲われ、壊滅的な打撃を受けた:
ビザンティウムの伝染病は4カ月の経過をたどり、最大の猛威は3カ月ほど続いた。最初は死者が通常より少し多かったが、その後、死亡率はさらに上昇し、その後、死者の数は毎日5千人に達し、再び1万人に達し、さらにそれ以上になった。初めのうちは、各人が自分の家の死者を埋葬し、発見されないように、あるいは暴力を用いて、死者を他人の墓に投げ入れた。. . . そして、以前からあった墓がすべて死者で満たされるようになると、彼らは町中のあらゆる場所を次々に掘り起こし、死者をそこに安置して、ひとりひとりできる限りそこに安置して立ち去った; しかしその後、この塹壕を作っていた者たちは、もはや死者の数に追いつけなくなり、シケの要塞の塔に登って屋根を引き剥がし、そこに死体を無秩序に投げ込んだ。
8世紀後と同じように、伝染病は止められないことが証明された: 542年の夏にはシリアが、同年末には北アフリカが、543年にはイタリア、スペイン、南フランス、バルカン半島が襲われた。東はイランとメソポタミア、西はイベリア半島、北はイギリス、アイルランド、スカンディナビア、南はイエメン、そしてその間のすべての地域で発生したことが記録されている7。
歴史的な記述はY. pestisと一致している。ビザンチンの資料には、ペストの典型的な症状である鼠径部の腫れが繰り返し強調されている。腫れは脇の下、耳の後ろ、大腿部など、他の部位にも現れたとされる。同様に、死の前兆とみなされた黒い癰、昏睡、せん妄、吐血、猛烈な発熱もあった。さらに、分子生物学によって当時のY. ペスティスの存在が確認されている。バイエルンのアッシュハイムにあるローマ時代後期の墓地から発見された12体の骸骨のうち10体からY. ペスティスのDNAが検出された。これらの骸骨の一つから発見されたビーズは、ユスティニアヌス帝ペストが最初に発生した紀元6世紀第2四半期と推定されている8。
報告されている死亡率の数字は非常に高い傾向にあるが、一般的には信頼できないようである。コンスタンチノープルで最初に発生したペストでは、1日に数千人、多いときには1万人が死亡し、都市の人口が半分以上減少したと、観察者たちは想像していた。同じような極端な主張は、時折、同じ場所や他の場所でのその後の大流行についてもなされた。疑う余地のないのは、圧倒的な死亡率の印象であり、観察者たちはそれにステレオタイプな数字をつけた。この病気が中世後期と同じで、同じくらいの期間活動したことを考えると、全体的な死亡率も同じようなもので、おそらくユーラシア西部と北アフリカの人口の4分の1から3分の1程度であったと思われる。このような規模の大量死は、労働力の供給に大きな影響を与えるに違いない。コンスタンチノープルでは、教会幹部のエフェソスのヨハネが、ペストの犠牲者の遺体を処理する者たちの利益や、洗濯代の高騰について、かなり無神経に苦言を呈した。ペスト発生からわずか3年後、ユスティニアヌス帝は労働者の要求の高まりを非難し、政府の命令で禁止しようとした:
われわれは、主なる神が与えた罰にもかかわらず、交易や文学に従事する者、さまざまな種類の職人や農業従事者、船乗りが、よりよい生活を送るべきときに、古くからの慣習に反して、利得の獲得に没頭し、2倍、3倍の賃金や給料を要求していることを確認した。したがって、この勅令によって、すべての人が貪欲という憎むべき情熱に身をゆだねることを禁じることが、われわれにとって得策であると思われる。いかなる芸術や商売の主人も、いかなる種類の商人も、農耕に従事する者も、今後、古来の慣習が定める以上の給料や賃金を要求してはならない。われわれはまた、建物、耕作可能な土地、その他の財産の測定者は、そのサービスに対して正当な額以上の料金を請求してはならず、この点に関して確立された慣習を守らなければならないことを命じる。われわれは、これらの規則を、作業を管理する者にも、資材を購入する者にも遵守させることを命じる。我々は、一般的な慣習で認められている以上の金額を支払うことを許可しない。これ以上の金額を要求する者、また最初に合意された以上の金額を受け取ったり、与えたりしたことで有罪判決を受けた者は、その3倍の金額を国庫に納めなければならないことを、ここに通告する9。
これは、伝染病に直面して交渉力を封じ込めようとした最も古い試みであり、中世のイギリスやフランス、初期のスペイン領メキシコにおける同様の措置の先駆けである。しかし、ペストが長引き、労働力需要が増大したため、この法令が賃金に及ぼした影響はせいぜい限定的なものであっただろう。経済学者たちが容易に推測してきたように、実証的証拠は中東、特に文書による証拠が他に類を見ないほど残っているエジプトに限られているにもかかわらず、実質賃金の伸びは広範囲に及んでいたと考えるのが妥当だろう。エジプトの実質賃金の記録は紀元前3世紀までさかのぼる。しかし、この証拠は不連続である。最初の1,000年間は、文書に記載されているのは非熟練農村部の賃金であり、中世には非熟練都市部の賃金である。そのため、これらのデータを同じ立場に置くことはできないが、同じ傾向を反映しており、一つの包括的な物語にまとまっている。農村の賃金では、小麦換算で3.5リットルから5リットルの日当がほとんどで、これは前近代社会の典型であり、生理的自給自足に近い生活水準に関連する3.5リットルから6.5リットルの中核的な範囲内である。これとは対照的に、紀元6世紀後半、7世紀、8世紀には、10リットルを超えるはるかに高い小麦賃金が記録されている(図11.2)10。
この実質収入の急増は、ユスティニアヌス帝ペストの余波を受けた未熟練農村労働者の補償に関するパピロロジー的証拠に由来する。ペストの人口的影響がピークに達したと思われる紀元6世紀後半から7世紀にかけてのいくつかの記録では、灌漑労働者は1日当たり小麦13.1~13.4リットルに相当する現金賃金を受け取ったと報告されている。同じ時期の他の事例では、現金賃金と食料手当を合わせて、1日当たり小麦7.7~10.9リットルを超える、つまり以前の約2倍に相当する現金賃金を受け取ったと報告されている。これらの調査結果は、熟練労働者の賃金がさらに高く、1日当たり最高25リットルであったという証拠によって裏付けられている。6世紀の前半から後半にかけて、つまり最初のペストが発生する直前から発生した直後にかけて、現存する無期限の土地賃貸借の割合が約17%から39%に増加したのに対し、1年契約の割合は29%から9%に減少したという観察から、さらなる裏付けが得られる。このことは、借地人がより有利な条件をすぐに要求できるようになったことを示唆している。このこと、とりわけ実質所得の異常な急増は、大規模な人口減少に対応して、熟練・未熟練を問わず、職業を問わず労働者の交渉力が大幅に高まったという文脈でのみ説明可能である11。
図11.2エジプトにおける非熟練農村労働者と都市労働者の1日当たり小麦賃金(紀元前3世紀から紀元後15世紀)(単位:小麦キログラム
図11.2 紀元前3世紀から紀元後15世紀までのエジプトにおける非熟練農村労働者と都市労働者の1日当たり小麦賃金(単位:kg図11.2に示すように、これらのデータは8世紀初頭のペスト末期に初めて入手可能となったが、中世末期まで続いている。実質所得は、740年代にエジプトでペストが発生したことが最終的に証明された1世紀後の850年頃まで上昇し、そのほとんどは1日当たり小麦換算で10リットル前後、つまり4人家族の基本的な自給の3倍近くという歴史的に高い水準であった。その後350年間、人口が回復するにつれて、カイレーンの小麦賃金は半分以下に落ち込み、14世紀後半の黒死病をきっかけに一時的に回復するまで、生理的に持続可能な最低水準にまで落ち込んだ。バグダッドの質の低いデータも、8世紀から13世紀にかけて、やや規模は小さいものの、実質所得が恒常的に減少していることを示している。カイロの非熟練都市労働者の名目賃金を、基本的な消費財の価格と関連付けた消費バスケットの再構築からも、同様の図式が浮かび上がってくる。この計算でも、ペスト発生中とその直後は実質所得が増加し、その後減少に転じ、黒死病の時期に再び回復していることがわかる。
中世後期と同様に、ユスティニアヌス帝のペストが連続して発生し、長期間にわたって人口が減少した。エジプトでは、541年から744年までの32年間に10回、つまり6年に1回の割合で疫病が発生したと言われている。メソポタミア南部では、558年から843年までの38年間に14回、つまり7年半に1回の割合で発生した。収入データが不足しているシリアとパレスチナでは、さらに多くの証言がある。シェヴケット・パムクとマヤ・シャッツミラーは、8世紀から11世紀にかけて「イスラムの黄金時代」とされたのは、ペストによってもたらされた高賃金環境によるものであり、それは中世後期のヨーロッパの一部で黒死病が嗜好や消費に及ぼした影響に似ているという見方をしている。その兆候は、サラリーマン中産階級の間で肉と乳製品が広く消費されたことを示す資料の記述に現れている。その他の要因としては、都市化と同時に分業化が進み、狭いエリートを超えて、製造品や輸入食材、衣料品への需要が高まっていたことが挙げられる13。
しかし、繰り返しになるが、こうしたプロセスが所得格差や富の格差に及ぼした影響は推測でしかない。直接的な資料がない場合、農村労働者の実質賃金が爆発的に上昇したことは、所得格差の縮小とエリート層の富の浸食を示す信頼できる代用品として受け入れてもよいだろう。非熟練労働者の実質賃金が限りなく低く、資産格差の水準が非常に高かったと記録されているような環境では、より一般化された平準化効果は十分に妥当であると思われる。中世ヨーロッパにおける黒死病と同様に、ユスティニアヌス帝のペストもまた、資源の不平等がかなり確立された時期に到来したのである。エジプトの土地と税金の一覧表は、紀元前3世紀から6世紀にかけての土地所有の不平等をある程度明らかにしている。これらの記録に共通しているのは、地域間の富と土地を持たない人々の両方を省くことによって、全体的な土地の不平等を大幅に過小評価している可能性があるということである。都市部の地主のサンプルでは、土地ジニスは0.623から0.815、村人では0.431から0.532である。ノーム全体または主要な行政区域における土地所有の構造を再構築すると、少なくとも理論的には、全人口の約3分の1以上を占める必要のない土地所有者だけのジニが0.56となる。ノームの住民の半数が土地を持たない労働者か借地人であった(あるいは、土地を持たない労働者はやや少ないが、エリート層の一部が他のノームにも土地を所有していた)という、より緩やかな仮定に基づけば、全体の土地ジニは0.75近くになるであろう。もしそうであれば、この集中度は、土地改革直前の1950年のエジプトの0.611(全土地所有者)、0.752(全人口)という高い土地ジニに似ていることになる。このように、ペストによって資産格差が平準化される可能性はかなり大きかった14。
エジプトにおける古代末期と中世初期の所得格差はまったく不明であり、永遠に知ることができない。とはいえ、経済分化と都市化は同時に不平等を生み出す新たなメカニズムを生み出しただろうが、こうした動きはすべて、労働者の利益と、土地から労働へのシフトを考慮すれば、伝統的な富裕エリートの損失と論理的に一致している。最も重要なことは、集団主義的不在主義が労働者の交渉を抑圧していたマムルーク朝時代とは異なり、私有地所有が優勢で、適度に自由な労働市場が、資産評価と賃金を土地/労働比率の変化に敏感に反応させる環境を作り出したことである。このような状況下では、地価の下落が富の不平等を縮小させるのと同様に、労働供給が著しく減少すれば、全体的な所得の不平等が縮小しないはずがなかった。非熟練労働者の実質所得が著しく上昇したことは、この再構成の最も強力な要素であり、所得圧縮の最も良い代用指標である。賃金上昇を抑制しようとした国家の試みは、黒死病後の西ヨーロッパで最終的にそうなったように、完全に失敗したことを示している。同様に重要なのは、人口動態の回復に対応して賃金上昇が徐々に損なわれていったことである。「第一次黒死病」とでも呼ぶべき激しい衝撃は、一見するとかなりの福祉的利益をもたらすことができたが、それは人口動態の衝撃そのものとともに消え去ってしまった。この点で、2つのペスト大流行には多くの共通点があった。
「廃墟と森しか残らなかった」の: アントニン・ペスト
パンデミックの平準化効果に関する情報は、時代をさかのぼればさかのぼるほど必然的に少なくなる。最も有望なケースは、アントニン・ペストとして知られる以前の出来事である。この伝染病は、紀元165年にメソポタミア遠征中のローマ軍が最初に遭遇し、翌年にはローマ市内に到達、紀元168年には帝国の大部分に広がったようである。医学的な原因は不明だが、天然痘を支持する説が多い。空気感染する天然痘ウイルスの吸入によって人と人の間で感染し、高熱を伴う発疹が皮膚の膿疱に発展する。より重篤な出血性のものも知られている。アントナイン・ペストが本当に天然痘で処女人口を襲ったのであれば、感染者の20%から50%が死亡し、感染率は全人口の60%から80%に達する可能性がある。この出来事についてカスタマイズされた唯一の疫学モデルは、総死亡率を約25%と予測している。
関連するパピルス文書が保存されているおかげで、エジプトはこのパンデミックの範囲と結果に関する唯一の詳細な情報を提供している。これらの記録によると、ファユムのカラニス村では、140年代から170年代初頭にかけて納税者の数が3分の1から半分に減少した。ナイル・デルタのいくつかの小さな村では、損失はさらに大きく、紀元160年から170年の間に70%から90%以上に達した。このような人口減少の一因は、死よりもむしろ飛行にあったかもしれないが、飛行そのものが伝染病の発生と切り離すことはできない。ソクノパイオウ・ネソス村では、登録された男性244人のうち78人が、179年の1月と2月のわずか2カ月の間に死亡している16。
現物での地代は、中エジプトのいくつかの地区で記録されている。記録されているすべての地域で、年間地代は流行前と流行後のデータがある年の間に大幅に減少した。ファユムオアシスでは、211年から268年の間(19件が確認されている)の平均地代と中央値地代は、100年から165年の間(34件)よりも62%と53%低かった。オクシルヒンクス市の領土では、紀元103年から165年の間(12件)と紀元205年から262年の間(15件)の間に、平均値は29パーセント、中央値は25パーセント低下した。ヘルモポリスのデータでも、同様の減少が見られる17。
というのも、伝染病が発生してから一世代も経たないうちに、物価水準は全体的にほぼ倍増したからである。つまり、ペスト前後のデータを直接比較できるように調整する必要がある。この調整作業により、2世紀初頭から160年代までと190年代から260年代までの2つの期間において、土地の富から労働への価値の一貫したシフトを示唆する全体像が得られた。その間のギャップは、実際のペスト時代の資料の少なさを反映しており、それ自体がこの災害の深刻さを物語っている。この調査では、すべての数値は小麦価格を基準にしている。小麦価格は両期間とも100で標準化されているが、名目ベースでは約125%上昇した。そのため、名目ベースでそれ以下の上昇しかしなかった数値は、ペスト後では100に届かず、その逆もまた然りである(図11.3)18。
図11.3 ローマ時代エジプトにおける100~160年代と190~260年代の実質価格と賃料の変化
契約書に記録されている農村労働の価値は、雇用期間にもよるが、数%から5分の1近くまで上昇したのに対し、同じく労働を表し、特によく記録されているロバの実質価格は半分に上昇した。逆に、石油や、特にワインといった非必需食料品の価格は、小麦の価格に比べて下落し、労働者はより高い地位の商品を購入することができるようになった。石油やワインで換算すると、実質賃金は小麦の賃金よりもかなり上昇した。土地の価値は、土地の質を一定に保つことができないため、時系列で比較することは難しい。それでも、大まかな調査では、実質地代の下落がより確実に証明されているのと非常によく似た結果が得られた。ここで最も重要なことは、異なるデータセットの質にばらつきがあるにもかかわらず、すべての変数が、人口減少に伴うマルサス的制約の緩和のモデルと一致する方向に動いていることである。さらに、小麦の価格は、それに匹敵する外需がなかった地元のワインや石油の価格とは異なり、ローマ国家が課した大規模な輸出によって支えられていた可能性がある。それがなかった場合、地元の需要が唯一の決定要因であったなら、小麦の価格はおそらく賃金や他の主食に比べて大きく下落していただろう。このことは事態を複雑にし、実質価格変動の実際の規模を見えにくくしている。地価に関する証拠によれば、実質価格変動の規模はもっと大きかったようだ19。
伝染病の流行後、耕作形態がどのように変化したかを示すスナップショットがある。疫病が到来する数年前のCE158年と159年のファユムのテアデルフィア村では、約4,000エーカーから4,300エーカーの土地に穀物が蒔かれ、約350エーカーの土地にブドウの木や果樹が植えられていた。紀元216年までには、耕作地は2,500エーカー、以前の総面積の約60%に縮小したが、樹木栽培地は1,000エーカー以上、以前の3倍の面積に拡大した。このように、疫病が流行する前と比べると、全体的に使用される土地は減少したものの、より高価値の作物が栽培されるようになったのである。これは、黒死病の後、気候が許す限り多くのワインが生産され、果樹が広がり、地中海ではサトウキビが栽培されたパターンに似ている。人口が減少し、限界集落の耕作が放棄されたことで収量が増加したため、基本的な主食に対する需要は減少し、より多くの土地と収入が高級品に割り当てられるようになった。これは、大衆の生活水準が向上したことを示す強力なシグナルとみなすことができるだろう20。
エジプトで同様の証拠がないことを考慮すると、この過程をより体系的に記録することはできないが、農産物価格の相対的な動きとよく一致する。より一般的には、小作人や村民の移動の増加、農民の土地逃亡、都市への移住、都市化水準の全体的な上昇などの兆候を学者たちが発見しており、これらはすべて、黒死病の後と同様に、労働者の機会が増加し、都市が繁栄するというペスト後のシナリオと一致している。繰り返しになるが、疫病が不平等に及ぼした影響について、直接定量化できる情報はない。前述した中世末から近世初頭にかけてのイタリアにおけるパンデミックのような例外を除けば、前近代におけるパンデミックに関する一般的な情報が欠如していることを考えれば、これは驚くべきことではない。原則として、流行による死亡率の平準化効果は、実質所得の上昇と消費体制の改善から推測される必要があるが、今回はその両方が記録されている。その人口は1870年頃の状況に匹敵する700万人に達した可能性があり、都市化率は少なくとも4分の1に達したが、3分の1以上と主張する人もいる。ローマ世界の他の地域でも、2世紀にわたる平和によって促進された長期的な人口増加が、農耕経済の限界を試した可能性がある。このような環境では、平準化の可能性は大きかった。黒死病が発生した当時の西ヨーロッパの状況に似ているが、中世エジプト後期のマムルーク朝時代の状況とは異なっていた。労働力不足と土地の切り下げが、所得と富のより公平な分配に表れないようにする強力な制度的制約はなかった21。
「それでは何の役にも立たない」: 平準化装置としての飢饉?
平等化する力としての伝染病についての考察を終える前に、大量死をもたらすもうひとつの、まったく似て非なるものである飢饉の貢献について考える必要がある。もし、非常に多くの人々が食糧不足で死んだとしたら、疫病がそうであるように、生存者間の物質的資源の配分を変えることができるだろうか?答えははっきりしないが、肯定的なものにはなりそうもない。飢饉は通常、伝染病ほど致命的なものではない。私たちが知る限り、2年連続で基準死亡率の少なくとも2倍になるような食糧不足(「飢饉」の控えめな基準値)は歴史上まれであり、もっと深刻な事態は極めて稀である。この理由だけで、飢饉は一般的に、人口規模を調整する上でかなり控えめな役割を果たしてきた。また、報告されている飢饉の死者数は、証拠の質と逆相関する傾向があることも、このことを物語っている。さらに、死亡率の推定は、不可能ではないにせよ、住民が被災地を放棄したことによる移住や、飢饉に日常的に伴っている伝染病の影響から切り離すことは難しい。1877年から1878年にかけて中国北部を襲い、900万から1,300万人の命を奪ったと考えられている飢饉のような特別に破滅的な出来事でさえ、影響を受けた人口1億800万人の基準死亡率を3倍以上にすることはなかっただろう。この災害が不平等に影響を与えたかどうかはわからないし、1770年と1943年のベンガル飢饉についても同じことが言える。
この観察から、もうひとつ疑問点が浮かび上がってくる。これまで記録された中で最も劇的な飢饉のいくつかは、確かに大規模な平準化の時期に起こったが、それ自体がそのプロセスの原因というわけではない。物質的格差を抑圧したのは、1932年から 1933年にかけてのウクライナの飢饉ではなく、むしろ当時実施された強制的な集団化プログラムであった。1959年から1961年にかけての大躍進によって引き起こされた中国の壊滅的な飢饉は、1950年代半ばに頂点に達した再分配とその後の集団化によって、すでに大規模な平準化が確保された後に発生した23。
2つの歴史的な飢饉は、その規模と所得と富の分配を再編成する可能性から、より詳細な注目に値する。ひとつは1315年から1318年にかけての「大飢饉」である。この年、ヨーロッパ北西部では異常な寒さと雨天が続き、農作物の不作が広まり、家畜を壊滅させる伝染病が発生した。前例のない規模の大量死が起こったのである。しかし、この災難がペストと同じような価格と労働力の変動を引き起こしたのだろうか?そうではない。労働者の賃金は少し上がったが、消費者物価は町でも田舎でももっと急速に上昇した。生産高の減少が物価の上昇を相殺したため、地主は圧力を受けることになったが、彼らはしばしば生き残るのに必死だった平民よりもはるかにうまく嵐を乗り切った24。
データは乏しいが、入手可能なわずかな情報からは、大幅な平準化は指摘できない。私がすでに使用したイタリアの富の分配に関する記録は、14世紀前半の変化を明らかにするには少し遅すぎるか、解像度が低すぎる。ロンドンとフィレンツェにおける、都市部の熟練賃金と非熟練賃金を物価に関連づける厚生比率は、1300年あるいは1320年から1340年の間に改善を示していない。また、イングランドの農村部の実質賃金も、1300年から1349年までほぼ横ばいで推移し、黒死病の後にのみ恒常的な上昇を経験した。この点で、2つの災害の結果の対比は際立っている。集団死亡は数年間に限られ、ペストの最初の波のときよりもかなり控えめであったようだ。大量死は数年に限られ、ペストの最初の波のときよりもかなり控えめであったようだ。既存の不完全雇用に緩衝され、消耗は長期化することもなく、連続ペストの経済的影響を予期するほど深刻でもなかった25。
1845年から1848年にかけてのアイルランドのジャガイモ飢饉が2番目の候補である。植物の)伝染病であると同時に食糧危機でもあったこの飢饉は、1846年と1848年に蔓延したフィトフトラ・インフェスタンスという水カビによって引き起こされた。100万人ものアイルランド人が命を落とした。移民や出生率の低下と相まって、この出来事は国勢調査人口を1841年の820万人から10年後の680万人まで減少させた。農業労働者の数はさらに急速に減少し、1845年の120万人から1851年には90万人にまで減少した。一見したところ、この人口縮小は、1347年から1350年にかけての黒死病の最初の波がもたらしたものと酷似している。そして、その波がそれ自体では永続的な変化をもたらすほどの破壊的なものではなかったかもしれないように、アイルランド飢饉の死者数は、全体的な生活環境の改善という点では「ほとんど何の役にも立たない」と、同時代のイギリス人観察者に言われたことで悪名高い。1850年から1914年の間に400万人が島を去り、最終的に人口は1840年代初頭のピークからほぼ半減した。しかし、ペストとは異なり、出国者は年齢に敏感で、主に10代後半から20代前半に集中していた。さらに、やはりペストとは異なり、ジャガイモ疫病は収量を減少させることで資本ストックに損害を与えた。このことは、機能的類推の価値を制限している26。
ある意味では、飢饉とそれに続く移住、そして少子化による人口動態の大幅な悪化は、大流行(パンデミック)に匹敵する経済的利益をもたらした。それまでの傾向とは異なり、飢饉後の実質賃金と生活水準は着実に上昇した。賃金が低かった地域では出国率が高くなり、地域間の不平等が縮小したはずである。同時に、最貧困層は、旅費に余裕のある人々よりも出国率が低かった。また、全体的な生活環境の改善が、資産や所得の分配における平等性の向上を伴っていたかどうかは不明である。脱走や立ち退きによって、飢饉の年には、1エーカー以下のごく小規模な土地所有者が激減した。その後60年間、分配の変化は緩やかなものにとどまったが、そのほとんどは下位層で起こり、小区画の割合が徐々に回復していった。1エーカーから15エーカーの所有地は、大規模な所有地が増加する一方で減少し、全体として逆進的な傾向を示した。ジャガイモ飢饉のような強力な人口統計学的ショックと、それに伴う持続的な流出があったとしても、黒死病で観察されたような規模の平準化は起こらなかったようだ。不平等を平らにすることに関しては、疫病が最高であった27。
「人が住む世界全体が変わった」の: 平準化要因としてのパンデミックと我々の知識の限界
不平等の平準化におけるパンデミックの役割に関する現在の知識の多くは、かなり新しいものである。黒死病が社会経済的な影響を及ぼしたことは古くからよく知られているが、その他の人口統計学的災害が所得や富に及ぼした影響について調べられるようになったのは、ごく最近のことである。そのため、アントニヌス帝やユスティニアヌス帝の災いに伴う物価変動に関するエジプトの証拠が分析され始めたのは21世紀に入ってからであり、近世メキシコの実質賃金や北イタリアの富の不平等の変化に関する最初の研究は2010年代に登場した。このような継続的な拡大は、さらなる資料が存在し、収集と解釈を待っているという期待を抱かせる。黒死病の時代とその余波のアーカイブは、最も有望な候補と思われる。また、アントニン・ペストと黒死病の両方でペストの発生が証明されている中国における大疫病の平準化効果に関する研究も必要である。
しかし、現存する情報だけでは、実質所得と不平等の問題を解明するには不十分な場合もある。その好例が、紀元250年代から260年代にかけてローマ帝国を襲った大流行、キプリアヌスのペストである。このペストによる人口動態の悪化は劇的なものであった。ローマ帝国第二の都市アレクサンドリアの司教ディオニュシオスは、「このような連続的な疫病……このような多様で広大な破壊……」と記している。アレクサンドリアの人口を大幅に減少させ、14歳から80歳の住民は、疫病が流行する前の40歳から70歳の人口よりも少なくなった。このカウントは、公的なトウモロコシ配給のための登録から得られたと言われているため、全くの架空である必要はなく、このカウントが意味する死亡の規模は驚異的としか言いようがない。モデル生命表によれば、報告されたシフトは、都市人口の60%以上の喪失に相当する。所得や富の不平等はおろか、実質賃金に関する現代のデータも入手できない。それでも、紀元250年代にエジプトの2つの農園で働く農村労働者の名目賃金が突然大きく跳ね上がったのは、この伝染病が引き金となった労働力不足を反映しているのかもしれない28。
キリスト教以前の時代に入ると、光はさらに暗くなる。人口減少によって実質賃金が上昇したことを示す現存する最古の証拠は、前6世紀のバビロニアにあると考えられる。前570年代、ネブカドネザル王の治世にバビロニア南部で、バビロンの王宮を建設していた労働者たちは、450リットルから540リットルの大麦、つまり月におよそ銀5シェケルを受け取っていた。前540年代のナボニドゥス治世のバビロニア南部では、1日9.6リットルから14.4リットル、中央値12リットルの小麦賃金が記録されている。これらの値はすべて、前近代の標準であったと思われる1日あたり3.5リットルから6.5リットルの中核的な範囲をはるかに上回っており、また、労働者が7.3リットル相当かそれ以下の量しか受け取っていなかった、一世代後の前505年頃のダレイオス1世の時代に報告された小麦賃金よりも高い。後のバビロンの実質賃金はさらに低く、前1世紀初頭には4.8リットルにまで落ち込んでいる29。
この一時的な新バビロニアの高騰は、現在のところ説明されていない。楽観的な観察者であれば、市場志向の農業における生産性の向上、高度な労働力の専門化、貨幣化の進展など、この時代に証明されているすべての要因による一時的な勃興を想像したくなるかもしれない。しかし、前7世紀末近くのアッシリア帝国の血なまぐさい崩壊の際に被った人口的損失から得た利益が薄れるという選択肢もある。後者は、バビロニアのはるか南方でペストによる大規模な人口減少を刺激した可能性がある。しかし、それはあくまで推測に過ぎず、前6世紀後半の実質賃金の急激な悪化は、純粋に人口動態の回復という観点だけでは説明しにくいように思われる。
しかし、このようなわれわれの知見に根強いギャップがあるにもかかわらず、かつては黒死病が主な原因であった、あるいは黒死病だけが原因であったペストによる平準化プロセスが、現在では世界史の中で繰り返し起こってきた現象であったことを示すことができる。本章で提示されたすべての知見は、制度的枠組みによって人口が強制的に平準化されるというマルサス的シナリオを支持することに収斂する。これらの平準化のエピソードに共通するのは、いずれも数千万人規模の人命が失われたことである。人口動態の回復がほとんど必ずこのような損失を吸収したためである。パンデミックはこのように、所得と富の不平等を圧縮するメカニズムとして機能した。この二つの点で、パンデミックは、これまでに検討された他の効果的な平準化過程、すなわち、大量動員戦争による犠牲、変革革命による残虐行為、国家崩壊による荒廃と、いいとこ取りをしている。これらの出来事はすべて、莫大な流血と人間的苦痛を与えることによって、物質的不平等を平らにした。私たちの四頭立ての騎馬民族はこれで完成した。
「神は高かったものを低くされた」: 30年戦争のアウグスブルク
四騎士の四部構成:歴史上の主要な平定者をきれいに分けることは、議論を構成するのに役立ったが、必然的に、過去の現実の生活のより厄介な状況を正当に評価することはできない。異なる平準化メカニズムが並行して作動し、相互作用する中で、2つ以上の騎馬民族が力を合わせることがしばしばあった。17世紀の南ドイツの都市アウクスブルクの経験は、さまざまな要因(この場合は戦争とペスト)が複合的に影響し合うことを見事に示している30。
アウクスブルクは近世南ドイツ経済の中心地のひとつであり、中世後期の黒死病からの復興の原動力となった。1500年に2万人だった人口が1600年には4万8000人に増え、当時ドイツ第2の都市となった。経済発展と都市化は、富の拡大と偏在が進むにつれて、資源の不平等を助長した。都市部の全世帯の定期的な評価に基づく富裕税の詳細な登録は、実際の資産とその分配のかなり正確な代用品として役立っている。いくつかの交絡変数を考慮する必要がある。課税対象財産を持たないと記録された居住者であっても、個人的な財産を所有していたはずであり、それらを含めることで不平等の測定値がいくらか減少する可能性がある。同時に、全世帯の最初の現金500グルデンには一般的な免税が適用された。この金額は、0.5%の課税で2.5グルデンの納税額に相当し、1618年に所得分布の上位5分の1以下の人々が支払った額よりも多かった。宝石や銀製品も同様に非課税であった。これらの例外はすべて富裕層に有利であり、非課税の貧困層のわずかな持ち物の省略を補って余りあるものであったに違いない。全体として、観察された傾向はかなり代表的なものであるように思われる。このデータは、時間の経過に伴う顕著な変化を記録している。資本の蓄積と集中のおかげで、富裕税における不平等のジニ係数は1498年の0.66から1604年には0.89に上昇した(図11.4)31。
1618年の経済階層化は激しく、富裕層の10%の世帯が富裕税の91.9%を負担し、ジニ係数は0.933であった。この特権階級でさえ階層化が激しく、パトリシアンと最も裕福な商人からなる上位1パーセントが、富裕税収入のほぼ半分を占めていた。登録されている織物職人や建設労働者の3分の2はまったく税金を納めておらず、日雇い労働者の89パーセントも税金を納めていなかった。アウクスブルク社会の底辺には、約6,000人の貧困層があり、その中には約1,000人の浮浪乞食、1,700人のほとんど施しで生活する人々、さらに3,500人の一部で生活する人々が含まれていた。富裕層や裕福層は人口のわずか2%、中流層が3分の1、貧困層が3分の2(しかも、その少なくとも半数はギリギリの生活をしている)であり、経済成長に支えられた中産階級が台頭する兆しはない。その代わりに、前章で調査した他の都市人口の多くと同様に、実質賃金の低下が見られる32。
図11.4アウクスブルクにおける富の不平等:納税者数、平均納税額、納税額のジニ係数(1498-1702年
このような状況は、ドイツ史上前例のない壊滅的な大火災を引き起こした、複雑で長期にわたる一連の軍事作戦である三十年戦争が始まった直後のことであった。住宅や資本が広範囲にわたって破壊され、莫大な人命が失われた。敵対行為は、ペストの再発や、比較的新しい病気であるチフスの蔓延と重なり、死亡率をさらに高めた。戦争の初期段階において、アウクスブルク市は直接的な標的とはならず、間接的な影響を受けただけであった。戦費を賄うための貨幣の減価は、1620年代から1630年代にかけて物価上昇を引き起こし、当初は最大で一桁の差があった。低所得者層が最も被害を受けたと思われるが、その一方で、主に苦境に陥った中流階級の所有者から不動産を買い取った裕福な商人には純益がもたらされた。1625年と1618年の納税額を比較すると、以前よりもさらに多くの商人が納税するようになり、その総額は4分の3に増加していた。「オールドマネー」の代表であるパトリシアンの間では、勝ち組と負け組が均衡していた。商人資本の機敏な所有者は、戦争に関連した通貨の不安定化を利用するのに最も適した立場にあった。貧乏人はより貧しくなったが、より裕福な中流階級の住民の間では、より多くの利益が記録されている。勝者には、貴金属や食料といった希少品を直接入手できたおかげで、金細工職人や宿屋経営者などが含まれる33。
しかし、そのような利益は、アウクスブルクを疫病と戦争が襲うと、たちまち消え去った。最初の大打撃はペストで、アムステルダムからドイツを横断し、イタリアにまで押し寄せた大波の一部だった。戦争は1627年10月、寄宿していた兵士を介してこの街に疫病を持ち込むことになった。ペストはその年の残りと1628年にかけて街を襲い、40,000人から50,000人の住民のうち約9,000人が死亡した。1625年から1635年にかけての生活保護費の空間分布とアウクスブルクの人口減少の空間分布は密接に一致しており、このことはペストが貧しい人々を不当に殺したことを示唆している。1632年から1633年にかけて発生した二度目のペストも同様の影響を及ぼした。この不均衡は、都市全体が平準化される一因となった。その結果、流動性も低下した。1629年、市は債権者に「ヘアカット」を課し、前年に借り入れたローンの高利払いを減らした。訴訟を起こそうとする債権者は、そのような訴訟が裁かれる間、利息や元本の支払いを停止することで抑止した34。
スウェーデン軍は1632年4月に到着した。1632年4月、スウェーデン軍が到着した。平和的な占領であったにもかかわらず、高い占領費用が住民の負担となった。約2,000人の軍隊が市内に宿営し、大規模な要塞化工事の費用を支払わなければならなかった。緩やかな累進課税を含む特別税が導入された。市は破産に直面し、利子の支払いは完全に停止した。資本所有者が主な犠牲者となった。占領中、1632年にペストが再発し、カトリック勢力による封鎖が飢餓を引き起こしたため、死亡率が再び急上昇した35。
1634年9月のネルトリンゲンの戦いでスウェーデンが敗北すると、状況はさらに悪化した。1634年9月のネルトリンゲンの戦いでスウェーデンが敗北すると、状況はさらに悪化した。帝国軍は時間をかけずにアウクスブルクを包囲下に置いた。包囲は1635年3月まで半年近く続き、多大な苦難をもたらした。年代記記者のヤコブ・ワーグナーは、動物の皮や犬猫、人間の死体を食べるしかなかった人々のことを語っている。後者は単なる決まり文句ではなかった。墓掘り人たちの報告によれば、乳房やその他の体の一部から肉がなくなっており、また、路上に横たわっていた死んだ馬の骨をかじっている市民も目撃されている。死者の悪臭が街を覆っていた。一方、スウェーデンの守備隊は地元の統治評議会に容赦ない圧力をかけ、評議会は莫大な臨時の寄付金を集めざるを得なくなった。このような要求を満たすことができるのは富裕層だけであった36。
1635年3月、守備隊は降伏条件を受け入れ、隠れて出発することを許可されたが、市は帝国軍の受け入れと賠償金の支払いを余儀なくされた。1635年3月、守備隊は降伏条件を受諾した。この条件は、守備隊の撤退を認めるものであったが、帝国軍の受け入れと賠償金の支払いを強いるものであった。同じ年に行われた国勢調査が、この状況を明らかにしている。所有不動産の分布はほとんど変化していなかったが、住宅はその価値を大きく失っていた。家賃は下落し、売りに出されている家屋の状態は悪く、投機家候補は流動資金がないために割安な資産を手に入れることができなかったからだ。4年後、ヤコブ・ワグナーは、住宅価格は入居前の3分の1にまで下落し、職人の作業場は半分空っぽになっていると主張した。街のエリートたちはその負担に不満を漏らした。1636年、ニュルンベルクのハプスブルク皇帝に派遣された代表団は、アウクスブルクに残る1600のプロテスタント家族が、宿舎やその他の費用に莫大な出費を強いられ、非常に困窮していると訴えた。守備隊が撤退した翌年の1840年には、別の公使館が、アウクスブルクのプロテスタントは過去5年間に8倍の税金を支払わなければならず、100万グルデン以上の損失を被ったと報告している。
1646年までのペストと戦争の累積的な影響のバランスシートを読むと、厳しいものがある。アウクスブルクの人口は1616年から1646年にかけて50%から60%減少したが、これはミュンヘン、ニュルンベルク、マインツといった他の大きな被害を受けた都市と同様であった。しかし、社会経済的な構成は、その両端でさらに根本的に変化した(表11.1)。貧しい住民の数が不均衡に減少した。織物職人の世帯の5分の4が消滅したが、これは単に死亡や移住のためだけでなく、多くの人が職業を諦めざるを得なかったためでもあった。彼らのほとんどが貧困であったため、この損失は、当初は都市住民のかなりの割合を占めていた貧困層の極端な減少とともに、貧困にあえぐ人々の割合を大幅に減少させ、平準化を誘発した38。
表11.1 アウクスブルクにおける課税世帯の階層別シェアと世帯数(1618年と1646年)
Kr.:クロイツァー fl.:グルデン
都市社会のトップ層にも大きな変化があった。かつての超富裕世帯は今や単なる富裕世帯となり、単なる富裕世帯の数は6分の5に減少した。ゆとり層や中程度の裕福層の数は半減したが、(かなり減少した)総人口に占める割合はほぼ横ばいだった。貧困層や困窮層の割合が減少しても、最低限度の生活以上の所得層に属する人々の割合は膨れ上がった。全体的な平準化効果は大きかった。
このような変化は、課税対象となる富の減少を伴っており、これは人口規模の減少よりもさらに深刻であった。富裕層別の税収の内訳を見ると、この急激な落ち込みは、ほぼ完全に上位10%の富裕層の損失によって引き起こされたことがわかる。1618年には上位10%の富裕層が富裕税の91.9%を負担していたのに対し、1646年には84.55%となっている。絶対額で見ると、この層の支払額は52,732グルデンから11,650グルデンに減少しており、これは富裕税収入減少全体の94パーセント以上に相当する。貴族階級に代表される「オールドマネー」が最も大きな打撃を受け、その平均納税額はほぼ5分の4に減少した39。
1646年には、フランス軍とスウェーデン軍による2度目の包囲が行われたが、失敗に終わり、それでも年間死亡率は2倍になった。この年、地元の商人たちによって作成された追悼文は、襲撃、略奪、関税の新設や引き上げによる商業の衰退を嘆いていた。これらの要因が重なると、投資や信用の機会が減少し、資本家の利益が損なわれると言われた。戦争の最終年である1648年には、再び包囲の危機が訪れ、最終的に和平交渉が成立するまで、2400人の兵士が街に駐留した40。
生き残った都市は、かつての面影はなかった。戦争前の人口の半分以下にまで減少したこの都市では、何千人もの最貧困層が疫病と飢餓に見舞われ、その一方で首都を所有するエリート層は血を流し尽くされた。非常に大きな財産は姿を消し、それ以下の財産はその数を大幅に減らしていた。不動産は価値を失い、ローンは無価値となり、安全な投資機会は減少した。結局、深刻な人口減少は生き残った人々の労働需要を増大させ、労働者階級の境遇は、彼らの多くがそれまで苦しんでいた絶望的な貧困以上に改善された。戦争が終わるころには、課税対象の富のジニ係数は0.9以上から約0.75に低下し、依然として高く、実際、黒死病の後よりもはるかに高かったが、以前ほど極端ではなかった。この平準化効果は、手痛い高値で買われ、17世紀の残りの期間持続した41。
*
アウクスブルクが、黒死病以来の疫病が蔓延していた時期に、西ヨーロッパで起こった最も恐ろしい戦争のひとつで経験したことは、並大抵のことではないと思われるかもしれない。しかし、所得と富の不平等が平坦化する原動力は、ほとんど珍しいものではなかった。富裕層を奪い、労働人口を減少させ、生き残った人々が明らかに裕福になる程度にするには、大規模な暴力と人的被害が必要だった。社会スペクトルの上部と下部の両方において、さまざまな形の消耗が、所得と富の分配を圧縮することに収斂した。青銅器時代のギリシャから第二次世界大戦中の日本まで、黒死病のイギリスや大西洋交換の渦中にあったメキシコから毛沢東の人民共和国まで、本書とこれまでの3部作で見てきたように、同じような過程が非常に異なる環境と多種多様な理由で起こった。記録された人類史の大部分と複数の大陸にまたがっているが、これらの事例に共通しているのは、資源の不平等を大幅に縮小するためには、暴力的な災害が必要だったということである。このことは、2つの差し迫った問題を提起している: 不平等を平準化する方法は他になかったのだろうか?そして今、それはあるのだろうか?今こそ、四騎士に代わる、より血なまぐさい代替手段を探る時なのである。
第6部 代替案
第12章 改革、後退、そして代表
「万人の父にして万人の王?」 平和的平準化を求めて
ここまでの章はすべて、かなり憂鬱な読み物であった。貧富の差の大幅な縮小が、人間の苦しみという高い代償を払って実現されたことを、私たちは何度も目にしてきた。しかし、すべての暴力がこの目的を果たすわけではない。ほとんどの戦争は、どちらの側につくかによって、不平等を拡大することもあれば縮小することもあった。内戦も同様に一貫性のない結果をもたらしたが、ほとんどの場合、不平等は縮小するどころか拡大する傾向にあった。例外的な暴力が例外的な結果をもたらしたことから、軍事的な大量動員は最も有望なメカニズムであることが判明した。しかし、人類史上最悪の戦争である2つの世界大戦ではおおむねそうであったが、それ以前の時代では、この現象とその平等化の結果はまれであった。また、最も激しいタイプの戦争が所得格差や貧富の格差を縮小させる可能性が最も高いとすれば、最も激しい革命はなおさらそうであった。これとは対照的に、フランス革命のような野心的でない革命は、より弱い効果をもたらし、歴史上のほとんどの民衆不安は、まったく平等化できなかった。
国家の崩壊は、より確実な平準化の手段として機能し、富と権力の階層が一掃されるにつれて格差が破壊された。大衆動員戦争や変革的革命と同様、平等化には大きな人間の不幸と荒廃が伴った。最大規模のパンデミックは、不平等を徹底的に平定したが、不平等に対する救済策が病気よりも劇的に悪いものであったとは考えにくい。かつては、平定の規模は暴力の規模の関数であった。これは鉄則ではないが、例えば、すべての共産主義革命が特に暴力的だったわけではないし、すべての大衆戦が平準化したわけでもない。これは間違いなく、非常に暗い結論である。しかし、これが唯一の方法だったのだろうか?デモクリトスによれば、戦争が「万物の父にして万物の王」であるように、暴力は常に平定をもたらすものだったのだろうか。同じような結果をもたらす平和的な代替案はあるのだろうか?本章と次章では、土地改革、経済危機、民主化、経済開発など、さまざまな可能性を検討する。最後に、大規模な暴力的ショックがなければ、20世紀の間に不平等はどのように発展しただろうか、という反事実的な選択肢を検討する1。
「すべてを根こそぎにする大嵐になるまで」?土地改革
土地改革は、過去のほとんどの時代において、ほとんどの人々が土地に住み、耕作地が一般的に私有財産の大部分を占めていたという単純な理由から、誇るに値するものである。300年前のフランスでは、土地は全資本の3分の2を占めていた。これは、何千年とは言わないまでも、世界中の何百年という歴史の典型であったろう。このように、土地の分配は不平等の重要な決定要因であった。土地所有権を貧困層に有利なものに変えようとする試みは、記録された歴史を通じて行われてきた。理論的には、社会が平和的に土地の所有権を調整し、貧しい人々に利益をもたらすことを妨げるものは何もない。しかし実際には、事態は通常とは異なっていた。後述するように、土地改革が成功するかどうかは、ほとんど常に暴力の行使や脅しに依存していたのである2。
最も顕著な例は、すでに第7章で述べたとおりである。ソビエト革命や中国革命の暴力的な性質や水平化する力には疑問の余地はないが、キューバ革命のように、暴力が広く表現されるよりもむしろ潜在的なものであった場合もある。1970年代から1980年代にかけてのカンボジア、エチオピア、ニカラグアは、記録に残っている最近の例である。1970年代から1980年代にかけてのカンボジア、エチオピア、ニカラグアがその代表例である。それ以降、強制的な土地再分配が行われた主な事例はジンバブエだけである。ジンバブエでは、1980年代から1990年代にかけて土地改革が穏やかなペースで進み、農地の約10分の1が白人農家から7万世帯の貧しい黒人農家に移転された。過激化は1997年に始まり、解放戦争の退役軍人が白人の大地主の所有地を占拠する「土地侵略」を行った。これを受けて、さらに8分の1の農地が強制買収の対象となった。現在では、1980年当時6,000戸の白人農家が所有していた土地の90%が、25万世帯に与えられている。全土地に占める白人所有の大規模農場の割合は、39%から0.4%に減少した。これは、少数のエリートから貧困世帯への巨額の富の移転を意味する。1997年以降の、より積極的な土地改革の第2段階は、退役軍人の暴力的な扇動に負うところが大きかった。ムガベ政府が福祉や財政支援の約束を守らなかったため、退役軍人と彼らが動員を支援した人々は、白人入植者だけでなく当局にも異議を唱え、ムガベに圧力をかけて白人所有の商業農場の強制接収に同意させた。当初はこの運動を抑制しようと試みたが 2000年、ムガベはこのような農場を標的にし、占拠者を保護する措置を制定することで、この運動に加わった。ここには、20世紀初頭のメキシコ革命の反響が見られる。地元の暴力は、土地再分配、ひいては富の平等化の範囲を拡大するための重要な手段だった3。
歴史上の多くの土地改革は戦争の結果であった。第4章では、特に極端な事例として、アメリカ占領下の日本における土地改革を取り上げた。この改革は、事実上補償のない没収と、全国的な土地所有権の大規模な再編成を伴うものであった。これは、第二次世界大戦後の時代には見られなかった斬新な現象である。それまで、外国の占領者が再分配的な政策を推進したことはなかった。中欧におけるソビエトの支配は、征服軍による平等化の主要な現れであった。歴史的には、戦争は他の方法で土地改革のきっかけを与えてきた。確立されたメカニズムのひとつは、戦争の脅威に対応するための改革であり、国の軍事力を強化する手段として用いられた。
西暦645年以降に日本で行われた大化の改新は、このプロセスの初期の例と解釈されることもある。中国近隣の隋や唐の支配者が行った土地均等化計画に倣い、農地は測量され、等しい大きさの区画からなる碁盤の目状に再編成された。割り当てられた圃場は、表向きは公有地だが、所有権はないことになっていた。よくあることだが、この野心的なプログラムが実際にどの程度広く、忠実に実施されたかは定かではない。ここで重要なのは、内戦と外戦の脅威のもとで進行中の改革の中で実施されたということである。660年代の朝鮮半島への関与は、日本を唐の中国と対立させ、隣の大国による軍事侵攻の懸念を高めた。軍事化は続き、672年と673年の壬申の乱によって中断された。689年には史上初の国勢調査が行われ、すべての成人男子を対象とした国民皆兵制が導入された。戦争の脅威は、地方のエリートを抑圧し、軍事動員に備える一般民衆の団結力を養うことを目的とした国内改革のきっかけとなったようだ4。
我々は、ロシア皇帝の方が安全な立場にいる。1853年から1856年にかけてのクリミア戦争での敗北から1カ月も経たないうちに、皇帝アレクサンドル2世は「すべての人に等しく公正な法律」を約束した。改革には5年以内の農奴解放が含まれ、これは国民皆兵制によってより大規模な軍隊を創設するための措置だった。農民は耕作地を所有できるようになった。しかし、農民は土地価値の75%または80%に相当する償還金を支払う義務を負っていたため、平等化は妨げられた。資金調達は国債によって行われ、農民は49年間にわたって6%の利子で返済しなければならなかった。土地を手にする者もいれば、そうでない者もおり、貧しい農民はプロレタリア化し、裕福な世帯はそれ以外の世帯から引き離されていった。1905年の対日戦争敗戦後の動乱は、再び土地改革を引き起こした。当時、農民はまだ全土地の3.5%しか所有していなかった。農民たちはさらなる贖罪の支払いを拒否し、ストライキを起こし、領地を襲撃し、1000軒以上の荘園を略奪した。この暴力に対し、未払いの贖罪金はすべて取り消され、農民は土地を世襲財産として主張する権利を与えられた。その結果、第一次世界大戦までには、全土地の半分以上が農民の所有となった。それでも、少数の大農地と多数の小農地との間の富の格差が根強く残っていたため、全体的な土地の不平等が高まり、労働力は以前よりも不平等に分配されるようになった5。
これは孤立した事例ではない。不平等を悪化させる結果となった戦争主導の土地改革には、長い血統がある。ナポレオン戦争は多くの国で土地改革を引き起こしたが、長期的には好ましくない結果を招いた。プロイセンでは、1806年の敗戦のショックが翌年の農奴制廃止を促し、借地人は貴族や王室から土地を購入することが許されたが、価格は高騰し、大土地所有者(ユンカー)は土地に対する支配力を強め、1945年に共産主義者がすべての大土地を無償で収用するまで支配的地位を保持した。スペインでもナポレオン戦争が自由化を促した。1812年に柵が廃止され、公有地が売りに出されたが、その後の内戦によって、ポルトガルのように土地所有権の集中がますます進んだ。オーストリアでは、1848年の革命が政府を説得し、農奴を封建的義務から解放した。譲渡された土地の償還価格は年収の20倍に設定され、農民、国家、地主(地主は土地資産の3分の1を没収された)の間で均等に分配された。
戦争が動機となった他の改革の試みはより急進的だったが、短命に終わった。1901年に設立されたブルガリア農民民族同盟は、降伏、政治的混乱、領土喪失を招いた第一次世界大戦の敗戦という大きな衝撃が1920年に政権を握るまで、農村大衆に浸透することができなかった。その土地改革プログラムは野心的なものだった。所有権の上限は30ヘクタールとし、過剰所有地はスライド制の強制売却の対象とし(補償水準は規模が大きくなるにつれて縮小)、土地所有者や小農に譲渡した。これはすぐに体制派の激しい反発を引き起こし、政府転覆につながった。第二次世界大戦中と戦後のグアテマラでは、戦争の影響がより間接的な形で現れた。戦時中、大土地所有者の抑圧的な支配は、ドイツのコーヒー市場の喪失と、アメリカの圧力で行われたドイツ所有のコーヒー農園の国有化によって弱体化した。大規模農地の土地は再分配され、所有者は、彼らが申告していた一般的に大幅に過小評価された税額に応じた価格の国債で補償された。1954年までには、平和的かつ秩序だったプロセスで、農村人口の40%が土地を手に入れた。しかし、その年のクーデターにより軍事政権が樹立され、土地改革は無効となり、弾圧が再開された。その後の長い内戦で15万人が死亡した。1990年代には、3%の所有者が全土地の3分の2を所有するようになり、農村人口の90%はほとんど、あるいはまったく土地を持たないようになった。暴力はこのプロセスにおいて、さまざまな形で登場した。まず遠隔的に変化を促し、次いで暴力的介入や抑圧にはかなわないことが証明された平和的政府のもとで、暴力が不在となった7。
また、内外の潜在的暴力に対する懸念が土地改革を促したケースもある。反共主義は特に強力な動機付けとなった。第二次世界大戦末期、韓国の土地格差は大きく、農村世帯の3%未満が全土地の3分の2を所有していたのに対し、58%は土地を所有していなかった。その後の土地改革は、1946年の時点で自国の土地を収用していた北朝鮮の共産主義者が、南部の農民を動員するのではないかという懸念によって推進された。アメリカの支援と、1948年の第1回選挙を争ったすべての政党による土地改革へのコミットメントによって、大規模な土地収用と再分配が行われた。まず、日本の植民地保有地がすべて接収された。1950年代初頭には、私有地は良質の耕作地3ヘクタールを上限とし、余剰地は最小限の補償金(年賃料の1.5倍)で接収または売却することで農民に譲渡され、他人の土地を耕作し続ける農民の賃料は低水準に固定された。全土地の半分強の土地が手に渡った。地主が収入の80%を失ったのに対し、農村の下位80%の世帯は20%から30%の収入を得た。1956年までには、地主のうち最も裕福な6パーセントが全土地の18パーセントを所有するにすぎず、借地人の割合は49パーセントから7パーセントに減少した。1945年には0.72または0.73と高かった土地所有のジニ係数は、1960年代には0.30台にまで低下した。ほとんどの工業用地や商業用地が破壊され、ハイパーインフレによって補償金が無価値になったため、土地エリートは完全に姿を消し、高度に平等主義的な社会が出現した。この場合、戦争や革命に対する不安は、実際の大量動員戦争に追い越され、第5章で遭遇したような平等化の結果をもたらした8。
革命への不安と実際の戦争は、南ベトナムでも同様に収束した。南ベトナムは1970年、米国の働きかけで土地改革を実施し、借地はすべて耕作者に引き渡され、耕作者は一定額を無償で受け取り、所有者には補償金が支払われた。この改革は3年以内に実施され、その後借地率は劇的に低下した。たとえばメコンデルタでは60%から15%に低下した。対照的に台湾では、戦争そのものよりも戦争に対する一般的な懸念が平準化の主な要因となった。戦勝した共産党によって大陸から追い出された国民党政府は、1949年、地元の支持を固める手段として土地改革に乗り出した。アメリカの支持者も同様に、共産主義に対抗するための再分配を求めた。指導部は地元の地主に対して何の義務も負わず、敗因を本土での土地改革の失敗とする者も多かった。韓国と同様、個々の土地に上限が設けられ、賃料が引き下げられた。公有地が借地人に売却された後、1953年、地主は市場価格を大幅に下回る補償金と引き換えに余剰地を売却せざるを得なくなった。その結果、農家所得は上昇し、借地人の割合は1950年の38%から10年後には15%に減少し、土地所有のジニ係数は同じ期間に約0.6から0.39~0.46に低下した。所得全体のジニ係数は、1953年の0.57から1964年には0.33へと劇的に低下した9。
1921年にルーマニアで行われた土地改革は、こうした封じ込め戦略の初期の例であったかもしれない。収用された土地を手にした貧しい農民や小作農に恩恵をもたらしたこの改革は、隣国ソ連から革命が広がるのではないかという懸念が動機となったと考えられることもある。共産主義者の扇動に対する恐怖も、ラテンアメリカ諸国の改革に拍車をかけた。1960年、カストロによるキューバ支配に対抗して米国が設立した「平和のための同盟」は、土地改革を推進し、そのための助言と資金援助を行った。チリはその候補であった。1964年に選挙で敗北することを懸念した右派と中道派の連立政権が、外国からの支援を受けてより広範な土地改革を実施した。1970年までに多くの広大な土地が収用されたが、払い戻しは緩やかだった。アジェンデ左派政権は、1973年のクーデターで崩壊するまで、さらに前進した。このクーデターによって土地収用は中断されたものの、わずか10年前には10分の1であった土地の3分の1が小農によって所有されるようになった10。
1960年代を通じて、ペルーでは高い不平等と農村部での暴力が続いていたが、1968年の軍事クーデターの指導者たちは、ペルーの伝統的な寡頭政治に反対し、米国の対反乱原則の訓練を受け、全面的な内戦を食い止める手段として土地改革を選択した。数年のうちに、ほとんどの大農地が収用され、全農地の3分の1が譲渡され、農業従事者の5分の1が恩恵を受けた。大土地所有者の力を断ち切ることは、貧困層よりもむしろ、主に軍人と中堅農民に利益をもたらした。エクアドル、コロンビア、パナマ、ドミニカ共和国でも、同様の動機による措置がとられた。エルサルバドルでは、ゲリラ戦が勃発した1年後の1980年に、アメリカの奨励と財政支援を受けて、政権が土地改革を開始した11。
その10年前、エジプトでも革命への恐怖が土地改革を促した。その10年前には、革命への懸念もエジプトの土地改革を後押しした。それまで土地は(極端ではなかったものの)かなり偏在しており、上位1%の地主が5分の1を、最富裕層の7%が3分の2を所有していた。借地率は高く、借地人の地位は労働者のそれに似て劣悪だった。1952年にナセルが軍事クーデターを起こすまでの10年間、この国は不安定な状態に陥っており、17の政権が次々と誕生し、戒厳令、ストライキ、暴動が起こった。支配階級のメンバーは暗殺の標的になっていた。新政権が誕生した年に土地改革が始まった。同時期の東アジアと同じように、アメリカは共産主義の影響力を封じ込めるために擁護と支援を行った。農相のサイード・マレイは、改革を正当化するために、そのような懸念を口にした:
我々は1952年7月の革命前の日々を覚えている。危険な扇動の結果、エジプトの村がどのように落ち着かなくなったかを覚えている。大土地所有者たちは、この不安の中を吹き抜ける風にさらされ、欠乏と貧困を搾取され、すべてを根こそぎにする大嵐になるまで放置されることを望んだだろうか??
個人の土地所有には上限が設けられたが、所有者は補償金を受け取り、土地を受け取った者は、1861年以降にロシア皇帝が考案したのと同じような方式で、数十年にわたって国に返済することが義務づけられた。この返済額はそれまでの地代よりもはるかに低かったため、この制度は農民に有利に働いた。富の分配は所得の分配ほど影響を受けず、土地の10分の1程度が入れ替わった。イラクでは、クーデターとバース主義の支配がより大きな影響を及ぼし、集団化が1960年代と1970年代に土地所有の不平等を大幅に縮小させた。1971年にスリランカで共産主義者の蜂起が失敗し、数千人の犠牲者を出したと考えられているが、その翌年に土地改革が行われ、一定の上限を超える私有地、後には企業の土地が収用されることになった。再び暴力によって促されたこの介入は、独立以来、土地の不平等への取り組みに失敗してきたこれまでの政府とは根本的に異なるものであった12。
これらの例はすべて、意味のある土地改革を実現するためには、暴力が適用されるにせよ潜在的に存在するにせよ、最も重要であることを一貫して指摘している。しかし、その結果は千差万別である。実際、土地改革が不平等を緩和した実績は乏しい。20世紀後半に行われた27の改革を調査したところ、その大部分(21、つまり78%)で、土地の不平等はほとんど変わらないか、あるいは時間の経過とともに拡大することさえあった。縁故主義は平和的な土地改革を損なうかもしれない。1960年代のベネズエラでは、民主的に選出された政府が国内の農地の10分の1を再分配し、半分は土地収用から、半分は国有地から、土地を持たない貧困層の4分の1に分配した。当時、同国は農業中心の経済から石油輸出に基づく都市経済へと移行しつつあった。そのため、政府は石油収入から手厚い補償金を支払うことができた。実際、地主たちは労働者によるストライキや土地要求を推進し、彼ら自身が収用の対象となり、市場水準を上回る補償金を受け取れるようにした。このような改革は、実質的な不平等を緩和する効果はほとんどなかっただろう13。
補償が裏口から導入されることもあった。古代ローマ共和国は、イタリア半島全域に拡大する過程で、敗走する敵から大量の耕地を没収し、それを公有地に転換して入植者に割り当てたり、賃貸したりした。後者は、広大な土地を耕作し投資する余裕のある人々に利益をもたらし、公有地が富裕層に集中する原因となった。このような土地へのアクセスに法的制限をかけようとする動きが以前からあったが、紀元前133年、寡頭支配層内部の改革派であるティベリウス・グラックス(Tiberius Gracchus)が、各所有者の公有地面積を300エーカー強に制限する再分配計画を推し進めたことで、事態は急転した。過剰な所有地は先行投資の補償なしに接収され、貧しい市民に割り当てられた。割り当てられた畑は、富裕層や権力者が新たに生まれた小農を買収したり、その他の方法で追い出したりするのを防ぐため、不可侵とされた。この改革に対するエリートの反対は段階的に進んだ。入植者に起業資金を提供することでこのプログラムを強化しようとしたグラックスは、激怒したオリガルヒの手によって命を落とした。再分配制度は4年足らずでその発案者を生き延び、前110年代には賃料が廃止され、公有地の所有者(最大許容額を所有していた者を含む)はすべて、売却可能な私有財産として享受するようになった。したがって、このプログラムによって、それなりの数の小作人(市民人口の数パーセントに相当)が新たに生まれたかもしれないが、土地の富の分配に対する長期的な効果は、せいぜい控えめなものであったと思われる14。
現代のフィリピンでは、戦争や革命の脅威がなかったため、地主エリートは足を引っ張ることができた。土地改革が何十年もの間、キャンペーンスローガンとして掲げられても、ほとんど変化はなかった。1988年以降、より本格的な試みが行われたとしても、インド、パキスタン、インドネシアと同様、成果はわずかなものだった。1970年代のイランでは、ほとんどの小作人が余剰地主の所有地を強制的に売却して土地を手に入れたが、このプロセスは、売り手の優遇主義と補償要件、国の支援の欠如のために、小作人間の不平等を実際に拡大させた。1848年のハワイの「グレート・マヘレ」は、平和的な土地改革が不公平な結果をもたらした、特に極端な例である。この時点で、それまで集団で耕作していた土地が、国王、首長、一般住民の間で共有された。私有権を確立するためには正式な請求が必要であったが、多くの平民世帯はこれを行わなかった。また、外国人土地所有法(Alien Landownership Act)がすぐに部外者の土地取得を許可したため、やがて王室が請求していない土地のほとんどは、ハワイ人以外の商業所有のものとなった15。
非暴力による土地改革が完全に成功したのは、ごくまれな場合だけであった。18世紀末のスペインにおける共有地の分配は、せいぜいその部分的な例である。1766年に国王シャルル3世をマドリードから逃亡させた暴動が引き金となり、したがって暴力的なきっかけがなかったわけではないが、その結果は地域の状況によって大きく異なるものとなった。農機具を買う余裕のある者だけが得をすることが多かった。地方によっては、農村労働者の資金不足とエリート層の策略的介入によって改革が失敗したところもあった。改革が成功したのは、商業エリートが支配していたマラガのように、上流階級が土地所有に特別な投資をしていなかったか、あるいはグアダラハラのように、豊富な土地と組み合わされた農村労働者の相対的不足が地主の交渉力を制限した場合だけであった16。
19世紀のセルビアでは、帝国支配からの独立が進んだことで、平等な土地改革が可能になった。オスマン帝国は、裕福なイスラム教徒の受益者に土地を割り当てる封建体制を敷いていた。さらに、有力なトルコ人はセルビアの農民を侵害することで、不法に準私有財産権を確立した。地元の農村住民は、高い賃料の支払いと労働奉仕を強いられた。1804年以降の反乱によって、1815年から1830年まで続いたオスマン・トルコの宗主権の下でのセルビアの自治という二重支配の過渡期が始まると、不法な財産請求権は取り消され、封建的な地主と地代は圧力を受けるようになった。1830年代初頭の和解により、ほとんどのトルコ人は土地を地元民に売却した後、数年以内にセルビアを去るよう命じられた。封建制は廃止され、セルビア人は土地の私有権を獲得した。退去したトルコ人が割譲した土地の一部は、小農に分配された。残された大土地所有者は、耕作者の家屋と一定の農地を、その土地を耕作する農民に売却することが義務づけられた。その結果、大土地所有はほとんど完全に姿を消し、土地所有は極めて広く普及した。1900年までに、セルビア人世帯の91.6%が家屋やその他の不動産を所有していた。この場合、不平等は、伝統的な特権の地位から追い出された「外国人」エリートの犠牲の上に軽減された。旧植民地やその他のエリートの所有地を対象とした土地改革は、他の国々でも同様に行われた17。
真に平和的な改革を行うには、地元のエリートの権力を牽制するような、何らかの形の外国による支配が必要であったように思われる。この改革は1940年代後半にプエルトリコで行われたが、そこでも大恐慌と第二次世界大戦を契機としたアメリカの平等化改革が発展したものであり、アメリカ占領下の日本におけるトップダウンの土地改革と同時期に行われたものであった。植民地支配はアイルランドの土地改革にも役立った。1870年代後半、いわゆる「土地戦争」と呼ばれる、公正な賃料と立ち退きからの借地人保護を求める運動が起こり、ストライキやボイコットという形で組織的な抵抗が行われたが、実際の暴力はほとんどなかった。英国議会は一連の法律でこうした不満に対処し、賃料を規制するとともに、意欲的な地主から土地を購入しようとする借地人に対し、固定金利での融資を提供した。1903年、ウィンダム法は、政府が借地人から提示された補償金と地主の要求価格との間に生じる12%のプレミアムを国家歳入から負担することに合意し、小作地の民営化を助成することで、ついに平和を勝ち取った。これにより、1920年代初頭の独立までに、小農がアイルランド全農地の半分以上を所有するようになった18。
平和的かつ効果的な土地改革の模索は、特に成功したわけではない。最も再分配的な介入は、フランス革命、メキシコ革命、ロシア革命、中国革命、ベトナム革命、ボリビア革命、キューバ革命、カンボジア革命、ニカラグア革命、エチオピア革命のように、しばしば暴力的な革命や内戦によって、またジンバブエのように暴力的な扇動によって可能になった。土地改革の平等化が、戦争による外国の占領(日本、中央ヨーロッパ、第二次世界大戦後の南北朝鮮ではある程度)、戦争の脅威(中世初期の日本、プロイセン、台湾)、その他の戦争関連の騒乱(グアテマラ)、革命の懸念(チリ、ペルー、エジプト、スリランカ)、あるいはそうした懸念と実際の戦争の組み合わせ(韓国と南ベトナム)の結果であったケースもある。最新の調査によれば、1900年から2010年の間にラテンアメリカ以外で実施された大規模な土地改革の87%以上が、世界大戦、脱植民地化、共産主義者による占領、あるいは共産主義者の扇動の脅威をきっかけに行われたものである19。
平和的な改革は、ハワイやベネズエラのように富裕層に利益をもたらすかもしれないし、アイルランドやプエルトリコのように手の届く範囲で実施されるかもしれない。平和的に展開され、大幅な平準化をもたらした自律的な土地改革に関する証拠は不足している。土地改革が切望されるような発展レベルにある社会では、暴力的な衝撃や暴力の脅威がより実質的な譲歩を促さない限り、エリートの抵抗は常に再分配政策を阻止したり、水を差したりする可能性があった。このことは、高い「床」(新しい小作地の大きさ)と低い「天井」(地主の財産に課された上限)を特徴とする非暴力的な土地改革が見かけ上行われなかったことの説明に役立つ20。
この図式は、より遠い過去にさかのぼっても変わらない。名目上は野心的な土地再分配計画は、中国の戦国時代や隋唐時代のように国家建設の特徴として、また漢民族のようにエリートの富を後退させようとする支配者の闘争の文脈で、繰り返し証明されている: これらについては以前の章ですでに触れた。古代ギリシアでは、土地改革とその関連施策、とりわけ債務救済は、一般的に暴力的なクーデターと結びついていた。その報告は、古代ギリシャ時代からヘレニズム時代まで、数世紀にわたって続いている。紀元前7世紀、コリントの最初の暴君キプセロスが、敵対する一族のメンバーを殺害または追放した際、再分配のためにその土地を押収した可能性がある。同じ頃か、あるいはその少し後に、隣接するメガラのポリスではテアゲネスが、貧しい人々の田畑に放牧されていた富裕層の家畜を虐殺した。その後の急進的な民主主義の時代には、富裕層は追放され、その資産は差し押さえられた。貧しい人々は富裕層の家に入り込み、タダ飯を強請ったり、暴力を振るったりしたと言われている。貸し手は借金の利子を返済するよう命じられたが、借金が帳消しになった形跡はない。前280年、アポロドロス(Apollodorus)という人物が、奴隷や製造労働者の助けを借りてカッサンドレイア(Kassandreia)という都市で権力を掌握した。彼は「金持ちの財産を没収して貧しい人々に分配し、兵士の給料を引き上げた」と言われているが、この状態はわずか4年しか続かなかった。同様の文脈で、クレアルコスは紀元前364年、土地再分配と債務帳消しのプログラムを謳い、ヘラクレア・ポンティカの専制君主となった21。
平和的な土地改革もスパルタではあまり進展しなかった。第6章で見てきたように、土地の富はますます不均等に分配されるようになり、市民のますます大きな割合を疎外するようになっていた。前4世紀半ばには、市民の数は700人(1世紀半前にはその10倍以上)まで減少し、そのうち約100人が富裕層に分類され、その他の人々はその債務者であった。さらに2,000人ほどのスパルタ人は、収入が必要な基準値を下回ったこともあり、二級市民に分類された。スパルタ社会の他の下位階層は言うに及ばず、市民内の極端な不平等が改革の道を開いた。
最初の介入は、前240年代にアギス4世によって流血を伴わずに達成されることを意図したもので、借金の帳消しと、市民だけでなく臣民ポーリスの適切なメンバーにも4500等分の土地を再分配することを目的としていた。この改革は、アギス4世が遠征に出かけている間に頓挫し、アギスは亡命して失敗に終わった。前227年、クレオメネス3世が傭兵の力を借りてクーデターを起こし、スパルタの5人の上級行政官(エフォール)のうち4人と約10人を殺害し、さらに80人を追放した。彼の計画はアギスのものと似ていたが、今回は軍事改革を伴って実際に実行され、軍事的・外交的成功によって迅速に報われた。前222年、ついにクレオメネスは軍事的敗北を喫し、国外に逃亡したが、彼の再配分が改ざんされた形跡はない。彼の再分配が改ざんされた形跡はない。しかし、この敗北で大量の人命が失われ、地主の数は大幅に減少したであろう。紀元前207年のさらなる軍事的災難は、ナビスに率いられた第三の最も急進的な改革を促し、彼は何千人もの「奴隷」(おそらくヘロート)を解放し、権利を与えた。彼は裕福なスパルタ人を殺害、拷問、追放し、その土地を貧しい人々に与えたとされる。紀元前188年、外国の介入によってスパルタ人が退位すると、反動的な和解によって、権利を得たばかりのヘロートたちは追放または売却された。これは、土地改革を成功させるためには、ある程度の暴力が必要とされる傾向があることを示すもう一つの例であり、また、このことが、反動としてさらに大きな反暴力を引き起こす可能性があることを示している22。
「石版を破る」: 債務救済と奴隷解放
私たちが知ることのできる限り、何らかの形で暴力と結びつかなかった土地改革が、所得と富の不平等と闘う有力な手段となったことは、あったとしてもほとんどない。同じことが債務救済についても言えるかもしれない。借金は確かに不平等を助長し、農民に土地を売らせ、可処分所得を減らしてきた。少なくとも理論的には、債務の削減や帳消しは、裕福な貸し手を犠牲にして貧しい借り手の立場を改善するのに役立ってきたかもしれない。しかし実際には、そのような措置が実際に効果を上げたという十分な証拠はない。債務救済プログラムは、記録に残る最古の識字社会から証明されている: マイケル・ハドソンは、紀元前2400年から1600年にかけてメソポタミアで行われた、利子や負債そのものの帳消し、負債保証人の解放に関する20以上の文献を集めている。シュメール人、バビロニア人、アッシリア人の王室救済令は、冒頭の章ですでに述べたように、余剰金の支配と課税・兵力調達能力をめぐる国家統治者と富裕エリートとの永続的な争いの一要素として理解するのが最も適切である。もし救済が効果的であり、かつ繰り返し行われたのであれば、救済は貸付条件に織り込まれていたと予想される(そのことが高金利を説明できるかもしれない)。いずれにせよ、債務救済が不平等是正の有力な手段であったと解釈するのは難しいように思われる23。
奴隷制度の廃止は、不平等是正の有力な手段のように思われるかもしれない。エリート資本の多くが奴隷に縛られていた比較的少数の社会では、奴隷解放は資産の不平等を圧縮する可能性があった。しかし実際には、大規模な奴隷解放運動はしばしば暴力的な騒乱と絡んでいた。1792年の試みが失敗した後、イギリス議会は1806年に奴隷貿易禁止を可決した。この措置は、当初はイギリス以外の植民地のみを対象とし、ナポレオン戦争中のフランスに対するイギリスの国益、より具体的には軍事的利益に資することを意図したものであった。奴隷廃止は、1823年にデメララで、特に1831年と1832年にジャマイカで起こった大規模な奴隷反乱によって始まった。1833年には奴隷解放法が即座に制定され、解放された奴隷は元の所有者のもとで数年間無給で働くことが義務づけられ、奴隷所有者には補償金が支給された。必要とされた2,000万ポンドの支出は巨額で、国の年間公共支出の40%に相当し、今日で23億ドル(当時も現在も英国経済に占める割合で表すと、現行ドルで1,000億ドル以上)に相当する。これは解放された奴隷の市場価値(当時の推定では1500万ポンド、2400万ポンド、7000万ポンド)を下回るものであったが、4年から6年間の無給の見習い期間と合わせると、補償金の総額が大きく不足することはなかった。報酬の半分以上は、不在のオーナーや債権者(そのほとんどがロンドンを拠点とする商人や賃借人)に支払われた。大規模な賃借人の中で補償を辞退した者はいない。このような状況下では、平準化はせいぜいごく限られたものに過ぎなかった。さらに、イギリスの国家歳入が関税や物品税などの間接税に大きく依存していた当時、この制度の資金を調達するために多額の債務を負う必要があったため、国民の大多数から、より裕福な奴隷所有者や公債の購入者へと事実上所得が再配分された24。
奴隷解放が暴力的な紛争とさらに直接的に結びついた例もある。フランスはフランス革命のさなかの1794年、サン=ドマング(現ハイチ)の反乱奴隷を自国の側に引き戻し、敵から遠ざけるための戦術的措置として奴隷制を廃止した。この措置はその後、ナポレオンによって撤回された。1804年、ハイチが独立を宣言すると、元奴隷所有者は追放され、残った者はその年の白人虐殺で殺された。1848年の革命は、ヨーロッパ全体に波及した動乱の一部であり、再びフランス王政を崩壊させ、即時奴隷解放をもたらした。所有者たちは、イギリスほどではないにせよ、現金と信用でいくらかの補償を受けた。ラテンアメリカのほとんどのスペイン植民地では、戦争が奴隷制廃止に貢献した。1808年にナポレオンがスペインに侵攻し、植民地支配が地元の反乱に屈した後、新たに成立した州はすぐに奴隷解放法を可決した。第6章では、アメリカ南北戦争における奴隷制の暴力的破壊について論じたが、この戦争では、奴隷所有者の無報酬の収奪が、非エリート集団の付随的損害によって一部相殺され、全体的な平準化の程度は軽減された。一方、イギリスによる大西洋奴隷貿易の制圧は、本質的に国家的暴力行為であり、ラテンアメリカに残存していた奴隷制の衰退に貢献した。ブラジルとキューバがその主な生き残りだった。キューバ(とプエルトリコ)の場合、政策変更を促したのは再び暴力的な紛争だった。1868年にキューバで革命が起こり、10年続いた戦争中に島の一部で奴隷解放が行われた。1870年から1886年に奴隷制度廃止が達成されるまで、改革によって奴隷制度は縮小された。ブラジルが外交公約に反してアフリカ人奴隷を輸入し続けたため、イギリス海軍は1850年にブラジルの港を攻撃して奴隷船を破壊し、ブラジルに奴隷貿易を禁止させた。1871年以降、奴隷制度は徐々に解体され、1888年の最終的な廃止には所有者への補償は伴わなかった25。
大雑把に言えば、戦争や革命など暴力が伴うほど、より効果的な平準化が行われた(ハイチ、ラテンアメリカの大部分、アメリカのように)。一方、プロセスが平和的であればあるほど、より多くの補償が行われ、所有者はこの移行についてよりうまく交渉することができた(イギリスやフランスの植民地のように)。ブラジルのみが部分的な例外である。このように、富の不平等を縮小させる奴隷解放は、本書の前章で取り上げた暴力的な平準化勢力と一般的に関連していた。逆に、平和的でありながら(物質的な面で)著しく平等化する奴隷解放はまれであり、おそらく存在しなかった。より一般的には、土地所有者が定期的に土地の支配権を保持し、ポストベルム南部における小作農のような代替的な搾取的労働の取り決めから利益を得ることができたことを考慮すると、奴隷廃止の出来事は所得格差にさらに弱い影響を及ぼした。
「健全で豊かな基盤の上に」: 経済危機
これまで見てきたように、経済収縮は不平等を縮小させることが可能であった。第9章で論じたシステムの崩壊による大規模な景気後退は、考古学的証拠から見分けることができる平準化効果をもたらした。変革的な革命に伴う深刻な経済的混乱も、劇的な規模こそ小さいものの、同様の結果をもたらす可能性がある。しかし、「平和的な」マクロ経済危機、つまり暴力的なショックに根ざしていない景気後退は、どのような役割を果たしたのだろうか。人類史の大半において、このような危機が不平等の発展に及ぼした影響を調査することは不可能である。初期の例としては、スペインにおける持続的な恐慌が挙げられる。この恐慌では、羊毛の輸出、貿易、都市活動の衰退に伴い、17世紀前半を通じて一人当たりの実質生産高が減少した。この時期、賃金に対する地代の比率は低下し、土地よりも労働への収益が高く、所得格差が縮小したことを示唆したが、名目賃金に対する名目一人当たり生産高の比率はかなり安定したままであり、所得分配に大きな変化がなかったことを示唆した。このことは、入手可能なデータの限界もあるが、前近代社会における経済的な力によって誘発された平準化を探ることの難しさを浮き彫りにしている26。
実質的な証拠は、より最近の過去についてのみ入手可能である。主要な経済危機は、不平等に系統的な悪影響を及ぼしていない。現在までに行われた最も包括的な調査では、1911年から2010年までの72件のシステミックな銀行危機と、1911年から2006年までの間に、ピーク時から少なくとも10%減少した100件の消費と、同程度減少した101件のGDPを調査している。例えば、銀行危機のうち18件だけが景気後退と重なった。25カ国で発生した72件のシステミックな銀行危機のうち37件が有用な情報をもたらした。所得格差が縮小したケースはわずか3件であったのに対し、格差が拡大したケースは7件であり、危機前のデータがないケースを含めると13件になる。消費減少の方が、異なる結果をもたらす可能性が高い。36の使用可能なケースのうち、不平等は7つのケースで低下し、2つのケースでのみ上昇した。GDPの縮小については、明確な傾向は見られない。両タイプのマクロ経済危機のうち、大半のケースで不平等にほとんど変化が見られなかった。発展途上国における67のGDP崩壊事例に関する別の研究では、このような出来事によって不平等が上昇した事例が10件確認されており、貧しい国ほどこの種のショックに対して脆弱である可能性を示している。マクロ経済危機は平準化の重要な手段としては機能せず、銀行危機は逆効果になる傾向さえあると結論づけざるを得ない27。
1880年から2000年までの16カ国を対象とした調査では、この最後の知見が確認されたが、時間的な側面が追加された。金融危機は、第一次世界大戦争前と第二次世界大戦後に、上層部の所得よりも下層部の所得を急速に押し下げることで、不平等を拡大させる傾向があった。主な例外は大恐慌で、資本収入に大きく依存していた富裕層の所得が減少したにもかかわらず、実質賃金は上昇した。大恐慌は、米国の経済格差に強力な影響を及ぼした唯一のマクロ経済危機であった。1928年から1932年にかけて、米国人の上位1%の富裕層の富のシェアは51.4%から47%に減少したが、それと同時に上位1%の所得のシェアは1928年の19.6%から3年後には15.3%に、キャピタルゲインを含めると同期間に23.9%から15.5%に減少した。上位0.01%の損失は特に顕著で、キャピタルゲインを含む所得シェアは1928年から1932年の間に5%から2%に減少した。それに応じて富裕層の層も縮小した。全米製造業者協会の会員数は1920年代初頭から1933年の間に3分の2以上減少し、銀行の数は1929年から1933年の間に約25,000行から14,000行に減少した28。
大恐慌が不平等に及ぼした世界的な影響は、一般にもっと緩やかであった。オーストラリアでは、上位1%の所得分配率は1928年の11.9%から1932年には9.3%に低下したが、1936年から1939年までの平均は10.6%であり、大恐慌前の水準を大きく下回ることはなかった。フランスでは、1928年の17.3%から1931年には14.6%に低下し、その後わずかに回復した。オランダでは、1928年から1932年にかけて18.6%から14.4%に低下したが、同様にその後部分的に回復した。1928年から1932年にかけて、オランダでは18.6%から14.4%に低下した。この間、ドイツ、フィンランド、南アフリカでは最高所得シェアは横ばいで、カナダとデンマークでは上昇した。このように、大恐慌がもたらした平等化の結果は、米国に限定されたように思われる。数年間の平準化の後、所得集中は戦争が始まるまで安定を保ったが、富の不平等に関するさまざまな指標は相反する傾向を示している29。
ハーバート・フーバー大統領が、1929年10月29日の株価暴落の4日前に行った演説で、「この国の基本的な事業、すなわち商品の生産と流通は、健全で豊かな基盤の上にある」と断言したのは有名な誤りである。1930年代後半にエリートの所得と富が回復した兆しは、この傾向が世界大戦の再燃によって消滅していなければ、どれほど長く続いていただろうと思わせるものであった。結局のところ、所得上位層の回復と反発は、より最近の典型的な例でもある。1987年の株式市場の大暴落は、当時の最高所得の着実な上昇を止めることはできなかったし 2000年のドットコムバブルの崩壊と翌年の9.11の混乱によるささやかな平等化効果は 2004年までには完全に消え去っていた。2008年の大不況も同様で、最高所得シェアへのマイナスの影響は4年後には完全に解消していた。このことは、アメリカの所得シェアが上位1%、0.1%、0.01%のいずれであったとしても同様である。他の先進諸国における均等化効果も異質ではあるが、同様に緩やかであった。経済危機は深刻なショックかもしれないが、暴力的な圧力がなければ、通常はそれだけで不平等を縮小させることはできない30。
「しかし、両方を手に入れることはできない」: 民主主義
一見すると、民主主義制度の拡大は、平和的な平準化手段としてはもっともらしい候補のように思われるかもしれない。しかし、第5章と第6章で見てきたように、形式的な民主化を暴力行為と無関係な自律的発展として簡単に扱うことはできない。古代アテナイの民主主義の発展が大衆動員戦と絡み合っていたように、20世紀前半の特定時点における多くの西欧諸国におけるフランチャイズの拡大は、2つの世界大戦の衝撃と非常に大きく関連していた。この理由だけで、民主化がこれらの社会における物的資源の分配を均等化する効果があったことを示すことができたとしても、そのような過程は少なくとも部分的には戦争の圧力によって推進されたであろう31。
さらに、民主主義と不平等の関係に関する研究は、長い間、矛盾した結果を生み出してきた。このような結果の曖昧さは、現在、この問題に関する最も野心的で包括的な調査によって確認されている。ダロン・アセモグル(Daron Acemoglu)らは、独立または1960年(どちらか遅い方)から2010年までの184カ国538件の調査から、民主主義が市場や可処分所得の不平等に一貫した影響を及ぼしていないことを発見した。可処分所得分配のジニ係数に負の効果が観察されたとしても、統計的有意性には達しなかった。不平等の基礎となる尺度の精度が低いため、疑問の余地があるのは事実である。しかし、民主主義がGDPに占める税収の割合に確固とした影響を及ぼしていることから、有意な関係の欠如はより顕著である。このことは、資源の純分配を形成する上で民主主義が果たす役割は複雑かつ異質であり、民主主義と再分配政策の平等化との関連性がしばしば推定されるが、それは一筋縄ではいかないことを示唆している。それは、民主主義が有力な有権者に「取り込まれ」てしまうと平等化が阻害される可能性があることと、民主化が経済発展の機会を提供するが、それ自体が所得格差を拡大させる可能性があることである32。
ケネス・シーヴとデイヴィッド・スタサヴェージによるより具体的な研究は、欧米における民主化が物質的不平等を抑制するという考え方を根底から覆すものである。彼らは、1916年から2000年までの13カ国において、党派性(政府が左派政党に支配されているか否かにかかわらず)が全体的な所得格差に影響を及ぼさず、上位1%の所得シェアにわずかな抑制効果をもたらしただけであったことを明らかにしている。中央集権的な全国レベルの賃金交渉も、同様に大きな違いを生むことはなかった。彼らはまた、一方ではフランチャイズ延長と党派性、他方では所得税の最高税率との関係を探っている。最高税率は不平等と負の相関を持つ傾向があり、不平等よりもよく記録されていることが多いので、信頼できる不平等指標が利用できるようになる前の期間の大まかな代理として役立つ可能性がある。ScheveとStasavageは、男性普通選挙の導入が所得税の最高税率に強い影響を与えなかったことを発見した:15カ国において、男性普通選挙が導入されるまでの5年間の最高税率の平均は、その後の10年間よりもわずかに低かっただけであった。1832年の改革法から1918年の男子普通選挙導入までの間の英国のように、段階的な選挙権の拡大も、最高税率を上昇させることはなかった。これらの税率は第一次世界大戦によって上昇し、選挙制度改革はこの急激な上昇に先行したのではなく、むしろその後に行われたのである。最後に、左翼政権への移行前後の平均最高所得税率を比較すると、このような出来事の前後5年間の平均上昇率はわずか3%ポイント(48%から51%)であった33。
対照的に、労働組合の力は不平等と負の相関関係にある。しかし、第5章で示したように、労働組合の組織率は2つの世界大戦のショックに非常に敏感であったため、民主主義それ自体の直接的な機能や現れとは考えられない。米国最高裁判事のルイス・ブランデイスはかつて、「この国では民主主義を持つか、巨万の富を少数の手に集中させるかのどちらかだが、両方を持つことはできない」と述べた。少なくとも、この高名な学者が間違いなく意図していたであろう、より広範な実質的な意味ではなく、形式的な意味で民主主義を定義する限りは。逆に、社会主義国以外でも、強力な民主主義政府が存在しないことが経済的平等と決して両立しないわけではない: 韓国と台湾は、1980年代後半に民主化が本格化するはるか以前から、それ以前の暴力的なショックによってもたらされた平等化の利益を維持するという優れた記録を残してきたし、シンガポールもかつては同じであった34。
第7部 不平等の再来と平準化の未来
第15章 現代において
再燃する不平等
世界大恐慌を生き抜いた最後の世代は、急速に衰えている。第二次世界大戦に従軍したアメリカ人の95%が他界し、生き残った人々のほとんどは90代である。人と同様、平準化も同様である。先進国では、1914年に始まった格差の大幅な縮小はとっくに終わっている。10年か10年か、およそ1世代にわたって、信頼できるデータのあるすべての国で所得格差は拡大している(表15.1、図15.1)1。
26カ国のサンプルでは、1980年から2010年の間に上位の所得シェアは半分になったが、市場所得の不平等は6.5ジニ・ポイント上昇した。統計的には、1983年が大きな転換点であり、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、日本、スイスで不平等の低下傾向が逆転した。イギリスでは1973年に、アメリカでは1973年か1976年に、アイルランドでは1977年に、カナダでは1978年に、オーストラリアでは1981年に不平等が始まった。アメリカの賃金格差はすでに1970年ごろから始まっている。他の指標もこの図式を裏付けている。等価可処分家計所得ジニスと上位と下位の所得シェアの比率は、一般に1970年代か1980年代以降に上昇した。1980年代以降、OECD加盟国の多くで、中程度の所得を持つ人口の割合が、高所得者層や低所得者層に比べて相対的に後退している2。
表15.1 1980年から2010年までの一部の国における上位所得シェアと所得格差の傾向
図15.1 OECD20ヵ国における上位1%の所得シェア(1980-2013)
より詳しく見てみると、この傾向の部分的な例外さえほとんど見られない。表15.1では、上位1%の所得シェアに関するデータのカバー率にばらつきがあるため、単一の基準年を用いている。このため、スペインとニュージーランドでは不平等がわずかに低下し、フランスでは横ばいのように見える。その代わりに5年間の移動平均を適用すると、1990年前後から最高所得シェアが少なくとも最低限上昇していない国は、このグループに1つもないことが明らかになる。同じ方法でジニ係数を追跡してみると、オーストリア、アイルランド、スイスを除くすべての国で可処分所得の不平等が拡大し、市場の不平等も例外なく拡大していることがわかる。そして、ほとんどの場合、所得の集中はより顕著になっている。所得上位占有率が公表されている21カ国のうち11カ国では、1980年から2010年の間に、全所得のうち「1%」の所得が占める割合が50%から100%以上に上昇した3。
2012年、米国の不平等はいくつかの記録を更新した。この年、上位1%の所得シェア(キャピタルゲインの有無にかかわらず)と、世帯の0.01%の富裕層が所有する個人資産のシェアは、1929年の高水準を初めて上回った。さらに、公表されている所得分配のジニ係数は、最も裕福な世帯の情報を把握するのが難しい調査から導き出されたものであるため、実際の不平等のレベルを控えめにしている可能性が非常に高い。米国の場合、様々な調整により、ジニ係数はかなり高くなっており、しかも時間の経過とともに徐々に高くなっている。1970年から2010年にかけて、公的な所得分配のジニ値は約0.4から0.48に上昇したが、実際には1970年には0.41から0.45程度であった可能性があり、2010年には0.52から0.58にまで達した。最も保守的な修正でさえ、この不平等指標は1970年の0.41から2010年の0.52へと4分の1以上急騰したと見ている。1979年から2011年まで、上位1%の年間所得成長率は、課税・移転前で平均3.82%、移転後で平均4.05%であったのに対し、下位5分位ではそれぞれ0.46%、1.23%であった4。
この傾向は、決して表15.1の調査対象国に限ったことではない。第7章で詳しく示したように、形式的に、あるいは事実上ポスト共産主義社会となった国々では、物質的不平等が大幅に拡大している。同様にロシアでも、市場所得ジニが2008年以降0.5を超える水準で推移しており、ソビエト連邦が解体した1991年の0.37から、さらに低かった1980年代初頭の0.27から上昇している。インドの市場所得ジニは1970年代半ばの0.44-0.45から2000年代後半には0.5-0.51に上昇し、上位1%の所得シェアは1980年代後半から1999年の間に倍増した。パキスタンの市場所得ジニは、1970年頃の0.3台前半から2010年には0.55まで爆発的に上昇した。しかし、発展途上国の多くでは、首尾一貫した長期的トレンドを見極めることは難しい。例えばインドネシアでは、1990年代を中心とした所得集中の大波から回復したとはいえ、ジニ係数と上位所得シェアは1980年頃よりもまだ高い。アフリカとラテンアメリカの不平等の複雑さについては、すでに第13章で述べた。1980年代後半から2000年前後にかけて、低所得国を除くすべてのタイプの経済において、低中所得国、高中所得国、高所得国、そして世界的に所得の偏在が進んだ。世界のどの地域でも、1990年代から2000年代初頭にかけて、上位20%の所得シェアが拡大した5。
この不平等化のプロセスを、開発レベルの異なるさまざまな国々が共有していることは注目に値する。2つの例を挙げれば、ロシアと中国は、一方が経済破綻を経験し、もう一方は例外的に力強い成長を遂げたにもかかわらず、所得と富の劇的な集中を経験した。その結果、1990年から2010年にかけて、抽出率(理論上可能な最大不平等の程度が実際に到達した割合)は、中国では1人当たりGDPとジニ係数が連動して上昇したため、ほぼ横ばいにとどまったが、ロシアでは生産高がソビエト連邦の水準を超えることができなかったため、2倍に上昇した。より一般的には、中央計画から市場経済への移行の結果、中・東欧と中央アジアでは所得格差が拡大したが、東アジアでは力強い経済成長によって、ラテンアメリカでは2002年頃までマクロ経済危機と構造転換によって牽引された。さらに、欧米の豊かな国々における同様の変化についても、さまざまな原因が挙げられている6。
ラテンアメリカを除いて、これらの社会に共通しているのは、1910年代から1940年代にかけての大恐慌と、その緩やかな平等化の余波に参加したということである。世界大戦に直接参加した国々は、現在、世界の名目GDPの4分の3以上を占めており、ヨーロッパの傍観者や大きな影響を受けた旧植民地を含めると、この割合は5分の4以上に拡大する。したがって、最近の広範な不平等の増加は、不平等を異常に、そしておそらくは持続不可能なほど低い水準にまで押し下げた、以前の暴力的ショックによる平等化の結果の緩和として理解するのが最も適切かもしれない。
市場と権力
私は本書の冒頭で、人類の夜明けから20世紀までの所得と富の不平等の変遷について概説した。数千年にわたる歴史的記録をサンプリングし、少数の手に資源が集中するようになった主な要因を2つ挙げることができた。経済の発展と、経済学者がレント(賃料)と呼ぶ、競争市場において彼らの活動が獲得しうる額をはるかに上回る富を収奪するのに十分な力を持つ人々による略奪的行動である。これらのメカニズムは、現在もなお有効である。つまり、一方では需要と供給を通じて働く市場原理が、他方では制度や権力関係が相対的に重要であるということである。これらすべてが先進国における所得格差の拡大に大きく寄与していることを否定する真摯なオブザーバーはほとんどいないだろうが、その具体的な内容については非常に多くの議論がある。近年、制度や権力をベースとした説明が台頭しているが、これは需要と供給の支持者たちが、技術や技能、効率的な市場の重要性を強調する、これまで以上に洗練されたモデルを考案しているのと同じである7。
多くのオブザーバーは、所得格差の拡大が、特に米国における高等教育の収益率の上昇に起因しているとしている。1981年から2005年の間に、高卒者と大学に進学した者の平均所得格差は、48%から97%へと倍増した。1980年から2012年にかけて、男性の大卒者の実質所得は20%から56%上昇し、その最大の恩恵はバカロレア後の学位取得者にもたらされたが、高卒者では11%、高校中退者では22%減少した。1980年前後から2000年代初頭にかけての賃金格差の拡大のおよそ3分の2は、大卒労働者によるプレミアムの拡大に起因している。1960年代から1970年代にかけて全労働時間に占める大卒労働者の割合が急速に増加した後、1982年ごろからその増加は鈍化し、熟練労働者に対する需要が供給を上回るにつれてプレミアムが上昇した。技術革新だけでなくグローバリゼーションも重要な役割を果たしたと思われ、オートメーションが定型的な人間労働に取って代わり、製造業が海外生産者にシフトし、正規教育、技術的専門知識、認知能力に対する需要が一般的に高まった。このため、低賃金で手工業的な職業と、高賃金で抽象的な職業との二極化が進み、中堅層の仕事が奪われ、所得分配の中間層が空洞化した。発展途上国では、技術革新がさらに強力に不平等化する結果をもたらした可能性がある8。
解決策として、教育への投資拡大が挙げられている。2004年から2012年にかけて、米国では大卒労働者の供給が再び増加し、技能プレミアムが(高水準ではあるが)横ばいになった。英国を除き、ほとんどの欧州諸国と東アジア諸国では、技能プレミアムはほぼ横ばいか、あるいは低下した。各国間の違いは、教育を受けた労働者の供給水準と関連している。実際、教育に対するリターンは国によって大きく異なり、アメリカではスウェーデンの2倍にもなる。このことは、学校教育プレミアムが高いほど世代間の所得移動が低くなるため、重要であることは言うまでもない9。
それでも、批評家はこのアプローチの様々な限界を指摘している。高賃金職種と低賃金職種の二極化現象はエビデンスによってあまり裏付けられていないかもしれないし、技術革新と自動化は1990年代以降の賃金比率の発展を適切に説明することはできない。むしろ、職業間よりもむしろ職業内における所得のばらつきが不平等の重要な原動力であるように思われる。さらに、最高所得の大幅な上昇は、特に学歴で説明するのが難しい。さらに、米国では学歴と雇用のミスマッチが拡大しており、労働者の仕事に対する資格の過剰化が進んでいる。
グローバリゼーションは一般に、不平等を拡大する強力な力と見なされている。19世紀後半から20世紀初頭にかけてのグローバリゼーションの第一波は、欧米だけでなくラテンアメリカや日本でも不平等が拡大または安定(かつ高水準)した時期と一致していたが、1914年から1940年代にかけては、戦争と世界恐慌によって不平等が拡大した時期であった。1970年から2005年にかけての約80カ国の動向を調査したところ、国際貿易の自由化と同時に規制緩和が進み、不平等が著しく高まったことがわかった。グローバリゼーションは一般に経済成長を促進するが、先進国でも発展途上国でも、エリートは不釣り合いに利益を得る傾向がある。この不均衡にはいくつかの理由がある。ひとつには、中国の資本主義受け入れ、インドの市場改革、ソビエト圏の崩壊によって、資本が同じ割合で増加せず、世界の労働人口に占める熟練労働者の割合が低下したにもかかわらず、世界経済における労働者数は事実上倍増した。海外直接投資による金融のグローバル化は、技能プレミアムを上昇させ、場合によっては資本収益率も上昇させる。対照的に、完成品の貿易を通じた低賃金国との競争は、米国の不平等にわずかな影響しか与えていないように思われる。貿易のグローバル化がもたらす平等化の結果が、資本の不平等な移動と競合するためである11。
グローバリゼーションは政策立案にも影響を与えることができる。競争の激化、金融の自由化、資本の流れに対する障害の撤廃は、財政改革や経済規制の緩和を促す可能性がある。その結果、グローバリゼーションは税制を法人税や個人税から歳出税へとシフトさせ、税引き後の所得分配の平等性を低下させる傾向がある。とはいえ、少なくともここまでは、国際的な経済統合と競争は、理論的には特定の種類の再分配政策のみを制約すると予想され、実際には一般に福祉支出を損なうことはなかった12。
富裕国では、人口動態的要因が所得分配にさまざまな形で影響を与えている。豊かな国々では、人口動態的要因が所得分配に与える影響はさまざまである。移民は、米国では不平等にわずかな影響しか与えず、一部の欧州諸国では平等化の結果さえ生み出している。逆に、同類婚、より具体的には、結婚相手の経済的類似性の高まりは、世帯間の格差を拡大し、1967年から2005年の間にアメリカの所得格差が拡大した全体の25%から30%をもたらしたとされている。
制度の変化も顕著な原因である。組合加入率の低下や最低賃金の低下は、所得格差の拡大に寄与している。政府の再分配は、組合密度や団体賃金交渉と正の相関関係があることが分かっている。強力な組織労働と雇用保護は技能へのリターンを低下させる。より一般的には、組合加入は公平規範を制度化することによって賃金の不平等を圧縮する傾向がある。米国では、1973年から2007年の間に民間組合員数が男性で34%から8%へ、女性で16%から6%へ減少したことは、時間当たり賃金の不平等が40%以上増加したことと一致し、この期間の不平等全体の大きな割合を占め、技能プレミアムの上昇と同様の規模であった。これに比べ、最低賃金がこのプロセスで果たした役割ははるかに小さかった。同時に、ヨーロッパ大陸では、より公平な労働市場制度が不平等の拡大を抑制する上でより効果的であった14。
労働市場制度が労働の対価の配分方法の形成に役立つのと同様に、財政制度も可処分所得の配分を決定する上で重要な役割を果たす。第二次世界大戦中から戦後にかけて、多くの先進国では所得に対する限界税率が過去最高まで高騰した。OECD加盟18カ国を対象としたある調査によれば、2カ国を除くすべての国で、1970年代または1980年代以降、最高限界税率は低下している。特に最高所得分配率は税負担と強い相関関係がある。大幅な減税を実施した国では、他の国では減税が実施されなかったにもかかわらず、最高所得が大幅に増加した。富裕税課税の規模も同じ傾向にある。戦後、多額の相続税が巨額の財産の再建を妨げてきたのに対し、その後の減税は新たな蓄積を促進した。米国では、資本所得に対する課税の引き下げによって税引き後所得全体に占める資本所得の割合が上昇し 2000年代の減税に伴ってキャピタルゲインと配当の相対的な比重が大幅に高まった。1980年から2013年の間に、上位0.1%の世帯の平均所得税率は42%から27%に低下し、平均富裕税は54%から40%に低下した。所得格差の拡大は主に賃金の乖離によって引き起こされているのに対し、税の累進性の低下は、アメリカの富の分散における最近の増加の約半分を占めている。ここ数十年、ほとんどのOECD加盟国で再分配の規模が拡大したとはいえ、税と移転は市場所得格差の拡大に追いついておらず、1990年代半ば以降、平等化の手段としてはあまり効果的でなくなっている15。
税金、事業規制、移民法、労働市場の諸制度は政策立案者によって決定されるため、前述の不平等の原因のいくつかは政治的領域にしっかりと埋め込まれている。グローバリゼーションの競争圧力が国家レベルでの立法結果に影響を及ぼす可能性があることはすでに述べた。しかし、政治と経済的不平等はさまざまな形で相互作用している。米国では、両政党とも自由市場資本主義にシフトしている。点呼票の分析によれば、1970年代以降、共和党は民主党の左派化よりも右派化が進んでいるにもかかわらず、後者は1990年代に金融規制緩和の実施に尽力し、伝統的な社会福祉政策よりもジェンダー、人種、性的アイデンティティといった文化的問題にますます重点を置くようになった。1940年代に底を打った議会の政治的偏向は、1980年代以降急速に拡大した。1913年から2008年にかけて、最高所得分配率の推移は二極化の度合いと密接に関連していたが、約10年のタイムラグがあった。同じことが、アメリカ経済の他のすべてのセクターに対する金融セクターの賃金と教育レベルにも当てはまる。このように、エリート層の所得は一般的に、そして特に金融部門の所得は、立法府の結束の度合いに非常に敏感であり、膠着状態の悪化から利益を得てきた。
さらに、有権者の投票率は富裕層に強く偏っている。1970年代以降、低所得層の投票率が伝統的に低かったが、市民権を持たない低所得労働者が大量に移民してきたことで、それが増幅された。2008年と2010年の選挙では、有権者の投票率は所得と密接に相関しており、低所得世帯から高所得世帯へとかなり直線的に上昇している。アメリカの「1%」は、国民全体よりも政治的に積極的であり、税制、規制、社会福祉に関しても保守的である。最後に、項目別献金件数の大幅な増加にもかかわらず、選挙献金は時間の経過とともに集中している。1980年代には0.01%の高所得者が選挙資金全体の10%から15%を拠出していたが、2012年には40%以上を占めるようになった。その結果、候補者や政党はますます大金持ちの献金者に依存するようになり、この傾向は、高所得有権者の選好を支持する議員のより一般的な観察可能バイアスをさらに強めることになる16。
これらのことは、力関係の変化が、技術革新とグローバル経済統合から生じる不平等化圧力を補完し、悪化させるのに役立ってきたという結論を十分に裏付けている。現在では、所得と富の分配の最上位層における変化は、制度的・政治的要因に特に敏感であり、時には劇的な結果をもたらすというコンセンサスが高まっている。米国では、1979年から2007年にかけての市場所得の増加分の60%が「1%」に吸収されたのに対し、下位90%の増加分はわずか9%に過ぎなかった。同じエリート層が税引き後所得の伸びの38%を占めたのに対し、下位80%は31%だった。1990年代初頭から2010年代初頭の間に、アメリカ人世帯の0.01%の高額所得者が占める割合は2倍以上に増加した。所得の分散は一貫して高所得層に集中している。米国の所得は、90パーセンタイルと50パーセンタイルの比率は1970年代から継続的に伸びているが、50パーセンタイルと10パーセンタイル(つまり、中位と低位の間)の所得の比率は1990年代以降、ほぼ横ばいである。言い換えれば、高所得者が他の人々から引き離されているのである。この傾向はアングロサクソン諸国全般に見られるが、他のほとんどのOECD諸国ではかなり弱いか、あるいは見られない。それでも、全体的な所得格差は、長期的には普遍的に上位の所得シェアに敏感である。多くの国で、上位「1%」以下の9%の世帯のシェアは、1920年代から現在に至るまで安定している(約20%から25%)のに対し、上位のシェアははるかに不安定である。同様の傾向は上位の富裕層にも観察されている。これらのことは、最大所得者の相対的規模が不平等全体の主要な決定要因であり、特別な注目に値することを示している17。
なぜ高額所得者は他の人々を凌駕してきたのか?経済学者や社会学者はさまざまな説明を提唱してきた。役員報酬の上昇と企業価値の増大との関係、特定の経営能力に対する需要の増大、企業取締役会を巧みに操る経営者によるレントの獲得、資本所得の重要性の増大など、経済的要因に焦点を当てる者もいる。また、保守的な政策に偏った党派性や政治的影響力、金融セクターの規制緩和、税率の低下といった政治的な理由を強調したり、最高給与の設定にベンチマーキングや上方偏向したサンプルや向上心のあるサンプルの使用、さらに一般的には社会規範や公平性の概念の変化といった社会的プロセスの役割を強調したりする者もいる。制度的な原因を重視する傾向が強まっているにもかかわらず、需給を前面に押し出した説明には回復力があることが証明されている。1980年から2003年の間に大企業の株式市場価値が6倍になったことで、米国における最高経営責任者(CEO)の給与が同時に6倍になったことを完全に説明できると主張されてきた。勝者総取りモデルの前提に立てば、市場規模が大きくなれば、それだけでトップの報酬が上昇することが期待できる。
しかし、企業規模と役員報酬の相関関係は長期的には成立せず、ここ数十年でさえ、トップ所得の不均衡な上昇は、経営幹部やその他の「スーパースター」にも及んでいる。経営権力を強調する説明は、比較的少数の最高経営責任者(CEO)のみに関係するものであり、他の役職の給与の相対的上昇が同様かそれ以上であることを説明するのは困難である。技術革新(特に情報通信技術)の影響と、特定の事業のグローバルな規模の拡大が相まって、トップパフォーマーの相対的な生産性が、所得シェアの拡大に合わせて上昇する可能性がある18。
しかし、「豊かさは、経済生産性とはほとんど、あるいはまったく関係のない要因に強く影響される」という批判もある。金融セクターでは、報酬水準は規制緩和と密接に結びついているが、観察可能な要因だけでは説明できないほど高い。1990年代までのアメリカの金融労働者の学歴調整後の賃金は他のセクターの労働者と同程度であったが 2006年までには50%のプレミアムを享受し、エグゼクティブになると250%、300%にまで上昇した。このばらつきのかなりの部分はまだ説明されていない。企業幹部だけでなく、金融の専門家にもこのような不釣り合いな利益があることは、競争市場でサービスを確保するために必要な所得を超える所得と定義されるレント・テーキングを示唆している。1978年から2012年の間に、アメリカのCEOの報酬は2012年の恒常為替レートで876%上昇し、スタンダード&プア株価指数の344%、ダウ・ジョーンズ株価指数の389%を劇的に上回った。また、1990年代には、他の最高所得や賃金と比べても、かなり劇的に増加した。
需要に対する教育の供給はこうした動きとは無関係であり、同じ学歴グループ内での所得のばらつきを説明することはできない。実際、雇用や事業活動の中で最も収益性の高い分野では、正規の学歴よりも社会的スキルの方が重要であり、トップエグゼクティブは、企業がアクセスし管理する必要のある顧客、サプライヤー、マネジャーといった譲渡不可能なネットワーク内での地位が評価される部分が大きいのかもしれない。高騰する役員報酬と経済の「金融化」は、最近のトップ所得の増加の直接の原因の一部に過ぎないが、法律や医療など他の分野への影響は、不平等化効果を増幅させている。さらに、富裕層に対する優遇措置は民間産業だけでなく公的領域にも及んでおり、OECD諸国全体で最高税率引き下げの恩恵を受けている。莫大な富の創出は政治的影響力や略奪行為に負うところが大きいが、非西洋社会では力関係がより重要である。中華人民共和国では、政治に精通した、あるいは政治と強いつながりを持つ最高経営責任者(CEO)の報酬が他より高いが、その理由のほとんどはそこにある19。
最後に資本である。富は所得よりも常に偏在し、富裕世帯に強く集中するため、資本所得の相対的重要性が高まったり、富が集中したりすると、所得格差が拡大する可能性が高い。資本の復活はピケティの最近の研究の中心テーマである。この傾向は、大恐慌時に急落した国富の対国民所得比の回復に最も明確に表れている。それ以来、富の相対的な規模は、多くの先進国で、また世界中で大幅に拡大している。同様の傾向で、個人富の国民所得に対する比率と、個人資本の可処分所得に対する比率も上昇した。この発展が不平等に及ぼした全体的な影響については、いまだ論争が続いている。批評家たちは、この増加の大部分は個人住宅の価値上昇を反映しており、資本ストックに対する住宅の寄与の計算方法の調整によって、1970年代以降、いくつかの主要国では資本/所得比率は上昇するどころか、むしろ安定していると主張している。また、国民所得に占める資本所得の割合は、この間OECD加盟国の多くで上昇しているが、高所得者層における資本からの所得と賃金からの所得の相対的な比重は、1970年代から2000年代初頭にかけて一貫して変化していない20。
富の不平等は、異なる軌跡をたどってきた。1970年代以降、フランス、ノルウェー、スウェーデン、イギリスでは、1%の富裕層が保有する個人資産の割合はほとんど変化していない。アメリカの富は、アメリカの所得以上に急速に集中した。1970年代後半から2012年の間に、「1%」が保有する全個人資産の割合は2倍弱になったが、上位0.1%の富裕層では3倍に、上位0.01%の世帯では5倍になった。これは資本所得の分配に劇的な影響を与えた。同じ期間に、課税資本所得全体に占める「1%」の割合は、国全体の3分の1から3分の2へとおよそ2倍になった。2012年には、このグループが配当と課税利子の4分の3を占めた。最も顕著な増加は、このカテゴリーに属する上位0.01%の世帯が獲得する全利息のシェアに関するもので、1977年の2.1%から2012年には27.3%へと13倍に増加した21。
2001年から2010年の間に、純資産分布のジニ係数は0.81から0.85に、金融資産のジニ係数は0.85から0.87に上昇した。勤労所得と資本所得の分布はより密接に関連しているが、賃金所得の相対的重要性は「1%」の間で緩やかに低下している。1990年代以降、投資からの所得は上位所得者にとってより重要なものとなり、低税率化によって税引き後所得への寄与度が高まり、エリートのより多くの部分が投資所得に完全に依存するようになった。1991年から2006年にかけて、キャピタルゲインと配当の変化は、税引き後所得の不平等を高める上で極めて重要であった22。
米国が突出しているとしても、富の集中の拡大は非常にグローバルな現象である。1987年から2013年にかけて、地球上の2,000万人に1人、または1億人に1人の富裕層と定義される超富裕層の富は、世界の平均的な成人が2%であるのに対し、年平均6%の成長を遂げた。さらに、世界の家計資産の8%がオフショアのタックスヘイブンに保管され、その多くが記録されていないと推定されている。富裕層がこのような行為に偏って関与していること、また米国の資産(4%)の推定割合が欧州のそれ(10%)よりはるかに低いことを考慮すると、平等主義的とされる欧州諸国における実際の富の集中度は、税務上の記録から推測されるよりもかなり高い可能性がある。発展途上国のエリートは、海外に資産を分散させている割合がさらに高く、ロシアの場合、国全体の個人資産の半分に達することもある23。
*
過去数十年間における所得と富の不平等の広範な復活は、序論で述べた物語を継ぎ目なく引き継いでいる。本節で検討した変数の多くは、国際関係と密接に結びついている。格差拡大の強力な推進力である貿易と金融のグローバリゼーションは、19世紀に世界的な経済統合が始まったときに大英帝国が保証するようになり、その後、米国の実質的な覇権の下で再確立され、冷戦の終結によってさらに強化されたような、比較的平和で安定した国際秩序を前提としている。労働組合の結成、民間部門の賃金設定への公的介入、所得と富に対する累進性の高い課税など、平等化の主要なメカニズムはすべて、第二次世界大戦中と戦後の完全雇用と同様、世界的な戦争の状況下で初めて脚光を浴びた。米国では、政治的二極化という不平等化現象は、大恐慌の後と第二次世界大戦中に急速に緩和された。継続的な技術革新は当然のことであるが、それに対抗する教育の提供は、まさに公共政策の問題である。最終的な分析によれば、ここ数十年の不平等化シフトの原動力は、大恐慌以降の国家間関係とグローバルな安全保障の進化を反映している。暴力的なショックがグローバルな交流ネットワークを破壊し、社会的連帯と政治的結束を高め、積極的な財政政策を持続させた後、その緩和が所得の分散と富の集中に対するこうした歯止めを侵食し始めている24。
第16章 未来はどうなるのか?
圧力を受けて
この問いに取り組む前に、世界中で経済的不平等は、標準的な指標に頼るだけでは見かけ以上に大きいことを再確認しておく価値がある。まず第一に、所得不平等を測定する手段として最も広く使われているジニ係数は、超高所得者の寄与を把握する上で限られた価値しかない。この不足分を調整すると、実際の不平等水準は全体としてかなり高くなる。第二に、もし報告されていないオフショア資金を個人家計の富の統計に組み入れることができれば、不平等はそのカテゴリーにおいてもより高いことが判明するだろう。第三に、私は一般的な慣例に従い、所得と富の分配の相対的な指標に焦点を当ててきた。しかし、絶対的不平等(高所得者と低所得者の間の格差の幅)の観点からは、西ヨーロッパ諸国の一部で観察されるジニ係数や上位所得シェアがかなり一定であるか、緩やかな上昇にとどまっている場合でさえ、経済成長を考慮に入れると、実際の所得(ユーロまたは他の国の通貨建て)の不均衡が拡大していることになる。
この影響は、資源配分の偏りと成長率の上昇の両方を経験した米国のような社会でより強くなっている。1980年代以降、所得分配のジニ係数が2倍以上になり、1人当たりの平均実質生産高が6倍になった中国では、絶対的不平等が一気に拡大した。最近の相対的所得格差の縮小が力強い経済成長と重なったラテンアメリカでも、絶対的所得格差は拡大し続けている。世界全体では、絶対的所得格差は新たな高みへと上昇している。1988年から2008年にかけて、世界の上位1%の実質所得は、世界の第5、第6、第7階層の所得と同程度のパーセンテージの上昇を記録したが、一人当たりでは約40倍の伸びを示した。最後に、付録で詳しく述べるが、ある社会で理論的に実現可能な所得格差の最大程度は、一人当たりGDPによって異なる。先進国の経済が農耕時代の前身に比べ、極端な資源偏在に対して制度的に寛容でないことを考慮すると、今日の米国が100年前や150年前と比べて不平等が実質的に縮小していることはまったく明らかではない。
最後の注意点は、名目的な不平等が比較的大きい現代経済にのみ当てはまることは事実である。高水準の経済発展が可処分所得のより公平な分配と結びついているヨーロッパ大陸の多くでは、実効的不平等(実現可能な最大不平等のうち実際に達成されている不平等の割合として定義される)が、現在、世界大戦争前に比べてはるかに低くなっていることは疑いない。とはいえ、これらの国々における上位所得者の所得シェアは米国よりも小さい傾向にあるが、可処分世帯所得における比較的緩やかな不平等は、一般的に高いレベルの市場所得不平等を相殺する大規模な再分配の結果であることが非常に大きい。2011年、再分配で有名な5つの社会(デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、スウェーデン)の市場所得(税引き前と移転前)のジニ係数は平均0.474で、米国(0.465)や英国(0.472)とほとんど変わらない数字であった。可処分所得の平均ジニ(0.274)だけが、イギリス(0.355)やアメリカ(0.372)よりもはるかに低かった。
ヨーロッパのいくつかの国々は、ここで挙げた5つのケースよりも市場所得の不平等がいくらか低いものの、再分配の規模が、ごく少数の例外を除いて、アメリカよりも高い(そしてしばしばはるかに高い)ことは、ユーロ圏とスカンジナビアに典型的な、より均衡のとれた最終所得の分配が、主として、強力に平等化する国家介入の拡大した高価な制度の維持に依存していることを示している。このような仕組みは、欧州の平等の将来にとって良い結果をもたらさない。社会的・再分配的な公共支出は、ヨーロッパの大部分ですでに非常に高額になっている。2014年には、欧州11カ国がGDPの4分の1から3分の1を社会支出に充てており、これらの国では中央政府がGDPの44.1~57.6%(中央値は50.9%)を吸収している。政府規模が経済成長に及ぼす悪影響を考慮すると、この割合がこれ以上大きくなる可能性は疑わしい。1990年代初頭から2000年代後半にかけて、国民生産高に占める社会支出の割合は、欧州連合(EU)でも米国でも、またOECD加盟国全体でも、ほぼ横ばいで推移していた。2009年、社会支出は、経済実績の低迷の相関として、また世界金融危機による需要増に対応して再び上昇したが、それ以来、新たに上昇した水準にとどまっている2。
このような均衡のとれた福祉制度が、増大する2つの人口動態の課題にどれだけ耐えられるかは、未解決の問題である。欧州の人口の高齢化はそのひとつである。出生率は長い間、代替水準をはるかに下回っており、当分の間はこの状態が続くだろう。欧州の人口の年齢中央値は、2050年までに39歳から49歳に上昇すると予想されているが、生産年齢人口はすでにピークに達しており、現在から2050年までの間に約20%減少する可能性がある。現在から2050年または2060年の間に、扶養比率(15歳から64歳までの人口に占める65歳以上の人口の割合)は0.28から0.5以上に爆発的に上昇し、80歳以上の人口に占める割合は2005年の4.1%から2050年には11.4%に増加する。それに伴い、年金、医療、介護の需要も増加し、GDPの最大4.5%増となる。このような年齢分布の根本的な再編成は、過去数十年間よりも低い経済成長率を伴うだろう。2031年から2050年までの平均成長率は1.2%、2020年から2060年までの平均成長率は年1.4%または1.5%と、さまざまな予測がなされているが、実際、欧州連合(EU)の主要加盟国ではもっと低くなる3。
ここ数十年の高齢化率は緩やかであったため、不平等に大きな影響を与えることはなかったが、この状況は変化する可能性が高い。原則として、労働者に占める退職者の割合の縮小は、単身世帯の割合の増加と同様に、不平等を高めると予想される。重要性が増すと思われる私的年金は、不平等を維持または増加させる傾向がある。ある研究では、高齢化の結果、2060年のドイツでは格差が大幅に拡大すると予測している。外国生まれの人口が住民に占める割合がEUや米国よりはるかに小さく、扶養比率がすでに0.4に達している日本では、所得格差の拡大が人口の高齢化に大きく起因している。韓国や台湾と同様、高度に制限的な移民政策によって、税引前・移転前の所得分配が比較的平等主義的に維持されてきたことを考えれば、これは悲しむべき結果である4。
これらの予測はすべて、相当量の移民が継続的に流入することを前提としている。このような人口動態の寄与がなければ、ヨーロッパの扶養比率は2050年までに0.6にまで上昇する可能性がある。したがって、何百万人という新参者の入国は、長期的な高齢化の進行を緩和するだけにすぎない。同時に、移民は再分配政策に前例のない試練を与えるかもしれない。著名な人口学者であるデビッド・コールマンは、「第三次人口移行」と名づけた先駆的な研究の中で、移民率や移民の出生率について保守的な仮定を置いた場合でも、2050年までに外国出身者(その定義は国によって異なる)が国民人口に占める割合は、彼が検討した7カ国中6カ国で4分の1から3分の1に達すると計算している: オーストリア、イングランドとウェールズ、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデンである。これらの国々は西ヨーロッパの人口の約半分を占めており、他の多くの国でも同様の変化が起こるだろう。さらに、教育を受けている子供たちや若年労働者の間では、このカテゴリーに属する個人の存在が非常に大きくなり、国全体の半分に達するケースもある。非西洋からの移民は、ドイツとオランダの人口の最大6分の1を占めると予測されている。このような傾向が今世紀半ばまでに緩和されると仮定する説得力のある理由はないため、オランダとスウェーデンは2100年までに、外国に起源を持つ人口が過半数を占める国になる可能性がある5。
このような規模の人口の入れ替わりは、農業の勃興以来の世界史において前例がないだけでなく、予測不可能な形で不平等に影響を与えるかもしれない。経済的観点からは、移民の統合が成功するかどうかにかかっている部分が多い。移民の教育水準は欧州の国民よりもはるかに低く、雇用率は多くの国で、特に女性で低い。こうした問題の持続や悪化は、当該社会に不平等な結果をもたらす可能性がある。さらに、移民一世や最近外国に出身した家族背景を持つ人々のコミュニティの成長は、社会福祉や再分配支出に関する態度や政策に影響を与える可能性がある。アルベルト・アレッシーナとエドワード・グレイザーは、福祉政策は民族的同質性と相関しており、米国が欧州諸国に比べて弱い福祉国家を発展させた理由を説明するのに役立つと主張している。彼らは、移民の増加がヨーロッパの福祉国家の寛大さを損ない、反移民感情が再分配政策を解体するために利用され、「最終的には大陸をよりアメリカ的なレベルの再分配へと押しやることになるだろう」と予想している。少なくともここまでのところ、この予測は実際の展開では裏付けられていない。最近の包括的な調査でも、移民が社会政策に対する国民の支持を損なうという考え方は支持されていない6。
しかし、より具体的な観察によれば、懸念材料はある。しかし、より具体的な観察によれば、懸念すべきことがある。異質性が高まり、移民が増えることは、実際、貧困や不平等のレベルが高くなるだけでなく、社会政策の規定がより手厚くなくなることと関連している。欧州のOECD諸国では、民族の多様性は公的社会支出の水準とは弱い逆相関しか示さないかもしれないが、失業率を媒介とする態度にはより強い負の影響を及ぼす。財政負担の多くを担っているヨーロッパの豊かな人々は、社会の低所得層の多くが少数民族に属している場合、再分配への支持を表明する。英国の調査によれば、民族の多様性によって貧困層が異質な存在として認識されるようになると、税制面での再分配選好が弱まる。異質性の源泉と次元は極めて重要である。移民と宗教的異質性は、民族的マイノリティの存在よりも福祉国家の規定に強力な悪影響を及ぼす。これら最初の2つの要因は、すでにヨーロッパの経験を特徴づけるものとなっており、中東やアフリカからの移住圧力が持続する可能性が高いことから、その関連性は今後も継続し、間違いなく高まるだろう。これらすべてにおいて、欧州の「第三次人口動態の変遷」は、代替出生率以下の人口と移民に対応して各国の人口構成を変容させるものであり、まだ初期段階にあることを認識することが重要である。次世代にかけて、再分配と不平等の既成のパターンが、予測不可能な形で変化する可能性がある。現在の制度にかかる高いコストと、高齢化、移民、異質性の増大がもたらす不平等化圧力とを考慮すると、こうした変化は不平等を抑制するよりも、むしろ不平等を拡大させる可能性の方が高いだろう7。
すべての人口統計学的要因が等しく不平等のさらなる進化に大きな影響を及ぼす可能性があるわけではない。世帯間の所得格差や貧富格差を拡大させる可能性のある同系交配の頻度が、近年米国で増加しているという良い証拠はない。同様に、所得面での世代間移動も鈍化しているようには見えないが、決定的な知見を得るにはより長い期間が必要かもしれない。逆に、アメリカで増加傾向にある所得による居住分離は、長期的には不平等により強い影響を与えるかもしれない。隣人の所得が間接的に自分の社会経済的成果に影響を及ぼし、特定の所得集団の空間的集中が地域財源による公共財の配分を歪める限り、人口の物理的分布における経済的不均衡の拡大は、将来の世代における不平等を永続化させ、実際に不平等を強化すると予想される8。
資本投資の収益率が経済成長率を上回るにつれて、蓄積資本が国民所得に占める割合と、国民所得に対する全体的な重要性の両方が高まり、格差に上昇圧力がかかるというピケティの主張は、かなりの批判を集め、その主唱者はこうした予測に伴う不確実性を強調するようになった。しかし、所得と富の分配における既存の格差を悪化させる可能性のある経済的・技術的な力には事欠かない。グローバリゼーションは、特に先進国において不平等化効果をもたらすと信じられてきたが、近い将来にそれが収まる兆しはない。このプロセスが、「ダボスマン」のイメージに代表されるような、国の政策に縛られないグローバルなスーパーエリートを生み出すかどうかは、まだわからない。オートメーションとコンピュータ化は、その性質上、より自由なプロセスであり、労働への見返りの分配に影響を与えるに違いない。ある試算によると、アメリカの労働市場全体で702の職種の雇用のほぼ半分が、コンピューター化のリスクにさらされている。自動化がいつまでも労働市場を高所得者と低所得者の間で二極化させることはないだろうという予測にもかかわらず、機械が一般的な知能の点で人間に追いつき、あるいは追い越すことを可能にする人工知能の将来の飛躍的進歩は、長期的な結果を予測する試みを無意味なものにしている9。
私たちが人体を作り変えることで、不平等の進化に新たなフロンティアが開かれるだろう。サイバネティック・オーガニズムの創造と遺伝子工学は、個々の人間、さらにはその子孫の間の格差を、天賦の資質や、その人びとが持つ体外的な資源をはるかに超えて拡大する可能性を持っており、それは将来の所得と富の分配にフィードバックする形で行われるかもしれない。ナノテクノロジーの進歩によって人工インプラントの用途と有用性が大幅に拡大するにつれ、その用途は機能回復から機能強化へとますますシフトしていく可能性がある。ここ数年、遺伝子編集の進歩により、ペトリ皿でも生体でも、特定のDNA断片をかつてないほど簡単に削除したり挿入したりできるようになった。このような介入がもたらす結果は個々の生物に限られるかもしれないが、精子や卵子、小さな胚の遺伝子構成を操作することによって遺伝させることもできる。生存不可能な)ヒト胚のゲノムを改変する最初の実験結果が2015年に発表された。この分野における最近の進歩は極めて急速であり、今後も未知の領域へと我々を導いていくだろう。コストと入手可能性次第ではあるが、富裕層はこうしたバイオメカトロニクスや遺伝子改良の一部への特権的なアクセスを享受できるようになるかもしれない。
公衆衛生とは異なり、機能強化はアップグレードであるため、不平等な供給が可能である。すでに提案されている欧米の民主主義国家における法的規制は、私的治療が提供される国々(最も可能性が高いのはアジアの一部)において、私的治療を受ける余裕のある人々に有利な条件を与えることになり、さらに不平等な結果を招きかねない。長期的に見れば、富裕層やコネのある人々のためにデザイナーズ・ベビーを作ることは、遺伝子を持つ者と持たざる者の間の流動性を抑制し、少なくとも理論的には、最終的にプリンストン大学の遺伝学者リー・シルバーが思い描くような、遺伝的エリートである「ジェンリッチ」と「ナチュラル」、あるいはそれ以外の人々のような、2つの異なる種への分岐をもたらすかもしれない10。
教育は長い間、技術革新に対する既定の対応策であった。教育は、技術革新に対する既定の対応策であり続けてきた。グローバル化が進み、コンピュータ化がさらに進展しても、おそらくある時点まではそうであろう。しかし、遺伝子操作や身体と機械のハイブリッド化、あるいはおそらくその両方によって、人間がより不平等になった後では、このパラダイムは限界点まで引き伸ばされるだろう。教育は、人工的な肉体的・精神的強化のまったく新しい程度に対抗できるだろうか?しかし、先走るべきではない。超人の言いなりになるスーパーロボットについて心配する時が来るずっと前に、世界は所得と富の不平等という、より平凡な課題に直面しているのだ。最後にもう一度、本書の中心テーマである「不平等の是正」に戻ろう。では、平準化の見通しはどうなのだろうか?
レシピ
現在、不平等を是正する方法に関する提案には事欠かない。ノーベル経済学賞受賞者たちは、あまり有名ではないが、時には売れ筋の同業者やジャーナリストたちに混じって、所得と富の分配を均衡させるための方策を長々と列挙して発表するという、儲け話に興じている。税制改革はその中でも重要な位置を占めている。(特に断りのない限り、以下は米国の状況を指している)。キャピタル・ゲインを経常所得として課税し、資本所得全般に対してより高い税金を課すべきである。富には直接課税し、世代を超えた富の移転を抑制するような方法で課税すべきである。貿易関税のような制裁措置や世界的な富の登録簿の作成は、オフショアでの脱税を防ぐのに役立つだろう。企業は世界的な利益に対して課税され、隠れた補助金は廃止されるべきである。フランスのエコノミストたちは、富に対して毎年課税し、源泉徴収することを提案している。さらに、資本に対する一時的な課税を強化することで、公的債務を減らし、私的財産と公的財産の比率を均衡させることができるだろう。先に述べた技能に対する需要と供給のアプローチにより、教育の役割が注目されている。公共政策は、学校教育へのアクセスとその質を平等にすることで、世代間の流動性を高めることを目指すべきである。学資を地方の固定資産税から切り離すことは、その方向への一歩となるだろう。就学前教育の普遍的な提供は有益であり、高等教育には価格統制が課されるかもしれない。より一般的には、教育の改善は、競争の激しいグローバル環境における労働力の「スキルアップ」につながるだろう。
支出面では、住宅価値から労働者所有の協同組合、人々の健康まで、低所得者層の資産価値を外生的ショックから守る保険形態を公共政策が提供すべきである。国民皆保険は、そのようなショックに対する緩衝材となるだろう。富裕層でない人々も起業のための信用を確保しやすくし、破産法も債務者に寛容なものにすべきである。貸し手にはインセンティブを与えるか、そうでなければ住宅ローンのリストラを強制すべきである。より野心的な制度としては、ベーシックミニマムインカム、個人の貯蓄に対する上限までのマッチンググラント、株式や債券の最低寄付金を各子供に支給することなどがある。企業規制もアジェンダのひとつだ。特許、独占禁止、契約に関する法律を改正し、独占を抑制し、金融部門をより厳しく規制することで、所得の市場分配を調整することができる。法人税は、CEOの報酬と労働者の賃金中央値の比率に連動させることができるかもしれない。コーポレート・ガバナンスの改革を通じて、経営陣の賃借行動に取り組むべきである。株主と従業員の地位は、後者の代表権と議決権を確保し、利益を労働者と共有するよう企業に強制することによって強化されるべきである。制度改革では、組合の力を復活させ、最低賃金を引き上げ、社会的地位の低い人々の雇用へのアクセスを改善し、連邦政府の雇用プログラムを創設すべきである。移民政策は、技能プレミアムを引き下げるために、熟練労働者の輸入を促進すべきである。グローバル化の不平等化の影響は、労働基準の国際的な調整と、生産地に関係なく海外収益と企業利益に課税することで緩和できる。特に大胆な提案によれば、アメリカは貿易相手国に対し、それぞれの国の中央値賃金の半分に相当する最低賃金を制定するよう求めることもできる。政治分野では、アメリカは選挙資金改革を成立させることで不平等と闘い、投票率を上げる対策を講じるべきである。メディアへの介入は、報道を民主化するかもしれない11。
最近の議論では、コストと便益の規模や現実の政治的実現可能性に十分な注意を払うことなく、政策措置の内容に焦点が当てられている。いくつかの例を挙げれば十分だろう。フランソワ・ブルギニヨンは、アメリカの「1%」に対する実効税率を35%から67.5%へとほぼ倍増させなければ、可処分家計所得に占める彼らの割合を1979年の水準にまで下げることはできないと見積もっている。ピケティは、経済コスト対平等便益の観点から、最高所得税率80%を「最適」と考えているが、「そのような政策がすぐに採用される可能性はかなり低いと思われる」とあっさり認めている。効果的な世界的政策協調を成功の前提とする提案は、そのハードルをめまいがするほど高くしている。ラヴィ・カンバーは、労働基準を調整する国際機関の設立を提唱している。これは、グローバリゼーションの圧力に対抗するための奇跡の武器に等しいが、「そのような機関の政治的実現性や運営上の現実性はさておき」である。ピケティは、この「グローバル資本税」案はユートピア的なアイデアだと明言しているが、ヨーロッパ全体の富裕税が現実的でない「技術的な理由はない」と考えている。しかし、この種の高尚なアイデアは、役に立たないだけでなく、より実現可能な対策から注意をそらす恐れがあり、逆効果になりかねないと批判されてきた。これらすべてにおいて、この提唱のいずれかを実施するために政治的多数派を動員するために必要な手段についての真剣な考察がないことが目立つ12。
アンソニー・アトキンソンが最近発表した、イギリスにおける不平等削減のための青写真は、このような政策志向のアプローチの限界を物語っている。数多くの、そしてしばしば野心的な施策が、包括的な改革パッケージとして積み上げられるの: 公共部門は、「労働者の雇用可能性を高めるイノベーションを奨励」することによって技術革新に影響を与えるよう努めるべきであり、立法者は「消費市場における市場支配力を削減」し、組織労働者の交渉力を復活させるよう努めるべきであり、企業は「倫理原則を反映」した方法で労働者と利益を共有するか、公的機関への供給を禁止すべきであり、所得税の最高税率を65%に引き上げるべきであり、資本からの所得には労働からの所得よりも積極的に課税すべきであり、遺産や贈与に対する課税を強化すべきであり、固定資産税は最新の評価に基づいて設定すべきである; 国民貯蓄債券は、個人の上限まで「貯蓄に対するプラスの(場合によっては補助金付きの)実質利子率」を保証すべきであり、法定最低賃金は「生活賃金に設定」されるべきであり、すべての国民は満期またはそれ以降の日に、資本養老金を受け取るべきであり、「政府は、生活賃金での雇用を、それを求めるすべての人に保証する」べきである(アトキンソン自身は「突飛に見えるかもしれない」と認めている)。さらに、毎年の富裕税や、「個人納税者を対象とした、総資産に基づくグローバルな税制」なども追加される可能性がある。さらに、欧州連合(EU)を説得して、国民所得の中央値に連動する課税給付として、「子どもに対する普遍的ベーシックインカム」を導入すべきである。
アトキンソンは、これが実際に実現可能かどうかについて、経済へのコスト(これは依然として不透明である)、グローバリゼーションの対抗圧力(これは欧州または世界的な政策協調を通じて対抗することを望んでいる)、財政的余裕に焦点を当てた議論を展開している。所得税の引き上げと累進化、低所得者層への所得控除、子ども一人につき多額の課税給付金、全国民の最低所得という4つの主要政策が実施された場合、等価可処分所得のジニ係数は5.5ポイント低下し、英国とスウェーデンの不平等格差は半分強縮小する。もっと限定的な変更であれば、それに応じて3~4%ポイント程度の改善で済むだろう。これを考慮すると、彼自身の説明では、同じイギリスのジニは1970年代後半から2013年の間に7ポイント上昇している。このように、かなり急進的で歴史的に前例のない政府の介入をいくつか組み合わせても、不平等の復活の影響を部分的にしか覆すことはできない。
騎馬民族のいない世界?
「ユートピア的でなくても、こうした政策提言の多くは歴史認識の欠如に苦しんでいる。ギリギリの改革が、市場所得と富の分配における現在のトレンドに大きな影響を与えるとは考えにくい。アトキンソンの議論は、野心的な政策パッケージの価格と、可処分所得の不平等に対する効果の両方を考慮するというユニークな利点がある。より一般的には、このような提案を現実のものにする方法や、それが大きな変化をもたらすかどうかについての関心は驚くほど低いように思われる。しかし、歴史は平準化について2つの重要なことを教えてくれる。ひとつは、急進的な政策介入は危機の時に起こるということだ。世界大戦や大恐慌の衝撃は、共産主義革命の数々は言うに及ばず、これらの特殊な状況に負うところが大きく、異なる状況下では、少なくとも同じ規模では実現できなかったかもしれない均等化政策手段を生み出した。第二の教訓はさらに単純で、政策立案ではここまでしかできない、ということである。社会内の物質的不均衡の圧縮は、人間の手に負えない暴力的な力によって、あるいは現在ではいかなる実行可能な政治的アジェンダの範囲をもはるかに超えた力によって、幾度となく引き起こされてきた。四騎士は馬を降りた。四騎士は馬を降りた。そして、まともな神経を持つ者は誰も、彼らが再び馬に乗ることを望んでいない」
大量動員による戦争は、その役割を終えた。軍事衝突の形式は、常にテクノロジーによって決定的に形作られてきた。古代の戦車や中世の騎士のような高額資産への投資が有利に働くこともあれば、低コストの集団歩兵が有利に働くこともあった。西洋では、近世に財政軍事国家が成熟すると、傭兵に代わって国家的な大衆軍が登場した。民衆の軍事動員はフランス革命で新たな高みに達し、2つの世界大戦を戦うために集められた数百万の軍隊で頂点に達した。それ以来、趨勢は量から質へと、再び逆の方向に動いている。理論的には、核兵器によって大規模な通常戦争は1940年代後半にはすでに時代遅れになっていた。徴兵制は衰退し、より高度な装備を扱う専門家からなる志願兵に取って代わられることが多くなった。
現在も軍事作戦に従事している比較的少数の先進国では、兵役はしばしば主流社会から切り離され、平等な「動員効果」は消滅した。米国では、戦争費用のための増税が真剣な議論なしに可決されたのは、1950年が最後だった。徴兵制がまだ残っていた1964年の歳入法では、ベトナムへの軍事介入が拡大していたにもかかわらず、1981年以前のアメリカ史上最大の減税が行われた。1980年代と2000年代のアフガニスタンとイラクへの侵攻におけるアメリカの軍事費の急増は、減税と同時に所得と富の不平等を拡大させた。1982年のフォークランド紛争前後のイギリスも同様だった。
最近の紛争は比較的小規模であったり、冷戦の場合は実際に敵対行為に発展することはなかったが、より大規模な戦争が勃発したとしても、今後数十年の間にこの軌跡が変わることはないだろう。熱核爆発を除けば、想像しうる最大の紛争である米中全面通常戦争が、非常に大規模な軍隊を巻き込んで生産的に行われるとは考えにくい。70年以上前の太平洋戦争でさえ、大規模な歩兵部隊よりも高価な艦船や航空戦力のほうが優遇されていた。極端な話、核戦争もありえない。ロシアは現在、徴兵制を廃止して志願兵を採用しており、EU諸国の大半はすでに徴兵制を廃止している。大規模な戦争に巻き込まれる可能性のあるインドとパキスタンも、同様に志願兵に頼っている。不安定さを増す近隣諸国の軍事力を凌駕するイスラエルでさえ、この種の移行を構想している。
結局のところ、21世紀の戦場で、非常に大規模な歩兵部隊がどのような成果を上げることができるのかは、明らかではない。将来の戦闘のあり方に関する現在の予測では、「ロボット工学、スマート軍需品、ユビキタスセンシング、極端なネットワーキング、そしてサイバー戦争の潜在的な影響力」に焦点が当てられている。外骨格やインプラント、ひいては遺伝子強化によって身体的・認知的に強化された、数は少ないが高性能な人間の戦闘員が登場するだろう。彼らは、昆虫のような小型のものから自動車のような大型のものまで、あらゆる形や大きさのロボットと戦場を共有することになり、レーザーやマイクロ波などの指向性エネルギー兵器や力場を操作することになるかもしれない。武器の小型化によって、無差別的な武力投射に代わって、特定の個人レベルまで正確に照準を合わせることができるようになり、高速・高高度のスーパードローンが人間のパイロットを不要にするかもしれない。このようなシナリオは、以前の工業化された戦争形態からは大きくかけ離れたものであり、軍と民間の分離をさらに強化するものである。このような紛争がもたらす平等化の効果は、金融市場に集中する可能性が高く、最近の世界金融危機のような混乱が引き起こされる。
小規模な核兵器が限定的に戦術的に使用される戦争についても、ほぼ同じことが言える。全面的な熱核戦争だけが、既存の資源配分を根本的にリセットするかもしれない。公的機関がまだ機能し、十分な量の重要なインフラが無傷のまま残っている時点でエスカレーションを抑えることができれば、政府と軍当局は賃金、物価、家賃を凍結し、銀行からの不要不急の引き出しを阻止し、食料の包括的配給制度を課し、必要な物品を徴発し、希少な資源を戦争努力、政府の運営、生存に不可欠なサバイバル用品の生産に有利に集中配分するなどの中央計画の形態を採用し、住宅を割り当て、場合によっては強制労働に訴えるだろう。アメリカの「デイ・アフター」計画では、経済全体で戦争損失を分担することが、長い間、重要な政策目標だった。大国間で戦略レベルの核弾頭交換が行われれば、物的資本は膨大な規模で一掃され、金融市場は大混乱に陥るだろう。最も可能性の高い結末は、GDPの劇的な低下だけでなく、利用可能な資源の均等なリバランスと、資本から労働へのシフトであろう。
無制限核戦争という終末のシナリオは、これらの予測結果をはるかに超える水準になるに違いない。それはシステム崩壊の極端なバージョンであり、第9章で論じた初期文明の劇的な崩壊をも上回る深刻さである。終末後の世界を描いた現代のSF小説では、乏しい重要資源を支配する者と、奪われた多数派との間に高度な不平等が生じることが想定されることがあるが、前近代史の崩壊後の社会が徹底的に貧しく、階層化されていなかった経験は、将来の 「核の冬」の状況を考える上で、より良い指針となるかもしれない。しかし、そうなる可能性は低い。核拡散は、地域的な舞台におけるゲームのルールを変えるかもしれないが、1950年代以降、大国間の核戦争を防いできたのと同じ存亡の危機が引き続き適用される。さらに、核兵器の備蓄が存在するだけで、米国や中国のような中核地域が通常戦にさえ大規模に巻き込まれる可能性は低くなり、紛争は世界の周辺地域に移される。
兵器技術は物語の一部に過ぎない。人類が時間の経過とともに、より平和的になってきた可能性も考慮しなければならない。石器時代までさかのぼるさまざまな証拠が、人が暴力的な原因で死亡する平均確率が、長い歴史の中で減少していること、そしてこの傾向が続いていることを強く示唆している。この世俗的な変化は、国家権力の増大とそれに伴う文化的適応によってもたらされているように見えるが、すでに述べたような、より具体的な要因が、私たちの種の平和化を強化しようとしている。他のすべての条件が同じであれば、人口の高齢化は、欧米ではすでに始まっており、いずれ世界のあらゆる場所で起こるだろう。このことは、将来の米中関係や東アジア諸国間の関係を評価する上で特に重要である。これらのことは、ミラノヴィッチの「100年前とまったく同じような状況に直面している人類が、世界大戦という大変革を不平等の悪弊の救済策とすることを許さないだろう」という希望を裏付けている17。
黙示録的平準化の次の2頭の騎手は、それほど注目する必要はない。変革的革命は、大量動員戦争よりもさらに徹底的に廃れてしまった。第8章で示したように、単なる一揆が成功することはめったになく、実質的な平等化を達成することも通常はない。所得と富の不均衡を大きく平準化できるのは共産主義革命だけである。しかし、1917年から1950年にかけての共産主義支配の大規模な拡大は、世界大戦に根ざしたものであり、二度と繰り返されることはなかった。その後の共産主義運動は、キューバ、エチオピア、南イエメン、そしてとりわけ1975年までの東南アジアで、ソ連の支援を受けながら時折勝利を収めただけであった。1970年代後半には、アフガニスタン、ニカラグア、グレナダで、最後のささやかな政権奪取が目撃されたが、それは儚いものであったか、政治的に穏健であったかのどちらかであった。ペルーの大規模な共産主義反乱は1990年代にほぼ鎮圧され 2006年までにネパールの毛沢東主義者は内戦を放棄し、選挙政治に参加した。市場改革は、残るすべての人民共和国の社会主義的基盤を効果的に侵食した。キューバや北朝鮮でさえ、この世界的な流れから逃れることはできなかった。現時点では、これ以上の左翼革命は見当たらないし、暴力的な平定に匹敵する可能性を秘めた代替運動も登場していない18。
第9章で論じたような規模の国家破綻やシステム崩壊も、同様に極めて稀なものとなっている。最近の国家破綻の事例は、中央・東部アフリカと中東周辺部に限定される傾向にある。2014年、Center for Systemic PeaceのState Fragility Indexでは、中央アフリカ共和国、南スーダン、コンゴ民主共和国、スーダン、アフガニスタン、イエメン、エチオピア、ソマリアが世界最悪のスコアを記録した。ミャンマー1カ国を除き、次に脆弱な17カ国もアフリカか中東に位置している。1990年代初頭のソビエト連邦とユーゴスラビアの解体や、現在進行中のウクライナでの出来事は、先進中所得国であっても決して崩壊圧力と無縁ではないことを示しているが、現代の先進国、そして実際、多くの発展途上国が同じ道をたどる可能性は極めて低い。近代的な経済成長と財政拡大のおかげで、高所得国の国家機構は一般に、政府機構の全面的な崩壊や同時並行的な平準化が起こるには、あまりにも強力になりすぎ、社会に深く定着しすぎている。また、最も恵まれない社会であっても、国家の破綻はしばしば内戦と結びついてきた。内戦は、通常は平等な結果をもたらさない暴力的ショックの一種である19。
残るは第4の、そして最後の騎手である深刻な伝染病である。新奇で壊滅的な大流行のリスクは、無視できるものではない。熱帯諸国における人口増加と森林伐採のおかげで、動物を宿主とする人獣共通感染症は増加の一途をたどっている。畜産業は微生物が新しい環境に適応しやすくしている。病原体の兵器化やバイオテロリズムの懸念も高まっている。とはいえ、新たな感染症の発生や蔓延を助長する要因-経済発展や世界的な相互接続性-は、こうした脅威の監視や対応にも役立っている。DNA塩基配列の迅速な決定、現場で使用できる実験器具の小型化、コントロールセンターの設置やデジタルリソースの活用による発生状況の追跡能力は、我々の強力な武器である。
この研究の目的には、2つのポイントが重要である。第一に、第10章と第11章で取り上げた前近代における主要なパンデミックの規模に匹敵するようなものが発生した場合、現在の世界で数億人が死亡する必要があり、これは最も悲観的なシナリオをはるかに上回るものである。さらに、将来世界的な大流行が起こったとしても、その大部分は発展途上国に限られるかもしれない。1918年から1920年にかけて世界的に大流行したインフルエンザの死者数は、既存の治療介入ではほとんど差がなかった100年前でさえ、一人当たりの所得水準に強く左右された。今日、医療介入を行えば、同じような重症型のインフルエンザが大流行した場合の全体的な影響は小さくなり、死亡率は高所得国にさらに強く偏るだろう。「スペイン風邪」で報告された死亡率から2004年までの死亡率を推定すると、全世界で予測される5000万人から8000万人の死亡者のうち96%が発展途上国で発生する可能性がある。洗練された兵器化によって、より強力なスーパーバグが生み出されるかもしれないが、そのような病原体を放つことは、国家レベルの行為者にとってはほとんど利益にならないだろう。一方、バイオテロリズムが成功する可能性はごくわずかであり、国家規模あるいはそれ以上の規模で本物の大量死をもたらす可能性はさらに低い。
第二のポイントは、将来の伝染病がもたらす分配経済的影響である。感染症による突然の壊滅的な死亡が、農耕時代のように所得や富の不平等を平準化するかどうかは定かではない。1918年から1920年にかけて世界的に大流行したインフルエンザが、当時の世界人口の3%から5%にあたる5,000万人から1億人を死亡させたと考えられているが、第一次世界大戦の戦火と重なり、物質的資源の分配に大きな影響を及ぼしたかどうかさえわからない。今日のインフルエンザのような一般的な感染症は、貧困層により深刻な影響を与えるが、経済全体がほぼ無傷であったとしても、低技能労働の価値を押し上げるような階級特有の死亡危機を単純に推測することはできない。現代の伝染病が世界中で何億人もの命を奪うような大惨事となるためには、少なくとも短期的には封じ込められず、国境や社会経済的な範囲を超えて人々を殺傷しなければならない。その場合、複雑で相互接続された現代経済とその高度に分化した労働市場への破壊的な影響は、労働供給と資本ストックの評価に関する平等化効果を上回るかもしれない。はるかに統合度の低い農耕社会でさえ、疫病は短期的な混乱を引き起こし、人々を無差別に傷つけた。長期的には、分配の結果は、資本を労働に置き換える新たな方法によって形成されるだろう。疫病で疲弊した経済では、やがてロボットが行方不明になった労働者の多くを代替するかもしれない20。
文明の黎明期以来、歴史に穴を開けてきたような激しいショックが、今後何年も起こらないとは断言できない。大きな戦争や新たな黒死病が、既成の秩序を打ち砕き、所得と富の分配を再編成する可能性は、小さくとも常にある。私たちにできる最善のことは、最も経済的な予測を特定することである。このことは、将来の平準化の実現可能性に重大な疑問を投げかけるものである。歴史的な結果には多くの要因が寄与しており、平準化の歴史も例外ではない。制度的な取り決めは、圧縮的ショックの分配的帰結を決定する上で極めて重要であった。支配者と資本所有者の強制力にばらつきがあったため、ペストによって実質賃金が上昇した社会もあれば、そうでない社会もあった。世界大戦によって市場所得の分配が平坦化した経済もあったが、野心的な再分配制度が奨励された経済もあった。
毛沢東の革命は「地主」を一掃したが、都市と農村の不平等を助長した。しかし、実質的な平準化の既知のエピソードの背後には、常に一つの大きな理由があった。ジョン・D. ジョン・D・ロックフェラーが、1世代後、2世代後の富裕層よりも実質的に一桁も豊かであった理由、ダウントン・アビーのイギリスが、国民皆保険制度と強力な労働組合で知られる社会になった理由、世界中の先進工業国で20世紀第3四半期に貧富の格差がその当初よりもはるかに縮小した理由、そして実際、100世代前の古代スパルタ人やアテネ人が平等の理想を受け入れ、その実践に努めた理由である。1950年代までに、中国の張荘村が完全に平等主義的な農地配分を誇るようになったのには、ひとつの大きな理由がある。3000年前の下エジプトの有力者たちが、死者をお下がりや粗末な棺に埋葬しなければならなかったのも、ローマ貴族の残党がローマ法王からの施しを求めて列をなし、マヤの族長の後継者たちがホイポロイと同じ食事で生計を立てていたのも、ひとつの大きな理由がある; そして、ビザンチン時代や初期イスラム時代のエジプトで地味な農夫が、中世後期のイギリスで大工が、近世のメキシコで雇われ労働者が、後にも先にも同じような人々よりも多くの収入を得、より良い食生活を送っていた大きな理由のひとつである。これらの大きな理由はすべて同じではなかったが、1つの共通した根源があった。記録された歴史の中で、大衆動員による戦争、変革革命、国家破綻、パンデミックによってもたらされた不平等の周期的な圧縮は、完全に平和的な手段による平等化の既知の事例を常に凌駕してきた。
歴史が未来を決めるわけではない。もしかしたら、現代は本当に違うのかもしれない。長い目で見れば、そうなるかもしれない。シンギュラリティ、つまり全人類が地球規模で相互接続された、身体と機械のハイブリッド超生物へと融合し、もはや不平等を心配する必要がなくなるような段階へと、私たちは向かうのかもしれない。あるいは、技術の進歩によって、バイオメカトロニックと遺伝子工学によって強化されたエリート層と、一般的な人間層とが分断され、不平等が新たな極限に達するかもしれない。あるいは、上記のどれにも当てはまらない可能性もある。私たちは、まだ想像すらできない結果に向かっているのかもしれない。しかし、SFは私たちをここまでしか導いてくれない。当分の間、私たちは今ある精神と肉体、そして彼らが作り上げた制度から抜け出せない。このことは、将来的な平準化の見込みが乏しいことを示唆している。ヨーロッパ大陸の社会民主主義国家が、高率課税と広範な再分配という精巧な制度を維持・調整するのも、アジアの最も豊かな民主主義国家が、税引前所得の異例なほど公平な配分を維持し、進行するグローバリゼーションと前例のない人口動態の変革が圧力となり、ますます強まる不平等の潮流を食い止めるのも、困難なことである。格差はどこの国でもじりじりと拡大しており、この傾向は紛れもなく現状に反している。既存の所得と富の分配を安定化させることがますます難しくなるとすれば、それをより公平なものにしようとする試みは、必然的にさらに大きな障害に直面することになる。
何千年もの間、歴史は不平等の長期的な上昇と高位安定を交互に繰り返してきた。1914年から1970~80年代までの60~70年間、世界の豊かな経済も、共産主義体制に陥った国々も、記録された歴史の中で最も激しい平準化を経験した。それ以来、世界の大部分は、資本蓄積と所得集中の持続的な復活という、次の長期戦に突入している。もし歴史がそうであるなら、平和的な政策改革では、今後ますます増大する課題に対応できないことが証明されるかもしれない。しかし、それに代わる選択肢はあるのだろうか。経済的平等の拡大を望む私たちは皆、ごく稀な例外を除いて、経済的平等は悲しみの中でしかもたらされなかったことを覚えておいた方がよいだろう。何を望むかには気をつけよう。
付録
不平等の限界
不平等はどこまで拡大するのだろうか?ある重要な点において、所得の不平等の測定方法は富の不平等の測定方法とは異なる。ある集団の中で富がどれだけ不平等に分配されるかに限界はない。理論的には、ある人が所有するものすべてを所有し、他の人は何も所有せず、労働や移転による収入で生き延びることができる。このような分配では、ジニ係数は~1、あるいは富のトップシェアは100%となる。純粋に数学的な言い方をすれば、所得ジニも完全平等の0から完全不平等の~1まである。しかし、実際には~1に達することはない。なぜなら、誰もが生きていくために最低限の所得を必要とするからである。この基本要件を説明するために、ブランコ・ミラノヴィッチ、ピーター・リンデルト、ジェフリー・ウィリアムソンは、「不平等可能性フロンティア」(IPF)という概念を開発した。一人当たりGDPが低ければ低いほど、一人当たりの生活余剰は小さくなり、所得可能フロンティアはより制限的になる。
一人当たり平均GDPが最低生計費に等しい社会を想像してみよう。この場合、所得ジニは0でなければならない。なぜなら、所得のわずかな格差でさえ、この集団の一部の構成員を生存に必要な水準以下に押し下げてしまうからである。一部の人々が豊かになる一方で、他の人々が飢えるということは確かに起こりうるが、長期的には持続可能ではない。一人当たりの平均GDPが自給自足を少し上回る程度(例えば、100人の人口で1.05倍)であれば、一人の人間が自給自足の6倍の所得を主張する一方で、他の人間は最低限の所得水準で生活することができる。ジニ係数は0.047となり、上位1%の所得分配率は5.7%となる。平均GDPが最低自給の2倍(貧しい現実の経済にとってより現実的なシナリオ)の場合、利用可能な余剰をすべて1人で独占することになり、この孤独なトップ所得者は全所得の50.5%を要求し、ジニ係数は0.495%に達する。このように、IPFは一人当たりGDPの成長とともに上昇する。一人当たり平均生産高が自給の5倍になると、実現可能な最大ジニは0.8近くになる(図A.1)1。
図A.1不平等可能性フロンティア
図A.1は、IPFが最も大きく変化するのは一人当たりGDPが非常に低い水準であることを示している。このため、この基本的なIPFは、主に前近代社会と現代の低所得国における不平等を理解する上で重要である。最低生計費を1990年の国際ドル換算で300ドルの年間所得と定義した場合、これは従来のベンチマークであるが、それよりもいくらか高いレベルの方がより妥当かもしれない。つまり、図A.1に描かれている範囲は人類史のほとんどをカバーしていることになる。国レベルでは、300ドルの自給自足レベルの所得の5倍という閾値に初めて達したのは16世紀初頭のオランダで、1700年ごろのイギリス、1830年までのアメリカ、19世紀半ばのフランスとドイツ、1910年代の日本、そして中国全体では1985年になってからであり、インドではその10年後である2。
観察された所得ジニ係数を最大可能値(IPF)で割ると、「抽出率」が得られる。これは、理論上可能な不平等のうち、生計を維持する以上の所得を持つ者が実際に抽出した割合を測定するものである。抽出率は、完全平等の条件下での0%から、一人当たりの総生計を超える全生産を一人が吸収した場合の100%までの幅がある。観測されたジニスとIPFの差が小さければ小さいほど、抽出率は100%に近づく。Milanovic、Lindert、Williamsonは、ローマ帝国から英領インドまでの28の前近代社会について、所得分配の粗い指標を提供する社会表(1688年のGregory Kingの有名なイギリスの社会表に遡る形式であり、領主から貧困層までの31の階級を区別している)と、入手可能な限りの国勢調査情報を組み合わせて、抽出率を計算している(図A.2)3。
これら28の社会における所得の平均ジニ係数は約0.45であり、抽出率は平均77%である。より貧しい社会は、より先進的な社会よりもIPFに近い傾向がある。1990年の国際ドル換算で1人当たり平均GDPが1,000ドルを下回る21の社会では、平均抽出率は76%であり、1人当たり平均GDPが1,000ドルから2,000ドルの7つの社会の平均抽出率78%と実質的に同じである。これは、一人当たりGDPが最低生活費の4倍から5倍のレベルまで経済的パフォーマンスが向上して初めて低下する。1732年から1808年までのイングランドとオランダ、またはオランダの平均抽出率は61%である。サンプルの中で最も高い5つの抽出率は97%から113%であるが、これはデータが不十分なためであり、特に推定されるジニが暗黙のIPFを大幅に上回っているケースである。現実の社会では、実際の不平等水準がIPFに達することはなかったし、それに近づくこともなかったはずである。なぜなら、一人の支配者やごく少数のエリートが、他のすべての人々が自給自足しかできないような人口を支配できるような社会を想像するのは難しいからである。それでも、これらの5つの社会が植民地支配や外国からの征服エリートによって支配されていたことは注目に値する。
図A.2 先工業化社会における推定所得ジニ係数と不平等可能性フロンティア
IPFと搾取率を計算することで、2つの重要な洞察が得られる。それは、初期の社会は不平等になりがちであったという事実である。貧困にあえぐ農耕民の上に、裕福な「1%」と、兵士、行政官、商業仲介者からなる「数%」が重なり合った社会だけが、IPFに近い採掘率を生み出すことができたのである。しかし、これはよくあるパターンだったようだ。図A.2にプロットされた推定値の内的一貫性から、私たちはいくらかの安心感を得ることができるかもしれない。これらのデータセットがすべて同じ方向に私たちを導き、その結果、過去の不平等水準について重大な誤解を招くような印象を与えるということはありそうにない。2つ目の重要な観察は、集約的な経済成長によって最終的に抽出率が低下したことである。この現象の規模は、サンプリングされた28の社会と 2000年前後の同じ国または一部併存する16の国との比較によって示されている(図A.3)5。
図A.3産業革命以前の社会(実線)とそれに対応する現代社会(空洞)の抽出率
抽出率に見られる不連続性は、1人当たり平均GDPの水準が大きく異なる場合、所得ジニ係数を比較することがいかに誤解を招きかねないかを示している。0.45と0.41で、前近代と近現代のサンプルの平均ジニ値はかなり似ている。額面通りに受け取れば、近代化の過程で不平等が緩和されたことを示唆しているに過ぎない。しかし、一人当たり平均GDPは、近代サンプルではそれ以前のサンプルの11倍であったため、平均抽出率は76%に対し44%とはるかに低かった。この尺度で見ると 2000年までにこれらの社会は、より遠い過去に比べてはるかに不平等ではなくなっていた。上位所得シェアの未調整比較はさらに問題がある。平均一人当たりGDPが最低生活費の1.05倍に相当し、上位1%の所得シェアが5.7%である架空の社会における、1人の裕福な個人と99人の貧しい個人の例を思い出してほしい。まさにこの上位1%の所得シェアが 2000年のデンマークで確認されたのである。この国の平均一人当たりGDPは、私の思考実験の73倍以上であった。経済発展のレベルが劇的に異なれば、不平等も表面的には同じようなレベルになる。歴史的な所得分布の未修正推定値は、私が「実効的不平等」と呼ぶもの(理論的に実現可能な不平等の程度との関係で定義される)が時間とともにどのように変化したかの理解を曇らせる可能性がある。これらの数値の信頼性の問題はさておき、イングランドの所得ジニ係数は1290年頃に0.37,1688年に0.45,1759年に0.46,1801年に0.52であり、不平等が徐々に拡大していることを示唆している。オランダでは、所得ジニスは1561年の0.56から1732年には0.61に上昇し、1808年には0.57に低下した。これらの数字にまつわる不確実性を考慮すると、これらの特定の観察に過度の重きを置くのは賢明ではない。重要なのは原則である。採掘率は、ジニ係数だけよりも現実の不平等をよりよく知ることができる。
ということは、従来の不平等指標は、現代社会における実質的な所得不平等の程度を、より遠い過去や今日の最貧発展途上国のそれと比べて過大評価しており、結局のところ、経済発展が実質的な平和的平準化を支えてきたということなのだろうか。この疑問に対する答えは、実効的不平等をどのように定義するかに大きく依存する。標準的な不平等指標を文脈に応じて調整することは、虫の居ぬ間の話となる。実際の所得水準は、単に生理的な自給自足だけでなく、強力な社会的・経済的要因によっても決まる。ミラノヴィッチは、IPFと抽出率の概念を導入した直後、生計の社会的側面を考慮することで、このアプローチを洗練させた。1990年の国際ドル換算で300ドルという最低年収は、確かに肉体的な生存には十分であり、超低所得社会では実行可能な基準でさえあるかもしれない。しかし、経済が豊かになり、社会規範が変化するにつれて、自給自足の必要性は相対的に高まっていく。今日、公的な貧困ラインが従来の最低生活水準と一致しているのは、最貧国に限られている。他の国々では、一人当たりGDPが高いため、より寛大な制限が設けられている。社会的に許容される最低限度の生活とは何かという主観的な評価もまた、全体的な生活水準に敏感であることを示している。アダム・スミスが自身の時代における最低必要条件を定義したのは有名な例である。彼の意見では、最低限必要なものには、「生活を維持するために欠くことのできない商品だけでなく、その国の習慣によって、信用できる人々、たとえ最低の階級の人々であっても、これがないと不潔であるとされるもの」、たとえばイギリスではリネンのシャツや革靴などが含まれる。しかし、貧困水準はGDPと同じ速度で変化するのではなく、むしろ遅れている。弾力性を0.5として計算すると、ミラノヴィッチは、社会的ミニマムで調整した場合、一人当たり平均GDPが一定水準にある場合のIPFは、むき出しの生理的自給ニーズだけで決定されるIPFよりも大幅に低くなることを示している。平均一人当たりGDPが1,500ドルの人口では、IPFは0.8から0.55に低下し、3,000ドルでは0.9から0.68に低下する(図A.4)6。
図A.4 社会的最小値の違いによる不平等可能性フロンティア
社会的最小値の変化を考慮するしないにかかわらず、イングランドでは1688年から1867年の間、アメリカでは1774年から1860年の間、抽出率は安定していた。しかし、GDP成長率に対する社会的ミニマムの弾力性0.5をIPFの計算に組み入れると、これらの2つの期間において、暗黙の抽出率はおよそ80%となり、観察された不平等を生理的最低生計費に関連づけることで得られるおよそ60%よりもはるかに高くなる。これとは対照的に、第二次世界大戦以降の抽出率は、どちらの定義にせよ、かなり低くなっている。20世紀以前は、経済生産高が増加している間でも、エリートが利用可能な余剰のかなり一定したシェアを獲得し続けたため、実効的不平等は高いままであった。このことは、暴力的な圧縮期を除けば、社会的に決定された生計基盤に制約された実効的不平等は、前近代の歴史を通じてだけでなく、工業化の初期段階においても一般的に高かったことを示唆している。したがって、ジニ係数や上位所得分配率で表される名目的不平等と、社会的最小値で調整された実質的不平等の尺度は、大圧縮以前の大規模な所得格差の印象を支持することに収斂する7。
しかし、現在はどうだろうか。21世紀の最初の10年の終わりまでに、社会的ミニマムの調整の有無にかかわらず、米英の抽出率は約40%で、1860年代の半分に過ぎなかった。このことは、最近の不平等が復活した後でも、この2カ国が実質的には過去よりもはるかに平等主義的であることを意味するのだろうか?そうとは限らない。重要なのは次のような問題である。化石燃料の採掘に依存するのではなく、食料生産、製造業、サービス業をある程度組み合わせた経済において、一人当たりGDPが一定水準であれば、経済的に実現可能な所得不平等の最大水準はどの程度なのだろうか?米国の可処分所得のジニ係数は、理論的に可能な最大値として、生理的な最低生活を超える余剰をすべて1人でまかなうシナリオでは0.99、社会的に決定された最低所得を超える余剰をすべて1人でまかなうだけのシナリオでは約0.9となる。議論のために、このような社会が何らかの形で政治的に存続可能であることを認めるとして、たとえそのために一人富裕層が3億2,000万人の同胞を取り締まるためにロボットの軍隊を雇う必要があるとしても、一人当たり平均年間GDP53,000ドルを生み出す経済を維持できるかどうかを問わねばならない。このような贅沢な不平等社会では、人的資本を生産・再生産し、このレベルの生産高を達成するのに必要な国内消費(アメリカのGDPの70%近くを占める)を支えることはできないだろう。したがって、「実質」IPFはかなり低くならざるを得ない8。
しかし、どの程度低いのだろうか。米国の可処分所得のジニ係数は現在0.38に近い。仮に、2010年のナミビアのジニ係数が0.6であったとすると、一人当たりの平均GDPは現在の水準を下回ることになる。この場合、有効採掘率は63%となる。別の文脈で、ミラノヴィッチは、実現可能な労働と資本の所得格差に関するかなり極端な仮定の下でさえ、アメリカの所得分配全体のジニ係数は0.6を超えることはないと主張している。しかし、アメリカ型の経済にとっては、0.6でも高すぎるかもしれない: ナミビアの1人当たりGDPは実質的に米国の7分の1程度であり、経済は鉱物輸出に大きく依存している。仮に真の上限が0.5だとすると、アメリカの現在の有効採掘率は76%で、前述の28の前近代社会の平均値に相当し、1860年のアメリカの84%に近い。1929年の可処分所得のジニ係数は0.5を下回ることはなく、社会的最小値で調整したIPFが0.8近くであることから、抽出率は約60%となる。しかし、一人当たり実質GDPが現在の4分の1以下だった1929年でさえ、経済的に実現可能な最大ジニは、現在より高いとはいえ、0.8未満であったはずである。現時点では、さまざまな数値の実験から得られるものはほとんどない。不平等が経済成長に及ぼす悪影響を測定することが可能であるならば、現在の生産水準が達成できなくなる不平等の水準も推定できるはずである。経済学者がこの問題に取り組むことを期待したい9。
歴史の全過程において、所得格差の可能性はさまざまな要因によって制限されてきた。経済的パフォーマンスが非常に低い水準にある場合、不平等は、まず第一に、最低限の生理的生計を確保するのに必要な量を超える生産量によって制約される。ジニ係数が0.4という現代の基準からすると中途半端な数値は、一人当たり平均GDPが最低生計費の2倍しかなく、不平等の可能性が0.5程度の所得ジニに制限されている社会では、実効的不平等が極めて大きいことを示している。開発の中間レベルでは、社会的最小値が主要な制約となる。例えば、1860年、米国の平均一人当たりGDPが最低生計費の7倍に達したとき、社会的ミニマムが意味する実現可能な最高ジニまたはIPFは、裸の生計費だけで決定されるジニ0.86に対して0.63と非常に低く、それに応じて有効抽出率も62%ではなく84%と高かった。人口の半数以上がまだ農業に従事していた当時、理論上の所得不平等の可能性はかなり高かっただろう。社会的ミニマムに基づくIPFジニスが0.7台や0.8台に上昇し、近代的な経済発展に伴うIPFが低下するにつれて、この状況は変化した。ある時点で2つのフロンティアは交差し、後者が潜在的不平等を最も強力に抑制するようになった(図A.5)10。
私のモデルは、IPFが歴史的な所得分配の全領域にわたってかなり安定していることを示唆している。一人当たり平均GDPが最低生計費の2~3倍に相当する社会における0.5台と0.6台の実現可能な最大ジニスは、一人当たり平均GDPが最低生計費の5~10倍に相当する、より高度な農耕社会と初期工業化社会のジニスに酷似している。変わってくるのは、主要な制約の性質であり、裸の自給自足から社会的ミニマム、そして経済的複雑さへと変化する。私はIPFの経済パフォーマンスに対する感度の低さを「不平等の開発パラドックス」と呼んでいる。IPFが経済発展の異なる段階間で大きく変化しないのであれば、古代から現在までのジニ係数を直接比較することは正当である11。
図A.5さまざまなタイプの不平等可能性フロンティア
今日のアメリカやイギリスにおける不平等の実質的な抽出率が150年前と同程度に高いかどうかは未解決の問題であるが、社会的最小値だけに基づく計算が示唆するように、当時と現在とで不平等が半減したり、それに匹敵する程度に低下したりしたわけではないことは間違いない。アメリカにおける現在の有効抽出率は、1929年当時よりも低いことはほぼ間違いないが、不平等は実質的に著しく持続している、あるいは復活している。しかし、どこでもそうだというわけではない: スカンジナビア諸国のような0.2台半ばの可処分所得のジニ係数は、IPFをどのように定義するかにかかわらず、より遠い過去に比べればはるかに低い。最後に、潜在的不平等に対する制約が国際比較にどのような影響を与えるかを簡単に説明し、この専門的な解説を終える。可処分所得はスウェーデンと比べて米国ではどの程度不平等に分配されているのだろうか。ジニスが約0.23と0.38であることから、アメリカの不平等は約3分の2高いと言える。この比率は、想定上の最大値を設定するためにIPFを課しても変わらない。両国のGDP関連IPFを0.6と仮定すると、アメリカの抽出率63%はスウェーデンの38%よりも3分の2高い。しかし、所得格差の可能性は、単に上限に達するだけではない。市場経済では、一人当たりの生産高を高水準に維持するためには、可処分所得の不平等がゼロを大幅に上回る必要がある。これまでの上限である0.6に加え、例えば0.1という実現可能な最小ジニを挿入すれば、50%ポイントの不平等可能空間(IPS)と呼ぶべきものが生まれる。スウェーデンの不平等がこの空間の約4分の1を占めているのに対し、アメリカは半分強である。この調整により、アメリカの可処分所得分布は、実質ベースでスウェーデンのそれの少なくとも2倍の不平等となる。
