Contents
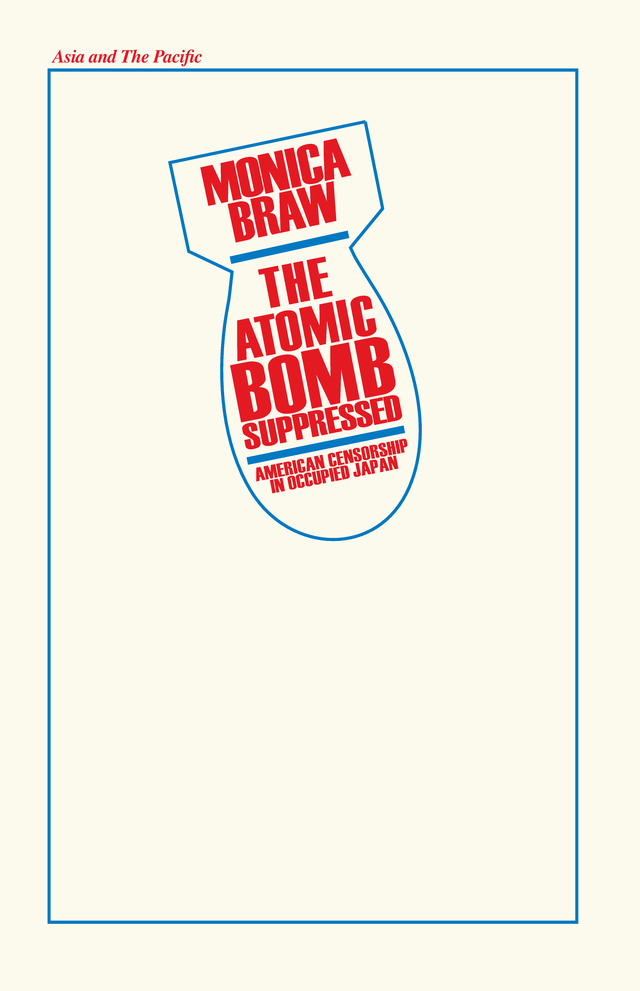
The Atomic Bomb Suppressed: American Censorship in Occupied Japan
目次
- 図
- 序文
- 略語
- 第2版への謝辞
- 謝辞
- 1. はじめに
- 2. 世界に提示された原爆
- 3. 米国の占領計画と検閲の理想と目標
- 4. SCAPが日本の報道を指揮する
- 5. 連合国と占領
- 6. 検閲の実際
- 7. 違反に対する処罰
- 8. 原爆の検閲
- 9. 原爆禁止の理由
- 10.日本におけるアメリカの検閲活動の結果
- 備考
- 参考文献
- 索引
図
- 1. SCAPスタッフ
- 2. 民間検閲分遣隊の組織図
- 3. 検閲地区の担当区域
- 4. 報道局、PPB、CCDの組織図
- 5. 検閲の対象となる新聞資料の流れ
- 6. 検閲の例
- 7. 外国産の検閲
- 8. SCAP内での検閲に関する議論の例
- 9. 広島・長崎への原爆投下に関する日本の報告書の分類
- 10. 郵便検閲の例
序文
マーク・セルデン
1945年夏、広島と長崎への原爆投下によって第二次世界大戦の勝利の頂点に立ったアメリカは、敗戦国日本を自由で民主的な資本主義社会として作り直すべく、自国のイメージに沿った占領作戦を開始した。この占領は、戦争と平和的移行の歴史において稀有な成功であったと広く評価されている。わずか6年間で、アメリカは永続的な民主政治の種を蒔き、荒廃した経済を急速に回復させ、その後の経済大国としての道を開き、日本の主権を回復させたのである。
モニカ・ブラウは、この入念な調査とニュアンスに富んだ著作の中で、機密指定を解除された米国公文書館や、原爆被害者や日本政府当局者へのインタビューをもとに、検閲や言論の自由、原爆外交、米国の占領政策について厄介な問題を提起し、戦後の世界秩序の中心的な前提条件を再考するよう促している。
米国が日本帝国国家の検閲と抑圧の機構を破壊し、ファシズムの経済的根源と指摘した巨大財閥企業を解体し、民主的で立憲的な統治へのコミットメントを宣言していたまさにその時、占領当局はダグラス・マッカーサー元帥の指揮の下、検閲の秘密機構を導入した。米国の検閲官は、日本の世論を形成し、米国を世論の批判から守り、原爆の被害者への影響に関する情報を米国が独占することを目的としていた。
この研究は、日本への原爆投下に関連した米国の検閲機構の内幕を詳述し、日本の民主主義、世界的大国としての米国、世界平和、そして原爆の被害者に対するさまざまな影響を評価する。本書は、米国の検閲官が日本の報道機関に対し、包括的な検閲と検閲後の統制をどのように実施し、小説、詩、童話などの文学作品や、原爆投下という厄介な問題を扱った映画をどのように禁止したかを示している。占領軍検閲の最高位に達したある異常なケースでは、チャールズ・ウィロビー将軍が、カトリックの医師ナガイ・タカシの個人的な体験談の出版を最初は拒否し、後に許可した。ただし、『長崎の鐘が鳴る』をフィリピンでの日本軍の残虐行為に関する体験談と一緒に出版するという条件付きだった。その結果、日本の民間人に対する原爆投下は、日本の戦時中の残虐行為と道徳的に同等であることを、知らず知らずのうちに黙認することになった。検閲の仕組みが整いつつあった時でさえ、アメリカ当局は日本の新憲法(第21条)に「検閲は、これを保持しない」と書き込んだ。
ブラウの検閲問題の公平な扱いは、一般的な検閲と特に原爆検閲の問題をめぐる占領軍内部の深く根強い分裂を明らかにしている。体制が一枚岩からほど遠いものであったとしても、この研究はそれにもかかわらず、検閲が次のようなものであったことを示している:
- 原爆被害者の声を封じ込め、原爆戦争全般と放射線の影響に関する基本的な情報を隠すことによって、戦後の世界的な核の議論を歪めた;
- 秘密主義を強調し、医学的研究結果の普及を禁止することで、原爆被害者の治療を妨げた。このようなアプローチは、被害者を救済するためというよりも、米国の核覇権を維持するためのものであった;
- 原爆被害者や原爆批評家が不満を表明する場を否定し、民主主義政治に二枚舌の基準を設けることで、戦後日本の政治と意識を形成した。
歴史家、調査報道ジャーナリスト、小説家であるモニカ・ブラウは、核戦争、米国の世界的役割、民主主義移行の本質をめぐる継続的な世界的議論に貢献する洞察をこの研究にもたらした。
- 略語
- ABCC 原爆傷害調査委員会
- AEC 原子力委員会
- AFPAC 太平洋軍
- AFSWP 南西太平洋軍
- ASF 米軍サービス部隊
- CCD 民間検閲分遣隊(SCAP)
- CCS 統合参謀本部 CIC防諜部隊分遣隊(SCAP)
- CIE 民間情報教育課(SCAP)
- CIS 民間情報部(SCAP)
- ESS 経済科学部(SCAP)
- FEC 極東委員会
- G-2 情報部;情報課長(GHQ)
- GHQ General Headquarters (SCAP); 特に日本語ではSCAPと同義に使われる。
- JCAC 陸海軍合同民政委員会
- JCS 統合参謀本部 JIC 統合情報委員会
- MED マンハッタン工区
- MLC 軍事連絡委員会(AEC対JCS)
- OCCI 防諜局長室(SCAP)
- OSRD 科学研究開発局
- OSS 戦略サービス局
- POLAD SCAP政治顧問(国務省)
- PPB 報道・画報・放送部(SCAP)
- PPS 国務省政策企画スタッフ
- RG 米国国立公文書館記録グループ
- SCAP 連合国最高司令官 (SCAPの地位にあったダグラス・マッカーサー元帥と占領当局全般を指す言葉としてよく使われる。GHQも参照のこと)
- SPU特別プロジェクトユニット、ESS、SCAP
- SWNCC 州・海軍調整委員会
第2版への謝辞
『The Atomic Bomb Suppressed』の初版は、スウェーデンのルンド大学の博士論文として出版された。この改訂第2版では、1986年以降に私が注目した研究や情報を盛り込み、読者がより理解しやすいように、いくつかの部分を省略した。
特に、マーク・セルデンとM.E.シャープのアニタ・オブライエンに感謝したい。『The Atomic Bomb Suppressed』を日本語に翻訳した立花誠逸氏には、改良と追加情報を提供していただいた。日本占領政策学会はまた新しい知識を提供してくれた。ユッシはコンピューターを共有してくれただけでなく、明るく批評的であり続けてくれた。
東京
1990年11月27日
謝辞
スウェーデンから日本、そしてアメリカへと続くこの仕事において、数カ国の多くの人々が私を助け、励ましてくれた。私の最大の恩人は、今も広島と長崎に住み、自分たちの体験を世界に伝えようとたゆまぬ努力を続けている被爆者の皆さんである。特に、長崎の岩松重利教授と広島の今堀誠司教授を挙げたい。特に天川明教授は私の研究に関心を示してくれた。江藤淳教授には、占領軍の検閲に関する膨大な資料の多くを快く共有していただいた。また、読売新聞の前澤武氏、雄松堂書店の新田光男氏にも感謝したい。
米国では、ウィルコム・E・ウォッシュバーン博士が多くの有益な紹介をしてくれた。国立公文書館では、特にエドワード・リースとジョン・E・テイラーが貴重な資料を紹介してくれた。メリーランド大学のゴードン・W・プランゲ・コレクションでは、フランク・シュルマンと奥泉栄三郎が重要な資料を紹介してくれた。マーリーン・E・メイヨー教授は占領政策について議論し、故ゴードン・W・プランゲ教授はすでに重病を患っていたが、私の質問に答えてくれた。
スウェーデンでは、特に私の大学時代の恩師であるラース=アルネ・ノルボルグに感謝したい。スウェーデン放送協会の科学・研究部門の編集長であった故ゲルトルート・ブルンディンは、私を励まし、仕事と勉強を両立させる機会を与えてくれた。兄のクリスチャンは、私に多くの助言を与えてくれた。ルンド大学歴史学科では、レイフ・エリアソンとトゥリ・アグレルが、私が必要とするすべてのものを手配してくれた。Britt Hörnstedtは揺るぎない支援を与えてくれた。また、ABF/TBV(スウェーデン労働者・公務員研究組織)内の平和教育の一環として、この仕事の成果を一般の人々に広めてくれた。スウェーデン外務省の平和財団からの助成金により、この著作のスウェーデン語による要約・普及版が可能となった。
クリス・クリーマイヤーとバーバラ・イェーツには、私の英語に対する批判やその他のコメントをいただいた。アキ・タカヤナギは、私のワープロ作業を手伝ってくれた。ラピッドプリンティングの平尾元彦氏も私の仕事に大きな関心を寄せてくれ、アメリカ占領下の郵便検閲官の仕事についてさらに詳しく教えてくれた。
最後に、私の教授であり指導教官でもあるヨーラン・リスタッドは、アドバイス、コピー、連絡先、本などを含む数え切れないほどの手紙で私を導いてくれた。私の父ラース・ブラウは、言葉でも行動でもたゆまぬサポーターであり、最初から私に何でもできると信じさせてくれた。夫のユハニ・ロンポロは、叱咤激励しながら私の努力を支えてくれた。
東京
1986年2月19日
抑圧された原爆
占領下の日本におけるアメリカの検閲
1 はじめに
1945年8月に広島と長崎を破壊した原子爆弾から45年、世界は核兵器の結果に関する資料で溢れている。私たちは、核兵器が世界中の主要都市に向けられ、新たな「装置」が絶えず設置されているという事実を知っているだけでなく、もし核兵器が使用された場合の筆舌に尽くしがたい結果を実感している。人類が生活するのに適した環境を残さない「核の冬」や、建物は残るが生命を残さない中性子爆弾の話は聞いたことがある。
それに比べれば、広島と長崎の原爆はとんでもなく小さなものだった。被害を受けたのは50万人にも満たない。今日、破壊された都市は、大惨事の痕跡を探さなければならないような、広大な中心地となっている。初めて広島と長崎を訪れる人は皆、驚き、そして恐らく、少なくとも一瞬は、45年前に現実のものとなった恐怖を疑いたくなるだろう。しかし、それらの恐怖は、過去に対する悪夢として、また未来や生まれてくる世代の健康に対する恐怖として、いまだに被爆者を悩ませている。
ヒロシマとナガサキの被爆者は、核戦争から生き延びるということがどういうことなのかを語ることができる唯一の人間である。にもかかわらず、世界は時折しか彼らの声に耳を傾けてこなかった。実際、世界が核兵器の影響に関心を持つようになったのは、ごく最近のことである。今日、私たちはこのような懸念が広まる時代に生きているが、1969年にはそうではなかった。当時は、私のような若いスウェーデン人女性が広島に到着し、広島への原爆投下が何を意味するのかをほとんど理解していなかったことに愕然とすることもあり得た。私は、自分自身の認識不足と、被爆者の話を聞いてもらえなかった悲しみに打ち震えた。
そのとき私は、ヒロシマやナガサキが一般の人々の記憶にないのは、単に無関心と惰性によるものだと思っていた。私の母国スウェーデンの歴史書では、なぜ原爆投下についてほんの少ししか触れられていないのか、私には説明がつかなかった。しかし、作家である私は、被爆者にインタビューし、彼らの話を出版することで、この知識不足をできる限り解消したいと思った。
しかし、私はすぐに、そのようなインタビューは常に可能だったわけではなく、ましてや出版することは不可能であったことに気づいた。私が会った被爆者の多くが、原爆やその影響、広島・長崎の被爆者の状況に関する資料は検閲されていると話してくれた。その一人が西森一誠という医学博士で、病理学、特に血液中の白血球数を専門としていた。長崎への原爆投下当時、彼は医学生だった。戦後、彼は原爆の人体への影響に関する研究に専念することにした。しかし、それは非常に困難なことであった:
研究する余裕がなかったからでもある。生計を立てなければならなかったからだ。しかし、研究を行ったとしても、その結果を公表することができなかったからでもある。原爆投下直後のこの時期の研究は重要だっただろう。アメリカは私たちに中止を命じはしなかったが、多くの制限を課し、例えば、すべてを英語に翻訳しなければならなかった。
また、私たちが集めた検死資料をすべて取り上げ、アメリカに送ってしまった。その半分でも残っていれば、私たち病理学者は原爆の人体への影響について研究できただろうに。しかし、原爆投下とその直後という重要な時期の剖検資料がなかったのである。その資料は30年もの間、私たちに返却されることはなく、私たちが何度も求めてようやく返却された。
1947年に広島で始まった原爆傷害調査委員会(ABCC)の調査結果についても、私たちは何も知らされなかった。結果はすべてアメリカに送られた。日本で発表される可能性はなかった。加えて、ABCCは調査だけを行った。治療しようとはしなかった。ABCCは多くの秘密を守っていた。そのため、被爆者は自分たちが実験動物であるかのように感じていた。私は医師として、研究中に何か新しいことを発見したら、全人類のためにそれを公表するのが常識だと思う。しかし、ABCCはその研究を共有しなかった。もし、医学において高い知識を持つアメリカ人がそれを実行していたら、多くの患者が救われていただろう1。
原爆投下に関する情報拡散の限界について教えてくれたもう一人の人物は、日本映画社のカメラマンであった井上末男氏:
私たちの計画は、ジュネーブの赤十字に原爆の非人道性を訴えることだった。私たちのチームは、原爆の影響について研究する学術調査グループにも属していた。私たちは32人か33人だった。月16日、私たちは長崎で撮影を開始した。私たちは10月24日まで撮影を続けたが、アメリカの憲兵隊に逮捕された。その後、すべての作業が中止された。フィルムはすべて没収された。私は東京に戻るように言われた。
会社は没収に抗議したが、アメリカ海軍の命令だと言われた。アメリカ海軍の命令だと言われた。それで彼らは命令を変更し、もっとフィルムを撮る許可をくれた。私たちは広島での撮影を終え、長崎に戻った。12月までに私たちは仕事を終えた。そして、フィルムの編集を命じられた。フィルムはアメリカに持ち帰られた。私たちが撮影し編集したものすべて、小さなカットも含めてだ。全部で3万フィートのフィルムだった。フィルム代は日本政府が負担しなければならなかった。
しかし、アメリカ人に渡す前に、こっそりフィルムをコピーした。このフィルムのことを知っていたのは4人だけだった。もし進駐軍の当局が知っていたら、おそらく私たちを沖縄に送って重労働をさせていただろう。コピーした理由は、原爆の非人道性を証明したかったからだ。そのフィルムをジュネーブの赤十字に送りたかった。しかし、占領下にあっては、それをする勇気はなかった。占領が終われば、上映できるかもしれないと思ったからだ2。
情報、新聞、映画製作とは無関係の人々でさえ、規制の存在を知っていた。1945年、内田司は長崎の小学生だった:
原爆が投下された浦上地区は、アメリカによってブルドーザーが運び込まれた。瓦礫の下にはまだ多くの死者がいた。にもかかわらず、アメリカ人はブルドーザーを猛スピードで走らせ、死者の骨を砂や土と同じように扱った。土は低いところまで運び、道路を広げるのに使った。彼らのやっていることを写真に撮ろうとした人が憲兵に声をかけられた。憲兵は銃を向け、撮った写真は没収すると脅した。
プレスコードのため、このような事件について書くことはできなかった。新聞記者はそれを語らず、読者欄にも載らなかった。
しかし、永井隆博士は自分の書いたものを発表することを許された。彼はカトリック信者だった。彼は原爆を一種の洗礼と呼んだ。長崎の原爆投下後の惨状にもかかわらず、多くのカトリック信者が住んでいた浦上地区に原爆を投下させたのは、神の特別な意味があったに違いないと語った3。
東名通信の記者だった松野秀夫は、私にこう言った: 「プレスコードのせいで、自由に書くことができなかった。いつか発表できる日が来ると思って、長崎に関する報道を続けていた」4。
広島でも、私は詩人の栗原定子から同じようなことを聞いた。インタビューの最中、彼女は突然こう言った: 「私たちは、占領下での原爆体験を書くことはできなかった。「なぜなら検閲があったからだ」5。
他の多くの人たちと同じように、私は検閲をアメリカの日本占領と結びつけて考えたことはなかった。この時代に関する多くの歴史を読んだが、検閲について聞いたことはなかった。私は検閲を独裁と結びつけて考えていた。一方、占領は、敗戦国であり軍国主義的な日本の民主化だと思っていた。「占領下では、原爆について書くことは許されなかった。原爆について書いてはいけないと言うことさえ許されなかったのです」と栗原さんは説明した。
なぜだろう?占領軍の検閲について初めて耳にした1970年代の当時から、私はその答えを知りたかった。しかし、入手可能な占領に関する文献を調べても、検閲について言及されているものはほとんどなく、どちらかといえば通り一遍のものであった。原爆の検閲については、栗原貞子のような体験者の短い回想があるだけだった。
1977年、アメリカは日本占領に関する公文書の機密指定を解除した。連合国軍最高司令官総司令部の記録は、一部を除いて完全に公開された。この膨大な資料のコレクションは、整理が極めて不十分であったとはいえ、これまでで最も大規模な社会工学の試みのひとつ、つまりアメリカの民主主義のイメージで日本を作り変えるという試みに関する研究に、まったく新しい可能性を開いた。
また、アメリカ占領下における検閲についても、初めて広範な研究が可能になった。それまでは、このテーマに関する包括的な研究は書かれていなかった。占領軍当局の市民情報教育課の活動を通じて日本人の心がどのように変化していったか、例えば教育制度の改革などが研究されてきた。一方、検閲業務は、日本人の知識や意見に重要な影響を与えたことは確かだが、ほとんど研究されていない。このため、私が原爆の検閲を研究し始めたとき、まず検閲全般について調べる必要があった。
私の最初の疑問はこうだった:なぜアメリカの占領下で検閲が行われたのか?なぜ、どのようにして検閲を導入することになったのか?検閲は民主主義の概念にまったくそぐわないものではなかったのか?日本に民主主義を導入することが連合国側の目的だった。戦争で軍隊が敵の領土を占領している場合、検閲が必要かもしれないことは理解できる。しかし、日本は降伏後、敗戦国としてのみ見なされたわけではない。日本人は戦争を引き起こした軍事的信念を捨て、平和を保証する民主主義を支持することになった。要するに、それがアメリカの意図だった。このような出発点から、検閲は軍事作戦として想定されていたのだろうか?それとも、実際には計画とは別のものになったのだろうか?アメリカや他の連合国はどのように判断したのか?
検閲計画を研究し始めてすぐに、検閲作戦が非常に広範なものであったことを理解した。一般的に言って、アメリカ人にとって日本は未知の国であり、たとえ各部門の日本専門家が広範な報告書を作成したとしても6。検閲の観点からさらに重要なのは、日本語を理解できるアメリカ人がほとんどおらず、習得するのが極めて困難であったことである。このような状況下で、検閲はどのように実現可能だったのだろうか?検閲官は誰だったのか?彼らはどのように働いていたのか?
現実的な側面はさておき、検閲官は何を検閲したのだろうか?まず思い浮かぶのは、検閲官は自分自身や自分が代表する支配者に対する批判を削除するということだ。自由な政治的議論を認めるという民主主義の大前提にもかかわらず、日本ではそうだったのだろうか?このような状況下で、何を許し、何を禁止するかの線引きはどのように可能だったのだろうか?明確な制限なしに、検閲は有効なのだろうか?
これらの疑問が解決されない限り、原爆資料の検閲を取り上げることはできないだろう。西森さん、井上さん、内田さん、松野さん、栗原さんは、原爆について自由に書くことは許されなかったと述べている。にもかかわらず、占領時代に出版された本の書誌を見ると、原爆をテーマにした作品がいくつか出版されている。なぜそんなことが可能なのか?私がインタビューした日本人は間違っていたのだろうか?
アメリカの検閲規則であるプレスコードには、原爆についての記述はなかった。実際、規則はかなり曖昧だった。しかし、検閲官自身が書いた検閲の報告書を見つけると、原爆に関する多くの資料が実際に検閲されていたことが明らかになった。何が許され、何が禁止されたのか。どんな動機で?そして何よりも、その決定はどこで下されたのか?日本における原爆に関する検閲方針は、現地で決定されたのか、それともワシントンで決定されたのか。そのような資料を検閲する理由は何だったのか?結局のところ、1945年8月6日に広島がそのような原爆によって消滅したことは、すでに世界中で知られていた。ヒロシマとナガサキは秘密とは言い難かった。全体として、私は広島と長崎への原爆投下後4年間の日本における原爆検閲の結果を知りたかった。
これらの疑問に、この研究は答えようとしている。主に新聞検閲に限定せざるを得なかったが、このテーマは検閲全般を代表するものだと思う。さらなる詳細な研究が必要である。私は、占領軍自身がどのように推論し、どのように動いたかを説明し、彼らの行動の結果を見出すために、占領軍のアメリカの公文書を検索した。そうすることで、被爆者や、占領下で生きること、検閲下で書くことがどのようなものであったかについての彼ら自身の証拠を忘れてしまったように思われるかもしれない。しかし、彼らは忘れられてはいない。彼らがいなければ、この研究は決して行われなかっただろう。私はこの研究を行うことで、核兵器の恐ろしさとその重要性、核兵器を保有する者とその犠牲者の両方に対する核兵器の理解に貢献したいと願っている。
10 日本における米国の検閲活動の結果
戦後の日本占領計画の中で、アメリカは検閲活動の基礎を固めた。これは、敵地を占領する際の通常の軍事事業とみなされていた。しかし、次第にその概念は変わっていった。ドイツとは対照的に、日本は進駐軍が運営する軍事政権が主導するのではないことが明らかになった。日本政府と日本の制度は、ほとんどが新しい指導者の下であったとはいえ、維持されることになった。しかし、その政策は連合国軍最高司令官によって決定されることになっていた。進駐軍はこれらの政策の実行を監督する。政策の形成と実行の境界線がしばしば非常に曖昧になることはよく知られている。最も有名な例は、新憲法の制定である。新憲法は実際にはSCAPによって日本政府に提示され、受諾された。
日本は長い歴史の中で占領を経験したことがなく、また戦争があまりに苛烈であったため、日本政府は進駐軍の到着にどう備えればいいのか途方に暮れていた。日本の将来は不透明で、人々は最悪の事態を恐れていた。降伏宣言からアメリカ軍が到着するまでの約2週間の間に、政府は準備を進めた。その目的は当然、占領軍に協力しつつ、旧体制をできるだけ維持することだった。双方の疑心暗鬼は当然のことながら大きかった。SCAPに批判的でありながら、日本側にも疑念を抱いていたジャーナリストのマーク・ゲインが書いたことは、おそらく正しかったのだろう:
日本はやみくもに降伏したのではない。日本の統治者たちは降伏を決めるや否や、戦勝国への誓約を回避するために、緊密に結びついた効率的な日本の政府機構全体を投入した。降伏の発表から最初のアメリカ軍部隊が到着するまでの2週間の間隔を、彼らはうまく利用した。文書は燃やされた。政府資金は最も有益と思われる場所にばらまかれた。貴重な物資の在庫は隠された。征服者の命令がどうであれ、政府機構を無傷で維持するための詳細な計画が立てられた1。
SCAPの部局間の意見の相違は、検閲の分野に見られるように、一般的な政策上の問題についても、個々の事例についても、数多くあった。さらに、ワシントンの政権内の異なる部局間の対立は、日本での政策実施に影響を与えた2。SCAPは、日本の機関が実施すべき政策を導入し、監督していただけであったため、必然的に衝突だけでなく、日米間の同盟関係も存在した:
形式的な権力は間違いなくアメリカ人の手中にあったが、占領下では、アメリカ人占領軍が日本人の団結した(そしておそらくは反対した)集団を改革しようとすることは、あったとしてもめったになかった。親しみやすさ、絶え間ない接触、そして日米の特定のグループ間の相容れる目標の出現が、むしろ国境を越えた多くの機能的・組織的提携をもたらしたのである3。
検閲業務の結果を評価する際には、これらの点を考慮しなければならない。他のほとんどの地域とは対照的に、SCAPは検閲に関する執行権を持っていた。しかし、検閲の概念そのものが占領中に何度か変化した。検閲は日常的な軍事事業から、はるかに大規模で複雑な作戦へと変化した。もともとは、検閲は主に情報収集、治安維持、軍事秩序違反の企てを発見するためなどに使われていた。しかし、占領軍の目的は、1945年9月10日にSCAPが発表した「言論の自由に関する指令」の言葉を借りれば、日本が「敗戦から平和を愛する世界の国々の一員となる資格を持つ新しい国として立ち上がる」ことだった。この努力において、検閲は不可欠な手段であった。検閲を通じて、軍国主義と天皇への畏敬の念は根こそぎ取り除かれ、民主主義の理想に取って代わられるだろう。検閲はまた、「自由で事実に基づいたニュースの普及を助ける」ものでなければならない。アメリカの声明は、誰もが世界の情報やニュースに自由にアクセスでき、誰もが好きなことを言ったり書いたりでき、検閲のない日本を想定していた。これらは、ダグラス・マッカーサー最高司令官が言ったように、連合国が戦争を戦った理由である自由であった。
しかし、占領と検閲活動にはもう一つの側面があった。その目的は、日本を囲む輪を作り、日本との間に不正な情報が入り込まないようにすることだった。この角度から見ると、日本は、アメリカの同盟国を含む世界の大部分から切り離された領土だった。日本はアメリカのイメージで作り直されることになった。また、変容が達成されるまでは、自国の過去からも、世界の発展からも切り離されることになっていた。
この占領のバージョンでは、日本人は外の世界とコミュニケーションをとることができなかった。渡航の禁止や私信の検閲だけでなく、日本人が自国の出来事を世界に伝える能力も断たれた。1945年9月、通信社「東名」の海外発信が禁止されたときから、日本の状況についての情報は、アメリカの情報源か、SCAPによって承認された数少ない訪日客からのものでなければならなくなった。
アメリカからの通信や情報は、占領軍の検閲官によって選別された。占領軍の目的に反すると判断されたものは、入国を禁じられた。このような規則のもとでは、日本国外でなされた占領軍への批判でさえ、日本国内に入ることは許されなかった。
この制度の下で、日本人が世界について知る手段は限られていた。「世界のニュースソースに自由にアクセスできる」代わりに、世界情勢と国内情勢の多くの側面について知ることは許されなかった。
世界はまた、アメリカ占領下の日本についての知識も制限されていた。日本を訪れたり、日本で仕事をしようとする外国人ジャーナリストはすべて、占領当局の認定を受けなければならなかった。それらのジャーナリストは、大部分はアメリカ人であった。1946年5月、日本には70人の連合国特派員がいたが、そのうち非アメリカ人はわずか14人だった。最大で最も影響力のあるイギリスのメディアでさえ、自前の特派員を持っていなかった。その代わり、アメリカの通信社や記者から時折送られてくる記事に頼っていた4。
訪問者が自由に仕事をするのは難しいことが多かった: SCAPの)広報課は、来日者、特に彼らが広報担当者である場合は、適切な 「オリエンテーション」が行われるように手配することに苦心した。SCAPの)広報課は、日本への訪問者、特に広報担当者が適切な『オリエンテーション』を受けられるように手配するのに苦心した」と、連合国評議会のマクマホン・ボール英連邦代表は書いている5。
占領について批判的な報道をした人々は、就労許可の妨害や不更新など、SCAPとの緊張した関係についてしばしば語ってきた。特派員たちは、ほとんど最初から不満を抱いていた。戦闘部隊に認定された彼らは、まだ軍の検閲下にあった。しかし、占領軍の検閲が設けられるまでは、日本のメディアは比較的自由だった。例えば、道新は当初、世界に向けて自由にニュースを発信することができた。連合国側の特派員たちはSCAPに不満を漏らした。「自分たちのニュースで叩かれるなんて、世界の笑いものにされている」6 1945年10月6日まで、日本では外国人特派員に対する検閲は解除されなかった7。何人かのジャーナリストが追放されたが、最も有名なケースは、日本の企業幹部の粛清に関するGHQの秘密会議を報道したマーク・ゲインのケースである。ゲインは情報源の名前を出すことを拒否した。その後、特派員たちはこう通告された: 「SCAPの将校は、どんな資料でも機密扱いとすることができる。彼(マッカーサーの広報担当官であったフレイン・ベーカー准将)はまた、日米は厳密にはまだ戦争状態にあったのだから、そのような情報を公表した報道関係者は、戦時規定に基づいて軍法会議にかけられる可能性があると指摘した」8。
1948年、特派員たちはなおも不満を募らせ、アメリカ新聞編集者協会の報道の自由に関する委員会の委員長に、SCAPによって妨害されたいくつかの事例を挙げて報告書を書いた。その中には、SCAP職員が軍事機密を口実に、占領に批判的な記事を書いた特派員を日本から追放しようとしたこともあった。彼らはまた、平時の安全保障の明確な定義を得るために18カ月間努力したが、成功しなかった。「東京の圧力が彼らを従わせることができなければ、問題のある特派員を追い出すためにあらゆる努力が払われた」とボールは書いている9。
アメリカの日本改造は、軍国主義への憎悪だけが動機だったわけではない。そのことは占領の過程で明らかになった。この点については、検閲政策が明らかにしている。当初は、特に連合国全体を批判から守ることを明確な目的としていた。しかし後年、ソ連に対する批判は除外されるようになった。この変化は、極右より左のすべての政治的見解が奨励される非軍事化と民主化から、左翼が政府の役職や教職だけでなく、出版などの民間企業からも追放される「レッド・パージ」へと、占領軍の政策が完全に方向転換されたと思われる時期と重なる。
このような概念は、ソ連の指導者たちにとって完全に異質なものであったようには思われない。スターリンとの会談で、アメリカのアヴェレル・ハリマン駐ソ連大使は、北海道の最北端の島に軍隊を駐屯させることによって、ソ連が占領の一翼を担うことをアメリカは許さないと述べても、まともに拒絶されることはなかった。
アメリカにとって日本改造がいかに重要であったか、そしてこの事業において検閲がいかに重要な役割を担っていたかを考えると、検閲業務の実際を研究することは驚くべきことである。アメリカの検閲が有効性と一貫性の点で不十分であったことは明白である。当初から、検閲には一種の軽率さがあった。計画者たちは、検閲を敵を制圧するための日常的な軍事作戦とみなしていたが、重要な情報源は完全に無視していた。ラジオや報道機関、その他のマスメディアも含めるべきだと指摘したのは、検閲局の局長だった。
また、日本語を話す職員があまりに少ないことに驚かされるほど、実践的な計画の欠如も深刻だった。そのことに気づいたとき、語学力があるという理由だけでさまざまな国籍の人が起用された。日本語と英語の両方を知っていても、職業的な意味での検閲官としての能力も、アメリカの理想に忠実であることも、ほとんど保証されなかった。
しかし、アメリカの理想とは何だったのだろうか?検閲の効果という点から見た最も基本的な批判は、理想に一貫性がないということだった。ガイドラインは頻繁に変更され、その理由が検閲官に明確であることはほとんどなかった。例えば、ある時はソ連について否定的なことは何も言えなかったが、ある時は何でも許された。
占領軍当局の側にも、検閲が存在するという事実に神経質になっているところがあった。自由というアメリカの公式な理想にそぐわなかったのだ。検閲は非アメリカ的だった。せめて別の呼び名にすべきだという意見もあった。また、検閲は存在しなければならないと、特に外国人特派員を説得しようとする者もいた。外国特派員がどう反応するかを気にして、検閲を避けるケースもあった。
検閲の難しさから、多くの占領軍関係者は、本当に検閲をする価値があるのだろうかと考えるようになった。1946年、SCAPの内部では、検閲を廃止すべきだと主張する者もいた。最終的に1949年に破棄されたとき、公式には「日本は十分に民主的になった」という理由が示された。
日本は何が期待されているかを知っていた。検閲違反に対する罰は、没収から数年の重労働まで存在したが、公にされることはなかった。しかし、アメリカにとって刑罰が支配を拡大する主な手段であったことはなかった。検閲は警告と提案によって支配されていた。占領前は、編集者は数年の懲役、あるいは死刑に処せられることもあった。戦争中、検閲はあらゆるところに浸透していた。日本人はそれに慣れ、用心のためにある程度の自己検閲を行っていた。アメリカ人が来ても、この考え方や反応を続けることは難しくなかった。しかし、アメリカ人はまた、戦時中にアメリカで行われていたのと同じような方法で、民主主義をアピールして日本のメディアをコントロールした。日本人は常に、戦争中の自分たちの振る舞いに罪悪感を感じるべきであり、自分たちの邪悪な理想に代わるものはアメリカ流の民主主義であると言われ続けた。日本人は、アメリカ人が何を言いたいのかよくわからなかった。他の多くの分野と同様、検閲においても、日本人とアメリカ人は同じ言葉を使っても、しばしば理解し合えなかった。間違いなく、ほとんどの日本人は軍国主義よりも民主主義の方が優れていると確信するようになった。たとえ納得がいかなかったとしても、あるいはアメリカのやり方に疑問を抱きたかったとしても、当局との関係には慎重になり、論争を避けることに慣れていた。検閲に慣れていたため、おそらくアメリカ版にはそれほど動揺しなかったのだろう。おそらく彼らは、自分たちの状況を民主主義の理想ではなく、占領前に住んでいた社会と比較していたのだろう。加えて、彼らはアメリカの民主主義の解釈しか知らされていなかった。彼らは、民主主義の観点から見て良いものを公表すればいいと言われた。そうでないものは検閲された。その定義からすると、検閲された文章は非民主的な、少なくとも反占領的な考え方の一例であった。
さらに、検閲の存在を知る人はほとんどいなかった。検閲の存在を知っていたのは、検閲官と直接接触していた人たち、つまり作家、編集者、ジャーナリストだけだった。彼らは検閲があったという事実さえ公表することを許されなかった。その存在は秘密だった。
日本におけるアメリカの検閲は不規則だった。検閲官たちは自分たちの仕事について、また時には自分たちが働いている国についても知らなかった。コストがかかった。少なくとも、民主主義の理想には反していた。検閲は、連合軍を保護し軍国主義を根絶するためだけに使われたのではなく、情報を統制しふるいにかけるために使われた。しかし、その欠点にもかかわらず、検閲はかなり効果的だった。その一例が、原爆の影響や結果についての知識や議論を統制するために使われたことである。
原爆の検閲
検閲活動において、原爆のケースほど米国のニーズや目標とその理想との食い違いが明白になったものはない。検閲は日本を民主化するために導入されたとされている。しかし、被爆地広島・長崎の状況を伝える資料の公開が、日本の民主主義の発展に何らかの害を及ぼしただろうか?
占領下の日本で出版できるものの基準として使われたプレスコードのさまざまな点は、民主主義を促進し、占領軍を保護するためのものとして正当化することができた。しかし、原爆に関する報道に対する検閲は異なっていた。これらの報道は、プレスコードのどのルールとも直接の関係はなかった。原爆報道が検閲される場合、最も弾力的な規則が使われた。これは、世界中の検閲官が、他の方法では正当化できないものの検閲を正当化するために使う規則である。日本では、日本の非軍事化や民主化とは無関係な、もっぱらアメリカの利益を守るために使われた。
占領軍の検閲全般と同様、原爆の検閲も不安定だった。原爆は、アメリカの検閲一般が不安定であっただけでなく、アメリカの行政、社会、GHQの中で広く対立する見解の犠牲者であった。
日本占領が始まると、その雰囲気は軍事的なものだった。日本は征服すべき敗戦国であった。敗戦国である日本には何の地位もなく、尊敬される資格もなかったのだ。自分たちに降りかかったどんな大惨事も、自分たちが招いたことだと認識させるべきだった。悔い改めるまでは、彼らは疑われる存在だった。広島と長崎への原爆投下に関する情報を公表しようとすれば、それは米国の非人道性を非難するといった誤った理由によるものでしかなかった。こうして、この情報は封じ込められた。
しかし、最も厳格な軍人たちでさえ、発表の問題について考えを変えることがあった。日本に対する印象が変わったからではなく、公開した方がアメリカにとってプラスになるからである。世界は日本のように閉鎖的ではなかった。原爆の事実は知られていた。日本人にも知らせよう。日本人の恨み、あるいは敵意があるのなら、SCAPが結果に影響を及ぼし、武力や弁論でアメリカを守ることが可能なうちに、公表した方がいいという理屈もあった。
原爆投下を効果的に擁護できるかどうかは、一部のアメリカ人にとって懸念事項だった。終戦直後の世界では、アメリカはナチズムやファシズム、そしてそれらがもたらした恐怖からの偉大な救世主と広くみなされていた。広島と長崎の荒れ地は、人道主義的で利他的なアメリカというこのイメージとは一致しなかった。細菌兵器やガス兵器よりもひどい兵器を使用したことで、アメリカも国際法を破ったという非難は、特に日本のような残酷な敵からは許されなかった。占領下では、原爆の残酷さが、日本人の残酷さを終わらせる手段として正当化されることもあった。しかし多くの場合、そのような非難は完全に禁止されていた。
しかし、政治的な意味でも、やや広範な軍事的な意味でも、やがて日本はもはや敵国とはみなされなくなった。それどころか、同盟国になるよう仕向けられたのだ。このような状況を踏まえて、占領軍当局の間で広島と長崎について議論されたのは、原爆投下に関する詳細が公表されることで良い結果がもたらされるかもしれないということだった。原爆投下は戦争の恐ろしさを知らしめることになるかもしれない。また、日本が信頼できる協力者となり、新兵器の恐ろしい結果が研究され、この兵器が二度と使われないようになったことも強調された。
原爆が人間や環境に与える影響を測定しようとしていたアメリカの科学者たちは、日本における原爆研究の情報公開を懇願した。公開されれば、日本の科学者たちが広島や長崎で追跡調査を続ける励みになるだろう。米国は、その結果を見つけるために日本の科学者を必要としていた。彼らは、現在だけでなく今後何十年にもわたって、米国の核開発と民間防衛のために必要な研究を行うことができる。広島と長崎は、結局のところ、新兵器のユニークな実験場だったのだ。
アメリカから見れば、広島と長崎の状況についての事実を公表することは、国民の平穏が大きく損なわれる危険性があった。米国と占領軍に対する憤りは一面に過ぎない。もう一つの、そしておそらくより重要なことは、原爆による直接的な被害だけでなく、将来の影響についても知れば、多くの人が苦悩を感じるだろうということである。
マンハッタン工区と原子力委員会にとって、原爆に関するすべての事実は「生まれたときから」秘密であった。しかし、この見解は、原爆に関する情報をどう扱うかの決定に直接関わった人々の間で、決して一致していたわけではない。年8月、原爆プロジェクトの主要科学者の一人、アーサー・コンプトンは、科学者たちの意見について覚書を書いた。彼は、技術的な知識を持つ者は、原爆使用に伴う政治的、社会的問題について意見を述べることを許されるべきだと提案した。さらに、原爆の設計と効果に関する科学的な情報はすべて公表されるべきである。「新たな戦争の代償を考えるためにも、世界は新兵器の潜在的な破壊力を知るべきだ」と、コンプトンは広島攻撃後に書いている15。
もう一人の科学者、エドワード・テラーは、より大きく、より優れた水爆を作ることに執着していたが、別の理由で秘密主義に憤慨していた。何年も経ってから、彼は戦後の軍部との会議を思い出した。彼は、彼らは原爆が技術的、政治的に持つ本当の意味を全く知らなかったと主張した。彼はその状況を秘密主義のせいにした。
秘密主義があらゆる新事実の議論を妨げているのだから、軍人がこの奇妙な原子世界の中で、受け入れなければならない変化だけを受け入れるのは当然のことだった。爆弾」は揺るぎない事実であり、受け入れなければならなかった。しかし、秘密主義のためにチャンスはなく、惰性のために先を考える動機もなかった。戦後間もない頃、過去にしがみつく軍人と、恐ろしい未来から目を背ける科学者の間には、秘密主義が強力な障壁となっていたと私は確信している12。
原爆計画に関する公式報告書であるスマイス報告書でさえ、こう述べている: 「軍事安全保障上の制約から、議会や国民が(原爆が全人類に及ぼす影響などの)疑問について議論する機会はなかった。わが国のような自由主義国家では、このような問題は国民によって議論されるべきであり、決定は国民が代表者を通じて行わなければならない」13。
しかし統合参謀本部は、原爆に関する自由な情報は軍拡競争を加速させ、米国を原爆攻撃に対して脆弱にし、原子力の国際的統制を妨げ、少なくとも弱さの表れであると判断した。彼らは話し合いの中で、ソ連から原爆の知識を隠すことを公然と口にした。大統領への勧告の中で、ソ連の名前を公然と出さなかったのは、外交的、あるいは戦略的な意味合いだけであった。しかし、彼らの意見は一致していた。原爆に関する最も大まかな事実のみを公表するというものであった。
にもかかわらず、もちろん秘密は漏れた。ソ連は独自の原爆を手に入れ、いくつかの国の科学者たちは、時にはスパイに助けられながら、独自の再発見を行った。やがて、秘密でない秘密を守ることは面倒になった。原子力委員会は資料の機密指定を解除し始めた。このような資料は、米国でさえすでに公表されていることもあった。最後に、日本人は世界の他の国々がすでに知っていること、彼ら自身が生きていることを知ることを許された。
広島と長崎への原爆投下に関する情報公開について、見解の相違が調整されることはなかった。現地の占領政策は、下級の検閲官とSCAP自身ほど離れた人物に依存していた。マッカーサーは、検閲を完全に廃止するつもりがない限り、検閲の問題で最終決定権を握っているように見えたが、重要な案件はワシントンに委ねた。マッカーサーは、国家安全保障を理由に、統合参謀本部からそうするよう促された。
日本からワシントンに、原爆資料の公開に関する決定を求める要請が来たとき、混乱、延期、不作為を引き起こした。冷戦がすでに国際政治を支配していた時代であれば、答えは簡単に見つかったと思われる。しかし、まるで日本が大きなパターンに当てはまらないかのようだった。日本における原爆資料の検閲に関する決定要請は、混乱を招き、あらゆる部署に決定が回された。
日本における原爆検閲は、日本人が原爆について知っていることと、世界が知っていることの間にギャップを生んだ。日本人は1945年8月から9月にかけての降伏から占領までの数日間、初期の恐怖をよく知っていた。新聞やラジオ放送は、廃墟と化した都市から大々的に報道した。占領が始まると、報道は乏しくなり、不規則になった。発表されたニュースは、生存者全員が元気になったという良いニュースもあった。また、広島や長崎では、なぜ原爆が投下されたのかと尋ねられた被爆者が、運命や神の御業だと答えたという話も聞いた。日本ではその程度のことしか許されなかった。
世界の他の国々も、海外から送られてきた最初の報道を聞いていた。破壊された都市を見て衝撃を受けたアメリカ人飛行士の反応を読んだのだ。アメリカのジャーナリスト、ジョン・ハージーによる広島からの詳細なインタビューも読んだ。科学者たちがその影響について推測し、時には研究結果を発表するのを聞いた。そして何よりも、この兵器がアメリカにとって、また世界にとって何を意味するのかについての議論を追いかけ、それに参加することができた。
しかし、日本人、アメリカ人、すべての人が、断片的な情報しか得ることができなかった。原爆に関する事実が散見された。広島と長崎からいくつかの声が聞こえてきた。しかし、そこには秩序もなく、全体像もなかった。しかし、原爆に関しては、アメリカの検閲のせいで、それなりに正確な全体像が描けるにもかかわらず、描けなかった側面がある。それは、広島と長崎に投下された原爆の後遺症である。「原爆症」は原爆投下直後に多くの命を奪った。今日に至るまで、被爆者はその影響で病気になり、命を落としている。病気にならなかった人も、病気になるのではないかという恐怖を抱えながら生きていかなければならない。さらに悪いことに、自分の子供が不治の病を受け継ぐのではないかという恐怖とともに生きている。遺伝性のリスクはないという研究結果が出ているようだが、絶対的な証拠はない。何よりも、恐怖が続いている。原爆に対する無知は、多くの被爆者に差別、貧困、孤独をもたらした。このような影響を知り、議論することは、原爆についての意見を述べるための情報となるだけでなく、広島や長崎の被爆者を治療しようとした医師たちが働くための具体的な根拠となっただろう。医師たちは、被爆者とその家族の肉体的、心理的、社会的苦痛を和らげる手助けができたはずである。しかし、作成された何百もの報告書や研究結果は、極秘扱いでアメリカの公文書館に消えてしまった。そのままでは、憶測を交えた適当な事実しかなかった。
広島と長崎への原爆投下に関するアメリカの検閲の結果、核兵器が使用された場合に何が起こるのか、その全容が何年もの間、世界に知られることはなかった。原爆が恐ろしい物理的破壊を引き起こし、多くの人々が即死したことはよく知られていた。また、この新しい兵器によって世界が変わったことも理解されていた。破壊の力によってパワーバランスが変わったのだ。しかし、人間への影響は隠されていた。検閲によって特定の事実が削除されただけでなく、被爆者が自らの体験について語ることも妨げられた。被爆者たちは、アメリカへの敬意から、恐怖から、あるいはトラブルを避けるために、話すことができなかったし、話そうとしなかった。検閲によって、日本は世界に閉ざされた。ヒロシマ・ナガサキについて漏れ出てきた事実は、同じ事実が多くの記者の目やペンや声によって倍加されるのに比べれば、どう考えても影響は少なかっただろう。
被爆者の声を封じることによって、「世界情勢に決定的な影響を与える重要な可能性が失われた」と述べた日本の歴史家、今堀誠司に同意しないわけにはいかない14。
モニカ・ブラウはスウェーデンのルンド大学で歴史学の博士号を取得した。1969年からジャーナリストとしてアジアを取材し始め、1984年からはスウェーデンの新聞『スヴェンスカ・ダーグブラデット』の東アジア特派員を務めている。中国や日本に関する本、小説、短編小説集など11冊の著作があり、スウェーデン語、フィンランド語、ドイツ語、英語、日本語で出版されている。
