Contents
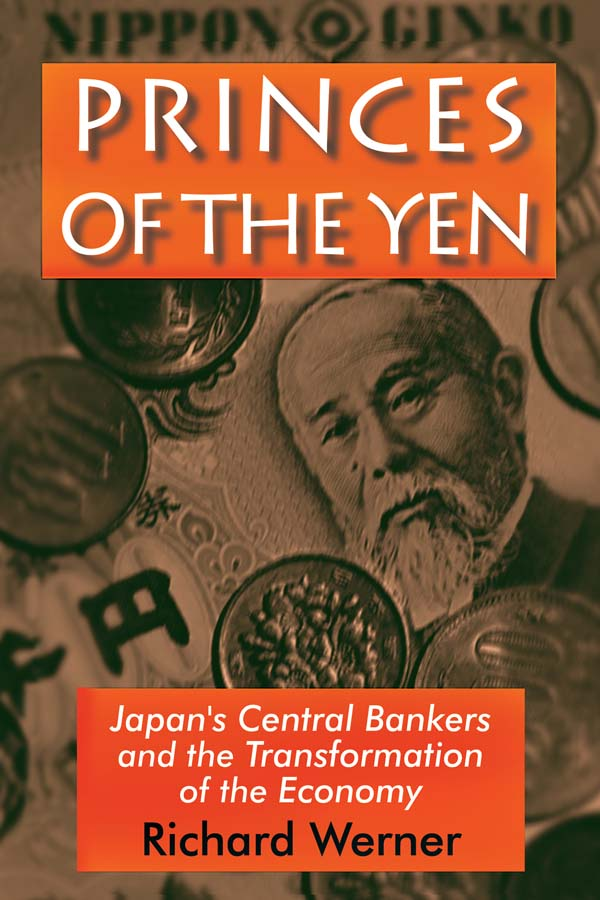
Princes of the Yen
プリンセス・オブ・ザ・イェン
『Princes of the Yen』日本語版へのコメント:
「力作」である。
-榊原英資(元財務副大臣) 週刊エコノミスト、東京
「これは普通の経済学書ではない。読者は目の前のカーテンを取り払われるような感覚を覚えるだろう。20世紀全体という時間軸と、世界の中央銀行の動きという広い範囲から、経済学とはかくも面白いものかと感嘆させられる秀作である。リチャード・ヴェルナーは、日本銀行の煙幕を見破ったのである。その事実を一歩一歩明らかにしていく過程は、まるでスリラーのように手に汗握る。彼の分析は国際的にも高く評価され、エコノミスト誌で大きく取り上げられ、アラン・グリーンスパン連邦準備制度理事長が読んでいる。」
-立花隆(『週刊文春』著者)
日本の経済政策の黒幕に光を当てた、示唆に富む一冊。著者は、一握りの日銀のエリートが、日本の経済構造の改革を視野に入れ、いかに日本の金融政策を歪めてきたかについて、驚くべき証言をしている。
-朝日新聞社、東京
本書は、単に経済問題を扱うだけでなく、その背後にある真の原因や権力者の存在を明らかにしている…。1920年代の日本にあった「アメリカ型自由化経済」を復活させ、戦後の高度成長を可能にした統制された戦争経済を解体しようとする日銀諸侯の密かな戦いが描かれている。
-毎日新聞社、東京都
本書は魅力的な読み物に仕上がっている。ヴェルナーは、日銀が金利を下げることで景気回復に全力を尽くしているという主張は『事実と異なる』と言う。彼はマフィアのような名簿を入れるほどで、佐々木、前川、三重野、そしてもうすぐ就任する福井俊彦が、いかに連綿と日本を支配しようとしてきたかについて、証拠を示している。この示唆に富む本の著者に初めて会ったのは、11年前だった。彼はすでに、その分析力で株式市場の動きを高い精度で予測する、精度の高い戦略家として有名だった。
-今井清・東京大学経済学部教授
「日銀に対する正当な批判」
-井尻一夫、東京都、ボイス
「いったいなぜ日本の不況が10年以上も続いているのか、私たちは皆、困惑している。不況の原因や対策を説明する学者は数え切れないほど現れては消えていった。私たちはこの著者の警告に真剣に耳を傾けるべきである」
-舛添要一(参議院議員)、国際政治学教授 電気新聞社、東京
円のプリンスたち
リチャード・A・ワーナー
初版 2003年 M.E. Sharpe刊
2015年ラウトレッジ社より刊行
ロミへ
目次
- 表と図のリスト
- 序文
- 謝辞
- 頭字語・略語、人名表記に関する注意事項
- 1.日本語の授業
- 2. 総力戦の経済
- 3. 平和を勝ち取るために戦争中の経済
- 4. 銀行の錬金術
- 5. 信用:経済の最高司令部 6. 中央銀行独立のための第一次入札
- 7.日本初のバブル経済
- 8. 謎のマネー: 円の浮き沈み
- 9. 円の大いなる錯覚クレジットバブルとバスト
- 10. 不況を長引かせる方法
- 11. 円の戦い
- 12. 銃のトリガーで
- 13. 円のプリンスたち
- 14. 金融政策が目指すもの
- 15. バック・トゥ・ザ・フューチャー アメリカ型資本主義の復活
- 16. リフレ:もうひとつの奇跡を起こす
- 17. アジア危機と中央銀行団
- 18. プリンスにもっとパワーを
- 19. ライヒスバンクの復活
- 付録:1990年代の日本の財政・金融政策
- 備考
- 書誌情報
- 著者名索引
- 総索引
- 著者紹介
- 表と図のリスト
表
- 12.1 窓口指導の貸出金増加枠(WG)と貸出金増加実績(1974~1991)の推移
- 13.1日本銀行総裁・副総裁の推移
- 13.2 戦後6人の「プリンス」
- A.1 GDPモデルの推計結果
- A.2 民間需要モデルの推計結果
図
- 9.1 銀行の不動産業への貸し出しと地価の推移
- 9.2 GDP取引に使われた信用創造と日本の名目GDP
- 9.3 ネット長期資本フローと銀行による不動産企業への貸出額
- 10.1日本銀行の信用創造
- 11.1 円/米$レートと日米金利差の推移
- 11.2 米連邦準備制度理事会(FRB)と日本銀行の相対的信用創造と円/米$レート
- 11.3日本銀行と連邦準備制度理事会(FRB)による信用創造
- 12.1日銀の窓口指導と3カ月後の銀行貸出の実態
- 15.1日本の実質GDP成長率
- 15.2 製造品目の輸入シェア
- 15.3日経新聞の「あまくだり」をキーワードにした記事
- 15.4日本経済新聞に「内外価格差」のキーワードを持つ記事
- 15.5日本経済新聞に「規制緩和」のキーワードを持つ記事
- 16.1 邦銀の「その他資産」
- A.1 10年国債利回りとコールレート
- A.2 「実質流通量」と名目GDPの信用度
- A.3 民間と政府の需要
- A.4日本銀行の信用創造とコールレート
- A.5 国債発行による財政出動
- A.6 銀行借入による財政出動
はじめに
2001年1月、欧州のある国の駐日大使が、東京の公邸で年越しパーティーを開いたときのことを話してくれた。ゲストの中には、日本の大蔵省の高官も含まれていた。ほとんどの招待客は楽しいムードに包まれていた。21世紀の幕開けを待ち望んでいたのだ。シャンパンを片手に、パーティーは大いに盛り上がった。しかし、誰もがハッピーというわけではなかった:
「時計が深夜に近づくにつれ、この紳士がだんだん悲しげになっていくのがわかったのである。大蔵省の人なのだが、すごく落ち込んでいるのである。どうしたんだろう。珍しいと思った。そして、深夜0時を回ると、彼は私のところにやってきて、とても悲しそうな声でこう言った」
「これで……すべて終わったんだ……」と。
「どういうことだろうか?」と私は彼に聞いた。
「われわれは名前を失ったんだ。終わったんだ……」2001年1月から、大蔵省はなくなってしまったんだ。
私は、「まあ、でも、名前だけのことだから、あまり気にしないほうがいいよ。省はまだある。あなたはまだ権力と影響力を持っているのだから』。
しかし、彼は言った。「せめて名前を残してくれていたら…彼らはすでに私たちの力を奪ってしまった。」
大蔵省が単に大蔵省として知られていた多くの英語圏の人々には気づかれなかったが、長く輝かしい歴史は2001年1月、突然に幕を閉じた。過去100年の間、少なくとも法律上は、大蔵省は日本で最も強力な機関であった。その歴史は、税金が現物支給されていた時代までさかのぼり、文字通り全国から届く米の貯蔵庫であった。
構造改革
大蔵省がなくなっても、一般国民は涙を流すことはない。大蔵省は、1980年代のバブルと1990年代の長期不況という、日本の平時の近代史の中で最も悪質な経済失政の責任を負っていると一般に言われている。
この不況は、官僚を頂点とする日本の古い経済システムはもう機能しない、だから抜本的に改革しなければならない、という一般的な信念を生み出した。今ではほとんどの論者が、構造改革が「ひどく必要だ」と主張している。小泉純一郎首相が最も繰り返しているスローガンは、「構造改革なくして景気回復なし」である。日本の中央銀行の幹部は、ほとんど毎日のように大幅な構造改革を要求している。日本経済の回復には、自由化、規制緩和、民営化、つまり米国型資本主義の導入が必要だというのである。
しかし、日本型資本主義を捨てることが本当に必要なのだろうか。90年代の経済の惨状を見れば、そう考えるのが普通であろう。しかし、1980年代の日本の経済システムは、はるかに閉鎖的で、カルテル化され、統制されていたにもかかわらず、誰も経済成長が遅すぎると文句を言わなかったのは不思議である。1950年代や1960年代には、ほとんど完全にカルテル化された経済が2桁の成長を実現していたのに、である。しかも、米国経済そのものが、いまだに景気循環や不況に悩まされている。つまり、同じ経済構造であっても、高成長も低成長もあり得るし、成長のパフォーマンスは他の要因にも左右される。本書は、日本の景気後退が、景気循環の主役である「お金」に起因するものであることを明らかにしている。構造改革の主な推進者が、まさに日本の貨幣を支配している人たちであることは、偶然ではない。
反抗的な日本銀行
日本銀行は、政府、財務大臣、首相が、景気刺激策や長期不況の解消のために資金を増やすよう求めたのに対し、一貫して反抗してきた。1992年、1993年、1995年初頭、1999年の大部分など、重要な局面では、日本銀行(BOJ)は経済界に出回るお金の量を積極的に減らしてさえいる。このため、購買力が低下し、内需が縮小し、政府の為替介入も効かなくなり、円高が進み、せっかくの景気回復も頓挫してしまった。金融政策が十分でなかったため、政府は財政政策に頼らざるを得なかった。しかし、その効果はなく、先進国の中で最大の国債の山を築くことになった。
1990年代の大きな謎は、記録的な失業とデフレにもかかわらず、なぜ日本銀行が貨幣量をさらに拡大し、景気回復、デフレ脱却、雇用の安定を実現できなかったのかということである。その答えとして、インフレへの恐怖があげられることがある。しかし、日本では1990年代前半にインフレ率が急低下し、後半には完全なデフレに陥った。物価が上昇し、インフレになれば、金融政策が緩みすぎていて、お金が作られすぎていることがわかる。中央銀行が引き締める必要がある。物価が下がり、デフレになった場合、中央銀行には購買力を高める義務がある。一般に、中央銀行の仕事は、実際の成長率を潜在成長率に近づけ、インフレとデフレの両方を回避するために十分な量の資金を作り出すことである。
デフレの問題が明らかであるにもかかわらず、日本銀行はしばらく前に、インフレへの懸念が慎重姿勢の理由ではないことを認めている。それどころか、日銀はここ何年も、金利をゼロまで下げたことに触れながら、懸命に経済を刺激しようとしていると言ってきた。しかし、問題はお金の需要がないことだと主張している。しかし、世界最大の資金需要が、まさに日本にあることは明らかだ。第一に、政府部門が財政支出のために記録的な量の資金を要求していること。そして、日本の主要な雇用主である多くの中小企業が、お金を借りたいのである。しかし、不良債権を抱えた銀行は、リスクの低い大企業にしか貸し出そうとしない。だから、中央銀行が彼らの貸し出しの代わりになる必要がある。
日本銀行は、すでに多くの資金を経済に注入していると主張することがある。しかし、そのほとんどは、銀行だけがアクセスできる非常に狭い金融市場に資金を注入している。また、デフレの心配に対しては、「デフレは望ましい構造変化によるものだから良い」と反論することもある。しかし、その構造変化によって日本経済の生産性が高まったとすれば、潜在成長率が上昇し、実際の成長率とのギャップがさらに大きくなる。その場合、中央銀行はデフレギャップを縮小するために、さらに多くの通貨を作らなければならない。
中央銀行の最近の主張は、首相と経済財政政策担当大臣も支持しているようだが、日本には「過剰設備」が多すぎるというものである。これは事実であり、別の言い方をすれば、総供給が総需要より大きいということである。しかし、中央銀行が簡単にできるように、需要を刺激するという論理的な結論を導き出す代わりに、企業を閉鎖することによって供給を制限することがアドバイスされる。日本、ドイツ、アメリカの大恐慌時代の政治家が行った不運な政策を思い起こさせるように、この「過剰生産能力」は「過剰競争」をもたらし、倒産によって対処しなければならないとされている。皮肉なことに、この議論は、日本が「競争の欠如」に苦しんでいるから規制緩和が必要だと主張するのとまったく同じ論者によって提案されている。
日本銀行の主張はさまざまで、反論されるとすぐに変わってしまうが、結論はいつも同じだ。つまり、中央銀行の金融政策は適切であり、日本の経済構造に責任があるのだ。
日本銀行は助けることができたが、助けなかった
お金は通常、銀行が作るものである。銀行が貸さないからこそ、中央銀行が経済に直接資金を注入する必要があったのである。他の中央銀行もそうしてきたし、実際、日本銀行も1945年以降、銀行のバランスシートが1990年代よりはるかに悪化していたときにそうしてきた。1945年以降の数年間は、これが非常にうまく機能し、信用の伸びはすぐに回復し、経済は好況を呈した。しかし、1990年代の大半を通じて、日本銀行はこうした試行錯誤を重ねた政策をとらず、持続的な景気回復のための十分な資金を創出することができなかった。しかも、最もお金を必要としている人たち、つまり政府や中小企業への貸し出しを拒否してきた。日本銀行はまた、銀行システムにある不良債権の山を、自分自身や納税者、社会全体に負担をかけることなく、すべて取り除くことができる力を持っていた。しかし、日本銀行は行動を起こさないことにした。なぜか。
無能の仮説から入るのが自然である。確かに無能であれば、このドラマの一部の役者の行動は説明できるかもしれない。例えば、1990年代の大蔵省と政治家は、財政支出の方法を変えるだけで、景気回復を実現できたはずだ。国債を発行して国民から借り入れ、経済から資金を流出させる代わりに、銀行からの直接融資契約で公的部門の借り入れを賄うことができたのである。銀行が融資を行えば、経済からお金を引き抜くことなく、無からお金を生み出すことができる。そうすれば、実際に起こったように、財政政策が民間の活動を一円一円圧迫することはなかった。このことを十分に理解していれば、きっとこの方法で景気回復を実現したことだろう。しかし、このメカニズムは、日本、欧州、米国を問わず、経済学者の間ではほとんど知られていない1。
より明白でよく知られているのは、経済学の入門書にも規定されているメカニズム: 中央銀行は、銀行が倒産しても、国債を含む資産の買い入れを増やすことで、経済に直接資金を注入できるのである2。しかし、中央銀行はこの事実を何年も否定している。信用収縮に起因する過去のいくつかの不況(1960年代の不況など)では、中央銀行は企業部門や政府への融資を増やした。また、今日でも、中央銀行にはこれを実現するための多くの選択肢がある。例を挙げると、企業が発行する債券を購入する、政府に貸し付ける、債券を買い増す、不動産を購入して公共の公園にする、あるいはただお金を刷って国民一人一人に少し手渡す、などである。どのような場合でも、購買力は高まり、需要は刺激されるだろう。また、お金を刷れば円安になり、輸出が促進されるかもしれない3。
中央銀行の信用創造を拡大することで、1990年代のいつでも景気回復を図ることができたはずだ。日本銀行がそれを望めば、日本は1990年代を通して高成長を遂げることができたはずだ。
これらはすべて、ロケット科学ではない。さらに、今日の中央銀行は、日本銀行や、同じ問題に取り組んできた他の中央銀行、例えばドイツの中央銀行や米国の連邦準備制度理事会の豊かな歴史と経験を振り返ることができる。だから、パズルが残っている:なぜ日本銀行はもっとお金を作らなかったのだろうか?
1990年代、大蔵省が、その後誕生した多くの政府と同様に、景気回復を実現するためのあらゆるインセンティブを持っていたことは疑いようがない。激しい批判の矢面に立たされた大蔵省は、長い不況が自らの法的優位性と戦後の経済構造を危うくすることを痛感していた。しかし、よくよく考えてみると、中央銀行の動機はあまり明確ではない。
1992年、日本銀行に客員研究員として勤務していた私は、信用創造とその配分の重要性を知っていた。中央銀行が適切な政策を実施しなければ、日本の不況はさらに悪化し、失業率は急上昇することになると悟ったのだ。金利の引き下げや財政政策だけでは不十分だった。必要なのは、中央銀行によるより多くの資金創出だったのである。しかし当時、中央銀行はその逆で、経済から積極的にお金を引き出していた。私はその理由がわからず、日本銀行のさまざまなメンバーに答えを求め続けた。そしてついに、ある中央銀行員が私にこう説明した: 「もっとお金を刷れば、景気は回復するだろう。しかし、それでは何も変わらない。日本の構造的な問題は解決しない」と。当時、私はその言葉を信じることができなかった。日本の中央銀行は、経済構造を変えるために、わざと不況を長引かせるのだろうか?このような経済的、社会的な変化、特にこれほどの規模の変化、これほどの経済的、人的コスト、そしてこれほど不透明な方法で変化をもたらすことが、中央銀行の仕事なのだろうか?1998年までに自殺者は戦後最高を記録し、その多くは不況が原因で引き起こされたものであった4。
日本銀行の政策に関する公式声明は、非常に矛盾している。一方では、不況の原因は中央銀行の政策にあるのではなく、経済構造にあると主張している。そのため、金融緩和ではなく、構造改革が必要であったと、中央銀行の担当者は繰り返し述べている。しかし、中央銀行職員(総裁を含む)は、景気刺激策を取りたくない(取れることは認める)、なぜならそれは「ひどく必要な」構造改革を先送りすることになるからだ、とさえ述べている5: 「消去法で、日銀の政策委員の発言を注意深く読むと、日本経済の構造変化を促進したいという思いが、日本銀行がデフレを消極的に受け入れている主な動機であるという結論に至る」7。もし読者が1990年代前半の私と同じように懐疑的なら、これは受け入れがたい結論である。
日本銀行の台頭と復活
景気回復が構造変化を妨げるのであれば、景気回復に構造変化は必要ないことになる。では、なぜ構造改革が必要なのだろうか。日本のシステムは問題が多く、特に生活の質の向上、住宅の広さ、余暇の充実、公園の数など、改善の余地があるが、米国型の経済システムで生活水準が大きく改善されるとは思えない。また、アメリカ型の経済システムにはデメリットもある。日本の経済システムには、構造改革について国民的な議論があれば、維持できたかもしれない良い面がたくさんあった。
実際、1990年代の不況は、多くの専門家が「驚くべき」と称する構造転換を引き起こした8。2000年の大晦日、旧大蔵省の官僚たちは涙を流していたかもしれないが、シャンパンのコルクは別の場所で弾かれていたかもしれない。大蔵省が廃止されたとき、その業務はすでに廃止されたり、他の機関に移管されたりしていた。1998年、金融政策は独立した日本銀行に、金融セクターの規制は独立した金融庁に委ねられた。金融庁の有力者の多くが中央銀行出身であったため、行政の再編成の中で明確な勝者が現れたのである9。それは、財務省の長年のライバルであった日本銀行にほかならない。日本銀行はついに勝利を収め、かつてないほど強力になった。
法的には財務省が優位に立つが、カードは中央銀行の方が上: 中央銀行は、あまり知られていない、非合法な信用管理機構を担当していたのだ。このようなことが可能だったのは、中央銀行が金融政策について透明性を欠き、意味のある説明責任を果たしていなかったからだ。
中央銀行の独立性
新日本銀行法は、1997年に橋本首相の行政改革の一環として提案されたものである。当時の日本銀行副総裁の福井俊彦は、マスコミや政治家に働きかけ、新日銀法は「日本銀行がより迅速かつ柔軟に金融政策を決定できるようになり、金融市場からの信頼性が高まる」11と主張した。
これは、新法が議論されていた1997年に私が恐れていた通り、実際には起こらなかった。当時、私は十分な調査を行い、日銀新法が日本国民の利益に反するものであり、他国の民主主義にも脅威を与えるものであると確信していた。そこで私は、この法律の成立を阻止するために全力を尽くした。できる限り多くの国会議員に手紙をファックスした。また、関連する国会の委員会のメンバーとの面談を手配しようとした。多くの議員が私のファックスや電話を無視した。しかし、かなりの数の議員が私に会い、私の話を聞く時間を取ってくれた。しかし、それは困難な戦いであった。私が日本銀行について長年研究する前に考えていたように、ほとんどの専門家も、中央銀行の独立は良いことだと考えていた。ヨーロッパでもアジアでも、中央銀行の独立を支持する議論には重大な欠陥があることは、本書の後半で確認する。その中には、ドイツのブンデスバンクの大成功は、その独立性に基づいているという議論も含まれている。しかし、その真実は、後述するように、まったく逆であった。
日本銀行新法が成立した。そして、今日、政府が金融政策をコントロールできなくなったのはそのためだ。2001年 2002年の株価下落の後、多くの政治家が日銀総裁の辞任を要求した。速水氏はそうした批判に対して、日本人が終身雇用をあきらめ、雇用の安定を失うことに直面することを要求した。自分自身の雇用の安定は確保されていた。政府が彼をクビにすることはできない。日銀法には、健全な経済成長を実現することが中央銀行の仕事であることが明記されていないため、彼は何も悪いことはしていない。
政治家が意思を示すには、中央銀行法をもう一度変える以外には、メカニズムはない。好景気になるか不景気になるかを決めるのは、政府ではなく日銀なのである。
中央銀行とは何者か?
中央銀行員は目立たないようにするのが得意だが、そのキャリアパスは一般市民や政治家のそれよりも予測しやすい傾向がある。次の財務大臣が誰になるのか、現在の首相がいつまで続くのか、予想できる人はほとんどいない。戦後、日本銀行のトップは、そのような不確実性はない。
戦後58年間で、26人の総理大臣が誕生している。しかし、日本のお金、つまり経済の中心を支配してきたのは、もっと少ない人数だった。日本銀行は、「プリンス」と呼ばれ親しまれてきた。日本の文楽の人形遣いのように、黒装束に身を包んだ彼らは、戦後日本の歴史の中で重要な出来事を形作った。政治家、政府、官僚、さらには大蔵省までもが、知らず知らずのうちに彼らのマネーゲームの操り人形になっていた。しかし、これまで彼らや彼らの政策手段については、ほとんど知られていなかった。本書が、彼らの活動に少しでも光を当て、選挙で選ばれたわけでもない中央銀行が持つ権力について、読者の皆さんに知っていただくきっかけになればと思う。
今日でも、多くのジャーナリストやコメンテーターが、誰が次の日銀総裁になるかを確信しているようだ。2001年5月、本書が出版された同じ週に、富士通総研の福井俊彦が、速水総裁の後を継いで新総裁になろうとする動きがあった。メディアは、福井を「日銀総裁の最有力候補」「トップの座を狙える」と持ち上げ、日本を代表する金融新聞である日本経済新聞は、早々と表紙と写真入りで新総裁として紹介した12。結局、速水総裁は辞任を拒否した。しかし 2003年3月で5年の任期が終了する。昨年12月まで、他に有力な候補者がいたにもかかわらず、メディアは最も有力な後継者を決めていた: 福井俊彦は、フィナンシャル・タイムズ紙で「妥協の産物」と呼ばれた。福井俊彦は、『フィナンシャル・タイムズ』紙が「妥協候補の筆頭」と呼んだ人物である。
実際のところ、戦後の歴史において、日銀の真のトップ選びにおいて妥協はほとんどなかった。1989年に三重野康が総裁になる前も、その10年前に前川治男が総裁になる前も、マスコミや識者の間では同じことが言われていた。今回も、その10年前に佐々木正が知事になることは、内部の人間にはわかっていた。本書では、福井、三重野、前川、佐々木の4人に多くの共通点があることがわかる。1970年代から日本の経済構造を根本的に変えるべきだと主張してきた経済同友会で主導的な役割を担っていたこと、そして中央銀行のトップに10年ずつ立っていたことである。さらに不吉なことに、彼らは皆、中央銀行での若い頃から「プリンス」と呼ばれ、将来の日本銀行のトップとして指名されていたのだ。プリンスとは、10年に1人しかなれない中央銀行総裁の称号であり、決して軽くはない。
本書は、1980年代の金融バブルの発生と1990年代の10年にわたる不況をもたらした出来事における福井の極めて重要な役割を含め、日本国民がこれらのプリンス、彼らの目標、政策の実施方法について認識を深めることに貢献した。さらに、日本銀行が日本の不調の主な原因であり、中央銀行がより支持的な政策をとることが景気回復の必要条件であることを理解する政治家が増えているようだ。小泉首相は2002年12月下旬、「デフレ脱却に積極的な人」を日銀総裁に任命すると明言した14。「プリンス」福井は、過去の行動だけでなく最近の発言からも、デフレ脱却に消極的であると思われた15。
本書では、大蔵省出身者や民間出身者が日銀総裁に就任した場合、実際の金融政策の実施に関する「技術的」な内容、すなわち中央銀行の信用創造の量については秘密にしておくという、よく知られた方法をとっていたことを確認する。これを決めるのは、5年後に正式な総裁となる皇族の一人である副総裁である。
最初の5年間は、金利と銀行の中央銀行への準備金というマイナーな政策手段を公式総裁がコントロールし、信用量をコントロールすることで守旧派が主導権を握ることになる。
結果的に、35年前の計画通り、福井俊彦が再び出馬した。2000年当時、本書の日本語版を執筆する際に、私は彼が次期日銀総裁になると予想した。しかし、総理大臣が反対したのにもかかわらず、また、サプライズ人事で有名な政権であるにもかかわらず、彼が正式に任命されたことは、皇族の力の大きさを示すものでしかない。
国民的議論が必要
現在、首相が好んでいるとされるインフレターゲットの導入も、それ自体が解決策にならないことは、福井プリンスが一番よくご存じである。必要なのは、信用創造を拡大する政策であることを、福井プリンスは知っている。しかし、日本銀行は、ワイマール共和国時代のライヒスバンクのように、説明責任を果たさないまま、職務を著しく逸脱した不適切な信用政策を行っている。欧州中央銀行や米国連邦準備制度理事会(FRB)が、こうした中央銀行の足跡をたどる危険性がある。
中央銀行といえども人間である。そのため、他の誰よりもエラーや利己的な行為に陥りやすい。彼らに必要なのは、こうした傾向を抑制するための適切なインセンティブ構造、すなわち民主的なチェック&バランスである。このようなチェックを行うことは、貨幣を蕩尽し、インフレを許容することを意味しない。それどころか、安定した貨幣の唯一の保証は、正しい政策目標を与えられた中央銀行の説明責任であることは、歴史が教えていることである。
民主主義国家における中央銀行の正しい役割について、より広範な議論が必要である。そのような議論は、中央銀行の事実と歴史に関する知識に基づくものでなければならない。これには、中央銀行がしばしば金利を煙幕として使い、本来の政策から目をそらすことがあるという認識も含まれる。このような政策は、通常、信用量を測定することでよりよく判断することができる。
拙著がこのような取り組みにささやかな貢献をしたことを報告できるのは嬉しい。日本語版は15万部発行され、ベストセラーの第1位となった。多くの国会議員に読んでもらった。自民党の何人かは、この本を読んで、「自民党中央銀行改革研究会」を立ち上げた。英語版が、海外でもこのような議論の活性化に貢献することを期待している。
2003年2月28日、東京
リチャード・A・ワーナー
謝辞
この10年間の研究期間中、私は多くの人々の支援、励まし、指導、助言を受けることができたが、彼らがいなければ本書は完成しなかっただろう。すべては、ホスピタリティあふれるオックスフォードのリナクレ・カレッジのボリ・ミナコヴィッチが、私にこの本を書くように促したことから始まった。彼は1991年にこの本を書いたとき、もっと早い時期に完成することを予期していたのだと思う。そして、私の家族や友人も同様で、あまりにも長い間、私がこの本について話すのを聞かなければならなかった。彼ら、特に両親、Dr. med. Günter H. Werner and Walfriede Franziska Werner, and my parents-in-law, T. John Cooke and Anne Cooke, for their support and patience, そしてもちろん私の妻、Romiの疲れ知らずのアクティブなサポートとアドバイスに感謝したい。研究の過程で、私は多くの教師、指導者、同僚、日本や経済学を学ぶ仲間、そして多くの誠実で高潔な中央銀行員から助けられ、学んだ。長いリストになるので、そのすべてを紹介するのは難しい。同時に、匿名を希望される方もいらっしゃいた。無名の方々、ならびにロバート・アリバー、リュビンカ・アニック、浅野幸博、ダニエル・バブレク、ジョン・ボールドウィン、ベンジャミン・ブーカン、ケネス・コーティス、クライヴ・クルック、ロード・メグナド・デサイ、ニコラス・ディームスデイルに感謝します、イーモン・フィングルトン、ダニエラ・フラウボーズ、ジェームズ・ゴードン、平野淳一、堀内昭義、ティム・ジェンキンソン、チャルマーズ・ジョンソン、ジェニファー・ジョセフ、貝塚啓明、金森一夫、加瀬政男、リチャード・クー、荒見倉井、C. H. クワン、マックス・フォン・リヒテンシュタインプリンス、クラウディア・マーズ、松原淳子、ポール・マクネリス、ウィリアム・ミラー、宮本雅夫、スティーブン・ニッケル、野口哲也、野口悠紀雄、尾形和彦、奥村弘彦、押尾孝、ゴン・リー、フロレンティノ・レダオ、坂井恵子、佐藤隆三、澤順三、クリストファー・スコット、アリサ・シャム、ニコラス・スターン、ポール・サマビル当麻理恵子、カレル・ファン・ウォルフレン、ピーター・ウォーバートン、山村浩三、吉田理子、吉野直行、旧日本開発銀行のフレンドリーなスタッフ、野村総合研究所で出会った親切なスタッフ、日本銀行の多くの誠実なスタッフ(名前を伏せた方が良い人)、財務省の研究所のメンバーたち; 上智大学の加賀美信光さん、デクラン・ヘイズさん、その他支えてくれた同僚、オックスフォード大学の先生や友人、ジャーディン・フレミング証券の元同僚、東京渋谷ハーベストのデビッド・キム牧師と友人たち; プロフィット・リサーチ・センターとProfitFundCom AGの過去と現在のチーム、すなわちジェニー・アルフ、クリス・バッファ、ローズマリー・クック、ニコラ・ディース、オルトウィン・ギアハケ、五箇清、五箇祐樹、ティホミール・カタルディエフ、マグヌス・ラガーレン伯、南陽子、長森誠、坂本葵、関康義、鈴木頼子、谷智則、ミヒャエル・トン、ロナルド・ヴェルナー、山田修二、そしてミヒャエル・フォン・リヒテンシュタインプリンス、アルベルト・マイヤー、マティアス・ヴォイトとマルティナ・ヴォイト、マヌエラ・ウルマー、クリスティン・エアハルトである。
さらに、この10年間、私の話に耳を傾け、私の研究成果を取り上げてくれた、日本や世界の良心的なメディアの多くの人々に感謝したい。
特に、マーク・メッツラーと妻のロミは、自らタイプスクリプトをすべて読み、改善のための多くの示唆を与え、私を誤りから救ってくれたことに感謝したい。また、編集者のパトリシア・ルー、M.E.シャープのアンジェラ・ピリオラス、スー・ワーガ、そして彼らの専門的指導とこのプロジェクトに対する大きな熱意に感謝したい。残りの誤りはすべて私のものだが、すべての功績は私の光である主によるものである(詩篇27:1)。
最後に、著作権者、特にM.E.Sharpe、East Asian Economic Association、Blackwell Publishers Ltd.から、過去の出版物の一部を複製する許可を得たことを謝辞として述べたい。また、過去12年間に、主に英国経済社会研究評議会(したがって英国の納税者)、Berthold Beitzの強力なリーダーシップによるKrupp財団、シティグループ財団、日本の文部省、日本財団(したがって日本の納税者)、欧州委員会(したがって純貢献国の納税者)、アジア開発銀行および株式会社Profit Research Centerから受けた研究資金援助を感謝するものである、東京)、アジア開発銀行、株式会社プロフィット・リサーチ・センター(以下、プロフィット・リサーチ・センター)(以上、全世界の顧客)である。
R.A.W.
頭字語および略語
- APEC アジア太平洋経済協力
- BIBF バンコク国際銀行ファシリティ
- BIS 国際決済銀行(Bank for International Settlements)
- CP コマーシャルペーパー
- ECB 欧州中央銀行
- EMEAP 東アジア・太平洋地域の中央銀行幹部会議
- EMI 欧州通貨研究所
- EMS 欧州通貨制度
- EMU 欧州通貨同盟
- ESB 経済安定理事会(Economic Stabilization Board)
- 欧州中央銀行制度(ESCB)
- 欧州中央銀行制度(European System of Central Banks)
- EU 欧州連合
- FDI 海外直接投資
- FY 会計年度
- GATT 関税と貿易に関する一般協定
- GDP 国内総生産(Gross domestic product)
- GHQ SCAP総本部 GNP
- 国民総生産(GNP)
- IBJ 日本興業銀行
- IMF 国際通貨基金(International Monetary Fund)
- JDB 日本開発銀行(現日本政策投資銀行)
- 自民党
- 日本の自由民主党
- LTCB 日本長期信用銀行
- LTCM ロングターム・キャピタル・マネジメント
- NSDAP 国家社会主義者ドイツ労働者党
- OECD 経済協力開発機構
- SCAP 連合国軍最高司令官
- WPI 卸売物価指数
- WTO 世界貿易機関
第1章 日本語レッスン
日本の新時代の幕開け
日本の経済、社会、政治の仕組みが根本的に変わったのは、近代日本の歴史上、19世紀末の明治時代と、60年前の敗戦時の2回だけだ。いずれの場合も、危機が変化の引き金となった。明治の改革は、外国による植民地化の脅威が後押しした。世界恐慌、太平洋戦争、そしてその結果としての敗戦は、2度目の大きな異変の引き金となった。
戦後の奇跡のような高度成長は、その成果にもかかわらず、量的変化であり、それまでの経済・政治制度の中で行われたものであった。今日、日本は再び岐路に立たされている。1990年代の危機は、これまでの「日本型」経済システムの終わりを告げている。日本は今、米国型の自由市場経済という、これまでとは根本的に異なる経済形態への転換を図っている。
バック・トゥ・ザ・フューチャー、フォワード・トゥ・ザ・パスト
皮肉なことに、このシステムは日本にとって新しいものではない。戦争前の日本では、自由市場がほとんど当たり前だったという事実を知る人は少ない。1920年代には、有名な戦後日本のシステムは存在しなかったのである。激しい競争、積極的な採用・解雇、大企業同士の買収合戦、官僚の統制の少なさ、高配当を求める強い株主、銀行ではなく市場からの資金調達など、日本経済は多くの点で今日の米国経済のコピーに見えた。しかし、戦後ずっと日本経済はその逆であった。高度に規制され、カルテルが競争を制限し、銀行融資と株式持ち合いが株主の力を弱め、買収はなく、終身雇用と年功序列の労働市場が凍結されている。
この戦後の経済システムの特異な性質は、何十年もの間、観察者たちを困惑させてきた。主要な経済理論では、成功に導くことができるのは自由市場だけであるとされている。しかし、日本は自由市場という「見えざる手」に頼ることなく、先進国から数十年で世界第2位の経済大国にまで成長した。この謎を説明するために、多くの理論が提唱されている。
戦争経済
日本を変えたのは、戦争前と戦後の間に起こった「戦争」という、日本研究において軽視されがちな出来事である。日本の経済システムは、大部分が第二次世界大戦中に作られたものである。その本性は、生産量最大化の動員型戦争経済である。
日本企業は、1940年代初頭から戦争態勢にあった。戦後間もない頃、米国は占領後の日本が自国のイメージ通りに生まれ変わったことを世界にアピールすることに躍起になっていた。しかし、実際には、冷戦の始まりとともに、米国は日本の戦時体制を維持し、戦時中の官僚エリートの権力を維持することを決定した。
ドイツの戦時経済大臣アルベルト・シュペーが戦犯としてシュPANDAウ刑務所に収監されている間、日本の戦時中の同僚が首相となり、その弟とともに12年間にわたり日本を統治する重要な役割を果たした。50年代後半から70年代前半にかけて、戦時中の官僚エリートは、戦時中に急速な資源動員を実現した「トータル・エコノミー」のシステムを完成させ、支配のレバーを握ったままである。制限された国内経済よりもはるかに大きな市場にサービスを提供することができるため、海外に進出する必要があった。日本の強化に関心のあるアメリカは、これを容認した。戦後、日本が世界市場を制覇するための先鞭をつけたのは、戦争経済の動員体制であった。
日本の経済システムの非凡さが長い間知られていなかった主な理由は、現在の多くの経済理論が非歴史的であり、通常は反事実的なアプローチであるためだ。歴史は、科学的な経済学者が研究するためのデータセットを提供するものである。歴史を無視することは、事実を無視することである。
日本の奇跡のモデルには、大企業や政治家の役割もあった。しかし、結局、経済は、企業、政治家、官僚のトライアングルではなく、財務省、通産省、日本銀行という狭いトライアングルによってコントロールされていた。この3つの機関の中で、日本銀行は最も目立たない存在だった。これほどまでに自己顕示欲が強いのには理由があった。日本銀行は、最強のコントロールツールに関する技術的知識を持っているため、実際には中央銀行が日本を支配していたが、法的には財務省に従属していた。そのため、常にほとんど権力を持たないように見せかけてきた。本書は、その権力の行使と誤用の真相を語るものである。
政府の介入は急成長をもたらす
経済的成功と自由市場経済は、今日、多くのオピニオンメーカーの目には事実上同義語に映っている。だからこそ、発展途上国は、世界銀行やIMFの信条である自由化、民営化、規制緩和を採用し、経済発展を遂げるよう説得される。鉄のカーテンが崩壊し、多くの共産主義国が市場志向の経済システムを採用したとき、一部のオブザーバーは「歴史の終わり」が来たと主張した: 自由市場主義の勝利である。
しかし、日本は自由市場を利用せず、世界第2位の経済大国になった。しかし、日本は自由市場を利用して世界第2位の経済大国になったわけではなく、計画者の手が非常によく見える資本主義経済システムが存在し、持続的に経済成長率で他のシステムを凌駕してきたのである。
日本の経験はまた、政府の介入がこれまで誤解されてきたことを教えてくれる。なぜなら、それは計画経済のようなお節介なマイクロマネジメントという形ではなかったからだ。その代わり、戦時中の日本の政府関係者は、高度成長のための適切なインセンティブ構造を作り出すことを目的とした意識的な制度設計によって、主に目に見える形で介入したのである。政府の介入を成功させるためには、組織設計が重要であり、勝者を選ぶことではない1。
制度設計
ドイツの思想家の影響を受けた戦争経済の指導者たちは、大規模な企業の創設を奨励した。彼らは、大企業に関わる3つのステークホルダー(経営者、株主、従業員)のうち、株主の目的が、計画者の全体目標である急成長に最も合致していないことに気付いた。そこで、株主は排除され、経営者は昇格し、従業員は企業内組合や雇用保障によって動機づけられた。
配当重視の株主から株式の持ち合いによって解放された経営陣は、利益を配当せず、再投資するようになった。その結果、経営者は会社を成長させ、市場シェアを拡大させることができた。そして、日本経済を高度成長へと向かわせた。
国内では、カルテルの形成により、熾烈なシェア争いを抑制する必要があった。しかし、カルテルが成立したからといって、競争がなくなるわけではなく、カルテル内での順位を競い合うことになる。最も重要なことは、海外での競争を制限するカルテルが存在しなかったことである。世界の門戸が開かれ、市場が自由になったことで、日本の成長マシンは大混乱に陥った。1960年代から1970年代にかけて、米国を代表する産業が次々と淘汰された。自由貿易にこだわらないヨーロッパは、日本の参入を制限した。日本人は、管理貿易に慣れ親しんでいたため、それに応じ、欧州との貿易摩擦が大きな問題になることはなかった。
成功の高い代償
戦争経済体制は、急速な経済成長という目標を達成するために大きな成功を収めた。しかし、そこには代償があった。労働者の利益は、大企業に雇用された少数派に奪われてしまった。現在でも全従業員の約3分の2が中小企業で働いているが、そこでは大企業が提供する終身雇用、住宅・福祉支援、多額の経費計上を享受することはできなかった。多くのメカニズムが、労働者の大多数に、せっかく稼いだ収入の多くを消費せず、節約することを強いた。税制優遇、食費や教育費などの生活必需品の高騰、地価の高騰、バラバラな年金制度などである。
世界ランキングの上位を目指す競争の中で、生活の質や環境、個人の自由や選択といった目標は優先順位が低いと判断された。日本の生活環境はまだ比較的貧しく、少なくとも世界第2位の経済大国としての地位には見合っていない。家は狭く、満員電車での通勤はしばしば2時間以上かかり、余暇は限られている。一部の都市部に集中し、レジャーのパターンまで統一されているため、休日の質も制限されている。
同時に、日本のシステムは所得と富の平等を実現し、その結果、社会的結束、安定、平和をもたらした。日本の犯罪率の低さは、今でも世界の羨望の的である。多くの発展途上国は、成功のためにこのような代償を受け入れるだろう。非資本主義体制から資本主義体制に移行する途上国にとっても、自由市場を導入して見えざる手による成長を待つよりも、日本の動員型経済モデルを採用した方がはるかに良い結果を得られる可能性があるということである。自由市場と動員経済、どちらの経済社会システムが望ましいかは、政治的な判断である。それは政治的な判断であり、そのように扱われなければならない。
日本にとって重要なことは、日本のシステムは不変ではないということである。2,000年以上前に遡ることはできない。戦後の戦争経済体制は、60年前にやっと導入されたものである。このことは、日本が劇的な変化を遂げることができることを証明している。必要なのは危機であり、変化の引き金となるような大きなショックである。
ヒトラーのコントロールツール
日本経済への介入は間接的、市場的なものが多かったが、強力な直接介入に使われたコントロールツールがあった。しかし、それは非常に微妙な形で機能するため、今日でも多くの経済学者がその存在に異議を唱えるだろう。そのツールとは貨幣である。戦時中の官僚たちは、貨幣とは何か、貨幣はどこから来るのか、そして貨幣が経済のあらゆる側面をコントロールするためにどのように使われるのかを理解していた。
ヨーロッパでは、貨幣経済学の進化は、その経済システムの後進性によって妨げられていた。中国の皇帝が紀元10世紀にはすでに紙幣を発明し、それを使って帝国を完全に支配していたのに対し、ヨーロッパの支配者たちはまだ貴金属だけが貨幣になり得ると考えていた。そのため、ヨーロッパの支配者たちは貨幣の供給量を管理することができず、自国を支配することができなかった。そのため、金は金細工職人に預けられ、彼らが最初の銀行家となった。銀行が貨幣を作り、それを誰が手に入れるかを決めるという事実が持つ広範な意味を無視したため、彼らの活動に対する誤った理解が、何世代もの政治家や経済学者を迷わせたのである。一方、戦時中の官僚たちは、銀行の役割を理解し、貨幣が経済の生命線であることを認識していた。
ヒトラーの中央銀行家、ヒャルマル・シャハトの手法に影響され、日本の戦争経済の指導者たちは、信用創造を全体統制のための最も強力なメカニズムに変えた。彼らは銀行システムを意図的かつ巧みに利用し、狙った産業に資源を配分したのである。
窓際指導
戦争官僚が用いた信用管理は、戦後もほとんど変わることなく存続した。それは、日本銀行が行った超法規的で秘密主義的な「窓口指導」という形であった。この「指導」は、中央銀行が厳格に実施する直接的な信用割当からなるものであった。これが戦後日本の経済的成功の核心であった。また、日本が戦時中に同じものを導入し、戦後の指導者がそれを使い続けた韓国や台湾の成功も、この説明でわかる。
1950年代から60年代にかけて、窓の誘導制御は、強大な権力を持つ大蔵省と法的に従属する日本銀行との間の覇権争いの中で、重要な役割を果たすようになった。大蔵省が最初の政争に勝利し、日本銀行法(1939年のヒトラーのライヒスバンク法の翻訳として1942年に導入された)の改正を回避した一方で、日本銀行は窓口指導を単独で担当することになった。日本銀行は、金利をコントロールできるようにし、量的信用政策の重要性を軽視することで、日本銀行に誤った安心感を与えていた。日本銀行の一連の研究は、従来の新古典派経済学(よく言えば信用政策の役割はなく、悪く言えば貨幣が存在しないと仮定している)に支えられ、信用規制が効果的でないことを「証明」した。そこで、日本銀行は信用規制の廃止を発表した。信用規制の強力な性質に関する記憶は、年月とともに薄らいでいった。1970年代には、大蔵省が君臨していても、支配しているのは日本銀行であるという事実を認識している人はほとんどいなかった。
テストラン最初のバブル
1970年代、日本銀行は、経済運営の自律性の限界を試すために、与信管理機能を強化した。日本銀行は、投機的な不動産の借り手に対して融資を拡大するよう、窓口指導で銀行に命じた。その結果、地価は高騰し、日本は戦後初のバブル経済の真っ只中に置かれた。その後、大蔵省を中心としたエリート層が不況に見舞われるのは必然だった。窓販の役割はほとんど知られていなかったので、日本銀行にはほとんど何の責任もなかった。
この経験は、1980年代から1990年代にかけての出来事の基礎を築いた。中央銀行は、戦争経済に代わる日本の新しい経済、社会、政治システムに関する独自の計画を策定するようになったのである。この新システムは、米国流の自由市場をモデルにしていた。日本銀行は、従業員など他の利害関係者ではなく、株主が主導権を握っていた日本の自由市場の過去から「未来に戻る」ことを望んだ。同様に重要なのは、自由市場制度では、しばしば中央銀行が経済に対する文句のつけようのない権威として残ることである。もちろん、このような深い構造改革を導入するためには、戦争経済システム全体を解体する必要がある。それは革命に等しい。革命は危機の時にしか起きない。
世界を買い占める
1986年頃から1990年頃まで、日本のお金が世界中に溢れた。ニューヨーク、ハワイ、オーストラリアの不動産から、アメリカ、ヨーロッパ、アジアでの企業買収まで、日本のお金は地球を買い占めるかのようだった。海外投資の規模は前代未聞で、そのあまりの大きさに専門家も釈然としないものがあった。1987年、日本の純長期対外投資は、過去最高の経常黒字の約2倍に達していたのである。このような規模の外国投資は、従来の経済モデルを覆すものであった。しかし、日本のお金の流れは謎のままであった。1991年、日本は史上最大の資本純輸出国から資本純輸入国に突然転じ、事態はさらに深刻化した。その原因は何だったのだろうか。
信用バブルとバスト
1980年代後半、日本はお金を作りすぎ、その一部が海外に流出した。国民所得が約6%しか伸びなかったのに、銀行の信用創造は約15%の割合で拡大した。新しく作られたお金は、生産的に使われることはなかった。土地や株の投機的な購入に回された。膨大な量の新しい購買力が、資産価格を目もくらむような高さに押し上げた。1989年、東京の皇居を囲む小さな土地は、カリフォルニア州全体と同じ市場価値を持っていたのである。バブルだったのだ。
長い目で見れば、生産的に使用されない信用創造は、返済されない。経済のニーズを超えた過剰な信用創造は、不良債権にならざるを得ない。これが1990年以降に起こったことである。銀行融資の伸びは鈍化した。資産価格の下落に伴い、投機筋は破産し、銀行は袋叩きにされた。日本のGDPの5分の1にあたる約100兆円相当の融資が、1990年代に不良債権化した。銀行は麻痺状態に陥り、融資を停止した。信用収縮は失業率を押し上げた。そして、世界恐慌以来最悪の不況に突入した。
誰が悪いのだろうか。大蔵省の責任だとする見方が大半だった。財務省もそう考えていた。しかし、景気回復のための試みはことごとく失敗に終わった。記録的な低金利と前代未聞の財政出動にもかかわらず、景気は回復しなかった。ほとんどのオブザーバーは、「このシステムはもう機能していないようだ」と結論づけた。1990年代の長期不況は、日本の戦後の奇跡から輝きを奪い、戦争経済を維持してきたコンセンサスを崩壊させた。
しかし、好景気から不景気になったのは、システムが原因ではない。また、金利を下げたり、財政政策が役に立ったわけでもない。1993年か1994年の段階で、簡単に景気回復を実現できた簡単な政策があった。銀行が十分な資金を作らないため、物価は下がり、需要は縮小し、失業率は上昇した。経済にはもっとお金が必要だったのである。日本銀行が印刷機のスイッチを入れるだけで、これほど簡単なことはない。
円の戦い
では、1990年代に日本銀行はどれだけお金を刷ったのだろうか。ごくわずかである。大蔵省が必死に景気回復を図ろうとする中、日本銀行は焦る様子もない。大蔵省の指示で金利を下げたが、同時にお金の流通量も減らしてしまった。ゼロ金利といっても、大多数の企業(中小企業)がいくらお金を借りてもダメなのではどうしようもない。総務省が財政支出を増やしたとき、中央銀行は新たな貨幣創造で資金を賄うことができなかった。そのため、民間投資家への債券発行によって資金を調達したが、これは単に民間需要を圧迫するだけだった。1995年初め、円安で輸出を伸ばそうとした財務省が絶望し、記録的な量の為替介入を指示したとき、中央銀行は静かにすべての介入を不妊化した。円は強いままだった。1995年3月、中央銀行は過剰不胎化を行い、円を戦後最高値の79.75円まで上昇させた。これは、経済と経済産業省に再び大きな打撃を与えた。
90年代の不況は、中央銀行の政策の結果であることは間違いない。それは信用量によって微調整することができた。しかし、中央銀行の行動を分析すると、不況を長引かせることを選択したことがわかる。
一方、中央銀行は財務省の権力基盤に正面から攻撃を仕掛けた。1960年代以来初めて、日銀法に関する議論を再燃させ、政治家への働きかけを行った。その目的は、法的な独立を果たすことであった。不況の原因を日銀に求めた結果、中央銀行が勝利した。総務省は敗北し、すべての重要な権力手段を奪われた。中央銀行は今や独立し、責任を負うことはできない。アジアでは、敗れた敵は少なくとも面目を保つことが許されることが多いのだが、中央銀行にはそのような慈悲はない: さらに追い打ちをかけるように、この省はその偉大な旧名称を剥奪された。2001年1月、大蔵省は消滅した。
中央銀行の奇妙な政策
日本銀行はなぜ90年代の不況を長引かせたのか。その答えは、もう一つの謎が解けたときに初めて見つかる。1990年代の出来事は、1980年代のバブルに根ざしている。そもそも、平時の歴史上最大の資源配分のミスであるバブルは、どのようにして発生したのだろうか。それは、銀行による過剰な信用創造が原因であることは分かっている。しかし、なぜ銀行はこれほどまでに融資を行ったのだろうか。
1940年頃から1970年代末まで、銀行の貸し出しは日本銀行の窓口指導によって決定されていたことが分かっている。しかし、日本銀行の公式発表によれば、こうした信用管理は廃止され、重要な1980年代には使用されていなかった。これが現在までの通説である。それは本当だろうか。窓販指導が継続されていたという証拠がある。これは決定的な証拠である。誰が引き金を引いたのか?意思決定者の動機は何だったのか?その答えは、日本銀行がなぜ1990年代の不況を長引かせたのかを解明する手がかりとなるであろう。
日本の驚くべき物語は、並行するものがないわけではない。1990年代初頭、韓国、タイ、インドネシアの中央銀行は、1980年代の日本銀行と同じような政策に着手している。ドイツのライヒス銀行が先駆けた銀行融資の超法規的な「指導」を用いて、銀行が不動産投機家に過剰な融資をするように仕向けた。バブルは、中央銀行の政策により、過大評価された固定為替レートと外国より高い国内金利を維持することでさらに膨れ上がった。投機家は、海外から借金をするためのあらゆるインセンティブを与えられた。記録的な量の米ドルがアジア地域に流入し、バブルをさらに煽り、状況をより不安定なものにしていった。1997年、投資家は撤退した。同時に、中央銀行は商業銀行に対して信用創造を制限するよう迫った。バブルは崩壊した。
中央銀行は自国通貨を速やかに変動させる代わりに、高すぎる為替レートを守ろうとする無駄な試みで、多額の外貨準備を確実に浪費させた。1997年後半には、3カ国とも債務超過に陥った。中央銀行が信用創造をさらに減らしたため、危機は不況に転じた。なぜ、3カ国とも同じような悲惨な政策をとったのだろうか。
第二の経済的奇跡の前途
1970年代に入ると、日本の戦時体制ではもう高成長は望めないとする声が大きくなった。戦時中のシステムは、土地、労働力、資本、技術などのインプットを増やすことでアウトプットを最大化するものであった。しかし、1970年代に入ると、日本はインプットを使い果たし、潜在成長率が低下していったのである。1990年代には、他のアジア諸国でも同じようなことが言われた。その解決策の一つとして、米国型の資本主義を導入して生産性を高めることが提案された。
導入され、極めて成功した実績から約60年後、日本の戦争経済構造は廃棄された。1990年代の歴史的な規制緩和、法改正、市場原理主義的な改革がその土台を崩した。市場原理は今、米国型市場の目標に向かってますます加速している。規制緩和によって新しい産業が生まれた。
国内経済は生産性が向上し、最大で4%の非インフレ成長を実現できるようになった。これは、日本のような先進国にとって、第二の経済的奇跡にほかならない。では、日本とアジアの近隣諸国は、すべて順調なのだろうか。私たちは、すべての不可解な質問に答えて初めて知ることになる。
