Contents
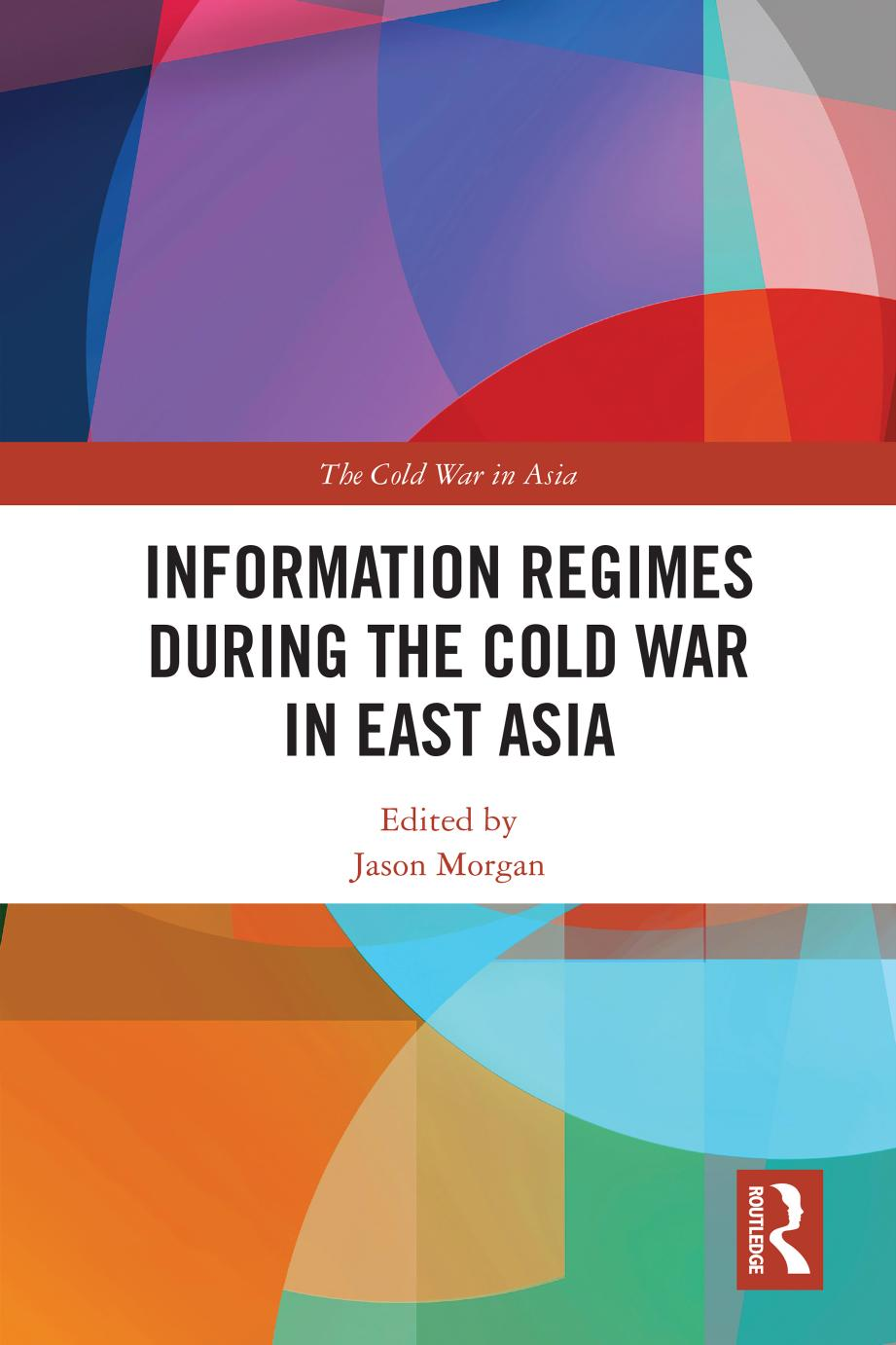
Information Regimes During the Cold War in East Asia
東アジア冷戦期の情報体制
モーガンと寄稿者たちは、冷戦期の東アジアにおける情報の利用、濫用、統制を理解する方法として、情報レジームという概念を展開している。
冷戦時代、戦争そのものが変化し、国家運営も変化していた。情報は最も価値のある商品として台頭し、世界中の社会の重要な構成要素となった。第二次世界大戦後に結ばれた軍事同盟が最も厳しい試練にさらされた東アジアでは特にそうであった。こうした試練は、米ソ間の敵対関係や同盟内の圧力という形で現れ、最終的には中華人民共和国をモスクワから離脱させ、1950年代から1960年代にかけては日本も一時、ワシントンから離脱する構えを見せた。軍事力や経済的影響力よりも重要だったのは、「情報体制」、つまりパラダイム、イデオロギー、政治的配置を獲得した領土の広がり、である。情報体制は必ずしも国家中心ではなく、本書の寄稿者の多くは、そうでない事例に焦点を当てている。このような焦点によって、東アジア冷戦は実際には「冷戦」ではなかったが、人間相互作用の決定的要素としての情報の活発な、争いの絶えない誕生の震源地であったことを知ることができる。
本書は、東アジアと20世紀の情報管理の発展を研究する歴史家にとって貴重な資料である。
ジェイソン・モーガンは麗澤大学グローバル・スタディーズ学部准教授である。
目次
- 寄稿者リスト
- シリーズ・エディター序文
- 序文
- 謝辞
- はじめに
- 第1部 外交、パブリック・ディプロマシー、スパイ活動
- 1 カーテンの向こう側:ソ連の諜報部員と日本人ジャーナリストはいかにして北方領土返還を伴わない日ソ国交正常化をもたらしたか?
- 2 中国を救い、中国を失う:戦争前から冷戦期への情報体制の変容
- 3 「壊れた対話」を繋ぎ合わせる:ダグラス・マッカーサー駐日大使とフォーリン・アフェアーズ論文をめぐる論争
- 第2部 知識ネットワークと学術
- 4 「強制動員」: 北朝鮮に触発されたパク・キョンシクと在日アイデンティティ
- 5 1950-1971年、イギリス領マラヤにいたオーストラリア人に与えた中国共産主義の影響:ほぼ「原住民化」することでイデオロギーから逃れる
- 第3部 イデオロギー、宗教、文化
- 6 日本におけるカトリックと冷戦
- 7 外交主体としての北朝鮮にとってのゲシュタルトとしての冷戦
- 8 東アジアにおけるローマクラブ:米国主導の人口管理情報レジームと極東冷戦の遂行
- 索引
序文
本書は、情報の本質と冷戦の歴史的現実について、学者と編集者の間で交わされた長い対話の成果であり、成果物である。私がこのような書物を提案した当初の意図は、情報が冷戦における闘争の重要な要素としてどのように見なされ、利用されたのか、また、冷戦の歴史(そして実際、他のいかなる時代や場所の歴史も)が、国家や階級や歴史的過程ではなく、むしろ私たち全員が生涯を通じて行っていること、すなわち、情報を理解し、それを最大限の効果を発揮させるために管理しようとすることを前景化することによって、どのように異なって理解され、おそらくはより良く理解されるのかを、さまざまな視点から探求することであった。
これは必ずしも壮大なことではない。Y店の方が牛丼が安いが、X店の方が牛丼が美味しいと知っていれば、X店に行くことを決め、効率的に食事をすることができる。牛丼の広告主や他のレストランの広告主は、できる限り私に影響を与えようとしてきた。これはミニチュアの情報体制であり、大小の情報体制はどこにでもある。子供や犬でさえ、ある行動の結果から隠れようとするとき、あるいは猫が鳥に忍び寄るとき、そこには情報のやり取りがある。私たちは自分が知っていることに反応し、他人が自分が知っていると思うことに反応する。
しかし、これが政治的な問題となり、国家や組織、大きな思想が関与し、人命が危険にさらされ、帝国全体が根底から覆される危険があるとき、日々の情報闘争はまったく異なる種類の緊急性と即時性を帯びる。人間の制度的・組織的衝動に組み込まれた理由から、誰かが、あるいはある集団が、YではなくXを信じていることが絶対不可欠となる。これは、プロパガンダよりも、広告よりも、ディセンブルやフェイントよりもずっと深い。これは、特に人間的な分野としての情報であり、さらに政治的で、政治的結果のさまざまな段階における必然的な公的行為者として私たちの生活に浸透している、深くマッピングされた分野である。私たちが自らを政治的な人間だと考えるかどうかにかかわらず、このような情報の形成は、私たち自身の一部となり、私たちの信念を形成し、私たちの環境を再編成する過程で、今度は私たちを再編成する。私たちは常に情報を整形し、他人によって整形された情報を常に取り入れている。奇妙な服装に関する白々しい嘘から、戦争の結果に影響を与えるための重要な事実の選択的報道まで、人間は情報的存在であり、常に変化する情報環境に適応している。
このような情報の完全な参加型という性質が、私の言う情報体制である。それは、情報を、食料、住居、水、電力、生命と並ぶ、人間生活の根幹をなす要素として捉えることであり、生存と繁栄のために必要な他の何かと同様に、人間の存在にとって基本的な要素である。歴史としての情報体制と歴史学的解釈法としての情報体制は、知る主体としての人間を全面的に捉え、歴史研究に情報を再統合するという意味で、人々の歴史を構成する。現場の人間が見たように物事を見、思考過程をリアルタイムで再現し、読者を脳と感情の複雑な過去へと誘うことが、情報体制史の目標である。私たちが歴史を理解しているつもりになっている方法は、しばしば実際のあり方とは異なる。本書は、モダンとポストモダンを結びつける試みであり、確固たる事実の間に情報の差異を確立し、情報がいかに出来事の周囲を流れ、出来事を通して流れ、出来事に対して流れるかを示し、過去研究の新たな展望を切り開くものである。
本書の編集にあたり、私は誰よりも情報体制について学んだ。冷戦は非常に複雑な現象であり、出来事であり、歴史的過程であり、歴史認識の新たな様式を試すためにこの茨の道に飛び込むには、勇気と気概、そして多くの知識と専門知識が必要だった。本書の執筆に携わった研究者たちは、この難題に見事に立ち向かったと思う。彼らは確実に私の尊敬を集めている。寄稿者たちは、情報、歴史、学問に対する私の考え方を刺激的な方法で変えてくれた。本書があなたにも同じことをもたらすなら、本書はそれ自体が情報体制として成功したことになる。
はじめに
冷戦とは、1945年の第二次世界大戦終結から1991年のソビエト連邦崩壊までの約半世紀の間、世界の多くがソビエト連邦とアメリカという2つの巨大帝国に分断されていた時代のことである。冷戦期には、朝鮮半島、東南アジア、東欧、アフガニスタン、中東、ラテンアメリカなどで活発な軍事衝突があったのは確かだが、冷戦は定義上、両帝国が互いに直接的で本格的な軍事的敵対行為を公然と行わない自制の期間であった。
しかし、「冷戦」という言葉には、もっと大きな現実が隠されている。冷戦の間、戦争そのものが、国家運営やその他ほとんどすべての人間の活動や制度と同様に、変化していたのである。20世紀には、情報が最も価値のある商品として台頭し、やがて世界中の社会の重要な構成要素となった。冷戦が軍事的に「冷たかった」のは、サイバー戦争(選挙や政治プロセス全体への干渉を含む)が「ホット」であるのと同じ理由である。
冷戦時代の東アジアでは特にそうだった。東アジアでは、第二次世界大戦後に2つの帝国超大国が結んだ軍事同盟が最も厳しい試練にさらされた。こうした試練は、米ソ間の敵対関係や、同盟内部からの圧力という形でもたらされた。この圧力は、最終的に中華人民共和国をモスクワから離脱させ、1950年代から1960年代にかけては、日本が一時、ワシントンから離脱する構えを見せたこともあった。
しかし、軍事的な優位性以上のものがあった。冷戦の間、国家対国家、個人対個人の旧態依然とした交流は枯渇した。軍事力よりも、経済的影響力よりもさらに重要だったのは、「情報体制」、つまりコンセンサス、パラダイム、イデオロギー、共有された一連の前提、精神的屈折、政治的配置が得られる領土(地理的に連続しているかどうかは問わない)の創出だった。情報体制は必ずしも国家中心ではない。実際、本書の目的のひとつは、東アジアの冷戦について考える際に、国家中心主義から脱却することである。そうすることで、学者や他の研究者は、東アジア冷戦を「冷戦」ではなく、戦後における人間相互作用の決定的な要素としての情報の、活発で、騒々しく、論争的で、波乱に満ちた誕生の場として捉えることができるようになる。
「情報レジーム」は歴史分析においてはかなり斬新なもので、これまではマーケティング用語として使われることがほとんどだった。例えば、Organization Science誌の2000年6月号に掲載されたエッセイ「When Market Information Constitutes Fields: N.アナンドとリチャード・A.ピーターソンは、「競争的な分野では、市場が磁石の役割を果たし、その磁石の周りに行為者のグループが集約される。
しかし、ここでの「情報体制」は、製品ブランディング以上の意味を持つ。歴史的ヒューリスティックとして「情報体制」をより広範に使用するための試金石は、アルフレッド・マッコイ教授(ウィスコンシン大学マディソン校)が2013年にカロライナ大学で行った講義「帝国の認識論」:」帝国の認識論:アジア戦争、情報体制、そしてアメリカのグローバルパワーの未来”と題された。私の知る限り、マッコイの研究は、「情報体制」が国家の行動や政治的・軍事的パワーの行使を示すために世界史的文脈で使われた初めてのケースである。たとえばマッコイは、アメリカの歴史には3つの「情報体制」があったと主張している。第1は1898年のフィリピンの反乱、第2はベトナム戦争、第3はイラクとアフガニスタンの占領である。マッコイは、『アメリカの帝国を取り締まる』(Policing America’s Empire)の中で、彼の「情報体制」アプローチを最も顕著に示している: The United States, the Philippines, and the Rise of the Surveillance State』(2009)や『In the Shadows of the American Century: The Rise and Decline of US Global Power』(2017)である。
2013年の講演でマッコイは、現代世界におけるインペリアの評価において、「経済力と軍事力という鉄の二元論を超えて」学者たちが目を向けることを提案した。本書では、マッコイの呼びかけに触発され、国家や政治的アクターを経済システムや軍事的取り決めだけで見るのではなく、さまざまな思想家や専門家が「情報体制」というレンズを通して東アジアの冷戦をあらためて考察している。ベネディクト・アンダーソンのよく知られた「印刷資本主義」のアプローチとは異なり、ここでの「情報体制」には、ナショナリストの感情を生み出す以上のものが含まれる。カテゴリーとしてもヒューリスティックとしても、「情報体制」は、特に東アジアにおける冷戦闘争の重要な要素として、国家ではなく情報を前景化している。情報が争点となり、政治が情報に左右されるところでは、情報体制が争われることになる。結局のところ、「人の心をつかむ」ということは、特定の軍や政府が行うよりもずっとずっと大きなプロジェクトであった。他の学者たちも冷戦期の情報を研究しようと試みているが、その方法は限られている。例えば、冷戦期のスパイ工作や偽情報、つまり敵の支配下にある地域を弱体化させ不安定化させるための情報利用については、膨大な文献がある(例えば、Ion Mihai Pacepa中将とRonald Rychlak著『Disinformation』(2013)を参照)。東アジアの冷戦以外でも、国家や帝国、そして企業やその他の主要機関が、自らの勢力圏内の住民に影響を与えるために情報を利用することに関する重要な書籍がある。例えば、ジャック・エルールの『プロパガンダ』: 1962)、エドワード・バーネイズの『プロパガンダ』(1928)、バーネット・ヘシェイとの共著『米国の海外情報政策とプログラム再評価のケース』(1970)、ウォルター・リップマンの『世論』(1922)、『冷戦』(1947)はいずれも、社会や戦争を調査する主要な手段として情報を前面に押し出した初期の試みである。
文化もまた、しばしば冷戦の文脈で研究されてきた。例えば、Annette Vowinckel、Marcus M. Pavk、Thomas Lindenbergerの『Cold War Cultures』: 2012)、アンドリュー・デフティの『イギリス、アメリカ、反共プロパガンダ1945-53:情報研究部』(2004)、ジュディス・デブリンとクリストフ・H・ミュラーの『言葉の戦争』(2004)などがある: 2013)は、経済力と軍事力というマッコイの「鉄の二元論」の外側で冷戦を検証する方法として、情報と文化を見ている。その他、李暁冰『東アジアの冷戦』(2017)、オッド・アルネ・ウェスタッド『冷戦:世界史』(2017)、デイヴィッド・S・ペインター『冷戦:国際史』(1999)、S・J・ボール『冷戦:国際史 1947-1991年』(1998)、リチャード・J・クロッカット『冷戦:国際史 1947-1991年』(1998)などがある。Crockattの『The Fifty Years War: The United States and the Soviet Union in World Politics, 1941-1991』(1994)は、冷戦を世界史の文脈に位置づけ、モスクワやワシントンから遠く離れた地域に与えた影響という、冷戦のより広範な輪郭を浮き彫りにしようとしている。しかし、いずれの著作も国家中心の冷戦パラダイムから脱却していない。オッド・アルネ・ウェスタッド(Odd Arne Westad)の『Reviewing the Cold War: Approaches, Interpretations, Theory』(2000)でさえ、冷戦を国家間の争いであり、国家を起源とし、国家に指示された権力の行使であるという見方を維持している。
この観点から、本書は東アジアにおける冷戦を研究する新しいアプローチであり、現代の情報と情報交換の世界を研究するものでもある。ここに収められた論考はいずれも、国家と非国家アクターの両方が、人間相互作用の重要な組織原理としての情報の台頭にどのように適応していったかを示している。冷戦時代には、東アジアにおける共同生活の原動力はますます情報であった。したがって、「冷戦」の膠着状態から熱狂的な情報活動へと焦点を移すことで、今後の研究に新たな道が開かれ、学者も一般人も、帝国に象徴される冷戦ではなく、情報の重力を形成しようとする試みが生きていた冷戦を再考することができるだろう。
第1部「外交、パブリック・ディプロマシー、スパイ活動」では、日本のロシア史・政治学者で元防衛大学校教授の滝沢一郎が、1956年の日ソ国交樹立交渉の幕開けに光を当てる。滝沢氏の研究によって、日本に駐在していた2人のソ連情報将校が、日本側との交渉の開始と遂行において非常に重要な役割を果たしていたこと、また、日本における親ソ情報体制の育成において、ソ連にとって非常に有益であったことが明らかになった。その一人がアンドレイ・イワノビッチ・ドムニツキーである。彼は、ある夜、闇に紛れて、日本の左翼記者の協力を得て、首相官邸の裏口から忍び込み、鳩山一郎首相に私信を手渡し、外交交渉を開始した。ドムニツキーは数年前まで知られていなかったが、滝沢がソ連の資料を発掘し、ドムニツキーが第二次世界大戦中、極東戦線で豊富な作戦経験を持つプロの海軍情報将校であったことを明らかにした。もう一人のソ連軍将校は、2018年2月に99歳で亡くなったセルゲイ・ティフヴィンスキーである。ティフヴィンスキーは中国通で、ロンドンに滞在していたが、急遽、東京のソ連外交団長に召集された。滝沢のエキサイティングな新研究は、日本におけるソ連外交官のスパイ活動の詳細を明らかにし、冷戦期、特に日本における情報の極めて重要性と、個人に影響を与え、国家や国際的な政策にさえ影響を与えるために、地域に根ざした情報体制の構築が不可欠であったことを示している。これまで知られていなかった2人のソ連の情報戦士によって冷戦下で醸成された情報体制の結果、日本は領土的にもその他の面でも不利な立場に置かれ続けている。
第1部第2章では、政策アナリストであり日本近代政治史研究者でもある江崎道朗と私が、戦争前から冷戦初期にかけての中国大陸と台湾を取り巻く情報体制の変化について調査する。中国でキリスト教の布教活動が盛んに行われていた時代、それ自体が情報体制であったため、宣教師をはじめとする西洋人はしばしば中国を「救う」と口にした。というのも、ある者は中国の人々をキリスト教に改宗させることで中国を救うと語り、ある者は日本から中国を救うと語り、またある者は資本主義や共産主義から中国を救うと語り、さらにある者はこれらの2つ、あるいは3つすべてを混同して語ったからである。例えば、戦争前の中国のYMCAには、モスクワを拠点とする共産主義インターナショナル(コミンテルン)の諜報員が入り込んでいた。YMCAの幹部の中には、初期の宣教師たちを中原に駆り立てたキリスト教的救済論を維持する者もいれば、イエスではなく、マルクスとエンゲルス、後にレーニン、そして最終的にはスターリンによる政治的救済を意味するメッセージを微妙に陰らせ始めた者もいた。アメリカ政府が何が起きているのか理解したときには、時すでに遅しであり、情報体制は、中国を救うための希望的観測から、中国を失った責任を他者になすりつけるものへと変化していた。冷戦期の日本におけるスパイ機関の役割を再検討し、「戦争」と「平和」、「安全保障」と「同盟」についての対話と物語を形成する上で、情報がいかに重要であったかを示す。シンクタンク、出版物、シンポジウム、その他の組織や機関は、冷戦体制における国家権力の代理人として見なされることが多いが、江崎と私は、舞台裏の現実の流動的で争いの多い性質を示そうと試みている。日本の戦争前・戦中期には、調査会社や南満州鉄道会社の事務所など、日本政府の機関に国家権力が入り込んでいたが、こうした国家権力者と、ソビエトや他の政府に情報や協力を提供する個人との相互作用は非常に複雑であり、最終的には、日本国民を外国の大義に取り込み、忠誠を維持するための高度に地域化された「情報体制」の構築に依存していた。この複雑さは、冷戦下のアメリカ、日本、台湾、中国を構成する他のトランスナショナルな力学と結びついたとき、何倍にも膨れ上がった。
日米関係史の専門家であるロバート・D・エルドリッヂ(中曽根平和研究所客員研究員)は、第1部の最終章である第3章で、東アジアにおける冷戦の重要な瞬間、エドウィン・O・ライシャワーの有名な1960年のフォーリン・アフェアーズ誌の記事「壊れた対話」と、この記事が引き起こした、在日アメリカ大使館が日本の左翼知識人と関わるべきかどうか、どこまで関わるべきかという議論について書いている。 The Return of Amami Islands: The Reversion Movement and U.S.-Japan Relations」(Lexington, 2004)、「日米関係における硫黄島と小笠原」(Lexington, 2004)などがある: エルドリッヂは、当時ハーバード大学の教授であったライシャワーが、『フォーリン・アフェアーズ』誌上で、日米間の「壊れた対話」は、戦後の日米関係の基盤であった安保条約に批判的な声をアメリカ人が取り入れないことが主な原因であると主張した後、ダグラス・マッカーサー2世やアメリカの外交体制からの強い圧力に直面したことを明らかにしている。 S.- エルドリッヂの章は、戦後の日米同盟の基盤である安保条約に批判的な声を取り上げることをアメリカ人が拒否した結果である。エルドリッヂの章は、情報体制の構築をめぐる特定の、しかし重大な戦いについての詳細な調査である。アメリカ政府は、アメリカ当局のコントロールの及ばないところで、(ライシャワーは生粋の日本人であったため、主に日本語で)知識人たちによって作り上げられた情報体制に制限を加えようとしたが、結局は失敗した。情報体制の構築はしばしば個人と国家との間の交渉であり、エルドリッヂのエッセイは、情報をめぐる戦いにおいて個人が国家に関与する緊張と可能性を浮き彫りにしている。
次のパート「知識ネットワークと学問」は、知的歴史と、思想が文脈の中でどのように機能し、情報が現実の歴史的時間の中でどのように争われるかについての鋭い理解を組み合わせた2つのエッセイから成る。『強制動員』では、パク・キョンシクとZ: ハワイ大学マノア校アジア研究科の教員であり、韓国の専門家であるチズコ・T・アレン氏は、「強制動員:パク・キョンシクと北朝鮮に触発された在日のアイデンティティ」において、冷戦時代に数人の韓国人学者が、日本による韓国併合時代(1910-1945)に対する多くの韓国人の認識を変える上で果たした役割を検証している。日本は今日、第二次世界大戦争前と戦時中に韓国人に対する犯罪を犯したと非難されることが多いが、そのどれだけが歴史的なもので、どれだけが冷戦時代の情報体制によって生み出されたものなのだろうか?アレンは、パク・キョンシク(1922-1998)の著作が、韓国人と日本人の戦争前・戦中の記憶の仕方に大きな影響を与えたことを示し、冷戦時代の感性が、東アジアの歴史学の支配的なパラダイムとして続いている日本の残虐性と抑圧の情報体制をいかに生み出したかを明らかにする。植民地時代の日本の蛮行を強調する韓国ナショナリストの歴史パラダイムは、韓国人の集団的経験から生まれたものではなく、1960年代から1970年代にかけて日本で出版された韓国人学者の著作から生まれたものである。1940年代末の朝鮮半島分断によって在日コリアンが二つの陣営に分かれると、パクは北朝鮮の側に立ち、東京の北朝鮮学校で教え始めた。社会主義史観の影響を受け、パクは戦時中の朝鮮人男女の動員を中心に、日本の植民地主義を批判的に書いた。帝国日本は抑圧者であり、朝鮮人は被害者であるという彼の描写は、日本の知識人社会に聴衆と支持者を見出しただけでなく、韓国の最近の過去に対する認識に長い影を落とした。この情報体制は後の歴史学を歪め、21世紀の東アジアやそれ以外の地域でも冷戦時代のメンタリティを再現し続けているとアレンは主張する。
第2部最終章では、政治学博士(ハーバード大学)で現在アジアを専門とする政治アナリストのアンダース・コーが、冷戦期のマラヤにおけるイギリス帝国主義と中国共産主義のイデオロギーに注目する。コールのユニークなアプローチは、1950年から1971年までマラヤにいたオーストラリア人錫鉱夫、トム・ヌナンの日記を中心に据えている。ヌナンは、相反する情報体制が存在した時代と場所に生きており、彼の日記とコアの研究は、それらの情報体制が現場でどのように操られていたかを示している。中国共産党は、第二次世界大戦終結直後から、イギリス帝国主義に対抗するため、マラヤで中国人の反乱軍を動員した。イギリスによって1948年から1960年の「非常事態」と名付けられたこの反乱は、ヌナンが生活の糧としていた鉱山事業に悪影響を与えた。この非常事態はまた、マレー民族主義の発展とマレーシアの独立を早め、マラヤナイズを通じてイギリスとオーストラリアのビジネスと社会生活にさらなる影響を与えた。その結果、1950年代後半から1960年代にかけて、マラヤにおけるイギリスの経済力と政治力は、それぞれ中国人とマレー人に移行し、東アジアの冷戦期における主要な情報体制、すなわち中国共産主義の台頭を示すことになった。このことは、同時に台頭してきたマラヤ化と相まって、1950年代初頭にヌナンが説明し生きてきた、それ以前のイギリス帝国あるいは植民地的な情報体制を侵食した: 「エキゾチックな冒険」の地における。「白人の優越性」である。彼はほぼ「ネイティブ化」することで、イギリスと中国の共産主義の情報体制とヒエラルキーから逃れようとしたのである。冷戦期の中国共産党の情報体制は、中華人民共和国の国境をはるかに越えて広がっていた。マレー人、中国人、ユーラシア人を含む、ヌナンの人生と民族的に多様な交友関係は、イギリスの植民地主義を「人種差別的抑圧」として一元的に描こうとした中国共産党と、排除政策を通じて人種的・経済的ヒエラルキーを維持しようとしたイギリスの植民地主義者の両方のイデオロギーに、個人がどのように対抗することができたか、そして実際に対抗したかを示している。情報体制は常に、歴史家が現場の出来事に近づけば近づくほど複雑さを増すものであり、コールのエッセイはこの公理を完璧に検証している。
第3部「イデオロギー、宗教、文化」の小論は、組織原理としての情報レジームの多機能性を示すと同時に、アプローチを緊密にすることの有益性を示している。第1章「日本におけるカトリシズムと冷戦」では、ジョージタウン大学教授であり、日本の法律、宗教、政治哲学の専門家であるケヴィン・ドークが、冷戦期の日本のカトリシズムについて書いている。ドークは、本書が冷戦期の非国家主体に重点を置いていることに応える有効な手段として、冷戦期の日本におけるカトリシズムの役割を前景化している。カトリシズムは、日本語の出版物を通じて非日本人を日本人と対話させる世界的な「情報体制」であった。また、カトリック教会は世界的な存在として、反共産主義を非国家的に制度的に支援した。日本における冷戦期のカトリック情報体制のこうした側面は、1950年代の10年間、日本の最高裁判所長官を務めたカトリック信者の田中耕太郎の仕事を通して最も強く浮かび上がってくる。田中裁判はその判決において、日本の冷戦における重要な役割を果たした。しかし、田中や田口善五郎司教のようなカトリック信者は、自分たちの反共主義を、単にアメリカの仕事をすることではなく、戦争前の活動主義と連続したものとしてとらえていた。ドークが彼の鋭い章で詳しく説明しているのは、このような日本の地域的な反共情報体制である。
ドークが戦後日本のカトリシズムの歴史を語る上で最も魅力的な点のひとつは、占領期も占領後も、アメリカから発信された、完全な世俗主義ではないにせよ、主としてプロテスタント的な冷戦イデオロギーから独立した、反共主義的な日本人の自律的な空間がどのように明らかにされたかということである。冷戦期の日本における反共主義は、アメリカによる日本占領と、それに続くアメリカの政治的・軍事的影響力の副産物であったと理解されることが多いが、この見方は、日本国内のさまざまな反共主義の伝統、特に冷戦争前と冷戦中に日本のカトリックが反共主義的見解を表明したことを見落としている。そこでドークは、田中のような日本のカトリック信者が、教皇ピウス11世や教皇レオ13世、イエズス会のペドロ・アルペ、マルクス主義者の戸坂潤、徳田球一、志賀義雄らの著作にどのように反応したかを検証する、 また、プルタルコ・エリアス・カジェス大統領によるメキシコでのカトリック迫害(「クリステロ戦争」)や、ソ連支配下のハンガリーでのヨゼフ・ミンツェンティ枢機卿の逮捕といった出来事も、アメリカの政治的配慮ではなく、日本のカトリシズムに根ざした反共産主義的な冷戦情報体制を形成する上で重要であった。これは多面的でマルチモーダルな情報体制であり、戦後アメリカの支配下にあった日本における冷戦期の影響力と同様、今日でも十分に研究されていない。
第2章「外交主体としての北朝鮮のゲシュタルトとしての冷戦」では、ソウル女子大学助教授のデイヴィッド・A・ティザードが、外交主体としての朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の系譜を辿り、国内におけるチュチェ・イデオロギーを含め、北朝鮮の国際姿勢を決定付けるゲシュタルトを冷戦に見出した。この時期、北朝鮮が外交を重視したのは、ハードパワーの要素から、3つの具体的で差別化された流通経路、すなわち3トラック情報体制を使って、国家のイメージを向上させ、海外に宣伝するためのものへと焦点が移ったことを示すものであった。ティザードは、分類と組み合わせが巧みに適用されることで、北朝鮮が冷戦の現実の中で、少なくとも政治的には生き残り、繁栄することさえできたことを示している。多くの大国が北朝鮮と外交的に関わることに消極的だったため、北朝鮮は戦術的に第三世界、FIFAワールドカップのような権威ある国際スポーツイベント、ブラックパンサーのような対外的な国内社会運動に焦点を当てた。北朝鮮はその地位を固め、冷戦、そして朝鮮戦争を征服することなく生き延びたのである。冷戦を「外交主体としての北朝鮮」の「ゲシュタルト」と見なしたティザードは、情報体制の概念を駆使して、新たな方法で認識や既成の知識体系に疑問を投げかけている。ティザードは、チュチェ・イデオロギーを北朝鮮の外交主体形成における連続性の解釈学としてとらえ、「冷戦」を1991年から前方に投影することで、「情報体制」アプローチによって可視化される深い歴史的連続性を示している。
最後に、第3部第3章「東アジアにおけるローマクラブ」がある: 米国主導の人口統制情報レジームと極東における冷戦の遂行」は、東アジアにおける冷戦研究に、一種の人民史的アプローチを持ち込もうとする試みである。多くの「人民史」はマルクス主義やマルクス主義の立場から書かれているが、ここでは「人民」を階級闘争の主体としてではなく、必然的に政治的な方法で環境と相互作用する生物として、生政治的な存在としてとらえる。冷戦時代、太平洋の覇権国であったアメリカは、当初、大規模な生産のうねりに支えられていた。それは、アメリカが第二次世界大戦に勝利し、地球の半分の支配者としての地位を確保するのに役立っただけでなく、ヘンリー・ルースが「アメリカの世紀」と呼んだような軌道に乗せることにもなった。しかし、ハーバード大学の学者チャールズ・マイヤーが指摘しているように、1960年代から1970年代にかけて、アメリカの実験は重大な変化を遂げた。特筆すべきは、帝国としてのアメリカが、生産に依存するものから消費に依存するものへと変化したことである。アメリカ人とその政府は借金を重ね始めた。ニクソンは米国をゴールド本位制から離脱させ、ユーロドルとオイルマネーはグリーンバックの世界的支配を混乱させ、米国は以前の優生主義的傾向に回帰し始めた。ヘンリー・キッシンジャーの指揮の下、アメリカはNSSM-200を発表した。これは、「人口爆弾」に対する新たな不安に根ざし、ローマクラブやロックフェラー財団やフォード財団といったグローバリスト・インターナショナリストの機関によって育成された人口管理プログラムであった。人口抑制の情報体制は、アジア諸国の指導者や市民にアピールするよう慎重に作られたが、ワシントンの現実はまったく違っていた。このようにして、アメリカ政府は自国の利益のために巧みに認識を操作したのであり、情報体制の構築と維持の典型的な例である。このような情報体制は、東アジアにおける冷戦の遂行に極めて重要であり、経済戦争の基盤としての情報についての理解を複雑化し、粒状化するのに役立っている。
これら8つの章を総合すると、それ自体が重要な研究であるばかりでなく、「情報体制」を人間の相互作用を再考し、批判的に再評価するための強力なツールとしてとらえ、東アジアにおける冷戦史の新たな出発点としている。世界が情報の力に目覚めつつある今、情報の優位性に関するこれらの洞察を過去に適用し、より大きな通時的連続性、すなわち「冷戦」(これは戦争という古く時代遅れの意味においてのみ「冷戦」であった)や他の人間相互作用の形態に暗黙の形を与える連続性を見出すべき時である。歴史は権力だけの問題ではない。さまざまな行為者によって実際に展開された修辞的なもの、政治的なもの、知的なもの、イデオロギー的なもの、さらには精神的なものまでを絶えず前景化することによって、組織原理としての「情報体制」は、これまでの標準的なカテゴリー(軍事、経済、外交など)のもとで可能であったよりもはるかに豊かで、現実的で、人間的な冷戦の物語を語るための事実上無限の可能性を切り開く。人は通常、何らかの信念、(誤った)理解、知的コミットメントに起因する理由から意図的に行動するものであるため、「情報体制」–人を常に知的・行動的な環境に身を置き、常に何らかの形で他者の考え方に影響され、また影響を及ぼしているとみなす–は、情報が他の努力の中心となった時代として冷戦の過去を理解する全体論的な方法である。
その点で、また対照的に、私が「情報」をあまりに大雑把に使っているために、包括的な概念として「情報」という言葉が緩やかになりすぎているのではないか、と思う人もいるかもしれない。確かに、私は「情報レジーム」をモジュール化しており、様々な学者がこの発見的概念を探求する中で、この用語の新たな解釈を加えることができるようになっている。「情報レジーム」はオープンソースのアイデアであり、私自身もそれを借用し、再利用している。しかし、その断片には輪郭があり、分野にはパターンがある。「情報」とは単なるデータではなく、コード化された断片でもなく、ある集団がどのように考え、信じ、行動するかを(どちらの意味でも)伝える言葉の果てしない流れでもない。この意味で、「情報」はアンダーソンの「印刷資本主義」よりもはるかに統制された形で使われている。アンダーソンは、印刷物の全体が「想像された共同体」を形成していると理解し、その結果、「情報」の暗黙の意味を地平線まで無限に広げている。逆に、「情報体制」とは、指示された、意図的に配置された、「狙いを定めた」情報を意味し、ある特定の人物や集団の考え方や、その結果としての行動様式を変えるために、ある人物や人々によって利用される。
「情報レジーム」が概念としてどのように理解されるべきかを示す最良の例のひとつが、Chizuko T. Allenの冷戦期の在日朝鮮人に関する章である。アレンの研究は、韓国の活動家であり教授であったパク・キョンシクが、他の韓国人(ひいては他の国の人々)の日本に対する見方や冷戦期の日米関係全体のダイナミックさに影響を与えるために、歴史的誤解というまったく新しいパラダイムを意図的に作り出したことに焦点を当てている。アレンが述べているのは、情報レジームの典型的な例である。情報レジームとは、人間の意志と戦略的コミュニケーション(たとえ矛盾していたり、真実でなかったりしても)の産物であり、望ましい結果をもたらすようにデザインされたものである。情報体制とは、冷戦の過去を見る上で、人間とその意思決定を第一に考え、軍事力や経済イデオロギー、外交工作以上に、情報がいかに冷戦の現場のアクターに影響を与えたかを示すものである。
間違いなく多くの人が気づいているように、新しいアーカイブの開設と古い情報レジームの廃止は、受け入れられてきた歴史叙述に疑問を投げかけるための修辞的空間を大きく広げている。しかし、全体的な分析なしには、アーカイブも修正主義も、情報がリアルタイムで、誰によって、どのように展開され、どのような効果があったのかを教えてはくれない。冷戦時代、情報は社会の中心的存在であったため、国家は世論や個人の行動を左右する膨大な数の他の影響者と競争しなければならなかった。本巻の初期のレビュアーの一人が指摘したように、国家は世論や個人の行動を左右する他の膨大な影響力と競争しなければならなかった:
学者たちはまた、国家主義的で公的な視点だけでは冷戦の経験を完全に語ることはできないことにも気づいている。情報、メディア、非公的産業といった他の分野に焦点を当てることが、冷戦の全体像をより包括的に示すために必要なのである。
私はまさにこの思いを共有している。東アジア冷戦における情報レジーム』は、冷戦を歴史や出来事としてではなく、生きた情報戦として理解するために、人々が争った情報を中心的なものとして捉えることで、冷戦を再考する長い道のりの第一歩となる。
8 東アジアにおけるローマクラブ:米国主導の人口統制情報体制と極東における冷戦1
ジェイソン・モーガン
はじめに:生産の帝国から消費の帝国へ
ハーバード大学の歴史学者チャールズ・マイヤーは 2007年の著書『帝国の間で(Among Empires)』の中で、冷戦期のアメリカ帝国における断絶の解釈学を提唱している。第二次世界大戦から1970年代まで、アメリカは彼が「生産の帝国」と呼ぶものを追求してきたとマイヤーは主張する2。コロンビア大学の歴史家スティーブン・ワートハイムは、マイヤーの見解を次のように要約する:
ヨーロッパのエリートたちがワシントンの軍事的・社会経済的リーダーシップを容認し、アメリカの経済構造とフォーディズム的生産方式を旧世界に広めたからである。その一里塚としてマーシャル・プランが浮かび上がってくる。自国のマーシャル・プラン事務所や訪米から、ヨーロッパの労働者は、賃上げは生産性の向上を超えてはならないというアメリカのコンセンサスを学んだ3。
マイヤーにとって、「アメリカの世紀」の最初の30年間ほどは、さまざまな意味で、混合資本主義とテイラー主義的生産性向上というアメリカ・モデルの延長線上にあった。中間管理職によって微調整され、進歩主義的な地政学的・イデオロギー的拡大主義と結びついたアメリカ経済エンジンの巨大な工業生産性は、世界の舞台におけるアメリカの主導的役割の第一幕のモチーフであった4。
しかし1970年代以降、アメリカは生産の帝国から消費の帝国へと根本的に変貌を遂げたとマイヤーは主張する。1970年代、アメリカの帝国的支出は産業生産性を上回るようになった。冷戦期の介入主義や、「自由と民主主義」という地政学的情報体制の多国間・複数レベルでの維持によって蓄積された負債を賄うために、アメリカはその帝国を、工業製品や生産性を輸出する能力の範囲としてではなく、爆発的に増大する予算不足と恒常的な赤字支出を賄うための資源としてとらえ始めたのである5:
マイヤーは、他国ではもっと高い利回りが得られ、ドル安が進行しているにもかかわらず、なぜ外国人は米国債を買ったのかと問うことで、(アメリカが「消費の帝国」であるという疑問に)迫っている。彼の答えは、中核と周縁の暗黙の交流にある。米国は製造業の雇用と社会資本を海外に送り出し、外国人は米国の債務増大と放蕩消費を賄うために国庫短期証券を購入したのである。[マイヤーは、米国の雇用が輸出された場合、エリートたちは「豊かになるための新たな機会に対する支払いとして、その下で生産された商品の一部を返却した」と論じている6。
言い換えれば、1970年代はアメリカ帝国の劇的な再編成をもたらしたとマイヤーは見ている。かつて国際的な視野を持つアメリカ人は、世界を(イデオロギー的、地理的、あるいはそれ以外の)征服のための空間とみなしていたが、1970年代には、アメリカの国際主義者たちは、世界を自国におけるアメリカの消費習慣を維持するために管理すべき人口とみなすようになった。アメリカ帝国は、世界規模での赤字支出による帝国的消費の弁証法を支えるために、世界中に借金を作り始めたのである。マイアーの洞察は深遠であり、冷戦の理解にまだ十分に取り入れられていない。実際、アメリカ帝国は生産の帝国であり、次に消費の帝国であるというマイアーの区別は、特にアジアにおける冷戦について受け入れられてきた物語に挑戦するものである。本論では、冷戦期の東アジアにおける経営消費主義的な情報体制を例に、アメリカ帝国に対するマイアーの評価が正しかったことを示したい。特に、1970年代初頭以降にアメリカ政府の上層部で策定された人口抑制計画は、それ自体がさらに大きな情報レジームの一部であり、差し迫った人口災難と地球上の人口数を劇的に減らす必要性を説くローマクラブの思想は、マイアーのテーゼを裏付けるものである。さらに重要なことは、ローマクラブのイデオロギーは、冷戦期におけるアメリカ主導の東アジアにおける消費と統制の情報体制の重要な特徴でもあるということである。
「ローマクラブ思想」とは何か?
1968年、実業家や知識人のグループが、キング・キャンプ・ジレットが提唱したような、成長を抑制し人口膨張を抑制する戦争前の指令経済や社会主義・消費主義経済の復活を目指した。ローマクラブは、目先の成長見通しと長期的な経済・人口成長悲観論を組み合わせることで、「プロブレマティーク」と呼ばれる、成長という考え方そのものに対するプログラム的・イデオロギー的懐疑主義を提唱した。ローマクラブの信奉者たちは、自分たちの運動を自分たちの言葉で説明している:
ローマクラブは、経済成長マニアが頂点に達していた1968年、ローマのアカデミー・デ・リンチェイでアウレティオ・ペッチェイとアレクサンダー・キングによって創設された。1972年に最初の報告書『成長の限界』が発表された直後、世界は石油危機に見舞われた。
[この危機は、先進工業国経済の脆弱性に対する明確な警告であった。原材料とエネルギーの安定供給は、自分たちの手に負えない遠くの出来事によって左右されるのである8。
ローマクラブのグローバルな反成長主義の情報体制、つまり彼らの「世界問題主義」は、彼らが「解決主義」と呼ぶ、管理された生産の衰退に対抗するものである。診断と処方箋の両方において、ローマクラブの情報体制は、アメリカ政府が研究してきた生産帝国から消費帝国への転換のために作られたように見える。ローマクラブ会長のリカルド・ディアス=ホホライトナーが1991年に発表したローマクラブの大衆向け報告書の序文にこうある:
1968年は大分裂の年だった。1968年は、戦後長く続いた先進国の高度経済成長期の終わりであり、頂点でもあった。しかしこの年は、多くの国々で学生反乱をはじめとする疎外感や反文化的抗議の表出が見られ、社会不安の年でもあった。[意思決定のポイントに近い多くの人々が、政府や国際機関が実質的な物質的成長の結果を予見できない、あるいは予見しようともしないことに懸念を抱くようになり、前例のない一般的な豊かさが可能にするはずの生活の質について、十分な配慮がなされていないように思われた9。
ローマクラブの情報体制は、少なくとも第二次世界大戦後のマーシャル・プラン(およびアジア向けの同様のプログラム)以来、アメリカの帝国主義が前提としてきた債務帝国主義のシステムを、多くの点でデグリンゴラード化したものであった。実際、第二次世界大戦と第一次世界大戦の戦費は、赤字支出と通貨操作によって賄われた。これは、イギリスとヨーロッパが財政破綻し、軍備やその他の戦費のために巨額の出費をした結果、植民地政治から撤退したことに伴う帝国の再編成から生まれた、別の情報体制であった。
国家安全保障研究覚書200(NSSM-200)
しかし、ローマクラブの考えは、他の緊縮プログラムとは異なり、通貨供給や金利ではなく、国民そのものに焦点を当てたものであった。ローマクラブのグループは、問題は世界経済で動くお金が多すぎることではなく、天然資源を消費する人が多すぎることだと主張した。さまざまな地域、ひいては世界全体が、資源をめぐって混乱や戦争に陥るのを防ぐためには、人口とその消費を、選ばれた専門家グループによって管理する必要がある、とローマクラブは主張した。アメリカ政府の上層部の多くがこの警告に注目し、リチャード・M・ニクソン大統領の国務長官兼国家安全保障顧問であったヘンリー・キッシンジャーをはじめとするいくつかの機関や高官は、ローマクラブの発表に基づいた行動計画を策定した。
ローマクラブの情報体制が冷戦期のアジアの地政学をどのように形成したかを説明する重要な文書(これまでに機密解除されたもののうち)は、1974年12月10日に米国家安全保障会議が公布した「国家安全保障研究覚書200(NSSM-200)」である10。キッシンジャー報告書は、米国が自国の消費水準を維持する能力という観点から、高度冷戦期の地政学をきわめて率直に評価したものである。報告書は臆面もなく、世界の他の地域、特にアフリカとアジアを、主要資源(石油、スズ、銅、チタン、亜鉛、鉄、ゴールドなど)の供給国であると同時に、これらの資源の安定供給を政治的に混乱させる潜在的な場所、やはり特にアフリカとアジアと見なしている。世界は二分されつつも、相互に絡み合って理解されている。米国政府が国境の外から(特に、伝統的な欧米文化の共鳴圏を越えて)調達し続けたいと望む物質的な商品がある一方で、それらの鉱物資源の上に暮らす人々は、米国政府が帝国的支配を維持するために管理しなければならないと理解している途方もないリスクをもたらしているのだ。NSSM-200は、NSSM-200が内部で公布されてから約30年半後にチャールズ・マイヤーが詳述することになる、生産帝国から消費帝国への移行をアメリカ政府がはっきりと理解していることを示すという点で、注目に値する文書である。
NSSM-200はこう述べている:
米国はここ数十年、発展途上国からの鉱物輸入にますます依存するようになっており、この傾向は今後も続くであろう。[鉱物供給の真の問題は、基本的な物理的充足にあるのではなく、アクセス、探査と開発の条件、生産者、消費者、受入国政府間の利益分配といった政治経済的な問題にある。極端な場合、人口の逼迫によって飢饉が蔓延し、食糧暴動が発生し、社会秩序が崩壊するような状況では、鉱床の計画的な探査や、開発に必要な長期的な投資はほとんど望めない。[政府の行動、労働争議、サボタージュ、内乱のいずれを通じてであれ、必要な物資の円滑な流れは危うくなる12。
全体として、アメリカ国内での継続的な消費を可能にするために必要な資源を確保するために、世界人口を管理するようアメリカ政府への勧告に溢れているこの報告書の別のカ所では、著者たちは、インドとバングラデシュについて、「将来、人口撹乱の増加が予想される」と厳しく指摘している。「アジアにおける民主主義の支柱としてのインドの存在は脅かされるだろう」13。もしこれが失敗した場合、報告書は「米国は、人口増加を抑制できない/しようとしない人々を助けるために、食糧配給を受け入れる用意があるのか」と問う14。逆説的だが、成長とは緊縮財政を意味し、少なくともアメリカの冷戦時代の顧客国家の周辺にある世界の地域にとっては、緊縮財政が必要だった。
オイルショックと、ニクソンによる金本位制からのドル切り離しによるブレトンウッズ体制の解体を経験した1970年代初頭は、帝国の赤字支出体制の崩壊であったが、同時に、多くの意味で、それを倍加させるものでもあった。アメリカはもはや、冷戦帝国の広大なフロンティアを取り締まるために必要な戦争物資を生産することはできず、ベトナム戦争と軍事的成功の「死体数」の定義によって、1961年にジョン・F・ケネディ大統領が当初楽観的だった1960年代の初めに発表したように、「いかなる代償を払っても」「いかなる重荷を負っても」冷戦と戦うというアメリカのプログラムに対して、アメリカは、そして世界の一般大衆は深く失望した15。これは、中央政府、特にアメリカ連邦政府による通貨管理から人口管理へと移行することによって行われることになっていた。キッシンジャー報告書は確かに資源に関するものだが、この文書の主な「問題点」は、資源が採掘される場所を占める人々である。それだけでなく、NSSM-200では、世界的な現象としての人口、食料を使い果たし、世界の気候を悪化させる一般化された消費傾向が、予備的ではあるが、非常に率直な方法で明示されている。それは単に「発展途上国」(あるいはキッシンジャー報告書の用語で言うところの「LDC(後発開発途上国)」)に人口が多すぎるということではなく、世界人口全体がアメリカ国民の消費特権を侵害することによって、アメリカのライフスタイルを危うくしているということである。
繰り返すが、ローマクラブは、この人口・資源・気候が交差する情報体制の先駆者:
ほとんどの発展途上国の問題は、人口爆発によって大きく悪化している。現在50億人強の世界人口(1900年には18億人)は、国連の予測(中央値)によれば 2000年には62億人、2025年には85億人を超えると予想されている。飢え、教育を受けず、失業し、怒り狂った人々の大群から自分たちを守るために、高度な武器で武装した富裕国のゲットーが外に広がる未来の世界を、私たちは想像できるだろうか。[したがって、貧しい国々の経済状況を改善すると同時に、効果的な人口抑制手段を導入することが急務である。経済格差の是正と、賢明で協力的な開発援助は、人道的なジェスチャーであるどころか、豊かな国々にとって根本的な自己利益であることを強調したい18」
このことは、1991年のローマクラブの報告書「人類共通の敵は人間である」に簡潔にまとめられている:
これらの危険(汚染、地球温暖化の脅威、水不足、飢饉など)はすべて人間の介入によって引き起こされたものであり、それを克服することができるのは、態度と行動を改めることによってのみ可能である。真の敵は人類自身なのだ19。
1991年に発表されたローマクラブの報告書は、豊かな(そしてほとんどヨーロッパ系アメリカ人だけの)「先進国」が世界の資源を覇権的に支配し続けることを脅かしている問題について、露骨で無愛想ですらある診断を下していたが、その17年前に発表されたキッシンジャー報告書は、脱植民地化と植民地支配後の混乱と再考がまだ差し迫った脅威であった世界を反映していた。ベトナム戦争はまだ米国が完全に負けたわけではなく、世界的な紛争が再燃し、おそらくアジアから勃発し、それが急速にエスカレートしてソ連と米国を第三次世界大戦に巻き込む(冷戦の急速な逆転)可能性が差し迫っていた。NSSM-200の起草者たちは、婉曲な表現と政策的な誤魔化しの組織の下に、「男女の不妊手術」の義務化20を含む彼らの真の動機を隠し、身軽に行動しなければならないことを知っていた21。
冷戦期の反人口情報体制の先駆けとしての優生学
アジアをはじめとする世界の非白人地域の生政治に介入するこのプログラムは、その範囲においては新しいものであったが、その基本的な輪郭においては、大規模な工業生産に支えられたそれ以前の、より積極的な拡張と征服の帝国に代わって、アメリカの消費帝国という新たな情報体制が形成される数十年前から、実際に展開されていたものであった22。アメリカ帝国がソビエト帝国と対峙することで、知らず知らずのうちに冷戦と呼ばれる世界的な情報体制が形成され、イデオロギー的な対立が武力衝突との境界線で縁取られるようになった(そして、相手のイデオロギー的な威容を弱めようとする試みが撃ち抜かれるようになった)、 冷戦の弁証法の第3項として、「成長の限界」のグローバル化した認識と、それ以後は必然的に、すでにある程度イデオロギーの支配下にあった地域の征服から管理へと、支配の再計算が行われたのである。
世界は分割され、残されたのは、冷戦体制を維持するための継続的な資源の供給を確保することだった。
当初の冷戦は武力によるにらみ合いであったかもしれないが、1960年代になると、人口を管理する情報体制は、アメリカがソ連との惑星的なライバル関係や、その場限りのアメリカ帝国における他国の位置づけを考える上で、軍事的な配慮とさえ競い合うようになっていた。たとえば、1965年 1月、ケネディ大統領が「人間はその死すべき手に、あらゆる形態の人間の貧困とあらゆる形態の人間の生命を廃絶する力を握っている」と宣言してからわずか 4年後、後任のリンドン・B・ジョンソン大統領は自らの就任演説で、「私は、世界人口の爆発的増加と世界資源の不足の増大に対処するために、我々の知識を役立てる新しい方法を模索する」と述べた23。以後、人口抑制はジョンソン政権、さらには連邦政府機構全体のテーマとなった。ジョンソン大統領は1965年6月25日、国連設立20周年記念式典のスピーチで、「人口抑制に投資される5ドル未満は、経済成長に投資される100ドルに値する」と宣言した24。 同年8月、ジョンソンはベオグラードで開催された第2回世界人口会議において、国連事務総長ウ・タントに対し、「平和に次いで(中略)この超越的な問題(過剰人口)は人類最大の課題である」と演説した25。その後の大統領もこのテーマを引き継いだ26。
しかし、冷戦はこうした過剰人口に関する嘆きを色濃く反映していたとはいえ、グローバル化した帝国は、直感に反するかもしれないが、冷戦の情報体制から生まれたものではない。それは冷戦よりもかなり前のことだった。鉄のカーテンでもなければ、赤狩りのようなものでもない。第一次世界大戦から広範な支持を得ていた優生主義的な情報体制が、征服された領土を維持することに冷戦の主要な傾向をもたらし、1970年代からは、国内での継続的な消費を確保するためにアメリカ帝国を管理するようになったのである。アウシュビッツと国家社会主義体制の恐怖は、第三帝国の崩壊と、第二次世界大戦における優生主義者の反人口生産主義(すなわちショア)の否定しがたい暴露の後、情報体制としてあからさまな優生学を成り立たなくした。しかし、1974年にNSSM-200を生み出した北米もまた、優生学という疑似科学の本家本元であったことを思い起こすべきである27。NSSM-200は近接的には冷戦の機能であったが、歴史的には、そして実質的には、適切な種類の人々だけが子供を持てるようにすることで米国の生活の質を向上させるという、より古い考え方の継続であった。
進歩主義のマルサス的ルーツ
マルサス的、より正確にはネオ・マルサス的思考は、アメリカにおける進歩主義の定番であった。どちらかといえば、両者は同一であるとも言える。しかし、この情報体制を理解し、それが冷戦期の地政学にいかに重大な、いや形成的な影響を及ぼしたかを理解するためには、まずアメリカ史の生政治観を理解しなければならない。
コルソン・シュロッサーが、第二次世界大戦後のアメリカにおける新マルサス主義とその生政治的ガバナンスへの影響に関する2009年のエッセイで説明しているように、アメリカ独自の生政治への貢献は、国家に奉仕する優生学の受け入れにあった。フランスの哲学者ミシェル・フーコーとイタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンは、生政治がどのように機能するかを詳述している。要するに、国家が人間の生命の生物学的側面を支配することを想定し28、「生物学的なものを政治的なものと融合させる」ことによって、人間主体に対する国家の支配を全体化するのである。 生政治とは、「集団として理解される生き物の集団が、統治されるために測定される手段」であり29、生政治的国家は集団を統治されるべき管理上の重荷と見なすため、必然的に、エリート、つまり中心が、エリートの物質へのアクセスや権力の他の特権を脅かす、あふれかえる大衆の周辺部を規制するという、ある体制の二分化が生じるのである30。
トーマス・マルサス自身は、大英帝国がほぼピークに達していた1798年にこう書いている。インドとアフリカの植民地の導入は、メトロポールとフロンティアの区別を鮮明にした。それはイギリス国内でも同様だった。マルサスは、急成長するロンドンにはまったく人口が多すぎると考え、彼や彼の後を継いだ人々は、人口が資源をまだ上回っていないとしても、やがて上回るだろうと嘆いた。その精神に基づき、1877年にロンドンのマルサス同盟が結成され、特に「富裕層にとって過剰人口がもたらす結果」を理由に、人口削減を呼びかけた31:
過密、半飢餓、汚部屋は、発祥の地を越えて富裕層の家に伝染することを厭わない病気の実り多い発生源である。現代社会は、死をもたらす呼気で大気を満たす瘴気の沼地に建てられた壮麗な宮殿に例えるのが適切かもしれない32。
マルサス同盟が前述の引用文を発表した1911年までには、確かにそうであったが、それよりもずっと以前にも、帝国という現実が、英国社会の上層部に重くのしかかり始めていた、 イギリスの知識人たちは、帝国の意味合いや、科学の進歩、たとえば壊血病の治療法やビタミンの前発見など、帝国の拡大の過程で発見されたものの多くが、人類の人口増加につながり始めていることを徐々に考え始めていたのである。 33
アメリカでは、この新マルサス主義は、人種主義や優生主義の疑似科学や、生物学的および社会的なダーウィニズムによって大きく汚染されていた。初期のアメリカの新マルサス主義者たちは、非白人、非アングロサクソン、非プロテスタントの移民がアメリカに流入することが暗黙の了解となっていると考え、「人種の自殺」を憂慮した。「マーガレット・サンガー(Margaret Sanger)のような避妊擁護者たちは、非白人人口を劇的に淘汰するという呼びかけを、人種差別的な最も粗野な言葉で表現した。
進歩主義的な反出生主義の世界的な広がり
人口問題を理解したのはサンガー一人ではなかったし、人口問題を米国の枠を超えてグローバル化したのも彼女だけではなかった。シュロッサーが指摘するように
人口学者のウォーレン・トンプソンは、『世界人口の危険地帯』(1929)の中で、人口が戦争を引き起こす可能性を残している。トンプソンにとって、(当時の)近代戦争の多くは、これらの地域から資源が「余っている」地域へと人口が拡散したことに起因している。人口学分野の第一人者であるトンプソンの分析は、世界人口を「向こう側」で急増する人口が「こちら側」の平和な人口を脅かす地域に基本的に分類することに貢献した。[人口論議は、この時代の地政学的イマジナリー構築の重要な要素であった36。
第二次世界大戦後、『略奪された地球(Our Plundered Planet)』と『生存への道(Road to Survival)』の著者であるフェアフィールド・オズボーンとウィリアム・ヴォーグトは、人口対資源利用可能性の議論を冷戦の勃興のために再構築することに貢献し、オズボーンは「両世界大戦、メキシコ革命、さらにはマヤ帝国の崩壊さえも、増大する人口と天然資源との不均衡のせいである」とまで非難した37。
オズボーンはこう続ける:
個々の国の攻撃的な態度や、現在の集団間の不和の主な原因のひとつが、生産可能な土地の減少と人口増加の圧力にあることが、いつ公然と認識されるようになるのだろうか。すべての国、すべての世界が、迫り来る危機の脅威に直面しているのだ38。
アメリカ優生学会の会長であり、アメリカ産児制限連盟の著者でもあったガイ・アーヴィング・バーチは、1945年の著書『Population Roads to Peace and War(平和と戦争への人口道)』の中で、戦勝国は「生物学的にも社会的にも不適切なすべての人」の「強制不妊手術」を「主張」すべきだと書いている。そうでなければ、第二次世界大戦での連合国の勝利によって得られた平和は、「ヴェルサイユ条約の結果のように一過性のもの」になってしまうだろう39。
サンガーもまた、人口と地政学について、おそらくそれほど終末論的ではないにせよ、彼女なりの懸念を抱いていた。例えば、サンガーは1922年に出版した『文明の枢軸』の第5章「慈善の残酷さ」で、中国の宣教師からの手紙を再現して、資源が危機に瀕しているというよりも、慈善そのものが人々から物質的な豊かさを奪っているという主張を展開している:
アメリカ国民は最近、伝統的な寛大さを発揮して、中央ヨーロッパで飢餓に苦しむ300万人、50万人の子どもたちを生かそうとするヨーロッパ救済評議会の活動を援助するだけでなく、人口が密集し、不活発なこの国をたびたび襲う飢饉のために飢餓の危機に瀕している3000万人の中国人を救うために、その莫大な基金に寄付するよう求められている。[現代の「博愛」に対して問われうる最も深刻な罪は、欠陥者、非行者、依存者を永続させることを奨励しているということである。これらは世界社会における最も危険な要素であり、人間の進歩と表現にとって最も破壊的な呪いである。フィランソロピーとは、現代ビジネスに特徴的な、社会全体から搾取した利益を不適格者に惜しみなく与える行為である。公平に見れば、この代償的な寛大さは、その最終的な効果において、利益供与という最初の慣行や、ある者は富みすぎ、ある者は貧しすぎるという社会的不公正よりも、より危険で、より異質で、より殺伐としたものであろう40。
しかし、サンガーの避妊イデオロギーがアジアに到達する最も有力な媒介となったのは、中国ではなく日本だった。実際、日本は、アメリカの駆け出し優生主義情報体制の最初の世界的受容国であった。
アメリカで優生学運動が始まった当初から、日本の生物学者や原始優生学者たちは、アメリカで台頭しつつある疑似科学に注意を払っていた。日本のフェミニストでマーガレット・サンガーの愛弟子であった石本静江(「シヅエ」とも表記される)が1939年に自伝『Facing Two Ways』を出版したとき、『ロサンゼルス・タイムズ』紙で「『社会優生学』というコラムを書いていたアメリカ優生学会の活動的メンバー、フレッド・ホーグ(Fred Hogue)」は石本とその著書を称賛した42。社会史家の竹内デミルキ愛子が『避妊外交』の中で説明しているように、ホーグと他のアメリカ人優生学者が、石本と彼女の著書を『ロサンゼルス・タイムズ』紙で賞賛したのである42:
ホーグをはじめとするアメリカの優生学者が日本に避妊法を広めることに関心を持ったのは、世界中の人種間の出生率の差について進行中の議論を象徴するものであった。[人口学的な黄禍は、白人の世界覇権の安定を脅かすと思われた。このような優生学的恐怖が、カリフォルニアにおける反日移民運動を推進した。[優生学者が見る限り、移民政策は人種関係という国内問題にしか対処できなかった。したがって彼らは、世界平和のためには、世界各国の出生率の差に対処するための国際的な協力や合意がさらに必要であると考えた43。
ハーバード大学出身の歴史家であり、優生学者でもあったロスロップ・ストッダードが1920年に出版した『The Rising Tide of Color against White World Supremacy(白人至上主義に対する有色人種の潮流)』は、「差し迫った黄禍という考え方を一般に広める一助となった」とタケウチ・デミルキは書いている44。
日本国内でも、「日本の優生学者たちは、優生学的な理由に基づいて、繁殖力の強い非白人人種の人口増加を抑制しようとする西洋の試みをどう解釈すべきか議論した」45。このようなレトリックを「損傷」だと考える日本の優生学者もいたが、生物学者の田中芳麿のように、「日本人は一般的に白人より身体的に劣っていることを認めると同時に、日本人には日本人にしかない多くの資質があり、遺伝的に優れていると主張した」者もいた。 46「ほとんどの日本の知識人」は、「精神的、肉体的にハンディキャップを負った人々や、国家のお荷物となる運命にある人々の出生率を減らすために、トップダウンの対策が必要であることに同意していた」とAiko Takeuchi-Demirciは書いている47。
米国で最も尊敬されている知識人の中には、優生主義的な見解や実践を採用することの賢明さを日本の人々に納得させるのに貢献した人もいた。例えば、ジュリアス・ローゼンワルド財団理事長でロックフェラー財団副理事長のエドウィン・R・エンブリーは、プリンストン大学の生物学教授エドウィン・コンクリンとともに、人間生物学委員会(1924-1927)の後援の下、1926年に来日した。2人は、日本が人口問題を抱えているという点で、日本の優生主義者たちと意見が一致した。「日本では、古代の芸術や近代産業よりも、赤ん坊の存在が際立っている。「彼らはどこにでもいる」48。
戦争前、戦後、冷戦下の東アジアにおける情報体制としての優生学
1945年8月に広島と長崎に投下された原爆が「冷戦の最初の一発」であったというのは、冷戦に関する記述の常套句である49。冷戦を米ソ間の軍事的睨み合いと理解するなら、この主張は説得力がある50。しかし、アメリカ帝国が征服から消費へとその様相を変えたというマイアーの洞察が真実であるとすれば、東アジアにおける冷戦のもう一撃は、原子爆弾の爆発という形ではなく、人口爆弾という新しい種類の爆弾の爆発という形で、もっと微妙にもたらされたといえる51。ソ連の原爆開発は、米国とその冷戦同盟国にとって深い悩みの種であったが、米国政府が独自の5ヵ年計画を策定したことは重要であり、それは核兵器の同等性ではなく、世界的な人口増加の管理に関するものであった52。実際、1973年には、元国防長官(1961~1968)で自動車会社の重役であったロバート・マクナマラが、「管理不能な人口圧力の脅威は、核戦争の脅威に非常によく似ている」と宣言している53。
こうした感情は新しいものではなかった。日本への原爆投下直後、人口爆弾に対する恐怖の高まりを東アジアの政策に反映させたのは、クロフォード・F・サムス准将(1902~1994)だった。現在ではほとんど耳にすることのないサムス准将は、米軍が日本を占領していた間、事実上の日本軍医総監として、人口に関する優生思想の古い流れを引き継いでいた。トロイ・J・サクセティはサムスの公式戦史の中でこう書いている:
1945年、【サムスは】連合国軍最高司令官総司令部(SCAP)公衆衛生福祉課長として、占領下の日本軍政のために日本に赴任した。[日本と朝鮮の両方で、サムスは栄養状態を改善し、天然痘、コレラ、ジフテリア、チフスなどの病気の発生を食い止めたり予防したりした。]
この成功にはプロパガンダ的価値があった。伝染病をコントロールする能力は、「共産主義者と民主主義者の能力を比較するテストだった。もし我々がこれらの病気をコントロールすることができ、共産主義者ができなかったら、共産主義者のプロパガンダに直接的かつ決定的な打撃を与えることになるだろう。
マッカーサーの指示の下、サムスは日本政府に「優生保護法」の成立を促したのである56。確かに、アメリカの占領が始まろうとしていた頃、日本国民は窮地に立たされていた。サッケティが主張するように、飢饉と病気が蔓延していた。しかし、冷戦という新たな情報体制の中で、ソ連との世界的な対決の最前線で仕事をしていたサムスは、その状況によって、事実上、「人」よりも「集団」に焦点を当てることを余儀なくされた。ワシントンの中央政府によって管理される「集団」への集約は、冷戦期のアメリカ帝国を特徴づけるものである。もし人口が自分たちの意のままになれば、飢餓や病気、その他の悪が自由世界に対するアメリカの支配力を弱体化させる可能性がある。人口研究者で中国の専門家であるスティーブン・W・モシャーはこう書いている:
人口管理は冷戦の武器となった。おそらく最初に「成功した」人口抑制計画は、戦後の日本で実施された。[マッカーサーは、急増している日本の人口と限られた資源との間の「不一致」は、少子化対策以外のいかなる「人道的」方法でも対応できないと主張する、彼の[SCAP]事務所の自然資源課が起草した報告書を発表した。日本の国会は1948年に優生保護法を可決した57。
この法律の成立後、日本における中絶に対するかつての法的規制はほとんど撤廃された。1950年代の一時期、日本の人工妊娠中絶率は世界で最も高かった58。
冷戦の初期段階までに日本の人口が完全に抑制されたことで、米国はアジアの他の国々の人口急増に直面することになった。ロバート・マクナマラもまた、世界の過剰人口を憂慮したことで有名であり、極東の人口に介入しようとする米国の試みに、「ボディ・カウント」という類似した精神論を持ち込んだ。ベトナムが泥沼化し、米国政府が海外でも国内でも人口管理に失敗し、ケネディとジョンソンの楽観主義が挫折、失望、絶望へと変わっていくにつれ、米国は、1967年に設立され、米国と米国が寄付を強要する他の加盟国が資金を提供する国連人口活動基金などの国際機関を通じて、より積極的に活動し始めた。NSSM-200が明らかにしているように、米国務省とその国際開発庁(USAID)は、「AIDや他の援助国の二国間活動を補完するものとして、人口に関する多国間活動の先頭に立つ国連人口活動基金(UNFPA)の設立に重要な役割を果たした」60。
言い換えれば、世界共産主義の軍事的「封じ込め」が東南アジアで崩壊しつつあったとき、アメリカ政府は冷戦を遂行するために、爆弾や地上軍以外の方法を積極的に模索していたのである。
リチャード・M・ニクソン大統領が1971年、アメリカはドルをゴールド本位制から切り離すと発表したのは、ベトナム戦争での出費が主な原因であった61。また、優生主義的な人口統制という冷戦以前の情報体制から、アメリカ帝国のための人口統制という冷戦期の情報体制、そしてチャールズ・マイヤーが詳述した消費主義的な情報体制への移行を管理するのもニクソンであった。カスンはこう説明する:
リチャード・ニクソンは、[ジョンソン大統領の]人口計画のさらなる資金拡大を求めるメッセージを議会に直接送った最初の大統領であり、1970年には、人口評議会の創設者であり反出生主義運動の熱心なメンバーであったジョン・D・ロックフェラー3世を委員長とする、今では有名な「人口増加とアメリカの未来に関する委員会」を任命して新境地を開いた。この委員会は、自由な中絶の要求、性教育、より容易な自主的な不妊手術、10代の若者への避妊具の公募など、人口抑止策に力を注いだ。ロックフェラーは、この委員会の報告書を議会に提出する書簡の中で、これ以上の人口増加は「ビジネスの活力」といった本質的な国益を促進しないので、止めた方がよいと説いた62。
ニクソン大統領はしぶしぶこの報告書を受諾したが、そのときまでに、情報体制は現在の方向に向かっていた。「議会は、(その後の)一連の法案を通じて、国内外で世界最大の公費による避妊プログラムを提供し、人口と家族計画に関する世界的研究の90%を実施した」とカスンは指摘する。
ロナルド・レーガンとその政権の一部は、世界的な生物政治へのアメリカ政府の介入を抑制しようとしたが、ジェラルド・フォード、ジミー・カーター、ジョージ・H・W・ブッシュは、1991年のソビエト連邦崩壊まで、この情報体制を継続し、ある意味ではさらに強化した。ロックフェラーが1973年に「北米、西ヨーロッパ、日本が直面する問題を分析するため」に結成した三極委員会には、カーター、ブッシュ、カーターのウォルター・モンデール副大統領、カーターのサイラス・ヴァンス国務長官、カーターのウォーレン・クリストファー国務副長官(そしてクリントンの国務長官)、カーターのズビグネフ・ブレジンスキー国家安全保障顧問、その他ワシントンのエリートたちがメンバーとして名を連ねていた。その任務は、「大国の経済当局者」を説得し、「国家間の国際経済関係を管理するだけでなく、単一の世界経済を管理するという観点から考える」ようにすることだった。[人口計画は社会的・経済的発展の不可欠な一部であるべきだ」63。
結論
冷戦はしばしば、フランクリン・D・ルーズベルト大統領が1940年に自由民主主義国家に武器と物資を供給する米国の努力を表現したように、「民主主義の兵器庫」の延長線上にある生産競争として、また一般的な歴史家アーサー・ハーマンの言葉を借りれば「自由の鍛冶場」として描かれる。「ミサイル・ギャップ」騒動からロナルド・レーガン大統領下の戦略防衛構想に至るまで、東アジア冷戦を含む冷戦は通常、どちらが相手を上回る生産ができるかをめぐる競争として理解されている。
しかし、人口をコントロールする情報体制は、この見方に大きな挑戦を突きつけている。中央計画は、小麦生産のための5カ年計画であれ、ジミー・カーター大統領の下で発表された「プラン2000」報告書であれ、生産ではなく家族計画というトップダウンでワシントンが強制する体制によって十分な収穫を確保するためのものであり、1960年代後半から1970年代初頭にかけて、冷戦の支配的な情報体制となった。チャールズ・マイヤーが主張するように、アメリカ帝国は1970年代に生産モードから消費モードへと移行したのである。本稿では、この転換には、出生促進的な生政治計画から反出生主義的な人口抑制計画への転換も伴っていたことを論じた。つまり、アメリカは、世界中の顧客国家を支えるために必要な「民主主義の武器庫」や「自由の鍛冶場」を維持するのに十分な商品を生産する必要性よりも、国内の消費経済を優先するようになったのである。
その中心が人口抑制だった。戦争前、主にアメリカで優生学と特許人種差別として始まり、ドイツ、日本、その他の国々に輸出された人口管理情報体制は、冷戦の中で、アメリカのアジアのクライアント国家管理と絡み合うようになった。ローマクラブの考え、すなわち、「人口爆弾」が爆発し、人口過剰の世界的危機と、それに続く、飢えた貧しい人々の「大群」が世界の豊かな国々に押し寄せるというマルサス的ディストピアをもたらすという考えは、アメリカ帝国を支配する情報体制となった。1970年代に始まった冷戦は、アメリカにとって、人々の心をつかむことではなく、ワシントンDCが主に管理する地球上の人間の数である「ボディ・カウント」をコントロールする問題となった。
注
- 1 J. Mark Ramseyer教授は、本稿の初期草稿に対して、広範かつ多大な洞察に満ちたコメントを寄せてくれた。すべての解釈と欠点は私だけのものであるが、ラムゼイヤー教授のおかげで多くの誤謬から救われ、また小論文全体のまとまりを向上させるのに大いに役立った。彼に感謝している。また、NSSM-200の存在を教えてくれたリガヤ・アコスタ博士にも感謝している。
- 2 Charles S. Maier, Among Empires: Charles S. Maier, Among Empires: American Ascendancy and Its Predecessors (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007). Charles S. Maier, In Search of Stability: Explorations in Historical Political Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 1987)、特に第1章「工場としての社会」、19-69を参照のこと。
- 3 Stephen Wertheim, ”The Final Frontiers? チャールズ・マイヤーの帝国間の突破口」『ハーバード・インターナショナル・レビュー』2007年11月22日号
- 4 アメリカの資本主義については、ロバート・ヒッグス『危機とリヴァイアサン』を参照: Critical Episodes in the Growth of American Government (Oxford: Oxford University Press, 1987)を参照のこと。アメリカの経済・政治生活の官僚化における中間管理職の役割については、James Burnham, The Managerial Revolution: What Is Happening in the World (New York: John Day Co., 1941)、サミュエル・T・フランシス『リヴァイアサンとその敵』(Samuel T. Francis, Leviathan and Its Enemies)を参照のこと: Mass Organization and Managerial Power in Twentieth-Century America (Arlington, VA: Washington Summit, 2016)がある。アメリカの世紀」という言葉は、ヘンリー・ルースが1941年2月17日付の『ライフ』誌の社説「The American Century」で広めた。
- 5 経済学とアメリカ帝国については、ロバート・M・コリンズ「1968年の経済危機と『アメリカの世紀』の衰退」『アメリカン・ヒストリカル・レビュー』101巻2号(1996年4月)396-422を参照。
- 6 Stephen Wertheim, 「The Final Frontiers?」 ハーバード・インターナショナル・レビュー, op. Harvard International Review, op.
- 7 Scott O’Bryan, The Growth Idea: キャロル・クイグリー『悲劇と希望:現代の世界史』(ニューヨーク:マクミラン、1966)、そしてキング・キャンプ・ジレットと世界経済の社会主義的管理については、マイケル・レクテンウォルド『グーグル群島』(日本経済新聞出版社 2009)を参照されたい: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom (Nashville, TN and London: New English Review Press, 2019)がある。
- 8 アレクサンダー・キングとバートランド・シュナイダー『The First Global Revolution-A Strategy for Surviving the World: 惑星的・生態学的な組織原理を提唱した初期の例としては、ジョン・マクヘイル『未来の未来』(ニューヨーク:ジョージ・ブラジラー、1968)などがある。
- 9 Alexander King and Bertrand Schneider, The First Global Revolution, op. cit., vii.
- 10 Brian Clowes, Kissinger Report 2004: NSSM-200の「要旨」は、ブレント・スコウクロフトとジェラルド・フォード、「米国の国際人口政策」、『人口と開発レビュー』第8巻第2号(1982年6月)、423 ff.にある。
- 11 Brian Clowes, Kissinger Report 2004, op. cit., 4.
- 12 1974年12月10日、「国家安全保障研究メモランダムNSSM 200:米国の安全保障と海外利益に対する世界的な人口増加の影響(キッシンジャー・レポート)」Harry C. Blaney, IIIにより機密扱いとされたが、1989年7月3日、国家安全保障会議F. Graboskeによる大統領令12356の規定に基づき、機密扱いを解除/公開された。第3 章「鉱物と燃料」40 より引用。
- 13 「National Security Study Memorandum NSSM 200」, op. cit., Chapter 5, ”Implications of Population Pressures for National Security,” 61-62. バングラデシュについては、同国の過剰人口が国家や地域の安定だけでなく、将来の世界秩序にも影響を及ぼすとされた。バングラデシュがその経済的・人口的悪夢から目覚めるのを助けるための政策を策定するという試練を、われわれや世界共同体の他の豊かな要素が満たさなければ、ある意味で、われわれは、将来数十年の間に、米国の利益にとって政治的・経済的影響がはるかに大きい他の国々における同様の問題の結果に対処する準備ができないだろう。
- (国家安全保障研究メモランダムNSSM 200」(前掲書、63)、1974年6月19日の[米]ダッカ大使館の報告書(ダッカ3424)を引用している)。
- 14 「国家安全保障調査メモランダム NSSM 200」(前掲書)、第Ⅱ部、第Ⅰ節、「米国の世界人口戦略」(前掲書)。
- 「米国の世界人口戦略」、83。
- 15 ジョン・フィッツジェラルド・ケネディ大統領、就任演説、1961年1月20日。ジョン・F・ケネディ大統領図書館・博物館のウェブサイトwww.jfklibrary.org/learn/about-jfk/historic-speeches/inaugural-address。同演説より: 「人間はその死すべき手に、あらゆる形態の人間の貧困とあらゆる形態の人間の生命を廃絶する力を握っている」
- 16 アレクサンダー・キングとバートランド・シュナイダー『第一次世界革命』(op. cit., 23.
- 17 アレクサンダー・キングとバートランド・シュナイダー『第一次世界革命』(op. cit., 49.
- 18 アレクサンダー・キングとベルトラン・シュナイダー『第一次世界革命』(op. cit., 54-56)。
- 19 アレクサンダー・キングとバートランド・シュナイダー『第一次世界革命』(op. cit., 102.
- 20 「国家安全保障調査メモランダム NSSM 200」(前掲書)、第Ⅱ部、第Ⅳ節、「家族計画サービス、情報および技術の提供および開発」、110。
- 21 一般に、「国家安全保障調査メモランダム NSSM 200」(前掲書)、第6章「世界人口会議」、66 ff.を参照のこと。
- 22 生政治学については、例えば、トーマス・レムケ、エリック・フレデリック・トランプ訳『生政治学入門』(ニューヨーク、ロンドン)を参照のこと: A. vanced Introduction (New York and London: New York University Press, 2011)、特に序論、第1章「政治の基礎としての生命」、第2章「政治の対象としての生命」を参照のこと。
- 23 『Public Papers of the Presidents, Lyndon B. Johnson, 1965, Vol: A Chronological Account,” Population and Development Review, vol. 19, no. 2 (Jun., 1993), 305, endnote 8.
- 24 Marshall Green, ”The Evolution of US International Population Policy,” op. cit., 306, endnote 12.
- 25 Marshall Green, ”The Evolution of US International Population Policy,”, op. cit., 306, endnote 13.
- 26 Amity Shlaes, Great Society: A New History』(New York: HarperCollins, 2019)を参照。
- 27 Stefan Kühl, The Nazi Connection: Stefan Kühl, The Eugenics, American Racism, and German National Socialism (Oxford: Oxford University Press, 1994) and Paul A. Lombardo, ed., A Century of Eugenics in America: From the Indiana Experiment to the Human Genome Era (Bloomington: Indiana University Press, 2011)がある。
- 28 アガンベンはフーコーとは異なり、バイオポリティクスを歴史を通じて国家権力に常に付随するものと見なしているが、これは政治的動物として厳密に人間に関与するという国家の伝統的な保証をはるかに超えるものであった。Kolson Schlosser, 「Malthus at Mid-Century: Kolson Schlosser,」Malthus at Mid-Century: Neo-Malthusianism as Bio-political Governance in the Post-WWII United States,” Cultural Geographies, vol. 16, no. (2009). 4 (2009),
- 467. 2世紀のテルトゥリアヌスによるカルタゴの人口制限の呼びかけや、4世紀の聖ジェロームによる全世界の人口制限の呼びかけも参照のこと。Tertullian, De Anima: A Treatise on the Soul, and St. Jerome, The Principal Works, both cited in Jacob Viner, Religious Thought and Economic Society (Durham, NC: Duke University Press, 1978), 34. Jacqueline Kasun, The War against Population: The Economics and Ideology of World Population Control (San Francisco, CA: Ignatius Press, 1988), 46.
- 29 Matthew Gandy, ”Zones of Indistinction: Zones of Indistinction: Bio-Political Contestations in the Urban Arena” Cultural Geographies, vol. 13, no. 4, October 2006, 500, cited in Schlosser, 「Malthus at Mid-Century」, op. cit., 467, endnote 16.
- 30 Schlosser, 「Malthus at Mid-Century,」 op. cit., 467, endnote 15, cited Stuart Elden, 「Rethinking Governmentality,」 Political Geography (2006), vol. 26, no. 1, 29-33.
- 31 Schlosser, 「Malthus at Mid-Century」, op. cit、
- 32 Schlosser, 「Malthus at Mid-Century」, op. cit., 468, endnote 25, quoted The Malthusian League, The Malthusian Handbook, Designed to Induce Married People to Limit their Families within their Means (5th Edition) (London: W.H. Reynolds, 1911), p. 47.
- 33 Stephen R. Bown, Scurvy: How a Surgeon, a Mariner, and a Gentleman Solved the Greatest Medical Mystery in the Age of Sail (New York: St. Martin’s Press, 2003)を参照。帝国と人口管理については、ダイアン・B・ポール、ジョン・ステンハウス、ヘイミッシュ・G・スペンサー編『帝国の端における優生学』(Diane B. Paul, John Stenhouse, and Hamish G. Spencer, eds: New Zealand, Australia, Canada and South Africa (Cham: Palgrave Macmillan, 2018)を参照のこと。
- 34 Schlosser, 「Malthus at Mid-Century,」 op. cit、
- 35 「黒人の人口」1939年12月19日、サンガーからクラレンス・ギャンブル博士への手紙より。「マーガレット・サンガー『避妊の歴史における重要な出来事』より: Article I,” The Thinker, October, 1923 www.nyu.edu/projects/sanger/ webedition/app/documents/show.php?sangerDoc=306641.xml.
- 36 Schlosser, 「Malthus at Mid-Century」, op. cit., 471, endnotes 52 and 53, cited Warren Thompson, Danger Spots in World Population (New York: Alfred A. Knopf, 1929), 6, and Alison Bashford, ”Nation, Empire, Globe: Nation, Empire, Globe: The Spaces of Population Debate in the Interwar Years,” Comparative Studies in Society and History, vol. 49, no. 1 (2007), 170-201.
- 37 Schlosser, 「Malthus at Mid-Century」, op. cit., 472, endnote 58, cited Osborn, Our Plandered Planet, vii.
- 38 Osborn, 200-201, cited in Schlosser, 「Malthus at Mid-Century」, op. cit., 472, endnote 60.
- 39 Guy Irving Burch and Elmer Pendell, Population Roads to Peace or War (Washington, DC: Population Reference Bureau, 1945), 103, cited in Jacqueline Kasun, The War against Population, op. cit., 161.
- 40 マーガレット・サンガー、『バース・コントロール・レビュー』第5巻第4号に掲載された書簡。4. p. 7.
- 41 カレン・J・シャフナー「日米優生学のつながり」カレン・J・シャフナー編『日本における優生学』(福岡大学出版会、1998)、
- Eugenics in Japan” (Fukuoka: Kyushu University Press, 2014), 72.
- 42 Aiko Takeuchi-Demirci, Contraceptive Diplomacy: Reproductive Politics and Imperial Ambitions in the United States and Japan (Stanford, CA: Stanford University Press, 2018), 83. 石本については、Elise K. Tipton, 「Ishimoto Shizue: The Margaret Sanger of Japan,」 Women’s History Review, vol. 6, no. 3 (1997), 337-355. Baroness Shidzue Ishimoto, Facing Two Ways: The Story of My Life (New York: Farrar and Rinehart, 1935).
- 43 竹内愛子・デミルキ『避妊外交』(op. cit., 83-84)。44 竹内愛子『避妊外交』(前掲書、89)。
- 45 竹内愛子『避妊外交』op. cit., 98は、セオドア・ロスロップ・ストッダード『色彩の上昇する潮流:白人至上主義に対する脅威』(ニューヨーク:チャールズ・スクリブナーズ・サンズ、1920)を引用している。
- 46 竹内デミルキ愛子『避妊外交』(op. cit., 98, endnote 53)は、田中芳麿「幽世学から見た日常」『幽世学』2 巻 6 号(1925)39-46を引用している。田中とその時代については、山崎清子「遺伝学と優生学の誕生」(カレン・J・シャフナー編『日本の優生学』所収、15-33)参照。
- 47 竹内デミルキ愛子『避妊外交』(前掲書、98)。日本の知識人と優生思想については、横山隆「戦争前日本における優生政策と全国禁酒同盟運動について」『ヒストリア・サイエンティアリウム』28巻3号(2018)、353-3。3 (2018), 353-376.
- 48 Aiko Takeuchi-Demirci, Contraceptive Diplomacy, op. cit., 99-100. エドウィン・R・エンブリー『日記』1926年1月-2月より引用、竹内-デミルキ『避妊外交』(op. cit., 100, endnote 64.
- 49 例えば、オリバー・ストーンとピーター・クズニック『The Untold History of the United States』(ニューヨーク:ギャラリーブックス、2012)、特に第4章「原爆」参照: The Tragedy of a Small Man ”を参照のこと。
- 50 よりニュアンスの異なる見解については、ジョン・ルカックス「ドイツ人の二つの戦争:ハイゼンベルクとボーア」と「冷戦の起源」(『歴史と人間の条件』所収)を参照のこと: A Historian’s Pursuit of Knowledge」(Wilmington, DE: ISI Books, 2013)の第3章と第5章を参照されたい。
- 51 古典的な文献はポール・R・エーリック夫妻『人口爆弾』(Cutchogue, NY: Buccaneer Books, 1968)である。この新種の「爆弾」に対する恐怖が米国で広まったことについては、エリザベス・ムーア「アメリカの大企業はいかにして人口爆弾を売りつけたか」『The Uncertified Human』1978年8月号、3-6、ジャクリーン・カスン『人口との戦争』(前掲書、162)参照。
- 52 1974年8月にルーマニアのブカレストで開催された世界人口会議で、行動計画が策定された。NSSM-200は、行動計画における「人口動向と政策の包括的な見直しと評価」を」5年ごとに実施する。”よう求めていた。「National Security Study Memorandum NSSM 200,「op. cit., Chapter 6,」World Population Conference,” 71.
- 53 Robert McNamara, One Hundred Countries, Two Billion People (London: Pall Mall Press, 1973), 45-46, cited in Steven W. Mosher, Population Control: Real Costs, Illusory Benefits (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2008), endnote 65, 68-69に引用されている。マクナマラについては、Mosher, Population Control, op. cit., 46-49も参照のこと。
- 54 Crawford F. Sams, 「Medic」: Crawford F. Sams, 「Medic」:The Mission of an American Military Doctor in Occupied Japan and Wartorn Korea (Armonk, NY: East Gate, 1998), xvii-xxi.
- 55 Sams, 「Medic」, op. cit., 217を引用している。Troy J. Sacquety, ”A Civil Affairs Pioneer: ヴェリタス』第6巻第1号、2010年、1。
- 56 ジェイソン・モーガン「菊田昇と日本における養子縁組法」『麗澤大学紀要』第102号、2019年3月、35-44、引用:Samuel Coleman, Family Planning in Japanese Society (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983), Matsubara Yō ko、
- 松原容子「科学史研究 ̄」(2002年6月)104-106、下川正治『望郷のひきあげ志-和泉聖一と二日市報世』(福岡: 玄書房、2017)、豊田真帆「アメリカ戦力化のニッポンにおける選択の可能性-勇星法語の実践・談話」『アメリカ史研究』No. 36, 2013, 63-82, Lynn D. Wardle, ”’Crying Stones’: 山本清子「近代日本における妊娠中絶制度と家族制度に関する歴史的考察」『園田学園女子大学論文集』第37 号(2002年 12月)。37 (Dec., 2002), 99-110. 東アジアにおける宗教と人口の結びつきについては、例えば、Vegard Skirbekk, Setsuya Fukuda, Conrad Hackett, Marcin Stonawski, Thomas Spoorenberg and Raya Muttarak, 「Is Buddhism the Low-Fertility Religion of Asia?」を参照のこと。Demographic Research, Max Planck Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften, vol.32 (Jan.-Jun., 2015), 1-28.
- 57 Mosher, 51, また巻末注80, David Cushman Coyle, 「Japan’s Population,」を引用している。
- Population Bulletin vol.15, no.7, 1959, 119-136を引用している。
- 58 Lynn D. Wardle, 「’Crying Stones’,」 op. cit.日本における堕胎問題の背景については、Fabian Drixler, Mabiki: Fabian Drixler, Mabiki: Infanticide and Population Growth in Eastern Japan, 1660-1950 (Berkeley: University of California Press, 2013)を参照のこと。
- 59 James Robenalt, January 1973などを参照: Watergate, Roe v. Wade, Vietnam, and the Month that Changed America Forever (Chicago, IL: Chicago Review Press, 2015)を参照のこと。
- 60 Jacqueline Kasun, The War against Population, op. cit., 199, cited U.S. Government Document NSSM 200, ”Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests,” December 10, 1974, declassified on December 31, 1980, 121, UN Fund for Population Activities, 1983 Report, and Agency for International Development, 「Rationale for AID Support of Population Programs,」 January 1982, 24. 1979年、UNFPAが中国本土で、労働者を訓練し、データを収集し、避妊具や人工妊娠中絶器具を製造するために、猛烈な人口抑制プログラムを支援し始めたのは、おそらく中華人民共和国におけるベトナムの二の舞を防ぐためであった。1984年末までにUNFPAは、アジアにおけるUNFPAの地域プロジェクトの中国側の取り分を除いて、5400万ドルを中国のプログラムに注ぎ込んだ。中絶と嬰児殺しの強制という、新しい一人っ子プログラムの厳しい現実が生々しく語られる一方で、国連人口基金(UNFPA)の1981年報告書は、「例外的に高い実施率」、「高いコミットメント」、「驚くほど効率的な財務報告」といった高い評価で輝いていた。このような友好的な賛辞は、人口ネットワークからも広く寄せられた: カーター政権の保健福祉局長官であったパトリシア・ハリスは、中国政府の代表者と家族計画に関する共同研究協定を締結し、人口参考局は中国のプログラムを「よく設計された家族計画プログラム」の例として挙げ、ワールドウォッチのレスター・ブラウンは「新しい経済時代のための人口政策」の中で、このプログラムを有望なモデルであるとし、国際家族計画連盟は「第三世界のモデル」としての役割を果たすことができるのではないかと考え、韓国家族計画連盟は独自の一人っ子家族計画を開始した。
- Jacqueline Kasun, The War against Population, op. cit., 199-200, UN Fund for Population Activities, Reports for 1980, 1981, 1982, 1983, and Summary of Allocations, 1984, Christopher S. Wren, ”Chinese Region Showing Resistance to National Goals for Birth Control,「New York Times, May 16, 1982, 29, Michele Vink,」Abortion and Birth Control in Canton, China,” Wall Street Journal, November 30, 1981, Henry P. David, ”China’s Population Policy: Intercom, September/October, 1982, 3-4, 米国務省が公式に確認した妊娠後期の強制堕胎の報告(1983年の人権実践に関する国別報告書、下院外交委員会および上院外交委員会に提出、1984年2月、743号)、UNFPA, 1981 Report, 52, Intercom, July 1980, 4, Intercom, March/April 1983, 7, Lester Brown, Worldwatch Paper #5 3, International Planned Parenthood Federation, People, vol. 10, no. 1, 1983, 1983. 10, no. 1, 1983, 24, and International Planned Parenthood Federation, People, vol. 10, no. 2, 1983, 28.
- 61 一般的には、「アメリカの自殺未遂」(ポール・ジョンソン『モダン・タイムス』所収)参照: New York: Harper Perennial Modern Classics, 1992)、第18章。
- 62 ジャクリーン・カスン『人口との戦い』(前掲書)、163-164: 1965-1975-A Decade of Global Action (Washington, DC: The Population Reference Bureau, April 1976), 185, Population and the American Future: The Report of the Commission on Population Growth and the American Future (New York: New American Library, 1972), 137, 171, 178, 189-190, John D. Rockefeller III, Letter to the President and Congress, transmitting the Final Report of the Commission on Population Growth and the American Future, dated March 27, Alan Guttmacher Institute, Informing Social Change (New York: The Alan Guttmacher Institute, 1980), 19, and Population Reference Bureau, World Population Growth and Response, op.cit., 187.
- 63 Jacqueline Kasun, The War against Population, op. cit., 197, cited The Reform of International Institutions: The Reform of International Institutions: A Report of the Trilateral Task Force on International Institutions to the Trilateral Commission (New York: The Trilateral Commission, 1976), 22, and Reducing Malnutrition in Developing Countries: 南アジアと東南アジアにおける米の増産: 開発途上国の栄養不良の削減:南・東南アジアにおける米の増産:三極委員会に対する三極南北食糧タスクフォース報告書」(ニューヨーク:三極委員会、1978)、xi。原文では強調されている。
- 64 ルーズベルトの「民主主義の兵器庫」演説は、真珠湾攻撃によってアメリカが他の交戦国と直接軍事衝突するほぼ1年前の1940年12月29日にラジオを通じて放送された。真珠湾攻撃以前から、ルーズベルトが自由を守る鍵として生産性を訴えていたことは注目に値する。「自由の鍛冶場」については、Arthur Herman, Freedom’s Forge: How American Business Produced Victory in World War II (New York: Random House, 2012)を参照のこと。
