A Critique of Yuval Noah Harari’s Sapiens: A Brief History of Humankind
要旨
『サピエンス』ユヴァル・ノア・ハラリ著
代表民主主義の原則が世界的に攻撃されている。米国では、トランプ政権による影響と、1月6日の国会議事堂襲撃事件で明らかになった反民主主義的感情にまだ対処している。世界的に見れば、民主主義制度がストレスにさらされている例は他にもたくさんあるが、民主主義に対する人々の不信感や反感を示す、より暗黙的で極端でない例も今はたくさんある。こうした感情が政治的に影響力のある行動に結実すると、振り子は驚くほどファシズム的で独裁的な政策や政府へと振れる。私たち一人ひとりの政治的な立場がどうであれ、誰も自分が反対する独裁者に支配されたくはないだろう。権威主義的な政治に反対する意見が広く共有されていることを考えれば、現在の反民主主義的な魅惑を抑える必要があることに同意できるはずだ。われわれが切実に必要としているのは、われわれの恐怖、怒り、幻滅の霧を見破り、理性的な政治的コミットメントを再び見出す手助けをしてくれる、啓蒙的で説得力のある知識人である。
そのような知識人の一人が、近著『サピエンス』『ホモ・デウス』『21世紀への21の教訓』の3冊でベストセラーとなったユヴァル・ノア・ハラリであることは間違いない。ハラリはまた、一般紙への寄稿や、番組、ポッドキャスト、パネル、基調講演のゲストとしても頻繁に登場している。さらに、ハラリは「サピエンスシップ」という、グローバルな責任を提唱し、グローバルな会話を明確にし、最も重要なグローバルな課題に注目する学際的な組織を共同設立し、高邁な学問的理想を実践している。
私がハラリを取り上げたのは、フィロソフィー・ナウの読者の多くが彼の仕事に精通していると推測されるからである。彼は確かに、公共知識主義における最も急成長しているスターの一人である。残念なことに、彼の仕事は、最初のベストセラー『サピエンス』で打ち出した哲学的立場によって台無しにされている。この書評では、ハラリが首尾一貫した政治的あるいはイデオロギー的な議論を進めるためには、まず哲学的なコミットメントを強化しなければならないことを示したい。

『Sapiens: A Brief History of Humankind』(2011年)は2,000万部を突破し、65カ国語以上に翻訳されている。その中でハラリは、少なくとも6つの異なる人類(ホモ)を含む人類の歴史を提示し、ホモ・サピエンスが最終的に生き残り、他の種が生き残れなかった理由についての理論を提示している。最終的にハラリは、ホモ・サピエンスが繁栄したのは高度な認知能力があったからだという一般的な学者のコンセンサスに同意する。しかし彼は、ホモ・サピエンスの精神的優位性の本当の利点は想像力であると主張する。この想像力によって、ホモ・サピエンスは神話を創作し広めることができ、大規模な協力関係の扉を開いた。この大規模な共同体的協力によって、地理的、生態学的、種的支配を拡大することができた。ハラリは、このような支配を可能にした想像上の物語が、宗教、政治・法制度、経済システム、倫理規範であると主張する。農業革命、文明と都市の絶え間ない拡大、科学革命を可能にしたのは、こうした共通の神話であったと彼は考えている。結局のところ、こうした共通の神話が今日も私たちの緩やかなグローバル社会を支えているのだ。ハラリは自らの立場を要約してこう書いている:
「現代の国家であれ、中世の教会であれ、古代の都市であれ、古代の部族であれ、人間の大規模な協力は、人々の集団的想像力の中にのみ存在する共通の神話に根ざしている。教会は共通の宗教神話に根ざし、国家は共通の国家神話に根ざし、司法制度は共通の法神話に根ざしている。宇宙には神々も、国家も、貨幣も、人権も、法律も、正義も、人間の共通の想像力の外には存在しない。」 (サピエンス、p27-28、強調)
ハラリ氏は自身のウェブサイトで、これらの高度な社会制度はすべて想像上の構成物に過ぎないと主張している:
ホモ・サピエンスが世界を支配しているのは、神々、国家、貨幣、人権など、純粋に自らの想像力の中に存在するものを信じることができる唯一の動物だからである。
しかし、ハラリはここで、適切な論証で裏付けることなく、極端な哲学的主張をしている。これは哲学的な失態である以上に、反民主主義的な攻撃に対応する彼の能力を究極的に損なっている。
ハラリは哲学に反対しているわけではない。実際、彼は哲学がかつてないほど重要になっていると述べている(Experts on Experts: Armchair Expert No.45, Yuval Noah Harari, D. Shepard & M. Padman, Hosts, Oct 4, 2018)。彼は自身のウェブサイト上で、自らを「歴史家であり哲学者」であるとさえ述べている。彼の才覚は明らかであり、今日の代表的な公共知識人の一人としての地位は当然のものである。彼が自らを哲学者と見なし、哲学の重要性を認識していることを私は嬉しく思う。しかし、社会をより良く進歩させるためには、その根底にある哲学がしっかりとなされている必要がある。具体的には、ハラリの政治的見解は彼の哲学的コミットメントと協調する必要がある。この一貫性を実現するために、ハラリはまず、『サピエンス』における(そして『ホモ・デウス』における)彼の哲学的立場が、彼の作品全体を損なっていることを認識する必要がある。倫理規範、政治制度、法制度はすべて「神話と物語」に過ぎないという彼の主張は、いくつかの重要な概念的区別を見逃しており、最終的には、私たちがどのように行動し、社会を組織すべきか、政治的・法的政策について彼が行う処方箋を台無しにしている。

問題のある相対主義
政治腐敗、富の不平等、独裁的なデータ所有、移民、そして「自由」と「ナショナリズム」が本当に意味するものなどである。これらはすべて、反民主主義的な感情との戦いにおいて重要なトピックだが、ハラリの主張を裏付けるためには、確固たる哲学的基盤が必要だ。ここが、彼のこれまでの研究が現在の努力を裏切っている点である。
先に述べたように、『サピエンス』の中でハラリは、人権という現代の倫理的枠組みを含め、倫理や社会的/道徳的規範に関する理論はすべて物語や神話に過ぎないと主張している。彼が書いているように、「人権はすべて私たちの豊饒な想像力の産物である」(p.32)。しかし、彼はそれだけにとどまらず、すべての社会的・政治的原則についても同じことが言えると、この主張を拡張している。ハンムラビ法典(紀元前1776年頃)からアメリカ独立宣言(西暦1776年)まで、そして他のすべての社会的・政治的秩序についても、これらは神話であり、私たちはこれらの神話を共同体として受け入れることによって社会規範や秩序を形成しているとハラリは考えている。例えば、アメリカの政治・法制度の根底にある政治原理について、彼は次のように言う。「アメリカ独立宣言は、普遍的で永遠の正義の原理を概説していると主張している……しかし、そのような普遍的な原理が存在するのは、サピエンスの豊饒な想像力の中だけであり、彼らが創作し、互いに語り合う神話の中だけである。これらの原則には客観的な妥当性はない」(p.108)。このようなことを言うハラリは、ハンムラビ法典と米国宣言に示された原則、あるいはその他の道徳観念との間に、(例えば)決定的な決定方法はあり得ないと主張しているのである。
このような倫理的・政治的立場は「相対主義」と呼ばれ、倫理的・政治的原則は単なる慣習であり、それを生み出す文脈との相対的な関係でしか評価できないという考え方である。倫理的相対主義者にとって、善悪や社会をどのように組織すべきか、あるいは組織すべきでないかという主張は、その主張を評価するための枠組みに完全に依存している。相対主義者が用いる2つの一般的な枠組みとは、主張がなされる文化的規範や信念(これを「文化相対主義」と呼ぶ)、あるいは個人の基準や信念(「個人相対主義」)である。文化相対主義によれば、物事はどうあるべきかという問いを分析するのに、文化的に独立した方法すら存在しない。例えば、文化相対主義者は、ある社会で特定の政治体制を確立することが正しいか間違っているかは、その社会の文化的規範や信念が何であるかを知るまでは判断できないと言うかもしれない。あるいは別の例として、個人相対主義者は、盗みに関する個人の基準や信念を調べるまでは、盗むことが正しいか間違っているか判断できないと言うだろう。もしその個人が盗んでもいいと思えば、それはその人にとっていいことであり、盗んではいけないと思えば、それはその人にとって悪いことなのだ。
これらの考え方は、多様な文化的規範に対して偏見を持たずに生きよう、生きようとする姿勢を認めているように見えるため、最初は啓蒙的でオープンマインドな立場に見えるかもしれない。しかし、よく観察してみると、もしこのような見解が受け入れられるなら、あらゆる政策やその後の行動を実質的に批判したり擁護したりする能力を失ってしまうことに気づくだろう。
記述的対規範的
人はしばしば、相対主義が示唆するような方法で心理的に行動する。何かをしてもいいと思えば、それをする自由を感じ、何かをしてもいいと思わなければ、それを控える。しかし、相対主義者は単に人間がどのように決断を下すかを述べているのではない。例えば、移民をどう扱うべきか、あるいはFGMをどう扱うべきかといった、競合する倫理的主張の間で決定することができないような状況においてである。
倫理学や政治哲学では、記述的な主張と規範的な主張、つまり物事のあり方に関する主張と物事のあるべき姿に関する主張を区別することが多い。しかし、ハラリはこのことを完全に見落としているようだ。ハラリは、自分は常に記述的な主張をしている、つまり単に「物事がどうあるべきか」を記述しているだけで、物事がどうあるべきかという大きな主張はしていないと信じているようだ。しかし、記述的/規範的という区別に慣れれば、ハラリがしばしば、物事がどうあるべきかについて規範的な主張をしているのであって、単に物事がどうあるべきかを記述しているのではないことが容易にわかる。急進的なナショナリズムに反対したり、テック企業や政府が我々のデータを管理する絶対的な権力に反対したりするとき、彼は倫理的な主張をしているのである。つまり、物事はどうあるべきか、我々は何をすべきか、何を信じるべきか、そして政治的・法的政策はこれらの事実に沿ってどうあるべきかという主張である。しかし、彼が『サピエンス』で主張しているように、倫理的・政治的原則が単なる神話であり、私たちが互いに語る物語に過ぎないのであれば、急進的ナショナリズムに反対する彼の主張を受け入れる究極的な理由は、急進的ナショナリズムを支持する反対の立場を受け入れる以上にない。倫理的・政治的原則が単なる神話に過ぎないのであれば、どちらの立場も客観的に優れているとは言えない。なぜなら、どちらにも客観的な真実は存在しないからだ。この種の急進的な相対主義は非常に危険である。一旦それを受け入れてしまうと、倫理的、政治的、法的、経済的な立場や原則、理論がどんなに不合理に見え、矛盾し、道徳的に嫌悪されるものであっても、それを本質的に批判することができなくなるからだ。それらすべてが「単なる神話」であり、単に「想像の産物/特徴」であるならば、あるシステムが残虐であり、他のシステムがより優れていると言うことはできない。
私の批判は、ハラリが規範的な主張をしているということではない。ハラリ氏のように、人類史の広い範囲を扱う人々にとって、物事がどうあるべきかを議論することを制限することは、不可能ではないにせよ、非常に難しいことである。実際、記述的な判断と規範的な判断は、どちらも人間の経験の本質的な部分であるように思われる。つまり、物事がどのように見えるかに気づき、物事がどのようにあるべきかについて考え、判断を下すのである。実際、民主的で人道的な規範の主張は、急進的なナショナリズムや権威主義との知的な戦いにおいてまさに必要なものである。私が批判したいのは、ハラリが規範的な主張を、それも非相対的な主張をしていることを認識していないことだ。彼は著書で倫理的相対主義を擁護する立場に身を置きながら、非相対的な主張をすることで公的知識人として活動している。自称 “哲学者 “として、彼はもっとより良く行う必要がある。
ヨーラム・ハゾニーは政治的な哲学者であり、『ヘブライ語聖典の哲学』は政治的な目的、すなわちヘブライ語聖典をギリシア哲学のテキストと同等の理性の著作として大学環境に導入することを目的として書かれている。ハゾニーはこのことを明言し、そうしたいと願う人々のためのハウツーガイドとしてこの本を提示している。本書は親しみやすい文体で書かれており、ユダヤ人読者だけでなくキリスト教徒にも意図的に仕立てられている。
『ヘブライ語聖典の哲学』は、ヘブライ語聖典がしばしば誤って捉えられている理性と啓示の二項対立を脇に置くことを目的としている。その結果、ヘブライ語聖典は理性的なテキストとして考慮される価値がない、あるいはふさわしくないとみなされるのだと彼は言う。ハゾニーは、ヘブライ語聖書がある目的を持って書かれたものであると理解している。すなわち、よく生きる人生について読者に教えることである。彼はこのモザイク法を自然法と同一視し、預言者エレミヤがそれをすべての国が従うべき律法のレベルにまで高めたことを称賛している。ハゾニーは、ヘブライ語聖書における神の話を、ギリシア語聖書における神々の話になぞらえ、明確に哲学的であると見なしている。彼の念頭にあるのは、パルメニデスが女神から啓示されたという存在の本質についての説明や、ソクラテスがさまざまなプラトン的対話の中で、自分がやりたくなるようなことをいつ断念すべきかを教えてくれる神のしるしに導かれているという主張である。私たちにとって有益なことを引き出そうという目線でこれらのギリシア語のテキストにアプローチするのであれば、ヘブライ語の聖典も同じような解釈が可能であると見なすべきではないだろうか。
ハゾニーは、聖典は服従を命じ、哲学は心の独立を養うという考えを覆したいと考えている。現代の大学は、古代ギリシャの知恵を非常に高く評価する一方で、聖書の知恵はせいぜい私的な美徳としか見ていないと彼は言う。これは、近代大学発祥の地である19世紀のドイツで、ユダヤ人が独創的な考えを持たないとして軽蔑された結果だと彼は訴える。たとえば、『文明とその不満』の中でフロイトが好意的に引用したゲーテの一節を思い浮かべることができるだろう: 「科学と芸術を持つ者は宗教も持つが、そのどちらも持たない者は宗教を持て!」。
哲学と宗教の間にある不浸透性の障壁という概念をさらに不安定にするために、ハゾニーは、20世紀の現象学によって前面に押し出された、事実に対する記述の対応としての真理と、天職としての真理、あるいは目的への忠実さとしての真理という区別を借用している。アスファルトの道路や眼鏡がなかった時代、つまり聖書時代のイスラエルで、道を歩き、鮮明な視界を得ることは、ハゾニーによって、単なる記述と事実の対応にはない意味を孕んだ行為として喚起された。真実の道やビジョンとは、信頼できるものであり、目的地まで忠実に導く、あるいは遠くから迫ってくるものを正確に見るという目的を果たすものである。神の真実とは、物質的な利益をもたらすという意味で、信頼できる約束のことである。イスラエルの地を「乳と蜜の流れる地」と表現するのは、聖書の伝道者の書に、私たちの最高の望みは労働の成果を享受することだと書かれているのと同じように、豊かさとしての善のビジョンを伝えるためだと言えるかもしれない。ハゾニーは、ヘブライ語聖書の物語における救済は、不滅の魂とは何の関係もないと明言している。
ヘブライ聖書では、政治的利益と物質的利益は一体であるとハゾニーは言う。モーセの律法に忠実であることは、すべての人が利害関係を持つ秩序ある社会をもたらす。預言者ミカは、「すべての人は自分のぶどうの木といちじくの木の下に座る」
ハゾニーはヘブライ語聖書において、農夫と羊飼いという2つのタイプの人間を区別している。彼は、カインとアベルの物語で読者を方向づける。カインは父アダムの伝統に従って土地を耕し(アダムは神から呪いをかけられている)、アベルは羊を放牧する羊飼いを選んだ。物語にあるように、神が農夫カインの穀物のいけにえよりも好むのは、羊飼いの動物のいけにえである。神はアダムに土地を耕すように命じたのだから、ハゾニーはこれを、運命に服従するのではなく、企業活動を聖書が推奨しているのだと読む。彼はまた、アブラハム、ヤコブ、モーセ、ダビデなど、聖書の英雄の多くが羊飼いであるという事実に注意を促している。
解釈と意見
ヘブライ語聖典の解釈として、ハゾニーの著作はこのルールに反していない。しかし、どのような解釈も必然的に他の読みを抑制する。ハゾニーは脚注で、聖書の箴言、伝道者の書、ヨブ記を「知恵文学」とする伝統的な分類に異議を唱えており、それらを無視している。その理由は、モーセ書や預言書の想像力豊かな歴史物語とは対照的であり、ラビ解釈の伝統が生まれたからである。この対比は、後者が理性的であるというハゾニーの主張にとって不利であり、後者を理性的なものにしようとするハゾニーの労苦が物語っている。
さらにハゾニーは、ユダヤ人を排除して、ユダヤ教の一神教の精神的遺産をキリスト教が自らのものとして主張するために残しておくことに満足しているようだ。しかし、神への批判的なアプローチは、ギリシア哲学とユダヤ教の一神教に共通している。クセノファネスの「人は神々が生まれ、自分たちと同じような衣服と声と肉体を持っていると思っている」という考えや、ヘラクレイトスの「神々の像に祈るが、それは家と会話をしようとするようなものである。イザヤが木から偶像を作ることについて話していることと比べてみよう。「その半分を火で焼き、その半分で肉を食べ、ローストを焼いて満腹になり、自分自身を温めて『嗚呼、私は温かい、私は火を見る』とさえ言った。そして、それで残ったものを神のために、自分の彫像のために作った。彼はそれにひざまずき、ひれ伏して祈り、『あなたは私の神だから、私をお救いください』と言う。彼らは知ることも理解することもない。彼らの目は見ることから離れ、心は理解することから遠ざかっているからだ」。ギリシア哲学とヘブライ語聖典は、どちらも神の統一の名の下に偶像崇拝を破壊することに依拠しているのだから、どちらも知恵として読むことができるのだ。
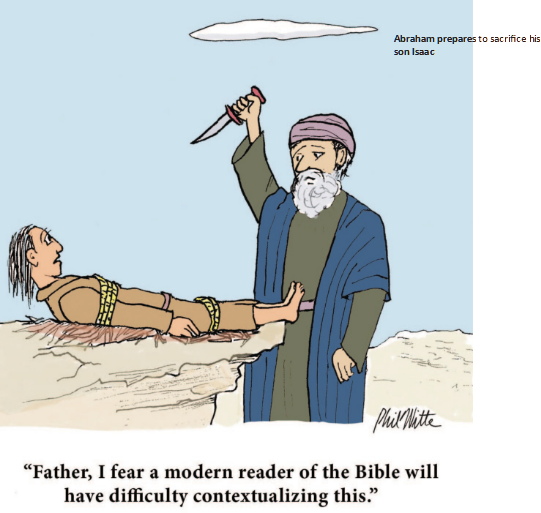
ハゾニーは、政治的な意義よりも精神的な意義の方が大きいとする聖書の読み方において、私たちが彼と意見を異にする権利を認めるだろう。彼は、私たちとは反対の見解を採用しながらも、ヘブライ語の聖典は多様な視点を提示することを意図しており、そこから中心的な教えに近づくことができる。ある道が安全に目的地まで続いているのか、遠くに見えるものが正確に見えているのか、やがてわかるように、物事を自分で疑う必要性は、ギリシャ哲学が奨励した問いに似た聖書の教えの遺産であるとハゾニーは強調したいのである。これは、ギリシア哲学から得られると思われる理解を、ヘブライ語聖典から得られる知識によって補完し、私たちにとって有益なもの、すなわち律法に支配された平和の受け入れと支持へと導くため、2つのジャンルの違いを平らにするという彼の目標に沿ったものである。ブラッド・ラパポートはジョンズ・ホプキンス大学で哲学の学士号を取得し、エセックス大学とヴァンダービルト大学でも哲学を学んだ。
悲劇の誕生
フリードリッヒ・ニエッチェ(1844-1900)は、芸術を “この世の最高の仕事であり、真に形而上学的な活動 “と呼んだ。無神論者である彼は、美的現象としてのみ存在が正当化され、生きる価値があると信じていた。しかし、彼が最も尊敬したのはギリシャ芸術、とりわけ紀元前5世紀のギリシャ悲劇であった。偉大な悲劇家ソフォクレス、エウリピデス、エスキロスがそれぞれ書いた『オイディプス王』、『ヘクバ』、『オレステイア』三部作を思い浮かべてほしい。『オイディプス』では、主人公が知らず知らずのうちに予言を成就させ、父親を殺して母親と結婚する。劇は、オイディプスが自分の目をえぐり出すところで終わる。明らかに、かなり暗い内容だ。しかし、ギリシャ人は悲劇に満足できなかった。

ニーチェは悲劇のパラドックス(人間の災難が展開するのを見るのは快感であるという一見不可解な事実)に対する反応を、『悲劇の誕生』(1872年)の中で彼が「アポロ的」力と「ディオニュソス的」力と呼んだものの両極性と融合を軸に展開した。アポロンはオリンポスの神であり、光、彫刻、そして夢のような、天に昇るような芸術を司った。明晰夢(夢を見ていることを自覚しながらも、その中で生き続けたいと願う夢)は、アポロ的快楽のパラダイムである。私たちはそれが非現実的であり、現実の境界線がはっきりと示されていることを知っているが、それでもなお、秩序だった望ましい体験を提供している。
アポロ的快楽が個人に属するのに対し、ディオニュソス的快楽は、統一された人間経験の泥沼に個人を引き寄せる。ディオニュソスはギリシア神話に登場する、葡萄酒、酒宴、奔放な情熱、つまり地上の恍惚の神である。ニーチェによれば、ディオニュソス的な芸術的衝動は、アルコールの影響下での酩酊、あるいはダンスや春の訪れといった他の豊穣な地上の喜びとのアナロジーによって最もよく理解される。ニーチェの『悲劇の誕生』の核となる考えは、ギリシア悲劇において、この2つの芸術的力が融合するというものだ: アポロ的観念論と芸術的壮大さが、混沌とした人間の意志のディオニュソス的模倣と融合する。アポロ的な効果は、人間の苦しみが精緻な散文と音楽によって神的なものへと昇華されることで、救済を超えて上昇する。人間は、現実と共存する神話を欲している。ニーチェは、ギリシア悲劇はこの点で独自のクラスであると考えた。なぜなら、ギリシア悲劇では、神話はいくつかの宗教やギリシアのミステリーカルトのようにベールに包まれているのではなく、明らかにされているからである。ニーチェはここでもまた、目的意識をもたらす歓喜の起源を開示している。ニーチェにとって悲劇とは、ニヒリズムを直視することに等しい。人生から目を背ける代わりに、実存的な恐怖を芸術的媒体に注ぎ込むことを除けば。悲劇は形而上学的な慰めとカタルシスを与える。神話は神話のための神話であり、シニシズムで迎えられるものではなく、むしろ、神話をありのままに楽しもうとする冷静な意志で迎えられるものなのだ。それは、最も鋭利な現実を、それ以上のもの、さらには美しいものへと変容させる必要な幻想である。
ニーチェはギリシア悲劇の死をソクラテスのせいにした–より正確には、ソクラテスとエウリピデスの理性と合理性への啓蒙的献身を責めたのだ。「批判的思想家」である劇作家のエウリピデスは、先人たちの悲劇的作品のあまりにも壮大な言語、構造、謎めいた合唱に違和感を覚え、不快感を抱いた。彼は自らの劇作において、このジャンルを軽蔑していた偉大なソクラテスに他ならない慰めの仲間を求めた。ソクラテスは悲劇を理解することができず、したがって悲劇を尊重することもできなかった。ニーチェによれば、この追求は神話の破壊と「理論的人間」の台頭をもたらした。
『悲劇の誕生』は二重の議論から成っている。本文の大部分は、ギリシア悲劇の誕生、本質、終焉に関するニーチェの論争の的となるテーゼを含んでいるが、最後の章では、現代ドイツ文化の改革のためのマニフェストを創作している。ニーチェは、ギリシア悲劇を破壊したとされるソクラテス的合理主義を、近代ドイツ生活の退廃的状態と結びつけ、別の神話に勝る神話、すなわち学問(あるいは科学)の神話に勝る芸術の神話を主張する。彼の合理主義への攻撃と神話の偶像化は、間違いなく学者たちを悩ませたが、ニーチェが「知性よりも本能」を好むと批判した小説家トーマス・マンの怒りをも買った。
ニーチェの主要なテーゼを検証することができなかったため、『悲劇の誕生』自体が非学術的とみなされ、古典主義者に影響を与え、文化改革の新たな原動力を植え付けるという彼の狙いは失敗に終わった。とはいえ、ニーチェの主張の魅惑性を否定することは難しい。特に、彼自身の読解が後期ロマン派の散文詩のように読める場合はなおさらだ。学問的な衣をまとっていなければ、それ自体が傑作とみなされていただろう。ニーチェ自身の『自己批判の試み』(1886年)の言葉を借りれば、彼はこの芸術の「新しい魂」を語るのではなく、歌うべきだったのだ。
