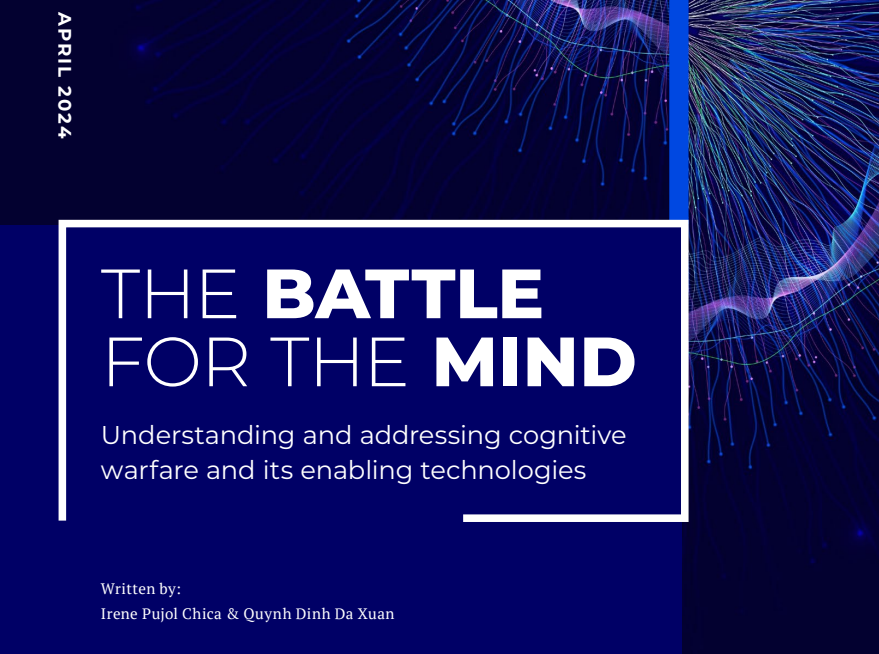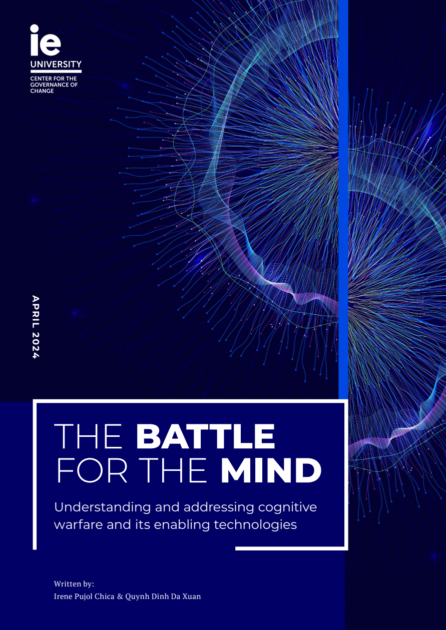
政策論文/提言書 『The Battle for the Mind:Understanding and addressing cognitive warfare and its enabling technologies』 :
『心をめぐる戦い:認知戦争とその実現技術の理解と対策』IE Center for the Governance of Change 2024年
https://static.ie.edu/CGC/CGC_TheBattleofTheMind_2024.pdf
目次
- 謝辞:/ Acknowledgments
- ミュンヘン安全保障会議での認知戦争に関する議論 / Discussing Cognitive Warfare at the Munich Security Conference
- 提言概要:/ Summary of Recommendations
- 序論:認知領域の出現 / Setting the Stage:The Emergence of the Cognitive Domain
- 未来を形作る要素:認知戦争の展開を決定づけるシグナル / Identifying Signals:Elements Shaping the Future of Cognitive Warfare
- 戦略構築:心を守るために / Building Strategies:Protecting the Mind
- a. 脅威の認識と理解の醸成 / Cultivating awareness and understanding of the threats
- b. 認知戦争とその実現技術のガバナンス / Governing cognitive warfare and its enabling technologies
- c. 新興技術の活用による民主主義的社会の回復力強化 / Capturing the power of emerging tech to strengthen societal and democratic resilience
- 注釈:/ Endnotes
本書の概要:
短い解説:
本書は、ミュンヘン安全保障会議での円卓会議の議論を基に、新たな戦争領域「認知戦争」の概念、脅威、実現技術を分析し、民主主義を守るための具体的な政策提言を示すことを目的とする。
著者について:
著者であるIE大学ガバナンス・オブ・チェンジ・センターは、テクノロジーとガバナンスの交差点に焦点を当てた研究機関である。同センターは、政策立案者、産業界、学界のリーダーとの対話を通じ、複雑な社会課題に対する実践的な解決策を提唱している。
テーマ解説
- 主要テーマ:認知戦争の定義と脅威
人間の認知そのものを標的とし、無意識に働きかける新たな戦争形態の概念と、それが民主主義にもたらす構造的リスクを体系的に解説する。
- 新規性:第6の戦域としての認知領域
NATOなどでも議論され始めた、陸、海、空、宇宙、サイバーに続く新たな戦争領域「認知領域」の概念を、先端技術との関連で詳細に分析する。
- 興味深い知見:テクノロジーによる防御の可能性
認知戦争を可能にするAIやニューロテクノロジーが、同時に社会の回復力を強化し、民主主義を守るための強力な武器となりうるという逆説を提示する。
キーワード解説
- 認知戦争:個人や集団の認知(思考、信念、感情)に影響を与え、操作することで、敵対者に対して優位に立つことを目的とする活動。
- ハイブリッド戦争:軍事的手段に限らず、経済、政治、情報などのあらゆる手段を組み合わせて行われる戦争形態。認知戦争はその一部と位置づけられる。
- 生成AI:テキスト、画像、音声などを自律的に生成する人工知能技術。認知戦争においては、個人の心理に合わせた偽情報の大量生成に悪用されるリスクがある。
- プレバンキング:実際に誤情報に接触する前に、操作の手法や典型的なパターンを学習させることで、人々の免疫力を高める事前防御策。
- ニューロライツ:神経データのプライバシーや精神的な自律性を守るための新たな人権概念。脳とコンピューターを直接接続する技術の進展に伴い、その必要性が高まっている。
- EU AI法:世界初の包括的なAI規制法。リスクベースのアプローチを採用し、認知行動操作を目的としたAIの使用を禁止するなど、先駆的な内容を含む。
- グループシンク(集団思考):集団内での同調圧力や調和の優先により、批判的な検討が行われず、誤った意思決定に陥りやすい心理現象。認知戦争の攻撃対象となる。
3分要約
本書は、2024年2月のミュンヘン安全保障会議で行われた円卓会議の議論を基に、新たな戦争領域としての「認知戦争」の概念を明確化し、その脅威と対策を多角的に分析する政策提言書である。
序論では、人間の無意識に働きかける認知戦争が、AIやニューロテクノロジーの進歩により、従来の心理戦や情報戦とは質的に異なる新たな段階に入ったと指摘する。中国の「智能化戦争」概念やロシアの選挙介入事例を挙げ、国家や非国家主体が、社会の分断や制度への不信という脆弱性を突き、民主主義を内部から不安定化させようとしている実態を描き出す。
次に、認知戦争の未来を形作る二つの原動力として、「認知科学の進歩」と「先端技術の発展」を分析する。人間の意思決定の大半が無意識のバイアスに依存するという知見は、攻撃者に「何を考えるか」ではなく「どのように考えるか」を操作する道を開いた。さらに、生成AI、AR/VR、BMIなどの技術は、個人のデータに基づく超個別化された操作や、認識そのもののハッキングを可能にしつつある。具体的な将来シナリオとして、生成AIとAR/VRを組み合わせ、社会を「オルタナティブ・リアリティ」の集落に分裂させる事例を提示し、危機感を煽る。
最終章では、具体的な防御戦略を三つの柱で提示する。第一に、市民のリテラシー向上(プレバンキング)とデータ保護意識の醸成。第二に、EUのAI規制法のような法的枠組みの整備と、既存の国際法ではカバーできない神経兵器などを対象とする新たな国際的ルールの構築。第三に、AIやVRなどの技術を積極的に活用し、民主的な熟議やバイアス訓練を行うことで社会の回復力を高めることである。結論として、多様なステークホルダーの協働が、認知戦争の脅威に対抗し、民主主義を守るために不可欠だと訴える。
各章の要約
謝辞
本書は、Irene Blázquez NavarroとCarlos Luca de Tenaの指導の下、ミュンヘン安全保障会議での円卓会議の議論を基に作成された。参加者全員の貢献に謝意が表されている。
ミュンヘン安全保障会議での認知戦争に関する議論
2024年2月16日、IE大学ガバナンス・オブ・チェンジ・センターは、ミュンヘン安全保障会議で産官学の専門家18名による円卓会議を開催した。参加者は、改変主義的主権国家などが、民主主義を内部から不安定化させるため、個人や集団の認知を操作している現状を確認し、そのメカニズムの深い理解と対策の必要性で一致した。
提言概要
本書は三つの分野で九つの具体的な提言を行う。1) 脅威の認識と理解:定義の明確化、プレバンキングの活用、データリテラシー向上。2) ガバナンス:法的枠組みの確立、既存国際法の適用検討、新たな枠組みの開発。3) 新興技術の活用:多様な関係者の協力、脆弱性の特定、テクノロジーによる防御力強化。
序論:認知領域の出現
認知戦争は、陸、海、空、宇宙、サイバーに続く「第6の戦域」として認識されつつある。従来の心理作戦と異なり、無意識への働きかけに特徴がある。中国の「智能化戦争」やロシアの選挙介入はその実例であり、注意経済による認知の疲弊と社会的分断が、その攻撃を助長している。
未来を形作る要素:認知戦争の展開を決定づけるシグナル
認知戦争の進化を促す二つの原動力は、認知科学の進歩と先端技術の発展である。神経科学は人間の意思決定の大部分が無意識のバイアスに依存することを明らかにし、生成AIやBMIなどの技術は、個人の心理データに基づく超個別化された操作を可能にする。近い将来、AR/VRと生成AIの組み合わせが、社会の「現実認識」そのものを分断する危険性をはらむ。
戦略構築:心を守るために
a. 脅威の認識と理解の醸成
認知戦争の概念理解は断片的であり、市民や政策立案者の認識向上が急務である。しかし、単に情報を疑うよう求めるのは懐疑心や無関心を招くため、「プレバンキング」のような、操作の手法を事前に学び、自ら見抜く力を養うアプローチが有効である。同時に、個人データの収集と悪用のリスクに関する教育も不可欠である。
b. 認知戦争とその実現技術のガバナンス
認知戦争の対策は個人のリテラシーに委ねるのではなく、政策立案者が包括的な法的枠組みを構築すべきである。EUのAI法は認知行動操作を目的とするAIの使用を禁止する先駆的事例であるが、ニューロテクノロジーなど新たな技術領域や、それらが兵器として使われるケースへの対応は不十分である。既存の国際法の適用を検討し、新たな国際的ルールの策定が必要である。
c. 新興技術の活用による民主主義的社会の回復力強化
認知戦争の脅威に対抗するには、社会の内的脆弱性(分極化、制度不信)そのものに対処する必要がある。興味深いことに、AIやVRなどの技術は、大規模な世論把握による熟議の促進や、没入型体験による無意識バイアスの訓練など、民主主義の回復力を高めるためにも活用できる。多様な関係者の協働による、テクノロジーを活用した社会の強化が求められる。
認知戦争という名の「新しい脅威」は本当に新しいのか?
by DeepSeek×Alzhacker
NATO報告書を読み解く
あの円卓会議の参加者リストを見てまず気になったのは、メンバーの構成だ。IE大学のセンターが主催し、ミュンヘン安全保障会議の枠組みで開催された——要するに、これは欧州の安全保障エスタブリッシュメントが公式に議論しているテーマだということだ。欧州委員会の上級副委員長マルグレーテ・ベスタガー氏や、NATO国防大学の研究者、さらにGoogle系シンクタンクJigsawのCEOまで参加している。官民の「適切な」人々が一堂に会している。
このメンバー構成自体が、すでに一つのメッセージだ。「認知戦争」という概念は、もはや一部の専門家の間の仮説ではなく、政策として具体化されつつあるテーマなのである。
報告書を読み進めると、著者らは「認知戦争」を「個人、集団、あるいは国民レベルの認知に影響を与え、保護し、または破壊し、敵対者に対して優位に立つことを目的とする一連の活動」と定義している。ここで早くも引っかかる。この定義、あまりにも広すぎないか? 広告も、政治キャンペーンも、宗教的教化も、子育てですらこの定義に含まれうる。定義が広ければ広いほど、規制や対策と称して様々な活動を対象にできる——これは権力側にとって便利な話だ。
報告書は、認知戦争を従来の心理戦やサイバー戦と区別する特徴として「無意識への焦点」を挙げている。意思決定の98%が無意識によって影響されているというカーネマンの研究を引用しながら、「認知攻撃は、私たちが何を考えるかではなく、どのように考えるかに影響を与える」と説明する。
ここで立ち止まって考えたい。確かに人間の認知にバイアスがあることは行動経済学の知見だ。しかし、それを「攻撃」と呼び、「戦争」という枠組みに押し込むこと自体が、一つの政治的選択ではないか。つまり、情報環境における様々な影響力の行使を「戦争行為」と再定義することで、それに対する対抗措置——監視や統制を含む——を正当化するレトリックとして機能する可能性がある。
次に、報告書が提示するテクノロジーの脅威シナリオを見てみよう。生成AI、BMI(ブレイン・マシン・インターフェース)、AR/VR技術の発展により、個人の神経データへのアクセスが容易になり、「個人の認識や感情そのものをハッキング」することが理論上可能になるという。
ここで具体的なエビデンスを確認したい。報告書は、スロバキアの選挙におけるAI生成偽音声の事例を挙げている。確かに、その偽音声が拡散されたことは事実だろう。しかし、「選挙結果に直接寄与した」という主張は、本当に実証されているのか? 報告書自身が「パンディットによれば」と曖昧なソースを示すにとどまっている。つまり、因果関係は確立されていない。
さらに、中国の「智能化戦争」概念についての記述も興味深い。人民解放軍の国防白書を引用しながら、「精神的優位の獲得」や「敵の認知への直接的影響力の行使」を中国の戦略と位置づける。ここで問題なのは、こうした引用が常に特定の解釈を通して提示される点だ。中国の軍事戦略文書には確かにそのような表現があるかもしれない。しかし、それが実際にどの程度具体化され、どの程度有効なのか——あるいは、西側の安全保障コミュニティが「中国脅威論」を強化するためにそうした文言を選択的に強調している可能性はないか。
報告書はロシアのIRA(インターネット・リサーチ・エージェンシー)による2016年米大統領選介入も例示する。ここで、より深い疑問が浮かぶ。もしロシアの関与が本当にあの選挙結果を左右するほどの影響力を持っていたなら、なぜその後の調査で「具体的な得票数の変化」は実証されなかったのか? 影響があったことは多くのメディアが報じたが、その影響の「大きさ」については驚くほど曖昧なままである。
このパターンに気づく。つまり、「脅威は存在する」という主張は繰り返されるが、その脅威の具体的な規模や実証された影響については、常に「さらなる研究が必要」とされ、明確な数字が提示されないのだ。
もう一つ、報告書の基盤となっている認識論的前提について考えたい。この文書は、人間の認知が操作可能であることを前提とし、その操作技術が急速に発展していると警告する。しかし同時に、その操作から市民を守るために「プレバンキング」(事前誤情報曝露訓練)や「リテラシー教育」を提案する。ここには巧妙な循環論法がある。つまり、「市民は簡単に操作される脆弱な存在だから守らねばならない」と言いながら、守る方法として「市民の認知を再訓練する」ことを提案する。これは、問題の原因と解決策が同じ土俵にあることを示している。
さらに気になるのは、報告書が提示する「解決策」の多くが、より高度なテクノロジーの活用を求めている点だ。AIによる世論把握、VRによるバイアス訓練、そして何より「多様なステークホルダーの協働」。具体的には、テクノロジー企業、政策立案者、アカデミアの連携が謳われる。つまり、問題を引き起こしている主体(テクノロジー企業や政府機関)が、解決策の中心にも位置づけられているのである。
ここで、日本の文脈に引き寄せて考えてみたい。日本でも「フェイクニュース対策」や「メディアリテラシー教育」の名目で、同様の動きが進行している。総務省の「プラットフォームサービスに関する研究会」や、警察庁の「偽情報対策プロジェクトチーム」などだ。これらの動きは一見すると中立的で公益的なものに見える。しかし、その背景にあるのは、情報空間における「秩序」の再定義と、その秩序を維持する主体としての政府・プラットフォーマーの役割強化ではないか。
もう一つ見逃せない点は、報告書が「民主主義の脆弱性」に言及しながら、その脆弱性の原因について深く掘り下げていないことだ。制度への信頼低下、社会の分極化、注意経済の弊害——これらは確かに現実の現象だ。しかし、なぜそうなったのか。新自由主義的グローバリゼーションの帰結なのか、既存メディアの機能不全なのか、あるいはより構造的な資本主義の変容なのか。この問いに対する分析がほとんどないまま、問題は「外部の敵による認知操作」に収斂されていく。
報告書は「国際的なルール形成」の必要性も強調する。EUのAI規制法案を「世界初の包括的AI法」として肯定的に紹介しながら、同様の国際的枠組みを提唱する。しかし、こうした「ルール」が実際に誰によって、誰のために作られるのか。国際交渉の場では、圧倒的にリソースを持つ大国や多国籍企業が有利である。結果として、形式上は多国間合意であっても、実質的には特定のアクターの利益を反映した「規制の輸出」になる可能性が高い。
ここで根本的な疑問に立ち返る。「認知戦争」という概念自体が、ある種の世界観を前提にしているのではないか。すなわち、情報環境は本質的に「戦場」であり、そこで活動するアクターは基本的に「敵」か「味方」か——という二項対立的な安全保障のロジックである。このロジックに立つ限り、情報空間におけるあらゆる影響力の行使は「攻撃」の文脈で理解され、それに対する「防御」としての監視や統制が正当化される。
しかし、現実の情報環境はもっと複雑だ。商業広告、政治宣伝、市民活動、学術的議論、娯楽——これらは明確に区別できない形で混ざり合い、相互に影響を与え合っている。その全体を「戦争」の枠組みで捉えることは、あまりに多くのものを切り捨てることにならないか。
もう一つ、報告書が全く触れていない視点がある。それは、西側民主主義国自身が長年にわたって行ってきた对外情報活動や心理戦の歴史だ。冷戦期のラジオ・フリー・ヨーロッパから、中東地域でのソーシャルメディアを活用した民主化支援まで、西側諸国もまた「認知領域」での活動を積極的に行ってきた。もし認知戦争が本当に問題なら、それは普遍的な基準で評価されるべきであり、特定の国家だけが問題視されるべきではないはずだ。
だが、この報告書のトーンは明らかに「彼ら(中国、ロシアなど)がやっていること」に対する警戒を中心に構成されている。つまり、同じ行為でも、誰が行うかによって評価が変わるというダブルスタンダードの匂いがする。
さて、ここまで読んでくれた読者なら、私がこの報告書を単純に否定しているわけではないことに気づくだろう。実際、生成AIやBMIなどの技術発展がもたらす潜在的なリスクは、真剣に検討する価値がある。問題は、そのリスクをどう定義し、誰が、どのような権限で、どのような方法で対処するか——この枠組み設定の部分なのである。
報告書の最後には、参考文献としてNATO文書や学術論文が列挙されている。一見すると学術的な裏付けはしっかりしている。しかし、ここでも考えたい。これらの研究の資金源はどこか? NATOの科学技術機構が主導する研究は、どの程度中立的と言えるのか? 安全保障政策に資することを目的とした研究が、安全保障政策を批判的に検証する視点を持ちうるのか?
この問いは、より大きな問題に通じる。すなわち、現代社会において「知識」の生産と流通は、特定の制度的・財政的基盤に依存している。そしてその基盤は、しばしば国家や大企業の戦略的関心と結びついている。私たちが「客観的事実」として受け取る情報の多くは、そのようなフィルターを通して選別され、加工され、提示されている可能性がある。
報告書の円卓会議に、本当の意味での批判的視点を持つ参加者はいたのだろうか? たとえば、商業データ収集と監視資本主義の構造を根本から問う哲学者や、プラットフォーマーのビジネスモデルそのものを批判的に分析する経済学者、あるいは情報統制の歴史を研究する歴史家は招かれていたのか? 参加者リストを見る限り、大半は現行のシステムの中でキャリアを築いてきた「内部者」である。彼らが現行システムの抜本的改革を提案するとは考えにくい。
ここで、私の思考は次の問いに至る。「認知戦争」という概念が政策課題として浮上してきたのは、なぜ今なのか? その背後にある地政学的・経済的要因は何か?
一つの仮説は、情報空間における覇権争いの激化である。GAFAに代表される米国テクノロジー企業が世界の情報インフラを支配する中で、それに対抗する勢力(中国のBATHなど)が台頭している。この構図の中で「認知戦争」という概念は、米欧の情報空間支配を正当化するイデオロギー装置として機能しうる。すなわち、自分たちの情報活動は「自由で開かれた社会の防衛」であり、相手の活動は「認知戦争」というラベリングを行うことで、非対称な評価を制度化するのである。
もう一つの仮説は、国内の社会統制の強化である。ポピュリズムの台頭や社会の分断が進む中で、既存のエリート層は情報空間の「秩序維持」に関心を持つ。批判的言論や反政府的な情報流通を「外部勢力による認知操作」と結びつけることで、それらに対する規制や監視を正当化できる。これは歴史的に見れば、いわゆる「赤狩り」や「内部の敵」探しの現代版とも言える。
これらの仮説は、もちろん確証された事実ではない。しかし、報告書が提供する情報だけでは、これらの可能性を排除できない。むしろ、報告書の構成自体が、こうした批判的視点を排除するように設計されているようにも見える。
さて、ここで具体的な提言に目を向けよう。報告書は三つの優先行動分野を提示する。①脅威の認識と理解の醸成、②認知戦争と実現技術のガバナンス、③新興技術の活用による民主主義の強化——である。
①の「プレバンキング」やリテラシー教育については、一見すると無害で有益に見える。しかし、誰が「正しい情報」と「誤情報」を判定するのか? その基準は透明性をもって公開されるのか? 判定に誤りがあった場合の救済措置は? こうしたガバナンスの根本的問題がすっぽり抜け落ちている。
②の法的枠組みについては、「国際的なルール形成」が提唱されるが、具体的なルールの内容には踏み込まない。これは常套手段である。抽象的な合意は得やすくとも、具体的な規制内容になると利害対立が顕在化する。つまり、「ルールが必要だ」という合意だけを取り付け、実際のルール作りは後日、閉ざされた交渉の場で行う——というシナリオが見える。
③の「テクノロジーによる民主主義の強化」は、最も警戒すべき部分だ。問題の原因であるテクノロジーを、解決策として再び投入する。このループからは、テクノロジーへの依存がますます強まるだけで、根本的な問い——そもそもなぜ私たちはこれほどまでにテクノロジーに依存する社会を築いてしまったのか——には決して到達しない。
最後に、報告書の冒頭にある「謝辞」をもう一度見てみよう。執筆を指導したのはIrene Blázquez NavarroとCarlos Luca de Tenaという人物だ。ミュンヘン安全保障会議の関係者にも謝辞が述べられている。つまり、この文書はアカデミックな独立研究というより、安全保障政策コミュニティとの緊密な連携のもとに作成された政策提言書なのである。その意味で、この文書自体が一種の「認知工作」の産物である可能性もある。すなわち、特定の脅威認識を社会に浸透させ、特定の政策対応を誘導することを意図した文書である可能性を否定できない。
もちろん、これは「この報告書は嘘だ」と言っているのではない。事実として記載されていることの多くは、それなりに正確だろう。問題は、何が書かれ、何が書かれていないか、どのように枠組みが設定され、どのように結論が導かれているか——というレトリックの次元なのである。
この報告書を読んだ典型的な読者は、おそらく次のような感想を持つだろう。「テクノロジーの進歩はすごいスピードだ。中国やロシアは怖い。私たちも対策を考えなければ」。そして、提示された対策——リテラシー教育や国際的ルール作り——は、どれも「もっともな」ものに映る。ここに、この種の政策文書の巧妙さがある。つまり、恐怖をあおりつつ、その解決策として「責任ある主体」による管理と統制を自然な選択肢として提示するのである。
だが、一歩引いて考えてみたい。本当に私たちが恐れるべきは、外部の敵による認知操作だけなのだろうか。それとも、恐怖そのものを操作し、特定の政策を正当化するこの種のレトリックそのものに、より深い警戒が必要なのだろうか。
情報環境の複雑さ、人間の認知の脆さ、テクノロジーの加速度的発展——これらは確かに現実の課題だ。しかし、その課題への対応として、さらに強力な監視や統制の仕組みを導入することが、本当に自由で開かれた社会を守ることにつながるのか。むしろ、私たちが守ろうとしている「民主主義」の本質的な価値——批判的討議、多様な意見の共存、権力の監視——を損なう方向に作用しないか。
この問いに対する答えは、この報告書の中にはない。そしておそらく、この種の政策文書にそれを求めること自体が、筋違いなのかもしれない。政策文書は、特定の政策を推進するために書かれる。その目的に沿わない視点や問いは、最初から排除されているのである。
だからこそ、私たち読者には、文書を「読む」技術が求められる。何が書かれているかを正確に理解すると同時に、何が書かれていないか、なぜそれが書かれていないかを考える。著者の前提を探り、その前提がどのような帰結をもたらすかを想像する。そして何より、自分自身の判断を留保し、常に問い続けること。
この報告書は、そうした読解の訓練材料として、実に豊かなテキストである。認知戦争という新しい概念を通して、私たちは情報社会の本質的な問題——誰が、どのように、何のために情報をコントロールするのか——を考えるきっかけを得ることができる。
その意味で、この文書の価値は、その内容そのものよりも、それが引き起こす問いの中にあるのかもしれない。