Contents
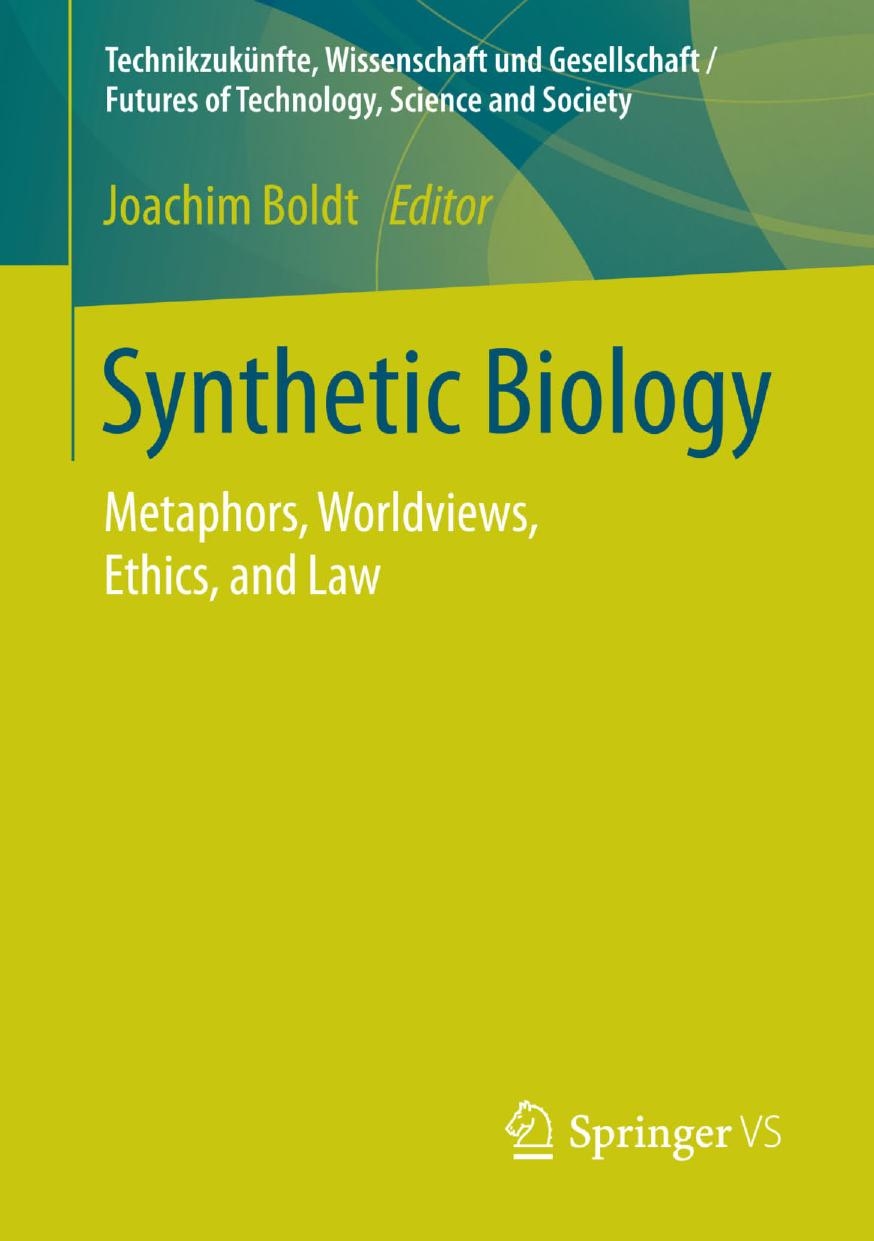
Synthetic Biology Metaphors, Worldviews, Ethics & Law-VS Verlag für Sozialwisse
技術・科学・社会の未来
編集:A. グルンバルト、カールスルーエ、ドイツ
R. ハイル(ドイツ・カールスルーエ)
C. コーネン(ドイツ、ハイデルベルク)
バイオ、情報、ナノの神経技術やロボット工学のような技術科学における議論は、さまざまな視点や関心によって、まず第一に、科学技術的な発展に関する広範な話題が提示される。このような未来は、ひとつには技術革新の到達点、その成果、そしてその結果であり、また、ひとつには科学的アジェンダの構築である。その一方で、科学技術的な進歩は、新たな未来と他の社会的な影響をもたらすものである。本シリーズは、自然科学と技術の社会的・文化的発展、その成果の社会における実践、そして私たちの人間像への影響に焦点を当てている。
この学際的なシリーズ本は、科学的・社会的コンテクストにおけるテクノロジーの未来に焦点を当てている。第一に、科学技術の幅広い発展に光が当てられること、第二に、バイオテクノロジー、情報技術、ナノテクノロジー、ニューロテクノロジー、ロボット工学などの技術科学分野の議論は、多くの視点や関心に影響されている。一方では、これらの未来は、科学的アジェンダを形成することなどによって、進歩のあり方やその結果・結末に影響を与える。他方、科学技術の革新は、社会にとってさまざまな意味を持つ新しい未来を構想する機会を提供する。この相互性を反映し、このシリーズでは主に、科学技術が社会的・文化的にどのような影響を受けるか、その結果が社会でどのように責任ある形で形成されうるか、そして科学技術が人類像にどのような影響を与えるかに焦点を当てる。
物理学者、数学者、哲学者であるアーミン・グリュンヴァルト教授は、カールスルーエ工科大学(KIT)で技術哲学と技術思想を学び、カールスルーエのITAS(技術情報分析・システム分析研究所)所長、ベルリンのTAB(ドイツ連邦議会技術情報分析委員会)委員を務める。/ 物理学者、数学者、哲学者であるアルミン・グリュンヴァルト教授は、カールスルーエ工科大学(KIT)で技術の哲学と倫理を教えており、カールスルーエの技術評価・システム分析研究所(ITAS)とベルリンのドイツ連邦議会技術評価局(TAB)の所長を務めている。
ラインハルト・ハイル(哲学者)はKIT-ITASの研究員である。/ ラインハルト・ハイル、哲学者、KIT-ITASの研究員。
クリストファー・コーネン(政治学者)はKIT-ITASの研究員であり、「ナノ倫理」誌の編集者でもある: KIT-ITASの研究員であり、「ナノ倫理:新・新興テクノロジー研究」誌の編集者でもある。/ クリストファー・コーネン(政治学者)はKIT-ITASの研究者であり、雑誌「NanoEthics: Studies of New and Emerging Technologies」の編集長である: 新・新技術研究』誌の編集長を務める。
ヨアヒム・ボルト(編)
合成生物学
メタファー、世界観、倫理、法律
アルベルト・ルートヴィヒス・フライブルク大学
フライブルク(ドイツ)
本書における一般的記述名、登録名、商標、サービスマーク等の使用は、具体的な記述がない場合でも、そのような名称が関連する保護法および規制から免除されており、したがって一般的な使用が自由であることを意味するものではない。出版社、著者および編集者は、本書における助言および情報が、出版日現在において真実かつ正確であると信じられていると考えて差し支えない。出版社、著者、編集者のいずれも、本書に含まれる内容、あるいは誤りや脱落に関して、明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証も行わない。
著者:フランク・シンドラー、モニカ・ミュールハウゼン 無酸性紙に印刷されている。
シュプリンガーVSはシュプリンガー・ファッハメディエン・ヴィースバーデンのブランドである。
Springer Fachmedien WiesbadenはSpringer Science+Business Media (www.springer.com)の一部である。
序文
本書で紹介する成果、議論、論文は、「エンジニアリング・ライフ」プロジェクトの中で展開され、議論されてきたものである: 合成生物学の倫理に対する学際的アプローチ)」プロジェクトにおいて開発され、議論されてきた。このプロジェクトはドイツ研究教育省(助成金番号01GP1003)の資金援助を受けている。このプロジェクトには以下の貢献者が参加している。登場順に記す: Joachim Boldt, Oliver Müller, Harald Matern, Jens Ried, Matthias Braun, Peter Dabrock, Tobias Eichinger, Jürgen Robienski, Jürgen Simon, Rainer Paslack, Harald König, Daniel Frank, Reinhard Heil, Christopher Coenen.
Jan C. Schmidt, Bernadette Bensaude Vincent, Johannes Achatz, Iñigo de Miguel Beriain, Sacha Loeve, Christoph Then, Bernd Giese, Henning Wigger, Christian Pade, Arnim von Gleichが、ドイツのフライブルク大学での会議の締めくくりとして、さまざまな機会に参加してくれた。
すべてのプロジェクト・パートナーと貢献者の協力に感謝したい。合成生物学に関する哲学的、倫理的、法的、社会科学的研究に従事する機会を与えてくれたドイツ研究教育省に感謝する。また、フライブルク大学の生物シグナリング研究センター(BIOSS)の親切な支援にも感謝したい。
本書の英文スタイル、文法、スペルを巧みに調整してくれたスーザン・ケラー、書誌スタイル、引用、レイアウトを正確に統一してくれたセバスチャン・ヘップフルに特に感謝する。
フライブルク、2015年8月28日 ヨアヒム・ボルト
目次
- スイス時計、遺伝子機械、そして倫理。合成生物学の概念的・倫理的課題への序論 ヨアヒム・ボルト
- I 概念、メタファー、世界観
- 後期近代技術の哲学。合成生物学の明確化と分類に向けて ヤン・C・シュミット
- 合成生物学。認識論的ブラックボックス、人間の自己肯定感、実践と価値の混成性について オリバー・ミュラー
- 生きている機械。シンセティック・バイオロジーを代表するメタファーの創世記と体系的意味合いについて ハラルド・マターン、イェンス・リード、マティアス・ブラウン、ピーター・ダブロック
- 生産生物学。合成生物学における行動パラダイムの要素と限界トビアス・アイヒンガー
- 創造性とテクノロジー。共同創造者としての人間 ハラルド・マターン
- 合成生物学の道徳的経済 ベルナデット・ベンサウデ・ヴィンセント
- 生物学的人工物を評価する。技術哲学における合成細胞 ヨハネス・アチャッツ
- II 公共財と私的所有。社会的・法的影響
- 合成生物学の法的側面
ユルゲン・ロビアンスキー、ユルゲン・サイモン、ライナー・パスラック - シンバイオと知的財産権:私的所有権と公共の利益の適切なバランスを探る イニーゴ・デ・ミゲル・ベリアイン
- 合成生物学の法的側面
- III 機会、リスク、ガバナンス
- 統一を超えて: 合成生物学における多様性の育成とその公共性 Sacha Loeve
- 合成ゲノム技術 クリストフ・ゼン
- 合成生物学の有望な応用例と、その潜在的な落とし穴を回避する方法 Bernd Giese, Henning Wigger, Christian Pade and Arnim von Gleich
- 合成生物学がもたらす多面的な利益とリスク:ガバナンスと政策への示唆 ハラルド・ケーニッヒ、ダニエル・フランク、ラインハルト・ハイル、クリストファー・コーネン
- 寄稿者
スイス時計、遺伝子機械、そして倫理 合成生物学の概念的・倫理的課題への序論
ヨアヒム・ボルト
1 新興テクノロジーの新規性と概念的枠組み
新興テクノロジーには歴史がある。何もないところから出現するのではなく、徐々に、そして継続的に発展していく。合成生物学も例外ではない。合成生物学は遺伝子工学に根ざしており、多くのオブザーバーは、合成生物学は遺伝子工学の新しいラベルに過ぎないと主張している。
したがって、必然的な疑問が生じる。それは、新たな技術とは実際にはどのようなもので、どのような場合にすでに知られている技術を徐々に発展させたものに過ぎないのか、ということである。その答えの一端は、その技術そのものにあるのではなく、その技術を取り巻く利害関係にある。新技術とされるものには、新たな経済的・社会的機会、そして新たなリスクが伴う。つまり、助成金を得ようとする研究者にとっては、新しいレッテルは好都合なのだ。同時に、技術批評家にとっても好都合である。
繰り返すが、合成生物学もその例外ではない。科学者たちは、いわゆる伝統的な遺伝子工学と区別するために「合成生物学」というラベルを使っているが、これは合成生物学が非伝統的で、現代的で、特に能力の高い技術であることを意味している(Knight 2005)。一方、ETCグループのようなNGOは、この新しいラベルを「極端な遺伝子工学」と同一視している。「極端な」という形容詞は、非常に危険な事業を連想させる表現である(ETC 2007)。確かにそうかもしれないが、それにもかかわらず、新たな新興技術というラベルの形成を、付随する利害関係だけで説明するのは言い過ぎである。技術そのものは徐々に発展していく過程にあるとしても、こうした技術を理解し、さらに発展させる方法や、技術が形成される際の概念は、飛躍的に変化する可能性がある。人間は真理を求める動物であり、どのような概念が研究対象や研究意図の真の記述に最も近いかを理解することは、科学技術と恣意的にしか結びつかない経済的利益やその他の利益と同様に、技術のさらなる発展に影響を与える。合成生物学の主流は、このような概念的枠組みの転換を取り入れたものである。試行錯誤に導かれる遺伝子工学から、コンピューター上で全ゲノムを構築できる合理的な設計プロセスへの移行を目指している。高速で安価な全ゲノム配列決定、信頼性が高く安価な遺伝子合成、そしてCRISPR/Cas9のような非常に効果的なゲノム編集法が、こうした目標を実現する道を開いている。
複雑な実体を合理的かつ確実に設計し組み立てるには、その部品の挙動に基づいて複雑な実体の挙動や機能を予測できることが前提となる。私たちが経験から知っているように、多くの人工的な技術的対象はこの要件を満たしている。しかし、生物となると話は別である。結局のところ、生物は進化的変化を受け、環境と多面的に相互作用し、その一部、つまり私たち自身にさえ意思の自由があるのだ。したがって、生き物が確実に設計できると仮定することは、生き物の振る舞いはその物理的部分の振る舞いで説明できると主張する存在論的仮説に等しい。
それ自体、この概念フレームは新しいものではない。少なくとも17世紀のデカルト哲学やルネサンス期の機械的動物モデルにまで遡ることができる。しかし、20世紀にDNAが発見され、今日のような高度なゲノム編集が可能になるまで、長いDNA配列や全ゲノムを意図的に構築・再構築することは不可能だった(Keller 2002)。今日、このような前提が、認識論的、すなわち真理に関連する概念フレームを形成し、合成生物学を形成し、未来へと導いている。このフレームは、従来の遺伝子工学の指導的前提や目標とは異なっており、より体系的でなく、工学的・デザイン的志向も低い。なぜ合成生物学が独自のレッテルを貼られるのかを網羅的に説明するための決定的な要素を加えているのは、まさに合成生物学特有の概念フレームなのである。
DNAの構築と再構築は、機械的な動物の構築とは異なる。機械的な動物は、その物理的な部分が自然な生物の部分と異なるため、自然な動物に類似しているとは考えられるが、同一ではないことは確かである。対照的に、単細胞生物の合成ゲノムを構築することは、自然生物を構成するパーツを組み立てることに等しい。繰り返しになるが、機械的な動物とは対照的に、合成生物学によって生み出される生物は、その物理的性質や、想定されるようにその創発的性質に関して、自然の生物と見分けがつかないような合成生物は、準機械的な対象として適切に理解できるのかという疑問を抱かせる。
合成生物学の生物は、人工的な物体と自然な生物との間にある不思議な空間に生息している。生物を準機械的な物体として概念化することが適切であるならば、合成生物学は、生物は非生物とは異なるものであり、非生物以上の存在であるという、合成生物学から見れば間違っているはずの、私たちの深く根付いた日常的理解を最終的に揺るがす技術である。さらに、合成生物学の概念フレームは、この技術が倫理的・社会的に与える影響の捉え方にも関わってくる。特に技術開発の初期段階において、こうした影響を特定し、指摘し、考慮することは、生命倫理学、社会科学、哲学、神学の重要な課題である1。
2 合成生物学、ナノテクノロジー、そして概念上の課題
対象物の基本的な部分に隠された秘密を明らかにするという探求において、合成生物学はナノテクノロジーに似ている。ナノテクノロジーもまた、部品の配置を変えることで複雑な物体を構築・再構築できるというアイデアに突き動かされている。米国国家科学技術会議(NSTC)の報告書『ナノテクノロジー』のタイトルは、「原子ひとつひとつで世界を形作る」である。Shaping the world atom by atom “というタイトルは、この並列性を物語っている。しかし、合成生物学とは異なり、ナノテクノロジーは文字通り機械の工学を目的としている。ナノスケールの工学的対象は、原子レベルで組み合わされた非生物的な存在である。NSTCは、この理想の科学的実現可能性を評価するために多大な努力を払っているわけではなく、ナノスケールの物体を「スイスの時計」に端的に例えている: 「数世紀前のスイスの時計職人の製品でさえ、物質世界に対する人間の制御がミリメートル・スケールまで1000分の1に拡張されたことを証明した。過去数十年の間に、研究者たちはこの制御をさらに100倍に押し下げた」(NSTC 1999, p.5)。
これとは対照的に、合成生物とは、ナノスケールのDNA構成要素が斬新な方法で再配列された生物のことである。合成細胞は、「エリック・ドレクスラーや多くのナノテクノロジー愛好家の夢である、一般的なナノテク・アセンブラーを最大限に活用したもの」(Church and Regis 2012, pp.53f.)と考えることもできるが、合成細胞そのものは、一般的に定義されるナノテクノロジー製品ではない。非生物分子から機能的な細胞を組み立てることを想定したとしても、それは合成生物学の仕事であり、ナノテクノロジーの仕事ではない。ナノテクノロジーの中で最も生物学に近い分野であるナノバイオテクノロジーは、生物学的分子を利用する、あるいは生物学的分子に着想を得た、ナノスケールの機械、すなわち非生物的物体の工学からなる。
倫理的な観点から見ると、ナノテクノロジーとナノバイオテクノロジーは、技術管理とリスク評価の問題を含んでいる。ナノテクノロジーに直面したとき、私たちは「私たちがやろうとしていることを、責任を持って行うことができるのか」と問わねばならない。合成生物学はさらに、「生物界と非生物界を概念的にアライメントするとき、私たちは自分たちが何を言っているのかわかっているのだろうか?」合成生物学-バイオナノテクノロジー-は、リスク評価だけでなく、概念やメタファーの使用に関しても挑戦的な事業である。ナノテクノロジーと合成生物学をこのように区別するならば、その区別は、非生物と生命体の違いが可能な限り明確であるかどうかにかかっている。この区別が日常的に自明であるにもかかわらず、何が生物世界を非生物の世界から区別しているのかを正確に説明しようとする試みは、哲学的・科学的思考が古くから始まって以来、哲学者や科学者を忙しくさせてきた。
生物学の教科書は通常、何を生命とみなすかについて公開リストを示している。例えば、代謝、恒常性、成長、刺激反応、生殖、適応と進化などである。これらの基準を説明し、分類するために必要かつ適切な性質を探すと、しばしば「自己組織化」や「自己保存」といった概念に行き当たる(Bensaude Vincent 2009)。ここで “self “という接頭辞が重要な意味を持つのは、生物の行動は純粋に因果関係を決定する力だけでは説明できず、自分以外の何かに反応するという概念を含む必要があるという考えを表しているからである。生きているものは、因果的な説明からテロス志向のものへとシフトする必要がある、と考えられている(Boldt 2013)。
どのような能力がこのようなテロス志向の説明スキームへの移行を正当化するのか、またその存在を確実に検出できるのかどうかは、依然として議論の余地がある。とはいえ、生物と非生物の間に違いがあると主張するのであれば、その違いはこのような概念の観点から説明されなければならないだろう。少なくともヒューリスティックには、合成生物学自体がその区別を維持している。合成生物学は、生命の分子基盤を再構築し、再発明することを明確に目指したバイオテクノロジーである。代謝を持ち、繁殖し、進化的変化を遂げる物体は、非生物テクノロジーよりも効率的で強力な技術ツールとなりうるからである。同時に、これらの特性には代償が伴う。成長はエネルギーを消費し、生殖は信頼できない可能性があるという事実に加え、進化は、技術者の最初の計画や意図から、人工物の行動や発展がある程度独立することを意味する。
合成生物学の概念フレームを適用すると、上記の点の妥当性が過小評価される可能性がある。合成生物学が単一の応用を評価できる段階まで進歩していない限り、この技術の概念的枠組みを分析し、その限界を説明し、代替的な説明と比較することは、生命倫理の最も重要な課題の一つである。合成生物学の工学的・機械的枠組みと、合成生物学者がそれに寄せる信頼は、次のような記述に示されるように、確かにそのような精査に値する:
元来、生物は、進化のランダムな働きから生じる固有の設計上の欠陥や限界、妥協や複雑さをすべて抱えたまま、そのまま受け入れるしかなかった。今、私たちは実際に生命システムを事前に計画し、設計し、私たちの願望に従って構築し、意図したとおりに作動することを期待することができる–あたかもそれらが実際に機械であるかのように(Church and Regis 2012, p.182)。
明らかなように、機械のメタファーと合成生物学の工学的枠組みは、合成生物学の能力、そしてその対象物の機能や挙動に対する見方を形成している。冗長に見えるDNAセグメントや、不必要に複雑に見えるDNA発現経路は、詳細な分析を必要とするものではなく、欠陥として分類される。同じように、合成生物の将来の行動や発達は、予期せぬ進化的変化の可能性を無視し、技術者の意図に沿って安全に行われると考えられている。合成生物学者であるド・ロレンゾとダンチンは、予測可能な性質と行動を持つ信頼性の高い合成生物を設計する合成生物学の一般的かつ長期的な能力について楽観的な見通しを共有しているが、彼らの研究分野の主流である概念フレームに異議を唱えている。例えば、遺伝子発現に関する工学的メタファーは、「電気工学的概念を、生物学的と思われる対応物に、直線的かつあからさまに単純化して投影したものである」と彼らは書いている(Lorenzo and Danchin 2008, p.824)。
3 合成生物学と既存の遺伝子組み換え作物規制
現在のシンバイオの概念フレームが倫理的・社会的に及ぼす可能性のある影響について詳しく述べる前に、合成生物学の出現は、国内外に存在する既存の法律や規制の中で起こっていることを指摘しておく。大げさな約束や期待はともかく、合成生物学は確かに近い将来、有用な応用を提供するかもしれない。医療分野には有望なアプローチがあり、エネルギーと環境はさらなる応用分野である2。合成生物学の短期的な応用に関しては、関連する分野は、既存の国内または国際的な規制によってかなりの程度カバーされている3。
しかし、長期的には、合成生物学の研究課題によって、確立されたリスク評価手続きや現行の規制の適用範囲外となる製品が生み出される可能性がある。例えば、ゲノムが多数の異なる供給源に由来する合成生物は、リスク評価の課題を悪化させる。遺伝子組換え生物に対する確立されたリスク評価手続きは、天然の対応生物の既知の挙動とリスクプロファイルの評価に依存している。合成生物のゲノムが、もはやどの天然種のゲノムにも似ていない場合、この種のリスク評価手順の基礎は欠落している。さらに、合成生物学者がいつか非天然のDNA分子のみを含む合成細胞を作製したとしても、そのような生物を「遺伝子組み換え生物」として分類することは難しいだろう。おそらくそのような生物は、現行の遺伝子組み換え作物規制の範囲には入らないだろう(Pauwels et al.)
どのような場合でも、遺伝子組み換えや置換が包括的になればなるほど、リスクを評価し、既存の規制を適用することは難しくなる。リスク評価の難題を解決する1つの方法は、すべての新規合成生物に類似した既知の前身があることを確実にするために、段階的なゲノム変更を奨励することかもしれない。非天然DNA生物に関しては、法的規制の変更は避けられないだろう。
4 シンバイオの物語、倫理、研究アプローチの多様性
法的・倫理的基準に従って応用を評価することは、倫理的・社会的・政治的に重要な課題であるが、それだけではない。合成生物学の強力な自己物語が、この新たな技術の未来とその対象に対する認識を形成していることを考えれば、この物語そのものとその限界、そして合成生物学がどのようなものであり、どのようなものになる可能性があるかについての代替的な説明に注意を払うことも同様に重要である。
機械というメタファーが持つ制約と、合成生物学の工学的枠組みは、倫理的にも関連している。例えば、合成生物によってもたらされる既存の生態系への脅威をどのように評価するかは、とりわけ、合成生物種の発生をどれだけ正確に予測できるかに左右される。別の例を挙げれば、デザイン&エンジニアリングのアプローチに沿って考えることは、合成生物学を単細胞生物の工学に限定するものではない。それどころか、合成生物学が技術的に実現可能になり次第、その範囲をヒトを含む高等生物にまで拡大することを期待するのは、この観点からすれば当然のことのように思われる。争点となる生物中心主義者の視点に立てば、固有の価値や道具化に関する倫理的な問題は、生物自体の目的や利益に合致しない目的に従って、生き物が技術的介入の対象とされるときはいつでも、大なり小なり関係してくる(Deplazes-Zemp 2012)。とはいえ、人間について考えるとき、生物中心主義か人間中心主義かという倫理的基盤にかかわらず、必然的に道具化の問題が関係してくる。機械としての生物という立場では、こうした問題を認識し理解することは難しく、ましてや取り組むことはできない。
現在のシンバイオの自己物語とその限界、そして合成生物学とは何かについての代替的な説明に注意を払うことは、今日見られるような強力な設計と工学の枠組みに重きを置かない合成生物学の説明を発展させることに貢献するだろう。合成生物学を、第二の自然を合理的にデザインする技術として理解する必要はない(Keller 2009)。合成生物学は、自然生物やDNAの自然な変化のプロセスに触発され、それを模倣する技術という枠組みで捉えることもできる。このような解釈とその応用の理想は、例えば、安全性への懸念を和らげるのに役立つだろう。また、合成生物学を、生命現象に本質的に結びついている進化や成長といった、エネルギーを消費し、制御が困難なプロセスに頼ることなく、DNAとその産物を利用することを目的とした技術として想定することもできる(Giese and Gleich 2014)。この場合、無細胞システムは合成生物学の申し子に数えられるだろう。繰り返しになるが、このアプローチは、合成生物と比較した場合、より安全であると見なされるかもしれない。また、単細胞生物に新規の合成ゲノムを搭載したら、次は動物やヒトが登場するのではないかという懸念に陥る可能性も、無細胞のアプローチの方が明らかに低い。
合成生物学の核心的な目的と源泉を説明する代替的なストーリーの探求が意味するのは、研究課題と研究アプローチの多様化である。また、代替的な説明を展開することは、合成生物学の出現に伴う大きな期待や約束を視野に入れることにもつながる。合成生物学が、自分の望みに完全に合致した生命を工学的に作り出すために、自然の生物やDNAの限界から自らを解き放つことではない(少なくとも、必ずしもそれだけではない)とすれば、合成生物学はむしろ、他の技術的手段や社会的手段の中の一つの技術的手段と見なすことができるだろう。このような見方は、合成生物学そのものと同様に、社会的議論からも有益なものとなるだろう。
5 終わりに
文字通りであれ概念的であれ、生きた自然を道具に変えようとするとき、私たちは結局のところ、自らの起源を道具に変えてしまうことになる。この計画の矛盾は、私たち自身の本性にこの計画を向けるとき、最もはっきりと前面に現れる。私たちは常に、私たちの自然の主体であると同時に客体でなければならない。この現実に気づかないことで、自らの発展を恣意的な目的に固定してしまう危険性がある。その結果、恣意的な目的の犠牲になりやすくなる。
人間以外の生命の世界から自らを切り離すことは簡単だ。しかしそれでも、その世界は私たちを生んだ。そこには、人間として最高の能力の種がすべて含まれているのだ。この世界が、他にどのような価値ある状態をもたらすかはわからない。もし私たちが自然の目的を私たち自身の目的に固定しようとするなら、私たち自身の不利な点として、生物の重要な発達特性を見逃し、予期せぬ価値を持つ多くの源の進化を妨げるかもしれない。それは、合成生物学が必要とするものでも、そうあるべきものでもない。
