Contents
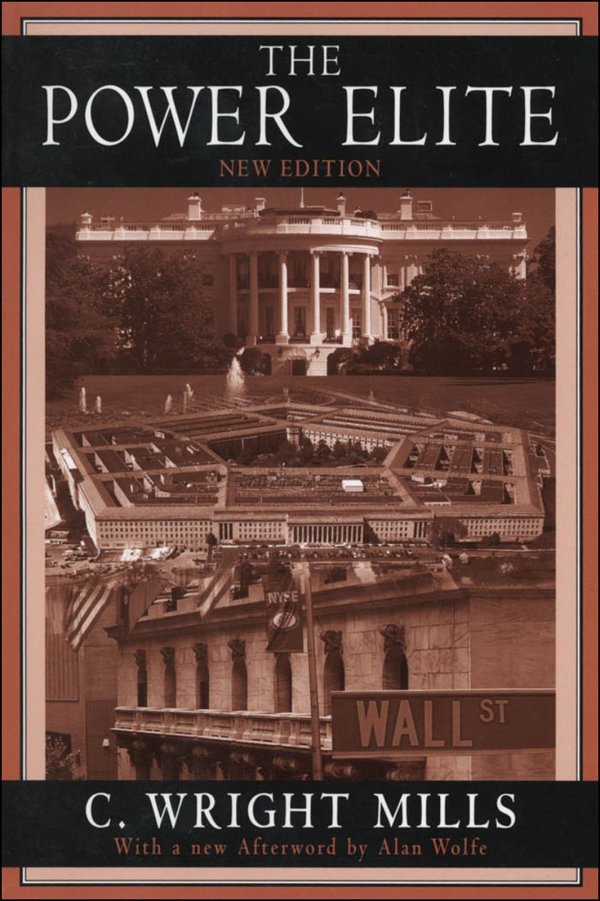
パワーエリート
アラン・ウルフによる新しいあとがき付き
初版は1956年にニューヨークのオックスフォード大学出版局から出版された。
1959年、オックスフォード大学出版局ペーパーバックとして初版発行。
米国議会図書館目録データ Mills, C. Wright (Charles Wright), 1916-1962.
パワーエリート / C. ライト・ミルズ; アラン・ウルフによる新しいあとがき付き。
原著:1956年。
目次
- 1 高次サークル
- 2 ローカル・ソサエティ
- 3 メトロポリタン400
- 4 セレブリティ
- 5 大金持ち
- 6 最高経営責任者
- 7 企業富裕層
- 8 軍閥
- 9 軍事的地位の上昇
- 10 政治家
- 11 バランス理論
- 12 パワーエリート
- 13 大衆社会
- 14 保守ムード
- 15 高次の不道徳
- あとがき
- 謝辞
- 注釈
1. 高次のサークル
しかし、仕事、家族、近所付き合いといった日常生活の中でさえ、理解することも支配することもできない力によって動かされているように見えることがしばしばある。「大きな変化」は彼らの手に負えないが、それにもかかわらず彼らの行動や見通しに影響を与える。現代社会の枠組みそのものが、彼らを自分たち自身のプロジェクトではなく、大衆社会の男女のプロジェクトに押し込めているのだ。
しかし、すべての人がこのような意味で平凡なわけではない。情報と権力の手段が中央集権化されるにつれて、アメリカ社会で、いわば俯瞰できるような地位を占めるようになり、その決定によって、普通の男女の日常生活に大きな影響を与えるようになる。彼らは仕事によって成り立っているのではなく、他の何千もの人々のために仕事を作り、また壊し、単純な家庭の責任に縛られることもなく、逃げることもできる。彼らは多くのホテルや家に住んでいるかもしれないが、ひとつの共同体に縛られることはない。彼らは単に「その日、その時の要求を満たす」だけでなく、ある部分では、これらの要求を作り出し、他の人々に要求を満たすよう仕向けるのである。彼らがその力を公言しようがしまいが、彼らの技術的、政治的経験は、その下にいる人々のそれをはるかに凌駕している。ジェイコブ・ブルクハルトが「偉人」について言ったように、アメリカ人の多くはエリートについてこう言うかもしれない。
パワーエリートは、普通の男女の普通の環境を超越することができる立場にある人々で構成されている。彼らがそのような決定を下すか下さないかは、彼らがそのような極めて重要な地位を占めているという事実よりも重要ではない。彼らが行動を起こさないこと、決定を下さないこと、それ自体が、しばしば彼らが下す決定よりも大きな結果をもたらす行為なのである。なぜなら、彼らは現代社会の主要な階層と組織の指揮を執っているからだ。彼らは大企業を支配している。国家の機構を動かし、その特権を主張する。軍事組織を指揮する。彼らは社会構造の戦略的な司令塔を占め、そこに権力と富と名声を享受するための有効な手段が集中している。
パワーエリートは孤独な支配者ではない。アドバイザーやコンサルタント、スポークスマンやオピニオンメーカーが、彼らのより高度な思考と決断のキャプテンであることが多い。エリートのすぐ下には、議会や圧力団体、町や都市や地域の新旧の上流階級など、権力の中間に位置するプロの政治家たちがいる。彼らに混じっているのは、これから説明するような不思議な方法で、絶えず見せられることで生きているが、有名人であり続ける限り、決して十分に見せられることのない職業的有名人たちである。そのような有名人は、支配的なヒエラルキーの頂点にいるわけではないが、大衆の注意をそらしたり、大衆にセンセーションを与えたりする力を持っている。多かれ少なかれ、道徳の批評家として、権力の技術者として、神の代弁者として、大衆の感性の創造者として、このような有名人やコンサルタントは、エリートのドラマが演じられる直接的な場面の一部である。しかし、そのドラマそのものは、主要な組織のヒエラルキーの司令塔が中心なのである。
1. エリートの本質と権力に関する真実は、事情通が知っていても口外しない秘密などではない。そのような人々は、一連の出来事や決定における自らの役割について、実にさまざまな理論を持っている。多くの場合、彼らは自分の役割について不確かであり、さらに多くの場合、恐怖や希望が自分の力の評価に影響を与える。自分の実際の力がどれほど大きくても、それを利用しようとする他人の抵抗に比べれば、それをあまり鋭く意識しない傾向がある。さらに、アメリカの政治家の多くは、パブリック・リレーションズのレトリックをよく学んでおり、場合によっては、自分ひとりでいるときにそれを使うことさえある。行為者の個人的な意識は、高次のサークルを理解するために調べなければならないいくつかの情報源のひとつにすぎない。しかし、エリートは存在しない、少なくとも重要なエリートは存在しないと考える人の多くは、自分自身について信じていること、少なくとも公の場で主張していることを論拠にしている。
漠然とではあるが、アメリカには現在、非常に重要でコンパクトかつ強力なエリート層が存在していると感じている人々は、しばしばそのような感覚を、現代の歴史的傾向に基づいている。たとえば、彼らは軍事的な出来事の支配を感じており、そこから将軍や提督、そして彼らに影響された他の意思決定者たちが絶大な力を持っているに違いないと推測する。議会がまたもや、戦争か平和かという問題に明らかに関係する決定を、一握りの人物に委ねたと聞く。彼らは、原爆がアメリカ合衆国の名において日本に投下されたことを知っている。彼らは、自分たちが大きな決断を迫られている時代に生きていると感じている。したがって、現在を歴史として考えるとき、その中心で決断を下したり下せなかったりしているのは、権力のエリートたちに違いないと推測する。
一方では、歴史的大事件についてこのような感覚を共有する人々は、エリートが存在し、その権力は大きいと仮定する。他方、大きな決断に関わったと思われる人物の報告に注意深く耳を傾ける人たちは、決定的な結果をもたらす力を持つエリートが存在するとは信じていないことが多い。
どちらの意見も考慮しなければならないが、どちらも適切ではない。アメリカのエリートの力を理解する方法は、出来事の歴史的なスケールを認識することだけにあるわけでも、明らかな決断を下した人物が報告する個人的な意識を受け入れることだけにあるわけでもない。このような人物の背後には、そして歴史の出来事の背後には、両者を結びつける現代社会の主要な制度がある。国家、企業、軍隊といったこれらの階層は、権力の手段を構成している。そのようなものとして、それらは今や人類史上かつてない結果をもたらしており、その頂点には、アメリカにおける上層部の役割を理解するための社会学的な鍵を与えてくれる、現代社会の司令塔が存在している。
アメリカ社会では現在、主要な国家権力は経済、政治、軍事の領域に存在している。他の制度は近代史の脇役に過ぎず、時にはそれらに従属することもある。大企業ほど国政に直接的な力を持つ家庭はない。軍事組織ほど、今日のアメリカの若者の外的伝記に直接的な力を持つ教会はない。宗教機関、教育機関、家庭機関は、国家権力の自律的な中心ではない。それどころか、これらの分散化した領域は、今や決定的かつ直接的な結果をもたらす展開が起こるビッグ3によって、ますます形成されるようになっている。
家庭、教会、学校は現代生活に適応し、政府、軍隊、企業は現代生活を形成する。宗教施設は軍隊にチャプレンを提供し、軍隊の士気を高めて殺戮の効果を上げる手段として使われる。学校は、企業での仕事と軍隊での専門的な仕事のために男性を選抜し、訓練する。もちろん、大家族は産業革命によって崩壊して久しい。そして今や、国家の軍隊が招集をかけるたびに、息子と父親は、必要であれば強制的に家族から引き離される。そして、これらすべての小さな制度の象徴は、3大組織の権力と決定を正当化するために使われている。
現代の個人の運命は、生まれた家庭や結婚によって入った家庭に左右されるだけでなく、最良の時期の最も注意深い時間を過ごす会社に左右されることも増えている。
中央集権的な国家が、公立・私立の学校で民族主義的な忠誠心を植え付けることを当てにできないとすれば、その指導者たちは速やかに分権的な教育制度を修正しようとするだろう。上位500社の倒産率が、3,700万組の夫婦の離婚率並みに高ければ、国際的な規模で経済的大惨事が起こるだろう。もし軍隊の構成員が、所属する教会に信者が捧げる以上に軍隊に命を捧げなければ、軍事的危機が起こるだろう。
3大組織のそれぞれにおいて、典型的な組織単位は拡大し、管理的になり、その決定権において中央集権的になっている。このような発展の背後には、素晴らしいテクノロジーが存在する。制度として、これらの組織はこのテクノロジーを取り込み、それが彼らの発展を形作り、歩調を合わせながらも、それを導いてきた。
経済は、かつては小さな生産単位が自律的なバランスを保ちながら散在していたが、今では200~300の巨大企業が支配するようになり、行政的にも政治的にも相互に関連し、経済決定の鍵を握っている。
政治秩序は、かつては弱い脊髄を持つ数十の国家からなる分散型の集合体であったが、今では中央集権的な行政機構となり、以前は散在していた多くの権力を自らの中に取り込み、社会構造の隅々にまで入り込んでいる。
軍事組織は、かつては州兵による不信の中で細々とした組織であったが、今では政府の最大かつ最も費用のかかる組織となり、微笑ましい広報活動には精通しているものの、今や広大な官僚組織の領域のような重苦しく不器用な効率性を備えている。
これらの各制度領域では、意思決定者が自由に使える権力手段が膨大に増大し、中央行政権が強化され、それぞれの領域で近代的な行政ルーチンが精緻化され、強化されてきた。
これらの各領域が拡大し、中央集権化するにつれて、その活動の帰結はより大きくなり、他の領域との交通量も増加する。一握りの企業の決定は、世界中の軍事的、政治的、経済的発展に影響を及ぼす。軍部の決定は、経済活動のレベルだけでなく、政治生活にも影響を及ぼし、重大な影響を与える。政治的な領域で下された決定が、経済活動や軍事計画を決定する。もはや、一方に経済があり、他方に政治や金儲けにとって重要でない軍事組織を含む政治秩序があるわけではない。政治経済が、千差万別の方法で軍事機構や決定と結びついているのだ。中央ヨーロッパとアジア環太平洋を貫く世界分断の両側では、経済、軍事、政治構造の連動がますます強まっている。2 企業経済への政府の介入があれば、政府プロセスへの企業の介入もある。構造的な意味では、この権力のトライアングルが、現在の歴史的構造にとって最も重要な連動取締役の源なのである。
連動という事実は、現代資本主義社会の危機的状況-不況、戦争、好況-のそれぞれにおいて、はっきりと明らかにされている。それぞれにおいて、意思決定者は主要な制度秩序の相互依存性を認識するようになる。あらゆる制度の規模が小さかった19世紀には、それらの自由主義的統合は、自動的な経済においては市場原理の自律的な戯れによって、自動的な政治領域においては交渉と投票によって達成された。そして、当時可能であった限定的な決定に続く不均衡と摩擦から、やがて新たな均衡が生まれると考えられていた。もはやそのようなことは想定できないし、3つの支配的ヒエラルキーのそれぞれの頂点に立つ人々も想定していない。
なぜなら、その結果の範囲を考えると、これらのどれかの決定と優柔不断が他のどれかに波及し、それゆえトップの決定は協調的になるか、命令的な優柔不断につながるかのどちらかになりがちだからである。昔からこうだったわけではない。たとえば、多数の小規模な企業家が経済を構成していた時代には、その多くが失敗しても、その結果は依然として地元にとどまっていた。しかし今、政治的期待や軍事的コミットメントを考えると、民間企業経済の主要部門がスランプで崩壊するのを許す余裕があるのだろうか?彼らが経済問題に介入することはますます増えており、そうするにつれて、それぞれの秩序における支配的な決定が、他の2つの秩序の代理人によって検査され、経済、軍事、政治の構造が連動するようになる。
拡大され中央集権化された3つの領域のそれぞれの頂点に、経済、政治、軍事のエリートを構成する高位のサークルが生まれた。経済の頂点には、企業富裕層の中に最高経営責任者がいる。政治秩序の頂点には、政治理事会のメンバーがいる。軍事機構の頂点には、統合参謀本部とその周辺に集まる軍人・政治家のエリートがいる。これらの各領域が他の領域と重なり、決定がその結果において総体的なものになる傾向があるため、3つの権力の各領域(軍閥、企業の頭領、政治局長)の有力者が集まり、アメリカのパワーエリートを形成する傾向がある。
2. これらの司令塔とその周辺に位置する高位のサークルは、しばしばそのメンバーが所有するものという観点から考えられる。この観点からすると、エリートとは、一般に、金銭、権力、名声、さらにはそれらにつながるあらゆる生活様式を含む、「持つべきもの」を最も多く持っている人たちのことである3。というのも、このような制度は、権力、富、名声の必要な基盤であり、同時に、権力を行使し、富を獲得し、維持し、より高い名声の要求を現金化するための主要な手段でもあるからである。
権力者とは、もちろん、たとえ他人がそれに抵抗しようとも、自分の意志を実現できる人たちのことである。それゆえ、主要な制度の指揮権を握らない限り、誰も真の権力者になることはできない。政治家や政府の要職にある者は、このような制度上の権力を握っている。提督や将軍もそうだし、大企業のオーナーや重役もそうである。すべての権力がそのような制度に固定され、その制度によって行使されるわけではないのは事実だが、そのような制度の中だけで、またそのような制度を通じてのみ、権力は多かれ少なかれ継続的かつ重要なものとなる。
富もまた、制度の中で、また制度を通じて獲得され、保有されている。富のピラミッドは、単に大金持ちの観点からだけ理解することはできない。後述するように、大金持ちの家系は現在、現代社会の企業制度によって補完されている。
現代の企業は富の主要な源泉であるが、後世の資本主義においては、政治機構もまた富への多くの道を開いたり閉じたりしている。所得の量と源泉、消費財に対する権力と生産資本に対する権力は、政治経済内での地位によって決まる。大金持ちへの関心が、彼らの贅沢な消費やみすぼらしい消費にとどまらないのであれば、彼らの近代的な企業財産形態や国家との関係を検討しなければならない。
社会構造の主要な制度単位には、大きな威信がますますつきまとうようになっている。名声が、多くの場合、現代アメリカのあらゆる大きな組織の中心的かつ通常の特徴となっている宣伝機関へのアクセスに、かなり決定的に左右されることは明らかである。さらに、企業、国家、軍部などのヒエラルキーの特徴のひとつは、そのトップの地位がますます入れ替わりやすくなっていることである。その結果のひとつが、名声の蓄積性である。例えば、威信の主張は、最初は軍事的役割に基づき、次に企業幹部が運営する教育機関で表現され、増強され、最後に政治的秩序で現金化されるかもしれない。富や権力と同じように、名声も蓄積される傾向がある。富裕層は貧困層よりも権力を得るのが容易であり、地位のある者は地位のない者よりも富を得る機会をコントロールするのが容易である。
アメリカで最も力のある100人、最も裕福な100人、最も有名な100人を、現在彼らが占めている組織的地位から遠ざけ、男や女や金という資源から遠ざけ、現在彼らに焦点が当てられているマス・コミュニケーション・メディアから遠ざければ、彼らは無力で貧しく、賞賛されることもないだろう。権力は人のものではないからだ。富は富裕層にあるのではない。セレブリティはどんな人格にも内在するものではない。有名になるには、裕福になるには、権力を持つには、主要な制度にアクセスする必要がある。男性がこのような価値ある経験を持ち、それを保持するチャンスは、制度上の地位によって大きく左右されるからだ。
3. 上層部の人々はまた、社会階層の最上位に位置する集団、つまり、その構成員が互いに知り合い、社交上や仕事上で互いに顔を合わせ、意思決定を行う際に互いに配慮し合う集団として考えることもできる。この概念によれば、エリートは自分自身を「上流社会階級」の内輪であると感じ、また他人からもそう思われている4。彼らは多かれ少なかれ、コンパクトな社会的・心理的実体を形成しており、社会階級の一員であることを自認している。人々はこの階級に受け入れられるか受け入れられないかのどちらかであり、単に数値的な尺度ではなく、質的な分裂がエリートとそうでない人々を分けている。彼らは多かれ少なかれ、自分たちが社会階級であることを自覚しており、他の階級の人たちに対する態度とは異なる態度で互いに接する。彼らは互いを受け入れ、理解し合い、結婚し、仕事をし、少なくとも同じように考える傾向がある。
さて、我々はこの定義によって、司令部のエリートがそのような社会的に認知された階級の意識的な構成員であるかどうか、あるいはエリートのかなりの割合がそのような明確で区別された階級の出身であるかどうかを予断するつもりはない。これらは調査すべき問題である。しかし、われわれが調査しようとしていることを認識するためには、富裕層や権力者、著名人の伝記や回想録がすべて明らかにしていることに注意しなければならない。「同じテラスに座っている」人々の間には、一種の相互吸引力がある。しかし、このことはしばしば、彼らにも他の人々にも、一線を引く必要性を感じた時点で初めて明らかになる。共通の防衛のために、自分たちの共通点を理解するようになり、部外者に対して隊列を閉じるようになって初めて明らかになるのだ。
このような支配層という考え方は、その構成員のほとんどが似たような社会的起源を持ち、生涯を通じて非公式の人脈ネットワークを維持し、金や権力や有名人といったさまざまな階層の間で、ある程度地位の交換が可能であることを意味している。もちろん、そのようなエリート層が存在するとしても、その社会的な知名度や形態は、非常に確固たる歴史的な理由から、かつてヨーロッパ諸国を支配していた貴族階級のそれとはまったく異なるものであることに、すぐに気づかなければならない。
アメリカ社会が封建的な時代を通過したことがないということは、アメリカ人エリートの性質にとって、また歴史的全体としてのアメリカ社会にとって、決定的な重要性を持つ。それは、資本主義時代以前に確立された貴族や貴族階級が、高位のブルジョアジーと緊迫した対立関係に立たなかったことを意味するからである。このブルジョワジーが富だけでなく、名声や権力も独占してきたことを意味する。つまり、一般的に高く評価されている価値観を独占し、トップの地位を占めた貴族は存在しなかった。つまり、教会の高官や宮廷貴族も、名誉を重んじる地主も、軍隊の高いポストを独占する者も、豊かになったブルジョワジーに対抗し、生まれと特権の名の下に、ブルジョワジーの自作自演に抵抗することに成功した者はいないということだ。
しかし、だからといって、米国に上層階級が存在しないわけではない。貴族的な上層階級を認めない「中産階級」から生まれたからといって、莫大な富の増加によって自分たちの優位性が可能になったとき、彼らが中産階級のままであったわけではない。彼らの出自とその新しさによって、アメリカでは他の地域よりも上層階級が目立たなくなったのかもしれない。しかし、今日のアメリカには、中流以下の人々がほとんど知らず、夢にも思わないような富と権力の階層や範囲が実際に存在する。単に裕福なだけの人々や、もっと下の階層の人々が感じる経済的な揺れや動揺から、かなり隔離された裕福な家庭がある。また、ごく小さな集団の中で、その下にいる人々に甚大な影響を及ぼす決定を下す権力者もいる。
アメリカのエリートは、事実上、無敵のブルジョワジーとして近代史に登場した。後にも先にも、このようなチャンスと優位性を持った国家のブルジョワジーは存在しない。軍事的な隣国を持たなかった彼らは、天然資源を蓄え、意欲的な労働力に絶大な魅力を持つ孤立した大陸を容易に占領した。権力の枠組みも、それを正当化するイデオロギーも、すでに手元にあった。重商主義の制限に対して、彼らは自由放任の原則を継承し、南部のプランターに対して、産業主義の原則を押し付けた。独立戦争は、忠誠心の強い人々が国外に逃亡し、多くの邸宅が解体されたため、植民地時代の貴族階級への憧れに終止符を打った。ジャクソニアンの身分革命は、ニューイングランドの旧家による血統独占の気取りに終止符を打った。南北戦争は、前ベラム期の南部の名士たちの権力を失墜させ、やがて名声も失墜させた。資本主義全体の発展のテンポは、アメリカにおいて継承される貴族が発展し存続することを不可能にした。
農耕生活に根ざし、軍事的栄光に花開くような固定した支配階級は、アメリカでは商工業の歴史的推進力を封じ込めることはできなかったし、例えばドイツや日本で資本家が従属させられたように、資本家エリートを従属させることもできなかった。また、工業化された暴力が歴史を決定するようになったとき、世界のどこであれ、そのような支配階級がアメリカの支配階級を封じ込めることはできなかった。20世紀の2つの世界大戦におけるドイツと日本の運命を見よ。そして、ニューヨークが西側資本主義世界の必然的な経済的首都となり、ワシントンが必然的な政治的首都となったときの、イギリス自身とその模範的支配階級の運命を見よ。
4. 司令塔のポストを占めるエリートは、権力と富と名声の所有者と見なされるかもしれない。彼らは資本主義社会の上層部の一員と見なされるかもしれない。また、心理的、道徳的な基準から、ある種の選ばれた個人として定義されることもある。このように定義されるエリートとは、端的に言えば、優れた人格とエネルギーを持つ人々のことである。
例えば、ヒューマニストは、「エリート」を社会的なレベルやカテゴリーとしてではなく、自分自身を超越しようとする個人の散らばりとしてとらえることができる。貧しかろうが金持ちだろうが、地位が高かろうが低かろうが、賞賛されようが軽蔑されようが関係ない。残りの人々は大衆であり、この考え方によれば、大衆は居心地の悪い平凡さの中にのんびりとくつろいでいるのである5。
しかし、エリートに対する道徳的・心理的観念のほとんどは、もっと洗練されておらず、個人ではなく層全体に関するものである。実際、このような考え方は、一部の人々が他の人々よりも多くのものを所有する社会では常に生じるものである。優位性を持つ人々は、自分がたまたま優位性を持つ人々であっただけだと信じたがらない。彼らは、自分が本来持っているものに価値があると定義し、自分が「生まれながらにして」エリートであると信じ、実際、自分の所有物や特権は、エリートである自分自身の自然な延長であると想像するようになる。この意味で、より優れた道徳的性格を持つ男女で構成されるエリートという考え方は、特権的支配層としてのエリートのイデオロギーであり、このイデオロギーがエリートが作ったものであろうと、他人が作り上げたものであろうと同じである。
平等主義的なレトリックの時代には、下層階級や中層階級の中でも、より知的な人々や、より明晰な人々、そして上層階級の罪深い人々が、反エリートの思想を抱くようになるかもしれない。西洋社会には、実のところ、貧しい人々、搾取される人々、虐げられる人々が、真に高潔であり、賢明であり、祝福された人々であるという長い伝統とさまざまなイメージがある。キリスト教の伝統に由来するこの対エリートという道徳的観念は、本質的に低い地位に置かれたより高次のタイプで構成され、支配的エリートに対する厳しい批判を正当化し、来るべき新たなエリートのユートピア的イメージを称揚するために、根底にある人々によって利用されることがあり、また利用されてきた。
しかし、エリートに対する道徳的観念は、常に単に恵まれた人々のイデオロギーや恵まれない人々の対抗イデオロギーであるとは限らない。それはしばしば事実である。経験や特権をコントロールすることで、上位層の多くの人々は、やがて彼らが体現していると主張する性格のタイプに近づいていくのである。エリートは生まれながらにしてエリートであるという考えは捨てなければならないが、彼らの経験や訓練が特定のタイプの人格を形成するという考えを否定する必要はない。
というのも、トップ・ポジションに抜擢され、その地位を形成している人々には、多くのスポークスマンやアドバイザー、ゴースト、メークアップ・マンがいて、彼らの自己概念を修正し、パブリック・イメージを作り上げ、彼らの意思決定の多くを形成しているからである。もちろん、この点ではエリートの間にもかなりの違いがあるが、今日のアメリカでは一般論として、主要なエリート集団を表向きの人員だけで解釈するのは甘いだろう。アメリカのエリートはしばしば、人物の集まりというよりも、企業体の集まりのように見える。企業体はその大部分において、標準的なタイプの「人格」として作られ、語られる。最もフリーランスに見える有名人でさえ、たいていは規律正しいスタッフによって毎週作られる一種の合成作品であり、そのスタッフは、有名人が「自発的に」反響する安易なアドリブギャグの効果を系統的に熟考している。
しかし、エリートが社会階級として、あるいは司令塔として栄える限り、エリートはある種の人格を選別し形成し、他の人格を拒絶する。男性がどのような道徳的・心理的存在になるかは、彼らが経験する価値観と、彼らが果たすことを許され期待される制度的役割によって、かなりの部分が決定される。伝記作家の視点に立てば、上流階級の人間は、自分と同じような他者との関係によって形成される。つまり、エリートとは、選抜され、訓練され、認定され、近代社会の非人間的な制度的階層を指揮する人々との親密な接触を許された、高次のサークルのことなのである。エリートの心理学的な考え方の鍵があるとすれば、それは、非人間的な意思決定に対する意識と、互いに分かち合う親密な感覚を、エリートが兼ね備えているということである。社会階級としてのエリートを理解するためには、一連の小規模な対面的環境を検討する必要がある。歴史的に最も明白なのは上流階級の家族であるが、今日最も重要なのは、適切な中等学校とメトロポリタン・クラブである6。
5. エリートに関するこれらのいくつかの概念は、適切に理解されるならば、互いに複雑に結びついている。私たちは、エリートの候補としていくつかの高次のサークルのそれぞれを研究し、アメリカの社会全体を構成する主要な制度という観点からそれを行う。しかし、われわれの最大の関心事は、現在司令塔を占めている人々の権力と、彼らがこの時代の歴史の中で果たしている役割である。
このようなエリートは全能であり、その力は隠された偉大な計画であると考えられる。このように、低俗なマルクス主義では、出来事や動向は「ブルジョアジーの意志」に言及して説明され、ナチズムでは「ユダヤ人の陰謀」に言及して説明され、今日のアメリカの小右派では、共産主義者のスパイという「隠された力」に言及して説明される。このような歴史的原因としての全能のエリートという概念によれば、エリートは決して目に見える存在ではない。実際、エリートは神の意志の世俗的な代用品であり、一種の摂理によって実現されるのだが、通常、エリートでない人間はそれに対抗し、最終的にはそれに打ち勝つことができると考えられている。
エリートは無力であるという正反対の見方は、リベラル志向の観察者たちの間で現在非常に人気がある。エリートは全能であるどころか、歴史的な力としての一貫性を欠くほど散在していると考えられている。彼らの不可視性は、秘密の不可視性ではなく、多数の不可視性である。形式的な権威の場を占める人々は、圧力をかける他のエリートや、選挙民としての国民や、憲法上の規範によって牽制されるため、上流階級は存在しても支配階級は存在せず、権力者は存在してもパワーエリートは存在せず、階層化システムは存在しても有効な頂点は存在しない。極端な言い方をすれば、このような見方やエリートは、妥協によって弱体化し、無価値なまでに分裂したものであり、非人間的な集団的運命の代用品である。
国際的には、全能のエリートというイメージが優勢になる傾向がある。国際的には、全能のエリート像が優勢になる傾向がある。良い出来事や喜ばしい出来事はすべて、オピニオンメーカーたちによって自国の指導者にすぐに帰属させられ、悪い出来事や不愉快な経験はすべて、海外にいる敵国に帰属させられる。どちらの場合も、悪の支配者あるいは高潔な指導者の全能が前提となっている。国内では、このようなレトリックの使い方はむしろ複雑である。人々が自分たちの党やサークルの権力について語るとき、彼らや彼らの指導者はもちろん無力であり、「国民」だけが全能である。しかし、敵対する政党やサークルの権力について語るとき、彼らは彼らに全能感を与える。
もっと一般的に言えば、アメリカの権力者は、慣例として、自分が権力者であることを否定する傾向がある。官僚や役人になるのではなく、公僕になるのだ。そして今日、すでに指摘したように、このような姿勢はあらゆる権力者の広報プログラムの標準的な特徴となっている。権力を行使するスタイルの確固たる一部となったため、保守的な作家は、「無定形の権力状況」への傾向を示していると容易に誤解している。
しかし、今日のアメリカの「権力状況」は、それをロマンチックな混乱とみなす人々の視点に比べれば、不定形ではない。それは、平坦で瞬間的な「状況」ではなく、段階的で耐久性のある構造なのだ。そして、その頂点に立つ者が全能ではないとしても、無力でもない。エリートが持ち、行使している権力の程度を理解するためには、権力のグラデーションの形と高さを調べる必要がある。
もし、決定された国家的問題を決定する権力がまったく平等に共有されるのであれば、パワーエリートなど存在しない。反対に、問題を決定する権力がある小さな集団に完全に独占されているとしたら、そこには権力のグラデーションはなく、単にこの小さな集団が指揮を執り、その下に未分化で支配的な大衆が存在するだけである。今日のアメリカ社会は、この両極端のどちらにも当てはまらないが、この両極端の概念を理解することは有益である。
現代社会の最も強力な制度的秩序のそれぞれには、権力のグラデーションがある。道端の果物屋の主人は、社会的、経済的、政治的意思決定のどの分野においても、数百万ドル規模の果物企業のトップほどの権力は持っていない。ペンタゴンの参謀総長ほどの権力を持つ警部補はいない。従って、パワーエリートの定義の問題は、どのレベルで線を引くかということに関わる。線を引けば、エリートは存在しなくなり、線を引けば、エリートは非常に小さな輪になる。予備的かつ最小限の方法として、私たちは粗雑に、いわば木炭で線を引く: パワーエリートとは、政治的、経済的、軍事的なサークルのことであり、これらのサークルは、複雑に重なり合った徒党の集合体として、少なくとも国家に影響を及ぼす決定を共有している。国家的な出来事が決定される限り、パワーエリートはそれを決定する人々である。
現代社会には、権力や意思決定の機会に明らかな段階があると言っても、権力者たちが団結しているとか、自分たちの行動を完全に把握しているとか、意識的に陰謀を企てているとか、そういうことではない。このような問題は、まず第一に、権力者の意識の程度や動機の純粋さよりも、権力者の構造的な立場や、彼らの決定がもたらす結果について関心を持つことが最善である。パワーエリートを理解するためには、3つの主要な鍵に注意を払わなければならない:
I. ひとつは、それぞれの高次サークルについての議論を通じて強調したいことだが、それぞれの環境におけるエリートたちの心理である。パワーエリートが似たような出自と教育を受けた人々で構成されている限り、彼らのキャリアと生活様式が似ている限り、彼らの団結には心理的・社会的基盤があり、それは彼らが似たような社会的タイプであるという事実に基づいており、彼らが容易に交わるという事実につながっている。この種の団結は、有名人の世界で得られる名声の共有において、より泡沫的な頂点に達する。
II. このような心理的・社会的一体性の背後には、政治家、富裕企業、高級軍人が現在統率している制度的ヒエラルキーの構造と仕組みがある。これらの官僚的領域の規模が大きくなればなるほど、それぞれのエリートの権力の範囲も大きくなる。それぞれの主要な階層がどのように形成され、他の階層とどのような関係を持つかは、その支配者の関係を大きく左右する。これらの階層がばらばらであれば、それぞれのエリートもばらばらになりがちであり、相互のつながりが多く、利害が一致する点が多ければ、エリートは首尾一貫した集団を形成する傾向がある。
エリートの結束は、制度の結束を単純に反映したものではないが、人間と制度は常に関連しており、パワーエリートという概念は、その関係を見極めるようわれわれを誘う。今日のアメリカでは、政治的空白の内部で、私企業化された経済による恒久的な戦争体制が発展していることを含め、これらの制度的領域の間に、関心を呼ぶいくつかの重要な構造的一致点がある。
III. しかし、パワーエリートの団結は、心理的な類似性や社会的な交わりだけにかかっているわけではないし、指揮官としての地位や利害の構造的な一致だけにかかっているわけでもない。時として、それはより明確な協調による統一である。これら3つの高次のサークルはますます協調しており、これが団結の1つの基礎であり、時には-戦争中のように-そのような協調がきわめて決定的であると言っても、その協調が完全であるとか、継続的であるとか、あるいは非常に確実であるとかいうことではない。ましてや、意図的な協調が彼らの団結の唯一の、あるいは主要な基盤であるとか、パワーエリートが計画の実現として出現したということではない。しかし、現代の制度的な仕組みが、それぞれの利益を追求する人々に道を開くにつれて、彼らの多くが、より正式な方法だけでなく非公式な方法においても、協力し合えば、これらの利益をより容易に実現できると考えるようになり、それに従ってそうしてきたということである。
6. 人類史のあらゆる時代、あらゆる国家において、創造的な少数派、支配階級、全能のエリートがすべての歴史的出来事を形成しているというのが私のテーゼではない。そのような記述は、注意深く吟味してみると、たいていの場合、単なる同語反復であることが判明する7 し、そうでない場合でも、現在の歴史を理解しようとする試みには役に立たないほど、まったく一般的なものである。パワーエリートとは、重大な結果を決定するあらゆることを決定する人たちである、という最小限の定義は、このエリートのメンバーが常に、そして必ずしも歴史を作る人たちであることを意味するわけではない。われわれが定義したいエリートの概念と、エリートの役割に関する一つの理論、すなわちエリートが現代の歴史を作る者であるという理論を混同してはならない。例えば、エリートを「アメリカを支配する人々」と定義することは、概念を定義するというよりも、エリートの役割と権力に関する一つの仮説を述べることである。エリートをどのように定義しようとも、その構成員の力の程度は歴史的に変化するものである。もし独断的なやり方で、一般的な定義にその変動を含めようとするならば、必要な概念の使用を愚かにも制限してしまうことになる。エリートを、継続的かつ絶対的に支配する厳密に調整された階級として定義することを主張するならば、私たちは、より控えめに定義された用語が私たちの観察に開くかもしれない多くのものを、視野から閉ざしてしまうことになる。要するに、パワーエリートの定義には、どこの国でも支配者集団が持つ権力の程度や種類に関するドグマを適切に含めることはできない。ましてや、歴史論を議論に持ち込むことは許されない。
人類の歴史の大半において、歴史的な変化は、それに関与した人々、あるいはそれを実行した人々にさえ、目に見えるものではなかった。たとえば、古代エジプトとメソポタミアは、その基本的な構造をわずかに変えながら、400世代にわたって存続した。これは、60世代しか存続していないキリスト教の時代全体の6.5倍の長さであり、アメリカの5世代存続の約80倍の長さである。しかし現在、変化のテンポは非常に速く、観察手段は非常に利用しやすくなっているため、出来事と決断の相互作用は、注意深く、適切な視点から見ることさえできれば、しばしば歴史的に見ることができるように思われる。
知識豊富なジャーナリストが「大きな決断を形作るのは人間ではなく出来事である」と語るとき、彼らは「ファウチュン」、「チャンス」、「運命」、あるいは「見えざる手」の働きとしての歴史論を唱えているのである。「出来事」とは、これらの古い考えを現代風に言い換えたものに過ぎないのだ。これらの考えはすべて、歴史形成から人間を切り離すものであり、歴史は人間の背後で進行していると私たちに信じ込ませるものだからだ。歴史は支配者のいない漂流物であり、その中には行動はあっても行為はない。歴史は単なる出来事であり、誰も意図していない出来事である8。
現代における出来事の成り行きは、必然的な運命というよりも、一連の人間の決断に依存している。「運命」の社会学的な意味とは、簡単に言えば、決定が無数にあり、その一つひとつが小さな結果であるとき、そのすべてが人間の意図しない形で積み重なり、運命としての歴史になるということである。しかし、すべての時代が同じように運命的であるわけではない。意思決定者の輪が狭まり、意思決定の手段が中央集権化され、意思決定の結果が莫大なものになると、大事件の行方はしばしば決定可能な輪の意思決定にかかってくる。だからといって、同じサークルの人間が、ある出来事から別の出来事へと、歴史のすべてが彼らの筋書きにすぎないような形で続いていくとは限らない。エリートの権力があるからといって、歴史が一連の小さな決定によって形成されるとは限らない。百の小さな取り決めや妥協や適応が、進行中の政策や生きている出来事の中に組み込まれていないとは限らない。パワーエリートという考え方は、意思決定のプロセスそのものを意味するものではない。それは、誰がそのプロセスに関与しているかという概念である。
重要な意思決定に関与する人々の先見性と統制の度合いも様々であろう。パワーエリートという考え方は、意思決定の根拠となる予測や計算されたリスクがしばしば間違っていたり、結果が意図したものでなかったりすることを意味しない。多くの場合、決断を下す者は自らの不十分さに囚われ、自らの過ちに目を奪われている。
しかし、私たちの時代には極めて重要な瞬間が訪れ、その瞬間、小さなサークルが決断を下したり、下せなかったりする。どちらにしても、彼らは権力のエリートなのだ。日本への原爆投下はそのような瞬間であった。朝鮮半島に関する決定はそのような瞬間であった。クエモイと馬祖に関する混乱も、ディエンビエンフー以前の混乱もそのような瞬間であった。現代の歴史の多くが、そのような瞬間によって構成されているというのは事実ではないだろうか。そして、私たちが大きな決断の時代、決定的に中央集権化された権力の時代に生きていると言われるのは、そういう意味ではないだろうか。
私たちの多くは、ギリシア的な永遠の回帰を信じたり、キリスト教的な来るべき救済を信じたり、人間の進歩の着実な歩みを信じることによって、この時代を理解しようとはしない。たとえそのようなことを考えなくとも、私たちはブルクハルトと同じように、単なる出来事の連続の中に生きているのだ。歴史とは、次から次へと起こる出来事に過ぎない。歴史とは、決定された筋書きを実現するものではないという点で、無意味なものなのだ。もちろん、われわれの連続性に対する感覚や、われわれの時代の歴史に対する感覚が、危機に影響されることは事実である。しかし、私たちは目前の危機や、その先にあると思われる危機の先を見ることはほとんどない。私たちは、運命も摂理も信じていない。そして、「私たち」(国家として)は未来を決定的に形作ることができるが、「私たち」個人はどうにかしてそうすることはできないと、口に出さずに思い込んでいる。
歴史にどのような意味があるにせよ、それは「私たち」の行動によって与えられなければならない。しかし実際には、歴史の中にいる私たち全員とはいえ、全員が等しく歴史を作る力を持っているわけではない。そのように装うことは、社会学的にナンセンスであり、政治的に無責任である。ナンセンスなのは、いかなる集団や個人も、まず第一に、その指揮下にある技術的・制度的な権力手段によって制限されるからである。「私たち」全員が歴史を作る者であるかのように装うことは、政治的に無責任である。なぜなら、それは、権力手段を利用することのできる人間たちの結果的な決定に対する責任を明確にしようとする試みを鈍らせるからである。
西側社会の歴史を最も表面的に検討しただけでも、意思決定者の権力は、まず第一に、ある社会で支配的な権力と暴力と組織の手段である技術のレベルによって制限されることがわかる。この関連で、我々はまた、西洋の歴史を通して、上方に向かってかなりまっすぐな線が走っていること、抑圧と搾取、暴力と破壊の手段が、生産と再建の手段と同様に、漸進的に拡大され、ますます中央集権化されてきたことを学ぶ。
制度的な権力手段と、それらを結びつける通信手段が着実に効率的になるにつれて、現在それらを支配している人々は、人類の歴史上まったく比類のない支配手段を手にするようになった。そして私たちはまだ、その発展の絶頂期には至っていない。われわれはもはや、前時代の支配者集団の歴史的浮き沈みに寄りかかることも、軟弱な慰めを得ることもできない。その意味で、ヘーゲルは正しい。われわれは歴史から学べないことを歴史から学ぶのである。
あらゆる時代、あらゆる社会構造において、エリートの権力という問題に対する答えを導き出さなければならない。人間の目的はしばしば希望にすぎないが、手段は一部の人間が支配できる事実である。だからこそ、権力を掌握するエリートにとっては、あらゆる手段が目的になりがちなのである。だからこそ、権力エリートを権力手段の観点から定義することができるのである。今日のアメリカのエリートに関する主要な問題-その構成、団結、権力-は、今こそ、エリートが利用できる強大な権力手段に十分な注意を払いながら直面しなければならない。カエサルがローマでできたことは、ナポレオンがフランスでできたことよりも少ない。ナポレオンがフランスでできたことは、レーニンがロシアでできたことよりも少ない。レーニンがロシアでできたことは、ヒトラーがドイツでできたことよりも少ない。カエサルの権力は、ソビエト・ロシアやアメリカの臨時政権の側近の権力に比べれば、絶頂期にはどうだっただろうか。どちらのサークルの人間も、一晩で大都市を消し去り、数週間で大陸を熱核の荒れ地に変えることができる。権力機構が巨大化し、中央集権的になったということは、小さな集団の決定がより重要な意味を持つようになったということだ。
しかし、現代の社会構造の頂点にあるポストが、より威厳のある決断を可能にしていることを知ることは、そのポストに就いているエリートが歴史を作っていることを知ることではない。拡大し統合された経済的、軍事的、政治的構造が、命令的な決定を可能にするような形になっていることは認めるかもしれないが、それでもなお、いわば「自走している」、要するにトップに立つ者は「必然性」によって決定されるのだと感じるかもしれない。
エリートたちは、自分たちが果たす役割を決定するのだろうか?それとも、制度がエリートに与える役割がエリートの権力を決定するのだろうか?一般的な答えは、一般的な答えでは不十分であるが、異なる種類の構造と時代において、エリートは果たす役割とまったく異なる関係にあるということである。エリートの性質や歴史の性質が答えを決めるわけではないのだ。また、ほとんどの男女が許された役割を、その地位によって期待されたとおりに演じるとすれば、エリートはまさにそのようなことをする必要はなく、しばしばしない。彼らは、構造、その中での自分の立場、あるいはその立場を演じる方法に疑問を投げかけるかもしれない。
アドルフ・ヒトラーがヒンデンブルク大統領が死去したその日に「指導者兼首相」を宣言し、大統領職と首相職を統合して役割を廃止・簒奪することを、誰も求めなかったし、許さなかった。フランクリン・D・ルーズベルトが、米国を第二次世界大戦に参戦させるに至った一連の決断を下すことを、誰も要求しなかったし、許可もしなかった。「歴史的必然性」ではなく、広島への原爆投下を決めたのはトルーマンという男だった。ラドフォード提督のディエンビエンフー前での原爆投下案を打ち破ったのは、歴史的必然性などではなく、ごく一部の人間の中での議論であった。現代のエリートは、制度の構造に依存するどころか、ある構造を破壊して別の構造を作り上げ、そこでまったく異なる役割を演じることもある。実際、このような制度的構造の破壊と創造は、出来事がうまくいきそうなときには、あらゆる権力手段とともに、まさに「偉大なリーダーシップ」に関わってくるものであり、悪くなりそうなときには、「偉大な専制政治」に関わってくるものなのである。
もちろん、典型的な役割決定型のエリートもいるが、役割決定型のエリートもいる。彼らは、自分が演じる役割だけでなく、今日では他の何百万人もの男性の役割も決定している。極めて重要な役割の創出とその実現は、社会構造がブレイクスルー転換期を迎えているときに最も容易に起こる。アメリカが2つの「大国」のうちの1つへと国際的に発展したことが、殲滅と行政的・精神的支配の新たな手段とともに、20世紀半ばのアメリカをまさにそのようなブレイクスルー枢軸にしたことは明らかである。
歴史には、パワーエリートがそれを作ることができないと教えてくれるものは何もない。確かに、そのような人たちの意志には常に限界がある。しかし、その限界がこれほど広範であったことはない。このことが、われわれの状況を非常に不安定なものにしているのであり、アメリカのエリートの権力と限界についての理解をより重要なものにしているのである。このエリートの性質と権力の問題は、責任ある政府の問題を再び提起するための、現実的で真剣な唯一の方法なのである。
7. アメリカの新たな祭典に対する批判を放棄した人々は、エリートは無力であるという見解を容易に受け入れる。もし彼らが政治的に真剣であれば、その見解に基づいて、アメリカの政策を担当していると思われる人々にこう言うべきだ10。
近々、爆弾を投下する機会があるとか、同盟国やロシアとの関係をさらに悪化させるチャンスがあると考えるかもしれない。しかし、本当に選択肢があると信じるほど愚かではない。選択肢もチャンスもない。あなた方がバランスをとっている部分に過ぎない複雑な状況全体が、経済的・社会的な力の結果であり、運命的な結果をもたらすのだ。だから、トルストイの将軍のように静かに傍観し、成り行きに任せればいい。たとえ行動したとしても、その結果は、たとえ意図があったとしても、あなたの意図したものにはならないだろう。
「しかし-もし出来事がうまくいったなら、自分が決めたかのように話すのだ。その時、人は道徳的な選択をし、それをする力を持ち、もちろん責任があるからだ」
もし悪い結果になったら、あなたには本当の選択がなかったと言い、もちろん責任はない。あなたが世界の軍隊の半分を指揮し、どれだけの爆弾や爆撃機があるか神のみぞ知る状態であっても、あなたはこの言い逃れができる。道徳的責任とは幻想であり、実に注意深い広報の仕方で扱えば、大いに役立つものではあるがね』。
このような運命論から導き出されるひとつの含意は、もし運や摂理が支配するのであれば、いかなる権力エリートも歴史的決断の源泉とは正当に見なされないということであり、ましてや責任あるリーダーシップを要求するという考えは、無為で無責任な考えであるということである。明らかに、歴史のおもちゃである無力なエリートは、責任を問われることはない。現代のエリートが権力を持たなければ、責任を問われることはない。困難な立場にある彼らは、私たちの共感を呼ぶはずだ。アメリカ国民は、主権者の幸運に支配されている。彼ら、そして彼らエリートは、自分たちではコントロールできない結果に致命的に打ちのめされているのだ。もしそうであるなら、私たちは皆、多くの人々が実際にすでに行っているように、政治的な考察や行動から完全に身を引き、物質的に快適で完全に私的な生活を送るべきである。
一方、戦争と平和、不況と繁栄は、まさに今、もはや「幸運」や「運命」の問題ではなく、これまで以上に「コントロール可能」な問題であると考えるのであれば、誰にコントロールされるのかと問わねばならない。答えはこうだ: 巨大化し、決定と権力を決定的に中央集権化した手段を指揮する者たち以外の誰によってであろうか?では、なぜ彼らはそうしないのか?その答えのためには、今日のアメリカのエリートの背景と性格を理解しなければならない。
エリートは無力であるという考え方は、このような問いを立てることを躊躇させるものではない。アメリカのエリートは全能でも無力でもない。これらの言葉は、スポークスマンが言い訳や自慢として公の場で使う抽象的な絶対的表現である。しかし、この言葉によって、われわれは目の前の政治的問題を明らかにすることができる。
私たちの時代の「歴史の本質」には、意思決定者の小集団が極めて重要な役割を果たすことを否定するものは何もない。それどころか、現在の構造は、この見方を合理的であるだけでなく、むしろ説得力のあるものにしている。
「人間の心理」にも、現代社会の司令塔のために、あるいは司令塔に選ばれる人間の社会的なあり方にも、彼らが選択に直面し、彼らが行う選択、あるいはそれに直面しなかったことが、その結果において歴史を作るという見方を不合理にするようなものは何もない。
したがって、政治家たちは、現在の歴史を構成する歴史的出来事の決定的な範囲について、アメリカのパワーエリートに責任を負わせる十分な理由を持っている。
30年代に、支配階級の悪党がすべての社会的不公正と大衆の不安の原因だと考えるのが流行ったように、今、パワーエリートなど存在しないと考えるのが流行している。ある単純で一方的な支配階級が、アメリカ社会の原動力としてしっかりと位置づけられると考えるのは、今日のアメリカにおけるすべての歴史的変化が、単なる無個性な漂流に過ぎないと考えるのと同じくらい遠いことだ。
すべては盲目的な漂流に過ぎないという見方は、自分の無力感を運命論的に投影したものであり、おそらくは、原理的な方法で政治的な活動をしたことがある人なら、罪悪感を癒すためのものだろう。
また、歴史のすべてが、悪人や英雄の陰謀によるものだとする考え方も、社会構造の変化がどのようにさまざまなエリートに機会を与え、さまざまなエリートがどのようにその機会を利用したり、利用しなかったりしたかを理解するための困難な努力からの、急ごしらえの投影である。すべての歴史は陰謀である、あるいはすべての歴史は漂流である、というどちらの見方も受け入れることは、権力の事実と権力者のやり方を理解する努力を緩めることになる。
8. 現代の権力エリートの姿を見極め、「彼ら」という匿名的な存在に責任ある意味を与えようとする試みにおいて、私はまず、多くの人々が最もよく知っている上位の要素、すなわち地方社会の新旧の上流階級と首都圏の400人について簡単に調べることにする。そして、アメリカ社会の名声制度が、今や初めて真に全国的な広がりを持つようになったこと、この全国的な地位制度のより些細で華やかな側面は、同時に、より権威主義的な特徴から注意をそらし、しばしば隠蔽される権力を正当化する傾向があることを示そうとする。
大金持ちと最高経営責任者について考察する中で、『アメリカの60家族』も『経営者革命』も、今日の企業富裕層という特権階級に組織された上流階級の変容について、いかに適切な考えを提供していないかを指摘したい。
アメリカの政治家を歴史的なタイプとして説明した後、進歩主義時代の観察者たちが「見えない政府」と呼んでいたものが、今ではかなり目に見えるものとなっていること、そして、通常政治の中心的な内容であると考えられているもの、つまり圧力や選挙運動や議会工作が、今ではかなりの部分で権力の中間に追いやられていることを示そうと思う。
軍部の台頭を論じるにあたって、私は、提督や将軍が政治的・経済的に決定的な関連性を持つ地位を占めるようになった経緯と、そうすることによって、彼らが企業富裕層や目に見える政府の政治部門と利害が一致する多くの点を見出した経緯を明らかにしようと思う。
このような傾向やその他の傾向を、私ができる限り明らかにした後、私はパワーエリートの主な問題に戻り、大衆社会という補完的な概念を取り上げることにする。
私が主張したいのは、この特定の時代において、歴史的な状況の連動が権力エリートの台頭をもたらしたということである。このエリートを構成するサークルの人々が、現在、単独で、また集団として、重要な決定を下しているということである。そして、現在利用可能な権力手段が拡大し、中央集権化されていることを考えると、彼らが下す、あるいは下さなかった決定は、人類の世界史においてかつてなかったほど、より多くの人々に影響を及ぼすということである。
私はまた、権力の中間レベルでは、半組織的な膠着状態が生まれ、最下層では、自主的な団体や古典的な大衆が権力の鍵を握る社会のイメージとは似ても似つかない大衆的な社会が生まれたと主張している。下層部に存在するような意志を表明することもなく、上層部の決定を決定することもない中途半端な権力の単位に気を取られている人々が一般に考えているよりも、アメリカの権力システムの上層部ははるかに統一され、はるかに強力であり、下層部ははるかに断片化され、実のところ無力なのである。
あとがき
アラン・ウルフ
1. C. ライト・ミルズの『パワー・エリート』が出版されたのは1956年で、ミルズ自身が言うように、アメリカ人が「物質的ブーム、ナショナリズムの謳歌、政治的空白」を生きていた時代である。ミルズが告発したように、アメリカ人がなぜ自己満足していたのかを理解するのは難しくない。
1956年当時、あなたが典型的な35歳の有権者だったとしよう。それまでの人生を想像してみよう。あなたが8歳のとき、株式市場は大暴落し、その結果、あなたが小学3年生か4年生になったとき、世界大恐慌が始まった。したがって、あなたの子供時代は、アメリカ史上最大の経済的大惨事による貧困と失業との戦いに明け暮れた。あなたが21歳になり、正式に成人になったとき、日本軍が真珠湾に侵攻し、若い大人としての年月は、特に男性であれば、ヨーロッパの地上やアジアの島から島への戦闘に費やされることになった。幸運にもその体験から生還できたなら、あなたは24歳という熟年になって帰国し、普通の生活を取り戻す準備ができた。
1956年の大統領選挙で一票を投じようと考えたとき、アイゼンハワー大統領の再選に投票したくなったとしても不思議ではない。何しろ彼は第二次世界大戦で連合軍を指揮したのだから。確かに、アイゼンハワーは演説で元気がないように見えることがしばしばあったし、金持ちのビジネスマンと付き合うのが一番楽だった。それでもアイゼンハワーは、正反対のことしか知らなかった有権者に安定をもたらした。ジョン・フォスター・ダレス国務長官がロシアの脅威について威勢のいいことを言う割には、大統領自身は外交政策からやや離れているように見えた。彼の国内計画は、アイゼンハワー自身がやがて 「軍産複合体」と呼ぶことになる仕事を求めてロサンゼルスへの移住を考えている人たちが利用する予定の高速道路を建設する程度のものだった。
このような環境の中で、パワーエリートは爆発的に成長した。C・ライト・ミルズは、アイゼンハワー時代の自己満足だけでは不十分だと書いた、アメリカで最初の知識人の一人である。彼の非難は妥協のないものだった。一方では、アメリカには巨大な権力が集中し、アメリカの民主主義を愚弄していると主張した。他方で、彼は仲間の知識人たちがアメリカの保守的なムードに売り渡し、彼らの聴衆であるアメリカ国民そのものを、アメリカが打ち負かした、あるいは現在戦っている全体主義体制と衝撃的な類似性を持つ無知と無関心の状態に置き去りにしていると告発した。
ミルズが『パワー・エリート』で自らに課した目標のひとつは、読者(ここでも読者がおよそ35歳であると仮定している)が生きている間にアメリカの権力組織がどれほど変化したかを伝えることであった。この典型的な読者が生まれた1920年代には、ミルズが「地方社会」と呼ぶ、アメリカ全土の町や小都市が存在し、その政治的・社会的生活は居住する実業家によって支配されていた。小さな町のエリートたちは、たいていの場合共和党支持者であり、議会でも強い発言力を持っていた。なぜなら、彼らの代表である議員のほとんどが、支配的な一族の一員であるか、彼らと密接な経済的つながりを持っていたからである。
ミルズがこの本を書いたころには、このような地方エリートの世界は、電信機と同じように時代遅れになっていた。アメリカでは権力が国有化され、その結果、相互の結びつきが強くなっていたのだ。『パワー・エリート』は、アメリカにおける権力の3つの側面に注目した。第一に、ビジネスの中心が、労働力と顧客基盤において主に地域的な企業から、全国市場で製品を生産し、全国的な利益を展開する企業へと移行した。かつては実物資産の所有に結びついた資産家階級であったものが、経営者階級となり、企業という広大な範囲を組織して利益を拡大し続ける原動力とする能力によって報われるようになった。もはや、企業の最高経営責任者は、社会的背景が適切であるという理由で選ばれることはなかった。コネクションは依然として重要だが、官僚的なスキルも重要だった。そのようなスキルを持つ者は、その努力に見合った報酬を得ることができた。経費を支給され、高額の報酬を得た彼らは、会社を通じてだけでなく、「国益」のために求められる役割を通じて、国家的影響力を行使することができた。
同様の変化は、アメリカ社会の軍事部門でも起こっていた。ミルズは、第二次世界大戦とそれに続く冷戦の開始が、アメリカにおける「恒久的な戦争経済」の確立につながったと主張した。ミルズ氏は、軍部とその文民同盟を指す彼の言葉である「軍閥」は、かつては「アメリカのエリートの中では不穏で貧しい関係にすぎなかったが、今ではいとこ同士であり、やがて兄になるかもしれない」と書いている。したたかに見せようとする政治家たちに無制限の当座預金を与え、素晴らしい技術的・科学的成果に後押しされ、アメリカの教育機関に根を下ろしている軍部は、ますます自律的な存在になりつつあるとミルズは考えていた。パワーエリートのあらゆる部位の中で、この「軍部の台頭」は最も危険な意味を持っていた。アメリカの軍国主義が完全に発展した形では、生活のあらゆる分野で軍事的形而上学が勝利することを意味し、それゆえ他のあらゆる生活様式が軍事的形而上学に従属することになる」
軍部や企業エリートとともに、ミルは「政治局長」と呼ぶものの役割を分析した。かつて地方エリートは議会で強く代表されていたが、議会そのものが行政府に権力を奪われてしまったとミルズ氏は指摘した。そして、その行政府の中で、ミルズが「現在、アメリカ合衆国の名において行われる行政上の決定を担当している」と考える人物は、およそ50人を数えることができた。国務長官や国防長官のような非常にトップの地位には、アメリカの主要な国営企業と密接な関係を持つ人物が就いていた。これらの人々は、金目当てでその地位に就いたわけではない。多くの場合、民間企業で働くよりも収入は少なかった。むしろ彼らは、中央情報局(CIA)の運営や財務長官になることが、国の方向性に大きな影響力を与えることを理解していた。軍事部門や企業部門と固く結びついたアメリカの政治指導者たちは、国家全体にとって何が良いことなのかよりも、むしろ自分たちの階級に有利なアジェンダを作り上げた。
『パワー・エリート』は、その時代の産物として書かれたにもかかわらず、驚くべき持続力を持っている。この本は原書のまま44年間も印刷され続けている。つまり、最初にこの本を読んだ35歳の人は、現在79歳ということになる。若い読者なら、ミルズが言及した企業、軍、政治のリーダーたちの名前をほとんど知らないだろう。しかし、アメリカが理論上と同様に実際にも民主的であるかどうかという根本的な問題は、依然として非常に重要なのである。
2. 現代の『パワー・エリート』の読者にとって明らかな疑問は、その結論が今日のアメリカに当てはまるかどうかである。ミルズ著の中で有用なものと時代遅れになったものを選別することは、取り組む価値のある仕事のように思われる。
『ファウチュン』誌は毎年、アメリカを代表する500社のリストを発表している。1956年の上位50社と1998年の上位50社を比較した表1を見ると、ミルズの著書が書かれた当時、経済を支配していた50社のうち、鉄鋼、ゴム、食品など、かつては難攻不落に見えた業種の企業を含め、約30社がもはやそうではないことがわかる。別の言い方をすれば、1998年のリストには、ミルズにとってなじみの深い企業の名前が多く含まれている: 1位はゼネラル・モーターズ、2位はフォード、3位はエクソンである。実際、アーカンソー州の庶民的な商人が始めた小売店チェーンが、いつの日かモービル石油やゼネラル・エレクトリック、クライスラーを凌ぐ存在になるとは考えもしなかっただろう。さらに、ある産業が衰退したのと同じように、1956年以降、アメリカではまったく新しい産業が登場している。ミルズが執筆した当時、IBMは59位で、現在の『ファウチュン500』誌の6位にランクされるコンピュータの巨人にはほど遠かった。(ミルズが著書を書いた当時、IBMは59位であり、現在のファウチュン500の6位というコンピュータの巨人ではなかった(ミルズが著書を書いた当時は存在しなかったコンパックとインテルも、1998年のリストでは50位以内に入っている)。ミルズ氏は、パワーエリートの閉ざされた世界を説明するために、1950年当時、アメリカの上位25社のうち4社の取締役を務めていたのは、駐英アメリカ大使のウィンスロップ・W・アルドリッチという人物であったという事実に注目した。対照的に、1998年には、そのうちのたった1社、AT&Tだけがトップ企業の仲間入りを果たしている: チェイス
表1 1956年と1998年の50大企業
マンハッタンは27位、メトロポリタン生命は43位に転落し、ニューヨーク・セントラル鉄道は見当たらなかった。
企業ヒエラルキーの上位が入れ替わる理由のひとつは、圧倒的な市場シェアを確保するために、アメリカの企業が絶えず合併を繰り返しているからだ。1998年末、アメリカ第3位のエクソンは、第8位のモービルと合併し、ミルズが考えていたものを凌駕する規模の新会社を作る計画を発表した。実際、ミルズがこれほどまでに企業規模に注目した理由のひとつは、1898年のシャーマン法にさかのぼる、独占を法律で阻止すべき悪とみなすアメリカの長い伝統にあった。この伝統の影響により、いくつかの大企業は解体され、新しい企業-BCコミュニケーションズ、ルーセント・テクノロジーズ-が設立されるようになった。しかし、共和党政権も民主党政権も、アイゼンハワー政権時代ほどには政府による経済規制を好まないため、シャーマン法が発動されることは少なくなった。アイゼンハワーの国防長官でもあったゼネラルモーターズの元CEOが、自分の会社にとって良いことはアメリカにとっても良いことだと発言したとき、人々は衝撃を受けた。今日、この発言は、おそらくは暗黙のうちに、政府と企業の関係についての適切な指針とみなされているだろう。
ミルズ氏は企業エリートについて多くのことを正しく理解している。例えば、企業を経営する人々が大金持ちであることは確かだ。CEOの収入と労働者の収入の差は非常に大きい。しかし、ミルズが描いた世界と今日の世界には、看過できないほど顕著な違いがある。奇妙に聞こえるかもしれないが、ミルズによる資本主義理解は十分に急進的ではなかったのだ。当時の社会学の影響を色濃く受けた『パワー・エリート』は、企業幹部を「すでにトップにいる者たちに「馴染まなければならない」組織人として描いている。彼らは自分の印象を管理することに気を配らなければならず、あたかも良い結果を出すという見かけが、その実際よりも重要であるかのようである。ミルズ氏は、一流のビジネスマンが特別有能であるという考えを軽蔑していた。「適任者が生き残るのだ」と彼は書いている。「適任とは、形式的な能力ではなく、すでに成功した人たちの基準に合致していることを意味する。
1950年代には、企業のリーダーが特別な創意工夫をすることはなかったのは事実かもしれないが、もしそうなら、それは彼らが比較的少ない課題に直面していたからである。もしあなたが1956年のゼネラル・モーターズのトップなら、アメリカの自動車会社が市場を支配していることを知っていた。労働者を組織する労働組合は好きではなかったが、賢明であれば、経済が成長し続ければ、労働市場の安定と引き換えに労働者の高賃金を引き出せることに気づいたはずだ。部品を供給する中小企業は、注文をあなたに依存していた。毎年、あなたはフォードやクライスラーに勝ちたかったが、彼らがあなたの価格を下回らないように、またあなたが彼らの価格を下回らないように、入念なシグナル・システムを彼らと構築していた。1956年の市場シェアがどうであれ、言い換えれば、1957年も同じであることは間違いない。それなのになぜ揺さぶりをかけるのか?ミルズが主張したように、新進の経営者たちは、出世するための最良の方法はこのまま行くことだと思い込むことだったのだ。
20世紀末現在、このような図式はほとんど正確に残っていない。労働者全体に占める組合員の割合は劇的に低下し、このことは、企業が労働者に支払う賃金を低くできることを意味するが、同時に、労働者が生涯その会社にとどまることを前提に、労働者の訓練に多くの投資を期待できないことも意味する。かつてはごくわずかであった外国との競争は、今やほとんどのアメリカ企業にとって経験則となり、多くの企業が企業の一部を海外に移転し、独自のグローバル・マーケティング体制を構築するに至っている。アメリカで最も急成長している産業は、ミルズが予期していなかったハイテク分野である。(産業発展に関する現代の理論の多くは、技術的発展を強調しているが、大金持ちの発明者の数は評価できないほど少ない」と彼は書いている)。ミルズが疑念を抱いていたもうひとつの現象である)自営業者によって支配されていることが多いこれらの企業は、冷酷なまでに競争的であるため、価格をコントロールするための紳士協定を結ぶ可能性がある。このような状況下では、ミルズが述べたパターンに従おうとする経営者は、大学に移って終身在職権を得るのが最善であろう。
アメリカ資本主義の競争力学におけるこのような急激な変化は、今日のパワーエリートを特徴づけるあらゆる努力にとって重要な意味を持っている。C.ライト・ミルズはドイツの社会学者マックス・ウェーバーの翻訳者であり解釈者であったが、彼はウェーバーから、官僚化が進んだ社会は安定した保守的な社会でもあるという考え方を借用した。比較的変化の少ない社会においてのみ、エリートが権力を持つことがそもそも可能なのだ。もし出来事が急激に変化するならば、出来事をコントロールする人間よりも、むしろ出来事をコントロールする人間になりがちだからである。アメリカの企業ヒエラルキーで最も高い地位にある人々が、ミルズ時代と同様、最も権力を持つアメリカ人であることに疑いの余地はない。しかし、急速な技術革新、熾烈なグローバル競争、変化し続ける消費者の嗜好を、彼らでさえコントロールすることはできない。アメリカの資本主義は、あまりにダイナミックであるため、誰にも長い間コントロールできないのである。
『3. パワー・エリート』が書かれたのは、アメリカ人の生活において軍隊が果たすであろう正確な役割が、非常に大きく揺らいでいた時期である。歴史的にみて、アメリカ人は、敵から国を守るために軍隊の常設が必要だという考えに共感したことはなかった。確かに、アメリカ人は愛国心の表現では誰にも引けを取らなかった。彼らは将軍を賞賛し、彼らを大統領に選出する傾向が顕著だった。国益を守るために戦争が必要になれば、アメリカ人は失われた命と失われた機会という代償を払うことになる。同時に、アメリカ人は地理的に世界から孤立していることに満足する傾向があった。平時が普通で、戦争は例外だと考えていたのだ。米国が戦った主要な戦争が終わるたびに、米国人は孤立主義に後退した。
軍隊が自分たちの生活で継続的な役割を果たすことを嫌うアメリカ人は、共和党の指導者たちからかなりの支援を受けた。効果的な軍隊を組織するためには、政府を利用する以外に方法はないが、もし政府が民間企業への契約提供に関与すれば、それらの企業が請求する価格や、彼らが実践する労使関係の種類、さらには利益をどれだけ大きくできるかまで、政府が規制するようになる日もそう遠くはないだろうと保守的な孤立主義者たちは考えていた。
ミルズが『パワー・エリート』の中で主張した重要な論点のひとつは、冷戦の勃発が、アメリカの恒久的な軍事体制に対するこの歴史的な反対を完全に変容させたということである。実際、ミルズの著書の重要なテーマは、アメリカの軍事エリートが今や経済・政治エリートと結びついていることを強調した。人事は絶えず企業の世界から軍の世界へと行き来していた。ゼネラルモーターズのような大企業は、軍事契約に依存するようになっていた。軍がスポンサーとなった科学技術革新は、経済の成長を後押しした。こうした経済と軍事の結びつきが封印される一方で、軍部は積極的な政治勢力となっていた。かつては軍を敵視していた議会の議員たちも、今では将校を厚遇するようになった。どの大統領も、軍との相談なしに国務省の人員配置、情報将校の発掘、大使の任命は望めなかった。
ミルズは、軍隊がアメリカ生活の重要な力として台頭するには、かつて世論を特徴づけていた孤立主義を徹底的に攻撃する必要があると確信していた。彼は、「軍閥は、仲間の旅行者や代弁者たちとともに、自分たちの形而上学を国民全体にしっかりと植え付けようとしている」と主張した。彼らの目標は、現実の再定義に他ならず、その中でアメリカ国民は、ミルズが『終わりの予見できない非常事態』と呼ぶものを受け入れるようになるのだ。彼は、『戦争あるいは戦争準備態勢が高い状態にあることが、アメリカの正常で永続的と思われる状態であると感じられる』と書いている。このような絶え間ない戦争熱の状態では、アメリカはもはや本物の民主主義国家とは言えない。民主主義は、まさに軍事的な現実の定義では許されない反対意見や不一致によって繁栄するものだからである。ミルズが述べた変化が本当に永続的なものであったとすれば、『パワー・エリート』は、アメリカの本質における、深く急進的で憂鬱な変容の描写として読むことができるだろう。
ミルズが当時について書いたように、議会が軍に極めて友好的であることは今日でも真実である。軍事基地は多くのアメリカ人にとって重要な雇用の源である。ロッキードやボーイングのような軍用機器を製造するすべての企業にとって、政府による軍事支出は極めて重要である。アメリカ企業は世界の武器市場のリーダーであり、あらゆる場所に武器を製造・輸出している。『スター・ウォーズ』のように、飛んでくるミサイルを撃退するために設計された兵器システムであっても、軍事的な必要性が証明されなければ、決して廃れることのないものもある。少なくとも最近のアメリカ大統領の一人であるロナルド・レーガンは、ソ連を「邪悪な帝国」と宣言し、軍拡競争でロシアを出し抜く意思を示すことで人気を高めた。
しかし、こうした1950年代との類似点にもかかわらず、世界もその中でアメリカが果たす役割も変化している。ひとつには、アメリカはベトナム以来、対外紛争で継続的に戦力を投入することができないでいる。アメリカ人の命が失われることに対する国民の反発を懸念して、アメリカ大統領は海外での軍事的冒険を控えるか、ブッシュ大統領やクリントン大統領がイラクで追求したような迅速な攻撃にとどめている。さらに1989年以降、ソ連と東欧の共産主義が崩壊したことで、アメリカのエリートたちは、ソ連の脅威を理由に軍事支出への支持を動員する能力を失った。ミルズが執筆した当時は深刻な脅威と見なされていた中国も、今ではアメリカのビジネスマンに大きな潜在的投資源と見なされている。要するに、米国の大規模かつ恒久的な軍事施設に対する国内政治的支持は、もはや当然視されなくなったのである。
世界のパワーバランスにおけるこうした変化の直接的な帰結は、アメリカ経済が国防に割く割合が劇的に減少したことである。ミルズが執筆した当時、国防費は連邦政府支出の約60%を占め、国内総生産の10%近くを消費していた。1990年代後半には、その割合は連邦政府支出の17%、国内総生産の3.5%にまで低下した(図1参照)。『パワーエリート』が出版された当時、300万人近いアメリカ人が軍隊に所属していたが、今世紀末にはその数は半減していた。図1米国の経済と政治システムの両方が、軍によってますます支配されるようになるというミルズの予測は、彼の時代以降の歴史的展開によって裏付けられることはない。
図1
これらの図の重要性は、彼らを生み出した文化的、政治的な力によって強化されている。ミルズは、軍による現実の定義と、孤立主義に向かうアメリカの大衆的傾向との間の対立は、前者に有利に解決されると信じていた。しかし、1990年代には、海外での軍事的冒険に反対する声が高まり、外交政策でも国内政策でも軍が思い通りに行動する能力が著しく低下したことは明らかである。ほとんどのアメリカ人は、自分ができる最高の生活を送るのに十分なお金を稼ぐという仕事に取り掛かりたいだけなのだ。増税に反対する彼らが、軍を成長させることを不可能にしているのだ。緊急事態のレトリック、そしてそれに伴う多大な個人的犠牲の必要性は、彼らが惹かれるレトリックではない。一般的に、子供たちが戦争に行くのを見たくないだけでなく、平時の強制徴兵制にも消極的である。
このような変化は、アメリカ人の生活における軍隊の役割が、逆転したというよりも修正されたことを示唆している。戦略家たちは、たとえアメリカ軍の使用を避けるために最善を尽くそうとしても、起こりうる戦争を計画し続けている。若者を兵役に就かせようとする努力はなされているが、そのような措置が国ではなく自分のキャリアにいかに役立つかを強調することによってのみである。国防総省は科学技術の革新に資金を提供し続けるが、それらの革新が民間で利用される可能性は強調される。共和党はより強いアメリカを求めるが、1998年末の弾劾論争でクリントン大統領のイラクでの軍事的動きを批判した指導者を擁する政党でもある。アメリカは、ミルズが『パワー・エリート』を書く以前の歴史の大半を特徴づけていた劇的な孤立主義には戻っていない。しかし、1956年にミルズが描いたような劇的な(そして危険な)軍事的台頭を目の当たりにしたというのは正しくないだろう。
どうしてそうなったのだろうか?アメリカ生活において依然として最も強力な力であるビジネス企業は、その性質上ますますグローバル化しており、おそらく少数派であろう従業員が住み、働く国の防衛よりも、どこで生産されようともその利益を守ることに関心を寄せている。アメリカの大企業のリーダーのほとんどが、他国を侵略するか、その国の産業に投資するかの選択を迫られれば、前者ではなく後者を選ぶに違いない。ミルズ氏は、1950年代にアメリカの歴史上初めて、軍事エリートが経済エリートと強力な同盟を結んだと考えた。今となっては、アメリカの経済エリートは自国の軍事エリートよりも他国の経済エリートとの共通点を多く見出していると言った方が正しいだろう。パワーエリートは、パワーエリートの重要な要素の少なくとも1つが、自国の運命とそれを生み出した国の運命をもはや同一視しないという状況を予見できなかったのである。
4. 行政府と立法府を掌握する政治家と公務員は、パワーエリートの第3の足を構成する。ミルズは、当時の政治家たちはもはや、国政への階段を上る前に地方で修行する必要はないと考えていた。企業や軍部が政府とこれほどまでに連動し、しかもどちらも国家機関であるため、「政治の国有化」とでも呼ぶべき事態が起こるのは必然だった。政治家の新しいタイプは、不動産ブローカーや貯蓄貸付組合幹部とファーストネームで呼び合うような人間ではなく、将軍やCEOSと懇意にしている人間である。
ミルズは、彼が書いた当時、『政治家はマスメディアに頼らねばならず、マスメディアへのアクセスには金がかかる』と考えていた。しかし、半世紀後に選挙に出るのにどれほどお金がかかるようになるかは、ミルズでさえ予想できなかっただろう。テレビは、9インチの画面で3つの白黒チャンネルを見ることに慣れていた人々には想像もつかないほど、政治運動の一因となっている。選挙運動は、ミルズが執筆した当時よりも長期化し、より党派的になり、一般に競争が激しくなっている。永続的な選挙運動に従事する政治家たちは、資金集めに精を出さなければならなくなった。そして、その活動資金を調達するためには、資金を提供する余裕のある人々に頼らなければならない。労働組合は、特に民主党にとって重要な資金源であることに変わりはないが、両党の政治家は、現職も挑戦者も含めて、資金援助の大部分を企業から得ている。企業が資金を提供する場合、市民としての義務感からそうすることはほとんどない。政府が企業のために提供できることのリストは、企業が政府に関与してほしくないことのリストと同じくらい長い。いずれも、企業が政治家に私腹を肥やす法律を通すという明確な見返りを求めて資金を提供するという意味ではない。しかし、政治にこれだけお金がかかるのだから、ミルズが著書を書いた当時よりも、現在の方が、どう考えても企業の方が議員に対して大きな力を持っているということだ。
ミルズにとって政治とは、いずれにせよ主に見せかけのものだった。歴史的に言えば、アメリカの政治はバランス理論に基づいて組織されていた。各政権部門が他の部門とバランスを取り、競争政党が適切な代表を保証し、労働組合のような利益団体が企業のような他の利益団体に対抗する役割を果たす。しかし、パワーエリートの出現は、均衡理論をロマンチックなジェファーソン神話に変えてしまった。ミルズによれば、アメリカはパワーエリートの支配下で反民主的になり、ほとんどの決定は舞台裏で行われるようになった。その結果、議会も政党も実質的な仕事をすることがなくなった。主要政党の間に政策的な相違がなければ、プロの政党政治家は語るべきテーマを考案しなければならない」とミルズ氏は書いている。
ミルズが、18世紀や19世紀のイメージが20世紀アメリカの政治権力の実態とは無関係であることを強調したのは正しかった。しかし、それゆえに政治が空虚な演劇ショーのようなものになってしまうというのは、必ずしも正しいとは言えなかった。ミルズは、実質的な中身がなければ、政党は互いに似てくると考えていた。しかし、今日、共和党と民主党のイデオロギー的な違いは深刻である。ジョセフ・マッカーシー(ウィスコンシン州選出の保守派反共上院議員)は、ミルズの著書が書かれた時代にその名を残しているが、『パワー・エリート』には何度か登場するが、主要人物ではない。政治と経済に重点を置くあまり、ミルズ氏は、共産主義者の影響力を追及したマッカーシーの魔女狩りを含め、強力な象徴的・道徳的十字軍がアメリカ生活で果たしてきた重要な役割を過小評価していた。マッカーシズムにもっと注意を払っていれば、1998年から99年にかけて共和党がクリントン大統領を弾劾しようとしたこと、アメリカ政治において中絶、移民、アファーマティブ・アクションといった分断的な問題が果たした役割、ネガティブ・キャンペーンの継続的な重要性といった出来事を予測できただろう。アメリカの政治的アジェンダの上位に真の本質があるわけではないかもしれないが、だからといって政治が重要でないわけではない。政治システムを通じて、私たちは自分たちがどのような人間であると想像するかを決定しているのであり、だからこそ20世紀末には、どの政党が政権を握っているかが大きな意味を持つのである。
5. では、『パワー・エリート』は振り返ってどうなのだろうか?古典と見なすべきなのだろうか。過去の説明であると同時に、現在への指針として読むことができるのだろうか。これらの疑問に対する答えは、『パワーエリート』が実際には2冊の本であるという事実にかかっていると私は考えている。その最初の章(第1章から第10章まで)で、ミルズはアメリカにおける権力の構造を描写することを目的とした、やや臨床的な言葉で書いている。この部分はデータに基づいており、広範なオリジナル・リサーチを駆使している。自分の主張を述べた後、ミルズは(第11章から第15章までで)怒りの言葉へと移行する。ミルズの最も有名なフレーズである、「クラックポット的現実主義」、「高次の無知」などが登場するのはこれらの章である。これは社会批評家としてのミルズであり、記述的な科学を置き去りにして、パワーエリートに対する感情を際立たせている。
現代の論者たちは、ミルズが傑出した社会批評家ではあったが、必ずしも一流の社会科学者ではなかったと考えている。しかし私は、『パワーエリート』は社会批評というよりも社会科学の著作としてよりよく生き残っていると信じている。
ミルズが執筆していた当時、アカデミックな社会学は自らを科学であると宣言する過程にあった。ミルズの同僚の多くは、社会学者の適切な役割は、小手先の仮説の綿密な実証的検証に重点を置いた、価値観にとらわれない研究を行うことであると信じていた。壮大な科学はやがて、自然科学の最良のもののように、方法論の革新と技術的熟練を強調する高度に専門化された学術誌に発表されるような、広範な経験的研究の上に構築されるであろう。実際、ミルズは科学的社会学に対する辛辣な批評を書いており、このような目標に決して賛同していなかったため、ミルズは社会学の仲間たちから優れた科学者とみなされることはなかった。
とはいえ、1950年代のアカデミックな社会学はあまり残っていない。ミルズは彼なりに、同時代を理解するために多くの貢献をした。1950年代の社会科学者は多元主義を強調していたが、ミルズが均衡理論への批判で攻撃したのはこの概念であった。当時の支配的な考え方は、アメリカにおける権力の集中は、ある集団が常に他の集団の権力と均衡を保っているため、過剰なものとはみなされるべきではないというものであった。アメリカが直面している最大の問題は、権力の集中ではなく、社会学者が「イデオロギーの終焉」と呼び始めたことにあった。イデオロギーをめぐる壮大な情熱が枯渇する時点に、アメリカは到達したと彼らは考えた。これからは、知識人の思索ではなく、技術的な専門知識が問題解決に必要なのだ。
このような考え方に比べれば、ミルズが描くアメリカの現実は、誇張はあるにせよ、より的を得ているように思える。科学のテストが現実を正しく理解することだとすれば、C・ライト・ミルズの非常に情熱的な信念は、同時代の客観的で臨床的な研究者たちよりも、アメリカ社会をより科学的に把握することに彼を駆り立てたのである。したがって、『パワー・エリート』は、書かれた当時のアメリカで何が起きていたかをかなりよく説明したものとして読むことができる。
しかし、社会批評家としてのミルズには不満が残る。その役割において、ミルズは自らを真実のための孤独な闘士として描いており、権力や富のサイレンのような呼び声に誘惑される人がどれだけいようと、自分の正しさを主張する。これは彼の本に感情的な力を与えるが、ある種の無責任さを代償としている。ミルズが典型的な一節で書いているように、「今日のアメリカでは、問題のある人間は独断的というより、無頓着である」しかし、1950年代に権力を握っていた人々が下した決断がいかに気に入らないものであったとしても、意思決定者である彼らは、その行為の結果に責任を負っていたのである。何千人もの労働者を巻き込む企業の意思決定や、人命が失われるかもしれない軍事行動の可能性を検討したり、道路と福祉のどちらに公的資金を使うべきかを決定したりすることが実際に何を意味するのかを理解するよりも、遠くから批判する方が簡単なことが多い。ミルズ氏は、公務員を心ない人呼ばわりすることで、彼らがどのように行動すればよかったかを知っていることを暗に示している。しかし、もし知っていたとしても、彼は『パワー・エリート』の読者に語ることはなかった。ミルズが信じた価値観に世界がもっと合致するようにするために、具体的に何ができるのかが、この本には書かれていないからだ。
さらに、パワーエリートを攻撃することと、その批判を他の知識人、さらには一般大衆にまで拡大することは別のことである。後者に走ると、ミルズがアメリカは反民主主義的な国になってしまったと考えるのと同じように、反民主主義的な国になってしまう危険性がある。本書の最後に、ミルズがかつて保守派の政治理論家と強く結びついていた言葉を引用する。
「民主主義の広がりに愕然としたヨーロッパの保守的な作家たちは、20世紀を「大衆社会」の時代と宣言した。この理論によれば、大多数は決して理性的に行動することはなく、あるときはヒステリックに熱狂に巻き込まれ、あるときは無関心で引きこもり、群衆のように反応するという。アメリカは完全に大衆社会というわけではない」とミルズ氏は書いたが、その後はあたかも大衆社会であるかのように書き続けた。独立心を失い、さらに重要なのは、独立したいという願望を失っていることである。ミルズが権力エリートの力を信じ込んでしまったために、アメリカ国民が自分たち自身を見出し、彼が察知した虐待に歯止めをかけることができるという希望をすっかり失ってしまったようだった。
この諦観したような苦渋の口調は、現代の読者には傲慢に映るかもしれない。あたかもミルズだけが、他の誰にも理解できない真実を見抜くことができるかのように。優れた社会批評には、疎外だけでなく愛着も必要だ。何かに共感し、賞賛さえしなければ、それを批判することに意味を見出すことはできない。ラルフ・ウォルドー・エマーソンやウォルト・ホイットマンのような作家は、自国をより高い基準で捉えようとした。ミルズがアメリカの生活に対する彼らの寛大な感覚を共有していないことはあまりにも多く、その代わりに、カンタンな批評家として、怒りにまかせて不機嫌に、周囲の世界を拒絶するように書いている。そのため、社会批評家としてのミルズが、社会科学者としてのミルズほど効果的であるとは限らない。
『パワー・エリート』のいくつかの問題点を指摘したところで、この本が現代の古典としての名声にふさわしいものでなかったと言いたいわけではない。何世代もの学生や情報通の読者は、『パワー・エリート』を読むことによって、自分たちがどのような社会にいるのか、そしてどのような社会を望んでいるのかを考えるよう刺激されてきた。なぜなら、この本は、私たちの分析力と情熱的なコミットメントを結びつけることの重要性を思い出させてくれるからである。ミルズの本が出版されたからといって、パワーエリートの構成や性格が変わったわけではない。しかし、その存在を明るみに出したことは事実であり、ミルズを生んだ社会学の教授にとって、その学問分野からはいささか疎外された存在であったとしても、決して小さくない功績である。
さらなる読書のために
ミルズの本の重要性を示す一つの指標は、この本が他の社会科学者や社会批評家たちに、アメリカにおける権力に関する研究を進めるよう促したことである。その結果、アメリカで最も影響力のある人々をパワーエリートと呼ぶべきか支配階級と呼ぶべきか、ビジネスが政府を支配しているのか、それとも政府がビジネスからある程度の自律性を保っているのか、ビジネスの利益に反する法律を民主的政府が通過させることは可能なのか、外交政策の決定を支配しているのは軍人なのか民間人なのか、ミルズが論じた3つの制度に教育、娯楽、スポーツといった新たな制度を加える必要があるのか、といった疑問をめぐる数多くの学術的論争が起こった。
ミルズが確立した伝統の中で、おおよそ次のようなことを書いている代表的な人物がいる: Michael Schwartz and Beth Mintz, The Power Structure of American Business (Chicago: University of Chicago Press, 1985)などがある。デイヴィッド・ヴォーゲル『Fluctuating Fortunes』(邦訳『アメリカにおけるビジネスの政治力』講談社、1985): The Political Power of Business in America (New York: Basic Books, 1989)は、ビジネスの権力を必ずしも所与のものとしてではなく、ビジネスが得たり失ったりしうるものとして扱っている。最近の学者の多くは、ビジネスが政治において常に望むものを得られるとは限らないという立場に傾いている。ビジネスエリートの経営的性格に関するミルズの理解は、スティーヴン・ブリント『専門家の時代』(In an Age of Experts: The Changing Role of the Professions in America (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1994)を読んで補うべきである。
軍に関するミルズ氏の考えを最新のものにしようとした研究に、ジョン・L・ボイズ『ハルマゲドンのために買う』がある: Business, Society, and Military Spending Since the Cuban Missile Crisis (New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 1994)がある。少なくとも1冊の最近の本は、軍隊を反民主的なものとするミルズ氏の特徴付けに強く反対しており、例えば、軍隊はアメリカで大規模な人種統合が行われた数少ない場所の1つであると指摘している: Charles C. Moskos and John Sibley Butler, All That We Can Be: Black Leadership and Racial Integration the Army Way (New York: Basic Books, 1996).
政治エリートの性格を形成する上で、金と企業の権力が果たす役割に関する最近の著作には、トーマス・ファーガソン『黄金律』がある: The Investment Theory of Party Competition and the Logic of Money-Driven Political Systems (Chicago: University of Chicago Press, 1995)や、Ronald Frederick King, Money, Time, and Politicsなどがある: Investment Tax Subsidies and American Democracy (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1993)がある。しかし、ビジネスがしばしば矛盾したことを望んでいるため、国家が企業エリートの直接的な奉仕者として機能することは不可能であると指摘する学者もいる。キャシー・J・マーティン『Shifting the Burden: The Struggle over Growth and Corporate Taxation (Chicago: University of Chicago Press, 1991)を参照のこと。
最近出版された2冊の本が社会批評を扱っており、何が社会批評を効果的なものにするのか、社会科学との関係はどうなっているのかといった問題を扱っている: Michael Walzer, In the Company of Critics: Michael Walzer, In Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century (New York: Basic Books, 1988)とAlan Wolfe, Marginalized in the Middle (Chicago: University of Chicago Press, 1996)である。
謝辞
現代社会の最上層も最下層も、本を読んだり書いたりする人間にとっては普通の世界ではない。中流階級を理解するためには、実際に身の回りにあるものを見るしかないが、最上層や最下層を理解するためには、まず発見し描写することを求めなければならない。現代社会の最上層はしばしばアクセスしにくく、最下層はしばしば隠されている。
また、彼らの性格や活動に関する多くの公的情報は、組織的に誤解を招くものであり、彼ら自身も多忙で飄々としており、秘密主義的ですらある。多くの未解決の資料がすぐに手に入るかどうかで研究分野を選ぶとしたら、決してエリートを選ぶべきではないだろう。とはいえ、私たちが生きている社会の本質を理解しようとするならば、厳密な証明が不可能だからといって、重要だと信じるものを研究しないわけにはいかない。権威も公的な援助もなく、何かを調査しようとするとき、その調査には失敗がつきものである。しかし、そのような状況下でできることを主張することで、彼らや彼らの代理人を論争に巻き込み、より多くのことを学ぶことができる。
きっちりとした証明を求める私たちの欲求や、事実に対する真のニーズは、推論を共にすることが、真理に到達するための適切な方法として、今でも非常に重要な部分ではないということを、まったく意味しない。この種の本は3つの会話からなる: ひとつは、作家が自分自身や架空の人物と交わす会話で、これはここに記録されている。その下には、作者が知ってか知らずか、ある影響力のある思想家や観察者たちの会話があり、彼らの見解は作者の心の中にも、読者の心の中にも入り込んでいる。そしてまた、読者の心の中では、自分自身と彼との、もうひとつの暗黙の会話が進行している。従って、作家の仕事のひとつは、この2つの暗黙の会話をできるだけ多く自分の書いた作品に取り込もうとすることである。読者とともに推論することで、彼は自分の見解を述べる以上のことをする。また、それを明確にし、そうすることで、自分でも知らなかったアイデアに気づくのである。
私たちは、ディテールに忙殺されるあまり、そのディテールが存在する世界を当たり前のものと考えたくはない。私たちは世界を当然だとも、単純な事実だとも思っていない。私たちの仕事は、私たちの考えをひっくり返したり、確固たるものにしたりするために必要な限りにおいてのみ、事実を扱うことである。図や数字は、適切な研究の始まりにすぎない。私たちの興味は、自分たちが知っている、あるいは容易に知ることができる事実を理解することにある。私たちの重要な疑問のほとんどは意味の問題だからである。
もちろん、私たちは共に推論する対話の外に出て、さまざまな種類の特別な研究によってできることを発見し、その結果を「私たちのインナーシティ」で行われている会話に導入してきた。私たちがこのようなエッセイのような推論方法を採用すべき理由は十分にある。便利で、実りあるものであることを願っている。この方法によって、効果的なさまざまな視点と技術を結集することができ、読者をアメリカのより高いサークルについての対話の一員に誘うことができる。
本書のための研究資金はコロンビア大学の社会科学研究評議会から提供された。また、オックスフォード大学出版局(ニューヨーク)からも資金を提供していただいた。オックスフォード大学出版局は、通常の出版社の枠を超えて、本書や他の本の執筆を支援してくれた。1953年春、ブランダイス大学にビジターとして滞在している間に、この資料の最初の草稿が完成した。1954年の夏、私と妻はカリフォルニア州パシフィック・パリセーズのハンティントン・ハートフォード財団のレジデント・フェローとして滞在した。
妻のルース・ハーパー・ミルズは、主任研究員兼編集顧問として、本書の多くを形作ってくれた。ウォルター・クリンク、ポール・ルーカス、ウィリアム・テイバーは、研究メモを書くことで私を助けてくれた。また、キャサリン・スタントン夫人の秘書業務にも感謝したい。彼女なしには、本書は存在せず、混沌とした原稿ファイルだけが残っていただろう。
連邦政府、軍、大企業を直接知っている何人かの人々には、大変お世話になった。彼らの援助がなければ、この本はもっと貧弱なものになっていただろう。そのため、彼らの要請で名前を挙げて謝辞を述べることができないという事実が、私にとっていっそう重荷となっている。
彼らの助言を惜しみなく与えてくれた他の友人には、次のような人たちがいる: ルイス・コーザー、ルイス・フリードランド、ハーバート・ゴールド、リチャード・ホフスタッター、アーヴィング・ハウ、フロイド・ハンター、パオロ・ミラノ、ハリー・L・ミラー、ウィリアム・ミラー、アーヴィング・サネス、ベン・セリグマン、ケネス・M・スタンプ、ハーヴィー・スワドス。
索引
注:この索引にはNOTES, pp.365-412に掲載されている名前や肩書きは含まれていない。
以下の「FOURTEEN:保守ムード」を参照のこと。
共産主義者の工作員が政府に入り込んでいる、あるいは入り込んでいると告発する人々や、彼らに怯える人々は、「では、共産主義者が上層部にいるとして、彼らはどれほどの力を持っているのか」という疑問を決して口にしない。上層部に共産主義者がいるとして、彼らにどれほどの権力があるのだろうか?』彼らは、上層部にいる人物、あるいはこの場合はそのような人物に影響を与える可能性のある立場にいる人物でさえ、重要な出来事を決定するのだと思い込んでいるだけなのだ。共産主義者の工作員が中国をソ連圏に奪われた、あるいは忠実なアメリカ人に影響を及ぼして中国を奪われたと考える人々は、積極的に、あるいは怠慢や愚かさによって、そのような事柄を決定する一連の人物がいると単純に思い込んでいる。共産主義者の影響力がそれほど強かったとは考えない他の多くの人々は、忠実なアメリカの意思決定者たちが自分たちだけで中国を失ったと思い込んでいる。
無力なエリートという考え方は、『ELEVEN:均衡の理論』で述べるように、権力の問題が経済エリートにとって、その存在を否定することで解決される自動経済の考え方によって、大いに裏付けられている。誰も本当の変化をもたらすだけの力を持っていない。出来事は匿名の均衡の結果なのだ。政治エリートにとっても、均衡モデルは権力の問題を解決する。市場経済と平行して、リーダー不在の民主主義があり、そこでは誰も何事にも責任を負わず、誰もが何事にも責任を負う。
新上流階級の女性は、やや異なるイメージを持っている。彼女はしばしば、旧上流階級の威信を「文化的」なものとして評価する。彼女はしばしば、古い身分に「教育的」な意味を与えようとする。これは特に、夫が専門職の男性で、自分自身も「良い大学」出身である駅馬車族の若い女性たちに当てはまる。自らも教育を受け、文化的なコミュニティ活動を組織するための時間とお金を持っている新しい上流階級の女性たちは、男性よりも古い上流階級のスタイルの「文化的」要素を尊重している。こうして旧上流階級の社会的優位性を認めることで、新しい上流階級の女性たちは、自分たちも利用できる旧上流階級のテーマを強調する。しかし、そのような女性たちは、今日、小さな町の旧上流階級の身分主張にとって、最も信頼できる換金所を形成している。彼女たちは文化的なことに興味はあるかもしれないが、その機会も素養も教養もない。彼女たちはレクチャー・シリーズを利用することはできるが、それを主宰する素養はない』。
下記、『FOURTEEN:保守ムード』参照。
旧来よりも積極的な新しい上流階級の基準は、本当に一流の人々にとって、彼らが金持ちであることだけでなく、彼らよりもさらに大きな方法で『一流』になり、『一流』になりつつある他の人々とのコネクションを持っていることである。ある典型的な小都市では、新しい上流階級のヒーローたちは、『ダイナマイトをたくさん持っている少年たち……彼らは一緒にあちこちに行き、(都市にとって)良いことなら何でもやっている。彼らは全国的に活動している。彼らは地元のことにはあまり積極的ではないが、活動的な男たちだ。彼らはいたるところに積極的な投資を行っており、何もせずにただお金を眠らせているわけではない。没落した旧家と、勃興した活発な新家の話は、新しい上流階級に「民主主義の仕組み」と「エネルギーと頭脳があれば誰でも出世できる」可能性を示している。このような物語は、彼ら自身の地位とスタイルを正当化するのに役立ち、賢く働く方法を知っている者が必然的に成功するという、公的な神話の全国的な流れを利用することを可能にする。旧来の上流階級は、少なくともよそ者にはそのような話はしない。彼らの間では、名声とはそれ自体肯定的なものであり、彼らの生き方、いや、存在そのものに内在するものだからだ。しかし、新しい上流階級の人間にとっては、名声とは、彼自身は本当に持っているわけではないが、自分のビジネスや社会的地位の向上のために大いに利用できるもののように思われる。この町では、彼ら(旧上流階級)がいなければ何もできない。この町では、彼ら(旧上流階級)なしには何も始まらないんだ」投資家とか経営者とか、そういう人たちは、僕らがそうするまで、ただ我慢しているんだ。そうでなければ、世界最高のプロジェクトがあったとしても、死んで生まれてくることになる」
しかし、授業の速い動きだけがショーを混乱させるわけではない。動きの速いものはほとんど何でもそうだ。というのも、生活様式の慣習は、その地域社会の威信にとって重要であり、階級と地位の関係が安定しているところでのみ、慣習は安定するからである。慣習が本当に厳格であれば、服装は「衣装」となり、慣習は「伝統」となる。先祖の高い威信、老齢の威信、古い富の威信、骨董品の威信、居住地の「年功序列」の威信、会員権の威信、何事にも古くからのやり方の威信-これらは一体となって、安定した社会における固定したサークルの身分慣例を構成している。
社会が急速に変化するとき、名声は、たとえそれが呪われたものであったとしても、若く美しいものに、たとえそれが低俗なものであったとしても、単に変わったもの、「斬新なもの」に向かう傾向がある。コスチュームは「古臭い」ものとなり、何よりも重要なのは「ファッショナブル」であることだ。家の外観の価値、そしてマナーや自分自身までもが、流行に左右されるようになる。要するに、新しいものがそれ自身のために評価されるのである。このような状況では、ドレス、車、家、スポーツ、趣味、クラブなど、ダイナミックで急勾配の消費パターンの違いについていけるかどうかは、お金で簡単に決まる。もちろん、ヴェブレンが「仰々しい消費」や「目立つ浪費」という言葉を使ったのは、このような状況に対してであって、安定した余暇階級に対してではない。アメリカ、そしてヴェブレンが書いた時代の第二世代にとって、ヴェブレンの言葉はおおむね正しかったのである。
幸いなことに、ソーシュタイン・ヴェブレンの『有閑階級の理論』(1899)がいまだに読まれているのは、アメリカの上流階級に対する彼の批判がいまだに適切だからではなく、批判がまじめに受け止められていなくても、彼の文体がそれをもっともらしくしているからである。彼の書いたものは、たとえ事実が現代に出現した場面や人物を取り上げていないとしても、真実として強く残っている。それは、彼が何を、どのように書いたかがわからなければ、私たちが現代の新しい特徴を見ることができなかったからである。それは、彼の偏見がアメリカの社会的抗議文学の中で最も実り多いものであるという事実の一つの意味でもある。しかし、すべての批評家は死すべき存在であり、ヴェブレンの理論は一般に、アメリカの威信のシステムを説明するにはもはや適切ではない。
『有閑階級の理論』は、有閑階級の理論ではない。それは、ある国の歴史のある時期における上流階級の特定の要素についての理論である。特に、ヴェブレンの形成期、すなわち19世紀後半のアメリカ、ヴァンダービルト、グールド、ハリマン、サラトガスプリングス、ニューポート、きらびやかな金と金のアメリカにおいて顕著であったヌーボーリッチについての考察である。
これは、金をステータスの象徴に変換することによって社会的に上昇しつつある上流階級を分析したものだが、その象徴が曖昧なステータスの状況下でそうしているのである。さらに、ヴェブレン劇の観客は伝統的なものではなく、役者も封建制のように受け継がれた社会構造の中にしっかりと固定されているわけではない。したがって、消費パターンだけが地位の名誉を競う唯一の手段なのである。ヴェブレンは、旧来の貴族社会や、廷臣が成功した生活スタイルであった宮廷社会を分析しているわけではない。
ヴェブレンは、アメリカ人の高尚な生活様式を描くにあたって、彼が書いた俳優たちと同じように、貴族とブルジョアの特徴を混同しているように見える。一つか二つの点で、彼は明確にそうしている: 貴族的特質とブルジョア的特質、つまり破壊的特質と金銭的特質は、主として上流階級の間に見出されるべきものである……18。
ヴェブレンが知っていたように、「目立つ消費」は上流階級に限ったことではない。しかし今日では、新しい上流階級の一要素、つまり新しい企業特権を享受するヌーボー・リッチ、つまり経費勘定をする男たちや、その他の企業特権を享受する者たちの間で特に蔓延していると言うべきだろう。また、舞台やスクリーン、ラジオやテレビのプロの有名人たちの生活水準やスタイルには、さらに深刻な影響を与えている。そしてもちろん、「テキサスの大富豪」によってドラマ化された、より古風なヌーボー・リッチたちも同様である。
ヴェブレンが観察した19世紀末と同じように、20世紀半ばにはファンタスティックな出来事が起こっている: テノール歌手のマリオ・ランツァは、金メッキのダッシュボードを備えた特注の白いキャデラックを所有している……レストラン経営者のマイク・ロマノフは、シルクと紬のシャツをマンハッタンのスルカに航空便で送り、きちんと洗濯してもらっている……建設王のハル・ヘイズは……キャデラックにビルトインのバーを備え、自宅にはスコッチ、バーボン、シャンパン、ビール用の蛇口を備えている……」19。 19しかし、地元の既成社会では、第4世代と第5世代の男女は、静かに高価で、高価なほど静かである。実際、彼らはしばしば、意図的に目立たない消費をしている。気取らない農家や避暑地で、彼らはしばしば極めてシンプルに暮らし、確かに下品な豪華さを仰々しく見せることはない。
ヴェブレンの理論の用語は、今日の既成の上流階級を説明するには適切ではない。さらに、第4章で述べるように、ヴェブレンの著作は、アメリカの身分制度の理論として、制度化されたエリートの台頭やセレブの世界を十分に考慮していない。もちろん、彼は1990年代に、マス・コミュニケーションとエンターテインメントの全国的メディアの一部として生まれた「職業的セレブリティ」が、真に国民的な身分制度にとってどのような意味を持つかを見抜くことはできなかっただろうし、デビュタントが映画スターに取って代わられ、地方社交界の貴婦人たちが、今や多くの人々が自分たちの頭領として讃える軍人や政治・経済的経営者-「パワー・エリート」-に取って代わられるような、国民的な魅力の発展を予想することもできなかっただろう。
1933年でさえ、50人ほどのニューヨーカーがボストンのサマセット・クラブの会費を維持していた20。
産業界のリーダーや偉大な職業人の娘は、女性の家庭的な美徳、すなわち柔和さと慎み深さ、真面目さと神々しさをあまり重視しない複雑な文明の中で成長しなければならない。しかし、そのような人物は、その種の風習に従って、自分の娘を、このような基礎の上に規範を置く一握りの教育機関のひとつに通わせなければならない……この国にある1,200余りの私立女子校のうち、不思議なことに、本当に重要なのはわずか5校かそれ以上である……ある学校と別の学校を区別するものは非常にはかないものであり、実に無形のものである」24。
『ファウチュン』誌の編集者は、「このような男子校は、入学者数に比してはるかに目立っている」と書いている。現在(1944)、アメリカでは700万人以上の少年少女が中等教育を受けているが、そのうち46万人は私立学校である。このうち36万人以上がカトリックの学校に在籍し(1941年の数字、入手可能な最新のもの)、1万人以上が軍学校に在籍している。残りのうち、職務が比較的明確な女子校が3万人近くを占めている。4万人余りが男女共学で、主にデイスクールに在籍していた。2万人ほどは、特に自己正当化を望む集団である男子校であった26。
「企業富裕層」を参照。
アイダ・ターベルはオーウェンD.ヤングについて、「……彼のビジネスや法律関係の仲間内では、彼が、「偉大な大統領」になるであろうことは誰もが認めるところだが、ある男が私に言ったように、「大統領職によって台無しにされる」には、彼が今いる場所であまりにも貴重な公僕であるという思いがある……彼には同じくらい親密な崇拝者が他にもいる: ウィル・ロジャースは彼を「誇りをもって指差せる」存在にしておきたいと考えている。ニコラス・マーレー・バトラー博士は、1930年秋の晩餐会で彼を紹介する際にこう言った: 「私たちの主賓は、公職には就いていないが公務員である。公僕が公職に就くかどうかは偶発的なものであり、もしこの公僕が偶発的に公職に就いたとしても、公僕の公共サービスを大きく低下させる可能性はないに等しい」28。
ヤング氏は1931年、自身の経済形而上学でこう述べている: 民主的な政治を機能させるための舞台効果として、ある程度の馬券遊びが必要なようだ。世界は、政治にはある程度のおふざけが許されることを学んだ。政治が舞台の上では魅力的であっても、楽屋ではしばしば小心で小心者である……過去10年間の経験から、経済機構、特に金融を政治の支配や統制から自由にしておく必要性ほど明らかなことはない」29。
** このように、ハロルド・イクスは、「ある政治団体の首脳が別の政治団体の首脳を国賓訪問した」ことについて、こう書いている: 国王夫妻がほとんどの時間を過ごしたポーチに座るよう求められたのは、選ばれたわずかな人々だけで、ハル夫妻を除けば、閣僚の中で選ばれるに値すると思われたのはジム・ファーリーだけだったようだ。しかし、J・P・モルガンはそこにいたし、ジョン・D・ロックフェラー・ジュニア、コーネリアス・ヴァンダービルト夫人などもいた。それ以外の閣僚たちは、芝生に下りてきた一般の群れ、約1500人と一緒にわいわいしていた。あまり頻繁ではないが、国王夫妻は優雅に群れの間を下りて行き、あちこちでお辞儀をしたり、より選りすぐりの人たちを紹介されたりしていた」30。
フランスでは、「威信」という言葉は、詐欺や幻想の技術、あるいは少なくとも不純なものを連想させる。イタリアでも、この言葉はしばしば「まばゆいばかりの、欺瞞的な、伝説的な」ものを意味する言葉として使われる。また、ドイツでは、間違いなく外来語であるが、ドイツ語のアンシェン(Anshen)や「尊敬」、あるいはデア・ニンバス(der Nimbus)に相当し、これはわれわれの「魅力」に近い。
大金持ちを選ぶ際の手順については、この脚注を参照のこと。
もちろん、同じ金額でも時代によって価値は異なる。しかし、この事実によって我々のリストが修正されることはない。1900年の1,500万ドルの価値が、1950年の価値では3,000万ドルなのか4,000万ドルなのかという問題には、ここでは関心がない。われわれの唯一の関心は、他の時代の富裕層と比較した場合、あるいは国民全体の所得や財産と比較した場合に、それがどの程度の富裕層であったかにかかわらず、それぞれの時代の富裕層にある。したがって、各世代の富は、各世代が約60歳の壮年期に達した時点のドル価値で示されている。
億万長者のハントを含む1950年の世代では、3億ドル以上を所有する人が6人いると推定されるが、1900年や1925年にはそのような人は3人もいなかった。このような高貴なレベルからさらにピラミッドを下ったところでは、財産の大きさによる分布は3世代ともほぼ同じである。大体、各グループの約20%が1億ドル以上の層であり、残りは5,000万ドルから9,900万ドルの層と3,000万ドルから4,900万ドルの層の間でほぼ均等に分かれている。
ヴェブレンの上流階級に対する観念の多くが依拠している労働の恥ずべきものという考え方は、多くの上流階級の要素を含むアメリカ生活の多くに特徴的なピューリタン的労働倫理とはあまり一致しない。ヴェブレンが余暇階級について書いた本の中で述べているのは、中流階級ではなく上流階級についてのみであろう。彼は上流階級のビジネスマンのすることを「仕事」と呼びたくなかった。ヴェブレンにとっては、余暇階級という言葉そのものが上流階級と同義語になってしまったのである。ヴェブレンが彼らの労働を認めず、実際、労働という言葉を与えることを拒否したことは、彼の肯定的な言葉の一つである労働とは無関係である。しかもこの場合、上流階級という社会形成についての理解を曖昧にし、歪めてしまう。しかし、ヴェブレンがこの単純な事実を全面的に認めれば、彼の視点全体が破壊され(あるいは、彼の批判の主要な道徳的基盤の一つが破壊され)、より洗練されたものにならざるを得なかっただろう。
ヴェブレンは、数少ない明確なアメリカ的価値観のひとつである効率性、有用性、実際的単純性を心から受け入れていたのである。彼のアメリカ社会の制度や人事に対する批判は、例外なく、それらがこのアメリカ的価値を十分に満たしていないという信念に基づいていた。私が考えるように、彼がソクラテスのような人物であったとすれば、彼は彼なりのやり方で、ソクラテスがアテナイ人であったように、アメリカ人であったのである。ヴェブレンが批評家として効果的であったのは、まさに効率性というアメリカ的価値観を使ってアメリカの現実を批判したからである。彼はただこの価値を真剣に受け止め、破壊的なまでに体系的な厳密さをもって利用したのである。それは、19世紀のアメリカの批評家にとって、あるいは現代のアメリカの批評家にとって、奇妙な視点であった。ヘンリー・アダムスのようにモンサンミッシェルから見下ろしたり、ヘンリー・ジェームズのようにイギリスから見渡したりしたのである。ヴェブレンによって、おそらくアメリカの社会批評の性格は一変した。ノルウェー移民の息子、中西部の大学で英文学を教えるニューヨークのユダヤ人、ニューヨークを墜落させるために北上してきた南部人などである。
20歳から始めて50歳くらいまで働き、年間20万ドルを貯めたとしても、5%の複利で1400万ドルにしかならない。
しかし、もしあなたが1913年にゼネラルモーターズ株を9900ドル分しか買わず、自分の判断力を働かせる代わりに昏睡状態に陥り、その収益をゼネラルモーターズに積み上げたとしたら、1953年には約700万ドルになっていただろう。
また、ゼネラル・モーターズを選ぶという判断も働かず、1913年に上場された480銘柄にそれぞれ1万ドルずつ、合計約100万ドルを投資し、その後1953年まで昏睡状態に陥っていたとしたら、1000万ドルの価値が生まれ、さらに1000万ドルの配当金と権利を受け取っていたことになる。値上がり率は約899%、配当利回りは999%である。いったん100万ドルを手にすれば、昏睡状態にある人間にとっても、メリットは蓄積されていくだろう18。
連邦取引委員会のジョン・M・ブレアは、「少なくとも、単一企業による複数の生産単位の所有と管理が効率性に寄与するという広く受け入れられている仮定は、裏付けとなる事実が圧倒的に欠如していることの上に成り立っているように思われる」と主張している。これらの大企業が達成した唯一の顕著な利益は、原材料の購入においてであり、これは間違いなく、技術的または経営的な効率性よりも、その優れた購買力によるものである」14。
経済学者ジョン・K・ガルブレイスが行った対抗力の新たな均衡の模索も、法律理論家A・A・ベール・ジュニアが行った抑制的な企業良心の模索も、どちらも説得力がない。両者とも、企業の認められている権限に対する抑制を示すことに関心を持っている: ガルブレイスは、均衡理論の新しいバージョンにおいて、それを外から発見し、ベルルは、権力者の良心についての奇妙な見解において、それを内から発見したのである。
I. 新たな巨大企業の間に存在するかもしれない均衡には、多くの例外があることに注意しなければならない。ある産業は、供給源から最終消費者まで統合されている。また、住宅建設のように、個々の請負業者が、強力な職人組合と強力な供給業者の間で、均衡を保つどころか、圧迫されている産業もある。さらに、ガルブレイス氏自身が認識しているように、「対抗力」はインフレ期には機能しない。インフレ期には、賃金要求に対する企業の抵抗力が低下し、コスト上昇分を消費者に転嫁することが容易になる。このような時代には、大組織は対抗するどころか、「大衆に対抗する連合」となる。大きな権力集団は、互いに対抗することによって消費者に利益をもたらすというよりも、むしろ消費者を束縛するのである。鉄道を除けば、30年代に政府がバックアップするまで、強力な産業で強力な組合が発展することはなかった。また、チェーンストアは自動車や石油に対抗して繁栄するのではなく、むしろ食品供給業者という比較的集中度の低い分野で繁栄するのである。要するに、新しい均衡は自主規制的なものではないのだ。権力が自動的に対抗力を「生む」わけではないことを知るには、農業労働者とホワイトカラー従業員のことを考えればよい。しかし、ガルブレイス氏は、弱い方の単位は反対勢力を組織すべきだと主張する。そうすれば、おそらく政府の援助を得られるだろうし、政府は不均衡の弱い側を支援すべきである。こうして、強さだけでなく弱さも対抗力につながることになり、大きな均衡の理論は、現実の理論ではなく、公共政策への指針、戦略的行動への道徳的提案になる。さらに、政府は均衡の不可欠な要素であるというよりも、市場力の弱い人々を補強することに偏った審判者であると想定される。大きな均衡の概念を、適用されなければならない資格や例外と並べてみると、「対抗力」という大胆な最初の声明ほど説得力はないように思われる。これに取って代わろうとする小企業家間の「競争」と同様、大ブロック間の「対抗力」も、事実の説明というよりはイデオロギー的な希望であり、リアリズムというよりはドグマである15。
II. ベール氏の企業良心の探求については、それを発展させたと思われる人物についての説明は、本章の残りを参照されたい。貨幣経済においては、便宜主義は長期的なものにも短期的なものにも従う。政治的制度と一体化し、軍事的購入によって補強された経済において、より長期的な利益を求め、安定的な利益を得ようとする彼らの傾向は、企業がより政治的になることを要求する。そして今日、企業は経済機関と同じくらい政治的な機関となっている。政治機関としては、もちろん全体主義的で独裁的であるが、対外的には公共的な関係や自由主義的な防衛のレトリックを多く示している。ベルル氏は、要するに、都合のよい広報を「企業の魂」と勘違いしているのである16。
以下、「SEVEN:企業富裕層」を参照のこと。
官僚のキャリアについては、以下の「ELEVEN:バランス論」を参照のこと。
昼食会の席上、ヤングはホワイトに「最高執行責任者(COO)」の肩書きとストックオプション(株価が上がらない限り、セントラルの株式を固定価格で購入できる権利)を提案した。ホワイトはこれを拒否し、ヤングが移籍してきたら、65歳で定年退職するまで年俸12万ドル、その後5年間は年7万5000ドルのコンサルタント料、その後は年4万ドルの終身年金という契約を放棄すると発表した。
すぐにホワイトは、セントラルの資金から年間5万ドルプラス経費で広報会社を雇い、セントラルの1億2500万ドルの広告予算を来るべき戦いに回し、ウォール街からプロの委任状勧誘者を雇った。ヤングはパームビーチから、富裕層や人脈を持つ友人たちの間で徒党を組み、不動産の区画を支配するための工作を始めた。ウールワース財閥のアレン・P・カービー、そしてそれぞれ3億ドル以上の資産を持つ2人だ: クリント・マーチソンは以前ヤングと取引があり、シド・リチャードソンはヤングの牧場を訪れたことがあった。取引は、1株26ドルで80万株(2,080万ドル相当)のブロックを確保する形でまとまった。もちろん、大富豪たちは現金を用意する必要はなかった: 主にアレゲニー社から借りたのである。アレゲニー社はヤング氏の個人資産として扱うことができ、ヤング氏はその0.07%を個人的に所有している。そして、20万株を除くすべてのリスクをカバーする形で借りた。彼らは予定されていた新取締役会に参加していた。ヤングは80万株の議決権を持っていた。
ロックフェラーの銀行であるチェース・ナショナル・バンクは、これらの株式の管理信託を受けていたが、現在はマーチソンとリチャードソンに売却していた。銀行の取締役会長ジョン・J・マクロイは、ホワイトをリチャードソンとマーチソンに会わせる手配をし、翌日ニューヨークへ飛んだ。ニューヨーク・セントラルの株式の12.5%を所有することになったテキサンズは、妥協案を取り決めようとした。そして、より分散した所有者の票をめぐる争奪戦が始まった35。
ヤング側は305,000ドルを費やした。(ヤング側は30万5,000ドルを費やした(後にニューヨーク・セントラルが返済したため、勝者と敗者の双方が負担することになった)。海岸から海岸まで100人のホワイトの勧誘員が株主を訪ね、鉄道のボランティア従業員も数百人いた。ヤングは委任状勧誘の専門会社にも依頼した。また、マーチソンが所有するオフィス家具製造会社、ダイボルド社にも委任状勧誘のために250人の営業マンを雇った。ヤングが勝てば、ニューヨーク・セントラル社のオフィス家具は今後ダイボルド社製になるかもしれない36。
最近、98人の経営幹部と人事企画担当者に、「人間関係を第一に考える」経営幹部と、「個人的な強い信念を持ち……常識にとらわれない決断を下すことを恥ずかしがらない」経営幹部のどちらを選ぶかを尋ねたところ、63人がその選択を厭わなかった。
このシフトは、もちろん1936年から1951年の間と比べればさらに決定的なものであるが、一般的にはいくつかの経済的事実に起因している。(2) 家庭内の所得が大幅に倍増した。1951年には、2,000ドル未満と15,000ドル以上の両極端の家庭のうち、妻も働いている家庭の割合はそれぞれ16%未満であったが、3,000ドルから9,999ドルの所得範囲では、働いている妻の割合は家庭の所得とともに16%から38%へと徐々に増加した4。(3) 20年代から30年代にかけては、極貧層の多くが農家であったが、現在では農家は減少し、農家を営む人々にとっては、さまざまな政府補助金によって繁栄が支えられている。(4)組合の圧力-30年代後半以来、賃金の絶え間ない上昇を余儀なくされている。(5)30年代から始まった政府の福祉プログラムは、最低賃金、高齢者社会保障、失業者や障害退役軍人のための年金によって、所得を下支えしてきた。(6)もちろん、40年代と50年代の繁栄の根底には、戦争経済という構造的事実がある。
1949年に1万ドル未満の税金を納めていた人々が受け取ったお金の約86パーセントは、給与と賃金によるものであった。
年間1万ドルから9万9,999ドルの所得を受け取っている人々の間で、企業家による引き出しの割合が最も大きくなっている。この所得レベルの人々が得ている所得の34パーセントが事業利益であり、41パーセントが給与および賃金、23パーセントが財産である。(2パーセントは「雑所得」、年金や年金である)。
もちろん、このような図は、インフレの要素を考慮していないため、大金の意味を示す粗い指標にすぎない。ある年の企業富豪の数は、100万ドルの所得の数と同様に、税率と企業の利益水準に関係している。1929年という理想的な年には、513人の個人、遺産、信託が100万ドル以上の所得を得たと政府に申告した。これらの百万ドル所得の平均は236万ドルで、税金を差し引いた平均的な百万ドル所得者は199万ドルを手にしていた。1932年の不況の年にも、100万ドル以上の所得を申告した人は20人いた。1939年には、アメリカ全世帯の4分の3が年収2,000ドル以下であったが、そのような100万ドル所得者は45人いた。しかし、戦争が始まると、一般的な所得水準と同様に、100万ドル所得者の数も増加した。利益も税金も高かった1949年、100万ドル以上の所得を得たと政府に申告した120人の平均所得は213万ドルで、税金を引くと91万ドルになる。しかし、1919年には、利益は少し減少していたものの、税金と利益が高かったため、100万ドル以上の所得を得たのは65人にすぎず、税引き前の平均は230万ドルだったが、税引き後は82万5000ドルにすぎなかった8。
例えば、ある人が神学大学院に10,000ドル相当の株式を寄付した場合、節税のため、実質的な負担は4,268.49ドルにしかならない。10年後、その株式は時価で16,369.49ドルに値上がりし、男性は贈与費用より50%多い6,629ドルの所得を受け取るとする。この男性が死亡した場合、もちろん神学校が株式を所有し、その収益を受け取ることになる12。
25,000ドルの投資に対する1,000ドルのリターンを含め、30,000ドルの課税所得がある。税引き後では、この1,000ドルの所得は450ドルの価値しかない。これを4%の複利で10年間積み立てると、彼の家族のための資金はせいぜい5,650ドル程度になる。しかし、この男性が25,000ドルの投資を短期信託に移したとしよう。一定の条件を満たせば、信託は1,000ドルの収入につき約200ドルの税金を支払うことになり、800ドルが残る。10年後には約9,600ドルに積み上がる可能性があり、これは信託なしで積み上がった場合よりも70%の利益となる。蓄積された所得は信託の受益者、つまり課税の軽い身内の誰かに渡ることになる」14。
ビジネスマンは現在、年間400万時間近く自家用飛行機で移動している。
** 例えば、「過去2年間で、300人以上の下院議員が、非公式に見積もられた米国納税者の負担額は350万ドル以上である。その多くは、疑いなく有益で合法的な視察や調査であった。その他は、疑いようもなくタダ乗りであった。先週、下院規則委員会は、ジャンケットに蓋をするよう通告した。
すべての調査権限を承認しなければならない同委員会は、外務、軍事、島嶼問題委員会の委員に限り、自由な海外旅行を承認する予定だと述べた。ニューヨーク・タイムズ紙は、「議会周辺では先週、この夏にパリで通常の定数を集めるのは難しいという箝口令が敷かれた」と結論づけた28。
ハワード・ヒューズが関係している提案のひとつに、フロイド・オドラムからRKOを約900万ドルで買収するというものがある。天然痘が必要だったように、それが必要だったんだ!」この動きについて説明を求められたヒューズは、「…フロイド・オドラムからRKOを買った唯一の理由は、購入の詳細を話し合っている間、インディオ(カリフォルニア州)の彼の牧場まで何度も飛行機で行って楽しんだからだ」と真面目に答えている36。
共和党への献金リストのトップは、ロックフェラー家(94,000ドル)、デュポン家(74,175ドル)、ピュー家(65,100ドル)、メロン家(54,000ドル)、ウィアーズ家(21,000ドル)、ホイットニー家(19,000ドル)、ヴァンダービルト家(19,000ドル)、ゲーレット家(16,800ドル)、ミルバンクス家(16,500ドル)、ヘンリー・R・ルース(13,000ドル)であった。民主党への献金リストのトップは、ナッシュビルのウェイド・トンプソン夫妻(22,000ドル)、ケネディ夫妻(20,000ドル)、フィラデルフィアのアルバート・M・グリーンフィールド夫妻(16,000ドル)、ペンシルベニアのマシュー・H・マクロスキー夫妻(10,000ドル)、マーシャル・フィールズ夫妻(10,000ドル)であった40。
第二次世界大戦中、ワシントンにいた年俸制の人たちの経歴を調査してみると、産業界が政府に融資したのは、ごく少数の人たちを除けば、金融の専門家であって、生産経験のある人たちではなかったことがわかる。この男たちが仕事に対して特別な資格を持っているというアリバイは、先月のうちにWPBが……彼らに工業生産の基礎を教えるための特別訓練コースに通わせる必要があると判断したときに、ものすごい打撃を受けた……そして、WPBの給料を水増ししている、彼らの会社のセールスマンや購買代理店のドル箱男たちに行き着くのである。年俸制の男たちは、戦争に勝つために産業界のトップマネジメントの専門家や財務の専門家を政府に貸し出すはずだった。いまや産業界のトップマネジメントは、生産の専門家と金融の専門家という2種類の人間で構成されている。
エグゼクティブの政治的役割については、後述の「TWELVE:パワーエリート」を参照のこと。
1935年、『ファウチュン』誌の編集者はこう書いている。「アメリカの軍事的理想は平和であると一般には思われている。しかし、この高校生の古典にとって不運なことに、1776年以来、アメリカ陸軍は、イギリスの陸軍を除けば、世界中のどの陸軍よりも、軍事征服によって地球上のより多くの平方マイルを奪ってきた。イギリスとアメリカは接戦で、イギリスは1776年以来350万平方マイル以上を征服し、アメリカは(インディアンからルイジアナ買収を含めると)310万平方マイル以上を征服している。この点で、英語圏の人々は自らを誇りに思っている」4。
1906年12月、アメリカ海軍の最年少艦長の年齢は55歳で、その階級での平均在任期間は4.5年であった。フランス、ドイツ、日本の図もイギリスと同様である。同じ状況は旗艦士官にも当てはまった。米国では通常、退役までのその階級での平均在職期間はわずか1.5年だったが、英国、フランス、ドイツ、日本では6年から14年だった」7。
統合参謀本部議長のアーサー・W・ラドフォード提督は土木技師の息子であり、海軍作戦部長のロバート・B・カーニー提督は海軍司令官の息子であり、陸軍参謀総長のマシュー・B・リッジウェイ大将は陸軍将校の息子であり、空軍参謀総長のネイサン・F・トワイニング大将にはアナポリス出身の2人の兄弟がいる13。
** 例えば、1953年に任命された統合参謀本部参謀は、全員が太平洋の主要な司令部を歴任しており、彼らが任命された当時は、彼らが後任となったヨーロッパ志向の強いブラッドリー、コリンズ、バンデンバーグ、フェヒテラーよりもアジア志向が強いとの見方もあった。また、彼らは全員、航空戦の戦略面よりも戦術面を重視していたと伝えられている。実際、ラドフォード提督は太平洋艦隊司令長官として、1949年の予算論争でB-36に対する「提督たちの反乱」を主導した16。
わが国の陸軍将校の給与が世界のどこよりも高いことは事実であるが」、1903年に権威ある言明がなされた。外部に収入源がない場合、給与の範囲内で生活することが期待され、60 パーセントかそれ以上は給与以上の収入がない(40 パーセントはそうだった)。
日曜日には教会への出席が義務付けられている……(これは)自分が単なる個人ではなく、組織の一員であることを自覚させるのに役立っている。
ウェストポイントに入学した日から、死によってアーリントンに栄誉ある埋葬を受ける資格を得る日まで、顧みられることのない教育の過程で、すべての軍事責任者に叩き込まれるのは、政治的決定らしきものから手を引くこと、そして、文民の権威から自分の責任を隔てる境界線らしきものから、自分の側にうまくとどまることである。リーリー提督はこう書いている。「私には政治的な選挙運動の経験がまったくなかったので、意見をまとめることができなかった。すると大統領(F.D.R.)が、『ビル、君は政治的には中世に属している』と冗談で言った」2。
** 下記「TEN:政治局長」を参照のこと。
これは、外交官に低額の給与を支払うという政策によって確保されてきた。外交官としての社会的義務を考えると、世界の主要都市で大使給与だけで生活することはほとんど不可能である。40年代初めには、重要なポストの大使がその地位にふさわしい接待をするためには、年間75,000ドルから100,000ドルの費用がかかると見積もられていた。
** 1899年のトップ大使18人のうち、成人してからの人生の大半を外交官として過ごしてきたという意味で、「キャリアマン」と呼べる人物はいなかった。そのうち10人は大使になるまで外交官ポストに就いたことがなく、さらに6人は1899年以前に外交官になってから9年も経っていなかった。10年以上前に外交官になった者は2人だけだった: トルコ大使のオスカー・S・ストラウスとドイツ大使のアンドリュー・D・ホワイトである。これらの大使のほとんどは、党への忠誠の報いとして任命されたようで、11人が政界で活躍し、そのうち約半数は弁護士としてのキャリアを積んでいた。教授が1人、ジャーナリストが1人、残りの5人は実業家で、やはり法律家としてのキャリアを積んでいた。1899年の大使たちは総じて、裕福な家庭の出身で、しばしば大金持ちであり、アメリカやヨーロッパの一流校で教育を受け、そのうち6人はアイビーリーグの学校を卒業し、実業界や政治界で重要な地位に就いていた15。
もちろん、これは外務省のまったく新しい特徴ではなかった。例えば、「重要な時期に中国部の報告の基本的な重荷は、中国共産党と蒋介石の避けられない衝突では、蒋介石が敗者になるということであった。しかし、この判断の正しさは、集団的にも個人的にも、中国支局の名誉にはつながらなかった。中国は共産主義化してしまったのだ。何らかの形で、中国軍の兵士たちは責任を負わされたのだ。したがって、中国勤務はもはや存在しない。第二次世界大戦が始まる前に入隊した22人の将校のうち、1952年にワシントンの国務省でまだ使われていたのは2人だけだった……残りのほとんどはまだアメリカ政府に仕えていたが、……われわれが朝鮮半島で必死に戦争している中国についての彼らの深い知識が役に立つことはなかった」24。
1954年4月、陸軍は在外将校の日記を禁止した。モスクワ駐在武官のグロー少将が、ソ連との戦争を提唱し、大使への嫌悪感や人脈への嫌悪感を表明した日記をつけていたことが世間に知れ渡ったためである。ドイツのフランクフルトを訪問中、彼は日記をホテルの部屋に置き忘れたが、すぐに盗まれて写真に撮られ、返却された。ソ連はプロパガンダを行った。この将軍は明らかに諜報活動には不向きなタイプだったが、おそらく責められるべきは、彼がモスクワに配属された陸軍諜報システムの「戦利品システム」ではないだろうか。グロウ将軍の無能さは孤独ではない。戦後最も重要なアタッシェのポストは、アイアン・マイク・オダニエル将軍が務めたが、その二刀流の戦いぶりは、しばしば彼の唯一の長所と思われた。戦後、東欧に駐在した2人のアタッシェは「悪名高く、1人は和気あいあいとした習慣で、もう1人は余分な衣類を闇市場で売っていた」また、戦時中のG2総局長は、闇取引の容疑でロンドンから呼び戻された28。
1789年から1917年の間に、アメリカ政府は約2905億ドルを支出したが、1952年の単年度では、軍事費だけで400億ドルが割り当てられた。1913年、国民一人当たりの軍事費は2.25ドルだったが、1952年には250ドル近くになった35。
ドイツで部隊を指揮し、占領軍司令官として政治の世界に入ったルシウス・D・クレイ大将は、現在コンチネンタル缶会社の取締役会長である。日本が降伏する直前に第8空軍を率いたジェームズ・H・ドゥーリットル将軍は、現在シェル石油の副社長である。1955年2月、ブラッドレー会長は、スイスの時計ムーブメントに課された新関税を軍事的必要性を理由に支持する全面広告に、「オマール・N・ブラッドレー陸軍大将」という名前を使うことを許可した。ダグラス・マッカーサー元帥は、日本と朝鮮半島の政治的将軍であり、現在はレミントン・ランド社の取締役会長である。中国戦線の米軍司令官であったアルバート・C・ウェデマイヤー大将は、現在AVCO社の副社長である。ベン・モレル提督は現在、ジョーンズ・アンド・ラフーリン・スチール社の会長である。ジェイコブ・エバース大将は現在、フェアチャイルド・エアクラフト社の技術顧問である。アイラ・イーカー将軍は現在、ヒューズ・ツール社の副社長である。ブレホン・ソマーベル大将は、かつて陸軍調達担当だったが、1955年に亡くなる前にコッパーズ社の会長兼社長になった。アラン・G・カーク提督は駐ロシア大使を務めた後、高精度冶金を専門とするメルカスト社の取締役会長兼最高経営責任者に就任した。マンハッタン計画の責任者であったレスリー・R・グローブス将軍は現在、レミントン・ランドの副社長で先端研究を担当している。水爆実験の責任者であったE・R・ケサダ将軍は現在、ロッキード・エアクラフト社の副社長である。リッジウェイ陸軍参謀総長は、カイザーの自動車によるアルゼンチン侵攻の指揮を断ったようだが、メロン工業研究所の取締役会長に就任した42。
これらの傾向の詳細については、後述の「TWELVE:パワーエリート」を参照のこと。
南北戦争中、各州にランドグラントカレッジが設立され、そのカリキュラムには軍事訓練も含まれていた。南北戦争から第一次世界大戦までの間、この訓練は任意で行われたカレッジもあれば、大学在学中のさまざまな期間、強制的に行われたカレッジもあった。1916年、陸軍省は、ランド・グラント・カレッジの最初の2年間は軍事訓練を必修とすることを標準化した。しかし1923年、ウィスコンシン州議会は、ランドグラント機関である同州の大学に対してこの取り決めに異議を唱えることに成功し、他の数校もこれに追随した。第一次世界大戦中、予備役将校訓練部隊(ROTC)がさまざまなカレッジに設置された。これらのROTCプログラムは、カレッジや大学のキャンパスで拡大されてきた。もちろん、普遍的な軍事訓練は、軍部によって着々と進められているが、それは、すべての若者が軍事技能と適切な態度について、4年制大学のコースの半分の期間、おそらく2倍の集中的な訓練を受けることを意味する。
例えば、ルイス科学技術大学学長ハーバート・J・グラッシー少将、カリフォルニア大学バークレー校摂政チェスター・ニミッツ提督、イサカ・カレッジ理事フランク・キーティング少将、ジョージ・ワシントン大学ロースクール学長オズワルド・コルコー少将、セントルイス医科大学学長メルビン・A・キャスバーグ大佐、カリフォルニア州教育委員会委員チャールズ・M・クック・ジュニア提督などである54。
1789年から1825年の政治エリートのうち、このような職業に就いたのは約20パーセントにすぎず、歴史全体の平均は約25パーセントである3。
1801年から25年には、政治エリートの63パーセントが下院議員、39パーセントが上院議員であった。1865年から1901年には、その割合は32パーセントと29パーセントであったが、1933年から53年の時代には、23パーセントだけが下院議員、18パーセントだけが上院議員であった。アイゼンハワー政権の目に見える政権では、その割合は14%と7%であった。
1953年5月現在4
アイゼンハワーのゴルフと橋の「取り巻き」についての最近の記述で言及されている27人のうち、厳密に「政治家」と呼べるのは2人だけであった。オーガスタ・ナショナル・ゴルフ・クラブの地元の実業家であることが判明しているのは3人だけだった。残りはすべて、異業種に散らばるさまざまな企業の最高幹部で、たいていは東海岸沿いにいる。1953年6月から1955年2月までの間に、アイゼンハワー氏は38回の「スタッグ・ディナー」を開き、「294人のビジネスマンと実業家、81人の政権幹部、51人の編集者、出版社、作家、30人の教育者、23人の共和党党首をもてなした。その他にも、農場、労働者、慈善団体、スポーツ団体など12もの団体が、より少人数のゲストを招いた」6。
セオドア・ルーズベルトは、彼のさまざまな仲間について、次のように語ったことがある。『私は、このような莫大な数の人々が本当に感じていることが明らかな、大金持ちに対する尊敬の態度を、自分自身にとらせることができないだけだ。ピエールポント・モルガンやアンドリュー・カーネギー、ジェームズ・J・ヒルに対しては喜んで礼儀を尽くすが、彼らの誰か一人に対しては、たとえばビューリー教授や北極探検家のピアリー、歴史家のローズを尊敬するように、たとえそうしたくても、無理にそうすることはできない。アイゼンハワー大統領の交友関係について、鋭い観察者であるメリマン・スミスは次のように語っている。『彼が金融や産業の王たちの交友を好むのは、純粋にダン・アンド・ブラッドストリートの格付けが高いからだというのは不公平だろう。フォード・モーター・カンパニーの社長、スクリプス・ハワード新聞社の社長、大学の学長、大司教にまで上り詰めた人なら、その人は確かに多くのことを掴んでいて、自分の分野を知り尽くしており、読み書きができ、興味深い人物だろう」と彼は考えている。これに対してウィリアム・H・ローレンスは、『出世のための仕事というのは、若いヘンリー・フォードや若いジャック・ハワードにとっては、かなりの驚きであろう』と付け加えている7。
『ファウチュン』誌の編集者は、「ある仕事は単純に廃止できる。他の者は肩書だけ残して、他の者に実権を与え、部長に直接アクセスさせることができる。より悪名高いフェア・ディーラーの一部は、無害で無計画なプロジェクトに振り落とされるかもしれない。政府関係者の間では、このような手法をこう呼ぶ: 「つるのまま干上がらせる」とか、「閲覧室に送り込む」とかいうのだ。このような方法は無駄である。一方では、共和党の政策にあからさまに、あるいは密かに敵対的なイデオロギーを持つ一流のキャリアを排除し、他方では、政府の仕事を機能させ、それによって一流の人材を惹きつけようとする。
** 外交の没落については、前掲書「9:軍部の台頭」を参照のこと。
以下、「THIRTEEN:大衆社会」を参照のこと。
現在、典型的な上院議員は大学教育を受けた57歳前後の男性である。典型的な下院議員もまた、大学に行ったことのある成人人口の10%未満から選ばれており、年齢は52歳くらいである。上院議員も下院議員もほとんど全員が地方や州の役職を経験しており、約半数がいずれかの戦争の退役軍人である。また、ほぼ全員が政治家以外の職業に就いており、通常は職業階層の上位15%の職業に就いている。例えば、1949-51年の議会では、上院・下院とも69%が専門職の男性で、上院の24%、下院の22%が実業家または管理職だった。上院には賃金労働者、低賃金のホワイトカラー、農業労働者はおらず、下院には1人か2人しかいない12。
彼らの主な職業は、もちろん法律である。この法律に従っているのは、米国で働く人々のわずか0.1%だが、上院議員と下院議員のほぼ65%は法律家である。彼らが主に弁護士であることは容易に理解できる。弁護士の言語能力は、政治家が必要とする能力とは似て非なるものである。どちらも交渉や折衝に携わり、ビジネスや政治で意思決定を下す人々に助言を与える。弁護士もまた、勝つか負けるかにかかわらず、政治は自分の仕事を世間に知らしめるので、法律という職業に役立つと感じることが多い。加えて、ブリーフケースに入れて持ち運べる個人弁護士事務所は、ほとんどどこにでも設立できる。従って、政治家としての弁護士には、再選されなかったときに頼れるものがあると同時に、当選したときに頼りたいものがある。実際、弁護士の中には、政治家としての任期を1期か2期と考える者もいるし、実際、ワシントンでも故郷でも、より大きな法律事務所への足がかりに過ぎない者もいる。弁護士業を営むことで、多くの場合、さしたるリスクもなく政界に進出でき、選挙民の気まぐれとは無関係の主な資金源に有利になる可能性もある13。
過去15年間、そしておそらくそれよりもずっと長い間、連邦議会議員のほとんどは、過去10年間に彼ら自身が辿ったのと同じ専門職や起業家の職業に就いてきた。彼らの90%から95%は、専門職、実業家、農家の息子である。しかし、彼らが生まれた1890年当時、こうした起業家層の労働力は全体の37%にすぎず、そのすべてが結婚して息子を持つ男性だったわけではない14。
過去半世紀の間、上院議員に黒人は一人もおらず、下院議員に黒人が二人以上いることはなかった。1845年以来、上院議員に占める外国生まれの割合は8%を超えたことはなく、人口に占める割合よりもずっと小さい。例えば1949年から51年にかけては、代表的な割合の2分の1以下であった。さらに、一世議員も二世議員も、南欧や東欧からの新しい移民ではなく、北欧や西欧からの古い移民の傾向がある。プロテスタントの中でも地位の高い宗派(エピスコパル、長老派、ユニテリアン、会衆派)は、人口に占める代表的な割合の2倍の下院議員を擁する。中堅プロテスタント(メソジスト派とバプテスト派)の議員数は人口にほぼ比例しているが、カトリックとユダヤ教徒は少ない: たとえば第81回連邦議会では、カトリック教徒は下院で16%、上院で12%にすぎなかったが、1950年の人口全体では34%であった15。
第二次世界大戦終了後から1955年まで、下院議員は年間15,000ドル(2,500ドルの非課税経費手当を含む)を受け取っていたが、投資、ビジネス、職業、執筆や講演を含む平均収入は、1952年時点で下院議員は約22,000ドル、上院議員は約47,000ドルであった。1955年3月1日付で、下院議員の年俸は22,500ドルに引き上げられた16。
** あるベテラン下院議員は最近、1930年には7,500ドルで選挙戦に出られたが、今日では25,000ドルから50,000ドル、上院ではそれ以上になるかもしれないと報告している。マサチューセッツ州の民主党議員ジョン・F・ケネディ(大富豪ジョセフ・P・ケネディの息子)は、1952年の選挙運動で15,866ドルを費やしたと報告されているが、「彼のために州の靴、漁業、その他の産業を改善するための委員会は、217,995ドルを費やした」19。
ある州では、人種差別撤廃の問題が最も重要なようであった。別の州では、アイルランド人女性と結婚したイタリア人が、両方の名前を使い分けていた。ある州では、候補者が2歳のときに話した「警察官は誰と結婚する傾向があるか」という話を録音したテープが重要なようで、別の州では、候補者が自分の妹に十分親切だったか、あるいは親切すぎたかが重要なようだった。ここではビンゴ法が重要であり、そこでは上院議員に立候補する年配の男性が十分に男らしいかどうかが大きな問題となった。ある重要な州では、ある候補者が桟橋の賃貸料を判事に貢いでいた蒸気船会社と結託していたという20年前の告発が、テレビで大々的に取り上げられた。最も著名な上院議員の一人は、対立候補(それもかなり著名な老富豪)について、「不正直か、間抜けか、愚かなカモのどちらかだ」と断言した。また別の候補者は、プレッシャーに押しつぶされ、自分の戦争記録について詳細な嘘をついていたことを告白した。そしていたるところで、不信感の中で、対立候補は、実際にはソ連のタコツボから金をもらっていないとしても、赤のスパイと関係があることがほのめかされ、ほのめかされ、主張され、推測された。民主党は不況と戦い、共和党はアルジャー・ヒスを刑務所に入れる決意をした。
企業富裕層と同様、労働指導者集団も完全に統一されているわけではない。しかし、よく指摘されるように、「相手側」が、一方の側面の一部によるいかなる動きも、全体から見れば重要な意味を持つものと見なす傾向は、これらの人々の見解、期待、要求が、不本意ではあっても、ブロックを形成していることを明確に示している。彼らは互いをブロックのメンバーとして見ており、実際、さまざまな、かなり入り組んだ方法で互いに結びついている。個々の組合は特定の利害のためにロビー活動を行うかもしれず、それが労働という括りが示すような団結の欠如の1つの鍵である。しかし、労働組合が直面する問題や、労働組合が直面しなければならない文脈は、ますます全国的な範囲と効果を持つようになっており、そのため労働組合は、権力を失うことを覚悟で、全国的な文脈を参照しながら労働組合の路線を調整しなければならない。
企業幹部は、労働指導者と同様、現実的な人間であり、日和見主義者である。しかし、彼にとっては、他の目的のために開発された永続的な手段が、ビジネス・労働問題だけでなく、政治問題の遂行にも利用可能である。企業は現在、非常に安定した経営基盤となっている。事実、アメリカの体制を継続するためには、終身雇用の家族よりも安定しており、より重要である。パワーエリートのビジネス・メンバーは、短期的な目標や日和見主義的な策略を追求する際に、企業を頼りにすることができる。しかし、労働組合はしばしば抗議の状態にあり、時には実際に、また常に潜在的に敵対的な社会の中で守勢に回っている。組合は、ビジネス・エリートが自由に使える既製のような永続的な手段を提供しない。そのような手段を望むのであれば、たとえ小さな目標であっても、労働指導者自身がその手段を構築し、維持しなければならない。さらに、30年代の大組織化騒動は、産業労働者の要求に十分に応えられない役員が権力を失いかねないことを示した。一方、会社経営者は、会社という文脈では、同じ意味で選挙で選ばれた役人ではない。彼の権力は、彼の下で働く労働者の忠誠心に左右されることはなく、労働組合が彼の工場に侵入することに成功しても、彼は通常職を失うことはない。彼らの責任は、雇用している労働者ではなく、彼ら自身と散り散りになった株主に対してある。
このような権力状況の違いは、ビジネス・リーダーの権力は、労働者リーダーの権力よりも継続的で確実である可能性が高いことを意味する。労働者リーダーは、「商品を届ける」ことに失敗した場合、自分の仕事が不安定になる可能性が高い。
企業や政治エリートがどうであれ、現在の労働リーダーには、個人としても集団としても、最大限の適応という戦略を超えられる、あるいは超えられるだろうと思わせるような要素は何もないように思える。つまり、彼らは指導するよりも反応し、権力と優位の星座における地位を維持・拡大するためにそうしているのだ。現在の労働指導部やその一部が没落し、他のタイプの指導者が労働組合の権力者になる可能性もあるが、現在の労働指導者たちは、パワーエリートの役割を果たさないまま、主要なドリフトの従属変数として設定されている。労働指導者も労働組合も、現在の時点では、全国的な文脈において「独立変数」になる可能性はない41。
前掲『ONE』参照: 高次のサークル」を参照。
「支配階級」というのは、ひどく荷が重い表現だ。「階級」は経済用語であり、「支配」は政治用語である。「支配階級」という言葉には、経済階級が政治的に支配するという理論が含まれている。その短絡的な理論が真実である場合もあれば、そうでない場合もある。しかし、私たちは、問題を定義するために使用する用語に、そのような単純な理論を持ち込むことを望んでいない。具体的には、一般的な政治的意味合いでの「支配階級」という表現は、政治秩序とその代理人に十分な自律性を認めておらず、軍隊については何も語っていない。経済界の高官が国家に関わるすべての決定を一方的に下すという単純な見方を、我々が適切なものとして受け入れていないことは、もう読者には明らかだろう。このような「経済的決定論」という単純な見方は、「政治的決定論」と「軍事的決定論」によって精緻化されなければならず、これら3つの領域それぞれの高位の主体は、現在、しばしば顕著な程度の自律性を持っており、しばしば複雑に入り組んだ連合の方法によってのみ、最も重要な決定を構成し、遂行するのだと、私たちは考えている。権力という観点から上位サークルを考察する際、「支配階級」よりも「パワーエリート」という表現が好まれる主な理由はここにある。
上記「4:セレブリティ」を参照のこと。
上記「3:メトロポリタン」参照。
特に、独立した中産階級の衰退についての分析、『ELEVEN:均衡論』を参照。
同時にまた、大都市における分離と気晴らしのせいでもある。
もし学校がその役割を果たしているのであれば、教育者は国民の知的水準を向上させるという重要かつ議論の余地のない成果を挙げるはずである。それはおそらく、一人当たりの書籍やまじめな雑誌の発行部数の増加、映画やラジオ番組の趣味の確実な向上、政治的討論の水準の向上、言論や思想の自由の尊重の高まり、大人による漫画の乱読のような精神遅滞の顕著な減少によって測られる」11。
私はすでに、このロマン主義的多元主義を提示し、分析した。上記「ELEVEN:バランス論」を参照のこと。
** 前掲『TWO』参照: 地域社会」参照。
私は、米国が技術的独創性でリードしていると言いたいのではない。実際、米国の製品は一般に、ドイツや英国の製品とはデザインでも品質でも比較にならないと考えている。
上記「ELEVEN:バランス理論」を参照のこと。
以下の「第五十一章:高次の不道徳」を参照のこと。
数年前、アメリカの高等軍事学校の中心であるウェストポイント(陸軍士官学校)で、入念に選抜された若者の何人かが、試験で不正を働いていたことが発覚した。他の高等教育機関でも、不正なギャンブラーの金目当ての不正なバスケットボールが行われている。ニューヨークでは、かなり立派な家庭で育った少女が、休暇を過ごす企業の重役たちによって、大金持ちの家のプレイボーイたちから数百ドルで買われている。ワシントンでも、他の大都市と同様に、高官の男たちが賄賂を受け取り、引き抜きに屈した。1954年9月までに、40年代後半に横流しされた1400件もの大もうけの事例が判明した。連邦住宅局の賃貸住宅を建設したり投資したりした企業は、建築費以上の住宅ローンを組み、その差額を懐に入れた。もちろん戦争末期には、金とコネさえあれば、闇市場の肉やガソリンをいくらでも手に入れることができた。そして最近の大統領選挙キャンペーンでは、国民の不信感は苛烈で冷笑的なトーンに達し、前代未聞のジェスチャーとして、この国の最高権力者の有力候補者それぞれが、自分の個人所得を公表する必要性を感じた。
非合法な企業では、手っ取り早く素晴らしい見返りのある小額の投資が盛んに行われる。このような産業は、朝鮮半島での犯罪増加後の活況の中で、何十種類も栄えている。『ニューヨーク・タイムズ』紙は、「率直に言えば、より多くの人々が銀行からより多くの金を盗んでいる」と報じている14。麻薬やハイジャック、横領や偽造、税金泥棒や万引きはすべて、大きな利益をもたらしている。
単刀直入に言えば、ビジネスライクに組織化された犯罪は儲かるのだ。アメリカの暴力団は、全国的なビジネスの専門家であり、互いに、また地方公共団体とシンジケート化されたコネクションを持っている。しかし、非合法ビジネスが現在では十分に組織化された産業になっているという事実よりも重要なのは、20年代の「フード」が40年代や50年代にはホテルや蒸留所、リゾート施設やトラック運送会社を所有する実業家になっているという事実である。このような成功の友愛のメンバーの間では、警察に前科があるということは、単に適切な人物を知らなかったということを意味する15。
裏社会の組織犯罪は、略奪的成功の個人主義的哲学、公共の利益への無関心、利潤動機のフェティッシュ、自由放任主義国家を極限まで高めている。アメリカ文化の不可欠な部分として、「裏社会は……非合法と定義されているが、それにもかかわらず立派な人々の強い需要がある商品やサービスの需要を満たす役割を果たしている……それはわれわれの経済的、政治的、法的、社会的組織に暗黙のうちに存在している……われわれが犯罪者を抱えるのは、このような意味においてである」16。
ニュージャージー州の銀行家ハロルド・G・ホフマンにとって、犯罪は報われた。彼は市長、下院議員、州知事となったが、1954年に亡くなって初めて、10年以上にわたって30万ドルの州資金を持ち逃げし、さらに州政治の道徳劇の中で、名だたる銀行、保険会社、地位の高い個人を巻き込んだ汚職のネットワークに深く関与していたことが発覚した。陸軍のPxは、「ミンクのコートや高価な宝飾品などの非軍事品」を小売価格を大幅に下回る価格で販売してきた。慈善事業が私利私欲のために行われていることも判明した。1954年2月、余剰船取引で政府を欺いた罪で18人と7つの企業が起訴されたが、その中には元ロンドン米国大使館公使で国務長官特別補佐官のジュリアス・C・ホームズも含まれていた。地方の労働組合の皇帝たちは、恐喝とゆすり、賄賂と組合福祉基金によって自分たちを豊かにしてきた。私立病院の高名な経営者たちは、アスピリンを9.83ドルで卸売りし、患者に600ドルで売っている。ロデリック・アレン少将は1954年3月、軍費1200ドルを自分のシベリアンハスキー用の犬小屋に使わせた。新聞だけでなく、ビジネス・マニュアルを読んでいる人なら、1954年までに、40歳代の中流階級の内国歳入庁職員とその友人214人が起訴され、連邦政府の徴税局長を含む100人が有罪判決を受けたことを知っている17。そして、国中で、中流階級と上流階級の税金逃れが、春が来るたびに、巧妙な嘘と巧みなごまかしのゲームへの招待状として個人的に扱われている。上層部からの暴露は、陸軍長官とその補佐官たちが上院議員とその補佐官たちともめた1954年の春に、ある種のクライマックスを迎えた。すでに述べたように、マッカーシー・陸軍公聴会は、高官と多数の上院議員から威厳と地位をすべて奪い去った。すべての公式の仮面がはぎ取られ、2組のトップサークルが卑小な不道徳の典型例であることが示された。
歴代大統領のアドバイザーであるバーナード・バルークは最近、次のように述べている。「もし彼らが本当に多くのことを知っていたら、彼らはすべてのお金を持っていて、われわれには何もないだろう」そしてまた彼は言う: この人たち(経済学者)は、事実や数字を取り上げてまとめることはできるが、彼らの予測は私たちの予測以上の価値はない。もしそうなら、彼らはすべての金を手にし、われわれは何も手にすることができないだろう」8。
少なくとも国民に知られ、尊敬され、おそらくは習慣的に尊敬され、愛されている貴族たち、すべての人の視線が注がれ、その一挙手一投足が注目される王子や王たち、彼らの感情を傷つける結果は恐ろしい。互いの立場に少しでも変化が生じれば、劣位にあった者が優位に立たされれば、それが明白な方針と必要性によって不名誉を取り除くような固定された法律によるのでない限り、戦争、殺戮、復讐以外の何ものでもない。
どのような知的時代においても、ある学問分野や学派がある種の共通項となる。今日のアメリカの保守的ムードの共通項は、アメリカ史である。今はアメリカ史家の時代なのだ。もちろん、ナショナリストの祝典はすべて歴史的な用語で語られる傾向にあるが、祝典を挙げる人々は、過去の出来事としての歴史を理解することだけを目的としているわけではない。彼らの目的は、現在を祝うことなのである。(1)アメリカのイデオロギーが歴史志向である理由のひとつは、あらゆる学者集団の中で、このような公的な前提を作り上げる可能性が最も高いのが歴史家だからである。というのも、あらゆる学術的な著述家の中で、歴史家は文芸的な伝統を持っているからである。他の 「社会科学者」は、英語の用法に疎い可能性が高く、しかも公共の関心事である大きなテーマについて書くことはない。(2)「優れた」歴史家とは、高位のジャーナリストの公的な役割を果たし、世間の注目を浴び、日曜日には賞賛を浴びる歴史家であり、現在のムードと関連性を持たせてアメリカの過去を最も素早く再解釈する歴史家であり、ひいては、楽観主義と叙情的な高揚を最も容易に生み出す人物や出来事を、今まさに過去から選び出すことに最も長けている歴史家である。(3)本当は、ノスタルジアに浸ることなく、アメリカの過去はアメリカの現在についての神話の素晴らしい源泉であることに気づくべきである。アメリカは、その起源と発展の初期において、非常に恵まれていた。現在は複雑であり、特に訓練を受けた歴史家にとっては、まったく文書化されていない。それゆえ、一般的なアメリカのイデオロギーは、歴史と歴史家によるものとなりがちである4。
