Contents
The Ethics of Invention: Technology and the Human Future
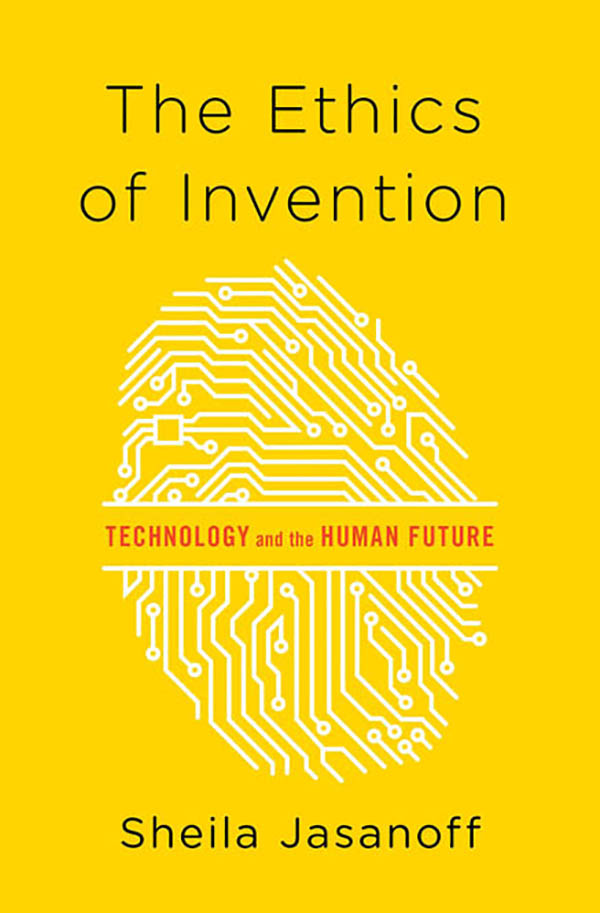
目次
- タイトル
- 内容
- 第1章 テクノロジーの力
- 第2章 リスクと責任
- 第3章 災害の倫理的解剖学
- 第4章 自然を作り変える
- 第5章 人間いじり
- 第6章 情報のワイルド・フロンティア
- 第7章 誰の知識か、誰のものか?
- 第8章 未来を取り戻す
- 第9章 民衆のための発明
- 謝辞
- 注釈
- 索引
- シーラ・ジャサノフも執筆している
- 著作権について
第1章 技術の力
私たちの発明は世界を変え、発明された世界は私たちを変える。今日の地球上の人間の生活は、わずか100年前とは全く異なっている。それは、この間に発明された技術のおかげでもある。かつては陸上では足と車輪、海上では船で移動していたのが、今では飛行機で移動するようになり、毎日800万人以上の乗客が数時間の飛行で大陸を横断している。ヴァージン・ギャラクティック社の創業者リチャード・ブランソン氏が、世界初の商業用宇宙船を建造するという夢を実現すれば、普通の人が宇宙飛行士になる日も近いかもしれない。通信もまた、時間と距離の束縛から解き放たれている。私がインドを離れた1950年代半ば、私が生まれたコルカタと、家族が最初に定住したニューヨークのスカースデールとの間を往復する手紙には3週間を要した。郵便はなかなか届かない。切手が盗まれたり、小包が届かなかったり。それが今では、夜中にアメリカ東部から電子メッセージを送ると、ヨーロッパやアジアの友人からすぐに返事が届き、その日のうちに一日が始まるのである。最後になったが、私たちは、ヒトゲノムの解読によって生物と非生物の秘密を解明し、新しい人造物質の世界を創造し展開することができるようになった。
スピード、接続性、利便性も重要だが、地球上の70億の人々の多くにとって、生活の質はより重要である。ここでも、加速する技術革新の1世紀が私たちを変えてきた。仕事はより安全になった。世界の多くの地域で、空気と水は驚くほどきれいになっている。私たちは明らかに長生きしている。世界保健機関(WHO)によると、「1955年の出生時の平均寿命はわずか48歳だったが、1995年には65歳になり、2025年には73歳に達するだろう」2という。技術革新により、衛生設備、飲料水、ワクチン、抗生物質、より豊富で健康的な食品などが改善されている。人々は長生きするだけでなく、旅行やレクリエーション、様々な食べ物、そして何よりもヘルスケアの向上により、より楽しく生活することができるようになった。1916年と2016年のどちらに住みたいかと問われれば、たとえ戦争がなかったとしても、100年前に住みたいと思う人はほとんどいないだろう。
第二次産業革命と呼ばれるように、この100年の技術の進歩は、豊かな国々を知識社会の地位に押し上げた。人々の遺伝的体質、社会的習慣、購買行動などに関するかつてないほどの量の情報を手に入れた、あるいは手に入れようとしている。これらのデータは、新しい形の商取引や集団行動を可能にすると期待されている。大量のデータを収集できるのは、もはや国の国勢調査局だけではない。GoogleやYahooなどの検索エンジンも、政府に匹敵するほど膨大なデータを収集するようになった。個人でも、FitbitやApple Watchのようなデバイスを使って、日々の活動をモニターし、大量の情報を記録することができる。デジタル技術は、これまで不可能だったデータの結合を可能にし、物理的記録、生物学的記録、デジタル記録の間に有用なコンバージェンスを生み出している。今日では、身長、体重、民族、髪の色といった身体的な特徴だけでは、その人について知ることはできない。また、住所や電話番号のような固定的な情報だけで、その人を特定することもできない。その代わりに、バイオメトリクス(生体情報)が普及している。例えば、パスポートは、国境を越えた人の指紋や虹彩スキャンから得られる情報とリンクしている。アップル社は2010年代、スマートフォンにデジタル指紋センサーを搭載し、暗証番号の代わりにセキュリティの強化を図った。
コンピュータ性能の飛躍的な向上による情報爆発が、経済や社会の発展を後押ししている。新薬や治療法を研究したい患者、安定した市場に参入しようとする中小企業経営者、地域の問題について知識を共有し、当局に行動を促す市民など、さまざまなレベルでインターネットは前例のない情報資源を人々の手元に置き、民主主義の一助として機能しているのだ。ハイテク社会では、人々の行動のほとんどすべてが情報的な痕跡を残し、それらを統合することで、人々の人口統計学的プロファイルや表現されていない願望まで、驚くほど正確に描き出すことができるのである。医療から商業まで、「ビッグデータ」の概念は、人々が何を知ることができるか、情報がどのように新しい市場を開拓し、より良い公共サービスを提供できるかについて、想像力を広げ始めている。この時代、多くの政府が認識しているように、知識そのものがますます貴重な商品となり、希少な天然資源のように採掘、保管、開発が必要になってきている。ビッグデータ時代はビジネスチャンスのフロンティアであり、若い技術系起業家が新たなゴールドラッシュを牽引する象徴的な存在となっている。
今日の情報通信技術は、新たに豊富になったデータソースを創造的に利用することができれば、誰にでも大きな可能性を与えてくれる。AirbnbやUberは、個人宅や自家用車の未使用のキャパシティを利用し、喜んで不動産を所有する人をホテル経営者やタクシードライバーに変えた。このシェアリングエコノミーがうまく機能すれば、未使用の能力が活用され、満たされていないニーズがより低いコストで効率的に満たされるため、誰もが利益を得ることができるのである。ホテル代を払う余裕のない家族も、お金をかけずに夢のような休暇を楽しむことができる。UberやZipcarのような企業は、道路を走る車の数を減らし、化石燃料の使用と温室効果ガスの排出を削減することができる。このように、世界の経済が停滞している地域でも、新たな希望を見出すことができるようになったのである。なぜなら、テクノロジーと楽観主義は、どちらも未知の未来に目を向け、現在の病からの解放を約束してくれるからだ。
しかし、技術文明はバラの花壇のようなものではない。発明の魅力的な約束を打ち消すのは、本書の残りの部分を構成する3つの困難でとげとげしい問題である。第一は、破滅的な規模のリスクである。今日、人類が人類存亡リスク、すなわち地球上の知的生命体を絶滅させかねない脅威に直面しているとすれば3、その原因は、私たちの生活をより快適で楽しいものにし、生産性を向上させてきたのとまったく同じ技術革新にある。特に化石燃料に対する欲求は、地球を温暖化させ、気象パターン、食糧供給、人口移動に大規模な破壊的変化が不気味なほど迫っている状態を生み出している。鉄のカーテンが崩壊して以来、全面的な核戦争の脅威は少し後退したが、壊滅的な局地的核戦争は依然として可能性の範囲にある。感染症対策は成功したが、抗菌剤に耐性を持つ菌が増殖し、パンデミックを引き起こす可能性がある。1980年代の英国初の「狂牛病」危機は、規制が不十分な農法が動物や人間の生物学と相互作用して病気を蔓延させる可能性があることを予感させるものであった4。特にヨーロッパでは、タクシー会社がUberに激しく反対しているが、これは、最近ボストンで深夜にタクシーに乗ったときに私に言われた、「タクシー運転手は絶滅危惧種だ」という不安を反映している。
第二の問題は、不平等である。テクノロジーの恩恵は不均等に配分されたままであり、発明によって格差が広がる可能性さえある。例えば、平均寿命。2013年の国連世界死亡率報告書によると、富裕国の出生時平均寿命は77歳以上だが、後発開発途上国では60歳であり、17歳も短くなっている5。インターネットとインスタント・コミュニケーションの時代に、米国国勢調査局は、マサチューセッツ州の80%がブロードバンド接続を持つのに対し、ミシシッピ州では60%未満であるなど、米国内のブロードバンド接続には大きな差があると報告している8。カンザスからカブールまで、同じテクノロジーがあっても、住む場所、収入、教育水準、生業の内容によって、人々は異なる体験をしている。
第三の問題は、自然の意味と価値、より具体的には人間の本質にかかわるものである。技術的な発明は連続性を乱す。この点でも、変化は必ずしも有益なものとは感じられない。ドイツの社会学者マックス・ウェーバーからアメリカの環境保護主義者ビル・マッキベンに至るまで、1世紀以上にわたって、テクノロジーによって機械化され、幻滅させられ、止めどなく続く進歩に脅かされる変性した世界に対して、私たちが驚嘆する力を失っていることを嘆いてきた。しかし、その可能性はさらに広がっている。特に生命科学やテクノロジーにおける限りない新しい発見が、人類を自己形成と制御の脚本に駆り立て、自然や人間性を操作可能な機械へと変貌させる。今日のディープ・エコロジストは、自然の本質的な価値を守ることに力を注ぎ、自動車や化学物質など、私たちに最も普及している発明品の時計の針を戻したいと考えている。環境保護活動家ポール・キングスノースが創設し、率いるイギリスのダーク・マウンテン・プロジェクトは、「進化し続ける食欲を満たすために、地球上の生物の多くを破壊する」という産業界の悪夢「エコサイド」をテーマに活動している9。この作家やクリエイティブアーティストの集団は、芸術や文学を通じて「未開」を推進し、人類をより破壊的ではない方向に導くよう努力している。
テクノロジーの進歩がもたらすより直接的な結果として、コミュニティの分断と喪失、つまり、人間の生活を有意義なものにしている社会的なつながりの弱体化があると主張する批評家もいる。ハーバード大学の政治学者ロバート・パットナムは、「一人ボウリング」のアメリカを嘆く10。彼の考えでは、人々は教会や市民活動に参加せず、家でテレビを見ている。また、平等と経済的自立を求める女性が、母親や学校の教師など地域社会を中心とした職業から、法律事務所や企業の役員室での高収入の仕事を求めているアメリカもそうだ。このような主張は、ソーシャルメディアを通じてますます多様化するコミュニティとのつながりを感じている今日の20代の若者にとっては、とんでもないことに思えるかもしれない。しかし、マサチューセッツ工科大学の心理学者シェリー・タークルは、今日のアメリカの若者を「alone together」11と表現し、スマートフォンやその他の通信機器による個人の孤独な世界に没頭し、そこから抜け出して有意義で多次元的なリアルワールドのつながりを形成することができないでいる、と述べている。
つまり、テクノロジーはここ数十年で飛躍的な発展を遂げたが、その発展は倫理的、法的、社会的な問題を引き起こし、より深い分析と賢明な対応を求めているのだ。最も顕著なのは、おそらくリスクに対する責任だろう。今日の複雑な社会では、テクノロジーがもたらす負の影響を予見したり、未然に防いだりすることは誰の義務なのか、また、私たちは被害を予見し防ぐために必要なツールや手段を有しているのだろうか。不平等も同様に緊急な問題を提起している。技術開発は既存の富と権力の格差にどのような影響を与えているのか、また、技術革新がこうした格差を悪化させないためにはどのような手段を講じればよいのだろうか。3 つ目の懸念は、自然や、とりわけ人間に対する道徳的に重要なコミットメントが損なわれることに焦点を当てるものである。技術開発は、大切な景観や生物学的多様性、さらには自然な生活様式という概念そのものを破壊するおそれがある。遺伝子組み換え、人工知能、ロボット工学などの新しいテクノロジーは、人間の尊厳を侵害し、人間であることの基本的な価値を損なう可能性がある。これらの懸念はすべて、主にテクノロジーの物理的・環境的リスクを規制するために作られた制度が、発明の倫理を深く考察する作業に適しているかどうかという現実的な問題にも通じている。技術、社会、制度の間の複雑な関係、そしてそれらの関係が倫理、権利、人間の尊厳に及ぼす影響を考察すること、それが本書の第一の目的である。
自由と制約
「テクノロジー」という言葉は、特定不可能であると同時に、非常に大きな意味をもっている。この言葉は、道具や器具、製品、プロセス、材料、システムなど、驚くほど多様なものを含んでいる。ギリシャ語のtechne(技術)とlogos(研究)の合成語である「テクノロジー」は、17世紀には熟練工の研究という意味で使われていた。今日、この言葉から最初に連想されるのは、コンピュータ、携帯電話、タブレット端末、ソフトウェアなど、ハイテク社会のケイ素世界を構成するチップや回路に支えられた電子機器の世界であろう。しかし、テクノロジーには、軍隊の武器庫、製造業の活力源、遺伝子組み換え生物の造形物、ロボット工学の巧妙な仕掛け、ナノテクノロジーの目に見えない製品、現代の移動手段の乗り物とインフラ、望遠鏡や顕微鏡のレンズ、生物医学の光線とスキャナー、私たちが触ったり使ったりするほとんどすべてのものが作られる複雑な人工材料の世界も含まれていることを思い出してほしい。
日常生活に追われていると、見るもの、聞くもの、味わうもの、嗅ぐもの、行うもの、さらには知るもの、信じるものを制御する無数の機器や目に見えないネットワークにほとんど気づかない。しかし、自動車、コンピューター、携帯電話、避妊薬などの高度な機器だけでなく、信号機のような普通のものも、私たちの欲望を支配し、ある程度、私たちの思考や行動を導いているのである。
現実的なものであれ理想的なものであれ、テクノロジーは統治の道具として機能しているのだ。本書の中心的テーマは、膨大な数のものからなるテクノロジーは、法律と同じように私たちを支配しているということである。テクノロジーは物理的な世界だけでなく、私たちが生活し、行動する倫理的、法的、社会的環境をも形成している。テクノロジーは、ある活動を可能にする一方で、ある活動を困難または不可能にしている。交通規則のように、テクノロジーは私たちが複雑な手続きを踏まずに行えることと、危険や高い社会的コストを伴うことを規定するのである。スタチンは血中コレステロール値を下げ、心臓血管の健康を改善するが、スタチン服用者はグレープフルーツとグレープフルーツジュースに近づかないように気をつけなければならない。マックユーザーは手軽さとエレガンスを買うが、PCユーザーのようにコンピュータに内蔵されたデザイン機能を簡単に支持することはできない。電気自動車の購入者は、より環境に優しい車を運転するが、ガソリン給油所に比べて充電スタンドが少ないという現実を直視しなければならない。豊かな国の食の雑食者は、世界中から調達した新鮮な農産物の想像を絶する豊かさを享受しているが、その食習慣は、貧しい人々や徹底したロカボの人々の食生活よりもはるかに多くの二酸化炭素排出量を残し、環境に負担をかけている13。
現代の技術システムは、社会を秩序づけ、統治する力において、法的な憲法に匹敵する。どちらも人間の基本的な可能性を可能にし、また制約するものであり、主要な社会的行為者の間に権利と義務を確立するものである。さらに、現代社会では、法とテクノロジーは徹底的に結びついている。例えば、赤信号は法律と物質のハイブリッドであり、その規制力は赤を停止と同一視する強制力のある交通法規に依存する。現代のテクノロジーは、契約、責任、知的財産など、法律によるサポートがなければ実現できないものが多い。例えば、スピード違反の車両や警察官の発砲を撮影するカメラなどである。しかし、何世紀にもわたる法学や政治学の理論に匹敵するような、テクノロジーが私たちを支配するための原理を明確に示す体系的な思想は、まだ存在しない。また、過去半世紀の間に発明された予測・規制手段は、テクノロジーが人類共通の未来をどのように定義するかを制御するのに十分な力を必ずしも持っていない。
テクノロジーが私たちを支配する方法
技術的な発明がいかに広く私たちの行動や期待を支配しているかを誇張するのは難しいだろう。ありふれた例を挙げれば、そのことがよくわかるだろう。2007年の夏まで、私はマサチューセッツ州ケンブリッジにあるオフィスの近くのT字路を信号なしで歩いて渡っていた。ハーバード・スクエアに出入りする大動脈である2本の道路を、車がひっきりなしに走っている。そのスピードと、安全に横断できる幅の道路を見極めなければならない。交通量が多くて何分も待たされることもあれば、マサチューセッツの運転手がどこからともなく現れるかもしれないと思いつつ、ほとんど間を置かずに道路に出ることもあった。私は、地元の道路とドライバーに関する知識だけを頼りに、いつ止まり、いつ行くかを個人的に判断していた。
今、その交差点は規制されている。歩行者用信号が出るまで信号が3回変わるのを待たなければならないが、その後19秒あれば安全に反対側まで行ける。その短い時間、予測可能な周期で繰り返される横断は、歩行者のものである。ドライバーは、赤が青に変わるのを待ちながら、刻一刻と迫る時間を見守っている。横断歩道は今や、ほとんど静寂に包まれているように感じられる。この由緒ある大学の町では、学生の特権である信号無視は、急いでいる人の選択肢として残っているが、以前は判断の問題であったものが、今ではほとんどモラルの問題になっている。法律を守って待つべきか?信号無視をして、車のスピードを落としたり、自転車にひかれたり、他の歩行者に危険な前例を作ってしまう可能性がある。目に見えない専門家と目に見えない電気回路に支えられた無生物の信号は、かつては危険で、個人的で、自由だった行動を律するために介入してきたのである。
信号機は、テクノロジーには専門家の判断と政治的な判断が含まれており、日常生活ではアクセスできないことを思い出させてくれる。この交差点に信号が必要だと判断したのは誰か、歩行者の安全と車のスピードを保つのに19秒という数字が適切だと判断したのは誰か。ケンブリッジ市の職員は市民に相談したのだろうか。それとも専門家に依頼したのか、あるいは信号機の設計を専門に行うコンサルティング会社に委託したのか。疑問は尽きない。専門家が誰であれ、どうやって交差点での交通行動をモデル化し、車と人の時間配分を決めたのか。どんなデータを使って、その情報の信頼性は?健常者と歩行者を同じように想定しているのか、それとも体の弱い人や障害者のために時間を余分に確保しているのか。通常、このような疑問を抱くことはないだろう。交差点で事故が発生し、専門家が悲しい過ちを犯していたことが明らかになり、誰かが責任を問われるようなことがない限りは。
テクノロジーを賢く民主的に管理するためには、機械の表面の裏側、つまり、何が許され何が許されないかという線引きを形作った判断と選択に目を向けることが必要なのである。不思議なことに、社会理論家は、信号機のような優れた技術的対象物を設計する方法よりも、優れた法律を作る方法について考えることに多くのエネルギーを費やしてきた。この非対称性は不可解である。民主主義社会では、権力の無秩序な委譲は自由に対する基本的な脅威と見なされている。立法も技術設計も、前者は法律家に、後者は科学者、技術者、製造者に委ねられる。しかし、歴史的に見ると、私たちは技術的なシステムよりも人間に権力を委ねることを重視してきた。もちろん、歴史は重要だ。哲学者や社会科学者は、何世紀にもわたって君主制権力の乱用について懸念してきた。テクノロジーの潜在的な強制力は、より最近の現象である。しかし、もし私たちが人間の自由を維持したいのであれば、私たちの法的・政治的洗練はテクノロジーとともに進化する必要がある。テクノロジーに支配された世界で人権を取り戻すためには、私たちはどのように力がテクノロジー・システムに委ねられるかを理解しなければならない。そうして初めて、秩序ある自由と情報に基づく自治を求める私たちの願いを満たすために、委任を監視し監督することができるのである。
法と技術の間の類似点が重要であるのと同様に、相違点もある。法は全体として人間同士の関係、そして人間と社会機構の関係を規制している。例えば、電話によってセールスマンやロビイストが、物理的な侵入を禁じられていたプライベートな空間に入り込むことができるようになったように、テクノロジーもまた対人関係に影響を与える。しかし、法律の効力が人間の行為と解釈に依存するのに対し、テクノロジーは、心ない無生物と心ある有生物の間に代理権を分けることで機能し、その結果、責任とコントロールに広範囲な影響を及ぼす。信号機の例で続けると、規制された交差点での死亡事故は、信号のない交差点での事故とは異なる過失と責任の問題を提起する。赤信号を無視することは、それ自体が悪事の証拠となる。なぜなら、私たちは赤という色に法的効力を持たせることを選択したからだ。信号のない交差点では、誰が悪いかを決めるには、誤りを犯しやすい人間の傍観者の判断など、他の種類の証拠が必要となる。このような強力な規制の対象への委任をいつ行うか、また行わないかは、依然として深い倫理的な問題である。
従来の常識に反する
新しいテクノロジーは、単なる無生物の道具の配列ではなく、また、物事を成し遂げることを容易にする相互に連結した大規模なシステムでもなく、自己と他者、自然と人工の間の境界線を描き直している。技術的な発明は、私たちの身体、心、そして社会的な相互作用に浸透し、人間であれ非人間であれ、他者との関わり方を変えてしまう。これらの変化は、単に自動車やコンピュータ、医薬品の改良という物質的なものにとどまらず、人間のアイデンティティや関係性を一変させるものである。存在の意義に影響を与えるのである。例えば、生物学的物質を操作できるようになったことで、生と死、財産とプライバシー、自由と自律性についての考え方が大きく変わった。1930年代にデュポンが掲げた「より良いものを、より良い暮らしのために-化学をとおして」という宣伝文句は、人間の体から生きた惑星環境まで、生命そのものがデザインの対象となった現代では、絶望的にナイーブに聞こえる。
本書は、このような変革の可能性を考慮し、技術と社会の関係について広く受け入れられているが、欠陥のある3つの考え方を否定している。それは、技術的決定論、テクノクラシー、そして意図せざる結果である。これらの考え方は、社会におけるテクノロジーの役割について人々が一般的に信じていることの多くを、単独または複数で支えている。どの考え方も、技術をうまく制御する方法を考える上で有用な指針を与えてくれるが、いずれも限界があり、最終的には誤解を招くものである。最も危険なのは、いずれもテクノロジーを政治的に中立で、民主的な監視の対象外であると見なしていることである。この点で、3つの概念はすべて、技術の進歩は不可避であり、それに抵抗することはおろか、停止、減速、方向転換を試みることも無益であると主張しているのである。言い換えれば、テクノロジーを民主主義のために取り戻すためには、これらの強力な神話を脇に置く必要がある。
決定論者の誤謬
「技術的決定論」という考え方は、技術的変化に関する議論に浸透している。この言葉自体は、従来の常識を共有するすべての人にとって馴染みがないものだろうかもしれない。これは、技術は一度発明されると止められない勢いを持ち、その飽くなき要求に合わせて社会を作り変えていくという理論である。技術的決定論はSFによく見られるテーマで、機械が人間の支配から逃れ、自らの意志を獲得する。HAL は、人間の言葉を読み取るには十分な知識をもっているが、人間的な思いやりに欠けており、プログラムされた非道徳的な精神を切断しようとする宇宙飛行士の計画を「聞いた」ときに、宇宙船で同行していた宇宙飛行士たちのほとんどを殺してしまう14。
2000年、Sun Microsystemsの共同設立者で元チーフサイエンティストのビル・ジョイは、『Wired』 誌に「Why the Future Doesn’t Need Us」15という記事を書いて広く注目を集めた。彼は、21 世紀の非常に強力なテクノロジー、すなわち遺伝学、ナノテクノロジー、ロボティクス、または GNRと呼ばれるテクノロジーは、その消滅の可能性のために私たちの大半が取っているよりもはるかに真剣に考慮すべきであると主張した。ジョイは、この新しい時代と以前の時代との違いを、新しいGNR技術の自己複製可能性と、その製造に必要な材料の比較的平凡な点に見いだしたのである。その理由は、GNRの新技術が自己複製する可能性を持っていることと、それを製造する材料が比較的ありふれたものであることだ。正しい知識を持った個人の小さなグループが、「知識を利用した大量破壊」を可能にするのだ。ジョイは、究極のディストピアを想像していた。
「その可能性は、大量破壊兵器が国民国家に遺したものをはるかに超えて、極端な個人の驚くべき、そして恐ろしい力の増大へと広がっている」16。
一見したところ、ジョイのビジョンは、少なくとも「極端な個人」による人間の行動と意思の余地を残している点で、完全に決定論的とは言えないように思われる。しかし、より深いレベルでは、技術そのものに内在する特性が、そのような技術の開発を漫然と続ければ、「極悪の完成」を事実上確実なものにしてしまうと確信しているようだ。才能あるコンピューター科学者のこのエッセイを読むと、人間が機械をコントロールし続けるには、非人間的な抑制をする以外にない、つまり、私たちの破壊を脅かす魅力的な能力を開発しないことだ、と信じるのは難しい。しかし 2001年のHALの歪んだ知能には、自然なものも、定められたものも何もなかった。この殺人コンピュータは、人間の意図、野心、エラー、誤算の産物だったのだ。HALのような機器を自律的なものとして扱い、行動を起こしたり、行動を形成したりする独立した能力を持たせることは、それを設計した創意を軽んじ、この驚異的だが制御不能な機械を作った人間の責任を剥奪するものだ。
また、ジョイが懸念しているように、いったん技術革新という目まぐるしい冒険に乗り出したら、もう後戻りはできないというのは本当なのだろうか?責任ある倫理的な技術進歩のためには、奔放な熱狂と時代錯誤のラディズムの間に中間地点はないのだろうか?ジョイのエッセイはそのような場所を教えてはくれないが、私たちは進歩という滑らかな壁の上に他の手掛りを見出すことができる。
信号機の話に戻ろう。ゼブラゾーンを走る歩行者のように、ある行為者が常に他の行為者よりも先に進むことを認める原則的な通行権か、あるいは私のオフィス近くに新しく設置された信号機のように、異なる種類の交通に対して順次規制されるアクセス権のどちらかによって、今日の米国では、それぞれの交通が交差点に対して制御された権利を持っていると考えられている。イギリスのコモンローでは、道路利用者はすべて平等であると考えられていたが、自動車が都市景観を支配するようになると、歩行者は自動車に道を譲らなければならなくなった。自動車は渋滞を引き起こし、交差点以外の場所では自動車に道を譲ることでしか、渋滞を解消することができなかった。1920年代にテキサス州で始まった交通信号機は、コストのかかる人間の警察官に取って代わり、急速に世界中に普及した。このように、どこでも同じ意味を持ち、ほぼ同じ行動を強制する交通信号が世界中に急速に普及したことは、現代の技術革新の大きなサクセスストーリーの一つである。信号が設置されると、信号無視はどこでも危険で、アメリカのいくつかの州では厳しい罰金で処罰される目立つ行動となった。
しかし、信号機にも限界がある。交通量の多さに圧倒されたり、事故を防げなかったりするのだ。21世紀に入り、オランダの道路技術者ハンス・モンダーマンは、交通量の多い道路での混合交通の問題を根本的に解決するような方法を考え出した。それは、「シェアード・スペース」という概念である。つまり、信号や標識、バリアなどのわかりにくい目印を一切なくし、道路やインターチェンジをシンプルにすることである。その代わりに、道路や交差点は、利用者が自分や他人の安全に気を配れるような作りにすることを提案した。ライト、レール、ストライプ、そして縁石も、よりシンプルで村のようなデザインに変え、ドライバーに注意を促した。モンダーマンは、道路の利用者を分けるために物質的な構造を用いる代わりに、敬意と配慮という社会的本能を頼りにして交差点を落ち着かせた。

2004年の『Wired』誌のインタビューで、モンダーマンは、かつて自動車利用者以外にとって悪夢であったドラヒテンの町の交通環状道路について、次のようにコメントしている。
「私はこれが大好きだ。以前は歩行者や自転車がこの場所を避けていたが、今では見てもらったように、自動車が自転車に気を配り、自転車が歩行者に気を配り、みんながお互いに気を配っている。交通標識や道路標示がそのような行動を促すとは思えない。道路のデザインに組み込まなければならない」18。
モンダーマンの交通実験は成功し、ロンドンからベルリンまで、大都市のビジネス街で導入された。モンダーマンの交通実験は大成功を収め、ロンドンからベルリンまでの大都市ビジネス街で導入された。事実上、彼はすべての利用者が道路に対して平等な権利を有していた、より優しく穏やかな時代へと時計を戻したのである。これは、ある技術システムの根底にある仮定を熟考し、批判的に考察することで、その技術を利用する人々、たとえ内蔵された構造に対する代替案が想像可能かどうか尋ねることを止めなかった利用者にさえ、非常に大きな解放的効果をもたらすことができるという、小さな一例であった。
もし私たちが、設計され規制された生活様式を作り出した権力や意図に対してしばしば盲目になるとしたら、それは「テクノロジー」という言葉そのものが、人間の創意工夫による機械的生産物がその社会的・文化的基盤から独立していると考えるよう誘惑しているからかもしれない。アメリカの著名な文化史家であるレオ・マルクスは、技術の研究から技術の産物へと、この言葉の意味が変化したことは、後の思想に大きな影響を与えたと述べている。この言葉によって、テクノロジーは「表向きは独立した存在であり、事実上自律的で、すべてを包括する変化の主体になることができる」と考えられるようになったのである19。
しかし、そのような自律性の感覚は幻想的で危険なものである。より思慮深い見方をすれば、テクノロジーは人間の欲望や意図から独立しているどころか、終始社会的な力に従属しているのだ。技術的決定論の著名な批判者であるラングドン・ウィナーは、1980年のエッセイで「人工物には政治性がある」20と言っている。人間社会が生み出した技術に関して、厳格な決定論的立場に疑問を呈する多くの理由が提示されている。生産面では、私たちが作る技術は、社会が直面している、あるいは直面していると考えているニーズの種類を規定する歴史的・文化的状況から必然的に発展するものである。原子の内部構造に関する知識は、原子爆弾の製造につながる必要はなかった。戦争中の国家が物理学者の理論的知識を利用して、金で買える最も破壊的な兵器を作ったから、そのような結果になったのである。政治は、製品が市場に出た後でも、技術の使用や適応に影響を与える。2011年のアラブの反乱は、一時期ツイッター革命と呼ばれ流行したが、スマートフォンやソーシャル・ユーティリティが引き起こしたのではない。むしろ、野蛮なイスラム国を含む既存の抗議活動のネットワークが、この地域の権威主義的な宗派政治の蓋の下で何年も煮詰まっていた不満を声に出すために、電話やビデオカメラ、そしてTwitterのようなサービスを便利だと感じたのである。このような観察から、アナリストはテクノロジーを政治の現場と対象として捉え直すようになった。テクノロジーの設計には人間の価値が入り込む。そして、さらにその下流では、人間の価値観がテクノロジーの利用方法を形成し続け、時にはモンダーマンの交通渋滞緩和のように否定されることさえあるのである。
テクノクラシーの神話
「テクノクラシー」という考え方は、技術的な発明が人間の行為によって管理・制御されることを認めるが、専門的な知識と技能を持つ者だけがその任務に就くことができると仮定している。健康への影響に関する医学的知識なしに新薬を承認したり、工学的専門知識なしに原子力発電所を認可したり、金融や経済学の訓練なしに中央銀行を運営したりすることを誰が想像できるだろうか?19世紀初頭、フランスの貴族で初期の社会主義思想家であったアンリ・ド・サンシモンの思想にさかのぼる21。サンシモニズムと呼ばれる彼の哲学は、社会の運営に科学的アプローチが必要であり、それに応じて訓練を受けた専門家に権威ある地位が必要であると強調したのである。20世紀初頭の米国では、進歩主義時代において、科学技術に基づく進歩の必然性と、政府のあらゆるレベルにおいて専門家が顧問として必要な役割を果たすという、同様の信念が生まれた。しかし、第二次世界大戦が終わると、新たな動きが出てきた。戦時中の豊富な公的資金に育まれた科学者たちは、しばしば国政における自らの役割を喜び、より多くの、より優れた科学を公的な意思決定に反映させようと懸命に働きかけを行った。諮問機関や役職が急増し、従来の立法府、行政府、司法府の横に、実質的に政府の「第五の支部」が誕生し、専門家による規制機関という影響力のある「第四の支部」を補うことになった22。
しかし、テクノクラートへの信頼とその技術への依存は、懐疑と幻滅と隣り合わせのものであった。20 世紀の短い戦間期に影響力を持ったイギリスの経済学者、政治学者であるハロルド・ ラスキーは、1931年のパンフレットで専門知識の限界について書き、後の疑念と反省を予見している。
(専門知識は)謙虚さを欠いていることがあまりにも多く、そのことが、専門知識の所有者に、まさに鼻の前にある明白なことを見落とさせるような、割合の失敗を生み出すのである。また、専門家にはある種のカースト精神があり、専門家は自分たちの階級に属さない人たちから得たすべての証拠を無視する傾向がある。とりわけ、おそらく、人間の問題に関わる場合、最も緊急なことだが、専門家は、純粋に事実に基づかない判断は、それについて特別な妥当性を持たない価値体系をもたらすことを理解できない23。
アメリカの進歩主義時代の友人たちを含む当時の他の知識人たちとは異なり、ラスキーは優生学や知能テストに頼りすぎることに先見的な注意を促している。最高裁判事のオリバー・ウェンデル・ホームズは、ラスキーとの手紙のやり取りによって、憲法修正第一条に関する見解をますますリベラルなものにしていったが、1927年のバック対ベル裁判では、優生学的不妊手術を支持したことは有名である24。ドイツの生物学者がナチの人種主義を科学的に支援したというホロコーストの行き過ぎは、ラスキの懐疑心が悲劇的に十分に根付いていたことを証明するものであった。
技術的な失敗に関する最近の多くの例は、後の章で詳しく説明するが、専門家が自分たちの立場の背後にある確実性の程度を過大評価し、自分たちの閉じた陣営の外から来る知識や批判に対して盲目になるという、ラスキが以前から主張していたことを裏付けるものである。1986年に起きたスペースシャトル「チャレンジャー号」の事故では、NASAが公開調査を行ったが、早期警告サインの発見と伝達を妨げていたNASA内部の問題は発見されなかった。2003年に2機目のシャトル、コロンビア号が失われた後、社会学者ダイアン・ヴォーン25と相談して初めて、NASAはその専門家の組織文化の欠陥を認めたのである。受賞歴のあるドキュメンタリー映画『インサイド・ジョブ』の中で、チャールズ・ファーガソン監督は、「疑いなく優秀な」26 ローレンス・サマーズを含む経済顧問の小集団が、金融規制緩和を提唱し、早期警告を「遅れたもの」として2008年の金融危機の前に却下したことを詳細に語っている。これらの例は、専門家の意思決定における透明性の向上と公的監視を強く主張するものである。
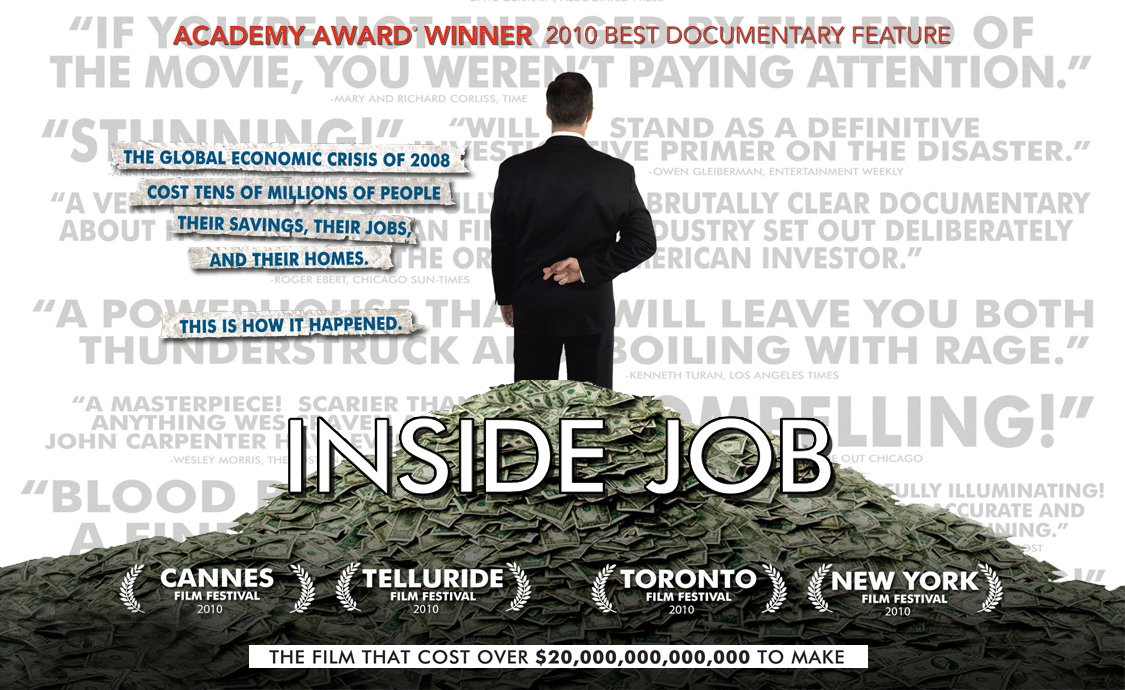
意図的な結果と非意図的な結果
技術的決定論やテクノクラシーとしばしば並行する第三の考え方は、「意図せざる結果」というものである。技術が失敗することはよく知られているが、誰がどのような状況で失敗を非難されるべきかは、あまり明らかではない。実際、失敗が劇的であればあるほど、その物やシステムを設計した人たちが意図していたことはおろか、想像していたことも受け入れられなくなる。トースターが壊れたり、凍えるような朝に車がエンストしたりすると、私たちは誰かを呼んで故障を修理してもらう。あるいは、人と同じように物にも寿命があることを知っているので、少し不平を言って、耐用年数が過ぎたものの代替品を購入する。保証期間や耐用年数内に動かなくなったものは、「レモン」と呼んでお金を返してもらう。その故障が深刻であったり、怪我をさせたりした場合は、消費者金融にクレームを入れたり、裁判を起こしたりして救済を求めることがある。しかし、人間と機械が共に生活している以上、その多くはごく当たり前のことであり、社会の基本的なリズムに大きな波紋を投げかけることはない。また、災難は自然現象であり、生物と同様に非生物をも苦しめる老化現象の結末として予測される。
技術的な誤作動や事故、災害が意図しないものに見えるとしたら、それは技術の設計過程が一般に公開されることがほとんどないからだ。製鉄所やチョコレート工場、食肉加工工場を見学したことがある人なら、見学者は限られた透明性と引き換えに厳しい規則を守らなければならないことを知っているだろう。見てはいけない場所、開けてはいけないドアがある。たまに、生産上のミスが表に出て、設計者が非常に恥ずかしい思いをすることもあるが、それは例外であって、ルールではない。2010年7月、アップル社が「iPhone 4」を発売し、わずか3週間で300万台を売り上げたときのことだ。ところが、このiPhone 4をある方法で保持すると、接続ができなくなり、電話として機能しなくなることが判明した。そのため、ブログなどでは、、「iPhone4が売れないのはおかしい」と大騒ぎになった。この出来事は、「アンテナゲート」と呼ばれ、揶揄された。しかし、アップル社の共同創業者であり、偉大なセールスマンであったスティーブ・ジョブズ氏が、その批評家たちを黙らせるために、見事な演出を施したのである。
ジョブズ氏は、公開ミーティングと広報用ビデオで、あるテーマを何度も繰り返し強調した。「私たちは完璧ではない」「携帯電話は完璧なものではない」27 完璧ではないが、人間が手に入れられるのと同じくらい良いものであり、iPhone 4の場合は、市場にあるどの競合製品よりもはるかに優れている、と彼は主張したのである。ジョブズは、この主張を裏付けるように、iPhoneアンテナの性能テストに費やされた膨大なデータを発表した。あるブロガーが指摘したように、「iPhone 4は、原始人が組み立てたものではない」と視聴者に確信させるための華麗なパフォーマンスだった28。もし不完全な部分が残っていたとしても、それは人間も機械も完全無欠で安全な世界では避けられない事態である。しかし、重要なことは、ジョブズが会社の責任を認め、Appleの社員が問題解決のために残業していることを強調し、Appleはすべてのユーザーの幸せを願っているという言葉を繰り返したことである。そして、iPhoneのカバーを無償で提供し、初期購入者の不便を補うという宥和策をとった。
「意図せざる結果」というテーマは、技術的な失敗を全く別の方向に紡ぎ出す。このストーリーラインは、スティーブ・ジョブズが告白した人間と機械の欠陥とは別物である。ジョブズは、アップルのエンジニアは、たとえ完璧なマスターベーションができなかったとしても、問題に対してできる限り一生懸命に考え、事前に解決しようと努力していると主張した。その一方で、万が一の失敗を想定して、設計を見直すこともある。これに対して、意図しない結果という言葉は、最終的にどのようなことが起こるかについて前もって考えることは不可能であり、また必要でもないことを意味している。例えば、数十年にわたる成層圏へのフロンガス放出によって引き起こされた「オゾンホール」の発見や、1984年にインドのボパールで発生し、数千人の犠牲者を出したガス漏れ事故 2008年の世界金融市場の崩壊のような大惨事の後、この言葉は通常、悲惨で破滅的な出来事の後に発せられる言葉である。これらの災害は、私たちを無力にし、どのように対応すればよいのか、また、どのように被害を軽減すればよいのか、まったく分からなくさせるものである。このような大規模な崩壊は意図的なものではなかったと主張することで、麻痺と罪悪感の集合的な感覚を和らげることができる。このような致命的な出来事を、自然災害、あるいは保険会社でいうところの神の御業になぞらえることができる。そうすることで、既知の関係者は、何が悪かったのか、また、何が起きたのかについての責任を暗黙のうちに免れることができる。
しかし、意図しない結果という考え方は、厄介な問題をはらんでいる。設計者の意図したとおりにならなかったという意味なのか、それとも、誰もその技術がどのように使われるかを事前に知ることができなかったために、設計者の意図の範囲外のことが起こってしまったという意味なのか。この2つの解釈は、法的にも道徳的にも全く異なる意味を持つ。例えば、ロバート・マーティン・サンチェス氏は 2008年9月にロサンゼルスで起きた列車事故において、仕事中のメール送信により、同氏と24人の死者を出すという重大な事故を引き起こした。電話の設計者は、高度な注意力を持続的に必要とする職業に就く人がこの発明を使用することを意図していなかったと考えるのが妥当であろう。救済措置としては、製造者だけでなく、使用者にもより高い注意基準を強制するための法律や規制の変更が考えられる。例えば、自動車が大量に普及した数十年後に気候科学者が、化石燃料を燃やす自動車からの排出ガスが気候変動の主な原因であることを発見したような場合である。この場合の失敗は、想像力、予期、監督、そしておそらく無制限の欲望であり、予防政策や技術設計の改善によって簡単に治るものではない。
残念ながら、この2つのシナリオは論理的には異なるものの、実際には切り離すことが困難な場合が多い。問題の一つは、「unintended」という言葉の曖昧さにある。結局のところ、ある技術が意図した結果とは何なのだろうか。その場合、起こりうる事故について積極的に考える必要のある設計者や規制当局にとって、その答えはあまり有益ではないだろう。また、この言葉の使い方には、良い結果は常に意図されたものと考えられ、悪い結果だけが後から意図されていないというレッテルを貼られるというような偏りがあるのだろうか。その場合、意図しない結果という言葉は、主に、技術革新が基本的に進歩的で有益なものであることを私たちに安心させるために使われる。つまり、人類に有益な役割を果たすはずの機器に、大惨事を引き起こす可能性を意図的に組み込むようなことはしない、という希望を表明しているのだ。
第二の問題は、「意図せざるもの」という言葉が、意図(少なくとも道徳的に適切な意図)をある特定の時点で固定してしまうように思われることである。メール送信の列車技師サンチェスの物語は、技術が世に出た後、いかに社会と複雑かつ変化する関係を獲得するかを物語っている。2008年に起きたロサンゼルスの通勤電車で起きた死亡事故の前もそうであったように、携帯電話と電車、メールと通勤は、ほとんどの場合、私たちにとって異なる概念的領域に存在しているのかもしれない。しかし、人間は、現代社会が手の届くところに置いた機器を、独創的、想像的、そしてクリエイティブに使いこなすものである。その変化する使い方を追跡する責任は誰にあるのだろうか。ロサンゼルスでの悲劇的な事故は、誰も事前に計画していなかったが、監督者が目を凝らせば、かなり広範囲に渡っていたかもしれない、ある種の相乗効果に注目させた。もし、ある技術者がそのような不注意を犯していたなら、他の技術者も同じようなことをしていた可能性がある。この事故の連邦調査委員会の委員長を務めたキャサリン・オリアリー・ヒギンズは、乗務員の携帯電話の使用を国家的な問題であると断言した。「これはある日、ある列車、ある乗務員の出来事であり、他に一体何が起こっているのかという疑問を私に抱かせるものである」29。
立場と方法
技術革新は、人間の多様性と同じくらい広範なものであり、それを分析的に理解しようとする試みには、いくつかの枠組みを選択することが必要である。私自身は、このような選択を、一部は学問的な訓練によって、また一部は個人的な世界の経験によって、行っている。本書で扱う実証的な資料の多くは、法律学者として、科学、技術、法律の接点で起こる論争に深く精通していることに由来している。また、科学技術の社会的実践が、法律など社会の他の制度とどのように関連しているかを理解するための比較的新しい学問分野である、科学技術研究(STS)の分野でも二次的な訓練を受けている。STSの分析では、特に、技術的・社会的な不確実性がどのように解決されるのか、また、信じられるような世界の説明をするために何が失われ、何が単純化されるのかに細心の注意を払う必要がある。STSが特に関心を寄せるのは、技術システムが十分に安全かつ効果的に機能すると宣言し、疑念を傍観するような決定である。このような観点から、リスク評価などの専門的プロセスに関する文献が数多く発表されており、本書で提起されている倫理的・道徳的問題に影響を与えている。
もう一つの方法論は、科学技術政策と環境規制の国際比較に長年携わってきたことに起因している。科学的根拠に基づく合理的な意思決定と公衆衛生や安全性の徹底的な保護を掲げる国々であっても、技術システムに対する規制の程度や種類が異なる場合があることが、こうした調査によって明らかになった30。ドイツは反原発に熱心だが、フランスは全体として好意的である。どちらも自国内に油田やウラン鉱山を持たず、政策の相違は経済的、地政学的な利益だけでは説明しきれない。このような相違は、技術的未来に関する倫理的推論において歴史と政治文化が重要であることを示唆しており、本書はそのような観点からも重要な示唆を与えている。
また、本書で取り上げた事例には、様々なレベルでの個人的な選択や経験が反映されている。なぜなら、これらの分野では、プライバシーや監視といった問題がまだ流動的なデジタル分野よりも、倫理的・法的問題が早くから明確にされていたからだ。また、個人的な関心と知的な関心が混在する南アジア、特にインドでの事例も取り上げている。インドと米国には、リスク、不平等、人間の尊厳というテーマに関わる顕著な類似点と相違点がある。両国とも技術開発に力を入れ、民主的な社会であり、社会動員や言論の自由といった立派な伝統を育んできた。しかし、インドは米国より明らかに貧しく、技術的な大失敗や災害が何度も起きている。両国の議論を並べると、不平等な世界における責任ある倫理的なイノベーションの課題が浮き彫りになる。
責任感の欠如
近代の環境を構成する人間が作り出した機器やインフラの利点を否定するのは、よく言えば愚か、悪く言えば危険なほど無邪気なことだろう。しかし、テクノロジーを人間の自由な選択に従って進化する社会の受動的な背景として扱うにせよ、テクノロジーに私たちの運命を形作る超人的な力があるとするにせよ、私たちの幸福を脅かす概念の誤りを犯す危険性があるのだ。数世紀にわたる発明は、人間の生活をより甘やかされ、自立し、生産的にしてきただけでなく、古典的な政治・社会理論にはほとんど名前がなく、ましてや善政の原則もないような抑圧と支配の形態を永続させてきたのである。テクノロジーが階層構造や不平等を含む社会的相互作用の基本的な形態にどのような影響を与えるかをもっと理解しない限り、「民主主義」や「市民権」といった言葉は、自由な社会の羅針盤としての意味を失ってしまう。
技術的決定論、テクノクラシー、意図せざる結果といった教義は、技術に関する議論から価値、政治、責任を排除する傾向がある。もし機械が独自の論理を持ち、社会を必然的な道筋に向かわせるのであれば、道徳的に重要なことはほとんど議論に残らない。その場合、テクノクラートは、専門家による統治が唯一の有効な選択肢であると主張する。なぜなら、私たちが望むのは技術がうまく機能することであり、工学設計や技術的リスクの評価は、普通の人々に任せるにはあまりにも複雑だからだ。さらに、すべての大規模な技術システムが複雑であることを考えると、予測できない脅威を含む不確実な未来と共存する現実的な選択肢はない。予期せぬ結果というレンズを通して見ると、テクノロジーの多くの側面は、事前に知ることも、効果的に防御することもできない。ヘンリー・フォードがT型を開発したとき、どうして気候変動を予見できただろうか?社会は創意工夫をし、創造的で、リスクを恐れず、悪いことが起きてもうまく対処できるようになる方がよいに違いない。
このような議論は、テクノロジーによって脅かされたり、制限されたりしている現代生活の側面について、宿命論や絶望をもたらす可能性がある。しかし、私たちは、従来の常識が誤りであることを見ていた。テクノロジーを本質的に非政治的あるいは非ガバナンス的なものとして表現する理論は、テクノロジーも技術者も政治、道徳的分析、ガバナンスの範囲外には存在しないという反証を生んだのである。現代社会の課題は、有意義な政治的行動と責任あるガバナンスの可能性がどこにあるのかを知るために、テクノロジーについて十分に強力で体系的な理解を深めることである。人間の能力を向上させるために行われる交渉は、盲目的な無知や還元できない不確実性の条件下で不平等な交渉相手との間で結ばれるファウスト的なものである必要はないのである。
しかし、テクノロジーが人間のコントロールから外れないようにするための最も有望な手段は何か。また、増殖する無生物の創造物を抑制するために、概念的あるいは実際的にどんなツールを展開することができるのだろうか。本書の残りの部分では、社会が技術的発明に対してより責任ある行動を取るためには、リスク、不平等、人間の尊厳といった問題に対処する必要があるとして、これらの問題を取り上げている。
第2章では、ほとんどすべての技術革新に付随するリスクについて、その発生源と管理のあり方を問う。技術的リスクはどのようにして生じるのか、誰が評価するのか、どのような証拠や証明の基準によって、またどのような種類の監督や管理のもとで、リスクは発生するのか。
第3章と第4章では、技術的に進歩した社会における不平等と不公正の構造的基盤というテーマを扱っている。第3章では、技術システムにおけるいくつかの劇的な失敗を検証し、リスクや専門知識が国境を越えて偏在し、予測や補償の責任を特定することが困難な世界において、より倫理的なガバナンスシステムはどのように考案され得るかを問うている。
第4章では、動植物の遺伝子組み換えをめぐる論争をたどり、科学者が地球規模で自然に手を加える際に生じる国境を越えた倫理的・政治的ジレンマを明らかにする。次の3つの章では、新たな技術システムにおいて個人の自由と自律が果たす役割の進化について、さまざまな角度から考察している。
第5章では、生物医学の科学と技術の変化がもたらす倫理的・道徳的意味を考察し、人間の生物学を操作することの限界について、どのような制度とプロセスによって意思決定がなされるのかを検証している。
第6章では、急速に拡大する情報とソーシャルメディアの世界を掘り下げ、デジタル革命の初期の数十年間に生じたプライバシーと思想の自由に対する挑戦をマッピングしている。
第7章では、知的財産の問題を取り上げ、自由な探求の理想と所有権のある知識の現実との間の緊張関係を支配するルールについて考察する。最後の2つの章は、コントロールとガバナンスの問題を探求している。
第8章では、技術的未来の設計と管理においてより積極的な役割を果たすよう、一般市民を巻き込むために考案されたさまざまなメカニズムについて検討する。
第9章は、本書の冒頭で述べた究極の問いに立ち戻る。あまりにも急速で、あまりにも予測不可能で、あまりにも複雑で、古典的な善政の概念を適用することができないと思われる技術的な力に対して、どのようにして民主的統制を回復できるのか。
第2章 リスクと責任
最も単純な定義では、技術とは目的達成のための手段であり、現代においては、実用的な目標を達成するために専門家の知識を応用することである。しかし、このような技術の理解には、明らかな限界がある。それは、発明の「目的」はあらかじめ決まっていて、「工夫」は主としてその「目的」を達成するために行われるということである。人類の祖先は、食料を探し、天候や敵から身を守り、避難することが主な目的であった。そのため、パチンコや矢が発明され、川や湖を渡らなければならなかったので、橋が架けられ、木の幹をくりぬいたものが浮かべられた。先史時代の博物館には、古代の道具職人の埃まみれの手仕事が展示されている。研いだ火打石、斧の頭、石臼と杵、粗末な農具など、一見無尽蔵にあるように見える。
しかし、現代のテクノロジーは、そのような一面的なものではない。しかし、現代のテクノロジーは、手段と目的が一対一に対応するような単純なものではない。その理由の一つは、社会における技術の目的は決して固定的なものではなく、技術システムは、それが組み込まれた社会とともに、生物学的な生物と同じように進化していくからだ。最も有用で永続的な技術的発明は、車輪、歯車、電気、トランジスタ、マイクロチップ、個人識別番号(PIN)など、様々な用途に使われるようになったものである。1 電球も、新素材の登場や、コンパクト蛍光灯やLED電球が従来の白熱電球の何分の一かのエネルギーで家庭や街を照らせることがわかると、形や機能が多様化する。今日の自動車がヘンリー・フォードのT型フォードと大きく異なるのは、レーシングカー愛好家からキャンプや長距離ドライブを好む大家族まで、さまざまなユーザーに対応するようになったからだ。しかし、適応しない技術は、静かに廃れていく。例えば、固定電話は、人の声を定点で受信し、別の場所に伝達するという目的に非常に適していた。しかし、携帯電話は、通話ができるだけでなく、持ち運びができるため、従来の電話機に押され気味であった。そして、通話だけでなく、メールやインターネット、記念撮影など、さまざまな機能を備えたスマートフォンが登場した。
さらに、手段と目的を結びつける技術も複雑化している。安全でクリーンな自動運転(および自動駐車)の理想に近づいた車の機能の多くを制御するソフトウェアを理解しているドライバーは、ほとんどいないだろう。しかし、エアバッグが警告なしに激しく膨らむなど、隠されたアクセス不能な計器類が新たな死亡事故を引き起こすこともある。マフラーやバッテリーの異常を知らせる警告音もなく、高速道路で停止することもある。新時代のリスクの教科書的な事例として、世界で最も尊敬されている自動車メーカーの一つであるフォルクスワーゲンは、2015年秋に、排ガス試験中にディーゼルエンジンから誤解を招くような数値を表示するソフトウェアを故意に操作していたことを公表した2。これらの「ディフィートデバイス」は、VW車が試験以外の条件で運転すると著しく性能が落ちる事実を隠蔽していた。約1100万人の消費者は、突然、再販価値が低く、適用される大気質基準を満たさない車を手にすることになったのである。フォルクスワーゲンは、自ら認めているように、故意に法的要件を無視しただけでなく、VW車の所有者である顧客の将来に対する期待を裏切ってしまったのである。
手段と目的の結びつきが緩くなったことで、技術的な道筋が直線的でなくなり、予測が難しくなった。オゾン層破壊の現象は、その一例である。クロロフルオロカーボンは、1960年代に不活性で無毒、不燃性の冷媒として広く使われるようになり、その後、エアゾールスプレーなど多くの新しい用途に使われるようになった。しかし1972年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の2人の化学者、F・シャーウッド・ローランドとマリオ・モリーナが、この化学物質が成層圏のオゾン層を破壊しているという驚くべき事実を突き止めたのだ。この発見は、当初は学界や産業界の化学者たちによって否定され、2人の研究が認められるまでに15年以上、ノーベル賞受賞までにはさらに長い年月を要した。そして、国際社会はモントリオール議定書という条約を締結し、安全だと思われていた化学物質が、今後人類社会で生産・使用されることがないようにしたのである。
何十年もの間、私たちは技術開発を取り巻く不確実性と懸念の多くを、リスクという見出しで括ってきた。規制当局は、リスクを評価し、被害が発生する前にコントロールすることに全力を尽くした。リスクとは、辞書で調べると、飛行機に乗っていて乗客が死亡する確率や、火事で家を失う確率のように、怪我や損失を被る可能性のことである。技術的リスクとは、人間が作り出した機器やシステムの使用や操作に起因するリスクであり、地震や嵐、伝染病など、人間がコントロールできないと想定される自然災害によるリスクとは対照的である。この区別は、相互依存の世界では維持することが困難である。例えば、気候変動は、自然と技術の境界線を越えている。気候変動は、人間が引き起こした自然現象であり、現在では「人新世」3と呼ばれる、人間の活動が地球環境に大きな影響を及ぼしている時代と定義されている。工業化の進展に伴い、人間の知恵の産物であるリスクは、生活のあらゆる場面で見られるようになった。また、気候変動のように、風、天候、海流などの自然現象にも組み込まれている。ゼロリスク、つまり、機械やデバイスがやるべきことを正確に行い、誰も傷つくことのない完璧に機能する技術環境という理想は、依然として実現不可能な夢である。
1986年、ドイツの社会学者ウルリッヒ・ベックは、テクノロジーが失敗したときに顕在化する脅威、不確実性、制御不能の組み合わせを捉えるために「リスク社会」(Risikogesellschaft)という言葉を作った4。新しいリスクは、放射線やオゾン層破壊といった無形のものであり、そうしたリスクが現実化したときにどう対処すべきか、これまでの経験では何も教えてはくれなかった。ベックは、私たちは近代化の段階に入り、人種、階級、ジェンダーといった旧来の社会的分類と同様に、さまざまな形の手に負えないリスクにさらされることによって社会が特徴付けられるようになった、と主張した。チェルノブイリ原発事故の年に出版されたベックの分析は、ドイツでは深い不安のコードに触れ、その濃密で学術的な社会学的論文は予想外に何千部も売れた。しかし、その影響は事故の後遺症よりも長く続くことになった。この本は、現代社会が技術的な冒険の意味合いと結果についてもっと深く考え、もっと責任を持つようにという警鐘として読まれたのである。

ベックは、私たちを取り巻くリスクの全容を理解し、コントロールできると主張することのできない、統治機関の「組織的無責任」に注意を喚起した。科学は、この時代の不安を和らげることはほとんどできない。なぜなら、新しい知識は、疑いと懐疑の境界を切り開く傾向があるからだ。気候科学は、ベックが著作を書いた当時はまだ初期段階にあったが、知識の大きな進歩がいかに重要な不確実性を新たに生み出すかを示す説得力のある実例である。しかし、これらの変動が地域や特定の社会経済集団の生活や生計にどのような影響を及ぼすかは、不確実性に覆われている。
本章では、技術的なリスクを抑えるために過去1世紀にわたって作られた公式なガバナンスの仕組みと、それらが市民のエンパワーメントやディスエンパワーメントに果たした役割について考察する。この分析から、リスクを評価するために最も一般的に用いられている方法は、価値中立的なものではなく、達成可能で望ましい人間の未来に対する明確な方向性を組み込んだものであることが明らかになる。リスク評価には、変化を支持する暗黙の前提があり、新しいものは、それが今日の基準で判断すると耐え難い損害をもたらすものでない限り、受け入れるべきであるという偏見がある。もうひとつは、良い結果は事前に知ることができるが、害はより推測しやすいため、計算可能で即座のものでない限りは割り引かれる、というものである。本章ではまず、技術的な失敗を意図せざる結果と解釈し、害をもたらしたのは適切な予見能力の欠如に他ならないという見解を永続させる典型的な手口を紹介する。次に、リスクが発生する状況の複雑さと曖昧さを減らすことで、統治不可能な未来を統治可能だろうかのように見せる計算技術に目を向ける。全体として、これらの例が示唆するように、専門家によるリスク評価は、継続性よりも変化、環境や生活の質に対する長期的影響よりも短期的安全、そして社会の他の構成員に対する公正よりも開発者に対する経済的利益を重視する傾向がある。
安心の物語
技術的リスクとは、人間と非人間が共に作用することによって生じるものである。最も地味なものから最も複雑なものまで、どんな製造物も、人間が設計を誤ったり、不適切な取り扱いをしたりすれば、危険なものになり得るのだ。しかし、実際に、あるいは意図的に無知であるために、私たちはしばしば、物質的な人工物とその操作者である人間との間に安心できる区別をすることで、それらに罪はないと考えている。その結果、テクノロジーは有用であり、実現可能であり、継続的に進歩するものとされ、その悪影響は不運なヒューマンエラーとして処理される。
例えば、銃、自動車、娯楽用麻薬など、広く普及している技術の場合、人々は、たとえそれが大きな損害を与えたとしても、その発明を非難したがらないようである。米国では、憲法修正第2条が武器を持つ権利を保障しているため、銃は特別に保護された役割を担っている。アメリカでは年間約3万人が銃で死亡しており、交通事故死を上回っているが、アメリカの強力な銃ロビーである全米ライフル協会(NRA)は、「銃が人を殺すのではなく、人が人を殺す」と主張するのは有名な話である。NRAの主張では、犠牲者が出るのは、本質的に自由な道具が、悪い、あるいは不注意な手に渡ったからだ。この観点からすれば、「銃による暴力」は誤用であり、この国の銃文化が意図せずに生んだ副産物である。一部の行為者は病んでいるか、怒っているか、責任を持って武器を扱わなかったのであり、死者や負傷者は悲しいことに、事故が起こったときにたまたま彼らの目の前にいたのである。NRAの引き金好きな想像の中では、これらの犠牲者の多くは、もし自分たちも武装して他人の病理から身を守る準備ができていれば、生きていられたかもしれないのだ。
ある技術が個人の生活に及ぼす有害な影響を集計することを怠ると、重大なリスクが長い間気づかれないままになってしまうことがある。1980年代から1990年代にかけて、使い捨てライターが爆発し、何千人もの負傷者や死者を出した。このような事故は、被害者が訴訟を起こし、業界がより厳しい基準を採用するようになるまで、裁判記録を封印し、目に見えないままだった。その15年後、GMのシボレー・コバルトやその他の小型車のイグニッション・スイッチの欠陥により、エアバッグが作動せず、多くの死傷者が出た。5 さらに一般的には、自動車は都市や高速道路にあふれかえっているが、米国では年間3万人以上が交通事故で死亡しており、これはベトナム戦争で米軍が戦死した数に匹敵する。軍事技術は非人間的な規模で死をもたらすように設計されており、安全保障上の必要性を超えている。しかし、国民は毎年その製造に再承認を与えているが、武力紛争の世界的犠牲者数はほとんど集計されないため、国民の意識から消し去られてしまう。
目に見える技術的な失敗をきっかけに行われた調査は、社会が人間の注意をもう少し払えば安全を確保できたと安心させる動きについて、さらに多くの光を投げかけている。米国は、1986年のチャレンジャー号と2003年のコロンビア号の2機のスペースシャトルを、設計上の欠陥が原因で失い、いずれも乗員7名が死亡している。シャトルの事故は、多大な犠牲と悲劇、そしてNASAの名声を傷つけたが、リスク分析のいくつかの特徴を示しており、それは技術システムの倫理的、民主的ガバナンスにとって極めて重要なものである。
第一に、最も徹底的に研究され、慎重にテストされた技術であっても、危害の予測は依然として不正確な科学である。故障に至る因果の連鎖は無限にあり、それゆえ事前に完全に把握することはできない。社会学者のチャールズ・ペローが指摘するように、複雑なシステムでは、小さな誤作動でも悲惨な結果を招き、構成要素が非常に緊密に結合しているため、いったん破壊の連鎖が始まると、システムは最初の誤りを許せるほど回復力がない6。放出されたガスは隣接する外部燃料タンクを包み込んだ。炎、熱、爆発は重要な接合部を曲げたり壊したりし、離陸から2分も経たないうちに機体全体が崩壊し、その様子を恐怖に満ちた視聴者がテレビで生中継していた。乗員室は、たとえ内圧を失うことなく崩壊を免れたとしても、誰も助からないほどの衝撃で海に着水した。
コロンビア号の場合、シャトルの外部タンクから発泡断熱材の小片が外れ、シャトルの左翼の端にぶつかり、大気圏再突入時の熱から船体を守る保護システムが損傷したのである。NASAの上級管理者は、中途半端な修理はできないと考え、損傷部分の目視点検を命じなかった。船とクルーの運命は、最初の破片の衝突の瞬間に事実上封印されたが、クルーは何が起こるかわからないままであった。2週間後、地球への帰還予定時刻の16分前に、高温のガスが損傷した翼の部分に侵入し、まさに恐れていた通り、船は壊れ、クルーは全員死亡した。
第二に、シャトルの事故は、早期警告のシグナルがそれぞれの事象に先行していたにもかかわらず、それが認識されなかった、あるいは尊重されなかったことを示した。何を知っているかは、その人の訓練、傾向、技術システムの中での位置づけに依存する。例えば、それぞれの悲劇に至る状況を丹念に再現すると、エンジニアは致命的な事故を引き起こした欠陥について、それぞれの失敗したミッションのかなり前から知っており、懸念していたことが明らかになった7。NASAの請負業者でありチャレンジャー号のブースターロケットを製造したモートン・ チオコール社のエンジニアであるロジャー・ボイスジョリーは、1月末のフロリダ州で異常に寒い日にチャレンジャー号を発射しないよう勧告していた。しかし、会社の上司やNASAの管理職は、すでに大幅に延期されていたパブリックイベントを進めるために、ボイスジョリーの意見を無視した。チャレンジャー号のOリングは、過去にも故障したことがあったが、その時は予備のOリングがあったため、完全な故障には至らなかったという事実が、賛成派を安心させた。
同様に、コロンビア号も最終フライトの前に泡の破片でボディがへこみたが、そのダメージは予防措置をとるほど深刻なものではなかった。その代わりに、致命的な故障は、想像上の完璧さと現実のギャップの一部と見なされ、どのケースもリスクは許容範囲内にあると見なされていたのである。NASAは後から振り返って初めて、組織が自己満足の文化を発展させ、重大な警告であるはずのものが日常の災難として再認識されるようになったことを認めた(スティーブ・ジョブズがアンテナゲート事件後にAppleに降りかかることはないと主張した自己満足の一種である)。社会学者のダイアン・ヴォーンはこの現象を「逸脱の常態化」と呼んでいる8。これは、組織が大惨事を引き起こす可能性の高い技術を運用しているときでさえ、十分な警戒レベルを維持できないような、一種の構造的な忘却であると言える。
シャトルの事故が浮き彫りにした第三の点は、ベックが指摘したように、複雑な技術システムの管理責任が、説明責任を制限するような形で分散されていることである。部品は、最終製品の組み立てや運用を行わない企業によって製造される。チャレンジャー号の例では、モートン・ティオコールの技術専門家とNASAの政治的思惑のあるリーダーとの間で知識と権限が分断されたことが示されている。しばしば、先見の明のあるエンジニア、ボイスジョリーのような、実際に物事がどのように動いているかの詳細に最も近い人たちは、技術的専門知識が最も遅れ、経済的・政治的偶発性に最も従順であると思われる上層部の考えには影響を及ぼさないのである。悲劇的なことに、両シャトルの事故は、このような分散した監督とそれに伴う機械的、人的、制度的ミスの結果が、自分たちの運命を左右する意思決定にほとんどあるいはまったく口を出せなかった無実の犠牲者に降りかかる傾向があることを示している。
責任の所在を明らかにすることの難しさは、意図せざる結果の神話の裏返しと見ることができる。テクノロジーに関わる多くの場面で、一人の人間が全体像を把握することができないからこそ、明らかな意図とは無関係に被害が発生するのだ。ロサンゼルスで亡くなった24人の通勤客と不幸なロバート・マーティン・サンチェスは、自分たちが致命的な旅に出るとは知り得なかっただろう。なぜなら、列車の機関士が仕事中にメールをしようと考えるとは誰も予想できなかったからだ。乗客にとっては、賑やかな西部の大都市でいつもと変わらない一日を過ごし、たまたま悲劇的な結末を迎えただけのことだった。シャトルの打ち上げは、決して通勤電車のような日常的なものではなく、それぞれの装置は、人類が作り出したあらゆる機械の中で最も慎重に作られ、テストされたものであった。しかし、チャレンジャー号に同乗した教師クリスタ・マコーリフや、コロンビア号に同乗したイスラエル空軍大佐でホロコーストの生存者の息子イラン・ラモンの死の責任は、単一の行為や行為者にはないのである。このような個々のケースに見られる責任の分断は、次章で改めて見るように、グローバル化とともにより広範なものとなってきている。
リスクと先見性
シャトルの事故は、チャールズ・ペローの言葉を借りれば「普通の事故」だが、他の面では「普通」とは程遠いものであった。どちらも、リスクの専門家が「低確率、高結果」と呼ぶ事象を表している。このような事象は稀であり、予測も不完全だが、発生した場合の影響は組織、地域社会、さらには国家にさえも壊滅的なものとなり得るのだ。チャレンジャー号とコロンビア号の事故で失われた命は、14人の非常に勇敢な人々に限られたが、NASA、宇宙計画、そして有人宇宙飛行をその技術力と世界的地位の究極のシンボルと考えるよう訓練された国家にとって、経済的、心理的影響は甚大なものだった。
原子力発電所、飛行機、処方箋薬の導入の前後は、極めて先見の明があったおかげで、それぞれの故障、事故、副作用は、影響が大きい故障は依然として起こるものの、確率が低く、影響が大きい事象というカテゴリーにほぼ収まっている。しかし、技術的なリスクは、その確率や結果に様々な段階がある。交通事故は、自動車の安全性が大幅に向上したにもかかわらず、毎年多くの人命を奪っている。化石燃料の排出による地球温暖化や気候変動への影響を考慮しなくとも、社会全体への影響という点では、自動車の使用は高確率・高結果のリスクに分類されるのが合理的である。一方、はしごや自転車からの転落、芝刈り機の事故、水道の蛇口の不具合によるやけどなどは、通常、致命的なリスクではない。たとえ、毎年多くの不幸な人々に重傷や致命傷を与えるとしても、社会全体に与えるコストは比較的低い。ましてや、はしごに登ったり、芝を刈ったり、家のお湯を出したりするのは、その道具がどのようなものだろうかを知っている人たちである。つまり、これらの事故は、「確率は高いが、結果が比較的小さい」事象の一例と言える。低確率・高結果のリスクとは、その頻度や社会経済的影響だけでなく、使用者と使用する道具の間にある親近感という根本的な関係も異なる。
表1.リスクの類型化
【原文参照】
複雑な技術の製造者と消費者は、そのリスクについてどの程度知っているか、また予防的な行動が取れるかについて、全く異なる土俵で活動している。原子力発電所の近くに住む人々は、一般的に発電所の安全性に関して無知であり、事故の際に自分自身を守ることができない。2015年にジャーマンウイングスの副操縦士アンドレアス・ルビッツがパートナーを操縦室から締め出し、飛行機をピレネー山脈に突っ込ませ、乗員全員が死亡したように、これらは自分たちの生命に影響を与える可能性があるのに、飛行機の乗客はパイロットの飛行経験や精神状態について知りえないのである。処方薬を使用する患者は、多くの情報を持っていても、自分自身や自分の子供に起こる深刻な副作用を予測したり、予防したりすることはできないかもしれない。倫理的に受け入れられるリスク管理のシステムは、危険な技術のスペクトル全体にわたって、原因、結果、知識の分布にこのような大きなばらつきがあることを考慮に入れなければならない。
すなわち、市民が重大な、あるいは広範な被害にさらされる前に、体系的なリスク分析を行い、その後、リスクを低減するために必要な規制を行うことである。概念的には、19世紀半ばからの保険業界の台頭と国家福祉計画との連携に負うところが大である。リスク分散の原則は、リスクにさらされた集団のメンバー全員から少額の資金を徴収し、実際に損害を被った少数の人々に補償するというもので、そのルーツは古くからある。バビロニアのハムラビ法典では、農民に対して初歩的な保険を提供し、嵐や干ばつで作物が枯れたり、失敗したりした年には、債務者のローンが免除されることを定めている。今日、損害を与える可能性のある社会的活動は、誰かが保険をかけなければほとんど起こらない。例えば、カリフォルニア州にあるファイアーマン保険ファンドは、映画業界がスタント演技や模擬災害による怪我を補償するための保険である。
しかし、近代国民国家が出現して初めて、政府は、職業上の危険、自動車事故、高齢化と失業、病気や障害といった集団的な問題に対して、国民に保険をかけることを日常的に行うようになったのである。これらの問題は、誰もが人生のどこかで遭遇する可能性のあるものだが、被災者の社会的立場によって、生活や社会的立場へのダメージの程度は異なる。近代ドイツ国民国家を築いたオットー・フォン・ビスマルクは、欧州の福祉国家のモデルとなる年金・保険制度を次々と確立した。米国でも、福祉国家モデルに対する慢性的な政治的反対にもかかわらず、20世紀初頭には各州が労働者災害補償法を制定し、仕事中に負傷した従業員に自動的に補償を提供するようになった。2010年にオバマ大統領が制定した「医療保険法」は、この保険原則をさらに拡大し、すべてのアメリカ人の健康保険に適用したものである。
リスク評価は政策手段であり、それ自体が目的ではない。通常、健康、安全、環境を守るための規制措置に先立ち、そのための情報を提供する。社会保険制度と同様、規制によるリスク評価も、影響を受ける集団に害が及ぶ確率を事前に計算できるという原則の上に成り立っている。しかし、その目的は、個人に対する傷害や損失の補償に十分な資金を確保することではなく(公的保険と民間保険の主要目標)、主要な技術開発による損害の総量が社会が許容できると考える範囲内に収まるようにすることである。危険な技術のリスク評価を行うにあたり、国家は人為的な危険から市民の生命と健康を守るという、極めて一般的な責任を確認することになる。米国の法律では、医薬品、農薬、食品添加物、医療機器は、それらがもたらすリスクを事前に評価することなく販売することはできず、ほとんどの場合、政府の明確な承認がなければ販売することはできない。
これらのリスクを評価し、軽減する義務を負うことによって、国家が主催するリスク評価は、少なくとも原理的にはウルリッヒ・ベックの組織的無責任という非難に対抗するものである。また、民主的な機能も果たしている。多くの国では、行政手続きによって技術リスクに関する情報の公開が義務付けられており、利害関係者は国や企業のリスク専門家に質問する機会を与えられている。このように、規制リスク評価は、工業生産の過程では得られない技術の内部構造を知るための窓を提供する。それは、近代化の目に見えないリスクについて知る権利を市民に与えるものである。
技術的リスク評価の仕組みは、実際にはどのように機能しているのだろうか。20世紀半ば以降、このプロセスを日常化し、身近で実現可能なものにするために、多くのことが起こってきた。1983年、リスクベースの規制決定をめぐる長引く政治的論争に対応して、米国学術会議(NRC)は、リスクの評価と規制を任されているすべての連邦政府機関向けに、リスク評価のプロセスを体系化した報告書を発表した。その核心は、「リスク評価」を主として科学的な作業として扱い、その後の「リスク管理」と呼ばれる価値に基づく意思決定のプロセスから切り離すことを命じたことであった10。この方式によれば、リスク評価は個別の直線的なステップで行われ、それぞれが利用可能な科学的証拠のみに基づき、政策オプションの策定前にすべて実施された。主要な段階は、ハザードの特定、線量反応評価、暴露評価、リスクの特徴づけである。
NRCの提案は、表面的には非常に理にかなっている。リスクを理解することが、自然や社会に関する事実を知り、評価することに主眼を置くのであれば、その事実探求のプロセスを政治的な操作から守ることが重要である。したがって、リスク評価をリスク管理から切り離すことは、賢明な政策であると思われた。1983年のNRCの報告書で示されたリスク評価の4つの段階も、同様に単純明快に思えた。ハザードが存在することを認識することは、リスクを最小化または排除しようとするあらゆる試みの論理的出発点である。がんに対する国民の関心が高まっていた当時、NRCの著者らは、環境化学物質による健康への有害な影響を模範的な例として取り上げたのである。したがって、リスク評価プロセスの第2段階は、有害性が常に用量に比例すると考えられている毒性学からインスピレーションを得たことは驚くには当たらない。線量反応評価とは、身体的被曝と影響の重大さとの関係を明らかにする科学的試みであり、毒性化学物質だけでなく放射線にも適用される計算方法である。NRCの枠組みの第3段階である被曝評価では、誰がどのような経路で被曝するかを調べることにより、ある集団に対するハザードの影響を測定する。大気汚染物質や鉛のような難分解性物質のような普遍的な化合物は、例えば、少数の限られた患者の治療に使われる専門薬よりも、より高いレベルの集団被ばくを伴う。最後に、リスク判定のステップでは、集団全体に様々なレベルの曝露が行われた場合の危害の量と分布を推定する。これには、子供、妊娠中の母親、持病のある人など、特別に弱いグループに対する害の測定が含まれる場合がある。この判断は、社会全体のリスクレベルを低減させるための合理的な政策オプションを定義するのに役立つ。
リスクの枠組み:価値観の問題
NRCのリスク評価の枠組みは一見合理的に見えるが、リスク評価が技術革新に関する質問を狭めてしまうという微妙な、あるいはそうでない批判を正当な形で引き起こしている。最も基本的な限界は、リスク評価が集団の幸福にとって最適な結果をもたらさない可能性のある方法で問題を囲い込むことである。アメリカの社会学者であるアーヴィング・ゴフマンは、社会学や社会理論におけるフレーミングの概念を普及させた11。フレーミングは、個人や集団が以前は整理されていなかった経験に意味を持たせる、広く認知された社会的プロセスである。ゴフマンは、最もありふれた出来事であっても、その要素を特定し、ラベル付けし、互いに関連付けることができなければ、私たちにとって何の意味もないと指摘している。例えば、火星人や自動車以前の文化圏の人は、赤信号を無視することの現地語の意味を知らないかもしれない。その行為を違法と解釈するには、世界的な運転文化の一員である必要があるのだ。しかし、意味を理解しようとするあまり、フレーミングは社会システムにすでに組み込まれているバイアスを強調し、重大な倫理的問題を引き起こす可能性がある。
フレーミングは必然的に、感覚的な経験を重要性の異なる層に分類することを要求する。ある要素はストーリーの中に属し、他の要素は属さない、そして全体は要素が適切に配置されている場合にのみ意味をなす。私たちは夜の散歩に出かけ、見知らぬ女性とすれ違う。彼女は独り言を言っているようで、これは精神障害の兆候だと私たちは考え、避けて通り過ぎた。しかし、今度は、彼女が自分以外の誰かと話していることを示すイヤホンを探すように、私たちは誘導される。突然、何も恐れることはない。この状況は、携帯電話とともに生まれた行動パターンに当てはめられ、以前は奇妙な行動(人前で目に見える相手と話さない)だったのが、理解可能で脅威のない行動(人前で見えないが本物の相手と話す)になったため、普通に見えるようになったのだ。
私たちが正常とみなすもの、異常と説明しようとするものは、客観的でも中立的でもない認識である。それらは根深い文化的な素因を反映している。2012年2月、フロリダのゲーテッド・コミュニティで起きた、丸腰のアフリカ系アメリカ人青年トレイボン・マーティンの射殺事件は、フレーミングにおける文化の力を如実に示している。多くのコメンテーターが指摘するように、ヒスパニック系の自警団員ジョージ・ジマーマンは、同じ環境下で白人の若者を識別し、尾行し、死闘を繰り広げることはなかったかもしれない。このような状況で人種が疑惑の枠を作り出し、悲劇的な結果を招いたのである。このように、危険な状況を誰がどのような目的でフレーム化するかは、徹頭徹尾政治的な問題であり、政治はその後の同様の出来事に対するフレームを変化させることができる。その後、2013年にミシガン州郊外で起きた丸腰の10代の若者レニーシャ・マクブライドと、2014年にミズーリ州ファーガソンで起きたマイケル・ブラウンの射殺事件は、全米に議論を巻き起こし、ブラウンの場合は彼の故郷で持続的に市民騒動を引き起こした。マクブライドを殺したのは一般市民で、17年の実刑判決を受け、ブラウンを殺したのはブラウンに殴られた警察官で、不起訴処分となった。つまり、「ブラック・ライブズ・マター」運動が起こるほど、法の執行によって若い黒人の命が奪われることを甘んじて受け入れる社会ではなく、同時に、殺傷力の行使に対して警察官を不当に罰する用意がない、というフレームシフトが起こっていることを示しているのだ。
従来のリスク評価の第二の欠点は、リスクのシステム的・分配的帰結を無視していることである。ベックによるリスク社会の普遍化概念に挑戦してみると、危険な技術は実際には空間や社会集団にランダムに、あるいは均等に広がっていくわけではない。危険な技術は、貧しい地域や政治的に不利な地域に集まる傾向がある。(そして、ますます世界の貧しい地域にも)そこでは、危険な開発を地元から排除するために必要な技術的専門知識も人脈も影響力もない人々が暮らしているのだ。1970年代、先進工業国の多くの裕福な地域社会では、焼却炉、空港、原子力発電所など、危険な、あるいは有害な技術的施設を排除するために組織的な取り組みが行われた。このような取り組みは、「NIMBY(not in my backyard)症候群」と呼ばれるほど広まった。例えば、ニューヨーク州イサカの市民は、コーネル大学の科学者を動員して、ニューヨーク州ガス電気会社が風光明媚なカユーガ湖に原子力発電所を建設するのを阻止した12。マサチューセッツ州ケンブリッジは、科学審査委員会を設立し、リスクの高い遺伝子工学研究を市内で行うことの妥当性について助言した。この委員会は、最も危険な実験(いわゆるP4または最も厳しい封じ込めのレベル)は、市内で許可されるべきではないと決定した13。どちらの事例も、大学都市では市民が集められる専門知識があればNIMBY症候群は成功するが、国や地域規模ではそのような資源は利用しにくいことを示している。したがって、技術的な主張が可能で、政治的な影響力のある人たちに拒否された企業は、そのようなリソースが不足しているところに移っていく傾向がある。
第三の批判は、従来のリスクアセスメントが、分析プロセスに入る証拠の範囲を制限している点にある。つまり、査読付き雑誌に掲載されたり、認可された専門家の助言プロセスを通じて得られた知識である14。このことは、長い歴史的経験に基づき、共同体の観察によって繰り返し検証されてきた一般市民の知識は、主観的または偏ったものとして脇に置かれる傾向があり、したがって、信頼できる証拠ではなく単なる信念であることを意味している15。しかし、こうした経験的知識は、それが機械や自然環境との直接的な相互作用に基づいている場合には、特に貴重なものとなり得る。産業労働者は設計技師よりも職場のリスクを理解しているかもしれないし、農家は地球気候モデルよりも畑での作物行動の周期を知っているかもしれないのだ。さらに、リスク評価の枠組みは、特定の特定できるハザードに焦点を当てるため、個々の化学物質や特定の施設からの排出物など、単一の原因を強調する傾向があり、複数の有害な被曝がもたらす相乗効果の可能性を過小評価することになる。しかし、日常生活において、人は様々な形で、また複数の原因からリスクに遭遇する傾向がある。それらの複合暴露は、リスク評価者の分析枠の外に完全に残っている影響を持つかもしれない。
このような複雑性は、単一の明確に定義されたハザードから始まり、集団規模の暴露調査を通じてその経路をたどる典型的なリスク評価の線形モデルで捉えることは困難である。低所得者層が住む地域では寿命が短く、健康指標も悪いことが分かっている。そこでは、栄養不良、薬物やアルコールの乱用、失業、結婚の破綻、精神疾患、都市部の暴力といったストレスなど、肉体的・心理的な傷害ストームに人々がさらされているのだ。リスク評価の枠組みは、専門家の査読を経た科学的研究に重点を置き、一度に一つの暴露に焦点を当て、きれいに区分けされているが、不幸が集中する地帯を作り出す複雑な社会的、自然的原因については、ほとんど、あるいは全く、購入することができない。無知は不平等を悪化させる。リスクが集中しがちな場所は、物理的、生物学的、社会的条件のベースラインに関する信頼できるデータを作成するための資源に最も恵まれていない場所でもあるのである。
第4に、ある意味で最も厄介なのは、NRCのリスク管理アプローチの問題点として、技術がまだ構想段階あるいは初期段階にあり、経済的・物質的な投資によって撤退や大幅な再設計が不可能になる前に、利益に関する公開審議の余地がほとんどないことが挙げられる。利益計算は通常、費用便益分析という形で行われ、NRCモデルでは比較的下流、つまりリスク管理の段階で初めて視野に入ることになる。言い換えれば、リスク評価とリスク管理のパラダイムは、指定された技術的道筋に対する代替案を早期に一般に検討させることを許さないのである。
例えば、リスク評価者は通常、代替シナリオのリスクと便益を比較する立場にはない。核廃棄物管理の場合、高レベル放射性廃棄物をネバダのユッカマウンテンのような特定の場所の永久地層処分場に安全に保管できるかどうかを問うことが認められている。例えば、国内に100以上ある一時的で比較的安全でない施設に廃棄物をそのまま置いておくとか、受け入れに前向きな他の国に輸送するなどの代替案について本格的な調査を行う権限はない。米国の核リスク評価者は、オーストリアやドイツでさまざまな結果を生んだように、原子力発電という選択肢を完全に排除するという極端なシナリオに直面することはなかった。技術的道筋にノーと言うべきかどうかは、米国では科学的な問題ではなく政治的な問題とみなされており、したがって標準的なリスク評価の一部にはなっていない。
しかし、これまでの経験から、根本的な政治的価値をリスクの技術的分析から切り離そうとする試みは、しばしば逆効果となり、高価で扱いにくい論争を引き起こすことが分かっている。米国は、オバマ政権が2009年にプロジェクトの放棄を宣言するまで、20年以上と100億ドルを費やしてユッカマウンテン処分場を研究してきた。この間、ネバダ州の人々は、自分たちの州が核廃棄物の貯蔵所として使われることを決して容認してこなかった。ユッカマウンテン中止の決定は、科学的分析だけでは、1つの州がエネルギーへの欲求の矢面に立つという、倫理的・政治的に難解な核廃棄物処分場建設の問題を解決できないという、米エネルギー省の暗黙の結論を反映したものである。このような状況において、事実に基づく主張への挑戦は、社会的嗜好の未解決の二極化の現れに過ぎない。このような争いの場では、科学だけでは水も漏らさぬ安全性を証明することはできない。目的、意味、価値観の一致を図り、議論を封印することが必要である。
政治的な計算
リスク評価の有用性には、フレーミングに次いで定量化が重要な鍵を握っている。大気汚染と失業、生物多様性の喪失と飢餓、マラリア予防と鳴禽類の減少など、さまざまな種類の害に数学的確率を体系的に割り当てることによって、リスク評価者は極めて多様な原因による脅威を比較することができる。さらに、このようなリスク間の比較は、政策立案者に、どのリスクが最も管理する価値があるか、また、資源が限られている中で、どの程度厳しく管理すべきかを決定する、一見強固な根拠を与える。このような長所は、20世紀最後の四半世紀にリスク評価が技術の危険性を制御するための最も一般的な手段となった理由を説明するのに役立つ。
シナリオに数値を割り当てること自体、枠をはめる手段であり、したがって政治的行為でもある。たとえ公共の福祉にとって極めて重要であったとしても、定量化が容易でない問題の側面は、ほとんど定義上、軽んじられる。ロバート・F・ケネディ上院議員は、1968年の大統領選挙において国民総生産(GNP)を批判した際、このような数値化の側面について雄弁に語った。
しかし、国民総生産は、子供たちの健康、教育の質、遊びの喜びを考慮に入れていない。国民総生産には、詩の美しさや結婚の強さ、公の場での議論の知性や公務員の誠実さは含まれていない。機知も勇気も、知恵も学識も、思いやりや国への献身も測れない。要するに、人生を価値あるものにするもの以外のすべてを測っているのだ。そして、なぜ私たちがアメリカ人であることを誇りに思うのかを除いて、アメリカについてのすべてを物語っている。
何を測定し、何を測定しないかという選択が、人々の生活や健康に直接的かつ直接的な影響を与える可能性があるということを前提に、国のGDPよりも小さなスケールでの技術的リスクと利益の定量化についても同様のことが言える。
農薬、食品添加物、医薬品、職場の化学物質、遺伝子組み換え生物(GMO)など、多くの化学・生物製品の評価に用いられている手法は、未来を予測するための主要な手段として数字を用いることの限界を明らかにするものである。定量的リスク評価では、特定のハザード源にさらされることによる既知の疾病や傷害など、非常に特殊な種類の危害を測定する。したがって、リスク評価の手法では、ベンゼンや塩化ビニルなど、よく知られた有害化学物質に様々な濃度で暴露された人の発がん性の増加確率を高い精度で推定することができる。リスク評価では、遺伝子組み換え作物から近縁の非改造種や、その遺伝子の受け皿として狙われていなかった生物に、有害となりうる遺伝子が移行する可能性を、もっともらしく見積もることができる。例えば、職場や大気中のベンゼンや塩化ビニルの許容濃度の基準設定や、遺伝子組み換え作物を植えた農地と遺伝子組み換え作物を植えてはならない地域との間の距離の決定などである。
しかし、このような典型的なリスク評価では、必ずと言っていいほど、人々が関心を寄せる問題が抜け落ちている。例えば、化学物質の場合、製品ごとのリスクアセスメントでは、複数の汚染物質の相乗効果、特に有害産業の流入から自衛できない貧困層や無力なコミュニティに集中する汚染物質には注意が払われないことを、私たちは苦い経験で学んだ。このような背景から、1994年にクリントン大統領は、各連邦機関に「環境正義の実現を使命とする」ことを求める大統領令(行政機関の業務に適用される規則)を発出した。この命令により、米国の機関は、そのプログラムや政策がマイノリティや低所得者層に与える「不均衡で高い、人の健康や環境への悪影響」を特定し、対処しなければならなくなった。ここで重要なのは、環境正義はリスク管理政策の分野では比較的後発であったということだ。しかし、人間一人ひとりが幸福と生存を環境に依存する世界では、この原則を基本として扱うことが理にかなっている。「標準的な」曝露量における「標準的な」身体のリスクを最小化することを目的とした定量的リスク評価が、すべての地域社会のすべての人々に同じレベルの保護を保証するわけではないことは、当初予見されていなかった。個人の安全確保を第一義とする政策アプローチは、事実上、リスクの不平等という深い構造的政治性を覆い隠していた。
定量的リスク評価に基づく政策立案では、他の重要な問題も常に脇役にされることになった。ひとつは、相対的な費用と便益の問題である。評価は通常、新製品の開発やマーケティングといった技術的なプロジェクトがすでに進行している場合にのみ実施される。リスク評価者は、より影響の少ない代替案が利用可能かどうかを検討する義務はなく、実際、事実上の根拠もない。したがって、製品やプロセスを全く使わないという無効な選択肢を含む代替案が、直接調査されることはない。また、同じ結果を得るための異なる方法の相対的なリスクと便益を比較することも通常ない。したがって、新しい化学農薬は、人間の健康や環境に不合理なリスクをもたらさない限り、一つずつ承認される。リスク評価では、農薬の使用そのものと、害虫管理に根本的に異なるアプローチを用いた場合の利点やリスクを並べて考えることはない。同様に、遺伝子組み換え作物も、それ自体は評価されるが、(第5章で改めて見るように)代替的な農業生産の形態との関連では評価されない*。
ほとんどの定量的リスク評価でさらに基本的な欠落があるのは、技術を機能させるための社会的行動である。もちろん、害を及ぼす可能性があるのは、技術システムの無生物的な構成要素だけでなく、人々が物と相互作用する無数の方法であることは承知している。タバコは人が吸わない限り害はない。銃は人が撃たなければ人を殺さない。自動車は運転しなければ衝突事故を起こしたり、大気中に炭素を放出したりしない。化学物質が空気、水、食物連鎖の中に入るには、棚から取り出して使う必要がある。言い換えれば、近代のリスクは、純粋に技術的なもの、つまり機械の故障ではなく、ハイブリッドで、ダイナミックで、社会技術的なものなのである。しかし、リスク評価は、技術が社会の仕組みに組み込まれていることを不完全にしか考慮していない。
リスク分析の曝露評価の段階では、人間の行動に関するいくつかの基本的な側面が考慮される。個人および集団があるハザードに接触する期間、強度および範囲を計算する際、リスク評価者は、人々の起こりうる行動を考慮しなければならない。例えば、リスク集団が汚染工場の近隣住民で構成されている場合、彼らは生涯を通じて工場から同じ距離に住むのだろうか、それとも何年か後に離れていく可能性が高いのだろうか。このような質問に対する数値的な回答は原理的には可能だが、ここには過度な単純化と不正確さの余地が多くある。衣料品業界と同様、被曝量を測定したい「典型的な」人物は有用なフィクションである。私自身、機械の不合理さに比較的無害な形で遭遇した小さな出来事が、この話を物語っている。米国国境警備当局に信頼された旅行者であることを証明しようとしたとき、政府の指紋読み取り機は最初の2回で私の指先を正しく記録することを拒否したのである。結局、親切な係官が「女性の場合はうまくいかないことがあるんだ」と説明してくれた。(指を画面に押し付ける前にハンドローションを塗るといいそうだ)。機械の設計は、それほど無邪気なものばかりではない。例えば、米国で起きた、成人の前席乗員を保護するためのエアバッグが膨らみすぎて、小さな子供が何十人も死亡した事故のように、標準的なユーザー向けの安全機能が、標準的でない身体に出会うと悲劇が起こるかもしれない。
このように、人間と技術の相互作用に関するより複雑な問題は、リスク分析において完全に無視される傾向がある。例えば、人間の身体能力や知的成熟度が全く異なる技術を使うことを、どのようにリスク評価に反映させればよいのだろうか。安全な自動車を設計する場合、想定されるドライバーは堅苦しい中年の親なのか、無謀な10代の若者なのか、酒癖が悪いのか、レーシングカー好きなのか、視力が低下した高齢者なのか、それともこれらの人工的なハイブリッドなのか?今日の技術の多くが地域や政治的な境界を越えていることを考えると、メーカーのリスクアセスメントは、遠く離れた国のエンドユーザーの全く異なる可能性のある知識や習慣にどのように対応したらよいのだろうか。最も単純な欠落が致命的な結果をもたらすことがある。例えば、英語で書かれた農薬の警告ラベルは、非英語圏の農家に対して警告を発することができなかった。逆に、輸入された技術のリスクを評価する場合、技術の供給者やそれを適切に評価するために必要な情報の正確性や信頼性、あるいは誠実さを数字で把握することができるだろうか。悪名高いフォルクスワーゲンの「ディフィートデバイス」事件(第2章参照)は、確かにそうではないことを示唆している。
まとめると、20世紀後半に政策立案者によって実践されるようになったリスク分析は、民主主義にとって大きな問題の根源である。それは、現実の比較的薄い記述の上に成り立っている。技術発展の過程で遅れをとりがちであり、社会技術システムの複雑さに対する認識も浅い。リアルワールドの社会技術的相互作用の複雑さとダイナミズムを減少させる典型的または標準的なシナリオを構築する。また、非歴史的であり、自らの規範的前提を顧みない。テクノロジーのガバナンスを改善するためには、人間が未来を考える際に気にかけるあらゆる価値観、すなわち変化の価値だけでなく継続性の価値、物理的安全性だけでなく生活の質、経済的利益だけでなく社会的公正も考慮する必要がある。次の章では、技術の特定の分野を管理する上での計算合理性の限界と失敗を示すいくつかの例について見ていこう。
バイオテクノロジー産業は、遺伝子操作による害虫抵抗性を備えた遺伝子組み換え作物は、化学農薬よりも自然であり、環境破壊も少ないと主張してきた。しかし、異なる種類の工業的農業のための市場のニッチを切り開くこの試みは、有機食品生産または統合的害虫管理などの様々な競合する代替案と一緒にテストされたことはない。
第3章 災害の倫理的解剖学
災害は、人類がその技術的創意工夫の産物と調和して生きていくことに失敗した劇的な例である。災害は、しばしば地名と結びついて、災厄の現場として歴史に刻まれる。1976年にイタリア北部のミラノ近郊のセベソで発生し、子供たちの皮膚に炎症を起こし、何千匹もの動物を殺した猛毒のダイオキシン、1984年にインド中部の広大な都市ボパールを包んだイソシアン酸メチルによる致命的な毛布、そして、1986年にイタリアで発生した原発事故。1986年にウクライナのチェルノブイリで、2011年に日本の福島で発生した壊滅的な原発事故、1957年にイギリスのウィンズケール(後にセラフィールドと改名)、1979年にペンシルバニア州ハリスバーグ近郊のスリーマイル島発電所で、被害は少ないものの予兆があった。炭鉱、石油採掘場、高速道路、踏切、スタジアム、ダム、橋、飛行場、工場などで起きた悲劇を記念して、世界のどの工業国でも、あまり知られていない地名を列挙することができる。技術的な事故によって失われた命、汚染された環境、破壊されたビジネス、病気や使い物にならなくなった身体は、数え切れないほどある。
技術的な災害は、失敗や損失以上のものを意味する。技術災害は、失敗や損失だけでなく、不注意や行き過ぎに関する道徳的な物語でもあるのだ。これらの出来事のストーリーラインには、テクノロジーとの付き合い方で私たちが最も犯しやすい過ちと、最も予見しにくい結果についての教訓が含まれているのだ。富と人口密度の増加、資本と産業の流動化により、災害の影響が増大する一方で、その原因を予測・特定することが容易でなくなった現代において、こうした教訓は特に重要である。また、災害は社会的不平等の力学を解明するものである。そのため、災害は倫理的、政治的な分析に適した題材である。
統計によれば、災害は、富裕層よりも貧困層の方がより多くの被害を受けるという、ある共通の問題点を含んでいる。貧しい人々は、より危険な状況でより長く働き、より保護されていない住居に住み、災害が起こったときに自分たちを守るための資源をより少なく持っている。多くの場合、彼らのコミュニティは孤立しており、役人に損失や苦しみから守るよう圧力をかけることができない。2013年春、バングラデシュの繊維工場で起きた事故は、このよく知られた脚本を悲劇的に演じた。4月24日、ダッカ郊外の工業地帯にある9階建てのラナプラザビルが倒壊し、そこにいた1,129人の労働者が死亡したと報告されている1。驚くべきは、建物が倒壊したことではなく、あらゆる警告にもかかわらず、それが数千人の職場として使用されていたことである。ラナプラザは、青いガラス張りの堂々としたエントランスのファサードと広い正面階段で、世間を欺くような外観をしていた。コンクリートには大量の砂が混ざっており、湿地帯に、検査官や政治当局から疑わしい許可を得て、規格外の材料で建てられたものだった2。上層階では、ダッカで頻繁に起こる停電の際に、重い発電機が電気のバックアップとして稼働していた。この発電機が作動すると、その振動でビルが揺さぶられ、壁や支柱が弱くなり、4月の朝、致命的な被害を受けたのである。
災害の前日、エンジニアが建物の壁と耐力柱に驚くべき亀裂を発見し、全従業員を避難させた。工場のオーナーと3,500人の従業員は、事故当日の朝、工場に入れるかどうか心配そうに外で待っていた。工場のオーナーと3,500人の従業員は、事故の朝、自分たちが入れるかどうか心配そうに外で待っていた。そして、2人(1人は構造エンジニア)が呼ばれ、ひび割れを検査し、建物の安全性を宣言した。彼は35歳で、バングラデシュの多数政党であるアワミ連盟に所属し、不動産や麻薬などの怪しい商売を合法的に行っているギャング風のボスである。午前8時30分、定刻に作業員が集まってきてから30分後、停電が起こり、発電機が動き出した。わずか10分ほどで、建物の一角が崩れ落ち、その数分後には建物全体が崩壊した。その時、ラナ自身もビルの地下にいた。彼は一命を取り留め、正義から逃れようとしたが、インド国境付近で捕まり、ダッカに戻されて殺人の裁判を受けることになった。
ソヘルラナが捕まり、投獄されるまで、彼の名を冠した建物の喪失は、リスクと貧困に関するあらゆる悲しい予想を裏付けるかのようであった。貧しい人々はわずかな利益のために労働し、ディケンズのような不公平で悲惨な状況で働き、金持ちは利益を得てさらに金持ちになる。生産と消費は長いサプライチェーンによって切り離されている。バングラデシュの人々は月給15ドルという低賃金で働きながら、遠く離れたヨーロッパやアメリカでその何百倍もの収入を得る購入者のためにファスナーやシャツの襟を縫っているのだ。このような産地と販売地の間の富と権力の格差は、ラナのような政治家への賄賂が日常的に行われるような腐敗の空間を生み出している。物事がうまくいかないとき、その矢面に立つのは貧しい人々であり、時には多数の死者を出し、金持ちはその日暮らしになる。
しかし、技術の世界では、リスクは必ずしも金持ちに優しくはない。私たちは皆、ある程度、リスク社会の脆弱な住人である。2011年にドイツで発生した大腸菌による食中毒は、ラナプラザの話と対をなす教訓的な事件である。その年の5月21日から、ドイツの保健当局は、特に若い女性の間で急性下痢の患者が増加していることを報告し始め、このような感染症の後にしばしば発症し、腎不全や死に至る可能性のある溶血性尿毒症症候群と呼ばれる症状が発生した3。この危機が終わるまでに53人が死亡し、そのうちの2人はドイツにいた。4 生きている犠牲者の多くは後遺症が残り、透析などの長期医療を必要とした。大腸菌感染症は過去2世代で最悪の記録であり、経済的損失は農家と産業界だけで13億ドル(世界保健機関)に上ると推定され、食品を媒介とする疾病の過去の事例を上回るものであった可能性が最も高い。
世界で最も豊かで、最も健康に対する意識が高く、最も技術的に洗練された国の一つである日本で、なぜこのような壊滅的な公衆衛生の危機が起こったのだろうか?感染原因を特定する初期の困難さは、食品生産が分散していること、裕福な欧米でさえも食卓に食品を届けるサプライチェーンを消費者や規制当局がコントロールできていないことを浮き彫りにしている。当初、同じ場所で食事をした感染者と非感染者の比較から原因を特定しようとしたが、生サラダとの関連が示唆され、このことは感染者に成人女性が偏っていることと矛盾しない。このため、レタス、キュウリ、トマトなど加熱していないサラダの材料を食べないようにという公式勧告が出された。ハンブルグの公衆衛生当局は、まずスペイン産のキュウリから毒素が検出されたと自信満々で非難した。しかし、この時点で、スペインの野菜生産者は大きな痛手を負っていた。この混乱の中、ロシアは6月にEUからの生鮮食品の輸入を1カ月間モラトリアム(一時停止)することを宣言した。
ドイツでの最初の報告から約1カ月後、フランスのボルドー近郊のイベントで一緒に食事をした人たちの間で、規模は小さいが同様の集団感染が発生した。この一見無関係に見える集団感染の原因を追究した結果、ハンブルクから50マイルほど離れた小さな町、ビーネンビュッテルにある特定の有機農場で発芽させたフェヌグリークの種が原因であることが判明した。しかし、この連鎖は止まらない。結局、保健当局はエジプトから輸入されたフェヌグリークの種子が原因である可能性が高いと結論づけた。しかし、ビエネンビュッテルの農場で発見された種子から、実際に該当する細菌が分離されたことはなかった。調査を依頼された欧州食品安全機関(European Food Safety Authority)は、釈然としない様子でこう言った。
疑わしい種子から大腸菌O104:H4が検出されなかったことは、予想外ではない。サンプリング時に汚染された種子が在庫切れになっていた可能性もあるし、たとえ在庫があったとしても、菌の分離が不可能なレベルで汚染されていた可能性もある。しかし、だからといって、種子や発芽した種子に腸内細菌が存在しなかったとは言い切れない5。
つまり、ヨーロッパ有数の健康研究所の専門知識を結集しても、一国も規制機関も完全には監視できないサプライチェーンで運ばれる疾病に関する不確実性をすべて解決することはできなかったのである。
ラナプラザの崩壊とドイツの大腸菌感染症は、グローバルなリスク市場において繰り返される分配的公正の問題を示唆している。災害の矢面に立たされるのは、往々にして、その被害をもたらした状況をほとんど制御できなかった人々である。危険な工場で働く人々、輸入食品の消費者など、長い生産の連鎖の始点と終点にいる人々である。彼らは、雇用者、役人、専門家、商品の供給者といった仲介者や上層部の知識や判断に欠陥があることが判明したため、被害を受けたり死亡したりしたのである。災害もまた、動きが早く、混乱を生む。不安定で落ち着かない環境では、責任の所在を誤ってしまい、さらに多くの損失と悲しみを引き起こす可能性がある。スペインの野菜農家が栽培したキュウリは、最終的に大腸菌が検出されないことが確認されたが、危機の最中、スペイン経済に1日あたり推定850万ドルの損失を与えないほど早くはなかった6。災害後、支援の到着が遅れ、到着しても不十分なことが多く、犠牲の連鎖が持続している。集団中毒は慢性的な健康被害を引き起こし、高額で長期的な治療が必要となる場合がある。災害時やその後に収集された証拠は信頼性が低く、不完全であることが多いため、法的手続きによって賠償請求が何年も待たされることもある。いずれにせよ、子供や親、一家の大黒柱を失った高齢の両親や小さな子供たちを十分に補償できるものはない。
テクノロジーの倫理的ガバナンスの重要なステップは、なぜ災害の周辺にこうした不公平のパターンが残るのか、そしてその最悪の影響を緩和するために何ができるかを理解することである。この目的のためには、災害の3つの側面、すなわち専門家の予測の限界、補償の制約、技術システムの管理における構造的不平等の原因をより詳しく調べる必要がある。これら3つの側面は、1984年にインドのボパールにあるユニオン・カーバイド社の子会社が所有する化学工場から放出されたイソシアン酸メチルガスという世界最悪の産業事故において、はっきりと浮き彫りにされたのである。ボパールの悲劇は、絶え間なく研究され、絶え間なく議論されているが、原因と結果に関する首尾一貫した物語を頑なに拒んでいる7。このため、この事件は、災害の倫理的解剖学を探求するのに特に有効である。ボパールの物語は、この意味で時間を超越している。確かに、それは一世代前に、外部の人間がほとんど訪れることのない都市で起こった出来事であった。しかし、その原因となった悲劇的な失敗が重なり、ボパールガス災害は現代人の行き過ぎと怠慢のたとえ話になってしまったのである。
真夜中の死
ジョージ・オーウェルは、「1984」という数字をディストピアの代名詞にし、すべてを見通す権威主義的な国家が市民から個人主義の精神を押しつぶす世界を描き出した。1984年末のインドは、別の意味でディストピアであり、リーダーシップもビジョンもない無軌道な国家であったように思える。ネルーの娘であるインディラ・ガンジーは、3期目の首相を務めて4年目であった。1977年の選挙では、いわゆる緊急事態と呼ばれた2年間の権威主義的支配に対する国民投票の結果、不名誉にも首相を追われたのである。1980年に政権に復帰したガンディーは、反対意見に寛容であったが、国をまとめることはできなかった。彼女は、北部パンワクチン州のシーク教徒による分離主義運動の勃発を、アムリトサル市にあるシーク教の聖地、黄金寺院への流血の軍事攻撃で鎮圧した。その4カ月後の1984年10月31日、ガンディーはアムリットサルの事件に対する報復として、シーク教徒の護衛の2人に暗殺された。その後、首都デリーに集中した反シーク教徒の激しいデモにより、数千人の死者と数千人以上の避難民が出た。
ボパールの事故は、このような流血と政治的混乱を背景にして起こったが、その根はずっと以前に、経済的独立と政治的独立を達成するためにインドが戦ってきた歴史に根ざしていたのである。インディラ・ガンジーが首相に就任して間もない頃、インドでは「緑の革命」が起こった。農業の革新によって、屈辱的な外国産穀物への依存から国を救った時代である。科学的奇跡と称された「緑の革命」の種は、米国の農学者ノーマン・ボーローグにノーベル賞が贈られるにふさわしいものだった。しかし、種は手をかけなければその能力を発揮できない。ボーローグが育てた短稈で頑丈な高収量品種も例外ではなかった。緑の革命の批判者たちから「高投入品種」と揶揄されたこれらの救命穀物は、水、肥料、農薬、電力に膨大な投資を必要とし、その複合コストと不平等な分配インパクトは、この高く評価された社会技術的達成の歴史の一部となっている。ボパールの災害も同様で、高収量を実現するために化学薬品にますます依存するようになった農業生産システムに関連する工場で発生したものである。
1960年代後半、アメリカの化学会社ユニオン・カーバイド・コーポレーション(UCC、本社コネチカット州ダンベリー)は、当初電池の製造会社としてボパールで操業を開始した。1974年には、UCCの代表的な製品であるセビン(カルバリルという化合物を含む殺虫剤の商品名)を製造するための大規模な新工場の建設許可を得た。インドでは、子会社のユニオン・カーバイド・インド社(UCIL)を通じて事業を展開していた。当時のインドの法律では、外国人の持ち株比率は50%以下に制限されていたが、ユニオン・カーバイドは農薬の供給元としての重要性から、例外的に50.9%の株を持ち、残りの49.1%をインドの金融機関や個人投資家が保有して、支配権を維持することが許されていたのである。
カルバリルはDDTと異なり、動物組織や環境中に蓄積されないため、食用作物への使用が特に望ましい農薬とされていた。しかし、害虫と益虫の区別がつかないという問題があり、多くの国で農薬としての使用が許可されていない。さらに、セビンの製造に使われた原料の中に、イソシアン酸メチル(MIC)という有毒な中間体があったことが、ボパールを語る上で重要なポイントである。この化合物は水との反応性が高く、液体のMICは気体に変化することが知られていた。MICは、極微量でも目、鼻、喉への強い刺激、皮膚の火傷、内臓の損傷、肺に液体を溜め込んで咳き込み、窒息し、多くの場合死に至らしめる。
1984年12月2日深夜、UCIL工場のイソシアン酸メチル入り地下貯蔵タンクの1つに大量の水が侵入した。そして、深夜12時過ぎに工場外の空気にガス状のMICが漏れ始めた。ガスが漏れる前に中和するためのスクラバーシステムが作動していないのだ。工場外の住民に事故が起きたことを知らせる警報装置も、手遅れになってから鳴った。30分もしないうちに、ガスの濃い霧が、原発の南東にある労働者階級の密集した地域の何万という家々に入り込んだ。そのため、原発の南東に位置する労働者階級の家々では、数万戸の家屋にガスが充満し、人々は目を覚まし、窒息し、何が起こったのかわからなくなった。多くの人がベッドの上で死んだ。そうでない人たちは、息苦しいガスから逃げ出そうと、もがきながら通りに出て行った。ボパールから1週間後に取材したニューヨーク・タイムズ紙の記者は、その恐ろしい光景をこう語っている。
何千人もの人々が、窒息し、嘔吐し、焼けつくような涙を流しながら、どこにでも漂ってくるような霧の苦しみから逃げ惑う人々の群れに加わり、通りによろめきながら出てきた。ある者はパニックの中で自動車やトラックに轢かれた。また、水牛、犬、山羊、鶏と一緒に、先に進むことができずに側溝に落ちて死んでいった人もいた8。
この夜、少なくとも2,000人が死亡し、さらにその後1,500人が死亡したと考えられている。公式な推定では、即死者数は3,500人前後だが、被曝したイスラム教徒が多い地区で売られていたシュラウドを引き合いに出して、実際の数は8,000人を超えると考える人が多いようである。パニックになって街から逃げ出した人は40万人、ガスによる重傷者は15万から20万人と推定されている。死傷者の総数は、総務省の長期的な影響がより多くの命を包み込むにつれ、徐々に増加し、今日まで争われている。しかし、この事件は、民間人に対する史上最大の毒ガス攻撃であり、しかも戦争という状況下で起きたものであることは明らかである。
現在、UCILの工場跡地は、金網とゲートで囲まれ、牛が草を食むだけの荒れ果てた状態になっている。UCILは、1994年にMcLeod Russell (India) Limitedに売却され、Eveready Industriesと改称され、もはや企業としては存在しない。ユニオン・カーバイド社は、ダウ・ケミカル社の100%子会社で、従業員数は2,400人、事故当時は9万8千人余りだったのが、ほとんどゼロになってしまった。しかし、ボパールとカーバイドの名前は、人々の記憶に深く刻まれ、今は亡き同社がその記憶を管理・消去するために、ホームページで苦心しているほどである。
専門知識の非対称性
UCCのホームページには、同社の歴史が掲載されており、多国籍企業の栄枯盛衰を示す年表となっている。1984年の項目には、次のように書かれている。「12月、インド、ボパールの工場で妨害行為によるガス漏れが発生し、悲劇的な人命被害が生じた」9 これは、ユニオン・カーバイド社が事故直後から、法的手続き、公的声明、そして自社の自己認識の一部として頑なに守ってきた姿勢である。同社によれば、防護システムは正常に機能していたのだから、水が偶然に工場内に侵入することはありえない。同社は、1986年の時点でその身元を確認しており、インド政府もそれを知っていたというが、公表すればUCCの法的責任が免除されるため、公表しなかったという。「不満を持つ従業員」による故意の行為だったのだ。ユニオン・カーバイド社以外、ボパールの悲劇で不満を持った従業員説を支持した者はいない。
ガス漏れを妨害行為とすることは、事故後に明らかになった知識の格差や権力の非対称性に関する重要な問題をうまく回避することになる。MICの人体への長期的・短期的影響について、事前にどの程度知られていたのか、あるいは知られていなかったのか。なぜそのような毒性を持つ物質が、密集した都市環境の中で敷地内に保管されていたのか?どのような緊急対策がとられていたのか、そしてなぜそれが不十分だったのか。事故直後だけでなく、長期的な医療や慢性疾患の社会的監視を通じて、犠牲者をケアする責任は誰にあったのか?UCCは、事故ではなく悪意が災害を引き起こしたとしきい値をつけたことで、事実上、公の場でこれらの疑問に答える義務を免れた。しかし、責任を回避しようとする努力にもかかわらず、同社につきまとった数十年にわたる調査や法的活動から、いくつかの答えを導き出すことができるかもしれない。
MICは、毒性学の分野で標準的な技術で研究するのは困難だった。毒性学者は通常、人間の代用としてラットやマウスなどの動物を使って、対象となる化学物質の曝露による影響を最長で2年間観察し、その間に健康への悪影響が現れると考えられている。1984年当時、MICについてはほとんど知られていなかった。毒性学者がMICという刺激性の化合物を扱うのが非常に不愉快で、徹底的にテストする研究を行わなかったからだ。つまり、長期間の治療はおろか、緊急事態に備えることもできないほど性質が解明されていない物質を、無意識のうちに被験者に投与するという、最悪の自然実験が行われたのである。
事故後、多くの被害者とその支援者たちは、会社や州当局の責任逃れによって、ガスにさらされた人々が必要としていた治療法が奪われたと確信し、激しい医学論争が起きた。シアン中毒の解毒剤として知られるチオ硫酸ナトリウムの配布と使用について、意見の相違があった。シアン化水素を含むガスが噴出したことが判明すれば、世論に大きな反発を与えることを恐れたのであろう。しかし、ユニオン・カーバイド社の幹部は、「個人的な報告は信用できない」「シアン化合物は検出されなかった」と否定し、被害者は「チオ硫酸を注射してよかった」と言った。マディヤ・プラデーシュ州は、ボパールにできた民衆診療所でのチオ硫酸ナトリウムの投与を警察を動員して停止させ、被害者のために働くボランティアの医師たちを一時的に牢屋に入れたりもした。
そんな診療所の医師、ミラ・サドゴパルさんは、被害者の訴えと医療側の立場との間にある溝をこう表現した
しかし、頭痛、筋肉痛、不眠、胸痛、息苦しさ、動悸、目のかすみといった特定の症状について、人々ははっきりとした症状の緩和を語っているのである。
一方は、科学的知識のない貧しい人々の主観であり、もう一方は、権威あるインド医学研究評議会を含む正統派医学の専門知識であった。どちらの見解が正しいか、関係者の間ではほとんど疑問の余地がなかった。しかし、UCCに対して行われた証拠開示手続きで、かなり後になってから集められた資料からは、信頼できる知識が不足していたことがうかがえる。
12月3日以降に現場に到着したUCCの医療関係者は、毒性学的な無知から出発しており、総務省が実際に人体にどのように作用するのか、大量被曝が長期的、集団的にどのような影響を及ぼすのかを詳しく知らないままであった。ボパールの事故について話し合うために開かれた1985年1月3日の化学工業協会(後の米国化学工業協会)の議事録は、それを裏付けるような内容だった。「事故後ボパールに派遣された医師は、生存者のほとんどに当面の身体的問題はおそらくなくなると言っている」11。この楽観的な評価は、目、肺、生殖器などの疾患や心理的影響が災害後何年も続いていることから、まったく正当化できないことが判明した。被災者の体感的な知識と、医師の推測的で裏付けのない主張との戦いでは、前者がより信頼されるべきだと考えるのが妥当であろう。しかし、チオ硫酸を投与する診療所の閉鎖が示すように、客観的な科学の名の下に、確たる証拠がないにもかかわらず、被災者の証言を無視する既成医学がまかり通ってしまった。
法の不当性
医学の専門知識が、ボパール犠牲者の苦悩の日々に役立たなかったとすれば、インドでも米国でも、法の制度はそうではなかった。このような過失による被害は、不法行為と呼ばれる私的な行為による損害を扱う法律の一分野に属する。ボパールで起きた事件に不法行為法の原則を適用しようとすると、すぐに2つの重大な現実的問題が発生する。第一に、当時のインドは工業化が進んだばかりの国であり、インドの裁判所はボパールで起きたような規模の賠償請求に対応する準備ができていなかったことである。第二に、ラナプラザやビエンエンビュッテルで起きた事件を数十年先取りして、ボパール災害の原因と結果が国境を越えたものであったことである。米国から輸入した製造技術に基づく米国企業のビジネスが、インドで何千人もの人々に害を及ぼしたのだ。その被害者の請求は、緊急のものから疑問のあるもの、日和見的なものまで多岐にわたり、災害の全容が明らかになるにつれ、新たな請求が多数発生する可能性もある中、数え切れないほどの被害者を誰が最も効果的に代表できるのだろうか。大陸にまたがるこの事件を管轄するのはどの国なのか?そして、どのような法律に基づいて原告の主張を聞き、決定すべきなのか。ボパール訴訟のすべてが前例のないものであり、これらの問題に取り組むために20年以上にわたって行われた紆余曲折は、それ自体が記念碑的な歴史となるに値するものであった。しかし、この災害の倫理的意味を考察する上で、ボパールの特殊性を超えて、特に顕著な側面がある。
事故のニュースが流れるとすぐに、集団不法行為訴訟の経験を持つアメリカの著名な裁判弁護士が、有望なクライアントを確保するためにこの街に押し寄せた。アメリカの裁判員たちは、「成功報酬」、つまり、前払い金は最低限で、最終的には賠償金の4分の1から3分の1を原告に支払うという条件で仕事をすることに慣れている。このようなひどい損害の場合、アメリカの不法行為弁護士は、賠償金が新記録になるかもしれないと想像したくなるものである。カーバイド社の本拠地である米国で裁判が行われれば、被害者は一つの集団訴訟として団結し、カーバイド社に大きなプレッシャーを与えることができるだろう。また、高額の懲罰的損害賠償が期待でき、それに応じて原告側弁護団も大きな利益を得ることができる。当時、アメリカの訴訟業界で最も有名な弁護士たちが、まるで巨大な蜜蜂のようにボパールに集まってきたのも不思議ではない。
インド政府は、多くの人が見苦しいと思った国境を越えた救急車追跡をやめさせるために介入した。事故から4カ月後の3月29日、国会は「ボパールガス漏れ災害(請求処理)法」(略称「ボパール法」)を制定したのである。この法律は、古代の慣習法である「国の親(parens patriae)」の原則に基づいており、自らを守ることができない臣民を国が保護することを認めている。この法律により、インド政府は、あの致命的な12月の夜の出来事に起因する請求を行っている人、または将来行う可能性のある人を代理する排他的権利を付与されたのである。この権利には、ボパールの賠償請求者のために訴訟を起こし、追求する権限と、賠償請求の和解を成立させる権限も含まれていた。この法律は、ボパールで発生した大量の被害から大きな利益を得ようとする民間弁護士の希望を打ち砕いたが、同時にインド政府が被害者の訴えを効果的に代弁し、公正で公平な法的結果を確保する能力に、すべての被害者の希望を託すことになった。
ボパール法では、誰が被害者の代理を務めるかは決まったが、どこで務めるかは決まっていない。この問題は、裁判管轄が異なる場合、被告や証人に過度の負担をかけない場所で裁判を行うべきだという「フォーラム・ノン・コンビニエンス(不便な法廷)」の原則に基づいて解決されなければならなかったのである。通常、不法行為訴訟の場合、その裁判地が不適切であることが示されない限り、損害が発生した裁判地がこれに該当する。インド政府は、自国の司法制度ではこのような大規模な紛争に対応できないので、米国で裁判を行うべきだと主張し、ユニオン・カーバイド社はインドの裁判所でも十分対応できると反論するという奇妙なパ・ド・ドゥが続いた。そこで、ユニオン・カーバイド社は、インドの裁判所は十分な能力を備えていると反論し、それぞれ相手国の専門家を雇い、経験則に基づく立証を求めた。インドは、ウィスコンシン大学の法学部教授で、インドの法制度に関するアメリカの権威であるマーク・ガランター(Marc Galanter)を主任専門家として起用した。UCCは、N. A. PalkhivalaとJ. B. Dadachandjiの両名に依頼した。両名はインド最高裁のベテラン弁護士であり、上級弁護人である。パルキヴァラは1977年から1979年まで駐米インド大使を務めていた。
重要な判決を下すのはニューヨーク南地区連邦地方裁判所のJohn F. Keenan判事で、カーバイド社に有利な判決を下した12。Keenan判事にとって重要だったのは、書類の大半と争われた行動や決定のすべてがインドにあり、被害者本人もいるので、訴訟をニューヨークへ移す意味はほとんどないというUCC側の主張だった。これでは、アメリカの司法資源に不当な負担をかけることになる、と判事は結論づけた。また、この訴訟はインドの主権に関わる政治的に微妙な判決であると、キーナンは考えていた。したがって、インドの法体系の革新能力、適応能力、特別な手続きに関するあらゆる点について、キーナンはガランターの悲観的な歴史的、社会学的評価を否定し、カーバイド社の、危機に瀕したインドは挑戦してくるとする、インドの優れた弁護人に裏打ちされた確約を受け入れたのである。
そして、63ページに及ぶ意見書の最後に、キーナンは、インドの国家としての地位を讃える言葉を述べた
1986年、インド連邦は世界の大国となり、その裁判所は公正で平等な正義を実現する能力を備えている。インドの司法が世界の前に堂々と立ち、自国民のために判決を下すこの機会を奪うことは、インドがそこから生まれた従属と隷属の歴史を復活させることになるのである。
皮肉なことに、キーナンはボパール原告の米国裁判所へのアクセスを拒否することによって、集団訴訟や成功報酬など、米国の集団不法行為被害者の救済の道をかなり容易にしてきた法律の革新の恩恵をも否定してしまったのである。キーンは、2つの法制度の違いについて、原告側に不当な不利益をもたらす可能性があるとして、2点だけ譲歩した。それは、ユニオン・カーバイド社が、原告に訴訟関連記録へのアクセスをかなり自由に認める米国連邦公判前開示規則に従うこと、そしてインドの裁判所が下した判決に従うことを条件に、連結訴訟をインドに送り返したことである。
しかし、インドの法制度に革新的な試みがなされたこともあり、Keenan判事の楽観論は事実上否定されることになった。それは「多国籍企業責任」の原則で、親会社はその活動が損害を与えないようにする義務を委ねることはできないとするものであった。これが認められれば、カーバイド社は「ボパール事故の責任は、ダンベリーにあるUCC本社の責任ではなく、子会社であるUCILにある」と主張することができなくなる。インドの弁護士は、現行法には企業責任を推定する先例がないことを非公式に認めたが、この異常なケースの状況には新しいルールが必要であるとの立場をとった。そうでなければ、多国籍企業は、途上国での危険な活動と自社との間に子会社というファイアウォールを作るだけで、常に責任を回避することができることになるからだ。カーバイド社の反論は、前例がないことを理由に、このルール案を真っ向から否定した。被告は、法律上、「多国籍企業」や「一枚岩の多国籍企業」といった概念は存在しないと主張する」13。
結局、多国籍企業責任ルールの有効性が争われることはなかった。カーバイド社は、長引く訴訟手続きに費用と恥を費やす代わりに、訴訟を解決する可能性が常にあったのだ。問題は、いつ、どの債権について、そして何よりも、いくらで和解するかであった。しかし、1989年2月、インド政府は4億7千万ドルで和解することを決めた。これは、当初の要求額の15%に過ぎず、15万から20万人の被害者が受けた被害と、今もなお受け続けている被害に対して、あまりにも不充分な補償であった。しかし、インド最高裁は12月、ボパール法の規定に基づき和解の合法性を認め、ボパールにまつわる論争の中で最も目につきやすく、最も疲弊させる論争に終止符を打つことになった。
しかし、企業責任の概念をめぐるやりとりは、キーナン判事によるインドの法革新への高邁な希望と、先進国で何世紀にもわたって発展してきた、企業が予期せぬ責任から逃れるための会社法や不法行為法の現実的制約との間に、ほとんど埋めがたい溝があることを示すものであった。インドと米国が英国から受け継いだコモンローは、経済的・政治的権力に対して中立的なものではない。それは、革命を阻止するためのものである。コモンローは、その推論の形式や裁判所の役割の考え方において、現状を維持する傾向がある。コモンローは、ある事実から別の事実へと類推し、推測や純粋な原理からの議論に抵抗する。コモンローの裁きは、断固として経験主義であり、「泥臭い」ことを好む英国の政治文化と同様に、漸進主義に傾倒しているのだ。さらに、コモンローの裁判所は、判例や解釈のルールによって、その時々に適用される法について、コンセンサスのある立場から大きく逸脱しないよう拘束されている。解釈の許容範囲を超え、新しいルールを適用していると見なされると、裁判所が政策決定に関与することになり、一般弁護士は立法府や行政府に留保されている、つまり司法権の特権の外にある機能だと考えているのだ。
当時のインドは独立国だったが、訴訟に対するアプローチを自由に選択できるわけではなかった。ボパールの市民が訴えを追求しなければならない法体系の基盤には、変化に対する抵抗が組み込まれていた。責任に関する最も基本的な規則でさえ、蓄積された財産と組織化された資本の利益を優先する保守的な偏見を反映していた。勝訴するためには、原告の主張は「証拠の優越」、つまり原告の主張が真実である可能性が高いということに裏付けられなければならないのである。ボパールでは、法律上の規則や推論のスタイルに科学的な不確実性が加わり、被害者の訴えは通常の裁判の枠組みでは勝つことが難しくなった。
化学物質暴露の裁判では、がんや慢性疾患などの影響が暴露後かなり経ってから現れることが多いため、因果関係の主張があいまいになり、また、暴露の量や期間が正確にわかることがほとんどないため、証拠と立証の問題が特に深刻である14。農作業やガソリンスタンドの店員など、一過性の仕事や屋外で働く人々は、日常的に職場で暴露されているかどうか監視されていない場合が多く、地域社会の有害物質暴露について正確に立証することはさらに困難である。災害後の状況では、高品質の証拠を得ることはさらに難しくなる。責任の所在は流動的であいまいであり、信頼できるデータを収集するための基準もなく、意見の相違も多く見られる。ボパールでは、チオ硫酸ナトリウムの論争が将来の問題を予見させるものだった。異なる立場の医学専門家が、自分たちが見ているものは何か、それに対して何をすべきかをめぐって争ったからだ。そして、その規模の大きさには圧倒された。ガス雲の影響を受けた何十万人もの人々を診察し、現在も続いている健康被害の性質、程度、深刻さを判断する複雑な作業は、世界中のどの医療機関でも対応できなかっただろう。
このように、国境を越えた法的請求は、従来の会計処理では算出できない不均衡を明らかにする。多地域間紛争における富裕な被告と貧困な原告との出会いは、誰の正義が優先されるべきかという問題をはらんでいる。経済的に優位に立つ被告は、安定性と定着した規範の適用を主張し、原告は自分たちの問題を引き起こしたルール構造そのものを見直す必要性を感じている。これは大変なことだ。1984年の1年ほど後、当時教えていたコーネル大学で、ボパールに関するセミナーを開催したことがある。ニューヨークの大手法律事務所で、ユニオン・カーバイド社の代理人を務める著名な弁護士を講師に招いた。私は彼女に、「多国籍企業責任論」が成功する可能性について質問した。その時、私は彼女に「多国籍企業責任法」の成功の可能性について質問したところ、「そんなものは法律にはない。それは、法律的な根拠がない。
この問題は裁判にならなかったので、答えはわからないが、形式的には彼女の言うとおりかもしれない。しかし、より重要なことは、企業責任という新しい原則は、法律が確立した専門家の推論ではなく、実際の状況、この場合は前例のない恐怖と損失の経験によって保証される正義の感覚を反映しているということである。それは、劇的に新しい考え方を必要とする状況への革命的な対応であり、したがって、危険な企業がグローバル化するずっと以前に成文化された企業責任に関するルールからの自意識的な逸脱であった。しかし、経験豊富な欧米の企業弁護士が内面化した慣習としての法律そのものは、何よりもまず正義にコミットする新しい法秩序を構想する側には向いていなかったのである。特に企業法には、安定性、予測可能性、現状維持といった資本の利益を優先させるバイアスが組み込まれている。キーナン判事がインドに可能であると信じたイノベーションの要求は、論理と判例というフィルターを通らなければならず、根本的な新しさを阻害するように設計されていたのである。ある意味で、ボパールの裁判の歴史は、法と正義の戦いであり、法が優位に立ったのである。
確かに、1989年の和解は、UCIL工場の跡地から亡霊のように立ち昇る付帯請求の数々を消滅させることはできなかった。しかし、1989年の和解でも、UCILの工場跡地から噴出する亡霊のような付帯請求は消えなかった。そして、被害者や地元の支援者たちが、自分たちの状況を把握し、自分たちのために主張する方法を学ぶにつれ、その戦略はより洗練されたものになっていった。しかし、時間は彼らに味方してくれなかった。1989年の和解案で却下されたケースや、年齢が高すぎる、立証が難しい、適切な原告団がいない、などの理由で却下されるケースが続いた。また、請求が認められる前に、請求者が亡くなってしまうこともあった。このように、付随的な請求は、1984年の震災に起因する最初の訴訟と同様に、20年以上にわたって連邦裁判所を駆け巡り、結論が出ない状態が続いた15。
法律は、裕福な国であっても、必ずしもタイムリーで効率的な正義を実現するとは限らない。ハムレットは「法の遅れ」を訴え、チャールズ・ディケンズは1852年の名作『荒涼館』の背景として、終わることのない訴訟の苦難を利用したのである。しかし、その面倒な性質にもかかわらず、米国ではインドよりも法律の応答性が高く、結果が早く出ることを否定するのは単純なことだろう。ノースカロライナ州のデューク・エナジー社が大量の石炭灰をダン川に流出させ、70マイルを汚染したとき、連邦検察は直ちに同社の責任を追及する行動に出た。1年ほど後、デューク・エナジー社は、この流出事故による混乱を一掃するため、1億200万ドルの罰金を支払うことに同意した。同年末、同社は大気浄化法に基づく15年間の係争中の訴訟を解決するために、さらに540万ドルを支払うことに同意した16。2015年9月にフォルクスワーゲンが、ディーゼルエンジン車の米国排出ガス規制の遵守を組織的に回避するために、欺瞞的なソフトウェアを使用していたことを驚くほど明らかにした後も、同様の検察の熱意が続くという兆候は十分にある。
権力のアンバランス
キーナン判事は、インドの「世界の前に堂々と立つ」能力を信頼しているが、それはアメリカの社会思想の特徴であると言う人もいる「代理の力」に対する自信を反映している。これは、意思と想像力に恵まれた行為者、特に大きな国民国家は、法的・政治的救済の手段を用いて望む結果を得ることができるという考え方に基づくものである。裁判官は特にインドの裁判所が「公正で平等な正義を実現する能力があることが証明されている」と指摘した。しかし、ボパールでは公正さが問題ではなかった。問題は、インドの裁判所がカーバイド社に、同社の事業がもたらした損失に見合った規模の補償をさせる手段や権威を有しているかどうかである。インドの現場には、その答えは明らかで、否定的なものであった。インド人の目には、キーナンが暗黙のうちに作り上げたインドとアメリカの法制度の同等性は、危険なほどナイーブに映ったようだ。
ボパールの多数の犠牲者にとって最も重要なことは、この災害の前提条件を生み出した交渉力の不平等である。カーバイド社がボパール工場の過半数を所有していたこと。UCC弁護士は、操業管理はすべてボパールのUCILに委ねられていたため、この事実は関係ないと断じた。このことは、1970年代になっても、インドのような脱植民地化国家を悩ませる深い依存関係を示していた。インドの初代首相ネルー氏が熱烈に支持した技術的近代化は、依存関係を根絶することなく、その線引きを変えてしまった。1970年代半ば、インドがカーバイド社にセビンの製造を許可したとき、国の食糧安全保障問題を解決する必要性は目に見えていて緊急性があったが、インドは事実上、危険で閉鎖的な技術的ブラックボックスをユニオン・カーバイド社から購入したのである。しかし、インドはユニオン・カーバイド社から、危険で閉鎖的な技術のブラックボックスを購入したに等しい。工場や製造工程を輸入することは、そのシステムの危険性を完全に把握し、安全や管理に関する専門知識を身につけることと同じではない。例えば、ボパールの姉妹工場であるウエストバージニア州のインスティテュート工場は、化学工業で何世代にもわたって訓練された労働者によって運営されていた。しかし、事故後の調査によって、インスティテュート工場には、UCCのインド工場に警告を発したかもしれないエピソードがあったことが明らかになった。
また、被害者をケアし、最終的には法的手続きで代理人を務めるはずの政府との関係も不平等なものとなった。インド政府も、事故が起きたマディヤ・プラデシュ州も、災害後の現場には全く手を汚さずにやって来たわけではない。ユニオン・カーバイド社は、セビンを製造するプロセスと工場を設計し、化学工業界で最も致死性の高い化合物を使った、まだ十分にテストされていない技術を、世界で最も人口密度の高い地域の1つに輸入することを平然と許可したのである。しかし、工場を検査せず、以前の警告のサインに耳を傾けなかった地元政府当局には、十分な非難が集まった。スクラバーが作動しなかったことも、事故当夜にサイレンが鳴らなかったことも、設計、管理、施行の失敗であった。しかし、ボパールの市民が、権力者たちが自分たちの命をかけてロシアンルーレットを演じていたことに気づいたのは、壊滅的な規模の悲劇が起こってからだった。
災害が弱者や無防備な人々に不釣り合いな影響を与えることは、悲しいかなよく知られている。極端な環境は、たとえ豊かな国であっても、根強く残る不平等を悪化させる。別の言い方をすれば、構造が重要なのである。ハリケーン・カトリーナ後のニューオーリンズや2004年の大津波後のバンダ・アチェでは、女性、子供、老人、貧しい人々が、富裕層や健常者よりも多く死亡したり、土地を奪われたりしている17。幸運なことに、その夜、風がガスをスラム街(市内のイスラム教の貧しい地区)に向かわせ、乱気流が比較的少なかったため、ガスは低レベルに沈降し、シャンティタウンによく見られる平屋に住む人々が最もガスを吸い込みやすい場所となった。ボパールで現在行われている正義と補償を求める運動のリーダーたちは、1984年12月2日の風が南東以外の方向から吹いていたら、法の歯車はもっと早く、もっと効果的に回っていただろうと確信し続けている。
このような権力闘争の中で、被害者たちが会社関係者に個人的な責任を問うことを強く望んでも、それはほとんど叶わなかった。カーバイド社のCEO、ウォーレン・アンダーソン氏は、事故の数日後にボパールに向かい、逮捕されて一時拘束されたが、保釈された。彼はすぐにアメリカに帰国し、その後も数千人が彼の裁判と投獄を求め続け、1992年に裁判所が彼を逃亡犯と認定した国には、生涯戻らなかった。2010年6月、インドの裁判所は、高齢のUCIL元職員7人に過失致死傷罪の有罪判決を下した。しかし、「遅きに失した」と言っても、ボパールの法律家たちが抱く不満は計り知れない。ボパールで起きたことは 2001年9月11日にニューヨークやワシントンで起きた事件に匹敵する重大な犯罪であると多くの人が考えていた。彼らにとって、この2つの悲劇は、自分たちが覆すことのできない不平等を再び浮き彫りにするものだった。ボパールの抗議者たちは、「指名手配中」の看板の下にウォーレン・アンダーソンを描いたプラカードを頻繁に掲げた。2004年、私が見たプラカードは、「オサマが欲しいならアンダーソンを出せ」と訴えていた。しかし、この要求は、ボパールの他の多くの要求と同様に、聞き入れられることはなかった。
おわりに
ラナプラザの事故後、バングラデシュ内務省のマインディン・カンダカーが執筆した500ページ近い報告書では、すべての主要な関係者の間に十分な責任があることが判明した。強欲な家主の典型であるソヘル・ラナ自身、いわゆる専門家、工場所有者、関係各国政府などだ。しかし、ドイツのニュース雑誌『シュピーゲル』の記者に対して、カンデーカーさんは、もっとはっきりとこう言った。「あの日、あの4月24日は、グローバル・マーケットの必然的な結果だった」言い換えれば、ある種の悪しき行為機関が不正の構造の中で力を発揮することがあったとしても、構造は行為機関よりも重要なのである。
本章で述べたような技術的災害は、近代が誇る経済的・社会的成果の多くを支えてきた倫理的矛盾に不名誉な光を投げかけている。世界がより緊密になり、お金と商品の世界的な流れがより密になるにつれて、こうした矛盾はしばしば悲劇的に明らかにされるようになった。第一に、グローバル市場における技術的な商品とサービスの生産者と消費者をしばしば隔てる、知識と力の計り知れない不一致がある。ラナプラザで働く人々、ドイツでもやしを買う人々、ボパールのカーバイド工場の近隣住民など、受け取る側にいる人々は、自分たちの日常生活のすぐ向こうにあるリスクを知る立場になかったのである。そして、物事がうまくいかなかったとき、彼らの傷ついた身体は、他人の貪欲さと配慮のなさを無邪気に証明してみせた。ウルリッヒ・ベックが情熱的に批判した世界リスク社会の無力な犠牲者であり、彼らはその設計や管理プロセスに対して何の発言権も持っていなかった。
災害がもたらすグローバル市場の第二の特徴は、市場を機能させるためのルールや規範の非対称性である。外資を誘致するために、外資の受け手は常に譲歩を迫られる。ボパール工場のカーバイド社による異例の過半数所有や、ラナプラザのメーカーによる警告を無視した従業員の再就職への熱意は、経済力の不均衡を示す一例である。しかし、事故が起きると、被害者は疑わしい規制を行ったのと全く同じ当局に、また再分配の要求から資本を保護するのと同じ法体系の中で、救済を求めなければならないのである。ボパール訴訟で明らかになったように、不公平を痛感するだけでは、法の硬直性を克服するには十分ではない。
法律も市場も、社会的相互作用は、開かれた情報と公平なゲームのルールによって、すべての人にとって平等になる、公平な競技場で演じられると想像している。これは便利なフィクションである。実際には、平らな土俵の上で、土俵自体に内蔵された傾斜や亀裂に起因するクレームを選別することはできないのである。では、災害から何を学ぶことができるのだろうか。私が「謙遜の技術」と呼んでいるものに改めて注意を払うことが、その答えの一部である18。謙遜の技術には、技術的リスクの枠組みや測定の方法に対する高い関心、最も脆弱な人々のニーズへの着目、技術の不平等な分配的影響の評価、過去の誤りを思い出すための意識的な取り組みが含まれる。このような控えめなルールを適用する適切なタイミングは、リスクの高いプロジェクトが実施された後ではなく、その前なのである。これらの点については、最終章で詳しく説明することにする。
第4章 自然を作り変える
古い植物に新しい植物を
長い技術革新の歴史の中で、自然は、協力者として、資源として、時には不本意な戦友として、数え切れないほどの形で人間に奉仕してきた。人類はどこに行っても食べ物を探し、やがて経験的、理論的知識をフル回転させて、自分たちの食欲を満たし、社会的一体感を維持するための商品を地球に多く生産させるようになった。アメリカの歴史家ウィリアム・クロノンは、そのブレイクスルー著書『ネイチャーズ・メトロポリス』の中で、シカゴの後背地が、都市が成長し食料を必要とするにつれ、草原をトウモロコシ畑に変え、野生のバッファローの群れを減らし、森林を切り倒し、見違えるように変わっていったことを記録している。シカゴは、その自然を再構築する能力において、人類が地球全体に与える影響を代弁している。この点で、シカゴは小宇宙であり、世界の縮図である。
狩猟採集民の祖先が定住農業を始めたときから、彼らは植物や動物の新しい品種を選択し、交配し始めた。彼らは、利用可能なものから最良のものを得るという実用主義的な衝動に駆られたのである。農民たちは、遠く離れた市場に向けて、より高収量で、より美味しく、より魅力的な、そして最終的には腐敗しにくい品種を作ろうとしたのである。植物育種には、美的感覚や、五感を満足させる新しい香りや色を求めるという軽い側面もあった。オランダのチューリップ栽培農家は、何世紀にもわたって真っ黒なチューリップの品種改良に取り組んできた。最近では、サントリーが遺伝子操作による青いバラのコンペティションに出資し、何年もの努力の結果、冷静に観察すると青というよりラベンダーに近い色の花を咲かせた。果物や野菜の生産者は、種無しスイカから、プラムとアプリコットを掛け合わせたプルート、オレンジとザボンを掛け合わせたタンジェロなど、数え切れないほどのハイブリッド品種を作り続けている。
このように自然を操作してきた長い歴史から、20世紀後半の農業界は、遺伝子操作という新しい技術によって、植物の品種改良や畜産を近代化することに何の問題もないと考えた。米国では、19世紀半ばから、農民や生産者が大学で教育を受けた農業科学者と協力し、研究と応用を結びつけてきた。2 今、学術研究所で開発された高度な遺伝子組み換えは、収穫量の向上、新しい治療・栄養特性、極度の環境ストレスへの耐性など、商業的に価値のある特性を持つ遺伝子組み換え生物の新品種を大量に生み出すことを約束しているのだ。種間で遺伝子を移動させることにより、科学者は通常の進化の過程では生じないような遺伝子組換え系統を作り出すことができる。これらの特性は、害虫から干ばつや気候変動の影響に至るまで、自然界で最も根強い脅威に植物が立ち向かうのを助けることができるだろう。しかし、農業バイオテクノロジーは、その壮大な約束とは裏腹に、最近の技術応用の中で最も議論を呼ぶものの一つとなり、現代の工業生産に広範な変革を導入する際に避けるべきことを示すパラダイムケースとなった。
魅力的で、実現可能で、広く応用でき、貧しい人々や飢えた人々に大きな利益をもたらす可能性があり、商業的にも利益をもたらすと思われた技術が、なぜ倫理的、政治的に大炎上し、沈静化しようとしないのだろうか。このパズルを理解するためには、「グリーン・バイオテクノロジー」を 2000年代における世界の農業生産の政治経済、それも複数の政治経済という文脈で理解する必要がある。この技術開発をめぐる議論は、前章で述べたボパール災害につながった発明、市場の拡大、世界的流通の歴史と同じように、重なり合った歴史から発展してきたことが分かるだろう。
研究室で生まれた発見は、ベンチサイエンティストにとっては価値のないものに見えるかもしれないが、それが現場や商業の場に出てくると、ガバナンスの茨の道を歩むことになる。先進工業国の科学技術の成果が世界の他の地域に広まると、リスク、安全性、自然の価値に関して、全く異なる農法や消費者の嗜好とぶつかり、予期せぬ対立が起こるかもしれない。米国の科学者が初めて遺伝子組み換えの技術を開発したとき、このような配慮は最前線にはなかった。大学の科学者も産業界も政策機関も、遺伝子組み換え作物が健康や安全に対して重大なリスクをもたらさない限り、疑う余地のない利益として受け入れられると想定していたのである。さらに言えば、リスク評価は生物学的プロセスを理解する専門家の仕事であった。消費者は、自分たちが何を食べ、どのように育てたかについて、強く正当な意見を持っていることが事後的に判明しても、製品開発の初期段階において、消費者の好みについて相談されることはなかった。このような初期の国民的議論の欠点は、いくら政策が追いついても補うことはできない。
21世紀初頭の農業バイオテクノロジーの物語は、野心的な技術推進者の希望と、バイオテクノロジーを管理不能な力、破壊的な文化的価値の担い手とみなす人々の疑念と恐怖の間を、既存の制度が仲介できないことに大きく関わっている。利益に関しては、多くの人が、まだ生まれたばかりの産業が追求する製品やプロセスの革新が、世界で最も困窮している人々に奉仕するために最適なものだろうかどうかを疑問視してきた。また、技術開発を推進する利益追求型の企業が、リスクを十分かつ冷静に見極めているのか、という疑問もある。利己的なメーカーが、自然の生物多様性を破壊するような手に負えない生物を作り出したり、人間やその環境に毒を盛ったりするリスクを、責任を持って計算できるのだろうか?リスクと利益という話自体が、伝統的なライフスタイルと世界の食料安全保障を脅かす社会技術的変革のための薄い化粧品なのだろうか?これらの疑問は何十年にもわたって議論されてきたが、その答えは、根本的な政治的立場と同じくらいに大きく隔たったままである3。
戦略的誤り
3 戦略的誤り農業バイオテクノロジーの始まりから、誇張された主張と戦略的誤りがつきまとっていた。イノベーションは、生産者のニーズよりも、ましてや顧客が何を買いたいか、何を食べたいかよりも、産業界が何を想像し実行できるかによって導かれるものであった。初期のいくつかのアイデアは、政治的に破壊的であり、商業的には実現不可能であることが証明された。それは、一般的な細菌であるシュードモナス・シリンガエ(P. syringae)の遺伝子を1つ削除し、表面に氷の結晶を形成する能力を減らした変種、いわゆるアイス・マイナスであった。提案者は、この遺伝子を欠いた細菌をイチゴのような傷みやすい植物に散布することで、突然の霜や収穫量の低下から守ることができると期待したのである。しかし、このアイス・マイナスは自然界にすでに存在する突然変異株であり、新しい生物ではないとのことであった。環境保護団体は、アイス・マイナスを大規模に散布すると生態系のバランスが崩れ、誰も注意深く研究していない有害な影響が出るのではないかと懸念していた。結局、遺伝子操作された微生物を環境中に放出するのは時期尚早であるというコンセンサスが形成された。そこで、産業界の関心は、作物や家畜を改良し、商業的に利用できるようにすることに向けられた。
しかし、これも紆余曲折があった。例えば、「フレイバー・セイバー」というトマトがそうである。1980年、カリフォルニア大学デービス校の農業科学者たちは、自分たちのアイデアを研究室から畑に持ち込むためにカルジーン社を設立した。カルジーン社は1980年、カリフォルニア大学デービス校の農業科学者たちが、研究室から畑へアイデアを展開するために設立した会社である。彼らの計画は、より長く樹にとどまり、より風味豊かで、しかも遠くの市場まで輸送できるトマトを開発することだった。Flavr-Savrと名付けられたこのトマトは、果実が熟すと細胞壁を軟化させる酵素の生産量が少なくなるように遺伝子操作されたものである。カルジェン社の科学者たちは、その目的は達成したが、Flavr-Savrは商業的には期待外れであった。熟成を遅くしても、科学者が期待したような味の向上は見られなかった。また、出荷もうまくいかなかった。また、生産・流通コストが高いため、従来のトマトと競合することができなかったのである。カリフォルニア産のFlavr-Savrトマトをトマトペーストに加工し、イギリスの大手スーパーで販売していた時期もあったが、イギリスでは遺伝子組み換え作物に対する国民の抵抗感が高まり、1990年代末にはその市場も枯渇してしまった。カルジーン社は、バイオテクノロジー分野で成功した多くの新興企業に見られるようなライフサイクルを歩んできた。そして、1996年にモンサント社に買収された。
遺伝子組み換え技術を畜産に利用しようとする業界の初期の試みは、アイス・マイナスやフレイバー・セイバーほど満足のいくものではなかった。またしても、技術的に可能だという誘惑が、バイオテクノロジー産業と一般市民との関係を誤った方向に導いてしまったのである。米国政府の援助で行われたヒト成長ホルモンの遺伝子を豚に組み込むプロジェクトでは、関節炎やその他の病気に苦しむ動物が生まれた。有名な話だが、19匹の「ベルツビル豚」のうち17匹が1年以内に死んだ。また、乳牛の乳量を増やすために遺伝子組み換えの牛成長ホルモン(rBGH)を使用したところ、乳房に痛みを伴う炎症が起きるなど、体に不調をきたす動物が続出した。このような感染症は、抗生物質の使用を増加させ、抗生物質耐性菌の発生を危惧させた。また、rBGHの使用は、収穫量増加の恩恵を受けられる大規模農家を優遇するため、経済的な要因も絡んでくる。欧州連合(EU)やその他の国々の規制機関は、これらの結果を重く見て、自国の酪農業でrBGHを使用することを禁止した。しかし、米国食品医薬品局(FDA)は、その責任をより狭く解釈していた。FDAは人間の健康に責任を持つ機関として、rBGHを投与された動物のミルクは人間に害を与えないという理由でrBGHの使用を許可したのである。このような政府の規制の不備は、小規模農家や動物愛護団体を憤慨させ、rBGHを含まない有機乳製品を求める声が高まった。アメリカの消費者の多くは、いまだにrBGHを投与された牛の乳や乳製品を買うことを拒否しており、このホルモンの蔓延は、バイオテクノロジーの無頓着な利用の典型例と見なされている。しかし、既存の法律と政策のもとでは、米国の連邦政府機関は、こうした倫理的、経済的な懸念や、遺伝子組み換え製品の世界的な広がりに伴う生態系の不確実性をすべて考慮する明確な権限を持っていない4。
米国の農業バイオテクノロジーは、初期には挫折もあったが、1990年代には、生産に大きな損失をもたらしているオオタバコやヨーロッパトウモロコアザミウマなどの特定の植物害虫に対抗しようとするメーカーと商品作物生産者の間の提携によって大きな前進を遂げた。特に、バチルス・チューリンゲンシス(Bt)と呼ばれるバクテリアの遺伝子を作物の植物に組み込む遺伝子工学は、生産者たちに歓迎された。Bt遺伝子は、有害な昆虫の幼虫を殺すタンパク質を生成するが、人間やハチやチョウなどの益虫には無害と考えられている。第二の成功は、除草剤に耐性のある作物を作ることである。この発明により、米国の化学大手モンサント社は農業バイオテクノロジーの世界的な顔役に躍り出た。モンサント社は、グリホサートという化合物をベースにしたラウンドアップという除草剤を製造しており、広く使われている。モンサント社は、遺伝子組み換え技術によって、すでに人気のある除草剤とセットで販売できる「ラウンドアップ・レディ」の各種植物を生産できるようになった。農家は、除草剤が雑草だけを枯らし、換金作物を枯らさないことを知りながら、生育期にラウンドアップを安全に散布することができるようになった。ラウンドアップは現在も生産者の間で非常に人気があるが、グリホサートがヒトに対して発がん性を持つ可能性があるという懸念が、結論に至らない研究に基づいて提起されている5。
1996年頃に初めて導入されてから20年足らずで、米国では遺伝子組み換えの大豆、トウモロコシ、綿花の割合が急増した。米国農務省の調査によると、2015年に栽培された大豆のうち、除草剤耐性大豆は94%、除草剤耐性綿花とトウモロコシはいずれも89%であった。これらの数字は、遺伝子組み換え作物の世界平均使用量をはるかに上回り、米国のバイオテクノロジー産業と米国の汎用作物生産者との間の快適な同盟関係を証明するものであった。
庭のすべてがバラ色ではない
国内での成功に後押しされ、モンサント社をはじめとする遺伝子組み換え作物生産に携わる米国企業は、1990年代に世界市場に目を向けた。ところが、この世界市場において、モンサント社をはじめとするアメリカの遺伝子組み換え作物生産企業は、不意打ちを食らったような猛烈な拒絶反応を示すようになった。欧州の政府やブリュッセルの規制当局の多くは、この技術を有益で市場拡大が期待できるものとして好意的であった。しかし、一般市民はそうは考えなかった。ヨーロッパの環境保護主義者や小規模農家は、アメリカからの技術的侵略に対し、多くの人が未検証で不必要、かつ持続不可能であると考え、反対を唱えたのだ。大西洋を挟んで、議論は二極化した。アメリカの生産者とその政治的同盟者は、ヨーロッパ人の無知で非科学的な判断を嘆き、一方ヨーロッパ人は、アメリカの安全性の主張はしばしば信頼できる科学というよりむしろ無知と当て推量に基づいていると主張し、異議を唱えた。モンサントは、傲慢で、文化的に無神経で、自国の科学的知識と技術的能力の限界を認めようとしない 2000年当時のアメリカの対外的な態度に問題があると思われる多くの事柄の避雷針となったのである。
世紀末に起こった遺伝子組み換え作物の大論争は、遺伝子にコード化された情報が複雑な生物の中でどのように機能しているか、ましてや大規模な生態環境の中で機能しているかという点で、科学の理解に多くの欠陥があることを明らかにした。私たちの目的にとって重要なのは、この論争によって、世界的に普及しつつある新興技術を管理する責任を負う制度の弱点も浮き彫りにされたことである。事実が未知であったり不明であったりする場合、最終的に責任を負うのは誰なのだろうか。足りない知識を生み出すこと、予防とリスクテイクのバランスを取ること、自然と持続可能性に関する相反する考えを調停すること、そして事故が起こったときにそのコストを負担することは誰なのだろうか。いずれの場合も、国や地球規模でのグッドガバナンスの観点から、その答えはまだ見つかっていないか、あるいは深い問題を抱えている。
「Unknown Unknowns」
奇妙なことに、米国のある政治家が、遺伝子組換え作物をめぐる政策上の問題提起をする際に、広く取り上げられるような言葉を提供した。一つは、イラクとアフガニスタンにおける「テロとの戦い」がもたらした経済的・政治的腐敗、もう一つは、近代におけるあらゆる目的のある行動の矛盾を要約した、即座に流行した言葉である。その言葉とは、「unknown unknowns」である。ラムズフェルドは 2002年の記者会見で、俳句のようにシンプルな表現でこう述べた。
既知のことがある
私たちが知っていることがある
また、既知の未知があることも知っている。
つまり、私たちが知らないことがあることも知っている
しかし、未知の未知数もある。
私たちが知らないことを、私たちは知らないのだ
この「一般的な認識論の見事なまでにピタリと言い当てた言葉」7 は、ラムズフェルドが2011年に出版した回顧録『Known and Unknown』のタイトルに採用されるほど、広く知られるようになったのである。ミステリーを愛する有名なドキュメンタリー映画監督エロール・モリスは、さらに一歩進んで、ラムズフェルドに関する2014年のドキュメンタリー映画に、長官が唯一ラベルを付けずに残した組み合わせ「The Unknown Known」にちなんだ名前を付けたのである。あらゆる決定的な行動の基礎となる知識に依存する社会で、未知の未知という概念が深い不安の和音を奏でたことは明らかである。
第2章で説明したように、リスクアセスメントは既知の未知を扱うことが多い。それは、すでに人間の想像の範囲内にあり、したがって知ることのできる領域にある結果について、その確率を束ね、定量化しようとする努力である。遺伝子工学の初期には、このような枠組みが責任ある規制のために適切であると考えられていた。1975年、カリフォルニアの有名なアシロマ・カンファレンス・センターに一流の分子生物学者が集まり、自然界では見たこともない危険な病原体を含む遺伝子組み換え作物が、実験室から偶然に抜け出して人間の健康や環境に害を与えないようにするにはどうすればよいかを議論した。会議参加者は、自分たちの研究室での仕事から、偶発的な放出が起こることを知っていた。そして、既知の危険性が予測されるリスクを政策によって抑えようとしたのである。その結果、アシロマール研究所で想像されたような恐ろしい事態が決して起こらないよう、物理的、生物学的な研究管理システムを構築することになった。
しかし、当時はまだ、組み換えDNA技術は、熱心な子供たちが手にする玩具のようなものであった。アシロマに集まった分子生物学者の中には、遺伝子組み換え作物を意図的に環境中に放出することによって、新たな産業が興ることを予期していた者はほとんどいなかった。また、トウモロコシや綿花などの主食用作物の遺伝子組換え作物が、いつの日か自然界に存在する品種にほとんど取って代わられるとは想像もしていなかった。つまり、科学者たちは、自分たちが最もよく知っている研究室、特に生物医学の研究室に集中しており、商業化にはまだ関心が向いていなかったのである。除草剤や殺虫剤に耐性のある作物を意図的に大量に導入する「意図的な放出」から生じる危険性は、ラムズフェルド長官の言葉を借りれば「未知のもの」であった。しかし、わずか数年の間に、モンサント社やシンジェンタ社など、遺伝子組み換え作物が登場する以前から農業技術に深く関わってきた業界のリーダーたちによって、その見通しは現実のものとなってしまったのである。
意図的な放出のリスクに関する知識は、事前の評価というよりも、その場しのぎの経験によって、ゆっくりと、そして断片的に蓄積されていった。遺伝子組み換え作物に関する一連の事故は、統治可能なリスクに関する米国の支配的な想像力におけるギャップや穴について光を当てている。2000年、スターリンクと呼ばれるBtトウモロコシの一種が、飼料用としては認可されているが食用としては認可されていないにもかかわらず、クラフト・フーズ社が製造し、ファストフード・チェーンのタコベルが販売したトウモロコシ製品から検出された。この遺伝子組み換え品種には、米国環境保護庁(EPA)がヒトへのアレルゲンとして分類していたCry9Cと呼ばれるタンパク質が含まれていた。遺伝子組み換えに反対する環境保護団体や消費者団体のコンソーシアムであるジェネティック・アイディー社は、タコベル社の製品を検査し、決して起こってはならない汚染を特定した。しかし、この事件は、回避可能な事故、つまり、基本的に善意で行った行動の「意図しない結果」として広く見過ごされた。ある議論によれば、EPA はスターリンクを動物飼料用としてのみ認可すべきではなかった。なぜなら、複雑な製造環境において、認可されたトウモロコシ品種と認可されていない品種を分別することは困難であることをEPA は知っていたはずだからだ。10 あるいは、穀物取扱者がもっと注意深く、規則を守っていれば、混同は発生しなかっただろう。さらに、この恐怖は、実際に疾病管理センターに報告されたごく少数のアレルギー反応の記録とは全く比例しないとも言われた。要するに、バイオテクノロジー擁護派にとって、スターリンクは植物の遺伝子組換えというプロセスに本質的な問題は何もないことを明らかにしたのである。この事件は、規制と製造の適正を逸脱した不幸な事件であり、それに世間の過剰反応が追い打ちをかけただけである。
しかし、スターリンク社のエピソードは、新しいテクノロジーに関しては、想像上の未来と知識の流れや責任に関する制度上の現実とがうまく対応しないことも浮き彫りにしている。第2章では、特に非知識は絶対的なものではなく、相対的なカテゴリーであることを見た。遺伝学者や医学者が人間のアレルギーについて知っていることと、穀物エレベーターのオペレーターが種子の貯蔵や出荷の条件について知っていることは、大きく異なるのだ。これらの複数の形式の知識は、通常、産業処理の過程で互いに分離される。実のところ、抽象的な科学的知識はリスク評価者により優遇される傾向がある。サイロの作業員によって処理されるような実用的な知識が、査読付きの科学論文や、公表された科学に依拠するリスク評価や政策立案の希薄なフォーラムに入り込むことはほとんどない。その結果、複雑な技術システム全体のリスクや安全性に関する公式見解は、誤解を招くような部分的かつ不完全なものになる可能性がある。
そして、「誰にとっての未知か」が重要な閾値となり、誤った判断による回答は、社会にとって有害であると同時に、倫理的に問題となり得るのだ。科学技術の未知が未知に見えるのは、最も権威ある知識人が、より高次の視点から得られるかもしれなかった視点を欠いているからにほかならない。このように、遺伝子組み換え作物に関する規制当局の初期の言説を支配していた分子生物学者は、自分たちが想像しうる種類の偶発的な放出によるリスクに最も敏感であった。彼らは、遺伝子組み換え作物が非標的種に及ぼす有害な影響、耐性形質の出現、組み換え生物と非組み換え生物間の遺伝子移動のリスクについて、後に生態学者が抱くようになる知識も、実際、懸念も持ち合わせてはいなかった。また、乱雑な生産システムにおけるモニタリングやコントロールの失敗は、高邁な志を持つアシロマーの科学者たちにとっては、なおさら異質なものであった。こうした懸念は、後になって、異なる分野の専門家同士の対立や、米国のバイオテクノロジー産業と他国の消極的な農家や消費者との対立の中で、初めて浮かび上がってきたのである。しかし、米国メーカーは、自国の規制リスク評価の経験を健全な科学のゴールドスタンダードとして受け入れ、他国からの批判を科学的でないとして退けてきたのである。
遺伝子組み換え作物の規制の歴史は、科学的、政治的立場を問わず、権力者がリスクを評価し管理する際に、自分とは異なる視点を求めるインセンティブがいかに欠如しているかを物語っている。支配的な思考の枠組みの外から届く主張は、無知、根拠なし、科学的妥当性なしとして拒絶されることが多い。このように考えると、「未知の領域」という現象は、関連する知識の絶対的な空白というよりも、権力の不平等な分配(誰の知識がどのような目的でカウントされるかを決定する権力)に関する記述と見ることができる。
リスクか予防か?
知るということは視点の問題であり、完全な知識は達成不可能な理想であるため、グローバル化する世界では、ある集団が物事を知っていると主張すると、より優れた知識や疑うに足る理由を主張する別の集団によって否定または否定される状況が多く見られる。遺伝子組み換え作物の国際取引は、そのような長期にわたる対立の一例であり、何を知るべきか、不確実性や価値の対立にどう対処すべきかについて、大きく異なる意見を調停するには、既存の国際機関が不十分であることを改めて浮き彫りにしている。
2000年代初頭までに、農作物である遺伝子組み換え作物の扱いについて、「科学に基づく」あるいは「リスクに基づく」アプローチをとる国や組織と、「予防」を支持する国々との間に大きな亀裂が生じた12。これらの用語は様々な形で法律や政策に盛り込まれており、単一の単純な定義はないが、科学知識の限界についてそれぞれが意味するところは一貫して異なっている。大まかに言えば、科学的根拠に基づく(あるいはリスクに基づく)アプローチは、問題を既知の未知数として捉え、現在の知識に基づいて、あるいは目標とするさらなる研究によって、将来についての信頼できる予測が可能であると仮定する。これに対し、予防的アプローチでは、重要な事柄は科学的探求の限界を超えていることを当然と考え、その中には未知の未知というカテゴリー全体も含まれる。リスク評価者が行おうとしているように、想像すらできない問題に対して、どうやって確率の見積もりをすることができるだろうか。ある技術の将来の軌道が深刻な不確実性をはらんでいる場合、科学を増やすことが必ずしも良い答えとはならない。実際、科学は、理解されていないことについての知識を増やすことで、科学者の常識の枠外にある、よりよく知られた問題から注意をそらす可能性さえあるのだ。
リスクと予防措置の衝突は、遺伝子組み換え作物をめぐる大西洋横断貿易戦争へと発展した。2003年、穀物輸出大国であるアメリカ、アルゼンチン、カナダは、世界貿易機関(WTO)で欧州連合(EU)を相手に裁判を始めた。EUは、遺伝子組み換え作物の輸入を禁止するモラトリアム(一時停止措置)をとっており、自由貿易の国際ルールに違反していると訴えたのである。リスク評価で安全性が確認されているのに、EUが遺伝子組み換え作物の輸入を認めないのは違法であり、遺伝子組み換え作物を排除する有効な科学的根拠がなかったからだ。遺伝子組み換え作物のリスク評価は、どれも人間の健康や環境に害を与えるという示唆はなかった。従って、リスクに関する科学的根拠がないのに、これらの製品に障壁を設けることは違法である。このような裏付けのない行動は、すべてのWTO加盟国が信奉する自由貿易の原則に背くものであった。
それから2年後、WTOの紛争解決手続きは、EUが遺伝子組み換え作物の承認を「不当に遅らせる」ことによって、遺伝子組み換え作物に対する違法なモラトリアムを維持したという1000ページに及ぶ意見書を発表した。しかし、ヨーロッパの消費者や一部のEU加盟国の反応は、あまり芳しくなかった。これは、アメリカのリスク評価が、生態系や公衆衛生に関する未知の事項の検証が不十分であるとして、他国の正当な疑義に優先するように思われたケースである。WTOの推論は、自由貿易と、国家が互いの技術製品や暗黙のうちにその安全基準を購入する際に、どの程度の、どの種類の不確実性を許容できるかという政治的判断の間の未解決の緊張を認めたものである。この事件は、科学に基づく世界観と予防的世界観の対立を鮮明にした。形式的な法的問題としては科学が勝ったが、法的確証の力にもかかわらず、米国の科学の普遍的な主張に対する疑念は沸き起こり、消え去ることはないのである。
WTOの立場からすると、この紛争は条約の重要な文言、特に各国が採用する貿易制限措置の根拠となる5条1項と5条2項の解釈が中心であった。特に5.1条は、国境を越えた技術の移動を規制するための科学に基づくアプローチを明確に支持している。
加盟国は、その衛生または植物検疫措置が、状況に応じて、関連する国際機関により開発されたリスク評価技術を考慮に入れた、人間、動物または植物の生命または健康に対するリスクの評価に基づくことを確保するものとする。(強調)
5.2 条はさらに、リスク評価は「利用可能な科学的証拠」に基づかなければならないと規定し、5.7 条は、科学が不十分であると考える場合、国家には「リスクのより客観的な評価に必要な追加情報を入手する」義務があると主張している13。これらの規定を合わせると、現存する、あるいは実用的に入手可能な科学によって、GMOの取引に関する不確実性を解消できるという見解を強く支持している。自然が複雑すぎる、起こりうるすべての因果関係の経路を想像できない、あるいは必要とされる研究に法外な時間や費用がかかるなどの理由から、さらなる研究によって排除できない不確実性があることを考慮する余地は、ここにはほとんどない。
貿易紛争の中立的な裁定者としての科学へのコミットメントは、WTOを厄介な立場に追い込んでいる。科学と法律の客観的原則を適用しているのか、それとも国家主権に不当に介入しているのか。リスク評価自体が不確実性を管理するための価値観を伴う手段であるとすれば、主権国家は、国民が未知の未知に直面してより大きな予防措置を要求する場合、異なるアプローチを採用することを選択できるだろう14。しかし、WTOは、条約締結国がWTOの認識論的選好に従う意思があるかどうかについて、事前に何ら明示的な検討を行うことなく、条約執行権の不文律的付随事項として、ほとんど当然のように超越的主権の地位を獲得したのである。
自然を味わう
WTO条約に盛り込まれた科学的根拠に基づく不確実性へのアプローチは、自然を改変し商品化しようとする試みに必ず付きまとう価値観の対立を排除している。多くの人々が遺伝子組み換えに不信感を抱いている。それは、遺伝子組み換えがあまりにも速く、伝統的な農業や育種技術の枠を超えすぎていると考えるからだ。懐疑論者には、特に小規模農家、ロカボ愛好家、特殊作物や伝統作物の栽培者、倫理的な観点から有機食品を購入する人たちが含まれる。これらのグループはすべて、遺伝子組み換え技術を含む工業化された農業が、自分たちが好む食料の栽培や消費の方法に取って代わるのを見たくないという強い願望を持っている。大西洋の両岸、そして世界的に、有機農業に対する消費者の嗜好の高まりに応えるために、市場とサプライチェーンが立ち上がり、有機と非有機の区別に細心の注意が払われている。例えば、マサチューセッツ州ケンブリッジにあるスーパーマーケット「ホールフーズ」のコーヒーグラインダーには、次のように書かれている。「このグラインダーは、有機栽培のコーヒー豆と慣行栽培のコーヒー豆の両方に使用することができる。このグラインダーは有機栽培のコーヒー豆にも、慣行栽培のコーヒー豆にも使える。”コーヒーの有機性を維持することに熱心なお客様は、自宅で豆を挽くことをお勧めする。
この看板は、やや皮肉な表現ではあるが、ホールフーズ・マーケットが2013年3月に採用した「GMの完全な透明性」という店全体の方針を反映している。同社は5年という期限を設け、北米の店舗で販売する全商品にGM原料の有無を表示することを発表した。政府の対応より、民間のイニシアティブが先行している。これは、消費者が食品の販売に関して連邦政府から同様の措置を受けることができないのと対照的である。実際、米国の政策では、遺伝子組み換えの表示を積極的に控えている。有名なケースとして、FDAと米連邦取引委員会(FTC)は、人気アイスクリームメーカーのベン&ジェリーズなどの乳製品専門メーカーに対し、自社の製品に遺伝子組み換えウシ成長ホルモンが使われていないことを証明すれば、虚偽・欺瞞広告として有罪になると警告したことがある。そのため、オーガニック乳製品メーカーは、「rBGHを使用していないことを保証する農家から牛乳を仕入れている」とだけ主張する、より歪んだ方法を取らざるを得なくなった。その場合でも、ラベルには、FDAがrBGH処理牛と未処理牛のミルクに有意差はないことを宣言する必要がある。
遺伝子操作に反対する農家は、オーガニック製品を求める消費者の増加と、その製品で価格を下げ、非遺伝子操作市場のニッチを拡大させないために多額の資金を費やす強力な業界ロビーの間で板挟みになっているのである。米国では、遺伝子組み換え作物の表示を義務付ける州法が重要な争点となっており、それは酪農業におけるrBGHの使用という比較的限定された領域をはるかに超えて広がっている。2012年にカリフォルニア州で行われた遺伝子組み換え作物の表示を義務付ける州民投票「プロポジション37」は、賛否両論を巻き起こし、失敗に終わった。しかし、この住民投票に対して、遅まきながら多くの資金が投入された結果、約51.4%の反対票を集め、僅差で否決された。モンサント社とデュポン社を筆頭とするバイオテクノロジーと食品産業は、賛成派の900万ドルに対し、4600万ドルという巨額の資金を投入し、賛成派を圧倒した。2013年にワシントン州で行われた同様の取り組みも、やや大差で敗れた。しかし、いくつかの州議会でラベル表示を義務付ける法案が審議中であり、この戦いは続いている。
工業的農業と非工業的農業を区別したいという願いは、自分自身や家族のために、より自然な食生活を望む消費者に限ったことではない。有機農産物の生産者は、自分たちの農産物がGMに汚染されていないことを購入者に確信させることができるかどうかに、農産物の市場がかかっていることを認識している。各国政府も、有機農産物の生産者のような選択的経済部門が、不慮の汚染によって耐え難い損失を被ることがないようにすることに関心を持っている。欧州連合が採用しているような厳しい「共存」規則は、遺伝子組み換え製品が追跡可能であること、つまり署名マーカーによって識別可能であることを保証しようとするものである。完全な純度を達成することは不可能であるため、EUの共存規則では、GM成分の含有率が0.9%未満であれば、GMフリーと指定することができると定めている。オーストラリアとニュージーランドでは、四捨五入して1%としているが、これらの数値は現実的に可能であると考えられている。米国では、FDAがGMフリーの表示を推奨している。この表示は、100%純粋だろうかのように誤解を与えるからだ。
しかし、無秩序な自然と整然とした官僚的論理は相容れない。欧州の規制当局は、遺伝子組み換え作物をめぐる論争を「共存の原則」で切り抜けようとしたときに、このことを知った。共存の原則とは、消費者の自由な選択を尊重し、あらゆる形態の農業がヨーロッパで繁栄するチャンスを与えられるべきであるという公約を示すものである。共存を実現するために、EU当局は、遺伝子組み換え作物の栽培地域と非組み換え作物の栽培地域の間に維持しなければならない距離を規定した。この距離は通常、風による花粉の飛散を防ぐのに十分であるが16、ミツバチが遺伝子組み換え作物と非組み換え作物の区画を飛び回り、両方の植物の花粉を吸うのを防ぐには不十分であることが判明した。このような規律を欠いたミツバチから採れる蜂蜜には、GMフリー指定に必要な0.9パーセントを超えるGMが含まれている可能性がある。そのような蜂蜜を、自然食品の消費者と判断して販売する養蜂家は、収入の減少に直面する。さらに、ヨーロッパの小規模養蜂家は、共存は、最高の花粉源を求めてコロニーを自由に移動させる旅人農家に依存する農業生活形態にとって本質的な害悪であると見ている。ドイツの養蜂家たちは、過度に寛容な規制体制に制約と脅威を感じ 2008年にミュンヘンで、自分たちの土地から追い出されたと主張するハチへの政治亡命を要求するために動員された17。
より大規模な政治的スケールでは、ヨーロッパの数カ国が遺伝子組み換え作物の一部または全部の栽培を禁止すると宣言した。ターゲットには、最も顕著に、モンサントの昆虫耐性ハイブリッドコーン MON810が含まれる。これはヨーロッパで植栽が承認された数少ない遺伝子組み換え種の一つである。例えば、2011年に欧州司法裁判所が下した、フランスにおけるMON810の栽培禁止を違法とする判決に基づき、同社はこれらの禁止が違法であると主張している18。モンサントはまた、欧州食品安全機関など、あらゆる健康安全機関が、ヒトや動物、非標的種への危害のリスクを発見できなかったことを挙げている19。しかし、これらの主張は、リスクベースの規制アプローチを信奉する業界と、未知の未知を恐れ、より地域に根ざした異なる農業生産方式を選択した消費者と生産者の同盟の間の埋めがたい価値の溝を強調しているだけである。物理的・生物学的安全性のみで構成された議論では、一握りの多国籍大企業が支配する遺伝子組み換え製造を通じて、植物や種子の品種に対する危険な力の集中、それによる食糧供給の多様性の減少に関する懸念に対処することはほとんどできない。
誰が負担するのか?
結果が不確実な場合、人々は、思いもよらないことが起こったときに、誰かがその費用を負担してくれると知っていれば、安心することができる。火災、洪水、交通事故、その他現代生活の一般的な危険に対して保険をかけるのはこのためである。しかし、大規模な技術システムの故障によって被害が発生した場合、誰がどのような損害を負担すべきなのか、特に確率が低く結果が大きい事象については、事前に明確に規定されているとは限らない。スターリンク社のエピソードに代表されるように、その影響は予測不可能な場合が多い。市販のタコスの殻にCry9Cが検出されたことで、費用のかかるリコールが必要となり、最終的には数百の製品におよび、米国とメキシコの企業に影響がおよび、米国から日本と韓国への輸出が脅かされた。国内のトウモロコシ生産者を保護するため、米国農務省は1500万ドルから2000万ドルを投じて、未使用のスターリンク種子を買い戻した。StarLinkを販売した子会社である独仏のアベンティス社は 2003年に、トウモロコシ価格の下落で損害を受けた農家に対して 1 億 1,000 万ドル、リコールの影響を受けたその他の人々に対して総額 5 億ドル以上を支払うことに合意した20。これらのコストは、アベンティス社と、まったく罪のない公的・私的関係者との間でどのように配分されたのか、正確な計算がなされないまま、社会全体に拡散していった。
21世紀初頭のインドにおける遺伝子組み換え綿花の導入では、これとは別の、より悲劇的な代償と責任の物語が繰り広げられた。1990年代、貿易の自由化によってインド市場は外資に開放された。この政策変さらにより、多国籍アグリビジネス企業は、それまで伝統的な種子に頼っていた小規模農家が世界一多いこの国で、毎年保存していた種子を植え替えて、自社の種子を売り始める道を開いたのである。モンサント社のBtコットン(商品名ボルガード)は、ボルワームの蔓延で作物が壊滅状態にあるインドの綿農家にとって、天の恵みと思われた。3年間の試験期間を経て 2002年にインド政府はBtコットンの商業利用を承認し、10年以内にインドの綿花収穫量の約95パーセントを占めるようになった。オオグソクムシを駆除することで、農家はより安定した利益を得られるようになり、化学農薬の使用量も減り、生物学的に有益な昆虫や植物への害も少なくなることが約束されたのだ。つまり、世界のバイオテクノロジー産業は、インドの綿花メーカーとユーザーにとってWin-Winのシナリオを約束し、インド経済にも大きな見返りをもたらしたのである。わずか10年の間に、非遺伝子組み換えの前駆体からほぼ完全に引き継がれたBtコットンは、米国での発展と同様、その約束を果たすかのように思われた。
しかし、1990年代後半にはすでに、インドの農民の自殺率が異常に高いという話が出始めていた。物価の下落や経費の高騰で生活が苦しくなり、首吊りや有毒な農薬を飲み込むなどして自殺する人が後を絶たなかった。21 農民の自殺が特に多い州や国は、債務救済法を制定し、困窮する農民とその家族を救済したが、その範囲は悲劇を防ぐのに十分なものであったとは言い難い。
経済自由化、遺伝子組み換え綿花の承認、農民の死亡が重なり、外国企業によるインド農業の独占を懸念する活動家たちは困惑した。その中で、自殺者増加の具体的な原因として、遺伝子組み換え綿花を挙げる意見があった。それまで種子をほとんど買わなかった小作農が、高価な種子、農薬、肥料をセットで買わされるようになり、利潤が減り、不作や借金が増えやすくなったというのである。バイオ業界は、アルコール依存症や子供の教育費の使い過ぎが原因だとしたり、遺伝子組み換え綿花導入後の農家の自殺率に大きな変化はないという研究を引用したりと、さまざまな反論をした。
予想通り、この論争は統計の取り合いとなり、互いの因果関係を否定しようとするものだった。これは、単に過激派が強硬な立場をとり、自分たちの主張に合うようにデータを選択的に引用しているというだけの問題ではない。むしろ、主流派の研究者の間でも分極化が進み、事実と価値観が密接に結びつき、中立的な判断が本質的に不可能な、複雑なグレーゾーンに位置する問題であることが示されたのである。2014年3月、立派な専門家の意見を代弁するエコノミストは、マンチェスター大学の研究者イアン・プレウィスが、インドの農民の間で「自殺が相次いでいない」ことを実証したと、そのブログ「Feast and Famine」で好意的に引用した22。プレウィスによれば、インドでの自殺率はフランスやスコットランドよりも高くなく、最も被害の大きかった地域の農民は非農民よりもわずかに低い割合で自殺していて、遺伝子組み換え綿の栽培が始まった2002年の後は安定していたのだ。遺伝子組み換え作物の安全性についての業界の主張は別として、この議論を放置しておけば、農家の自殺の問題はなかったことになる。
しかし、社会経済や技術が大きく変化している現場では、物事がそう単純に進むことはない。2014年4月、ケンブリッジ大学とユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの共同研究は、「インドの州間の自殺率の大きなばらつきは、農民や農業従事者の自殺によってほぼ説明できることを示す重要な因果関係を発見した」23。この研究は特に遺伝子組み換え綿を犯人として指摘していないが、最も脆弱な農業人口、1ヘクタール未満の区画で、借金まみれの状況で働き、綿やコーヒーなど世界的に大きな価格変動に対して極めて敏感な換金作物を栽培する州で、自殺者がより多くなっていると指摘していた。
社会学者がインドの農家の苦境の原因とその意味を議論する一方で、遺伝子組み換え作物の評価と管理に関する規制構造の欠陥に対処するために、国の最高裁判所がその任に就いたのである。反GM活動家たちは、厳格で透明性の高い承認プロセスが確立されるまで、新たな圃場での栽培を阻止するよう、Writ(令状)申請という手続きで裁判所に訴えた。2013年8月、裁判所が任命した技術委員会は、安全性に関するいくつかの前提条件が満たされるまで、遺伝子組み換え作物の無期限モラトリアムを勧告した。パネルの報告書では、インドはゴールデンライスやBtブリンジャル(ナス)などの遺伝子組み換え食用作物の導入を正当化するほどの食糧不足には陥っていないと指摘されている。特に米については、輸入国の消費者が望むGM品種と非GM品種の分別表示に関する規定がまだないため、GM品種が生物多様性を脅かし、米輸出国としてのインドの立場を危うくする恐れがあると注意を喚起している。この報告書は遺伝子組み換え反対派を勇気づけたが、専門家の意見の表明に過ぎず、政治とガバナンスの根本的な問題の解決にはほとんど役立たなかった。
信頼の欠如
新世紀に入り、欧米、特にアメリカの農業科学者や産業界と、世界の農家や消費者との信頼関係が大きく崩れ、遺伝子組み換え農業が大きな障害に直面していることが明らかになった。遺伝子組み換えのゴールデン・ライスをめぐる長年の論争は、その典型的な例である。この遺伝子組み換え米の開発プロジェクトは、商業的な動機というより、むしろ人道的な動機で始まった。このプロジェクトは、農業科学者が栄養面だけでなく、薬用植物として開発した最初の試みである。この2つの要素が、モンサント社の製品が巻き起こしたような論争からゴールデン・ライスを守るはずだったのだが、実際には不十分であった。
1990年代初頭、ドイツで教育を受けた2人の著名な植物学者、インゴ・ポトリクスとピーター・バイヤーが共同で、アジアとアフリカで何十万人もの子供たちを苦しめているビタミンA欠乏症を補う米の品種を作ろうとした。重度のビタミンA欠乏症は失明や死亡の原因となるが、幼少期に適切な栄養を摂取することで容易に予防することができる。裕福な国では、この種のビタミン欠乏症はほとんど知られていないが、米を主食とし、野菜をほとんど補わない地域の貧しい子供たちは、その危険性が非常に高いのである。
ポトリクスとバイヤーは、植物遺伝子工学を発展させ、主要な主食作物の栄養価を高め、公衆衛生上の深刻な問題を一挙に改善する絶好の機会を得たと考えた。欧州連合(EU)やロックフェラー財団、さらにはスイスのバイオテクノロジー企業シンジェンタの支援を受けて、科学者たちはビタミンAの前駆体であるベータカロチンを蓄積するようイネを改良することに成功した。この米を食べることは、ビタミンAを錠剤などで摂取するのに代わる有望な方法であると、推進派は考えている。実際、ゴールデンライスプロジェクトの参加者は、国家的な公衆衛生活動の失敗を例に挙げ、信頼性の低い医療制度で問題を解決しようとするよりも、地元の食生活を通じてビタミンAを届ける方が効果的であると指摘している。
しかし、グリーンピースなどの国際的な活動家は、政治的、経済的、環境的な理由でゴールデンライスの導入に猛反対した。グリーンピースのキャンペーンで、遺伝子組み換え作物は地域の生活を脅かすと説得され、怒った農民たちは苗を根こそぎ奪い、フィリピンで行われた実地試験を妨害した。科学者や主要メディアはこの破壊行為を非難したが、答えのない問題を指摘するのは過激派ばかりではない。インド最高裁の遺伝子組み換え作物試験技術委員会は、安全性に関する科学的評価は、ゴールデンライス開発の初期に行われるべき文化的価値や社会経済的影響に関する本格的な議論と同等ではなく、それに代わるものでもないという、より微妙な判断を示している。
結論
植物や動物の遺伝的特性を理解することは、人間と自然の相互作用に革命的な1章を開く可能性があり、増大する世界人口の食糧需要を満たす、より持続可能な方法につながることを否定する人はほとんどいないだろう。しかしながら、農業技術の革新に対する歴史的に優勢なアプローチは、遺伝子組み換え革命によって露呈した様々な問題に対処するには不適切であることが証明された。ここ数十年の間に展開された農業バイオテクノロジーは、生産の独占的支配や知的財産権の主張を通じて、特定の機関や地理的地域への権力の集中について重大な問題を提起している。この問題については、第7章でより詳細に扱う。
技術革新の導入に関する従来の線形モデルは、ハザードを事前に多かれ少なかれ確実に特定でき、その評価に信頼できる方法が存在し、イノベーションの上げ潮がすべての船を持ち上げると想定している。要するに、技術革新はそれ自体が善であると想定され、さらに、科学と経済の現実が相俟って、人々が脅威を感じたり口にすることができないような製品を産業界が開発することはないと想定されているのだ。しかし、遺伝子組み換え農業の出現は、こうした期待の大部分を覆すものであった。遺伝子操作の一見した正確さは、新しい作物や動物の生産と商業化の過程で明らかになった複雑な相互作用の予測には適していなかったのである。生物学は、フラヴル・サヴル・トマトやベルツビル豚のような個々の生物のレベルでも、生態系全体のレベルでも、依然として大きな未知数なのである。度重なる脱走や事故、そして生物学的抵抗力の台頭は、植物遺伝子工学の制御可能性についての推定が、アシロマール会議当時に分子生物学者が予想していたよりも楽観的であったことを示した。今にして思えば、初期の遺伝子組み換え農業は、責任ある技術革新というよりは、行き当たりばったりで、子供じみた自然いじりのようにさえ見える。
さらに深刻なのは、これらの歴史が、新製品を設計し販売する人々と、技術革新の影響を最も受けやすい人々の間の力の極端な不均衡に注意を促している点である。米国の大手バイオテクノロジー企業や大手アグリビジネスを支援する遺伝子組み換えトウモロコシなどの製品は、生物多様性の損失や非標的種への脅威を懸念するヨーロッパの小規模農家や消費者を満足させることができなかった。インドでは、新しい技術システムのコストは、国の農業経済の屋台骨を構成する小規模農家にとって持続不可能に見える。モンサントやシンジェンタといった企業が、インド亜大陸で最大の利益を生み出すのはどの害虫耐性作物と除草剤耐性作物かを決定する際に、彼らのニーズは考慮されなかったのである。ゴールデン・ライスのような「人道的」製品でさえ、こうした作物は実質的にトロイの木馬であり、隠れた企業の利益が最終的にその国の穀物生産システム全体を支配することになるという疑念を静めてはいない。
技術革新が世界の最も貧しく、最も力のない市民に恩恵をもたらすためには、グローバル・ガバナンスの理論と実践にも並行した革新が必要である。遺伝子組み換え作物をめぐる米国とEU加盟国間の長引く論争は、現在のグローバルな貿易体制が、経済的・技術的不平等の重荷を克服することはおろか、革新をめぐる潜在的な価値対立に対処する能力も十分でないことを示唆している。これらの点については、結論の章で再び触れることにする。
第5章 人間いじり
明らかになった暗号
20世紀半ば、生命は科学と社会の中で新たな意味を持つようになった。生物学がこの数世紀で最も大きく変化したのは、象牙の塔と呼ばれるケンブリッジ大学の物理学と生物学の有名な研究センターであるキャベンディッシュ研究所で始まった。当時36歳だった英国の分子生物学者兼生物物理学者フランシス・クリックと、米国からの早熟な後輩で25歳のジェームズ・D・ワトソンは、大西洋の両岸で数十年にわたり聡明な人々を困惑させてきたパズルを解いたのである。彼らは、すべての生物の発生と機能を制御する基本物質であるデオキシリボ核酸(DNA)の構造を解明したのである。DNAは、4つの塩基が固定対で繰り返された二重らせん構造であることを発見したのだ。このブレイクスルー成果は、1953年4月25日、イギリスの科学雑誌『ネイチャー』に2ページにわたって掲載された。60年以上たった今でも、この基本的発見の倫理的、法的、社会的影響は、法律や政策が生物科学やテクノロジーと交わるところ、特に人間の本質や人間の尊厳に関わる問題である場合に、議論されている。
今日、ワトソン・クリックの大発見の概要は、科学文献、ニュースメディア、そして最近ではフィクション、映画、テレビなどで数え切れないほど紹介されている。DNA分子の二重らせんは、最もよく知られた科学的イメージの1つである。このイメージは、私たちの言葉による辞書に「生命」という言葉があるように、私たちのサインやロゴのレパートリーの中で即座に参照され、ブックマークされる場所を占めている。地球という惑星のイメージのように、二重らせんはキャプションなしで理解される。化学者でありノーベル賞受賞者でもあるライナス・ポーリングのような著名な科学者が、ワトソンとクリックが根本的な修正を発表する前に、DNAの三重らせん構造を想像していたことを思い出す人は、今ではほとんどいないだろう。今日では、生命科学の初歩的な知識しかない人でも、DNAが生命と遺伝のモーターとして機能する基本的なメカニズムについて知っている。
DNA分子の3つの特徴は、現代の生物医学とバイオテクノロジーに大きな変化をもたらすことが証明された。第一に、DNAは情報の容器であり、しばしば生命の暗号と呼ばれる。この暗号通貨は、ゲノムという、ある生物に特有の完全な情報設計図であり、その細胞の一つ一つに含まれている。ゲノムの構成要素で最もよく知られ、広く研究されているのは、タンパク質を生成するためのコードを提供する遺伝子と呼ばれるDNAの配列であり、これが特定の生物の構造と機能を規定する。しかし、タンパク質をコードする遺伝子は、ゲノムを構成する塩基対の総数のほんの一部に過ぎない。ゲノムの非コード部分の機能は、まだ科学的研究の未解決のフロンティアのままである。種間の違いは、ゲノム中の特定の遺伝子の有無と重要な関係がある。ある種が他の種に近ければ近いほど、それらの間で共有されている遺伝子の数が多くなるのだ。したがって、チンパンジーとボノボは、ヒトと約99パーセントの遺伝子を共有している。
第二に、DNAの優雅で単純な構造が、複製のためのレシピを提供してくれる。DNA分子はアデニン、チミン、グアニン、シトシン(便宜上A、T、G、Cと略す)という4つの塩基で構成されている。これらの塩基は、A-T、G-Cという、ねじれた二重らせんのはしごのように決まった対で結合している。こうしてできた一本鎖DNAは、同じ配列で再結合することができる。各塩基は、化学的に反対側の塩基に結びつけられ、以前は一本だったところに、同じらせん構造を二本作り出すのである。このように、一本鎖はそれ自体を正確に再現する。この事実について、ワトソンとクリックは非常に控えめな表現で言及している。「私たちが仮定した特定の組み合わせが、直ちに遺伝物質の複製機構の可能性を示唆していることは、私たちの注意を逃してはならない」1。
第三に、人間の重要な物理的特性や性質は、遺伝暗号の観点で表現されると、より明確になる。遺伝暗号通貨は、事実上、人間のアイデンティティや人間性のある側面を表現するための別の言語を提供しているのである。例えば、ある人はハンチントン病の遺伝子を持っているのか、乳がんや早発性アルツハイマーのリスクが高い遺伝子を持っているのか、といった具合だ。また、DNAを知ることで、身体をより操作しやすくなる。DNAの構造は極めて単純であるため、ある種の検査や再構築が可能なのだ。DNAの鎖全体が持つ自己複製能力や情報伝達機能を損なうことなく、様々なソースからDNAの断片を切り貼りすることが原理的には可能なのだ。挿入されたDNAがそれ自身のコーディング特性を持つ遺伝子である場合、その特性は単に再設計された宿主DNAに移される。例えば、ヒトの遺伝子の一部を組み込んだバクテリアのDNAは、バクテリア自身の天然タンパク質とともに、組み込まれた遺伝子の指示通りにヒトのタンパク質を産生する。原理的には、ヒトのDNAもこのように改変して新しい形質を作り出すことができる。もし、精子や卵子の細胞で改造が行われた場合、挿入されたDNAとそれがコードする形質は、操作された細胞から生じる後続の世代に受け継がれることになる。これは生殖細胞への遺伝子操作と呼ばれ、生物医学の研究が盛んな世界のほとんどの地域では、現在、人間への遺伝子操作は禁止されている2。
どんなにブレイクスルー科学的発見も、アイデアだけでは実用化されない。2 どんなにブレイクスルー科学的発見であっても、アイデアだけでは応用には至らない。応用を実現するためには、新しい技術や技能、資材、資本、組織的支援など、さらに多くのインプットが必要である。1970年代初頭、スタンフォード大学では、DNAとは何か、DNAはどのように機能するかという知識を製品に応用するための大きなブレークスルーがもたらされた。遺伝子スプライシング」として知られるこの技術は、DNA配列(通常は遺伝子)を供給元の生物から取り出し、宿主の生物に移植するものである。宿主の内部で、外来DNAは生物自身のものとともに複製される。スタンフォード大学のスタンレー・コーエンとポール・バーグ、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のハーバート・ボイヤーが開発した遺伝子スプライシングの技術により、科学者はDNAを種間で移動させ、自然界には存在し得ない生物、例えば、人間のインシュリンを作り出すバクテリア、暗闇で光る蓄光クラゲの遺伝子を持つ植物などを作り出すことができるようになったのだ。スタンフォード大学は1974年に、コーエンとボイヤーを発明者としてrDNA技術の特許を申請した。この間、rDNA分子の利用は製薬業界や農業界に浸透し、両業界に革命をもたらした。
ヒトの生物学を操作することは、第4章で見た植物に関わる問題よりもさらに複雑な倫理、法律、政策の問題を提起する。生物医学において最も恐れられているのは、人間の尊厳が侵害され、人間であることの根本的な意味が損なわれてしまうことである。遺伝子コードという新しい方法で人間の体を知ることは、自由、平等、プライバシーといった大切な権利に前例のない侵害をもたらす可能性がある。医学の第一の使命は、病気の人を完治させ、リスクのある人を健康に保つことだが、遺伝子治療による欠陥の治療と遺伝子強化による超人的能力の付与の境界線は曖昧で、論争の的になっている。生殖医療は、不妊症の人々の妊娠を助け、多くの人々の生涯の夢をかなえる。しかし、それは同時に家族関係の意味を弱め、親としての責任を希薄にする道を開く。20世紀後半に生命倫理学が学問として発展したことは、こうした懸念の深刻さを物語っている。しかし、民主主義社会が倫理学の専門家にどれだけの権限を委ねるべきかという根本的な問題を含め、多くの問題が論議され、未解決のまま残されているのである。
透明な身体
どのような革命でもそうであるように、ポストゲノム生物医学の偉大な約束は、その跡に影を残している。この場合、心配の中心は、純粋に短期的な利益利益によって引き起こされる不注意で無責任な産業界の行動だけではなく、制御不能な科学という想像や、人間という概念そのものを脅かしかねないテクノロジーと政府や企業の権力との間の同盟関係にも向けられている。自然をいじくり回す好奇心と喜びが、科学者を社会から忌み嫌われる実験場へと誘い、そのような行き過ぎを防ぐために新しい制度が必要なのだろうか。遺伝子の知識が増えれば、個人と組織の間にすでにある厄介な不均衡を悪化させることになるのだろうか。自由とプライバシーの権利を脅かすことになるのだろうか?限界集落にさらに汚名を着せることになるのか、それとも彼らがより自律的に行動できるようになるための資源を与えることになるのか?これらの疑問に対する新たな答えを評価するために、私たちはまず、遺伝学とバイオテクノロジーが人体をより読み取りやすくし、潜在的には技術的介入をより受け入れやすくした装置を見なければならない。
遺伝暗号という4文字のアルファベットは、生物医学に、遺伝性疾患の正確な原因を突き止めるための強力なツールを提供している。遺伝子は、種間だけでなく、同じ種の個体間の変異を説明するのに役立つ方法で、情報をコード化し、伝達する。例えば、人間の目の色や肌の色、あるいはグレゴール・メンデルがチェコの都市ブルノにある自宅の庭で観察したエンドウ豆のしわや丸い種の形などである。このような変異株は「対立遺伝子」と呼ばれる。多くの遺伝病は、情報伝達の不具合を引き起こす対立遺伝子と関連している。これらの欠陥は、身体の成長や健康に不可欠なタンパク質を生成したり、癌やその他の病気の発症に対抗する能力を損なう。例えば、アシュケナージ・ユダヤ系の女性で、いわゆるBRCA1およびBRCA2遺伝子の有害なバージョンを受け継いだ人は、乳がんや卵巣がんにかかるリスクが著しく高くなる。このような情報伝達の誤りを発見し、可能であれば修正することが、遺伝医学の中心的な目標である。
遺伝的変異の研究は、ヒトのDNAを構成する塩基対の全塩基配列を明らかにする国際的な取り組みである「ヒトゲノム計画」の完了により、勢いを増した。米国では、国立衛生研究所(NIH)とエネルギー省が連邦レベルで資金を提供し、ジェームズ・ワトソンがNIHプログラムの初代ディレクターを務めた。1990年に正式に発足したこのプロジェクトは、当初15年かかると言われていた完成時期を大幅に早め 2000年に配列のドラフトを完成させた。しかし、当初は公的な「ビッグサイエンス」であったこのプロジェクトは、予想に反して民間企業との競争に発展してしまった。NIHの職員であったJ.クレイグ・ベンターは、政府とは異なる技術的アプローチを用いることで、より早く、より安く遺伝子配列を決定できることを証明するために、脱サラして自身の会社「セレラ・コーポレーション」を設立した※。さらに最近では、バイオバンクと呼ばれる大規模な遺伝資源の収集により、遺伝的変異の研究が個人や家族の規模から、特定の遺伝的特徴を持つ集団や、より広い民族的・人種的所属を持つ集団へと拡大されている。
検査とプライバシー
遺伝医学が最初に開けた扉は診断だった。特定の遺伝子が特定の病気や病気に対する素因と関連していることを知ることで、人々はより早く、より多くの情報に基づいた医療上の選択をすることができるようになる。乳癌の変異遺伝子を持つ女性は、癌のリスクを減らすために予防的な乳房切除を受けるべきだろうか?特に、母親や姉妹を病気で亡くした経験のある女性は、不安から解放されるために、このような思い切った手段を選ぶかもしれない。女優で世界的に有名なアンジェリーナ・ジョリーは、BRCA1遺伝子の保有者として、乳がんの発症リスクが87%、卵巣がんの発症リスクが50%であることが分かった2013年に、二重乳房切除術を選択し、大きな話題となった5。
BRCA遺伝子の変異がもたらす結果は比較的よく理解されているが、すべての遺伝子の知識がこれほど明確なものであるわけでもない。遺伝子検査の結果は、たとえ責任を持って入手し、伝達されたとしても、その解釈は非常に難しい。遺伝子検査によって、ハンチントン病やアルツハイマー病など、現代の生物医学ではまだ治療法のない病気のマーカーが見つかった場合、患者は絶望したり、賢明でない選択をしたりすることがある。このような素因を持つ人は、知ることによって汚名を着せられたり、希望を失うだけだと考え、無知を好むことがある。実際、変化や緩和が望めない症状前の状態を知らない権利があると主張する人々もいる。さらに、アフリカ系アメリカ人の鎌状赤血球貧血のように、特定の人種が不当に苦しめられる病気もあるため、遺伝子の知識が潜在的な人種差別を悪化させるのではないかという懸念が、遺伝医学の初期段階からつきまとっていたのである6。
遺伝子診断に関連して生じる倫理的な問題は、伝統的に医師と患者の関係の枠組みの中で扱われてきた。この関係では、患者の幸福に配慮する義務が医師と医療機関に委ねられている。現在、先進国の病院では、診断を受けた患者が結果を適切に解釈し、治療の選択肢を十分に理解できるように、遺伝カウンセリングサービスを日常的に行っている。検査結果はせいぜい害のある確率を伝えるものであり、絶対確実なものはほとんどないため、カウンセリングは、患者がリスクを回避しすぎず、自己満足に陥らないような決断ができるようにすることを目的としている。
しかし、遺伝子検査費用の急激な低下により、患者の遺伝子情報の管理は医療制度から通常の商業活動に移行している。2007年頃から、民間企業がDTC(Direct to Consumer)検査に市場の可能性を見いだし、資本参加するようになった。23andMeやdeCODEといった企業は、唾液のサンプルを消費者に送り、遺伝や特定の遺伝病に対する脆弱性についての情報を受け取る機会を提供し始めたのである。DTC検査は、その信頼性、健康上のメリット、法的地位について多くの不確実性を残したまま、今後数年間で大幅に成長することが期待されている。消費者にとっての懸念は、検査の正確性や臨床的妥当性、企業が保有する情報のプライバシー、DTC企業が倒産したり売却された場合の情報の行方などに関する疑問である。2013年、食品医薬品局(FDA)は遅ればせながら、DTCテストを事前承認が必要な医療機器とみなすと宣言し、規制監督を強化する動きを見せた。その数カ月後、FDAは23andMe社に対し、承認が得られるまで検査の販売を停止するよう命じた。
プライバシーに関する懸念は、DTC検査の文脈に限られたものではない。遺伝子検査が始まった当初から、人々は自分の遺伝情報が悪人の手に渡り、雇用主や有力な立場の人が自分を差別することを恐れていた。将来の従業員が、高額な医療費がかかる可能性のある病気のリスクが高いことを知れば、保険を拒否されたり、職を失ったりする可能性があるからだ。しかし、遺伝子のプライバシーが市民の自由だけの問題であり続ける限り、議員たちはこの問題になかなか踏み切れないようであった。しかし、ヒトゲノム・プロジェクトの終了に伴い、状況は一変した。個人の遺伝的プロファイルに基づいた治療法である精密医療に明るい展望が開けたことで、プライバシー保護の強化が遺伝子検査の普及を促し、臨床・製薬研究において有益な進歩をもたらすと、米国の立法者たちを説得したのである。要するに、十分な保護措置なしに検査を受けることを嫌がる人への誘因として、プライバシーに対する市場の要求が高まっていたのである。2008年のGenetic Information Nondiscrimination Act(GINA)7は、雇用主や保険会社による遺伝情報の悪用に対して連邦政府の保護を与えるものだが、この法律は生命保険、障害保険、長期介護保険を除外しており、高齢化社会にとっては重大な除外事項である。GINAも同様に、DTC検査会社がそのサービスを自発的に利用する人々から得た情報を保護しない。
データとしての母集団
身体的形質を「情報」という抽象的な言葉に変換することがガバナンスの問題を引き起こすとすれば、遺伝情報がデータ革命と絡み合うにつれて、さらなる難問が待ち受けている。バイオバンク、すなわち生物学的サンプルとそれに含まれる情報の大規模な収集は、社会がまだ明確な答えを持っていない多くの新しい問題を提起している。人体組織のバンクという概念は、遺伝子の時代よりもずっと前からあった。例えば、血液や精子は、いわゆるバンクに集められ、輸血や男性不妊治療が必要な人が必要な時に利用できるように保管されていた。遺伝子のバイオバンクは、多かれ少なかれ永続的な情報の保管庫であり、また腐敗する可能性のある物理的な物質の保管庫であるという点で、これらの前身とは異なっている。バイオバンクが保有する情報の商業的価値は、その情報が個々のドナーや受益者とは無関係に診断や用途のために採掘されうるという事実に大きく由来している。
現代のバイオバンクは、所有権、同意、プライバシーの問題を提起しているが、これは以前の時代の血液や精子のバンクの管理には関係のない問題である。遺伝子のバイオバンクを構築する最初の試みの1つがアイスランドで行われたが、この計画は構想通りには進まず、その失敗は今でも示唆に富んでいる8。まず、アイスランドは人口が少なく、比較的自己完結していること(提案当時は30万人弱)、系図記録を維持する長い伝統があることである。そのため、家系的な特徴や集団的な変異を比較的容易に特定することができる。さらに、医療システムの整った国では、家系データを個人の健康記録と並列させることも可能である。アイスランドには、国民全員から遺伝データを収集できるインフラも整っており、提案されている国家健康部門データベース(HSD)の第3の重要な要素となる。
科学者と起業家のカリスマ、Kári Stefánssonが率いるバイオ製薬会社deCODE Geneticsが主導し、HSDは官民パートナーシップとして構想され、アイスランド議会の過半数から熱烈な支持を得た。1996年に制定された「医療分野データベース法」に基づき、公共部門がデータを提供し、民間部門(事実上deCODE)は、情報を多発性硬化症などの病気に対する救命薬に変換するノウハウを提供することになっていた。国民のほぼ全員が登録されることが、データベースの成功の鍵となるため、設計者はオプトアウト方式を選択した。最初の登録時に明確にオプトアウトを選択しない限り、「推定同意」の原則の下、国民の医療情報と家系情報が含まれることになる。
アイスランド国民の約1割はすぐに不参加を表明したが、不参加表明だけでは飽き足らず、このプロジェクトを阻止するために法的措置を取る者もいた。原告側は、無自覚な被験者として登録されたこと、登録後に辞退するための規定がないことに異議を唱えている。一方、広く使われている倫理指針では、臨床試験に登録された患者は自由に辞退できることになっている。訴訟参加者は、同意するはずのない死亡者の記録が含まれ、その情報が同じ遺伝子を持つ家族のプライバシーを損なうことは必至であり、たとえその家族自身がデータベースから離脱したとしても、特に不快感を表明した。さらに原告は、deCODEが12年間唯一のライセンシーとして、国全体の医療記録と遺伝子記録を独占的に管理していることも問題視した。2003年、アイスランド最高裁はHSD法を破棄した。その条項は完全に実施されることはなかったが、deCODEは遺伝的変異に関する研究を続け、統合失調症や心血管疾患の遺伝的原因に関する重要な出版物を作成した。
このような挫折にもかかわらず、バイオバンクは他の国でも普及し続け、同時に継続的な倫理的課題も提起している。そのような取り組みの中で最大かつ最も野心的なものの1つであるUKバイオバンクは 2006年に英国政府と生物医学研究に対する民間最大の助成機関であるウエルカム財団との官民パートナーシップによって開始された。批評家たちは、重大な病気を診断するための主要な手段として遺伝子情報が過度に誇張されることを懸念した。この懸念は、ヒトゲノムの解読以前に考えられていたほどには、遺伝子だけでは健康状態の転帰を決定できないかもしれないという知識が広まったことも一因となっている。また、参加者に求められる同意の範囲や、最終的にバイオバンクが商業研究者や場合によっては法執行機関に開放されることについても疑問が生じた。しかし 2009年までにUKバイオバンクは40歳から69歳までの50万人の被験者を登録することに成功し、英国はバイオバンクの数と規模において世界のトップレベルにあることが確認された。
米国では、遺伝情報の収集を一元化する資源と誘因を持つ国家医療制度が存在しないため、これまでのところ、よりローカルな取り組みにとどまっている。しかし、このようなデータ収集は、世界有数の生物医学研究コミュニティーの中で強力な支持を得ている。2009年、バラク・オバマ大統領の保健政策顧問を務めた著名な医学者・生命倫理学者エゼキエル・エマニュエルは、市民には臨床研究に参加する積極的義務があると主張する論文を共著で発表した9。このような公共財の理論に基づけば、ある国の国民全員が、国のバイオバンクに遺伝情報を提供することを義務付けることは、比較的容易なことであろう。
エマニュエルの構想は、今のところ想像の域を出ない。国家が管理する生物学的市民を描いたオルダス・ハクスリーのディストピック小説『ブレイブ・ニュー・ワールド』に、あまりにも近いと感じる人もいるかもしれない。しかし、民間や非営利団体によって作られ管理されるバイオバンクの急増は、すでに所有と管理に関する厄介な問題を提起している。生命は誰のものなのか?また、所有権の概念が、生物から抽出された情報と同様に、生物からの物理的物質に及ぶ場合、正確にはどのような権利を伴うのだろうか。これらの疑問は、ハイテク時代の知的財産権についてより一般的に扱った第7章でより詳細に述べられている。
生殖補助医療
コーエンやボイヤーといった分子生物学者がDNAの構造をいじり、現代のバイオテクノロジー産業の基礎を築いていた頃、イギリスの科学者2人は、生命にとって最も基本的で親密なプロセスの一つである人間の生殖について実験を行っていた。ケンブリッジ大学の発生生物学者ロバート・エドワーズは、マンチェスターのロイヤル・オールダム病院の婦人科医パトリック・ステップトーと共同で、現在体外受精(IVF)として知られている人間の不妊症を治療する新しい技術を開発したのである。このブレイクスルー研究は、人間の自然な生殖サイクルの始まりである受胎を、女性の子宮の中から実験室のガラス瓶という人工的な場所に移し、事実上、その場を提供するものであった。1978年4月25日、体外受精で生まれたルイーズ・ブラウンさんは、たちまち世界初の「試験管ベビー」と呼ばれるようになった。
ルイーズの誕生は、多くの人にとって、子供を持てない夫婦に生物学的な親になることを約束する奇跡であった。実際、30年後、技術的な支援によって生まれた赤ちゃんの数は、全世界で500万人に達したと推定されている。少なくとも、体外受精という高額な治療費を支払う覚悟のある人たちの間では、世界的な需要があることは明らかである。しかし、初期の段階から、思慮深い観察者たちは、人体の最も自然な機能の1つを操作や実験の領域に持ち込むことの意味を広く考えていた。親であること、子供であることの意味をどのように変えるのだろうか?産児制限」とは、望まない子供を生まないようにするだけでなく、出産適齢期の夫婦による異性婚など、社会が当然と考える範囲でのみ子供を持つことを意味する社会では、子供を持たないことが汚点になるのだろうか。受胎、妊娠、出産を人間がコントロールできるプロセスに変えるという滑りやすい坂道には、どんな落とし穴があるのだろうか。
体外受精が初めて成功した直後、その直接的な結果としてではないが、ある種の実験が行われた。それは、代理母出産(サロゲート・マザー)である。代理母出産とは、他のカップルのために子供を産むという明確な目的のために、同意した第三者を交際させることである。1986年に米国で起きた「Baby M」事件で、この慣習は広く知られるようになった。この事件は、論争の中心となった赤ちゃんのメリッサにちなんで名づけられた。メアリー・ベス・ホワイトヘッドはニュージャージー州に住む既婚の二児の母親で、ウィリアムとエリザベス・スターンのために子供を妊娠し、身ごもることに同意した。スターン夫妻は高学歴の専門家であり、エリザベスの多発性硬化症によって無事に子供を産むことができないのではないかと心配し、この取り決めをしたのである。しかし、ホワイトヘッドは、子供が生まれても手放せないと感じ、ニュージャージー州最高裁判所までもつれ込んだ苦しい法廷闘争の舞台となった。裁判所は、代理出産契約はニュージャージー州の法律では無効であるとしながらも、それが子どもの最善の利益につながるとして、親権をスターン夫妻に認めるという初めての判決を下した。ホワイトヘッドは実の母親として面会権を保持したが、2人の関係は次第に遠ざかることになった。18歳になったメリッサは、エリザベスの養子となることを選択し、ホワイトヘッドとの関係を法的に断ち切った。
代理出産と体外受精によって、閉経後の母親、ゲイやレズビアンの親、外国人女性など、これまで考えられなかった親子関係が可能になり、「ベビーM」が提起した倫理的な問題はさらに大きくなった。体外受精の導入から20年後、人間以外の哺乳類の生殖に関する技術開発が行われ、人間の生命操作の倫理的限界について、さらなる難問を投げかけた。エジンバラのロズリン研究所は、動物の健康と福祉、そしてその研究が人間の健康に及ぼす影響について研究する、英国を代表する研究所である。ドリーは、通常の哺乳類とは異なり、母親の遺伝子を正確に再現したクローンである。植物育種家たちは、何世紀にもわたり、遺伝子の同一性を保つ挿し木から、非常に望ましい形質を持つ品種を繁殖させてきた。しかし、哺乳類の有性生殖は、母親の卵子と父親の精子の遺伝子を組み合わせて、片親ともう片方の親から半分ずつ遺伝子を受け継いだ子供を産むものである。「競走馬の特徴を再現したい」「赤身の多い牛や豚の特徴を再現したい」「愛玩動物の特徴を再現したい」と思っても、従来の畜産では不可能であった。しかし、ロズリン大学のイアン・ウィルマット教授率いる科学者チームが、成羊の細胞から生まれたばかりの子羊のクローンを作り、母羊のゲノムをそのまま子羊に移植することに成功し、この障壁は取り除かれたのである。
動物でもヒトでも、クローンを作るプロセスは、今ではすっかり定着した体外受精の技術を基礎にしているが、新たな工夫が加えられている。まず、動物の体から、その動物の全遺伝コードを含む細胞の核を取り出し、同じ種の別の動物の卵の中に入れる。そして、その卵子を新しい母親の子宮に移植し、出産させると、妊娠した母親の遺伝子の子孫ではなく、卵子の核を取り出した元の成体の若い複製として生まれる。しかし、その一方で、この技術が農家の人たちに与える影響も大きいのである。羊のような哺乳類にクローンを作ることができるのなら、人間にもできるかもしれない。かつてはSFの世界でしか考えられなかったシナリオ、特にオルダス・ハクスリーの小説にあるような、段階的に工業的に生産された人間というものが、今や十分に可能な範囲にあると思われたのである。
生殖生物学におけるこの障壁を破ることへの懸念は、政治的に最も重要なレベルまで高まった。10 クリントン大統領は、倫理諮問委員会にヒトのクローン作製の意味合いを分析するよう要請し、その後、バラク・オバマ大統領らによってクローン人間の禁止が支持され、ほとんどの先進工業国でそのまま維持されている。しかし、関連性の高い他の技術については、胚から胎児、そして最終的には家族や国家の一員となる人間の扱いについて、大きな意見の相違があることが明らかになった。
その一つが、「三親等胚」の作製である。この技術は、母親の卵細胞からミトコンドリアDNA(核の外に留まるDNA)によって伝えられる遺伝病を持たない健康な胚を作ることを目的としている。そのため、母親の卵子から核を取り出し、核を取り除いた別の女性の提供卵細胞の中に入れる。2つの卵子が融合してできた胚と未来の子供は、母親のゲノムを含んでいるが、細胞の残りの部分からミトコンドリア病が遺伝する危険はない。この技術は、幅広い市民協議の後、2015年2月に英国議会で使用が承認されたが、米国では依然として議論の的であり、ドイツでは禁止されている。
もう一つの活発な議論は、生物医学的に先進的な民主主義国の多くで生殖細胞遺伝子編集に対する明示的または暗黙の禁止事項が撤回される可能性に関わるものである。CRISPR(clustered, regularly interspaced, short palindromic repeat)技術は、遺伝子を正確かつ迅速に改変し、病気の部分を取り除き、健康な対立遺伝子に置き換える技術である。もし、ヒトの体外受精胚の病気の修復に使われれば、その結果生じた変化した形質は、どの子もその子孫に引き継がれることになり、欧州評議会の「人権と生物医学に関する条約」などの法的拘束力のある文書で禁止されていることに違反することになる。このように魅力的で広く応用可能な技術の使用に制限を設けるには、どのような機関、どのような形式の審議が最も適しているのだろうか。この問いは、正しいガバナンスのあり方や、専門家による予測の適切な領域について、新たな思考を求めるものである。今日まで、この議論は、法律、宗教、倫理よりも、グローバルサイエンスのエリートたちによって導かれてきた。11 未来の遺伝的遺産を議論しているグローバル市民は、形を持たず、代表されず、話すこともできないままである。
デザインされ、選択された生命
rDNAの発見と同様に、体外受精とクローン技術は、ある夫婦の不妊治療や、特に有望な家畜の繁殖よりもはるかに広い社会的意味を持つ発見や発明の連鎖への道を開くものであった。研究所やクリニックは、かつて親になろうとする者たちが自分たちの領域とみなしていた人間の生殖サイクルの一面に介入する立場になったのである。母体から切り離された胚は、それ自体、不確かな地位にある物体であり、潜在的な人間として大きな道徳的意味を持つが、思考や感情の能力を持たず、技術的支援なしには生存し得ない。研究者はこうした存在の研究にどこまで踏み込むべきなのか、とりわけその研究が人間の胚を破壊することになる場合、どうすればよいのか。体外受精の利用者は、どのような原則と限界のもとに選択を行うべきなのだろうか。移植されていない胚をどうすべきかは、誰が決めるのだろうか?表向きは同じ基本的価値観を共有する先進工業国間で、問題の変遷、答えやアプローチの流動性を説明するのに役立つのが、3つの対立領域である。それらは、ヒト胚性幹細胞を用いた研究、デザイナーズチルドレン、そして適切な親としてのあり方に関する問題である。
ヒト胚性幹細胞
体外受精は、安全な妊娠と健康な出産の可能性を最大限に高めるために、母親の子宮に移植されるべき、あるいは移植できるよりも多くの胚を生産するプロセスとして、医療現場で標準化されている。残りの「予備」胚は、妊娠を希望する他の不妊カップルのため、あるいは以前は治らなかった病気の治療に使用できるヒト胚性幹細胞(hESC)の誘導のため、他の目的で使用することができる。
生殖周期から切り離された生物としてのヒト胚が突然利用可能になったことで、生物医学研究に全く新しいフロンティアが開かれたのである。幹細胞は、ゲノムにその性質がコード化された成熟した生物に至る複雑な分化プロセスを開始する前に、生物から採取した初期段階の細胞である。特に、胚盤胞(8細胞)の状態のヒト胚から採取した細胞は、まだ血液や脳、皮膚、骨になるように特殊化されていない。つまり、移植される状況に応じて、どんな形にもなることができる「多能性」なのだ。生物医学の分野では、この適応性の高い細胞を使って、パーキンソン病、アルツハイマー病、白血病、乳児糖尿病など、体内で健康な新しい細胞を作り出すことができないために起こるさまざまな病気を治すことができるかもしれないという希望が生まれつつある。1990年代初頭、ウィスコンシン大学のジェームズ・トムソン教授が初めてヒト幹細胞を分離したとき、この希望は現実に大きく近づいた。それ以来、幹細胞研究のためのセンターが米国をはじめ多くの先進工業国に誕生したが、ほとんどの場合、ある程度のスキャンダルと論争を伴っている。
ヒト胚性幹細胞研究における倫理的な問題の核心は、hESCの元となる胚の状態、胚が作られた生殖細胞の持ち主の同意、そして大多数の人々が道徳的な理由から好ましくないと考える研究や治療のために幹細胞が悪用される可能性に関わるものである。これらの問題を解決するためのアプローチは国によって大きく異なり、倫理団体や法律家による解決策も様々である。これらの相違は、胚を研究対象として使用することのリスクに対する理解や、研究や技術開発の方向性を選択する際に社会が科学に認める自律性の度合いが大きく異なることを反映している。
幹細胞は通常、治療上有効な細胞が抽出された胚を破壊する。胚をすでに人間の生命の一形態と見なす人々にとって、このプロセスは殺人に等しい。ジョージ・W・ブッシュ元大統領がよく使う表現で言えば、「生命を救うために生命を破壊する」ということになる。米国、英国、ドイツにおける3つの全く異なる政策対応は、西欧の立憲民主主義国家でさえ、この問題に関して大きな隔たりがあることを物語っている。米国の裁判所と議会は、人間の生命がいつ始まるかという問題に関して、全国的に適用できる確固とした立場をとっていない。研究政策を立案し、実施するための米国の制度的メカニズムは高度に分権化されており、単一の立法命令によって支配されているわけでもない。しかし、熾烈で長期にわたる妊娠中絶の議論から派生した、ディッキー・ウィッカー修正案として知られる連邦法は、研究のための胚の作成と、人間の胚を破壊または廃棄する研究に対する連邦政府の資金提供を禁止していることは、あまり知られていない。この修正案は1996年にNIHの予算法案に添付され、それ以来毎年更新されている。その結果、米国では、民間または連邦政府以外からの資金提供によってのみ、研究のためのヒトES細胞作製が可能になった。長年に渡る紆余曲折を経て、NIHは連邦法に従って開発された承認済みの幹細胞株に関する研究に継続的に資金を提供していた。NIHの資金は、研究プロトコルを審査し、該当する州や国のガイドラインに従って承認する適切なESCRO(Embryonic Stem Cell Research Oversight)組織を維持する機関のみが使用することができる。
一方、英国は、生後14日以前の胚は、その切断点以降の状態とは異なる道徳的地位を有するという立場を正式に採用した。英国の政策では、初期の胚は、人間の生命を保護することに懸念を抱かせるような特性を持っていないとしている。しかし、14日を過ぎると、胚は原始的な神経系を発達させ始め、明らかに人間ではない物体としてみなされなくなる。その時点から、少なくとも前人間である。この「14日ルール」は、オックスフォード大学の道徳哲学者メアリー・ウォーノックが委員長を務めた(そしてその名を冠した)生命倫理団体による、これまでで最も重要な決定かもしれない12。ウォーノック委員会は、胚に関わるすべての活動を監督する義務を持つ新しい団体をイギリスに設立するよう勧告した。1990年に制定されたヒト受精・胚培養局(HFEA)は、四半世紀の間、すべての体外受精クリニックを認可し、すべての胚研究申請を審査し、定期的に市民と協議して、論争の的になっているヒト生殖研究の最前線をどう進めるかについてコンセンサスを形成している。
ドイツもまた、人間の生命の始まりを生物学的に定義しているが、その定義はイギリスとは著しく異なっており、第二次世界大戦後のドイツ国家を支える基本法における正確さの要求を満たすものである。基本法第1条第1項は、ホロコーストに対するドイツの憲法上の対応であり、人間の尊厳は不可侵であり、国家にはそれを保護する義務があると断定的に述べている。人間の尊厳は不可侵であり、国家はそれを守る義務がある。この大命題を達成するために、ドイツの法律家や裁判所は、人間の生命は卵子の核と精子の核が融合した瞬間に始まる、つまり遺伝的に異なる存在が生まれると決めたのである。したがって、ヒト胚から幹細胞を得ることは、潜在的な人間の生命を破壊することになり、法律で禁止されている。しかし、hESCの輸入は別問題として扱われる。ドイツの研究者は、外国で作られた輸入されたhESCを使うことができる。なぜなら、そうすればドイツの科学から、その細胞が由来する胚を破壊したという汚点が取り除かれるからだ。ただし、ドイツの法律では、国境を越えた胚の破壊を固く禁じている。一方、米国の法律では、胚の死を支援した連邦政府の責任は免除されるが、州や民間がそうした研究に資金を提供し続けることは認められているのだ。それぞれの国の倫理的解決は、科学、宗教、公衆衛生という相反する要求のバランスを取るための正しい方法についての、独特の国民的期待を反映している。
デザイナーベビー
体外受精とクローン技術、そして遺伝子検査は、不妊症の夫婦にも赤ちゃんを授かる可能性を開くだけでなく、どのような赤ちゃんを授かるかを制限の範囲内で選択することも可能にしたのである。通常の体外受精では、生殖のために移植される胚の数よりも多くの胚が作られる。そのため、最終的に妊娠する赤ちゃんが両親のニーズや希望に沿うように、ある程度意識的に選択することができる。親にとって最も重要なのは、通常の妊娠では感染する可能性のある遺伝性疾患や障害を持たない子供を望むことである。現在では、胎児がダウン症やテイ・サックス病のような重い先天性異常の遺伝子を持っているかどうかを判断するために、胎児細胞を一連の検査にかけることが日常的に行われている。異常のある胎児を中絶し、次に妊娠するときに病気のない赤ちゃんを望むこともできるが、これは両親にとってストレスや心痛を伴うだけでなく、母親になる人にとってもリスクが伴う。体外受精と同時に行われる着床前遺伝子診断(PGD)は、このトラウマや危険を伴う中絶を回避するための技術である。PGDは、体外受精卵が移植される前に遺伝子異常をスクリーニングすることを可能にし、両親は最終的に健康な赤ちゃんを持つことができるとより確信を持って妊娠に踏み切ることができるようにする。
胚を選択する機会は、多くの選択肢とジレンマを生み出す。胚は原則的に、人間の多様性に関わるが病気とは無関係な特徴を持つかどうかを選別することができる。最も悪名高い例は、出生前または着床前スクリーニングを利用して、親が子供の性別をあらかじめ選択できるようにすることである。男女のバランスのとれた家族を実現するために性別を選択することを支持する人は多いが、男児に対する根強い文化的選好があるため、インドのように胎児の性別選択が法律で禁止されている場合でも、出生児が女性に対して男性の割合が集団全体で過剰になっているという困った事態を招いている社会がある。技術がさらに進歩すれば、体外受精卵に望ましい形質を持たせることができるようになるかもしれない。しかし、共感してくれる生物倫理学者や熟練した臨床医の助けを借りて、親ができることの例はすでに目前に迫っている。
PGDは、胎児自身の遺伝子異常を調べるだけでなく、生きるために健康なドナーからの移植を必要とする現存する子供の組織と適合するかどうかを判断するために用いることができる。例えば、ジョディ・ピコールのベストセラー小説『My Sister’s Keeper』やカズオ・イシグロの『Never Let Me Go』では、こうした「救世主兄弟」の選別の倫理が大衆文化に波及している13。ピコールは、急性白血病の姉とその血液、骨髄、ひいては腎臓ドナーとなるべく妊娠したもうひとりの姉との関係を描いている。ピコールは、急性白血病の姉妹と、彼女の血液・骨髄・腎臓の提供者となる姉妹の関係を描き、石黒は、英国の寄宿学校小説とSFを融合させ、「普通の人」のために臓器提供者として生き、死んでいく子供たちの物語を描いている。両作品とも、人が主に他人の医療ニーズに応えるために存在するようになるかもしれない未来に対する、まだ解決されていない痛みを伴う不安感を表現している。
幸いなことに、現実の社会はフィクションよりもゆっくりとしたペースで動いており、石黒が想像したようなドナー・クラスが実現することはないかもしれない。しかし、個々のケースはすでに生まれている。2010年、イギリスでは、難病の治療法として初めて、兄弟の組織を使った治療が成功したと報告された。ミーガン・マシューズさんは、毎週輸血を受けなければならない珍しい血液の病気を持って生まれたが、生まれたばかりの弟のマックスさんの骨髄移植で治ったのである。マシューズ家の両親は、体外受精とPGDによってマックスを妊娠させ、移植された胚が病気でなく、病気の娘によく合う組織であることを確認したのである。この医学的サクセス・ストーリーに先立つ数年にわたる法的論争は、助け合う愛情に満ちた家庭を築いていると信じる両親と、英国のプロライフ活動家ジョセフィン・クインタヴァレのように、他人の治療目的のために子供を作ることに根本的に反対する人々との間に、埋めがたい溝があることを露呈させた。
再構成された家族
Mちゃん事件は、3人家族の可能性を世間に示した。これは、不妊症の男性がドナー精子による人工授精で長年享受してきたのと同じように、女性も不妊治療を受けられるようになったという見方もあった。しかし、代理出産と体外受精の組み合わせが、数十年のうちに可能な家族の形を再定義し、代理出産の法的・倫理的影響が、新しい世紀を迎えても衰えることなく響き続けることを予想した人はほとんどいなかっただろう。
生殖補助医療をめぐる論争の多くは、両親の異性愛、年齢、夫婦関係といった伝統的な家族の概念に社会がどの程度コミットしているかという点に集中している。また、これらの問題を法律で規制すべきか、それとも顧客とクリニックの間の個人的な取り決めに任せるべきかという点でも、意見の相違が続いている。下の表は、この2つの変数の組み合わせの違いによって、社会が許容する「普通」の範囲内の家族のあり方が大きく異なることを示している。
表2:
【原文参照】
欧米諸国の中で、米国は新しい生殖技術の規制について最も寛容で分散化されている。生殖技術の使用に関する連邦法は国レベルでは存在せず、州の監督も緩いことが多い。そのため、予想通り、米国は世界有数の生殖実験の場となっている。妊娠代理出産14(生物学的に無関係な子供を妊娠させる方法)の最初の事例や、体外受精による八つ子の最初の出産、50歳以上の女性の出産が多数記録されている。
規制が緩いと、複数の親子関係の実験を助長するだけでなく、ベビーMのように契約から離脱した場合の法的紛争や、体外受精児誕生後に夫婦が別々の道を歩むという生殖に関する無責任の教科書的な事例が発生する可能性がある。特に奇妙な例は、1995年にカリフォルニアで生まれたジェイシー・バザンカの話である。彼女は、5人の大人に対して親権を主張することができるが、法律的には3年間「親なし」の状態で過ごすことになった。ジェイシーは、ある夫婦から提供された受精卵を、別の夫婦であるジョンとルアンヌ・バザンカのために身ごもる契約をした、結婚していない代理母に託されて生まれた。バザンカ夫妻はジェイシーの誕生前に離婚し、ジョンはその子に対する責任を放棄していた。裁判では当初、ルアンヌは子供を産んでおらず、遺伝的な関係もないため、ルアンヌが望むような法的な母親にはなれないとされた。しかし、カリフォルニア州最高裁判所は、医療行為を開始した「意図的な親」は、その後の意思の変さらにかかわらず、子どもの法的な親でもあるという判決を下し、最終的に法律を明確化したのである。
フランスやドイツなど代理出産に厳しい国の夫婦が、アメリカやインドなど法律が寛容な国で代理出産して子供を得たケースでは、親権の問題が国籍や市民権の問題と合体している。フランスのMennessonsとLabasseesの2家族は、カリフォルニア州の代理出産に関する自由な環境を利用し、カリフォルニア州で子供を持つことを選択し、未確定の管轄権の水をテストした。フランスは当初、生まれながらにして米国籍を持つ彼らの娘たちの市民権を否定していた。2014年6月、欧州人権裁判所(ECHR)は、そうでなければフランス人の親を持つ他の子どもたちに対してアイデンティティと権利を低下させて成長することになるため、フランスは両家の子どもたちに市民権を与える義務があるとの判決を下した。ECHRはこれを、子どもたちに「私生活および家族の生活を尊重する権利」を認める欧州人権条約第8条の違反とみなした15。批評家は、ECHRが、国内では禁止されている行為を海外で行ってもフリーパスを受け取ることができると親たちに示すことによって、フランス国内の公共秩序を損ねるものだと訴えた。しかし、この裁判は子どもの最善の利益のために行われたと狭く解釈されるべきで、フランスの主権やフランス民法の有効性に関する大きな問題は存在しないと反論する者もいた。いずれにせよ、フランス政府は、メネソンとラバッセの娘たちに関するECHRの判決に異議を唱えないことを決定した。
生活と法律
本章の主要なテーマは、いったん技術が研究所や実地試験という閉じた世界から抜け出せば、ある程度はすべての人の所有物となる、ということである。さらに、テクノロジーの用途が広がると、自分たちに何ができるのか、さらには自分たちが何者なのか、斬新で予測不可能な方法で理解するようになり、ユーザー自身のアイデンティティと可能性に対する感覚が変化する。新しい道具を手に入れることで、人々は新しい未来を想像し、実現することができるのである。しかし、倫理や規制に関する分析のほとんどは、発明と市場の間に挟まれた直線的な経路を進み、生産的な発明が複雑で動的な社会的文脈に組み込まれる際に生じるフィードバックや創造的拡張に気づかないままである。
遺伝暗号が解明されてからの数十年間は、生命に関する社会的実験が激しくかつ広範囲に行われた。技術的な専門家だけでなく、社会の普通の人々も、遺伝子の知識やノウハウに基づいて行動する用意があることを示し、新しい市場の需要を生み出し、市民と科学者の間で新しいパートナーシップを結び、子孫を残し、家族を形成するための新しい習慣を採用したのである。このような社会的混乱から明らかになったことは、生命の法則を解きほぐすと同時に、生命と法の間に新たな関係を作り出すということである。古くからある疑問が新しい形で再浮上し(幹細胞時代、生命はいつ始まり、いつ終わるのか)、人々が長い間解決したと考えていた疑問が疑わしくなった(自然な母親とは誰か)。これらの疑問は、科学だけでは解決できない。政治、倫理、法律と同じか、それ以上に属するものだったのである。
このような場合、法律や倫理が科学技術に追いつくために絶え間ない競争をしていると見るのは魅力的である。Mちゃんをめぐるスターン=ホワイトヘッド論争や、ジェイシー・バザンカ事件における親権の割り当てをめぐるパズルを解決するためのルールは、すでに存在していなかったのだからだ。しかし、法と公序良俗が常に遅れていると見なすと、技術的決定論の罠にはまることになる。それは、テクノロジーが独自の道徳規範を設定し、公共の価値は単に後から追いつくというものだ。この章では、生命を特徴づけ、操作する新しい方法に直面した人々が、エネルギーと創意工夫をもって、生命の保存と保護、人間の尊厳の維持、母性や父性などの制度の維持といった基本的な道徳的公約を、以前より幅広い可能性と想像力をもって再定義しようと努力していることを、はるかに多く見てきたのである。いずれの場合も、こうした社会技術的な自己形成の試みは、技術の物質的資源と法の規範的資源を同時に、しかも同等に利用してきた。
確かに、生物学的な自己形成の試みは、社会や個人にとって必ずしも有益なものとは言えない。ブザンカ事件で明らかになったように、新しい生殖技術を利用できる親は、自然な方法で妊娠した悪い親と同じように、自分の子供に対して無責任な振る舞いをする可能性があるのだ。遺伝子検査は、人々に自分の健康上の将来について自覚させ、より賢明な計画を可能にする。しかし、不注意に、カウンセリングなしに、あるいは不適切な対象に対して行われると、人々の現在の健全な楽しみを不当に損なう可能性があるのだ。また、企業の雇用主、法執行機関、民間の検査会社などの大きな組織は、不適切な形の社会的統制のために遺伝情報を悪用する力を保持しているのである。
しかし、本章で紹介した生命に関する実験は、裁判所や立法府が定めた正式な規則の枠を超えて、法と合法性の概念を広げるよう私たちに呼びかけている。実際、科学者たちが技術的、倫理的、さらには政治的な観点から何が実現可能かを定義しようと奮闘する中で、合法性の感覚はしばしば実験室の奥深くで始まる。生命倫理のような新しい専門分野やESCRO委員会のような新しい制度は、こうした審議が過度に隔離された環境で行われないようにするために生まれたもので、そこでは科学は、倫理的妥当性の内部感覚によって抑えられた、信頼できる研究に対する実践者の熱意だけに説明責任を負っている。とはいえ、何が「自然」だろうかについての社会の理解の多くは、どのような種類の生物学的新規性が安心して生み出され、どのような種類のものが社会の現状から見てリスクが高すぎるかについて、研究所や診療所で行われる決定から始まっている。次の章では、情報通信技術の進歩が生んだデジタル革命から生じた、同様の疑問とパズルを取り上げる。
NIHでは、まずゲノムの中の大きなDNA断片を見つけ出し、それを細断して配列を決定する「階層的ショットガン戦略」を採用していた。一方、セレラは、ゲノム全体を細かく切断し、その断片を膨大な計算能力で配列決定し、最終的にその結果をつなぎ合わせる「ホールゲノムショットガン戦略」を採用していた。当初は熾烈な競争を繰り広げていたが、やがてこの2つの手法は、互いに補完し合う形で利用されるようになった。
第6章 情報のワイルド・フロンティア
遺伝学やバイオテクノロジーの進歩によって、私たちの身体が外部の人間から読み取れるようになったとすれば、新しい情報テクノロジーは、私たちの心を並行して検査・管理できるようにしたと言っていいだろう。ラップトップ、iPhone、iPad、その他空港のセキュリティカウンターに豊富に展示されているあらゆる電子機器を手に、私たちはデジタル時代の考えるガジェットとの親密なパートナーシップを宣言する。カレンダー、フォトアルバム、ミュージックセレクション、そして数え切れないほどの保存書類など、電子機器は私たちの過去を記録し、私たちの未来を予測する、誤りやすい人間の頭脳よりも優れた存在である。パーソナル電子機器は、私たちが多かれ少なかれ自由に選んだパートナーなのである。しかし、私たちは日々、自分の習慣や好みをグーグルや国家安全保障局(NSA)などのデータ記録装置に知られるようになり、インターネット上でますます多くのことを行うようになると、ほとんどの人がぼんやり想像する程度の監視や社会統制を行うことができるようになる。
サイバースペースに接続することで、私たちは無限の情報にアクセスできるだけでなく、自分自身が情報になり、新しい形の監視、モニタリング、追跡の対象になりやすくなる。消費行動、社会的所属、画像、そしてツイッターで表現される一瞬の思考さえも、デジタルメディア上に無秩序に散在し、収集、保存され、つなぎ合わされて、かつてプライベートで侵すことのできないものと考えられていた自己の行動プロフィールが、驚くほど包括的に作り上げられるのだ。そして、許しやすく忘れやすい人間の記憶とは異なり、サイバースペースの記憶は簡単に薄れることはない。
これほど多くの情報が、情報収集と探索の意欲がある人なら誰でも簡単に入手できる世界で、人々を虐待や乱用から守るために、どのような保護が発展してきたのだろうか。情報化時代の巨大なパワーと可能性を、社会全体の利益のために利用し、責任を負わない機関にさらに権力を集中させないようにする責任は誰にあるのだろうか。その答えは、憲法などの既存の法的・倫理的枠組みが、自由に関する新たな想像を受け入れ、拡張することができるかどうかにかかっている。バーチャル・ワールドの可能性と制約がこれまでのものとは大きく異なるため、新しい形の結社と審議、そして新しい規制手段がほぼ間違いなく必要になるであろう。
この章では、情報化時代の倫理的ジレンマにいくつかの対立軸からアプローチし、デジタルと物理的な自己、公共と私的なデータ収集、米国とその他の国々といった対立軸のどちらかに問題があると認識される場合に何が関係するのかを問うことにする。これらの問題は、言葉にならない、一貫性のない、変化する規範に支配された、動くフロンティアを表している。私たちの目的は、デジタル・パーソネルフッドの時代における自由とプライバシーに対する社会的期待の変化に合わせて、誰がこれらの規則を作り、施行し、改訂する責任を負うのかを明らかにすることである。
憲法上の保護措置
まず、米国最高裁判所の神聖な保護区である伝統から始めよう。2014年6月、同裁判所は個人の自由に関する問題で、稀に見る全会一致の判決を下した。ジョン・ロバーツ最高裁判事は、ライリー対カリフォルニア裁判において、警察による携帯電話の捜索は、令状がない限り違法であるとしたのである1。多くのブレイクスルー憲法判例がそうであるように、この判決もごく普通の出来事から始まった。南カリフォルニアのサンディエゴの路上で、期限切れの登録タグをつけて運転していた男が、日常的に交通違反の取り締まりを受けていた。南カリフォルニアのサンディエゴの路上で、期限切れの登録タグを付けて運転していた男を交通違反で取り締まり、その男が免許停止中であることを知った警察官は、彼の車を徹底的に調べ始めた。ボンネットの中から、2週間前に起きたギャングによる銃撃事件に関連する拳銃が見つかった。さらに警察官はライリーのサムスン製スマートフォンを押収し、逮捕現場と警察署で2回にわたって中身を調べた。その結果、ライリーを悪名高いクリップスギャングと結びつける証拠となる写真やビデオが発見され、ライリーに対する殺人未遂を含むいくつかの重罪の根拠となったのである。ライリーは有罪判決を受け、15年の懲役を言い渡された。しかし、スタンフォード大学ロースクールの学生クリニックが、デジタル時代のプライバシーに関する新しい議論を展開するために、彼の事件を取り上げた。
最高裁へのブリーフは、請願者が最高裁に訴えたい法的問題を述べなければならない。ライリーのブリーフは、「申立人の裁判で認められた証拠(すなわち、あるデジタル写真とビデオ)が、申立人の携帯電話の捜索によって得られたものであり、申立人の修正第4条の権利を侵害したかどうか」という、簡潔で的を射たものであった。これらの権利には、「不当な」捜索や押収に対する保護が含まれており、その規定の意味は、市民自身の信念に決定的に依存するものである。捜査が、自宅、職場、車内、そして何よりも自分の身体の中にある、市民が合理的に予想できるプライバシーの領域を侵害したかどうか。2 その領域の範囲と境界を決定するために、裁判官は、国家の利益と市民の正当な期待のバランスを取らなければならない。もちろん、両者は、合理性に関する独自の文化と専門家の理解を通してフィルターにかけられなければならない。
裁判所は、権利や資格に対する期待は、科学技術の発展とともに変化し、私たちが正常とみなすもの、また同様に、私たちが侵入的または異質とみなすものを永遠に再構成していくことを長い間理解してきた。そして、法律、特に憲法は、「新しい普通」が権利の領域で守るべきものとして成文化されるための道具となる。こうして、血液アルコール検査が広く普及したとき、最高裁は、酩酊しているが同意していないドライバーは、憲法修正第4条に違反することなく、令状なしの採血を受けることができるという判決を下したのである3。法執行機関がDNA指紋を法医学で利用できる最も正確な識別手段として採用したとき、最高裁は、正当な根拠に基づいて逮捕された容疑者のDNA頬粘膜採取は、令状なしに実行されたが、修正第四条に違反しないとの判決を下した4。ケネディ判事は、頬の粘膜を採取することを、指紋採取や写真撮影といった日常的な逮捕手続きと比較して、その軽さに注目し、遺伝子のコードによって明らかになる情報の深さには注目しなかったのである。こうして、逮捕者のDNA検査は、5人の判事が1つのテストケースについてそう判断したため、警察手続きに期待され、合法的な側面として、平凡なものとなったのである5。
しかし、携帯電話の令状なしの捜査に直面すると、最高裁判事の想像力と直感は、警察にとってはるかに不都合なものであることが明らかになった。ロバーツ最高裁判事は、携帯電話は、警官が自らの安全を守るため、あるいは違法薬物の可能性がある粉末や通常のタバコとは異なるタバコのように本質的に疑わしいという理由で「合理的に」押収する物とは異なると指摘した。携帯電話は、「火星からの訪問者が人体構造の重要な特徴であると結論づけるかもしれないほど、今や日常生活に広く、しつこく浸透している」と指摘した。携帯電話の情報は、逮捕する側には何の危険もなく、逮捕された人が逃げ出すのにも役立つことはない。携帯電話には、写真、ビデオ、ボイスメッセージ、インターネット検索記録、電子メールなど膨大な種類の記録が保存されており、その人の私生活をすべて復元することができるのだ。ロバーツ判事は、小さな携帯電話に詰め込まれたデジタル情報の膨大さを考慮し、携帯電話は逮捕時に押収される他の物体と「実質的に区別がつかない」という政府側の主張をあっさりと退けた。「それは、馬に乗ることと、月へ飛ぶことと、実質的に区別がつかないと言うようなものだ」
ロバーツ最高裁判事は、携帯電話は電話ですらないと指摘した。「カメラ、ビデオプレーヤー、名簿、カレンダー、テープレコーダー、図書館、日記、アルバム、テレビ、地図、新聞と同じように簡単に呼ぶことができるだろう”と。これほど多くの機器、一度に部屋全体、書籍の場合は部屋以上埋め尽くすほどの機器を、財布やポケットの中に入れて持ち運び、スリムなジャケットの仕立てたシルエットをほとんど崩さないというのは、驚くべき技術的な偉業といえるだろう。しかし、携帯電話は、単にユーザーの指先に情報の世界をもたらすだけでない。ライリー氏が雄弁に語ったように、携帯電話は、逮捕に関連する捜査を行う警察官など、携帯電話の中身に目を通す時間と資源がある人なら誰でも、その持ち主の情報を読むことができるようにするものでもあるのだ。携帯電話は、その所有者と同一ではないかもしれないが、所有者個人を認識し、識別し、ユニークにする多くのものの貯蔵所であることは確かである。
思考機械と情報や思考を共有する人は、そのようなテクノロジーに出会ったことのない人と同じ自我の認識を持っているわけではない。数年前、私は大学から別の大学へ転勤した。引っ越しはいつでも大変なもので、住み慣れた家が取り払われるのを見るのは、たとえ別の場所に巣立つことを楽しみにしていたとしても、心が痛むものだ。しかし、私が最も別れを実感したのは、引越しの前夜、会社のパソコンのコンセントを最後に抜いたときだった。場所や家、友人のネットワークだけでなく、これまでの学者としての側面、人間としての側面も残していくことになるのだと、そのとき身につまされた。自分の意識の一部を閉ざすような感覚だった。倫理的、法的、社会的な分析機関が、ある意味で最も親密な仲間、心の延長、潜在的な自己の延長となったテクノロジーとの相互作用によって生じるこの種の主観的変化をどの程度受け止めることができるのか、現在と未来の自己を形成するために、問うことは重要である。
フィジカルセルフとデジタルセルフ
サイバースペースを発明したコンピュータ科学者やエンジニアの想像の中では、サイバースペースは当初、自己形成の助けというよりも、むしろその領域であった。それは何よりも、制約のない場所であり、人々が地に足の着いた地上の組織にはない自由さをもって自己表現できる場所であると考えられていた。少なくとも、デジタルのパイの一部を自分のものにする方法を理解している人々にとっては、アクセスは事実上無価値であった。ニューヨーク・タイムズ』などの主要な日刊紙の1ページを購入することは、ほとんどの人にとって法外な値段だった。インターネットはその障壁をほぼゼロにし、新しいツールが開発されるにつれて、プログラミングのスキルさえもインターネット上に自分のコンテンツを置くことと無関係になりつつある。スペースもまた、可塑的で無限に利用可能であり、紙や帯域やセメントといった物理的な制限に縛られることはなかった。今日、わずかなコンピューター知識しかないユーザーでも、わずかな費用でサーバーにウェブサイトを立ち上げ、自分の意見を発信したり、商品を陳列して、誰でもその商品を閲覧することができるようになった。
しかし、その自由は、仮想空間の先駆者たちが全く予見していなかったコントロールの可能性を伴っている。デジタル取引、特にインタラクティブなWeb 2.0時代の取引は、双方向のものである。サイバースペースに身を置くことで、人は広範かつ永続的な観察への道を開くことになる。2013年に諜報活動家のエドワード・スノーデンがNSAの文書を大量にリークして明らかにしたように、私たちの電子通信は、かつて米国市民が信じていたほどには政府による令状なしの捜査から守られてはいないのである。また、監視の主体は国家だけではない。アマゾンのような巨大な商業市場は、世界中の商品を購入者の手元に置く。しかしその見返りとして、アマゾンは購入や嗜好の履歴をすべて記録し、時間をかけて集計し、アルゴリズムで分類し、広告主やそのユーザーがもともとアクセスした商品以外の商品の販売者のターゲットとなりうる各ユーザー像を作り上げることができる。
Googleも同様に、各ユーザーの検索記録を保持し、後述するように、Gmailのユーザーの電子メールに違法なコンテンツがないかスキャンすることができ、実際に行っている。さらに、ユーザーは単に情報を求めて無意識のうちにデータソースとなるだけではなく、Facebook、Flickr、YouTube、Pinterest、Twitterなどのソーシャルネットワーキングサイトを通じて意図的に情報を共有するようになっている。サイバースペースという自由なメディアで共有する相手の範囲は、共有者自身が完全にコントロールできるものではない。心理学者でインターネット評論家のSherry Turkleの言葉を借りれば、RileyでRoberts最高裁判事が指摘した電子機器の遍在性は、「常にオン/常にオン」なのである6。
デジタルな自己の透明性の高まりを問題視するか、虐待とさえみなすかは、年齢、性別、出身地など、その人の社会的、政治的嗜好によって異なり、決定的な重要な役割を担っている。例えば、ハーバード大学のキャス・サンスタイン教授は、消費者は自分のニーズを明確にする前から、「予測的ショッピング」によって自分の心を読み、自分の希望に沿うことを望んでいると主張している7。しかし、こうした人間の心の読み取りのすべてが良性とは言えないし、市場で自由と効率のどちらかを選ぶときにすべての消費者が同じような反応を示すとも限らない。デジタルな自己を保護することは必要だが、その保護策はどこから来るのか。また、古い原則のワインは、デジタル時代の新しいボトルにどの程度まで劣化せずに注ぎ込むことができるのだろうか。
望まない侵入から個人を保護する法律は物理的な世界で発展し、裁判所が好んで用いる類推的な推論は、今でも主にその世界の前提から導き出されるものである。物理的な想像力は、憲法修正第4条の「人民がその身体、家屋、書類および物品において安全である権利」の保証を支えるものである。一般市民も裁判官も、政府職員が正当な理由なく自宅のドアを蹴破り、所持品を押収し、身辺を襲撃するような不法侵入を想像する。例えば、1965年に連邦最高裁は、既婚女性への避妊薬の処方を禁じたコネチカット州の法律を破棄した8。ウィリアム・O・ダグラス判事は、7対2の多数決で、憲法は家庭内で保護される「夫婦のプライバシー」の権利を保護していると結論づけた。そして、避妊具の使用禁止は、夫婦の寝室とその中にある古くからの関係の神聖さへの物理的な侵入であるとしたのである。ダグラス判事は、この「生活の調和」と「二人の忠誠」に携わるカップルが、避妊具の使用に関するカウンセリングを受けることを否定することはできないと判断した。
同様の類推により、世界人口の大部分がデジタルプロファイルを取得する以前から、裁判所は人々の非物理的痕跡に保護を拡大することができたのである。したがって、人々は、一般的な「パブリシティ権」または「人格権」に基づき、自分の名前、画像または肖像、さらには特徴的な身振りや物腰の普及をコントロールする権利を有する。これらの標識の財産としての位置づけについては、第7章で議論する。ここで重要なのは、こうした仮想的な拡張が、あたかも物理的な人物の一部だろうかのように、人格や自我の構成要素と見なされていることである。物理的な肖像はともかく、身振りや署名(例えば、独立宣言のジョン・ハンコック)は、個人と非常に密接に関連しているため、メトニムの役割を果たし、瞬時にその人全体を想起させ、それゆえ同じように保護するに値する。
また、寝室やロッカールーム、試着室など、通常部外者が立ち入れないとされる物理的な場所にも法的保護が及んでおり、多くの州ではこうした空間での無許可の盗撮や映像記録を刑事犯罪として扱っている。このような法律は、人が空間的に位置する物理的存在として享受する権利(自由、自律性、プライバシー、身体的統合性)を、侵すことのできない自己に不可欠とみなされる表現にまで拡大するものである。しかし、物理と仮想の間の類推的なマッピングは、私たちの代理的なデジタル自己が直面する課題に対応するのに十分なのだろうか。この問いには、私たちがますますインターネットに託している自己の具体的な性質にもっと注意を払う必要がある。その答えは、現実のアイデンティティと仮想のアイデンティティの関係をどのように概念化するかにかかっており、それは争われ、進化するプロセスなのである。
新たな脆弱性
デジタルの人物の痕跡は、物理的な痕跡とは異なるため、物理的な人物や空間との直接的な類似を描くことは、より問題が多く、有用でもない。第一に、個人の自律性に関する新しい問題がある。「ビッグデータ」はWeb2.0の時代に大きなビジネスとなったが、その理由の一つは、大規模なデータセットによって、人間の思考や意図のこれまで隠されていた特徴にアクセスできるようになったからだ。数え切れないほどのオンライン上のやりとりから得られるデジタルデータを集約し、グループ化することで、ある人物のアイデンティティ、態度、行動に関する極めて正確な合成写真を作成することができる。データによって、その人物の身体や外見だけでなく、内なる思考と行動の自己にアクセスすることができるのだ。第二に、デジタル情報は相互的なものであり、プライバシーに関する新たな問題を提起する。人は自分に関するデータをWWW上に置くだけでなく、その行為を通じて、監視、商業、さらには実験の対象となりうる。そして、人とその行動は、モノのインターネットにおける無数のデータ収集装置に接続され、かつてないほど追跡可能になっている。第三に、物理的な動きとは異なり、情報の痕跡は永続的であり、ある人は容赦なく、非難的であるとさえ言うかもしれない。情報的な痕跡は時間と共に持続し、デジタル化される前の時代に生きていた人々よりも、個人的なコントロールや消去が困難な歴史を堆積させる。この3つの側面はすべて、物理的な痕跡だけでは推し量れない人格の側面に部外者がアクセスすることを可能にし、倫理と法律にジレンマをもたらす。
インターネットは情報収集の場となった。公開された情報によって人々が追跡されたり、追跡されたりしている例は枚挙にいとまがない。この種のものとしては初めて、このようなデータがプライバシーの領域にまで入り込むことを可能にした、印象的な例がある。2004年末、匿名の提供者の精子で妊娠した15歳の少年は、自分の遺伝的父親を探そうとした。彼は「綿棒で頬の内側をこすり、それを小瓶に入れて、オンラインの家系図DNA検査サービスに送った」9カ月後、289ドルの手数料で、そのサービスはDNAが密接に一致する二人の人物を特定し、少年に近親者である可能性を明らかにした。そして、二人の共通の姓と、母親から聞いた父親の生年月日から、条件に合う人物のリストをインターネット上の家系図作成サービスから購入した。そして、その中から一人、正しい姓を持つ人を探し出し、ついに答えを出した。この男は、DNAをデータベースに提供したことも、精子提供者であることを公表することに同意したこともなかった。しかし、15歳の少年の創意工夫と執念が、照会者にほとんど負担をかけずに彼を明らかにしたのである。「カナダの生命倫理学者は、「この事件は、私たちが考えもしなかった生殖補助医療に関する倫理的、社会的懸念があることを示している」と述べている9。このコメントは、プライバシー侵害を意図せざる結果としているのが特徴だが、もちろん、データが簡単に入手できるということは、バグではなく、意識的に設計された特徴であり、サイバー空間の創始者が戦い、高く評価した特性の一つである。
15歳の少年は、独創的な常識を駆使して父親を探し当てた。より高度な計算技術を、デジタル環境から公開されたデータに適用することで、人々が公開するつもりのなかった個人的な特徴を明らかにすることができる。例えば、ケンブリッジ大学が58,000人のボランティアを対象に行った研究は、権威ある米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載され、彼らのFacebookの「いいね!」を数学的に分析した結果、「88%のケースで同性愛者と異性愛者を、95%のケースでアフリカ系アメリカ人と白人アメリカ人を、85%のケースで民主党員と共和者を、さらに82%のケースでキリスト教徒とイスラム教徒を正しく識別する」ことができたと報告している10。著者らは、情報漏洩の脅威がデジタル技術の利用を躊躇させることを懸念しながらも、情報の透明性と管理の向上により、技術提供者と利用者の間に十分な信頼と好意が確保されるという、ポリアンナ的な希望を表明している。
現状では、どのようなデジタル行動であっても、ある程度は自分を調査対象として開放することなく、行動することは難しい。検索エンジンやオンラインショップ、サービスを利用する人は、一般に、プロバイダが自分の電子メールアドレスやその他の情報を利用できるようにする相互協定を通じて、プライバシーがある程度犠牲になることに同意しなければならない。プロバイダーの中には、ユーザーの個人情報を共有しないことを約束しているところもあるが、どこまで約束を守っているかはユーザーにはわからないし、個人情報の盗難を目的としたハッカー文化が世界的に活発化していることも、さらなる脅威になっている。2014年のクリスマスイブに起きたソニーのハッキング事件では、同社の内部管理に関する機密情報が大量に流出するなど、ビジネスサイトへの攻撃は数多く報道されている。2015年7月に不倫サイト「アシュレイ・マディソン」がハッキングされ、約3700万人のユーザーのメールアドレスやアカウント情報が流出した事件11ほど、露骨で恥ずかしい攻撃はない。ハッカーは、自分たちの行為が気に入らない企業を抑止する目的もあったと主張したが、その行為はサイトユーザーの配偶者や子供など、実質的には無実の傍観者に被害を与えてしまったのだ。名前公開と関連した自殺者が数名出たという報告もある。
意図的なサイバー攻撃がない場合でも、ソーシャルメディアの利用は個人のプライバシーを侵食し、多くの場合、利用者の知らないうちに、あるいは同意なしに、プライバシーを侵害している。ソーシャルメディア革命を起こしたフェイスブックは、その比較的短期間の間に多くの抗議や法的措置まで引き起こし、ウィキペディアは「フェイスブック批判」のページ全体を割いている。たとえば、同社がサーバーからアカウントを永久に削除することを認めないことを決定したとき12、同社はその後その方針を撤回した。
さらに陰湿なことに、Web 2.0の双方向性は、大衆に無差別に向けられた旧来の宣伝キャンペーンを超える、一種の心理的実験を可能にしている。多くの企業は、表向きには、提供する製品を改善し、個々のユーザーのニーズに合わせてより慎重に調整するために、顧客データに関する継続的な調査を行っている。このような行為は、一般に、ビジネスを運営する上での合法的な補助手段として受け入れられている。インターネットサービスプロバイダも、より良いメッセージングのために顧客データを使って調査を行っている。このような「運営上の」目的のために自分の情報を利用することへの同意は、サイトを利用するための条件であることが多いのだが、ユーザーが読むのに苦労するような細かい字で書かれていることがある。このような利用は、特に他のサービス・プロバイダーとの情報共有に関わる場合、多くの人にとって好ましくないかもしれないが、間違いなく、当初の契約関係の延長として許容されるものである。しかし、許容される研究と非倫理的な研究の境界線は曖昧であり、規制管理の事実上の空白地帯にある企業は、それを踏み越えることができるし、実際にそうしているのだ。
フェイスブックのユーザーは、このサイトでの自分の行動が心理学的研究の被験者になるとは想像もしなかっただろう。しかし、2012年初頭、フェイスブックは、約70万人の匿名ユーザーに対して、彼らの知識や同意なしに気分の実験を行った13。2014年6月に評判の科学雑誌PNASに掲載されたこの研究は、フェイスブックがユーザーに送られるニュースフィードの感情コンテンツを意図的に1週間変更し、一部の研究対象者に対して感情的にネガティブな言葉を含むメッセージを「非優先化」するという方法でコンテンツをよりポジティブまたはよりネガティブにチューニングしたと報告した14。その結果、比較的ポジティブな刺激を受けた人は、全体的にややポジティブな投稿を行い、ネガティブな刺激を受けた対照群はその逆の結果を得た。著者であるFacebookのデータアナリスト、アダム・クレイマーとコーネル大学の統計学者2人の3人は、これは、個人と個人の接触がなくても、感情の伝染がネットワークを通じて広がるという証拠であると結論づけた。
その後、全米が大騒ぎになった。この研究は法的には何の問題もなかったが、研究者の倫理観に対するメディアの論評は、圧倒的に否定的なものだった。フェイスブック社内の審査員だけが、この研究を事前に承認していたのだ。コーネル大学の研究者は自ら被験者データを収集しておらず、外部のデータセットを評価していたため、大学の機関審査委員会(IRB)はデータ分析への関与を承認する必要がないと考えたのである。クレイマー氏自身は、Facebookに釈明と謝罪を投稿する必要性を感じていた。「この論文について不安を抱く人がいることは理解できるし、私と共著者たちは、この論文の記述の仕方と、それによって不安を抱かせたことを大変申し訳なく思っている。今にして思えば、この論文の研究効果は、このような不安をすべて正当化するものではなかったかもしれない」15 倫理学者の中には、この問題は大げさだと感じる人もいたが、誰もがクレイマーの事後の対応に満足したわけではない。コロラド大学の法学部教授で、インターネット上の力の不均衡を長年にわたって批判してきたThomas Ohmは、「倫理が議論されることを望んできた」と観察している。インターネット上での活発な議論にもかかわらず、企業が主催する研究が人々を顧客として扱うことが許されるのか、それとも実験用のネズミとして扱うことが許されないのかを解決する作業は、今のところ主に設計者側に委ねられている。このような研究を事前に精査する倫理的な仕組みは、単純に存在しないのだ。
時間と記憶もまた、物理的な自己とデジタルな自己とでは異なる働きをする。身体は死に、記憶は崩壊するが、デジタル・データは永久に生き続けることができる。一般人が自分のパソコンのハードディスクを掃除するのは大変なことだ。サイバースペース上に散らばった情報を排除するのは、はるかに難しい。Facebookで友人を楽しませるために投稿した写真が、数年後に将来の雇用主がそれを見て、危なっかしい、あるいは見苦しいと感じ、仕事を失うことになった17。Twitterは、個人の最も非公式で儚い考えを捉えることを目的としたメディアだが、目に見えて公開され、あらゆる実用的目的のために永久的でもあるサイトであることが判明した。人間関係の破綻や職場の危機の際に送信されたツイートによって、何年も何十年も悩まされることになるかもしれない。Facebookのような企業は、一度投稿された個人情報を削除できるかどうかについて、方針を巡って二転三転している。Facebookのような企業では、一度投稿した個人情報を削除できるかどうかで方針が分かれており、公開したくない情報を追跡して削除するための新しい商用サービスも登場している。しかし、自分自身のデータの寿命をどの程度までコントロールできるかについては、まだ流動的であり、以下に述べるように、国によって違いがある。
公的か私的か
情報化時代の先駆者たちは、物理的な領土を越えて主権を行使する国民国家の束縛からの解放を謳歌していた。ニューロマンサー』の著者であるウィリアム・ギブソンの造語を借りて、かつてグレイトフル・デッドの作詞家であり、初期のインターネットの第一人者であったジョン・ペリー・バーロウは、サイバースペースの独立に関する反骨の宣言を起草した。「産業界の政府、肉と鋼の疲れた巨人たちよ、私はサイバースペース、心の新しい故郷から来た。産業界の政府、肉と鋼の疲れた巨人たち、私はサイバースペースから来た。あなた方は私たちの間で歓迎されていない。「私たちが集う場所に君らの主権はない」予言的でユートピア的な彼の言葉は、コンピュータの魔法使いの若者たちが、新しい、一見無限に見える土地を発見し、そこでは誰もが対等に立ち入ることができ、あらゆる形の言論と表現が自由であるという勝利に酔いしれた世代に響いた。
しかし、今日、私たちはそれ以上のことを知っている。ブラッドリー(後のチェルシー)・マニングが米国の機密文書をウィキリークスにリークした罪で35年の実刑判決を受け、ウィキリークス創設者のジュリアン・アサンジがロンドンのエクアドル大使館に長期にわたって匿われ、エドワード・スノーデンが米国の裏切り者として告発を免れロシアに避難したことを受けて、国家主権がインターネット上のコンテンツの規制にも生きていると疑う者はいないだろう-少なくとも、国家が定める国家安全に関わるコンテンツの場合は、である。インターネットは、バーロウや他の先駆者たちが考えていたような完全な個人の自由の空間とはほど遠く、そこに入る人々を目に見えない、予測不可能な方法で巻き込む権力の線が交差する空間として出現しているのだ。公的機関も私的機関もサイバースペースにおける個人の自由を支配しているが、異なるメカニズム、異なる透明性と説明責任のルールのもとで支配しているのだ。
グローバルな規範はない
スノーデンの暴露がもたらした大きな反響を考えると、彼を英雄と見るべきか裏切り者と見るべきか、内部告発者と見るべきか犯罪者と見るべきかについて、世界の世論がこれほどまでに大きく分かれているのは驚くべきことである。その理由の一つは、確かに1970年代に知られていたような領域性の解消と、それに伴う国家機関の力の弱体化と関係がある。忠誠心や国家安全保障といったスローガンのもとに世論をまとめる力は弱まったが、このような断片化は、サイバースペースが「心の新しい故郷」として出現したことだけが原因ではないし、それが主な原因でもないだろう。他の移動と分散のテクノロジーも重要であり、電子メディアは重要な役割を果たしている。
スノーデンと、かつてアメリカの国家機密を公開した記録を持つダニエル・エルズバーグのケースの違いは、魅力的であると同時に示唆的である。エルズバーグは反戦活動家であり、ハーバード大学で学んだ決定論者で、上司であるロバート・マクナマラ国務長官のために作成した極秘レポート「ペンタゴン・ペーパーズ」を密かにコピーしていた人物である。エルズバーグは、その文書をニューヨーク・タイムズなどの新聞社に提供した。1971年6月、タイムズ紙とワシントンポスト紙は、この文書を基にした記事を掲載し始め、たちまちニクソン大統領率いる司法省から裁判を起こされた。ペンタゴン・ペーパーズの公開を続ければ、米国の外交関係を損ない、敵国を助けることになると主張し、タイムズ紙とポスト紙に対する差し止め命令を求めたのである。エルズバーグはスパイ活動法の下で裁判にかけられたが、政府の証拠の入手や処理に違法な盗聴などの重大な違法行為があったことが明らかになり、裁判長は告訴を取り下げた。エルズバーグは、80歳を過ぎても言論の自由の侵害に対して発言し続け、デモを行い、一種のフォーク・ヒーローとなった。
ペンタゴン・ペーパーズの物語は、一国の領土の中で展開され、主にその国民、ニュースメディア、国家機密、法律、法執行者、そして裁判官が関与していた。これに対し、スノーデン事件は、エルズバーグ事件と同様、米国市民が米国政府の機密記録を盗み出し、公開したことが中心ではあるが、法的にも政治的にも、そして物理的にも、その起源から分散している。スノーデン自身はハワイでNSAの契約職員として働いていたが、ドキュメンタリー映画監督のローラ・ポイトラスと弁護士でジャーナリストのグレン・グリーンウォルドという2人のアメリカ人と会うために香港に飛んだ。グリーンウォルドは、アメリカの結婚防衛法(Defense of Marriage Act)によって、同性のパートナーがアメリカで一緒に暮らすことができないため、ブラジルに住んでいたとされる。ポイトラスとグリーンウォルドは、2013年6月5日にNSAの監視に関する記事を掲載した英国の新聞「ガーディアン」で働いていた。その4日後、スノーデンが名乗りを上げ、リークの背後にある顔として姿を現した。6月23日、スノーデンは中国からロシアに飛び、そこで身分不詳の難民として、またパスポートを剥奪された米国政府から見て逃亡者として滞在していた。彼の情報公開は、2013年7月に英国政府の要請でガーディアンが流出文書の入ったハードディスクを解体したこと、2014年3月にスノーデンが欧州議会でテレビ証言したこと、グリーンウォルド、ポイトラス、ユアン・マカスキルによる公共サービス報道でガーディアンとワシントンポストが2014年のピューリッツアー賞を受賞したこと、などの様々な出来事を引き起こした。
これらのエピソードはすべて、飛行機、電話、テレビ、コンピュータ、電子メール、電子新聞といった近代的なテクノロジーによって密に相互接続された世界でありながら、その接続が国家間の対立や主権争いという基盤の上に重ねられていることを明らかにしている。2013年7月、ボリビアのエボ・モラレス大統領が乗った飛行機が、スノーデンをロシアから移送しているのではないかという疑惑でオーストリアへの予定外の着陸を余儀なくされ、米国とラテンアメリカの関係は悪化した。スノーデンが開示した文書に基づき、NSAがアンゲラ・メルケル首相の私用電話を盗聴していたという報道は、ドイツとヨーロッパを激怒させ、世界的危機が高まっていた時期にメルケル首相とバラク・オバマ大統領の関係を緊張させた19 一方、スノーデンは多くの人から自由の旗手として見なされ続けた。2014年初頭、彼は共同設立者のエルズバーグや、グリーンウォルド、ポイトラスらの招きで、報道の自由財団の理事に就任した。
スノーデンの大胆な行動は、監視に関するグローバルな公開討論に拍車をかけ、世界中のハイレベルな政治的反響を呼び起こした。世界の指導者や安全保障機関を困惑させ、立法府の調査に拍車をかけ、米国では憲法の反省を促し、報道機関を脅かすと同時に報い、民主主義国家の国民に自国の安全保障機構における膨大かつ不測の事態の可能性を認識させることになった。同時に、ペンタゴン・ペーパーズ事件とは対照的に、スノーデン事件とその波及効果は、スノーデンが明るみに押し出した問題の収束の難しさをも物語るものであった。9.11以降の世界では、米国憲法はもはや言論の自由を保護するものではなく、エルズバーグのように、公平な法廷での正当性を主張するために起訴される危険を冒していたかもしれない人々も保護しないと多くの人が感じている。また、メタデータ検索や大陸間電話盗聴の時代には、監視の倫理を裁く制度も整っていなかった。スノーデン氏の事件は、50年前には想像もできなかったような多角的な議論に世界社会を巻き込んだが、同時に、国益と国家間の政治的分裂や連携によって大きく分断された世界において、集団規範を形成することの難しさを浮き彫りにした。
データオリガルヒ
技術系億万長者が社会階級として登場したのは21世紀初頭のことだが、カリフォルニアの有名なシリコンバレーを中心に、少数の手に並外れた富が集中していることは、個人情報という新しい資源が比較的少数の者によって管理されるようになったことを象徴している。グーグルやフェイスブックは、「データオリガルヒ」と呼ばれている。彼らは大衆に比類ない情報ゲートウェイを開いているが、同時に、その範囲と多様性によって膨大な潜在的価値を持つ大量の情報をも支配している。技術的には民間企業、つまり非国家企業でありながら、これらの企業はデータの使用や誤用に対して国家が責任を負うことが困難な境界線をまたいでいる。
グーグル社は、サイバースペースにおける権力と説明責任の相互作用について、特に興味深い事例を提供している。グーグルは当初、ユーザーが検索するものに関して、正確で偏りのない情報を迅速に提供する、最高の検索エンジンになることを目指していた。同社の有名なモットーである「Don’t be evil」は、社会的責任と善行への総合的なコミットメントをテーマとしており、これはGoogleのトレードマークの1つとなっている。例えば、中国での事業では、中国政府との度重なる対立や閉鎖の危険を冒して、検閲に立ち向かった。しかし、会社の成長とともに、製品は多様化し、その意欲は拡大していった。興味深いことに、アルファベットは「Don’t be evil」というスローガンを行動規範の一部として採用しなかった21。
Googleは、単に世界で最も人気のある検索エンジンではなく、Gmail、Google Maps、YouTube、Chromeブラウザ、Android携帯など、数多くのインターネット製品やサービスも販売している。その利益は年間500億ドルを超えている。グーグルは、ある面では国家のように振る舞い、毎月10億人以上の検索者に情報や広告を提供し、大規模な国家政府のような規模で行動している。しかし、グーグルはその権力を、当初の行動規範で求められていたような有益な方法で使っているのだろうか。
グーグルは、米国政府および欧州連合(EU)の両方と摩擦を起こすことで、問題を指摘されている。グーグルは長年にわたり、その巨大な市場シェアを利用して競合他社に不当に不利益を与えている(例えば、自社の地図サービスや検索サービスを優先して検索結果を表示している)という嫌疑から、独占禁止法違反の調査を受けてきたのである。2011年に開かれた米上院の反トラスト法公聴会で、グーグルのエリック・シュミットCEOは、自社の市場シェアが独占的に見えることを認めた上で、これは最終的には裁判所の問題であるとし、「私たちがその領域にいることは同意する。. . . 米国での調査は、深刻な規制や罰金には至らなかったが、最終的に欧州で行われる和解は、より踏み込んだものになる可能性がある23。
人々が検索する際に目にする情報の種類をコントロールすることは、新しい種類の私的権力であり、規制されていない。かつて、情報の流れを規制していたのは、主に国民国家であり、公教育や、大なり小なり報道機関も規制していた。実際、政治理論家のベネディクト・アンダーソンは、ナショナリズム自体がこうしたトップダウンの統制の産物であり、自らを一つの国家に属するものとみなすよう誘導された人々の「想像の共同体」を生み出すものだと論じている24。しかし、たとえば中国のように、グーグルが国有メディアや国家統制メディアから人々を解放すると言っても、それは明らかに全体像ではないだろう。利益を念頭に置いた私企業である同社は、国民国家に劣らず、情報を選択的に公開・非公開にすることで、ユーザーが何を見、どう考え、行動するかまでコントロールすることに大きな関心を持っている。Cass Sunsteinのコメントにあるように、このようなマインドコントロールは、それが「予測的ショッピング」のような選択の言葉で飾られている限り、一部の消費者にとっては不快なことではないかもしれない。しかし、Googleはもっと直接的で、穏やかでない支配を、その従業員を始めとして、人々の生活に対して及ぼしているのだ。
アップルの象徴的なトップであったスティーブ・ジョブズの死後間もなく、6万人以上の技術労働者が、アップル、グーグル、その他の著名なハイテク企業の雇用慣行における独占禁止法違反について集団訴訟を起こした25。ジョブズは、シリコンバレーにおける彼の神話的地位が他の企業を説得し、低賃金と低競争がすべての雇用者に利益をもたらすという、このような状況の重要な立役者であった。このような談合によって、労働者は30億ドルもの補償を失ったと言われている。訴訟開始から3年後、カリフォルニア州サンノゼの連邦地方裁判所のルーシー・コー判事は、3億2400万ドルという和解案をまったく不十分なものとして却下した。陪審員は、ジョブズとその同僚が提出した証拠に説得力があり、提案された金額の何倍もの賠償責任を負う可能性があると強調した。結局、裁判官は、当初の提案の3分の1である4億1,500万ドルというかなり低額の和解金を承認した。
ハイテク企業と高度な技術を持つ従業員との関係に見られる、自分たちのルールを作り、それに従って生きるという傾向は、ベイエリアの地域社会との関係にも波及している。グーグルは、従業員の心身の健康を考え、フィットネスセンターから壁の色に至るまで、あらゆることに気を配りながら職場を調整することに重点を置いている。しかし、そのような福利厚生や富の流入が、技術者層とその出身地である都市部との格差を拡大させることになった。2014年初頭、サンフランシスコでは、グーグル、アップル、ヤフーなどの有名な「キャンパス」に社員を運ぶバスに対して予想外の怒りのデモが発生し、一部の人々は市内のバス停を不法に使用していると指摘した27。2週間の一般投票期間中にコミュニティによって選ばれた勝者には、総額500万ドル、上位4名にはそれぞれ50万ドルの賞が授与された。注目すべきは、公共事業への支出や選挙による承認(5月22日から6月2日までに191,504票が投じられた)という古典的な民主主義のプロセスを模倣しながら、公聴会や市民参加の積極的な取り組みといった、従来の民主的審議の特徴を排除したことである。
データ収集者であるグーグルは、法執行の特定の分野で行ってきたように、政府当局とパートナーシップを結ぶと、私企業としての機能をさらに低下させる。同社は日常的にGmailユーザーの電子メールをスキャンし、連邦法の下で犯罪とされる児童ポルノの証拠を探している。全米行方不明・被搾取児童センターは、行方不明または被害にあった児童のデジタル化・暗号化された画像のデータベースを管理している。Gmailで送信した際にこれらのうちの1つが表示された場合、Googleはそれを当局に報告する。こうした情報提供を受けて、テキサス州警察は2014年8月、20年前に性的暴行で有罪判決を受けたレストラン従業員の電子デバイスを捜索した。ポルノ資料や関連するメッセージを発見し、この男の逮捕につながった。児童虐待の可能性のある人物を特定したことを問題視する人はほとんどいなかったが、オブザーバーは、グーグルが児童ポルノの検出に使用しているのと同じ種類の技術が、他の種類の情報の取得に使用される可能性があり、グーグルを滑りやすい坂道に導き、国家が適切に対処できないような事柄について国家の代理の目として実質的に作用する可能性があると指摘している。
Googleや他のハイテク企業が、政府の極秘電子監視プログラムであるPRISMにどの程度関与しているかも、世間を騒がせることになった。スノーデン氏のリークにより、NSAが英国の諜報機関長官と協力して、外国人だけでなく米国人の電子通信パターンに関する膨大な情報を日々収集していたことが明らかになった。それらの「メタデータ」には、発信者と受信者の番号、通話時間など、ほとんどの電話の通話記録が含まれている。また、電子メール、写真、音声やビデオチャット、文書などもNSAのデータ収集の対象に含まれている。PRISMプログラムは、1978年に制定された外国情報監視法(FISA法)に基づき運用されている。特定の状況(監視期間が1年未満の場合など)を除き、NSAは外国情報監視裁判所(FISC)からの裁判所命令を必要とする。FISCは、米国最高裁長官によって任命された7人の裁判官によって構成されており、NSAの令状請求を却下することはほとんどないが、裁判所の実際の判断は秘密に包まれている。
グリーンウォルドとマカスキルは、スノーデンのリーク文書に基づくガーディアン紙の最初の記事の一つで、NSAがグーグル、フェイスブック、アップル、ヤフー、その他複数の米国インターネット企業の中央サーバーに直接アクセスしたことを報じた28。しかしグーグルは、NSAが自社のデータシステムに直接または間接的にアクセスしたことを断固として否定し、他のハイテク大手とともに、データの開示はケースバイケースであり徹底した内部審査を経て初めて行うと主張している。2014年9月、FISCの令状却下を審査する上訴裁判所が公開した文書により 2008年に米国政府がヤフーに対して、PRISMプログラムの下で通信データの引き渡しを拒否すれば1日あたり25万ドルの罰金を課すと脅していたことが明らかになった29。ヤフーは、大量の電子データを要求する法律の合憲性を争ったが、FISCではその努力は失敗に終わった。
簡単に説明すると、2016年の冬、またしてもテック業界の巨人が米国を相手にテストケースを行うことになるかと思われた。米連邦捜査局(FBI)は、カリフォルニア州サンバーナーディーノでクリスマス前のオフィスパーティーで同僚14人が殺害されたテロ事件の犯人の1人のiPhoneのロックを解除するようAppleに求めた。FBIとの協議が難航すると、AppleのCEO であるTim Cook は、2月 16日の声明で、「FBI はこのツールを説明するのに別の言葉を使うかもしれないが、間違いない」と宣言し、Appleの主張を米国民に伝えた。このようにセキュリティをバイパスするiOSのバージョンを作ることは、紛れもなくバックドアを作ることになる。そして政府は、このツールの使用は今回のケースに限られると主張するかもしれないが、そのような制御を保証する方法はない」31と述べている。数週間後、司法省がアップルの協力なしに問題の携帯電話をハッキングする秘密の方法を見つけたと発表すると、醜い法的戦いの見込みは消え失せた。この事件は、データセキュリティに関する膨大で未解決の技術的な問題だけでなく、より重要なこととして、ロバーツ最高裁長官の言葉を借りれば、デジタル機器が「人体構造の重要な特徴」に似ている時代に、市民が保護について国家と民間企業のどちらに期待すべきかを明確に示している。
世界の中の米国
スノーデンが暴露した情報の中で、米国情報機関がメルケル首相の私用電話を盗聴していたという報告ほど、意見が分かれる疑惑はない。世界史において西側諸国の結束が重要と思われた時期に、伝統的に緊密な同盟国であるドイツとアメリカの関係に不信のくさびを打ち込んだのである。この報告書が公表されてからほぼ1年後、メルケルは米国を公式訪問したオバマに、安全とプライバシーのバランスをとる際の「比例」についての考え方が両国間でまだ異なっていることを示した32。まるで、米国が欧州で最も強力な指導者の電話を盗聴することによって、電子時代における国際関係の倫理と許容範囲に関する国境を越えた深い溝にも踏み込んでしまったかのようであった。
第二次世界大戦中のファシズムと社会主義の経験で鍛えられたヨーロッパ人は、しばしば米国人よりもプライバシーに深い関心を持つと言われる。ホロコースト記念館(ワシントンD.C.)に入ると、まず最初に目に入るのが、1939年のドイツの国勢調査に使われた、現代のコンピューターの先駆けともいえるホレリス・マシンである。アメリカ人は安全保障に関心が高い、特に9.11以降、テロに心を奪われている、という反論だ。このような平板な一般論は慎重に扱うべきですが、実質的な政策の相違は、国家がデジタル市民との関係をどのようにイメージしているか、大西洋の両側で大きな違いがあることを示唆している。
欧州連合(EU)は1990年代以降、加盟国全体で個人データ保護のための統一的な枠組みを構築するための措置をとってきた。1995年のデータ保護指令は、「データ主体」が公的または私的な「データ管理者」に対して主張できる一連の権利を制定した。データ対象者とは、番号によって、または身体的、精神的、経済的、文化的、社会的アイデンティティの特定の特徴によって識別可能な自然人(すなわち人間)である。この指令では、データ対象者は、対象者自身の保護や徴税などの公的機能のためなどの特定の条件を除き、明示的なインフォームドコンセントなしに自分のデータを収集または「処理」されない権利を有していると定めている。2012年以降、EUは、各国の実施体制がバラバラな現行の指令を、EU全域の法律として適用される単一の規則に置き換える作業を続けている。新法は、企業のデータ保護プロセスを合理化する一方で、データの収集や処理に対する明示的な事前同意の原則や、明確な「忘れられる権利」など、個人に対するプライバシー規定を強化することも目的としている。
欧州連合司法裁判所は2014年5月に後者の問題を先取りした33。スペインの弁護士であるMario Costeja Gonzálezは、2010年にスペインのデータ保護機関に対し、自分の名前をGoogleで検索すると、1998年にそれ以前の社会保障費の未払いにより自分の財産が強制売却されたと報じたスペインの大新聞の2ページがリンクされると訴えた。コステハ氏は、このページは「もはや関連性がない」と主張し、ページの変更または削除、およびGoogleとそのスペイン子会社によるリンクの削除を要求した。Costejaの主張を検討した司法裁判所は、いったん合法的に収集・保存されたデータであっても、時間が経過すると、「データが不適切、無関係、またはもはや関連性がないように見える」場合には、データ保護の義務に抵触する可能性があると判断した。また、裁判所は、データの削除を求める権利は絶対的なものではなく、データ主体の権利と公共の利益の間で「公正なバランス」がとられるべきであると述べている。
この判決の影響はまだ浸透していないが、このプロセスがグーグルや他の大規模データ管理者にとって非常に大きな負担となる可能性があることは、数カ月のうちに明らかになった。グーグルは、すぐに殺到した何万もの要請について、判決に準拠しているかどうかを審査すると発表した。しかし、そのためには、問題となったデータが本当に古いのか、あるいは無関係なのか、その性質を詳しく調べるとともに、その情報にアクセスすることに対する公衆の利益を判断する必要がある。例えば、公人や権威ある地位を求める人物に関する古い情報は「関連性がある」とみなされるかもしれないが、コステハの10年前の不良債権の記録のような純粋にプライベートな情報をいつまでも維持することは「過剰」だとみなされるかもしれないのだ。
自分のデジタル上の過去の長い影をコントロールする権利は、データ保護の新しい重要な原則だが、この原則がどれだけ有効だろうかは、時間が解決してくれるだろう。例えば、忘れられる権利のような原則についてEUと米国の間で食い違いが生じた場合、経済的、社会的にどのような影響があるのだろうか。これは仮定の問題ではない。初期の反応では、かなりの意見の相違が見られた。ハーバード大学の法学部教授であるJonathan Zittrainは、New York Times紙に「非常に現実的な問題に対する悪い解決策だと思う」と述べ、オックスフォード大学のインターネットガバナンスの教授であるViktor Mayer-Schönbergerは、判決は既存の法律を肯定するだけで、「デジタル以前の時代のはかなさと忘却」への回帰を歓迎している34と述べている。
現在のところ、農業バイオテクノロジー(第4 章参照)と同様、大西洋の両岸にある2 つの強力な政治・経済圏は、国家、市場、個人の間の良好な関係に関するそれぞれの長年の確信に沿いつつ、異なる概念と規制の道筋を辿っているように思われる。米国には、EU指令や提案されている規制のようなデータ・プライバシーに関する包括的な法律はない。その代わりに、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律に基づく医療記録に関する高い国家基準から、消費者の嗜好や自発的にアップロードされた個人情報に関するデータの収集と処理に対する事実上の保護まで、保護制度はつぎはぎ状態である。このような状況は、米国が業界の自主規制を重視し、抜け穴が政治的に重要視されるようになってから国の法律が介入し、健康、医療、医療保険の拒否に関わる問題でプライバシーを重視する国民性によって緩和されたものである。
ギリギリの生活
電子フロンティアの拡大により、世界の多くの人々の生活様式が変化している。クリスマスカードを書き、手紙を出し、本を読み、そして多くの人々が小切手を出すという昔ながらの儀式はもうない。特にアメリカのミレニアル世代にとって、紙を使う取引は20世紀的であり、過ぎ去った時代の厄介な遺物のように感じられる。Facebookやメール、Twitterで友人との会話を楽しむようになり、電話で伝える人の声さえも時代遅れになっている。郵便局、近所の本屋、図書館、ショッピングモールといった伝統的な出会いの場は、愛されることなくゆっくりとその生涯を終えていく。カリフォルニアの有名なシリコンバレーは、デジタル空間という無限の富を掘り起こそうとする若い起業家たちのゴールドラッシュを誘致している。
このような喧騒がもたらした目に見えない副産物は、インターネットに少しは顔を出しているすべての人々のデジタルな分身が出現したことである。検索エンジンやソーシャルメディアの常用者は、ある面では、昔ながらの対面での接触よりも、デジタル上の痕跡を通じて知ることができる。インターネットは、彼らのふとした考えや、何気なく撮った写真、書き溜めた文章、発言、購入したもの、そしてごく一部のケースでは、彼らの暗い、怪しい、あるいは犯罪的な衝動を記録し、そしておそらく永遠に保存しているのだ。この手に負えない宇宙の支配者は政府だけではない、とはいえ、当初の宣伝文句に反して、国家主権はインターネット上では依然として強力な力を持っている。しかし、人々を「読み」、人間の行動をコントロールする能力において国家と肩を並べるのは、新しいデータ寡頭勢力である。Google、Microsoft、Apple、Amazon、Facebook、Twitter、Yahoo、YouTube、その他まだそれほど知られていない、あるいは遍在していない企業である。
インターネットガバナンスは今や十分に認知された政策領域だが、インターネットへのアクセスの価格設定という観点でそれを見る人は、現実の人間がデジタル資源を使ってリアルタイムに行動することによって生み出された仮想的かつ不滅の主体や集団を統治することに伴う、巨大な倫理的・法的ジレンマを見逃している。立法府は、経済成長と技術開発を阻害するのではないかという懸念に阻まれ、対応が遅れている。裁判所は、物理的な世界との類似性に想像力を制約され、部分的で一貫性のない判決を下してきた。21世紀において人間であるだけでなく、移動し、変化し、追跡可能で、意見を持つデータ主体であることの意味を、新しく、創造的に再定義しようとするものである。
第7章 誰の知識、誰の財産か?
人は法律と倫理において、誰も侵害したり取り除くことのできない権利を持っている。私たちは、人間は尊厳を持つ不可欠な存在であり、身体的な自分自身、持ち物、および身の回りのものを不法な攻撃や侵入から守る権利を持つと考える。これらの人格権は、各国の憲法から国連の世界人権宣言に至るまで、さまざまな法的・倫理的枠組みにおいて侵すことのできない不可侵のものとして扱われている。こうした点で、人はモノ、特に所有できるモノ、つまり財産とは著しく異なる。所有するモノは、法律で明確に禁止されていない限り、所有者の意思で使用したり使い切ったり、売ったり、物々交換したり、分割したり、贈与したり、破壊したりすることができる。しかし、新しい生物学的技術や情報技術は、かつて考えられなかったような方法で、事実上、人が自己存在の側面を分配することを可能にし、人と物の間の境界線を曖昧にした。遺伝子などの物理的実体であれ、私たちの言葉や取引のデジタル記録であれ、私たちの身体や自己に由来する物質の地位はどのようなものなのだろうか。この章では、人称の技術的な区分と拡張がもたらす難問のいくつかと、これらの課題に対する新たな対応について考察する。
不死細胞
現代のスフィンクスの謎かけのようなものかもしれない。死んでいるのに生きているもの、名前がついているのに名前がないもの、一人の命を傷つけたのに多くの命を救えるものは何だろう?その答えは、創薬を目指す現代の生物学研究室に物理的な形で存在する、ヒトの「細胞株」である。死にかけた、しばしば病気にかかった人の体から抽出された細胞集団は、適切な条件下で永遠に生き続け、人類にとって最も恐ろしい、衰弱した病気の治療につながる研究の材料を限りなく供給することができる。
通常の細胞は有限の寿命を持ち、その後死んでしまう。しかし、細胞株は突然変異を起こし、人体の外でも無限に分裂を続ける、いわば不死身の細胞である。このように増殖し続ける遺伝子的に同一の細胞は、現代の生物医学研究において欠くことのできないツールである。また、クローン技術により、何倍にも増やすことができる。科学者たちはこの豊富な資源を利用して、希少な材料ではできなかった研究を行うことができる。また、細胞株で有望な治療法を試すことで、実験薬にありがちな有毒な副作用を生きた人間にさらすこともない。もちろん、薬は最終的には実際の人間を使った試験で承認されなければならないが、最初に細胞株を使うことで、その過程で誰にも害を与えることなく、より有望な道筋とそうでないものを分けることができる。しかし、人の体から取り出した細胞や遺伝情報は誰のもので、誰がそれを使って何ができるかを決め、成功する治療法が現れたら誰がその利益を分配するのだろうか。
2013年8月、米国立衛生研究所(NIH)のフランシス・コリンズ所長と科学・アウトリーチ・政策担当のキャシー・ハドソン副所長は、ある特別なケースに関連して、こうした極めて基本的な疑問のいくつかに取り組んだ。ハドソンとコリンズは、Nature誌に寄せたコメントの中で、1951年に進行性の子宮頸がんのためわずか31歳で亡くなったアフリカ系アメリカ人女性、5人の子供の母親とNIHの間で結ばれた異例の協定について述べている1。この契約は、生物医学研究者が長い間「HeLa」と呼んでいた細胞株から得た彼女のゲノムに関する情報を、将来の研究者が彼女の家族も含めて検討した上で、アクセスできるようにするものであった。このようにして、HeLa細胞という無生物の科学的道具が、人間性の典型的な指標を獲得したのである。つまり、その細胞に含まれる情報をさらなる研究に利用する前に、その細胞が由来する人物の生きた代理人を介して、インフォームドコンセントを与える権利である。
この同意とその背後にある物語は、医学研究の歴史においてユニークなものである。もし、スタンフォード大学の法律クリニックが彼を憲法判例にしなければ、デビッド・レオン・ライリー(第6章参照)が、収容された大勢の人々の中の失われた魂の一人に過ぎなかったかもしれないように、もし、21世紀の科学作家レベッカ・スクルートが彼女の話を復活させず、彼女の名前を復活させていなければ、ヘンリエッタ・ラックスも医学史の脚注にとどまったかもしれない2。スクルートがヘンリエッタを知ったのは、16歳のとき、コミュニティカレッジの生物学の授業で細胞分裂について学んだときだった。生物学の学士号を取得するにつれ、彼女に対する好奇心は高まり、科学出版物や自分の研究室でもHeLa細胞を見つけることができるようになった。10年にわたるひたむきな研究が、2010年に出版されたスクルート著『The Immortal Life of Henrietta Lacks』に結実した。この本は、貧しく、学歴もないが、驚くほど回復力のある黒人女性が、治療不可能ながんで死亡し、その細胞が、彼女や家族の知らないうちに、あるいは同意なしに採取され、急成長する生物医学研究分野で最も役立つツールの一つとして生き続ける様子を描いたものである。60年の間に、HeLa細胞は何十億ドルもの利益を生み出し、6万以上の科学論文を生み出したと言われている3。
ヘンリエッタ・ラックスの物語は、人種、生命倫理、経済的・社会的不平等、そして若い母親の早すぎる死が混ざり合い、国民の神経を逆なでするものだった。人の体から採取された組織が、その人の死後、科学的利用のために不死化される可能性があること、また、その利用には必ずしも提供者の承認や同意が必要ではないことを、ほとんどの人は知らなかったのだ。スクルート氏が提示したように、この事件は、不公平が行われたことを認め、何らかの補償がなされるべきであると叫んでいる。ヘンリエッタの家族が貧しく、基本的な医療も受けられないままなのに、HeLa細胞を使った研究で金持ちになった人たちがいるのだから。しかし、ヘンリエッタの細胞は、ゲノム配列が完全に解読された細胞として、さらに3度目の人生を歩むことになるという見通しが、NIHを予防的措置に向かわせたのである。
細胞は物質的なものである。細胞は物質であり、皿の中で育て、栄養を与え、毒素にさらし、光らせ、現代科学が利用できる高度な機器を使って写真に撮り、数を数えることができる。しかし、ゲノム医学の時代には、細胞は、これまで見てきたように、より重要な情報の図書館でもあるのである。もちろん、それぞれの細胞には、人、バクテリア、植物など、その細胞が由来する生物のゲノム、すなわち全遺伝コードが含まれている。この情報は診断に利用され、遺伝子と元の生物の好ましくない状態との関連性を調べることができる。例えば、ヒトの場合、ゲノム情報は、目の色や数学的能力といった身体的・精神的特徴の指標となるだけでなく、ある人がある遺伝性疾患にかかりやすいかどうかを予測する根拠にもなる。遺伝子は世代を超えて受け継がれるため、ゲノム情報は本人だけでなく、家族に関する情報も提供する。例えば、乳がんや卵巣がんのリスクを高めるBRCA遺伝子が変異していると診断された女性の妹や母、叔母も、同じ変異を持ち、同じリスクにさらされている可能性がある。つまり、ゲノム情報は、その人の家族、一族、部族、民族のコミュニティに関する情報であり、完全に個人的なものではありえないのだ。
2013年3月、ドイツ屈指の生物医学研究拠点であるハイデルベルクの欧州分子生物学研究所(EMBL)のラース・スタインメッツとその研究チームは、HeLa細胞のゲノム配列を決定した。スクルートの著書ですでに提起された財産と同意の問題を考えると、アメリカの研究者がHeLa細胞をめぐって渦巻く生命倫理論争に目をつぶって入っていくとは考えられなかった。しかし、欧州のスタインメッツのチームは、まさにそれを実行した。彼らは、自分たちの研究が論争を巻き起こすかもしれないとは露知らず、HeLaのゲノム配列をオンライン医学雑誌『G3: Genes, Genomes and Genetics』に発表したのである。自分たちに相談がなかったことに落胆し、憤慨したラックス一家は、スクルート氏の強力な擁護に支えられ、G3論文の即時撤回を要求した。NIHのフランシス・コリンズ所長は、研究業界のリーダーが包括的な解決策を見出さない限り、科学は脅威にさらされると考えたのである。当然のことながら、彼は、科学が法律や政策の先を行くという、よく使われる比喩を持ち出した。「今回のHeLaの事態は、私たちの政策が科学に何年も、あるいは何十年も遅れていることを如実に示している。もちろん実際には、科学者は長い間、ヒト生物試料を使用する際の行動の適切・不適切について非公式の倫理的判断を行っており、今回の件でもNIHは、より公然とではあるもののその実践を継続しただけである。その結果、将来の研究者がHeLaゲノムの塩基配列にアクセスすることを認めるという歴史的な取り決めがなされたが、それはラックスの家族がその場に同席して検討した後でなければならなかった。
ヘンリエッタ・ラックスの生と死の正確な状況、そしてHeLa細胞株の驚異的な成長と活力は、決して再現されることはないだろう。しかし、この事件は、科学や技術が新たに利益を生む生産分野に進出する際に生じる、所有権や管理権に関するもろもろの問題に注意を喚起するものである。そもそも、財産と人格の境界線はどこに引かれるべきなのか。さらに、社会はどのような発見や発明に報いるべきなのか、発明者や新しい知識の生産に携わる人々の間で利益を共有するとしたら、それはいつ、どのように行われるべきなのか。その答えは、知的財産権の領域にある。この法的領域は、それが規制しようとする発明の領域と同様、不透明で、技術的で、結論の出ない図式化されたものである。また、科学技術が生物と非生物、人間と非人間との境界線を越えるような実体を生み出す場合、何が財産としてカウントされるかという概念の発展にも、答えが見出されることがある。
発明の報酬
現代の知的財産権はしばしば15世紀にまで遡ることができるが、王や政府は人類史の始まりから発明家を奨励し、褒賞を与えてきた。近世になると、国家にとって価値のあるもの(後に公共的価値のあるもの)を発明した者は、その発明の成果に対して、必ずしも永久にというわけではないが、排他的権利を与えられるべきであるという原則が生まれ始めた。アメリカ合衆国の建国者たちは、この原則を非常に重要視し、憲法に書き込んだ。第1条第8項には、「議会は、科学および技術の進歩を促進するため、その権能を有する。議会は、科学と有用な芸術の発展を促進するため、著作者および発明者に、その著作物および発見について、限られた期間、独占権を確保する権能を有する。この権利を実現するために、議会は1790年に米国初の特許法を制定したが、1793年にはより行政的負担の少ない特許法に取って代わられた。
国務長官として国家初の特許審査官を務めたトーマス・ジェファーソンは、知的財産の独占という概念を特に不快に感じていた。アイデアや発明を独占的に管理することは、知識やアイデアを自由に共有することを自由民主主義の基礎と考える彼の啓蒙主義的想像力にはそぐわないものであった。1813年、ボストンの工場主アイザック・マクファーソンに宛てた手紙の中で、ジェファーソンは、アイデアを火に例えて、「火は、人から人へ渡しても、光を失うことはない。「その特異な性質は、誰もがその全体を所有しているため、少ない量を所有することができないことである。私から考えを受け取る者は、私の考えを減らすことなく、自らも教えを受けることになる。6 現代の経済用語では、思想は非競合的な財である。ある人が使用することによって、他の人の効用が制限されたり減少したりすることはない。ジェファーソンは、同じ書簡の中で、社会にとって有用な「アイデアを追求する人間の励みとして、そこから生じる利益の独占権を与えることができる」と述べているが、一般的には、無制限の独占は「社会にとって利益よりも厄介なことをもたらす」
ベンジャミン・フランクリンや他の人々が支持した独占的権利の期限制限のほかに、米国の知的財産法には、特許がコストよりも利益をもたらすことを保証するためのさらなる条項が含まれていた。最も重要なのは、特許を取得できるものの種類を制限することであった。このリストは、専門的には「特許可能な主題」として知られ、1793年の特許法では「あらゆる新しくて有用な技術、機械、製造、物質の組成物」、およびこれらの項目の新しくて有用な改良を含んでいた7。ジェファーソンは、マクファーソンに宛てた手紙の中で、すでに特許を取得しているものから用途、材質、形状を変えただけという理由で、特許を取得できない発明について長々と述べている。このような小さな変更は、社会にとって真に価値のある発明を奨励し、それに報いるという法の中心的な目的を達成することができないからだ。
特許の付与と異議申し立ての手続きは、ジェファーソンの時代とは比べものにならないほど変化している。1982年に連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が設立され、重要な制度改革が行われた。CAFCは、12人の裁判官からなる専門法廷で、すべての特許不服審判を審理する。しかし、この法律の主題条項は、18世紀の原文に極めて近く、「技術」の代わりに「プロセス」という言葉が使われているに過ぎない。
新しい有用な方法、機械、製造、組成物、またはそれらの新しい有用な改良を発明または発見する者は、本号の条件と要件に従って、そのために特許を取得することができる9。
さらに、この法律は、発明が自明でないこと、すなわち、関連分野の技術状況に精通した者が既存の発明から直ちに導き出すことができないものでなければならないと定めている。「新規」、「有用」、「非自明」という 3 つの重要な法律用語の意味と、特許可能な主題を定義する用語は、科学と産業の状況の変化に合わせて絶えず再解釈されてきた。民主主義的価値観の観点から特に重要なのは、バイオテクノロジーに関連する発展である。ヘンリエッタ・ラックスの物語が示すように、生命のあらゆる側面の所有に関わる事件は、自由な科学的探求、技術的発明、そして人間の生命の尊厳と完全性という要求の間の適切なバランスについて、厄介な倫理的問題を提起するものである。
身体、細胞、そして自分自身
NIHがラックス一家と結んだ歴史的な妥協案は、HeLa細胞が科学研究所で流通し続けることを認めながらも、その細胞の情報内容へのアクセスを管理するというもので、ユニークな状況から生まれたものであった。それは、生物医学研究における支配と差別のパターンを思い起こさせる痛みを伴うものであり、国のトップ科学者たちがこれをきっぱりと終わらせたいと願っていたものであった。NIHの指導者は、この決定を商業ではなく、倫理に基づくものとして扱おうと決意していた。NIHとラックスの取引では、金銭の授受はなかった。しかし、遺族から補償の問題が持ち上がった。しかし、ラックス博士のケースは、一般的なものではないということで意見が一致した。一般化できるものではない。NIHのハドソン副所長も、「これは前例にはならない」と強調している10。
このように、HeLaの和解は、第5章で未解決のままになっていた、より広範な問題に対する一般的な解答を提供するものではなかった。抽出された生物試料は誰のもので、その使用から生じるかもしれない医学的に有用な派生物から利益を得る権利を有するのは誰なのか。あらゆる種類の医療プロセスにおいて、血液、尿、唾液、あるいは外科手術で摘出された臓器の組織など、患者の体内から細胞や組織が抽出される。米国各地のバイオバンクには、このような生物試料が何億と保管されているが、これは遺伝子解析が容易にできるようになるずっと以前、つまり生物学とデータまたは情報との境界が破られる前に収集されたものである。初期には所有権に関する境界線の問題があったが、それは州裁判所で断片的に解決され、首尾一貫した公共政策には至らなかった。その結果、ヒトの生物学的標本から抽出された情報に対する知的財産権を法律がどのように規定すべきかは、依然として不明確なままである。
1970年代、カリフォルニア州で初期のテストが行われた。シアトルの実業家ジョン・ムーアは、まだ31歳だった1976年、毛状細胞白血病の治療のため、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)に向かった。UCLAのデビッド・ゴルド博士率いる医師たちは、彼の脾臓を摘出し、命を救った。しかし、ムーアの知らないところで、彼らは彼の体から摘出した組織の研究を続け、「Mo」という特許を持つ細胞株に発展させたのである。しかし、UCLAの研究者たちが突然、自分の組織から作られた製品に関するすべての権利を放棄する同意書にサインするように要求し始めたので、ムーアは不審に思った。この時初めて、UCLAの研究者たちが、Mo細胞株やその他の特許をもとに、いかに大きな利益を得ているかを知った。
カリフォルニアの裁判所は、ムーアの訴えが提起した、道徳的に重大な意味を持つ問題について、これまで一度も検討することを求められていなかった。私たちの身体と自己の関係はどうなっているのだろう?私たちの身体は、物理的な所有物と同じで、どうなるか完全にコントロールできるのだろうか?それとも、私たちは自律的な代理人として、医療行為などの物理的干渉に同意する権利だけはあるが、切除された組織やその他の遺物をどうすべきかを指示する権利はないのだろうか。カリフォルニア州最高裁判所は1990年、John Mooreは通常の意味での癌細胞を所有しておらず、その切除と生物医学研究への使用は違法ではないとの結論を出した12。7年にわたる訴訟の末、ムーアさんは、その見落としに対して、形だけの補償を受けた。その後 2001年にがんで56歳で亡くなるまでの20年間、患者の権利の擁護者となった。
前立腺外科医として知られ、ワシントン大学に長年勤務していたウィリアム・カタローナ博士は、何千人もの患者を治療し、研究参加者となり、自分が研究責任者となる研究のために組織サンプルを保管することに長年にわたって同意していた。2001年、カタローナは前立腺癌の遺伝子検査に協力するため、バイオテクノロジー企業に自分のサンプルを提供することを申し出た。大学の技術管理室は、この計画を知って、大学に利益がもたらされる可能性があると考え、WUにもっと経済的な利益をもたらすような取引を交渉しようとした。カタローナ氏は、この妨害行為に業を煮やしたのか 2003年にWUからノースウェスタン大学へ移ることを決意し、組織コレクションの一部を持ち出すための準備を始めた。彼は、WUの研究参加者約6万人に手紙を送り、次のような文言を含むリリースフォームに署名するよう依頼した。
私は、ウィリアム・J・カタローナ博士の研究のために、組織や血液のサンプルを提供した。ノースウェスタン大学のカタローナ博士の要請に応じて、私のサンプルをすべて開示してほしい。私は、これらのサンプルをカタローナ博士の指示の下、博士の明確な同意を得て研究プロジェクトにのみ使用するよう託した。
カタローナ博士は6,000枚の試料を受け取ったが、今度は大学が介入し、試料提供の妨害と保管資料の所有権を得るためにカタローナ博士を提訴した。
5年余りの法廷闘争の末、第8巡回区連邦控訴裁判所は、大学側に有利な判決を下した14。裁判所が見た主要な問題は、医学研究のために故意に生体試料を研究機関に提供した者は、第三者に所有権を譲渡する権利を保持するかどうかということであった。裁判所の答えは、「ノー」であった。研究に参加する際に署名した同意書に基づいて、参加者はWUに自発的に贈与したと結論づけたのである。そして、研究参加者の権利として残っているのは、研究参加への同意を取り消す権利と、場合によってはサンプルの廃棄を要求する権利だけである。カタローナ博士にサンプルを渡すという選択肢はなかったのだ。
しかし、組織の所有権をめぐる一連の州裁判所の判決は、創薬や商業的利益につながる研究が、生物試料の保護という個人の利益よりも重視されるという優先順位の尺度を指し示している。ある州の法的判断が他の州を正式に拘束することはないが、MooreはCatalona事件における第8巡回控訴裁の考え方に影響を及ぼした。ムーア、カタローナ、および関連する数多くの訴訟では、研究参加者が自分の物理的試料に対する権利をほとんど持たず、ましてやそこから得られる情報や製品に対する権利もないままであった。こうして、病気の身体から採取された物質は、単なる物質となり、患者個人がコントロールできるような物質ではなくなってしまったのである。後述するように、このような線引きの正当性は、技術の進歩が妨げられるという恐怖から生まれたものである。この恐怖は、たとえ裁判所が、人間の自己を市場性のある商品に変えるという行き過ぎを抑制しようとするときでさえ、生物学と知的財産に関する司法判断の領域全体に大きく立ちはだかる。
特許のための生命の再創造
初期の特許法制定者は、「新規かつ有用な技術、機械、製造、組成物」を特許の対象として挙げたとき、何を念頭に置いていたのだろうか。そのヒントとなるのが、彼らが用いた事例である。トーマス・ジェファーソンは、マクファーソンへの手紙の中で、帽子、靴、櫛、バケツ、粉砕機、農機具など、最も家庭的なもの、つまり実用的なもの、そして完全に無生物であるものを例に挙げて、自分の主張を説明したのである。特許法制定後の最初の数年間の特許実務は、初期の立法者たちが何を適切な主題と見なしていたかについて、さらなる洞察を与えてくれる。米国初の特許は、1790年7月31日、サミュエル・ホプキンスに、カリウムベースの工業用化合物であるポタッシュとパールアッシュの新しい製造装置と製造方法に対して与えられた。この最初の年に特許を取得したのは、ロウソクの新しい製造方法と、アイザック・マクファーソンと敵対していた多作な発明家オリバー・エヴァンズの自動製粉機の2件だけであった。これらの発明や製法が特許に値するものであることは間違いなく、その実用性にも疑問の余地はなかった。ただ、その新規性だけが問われた。特許制度をめぐる初期の対立の中心は、当然のことながら、新規性を立証するためのコストと遅延であり、発明家たちはこれを苛立たしく、あるいは耐え難いものと感じていた。
しかし、20世紀の最後の四半世紀になると、工業生産は機械、化学薬品、鉄鋼など日常的に使用されるハードウェアとの従来の関わりから、生命体である生物にも及ぶようになった。自然界のデザインは、第二次産業革命と呼ばれ、ナノテクノロジー、認知科学、情報技術などの進歩の中心的な存在となった。新しい種類の価値ある商品が誕生し、何が特許可能な対象物だろうか、また、より一般的な財産だろうかという旧来の概念に疑問を投げかけることになった。法的判断により解決された問題もあったが、発明者の主張が、生命のある側面は私的所有権の主張の対象とすべきではないという根強い文化的期待にぶつかり、新たな問題が生じたのである。
生命に関する特許
1970年代初頭、インドの西ベンガル地方で生まれ教育を受けたアメリカ人生化学者のアナンダ・M・チャクラバーティは、ニューヨーク州シェネクタディのゼネラルエレクトリック(GE)研究所に入社し、石油中の炭化水素の混合物を分解するバクテリアの設計に取りかかった。チャクラバーティは、バクテリアが石油を分解するための遺伝子がバクテリアの染色体ではなく、プラスミドと呼ばれるDNAの輪の中に存在し、生物間で移動可能であることを発見した。そして、このプラスミドを使いこなすことが、やがて功を奏する。やがてチャクラバーティは、既存の4種類の細菌のプラスミドからDNAの断片を融合させ、油を分解する新しい種類のシュードモナス細菌を作り出したのである。
GE社の上司は、この成果を知ると、GE社の製品ラインから大きく外れているにもかかわらず、産業界の研究所では当たり前のように、この発明の特許を取るように勧めた。チャクラバーティは、歴史家のダニエル・ケブレス(Daniel Kevles)に、「製薬会社なら、自然界に存在するものには特許を出せないという 「product of nature」の適用除外があるので、生物を特許化するのは躊躇するだろう」と言った。しかし、この事件を担当したGEの特許弁護士レオ・I・マロッシは、「冷蔵庫、プラスチック、ジェットエンジン、原子力発電所などの特許出願に慣れており、何か新しく有用なものを発明したならば、それについて合法的に主張できることは何でも特許にするのが当然だと考えていた」と述べている。「マロッシは、米国特許商標庁(USPTO)、そして最終的には裁判所を説得して、特許法上、人間が作ったバクテリアはGEが保有する他の有用な機械と何ら変わりはないことを認めさせなければならなかったが、それでも前進したのだ。
チャクラバーティ氏の主張は、1980年に最高裁に到達するまで、ジェットコースターのように不確かなものであった。米国特許商標庁(USPTO)は、当初、生物は特許にならないという理由で、彼の訴えを却下した。その後、この事件は、現在の連邦巡回控訴裁の前身である関税特許審判院に移り、数学的アルゴリズムの特許性に関する最高裁判決の前と後の2回に分けて審理が行われた。その結果、2回ともUSPTOの判断を覆し、Chakrabartyの主張を支持した。その後、特許商標庁は最高裁に上告し、最高裁は5対4で、チャクラバーティ氏のバグに対して特許を付与することを妨げる法律は存在しないとの判決を下した。Diamond v. Chakrabarty事件の判決は、生物と非生物の違い17は、発明者の製品特許の主張とは無関係であると結論づけた。1952年の議会報告を引用して、裁判所は、「太陽の下で人間が作ったものなら何でも」特許を与えることができるという、主題条項の事実上無制限な解釈を支持したのである。
特許を取得できる対象を非生物的なものに限定することを嫌った多数派の主張は、アミカス・キュリエ(法廷の友人)による主張から強い支持を得ることができた。特に影響力が大きかったのは、遺伝子スプライシングや組み換えDNA(rDNA)の技術の共同発見者であるハーバート・ボイヤーが設立したバイオテクノロジーの新興企業、ジェネンテックが提出したアミカス・キュリエであった。ジェネンテック社が資金を提供した研究により、1978年に実験室で作られた最初のヒトインスリンが作られた。科学者たちはrDNA技術を使ってインスリン産生遺伝子を合成し、それを大腸菌に挿入し、インスリンを作るための生きた「工場」として機能させた。この方法は、牛や豚の膵臓からインスリンを抽出する従来の方法に代わるものであった。この方法によって、インスリンがより安く、より豊富になることが期待された。
ジェネンテック社が最高裁に提出した準備書面では、チャクラバーティーの細菌と、法律が当然保護しようとする生命の尊厳との間に類似性があることを軽視しようとした。事実上、同社は、要求された特許は生命体ではなく、バクテリアの体内にあるプラスミド、すなわちDNAの無生物的なリングに対するものであると主張した。プラスミドは「死んだ化学物質」であり、「物質の組成物」という表現で適切にカバーされるはずだ。さらに、ジェネンテック社は、USPTOはプラスミドと藁の混合物の特許を喜んで認めているようだ、と指摘した。バクテリアの中のプラスミドと何がそんなに違うのか?この準備書面は、修辞学的な質問を投げかけている。「議会は、無生物である藁の中の生物に特許を与えることを意図し、微生物の中の無生物である化学物質の断片には特許を禁止したと言えるのだろうか。
このような常識への訴求は、司法判断の一般的な文化によく合致していた。コモンローの裁判官は、漸進的な議論を受け入れるように仕向けられており、司法の権威を利用して推測的で遠い未来を予測したり介入したりすることを好まない19。これとは対照的に、法律は前例を振り返り、直近の、容易に想像できる被害から身を守るために主に前進する。従って、予想通り、ジェネンテック社の主張は、当時、遺伝子操作の無秩序な発展を最も声高に批判していたジェレミー・リフキン氏が主張した、より遠い、ディストピア的、そして彼らの見解では政治的配慮よりも説得力がある、と判断したのである。リフキンの組織である人民商会(PBC)は、アミカスブリーフの中で、生命あるものに特許を与えれば、必然的に生命の商業化が進むと警告した。「もし微生物に特許が認められれば、科学的にも法的にも、より高等な生命体に特許を拡大することを阻む『生命』の定義は存在しないことになる」20。「20 裁判所は、このような坂道の構想を否定し、その意見の最初の行から、唯一の狭い関心事は「生きた人間が作った微生物が35 U.S.C. § 101の下で特許可能な対象物だろうかどうかを判断すること」であると主張している。
後知恵で考えれば、リフキンの立場はいくつかの点で先見の明があったように思われる。PBCが予言したように、チャクラバーティは、より高次の生命体の特許化への扉を開いたのである。生命と非生命の区別がなくなれば、牡蠣やマウス、あるいはもっと大きな哺乳類の特許を否定する正当な理由は誰も見いだせなくなるのだ。しかし、USPTOは慎重な姿勢で臨んだ。ハーバード大学の研究者が、遺伝子操作によって癌になりやすくした実験動物で、抗癌剤の実験に大いに役立つとされるオンコーマウスの特許を取得したのは、1988年になってからだ。それ以来、米国は遺伝子操作動物に関する何百もの特許を発行してきたが、すべての国がそれに追随しているわけではなく、また同じように熱狂的な支持を受けているわけでもない。
欧州特許庁(EPO)も動物特許を認めているが、特許は公序良俗に反してはならないという欧州法の制約がある。公序良俗とは、フランス語で文字通り「公序」を意味するが、特許の文脈ではしばしば「道徳」と訳される22。2つの特許出願は、1つは許可され、もう1つは却下されたが、このようなバランス調整の影響を示している。一つ目は、ハーバード・オンコーマウスの欧州特許に関するもので、EPOは度重なる評価を経て2004年に承認したが、特許の対象をマウスに限定し、他の非ヒト種を排除している。2つ目は、アップジョン社が毛髪再生や羊毛育成のための製品を試験するために作製したヘアレスマウスに関するものである。オンコーマウスの場合は医学的な効果が期待できたが、EPOはマウスに与える影響を相殺するような効果はないと判断し、特許を認めなかった。
2002年、カナダの最高裁は、ハーバード大学のオンコーマウスの特許を否定すると同時に、すべての高等動物に対する特許を広く否定する判決を下し、さらに別の道を選んだ。この判決は特に興味深いもので、カナダは特許可能な主題の定義に米国とほぼ同じ言葉を用いている(カナダは「プロセス、機械、製造または物質組成物」とともに「芸術」という言葉を残している)。しかし、カナダ最高裁の大多数は、動物は単に「物質の組成物」の一つとして扱われるべきだという米国の見解に同調することを拒否している。マウスは、たとえオンマウスであっても、その遺伝的組成を超える品質と特性を有している、と裁判所は結論づけた。この見解によれば、動物は、ジェネンテックが「死んだ化学物質」と呼ぶものに適用される単なる工学的スクリプトではない。そうではなく 「マウスが癌の素因を持ち、それが人間にとって価値あるものだろうからといって、マウスが他の動物生命体とともに、その構成要素である遺伝物質のみを基準として定義されることを意味するものではない」23。
カナダの裁判所は、特許を受けることができない高等動物と特許を受けることができる下等生物を分けるものは何かを論じておらず、そのような基準は他のどこにも明示されていない。カナダでは、バクテリアは特許が取れ、マウスは特許が取れないということだけが分かっている。より寛容な米国の体制においても、人間は特許の範囲外である。しかし、どこまでが範囲外かはまだ定義されていない。この問題は、生物学的研究によって、ヒトの幹細胞をネズミなどの動物に挿入したヒトと動物のハイブリッド、すなわちキメラが新たに作られるにつれて、より重大になる可能性がある。1997年、ジェレミー・リフキンはニューヨーク医科大学の発生生物学者スチュアート・ニューマンと組んで、キメラの特許性について明確な線を引くようUSPTOを刺激した。彼らは、ヒトとチンパンジーの仮想的な交配種(ヒトジー24と呼ばれる)について、そのような交配種の構築方法をいくつか提案した上で、特許を申請したのである。しかし、USPTOは1999年に彼らの申請を却下し 2005年に再び却下している。2004年、米国議会は予算案に、「ヒト生物を対象とした、またはヒト生物を包含する請求項に関する特許を発行するために連邦資金を使用する」ことを禁止する修正案を追加した。この「directed to or encompassing」という言葉の正確な意味はまだ不明だが、USPTOは、ニューマンが説明したヒトジは、議会の禁止する範囲に入るほど人間に近いかもしれない、と述べている25。
遺伝子に関する後戻り
これまで見てきたように、自然界に存在するものを特許化することはできないというのが、特許法の定説である。すでに存在するものを単に発見しただけでは、発明とは言えず、発見者に特別な所有権を与えるべきでないという論理である。さらに、これまで記録されていない木や新しい種類の宝石を1つ見つけたからといって、その種のすべての木やすべての宝石を所有する権利を与えるべきではない。しかし、バイオテクノロジーは、自然界に存在するものを分離・精製する技術や、基本的な物質から複雑な物質を合成する技術を開発し、この原則の限界を試した。しかし、発明者や新興企業は、貴重なタンパク質をコードする単離されたDNAの列は「自然の産物」ではなく、特許を取得するべきだと主張した。1990年代初頭には、USPTOは、ヒトの遺伝子を含む単離および合成されたDNA配列に日常的に特許を付与するようになった。1990年初頭には、USPTOは、ヒトの遺伝子を含むDNA配列の単離および合成に関する特許を日常的に付与し、バイオテクノロジー企業は、単離された遺伝子に基づく診断検査やその他の製品を開発する独占権を得て、巨額の利益を得るようになったのである。このような政策に歯止めがかかることを期待する人はほとんどいなかった。
米国自由人権協会(ACLU)のタニア・シモンチェリ氏は、異なる見方をしていた。GEのマロッシ弁護士が、製薬会社の弁護士が恐れをなして踏み込まないような道を突き進んだように、シモンチェリもまた、正規の法的訓練を受けなかったが、法の固定性という前提にとらわれることなく、物事を考えていたのである。サイモンチェリは 2003年にニューヨークのACLUに、同組織初の科学顧問として入局した。コーネル大学在学中から長年にわたって公益活動に没頭し、バイオテクノロジーに関する政策問題にも関心と能力を発揮してきたシモンチェリは、新しい仕事(まだ定義は定かではないが)に臨むことになった。生物学と社会という専攻の一環として、科学と法のクラスでダイアモンド対チャクラバーティを読んで以来、彼女は生体の商品化、商業化が進むのを不快な思いで見ていた。そして、特許法の複雑さに心を奪われることのない、良識ある人々のほとんどが、彼女の考えに共感してくれるだろうと確信したのである。ACLUで彼女は自分の直感を試し、一見揺るぎない法原則を攻撃するための強力な味方を得た。
当時、ACLUのシニアスタッフカウンセルだったクリス・ハンセン氏は、サイモンセリ氏から「企業が人間の遺伝子を特許化している」と初めて聞いたとき、信じられなかった。「そんな馬鹿な!」と彼は言ったと記憶している。「その答えは、それほど単純なものではなかった。ハンセンは、訴訟の経験は豊富だが、弁理士ではなかった。シモンチェリ氏と組んだこの訴訟は、勝訴に至るまで7年の歳月を要した。まず、ハンセン氏がすぐに思いついたのは、有力な被告を見つけることであった。しかし、裁判所に認めてもらえるような原告をそろえるのも、技術的な論拠を示す科学専門家を登録するのも、簡単なことではなかった。どの作業も何年もの準備と努力が必要であり、その結果は途中の重要な段階での運に左右されるものであった。
ACLUチームが最終的に狙いを定めた被告は、ユタ州に拠点を置くミリアッド・ジェネティックス社だった。同社は、癌の原因となるBRCA遺伝子の特許を保有し、その遺伝子の存在を検出するBRCAnalysis©という商品名のテストを販売し、利益を得ている。ミリアド社は、他の特許保持者以上に、その市場を守るために冷酷な態度をとった。BRCAテストを実施することで縄張りを侵すと判断した科学者やクリニックには、断固とした態度で臨んでいた。その標的の一人が、ニューヨークのアルバート・アインシュタイン医科大学の遺伝学者ハリー・オストラー博士であった。1998年、ミリアドはオストラーに、もしオストラーが自分のクリニックで乳がん診断検査をしようとするならば、特許に基づくロイヤルティを要求する手紙を送ってきた。Ostrerはその手紙を保管しており、数年後、Myriad社の特許がBRCA検査の実施を妨げていると主張する根拠となる文書を手に入れたのである。この実害の主張により、オスラーは、彼を排除しようとするすべての試みから生き延びた唯一の原告であることが証明された。特に、ハーバード大学ミシガン大学ブロード研究所の創設者であり、オバマ大統領の科学顧問会議の共同議長でもあるEric S. Landerは、その代表的な人物である。
多くの要因がACLUに有利に働いたが、長年にわたって確立されてきたUSPTOの方針を打ち破り、何千もの特許と巨大な成功を収めている米国の製薬産業に影響を与える可能性があるこの取り組みは、多くの人にとって奇想天外で軽薄でさえあると映っただろう。しかし、その結果は最後まで不透明であり、Chakrabarty事件と同様、大きな浮き沈みがあった。ACLUに幸運が訪れたのは、ニューヨーク南地区連邦地方裁判所のロバート・W・スウィート判事にランダムに割り当てられた時だった。1922年生まれのスウィート判事は、ジミー・カーター大統領によって連邦判事に任命され、1991年に高齢のため引退していたが、現在も精力的に裁判をこなしている。その時の法律事務員が、バークレー校で学んだ遺伝学者のハーマン・H・ユエで、彼の専門知識は判事の審議に大いに役立つことになった。
2010年、Sweet判事は、Myriad社のBRCA特許を無効とする判決を下し、SimoncelliとHansenをはじめ、誰もが驚いた。しかし、この判決の根拠となった原則は、「自然の産物」の原則にほかならない。BRCA遺伝子は、Chakrabarty判決が要求したように、人体に存在する遺伝子と「著しく異なる」ものではなかったからだ。それどころか、「単離された」DNAは、その生物学的機能においても、コード化された情報においても、体内に存在する本来のDNAと同一であったのだ。したがって、自然界に存在する配列を含む「単離されたDNA」を対象とする本件特許は、法律上維持できず、35 U.S.C. § 101の下では特許性のない主題と見なされる」とSweet判事は結論付けた28。
しかし、ACLUが勝訴を宣言するには、連邦司法の階段をさらに2段上がらねばならない。Myriadは連邦地裁の判決を不服として控訴したが、次の段階は、挑戦者側にとってそれほど順調ではなかった。CAFCの3人の裁判官は、その設立以来、批評家たちからprobusiness and propatent *とみなされているが、最高裁が再考を求める前と後に、毎回2対1の多数決で、Myriadに有利な判決を下している。この2度とも、多数意見は、単離された遺伝子は特許性の基準を満たすと結論づけた。また、多数意見は、最も信頼できる構造的支柱の一つを解体することによって、繁栄する産業を弱体化させることに重大なためらいを示している。
不思議なことに、司法省は、ミリアドの遺伝子特許は無効であるというACLUの主張を支持する法廷報告書を提出した。USPTOに対抗して、政府は、Myriad社が望むものの多くを与えるが、分離したBRCA1およびBRCA2遺伝子を所有するという究極の報酬は与えないという中間経路を導こうとしたのである。この準備書面では、単離されたDNAと相補的DNA(cDNA)を区別し、後者は逆転写酵素という酵素を使ってメッセンジャーRNA(mRNA)から合成されるものであることを主張した。この違いを主張するために、政府準備書面は空想に頼り、単離された遺伝子は「魔法の顕微鏡」テストに引っかかるため、特許を取得できないと主張したのである。「しかし、人間が作ったcDNAは、天然のDNA配列とは異なり、cDNAは遺伝子のコード部分(エクソン)のみからなり、自然界に存在する鎖全体を構成する非コード部分(イントロン)は含まれないため、このような顕微鏡で見ることはできない29。したがって、cDNAはタンパク質を発現させるという点では対応するDNAと機能的に似ているが、人体の内部を顕微鏡で見た場合、まさにそのような相補的な配列を見つけることはできないのである。
政府の巧妙な類推は、CAFCを説得することはできなかった。顕微鏡で分子を見ることは、「手元にあり、使用可能な単離されたDNA分子を所有することとは、全く別物」だと考えたのだ。見ることは単なる発見であり、科学の仕事であり、好奇心を満足させることである。それに対して、遺伝子を単離することは、物質を操作し、有用なもの、それまで自然界になかったものを作り出すことであり、まさに特許法が奨励しようとする技術的な発明である。しかし、Eric Landerが最高裁に提出した準備書面は、CAFCの立場を大きく後退させるものであった。Landerは、科学的にも政策的にも最高権威の立場から、CAFCが、分離したDNAは体内では発生しないと考えるのは間違いであると最高裁に伝えたのである。それどころか、「ヒトの染色体の分離したDNA断片が、日常的にヒトの体内に存在することは、30年以上前から十分に立証されている。さらに、これらの分離されたDNA断片は、BRCA1およびBRCA2遺伝子を含む、ヒトゲノム全体に及んでいる」30。
最終的な判決を下すのは、今や最高裁の手に委ねられたのである。最高裁に提出された質問は、「ヒトの遺伝子は特許が取れるか」という簡潔で的を射たものであった。これに対し、裁判所は全会一致で司法省の中道的な立場を批准した。単離された遺伝子は、体内に存在するDNA配列と同じである。したがって、自然の産物として、特許を取得することはできない。一方、自然界に存在する分子のエキソンのみからなるcDNAは、自然界の産物ではないので、特許を取得することができる。何年にもわたる訴訟、矛盾した判決、そして絶え間ない不確実性の後、すべてが突然、とてもシンプルになったように思えた。アントニン・スカリア判事でさえも、彼の好きな花火のような言葉を抑え、同僚たちの判決に同意する一文にとどめたのである。
国境を越えた権利
生物学的情報とそれを医療や商業に役立てる能力は、今日、ますます多様化する関係者の間に分散している。各当事者は、新しい発明が最終的に構築されなければならない基盤の重要な部分を支配している。バイオテクノロジー企業は細胞や遺伝子を操作して、精製、分離、合成された製品を作り、製薬会社は検査や医薬品をコンセプトから市場に出すための研究開発を行う。ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)の改良で1993年にノーベル化学賞を受賞したアメリカの生化学者カリー・マリスのように、ブレイクスルー発見をしたのは一人であるとされる場合でも、そうした仕事は、経済、社会、法律の基盤の上に成り立っており、それなしには、受賞に値するような発見が価値を生み出すことはなかっただろう31。
18世紀西欧の知的財産法を活気づけた独創的な発明家という考え方は、21世紀の高度に分散した知識システムから生まれる複雑な所有権の主張を扱うには、あまりにも限界があるように思われる。知的財産の主張が国境を越えるとき、その適合性の欠如は最も顕著になる。国際条約や協定を通じて、このような国境地帯を規制する試みがいくつかなされているが、海賊行為と不当利得の両方が深刻な問題を引き起こす、依然として管理不十分な空間である。
先住民の知識
先住民の知識と、近代生物医学の発見や販売との関係も問題である。植民地時代、軍事的征服者や宣教師は、さまざまな病気に対して伝統的な植物性医薬品を使用する地元の人々の知識と習慣を自由に流用した。そして、その知識は帝国主義の中心地に持ち帰られ、新興の製薬産業の基礎となったのである。例えば、1630年代にはすでに、イエズス会の宣教師たちがエクアドルとペルーからキナノキの樹皮をヨーロッパに送り、マラリア熱による戦慄の治療に用いていたのである。やがて、キナノキは救命薬であるキニーネの原料になった。先住民の知識と資源から文字通り、そして比喩的に価値が引き出されたが、その見返りはなかった。
多くの人々は、今日の問題は、歴史的な支配と不当な富のパターンを引き継いでいると考えているようだ。先住民の治療者たちは人類にとって非常に価値のある資源を持っているが、西洋の知的財産法を定義する新規性、有用性、非自明性という考え方は、知識が共同的に保有され、健康上の利益が住民全体にもたらされる産業革命以前の社会の集合知を保護することはほとんどない。1992年の生物多様性条約(CBD)は、この不均衡を是正するために、先住民がその知識と資源の使用と利用に対して適切な見返りを受けるべきであると規定したのである。利益配分は、生物多様性の保全やその構成要素の持続可能な開発とともに、CBDの主要目的の一つである。第8条(j)は、締約国に対し、「先住民および地域社会の知識、技術革新および慣行を尊重し、保存しおよび維持」し、「当該知識、技術革新および慣行の利用から生じる利益の公正な配分を奨励する」よう指示している。
これらの規定は、生物多様性保護を促進するために植物や微生物の遺伝資源を採掘して収入を得る「バイオプロスペクティング」を奨励することを目的としている。CBDはまた、北半球の裕福な研究機関が、先進的な技術やノウハウと引き換えに地元の知識を共有することに同意する、それほど裕福でないパートナーを南半球に見つけることを奨励することによって、技術移転の基礎を作った。このような協定は、しばしば現地のパートナーが拘束力のある協定を結ぶ能力を見誤り、そのようなコミュニティにおいて誰が実際に自然の代弁者なのかという騒々しい議論を引き起こした32。しかし、一部のアナリストは、CBDの施行から20年の間に、制度的な学習が進んだと見ている33。
ジェネリック医薬品
もう一つの問題は、知的財産権制度が保持しがちな現代の社会経済的不平等から生じている。豊かな国は、貧しい国よりもはるかに容易に新しい技術的製品やサービスを生産し、アクセスし、代価を支払うことができる。その結果、貧しい国々は、海賊行為や特許侵害によって、欧米の特許制度が作り出した独占を回避しようとする多くの誘因が存在するのだ。世界の公衆衛生に甚大な影響を及ぼす行為として、特許を取得した医薬品の後発品を製造し、本来のコストのほんの一部で市場に流通させることがある。1994年以前、多くの発展途上国は、医薬品が生命と健康を維持するために必要であるという理由で、医薬品を特許保護の対象から除外していた。そのため、インド、ブラジル、アルゼンチンなどの国々では、北欧で特許保護されている変異株と化学的に同一または酷似しているが、はるかに安価なジェネリック医薬品の生産能力を大きく向上させることができたのである。北側のメーカーによれば、ジェネリック医薬品は、北側のメーカーに発明の苦労と失敗のリスクを負わせ、イノベーションを起こさず、単なる模倣をした企業に利益を還元するものだという。
1994年、ウルグアイ・ラウンドと呼ばれる国際貿易協議の場で、このような議論が展開され、貿易法の改正が行われた。関税貿易一般協定(GATT)において、関税障壁の低減の恩恵を受けるためには、知的財産権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)において、先進国並みの著作権や特許の保護を行う知的財産法を導入することが義務づけられたのである。法律は変わったが、TRIPSは富を貧しい国から豊かな国へ移すための新たな手段であると考える批判者たちをなだめることはできなかった。世界貿易機関(WTO)加盟国は、貿易システム全般の改革を迫られる中 2001年のドーハ会議で、低開発国への圧力をある程度緩和することに合意した。TRIPSに関する特別宣言では、HIV/AIDS、マラリア、結核などの公衆衛生上の危機に直面している国は、国民に必須医薬品へのアクセスを提供するためにTRIPSの要件を破る必要があるかもしれないことを認識した。このような状況下では、各国は強制実施権によって特許保護を回避し、必要な医薬品の価格を引き下げることができる。皮肉なことに、この改正条項が早くから試されたのは、発展途上の南半球ではなく、先進国の北半球であった。9.11とそれに続くアメリカでの炭疽菌テロ事件で、ドイツの製薬会社バイエルは、炭疽菌に対する抗生物質の治療薬として特許を持つシプロの価格を、アメリカによる強制実施権の脅威の下に大幅に下げることを余儀なくされたのである。
また、スイスの大手製薬会社ノバルティスが製造する抗がん剤グリベックについて、インドで訴訟が起こり、ジェネリック医薬品に対する現在の国際特許制度が不安定であることを示すシグナルがもたらされた。インド企業は、TRIPS以前、インドがまだ医薬品に関する特許を認めていなかった時期に、イマチニブという化合物の結晶体であるグリベックの後発品を製造・販売するようになった。その後、インドでTRIPSを導入する国内法が成立すると、ノバルティスは自社版の特許を申請し、その結果、価格は入手可能な後発品の10倍となり、ほとんどのインドの消費者にとって手の届かないものとなってしまったのである。2013年、インド最高裁は、グリベックは新特許法第3条(d)に該当しないと判断した。この特許法は、治療上の利点をもたらさないわずかな改良に基づく特許更新を禁止しており、一般に「エバーグリーン化」として知られている34。裁判所の見解では、ノバルティスは、特許申請をしたグリベックの特定の形態が、すでに市場に出回っている安価な特許切れバージョンよりも有効性が高いことを証明できず35、旧製品のエバーグリーン化でしかないとされている。
グリベック事件は、インド政府が既存の特許保護をTRIPSに同化させようとしていた時期に発生した。ノバルティスは、この移行期の最初と最後に、製品仕様を多少変えて2度グリベックの特許を申請している。このような状況は、他の多くの医薬品でも繰り返されることはないだろう。しかし、インド最高裁は、特許法の非中立性、政治的価値と知的財産保護の密接な関係、そしてその結果として知的財産に関する先進国と途上国の倫理的要求の不一致をわざわざ強調したのである。同裁判所は、他の裁判官が執筆した1957年の特許改革に関する報告書を、明らかに承認して引用した。
Ayyangar判事は、特許法の規定は、その国の経済状況、科学技術の進歩の状況、将来のニーズ、その他の関連要因を特に考慮し、特許独占の制度が陥りうる乱用を排除しないまでも、最小限に抑えるように設計されなければならない、と述べている36。
ノバルティス社の事件により、インドにおけるグリベックの特許性には決着がついたが、より大きな倫理的問題が残されている。知的財産法は無価値なものではなく、特定の国や地域の政治的・経済的嗜好を表現したものであるというAyangar判事の主張を受け入れるならば、特許制度間の差異はどの程度正当化されるのだろうか。2014年9月、C型肝炎の高価な治療薬を製造するカリフォルニア州のギリアド・サイエンシズが、インドのジェネリック医薬品メーカー7社と、層別グローバル価格体系を生み出すライセンス契約を締結したことが、今後の可能性を示唆している37。この契約により、ギリアドはインドで同社の薬を1錠10ドル(米国での価格の100分の1)で販売することとなった。この協定では、ギリアドはインドで、米国の100分の1の1錠10ドルで薬を販売し、インドのメーカーはギリアドにライセンス料を支払うが、患者が高価格の薬を買うことができない貧しい国々で、ジェネリック薬の販売を続けるというものである。しかし、これは2国の製薬会社間のその場限りの私的な合意であり、他の医薬品、企業、患者層にとって法的にも前例的にも価値のないものであった。
結論
科学は絶えず生命という書物のページをめくり、新しい事実と発明の機会をもたらしている。法の役割は、生命を尊重し、その多様性と繁栄に配慮するといった人間の基本的価値観に従って、社会がそれらのページの内容を読み、利用できるようにすることである。発明を奨励することを主目的とする知的財産法も例外ではない。発見者や発明者が夢見るものすべてに報いる必要はないのである。実際、資源配分が極端に不平等な世界では特にそうであるように、科学技術が広く共有されている価値観をあまりにも早く、あるいは軽率に先取りしているようであれば、法律はページを戻すことさえできる。このような場合、発明が常に国家的あるいは世界的な規模で公益とうまく調和しているという前提を再検討し、批判的に問い直し、それに伴って政策や法律を変更することができる。
欧州特許法の公序良俗規定は、特許性に道徳的な限界を設けることができることを思い起こさせる。オンコーマウスの特許を認めなかったカナダは、生命の商品化に対して上限を設定した。リベラルな米国でさえも、ダイヤモンド対チャクラバーティ裁判では、米国特許法は「太陽の下、人間が作ったものなら何でも」対象になると解釈し、米国の倫理、米国法、さらには米国の科学の基準からすると、時が経つにつれ、拡大しすぎていることが証明されたのである。NIHのラックス家との協定やミリアド社の遺伝子特許事件は、社会の価値観が「これは行き過ぎだ」と宣言すれば、自らの定説を覆すことさえある、法の創造的非線形性を見事に示している。
また、特許紛争は、個人の行動が既成の前提を覆す力を持つことも示している。チャクラバーティーの弁護士は、生命に関する特許を認めるよう最高裁に働きかけ、「自然の産物」の原則を回避することに成功した。NIHは、HeLaゲノムの情報へのアクセスを管理するためにラックス家を参加させることで、ラックス家の家長であるヘンリエッタ・ラックスの記憶を称えるレベッカ・スクルートの一途な活動に敬意を表したのである。NIHの決定は、自分の体を自分の知らないうちに、あるいは同意なしに研究に提供した女性に、死後の声を与えるものであった。ヒトの遺伝子特許については、米国特許商標庁という官僚的な機関が、単離された遺伝子も特許の対象になると解釈していた。タニア・シモンチェリとクリス・ハンセンが、多くの専門家が決まっていると考えていたこの政策を覆すために、ありえないようなキャンペーンを始めるまで、広く社会がこの問題についてどう考えているかは試されることはなかったのである。命に関わる問題である場合、個人の声がより深い流れに乗り、例外的に一般の価値観と難解な法律との間に再調整をもたらすことができるのは心強いことである。
例えば、ある地域で長年培われた文化的知識が、別の地域で大ヒット商品とそれに伴う利益の根拠となる場合、あるいは独占的な価格設定によって、必要な医薬品が手の届かない患者の手に届かない場合、特許権主張によって国境を越えた格差が生まれるとき、知的財産法が持つ正義感は最も痛切に感じられるものである。TRIPSによって知的財産権保護のグローバル化が試みられたが、その倫理的意味合いには疑問が残り、ドーハで署名された強制実施権条項によってそのすべてが解決されたわけではない。米国の特許法が生命の過剰な商品化に直面したときに調整を余儀なくされたように、世界社会は、必須医薬品に関する厳格な強制力を持つ特許を通じて生と死を規制する製薬業界の力について、いくつかの難しい考えを残さなければならないのである。幸いなことに、製薬会社、患者団体、活動家である医師や弁護士、そして世界の貿易体制は、すでにグローバルな生物医学の倫理にとって重大な意味を持つ対話に参加しているのだ。
CAFCが設立されたのは、特許判決には専門的な知識と特許政策への一貫したアプローチが必要だと考えられたからだが、設立以来、多くの人がCAFCの判決には重要な深みがなく、特許業界の虜になっているようにさえ感じてきた。例えば、David Pekarek-Krohn and Emerson H. Tiller, 「Federal Circuit Patent Precedent.」を参照のこと。David Pekarek-Krohn and Emerson H. Tiller, ”An Empirical Study of Institutional Authority and IP Ideology,” Northwestern University School of Law Scholarly Commons, Faculty Working Papers, 2010.を参照のこと。
第8章 未来を取り戻す
これまで見てきたように、テクノロジーはしばしば道具的な用語で定義され、あらかじめ定められた目的に対する手段として扱われる。しかし、そのような考え方は、現代の人間社会があらゆる道具や機器と築いてきたダイナミックで多面的な関係を包含するには、あまりにも狭すぎる。そもそも、道具的な技術理解は、人間の目的が明確に定義され、固定化されたものであることを暗に示している。しかし、このようなありふれた目的のために道具を使うことは、人間特有の行為ですらない。鳥類はそうである。ニューカレドニアのカラスは、長い棒を使って木の幹や動物の死骸から木を食い荒らす昆虫を掘り出す。実験では、このカラスは複数の道具を連続して使うことや、ワイヤーを曲げてよりよい把持具を作ることまで学んでいる。
ジェーン・グドールは、タンザニアのゴンベ川国立公園での野外調査で有名になったが、チンパンジーがさまざまな用途の道具を作り、使っているのを観察している。葉っぱやコケは原始的なスポンジとして、水を飲むための道具になる。枝や小枝、石はシロアリの巣を叩いたり浸したり、木の実や動物の骨を砕いて中身をすくい取ったり、ディスプレイにも使われる。ゾウもまた、非常に優れた道具の使い手である。ハエたたきとして使うために枝を切り落としたり、水を掘ったり、邪魔なものを壊すために石を使ったりする。また、訓練次第では、装填された絵筆を体幹の先で正確に操作し、同じ絵を何度も描くことができる2。しかし、これらの印象的な例に欠けているのは、実行すべき作業の本質に関する考察や、その結果、道具の使い手が最初から達成すべきと考えた目的の変化である。
実用性も予測可能性も、人間とテクノロジーの進化する関係を捉えていない。人間の技術的な巧妙さは、単純で決められた目的のために反復的な作業を行うことをはるかに超えている。芸術性、想像力、そして未知への挑戦が、技術への意志を支配してきたのである。2010年、ドイツの著名な映画監督ヴェルナー・ヘルツォークが、人間の手によって作られた最古の造形美術のいくつかを紹介した「忘れられた夢の洞窟」に足を踏み入れてみてほしい。アルデシュ川の旧流域の上にある崖の奥深くにあるフランスのショーヴェ洞窟の壁には、ポン・ダルクの壮大な開口部を通過する前に、氷河期の芸術家が動物を描き、その驚くべき数々を描いている。ショーヴェ洞窟の芸術は、その凝縮された豊かさと卓越した技術においてユニークだが、この時代、古代人は石や角や象牙を実用性のない表現に変え始め、芸術はより広範に開花したのである。ライオンの頭を持つ男や、ピカソに影響を与えた女性像など、ありもしないものを想像していたのだ。2013年に開催された大英博物館の氷河期美術展では、この抽象化とミニマリズム、そして先史時代の洗練された象徴主義を眺めながら、この時代が「現代人の心の到着点」であると宣言している。
氷河期の穴居人(そしておそらく女性も)が道具を使って、心の中にしか存在しないものを描いたり彫ったりしていたとしたら、私たち現代人はどれだけテクノロジーを使って、私たちの存在の最も基本的な目的を再想像しているのだろうか。私たちは何者なのか、何のために生きているのか、どう生きるべきなのか、未来はどうなるのか。美的・象徴的な感性の最初の萌芽から大きく飛躍したのは、テクノロジーが個人の目的だけでなく、集団的な目的にも役立つようになったときである。洞窟の壁に熊やバイソンやアイベックスを描くことは、孤独の中で可能であった。しかし、今日の技術的想像力は、世界をより深く、より多くの人々のために、そしてしばしば取り返しのつかないほどに変えることができる。もし合成生物学者が新しい生物の創造に成功すれば、あるいはコンピュータ科学者が人間の脳を越えて思考を結びつける方法を発見すれば、これらの発明は生命の始まりと終わり、認識の意味、そして人間の自己とは何かについての私たちの共通理解を変えることになるだろう。神経工学者がナノスケールの脳内インプラントによって人間の記憶を活性化したり抑制したりする方法を解明すれば、そのような可能性があるというだけで、忘却や、もしかしたら許しに関する私たちの現在の期待が一変することになるだろう。地球温暖化を防ぐために太陽放射を管理するジオエンジニアがいれば、大気中に放出されるエアロゾルが空を白くしたり明るくしたりして、地球上のすべての人の自然体験が変わるだろう。
つまり、テクノロジーは単に私たちが予見している目的を達成するためのものではなく、未知の、しばしば不確実な未来への扉を開くものであり、そこでは現在の社会的理解や慣習が根本的に変容する可能性があるのである。さらに、不確実性は、誘惑と同時に抑止力にもなり得る。人間社会にテクノロジーへの投資を促す明るい光は、約束が失敗し、予期せぬ故障が大規模に発生した場合に何が起こるかという暗い不安と手を取り合って行進する。SFは、そのような恐ろしい思惑に満ちている。故マイケル・クライトンは、恐竜を甦らせる知識と技術を持った科学者が、野生の生物の繁殖を制御しきれないという『ジュラシック・パーク』の世界を夢想している。クライトンは、『プレイ』という小説で、自己複製するナノボットの大群が、対抗技術で破壊する手段が見つかるまで、人体を殺し、コロニー化することを想像している。
フィクションは、技術的未来の限界を、非現実的な、時には不条理なまでに押し広げる。しかし、第2章で見たように、慎重な社会は長い間、将来の危害から身を守るために投資してきた。保険やリスク評価は、最悪のシナリオが何の警告もなく訪れ、人々を破滅に追い込むことがないようにするために発展してきたのであり、そこには技術進歩に伴うリスクも含まれる。確かに、農民が干ばつで、商人が嵐で、住宅所有者が地震、火災、洪水で被害を受けるという統計的に予測可能な事態を計算し、それに備えることは比較的容易である。例えば、合成病原体が逃げ出し、人間の免疫システムを圧倒して何百万人もの死者を出す、ナノボットが制御されずに複製されて製造者を殺す、あるいは気候変動が前例のない規模で世界の農業を荒廃させる、といった可能性である。しかし、こうした比較的遠い可能性をも想定し、回避しようとする努力はなされてきた。というのも、現在の目や頭ではほとんど予見することができないからだ。
この章では、現代社会が技術的未来を統治可能な空間として取り戻そうとした主な手続き的メカニズムを概観する。この空間は、社会の善の概念に適合し、制御の可能性を回避しないために安全に居住することができるものである。しかし、それぞれのメカニズムが、権力と熟慮のジレンマを引き起こしている。最も重要なのは、「包含」の問題である。熱心な技術生産者が世界の舵取りをしたいと望む未来を想像することに、誰が参加できるのだろうか。この最も基本的な民主主義の問題に加えて、テクノロジーの可能性について真に集団的な考察を可能にするような制度の設計に関する、より具体的な問題がある。技術評価、すなわち代替技術経路の体系的マッピングとその派生型である建設的技術評価、倫理的分析、そして熟議民主主義の再活性化を目指した市民参加の方法である。
テクノロジーアセスメント
振り返れば、1972年はベトナム戦争の終結やバングラデシュの誕生など、世界を変えるような政治的出来事があった年だった。また、スウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議、DNAの組み換えに初めて成功した実験室、そして最後の有人月面飛行となったアポロ17号の打ち上げなど、人類にとって重要な、技術的にもブレイクスルー年であったと言えるだろう。このような大きな出来事の中で、ほとんど注目されなかったのが、この年の10月に米国議会で制定された法律である。ハーバード大学の物理学・工学部長であったハーベイ・ブルックスを中心とする有力な学識経験者の発案によるものであった。彼らは、急速な技術革新に直面する連邦議会議員に、合理的な政策を立案する能力を身につけさせようと考えたのである。この法律の目的宣言には、「既存および新たに発生する国家的問題に対する公共政策の決定において、可能な限り、技術的応用の結果を予測、理解、検討することが不可欠である」と記されている。
この法律は、政策に関連した助言を求める議会のニーズに応えるため、新しい行政機関である技術評価局(OTA)を創設した。しかし、議員たちは、より良い情報の必要性に屈することで、専門家に権限を委ねすぎたり、暴走する政治的な派閥がOTAの専門知識を自分たちの都合の良いように利用するのではないかと懸念した4。議会は最終的に、小規模で、政治的にバランスが取れ、組織的にフラットで、外部のコンサルタントに大きく依存する制度設計に落ち着いた。OTAを統治するのは、上院と下院からそれぞれ6名ずつ、二大政党を均等に代表する12名のメンバーからなる技術評価委員会(TAB)である。理事会はOTAの理事を任命し、OTAが実施するすべての調査を承認した。OTAの職員は200人弱で、そのうち4分の3は研究者であった。それ以外は、産業界や大学から専門知識を持った臨時のコンサルタントのネットワークを使って研究を行っていた。政治に理性を持ち込むことを唯一の目的とした組織が、立法過程の荒波の中でどのように機能したのだろうか。OTAの22年間は、その不安定なバランス感覚と、より一般的には、アメリカの政治的意思決定に技術的知識を持った声を反映させることの限界について、いくつかの洞察を与えてくれる。
緊張はすぐに表面化した。ニクソン政権の末期は、軍備管理、医薬品の安全性、環境保護など、技術的な要素を含む多くの問題でリベラル派と保守派が分かれ、政治的に激しく対立した時期であった。OTAの初代所長のエミリオ・Q・ダダリオは、コネチカット州の元民主党下院議員で、OTA設立法の主唱者であったが、就任当初から党派的な雰囲気が漂い、バランスのとれた運営を期待することはできなかった。ダダリオは、TABの初代議長であるマサチューセッツ州選出のエドワード・M・ケネディ上院議員のもとで、主に民主党の政治家がTABを牛耳っていたため、あまりに擁護的であると見られていた。共和党のTABメンバーは、ケネディがOTAを買収し、自分のスタッフと政治的アジェンダの延長として再構築しようとしている、と非難したのである5。
その後のOTAのトップは、OTAを党派性から政治的中立性へと導き、議会の委員会から広く支持を得るようになった。三代目で最も長く長官を務めたジョン・H・ギボンズは、12年間の在任中にOTAのアイデンティティを大きく変化させた。1970年代にはほとんど単一の委員会がOTAの活動を後援していたが、1990年代には、1つの研究に平均して3つの委員会が後援するようになった。中立性を保つために決定的に重要な戦略は、直接的な政策提言を行わないことであった。その代わり、OTAは代替案を提示し、それぞれの選択肢の長所と短所を説明した。例えば、1991年に自動車の燃費向上を検討するよう求められたOTAは、基準の引き上げだけでなく、より効率的な燃料使用につながる経済的インセンティブや技術的設計など、他の選択肢も検討した。1980年の選挙でレーガンがホワイトハウスに当選し、規制緩和が叫ばれる中、ギボンズはOTAを廃止しようとする動きを阻止し、早くも政治的成功を収めた。その後14年間は比較的平穏だったが、1994年に起きた共和党の革命と呼ばれる2度目の激変をOTAは乗り切ることができなかった。
1994年の中間選挙では、ニュート・ギングリッチ下院議長が主導し、40年ぶりに共和党が連邦議会の両院を支配することになった。選挙公約「アメリカとの契約」は、減税、連邦予算の削減、民主党が過去に導入した数々の社会福祉制度の廃止など、10項目に及ぶもので、ギングリッチ氏は勝利に沸いた。勝利に酔いしれた新議会の多数派は、自らの支出を削減する必要性を象徴的にとらえ、OTAが再び俎上にのぼったとき、それを救おうとする熱意と意志はほとんど感じられなかった。OTAは、ある意味で自らの成功の犠牲者となってしまった。あるアナリストによれば、こうだ。
結局、OTAの資金援助が打ち切られたのは、それが大きすぎたからではなく、あまりにも小さかったからだ。OTAを廃止しても、議会は大規模な、あるいは十分に制度化された業務の損失を吸収する必要はない。予算削減への実質的な貢献はわずかであり、政府規模の縮小に対する議会のコミットメントをより大きく象徴しているように思われた6。
OTA は、アメリカの政策シーンにおける生きた存在として消滅したが、消滅したのはその資金であって、認可ではない。その結果、OTAは、アメリカの科学と工学の上級指導者たちの間で、黄金時代の亡霊のような存在として、また、気候変動のような緊急課題に取り組む理性のために立ち上がる勇気を持った議会が再び呼び起こすことができる存在として、生き延びているのだ。このように、元全米科学財団理事で著名な科学政策アドバイザーのニール・レインを委員長とする米国芸術科学アカデミーの権威ある委員会が2014年に発表した報告書「Restoring the Foundations」は、「国家の科学技術問題に取り組み、大統領と政策を調整する仕組みが議会にないことは、依然として大きな政策課題である”と指摘している。さらに本文では、OTAの「権威ある分析は、科学技術に関連する立法府の意思決定に不可欠であった」7と述べている。
しかし、20年後の今、OTAが「権威ある分析」を議会に提供するという使命をどの程度果たしたのか、また、その政策レポートが立法にどの程度影響を与えたのかは、依然として不明である。OTAの技術政策への貢献と、技術的意思決定の民主化および国家の技術的未来を健全な基盤の上に置くという包括的な目的を説明するものとして、3つの事例を取り上げることができる。ここでは、軍備管理、バイオテクノロジー、技術評価に関する事例を紹介する。
スターウォーズの議論
最初の事例は、国防政策、特に1983年にレーガン大統領が提案した戦略的防衛構想(「スターウォーズ」)に対するOTAの評価である。その1年後、OTAは反核団体「憂慮する科学者同盟」と協力して、大統領とその顧問が提唱したシールドは技術的に実行不可能であることを示す背景文書を発表した。この論文は、OTAの元職員で核分析の第一人者であり、このプロジェクトに関わったことでハーバード大学のジョン・F・ケネディ行政大学院の教授になり、最終的にはバラク・オバマ大統領の国防総省のトップになったMIT物理学者アシュトン・カーターの研究を大いに引用したものであった。しかし、リベラル派がOTAの評決を、科学が政治に打ち勝った素晴らしい例として賞賛したのに対し、この論文は、政治によって引き起こされた悪い科学であり、国家安全保障に対する無責任な無視だと、ヘリテージ財団やウォールストリートジャーナルなどのレーガン支持者から怒号が上がった9。反対派は、報告書を委託したOTA委員会がマクジョージ・バンディなどケネディ、ジョンソン政権のイデオローグで占められていたこと、報告書の主要作成者であるカーターが特別機密扱いで入手したデータを公開したことで特別な非難を浴びたことを非難した。
OTAの分析結果を支持する人々は、ミサイル・シールド案は実行不可能であるばかりか、ソ連のパラノイアに火をつけ、世界的な敵対国の膨大な核兵器を制御するために苦労して得た「恐怖の均衡」を不安定にすると反論している。その後、ベルリンの壁が崩壊し、ソ連が解体した後、一部の保守的なアナリストは、恐怖の力学が実際に米国に有利に働いたと主張した。つまり、競争的で防衛的な軍拡競争に参加したことがソ連の財政を疲弊させ、共産主義の崩壊につながったのだ。これらの議論は、十分な時間が経過し、綿密な歴史研究に必要な機密文書が入手可能になるまで、何十年も未解決のままであろう。しかし、今回のOTAの介入は、設計者が期待したような中立的な専門家の空間を切り開くことはできなかったと結論づけるのが妥当であろう。スターウォーズの背景論文は、冷戦時代の国防政策に関する不協和音のような議論の中で、もうひとつの大きな不協和音となった。リベラル派からは信頼され、受け入れられ、保守派からは政治的策略と見なされて、OTAの分析が、情報に基づく熟議民主主義の大義を著しく推進したと主張するのは難しいだろう。
OTAとバイオテクノロジー政策
OTAのホームページには、「生物学的研究と技術」という見出しで28の報告書が掲載されており、1981年の「応用遺伝学の影響」研究から、すでに閉鎖されたOTAが1995年9月に発表した「連邦技術移転とヒトゲノム計画」についての遺稿報告書までがある。その間にOTAは、遺伝子スクリーニングの職場への影響、法医学的DNA検査、他国の発展との関連における米国のバイオテクノロジー産業の位置づけなど、政策に関連する幅広いテーマについての報告書を作成した。1987年から1989年にかけて出版された5つの報告書は、特許から一般大衆の認識まで、バイオテクノロジーの「新展開」を取り上げている。しかし、1年に1回程度の報告書というこの素晴らしい記録は、最近の米国史の中で最も収益性が高く、論争も多いこの新興技術分野の倫理、政治、政策にどのような影響を与えたのだろうか。
レーガン政権時代に行われた最も重要な規制の決定の一つは、バイオテクノロジーに寛大であったことである。1980年に連邦最高裁が、生命体の特許は「人間が作った天下のもの」の特許と変わらないとしたように、大統領の科学技術政策室は1986年6月に、遺伝子工学にはバイオテクノロジーを対象とした法律を制定するほどの新しさはない、と判断したのである。バイオテクノロジー規制のための調整された枠組み」は、概して、既存の法律がバイオテクノロジーの製品をカバーするのに十分な管轄権を提供していると結論づけた。10 連邦政策は、製品の分類ごとに主導機関を指定する、「新規(世代間)生物」や「病原体」といった重要な用語の定義を統一する、機関間のタイムリーな情報交換を提供するといった手段によって、業務を合理化できるだろう。
このようなバイオテクノロジーに対する比較的自由なアプローチにより、米国は農業(グリーン)および医薬品(レッド)の両バイオテクノロジーにおいて、早くから業界のリーダーとしての地位を確立していたのである。しかし、第5章で見たように、米国の植物バイオテクノロジーが国境を越えて製品を輸出しようとするや否や、特に、より予防的なアプローチと有機農業への幅広い取り組みに基づく規制があるヨーロッパでは、次々と抵抗勢力に遭遇することになった。アメリカの消費者ですら、モンサントの市場帝国主義をまったく快く思っていないことが明らかになった。遺伝子組み換え食品をオーガニックと称して容認しない消費者や、遺伝子組み換え食品を含む食品の明確なラベル付けを求める州ごとのキャンペーンは、疑惑と、多くの人にとって完全な拒絶の環境を証明するものであった。
OTAがこのような問題を予見していたことを示すものはほとんどなく、また、調整フレームワークの代替案について効果的に議会に助言していたこともない。OTAは、その「新たな展開」シリーズである遺伝子組み換え(GM)生物の野外試験に関する1988年の報告書の中で、後に公然と論争となった技術的疑問の多くを検証している。例えば、この報告書は生物学的に類似した生物間で遺伝子が流れる可能性を指摘しながらも、破滅的な事故が起こる確率が極めて低いことを強調することによって、なぜか無害だろうかのように表現しているのだ。技術の新規性、リエンジニアリングに開放された生命システムの複雑さにもかかわらず、未知の未知(4章参照)はOTAの視野になかった。カリフォルニアで大論争を巻き起こし、結局商業的に成立しないことが判明したアイス・マイナス・バクテリアに関しても、OTAはほとんど心配ないと結論づけた。「しかしながら、いくつかの異なる研究が、長い最悪のケースの仮定(その多くは既知の事実と矛盾する)の下でも、アイスマイナス・バクテリアの大規模農業応用によって気候パターンが変化することはありえないと示唆している」しかし、これらの仮定の多くは、さらなる研究によって検証されることが有益である。
まとめると、OTAは、遺伝子組み換え作物の環境中への導入計画に関する申請書を審査する際に、議会に対して3つの選択肢を示したことになる。つまり、「生体の成長、繁殖、非標的種への遺伝物質の伝達能力に起因する問題」が存在する可能性を認めてはいても、他の市場前審査と何ら変わるところはないというものだ12。3番目の、最も好ましくない選択肢は、各申請を最大限の精査の対象とすることであった。
OTAの役割の一つが、価値ある問題に関して、より民主的な場である議会に専門知識のバランスホイールを回すことであったとすれば、そのバイオテクノロジーレポートは、振り返ってみると、その使命を果たしていないように思われる。OTAの政策提案のタイミングと内容は、将来の困難を予見するどころか、バイオテクノロジーについて独自に考えるよう議会世論を動員することにも著しく欠けていたのである。1988年には、ホワイトハウスはすでに「調整された枠組み」を発表し、実質的にOTAの最初の、最も押しつけの少ない選択肢を強く支持していた。この提案は米国の政策となり、現在もそうなっている。しかし、OTAが指摘した生物の特異性は色あせることはなかった。同様に、遺伝子の種間伝達は、カリフォルニア大学バークレー校のイグナシオ・シャペラによる、米国産トウモロコシの遺伝子組み換え形質がメキシコの地元で評価されている在来種を汚染したとする物議を醸した研究のように、バイオテクノロジーにつきまとう形で定期的に復活している14。
建設的な技術評価
OTAの米国外における影響力は、米国の国内政策に及ぼした影響力を上回ったかもしれない。しかし、ここでもOTA は、ベストプラクティスのモデルというよりは、ある考え方のインスピレーションとしての役割を果たした。1980年代には、欧州の多くの国が技術評価の原則を採用し、科学技術的な要素を含む事柄について国会議員を支援する専門機関の考えを導入した。デンマークとオランダはいち早くOTAと同様の事務所を設立し、いずれも1980年代中頃に設立された。英国は1989年にParliamentary Office of Science and Technology(POST)を設立し、委員会や個々の議員に情報提供やブリーフィングを行っている。POSTの任務の中に科学が含まれていることは、英国における研究と研究政策の重要性を物語っており、他の類似機関とは異なり、POSTは技術予測や政策アドバイスよりも情報提供の面でその役割を明確にしている。欧州全体の組織である欧州議会技術評価ネットワークは、様々な国の組織の間で情報共有や共同プロジェクトの機会を提供している。
技術評価は、多様な組織や政治文化にまたがって増殖し、技術分析を民主的な審議に結びつけるという各国固有の伝統に従って、さまざまな路線で発展してきた。1984年にオランダ技術評価局(NOTA)が発表した政策文書に見られるように、建設的技術評価(CTA)として知られるようになった戦略もその一つである。NOTAの出発点は、技術の設計に市民の意見を取り入れるべきであるという見解であった。これは、コンセンサス会議のような参加型プロセスを通じてのみ可能であり、プロトタイプの市民が政策立案者のために、与えられた技術をどのように進展させたいかを積極的に明確にするものである。CTAは、「アクターの歴史的経験、彼らの未来に対する見方、インパクトの約束や脅威に対する彼らの認識」がテクノロジーの進歩に絶えずフィードバックされるように、テクノロジーと社会の間で常にコミュニケーションが必要であると想像している15。このビジョンは、コンセンサスベースの政策立案の強い伝統を持つ国で反響を呼び、オランダのさまざまな機関や業界団体が、医療政策などの問題について市民参加の手続きを採用している。
CTAは、多様な視点を代表する専門家に依存しながら、市民や他のアクターから直接インプットする場を持たなかったOTAのアプローチとは、その設計において根本的に異なっているように思われる。しかし、CTAであっても、技術的軌道の設計段階に多様な主体が参加できるような、真に平等主義的な想像の空間を開くものなのか、それとも、政府や産業界があらかじめ決めた選択に対する国民の納得を得るための現実的な運動なのか、疑問が残るところではある。技術評価の派生形であるCTAには、技術評価の欠点と同時に、未来を集団で想像し適応するための様式としての長所も集約されているのであろう。
問題の核心は、CTAが政治ではなく、政策の側にどっしりと腰を据えていることにある。「建設的」という言葉は、技術に対する積極的なコミットメントを示し、時にはコミットメントを撤回することもあるが、それ自体が疑問の余地のないものである。CTAは進化的であり、革命的ではない。その手続き的なアプローチは、賢明で進歩的な傾向を確認するものだが、技術向上のための壮大な計画の倫理と格闘する場というよりは、実施のための技術として運営されている。したがって、CTAは対話、包括、情報に基づく討論を重視するあまり、石油経済の脱炭素化、人間の頭脳の強化と相互接続、絶滅種の復活、地球を冷却するための空の再設計など、通常の政治の範囲を超えた目的を達成するために人間が拡大し続ける技術力をどのように展開すべきかという、広範囲かつ険しい意見の対立には向いていないように思われるのだ。2つのグリーン・エネルギー・イニシアティブ(いずれも失敗作)は、技術政策の政治性がいかに国民の会話を傍観し、建設的な国民参加の可能性を本質的に排除しているかを、より詳しく見ることができる。どちらも、近代国家とその主要産業が密接に連携し、細分化された小規模な政治主体が排除されるというダイナミズムを物語っている。
第一は、米国におけるゼロエミッション車(ZEV)、すなわち電気自動車の話である。1990年、カリフォルニア州大気資源委員会は、ゼネラルモーターズを含む主要自動車メーカーに対し、ガソリン車の販売を継続する代わりに、今後8年間で保有車両の2%をZEVに転換するよう要求した。理論的には、CTAはこのような義務付けを実現するために必要な多層的な対話を行うことができたはずだ。しかし実際には 2006年の映画『誰が電気自動車を殺したか』で示唆されているように、ゼネラルモーターズは消費者の需要を損ない、おそらくは連邦政府や州の規制当局と結託して、今世紀に入るまでにカリフォルニア州のZEV義務付けを縮小させるように仕向けたのである。このドキュメンタリーでは、潰された電気自動車が、潜在的な関心を持つ一般大衆の力に比べて、企業-政府関係の乗り越えられない力を象徴している。
2つ目は、サハラ砂漠をソーラーパネルで覆い、北アフリカとヨーロッパに電力を供給するという、約5500億円をかけた野心的な計画「デザートック」の話だ。21世紀初頭のこの計画は、当初は技術的に可能性があるとされ、シーメンスやボッシュなどドイツの大実業家の間で盛り上がったが、期待された資金的裏付けを得ることができず、結局シーメンスなどの有力者が関心を失ったことで頓挫した。しかし、シーメンス社をはじめとする有力企業が関心を失ったため、結局は頓挫してしまった。イスラム原理主義が台頭してきたこともあり、北アフリカの混乱はエネルギー技術者の意表をついたようだ。最終的には「ユートピア的」「一面的」として退けられてしまったが、デザートックは、トップダウンの概念計画の限界、そしてより決定的なのは、技術政策の初期段階において、社会的知性を発揮して関係者を巻き込むための入り口が存在しないことを物語っている。
発明の倫理的な難問
人間が発揮することのできない、しかしどうしても発揮したい種類の変革的な力は、かつて神のみに帰するものとされていた。古代の病気や不正の悪を排除し、人間の心の奥底を探り、地球やその周囲で動くあらゆるものの働きを導くことができるのは神の知識だけだと、私たちの先達は考えていたのである。科学技術の進歩は、こうした超人的な能力の多くを私たちの手の届くところにもたらし、事実上、単なる人間が「神を演じる」ことを可能にした。しかし、傲慢さや無知による行き過ぎた行為に対する不安は根深い。技術開発が破滅的な被害をもたらす可能性を解き放ち、自然を人工物に変えてしまう恐れがあるとき、あるいは第5章で述べたように、人々が善意による改造から守られるべきと考える人間の本質的な特徴を破壊してしまうとき、こうした不安はすぐに表面化する。
国家の対応策のひとつは、政策によって、技術的な侵入を排除すべき領域を明確にすることであった。20世紀を通じて、多くの国が忌み嫌うような開発は行わないという合意のもとに、各国は団結してきた。国際条約は、人類の生存や地球環境を脅かす技術や、技術に支えられた社会的行動に制限を設けるものであった。核軍縮と核不拡散、化学兵器、地雷、残留性有機汚染物質の禁止、オゾン層破壊物質の段階的削減、絶滅危惧種の保護、無差別工業化に対する生物多様性と特異な自然環境の保護など、さまざまな協定が結ばれている。これらの行動のほとんどは、健康、安全、環境に対する物理的な損害に焦点を当てたものであり、限界的には人間の存在に焦点を当てたものであった。より稀なケースとして、取り返しのつかない精神的損害を与える可能性のある技術的活動を行わないという合意が生まれた。事実上、世界的に禁止されているクローン人間や遺伝的特性の改変は、まさにバイオテクノロジーが越えてはならない境界線に関する、広く(普遍的ではないものの)共有された直観に基づいているのである。
新しい技術や出現しつつある技術は、多くの倫理的な問題を引き起こすが、核兵器や人間のクローンがもたらす存亡の危機のレベルには達していない。新しい知識と新しい能力を求めて猛進する中で、科学とテクノロジーが公共の価値との接点を失い、言葉にはできないが現実の道徳的感覚を踏みにじることがないように、社会はどのようにして確認すればよいのだろうか。過去半世紀にわたる公的な倫理機関の発展は、その答えの一端を示すものである。多くの国が、技術進歩と社会的価値との調和を目指す政策実践として、倫理的審議を採用しているのだ。技術評価の様々な形態と同様に、これらのプロセスもまた、技術的未来に対する民主的統制を確保する上で独特の美点と限界を提供する。
技術に関する倫理的考察は、多くの西洋社会で生物医学とバイオテクノロジーの進歩に伴って始まった。この動きは、第二次世界大戦中にドイツの医学が行った恐ろしい虐待が明らかになることで緊急性を増した。主要な戦争犯罪裁判の後に軍事法廷で行われたニュルンベルク医師裁判では、23人の著名な医師や役人が、違法な医療実験と大量殺人の罪でドックに収監された。その結果、人間を対象とした研究の原則である「ニュルンベルク綱領」が採択された。その第一は、現代の生物医学倫理の基礎となる「インフォームド・コンセントの原則」である。この原則は、あらゆる実験において、「被験者の自発的な同意が絶対的に必要である」と述べている16。今日、世界中の主要な研究機関には、研究者が危険性のある研究に着手する前に有効なインフォームドコンセントを得ることを保証するために、米国では施設審査委員会(IRB)として知られる常設委員会が設置されている。
インフォームド・コンセントの原則とそれに関連する保護措置は、研究者個人とその実験対象者の間に最も直接的に適用されるものである。しかし、このようなニュルンベルク綱領の狭い解釈は、特に技術の進歩が親密な社会関係やリスクと利益の配分に大きな混乱をもたらす恐れがある場合、社会は技術やそのスポンサーに倫理的に責任を持たせる権利があるという戦後生まれのより広いコンセンサスの中に位置づけられるものである。この原則を正式に発表した単一の規範や憲法はないが、過去半世紀にわたる多くの個別の制度的発展が、事実上の超国家的立憲主義とみなすべきものの要素として、倫理的予測と配慮を支持している。その中核は、従来の技術評価における健康、安全、経済、環境への影響を補完する、倫理的な意味合いと結果の事前評価である。
技術革新の倫理的側面について社会が考察することを可能にする制度には、大きく分けて2つの形態がある。政治的に任命され、しばしば国家政策の問題に直接言及する非常に目に見える機関と、研究の日々のダイナミクスを管理する、ほとんど目に見えない経営的な機関である。国家レベルの委員会は、議題設定の権限を持つこともあるが、緊急の新しい問題に取り組むよう政治家から要請されることもある。さらに、このような委員会は、それぞれの国の政府の意思決定機関に対して非常に異なる位置を占めており、その権限はそれに応じて形成され、制限されている。
米国では、1974年に連邦議会が保健教育福祉省に生物医学および行動学研究の被験者保護のための国家委員会の設立を要請し、国家倫理機関が活動を開始した。この委員会の最も重要な貢献は、脳死に関する基準や、人間を対象とする研究を承認するための機関審査委員会の設置などであった。しかし、1988年から1990年にかけて運営された短命の生物医学倫理諮問委員会(Biomedical Ethical Advisory Committee)の失敗によって、立法府の主導は終わり、そのメンバーは両院から均等に集められたが、米国の中絶政治における厳しい行き詰まりを克服するには至らなかった。1996年以降、クリントン政権になると、国家生命倫理機関は大統領の明確な指示のもとに運営されるようになった。
大統領の意向であれ、議会の意向であれ、米国の国家倫理委員会は明らかに政治的圧力にさらされている。特にホワイトハウスが設置する委員会は、大統領の政治的・政策的嗜好に広く同調する傾向のある人々が率いている。2001年から2005年までブッシュ政権下の大統領生命倫理委員会の委員長を務めたレオン・キャス博士は、生物医学研究に関して保守的な傾向を持つことで知られている。一方、オバマ大統領は、大統領生命倫理問題調査委員会の委員長に、リベラル派として申し分のない政治哲学者であるエイミー・グットマン教授を任命した。グートマン教授の指揮の下、委員会は新技術の将来性を科学に委ねる一方、リスクが明白と思われる分野では主に注意を促した。例えば、著名な科学者であり起業家でもあるJ. クレイグ・ベンターが、自社が新しい合成微生物を生み出したと主張したとき、委員会は規制の必要性はないと結論付けただけでなく、報道機関が「神の演技」といった刺激的な言葉を用いて誤解を招く恐れを助長しないよう、公共の監視役を任命するよう勧告した18。
米国の主要大学において、研究の実施を監督する倫理委員会の一群が果たす役割は、それほど大きくはない。これには、人間を対象とした研究を担当するIRB、動物実験を担当するIACUC(Institutional Animal Care and Use Committees)、そして最近では、ヒト胚から幹細胞を採取することに対するアメリカ国民の関心に応えて作られたESCRO(Embryonic Stem Cell Research Oversight、または単にSCRO)組織が含まれる。国の倫理委員会とは異なり、試験管ベビーであるルイーズ・ブラウンやクローン羊のドリーの誕生など、一見するとブレイクスルー技術革新の後には、彼らの判断と安心感が求められることが多いのだが、IRB、IACUC、ESCROは研究事業のほとんど見えない召使いとして機能する。彼らは著しい倫理違反を防ぐことを任されているが、同時に科学者が考えるような科学の進歩を妨げないことも期待されている。委員は大学管理者によって学内の教職員から選ばれるが、(国家委員会の委員とは異なり)その専門性によって選ばれ、明らかな政治的選別やイデオロギー的バランスの要求の対象にはならない。
これらの委員会もまた、その倫理的想像力の範囲を制限する制約のもとに運営されている。委員会の立場は門番であり、委員会が分析を担当する理由によってリスクが高すぎると思われる研究の路線を阻止する力をもっている。倫理委員会は、所属する研究所の風評被害はもちろん、公的研究助成機関が重大な違反を発見した場合、罰金や研究員の停職といった重大な事態が発生する可能性があることを強く意識している。このような配慮から、ガイドラインの適用には細心の注意が必要だが、監視の目はしばしば、すべての正しいボックスにチェックが入れられているかどうかを確認する、かなり機械的なプロセスに還元される。一方、一流研究大学の倫理委員会も、優れた科学者にかかるプレッシャーには敏感である。最近の高水準の科学は激しい競争下にある。有名な出版物、助成金、賞は、大きな成果を得るだけでなく、それを最初に得るかどうかにかかっている。倫理委員会は、その構成と任務から、科学者の野心と優先順位に同情的で、急速な科学の進歩に対する社会の正当な利益と見なされるものに対して障壁を作りたくないという傾向がある。つまり、倫理委員会は新しい科学研究や技術革新の基本的な目的を問うのに最適な立場にないのだ。ほとんどの場合、倫理委員会はこれらの目的を所与のものとして受け入れ、その役割は監督者や敵対者ではなく、科学の助力者であると考える。
米国の技術開発プログラムでは、国民の倫理的考察のための資金を何度も確保していたが、そのような考察をどのように行うのが最善だろうかについて、単一のモデルは出現していない。最もよく知られているのは、1990年に開始されたヒトゲノム計画における倫理的、法的、社会的影響(ELSI)プログラムであろう。ELSIは当初、国立衛生研究所とエネルギー省が管理する集中的な資金提供プログラムとして運営されていた。その使命は、「問題を予測し、可能な解決策を見出す」ことであり、主に研究者主導の提案に資金を提供することであった。ELSIの研究は国立ヒトゲノム研究所で継続されているが、1990年代後半にプロジェクト資金は分散化され、ELSI 研究アドバイザ ーグループの監督下に置かれた19。
ELSIの歴史は、科学界もそのスポンサーである連邦政府も、倫理研究の資金調達に対するNIHの初期のアプローチに満足していなかったことを示唆している。その後、ナノテクノロジーや合成生物学への助成プログラムなど、それぞれの領域の倫理的、社会的側面に関する研究に対して、より厳しく管理されたアプローチを選択するようになった。当然ながら、このようなイニシアチブから出される提言は、「責任あるイノベーション」や「予見的ガバナンス」といった名目で、科学者が自ら取ることのできる行動を強調している。その前提は、研究過程に身を置く科学者が、場合によっては社内の倫理顧問の助けを借りながら、自らの研究に関連するあらゆるジレンマを理解し解決するのに最適な立場にあるというものである。倫理的分析は、広範な民主主義的目的よりも、むしろ道具的な目的に資するものと考えられている。
このような目的に適わない倫理的分析は、国民の支持に値しないものとして軽視される傾向にある。例えば、2010年には、カリフォルニア大学バークレー校にある合成生物工学研究センター(SynBERC)の倫理的側面を調査するために雇われた人類学の権威、ポール・ラビナウ教授と全米科学財団の間で異例の争いが起こった。NSFの審査では、ラビノフらが行った研究のある側面は、「積極的かつ発展的というよりは、主に観察的な性格を帯びているようだ」という結論が出された21。この言葉を解読すると、NSFは、危険性のある生物研究のためのセキュリティガイドラインを策定するSynBERCの進捗に不満であり、その目標は合成生物学の他の倫理面の探求よりも優先されるということであった。ラビノーは、倫理的な問題を研究するプロジェクトのThrust 4の主導権を事実上失い、代わりに内部の科学者であるドリュー・エンディがこの取り組みのリーダーシップをとることになったのである。ラビノーは数カ月間研究員として在籍したが、最終的にはSynBERCを辞職し、科学者が「生命操作の委託を受け、資金を提供しているより大きな社会に対する責任」に無関心であることを非難した22。
倫理機関の設計と運営は、国家間でも国内でも大きく異なり、公共の価値を取り込むための障害と機会がさまざまに混在している。ドイツとイギリスでは、道徳的に問題のある技術開発、特に生命科学や技術に関わる問題に対処するために、一般市民の意見がより多く反映されている。ドイツでは、行政ではなく議会が倫理的な審議のための国家機関を管理している。2007年に制定された倫理評議会法は、「研究開発に関連して生じる倫理、社会、科学、医学、法律の問題、および個人と社会に生じるであろう結果を追求する」ことを職務とするドイツ倫理評議会(Deutscher Ethikrat)を設立した23。意見、勧告、年次報告書を交えながら、評議会は生物医学研究の最前線を網羅し、特に既存の法律の適用範囲に隙間があると思われる問題には目を光らせている。例えば、2011年のヒトと動物のキメラに関する報告書では、「サイブリッド」(動物の卵子にヒトの核を移植したもの)のヒトの子宮への着床を禁止するよう胚保護法を改正するよう勧告している24。
科学、倫理的分析、法律の制定を公式かつ集中的に行うことを選択したドイツとは対照的に、イギリスは公共の倫理的審議に対して緩やかに構成された非公式なアプローチを採用することで、もう一方の極に向かった。Nuffield Council on Bioethicsは、英国の生物科学とバイオテクノロジーに関わる倫理的問題について継続的に審議と助言を行う最も著名な機関である。1991年にナフィールド財団によって設立され、英国の主要な生物医学研究資金源であるウェルカム財団と政府の医学研究評議会からの助成金によって支援されている。米国のELSIがそうであったように、同協議会のミッション・ステートメントには「予見」が大きく掲げられている。評議会の第一の目的は、「最近の生物学的および医学的研究の進歩によって生じる倫理的問題を特定し、定義することによって、公衆の関心に応え、これを予測すること」25 である。ここでは、専門家団体は一般の人々よりもはるかに先を見ることができ、その助言によって、政策立案者が公衆の懸念を払拭し得るという前提に立っているのだ。
ナフィールド審議会は、法律や行政命令によって招集されるわけではないが、その正統性を守るため、一般的な民主主義的規範に準拠している。最長2期3年の任期を務めるメンバーは、公募や専門家のネットワークを通じて選出される。他の公的機関と同様、性別、民族、専門分野などのバランスが保たれるように努めている。また、研究テーマは協議によって決定されるが、ホームページで一般からの提案も募集している。これらの手続きは、公的な国家機関が採用するようなものだが、審議会の最終報告に責任を持つ政治機関やアクターは存在しない。
まとめると、これらの事例が示すように、技術的未来に関する倫理的な審議の原則は、産業社会では当たり前のものとなっている。タイムリーな予測や予防的行動を通じて、起こりうるモラル上の危害を予見し、食い止めるという国境を越えた取り組みが行われている。しかし、政治的に任命された国家倫理委員会の声明や、多くの下部組織倫理団体の国内的で大部分は規則に従った仕事のように、最もしっかりと制度化された倫理分析の様式は、支配的イデオロギーと一緒になってしまうことがあまりにも多いようである。このような組織の急増は、優れた技術的未来に対する民主的な想像力、すなわち公共的な社会技術的想像力27と呼ぶべきものに取って代わり、組織の評判や被験者の健康や安全に対するリスクが明白であると専門家が認めた場合にのみ研究にブレーキをかける、より狭い技術的な展望を持つようになったようだ。では、一般市民を直接巻き込んで技術的未来を議論する取り組みは、果たして有効なのだろうか。
市民参加 万能薬かプラシーボか?
国家は、テクノロジーが、民主主義が最終的に依拠する基盤である被支配者の同意を確保するための強力なリソースであることを、長い間認識してきた。特に国家が攻撃を受けているとき、技術的なデモンストレーションは、政府が死や荒廃から国民を守る能力があると国民を説得することができる。裏を返せば、大きな技術的失敗が国家への信頼をひずませたり、損なわせたりする可能性があるということだ。1984年のインドのボパール事故、1986年のソ連のチェルノブイリ原発事故、1990年代のイギリスの第二次「狂牛病」などがその例である。狂牛病とは、致命的な変性脳症が牛から人間へと伝播し、専門家がその可能性は極めて低いと確信していたにもかかわらず、このような事態が発生した。これらの事件では、国家は、程度の差こそあれ、崩壊した国民の信頼の破片を拾い集めることを余儀なくされた。このような教訓的な物語は、民主主義の言説の中に入り込み、政府が大きな被害をもたらす可能性のある技術的プロジェクトに着手する際には、事前の同意が必要であることを強調するようになった。技術的意思決定への市民参加、より最近の用語ではパブリック・エンゲージメント(市民参加)は、市民が科学者、エンジニア、公務員と協力して、より包括的な技術的未来を構想する機会を提供するものである。このような活動は実際にはどのようなものであり、どの程度、技術開発の過程に市民の価値観を反映させることができたのだろうか28。
技術の制御に関する意思決定に市民を参加させる試みは、伝統的に法の傘の下で、伝統的な敵対的プロセスのメカニズムを用いて行われてきた。1946年には、連邦議会は行政手続法(APA)を制定している。これは近代的な法律制定におけるブレイクスルー出来事で、連邦規制力を行使する際の要素として、市民との協議の原則を明文化したものである。APAが成立する前の上院での審議で、この法律の主唱者の一人であるネバダ州のパトリック・マッカラン上院議員は、行政という「4次元」の統治が開かれたことを指摘したが、これは憲法が予見せず、明確に認めてもいない次元である。マッカランは、APAを「連邦政府機関によって何らかの形で管理・規制されている何十万人ものアメリカ人のための権利章典」29として、憲法用語で言及したのである。
APAが、専門家である連邦政府機関によってますます運営されるようになる民主主義の憲法上の基礎を築いたとすれば、1970年代の健康、安全、環境に関する法律の急増は、その基礎の上に、20 世紀後半の政府のスカイラインを支配する上部構造を築き上げたのである。大きな政府を批判する保守的な人々は、これを「政府の暴走」と断じるが、こうした立法は、連邦政策の最も難解な側面でさえも理解し影響を及ぼすことができる市民の能力に対する、あまりにも見過ごされがちな自信を示している。これらの法律は、市民を必ずしも「知っている」のではなく、「知ることができる」存在、つまり、効果的な自己統治に必要な知識を必要に応じて習得することができる存在として考えている。この認識論的に有能な市民という考え方は、トーマス・ジェファーソンからジョン・デューイ、そしてそれ以降のアメリカの政治思想に通底している。1980年代に盛り上がった規制緩和と新自由主義の熱気は、公共問題を解決する政府の能力だけでなく、共通の価値観に対して技術に責任を持たせる市民の能力にも疑問を投げかけた。事実上、規制緩和の流れは、数十年にわたる民主化法によって可能になった下からの継続的な批判的監視なしに、民間部門とその最も強力な代表者に、議題を設定し、専門知識を開発し、デザインの選択を行う権利を譲り渡したのである30。
100年にわたる米国の行政実務は、法的強制力のあるセーフガードの下で国家がイノベーターを規制するという技術民主主義のビジョンと、技術生産者が大衆の求めるものを想定し、主に市場の法律に従って商品を提供するという、より自由なビジョンの間を行き来してきた。しかし、リバタリアンたちは、デジタルメディアによって生み出された自己表現と自己統治の新たな可能性を、直接民主主義への歓迎すべき幕開けであり、国家のパターナリズムや、アグリビジネス、大手製薬会社、さらには正統派医学などの強力な利益団体による審議空間の占有に対する改善策であると捉えている。しかし、第6章で論じるように、インターネット時代の民主的な約束が、個人と集団の運命の支配を強めるのか、あるいは弱めるのかは、まだわからない。
米国における参加型の発展は、歴史的に国家がジャン・ジャック・ルソーのいう「一般意志」の管理者・実現者として大きな権限を享受してきた国々のそれとは著しく対照的である。アメリカの20世紀半ばを特徴づける市民の参加型権利の拡大は、西ヨーロッパの多くでは起こらなかったか、あるいはアメリカほど広範囲なものでなかった。権威主義的な国家や発展途上国は、例えば農業、エネルギー、経済、医療、産業政策など、政府によって大きくコントロールされる技術的選択の影響を受ける市民に声を与える手続き的な改革を採用するのがまだ遅かった。農業バイオテクノロジーの導入に反対する世界的な抗議運動(第4章参照)は、この観点から、直接民主主義の世界的事例として捉えることができる。一連のデモを通じて、世界中の小規模農家、環境保護主義者、開発批判者、その他の懐疑論者が、特定の形態の技術革新のみならず、その世界的普及を支える国家中心の政治に挑戦し始めたのである。
世紀末のイギリスにおける動きは、アメリカのケースとの対比において特に有益であり、市民参加に対する多様なアプローチの長所と短所を明らかにするものである。英国の行政実務は、政策の基礎として、緊密なネットワークを持つエリートたちの非公式な協議に歴史的に依存してきた。ごく最近まで、意思決定をオープンにするための正式な指令はほとんどなかった。米国の情報公開法は1966年に始まり、1974年にはウォーターゲート事件の公聴会に対応して大幅に拡大されたが、英国では政府情報へのアクセスをより限定的に許可する法律が2000年に制定されたばかりである。政策決定の基本は依然としてコンサルテーションだが、無審査の多人数を受け入れることによる混乱を恐れるかのように、ほとんどの場合、国家がコンサルテーションを受けるべき人を決定している。したがって、英国のアナリストの中には、より幅広い市民の意見や価値観を政策決定に取り入れることを目的とした「招かれざる客」の参加を求める声もある32。
テクノロジーに関する公開討論に多くの市民を参加させようとするある野心的な取り組みは、伝統的に閉鎖的なプロセスを開放しようとする試みが生み出す緊張を明らかにしている。これは、遺伝子組み換え作物の導入について世論を喚起するために、イギリス政府が1年がかりで行った「GM Nation」である。2003年、短命に終わったが影響力のある農業環境バイオテクノロジー委員会(AEBC)の助言で実施された33。GMネーションは、遺伝子組み換え作物に関する新しい重要な政策声明に情報を提供するためとされ、国内各地で600以上の公開会議とイベントが行われた。その結果、GM作物を支持する人はわずか2%で、95%が非GM農業の汚染を懸念していることが明らかになった。ほとんどの参加者は、農業バイオテクノロジーの利点についてかなりの不安を表明し、長い間主要な業界関係者の虜になっていると見られていた領域に対する独立した監視が存在しないことについてコメントした。しかし、「GMネーション」は明確な結果を出し、政府の規制当局も注視し、多くのマスコミの論評を呼んだが34、将来の審議のモデルにはならなかった。バイオテクノロジー擁護派は、この会議を反テクノロジー勢力の自己選択的な場とみなし、反対派は、政府がこの会議の結果にかかわらず遺伝子組み換え推進政策をとる決心を固めたと非難した。この議論から得た教訓に関する政府の報告書は、科学的・経済的な技術評価と世論を統合することに失敗したことを強調し、明らかにあいまいなものだった35。言い換えれば、GMネーションは、国家の望ましい政策姿勢に国民を同調させることができなかったため、公式には失敗と見なされた。
今にして思えば、新技術の倫理的・社会的意味合いについて国民を対話に巻き込むというイギリス独自の試みは、あまりにも小さく、あまりにも遅く、あまりにも特異なものであったといえるだろう。この試みは、歴史的に閉鎖的で内向きな政策文化、信頼できる内部の人間同士の交渉に依存していたものを、珍しくオープンで包括的な自治の実践に改めようとするものであった。しかも、その取り組みは、この問題がすでに徹底的に分極化し、反対意見という巨大な魔物が、政策封じ込めの小さな瓶から抜け出してしまった後に行われたのである。このような状況下では、「GMネーション」はほとんど失敗する運命にあった。AEBCのメンバーであるロビン・グローブ・ホワイトを含むランカスター大学の著者グループは、「農業GMの経験は、新しい状況や技術に直面したとき、規制当局が以前の技術のために開発し、既存の議論に結びついた評価の枠組みに頼る傾向があることを証明している」と結論付けた。著者の見解では、このような前哨戦への回帰が、特定の新技術の特徴や特性について、適切に「探索し、社会的に現実的な分析を行う」ことを妨げている36。
結論
これまで見てきたように、テクノロジーは単に実用的な目的を達成するための道具ではなく、現代社会が将来の生活について、より自由で意味のあるデザインを模索し、創造するための装置なのである。テクノロジーによって、人間社会は自分たちの希望、夢、そして欲望を明確にすると同時に、それを達成するための物質的な道具を作るのだ。さらに、社会が新しいテクノロジーに慣れ、それを使って変化した理解や目的を追求するにつれて、集団のビジョンや願望は変化し、進化していく。技術的な選択はまた、本質的に政治的なものである。社会を秩序づけ、利益と負担を分配し、権力を行使するものである。20世紀後半まで、近代国家の統治において、テクノロジーと民主主義が互いに距離を置いていたことは驚くべきことである。国家公務員、企業、科学者、発明家、金融業者などのエリートは皆、現代社会を支える巨大な技術基盤の構築に参加しており37、国民は特定の進歩の方向性が望ましいか否かについてほとんどあるいは全く意見を述べることができなかった。
過去数十年間に行われた3つの政策イニシアチブは、技術企業家とその企業や政府の支援者から未来を取り戻したいという市民の願望に応えるものであった。いずれも米国の政策に早くから根ざしているが、リスクと便益に対する国民の評価や、国民が政府に期待する権利についての基本的な考え方の違いを明らかにする形で、他国にも波及している。特に、説明責任が技術の進歩を遅らせたり、遺伝子組み換え作物の場合のように、自然と文化の関係を再構築する特定の方法の収益性を制限することを意味する場合、科学や産業に公的価値に対する説明責任を持たせることの難しさを示す障害にも直面した。米国はかつて技術論争の民主化において世界をリードしていたが、米国の政策における民営化と市場メカニズムへの転換は、3つの政策領域すべてにおいて、かつて優位にあったその地位を侵食した。
技術評価は、社会技術的な未来を予測し、コントロールするための最も直接的で正式な手段であり、米国技術評価庁の設立後、欧米諸国に広く普及した。OTAの分派や模倣の多くは、そのモデルよりも耐久性があることが証明されたが、OTA自身の消滅は、技術をより民主的にするためのアプローチのいくつかの欠点に注目させることとなった。その評価作業は立法過程に縛られており、現在の政治に囚われ、不確実な公的資金に依存し、民意や状況の急激な変化への対応力が弱いという、法律制定そのものの欠点に悩まされていたのである。建設的技術評価は、原理的にはより包括的で、影響を受けるグループを引き込み、ユーザーが認識するニーズに対して技術に責任を持たせようとするものである。しかし、ゼネラルモーターズの電気自動車やデザーテックの例が示すように、CTAが効果を発揮するのは、社会の未来が広く描かれた後であることがほとんどである。どちらのケースでも、想定された技術的未来の採用や最終的な放棄は、それらのプロジェクトが生活に最も直接的に影響を与えるであろう一般市民とはあまり関係がない。
倫理委員会や市民参加型の活動は、問題を明確にする上では価値があるが、民主的ガバナンスのメカニズムとしては欠点がある。米国における生命倫理審議の歴史は、深遠な道徳的問題が、日常的なリスク評価や、倫理的基準が満たされていると公衆を満足させながら研究の歯車を回し続ける功利主義的な動きといかに同化してきたかを示している。機関審査委員会のような機関は、遺伝子革命が提起する人間であることの意味を含む基本的な憲法上の問題を議論する場としてはふさわしくない。生命倫理は、民主的な監督という安心感を与える一方で、企業家的な科学技術の想像力に、何が公共の利益とみなされるかを実質的に決定する自由裁量権を与える、もう一つの専門的言説となってしまった。
最も逆説的なのは、意思決定の場に一般市民を招き入れようとする試みでさえ、凝り固まった意思決定の伝統に風穴を開けることには、そこそこの成功しか収めていないことである。GM Nation ”は一つのパラダイムを提示している。この事例では、特定の技術的経路について国民から意見を求めるという、これまでで最も広範な試みが国家政府によって行われたが、最終的に正しい国民が意見を表明したのかどうかについて意見の相違が生じた。一般に、協議は国家によって招かれるものであるという政治文化において、英国当局は、バイオテクノロジーの批評家が真に民主化するとみなすような「招かれざる参加」を受け入れることが困難であることに気づいたのである。アメリカの、より開かれた行政プロセスでさえ、原則的には、技術を管理する上で発言権を持ちたいと望む利害関係者や影響を受けるすべての人々にアクセスを認めているが、選択の自由という誘惑の歌に屈してしまったのだ。テクノロジーを政治の一形態としてではなく、消費者の権利の源泉として捉え直すことで、アメリカの政策は、情報に基づく消費者主義という容易な道を選ぶために、審議という困難な規律を犠牲にしてきたのである。次章では、今日の技術的進歩の展望と、グローバルに絡み合いながらも依然として深い不平等を抱える世界において、熟慮に基づく倫理的な未来づくりの展望に目を向けることにする。
[/passster]
第9章 民衆のための発明
20世紀を通じて、「テクノロジー」という言葉は、第一次産業革命の汚く、錆びついた、臭い、目に見えないインフラを思い起こさせるものであった。ウィンストン・チャーチル(Winston Churchill)は、政府に助言を与える科学者について、こう述べたという。「蛇口はあるが、上にはない」と。しかし、今世紀に入ると、テクノロジーは社会を変えるダイナミックな力と見なされるようになり、テクノロジーは人間の存在の目的と条件を劇的に、そしておそらくは取り返しのつかないほどに変えることができるという認識が世界の人々に広まり、より大きな希望と恐怖をもたらすようになった。20世紀後半の技術革新は、世界の人々全体にとって、より良い健康、より迅速なコミュニケーション、よりクリーンな環境、そして想像を絶する豊かな知識と情報を約束するものであった。人間個人のレベルでは、ナノ、バイオ、情報、認知科学の進歩に支えられた同じテクノロジーが、自己を改造する広大な機会を生み出し、これまで想像もできなかったような生活の向上をもたらすとともに、そうしたパワーが誤って使われたり、使いすぎて人類に永遠の不利益をもたらすかもしれないという懸念が生まれた。
核兵器の消滅という脅威は、技術的リスクに対する新たな世界的注目を集める強力な原動力となったが、1980年代以降、内部関係者が「収束的破壊」と呼んだ技術は、人間の能力の向上に対する人々の期待を高める一方で、技術の支配と浸透の影響に対する新たな不安を呼び起こすようになった。バイオテクノロジーは生命と健康の奇跡を約束したが、環境の悪化とモラルの崩壊に対する根深い懸念を呼び起こした。最近では、ナノテクノロジー、合成生物学、認知科学、神経科学、そして何よりもコンピューティング能力の発展が、人間であることの意味を再定義するテクノロジーの巨大な可能性に注目するようになった。特に情報技術は、個人情報の利用が拡大し、人間がかつてないほど採掘や監視の対象となりやすくなり、ビッグデータとアルゴリズムが人間の裁量に代わって、一見無謬の統治手段となる時代を予見している。一方、旧来の工業生産の遺産である気候変動は、私たちの技術的進歩への欲求を抑制しない場合に何が起こり得るかを示す妖怪として、地球上に漂っている。地球を冷却する地球工学、汚染を伴わない成長を可能にする新しいエネルギー技術、あるいは人間の誤った管理によって破壊されていない惑星への逃避という究極のSFファンタジーなど、この極限の脅威に直面してもなお、テクノロジーは自らの毒に対する最高の解毒剤になると確信している人たちがいる。
一般に信じられているが欠陥のある3つの信念は、それぞれ技術が基本的に管理不可能であり、したがって倫理的分析や政治的監視を超えるものであることを示唆しており、技術の統治に関する体系的思考を長い間妨げてきた。第一は技術的決定論で、何世紀にもわたる歴史的経験に反して、技術には歴史の流れを形成し推進する勢いがあるとするものである。第二はテクノクラシーで、熟練した知識を持つ専門家のみが技術の進歩を管理する能力を有するとするものである。第三は意図せざる結果という概念で、テクノロジーによって引き起こされる害は意図や予見の範囲外であると暗に位置づけ、人間以外の機械や認識の協力者を人間の意味のあるコントロール下に置く可能性について宿命論を育んでいる。
私たちは本書を通じて、技術的なシステムが実際にはこうした従来の常識よりも可塑的で、倫理的・政治的な監視に従順であることを見ていた。テクノロジーを作り出し、展開することは、個人の価値観や信念をいかに守るか、また、独特の法的・政治的文化に支えられた国民国家の政策的直観をいかに尊重するかなど、さまざまなレベルで倫理的問題を生じさせているのだ。このような問題は、20世紀後半に技術が世界的に普及したことによって緊急性を増し、技術先進国である社会に対して、積極的な社会的考察と対応の義務を課している。例えば、かつて医薬品は、医学の知識と実践における奇跡的なブレークスルーであり、全人類に利益をもたらすと考えられていた。しかし、グローバルな市場において、医薬品は国内のみならず国境を越えた権利と義務に関わる多くの規範的な問題と絡んでくるようになった。例えば、ヒト生物試料の所有権、医療データのプライバシー、臨床試験への同意、被験者研究の倫理、ジェネリック医薬品の製造、実験薬および必須医薬品へのアクセス、先住民の知識の保護、その他多くの関連事項が含まれる。これらすべての問題において、利害関係や期待は、病める者と健やかなる者、富める者と貧しい者、生産者と消費者、先進国と発展途上国の国民など、観察者の社会経済的立場によって大きく異なる。つまり、医薬品は科学、医学、経済、法律、政策の対象として、国境を越えた空間で人体を再構築する。しかし、医薬品開発の政治と倫理に関する審議のプロセスは、国家レベルに比べて超国家レベルではまだ著しく不十分である。
グローバル化する世界の倫理的ニーズを満たすために、私たちの広範囲に及ぶ技術的発明はどのように管理されるべきなのだろうか。技術革新のリスクと利益を誰が評価するのか、特にその結果が国境を越える場合、誰の基準に従って、どのような影響を受けるグループと協議して、どのような手続き上のセーフガードに従って、そして決定が誤ったものであったり有害であったりした場合にはどのような救済措置があるのだろうか。技術的な誤謬や失策は、社会的、政治的、法的により深い分析の必要性を絶えず私たちに警告している。しかし、善悪に関する多くの基本的な問題は依然として深く争われており、それらを解決するための原則はせいぜい弱々しく地平線上にかすんでいるに過ぎない。本章では、これまでの数十年にわたる技術システムのガバナンスに関する国内および世界的な経験から得られた主要な洞察をレビューしている。そして、これらの歴史をつなぐ3つのテーマ、「予見」、「所有」、「責任」の下に、依然として待ち受ける課題をまとめていく。
期待:不平等な贈り物
技術に関するすべての政策言説を貫く糸があるとすれば、それは賢明な先読みの必要性である。1970年代から1980年代にかけての技術評価プログラムは、技術によって引き起こされる物理的・環境的な害を予見し、それを回避することへの関心から生まれた。同様に、新しい技術の倫理的意味を評価するプログラムは、耐え難い道徳的被害を予見し、それを回避したいという広く分散した願望を反映している。当然のことながら、現代社会では、物理的および道徳的な結果に対する予測は、専門家による起こりうる結果の予測と密接に結びついている。技術政策の線形モデルは、リスク評価から始まり、後になってから意思決定に価値を注入するもので、最初の予測段階は、技術がどのように作動し、どこで間違うかを最もよく理解していると考えられている専門家、つまりテクノクラートに委ねられる。しかし、これまでの章に散見されるように、専門家の想像力は、その専門性によって制限されることが多い。既知のものが未知のものよりも優先されるのだ。したがって、専門家による予測は、短期的で計算可能な、議論の余地のない効果に重きを置く傾向があり、思わせぶりな、突飛な、あるいは政治的に議論の余地のある効果を優先させる。そして、ブレイクスルー科学的洞察に長けているにもかかわらず、専門家はハイブリッドな社会技術システムの複雑さを過小評価しがちで、人間と人間以外の要素間の理解されていないダイナミクスやフィードバックが、実験室ベースの予想の正確さを混乱させるのだ。
誰が未来を想像するのか?
技術革新の初期の有望な段階においては、先見性はしばしば専門家の支持者の学問的能力によって形成され、制限される。アシロマーの分子生物学者たちは、生物学的大災害を防ごうと決意していたが、商業的バイオテクノロジーによって再構築された世界が、主要な遺伝子組み換え作物が日常的に野生作物に取って代わるとは想像もしていなかっただろう。サハラ砂漠からヨーロッパへの太陽エネルギー輸送を構想したドイツのエンジニアリング会社は、文化も経済も大きく異なるこのような大胆なトランスナショナル・プロジェクトの政治的管理について考えていなかった。
また、制度的な保守性も、先見の明を阻む。例えば、裁判所は法律の安定性を確保しようとするが、その代償として技術の変容がもたらす価値を無視することになる。ジェネンテック社は、アナンダ・チャクラバーティ氏のバクテリアを単なる物質とみなし、ジェレミー・リフキン氏のバクテリアの特許から高等動物の特許への滑り台という一見根拠のない懸念よりも、バイオテクノロジー企業の段階的なビジョンを優先したコモンロー高裁に勝利したのだ。しかし、今にして思えば、リフキンは、ジェネンテックや科学界におけるその著名な擁護者よりも、生命特許化の起こりうる軌跡をより正確に予見していたように思われる。カナダの最高裁がオンコーマウスの特許を否定し、米国の最高裁がヒトの遺伝子の特許を退けたことは、生命を特許化することの極端な意味合いを遡って(遅きに失したとも言える)否定するものであったと言える。
専門家の思考においても、isとoughtの間にしばしば暗黙の乖離が生じ、倫理的懸念の端緒が鈍ることがある。科学者の常識から逸脱することは、不合理、虚構、幻想と見なされ、(まだ)できないことは心配する価値がないとされる。これまで見てきたように、発明はそれ自体が善とみなされる傾向があり、倫理的な監視は主に、約束された善が無謀な利益欲によって狂わされないことを保証するために発動されるのだ。技術的にありえないという予測は、潜在的に「非現実的」な倫理的憶測や早まった大衆の不安を防ぐバリアとして機能するのだ。例えば、サイエンス誌が2013年に発表した「ブレイクスルー・オブ・ザ・イヤー」の次点リストに掲載された簡単な項目を考えてみよう。同誌は「ついに実現したヒトクローン」という見出しで、「今年、研究者たちはヒト胚のクローンを作り、長年の夢だった胚性幹(ES)細胞の供給源として利用することを発表した」と報じているのだ。同誌はさらに、この開発の倫理的意味を軽視し、社会が心配する必要がない理由として、道徳的嫌悪感よりも可能性が低いことを挙げている:「この偉業は、クローン赤ん坊に対する懸念も引き起こす。しかし、今のところその可能性は低いと思われる。オレゴン大学の研究者によれば、何百回と試したが、サルのクローン胚が代理出産で妊娠した例はない」(強調)1と言うのである。仮に、妊娠が成立し、クローン赤ん坊の可能性が高まったとしよう。私たちのような無限の創造力を持つ社会が、人間の尊厳に対する脅威がドアをノックした後に、このような広範囲に及ぶ技術的実験の倫理的意味について考えるのは適切なことなのだろうか。
サイエンス誌が想像する技術革新の世界では、クローンベビーについて一般大衆が懸念を表明することが適切であるとすれば、それはいつになるのだろうかと疑問に思う。オレゴンかどこかの研究者がクローン胚の妊娠に成功したと発表した後であろうか?しかし、その段階までには、新しい「is」が、より微妙で予防的な「ought」の可能性を圧倒してしまうだろう。例えば、倫理的に議論のある妊娠を誘発するために「何百回も試みる」前に、研究者によく考えさせる、あるいは人前で声を出して考えさせるような規則のようなものが考えられる。さらに、ヒト胚のクローニングを「長年の悲願」と表現することは、胚がどこで終わり、赤ん坊がどこで始まるかについて、国によって争われ、異なる道徳的決着があることを見落としている。たとえばドイツでは、研究の過程でアメリカよりもさらに上流で懸念が生じるかもしれない。これは、倫理的思考がどちらの場合も「西洋」の伝統に根ざしている二つの国において、功利主義的議論とは対照的に擁護主義的議論を好む傾向が異なることを示している。倫理的な推論に対する基本的なコミットメントにこのような格差があることを考えると、人類という種全体にとって重大な決定を、技術的に一流の国々が単独で行うことは、果たして適切なのだろうか。
専門家の自信に満ちた主張が道徳的分析のベースラインである以上、倫理的評価はいずれにせよ、起こりうるシナリオのコストと便益に関する功利主義的分析に陥りがちである。米国の2つの大統領倫理委員会がそれぞれヒトクローンや合成生物学を評価したときがまさにそうであった。いずれのケースでも、倫理委員会は、この技術はまだ十分に安全ではないため、現時点では倫理的な懸念はないと結論付けている2。このような失望するほど制約の多い活動は、構成的技術評価(第8章参照)のような手続きによって実現される先見的ガバナンスが、「技術科学の長い弧をより人道的な目的へと曲げることに貢献できる」という一部の民主主義理論家の期待に反している3。
トリクルダウン・イノベーション
現代社会は、技術的に不利な未来を予測し、潜在的な悪影響を回避するために、資金や専門知識といった膨大なリソースを投入しているが、それらのリソースは国や技術領域によって偏在している。2013年にバングラデシュで起きたラナプラザ工場の崩壊のような出来事は、貧しい人々の生活が、豊かな国では耐えられないとみなされるような方法で危険にさらされているグローバルな政治経済を物語っている。1984年、ボパールのユニオン・カーバイド工場からイソシアン酸メチルの死雲が放出され、何も知らずに眠っていた街に降り注いだときと同様、繊維産業で過去最悪の災害が起きた2013年も、驚くことに責任の所在を明らかにすることは困難だった。ソヘルラナの容疑が正式に固まるまで、2年以上を要した。バングラデシュの労働者を雇用する多くのアパレル企業が補償基金への拠出を約束したものの、責任の所在を正式に明らかにし、主要な多国籍企業が公に責任を負うようなグローバルな場は存在しなかった。リスクアセスメントがこのような恐ろしい事故を予見し、防止するためのものである限り、それは深刻なグローバル経済、政治、情報の不平等の状況下での予見と保護という課題にまだ追いついていないのである。
リスク評価の失敗は、歴史的に広く使われてきたこの予測技術を支えてきた狭い因果関係の枠にも起因している。「科学」としてのリスク評価は、常に社会的要因を軽視し、リスク創出に対するより捉えどころのない経済・制度・文化的貢献に対して、定量化可能な変数を過度に強調してきた。米国の事故専門家が、NASA内の組織的な状況がこれらの悲劇を可能にしたと指摘し始めるには、コロンビア号とチャレンジャー号の2つのスペースシャトル事故が必要であった。ボパール事故は、それに匹敵するような清算の瞬間を生み出さなかった。ボパール事故は、多くの人々が時期尚早で不当な和解と見なし、富と専門知識が同等でない国家間で非常に危険な技術が移転されたときに起こったすべての問題の公正な裁定を妨げてしまったのである。
ガバナンスの道具としての限界はあるにせよ、予期はどの社会にとっても無くてはならない価値である。歴史上、人間は現在の恐怖や試練を打ち消す手段として、現世であれ来世であれ、未来を予見することに目を向けてきた。蒸気機関、綿繰り機、電球から、今日の遺伝子組み換えジャガイモ「イネイト」に至るまで、より良い世界のビジョンが発明家たちを動かし、新しい道具を想像し、創造してきた。4 解放のビジョンが、カリフォルニアに拠点を置くシンギュラリティ大学の、一度に10億人の生活を飛躍的に改善するという野心につながっている。投資家は、研究開発の長い道のりのどこかで利益が上がることを期待して、設立間もないテクノロジー企業の株式を購入する。消費者もまた、アップルの最新の動きに注目し、洗練された機能、多様性、スピードなど、想像を絶する進歩を期待して、その役割を担っている。近代化の恩恵のひとつは、アイデアと現実化の間のギャップが縮まったことだ。知識を発明に結びつける能力は、科学的、経済的資源とともに成長した。人類の歴史上、優れたアイディアが素早く注目され、ベンチャーキャピタルや、グローバル市場に投入するために必要な法的・政治的支援を、使いやすい形でリアルタイムに受けられるようになった時代は、かつてないほど長く続いた。
しかし、今のところ、ポジティブな期待を抱くことができるのは、すでに多くのものを手に入れ、さらに多くのものを手に入れることを夢見ることができる人たちに限られているのが実情である。スティーブ・ジョブズの有名な主張、「消費者が何を欲しがっているか、彼ら自身よりも先に知っている」というのは、「欲しい」ではなく「たくさんある」という経済の中で生まれた言葉だ。ジョブズは、自分が夢見た美しいガジェットを、人々が欲しいだけでなく購入する資源も持っていると仮定していたのだ。しかし、世界の大衆の多くは、テクノロジーの進歩がもたらす直接的な利益や長期的な展望を自ら予測することはできない。彼らは、技術のフロンティアに近いところで、大規模な変化をもたらす資本とノウハウを持つ起業家が、別の場所で設計した発明によって自分たちの生活が改善されるという善意の部外者の約束を受け入れるしかないのである。このように、技術革新の公正なガバナンスを阻む未解決の倫理的・政治的障壁として、アクセスだけでなく、予見に関する不平等が浮かび上がってくるのだ。
技術的・経済的に恵まれた社会が享受する不公平な想像力の優位性を相殺するために、「質素なイノベーション」あるいは「質素なエンジニアリング」という考え方が定着してきた。ここでいう倹約とは、裕福でない人々の手段によりよく適応した技術を作ることを意味する。2005年にマサチューセッツ工科大学のニコラス・ネグロポンテが始め、前国連事務総長のコフィ・アナンが受け入れた100ドルノートPCプロジェクトはその典型である。その目的は、不必要な装飾を取り除き、発展途上国の多くを悩ませる不安定な電力供給のような不利な条件下でも動作するように装備することで、世界中に簡単に配布できる手頃な価格のコンピュータを作ることであった。インドのタタ・グループが開発した世界一安い自動車「ナノ」や、携帯電話「ノキア1100」、ユニリーバが開発した使い捨てのトイレタリー製品など、「質素な技術革新」は、あらゆるものを包含している。さらに、「余分な」部屋、車、ペットまでもが余剰資本となる「共有経済」の台頭は、「持てる者」の余剰財を「持たざる者」の利益のために利用する可能性のある一種の倹約的イノベーションであると考えることもできるであろう。
共有経済は、豊かさの経済学で確立されたものではあるが(他にこれほど多くの余剰物資があるだろうか)、間違いなく、ムハマド・ユヌスによる影響力のあるマイクロクレジットという概念と同系列のものであり、この概念も、人は多くを持つ必要がなく、共有できるため、すべての人に多くの利益を生み出すという原理に基づいている。さらに、無煙調理器、コンポストトイレ、簡易浄水器など、貧しい人々のための物質的なイノベーションは、北欧のエンジニアや科学者の注目を集め、大きな利益をもたらす可能性がある。しかし、全体として、貧困層を対象とした生活革新と、裕福な社会の収束技術におけるブレイクスルー開発を推進するような先見の明との間のギャップは、相変わらず驚異的である。
つまり、富裕層が達成した技術的な成果が、恵まれない人々の将来の見通しを決定してしまうのである。富裕層が自分たちの状況に合うように発明したものが、貧困層が必要とし、欲しがるべきものの金字塔であり続けている。イノベーションの問題が逆に問われることはほとんどない。1日2ドル未満で生活する世界人口の5分の2かそこらの人々にとって、どのような技術的未来が最も理にかなっているだろうか。7 彼らが少ない収入の50日を子供用ラップトップに費やすべきか、それとも技術がより有利に修正できるもっと緊急の需要があるのだろうか。いずれにせよ、ラップトップがあれば、富裕層が容易に想像し、満喫できるような、遊び心と生産性を兼ね備えたつながり(Facebook、Reddit、Pinterest、Instagram)への扉が開かれるのだろうか。
テクノロジーの未来設計に浸透している力の差は憂慮すべきものだが、それは人類にとって唯一の倫理的関心事ではない。実際、大量消費型のライフスタイルが持続不可能であることをこれまで以上に意識する時代にあって、金持ちが思い描く未来が貧乏人の想像力よりも優先されるべきかは不明である。ダウンサイジング、緑化、簡素化、さらには「フリーガニズム」(他人の不要なゴミで生活すること)が若者の間で人気を集めているように、地球上でより軽やかに生きるためのより良いアイデアは、下層から生まれる必要があるかもしれない。それは、生物および非生物の絶えざる帝国主義的搾取よりも、社会の結束と責任という価値観に注目したアイデアなのである。
所有と発明
過去数世紀にわたる技術開発は、財産や私的利益に関する考え方と同様に、集合的利益に関する予見に負うところが大きい。新しい技術には新しい採掘方法が含まれることが多く、以前は利用されていなかった資源にアクセスし、分配する方法を発見した人々には莫大な利益がもたらされる。探鉱や採掘がその例だが、テクノロジーは他の多くの資源利用を可能にし、しばしば国家や帝国の拡張計画と結びついてきた。19世紀半ばにカリフォルニアは近代的な州となったが、それは新発見の金のために何十万人もの移民が押し寄せたからだ。ダイヤモンド鉱山は南アフリカでセシル・ローズの帝国的野心を支え、ゴムと象牙の取引はコンゴでのレオポルド2世の残忍な政権を支えた。搾取、残虐行為、権力の悪用はこれらの事業に影を落としているが、それらが生み出す商品に対する需要がある限り、技術、経済、政治が一体となって圧政を維持することができたのである。
初期の採掘技術が、岩石、土、植物、海洋から、人々がすでに価値を認めていたものを採取したのに対し、今日の多くの技術は、歴史的に商品として扱われていなかったものに価値を与えている。遺伝子から、癌になりやすいハーバード大学のオンコーマウスのような研究所で作られた新しい存在まで、あらゆる生物学的素材がこのカテゴリーに含まれる。炭素市場や生態系サービスといった仕組みは、自然の一部を取引可能な商品へと変えてしまったが、金を使うように自然を所有したり利用したりすることはできない。ソーシャルメディアは、大規模な集積によって、人々の習慣や嗜好、記憶や願望を商品化している。フェイスブックは、10億人以上の人々が「友達」とつながることを望み、その友達とつながり、彼らの近況を知る見返りとして、大量の個人情報を私企業に提供することをいとわないという事実を利用している。Twitterは、140字の文字と添付された画像で、人々の過ぎ行く思いを利用する。インターネットが、精神的または視覚的な一瞬の印象を世界中のオーディエンスに広めることを可能にするまで、共有することに適していると考える人はほとんどいなかっただろう。ピンタレストは、結婚式、旅行、家の改築など、人々が予想される未来に迎え入れたいと思う夢を共有することで繁栄している。消費者向け検査会社は、自発的に提供された遺伝子情報をデータベース化し、医薬品の研究開発のための商業的な可能性を持っている。これらの技術システムはすべて、新しい方法で人々から利益を得ている。人々の思考、言葉、習慣、身体、感情を資源として採掘し、新しい市場性のある商品を作り出している。
HeLa細胞株に関する苦難の物語は、人々が自らの身体、そしておそらくはそれ以上に心に対して抱いている支配意識が、既存の法律や政策に組み込まれた所有権の推定と大きく乖離する可能性があることを明らかにした。レベッカ・スクルートが受賞したヘンリエッタ・ラックスの物語の再構築は、現代生物学の最も有用な研究ツールの一つと、アメリカの長年にわたる悩ましい人種と貧困の物語とが、不安定に混ざり合ったものに火をつけた。国立衛生研究所は、生物医学倫理の過去の失敗と密接に結びついた歴史的に排除された集団の道徳的主張が放置されれば、広報上の災難になることを認識していた。NIHの当面の問題は、ラックス家に先祖の生物学的遺産に関わる意思決定に参加する権利を与えるという、一回限りの手続きで解決された。しかし、HeLa細胞は、そのユニークな歴史的、政治的背景を除けば、Henrietta Lacksを二度目の死に追いやることになり、失敗に終わったであろう。このような特別な例は、科学とその研究対象が対称的でない交渉関係を享受する状況において、説得力のある前例となるとは考えにくい。
技術革新を支配する知的財産権制度は、ほとんどの場合、200年ほど前に近代産業界で生まれた所有権と資本に関する考え方を支持し続けている。もちろん、こうした考え方は、欧米諸国であっても完全に同質なものではない。欧州特許法は、米国特許法とは異なり、公序良俗に反する発明を禁止する明確な規定がある。また、特許商標庁が一時期、実用性が証明されていない単離されたDNA断片に特許を認めたように、欧州法は、最も寛容な段階にある米国法よりも「進歩性」を構成するものの立証に高いハードルを設定している。しかし、全体として、知的財産は、集団的努力よりも個人の起業家精神を優先させるなど、その規範的基盤を技術的中立のベールの下に隠しているのだ。グリベック事件(第7章参照)において、インドの最高裁判所は、特許法は経済発展の手段であり、その保護の範囲と性質は「国の経済状況」を反映すべきであると明確に述べている9。知的財産権の規範的基礎と権力の非対称性を強調するこうした表現は、欧米の法的判断ではほとんど見受けられない。
しかし、自律性、プライバシー、生命、あるいは健康についての公共の関心事と絡み合う所有権の主張を、法律が確認したり、不安定にしたりすることもできる。2013年に米国最高裁がヒト遺伝子の特許取得を中止する判決を下し、何十年にもわたり特許商標庁の方針を覆して、法的な力が顕著に表れた。公益団体である米国自由人権協会による長年の活動は、ヒトゲノムの一部を私有化することの正当性に関して、暗黙のうちに広く保持されている公共の価値観を侵害する商品化の動きを取り消した。国際的な場においても、このような事態は起こりうる。ただし、この場合の推進力は、人間性の政治学というよりはむしろ政治経済学である傾向がある。生物多様性条約は、先住民の知識保有者の所有権の主張を認めることで、何世紀にもわたって無秩序に行われてきた生物学的海賊行為を覆そうとしたのである。この条約は、地域社会と、地元の知識や材料を用いて新しい治療用化合物を開発するバイオプロスペクティング企業との間で利益を共有することを規定している。2001年のドーハ宣言で、知的財産権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)が改正されたのは、医薬品の生産よりも流通における経済格差が動機となったからだ。TRIPSは、エイズ危機のような緊急事態において、必須医薬品への迅速なアクセス拡大が必要な場合、各国が医薬品の特許権を回避することを可能にする。発明が、以前は不可能だった地政学的境界を越えた人、アイデア、材料の流通と相乗効果にますます依存するようになった今、知的財産の分散所有権をどのように認めるか、といった将来への未解決の問題がある。
責任:公的責任と私的責任
技術の進歩は個人の自律性や公的な審議の機会だけでなく、おそらくより重大に、個人と集団の責任の規範に影響を与える方法で、公的空間と私的空間の間の区分を作り変えることができる。カール・マルクスからハーバート・マルクーゼに至るまで、社会理論家は工業的労働慣行や大衆文化の普及を通じて、テクノロジーが人間の精神を平坦化し、標準化し、鈍化させることに警鐘を鳴らしてきた。大規模な技術システムの鉄の檻の中で、組立ラインと生産割当の専制に従うと、解放と自己への責任が宇宙的なジョークに聞こえるかもしれない。新しい生物学的技術と情報技術は、特に遺伝性疾患からの解放を大きく約束する。しかし、それらはまた、身体と精神への前例のないアクセスを可能にし、『1918年宇宙の旅』のオーウェル的悪夢さえ凌ぐ社会統制の可能性を作り出す。
デジタル時代には、ある程度、人々自身がプライベートの境界を狭めることに加担していることが証明されている。セルフィー(携帯カメラで撮影した自画像)文化の台頭と、他人の視線を集めたいという人々の無限の欲望は、軽率な行動が雇用の見通しを狂わせ、政治的キャリアを台無しにし、かつて有名人でさえ自分だけのものにしていた領域に侵入しうる、酔わせる空間を生み出している10。データ・オリガルヒは現在、グーグルとフェイスブックのプライバシー・ポリシーのような、国家がスポンサーとなり、また自ら課した規制のパッチワークの下で運営されており、異なる規範的コミットメントを反映している。情報の荒々しいフロンティアを組織的な統制に近づけるには、EUの「データ主体」のような概念をより広く採用し、人々が自分の好みや個人に関するデータの流通について何を知り、期待し、許容するのかを持続的に議論することが必要かもしれない。
市場原理と新自由主義的な統治形態が支配する時代において、「公共性」という概念そのものが縮小していることから、別の種類の倫理的な心配が生じる。大金がさまざまな経路を通じて世論に圧力をかけることができる時代には、代表民主制の伝統的な場である議会の存在意義がますます薄れているように思われる。企業家は、法律が常に科学技術に遅れをとっているため、イノベーションを阻害すると主張し、立法に激しく抵抗している(特に米国において)。World Wide Webの発明者であるSir Timothy Berners-Leeやヒトゲノムの共同解読者であるCraig Venterなどのカリスマは、インターネットの成功とバイオテクノロジーの普及を、自由放任の技術開発の利点の典型例として挙げる。一方、立法府はしばしば反撃する勇気と専門知識を欠いており、理論的には抑制することが約束されている利益団体に政治的に肩入れしている場合がある。
バイオメディシン、ナノテクノロジー、合成生物学、神経科学など、特定の技術開発に特化した倫理機関の爆発的な増加は、公的な政策決定機関が私的に支配されるのを防ぐ効果があるはずだが、実際にはこうしたしばしば目に見えない委員会が、倫理的懸念をさらに増大させることになるのである。研究事業と密接に結びついた場合、人間を対象とした研究を監督する機関審査委員会のような組織は、所属機関や科学界のスターに過度の負担をかけないよう暗黙の了解のもとに運営される傾向がある。これまで見てきたように、より目立つ国の倫理委員会でさえ、新しい研究分野の長期的な公共利益について厳しい質問をするよりも、差し迫った技術的未来についての費用便益分析という安住の地を好むのである。例えば、英国のワーノック委員会は、14日以前の胚を研究目的のために非人間とすることで、現代の生物医学に大きな貢献をしている。イギリスでは、この明瞭な線によって、胚組織を用いたフロンティア研究に寛容な空間が生まれ、病気の子供に適合する組織を提供するための「救世主兄弟」の利用や、母親のミトコンドリア遺伝病を取り除くための3人胚の作成など、新しい倫理的拡張が初めて承認されるに至ったのである。しかし、このような閉鎖的な倫理団体内部での公共道徳の相対的私物化を放置すれば、公衆の疎外と規範的拒絶を産み出すかもしれない。幹細胞研究のような問題をめぐる現在進行中の論争は、倫理専門家による規範的な線引きの政治的脆弱性を明らかにするものである。
結論
現代社会は、過去100年の間に、多くの奇妙で素晴らしいものを発明し、移動、コミュニケーション、計算、生命と健康の維持において、想像を絶する障壁を打ち破ってきた。テクノロジーによって、私たちは飢餓を余剰に変え、殺人的な病気をなくし、海や成層圏を掘り起こし、宇宙を人間の想像力の及ぶ範囲に収め、人間の心の奥底を目標とする探索のために開放してきた。ロボットが火星や彗星に着陸したとき、世界の多くの人々は喜ぶ。それは、ロンドンからハンマーを投げてニューデリーの釘を打つようなものだとも言われるほど、精度の高い偉業なのである。2015年12月、米国の技術起業家イーロン・マスクが率いる企業が、人工衛星を軌道に打ち上げた後、地球に帰還するロケットの着陸に成功し、再利用可能なロケット建設の夢が現実となった。同時に、技術活動が健康や環境、社会に与える影響のモニタリング、モデル化、測定も大きく進展している。19世紀の工場が手つかずの風景に煙やほこりを吐き出し、有毒な染料が無秩序に川に流れ込み、企業がアスベストにさらされた労働者が何千人も肺病で死んでいるという証拠を隠していた頃のように、技術文化はもはや自然に対して無頓着ではなくなっているのである。
しかし、これまでの章で見てきたように、制度的な欠陥、不平等な資源、自己満足的な語り口が、テクノロジーと人間の価値の交錯と相互影響に関する深い考察を妨げているのが現状である。注意や予防を促すような重要な視点は、時に新しいものへの無頓着な突進のように感じられ、脇に追いやられてしまう傾向がある。その結果、テクノロジーが持つ解放、創造性、エンパワーメントの可能性が満たされないまま、あるいはせいぜいうまく分配されないままになっている。ゲノム革命や情報革命のような、慎重な先見性と持続的な世界的関心を必要とする問題は、部分的に経路に依存する日和見的なデザインの選択によって非政治化されるか、あるいは見えなくなり、将来の創造性と解放が挫折させられるのだ。
20世紀で最も成功した技術的発明の一つであり、今なお世界中の富のフェチである自動車の歴史は、人間の先見性の限界を示す模範的なケーススタディであり続けている。自動車は個人の自由と生産性に計り知れない可能性をもたらしたが、それは同時に、誰も想像しなかった、あるいは適時に規制することのできなかった社会への劇的な影響ももたらした。毎年世界中で100万人を超える交通事故死、殺伐としたルーチンワークの蔓延、都市の大気汚染、コミュニティの分断、かつて巨大だった製造拠点の衰退、そしてついには世界を脅かすほどの気候変動。現在の責任あるイノベーションと先見的なガバナンスの実践は、自動車の歴史が悲劇的な道をたどる前に、その流れを変えることができただろうか。大量に普及し、経済的・社会的に莫大な影響を及ぼす技術については、国民国家が指揮する局所的かつ一時的なガバナンスのプロセスは、悲しいほど不十分であるように思われる。さらに、時折の動員では、予見の非対称性の核心に迫ることはできない。あらゆる実際的な目的のために、テクノロジーを支配するためのゲームのルールを設定する権限は、資本と産業界にあり、労働し、消費し、あまりにも頻繁に苦しんでいる大衆の政治的代表にはないのである。
この深い民主主義の欠陥は、手続き的な応急処置で治すことはできない。最近盛んに行われている公開協議、建設的技術評価、倫理審査などの実験は害を及ぼすものではなく、確実に継続されるべきものである。これらの試みは、日常生活に関わる決定に人々を関与させるという利点があり、やがて技術による支配に対する社会の嗜好を明らかにするかもしれない。しかし、このようなアドホックなプロセスは、テクノロジーとのグランド・バーゲンが事実上要求しているような憲法会議の代用にはならないのである。民主的想像力の可能性を解き放つために、現代社会はまず、テクノロジーが自走するものでも、価値のないものでもないことを認識しなければならないだろう。控えめな技術改良であっても、かつては規制されていなかったケンブリッジの交差点を信号機の監視下で横断しなければならないときのように、新たな規範的権利と義務を生み出している。このように、テクノロジーと法律の類似性は、前者が後者に劣らず、私たちの集合的な未来を形作る強力な道具であることを明らかにしている。この認識は、テクノロジーのガバナンスに倫理的・政治的に深く関与することに拍車をかけるはずだ。テクノロジーが私たちの心や精神、そして集合的な信念や行動を形成する力を認めてこそ、ガバナンスの言説は宿命論的な決定論から自己決定の解放へと移行するのだ。そうして初めて、先見性のある平等な権利の倫理が、私たちの壊れやすく負担の大きい惑星における人類の文明の基礎として受け入れられるのだ。
謝辞
本とは旅の終わりを意味し、良い旅は仲間と共にするものである。この本は、当初の予定よりも長い道のりを歩んできた。当初は現代技術のリスクに関するシンプルなモノグラフとしてスタートしたが、出版社のシリーズ構想の変さらに伴い、人類の技術的未来を作り上げる上での政治的包摂と排除に関するより複雑な考察へと変化していったのである。このような変化を着実にサポートしてくれたノートン社の編集チームに感謝したい。アンソニー・アピアは、私にこのプロジェクトを引き受けるよう促し、事態を進展させた。また、Roby Harringtonは、原稿が止まっている間、辛抱強く対応してくれた。Brendan Curryのスマートで丁寧な読みは、時に説明的になりがちな原稿の主要なメッセージを明確にしてくれるのに役立った。また、編集と出版を円滑に進めてくれたソフィー・デュヴェルノワとナサニエル・デネットにも感謝している。
本書で扱った実証的な資料の一部は、法と技術に関する新しい研究であり、残りの多くは、新しい分析的文脈で見直された過去の研究に由来するものである。その結果、この本は特定の個人やプロジェクトによるものというよりも、私がハーバード・ケネディスクールで指導している「科学技術研究プログラム」で培われた集団的な思考法や作業方法によるものとなっている。過去数年にわたる同プログラムのフェローたちとの毎週のミーティングは、テクノロジーを管理することの倫理的・政治的側面に関する私の考えを深め、研ぎ澄ます場を提供してくれた。会話のパートナーとして、3人の名前を挙げることができる。Rob Hagendijk、Ben Hurlbut、そしてHilton Simmetである。近代におけるテクノロジーと民主主義の構成的、憲法的役割について本書が語ることの多くは、彼らとの継続的な交流を反映したものである。
また、本書の主題に関連する全米科学財団(NSF)の2つの助成金に主任研究員として携わったことも、非常に有益であった。「福島原発事故と日米における原子力の政治」(NSF 賞番号 1257117)と「イノベーションの旅するイマジナリー」(NSF 賞番号 1257117)である。また、「Traveling Imaginaries of Innovation: The Practice Turn and Its Transnational Implementation」(NSF賞番号:1457011)。NSF は私のキャリアの発展において、また科学技術研究の分野を構築するための努力において、極めて重要な役割を担っており、改めてその支援に感謝したいと思う。また、過去6年間、私のすべてのプロジェクトを成功に導いてくれたシャナ・ラビノウィッチにも感謝の念を捧げたいと思う。
[/passster]
第9章 民衆のための発明
20世紀を通じて、「テクノロジー」という言葉は、第一次産業革命の汚く、錆びついた、臭い、目に見えないインフラを思い起こさせるものであった。ウィンストン・チャーチル(Winston Churchill)は、政府に助言を与える科学者について、こう述べたという。「蛇口はあるが、上にはない」と。しかし、今世紀に入ると、テクノロジーは社会を変えるダイナミックな力と見なされるようになり、テクノロジーは人間の存在の目的と条件を劇的に、そしておそらくは取り返しのつかないほどに変えることができるという認識が世界の人々に広まり、より大きな希望と恐怖をもたらすようになった。20世紀後半の技術革新は、世界の人々全体にとって、より良い健康、より迅速なコミュニケーション、よりクリーンな環境、そして想像を絶する豊かな知識と情報を約束するものであった。人間個人のレベルでは、ナノ、バイオ、情報、認知科学の進歩に支えられた同じテクノロジーが、自己を改造する広大な機会を生み出し、これまで想像もできなかったような生活の向上をもたらすとともに、そうしたパワーが誤って使われたり、使いすぎて人類に永遠の不利益をもたらすかもしれないという懸念が生まれた。
核兵器の消滅という脅威は、技術的リスクに対する新たな世界的注目を集める強力な原動力となったが、1980年代以降、内部関係者が「収束的破壊」と呼んだ技術は、人間の能力の向上に対する人々の期待を高める一方で、技術の支配と浸透の影響に対する新たな不安を呼び起こすようになった。バイオテクノロジーは生命と健康の奇跡を約束したが、環境の悪化とモラルの崩壊に対する根深い懸念を呼び起こした。最近では、ナノテクノロジー、合成生物学、認知科学、神経科学、そして何よりもコンピューティング能力の発展が、人間であることの意味を再定義するテクノロジーの巨大な可能性に注目するようになった。特に情報技術は、個人情報の利用が拡大し、人間がかつてないほど採掘や監視の対象となりやすくなり、ビッグデータとアルゴリズムが人間の裁量に代わって、一見無謬の統治手段となる時代を予見している。一方、旧来の工業生産の遺産である気候変動は、私たちの技術的進歩への欲求を抑制しない場合に何が起こり得るかを示す妖怪として、地球上に漂っている。地球を冷却する地球工学、汚染を伴わない成長を可能にする新しいエネルギー技術、あるいは人間の誤った管理によって破壊されていない惑星への逃避という究極のSFファンタジーなど、この極限の脅威に直面してもなお、テクノロジーは自らの毒に対する最高の解毒剤になると確信している人たちがいる。
一般に信じられているが欠陥のある3つの信念は、それぞれ技術が基本的に管理不可能であり、したがって倫理的分析や政治的監視を超えるものであることを示唆しており、技術の統治に関する体系的思考を長い間妨げてきた。第一は技術的決定論で、何世紀にもわたる歴史的経験に反して、技術には歴史の流れを形成し推進する勢いがあるとするものである。第二はテクノクラシーで、熟練した知識を持つ専門家のみが技術の進歩を管理する能力を有するとするものである。第三は意図せざる結果という概念で、テクノロジーによって引き起こされる害は意図や予見の範囲外であると暗に位置づけ、人間以外の機械や認識の協力者を人間の意味のあるコントロール下に置く可能性について宿命論を育んでいる。
私たちは本書を通じて、技術的なシステムが実際にはこうした従来の常識よりも可塑的で、倫理的・政治的な監視に従順であることを見ていた。テクノロジーを作り出し、展開することは、個人の価値観や信念をいかに守るか、また、独特の法的・政治的文化に支えられた国民国家の政策的直観をいかに尊重するかなど、さまざまなレベルで倫理的問題を生じさせているのだ。このような問題は、20世紀後半に技術が世界的に普及したことによって緊急性を増し、技術先進国である社会に対して、積極的な社会的考察と対応の義務を課している。例えば、かつて医薬品は、医学の知識と実践における奇跡的なブレークスルーであり、全人類に利益をもたらすと考えられていた。しかし、グローバルな市場において、医薬品は国内のみならず国境を越えた権利と義務に関わる多くの規範的な問題と絡んでくるようになった。例えば、ヒト生物試料の所有権、医療データのプライバシー、臨床試験への同意、被験者研究の倫理、ジェネリック医薬品の製造、実験薬および必須医薬品へのアクセス、先住民の知識の保護、その他多くの関連事項が含まれる。これらすべての問題において、利害関係や期待は、病める者と健やかなる者、富める者と貧しい者、生産者と消費者、先進国と発展途上国の国民など、観察者の社会経済的立場によって大きく異なる。つまり、医薬品は科学、医学、経済、法律、政策の対象として、国境を越えた空間で人体を再構築する。しかし、医薬品開発の政治と倫理に関する審議のプロセスは、国家レベルに比べて超国家レベルではまだ著しく不十分である。
グローバル化する世界の倫理的ニーズを満たすために、私たちの広範囲に及ぶ技術的発明はどのように管理されるべきなのだろうか。技術革新のリスクと利益を誰が評価するのか、特にその結果が国境を越える場合、誰の基準に従って、どのような影響を受けるグループと協議して、どのような手続き上のセーフガードに従って、そして決定が誤ったものであったり有害であったりした場合にはどのような救済措置があるのだろうか。技術的な誤謬や失策は、社会的、政治的、法的により深い分析の必要性を絶えず私たちに警告している。しかし、善悪に関する多くの基本的な問題は依然として深く争われており、それらを解決するための原則はせいぜい弱々しく地平線上にかすんでいるに過ぎない。本章では、これまでの数十年にわたる技術システムのガバナンスに関する国内および世界的な経験から得られた主要な洞察をレビューしている。そして、これらの歴史をつなぐ3つのテーマ、「予見」、「所有」、「責任」の下に、依然として待ち受ける課題をまとめていく。
期待:不平等な贈り物
技術に関するすべての政策言説を貫く糸があるとすれば、それは賢明な先読みの必要性である。1970年代から1980年代にかけての技術評価プログラムは、技術によって引き起こされる物理的・環境的な害を予見し、それを回避することへの関心から生まれた。同様に、新しい技術の倫理的意味を評価するプログラムは、耐え難い道徳的被害を予見し、それを回避したいという広く分散した願望を反映している。当然のことながら、現代社会では、物理的および道徳的な結果に対する予測は、専門家による起こりうる結果の予測と密接に結びついている。技術政策の線形モデルは、リスク評価から始まり、後になってから意思決定に価値を注入するもので、最初の予測段階は、技術がどのように作動し、どこで間違うかを最もよく理解していると考えられている専門家、つまりテクノクラートに委ねられる。しかし、これまでの章に散見されるように、専門家の想像力は、その専門性によって制限されることが多い。既知のものが未知のものよりも優先される。したがって、専門家による予測は、短期的で計算可能な、議論の余地のない効果に重きを置く傾向があり、思わせぶりな、突飛な、あるいは政治的に議論の余地のある効果を優先させる。そして、ブレイクスルー科学的洞察に長けているにもかかわらず、専門家はハイブリッドな社会技術システムの複雑さを過小評価しがちで、人間と人間以外の要素間の理解されていないダイナミクスやフィードバックが、実験室ベースの予想の正確さを混乱させるのだ。
誰が未来を想像するのか?
技術革新の初期の有望な段階においては、先見性はしばしば専門家の支持者の学問的能力によって形成され、制限される。アシロマーの分子生物学者たちは、生物学的大災害を防ごうと決意していたが、商業的バイオテクノロジーによって再構築された世界が、主要な遺伝子組み換え作物が日常的に野生作物に取って代わるとは想像もしていなかっただろう。サハラ砂漠からヨーロッパへの太陽エネルギー輸送を構想したドイツのエンジニアリング会社は、文化も経済も大きく異なるこのような大胆なトランスナショナル・プロジェクトの政治的管理について考えていなかった。
また、制度的な保守性も、先見の明を阻む。例えば、裁判所は法律の安定性を確保しようとするが、その代償として技術の変容がもたらす価値を無視することになる。ジェネンテック社は、アナンダ・チャクラバーティ氏のバクテリアを単なる物質とみなし、ジェレミー・リフキン氏のバクテリアの特許から高等動物の特許への滑り台という一見根拠のない懸念よりも、バイオテクノロジー企業の段階的なビジョンを優先したコモンロー高裁に勝利したのだ。しかし、今にして思えば、リフキンは、ジェネンテックや科学界におけるその著名な擁護者よりも、生命特許化の起こりうる軌跡をより正確に予見していたように思われる。カナダの最高裁がオンコーマウスの特許を否定し、米国の最高裁がヒトの遺伝子の特許を退けたことは、生命を特許化することの極端な意味合いを遡って(遅きに失したとも言える)否定するものであったと言える。
専門家の思考においても、isとoughtの間にしばしば暗黙の乖離が生じ、倫理的懸念の端緒が鈍ることがある。科学者の常識から逸脱することは、不合理、虚構、幻想と見なされ、(まだ)できないことは心配する価値がないとされる。これまで見てきたように、発明はそれ自体が善とみなされる傾向があり、倫理的な監視は主に、約束された善が無謀な利益欲によって狂わされないことを保証するために発動される。技術的にありえないという予測は、潜在的に「非現実的」な倫理的憶測や早まった大衆の不安を防ぐバリアとして機能する。例えば、サイエンス誌が2013年に発表した「ブレイクスルー・オブ・ザ・イヤー」の次点リストに掲載された簡単な項目を考えてみよう。同誌は「ついに実現したヒトクローン」という見出しで、「今年、研究者たちはヒト胚のクローンを作り、長年の夢だった胚性幹(ES)細胞の供給源として利用することを発表した」と報じているのだ。同誌はさらに、この開発の倫理的意味を軽視し、社会が心配する必要がない理由として、道徳的嫌悪感よりも可能性が低いことを挙げている:「この偉業は、クローン赤ん坊に対する懸念も引き起こす。しかし、今のところその可能性は低いと思われる。オレゴン大学の研究者によれば、何百回と試したが、サルのクローン胚が代理出産で妊娠した例はない」(強調)1と言うのである。仮に、妊娠が成立し、クローン赤ん坊の可能性が高まったとしよう。私たちのような無限の創造力を持つ社会が、人間の尊厳に対する脅威がドアをノックした後に、このような広範囲に及ぶ技術的実験の倫理的意味について考えるのは適切なことなのだろうか。
サイエンス誌が想像する技術革新の世界では、クローンベビーについて一般大衆が懸念を表明することが適切であるとすれば、それはいつになるのだろうかと疑問に思う。オレゴンかどこかの研究者がクローン胚の妊娠に成功したと発表した後であろうか?しかし、その段階までには、新しい「is」が、より微妙で予防的な「ought」の可能性を圧倒してしまうだろう。例えば、倫理的に議論のある妊娠を誘発するために「何百回も試みる」前に、研究者によく考えさせる、あるいは人前で声を出して考えさせるような規則のようなものが考えられる。さらに、ヒト胚のクローニングを「長年の悲願」と表現することは、胚がどこで終わり、赤ん坊がどこで始まるかについて、国によって争われ、異なる道徳的決着があることを見落としている。たとえばドイツでは、研究の過程でアメリカよりもさらに上流で懸念が生じるかもしれない。これは、倫理的思考がどちらの場合も「西洋」の伝統に根ざしている二つの国において、功利主義的議論とは対照的に擁護主義的議論を好む傾向が異なることを示している。倫理的な推論に対する基本的なコミットメントにこのような格差があることを考えると、人類という種全体にとって重大な決定を、技術的に一流の国々が単独で行うことは、果たして適切なのだろうか。
専門家の自信に満ちた主張が道徳的分析のベースラインである以上、倫理的評価はいずれにせよ、起こりうるシナリオのコストと便益に関する功利主義的分析に陥りがちである。米国の2つの大統領倫理委員会がそれぞれヒトクローンや合成生物学を評価したときがまさにそうであった。いずれのケースでも、倫理委員会は、この技術はまだ十分に安全ではないため、現時点では倫理的な懸念はないと結論付けている2。このような失望するほど制約の多い活動は、構成的技術評価(第8章参照)のような手続きによって実現される先見的ガバナンスが、「技術科学の長い弧をより人道的な目的へと曲げることに貢献できる」という一部の民主主義理論家の期待に反している3。
トリクルダウン・イノベーション
現代社会は、技術的に不利な未来を予測し、潜在的な悪影響を回避するために、資金や専門知識といった膨大なリソースを投入しているが、それらのリソースは国や技術領域によって偏在している。2013年にバングラデシュで起きたラナプラザ工場の崩壊のような出来事は、貧しい人々の生活が、豊かな国では耐えられないとみなされるような方法で危険にさらされているグローバルな政治経済を物語っている。1984年、ボパールのユニオン・カーバイド工場からイソシアン酸メチルの死雲が放出され、何も知らずに眠っていた街に降り注いだときと同様、繊維産業で過去最悪の災害が起きた2013年も、驚くことに責任の所在を明らかにすることは困難だった。ソヘルラナの容疑が正式に固まるまで、2年以上を要した。バングラデシュの労働者を雇用する多くのアパレル企業が補償基金への拠出を約束したものの、責任の所在を正式に明らかにし、主要な多国籍企業が公に責任を負うようなグローバルな場は存在しなかった。リスクアセスメントがこのような恐ろしい事故を予見し、防止するためのものである限り、それは深刻なグローバル経済、政治、情報の不平等の状況下での予見と保護という課題にまだ追いついていないのである。
リスク評価の失敗は、歴史的に広く使われてきたこの予測技術を支えてきた狭い因果関係の枠にも起因している。「科学」としてのリスク評価は、常に社会的要因を軽視し、リスク創出に対するより捉えどころのない経済・制度・文化的貢献に対して、定量化可能な変数を過度に強調してきた。米国の事故専門家が、NASA内の組織的な状況がこれらの悲劇を可能にしたと指摘し始めるには、コロンビア号とチャレンジャー号の2つのスペースシャトル事故が必要であった。ボパール事故は、それに匹敵するような清算の瞬間を生み出さなかった。ボパール事故は、多くの人々が時期尚早で不当な和解と見なし、富と専門知識が同等でない国家間で非常に危険な技術が移転されたときに起こったすべての問題の公正な裁定を妨げてしまったのである。
ガバナンスの道具としての限界はあるにせよ、予期はどの社会にとっても無くてはならない価値である。歴史上、人間は現在の恐怖や試練を打ち消す手段として、現世であれ来世であれ、未来を予見することに目を向けてきた。蒸気機関、綿繰り機、電球から、今日の遺伝子組み換えジャガイモ「イネイト」に至るまで、より良い世界のビジョンが発明家たちを動かし、新しい道具を想像し、創造してきた。4 解放のビジョンが、カリフォルニアに拠点を置くシンギュラリティ大学の、一度に10億人の生活を飛躍的に改善するという野心につながっている。投資家は、研究開発の長い道のりのどこかで利益が上がることを期待して、設立間もないテクノロジー企業の株式を購入する。消費者もまた、アップルの最新の動きに注目し、洗練された機能、多様性、スピードなど、想像を絶する進歩を期待して、その役割を担っている。近代化の恩恵のひとつは、アイデアと現実化の間のギャップが縮まったことだ。知識を発明に結びつける能力は、科学的、経済的資源とともに成長した。人類の歴史上、優れたアイディアが素早く注目され、ベンチャーキャピタルや、グローバル市場に投入するために必要な法的・政治的支援を、使いやすい形でリアルタイムに受けられるようになった時代は、かつてないほど長く続いた。
しかし、今のところ、ポジティブな期待を抱くことができるのは、すでに多くのものを手に入れ、さらに多くのものを手に入れることを夢見ることができる人たちに限られているのが実情である。スティーブ・ジョブズの有名な主張、「消費者が何を欲しがっているか、彼ら自身よりも先に知っている」というのは、「欲しい」ではなく「たくさんある」という経済の中で生まれた言葉だ。ジョブズは、自分が夢見た美しいガジェットを、人々が欲しいだけでなく購入する資源も持っていると仮定していたのだ。しかし、世界の大衆の多くは、テクノロジーの進歩がもたらす直接的な利益や長期的な展望を自ら予測することはできない。彼らは、技術のフロンティアに近いところで、大規模な変化をもたらす資本とノウハウを持つ起業家が、別の場所で設計した発明によって自分たちの生活が改善されるという善意の部外者の約束を受け入れるしかないのである。このように、技術革新の公正なガバナンスを阻む未解決の倫理的・政治的障壁として、アクセスだけでなく、予見に関する不平等が浮かび上がってくるのだ。
技術的・経済的に恵まれた社会が享受する不公平な想像力の優位性を相殺するために、「質素なイノベーション」あるいは「質素なエンジニアリング」という考え方が定着してきた。ここでいう倹約とは、裕福でない人々の手段によりよく適応した技術を作ることを意味する。2005年にマサチューセッツ工科大学のニコラス・ネグロポンテが始め、前国連事務総長のコフィ・アナンが受け入れた100ドルノートPCプロジェクトはその典型である。その目的は、不必要な装飾を取り除き、発展途上国の多くを悩ませる不安定な電力供給のような不利な条件下でも動作するように装備することで、世界中に簡単に配布できる手頃な価格のコンピュータを作ることであった。インドのタタ・グループが開発した世界一安い自動車「ナノ」や、携帯電話「ノキア1100」、ユニリーバが開発した使い捨てのトイレタリー製品など、「質素な技術革新」は、あらゆるものを包含している。さらに、「余分な」部屋、車、ペットまでもが余剰資本となる「共有経済」の台頭は、「持てる者」の余剰財を「持たざる者」の利益のために利用する可能性のある一種の倹約的イノベーションであると考えることもできるであろう。
共有経済は、豊かさの経済学で確立されたものではあるが(他にこれほど多くの余剰物資があるだろうか)、間違いなく、ムハマド・ユヌスによる影響力のあるマイクロクレジットという概念と同系列のものであり、この概念も、人は多くを持つ必要がなく、共有できるため、すべての人に多くの利益を生み出すという原理に基づいている。さらに、無煙調理器、コンポストトイレ、簡易浄水器など、貧しい人々のための物質的なイノベーションは、北欧のエンジニアや科学者の注目を集め、大きな利益をもたらす可能性がある。しかし、全体として、貧困層を対象とした生活革新と、裕福な社会の収束技術におけるブレイクスルー開発を推進するような先見の明との間のギャップは、相変わらず驚異的である。
つまり、富裕層が達成した技術的な成果が、恵まれない人々の将来の見通しを決定してしまうのである。富裕層が自分たちの状況に合うように発明したものが、貧困層が必要とし、欲しがるべきものの金字塔であり続けている。イノベーションの問題が逆に問われることはほとんどない。1日2ドル未満で生活する世界人口の5分の2かそこらの人々にとって、どのような技術的未来が最も理にかなっているだろうか。7 彼らが少ない収入の50日を子供用ラップトップに費やすべきか、それとも技術がより有利に修正できるもっと緊急の需要があるのだろうか。いずれにせよ、ラップトップがあれば、富裕層が容易に想像し、満喫できるような、遊び心と生産性を兼ね備えたつながり(Facebook、Reddit、Pinterest、Instagram)への扉が開かれるのだろうか。
テクノロジーの未来設計に浸透している力の差は憂慮すべきものだが、それは人類にとって唯一の倫理的関心事ではない。実際、大量消費型のライフスタイルが持続不可能であることをこれまで以上に意識する時代にあって、金持ちが思い描く未来が貧乏人の想像力よりも優先されるべきかは不明である。ダウンサイジング、緑化、簡素化、さらには「フリーガニズム」(他人の不要なゴミで生活すること)が若者の間で人気を集めているように、地球上でより軽やかに生きるためのより良いアイデアは、下層から生まれる必要があるかもしれない。それは、生物および非生物の絶えざる帝国主義的搾取よりも、社会の結束と責任という価値観に注目したアイデアなのである。
所有と発明
過去数世紀にわたる技術開発は、財産や私的利益に関する考え方と同様に、集合的利益に関する予見に負うところが大きい。新しい技術には新しい採掘方法が含まれることが多く、以前は利用されていなかった資源にアクセスし、分配する方法を発見した人々には莫大な利益がもたらされる。探鉱や採掘がその例だが、テクノロジーは他の多くの資源利用を可能にし、しばしば国家や帝国の拡張計画と結びついてきた。19世紀半ばにカリフォルニアは近代的な州となったが、それは新発見の金のために何十万人もの移民が押し寄せたからだ。ダイヤモンド鉱山は南アフリカでセシル・ローズの帝国的野心を支え、ゴムと象牙の取引はコンゴでのレオポルド2世の残忍な政権を支えた。搾取、残虐行為、権力の悪用はこれらの事業に影を落としているが、それらが生み出す商品に対する需要がある限り、技術、経済、政治が一体となって圧政を維持することができたのである。
初期の採掘技術が、岩石、土、植物、海洋から、人々がすでに価値を認めていたものを採取したのに対し、今日の多くの技術は、歴史的に商品として扱われていなかったものに価値を与えている。遺伝子から、癌になりやすいハーバード大学のオンコーマウスのような研究所で作られた新しい存在まで、あらゆる生物学的素材がこのカテゴリーに含まれる。炭素市場や生態系サービスといった仕組みは、自然の一部を取引可能な商品へと変えてしまったが、金を使うように自然を所有したり利用したりすることはできない。ソーシャルメディアは、大規模な集積によって、人々の習慣や嗜好、記憶や願望を商品化している。フェイスブックは、10億人以上の人々が「友達」とつながることを望み、その友達とつながり、彼らの近況を知る見返りとして、大量の個人情報を私企業に提供することをいとわないという事実を利用している。Twitterは、140字の文字と添付された画像で、人々の過ぎ行く思いを利用する。インターネットが、精神的または視覚的な一瞬の印象を世界中のオーディエンスに広めることを可能にするまで、共有することに適していると考える人はほとんどいなかっただろう。ピンタレストは、結婚式、旅行、家の改築など、人々が予想される未来に迎え入れたいと思う夢を共有することで繁栄している。消費者向け検査会社は、自発的に提供された遺伝子情報をデータベース化し、医薬品の研究開発のための商業的な可能性を持っている。これらの技術システムはすべて、新しい方法で人々から利益を得ている。人々の思考、言葉、習慣、身体、感情を資源として採掘し、新しい市場性のある商品を作り出している。
HeLa細胞株に関する苦難の物語は、人々が自らの身体、そしておそらくはそれ以上に心に対して抱いている支配意識が、既存の法律や政策に組み込まれた所有権の推定と大きく乖離する可能性があることを明らかにした。レベッカ・スクルートが受賞したヘンリエッタ・ラックスの物語の再構築は、現代生物学の最も有用な研究ツールの一つと、アメリカの長年にわたる悩ましい人種と貧困の物語とが、不安定に混ざり合ったものに火をつけた。国立衛生研究所は、生物医学倫理の過去の失敗と密接に結びついた歴史的に排除された集団の道徳的主張が放置されれば、広報上の災難になることを認識していた。NIHの当面の問題は、ラックス家に先祖の生物学的遺産に関わる意思決定に参加する権利を与えるという、一回限りの手続きで解決された。しかし、HeLa細胞は、そのユニークな歴史的、政治的背景を除けば、Henrietta Lacksを二度目の死に追いやることになり、失敗に終わったであろう。このような特別な例は、科学とその研究対象が対称的でない交渉関係を享受する状況において、説得力のある前例となるとは考えにくい。
技術革新を支配する知的財産権制度は、ほとんどの場合、200年ほど前に近代産業界で生まれた所有権と資本に関する考え方を支持し続けている。もちろん、こうした考え方は、欧米諸国であっても完全に同質なものではない。欧州特許法は、米国特許法とは異なり、公序良俗に反する発明を禁止する明確な規定がある。また、特許商標庁が一時期、実用性が証明されていない単離されたDNA断片に特許を認めたように、欧州法は、最も寛容な段階にある米国法よりも「進歩性」を構成するものの立証に高いハードルを設定している。しかし、全体として、知的財産は、集団的努力よりも個人の起業家精神を優先させるなど、その規範的基盤を技術的中立のベールの下に隠しているのだ。グリベック事件(第7章参照)において、インドの最高裁判所は、特許法は経済発展の手段であり、その保護の範囲と性質は「国の経済状況」を反映すべきであると明確に述べている9。知的財産権の規範的基礎と権力の非対称性を強調するこうした表現は、欧米の法的判断ではほとんど見受けられない。
しかし、自律性、プライバシー、生命、あるいは健康についての公共の関心事と絡み合う所有権の主張を、法律が確認したり、不安定にしたりすることもできる。2013年に米国最高裁がヒト遺伝子の特許取得を中止する判決を下し、何十年にもわたり特許商標庁の方針を覆して、法的な力が顕著に表れた。公益団体である米国自由人権協会による長年の活動は、ヒトゲノムの一部を私有化することの正当性に関して、暗黙のうちに広く保持されている公共の価値観を侵害する商品化の動きを取り消した。国際的な場においても、このような事態は起こりうる。ただし、この場合の推進力は、人間性の政治学というよりはむしろ政治経済学である傾向がある。生物多様性条約は、先住民の知識保有者の所有権の主張を認めることで、何世紀にもわたって無秩序に行われてきた生物学的海賊行為を覆そうとしたのである。この条約は、地域社会と、地元の知識や材料を用いて新しい治療用化合物を開発するバイオプロスペクティング企業との間で利益を共有することを規定している。2001年のドーハ宣言で、知的財産権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)が改正されたのは、医薬品の生産よりも流通における経済格差が動機となったからだ。TRIPSは、エイズ危機のような緊急事態において、必須医薬品への迅速なアクセス拡大が必要な場合、各国が医薬品の特許権を回避することを可能にする。発明が、以前は不可能だった地政学的境界を越えた人、アイデア、材料の流通と相乗効果にますます依存するようになった今、知的財産の分散所有権をどのように認めるか、といった将来への未解決の問題がある。
責任:公的責任と私的責任
技術の進歩は個人の自律性や公的な審議の機会だけでなく、おそらくより重大に、個人と集団の責任の規範に影響を与える方法で、公的空間と私的空間の間の区分を作り変えることができる。カール・マルクスからハーバート・マルクーゼに至るまで、社会理論家は工業的労働慣行や大衆文化の普及を通じて、テクノロジーが人間の精神を平坦化し、標準化し、鈍化させることに警鐘を鳴らしてきた。大規模な技術システムの鉄の檻の中で、組立ラインと生産割当の専制に従うと、解放と自己への責任が宇宙的なジョークに聞こえるかもしれない。新しい生物学的技術と情報技術は、特に遺伝性疾患からの解放を大きく約束する。しかし、それらはまた、身体と精神への前例のないアクセスを可能にし、『1918年宇宙の旅』のオーウェル的悪夢さえ凌ぐ社会統制の可能性を作り出す。
デジタル時代には、ある程度、人々自身がプライベートの境界を狭めることに加担していることが証明されている。セルフィー(携帯カメラで撮影した自画像)文化の台頭と、他人の視線を集めたいという人々の無限の欲望は、軽率な行動が雇用の見通しを狂わせ、政治的キャリアを台無しにし、かつて有名人でさえ自分だけのものにしていた領域に侵入しうる、酔わせる空間を生み出している10。データ・オリガルヒは現在、グーグルとフェイスブックのプライバシー・ポリシーのような、国家がスポンサーとなり、また自ら課した規制のパッチワークの下で運営されており、異なる規範的コミットメントを反映している。情報の荒々しいフロンティアを組織的な統制に近づけるには、EUの「データ主体」のような概念をより広く採用し、人々が自分の好みや個人に関するデータの流通について何を知り、期待し、許容するのかを持続的に議論することが必要かもしれない。
市場原理と新自由主義的な統治形態が支配する時代において、「公共性」という概念そのものが縮小していることから、別の種類の倫理的な心配が生じる。大金がさまざまな経路を通じて世論に圧力をかけることができる時代には、代表民主制の伝統的な場である議会の存在意義がますます薄れているように思われる。企業家は、法律が常に科学技術に遅れをとっているため、イノベーションを阻害すると主張し、立法に激しく抵抗している(特に米国において)。World Wide Webの発明者であるSir Timothy Berners-Leeやヒトゲノムの共同解読者であるCraig Venterなどのカリスマは、インターネットの成功とバイオテクノロジーの普及を、自由放任の技術開発の利点の典型例として挙げる。一方、立法府はしばしば反撃する勇気と専門知識を欠いており、理論的には抑制することが約束されている利益団体に政治的に肩入れしている場合がある。
バイオメディシン、ナノテクノロジー、合成生物学、神経科学など、特定の技術開発に特化した倫理機関の爆発的な増加は、公的な政策決定機関が私的に支配されるのを防ぐ効果があるはずだが、実際にはこうしたしばしば目に見えない委員会が、倫理的懸念をさらに増大させることになるのである。研究事業と密接に結びついた場合、人間を対象とした研究を監督する機関審査委員会のような組織は、所属機関や科学界のスターに過度の負担をかけないよう暗黙の了解のもとに運営される傾向がある。これまで見てきたように、より目立つ国の倫理委員会でさえ、新しい研究分野の長期的な公共利益について厳しい質問をするよりも、差し迫った技術的未来についての費用便益分析という安住の地を好むのである。例えば、英国のワーノック委員会は、14日以前の胚を研究目的のために非人間とすることで、現代の生物医学に大きな貢献をしている。イギリスでは、この明瞭な線によって、胚組織を用いたフロンティア研究に寛容な空間が生まれ、病気の子供に適合する組織を提供するための「救世主兄弟」の利用や、母親のミトコンドリア遺伝病を取り除くための3人胚の作成など、新しい倫理的拡張が初めて承認されるに至ったのである。しかし、このような閉鎖的な倫理団体内部での公共道徳の相対的私物化を放置すれば、公衆の疎外と規範的拒絶を産み出すかもしれない。幹細胞研究のような問題をめぐる現在進行中の論争は、倫理専門家による規範的な線引きの政治的脆弱性を明らかにするものである。
結論
現代社会は、過去100年の間に、多くの奇妙で素晴らしいものを発明し、移動、コミュニケーション、計算、生命と健康の維持において、想像を絶する障壁を打ち破ってきた。テクノロジーによって、私たちは飢餓を余剰に変え、殺人的な病気をなくし、海や成層圏を掘り起こし、宇宙を人間の想像力の及ぶ範囲に収め、人間の心の奥底を目標とする探索のために開放してきた。ロボットが火星や彗星に着陸したとき、世界の多くの人々は喜ぶ。それは、ロンドンからハンマーを投げてニューデリーの釘を打つようなものだとも言われるほど、精度の高い偉業なのである。2015年12月、米国の技術起業家イーロン・マスクが率いる企業が、人工衛星を軌道に打ち上げた後、地球に帰還するロケットの着陸に成功し、再利用可能なロケット建設の夢が現実となった。同時に、技術活動が健康や環境、社会に与える影響のモニタリング、モデル化、測定も大きく進展している。19世紀の工場が手つかずの風景に煙やほこりを吐き出し、有毒な染料が無秩序に川に流れ込み、企業がアスベストにさらされた労働者が何千人も肺病で死んでいるという証拠を隠していた頃のように、技術文化はもはや自然に対して無頓着ではなくなっているのである。
しかし、これまでの章で見てきたように、制度的な欠陥、不平等な資源、自己満足的な語り口が、テクノロジーと人間の価値の交錯と相互影響に関する深い考察を妨げているのが現状である。注意や予防を促すような重要な視点は、時に新しいものへの無頓着な突進のように感じられ、脇に追いやられてしまう傾向がある。その結果、テクノロジーが持つ解放、創造性、エンパワーメントの可能性が満たされないまま、あるいはせいぜいうまく分配されないままになっている。ゲノム革命や情報革命のような、慎重な先見性と持続的な世界的関心を必要とする問題は、部分的に経路に依存する日和見的なデザインの選択によって非政治化されるか、あるいは見えなくなり、将来の創造性と解放が挫折させられるのだ。
20世紀で最も成功した技術的発明の一つであり、今なお世界中の富のフェチである自動車の歴史は、人間の先見性の限界を示す模範的なケーススタディであり続けている。自動車は個人の自由と生産性に計り知れない可能性をもたらしたが、それは同時に、誰も想像しなかった、あるいは適時に規制することのできなかった社会への劇的な影響ももたらした。毎年世界中で100万人を超える交通事故死、殺伐としたルーチンワークの蔓延、都市の大気汚染、コミュニティの分断、かつて巨大だった製造拠点の衰退、そしてついには世界を脅かすほどの気候変動。現在の責任あるイノベーションと先見的なガバナンスの実践は、自動車の歴史が悲劇的な道をたどる前に、その流れを変えることができただろうか。大量に普及し、経済的・社会的に莫大な影響を及ぼす技術については、国民国家が指揮する局所的かつ一時的なガバナンスのプロセスは、悲しいほど不十分であるように思われる。さらに、時折の動員では、予見の非対称性の核心に迫ることはできない。あらゆる実際的な目的のために、テクノロジーを支配するためのゲームのルールを設定する権限は、資本と産業界にあり、労働し、消費し、あまりにも頻繁に苦しんでいる大衆の政治的代表にはないのである。
この深い民主主義の欠陥は、手続き的な応急処置で治すことはできない。最近盛んに行われている公開協議、建設的技術評価、倫理審査などの実験は害を及ぼすものではなく、確実に継続されるべきものである。これらの試みは、日常生活に関わる決定に人々を関与させるという利点があり、やがて技術による支配に対する社会の嗜好を明らかにするかもしれない。しかし、このようなアドホックなプロセスは、テクノロジーとのグランド・バーゲンが事実上要求しているような憲法会議の代用にはならないのである。民主的想像力の可能性を解き放つために、現代社会はまず、テクノロジーが自走するものでも、価値のないものでもないことを認識しなければならないだろう。控えめな技術改良であっても、かつては規制されていなかったケンブリッジの交差点を信号機の監視下で横断しなければならないときのように、新たな規範的権利と義務を生み出している。このように、テクノロジーと法律の類似性は、前者が後者に劣らず、私たちの集合的な未来を形作る強力な道具であることを明らかにしている。この認識は、テクノロジーのガバナンスに倫理的・政治的に深く関与することに拍車をかけるはずだ。テクノロジーが私たちの心や精神、そして集合的な信念や行動を形成する力を認めてこそ、ガバナンスの言説は宿命論的な決定論から自己決定の解放へと移行するのだ。そうして初めて、先見性のある平等な権利の倫理が、私たちの壊れやすく負担の大きい惑星における人類の文明の基礎として受け入れられるのだ。
謝辞
本とは旅の終わりを意味し、良い旅は仲間と共にするものである。この本は、当初の予定よりも長い道のりを歩んできた。当初は現代技術のリスクに関するシンプルなモノグラフとしてスタートしたが、出版社のシリーズ構想の変さらに伴い、人類の技術的未来を作り上げる上での政治的包摂と排除に関するより複雑な考察へと変化していったのである。このような変化を着実にサポートしてくれたノートン社の編集チームに感謝したい。アンソニー・アピアは、私にこのプロジェクトを引き受けるよう促し、事態を進展させた。また、Roby Harringtonは、原稿が止まっている間、辛抱強く対応してくれた。Brendan Curryのスマートで丁寧な読みは、時に説明的になりがちな原稿の主要なメッセージを明確にしてくれるのに役立った。また、編集と出版を円滑に進めてくれたソフィー・デュヴェルノワとナサニエル・デネットにも感謝している。
本書で扱った実証的な資料の一部は、法と技術に関する新しい研究であり、残りの多くは、新しい分析的文脈で見直された過去の研究に由来するものである。その結果、この本は特定の個人やプロジェクトによるものというよりも、私がハーバード・ケネディスクールで指導している「科学技術研究プログラム」で培われた集団的な思考法や作業方法によるものとなっている。過去数年にわたる同プログラムのフェローたちとの毎週のミーティングは、テクノロジーを管理することの倫理的・政治的側面に関する私の考えを深め、研ぎ澄ます場を提供してくれた。会話のパートナーとして、3人の名前を挙げることができる。Rob Hagendijk、Ben Hurlbut、そしてHilton Simmetである。近代におけるテクノロジーと民主主義の構成的、憲法的役割について本書が語ることの多くは、彼らとの継続的な交流を反映したものである。
また、本書の主題に関連する全米科学財団(NSF)の2つの助成金に主任研究員として携わったことも、非常に有益であった。「福島原発事故と日米における原子力の政治」(NSF 賞番号 1257117)と「イノベーションの旅するイマジナリー」(NSF 賞番号 1257117)である。また、「Traveling Imaginaries of Innovation: The Practice Turn and Its Transnational Implementation」(NSF賞番号:1457011)。NSF は私のキャリアの発展において、また科学技術研究の分野を構築するための努力において、極めて重要な役割を担っており、改めてその支援に感謝したいと思う。また、過去6年間、私のすべてのプロジェクトを成功に導いてくれたシャナ・ラビノウィッチにも感謝の念を捧げたいと思う。
最後に、私の人生における家族の存在は、多くの謝辞を必要とするほど基礎的なものである。この本は未来についての本なので、私がせいぜいぼんやりとしか想像できないような世界の形成に手を貸してくれるであろうニーナに捧げるのが特に適切であると思われる。
