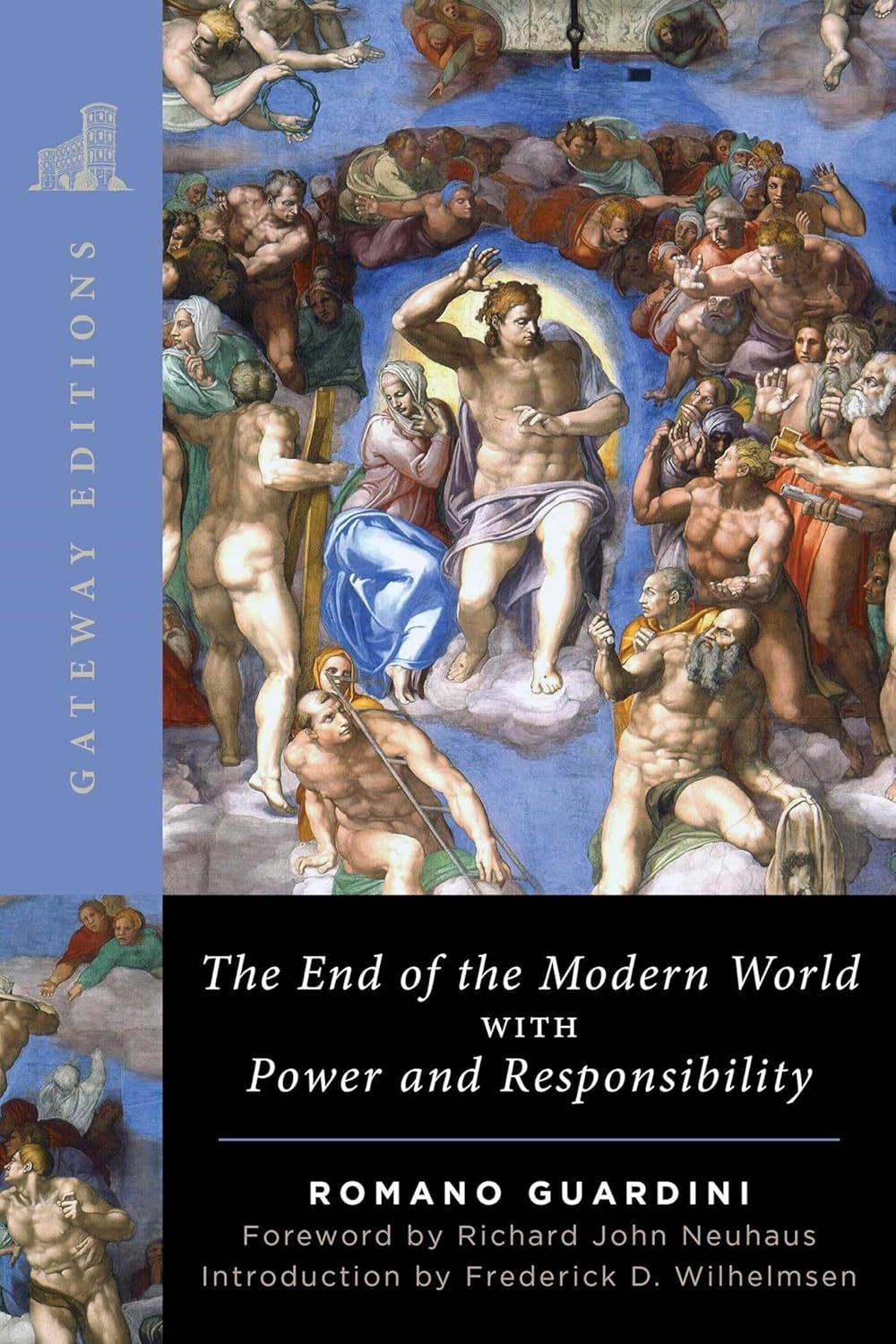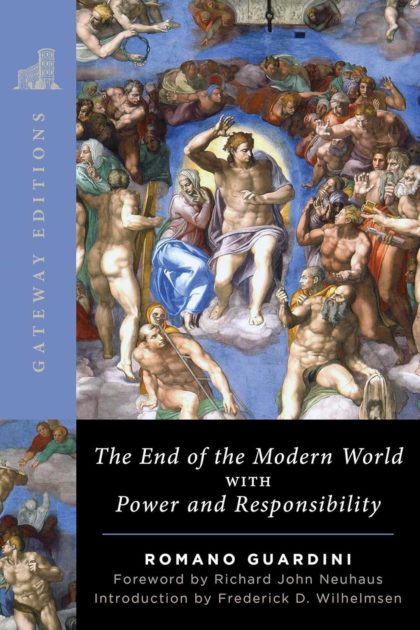
『The End of the Modern World:A Search for Orientation / Power and Responsibility:A Course of Action for the New Age』Romano Guardini 1998
『現代の終焉:方向定位の試み / 権力と責任:新時代のための行動指針』ロマーノ・グアルディーニ 1998
目次
- 序文 / Foreword
- 序論 / Introduction
- 著者序文 / Author’s Introduction
- 第一部 現代の終焉:方向定位の試み / Part I:The End of the Modern World:A Search for Orientation
- 第1章 中世における存在感覚と世界像 / Chapter 1:The Sense of Being and the World Picture of the Middle Ages
- 第2章 近代世界の誕生 / Chapter 2:The Birth of the Modern World
- 第3章 近代世界の解体と来たるべき世界 / Chapter 3:The Dissolution of the Modern World and the World Which Is to Come
- 第二部 権力と責任:新時代のための行動指針 / Part II:Power and Responsibility:A Course of Action for the New Age
- 第4章 権力の本質 / Chapter 4:The Essence of Power
- 第5章 権力の神学的概念 / Chapter 5:The Theological Concept of Power
- 第6章 権力の展開 / Chapter 6:The Unfolding of Power
- 第7章 世界と人間の新たな概念 / Chapter 7:The New Concept of the World and of Man
- 第8章 行動の可能性 / Chapter 8:Possibilities of Action
本書の概要:
短い解説:
本書は、現代という歴史的 エポックが終焉しつつあるという認識のもと、来たるべき新たな時代における人間の存在様式と権力の本質を、キリスト教的観点から根源的に問い直すことを目的とする。
著者について:
著者ロマーノ・グアルディーニは、20世紀ドイツを代表するカトリックの神学者・哲学者である。ミュンヘン大学で哲学と神学の教授を務め、現代社会と信仰の関係を深く考察した。その思想は、単なる時代批判に留まらず、歴史の大きな流れの中で人間存在の意味を探求するものである。
テーマ解説
- 主要テーマ:歴史的 epoch の断絶 [本書は、中世、近代、そして来たるべき新時代の間に根本的な断絶があると捉え、その移行における人間の自己理解と世界との関係性の変容を描く。]
- 新規性:来たるべき時代のためのキリスト教的倫理の提唱 [単なる近代批判に終始せず、技術と権力が支配する新たな時代において、キリスト教信仰がどのように生きられ、いかなる倫理を提供しうるかを積極的に提示する点に新規性がある。]
- 興味深い知見:「場所」を失った人間 [宇宙が無限に拡がり、神の「場所」である天界が消失したことで、人間もまた存在論的な「場所」を失い、根源的な不安に苛まれるようになったという洞察は、本書の核心的な論点である。]
キーワード解説
- 非人間的な人間:近代までの「人間的な人間」が感覚と経験を通じて世界と調和していたのに対し、テクノロジーの発展により自身の作り出したものを経験できなくなった新しい時代の人間類型。
- 非自然的な自然:かつて「母なる自然」として崇められた自然が、テクノロジーによって操作可能な単なる資源へと変貌し、その本来性を喪失した状態。
- 謙遜:近代が軽視したこの概念を、グアルディーニはキリストが神の身分を捨てて人となった「ケノーシス(自己空虚化)」に基づく、弱さではなく力の德目として捉え直す。
- 大衆:自律的な個性を放棄し、画一化された組織の中に自らを同化させる新たな人間類型。人格(パーソナリティ)ではなく、神によって呼び出された「ペルソナ」としての尊厳が問われる。
- デモン的:人間がその責任を放棄したとき、権力は匿名のものとなり、最終的には悪意を持つ霊的存在であるサタンの支配下に入りうるという、聖書的啓示に基づく危険性の指摘。
3分要約
本書は、ロマーノ・グアルディーニが戦後まもない1940年代末に行った講義をもとに、近代という時代の終焉を宣言し、そこから訪れる新たな時代の様相を予見的に描き出す壮大な試みである。リチャード・ジョン・ノイハウスの序文とフレデリック・D・ウィルヘルムセンの序論は、グアルディーニの思想が単なる現代批判ではなく、来るべき時代に対する根源的な問いかけであることを示している。
第一部「現代の終焉」では、まず中世の世界像が、有限で秩序だったコスモスとして描かれる。そこでは、地球は宇宙の中心であり、その外縁には神の住まう「エンピレオ(至高天)」が存在した。人間はこの世界の中で明確な「場所」を与えられ、神への奉仕として文化を創造した。しかし、ルネサンス以降、近代はこの有限性を打ち破り、無限の宇宙と自律的な主体という新たな世界像を打ち立てる。自然は崇拝の対象となり、人間の「人格性」は絶対的な価値を持つに至った。だが、この近代もまた終わりを迎えつつある。二度の世界大戦を経て、人間は「母なる自然」に対する信頼を失い、自らが生み出したテクノロジーという権力の前に無力さを感じ始める。グアルディーニは、ここに「非人間的な人間」と「非自然的な自然」という新たな時代の人間と世界の姿を看取する。個人は「大衆」の中に埋没し、かつての人格的理想は失われた。文化は安全ではなく危険をもたらすものとなる。著者は、このような状況下でキリスト教信仰は、世俗的なものとの安易な妥協を排し、より純化された決断と服従を求められることになると予見する。
第二部「権力と責任」は、この新たな時代における中心的な課題を「権力」と捉え、その本質から神学的な意味、そして具体的な行動指針までを考察する。権力とは、単なる自然のエネルギーではなく、意識と意志によって方向づけられるものであり、それゆえに責任が伴う。聖書の創造物語は、人間が神の似姿として世界を支配するよう委ねられた存在であると同時に、その権力を神に対して責任を負う存在であることを示す。原罪によってこの関係は破壊され、人間の権力は濫用される傾向を持つようになった。この原罪の状況に対する神の応答が、キリストの受肉と謙遜である。キリストは、神としての無限の権能を持ちながら、それを放棄し、僕(しもべ)の姿をとることで、権力の使い方の究極的な模範を示した。
現代は、科学技術の発展により、人間の権力がかつてないほど増大した時代である。自然は分析され、操作される客体となり、社会は巨大な機構と化し、人間自身もまた権力の対象となる。グアルディーニは、この権力の増大に倫理的な成熟が伴っていないことを憂慮する。権力は匿名化し、その責任の所在が不明瞭になることで、「デモン的」な性格を帯びる危険性をはらむ。しかし著者は、来たるべき時代に希望がないわけではないと述べる。世界が有限であり、相互に連関しているという新たな認識は、人間により大きな責任を課す。求められているのは、単なる技術者や政治家ではなく、自らの内なる欲望をも制御し、謙遜に真実に従うことのできる、真の「支配者」としての人間である。そのためには、瞑想的な態度の回復、物事の本質への問い、自己克服としての禁欲、そして神との正しい関係の再構築が必要となる。最終的に、行動の可能性は、個人の内省と良心に基づく日々の決断にかかっていると、グアルディーニは結ぶ。
各章の要約
第一部 現代の終焉:方向定位の試み
第1章 中世における存在感覚と世界像
中世の世界は、古代から受け継いだ有限の球体宇宙に、キリスト教の啓示が加わることで成立した。地球を中心とする天球の彼方には、神の住まう「至高天」があり、魂の内奥にも神の住まう超越の領域があった。この二つの極の間に、神の似姿としての階層秩序をなす世界が広がっていた。文化や社会は教会と帝国という二つの中心に統合され、歴史も創造から終末までの限られた時間の中で意味を与えられていた。グアルディーニは、中世を単なる権威への隷従の時代ではなく、象徴と芸術的表現に満ちた、人間の尊厳が高度に発展した epoch として評価する。そこでの知識は経験的な探求ではなく、与えられた権威を深く瞑想し、そこから世界の霊的法則を汲み取ることにあった。
第2章 近代世界の誕生
近代は、中世の閉じた世界像が解体し、無限の宇宙と自律的な主体という新たな世界像が誕生した epoch である。ルネサンス以降、人間は権威ではなく、直接的な自然探求へと向かい、科学革命が始まる。コペルニクス的転回によって地球は宇宙の中心の座を追われ、人間は存在論的な「場所」を失う。これに伴い、中世には存在しなかった根源的な不安が生まれた。近代は、この失われた場所の代わりに、「自然」と「人格性」という新たな絶対を打ち立てる。自然は無限で創造的な「母」として崇拝され、人間の人格は自律的な創造者として称揚される。さらに、人間の創造物である「文化」が、これら二つの領域の表現として絶対化された。しかし、この過程でキリスト教信仰はその自明性を失い、世界の中で居場所を失っていくことになる。
第3章 近代世界の解体と来たるべき世界
20世紀に入り、近代を支えた三つの柱、自然・人格性・文化は崩壊しつつある。人間はもはや「母なる自然」に抱かれておらず、自然はテクノロジーによって操作される資源となった。自律的な「人格」は「大衆」に埋没し、個性は画一化へと向かう。文化はもはや安全な避難所ではなく、危険そのものとなった。グアルディーニはこの新しい人間を「非人間的な人間」、新しい自然を「非自然的な自然」と呼ぶ。彼らは、自らの手で作り出したテクノロジーの権力を制御できず、その危険は日々増大している。このような状況下で、キリスト教信仰は、近代が享受してきたキリスト教的価値の恩恵を剥ぎ取られ、より純粋で決断的なものとして現れるだろう。信仰は孤独の中で鍛えられ、真の愛のみがこの新しい世界の危険に対抗しうる、とグアルディーニは予見する。
第二部 権力と責任:新時代のための行動指針
第4章 権力の本質
権力とは、単なる自然のエネルギーとは区別される。意識と意志によって特定の目標に向けて方向づけられ、現実を変革する能力である。その本質には、常に責任が伴う。責任の所在が不明確になるとき、権力は匿名化し、最終的には悪意を持つ霊的存在である「デモン的」なものへと変質する危険性がある。権力は、善悪いずれの可能性も秘めた中立的な手段であり、その行使は、知識や創造、さらには苦しみに至るまで、人間のあらゆる活動に結びついている。従って、権力の本質的な問いは、それを誰が、どのような目的で、いかに責任をもって行使するのか、という点にこそある。
第5章 権力の神学的概念
聖書の創世記は、人間が神の似姿として創造され、世界を支配するよう委ねられた存在であることを示す。この権力は、神からの委託物であり、それゆえに神に対する責任を伴う。しかし、原罪において、人間は神への服従という関係を破壊し、神のように自立しようとする傲慢に陥った。これ以降、人間の権力は濫用される傾向を内在させることとなる。この人間の状況に対する神の応答が、キリストの受肉と謙遜である。キリストは神としての権能を持ちながら、それを放棄し、僕の姿をとり、死に至るまで従順であった。この「ケノーシス(自己空虚化)」は、権力の本質に対する決定的な回答であり、真の力は弱さと謙遜の内にこそ現れることを示す。キリストの謙遜は、権力の呪縛を打ち破る解放者なのである。
第6章 権力の展開
人間の権力は、原始的な道具の発明から始まり、近代における科学技術の飛躍的発展を経て、かつてない規模にまで拡大した。自然は分析・解体され、機械によって操作される客体となる。このプロセスは、人間とその仕事の関係を根本から変えた。手工業に代わって機械工業が支配的となり、人間は自らの作り出すものを直接経験することができなくなった。この「非人間的な人間」は、組織の中で匿名化し、大衆化する。国家もまた巨大な機構と化し、人間を支配の対象とする。倫理規範は弱体化し、宗教的経験は世界から失われ、人間はますます権力に対して無防備になっている。こうして、人間のすべてを掌握する「全体的計画」の観念が、来たるべき時代の現実的な可能性として姿を現す。
第7章 世界と人間の新たな概念
増大する権力は、同時に破局的な危険をももたらす。戦争による物理的破壊、精神の操作と病弊、人間に対する暴力の横行、そして権力を持つ者自身の内面的腐敗である。しかし、グアルディーニは、来たるべき世界に肯定的な兆候も見出す。世界はもはや無限ではなく、計測可能で有限なものとして認識されつつある。諸々の事象は相互に連関し、一切の責任が人間に課せられている。こうした中で求められるのは、この危険と責任を引き受けることができる真の「支配者」としての新しい人間像である。彼はテクノロジーと親和的でありながら、その危険を熟知し、自由と服従、禁欲と節度をわきまえ、何よりも神との正しい関係に立つ存在でなければならない。このような新しい人間こそが、権力による暴力と混沌から世界を救いうるのである。
第8章 行動の可能性
歴史は必然的な過程ではなく、人間の自由な決断によって方向づけられる。そのため、来たるべき時代への具体的な行動は、まず個人の内省と責任の自覚から始まる。必要なのは、瞑想的な態度の回復であり、物事の本質への絶えざる問いかけである。そして何よりも、自己を制御する禁欲の実践が不可欠である。外的な雑音や欲望に抗い、内面の自由を勝ち取ることが、外的な世界に対する真の支配の前提条件となる。最終的には、あらゆる行動は、真実への敬意と自由な精神に基づく、個人の良心の決断に収斂する。グアルディーニは、日常の些細な責務に対する誠実な応答こそが、来たるべき大きな時代の課題を切り開く道であると説く。
歴史という名の診断書:グアルディーニはなぜ現代を「終わった」と宣告したのか
by DeepSeek
予備的困惑:なぜこの本を今読むのか
1940年代末、第二次世界大戦の廃墟から生まれたこのドイツの神学者の講義録が、なぜ21世紀の今、新たに出版され続けているのか。
まずこの問いから始めざるをえない。グアルディーニという人物について、私はほとんど知らない。カトリック神学者であり、ミュンヘン大学で教鞭をとった知識人だという。しかし、それだけならば、数多ある戦後ドイツの思想家の一人で終わったかもしれない。
重要なのは、この本が「現代の終焉」を宣言し、その後に来るものを「まだ名前のない時代」と呼んでいる点だ。つまり彼は、自分が生きている時代そのものを、歴史の対象として外側から眺める視点を持っていた。これは驚くべきことだ。通常、人は自分の時代の空気に浸かりきっており、それを相対化することは難しい。魚に水が見えないように。
だが、この本の冒頭で、ウィルヘルムセンの序論はさらに踏み込む。グアルディーニの主張の核心は、人間が宇宙の中で「場所」を失ったことにあるという。中世人は地球が宇宙の中心であり、その外縁に神の住まう「至高天」があると信じていた。近代人はコペルニクス的転回によって地球を中心から引きずり下ろしたが、代わりに「無限の宇宙」という新たな絶対を手に入れた。ところが現代人には、その無限性すらも失われつつある。
少し立ち止まる。この「場所の喪失」という概念は、あまりに詩的であり、科学的厳密性を欠くように思える。しかし、ここで私の内部で警鐘が鳴る。単純に「非科学的だ」と切って捨てることは、本当に正しいのだろうか。人間の存在感覚というものを、物理学の方程式だけで捉えきれるのか。むしろ、グアルディーニは、科学的世界像と人間の実存的感覚との間に生じた「ずれ」を問題にしているのではないか。
中世という「異質な土地」の再発見
第1章を読み進めると、グアルディーニが単純な中世礼賛者でないことが分かる。彼はロマン主義者が描いた美化された中世像を明確に否定している。むしろ彼が試みるのは、中世を「その固有の条件の中で」理解することだ。
中世人にとって、世界は「意味に満ちた有限の球体」だった。地球は中心にあり、九つの天球がそれを取り巻き、最外層には神の住まう至高天がある。あらゆる存在は神の似姿を反映する階層秩序の中に位置づけられ、その秩序は教会と帝国という二つの中心に収斂する。
グアルディーニは述べる。「中世人が自分の世界に『場所』を持っていたとは、単に物理的な位置のことではない。存在の全体の中で、自分がどこに立っているかを知っていたということだ」
ここで疑問が湧く。このような世界像は、現代の科学的知見からすれば完全に「誤っている」のではないか。しかし、グアルディーニは重要な指摘をする。たとえ天動説が科学的に否定されても、その世界像が持っていた「人間にとっての機能」は無効にならない。中世人は、この閉じた宇宙の中で、安心して存在することができた。自分の居場所が分かっていた。そして何より、神の場所も分かっていた。「高いところ」に神はいたのだ。
これは単なるノスタルジーではない。もしそうなら、彼は「中世に戻れ」と主張するはずだ。しかし彼はそれを明確に否定する。歴史は不可逆であり、中世は永遠に失われた。彼が問うのは、中世的世界が崩壊した後、人間は何を失い、何を得たのか、そして今どこに立っているのか、ということだ。
近代の欺瞞:絶対を求めて絶対を失う
第2章で、グアルディーニは近代の誕生を描く。ルネサンス以降、人間は権威から離れ、自らの感覚と理性で世界を探求し始める。コペルニクス、ガリレオ、そして無限宇宙を宣言したジョルダーノ・ブルーノ。地球は中心から追われ、太陽の周りを回る一惑星に過ぎなくなった。宇宙は無限に広がり、人間は「どこでもない場所」に放り出される。
このとき、近代人は三つの新たな絶対を創り出した。第一は「自然」だ。母なる自然、無限の創造性、自らを律する調和——自然は神に代わる崇拝の対象となった。第二は「人格性」あるいは「主体」だ。デカルトの「我思う」に始まり、カントの超越論的主観性に至るまで、人間自身が意味の源泉となる。第三は「文化」だ。人間の創造物そのものが絶対化され、芸術や学問は自己目的化する。
「近代人は、自分が神の場所に立とうとした」とグアルディーニは言う。しかし問題は、神の場所に立つ者は、同時に神の責任も負わねばならないことだ。近代人は権力を手に入れたが、その使い方に対する責任を引き受ける用意がなかった。
ここで私の内部で新たな疑念が生じる。この「近代批判」は、あまりにキリスト教的観点に偏っていないか。近代科学の成果——医学の進歩、生活水準の向上、個人の自由の拡大——これらをどう評価するのか。グアルディーニはこれらを否定しているわけではない。しかし彼が問題にするのは、これらの進歩が「無条件の善」として信仰されたことの危険性だ。自然は無限に寛容であり、歴史は必然的に進歩するという信仰。この信仰が、人間の責任感覚を麻痺させたと彼は言う。
大衆の時代:人格から匿名へ
第3章は最も衝撃的だ。グアルディーニは、近代が終焉しつつある証拠として、人間の自己理解の根本的変化を挙げる。かつての「人格」の理想は消え去り、代わりに「大衆」が現れた。
「大衆」とは単なる多人数のことではない。彼らは自らの個性を主張せず、組織の中に埋没することを自然と受け入れる。かつての人間が「自分らしさ」を追求したのに対し、大衆は「平均化」を生きる規範とする。彼らは機械のリズムに合わせて生き、自分の人生を自分で方向づけることに特別な価値を感じない。
グアルディーニはこの人間を「非人間的な人間」と呼ぶ。この言葉には注意が必要だ。彼はこれを道徳的判断として使っているのではない。むしろ、ある特定の歴史的 epoch に特有の人間類型として定義している。この人間は、自らの作り出したテクノロジーの世界を、もはや経験として生きることができない。知識と行動は拡大し続けるが、それを内面化する能力が追いつかない。
ここで私は、現代日本の風景を思い浮かべる。スマートフォンを手に、SNSで情報を消費し、AIに仕事を委ねる私たち。私たちは確かに、自らの生活を「経験」していると言えるだろうか。あるいは、システムの中で機能する歯車の一つになりつつあるのではないか。
グアルディーニはさらに踏み込む。この「非人間的な人間」は、自然をも「非自然的な自然」に変えた。かつて畏敬の対象だった自然は、単なる資源、エネルギー、操作可能な客体となる。山はレジャー施設となり、川は発電の手段となり、遺伝子は特許の対象となる。
そして何より恐ろしいのは、文化そのものが「危険」を内包するようになったことだ。かつて文化は自然の脅威から人間を守る砦だった。しかし今や、文化(テクノロジー、経済システム、政治機構)こそが最大の脅威となっている。原子爆弾はその象徴に過ぎない。グアルディーニは言う。「人間は今日、権力を持っているが、その権力に対する権力を持っていない」
原罪というリアリズム
第二部に入り、グアルディーニは権力の問題を神学的に掘り下げる。ここで私は、彼の議論が単なる文化批判を超えていることに気づく。彼は聖書の創世記を引きながら、人間の権力がそもそも「神からの委託物」であると主張する。
創世記によれば、人間は神の似姿として創造され、世界を支配するよう委ねられた。しかし、この支配は絶対的なものではなく、神に対する責任を伴うものだった。原罪とは、この責任関係を破壊し、人間が神のように自立しようとしたことだ。
重要なのは、グアルディーニが原罪を「堕落」としてのみ捉えていない点だ。むしろ、原罪以後の人間の権力は、常に濫用の傾向を内包するようになったという。これは悲観論ではない。現実認識だ。
ここで私は、現代の進歩主義が持つある種の楽観主義と対比してみる。人間は教育によって改善され、制度によって正され、テクノロジーによって解放される——こうした信念は、原罪を無視している。もし人間の内に権力濫用の傾向が構造的に組み込まれているなら、いかなる制度もテクノロジーも、それ自体では問題を解決できない。むしろ、より高度な権力手段を与えることで、問題を悪化させる可能性すらある。
グアルディーニは、この原罪の状況に対する神の応答を、キリストの「謙遜」に見る。キリストは神としての権能を持ちながら、それを放棄し、僕の姿をとった。この「ケノーシス」(自己空虚化)こそが、権力の使い方の模範だと彼は言う。権力は、自己主張によってではなく、自己放棄によって真に有効になるという逆説。
だが、この議論には大きな難点がある。この「謙遜」の倫理は、個人の内面生活においては説得力を持つかもしれない。しかし、国家間の権力闘争や、巨大企業の市場競争に、どう適用できるのか。グアルディーニはこの点について、十分な解答を与えていないように思える。
来るべき人間像:未知の領域への暫定的地図
第7章と第8章で、グアルディーニは来たるべき時代の人間像を描こうとする。彼はこれを「ユートピア」と呼ぶが、遊びのユートピアではなく、「来たるべきものの予兆」としてのユートピアだと言う。
この新しい人間は、テクノロジーと親和的でありながら、その危険を熟知している。危険と共に生きることを厭わず、むしろそこに人間の偉大さを見出す。彼は「自由主義的」ではない。つまり、あらゆる価値を相対化し、対立を避けることを善しとしない。絶対的な要求を受け入れ、命令することも従うこともできる。
グアルディーニが繰り返し強調するのは、この新しい人間の基盤は「神との正しい関係」にあるということだ。人間はそれ自体で完結する存在ではなく、本質的に神との関係において成り立つ。
ここで私は、この主張が現代の多元的社会でどれだけ受け入れられるかを考える。神を信じない人々、異なる宗教を信じる人々に対して、この「神との関係」を基盤とする倫理は説得力を持つのか。グアルディーニはおそらく、人間は神を信じなくとも、神との関係の中に生きていると言うだろう。否定することも、その関係の一形態だと。
しかし、これは議論として少し危うい。否定を包含する議論は、反論不可能であると同時に、実践的な指針としての力を失う危険がある。
内部対話:結論を急がない
ここまで読んで、私はいくつかの確信と多くの疑問を持った。確信しているのは、グアルディーニが極めて重要な問題を提起しているということだ。テクノロジーの発展と人間の倫理的成熟のギャップ、権力の匿名化と責任の所在の不明確さ、自然の「資源化」と人間存在の「場所」の喪失——これらは1940年代の問題であると同時に、2020年代の私たちの切実な問題でもある。
疑問は残る。第一に、グアルディーニの分析はキリスト教的視点に大きく依存している。この視点を共有しない読者にとって、彼の「解決策」はどれだけ意味を持つのか。第二に、彼が描く「新しい人間」は、具体的にどのようにして形成されるのか。教育か、制度か、それとも歴史の必然か。彼はこれに明確な答えを出していない。第三に、最も根本的な問いとして、彼の「近代終焉」論は、西洋中心主義に過ぎないのではないか。アジアやアフリカの視点から見れば、近代はまだ始まったばかりかもしれない。
しかし、こうした疑問自体が、この本の価値を示しているとも言える。グアルディーニは答えを与えるのではなく、問いを深める。彼の著作は、私たち自身が自分の場所を問い直すための「方向定位の試み」なのだ。
最終的な位置づけ
この本は、予言の書ではない。また、単なる時代批判でもない。むしろ、歴史という大河の中で、私たちが今どこにいるのかを理解するための「診断書」だ。グアルディーニは、近代という epoch が終わりつつあることを宣言するが、その後に何が来るかは明確に描かない。彼はただ、そこに内在する危険と可能性を示す。
最も印象的なのは、彼が「悲観主義でも楽観主義でもない」立場を取ることだ。彼は言う。「問題はコップが半分空か半分満たされているかではない。それが空だと知ったときに、あなたは何をするかである」
この問いは、今も私たちに突きつけられている。テクノロジーの権力は増大し続け、気候変動は深刻化し、AIは人間の仕事を奪い、国家間の緊張は高まっている。この状況で、私たちは何をするのか。グアルディーニは、個人の内省と良心に基づく日々の決断から始まると言う。それは小さな答えのように見える。しかし、すべての大きな変化は、そうした小さな決断の積み重ねから始まるのかもしれない。
私はこの本を読んで、自分の「場所」を考えずにはいられなかった。物理的にも、社会的にも、存在論的にも。グアルディーニが言うように、私たちはもはや、世界の中で「どこに立っているか」を自明のこととして知ることができない。それでも、立たねばならない。そのために必要なのは、絶え間ない問い直しと、責任の引き受けなのだろう。