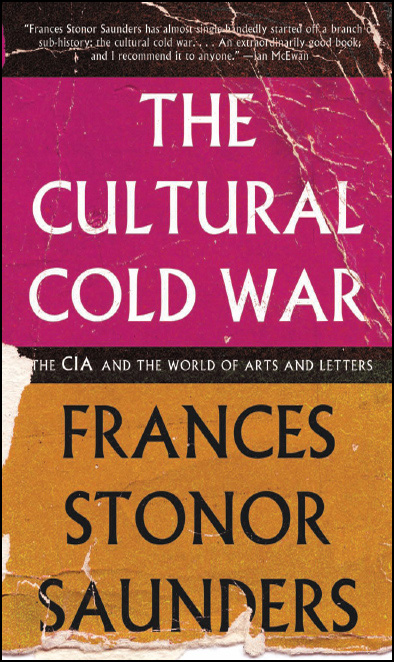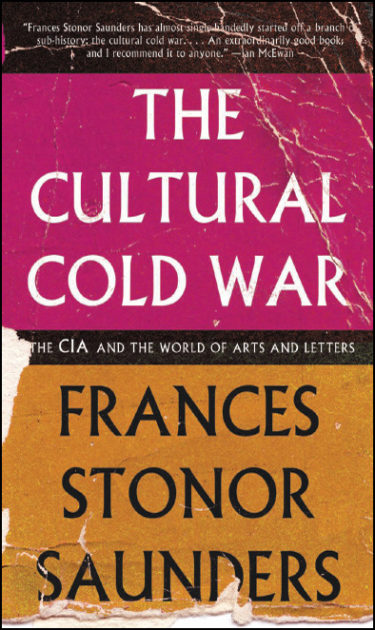
要約指示に基づく『THE CULTURAL COLD WAR』の要約
英語タイトル:『THE CULTURAL COLD WAR:THE CIA AND THE WORLD OF ARTS AND LETTERS』Frances Stonor Saunders 2000
日本語タイトル:『文化的冷戦:CIAと芸術・文学の世界』フランシス・ストナー・ソーンダーズ 2000
目次
- 第一部 文化的冷戦の始まり
- 第1章 エクスキジット・コープ / Exquisite Corpse
- 第2章 運命の選民 / Destiny’s Elect
- 第3章 ウォルドーフのマルクス主義者たち / Marxists at the Waldorf
- 第4章 民主主義のコミンフォルム / Democracy’s Deminform
- 第二部 CIAの文化的介入の構築
- 第5章 「十字軍」という思想 / Crusading’s the Idea
- 第6章 「オペレーション・コングレス」 / “Operation Congress”
- 第7章 キャンディ / Candy
- 第8章 このアメリカ的祝祭 / Cette Fête Américaine
- 第9章 コンソーシアム / The Consortium
- 第10章 真実キャンペーン / The Truth Campaign
- 第三部 前線の活動とイデオロギー
- 第11章 新しい合意 / The New Consensus
- 第12章 雑誌「X」 / Magazine “X”
- 第13章 神聖なる意志 / The Holy Willies
- 第14章 音楽と真実、だがあまりに / Music and Truth, ma non troppo
- 第15章 ランサムの息子たち / Ransom’s Boys
- 第16章 ヤンキー・ドゥードゥル / Yanqui Doodles
- 第四部 ネットワークの拡大と軋み
- 第17章 守護の復讐の女神たち / The Guardian Furies
- 第18章 エビが口笛を吹くとき / When Shrimps Learn to Whistle
- 第19章 アキレスの踵 / Achilles’ Heel
- 第20章 文化的NATO / Cultural NATO
- 第21章 アルゼンチンのカエサル / Caesar of Argentina
- 第22章 ペン・フレンズ / Pen Friends
- 第五部 暴露と終焉
- 第23章 文学的なピッグス湾事件 / Literary Bay of Pigs
- 第24章 胸壁からの眺め / View from the Ramparts
- 第25章 沈みゆく感覚 / That Sinking Feeling
- 第26章 悪い取引 / A Bad Bargain
- エピローグ:/ Epilogue
本書の概要
短い解説:
本書は、冷戦期にアメリカ中央情報局(CIA)が主導した大規模な文化的プロパガンダ作戦、「文化的冷戦」の全貌を、一次資料と関係者へのインタビューに基づいて初めて体系的に明らかにした歴史ノンフィクションである。主に対象となるのは、CIAがヨーロッパを中心とした知識人、芸術家、作家を動員し、反共産主義の「自由」陣営を構築しようとした過程であり、芸術と文学がイデオロギー闘争の前線となった複雑な実態を読者に提示する。
著者について:
著者フランシス・ストナー・ソーンダーズはイギリスの歴史家・ジャーナリストである。膨大なアーカイブ資料(アイゼンハワー図書館、ハリー・ランサム人文研究センターなど)の発掘と、当時のCIA関係者、関与した知識人・芸術家へのインタビューを丹念に行い、表裏のないアメリカの「自由」の言説の背後で展開された、秘密裏で時には非民主的な文化操作の実態を実証的に描き出した。著者はあくまで歴史的事実の記述者としての立場を維持しつつ、知的自由と民主主義の本質について深く問いかける。
テーマ解説
- 主要テーマ:イデオロギー闘争としての文化の武器化。冷戦が軍事・政治対立に留まらず、芸術、文学、音楽、学術といった「文化」の領域で、両陣営が「 hearts and minds (人心)」を争う戦場となった過程。
- 新規性:CIAによる文化工作の「コンソーシアム」モデルの解明。政府機関が直接関与せず、民間の財団(フォード、ロックフェラーなど)や個人を迂回させることで、工作活動の隠蔽と正当化を図った巧妙なシステム。
- 興味深い知見:「自由」の言説の二重性。ソ連の全体主義に対抗する「自由世界」の理念を掲げながら、その宣伝のために非民主的な秘密工作、言論操作、そして時に右翼独裁政権との協力をも厭わなかった矛盾。
キーワード解説
- 文化的冷戦(Cultural Cold War):冷戦期、アメリカとソ連が自陣営の文化的優位性と政治的正当性を世界に宣伝するために行った、芸術・思想・学術を巻き込んだ大規模なプロパガンダ・イデオロギー闘争。
- 文化自由会議(Congress for Cultural Freedom, CCF):本書の中心的な題材。西側の知識人・芸術家を結集し、反共産主義の文化的言説を発信することを目的として1950年に設立された組織。その資金と運営の実権がCIAに握られていたことが後に暴露される。
- ニューヨーク知識人(New York Intellectuals):『パルチザン・レビュー』などを舞台に活躍したユダヤ系を中心とするアメリカの知識人グループ(アーヴィング・クリストル、ダニエル・ベル、ハンナ・アー�レントなど)。多くが初期には左翼的だったが、冷戦の進展と共に反共産主義に転じ、CCFを支える思想的支柱となった。
3分要約
本書『文化的冷戦』は、第二次世界大戦後の冷戦構造が決定的になる中で、アメリカ合衆国、特にその中央情報局(CIA)が、ソ連の文化的プロパガンダに対抗するため、あるいは先制するために展開した、極秘の大規模な文化工作活動の全史を描く。その活動の核心には「文化自由会議(CCF)」という、一見すると西側の知識人や芸術家による自発的な反共産主義団体があった。CCFは『エンカウンター』をはじめとする高級文化誌の出版、国際的な学会や芸術祭の開催、作家や音楽家への援助を通じて、「自由世界」の文化的優位性と活力を全世界に喧伝した。しかし、その華やかな活動の背後には、CIAからの膨大かつ秘密裏の資金供給と、その戦略的指導があった。
著者は、アイゼンハワー大統領図書館をはじめとするアメリカの公文書館で一次資料を発掘し、また当時のCIA工作員や関与した知識人へのインタビューを重ねることで、この隠されたシステムを明らかにする。CIAは「ラッセル・トラスト基金」などの擬装機関や、フォード財団やロックフェラー財団といった巨大民間財団を資金の迂回路として利用し、その痕跡を消した。この工作の目的は、ヨーロッパを中心とする知識人社会における「中立主義」や親共産主義的傾向を封じ込め、アメリカ主導の反共産主義陣営に組み込むことにあった。
作戦は当初、大きな成功を収めたように見えた。サルトルやカミュのようなフランスの知識人、アイザイア・バーリンやステファン・スペンダーといった英米の知識人、さらにはストラヴィンスキーやバーンスタインなどの芸術家が、CCFのネットワークに引き込まれ、あるいはその活動に協力した。彼らの多くは、自分たちの活動がCIAの資金で賄われているとは知らなかった。CIA側も、「文化」という目に見えにくい領域での影響力行使は、軍事力に頼らない「冷戦」の本質的な部分であり、ソ連の脅威に对抗するための「必要悪」であると信じていた。
しかし、この構図には根本的な矛盾と「ダブルシンク(二重思考)」が潜んでいた。ソ連の全体主義に対抗する「自由」の理念を掲げながら、その理念を広める手段として、秘密工作、言論操作、情報の隠蔽といった非民主的・非自由的な方法を採用したのである。さらに、この「自由のための戦い」は、文化的戦線だけでなく、グアテマラやイランのクーデター、そして後にベトナム戦争へとつながる政治的・軍事的介入とも無関係ではなかった。CCFのネットワークは、時にそうしたアメリカの外交政策を文化的に正当化する役割も担った。
1960年代後半、ベトナム戦争の泥沼化と国内の反戦運動の高まりの中で、「文化自由会議」のCIA関与は『ニューヨーク・タイムズ』などの調査報道によって暴露される。このスキャンダルは、関わった知識人社会に深い衝撃と分裂をもたらし、CCFはその信用を失って解体へと向かった。著者は、この結末を単なる工作の失敗としてではなく、民主主義社会が国家の秘密工作と知的誠実性の間で直面する根源的なジレンマの表れとして描く。
最終的に本書が提示する問いは、文化と政治、芸術とプロパガンダ、知的自由と国家的利益の境界線はどこにあるのか、という重いものである。「自由」を守るために「自由」を損なう手段を取ることの倫理的コストは何か。冷戦という特殊な状況下で生まれた「文化的冷戦」の装置は、現代の情報戦やナラティブの争いにおいても、様々な形で継続しているのか。著者は読者に、過去の歴史的事実を通して、これらの現在的な課題を考えることを促している。
各章の要約
第一部 文化的冷戦の始まり
第1章 エクスキジット・コープ
冷戦の文化的戦線は、第二次世界大戦直後、ヨーロッパの荒廃と米ソの対立の深まりの中で始まった。アメリカの政策立案者たちは、軍事・経済援助(マーシャル・プラン)だけでなく、ヨーロッパの「人心」をソ連の影響から守る必要を認識した。戦前・戦中のプロパガンダの経験(例えばOSSの心理戦部門)を持ち、芸術や思想の力を信じる一群のエリートたちが、文化を新しい戦場とする構想を練り始める。それは、ヨーロッパの知識人や芸術家を、アメリカが主導する「自由世界」の陣営に取り込むための長期的な作戦であった。
第2章 運命の選民
CIA内で文化的活動を推進した中心人物たちが紹介される。その筆頭がコード・マイヤーである。理想主義的な元海兵隊員で世界連邦運動にかかわっていたが、冷戦の現実主義者へと転向し、CIAの国際組織部門の責任者となる。彼のような人物が、ソ連の情報工作に対抗するためには、秘密裡の文化的介入が必要だという信念を抱き、その実行部隊を組織した。彼らは自分たちを、自由民主主義を守るための「運命の選民」と自負していた。
第3章 ウォルドーフのマルクス主義者たち
1949年、ニューヨークのウォルドーフ・アストリアホテルで開催された「文化と科学の世界平和会議」が転換点となる。この会議はソ連主導のプロパガンダ色が強く、ショスタコーヴィチなどが参加した。アメリカの反共産主義知識人(シドニー・フックなど)は、これに対抗する示威行動を組織し、会議を混乱させた。この事件は、文化的対立が公然化した瞬間であり、アメリカ側に「組織的で継続的な文化的反撃」の必要性を強く認識させた。文化の戦いが、すでに始まっていることを示す契機だった。
第4章 民主主義のコミンフォルム
ウォルドーフ会議への対抗から、より恒久的な反共産主義知識人組織の構想が具体化する。それは、ソ連のコミンフォルム(共産主義情報局)に対抗する「民主主義のコミンフォルム」となるべきものだった。アメリカ政府(国務省)は当初、直接関与に慎重だったが、CIAは秘密工作としてなら可能だと考えた。こうして、政府の公式プロパガンダ機関(USIAなど)とは別に、一見「独立した」民間組織を通じて文化的影響力を行使するという、CIA文化工作の基本モデルが形成され始めた。
第二部 CIAの文化的介入の構築
第5章 「十字軍」という思想
1950年、西ベルリンで「文化自由会議(CCF)」が開催される。冷戦の最前線であるこの地での開催は、強力な政治的シンボルとなった。会議にはイグナツィオ・シローネ、アーサー・ケストラー、レイモン・アロンなど、ヨーロッパの著名な反共産主義知識人が結集し、ソ連の全体主義と文化的統制を糾弾し、「知的自由」を宣言した。この会議は大成功を収め、恒久的な組織としてのCCFの発足へとつながる。その背後では、CIAの資金とロジスティック支援が決定的な役割を果たしていた。
第6章 「オペレーション・コングレス」
CCF創設の舞台裏が明かされる。会議の準備、著名人への参加依頼、資金調達、プロパガンダ効果の最大化など、全ての運営はCIA工作員(特にマイケル・ジョセルソンが後に中心となる)によって緻密に計画・実行された「オペレーション」だった。参加者の多くはCIAの関与を知らされていなかった。この作戦は、ヨーロッパ知識人を反共産主義の大義に動員する最初の大規模な実験であり、その手法はその後、CCFの標準的な活動様式となる。
第7章 キャンディ
CIAがCCFなどの文化工作に資金を供給するために用いた、巧妙な資金洗浄システムが解説される。中心となったのは「ラッセル・トラスト基金」などの「受託基金」であった。CIAはここに資金を投入し、そこからさらにフォード財団、ロックフェラー財団、カーネギー財団などの巨大民間財団を経由して、最終的にCCFなど対象団体へと資金が流れる経路を作った。この「三重、四重の迂回路」により、資金の出所は完全に隠蔽され、CCFは「民間からの寄付」で運営される独立団体としての体裁を保つことができた。
第8章 このアメリカ的祝祭
CCFのプロパガンダ手法の具体例として、1952年にパリで開催された「20世紀の芸術の傑作」展が取り上げられる。この展覧会は、抽象表現主義を中心としたアメリカ現代美術を大々的に紹介し、ニューヨークがパリに代わる世界の芸術の中心であること、そしてそこに表現される自由と創造性が、アメリカの民主主義の勝利の証であることを宣伝することを目的としていた。文化(特に前衛芸術)が、その政治的メッセージを明言することなく、イデオロギーの優位を示す「武器」として利用された典型例である。
第9章 コンソーシアム
CIAの文化工作は、CCFだけにとどまらなかった。著者はそれを「コンソーシアム」と名付ける。大学(ハーバード大学の国際セミナーなど)、出版社、ニュースサービス、労働組合、学生組織など、多様な民間組織が、知らぬ間にCIAの資金と影響力のネットワークに組み込まれていった。これは、アメリカ社会のあらゆる層から「信頼できる」人物や組織を動員し、幅広い文化的戦線を形成することを意図した、総力戦的なアプローチであった。
第10章 真実キャンペーン
CIAの文化工作は、積極的なプロパガンダだけでなく、ソ連や親ソ連勢力による情報・宣伝(「ディスインフォメーション」)への対抗、すなわち「真実」を伝えるキャンペーンも重要な任務だった。その一環として、ソ連の強制収容所(グラグ)の実態を暴露する工作が行われる。また、東欧からの亡命知識人を支援し、彼らを通じてソ連圏の抑圧の実態を西側に伝えさせることも、この「真実キャンペーン」の重要な要素であった。
第三部 前線の活動とイデオロギー
第11章 新しい合意
CCFの思想的支柱となったのが、主にアメリカの「ニューヨーク知識人」たちであった。彼らは多くの場合、1930年代にはトロツキストなど急進的左翼に傾倒していたが、スターリン主義の恐怖と冷戦の現実の中で「幻滅した急進派」となり、強硬な反共産主義者へと転向した。彼らが提唱した「新しい合意」とは、穏健な社会民主主義と修正資本主義を受け入れ、革命的イデオロギー(特にマルクス主義)を拒絶するという立場であり、ダニエル・ベルの『イデオロギーの終焉』に代表される。CCFはこの「非イデオロギー的」立場を、ソ連の「イデオロギー的」全体主義に対置する世界的な運動にしようとした。
第12章 雑誌「X」
CCFの最も重要な活動の一つが、各国語で発行される高級文化誌のネットワークの構築だった。その中核となったのが、ロンドンで発行された英文学誌『エンカウンター』である。編集者にはステファン・スペンダーとアーヴィング・クリストルが就き、T.S.エリオット、ジョージ・オーウェル、オーデンなど一流作家の作品を掲載して高い評価を得た。しかしその編集方針はCIAの意向を反映し、親ソ的または中立主義的な見解を排除し、反共産主義の文化的言説を促進することに傾いていた。雑誌は文化的威信と政治的メッセージを融合させた、極めて効果的なプロパガンダ媒体となった。
第13章 神聖なる意志
CCFの活動には、強固な信念と時として排他的なまでの「正義」感に駆られた人物たちが深く関わっていた。その一人がメルビン・ラスキー(『エンカウンター』の事実上の発行人)であった。彼のような人物は、自分たちの活動が自由のための「聖戦」であると信じ、その目的のためならば手段(秘密工作、資金の隠蔽)を選ばない「結果倫理」を受け入れていた。この章では、文化的冷戦の実務を担った者たちの内面的な動機と倫理的ジレンマが描かれる。
第14章 音楽と真理、だがあまりに
文化工作の対象は文学や思想だけではなかった。音楽も重要な戦場と見なされた。CCFは、ソ連が政治的プロパガンダに利用していた「社会主義リアリズム」音楽に対抗して、「形式主義的」とソ連で非難されていた現代音楽(シェーンベルク、ストラヴィンスキーなど)を支援し、自由な創造のシンボルとして宣伝した。しかし、音楽の「純粋性」と政治的利用の間には緊張関係が生じた。また、CIAが黒人ジャズ音楽家(ルイ・アームストロング、ディジー・ガレスピーなど)を「文化大使」として東欧や中東に派遣し、アメリカの文化的開放性と人種的調和(実際には矛盾していたが)をアピールする工作も行われた。
第15章 ランサムの息子たち
CIAは、海外での工作だけでなく、国内の知的風土の形成にも影響力を及ぼそうとした。その重要な回路の一つが、名門大学(特にイェール、ハーバード、プリンストン)の教授陣や、『パルチザン・レビュー』『ケニヨン・レビュー』などの文学誌のネットワークであった。クレオ・ランサム編集長の『ケニヨン・レビュー』は、ニュー・クリティシズムの牙城として文学界に大きな影響力を持ち、その周囲には反共産主義的な若い知識人(「ランサムの息子たち」)が集まった。彼らは後にCCFや政府の政策に深く関与していく。
第16章 ヤンキー・ドゥードゥル
CCFの活動はヨーロッパが中心だったが、そのネットワークはラテンアメリカにも拡大された。この地域では、アメリカの経済的・政治的支配への反感が強く、知識人階級に親共産主義や反米的な民族主義が広がることをアメリカ政府は危惧した。CCFは、ラテンアメリカの知識人を支援し、親米的な民主主義の言説を広めることを目指した。しかし、そこには「ヤンキー・ドゥードゥル」(アメリカ的なもの)を押し付けるという文化的帝国主義の側面と、時に現地の反共軍事政権と協力するという矛盾がつきまとった。
第四部 ネットワークの拡大と軋み
第17章 守護の復讐の女神たち
1950年代のマッカーシズムの嵐は、国内の知識人社会を分断し、CCFの活動にも影響を与えた。CIAは国内の赤狩りからは比較的免れていたが、マッカーシズムの過剰な反共主義は、ヨーロッパの知識人にアメリカの「自由」の質への疑念を抱かせ、CCFの信頼性を損なう危険があった。また、マッカーシズムの犠牲となった人物をCCFが支援できるかどうかという難しい倫理的問題も生じた。文化的冷戦の前線と国内の政治力学は無関係ではいられなかった。
第18章 エビが口笛を吹くとき
1956年、フルシチョフによるスターリン批判とハンガリー動乱の鎮圧は、国際的な左派知識人社会に大きな衝撃を与え、多くの共産党員や同調者が離反した。CCFはこれをチャンスと捉え、これらの「幻滅した元共産主義者」を積極的に取り込み、その証言を反共プロパガンダに利用しようとした。しかし同時に、この事件は単純な反共主義の構図を複雑にし、社会主義の内部改革の可能性や、西側の対応の是非についての議論をCCF内部にも呼び起こした。
第19章 アキレスの踵
CCFの成功の陰で、その根本的な弱点、つまり「秘密」に依存する構造そのものが「アキレスの踵」であった。関与者のほとんどがCIAの資金源を知らない「善意の騙され役」であり、一部の上層部だけが真実を知っているという構造は、組織内の不信と、暴露された場合の破滅的な信用失墜のリスクを常にはらんでいた。また、資金の無尽蔵な供給は、組織の肥大化と官僚化、そして時として無駄遣いや不祥事を招く要因ともなった。
第20章 文化的NATO
CCFはヨーロッパ統合の理念も推進した。それは経済・軍事面でのNATO(北大西洋条約機構)に対応する「文化的NATO」の構築を目指すものであり、大西洋を挟んだヨーロッパとアメリカの知的連帯を強化することを目的としていた。しかし、これにはヨーロッパ側から、アメリカの文化的・知的支配への反発という問題が常につきまとった。CCFは「西洋」の価値の擁護者を自称したが、その実態はしばしば「アメリカ化」の推進機関と見なされる危険性があった。
第21章 アルゼンチンのカエサル
ラテンアメリカにおけるCCF活動の困難な実態を、アルゼンチンを例に詳述する。ペロン政権後のアルゼンチンでは、知識人社会が分裂し、CCFは反共産主義で親米的な自由主義知識人を支援しようとした。しかし、アルゼンチンの政治的混乱とアメリカの国益(経済的利害など)が絡み合う中で、CCFの文化的使命は複雑に歪められていった。文化的活動が、現地の政治闘争やアメリカの帝国主義的介入の道具として利用される可能性が常に存在した。
第22章 ペン・フレンズ
CCFはアジアやアフリカの新興独立国にも活動を広げようとした。ここでの課題は、欧米中心の「自由」の概念を、異なる文化的・政治的文脈にどう適用するかであった。CCFは現地の民族主義的知識人と接触し、「共産主義の新たな植民地主義」に対抗する「真の独立」の擁護者としての立場を打ち出そうとした。しかし、その背景にある西側への従属や、ベトナム戦争のような軍事介入を正当化する議論は、多くのアジア・アフリカの知識人には受け入れがたいものであった。
第五部 暴露と終焉
第23章 文学的なピッグス湾事件
1960年代に入り、CCFとCIAの関係に疑念を抱く報道が散発的に現れ始める。1966年、『ニューヨーク・タイムズ』のトム・ブラデンが、CIAが学生団体や文化団体に資金提供している事実を暴露する記事を書く。これが最初の大きな亀裂であった。CCFの内部では、秘密保持を続けるべきか、それとも「オープン」になるべきかという激しい議論が巻き起こる。この暴露工作は、文化的冷戦にとって「文学的なピッグス湾事件」(つまり、悲惨な失敗)の始まりであった。
第24章 胸壁からの眺め
1967年、状況は決定的に悪化する。『ランパーツ・マガジン』や『ニューヨーク・タイムズ』が相次いで、CIAが国内の学生団体、労働組合、そして文化団体(CCFがその筆頭)に秘密裏に資金を流している大規模な工作網の詳細をスクープした。特に『エンカウンター』誌がCIA資金で運営されていたという暴露は、文学界・知識人社会に激震を走らせた。編集者の一人、ステファン・スペンダーは自分が騙されていたことを知り、激怒して辞任した。
第25章 沈みゆく感覚
暴露のスキャンダルは、CCFとそのネットワークに致命的な打撃を与えた。多くの知識人や芸術家が、自分がCIAの工作に(無意識にせよ)加担していたことに恥辱と怒りを感じ、関係を絶った。CCFの信頼性は地に落ち、その存在意義は根本から問い直されることになった。CIAもまた、この大規模な文化工作の継続が不可能であると判断せざるを得なかった。組織は縮小・再編を余儀なくされ、かつての影響力は失われていった。
第26章 悪い取引
本書の結論として、文化的冷戦という「取引」の総括が行われる。短期的には、CIAの工作は、ヨーロッパ知識人社会における親ソ・中立主義的傾向を後退させる一定の効果を上げたかもしれない。しかし、長期的な代償は甚大であった。それは、アメリカの知的・文化的言説そのものの信用を傷つけ、知識人と国家権力の間に深い不信の溝を生んだ。さらに、「自由」を守るためにとられた秘密工作と欺瞞の手段は、その「自由」の理念そのものを掘り崩す自己矛盾をはらんでいた。著者は、この歴史が、民主主義社会が国家安全保障と知的誠実さ、文化的影響力とプロパガンダの間で直面する永続的な難問を浮き彫りにしていると述べる。
エピローグ
暴露から数十年後、かつての文化的冷戦の主役たち(コード・マイヤー、アーヴィング・クリストルなど)へのインタビューを通じて、彼らの現在の視点を描く。多くは自らの行為を正当化し、冷戦という特殊な状況下での「必要悪」だったと主張する。しかし、彼らが擁護した「新保守主義」的考え方は、冷戦終結後も、文化戦争や対外政策において影響力を保ち続けている。著者は最後に、文化的冷戦の遺産が、現代の情報化社会における「ナラティブの戦い」や「ソフト・パワー」競争にどのように受け継がれ、変容しているのかを読者に問いかけ、歴史からの教訓が現在にも重要であることを示唆して締めくくられる。
パスワード記載ページ(note.com)はこちら
注:noteのメンバーのみ閲覧できます。
メンバー特別記事