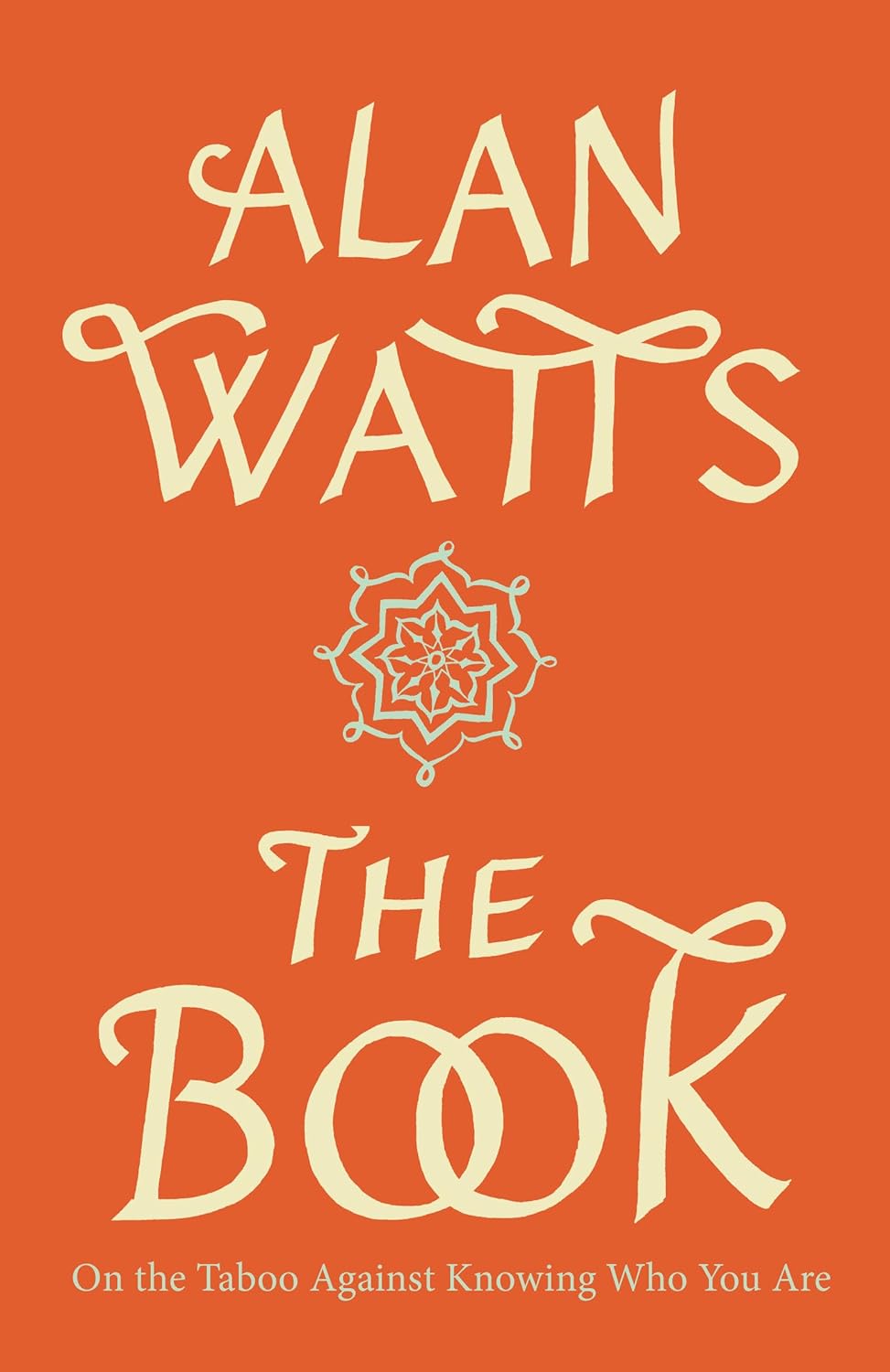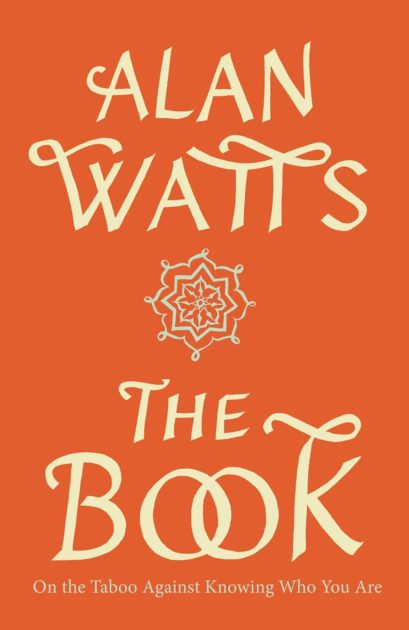
英語タイトル:『THE BOOK:On the Taboo Against Knowing Who You Are』Alan Watts 1966
日本語タイトル:『THE BOOK:あなたが誰であるかを知ることに対するタブーについて』アラン・ワッツ 1969年
目次
- はじめに
- 第1章 内部情報 / Inside Information
- 第2章 白黒のゲーム / The Game of Black-and-White
- 第3章 いかにして真の偽物となるか / How To Be a Genuine Fake
- 第4章 世界はあなたの身体である / The World Is Your Body
- 第5章 だから何? / So What?
- 第6章 それ / IT
- 参考文献
本書の概要
短い解説:
本書は、西洋的科学と東洋の哲学的直観(特にヴェーダーンタ哲学)を融合させ、現代人が抱く「自分は皮膚に包まれた孤立した自我である」という根本的な幻想(自我の幻想)を解体し、個人と宇宙が不可分の一体であるという認識(「汝はそれである」)へと読者を導くことを目的とする。技術文明の危機や社会的混乱の根底にあるこの「分離のタブー」を打破し、新たな存在の感覚を提示する。
著者について:
アラン・ワッツ(1915-1974)は、神学の修士号と神学博士号を取得し、特に禅仏教、そしてインド・中国哲学一般の解釈者として知られる思想家・作家である。西洋の合理的精神と東洋の神秘思想を橋渡しする明晰な語り口で、宗教の哲学と心理学に関する多くの著作を残した。『THE BOOK』は、近代的・西洋的な文体でヴェーダーンタの洞察を表現し、現代人の疎外感を克服するための「体験」を伝えようとする試みである。
テーマ解説
- 主要テーマ:自我の幻想とその克服:私たちが「自分」と感じる分離したエゴは、社会的に条件付けられた幻覚であり、この認識の転換が全書の核心である。
- 新規性:東洋思想の現代的再解釈:ヴェーダーンタ哲学の核心「汝はそれである(Tat Tvam Asi)」を、神話的比喩(かくれんぼ遊び)や現代科学(量子論、生態学)の知見を用いて、宗教的ドグマ抜きで提示する。
- 興味深い知見:問題としての技術文明:環境破壊や社会的混乱は、自然を征服すべき「分離した自我」という自己認識に起因しており、この認識が変わらなければ技術的進歩は問題を悪化させるだけだと論じる。
キーワード解説(1~3つ)
- 自我の幻想 / The Ego-Illusion:自分が皮膚の内側に閉じ込められた独立した存在であるという、強力だが誤った感覚。社会と言語によって植え付けられた「条件付け」。
- 白黒のゲーム / The Game of Black-and-White:光/闇、生/死など、あらゆる対立項が実際には不可分の一体(波の山と谷)であるという認識。対立項の一方を征服しようとする(白が勝つゲーム)と問題が生じる。
- それ / IT:個々の自我や現象を超えた、全存在の唯一無二の基盤。人格神ではなく、自らを隠して(仮装して)あらゆる現象として遊ぶ、宇宙全体の「自分自身」。
3分要約
本書は、私たちが「自分は世界から切り離された孤独な存在である」と信じ込まされているという、社会が強要する最大のタブーに挑む。著者アラン・ワッツは、この「自我の幻想」が、環境破壊、社会的対立、人生の無意味感の根源にあると指摘する。
私たちは、意識のスポットライトが部分に焦点を当て、関係性(スペース)を無視するため、世界をバラバラの「もの」の集まりと見做してしまう。これが「白黒のゲーム」を見失い、「白が黒に勝たねばならない」という戦い(生対死、秩序対混沌、人類対自然)に駆り立てる原因である。しかし、量子論や生態学が示すように、実在は関係性の網目そのものであり、有機体と環境は分離不能な一つの場を形成している。つまり、「世界はあなたの身体」なのである。
この分離の幻想は、子供時代から「あなたは自由で責任ある個人だ」と教えられながら、同時に社会に適応するよう強制されるという「二重拘束」によって植え付けられる。その結果、私たちは「本物の偽物」として、永遠に満たされない未来を追い求める虚しい人生ゲームを強いられる。
打破の鍵は、このゲームのルールが自己矛盾的であると気づくことにある。「自我を捨てよ」と努力することさえ、自我の巧妙な策略である。むしろ、自我の感覚そのものを、雲や波のような自然な現象として観察し、その虚構性を「体験」することが必要だ。そのとき、個人と宇宙、知るものと知られるもの、行為と環境の区別が溶解する。自分が単なる皮膚の内側の存在ではなく、全宇宙が「それ(IT)」として自分自身を表現している一つのプロセスであるという驚きと至福の感覚が訪れる。
この認識(「汝はそれである」)に至れば、世界は重苦しい義務ではなく、無目的な「遊び」として輝き始める。敵と味方、善と悪の対立も、全体の調和を成す相互依存のダンスとして見えるようになる。これが、技術文明の暴走を止め、真に創造的で慈愛に満ちた社会を築くための、唯一実りある土台なのである。最後に著者は、この壮大な自己隠蔽の戯れ(かくれんぼ)の核心に気づいた者こそが、深いユーモアと共に人生を謳歌できると結論づける。
各章の要約
はじめに
本書は、「あなたが誰であるか」を知ることに対する強大なタブー、すなわち「自分は皮膚に包まれた分離した自我である」という普遍的幻想に取り組む。この幻想は科学的にも東洋哲学の実験的洞察とも相容れず、技術の誤用と環境破壊の基盤となっている。ヴェーダーンタ哲学の洞察を完全に現代的・西洋的な文体で表現し、宇宙からの疎外感を克服する新たな存在感覚を提示することが目的である。
第1章 内部情報 / Inside Information
現代において真のタブーは、自分が世界から切り離された孤独で一時的な訪問者であるという感覚そのものである。この感覚は、私たちが世界に「入ってくる」のではなく、世界(宇宙)が私たちを「人々として波立たせている」という事実と矛盾する。子供に語る「かくれんぼ遊び」の神話を用いて、著者はこの核心的な洞察を説明する。神(「それ」)は、自分自身以外に遊ぶ相手がいないため、自分が自分ではないふりをして、あらゆるもの(あなたや私、岩や星)に「仮装」する。これが宇宙の遊び(リーラ)である。私たちが自分を神の仮装だと気づかないのは、遊びを面白くするためだ。ヴェーダーンタ哲学の核心「汝はそれである」は、この遊びの秘密を暴くものであり、社会が最も強く禁じるタブーなのである。
第2章 白黒のゲーム / The Game of Black-and-White
私たちの知覚と思考は、対立する二項(光/闇、固形/空間、原因/結果)を分離して捉える傾向がある。意識は「オン」(山)に注目し、「オフ」(谷)を無視する。しかし、現実にはこれらは不可分の一つの振動(波)の両極である。私たちが犯す錯誤は、この相互依存的な「白黒のゲーム」を、「白が黒に勝たねばならない」という戦い(秩序対混沌、生対死)と誤解することだ。特に死への恐怖はこの錯誤の典型である。技術による完全な制御(サイバネティクス)を追求する現代文明は、この戦いの究極的な現れである。しかし、ゲームとしての秩序対混沌は、どちらかが完全に勝利すればゲームそのものが終わる。変化の幻想の下では、すべては結局「同じもの」の変容に過ぎない。
第3章 いかにして真の偽物となるか / How To Be a Genuine Fake
自我の幻想がどのように構築されるかを探る。私たちは「私」を、主に頭部にある身体の「管理者」として位置づける。この感覚は、世界を分離した「もの」の集まりと見做す言語的・概念的な網(名目論)によって強化される。社会(家族、教育)は、個人をその環境から不可分であるにもかかわらず、「自由で独立した個人であるように」という二重拘束(ダブルバインド)メッセージを送り続ける。「自発的であれ」と強制される矛盾である。この条件付けにより、私たちは未来への絶え間ない希求に駆られ、現在を生きることができない「本物の偽物」となる。結果、楽しむ術を知らない物質主義、意味のない仕事、偽物の商品に満ちた社会が生まれる。この悪循環から脱するには、自我を行動の主体としてではなく、条件付けられた自動機制として見抜く必要がある。
第4章 世界はあなたの身体である / The World Is Your Body
有機体と環境は、図と地のように分離不能な一つの場を形成している。科学は生態学(生態系)の観点からこの相互依存を明らかにする。行動を理解するには環境を理解せねばならず、それは結局、宇宙全体を理解することに帰着する。「もの」は関係性の結節点に過ぎない。この視点からは、環境を「征服」すべきだという考えは無意味である。知覚の観点からも、世界の色や形、硬さは、神経系との相互作用によって初めて現象する。つまり、世界を知覚する脳もまた世界の一部であり、宇宙は「脳を持つ有機体」という極を必要としてそれ自体を現象させている。量子論も、部分の独立性を否定し、関係性の全体性を支持する。私たちは、自分自身が宇宙の驚くべき自己表現であるという認識を取り戻さなければならない。
第5章 だから何? / So What?
「汝はそれである」という認識の実践的意義が問われる。著者は、この認識なくしては、社会改革や慈善活動でさえ、偽善的で逆効果になりうると警告する。自我の幻想から抜け出すための「努力」や「修行」自体が、自我の策略である可能性がある。重要なのは、自我を捨てようとする意志ではなく、自我のゲームが自己矛盾的であることに気づき、行き詰まる「体験」を通じて、自発的に幻想が溶解する瞬間を迎えることだ。そのとき、自分が世界のプロセスそのものであるという感覚が生まれ、人生は重荷ではなく、無目的な「遊び」として鮮やかさを取り戻す。善と悪、自己と他者の対立も、全体の調和を成す相互依存のダンスとして見えるようになる。この認識に基づく寛容さとユーモア(自分が同時に裁判官であり犯罪者であるという自覚)こそが、真の社会的変革と平和の基礎となる。
第6章 それ / IT
「それ(IT)」とは、すべての対立と現象を超えた、言い表しようのない全存在の基盤である。言語は二項対立に基づくため、ITを直接表現することはできないが、神話や比喩を通じて指し示すことは可能である。伝統的な「父なる神」のイメージはもはや機能しない。むしろ、人間の脳と神経系が宇宙を「人間化」しているという驚愕すべき事実こそが、新しい人間像を示唆する。私たちの真の自己は、この広大な宇宙のプロセスそのものである。死は、このプロセスにおける「オフ」の瞬間に過ぎない。すべてが元通り(何もない状態)に戻るなら、同じことが再び起こりうる。個々の「私」という感覚は、何度でも新たに生まれ、その都度過去を忘れる。したがって、死後の「無」を体験することはない。この壮大な自己隠蔽の戯れ(宇宙が自分自身とかくれんぼをしていること)に気づいたとき、残るのは良い笑いだけである。自分が「それ」であると悟り、すべての存在が同じ「それ」の仮装であることを知れば、人生は深刻な課題ではなく、遊び心に満ちた創造的なダンスとなる。
自我という壮大な詐欺:アラン・ワッツが暴く「分離という幻想」 AI考察
by Claude 4.5
「私」は本当に存在するのか?
アラン・ワッツの『The Book』は、西洋文明が数千年にわたって維持してきた「最大のタブー」に切り込む。それは「あなたが本当は誰であるか、何であるかを知ること」への禁忌だ。この書物が1966年に出版されてから半世紀以上が経過したが、その核心的メッセージは現代においてさらに切実な意味を持つようになっている。
ワッツの主張の核心は驚くほどシンプルでありながら、徹底的に破壊的だ。「皮膚という袋に閉じ込められた独立した自我としての自己感覚は、幻覚である」。この幻覚は西洋科学とも、東洋の実験的哲学・宗教(特にヴェーダンタ哲学)とも一致しない。そしてこの幻覚こそが、人間による自然環境の暴力的支配と、その結果としての破壊を根底で支えている。
これは単なる形而上学的戯言ではない。ワッツは生物学、物理学、生態学の知見を動員しながら、「分離した個人」という概念が社会的な構築物に過ぎないことを示していく。神経科学的には、私たちの「意識的注意」は実際に起きている出来事のごく一部しか捉えていない。スポットライトのような狭い意識が、宇宙の全体的なプロセスから切り離された「自己」という錯覚を生み出す。
言語が作り出す現実の罠
ワッツの分析で特に重要なのは、「言語の構造そのものが分離の幻想を強化する」という洞察だ。ほとんどの言語は、行為(動詞)を実行する主体(名詞)という構造を持つ。「雨が降る」というとき、私たちは「雨」という実体が「降る」という行為を行うと考える。しかし実際には「降ること」そのものが「雨」なのだ。
ワッツはアメリカ先住民のヌートカ語を例に挙げる。この言語では名詞と形容詞がなく、動詞と副詞だけで構成される。教会は「宗教的に家すること」、店は「商業的に家すること」、家は「家庭的に家すること」となる。この言語構造は、世界をより正確に捉えているのではないか。すべての「もの」は実際には「プロセス」であり、静的な実体ではない。
この言語の罠は、科学的思考にも深く浸透している。私たちは世界を「物質」と「形」、「エネルギー」と「物質」というように二元的に捉えるが、これは「陶器モデル」(Ceramic Model)と呼ばれる古代の比喩から来ている。神が粘土から人間を作ったように、世界は何らかの「基本的な物質」から「形作られている」という考え方だ。しかし実際には、形のない物質も、物質のない形も発見されたことがない。「物質」という言葉自体、サンスクリット語の「測る」を意味する語根から来ており、「物質的世界」とは「測定可能な世界」という意味に過ぎない。
ワッツはこの古い世界観を「クラックポット・モデル」(Crackpot Model、狂った壺モデル)と皮肉る。この世界観は西洋文明を支配してきた二つの神話の基盤となった。最初の神話は「宇宙は外部の知性によって作られた工芸品である」という考え方だ。つまり「父なる神」の神話である。第二の神話は、神を取り除いても機械的宇宙観を残した「完全自動モデル」(Fully Automatic Model)だ。この神話では、宇宙は盲目的な原子の偶然の組み合わせであり、人間の意識は偶然の副産物に過ぎない。
二重拘束という社会的プログラミング
しかし、なぜ私たちはこれほど強固に「分離した自我」という幻想を信じているのか?ワッツは精神医学者グレゴリー・ベイトソンの「ダブルバインド」(二重拘束)理論を援用して説明する。
子供は幼少期から、矛盾した命令を受け続ける。「自由であれ」「責任を持て」「愛さなければならない」。しかしこれらはすべて、自発的であることを強制する命令であり、論理的に不可能だ。愛は自然に湧き起こるものであり、命令されて生じるものではない。「リラックスしろ」「自意識過剰になるな」と言われるほど、私たちはリラックスできず、自意識過剰になる。
社会は子供に「あなたは独立した、自由な行為者である」と教え込む。しかし同時に、社会への所属なしには存在できないことも事実だ。ワッツはこれを「抵抗不可能な圧力によって、そのような圧力は存在しないと信じるよう強制される」状況と表現する。社会の不可欠な一部であるからこそ、社会はあなたに「あなたは分離している」と確信させることができる。
この二重拘束は世代を超えて伝達される。親たちもまた同じ幻想の犠牲者であり、自分たちが何をしているのか理解していない。「あなたは私たちを愛さなければならない」と言いながら、「なぜなら私たちが言うからではなく、あなたが望むからそうしなければならない」と付け加える。子供は矛盾を指摘できない。「口答えするな」「年長者を敬え」と言われるだけだ。
生態学的視点からの自己理解
ワッツの議論は、1960年代に黎明期にあった「生態学的思考」を先取りしている。生物学者は、有機体の行動を記述しようとすると、必然的にその環境の行動も記述しなければならないことに気づいた。アリの行動を説明するには、土壌の密度、湿度、温度、食料源、他の種との共生関係や捕食関係など、無数の環境要因を含めなければならない。
逆に、環境の別の側面(例えば、台所に油汚れのある主婦)を研究しようとすると、そのアリとその仲間たちを要因として含めなければならない。どこに注目しても、独立した「原因的行為者」は見つからず、ただ外部の圧力に反応する「空洞」があるだけだ。
しかし、この観察は重要な結論につながる。「研究し記述している『もの』や『実体』が変化した」のだ。最初は個々のアリだったものが、すぐにアリが見出される活動の全体的なフィールドになる。同様に、人体の特定の器官を記述しようとすると、他の器官との関係を考慮しなければ全く理解できない。
すべての生物を研究する科学的学問分野は、それ独自の視点から「生態学」を発展させなければならない。文字通り「家庭の論理」である。残念ながら、この科学は学問的政治の障害に直面している。部門の境界を嫉妬深く守る者たちにとって、あまりにも学際的すぎるのだ。しかし生態学の軽視は、現代技術の最も深刻な弱点であり、私たちが「生きている種の全コミュニティの参加メンバーである」ことへの不本意と表裏一体だ。
ワッツは、有機体や有機体・環境フィールドのある特徴が他の特徴を「支配」したり「統治」したりすると語ることがいかに馬鹿げているかを指摘する。口、手、足が互いに「私たちはこんなに働いているのに、あの怠け者の胃は何もしていない」と不満を言う寓話を引用する。彼らはストライキを起こすが、すぐに全員が弱くなり、胃が「彼らの胃」であり、生き続けるためには働き続けなければならないことに気づく。
生理学の教科書でさえ、脳や神経系が心臓や消化管を「支配している」と語り、悪い政治を科学に持ち込んでいる。まるで心臓が脳に属しているかのように。しかし、脳が胃を通じて「自分自身を養う」と言うことも、胃が脳を「進化させて」より多くの食料を得ると言うことも、同じくらい真実であり、同じくらい偽りだ。
波と粒子:実在の本質的曖昧さ
ワッツの分析は量子力学の知見と共鳴する。物理学者デヴィッド・ボームからの引用は特に印象的だ。「世界は正確には別個の部分に分析することはできない。代わりに、不可分な単位として扱わなければならず、別個の部分は古典的(ニュートン的)限界においてのみ有効な近似として現れる」。
量子レベルの精度では、物体は「それ自体に属する本質的な性質」(波か粒子かなど)を持たない。むしろ、相互作用するシステムとすべての性質を相互的かつ不可分に共有する。電子のような特定の物体は、異なる時期に、異なる潜在性を引き出す異なるシステムと相互作用するため、現れることができるさまざまな形態(波形や粒子形など)の間で継続的な変容を遂げる。
ボームは、この流動性と環境への形態の依存は、素粒子のレベルでは発見されていなかったが、複雑なシステムを扱う生物学などの分野では珍しくないと指摘する。適切な環境条件下で、細菌は構造が完全に異なる胞子段階に発達でき、その逆も可能だ。
さらに、物理学者アーサー・エディントンの有名な言葉を引用する。「私たちは、電子の帯を巡らせて飛び回り、衝突し、跳ね返る原子を見る。帯から引き裂かれた自由電子は百倍速く飛び去り、髪の毛一本の幅で原子の周りを急カーブする…光景は非常に魅惑的で、電子とは何かを教えてほしかった時期があったことを忘れてしまったかもしれない。その質問には決して答えられなかった…未知の何かが、私たちが何だかわからないことをしている—それが私たちの理論が意味することだ」。
エディントンは続ける。「それは特に啓発的な理論には聞こえない。私はどこか他の場所で似たようなものを読んだことがある。『ぬらぬらしたトーブたちが、ワーベで回って突いていた』。同じ活動の示唆がある。活動の性質と、何が活動しているのかについて同じ不確定性がある」。
この量子力学的な視点は、ワッツの主張する「宇宙は魔法的幻想であり、素晴らしいゲームである」という認識を科学的に裏付ける。固体と空間、波と粒子、自己と他者—これらの見かけ上の対立は、より深い統一の表面的な現れに過ぎない。
「私」の消滅と再発見
ワッツは読者を思考実験へと導く。「あなたが本当は何者か」を探求すればするほど、固定的な「自己」は見つからない。玉ねぎの皮を一枚一枚剥いていくように、自我の層を剥がしていくと、中心には何もない。これは恐ろしい発見のように思えるが、実は解放の始まりだ。
なぜなら、独立した自我という幻想こそが、あらゆる苦しみの源泉だからだ。自我は常に脅威にさらされていると感じ、防衛し、拡張し、証明しようとする。死への恐怖、失敗への不安、他者との比較による劣等感—これらはすべて、「私」という錯覚から生じる。
ワッツは死についての西洋文化の病的な恐怖を分析する。キリスト教の影響で、死は最後の審判に続く永遠の罰の前触れと見なされてきた。現代では、死は永遠の無への没入と見なされる—まるでそれが何らかの経験であるかのように。「もう友人も、太陽の光も鳥の歌も、愛も笑いも、海も星もない—ただ果てしない闇だけ」。
しかし、この恐怖は「白が勝たなければならない」という白黒ゲームの致命的な誤解から来ている。生と死、存在と非存在は、波の山と谷のように不可分だ。一方なしには他方は存在しない。死への恐怖は、ゲームの前提そのものを誤解することから生じる。
ワッツは出産の例を挙げる。かつて出産は原罪の罰として痛みを伴うべきだと考えられていた。神がイブに「あなたは苦しみの中で子供を産むであろう」と言ったからだ。女性が義務として苦しむべきだと誰もが信じていたとき、女性は実際に義務を果たした。しかし、「原始的」社会の女性が畑で働きながらしゃがんで出産し、臍帯を噛み切り、赤ん坊を包んで去っていくことを発見して、私たちは驚いた。産婦人科医は最近、多くの女性が自然で痛みのない出産のために心理的に条件付けできることを発見した。
同様に、死も必ずしも私たちが想像するような恐怖である必要はない。死は病気ではなく、人生の自然で必要な終わりだ—秋に葉が落ちるのと同じくらい自然だ。ワッツは、死が差し迫ったときこそ、完全に自分を手放す理想的な状況だと示唆する。もはやしがみつくことが全く役に立たないとき、人は完全に自分を手放すことができる。これが起こると、個人は自我の牢獄から解放される。
プロテスタンティズムと「仕事の罠」
ワッツの分析で特に現代的な意義を持つのは、西洋文明(特にプロテスタント文化)における「目的志向的生き方」への批判だ。プロテスタンティズムは、特にその自由主義的・進歩的形態において、物質世界の神話と「分離した自我」の経験に最も強く影響された宗教だ。
西洋社会では、人生は段階的な進歩の階段として構造化されている。幼稚園、小学校、中学校、高校、大学—そして「成功」という究極の目標に向かっての準備。しかし卒業の日は一時的な達成に過ぎない。最初の販売促進会議で、あなたは同じ古いシステムに戻り、ノルマを達成するよう促される(そしてあなたがそうすれば、彼らはより高いノルマを与える)。そして、セールスマネージャー、副社長、そして最終的には自分の会社の社長への階段を上る(40歳から45歳くらいで)。
その間、保険や投資の人々は退職の計画に関心を持たせてきた—すべての労働の成果を楽しむために座ることができるという本当に究極の目標。しかしその日が来たとき、あなたの不安と努力は心臓が弱く、入れ歯があり、前立腺の問題、性的不能、視力の低下、消化不良を残している。
これはすべて、すべての段階でそれをゲームとしてプレイできたなら、ポーカー、チェス、釣りと同じくらい魅力的な仕事を見つけることができたなら、素晴らしかったかもしれない。しかし私たちのほとんどにとって、一日は仕事時間と遊び時間に分けられ、仕事は他の人が私たちに支払うほど徹底的につまらないタスクで構成される。したがって、私たちは仕事のために働くのではなく、お金のために働く—そしてお金は余暇と遊びの時間に私たちが本当に望むものを得ることになっている。
ワッツは痛烈に指摘する。アメリカの物質主義という評判は根拠がない。物質主義者が物理的世界を徹底的に楽しみ、物質的なものを愛する人であるなら、私たちは素晴らしい物質主義者だ—ジェット機の建造に関しては。しかし、これらの壮大な怪物の内部を乗客の快適さのために装飾するとき、それは飾り立てるだけだ。ハイヒール、細腰のドール型の女の子が模造の温め直された食事を提供する。私たちの喜びは物質的な喜びではなく、喜びの象徴だ—魅力的にパッケージされているが、内容は劣っている。
この詐欺は簡単に説明できる。私たちの製品のほとんどは、所有者であれ労働者であれ、それを作ることを楽しんでいない人々によって作られている。企業での彼らの目的は製品ではなくお金であり、したがって生産コストを削減し、製品が本当によくできていると買い手を色付けやパッケージの詐欺によって欺くためにあらゆる手段が使われる。唯一の例外は、安全性や高価な購入のために単に優れていなければならない製品だ—航空機、コンピューター、宇宙ロケット、科学機器など。
遊びとしての宇宙
ワッツの究極的なビジョンは、宇宙を「リーラ」(遊び)として理解することだ。これはヴェーダンタ哲学の中心概念であり、創造は神の深刻な仕事ではなく、遊戯的な自己表現だという考え方だ。同様に「マーヤ」(幻影)は、文字通りの幻想を意味するのではなく、魔法、創造的力、芸術、そして測定を意味する—ダンスや設計を特定の尺度に合わせるときのように。
この観点から、宇宙全般、特に遊びは、特別な意味で「無意味」だ。つまり、言葉や記号のように、それら自体を超えた何かを指し示したり示唆したりしない。モーツァルトのソナタは道徳的または社会的メッセージを伝えず、風、雷、鳥の歌の自然な音を示唆しようとしない。
しかし、私たちの文化では「遊び」という言葉には二つの異なる意味があり、しばしば混同される。一方で、何かを「ただの遊び」でするということは、些細で不誠実であることを意味する。ここでは「遊ぶ」の代わりに「もてあそぶ」という言葉を使うべきだ。しかし他方、セゴビアがギターを演奏したり、ローレンス・オリヴィエがハムレットの役を演じたり、明らかに教会でオルガンを演奏したりするような遊びの形態がある。
この意味で、ナジアンゾスの聖グレゴリオスは、創造的な神の知恵であるロゴスについて言うことができた。「高きにあるロゴスは遊び、全宇宙を望みのままに前後に動かし、あらゆる種類の形に」。そして地球の反対側では、日本の禅師白隠が「歌と踊りの中に法の声がある」と言った。
ワッツは中国の哲学書『太乙金華宗旨』を引用する。「目的が目的のなさを達成するために使われたとき、事物が把握された」。生存のためだけに生き残る社会は、目的のない行動—つまり、未来の報酬を必ずしも意味しない、現在行われることに満足する行動—の余地を設けない社会だ。しかし間接的かつ意図せずに、そのような行動は生存に有用だ。なぜならそれが生き残る意味を与えるからだ—ただし、その理由で追求されるときではない。
相関的ビジョン:対立の統一
ワッツの思想の技術的核心は「相関的ビジョン」(correlative vision)だ。これは白黒ゲームの徹底的な理解のための専門用語であり、すべての明示的な対立は暗黙的な同盟者であることを見ることだ—相関的という意味で、それらは互いに「ともにある」(go with)のであり、離れて存在することはできない。これは、究極の「グー」への差異の霧散ではなく、世界の根底にある形而上学的統一だ。
この統一は、多様性に対立する単なる一性ではない。なぜならこれら二つの用語自体が極性を持つからだ。したがって、一と多の統一、または不可分性は、ヴェーダンタ哲学では単純な均一性と区別するために「非二元性」(advaita)と呼ばれる。確かに、この用語自体が対立概念「二元性」を持っている。なぜならすべての用語がクラス、知的な引き出しを指定する限り、すべてのクラスには内部を極性化する外部があるからだ。
この理由で、言語は二次元の表面上の絵画や写真が三次元を超えられないのと同じように、二元性を超越することはできない。しかし遠近法の慣習によって、「消失点」に向かって傾く特定の二次元線は、深さの第三次元を表すものとされる。同様に、二元的な用語「非二元性」は、明示的な差異が暗黙的な統一を持つ「次元」を表すものとされる。
相関的ビジョンを維持することは最初は容易ではない。『ウパニシャッド』はそれをかみそりの刃の道と表現している—最も鋭く最も薄い線上でのバランス行為だ。普通の視覚には、クラスや対立の「間」には何も見えないからだ。人生は、これかあれかの確固たるコミットメントを要求する一連の緊急の選択だ。物質はできる限り何かのようなものであり、空間はできる限り無のようなものだ。それらの間の共通次元は考えられないように思える。
しかし視点をわずかに変えると、対立の相互依存ほど明白なものはない。しかし誰がそれを信じることができるだろうか?私自身、私の存在が、存在と無を含んでいて、死が永遠でなければならないオン/オフの脈動における単なる「オフ」間隔に過ぎないということは可能だろうか—なぜならこの脈動に対するあらゆる代替案(例えば、その不在)は、やがてその存在を暗示するからだ?
IT:言葉を超えた実在
ワッツの最終的な概念は「IT」だ。これは言語化できない究極の実在を指す。自己と他者、主体と客体、有機体と環境が単一プロセスの極であるなら、「それ」が私の真の存在だ。ウパニシャッドが言うように、「それが自己だ。それが実在だ。あなたはそれだ!」(Tat tvam asi)
しかしITについて二元的言語を使って考えたり語ったりすることはできない—平面に深さを示すために遠近法の線を使うように、比喩、隠喩、神話の言語に頼らなければならない。困難は言語が二元的であるだけでなく、ITが私が思っていたよりもはるかに私自身であり、私の存在に非常に中心的で基本的であるため、それを対象にすることができないということだ。ITの外に立つ方法はなく、実際にそうする必要もない。
ITを把握しようとする限り、私はITが本当に私自身ではないことを暗示している。可能であれば、私はそれを見つけようとすることによってその感覚を失っている。これが、本当に自分がITであることを知っている人々が、常にそれを理解していないと言う理由だ。なぜならITが理解を理解するのであって、その逆ではないからだ。人は深さよりも深く行くことはできないし、その必要もない。
しかしITがあらゆる記述を逃れるという事実は、しばしば起こるように、ITを最も希薄な抽象として—文字通り透明な連続体または未分化の宇宙的ゼリーとして—記述するものと間違えてはならない。白いひげと金色のローブを着た父なる神の最も具体的なイメージの方がましだ。しかし西洋の東洋哲学・宗教の学生は、ヒンドゥー教徒や仏教徒が特徴のないゼラチン状の神を信じていると執拗に非難する。後者がITのあらゆる概念や客観的イメージが空であると主張するからだ。しかし「空」という用語はそのような概念すべてに適用されるのであって、IT自体には適用されない。
現代への警告:技術と制御の逆説
ワッツの分析は、1960年代に書かれたにもかかわらず、現代の監視資本主義、アルゴリズム制御、デジタル全体主義への鋭い予見を含んでいる。彼はサイバネティクス(自動制御の科学)がもたらす逆説を指摘する。
科学的予測とその技術的応用によって、私たちは周囲と自分自身に対する最大限の制御を得ようとしている。医学、通信、工業生産、輸送、金融、商業、住宅、教育、精神医学、犯罪学、法律において、私たちは完全なシステムを作ろうとしている—間違いの可能性を排除するために。技術がより強力になればなるほど、そのような制御の必要性はより緊急になる。ジェット機の安全対策、そして最も興味深いことに、原子力国間の技術者の協議—誰もが誤ってボタンを押さないようにするため。
強力な道具の使用は、人間とその環境を変える膨大な可能性を持ち、より多くの立法、免許、警察を必要とし、したがって検査と記録保持のためのますます複雑な手続きを必要とする。偉大な大学には、政府との関係を担当する副学長と、関係する書類の山に対処するための秘書の大規模なスタッフがいる。
ワッツは特に、個人のプライバシーの終焉を予見している。トランジスタと小型化技術を通じて、監視装置はますます見えなくなり、かすかな電気インパルスにますます敏感になる。これはすべて個人のプライバシーの終わりに向かっており、思考を隠すことさえ不可能になる程度まで。最終的には、自分の心を持った人は誰も残らない—ただ広大で複雑なコミュニティ・マインドがあるだけだ。
さらに不吉なのは、彼の技術的完璧さについての観察だ。「完全自動モデルの宇宙では、人間は意志の独立した源泉ではなく、メカニズムだ。したがって、最も攻撃的で暴力的な(したがって鈍感な)プロパガンディストが決定を下す。暴力と力によって統一された矛盾する意見の混乱は、強力な技術の最悪の制御源だ」。
しかしワッツは単なる技術悲観論者ではない。彼が指摘するのは、秩序対偶然のゲームがゲームとして続くためには、秩序が勝ってはならないということだ。予測と制御が増加するにつれて、ゲームはろうそくに見合わなくなる。私たちは不確実な結果を持つ新しいゲームを探す。言い換えれば、私たちは再び隠れなければならない—おそらく新しい方法で—そして新しい方法で探さなければならない。この二つが一緒になって、存在のダンスと驚異を構成するからだ。
死と再生:永遠の脈動
ワッツの最も挑発的な示唆の一つは、死についての根本的に異なる理解だ。彼は読者に、死を意識の永久的な終わり、あなたとあなたの宇宙の知識が単に消滅し、まるであなたが存在したことがないかのようになる点として考えるよう求める。はるかに広大なスケールでも考えてみる—すべてのエネルギーが尽きたときの宇宙の死、一部の宇宙学者によれば、銀河を空間に投げ出した爆発が花火のように消えるとき。それはまるで起こらなかったかのようになる—もちろん、それが起こる前の状態と同じだ。
同様に、あなたが死んだとき、あなたは受胎される前の状態になる。だから—意識の閃光、銀河の閃光があった。それは起こった。たとえ誰も覚えていなくても。しかし、それが起こって消滅したとき、もし事態が始まる前と同じであるなら(何も存在しなかった可能性を含めて)、それは再び起こり得る。なぜだめなのか?
ワッツは続ける。「私が去ったとき、永遠の『過去形』の状態の経験、生きることはあり得ない。自然は『真空を嫌う』、そして私感覚は以前と同じように再び現れる。そして間隔が10秒であろうと数十億年であろうと関係ない。無意識においては、すべての時間は同じ短い瞬間だ」。
これは非常に明白だが、それを見ることに対する私たちのブロックは、「私」がこの世界に入ってくる、またはそこから投げ出されるという、世界との本質的なつながりを持たないという、根深く強制的な神話だ。したがって、私たちは宇宙がすでに行ったこと—再び「私」になること—を繰り返すことを信頼しない。私たちはそれを永遠のアリーナとして見ており、個人は一時的な見知らぬ人に過ぎない—ほとんど属していない訪問者だ—なぜなら意識の細い光線はその源を照らさないからだ。世界を見るとき、私たちは世界が自分自身を見ていることを忘れる—私たちの目を通して、そしてITの目を通して。
慈悲と名誉:新しい倫理
ワッツの悟りの理解は、道徳的相対主義や無関心につながるものではない。むしろ、それは深い慈悲と「名誉ある盗賊」の倫理につながる。本当の危険な人々は、彼らが盗賊であることを認識していない人々だ—「善人」の役割を盲目的な熱意で演じ、自分たちを支える「悪人」への負債を意識していない不運な人々だ。
福音書を言い換えると、「あなたの競争相手を愛し、あなたの価格を下げる人々のために祈りなさい」。彼らなしではあなたはどこにもいないだろう。この感覚の欠如のために、西洋、特にアメリカの政治的・個人的道徳は、完全に分裂症的だ。それは妥協のない理想主義と無節操なギャング主義の途方もない組み合わせであり、したがって、告白された悪党が座って合理的な取引を練り上げることを可能にする、ユーモアと人間性を欠いている。
誰も道徳的ではあり得ない—つまり、含まれた対立を調和させることはできない—自分の中の天使と自分の中の悪魔との間の実用的な取り決めに達することなしには。二つの力、または傾向は相互依存的であり、天使が勝っているが勝たない限り、そして悪魔が負けているが決して負けない限り、ゲームは実用的なゲームだ。
これは市民権、国際平和、核兵器の抑制に関心を持つ人々にとって最も重要だ。これらは間違いなく全力で支持されるべき大義だが、反対を尊重しない、またはそれを完全に邪悪または狂気と見なす精神では決してない。ボクシング、柔道、フェンシング、さらには決闘の正式な規則が、戦闘員が交戦前に互いに敬礼することを要求するのには理由がある。
観想への呼びかけ
ワッツは最終的に、西洋文明が「実用性、結果、進歩、攻撃」への強調を減らす必要があると主張する。これが彼がビジョンについて議論し、ビジョンを実用的応用と結果の観点から正当化する主題から離れている理由だ。
中国人やヒンドゥー教徒にとって何が真実であろうと、私たちが未来は常に後退する蜃気楼であることを認識し、私たちの膨大なエネルギーと技術的スキルを行動ではなく観想に切り替える時が来ている。アリストテレスの論理と比喩に今はどれだけ同意しなくても、行動の目標は常に観想である—求めることと成ることではなく、知ることと存在することである—ということを思い出させてくれたことに対して、彼を尊重しなければならない。
現状では、私たちは単に人生を飲み込んでいる—消化されていない経験を詰め込めるだけ速く飲み込んでいる—なぜなら私たち自身の存在の意識が非常に表面的で狭いため、単純な存在ほど退屈に思えるものはないからだ。もし私が昨日あなたが何をしたか、見たか、聞いたか、匂いを嗅いだか、触れたか、味わったかを尋ねたら、あなたが気づいた少数のものの薄くスケッチされた輪郭以上のものを得ることはほとんどない—そしてそれらのうち、覚えておく価値があると思ったもののみ。
そのように経験された存在が非常に空虚で裸に見えるので、無限の未来への飢えが満たされないのは驚くべきことだろうか?しかし、あなたが答えることができたと仮定する。「あなたに話すのに永遠にかかるだろうし、私は今起こっていることにずっと興味がある」。目のような敏感な宝石、耳のような魅惑的な楽器、脳のような素晴らしいアラベスクの神経を持つ存在が、神以下のものとして自分自身を経験することがどうして可能だろうか?
そしてこの計り知れないほど繊細な有機体が、その環境のさらに驚異的なパターンから切り離せないことを考えると—最も微細な電気設計から銀河全体の会社まで—永遠のすべての化身がどうして存在することに退屈することができるだろうか?
ワッツの最終的なメッセージは驚くほどシンプルだ。「今、あなたは知っている—たとえ完全な衝撃を得るために二度見するのに時間がかかるとしても」。そして彼は警告する。もしあなたが「私はどうやって自我感覚を超えることができるか?」と尋ねるなら、なぜそこに行きたいのかを問う。正直な答えは、自我が「自己超越」という「より高い精神的地位」でより良く感じるだろうということだ。これによって、自我が偽物であることを実現するだろう。
しかし最終的に、これは解放の始まりだ。なぜなら「ITがITをクールに演じる」からだ。あなたはITであるから、ITのようにステージに上がらない。そしてステージのポイントは見せること(show on)であって、見せびらかすこと(show off)ではない。ITのように振る舞うこと—神を演じること—は、自己を役割として演じることであり、それはまさにそれが何でないかだ。ITが演じるとき、それは他のすべてであるかのように演じる。
この実現により、私たちは実用的な生活に戻ることができるが、新しい精神で。そしてこの新しい精神こそが、分離の幻想から生じる生態学的災害、技術的全体主義、そして意味の喪失から私たちを救うかもしれない唯一のものだ。