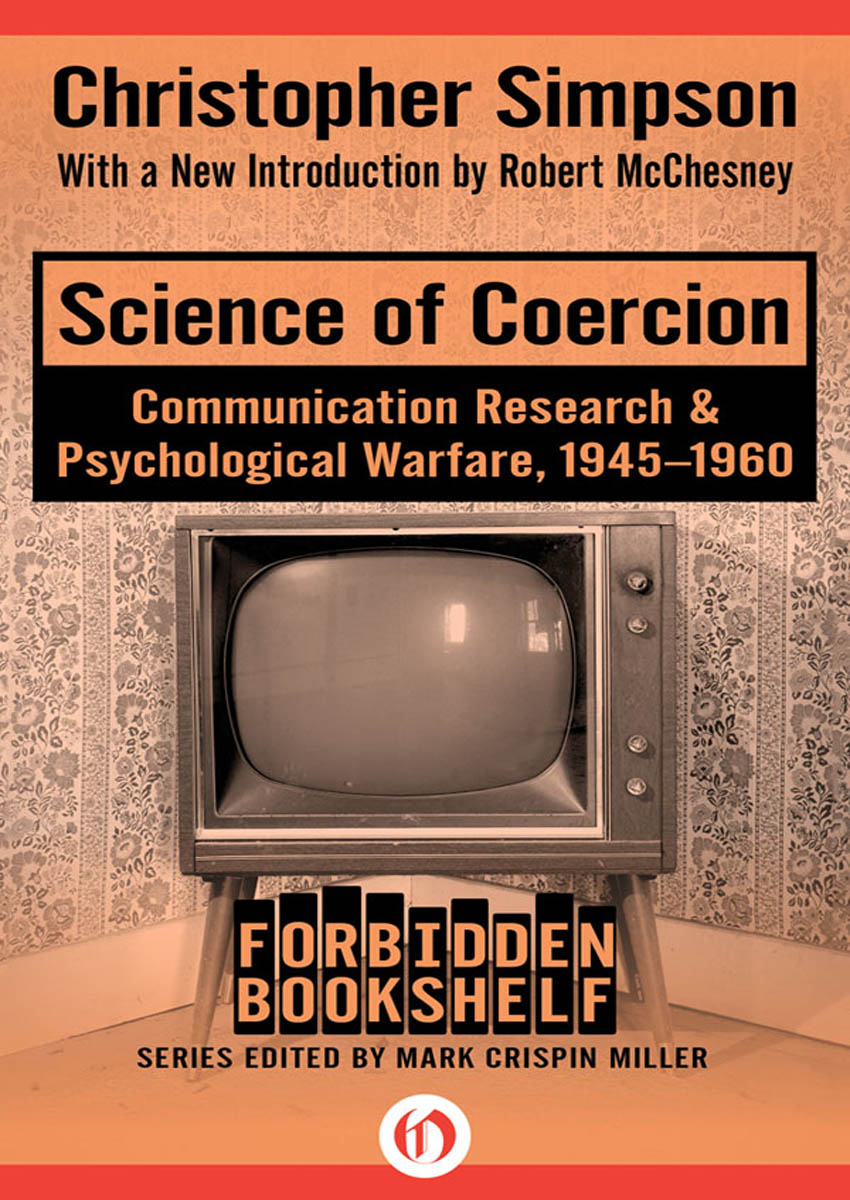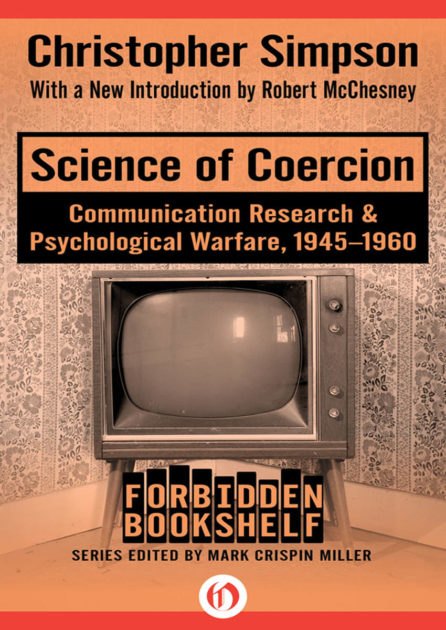
英語タイトル:『Science of Coercion:Communication Research & Psychological Warfare, 1945–1960』Christopher Simpson 1994
日本語タイトル:『科学としての強制:コミュニケーション研究と心理戦、1945–1960』クリストファー・シンプソン 1994
目次
- 第1章 心理戦の定義 / Defining Psychological War
- 第2章 世界大戦と初期近代コミュニケーション研究 / World War and Early Modern Communication Research
- 第3章 「社会科学者の多大な貢献」 / “The Social Scientists Make a Huge Contribution”
- 第4章 学術的提唱者 / Academic Advocates
- 第5章 政府の前哨基地 / Outposts of the Government
- 第6章 「兵舎と塹壕の仲間」 / “Barrack and Trench Mates”
- 第7章 支配のパラダイムの内在化と強化 / Internationalization and Enforcement of the Paradigm of Domination
- 第8章 心理戦の遺産 / The Legacy of Psychological Warfare
- 付録:スチュアート・ドッド博士の「リヴァー関連論文」リスト (1958) / Appendix:Dr. Stuart Dodd’s List of “Revere-Connected Papers” (1958)
- 文献エッセイ:/ Bibliographic Essay
本書の概要
短い解説:
本書は、1945年から1960年の冷戦初期において、米国の軍事、情報、プロパガンダ機関による心理戦プログラムが、大学を拠点とするマスコミュニケーション研究という学問分野の成立と発展に決定的な影響を与えた経緯を、豊富な一次資料と詳細な調査に基づいて明らかにするものである。社会科学、メディア研究、現代史に関心を持つ研究者・学生を主な対象としている。
著者について:
著者クリストファー・シンプソンは、米国を代表する調査報道ジャーナリスト・歴史家であり、冷戦期の情報工作、戦争犯罪、プロパガンダの研究で知られる。米国政府の機密文書開示請求を駆使した実証的なアプローチを特徴とし、権力と知識の交錯点を鋭くえぐる。本書でも、心理戦という「応用研究」が「基礎科学」の衣をまとって学界に浸透する過程を、資金の流れと人的ネットワークに焦点を当てて批判的に追跡する。
テーマ解説
- 主要テーマ:知識の社会学。国家的資金援助と学問的「パラダイム」(支配のためのコミュニケーション観)の形成との密接な関係。
- 新規性:ラザースフェルド、キャントリル、シュラムら「コミュニケーション研究の父」たちの仕事の多くが、政府の心理戦プロジェクトから直接的に資金提供を受け、その目的に奉仕していたことを具体的に立証した点。
- 興味深い知見:「コミュニケーション」そのものが、エリートによる大衆の支配・説得の道具として再定義され、その狭い定義が「主流派」科学として制度化されていった過程。
キーワード解説
- 心理戦 (Psychological Warfare):広義には、プロパガンダ、破壊工作、サボタージュ、暗殺、ゲリラ戦などを含む、敵の意思・戦闘能力を心理的に破壊するための総合戦略。米軍の定義では「通常の軍事作戦以外の、精神的・物理的あらゆる手段」とされる。
- 「ホワイト」「ブラック」「グレー」プロパガンダ:送り手が明示される公式プロパガンダ(ホワイト)、送り手を偽装する秘密工作(ブラック)、その中間で出所が曖昧な情報操作(グレー)。
- パラダイムとしての支配:コミュニケーションを「誰が、何を、どのチャネルで、誰に、どのような効果をもたらしたか」という一方向的な説得・支配モデルとして捉える、冷戦期に確立された研究の基本的枠組み。
- 正当化可能な否定 (Plausible Deniability):秘密作戦(特にブラック・プロパガンダや破壊工作)を、政府が関与を否定できるように計画・実行すること。
- 開発理論 (Development Theory):冷戦後期にMIT国際研究センター等で発展した理論。途上国の「近代化」に伴う不安定性を管理し、親米的な開発経路へ誘導するために、コミュニケーション研究と低強度紛争を組み合わせることを提唱した。
3分要約
本書『科学としての強制』は、冷戦初期の米国におけるコミュニケーション研究という学問分野が、政府の心理戦プログラムの資金と要請によって形作られ、その本質として「支配のパラダイム」を内在化した過程を克明に描き出す。
第二次世界大戦は、ラスウェル、リップマンらが提唱した「コミュニケーション=説得・支配の道具」という視点を実践する場となり、多くの社会科学者を動員した。戦後、彼らは学界に戻り、オールドボーイ・ネットワークを形成した。冷戦の勃発とともに、トルーマン政権はNSC 4-AやNSC 10/2などの極秘文書により、CIAを中心とする大規模な秘密心理戦(ブラック・プロパガンダ、破壊工作、暗殺を含む)を承認した。
こうして巨額の政府資金が「国家安全保障」研究に流れ込んだ。コロンビア大学応用社会調査局(BASR)、プリンストン大学国際社会調査研究所(IISR)、MIT国際研究センター(CENIS)、ミシガン大学社会調査研究所(ISR)、国立世論調査センター(NORC)など、コミュニケーション研究の主要拠点の多くは、この資金に生存を依存していた。
学界の最前線をリードした学術誌『パブリック・オピニオン・クォータリー』(POQ)は、心理戦を公然と論じる場となり、その編集委員会には政府契約に依存する研究者が名を連ねた。ダニエル・ラーナーの『伝統的社会の消滅』(中東におけるVOA調査に基づく)や、ウィルバー・シュラムの『マス・コミュニケーションの過程と効果』(USIA資金による教科書)など、後に「古典」とされる著作の多くは、心理戦プロジェクトの産物だった。
研究の焦点は、効果測定、世論調査手法、内容分析、国家通信システムの分析など、「支配」をより効果的にするための技術的課題に集中した。この「支配のパラダイム」は、マッカーシズムの圧力や学界内部のイデオロギー対決の中で強化され、より批判的・双方向的なコミュニケーション観(儀礼的共有モデルなど)やマルクス主義的アプローチを排除・抑圧する方向に作用した。
著者は、この歴史的経緯が、現代の広告、PR、ジャーナリズム教育の基礎となる「主流派」コミュニケーション理論に、エリートによる大衆管理という視点を深く刻み込んだと結論づける。本書は、学問の「客観性」と「中立性」の神話を解体し、知識生産が常に権力と資金の文脈の中で行われることを想起させる、社会科学史における重要な批判的研究である。
各章の要約
第1章 心理戦の定義
心理戦とは、広義には敵の戦意を喪失させ、味方の士気を高めるためのあらゆる手段(プロパガンダ、破壊工作、サボタージュ、ゲリラ戦、暗殺など)を包含する概念である。米軍の定義によれば、それは「通常の軍事作戦以外の精神的・物理的あらゆる手段」であり、「白」「黒」「灰」のプロパガンダや特別作戦を含む。冷戦期、米国政府はこの戦略を、対ソ連・東欧のみならず、第三世界の民族主義運動や国内世論に対しても大規模に展開した。本書の目的は、1945年から1960年にかけて、この心理戦プログラムが米国のマスコミュニケーション研究という学問分野の成立、資金提供、理論的方向性に決定的な影響を与えた経緯を実証することである。
第2章 世界大戦と初期近代コミュニケーション研究
心理戦の近代的起源は第一次世界大戦にあり、ウォルター・リップマンやハロルド・ラスウェルらが、大衆社会における世論操作とプロパガンダの理論的基礎を築いた。ラスウェルの「誰が、何を、どのチャネルで、誰に、どのような効果をもたらしたか」という定式は、コミュニケーションを一方向的な支配・説得の過程として捉える「支配のパラダイム」の原型となった。第二次世界大戦は、OSS(戦略事務局)やOWI(戦争情報局)などで、キャントリル、ラザースフェルド、ストーファーら多くの社会科学者を動員し、戦時プロパガンダや士気調査に従事させた。この戦時経験が、人的ネットワーク(「オールドボーイ・ネットワーク」)と共通の研究アジェンダを形成し、戦後の学問分野の結晶化の基盤となった。
第3章 「社会科学者の多大な貢献」
第二次世界大戦後、心理戦の専門家たちはその能力を「平時」の冷戦に転用するよう政府に提言した。トルーマン政権は、1947年の国家安全保障法でCIAを創設し、続く極秘文書NSC 4-AとNSC 10/2により、CIAに秘密プロパガンダ、破壊工作、サボタージュ(「政策調整局」OPCを通じて)を公式に認可した。これにより、米国は「公式には否定可能」な形で大規模な心理戦を遂行する体制を整えた。OSS幹部の証言は、社会科学(特に社会心理学とコミュニケーション研究)が、この新たな「知的戦争」において不可欠な武器であると位置づけていた。
第4章 学術的提唱者
学術誌『パブリック・オピニオン・クォータリー』(POQ)は、心理戦を巡る議論の中心的な場となった。同誌には、心理戦を公然と論じる記事や、政府の外交政策イニシアチブを支持する書評が頻繁に掲載された。さらに重要なのは、その編集委員会に、デウィット・プール(CIA系組織「自由ヨーロッパ委員会」の長)や、政府契約に深く依存していたハドリー・キャントリル、ハロルド・ラスウェル、ポール・ラザースフェルドらが名を連ねていたことである。同誌は、心理戦を「応用コミュニケーション研究」として学問的に正当化し、その実践者たちに「権威ある」発言の場を提供する役割を果たした。
第5章 政府の前哨基地
冷戦初期、コミュニケーション研究への連邦政府資金の大半は、国防総省、CIA、USIA(米国情報局)などの国家安全保障機関から供給された。コロンビア大学応用社会調査局(BASR)、ミシガン大学社会調査研究所(ISR)、国立世論調査センター(NORC)など、主要な研究拠点は、政府契約なしには存続が困難なほどこの資金に依存していた。国防総省の「人的資源委員会」や、カーネギー財団、ラッセル・セージ財団といった主要財団の意思決定には、ストーファー、ホフランド、コットレルら、政府との緊密な関係を持つ学者たちが深く関与しており、研究資金の流れと方向性を事実上支配するネットワークが形成されていた。
第6章 「兵舎と塹壕の仲間」
1950年代に入り、心理戦研究は学術誌の主流となった。朝鮮戦争を機に、シュラムやライリーらが空軍の委託で行った研究は、学術論文と通俗プロパガンダ冊子の両方で発表された。VOA研究局長レオ・ローヴェンタールが編集したPOQ特集号は、BASRの中東調査など、政府契約に基づく研究を「国際コミュニケーション研究」として発表した。また、社会調査局(BSSR)は、USIAのために世論調査手法や「オピニオン・リーダー」理論を導入するなど、実践的な技術提供を行った。一方、MIT国際研究センター(CENIS)はCIAの資金を受け、ダニエル・ラーナーらによる「開発理論」を推進し、第三世界における心理戦と低強度紛争の理論的根拠を提供した。
第7章 支配のパラダイムの内在化と強化
社会科学者が心理戦研究に積極的に関与した理由は多岐にわたる。愛国心、専門的野心、冷戦への切迫した危機感に加え、マッカーシズムの脅威に対抗して学問的「正統性」を証明する手段としても機能した。学界は、「中心」のコンセンサス(反共産主義と政府協力)に回帰し、左右両翼の批判を排除する方向で結束を強めた。POQなどの主流誌は、アドルノ、ホルクハイマー、C・ライト・ミルズらの批判的著作をほぼ無視し、代わりに「支配のパラダイム」を精緻化する研究を称揚した。この過程で、コミュニケーションを支配の道具と見なす視点が、「科学的」で「客観的」な唯一のアプローチとして制度化されていった。
第8章 心理戦の遺産
ウィルバー・シュラムなど、コミュニケーション研究を定義づけた「創設者」たちの業績は、心理戦プロジェクトと不可分に結びついていた。政府資金は、効果研究、拡散研究(プロジェクト・リヴァー)、開発理論など、学問分野の礎となる重要な「マイルストーン」研究を可能にした。しかし、その見返りとして、学界は「コミュニケーションとは何か」という根本的な問いに対して、エリートによる大衆の管理と説得に奉仕する狭い答えを制度化してしまった。著者は、この歴史的経緯が、現代の広告、PR、メディア産業の思想的基盤に深く刻み込まれており、真に民主的で双方向的なコミュニケーションの可能性を考察する際の障害となっていると指摘する。心理戦の遺産は、学問が権力からいかに「自律的」でありうるかについて、重い問いを投げかけ続けている。
続きのパスワード記載ページ(note.com)はこちら
注:noteの有料会員のみ閲覧できます。