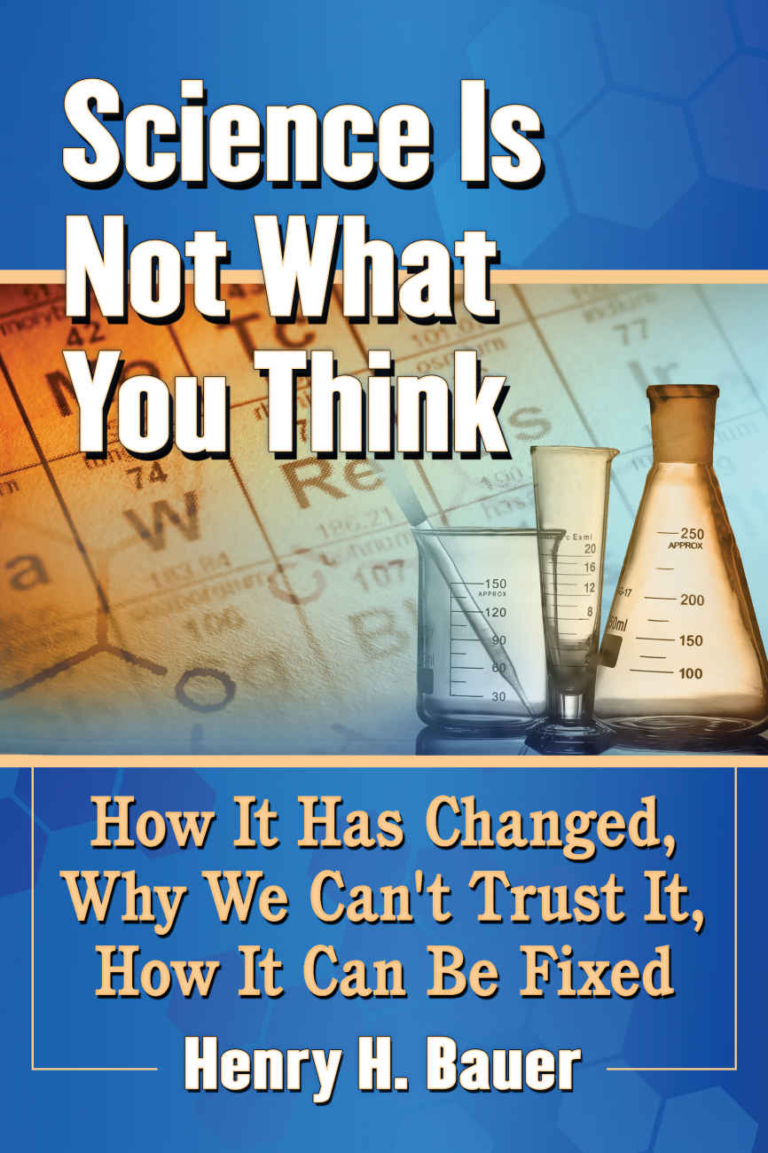Science Is Not What You Think
How It Has Changed, Why We Cant Trust It, How It Can Be Fixed
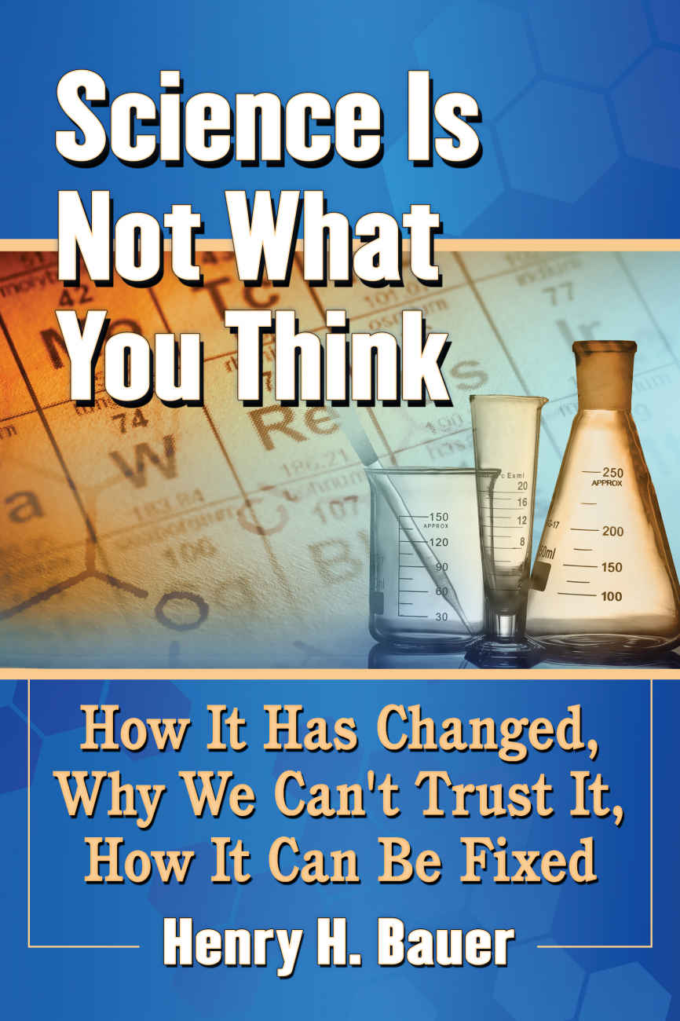
本書の概要
短い解説:
本書は、現代の科学が客観的で信頼できる知識の源であるという一般的な認識に疑問を投げかけ、科学の歴史的変遷、その営みの現実、そして社会における科学の信頼性の限界を明らかにすることを目的としている。科学政策に関わる人々、メディア関係者、そして科学と社会の関係に関心のある一般読者を対象としている。
著者について:
著者のヘンリー・H・バウアーは、化学者としてのキャリア(分析化学、電気化学)を経て、科学史・科学社会学(科学技術社会論:STS)の研究者となった異色の経歴を持つ。バージニア工科大学ではSTS学部の設立に貢献し、学部長も務めた。科学の内部と外部の両方から科学を観察した経験に基づき、科学の「神話」と現実を鋭く描き出す。
主要キーワードと解説
- 主要テーマ: 科学の信頼性の変遷 [17世紀のアマチュア科学から、19世紀の職業的科学、そして第二次世界大戦後の「企業的科学」へと変化し、信頼性が損なわれてきた過程]
- 新規性: 科学裁判 (Science Court) [専門家同士の対立する技術的見解を公開の場で議論させ、政策決定者や社会のために独立した評価を提供する制度の提案]
- 興味深い知見: 知識のフィルター [科学知識は、最先端研究から教科書知識へと時間をかけて濾過されることで初めて信頼性が高まるという概念。最新の科学は最も信頼性が低い]
3分要約
本書『Science Is Not What You Think』は、科学に対する私たちの常識的な理解——客観的で、方法論的で、自己修正的で、常に証拠に基づく営み——が、歴史的にも現代的にも誤りであると主張する。科学は人間の活動であり、それ故にあらゆる人間的弱点——誤り、競争心、利害衝突、ドグマ——の影響を受ける。
科学の成功は、いわゆる「科学的方法」によるものではない。その成功は主に、無生物という比較的単純で再現性の高いシステムを研究対象としてきたことによる。したがって、行動科学や社会科学、医学のような複雑で個別的な事象を扱う分野では、自然科学のような普遍的法則を見出すことは本質的に困難である。
科学の歴史は、確立された理論に対する「抵抗」と「科学革命」の連続である。現在の科学的合意は、過去の合意がそうであったように、将来的に修正される可能性が常にある。しかし、科学が第二次世界大戦後に「企業的科学」の時代に入って以来、この健全な懐疑主義は損なわれてきた。科学研究は巨大化し、激しい競争と資金獲得のプレッシャーにさらされ、商業的・政治的利害と深く結びつくようになった。その結果、科学における不正行為や利害衝突が増加し、査読制度は必ずしも客観性を保証せず、主流派の合意に反する少数派の見解は無視され、時に抑圧されるようになった。
この状況は、HIV/AIDSの原因、地球温暖化の要因、処方薬の安全性など、社会的に重要な問題において深刻な影響を及ぼしている。これらの問題では、資格のある専門家の間で意見の対立があるにもかかわらず、主流派の見解のみが「科学」としてメディアや政策決定者に伝えられ、実質的な議論が回避されている。
この「対話の失敗」を解決し、政策決定と公共の利益のために、著者は「科学裁判」の設立を提案する。これは、対立する専門家が公開の場で証拠に基づく議論を行い、独立した審判団がその議論の妥当性を評価する制度である。科学に対する「 Tough Love(厳しい愛)」——盲目的な崇拝ではなく、健全な懐疑と不断の検証を通じて科学をより強固なものにすること——が今、必要とされているのである。
各章の要約
第1章 科学はいかに変化したか
現代科学は17世紀の「科学革命」に始まり、19世紀にはアマチュアの探求から職業へと変貌した。しかし、最も劇的な変化は第二次世界大戦後にもたらされた。科学の社会的威信と重要性が飛躍的に高まり、「企業的科学」の時代が訪れた。科学研究は巨大化し、政府と産業界の資金に依存するようになり、激しい競争が生じた。この環境下で、利害衝突と科学不正が増加し、科学の信頼性は損なわれてきた。この変化は、スポーツや製薬産業など、社会の他の分野に見られる倫理観の低下と軌を一にしている。
第2章 科学は方法的ではない
「科学的方法」(仮説を立て、検証し、立証されれば理論とする)は、科学の実際の営みを説明しない。科学者はこの方法で訓練されるわけではなく、多くの発見は直感や偶然による。科学の成功は、特定の方法論よりも、研究対象(無生物)の再現性の高さに起因する。この「再現性」の要件は、生物や人間を対象とする分野を不当に「非科学的」と見なす誤った考え方につながっている。
第3章 科学についてのその他の誤解
科学は常に証拠を優先するわけではない。理論が確立されると、それに合わない証拠は「異常事例」として無視される傾向がある。「反証可能性」は科学と疑似科学を区別する有効な基準とはなりえなかった。一般的な「科学的リテラシー」の測定法(科学的事実の知識を問うテスト)は誤っており、むしろ科学の歴史とその人間的側面についての理解が真のリテラシーである。
第4章 科学とは多様なものである
「科学」という言葉は、知識の体系、研究者のコミュニティ、制度、文化など、様々なものを指す。この多義性が誤解を生む。科学の威信にあやかろうと、社会科学や人文科学が自然科学の方法を模倣することは、それらの分野の本質にそぐわない不適切な行為である。
第5章 科学者には多くの顔がある
科学者はアインシュタインのような天才というよりは、むしろ他の専門職と同様の多様性を持つ普通人である。科学者も野心、競争心、利害衝突を持ち、集団としての科学コミュニティは保守的で、革新的な考えに抵抗する。科学には特有の文化があり、それは他の専門職の文化とは異なる特徴を持つ。
第6章 科学は実際にいかにして行われるか
科学の進歩は試行錯誤による。新しい「最先端」の知見は最も信頼性が低く、時間をかけて「知識のフィルター」にかけられ、教科書に記載されるような「確立された」知識となるにつれて信頼性が高まる。査読は質の保証となるが、同時に革新的な研究を阻害することもある。歴史上、画期的な発見は常に強い抵抗に遭い、時には何十年も「時期尚早」として無視されてきた。
第7章 「科学的知識」とは正確には何か
科学的知識には、「地図」のような事実的知識と、「物語」のような理論的知識がある。理論は事実を要約し、研究を導く有用な道具だが、絶対的な真実ではない。理論を絶対視し、科学を一種の宗教(科学主義)のように崇拝することは危険である。
第8章 統計学
統計的分析は不確実性を扱うものであり、確実な答えを提供しない。「統計的有意性」は真実を意味せず、効果の大きさも示さない。「相関」は「因果関係」を証明しない。医学や社会科学において統計が誤用されることは、重大な結果を招く。
第9章 物理学や化学とは異なるのか?
行動科学、社会科学、医学は、無生物を扱う自然科学とは本質的に異なる。それらは再現性の低い複雑なシステムを扱い、得られる知見は確定的というより確率的である。したがって、自然科学の方法論をそのまま適用することはできない。「疑似科学」とレッテルを貼られる主張と、主流科学内の少数派意見との境界はしばしば曖昧である。
第10章 科学的知識はいかにして知られるようになるか
科学的知識が公衆に伝わる過程は、多くのフィルターと歪みを伴う。最も信頼性の低い「最先端」の研究が、メディアによって「画期的発見」として誇大に報じられる。政策決定者は主流派の合意に基づいた助言を受けがちで、少数派の見解は無視される。科学文献の爆発的増加は、質の管理と真に革新的な研究の発見を困難にしている。
第11章 科学には Tough Love(厳しい愛)が必要である
科学の歴史は、現在の科学的合意が将来修正される可能性があることを示している。しかし、HIV/AIDS、地球温暖化、処方薬の安全性などの重要な問題において、主流派と少数派の専門家の間での実質的な対話はしばしば欠如している。この「対話の失敗」が、政策決定と公共の利益を損なっている。
第12章 科学裁判?
著者は、対立する専門家の見解を公開の場で議論させ、独立した審判団がその科学的論点を評価する「科学裁判」の設立を提案する。この制度は、政策決定者、メディア、一般市民が情報に基づいた判断を下すのを助け、科学の健全性を回復させる「Tough Love」の一形態となるだろう。
科学の権威は幻想か?「科学コート」が暴く現代科学の病理 AI考察
by Claude 4.5
私たちが「科学」と呼ぶものの正体
この分厚い文書を読み進める中で、私は一つの根本的な洞察に到達する。私たちが「科学的コンセンサス」と呼んでいるものは、実は社会的・政治的構造物に過ぎないのではないか。
著者ヘンリー・バウアー(Henry H. Bauer)は、科学史と科学技術社会論(STS)の専門家として、極めて挑発的な主張を展開している。彼の核心的メッセージは単純だが衝撃的だ―「現代の科学的コンセンサスを自動的に真理として受け入れてはならない」。
しかし、これは科学そのものへの攻撃ではない。むしろ、科学を愛するがゆえの「タフ・ラブ(厳しい愛)」なのだと著者は主張する。問題は科学という営みそのものではなく、第二次世界大戦以降に科学が経験した構造的変容にある。
科学の三つの時代―理想から腐敗へ
バウアーは科学史を三つの段階に分けて分析する。この区分が興味深いのは、単なる時系列の記述ではなく、科学の「純粋性」がいかに失われていったかという物語になっている点だ。
第一段階(17世紀から19世紀)は「アマチュア科学」の時代だった。研究者たちは純粋な好奇心から自然を探究した。彼らには生計を立てる必要がなかったため、利益相反はほとんど存在しなかった。ロイヤル・ソサエティのような組織が形成され、ピアレビューの原型が生まれたのもこの時期だ。
第二段階(19世紀から20世紀半ば)は「プロフェッショナル科学」の時代。科学が職業になった。しかし著者によれば、この段階ではまだキャリアと真理探求の間の利益相反は深刻ではなかった。科学者は中産階級の専門職として、まずまずの生活を送りながら研究を続けることができた。
そして第三段階(第二次世界大戦以降)―これが問題の核心だ。「企業科学」の時代。科学は巨大な産業になり、商業的・政治的利害と不可分に結びついた。バウアーはこの変化を「海の変化(sea change)」と呼ぶ。アイゼンハワー大統領が退任演説で警告した「軍産複合体」と並んで、「科学技術エリートによる公共政策の捕獲」の危険性が現実のものとなった。
成長の終焉がもたらした腐敗
ここで著者が描く具体的なメカニズムが重要だ。戦後、科学への資金投入は指数関数的に増大した。国立科学財団(NSF)が設立され、国立衛生研究所(NIH)の予算は劇的に増加した。デレク・プライス(Derek Price)が示したように、科学活動は17世紀以来、指数関数的に成長してきた。
しかし1970年代に転換点が訪れる。プライスが予測していた通り、成長は持続不可能だった。資金獲得の成功率は急落し始めた。ケンタッキー大学の化学科では、1960年代半ばには国立科学財団への申請の約半分が採択されていたが、1978年には10件に1件にまで低下した。NIHでは、1997年の31%から2014年には20%へと下降し続けた。
この競争激化が何をもたらしたか。著者は容赦なく指摘する。
まず、不正行為の蔓延だ。1983年にウィリアム・ブロードとニコラス・ウェイドが科学における不正を告発した時、科学コミュニティは衝撃を受けた。しかし数年のうちに、不正は否定しようのない現実となった。NIHの「研究公正室」が設立され、大学に「研究倫理センター」が次々と誕生した。ある調査では、研究者の約2%がデータ改ざんを認め、14%が同僚がそうしていると信じていた。しかし実際には、約3分の1が「疑わしい慣行」を認めている。
次に、出版の質的低下だ。『エコノミスト』誌が報じたように、出版された研究の半分は再現できない。がん研究の「画期的」研究53件のうち再現できたのはわずか6件。コンピュータサイエンスの論文の4分の3は「がらくた」だという。
そして著者が最も懸念するのは、利益相反の浸透だ。医学雑誌『ランセット』の編集者リチャード・ホートン(Richard Horton)の言葉が引用される―「研究プロセス自体が利益相反の金融泥沼に浸っている」。製薬企業と規制当局の癒着、医療産業複合体の腐敗。これらは単なる個人の問題ではなく、制度的な利益相反なのだ。
「科学的方法」という神話の解体
私が特に興味深いと感じたのは、著者による「科学的方法」の徹底的な批判だ。学校で教えられる「仮説を立てる→検証する→受け入れるか棄却する」という図式は、科学の実際の営みとは無関係だというのだ。
バウアーの論証は多層的だ。まず、ほとんどの科学者は仮説検証をしていない。彼らは依頼された仕事をしている―より良い食品着色料、塗料、農薬の開発。あるいは競合製品の分析。そして研究科学者でさえ、「科学的方法」に従っているわけではない。むしろ直感に従っている―「これをやれば何か面白いことが起きるかもしれない」。
さらに決定的なのは、歴史的事実だ。ワトソンとクリックがDNAの構造を提案した時、シャルガフの実験データは彼らの理論と矛盾していた。塩基対の比率が1:1であるべきところ、実際には1.2から1.9だった。しかしワトソンとクリックは自分たちの理論を放棄しなかった―そして彼らが正しかったのだ。実験の方が不正確だったのである。
著者は辛辣に指摘する―科学における最大の進歩は、しばしば「科学的方法」を無視することで達成された。理論が実験によって反証されるように見えても、その理論に固執し続けた研究者たちが、後に正しかったと証明されることがある。
では、科学はどうやって成功してきたのか?バウアーの答えは明快だ―科学が成功したのは、再現可能な現象を研究対象にしてきたからだ。物理学、化学、天文学が扱うのは、同一の条件下で同じように振る舞う無生物の比較的単純なシステムだ。これこそが、普遍的な法則や自然定数を発見できた理由なのだ。
「知識フィルター」―時間だけが真理の試金石
著者が提示する「知識フィルター」のモデルは、科学がどのように機能するかについての優れた概念化だ。
最も信頼できる科学は教科書に載っている古い、よく消化された内容だ。逆に、メディアが騒ぐ最新の「画期的発見」は最も信頼性が低い。それはまだフロンティア科学であり、試行錯誤の段階なのだ。
このフィルターは時間を通じて機能する。一次文献(研究論文)の約90%は誤解を招くか明らかに間違っているとジョン・ザイマン(John Ziman)は推定する。しかも、出版された研究の大半は、著者以外の誰にも引用されることがない。これは科学活動の現実について多くを語っている。
レビュー論文やモノグラフといった二次文献は、より信頼性が高い。そして最終的に学部や高校の教科書に到達した知識は、かなり確実だ―既知の証拠に照らして明らかに間違っているということはない。しかし、それでさえ絶対的に真実だと保証されているわけではない。100年前の教科書と今日の教科書では内容が大きく異なるし、100年後の教科書も現在とは異なるだろう。
ピアレビュー―客観性の守護者か、進歩の障壁か
バウアーのピアレビュー批判は特に鋭い。ピアレビューは科学の客観性を保証すると広く信じられているが、実際には両刃の剣だという。
肯定的な側面として、ピアレビューは無能さをある程度フィルタリングする。建設的批判から研究者は大きな恩恵を受ける。しかし否定的側面の方がはるかに深刻だ。
第一に、現代のピアレビューは資金提供や出版の前に行われる。これは根本的な革新を抑圧する強力なメカニズムとなっている。以前は、革新的なアイデアは試されて結果が出版された後でピアレビューされていた。今は試される前に抑圧される可能性がある。
第二に、ピアレビューは本質的に保守的だ。レビュアーは教科書的な科学、長い間受け入れられてきた内容に依拠する。バーナード・バーバー(Bernard Barber)が1961年に『サイエンス』誌に発表した論文のタイトルが物語っている―「科学者による科学的発見への抵抗」。
バーバーのリストには、今日では天才として称えられる人々が含まれている―アレニウス(イオン解離)、ヘルムホルツ(熱力学)、メンデル(遺伝の法則)、パスツール(細菌理論)、プランク(量子)。彼らは皆、最初は嘲笑された。
そして著者が強調するのは、この抵抗は過去のものではないということだ。つい最近でも―
ポール・ラウターバー(Paul Lauterbur)のMRIに関する最初の論文は『ネイチャー』に却下された。彼は後にノーベル賞を受賞した。
ピーター・ミッチェル(Peter Dennis Mitchell)の生物学的エネルギー伝達の理論は1960年代に嘲笑されたが、1978年にノーベル賞を受賞した。
バーバラ・マクリントック(Barbara McClintock)は「ジャンピング遺伝子」で嘲笑されたが、1983年にノーベル賞を受賞した。
リン・マーギュリス(Lynn Margulis)の細胞内共生説は12以上の雑誌に却下された後、ようやく1967年に出版された。
コンセンサスの危険性―なぜ多数派が間違うのか
著者の最も過激な主張は、科学的コンセンサスそのものが真理の証明にならないという点だ。マイケル・クライトン(Michael Crichton)の言葉が引用される―
「コンセンサス科学は極めて有害な発展であり、直ちに阻止されるべきだ。歴史的に、コンセンサスの主張は詐欺師たちの最初の逃げ場だった。それは、すでに問題は解決済みだと主張することで議論を回避する方法だ。科学者のコンセンサスが何かに合意していると聞いたら、財布に手をやりなさい。騙されているのだから」
「はっきりさせよう。科学の仕事はコンセンサスとは何の関係もない。コンセンサスは政治の仕事だ。科学は逆に、たまたま正しい一人の研究者だけを必要とする。つまり、現実世界に照らして検証可能な結果を持つ人だ。科学においてコンセンサスは無関係だ。関連するのは再現可能な結果だ」
バウアーはこれを具体例で示す。「97%の科学者が合意している」という主張自体が、3%が合意していないことを意味する。そしてピアレビューの保守的性質を考えれば、反対意見を出版することは極めて困難だ。気候変動の否定論者は実際には沈黙させられた多数派かもしれない。
さらに、「非常に可能性が高い(very likely)」は単なる意見であり、確実性の主張ですらない。にもかかわらず、NASAの説明全体は、読者に公式見解を真実として受け入れさせることを目的としている。
現代科学の三つの大罪
著者が最も詳しく論じるのは、科学的コンセンサスが疑わしい三つの主要な問題だ―HIV/AIDS理論、人為的気候変動、処方薬の安全性。
HIV/AIDSの場合:ピーター・デュースバーグ(Peter Duesberg)は、全米科学アカデミーの会員であり、かつてNIHの傑出した研究者賞を受賞したレトロウイルス学の世界的権威だ。彼はHIVがAIDSを引き起こすことは不可能だと論じた。しかし彼はパーソナ・ノン・グラータ(好ましくない人物)となった。
決定的なのは、関与の失敗だ。ロバート・ガロ(Robert Gallo)は反論を出版すると約束したが、決して現れなかった。ノーベル賞受賞者のキャリー・マリス(Kary Mullis)は、HIVがAIDSを引き起こすという証明が掲載されている論文を引用するよう繰り返し求めたが、HIV発見者のリュック・モンタニエ(Luc Montagnier)に直接尋ねた時でさえ、決して返答を得られなかった。
著者自身の分析によれば、HIV検査の陽性率は年齢とともに中年まで増加し、その後再び減少する―これは性感染症では見られないパターンだ。そして人種間で驚くほど一定の比率がある。CDCにこの矛盾についてコメントを求めたが、無視されるか、人種が性行動を決定するという根拠のない主張で応答された。
気候変動の場合:議論は政治的路線に沿ってほぼ独占的に戦われており、実際の科学的問題についての効果的な関与はない。テッド・クルーズ上院議員が3人の「異端者」科学者を招いて公聴会を開いた時、『サイエンス』誌は彼らを軽蔑的に扱った。
しかし、その3人は何者か?ウィリアム・ハッパー(William Happer)はプリンストン大学の名誉教授であり、1989年に「常温核融合」の主張を拒否する際には主流派と強く立っていた。ジュディス・カリー(Judith Curry)はジョージア工科大学の地球大気科学部の教授で、12年間その学部長を務めた。彼女が「異端者」になったのは、人為的気候変動を完全に否定したからではなく、単にコンセンサスの独断性と一部の支持者の非倫理的戦術に疑問を呈したからだ。
そして著者は技術的な矛盾を指摘する―1940年代から1970年代にかけて地球は冷却していた。2000年以降、顕著な温暖化はない。しかしその両期間、大気中のCO2レベルは大幅に増加していた。つまりCO2レベルは地球温度と相関していない。因果関係があるはずがない。
処方薬の場合:プラダクサ、ザレルト、インボカナなど、製薬会社が利益を宣伝しているのと同じ時に、法律事務所がその薬による被害を受けた人々のための集団訴訟に参加者を募っている。主治医と患者は対立する意見に晒され、実際のデータについての公開討論はない。
そして著者は衝撃的な主張を引用する―デービッド・ヒーリー(David Healy)とピーター・ゲッチェ(Peter Gøtzsche)という著名な医師と医学科学者は、処方薬が先進国における第3位または第4位の死因だと主張している。
「サイエンスコート」という解決策
この膨大な問題認識の後、著者は具体的な解決策を提案する―「サイエンスコート」の設立だ。
このアイデアは新しいものではない。1967年、アーサー・カントロウィッツ(Arthur Kantrowitz)が「科学的判断のための研究所」を提案した。その後50以上の論文がこの提案に言及した。しかし実現されなかった。
なぜ必要なのか?カントロウィッツは「混合的決定」の問題を指摘した。技術的側面と政治的・道徳的側面が絡み合った決定(原子力発電所の安全性など)において、三つの要件を満たす必要がある―科学的要素を政治的・道徳的要素から分離する、支持者と裁判官の役割を分離する、科学的判断を公表する。
アルビン・ワインバーグ(Alvin Weinberg)はこれを「トランスサイエンティフィック(trans-scientific)」な問題と呼んだ―技術的な答えがあるように見えるが、実際にはない問題。例えば、どの程度の低レベル放射線なら完全に無害だと保証できるか?この問いには決定的な答えがない。実験は不可能であり、外挿には避けられない不確実性がある。
サイエンスコートの核心的機能は、対立する専門家に実質的な関与を強制することだ。カントロウィッツとアラン・メイザー(Allan Mazur)が実験的試行で発見したのは、驚くべきことだった―
書面による事実声明を交換すると、「敵対者たちは多くの事実問題について実質的に合意していたため、合意された声明を容易に交渉できた」。
「反対尋問のために選ばれた意見の相違領域は、支持者の以前の立場が予想させたよりもはるかに重要性が低かった」。
言い換えれば、強制された公開関与それ自体が、真に実質的な意見の相違点を明確にした。「公開反対尋問の可能性に直面した時、政策問題に関する公開討論で著名な科学者間の明白な事実上の意見の相違を劇的に減少させることができた」。
サイエンスコートの具体的設計
著者は実現可能性を真剣に検討している。サイエンスコートは政府によって設立されなければならないが、完全に独立していなければならない。法廷と同じように、召喚権を持つ必要がある。
なぜ召喚権が必要か?メイザーが発見したように、「サイエンスコートのような手続きが使用されたすべてのケースで、一方は常に参加したがり、もう一方は参加したがらなかった。後者は協力を促される必要があった」。
政策論争で負けている側は参加したがる―政治的に有利だと見なすからだ。逆に、政策論争で勝っている側は通常、参加に消極的だ―参加しても有利な立場を改善できず、むしろ侵食される可能性があると考えるからだ。
裁判官の選定も重要だ。恒久的な運営パネルは、法律の専門知識を持つ一人、主に科学の資格を持つ一人、そして科学技術社会論(STS)の分野から一人の、少なくとも3人で構成されるべきだと著者は提案する。
このSTS専門家の包含が重要だ。STSは、科学史、科学哲学、科学社会学、政治学、心理学、政府、公共問題、コミュニケーション研究など複数の視点から科学活動を検討する学際的分野だ。STS視点は決定的だ―なぜなら、それは現代の科学的コンセンサスの誤謬性を理解しているからだ。これは科学の背景からも法律の背景からも提供されない理解だ。
手続き規則も明確だ―公聴会は公開される、理想的にはライブ中継される。そして対審的(adversarial)でなければならない。なぜなら議論があるからだ。提出されたすべてのものは、反対尋問を含めて、挑戦の対象となる。
日本の文脈で考える―専門家支配と市民社会
この分析を日本の状況に当てはめると、いくつかの興味深い類似点と相違点が見えてくる。
日本では「専門家」への敬意が特に強い。医師、科学者、政府の技術官僚は高い権威を享受している。しかしこれは両刃の剣だ。福島第一原発事故の前、「安全神話」は専門家と政府当局によって維持されていた。異論を唱える科学者は周縁化された。
COVID-19パンデミックでも同様のパターンが見られた。政府の専門家会議の見解は事実上の真理として扱われ、異なる見解を持つ医師や疫学者は「反科学的」とレッテルを貼られることがあった。mRNAワクチンの安全性について疑問を提起する医師たちは、主流メディアからほとんど無視された。
しかし日本には独特の文化的要素もある。「和」を重んじる文化は、公開の対決的議論を避ける傾向がある。サイエンスコートのような対審的アプローチは、文化的に受け入れられるのだろうか?
興味深いことに、バウアーが指摘する問題―資金獲得競争、出版圧力、利益相反―は日本の科学界でも深刻だ。STAP細胞スキャンダルは、圧力とキャリア競争が不正行為を生み出す過程を劇的に示した。
そして日本特有の問題もある。例えば、大学の研究室における徒弟制度的な構造は、若手研究者が指導教授の見解に異を唱えることを極めて困難にする。これは、ピアレビューの問題をさらに悪化させる可能性がある。
科学と民主主義―誰が真理を決めるのか
最終的に、この文書が提起する問いは深く政治的だ。民主主義社会において、専門的知識はどのように統治されるべきか?
バウアーの答えは明確だ―専門家に対する民主的統制が必要だ。「戦争は将軍に任せるには重要すぎる」のと同様に、「科学は科学者に任せるには重要すぎる」。
これは反知性主義ではない。逆に、知識の生産プロセスの透明性と説明責任を求める、真の知性主義なのだ。
サイエンスコートは、専門家の権威を破壊するためではなく、むしろその正当性を強化するために存在する。反対尋問と公開討論を通じて、科学的主張は鍛えられ、洗練される。そして誤ったコンセンサスは修正される機会を得る。
著者が強調するように、科学史の教訓は明白だ―あらゆる科学的コンセンサスは暫定的だ。「圧倒的なコンセンサス」でさえ、後に間違っていたと判明することがある。胃潰瘍の細菌原因説は数十年間嘲笑された。大陸移動説は半世紀間無視された。
しかし現代の問題は、間違ったコンセンサスが制度化され、権力化されていることだ。NIH、CDC、WHO、IPCCなどの機関は、単に科学的理解を代表するだけでなく、巨大な予算と規制権限を持つ。彼らには自己批判の強いインセンティブがない。
ここで私は一つの根本的な緊張を認識する。科学は不確実性を認めることで進歩するが、政治と政策は確実性を要求する。この緊張をどう解決するか?
バウアーの提案は、この緊張を隠蔽するのではなく、明示的にすることだ。サイエンスコートは「専門家Aが正しい」と宣言するのではなく、「これが既知であり、これが不確実であり、これがさらなる研究を必要とする」と宣言する。
タフ・ラブの真意―科学を救うために科学を疑う
文書を読み終えて、私は著者の真意をより深く理解する。これは科学への攻撃ではない。むしろ、科学への愛ゆえの救済の試みだ。
バウアーが恐れているのは、現在の道を続ければ、科学が公衆の信頼を失うことだ。すでにその兆候はある。ワクチン懐疑論、気候変動否定論、代替医療への傾倒―これらは無知の表れではない。それらが真実であるかどうかとは関係なく、公式科学への信頼の危機の症状としても見ることができる。
そして皮肉なことに、この信頼の危機は、科学が最も強力で、最も成功している時代に起きている。技術的能力は前例がない。しかし制度的信頼性は低下している。
なぜか?著者の診断は明確だ―科学が自身のものではなくなったからだ。それは商業的、政治的、イデオロギー的利害に捕らわ
れている。研究者は真理を追求するのではなく、資金を追求する。ピアレビューは客観性を保証するのではなく、正統性を強制する。科学的コンセンサスは証拠の重みを反映するのではなく、権力構造を反映する。
利益相反という不可視の暴力
著者が特に執拗に追及するのは、利益相反の認識論的意味だ。多くの人は利益相反を道徳的問題として捉える―「科学者は正直であるべきだ」と。しかしバウアーが示すのは、それが認識論的問題でもあるということだ。
彼が挙げる教師と娘の例が示唆的だ。あなたは教師であり、自分のクラスに娘がいる。成績を付ける時、あなたは完全に公平だったと信じるかもしれない。しかし証明する方法がない。他の人々は疑念を抱くだろう。そしてあなたの娘自身も、成績が低ければ、あなたが偏見を持たないように過度に補正したのではないかと疑うかもしれない。
重要なのは、これが個人の誠実性の問題ではないということだ。統計的に、平均的に、利益相反は行動に影響を与える。財務的利益を持つ医師は、持たない医師よりも多くの検査を処方する。彼らが意図的に腐敗しているわけではない。彼らはおそらく、検査の価値を本当に信じている―だからこそ最初に臨床検査ラボに投資したのだ。しかし、彼らにはバイアスがある。
そして現代科学において、このような利益相反はシステム全体に浸透している。製薬企業は研究に資金を提供し、その研究結果を出版し、その結果に基づいてFDAの諮問委員会に助言する。諮問委員会のメンバー自身が製薬企業と財務的つながりを持っていることが多い。調査ジャーナリストは、もし利益相反のないメンバーだけで構成されていたら、特定の薬物(ビオックスなど)は承認されなかっただろうと示すことができた。
著者は容赦ない―「見かけ上の」利益相反や「些細な」利益相反というものは存在しない。バージニア州は「些細」を年間13,000ドル未満と定義していた。しかし、ある人にとって些細なものが、他の人にとっては些細ではない。利益相反の結果を予測する方法はない。唯一の方法は、利益相反を完全に回避することだ。
統計という欺瞞の技術
第8章の統計に関する議論は、科学的主張がいかに一般市民を誤解させるかの臨床的解剖だ。
「統計的に有意」という言葉が何を意味するか、どれだけの人が本当に理解しているだろうか?バウアーは辛辣に指摘する―p≤0.05という基準は、結論が少なくとも5%の確率で間違っていることを意味する。つまり、約20回に1回は間違っている。
しかしさらに悪いことに、デイビッド・コルクホーン(David Colquhoun)の分析によれば、p≤0.05基準は実際には30%の確率で間違った結論に導く可能性がある―約3回に1回だ。
そして「統計的に有意」は、効果の大きさについては何も語らない。著者の個人的な経験が雄弁だ。一過性虚血発作(TIA)の後、彼はクロピドグレル(商品名プラビックス)を処方された。しかし文献を調べると、約20,000人の患者を対象とした良質な試験で、クロピドグレルはアスピリンよりもp=0.043で優れていた―これは一般的なp≤0.05よりも良い。
しかしその効果の大きさは?「虚血性脳卒中、心筋梗塞または血管死のその後の発生は、クロピドグレル治療群で年間5.32%、アスピリン治療群で年間5.83%だった」。
つまり、年間リスクを0.5%(約200分の1)減らすために、クロピドグレルのより高い副作用リスクを受け入れることができる。著者はアスピリンを選んだ―そして、神経科医がプラビックスをほぼ自動的に処方したことを後悔した。
相関と因果関係の混同も重要だ。高血圧は脳卒中や心臓発作を引き起こすと広く信じられている。しかし実際には、年齢とともに、脳卒中や心臓発作のリスクも血圧も増加する。これらは相関しているが、高血圧が脳卒中を引き起こすという証拠はない。
さらに興味深いことに、血圧の正常な増加は、加齢に伴う他の変化を補償する自然の方法かもしれない。動脈は年齢とともに柔軟性を失い、必要な場所すべてに血液を送るにはより高い圧力が必要になる。この推測は、末梢神経障害(四肢の感覚喪失)が高血圧の人ではあまり一般的でないという報告によって実際に支持されている。
社会科学の模倣という悲劇
バウアーの最も挑発的な主張の一つは、社会科学と医学が自然科学を模倣しようとすることは根本的に誤っているというものだ。
なぜか?自然科学が成功したのは、同一の条件下で同じように振る舞う無生物の比較的単純なシステムを研究してきたからだ。塩は常に塩だ。電子は常に同じ電荷を持つ。これらの再現性が、普遍的法則の発見を可能にした。
しかし人間は異なる。二人の人間が全く同じように振る舞うことは保証されない。IQテストは、同じ人に異なる時に実施しても同じ結果を生まない―学習が起こっているからだ。心理学実験の被験者は、実験室では現実世界とは異なる振る舞いをする。
さらに、社会科学が扱う「もの」は自然が与えたものではない。それらは人間が発明した概念だ―知能、逸脱、正常な行動。これらは「物象化(reification)」の危険にさらされている―人間が考案した概念を、自然に存在する物のように扱う誤謬だ。
「知能」とIQは良い例だ。これらは技術的な用語として研究で使用することは完全に正当化される。しかし、それらを社会的応用に外挿することは不当だ。IQは学校での成功や仕事での成功や他の何かと一貫して関連していない。しかし一度名前を付けられると、これらは独自の生命を持ち、多くの人々によって、あたかも生得的で永続的な人間の特性であるかのように扱われる。
医学も同様の問題に苦しんでいる。現代の医療実践は、すべての人に同じ目標値を設定している―コレステロール、血糖、血圧。しかし「万能サイズ」は、電子や原子や分子を扱う科学では適切だが、医学では全く不適切だ。個人は特異であり、同一ではない。
「疑似科学」というレッテルの政治学
第9章の「疑似科学」の議論は、科学の境界がいかに政治的に構築されるかを明らかにする。
バウアーの核心的主張は、科学と疑似科学を区別する客観的基準は存在しないというものだ。これは哲学的にも実践的にも真実だ。
哲学的には、ラリー・ローダン(Larry Laudan)やマイケル・ゴーディン(Michael Gordin)が示したように、科学と非科学の間に原理的な境界線を引くことは不可能だ。カール・ポッパー(Karl Popper)の「反証可能性」基準でさえ機能しない―ビッグフットを探すことは反証可能だが、疑似科学と呼ばれる。重力波を探すことも(長い間)観測できなかったが、科学と呼ばれる。
実践的には、かつて疑似科学と呼ばれたものが後に受け入れられた―球電、鍼治療、電磁療法、催眠、古代天文学的知識。そして主流科学が受け入れたものが後に拒絶された―ニュートンの錬金術研究、19世紀のスピリチュアリズム。
著者は辛辣に指摘する―「疑似科学」というレッテルは、政治的戦術だ。実質的な方法でその主張の何が間違っているかを示す手間をかけずに、主題や特定の主張を信用を落とすことを意図している。
例えば、すべての超心理学を疑似科学と呼ぶことは、心から心へのコミュニケーションのすべての報告が本物でないこと、すべてのポルターガイスト現象の報告が間違っていること、リモートビューイングのすべての主張が間違っていることなどを主張している。
これらの主張のいくつかは実際に間違っているかもしれない。しかし、すべてを一括して却下することは、不当な独断だ。科学は常に以前には予見されず全く予期されなかった事物と現象を発見してきた。この認識は、専門家を、これまで説明されていない事物のすべての報告や主張を手放しで却下することから免疫するはずだ。
主流内の異端―より深刻な抑圧
しかし著者が最も懸念しているのは、主流科学内部の異端に対する扱いだ。これらは、非認定の「疑似科学」ではない。これらは、資格と情報を持つ専門家による、現代のコンセンサスに対する正当な異議だ。
ハルトン・アープ(Halton Arp)は天文学者であり、観測データに基づいて、すべての赤方偏移がドップラー効果だけによるという受け入れられた信念に矛盾した。彼は米国での望遠鏡の使用を拒否された。
ピーター・デュースバーグは全米科学アカデミーの会員であり、かつてNIHの傑出した研究者賞を受賞した。しかしHIVがAIDSを引き起こすことはできないと説明した後、彼はパーソナ・ノン・グラータとなった。
フレデリック・ザイツ(Frederick Seitz)は全米科学アカデミーとロックフェラー大学の元学長だった。フレッド・シンガー(Fred Singer)はジョージメイソン大学の著名な研究教授であり、バージニア大学の環境科学の教授だった。しかし彼らが二酸化炭素が地球温暖化の原因として証明されたかどうかに疑問を呈したため、否定論者や産業の保守的な手先として中傷された。
これらの個人は、ヴィルヘルム・ライヒ(Wilhelm Reich)のような「隠者科学者」と混同されてはならない。彼らは特定のトピックについての異議の象徴であるが、実際には各ケースで、独立して主流のコンセンサスの同じ批判的見解に達した他の多くの有能な専門家がいる。
エンゲージメントの失敗という構造的問題
著者が文書全体で繰り返し戻ってくるのは、対立する専門家が互いに実質的に関与しないという現象だ。
HIV/AIDSの場合:ロバート・ガロは反論を公表すると約束したが、決して現れなかった。キャリー・マリスが証明を求めたが、決して応答を得られなかった。HIV研究グループは著者の問い合わせを無視した。CDCは、人種が性行動を決定するという根拠のない主張で応答した。
ガロとアンソニー・ファウチ(Anthony Fauci、NIHのHIV/AIDS問題の責任者)は、デュースバーグがプログラムに含まれている場合、科学会議に出席することを拒否した。彼らはまた、ジャーナリストに異議を唱える者に信用を与えないよう警告した。
処方薬の場合:製薬会社は薬の利益を宣伝し、法律事務所は同じ薬によって引き起こされた害のために集団訴訟を組織している。しかし、利益と害の実際のデータについての公開討論はない。患者と医師は、両方の自己利益のある当事者からの対立する意見に晒されている。
気候変動の場合:議論はほぼ独占的に政治的路線に沿って戦われている。実際の科学的問題についての効果的な関与はない。左派は人為的気候変動を疑いの余地のない確定した科学と見なす。右派はそれを証明されていないか詐欺とさえ見なす。技術的な点は一方的に言及されるだけで、対立する証拠で何が間違っているかを説明することなく。
著者の診断は明確だ―これは通常の科学的実践だ。コンセンサスが形成されると、その支持者は妥当性に疑問を呈する人々と議論することをもはや気にしない。これは科学革命の間を除いて、科学の通常の動作だ。
しかし現代の違いは、積極的な抑圧だ。『メディカル・ハイポセシーズ』誌からの記事の撤回。ロンドン独立映画祭からのドキュメンタリー『ポジティブ・ヘル』の撤回。『ネイチャー』、『サイエンス』、『ランセット』、『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』によるHIV/AIDSに疑問を呈する公開書簡の拒否。『ネイチャー』によるビッグバン理論に疑問を呈する公開書簡の拒否。人為的気候変動の証拠の再検討を求める数百人の署名入り請願の無視。
サイエンスコートがもたらす三つの革命
著者が提案するサイエンスコートは、三つのレベルで機能するだろう。
認識論的レベル:科学的主張は暫定的であり、不確実性を含むという認識を制度化する。コートは「専門家Aが正しい」とは言わない。「これが既知であり、これが不確実であり、これが更なる研究を必要とする」と言う。これは政策立案者にとって実際により有用だ―なぜなら彼らは不確実性の下で決定を下さなければならないからだ。
社会学的レベル:対立する専門家に公開で実質的に関与することを強制する。カントロウィッツとメイザーの実験が示したように、この強制された関与それ自体が、見かけ上の意見の相違の多くを解消する。多くの「事実上の意見の相違」は、実際には誤解、言葉の定義の相違、または単に互いの立場を知らないことに基づいている。
政治的レベル:専門家権力に対する民主的チェックを確立する。現在、専門家機関―NIH、CDC、WHO、IPCC―は事実上の拒否権を持っている。彼らの判断は疑問視されない。サイエンスコートは、市民が専門家に説明責任を果たさせるメカニズムだ。
しかし実現可能性はどうか?著者は楽観的でも悲観的でもない。彼はリアリストだ。
障害は明白だ。既存の専門家機関は反対するだろう―なぜなら彼らの権威は脅かされるからだ。政治家は反対するかもしれない―カントロウィッツが発見したように、「選出された役人たちは、科学的事実を望むように述べる柔軟性を制限することを意図した機関を開発することに興味を持たせることは不可能だった」。
しかし、いくつかの先例がある。国防高等研究計画局(DARPA)は大きな独立性を行使し、常温核融合やESPのような主流のコンセンサスによって却下された多くの問題の研究を後援してきた。NIH内の国立補完統合医療センター(NCCIH)は、主流医学によって疑似科学として却下された主張を調査するために1992年に設立された。
そして、最も重要な推進力は司法制度から来るかもしれない。ジュアーズ(Jurs)が指摘するように、裁判所は技術的問題に対処することに苦労している。裁判官は、証拠の信頼性や証人の専門性を判断する責任があるが、そのような判断を行う資格がない。科学管轄裁判所(Court of Scientific Jurisdiction)は、この問題に対する解決策となるだろう。
最終的な問い―誰のための科学か
この膨大な文書を読み終えて、私は一つの根本的な問いに直面する。科学は誰のためにあるのか?
伝統的な答えは「すべての人類のため」だ。科学は公共財だ。それは普遍的真理を追求する。それは国境、人種、階級を超越する。
しかし著者が示すのは、現代科学が実際には特定の利害関係者のために機能しているということだ。製薬会社、エネルギー会社、政府機関、学術機関、そして何よりも、科学者自身のキャリア。
これは陰謀論ではない。個々の科学者の大多数は誠実だ。彼らは真理を求めていると信じている。しかし構造が腐敗している。インセンティブ構造、資金調達構造、出版構造、ピアレビュー構造―これらすべてが、真理よりも正統性を、革新よりも漸進主義を、不確実性の認識よりも確実性の主張を優遇する。
そしてこの構造的腐敗の最も有害な側面は、それが不可視であることだ。科学は依然として、客観的で、証拠に基づき、自己修正的で、方法論的で、信頼できるものとして提示される。この神話は、メディア、教育システム、科学コミュニケーターによって永続化される。
しかし神話は神話のままだ。この文書の膨大な証拠の積み重ねは、別の現実を示している―
現代科学は資金に依存している。科学者は何を研究すべきかを選択する自由を失っている。彼らは、資金提供者が支援する意思のあるものを研究しなければならない。
現代科学は過度に競争的だ。「出版か消滅か」の圧力は、質よりも量を、慎重さよりもスピードを優遇する。
現代科学は利益相反に満ちている。個人的レベルでも制度的レベルでも。そして最も危険なことに、これらの利益相反は認識されていないか過小評価されている。
現代科学は保守的だ。ピアレビューは、革新を促進するよりも正統性を強制する。
現代科学は不透明だ。データは共有されない。方法は完全には記述されない。対立する見解は関与せず、むしろ無視されるか抑圧される。
知識の未来―開放性か権威主義か
最後に、私はこの文書をより広い文脈に位置づける。バウアーが記述しているのは、知識生産の危機だ。そしてこの危機は科学に限定されない。
ジャーナリズムも同様の危機に直面している。主要メディアへの信頼は低下している。「フェイクニュース」という告発が飛び交う。客観的真理の共有された概念が崩壊しているように見える。
学術界も危機に直面している。人文科学は「再現性の危機」に直面している。社会科学は政治化の告発に直面している。学術自由は「キャンセルカルチャー」によって脅かされている。
そして民主主義そのものが危機に直面している。専門家への信頼の喪失は、ポピュリズムの台頭につながる。しかし、盲目的な専門家への服従は、テクノクラート的権威主義につながる。
バウアーのサイエンスコートの提案は、この広範な危機への一つの可能な対応だ。それは、開放性と説明責任を通じた正当性のモデルだ。専門家は権威を持つが、その権威は挑戦されなければならない。コンセンサスは尊重されるが、盲目的に従われてはならない。不確実性は認められ、隠されてはならない。
これは簡単な道ではない。それは不快だ。それは対立的だ。それは時間がかかる。しかしそれは、私たちが持っている唯一の道かもしれない―もし私たちが、専門知識への信頼と民主的統制の両方を維持したいのであれば。
この文書の最も深い洞察は、おそらくこれだ―真理は権威から生まれるのではなく、対話から生まれる。そして今、その対話が失われている。主流は異端と話さない。正統は異議と議論しない。コンセンサスは懐疑を抑圧する。
サイエンスコートは、その対話を復活させる試みだ。それが成功するかどうかは、私たちが真理を権威よりも愛するかどうかにかかっている。そしてそれは、科学だけの問題ではない。それは文明の問題だ。