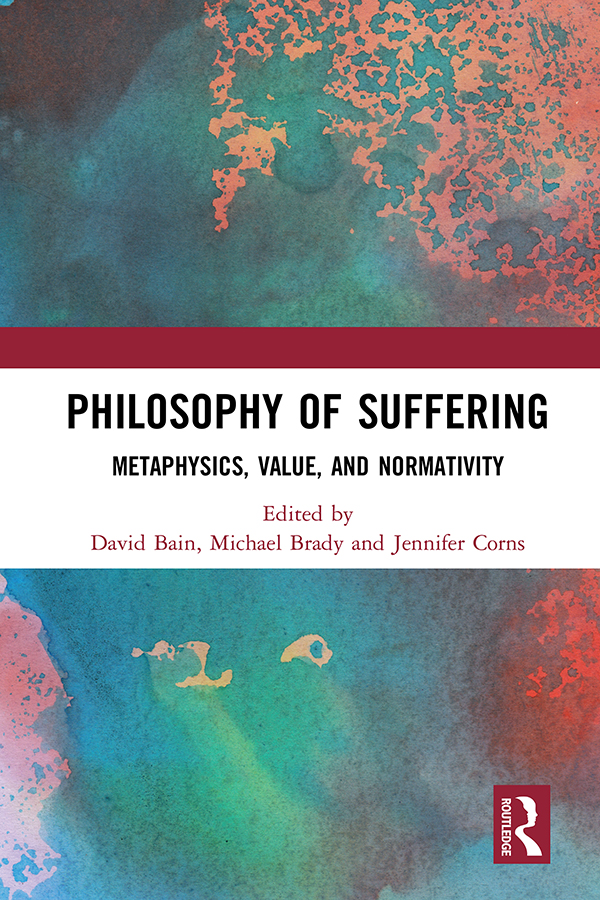
苦しみの哲学
苦しみは、私たちの生活の中心的な要素である。私たちは痛みに苦しむ。私たちは病気になる。私たちは失敗し、失敗させられる。私たちの愛する人が死ぬ。苦しみは、常に、どこでも、悪いものだと考えるのが普通である。しかし、苦しみは良いものでもあるのではなかろうかか?もしそうなら、苦しみはどのような点で肯定的な価値を持ち、また否定的な価値を持つのだろうか。
この重要な一冊は、これらの問いを検証し、哲学的観点から苦しみを初めて包括的に検討したものである。国際的に著名な寄稿者が、苦しみ、痛み、価値の本質、そして苦しみの価値、苦しみと道徳、合理性との関係を探求している。
苦悩の哲学。本書は、心の哲学、心理学の哲学、認知・行動心理学の学生や研究者、そして苦しみや痛みに関する概念的問題を研究する健康・医療関係者にとって、必読の書である。
デイヴィッド・ベインは、英国グラスゴー大学の哲学科教授である。
Michael Brady(マイケル・ブレイディ) 英国グラスゴー大学哲学科教授。
ジェニファー・コーンズ (Jennifer Corns) 英国グラスゴー大学哲学科講師。
苦悩の哲学
形而上学、価値、規範性
デイヴィッド・ベイン、マイケル・ブレイディ、ジェニファー・コーンズ
2020年初版
目次
- 図版リスト
- 寄稿者リスト
- 謝辞
- はじめに
- 第1部 苦しみの本質
- 1 苦しみに応じた世界
- 2 苦しみの崩壊モデル
- 3 痛み、苦しみ、そして意識
- 4 苦しみの痛み
- 第2部 痛みと価値
- 5 価値、身体的(非)快楽、そして感情
- 6 痛みと単なる味覚。価値ある知覚体験の態度表象理論に向けて
- 7 痛み 2つの頭を持つ態度
- 第3部 苦痛の価値
- 8 変容する経験としての苦しみ
- 9 動機づけの快楽主義を終えて 悪いと感じることは良いことであり、良いと感じることは悪いことである。
- 10 苦しみから満足へ。なぜ喜びを感じるために痛みが必要なのか
- 11 「馬も豚も、そしてみんなも変わってしまったようだ」。うつ病の回復における美の評価
- 第4部 苦しみの規範性
- 12 ヘドニックな合理性
- 13 理性の苦悩 苦しみと人間の合理性との間の不安定な結合
- 14 苦痛が合理的機関にもたらすいくつかのパラドックス
- 美徳としての苦悩
- 索引
- 図版
- 図4.1 苦痛と苦悩:3つの下位概念
- 表4.1 痛みと苦しみの4つの違い
寄稿者
マリリン・マッコード・アダムスは、2017年に亡くなった時点で哲学・神学の教授であり、エピスコパル司祭であった。UCLA、イェール、オックスフォードなど多くの大学で教鞭をとり、女性でアメリカ人として初めて神学部のレジアス教授に就任した。オックスフォードでは、クライスト・チャーチ大聖堂のカノンも務めた。彼女の専門は中世神学と哲学神学であり、特に悪の問題に関するブレイクスルー研究で有名である。5冊のモノグラフ、100以上の雑誌記事、百科事典の項目を出版した。
グラスゴー大学哲学科教授。彼の研究の中心は痛みと感情であり、苦しみと感情への関心が高まっている。マイケル・ブレイディ教授と共同で、疼痛プロジェクト(2012~2013)および苦痛の価値プロジェクト(2013~2016)の主任研究員を務めている。痛み、感情、色、ウィトゲンシュタインの私語論(www.davidbain.org)についての論文を発表している。
ブロック・バスチャンは、メルボルン大学心理科学部の准教授である。社会心理学者としての訓練を受け、倫理と幸福のテーマを幅広く研究している。2007年に博士課程を修了して以来、100以上の査読付き学術論文や本の章を発表しており、その中には人気科学書『The Other Side of Happiness』も含まれている。
ハギット・ベンバジ:ネゲヴ・ベングリオン大学哲学科准教授。痛み、感情、行為と因果関係、心身問題、色彩と色彩知覚、認識論、トーマス・リードの哲学、許しと寛容について発表している。
Michael Brady スコットランド、グラスゴー大学哲学科教授。感情の哲学、およびその道徳哲学や認識論との関連性を中心に研究している。2013年、著書『Emotional Insight』がオックスフォード大学出版局から刊行された。テンプルトンが資金提供するValue of Sufferingプロジェクトの共同研究者であり、その成果であるSuffering and Virtueは、2018年にオックスフォード大学出版局から出版された。彼の入門的な教科書Emotion: The Basics』も出版された。学外では、マンチェスターの劇団「Quarantine」の哲学者レジデンスを務めている。
ハヴィ・カレルは、ブリストル大学の哲学教授。ウェルカム・トラストの上級研究員で、Life of Breathプロジェクト(2014-2020; www.lifeofbreath.org)を主導し、Health Humanities’ Inspiration Award 2018を受賞している。著書に『病いの現象学』(2016)、『病い』(2008、現在第3版、ウェルカム・トラスト・ブック賞の最終候補)、『フロイトとハイデガーにおける生と死』(2006)がある。2016年の「ベスト・オブ・ブリストル」講師として学生から投票された。これまでAHRC、英国アカデミー、レヴァーハルム・トラストから助成金を得ていた(www.bristol.ac.uk/school-of-arts/people/havi-h-carel/index.html)。
Jonathan Cohen カリフォルニア大学サンディエゴ校の哲学教授、学際的認知科学プログラムの教員。カリフォルニア大学サンディエゴ校に来る前は、ブリティッシュ・コロンビア大学でキラム博士研究員として哲学を研究していた。ラトガース大学で哲学の博士号を取得。知覚の哲学(特に色彩と知覚様式内および様式間の相互作用)および言語の哲学(特に文脈感受性と意味論/語用論のインターフェースに関する問題)の分野で幅広く論文を発表している。著書に『The Red and the Real: An Essay on Color Ontology』 (OUP 2009)、共編著に『Color Ontology and Color Science』 (Mohan Matthenとの共著、MIT Press、2010)、『Contemporary Debates in the Philosophy of Mind』 (Brian McLaughlinとの共著、Wiley-Blackwell 2007)などがある。
サム・コールマンは、ハートフォードシャー大学の哲学科教授であり、主に心の哲学に関するさまざまな論文を執筆している。現在の研究は、心は意識の中で明らかにされるが、それにもかかわらず、精神活動の大部分は意識の外で進行しているという見方を探るものである。この理論は、オックスフォード大学出版局から近刊予定の『ダーク・マインド』で詳しく紹介されている。
ジェニファー・コーンズはグラスゴー大学哲学科の講師。研究テーマは、痛み、苦しみ、感情、死。Routledge社から出版予定の単行本「The Complex Reality of Pain」は、現代哲学、科学研究、臨床報告を用いて、痛みは実在するが、科学的一般化の対象として適切ではなく、医療介入の対象としても適切ではないことを論じるものである。哲学的手法と実証的研究の評価を用いて、学問の内外を問わず重要なテーマを前進させることを目指している。
Matthew Fulkerson:米国カリフォルニア大学サンディエゴ校哲学部准教授。触覚と触覚の探求に焦点を当てた研究を行っている。特に、身体意識と世界体験の関係や、触覚が他の感覚とどのようにつながり、相互作用しているかを理解することに関心がある。最近では、感情と知覚の関係を探求し、感覚状態の動機づけや感覚の喜びと苦痛に関する論文も執筆している。著書に『The First Sense: A Philosophical Study of Human Touch (MIT Press, 2014)がある。
Hilla Jacobson イスラエルのエルサレム・ヘブライ大学で哲学と認知科学の准教授を務める。彼女の研究は、意識、知覚、欲望、痛み、影響に焦点を当てている。彼女の研究の多くは、哲学的な関心事が心理学や認知神経科学の経験的研究と重なり、それを利用するところにある。現在、知覚の価値に関する一般的な理論を構築中。
アンッティ・カウピネン:ヘルシンキ大学実践哲学教授。幸福感、有意味性、道徳的感情、実践的合理性、規範性の本質に焦点を当てた研究を行っている。Methodology and Moral Philosophy (Routledge, 2019)の共同編集者 (Jussi Suikkanenと)、フィンランドアカデミー研究プロジェクトResponsible Beliefsの主席研究員である。Why Ethics and Epistemology Need Each Other (2019-2023)を担当。
イアン・ジェームズ・キッド (Ian James Kidd)は、ノッティンガム大学哲学科の助教授である。研究テーマは、病気の哲学、現象学、ヘルスケアのフェミニスト哲学など。共同編集者(ホセ・メディナ、ガイル・ポールハウス・ジュニアと)The Routledge Handbook to Epistemic Injustice(2017)、編集中(ヘザー・バタリ、クアシム・カサムと)Vice Epistemology(2020)。彼のウェブサイトはwww.ianjameskidd.weebly.com。
コリン・ウェイン・リーチは、アイデンティティ、感情、動機づけにおける地位と道徳を研究する社会・人格心理学者である。コロンビア大学では、バーナード・カレッジの心理学およびアフリカ研究の教授であると同時に、芸術科学部心理学科の上級研究員および大学院教員でもある。100近い学術論文や本の章を執筆しているほか、Psychology as Politics (Political Psychology, 2001), Immigrant Life in the US (Routledge, 2003), The Social Life of Emotions (Cambridge, 2004), Societal Change (Journal of Social & Political Psychology, 2013)を共編している。
オリヴィエ・マッサンは、ヌーシャテル大学哲学研究所の哲学教授。エクス・マルセイユ大学とジュネーブ大学で哲学の博士号を2つ取得。ジャン・ニコ研究所(パリ)の研究員、チューリッヒ大学哲学科の教授を歴任。これまで、「力とは何か?混合物とは何か?経済的交換とは何か?所有とは何か?継続性とは何か?快楽とは何か?苦しみとは?苦痛とは何か?欲望とは何か?決定可能性とは?試行とは?努力とは?触覚とは何か?
トム・マクレランドはウォーリック大学の研究員であり、レヴァーハルム・アーリーキャリア・フェローシップを授与されている。彼のプロジェクトMental Action and Cognitive Phenomenologyは、私たちがどのような精神的行動を選択するのか、また精神的行動の経験はどのようなものなのかを探求している。また、意識の問題、内観、知覚の内容、自己など、心の哲学のさまざまなトピックを研究している。また、美学にも手を染めており、映画の哲学に関する著書もある。
テイジア・スクラットンはリーズ大学の哲学・宗教学の准教授で、宗教哲学、精神医学の哲学、感情の哲学に関心を持っている。現在の研究の多くは、精神疾患(精神医学ではこう呼ばれる)に対する宗教的、霊的、医学的、その他の解釈について、その解釈が人々の経験をどのように形成するかを検証するものである。
ファブリス・テローニ:ジュネーブ大学哲学科准教授、スイス感情科学センター (CISA)プロジェクトリーダー。心の哲学と認識論を研究している。専門は、記憶、知覚、感情状態の哲学。感情の一般理論 (The Emotions: A Philosophical Introduction, Routledge)、恥 (In Defense of Shame: The Faces of an Emotion, Oxford University Press)、記憶に関する論文やモノグラフを多数発表している。
謝辞
本書は、ジョン・テンプルトン財団の助成による学際的かつ国際的な研究プロジェクト「苦しみの価値プロジェクト」から生まれたものである。その中心的なチームである主任研究員のデイヴィッド・ベインとマイケル・ブレイディ、博士研究員(現講師)のジェニファー・コーンズ、博士課程学生のアブラハム・サピエン・コルドバは、全員グラスゴー大学の哲学者であった。より広範なチーム(オーストラリア、フランス、ノルウェー、米国、英国に所在)は、心の哲学と認知科学、神学、神経科学、心理学、臨床の専門知識を備えていた。2013年9月から2016年6月にかけて、プロジェクトは6つのワークショップと3つのカンファレンスを開催し、そこから本巻への多くの寄稿が派生した。私たちは、本巻が研究のテーマとしての苦しみの豊かさを示し、この分野におけるさらなる研究の刺激となることを願っている。
序文
デイヴィッド・ベイン、マイケル・ブレイディ、ジェニファー・コーンズ
本書は、苦しみの性質と価値についての一冊である。苦しみは、すべての人間の生活の中心的な部分である。幸運にも戦争、飢餓、貧困、抑圧の惨禍から逃れることができたとしても、私たちの人生には様々な種類の苦しみが大きく関わっている。このように考えると、哲学、心理学、神経科学などの中核的な学問分野の研究者が、苦しみについてほとんど真剣に考察してこなかったことは驚くべきことである。これらの分野の研究者がこの問題を考えている限り、彼らはしばしば苦しみに関する問題を無視してきた。痛み(他の種類の身体的苦痛はやや除外されている)や、罪悪感、恥、悲しみなどの否定的な感情についてはかなりの研究がなされているが、最も一般的な疑問についてはほとんど扱われていない。これらの否定的な状態には何が共通しているのだろうか?これらの否定的な状態は、感情的あるいは快楽的な次元、つまり不快であることとどのように関係しているのだろうか。これらの様々な状態は、いつ、何のために、苦しみに関わるのか、あるいはそれ自体が苦しみの一種なのか。そして、苦しみの役割、目的、あるいは価値とは何なのだろうか。これらの問いはすべて無視されてきた。
少なくとも、最近まではそうであった。ここ数年、さまざまな分野の研究者が、負の感情や苦しみについて体系的な問いを投げかけ、その対象を広げ始めているからだ。心理学や神経科学の分野では、痛みのような比較的よく知られた現象と、価値、好感、動機といった重要だがより専門的な概念との関係に興味を持つ研究者が出てきている。また、哲学からの関心もある。痛みの哲学を専門とする研究者たちは、他の否定的な感情体験から痛みについて何がわかるか、痛みの研究における理論的発展が感情的な苦痛の本質をどのように照らし出すかを研究し始めている。感情哲学や神学に携わる人々は、苦しみの価値やその目的・機能についての疑問をますます深めている。近年、ポジティブ心理学の動きが、苦しみには教育的価値があるという考えとともに花開いた。同時に、レジリエンスやグリットなど、苦しみに対処するために重要な特性についても、ポピュラーサイエンスで注目されるようになってきた。
本書は、このような苦しみに対する知的転回の一翼を担っている。本書は、 (I)苦しみの本質、 (II)痛みと価の本質、 (III)苦しみの価値、 (IV)苦しみと他の規範的概念、という4つのパートで、苦しみに関する4つの中核的問題を扱うことを目的としている。以下、各章の中心的な問題について、理論的な概要を説明し、各章の概要を説明する。このようにして、私たちの生活の極めて重要な側面を特徴づける中心的な疑問と理論的な選択肢を明確にしたいと思う。
第1部 苦しみの本質
苦しみとは何だろうか。苦しみの理論は、この質問に答えることを目的としている。しかし、苦しみの理論を構築することは、言うは易く行うは難しである。ひとつには、感覚、知覚、思考、評価、欲望、身体的変化、そして-ある人は最も重要だと言うだろう-否定的な影響など、実にさまざまなものが苦しみに関与する可能性があるからだ。人が苦しむとき、これらはどのように関わっているのだろうか。これらは互いにどのように関係しているのだろうか。苦しみが何であるかを構成するものとして、1つを、あるいはおそらくいくつかのものを特定することができるだろうか。もうひとつ、苦しみにはさまざまな種類があるようだ。例えば、肉体的な苦しみと感情的な苦しみを区別することができる。しかし、それぞれのカテゴリーの中にも、かなりの多様性がある。そして、その多様な状態や体験は、どのように苦しみに関係するのだろうか。一つの考え方は、例えば痛みや悲しみは、単に苦しみの特定の種類、つまり属の種であるとするものである。しかし、これは正しいのだろうか。例えば、痛みが苦痛になりうる、あるいは苦痛に関与しうるとしても、それ自体が苦痛の一種なのだろうか。このような疑問に答えるのが、苦悩の理論の目的である。苦しみの複雑な性質を考えると、ここには多種多様な理論的選択肢があり、このセクションの各章は、将来の理論的進歩への刺激となることが期待されるだろう。
第1部の第1章はアンティ・カウピネンによるものである。彼は「苦しみに応じた世界」(第1章)において、苦しみの本質に関する斬新な理論的説明を展開し、苦しみがわれわれの世界を変容させる上で果たす役割を強調する。カウピネンはまず、例えば愛する人を失ったことによる苦しみと、肉体的な激痛による苦しみとは、まったく異なるものであることを指摘する。このことは、両者がともに苦しみの体験であるのはなぜか、という次の問いを提起する。カウピネンは、単に体験の不快さだけではないと主張する。しかし、ブレイディの最近の提案とは逆に、不快な体験をしたくないと願う事実もまた苦痛であるとする。しかし、私たちが負に苦しむことで、私たちの状況全体の見え方が変容することを主張したい。そのために、彼は否定的感情解釈という概念を導入している。この概念には、自分の状況が変化を求めていると実際に認識し、この認識を変化を求める気持ちと結びつけ、その変化は自分の力では無理だと考えることが含まれる。否定的な感情解釈が蔓延していると、不安の場合のように可能性の大部分を色づけしてしまうため、あるいは悲しみの場合のように痛いところに目をつぶってしまうため、私たちは(態度的に)苦しむことになる。この見解では、感覚的あるいは身体的な苦しみは、態度的な苦しみの特別なケースであり、痛みの不快さがネガティブな感情解釈を広範に引き起こす。私たちの世界を否定的に変容させない痛みは、苦しみにはならない。
カウピネンの説明の中心となるのは、felt aversion (強い嫌悪感条:仏語)という概念である。彼の考えでは、felt aversion は、被験者が自分の状況を実際的にどう解釈しているかを記録し、彼が感情的解釈と呼ぶものの一部である。このような解釈には、行動への誘いや余裕の知覚が含まれる。人は感情的に自分の状況を実際的な用語で考え、同時に何かをする動機付けを感じる。カウピネンは、態度的苦悩とは、被験者が自分の状況を否定的に解釈することが広く浸透していることであると主張する。そして、感覚的な苦しみは、態度的な苦しみの特殊なケースに過ぎず、感覚的な入力の苦痛によって引き起こされるものである、と主張する。つまり、苦しむとは、自分の状況を十分に広範に否定的に解釈し、それに対して嫌悪感や態度的不快感を感じることなのである。
第2章「苦しみの崩壊モデル」において、トム・マクレランドは、ある精神状態(痛み、悲しみ、罪悪感など)に苦しむことは、その状態があなたの広い精神生活を崩壊させることになるという、異なる説明を明確にしている。たとえば、激しい痛みは、苦痛、痛みに対する不安、痛みと緩和の見込みの両方についての熟考を引き起こし、その結果、通常の生活を送ることができなくなるかもしれない。また、悲しみは、怒りや恐れといった感情を生み、根強い信念や願望を修正することを必要とし、不可解さを残すような質問を投げかけるかもしれない。マクレランドは、これこそが「苦しみ」だと考えている。したがって、痛みとその本質的な不快さ(もしあるとすれば)だけでは不十分であり、同じように不快な痛みを持つ二人の人間が、異なる程度で苦しむかもしれない。
マクレランドは、この崩壊モデルが、例えば、愛の感情が精神経済を崩壊させても苦しむ必要がないという事実によって損なわれないようにするために、微調整が必要であると認めている(それゆえ、マクレランドは、愛の感情が精神経済を崩壊させても苦しむ必要がないことを明記している)。(それゆえ、マクレランドは、苦しみを構成する破壊は「全体的に不快」でなければならないと明記している)。混乱は展開するのに時間がかかるので、私たちが単なる一瞬の苦しみを受けることができない理由(痛みとは対照的)を説明し、私たちの苦しみは悩まされることで成り立っているので、私たちが苦しみに悩まされることがない理由を説明し(これも痛みとは対照的)、苦しみの多様なケースが、ある経験的共通性、すなわち不快な「心の衝撃」の経験を共有しながら、現象的に全く異なるかもしれないということが、どうして説明できるのかを論じている。
マクレランドが正しいとすれば、苦しみと主体性の間にも意外で重要な関係があることになる。破壊的な状態の精神的影響 (例えば、自分の痛みについて反芻すること)の一部は、自分に起こることではなく、自分が行うことなので、苦しみは部分的に主体的である、とマクレランドは主張する。これは、単に苦しまないことを決めればいいということなのだろうか。そうではなく、苦しみに関わる精神的な行動は強力な衝動に対する反応であり、それゆえ完全に自発的とは言えないからだ。(衝動に抵抗しようとすることは可能であるが、その抵抗自体が破壊的であることはマクレランドも認めている)。衝動は私たちに何をするよう促すのだろうか?「困難な」精神状態を同化させ、精神の恒常性あるいは平衡を回復させるような精神作用 (例えば、出席、評価、反射など)を行うことである。これが苦悩の役割だとマクレランドは主張し、私たちの中には、その均衡を達成することに他の人よりも長けている人がいると考えている。私たちの中には、他の人よりも優れた苦行者がいる。
第3章、サム・コールマンによる「痛覚、苦痛、意識」は、身体的苦痛、痛覚(苦痛特有の不快感として理解される)、そして苦痛という三つの事柄についての幅広い探究である。コールマンは、これらは確かに3つの異なる現象であると主張する。痛くない身体的な痛み(「感覚性」あるいは「S-pain」)は存在するのだから。そして、痛みや辛さとは異なり、苦しみは「特定の身体的な場所を持つものとして現れない」(後述の第4章も参照)。
しかし、ある状態を痛み、苦痛、あるいは苦しみの状態とするのは何だろうか。いずれの場合にも、コールマンは現象学を援用する。ある状態を苦痛とするのは、その「苦痛」な質的性格、つまりクオリアであると彼は主張する。この質的特性によって、私たちは自分が痛みを感じているかどうか、どのような種類の痛みであるかを内省的に知ることができる、と彼は主張する。コールマンは、内観からの並列的な議論によって、痛覚について同じ結論が得られると続ける。ある状態を苦痛にするのは、その質的な性格でもある。このとき、「異質性の問題」の一種が生じる。内観は間違いなく、私たちが痛みを伴う苦痛の中にいるときはいつでも存在する「一つの感情」を明らかにしない。しかし、コールマンは、イントロスペクションが一つの確定的なクオールを明らかにしない一方で、一つの確定的なクオールを明らかにする可能性は十分にあると答えている。要するに、痛みと辛さは質的な問題なのである。しかし、それらの相互の関係はどうなっているのだろうか。コールマンの答えは、痛覚は「二部的な自己表出状態の一つの構成要素として」痛みを伴う苦痛に内在するというものである。
苦しみに目を向けると、コールマンはこれもまた現象学に根ざしていると主張する。というのも、私たちは、苦しんでいる状態が苦しみを伴うからやめてほしいと思うのであって、その逆ではないからだ。そして彼は、苦しみは自分の精神経済の「全体として不快な」混乱から成るというマクレランドの考え(上述)が、それ自身の灯火によって破綻していると考えている。というのも、マクレランドは、そのような混乱が起こっているかのように「全体的な不快」を経験していれば、その混乱が現実であろうとなかろうと、あなたは苦しんでいることになると認めなければならないとコールマンは示唆しているからだ。しかしコールマンは、苦しみと「全体的な不快」を単純に同定することに抵抗し、その代わりに、苦しみは「何らかの、あるいは他の不快な一次特性をインスタンス化する」という「高次」の特性であると主張することによって、苦しんでいる状態の不快さと苦しみそのものとの間の密接な関係をとらえようとする。
痛み、辛さ、苦しみは確かに質的な事柄であるが、質的性格-「主観的意識」の不在-は意識を伴わない。それゆえ、無意識の痛み、無意識の辛い痛み、そして無意識の苦しみさえあるかもしれない、というのが彼の印象的な主張で締めくくられている。鎮痛催眠は、被験者が痛みを訴えるのを止めるが、血圧と心拍数は上昇したままであるため、そのような事例を提供するかもしれないと彼は考えている。
第1部の最終章はオリヴィエ・マッサンによるものである。「苦しみ」(第4章)は、痛みと苦しみの間の多くの区別と関係を明らかにし、これらのものが位置づけられる概念的空間を明らかにすることを目的としている。そうすることで、マッサンは、苦しみとは何かについて独自の理論的見解を展開し、このことが痛みについての理論化にとってどのような意味を持つかを見ている。マッサンはまず、痛みと苦しみは一般に非常によく似た現象であると考えられていることを指摘する。このことが、心の哲学が前者に焦点を当てる傾向がある理由を説明しているのかもしれない。しかし、マッサンは、痛みと苦しみは全く別のものであると主張する。1)痛みと苦しみは同一ではない、(2)痛みは苦しみの種ではなく、苦しみは痛みの種でもなく、痛みと苦しみは共通の(近接した)属である、(3)苦しみは痛みの悪さの知覚として定義することはできないし、苦しみは苦しんだ身体感覚としても定義できない、という3つの異なるテーゼに基づいて、この主張がなされている。これがマッサンの章の最初の4つのセクションを占めている。この章の残りの部分について、マッサンは次の三つの積極的な主張を行う。(4) 痛みと苦しみは、痛みとは局所的な身体的エピソードであり、苦しみとは非局所的な感情的態度であるというように、分類上区別される。(5)苦しみは表現できるが、痛みは表現できない。その結果、私たちは他人の苦しみに対して同情することはできるが、その人の痛みに対して同情することはできない。(6)痛みと苦しみの関係は、危険と恐怖、不正と憤り、悪事と罪悪感の関係に似ている。
次にマッサンは、彼の議論が痛みの哲学において有力な2つの見解を弱めるものであると主張する。第一は、痛みの経験は不可逆的であるというもので、痛みがあるように見えるということは、痛みがあるということを意味するという考え方である。この考え方は非常に大きな影響力を持っているが、マッサンは、この章の結果として、それが誤りであることを論じている。第二は、痛みは身体にあり、それゆえ客観的であると同時に、精神的であり、それゆえ身体にはないという理由で、痛みに関するわれわれの通常の概念は「逆説的」であるということである。マッサンは、痛みは身体の状態であり、人はそれを経験し、苦しむことによって反応するのだと理解すれば、このパラドックスは解消されると論じている。
第2部 痛みと価値観
苦しみの理解を深める方法の一つは、苦しみそのものに焦点を当てることだ。苦しみの構成要素は何か、苦しみの事例にはどんな共通点があるか、民間や他の学問分野は苦しみについてどう考えているか、その概念は歴史を通じてどのように私たちに伝わってきたか、などである。もう一つのアプローチとして、密接に関連する概念を理解し、そこから苦しみについて何が学べるかを考えてみるという方法がある。第1部の最終章ではこのようなアプローチを取った。第2部の各章では、苦しみと密接に関連する重要な現象について新しい説明を提案し、それを擁護することによって、このプロジェクトを進めている。その一つは、これまで見てきたように、痛みであり、ここでの更なる理論的進歩は、確かに苦しみとは何かということに光を当てることが期待される。そしてもうひとつは「価値」、つまり精神状態や経験を否定的か肯定的かに分類することだ。苦しみについて最も一般的に言えることは、苦しみは(その利点のすべてにおいて)ある意味で否定的であるということであるから、価値観は苦しみを理解する上で極めて重要である。それ自体はあまり有益ではないにせよ、それは真実のようだ。より良い理解のために必要なのは、価値とは何かについての説明である。しかし、この概念に関する説明の対立があるため、状況は複雑である。ある人は、快感や不快感といった感情や快楽の次元で価値を理解し、別の人は、例えば接近行動と回避行動の区別といった動機の次元で価値を理解し、さらに別の人は、それは特別に一般的なカテゴリーで、これらの他の要素に還元することはできないと考える。真実と思われるのは、苦痛と価値とは何かについてよりよく理解することが、われわれの目標とする苦痛の概念を理解するのに役立つということである。
第2部の第1章「価性、身体的(不)快楽、感情」(第5章)で、ファブリス・テローニは価性の性質と他の感情要素との関係を調査している。ヴァレンスは、快楽状態、気分、感情、情緒など、多くの状態の特性である。これらはすべて、肯定的か否定的かのどちらかで記述することができる。テロニは、価は感情状態の特徴であり、信念や記憶のような状態とは異なると考えている。このことは、価値観の本質についていくつかの問題を提起している。まず、価値とは何なのか。そして、「感情領域」の構造について、価は何を語ることができるのだろうか。テロニは、この問いに対する自然で一般的な答えである「中核的感情」アプローチを検証し、それがいかに価値、身体的(不)快楽、感情の間の関係について特定の見解を生み出し、支持しているかを示す。この見解は、彼が説明優先と封じ込めと呼ぶ2つのテーゼによって捉えられている。テロニが本章で取り組む中心的な課題は、これらの主張の見通しを評価することである。説明優先論によれば、身体的(不)快楽の価値観は、感情の価値観に対して説明的に先行する。つまり、快楽や不快といった快楽的な状態の肯定性や否定性に訴えることで、何が感情を肯定的・否定的にしているのかを説明できる。封じ込めテーゼによれば、感情は身体的な(不)快楽を含んでいる。したがって、封じ込め論は、なぜ(不)快感の価数が説明的に優先されるのかをきちんと説明している。
コア・アフェクトのアプローチを検討した後、テロニは身体的(不)快楽と感情の内部構造を詳細に検討する。彼は、身体的快楽は意図的な状態であり、その価は評価的経験によって理解されると主張し、それは自動的に、ほとんどの場合、サブパーソナルレベルで行われるとしている。この見解では、身体的(不)快楽と感情の価は同じであり、どちらもある対象の価値を知覚的に経験する問題であることが判明した。このように、快楽と感情の意図的な構造について説明することで、テロニは、説明優先も封じ込めも採用すべきではないと結論づける理由を示している。
第2部の他の2つの章は、次の意味での価値、すなわち経験の快・不快に焦点を合わせている。痛みと単なる味覚:価値ある知覚経験の態度表象理論に向けて」(第6章)において、ヒラ・ヤコブソンは痛みの不快感を、他の知覚経験の価値に関する議論を通じて、間接的に取り上げている。ヤコブソンは、痛みの不快感を十分に説明するには、他の知覚経験の価値観にまで踏み込まなければならないと主張する。例えば、ダイナにとってナスの味は快であるが、ダンにとっては不快である可能性や、ダイナにとってナスは他の文脈では不快であったが、今は快になっている可能性などである。このような「弁別の多様性」を受け入れるために、痛みの不快さに関するどのような理論が拡張されうるのだろうか。
ジェイコブソンは、評価論と彼女自身の態度表象理論 (ART)の2つを考えている。これらは、あなたの痛み体験がある身体的状態の知覚的表象であることには同意するが、その価数については異なる。評価論は、あなたの痛みの不快さは、身体的状態をあなたにとって悪いものとして表象することにあると主張し、ARTは、表象された状態に向けられた否定的観念や欲求に似た態度を痛みが伴うことにあると主張する(モデル:あなたの痛みは身体状態を表象している。(評価主義が正しければ、ある痛みの不快感は真偽のどちらかになるが、ARTが正しければ、それは真偽のどちらにもならない(ヤコブソンのように、観念的態度は真偽を認めないと仮定して)。この違いが、ジェイコブソンがARTを支持する論拠となっている。
評価主義やARTを味覚体験に拡張するにはどうしたらよいだろうか。ヤコブソンは、評価主義では、快・不快体験は、味わったものの与えられた特徴を、それぞれ良・悪として表現しているとする。また、ARTは、快・不快体験が、それぞれ、与えられた特徴に対する正または負の欲望的態度に関係するとする。したがって、この拡張評価主義の提唱者は、ARTが避けて通ることのできない難問に答えなければならない。誰のナスの経験が正確か。ダンナの体験か、ダンの体験か?
もし、ナスが良いものでも悪いものでもないと考えるなら、評価主義者は「両方だ」と答えることはできない。また、ジェイコブソンは、ナスは関連する価値特性を完全に欠いていると主張し、それに基づいて「どちらでもない」と答えることもできないと主張している。なぜなら、そうすると、われわれの味覚体験がありえないほど不正確であることを約束させられるからだ。その代わりに、「ディナだけ」あるいは「ダンだけ」と答えることはできないだろうか。ジェイコブソンは、これらの回答のいずれかを選択するのであれば、その選択の根拠が必要であり、どのような根拠があり得るかは極めて不明確だと考えている。このとき、評価論者は、最初に戻って、ナスは、関連する意味で、良いものにも悪いものにもなりうる、と主張するかもしれない。しかし、このような相対化の動きもまた、困難をもたらすとジェイコブソンは主張する。つまり、味覚の場合はARTを優先し、痛みの場合もARTを優先すべきであると結論付けている。
ヤコブソンが評価主義とARTを対比させるのに対して、ハギット・ベンバジによる第7章「痛み:二つの頭を持つ態度」は、この二つの立場には致命的な問題があることを主張する。手に不快な痛み(以下、「痛み」)を感じたとする。ARTも評価主義も、この痛みは、手の中の何かを変えるべき理由であると同時に、痛み止めを飲むなどして痛みそのものをなくすべき理由であると主張する。評価主義では、痛みは手の状態を自分にとって悪いものであると表し、その結果、手の状態を変える理由と、不快であるがゆえに(同じ評価的内容によって)それ自体が自分にとって悪いものとなり、痛みそのものをなくす理由の両方を与えてくれるというのである。同様に、ARTによれば、あなたの痛みには、あなたの手がそのような状態であってはならないという主観的に欲求不満な態度が含まれており、その態度は、あなたに手の状態を変える理由と、-欲求不満な状態は「主観的に欲求不満」である-痛みそのものをなくす理由を与えることになる。しかし、ベンバジは、この共有された図式は支離滅裂であると主張する。なぜなら、評価的経験であれ、欲求的状態であれ、何であれ、外界の何かを変える理由を与え、同時に、前の理由を排除する別の理由を与えることは、単一の状態にはできないからだと、彼女は主張する。彼女が言うように、「両方の理想を満たすことができる」状態は一つもない。なぜなら、自己指向的な理由に基づいて行動すれば、世界指向的な理由を排除することになるからである
弁財天は数々の反論を考えている。例えば、評価論者は、異なる種類の理由を区別し、あなたの痛みが手の状態を変える動機となる理由であるのに対し、痛みそのものをなくす正当な理由であることを主張すれば、彼らの絵は意味をなすと抗議するかもしれない。ART理論家の側では、世界を変える理由を与えるもの(欲求的態度)と、痛みそのものをなくす理由を与えるもの(その態度の主観的欲求不満)を区別しようとするかもしれない。しかし、どちらの回答も、彼女の「矛盾する理由」論争の背後にある深い心配に十分に応えていないと、ベンバジは主張する。それゆえ彼女は、実際、あなたの痛みはそれ自体をなくす理由を与え、その目的のためにのみ、外界を変える理由を与えると結論づける。このことは、痛みが完全に外界を欠いているとする従来の見解への扉を開くものである。
第3部 苦しみの価値
本書の最初の2つのパートは、苦しみの本質に関する問題を扱っている。どの理論的アプローチが最も妥当か、関連する概念がわれわれの中心的概念をよりよく理解するためにどのように役立つか、などである。最後の2つのパートは、規範的な問題への転換を意味している。このセクションでは、苦しみの価値に関する疑問、つまり苦しみがもたらす利益や、苦しみがもたらす条件について見ていくる。苦しみが重要な価値を持ちうることは、一般的な考え方においても、学術的な研究や考察においても、説得力があるが、しばしば無視される。しかし、間違いなく苦しみは本当に価値があるものなのである。痛みを感じられない人は一般的に若くして死ぬが、それはまさに肉体的な痛みが、身体的な損傷や脅威をわれわれに警告し、適切な行動的反応を動機付けるという重要な実用的価値を持つからだ。悲しみは喪失に、失望は期待に、飢えは食べ物の不足に、羞恥心は社会的不名誉に、それぞれふさわしい、それゆえ(間違いなく)価値のある反応である。もし私たちがこのような対象や出来事に対して、適切な形で苦痛を感じなければ、何か重大な問題があり、不適切であることは間違いなかろうか。罪悪感や恥を感じないということは、サイコパスの良い証拠かもしれないし、悲しまないということは、深い愛情がないことを示唆している。これだけではない。ネガティブなものであるにもかかわらず、苦しみはしばしば喜びや楽しみのようなものに不可欠であったり、しばしば強化されたりする。例えば、喉が渇いたときに飲む冷たいビールや、凍えるような寒さの中で過ごす暖かい家の中が、どれだけ楽しいか。であるから、私たち自身の経験や、他の人の経験について考えてみると、苦しみには大きな価値があることが強く示唆される。本節の各章では、この一般論を検証し、苦しみの価値を様々な次元で考察している。
第3部の最初の章は、Havi CarelとIan James Kiddによる「変容的経験としての苦しみ」である(第8章)。カレルとキッドは、苦しみの経験の多くは、L.A.ポールの造語を使えば、変容的経験の一形態として照らし出すことができると提案している。ポールの説明によれば、ある種の体験は、その変容能力によって際立った存在となる。このような経験は、以前は利用できなかった、あるいはアクセスできなかった知識を提供する限りにおいて、認識論的に変容させることができる。同様に、そのような経験は、人の価値観や好み、ひいてはアイデンティティを本質的な意味で根本的に変えるという意味で、個人的に変容させるものである。つまり、変革とは単に情報や知識を得ることではなく、その人の価値観や興味を変え、人格やアイデンティティを変化させることなのである。カレルとキッドは、パウロが強調するこのような特徴を、多くの種類の苦しみ体験が共有していると主張する。特に、人間の状態に内在する脆弱性、依存性、苦悩から生じる苦しみ体験に注目している。これらの特徴は、肯定的、否定的、両価的に評価されるさまざまな形の、認識論的・個人的に変容する経験を生み出すことができる。
カレルとキッドが注目する苦悩の体験は、変容的体験の文献で主に議論されているタイプではない。ポールや他の研究者たちは、一般的に肯定的な経験、つまり、人々が選択する、または選択した経験に焦点を当てているが、カレルとキッドは、非自発的と非自発的と名付けた、選択されない変容的経験の2つのカテゴリーに焦点を当てている。彼らは、これらのタイプの苦痛を伴う体験は、他のものよりも潜在的に変容的であると主張している。このことを示すために、カレルとキッドは、否定的な価値付けをされた変容体験の分類法を開発した。彼らは、Michael Bradyの定義に従って、このような経験を苦痛とする3つの特徴、すなわち強度、新規性、注意の集中を提案している。最後に、彼らは、苦しみの教育的能力に関する一つの可能な説明は、それがポジティブな経験よりも多くの変容を必要とすることに由来することを示唆している。
第9章「動機づけの快楽主義以後:悪いと感じることは良いこと、良いと感じることは悪いこと」では、コリン・ウェイン・リーチが、多くの心理学者に、苦しみは価値あるもの、楽しい状態は有害であるという方法を見えなくさせていると主張する正統派に反論している。
快楽の機能は「有利な状態」を知らせ、それを長引かせる動機付けとなる。不快な状態の機能は「不利な状態」を知らせ、それを避ける動機付けとなる。人間は「快楽に近づき、苦痛を避けたい」(これはリーチのタイトルの「動機付け快楽主義」である)。快楽の状態は幸福と適切な機能を示すが、不快な状態はわれわれにとって悪く、不適応である。この正統派は、快・不快状態の性質、重要性、動機づけのプロファイルに対するわれわれの概念を歪めているとリーチは主張する。
リーチは、不快な状態のうち、恥と怒りに着目している。心理学者は、恥を、自己破壊的な行動として「内面化」されるか、スケープゴートに対する敵意として「外面化」される、私たちにとって悪いものと考える傾向があると、彼は主張している。そして、恥は、肯定的な行動や「接近」行動よりも、それが警告するどんな「不利な」状況でも回避する、回避的な行動を動機付けると考えがちである。しかし、リーチは、正統派から生じるこの図式は不正確であると論じている。なぜなら、恥の原因となっている個人的な失敗が修復可能であると信じる対象においては、恥は実際、回避(「逃げる」「隠れる」「消えたい」)ではなく、積極的な行動、しかも、自己破壊ではなく自己改善を目指した建設的な行動を動機付けることができるとリーチは主張する。つまり、恥は私たちにとって良いものであるだけでなく、その動機づけのプロファイルは、正統派が私たちに信じさせるよりも、より肯定的(「嫌悪」については少ない)、建設的、かつ文脈依存的であるとLeachは結論付けている。Leachは怒りについても同様の指摘をしている。そして、怒りの原因となっている不正に対処できると信じている人の場合、怒りは、とりわけ返還を目的とした建設的な行動を動機付けることができると主張している。
ブロック・バスチャンは、「苦しみから満足へ:喜びを感じるためになぜ痛みが必要なのか」(第10章)でも、心理学の研究をもとに、苦しみは喜び、満足、意味の体験に強力に寄与し、必要条件でさえあると論じている。
彼はまず、二つの観察から始める。例えば、軽い不快感と激しい苦しみ、そして肉体的な苦痛と「社会的」な苦しみなど、広義には苦しみの状態を峻別する傾向があるが、根本的な心理的・生物学的メカニズムから見れば、そこには連続性がある(と彼は主張している)。また、私たちはネガティブな体験とポジティブな体験を峻別し、前者の害に焦点を当て、それを楽しんでいると報告する人を異常者と見なす。その結果、激しい苦しみでさえも、意味、共同体、幸福、喜びといった経験の「構成要素」として日常的に存在することを見逃しがちになると、バスティアンは主張する。
バスティアンは、苦しみが喜びや私たちの生活をより広く高めることができる様々な方法について詳述している。例えば、私たちの適応能力は、冷たい水の中に入って不快な思いをしない限り、熱い温泉に入る喜びが薄れることを意味する、と彼は主張する。不快な体験は、相手の処理のおかげで、単に不快な体験を取り除くだけでなく、「オピオイドのオーバーシュート」と快感、つまりランナーの高揚感をもたらすのだ、と彼は付け加えている。さらに、快感の強い出来事と苦痛の強い出来事は相互に依存しあっているため、それを記憶し、意味のあるものとして評価する傾向が強いと主張する。そして、鎮痛剤で痛みを麻痺させるとき、それによって快感も麻痺してしまうことを示唆する証拠を示している。
快楽から、苦しみが私たちの生活を向上させる他の方法に目を向けると、バスティアンは、痛みが罪悪感を軽減し、他の不快な感情、特に怒りなどのアプローチに関連する感情を軽減することができるという証拠を示している。さらに、バスティアンは 2001年9月11日のテロ攻撃(これはボランティア活動の急増をもたらした)のアメリカ人の経験から、集団での唐辛子の消費に至るまで、苦しみを共有することによって集団の連帯、信頼、協力、支援、創造性が高まると主張している。それゆえ、ある研究では、苦痛を伴う刺激に条件付けられたラットは「学習性無力感」を減少させ、また別の研究では、生涯を通じて中程度の逆境にある人間が氷水に手を浸すと、より幸福で痛みが少なくなると報告された。
バスティアンは、苦しみを増やすことを推奨しているわけではない。そして、自分の資源や能力を与えられた要求と同等に考え、その要求を脅威(コルチゾール放出)ではなく、課題(アドレナリン放出を引き起こす)として経験する傾向があるかどうかという個人差の重要性に注意している。彼はまた、苦痛を生み出すには、より害の少ない方法があるとし、自傷行為をする人は、代わりに激しい運動で苦痛を求めることで利益を得られるかもしれないと示唆する。しかし、彼が重要視しているのは、たとえそれが可能だとしても、人間の苦痛を完全に排除することは、われわれの幸福を促進するどころか、むしろ損なわせてしまうかもしれないということだ。
Tasia Scruttonの「”My horses and hogs and even everybody seemed changed”: appreciating beauty in depression RECOVERy」(第11章)は、苦しみがいかに重要な美的価値を持ち、美に対する経験を高めることができるかに焦点を当てている。苦しみは、少なくともその苦しみを生き抜き、そこから回復すれば、その人にとってプラスになると長い間考えられてきた。スクラットンは、うつ病やメランコリーなどの精神的苦痛に関する「意味づけ」の文献や説明のほとんどが、精神的苦痛の後に、同情、信頼や愛の増大、創造性、本当に価値のあるものへの理解といった道徳的特性が発達することを指摘している(苦痛が個人的に変化し啓発する方法については本編第8章を参照されたい)。苦しみを経験し、生き抜いた人は、その結果、より思いやり、信頼、希望、自己中心的でない、道徳的に優れた人間になる。しかし、Scruttonは、精神的苦痛の説明におけるもう一つの、あまり理論化されていないテーマが、道徳的な発達から美的なものへと焦点を移していることを指摘している。スクラットンは、精神的な苦しみを経験した人は、苦しみの経験中もその後も、美、特に自然言語の美に対する評価が高まることが多いと論じている。
この考えを検証するために、スクラットンは、多くの資料から、うつ病やメランコリーからの回復に関する記述に焦点を当てている。その中には、出版された自伝もあれば、ウィリアム・ジェイムズが論じた記録から得たものもある。第三の重要な資料は、アリスター・ハーディー・センター・フォー・レリジャーズ・エクスペリエンスのアーカイブからの報告書のコレクションである。これらの報告の多くは宗教的なものであり、スピリチュアリティと自然の美しさとの間に関連性があるかもしれないが、スクラットンは、うつ病やメランコリーにおける苦しみがどのように美に対する評価を高め、その結果、苦しみがいかに患者にとって価値あるものとなるかという、より一般的な問題に焦点をあてている。
第4部 苦しみの規範性
第3部の各章では、さまざまな方法で、苦しみと価値との関係に焦点を当てた。しかし、苦しみは他の規範的な領域、特に道徳や合理性とも関係がある。前者については、ある種の宗教的伝統(キリスト教、イスラム教、仏教)において、苦しみが道徳的行為や道徳的美徳の中心になりうるということが定番となっている。例えば、悪の問題に対する「徳の解決策」を考えてみよう。そこでは、意味のある選択のために必要であるという理由で、苦しみが仮に正当化され、これに基づく道徳的・精神的発展が行われる。あるいは、コーランや聖書に顕著な、苦しみが正当な罰であるために社会的な美徳を促進する、あるいは信仰の試練であるために神への信頼と献身を強化する、という考え方を考えてみてほしい。さらに、悲しみや恥といったある種の苦しみは、道徳的な発達や優れた道徳的性格を持つことの中心的な要素となっている。後者については、合理的な反射や問題解決のための私たちの能力、私たちの人生の意味や意味を理解する能力を、間違いなく強化することができるが、妨げにもなる。例えば、自責の念が私たちに謝罪と賠償の動機を与え、それによって社会集団への復帰を容易にするような場合である。多くの場合、これは、自分にとって何が最善であるかという意識的かつ合理的な考察とは相反する形で行われる。このセクションの各章はすべて、さまざまな形で、苦しみ、道徳的行為、合理性の間の関連に焦点を当てている。
第12章「ヘドニックな合理性」において、ジェニファー・コーンズは、われわれの精神状態の快・不快は「理由対応的」であると論じている。私たちは、信じること、行動すること、さらにはある種の感情を抱くことのみならず、「快・不快を感じる」ことにも理由を持ちうると、彼女は主張する。この論文を支持するために、彼女はグレンダという被験者が悲嘆に暮れるケースを説明する。グレンダの悲嘆状態(知覚、感情、思考、想像)が不快であることは合理的であると言うのはごく自然なことであるとコーンズは主張する。そして、他の場合には、被験者の状態の不快さは不合理であり、理解不能であるとさえ言うのが極めて自然であると、彼女は主張する。
しかし、コーンズの主張は、何を言うのが自然であるかということにのみ基づいているわけではない。彼女は、理性対応の重要な「指標」が、精神状態の「快・不快」(hedonics)に適用されると主張する。例えば、われわれは自分の精神状態が不快であることを支持する理由や、不快さが自分の他の状態と一致する方法について尋ね、時にはそれを見つけることができる、と彼女は主張する。さらに、彼女の結論に対する最も脅威的な反論にも対抗することができる、と彼女は主張する。例えば、理性に反応する状態は自発的でなければならないとか、内容を持たなければならないとか、目的を持たなければならないとか、非認知的でなければならないとかいう反論もあるだろう。しかし、いずれの場合も、コーンズは、快と不快によってその要件が実際に満たされるか、あるいは、その要件を放棄すべきかのいずれかを主張する。例えば、ある自発性の概念では、不快は非自発的であり、理性反応のまさにパラダイムである信念もそうである。しかし、自発性を合理性の観点から説明する別の概念では、信念は結局自発的とみなされるが、(コーンズの議論では)不快もまたそうである。
最後に、コーンズは自分の見解の潜在的含意を述べている。彼女の論文は、ある種の精神状態の不快な次元は、われわれが考えがちな以上に「合理的な介入」の影響を受けやすいことを示唆しているのかもしれない、と彼女は言う。また、理性に応じるものと応じないものとの間の区別そのものを放棄すべきことを示唆しているのかもしれない、と彼女は付け加えている。
第Ⅳ部の第2章でも合理性が扱われているが、全く別の角度からだ。「理性の苦悩」(第13章)において、マシュー・フルカーソンとジョナサン・コーエンは、「苦悩の状態」がわれわれの理性的生活の中で独特の位置を占めていると論じている。一方では、それらは合理的に動機づけを行う。他方で、それらは理性に反応するものではなく、「われわれの広範な理性的関心事」に対して明確に抵抗するものである。その結果、苦悩の状態が私たちの実践的な熟考において中心的な役割を果たす一方で、それらの状態の私たちの精神生活における統合は、独特に制限されると著者らは主張する。彼らは(そうでないにもかかわらず)「非合理的な、外部の影響」のように見えることがある。
これを説明するために、フルカーソンとコーエンは、ビーチとワクチン接種という二つのケースを対比させている。ビーチでは、リラックスして仕事の締め切りに間に合わせたい、ワクチン接種では、健康でいたい、痛い注射を避けたい、という欲望が競合している。どちらのケースでも、あなたは熟考の末、前者の欲求に基づく行動をとることを決定し、それゆえ、ビーチに行き、予防接種を受ける。しかし、フルカーソンとコーエンは、重要な違いがあると主張する。どちらの場合も、拒否された欲求は拒否された行為を行うプロタントな理由であり続け、どちらの場合も何らかの動機づけの「引力」を発揮し続けるかもしれないが、その引力は少なくともビーチではあなたの決断によって弱められるのに対し、ワクチン接種ではそのような弱まりはない。針が腕に触れたとき、あなたの抗痛欲求は「合理的熟慮がその仕事を終えた後でも。…..支配力を発揮し続ける」のである。とにかく予防接種を受けるかもしれないが、それは痛みと「戦い抜いた」後でなければならない。
このような苦痛の「粘着性」は、アクラジアや非意図的行動といった、より身近な現象に還元することはできないと著者らは主張している。ワクチン接種では、自分の良識に反して抗痛み欲求に「屈服」するのではなく、「抗戦」するのだという。そして、仮に反痛み欲求のままに行動したとしても、予防接種から遠ざかることは「痛みによる反射」ではない。なぜなら、苦しみが「強いる」のは動作ではなく、行動するための決断だからだ。つまり、苦しみの粘着性は実在する、とフルカーソンとコーエンは結論付けている。しかも、それは説明的である。というのも、この粘着性は、慢性疼痛が誘発するうつ病などの「二次的な苦しみ」に寄与しているからである、と彼らは指摘する。この図式では、慢性的な痛みを持つ人は、痛みが何の役にも立たず、動機づけもしないはずなのに、痛みがあるために、思考に入り込み、行動を妨げている。(このあたりは、本編第2章 (McClelland著)との関連もある)。
第14章「合理的行為に対する痛みの逆説」では、マリリン・マッコード・アダムスが、痛みは道徳的行為や意味づけに必要だが、同時にその両方を混乱させるという考え方の間の緊張を考察している。彼女の考えでは、痛みのシステムは生物学的なレベルでは両義的なものである。痛みは、認知的、動機づけ的、教育的な重要な役割を担っており、痛みを直接体験することは、他者への共感的関与、そこから生まれる道徳的配慮や主体性の中心をなすものである。道徳的な能力は、他人の痛みや苦しみに敏感で、共感することを必要とする。同時に、最悪の痛みや苦しみは圧倒的で、私たちが道徳的、あるいは理性的な主体として機能する能力を完全に損なわせてしまう。その一方で、痛みや苦しみは意味づけをする上で重要であり、創造的な問題解決につながる「筋書きの複雑化」であり、人の良さを引き出してくれるものでもある。私たちは、痛みや苦しみを経験し、それを乗り越えた人を、より興味深く、より賞賛すべき存在と感じる。同時に、痛みや苦しみは、自分の人生に意味や意義を見出そうとする試みを狂わせる。社会的に疎外され、トラウマの源となり、前向きな意味を破壊するものである。つまり、痛みや苦しみは、意味づけの中心でありながら、それを崩壊させる恐れがある。
そして、アダムスは伝統的なキリスト教の立場から、これらのパラドックスを検証する。神は、私たちが苦しむことがどのようなことか、そしてそれがどれほど悪いことなのかを理解することができるだろうか。神は圧倒的な痛みや苦しみを経験することができるのだろうか?リンダ・ザジェブスキーは、神が被造物のいずれでもないことを自覚しながら、被造物がそれぞれどのような経験をしているかを知っているという神の「全知全能性」に訴えて、このパズルを解決しようと試みていると紹介する。アダムスは、このことが、神を苦痛のパラドックスを解決する立場に置くと考えるが、悪の問題に関しては、懸念を表明している。しかし、悪の問題に関しては、神が私たちの経験する痛みや苦しみを補償する能力を持っていることを想起すれば、これらの問題は解決されるかもしれない。同様に、痛みや苦しみが私たちの意味づけの能力を破壊することを認めながら、神が私たちの痛みや苦しみを肯定的に理解できるように創造したという考え方も問題であると思われる。しかし、ここでもまた、神は、子なる神という人物を通して、苦しみが生み出す絶望に連帯して答えていると見ることができるかもしれない。このことは、人間の苦しみに、その人間にとって肯定的な意味を与える働きをすることができる。その結果、伝統的キリスト教の神は、少なくともある程度までは、痛みのパラドックスから逃れることを助けてくれる。
本巻の最終章では、苦しみと道徳的性格の関係に焦点が当てられている。美徳としての苦しみ」(第15章)において、マイケル・ブレイディは、苦しみそれ自体が本質的に価値あるものでありうることを提唱している。特に彼は、苦しみの経験は高潔な動機となり得ると主張し、また、苦しみに対する気質は、われわれの肉体的・感情的システムの美徳となり得ると述べている。痛みや自責の念といったものが、身体的損傷や道徳的不義といった価値なきものに対する適切な反応であり、それらに効果的に対処することを可能にすることを考えれば、苦しみの形態が美徳となりうるという考えは、あまり奇異に映らないはずだと、彼は主張している。ブレイディは、リンダ・ザジェブスキーの徳に関する説明(これによれば、徳は、ある目的を達成するために確実に成功する感情的動機付けの要素を含む)を借りて、苦しみを徳とする説明を具体化している。痛みや自責の念といったものの中心にある否定的な感情は、明確な動機づけの価値を持っている。そして、適切な状況下で適切な程度にこうしたものを感じる性質があれば、主体は身体を保護し、適切な賠償を行うことに確実に成功することができる。
また、「苦しみ」は本質的に悪いものであり、「徳のある動機」は本質的に良いものであるから、「徳のある動機」になり得ないというものである。これらの反論に対処するため、ブレイディは、肉体的苦痛の形態が(特質ではなく)能力的美徳となりうること、そして、トマス・ハーカの価値の「再帰的」説明に従って、それが悪いものを嫌う、あるいは反対するという形態である限り、本質的価値として数えられるという考えを打ち出す。
