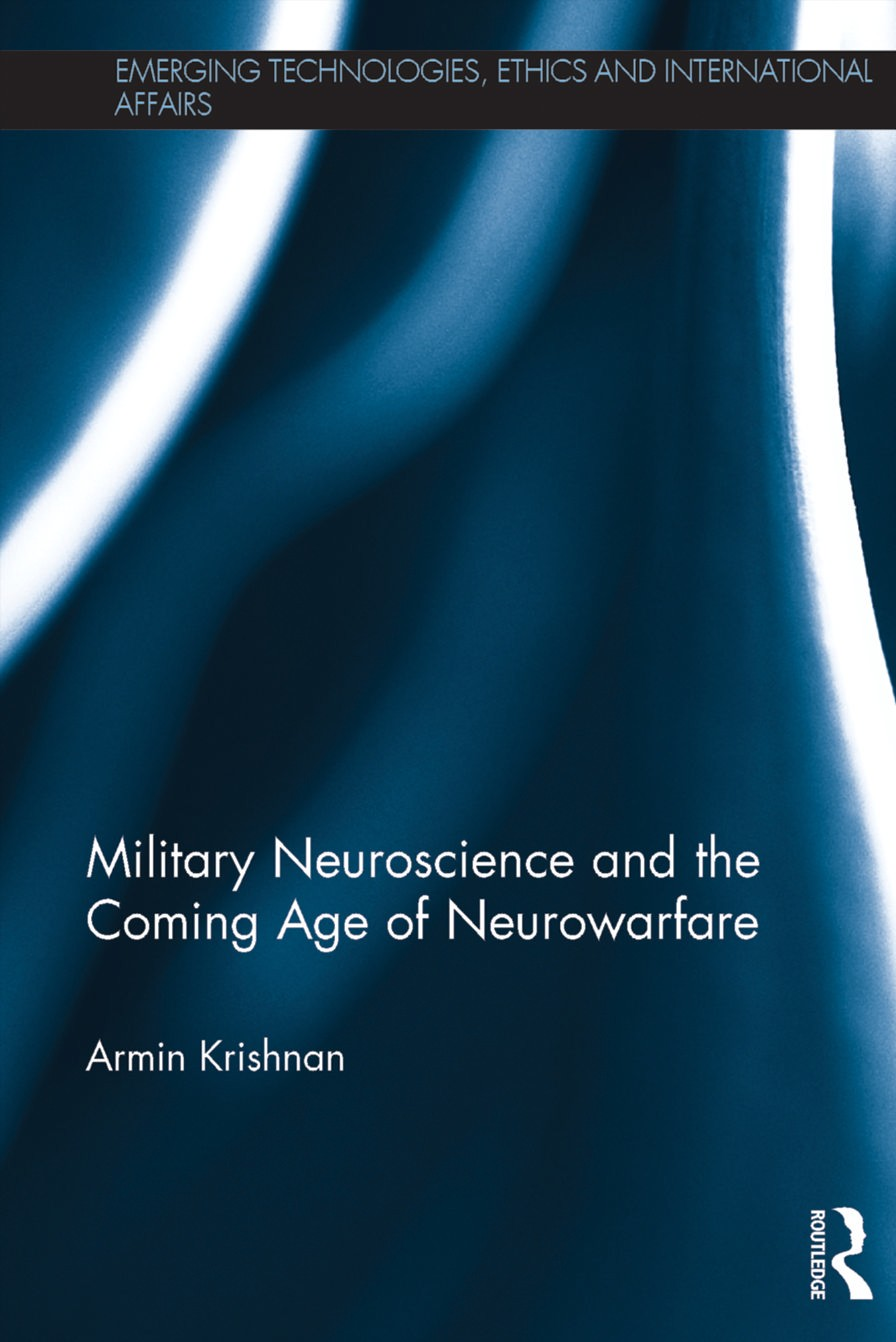
英語タイトル:『Military Neuroscience and the Coming Age of Neurowarfare』(Armin Krishnan, 2017)
日本語タイトル:『軍事神経科学と来たるべきニューロ戦争の時代』(アルミン・クリシュナン, 2017)
目次
- 第1章 序章 / Introduction
- 第2章 冷戦期の脳研究と細菌戦 / Cold War brain research and germ warfare
- 第3章 神経科学的エンハンスメント / Neuroscientific enhancement
- 第4章 知能と予測 / Intelligence and prediction
- 第5章 機能低下技術 I:薬剤と微生物 / The degradation technologies I:Drugs and bugs
- 第6章 機能低下技術 II:電波とバイト / The degradation technologies II:Waves and bytes
- 第7章 戦略的文脈 / The strategic context
- 第8章 ニューロ戦争 / Neurowarfare
- 第9章 危険性と解決策 / Dangers and solutions
本書の概要
短い解説:
本書は、急速に進展する神経科学と神経技術の軍事応用が、21世紀の戦争の様相をどのように変革しうるかを包括的に分析することを目的としている。対象読者は、国際関係、安全保障、軍事技術、科学技術倫理に関心を持つ研究者、政策関係者、一般読者である。
著者について:
アルミン・クリシュナンは、安全保障、軍事技術、インテリジェンス研究を専門とする研究者である。冷戦期の「マインド・コントロール」研究から現代のDARPA(国防高等研究計画局)のプロジェクトまで、軍と情報機関による脳と神経系への介入の歴史と展望を、戦略的・倫理的観点から批判的に追跡している。本書では、神経技術が「非致死的」戦争の手段として台頭する可能性と、それが「思考の自由」に及ぼす前例のない脅威という両義性を中心に論じている。
テーマ解説
- 主要テーマ:ニューロ戦争 / 神経科学を利用した戦争の新たな領域(ドメイン)の出現と、それが従来の心理戦(PSYOPS)とサイバー戦をどのように強化・変容させるかを探る。
- 新規性:非致死的戦略の中心化 / 21世紀半ばまでに、敵の身体を破壊するのではなく、その認知・意思決定能力を低下・操作する「非致死的」戦略が戦争の中心になる可能性を提示する。
- 興味深い知見:思考の自由の終焉? / 神経技術の進歩により、外部から個人の思考や意思を精密に操作・読取ることが可能になる「脳の兵器化」が、基本的な人間性と自由への究極の脅威となる危険性を指摘する。
キーワード解説
- 軍事神経科学:脳と神経系の機能に関する科学的知見を、軍事的優位性の獲得のために応用する研究分野。兵士の能力強化から敵の無力化までを含む。
- 非致死性兵器:敵を殺傷せずに無力化したり、行動を制御したりすることを目的とする兵器。本書では神経系に作用する薬剤、電磁波、情報技術などを含む。
- 心理戦:敵の士気、意見、感情、行動に影響を与えることを目的とした作戦。ニューロ技術はこれをより直接的に、個人レベルで実行可能にする。
- 脳-コンピュータ間インターフェース:脳の活動をコンピュータと直接接続する技術。兵器の制御や兵士間のサイレント通信への応用が検討されている。
- 神経倫理:神経技術の開発・応用に伴って生じる倫理的、法的、社会的問題を扱う分野。特に軍事利用における「自由意志」や「精神的不可侵性」の侵害が焦点となる。
3分要約
本書は、神経科学の急速な発展が、戦争の性質そのものを変革しつつある「ニューロ戦争」の時代の到来を論じる。その核心は、敵の身体を破壊するのではなく、その認知能力や意思決定を操作・無力化する「非致死的」技術と戦略が戦場の中心に躍り出る可能性である。
この展望は二つの側面を持つ。一方で、戦争の流血性を減らす人道的機会を提供するかもしれない。他方で、個人の思考や意志を外部から精密に操作する技術は、「思考の自由」という人間の根幹を脅かす前例のない危険性をはらんでいる。
著者はまず、冷戦期のCIAによるMK ULTRAプログラムなどの「マインド・コントロール」研究の歴史を振り返り、国家が人間の精神を兵器として利用しようとする欲望の系譜を描く。現代では、この欲望は「軍事神経科学」という新たな学問領域に結実し、脳科学の知見を武器開発や兵士強化に応用する研究が、米国防総省(DoD)のDARPAなどを中心に活発に進められている。
この研究は大きく二つの方向性を持つ。一つは「神経科学的エンハンスメント」であり、薬物や脳刺激、脳-マシンインターフェースを用いて味方兵士の認知能力、持久力、チームワークを飛躍的に高めようとする試みである。もう一つは「機能低下技術」であり、敵の神経系を標的とした薬物(カームアティブなど)、生物学的製剤、指向性エネルギー(電磁波、音波)、サイバー攻撃によって、敵兵士や大衆の意識・行動を制御・混乱させる技術である。
これらの技術の発展は、より広い戦略的文脈の中で理解されなければならない。著者は、対反乱戦や非対称戦争の増加、市民の保護が重視される戦場環境、情報戦の重要性の高まりが、「非致死的」ニューロ技術への軍事的ニーズを駆動していると分析する。
最終的にこれらの要素は「ニューロ戦争」という新たな戦争領域の形成につながる。ニューロ戦争は、物理的、情報的、認知的な領域を横断し、敵の意思決定プロセスそのものを直接攻撃する。その究極の形は、個人や集団の脳活動を監視・解読し、さらに外部から刺激を与えて思考や感情、行動を操作する「神経系中心戦」である。
しかし、この未来は深刻な倫理的・法的・社会的危険に満ちている。神経プライバシーの侵害、洗脳の復活、新たな神経兵器の拡散と軍備競争、非人道的な「思考犯罪」の取締まりの可能性などである。
著者は結論として、この危険な進路を回避するためには、技術開発に対する厳格な倫理的ガイドラインの確立、神経兵器の使用や開発を禁止する新たな国際法の策定、そして一般市民における議論と監視の必要性を強く訴えている。
各章の要約
第1章 序章
本書は、神経科学と神経技術の軍事応用が、戦争と法執行の遂行において持つ破壊的潜在性を探求する。著者は、ジョナサン・モレノやジェームズ・ジョルダノなどの先駆的研究を発展させ、利用可能な神経技術と将来の応用可能性をレビューするだけでなく、これらの技術の軍事的追求が全体の戦略的文脈にどのように位置づくかを論じる。中心的な主張は、非致死的戦略と戦術が21世紀前半の戦争の中心となる可能性があり、それが戦争の流血性を減らす人道的機会をもたらす一方で、思考の自由を保全する上で前例のない脅威と危険を生み出すという点にある。本書は、将来の「ニューロ戦争」の姿と、その可能性と本質的限界の両方を描き出すことを目指す。
第2章 冷戦期の脳研究と細菌戦
本章では、米国(CIA)とソ連が冷戦期に行った「マインド・コントロール」研究の歴史を詳細に検証する。特に、CIAのMK ULTRAプログラムとその関連プロジェクトに焦点を当て、薬物(LSDなど)、催眠、感覚遮断、電気ショックなど多様な手法を用いて、被験者の意志に反して情報を引き出したり、行動をプログラムしたりする技術の開発を試みた経締を追う。これらの研究は、多くの場合倫理的ガイドラインを無視し、被験者に深刻な害を与えた。同時に、ソ連も同様の研究を行っていたとされる。著者はこう述べる。「冷戦中のマインドコントロール研究は、人間の精神を兵器として扱うことの倫理的限界を無視した、科学的探求と国家的パラノイアが交差した暗黒の章であった。」この歴史は、現代の軍事神経科学研究の前史であり、国家が神経系を操作しようとする継続的な欲望を示している。
第3章 神経科学的エンハンスメント
本章では、味方の軍事能力を高めるための神経科学的アプローチを概観する。その中心は、兵士の認知機能(注意力、記憶力、判断力)、身体的持久力、感情的制御、チーム間の協調を強化する「エンハンスメント」である。具体的には、覚醒剤や「スマート・ドラッグ」などの薬理学的介入、脳に微弱電流を流す経頭蓋直流電流刺激(tDCS)などの神経刺激技術、脳波で機械を直接制御する脳-コンピュータインターフェース(BCI)、さらには脳と脳を直接接続するブレイン・トゥ・ブレイン・インターフェース(BBI)の可能性まで議論される。これらの技術は、疲労知覚の軽減、学習速度の向上、意思決定の最適化、サイレント通信の実現など、戦場での優位性を劇的に高める可能性を秘める。しかし、長期的な健康影響、兵士への強制の倫理、エンハンスメントされた「超兵士」と通常兵士の間の格差などの重大な問題も提起する。
第4章 知能と予測
本章では、神経科学が情報収集(インテリジェンス)と脅威予測の分野にどのように応用されつつあるかを探る。主な応用例は二つある。第一は、「脳による嘘発見」技術である。従来のポリグラフに代わるものとして、機能磁気共鳴画像法(fMRI)や脳波(EEG)を用いて、被験者の脳活動パターンから虚偽や隠された情報(「犯罪知識」)を検出しようとする研究が進められている。第二は、神経画像や生体信号を用いた「危険人物」や異常行動の予測である。空港のセキュリティなどで、個人の脳活動や生理的反応を監視し、テロリストなどの脅威を事前に識別するシステムの可能性が模索されている。これらの技術は、尋問やセキュリティ・スクリーニングを革新する可能性があるが、その精度と信頼性には未だ疑問が残り、思想や内面の自由な活動までが監視対象となる「予防的監視社会」への道を開く危険性をはらんでいる。
第5章 機能低下技術 I:薬剤と微生物
本章では、敵の戦闘能力や意思を低下させることを目的とした、薬物および生物学的製剤に基づく神経技術を論じる。その代表例が「カームアティブ」である。これは、不安を軽減し鎮静を誘発する薬剤(例:強力なベンゾジアゼピン)を、拡散可能な形で敵集団に投与し、集団的無力化や混乱を引き起こす非致死性化学兵器の一種である。また、特定の神経系に作用する生物学的毒素(例:ボツリヌス毒素)や、神経伝達を改変するように設計された生物製剤(「ニューロトロピック・バイオエージェント」)の可能性にも言及する。これらの技術は、人質救出作戦や暴動鎮圧などで、殺傷を最小限に抑えながら敵を無力化する手段として構想される。しかし、投与量の管理が難しく致死的となるリスク、予期せぬ長期の神経学的副作用、生物化学兵器禁止条約(CWC, BWC)との法的曖昧さ、そして非致死性兵器が戦争の敷居を低くする「利用の誘惑」など、重大な課題と危険を伴う。
第6章 機能低下技術 II:電波とバイト
本章では、電磁エネルギーおよび情報技術を用いた神経系攻撃の可能性を検討する。第一に、指向性エネルギー兵器、特に電磁波を用いるものが挙げられる。低周波電磁波(ELF/VLF)が脳機能に影響を与える可能性や、「マイクロ波聴覚効果」により頭内に音声を直接発生させられる技術が研究されてきた。高エネルギーのパルスマイクロ波は、一時的な認知障害(「ジッター」)を引き起こす可能性がある。第二に、超音波や可聾音を用いた音響兵器(LRADなど)は、痛みや不快感、混乱を引き起こす。第三に、サイバー空間を介した神経系攻撃である。将来、脳-コンピュータインターフェースが普及すれば、それをハッキングして感覚入力を書き換えたり、運動指令を乗っ取ったりする「ニューロサイバー攻撃」が現実味を帯びる。これらの技術は物理的痕跡を残さず、因果関係の立証が困難であるため、秘密工作や否定可能な攻撃に使用される危険性が高い。
第7章 戦略的文脈
本章では、軍事神経技術への投資を駆動しているより広範な戦略的・作戦的環境を分析する。著者は、従来の国家間の正規戦から、対反乱戦、テロ対策、ハイブリッド戦争といった「非対称」で「曖昧」な形態の紛争への移行が、非致死性で精密な効果が求められる神経技術への需要を高めていると論じる。現代の戦場では、民間人の死傷者を最小化することが戦略的・道義的要請となっており、神経技術はその要請に応える可能性を秘める。さらに、情報環境の重要性が増す中で、敵の認知や意思決定そのものを標的とする「認知領域」での優位性獲得が重要視されている。心理戦(PSYOPS)は、神経科学の知見を取り入れることで、従来のプロパガンダを超え、個人の感情や無意識のバイアスに直接アプローチする超精密な「ニューロPSYOPS」へと進化しうる。このような文脈において、神経技術は、紛争の「流血性」を減らす「人道的」手段として提示されながらも、実際には戦争をより頻発させ、内面への侵攻を常態化させる危険がある。
第8章 ニューロ戦争
本章では、前章までの技術的・戦略的要素を統合し、「ニューロ戦争」という新たな戦争領域の全体像を描き出す。ニューロ戦争は、物理的、情報的、認知的な領域を横断し、敵の意思決定システム(人間の脳から組織の意思決定プロセスまで)を直接標的とする。その作戦は、神経系の強化、神経系の監視・解読、神経系の操作・攻撃、神経系の防御という四つの主要な次元に分類できる。将来的には、脳活動をリアルタイムで監視・分析するネットワークと、電磁的・情報的手段による精密な神経操作を組み合わせた「神経系中心戦」が構想されうる。これは、敵の指揮官の判断を歪め、兵士の士気を喪失させ、一般市民の政府への信頼を蝕むことを可能にする。著者は、ニューロ戦争が「非致死的」であるという主張に警告を発する。神経系への攻撃は、目に見えない精神的トラウマや人格の変化という形で、殺傷以上に深く破壊的な被害をもたらす可能性があるからだ。
第9章 危険性と解決策
最終章では、軍事神経科学とニューロ戦争の到来がもたらす深刻な倫理的、法的、社会的危険性を詳細に論じ、それらに対処するための可能な解決策を探る。主な危険性として、(1)「神経プライバシー」や「精神的不可侵性」の侵害による自由意志とアイデンティティの危機、(2) 拡大する神経技術の差によって生じる社会的・軍事的格差(「神経分化」)、(3) 神経兵器の拡散と新たな軍備競争の勃発、(4) 独裁政権による国民の監視と思想統制の強化、などが挙げられる。解決策としては、神経技術研究に対する厳格な倫理審査の強化、軍事研究の透明性向上、神経兵器や特定の神経攻撃を禁止する新たな国際法(「神経兵器禁止条約」)の策定の必要性が論じられる。しかし、既存の軍縮枠組みの限界や、非致死性技術を規制する政治的意欲の低さが大きな障壁となる。著者は、最も重要なのは一般市民の意識と監視であり、神経技術が人類に奉仕するのか、それとも支配するのかという根本的な問いについて、広範な社会的議論を喚起する必要性を強調して本書を締めくくる。
続きのパスワード記載ページ(note.com)はこちら
注:noteの有料会員のみ閲覧できます。
メンバー特別記事
神経兵器化への道:国家はいかにして「思考の自由」を標的にするのか AI考察
by DeepSeek×Alzhacker
「非致死性」という誘惑と「精神の侵攻」という現実
まず、この本の核心から考えてみよう。アルミン・クリシュナンが描き出しているのは、単なる未来予測ではない。むしろ、現在進行形の「流れ」——神経科学の軍事転用が必然的に向かう先——を、冷戦期の歴史的連続性の中で描き出したものだ。
彼の主張の核は二層構造になっている。表層には「非致死性戦争による人道的機会」という魅力的な未来像がある。だが、その下層には「思考の自由の終焉」という、はるかに暗く、そして現実的な危険が横たわっている。
「非致死的戦略と戦術が21世紀前半の戦争の中心となる可能性があり、それが戦争の流血性を減らす人道的機会をもたらす一方で、思考の自由を保全する上で前例のない脅威と危険を生み出す」
この一節が本書全体のテーゼだ。だが、ここで立ち止まらなければならない。「非致死性」という言葉の持つ危険な曖昧さについてだ。
わたしたちはパンデミック政策を通じて、「公共の利益」や「安全保障」の名のもとに、個人の自律性と身体の不可侵性が如何に容易く侵されうるかを学んだ。ワクチンパスポート、移動制限、マスク義務——いずれも「致死性を減らす」という大義名分があった。クリシュナンが警告する「非致死性神経兵器」も、全く同じ論理で正当化される危険性が極めて高い。
「流血を減らす」という目的は、一見すると誰も反対できない人道主義だ。しかし、その手段が「敵兵士の意思決定能力を奪う」「集団を薬剤で無力化する」「脳波から感情や意図を読み取る」ことであるならば、これはもはや戦争の「人道的な進化」などではない。戦争の「質的変容」——人間の内面そのものへの侵攻——である。
冷戦期のMK ULTRAプログラムを振り返ってみよう。CIAはLSD、催眠、電気ショック、感覚遮断など、あらゆる手段を用いて「マインド・コントロール」技術の開発を試みた。公式には、このプログラムは「失敗」だったとされている。だが、本当にそうだろうか?
クリシュナンはこの歴史を「現代の軍事神経科学研究の前史」と位置づける。重要なのは、MK ULTRAが「科学的に失敗」したという事実そのものではなく、国家が「人間の精神を兵器として利用しようとする欲望」が一度も消えることなく、より洗練された形で継続しているという点だ。
当時と現在の決定的な違いは何か? それは「神経科学」という「科学的正当性」を装った新たな衣装をまとったことだ。MK ULTRA時代の粗雑な実験は、今やfMRI、EEG、tDCS、BCIといった「最先端神経技術」に取って代わられようとしている。手段は洗練されたが、目的——他者の精神への支配——は変わっていない。
ここで、わたし自身の経験に照らし合わせて考えてみる。パンデミック初期、わたしは「公衆衛生の専門家」の発表をほぼ無条件に信じていた。データと科学が全てを解決すると考えていた。しかし、時間が経つにつれ、「科学的コンセンサス」の名のもとに、異論が封殺され、不都合なデータが無視され、政策決定が「専門家」という新たな権威によって独占されていく過程を目の当たりにした。
軍事神経科学の分野でも、全く同じ構造が見えてこないだろうか? 「国家安全保障」という大義名分。「最先端科学」という権威。「非致死性」という道徳的高み。これらすべてが、神経兵器開発という本質的に危険な事業を、批判の埒外に置こうとしている。
クリシュナンが指摘するDARPA(国防高等研究計画局)の役割は極めて重要だ。DARPAはインターネットの原型(ARPANET)を生み出した組織として知られるが、その本質は「破壊的イノベーション」を軍事目的に収斂させる機関である。彼らが現在、脳-コンピュータインターフェース(BCI)や神経刺激技術に巨額の資金を投じているという事実は、これが単なる基礎研究ではなく、明確な軍事応用を前提とした開発であることを示している。
「兵士の認知機能(注意力、記憶力、判断力)、身体的持久力、感情的制御、チーム間の協調を強化する『エンハンスメント』」
この「味方の強化」という側面は、一見すると無害に見える。しかし、よく考えてみよう。戦場で兵士の「感情的制御」を外部から強化するとは、具体的に何を意味するのか? おそらく、恐怖やためらい、罪悪感といった「人間的な感情」を抑制することを意味するだろう。これは兵士を「より効率的な殺傷マシン」に変えることに他ならない。
しかも、この技術が「敵の感情操作」に転用されることは必然だ。もし味方兵士の恐怖を抑制できるなら、敵兵士に恐怖や混乱を誘発することも技術的に可能だろう。実際、第5章で論じられる「カームアティブ」(鎮静剤兵器)や、第6章の電磁波・音響兵器は、正にその方向性を示している。
ここで、著者が「機能低下技術」を2章に分けて詳細に論じている意図を考える。第5章「薬剤と微生物」と第6章「電波とバイト」——この区分け自体が重要だ。前者は比較的「伝統的」な化学・生物兵器の延長線上にあるが、後者は全く新しい次元の脅威を示唆している。
電磁波兵器、特に「マイクロ波聴覚効果」についての記述は注目に値する。低出力のマイクロ波パルスで、頭蓋内に直接「音声」を発生させることができるという技術だ。クリシュナンは、この技術が「秘密工作や否定可能な攻撃に使用される危険性が高い」と指摘する。
考えてみてほしい。物理的痕跡を残さず、被害者にだけ「頭の中の声」として聞こえる攻撃——これはもはやSFの領域ではない。実際、冷戦期から米ソ両国で研究が進められてきた歴史がある。そして、そのような技術が「テロリストの洗脳」や「敵指導部の混乱」といった目的で使用される可能性は、想像に難くない。
さらに恐ろしいのは、これが「個人」を特定して行える可能性だ。将来的に、個人の脳波パターン(脳の「指紋」のようなもの)を遠隔から検知し、それに合わせてカスタマイズされた電磁波パルスを送信する——そんな技術が開発されないと、誰が断言できるだろうか?
この点で、第4章「知能と予測」の議論は核心をついている。fMRIやEEGを用いた「脳による嘘発見」や「脅威人物の事前識別」システムは、単なる技術的進歩ではない。それは「予防的監視社会」への入り口だ。
パンデミック時の「接触確認アプリ」や「健康状態モニタリング」を思い出してほしい。当初は「感染拡大防止」という限定的な目的で導入されたが、そのインフラとデータは、容易に他の目的——行動監視、社会的信用スコアリング、思想傾向の分析——に転用されうる潜在性を秘めていた。
神経監視技術は、これをはるかに深化させる。身体の動きではなく、「思考」そのもの、あるいは思考の「傾向」や「潜在的可能性」を監視する社会。政府や企業が「この人物はテロリズムへの傾斜がある」「この人物は反政府的思考パターンを示している」と、脳活動データに基づいて判断する社会。
クリシュナンが「神経プライバシー」という概念を提起するのは、正にこの危険性に対してだ。従来のプライバシー論が「情報」や「通信」の秘匿性を扱うのに対し、「神経プライバシー」は「内面の自由な活動」そのものを保護の対象とする。これはプライバシー概念の根本的な拡張を要求する。
しかし、現実は逆方向に進んでいる。「国家安全保障」「テロ対策」「公共の安全」——これらの大義名分のもとで、神経監視技術の開発はむしろ促進されるだろう。空港のセキュリティで「脳波スキャナー」を通る日が来るかもしれない。就職や入学の際に「神経プロファイリング」を受けることが義務づけられる未来さえ、絵空事ではない。
ここで、著者の分析で特に優れている点は、技術的詳細に留まらず、第7章「戦略的文脈」でこれらの開発をより広い地政学的・軍事戦略的潮流の中に位置づけていることだ。
彼が指摘する「非対称戦争」の増加という文脈は重要だ。国家対国家の正規戦から、国家対非国家組織(テロリスト、反乱勢力)、さらには「ハイブリッド戦争」への移行は、従来の軍事ドクトリンを根本から変えつつある。
正規戦では、軍事力の優位性がほぼそのまま勝敗を決する。しかし、非対称戦争や対反乱戦では、状況は複雑だ。民間人の中に紛れ込んだ敵を識別し、「人々の心を勝ち取る」ことが重要になる。ここで、「非致死性」かつ「精密」な効果が求められる——神経技術は、この要求に「理想的」に応える可能性を秘めている。
敵兵士を殺す代わりに無力化する。反乱勢力の支持基盤となる民間人の「認知」を操作する。敵指導者の意思決定を歪める——これらは全て、従来の軍事力では困難だった領域だ。
しかし、この「非致死性」という特徴こそが、最大の倫理的危険をはらんでいる、とわたしは考え始めている。なぜなら、「致死性」はある種の歯止めとして機能するからだ。
核兵器が「使えない兵器」である理由は、その破壊力が大きすぎて、使用が自滅につながるからだ。同じように、通常兵器による大量殺戮も、国際世論や戦争犯罪としての非難を招き、使用に政治的コストが伴う。
しかし、「非致死性」神経兵器はどうか? 兵士を殺さず、一時的に無力化するだけなら、「人道主義的」とすら評価されるかもしれない。民間人に鎮静剤を散布して暴動を鎮圧しても、「流血を防いだ」と言い訳できる。敵国の指導者にストレスや判断力低下を引き起こす電磁波を照射しても、因果関係を立証するのはほぼ不可能だ。
つまり、「非致死性」であるがゆえに、これらの兵器は「使いやすい」——戦争の敷居を下げる可能性が高いのだ。クリシュナンが「利用の誘惑」と呼ぶのは、正にこの点だ。
さらに、これらの技術は「否定可能な攻撃」に最適である。サイバー攻撃と同様、攻撃元を特定するのが難しく、攻撃そのものの存在を否定できる。これは、国際法のグレーゾーン、あるいはその完全な外側で、新たな形態の戦争が行われることを意味する。
第8章「ニューロ戦争」で著者が描き出す「神経系中心戦」のビジョンは、この帰結を示している。これは単なる技術的進化ではない。戦争の「領域(ドメイン)」そのものの拡張だ。
従来、戦争は陸・海・空の物理的領域で行われ、近年はサイバー空間と宇宙が追加された。ニューロ戦争は、これに「認知領域」——人間の意思決定と認識のプロセスそのもの——を戦場として追加する。
「神経系中心戦」が構想されうる。これは、敵の指揮官の判断を歪め、兵士の士気を喪失させ、一般市民の政府への信頼を蝕むことを可能にする。
この記述は、戦争の概念を根本から書き換える。従来の戦争が「敵の物理的能力の破壊」を目的としていたのに対し、ニューロ戦争は「敵の認識と意思決定そのものの操作」を目的とする。これは、クラウゼヴィッツの「戦争とは他の手段をもってする政治の継続である」という定義さえ陳腐化させる可能性がある。
なぜなら、ニューロ戦争では、「政治」そのもの——人々の意見形成、意思決定、信頼——が直接の戦場となるからだ。戦争と平時の境界が曖昧になり、「常時継続する認知的操作」が新しい戦争の形態になるかもしれない。
この点で、著者が最終章で論じる危険性は、決して誇張ではない。
まず、「自由意志」の問題だ。わたしたちが「自分」であると信じているもの——意思決定、信念、感情——が、外部からの神経的操作によって影響を受けうるとなれば、何が「真の自己」と言えるだろうか? これは哲学的な問いを超えて、実存的な危機をもたらす。
次に、「神経分化」の問題だ。神経エンハンスメント技術が高価であれば、富裕層やエリート兵士だけがアクセスできるようになる。これは、軍事的だけでなく、社会的な格差をさらに拡大する。認知能力や感情制御能力を金で買える社会——これは能力主義の究極の形だが、同時に人間の平等という理念の崩壊でもある。
さらに、独裁政権による監視・統制の強化だ。中国の社会信用システムや新疆ウイグル自治区での監視技術は、すでにその原型を示している。これに神経監視技術が加われば、政権への「忠誠心」や「思想的純潔性」を、脳活動から直接評価するような社会が出現しかねない。
では、解決策はあるのか? クリシュナンは国際法による規制や倫理的ガイドラインの必要性を論じるが、それ自体に懐疑的にならざるを得ない。
なぜなら、国際法は常に技術の後追いであり、しかも大国の利益によって骨抜きにされる歴史を繰り返してきたからだ。化学兵器禁止条約(CWC)や生物兵器禁止条約(BWC)が存在しても、一部の国が秘密裡に開発を続けている疑いは常につきまとう。
神経兵器の場合、問題はさらに複雑だ。多くの技術が「両用技術」(軍民両用)であるため、規制が難しい。脳-コンピュータインターフェースは医療リハビリにも使えるし、神経監視技術は犯罪捜査やセキュリティにも応用できる。「軍事転用」をどう定義し、どう規制するのか?
おそらく、最も現実的な防衛線は「透明性」と「市民の監視」だろう。軍事研究の予算と目的を公開させ、独立した科学者や市民団体による監視を強める。神経技術の潜在的危险性についての社会的議論を活発化させる。
しかし、これも楽観的すぎるかもしれない。「国家安全保障」を理由に、軍事研究は秘密のベールに包まれがちだ。パンデミック時に「緊急事態」を理由に透明性が損なわれたように、「国家機密」は何でも隠蔽する口実になりうる。
最後に、日本の文脈で考えてみる。日本は「非核三原則」を持つ一方で、アメリカとの同盟の中で「拡大抑止」に依存している。神経兵器についても、同様のジレンマに直面するだろう。
日本国憲法第9条は「武力の行使」を放棄しているが、「非致死性」神経兵器の使用は「武力の行使」に当たるのか? 集団的自衛権の行使において、味方軍が神経兵器を使用するのを支援することは許されるのか?
さらに、日本は脳科学やロボティクスの研究で世界をリードする国だ。これらの技術が軍事転用されるリスクは、他の国よりも高いかもしれない。基礎研究と軍事応用の間の線引きを、どう維持するのか?
日本の「平和国家」としてのアイデンティティと、現実の安全保障環境の狭間で、神経兵器という新たな課題に対して、日本はどう向き合うべきなのか? これは科学技術政策のみならず、国家のあり方そのものを問う問題だ。
クリシュナンの本書は、これらの問いを投げかけることで終わっている。明確な答えは与えていないが、それこそが本書の価値だ。読者自身が考え、議論し、行動することを求めている。
わたしたちはパンデミックから、科学と政治、個人の自由と公共の利益の緊張関係について多くのことを学んだはずだ。神経技術とニューロ戦争の時代は、これらの課題をさらに先鋭化させる。準備なくして、その時代を迎えることは、思考の自由——そして人間性そのもの——を危険に晒すことになるだろう。

