Lessons Learned from Paleolithic Models and Evolution for Human Health: A Snap Shot on Beneficial Effects and Risks of Solar Radiation
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32918211/
太陽の光 ビタミンDと皮膚がん
アキテーヌ神経科学研究所、CNRSおよびボルドー大学、ペサック、セデックス、フランス
Haidong Dong, 米国ミネソタ州ロチェスター、メイヨー・クリニック、泌尿器科、免疫科
Heinfried H. Radeke, 薬理学・毒性学研究所、ゲーテ大学フランクフルト・マイン診療所(ドイツ、ヘッセン州、フランクフルト・アム・マイン
イラン、テヘラン医科大学小児医療センター、免疫不全研究センター、Nima Rezaei氏
Advances in Experimental Medicine and Biologyは、生物医学および生命科学の主要分野における科学的貢献のためのプラットフォームを提供している。このシリーズでは、微生物学、免疫学、神経科学、生化学、生物医学工学、遺伝学、生理学、がん研究などの分野における最新の研究をテーマ別に掲載している。基礎および臨床科学の新しいトピックや技術を網羅し、さまざまな分野の臨床家や研究者が集まっている。
第3版
編集者 Jörg Reichrath
臨床・実験光皮膚学センターおよびザールランド大学医療センター皮膚科 ドイツ、ホンブルク
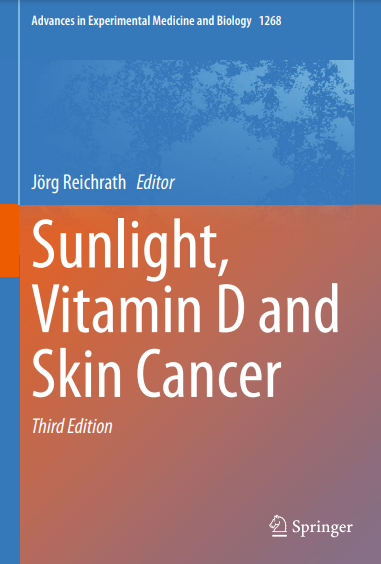
はじめに
強力な太陽の光は、現在の地球上の生命にとって必要不可欠な条件であり、人類の進化の大きな原動力となっている。しかし、太陽放射は人間の健康に良い影響と悪い影響の両方を与える。このジレンマの結果、環境医学の基本的な問題である「人間の健康に良い太陽の量」について、科学界や一般の人々の間で論争が続いている。2008年と2014年に出版された『Sunlight, Vitamin D and Skin Cancer』の初版と2版は、最新のレビューとして企画・構成され、このテーマに関するベンチマークとして広く認知された。今回の改訂版では、人間の健康にとってどれくらいの日光が良いのか/最適なのか、また、太陽と人工的な紫外線のプラスとマイナスの影響をどのようにバランスさせるのか、という現在進行中の議論の最も重要な側面をカバーする、広範囲で詳細な章が引き続き含まれている。本書は、紫外線によるビタミンDの合成が健康に及ぼす影響について多くの新しい情報を得た結果、多くの新しいトピックを含むように大幅に増補されている。一般的には、非黒色腫皮膚がんの発症には、紫外線への曝露が最も重要な危険因子であると考えられている。さらに、日焼けのパラメータを評価すると、悪性黒色腫の発症と短期間の強い紫外線照射、特に幼少期の火傷との間に関連性があることが一貫して示されている。そのため、紫外線から肌を守ることは、皮膚がん予防のための重要な要素となっている。しかし、あまり強くない紫外線を慢性的に浴びることは、メラノーマの危険因子にはならず、むしろ保護効果があるとする研究もある。さらに、他の多くの光生成物に加えて、必要なビタミンDの90%が太陽の作用によって皮膚内で生成される。ビタミンDの欠乏と、様々な種類の癌(大腸癌、前立腺癌、乳癌など)を含む多くの重篤な疾患との関連性が多くの研究で証明されているため、深刻な問題である。したがって、ビタミンDの欠乏と内部悪性腫瘍を含む様々な疾患との関連性は、皮膚科医や他の臨床医の間で、太陽および人工的な紫外線暴露のプラス効果とマイナス効果のバランスをどのようにとるかという議論を開いている。本巻の目的は、ビタミンDと皮膚がんに焦点を当て、紫外線曝露のプラスとマイナスの影響に関する我々の現在の知識を、読みやすく、最新かつ拡張した形で包括的に提供することである。内分泌学(非典型的なビタミンD代謝物の関連性を含む)疫学、組織学、光生物学、免疫学、細胞遺伝学、分子病理学などの最新の知見から、病気の予防や治療のための新しいコンセプトまで、第一線の研究者や臨床医がトピックを深く掘り下げて議論している。この分野の専門家だけでなく、これらの専門分野に深く関与していない医療従事者も、これらのトピックに関する最も重要でタイムリーな情報を提供している。この第3版の目的は、紫外線を浴びることによるプラスとマイナスの効果のバランスを取り、不十分な紫外線(ビタミンD欠乏症の発症など)や過剰な紫外線(皮膚がんの発症など)に伴うリスクを最小限に抑える方法に関心のあるすべての臨床家や科学者にとって、必要な最新情報をまとめることである。繰り返しになるが、すべての章がそれぞれの研究分野の専門家である著者によって執筆されており、本書への貢献を快く引き受けてくれたことに感謝している。今回の改訂版も、これまでの改訂版と同様に成功を収めることができると確信している。また、Larissa Albright氏、Anthony Dunlap氏、Murugesan Tamilselvan氏をはじめとするSpringer Nature社のスタッフの皆さんには、専門知識、勤勉さ、そして忍耐力をもって、この作品を完成させてくれたことに感謝している。
読書をお楽しみほしい。
ドイツ、Homburg/Saar Jörg Reichrath
目次 第1部 はじめに
旧石器時代のモデルと進化から得られた人間の健康に関する教訓 太陽放射線の有益な効果と危険性について
Jörg Reichrath
概要
強力な太陽の光をどのように扱うかは、環境医学の基本的な問題であり、皮膚がんの予防キャンペーンをはじめとする公衆衛生のさまざまな側面に影響を与えている。しかし、医師、科学者、その他の医療関係者が太陽光線の照射に関する推奨事項を作成する際には、ジレンマに陥る。プラスの効果は、少なくとも部分的にはUV(Ultra-violet)-BによるビタミンDの皮膚合成を介したものであるが、マイナスの効果は、UVを介した皮膚がんの光発がんを含むものである。前世紀になって、いわゆるビタミンD/がん仮説が登場してから、太陽の健康へのプラス効果に対する関心が飛躍的に高まった。1930年代後半、PellerとStephensonは、米国海軍の兵士の間で、皮膚がんの発生率は高いが、他のがんの発生率は低いことを報告した。その数年後、Apperlyは北米における緯度と癌死亡率の関連性を報告した。彼は、「がんに対する相対的な免疫力は、太陽光の直接的な効果です」と主張した。日光浴が癌に有効であるという仮説は早くから提唱されていたが、仮説を裏付けるこれらの観察結果は、明確なメカニズムが提案されるまで40年近く無視されていた。1980年代、GarlandとGarlandは、大腸がんに焦点を当てたパイロット研究を発表し、日光浴の効果がビタミンDに起因する可能性を示唆した。その後の研究では、ビタミンD化合物の抗がん作用の可能性が示唆された。今日では、太陽が人間の健康に及ぼす良い影響のすべてではないが、その多くは紫外線によって誘発されるビタミンDや他の光合成物の皮膚への合成によってもたらされることがわかっている。しかし、上記のようなジレンマがあるため、科学界や一般の人々の間では、どれくらいの日光が人間の健康に最適なのかという議論が続いている。本章では、第3版「Sunlight, Vitamin D and Skin Cancer」の内容を要約している。この本は、人間の健康にどれくらいの日光が適しているのか、太陽と人工的な紫外線のプラスとマイナスの効果をどのようにバランスさせるのか、という現在進行中の議論の最も重要な側面を網羅した最新のレビューとして、旧石器時代のモデルと進化から得られた教訓を含めて特別に企画・構成されている。
キーワード
進化?旧石器時代のモデル ? 皮膚 ? 皮膚がん ? 太陽放射?太陽 ? 太陽の光 ? 日焼け対策 ? 紫外線 ? ビタミンD ? ビタミンD受容体
日光浴に関する推奨事項を作成する際、医師や科学者、その他の医療関係者はジレンマに陥る。なぜなら、太陽光線は人間の健康にプラスとマイナスの両方の影響を与えるからである([11]参照)。プラスの効果は、少なくとも部分的にはUV-BによるビタミンDの皮膚合成を介しているが、マイナスの効果には、UVを介した皮膚がんの光発がんがある([11, 13]参照)。前世紀には、いわゆるビタミンD/がん仮説([12]参照)が導入された後、太陽の健康へのプラス効果に対する関心が劇的に高まった。日光浴が癌に有効であるという仮説は前世紀初頭に提案されていたが、説得力のあるメカニズムが提案されるまで、これらの観察結果は40年近く無視されていた([12]の改訂版)。1930年代後半、PellerとStephensonは、アメリカ海軍の兵士の皮膚がんの発生率が高く(つまり8倍)他のがんの発生率は低いことを報告した([16]; rev. in [12])。PellerとStephensonは、日光浴によって皮膚がんが誘発され、それが結果的に他のがんに対する免疫をもたらすことを示唆した([16]; rev. in [12])。その数年後、Apperlyは北米におけるカンフル死亡率と緯度の関係を報告した([1]; rev. in [12])。彼は、高緯度地域の人は低緯度地域の人に比べて総癌死亡率が高いことを観察した。彼は、「がんに対する相対的な免疫力は、太陽光の直接的な効果である」と主張した([1];Kim and Giovannussiに改訂)。1980年代、GarlandとGarlandは、日光浴の効果はビタミンDに起因する可能性があることを示唆した([7]、[12]参照)。彼らは、人間のビタミンDのほとんどが太陽の紫外線B(UV-B)を浴びることで作られるという前提に立ち、ビタミンDが大腸がんを予防するという仮説を立てた([7]; rev. in [12])。この研究は大腸がんに焦点を当てたものであったが、ビタミンDの保護的役割は、後に乳がん、卵巣がん、前立腺がんなど複数の部位のがんにも拡大された([12]参照)。その後の研究では、ビタミンD化合物の抗がん作用の可能性が示唆されている([12]参照)。今日では、太陽が人間の健康に及ぼす良い影響のすべてではないが、その多くが、紫外線によって誘発されるビタミンDやその他の光生成物の皮膚での合成によってもたらされることがわかっている([11]参照)。しかし、強力な太陽光が人間の健康に悪影響を及ぼす可能性もあるため、ジレンマに陥っており、どれくらいの太陽光が人間の健康に良いのか、科学界や一般の人々の間で論争が続いている。2008年に出版された初版「Sunlight, Vitamin D and Skin Cancer」は、最新のレビューとして企画・構成されており、このテーマに関するベンチマークとなってた。今回の増補版では、人間の健康に良い日光の量や、太陽と人工的な紫外線のプラスとマイナスの影響のバランスを取る方法について、現在進行中の議論の最も重要な側面を網羅した、広範囲で詳細な章が引き続き含まれている。旧石器時代のモデル(改訂版[22])や進化論[11]から得られた教訓を含め、紫外線によるビタミンDの皮膚合成が健康にもたらす効果についての新たな情報が山のように得られた結果、本書は多くの新しいトピックを含むように大幅に拡張された。
本書の第1章では、フォートバイオロジーとビタミンD化合物のポジティブな生物学的効果に焦点を当てている。第2章では、「Sun-light, UV-Radiation, Vitamin D and Skin Cancer: と題した第2章では と題された第2章では、マイケル・F・ホリックが、太陽光のビタミンであるビタミンDの様々な生物学的効果について、優れた概要を述べている[11]。日光を浴びると,紫外線Bの光子が皮膚に入り,7-デヒドロコレステロールを光分解してプレビタミンD3を生成し,これが体温で異性化されてビタミンD3になることを指摘している。さらに、ほとんどの人がビタミンDの必要量を太陽に依存しており、皮膚の色素、日焼け止めの使用、加齢、時間帯、季節、緯度などがプレビタミンD3の合成に劇的な影響を与えると説明している。マイケル・ホリックは、ビタミンD欠乏症は克服されたと考えられていたが、現在では世界人口の50%以上がビタミンD欠乏症のリスクを抱えていることが認識されていると報告している[11]。このような欠乏症は、食品へのビタミンDの強化が不十分であることや、健康的な食事には十分な量のビタミンDが含まれているという誤解が一因となっている[11]。ビタミンDが不足すると、子どもでは成長障害やくる病を引き起こし、大人では骨減少症や骨粗鬆症を誘発・悪化させ、骨折のリスクを高めることになる。さらにホリック氏は、ビタミンD欠乏症の蔓延は、一般的ながん、自己免疫疾患、感染症、心血管疾患のリスク増加など、その他の深刻な結果と関連していると説明している[11]。彼は、すべての人間が健康に必要なビタミンDを摂取するためには、適度な太陽光の有益な効果を改めて認識する必要があると結論づけている[11]。
「ビタミンDの状態とがんの発生率および死亡率」と題した第3章では、Hanseul KimとEdward Giovannucciが、日光浴とがんの発生率および死亡率との関係を研究するために多くの努力がなされてきたと説明している[12]。著者らは、1930年代後半に、PellerとStephensonが、米国海軍の兵士の皮膚がんの発生率が高く(すなわち8倍)他のがんの発生率が低いことを報告したことを指摘している([16];rev. in [12])。PellerとStephensonは、日光浴によって皮膚がんが誘発され、その結果、他のがんに対する免疫が得られると考えた([16]; rev. in [12])。数年後、Apperlyは北米における緯度とカンフル死亡率の関連性を報告した([1];改訂版[12])。彼は、高緯度地域の人は低緯度地域の人に比べて総癌死亡率が高いことを観察した。彼は、「がんに対する相対的な免疫力は、太陽光の直接的な効果である」と主張した([1]、[12]参照)。日光浴ががんに対して有益であるという仮説は早くから提唱されていたが、この仮説を裏付ける観察結果は、明確なメカニズムが提案されるまで40年近く無視されていた。1980年代、GarlandとGarlandは、日光浴の効果がビタミンDに起因する可能性を示唆した([7];[12]に改訂)。彼らは、人間のビタミンDのほとんどが太陽の紫外線B(UV-B)を浴びることで作られるという前提のもと、ビタミンDが大腸がんを予防するという仮説を立てた([7];改訂版[12])。この研究は大腸がんに焦点を当てたものだったが、ビタミンDの保護的役割の提案は、後に乳がん、卵巣がん、前立腺がん、その他の複数の部位のがんにも拡大された。その後の研究では、分化とアポトーシスの促進、増殖・浸潤・血管新生・転移の抑制など、ビタミンDの抗がん作用の可能性が示唆されている。本章では、ビタミンDと各種癌の発生率および死亡率との関連性に関する最新の疫学的証拠をレビューし、統合した。GarlandとGarlandの最初の仮説の後、多くの疫学的研究が、さまざまな部位の癌に対するビタミンD(または日光浴)の保護的役割を支持している。本章では、Hanseul KimとEdward Giovannucciが、まず、血清ビタミンD濃度とがん罹患率および死亡率との関連を評価した疫学研究について述べ、次に、最新の無作為化比較試験(RCT)データから得られた証拠を含む、ビタミンD摂取研究について述べる。著者のHanseul Kim氏とEdward Giovannucci氏は、3つの評価項目、すなわち、がん罹患率(当初はがんのない集団で調査期間中に新たに診断された症例)がん死亡率(当初はがんのない集団で調査期間中に発生した死亡症例)がん生存率(すでにがんと診断された人のがんによる生存または死亡率)について検討している。彼らは、過去数十年にわたり、ビタミンDは一般的ながんに関連してかなりの研究が行われてきたが、まれな悪性腫瘍についてはあまり研究が行われていないことを示している([12]に再掲)。がんの初期に関しては、観察研究に基づき、大腸がんでのみ一貫した逆相関が観察されている。また、RCTはビタミンDのがん罹患率に対する一般的な効果を支持していない。これらのRCTは、因果関係を示すより多くの証拠を提供する可能性があるが、重要な限界がある。癌の発生率に関する研究では、効果を観察するのに必要な期間が長くなる可能性があるため、より期間の長い試験が必要とされる。例えば、疫学的証拠によれば、カルシウムやビタミンDが大腸がんの発生に影響を及ぼすためには、少なくとも10年が必要である。ほとんどのがんは、一般的に長期間にわたる多段階のプロセスを経て発生するため、比較的短い期間の研究では、がんのリスクに対するビタミンDの効果があったとしても、それを捉えることはできない。また、試験では、影響を受けやすい人々が恩恵を受ける「適切な」または「有効な」投与量を1つだけ選ぶことは困難である。したがって、RCTは一般的にゴールドスタンダードと考えられているが、その結果は、上記の問題やノンコンプライアンスなどの問題から、やはり慎重に解釈する必要がある。がん罹患率に関する研究とは対照的に、RCTと、すべてではないが多くの観察研究は、ビタミンDががんの死亡率または生存率に役割を果たしている可能性を示唆している。プラセボよりもビタミンDサプリメントを摂取するように無作為に割り付けられた群では、総がん死亡率が約15%減少することが観察され、VITAL研究では、この効果の大きさは、ビタミンDの使用期間が長くなるにつれて大きくなる可能性が示唆された([12]参照)。これらの研究の追跡調査期間はほとんどが5年未満であった。VITAL試験では、最初の2年間を除いた後のリスク減少は25%であった。また 2000IU/日というかなり高用量でも、100nmol/L以上のレベルに達すると効果が見られた([12]参照)。全身がんの発生率と死亡率について異なる結果が得られた理由は明らかではないが、発がんの複数の段階でビタミンDが作用するというもっともらしいメカニズムが存在する([12]改訂版)。著者らは、ビタミンDが、発がんの後期に生じる可能性のある腫瘍の浸潤性および転移傾向を減少させる可能性があると説明している。死亡率に対する効果を示したRCTでは、ビタミンDの投与は一般的にがんの診断前に開始され、発がんの後期段階である可能性が高く、診断中および診断後も継続された。したがって、ビタミンDの状態ががんの死亡率に及ぼす潜在的な効果は、診断前の段階から、末期の腫瘍の進行(例えば、浸潤)および転移性の播種まで、発がんおよび腫瘍の進行のすべての段階で作用する可能性があり、治療段階では、おそらく治療法の効果を補完または増強することによって作用する可能性がある([12]で再掲)。Kim氏とGiovannucci氏は、ビタミンDの効果の一部が診断前の転移播種期に現れる可能性があるため、診断時にビタミンD治療を開始しても同様の効果が得られるかどうかは不明であると説明している。2018年には、世界で約1,000万人のがん死亡者が発生したと推定されている([12]で改訂)。人口規模の増加と高齢化に伴い、がんの罹患率と死亡率は時間の経過とともに増加していくと考えられる。著者らは、メタアナリシスの結果から、54?135nmol/L程度の25(OH)Dの循環レベルを達成することが、がん死亡率の低減に寄与することを支持すると結論づけている。予防のための最適な25(OH)Dレベルは確立されていないが、50nmol/L以上である可能性が高く、現在、世界の人口のかなりの部分がこの基準を下回っていると考えられる。内分泌学会では、25(OH)Dを75nmol/L以上に維持するために、少なくとも1,500〜2,000IU/日のビタミンD摂取を推奨している([12]参照)。著者らは、これらの知見を確認し、予防のための最適なビタミンDの摂取量と摂取時期を確立し、どのような種類のがんに効果があるかを明らかにし、その作用機序を解明するためには、さらなる研究が必要であると結論づけている([12]改訂)。
「ビタミンD受容体多型とがん」と題した第4章では、Patrizia Gnagnarella、Sara Gandiniらが、ビタミンDとがんのリスクとの関連性を裏付ける科学的証拠が増えていることを指摘している[9]。活性代謝物である1,25(OH)2Dは,標的遺伝子の転写活性化および抑制を媒介する細胞内受容体であるビタミンD受容体(VDR)に結合することでその活性を発揮する。1,25(OH)2DがVDRに結合することで、何百もの異なる遺伝子を制御することができる。VDRは、大腸、乳房、肺、卵巣、骨、腎臓、副甲状腺、膵臓のB細胞、単球、Tリンパ球、メラノサイト、ケラチノサイトなど、ほぼすべての組織で活性化されており、また、がん細胞でも活性化されている。VDR遺伝子の制限断片長多型とさまざまな種類のがんとの関連性については、多くの研究が行われている。Patrizia Gnagnarella、Sara Gandiniらは、民族性を異質性の重要な要因として考慮し、個々の悪性腫瘍に対するVDR多型(Fok1,Bsm1,Taq1,Apa1,Cdx2)の関連性を分析するために、文献の系統的なレビューを行った[9]。2018年12月までに、乳がん、前立腺がん、結腸直腸がん、皮膚がん(メラノーマおよび非メラノーマ皮膚がん)肺がん、卵巣がん、腎臓がん、膀胱がん、胆嚢がん、食道がん、甲状腺がん、頭頸部がん、肝臓がん、口腔扁平上皮がん、非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫、肉腫のリスク推定値を算出するデータを有する177の独立した研究を同定した[9]。前立腺癌(Fok1, Bsm1, Taq1, Apa1, Cdx2)乳癌(Fok1, Bsm1, Apa1, CdX2)大腸癌(Fok1, Bsm1, Taq1, Apa1)皮膚癌(Fok1, Bsm1, Taq1)では、VDR多型との有意な関連が報告されている。その他の部位のがんのリスク推定値を報告した研究は非常に少ない。ほとんどの悪性腫瘍について矛盾したデータが報告されており、現時点では、VDR遺伝子型ががんのリスクに重要であると断定することはできない。また、民族性、表現型、25(OH)D血漿レベル、紫外線暴露などの他の因子が交絡因子としての役割を果たし、不均一性をもたらしている可能性が高いと思われる。著者らは、VDR多型がいくつかのがん部位のリスクを調節する可能性があることを示唆しており、今後の研究では、VDR遺伝子変異をビタミンD状態の評価と統合し、民族によって層別化する必要があると結論づけている[9]。
「日光浴と全死因死亡率の関係について」と題された第5章では、Pelle G Lindqvistが日光浴と全死因死亡率に関する知識を簡単に紹介している[14]。日光浴をあまりしない習慣が、全原因死亡の主要な危険因子であるという仮説を裏付けるデータがあると指摘している[14]。日光浴の少なさは、心血管疾患(心血管疾患)および癌/非心血管疾患による死亡リスクの増加と、癌のリスクのわずかな減少に関連している[14]。日光浴を積極的に行う習慣は、皮膚がんの発生率を高めると同時に、全死亡率の面でも予後を改善するという二重の効果がある。著者は、太陽強度が低い地域では、バランスのとれた推奨を得るために、日光浴のリスクとメリットの両方を慎重に評価すべきだと結論づけている。2011年には、30年間にわたって年に1回以上日光浴をしていた人の全死亡率が30%低いことが報告された([14]に改訂)。南スウェーデンの女性のメラノーマ(MISS)コホートの15年間の前向き追跡調査では、日光浴習慣の増加に伴い、全原因死亡率が用量依存的に有意に低下することが示され、日光浴を避けている人では、最も日光浴をしているグループに比べて死亡率が2倍(2.0,95%CI 1.6 ? 2.5)になった(rev. in [14])。日光浴を避けているグループの死亡率の母集団帰属リスク(PAR)は3%と推定された。同じコホートの20年間の追跡調査では、競合リスクシナリオで分析した結果、日光浴を避けた女性の寿命が短いのは、主に心血管疾患(心血管疾患)および非がん・非心血管疾患による死亡のリスクが、中程度および高程度の日光浴をしたグループに比べて、用量依存的に有意に増加したためであることが示された([14]改訂版)。日光浴量の増加に伴い、心血管疾患および癌・非心血管疾患以外の死亡リスクは減少したが、寿命が延びた結果、癌による死亡の相対的寄与が増加した([14]改訂版)。したがって、がんによる死亡の全体的な有病率は増加したが、年齢調整後のリスクは増加しなかった。喫煙で層別化した分析では、日光照射を避けている非喫煙者の死亡リスクは、日光照射量の多いグループの喫煙者と同程度であった。Pelle G Lindqvist氏は、日光浴の回避は喫煙と同程度の全死因の危険因子であると解釈した。日光浴を避けている人の死亡率の増加は、主に心血管疾患と非がん・非心血管疾患による死亡リスクの増加によるものだと結論づけている。彼は、我々の発見が、日光浴が健康に及ぼす影響について、よりバランスのとれた適切な見解を示すことになると期待している。
本書の次の章では、皮膚がんの光発がんの主要な環境リスク因子としての太陽放射の役割に焦点を当てる。第6章では、「皮膚がんと紫外線の疫学 ? Update 2019」と題された第6章では、Ulrike Leiter、Ulrike Keim、Claus Garbeが、メラノーマとケラチノサイト皮膚がん(KSC)は、白い肌の集団に最も多く見られるタイプのがんであると説明している[13]。この2つの腫瘍は、世界的に罹患率が上昇しているものの、死亡率は安定しているか減少している。皮膚黒色腫(CM)とKSCの発生率が上昇しているのは、皮膚がんの主な原因となる危険因子である紫外線(UV)への曝露量が増加していることが主な要因である。基底細胞がん(BCC)と扁平上皮がん(SCC)からなるKSCの罹患率は、メラノーマよりもはるかに高い。基底細胞がんは主に幼少期や青年期に集中的に紫外線を浴びることが原因で発症し、SCCは数十年にわたる慢性的な累積紫外線照射が原因で発症する。死亡率は比較的低いが、KSCは医療サービスの問題として増加しており、重大な病的状態を引き起こしている。皮膚黒色腫は白人集団で急速に増加しており、過去数十年間で年間約3.7%の増加が推定されている。著者らはさらに、SCCとは対照的に、メラノーマのリスクは、間欠的かつ慢性的な日光への曝露と関連していると説明している[13]。メラノーマの発生頻度は、皮膚の構成色と地域に密接に関連している。過去70年間の屋外活動と日光への暴露の変化は、メラノーマの発生率を高める重要な要因となっている。メラノーマの死亡率は、米国、オーストラリア、ヨーロッパ諸国で安定している。米国では最近、死亡例が減少したことが報告されているが、これは新しい全身治療の効果を反映していると思われる。いくつかの集団(オーストラリアやニュージーランドなど)の若年層では、CMの発生率が安定しているか減少していることが観察されているが、これは紫外線への曝露を減らすことを目的とした一次予防キャンペーンが原因である可能性がある[13]。著者はさらに、対照的に、ヨーロッパのほとんどの国と米国では、CMの発生率は依然として上昇しており、メラノーマが薄くなる傾向が続いているのは、主に早期発見によるものであると説明している[13]。
次の論文では、「Solar UV Exposure and Mortality from Skin Tumors: 次の「Solar UV Exposure and Mortality from Skin Tumors: An Update」と題した論文では、Marianne BerwickとAmy Garciaが、皮膚がん、特に皮膚悪性黒色腫の病因と予後において、太陽紫外線への曝露が重要かつ複雑であると説明している[2]。日光浴とその「誘導体」の1つであるビタミンDは、メラノーマによる死亡率の低下に関係しているとされている。著者らは、これらの関係には一貫性がなく、現時点では、メラノーマの予後と日光浴の関係について明確な推奨を行うことはできないと結論づけている[2]。しかし、この関係は引き続き調査する必要がある。
第8章[5]では、Barbara BurgardとJörg Reichrathが、「ソラリウムの使用と悪性黒色腫のリスク:未解決の問題が多いが、議論を終わらせる時ではない」と題して、サンベッドの使用が黒色腫のリスクを増加させるかどうかの継続的な議論に光を当て、現時点で入手可能な科学文献を批判的に評価し、著者らが以前に発表したメタ分析に焦点を当てている。彼らの文献検索では、太陽熱発電所からの紫外線への常時暴露とメラノーマリスクとの弱い関連性を報告したいくつかのメタアナリシスが見つかった。しかし、これらのメタアナリシスに含まれる研究の質は、介入試験がないことや、多くの観察研究に大きな限界があることから、結果的にエビデンスレベルや推奨度は非常に低いものとなった。現在までに発表されたコホート研究や症例対照研究の結果は、Hillの基準でも因果関係を証明するものではない。これらの観察研究の全体的な質とその結果としてのエビデンスレベルは、バイアスにつながる重大な制限(観察されない、または記録されない交絡を含む)のために低い。これまでに発表された大多数の研究では、日光浴、日焼け、肌タイプなどの交絡因子の多くが、適切かつ体系的に記録され、調整されていないことを認識しなければならない。このように、個々の研究には多くの限界があり、その結果、証拠レベルや推奨度が低いため、現時点では、ソラリウムの使用とメラノーマのリスクとの間に因果関係を仮定することはできないと結論づけた。現時点では、適度で責任あるソラリウムの使用がメラノーマのリスクを高めるという説得力のある証拠はない。
本書の次の章では、皮膚がんの分子生物学と光化学的生成についてさまざまな角度から取り上げている。Molecular Biology of Basal and Squa-mous Cell Carcinomas(基底細胞癌と扁平上皮癌の分子生物学)」と題された次の章では、Lars Boeckmann、Christine Martens、Steffen Emmertが、皮膚のケラチノサイト由来の新生物として、基底細胞癌と扁平上皮癌が一般的であると説明している[4]。著者らは、いわゆる非黒色腫皮膚がんは、いずれもヒトに最も多く見られるがんであり、両腫瘍の共通の危険因子としては、日光への暴露、染色体の不安定性をもたらすDNA修復欠損、免疫抑制などがあると指摘している[4]。しかし、この2つの異なる腫瘍体の発生における基本的な違いは、これまでも、そして現在も明らかにされている。PTCH遺伝子とSMO遺伝子の後天的な変異により、ソニックヘッジホッグシグナル伝達経路が恒常的に活性化されることが、基底細胞がんの初期の発生を決定する要因であると考えられる。他のシグナル伝達経路も影響を受けるが、低分子ヘッジホッグ阻害剤は、現在の臨床試験では、局所的にも全身的にも基底細胞癌の最も有望な治療法として発展している。扁平上皮癌の発生では、p53遺伝子の変異、特に紫外線による変異が初期の事象として同定されている。しかし、上皮成長因子受容体、RAS、Fyn、またはp16INK4aシグナルを含む他のシグナル伝達経路は、扁平上皮癌の発生に重要な役割を果たしている可能性がある。著者らは、同じ種類の細胞が脱分化することで、異なる腫瘍体を形成する分子イベントの理解が深まったことで、低分子を用いた新たな分子標的の治療への道が開かれ始めたと結論づけている[4]。
「ヒトパピローマウイルスと皮膚がん」と題された第10章では,Sigrun Smolaが,ヒトパピローマウイルス(HPV)が扁平上皮に感染し,増殖性の病変を引き起こすことを説明している[21]。HPVは220種類以上の型が存在し、5つの属に分類されている。粘膜に存在する高リスクのHPVは、性器癌の発生において原因となる役割が確立されているが、皮膚に存在するHPVの生物学はあまり理解されていない。希少な遺伝性疾患である疣状表皮発育症(EV)の患者や動物モデルから、β属の皮膚HPVが紫外線(UV)と相乗的に作用して皮膚扁平上皮がん(cSCC)を発症することを示唆する証拠が蓄積されている。2009,国際がん研究機関(IARC)は、β-HPVの5型および8型を、EVにおける「がん発症の可能性がある」生物学的物質(グループ2B)に分類した。Sigrun Smolaがさらに説明するように、疫学的・生物学的研究によると、β-PV属の感染は、非EV患者の紫外線を媒介とした皮膚の発癌にも関与している可能性がある[21]。しかし、β-PV属は、むしろ発がんの初期段階で作用し、悪性の表現型を維持するためには不要となり、「ヒット&ラン」メカニズムと相まって、その役割を果たしている。以上のように、Sigrun Smolaは本章で、β-PV属感染症に関する優れた概要を示し、上皮発癌における皮膚とα-粘膜の高リスクHPVの類似点と相違点について論じている。
The Immune System and Pathogenesis of Melanoma and Nonmelanoma Skin Cancer」と題された第11章では、Kory P Schrom、InYoung Kim、Elma D. Baronが、腫瘍の発生は、遺伝子の異常と、自由な増殖を防ぐことができないことの結果であると説明している[19]。さらに著者らは、腫瘍形成につながる遺伝子の異常は様々であるが、免疫系は腫瘍の発生、予防、生成において重要な役割を果たしていると指摘している。本章では、Kory P Schrom氏、InYoung Kim氏、Elma D. Baron氏が、メラノーマと非メラノーマ皮膚がん(NMSC)の両方の皮膚がんの発生に関連する免疫系の重要性について論じている。著者らの説明によると、ヒトの免疫系は、病原体から我々を守るだけでなく、腫瘍の発生を防ぎ、悪性細胞を消滅させる機能も持っている。免疫系がこの任務を成功させるかどうかは、免疫系、腫瘍細胞、および分子メディエーターの間の複雑な相互作用によって決まる。Kory P Schrom氏、InYoung Kim氏、Elma D. Baron氏によると、現時点では、腫瘍が免疫系を回避し、その結果、増殖、拡散、そして最終的には宿主の死に至るまでの、単一のセンチネルイベントは見つかっていないという。現在、紫外線による免疫抑制と臓器移植患者(OTR)における癌の発生についての理解が深まったことで、皮膚悪性腫瘍の治療に免疫療法を用いて免疫系を利用することができるようになった。著者らは、免疫系の理解を深めるための科学的研究を継続し、癌の発生や皮膚癌関連の突然変異における免疫系の役割について理解を深めることが、皮膚悪性腫瘍に苦しむ患者の治療法に影響を与え、改善につながると結論づけている。
次の4つの章では、皮膚癌の発生と進行におけるビタミンD内分泌系の役割に焦点を当てている。第12章の「ビタミンD化合物による紫外線損傷および光発がんからの保護」では、Warusavithana Gunawardena Manori De Silva、Rebecca S. Masonらが、皮膚細胞が紫外線にさらされるとDNAが損傷し、修復が不十分だと突然変異を引き起こす可能性があると説明している[6]。また、紫外線によって誘発されたDNA損傷や、反応性のオキシゲンや窒素種は、適応免疫系の局所的・全身的な抑制を引き起こす。これらの変化が皮膚腫瘍の発生を支えているのである。ビタミンDに由来するホルモンであるカルシトリオール(1,25-ジヒドロキシビタミンD3)やその他の関連化合物は、ビタミンD受容体を介して、また少なくとも部分的には小胞体タンパク質57(ERp57)を介して働き、紫外線照射後のケラチノサイトやその他の皮膚細胞におけるシクロブタンピリミジン二量体や酸化的DNA損傷を軽減する。カルシトリオールとその関連化合物は、活性酸素種の減少、p53の発現および/または活性化の増加、修復タンパク質の増加、そして紫外線照射後にカルシトリオールが存在すると細胞内のエネルギー利用率が増加することもあって、ケラチノサイトのDNA修復を促進する。紫外線を浴びたケラチノサイトでは、ミトコンドリアが損傷している。ビヒクルではなくカルシトリオールの存在下では、紫外線照射後に解糖が増加し、エネルギーを節約するオートファジーが増加し、マイトファジーの強化と一致する変化が見られた。DNA損傷の減少とROS/RNSの減少は、紫外線による免疫抑制の軽減に役立つはずである。ヘアレスマウスにカルシトリオールおよび関連化合物を局所的に投与すると、紫外線による免疫抑制の軽減が観察された。著者らは、カルシトリオールおよび関連化合物のこれらの保護作用が、マウスに慢性的に紫外線を照射した後、カルシトリオールおよび一部の関連化合物を照射後に局所処理した際に観察された皮膚腫瘍形成の減少に寄与していると推定されると結論づけている。
Andrzej T. Slominskiらは、第13章「非黒色腫皮膚癌の病因および進行における古典的および新奇なビタミンDの役割」において、基底細胞癌および扁平上皮癌(SCCおよびBCC)を含む非黒色腫皮膚癌は、その比較的高い発生率のために重大な臨床問題となっており、世界中の医療システムに経済的負担をかけていると説明している[20]。紫外線(UVR: λ ? 290 400 nm)がBCCおよびSCCの発生と促進に重要な役割を果たしていることは認められているが、その中でもUVB(λ ? 一方で、UVBは皮膚でのビタミンD3(D3)の生成に必要であり、このプロホルモンの体内要求量の90%以上を供給している。また、UVBに長時間さらされると、タキステロールやルミステロールが生成される。ビタミンD3とその正則型(1,25(OH)2D3)および非正則型(CYP11A1-intitated)のD3-ヒドロキシ化合物は、皮膚において光保護機能を発揮する。これには、ケラチノサイトの増殖と分化の制御、抗酸化反応の誘導、DNA損傷の抑制とDNA修復機構の誘導、抗炎症作用などが含まれる。さらに、動物を用いた研究では、D3-hydroxyderivativesがUVBや化学的に誘発された表皮癌の発生を抑制し、SCCやBCCの成長を阻害することが明らかになっていると説明している。ゲノムおよび非ゲノム的な作用機序が示唆されている。さらに、ビタミンD3自体が、多くのがんに関与しているヘッジホッグシグナル伝達経路を阻害する。ビタミンD受容体をサイレンシングすると、UVBや化学的に誘発された表皮ガンの発生傾向が高まる。ビタミンD化合物の他の標的としては、1,25D3-MARRS、レチノイン酸オーファン受容体αおよびγ、アリルハイドロカーボン受容体、Wntシグナルなどがある。最近では、ルミステロールヒドロキシ化合物の光保護効果が確認されている。臨床試験では、光線性角化症の治療におけるビタミンD化合物の有益な役割が示された。著者らは、要約すると、ビタミンDの生物学と薬理学における最近の進歩は、皮膚がんの化学的予防と治療において新たなエキサイティングな機会を開くものであると結論づけている[20]。
ダニエル・D・バイクルは,第14章「皮膚における腫瘍抑制因子としてのビタミンD受容体」で,メラノーマやケラチノサイト癌(KC)を含む皮膚悪性腫瘍は,最も一般的な癌であり,米国では年間100万人以上が罹患していると説明している[3]。基底細胞癌と扁平上皮癌を含む角化細胞癌は、メラノーマよりもはるかに多く、本章の主題となっている。一般に、これらの悪性腫瘍の原因は、太陽光線を浴びることで生じるUVBとUVAの両方の紫外線(UVR)であると考えられているが、UVBは皮膚でのビタミンDの合成にも必要である。ケラチノサイトは表皮の主要な細胞である。ダニエル・バイクルは、この細胞がビタミンDを産生するだけでなく、ビタミンDを活性代謝物である1,25(OH)2Dに代謝する酵素機構を持ち、この代謝物の受容体であるビタミンD受容体(VDR)を発現していると説明している。これにより、細胞が生成した1,25(OH)2Dに反応することができる。Daniel D. Bikle氏は、文献で報告されているデータに基づいて、皮膚におけるビタミンDのシグナル伝達は、UVRによって誘発される表皮の腫瘍形成を抑制すると結論づけている。本章でDaniel D. Bikleは、ビタミンDのシグナル伝達が腫瘍形成を抑制する4つのメカニズムに焦点を当てている。この4つのメカニズムとは、増殖の抑制と分化の促進であり、ビタミンDによる増殖/分化の制御におけるヘッジホッグ、wnt/b-カテニン、ヒアルロン酸/CD44経路の役割を議論し、発癌性長鎖非コードRNAと癌抑制性長鎖非コードRNAのバランスの調整、免疫制御、DNA損傷修復(DDR)の促進である。
Jörg Reichrathらは、第15章「Cancer Prevention in Skin and Other Tissues via Cross-Talk Between Vitamin D- and p53-SIGNALING(ビタミンDとp53シグナルのクロストークによる皮膚およびその他の組織のがん予防)」で、ビタミンDとp53シグナルの経路が、自然発生的または発がん物質によって誘発される細胞の悪性形質転換に大きな影響を与えることを説明している[17]。ビタミンD受容体(VDR)とp53/p63/p73タンパク質(以下,p53ファミリー)は,いずれも刺激を受けて転写調節因子に変化する受容体/センサーとして典型的に機能するが,主な違いは,核のVDRが天然に発生するリガンド1と結合して転写活性化されることである。 一方、核内のVDRは天然由来のリガンドである1,25-ジヒドロキシビタミンDと高親和性で結合して転写活性化されるのに対し、p53クランは主に核形質に存在し、一般的にストレスと呼ばれる細胞のホメオスタシスにおける多くの変化に対応している。著者らは、ビタミンDシグナルとp53シグナルの間には、異なるレベルで起こるクロストークが存在し、ゲノム全体に影響を及ぼし、非黒色腫皮膚がんを含む多くの悪性腫瘍にとって非常に重要であることを示す証拠が増えていることを指摘している。その一つは、p53が皮膚の色素沈着を制御する能力に関わるものである。p53は、α-MSHやACTHなどのPOMC誘導体を介して皮膚の色素沈着をアップレギュレートすることが示されている。色素沈着の増加は、紫外線によるDNA損傷や皮膚の発癌性から皮膚を保護するが、一方でビタミンDの皮膚での合成を減少させる。紫外線照射後に生存している細胞は、1,25-ジヒドロキシビタミンDの存在下で、核内p53タンパク質の発現の増加とNO産物の著しい減少に関連して、 thy-mine dimersの著しい減少を示した。第3のレベルの相互作用は、ビタミンD化合物が、野生型p53の存在に依存して、ネズミの二重分(MDM2)遺伝子の発現を制御する能力によって証明されている。MDM2は、p53活性の主要な負の制御因子としての役割が確立されている。最後に、p53とそのファミリーメンバーは、VDRの直接的な制御に関与していると考えられている。Reichrathらは、その概要の中で、皮膚やその他の組織の発癌に対するビタミンDとp53のシグナル伝達のクロストークの意味を、ゲノムワイドな視点に焦点を当ててまとめている[17]。
「Sunlight, Vitamin D and Xeroderma Pigmentosum」と題された第16章では、Marie Christine Martens、Steffen Emmert、Lars Boeckmannが、必要なビタミンDの80~90%が皮膚で光合成される必要があるため、太陽光、特にUV-B放射が内因性のビタミンD産生にとって重要な因子であると説明している[15]。活性型ビタミンDであるビタミンD3(カルシトリオール)は,リガンド活性化転写因子であるビタミンD受容体(VDR)に結合し,ゲノムおよび非ゲノムに作用する。近年、カルシトリオールとその類縁体は、マウス、ヒトのBCCおよびSCC細胞株において、試験管内試験で抗増殖作用を示すことが明らかになっている。ビタミンDの光合成には紫外線が重要な役割を果たしているため、色素性乾皮症(XP)の患者に推奨されているような厳格な日焼け対策は、ビタミンDレベルに影響を与える可能性がある。色素性乾皮症は、常染色体劣性のまれな疾患で、世界的な有病率は100万人に1人といわれている。XPは、7つの異なる相補性グループに分けられる。XPは、XP-AからXP-Gまでの7つの相補性グループに分けられる。相補性グループは、基礎となる遺伝子の欠損に対応している。これらの遺伝子の欠損は、紫外線によって誘発されるDNA損傷(シクロブタンピリミジン二量体(CPD)や6-ピリミジン-4-ピリミドン二量体(6-4PP)など)を除去するために必要なヌクレオチド除去修復(NER)の欠損を引き起こす。さらに、翻訳型ポリメラーゼ23遺伝子(PolH)に変異がある変異株型(XP変異株(XPV)とも呼ばれる)も存在する。XPVの患者は、トランスレーショナル合成の欠損を示す。XPVの患者は、紫外線によって誘発された病変を修復することができないため、メラノーマだけでなく、基底細胞がん(BCC)や扁平上皮がん(SCC)など、紫外線によって誘発される非メラノーマ皮膚がん(NMSC)のリスクが高くなる。著者らは、XPに対する根治的な治療法は今日存在しないが、皮膚がんの治療と予防には多くの選択肢があると結論づけている。
第17章「Update: Solar UV-Radiation, Vitamin D and Skin Cancer Sur-veillance in Organ Transplant Recipients (OTRs)」では、Roman Saternus、Thomas Vogt、Jörg Reichrathの各氏が、過去数十年の間に大きな進歩があったものの、臓器移植を受けた患者(OTRs)の臨床管理は依然として困難であると説明している[18]。OTRは一般的に生涯にわたる免疫抑制療法を必要とするが、これは皮膚がん発症のリスクを高め、これらの悪性腫瘍の臨床転帰を悪化させることと関連している。そのため、OTRでは、疑わしい病変を早期に発見して治療するために、定期的な全身検査などの皮膚がん予防対策が必要である。アフターケアの頻度は、患者の個々の危険因子によって異なる。患者は、毎月の自己検診に加えて、日焼け止めや衣服による一貫した日焼け対策を行う必要がある。一方で、紫外線を避ける必要があると、ビタミンD欠乏症のリスクが高まり、それ自体が悪性腫瘍を含む多くの疾患のリスクを高めることになる。したがって、OTRは25(OH)Dの状態をモニターするか、ビタミンDのサプリメントを摂取すべきである。著者らは、皮膚科医による定期的な皮膚検査を含む、移植センターがコーディネートする学際的なアプローチが、OTRのための最善のケアを保証するために必要であることを強調しなければならないと結論づけている。
では、日焼け止めのリスクとベネフィットに焦点を当てている。第18章の「」では、Katherine S. Glaser*とKenneth J. Tomeckiが、米国では過去0年間、非黒色腫皮膚がんと黒色腫の発生率が上昇していると説明している[8]。紫外線(UVR)への曝露は、これらのがんの最も予防可能な環境的危険因子である。日光浴を避けることはもちろん,日焼け止めが最も効果的な保護手段であることに変わりはない。UVRは、DNAに直接ダメージを与え、活性酸素の生成を通じて間接的に細胞にダメージを与える。現行の日焼け止めは、吸収と偏向という2つの主要なメカニズムでUVRを防止する。米国では、FDA(Food and Drug Association:米国食品医薬品局)が、一般用医薬品とみなされる日焼け止め製品を規制している。2011年にFDAの新しい試験および表示要件が発表され 2014年にはSunscreen Innovation Actが制定されたことで、日焼け止めメーカーは、製品をサンプロテクションファクター(SPF)だけでなく、ブロードスペクトラムUVAプロテクションについても評価することが求められるようになった。米国皮膚科学会と米国小児科学会は、適切な日焼け対策と日焼け止めの使用方法について具体的な推奨事項を示しており、国民の意識向上と適切な日焼け対策の遵守を継続的に目指している。抗酸化物質、フォトリアーゼ、植物ポリフェノールは、UVRによる皮膚への免疫抑制効果を調整すると考えられる日焼け止めの添加剤として、あるいは単独で外用剤や経口剤として、興味深い研究対象となっている。著者らは、さらに、UVRは内因性のビタミンDの皮膚産生を誘導するが、食事やサプリメントで推奨量のビタミンDを容易に摂取できることを考慮すると、UVRの有害な作用はこのプラスの効果を上回ると結論づけている。
19章の「A Handful of Sunscreen for Whole Body Application」では、Ida M. Heerfordt、Peter A. Philipsen、Hans Christian Wulfの3人が、「手のひら一杯の日焼け止めを全身に塗る」という経験則が、いくつかの日焼け防止キャンペーンで使われていることを説明している[10]。これは,日焼け止めの塗布量を増やして,手の届く範囲の皮膚に2mg/cm2の量を得ることを意図したものである。本研究では,このアドバイスが実際にどのように機能するかを,塗布した日焼け止めの量と覆った皮膚の量で評価した初めての研究である。方法
水着を着た17人のボランティアに、以下のように尋ねた。”手のひらいっぱいに塗り、体全体に広げる”。日焼け止めを塗る前と後に、ボランティアをブラックライトで撮影した。
日焼け止めはブラックライトを吸収するため,日焼け止めの塗布量が増えるにつれて肌の暗さが増し,カバーしきれずに残った肌を識別することができた。日焼け止めの塗布量を定量化するために、日焼け止め容器の重量を前後で測定した。結果は以下の通りである。中央値で21%のアクセス可能な皮膚が完全にカバーされずに残されていた。79%のカバー領域は,中央値1.12mg/cm2で覆われており,期待された2mg/cm2ではなかった。著者らは、実際には、次のようなアドバイスがあると結論づけている。実際には、「手のひらいっぱいに日焼け止めをつけて、体全体に塗ろう」というアドバイスは、意図した効果に比べて、より良い保護効果をもたらしたが、まだ控えめであったと結論づけている。
第20章では、「紫外線暴露のシナリオ。Ann R. WebbとOla Engelsenは、「Ultraviolet Exposure Scenarios: Balancing Risks of Erythema and Cutaneous Vitamin D Synthesis」と題した第20章で、ほとんどの人にとって太陽の光を浴びることがビタミンDの主な供給源であると説明している[23]。しかし、公衆衛生上のアドバイスは、紅斑や皮膚がんのリスクがあるため、無防備な肌の露出を避けることに主眼が置かれてきた。ビタミンDの低下には健康上のリスクもあることから、この研究では、ビタミンDとそれに伴う紅斑リスクに関するさまざまな目標値を達成する可能性を探った。彼らは、提案されたいくつかのビタミンD経口等価用量を得るために必要な被ばく量を、緯度、季節、肌のタイプ、露出した皮膚面積の関数として計算し、関連する紅斑のリスクを最小紅斑用量で表した。モデルの結果から、推奨される1日の摂取量400IUは、正午の昼食時に気軽に日光浴をすることで、1年のうちのある時期には全緯度において、またある(低)緯度地域では1年を通して、紅斑のリスクなしに容易に達成できることがわかった。Ann R. WebbとOla Engelsenは、暖かい季節に下腕と下肢を露出させておけば、夏季の昼食時に1日1回、大麻以下の量を摂取するだけで、英国の全天候型の顧客が冬季のビタミンD欠乏症を回避するのに十分であることも示している。提案されている1000IUという高いビタミンD投与量でも、昼食時の日光浴はビタミンを摂取するための有効な手段であるが、より広い範囲の皮膚を露出させる必要があり、1年のうちの短い期間でしか効果が得られないことになる。ビタミンDの必要量が最も高いとされたのは、1日あたり4000IUであった。地球上の多くの地域、そして1年の多くの期間において、これはランチタイムの1時間では達成できず、可能な場合でも紅斑を防ぐために広い範囲の肌を露出しなければならない。肌タイプのみを考慮した場合、適量ビタミンDの生成に関する緯度および季節の制限は、肌タイプ2よりも肌タイプ5の方がより厳しいものであった。
第21章では、「The Paleolithic Nutrition Model in Relation to Ultra-violet Light and Vitamin D(旧石器時代の栄養モデルと紫外線およびビタミンDとの関係)」と題された最後の寄稿で、Reinhold Viethは、近年、25-ヒドロキシビタミンD(25(OH)D)の循環レベルに関して、食事政策が何を目標とすべきかについて、様々な議論が行われていると説明している[22]。彼は、食事のガイドラインは、リスク・ベネフィット・プロファイルに従っていると説明している。さらに、Reinhold Viethは、栄養政策立案者にとっての出発点は、一般的に健康とみなされる人々の典型的な栄養素の摂取量とレベルであると指摘している。要するに、パンデミックしている状態が出発点であり、栄養や政策には、その出発点からの変化を促すためのエビデンスが必要であるとする視点である。ラインホルド・ヴィース氏の素晴らしい論文の目的は、より生物学的な観点を提示することである。彼が指摘しているように、旧石器時代の栄養学は摂取した食物に焦点を当てているが、旧石器時代のモデルは食事を超えて環境を取り入れており、これは太陽光線の照射やビタミンDの摂取といった健康政策にも同様に関連している。生物学的な考え方は、病気のリスクには進化論的な背景があり、現代の人間の文化や環境は、自然や最適なものに代わるものではないだろうという大前提から出発している。ラインホルト・ヴィースは、自然淘汰とは、生殖に適したゲノムのマッチングを最適化するプロセスであると指摘している。しかし、緯度、衣服、太陽を避けることによる環境的ストレスは、人間の健康、病気、死亡率の多くの側面に関係している。政策立案者の伝統的な視点は、より多くの太陽やより多くのビタミンDの摂取が利益をもたらすという圧倒的な証拠がない限り、既存の規範を守ることである。しかし、人類の健康にとって最適なものは、最初の人類の環境と文化から始まると考えるべきであるという、別の視点が注目されている。ラインホルト・ヴィースは、原人が経験した日光浴を最適とみなすべきであり、日光やビタミンDへの曝露が減少することで人間の健康が損なわれるのはどの時点か、という従来の政策集団のアプローチを覆すことが合理的であると結論づけている。さらに、そのような環境剥奪に関する二重盲検プラセボ対照試験がなぜ行われないのかと問いかけている。どの程度の環境剥奪も、それを裏付けるレベル1の医学的証拠はない。
