Contents
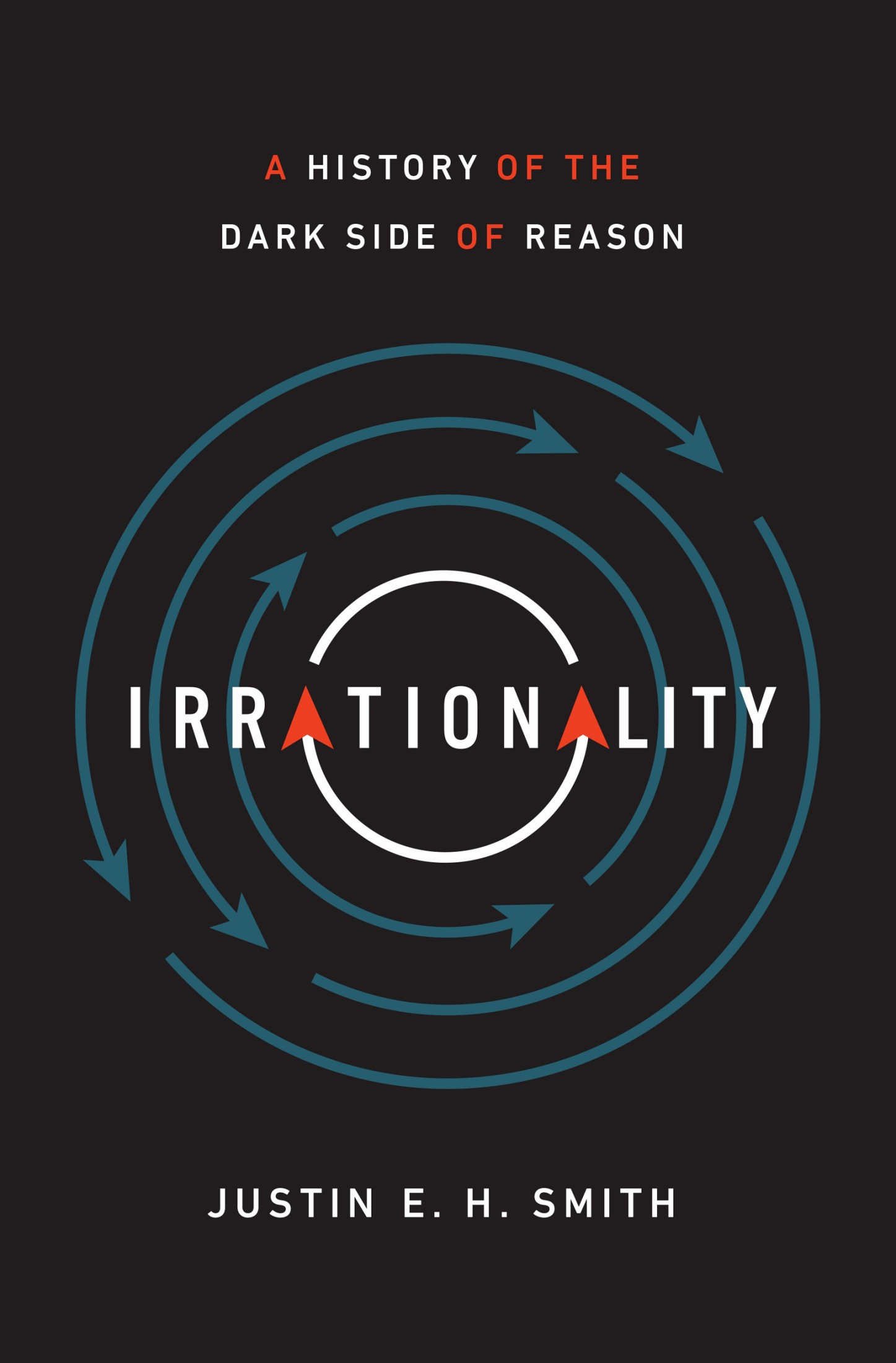
目次
- タイトルページ
- 著作権ページ
- 献辞
- 跋文
- 目次
- 前文 ある数学者の殺人
- 序文
- 理性の双子
- 神話への啓蒙
- 現在という瞬間
- 不合理 ロードマップ
- 第1章 自滅するタコ、あるいは、論理学
- 虚偽の操作
- 爆発
- カスパー・ハウザーと合理的選択の限界
- 語りえないものを語りつづける
- 第2章. 「ノー・ブレーナーズ」、あるいは自然界の理性
- 秩序ある全体像
- ブルート・ビースト
- 不完全な超能力
- 小さな痛点
- 第3章 理性の眠り、あるいは、夢
- 目覚めのとき
- 掟破り
- 霊、蒸気、風
- 声を聞く
- 苦い小さな胎動
- 追記:ファブロスム
- 第4章 夢を物に変える、あるいは芸術
- 多くの世界
- ブリーディング・アウト
- ジーニー、ジーニアス、インゲニウム
- 芸術とは何か?
- 二つのマギステリア
- 第5章 「不条理だから信じる」、あるいは「疑似科学」
- 星から地球へ
- 百花繚乱
- 代替事実、そして事実の代替物
- 二十一世紀におけるパラノイア・スタイル
- 第6章 啓蒙、あるいは神話
- より良い光
- 馬に乗った世界-魂
- 詩的な歴史
- 神話への啓蒙、再び
- なぜ民主主義なのか?
- 第7章 人間の野獣、あるいはインターネット
- エスカルゴティックな騒動
- 現代のシヴァ神
- 宇宙人は人間ではない
- さらなるジェンダー・トラブル
- 極端な時代
- 第8章 爆発、あるいはジョークと嘘
- 無の世界へ
- シャルリー・エブドとその後
- Pseudologia Generalis
- クロッキング
- 第9章 不可能なシロジズム、あるいは、死
- 長い目で見れば、私たちは皆、死んでいる。
- ラディカル・チョイス
- 青春とリスク
- 不可能なシロギズム (The Impossible Syllogism)
- 私を縛ってみよう
- カーゴ・カルト
- 愛に満ちた繰り返しの中で
- 結論
- 謝辞
- 注釈
- 書誌事項
- 索引
フランシスコ・ゴヤ『理性の眠りは怪物を生む』(1799)。
ジャスティン・E・H・スミス
プリンストン大学出版局
プリンストン・オックスフォード
あらゆる哲学には、ある種の後方部分、つまり非常に重要な部分があり、それらは、頭の後部のように、反射によって最もよく見えるものである。
-ハーマン メルヴィル『コンフィデンスマン』(1857)
前文
ある数学者の殺人
紀元前5世紀、タラント湾。彼らは、彼の息が切れるまで、その頭を海中に押さえつけた。この4人は、宗派の中で最も学問のない者の中から指導者自身が選んだもので、数学の理解力のなさを忠誠心を高めるための熱意で補った屈強な男たちだった。彼らは、貧しい犠牲者が網を引き上げるために船の側に行くのを待ち、彼の手足が痙攣しなくなるまで手を放してはいけないと指示された。彼は何が起こるかわからず、濡れたロープを船上に上げると、これから現れるであろうピッケルやボラのことを熱心に考えていたが、そのまま死の恐怖のビジョンに変わった。
人は宗派の秘密を裏切ることはない。ましてやその秘密が宗派の土台を崩すような場合はなおさらである。しかし、ヒッパソスはそれをやってしまったのだ。ピタゴラス学派を笑う人たちの間で、ローブを着ていない人たちの間で、物事のいわば足し算の方法にちょっとした問題があることが噂になったのだ。世界は数、比率、割合、理性から構築することはできない、なぜなら数学は芯から腐っていると彼らは言い始めていた。もし世界が数から作られるなら、それは数と同じように不合理でなければならない。このことは、最近宗門が正方形の対角線から発見したことである。対角線は正方形の辺と釣り合わない。それを計算しようとすると、自然な終わりのない十進法に行き着くのである。どうしてでしょう?その数が何であるかについて確定的な事実がないのなら、それが世界の特定のものを特徴づける数であるはずがないだろう。いや、これは間違っている。不合理だ。これを漏らした者は必ずや死ぬであろう。
この伝説の最初の記録は、イアンブリコスからだ。メタポントゥムのヒッパソスは、ソクラテスより100年ほど前に一時期活躍したピタゴラスの哲学者であるが、そのヒッパソスが溺死したという伝説である。この伝説の最初の記録者は、7世紀後に書いたが、ヒッパソスが海に投げ込まれたのは、宗派の仲間ではなく、神々によってであり、彼はそれが不合理の本質を明らかにした罪ではなく、宗派以外の者に球体に正十二面体を刻むというあまり議論の余地のない技術を教えたからだと信じているようだ1。イアンブリコスから数百年後の4世紀、アレクサンドリアのパッポスは、ヒッパソスが正方形の対角線の謎を明らかにしたために故意に殺されたと、ほぼ千年後に初めて示唆したようだ2。
この物語は、スタンリー・キューブリック監督の1969年の映画『2001年宇宙の旅』の冒頭のシーン、つまり原始人が骨を武器として使う力を発見し、最初は下等なバクを殺し、次に仲間のヒト科の動物を支配し殺す瞬間の哲学的アナロジーと考えなくはないだろう。科学的発見、技術革新、認識の飛躍的進歩は、人間の合理性を一歩前進させるが、それは同時に新しい暴力のエンジンとして機能し、世界がそれまで知らなかった新しい形の暴力を生み出す手段を提供するものでもある。合理性と残忍性は人類の歴史の両極にあり、骨から作る武器、火のコントロール、文字、火薬、インターネットなどの新しい技術革新は、それぞれの備蓄を増やすものである。私たちが思い浮かべた基本的にフィクションであるヒト科の動物とギリシャ人のケースでは、主人公の中で何かがクリックされ、そして彼、または私たちは運命づけられている。この「カチッ」という音は、神話ではパンドラの場合のように、外箱が開くという形で表現されることがあるが、内的な出来事、啓示、突破口と考えた方がより正確だろう。
新しい力は新しい危険を伴い、新しい暴力の機会をもたらす。このような例は、科学と技術の歴史から簡単に挙げることができる。素晴らしい理論的発見が、同時に人間の破壊の新たな章の始まりとなるのだ。ジェームズ・メリルは、1982年の詩『The Changing Light at Sandover』の中で、「物質の中心にある力」について次のように書いている。「目覚めさせるために茨を切り裂いて口づけをした」その力は、次のようなものである。
はげしく見開いた目で、息を吸いながら
そして、新たなメガデスの公式を語るだろう。
この言葉は、有名なスラッシュ・メタル・バンドの名前にもなっているが、実際には、核爆発による100万人の死という単位である。メリルは、このような単位で実際に計算をする可能性は、自然を探究し、理性によってその仕組みを理解しようとする私たちの欲求と切り離すことはできないと考えている。道具の使用、幾何学、理論物理学、これらはすべて、私たちの中の最良と最悪の部分を引き出してきたという点で共通しているように思われる。また、人類の歴史を冷静に振り返ると、進歩も退化もなく、問題解決と問題創造のバランスは永遠に変わらない。人間の精神の最も高貴な能力を発揮する場は、筋肉を柔軟にする場でもあり、それでも不十分な場合は、打撃を与える場でもあった。
パッポスの言うヒッパソスのケースは、ある意味ではこの長く繰り返される歴史の中の一つに過ぎないが、同時に何か特別なものがある。核兵器をもたらした発見は、世界の仕組みについて不合理なことを明らかにしたのではない。世界は、人間の生活に適合するには熱すぎたり冷たすぎたり、腐食したり切断したりする多くのもので構成されていることを、私たちはすでに知っていた。これらの発見は、私たちが互いに悪意を持って、より大きなスケールで行動する機会を増やしただけなのだ。ピタゴラス学派は、数学に代表される合理性を一種の崇拝の対象としており、まさにこの崇拝の表現として数学を研究し、その結果、崇拝の対象としているものの中心にある不合理性を知らず知らずのうちに発見し、その結果、不合理な暴力を自分たちの一人に放つことになるからだ。この一連の流れは、狭義の科学技術史から、社会史や政治史へと私たちを導き、その章はしばしば、まさにこの種の弁証法的な動きによって特徴づけられる。
これは合理性の歴史であり、したがって、合理性に付随する非合理性の歴史でもある。理性の高揚とその反対を根絶しようとする願望、人間生活における非合理性の必然的な耐久性、非合理性を排除しようと定めた運動において、おそらく特に、少なくとも困ったことに、非合理性に対する防壁として定めた思考と社会組織のまさに潮流が、最終的に非合理の自己破壊に陥っていくこと、である。個人レベルでは、非合理性は夢、感情、情熱、欲望、影響として現れ、麻薬、アルコール、瞑想によって強化される。社会レベルでは、宗教、神秘主義、物語、陰謀論、スポーツファンダム、暴動、レトリック、大衆デモ、決められた役割からはみ出す時の性欲、楽譜の音符から離れ、独自の生命を持つ時の音楽として表現される。それは人間の生活の大部分を包含しており、おそらく人類の歴史のほとんどの時代を支配してきた。しかし、人類がそれをうまく抑制していると自らを納得させるような歴史的な時代は、ほとんどない。
はじめに
理性の双子
過去数千年の間、多くの人類は、戦争と暴力の混乱、満たされない情熱や過剰に満たされた情熱の苦痛、獣のように生きることの堕落など、私たちが生まれながらにして抱えている混乱から抜け出す希望を、人類という種のすべてのメンバーが持っていると噂される、ある一つの能力に託してきた。私たちはこの能力を「合理性」あるいは「理性」と呼んでいる。理性は古代ギリシャで発見され、ヨーロッパで近代が始まると、ほとんど神格化されたとよく言われる。その象徴が、1789年のフランス革命で没収されたカトリック教会に短期間設置された「理性の殿堂」であろう。中世の崇高な礼拝堂を再利用することは、同時に、理性に従って人生を歩み、合理的な原則に基づいて社会をモデル化しようとする人間の努力に、否定しがたい矛盾があることを示す。理性的な神殿を与えることは、何か不合理なことであり、実に不合理なことである。その中で人は何をすればいいのだろう?祈るのか?お辞儀をするのか?しかし、それは、私たちが解放されるはずの教会で、それまで礼拝者が行っていたのと同じひれ伏し方ではないだろうか?
理性の勝利は一時的なものであり、元に戻すことはできない。物事を恒久的に整え、過激主義を追放し、合理的な原則に基づいて構築された社会の中で、すべての人に快適で静かな生活を確保しようとするユートピア的努力は、初めから破滅的なものなのである。この問題は、明らかに弁証法的な性質を持っている。望むものはその反対を含んでおり、社会を合理的に構築しようとする真剣な刺戟は、遅かれ早かれ、まるで自然法則によって、非理性的暴力の噴出へと交差していくのである。理性を求めて必死になればなるほど、理不尽に陥ってしまうようだ。合理性を押し付け、人や社会をより合理的にしようとする欲求は、原則として、非合理性の壮大な爆発へと変異する。その反動としてロマンチックな非合理主義を引き起こすか、あるいは、合理性とは力によって、あるいは賢明な少数の者が愚かな大衆を支配することによって押し付けられるものだという支離滅裂な考えを、その最も熱心な推進者に植え付けるのである。
本書は、豊富な図版と有益と思われる装飾によって進行するが、その核心は単純である。社会と私たち自身の精神的能力の行使の両方において、非合理性を排除しようとすることは非合理であるということである。排除しようとすると、フランスの歴史家ポール・ハザールが「攻撃的な理性(la Raison aggressive)」と呼んだように、その結果は非合理的なものとなる1。
神話への啓蒙
合理性と非合理性の両極の間の絶え間ない動き、つまり、理性がその反対側に変貌する攻撃的な方向性については、テオドール・アドルノとマックス・ホルクハイマーが1944年に発表した記念すべき著作『啓蒙の弁証法』で詳しく説明している2。つまり、万人のために社会の問題を解決するための理性の完成と応用に基づいた社会哲学が、ファシズムに変容し、硬化する可能性についてである。
1944年以来、実に多くのことが起こった。アドルノとホルクハイマーは先見の明があり、現在もその関連性を保っているが、彼らが予想できなかったことも多くある。マルクス主義は、学者にとって世界史の流れを理解するための貴重な分析ツールであり続けている。革命によって社会主義を確立しようとした最初の大きな試みが20世紀末に崩壊した今も、急進的な経済的再分配を目指す革命運動は、世界中の多くの人々にとって魅力的であり続けるのである。21世紀初頭、私たちはまだトランプ・プーチニズムという新しい現象を理解するのに苦労している。それは、その思想的な漠然さにおいて前例のないように見えるが、同時に、この直近の時代まで、願望や理想としての牙城をアメリカに置いていた自由民主主義の終焉、あるいは少なくとも生命にかかわる危機を明確に告げるものであるようにも思えるのである。
アドルノとホルクハイマーは、20世紀半ばに君臨した自由主義政治イデオロギーの反復(彼らの見解ではイデオロギーの不在を装っているだけ)が、自然にファシズムに向かう弧を描いていることを予言したとされている。最近、ドナルド・トランプの台頭によって米国で局所的に屈折したポピュリズムの世界的な高まりも、同様に、あるプロセスの必然的な帰結に過ぎないと主張する人たちがいる。リベラル・デモクラシーが脱皮し、出現したものは、ファシズムの巧妙な蛇か、ポピュリスト的ナショナリズムのありふれた庭の蛇か、さまざまに識別される。いずれの場合も、太陽の光を浴びて奇妙な亡命をした洞察力に富むドイツのマルクス主義者二人が、数十年も前に予測した出現であった。トランプは、ワシントン、ジェファーソン、リンカーンの後継者であるかのように装っているが、彼らが行ったのと同じことには関心を示さない。「アメリカを再び偉大にする」という命令は、かつてアメリカがそうであったという神話に根ざしており、それは啓蒙主義、すなわち私たちが誰であり、実際にはどこから来たのかを知ることとは根本的に相容れないものである。アドルノとホルクハイマーの公式が実現した。啓蒙主義が神話に回帰した。ドイツの作家たちは、このことを啓蒙主義そのものに問題があると考えたが、この後の章で見るように、他の説明も存在する。
いずれにせよ、トランプ自身が反啓蒙主義的なイデオローグであることは全く明らかではない。彼は、そのような明確なコミットメントに必要な明晰さや成熟さを持ち合わせていないように思われる。しかし、彼はそのようなイデオローグに囲まれてきた。彼は彼らの支持から利益を得て、反啓蒙主義の非合理的な代理人とは言わないまでも、少なくともその亜合理的なベクトルとなっている。彼の台頭は、啓蒙主義哲学の中核的な公約に対する首尾一貫した批判を明確にする多くの作家や人物が知的風景に登場するのと歴史的に一致している。第1に、私たち一人ひとりに理性が備わっており、自分自身と自然界や社会における自分の位置を知ることができる。第2に、社会の最良の構成とは、私たちが個人として成長し、社会のために自分なりの貢献をするために、理性を自由に使えるようにするものである、というものである。この大まかな啓蒙主義の定義に、さらに細かい修正を加えることも可能だろうが、今のところこれで十分だろう。特に、トランプやウラジーミル・プーチンとそのエピーギョン、ポスト啓蒙主義、ポスト民主主義の価値観を、時に意識的に、時に無意識的に醸成しているシリコンバレーの新参者たち、そして、平等や民主的参加といった社会にとって長く望まれてきたものを否定し、今のところ何とか「先鋭的」な知的風景に身を置いている様々な思想家たちが、今攻撃を受けているものが何かを理解するには十分なものであろうと思われる。
啓蒙の弁証法-ここでは本ではなく、その過程を意味する-は、マルクス主義者だけでなく、よく研究されてきた。新保守主義的なフランスの思想家、パスカル・ブリュックナーでさえ、1995年にはすでに、個人主義がその究極の論理的終着点として部族主義を持つと論じていた。
1973年の論文で「反啓蒙主義」という言葉を英語で広めたのは、リベラル派の哲学者アイザイア・バーリンである。ジーブ・スタンヘル(Zeev Sternhell)が指摘するように、この言葉はドイツ語ではGegen-AufklärungとしてFriedrich Nietzscheに初めて登場し、20世紀初頭のドイツで広まったものである。スタンヘル自身、リベラル派の思想史家として 2006年に『反啓蒙主義の伝統』という重要な研究書を発表している。そこでは、エドマンド・バークやJ・G・ヘルダーの仕事が、近代政治思想史にとって重要であることを詳述している。スタンヘルによれば、この二つの傾向は18世紀に共に生まれ、この時代は「合理主義的近代の誕生を示すだけでなく、そのアンチテーゼをも示す」4。テーゼとアンチテーゼが歴史的、概念的に共に現れるとすることは、反啓蒙を啓蒙の反対というよりは双子として、理性を反対というよりは統一され不可分の全体の暗部として見ることである。
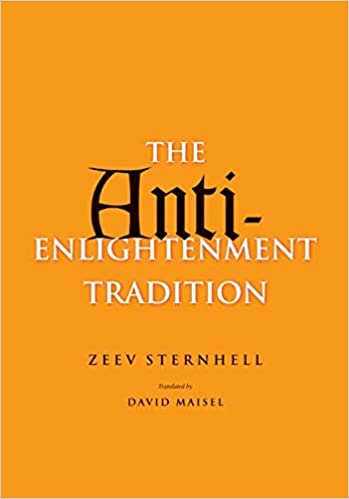
シュテルンシェルが指摘するように、反啓蒙主義は、運動や感性として、その名称が与えられるずっと以前から存在していた。18世紀初頭のナポリの思想家ジャンバティスタ・ヴィーコは、やがて啓蒙主義が普遍的なものの重要性を強調するようになるのに対して、救いようのない個人を重視する世界観を初めて明確にした人物であると彼は見ている。シュテルンシルの分類法は、啓蒙主義者と反啓蒙主義者の間の分裂のどちらの側に誰が属するかというもので、このような分類法の試みは実際そうでなければならないように、時に特異なものである。例えば、彼はジャン・ジャック・ルソーをフランス啓蒙主義の中心的人物と位置づけている。最近では、パンカジ・ミシュラ (Pankaj Mishra)が『Age of Anger』 また、パンカジ・ミシュラは『怒りの時代-現代の歴史』の中で、ヴォルテールの啓蒙思想とルソーの特殊主義を対比している。その象徴が、ポーランドの民族自決権問題をめぐる両者の立場であるとミシュラは考える。ヴォルテールは、ロシア皇后エカテリーナに仕え、ポーランド人は絶望的なまでに後進的で見識のない人々であり、そのことがロシア帝国によるポーランド征服の正当化に役立つと考えていた。そのため、ヴォルテールは、ポーランド人を力づくで啓蒙しなければならないと考えた。
一方、ルソーは1770年代初頭に書いた『ポーランド統治に関する考察』で、ポーランドは自国の習慣を維持し、均質化した汎ヨーロッパ文化に吸収されることを許すべきではないと主張した。このような文化的抵抗ができれば、外国勢力による政治的支配のもとでも、国民を完全に服従させたり消滅させたりすることはできない、とルソーは考えている。ルソーは、「ポーランド人がロシア人にならないようにしなさい」と書き、「ロシアがポーランドを服従させないことを保証する」5と書いている。ミシュラは、この二人の思想家のそれぞれの立場を、近代思想の全く異なる二つの系統の始まりに位置づける。ヴォルテールは、啓蒙主義を力づくで普及させようとする熱意と、物事を正しく行う方法は事実上ひとつしかなく、社会がどのように組織されるべきかという普遍的な基準があると信じていたが、その後裔として 2003年の新保守主義者が主導したイラク侵略のような失敗した冒険をすることになるであろう。ルソーは、20世紀から21世紀にかけて、普遍主義的な帝国主義やグローバリズムに抵抗する反覇権勢力、たとえばイスラム原理主義や、Brexitやドナルド・トランプの当選につながったさまざまなポピュリズムの祖先でもあるのだ。
この啓蒙主義は、右翼のポピュリズムの誘惑にも、左翼に出現したアイデンティティ・グループへの引きこもりやそれに伴う特権階層への偏愛、特に多くのアメリカの大学生の心を捉えている憤怒のアイデンティティ主義にも影響を受けない思想家や専門家たちによって推進、賞賛され、過去数年間にアメリカで再び広く世間の注目を集めるようになった。この両極を否定する思想家のなかには、個人の理性と自律性を否定する同じ非自由主義者の異形な表現と見なし、現在「急進的中道主義」と呼ばれるものを主張する者もいる。特に心理学者のスティーブン・ピンカーは、啓蒙主義の遺産を右派と左派の両方で広く、概して無反省に否定している現在の歴史的瞬間に、人類の進歩に対するその真の貢献を再評価して擁護すべき時であると、その功績を認めている。ピンカーの2018年の著書『Enlightenment Now:』しかし、ピンカーは、啓蒙主義哲学を科学的合理性と混同していると批判されることもある。
ピンカーの著作に向けられる一般的ではないが、それに劣らず深刻な批判は、私たちが啓蒙の弁証法と呼んできたものに対する彼の感受性の欠如と関係がある。ピンカーは、アドルノやホルクハイマーについてほとんど言及していないが、それ自体は必ずしも誤りではない。しかし、欠陥があるのは、啓蒙主義がその反対を内包していることは、その時代の哲学的・政治的遺産を現代に回収することに専念した本において、真剣に注目するに値しないという根拠のない前提にあることだ。この内包を真剣に受け止めなかったことは、左翼の立場にあったアドルノとホルクハイマーが最も関心を寄せた、自由主義からファシズムへの変異のようなものに対する真剣な検討が行われないことを意味するだけではない。例えば、1791年の世界人権宣言の擁護者たちが、オリンピ・ド・グージュのフェミニスト的反撃である「女性と女性市民の権利の世界宣言」を受け入れることを拒否したり、多くのフランス革命家たちが、彼らを鼓舞する価値がサン・ドミンギュの奴隷を反乱に駆り立てかねないと受け入れることを拒否したりしているのだ。これらは基本的によく練られたプログラムにおける単なる不具合ではなく、むしろ啓蒙主義が自らを矛盾させ、弱体化させる方法は、このプロジェクトにずっと内在していたという趣旨の、真剣な議論がある。たとえこれらの議論を否定したとしても、それらは周辺から来たものではないので、取り上げるに値するものである。
啓蒙主義からさらに下流に位置するのがジョーダン・B・ピーターソンで、彼は最近、まるでアドルノとホルクハイマーのテーゼを特に私たちに説明するかのように北米の文化シーンに登場した。ピーターソンは「古典的リベラル」を自称しているが、彼が獲得した支持は、不満を抱く若い男性のアイデンティティ主義が自然発生的に凝集したものと理解した方がいいかもしれない。つまり、人種差別、性差別、その他の抑圧が日常の社会的現実を構成し、意識的かどうかにかかわらず、すべての人の経験の幅を規定していることに、おおよそ同調している、おそらく超同調しているということである。ピーターソンのファンは、こうした覚醒したサークルから事実上排除されており(「味方」という平伏した無様な役割を引き受ける覚悟がない限り)、彼らは憤慨と新たに見出した自らのアイデンティティ主義的意識で、彼のもとに集まってくるのである。彼が引き寄せる群衆に罪はないかもしれないが、それ自体から見ても、啓蒙主義の後継者であるという彼の主張は、啓蒙主義が実際には何であったか、そしてその遺産が複雑に枝分かれしていることをあまり理解できていない。彼の永続的な関心事のひとつは、20世紀の国家共産主義がもたらした破壊である。アドルノやホルクハイマーがファシズムだけを啓蒙主義の弁証法的対極に位置づけるのとは異なり、ピーターソンは左翼権威主義を、彼が好むと主張する政治・社会哲学の単純かつ直接的な対極、つまり非弁証法的なものと捉えている。これは明らかに、1917年のボルシェビキから1970年代後半の大量虐殺を行ったカンボジア政権まで、20世紀の労働者と農民のさまざまな革命が、1791年の世界宣言に明示された哲学と実際に系譜をなしていること、それは啓蒙主義の哲学精神の蒸留物とみなすことができること、を見落としている。これは、クメール・ルージュを生み出した啓蒙主義を非難するのではなく、啓蒙主義の継承者であると主張する際に、他のすべての道を歩んだ継承者を認めない者は、たとえ疎遠であったとしても、誰も真剣に受け止めるべきでないという当たり前のことを認めるに過ぎないのだ。啓蒙主義は確かに擁護に値するものかもしれないが、少なくとも、非自由主義的な左派が言うように、啓蒙主義は十分に「問題」であり、その真剣な擁護者たちは、そのすべての欠点、人間の可能性に関する自らのビジョンを実現できなかったすべての方法を直視し、その説明を試みる義務を負っている。
今この瞬間
これは本であり、ソーシャルメディアの投稿ではない。そのため、原稿の最終提出から印刷されるまでの数ヶ月の間に、クリックの力だけで一時的に浮上した無名の人物に過度に関与するのは賢明ではないかもしれない。だから、私たちは、現在、安全に正典とされている資料に忠実であろうとする。正典とされる著者たちがどのように物事を分担し、どのような政治的志向をもって歴史学に臨もうと、アドルノとホルクハイマー、ベルリン、シュテルネル、ミシュラ、その他の著者は、近代思想史において普遍主義と特殊主義との間に基本的緊張が存在したことに同意し、説得力を持って示している。つまり、人類はすべての民族に等しく共有される自然によって一つの運命を担っていると考える人々と、各集団にはゾンダーヴェーグ(特殊な道)があり、そのために正しいことやふさわしいことが他の文脈に翻訳できず、ある集団の達成度を他の集団と比較したり順位づけしたりする階層的な仕組みの中に位置づけることができないと考える人々との間にある。この非常によく知られた物語を再び暗唱するつもりはない。たとえ、私たちの関心事が、この物語をよく暗唱してきたすべての人々の関心事と大きく交差することは避けられないとしても、である。啓蒙主義や反啓蒙主義の歴史家は、一般に、社会を組織する上で最良の理想や価値とは何 か、という理論に主に関心を寄せてきた。一方、反啓蒙主義者は、理性を常に称賛するわけではないにせよ、少なくともその反対を社会組織の最高原理として設定することには慎重であった。これらの著者は、ほとんどの場合、近代哲学において人間の心の特定の能力として概念化される理性にはあまり注意を払わず、啓蒙主義の政治哲学(プラトン共和国の中心的洞察を引用)が結局は人間の心の哲学である点にも注意を払っている。あるいは、19 世紀初頭にジェルメーヌ・ド・スタエルが言ったように、「社会秩序の基盤をなす原則の維持は、哲学に反するものではありえない、これらの原則は理性と一致 しているのだから」7。
魂と都市、個人と国家という二つの尺度の間を行き来することが正当化されるかどうかは別として、実のところ、プラトンがそうしたように、同時代の人々は自由に行き来しており、個人が本当に社会の縮図なのか、一方について学んだことが同時に他方にも当てはまるのか、と問うことは滅多にないと理解しておくことが重要であろう。したがって、ソーシャルメディアが私たちの認知機能や社会秩序に及ぼす影響という、今や共通のテーマに関する最近の報道例を挙げると、ポール・ルイスは2017年末のガーディアンの記事で、「アップル、フェイスブック、グーグル、ツイッター、インスタグラム、スナップチャットが、私たち自身の心をコントロールする能力を徐々に削り取るとすれば、民主主義がもはや機能しない時点が来るのではないか、と私は問いたい」8と書いている。そのようなコントロールの喪失は、まさに私たちがしばしば合理性と呼ぶものの喪失であり、必然的に社会の最良の配置の喪失でもあるのだろうか。
啓蒙主義の社会哲学が構築されたはずの理性という精神的能力に関する考察の歴史は、もちろん近代の始まりよりずっと前にあるのだが、たとえそれがアドルノとホルクハイマーの意味で広く神話化されるようになったのは近代に入ってからだ。古代ギリシャの初期には、それが広く共有される市民の美徳というよりは、ピタゴラス派のような奇妙なカルトのフェチのようなものであったにせよ。
私たちが「西洋」と呼ぶ地域とそこに住む人々の価値観は、世界史の中で独特の位置を占めており、「その他」と韻を踏んで蔑まれることのある地域とは異なる業績と記念碑を生み出していると多くの人が信じている。この見解に反論するのがここでの私の直接の目的ではないが、おそらくその方向で少し話をすることは有益だろう。ヨーロッパ人が初めてアメリカ大陸と出会ったとき、ヨーロッパはユーラシア大陸の半島で、比較的取るに足らない、つまり比較的生産性の低い、未完成の国だった。活動の中心はフランス、オランダ、イギリス、ドイツではなく、むしろ地中海、中東、中央アジア、東アジアであった。ヨーロッパが私たちの考える世界の中心になり始めたのは、より広い大西洋地域と極めて集中的な経済的共存を始めた瞬間であった。さらにこの時から、ヨーロッパは世界の他の地域をその中に取り込むことを使命とし、宿命とした。西欧化を必要としていると見なされる非西欧がその外側にない限り、「西欧」は存在しない。ヨーロッパはそれ自体では何もない。世界のどの地域も、過去にそうであったことはなく、またそうなりえたこともない。これは、ヨーロッパとその延長を軽視しているのではなく、基本的な地理的・歴史的リテラシーの問題に過ぎない。これは、最近の極端なアイデンティティ主義的政治に明らかに欠けているものであり、この怠惰な無知を破壊することが私の目的の一部なのである。
この無知は、最近ますますひどくなっている。真のコスモポリタニズムの時代が到来したと思われた矢先、世界中の社会が粗野なナショナリズムに退却し、世界の民族の中で自分たちが特別な地位にあるという幼稚な神話詩的説明を作り出したり復活させたりしている。例えば、古代インド人が飛行機を発明したとか、ヴェーダに飛行機のことが書かれているとか、神的または生物学的に定められた自分たちのゾンダーウェイのようなものである。主に、あるいは明らかにヨーロッパの血を引くアメリカ人の中には、ハプロタイプのように薄っぺらで、ほとんど理解されていないものをフェチとするアイデンティティ主義を受け入れている人がいる。それは、牛乳そのものが白いからであり、また、数千年前にヨーロッパ人の祖先の間で遺伝子の突然変異が起こり、乳糖耐性が相対的に優位になり、その結果、生存に有利になったと漠然と考えているからである9。旧石器時代にはそうであったかもしれないが、現在では、このような文化的な誇りが不思議なほど強く、その原動力を理解せずにはいられなくなっている。
インターネットが、公的な場における不合理主義の爆発的な増加に大きく寄与していることは否定できない。白人至上主義の酪農党は、文化的熱狂の瞬間の無数の表れの一つに過ぎず、持続不可能な強さで、新しい政治規範と新しい制度構造に支えられた、習慣と風俗の新しい、まだ予見できない風景への移行を示すものであるように思われる。そして、このような変革から最も恩恵を受ける立場にあるのは、周縁にいる人々、つまり失うものが何もない人々なのである。誰でもインターネットに接続し、騒ぎ立てることができる。そして、この悪化した状況から、権力を獲得する、あるいは少なくとも小規模な成功を収めるための新たな機会が生まれることを、周縁から荒らすときに望むのは難しいことではない。このように、インターネットは「加速主義」と呼ばれるものの偉大な手段である。失うものが何もない人々が、予見できない方法で早く良くなるように、意図的に状況を悪化させ、現在失うものがある人々には恐れる理由がある。これは、インターネットが革命的な道具であることの一面でしかない。
インターネットが、ジャーナリズム、学問、商業、映画産業、出版産業などを混乱させ、場合によっては破壊することを可能にしたように、インターネットもまた、それまで許容できる政治的言説とされてきたものを決定する体制的チェックの回避を可能にした。インターネットは、エミール・ゾラが1890年に発表した同名の小説の中で、鉄道との新しい関係において人類を特徴づけたように、人間の持つ情熱を閉じ込め、触媒し、加速させる装置の新しい変容なのである。
ほんの10年ほど前までは、この新しいフォーラムがユルゲン・ハーバーマスの言うところの「公共圏」、つまり熟議民主主義が行われ、集団的熟議によって最良の決定がなされる場所として機能するかもしれないと、もっともらしく期待することができた。合理的な発言に対する通常かつ予測可能な反応は、それが見知らぬ人からのものであれば、まったくの罵倒であり、しばしば協調的で大規模な罵倒のキャンペーンが行われる。そして、生身の人間であることを確認できた人を相手にしているのでなければ、インターネット上では、罵倒の対象が実在の人物からなのか、ボットや、ロシアのトロール農場で新しい虚偽を世間に植え付けるために働いている操り人形からなのか、わからないことが多い。さらに悪いことに、敵と味方の区別は、私たちと彼らという二項対立に従って社会的現実を切り分けようとする、私たちの生来の、しかし最近まで克服可能であった傾向にアルゴリズムが働きかけ、強化されたことが大きな原因となっているのだ。
さらに最近では、モデレートされていないコメント欄の無知で偏執的で憎悪に満ちた精神が、政治的現実にまで波及し、まさに合衆国大統領という人物に凝集されている。この落下と失敗の原因は数多くある。インターネット上の言説という、私たちがあまりにも長い間、基本的にテキストベースだと考えてきた言説に大量に参加したことで、(インターネット上での私たちの実際の実践が、テキストによるコミュニケーションの歴史における根本的な断絶を示しているにもかかわらず)知らず知らずのうちに、理詰めの議論ではなく、むしろ提案や画像、当てこすり、冗談でしか伝えられない種類の情報に関心が移ってしまったことも、その一端だろう。
理路整然とした議論によって自らの政治的コミットメントを正当化しようとする、あるいは正当化することにまったく関心を持たないインターネット・ユーザーはほとんどいない。その代わりに、ヒラリー・クリントンは病弱だ、バーニー・サンダースは演説をすると演壇に鳥を引き寄せる力を持った魅力的な老人だ、ドナルド・トランプには帝冠と杖が似合う、といった考えを関連付けたり並べたりするミームが増殖し、現実の考察のプロセスを経ずに政治の現実に対する私たちの認識を変化させるのである。私たちがあまりにも長い間、政治討論が新しいメディアに移行していると考えていたことは、実際には、私たちが絵本で知っているような、王女や魔法使い、裸の皇帝といったトロピーの交換に堕落してしまった。これらの人物は私たちにとってあまりにも身近で意味深いものであるため、民話として、これらの文化の単位、ミームが、政治参加が最高の状態で満たすと考えられてきたものとは全く異なる人間の欲求を満たしていることを忘れることができる。
これらの文化の単位は、一時的に想像力を満足させるが、世界は改善されないままである。政治から疎外された人々の慰めであり、政治参加そのものに適した手段ではない。2016年に政治がミーム戦の問題になったとき、私たちは、もはや熟議民主主義に生きているふりをすることができないだけでなく、純粋に文化的なレベルでの政治の追求を優先して、その志さえも放棄した状況に追い込まれた。この「政治」は、記憶された神話や背の高い民話とともに、社会の政治的生活に参加する見込みのない人々が想像力を自由に発揮することに古くから根ざしている。想像力は強力な道具であるが、最も権利を奪われ、情報を得られない人々でさえも、誰も奪われることのない能力であるため、絶望の中で展開されることもしばしばである。ヴァージニア・ウルフの1929年の短編小説「鏡の国の女」の語り手は、このような方法についてこう述べている。ヴァージニア・ウルフの1929年の短編小説「鏡の中の女性:回想」は、イザベラという無口で謎めいた人物に直面したとき、私たちが利用できる方法を説明している。「不条理であり、怪物的である。彼女がこれほど多くを隠し、これほど多くを知っているのなら、手近にある最初の道具、すなわち想像力をもって、彼女を開放的に評価しなければならない」10 想像力は物事を開放的に評価し、特に知識のないときには、それに頼ることになるのだ。想像力は、顕微鏡のスライドの細胞に注入された鮮やかな色の染料のようなもので、見えないものを見えるようにするものであるが、その手段によって、見たかったもの、知りたかったものが歪み、おそらく危険にさらされることになる。
もちろん、政治はある程度までは、最も賢明な時代においてさえも、視覚や示唆、ヒントやほのめかしを通して常に行われてきたし、感情的なレベルで私たちに働きかけてきた。しかし、この仕事を遂行するための新しいツール、つまり創造的想像力と技術的専門知識の両方を兼ね備えたツールは、私たちの政治的運命に対する大きな責任を、技術的知識はあるが議論には疎い人々、ミームメーカー、オンラインのサブカルチャー関係者に譲り渡してしまった。これらの社会部門が、その新しい巨大な力を責任ある方法で行使する用意が必ずしもできていなかったとしても、まったく驚くにはあたらないだろう。
私たちは今、極めて非合理的な、熱狂と歓喜、不安定化と恐怖の瞬間を生きている。私たちがここに到達した経緯の重要な部分は、合理的な手続きと審議を維持するための伝統的な保護措置が崩壊したことと、公の議論にあまりにも多くの有色色素を無意識に注入し、これらの色が当初より鮮明に見えるようにすることを意図した対象を完全に覆い隠してしまったことにあるように思われる。繰り返すが、このような方向性を歓迎する人々も大勢いることは明らかである。むしろ、慎重さや遠慮を重んじる人たちこそ、突然、自分が別の時代に属してしまったかのように感じ、目を覚ますと、自分たちの関心事や習慣、つまり、自分たちの世界がなくなっていることに気づくのである。つまり、紙媒体の購読を続け、本を出版し、人文科学の学位を取得し、主流の政党で主流の候補者を支持し、理路整然とした議論に耳を傾けるといった、古いやり方を維持しようとする人たちである。このような人々は、攻撃と混沌の勢力にインターネットが掌握されたことに最も鋭い失望を感じているはずだ。この瞬間にも、社会における人間の生活を合理的に秩序立てるエンジンとしてインターネットが役立つという壮大な主張が、最も最近の過去から響いてきている。
私たちは、数千年前にヒッパソスが発見した場所からそれほど遠くはないところにいる。ギリシャ人は幾何学の核心にある非合理性を発見した。私たちは最近、アルゴリズムの核心にある非合理性を発見した。少なくとも、非合理性の力による武器化を避けながらアルゴリズムを人間の生活に適用することは不可能であることを発見した。もし私たちが、技術的発見や概念的進歩が私たちの生活から不合理、不確実、無秩序を追い払う力を持っていると信じる強い意志を持っていなければ、つまり、人間の状況についてもっと哲学的になることができれば、私たちの最大の革新の後に常に続くように見える激しい反動を避けるために、おそらくはるかに良い位置にいることだろう。
非合理性 ロードマップ
第1章では、論理について、その限界、乱用、歪曲を考察した。歴史上、論理学はしばしば修辞学と対比されることが多かったが、実際には同様の目的のために共同利用されることも少なくなかったと見ている。この関連で、論理的には完全に正しいのに、不正としか言いようのない目的のために召喚される主張や議論という、独特で研究されていない現象、つまり「虚偽の作用を持つ」真理の現象について考察している。さらに、論理学の歴史における誤謬や詭弁へのこだわりと、それらが時に理性の科学の歪んだ鏡像ともいえるものを生み出すために展開された方法、そして現在では理不尽の科学へと変形していることについて考察していく。狭い意味での論理学の最初の調査から、隣接する合理的選択理論の領域へと進む。この理論が含む人間の行為と合理性に関する多くの無言の前提条件、つまり実際の人間の判断にしばしば働くものを明らかに捉え損ねる前提条件について調査する。神秘的体験は、その定義からして、主体が問題の体験を共有可能な命題として定式化することができず、したがって、それに関する主張を論理的精査に付すことができないものである。同時に、歴史的に見れば、神秘体験と、それが新しい宗教宗派の設立に社会的に動員される方法は、いくつかの哲学的宗派のパラドックス論争と多くの共通点を持っている。実際、私たちはカルトというと、部外者には理解しがたい、あるいは直ちに誤りとなるような教義に傾倒するものと考えているが、実際には、批判的思考や理性に対する共通の関心に基づいて形成されることも、同じぐらいあり得るのである。このように、最高原理としての理性への傾倒があまりにも簡単に理不尽に崩壊してしまうという、私たちの調査の核心にある問題の一例を見てとることができる。
第2章では、「ノー・ブレーナー」問題を取り上げる。歴史上、「理性的」という言葉の使われ方には、ある種の曖昧さがあった。「合理的」という言葉は、しばしば機械や自然全体、抽象的なプロセスやシステム、そして(あまり一般的ではありませんが)動物に適用される。これらのいずれもが、おかしくなったり壊れたりすることなく、適切または適当に機能することができる場合である。しかし、「合理的」という言葉は、人間や、おそらく神や天使が適切に機能するだけでなく、意識的な意思決定を行う場合にのみ使われる言葉である。人間は、脳を使って熟慮の末に意識的な決断を下し、その決断が誤りであることも、正しいこともある。このように熟考し、物事を間違う傾向があるため、脳がなく、熟考せず、その性質に従って自動的に行うすべてのものよりも、合理的ではない、むしろ合理的であると主張する人もいる。ある人々には最も合理的でないと見なされるもの、たとえば単なる動物が、他の人々には最も合理的であると見なされることがある。ある観点から見れば、人間は合理の模範ではなく、合理の誤った近似であると言うことができる。この関連で、私たちは特に、進化した超能力としての合理性についての最近の研究を紹介する。合理性は、多くの進化的適応のように欠陥があるが、それでも自然の摂理の中では驚くべき、稀なものである。次に、人間の生活における(そして著者の生活における)理性の失敗の具体的な例について述べる。これらの失敗は、理性が単なる適応であり、人間が生き残るためにできることはするが、限界があり、時には予期せぬ問題を引き起こすという状態を示しているように思われる。
第3章では、夢について、より正確には、人間の典型的な人生の約3分の1が錯乱した幻覚に支配されているという不思議で厄介な事実について取り上げる。夢はしばしば、世界の合理的な秩序について私たちが知っていると思っていることのすべてを覆す。最も厄介なのは、夢に支配されているとき、私たちの理性が失われているという事実が気にならないようであることだ。このような人間生活の不可避な特徴は、場所や時代によって異なる方法で扱われ、その違いは、ある社会における合理性の特定の価値について多くを明らかにしている。アリストテレスは、夢が予言的であるという考えには慎重な姿勢で臨んでいる。近世の北米先住民は、夢を中心に生活設計や集団の意思決定を行ったが、彼らと出会ったヨーロッパ人には非論理的で恐ろしいものにさえ映った。ヨーロッパでは、夢は目覚めたときに見るべきものであり、目覚めたときに見るべきものではないことを証明するために、哲学的な議論が必要であるという、対照的な感覚が生まれつつあった。同時に、もちろん、哲学が夢の重要性を最小化しようとしても、夢が完全に抑制されることはないだろう。夢は文化に広く浸透し続け、19世紀の終わりには、精神分析と、私たち個人のアイデンティティの本当の場所としての無意識の発見と称されるシーンに再び轟くことになる。それまでの3世紀ほどは、夢、それも睡眠中に見る狭義の夢だけでなく、心の幻影、外界と正確に一致しないイメージ、外部に話し手がいないのに聞こえる声などを中心に議論が行われてきた。こうした非合理的なものをどう扱うか、生産的な想像力と妄想的なファンタズムの境界をどこに引くかは、近代ヨーロッパにおける合理性の議論の多くを規定し、世界史における近代ヨーロッパの特異な位置づけに関する一連の考え方というか、思い込みの出現の中心をなすものであった。
第4章では、芸術が注目されるが、これは前章の関心から大きく逸脱するものではない。芸術作品の創造は、しばしば、夢の中で内側に起こる幻影の物質化として概念化されるからだ。近代に入り、夢が科学や政治などの領域から押し出される一方で、創造的な分野では夢が存続するようになった。古典主義では、芸術は自然界を支配する比率や秩序の反映であり、科学と同じ世界との関わり方の一部であると考えられていた。しかし、ロマン主義やそれに関連する運動では、創造性と理解、インスピレーションと秩序への愛情を隔てるギャップが生まれた。このことは、現代の天才崇拝を見れば一目瞭然である。かつてインゲニウムは、おそらく均等に分布しているわけではないが、特別に珍しいものでもない、学習する天性として理解されていたが、19世紀後半には、天才は非常に珍しいもの、あらゆる学習を超えた能力として見られるようになった。天才とは、どんなルールにも当てはまらないことをやってのける能力であり、その結果生まれた仕事は失敗ではなく、新しい成功の形と見なされる。これに対して、芸術を儀式と同じ活動範囲に置く古風な考え方(私はこの考え方にかなり共感している)や、芸術の創造がプロパガンダのために利用される全体主義社会によくある、道徳的向上や社会進歩の手段としての芸術という考え方(対照的に、私はこれに比例して反感を持っている)など、決して完全に抑圧されない他の対立する芸術概念が存在するのだ。
第5章では、疑似科学に目を向けるが、それは必然的に科学にも及ぶ。というのも、ある知識体系を提示したり追求したりするための偽り、変質、不正な試みとは一体何であるかを判断しようとすると、この二つの領域間の境界線の問題というものが自ずと出てくるからだ。ここでは、特に創造「科学」、地球平板説、ワクチン接種反対運動を取り上げ、ケーススタディを行う(スペースがないため、残念ながら気候変動否定論など、それほど重大ではないケースは意識的に省いている)。本章は、序論と同じく、アドルノについての議論、とりわけ1950年代のロサンゼルスにおける新聞の星占いに対する批判から始まる。また、ポール・ファイヤラベンドのよく知られた議論として、どのような探究プログラムや実践が原則的に科学の発展に寄与しうるかについての理解において、最大限の寛容さ、乱暴ささえも必要とすることを検討する。さらに、これらの分析が、様々な集団の人々が、既成科学の周縁で、あるいはそれに真っ向から対立して、様々な種類の探求を追求する理由の、かなり細かい多様性を捉えることに失敗している点を探っていくる。この多様な理由を考えてみると、ある疑似科学は、その擁護者の理論的コミットメントと主流科学のそれとの間の実質的な相違によって動機づけられているが、他の疑似科学は実際には自然界の仕組みに関する特定の理論の擁護とは全く関係がなく、実際には社会界の仕組みに関する陰謀論の隠れ蓑でしかないことがわかる。こうした区別がなされると、アドルノの厳格さも、ファイヤアーベントの柔軟さも、疑似科学の挑戦に対処するのに十分であるとは思えなくなる。
第6章では、啓蒙主義を取り上げる。私がこの文章を書いている間にも、ソーシャルメディア上では、この漠然とした歴史的現象が良かったのか、むしろ悪かったのかについて、大勢の若者たちが精力的に議論をしている。彼らの多くは啓蒙主義に関する本を読んだことがなく、「奇妙な政治ツイッター」や、テキストと画像の皮肉で不愉快な並置が議論や同様のオンラインコミュニティよりもはるかに説得力を持つ、同様のソーシャルメディアのサブカルチャーの奇妙で歪んだフィルターを通して知っていることを引き出している。しかし彼らの強い意見は、少なくとも、おそらくしばらくはなかった方法で、今日それが引き続き重要であることを示唆している。なぜなら、その遺産は重大な岐路に立たされており、生き残れないかもしれないからだ。この章では、啓蒙主義と反啓蒙主義の間の弁証法的な関係として、私たちがすでに慎重にもかかわらず認識していることをより明確に理解するために、歴史的資料を、それらが最初に明確にされた時点と文脈で再検討する。私たちは、啓蒙主義がその当初から、自らの普遍的正当性を偽って宣言する偏狭なプロジェクトであり、それゆえ、そこから利益を得るのは誰か、その代わりに社会や個人は何を諦めなければならないかという問題に対して偽善的、あるいは少なくとも不見識であったとする批判的視点と実体的に関わりを持っている。私たちにとって興味深いのは、啓蒙主義が神話と対照的でありながら、アドルノとホルクハイマーが警告したように、神話に堕落していく様相でもあることだ。神話とはいったい何なのか、そして神話が進歩や平等や社会の合理的秩序を妨げるものであるのかどうか、注意深く考えなければならない。ここでは特に、ジャンバティスタ・ヴィーコによる神話、歴史、詩の関係についての考察が有用である。最後に、啓蒙主義の価値、特に言論の自由が、明らかに啓蒙主義に反する目的のために曲解され、再利用される可能性があり、実際にそうされてきた方法について考察する。このようなことが可能であり、このような考え方の一般的な傾向である可能性さえあることを知っている私たちは、受け入れるか拒否するかという二者択一の通常の提示よりもはるかに慎重に啓蒙主義の遺産を検討せざるを得なくなる。
第7章では、ついに、冒頭から私たちを悩ませ続けてきたインターネットに目を向ける。この新しいコミュニケーション形態の台頭は、公的な議論をどのように歪め、合理的な言説の規範の退廃にどのような役割を果たしたのか、私たちはそれを明らかにしようとする。さらに、初期のユートピア的な約束がこれほど早く蒸発し、それがもたらす変革の程度について、論者たちがこれほどまでに不用心であったのはなぜだろうか。その目的は、近年インターネットに託されている期待が実はそれほど新しいものではないこと、そして世界をつなぐという事業が当初から欺瞞と操作の傾向に汚染されていたことを示すことである。特に、ソーシャルメディアが構造的に過激派を増長させ、対立する陣営の間に膠着状態を生み出すという点で、ネット上の言説の堕落を如実に示す事例をいくつか紹介することにする。この問題の深刻さを示す例として、ジェンダー・アイデンティティの本質をめぐるオンライン上の議論にかなりの時間を割いた。モビング、膠着状態、情報バブル、そして卑屈な同好の士は、オンライン議論の局所的あるいは一時的な弱点ではなく、その中に組み込まれている。このことは、アイデアを共有し議論をやり抜くことによって公的議論に参加しようとする一見合理的な傾向が、実際には本質的に非合理なシステムをさらに助長し、私たちが作り出したこの新しい怒れる獣に命を与える手助けしかしない、新しい、ほとんど矛盾した状況をもたらしている。
第8章では、ジョークと嘘に目を向けると、徹底的な話題の転換のようにしか見えないことに再び遭遇する。インターネットは、作家だけでなく、コメディアンやユーモリストをも失業させる恐れがある。なぜなら、匿名の自然発生的なユーモアは、専門家が作るほとんどのものよりも基本的にエッジが効いていて素早く、実質的に無限にネット上に供給されるからだ。しかし、この新たな過剰供給は、政治的規範や、どのユーモアが効果的な風刺であり、どのユーモアが行き過ぎであり、今や一般的になった「問題あり」というラベルを貼るに値するかについての考え方の猛烈な変容も伴っている。この議論の動機付けを行うために、パリの風刺作家グループの作品が超法規的暗殺で対応された2015年まで数年さかのぼる。この出来事に対する反応はすぐに風刺の本質の問題にまで広がった。つまり、宣言的なモードで得られるものとは異なる道徳的・政治的コミットメントによって特徴づけられる特別な風刺的モードで世界と関わることができるのか、という問題である。この議論は、啓蒙主義的価値観の偽善や言論の自由の限界という問題をも含むように拡大した。私は、パリの襲撃事件で問題となった風刺作家を当初は全面的に擁護していたが、翌年のアメリカ大統領選挙を機に、特殊な風刺様式の存在を擁護するためにそれまで展開してきた議論を見直さざるを得なくなったことを説明する。そこで、カントが冗談を「緊張した期待が突然無になること」と定義しようとしたことに特に注目する。このように定義されたジョークは、論理的な議論と奇妙な関係にある。いわば、変質した、あるいは曲がった三段論法であり、その目的は、前提から真の結論を引き出すことではなく、私たちの期待を裏切ることによって、真理の概念を歪曲することにある。それらはしばしば不誠実であるが、それでも真理と特別な関係を持ち続けている。特に、嘘の不道徳性とは別に、嘘がどの程度まで非合理とみなされるか、また、一貫して真実の主張のみを行うという正直者の理解がどの程度まで適切か、についてである。つまり、嘘つきと正直者の違いは、それぞれの発言の真偽にのみ帰着するのだろうか。この議論は、当然のことながら、最近の政治史を背景とし、そこから導き出された事例をもとに展開される。
第9章では、トルストイに触発されて私が「不可能な三段論法」と名付けたもの、つまり、自らの死を完全に理解することにつながる三段論法について考察し、死ぬための準備を始める。私たちは、何らかの形で私たち個人の将来の死を否定することで成り立っていると思われる非合理性について考える。また、この否定が同時に人間の生活を形成し、私たちの社会的存在に価値を与える方法についても考察する。
第9章 不可能な論理学、あるいは死
「長い目で見れば私たちは皆死んでいる」
第1章ですでに、合理性とは個々の行為者が個々の状況を改善するために行う決定を含むという考え方に疑問を呈した。例えば、自分自身の長期的な経済的幸福と健康を求めることが合理的であるという考え方である。これは、経済学のほとんどの研究において既定の合理性モデルであり、いわゆる合理的選択理論の礎となっている。ジョン・メイナード・ケインズは「長い目で見れば私たちは皆死んでいる」1と述べている。このように、個人の窮状を改善するために希望や期待を未来に投影するには限界があることを認めているが、ほとんどの場合、個人行動者の経済モデルは、彼または彼女(一般的には彼)が無限に続くもの、彼自身の有限性の地平の前に立っていないものとして想定する傾向がある。
最近の時代には、英語を母国語とする哲学者の多くが、こうした問題に関して経済学 者からヒントを得ているが、他の哲学者は、古代以来、一般に、人間の存在の基本 的条件あるいは地平線として、つまり、人間とは何かを理解する上で最も重要なものとして、死すべき定めであると考える傾向がある。多くの哲学者は、もし人間が死を免れないものであるならば、人間は人間ではなくなると考えてきた。人間とは、死を免れない理性的な動物である。これは、おそらく、種の定義として最も一般的な表現だろうが、冗長であるという事実がなければ、すべての動物は、いずれ分解されなければならない脆弱な有機体で構成されているので、定義上、死を免れない。人間の生が死によって規定されることを考慮せずに、人間の合理性を把握しようとすることは、目下の主題を回避することである。ソクラテスやモンテーニュが理解したように、哲学とは死に対する準備にほかならない。
ソクラテス独自の洞察は、死だけでなく、死に至る老いに関するものであり、人が老いるにつれて、地上の獲得物、区別、愛着がますます滑稽になっていくという認識に基づいている。そのバカバカしさの度合いは、死の早さに比例する。ペリー・アンダーソンが高齢のユルゲン・ハーバーマスについて述べたように、沈没したブレジネフ将軍のように勲章を授与され、地位の高い老人になることの喜びは何なのだろうか。2 そうした栄誉は、むしろ衰退を前にした悲しい慰めのように思えるかもしれない。音楽業界や芸能界で時々起こるように、若い人たちに報酬が与えられると、子供たちはそれをどうしたらいいかわからないようだ。まるでウランの固まりを渡されたようで、将来が心配になる。一方、知恵のついた老人は、それを喜べず、恥ずかしがりながら受け入れている。では、若くなく、老いなく、誰が賞賛されるのだろうか。
物事を成し遂げようとするとき、その分野で名を成そうとするとき、私たちは当然、何らかの形で認められるような成果を求めているのではないだろうか。死の地平を意識することで、外向きのプロジェクトや社会的地位の確立を目指すことを、単なる虚栄心で放棄してはならないのではないだろうか?結局のところ、単にそのこと自体が好きなのであれば、小説を書いて机の引き出しにしまっておくこともできるし、本を出版したり講演をしたりするのではなく、洞窟で哲学をすることもできるだろう。しかし、その場合、私たちが受賞する賞が少なくなるだけでなく、他の人たちも人生の中で本を読むことが少なくなり、考えることが少なくなってしまうだろう。正当な貢献が認められたのに、どうして恥ずかしがることが適切な反応なのだろうか。
2015年にフランスのレジオン・ドヌール勲章を辞退した経済学者トマ・ピケティ3や2006年にロックの殿堂入りを辞退したセックス・ピストルズの生き残りメンバーのように、公に賞を辞退することでこのジレンマから抜け出す道を模索した人もいる。しかし、このような公然の拒否を行う機会自体が報酬であり、それを行う機会を得た人々は、他の人々が自分よりもさらに年上の人物に胸にピンを刺されて喜ぶのと同じくらいに、それを喜ぶことは十分に明らかである。ピケティとジョニー・ロッテンが、公式の授賞式で直面するはずの恥をかかずに反抗を公にすることができたとしても、それはおそらく自己欺瞞の一つの形であり、公に拒否することによって授賞式を反転させること自体が自己祝福であり自己膨張なのである。では、どうすればいいのだろう。何の賞ももらえない方がいいのか?しかし、それは常に凡庸な仕事をする者の運命であり、最初からそれを目標にすることはできないはずだ。
いずれにせよ、死の地平は、私たちが望ましいと考えるものを変容させ、変容の意義そのものを変容させるのである。繰り返すが、合理的な代理人、つまり一般に年齢を問わない、あるいは一般に人生の最盛期にあるとされる代理人という抽象的な経済モデルに、その本質において合致する人間は存在しない。しかし、人は常に、俳優が自分自身を発見する人生の道程のステージを考慮しなければならない。このことは、哲学であれ、経済学であれ、あるいは現在大学の人文科学部門のかなりの部分を占めている様々な「私研究」部門であれ、現代の学問がほとんど怠ってきたことである。過去数十年にわたり、人間の多様性を徹底的に分析してきたが、人間にはさまざまな年齢層があり、人生の歩みには段階があるという事実から生まれる、人間の経験の多様性というものは、ほとんど無視され続けてきた5。しかし、例えば、八十代の老人が小学校一年生に入学する権利を持つべきだと主張しようとは誰も考えなかった。トランスジェンダーのアイデンティティと同じ理由に基づくトランスレイシャリズムのケースは(大きな論争がないわけではないが)あるが、例えば、「心は若い」と感じていると主張する高齢者が、あらゆる点で彼女を若く扱うことによって、自分が何者であるかという内なる感覚を他者に認めてもらうよう主張し始める「トランスジェネレイショニズム」を正当化しようとした人はほとんどいない。ある33歳の女性が身分を偽って高校のチアリーディング部に入部していたことが発覚したとき、非難が殺到し、彼女が受けた実刑判決が厳しすぎたと考える人はほとんどいなかった6。40代半ばの今、20代の若者が集うナイトクラブで歓迎されないことも知っているし、この不公平を訴える手段も全くない。結婚の定義を、当事者の性別に関係なく自由に変えることはできても、養親が養子より若いペアを含む「養子縁組」の定義を変えることは、ごく一部の例外を除いてできない。
つまり、社会における多様な役割を定義する要因として、一方では年齢への関心が低く、他方ではジェンダー、民族性、性的指向、その他のアイデンティティーのベクトルに膨大な関心が払われるという、とてつもない格差がある7。もちろん多くの例外はあるが、ほとんどの場合、人は生涯にわたって同じジェンダー・アイデンティティ、民族的アイデンティティ、性的指向を保ち続けるが、私たちは皆、必然的にいくつかの異なる年齢を通過する。世代にはある種の連帯感があり、多くの社会で高齢者が集まって、アメリカの退職者協会のような組織的な政治ブロックを形成している。しかし、定年退職者はそのように生まれたわけではない。彼らが夢を見るとき、しばしば人生の以前の段階、つまり現在のアイデンティティを構成し続けている段階に身を置いていることに気付く。
老化は奇妙であり、特異であり、その頂点である死と同様に、人間存在の基本的なパラメータを構成している。老化を無視した人間の主体性や合理性のモデルは、これらのいずれについても多くを語らないだろう。私たちは死ぬからこそ、そして死の地平が年齢を重ねるにつれて私たちの経験を形作るからこそ、経済モデルが私たちが好むはずのないものを好むようになる。例えば、子供たちや地域社会など、自分以外の善を好むようになるのだ。このような選好は、今どんなに物事がうまくいっていても、自分自身の地位の絶え間ない向上が永遠に続くことはありえないことを理解できるほど成長した人に最も典型的に見られる。この基本的な限界を考えると、多くの人にとって、自分の利益を最大化することをやめて、その代わりに優雅に、あるいは輝かしい出口を作る方法を考えることが合理的に思えるようになる。私たちの合理性の模範であるソクラテスは、裁判で自分自身について真実を語り、自分自身を守るために説得力のある説明をすることを拒否したとき、まさにこれを行った。なぜなら「人間、死から逃れることは難しくないが、悪意から逃れることははるかに難しい。それは死よりも速く走るからだ」8とソクラテスは考えている、嘆きと懇願は、70 歳の男、それによって不滅になるかもしれないように、悪役になる。
ソクラテスは非合理的だったのだろうか。私の父は、最後まで自分の喫煙習慣を、この好きなセリフで正当化していた。「80代であと5年はいらない。私は30代であと5年過ごしたい」。彼は不合理だったのだろうか?しかし、これは彼の主張ではない。私たちは皆死ぬのであり、この明白な事実が私たちの選択を必然的に規定し、経済学や合理的選択理論で最も頻繁に展開される人間の代理性の最も単純なモデルが理解できない方法で、合理的であることが何であるかに影響を及ぼすのである。
根本的な選択
合理的な計算では救われない人間としての私たちの真の苦境を理解させることに特に力を注いでいる文化分野があるとすれば、それはセラピー業界であると予想されるかもしれない。もちろん、実存的な心理療法という小さな伝統はあるが、これはおそらく、人間の幸福の中心的な条件として、人間の死を考慮しようとするものである。また、最近の傾向として、明らかに実存的ではないものの、「哲学的」なセラピーもある。これは、哲学することは死ぬ準備であるというソクラテスからの貴重な教訓を得ているが、クライアントが利用できる選択肢を批判的に考えて、最善の選択をするように訓練するのにほとんどのエネルギーを使っているように見える9。実際、ほとんどのセラピーは、正しい行動があること、そしてセラピストはその専門知識から、その行動を見つける手助けをする立場にあることを前提にしている傾向がある。
このような相互作用の中で私たちがしばしば経験するのは、実は一種の目撃者誘導であり、患者は明らかにジレンマに直面しているが、その2つの角のうちの1つに対して、合理的か不合理かを問わず、明確な暗黙の選好を持っており、セラピストは単に患者がこの選好と折り合いをつけるのを助けるだけである。したがって、もし誰かが自分の結婚が芯から腐っているという明確な確信を持ってセラピストのところに行き、同時に夫へのかすかな愛と新しい独身生活に踏み出すことへの恐れを表明したならば、セラピストはおそらく、自己主張すること、自分の運命を追求するために一人立ちすること、などの人生における重要性を強調しようとする。逆に、最初の段階で、患者が夫をどれほど愛しているか、最近の危機的状況や結婚生活の将来に対する疑念にどれほど悩んでいるかを強調する場合、セラピストは、粘り強く物事を続けること、約束を真剣に守ることなどの重要性を強調しようとするだろう。これとは対照的に、人は人生のある時点で客観的なジレンマに遭遇するかもしれない。それは、どうすればいいかという迷いに対する唯一の正しい解決策がなく、ただ二つの比類のない善の概念の間で根本的に自由に選択できる状況である。このようなケースは、一般的にセラピストの職業的責任の概念を超えている。
また、あるカップルの一人が不満を友人たちに打ち明けると、その友人たちは、そのカップルのもう一人が本当に悪いのであり、不満を打ち明けたその友人は明晰で合理的で正義の味方であることに気づくだろう、とあらかじめ予想することができる。同じシナリオが、同じ瞬間に、街の別の場所で、もう一人の夫婦とその友人たちの間で繰り広げられているかもしれないことは、ほとんど問題にはならない。この場合、セラピストの場合と同様に、正しい道は存在しない、従えば幸福が得られるというような正しい行動の公式は存在しない、という可能性を探る余地はほとんどない。セラピーは、専門家によるものであれ、善意の友人によるものであれ、真の実存的ジレンマを扱うことはめったにない。その選択は、それを行う際、またその後に行うコミットメントにおいて正しくなるかもしれないが、絶対的あるいは先験的に正しいと言える選択ではない。
キルケゴールは、別居や離婚の問題ではなく、そもそも結婚すること自体について何年も悩んだ末に、最終的に結婚をやめ、配偶者(この場合は、長く苦しんだレギーネ・オルセン)が居場所のない、より厳格で禁欲的な生活を送ることを決意した10。この決断によって、彼の人生は大幅に短縮された可能性が高いと、私たちは振り返ってみて思う。10 彼の人生は、この決断によって大幅に短縮された可能性がある。一人暮らしで孤立していた彼は、何年か集中的な生産性と人間の状態に対する独創的な洞察力を発揮したが、42歳の若さで亡くなっている。彼の作品は、今日、ある種の慰めを与えてくれるかもしれないが、それは治療的なものではない。どう生きたらいいかを教えてくれるわけでも、正しい決断をしたと安心させてくれるわけでもない。正しい決断はなく、根本的な選択しかない。最終的に選択することになる根本的な選択は、より早い衰退をもたらすものかもしれないし、合理的選択理論で定められた基準や、親切なセラピストがその選択を決定的に間違っていると思わせるような、あらゆる点で不利なものであるかもしれない。しかし、このことは、その過激な選択に対する反論にはなりえず、反対の選択の後に富や名声が得られれば、それが実際に正しい選択であったと確認できるかもしれないのと同じである。キルケゴールは、自分自身を、そして彼に従う覚悟のある読者を、この種の計算から完全に排除している。
近年、イギリス系の分析哲学者の中には、キルケゴールが深く考察した実存的選択に似たものを取り上げようとする人がいる。この選択は、期待される結果についての計算機で評価 することはできないが、その良い結果や悪い結果は、選択が行われた時点の自分の人生とはかけ離れており、人生の異なるステージにおける前後比較は不可能なのである。しかし、この文献に寄稿した人たちは、表向きは合理的選択アプローチから脱却することを目指しているが、その権威を認めすぎているのかもしれない。もし私が子供を持てば、私はこの経験によって大きく変容し、子供がいる私にとっての良さは、生成されていない私にとっての良さとは比較にならないだろう、と推論される。
では、子供を持つべきだろうか。当然のことながら、分析的実存主義は家畜化された実存主義でもある。キルケゴールが最終的に禁欲的な生き方を選んだのに対して、彼はその過激な選択の時点ですでにかなりの実体験をしている。少なくとも数人の子供と、それを育てることに同等の責任を負う「パートナー」、教育用の木のおもちゃの品揃えなどで人生を満たすべきだというのが、変容的選択に関する最近の分析的研究において当然の結論であるように思える。私の知る限り、この文献に寄稿した親たちは皆、自分のした選択に満足し、それを地域の人々にも知ってもらいたいと思っているようだ。
若者とリスク
ソクラテスは70歳のとき、真実への忠誠と、自分が知っていることから正しい推論をすることが、あと数年の命よりも愛着に値することを知った。同じ年頃、私の父も同じように喫煙に価値を見出した。ソクラテスの献身は合理的だ。理性への献身が合理的でないわけがないだろう。父のコミットメントは合理的でないように見える。しかし、なぜだろうか。それはソクラテスと実質的に同じで、自分の死が避けられないことを自覚した上で、自分の保身以外の何かにコミットしているのだ。父の場合は、人間が執着する対象が、抽象的な経済合理性モデルに回帰させたようだ。合理的とは、自己の利益を最大化することであり、喫煙によって自らの死を早めることほど、それを怠ることはない。なぜ、あるときはそうして、あるときはそうしないのか。それは、私たちが死ぬことを選んだ特定のもの、仕草、あるいは理想を、どのように評価するか、あるいは評価しないかによるようだ-繰り返すが、私たちはいずれ死ぬのである。実際のところ、このような理想や人生の選択のほとんどは、真実と快楽の間、理性と快楽主義の間のどこかに描かれている。
物語や映画でしばしば英雄的に描かれる一般的な出口戦略は、次の世代のために死ぬことである。例えば、救命ボートに乗れる人数が限られていて、沈没しそうな船に明るい未来が待っている若者が大勢いるような場合、年配の人が死のボランティアとして前に出ることが、実際、儀礼上、期待されているのだ。戦争ではその逆で、年寄りのために若者が死ぬことが求められる。戦争に参加する多くの人々は、この取り決めの合理性を自分自身に納得させようとする。なぜなら、そうしなければ長く豊かな人生を送れなかったからではなく、長く豊かな人生は、国家の栄光や継続的な生存を犠牲にするものであれば、生きる価値がないからだ。これはロマンチックな理想であり、自己利益の最大化という合理性の抽象的な経済モデルとも相容れないものである。
もちろん、残忍な占領という選択肢があるのなら、祖国を守ることは事実上合理性の表現かもしれない。しかし、戦争がこのような明確な二項対立を示すことはめったになく、おそらく一度もない。個々の兵士の戦争、特に遠く離れた外国の戦争への貢献は、勝敗を分けた小さな努力であることを測定して示すことはできない。また、戦争から帰還した兵士が長く豊かな人生を送るために必要な条件を祖国内で整え、維持するための努力であることを示すこともできない。にもかかわらず、国家への自己犠牲の動機となるロマンチックな理想は、しばしば合理的な計算の用語に不適切に翻訳される。「もし、あなたの自由が大切なら、兵士に感謝しなさい」。この定式は、特に、個々の兵士が私と不自由の間に立っているすべてであることを意味すると理解される場合、精査に耐えることはできない。しかし、この翻訳が試みられたこと自体、興味深い。ソルボンヌ大学神学部に宛てた『黙想録』の献辞で、デカルトは、神学者や他の真の信者のように根拠はないが無限の信仰を持たない人々のために、自分は宗教の真理を合理的に論証しようとしているだけだと断言している。兵士に感謝するよう促すバンパーステッカーやTシャツも、信仰を持たない人々のために、武道という生き方を費用対効果の観点から弁護しようとするものであるように思える。
ヒラリー・マンテルがトーマス・クロムウェルの生涯を描いた人気フィクション『ウルフ・ホール』では、老いたクロムウェルが若い兵士としての自分の人生を振り返る。16世紀のほとんどの兵士がそうだったように、自分の国のためではなく、外国の傭兵として戦った彼は、死を前にして戦場で何を考えていたのか、思い返す。まだやることがたくさんあるのに、今死んでしまうのはもったいない、と。一般に、青春は長く激しいものであり、そこから死の暴力へと投げ出され、後年の冷静な勤勉さがなければ、まったく存在しないよりもはるかに無意味なものに思えるだろう。しかし、彼が死ななかったことを考えると、戦争体験は価値があったのだろうか。クロムウェルが戦争に行ったのは祖国を守るためではなく、また、歴史上多くの若者が戦場に身を置いてきたのも、そのような理由からではないだろうか。
青少年は、深く根付いた原始的な理由から、危険と特別な関係を持つようだ。スピードを出しすぎる、複数のセックスパートナーを持つ、喧嘩をする、決闘する、一般的には自分の自由の限界を試す。人生が最も価値あるものであり、最も可能性に満ちているとき、そのような試練によって最も不安定なものになるのだ。戦争に行くことは、このリストにさらに追加されるだけかもしれない。これらの行動はすべて、短期的な個人の自己利益という観点からすれば非合理的である。しかし、人生全体を一度に俯瞰してみると、これらの行動は異なって見えるかもしれない。初期のリスクは、もしこれらのリスクのいずれかによって短縮されていたら、簡単に無意味なものになっていたかもしれない人生に形と意味を与えるのに役立っているのだ。さらに、種やその歴史のレベルまで拡大すると、人生のある段階での不合理なリスクの理由が、選択的な力としてさらに明確に浮かび上がってくる。
しかし、ここでは、そのレベルには進まないようにしよう。今重要なのは、人生における多少のリスクは人間の善と両立しうるという、おそらく全員が同意している事実である。リスクを負ってでも達成したい目標が自己認識の中心にある場合、たとえリスクが非常に高くても、人はそれに見合うだけの価値があると考えるかもしれない。このように、個人の自己認識が大きく異なるため、どのようなリスクを取るのが合理的かについても大きく異なる考え方がある。2017年にアレックス・オーノルドがヨセミテのエルキャピタン斜面をロープなしで登ったとき、死のリスクは確かに非常に高かったが、エルキャピタンを登らないまま長い人生を送るという見通しは、彼の人生観からかけ離れており、リスクに勝たなかった13。オノルドの母親のように、オノルド自身の幸福を見守ることが生活の中心となっている人々にとっては、この決断は傷つき、非良心的なものに見えるかもしれない(明らかに、彼は登頂の計画を事前に彼女に伝えることを避けていたのだ)14。
このような努力の適否を判断するための一定の基準はない。何をもって生きがいのある人生とするか、しないかについての固定的かつ統一的な概念がないのと同じである。また、ホーノルドの驚くべき偉業は賞賛と畏敬の念を呼び起こしがちだが(いずれにせよ、彼がそれに成功した今)、他の若者の無謀な行動-スピード狂、喧嘩好き、傭兵、決闘者-は一般に非難を浴びせる。これらの試みも、私たちの自由が死によって制限されているという事実を踏まえて初めて意味をなす。もし、オノルドが、崖から落ちるたびにワイル・E・コヨーテのように頭をぶつけるだけの危険を冒すなら、彼の功績はほとんど意味のないものになってしまうだろう。自由の行使は常に死の影で行われる。
このような感情表現は、少なくともそれを行う人々の自己理解に関しては、愛国者の危険と自己犠牲とは異なるものである。彼は、自己啓発や個人の人生の目標を追求するためではなく、個人の自己利益が国家の利益に従属しなければならないと信じるからこそ、戦争に行くのである。しかし、愛国者は傭兵や崖登りに似ている。少なくとも、危険を冒さなければ生きる価値のないような長い人生よりも、差し迫った死という高いリスクを好むという点では、愛国者は傭兵や崖登りに似ている。しかし、彼は喧嘩好きやスピード狂には似ていないようだ。彼らは、生きるに値するかどうかにかかわらず、将来のことをあまり考えずに自由の限界を試している。
自由と合理性の関係は複雑であり、この章で扱う範囲をはるかに超えている。非合理性にはしばしば、自分自身を客観的に考えることの失敗や拒否が含まれ、したがって、自分自身の苦境を、同じような状況にある他者を支配するのと同じ力によって決定されると考えることが含まれるということだけを指摘しておけば十分だろう。この拒否は、生存の可能性がほとんどないことを知りながら戦場に突入し、その後、死後に「勇敢」であるとみなされる場合のように、時として称賛に値することもある。このように突進するために必要なのは、望ましい結果の客観的確率を考慮しない能力である。通常、生存している傍観者によるこのような行動の評価は、視点の問題であろう。兵士は勇敢だったと言う人もいれば、無謀だった、見当違いの衝動から自分の命を投げ出したが、フォックスホールに残って、自分の戦闘能力がもっと有効に発揮される瞬間、あるいは別の日を待っていた方がよかったと言う人もいるはずだ。
それは、兵士を狐穴から連れ出したのは理性ではなく、むしろもっと深いもの、私たちが動物と共有しているもので、ギリシャ人が「トゥモス」と呼び、「気力」と訳されることもあるものである、ということだ。ギリシャでは「トゥモス」と呼ばれ、「気迫」と訳されることもある。これは、熟考することなく身体を動かす能力である。欲望に駆られたとき、モッシュピットに飛び込むとき、信頼できない相手とベッドインするときの推進力のようなものである。酔っているとき、激怒しているとき、大声で歌う群衆の連帯感やコミュニティによって活気づいたとき、私たちはこのような状態に陥りやすくなる。
このような非合理性は、「善悪の彼岸」という言葉があるように、明らかに存在する。もし、これらを完全に抑圧してしまったら、生活は成り立たなくなるだろう。しかし、どの程度までなら許容され、あるいは奨励されるべきなのだろうか。「合理的なバランスで」「ほどほどに」許容されるべきであると平然と言うのは良くないだろう。なぜなら、中庸の理想は理性に由来するものであり、理性と理不尽の間の競争において、理性が人間の生活に占める割合を決定することを認めるのは明らかに不公正だからだ。だから、理性をなくすことも、人間の繁栄にとって理想的な理性の量を正確に決めることもできないなら、おそらく、このことは常に争点であり続けること、人間は常に予想される結果を合理的に計算して行動することを怠ったり断ったりすること、傍観者や批判者や噂好きがその行動を非難するに値するか賞賛するかに常に反対することを受け入れるほかはないだろう。
スピード違反者や決闘者などは、自分の利益を最大化する決定を下すために、すでに知っていることから正しく推論することに失敗しているようには見えない。むしろ、これらの場合、生きるに値する人生であるためには、自分自身の長期的な利益を最大化しなければならないという人生観の否定がある。この拒絶の根拠は、善悪はともかく、自分には長期的な利益がない、あるいは現在のリスクや自己破壊的な行動を回避することを正当化するような利益がないという信念にあるのかもしれない。このような進め方は非合理的かもしれないが、ソクラテスがすでに示したように、永遠に生きられると思い込むのも非合理的である。この後者の非合理性と、衝動的で無謀な自己破壊の間には、無限に広大なグレーゾーンがあり、ある人には合理的と思われる行動でも、別の人には非合理的と思われる行動が無限にあり得るのである。この不確実性と、非合理性の両極の間の永続的なバランスはすべて、私たちが死すべき存在であり、ナボコフの言葉を借りれば、すべての決定を二つの永遠の闇の間で行っていると感じていることの直接的な含意である15。
不可能な対義語
不合理とは、一般に、単純な無知ではない。もしあなたが関連する情報を持っていないなら、正しい推論ができないとして非難されることはないだろう。不合理とは、むしろ、自分が持っている情報を最善の方法で処理することができないことである。
しかし、ある失敗が、無邪気に知らなかったことによるものなのか、それとも、知っていることを生かせなかったことによるものなのかは、しばしば判断に迷う。このような非合理性があるとすれば、カンザス州の平均的な有権者は、自分たちの利益を損なうような選択を故意に行わなくてはならないことになる。しかし、この種の有権者は、カンザスであれ、ラストベルトであれ、トランプのアメリカのその他のステレオタイプ化された赤い風景であれ、非難される筋合いはない、彼らは単に操作的なマスメディアや失敗した公教育システムの犠牲者であって、彼ら自身が主体ではない、という嘆願をこの数年間に何度聞いたことだろうか。そして、もし彼らが自分たちの利益に反する投票をしていることを知らないのであれば、どうして彼らを不合理と言えるのだろうか。
全く知らないで行動するという極端な状態と、何が最善かを知っていながらその反対のことをするという極端な状態の間には、巨大な中間領域が存在する。そこでは、人は知らずに知っているという逆説的な状態、つまり何かを「心の底」では知っているがそれを認めないという状態になることがある。例えば、ある人は、少なくとも自己の利益の最大化という合理性のモデルによれば、一人払いの医療が合理的に望ましいと心の底では思っているかもしれない。しかし、保険がなくなると個人的に大きな不利益を被ることも知っている。それにもかかわらず、そのような医療制度は自由の喪失につながる、権威主義に等しい、もっと悪いことに、不吉なグローバル勢力の陰謀であるという主張を守るために、そのような考えを封印するかもしれない。
私が思春期に過ごした社交界で思い出す方言英語では、友人から別の友人に向けられた、「You ain’t try to hear me!」(聞こうとしないのか!)という非難をよく耳にした。この奇妙な構文は、非難される側の複雑な状態、つまり、私が説明しようとしている不合理の種のようなものを明らかにしている。それは、知らない、聞こえないということではなく、また、知らない、聞こえないようにしようということでもなく、この後者の可能性とは微妙に異なる、知ろうとしない、聞こうとしない、ということだ。人は、必要な仕事をすること、必要な注意を払うことを拒否している。そして、正しい推論をするためには、仕事が必要である。その作業を怠ることは、道徳的に非難されるべきことであると同時に、認知的に不合理なことでもある。
哲学には、ソクラテスと最も密接に関連する長い伝統があり、知的な失敗はすべて道徳的な失敗であり、その逆もまた然りとされている。不道徳な行動をとることは、知的に健全ではない判断から行動することであり、逆に、過ちを犯すことは、道徳的に非難すべき方法で、過ちを回避できるような知識を求めることに失敗したことである17。Miles Burnyeatが要約しているように、「ソクラテスと共に知的、道徳的進歩を阻む最大の障害 は常に、人々が自分自身の無知と向き合おうとしないこと」18 である。これは、ジョパディで質問に正しく答えられなかった人が罰せられるべきだということではなく、一つには、この種の雑学の暗記は、知性の仕事と呼ぶにはあまりにも、些細であるからだ。私たちが道徳的・知的な面で失敗するのは、むしろ、私たちが知っていることから正しい推論を行おうとしていないことを示すときなのである。
政治的公約がどのように形成され維持されるかについて一定の理解があれば、少なくとも現代において公開討論の対象となる重要な問題については、私たちは皆、正しい推論を行うのに十分な知識を常に持っていることになる。トランプ大統領が単一支払いモデルを拒否するのは、保険アナリストが行った、単一支払いモデルの方が個人市民にとって経済的であり、長期的な健康につながるという研究結果を読み損ねたから、という単純な話ではない。このような特定の事実にもとづいて、一人払いの医療保険を拒否することはない。また、その人を納得させるような新しい情報もないだろう。この拒否反応は、集団への帰属意識と集団外の利益への敵意から生じている。それは不合理ではあるが、無知なわけではない。
共和党の有権者は、社会化された医療と見なされるものに反対するための合理化の中で、自分自身が十分な保険に加入しているかどうか迫られると、健康な家系だから個人的に医療は必要ないと否定することがよく知られている。また、すでに述べたように、オバマ時代の半ばに行われたティーパーティーのデモでは、健康保険がなくてもやっていける方法として、ネイティブアメリカンや古代中国の伝統的な治療法を勧める声も聞かれた。これらは大胆な発言である。単に医療費負担の社会化システムを否定しているのではなく、過去数世紀にわたって理解されるようになった医療そのものを否定している。また、近代における科学研究の進歩とされるものが、人間の健康や幸福にいかなる改善をもたらしてきたかを暗黙のうちに否定している。
前者は、健康であれば健康保険は必要ないというもので、死亡率に左右されない自由、身体とその最終的な必然的破壊に制限されない完全な自由を主張するもので、より大胆である。それは、「健康」がいかなる生体の本質的な性質でもないことを理解していない。どんな身体も、どんな家族も、本質的に健康ではない。一日が本質的に晴れであったり、海が本質的に穏やかであったりするのと同じである。健康であること、あるいは美しい天気に恵まれていることを喜ぶ瞬間は、物事がまさにそういうものであると想像することは、輝かしいことかもしれない。しかし、それは幼稚でもある。なぜなら、これらの財の成熟した理解には、常にそのはかない性格の自覚が浸透しているからだ。自分は本質的に永久に健康だから健康保険は必要ないと主張する抗議者は、自分の本当の状態に関して発育不良で妄想的であるか、あるいは不誠実であるかのどちらかである。あるいは、第三の可能性として、この二つの状態は二項対立的なものではなく、むしろその間にいくつかの点を持つスペクトルの両端を表している、という考え方もある。つまり、自己欺瞞と他者欺瞞の境界は完全には明確ではないかもしれない。抗議者は、自分が身体的存在という点では他者と同じであり、それゆえ、自分に健康保険を与えてくれるシステムを停止させようとすることは自分自身の利益を破壊している、という厳しい真実を、自分の発言や思考の中で直視したくないだけなのかもしれない。
彼女の抗議は、ティーパーティー運動の他のメンバーと同様に、表向きは自由を守るため、つまり強制的な様々な集団化からの自由を守るためのものである。私たちはすでに、おそらく早急に、彼女自身の不安定な状態の否定を、様々な道徳的失敗と判断している。しかし、それが単なる妄想ではなく、国家のために兵士を戦場に送り出すのと同じようなロマンティックな衝動に突き動かされているとしたら、おそらく私たちはその判断を撤回せざるを得なくなるだろう。妄想とは、自分が集団から抜け出し、特定の社会階級、共同体、生物種の一員として生まれながらにして持っている決定に逆らうことができたと偽り信じている人たちが行使する自由である。対照的に、死を受け入れる、あるいは死を早める道を選ぶロマンチストは、何が問題かを明晰に理解した上でそうするが、共同体の愛着や善のビジョンのために自分の命を捨てることは、個人の命を伸ばすが自分が異質だと思う集団的生命の形態に自分を結びつける他の妥協よりも好ましいと信じている。このロマンティックなビジョンの醜い反復は、もはやあまりにも見慣れたものである。要するに、「黒人大統領の健康保険なんて受け入れられるわけがない「ということだ。ソフトな」反復-ヘルダーのナショナリズムがソフトで、ヒトラーのそれが「ハード」だったのと同じようにソフトな-言い方をすれば、「なぜ遠く離れたところでスーツ姿の官僚たちが、私たちに生き方を教え、揚げ物を食べたりコーンシロップを飲むのをやめさせ、私たちの愛するもの、愛で結びつけるものを取り上げるのか」である。
重要なのは、抗議者が大きな政府とそれが束ねるという社会、つまり彼女が同調しない少数民族や沿岸部のエリートを含む社会から個人の自由を認めろと要求していることは、同時に彼女が同調するコミュニティ、苦闘する白人労働者階級、あるいは彼女がどう考えようと、それを認めろということでもある。この共同体がそのメンバーに課す言動、服装、態度に関する制約は、個人の完全な自由と大きく相容れないものであり、特に、肉体を失うことさえないほど例外的な個人にはふさわしくないように思われる。兵士が戦場で倒れるとき、あるいは戦闘機を敵の戦艦に突っ込ませるとき(少なくとも日本の神風特攻隊員がそうしたように、最後の瞬間にヘルダーリンの詩を朗読するかもしれない)、彼女の個人性が完全に溶解される共同体に吸収されたいという願望の表現なのだ19。
しかし、大人の人間が自分の死期を把握できないということが、本当に起こりうるのだろうか。トルストイは1886年の小説『イワン・イリイチの死』の中で、徹底的に吟味しない人生を送ってきたブルジョワの男が、壮年期に致命的な病に倒れる姿を描いている。死の床で彼は、学校で教わった有名な三段論法を思い出す。「すべての人間は死ぬ」「カイウスは人間である」「したがって、カイウスは死ぬ」というものである。死期が迫ったイワン・イリイチは、子供の頃から推論の条件をすべて理解し、推論が成り立つことも理解していたのに、なぜか自分の名前をカイウスの名前に置き換えられることに気づかず、このことでいずれ訪れる不幸に早くから備えられたかもしれないことに気づく。
心の底では自分が死ぬことを悟っていたのに、その考えに慣れていなかっただけでなく、単にそれを理解できなかっただけだったのだ。
キーゼヴェッターの『論理学』から学んだ三段論法がある。「カイウスは人間であり、人間は死を免れない、したがってカイウスは死を免れない」という三段論法は、カイウスに適用する分には正しいが、自分自身に適用する分には間違いないと彼にはずっと思われていた。しかし、彼はカイウスではなく、抽象的な人間でもなく、他のすべての人とはまったく別の生き物であった。彼は小さなワーニャで、ママとパパ、ミーチャとヴォローディア、おもちゃ、馬車手、看護婦、そしてカテンカと一緒に、幼年期、少年期、青年期のすべての喜び、悲しみ、楽しみを味わっていたのだ20。
イワン・イリイチは、人生の大半において、自分が知っていることを知らなかった。彼は、死を認め、それを恐れず、死を認識した上で自分のプロジェクトを構築するために自由な人生を送るために、自分がすでに持っている事実から適切な推論を行う気になれなかったのだ。トルストイはこの失敗を、主にブルジョアジーの特徴として捉えていた。19世紀のロシアでは、知識人たちは、些細なこと、社会的な気配り、壁紙のモチーフの選択といった気晴らしから作り出される自己イメージに固執すると考えられていた。近年では、ピーター・ゲイ21のような文化史家やデアドラ・マクロスキー22のような経済史家が、18世紀から19世紀にかけてヨーロッパ各地で生まれたブルジョワ階級の生活の完全性と内的深さについて、まったく異なる方法で説得力のある、愛すべき説明をしている。トルストイがイワン・イリイチに対して少し厳しい態度をとっていること、さらに言えば、この人物が死を否定するのは、彼の階級的所属というよりも、差し迫った個人の非存在と折り合いをつけるという、極めて単純に、人間らしい困難と関係していることを理解するために、すべての点で彼らに同意する必要はないだろう。
最近でも、アメリカで権利を奪われた労働者階級や、ブルジョワジー(プロレタリアートの階級意識が目覚めるのを恐れてのことだろう)ではなく、「中産階級」と呼ばれる層の腐食した底辺から転落してきた人々に、死の否定が見られる。不真面目な生活、つまり死について自己欺瞞に満ちた生活を送ることは、明らかに特定の社会階級に限定されるものではない。それは本質的に、特権の結果でもなければ、絶望の結果でもないようだ。トルストイの主人公がそうであったように、私的な失敗にとどまることもあれば、公的なものとなって政治運動に影響を与えたり、感染させたりすることもある。イワン・イリイチの三段論法の失敗は、自分以外の誰にも害を与えなかったようである。ティーパーティーでの抗議行動で、オバマケアから解放されることを望み、他者からオバマケアを奪うこともいとわなかった人々は、反ワクチン派たちが集団免疫にとってそうであるように、一般の社会善にとってかなり脅威的な存在である。この種の非合理性は、時に私的であり、時に公的である。ある文脈では社会的影響を受けることなく静かに墓場まで持っていける非合理な信念が、別の文脈では、理不尽で自滅的な政治が育つ社会情勢の種となることがある。
この文章を書いている今も、私は死生観に関する古い三段論法が持つ力を十分に理解しているかどうか、自信がない。私は、すべての人間は死を免れないと理解しているし、カイウスが人間であることも理解している。このことが何を意味するかは理解している。…..カイウスにとって。さらに言えば、カイウスはとっくに死んでいると思う。しかし、このことが私とどう関係するのか、正確に言えば、私は知っているようで、知らない。もし完全な合理性が、私自身の来るべき死と完全に折り合いをつけ、この事実に従って行動することを必要とするならば、私は完全な合理性が、今のところ、全く手の届かないところにあることを恐れているのだ。私は、自分の死期を認めないまま過ごす人生の不合理さなどについて、本を書くことができる。しかし、私は自分の死期を完全に認めることはできない。私は自分の名前を三段論法に置き換えることができない。私は、大きな誇り、しばしばパニックから生まれる誇りの瞬間には、特に自分を不滅の存在と考え、自分のむなしい、つまらない努力をすべて重要なものと考える傾向があることに気づくのである。ウィリアム・バトラー・イェイツが書いたように、「昼の虚栄心」は「夜の後悔」である23。私は、健康保険が必要になることを否定する女性とそれほど変わらないし、イワン・イリイチともさほど違わない。
イワン・イリイチは、より確かなものへの道を考えることに失敗し、ブルジョワの快適さと単純で究極に無意味な快楽によって構成される人生観でやり過ごす。トルストイにとって、より本物の人生とは、小説の範囲を超えているが、精神的な深みを帯びたものであり、トルストイ自身が実践したような、平和主義的な無宗派のキリスト教によって構成されているものである。しかし、19世紀末には、ブルジョワの自己満足を捨てた者にふさわしい生き方として、静謐な精神性ではなく、むしろ大胆で侵犯的な行動様式を見ることが一般的になっていた。このように、シャルル・ボードレールは、「退屈な砂漠の中の恐怖のオアシス」24 への渇望を喚起する。このような意味ある人生のビジョンは、20 世紀に、戦争と暴力に自己欺瞞的自己満足からの唯一の救いを見出した多くの人々を鼓舞することになる。パンカジ・ミシュラは、イタリアの貴族、詩人、戦闘機パイロットであったガブリエーレ・ダヌンツィオの事例を詳しく描いている。彼は、1919 年にフィウメの町を一時占領し、自らをイル・ドーチェと名乗った。ミシュラは、「彼は、後にナチスが採用した剛腕敬礼を考案し、海賊の髑髏と十字架のついた黒い制服をデザインし、殉教、犠牲、死について執拗に語った」と述べている25。
小さな安らぎと死の否定に費やされた人生の不十分さに対する解決策として暴力的な違反に向うことは、一般に非合理主義の表現として理解されている。これはロマン主義的で、反啓蒙主義的な傾向であり、20世紀を通じて、公正で平等なグローバル社会の構築を大きく阻害してきたと思われる。トランプ大統領の時代、そしてトルコやインドなどでナショナリズムが再燃している今日も、その傾向は続いている。イワン・イリイチが見抜けなかったこと、そして、一見正しく見えるが、彼の中にある非合理的なものを、少なくとも正しく捉えている。ダヌンツィオは死を直視し、イワン・イリイチは恐怖で背を向けた。ダヌンツィオは人間の生命の基本的条件を認識した。これは合理的ではないのだろうか。理性の権化であるソクラテスも、自らの死刑を受け入れたとき、こう言ったのではないだろうか?
死は人間の生命の地平であることを認識し、小さな快適さを求めるのではなく、人生の終焉に備えるために、それに従って人生を生きよ、という命令には、「他人を道連れにするな」という言葉がふさわしいかもしれない。ストア学派は、自殺がしばしば合理的で適切な判断であること、また自殺に絶対的な悪がないことを認めた26。トルストイやソクラテスが主張するように)自らの死期を認識しなければならないという命題 から、(ボードレールやダヌンツィオをはじめとする多くの人々が少なくとも擁護の姿勢を示 したように)他人の早死をもたらすことを正当化したり祝福したりするには、いったいどうすればよいのだろう。それは、一方では個人の精神的能力の欠点としての非合理性、他方では運動する大衆の政治的あるいは社会的現象としての非合理性の間の関係の問題の核心にあるものである。
私を縛る
これまで見てきたように、非合理性はしばしば、単に知的な失敗、つまり、既知の事実から正しい推論を行うことができない失敗であるかのように、不適切に扱われることがある。もしこれがすべてだとしたら、不合理性はあまり面白いものではない。人は推論上の間違いを犯し、それを言語化すれば、他者が親切に訂正してくれる、それだけのことなのだ。不合理を判断と行動の複合体として考えると、事態はより複雑になる。実際、行動に目を向けると、一般に不合理とされることの多くは、間違った推論に基づくものではなく、自分が知っていることを知らなかったというよりも、自分が望むことを望まなかったことに基づいていることがわかる。
人が行う非合理的な行為の多くは、実際には、自分が非合理的であることを十分、明確に認識した上で行われている。喫煙はその典型的な例であり、最も身近なものである。喫煙者がタバコに火をつけながら、「こんなことするんじゃなかった」「本当はやらないほうがよかった」と言うのをどれだけ聞いたことがあるだろうか。この種の非合理性は一般に「アクラティック」と呼ばれ、ギリシャ語の「アクラシア」(通常「意志の弱さ」と訳される)に由来している。これは、既知の事実からの誤った推論ではなく、正しい推論から導かれるとは思えない行動である。
喫煙が非合理的であると単純に決めつけることはできない。喫煙者は、厳格な費用便益分析を経て、将来のコストを冒してでも、「今」の快楽を得ることを選んだかもしれない。おそらく、血流中のニコチンの快楽だけでなく、喫煙者であることの快楽、「今」を生きる人間としての社会的アイデンティティ、きわめて単純で否定しがたい「かっこいい」人間であるという、より抽象的な快楽も得るために、喫煙を選択したかもしれない。あるいは、「好きなものを見つけて、ゆっくり殺す」という民間の知恵を生み出す、死生観に説得されるかもしれない。これは、喫煙に関するソ連の古いジョークの背後にある知恵である。ソ連では、喫煙を「緩慢な死」と糾弾する広告キャンペーンが行われていた。その広告を見て、ある男が「大丈夫だ、そんなに急ぐことはない」と言いながら、タバコに火をつける。このジョークを説明するならば、男はこの広告を読んで、喫煙は自殺の手段としては効果がないということだけを忠告していることになる。タバコは自殺の手段としては効果がないからだ。この人は、誤解しているわりには、喫煙と死についてかなり合理的な考えを持っているようだ。死の影がある人生も悪くない。
それに対して、喫煙やそれに類する行為は、「できればやりたくないが、ついやってしまう」ものであることがよくある。では、なぜそのようなことが可能なのだろうか?分析的マルクス主義者で合理的選択理論家のジョン・エルスターは、2冊のブレイクスルー本の中で、実践的不合理の中心的な特徴を見事に分析している。1979年の『ユリシーズとセイレーン』では、個々の人々が、将来、現在の自分が望むことと矛盾した非合理的な行動をとることを予期して、自らの制約を自由に選択するという不思議な現象に注目した27。続く 1983 年の『酸っぱい葡萄』では、ジャン・ド・ラ・フォンテーヌが描いた、最も美味 しい葡萄に手が届かないと知った狐が、葡萄は「trop verts … et faits pour des goujats」(青く、… 吸盤に適する)だからとにかく欲しくないと決心するという伝統的寓 話にエルスターは取り組んでいる28。
このように、一方の作品では、制約がなければどう行動するかを知っていて、行動しないように先手を打つ人の問題に直面し、他方の作品では、すでに制約を受けていることに気づき、それに応じて、制約を受けていなくても別に行動しないと思うほど自分の選好を修正する人の問題に遭遇する。このような行動は、明らかに不合理とは思えない。少なくとも最初の自己欺瞞は伴うが、それは現実を受け入れるためだけであり、現実を否定するためではない。少なくとも合理主義の哲学者の一人であるライプニッツは、現実が用意しているものは何であれ、定義上、本当に最高であり、さらに現実はそれ以外ではあり得ないと考えていたはずだ。もし私たちがそれを最高と感じないとすれば、それは私たちが不用意に世界の合理的秩序全体の観点からそれを評価することができないからにほかならない。
私の手の届かないところにある葡萄は、その本質的な性質から見て、実際には最良のものであるかもしれない。しかし、私が葡萄を手に入れたからといって、世界や私個人の生活が良くなるとは限らない。甘い食べ物や楽しい玩具を手に入れることによって、生活そのものが良くなると考えるのは、子供や発育不良の大人だけである。世の中の善はもちろん、私の繁栄に葡萄が必要ないことを認識する人生観になるような、自分への働きかけができるのは良いことだ。自分に対して不正直な手段を取ること、つまり、手の届かないところにあるブドウの本質的な性質はそれほど良くないと自分に信じ込ませることについては、道徳哲学上問題があるかもしれない。しかし、それでも不合理とは言えないようだ。
これに対してユリシーズの場合は、手に入らないものを欲しがらないように努力する人ではなく、欲しいものが手に入らないように手配し、しかも最初は手に入る状態にある人を相手にしている。この奇妙なシナリオをどう理解したらよいのだろうか。実は、まったく理解しがたいことではない。ホメロスの独創的な物語が完璧な流動性を持っているのは、実は、ユリシーズが何をしているかを認識し、彼の中に自分自身を見ることができるからだ。例えば、大酒飲みが予想される夜に、タバコを隠してくれるようあらかじめ友人に頼んでおくのと同じことである。理解することの難しさは、むしろ、何が起こっているかを分析し始めるとき、つまり、人間は同じものを欲しても欲しなくてもよいという人間特有の事実を明示的に綴り出すときに初めて生じるのである。
この条件は、文献上ではしばしば、一次的欲求と二次的欲求の対立として語られてきた。私の一次的欲求はタバコが吸いたい、二次的欲求は健康で長生きしたい。ユリシーズの一次的欲求はセイレーンに向かって急ぐことであり、二次的欲求は単に明日まで生きたいということである。現在の私と未来の私は十分に異なっており、異なるものを求め、異なる関心を持ち、異なる行動方針を取ることができるのだから、ここでも問題はない、と主張する人がいるかもしれない。時間の形而上学や時間の経過に伴う個人の同一性については戸惑いがあるかもしれないが、同じ記憶と同じ身体を共有するこの二人の異なる人間(おそらく、無限に多くの他の個人とともに、それぞれがほんのわずかな時間しか持たない)の間の違いを認識することに本質的に不合理なことは何もない。例えば、ある計画や行動を遂行できなかった場合、将来の自分が罰せられることに同意する、というような契約を結ぶことが許されるかどうか、というような政治哲学上の実際的な問 題が生じるかもしれない29。しかし、これらの問題は、非合理性とは本質的に関係がないように思われる。
イワン・イリイチが知らないことを知っているように、ユリシーズは欲していないものを欲している。イワン・イリイチは、自分は死なないと不合理に思っている、より正確には、自分が死ぬとは思っていない。この信念が不合理なのは、まさに、自分が死ぬことを完全に知っているからだ。彼は「すべての人間は死ぬ」で始まる三段論法を実行し、カイウスの名前を自分の名前に置き換えることができるが、そうすることを拒否している。ユリシーズは逆に、自分が欲しないものを欲していることを知っており、このちょっとした知識を自分が持っていることを知らないという感覚はない。したがって、彼は、この欲するものと欲しないものとを手に入れないために必要な手段をとる。彼の中にある一次と二次の欲望が共存していることが彼の非合理的な性質を証明しているにもかかわらず、ある理解では、彼のアプローチは完全に合理的である。彼の合理性とは、その非合理性を効果的に管理する手段を開発することである。よくやった、ユリシーズ。
カーゴ・カルト
「酸っぱいブドウ」とは、これまで見てきたように、「手に入らないものよりも、手に入れることを強いられているものの方が良い」と信じるようになる現象である。ラ・フォンテーヌの寓話とエルスターの関わり方は、実は、今日の私たちがこの言葉で普通に理解していることとはかなり異なっている。酸っぱい葡萄」を経験した人は、俗に言う「酸っぱい恨み」で顔を引きつらせ、他ではもっといいことがあるかもしれないのにと、積極的に煮えくり返る姿を想像される。ラ・フォンテーヌの狐は、ストア学派が「アタラクシア」と呼ぶ平静さを保ち、自分がいる場所だけが最高で、他には何もないと確信しているのだ。「酸っぱい葡萄」の別の解釈に従って生きている人、つまり、別の民間のことわざを引用すれば、柵の向こう側の草はいつも青いと信じている人とは対照的に、狐は確かに理性の模範のように見えるかもしれない。
この2つの解釈の間で揺れ動くこと、つまり、自国のことは自国のままでよいという信念と、自分たちの住む場所にもっと甘い果実をもたらすために努力をさらに拡大しなければならないという信念の間には、近代ヨーロッパの歴史と、一方では血と土の民族主義、他方では帝国主義の拡張という、対になり、一見正反対の運動の要約があるように思われるだろう。
近代に入ってからのヨーロッパ人の世界進出は、商業であれ、戦争であれ、植民地化であれ、その果実が手に入らないという認識によって制約されたことはほとんどない。つまり、既存の欲望を制限するのではなく、新たな欲望を生み出すために制限を克服する。近世のグローバリゼーションは、私たちが想像するように、それまで不足していた絶対必要な商品を探しに行くという切実なニーズによって、ヨーロッパの人々の間で推進されたわけではない。むしろ、スパイス、絹、コーヒー、タバコ、砂糖など、ヨーロッパ人がその存在を知るまで当然ながら必要としなかった多くの贅沢品を求めることが、その原動力となった。
ローマ人は、砂糖の生産に力を入れずとも、蜂蜜や果物を使った甘味料で十分だった。しかし、ヨーロッパ人は、ヨーロッパ人としての自意識を獲得するずっと以前から、新しい欲望を求めていた。10世紀には、異教徒のスカンジナビア人が東ヨーロッパ、ひいては中央アジアや中東に深く浸透し、毛皮や石鹸石をエキゾチックな贅沢品と交換した31。33 人類が誕生して以来、私たちは身近なものだけで満足することなく、遠くへ旅し、あるいは遠くへ旅した人を頼って、現地に到着するまで必要だと思わなかったものを探してきた。もちろん、私たちは、それがなければ個人として滅びてしまうという意味で、これらのものを必要としているわけではない。しかし、人間の文化は、自分が必要としないものを必要とし、それがなければ文化として滅びる可能性が高いようだ。
必要でないものを必要とするのが人間であり、知らないことを知っているのが人間であり、欲しくないものを欲しがるのが人間であるのと同様であることは明らかである。
この意味で、文化は非合理的であると言えるかもしれない。それは、物質的な意味においてはなくてもまったく困らないような、苦労して手に入れた商品の象徴的な価値に、その存在を依存している。現代において、この象徴的価値は、遠い国からもたらされた輸入品によってではなく、そのような国はもうないのだから、むしろ、高級品として販売する明確な目的を持って製造された商品によって、また、しばしば、そのように包装され販売されている程度にのみ高級品である商品によって、体現されている。多くの食品は、相対的な希少性とは無関係の理由で、高い地位にあるとみなされ、その結果、より高い値段がつけられている。人類学者のマーシャル・サーリンスによる有名な例を挙げると、牛肉の部位が豊富かどうかで価格を決めるとすれば、タンが最も高価であると考えられるが、実際には私たちの文化では価値は低く、低価格で販売されている34。この評価は、タンを食べることで、他の厳選された肉を食べることとは対照的に、味覚的な特性だけが関係していると考えるかもしれないが、実際には、文化、つまり、内部的には意味があるが外部的には 恣意的な基準に従って物事を切り分ける方法と関係がある。
ランボルギーニはクライスラーのKカーより工学的に優れているし、運転するのも楽しい。しかし、ある文化において高い価値を持つものの本質的な特性を訴えることは、ほとんどの場合、表面を削ることにしかならない。今、多くの人が、精製されたサトウキビ糖は、食べ物を甘くする手段として最も好ましくないものだと考えている。ハチミツや果実の甘味料、つまり、旧世界で古代から利用されてきた食材に戻りつつある。何百万人もの死者や避難者、肥満や糖尿病、虫歯など、何世紀にもわたる強制的な農園労働は何のためだったのだろう。甘いけれども味気なく、むしろ幼稚なサトウキビの味を、これほどまでに長い間、計り知れない犠牲を払う価値があると思わせたのは何だったのだろう?これは非合理性の極みではないだろうか。
繰り返すが、もしこれを非合理と呼ぶなら、近代ヨーロッパ人だけでなく、人類に対してこの非難を浴びせなければならない。なぜなら、これは結局、人類がずっとやってきたことをさらに発展させたものに過ぎないからだ。しかし、人間の文化にとって、厳密に言えば必要でないものに価値を見出すことが非合理的であると言うのは、かなり厳しいように思われる。なぜなら、唯一の代替案は、目先の必要を満たすだけで、それ以上のことはしない、むき出しの「動物」的存在であり、私たちも日常的に非合理と見なす存在形態である。砂糖やスパイスやシルクはそれ自体必要なものではないが、それらが与える文化的な満足感は、本質的に人間的であり、取り除くことができないもののように思われる。
私たちがサトウキビ糖やアガベシロップ糖の代用品、あるいはカスピ海キャビアやアンデス産キヌアを好むのは、一般にこれらの食品の感覚的な特性の知覚の範囲をはるかに超えた、世界経済と歴史の力によって条件づけられている。私たちが消費する商品には、私たちが接触する以前に、人間による労働や、おそらくは人間や動物、環境に対する苦しみがあったという歴史があることを理解するために、こうした直接的な特性を超えて考えることができないのは、マルクス主義者が「誤った意識」と呼ぶさまざまな非合理性である。これもまた、自分が知っていることを知らないということである。フランスの先駆的なマルクス主義社会学者ピエール・ブルデューが1979年に発表した『区別』 (Distinction)のような説明もある。偽りの意識を完全に克服するためには、食べ物や音楽、家具、パック旅行などの消費者として、私たちが持っていると信じているあらゆる嗜好は、私たちの階級的アイデンティティの純粋な表現であり、これらのものの固有の特性は、紛れもなく快適かもしれないが、私たちがそれらを求める理由の真の網羅的説明には全く無関係であるという認識を持つことが必要であろう。
この言葉は、第二次世界大戦中にニューギニアで初めて観察された文化現象に由来する。この文化現象では、メラネシアの先住民が、手に入る自然の素材を使って、駐留するイギリス軍に届けられた貨物に見立てたものを作る。彼らは滑走路を二重に作り、その上に飛行機を模した実物大の精巧な木彫りのオブジェを作った。これは戦時中の戦略的な囮(おとり)ではなく、実用的な目的は全くなかった。少なくとも、外部の人間が理解できるような目的ではない。それは、英国の技術的優位性に当然ながら強い感銘を受けたと思われる「原住民」の間で、自然発生的に起こった新しい宗教運動のシンボルであり、カルト的なものであったと結論づけられた。
実際、カーゴカルトはあらゆる文化の一般的なモデルであると言っても過言ではないだろう。最近行ったレストランでは、スマートフォンを擬人化したソルト&ペッパーシェイカーが置かれていた。彼らは笑顔の人であり、ポケット通信機器であり、調味料ディスペンサーであった。これはどういう理屈なのだろう。おそらく、2010年代前半から半ばにかけて、スマートフォンの斬新さと最先端の品質が、ある種の文化的威信を生み出し、それが何世紀にもわたって存在してきた塩入れやコショウ入れなどの他の多くの文化財の生産に利用され、単にその新しいスマートな子孫に類似させることができたのだろうと思う。しかし、なぜ人間の顔をつけたのだろうか。それは、ニューギニア人がすでに知っていたと思われるように、人間が作ったものには、作った人の人間性が宿っていることを思い出させるためであろう。
どこかの辺境の村で、その土地の歴史的な品々や、インターネットからプリントアウトした情報や古い写真をラミネートしただけの「博物館」に出会ったときにも、このような貨物崇拝現象が起こっているのではないだろうかと、さらに考えてみる。同じように、世界の片隅にある小都市の高級レストランを訪れたとき、私は高級レストランを訪れているというよりも、地元の人々が考える「遠い首都の高級レストランとはこういうものだろう」というシミュレーションを訪れているのだと感じることがよくある。サルトルは、パリのウェイターでさえ、ある意味でパリのウェイターの真似をしているのだ、と考えた。つまり、自分のような人間はこうあるべきだという理想的なイメージを、身振り手振りで人為的に演じるのである。彼はそれをやりすぎて、逆説的に自分らしくなりすぎることさえある。このような模倣は、パリではなく、例えばネブラスカやトランスニストリアのフランス風の名前のレストランにいるとき、より顕著に、そしてしばしばより過剰になることがある。地理的に離れた場所にいると、この儀式はより一層、馬鹿げたものに思えてくる。なぜ、このウェイターはこんなに儀礼的に水を注いでくれるのでしょう?なぜこのウェイターはこんなに儀礼的に水を注いでくれなければならないのか、巨大なペッパーミルを直接テーブルまで持ってきて、それを少し分けてくれるというのは、人のやることだといつから知ったのだろうか。高級レストランにまつわるあらゆることが不合理であるにもかかわらず、それがどこか遠く離れた場所で、正しく、完璧に、高らかに行われていることを引き合いに出して関係者によって合理化されるとしたら、それはさらに不合理さを増しているように思える。それは、その行為が他の場所で行われているのには理由があり、その理由を真似るだけで到達できる、と根拠なく想像してしまうからだ。
もう一つ例を挙げよう。数年前、私の故郷の友人たちが、ジェフ・クーンズ(あるいは彼の従業員)が作った彫刻を公費で購入するという市政府の意図について、かなりの時間とエネルギーを費やして討論したことがある。このような作品の存在は、市の知名度を上げるためにどれほど貴重なものであるかを、その取得に賛成する人たちはほぼ全員が指摘していた。その作品の美的価値や意味についてはほとんど議論されず、ただ、彼らにとってはすでに与えられた事実である、「意味は別の場所で作られた」ということを認めるだけであった。その意味は不可解かもしれない。しかし、この街では、それが何であるかを決めるのは私たちではないし、ましてや、意味の物質的蒸留物として世界に提示されるような作品を作るのは私たちではない。この街では、意味は他の場所から既製品として輸入され、その後、この街は、大都市に新しい鉄道がつながった町のように、意味の広い地図上に場所を獲得する。ここでもまた、ロンドンやニューヨークでジェフ・クーンズを買うことがいかに非合理的であろうとも、サクラメントでそれをすることは、単にそれがロンドンやニューヨークですることだと知っているという理由で、さらに非合理的なレイヤーとなる。-

しかし、私たちの多くが参加したいと思うこのアクションは何なのだろうか?クーンズの彫刻や完璧な壁紙の特別な力とは何なのだろうか。ケールやトヨタのプリウスが大好きだとか、ウェイターがコショウを挽くクランクを回すのが好きだとか、毎年行くフレンチ・リビエラへの旅行が欠かせないとか、何が私たちに宣言させるのだろうか。ブルデューとトルストイの洞察を組み合わせると、このような宣言の根底にある、実際に何を知っているかわからないという特殊な形態は、イワン・イリイチが壁紙の選択に夢中になったように、自分が死ぬという事実を直視することの難しさと関係があるのではないかと思えてくるのである。ブルデューもトルストイも、この困難に正面から向き合えないことを、人間の人生の可能性を十分に実現できていない大きな失敗だと考えている。また、サーリンズを含む他の人々は、この失敗をそれ自体、紛れもなく人間的なものと見なし、あの肉よりこの肉を、独特の隣人よりこの襟章や握手を好むことを、人間の文化に組み込まれた人間であることの不思議さの一部とみなす傾向がある。そのようなものに魅了され、自分が死ぬということを忘れてしまうというのは、なんと驚くべきことだろう。それは失敗ではなく、勝利なのだ。
人間文化のつまらないものへのこだわりから私たちを揺り起こし、自分の死という事実を直視させようとする人々は、しばしば、目覚めた後に何をするかという大きな計画、つまり、根本的に異なる、しばしばユートピア的な社会の再編成のビジョンに突き動かされてきたのであった。このような再編成には高い代償が必要であり、命さえも失われることが一般に認識されている。したがって、人々はより大きなもののために小さな快適さを捨てる覚悟が必要である。この取引、つまり壁紙を世界放棄のコミューンと交換したり、消費財を聖戦と交換したりすることを、実に多くの人が進んで行う。この取引に応じる人は、自分が死ぬことを正しく認識し、そのことから、善かれ悪しかれ、何かのために死ぬ方がよいという結論を出すのである。一方、自分の死を直視し、死を否定する日常生活の些細なことを軽蔑しながらも、特に大胆なことや自己超越的なことに参加したいとは思わない人もいる。クシシュトフ・キェシロフスキが映画製作から引退する際に宣言したように、暗い部屋に座ってタバコを吸うことだけを望むかもしれない。これは1994年のことで、その2年後、彼は心臓発作で54歳の若さでこの世を去っている37。
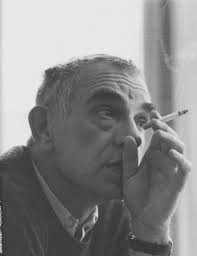
死の恐怖に対するあらゆる反応は、その非合理性を批判される可能性がある。もし私たちが家の装飾に没頭するなら、私たちは実際に知っていることを知らないことになる。もし私たちが飛び出して、何か輝かしい大義に参加するなら、私たち個人の利益を最大化しないことになる。もし私たちがただ座って、愛するものがゆっくりと(あるいは素早く)自分を殺すなら、友人や家族はそう、人生から最大限に得るためにできたはずのことをすべてしなかったのだ、と私たちに言うのである。残忍なまでに辛辣で、驚くほど正直で、自己認識の強いオーストリアの作家トーマス・ベルンハルトが1968年にオーストリア文学賞を受賞したとき、彼はその受賞スピーチでスキャンダルを起こし、ピケティと(生き残った)セックス・ピストルズが拒否を通してやりたかったことを、その受賞を通して成功させた。彼のスピーチは、「褒めるべきことも、非難すべきことも、批判すべきことも何もないが、すべてばかばかしい」(lächerlich)。
愛に満ちた繰り返しの中で
私たちは本書の中で何度か、私たちの人生を「秩序立てる」ということについて述べてきたが、「秩序」という概念は、コスモスとして、ロゴスとして理性と深い歴史的、概念的な関係を持っていることを明らかにした。多くの人は、宇宙が秩序づけられていることから、宇宙そのものが理性的であると考えた。また、人間の生活も、その秩序のあり方、つまり、信じるものからではなく、行うものから、部分的に理性を獲得していると多くの人が考えてきた。第4章で見たように、詩人のレス・マーレーは、自らのカトリック信仰を指して「愛に満ちた繰り返し」と表現しているように、多くの人々にとって、この秩序化は宗教的儀式という形をとっている。
近代哲学や近代思想が、人間の生活における意義の所在として言語に移行したことが、ピナ・バウシュの主張(第4章参照)とは逆に、繰り返しを「単なる繰り返し」として見せることになったのではないだろうか。哲学者のフリッツ・スタールは、何十年にもわたってバラモン教の儀式に没頭し、「意味なき規則」の体系としての儀式論を展開したが、彼は、概念的な道具ではないにしても、人間の存在に秩序と方向性を与えるという点では、実は言語よりも根源的なものだと考えるようになった39。プロテスタントの世界で育ち、宗教の本質は神との個人的な関係であると信じるように教育された多くの人々は、例えば南イタリアやバルカン半島に旅行して、初めて儀式-街角で教会を通るときのすばやい十字のサイン、断食と祝宴の周期、ろうそくの灯火と唱えられる祈り-が宗教信仰の生存にとって不可欠なものとされている宗教概念に出会うと驚かされる。このような宗教家は宗教家ではなく、迷信家であると主張する人もいる。
トルストイは、儀式に縛られた宗教を明確に否定し、代わりに「神の国はあなたの中にある」、したがって真の宗教性は、内観によって神を認識することにある、と主張したのは有名な話だ。しかし、もしスタールが正しいとすれば、宗教に付随する儀式を廃止することによって、宗教の純粋な核心に到達することを望むのは無駄なことであり、実際、儀式こそが人間の生活圏としての宗教を定義している。儀式は迷信的なものではありえない。なぜなら、スタールが指摘するように、儀式にはまったく意味がないからだ。したがって、スタールにとって儀式とは、合理化された宗教の小麦から取り除くことが期待される迷信的な籾殻にとどまらず、宗教の理性そのものなのである。世界を一つにまとめているのは儀式であると、ある人は感じている。
バルカン半島に長く滞在した経験から、私は当初、死をめぐる心ない迷信のように見えたものが、実は複雑で効果的な一種の文化的処理であることを知った。バルカン半島の文化は愛する人の墓を手入れし、死者を追悼するために定期的に祝宴と儀礼を行い、しばしば7年後に骨を掘り起こしてきれいにする。この地域の葬儀慣習に詳しいあるフランス人人口学者が指摘するように、バルカン半島では、死が共同生活の中心に位置し、それは西洋諸国におけるセックスに匹敵するものである40。これらの文化は、死と葬儀の間隔を社会生活の中心に据えることによって、それ自体不可 能なものを理解しやすくする方法を見出した。
E・E・カミングスの詩には、愛する人が「星々を引き離している不思議なもの」、つまり星々をその場にとどめ、星々が一緒に崩れてしまうのを防いでいると見なされるようになるほどの激しい愛が描かれている。しかし、その不思議を体現してくれる人が他にいない場合、多くの人は自分自身の行動によってその不思議を調節したり、処理しようとしたりしてきた。また、特定の宗教に属して儀式を行う必要もなく、儀式こそが世界を一つにまとめ、星々を離さないという結論に達することができる。アンドレイ・タルコフスキー監督の映画『サクリファイス』(1986)の主人公は、核による終末の危機に瀕したとき、「毎日、トイレを流すだけでもいいから、何か儀式をしていれば、世界はまとまったかもしれない」と考えた。もちろん、不条理な考えだが、恐怖や絶望よりも深いところから来ている考えである。理性が秩序であるならば、それを個々の人間の生活の中で実現するためには、反復すること以上に効果的な方法はないだろう。しかし、トルストイ、そしてマルティン・ルターやそれ以降のプロテスタントの神学者たちが信じてきたように、宗教儀式の強迫観念の奴隷になることほど、明らかに不合理なことはない。ここでは、しばしば、全く同じものが、私たちの判断の枠によって、合理性の高さとして、あるいはその反対として現れることがあることに気づく。
死を前にして、非合理性の正反対の表現を選択することは、すべてばかげている。しかし、私たちは、素敵な新しい壁紙を選び、祝祭日と断食日を尊び、祖先が自ら考案したリズムと間隔に従って敬い、祖先が自分たちを理解していた以上に理解しようと努め、そして彼らが想像もしなかった方法で敬うことによって、この秩序に一分の隙も与えずに、できる限り 頑張っている41。
結論
不合理は排除できない。私たちは夜寝るしかなく、その結果、排除された中間の法則を掴めなくなる。目が覚めたとき、社会がどう言おうと、夢の中で体験したことは、厳密に言えば不可能であっても、何らかの真実を含んでいると感じずにはいられない。また、重要な点で、自分にとって本当に良くないことに身を投じずにはいられない。この問題は深刻である。単にやり方が悪いというだけではないのだ。むしろ、自分にとって良いことばかりしていると、それ自体が自分にとって良くないことになると感じている。私たちは皆死ぬのだから、私たちの行動から期待される合理的効用はいずれ打ち消されることがわかっており、人生そのものが本質的に非合理的に見えやすく、合理性の強制に熱中しているときはなおさらそうであろう。
本書のテーゼ、すなわち非合理性は人間にとって根絶しがたいものであると同時に潜在的に有害であり、それを根絶しようとする努力自体がきわめて非合理的であるというテーゼは、決して新しいものではない。私から聞くまでもないことだ。少なくとも数千年前から、もう完璧に明白なことなのだ。しかし、過去を神話化することに反対し、未来に合理的な秩序を押し付けることができるという妄想に反対するという二重の主張は、常に新しくなされることで利益を得る。なぜなら、数千年前から完全に明白だったことが、それでもなお、私たちが知っているが知らないという広大なカテゴリーに再び滑り込み続けているからだ。
程度の差こそあれ、今回の作品のモデルとなった作品は他にもたくさんある。最もわかりやすいのは、1511年のエラスムスの『愚行讃歌』である。愚行、あるいは狂気とは、非合理の一種であるからだ。しかし、この偉大なオランダの人文主義者が賞賛し、称揚していることを、私たちはむしろ、問題の状態に賛成でも反対でもない精神で、理解し、必要に応じて対応することだけを求めてきた。これは、ドイツ語でNarrenliteratur(愚か者の文学)と呼ばれる、戯画や誇張によって人間の弱さを称えるものへの貢献ではない。実際、私は少なくとも、ミシェル・フーコーが1961年に発表した『狂気と文明』の精神に多少なりとも従ってきた。Folie et déraison. Histoire de la folie à l’age classique)において、ミシェル・フーコーは、愚か者は自分自身の愚かな思考や行動によってというよりも、社会がこのカテゴリーを押しつけることによって世界に発生すると述べている。さらに本書は、著者と同じく「歴史」であり、厳密な年表や因果関係を排し、現在の世界がいかにして生まれたかを広く描こうとする(フランス語では、やはり「歴史」と「物語」は同じ言葉である)。しかし、ここでも著者の関心は、私たちの関心を引く広い属性の中の比較的狭い種に注がれており、狂気の歴史的偶発性に関する彼の結論は、結局、単なる構築物や偶発性として分析し去ることのできない、私たちの種に生来備わっている愚かさのヒューマニスト的肯定からやや遠すぎるのだ。ウィリアム・バレットの『不合理な人間』の響きもある。1958年の『実存哲学の研究』は、その多くの長所にもかかわらず、歴史的な時代の関心事や、この本が息づく中世のムードにあまりにも左右されすぎていて、現在の瞬間に大きな意味を持つようにも、現在の瞬間から私たちを解放してくれる時代を超えた洞察を持つようにも見えない。1646年に出版されたトーマス・ブラウンの『Pseudodoxia epidemica』は、革命的な時代に流行した間違った信念の「流行」を、イギリス人作家が鋭利な魅力で記録したもので、ここにもきっと重要な残滓があるに違いない。人類のあらゆる学問が歴史上かつてないほどアクセスしやすくなり、実際、地球上の何十億という人間がポケットに入れた特別な装置で簡単にアクセスできるようになったにもかかわらず、誤った信念が相変わらず蔓延しているのは、現代の大きなパラドックスといえるだろう。
おそらく、もう一つのタイトルが言及に値するだろうが、事前の説明なしではありえない。本書の執筆中、主に2016年から2018年にかけて、私は酒をやめ、Fitbitと血圧計を買い、フェイスブックのアカウント(どんな薬物よりも悪い人類の疫病)を閉じ、ついに自分の人生のすべての人に完全に正直になることを約束し、長い間ずさんだった財務を整えた。私は自らを奮い立たせ、賢くなり、ついに「不可能の三段論法」を実行し、自分がやりたいことをすべてできる時間は有限であることを悟った。私は合理的になったのだ。この点で、私はリチャード・クラインの道をたどったのだと自分に言い聞かせる。彼は、あの不潔な習慣に対する素晴らしい賛歌『シガレットは崇高である』(1993)を書く過程で、ついに、思いがけずタバコをやめてしまった。真の自己啓発とは、自己啓発のプロや自信家の安易な教えではなく、善良なもの、愛するもの、また嫌いなもの、解放されたいと願うもののすべてを徹底的にやり抜くことにあることがわかった。つまり、人間の生活を良くも悪くもそうさせているすべての錯乱と妄想、熱狂、過剰、狂想曲、頑固、自己倒錯がそうさせるのだ。
謝辞
本書は、専門家としての生産性とエッセイストとしての探究心、楽しい仕事と真剣な遊び、理性と想像力が交錯する中で生まれた。この本を作るために交わした会話は、時には同僚と、時には旧友と、時にはその両方を兼ね備えた人々と、数え切れないほどの時間を共に過ごした人たちと、まだ一度も直接会ったことのない数人の人たちとのものだった。Noga Arikha、D. Graham Burnett、Emanuele Coccia、James Delbourgo、Philippe Descola、Jeff Dolven、Jerry Dworkin、Rodolfo Garau、Jessica Gordon-Roth、Geoffrey Gorham、Catherine Hansen、Philippe Huneman、Gideon Lewis-Kraus、Stephen Menn、Richard Moran、Yascha Mounk、Ohad Nachtomy、Steve Nadler、Sina Najafi、Paolo Pecere、S. Abbas Raza、Ambas Raza、Abad Nachomy、Paolo Pecer, S.,などであり、これらの人々は、私にとって、とても貴重な存在である。Abbas Raza, Anne-Lise Rey, Jessica Riskin, Jerry Rothenberg, Adina Ruiu, Jesse Schaefer, Kieran Setiya, J. B. Shank, Jean-Jacques Szczeciniarz, and Charles T. Wolfe.など。特にジャック・グディ、ダニエル・ランクール=ラフェリエールとは、私に初めて詩の読み方を教えてくれた(アレクサンドル・ブロックの「Двенадцать」)。キャサリン・ウィルソンやリチャード・ウォルハイムは、哲学を全身で行うことがいかに可能かを早くから私に教えてくれた。このテーマを扱うように説得してくれたエージェントのアンドリュー・スチュアート、そしてプリンストン大学の編集者ロブ・テンピオには感謝している。
第5章の最初の部分のかなりの部分は、「The Internet of Snails, Cabinet Magazine 58 (2016): 29-37」として既出である。第8章序盤の一部は、『ポイントマガジン14号』(2017年秋号)に「パンチング・ダウン」というタイトルで既刊された。117-23.
パリ、2018年8月

