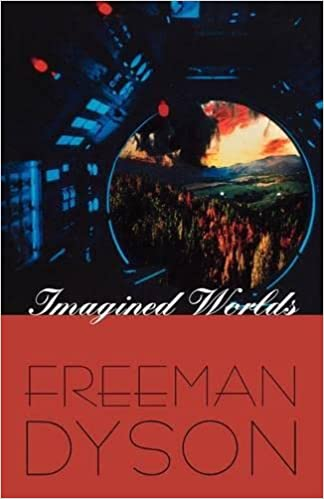
主催:エルサレム・ヘブライ大学、ハーバード大学出版局 THE JERUSALEM-HARVARD LECTURES
フリーマン・ダイソン IMAGINED WORLDS HARVARD UNIVERSITY PRESS ケンブリッジ、マサチューセッツロンドン、イギリス 1997年
謝辞この本は、1995年5月にエルサレムのヘブライ大学で行われた、ヘブライ大学とハーバード大学出版局の共催による一連の講演から生まれたものである。両校の寛大なもてなしと支援に感謝している。特に、主催者であるヘブライ大学学長(当時)のハノック・グートフロイントと、エルサレムのハーバード大学出版局代表のドロシー・ハーマンに感謝する。
ハーバード大学出版局の編集者であるマイケル・フィッシャー、スーザン・ウォレス・ベーマー、アン・ダウナー・ヘイゼルには、この講演を書籍化する際に協力と励ましをいただいた。15年前、私の友人であるジューン・グッドフィールドが『An Imagined World』(邦題:科学の未来)という、医学研究と詩作を両立させた驚くべき女性についての実話を出版した。グッドフィールドさんの本と私の本は、タイトル以外には何の共通点もない。彼女のテーマは単数形であり、私のテーマは複数形であるため、それぞれのタイトルがテーマに合致している。
1996年10月
序論
ローレンス・ツリー ジョージア・オキーフ作
オンケル・ブルーノは妻の伯父で、ドイツのある村の大きな家に住んでいた田舎の医者だった。彼は、その家を医業とともに父親から受け継ぎ、生涯その家に住み続けた。その頃、ドイツは帝国、共和国、国家社会主義、共産主義など、さまざまな勢力が支配していた。
オンケル・ブルーノは、ブレイの牧師のように、どの政党が政権をとっても、それに折り合いをつけて、自分の職業を続けていった。私は、彼がドイツ民主共和国の国民であった晩年に、彼の家を訪ねたことがある。彼は、自分の住んでいた共産主義社会には何の興味も示さなかったが、自分を安らかに残してくれた共産主義者たちに感謝していた。
立派な家と庭は、彼の晩年の誇りと喜びであった。私が家の前にある大きな樫の木に感心していると、ブルーノさんは淡々とした口調で「あの木はもう寿命だから、切り倒さなければならない」と言った。
私が見たところ、この木は元気で、倒れそうな気配はない。どうして切るんだか?と聞くと、「孫のためだ。あの木は私の時代は持つが、孫の時代には持たない。孫たちが私と同じ歳になったときに楽しめるような木を植えよう」
孫たちが自分の修業を受け継ぎ、自分の家で生活することを期待していたのだ。それが、彼の知っている世界でのやり方だった。
政権は移り変わるが、家族は存続する。子供たちのために、孫たちのために生きる。水平線は長く、100年先、つまり樫の木が成長するのにかかる時間を見据えるのが普通であり、自然なことなのだ。
私がイギリスのケンブリッジに留学していた頃、私の大学も同じような決断をした。川沿いにあるトリニティへの私道は、18世紀に植えられた立派なニレの並木道を通っていた。ニレはまだ美しいが、盛りを過ぎていた。大学は、オンケル・ブルーノと同じように、未来のために現在を犠牲にすることを決断した。
そして、その並木道は切り倒され、やせ細った苗木が2列に並べられた。そして、50年後の今、その苗木は成木になりつつある。そして、21世紀を迎えた今、その並木道は再び美しく成長し、その高さを誇っている。トリニティ・カレッジは、16世紀に創設されて以来、偉大な学問の中心地であり、21世紀も偉大な学問の中心地であり続けようとしているのだ。
1995年10月、私はスロベニアで開かれた娘の主催する東西ハイテク・フォーラムという会合に参加した。この会議の目的は、東西のコンピューターやソフトウェア業界のリーダーが一堂に会し、意見交換をすることであった。
ロシアや東欧から多くの人が、またアメリカや西欧からも同数の人が来ていた。彼らは皆、業績が良く、さらに良くなることを期待していた。東欧の人たちは、新しい波に乗っている。
東欧の人々は、古い共産主義社会の灰の中から立ち上がった新しい経営者の波であり、西欧の人々は、新しく開かれた東欧の市場に進出する前向きな企業の代表であった。歴史の波に乗っている」「自由市場経済の勝利は必然であり、その実現に貢献している」「視野が狭い」というのが、両者の共通認識であった。
*
彼らの属する情報化社会では、5年は長い、1年か2年で勝負が決まる。情報技術の進歩は予測不可能であり、自由市場の動きはさらに予測不可能である。彼らは、社会主義的な長期計画が失敗した世界で育ったので、いかなる長期計画にも美徳を感じないのである。
私が聞いた議論では、21世紀はほとんど語られなかった。社会主義経済の崩壊と自由市場の勝利が、すべての長期的な未来像を幻にしたかのように、現代社会は近年ますます近視眼的になっているように思われる。オンケル・ブルーノやトリニティ・カレッジのように、美しい自然の小島を孫の世代に残そうとする声も、変化の激しい時代には聞こえない、過去の声のようだ。
自然保護論者は過去を守ろうとし、自由市場経済論者は未来を年7パーセントの割引率で切り下げているのである。どちらの側も未来を代弁していない。現代において、誰が孫の代まで続く夢を持っているのだろうか。科学の声と宗教の声の二つが未来を語っている。
科学と宗教は、何世紀にもわたって存続し、私たちと子孫をつなぐ、人類の偉大な事業である。私は科学者であり、本書で未来を見通そうとするとき、科学の声で語りかける。
私は過去と未来を、私になじみのある科学的な観点から記述する。しかし、私は科学の声が唯一無二の権威を持って語っていると主張するものではない。宗教は、人間の運命を否定するという点では、少なくとも同等の権威を有している。宗教は人間の本性に近いところにあり、科学よりも広い範囲で通用する。
宗教が反映する人間の本性と同様に、宗教はしばしば残酷で倒錯したものである。科学が宗教に匹敵する力を得たとき、科学もまたしばしば残酷で倒錯したものになった。キリスト教信者であった詩人のW・H・オーデンは、古代末期の近代文学の誕生にキリスト教が重要であったことを次のように書いている。
「キリスト教の好き嫌いはあろうが、西洋文学を死から蘇らせたのがキリスト教と聖書であることは誰も否定できない。神の子が飼い葉桶に生まれ、重要でない地方のつつましい身分の者と関わり、奴隷として死んだが、富める者も貧しい者も、自由民も奴隷も、市民も野蛮人も、すべての人を救うためにそうしたという信仰は、人間に対するまったく新しい見方を必要とした」
もしすべての人が神の子で平等に救われる能力があるなら、地位や才能、悪徳か美徳かにかかわらず、詩人や小説家や歴史家が真剣に注目するに値するのだ。
オーデンは、宗教が私たち自身のイメージに与える影響について、強い主張をしている。また別のところでは、科学の重要性についても同じように強く主張している。
「私たちは物質でできた生物として、物理学と生物学の法則に従うが、自らの歴史を創造する意識的な人間として、その歴史をどうするかは自由に決めることができる。科学がなければ平等という概念もなく、芸術がなければ自由という概念もないはずだ」
ヨーロッパ以外の文化圏では、キリスト教以外の宗教が文明の発展に重要な役割を果たしてきた。どこの国でも、宗教と倫理は強く結びついている。
倫理と科学の結合は、本書の主要なテーマである。倫理的な関心によって結ばれた市民の集団が、過去にそうであったように、将来、歴史を形成するのに十分な力を得ることを期待してもよいだろう。しかし、倫理的配慮が近視眼的な利己主義に打ち勝つには、科学の声に宗教の声が加わって初めて可能になる。
もし私たちの倫理的選択が合理的で人道的なものであるためには、両方の声を聞かなければならない。科学は、私が所属する特権を与えられた友好的な国際クラブである。世界中の科学者が、私たち皆にとってより良い未来への希望を与えてくれる文化の中で団結しているのである。
しかし、地平線に目を向ける科学者は、大洪水に成長するかもしれない人の手ほどの大きさの雲を見極める努力もしなければならない。宗教と科学の両方の声から、私たちは用心深くなければならないと警告されている。アダムとイブが「善悪の知識の木」の禁断の実を食べたときに学んだように、知識は危険である。
知れば知るほど、善にも悪にもなる力を子どもたちに与えなければならないし、災害を早期に警告する責任も重くなる。科学は私のテリトリーだが、SFは私の夢の風景である。1995年は、H・G・ウェルズの『タイムマシン』が出版されて100年目の年であった。
ウェルズは、ドラマチックなストーリーで、同時代の人々に、起こりうる未来を垣間見せるようにした。彼の目的は、予測することではなく、警告することであった。彼は、人類の失敗と愚行に対して怒っていた。この制度は、人々を怠惰な金持ちと搾取される貧乏人に分け、金持ちは芸術と美の精華を楽しみ、貧乏人は無知と醜悪な生活に追いやられるものであった。
ウェルズは、読者、特にイギリスの上流階級の読者に対して、自分たちの社会の著しい不平等と不公正が災いをもたらしていることを警告していたのである。エロイは太陽の下で歌い踊り、モーロックは地下で機械を動かしている。エロイは不摂生で実用的、知的能力を失い、モーロックはかつての従兄弟たちを便利な食肉源として牛のように世話をしているのだ。ウェルズの著作が、イギリスの社会史にどれほどの影響を与えたかは計り知れない。
第二次世界大戦中、私が科学者として英国空軍に技術的助言を与える仕事をしていた時、主任のルーベン・スミードが、私たちの努力の指針としてあるルールを策定した。スミードの法則とは、「何かを成し遂げるか、その手柄を得るかのどちらか一方だけで、両方は得られない」というものだ。
政策に影響を与え、社会を変えるには、権力者に自分の考えを採用してもらわなければならない。個人的な影響力が決定的なものであったか、そうでなかったかは、誰にもわからない。ウェルズの場合、『タイムマシン』がすぐにベストセラーになり、ウェルズは社会的テーマについて、英国で最も広く読まれている作家となったことが知られている。
ウェルズとフェビアン協会の仲間たちは、社会正義の大義をたゆみなく説いていた。1895年の『タイムマシン』の出版から1946年に亡くなるまでのウェルズの50年間に、英国の支配階級が社会的良心を持つようになり、英国社会の不正や不平等が徐々に改善されたことが分かっている。
しかし、彼が亡くなってから50年の間に、イギリスは、彼が若い頃に戦い、小説の中で謳ったような激しい不平等を持つ階級制度に徐々に戻っていることが分かっている。このような証拠から、スメード・ルールにもかかわらず、ウェルズが生きている間にイギリス社会が改善されたことを評価することができると思うのである。
ウェルズは『タイムマシン』に、個人的な苦悩と科学的な冷徹さ、個々の人間の魂への共感と人間という種への非共感的な理解を注ぎ込んでいる。彼は、登場人物の個々の情熱や個性を、生物学的進化という大きな枠組みの中に位置づけた最初の小説家であった。
彼は、人間という種を、外的な災厄に屈しないまでも、内的な弱点によって失敗する可能性のある、深い欠陥を持った生物学的実験だと考えたのである。20世紀の悲劇的な歴史は、ウェルズのビジョンの説得力を失わせることはなかった。この小説は哲学的な憂鬱の中で終わる。
タイムトラベラーが恐怖と退化の物語を語り終え、機械と共に私たちの前から姿を消した後、物語の語り手は自分の航海の意味を考える。「私にとっては、未来はまだ黒く真っ白で、広大な無知であり、彼の物語の記憶によって、わずかな場所が照らされているにすぎない。
そして、私の慰めとして、2つの奇妙な白い花を持っている-今は縮れて、茶色で平らで脆くなっているが、心と力がなくなったときでさえ、人間の心には感謝と相互の優しさが生き続けていることを証するものだ。リア王』のラストシーンは、『マクベス』や『ハムレット』の死体だらけのラストシーンを超えて、より深い静けさに至るように、『タイムマシン』のエンディングは、従来のSFのエンディングの暴力や激変を超えたところにあるのだ。
芸術家としてのウェルズは、シェイクスピアと同様に多作で多面的であった。シェイクスピアのように、悲劇や喜劇、歴史などを書いた。シェイクスピアと違って、彼は悲劇から始めて、喜劇や歴史に進んだ。ウェルズより才能のない作家によって、他の不愉快な未来像も書かれたが、作品として『タイムマシン』に匹敵するものはない。
ウェルズ以来、私たちはさらに100年の科学から学び、100年の歴史から思索を深めてきた。
科学と歴史から学ぶ教訓の一つは、未来は予測不可能であるということだ。
ウェルズは生物学者として科学的な訓練を受けていたにもかかわらず、彼の死後すぐに分子生物学という新しい科学を生み出し、次の千年紀に向けて生物学の展望を支配することになる発見を想像することはなかったのである。
ウェルズは『歴史概説』の中で、ナショナリズムの象徴を「19世紀の部族の神々」と呼んだが、こうした部族的忠誠心の名残が20世紀末までさらに強い毒性をもって存続するとは想像もしなかっただろう。ウェルズが未来を予言しようとしたとき、後年しばしばそうしたが、たいていは失敗した。
しかし、小説家としての能力を駆使して未来の世界を想像し、私たちの視野を広げ、私たちの責任を思い起こさせたとき、彼は見事に成功したのである。未来に目を向けるとき、私はたまたま自分が最もよく知っているもの、つまりごく一部の科学とごく一部の技術について書くことにしている。
私は、想像や現実の物語を用いて、科学やテクノロジーと進化や倫理の相互作用を探求している。複雑系や超ひも理論といった流行の科学的トピックや、地球温暖化や人口過剰といった流行の環境問題は、黙って見過ごすことにしている。人間の問題を論じるとき、私は社会学ではなく、ケーススタディやSFに指針を求める。私にとってウェルズの『タイムマシン』は、どんな統計的分析よりも過去と未来の世界に対する洞察を与えてくれる。
第1章 ストーリー
BICYCLE SERIES I ジャネット・スターン作 1992年作者の許可を得て複製。成功したテクノロジーは、趣味から始まることが多い。ジャック・クストーがスキューバダイビングを発明したのは、洞窟探検が好きだったからだ。
ライト兄弟が飛行機を発明したのも、自転車の販売と修理という単調な仕事から解放されるためだった。また、自転車や自動車は、まだ道路が整備されていない時代に、レジャー用の乗り物として誕生した。しかし、いずれの技術も、開拓者たちは、お金も命もかけて、ただ楽しむだけであった。
スキューバダイビングは楽しい、飛行機は楽しい、自転車や自動車は楽しい、特に誰もやっていない初期のころは楽しい。この4つの趣味がそれぞれ巨大な産業に成長し、リスクを可能な限り低減するための法的規制が施行された今日でも、スポーツやレクリエーションは技術を前進させる動機の多くを供給しているのだ。
飛行の歴史は、技術と人間との相互作用を知る上で格好の例である。なぜなら、二つの全く異なる技術が生き残りをかけて競争していたからである-当初、それらは「Heavier-than-Air」「Light-than-Air」と呼ばれていた。
飛行機と飛行船は、物理的に形や大きさが違うだけでなく、社会的にも異なるものであった。飛行機は、個人的な冒険の夢から生まれた。一方、飛行船は帝国を夢見るものである。飛行機を作った人の頭の中のイメージは鳥であった。そして、飛行船を造った人たちの頭の中にあるイメージは、外洋旅客機であった。
この2つの技術の創造的な段階を、両者に深く関わり、また優れた作家でもあったネヴィル・シュート・ノーウェイが鮮明に描き出したことは、私たちにとって幸運なことである。パイド・パイパー』『アリスのような街』『オン・ザ・ビーチ』などで有名な小説家ネヴィル・シュートは、その前は航空技術者として、飛行機や飛行船の設計に専門的に取り組んでいた。
彼は、『Slide Rule』というタイトルで、エンジニアとしての人生を綴った自伝を執筆している。ノルウェーは、最初から飛行機に偏見を持ち、飛行船に反対していたわけではない。特に、飛行船R100の設計に携わったことは、彼の誇りであった。
1924年の構想から1930年の納入まで6年間取り組み、1930年にはロンドンからモントリオールまでの凱旋初航海に成功した。技術的な観点から見ると、当時の飛行船は飛行機よりも多くの利点があり、R100は技術的な成功を収めた。
しかし、ノルウェーは、飛行船と飛行機の運命は技術的な要因だけでは決まらないことをはっきりと見抜いていた。彼は、プロの作家となる以前から、ナットやボルトよりも人間に興味を持っていたのだ。彼は、飛行機作りを楽しくし、飛行船作りを悪夢にする人間的な要因を見抜き、記録した。
R100を完成させた後、ノルウェーは自分の会社、エアスピード・リミテッドを立ち上げた。1920年代から30年代にかけて、飛行機を発明し、製造・販売していた何百もの小さな会社のうちの1つである。ノルウェーは、この時代に10万種類の飛行機が飛んだと推定している。
世界中で、熱心な発明家たちが、勇敢なパイロットや設立間もない航空会社に飛行機を売り込んでいた。その結果、多くのパイロットが墜落し、多くの航空会社が倒産した。
10万種類の飛行機のうち、現代航空の基礎となったのは100種類ほどであった。飛行機の進化は、動物の種が絶滅するように、ほとんどすべての飛行機が失敗するという、厳密なダーウィン的過程であった。
その厳しい淘汰の結果、生き残った数少ない飛行機は、驚くほど信頼性が高く、経済的で、安全なものとなった。
ダーウィンのプロセスは、失敗を前提にしているので、冷酷である。
飛行機の進化は、飛行機が小さく、それを作る会社も小さく、失敗した場合の金銭的、人命的コストが許容範囲内であったため、うまくいったのである。
飛行機が墜落し、パイロットが死亡し、投資家が破滅しても、その損失の規模は進化のプロセスを止めるほど大きくはなかった。墜落しても、新しいパイロットや投資家が、新たな栄光の夢を抱いて必ず現れる。そして、淘汰は進み、飛行機も会社も大きくなり、淘汰は進まなくなった。その中で、ノルウェーの会社は数少ない生き残りで、商業的に利益を上げることができるようになった。
その結果、買収されてデハビランド社の一部門となり、独自の判断とリスクを取る自由を失った。デ・ハビランド社が買収する前から、ノルウェーは「もうこのビジネスは面白くない」と思っていた。飛行機づくりをやめ、小説家として新たなキャリアをスタートさせた。
飛行船の進化は、発明家よりもむしろ政治家が支配する、別の物語であった。1920年代のイギリスの政治家たちは、シーパワーに基づくイギリスの世界的な覇権の世紀が終わりを告げたことを痛感していた。大英帝国は依然として世界最大の帝国であったが、もはやそれを維持するために英国海軍に頼ることはできない。
保守党、労働党を問わず、有力な政治家の多くは、まだ帝国の夢を持っていた。彼らは軍や政治のアドバイザーから、現代世界ではシーパワーに代わってエアパワーが偉大さの象徴になりつつあると聞かされていた。そのため、イギリスを世界の頂点に立たせる未来の波として、航空パワーに注目していたのである。
そして、この文脈では、帝国権力の乗り物として、飛行機ではなく飛行船を考えるのは自然なことであった。飛行船は表面的には外航船に似ていて、大きく、視覚的に印象的であった。飛行船は帝国の端から端までノンストップ飛行が可能だった。
重要な政治家は、飛行船で遠隔地からロンドンでの会議に参加し、1カ月間、国内の有権者を無視することを強いられることはなかった。それに対して、飛行機は小さく、うるさく、不格好で、このような高尚な目的には全くふさわしくなかった。
当時の飛行機は、海の上を日常的に飛ぶことはできない。長くは飛べないし、どこもかしこも基地に頼っている。飛行機は局地的な戦いには有効だが、世界的な帝国の運営には使えない。飛行船に最も執着した政治家の一人は、労働党の貴族であるトンプソン卿で、1924年と1929年の労働党政権の航空担当国務長官であった。
トンプソン卿は、カーディントンにある政府所有の王立飛行船工場でR101飛行船を建造するプロジェクトの推進者であった。社会主義者であると同時に帝国主義者でもある彼は、政府工場に仕事をさせることを主張した。
しかし、保守党の反対を押し切るための妥協案として、民間企業であるヴィッカース社が姉妹船であるRlOOを同時に製造することを取り決めた。RlOlとRlOOは、新時代の大英帝国の旗艦となるはずであった。RlOlは大型で、イギリスからインド、そしてオーストラリアまでノンストップ飛行が可能であった。
RlOO号は、イギリスとカナダを結ぶ大西洋横断の定期便で、より小規模なものであった。ノルウェーは、RlOOを設計する技術者チームの一員として、両飛行船の運命を正面から見守っていたのである。RlOlプロジェクトは、当初から常識というよりむしろイデオロギーによって推進されていた。

何としても、RlOlは世界最大の飛行船でなければならず、1930年10月の決まった日までにインドに飛来し、トンプソン卿自身がカラチへの処女航海に乗り出し、ロンドンで開かれる帝国会議に間に合うように戻ってこなければならなかった。
インドからの生花を携えての飛行船での劇的な到着は、イギリスと帝国の偉大さを世界に示し、ついでに社会主義産業とトンプソン卿の優秀さを示すことになった。巨大なサイズと決まった日付は、致命的な組み合わせであった。巨大なガス袋を密閉して漏れないようにする技術的な問題は解決されなかった。
インドへの航海に先立ち、船を十分に揺り動かす時間もなかった。そして、トンプソン卿と彼の数千ポンドの大荷物を乗せ、悪天候の中、ずぶ濡れでようやく初航海に出た。船は係留マストの上にかろうじて浮き上がる程度であった。8時間後、船はフランス北部の野原に墜落して燃え上がった。
54人の乗組員のうち、6人が生存していた。トンプソン卿はその中に含まれていなかった。一方、R100はノルウェーの援助を受けて、より合理的な方法で製造されていた。ガスバッグは漏れず、設計された積載量を運ぶのに十分な揚力を持っていた。
R100は、R101がイギリスを出発する7週間前に、モントリオールまでの処女航海を無事終え、帰路についた。しかし、ノルウェーはこの航海が決して安心できるものではないことを知った。彼は、R100がカナダ上空の雷雨に激しく翻弄され、幸運にもバラバラにならずに済んだと報告している。
彼は、R100が旅客機として十分に安全であるとは判断していなかった。安全かどうかという問題は、R101の事故の後、意味をなさなくなった。このような事故が一度でも起これば、乗客は次の事故に志願することはないだろう。R100は静かに解体され、破片はスクラップとして売られた。
帝国飛行船の時代は終わりを告げたのである。R100の目的は、イギリスとカナダを週1回往復する信頼性の高い旅客サービスを提供することだと発表されていた。この飛行船が失敗した後、キュナード船舶会社のオーナーであるキュナード卿は、2隻のオーシャンライナーだけで大西洋を毎週横断するサービスを提供するにはどうしたらいいか、技術者に尋ねた。
当時、1隻の船が大西洋を横断するのに7〜8日かかっていたので、週1回の運航には少なくとも3隻の船が必要であった。2隻では、悪天候や荷物の積み下ろしのために2日の余裕をみて、5日で横断しなければならない。キュナード社の技術者たちは、クイーン・メリー号とクイーン・エリザベス号を5日間で渡るように設計した。

経済的にこれを実現するには、波浪抗力が速度と大きさに比例するため、2隻の船は他の外航船よりかなり大きくなければならなかった。キュナード卿は、船による旅客輸送のビジネスがあと数十年は利益を生むと確信し、この船の建造を命じた。
やがて、第二次世界大戦による中断を経て、この船は乗客を乗せて海を渡り、速度記録を更新しながら利益を上げていった。イギリス国民は、大西洋横断の最速記録として有名なブルーリボンを常時獲得しているこれらの船を誇りにしていた。
しかし、キュナード卿は、国民は船の目的を完全に誤解していると言った。キュナード卿は、毎週定期運航できる最小で最も遅い船を作ることが目的だったと語った。そのために記録を破る必要があったのは、不幸な事故であった。
この船は、ボーイング707が廃業するまで、長年にわたって週1便の運航を続け、利益を上げていた。/SB*オーシャンライナーがまだ全盛期を楽しんでいた頃、ボーイング707の勝利の前に、イデオロギーに基づいたテクノロジーが引き起こしたもう一つの悲劇が起こった。ジェット旅客機「コメット」の悲劇である。

第二次世界大戦中、爆撃機やジェット戦闘機を製造していたデ・ハビランド社は、より大きなものへの欲求を獲得していた。戦後は、当時のプロペラ機に比べて2倍の速さで飛行できる民間ジェット機「コメット」の設計を進めた。
同時に、英国政府は長距離航空路を担当する国営の独占企業「英国海外航空公社」を設立した。帝国は急速に崩壊しつつあったが、BOACの計画者たちに新たな栄光の夢を抱かせるに十分なほど、帝国は残っていた。
彼らの夢は、BOACが支配するロンドンからアフリカ、東はインド、オーストラリアまでの帝国路線にコメット艦隊を配備することであった。この夢は、動きの遅いアメリカより5年早く、イギリスがジェット機の時代に突入することを意味し、魅力的だった。
ボーイング社が躊躇している間に、コメット号は飛行を開始する。コメッツは、英国の技術の優位性を世界に示すとともに、帝国(現在は英連邦と改称)がまだ生きていることを証明するものだった。BOACの彗星が道を示した後、世界中の航空会社がデ・ハビランドに発注することになる。
コメット号が抱いた夢は、20年前にロールを抱いた夢と同じものであった。トンプソン卿の後継者たちは、彼の運命からほとんど学んでいなかったのだ。彗星は、RlOlと同じ過ちを犯し、政治的に決められたタイムテーブルの中で、困難で厳しい技術に突き進んだ。
コメットを1952年に就航させるという決断は、アメリカより5年先んじるという政治的要請からなされたものであった。そんな中、彗星に起こる災難を予見していた人物がいた。ネヴィル・シュートは、1948年に「ノー・ハイウェイ」という小説を発表している。
この小説は、4年後に起きた彗星号の事故と酷似している。彗星号の致命的な欠陥は、窓の角に応力が集中することだった。この応力によって、飛行機の金属表皮に亀裂が入り、裂けてしまうのだ。この亀裂は、機体が完全に加圧された高高度でしか発生しない。
その結果、機体は分解され、残骸が広範囲に散らばり、原因のはっきりした証拠が残らない。このようにして、インド上空とアフリカ上空で2機が破壊され、乗員全員が死亡した。2回目の墜落の後、コメット号は飛行を停止した。
その後、アメリカから信頼性の高いボーイング707が来るまで、5年間はジェット機が飛ぶことはなかった。コメット飛行を止めるには100人の死者が必要で、飛行船を止めるのに必要な数の2倍であった。
もし、最初のコメットが墜落したとき、航空庁長官が乗っていたなら、2度目の墜落は必要なかったかもしれないネヴィル・シュートは、R101とコメットが十分な飛行試験なしに乗客を運ぶことを許されたのはなぜか、と説明する。
それは、政治的文化と技術的文化という2つの文化の衝突が原因であった。政治家は、自分たちが理解していない技術的な事柄について、重要な決断を下していたのである。政治家の仕事は、決断を下すことである。政治的な決断は、しばしば不十分な知識に基づいて行われ、通常、大きな損害を与えることはない。
政治という文化では、リーダーはこう言って尊敬を集める。「The buck stops here」(責任はここにある)と言うことで、リーダーは尊敬される。優柔不断であるよりは、間違った決断をする可能性の方が高いのだ。エンジニアリングの文化は違う。
エンジニアは、こう言って尊敬を集める。「転ばぬ先の杖」である。エンジニアは、設計の弱点を探し、潜在的な災害を警告するように訓練されている。政治家がエンジニアリングのベンチャー企業を担当する場合、この2つの文化は衝突する。それが空を飛ぶ機械であれば、衝突は墜落につながりやすい。
航空は、最もミスに寛容な工学の一分野である。しかし、広い視野で見れば、その寛容さは美徳と言えるかもしれない。長い歴史の中で、「リオ1号」や「コメット号」の犠牲者は決して無駄死にではなかったのだ。彼らは、その悲劇の遺産として、極めて安全で信頼性の高い飛行機を残し、現在では世界中の大陸や海を毎日飛び回っているのだ。
災害と死という厳しい教訓なしには、現代のジェット旅客機は進化しなかっただろう。私の友人であるアルバート・ハーシュマンは、許さないことが美徳とされる場所を他にも見出している。彼は経済学者で、人生の大半をラテンアメリカ社会の研究に費やし、その政府に助言してきた。
アフリカの独立したばかりの国にもアドバイスをしている。彼はよく貧しい国の指導者たちから、「限られた資源を道路に回すべきか、それとも航空会社に回すべきか」という質問を受ける。なぜなら、道路に使うお金は地元の人々の雇用につながり、道路は社会のあらゆる階層に恩恵をもたらすからだ。
それに対して、国営航空会社の建設には外国の技術を導入する必要があり、航空会社を利用する余裕のある少数の国民にしか恩恵がない。しかし、アフリカやラテンアメリカでの長い経験から、ハーシュマンは、「道路」はたいてい間違った答えであることを学んだ。
現実の世界では、道路にはいくつかの欠点がある。道路建設に割り当てられた資金は、腐敗した地方公務員の手に渡りがちである。道路は作るのが簡単だが、維持するのは難しい。そして、通常起こることだが、新しい道路が数年後に崩壊しても、崩壊は緩やかで、大きなスキャンダルを引き起こすことはない。
道路建設の最終的な結果は、以前と同じように生活が続けられるということである。「道路」と言った経済学者は、地方公務員の富と権力を少しばかり増大させた以外には、ほとんど何も成し遂げていないのである。これを、国営航空会社の建設が現実にもたらす効果と対比してみよう。
資金が使われた後、その国には高価な飛行機と高価な空港、そして高価な最新設備が残される。外国人技術者は去り、地元の人々がシステムを運用するために訓練されなければならない。道路と違って、飛行機は優雅に朽ち果てていくわけではない。
旅客機の墜落事故は非常に目立つ出来事であり、その国の支配者に受け入れがたい威信の失墜をもたらす。犠牲者は富裕層や有力者が多く、その死は見過ごすことはできない。支配者に選択肢はない。一旦、航空会社を所有すると、その航空会社の経営がうまくいくように見届けなければならなくなる。
そのために、機械を整備し、定時に出勤し、自分の技術に誇りを持つ、意欲的な人たちを集めなければならない。その結果、航空会社は、直接的な経済価値よりも大きな間接的利益を国にもたらすことになる。それは、厳しい産業規律に慣れ、近代的な労働倫理を身につけた国民を大量に生み出すことである。
そして、このような国民は、やがて、飛行機の世話以外にも、自分の技能を生かせる他の有用な仕事を見つけるだろう。このように逆説的な言い方をすれば、航空はその寛容さゆえに、伝統的な社会に近代化の方法を教えるのに最も適した学校なのである。
容赦のない技術が世界を変え、伝統的な社会に変化を強いるのは、これが初めてではない。今日の航空が果たす役割は、産業革命以前の世界における帆船の役割と似ている。英国王ヘンリー8世は、英国の君主の中で最も残忍かつ最も聡明で、修道院の破壊者と大学の創設者、妻の殺害者とマドリガルの作曲家、その大恩に感謝して今でもケンブリッジのトリニティ・カレッジで定期的に魂の祈りを捧げているが、英国の近代化にとって最も有効な手段が英国海軍を創設することだと理解したのである。
18世紀の産業革命が、300年もの間、日常生活と経済が帆船文化に支配されていたイギリスで始まったのは、決して偶然のことではない。ヘンリーと同郷の若きロシア皇帝ピョートル大帝は、ロシア帝国の近代化を決意すると、造船所で見習いとして働き、その準備を進めた。/R101やコメットの悲劇は、イデオロギーの弊害を示す例であり、これらの場合のイデオロギーとは、昔ながらのイギリス帝国主義である。
現在では、大英帝国は古い歴史であり、そのイデオロギーも死んでいる。しかし、イデオロギーに基づく技術は、イデオロギーがそれほど時代遅れでなくても、問題を起こす可能性がある。もう一つ、強力なイデオロギーが問題になったのは、原子力エネルギーである。
第二次世界大戦後、広島と長崎の廃墟から平和で有用なものを作り出そうという強い思いから、世界中で原子力イデオロギーが花開いた。科学者、政治家、産業界のリーダーたちは、戦争で死傷者を出した自然の偉大な新しい力が、今度は砂漠に平和の花を咲かせるというビジョンに、同じように魅了されたのである。
核エネルギーはあまりにも不思議で強力なため、まるで魔法のように見えた。この魔法が、地球上の貧しい人々に富と繁栄をもたらすと信じるのは簡単なことだった。そこで、大国でも小国でも、民主主義国でも独裁国家でも、共産主義社会でも資本主義社会でも、原子力エネルギーがもたらす奇跡を監督するために、原子力庁が設立された。
そして、原子力は未来への確かな投資であると確信し、原子力研究所に巨額の資金が注ぎ込まれた。私は、そのような熱狂の渦中にあった英国の原子力研究所の中心、ハーウェルを訪ねた。ハーウェルの初代所長はジョン・コッククロフト卿で、一流の科学者であると同時に、誠実な公僕でもあった。私はコッククロフト氏と一緒に敷地内を歩き、工場から伸びる巨大な電線を見上げ、頭上を越えて遠くまで見渡した。
一般の人たちは、この発電所から電力が全国に送られていると思い込んでいる。私が、電気は全部反対方向に流れていると言っても、信じてはくれないんだ」原子力発電で電気を作ることは、昔も今も何も間違ってはいない。しかし、原子力は他のエネルギー源と競争し、悪ければ失敗することも許される、フェアなルールでなければならない。
失敗が許される限り、原子力は大きな害を及ぼすことはない。しかし、イデオロギーに支配された技術の特徴は、失敗が許されないということである。だから原子力は大変なことになった。イデオロギーは、原子力は勝たなければならないと言った。
原子力の推進者たちは、原子力は安全でクリーンで安価であり、人類に恵みをもたらすものだと信仰の対象として信じていた。しかし、その裏には、使用済み核燃料の最終処分や、使い古した機械の廃棄など、環境浄化のためのルール作りがなされていたのである。
このルールによって、原子力は推進派の思惑通りになってしまったのだ。このルールに従えば、原子力は確かに安く、クリーンで安全である。このルールを作った人たちは、国民をだまそうとは思っていなかった。自分たちの信念を否定する証拠を隠蔽する癖がついたのだ。
結局、原子力発電のイデオロギーは、失敗が許されない技術が明らかに失敗したために崩壊した。政府の補助金にもかかわらず、原子力の電気は石炭や石油を燃やして作る電気より格段に安くなることはなかった。軽水炉は安全だと言われているが、事故が起きることもある。
環境にもやさしいというのに、廃棄物の処理に問題があった。このように、原子力発電を推進する側の主張が、明らかに事実と異なるため、結局、国民は原子力発電に厳しい反応を示した。ある技術が他の技術との競争の中で失敗することが許される場合、その失敗は通常のダーウィンの進化の過程の一部であり、改善され、後に成功する可能性がある。
しかし、失敗が許されず、それでも失敗してしまった場合、その失敗のダメージははるかに大きくなる。もし、原子力発電が最初から失敗することを許されていたなら、今頃、国民が信頼し支持するような、より良い技術に進化していたかもしれない。
自然の法則は、私たちがより良い原子力発電所を作ることを止めるものではない。私たちを止めるのは、深く正当化された国民の不信感である。専門家が無謬であると主張するから、国民は専門家を信用しないのである。国民は、人間には間違いがあることを知っている。
イデオロギーに目がくらんだ人たちだけが、自分たちの無謬性を信じるという罠にはまる。核分裂エネルギーの悲劇は、米国に限って言えば、もうほとんど終わりを迎えている。誰も新しい核分裂発電所を作ろうとはしない。
しかし、もう一つの悲劇、核融合の悲劇はまだ続いている。核融合の推進者たちは、30年前に核分裂の推進者たちが犯したのと同じ過ちを犯しているのだ。核融合は、30年前の核分裂と同じ轍を踏んでいる。21世紀のエネルギー源はトカマクだ」とイデオロギー的に宣言しているのだ。
トカマクはロシアで発明され、発明者たちはそれを他の言語に音訳した名前をつけた。核融合の研究を本格的に行っているすべての国がトカマクを建設している。プリンストンには、最も大きく、最も高価なトカマクがある。
パイプとコイルが密集し、修理が必要なときに誰も入って修理するスペースがないのである。しかし、これを作った人たちは、これが人類のニーズに対する答えであると心から信じている。様々な国の核融合計画は、何十億ドルもかけて、将来の核融合発電の原型となる巨大な国際トカマクに集約されることになっている。
核融合発電は安全でクリーンである、というのが通常の主張であるが、推進者たちでさえ、核融合発電が安価であるとはもはや言っていない。既存の核融合計画は、推進派の希望を実際にかなえるかもしれない新しい技術の進化を止めてしまったのだ。
世界が必要としているのは、小型でコンパクト、かつフレキシブルな核融合技術であり、必要なときに必要な場所で電気を作ることができる。既存の核融合計画は、政府以外の誰も買えないような値段で、巨大な中央集権的電力源につながるものだ。
核分裂計画が崩壊したように、既存の核融合計画も遅かれ早かれ崩壊する可能性が高い。そして、その残骸の中から、より有用な核融合技術が生まれることを願うばかりである。イデオロギーに支配された技術に関する最後の話は、氷の池の話である。
テッド・テイラーは、氷の池の推進者であった。彼は、私の友人の中で、技術的な発明と高い倫理観とを最もよく結びつけている人物である。彼は若い頃、ロスアラモスで核兵器の設計をしていた。その後、ワシントンの国防総省で、核兵器の備蓄の安全管理を担当した。
プルトニウムなどの核物質が盗まれるのを防ぐため、公然とキャンペーンを展開した。プルトニウムなどの核物質が盗まれないような安全保障措置の充実を求める運動を展開した。
持続可能で環境に優しいエネルギー源を求めて、彼は氷の池に行き着いた。氷の池は、冬の夜の気温が年間10日以上氷点下になる地域であれば、冷凍のためのクリーンなエネルギー源となり得る。氷池のアイデアは、大量の雪を半年間貯蔵し、冬に雪を作り、夏に冷房に利用することである。冬に作る雪は、消防士が使うような霧吹きで水を噴射して細かい霧を作る。

気温が氷点下であれば、噴霧は雪や泥となって地上に落ち、池に溜まる。雪は断熱材で覆われている。池は、冷却する建物と水道管でつながっている。夏には、池の底から冷たい水を汲み上げ、温かい水を上部に戻す。池の大きさと深さが十分であれば、雪は夏まで続き、建物は涼しく保たれる。
雪を作り、水を循環させるポンプに必要なエネルギーは、従来の電気冷凍機に必要なエネルギーよりはるかに少ない。テイラーは、四季の自然のサイクルを利用して、公害をもたらす発電所の電力に代わるものを作ることを夢見ていた。
その夢を実現するために、プリンストン大学に氷の池を作り、小さなビルの冷凍に成功した。そして、プルデンシャル保険会社を説得し、より大きなビルの冷房のために、より大きな氷の池を設置することに成功した。
1981年、プリンストン・アイス・ポンドでクター・チーズ社を説得。プリンストン大学コミュニケーション・オフィスの許可を得て掲載している。ニューヨーク州にあるチーズ工場を冷蔵するための氷の池を建設するよう説得。ロングアイランドのグリーンポート村に、海水を浄化する目的で氷の池を建設するよう説得した。
グリーンポートの氷の池は、大西洋の塩水を使って雪を作るものだった。数週間もすると、雪山の底から塩が抜け、残った雪の大部分はニューヨーク州の飲料水の品質基準を満たすほど純度が高くなった。これらのプロジェクトは、いずれも氷の池(氷の池)の技術を追求するために行われたユニークなものだった。
その成功の度合いもさまざまであった。プリンストン大学の氷の池はうまくいったが、2年後に解体された。プルデンシャル社の氷の池は、テイラーの手を離れ、システムを理解していないプルデンシャル社の従業員に任されたため、満足に機能しなかった。
グリーンポート・アイス・ポンドは、技術的にはうまくいったのだが、地元の政治的な争いに巻き込まれることになった。グリーンポートの水道に接続されることはなく、最終的には村役場の多数決で解体された。クッター家の氷池だけが生き残り、今も持ち主の役に立っている。
テイラーは、これらの実証実験で氷の池の実力を世界に示した後、氷の池を商品化することを望んでいた。氷の池を製造し、販売することで利益を得ようと考えたのだ。買い手は、食品工場や商業ビルのオーナー、タウンハウスを建てるデベロッパーなどだ。
電気代の節約になるし、目に見える環境美化のシンボルにもなる。建物の横にある氷の池は、屋根の上にある太陽エネルギーの集熱器と同じように、自然のバランスを大切にするオーナーの気持ちを静かに主張するものであった。しかし、テイラーは買い手を見つけることができず、氷の池が定価で顧客に提供できる規格品になることはなかった。
なぜ、氷の池は失敗したのだろうか。失敗の理由はいろいろある。テイラーは、冬の野外で重機を操作することの現実的な難しさを甘く見ていた。積もった雪に毛布をかぶせるという作業が、思いのほか難しいことが分かった。毛布がうまく敷けなければ、雪は夏までもたない。
プルデンシャル社の氷の池が失敗したのは、この毛布の失敗が主な原因だった。氷の池を維持するためには、常に注意が必要だった。クッターの氷の池が成功したのは、チーズ工場のオーナーであったクッター兄弟が、何か問題が起きると長時間かけて機械の手入れをする熱心な人たちだったからだ。
しかし、悪天候の屋外での作業を好まない、冒険心のないオーナーにとっては、メンテナンスの問題は常に頭の痛い問題であっただろう。このように、氷の池は実用的な欠陥があるため、商業的な成功は望めなかった。
しかし、テイラーの夢が挫折したのには、もっと根本的な理由があった。それは、氷の池が市場に受け入れられることはなく、イデオロギーに引っ張られるだけであったということだ。
*
成功する技術は、売り手のイデオロギーに押されるのではなく、買い手のニーズに引っ張られるものである。テイラーは、ビジネスを成功させるための最初のルールを破ったのである。「市場を知ること」だ。氷の池は、飛行船や原子力発電所と同様、イデオロギーに振り回されて失敗した技術の一例である。
しかし、氷の池の失敗は、飛行船や原子力の失敗のような悲劇的なものではなかった。氷の池はすぐに失敗し、社会に与える損失も最小限であった。お金も人の命もほとんど無駄にはならなかった。
テイラー自身も、この失敗から立ち直り、新たな事業を始めようとする気概を持っていた。彼の氷の池への思いは、有用な知識として遺産として残された。氷池の技術は、未来への可能性として残っている。いつか、もっと鋭いテイラーの生まれ変わりが、氷の池を便利で使いやすいパッケージにする方法を見つけて、テイラーの希望をかなえてくれるかもしれない。
この氷の池の話の教訓は、イデオロギーに基づくテクノロジーが災いをもたらす必要はない、ということだ。競争から保護された技術でなければ、災難に見舞われることはない。ある技術がダーウィンの淘汰のプロセスにさらされるならば、それがもともと利益追求のためであろうと、イデオロギーのためであろうと、関係ない。
イデオロギーの押し付けは、それが市場でテストできる環境に優しい技術につながるのであれば、善のためのポジティブな力となり得る。
テッド・テイラーや彼の学生たちと一緒にプリンストン大学の氷の池を作るのを手伝った幸せな日々を私は後悔していない。私たちは、飛行船や原子力発電所を作った人たちよりも幸運だった。
「フリーマン・ダイソンは現代における真の天才の一人である。彼の最新作は、軽妙なウィットと深い知恵に満ちており、人類の将来の幸福、ひいては生存に関心を持つすべての人々の興味をそそるだろう」この本では、10年後、100年後、1万年後、そして100万年後の科学的な未来について概説している。
未来学は好きではないが、Imagined Worldsは魅力的であった。LYNN MARGULIS ”Freeman Dyson’s Imagined Worldsは、世界で最も明晰で聡明な科学技術評論家としての彼の名声を確かなものにし、読む者を楽しませてくれる。
