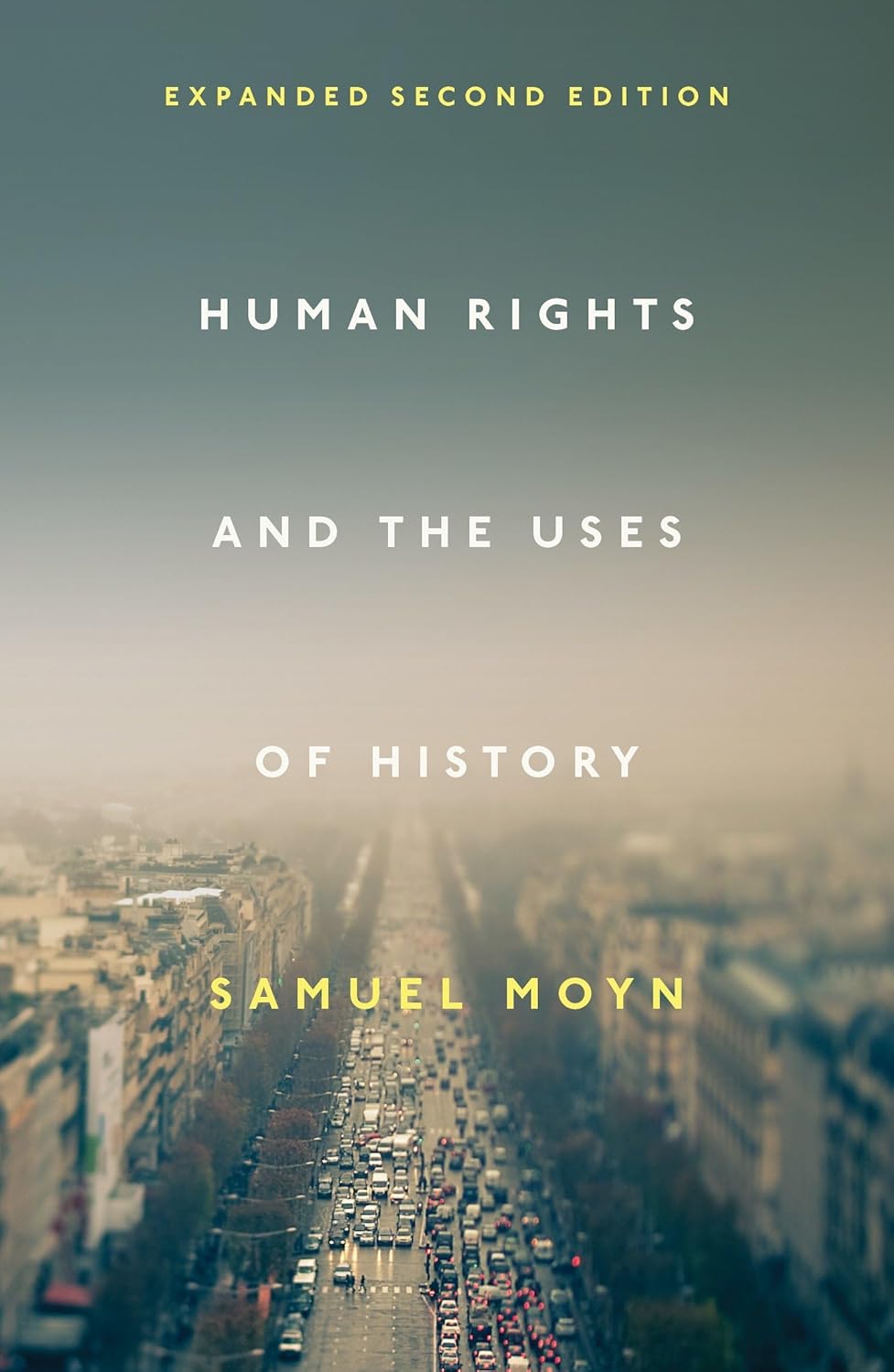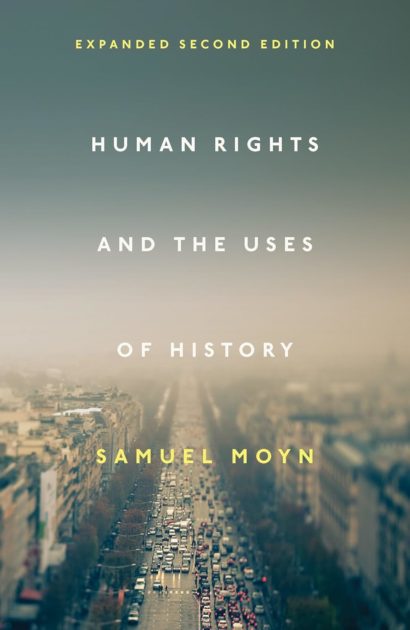
英語タイトル:『HUMAN RIGHTS AND THE USES OF HISTORY』Samuel Moyn 2014
日本語タイトル:『人権と歴史の使用法』サミュエル・モイン 2014
目次
- 第1章 道徳の系譜学について
- 第2章 人間の尊厳の驚くべき起源
- 第3章 明白な不正:人道的介入について
- 第4章 砂漠と約束の地:国際法廷について
- 第5章 歴史における人権
- 第6章 ホロコースト記憶との交差点
- 第7章 拷問とタブー
- 第8章 穏やかな販売:リベラル国際主義について
- エピローグ:人権の未来
本書の概要
短い解説:
本書は、現代の「国際人権」という政治思想・運動の歴史的起源を、従来の通説とは異なる視点から検証し、その限界と可能性を問い直すことを目的としている。歴史家、政治学者、哲学者、国際関係に関心のある一般読者に向けて、人権思想の「真正さ」を担保するための歴史探求がいかに誤用されうるかを示し、「歴史の批判的使用」の重要性を説く。
著者について:
著者サミュエル・モインは、コロンビア大学の歴史学・人権学教授であり、現代人権思想史研究の先駆者の一人である。本書では、彼の主著『The Last Utopia』の論点を発展させ、人権の起源を古代や18世紀の革命、第二次世界大戦直後にではなく、1970年代の冷戦下の政治的・思想的転換点に見出すという独創的な解釈を基盤に、歴史の「現代的利用」とその陥穽を多角的に論じている。
テーマ解説
- 主要テーマ:歴史の使用と濫用:歴史記述が現在の政治的・倫理的立場を正当化するために誤用される現象を批判的に分析する。
- 新規性:人権の「発明」としての1970年代:現代の国際人権規範・運動の成立を、冷戦構造の変容、帝国主義後の失望、他のユートピア主義(国家福祉主義、反植民地主義)の凋落という文脈で捉え直す。
- 興味深い知見:人権と帝国の共犯関係:人権や人道的レトリックが、過去の大英帝国や現代アメリカのリベラル国際主義において、覇権や介入を道徳的に正当化するために利用されてきたという指摘。
キーワード解説(抜粋)
- リベラル国際主義:自由、民主主義、人権、国際法に基づく国際秩序を構想し、アメリカの主導的役割を正当化する思想。著者はその歴史的起源と帝国主義的側面を批判する。
- 人道(的)介入:人道的危機を理由とする他国への軍事介入。歴史的には帝国主義の道具であり、現代でも同様のリスクをはらむと指摘。
- 人間の尊厳:憲法や国際文書の基盤となる概念。著者はその思想的起源を貴族の身分に求め、現代の普遍的価値としての定着にはカトリック思想や冷戦期の政治が大きく関与したと論じる。
- アンチ・ポリティクス(反政治):1970年代の東欧反体制派が採用した、イデオロギー的な政治闘争を放棄し、普遍的で道徳的な「人権」を盾に体制を批判する姿勢。人権運動の脱政治化の源流と見なされる。
- 歴史の批判的使用:過去を現在の自己満足のための鏡とするのではなく、現在の前提を相対化し、より良い未来を構想するための資源として活用する態度。著者が提唱する歴史家の姿勢。
3分要約
本書『人権と歴史の使用法』は、現代の「国際人権」という崇高な理念と運動が、その起源をめぐる歴史叙述によってしばしば誤った正当化を受けてきたことを批判的に検証する。著者サミュエル・モインは、人権の起源を古代や啓蒙思想、第二次世界大戦直後に求める従来の「起源神話」を退ける。
それらの時代の権利概念は、今日の国際的な個人保護や非国家アクターによる監視を軸とする運動とは本質的に異なっていた。真の転換点は1970年代である。冷戦下で国家社会主義や革命的ユートピアが退潮し、米国のベトナム戦争後の道徳的退廃と反省、東欧における反体制運動の「アンチ・ポリティクス」の戦略が交差する中で、「人権」は最小限の道徳的基盤として、失望と幻滅の後に残された「最後のユートピア」として登場した。
しかし、この歴史的文脈ゆえに、現代の人権は根本的な限界を抱えている。それは構造的な不正義や経済的権利よりも、目に見える身体的暴力(拷問、大量虐殺)への反応を優先させがちであり、政治的闘争よりも法廷やNGOによるモニタリングを重視する傾向にある。
著者は、英国帝国主義の「人道」的レトリックや、冷戦後のアメリカ主導の「リベラル国際主義」に人権が組み込まれる危険性を指摘する。人権は覇権の道徳的化粧として機能し、真の社会変革を阻害する可能性さえある。
最終的に著者は、人権が単なる悪の防止や被害者の救済に留まるのではなく、より積極的で再分配的、集団的な正義のビジョンへと脱皮する必要性を訴える。そのためには、人権の歴史を「批判的に使用」し、その概念を固定的なものと見なすのではなく、政治的に再解釈・再構築する闘争が不可欠であると結論づける。
各章の要約
第1章 道徳の系譜学について
リンダ・ハントの『人権の発明』を中心に、人権の起源を18世紀の啓蒙主義と民主革命に求める歴史叙述を批判する。このアプローチは、人権を連綿と続く進歩的伝統の頂点と見なし、現代の政治的課題(特にブッシュ政権下のイラク戦争と拷問)に過去を都合よく接合する「時代錯誤」である。著者は、18世紀の「人間の権利」が国民主権や財産権と不可分であり、今日の国際的な人権運動とは本質的に異なること、そして人権の真の世界的ブレイクスルーが1970年代であることを主張する。人権史は、現在の自己正当化のためではなく、過去の異質性を尊重しつつ、未来の可能性を拓くために書かれるべきである。
第2章 人間の尊厳の驚くべき起源
現代の憲法や国際法の基本概念である「人間の尊厳」の思想的起源を探る。ジェレミー・ウォルドロンが論じるような、貴族的な高貴さ(ランク)の民主化という単純な起源説では不十分である。むしろ、その近代的定着にはイマヌエル・カントの哲学以上に、20世紀半ばのカトリック思想(特に反共産主義と社会階層秩序の擁護)が決定的な役割を果たした。国際連合憲章や西ドイツ基本法に「尊厳」が挿入された背景には、冷戦下のキリスト教民主主義の影響があった。その意味で、尊厳概念は普遍的な哲学的原理というより、特定の歴史的・政治的コンテクストの産物であり、今日の世俗的・リベラルな解釈とは緊張関係にある。
第3章 明白な不正:人道的介入について
ギャリー・バスの『自由の戦い』を題材に、19世紀の「人道的介入」の事例(ギリシア独立戦争、ブルガリア問題等)を現代の介入の正当性の源泉として回収する試みを批判する。著者は、19世紀の人道的レトリックが帝国主義の拡大と不可分であったことを指摘する。人道主義は、センセーショナリズムやキリスト教徒への選択的同情、構造的な政治的経済的問題からの注意逸らしといった「症候群」を伴いがちである。21世紀の「人道的介入」の理論も、その起源に無自覚であれば、大義名分としての力を弱め、覇権の道具に堕する危険性がある。
第4章 砂漠と約束の地:国際法廷について
ジェニー・マルティネスの『奴隷貿易と国際人権法の起源』とキャスリン・シッキンクの『正義の連鎖』を検討し、国際刑事裁判所(ICC)に象徴される「国際司法による正義」の台頭とその限界を論じる。マルティネスは19世紀の奴隷貿易取締り混合委員会を国際人権法の先駆と称揚するが、著者はこれが英国の海上覇権確立の手段であり、真の権利付与ではなかったと批判する。シッキンクは国内・国際的な責任追及の拡大を「規範の普及」として肯定的に描くが、それが冷戦終結という地政学的転換と、より構造的な社会正義の追求が後退した文脈で生じたことを軽視している。著者は、刑事司法は重要だが、真の正義は再分配と構造的改革を伴わなければならないと論じる。
第5章 歴史における人権
著者の核心的論考。現代の国際人権運動の起源が1970年代にあることを体系的に論証する。1940年代(国連・世界人権宣言の時代)は、国家福祉主義の構築が主眼であり、国際的な個人保護を目指す人権運動は存在せず、ホロコーストへの応答でもなかった。その後、脱植民地化の時代には、人権は国家主権と結びつき、介入を阻む盾として機能した。1970年代、米国のベトナム戦争後の道徳的回復(カーター政権)、東欧の反体制運動の「アンチ・ポリティクス」、国家や革命への幻滅が重なり、アムネスティ・インターナショナルのようなNGOを中心に、最小限の普遍的モラルとしての人権が世界的に認知されるようになった。著者は、この「最後のユートピア」が、現在では新保守主義の戦争や新自由主義的秩序とすら結びつきうる危険性を指摘し、人権の再政治化とより深い社会変革への接続を呼びかける。
第6章 ホロコースト記憶との交差点
人権とホロコースト記憶の結びつきは自明ではないことを論じる。1940年代、人権はホロコーストへの直接の応答ではなかった。両者の結びつきが確立したのは、1970年代以降、ホロコーストの公的記憶が形成されると同時に、脱植民地化後の第三世界への失望が広がった時期である。この文脈で、人権は「最悪の悪」を防ぐという限定的な人道主義的使命と結びつき、「最善の善」(国家福祉や世界的経済正義)を構想するより壮大な政治的プロジェクトから人々の注意をそらす作用ももった。両者の関係史は、人権の現在の限界を理解する上で重要である。
第7章 拷問とタブー
現代における「拷問」のタブー化の歴史的背景と、それが象徴する政治的想像力の縮減を分析する。拷問禁止の世界的規範が確立したのは1970年代のアムネスティ・インターナショナルのキャンペーン以降であり、それは帝国主義的暴力からの撤退と国内民主主義の危機(ギリシャ、チリなど)への対応の文脈で生まれた。著者は、文学研究者エレイン・スキャリーと哲学者リチャード・ローティの思想を検討し、彼らが拷問を「最悪の悪」と位置づけ、私有領域での創造性の擁護と結びつけることで、公的領域での実質的な社会変革の構想から退却したと論じる。今日の拷問への過剰な関心は、より構造的な不正義(経済的不平等)への対処を阻害する危険性を含んでいる。
第8章 穏やかな販売:リベラル国際主義について
G・ジョン・アイケンベリーの『リベラル・リヴァイアサン』を批判的に検討し、米国主導の「リベラル国際主義」が、多国間主義と人権のレトリックで覆われた覇権(ヘゲモニー)にすぎないと論じる。著者は、この思想が英国帝国主義の「文明化の使命」と同型の「やわらかい販売」であると指摘する。アイケンベリーの歴史叙述は、冷戦期の米国の非リベラルな介入を「失敗」として軽視し、理想化された伝統を作り上げている。リベラル国際主義は、米国の衰退が予見される中で自らの価値を「固定化」しようとする企てでもあり、覇権の道徳的装飾という本質を見失わせる危険がある。
エピローグ:人権の未来
本書の論点を総括し、人権の未来について提言する。人権は「現実との妥協」から生まれたユートピアであり、ゆえに現実を変える力が弱い。著者は、人権が政治的闘争を隠蔽する「道徳的コンセンサス」の仮面を脱ぎ、より野心的で党派的な社会変革のプログラムとして再構築されるべきだと主張する。そのためには、裁判所への依存を脱し、草の根の動員力を強化するとともに、市民的・政治的権利だけでなく、経済的・社会的権利を中心に据え、集団的・構造的な不正義に取り組む必要がある。歴史の「批判的使用」は、人権を固定的な遺産としてではなく、未来に向けて創造的に再解釈・再発明されるべき理念として捉えることを可能にする。
パスワード記載ページ(note.com)はこちら
注:noteのメンバーのみ閲覧できます。