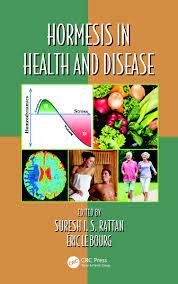
Hormesis in health and disease
目次
- まえがき
- 編集者
- 貢献者
- 第1節歴史と用語–
- 第1章 ホルミシスの略歴とその用語 3
- 第2節ホルミシスの前処理と後処理 13
- 第2章 ヒトにおけるホルミシスの証拠
- 第3章 運動とホルミシス線量反応曲線の形成 37
- 第4章 栄養成分 どのようにして適応能力を高めるのか 適応能力を高める方法 45
- 第5章 定期的な断食とホルミシス . 79
- 第6章 鉄分、メタボリックシンドローム、ホルミシス .93
- 第7章 放射線被曝 107
- 第8章 適応性ストレス応答としての熱水治療法。ホルミシスの重要性、メカニズム、および治療への影響 . 153
- 第9章 心臓虚血性プレコンディショニングと虚血・再灌流障害 . 167
- 第10章 脳虚血 . 185
- 第11章 最適ストレス、心理的回復力、およびサンドパイルモデル . 201
- 第3節ホルミシスの分子機構
- 第12章 ホルミシスの基盤となる分子ストレス応答経路 227
- 第13章 炎症反応経路 243
- 第14章 酸化ストレス応答経路: ホルミシスにおけるレドックスシグナルの役割 281
- 第5節リスクアセスメントにおけるホルミシス
- 第15章 ホルミシスを倫理と政策に関連づけるために概念的問題と科学的不確実性 .307
- 第16章 ホルミシスとリスクアセスメント 339
序文
現在、動物モデル、特にハエDrosophila melanogasterや線虫Caenorhabditis elegansにおいて、いくつかの穏やかなストレスが生存、健康、老化、および長寿にプラスの効果をもたらすという一般的な見解がある(レビュー:Rattan [2008] and Le Bourg [2009]などに記載)。また、培養中のヒト細胞を含む哺乳類モデルにおいても、特に老化や長寿に関して、このようなホルミシス効果に関する研究が行われている(例えば、Demirovic and Rattan 2013)。ストレスを利用して健康を増進させるという考え方は、一見すると逆説的である。なぜなら、Selye (1970)が定義したように、「厳密には、ストレスとは、生き物がある瞬間にさらされる消耗の割合である」ため、ストレスにさらされることは、通常私たちが望むことではない。さらに、Selye(1975)によれば、ストレスとは「客観的に測定可能な身体的症状を伴う症候群で、さまざまな感情的・身体的要因によって誘発される」ものである。この定義には、ストレスの有益性や生命維持効果という概念はなく、Selye(1975)は、このため、2種類のストレスを区別している。「適応のための要求で、同意できるもの、有益なものとして経験されるものは、苦痛と対立して、ユーストレスと呼ばれる」
その後、Sacher(1977)は、「少量の抑うつ剤や毒性物質が刺激となる現象のクラス」、すなわち、寿命に対するホルミシス効果を持つストレスの延命効果を検討した。しかし、ホルミシス効果は「健康な活動的な動物では起こりにくく、病気やうつ病の動物では顕著に現れやすい」と考え、「ホルミシスはある意味で老年学研究の道を阻む障害であり、それを理解し無効化する努力は十分に正当化できるだろう」とした。そのためには、「元気な動物の遺伝子型を繁殖させ、…動物の行動、生理、免疫の健康に最適な生活環境を開発する」(Sacher 1977)ことが必要であった。したがって、軽度のストレスが寿命に及ぼす好影響を観察した人は、その結果は興味なく、研究室での飼育方法が最適でなかったのだろうと結論づけることができただろう。
しかし、Sacher (1977)とは対照的に、Frolkis (1993) は、「1970年に私たちは、軽度の大きさの様々なストレス暴露の繰り返しが生物の防御機構を鍛え、…寿命を延ばすかもしれないと提案した」と書き、ラットでの成功体験を報告している(Frolkis [1982], pp.9, 92参照)。Sacher(1977)の論文は英語で、Frolkisら(1976)はロシア語で書かれた論文で結果を報告したため、Sacherの方が長年にわたって生物老年学者たちに大きな影響を与え、軽いストレスのプラスの効果を研究することは、当時、最優先事項として考えられていなかったことは驚くべきことではなかった。
しかし、これで終わりではなく、20世紀最後の10年間に、一部の生物遺伝学者が、主に無脊椎動物において、長寿とストレス耐性にマイルドストレスが正の効果をもたらすことを報告した(これらの初期の結果のレビューはMinois [2000]に掲載)。この総説が発表された後、軽度のストレスが老化や長寿に良い影響を与えることを示す多くの新しい結果が発表され、最適でない生活環境の使用では説明できないこれらの良い結果は、ホルミシスへの関心を復活させた。その後、軽度ストレスの老化への影響に関する最初の本が出版され(Le Bourg and Rattan 2008)、さらに一般的な本(Mattson and Calabrese 2010)がすぐに続き、ヒトへの軽度ストレスの使用に関する専門家の討論が行われた(Le Bourg and Rattan 2010)。このように、モデル生物において、マイルドストレスが老化、長寿、他のストレスに対する抵抗力にプラスの効果をもたらすという考え方にコンセンサスが得られただけでなく、マイルドストレスの正確な利用方法について十分な明確性がないとしても、人間においても利用できる可能性があることが明らかになった。
興味深いことに、著者たちがその結果を必ずしもホルミシス効果と解釈していないとしても、ヒトにおけるマイルドストレスの効果に関する研究が行われており、また現在も行われている。実のところ、ヒトの老化、健康、強いストレスや病気に対する抵抗力に対するホルミシスの効果を示す結果は数多く存在するようだ。しかし、これらのデータは文献に分散しており、必ずしもホルミシス効果として解釈されていないため、その完全な理解、評価、適用が制限されている。したがって、多くの著者がホルミシス効果の存在を無視していたとしても、そのような効果を示す結果を集めてきたというパラドックスがある。例えば、適度な運動を繰り返し行うことで、健康や寿命に良い影響を与えることが多くの研究で示されている(例えば、Paffenbarger et al. 1986)が、著者たちは、運動がホルミシス効果を持つ軽いストレスであるという結論には至っていない。
そこで私たちは、運動、放射線、温度、栄養、虚血、絶食、精神的挑戦によって達成されるヒトにおけるホルミシスの証拠をレビューし、ホルミシスのメカニズムや倫理的・法的問題を論じるとともに、1冊の本を捧げる時が来たと感じる。私たちの動機は、臨床医、研究者、医療関係者、医療産業、社会的・政治的政策立案者に、特に健康維持、疾病予防、さらには特定の疾病に対する治療アプローチとして、軽度のストレス誘発ホルミシスに関して、ストレスの二重性の強みと限界を学ぶ新しい戦略を開始し実行するように説得することである。しかし、編集者として私たちが目指したのは、このテーマの枠組みの中で、どのような方法でも自由に意見を述べることができる一流の専門家からの寄稿を集めることだったことを強調しなければならない。そこで本書は、ホルミシスに関する研究の現状、疑問、議論、疑義、論争を提示しようとするもので、歴史と用語、ヒトにおけるホルミシスの証拠、ホルミシスの分子機構、リスク評価におけるホルミシスの4つのセクションから構成されている。
第1節では、ホルミシスの歴史と用語について若干の情報を提供し、その主な特徴を述べているが、これは、様々な軽いストレスや刺激が健康寿命の改善に役立つという証拠を提示する前に必要なステップである。なお 2007年に発表された50名以上の著者によるコンセンサス論文(Calabrese et al. 2007)で提案されたホルミシスの用語とは別に、ホルミシスの可能性を持つあらゆる状態に対するホルメチン(Rattan 2008)、ホルミシスの研究分野または科学に対するホルメティクス(Rattan 2012)などの用語も提案・使用されていることも付け加えておく。
9つの章からなるセクションIIでは、ホルミシス効果が様々なストレスに依存し、様々な器官や生物レベルで観察されうることを示す。これらのストレスは多岐にわたり、身体運動、栄養成分、絶食、微量栄養素、放射線照射、熱、虚血、さらには精神的なチャレンジも含まれる。このように、さまざまな軽いストレス、チャレンジ、あるいは刺激が健康や健康寿命を改善する可能性がある。このことは、最も簡単で安価な健康増進手段として医師が日常的に推奨している運動だけでなく、虚血発作や心筋梗塞というしばしば致命的な結果に直面する際の虚血・心筋プレコンディショニングにおいても明らかだ。絶食については、例えば、がんに対する化学療法の効果を高めるために、1回の絶食でも役に立つ可能性があり(Lee and Longo 2011)、術後の回復を改善するために手術前の絶食を長くすることについて議論がある(Mitchell et al. 2010)。しかし、すべてのホルミシス効果が温度などの環境負荷に起因するわけではなく、栄養成分の中には、高用量で毒性を示すにもかかわらず、低用量で使用するとストレスフルな事象に抵抗する生物の能力を高めることによって有益な効果をもたらすと考えられるものもある。
第III章は3つの章で構成され、主に動物モデルを用いた実験により、これまでに解明されたホルミシスのメカニズムについて概説している。ホルミシス効果のメカニズムを解明することは、このようなホルミシス効果を持つ新しいマイルドストレスを発見することよりも、おそらく大きな課題である。確固たる答えはまだ出ていないが、受容体や後受容体転写因子、下流のエフェクターが関与するシグナル伝達経路や即時型、遅延型のストレス応答経路が関与していることは明らかなようだ。
第IV章では、リスクアセスメント規制やその他の倫理的側面におけるこの概念の導入に関する議論があるように、ホルミシスがいかに広い範囲に影響を及ぼす可能性があるかについて議論する。編集者は、科学において論争がある場合、他の科学者が自分自身の結論を出すのを助けるために、異なる意見の表明を支持することが適切であるという考えを支持する。しかし、リスク評価に関する議論は科学者の専売特許ではなく、例えば、安全規制を修正するかしないかは、すべての人にとっての関心事だからだ。
本書のすべての章は、動物モデルや体外で培養した細胞だけでなく、人間にも健康に役立つホルミシス効果が存在することを示している。しかし、疑問が残る。例えば、年齢を問わず、軽いストレスで健康寿命を延ばし、悪影響を与えないようにすることは可能だろうか?高齢になっても禁忌とされない運動では可能だと思われるが、例えばサウナはほとんどの人が何歳になっても利用できるのか、それとも治療的なアプローチでしか利用できないのだろうか。手術前の絶食期間を長くしたり(Mitchell et al. 2010)、心臓手術の回復を改善するために高気圧高酸素や一酸化炭素を利用したり(Lavitrano et al. 2004; Li et al. 2011; Liu et al. 2012)、将来の治療現場では軽度のストレスが一般的になるのだろうか。
予防および治療戦略としてホルミシスに頼ることは、話題性があり重要なことである。なぜなら、現代の医療は、生物学的および化学的に明確な原因物質が存在する疾患を治療するだけでなく、ライフスタイルや長寿の結果として生じる問題にも対処しなければならないからだ。アルツハイマー病、パーキンソン病、2型糖尿病、骨粗鬆症、サルコペニア、さらには癌など、ほとんどすべての加齢関連疾患は、複雑な起源を持ち、従来の意味での治療ができない(Rattan 2013)。さらに、このような疾患の長期的な管理や治療の試みにはコストがかかる。そのため、健康を維持し、病気の発症を予防・遅延させ、人間の健康寿命を延ばすための新たな方法を発見・開発・普及させることが必要である。ホルミシスの科学であるホルメティクスは、さらなる研究、開発、応用が期待できる分野であると思われる。本書はその一歩を踏み出すものである。
編著者紹介
Suresh I.S. Rattan, PhD, DSc, デンマーク、オーフス大学分子生物学・遺伝学部の細胞老化研究室で、国際的に有名な生物遺伝学者である。彼は、老化研究と介入におけるホルミシスの試験と応用のパイオニアの一人である。専門は、ヒトの細胞老化の分子メカニズムの解明で、特にタンパク質の合成、修飾、ターンオーバーに関する研究を行っている。現在、いくつかのスキンケア製品に使用されているカイネチンとゼアチンの老化調節効果を発見した。国際的な学術誌や書籍に多数の原著論文や総説を発表し、様々な国際的な出版社から数冊の書籍を編集・共同編集している。また、英語、パンワクチン語、ヒンディー語、デンマーク語など、複数の言語で子供向けの人気科学書の著者でもある。
フランス国立科学研究センター(CNRS)、ポール・サバティエ大学(フランス・トゥールーズ)に所属する国際的に有名なバイオジェロントロジスト。ショウジョウバエにおける軽度のストレスの影響に関する研究でよく知られているが、学習、行動、人口動態に関する研究にも取り組んでいる。学術雑誌、編集本、新聞などに多数の論文を発表しており、生物学、人口統計学、社会的な事柄について、一般市民や学者向けにフランス語で老化に関する本を数冊執筆している。
両編集者はこれまでに、『Mild Stress and Healthy Aging』(Springer, 2008)を共同で編集し、国際的な査読付き学術誌Bio gerontology(2006)とDose Response(2010)に2つの特集号を持ち込んでいる。
第1章 歴史と用語
1.1 略歴
ホルミシスの概念は、ヒューゴ・シュルツ(1887年、1888)が、いくつかの化学消毒剤が低濃度では酵母の代謝を促進し、高濃度では抑制することを発見したことに始まる。シュルツは、この発見をもとに、当時伝統医学と呼ばれていたホメオパシーの説明原理を発見したと主張し、大きな論争を引き起こした。このように、シュルツの二相性用量反応は、科学界や医学界で正当な評価を受ける前に、否定され、退けられることになった。これらの行動は、科学とは別の問題に基づいていたのである。シュルツと彼の線量反応は、その後50年間、急速に疎外され、嘲笑され、科学的な追放者として扱われるようになる(Calabrese 2005, 2011)。
シュルツが二相性の用量反応をホメオパシーと結びつけた理由は、相互に関連する一連の出来事に基づいていた(Calabrese 2011)。まず、シュルツは以前、ベラトリンというホメオパシー薬を用いて胃腸炎患者の治療に成功したという報告を読んでいた。その後すぐに、この症状の原因である細菌が特定され、培養された。シュルツはその後、その細菌を入手し、ベラトリンが病気の原因となる生物を殺すことができるかどうかを評価した。その結果、ベラトリンの投与量にかかわらず、細菌を死滅させることはできなかった。このベラトリンの失敗は、治療が有効であるというシュルツの信念に影響を与えなかった。ただ、その理由を説明することができなかったのだ。一方、シュルツは酵母を使った実験で、複数の化学消毒剤による低用量刺激と高用量抑制の代謝反応を確実に再現することに成功した。その後、同僚のRudolf Arndtと話し合い、Schulzはこの一連の観察結果、すなわち、ベラトリンによる発見と化学消毒剤による二相性用量反応とを統合することを目指した。そして、ベラトリンは胃腸炎患者を治癒させたが、それは病気の原因となる生物を殺すことによってではなく、感染に抵抗する個体の適応能力を高めることによってであると結論づけた。この結論は、酵母を使った所見に基づくもので、低用量の刺激は、適応反応に影響を与える身体の能力を表すものであった。このような背景から、二相性投与研究は、低用量(限りなく低用量ではない)のホメオパシー薬がどのように作用するかを示す理論的枠組みを提供するものであった。このように、シュルツは、二相性用量反応の概念をホメオパシーの実践と結びつけることで、医学界の人々がこの二相性用量反応モデルの科学的基盤を探求することを政治的に不可能にしたのである。実際、二相性用量反応とホメオパシーを結びつけ、伝統医学と政治的に対立させることで、その逆が起こるような状況を作り出したのである。彼の行動は、新しい二相性用量反応への関心よりも、敵意を生み出すことになったのである。低用量反応と二相性用量反応の領域は、体系的に研究されることはなく、二相性用量反応が観察されたとしても、しばしば些細なこと、あるいは単純な変動として割り引かれる傾向があった。このように、二相性用量反応の概念は、生物医学界で悪いスタートを切り、その後、生物医学者の世代が変わっても、完全に回復することはなかった。二相性の用量反応に関しては、歴史の流れは陰湿で統制がとれており、非常に巧妙に偽装された行動がその公正な評価を妨げてきた。
二相性用量反応は、シュルツの余生において、しばしば実験で他の人に見られ、一流雑誌に報告されるようになった(Calabrese and Baldwin 2000a-e)。これによって、少なくとも科学界や医学界がシュルツの二相性用量反応の概念を少しずつ受け入れるようになったと考えられるが、少なくとも1932年に79歳で亡くなった彼の生涯においては、そうはならなかった。その主な理由は、20世紀初頭の数十年間にかなりの影響力、権力、名声を得た伝統医学が、シュルツを疎外し続け、同時にホメオパシーの高希釈派と誤認させることで、シュルツとホメオパシーの関係を意図的に誤認させていたからである(Calamrese 2005, 2011)。20世紀第3四半期の終わりには、ホメオパシーはもはや医学の重大なライバルではなくなっており、シュルツはまもなく亡くなり、医学は教科書、専門学会活動、研究資金、政府の諮問活動から排除することで、二相性用量反応が決して台頭することがないようにし続けることになる。
ホメオパシーが用量反応モデルを採用することで伝統医学を凌駕したため、伝統医学は、二相性用量反応に挑戦するだけでなく、独自の用量反応モデルを提案することで対抗するだろう。伝統医学は、ライバルである二相性の用量反応関係を考慮することができず、閾値用量反応をデフォルトのモデルとして選択し、それを医薬品評価やリスク評価の中心に据えた。閾値用量反応は、選択されたモデルとして不合理なものではなかった。発表された文献の中には、閾値用量反応の概念を支持する論文があった(Shackell 1923, 1925; Shackell et al. 1924/1925)。閾値の概念は理解しやすく、飲酒や特定の薬物の摂取など、用量に関連する行為で自分の体験を振り返るような人々の共通体験に響くものであった。しかし、医学は、このモデルをリスク評価の領域で優先させる際に、デューディリジェンスを怠った。閾値線量反応モデルが、一般に人々が生活する低線量域で正確な予測を行う能力を検証することを怠ったのである。この検証の欠如は、21世紀の最初の10年間で、薬理学と毒性学の重大な失敗を浮き彫りにすることになった。彼らは、線量反応の検証要件を、集団の監視から逃がしてしまったのである。
ホルミシスが科学界に受け入れられた大きな問題は、医学とホメオパシーの間の強力な政治的対立を超えて、この二相性用量反応概念が、二相性用量反応の量的特徴、時間的特徴、一般性、最適化の条件、メカニズムに関して、シュルツを含む支持者によってもよく理解されていなかったことであった。特に重要なのは、ホルミシスの刺激が一貫して控えめで、ほとんど常に対照群の2倍以下であったという事実である。最大刺激量は、通常、対照群に比べて30%から60%程度に過ぎない。この控えめな刺激により、ホルミシス反応を検出し、バックグラウンドの変動と区別することが困難となった。第二に、低用量刺激は、時に明らかな直接的刺激反応とみなされることがある。しかし、他の生物学的モデルやエンドポイントでは、ホメオスタシスの初期破壊の後、あるいは適度な毒性の後にのみ観察される(Calabrese 1999, 2001; Calabrese and Baldwin 2002)。この後者の場合、実験では用量-時間応答が必要である。通常、低線量刺激反応の両者が発生すること、あるいは発生するとしても互いにどのような関係があるのか、また発生するとすればそれぞれの意義は何か、は明らかでなかった。20世紀初頭の放射線生物学の専門家の場合、直接的な刺激応答は生物学的に重要な意味を持つ可能性があると見なされたのに対し、代償的な刺激応答は些細な修復過程として却下されがちであった。しかし、その後、線量反応に関する文献を詳細に評価した結果、どちらのタイプの反応も起こりうること、そして線量反応の量的特徴も同じであることが判明することになる。このように、20世紀初頭の数十年間、研究者は、特に低用量域における用量反応の本質を理解し、その再現の概念に苦心したが、実際には低用量の刺激反応が本質的に控えめであることに気づいてはいなかった。1920年代初頭から科学界で影響力を拡大しつつあった仮説検定と統計的検出力の概念は、今日のようにホルミシス学的用量反応概念の初期進化に影響を与えることはなかった。このような状況下では、研究デザインの強さ、統計的検出力、研究結果の再現性、機構的理解などがより強く求められるようになるであろう。ホルミシス学的線量反応の一般的な性質が理解されないもう一つの要因は、放射線ホルミシス分野の研究が化学ホルミシス分野の研究者をほとんど認めず、引用しなかったことである。このような生物学的分野間の統合の失敗は、放射線ホルミシスと化学ホルミシスの両方の視点の強度を著しく低下させた(表11)。
1930年から1980年まで、ホルミシスの概念は、異なる用語のもとで少しずつ拡大し、ゆっくりと、しかし着実に出版されたが、大きな知名度や重要性を得ることはなかった。しかし、ホルミシスの概念が特別に評価される機会があっても、それが理解されていないために失敗し、その理解不足が評価に影響することもあった。例えば、米国農務省(USDA)は、電離放射線が商業目的のために野菜の成長と生産性を高める能力を評価しようとした(Alexander 1950)。
表11 化学的および放射線ホルミシスの歴史的限界に至る要因の評価
化学的ホルミシスと放射線ホルミシスのどちらかに特化した限界
ケミカルホルミシス
- ホメオパシーと歴史的に密接な関係がある
- 第一線の薬学者による強い批判
- 農業、工業、医療への応用が認識されていなかった
- ホルミシスの概念を裏付ける臨床的、疫学的データが不足していた
- 米国農務省の研究に見られるように、応用に失敗している。放射線ホルミシス
- 発表された放射線文献を整理するためにラッキーが努力したにもかかわらず、放射線ホルミシスのデータベースは化学ホルミシスに比べてはるかに弱かった。彼の努力は、まさに逆の印象を与えるほどであった
- 1936年に米国学術会議(NRC)がエドナ・ジョンソン(1936)論文でホルミシス概念を技術的に批判したことは、米国の最高レベルの科学専門家/評判におけるこの概念の受け入れに影響を与えた
- ハーマンJ.ミュラーや他の放射線遺伝学者の研究に基づき、非常に低線量でも突然変異による発癌の健康被害が懸念された
- 適応反応やDNA修復に関する発見は、線量反応の概念が確立された後に起こった。このことは、線量反応の歴史的基盤に大きな影響を与えた
化学ホルミシスと放射線ホルミシスに共通する限界
- ホルミシス学的な用量反応の定量的な特徴を理解できなかった
- 低用量での刺激が本質的に控えめであることを理解していなかった
- 毒性および/または薬理学的閾値以下の用量を適切な間隔で多数投与する、強力な試験デザインの必要性を理解できなかった
- ホルミシス学的概念を評価するために必要な余分な資源、特に被験者数、経時的なサンプリング、再現性の必要性に関して理解できなかった
- 用量反応の分野で研究している科学者が比較的少数であり、かつ多様な分野の科学者が存在したため、重要な科学者のプールや規模を開発することができなかった
- ホルミシスが広く受け入れられるには、歴史的なタイミングが良くなかった。より高い優先順位は、閾値以下ではなく、閾値以上の用量反応の性質を評価することに振り向けられた
- 地域社会や労働者の被曝基準を定めることが、政府にとってはるかに大きな必要性であった。このため、低線量ホルミシス効果は疎外されることになった
- 低線量域での線量反応の性質について組織的な存在感を示せなかったことは、資金調達、出版、その他の専門的・教育的出口に影響を与えた
彼らは1940年代半ばから後半にかけて、さまざまな野菜を使った精巧で多施設にわたる研究プログラムを作成した。しかし、この研究では、1つの線量しか取り入れず、テストした各野菜に同じ線量を使用した。さらに、ホルミシス療法が適用される可能性のある閾値以下の反応を特定するための予備試験も行われなかった。ホルミシス概念を商業的に応用するためのこの試みは、ホルミシスの用量反応に対する深い理解不足を反映しており、事実上、一般的なホルミシス反応を検出できないことになっていた(実際、検出された)。この米国連邦機関の多大な努力にもかかわらず、研究戦略と研究デザインはホルミシス仮説を検証するには不十分であり、不適切であった。今にして思えば、シュルツの死後15年経っても、担当者はホルミシスの用量反応関係の基本的な部分を理解していなかったことが明らかだ。しかし、米国農務省が行ったこの大規模な調査結果は、同省内のホルミシス概念に決定的な打撃を与え、他の省庁、大学、民間組織における並行活動の可能性に影響を与えたという意味で重要であった。ホルミシスの概念が新たな関心を呼ぶには、数十年(すなわち、科学者の新しい世代)を要する。
1970年代後半になると、用量反応領域で科学的変化が起きていた。非常に多様な生物学的分野から数多くの研究者が、二相性用量反応をそれなりに一般的な出来事として報告し始めた。これは、低線量での測定能力の著しい向上と、全動物実験よりも多くの濃度・用量を調べることができる細胞培養研究への関心の高まりがもたらしたものであった。さらに重要なことは、ホルミシス現象をかなり深く研究し始めた研究者がいたことである。特に注目すべきは、異なる生物学分野から来た3人の人物である。トーマス・ラッキー(Thomas Luckey)は、1980年に電離放射線を扱ったホルミシスに関する最初の実質的な本を出版した。彼は1980年に電離放射線を扱ったホルミシスに関する最初の本格的な本を出版し、その後、その本の詳細な更新を行った(Luckey 1991)。次に、神経薬理学者のElmer Szabadiは、薬理学の分野全体にわたって二相性用量反応の頻度をまとめた。彼はまた、このような反応を説明できる受容体ベースのメカニズムを提示した(Szabadi 1977)。3人目は、イギリスのプリマス研究所のトニー・ステッビングである。海洋毒性学者であるStebingは、海洋微生物に対する重金属の評価において、思いがけずホルミシス現象を発見した(Stebing 1976, 1981, 1998)。彼は、この現象について膨大な資料を作成するとともに、自分の観察を説明するために、サイバネティック・フィードバック・モデルのメカニズムを提案した。ホルミシス概念の再認識に貢献した同時代の研究者(Sacher 1963; Frolkis 1982)は他にもいたが、この3人は、科学界がホルミシス概念を新たに検討するよう刺激する最初の科学的指導力を提供したことになる。
ホルミシスの歴史における大きな出来事は、1985年8月にカリフォルニア州オークランドで開催された放射線ホルミシスに関する会議であった。日本電力研究所の服部禎男氏によると、1980年に出版されたラッキー氏の本に挑戦と刺激を受け、ホルミシスについてもっと学ぶ必要があった。もし、ルーキーが線量反応の性質について正しいのであれば、放射線のリスク評価や原子力発電を含む彼の産業にとって重要な意味を持つことになると彼は言った。服部は、カリフォルニア州パロアルトにある米国電力研究所に連絡を取り、そのやりとりの中で、1985年の会議が実現した。この会議の意義はいくつもある。ホルミシスというトピックに専門的な統一要素を提供したこと、国際的な範囲であったこと、この会議が日本の電力会社の資金による放射線ホルミシス研究プログラムの開発につながったこと、査読を受けた議事録が権威ある雑誌『ヘルスフィジックス』に掲載され、1989年に雑誌『サイエンス』でホルミシスシスに関する討論を行うことになったこと、マサチューセッツ大学で低レベル暴露の生体影響研究所を設立し長期にわたる研究および情報交換(例.また、マサチューセッツ大学の低レベル被曝生物学的影響研究所の設立につながり、ホルミシスに関する雑誌「Dose-Response」(旧Non-Linearity in Biology, Toxicology and Medicine)を含む長期的な研究・情報交換(会議、ワークショップ、出版車など)を行った。したがって、この努力は、ホルミシスというテーマを研究する他の人々を勇気づけ、エネルギー省、国立衛生研究所、国立科学財団、環境保護庁、軍などの米国連邦機関、およびさまざまな民間組織や財団による資金援助の機会を探るのに役立った。
Luckey(1980)の本やStebingの出版、Health Physicsの会議録にもかかわらず、1980年代のホルミシスやホルミシスに関する引用数は年平均10-15件に過ぎなかった。しかし、2012年には被引用数が4,500件に達し(図11)、総計は30,000件に近づいた。1990年代後半から始まった大きな増加は、米国原子力規制委員会(NRC)などの米国連邦政府機関からの資金援助や空軍の長期資金援助に関連している。
ホルミシスの評価を高めた微妙だが重要な科学技術の発展の一つは、先に述べたように、1980年代に細胞培養の使用へと劇的に変化したことである。これは、動物実験に比べ、より多くの濃度(用量)を評価するための費用対効果の高い方法として重要だった。過去15年間で、細胞培養によるホルミシス学的な用量反応を示す研究の割合は、全動物によるものをはるかに上回っている。
図11 Web of Knowledgeデータベースにおける「ホルミシス」または「ホルミシス」の引用文献
ホルミシス研究を促進するもう一つの科学的発展は、ホルミシス的二相性用量反応関係の基礎となるメカニズムの理解の進歩である。ホルミシス機構の解明は、受容体や細胞シグナル伝達経路のレベルで示されている。現在までに、400から500の再現性の高いホルミシス学的用量反応には、特定の受容体または細胞シグナル伝達経路を介した低用量刺激が存在する(Calabrese 2013)。受容体/シグナル伝達経路の阻害剤を使用することで、ホルミシス的な用量反応刺激をブロックすることができる。このように、ホルミシス現象は、記述的な現象から、根本的なメカニズムの理解へと大きく進展している。
1.2 バイオメディカル科学とホルミシス
製薬業界は、研究発表、規制当局への申請、広告においてホルミシスという用語を使用していないにもかかわらず、多くの医薬品は、基本的にホルミシス的な性質を持つ前臨床研究に基づいている。例えば、多数の抗不安薬(Calabrese 2008a)や抗けいれん薬(Calabrese 2008b)は、ホルミシス的な二相性用量反応関係を示し、定量的特徴はホルミシス的用量反応に完全に一致する。記憶を増強する薬剤の多くは、ホルミシス的な用量反応を反映して、二相性になる。米国食品医薬品局で承認されたアルツハイマー病治療薬の前臨床所見は、ホルミシス的な二相性用量反応を示している(Calabrese 2008c)。脳卒中関連の研究や脳外傷の予防・治療に関する研究でも、同様の用量反応プロファイルが報告されている(Calabrese 2008d; Zhao 2013)。特に重要なのは、神経変性、心臓病、脳卒中の予防や手術の成功率を高めるために適用されているプレコンディションとポストコンディショニングの概念が、ホルミシス概念に基づいていることである(Calabrese et al.2007).すなわち、プレコンディショニングやポストコンディショニングの治療を用量反応の枠組みで示すと、低用量の刺激と高用量の抑制というホルミシス的な結果が得られる。
生物医学の分野では、ホルミシスという言葉とその一般化の影響力が徐々に認識されつつある。しかし、ホルミシス的二相性用量反応概念は、生物学的性能を向上させることを目的とした薬剤の開発を導く主要な柱であった。ホルミシス概念は、医薬品の反応の上限と刺激反応の幅を規定するものであり、医薬品開発プロセスの中心的存在であるべきだ。実際、ホルミシスの用量反応には適度な刺激性があるため、反応性にかなりの不均一性があるヒトを対象とした臨床試験において、薬効を検出する上で大きな課題となる。
低用量刺激応答が有益と有害の両方の効果をもたらすという事実は、今後10年間で生物学および生物医学の分野でより統合されることが予想される。例えば、人工装具の感染に影響を与えるStaphylococcus epidermidisが作り出すバイオフィルムは、低用量の抗生物質によってホルミシス的に増強されることがある(Kaplan et al. 2011)。同様に、ホルミシス反応は、低用量で真菌の増殖が促進される懸念から、最近、農業に対する潜在的な脅威として認識されている(Garzon and Flores 2013)。内分泌撹乱化学物質をめぐる長引く議論の中心は、低用量域における用量反応の性質であり、非単調性という言葉を使うか、ホルミシス性という言葉を使うかにかかわらず、ホルミシス性用量反応の量的特徴に再び合致する(Calabrese 2008e)。このように、生物学的戦略は同じであり、すべてホルミシス学的な用量反応を反映している。
最近の用量反応分野の発展により、前処理、後処理、適応反応、非単調反応、Arndt-Schulz則、Yerkes-Dodson則、U型用量反応、J型反応、反動反応などの生物学的概念が収束しつつある(Calabrese 2007)。これらの一見多様な生物学的概念は、すべてホルミシス学的用量反応の現れであるという共通点がある。したがって、ホルミシス学的用量反応は、基本的で高度に保存された適応戦略に従って反応を統合する、これまで認識されていなかった一般的な生物学的原理を示すものである。この用量反応の概念は、医薬品開発、環境アセスメント、原因-便益分析、最適な老化を含むライフスタイルの選択などに深い示唆を与えている。
