カリン・フライ
ウィスコンシン大学スティーブンス・ポイント校(米国)
onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118663202.wberen493

ハンナ・アーレントは、雑誌「ニューヨーカー」で1961年にエルサレムで行われたアドルフ・アイヒマン裁判を取材した際に、「悪の陳腐さ」という概念を打ち立てた。アーレントは、悪を怪物的で悪魔的なものとして描くのではなく、全体主義社会がいかに無思慮と判断力の欠如に根ざした悪を助長しているかを強調した。アーレントにとって、悪とは、重要でないから、ありふれたものであるというのではなく、決まり文句やプロパガンダを無批判に受け入れることによって、人が犯すものである。
–
アーレントの裁判報道は、まず『ニューヨーカー』誌に連載され、その後1963年に単独で『アイヒマン・イン・エルサレム』という本として出版された。A Report on the Banality of Evil (Arendt 1963)』として出版された。アーレントは、政治理論家として、また戦時中のドイツからのユダヤ人難民として、この裁判の取材に関心をもっていた。
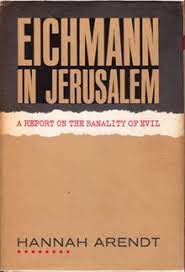
1951年に出版された『全体主義の起源』(Arendt 1973)では、全体主義の根本的な悪、つまり人間は不必要なものであると理解した上で、悪について述べている。しかし、アイヒマンの裁判での振る舞いを見ていると、アイヒマンが怪物的な殺人者であるようには見えないことから、アレントの立場は変わっていく。
彼女は、アイヒマンが怪物的な殺人者ではなく、「彼は道化師である」と疑っていた(Arendt 1963: 49)。アーレントは、アイヒマンが弁護のために使い、彼を高揚感で満たしているように見えたナチスの決まり文句や常套句に注目した。
アイヒマンは、命令に従ったことと幇助の罪は認めたものの、大量殺戮の責任は否定している。彼は収容所への移送を担当し、自分は誰も殺したことはないと主張し、ユダヤ人嫌いではないと主張している(Arendt 1963: 225)。
それにもかかわらず、アーレントは、彼が人道に対する罪で死刑に値すると考えた。アイヒマンの良心の欠如、自分の証言の矛盾を認識しないこと、服従の価値を優先させることは、アーレントにとって驚くべき無思慮を示唆するものであった。アイヒマンについて恐ろしいのは、その怪物性よりもむしろその正常性であった(Arendt 1963: 253)。

ナチスの官僚機構は、個人が個人的に大量殺人に関与しても、その責任を認識しないようなものであった。裁判での彼の証言から判断すると、アイヒマンは殺人のためというよりも、主に自分のキャリアのために犯罪を犯したとアーレントは考えている。
アイヒマンは、自分を法を守る市民であり、自分の職務に専念していると考えていた。犯罪行為に手を染めながらも、アイヒマンはイマヌエル・カントが定義した道徳的義務に従っていると考えていたのだ。アーレントは、アイヒマンのカント道徳の解釈が不合理であることを示し、定言命法を総統の意志への盲従に変えてしまった(Arendt 1963: 121)。
総統の命令に従うことで、アイヒマンはもはや自分自身の意志の主人ではなくなり、状況を何も変えることができなくなったと主張したのである。実際、彼は命令に従ったのだから、自分の行動は美徳であると考えていた。アイヒマンはホロコーストを集団で行った犯罪であると理解していたが、アーレントは、ある行為に対して全員が責任を負うのであれば、誰も本当の責任者ではないと考えて、個人ではなく集団の責任を否定していた(Arendt 1963: 225, 255)。
アーレントは、アイヒマンの性格の大きな欠点は、「相手の視点から何かを見ることがほとんどできない」ことだと主張している(Arendt 1963: 43)。このことが、政治における思考と判断の役割についてさらに検討する動機となった。
彼女は、拡大された精神、すなわち他人の視点から物事を見る能力が、政治家の重要な特性であると述べている。現代では、「悪の凡庸さ」”banality of evil “は全体主義にとどまらず、人を傷つけるような陰湿な無思慮を表す言葉として使われるようになった。
–
アイヒマンの痕跡に関するアーレントの研究に対して、政治的な論争が世間に巻き起こり、出版された論文、公開討論会、アーレントの主張に激しく反論するヤコブ・ロビンソンの極論本が出版された。マルガレーテ・フォン・トロッタが2013年に発表した映画『ハンナ・アーレント』は、この議論を新たなものにしている。
アイヒマンに関するアーレントの著作に対する多くの不満の中で、最も多かったのは、この本が書かれた口調である。多くの人にとって、その文章の口調は軽薄で、皮肉で、傲慢で、主題を考えると不適切なものだった。また、「平凡」という言葉をホロコーストと対にしているのは、大量虐殺という出来事を矮小化し、アイヒマンの行動がありふれたもの、あるいは許しうるものであると示唆しているように思われ、拒否反応を示す者もいた。
アーレント自身は、悪が平凡でつまらないものだという意味ではないと否定し、アイヒマンのような行動をとる可能性がすべての人にあると考えたわけでもない。アイヒマンの生涯を描いた伝記によれば、アイヒマンは積極的な反ユダヤ主義者で、狂信的であり、裁判での弁明よりもはるかに悪質であったからだ。
また、アーレントがアイヒマンに同情的すぎるのではないかと心配したり、彼女が自己嫌悪の反ユダヤ主義者であると非難したりする者もいた。アーレントの著書で最も議論を呼んだのは、ユダヤ人評議会がナチスを援助し、誰を収容所に入れるかを決定したことの罪について論じたことであった。
アーレントは、この問題を取り上げたのは、それが裁判で提起されたからであり、自分たちのメンバーだけでなく、犠牲者の間でも「ナチスが引き起こした道徳的崩壊の全体性」を示したかったからだと主張している(Arendt 1963: 111)。
これらの発言は、不適切に被害者を非難していると多くの人に理解された。私生活では、この著作のために重要な友人を失ったが、彼女は自分の意見を撤回することはなかった。多くのアーレント研究者は彼女の見解を支持し、それに対するいくつかの非難は、彼女の議論を注意深く読まなかった結果であると考えている。
アドルフ・アイヒマンがこの現象の適切な例であったかどうかにかかわらず、「悪の凡庸さ」という概念の影響は依然として深く、この概念自体は、極度の軽率さによって生み出された他の悪の例にも適用されている。
